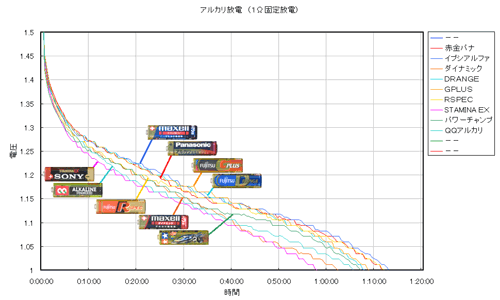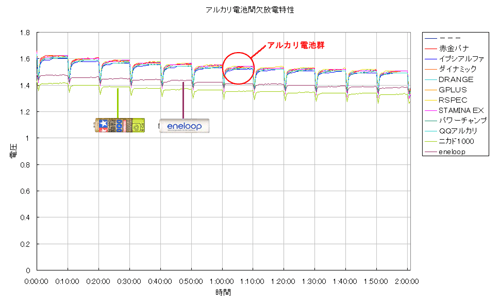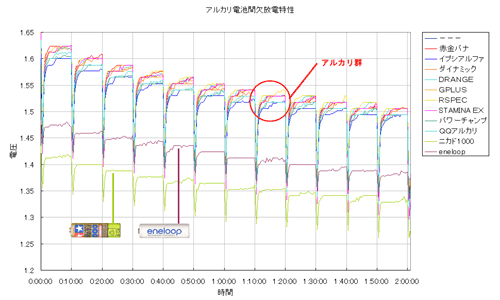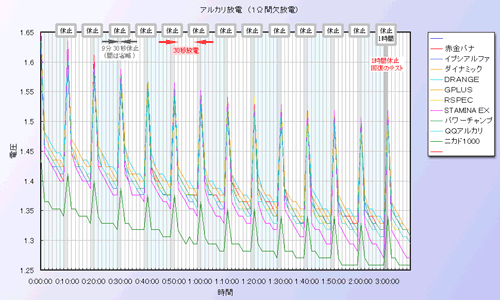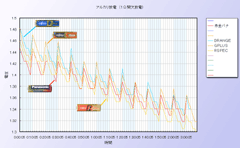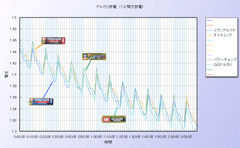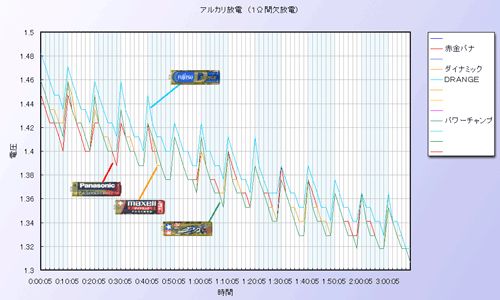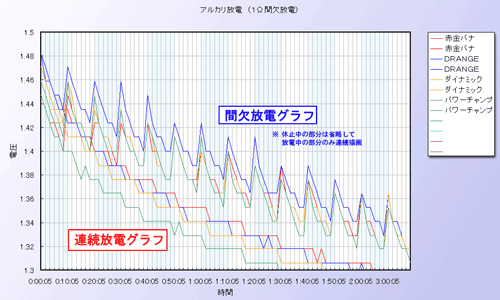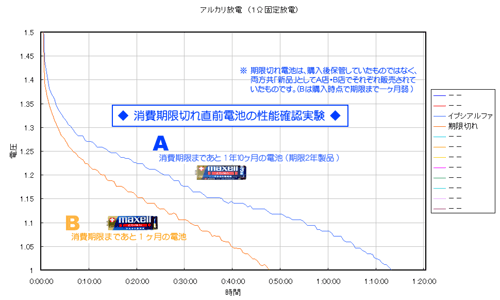|
※ Part-1,Part-2ページを統合しました (06/10/12)
100円ショップアルカリ乾電池性能評価試験で次回の予定としていました「有名メーカー製アルカリ電池性能評価試験」を行いました。
ここ最近の流れとして、各メーカーのアルカリ電池はデジカメ用途にあわせた高性能化が進んでいます。大電流をより効率良く取り出せるような改良が加えられ、更に大容量化された新電池が次々と発表されています。一見すると同じ電池でも、順次改良されて中身が変わってるものもあります。(おかげで店頭で古い在庫を買わされることも・・・)
日々進化を遂げるアルカリ乾電池の性能は製造各社で大きな違いはあるのでしょうか?
2006年7月現在で購入できる有名メーカー製アルカリ電池を量販店で購入し、その性能をみてみることにしましょう。
更に今回は通常の「大電流連続放電実験」とミニ四駆レースでの使用を想定した「間欠使用復活性能実験」を行います。
ここ最近の流れとして、各メーカーのアルカリ電池はデジカメ用途にあわせた高性能化が進んでいます。大電流をより効率良く取り出せるような改良が加えられ、更に大容量化された新電池が次々と発表されています。一見すると同じ電池でも、順次改良されて中身が変わってるものもあります。(おかげで店頭で古い在庫を買わされることも・・・)
日々進化を遂げるアルカリ乾電池の性能は製造各社で大きな違いはあるのでしょうか?
2006年7月現在で購入できる有名メーカー製アルカリ電池を量販店で購入し、その性能をみてみることにしましょう。
更に今回は通常の「大電流連続放電実験」とミニ四駆レースでの使用を想定した「間欠使用復活性能実験」を行います。
|
本記事では松下金パナの新型を「赤金パナ」と表記します。 ネット等では「赤パナ」と呼ばれている場合がありますが、「松下の赤」といえば「マンガン赤」電池[これ]のことですので、本ページでは混同しないようアルカリ電池の赤は金パナの進化形として「赤金パナ」と表記します。 |
| ■ 実験対象 |
実験に使用する電池は次の通りです。(2006年7月現在の各社最新製品)
※ 市販されている全ての電池を購入して試験できない事をご理解、ご了承ください。
※ 電池の性能は個体差、また製造ロットにより多少異なります。本試験は今回購入した品での比較であり、全ての同一種類電池の性能を厳密に指し示すデータではありません。
※ 電池性能は製造日からの経過日数により低下します(100円ショップアルカリ乾電池性能評価試験内の「電池の消費期限」囲み記事参照)。なるべく製造日から時間が経っていない電池を購入していますが、多少の日数差があることをご了承ください。
アルカリ電池の世界では、「青=大電流向け高性能電池」「赤=通常用途用汎用電池」という色分けが暗黙の了解になりつつあるようですね。
一時期は「金=高性能アルカリ」「それ以外=通常アルカリ」という風潮でしたが、いつの間にか「金はアルカリの代名詞」的なカラーリングの製品が多くなり、金の中で差別化を図らなければならないようになってしまったようです。しかしなんだか全て松下のカラーリングが他社でも踏襲されていってるような・・・? (マンガンの黒・赤もそうだったし…)
松下panasonicと日立maxellの2社の電池を主に扱っている某電器量販店の電池コーナーは真っ青と真っ赤に見事に色分けされていて、一見すると松下panasonicと日立maxellの2社の別電池が並んでいるようには見分けが付きませんでした。(どっちの売り場に見えたかは…)
●写真からメーカー公式サイトにリンクしています
●価格は4本パック品の、ある量販店店頭購入時価格です
●価格は4本パック品の、ある量販店店頭購入時価格です
※ 市販されている全ての電池を購入して試験できない事をご理解、ご了承ください。
※ 電池の性能は個体差、また製造ロットにより多少異なります。本試験は今回購入した品での比較であり、全ての同一種類電池の性能を厳密に指し示すデータではありません。
※ 電池性能は製造日からの経過日数により低下します(100円ショップアルカリ乾電池性能評価試験内の「電池の消費期限」囲み記事参照)。なるべく製造日から時間が経っていない電池を購入していますが、多少の日数差があることをご了承ください。
アルカリ電池の世界では、「青=大電流向け高性能電池」「赤=通常用途用汎用電池」という色分けが暗黙の了解になりつつあるようですね。
一時期は「金=高性能アルカリ」「それ以外=通常アルカリ」という風潮でしたが、いつの間にか「金はアルカリの代名詞」的なカラーリングの製品が多くなり、金の中で差別化を図らなければならないようになってしまったようです。しかしなんだか全て松下のカラーリングが他社でも踏襲されていってるような・・・? (マンガンの黒・赤もそうだったし…)
松下panasonicと日立maxellの2社の電池を主に扱っている某電器量販店の電池コーナーは真っ青と真っ赤に見事に色分けされていて、一見すると松下panasonicと日立maxellの2社の別電池が並んでいるようには見分けが付きませんでした。(どっちの売り場に見えたかは…)
| ★ 実験PART−1 ★ 大電流連続放電実験 ★ |
| ■ 実験方法 |
 今回の実験では、実験用の自作放電器Type-G(近日製作記事公開予定)を使用します。
今回の実験では、実験用の自作放電器Type-G(近日製作記事公開予定)を使用します。単3電池を同時に4本、「定抵抗負荷放電(1Ω)」と「定電流放電(0〜1A)」のいずれかの任意の設定で放電させることができます。
今回は強力懐中電灯やミニ四駆のモーター等と同じような状況が再現できる「1オーム定抵抗負荷放電」で実験を行います。終止電圧の設定は1.00Vとします。
自作放電器Type-Gにはデータロガー[K8047]を接続し、ノートPCで電圧を記録します。
最近の電池メーカーが電池の評価試験に使用しているデジカメを想定したCIPA規格準拠の放電方法(撮影と休憩を一定間隔で繰り返す)とは異なりますので、メーカーが宣伝している通りの性能差にならないことも考えられますが、前回行った100円ショップアルカリ乾電池性能評価試験の結果とも比較しやすいように定抵抗放電法で試験します。
(前回の2本2Ωとは違い、1本1Ω放電ですので細微な違いはあります)
※ CIPA準拠の試験方法に似たテストとして、ミニ四駆レースでの使用を想定した間欠使用状態での試験をPART-2で行っています。
| ■ 測定結果 |
測定結果のグラフです。
※ データは5秒間隔で記録したものを30秒間隔に変換(6サンプル毎平均化)しています。
※ 電圧分解能が3V/8ビットのため多少カクカクしたグラフとなっています。
※ 放電実験実施2006年7月4日、室温28度C(+−1度C)。
オキシライド電池が突出しているのがわかります。
やはりオキシライド電池はアルカリ電池とは同じカテゴリで比較できない別電池だということがわかりますね。
豆電球やモーター使用機器では通常のアルカリ電池より高い電圧(1.7V)で高性能を発揮しますが、機器の定格(設計)電流より多い過電流、また発熱の増加などで故障の原因となったり機器の寿命を縮める可能性もありますので使用には注意が必要です。
電圧の高い電池は、電源部にパルス式のDC−DCコンバータを使用した機器(デジカメ等)では、高い電圧ゆえに消費電流が少なく済み、より長時間の機器駆動が可能となりますので、このグラフでの持続時間とは異なるより長時間の耐久性能を発揮します。
それ以外の電池に関して、電圧だけを見ればこのグラフを見る限り大きな性能差があるようには見えません。
持続時間はかなりの差があるようです。
グラフが密集していて良くわかりませんので、1.0V以上の部分の拡大グラフにしてみましょう。(以後オキシライド電池・ニカド電池・ニッケル水素電池は省きます)
そのQQアルカリは100均電池対決では健闘するも、有名メーカー電池との対比ではごく普通のアルカリ電池性能といった感じです。(これが104円で買えるところは相変わらず凄いですが)
ダイナミック(maxell)は前半は中くらいの性能を発揮していますが、後半は伸びがありませんでした。
QQアルカリ、STAMINA EX、ダイナミックは、ほぼメーカーの設計意図通りに今回実験に使用した電池の中では大電流用途には向かないものに分類できます。(SONYは???)
(だからと言って小電力に向いているかどうかは別問題なのでまた別の機会に実験を)
この3本をグラフから消してしまいましょう。
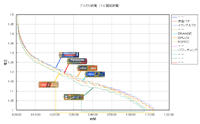 放電特性の似た6本が残りました。
放電特性の似た6本が残りました。
この中ではパワーチャンプ(タミヤ)とRSPEC(富士通)が前半は他との差が大きく開いています。
開封後のフルパワー状態から高い電圧を維持している初期の時間を特に使用したいミニ四駆・ダンガン用電池のパワーチャンプですが、他の残っている電池に比べると電圧が低くその差がマシンのスピード差に大きく現われそうです。(値段相応?、同じ製造元のRSPECと比べてみてもそんなに安くは無いんですけど…しかも電圧で常に負けてるし)
RSPEC(富士通)は同社のGDRシリーズの中では低消費電力向け電池という位置付けですので、GDの二本に比べると後半の延びは良いのですが、電流値の大きな前半の電圧が低くなっています。性格づけが非常によくわかる結果となりました。
続いて上記2本をグラフから消してしまいましょう。
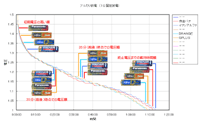 この最後の4本は混戦混戦大混戦!です。
この最後の4本は混戦混戦大混戦!です。
初期点電圧の高さでは赤金パナ(松下)がトップですが、中盤の落ち込みは見逃せません。(また後半延びますが)
「メカが目覚める!」イプシアルファ(maxell)は使用開始直後のパンチが足りないものの、20分時点では盛り返してトップに踊り出ています。パンチが無かったぶんパワーを長いスパンで維持しているようで、終止電圧までの維持時間も4本の中では最も長くなっています。平均的にパワーを分散させつつの持久戦型の使用には良いかもしれません。
富士通DGRシリーズ中のDRANGE(富士通)は、大消費電力用電池を謳っていますが1A放電ではその威力を発揮できずにいるのでしょうか? 全体を通して同社の中電力向け平均型GPLUSと甲乙つけがたいグラフを描いています。
GPLUS(富士通)は20分時点で一度落ち込んでいますが全体としてはDRANGEより高い電圧を出しているなど、このクラスの消費電流ではDRANGEよりはGPLUSのほうが適しているという感じがします。(値段差を考えれば安いほうでよい)
この4本のデータを見る限り、0.01V〜0.02V程度の差しか現われていませんので、家庭用機器での使用ではまず差は感じられないでしょう。
ミニ四駆レースではこの0.01Vの差がモータの回転数の数rpmの差となり、一周20〜100メートルといったコースを周回した時点でのわずか数センチの走行距離差が勝負を分けることもあるので見逃すことができません。(もちろん途中でクラッシュしたりコースアウトしなければ…)
【Part-1 総評】
有名メーカー製アルカリ電池では、電池のランク(用途向け設計)毎に分類すれば、ほぼ各社の製品間に使用中に体感できるほどの性能差は無いと言って良いと思います。
100円ショップアルカリ乾電池性能評価試験では、高価(?)な有名メーカー製電池と、100円くらいで買える電池との性能差を探るという「安い電池でも性能は良いのか?」という疑問に答えましたが、今回の有名メーカー製アルカリ電池の比較では、その性能差はほぼ設定ランク差程度のわずかな差であり、目的別に合った種類の電池を購入すれば良いということであまり面白みの無い結果となりました。
デジカメ用途など目的に合わせて特化されている各社の最もランクの高い電池は、今回の1A放電試験よりもっと大きな電流(しかも継続では無くパルス放電)で使用した際にその性能を他電池より発揮できるように調整されているように思えます。(でないと今回のデータでは1つ下の電池との差が少なすぎる…)
少し前までは単3電池で1A以上の消費電流の機器なんてほとんど無かったものですが、時代の流れと共に電池をとりまく環境も激しく変わって来ているようですね。
※ データは5秒間隔で記録したものを30秒間隔に変換(6サンプル毎平均化)しています。
※ 電圧分解能が3V/8ビットのため多少カクカクしたグラフとなっています。
※ 放電実験実施2006年7月4日、室温28度C(+−1度C)。
▼グラフをクリックすると拡大表示
|
540 円 |
やはりオキシライド電池はアルカリ電池とは同じカテゴリで比較できない別電池だということがわかりますね。
豆電球やモーター使用機器では通常のアルカリ電池より高い電圧(1.7V)で高性能を発揮しますが、機器の定格(設計)電流より多い過電流、また発熱の増加などで故障の原因となったり機器の寿命を縮める可能性もありますので使用には注意が必要です。
電圧の高い電池は、電源部にパルス式のDC−DCコンバータを使用した機器(デジカメ等)では、高い電圧ゆえに消費電流が少なく済み、より長時間の機器駆動が可能となりますので、このグラフでの持続時間とは異なるより長時間の耐久性能を発揮します。
それ以外の電池に関して、電圧だけを見ればこのグラフを見る限り大きな性能差があるようには見えません。
持続時間はかなりの差があるようです。
グラフが密集していて良くわかりませんので、1.0V以上の部分の拡大グラフにしてみましょう。(以後オキシライド電池・ニカド電池・ニッケル水素電池は省きます)
▼グラフをクリックすると拡大表示
STAMINA EX(SONY)は全般的に奮いません。4本104円のQQアルカリにも負けています。そのQQアルカリは100均電池対決では健闘するも、有名メーカー電池との対比ではごく普通のアルカリ電池性能といった感じです。(これが104円で買えるところは相変わらず凄いですが)
ダイナミック(maxell)は前半は中くらいの性能を発揮していますが、後半は伸びがありませんでした。
QQアルカリ、STAMINA EX、ダイナミックは、ほぼメーカーの設計意図通りに今回実験に使用した電池の中では大電流用途には向かないものに分類できます。(SONYは???)
(だからと言って小電力に向いているかどうかは別問題なのでまた別の機会に実験を)
|
370 円 |
360 円 |
104 円 |
▼グラフをクリックすると拡大表示
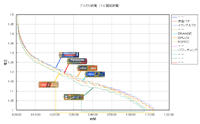 放電特性の似た6本が残りました。
放電特性の似た6本が残りました。この中ではパワーチャンプ(タミヤ)とRSPEC(富士通)が前半は他との差が大きく開いています。
開封後のフルパワー状態から高い電圧を維持している初期の時間を特に使用したいミニ四駆・ダンガン用電池のパワーチャンプですが、他の残っている電池に比べると電圧が低くその差がマシンのスピード差に大きく現われそうです。(値段相応?、同じ製造元のRSPECと比べてみてもそんなに安くは無いんですけど…しかも電圧で常に負けてるし)
RSPEC(富士通)は同社のGDRシリーズの中では低消費電力向け電池という位置付けですので、GDの二本に比べると後半の延びは良いのですが、電流値の大きな前半の電圧が低くなっています。性格づけが非常によくわかる結果となりました。
|
230 円(2本) |
340 円 |
▼グラフをクリックすると拡大表示
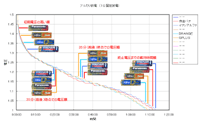 この最後の4本は混戦混戦大混戦!です。
この最後の4本は混戦混戦大混戦!です。初期点電圧の高さでは赤金パナ(松下)がトップですが、中盤の落ち込みは見逃せません。(また後半延びますが)
「メカが目覚める!」イプシアルファ(maxell)は使用開始直後のパンチが足りないものの、20分時点では盛り返してトップに踊り出ています。パンチが無かったぶんパワーを長いスパンで維持しているようで、終止電圧までの維持時間も4本の中では最も長くなっています。平均的にパワーを分散させつつの持久戦型の使用には良いかもしれません。
富士通DGRシリーズ中のDRANGE(富士通)は、大消費電力用電池を謳っていますが1A放電ではその威力を発揮できずにいるのでしょうか? 全体を通して同社の中電力向け平均型GPLUSと甲乙つけがたいグラフを描いています。
GPLUS(富士通)は20分時点で一度落ち込んでいますが全体としてはDRANGEより高い電圧を出しているなど、このクラスの消費電流ではDRANGEよりはGPLUSのほうが適しているという感じがします。(値段差を考えれば安いほうでよい)
この4本は今回の実験では僅差
|
490 円 |
510 円 |
|
530 円 |
460 円 |
この4本のデータを見る限り、0.01V〜0.02V程度の差しか現われていませんので、家庭用機器での使用ではまず差は感じられないでしょう。
ミニ四駆レースではこの0.01Vの差がモータの回転数の数rpmの差となり、一周20〜100メートルといったコースを周回した時点でのわずか数センチの走行距離差が勝負を分けることもあるので見逃すことができません。(もちろん途中でクラッシュしたりコースアウトしなければ…)
【Part-1 総評】
有名メーカー製アルカリ電池では、電池のランク(用途向け設計)毎に分類すれば、ほぼ各社の製品間に使用中に体感できるほどの性能差は無いと言って良いと思います。
100円ショップアルカリ乾電池性能評価試験では、高価(?)な有名メーカー製電池と、100円くらいで買える電池との性能差を探るという「安い電池でも性能は良いのか?」という疑問に答えましたが、今回の有名メーカー製アルカリ電池の比較では、その性能差はほぼ設定ランク差程度のわずかな差であり、目的別に合った種類の電池を購入すれば良いということであまり面白みの無い結果となりました。
デジカメ用途など目的に合わせて特化されている各社の最もランクの高い電池は、今回の1A放電試験よりもっと大きな電流(しかも継続では無くパルス放電)で使用した際にその性能を他電池より発揮できるように調整されているように思えます。(でないと今回のデータでは1つ下の電池との差が少なすぎる…)
少し前までは単3電池で1A以上の消費電流の機器なんてほとんど無かったものですが、時代の流れと共に電池をとりまく環境も激しく変わって来ているようですね。
| ★ 実験PART−2 ★ ミニ四駆レース向け比較 ★ |
Part-1 大電流連続放電試験に続き、part-2ではミニ四駆レース向け比較と銘打って試験を行いたいと思います。
Part-1 大電流連続放電試験では、1A程度(以上)の電流を流し続けるいわば「耐久試験」でした。
ミニ四駆レースではそのものズバリ「耐久レース」型の使用をした際での性能を評価したものと言えます。
しかし通常の公式レース、また街角レースでは「耐久レース」が行われるのは稀で、ほとんどが「タイムアタック」または「勝ち抜き戦」形式でコース周回スピードを競うものです。
どちらの場合も実際に走行するのはスタートからゴールまでわずか数十秒、早いものではわずか10秒程度で勝負が決まってしまいます。
そういった短期決戦タイプの電池使用では使う電池によって差が出るのか? そして差がある場合はどの電池が優位なのかを本実験では検証してみたいと思います。
Part-1 大電流連続放電試験では、1A程度(以上)の電流を流し続けるいわば「耐久試験」でした。
ミニ四駆レースではそのものズバリ「耐久レース」型の使用をした際での性能を評価したものと言えます。
しかし通常の公式レース、また街角レースでは「耐久レース」が行われるのは稀で、ほとんどが「タイムアタック」または「勝ち抜き戦」形式でコース周回スピードを競うものです。
どちらの場合も実際に走行するのはスタートからゴールまでわずか数十秒、早いものではわずか10秒程度で勝負が決まってしまいます。
そういった短期決戦タイプの電池使用では使う電池によって差が出るのか? そして差がある場合はどの電池が優位なのかを本実験では検証してみたいと思います。
| ■ 実験対象 |
Part-1 大電流連続放電試験のものと同じです。
但しオキシライド電池は公式に使用禁止の為テスト対象から外しています。
但しオキシライド電池は公式に使用禁止の為テスト対象から外しています。
| ■ 実験方法 |
 実験に使用する測定機器はPart-1 大電流連続放電試験で使用したものと同じです。
実験に使用する測定機器はPart-1 大電流連続放電試験で使用したものと同じです。Part-1実験と同じ1Ω固定抵抗による放電を行います。
Part-1実験と違うのは、本実験はミニ四駆レースを想定した「間欠放電」を行い、間欠放電による「アルカリ電池の回復力」がどのようなものか、またそれは「レースに影響するのか?」、「回復力に電池による差があるのか?」などを調べます。
ミニ四駆レースでは、「タイムアタック」または「勝ち抜き戦」や「総当たり戦」でマシンをコースを周回走行させます。一周20〜100メートル程度のコースをマシンが走行するのはわずか数秒〜30秒程度です。
そして一度走ったら、「トーナメント形式で敗退」しない限りは次に自分の順番が回って来るまでは時間待ち(休憩やセッティングの見直し)となります。
次に順番が回って来るまでの時間はレースによって様々で、2〜3分後に走らせる事もあれば、30分以上待たされる事もあります。
レースによっては電池交換ができる場合もありますが、今回は「電池交換禁止」レースで同じ電池を毎回使うものとしてテストを行います。
本試験では一回の走行サイクル(走行+待ち時間)を10分とし、「走行時、モーターONの時間は30秒」「待ち時間は9分30秒」の条件で試験を行います。
| 1サイクル10分 | 放電期間 | 30秒間 | 固定負荷放電 (モーター回転と同等) |
|---|---|---|---|
| 休止期間 | 9分30秒間 | 無負荷で回復 (休憩インターバル) |
12回繰り返した後に、2時間後の状態を確認する為に13回目の放電試験を行い、更にその後59分30秒の休止を取った後に「1時間休止での回復状態試験」を行います。
|
この試験方法では連続的に電流を流す実験とは異なり、デジカメを想定したCIPA規格準拠の放電方法(撮影と休憩を一定間隔で繰り返す)に似た使用条件となり、細かい部分では異なりますが「デジカメ用大容量、パルス放電に強い」などを謳う最新型電池がその性能を発揮してくれるのではないかという期待ができます。
CIPA規格の試験では電池の休憩時間(回復させる時間)は1時間ですので、今回の試験の最後の1回は1時間休止をさせて10分休止の場合との差も見てみましょう。
| ■ 測定結果 |
測定結果のグラフです。
これは2時間まで13回放電の試験結果です。
※ 電圧分解能が3V/8ビットのため多少カクカクしたグラフとなっています。
※ 放電実験実施2006年7月8日、室温28度C(+−1度C)。
やはりラインが密集して見づらいので、拡大グラフを作ってみましょう。
アルカリ電池の開放電圧が休止期間中に徐々に回復している様子がよくわかります。
それに対して、ニカド電池・ニッケル水素電池はほとんど回復曲線は描かずに放電停止時の開放電圧を保っているようです。
この事から、アルカリ電池は休ませればある程度回復するので間欠使用に向いている。ニカド・ニッケル水素充電池は休ませなくても連続使用出来る能力がある。という電池の性質が伺えます。
各電池共に未使用で能力いっぱいの状態(充電池はフル充電)の状態ですので、アルカリ電池は1.5V以上で電圧が高く、ニカド電池は1.4V程度からスタートという各電池の公称電圧の差がそのまま現われています。
これは2時間まで13回放電の試験結果です。
※ 電圧分解能が3V/8ビットのため多少カクカクしたグラフとなっています。
※ 放電実験実施2006年7月8日、室温28度C(+−1度C)。
▼グラフをクリックすると拡大表示
やはりラインが密集して見づらいので、拡大グラフを作ってみましょう。
▼グラフをクリックすると拡大表示
アルカリ電池の開放電圧が休止期間中に徐々に回復している様子がよくわかります。
それに対して、ニカド電池・ニッケル水素電池はほとんど回復曲線は描かずに放電停止時の開放電圧を保っているようです。
この事から、アルカリ電池は休ませればある程度回復するので間欠使用に向いている。ニカド・ニッケル水素充電池は休ませなくても連続使用出来る能力がある。という電池の性質が伺えます。
各電池共に未使用で能力いっぱいの状態(充電池はフル充電)の状態ですので、アルカリ電池は1.5V以上で電圧が高く、ニカド電池は1.4V程度からスタートという各電池の公称電圧の差がそのまま現われています。
| ■ 開放電圧(の回復力)で見る各電池比較 |
3回目までは赤金パナ(松下)の回復力がトップで、4回目で意外とRSPEC(富士通)が目立ちはじめ、後半になるとDRANGE(富士通)がすぐ後を追います。
ここから中くらいの位置にある数本はほぼ同程度で、それより下のランクの3本との間に大きな溝が開いています。
イプシアルファ(maxell)の回復状況が最低です。高負荷タイプなので放電後の回復力も高いと思ったのですが…。
続いてパワーチャンプ(タミヤ)、QQアルカリの2本が回復が遅いですね。
しかしちょっと待ってください。
STAMINA EX(SONY)のグラフをよく見てください。
開放時電圧の回復電圧を見る限り赤金パナ等と同じ電圧まで回復していますが、放電時の最低電圧を見ると全ての電池の中で最も低い電圧となっています。
これは「内部抵抗が高い電池」に見られる傾向で、何も負荷を繋いでいない状態では電池の起電力(アルカリなら1.5V)に近い電圧を示しますが、いざ使用して電流を流すと電池の内部抵抗が大きいとそこで電圧が下がり、電池外部で取り出せるエネルギーが少なくなってしまいます。
「大電流対応」を謳う電池は内部抵抗面での改良がされていて、大電流を流してもそれに比例して大きくなる内部抵抗でのエネルギーロスを少なくしています。
また、電池の内部抵抗は本当に電池の中に抵抗が一個入っているのではなく、電池の中の化学物質の性質で起きる抵抗効果で、電池が新しい時は内部抵抗が少なく、古くなってくる(使用して内部の化学反応が弱くなる)と見かけ上の内部抵抗が上がりこれが電流を流れ難くする性質があります。
弱った電池や、基本性能上内部抵抗が高い電池は、テスター等で無負荷状態で電圧を測ると無負荷で微小な電流しか流さないので内部抵抗の影響を受けずに1.5Vくらいの高い電圧を示しますが、「いざ機器に入れて使用を始めたらあっというまに電池が切れてしまった」なんて事になるのですね。
ということで、開放電圧の回復能力の比較はこれくらいにして、実際にレースに関係する放電時電圧を比較してみましょう。
ここから中くらいの位置にある数本はほぼ同程度で、それより下のランクの3本との間に大きな溝が開いています。
イプシアルファ(maxell)の回復状況が最低です。高負荷タイプなので放電後の回復力も高いと思ったのですが…。
続いてパワーチャンプ(タミヤ)、QQアルカリの2本が回復が遅いですね。
しかしちょっと待ってください。
STAMINA EX(SONY)のグラフをよく見てください。
開放時電圧の回復電圧を見る限り赤金パナ等と同じ電圧まで回復していますが、放電時の最低電圧を見ると全ての電池の中で最も低い電圧となっています。
これは「内部抵抗が高い電池」に見られる傾向で、何も負荷を繋いでいない状態では電池の起電力(アルカリなら1.5V)に近い電圧を示しますが、いざ使用して電流を流すと電池の内部抵抗が大きいとそこで電圧が下がり、電池外部で取り出せるエネルギーが少なくなってしまいます。
「大電流対応」を謳う電池は内部抵抗面での改良がされていて、大電流を流してもそれに比例して大きくなる内部抵抗でのエネルギーロスを少なくしています。
また、電池の内部抵抗は本当に電池の中に抵抗が一個入っているのではなく、電池の中の化学物質の性質で起きる抵抗効果で、電池が新しい時は内部抵抗が少なく、古くなってくる(使用して内部の化学反応が弱くなる)と見かけ上の内部抵抗が上がりこれが電流を流れ難くする性質があります。
弱った電池や、基本性能上内部抵抗が高い電池は、テスター等で無負荷状態で電圧を測ると無負荷で微小な電流しか流さないので内部抵抗の影響を受けずに1.5Vくらいの高い電圧を示しますが、「いざ機器に入れて使用を始めたらあっというまに電池が切れてしまった」なんて事になるのですね。
ということで、開放電圧の回復能力の比較はこれくらいにして、実際にレースに関係する放電時電圧を比較してみましょう。
| ■ 放電電圧(負荷接続時)で見る各電池比較 |
上のグラフでは放電30秒に対して開放9分30秒と圧倒的に開放時間のほうが長くて、放電時の詳しい状況がわかりません。
そこで開放時のグラフは消去して、電時の状況のみをグラフ化してみました。(eneloopは削除)
放電中の様子でも、ニカド電池の電圧が低いことと、STAMINA EXが連続放電時と同じく奮わない事が見て取れます。
グラフのいちばん右を見てください。
1時間休止の後の回復状況が、明らかに10分休止のものより少し大きく回復している様子がわかりますね。
全体としては10分程度の休止ではそれほど大きな回復力は発揮されないような感じもしますので、また別の機会にCIPA規格に準拠した試験を行いたいと思います。
このグラフでは各サイクルの最初に放電開始時の電圧(開放電圧)があり、そこが大きな山になっていて比較し辛いので更にその部分を削除し、放電中の電圧のみをグラフに残します。
この時点でニカド1000(タミヤ)とSTAMINA EXは省きます。
同一メーカーで複数の電池がある場合の各電池の性格の比較もできるようグループ分けをしました。
● 予選
● 決勝戦
予選を突破した4本の電池のグラフです。
決勝戦はグラフ上での差が見やすいよう、各メーカーの中での高性能な電池のみの対比を行いました。
決勝進出していない電池もデータでは決勝進出電池とほぼ同じ性能の物がありますので、各電池の性質などは次の寸評を参考にしてください。
連続放電ではGPLUSのほうが安定して高出力をマークしていましたが、短期放電と休止を組み合わせた「デジカメ用途に似た大電力使用」ではDRANGEが本領を発揮したと言える結果となりました。
決勝戦グラフでは、ランクBのラインは4〜6回目の放電やその他でも全くグラフが重なる部分が見受けられるなど、力関係が均衡しているように見えます。
これらの電池はグラフの各所で約0.01Vの差しか無いので、この程度の差には測定誤差も含まれますので、今回の条件のレースを想定した間欠放電ではランクBの4本はどの電池にも性能差はほとんど無いと言ってもいいでしょう。
【Part-2 総評】
Part-1の大電流連続放電試験の結果とかなり違う結果になった電池もあり、たいへん興味深い測定データが取れました。
「30秒間だけの瞬発力」が各電池からどれくらい引き出せるのか、また各電池が連続使用と間欠使用でどのような性格を現すのかを調べ、「どの電池が良い/悪い」は使用用途によって変わることがこの実験でもよくわかりましたね。
そこで開放時のグラフは消去して、電時の状況のみをグラフ化してみました。(eneloopは削除)
▼グラフをクリックすると拡大表示
放電中の様子でも、ニカド電池の電圧が低いことと、STAMINA EXが連続放電時と同じく奮わない事が見て取れます。
グラフのいちばん右を見てください。
1時間休止の後の回復状況が、明らかに10分休止のものより少し大きく回復している様子がわかりますね。
全体としては10分程度の休止ではそれほど大きな回復力は発揮されないような感じもしますので、また別の機会にCIPA規格に準拠した試験を行いたいと思います。
このグラフでは各サイクルの最初に放電開始時の電圧(開放電圧)があり、そこが大きな山になっていて比較し辛いので更にその部分を削除し、放電中の電圧のみをグラフに残します。
この時点でニカド1000(タミヤ)とSTAMINA EXは省きます。
▼グラフをクリックすると拡大表示
グラフが重なっている部分が多いので、少し分けて比べてみましょう。同一メーカーで複数の電池がある場合の各電池の性格の比較もできるようグループ分けをしました。
● 予選
| ● 予選Aグループ | ● 予選Bグループ | |
|
▼グラフをクリックすると拡大表示
DRANGE(富士通)とGPLUS(富士通)が安定した強さを見せています。連続放電実験ではあまりその性能を発揮できなかったDRANGEですが、やはり短時間使用と休憩を繰り返す間欠使用ではその能力を発揮しています。 RSPEC(富士通)はDGRシリーズの中では最も低い電圧値となり、そのまま各電池の位置付けが順位に現われているようです。 赤金パナ(松下)は連続放電時の初頭時期電圧では高い値を示していましたが、ここでは少し奮いません。個体差なのかもしれませんが初戦あたりの低さは気になり、後半に向けて安定しています。 富士通からはDRANGE、松下からは赤金パナを決勝戦に駒を進めます。 |
▼グラフをクリックすると拡大表示
こちらのグループの中ではパワーチャンプが安定した強さを見せています。連続放電ではそれほど強くはありませんでしたが、間欠使用ではこの4本中ではトップクラスです。まさにこういうレース用途に開発された電池!?イプシアルファ(maxell)がやはりあまり芳しくありません。同社のダイナミック(maxell)のほうが前半戦では高性能を発揮しています。(やはりイプシはいまいち…?) このグループは比較的差が少ないようで、QQアルカリもそれなりに高い能力を発揮していますが、後半徐々にパワーが落ちてきています。 日立からはダイナミック、そしてタミヤのパワーチャンプが決勝戦進出です。 |
● 決勝戦
予選を突破した4本の電池のグラフです。
▼グラフをクリックすると拡大表示
決勝戦はグラフ上での差が見やすいよう、各メーカーの中での高性能な電池のみの対比を行いました。
決勝進出していない電池もデータでは決勝進出電池とほぼ同じ性能の物がありますので、各電池の性質などは次の寸評を参考にしてください。
| ||||||
| ||||||||||
これらの電池はグラフの各所で約0.01Vの差しか無いので、この程度の差には測定誤差も含まれますので、今回の条件のレースを想定した間欠放電ではランクBの4本はどの電池にも性能差はほとんど無いと言ってもいいでしょう。
| ||||||||
【Part-2 総評】
Part-1の大電流連続放電試験の結果とかなり違う結果になった電池もあり、たいへん興味深い測定データが取れました。
「30秒間だけの瞬発力」が各電池からどれくらい引き出せるのか、また各電池が連続使用と間欠使用でどのような性格を現すのかを調べ、「どの電池が良い/悪い」は使用用途によって変わることがこの実験でもよくわかりましたね。
| ■ 連続使用と間欠使用の違い |
間欠使用のグラフを見てもわかると思いますが、アルカリ電池は休ませれば少しだけ体力を回復します。
具体的にどれくらいの差があるのかを比較グラフにして確認してみましょう。
実験Part-2の間欠放電グラフがPart-1の連続放電グラフより上のほうにあり、同じ電力消費時間であっても休憩を入れて回復させたほうがパワーが長持ちする様子がはっきりとわかりますね。
アルカリ乾電池などを普通の家庭で使用する場合、一度に放電しきってしまうような使い方では無く、「少し使っては機器の電源を切ってまたこんど使う」ような使い方のほうが多いと思います。
そういう断続的な使用では、アルカリ電池(マンガン電池)の回復特性はおおいに効果があるということですね。
具体的にどれくらいの差があるのかを比較グラフにして確認してみましょう。
▼グラフをクリックすると拡大表示
実験Part-2の間欠放電グラフがPart-1の連続放電グラフより上のほうにあり、同じ電力消費時間であっても休憩を入れて回復させたほうがパワーが長持ちする様子がはっきりとわかりますね。
アルカリ乾電池などを普通の家庭で使用する場合、一度に放電しきってしまうような使い方では無く、「少し使っては機器の電源を切ってまたこんど使う」ような使い方のほうが多いと思います。
そういう断続的な使用では、アルカリ電池(マンガン電池)の回復特性はおおいに効果があるということですね。
|
** ご注意 **
本レポートは今回購入した電池に関して行った結果であり、電池の個体差・製造時期・製造ロット・保管状況・経過日数・放電実験方法などにより性能及び計測結果が異なることがあり、市販されている全ての同一名電池、また全ての使用状況により全く同じ結果・性能差が現われることが無い可能性があることをご理解ご了承ください。 また今回の試験結果ではその性能差は非常に小さな電圧差であり、実用上の差異は感じられない可能性があります。 実際のミニ四駆での使用に際しては、使用するモーター・ギヤ・タイヤ径、ほか各レーサーのセッティングの違い、またコースレイアウトによりモーターにかかる負荷が異なるため電流値がそれぞれ異なります。走行中も変動します。 本試験では実際に測定したマシン走行時の平均的なモーター負荷に沿って約1A強での放電試験で擬似的に走行状態に似た放電特性を測定したもので、実際のモーター接続時とは多少異なるものであることをご了承ください。 |
| ■ 気になる電池の消費期限 (期限切れ電池は・・・) |
イプシアルファは今回試験した電池群の中で唯一消費期限が2年(*)の少し古い規格の製品です。(他は全て5年)
実は今回の実験用に探して最初に知人と一緒に購入したイプシアルファは2006年8月が消費期限で、あと一ヶ月で期限が来ます。(ソ●マップの電池売り場に1個だけ残っていた奴。見た目そっくりなオキシライド電池の棚に間違って置かれていた、単なる不良在庫っぽい…)
これでは気持ち良く比較実験ができないので、別途新しいイプシアルファを探しにいくつかの量販店を回り、ヨドバシ梅田店のデジカメ売り場に大量にあるのを見つけて品定めをして最も新しいものを買ってきました。(他にヤマダ電器labi1なんばなんて腐るほど山積み状態で売っています。本当に多すぎて売れ残って期限切れで腐りそうなくらい…)
各社の電池は5年対応に合わせてパッケージに大きく「消費期限5年」と表示していたり、パッケージに期限を印刷するか、電池に印字されている消費期限が見えるようにパッケージに穴を空けるなどの工夫がされています。
期限が切れる直前のイプシアルファはそういう期限を確認できないパッケージで、買っても封を切って電池を取り出してみないことには消費期限が分らない旧デザイン品でした。
買ってから消費期限切れスレスレ品であることに気付き、メーカーHPに行って新デザインの物に変わっているという事を知ったわけで、かなり痛手を食らいました。
同じ電池をまた買わなければならないという高い(?)勉強代を支払ったおかげで、次にオキシライド電池を買う時にはちょっと賢くなっていました。
近所のホームセンターコー●ンでオキシライド電池を買おうとした時に、電池販売コーナーでオキシライド電池を手にとってレジに並びました。
そしてふとレジ横の棚にあるオキシライド電池を見ると、電池コーナーで表示されていた価格と全然違う値段が表示されていたのです。
パッと見た目は電池のデザインに変わりはなく、青を基調としたパッケージもほとんど同じに見えます。
不審に思いレジでPOSに通してもらって値段を確認すると、やっぱり値段が違います。
これはおかしい!
店員に確認してもらい、レジ横のオキシライド電池を電池売り場まで持っていってよく見比べてみたところ、ビミョーにパッケージのデザインが違うことが判明。
並べて見比べてみてはじめて気付くくらいの相違で、レジ横に置いていたほうが新デザイン(少し高い)。電池売り場で山積のほうは旧デザイン(少し安い)の古い在庫品の山だったのです。パッケージ裏に印刷されている形式番号も確かに末尾のアルファベットが違う…
危うく古いほうの電池を買うところでした。
並べて置いていたら新・旧の違いに気付きますが、わざと売り場別に分けて置いているあたりにかなり作為的なものを感じます。
まだ赤になっていない金パナも大量に売っている店ですから、一時に大量に仕入れて仕入れ原価を安くし、日々の販売数はそれほど多くなくて在庫を抱えていそうなホームセンター等で電池を買う時にはかなり注意が必要ですね。
でも、5年対応でパッケージの外からも消費期限が見れるようになってからの電池なら買う前に消費期限を確認することができるので、100均電池比較の結論で書いた通り「電池は生物(なまもの)」だと思ってしっかりと期限を確認して買うようにしましょう。
雑談が長くなってしまいましたが、せっかく「期限切れスレスレ」なんていう面白い電池が手に入ったわけですので、これはこれで実験に活用してみない手はありません(笑)
急遽『期限切れ電池と出来たてホヤホヤ電池に激しい差はあるのか!? 同一メーカー同一電池比較実験』を追加してみました。
(デザインが変わってるので厳密には同一電池とは言い難いですが…)
しかしこれはどうでしょう?
明らかに弱っています。・・・いや、弱すぎ!
まさかここまで露骨に差が開くとは思ってもみませんでした。
出来たてホヤホヤの電池と、消費期限切れに近い電池ではこれほどの差が出ることがわかれば、やっぱり「電池は生物(なまもの)」。
購入する時は消費期限に気をつけて購入しましょう。
(*) イプシアルファに明確な消費期限2年表示はありませんが、
量販店の最新入荷品が約2年先期限ですので2年と判断します
消費期限が切れた瞬間に使えなくなるのでは無く、消費期限内であればJIS規格で規定した性能を保持しているというものですが、やはり出来たてホヤホヤの電池と消費期限が切れる直前の電池では性能に差が現われると予想されます。量販店の最新入荷品が約2年先期限ですので2年と判断します
実は今回の実験用に探して最初に知人と一緒に購入したイプシアルファは2006年8月が消費期限で、あと一ヶ月で期限が来ます。(ソ●マップの電池売り場に1個だけ残っていた奴。見た目そっくりなオキシライド電池の棚に間違って置かれていた、単なる不良在庫っぽい…)
これでは気持ち良く比較実験ができないので、別途新しいイプシアルファを探しにいくつかの量販店を回り、ヨドバシ梅田店のデジカメ売り場に大量にあるのを見つけて品定めをして最も新しいものを買ってきました。(他にヤマダ電器labi1なんばなんて腐るほど山積み状態で売っています。本当に多すぎて売れ残って期限切れで腐りそうなくらい…)
各社の電池は5年対応に合わせてパッケージに大きく「消費期限5年」と表示していたり、パッケージに期限を印刷するか、電池に印字されている消費期限が見えるようにパッケージに穴を空けるなどの工夫がされています。
期限が切れる直前のイプシアルファはそういう期限を確認できないパッケージで、買っても封を切って電池を取り出してみないことには消費期限が分らない旧デザイン品でした。
買ってから消費期限切れスレスレ品であることに気付き、メーカーHPに行って新デザインの物に変わっているという事を知ったわけで、かなり痛手を食らいました。
同じ電池をまた買わなければならないという高い(?)勉強代を支払ったおかげで、次にオキシライド電池を買う時にはちょっと賢くなっていました。
近所のホームセンターコー●ンでオキシライド電池を買おうとした時に、電池販売コーナーでオキシライド電池を手にとってレジに並びました。
そしてふとレジ横の棚にあるオキシライド電池を見ると、電池コーナーで表示されていた価格と全然違う値段が表示されていたのです。
パッと見た目は電池のデザインに変わりはなく、青を基調としたパッケージもほとんど同じに見えます。
不審に思いレジでPOSに通してもらって値段を確認すると、やっぱり値段が違います。
これはおかしい!
店員に確認してもらい、レジ横のオキシライド電池を電池売り場まで持っていってよく見比べてみたところ、ビミョーにパッケージのデザインが違うことが判明。
並べて見比べてみてはじめて気付くくらいの相違で、レジ横に置いていたほうが新デザイン(少し高い)。電池売り場で山積のほうは旧デザイン(少し安い)の古い在庫品の山だったのです。パッケージ裏に印刷されている形式番号も確かに末尾のアルファベットが違う…
危うく古いほうの電池を買うところでした。
並べて置いていたら新・旧の違いに気付きますが、わざと売り場別に分けて置いているあたりにかなり作為的なものを感じます。
まだ赤になっていない金パナも大量に売っている店ですから、一時に大量に仕入れて仕入れ原価を安くし、日々の販売数はそれほど多くなくて在庫を抱えていそうなホームセンター等で電池を買う時にはかなり注意が必要ですね。
でも、5年対応でパッケージの外からも消費期限が見れるようになってからの電池なら買う前に消費期限を確認することができるので、100均電池比較の結論で書いた通り「電池は生物(なまもの)」だと思ってしっかりと期限を確認して買うようにしましょう。
雑談が長くなってしまいましたが、せっかく「期限切れスレスレ」なんていう面白い電池が手に入ったわけですので、これはこれで実験に活用してみない手はありません(笑)
急遽『期限切れ電池と出来たてホヤホヤ電池に激しい差はあるのか!? 同一メーカー同一電池比較実験』を追加してみました。
(デザインが変わってるので厳密には同一電池とは言い難いですが…)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
▼グラフをクリックすると拡大表示
ここ2年以内のデザイン変更時に多少の性能アップも図られていると考えても、せいぜい+20%くらいの性能アップで、今までの実験結果を見てもわかるように1A放電実験ではメーカー(他社)の言う+20%の差というものはそれほど大きな差としてはグラフには現われませんでした。しかしこれはどうでしょう?
明らかに弱っています。・・・いや、弱すぎ!
まさかここまで露骨に差が開くとは思ってもみませんでした。
出来たてホヤホヤの電池と、消費期限切れに近い電池ではこれほどの差が出ることがわかれば、やっぱり「電池は生物(なまもの)」。
購入する時は消費期限に気をつけて購入しましょう。
記事掲載: 2006年7月6日
変更更新: 2006年10月12日
| |||||||
|
【投稿受付終了】 本ページ(この記事専用)の『迷い箱』(投稿コーナー)の受付は終了しました。 現在は過去の投稿の閲覧のみ可能です。 |
| 非公開の 皆様へ |
非公開で投書をくださいました皆様、全てのメッセージに目を通しています。 頂きましたご意見は今後の参考にさせて頂いています。 非公開ですので個別にお返事は掲載致しませんが、貴重な投書ありがとうございました。 |
|
|
乾電池に刻まれている数字は、消費期限ではなく、使用開始期限だと思います。 954 様
|
||
| お返事 |
たいへん申し訳ございませんが、本ページでは「100円ショップアルカリ電池」で囲み記事で書きましたものより表記を「消費期限」と統一しています。 「食品(牛乳)の選択方法と同じ」と解説した文章と統一性を持たせる為でもあります。 食品の「消費期限」と同じく、期限を切れた瞬間に食べられなくなるのではなく、その日までは品質が保持されるという意味では「電池のJIS性能保持期間」の表示と同じ意味です。 その日までは規格以内を保ち、過ぎると一瞬で劣化するのではなく保証未満になるという意味では間違っていません。 尚、メーカー各社の記載では「使用開始期限」ではなく「使用推奨期限」という新用語を作って統一されています。 「使用推奨期限」では「開始」ではなくこの日までに使って(使い切って)ください。という意味が強いのも消費期限と同じような意味合いにあたります。 「使用開始期限」とすると、期限日までに使用を開始すれば、その日から先の使用中には期限を大きく(何年も)過ぎてもJISで示された性能を保持できると誤解されることにもつながりかねませんね。 お返事 2007/3/2
|
|
|
「気の迷い」の更新をとても楽しみにしています。 このホームページに触発されて電子回路の基礎に再チャレンジしている昨今ですが前途多難です。 さて勝手なお願いなのですが、大ヒットページ「100円ショップアルカリ乾電池性能評価試験」の姉妹編で「100円ショップマンガン乾電池性能評価試験」をリクエストします。 私は以前どんな機器にも「金パナ」入れて満足していたのですが「気の迷い」とエネループ導入以後、電池の適材適所に少しだけ目覚め、8本100円のダイソーマンガン乾電池を購入することが多くなりました。そのためマンガン乾電池についてもイロイロ、他力本願で、知りたいなぁーってお願いするしだいです。(^^; 鈴木 様
|
||
| お返事 |
色々と楽しみにして頂いてありがとうございます。 マンカン電池の性能試験となると、マンガン本来の使用方法に近い超微弱電流で半年〜1年テストするとか、そういう非常に気の長いものになってしまいますが・・・ テスト結果を発表する頃には、既にその電池は売られていない可能性があるとか別製品に置き換わってしまっているとか、マンガンに関しては色々と難しい面があります。 マンガン電池が適している時計等(100均で買えるような物)を電池の種類ぶん並べて1年様子を見ながら一ヶ月おきに経過を発表するとか、一緒にアルカリ電池を入れてみて電池メーカーの言う「マンガンの代わりにアルカリで良い」というのがどこまで本当なのかを確かめるという手もありますね。 ただマンガン電池比較をするのに大きな問題なのは「微弱な消費電流が本当に各電池に対して同じなのか」ということを果たして計測できたり長期間維持できるのか、ですね。 比較的大きな電流なら調整して誤差1%以内(現在使用中の放電器の場合±0.5%)にできますが、数マイクロアンペア以下のクォーツ時計なんてまず統一した条件は確認できません。 最初から個体差は無視して「どの時計(使用機器)も消費電流は同じ」とみなしてしまうか(相手が中国製の安物だけに不安が…)、1年おきに電池と時計をローテーションして同じテストを何度も繰り返し、10年くらいかけて平均値を出して正しい結果を得る超長期試験をするか・・・ 辛うじてマンガン電池の使用目的に合っている数十ミリアンペア程度を消費するラジオ等(しかし既にアルカリ電池を推奨されている)と同等の使用条件でのランタイム試験くらいなら個人でも可能ですが、本当にマンガン電池が適している(と言われている)クォーツ時計やTVのリモコンでの使用を想定した比較試験は難しいですね。 お返事 2007/2/3
|
|
| 投稿 |
ご返事を繰り返し読みながら、やっぱ他力本願はだめかー!ってちょびっと反省しました。さしあたり今度100円ショップいったら2種類のマンガン電池を買ってみます。 鈴木 様
|
|
| お返事 |
あまりお力になれずに申し訳ございません。 マンガン電池でも消費期限の遠い(新しい)物のほうが良いのは違い有りませんので、なるべく回転の良いお店で電池を買われる事をお勧めします。 お返事 2007/2/7
|
|
|
条件を統一して比較検討されていてとても参考になりました。私も「どこの製品にしようか」、“電池は生もの”と日ごろ気にしていたことでしたがこの研究報告で迷いがとれました。感謝です。 ところで、単1乾電池や単3乾電池でもいろいろな種類が製造されていますね。例えば、単1乾電池でも「オキシライド」「アルカリ」「マンガン」などとありますが、使う機材(懐中電灯や時計、ラジカセなどの生活用品)によって、あるいは、用途によってなどの使い分けができると賢いといわれています。迷います。コストに合った効率のいい選び方・使い方を教えていただくとうれしいです・・・。 悩める主夫 様
|
||
| お返事 |
乾電池の「性能」は電池の種類ではマンガン→アルカリ→オキシライド/ニッケル乾電池の順に高くなってゆきます。 「性能」と共に「おねだん」も高くなってゆきます。 しかし何に使うのでも「高性能=高価格」な電池を入れれば良いというわけではありません。 オキシライド電池のように「大電流に強い」ように改良された電池は、確かにデジカメのように一瞬に大きな電流を必要とする機器ではパワーを発揮しますが、逆に微弱電流の機器では大電流特性は活かせずに普通のアルカリ電池以下の性能でしか使えない場合もあります。 クォーツ時計のように本当に微弱な電流しか必要とせず、どちらかと言うと長い間電池自体が衰えずに生き続けるマンガン電池が適した機器もありますね。 クォーツ時計やTVのリモコンのように少ない電気で長期間使用する機器には単価も安くて長寿命なマンガン電池。(だいたい半年〜1年で交換が目安です) ハイパワーを必要とするライトやラジカセ、モーターを回す機器にはパワー重視のアルカリ電池。(連続使用して数時間〜数日で電池を交換するもの) デジカメのように特にパルス特性に優れた電池が有効な機器には「デジカメ用」を謳った高性能電池を使えば、最も電池の性質と価格のバランスの取れた使用方法になります。 但し、電池メーカーの説明によると従来のマンガン電池が対応していた微弱機器での使用でも、アルカリ電池を推奨するように状況が変わってきています。 昔はアルカリ電池はハイパワーでも長期使用には適さなかったのですが、改良により現在の製品はマンガン電池と置き換えても支障が無いくらい超寿命になっているようです。またアルカリ電池の欠点であった長期放置時に液漏れを起こしてしまう症状も改善されています。 本ページの実験のように、単3電池を数時間程度で消費してしまうような用途では有名メーカー電池も100円ショップ電池もあまり性能に差はありませんので、消耗品としてとらえるなら単価の安い電池を使用したほうが経済的ですね。 毎日使って、数日で電池を交換しなければならない機器を使用されるのでしたら、使い捨ての乾電池を使用するより充電式のニッケル水素電池を使用したほうが、トータルコストでは安くなります。 ほぼ単3アルカリ電池と同じくらいの使用感で使える三洋「エネループ」や松下「HHR−3MPS(緑パナ)」が発売されて以来、単3電池や単2電池(アダプターを被せる)を使用する機器にはこれらの扱いやすい充電池を使用する人が増えています。 充電池2本と充電器がセットになって2千円弱という手軽な価格から販売されていますので、20〜50回ほど使えばアルカリ乾電池を買い換えるより経済的です。 あまり電池を買い替えない普通の家庭では、わざわざ高い充電池にするよりも手軽に手に入るマンガン/アルカリ乾電池を必要な時に必要な本数だけ購入するほうが賢い(なにしろ生物ですから)使い方だと思います。 お返事 2007/1/24
|
|
|
ここまでやっていただけるとは・・・いつも他人の電池を見ながらモヤモヤしていた気持ちがスッキリしました。 電池自由という子供のレースでオキシを選んだら優勝してしまったことがあるのですが、こんなに違うんですね。 コストパフォーマンスを考えながら選んで行きたいと思います。 しかし、富士通の電池ってスーパーなんかで見かけないのですが、電器量販店でしょうか? HHIRO 様
|
||
| お返事 |
電池自由のレース・・・面白そうですね。 レースでは電池とマシンセッティングの組み合わせで絶妙の走りができたり、パワーのある電池より少しパワーの弱い電池のほうが安定して走ったりと実に奥が深い所が楽しいです。 富士通の電池(GDRシリーズ)は扱っている店が少ないですが、電池コーナーの棚が広いホームセンターや電気店、ヨドバシやヤマダのような取り扱いメーカー数の多い大規模店で売っています。 スーパーやコンビニではGDRシリーズではなく廉価版の旧「富士通G」しか置いていないこともありますので、少し大きなお店を探してみてください。 お返事 2006/12/13
|
|
(C)2006 Kansai-Event.com
本記事の無断転載・転用などはご遠慮下さい