| ||||||||||
|
|
| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |
�d�r�E�o�b�e���[�E�[�d��
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���̃y�[�W�́u2009�N�̉ߋ����O�v�Z�N�V�����ł�
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���̃y�[�W�́u2009�N�̉ߋ����O�v�Z�N�V�����ł�
|
�y�ꗗ�z
���ŋ߂̓��e �y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂�
|
���[�d�ł��Ȃ�18650 ���e�ʃj�b���d�r�̑����A�����͉��Ȃ�ł��傤�� ���N���A��肢�v���܂� �������̎��₪����܂� �����̋L���������Ă�l�͑��v���ȁH ���[�d������ɂ��Ďg���Ă������ł����H ���P�O�d�r�̗ǔۂ��i����햳���Łj�ꔭ�Ō���������@ ���ŋ߁A����Ȗʔ����[�d�킪�o�Ă܂����B ���f�W�J����DC�J�v���[��Li-ion�[�d�r���q���œ����܂����H ������[�d��œd�r���ʂɓd�����`�F�b�N������@�H ���ԁE�z�b�Z�C�i�Y�}�n���i�͐M�p���܂����H ���Z���A USB Charger (���̂Q) ���Ԃ̗\���o�b�e���[�́H ���d�r�����������Ȃ���d�� ���p�i���[�v�̃f�U�C�����c�O������c�corz ���G�k |
|
��2012�N�̎G�k�E���̉ߋ����O �����{�����~���� ���A���v�Ƀj�b�P�����f�[�d�r������E�[�d������@�H ���Ȃ�ł���Ȏg����������̂ł��傤�H ��enelong super���o�܂��� ������Ȏg�����ł����̂ł��傤���H�� ��100�~�V���b�v��LR44���S���� ���d�����u���V�̏[�d�r���������܂����A���v�ł����H�� �����낢��o��悤�ł� ���@��̃j�J�h�[�d�r���j�b�P�����f�[�d�r�ƌ�������̂ł����E�E�E ���d���H��̃o�b�e���[�̔�r����]���܂� ���V���i�̉��ǔ�10000��ď[�d���\��3000mAh���e�ʂ̃��`�E���C�I���[�d�r ��XTAR�А�MP1�[�d��͂ǂ��ł����H�� ������̒�����] ���G�i�W���C�U�[CH1HR-2�ŃG�l���[�v�͂P���ԏ[�d�ł��܂����H ���X�C�b�`���ǂ���ɐ�ւ�������ł����H�� ���n�u�_�C�i���Œ��ԏ[�d���Ė郉�C�g�������H ���j�J�h�d�r�T�{������肵��5V�ŃX�}�z���[�d�����H�}��������܂��� �����o�C���u�[�X�^�[(�n)�̃o���G�[�V������������悤�ł� �����d�������Ă݂܂��� ���A���J�����d�r�[�d��H�����܂������܂��� ���Ԃ̃o�b�e���[����g�тȂǂ̏[�d�p�ɎO�[�q���M�����[�^�ł͉�����肪����܂����H �������ƌ����Ă���A���o�b�e���[�E�d�����]�Ԃ̘b�������ē��e���܂��I�����₪��I�� ���j�b�P�����f�d�r���j�b�J�h�[�d��ŏ[�d���Ă����v�H ��eneloop�͒������œd�r�ɃL�Y���t���܂��� �������̂ň����ς܂����� ���[��d�͗��p�̂��߁A�d���A�V�X�g���]�ԗp��Li-ion�o�b�e���[���g������ ������@�̃o�b�e���[�ɏ[�d�ł��Ȃ� ��docomo�p��AU�A���͂��̋t�ŏ[�d���Ă����͖����H ��IKEA��LADDA�́H�� �����̃o�b�e���[�͂������߂ł����H ���p�i��BQ-396�Ƃ����[�d�r�Ł@�G�{���^�̒P�O�[�d�r�Ȃ�Ȃ�ł��[�d���Ă����̂ł��傤�� ��BQ-370�������܂��� ��Li-ion�o�b�e���[��Pnasonic�̎��]�ԏ[�d��ŏ[�d������ ���m�[�g�o�b�̃{�^���^�j�b�P�����f�d�r�̌����ɂ��� ��MW1268���̏Ⴕ�����Ă���܂� ���G�l���[�v��1.7V�ɏ�������R���o�[�^�͂���܂����H |
|
��2011�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ���y�����R�[�_�[�̓���ȓd�r������������ ���o�b�e���[�t���z�������̏����Ǝ҂͂���܂����H ���d�r�̎�ւ��̎����ł����H ���d���A�V�X�g���]�Ԃ̃o�b�e���[���[�d�ł��܂��� ���d���A�V�X�g���]�Ԃ̃o�b�e���[�̒��̊�͏C���ł��܂����H ���d���A�V�X�g���]�Ԃ̏[�d��͌𗬂ł����A�����ł����H�� ���������\�ŏd����1/2�̃o�b�e���[���~���� ���d��������Ȃ��̂�DC/DC�R���o�[�^�����Ŏg������ �����C�����X�[�d��̂��肩���� ���J�[�X�e���I�̃o�b�N�A�b�v�d���ɂ͂ǂꂪ�ȃG�l�ł����H�� ���d�r���R�ȏ��g�p�𐄏��Ă����Ȃ����R�H�� ���R���r�j�ŁAUSB�[�d������̒P�O�d�r�������Ă��܂��� ���G�l���[�v(�P3,4)���p���[�A�b�v����Ƃ̂��� ���o�b�e���[�œ����n�ڋ@�̌����������ĉ����� ���A���J���d�r��{�ƃ}���K���d�r��{�ł͂ǂ������d�C�̗ʂ������H�� ���d���o�C�N�Ƀo�b�e���[��AC100V�C���o�[�^��ς�ŏo��ŏ[�d���� ���o���c�L�Ȃ���������ƌʂɏ[�d�E���d����[�d�큜 ���@�\�E���ށB�� ���}���K���d�r�A�I�L�V���C�h�d�r�A�[�d���d�r�͐�Ɏg�p���Ȃ��ł��������A�Ɩ��L����Ă��܂��B�Ȃ��ł��傤���H�� ��Mag-Lab��MMobile-5�͓d�r���c��ށ� ���h�R���|�P�b�g�`���[�W���[ �����`�E���C�I���[�d�r���A�j�J�h�p�[�d��ŏ[�d���Ă����ł����H ���Ȃ����`�E���d�r�����ߕ��d�������ɂ͔���[�d����̂ł��傤�H ������d���A�V�X�g���]�Ԃɂ����o�b�e���[�́H�� ����d���@�\�[���[�ɂȂ郊���[�����ł����̂ł��傤��?�� ���[�d����@���M���Ȃ�܂��A���v�ł����H�� �����`�E���C�I���ƃ��`�E���|���}�[�̈Ⴂ�� ���̔����Ă܂����� ���C�O�p�u�ψ���v��ʂ��ď[�d���遜 ���d�����]�Ԃׂ̈ɁA12V�o�b�e���[��24V�ɏ������钍�ӓ_ ��100V�Ȃǂ̍����d���̂�����ɂ͂������������܂��� ���������s���܂����A�ʂ̏ꏊ�͂ǂ��ł����H ���\�[���[�o�b�e���[�Ōg�ѓd�b�̏[�d�����肽���� ���[�d�r��10�{����{�Q�Z�b�g����Ŏg�� �������y���H ���p�[�t�F�N�g�`���[�W���[�͂ǂ��ł����H ���P�Q�j�b�P���[�d�r���P�O�����[�d���s������ ���[�d��̋L�����ŋߖ����� ���G�l���[�v�́A�ǂ���̕����߂����̂Ȃ̂ł��傤���H�� ���j�b�P�����f�[�d�d�r�̏d�ʂɂ��ā� ���_�C�\�[USB�[�d��AU�p�g�p���̕K�v�d���E�d���͂ǂꂭ�炢�ł��傤���H�� �����`�E���C�I����eneloop�Ƃǂ������L���ł����H ��UltraFire��3600mAh��18650���������ĉ������I ���V�ˁI�ł��� ��EOS-1D MarkII�̊O���d���ɉ��o�b�e���[ ���p�o�b�e���[�̔p���E��� ������܂����炱�̏[�d���]�����Ă��������I ��EVOLTA��CASIO��BC-K10NH�ŏ[�d���Ă����ł����H�� ���A���J�����d�r�̐��\�̔�r�������s���Ă��������� ���O�m�d�@�̊��d�r�̓p�i�\�j�b�N�ɂȂ�����ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H�� ���O�m�d�@�̎q��Љ���ɔ������ꂽ�G�{���^��T�C�N���G�i�W�[�̃S�[���h�� ���\�j�[�̃T�C�N���G�i�W�[�̓G�l���[�v��荂�e�ʂł��I ���_�C�\�[�̎蓮���d�Q�k�d�c���C�g�̉��� ���P���R�[�̃G�l���O�ׂĂ��������� �����z�d�r�Ɗ��d�r���ւ��ă��[�^�[���H ��USB�[�dBOX��Lite�n�[�d�r�͎g�p�֎~�H ��NC-TG1�Ɍ�LED��t���鎿�� ��WF-139�̌��� |
|
��2010�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ���}�b�`���A�A�Z���}�X�^�[���W�F���h�͂ǂ��ł����H�� ��BQ-CC05�ւ̌ʏ[�dLED�̕t���� �����������d�r����́A������`���Ɍ��܂������E������H �����܂�ł��܂���A���������Ă��������I �������͂�͂���� �������N�� ���Z���A�Ńj�b�P�����f�d�r���I ���~�j�l��ŏ����@ ��WF-188��3V�d�r�̏[�d�͂ł��܂����H ���P�O2900��Ah�̓d�r�� ��170mA����鑕�u���\�[���[�`���[�W���[�ŕ₦�܂����H �����z���œd�C��d�w�R���f���T�ɂ��܂��[�d�ł��Ȃ� ���Z���A USB Charger ���g�ѓd�b�̓d�r�̑��� ��BATTERY ANALYZER �����܂ɂ����g��Ȃ����o�b�e���[���Q�N���x�Ŏg���Ȃ��Ȃ�܂� �����}�nPAS�̃o�b�e���E�E�̘b��A���������ځH�� ���P�O�G�l���[�v���莝����FUJIFILM�̏[�d��ŏ[�d�͉\�ł����H ���{����ǂ�ł�������܂��� ���`�b�A�_�v�^�[ ��100�~USB�[�d��ŁAiPhone���[�d�ł��܂��� ���������Ă������� ���\�[���[�K�[�f�����C�g�̍����Z�����g ���j�b�P�����f�[�d�r�E�P�Z�����d���E�E�E�� �����[�I�� ����d����d���ł̏[�d�ł���_���ȃZ���ȊO�̏[�d���o����H�� ���G�l���[�v���P�`�Q���[�d���Ă����v�ł����H�� ���M�a�̋L�����Q�l�ɉ�������Ă݂����Ȃ�܂��� ���|���@�̓d�r���� �����z�d�r�Ń��}�n��PAS�𑖍s�[�d ��AC�A�_�v�^�[��ς��Ă݂� ��ORION EZ�`���[�W���[�̏��͂���܂��H�� ���j�b�P�����f�[�d�r�́u���˔\�d�r�v�ł����H ���V�d�r���Ă��܂��� ��UltraFire��Li-ion�[�d�r��15A���d�I ���[�d�ł��Ȃ��j�J�h�d�r�� ��Li-ion�[�d�r�̓d����0V�ł��� ���}���n�}�̃��[�Z���̃o�b�e���[�� �����]�ԗpLED���C�g�Ƀ��`�E���|���}�[�o�b�e���[ ���L�������^��QEC-F20�̒�R�ɂ��� ��5V�̓d�r�͂Ȃ��o���Ȃ��H�� ��Li-ion���R�{����ŏ[�d��������ėǂ����@ ����] ���d�r�Q�{�̏[�d��ƂS�{�̏[�d��̂ǂ��炪�����H ���V�[���h�o�b�e���[���Q�A����[�d���Ă����ł����H ���P�O�O�~�Ŕ����Ă�t�r�a�[�d��łǂ��ł��傤�� ���Â����W�R���p�̏[�d�큜 ���u���������[�d�n�j�v�Ə����Ă���[�d�큜 ���j�J�h�d�r���n���_�Â����Ďg������ ��1�{�����[�d����[�d���2�{�d�˂ď[�d�ł��܂��� ���m�[�g�p�\�R���̃o�b�e���[�̎g�p���@�H�� �����}�n�E�p�X�̓d�r�����������������Ȃ� ���d�r�͗①�ɂŗ�₷�ƒ������A�g�߂�ƕ�������H ���f�o�̓d�r�͕ς����̂��H ���A���J���ɏ[�d�\�Ȃ̂��A�������܂��H ��Li-ione18650�͒P�O�d�r�Ɠ����T�C�Y�H�� �����낢�� ��GP����łĂ���ReCyko ���d�r�̎�ނƗe�ʂ������Ă��炢������ ���f�����Z�� ���I�������̓d�����u���V�̓d�r�͌����ł��܂����H �����`�E���C�I���[�d�r�͉��܂����H ���d�r�͂ǂ�����č���Ă����ł����H�� ���d�r�̎g�p���Ԃ��Z���Ȃ������R�́H ���P�O�^�Ɠ����`��̃��`���[���d�r�͗L��܂����H�� |
|
��2009�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ���I�[���d�@�̃G�R�v���C�h (2) ���I�[���d�@�̃G�R�v���C�h �����|�d�r�Ɋւ�������A���肢���܂��B ��WF-138�ɂ͐F��Ȏ�ނ�����̂ł��傤���H ��TrustFire�̐V�^TR-001�H (�Q��ޖ�) ���P��}���K���ƒP�O�A���J���͂ǂ��炪�����g���܂����H �����Q�T�m�@�Ŏg�p����[�d�r ���\�[���[�p�l���̗e�ʁH ��USB�[�d�P�[�u���̈Ⴂ�ɂ��[�d�e�� ���d�r��g�ѓd�b�̏[�d���������� ��2�{��1�{�����܂��[�d����Ă��Ȃ����� ����ς݂̂͂��̎O�m2700�������Ɏ��ɂ܂��� ���V�^�G�l���[�v ���d�r���M���Ȃ�[�d����t�@���ŗ�₵�Ă��܂��A���v�ł��傤���H ���H���d�q�̏[�d��L�b�g������������M���Ȃ�܂� ���d���H��̏[�d���ėp�̏[�d��Ƃ��Ďg���Ă݂��� ��SONY�t���t�}���[���d��Ŏ�����DLG�P�R�O�O�Ƃ��̊C�O���d�r�͏[�d�ł��܂����H ��Ni-MH 3.6V 240mAh�p�̏[�d�� ���`���C����AC�A�_�v�^�[���q�� �����g���u���V�̓d�r���� ��Ni-Cd AA400mAh 4.8V ��������p�d�r���~���� �����`�E���d�r�̔ėp�[�d��͗Ǖi�H ��3.0V�^�C�v��RCR123A���[�d�o����[�d�� ��MH-C9000��YZ-114SP�͂ǂ��炪�����ł����H ���\�[���[�p�l���́u����ڑ��֎~�v�H �����[�^�[�̓d��������R ���f�W�J���̊O���d�� ��ipod nano�ɏ[�d����d�r��USB�A�_�v�^�̍����H ��OLIGHT T25 Regular�Ŏg�p����d�r ���A�����t�@�X���z�d�r�͓d�C��R�H ���T�C�o�[�V���b�g�̒P�l�d�r�̂����Ɏg����d�r�́H ��YUASA�̃j�b�P�����f�d�r ��MHR-R7344��NC-MR58�Ɠ����ł����H ���G�l���[�v�́u���[�d�W���v�u�[���d�����W���v�́H ��TrustFire�̐V�^TR-001�H ���j�b�P�����f�d�r�̊O���`���[�u ���d���H��̃T�[�}���v���e�N�^�[ ���f�W�g���i2SC3402�j�̓f�W�g���ł͖����H ���j�J�h�d�r�����[�^�[�����Ȃ��Ȃ�܂ŕ��d���Ă����ł����H ��UltraFire��WF-139�`�E���C�I���d�r�p�}���[�d����܂��� ���d�����]�Ԃ̃o�b�e���[�̒��g������������G���[���o�܂� ���d�����]�Ԃ̃o�b�e���[�𑼎Џ[�d��Ń��t���b�V�������� ���ԂŁA�T�u�o�b�e���[��DC/AC�R���o�[�^�E�[�d��o�R�ŏ[�d ���f�W�J����Li-ion�o�b�e���[���G�l���[�v�ɂ����瓮���܂��� ��(R)���D�F�̃G�l���[�v ��NEXcell��NC-60FC�ŏ[�d�������BQ-330�ŏ[�d����H ���P�O�d�r��ŕ��d�������̖�� ���d�����]�Ԃ̓d�r���������܂��� ������ƕ���̗����������Ďg�� ���p�^�XV�̒����͉\�� �����ł�impulse ��CGL3032�̂�����CR3032�͑�p�ł��܂����H ���z���_�̃C���T�C�g�̃o�b�e���[���� ���R�[�h���X�h�����̌����o�b�e���[����s�\ �����Ŏg���Ȃ��Ȃ���Li-ion�[�d�r �����z�d�r�ƃ_�C�\�[�R���o�[�^�[�ŃG�l���[�v���[�d�ł��܂��� ��THC-34RKC�Ń��t���b�V�� ��IC���R�[�_�[�̓d�r���k �����`�E���C�I���d�r�̃v���e�N�g��H�̗��p ���j�b�P�����f�d�r�̔����ւ������A���� �����`�E���C�I���d�r���G�l���[�v�H ���d���h�����̃j�J�h�o�b�e���[�����ɂ��� ��UltraFire ICR123A(3.0V)��WF-139�łQ�{����[�d�I�H ���^�~���j�J�h1000���j�b�P�����f�p�[�d��ŏ[�d�ł���H ������o�b�e���[�`�F�b�J�[�̕s�ǁH ���d�����]�Ԃ̂m���l�g�̌� �������ԃo�b�e���[�������̃o�b�N�A�b�v�c�[�� ���\�[���[���C�g�p�j�J�h�d�r |
|
��2008�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ��100�ς̃��[�J�[�i�d�r ���p�i�\�j�b�N��BQ-391�ɂ��� ���d���H���p�o�b�e���[�̕��d�� ���N���b�v�R���^�N�g�^�[�d�� ���\�[���[�p�l���ʼn��o�b�e���[�����[�d�H ���\�[���[�p�l���̋t���h�~��H�H �����^�̃X�|�b�g�n�ڋ@���� ���d�r�p�b�N��P�O���d�r�ő�p����ꍇ�̖��_�ɂ��� ���T�C�o�[�M�K�[�������̐V�^ ���d�r�Ƀn���_�Â� ��006P�j�b�P���[�d���d�r���A�}���ɏ[�d�ł����H�͂���܂��� ��LiFePO4,���`�E���t�F���C�g�d�r�ɂ��� ���x�m�t�B�����j�b�P�����f�[�d�r2300�A2500�ɂ��Ă� ���[�d���G�{���^���\ ��FDK�ɂ��OEM��������Ă���d�r�̌���������T�� ���d�����]�Ԃ̃j�b�P�����f�d�r������ ��LMC555�ŏ������Ă��d����1.43V��������܂��� ���f�V�J���ɓ����Ƃ����ɓd�r��\�����o�� �����v�̏���d�͂��Ⴂ���ߓd�r���M���M���܂Ŏg����H ���ԍڂ̃T�u�o�b�e���[���P�Q�u�R�O�`�̃����[�o�R�ŏ[�d�������B �����o��12W�^LED���C�g�Ɠd�r ���P��^�̏[�d�r�͂���܂��H ��CR123A�d�r�̑�p�[�d�r ���g�b�v�o�����[�d�r�ɂ��� �����z�d�r�Ńr�f�I�J�����̃o�b�e���[�[�d�H �����j�o�[�T���}���[���d�� ��12V�A0.5A�ŏ[�d�o����l�ɂ���ɂ�24���̒�R�ŗǂ��ł����H ���G�{���^�̓e�X�g���Ȃ��̂ł����H ���d�r�Ɋւ���G�k ���L�����^���A�G���N�g���j�N�X���Ƃ���̓P�� ���g�я[�d��l�^2�� ���q��@�p::���{�I�Ɂu�ߕ��d�v�Ƃ������ɑ���F�����܂�ňقȂ� ���T�C�N���G�i�W�[�O���[�� ��VOLCANO NZ�ɏ�������H ���\�j�[�̏[�d��iBCG-34HRME�j�ɂ��� ���u�[�d���v�̉�́H �������Ă��܂� ��������H�����������C�g�͕��d��ɍœK�H ���t�R�ꓙ�̊댯�x�̈Ⴂ�����ė~���� ���d�r�̎��ɕ� ���o�r�o�H ���ӂ������ĊC�O�ʔ̂Œ��ؓd�r���܂����d�d�Q|�P|�� ���u�C�̖����v�̕��d�ɂ��Ă̐����̖����_�ɂ��� ��Maxuss��AAA/1250mAh�AAA/3000mAh�̃j�b�P�����f�[�d�r ���C���^�[�v������FAD-701�Ȃ���d�� ���H����100�~�łQ���I�̏[�d���� �������d�r�̔�r ���Z���A�[�d��[�d�L�[�v�p�ɉ����\�H ���d�r�ƊE ���L�������h�D��100�~DC�R���o�[�^ ��Cyber Giga 01�����Ⴂ�܂����i�j ��1.4V�̑��z�d�r3���g���Đ��f�d�r��{���[�d�ł����H |
|
��2007�N�̎G�k�E���̉ߋ����O ���o�C�I���b�^ ���T�����[�̋}���[�d��NC-MDR02 ���A���J���d�r�̊O���̌��ޗ��H ���P�N���ȏ�O��eneloop ���C�ɂȂ�܂��H�i�j ��BQ-390�ŒP��d�r(min2800mAh)���[�d�ł��܂����H ���H���̑��z�d�r��6V���o�b�e���[���[�d ���Ԃ��k�d�c�̂a�p�|�R�X�O ���ue-keep�v�ƊE���̒P1����P4�E9V�A1000��g����[�d�r ������THC-34RKC�ƎO�mNC-TG1�̊�� ���T�����[�m�|�l�q�T�W�r���w�����܂������c ���L�т�d�r�I�H ���\�j�[��BCG-34HRE�͂ǂ��ł����H ���[�d��������i�ɔ��������܂� ���Z���A1300mAh�����S���Ȃ�ɂȂ�܂��� ���P�S��NiMH�̓s�s�`���H ���O�m�P�T���}���[�d�d�r ���P�O�^�̕x�m�t�B�����̃��`�E���d�r ��3AAA�̃��C�g��Li-ion�[�d�r ���t�r�a �b�d�k�k ���p�\�R������j�b�P�����f�[���d��̐��� ���t�����X�̏[�d�r���� ���d�r�v��PowerSmart�̐��\�A�ق��d�r�̎����y�[�W�̂��Љ� ��100�~�V���b�v�̏[�d��ɕ��d�@�\ ���������p�̊O���d������낤�Ǝv�����̂ł������܂������܂��� ���C�O�̂��������������^�C�v�d�r (���̂Q) ��LEXEL e-keep �̐�` ��SG-1000�̃V�[���h�o�b�e���[ ���f�W�J���Ŏg���Ȃ��A���J���d�r ���j�b�P�����f�d�r�p�}�����d��̐��� ��eneloop������Ɖ���Ζ��|���v�H ���C�O�̂��������������^�C�v�d�r ���O�m�Q�V�O�O�͌������Ă��炦�܂����H ���[�d�r�̍����A�����̊�́H ���C���e���N�g�̃o�b�e���[�̃e�X�g�����肢���܂� �������������R���̏���d���e�X�g�͂܂��ł����H ���Z���A��100�~�⌃���j�b���[�d�r�̐��\��r��������Ă������� ���ቷ���̃o�b�e���[���\��r���肢�v���܂� ���g���͂��߂Ǝg���I���̓�����R�H ���G�l���[�v�̂n�d�l�H ���b�q�P�Q�R�`�T�C�Y�݊��̃��`�E���C�I���[�d�r������܂� |
|
���� �o�b�e���[�E�@����g�p���� ���p�i���G�l���[�v���A�}���E�ʏ�^�C�v���A�ǂꂪ�悢�ł����H ���G�l���[�v�̎g�p�͂ǂ��łP��H�@�g�����Ǝ����̊W�́H ���u�A���J���d�r��p/�Ή��v�Ə����ꂽ�@��ɃG�l���[�v�H ���[�d�r�g�p�֎~�̊ߋ�ɃG�l���[�v ���G�l���[�v�͊��d�r�̑���Ɏg�p�o����H �o���Ȃ��H ���ƒ�ł̃��t���b�V�����d�̂������́H ���ߕ��d�ɂ��Ă̎���ł� ���������[���ʂ͉t�I�ȃ_���[�W�ł��傤���H�ߕ��d���邭�炢�Ȃ�r���[�d�̂ق����ǂ��ł����H ���ߕ��d�Ƃ͂ǂ̂悤�ɂ�����Ȃ�܂����H�@�������@�͂���܂����H ���J���d����V���x�ʼnߕ��d�H ������Ǝ��ȕ��d�������Ȃ�܂����H ���j�b�P�����f�[�d�r�̎c�ʂׂ���@�H ���o�b�e���[�`�F�b�J�[�́u�[�d�r�͎g�p�o���܂���v�Ƃ́H ��Ni-MH�d�r��ǍD�̏�Ԃŕۊǂ��邽�߂� ���ړ_�������@���낢�� ���[�d�G���[�����v���_�ŁA�}���[�d�͓d�r��ɂ߂�H(�ړ_�������@) ���[�d�r�����ɂ��ĕۊǂ���Ɠd�r�c�ʂ͓����ɂȂ�H �����`�E���C�I���[�d�r�̒��ӎ����H �����`�E���C�I���[�d�r�̕ۊǕ��@�H �����`�E���C�I���[�d�r�̌����ƕۊ� ���P�O�d�r�̗e�ʂ́H ���[�d�d���A���x�ɂ���ĕ��d�����A�[�d�e�ʂ͕ω�����̂� ���d�r���z���_�[�ɓ��ꂽ�܂ܕۊǂ��Ă��ǂ��ł����H ���� �[�d����E�[�d��E�݊��� ���G�l���[�v���p�i��BQ-390�ŏ[�d���Ă��ǂ��ł����H�i���Џ[�d�P�j ���G�l���[�v���p�i��BQ-390�ŏ[�d���Ă��ǂ��ł����H�i���Џ[�d�Q�j ���G�l���[�v���p�i��BQ-390�ŏ[�d���Ă��ǂ��ł����H�i���Џ[�d�R�j ���G�l���[�v�𓌎�THC-34-RHC�ŏ[�d���Ă������ł����H�i���Џ[�d�S�j ��Cycle Energy��FUJIFILM��Digi Charge�ŏ[�d���Ă��ǂ��ł����H�i���Џ[�d�T�j ���[�d���̓d�r�̕��������M ���j�b�P�����f�[�d�r�ɑ���g���N���[�d ���d�C�h���C�o�[�̏[�d��ɏ����Ă���u�d���v�̈Ӗ��́H ���[�d��̓K���o�b�e���[�ɂ��� ���� �@��̃o�b�e���[���� ���d�����]�Ԃ̃o�b�e���[���� ���R�[�h���X�d�b�@�̓d�r���j�b�P�����f�ƌ������đ��v�H ���R�[�h���X�d�b�@�p�̌����d�r��Ni-MH�ɕς���Ă��܂� ���V�F�[�o�[�̒��̃j�J�h�d�r���j�b�P�����f�d�r�ƌ��������� |
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �I�[���d�@�̃G�R�v���C�h (2) | |||||||||||||
|
�{���z�[���Z���^�[�R�[�i���ɂā@�n�g�l���̃G�R�v���C�h�Ȃ�j�b�P�����f�d�r���w�����܂����B �G�l���[�v�I�Ȏg�������E���݂����ōw�����܂����B 1.2V�@Typ.2000mAh Min.1900mPH �ƕ\�L����Ă��܂��B 1000��̏[�d���\���Ƃ̂��Ƃł��B �P3�^�C�v��4�{�̃u���X�^�[�p�b�N��698�~�ł����B �{���ɋ��G�l���[�v�Ɠ����̐��\�ł�����Ȃ肨���������ȁH �Ǝv���܂��ď������݂����Ă��������܂��� ���傢�̂股 �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�G�R�v���C�h�����s���ł����H ����̓��e�Ƃ��Ԏ� �� �� �� ���Ԏ� 2009/12/28
|
||||||||||||
| ���e |
���X�L�������܂��B �{�����F�ɍs�����甄���Ă�����ł������\���������ł��B �R�[�i���̓����ȊO�͎���o���Ȃ������ł��ˁE�E�E ���Ȃ݂ɏ[�d��Ƃ̃Z�b�g�̂�[�d���Ԃ��Z����Δ����������m��܂��[�d������\���Ⴛ���Ȃ̂Ń��o�C�����ł��� �h�p���� YOTUYO�h�Ɏ��Ă���Ƃ̏��L�������܂��B ���傢�̂股 �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�[�d��͒P�O��20���Ԃ��炢������̂ŁA���Ȃ�C���Ȑl�����ł��ˁB �@�ł��A�z�[���Z���^�[��F�̂悤�ȃX�[�p�[�Ŕ�����ƁA��w�w�ȂǏ]���͂��܂�[�d�r�ɋ�����������������ǂ��u�悭�s���X�ŃG�R(����POP�ɏ����Ă�����)�ȓd�r�������Ă�����I�v�Ƃ��������Ŕ����Ă䂭�l�������Ȃ邩������܂���ˁB �@���ǁA�d�r�̐��\���ǂ��Ƃ����A�����ɏ���҂̖ڂɎ~�܂��āA�����̗��s��́u�G�R�v�Ɉ����|���ď��������邩�ǂ����������������i�̔���s�������E����̂ł�����i�O�O�G ���Ԏ� 2010/1/3
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �I�[���d�@�̃G�R�v���C�h | |||||||||||||
|
�@�ŋ߁A�M�g�o���������Ă��������A���ɂȂ��Ă���܂��B �@������Ƌ����Ă��������������Ƃ�����̂ł����E�E�E �@���́A�p�i�\�j�b�N�ƃG�l���[�v������܂Ŏ�Ɏg�p���Ă��܂������A�ŋ߈����Ă����ȂƎv���A�������̂��I�[���d�@�̃G�R�v���C�h�i�P�R�j�ł��B����ɂ��Ẳ������i�ߋ��ɂ����ׂɂȂ������͒l�Ȃǁj������܂�����A�������������������̂ł����B �R����� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
 �@�I�[���d�@�̃G�R�v���C�h�Ƃ����d�r�ł����A�����z�[���Z���^�[�R�[�i���ɍs������V���ׂœ�������Ă��܂����̂ł͂��߂Ĕ����Ă݂܂����B
�@�I�[���d�@�̃G�R�v���C�h�Ƃ����d�r�ł����A�����z�[���Z���^�[�R�[�i���ɍs������V���ׂœ�������Ă��܂����̂ł͂��߂Ĕ����Ă݂܂����B�@�P�O���S�{�������p�b�N��698�~�I �@eneloop���S�{1480�~���炢�Ŕ����Ă��܂��̂Ŗz�Ƃ����j�i�l�ł��B �@�[�d��Ɠd�r�Q�{�̃Z�b�g��880�~�ƁA�͂��߂ď[�d�r���l�ɂ͎���o���₷���l�i�ł��B(�A������) �@������H�Ƃ���������ł����A�����͂��߂Ĕ������̂ŏ��������������킹�Ă��܂���B �@���܂������ƂɋA���ĊJ�����āA���߂Ă݂��Ƃ���ł��i�O�O�G  �@�{�̑��ʂ̃v���X�ɑ��̃t�^����Ă������ڂ��̃T�C�Y�ƁA�v���X�ɂ̃T�C�Y���ł����Ă���̂�PISEN�́u�p���� YOTUYO�v�ł��傤���B �@�ʂ̃T�C�Y�E�`���قړ����ŁA�{�f�B�Ɋ�����Ă��鏭�������̓������悤�Ȕ����t�B�����̎����A�����Ă��̏ォ�瓧���t�B��������d�ɂȂ��Ă���悤�ȊO���̍\���A���̊ʂɃv�����g����Ă��鐻���ԍ�(�d�r�ɂ���ĈႢ�܂���)����������Ɠ����Ă���̂���������ł��B �@�����A���̃t�B�����̂����eniTIME��e-keep�������悤�Ȋ����Ȃ̂ŁA�G�R�v���C�h���ǂꂩ�C�O�d�r�ƑS���������Ńt�B���������Ⴄ�����ǂ����͂��ꂾ���ł͓���ł��܂���B �@�d�C�I�ȓ����̃e�X�g�͓��ʂ���\��͂���܂���̂ŁA����ȏ�̉����������o�����鎖�͂ł��܂���B ���Ԏ� 2009/12/27
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���|�d�r�Ɋւ�������A���肢���܂��B | |||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āA�����M�d�ȏ�肪�Ƃ��������܂��B �@���́ARC��s�@����ŁA�ŋ߂̓��|�d�r�����C���Ɏg�p���Ă��܂��B �@���|�d�r�Ɋւ�������A���肢���܂��B �܂� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�͂��߂܂��āB �@���̓��|�d�r�Ƃ����Όg�ѓd�b�̃o�b�e���[�p�b�N���Amp3�v���[���[�̓����d�r���炢���������Ă��Ȃ��̂ł����A�����̏��ʼn��l������܂����H �@�ق��̃��|�d�r�͎g���p�r�������̂Ŕ��������������̂ł����E�E�E�B ���Ԏ� 2009/12/17
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| WF-138�ɂ͐F��Ȏ�ނ�����̂ł��傤���H | |||||||||||||
|
�@���߂܂��āB �@�����ł�����������āA���[���������肵�Ă��܂��B �@���͎��A�ŋ߁AWF-138���w�������̂ł����A����́A�P3�ƒP4�T�C�Y���[�d����^�C�v�Ȃ�ł��B http://www.kansai-event.com/kinomayoi/chg/Li_CHG_W.html �@��L�T�C�g�Ō�������́ACR123A�̏[�d��p�Ȃ�ł���ˁB �@�����i�ԂŁA�F��Ȏ�ނ�����̂ł��傤���B �@�����������ł�����A�����Ă��炦��Ɗ������ł��B mezamashi0 �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����i�ԂŁA�F��Ȏ�ނ�������ł��B �@WF-138�ɂ́u16340/RCR123�p��WF-138A�v�Ɓu10440/14500�p��WF-138B�v�̂Q�@�킪�����Ă��܂��B �@�������A�{�̂̃��x���ɂ��ǂ��ɂ�A��B�̌^�Ԃ͏�����Ă��炸�A�̔��X�ł��ǂ��������WF-138�ƕ\�L���Ă��܂��B �@DX�ł͐��N�O�܂ł͂ǂ�������i�����ɁuWF-138�v�Ə����Ă��܂������A����킵���̂ł����炩WF-138�������āuUltraFire 3.0V/3.6V CR123A Charger�v�ƁuUltra Fire 10440 14500 Ac Charger �v�Ə����悤�ɂȂ�܂����B �@�����܂Ń��[�J�[�T�C�g�ƌ����J�^���O�E�p���t���b�g��"����"A��B�̈Ⴂ�������邾���ŁA������^�Ԃŋ�ʂ��ĕ\�L���Ĕ����Ă���̔��X�͂قƂ�ǖ����Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/12/15
|
||||||||||||
| ���e |
�@���e�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@WF-138B���A���g�͐�ɉ������Ă���ʂ�Ȃ�ł��傤���B �@10440(�ی얳��)���[�d����ׂɍw�����܂����B �@�ߏ[�d�͂��قǐS�z�Ȃ��Ǝv���̂ł����A �@�ߕ��d�͒��ӂ��K�v�E�E�ƁA�M�T�C�g�Ŋw�т܂����B �@3.0V������邮�炢�����x�ɏ[�d�����������S�Ȃ�ł���ˁB mezamashi0 �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@WF-138B�����͔��������Ƃ������̂ŁA�����ɂ��Ă͌��y�ł��܂���B �@���̃��x���ɂ͓����o�͓d���E�d���l��������Ă��܂��̂ŁA�������ĈႢ�͖����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@����3.0V/3.6V�̐�ւ��X�C�b�`�������悤�Ȃ̂ŁAWF-139�Ɠ��l�ɍŏ�����X�C�b�`�W�̃v���O�������ȗ������}�C�R���`�b�v���悹���Ă���\��������A���������_�ł�WF-138A�ƒ��g���Ⴄ��������܂���B �@�ڂ����͕������Ă݂Ȃ��ƕ�����܂���̂ŁA�N���������̕����������Đ��\�Ȃǂ���͂���Ĕ��\�����Ɨǂ��ł��ˁB ���Ԏ� 2009/12/17
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| TrustFire�̐V�^TR-001�H (�Q��ޖ�) | |||||||||||||
|
�C�̖����l �͂��߂܂��āA13W�Ɛ\���܂��B �������������Ă��������Ă��܂��B ���́A�u�C�OLi-ion�[�d����ׂĂ݂��v��q�����A ������TR-001�Ɠ��삪�Ⴄ�Ȃ��Ǝv�������̎ʐ^���B�����̂ł����A�ǂ̂悤�ɂ����肵�悤���Ǝv�����e���������܂����B �����̕��͍��N��5����DX�ōw���������ł��B http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4151 ���삪�Ⴄ�ƌ����Ă������ŕ�����̂�LED���A�n�b�L���Ɩ��邭�_�����邱�Ƃ��炢�ł��B �[�d�d�r�͎��10440�A14500�Ȃ̂ŁA��ӏ[�d�����ςȂ��ƌ������Ƃ��Ȃ��A���ɏ[�d�������Ɗ��������Ƃ͂���܂���B �i�A�Q���A�s�ݎ��͏[�d�𒆒f���Ă��܂��j ���̓d�r�p�ɂ�WF-138��HXY-042V�i2�{�p�j���g�p���Ă��܂��B 13W 13W �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@13W�l�͂��߂܂��āB �@���������Ă���TR-001��2009/6/16�ɂ����Ă���uTrustFire�̐V�^TR-001�H�v�Ŏʐ^�Ղ��Ă���SN8P2711���ڂ����V�^�ł͂���܂��H �@��������Ă����炲�߂�Ȃ����B �@�������A���^�ł��Ȃ�SN8P2711���g�p�����^�C�v�ł��Ȃ��A��R��TR-001�ł���Ύʐ^�������Ē��������̂ŁA���̎|�����m�点���������B ���Ԏ� 2009/12/9
|
||||||||||||
| ���e |
�C�̖����l ���͂悤�������܂��B 2009/06/16�̋L���̎ʐ^�̕��Ƃ͈Ⴄ�悤�ł��B ���A�����g����UltraFire��3000mAh��18650��1�{�[�d���A ��12���[�d�����ł��̂܂ܕ��u���A���d���𑪂��4.23V�ł����B �X���b�g�̓d����4.25V�ł��B �[�d��������0.5�b���炢�ŐԂ���ɕς��܂����B �[�d�I����Ԃŗׂɓd�r������Ə[�d�I����LED���I�����W�ɂȂ�܂��B Yahoo�I�t�H�g�Ɏʐ^��UP���܂����̂Ō��Ē�������Ǝv���܂��B http://photos.yahoo.co.jp/ph/hidekisrx/lst?.dir=/41cf&.src=ph&.order=& .view=t&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/ 13W �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�Ȃ�قǁA��R��TR-001�Ƃ������ł��ˁB �@�Ƃ���ŁA���̎ʐ^������Ƃ��鎖�ɋC�t���܂��ˁB �@�����A�}�C�R�����䂩��P�Ȃ�CC/CV����ɕς��āALED�̓_�����d���l�̌��m�����ŐԂ���ɕς�^�C�v�ɂȂ��������� WF-139�Ƃ��������Ă��܂��H �@�g�p���i�A���i�z�u�A�p�^�[���̈����A��\�̃W�����p�[���̔�����E�E�E�B�ǂ����Ă��������Őv���ꂽ���A�����ȃR�s�[���i���ǂ��炩�Ɍ����܂���ˁB �@��̕\�ʂɃv�����g����Ă���uTR0001B 94V0�v�Ƃ����^�Ԃ��炵��TR001�̌�p���Ƃ͎v���܂����A������ WF-139�̊�ɂ��uTR0005 94V0�v�Ƃ����A������1B��5�����Ⴄ�����̑S�������������̌^�ԂƎv����ԍ����v�����g����Ă��܂��B �@�����ɍl����A94V0�Ƃ����v�R�[�h�̉�H�}�E���i�ō��ꂽ�o���@�̂悤�ł��ˁB �@���ۂɍڂ��Ă��镔�i(��R�Ȃ�)�ɂ��A�[�d�d����������肷��\���͂���܂����A����94V0��TR-001��94V0��WF-139�͂قړ������\�ɂȂ��Ă���Ƃ������ŁA�ǂ�����Ă��������Ĉ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2009/12/10
|
||||||||||||
| ���e 12/12 |
���肪�Ƃ��������܂��B ���������܂ł������肵�܂����B ���̏[�d��͍�����A10440�A14500�����̏[�d��̏�̃o�b�N�A�b�v�Ɏg���܂��B �ǂ������肪�Ƃ��������܂����B 13W �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �P��}���K���ƒP�O�A���J���͂ǂ��炪�����g���܂����H | |||||||||||||
|
�@�����y�����q�����Ă��܂��B �@�P3�̃A���J���̓u�����h���C�ɂ��Ȃ���Έ����i4�{100�~�ȉ��j�ŋ�������Ă��܂����A�P1��P2�͂܂��܂������ł��B �@����A�P1�E2�̓}���K���ł�3�{�`4�{��100�~�ł��B �@�P3���P1�E2�ւ̃X�y�[�T�[������A�y���ׂȂ�P1�E2�p�@��ɒP3���g���Ƃ������Ƃ��\�ł���ˁB �@�����ŁA�C�ɂȂ����̂��A�u�����ȒP3�A���J���ƁA�����ȒP�P�E2�}���K���ł͂ǂ��炪�����i����������j���H�v�ł��B �@�}���K���͊Ԍ��g�p�Ŕ\�͉��܂��̂ŁA�g�p�p�r�ɂ���ĒP����r�͏o���Ȃ���������܂��A�ّ�ł͒P1�E2�g�p�̃��W�J�Z�ł̃��W�I�̂ݗ��p��z�肵�Ă��܂��B �@���ɉߋ��ɓ��l�̎������Ȃ����Ă���悤�ł����炲�Љ�Ă��������Ă����\�ł��B �@�����ł�JIS�K�i�ȂǂׂĂ݂悤�Ƃ͎v���܂����A�������������Ȓ��؊��d�r��JIS�K�i�����邩���S�z�ł��i�j �݂��� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���W�J�Z�ƌ����܂��Ă��A���m�����ŃX�s�[�J�[�o�͂�500mW�������x�́u���W�I�ɖт����������x�̂��́v����A�X�e���I�ŏd�ቹ�X�s�[�J�[�܂Ŕ������o��10W�ȏ�̑剹�ʃ^�C�v(�悭�H��ʼn��y��炵�ėx���Ă���W�c���g���Ă���悤�ȁc)�̂��̂܂ŗl�X�ŁA�u���W�J�Z�v�Ƃ��������ł�����d�͂����v�Ȃ̂��킩��܂���B �@�܂����W�J�Z������d�͂����v�Ə�����Ă���Ƃ��Ă�(����͍ő�̕\�L�ł���)�A�Đ����鉹�ʂɂ�������ۂɏ����Ă���d�������`�Ȃ̂����킩��Ȃ�����A�d�r�̎����ɂ��Ă͏����ӂ₷���ē��肪�ł��܂����ˁB �@�Ƃ̒��ŐÂ��Ƀ��W�I���Ă��邾���̑��u�ł����Ă��A���\mA�`���SmA�Ƃ��Ȃ�̍�������܂��̂ŁA���ꂭ�炢��������Ƃǂ̓d�r�łǂ̂��炢�̎����Ȃ̂����S���u�@�펟��v�ƂȂ��Ă��܂��܂��B �@�����Ďc�O�Ȃ���A���̉Ƃł͒P��}���K���d�r���g�p����@��S�������̂ŁA�P��}���K���d�r�ƒP�O�A���J���d�r���@��Ŏg�p���Ď������ׂĂ悤�Ȃ��Ƃ͈�x�������A�d�r�e�ʂɊւ���������������Ă݂Ă���ɏ������悤�ɓ���̋@��ł̓d���l�ł������Ă����Ȃ�����͏���d���l�̕������肷���āA�}���K���̏����Ȃ̂��A���J���̏����Ȃ̂��͓���ł��܂���B �@����������܂������u�ǂ��̃��[�J�[�̃}���K�����d�r�����\���ǂ��̂��H�v�݂����ȃ}���K���d�r�̎������s���ɂ͋C�������Ȃ�悤�Ȏ��ԂƁA�����̋@��œ����ɔ�r���s���ۂɂ͋@�퓯�m�̕��d���\�𑵂��鎖�����ɍ���ł��̂ŁA���̎茳�ł͂��������������s���\��͑S������܂���B �@�^��Ɏv��ꂽ���̂��茳�ŁA�������W�I�Łu����d�r�v�������ςȂ��ɂ��āu������(���N�H)�v�g�p�ł��邩�������ׂ��������B������P�̓d�r���ꂽ��ʂ̓d�r�ɂ��Ă܂�������(���N�H)�Ԏg�p���āA�O�̓d�r�Ƃǂ��炪�����g���������m�F���Ă��������ق��́A���̃��W�J�Z�łǂ̓d�r�����������邩����肷����@�͂���܂���̂ŁB ���Ԏ� 2009/12/3
|
||||||||||||
| ���e 12/4 |
�@�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B �@�S�����������Ƃ���ŕ�����ő傫���ς��܂���ˁB���Ƀ}���K���d�r�͂ǂꂾ���x�܂����ł������ԕς���Ă���ł��傤�B �@�����悻�̖ڈ����m�肽�������̂ł����AJIS�Œ��ׂĂ݂�ƁA���Ƃ��Ε��ג�R10���A�I�~�d��0.9V�̏����ł́A �@�A���J���P3�@1H/D���d��11.5H �@�}���K���P1�@4H/D���d��35H �@�ƈ��������̕��d���Ԃ��Ⴄ���̂̃}���K���P1�̕����A���J���P3��3�{���x�̍������肻���ł��B �@���ؓd�r��JIS���[�����Ă��邩�ǂ����͂킩��܂��A���������Ⴄ�̂ŒP����r�͏o���܂���1�{������̂��l�i��3�{�ȓ��Ȃ�}���K���ł��ǂ������ł��ˁB �@�ڍׂɂ́A���������Ƃ���A���ۂɎg�p���ł����킩��Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�ڈ��͂��߂����ȂƎv���Ă��܂��B �@�����������܂����B �݂��� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���Q�T�m�@�Ŏg�p����[�d�r | |||||||||||||
|
�͂��߂܂��āA���Z�����Ƃ���A�����܂��A�����Ă��������B�{���d�q������Ё@HONDEX�@(�z���f�b�N�X�jHE-51C�Ƃ������Q�T�m�@�A�d���d���FDC11�`14V�@����d�́F3W�@�P3�d�r�~8�ʼnғ��B�i1,2���~8�ō쓮�̓��[�J�[��育�ԓ����������܂����B�j�Ɏg�p����A�[�d���d�r�́A���������߂ł����H�T2��A�e��10���ԂقǘA���g�p���܂��B���e�ʂ̕����ǂ��̂��Ǝv���Ă��܂����A�G�l���[�v�͍��e�ʂ͖������A�����Ă���������K���ł��B
�R�{ �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���d�r�œ����|�[�^�u�����T�ł����B �@11�`14V��3W�Ƃ������Ƃ́A����d����250mA�O��ł��ˁB �@�j�b�P�����f�[�d�r�W�{��8.4V�ł͒�i��12V�O�������d��������̂�������̂��A�d����H���ǂ��Ȃ��Ă���̂��킩��܂��画�f�ł��܂���̂ŁA����12V���Ɠ������炢��250mA�����Ƃ��āA��e��2500mAh�̃j�b�P�����f�[�d�r�ł�������10���Ԏg�p�ł��܂��B �@���[�J�[�̌����A���J���d�r��10���Ԃ̃����^�C���Ƃقړ����ł��ˁB �@����ɂ�10���Ԃ��炢�g�p����̂ł���A2500mAh�̏[�d�r�ł��傤�Lj���̏I���ɓd�r��ɂȂ邭�炢�ł��傤�B �@�ł�����A���Ƃ��u����̍Ō�ɂ܂��ނ�����Ă鎞�ɓd�r����Ă������A���̎��ɂ͗\���ɃA���J���d�r�ł��p�ӂ��Ă����A�^���ǂ���Έ���͓d�r���������Ȃ��Ă��ςށB�v�Ƃ����g�����������̂ł�����A2500mAh�̏[�d�r���g�p���Ă��������B �@�ł��A�[�d�r�͉�����g���Ă��邤���ɗe�ʂ������Ďg�p�\���Ԃ��Z���Ȃ�܂�����A����������10���Ԏg���Ȃ��Ȃ�܂���B �@2000mAh��eneloop�ł����W���Ԃ��������܂����B �@����g���ɂ͕K�������p���܂߂ĂQ�Z�b�g(16�{)�͗p�ӂ��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�W���Ԏg���ēd�r��ɂȂ�܂Ŏg���̂ł͂Ȃ��A�T���Ԃ��炢�ŗ\���d�r�ƌ�������Έ���̏I��荠�ł��r���œd�r��ɂȂ�S�z���Ȃ��A���d�r�����������Ԃ͂�����܂�������̍Ō�̂ق��Łu���d�r�����̂ł낤�H�v�Ƃ����S�z�����邱�ƂȂ��ނ�ɐ�O�ł��܂��B �@��������eneloop�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A2500mAh�̓d�r���g�����ł����傤�Lj��10���ԂŐ�邩��Ȃ����n���n�����Ȃ���g�����A�\���������P�Z�b�g�p�ӂ��Ă����ēr���ň���������悢�����ł��B �@���g���̋@��̓d�r�g�p�\���ԂƁA����Ɏg�p����鎞�Ԃ����傤�Ǔ������炢�ł��̂œd�r�P�Z�b�g�ň�����g�p����Ƃ����̂ɂ͂�����ƐS�z�ł��̂ŁA�d�r��̐S�z�������ɒނ�ɐ�O�ł���悤�d�r���Q�Z�b�g�p�ӂ��āA����̓r���Ō������邱�Ƃ����������߂��܂��B �@��������̂ł����eneloop�ł�2500mAh�̓d�r�ł��ǂ���ł��\���܂���B �@�e�ʂ͏��Ȃ��ǂ��l���Ă��P�Z�b�g(8�{)�ň����ʂ��Ă͎g���܂��A�\���܂Ŋ܂߂�16�{�������̂Ȃ�P���̈���eneloop�ł��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2009/12/1
|
||||||||||||
| ���e |
�A���肪�Ƃ��������܂��B���W�R�����y����ł������ɁA�j�b�J�h�d�r�́A�T�����[�Ƃ̎v��������܂��āA�F�X�A�������Ă�����A������ɁA�H�蒅���܂����B�J���b�N�ł̒ނ�ׁ̈i���A�g�A���ŕs����j���w�E�̂Q�Z�b�g�͌������ς킵�����Ǝv���Ă��܂��B���e�ʂł����߂͂���܂��H�l�i�͖₢�܂���B (������]) �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�J���b�N�ł����E�E�E�E����͋����ł��ˁB �@�l�i�͖��Ȃ��ƌ����܂��Ă��A�P�O�^�j�b�P�����f�[�d�r�ōő�e�ʂ̂��̂�Typ.2700mAh���x�̂��̂������݂̉Ȋw�͂ł͔�������Ă��܂���B �@�Ɠd�X�ȂǂŔ�����O�m��2700mAh�̕i���A�H�t���̐�Γd���Ŕ����Ă���BP��2750mAh�̂���(�l�b�g�ʔ̂���)���B �@12�{�܂Ƃ߂Ĕ����Ȃ�BP��2750mAh�������Ă����Ǝv���܂��B �@�e�ʂ�2700mAh�Ƃ͏�����Ă��܂������ۂ͂���ȉ��ł��B�A��2500mAh�̓d�r���͏����������炢�B �@���10���Ԃ̗��p�ɂ��肬��d�r����N�����Ȃ����ǂ����Ƃ����Ƃ���ł��傤���B �@���ꂾ���́u�����Ă݂āA���ۂ�10���Ԏg�p�ł��邩�������Ŏ����Ă��������v�Ƃ��������悤������܂���B �@�܂�2700mAh�N���X�̃j�b�P�����f�[�d�r��2500mAh�N���X�̓d�r��Aeneloop�Ȃǂɂ���ׂĂ��Ȃ�ϋv���ɖ�肪����A�J��Ԃ��g�p�ł�����Z���X���ɂ���܂��B �@�茳�Ŏg�p�������̂ł͎O�m��2700mAh�͓��ɗ��p�\�����Ȃ��ABP��2750mAh���ق��̓d�r�ɔ�ׂĂ��Ȃ菭�Ȃ��Ŏg�p�s�\�ɂȂ�܂����B �@���������_�܂��āA���T�Ŗ�10���Ԏg�p����ׂɑ�e�ʂ�2700mAh�N���X�̓d�r���w�����Ă��A���\��̎g�p���x�ŗ��p�\���Ԃ��Z���Ȃ���10���Ԏ����Ȃ��Ȃ�ꍇ������A���̏ꍇ��(�ނ�̓r���œd�r�������������Ȃ��ꍇ��)�܂�12�{�V�����d�r���w������A�Ɗ�����đ�e�ʓd�r���g�p����S�\�����K�v�ł��B ���Ԏ� 2009/12/2
|
||||||||||||
| ���e |
���Z�����Ƃ���A���肪�Ƃ��������܂����B�f���ɁA�G�l���[�v�ɂ��܂��B (������]) �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �\�[���[�p�l���̗e�ʁH | |||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�f�l����ł����A�\�[���[�p�l�����g�p���ĒP�S�d�r�R�{�ɏ[�d���ĈÂ��Ȃ�����t���b�V������E�E���Ȃǂ�LED�̑��u���o���邾�������ő�ʂɍ�肽���̂ł��� �P�@��E�����Ƃ�͂�Œ�RV�͕K�v�ł���� �Q�@�P�D�QV�P�S�d�r���R�{�łR�D�UV�ɂ����ꍇ�̃\�[���[�p�l���e�ʂ͂ǂ̂��炢�̂��̂��K�v�Ȃ̂ł��傤�� �@�g�p�͓��̂�����Ƃ��ɐݒu����LED�T�ӂ��Q�Ȃ����S���̂ݓ_�ł��������̂ł�����낵�����肢���܂� �������� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@������H�Ȃǂ��g��Ȃ�����A�ǂ����Ă�3V�ȏ�͕K�v�ł��ˁB �@�j�J�h�[�d�r��j�b�P�����f�[�d�r���R�{��3.6V�ɂ��āA�_�ʼn�H���o�Ē�R�œd����������LED�����点��悤�ȕ��������Ƃ������Ƃł��ˁB �@��Ԃ����A�������_�ł������LED�̏���d���͏��Ȃ��čςނ̂ŁA�P�l�d�r�ł������Ԓ��x�͓_�ł���ł��悤�ˁB �@�����ŏ[�d�ɕK�v�ȑ��z�d�r�ł����A�ł������̗ǂ��o�͏�Ԃ̎��ɓd�r�̓d����荂���d�����K�v�ɂȂ�܂�����A5�`8V(�ő�)���x�ƋL����Ă�����̂ŁA�d���l��100mA(�ő�)��������イ�Ԃ�ł��傤�B �@�ꖇ�ł��̂悤�ȕi��������A������������Ɍq���ŕK�v�v�������Α��v�ł��B �@�����A����͂����l�Ȃ̂ŁA�V�C�ɂ���Ă͏\���ɏ[�d����Ȃ���������܂�����A���̂�����͓K�X�������Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/11/23
|
||||||||||||
| ���e |
�@�ǂ��������肪�Ƃ��������܂��B��͂�TV�͕K�v�Ƃ������Ƃł��ˁB���Ƃ͓d���n�ł��ˁB�W�O��A�`�P�O�O��A�Ȃ�U�O�O�~�`�W�O�O�~���x�ł����ˁB�ł��邾���R�X�g�_�E�����������ǁA������x�̃t���[�d���ʼn����ԓ_�łł��邩�����Ă݂����Ǝv���܂��B���Ə[�d�r�i�v�ԂƂ��ĂQ�d�w�R���f���T�ɂ���Ȃ�A�P�ӂ��ƂTV�T�OF���炢�̗e�ʂ��K�v�ɂȂ��ł����ˁH�܂���낵������肢���܂��B �������� �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�lj��ŁA�������u���g�p����ꍇ�A�P�D�QV����ł������o�����ł����H�p�l���Ɠd�r�͉��i�𗎂Ƃ��邯�Ǐ�����H�ʼn��i���ǂ̂��炢�ł����ˁH����ł��܂����H������H�� (������]) �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d�C��d�w�R���f���T�ɂ���ꍇ�A�e�ʂ�F(�t�@���b�h)�ŕ\�����Ƃ��ł��A���̗e�ʂƏ���d���ł��������̎g�p�\���Ԃ͌v�Z�ł��܂����A�R���f���T�ł���ȏ�u�[�d�d�����ێ�����͍̂ŏ��̏u�Ԃ����ŁA�����Ƃ����܂ɓd���͉������Ă��܂��v�Ƃ������d�������l�����āA������H���g�킸��LED�ړd���d���œ_��������悤�ɐv�d�������Ԉێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȗp�r�ł́A�g�p�ɕK�v�ȗe�ʂ����{�`���\�{�̗e�����m�ۂ��Ă����Ȃ�������܂���B �@�j�b�P�����f�[�d�r�̕��d�O���t����i�d�����x���Ԉێ����čŌ�ɃX�g���Ɨ�����̂ɑ��āA�R���f���T�̕��d�͍ŏ��Ɉ�C�ɓd�����������Ă��܂��Č�͒�d���Ń_���_���ƁE�E�E�A�Ƃ����O���t���������Ƃ�������Ȃ�e�Ղɗ����ł��邩�Ǝv���܂��B �@5V�̃R���f���T��d���Ɏg�p����̂ł���A���̃R���f���T������d���ɏ������鏸���^DC/DC�R���o�[�^�Ȃǂ�v����ăR���f���T�̓d�����K�N�b�Ɨ����Ă�������LED��_���ł���悤�Ȑv�ɂ���邩�A�R���f���T��ɂ������q���œd�����グ��(������z�d�r����R�q����)�����d�����ƂĂ��������āA��C�ɓd�����������Ă��܂��K�v�d����荂���d�������o����悤�Ȃ��Ȃ��|����ȓd�r���j�b�g������āA��������~���^��DC/DC�R���o�[�^��LED�_���ɕK�v�ȓd�������o���Ȃǂ���Ƃ����ł��ˁB �@�ƂĂ���p�����i����������A�����ȑ��u�ł��B �@��C��d�w�R���f���T���g�����@�́A��������l�́u�ł��邾���R�X�g�_�E���������v�Ƃ�������]�Ɛ����̂��̂ɂȂ�܂��B �@�����܂ŕʂ̕��@�̖͍��ł���A�u�ł��邾���R�X�g�_�E���������v�Ƃ����������O���Ċw�K�̂��߂ɐv�����Ȃ�ʔ����Ǝv���܂���B(���́E�E�E�ʓ|�Ȃ̂Őv�͂��܂���) �@�d�r����{�ɂ��ēd����1.2V�A�������珸�������H��100�`300�~���炢�̕��i�łł���Ƃ͎v���܂��B �@�F�X��HP�ȂǂŏЉ��Ă���u�u���b�L���O���U��H�v���������̂ŁA�����̓l�b�g��ł�����ł�������܂���B �@�H���d�q�́u�d�r��{�Ŕ��FLED��_������L�b�g�v�ł͂�����ƕς�_�l�Ń^�C�}�[IC555���g�p���Ă̏�����H������邱�Ƃ��ł��܂��B �@�������ňꂩ���H�v���ł��Ȃ��ꍇ�A�����ĂȂ�ׂ������ړI��B���������ꍇ�͎s�̂́u�K�[�f���\�[���[���C�g�v���w�����ĉ�������̂��ł������ł��܂��B �� ���z�d�r �� �j�J�h�܂��̓j�b�P�����f�[�d�r(�ŋ߂͈̂�{) �� ������H �� �Â��Ȃ�Ǝ����œ_������Z���T�[��H �� ���FLED �@���ꂾ�����S�������ĂȂ��400�`800�~���炢�Ŏ�ɓ���܂��B(�����ƍ����X���c) �@�Č����̏��i�Ȃ̂ŁA�悭�Ăɂ͒l�����Z�[�������Ă��܂��ˁB�t�ɍ��̋G�߂͈������͓��荢�������܂���B �@�P�ɔ��FLED��_�������邾���̏��i�̏ꍇ�A�����o�͂����Ă��Ȃ��Ĕ��U�̃p���X�o�͂œ_�������Ă�����̂�����܂����A�u�V�F�ɐF���ς�I�v�Ƃ������i�ł͂��������@�\���������u�����_��LED�v��_�������Ă��܂��B �@�����_��LED��LED�̒��ɓ_�ŃR���g���[���p��IC�������Ă��܂��̂œd���d����5V���x�K�v�ł����A�����_���������Ă���Ƃ������Ƃ͓d���̓p���X�ł͖������������������^�����Ă���Ƃ������ƂŁA���������^�C�v�̃K�[�f���\�[���[���C�g����������ΖړI�́u��E����LED���t���b�V���v������̂�LED���u��E���̎����_��LED�v�Ɍ������邾���ōς݂܂���ˁB �@������H�̖����K�[�f���\�[���[���C�g�̏ꍇ�̓_�C�I�[�h�Ɠd���R���f���T���炢�ŊȒP�ȕ�����H�����Ă������Ă��̂��̂͗��p�ł���͂��ł��B���S�̂��߂Ƀc�F�i�[�_�C�I�[�h�ʼnߓd����h�~����Ί����ł��ˁB �@�s�̂̃K�[�f���\�[���[���C�g�̏ꍇ�A�u���FLED�����ӘA���_��������v(�ċG�ő��z�����R���і���Z���ꍇ)���炢�̓d�r�e�ʂƑ��z�d�r�p�l���������Ă��܂��̂ŁA����]��LED2�`4�̏ꍇ�͓_�œ���ŘA���_�����͓d�������Ȃ��ƌ�����ł��Ԃ�2���炢�܂łȂ猳�̉����O�̃��C�g�Ɠ������炢�̎��Ԃ͓_���ł���ł��傤�B �@��́A�g�p���鎩���_��LED�̃f���[�e�B�䎟��ł��傤���B�p�b�c�p�b�I�ƒZ���_������^�C�v�Ȃ����d���͏��Ȃ��čς݂܂����A�s�J�[�c�s�J�[�Ɠ_�����Ԃ��������̂͂�����Ƒ����ڂɏ���ē_�����������鎞�Ԃ͒Z���͂Ȃ�ł��傤�B �@���̕��@�Ŗ�ԂɎ����Ă݂āA�_�����Ԃ��Z���Ɗ������瑾�z�d�r�p�l���݁��d�r�̗e�ʃA�b�v����������ȂǁA���낢��ƌ������Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/11/25
|
||||||||||||
| ���e |
�@�f�l����Ȃ̂Ɂ@����f�����ǂ������肪�Ƃ��������܂��B �@�ڂ��ڂ������̕i����������Ă����̂ŁA�Q�d�R���f���T�[���������ĂƂɂ����������Ă݂悤�Ǝv���܂��B�i������H����Ĉ��肳���Ă݂܂��B�j����ƒP���ɂP�D�QV�d�l�ŏ����������̂ƂŁB�����̋߂��̃z�[���Z���^�[�ł��T�O�O�~�Ŋm���ɃK�[�f�����C�g�����Ă��͂��Ȃ̂ł���������ĕ������ĕ����Ă݂܂��B �@���Ȃ����͍H������ɂ���Ԃ��_�ł����炵����ł����Ǔd�����Ⴂ�̂Łi�Q�D�TV���炢�ł����j�Ԃ����ł��܂���ł����B �@�܂�������������܂���ł��������Ă��������B �@�ł́i�O���O�j �������� �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�K�[�f���\�[���[���C�g�͈����Ă����ł���ˁB�����N���X�}�X�p��3����998�~�̂��̂�5�Z�b�g�w�����ĐFLED�Ɋ������Ďg���Ă��܂��B�̔������̂͒P3��NiCd�ł������ŋ߂̂͒P4��NiMH�ł����B �@1�N�قnjo���ď[�d�r�̌��C���Ȃ��Ȃ�Ƒ��z�d�r�����n����y���݂�����܂����B(^^�U ���܁[��i�f�l�j �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�R��998�~�Ƃ͈����ł��ˁB �@�K�[�f�����C�g�����낢���ނ�����̂ŁA�������������Ĕ�ׂĂ݂�̂��y�����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/11/26
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����́A�{���S�X�W�~�ōw�������K�[�f�����C�g�炵����ł����A�P�D�QV�@�U�O�O��A�̉��F���d�r�t���i�P�{�j���F��LED�Ȃ�ł����@�X�C�b�`ON�œd�C������LED�̓d�ɂɃe�X�^�[���ĂĂ��P�D�OV�O�サ���オ���ĂȂ��̂Ɍ��\���邭����̂͂Ȃ��Ȃ�ł����H��H�ɂ́@��R�ƃR���f���T�炵�����̂ƂS�{���̃g�����W�X�^�݂����Ȃ��̂��������t���Ă��炸�A�Ɠx�Z���T�[���\�[���[�p�l���̒��ɓ����Ă�݂����ł���Ղ�Ղ�ł��B �@�d���Ď����Ă銴���ł͂Ȃ��悤�ł����A����ȃp�l���������Ă��ł����ˁH�搶�͂P�D�TV�d�r�ɏ[�d�ł�������ȃp�l���̔����Ă�Ƃ��������ł����H�����Ë�����LED�Q�_�łō쐬���Ă��T�O�O�~�͒��������Ȃ�ł����@��͂�Ǝ��̃��[�g�̑�ʐ��Y������ł����đf�l�ł͌��E�������ł��傤���E�E�E�����܂��p�l���̕����ł����Ă݂悤���Ǝv���܂��B �������� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����A1.0V�ł����邭���锒�FLED�����ڂ���Ă���̂ł��ˁI �@LED�̐����Z�p���i��ŁA1.0V�ł����イ�Ԃ�g����LED���J�����ꂽ�̂̓X�o���V�C���ł��I �@����LED���J�������l�͂��ԂN�̓m�[�x���܂���܂���ł��傤�B �@�E�E�E�E�Ƃ������Ȃ琢�E�̏����ς���ł��傤�B �@�Ȃ�1.0V�Ȃ̂���LMC555�ŏ������Ă��d����1.43V��������܂����ŏڂ����������Ă��܂��̂ł��ǂ݂��������B(���ɐ������Ă��鎖�����x�������̂͌��Ȃ̂�) �@�S�{���̉����H�A���邳�Z���T�[�����̑��z�d�r�H�A�S���������Ƃ�����܂���B �@�S�{���̉����͏����W��IC���Ƃ͎v���܂����A���ꂪ�����͎������������Ƃ������̂ʼn��������܂���B���i����������̂ɕ��i�������Ȃ�����̂͂悭�����Ȃ̂ŁA�����ł͂��������ȗ����ł��镔�i���J������čڂ����Ă���̂ł��傤�ˁB�ǂ�������H�}�łǂ������Ă���̂��͂��̃\�[���[�K�[�f�����C�g�������l�ɂ����킩��Ȃ��ł��傤�B �@�撣���ĉ�͂��āA�ړI�̓_�ʼn���Ȃ�����悤�ɂȂ�Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/11/28
|
||||||||||||
| ���e 11/30 |
�@���̃K�[�f�����C�g�́A�F���ω�������̂ł����A�{�^���ŐF���Œ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B �@��H�͌��Ă��܂��A�Q�̃j�J�h�ƂR�̂k�d�c���g���Ă���̂ŕ�����H�������Ă���͂��ł��B �@���Z���T�[���t���Ă��܂����A���z�d�r�����Z���T�[�Ɏg�����Ƃ��\���Ǝv���܂��B �@�p��ł����A�ȉ��̃T�C�g�́uNocturnal solar engines�v���Q�l�ɂȂ邩������܂���B http://www.solarbotics.net/ ���� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| USB�[�d�P�[�u���̈Ⴂ�ɂ��[�d�e�� | |||||||||||||
|
�@USB�[�d�P�[�u���̈Ⴂ�ɂ��[�d�e�ʂɂ��Ēm�肽���̂ł��B �@�A���X�e�B �p���t���`���[�W���[�ɃG�l���[�v4�{�����āAUSB�[�d��Ƃ��Ďg�p���Ă��܂��B �@���܂ł́A�莝����USB�P�[�u�����g���Ă����̂ł����A�P�[�u���������čd�����ߎ����悭���������ł��B �@����Ȃ��Ƃ�����A�ŋߊ�����莮�̃P�[�u��(�G���R�� USB-RLM515)���w�����܂����B �@���͗ǂ��Ȃ����̂ł����A�P�[�u�����ׂ�1.5m�ƒ������߃C���s�[�_���X�͍����Ǝv���܂��B �@�����Ŋ�{�I�Ȃ��Ƃ������̂ł����A��R�l���������Ƃɂ��d��(�d��)���~�����A�[�d���Ԃ������Ȃ邱�Ƃ͗����ł��܂��B �@�^��Ȃ̂́A�[�d�ł��鑍�e�ʂ͂ǂ��Ȃ邩��������Ȃ��̂ł��B �@�[�d�Ɏ��Ԃ͂����邪�A�[�d�e�ʂ͓����Ȃ̂��A �@�P�[�u���̒�R�l�ɂ��d���~���̓��X�ƂȂ��ēd�͂������āA���̕��[�d�e�ʂ����Ȃ��Ȃ�̂ł��傤���H �@PSP�[�d�Ɋւ���L����ǂ�ŁA�P�[�u���ɂ��[�d���Ԃ��ς�邱�Ƃ͕��������̂ł����A���d�r�i�[�d�r�j����USB�[�d��ŏ[�d�ł���e�ʂ��ǂ��Ȃ�̂���������܂���ł����B �@��{�I�Ȃ��ƂȂ̂ŏ펯�Ȃ̂����m��܂��A�����Ă��������Ȃ��ł��傤���H �@��낵�����肢�������܂��B ���Ƃ� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ł��ˁB�ׂ��P�[�u��(�C���s�[�_���X������)���g�p�����ꍇ�A�d�����h���b�v����̂ŋ@�푤�̏[�d��H���o�b�e���[�ɏ[�d������\�͂��Ⴍ�Ȃ�A�[�d���Ԃ��L�т܂��B �@���d�o�H�̓r���ɃP�[�u���̒�R�l������̂ŁA���R���d���Ă���[�q�ƁA��d���Ă���[�q�̊Ԃ��P�[�u����R�l�~����Ă���d���l�̂Q���Ԃ�̃G�l���M�[�͔M�����Ƃ��Ď����܂��B �@�ł�����A��������������d���𗬂��Ă��r���o�H�Ŏ�����G�l���M�[�Ԃ�̓o�b�e���[�ɂ͓���܂���A���R���X�����ԂȂ��e�ʂ̏[�d�ɂȂ�܂��B �@�u�e�ʂ����Ȃ��v�Ə����Ɓu�o�b�e���[�̒��ɓ��閞�e�ʂ�����Ȃ��H�v�݂����Ȍ����^���邩������܂��A�����Ԃ����ăo�b�e���[�ɂ͂����Ɩ��[�d�܂ŏ[�d����܂����A����Ɏg��ꂽ�d�r���狟�������d�͂͗]�v�ɑ����g���Ă����ƌ������ق����������ł��傤�B �@�����d�r���g���Ă��A�ׂ��P�[�u��(�C���s�[�_���X������)���g�p�����ꍇ�ɂ́u�Q�[�����ł��鎞�Ԃ͏��Ȃ��Ȃ�v�Ƃ������Ƃł��ˁB �@�����A�����P�[�u���ŏ[�d�������̂ɑ��čׂ��P�[�u���ŏ[�d�����ꍇ�́A���[�d�̃j�b�P�����f�[�d�r�ŏ[�d�ł��Ȃ��Ȃ�܂ŃQ�[���@��(����H)�[�d�����ꍇ�A���v�Ńv���C���Ԃ������Z���Ȃ邩�Ƃ����_�ɂ��Ă͎��ۂɂ���Ă݂Ȃ��Ɛ��l�͂킩��܂���ˁB �@�g�p����P�[�u����@��ɂ���Ă��ꂼ��Ⴄ�ł��傤����A�ʂ����Ă��ꂪ�v���C���Ă��ċC�t�����x�̍��Ȃ̂��A�قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ����Ȃ̂����ʂ̖��ɂȂ�Ǝv���܂��B �@USB��5V�Ƃ����K�i����ő�4.2V�܂�Li-ion�o�b�e���[���[�d����Ƃ����A������Ɓu�j�n��v�I�Ȃ��肬��̂Ƃ���œ��삳���Ă���[�d��H���قƂ�ǂł�����A������Ɠd���d��������������[�d���Ԃ����тĂ��܂��͉̂ߋ��̋L���̒ʂ�ł����A�P�[�u���Ń��X����G�l���M�[�͂��������ʂł͂Ȃ�(�G���Ă��M���Ȃ��ł���H)�̂ŁA���X�̗ʂ͎��p��͂قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ����x���������Ƃ͎v���܂���B ���Ԏ� 2009/11/23
|
||||||||||||
| ���e 11/25 |
�@�킩��₷���������肪�Ƃ��������܂����B �@����قNjC�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ������Ȃ��Ƃ��킩�����̂ň��S���܂����B �@�ł��A���ۂɂǂꂭ�炢�g�p���Ԃɍ�������̂��m�肽���C�����܂��ˁB ���Ƃ� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d�r��g�ѓd�b�̏[�d���������� | |||||||||||||
|
�@�d�r����ā@�O���قnjg�ѓd�b�̏[�d��Y��Ă��܂����@���[�d�������Ƃ���ł����@�[�d�̏�Ԃ��������������悤�ł��@���̂܂[�d�����ā@�g����悤�ɂȂ�܂���
�R�c�@�q�s �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�[�d�Ɏg�p���Ă���[�d��́A�g�ѓd�b���Ă����Ƃ��ɕt���Ă������[�J�[������AC100V�R���Z���g����q���[�d��/�N���[�h���ł����H �@���������i�œ��삪���������ꍇ�́A�̏�̉\��������܂����炽�����ɏ[�d���~���ă��[�J�[�ɂ��₢���킹���������B �@�����i�ł͂Ȃ��A���А��i�A���Ɋ��d�r���g�p���Čg�ѓd�b���[�d����悤�ȊȈՏ[�d��̏ꍇ�A���̏[�d��̐������Ɂu�g�ѓd�b�����S�ɓd�r��̏ꍇ�͏[�d�ł��܂����v��u�g�ѓd�b�����S�ɓd�r��̏ꍇ�͐ڑ����Ȃ��ł��������v�Ƃ͏�����Ă��܂���ł������H �@�����̊ȈՏ[�d��ɂ͂��̂悤�Ȓ��ӏ���������Ă��āA���ۂɊ��S�ɓd�r��̌g�ѓd�b�ɂ͐������[�d�ł��Ȃ��ꍇ�������ł��B �@�g�ѓd�b�Ŏg�p����Ă��郊�`�E���C�I���[�d�r�̎d�l�ŁA���S�ɋ�ɂȂ��Ă����Ԃł͏[�d�ɂ͑傫�ȓd����v������܂��B �@���d�r���̊ȈՏ[�d��Ȃǂł����\���Ⴍ���A���̂悤�ȑ�d����v�����ꂽ�ꍇ�ɂ͏o�͓d�����������Ă��܂��Čg�ѓd�b�̕K�v�d���������ɁA�g�ѓd�b������ɓ��삵�Ȃ��ꍇ������܂��B �@���̂悤�ȏ�ԂŌg�ѓd�b�삳����ƁA���̃R���s���[�^����쓮���Đ���ɏ[�d�ł��Ȃ������ł͂Ȃ��A�������[���e�������E�j���Ȃǂ̕s�ӂ̌̏�ɂ��q���邩������܂���̂ŁA�d�r����̏ꍇ�͂��̂悤�Ȓ��ӏ����̂���[�d����g�p���Ă͂����܂���B �@�d�r����̌g�ѓd�b���[�d����ꍇ�́A���[�J�[�̏����[�d����g�p���邩�A���d�r���Ȃǂ̊ȈՏ[�d��ł��u�d�r����̏�Ԃ���ł��[�d�ł��܂��v�ƃp�b�P�[�W��������ɖ��L���ꂽ�@������g�p���������B ���Ԏ� 2009/11/4
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �}���K���d�r�̎����͂��Ȃ��̂ł����H | |||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āA���ŋ߂��̃T�C�g��m��A�y���܂��Ă��������Ă܂� �@��ϒt�قȎ���Ő\����Ȃ��̂ł����A�Ǘ��l�l�̓}���K���d�r�̐��\�]�������͍s��Ȃ��̂ł��傤���H �@�����A�ߋ��ɂ����ɂȂ��Ă����玸��v���܂����B (������]) �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�}���K���d�r�͂ӂ���قƂ�ǎg��Ȃ��̂ŁA���ɋ����������̂Ŕ�r�Ȃǂ��s���܂���B �@�}���K���d�r�𐔕SmA�ň�C�ɏ���Ă�����̓}���K���d�r�{���̎g�p���@�ł͂���܂���ʔ�������܂��A�}���K���d�r�{���̎g�����ł������d���Œ����ԂƂ��������łȂ��ƃ}���K���d�r�{���̓������ׂ邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �@�����Łu�N�H�[�c���v�ɓ��ꂽ�牽�����������H�v�Ȃǂ̎��������邽�߂ɁA���v��10�قǔ����Ă��ăY���[���ƕ��ׂāA�e�Ѓ}���K���d�r�����ĂP�N�����u��������Ȃǂ��s���̂��ʔ�����������܂���B �@�������A���̒��x�̔���ȓd���ɂȂ�Ɓu���x�v�̖�肪����A���v�����i���w�������Ƃ��Ă������ɓd���𑽂��������́A���Ȃ��d���Œ����ԓ����Ă��܂����Ȃǂ̃o�����������ł��Ȃ��Ȃ�A�d�r�{���̐��\���������v�̐��\���̂ق����g�p�\���Ԃɉe����^���闦���傫���A�ƂĂ��d�r�̐��\���v���Ă�������Ƃ͌����Ȃ��Ȃ�܂��B �@���̂悤�Ȏ��v�̌̍��ɂ��s�K�����ɂ́A�g�p���鎞�v�͈�����Ő��\���͖�����Ԃɂ��A����ɓd�r�����ꂽ�������P�N�ԍs���B�����Ď��̂P�N�͂܂��ʂ̓d�r�����Čo�߂��ώ@����E�E�E�B�Ƃ������ɂ����d�r10�{�𑪒肷��Ƃ����10�N�قǂ����Ď������s��Ȃ���Ȃ�܂���B�P�N�Ɉ�{�Ƃ���̂͋G�߂ɂ�鉷�x���ł̓d�r�̕��d�\�͂̉e�������ɂ���K�v������ׂŁA���Ƃ��ΕK���u�P���Ɏ����J�n�v�Ƃ����ӂ��ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@���āA���̂悤�ȓd�r��{�𑪒肷��̂ɂP�N����������͉ʂ����ėL�p�ł��傤���H �@���d�r�͂����Ă��P�N�`���N���Ƃɉ��ǂ���Đ��\���ς���Ă��܂��B �@10�{�̓d�r��10�N�����đ��肵�Ĕ�r�O���t���������Ƃ��āA���̎��_�ł͊��Ɏs��Ŕ����Ă���d�r�͂����ƐV�^�ɕς��Ă��āA���肵���d�r�͂Ƃ��̐̂ɔp�ՂɂȂ��Ă��ăO���t�Ȃ��Ă��Ӗ��������I�Ƃ������ɂ͂Ȃ�܂��H �@10�N���̍Ό��������āA�Ӗ��̖������������鎖���̂ɈӖ������o����Ȃ炢���̂ł����A���ɂ͈Ӗ��𐬂��Ȃ��̂ł������������͍s���܂���B �@���ɂƂ��Ẵ}���K���d�r�Ƃ́A�ڊo�܂����v��s�u�̃����R�����ɓ���Ă����āA�������`�P�N���g�������ł����̂ł��B���ɒ������̃}���K���d�r��I��Ŕ����ȂǂƂ������͂��܂���B���̂ւ��100�~�V���b�v�Ŕ����i�Ŏ�����Ă��܂��B ���Ԏ� 2009/10/31
|
||||||||||||
| ���e 11/2 |
�@���Ԏ��L��������܂��B �@�Ȃ�قǁA10�N���������Ă�����ƂĂ��Ӌ`��������Ƃ͂����܂���ˁB �@���ꂾ���������Ԃ�������ƁA�@�ނ̗ɂ���R�̑���������ł��܂��E�E�E �@�����J�Ȑ����Ɋ��ӂ���̂Ɠ����ɁA���߂Ď����̖��m���ɐ\����Ȃ��v���Ă���܂��B �@�L��������܂������S�����i�T�C<(_ _)> (������]) �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| 2�{��1�{�����܂��[�d����Ă��Ȃ����� | |||||||||||||
|
�@�P�lVOLCANO2�{�Z�b�g��GPS���K�[�������Ă܂����A�ŋߎ��Ԃ������Ȃ��Ȃ��Ă����B �@���������Ǝv���ăo�b�e���`�F�b�J�[�Ŋm�F���Ă݂��1�{�͗e�ʂ��c���Ă���A����1�{�͕��d��ԁB �@2�Z�b�g�ڂ������X���ŁA�����̗e�ʂ��c���Ă���ق���g�ݍ��킹�ē��삳������1�{�ڌ���܂ł̎��Ԃƍ��킹�Ă����̎��Ԉʎ������B �@�Ȃ�2�{��1�{�����܂��[�d����Ă��Ȃ������B �@BQ-390�ŏ[�d���Ă��܂����A�c�e�ʂ̃o�����X�����d�r�̑g�ݍ��킹�ŏ[�d����Ƃǂ�����������݂����E�E�E�����ǁu�ʏ[�d�\���v�t���Ȃ��Ǝ��ۂɉ����N�����Ă���̂����f���܂��B jr7cwk �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d�r���Q�{�ȏ�Z�b�g(����)�Ŏg���Ă���ƁA���̂�����{��������������ɕ��S���������Č㔼�͂��̓d�r�����ɑ������܂��ˁB(�[�d�ł��Ȃ��Ȃ����������������� (��250��g�p)�̌��̂悤��) �@���Ԃ�VOLCANO NZ������������ق��ɕ��S���������ĂQ�{�̂����ő傫�ȍ����J���Ă���̂ł��傤�B �@���ɂ����m���Ƃ͎v���܂����A����������Ԃŏ[�d�Ǝg�p���J��Ԃ��Ă���ƁA���̎�����d�r�͏[�d��ɓ���Ă��[�d�J�n���炷���ɒ[�q�ԓd���������Ȃ��Ă��܂��āA�[�d�킩�猩��u���[�d�v�Ɗ��Ⴂ����Ă����ɏ[�d����~���Ă��܂��܂��B �@���������Ō��Ȃ̂́A���̓d�r���s�Ǔd�r�Ɣ��肳�ꂽ�̂ł͂Ȃ��A���ɖ��[�d�̏�Ԃ̓d�r�ɒǂ��[�d�����̂ł����ɖ�������������ꂽ�̂Ɠ��������Ɍ����邽�߁A�[�d��ɂ�����I���Ɣ��f����ăG���[�ł͂�����܂���B �@�������̂悤���j�Z�����d�r���������Ă��Ă��[�d��͂����܂��Ȃ��ɑ��̐���ȓd�r�̏[�d�𑱂��A���ׂĂ̓d�r���[�d����������[�d��Ƃ��I���܂��B �@���̎����ʕ\���@�\�����Ă���[�d��Ȃ�A�[�d�J�n�㐔���`10�����x�ő����[�d���I����Ă��܂��Ă���d�r�̓����v�܂��͉t���̕\���Ō����������̂ł����ABQ-390��NC-M57/58�̂悤���ʕ\���Ȃ��̏[�d��̏ꍇ�́A���ɂ��̂悤���j�Z�����d�r���������Ă������ƂɋC�t�����Ƃ��ł��܂���B�[�d���I����Ă�����u�����A�S���[�d�ł����ȁv�ƈ��S���đS���̓d�r�����o���Ă��܂��ł��傤�B �@�ʕ\���@�\���Ȃ��Ă��A�[�d�������ɓd�r�̓d�����e�X�^�[�Ōv������A�Ō�܂ł����Ə[�d���ꂽ�d�r��1.3xV�`1.4xV���x�̍����d���ł����A�����[�d���I�����Ă��܂��Ă���d�r��1.3xV�̉��̂ق���1.2V��ȂǑ��̓d�r���d�����Ⴂ�̂Ŋm�F�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@���̎茳�ł������̂悤�ɖ����@�E��M�@�Ŗ����d�r���g���ČJ��Ԃ��g�p�̑ϋv�e�X�g�I�Ɏg���Ă���d�r�́A�ǂ��̃��[�J�[�E�i��ł��������߂Â��Ă���ƈ�{���j�Z�����d�r�ɂȂ�܂��B �@���傤�Ǎ���enelong��POWER LOOP 2700�����̂悤�ȏ�Ԃł��B �@�����[�d�����Z�b�g���j�Z�����d�r���������Ă���ƁA�[�d��ɋ@��ɓ��ꂽ���ɂ͂����Ɠd��������A�d�����ꉞ��i�ȏ゠��̂Ńo�b�e���[��x���͏o�Ȃ��̂ł����A�g�p���͂��߂��炶���Ƀo�b�e���[��ɂȂ��ēd���������܂��B�ƂĂ����p�I�Ƃ͌����Ȃ��g�p�\���ԂɂȂ�܂��B �@���A�������A���̂悤���j�Z�����d�r�̏�Ԃ̎��ɂ����͂܂��d�r�̏[�d�\�e�ʂ͂��Ȃ�c���Ă���(�V�i�����猩���猸���Ă��܂���)�A�P�Ɂu�^���N�̑傫���͗L��̂ɁA���������[�d���Ă��Ȃ������v��Ԃ̂��̂������̂ł��B �@�������j�Z�����d�r�ŏ[�d�������ɒ�~���Ă��܂��[�d��ł͂Ȃ��A�L�����^����QEC-F20�̂悤�ɔ��肪�Â��ăK�V�K�V�[�d���� �@��قǗ��Ă��܂��Ė{���Ɏg���Ȃ��d�r�ɂȂ�O�ł���ABQ-391�́u�Ă��˂��[�d�@�\�v�ł����[�d���Ă����悤�ł��B �@�܂��A�j�Z�����d�r�̏�Ԃł��܂����x���y���ꍇ�́A���S�ɋ�ɂȂ��Ă��Ȃ��ł܂��d�r���ɓd�C���c���Ă���ꍇ�͓�����R�����܂�傫���Ȃ��Ă��Ȃ��̂ŁA�j�Z���������̒��x�����Ȃ���NC-M57/58��BQ-390�ł��r����~�����ɍŌ�܂ŏ[�d�ł��邱�Ƃ������ł��B �@�Ȃ̂ŋ@�킪�����Ȃ��Ȃ�܂ŕ��d�����ɁA�r���Ŏg�p����߂Čp�������[�d���s���Ɩ��e�ʂ܂ŏ[�d�ł�����A�܂���ɂȂ��Ă��Ă��������̏[�d��(���[�d���m�@�\�̖������d���̏[�d��Ƃ�)�ŏ����[�d���Ă���āA���ɂ�����x�d�C�������Ԃɂ��Ă��Ύc��͋}���[�d��ŏ[�d�ł��邱�Ƃ�����܂��B �@�ʕ\���@�\���̏[�d����g�p���āA�[�d�J�n����10����15�����Ɉ�x�\�����m�F���Ă݂�I�Ƃ����ʓ|�Ȃ��Ƃ�����Ȃ�l�Ԃ̖ڂł��������߂Â��Ă����d�r�̔��ʂ͉\�ł����A�����܂ł��ēd�r���Ǘ�����̂����Ȃ�ʓ|�ł���ˁB �@�t���\���Ōʂɏ[�d�����e�ʂ�mAh���l�ŕ\�����Ă����悤�ȍ��x�ȏ[�d��͈�䎝���Ă���Ε֗��ł������i�������ł����A��͂蒷���Ԏg���Ă���d�r�͂����͎�����������̂Ǝv���āA�g�p���Ԃ��Z���Ȃ��Ă����班���C�������ď[�d���̋�����d���Ȃǂ��v���Č��āA�ǂꂩ��{������Ă��Ȃ����A�o�����X�͈����Ȃ��Ă��Ȃ������`�F�b�N���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��悤�B �@��ɂ������܂������A�L�����^����QEC-F20�͂��Ȃ������d�r�ɂ� �@���łɁA�Q�FLED������(�L�����͂��Ă��܂��c)�����Ă����A������d�r�肵�ď[�d�d��(�P�T�C�N�����̎���)�����炵�Ă���l�q�Ȃǂ���Ɏ��悤�Ɍ�����悤�ɂȂ�̂ŁA�ɂd�r������Ɓu�����A�L�����^������������ď[�d���Ă���E�E�E �v�Ɠd�r�̏�Ԃ������܂��Ɋm�F�ł���悤�ɂȂ�܂��B(�����܂ł���l�͕��ʂ͋��Ȃ��ł��傤���c) ���Ԏ� 2009/10/23
|
||||||||||||
| ���e |
�@�N�`�R�~���ɂڂ����ƂԂ₢������ł������A�{�̌f���Ɏ��グ�ă��X�܂ł����������k�ł��B(�����̏��A��ς��Z�������ł����E�E�E) ���j�Z�����d�r �@�Ȃ�قǂł��B �@�l���Ă݂�Ƃ��̓d�r�A�g���n�߂��̂���N��6�����B �@�g�p�p�x�͕��ς���ƌ�2����x�Ƃ���Ȃɑ����Ȃ���ɁA���܂�ׂ����Ǘ�������(�@�킪�V���b�g�_�E���܂��̓o�b�e���x�����o�����_(���ɂ��̎��̓d������炩�̓`�F�b�N���Ă��܂���)�Ŏg�p�I���A�A���[�d�A�Ƃ����������B���܂Ɍy���g�p�����d������Ȃ������Ɂu�Ǐ[�d�v�Ƃ����P�[�X���L�B)�Ɏg�p���Ă܂����̂ŁA�R���f�B�V����������Ă��Ă����������Ȃ��g�������������Ǝv���܂��B �@�R���f�B�V���������邢�����������ɂȂ�܂����B �@����̏[�d�́A�������d�������m�ƁA�e�ʂ��c���Ă������m�̑g�ݍ��킹�ōs���Ă݂܂����B(2���BQ-390�ŕ��s�[�d) �@����g�p���͌��̃y�A�Ŏg���Ă݂܂����A�܂������悤�ȏ�ԂɂȂ�����A�y�A�̑g�ݍ��킹��ς��Ă݂悤�Ǝv���܂��B �@���ꂩ��[�d��������̓d���`�F�b�N�������Ă݂܂��B �[�d�큄 �@�L�����^���͎����ĂȂ��̂ŁA�ň��͏H���u��d���^�C�}�[���v�ɂ��u�����[�d�v�ɂȂ肻���B �@����ɂ��Ă��o�b�e���`�F�b�J�܂Ŏ��Q���A��ԓ��Ń`�F�b�N���Ă��܂������āE�E�E (����PSP�̏[�d�p�Ɏg�p���Ă���P�O4�{�~3�Z�b�g�̂ق����R���f�B�V���������āE�E�E��BQ-391�͂�����̏[�d���D��) jr7cwk �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�j�Z�����d�r�͌��̂Q�{�Z�b�g�ɖ߂����ɁA�u���Ȃ������d�r�v�̃}�[�N�ł������j�Z�����d�r���m�Ńy�A�ɂ��Ďg�p���ꂽ�ق��������ł���B �@�������j�Z������������Ė��[�d�܂ŏ[�d�ł����Ƃ��Ă��A�܂����C�ȓd�r���͗e�ʂ������Ă��܂����A�����g���������Ă���Ƃ�͂������d�r�̂ق��ɕ��S���������Č����_�����X�ɗ��邱�Ƃ𑁂߂�悤�Ȃ��Ƃɂ��Ȃ�܂��B �@�Ȃ�ׂ��R���f�B�V�����̗ǂ����̓��m���y�A�ɂ��āA�R���f�B�V�����������Ȃ����d�r�͂ق��̒�d���p�r�ȂǂɉĂ��܂��ق����A�@��ł̎g�p���ɗ\��(�\�z�H)��葁���d�r��ɂȂ����肵�Ȃ��čς݂܂��B ���Ԏ� 2009/10/25
|
||||||||||||
| ���e 10/26 |
�@���낢��A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B �@�d�r�ɂ͑S�Ĕԍ��������Ă��莯�ʂł��܂����A����̌��ʂŔ��f���܂��B (GPS��M��Ԃ̊m�F�ׁ̈A���X�\�������Ă��܂��̂ŁA�����Ă���C�����܂��B) �@����ƁE�E�E�@�킪�V���b�g�_�E������d�����m�F���˂B ����d���p�r�Ȃ� �@�d�r1�{�œ���MP3�v���[���[������̂ŁA�]�p��ɂ͂��ꂪ��ԗǂ������ł�(�ł�GPS���K�[�Ə���d���卷�Ȃ�������E�E�E(��)) �@���܂ɂ����g�p���Ȃ�FM���W�I�Ɏg�p����ɂ͌����Ȃ��ł����ǁB jr7cwk �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�d�r�̏����` BOX 1 �`�@�����������q�����܂����B �@�킴�킴�������Ă��������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B �@������������m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���̂��A�u�v�Ȃ̂��u�s�����v�Ȃ̂��E�E�E �@��͂胍�K�[���~�����Ȃ�܂��B �@����ƁA�ȈՓI�ȓ�����R�̑��肭�炢�͂��˂Ǝv���Ă���܂��B(�����דd���ƁA��d���ł̏[�d�܂��͕��d���̓d����r��) �@������Ƃ���������������ۑ肪�R�������Ă��܂����B(��) jr7cwk �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@NC-M58��BQ-390�ŕЕ����[�d�ł��Ȃ��Ȃ������_�ŁA�����Q�{�g�p���̓d�r�Ȃ痼���Ƃ����Ȃ�������s�������Ă���̂͊ԈႢ�����Ǝv���܂��B �@�����܂Ŏ��̎茳�̓d�r�ł́A�����Ȃ������_�ł́u�s�����v�Ƃ����\���͂܂�����܂���B �@�����Ԃ̋x�~�������킯�ł͂Ȃ�����I�Ɏg�p���Ă���d�r���ƕs�����ɂȂ闝�R���������ƁB �@����������̎����Ŗ�\������A�����Ė��[�d�ƕ��d��ł̊��S���d���J��Ԃ��āu���t���b�V���v���\����s�����ɂ��ւ�炸�A�d�r�̏�Ԃɕω��͖��������Ƃ������B(HP�Ō��J���Ă���O���t�͎����f�[�^�̂ق�̈ꕔ�ł�) �@�����s�����ł���A���ꂾ���A�����Ė��[�d�Ɗ��S���d���J��Ԃ��Ί���������Ă����Ɨe�ʂ�d�����オ��ł��傤���A�茳�̓d�r�ł͂��̂悤�Ȓ���͌��ꂸ�e�X�g����ʂ��Ď����������d�r�̏Ǐ��悵�Ă��܂��B �@�F����̂��茳�Œ����ԕ��u���Ă����d�r���Z���Ԃ����g�p�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł���A����͕s�����Ƃ�������������ł��傤���A�����A���g�p���Ă���d�r�Ŏg�p���Ԃ��Z���Ȃ�����A���ʎg�p�Ōp�������[�d���Ă���Ȃ�u�������[���ʁv�Ŏg�p���Ԃ��Z���Ȃ��Ă���(����̓��t���b�V���ʼnł���)�A�d�r��(�܂��͂���ɂ��Ȃ�߂�)�܂Ŏg�p���ď[�d���Ă���̂Ȃ����������(�͕s�\)�Ǝv���Ă��ǂ��ł��傤�B �@���d��ƃf�[�^���K�[������ΒN�ł��ȒP�ɓd�r�̏�ԂׂāA�V�i�̎�����ǂꂭ�炢���\�����������̂���r���ł���ł��傤���A�������������Ă����Ȃ��ł��傤����@��ł̎g�p�\���Ԃ̋L�^��V�i���ɂƂ��Ă����āA���ꂩ��ǂꂭ�炢�Z���Ȃ��������r���邾���ł��d�r�̃R���f�B�V������m�邱�Ƃ͂ł��܂��ˁB�V�i�d�r������g�p�\���Ԃ̃���������Ă������Ƃ������߂��܂��B ���Ԏ� 2009/11/11
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ��ς݂̂͂��̎O�m2700�������Ɏ��ɂ܂��� | |||||||||||||
|
�@�T�����[��2700mAh NiMH�ł����c �@���H�̎��R���d�̏��Ȃ��^�C�v�������ˑR�����܂��� �@����̓}�����c��C701�i�قڎ�M�̂݁j�p�ɃG�l���[�v�ƌ��Ŏg���Ă��܂��� �@�d�������I�t�������p�[�d��Ń��t���b�V���|���ď[�d����100��Ǝg���Ă��܂����i����50�`60�炢�j �@�O��g�p��A�t���[�d���Ă����1�����ۑ��������̂��G�l���[�v����ɂȂ����̂œ���ւ��ēd��ON������30�������Ȃ������ɃV���b�g�_�E�� �@�[�d��̎c�ʐf�f�Łu�v�[�d�v�A���t���b�V���|�����10���قǂŕ��d�I���A�[�d�J�n����10�������Ȃ������ɏI�� �@���̎��_�Ŏc�ʐf�f�|����Ɓu�v�[�d�v�Ƃ����Ǐ�ł� �@3��قǂ�����J��Ԃ��܂������Ǐ�͌Œ肵�Ă��܂� �@�\�����ʂ艽�S����g����Ƃ͎v���Ă��܂��ǁA�����ȉߕ��d�����킯�ł��A������Ɋ��ɎN�����킯�ł��Ȃ��̂ɁA������ƍ����Ȃ��Ǝv���܂����� �̂�L �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����͎S���ł��ˁE�E�E�E���Ȃ��̎g�������B �@�܂��AC701�Ŏ����œd��OFF����܂Ŏg������A�[�d�r�͂قڊ��S���d��Ԃł��B �@���܂����S���d��Ԃ܂ŕ��d�����Ă���̂Ȃ�A�r���܂Ŏg���Ē��r�[�d���J��Ԃ��g�����ł͖����̂��������[�����͂قƂ�NjN����܂��A�����N�����Ƃ��Ă����S���d�̈ʒu�ł̃������[�ł����炻��ȏ�d�r���g����킯�ł͖����̂Ŏ��p��͖��͂���܂���B �@C701�Ŏ����œd����OFF�ɂȂ����d�r�́A���������ɂ��̂܂[�d��ŏ[�d����̂������ł��B �@����C701�ŏ�L�̒ʂ�g���I������炻�̂܂[�d���邱�Ƃ��J��Ԃ��āA�������[���ʂŎg�p���Ԃ��Z���Ȃ����Ɗ������烊�t���b�V�����ă������[���ʂ��������܂��B �@�Q�`�R�t���b�V���Ə[�d�E�@��ł̎g�p���J��Ԃ��Ă��������Ȃ��̂ł�����d�r�͎������߂Â��Ă��܂��B �@���āA�u�g�����疈�t���b�V���v�Ƃ����̂͏I�~�d���܂ŕ��d�������d�[�x100%���d�ł�����A�d�r�̎����������ւ�Z������g�p���@�ɂق��Ȃ�܂���B �@�j�b�P�����f�[�d�r�̎����́AJIS�����̂悤��������菭���������炢�g���ēr���ŏ[�d������g�����������ꍇ��500���1000��̎g�p�ł͗e�ʂ�60%�܂ʼn�����Ȃ��Ƃ������ɑ��肳��Ă��܂��B �@�����ăj�b�P�����f�[�d�r�̓�������A100%�܂ŕ��d���Ă���[�d����g��������������̒l�̐��Ԃ�̈���x�̏[�d�Ŏ��������܂��B �@�@��̓d�r�ꔻ��̐ݒ�d���ɂ����܂����A�I�~�d���ɂ����߂��d���Ŏ�����~����悤�ȋ@��Ŗ���d�r��܂Ŏg���Ƃ����ւ�����ɂ͈����A�����d�r������Ă��܂��܂��B �@�t��JIS�����̂悤�Ȕ����ȏ�̎g�p�������ɁA���������g������Ԃŏ[�d������Ώ[�d�͔���I�ɐL�т܂��B�d�r�̓�����������Ō����ΐ����`�ꖜ��ȏ�̏[�d���ł��܂��B����g���e�ʂ͏��Ȃ��ł����A�����������g����Ό��ʓI�ɓd�r���R�g�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@�j�b�P�����f�[�d�r�͂ł��邾���I�~�d���܂ł̊��S���d�܂Ŏg���̂ł͂Ȃ��A�����ڂɏ[�d�����ق��������Ǝ��������т�̂ł��B �@���Ă����P�B �@C701�œd�������܂Ŏg���āA���̌�ɏ[�d��̃��t���b�V���@�\�Ŗ��t���b�V��������E�E�E�B �@���Ɋ��S���d�߂��܂Ŏg���Ă���̂œd�r�̒��ɂ͓d�C�͂قƂ�ǎc���Ă��܂���B �@�����烊�t���b�V�����Ă����t���b�V�����d�����Ă��鎞�Ԃ��Z���A�d�r�ɂ̓_���[�W��^���Ȃ��ƍl�����邩������܂���B �@�������A�j�b�P�����f�[�d�r�̂悤�ȏ[�d���̓d�r�̏ꍇ�A���d���ēd�r�̒��̃v���X�ƃ}�C�i�X�̓d�ɂ̊Ԃ̓d��(�d�ʍ�)���������Ȃ�ƁA�u�d�r�Ƃ��ċ@�\����ׂ̐��\���}���Ɏ������v�Ƃ�������������܂��B �@�قƂ�NJ��S���d���Ă���d�r�����t���b�V�����d����ƁA�[�d��̃��t���b�V�����d�@�\�͂������ēd���𗬂��܂��炩�Ȃ�������ƕ��d����A���Ȃ��Ƃ͂����قڏI�~�d���߂��̒�d�������t���b�V�����̎��Ԃ����Ƒ����āA���̊Ԃ͓d�r�̓d�ɂ́u�ǂ������Ă��������v�Ƃ�����Ԃɒu����܂��B �@����ȓd�r�C�W����J��Ԃ��Ă�����AJIS���l��500���10�Ԃ�̈���x�Ŏg���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��s�v�c�ł͂���܂���ˁB �@���Ƃ���Ȃ�A��Ј��̂`����Ƃa�����܂����B �@�`����͉�ЂŒ�����[���܂œ����A�d�����I����ăN�^�N�^�ɔ��Ē莞�ɑގЂ��ĉƂŗ[�т�H�ׂĕ��C�ɂ������Ă������薰�鐶�����J��Ԃ��܂����B�����đ傫�ȕa�C�����邱�Ƃ��������ώ����܂ōK���ɕ�炵�܂����B �@�Ƃ��낪�a����͒莞�ɂȂ��đ̂͂����N�^�N�^�ł��A�������狭���c�Ƃ������n����āA���͂��H�ׂ鎞�Ԃ��^����ꂸ�ɖ������_���ē|���܂œ������Â����܂����B �@���_����Ɠ����ɕ������ĉƂɑ���Ԃ���āA�Ƃł͂���Ƃ��͂�͐H�ׂ��܂��������ɓ��ɑ��������A�����Ƃ����܂ɉߘJ�����Ă��܂��܂����B �@�܂�Œ����̓z��̂悤�Ȉ����ł����B �@�����A�̂�L�l�̎g�����͂��̂a����̂悤�ɁA���̎g�p���Ԃ͏I����āA���������I����ĉ����Ă�����ׂ��d�r���A�X�Ƀ��`�ł��Ď��_����܂ŕ��d�����ăG�l���M�[�Ǝ������i��s�����A�ߘJ�������Ă��܂����̂Ɠ������ƂȂ̂ł��B �@�ߋ��ɉ��x�������Ă���悤�ɁA���t���b�V���͓d�r����������ȁH�Ǝv�������ɁA���ʂ�20�`30����x�̎g�p�Ɉ���s���悭�A����s������̓��t���b�V���ł͂Ȃ�������������ƂȂ�̂ł���B �@�J��Ԃ�1000��g����ƌ�����eneloop�ł����A�ߋ��ɋL���ɍڂ��Ă���悤��VR-120�Ŏ����œd�������Ƃ���܂Ŏg�������J��Ԃ���200����z���邠���肩�炩�Ȃ�}���ɗe�ʂ�ۑ����\���������Ă��܂��܂����B �@��500���̐��\�̎O�m2700mAh���A�����悤��VR-120��C-701�œd�������܂Ŏg���Ă��������Ȃ�100��O��͎g�����ł��傤�B �@����t���b�V���Ŏ��������炵�Ȃ���g���Ă����̂ł�����A�X�ɔ������x�Ɏg�p�\�����Ȃ��Ȃ��Ă������s�v�c�ł͂���܂���B �@�܂��O�m�̏[�d�r�͈����Ȃ�͂��߂����C�ɗ��i�݁A������Ԃ��Z�����߂��ˑR���̂悤�Ɍ����鐫��������悤�ł��B �@�u������ƍ����Ȃ��Ǝv���܂�����v�Ə�����Ă��܂����A�O�m��2700mAh�j�b�P�����f�[�d�r�����������̂ł͂Ȃ��A�g�����l�Ԃ̎d�ł��������̂ł��B ���Ԏ� 2009/10/16
|
||||||||||||
| ���e |
�@����͋M���̂悤�ɐ_�l�̂悤�Ȕ��w�������������炻��������̂ł��傤 �@��ʂ̗��p�҂ł����܂Ŕc�����Ă���l���ʂ����Ăǂꂾ������ł��傤���H �@�������������̂͂����Ȃ�ł����c �@�����m��Ȃ��l�������킩�炸�Ɏg���Ăǂ��Ȃ邩�Ƃ������Ƃł� �@���Ȃ݂ɑS�������悤�Ȏg���������Ă���}�N�Z���̃_�C�i�~�b�N1600��G�l���[�v�ł͓��e�̂悤�ȃg���u���͑S�������Ă��܂��� �@���̓d�r�Ɠ����l�ɂ�����2700���������Ƃ������Ƃł� �̂�L �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�������������̂͂����Ȃ�ł����c�v�ł����B �@�ŋߑ����Ȃ��Ă��܂����ˁB���╶�ł͏����Ă��Ȃ����Ƃ��u�������������̂́c�v�ƌォ�畢���l�B �@���╶�ɂ́u���������������v�����̒ʂ�̈Ӗ��ŏ�����Ă���ł��悤���B �@�}�N�Z��1600��G�l���[�v�͂܂��g���Ă���Ƃ����b�͂ǂ��ɏ�����Ă����̂ł��傤�B �@�������Ȃ����O���t�쐬�@�\���̕��d���f�[�^���K�[���������ł�����A���̃}�N�Z��1600��G�l���[�v����͂��Ă݂�Ƃǂꂾ�����i��ł��邩����Ɏ��悤�Ɍ����ł��悤�B �@���A�����������Ă��Ȃ��̂ł��������m�F���@�����Ȃ��ł��傤����A�d�r�̎������߂Â��Ă���̂��ǂ����͂킩�炸�Ɏg���Ă��邾�����Ǝv���܂��B �@�}�N�Z��1600��葁���O�m2700���ɂ�ł��܂����̂ɂ�����܂����A�����ŏ����Ă����Ȃ��ɂ́u����͋M���̂悤�ɐ_�l�̂悤�Ȕ��w�������������炻��������̂ł��傤�v�Ǝv���ďI���ł��傤�ˁB�����͏ȗ����܂��B �@�����m��Ȃ��l���g������ǂ��Ȃ邩�͏\���ɏ��m���Ă��܂����A�����ł����������Ă��E�E�E�Ƃ��������ł��B �@�Ȃ��Ȃ�A�����ł͊��ɂ��Ȃ葽���̎���ɓ����Ă��܂����A���̒��ɂ̓��t���b�V���̓������[���ʂ��N�����������s���悤�ɂ�������Ă��܂��B �@�ʂɉ�����ł����������Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA�̂�L�l�����ĊȒP�ɂ����̏��ɃA�N�Z�X���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�m��������B���Ă��āA�F����ɂ��������Ă��Ȃ��̂ł���Ύ��͂�����m���������Ă����̐l�ɂ͂����m�邱�Ƃ��o���Ȃ��̂Łu���Ȃ��͒m����������������v�Ƃ������_�͐��藧���܂����A�����ł͑����̏������J���ēd�r�ɑ��ċ^�₪�N�������͂����R�ɓǂ�ŕ����邱�Ƃ��ł��܂��B �@���t���b�V���̓������[���ʂ��N�����������s���Ă��������ˁA�Ə����Ă��鎄�ɑ��āu���t���b�V��������d�r���������܂����B�Ђǂ��d�r�ł��ˁI�v�ƌ����܂��Ă��A�ȑO������J���Ă��܂��ʂ�Ƀj�b�P�����f�[�d�r�̓����ƃ��t���b�V���̐����������ɂ��Ă��������邵������܂���B �@�����Ă��Ȃ��̕��͂ł́u�Ђǂ��d�r�ł����v�Ƃ��������ɏd�����u����Ă��܂�����A�j�b�P�����f�[�d�r�͂��������g����������Α�������Ă��܂��܂���B���R�͂����ł��B�������Ȃ��悤�ɂ悭�������Ďg���܂��傤�ˁA�Ə����ȊO�ɉ����ł��܂����H �@�u�}�N�Z��1600��G�l���[�v�͓����g�p���@�Ŏg���Ă����v�Ƃ������Ȃ��̂��茳�̏Ȃ�āA�����Ă��Ȃ������̐����͂ł��Ȃ��ł���H �@���낤���ăG�l���[�v�͎g���Ă���悤�ȋL�q������܂�������A�G�l���[�v�ł��[���d������Ύ��������ɒZ���Ȃ�Ƃ�������o�����Ƃ͂ł��܂����B �@�u�����ł��ˁ[�A�O�m2700�͍����d�r�ł��ˁ[�I�v�Ə����C�����ꂽ�̂ł��傤���B �@�啶���u�����ȉߕ��d�����킯�ł��A������Ɋ��ɎN�����킯�ł��Ȃ��̂ɁA������ƍ����Ȃ��Ǝv���܂������v�ł�������A����ɓ������ė~�������e���Ƃ͂킩��܂����A���̌������g�����̂ق��ɂ������͂��̂܂ܓ������āu�����d�r�ł����ˁ[�v�Ȃ�ď����܂���B �@��������ǂ̃��X�̎�ȓ��e���u���t���b�V�����d�r�𑁂��ɂ߂�Ȃ�Ēm��Ȃ������I�A���ʂ͒m��Ȃ����낤�I�v�ł���A����͂ǂ����O�m�d�@�̂��q�l�����ɑ��Ă��`�����������B �@�u���Ȃ��̃��[�J�[�̓d�r�E�[�d����Ă����g�������A�������ɂ�<���t���b�V�����Ă͂����Ȃ�>�Ƃ͏�����Ă��Ȃ������B���t���b�V�����d�r�ɗǂ��Ǝv���Ė��������̂ɁA���\����Ȃ��̂��H�v�ƁB �@�������g���ɂȂ�ꂽ�[�d�킪�O�m��NC-MR58�ł���A�������ɂ͂ǂ��ɂ��u���t���b�V���͖���s���Ă͂����܂����v�Ƃ͏�����Ă��܂���B �@���[�J�[�������Ă��Ȃ���ł�����A�_�l�̂悤�Ȕ��w�̎�����łȂ���Ζ��t���b�V�����s���Ă��ʂɂ��Ȃ��������ӔC�����K�v�͖����ł��ˁB �@���̌��ʂǂ��Ȃ������̐ӔC�́u�������ɏ����Ă��Ȃ����[�J�[�v�ɂ͂���ł��悤�B �@���Ȃ��Ƃ��u�C�̖����v�ł̓��t���b�V���̐������s�����͐������Ă��܂�����A�_�l�̂悤�Ȕ��w�̎�����łȂ��Ă������ɗ���l�ł�������m�邱�Ƃ��ł��܂��B ���Ԏ� 2009/10/16
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �V�^�G�l���[�v | |||||||||||||
|
1500��J��Ԃ����p�ł���V�ueneloop�v http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/07/news016.html �����j���[�X�����܂����ˁB �T�C�N������(���̒l)��1.5�{��1500��ƁA�Ȃ�Ƃ��̃C�I���̃u�c���������Ȃ�܂����ˁc(��) ���ȕ��d���X�ɗ}�������悤�ŁA���s�́u2�N��ł������g����v����u3�N��ł��i���j�v�ɂȂ����悤�ł��B �d�l�̑啝�ȕύX�͏��߂Ă���Ȃ��ł����ˁH �u�����g������ԁv�̕ύX�͂���܂������A��������ƕ\�L�����ύX�����}�C�i�[�`�F���W���Ċ����ł������B �����c�{�ɂ̏o�����肪���Ȃ� �����c�{�ɂ̏o������̉��P�AR�}�[�N�t�� ��O���c�e�ʕ\�L��min.�l�݂̂ւ̕ύX�AR�}�[�N�̊D�F�� ��l���c�R�ێd�l�ɕύX�A�����g������Ԃ�2�N��ɕύX ��(���s)�G�l���[�v�ł́A����4�p�^�[���ł��������H ���͂Ƃ�����A�y���݂ł����A���������܂��Ƃ��B �ڗ� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��{�I�ɂ͉����傫���ς����Ƃ�����ۂ������ł��ˁB �@�J��Ԃ����������Ƃ����A���ꂪ�ʂ����Ď����ł�����̕ω��ł��邩�ǂ����A�u�J�^���O�X�y�b�N�v�����オ���Ă��Ď��g�p�ł́u�̊��v���ł��Ȃ��Ƃ��܂�Ӗ�������܂���B  �@�d�r�{�̂�eneloop���S�ɑ傫���ueneloop1500�v�݂����ȃf�U�C���ύX�ł���������悩�����̂ł����E�E�E�B
�@�d�r�{�̂�eneloop���S�ɑ傫���ueneloop1500�v�݂����ȃf�U�C���ύX�ł���������悩�����̂ł����E�E�E�B�@�ł�eneloop1500�ł�1500mAh�݂����ł��ˁA����ueneloop�~1.5�v���ȁH ���Ԏ� 2009/10/16
|
||||||||||||
| ���e 10/21 |
�ꉞ�A�d�r�{�̂ɂ͉������t���Ƃ̂��Ƃł����A���Y�n�\�L��Japan����Maid in Japan�ɕύX����邻���ł��B �e�J���Ƃ��������Ƃ��́A���s�̍R�ێd�l�ƍ��͂Ȃ������Ɍ����܂��ˁB (���J����Ă���ʐ^�͈̔͂ł�) �p�b�P�[�W�̃V�[�����ł�1500��\�L����Ԃ킩��₷���ł���ˁB (�w���ڈ��Ƃ��Ă͍œK) �C���[�W�Ƃ��ẮA�u1.5�{���炢���N�����̒������ȃG�l���[�v�v�ł��ˁB �ڗ� �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�V�^��eneloop�ł����A�����͂���܂����������c�B �@�C�̖����l����������Ă��鎎�����ʂ��炷��ƌ��ǂ̂Ƃ���[�x���d���J��Ԃ��Η͖Ƃꂸ�A�����Ȃ�ƈ�ʂ̐l���g�����ɂ�1500�낤��3000��[���d�\���낤�Ǝ����͎g��������ƂȂ�܂��B���̋L���̂�����ɂ��G����Ă����悤�ɁAJIS�����̂悤�Ȏg�����O��̘b�ƂȂ��Ă��܂����ߍ���̐V�^�͂��܂���҂��Ă��܂���B�J��[�x���d�ɋ����Ȃ����Ƃ����̂Ȃ犽�}�ł����A���[�J�[�Ƃ��Ă��̕ӂ̉��ǂ͓���̂����m��܂���ˁB Sail �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�V�^�G�l���[�v�̂��b���Ɋ��荞�ݎ��炵�܂��B �@�G�l���[�v�̒P2�^�����͒P4�^��4�{���ꂽ�����̑e���ȍ�肾�ƌ����Ռ��̎�������������܂����I �@�l�̃u���O�����ǁA ttp://arakawabatta.blog59.fc2.com/blog-entry-521.html �@�P1�^�͒P3��3�{���ꂽ�������낤�Ƃ����\�ł��B �@���̂悤�ȎG�ȓd�r���o���Ă���O�m�ɂ��Ė������͂ǂ����l���ł����H �@�܂����������w�����ĕ�����͂���\��͂���܂��H �ʂ肷���� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
Sail�l�B �@��b�I�Ȑ��\���A�b�v���Ă���̂́A��������̕����Ŏ���������҂ɂƂ��ėǂ��_��^���Ă����̂ł��傤���AJIS�����ł͂Ȃ����ʂ̎g�����Ȃǂł��ڂɌ����āu�V�^�͂����Ȃ��I�v�Ɗ�������قlj������ς���Ă���Ƃ����̂ł����E�E�E�B �ʂ肷����l�B �@���[��B�f���炵���\���I �@�P���P��T�C�Y�̋����{�f�B������̓d�r�\���̊������Y���C���݂��Ȃ��Ă��A�����̒P�O�E�P�l�������C���ŃZ���Y���ăp�b�P�[�W�����lj�����Ί�������Ƃ����u�����œd�r�v������Ă����Ƃ����J���N���ł����I�H �@�������ɃG�l���[�v�P��E�P��͔����Ă��Ȃ��̂ł����������ɂ͑S���C�t���܂���ł����B (�茳�ɂ���e-keep�̒P��E�P��͎����������ł͂���ȍ\���ł͖����悤�ł�) �@PTC�������Ă��đ�d���p�r�ɂ͎g���Ȃ��Ƃ������b�͎f���Ă����̂ł����A���ꂾ���ł͂Ȃ��P��E�P��T�C�Y�Ƃ����������\���œ�����R�����Ȃ����đ�d���ɂ��g����Ƃ����傫�ȃT�C�Y�̓d�r�����������Ă��Ȃ������Ƃ́E�E�E�B �@�������ᓙ�Ń��[�^�[��~���̂��N�������̂��Ƃ��l����A�T�C�Y�ɉ�������d���𗬂���悤�ɂ��Ă����K�v�������Ɣ��f������ŁA�P��E�P��T�C�Y���o�������d�r�s��̃V�F�A��D���������\�Z�̖����O�m�d�@��������ꔭ�t�]�̔��z�Ȃ̂�������܂���ˁB �@�H������Ŏg�p����R�u�d�r��A�X�u��006P�d�r�̂悤�ɍ����d�����K�v�Ȃ̂Œ��ɕ����̃Z��������ɓ����Ă���Ƃ����p�^�[���͐̂���悭���܂������A�P���P��̒��ɂ��̂悤�ɏ��^�̓d�r�����������Ă���Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ��������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/10/22
|
||||||||||||
| ���e 10/27 |
���P2�^�G�l���[�v �@�u�e���v�Ƃ��u�G�v�Ƃ����\�������Ɉ���������܂����B �@�d�r�Ԃ̓����̂����������x�}���鎖���o���Ă��Ȃ���A�s�̗̂ʎY�d�r�ł���ȍ\���͎��Ȃ��Ǝ��͎v���̂ł����E�E�E (�ł����������̋������ǂ�ȋ�ɂȂ�̂��E�E�E������ƋC�ɂ͂Ȃ�܂��B) jr7cwk �l
|
||||||||||||
| ���e 11/23 |
�@�V�^�G�l���[�v�̃J���[�o�[�W���������ʌ����12��1���ɔ������邻���ł��B���I�ɂ͂����炪�~�����ł��ˁ[�B http://jp.sanyo.com/eneloop/lineup/tones.html �t�]�B �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d�r���M���Ȃ�[�d����t�@���ŗ�₵�Ă��܂��A���v�ł��傤���H | |||||||||||||
|
�y�����ǂ܂����đՂ��đ�ϕ��ɂȂ�܂��B���ݏ[�d���SONY�̉t���\���t��BCG-34HRMES���g�p���d�r�͒P3�T�����[�G�l���[�v�ƒP3�p�i�\�j�b�NHHR-3SPS��2230mah���g�p���Ă��܂��B�[�d��������p�i�\�j�b�N�͐G��Ȃ����O�ʔM���A�T�����[�͏����g�������x�ł��ǂ��������Ő���Ȃ̂ł��傤���H���[�d�킪�M���Ȃ�̂Œ�ʂ���t�@���ŗ�p���Ă��܂��B����ƈ��ʊW�͗L��̂ł��傤���H�[�d��{�̂��p���邱�Ƃŏ[�d�������ς�邱�Ƃ͂���܂��H��낵�����肢�v���܂��B �������蔪���q �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�d�r���G��Ȃ����炢�ɔM���Ȃ�v�Ƃ������ɂ��܂��ẮA�w�[�d���̓d�r�̕��������M�x�Ő������Ă��܂��̂ł��ǂ݂��������B �@�d�r�̓����ł��锭�M���x���z���č����ɂȂ��Ă���Έُ�ł����A�����łȂ��ꍇ(�[�d�킪����ƔF�߂Ă���͈�)�Ȃ�ΐ���ł��B �@�܂��Â��d�r�قǓ�����R���������ď[�d���ɂ͔��M���܂��B �@HHR-3SPS�Ƃ����ƍ��ł͂قƂ�ǓX���ł͔̔����Ă��Ȃ������i�ł����A���������Ďg���Â��̓d�r�Ŕ�r�I�V�����i��eneloop�Ɣ�ׂāu�M���Ȃ�v�Ƌ��Ă͂��܂��H �@���āA��Łu�[�d�킪����ƔF�߂Ă���͈͂Ȃ�ΐ����v�Ə����܂������A�}���[�d��ɂ͂����Ă����x�Z���T�[�������Ă��ēd�r�̂������̕���(�[�d��{�̂̒�)�œd�r���x�𑪂��Ă��܂��B �@���̉��x�����[�J�[�̒�߂��댯���x�ɒB����ƈُ�ƔF�߂ď[�d���~������A��U��~���ė�߂Ă���܂��ĊJ����Ȃǂ̈��S���u�������܂��B �@�����d�r�Ɉُ킪�����Ċ댯�ȍ����ɂȂ����Ƃ��āA�[�d����t�@���ŗ�₵�Ă��̈��S���u�������Ȃ�������H �@�d�r���댯�ȏ�Ԃł��[�d�𑱂��āA�d�r��ɂ߂�A�܂��͍ň��̏ꍇ�j��Ȃǂ̊댯�Ȏ��̂��N�����Ă��܂��܂��B �@�ł��邾���[�d��͌��̐v�̂܂܂ŁA�t�@���������蕪�����ċ�C��ʂ��悤�ȉ����͂�߂܂��傤�B �@BCG-34HRME��SONY���i�ł�����A�uSONY���i�͑��А��i���₽��ƔM�������ēd�C����R�H���I�v�Ƃ����̂͒N�ł��m���Ă���u�M�b�ASONY�I�v�Ȃ̂ő��v�ł��B����łȂ���SONY���i�Ƃ͌����܂���(��) �@�܂��A���̔M���̂������ő�����ꂽ�肷��̂ŁuSONY�^�C�}�[�����v�ȂǂƂ������Ă���킯�ł����B �@���d�r�^�C�v�̏[�d�r���[�d����[�d��̏ꍇ�A���ɏ����Ă̏ꍇ�͌��̎����������Ă���ɏ[�d���̔��M���v���X����Ċ댯���x�ɒB���Ă��܂��A�[�d�킪��������m���Ĉꎞ��~����Ƃ������͂����ł����x���m�F���Ă��܂��B����ȏꍇ�͓d�r�Ə[�d��ƑS�����@�ʼn������畗�𑗂��ė�₵�Ă����x�ł��イ�Ԃ�ł��B�Ԉ���Ă���������Ƃ����ď[�d��̃t�^���J���Ē��ɋ�C���ʂ�悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ł��������B �@�t�@�����g���ɂ��Ă��A�T�C�o�[�M�K�O�P�̋L���ɂ�����܂��悤�ɁA�d�r��K�v�ȏ�ɗ�₷�Ƃ���ǂ����[�d�������o�Ȃ��^���o�ł��Ȃ��Ŗ��[�d��������Ə[�d�𑱂��ēd�r�Ƀ_���[�W��^����ꍇ������A�d�r���₵������̂����ł��B ���Ԏ� 2009/9/19
|
||||||||||||
| ���e |
��ϖ��m�ȉL�������܂����A���[�J�[�̐v�͒ʏ�̎g�p�Ő��퓮�삷��悤�ɐv����Ă����ŋ�����p�͂����Ȃ����Ƃ�����FAN�͉����R��p�ɂ��܂����A�������M�@SONY�͕|���ł��ˁA�m���ɍ��܂Ŏg�p���Ă���SONY���i�͒Z���Ԃʼn�ꂽ�����w�ǂł��ꂩ���SONY���i�͔���Ȃ��ƐS�ɐ������̂ł����A�@�\�ʂŎ��ɍ����������ꂵ�����������̂ŋ��������w�����܂����A�i���t���b�V���@�\�A�d�r�c�ʕ\���A�[�d�i�s�A���̑S�Ă������ɌʂŊm�F�o���镨�j���������邩����܂����Ђ������@�\�̐��i���o���܂ʼn䖝���Ďg�p���čs���܂��B�B���SONY�ɑ��锽�R�Ƃ���SONY�̃��S�̏ォ��SANYO�̕����̃e�v���V�[����\��t���ꌩSANYO���Ɍ�����悤�ɂ��Ďg�p���Ă��܂��B���̓x�͑�ϑf�������ɗL�������܂����A���ꂩ�����낵�����肢�v���܂��B
�������蔪���q �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�P�O�E�P�l�S�{�}���[�d��ŁA�t���\�����t���Ă��āA���t���b�V���@�\�����ځB �@���̏�������SONY���ȊO��JTT�́uMy Charger View�v������܂��ˁB �@���̒m�����ߏ��̓d�C�X��z�[���Z���^�[���ł͎������������Ƃ������̂ŁA�l�b�g�ʔ̂��ǂ��������Ă���X��T���Ȃ��Ɠ��荢��i��������܂��ASONY���i�ȊO�łS�{�E�t���E���t���b�V���Ƃ����������Ɠ��{�����ł͂��ꂭ�炢�ł��傤���B �@���A�������u�T�C�o�[�M�K�O�P�v���S�{�E�t���E���t���b�V���ɂ͊Y�����܂����A��ʗp�ł͖����̂Ń��W�R���p�r�̃}�j�A�̕��ȊO�ɂ͂����߂����˂܂��B ���Ԏ� 2009/9/23
|
||||||||||||
| ���e |
�L�������܂��B���̏[�d���SONY���Ƃ͌�������������Ŗܑ̖����̂ʼn�ꂽ�甃�������鎖�ɒv���܂��B�Ԃł��g�p�o����̂ŕ֗��ł��ˁA�����b�ɂȂ�܂����B �������蔪���q �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�\�j�[�^�C�}�[���������Ȃ����Ƃ����F�肵�Ă��܂��I�i�O�O�G ���Ԏ� 2009/9/27
|
||||||||||||
| ���e 10/21 |
��������Ԉ��p���Ă���̂̓L�����^���i�N�C�b�N�G�R�j�Ȃ̂ł����A���̎��Ɉ��p���Ă���̂�BCG-34HRES�ł��B(�����b�g�����Ƃ������̂ŁA�����ɂ͌^�Ԃ͈Ⴂ�܂���) My Charger View�������Ă��܂����A�P3�ƒP4�ŏ[�d(���d)�d����ς��Ă��Ȃ��̂ŁA�P3�̏[�d(���d)�����Ȃ蒷���Ȃ��Ă��܂��܂��B ���P3�̏ꍇ�c1�`2�{���w��160�� (2����40��)�x�@3�`4�{���w��310�� (5����10��)�x ���P4�̏ꍇ�c1�`2�{���w��70�� (1����10��)�x�@3�`4�{���w��140�� (2����20��)�x �@�������d�r����̏�Ԃ���[�d�����ꍇ ���P3�̏ꍇ�c1�`2�{���w��690�� (11����30��)�x�@3�`4�{���w��1,380�� (23����)�x ���P4�̏ꍇ�c1�`2�{���w��300�� (5����)�x 3�`4�{���w��600�� (10����)�x �@�������d�r�[�d�̏�Ԃ�����d�����ꍇ �ƁA����Ȋ����ł��B http://kumarimu.jugem.jp/?cid=20 ������̕��ŁA�ȒP�ȃ��r���[�����Ă��܂��B �[�d����d���̗l�q������Ō�����Ă��܂��B �@���̏�d�r�̃G���[�\��������܂��B(���d�r�ő�p) �ڗ� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �H���d�q�̏[�d��L�b�g������������M���Ȃ�܂� | |||||||||||||
|
�H���d�q�̏[�d��L�b�g���w�����A�[�d�Ώۉ��d�r�i12V35AH�j���[�d���悤�ƃp���g��2N3055���_�[�����g���ڑ������̂ł����AR7�ƃu���b�W�����킪���ɔM���Ȃ�܂��B�ڑ��ɊԈႢ�͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��������Ԉ���Ă���̂ł��傤���B��낵�����肢���܂��B higenice �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͂��߂ɁA�Ȃ��H���̃L�b�g�̓��쎿����H���ɂ����Ɏ��ɂ���̂ł����H �@�H���Ȃ�d�b�ԍ���e�`�w�ԍ������J����Ă��܂�����A�����Ɏ��₷������Ǝv���̂ł����A�ǂ����ă��[�J�[�T�|�[�g�ɘA�������Ɏ��Ƃ����l�Ɏ��₳���̂�����ł��B �@�܂�͎��̐������Ԃ�����Ă܂ŏH�����i�̃T�|�[�g�����������Ƃ����C�^�Y���ł��ˁB �@�u�H���d�q�̏[�d��L�b�g�v�ƌ����Ă��F�X�Ɣ����Ă��܂�����A���ꂾ���ł͂ǂ̃L�b�g�Ȃ̂��͂����肵�܂���B �@�^�Ԃ▼�O������ł��傤�ɁA�Ȃ�����������Ȃ��̂��Ƃ����̂���ł��B �@�܂�͎��̐������Ԃ�����Ă܂ŏH���̐��i�ꗗ�ׂāA�ǂ̃L�b�g�����肹��Ƃ��������ł��ˁB �@�H���̏��i�ꗗ���瑽���u���~�d�r�[�d��p�[�c�L�b�g K-00074�v���Ɛ������܂������A����ō����Ă���ł��傤���H �@�Ԉ���Ă�����A���̌�����Ƃ͑S�ēk�J�ł��ˁB �@�u���~�d�r�[�d��p�[�c�L�b�g�v�͂�����̍�i�ł͂���܂����H���l�����킯�ł�����܂��A�H���d�q�ōw�����Ď莝���ł���킯�ł�����܂���B �@���������Ă킴�킴�ʔ̂Ŕ��킹�Ē��g���m�F����Ƃ������ł��傤���H �@�������������ł���A���ɉ�H�}��������Ȃ�Ȃ�Ȃ肵�Ē��g���m�F�����Ē����Ȃ��Ƃ��ꂪ�ǂ�ȉ�H�łǂ�ȕ��i���g���Ă���̂��킩��܂���B�܂��Ă₻�̏�ԂŁuR7���v�ƌ����܂��Ă�����R7���ǂ�Ȓ�R�Ȃ̂��A���Ɏg���Ă���̂��������������Ȃ��ƁA���\�͎҂ł��������肻��Ȑ����ł͂��ꂪ�Ȃ��M���Ȃ�̂��𐳂��������͂ł��Ȃ��ł��傤�B �@�܂�͎��̐������Ԃ�����Ă܂ŏH���̐��i�̉�H�}�ׂ�R7���������肹��Ƃ����A�d�ł��ˁB �@���͒��\�͎͂g���܂���A�����ɃC���^�[�l�b�g�Ƃ����֗��ȕ��Ɓu���ԁv�Ƃ����N�����������Ă��āA�g������A���Ă͗��Ȃ��M�d�ȕ����g���Ē��ׂĂ݂܂����B �@R7�͏[�d����pIC 723�̓d���Z���X�p��R�̂悤�ł��ˁB �@�L�b�g�ɂ�5��5W��1��5W�̂Q�{�������Ă��āA�g�p�ړI�ɂ��킹�čD���Ȃق�������悤�ɂȂ��Ă���悤�ł��B �@�d���𑽂����������ꍇ��2N3055�����_�[�����g���ڑ���������|�̐���������܂��ˁB �@�u�[�d�Ώۉ��d�r�i12V35AH�j���[�d���悤���v�Ƌ��Ă��܂����A���̃L�b�g��20Ah�̉��o�b�e���[�܂��Ɛ�������Ă��܂����A����Ȃ̂������ȏ���35Ah�̃o�b�e���[���[�d���悤�Ƃ���Ă���킯�ł����H �@�������z����o�b�e���[���[�d���悤�Ƃ���Ȃ�A�p���[�g�����W�X�^�𑝂₷�����ł͂��߂��Ǝv���̂ł����E�E�E�B �@���݂ǂ̂悤�ȓd���ݒ�ł��g���ɂȂ��Ă��邩���S�R������Ă��܂���̂ŁA�z�������Řb��i�߂܂��B �� �����ȓ��Ŏg���Ă��� �@���̃L�b�g�̑Ή��ő�e�ʂ�20Ah�Ŏg�p���邽�߁A�[�d�d���͍ő�l��2A�܂ł����{�����[�����߂��Ă��Ȃ��āA�ő�2A�Ŏg�p���Ă���ꍇ�B �@R7�́u6Ah�`10Ah(20Ah)��1���v�̐����ʂ�1��5W�̃Z�����g��R���Ƃ���Ă���Ǝv���܂��B �@�d�����m(�ő�d���̕ی�p)��R�ł�����A�����ɏ[�d�d���͑S�������̂ōő�[�d�d����R7�ʉߓd���ł���͉̂�H�}�̓ǂ߂���Ȃ炷���ɕ�����Ǝv���܂��B���ɏ[�d�d���������o�H�͖����̂ł�����B �@��͓d�C��H�̊�b���̊�b�́u�I�[���̖@�� V=R�EA�v�����m���Ă���A�ő�d���ŏ[�d���鎞��R7�̗��[�d���ƁA���̌���R7��������d���̌v�Z�͗e�Ղł��B �@�d����2A�Œ�R�l��1���Ȃ� V �� 1�� �~ 2A �� 2V�ɂȂ�܂���ˁB �@�d����2V�œd����2A�����ƁA�d���� W �� V �~ A�̎��ɂ��Ă͂߂� W �� 2V �~ 2A�� 4W�ɂȂ�܂��B �@�Z�����g��R�̂Ƃ����4W�̓d�͂��S���M�ɕς����̂ł�����A5W��R�̑傫���ł̓`���`���ɔM���Ȃ��Ă����ւ�Ȃ��ƂɂȂ�ł��傤�B �@�ꉞ��5W�̒�i���Ȃ̂ŃZ�����g��R���Ă����ꂽ�芄�ꂽ��͂��Ȃ��Ǝv���܂����A���̏[�d��̂悤��12���Ԓ��x���d���𗬂�������p�r�ł͂��܂�������g�����ł͂���܂���B �@��i�̔������x�Ŏg�p����̂����z�ł�����A4W�Ŏg�p����Ȃ���i10W�̃Z�����g��R���g�p���ׂ��ł��B �@�����Ă��Ƃ�10W�̃Z�����g��R���g�p���Ă��A��R���̂̑̐ς������ċ������_�Ō���Β�R�̕\�ʉ��x�͒Ⴍ�Ȃ�܂����A�����ԂŌ����4W�̔M����ɏo�Ă���̂Œ�R����͂ɔ��U�����M�ʂ͑����A�Z�����g��R����ɒ��t�����Ă���悤�ȏꍇ�ł͔M�Ŋ�����đ����ɂތ����ɂȂ�����ƁA���M�������Ȃ�g�����ł͕��i�̂Ƃ�����@��z�����@�ɂ����ӂ��āA�������Ƃ���Ȃ���Ȃ�܂���B �@���������v�Z�����ĕ��i��I��E����������@�́u�g�p�҂����R�����Ōv�Z�ł��邱�Ɓv�Ƃ��Đ������ɏ����Ȃ��̂��H���̗��V�ł��B �@�ƌ������A�قƂ�ǂ̓d�q�L�b�g�ł͍ŏ���������Ă��镔�i�ʼn�H�}�ʂ�ɑg�ݗ��Ă�"�ȊO�̉���"�͉����Ҏ��M�Ŋm���ɐv�l���v�Z�E�����čs�����̂ŁA�����łȂ��l�͉������Ă͂����܂���B(���Ă������ł����A�����N�����Ă����ȐӔC��) �@�u���b�W������͒��ɃV���R���_�C�I�[�h���S�����Ă��܂����A�����ł��V���R���_�C�I�[�h���������d���~���̂������ŗ��[�d�����������A�����d���~�d���Ԃ�̓d�͑����̔M���������܂��B �@�[�d�d���𑽂�������u���b�W��������M�����͓̂��R�̂��Ƃł��B �� �������z���Ďg���Ă��� �@�u�g�����W�X�^���lj��������A35Ah�̃o�b���e�[�Ȃ̂Ő������̒ʂ�~0.1����3.5A�ŏ[�d���I�v�Ƃ������ȒP���Ȕ��z�ŁA3.5A���̑�d���Ŏg�p���Ă�Ƃ��A���̂������g�����������ꍇ�B �@�v�Z���͏Ȃ��܂����AR7�ł�12.25W���̏���d�͂ɂȂ�A�L�b�g�t����1��5W�Z�����g��R�ł͂ƂĂ��ς����Ȃ����M�ɂȂ�ł��傤�B �@���Ȃ��Ƃ�20W�N���X�̃Z�����g��R�ƁA����痣���Ĉ��S���m�ۂ���K�v������܂��B �@�u���b�W����������Ȃ�̔��M�ɂȂ��ē��R�ł��B �@�L�b�g�t���̂��̂�4A�i���炢�̂悤�Ȃ̂ŁA�������8A�`10A�i�ɕς���Ȃǂ̑K�v�ł��B �@�Ȃ����̃L�b�g�̐������Ɂu�ő�20Ah�̃o�b�e���[�܂�(��{��10Ah�܂łƂ���Ă���)�v�Ə�����Ă���̂����킩��܂������H �@20Ah�̃o�b���e�[�p��2A�̏[�d�d���ɂ����ꍇ�A�L�b�g�ɕt����1��5W��R����i�����肬��ŁA����ȏ�̓d���𗬂��Β�i���z���Ă��܂��A�g�p�ɂ���Ă͂Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ������N�����\�������邩��ł��B �@�Z�����g��R�̒�i���g�p��A�t���̕��M��̑傫�����炱�̃L�b�g�͊�{�I�ɂ́u10Ah�̃o�b���[�܂Łv�Ƃ���Ă��܂��B �@�u�g�����W�X�^��lj�����Ƒ�d���ł��g����v�Ƃ͏�����Ă��܂����A�L�b�g���̂܂܂̕��i�ł͌��E�͂���ł��悤�B �@���������v�Z�����ĕ��i��I��E����������@�́u�g�p�҂����R�����Ōv�Z�ł��邱�Ɓv�Ƃ��Đ������ɏ����Ȃ��̂��H���̗��V�ł��B �@�ƌ������A�قƂ�ǂ̓d�q�L�b�g�ł͍ŏ���������Ă��镔�i�ʼn�H�}�ʂ�ɑg�ݗ��Ă�"�ȊO�̉���"�͉����Ҏ��M�Ŋm���ɐv�l���v�Z�E�����čs�����̂ŁA�����łȂ��l�͉������Ă͂����܂���B(���Ă������ł����A�����N�����Ă����ȐӔC��) �@��R��A��R�Ɏ��������̓d�q��H�ɓd���𗬂����ꍇ�A�d���̒l���Q�{�ɂȂ�Ə���d�͂͂S�{(�Q��)�ɂȂ�܂��B �@��R�ɓd���𗬂����ꍇ�̓d�͂̌v�Z�́A��ɏ������I�[���̖@���̎�������� W �� (R �~ A) �~ A �� W �� R �~ A^2 �ƂȂ�A��R�l�ɔ��A�d���l���Q��ɔ������Ƃ������Ƃ��v�Z���ŕ\����܂��B �@�����̉�H�̓d���𑝂₵�ăp���[�A�b�v�������ƍl���鎖�͑����ł��傤���A���̌��ʂ��̉�H�╔�i�ɂ͓d���𑝂₵���l(�䗦)�̂Q����̕��S��������Ƃ������͎��O�ɍl�����Đv��������s��Ȃ���Ȃ�܂���B �@���̏[�dIC 723���g�p������H�̏ꍇ�A2A�ȏ�̑傫�ȓd���ŏ[�d����ꍇ�͓d���Z���X��R�̒�R�l�������āA���M��}���Ă��K�Ȏg�p���ł����R�l��I�肷�ׂ��ł��ˁB �@�P���ɃZ�����g��R�̃��b�g�������傫�����Ė��ʂɔM���o������e�F����̂ƁA���̒�R�̕����Ŕ�������d���~���Ō��d��(�g�����X�H)�̓d�������イ�Ԃ��Ȃ��Ɨ\�肵�Ă����[�d�d���������Ȃ��Ȃǂ̕s����N���Ȃ����߂ɂ��A������������H�ɒ���ɓ����Ă����R�Ȃǂ͎��p�ł���͈͂̍ŏ��ɂȂ�悤�ɐv���ׂ��ł��B �@���̂�����̌v�Z���@�͍���͐������܂���̂ŁA�[�dIC 723���f�[�^�V�[�g�����ǂ݂ɂȂ�Ȃǂ��Ă������Ōv�Z�ł���悤�ɂȂ��Ă��������B �@���������v�Z�����ĕ��i��I��E����������@�́u�g�p�҂����R�����Ōv�Z�ł��邱�Ɓv�Ƃ��Đ������ɏ����Ȃ��̂��H���̗��V�ł��B �@�ƌ������A�قƂ�ǂ̓d�q�L�b�g�ł͍ŏ���������Ă��镔�i�ʼn�H�}�ʂ�ɑg�ݗ��Ă�"�ȊO�̉���"�͉����Ҏ��M�Ŋm���ɐv�l���v�Z�E�����čs�����̂ŁA�����łȂ��l�͉������Ă͂����܂���B(���Ă������ł����A�����N�����Ă����ȐӔC��) �@�������Ȃ��ƂȂ̂ŎO�x�����܂����B ���Ԏ� 2009/9/17
|
||||||||||||
| ���e |
�������炷��C�͑S������܂���A�����Ă݂ď��߂Ă����ł���˂ƌ����������ł��B���ɂ��݂܂���ł����B�����̖ړI�͎g��Ȃ��Ȃ����Ԃ̃J�[���W�I�ƃo�b�e���[���g�p���ċ��Ԃ�BGM�I�Ɏg�p���Ă��܂���(�ЊQ���ɒ�d���Ă��o�b�e���[������ǂ��Ǝv���Ďg�p���Ă��܂���)�B�������[�d����̂��ʓ|�ł����A�����ʼn��~�d�r�[�d��p�[�c�L�b�gK-00074���w�����ăt���[�e�B���O�[�d���o����Ȃ�Ε֗��Ǝv���Ďg�p���Ă݂܂����B����ƃL�b�g�Ɏg�p����Ă���g�����W�X�^�[��D1830�����M�ɂȂ肱��ł͂����Ȃ��Ɛ������̃p���[�g�����W�X�^�ɂ��Ă̗������āA�QN3055���w���A�ڑ������Ƃ���A���x�̓u���b�W�������R7�����M�ɂȂ�܂����̂Ŏg�p���邱�Ƃ��~�߂܂����B�ȏオ���Ƃ̎���ł��B�����ɐ�������ǂ����������ɂ܂��d�q��H�̂��Ƃ𗝉������ɖ��d�Ȃ��Ƃ����悤�Ƃ��Ă��������w�E�����Ȃ��Ă��܂��B���������肪�Ƃ��������܂����B����Ƃ����w����낵�����肢���܂� higenice �l
|
||||||||||||
| ���e |
���݂܂���ł����A����̃��[��(20:08)�����Ȃ��ō����E�ꂩ�炨�l�т̃��[���𑗂��Ă��܂��܂����B���[���ɂ���܂����悤�ɏ[�d���Ԃ͕ʂɖ₢�܂���̂ŁA���������Ȃ��āA�[�d�d���������ď[�d���Ԃ��������@�������Ē����Ȃ��ł��傤���A��낵�����肢���܂��B higenice �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����̓��e�̑O�ɔ���J�œ���������A����ɑ��āu�[�d���Ԃ͂����邪�A�H���L�b�g�{2N3055�̂܂܂Œ�i���Ŏg������ǂ��ł��傤�H�v�Ƃ�������Ă������Ē����܂����B �@���o�b�e���[�ł����A���̃L�b�g�ŕK��12���Ԃŏ[�d����K�v������Ƃ��A35Ah�̃o�b�e���[�͕K���~0.1��3.5A�ŏ[�d����K�v�����邩�Ƃ����ƑS�R����Ȃ��Ƃ͂���܂���B �@�H���̃L�b�g�t����1��5W��R�̂܂܂ł��ƍő��2A�����x(�ł�����1A���炢���]�܂���)�Ŏg���̂����E�ł�����A�p���[�g�����W�X�^�����₵�Ă���̂ōő�2A�Ŏg���悤�������Ă����u���[�d�܂Ŏ��Ԃ������邾���v�ōς݂܂���ˁB �@���Ԃ�������̂͂ǂꂭ�炢�ł��傤�B �@���̏[�d��̏ꍇ���o�b�e���[���[�d����̂ɓd���͗e�ʂ́~0.1�{�Ŏ��Ԃ�10�{�ł͂Ȃ�12�{�ƌv�Z���Ă��܂��B10�{�Ŗ����̂̓o�b�e���[�̏[�d�����̂��߂����������l�ɂȂ��Ă��܂��B �@35Ah�̃o�b�e���[��2A�ŏ[�d����ƒP���v�Z��17.5���ԁA�����1.2�`1.4�{�̎��Ԃ��|����21�`24���Ԕ���2A�[�d���̖��[�d�܂ŕK�v�Ȏ��ԂɂȂ�܂��B �@�ő�Ŋۈ��������܂����A�u12���Ԃŋ}���ŏ[�d���Ȃ��ƊԂɍ���Ȃ��I�v�Ƃ����悤�ȗp�r�Ŗ�������͋��e�ł���͈͂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�܂��A�L�����v�ȂǂɎ����čs���Ċ��S�ɋ�ɂ��Ă��܂����o�b�e���[���ł͖�������A�g�p�r���Ōp�������[�d����̂ł�����ꂾ���̎��Ԃ܂�܂邩����̂ł͂Ȃ��A�[�d����̂ɕK�v�ȂԂ��̎��Ԃōςނ͂��ł��B �@����̗p�r�̂悤�Ƀ��W�I�����炢�łقƂ�ǎg�p���Ȃ��ꍇ�́A�ŏ��Ɉ�x�[�d���鎞�ɂ���Ȃ�Ɏ��Ԃ��������Ă��A����͂ق�̏��������[�d���Ȃ��̂Ńt���ɓd���𗬂��ď[�d���鎞�Ԃ��Z�������Ƀg���N���[�d�Ɉڍs���܂��B �@�[�d�d������������@�͐������ɏ�����Ă���Ƃ���AR7�̗��[�̓d�����v��Ȃ���u�d����2A(�܂��͂���ȉ�)�ɂȂ�悤�{�����[�����v�Ō��\�ł��B �@�������ɂ���ʂ�ɂ���Ȃ�ɕ��d������Ԃ̃o�b�e���[���q���ŁA�e�X�^�[�Ōv��Ȃ��璲�߂��܂��B���[�d�▞�[�d�߂��̃o�b�e���[�ł̓g���N����ԂɂȂ��Đ������[�d�d���̒��߂��ł��܂���B�K�������g������Ԃ̃o�b�e���[���q���Œ��߂��Ă��������B ���Ԏ� 2009/9/19
|
||||||||||||
| ���e |
�@���肪�Ƃ��������܂����A��������Ă݂܂��B higenice �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�{�C�Łu�C�^�Y���v�u�����v�u�A�d�v�Ƃ͎v���Ă��܂���̂ŁA���l�ђv���܂��B �@�ŋ߂͂ǂ����b��[�܂��āA�ړI�̕����̈ꕔ�����������e�ŏ����Ȃ��l�������A������u�����ł͂���܂���v�Ƃ��A�u���͂����������Ɏg�����������̂ł����v�Ƃ��ォ���o�ė���l�����������Ă��܂��B �@�ŏ����炻�������Ă����Ă����A����ɍł��K�������@����o�����̂ɁA�ŏ��̓��e���e����ǂݎ�����e�ɑ��ĉ��Ă�����͎���҂̕��̈Ӑ}�Ƃ͑S�R������Ƃ������������Ȃ�܂����B �@�����̕����ڂ̑O�Ɍ����錻�ۂ݂̂ɒ��ڂ��āA���ꂾ��������Ă���悤�ł��B �@�����������Ɏg�����Ƃ��āA������Ă݂�����ǂ��܂������Ȃ��A�ǂ����Ăł��傤�H �@�Ƃ������Ȑ������ƌ�����Ή����e�Ղɒ͂߂܂���ˁB �@���ꂩ�瓊�e�������͂��Ђ����Ə������܂߂����e��S�����Ă��������B �@�u�C�^�Y���v�Ƃ��̏�k��ʂ�z���āA���͓d�C�̂ق��ł����Ɛ����l������܂����̂ŁE�E�E ���Ԏ� 2009/9/19
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d���H��̏[�d���ėp�̏[�d��Ƃ��Ďg���Ă݂��� | |||||||||||||
|
�R�[�h���X�d���H��̏[�d��ɂ��Ă������˂��܂��B�ėp�̏[�d��Ƃ��Ďg���Ă݂悤�ƍl���Ă���̂ł����A�d�l�̓��[�J�[�e�ЂňႢ�܂����A�d�ɂ���������A���̒��ɂ͒P���Ɂ{�A�|�̑��ɂr�C�k�d�C�k�r�Ȃǂ̕\���������ĉ��̂��Ƃ��A�悭�킩��܂���B�e�X�^�[�Ōv���Ă��A�v�����悤�ȓd���͂łĂ��܂���B�ǂ̂悤�ɗ�����������̂ł��傤���H �䂤���� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�r��k�d��k�r�Ƃ����[�q�̕t�����[�d��͌������Ƃ�����܂���̂ŁA���ꂪ�����͌��y�ł��܂���B �@��ʓI�ȁu�s�v�[�q�ł���A�T�[�~�X�^�[�q�ł��B �@�o�b�e���[�p�b�N�̒��ɉ��x�Z���T�[�ł���T�[�~�X�^�������Ă��āA�s�[�q�o�R�ŏ[�d���̃o�b�e���[���x�����m���āA�ُ킪�N���Ċ댯�ȍ����ɂȂ����玩���I�ɏ[�d���~����悤�ȓ������[�d�킪�����Ă��܂��B �@�T�[�~�X�^�������Ȃ�(���o�b�e���[�Ȃ�)���q���ł��[�d���n�܂�Ȃ��悤�ȉ�H�ɂȂ��Ă��镨�������ł��ˁB �@�䂤����l��������u�R�[�h���X�d���H��̏[�d��v����̉��p�̏[�d��ł���̂��S���킩��܂���A����ȏセ�̏[�d��̓�̒[�q�������͒��ׂ邱�Ƃ������ł��܂���B �@���Ƃ��A���`�E���C�I���o�b�e���[�p�Ŏg�p�o�b�e���[�d����7.2V�ȏ�ȂǕ����Z���ł���A���`�E���C�I���o�b�e���[�������Ȃ��ׂ̃o�����X�[�q�Ƃ��������l�����܂����A�p�\�R����f�W�^�����[�r�[���Ŏg�p���Ă���悤�ȃC���t�H���`�E���o�b�e���[�݂����Ƀo�b�e���[�p�b�N�̒��Ƀ}�C�R���`�b�v�������Ă��āA�o�b�e���[�g�p��������Ǘ����Ă��Ă�����O��(�[�d��)�ƒʐM����[�q�Ȃ̂�������܂���B �@�o�b�e���[�p�b�N�́{�Ɓ|�ȊO�̒[�q�ƌ����܂��Ă���R�̎�ނ�����܂�����A���ꂾ���̏��ł͂��ꂪ�����͓���ł��܂���B �@�u�ėp�̏[�d��v�ɂƂ������ł����A�����ȊO�ɂ��̏[�d��ŏ[�d�������o�b�e���[�͐��\�̌��E�Ȃǂ����̏[�d��̏[�d�\�͂�������Ă�����͂��Ȃ��̂ł��傤�ˁH �@�d���H��p�[�d��͂��̗��p�`�ԏ�A���ʂ̃o�b�e���[�p�̏[�d��ƈႢ�Z���Ԃŋ}���ɏ[�d����p�r�ɓ�������Ă�����̂��قƂ�ǂł��B �@���̒Z���ԏ[�d�p�̑�d���ȂǂɑΉ������o�b�e���[�łȂ���A�K��ȏ�̑�d���𗬂��Ă��܂����ƂɂȂ�A�o�b�e���[�̎�ނɂ���Ă͔���j��Ƃ��������l�����܂��B �@���������댯����̂��߂ɓƎ��̈��S��H�⌟�m��H���o�b�e���[�p�b�N�ɑg�ݍ���ł��郁�[�J�[������A�����������[�J�[�Ǝ��̌��o��H�p�̒[�q���t���Ă���Ƃ��l�����܂�����A�ȒP�Ɂu�d���H��p�[�d��v�Ƃ���������őS�Ẵ��[�J�[�E�@��p�̏[�d����ЂƂ܂Ƃ߂ɍl����킯�ɂ��䂫�܂���B �@���ꂼ��̌X�̏[�d�킪�ǂ̂悤�ȃ��W�b�N(������H����)�ŁA�ǂ̂悤�ȏ[�d�d���l�ŁA�ǂ̂悤�ɖ��[�d���m�����Ă���̂�����͂��Ē��g����������킩��Ȃ��ƁA�u�ėp�̏[�d��v�Ƃ��Ďg����㕨���ǂ��������킩��Ȃ��̂ł���B �@���g���m�F(���)���ď����ȊO�̃o�b�e���[�ɂ����S�ɏ[�d�ł���d�q��H�������Ă���Ɗm�F�ł����痬�p���Ă��\���܂��A�m�F�����Ȃ����̂͏����Ƃ̑g�ݍ��킹�ȊO�ɂ͎g��Ȃ��ق����悢�ł��傤�B ���Ԏ� 2009/9/10
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����̂����肪�Ƃ��������܂��B �@������e�ɏ���Ȃ����܂����悤�ŁA�\����܂���ł����B��������UC14YL�Ƃ����d���h�����̓d�r�p�b�N�p�}���[�d��ŁA7.2�`14.4V�i8A)�p�̂��̂ł��B �@�����ԗp�o�b�e���[�̋}���[�d��Ƃ��āA���邢�͎莝����Panasonic�̃h�����̓d�r�p�b�N�̏[�d�퓙�Ƃ��Ďg���Ȃ����ƍl���Ă���܂����B �@��H���m�F���邾���̋Z�ʂ�����܂���̂ŁA�N���ɏ��낤���ƍl���Ă��܂��B �@���S���ł�����ˁA��ώQ�l�ɂȂ�܂����B �䂤���� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��������UC14YL(������)�Ƃ����Ɠd���H��p�o�b�e���[�[�d��̒��ł����@�\�Ȃ��̂̂悤�ł��ˁB �@���`�E���C�I��/�j�b�P�����f/�j�J�h�ƂR��ނ̃o�b�e���[�p�b�N�ɑΉ����A�d����7.2V/9.6V/12V/14.4V���������ʂ��Ă����悤�ł��B �@LED�\�����c�莞�Ԃʂ��ĕ\������ȂǁA���Ȃ荂�x�ȏ[�d�Ǘ��p�̃}�C�R������������Ă���悤�ł����A��͂�l�b�N�̓o�b�e���[���������ސ�p�[�q�ł��傤���B �@�������܂ꂽ�o�b�e���[�����`�E���C�I���n�Ȃ̂��j�J�h/�j�b�P���n�Ȃ̂��͒P���ɓd�������邾���ł͔��ʂ����ɂ����̂ŁA��͂�[�q�̏ꏊ���Ⴄ������r��k�d��k�r�Ƃ����[�q�Ƀo�b�e���[�p�b�N���ʼn����q�����Ă��Ă���Ŕ��ʂ���̂ł��傤�B����͓����Ǝ��̎d�l�ł��傤������������ĉ�͂��Ȃ���Η��p�͓���Ǝv���܂��B �@�����ƃo�b�e���[�p�b�N�̉��x�𑪂��Ċ댯���������`�F�b�N�����Ă��܂�����(���}���[�d�ł͂�����܂��ł���)�A�����ԗp�o�b�e���[�̋}���[�d��Ƃ����Ȃ�Ă������x�Z���T�[�������Ȃ��o�b�e���[�ւ̏[�d�ɂ͂��̂܂܃v���X�ƃ}�C�i�X���q���������ł͎g�p�ł��Ȃ��ł��傤�B �@����ȑO�ɁA�[�d���W�b�N�����`�E���C�I��/�j�b�P�����f/�j�J�h�n��p�ɐv����Ă���[�d��ł����炱��������ԗp�Ȃǂ̉��o�b�e���[�Ɏg�p���邱�Ƃ͌��ւł��B �@Panasonic�ȂǑ��Ђ̓d���H��p�o�b�e���[�̏[�d�ɂȂ痬�p�ł������ł����A��͂�v���X�ƃ}�C�i�X�ȊO�̒[�q�łǂ̂悤�Ƀo�b�e���[�ʂ��Ă���̂����킩��Ȃ��ƁA���������o�b�e���[�ȊO�ւ̎g�p�͐���ɓ����Ȃ����댯�ł���Ǝv���܂��̂ŁA��͂ł��Ȃ��Ƃ������ŗ��p�͂�����߂�ꂽ�ق����ǂ��Ǝv���܂��B �@�u�莝���ŗ]���Ă���̂ŗ��p�������v�Ƃ������R�ȊO�Ɂu�ėp�̏[�d�킪�~�����v�Ƃ������R�ł���A���W�R���p�̏[�d��Ń��`�E��(���|)/�j�b�P�����f/�j�J�h/���o�b�e���[�ɑΉ����A�Z����(�d��)�����L���Ή�����ėp�̏[�d�킪�P���~����x���甄���Ă��܂��B �@����͗]���Ă��邩��Ƃ������ł��傤���炿����Ɖ����Ɉ��Ă��܂���������܂��A�ėp�����d��������͂�������������ėp�ɐv����Ă���[�d����w�����邱�Ƃ������߂��܂��B ���Ԏ� 2009/9/11
|
||||||||||||
| ���e 9/13 |
�@���J�Ȃ����܂��Ă��肪�Ƃ��������܂����B �@��ώQ�l�ɂȂ�܂����B �@���������܂Ń��P�h�i�H�j�������ɍς悤�ł��B �䂤���� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| SONY�t���t�}���[���d��Ŏ�����DLG�P�R�O�O�Ƃ��̊C�O���d�r�͏[�d�ł��܂����H | |||||||||||||
|
�@SONY�t���t�}���[���d��Ŏ�����DLG�P�R�O�O�Ƃ��̊C�O���d�r�͏[�d�ł��܂����H tgs �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@SONY�t���t�}���[���d��Ƃ�BCG-34HRME�ł��傤���A����Ƃ��O�����BCG-34HRMD�ł����H �@������ɂ��惁�[�J�[��SONY���̃o�b�e���[�ȊO�͂��̏[�d��ŏ[�d���邱�Ƃ��ւ��Ă��܂��B(���茳�ɂ����������ɏ����Ă��܂����) �@BCG-34HRME�ő��А��d�r���[�d����ꍇ�A������d�r���j���E�j��E���E�ЂʼnƂ��Ă����Ȃǂ̎��̂��N���Ă��S�āu���ȐӔC�v�ŁA�[�d�탁�[�J�[�E�d�r���[�J�[�̂ǂ���ɂ��ӔC����Ȃ��̂ł���s���Ă��\���܂���B �@�܂��A�u�C�̖����v�ŕ���������ȂǂƂ���������͒ʂ�܂��u�C�̖����v�͐ӔC���܂���̂ŁA�����܂ł������̔��f�ƐӔC�Łu����ėǂ��v�Ǝv������s���Ă��������B �@���Ђ̏[�d��ł���ȊO�̉�Ђ̓d�r���[�d����ꍇ�̒m���Ȃǂ́u�d�r�E�[�d��E�m�E�n�E�v�v�Ŋ��ɏq�ׂĂ���b���Q�l�ɂ��Ă��������B ���Ԏ� 2009/8/29
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| Ni-MH 3.6V 240mAh�p�̏[�d�� | |||||||||||||
|
�@�����������Ă���܂��B �@���Z�����Ƃ̎��Ŏ���͍T���Ă����̂ł����A�����Ē��������Ǝv���A����Ȃ��珑�����݂����Ē����܂��B �@����A�J�����𒆌Âōw�����܂����B �@���A�����d�r�iNi-cd�g�d�r�j�����Ղ��Ă���l�ŁA�t���b�V�����쓮���܂���B �@�[�d����Ȃ��̂Ŋm���Ȏ��͂킩��܂��A�o����ΐV�i�̓d�r�Ɍ����������Ǝv���Ă��܂��B �@�X�y�[�X�I�ɂ�VARTA��3/V250H�����肻���Ȃ̂ł����A�l�b�N�͏[�d��ł��B �@���\�l��3.6V��240mAh�Ȃ̂ł����A�����[�d����������ł����狳���Ē��������Ǝv���܂��B �@���́wNi-MH�p�[�d��̐���x�ɂ��āA�Q�l�����������Ē����܂�����K���ł��B �@���Z�����Ƃ͎v���܂����A�ǂ����X�������肢�v���܂��B Thief �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@3.6V��240mA�g�d�r�Ƃ����ƁA�����O�̋@��ł͂悭���ɓ����Ă����Ǝv���܂����A�����Ă��͋@��ɏ[�d��H���g�ݍ��܂�Ă��ċ@��ɓd���R�[�h���q���Ǝ����I�ɏ[�d����镨���قƂ�ǂ��Ǝv���܂��B �@�����������e�ʂ̑g�d�r���O���Ɏ��o���āA�u�[�d��v�Ɍq���Ƃ����̂͑������[�J�[�ł����s��Ȃ���ƂȂ̂ŁA�s�̕i�ł����������e�ʑg�d�r�ɑΉ������[�d��͒P�̂ł͍w������͓̂���ł��ˁB �@���������d���E�e�ʂ̃o�b�e���[���g���Ă��āA�O����AC�A�_�v�^�[�����̂܂[�d��ɂȂ��Ă���@�킪�����āA���̏[�d�킪�����œ���ł�������̂ł����E�E�E�B �@�e�Ղɍw���ł��Ȃ��ƂȂ�Ɛ��삷�邱�ƂɂȂ�̂ł����A�̂�Ni-Cd�g�d�r�ȂǗp�̏[�d��͂قƂ�ǂ��u����d���[�d��H�v�Ƃ���DC�d�������R����{����ɓ��ꂽ�����̂��̂����p����Ă��܂����B �@������R��{�ō���Ă������̂ł����E�E�E�E�����������͂��������}�V�ȕ��i������ł���̂ŁA������Ƃ�������(?)�ȉ�H�͂������ł��傤���H  �@10mA��CRD���Q�{����Ŗ�20mA�A��q��LED�ɗ����d���Ƃ��킹�ĕ�����22mA���x�ł��B �@�u��d���_�C�I�[�h�v�Ƃ͌����܂����A�w�K���W���X�gxxmA�ɓd����ۂx�Ƃ����f�q�ł�����܂���I �@�������d���ɂ�藬���d���l�͂킸���ɕω����܂��B(�ڂ����͊eCRD�̃f�[�^�V�[�g������������) �@�ł��̂ʼn�H��v���鎞�ɂ͈���d�����痬���d���l�ׂ���A�K�v�d���������d���ׂ���Ɩʓ|�Ȃ��Ƃ�����̂ł����A����̏ꍇ�́u�d���d����DC12V�v�u�q���d�r��Ni-MH�~�R�{�v�Ƃ������ƂŐv���Ă��܂��B �@�ʂɏ[�d���\���͖����ł������悤�ȏ[�d��ł����A�ꉞ���S�̂��߂ɏ[�d����\��LED�����Ă݂܂����B �@���܂�LED�ɑ�ʂɓd���𗬂��ƁA�F�X�ƁE�E�E���ɂ傲�ɂ�A�ǂ��Ȃ����Ƃ�����܂��̂ł����ł͂킸����mA���x�Ƃ��܂��B�ԐF�̍��P�xLED���g����Ώ\���Ȗ��邳�œ_�����܂��̂ŏ[�d�����킩��܂��B �@CRD�ň�艻���Ă���d���ƁALED�ɗ����d���̍��v�ŕ�����22mA�ł��B �@����d���[�d�ł́u0.1C��16���ԁv���x�Ƃ�������ȏ[�d���s���܂��B �@240mAh�̃o�b�e���[�ɑ���22mA�ł������0.09C�Ƃق�0.1C���炢�Ȃ̂ŁA�o�b�e���[�����S���d���Ă���ꍇ�͂��̏[�d��H��16�`18���Ԓ��x�[�d����Ζ��[�d�ɂȂ�v�Z�ł��ˁB �@������̉�H�ɂ͎�����~��H����S��H�Ȃ�Ă���܂���A�܂��o�b�e���[�ɓd�C���c���Ă���ꍇ�ɂ͓K�X�[�d���Ԃ�Z������ȂǁA�l�ԑ��ł̒��ӂ��K�v�ł��B ���Ԏ� 2009/8/28
|
||||||||||||
| ���e |
�@���Z�������A��H�}�܂ōڂ��Ē����܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B �@���̉�H���g���A�����̃��[���CA26���h��܂��B �@�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �@�������A�C�ɂȂ�̂́g�d���d����12V�ŗǂ��̂��H�h�Ƃ������ł��B �@3.6V�̏[�d�r�Ȃ�A�I���d����4.1V���x�ł���ˁH �@12V�i�h���b�v���Ă�10V�O��j����������A�Z���ԂŔj�܂��H Thief �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�Ȃ��d�r��12V(10V)��������̂�����ł��B �@����͓d�r���O���̂�Y��ĉ������A���\�����[�d�𑱂��邩��Ƃ������ł��傤���H �@�[�d���A�[�d�d����CRD�ɂ�萧������Ė�20mA�ŁA20mA�[�d������Ƃ��̂��炢�̗e�ʂ̃j�b�P�����f�[�d�r�̒[�q�d����1.4�`1.5V���x�ł���ˁH �@�R�{����̑g�d�r�ł�����p�b�P�[�W�̊O���̌�������̓d����4.2�`4.5V���x�A�d���d����12V�Ƃ̍���CRD�̃h���b�v�d���Ƃ��Č���Ă��̓d����7.5V�`7.8V���x��CRD�̓����Ƃ��Ď����I�ɒ��߂���܂��B �@���[�d�ɂȂ��Ă��d�r�͏���ɓd�C����Ă���Ȃ��̂ŁA���CRD�Ő�������Ă���20mA�O��̓d�������ꑱ���܂��B �@�d�r������ɓd�C����Ă����̂Ȃ玩����~���鍂�@�\�ȏ[�d��͕K�v�����킯�ŁA�����J�b�g���Ȃ��[�d��ł͓d�r�����[�d�ɂȂ��Ă��قړ����d����������ςȂ��ł��B �@���[�d�������20mA���x�̓d�������ꑱ�������A�j�b�P�����f�[�d�r�̒[�q�d���͂��Ȃ�̊��Ԃ�1.4�`1.6V���x���ێ����鐫��������̂ŁA�s�Ǔd�r�ȂǂłȂ������0.1C�[�d���x�łR�{�ł͂�����Ɩڂ𗣂�������4.8V���x���z���邱�Ƃ͂܂�����܂���B �@�����Ă��̊Ԃ�12V�Ƒg�d�r�̒[�q�d���̍���CRD�����̐����ɂ��z�����܂�����ACRD�̃h���b�v�d����7.2V���x�Ə[�d���ƂقƂ�Ǖς��܂��A���̓d����CRD���悤�ȍ��d���Ȃǂł͂Ȃ��̂ŁA�ǂ��l���Ă��d�r��12V(10V)��������Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����E�E�E�B(�ɒ[�ɉ����A���\�����d���𗬂�������Ƃ����b�ł͖�������c) �@�ߏ[�d��Ԃ������������A���̓d���t���͊�����Γd�r�̒��ɓd�C��~������u�d�C�𗬂��v���\�������A�����ڂ̒�R�l(������R)�������Ȃ��ē���20mA�𗬂���Ԃł��[�q�ԓd�����オ���Ă��܂��悤�ɂȂ�Ǝv���܂����A�����܂ł䂭�Ɗ��ɓd�r�Ƃ��Ďg�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ������ɕς��ʂĂĂ��܂��B �@���^�d�r�Ȃ���S�ق��t���Ă��ĉߏ[�d�Œ�����o���K�X�����o�����ł��傤���A�{�^���^�d�r�ł͂��̂悤�ȋ@�\���������������͂��ł�����A�������ߏ[�d����Ə�L�̂悤�ɒ[�q�ԓd���������Ȃ�ȑO�ɔj�Ă��܂��\��������܂��B �@����12V�̓d���Ƒg�d�r���R�����������Œ��ڌq�����琔�\�b�Ŕj�Ă��܂��ł��悤���A�[�d����̂ɓK�����d���ɐ������Ă���̂ɂ���ŒZ���ԂŔj��Ƃ�����A����͓d�r�Ƃ��Ă̓����������Ȃ��s�Ǔd�r�ł��B����ȓd�r�ł���A�K���[�d���Ԃ̐��{���x�܂łł���Ύア�[�d�d���ł͂����Ȃ�j���莀�S������͂��Ȃ��ł��傤�B �@�^�C�}�[�������Ȃ��A�u�X�C�b�`���̂�Y��ĉ������[�d�����ςȂ��ɂ��������v�Ƃ�����Ԃł���A�[�d�d����1/20C�`1/50C���x�܂ŏ��Ȃ�����(��mA��CRD��{�Ƃ�)�u�g���N���[�d�v��Ԃɂ��āA�Q���`�����ԏ[�d����Ƃ������@������܂��B �@�A���A�j�b�P�����f�[�d�r�͔���d���ł̃g���N���[�d�͂��Ȃ��悤�ɒ�߂��Ă��܂�����A�u�[�d�킪�����̂ōŏ��̂P���[�d�������v�Ƃ��̔��p�ŁA��x�[�d������@��ɓ���ċ@�킪���삵�āA�@��̏[�d��@�\�����삷��悤�ȁu�ŏ��͓����Ȃ��v�Ƃ����悤�ȓ���ȏꍇ�������ẮA�g���x�Ɏg�����Ԃ�[�d���J��Ԃ����ʂ̏[�d�r�̎g�����ł͂��Ȃ肨���߂ł��Ȃ��[�d���@�ł��B �@�e�ʂ̏����ȃK�X�����@�\�̖����d�r�ł���A�g���N���[�d���x�̔���d���ł̒����ԏ[�d�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂�����A�j�b�P�����f�[�d�r�͑S������[�d�֎~�Ƃ͌�����Ȃ��̂ŁA�g�p����d�r�̎d�l��(�f�[�^�V�[�g)�Ȃǂ���ɓ�����̓d�r�ɓK�����[�d���@��������Ă���Ǝv���̂ł���ɏ]���Ă��������B ���Ԏ� 2009/8/28
|
||||||||||||
| ���e 8/29 |
�@�Ȃ�قǁB����������ł������B �@������CRD�̓����𗝉����Ă��Ȃ������_�P�ł��ˁB���݂܂���B �@����ʼn��̋^����������ɁA���̉�H�ǂ���̃��m��g�ݗ��Ă��܂��B �@���Z�������A�ڂ������������Ē����܂��Ă��肪�Ƃ��������܂����B Thief �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �`���C����AC�A�_�v�^�[���q�� | |||||||||||||
|
�@��낵�����˂����������܂��B �@�l�p���XV�̓d�r�Ŗ�A�`���C���ɂ��Ăł����ADC�XV�Ƃ����Ă���A���������Ă��܂����A����ɁA�XV��DC�d���R�[�h���Ȃ���쓮����̂ł��傤���H �@9V�̕����Ȃ��ꍇ�́A���̕��A���Ƃ��A�V�D�TV�Ȃǂ͎g���܂����H ������ �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u9V�v�Ɖ��ɏ����Ă���A���̌��͊O���d���[�q�ł��傤����A������9V��AC�A�_�v�^�[���q���Γ��삵�܂��B �@AC�A�_�v�^�[���q���O���d���[�q�Ƃ����Ă��A�u�v���O�̃T�C�Y�v�Ɓu�d���v�u�ɐ��v�A������AC�A�_�v�^�[�́u�d���e���v������Ȃ��Ɠ��삵�܂��A�ň��͋@����Ă��܂��܂��B �@�u�v���O�̃T�C�Y�v�́A�v���O�̒��a������ނ���A�@��ɋĂ��錊(�\�P�b�g)�ɍ����T�C�Y�̃v���O�łȂ��Ƃ��܂��h����܂���B �@�̂̋@��Ȃ炽���Ă��́u2.1mm�v(�s���̑���2.1mm�A���a5.5mm)�Ƃ����K�i�̂��̂ō����܂����A�������̂Łu2.5mm�v��2mm���ׂ��u1.4mm�v�Ƃ������̂����݂��܂��B �@�܂��ŋ߂͍��ۓI�Ȋ���o���āA�d���ɂ��v���O�̒��a�����߂��Ă��܂��B�uEIAJ�v���O�v�ƌĂ�Ă���9V�̋@��Ȃ�u�d���敪�R 6.3�`10.5V�v(�s���̑���1.7mm�A���a4.75mm)���g�p����Ă���͂��ł��B �@���̋@��Ŏg�p����Ă���DC�W���b�N���ǂ̋K�i�E�T�C�Y�̂��̂��������ƒ��ׂȂ��ƁA���܂��h����Ȃ��Ďg���܂���B �@�u�d���v�͂��̂��̃Y�o���ADC�O���d���[�q�ɓ��͂���d�C�̓d���ł��B �@����̓W���b�N�̉��Ɂu9V�v�Ə����Ă���ꍇ��9V����͂��Ă��Γ��삵�܂��B �@�u7.5V�ȂǂŎg���܂����H�v�Ƃ����̂́A�g�p����@��ɂ���ĈقȂ�܂������T�Ɂu�g���܂��v�u�g���܂���v�Ƃ͂������ł��܂���B �@���d�r�œ����@��Ȃ炽���Ă��͂�����x�d�r�������ēd�����������Ă����삷��悤�ɂł��Ă���ł��傤����A9V�̓d�r��7.5V���炢�Ɍ����Ă�����͂���Ǝv���܂��B �@�������ꂪ�O���d���[�q������͂���d�����ʂ����ēd�r�Ɠ����悤�ɉ������Ă������̂��ǂ����́A�@��̐v�ɂ���ĈقȂ�܂����璆�g�ׂȂ��Ƃ��̃`���C�����ǂ��Ȃ̂��͂ǂ���Ƃ������܂���B �@���̉�H�E�z�����A�O���d���[�q�Ƀv���O���h�������ɂ͓d�r�̉�H����ĊO���d���ɐ�ւ�邾���̒P���ȃW���b�N�̐ړ_�ɂȂ��Ă���Ȃ瑽�������͒Ⴂ�d����AC�A�_�v�^�[���q���ł������Ƃ͎v���܂����A���̕ۏ�����܂���B
�@�u�ɐ��v�̓v���O�̒[�q�Q�̂����A�ǂ��炪�v���X�łǂ��炪�}�C�i�X�����������̂ŁA����͊ԈႤ�ƍň��͋@���j�Ă��܂��܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B 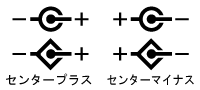 �@�@��̊O���d���W���b�N�̉���AAC�A�_�v�^�[�ɂ͉E�}�̂悤�ȋL�������Ă��܂��B
�@�@��̊O���d���W���b�N�̉���AAC�A�_�v�^�[�ɂ͉E�}�̂悤�ȋL�������Ă��܂��B�@���̃s���𒆐S�ɍl���āu�Z���^�[�v���X�v�Ɓu�Z���^�[�}�C�i�X�v�̂Q��ނ�����܂��B �@�t�ɂ���Ɠd���ɂ͋t�̓d�����������Ă��܂��A�d�q�@��ł���Β��̉�H�╔�i���j��Ă��܂��ł��悤�B �@�����ȋ@��ł́u�t�ڑ��h�~��H�E�ی��H�v�������Ă��܂����A�����ȋ@��ł́u�����܂Ń��[�J�[�����̎w���AC�A�_�v�^�[���q�������v�Ƃ��āA�t�ڑ��Ȃǂ͂��肦�Ȃ��Ƃ��ĕی��H�Ȃǂ͓���Ă��Ȃ��̂����ʂł��B �@�ɐ��͐�ɊԈ��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@�u�d���e���v�́A�g�p����AC�A�_�v�^�[���@��Ŏg�p����d�������イ�Ԃ�ɋ����ł�����̂��ǂ������m�F���Ă��������B �@�����@�킪�uDC9V / 500mA�v�ȂǂƏ���d�����ő�500mA�ƕ\�����Ă���̂ł�����AAC�A�_�v�^�[��500mA�ȏ�̓d���e�ʂ��o������̂��g�p���܂��B �@�ׂ�100mA���x�̋@��ɓd���e��5A��10A�̓d�����q���ł������ł���(����͓d���ƈႤ�Ƃ���)�A�莝���ŗ]���Ă���Ƃ��������̂ւ�ɓ]�����Ă����Ƃ��łȂ�����A���܂�傫������̂����ʂ�AC�A�_�v�^�[�����œd��������Ă��܂����肷��̂łقǂقǂɂ��܂��傤�B �@����܂ł̊e�v������AC�A�_�v�^�[�ł���A�@��̊O���d���Ƃ��Ďg�p�ł��܂��B �@�z�[���Z���^�[����d�C�X�ɍs���ƁA�����ւ��p�̃v���O�������ς��t�����u�e��v���O�ɑΉ��������R��AC�A�_�v�^�[/�T�C�Y�E�ɐ������R�ɑI�ׂ܂��v�Ƃ������̂������Ă��܂��B �@���̏��i�͂����Ă��͓d�����u6V/9V/12V�v�Ȃǂ��X�C�b�`�őI���ł���悤�ȃ}���`�Ȑv�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�ƒ�Ŏg�p����Ă���قƂ�ǂ̋@��̊O���d���Ɏg�p�ł��܂��B �@�@�푤�̃W���b�N�̃T�C�Y���ǂ̋K�i�łǂ̃T�C�Y���킩��Ȃ����́A���������}���`��AC�A�_�v�^�[���w�������ƕ֗��ł��ˁB ���Ԏ� 2009/8/12
|
||||||||||||
| ���e 8/19 |
�@���肪�Ƃ��������܂����B �@�d�C���ƁA�ނ��������ł��ˁB �@�����ƁA���������Ǝv���܂����B ������ �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���g���u���V�̓d�r���� | |||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�������S���Ȃ���ǂ܂��Ă��������Ă���܂��B �@�I�������̏[�d�����g���u���V�iHT-B421�j�̓d�r������Ă����̂ŕ������Ă݂܂����Ƃ���A�P�O�^�̓d�r��1�{�͂����Ă���܂����B�������d�l���ɂ́u�j�b�P�����f�d�r2�iNi-MH 2.4V 300mAh�j�v�Ƃ���������悭����ƃn�[�t�P�O�H�Ƃł����������ȓd�r��2�{�t�B�����Ńp�b�N�������̂悤�ł��B �@���̓d�r�͂ǂ̂悤�Ȗ��̂Ȃ̂ł��傤���H�܂�������@�Ȃǂ���܂����炨�������������B �@���Ǝ��u���V�{�͓̂d�r�{�b�N�X�̑̂��Ȃ��Ă���i�X�v�����O���t���Ă܂��j�A�d�r�̓^�u�t���ł��B�^�u�ɂ͐ԍ��̐����n���_�t������Ă���̂ł����A���̐�͓d�r�{�b�N�X�̓d�Ɂi�X�v�����O�j�̂悤�ł��B������ĐڐG�s�Ǒ�̔O�̂��߁E�E�E���Ċ����Ȃ̂ł��傤���H�Ȃ�Γd�r���^�u�t���łȂ��Ă��n���_�Ȃ��ł����邩�ȁH�Ǝv�����肷��̂ł����������ł��傤���H�@ maru �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�P�O�d�r�͊C�O�T�C�Y�\�L�ł́uAA�v�ƌĂт܂��B �@�����āA�����͂��̂܂܂Œ������Ⴄ�u2/3AA�v�u1/2AA�v�u1/3AA�v�Ƃ����Z���d�r������܂��B �@���̓d�r�͂��傤�ǒP�O�̔������炢�̒����Ȃ�1/2AA�T�C�Y�̓d�r�ł��B �@1/2AA�̃j�b�P�����f�[�d�r�͊C�O�ł͑�R�����Ă��܂����A���{�����ł͂قƂ�ǎ�舵���Ă��܂���B(���X�݂����܂����c) �@�ꎞ���ɂ̓��W�R���V���b�v�ŒP�O�d�r�̑����1/2AA���Q�{����Ĕ{�d���Ŏg���p�ɔ����Ă��܂����̂œ���͓���͖��������̂ł����A���������p�r�̃��W�R���������Ȃ��Ȃ��Ă���̓o�b�e���[����舵���͖����Ȃ�܂����B �@���{�ꂪ�ʂ���(���{��)�l�b�g�ʔ̃V���b�v�ł��o�b�e���[�X�y�[�X�Łu1/3AA Ni-MH 300mAh�v�������Ă��܂��̂ŁA�T�C�Y���������Ă��e�ʂ͂��̎��u���V�̓d�r�Ɠ���300mAh�ł�����A����ő�p�ł���ł��傤�B �@�Q�{�q���ł��Z���Ȃ�܂�����A���[�h�����n���_�Â����Ė{�̂ɐڑ����܂��B �@�Z���̂Łu���̂܂ܓ���Ă������̂ł́H�v�Ƃ���������ɂ͍��{�I�ɑΉ��ł��Ȃ��A�K�����[�h���Ńn���_�Â����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�������A�C�O�Ȃǂ�1/2AA��Ni-MH�d�r��T����Čl�A�������̂ł�����A�d�r�{�b�N�X�̂悤�ɂȂ��Ă��镔���ɂ��̂܂ܓ���Ă����v�ł��傤�B �@�ꌩ����ƃ��[�h���ɂ���K�v���͊������܂��A���g���u���V�Ɠ��̉��g�U���ŐڐG�s�ǂ��N���铙�A���̋@��Ɠ��̕s����N����\���͍l�����܂��̂ŁA�������[�h���ڑ��ɂ���Ă���̂ł������������d�r�����[�h���Ńn���_�Â����鎖�ɉz�������͂���܂���B ���Ԏ� 2009/8/4
|
||||||||||||
| ���e 8/5 |
�@���肪�Ƃ��������܂��B �@����Ȃɑ����A�킩��₷�����������������܂��Ċ������Ă���܂��B �@���ׂĂ݂܂������A�F��ȃT�C�Y������悤�Ȃ̂�1/2AA�����͂��܂薳���悤�ł��ˁB �@���������e�ʂ�������E�E�E�Ƃ����v�����������̂ł����[�d���Ԃ�16���Ԃƒ������̂ł��܂葝���Ă��g���Â炢�����H �@�������炭�͂��������ł�������ň��S���Ďg���������܂��B �@�l�N�Z���ŋƖ��p�H�Ȃ�A1/2AA�ł������p�b�N���ł���悤�ł����A1�ł͖����H�ł��Ă������Ȃ̂ł��傤�˂��H maru �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| Ni-Cd AA400mAh 4.8V ��������p�d�r���~���� | |||||||||||||
|
�@Ni-Cd AA400mAh 4.8V ��������p�d�r���~�����̂ł����H �@�ʔ́A�܂��͔̔��X�Ȃǂ��m�点���������B hidekusu12 �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u��������p�v�ƌ����܂��Ă����Ɏg���̂��A�`��̓p�b�N�i���o�����A�P�[�u���R�l�N�^�͕t���Ă���̂��H�A�Ȃǂǂ�ȕi���~�����̂��킩��Ȃ�������ł��̂ŁA�u�����ŁA����������v�Ƃ������E�Ȃǂ͂ł��܂���B �@�u4.8V�v�Ə�����Ă��܂�����S�{�p�b�N�i���Ƃ͎v���܂����A�S�{�p�b�N���Ɖ��ɂS�{����ł���̂��A�Q�~�Q�Ŏl�p���`�ɂȂ��Ă���̂��A�l�p���̂ɂ��Ă����Ă���ԂłS���ׂĂ���̂��Q�����Q���ׂ��悤�Ȍ`�Ȃ̂��A�����Ă���ς�P�[�u���E�R�l�N�^�t�����~�����̂��A���������n�[�l�X�͖����ēd�r�̒[�q�����Ŕ����o���ɂȂ��Ă���̂��E�E�E�E �@���̂ق��ł͏��s���œ���̏��i�����Љ�ł��܂���̂ŁA����Ȃ��Ȃ��ɂ҂�����̂��X���ꌬ�Љ�܂��傤�B �@�����́u�J�z�p�[�c�Z���^�[�v�Łu�j�b�J�h�g�d�r�̒����������܂��v�Ƃ����T�[�r�X���s���Ă��邻���ł��B �@�P��E��E�O�^�C�v������]�̖{���ŁA����]�̌`��(�������ɊG�ɕ`�����������ł�)�g�d�r�ɑg�ݗ��ĂĔ������Ă���܂��B �@�Ȃ�Đe�ŕ֗��ȃT�[�r�X�ł��傤�B �@�ڂ����̓V���b�v�ɂ��₢���킹���������B �@���A400mAh�̃j�J�h�[�d�r�Ƃ����̂͂��܂�ɌÂ��A���ł͍����ł͂܂���ɓ���܂���B �@�Œ�ł�500�`600mAh�A�ʏ��700�`1000mAh�̕i�����ʂ��Ă��܂��B�J�z�p�[�c�Z���^�[�l�̑g�d�r�T�[�r�X�ł��g�p����Ă���̂�700mAh�̃j�J�h�d�r�ł��B �@���́u��������v�Ƃ����̂������S���킩��܂��A����d���œ��ɖ��[�d���m������10���Ԉȏ�[�d�����ςȂ��ɂ���@��ł���Ώ[�d���Ԃ������Ζ��[�d�ł��܂����A�������炩�̖��[�d���m��^�C�}�[�E���S���u���t���Ă���ꍇ�͖��[�d�ł��Ȃ��ꍇ������܂��B �@�P�̂ŗe�ʂ̔�r�I���Ȃ��j�J�h�d�r���K�[�f�����C�g�p�̃j�J�h�[�d�r�v�̂悤�ȕi����^�d�C�X��z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă��܂��̂ŁA�P�i�ŗǂ��̂ł����炲�ߏ��̓X�ł��������d�r��T����Ă͂������ł��傤���B �@�������A�d�r�̎�舵���̑����d�q�p�[�c�X�E�l�b�g��̓d�r�ʔ̓X�ł��P�i�̃j�J�h�d�r�͈����Ă��܂��B �@��������������͂悭�����̂ł���(����J��]�������ł�)�A�����Ă��̕��͂ǂ�Ȍ`�ŃP�[�u���͕t���Ă��邩�ǂ������炢�͏����Đ�������܂��̂ŁA�u����Ȃ�~�~�����ɂ��遠���p�Ɏ�����������܂��B���茳�̓d�r�������čs���Č���ׂē����`�̕��������ł���B�v�ƃA�h�o�C�X�ł���̂ł����A����̂�����̂悤�ȓ��e�ł͂����S�������`�̕���m���Ă��Ă�����Ƃ͒m�炸�ɂ����������邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA�������炸���������������B �@���łƌ����Ă͉�(��)�ł����A�ŋ߂����k�������̂��˗��ł́u�X�����_�[�g�[���E�G�{�����[�V����(�ʔ̂Ŕ����Ă��鑉�g���)�̌����o�b�e���[���~�����v�Ƃ������e������܂����B(���P����Ő��K���[�g�ł͔����Ȃ���������ł�) �@��̓I�ɃT�C�Y�E�`���e�ʂȂǂ��������������̂ŁA�u����Ȃ�d�C�X�E�z�[���Z���^�[�̓d�b�q�@�p�����o�b�e���[�ɔ��Ɏ�����������̂ŁA���X�ɍs���ē��������������m�F���Ă��������B�R�l�N�^�����͈Ⴄ�`�łȂ������Ȃ��Ƃ����Ȃ������H�v�Ƃ����������Ē����܂����B �@���X�ɍs����āu�҂�����̕�(Panasonic HHR-T401�^)���L��܂����I�A�R�l�N�^�܂ňꏏ�ő喞���ł��B���������K�i��5000�~�ȏシ��̂ɂ�����1300�~�œ���ł��܂����I�v�Ƒ��т���Ă��܂����B �@�����Ƃ����܂ɉ����B�����Ċi���ōς݂܂����B �@����������������̂ŁA����������ꍇ�͂Ȃ�ׂ��ׂ��ȏ��̒����肢�v���܂��B �@�������A�s�̂���Ă��Ȃ����ɑ��Ă͍w���ł���Ƃ������͂ł��܂��B ���Ԏ� 2009/7/14
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���`�E���d�r�̔ėp�[�d��͗Ǖi�H | |||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB �@�d�C�ɂ��Ă͑S���̑f�l�ł����A�f�W�^���J�����ŗǂ��G�l���[�v��A���J�����g���̂ŁA�Q�l�ɂ����Ă��������Ă��܂��B �@���������m�ł����狳���Ă������������̂ł����A���`�E���d�r�̔ėp�[�d��Ƃ������̂�ʔ̂ŗǂ��������܂��B http://item.rakuten.co.jp/wilmart/ch010chnp70/ �@�������̂悤�ł����A�A�_�v�^�[��ւ���T�C�Y�̈Ⴄ�ǂ�ȏ[�d�r�ł��[�d���ł���Ƃ��c �@���̂悤�ȏ��i�̕]���͒�܂��Ă���̂ł��傤���H �@����Ƃ��A����o���Ȃ��ق����ǂ��̂ł��傤���c �@���萔�ł����A��낵�����肢�������܂��B �̂��̂� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͂��߂ɁA���͂��������[�d������������Ă��܂���̂ŁA����̋@��ɂ��Ă̕]���E���\�ɂ��Č��y�͂ł��܂���B �@�f�W�^���J�����⃀�[�r�[�Ŏg�p���Ă���o�b�e���[�p�b�N��3.7V(3.6V)��7.2V�����`�E���C�I���[�d�r���嗬�ł��ˁB �@���[�J�[�E�@��E�o�b�e���[�p�b�N�̌`������Ă��A���g�����`�E���C�I���[�d�r�ł���Ί�{�I�ɂ͏[�d��͓��������g���܂��B �E3.7V(3.6V)�p�ł����4.2V���z���Ȃ��A7.2V�p��8.4V���z���Ȃ�CC/CV��������B �E�ő�d����1C(�o�b�e���[�p�b�N�ɂ��قȂ�)���z���Ȃ��B �E�ł���Ή��x�Ď����o���āA�\�������ꍇ�͔��̑O�ɏ[�d���~�߂�B �@�Ȃǂ̗v�������������Ă���悢�킯�ł��B �@�]���Ă��̂悤�ȃT�[�h�p�[�e�B���ŁA�A�_�v�^�[�����ւ���Ηl�X�ȃ��[�J�[�̃o�b�e���[�p�b�N���[�d�ł���ėp�[�d��Ƃ����������邱�Ƃ͗e�ՂŁA����������Ă���o�b�e���[�ɑ��ĉ�����薳���[�d�ł��܂��B �@�܂����̐��i�̂悤�Ɂu80%�[�d�Ńo�b�e���[�̎�������������v���Ɠ��̋@�\��g�ݍ����ł��A�قƂ�ǂ̃��`�E���C�I���[�d�r�ɑ��Ă͓����悤�Ȍ��ʂ�����܂�����A���[�J�[�̌����ʂ�̏[�d�d�l�ō���Ă���Ȃ���ʂ͊��҂ł��܂��B �@��́A�]���E�]���ɂ��Ă͌X�̃��[�J�[�A�[�d��̌^�ԂȂǂɂ��l�X���Ǝv���܂��B �@���R�́u�[�d��H�������Ƃ������ɂȂ��Ă��Ȃ��e���i�v�ł�������A�A�_�v�^�[���̌`�����ɖ{���̃��[�J�[�i�ƈ���ĐڐG�s�ǂȂǂ��N�������́A�v���X�`�b�N�Ȃǂ̑f�ނ��e���ł����Ɋ���Ă��܂����̂ȂǁA�ߋ��ɔ�������Ă��鏤�i�����w���̍ۂɂ͒ʔ̃T�C�g�Ȃǂ̎g�p�҃��r���[���悭�ǂ܂�āA�Ȃ�ׂ��e���i���w�����Ă��܂�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������Ƃ���������͌����܂���B ���Ԏ� 2009/7/4
|
||||||||||||
| ���e |
�@�Ǘ��l���܁@�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@�����������A�h�o�C�X�A��ώQ�l�ɂȂ�܂����B �@�w���҂̕��̃��r���[��ǂ�ł��Ă��A���Ɏ��̂ɂȂ������Ƃ����͌�������܂��A�ȂɂԂ��̈ӌ��������邱�Ƃ��ł����s���Ȃ��ƁA�܂��Ǘ��l���܂̂悤�ɁA����̑e���i����������͂��Ȃ��̂ō���̍w���͌����낤�Ǝv���܂��B �@�������̂悤�ȏ��i������Α�ϕ֗��ł����A����������Ȃ��̂Ȃ�M���ł��郁�[�J�[���為�Џ��i�����Ă������������Ȃ��Ǝv���܂��B�f�W�J�����̐�p�[�d��͂����ւ��ł��̂Łc �@���肪�Ƃ��������܂����B �̂��̂� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�M���ł��郁�[�J�[�����{�����̑���L���d�@���[�J�[���w���̂��Ƃ�����A�܂������������[�J�[�����������ėp�[�d���o�����Ƃ͖����ł��傤�B �@�f�W�^���J�����⃀�[�r�[�̃o�b�e���[�p�b�N�ɂ́A�������̋��ʌ^�̂��̂�[�J�[�E�@��Ǝ��̕�������܂����A���ꂼ�ꂪ�`��Ȃǂ�����\�����Ă��邽�߂ɑ����[�J�[�������ɓK�������[�d������邱�Ƃ͂܂�����܂���B �@�܂������ҐӔC�@�Ȃǂ̊W�Ŋe���[�J�[�͎��А��[�d��ƃo�b�e���[�̑g�ݍ��킹�ȊO�ɂ͐ӔC�������܂���̂ŁA���А��i�Ƃ̑g�ݍ��킹�͋֎~���Ă��܂��B �@�ł��̂Łu�A�_�v�^�[�����ւ��āv�ȂǂƂ����[�d��͂����Ă��͊C�O���[�J�[������ē��{�̏��Ђ��A���̔����Ă���u������Ɛ��K�i�ł͂Ȃ����ǁd�d������I�v�@�����ɂȂ��Ă���̂�����ł��B ���Ԏ� 2009/7/5
|
||||||||||||
| ���e 7/16 |
�@���Ȃ�O����݊��o�b�e���[��⏕�p�b�N���o���Ă���uJTT(Japan Trust Technology)�v�Ђ́uMy Charger Multi�v http://www.jtt.ne.jp/products/original/my_charger_multi/index.html> �@�͓d����ɐ��̎�������ȂǁA�}�g�������ɂ݂͂��܂��ˁB (���A�����L�����[�J�Ƃ͌���Ȃ��H(��) �@���̂����A�̂��̂� ����̒��Ă��鐻�i��2�{�ȏ�̒l�i�ƂȂ��Ă���̂ŁA���ǂ͊e����҂��M�����ƒl�i�̐܂荇����|���V�[�őI�����邵���Ȃ��悤�ł��B Shimalith �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| 3.0V�^�C�v��RCR123A���[�d�o����[�d�� | |||||||||||||
|
�@3.0V�^�C�v��RCR123A���[�d�o����[�d����肵�܂����B http://www.bam-boo.cc/hg-1210w �@16340����18650�܂ŏ[�d�ł��ăX�C�b�`�̐ؑւ�3.0V�^�C�v��3.6(3.7)V�^�C�v�̗����ɑΉ����Ă��܂��B �@���͂��̉��ł�OK�^�C�v�̏[�d�킪�ӊO�ɂȂ���ł���ˁB �@���̏[�d��͈ȑO�����肵�����p����[�d��Ɠ������[�J�[�̂悤��LED�̌������������ł��A �@�[�d���͐� �@�t���[�d���߂Â��ƍ����_�� �@�[�d��ɂ���Ă������_�ł� �@�[�d�����ŗ� �@Ni-MH��Li-ion�������I�ɔ��ʂ��Ă���悤�Ȃ̂ł����A���g�����Ă��f�l�ڂɂ͂��܂荂�x�Ȏd��������悤�ȕ��i����������܂���(^_^;) �@�ȑO�����肵�����p����[�d��͍��x�Ȏd�g�݂ł����ł��傤���H(^_^;) takebeat �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���݂܂���A���������Ԃ�o���܂����u���p����[�d���v�͈�x���쎎��(LED���_�����邩)�����������ł܂����g�̉�H�}���������Ă��܂���B �@���g�͒�d����H�Ɠd�r�z���_�[�A�����Ɂu�I���{�[�h�������ꂽ�}�C�R���`�b�v�v(�܂荕�����[���h�Œ��g�͉����킩��Ȃ��㕨)���ڂ��Ă��邾���ł��B �@���̎�́u���`�E���d�r���A�j�b�P�����f�d�r�������[�d�ł����H�v�̂����݂͓d�r�ɂ͒�d���𗬂����ƂŁA�����Ɠd�r���[�ɔ�������[�d���̓d�r�[�q�d�����v��A�u1�`1.6V���x�ł���j�b�P�����f�d�r�v�u2�`4.2V�ł�����`�E���C�I���d�r�v�Ɣ��肷�邾���̊ȒP�ȃ��W�b�N�Ŏ����ł��܂��B �@�I�y�A���v��W�b�NIC�ʼn�H��g�ނ��APIC�̂悤�ȃ����`�b�v�}�C�R����A/D���͂Ńv���O�����Ŕ��肳����ق������̂͊y�ł��ˁB �@���̏�Ńj�b�P�����f�[�d�r�ł���Ώ[�d�����܂ł��̂܂ܒ�d���[�d������悢�����ŁA�|���u�����o���Ă�邩�A���̃s�[�N�d�������m���Ė��[�d�Ɣ��肷��܂������`�E���d�r��4.2V�܂ʼnߏ[�d����(�ꔭ�œd�r����)���܂����Ƃ͂���܂���B������}�C�R�����䂵�Ă��̂��y�ł��B �@���`�E���C�I���[�d�r�ł���d�������m����A�d������4.2V�������オ��Ȃ��悤�Ȑ������̒�d����H�ɂ��Ă�����4.2V�ɒB����Ό�͓d����������CC/CV�[�d�ł���悤�ȉ�H�����܂����A������������UltraFire�̏[�d��̂悤��4.2V�ȏ�̓d���܂ŏグ�ĉߏ[�d���݂ɏ[�d���ĊJ���d�����v���ď[�d���~�߂������������܂���B������Ɋւ��Ă��A�d�q���i�Ő��䂷����}�C�R���ŏ��������ق����y�ł��B �@�Ƃ������ŁA��d���d����H�Ɖ��炩�̃}�C�R���`�b�v������Ă���[�d��H�Ƃ����\���́A�ړI����v�ł����H���̂��̂̂���ł��B �@�u�ǂ���������p�������ł���̂��v�̗��_�͗e�Ղɑz�������܂����A��͐��i���ʂ����Ă����Ƃ��̒ʂ�ɓ��������ǂ����A�����ł��B �@����͂܂����ׂĂ��܂���̂ŁA�����_�ł͂��̃��[�J�[�̐��i�����S���Ďg�p�ł���{���́u���p�����v���ǂ����́E�E�E �@���̂Q�{�p�̉�H�ł����A�\�ʂ̕��i���ʐ^�ł͏d�Ȃ荇���Ă��Ă悭�����܂���̂ŁA�d�r�Q�{���[�d����ۂɂ͂����ƌʂɓd�������Ȃǂ��s���āA�ő��i�~�Q�œ����[�d�ł���̂��A�͂��܂���̏[�d��̂悤�ɓd�r�Q�{�ł͕���[�d�œd���͕��������Ă��܂��̂��E�E�E�B �@LED���������������������̂ł���A�W�{����IC���}�C�R���`�b�v�ŁA��{�p�̖��p����[�d��Ɠ������W�b�N�ŏ[�d�͂��Ă���̂ł��傤�B �@���ꂪ���S���ď[�d�ł��郍�W�b�N�𓋍ڂ��Ă��āA3.0V/3.7V�̐ؑւ��ł��ēd�r�T�C�Y��16340�`18650�܂Ŏ��R�Ɏh����X�v�����O����̒����ł����(�X��AC100V/DC12V�̗��p�H)�A���`�E���C�I���[�d�r���g���l�ɂ͎g�����肪�ǂ������ȏ[�d��̃z�[�v�ɂȂ肻���ł��ˁB ���Ԏ� 2009/7/4
|
||||||||||||
| ���e |
�@���b�������đ�ς��肪�����ł��A �@���O�̂��Ƃ��ЂƂ�ōl���Ă���Ǝv�l���~�܂��Ă��܂��܂�(^_^;) �@�^�ォ��B�����ʐ^��lj����܂��������ݓ����Ă��Ă��܂��B��Ă��邩���M������܂���B �@���̌�d�r�ɂ���ď[�d�d�����ς��̂����ׂ悤�ƃe�X�^�[������Ə[�d�����ƌ��m����Ă��܂��������肤�܂��v��Ă��܂���B �@���Ԃ͂�����܂����[�d���Ԃ���[�d��̑f���ׂ�����ł������Ǝv���Ă��܂��B takebeat �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��R�ʐ^���lj�����܂����ˁi�O�O�G �@���Ԃ�����ǂ�ȉ�H�Ȃ̂����Ă݂܂��B �@�d�r�̂Ƃ���Ƀe�X�^�[�����Ă��������v��Ȃ��̂͌����I�Ɂu����Ă͂����Ȃ�������@�v�ł���B �@���}�̒ʂ�A��d���[�d��H�ł͓d�r�Ƃ�������Ƀe�X�^�[�������ނƓd�r�d�������ł͂Ȃ��A�e�X�^�[�̓����̑���p��R�̗��[�ɃI�[���̖@���Ō����d���܂Łu�S���œd�r�̓d���v�Ƃ��ď[�d����ɓ`���邱�ƂɂȂ�A�e�X�^�[�����̒�R�l�͂����킸���ł����A����ɐ��SmA�̏[�d�d���������ΐ��\�`���SmV�̓d�����ɂȂ�A���ꂪ�[�d���̓d�r�̒[�q�d���ƍ��v�����ƊȒP�ɏ[�d�I�������ߏ[�d��s�Ǔd�r�ŃG���[�Ɣ��肳���d���܂ŏオ�邱�Ƃ�����܂��B 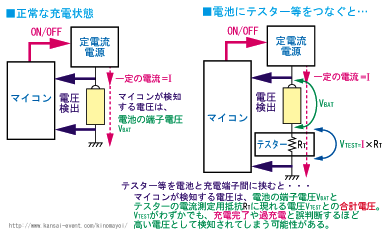 �@�������̏ꍇ�ł��e�X�^�[����ꂽ�܂[�d���Ă��Ă͐��������[�d�����m�ł��Ȃ��ŏ[�d�s�ǂɂȂ�Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/7/5
|
||||||||||||
| ���e 7/9 |
�@��͂�e�X�^�[��d�r�Ə[�d��̊Ԃɋ��ނ̂͌�쓮�̌���������ł��ˁA�����Ȃ����R���C���X�g�t���ő�Ϗڂ���������Ă���������ς킩��₷�����ӂ��Ă���܂��A�܂����̂��߂ɂ����ς킹�Ă��܂��{���ɐ\����܂���B �@���̉��x���[�d���s�����̋������`�F�b�N���Ă��܂����ALED�\�����ӊO�ɐ��m�Ȃ��ƂƁA�\�z�O�ɏ[�d�����������킩��ǂ��������������ȁH�Ƃق�����ł��܂�(^_^;) �@�����AAC�A�_�v�^���g����DC���͂Ŏg���Ə[�d�������̓d���������Ⴂ���ƂƁA�[�d��̗��̈ꕔ�������M�����̂ƁA�L�[���ƌ��������g��������̂�DC-DC�R���o�[�^�[�����܂����Ȃ̂��H�Ǝv�����肵�Ă��܂����E�E�E takebeat �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| MH-C9000��YZ-114SP�͂ǂ��炪�����ł����H | |||||||||||||
|
�@�����y�����ǂ܂��Ă�����Ă���܂��A�����ł����[���d������낢��ƒT���Ă��������L�̏��i���ǂ��Ƃ̃y�[�W���������܂��� Maha Energy Corporation�@MH-C9000 �@�w�����l���Ă���̂ł����ėp�����l��������R����YZ-114SP�@AC/DC�}���[�d���A������Ƃ�����قNj��z���ς��Ȃ��̂łǂ����悤�������Ă��܂��AMaha Energy Corporation�@MH-C9000�͑����p�`���L�����͋C����������̂ŋC�ɓ����Ă͋���̂ł����A�@�\���\�I�ɂ͂ǂ��ł��傤���H�g�p�p�r�̓��W�R���A�~�j�l����x�ł��B �@���w���̂قǂ�낵�����肢�ł���Ǝv���܂� brandy �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����MH-C9000��YZ-114SP�������Ă��܂���̂ŁA���ꂼ��̐��\�E�����E��`�ł͂������������Ă��邪���́E�E�E�Ƃ����_�ɂ��Ă͉������y�ł��܂���B �@�ǂ�����S�����������Ⴄ�[�d��Ȃ̂ŁA���ʂ͖������͖����Ǝv���̂ł����A���̃`���[�g�ɏ]���Ĕ��f���Ă��������B
���Ԏ� 2009/7/2
|
||||||||||||
| ���e 7/6 |
�@�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B���W�R���p�������ĂƏ����܂���������̓~�j�b�c�ʂȂ̂Ŋ�{�d�r�̊Ǘ��ɂȂ�܂����A��X�Ƀo�b�e���[�p�b�N�����g�����{�i�I�ȃ��W�R�����n�߂悤�Ƃ����v�������l���Ă����̂ł��A�����ł̂����₾�����̂ł����A���t���炸�Ő\����Ȃ������ł��A��������Ȃ��Ȃ����͂ł��^���ɓ����Ă��������ĂƂĂ����ӂ��Ă��܂��B �@�{��ł����A�d�r�Ǘ��̔ėp�����l�����ꍇMaha Energy Corporation�@MH-C9000���Ƃ肠�����w�����Ă݂悤�Ǝv���܂��A�V�D�QV��|�o�b�e���[�̎g�p�́A�܂������܂�������ɂȂ�܂��̂ŁE�E�E�A���肪�Ƃ��������܂����B brandy �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �\�[���[�p�l���́u����ڑ��֎~�v�H | |||||||||||||
|
�@�\�[���[�p�l���ɂ��Ď��₳���Ă������� �@����p�l���T�C�g��Ɂw�\�[���[�p�l���͊�{�I�ɒ���ڑ�������i���m�F������Ŏg�p������́x�ƋL�q������A���̏ڍא���������܂���ł����B���̂Ȃ̂��m�肽���̂ł���������Ă��炸�����Ŏ��₳���Ă������������v���܂��B �@�Ȃ����̃T�C�g�ł͖͌^���[�^�������x�̃p�l�����g�p���Ă̎����ł����B ���� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̃T�C�g�l�ɏ�����Ă�����e�ɂ��ẮA���̃T�C�g�̍�ҁE�Ǘ��җl�Ɏ�������Ă��������B �@�����͑��T�C�g�l�̃T�|�[�g�Z���^�[�ł͂���܂���B (�d�C�E��H�̂ق��ł������܂�����ˁH) �@���z�d�r�p�l���́u�P�Ǝg�p�v�u����g�p�v�u����g�p�v�u������g�p�v�̂ǂ̎g�p���@�ł��\���܂���B �@����g�p�̏ꍇ�́A�P�ł��e�ɂȂ�Ƃ��̉e�ɂȂ����p�l���̔��d�\�͂������A�����̓d�C��R�ɂȂ�̂Ń��j�b�g�S�̂̔��d�\�͂͒������ቺ���܂��B �@����������Ē���g�p���Ȃ��l�͋��邩������܂���B �@�u���z�����d�v���Ə̂��Ĕ����Ă���s�̂̑傫�ȑ��z�d�r���j�b�g�ł͑����̑��z�d�r����ڑ��ɂ��āA�ꕔ�̃p�l���̔\�͂������Ă����j�b�g�S�̂̔��d�\�͂ɂ͉e�����o�ɂ����悤�ɍl������Ă��܂��B �@�q���̉ċx�݂̍H�샌�x���ł���A�������x�̒���ڑ��ł��u(�ꕔ�ɂł�)����������Ȃ����甭�d���Ȃ��ˁ`�v�ōς܂�����̂ŁA����ڑ�������Ă��S�R���C�ł��B �@���̃T�C�g���Ȃ�����ڑ��������Ȃ��̂��̐^���ɂ��Ă͎��ɂ͂킩�肩�˂܂��̂ŁA�T�C�g��ҁE�Ǘ��҂̕��Ɋm���߂ė��R���m�F���Ă��������B �@���Ȃ��l�̏��ł́u���������Ă���v�Ƃ��������ł����A�����������炻�̃T�C�g�ŏЉ��Ă���u�g�p���@�̂ق��v�A�܂葾�z�d�r�p�l���̓����ł͂Ȃ��q����H�Ȃǂ̂ق��ɉ����[�����P�������������������ӏ��������Ă���̂�������܂���B�͌^���[�^�[�������ƌ����Ă��A�ڑ�����p�l���̖����₻�̃p�l���̔\�͂Ȃǂ��W���܂����A���[�^�[�������Ȃ̂������Ԃɉ�H��f�q�����ނ̂��ȂǁA��͂�F�X�Ə�s�����Ă��܂��B �@���̃T�C�g��URL���������u�����ƃT�C�g�ɏ����Ă������v�Ƃ����A���̃T�C�g�������ꕔ�����������`������̂͌�������`�B��������ł��������@�ł��̂ŁA�Ȍ��ɂ��Ȃ��悤�ɂ��肢���܂��B �@�܂��A�d�ˏd�˂��肢���܂����A�����́����T�C�g�̃T�|�[�g�Z���^�[�ł͂���܂���B���ŏ�����Ă��邱�ƂɊւ��Ă͂����̐ӔC�҂̕��ɂ��q�˂��������B ���Ԏ� 2009/6/30
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���[�^�[�̓d��������R | |||||||||||||
|
�@��������̉��肪�Ƃ��������܂��B �@���[�^�[�̌��ɂ��āA����Ȃ̂ł����A�~�j4��̃��[�^�[�i�d�r2�œ����j��2������ɂ��āA�d�r4�{�g���āA�����̂ł����A���[�^�[�̕ی��R�͉������炢�̂��̂������ł��傤���H �@��낵�����肢���܂��B spark sheet �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̂�����ɂ���R�ɂ��ĂȂǂ͉ł��܂����B �@�Ȃɂ���A���[�^�[�������A���̃��[�^�[�̒�i����ۂɉ��ɑg�ݍ��܂�āA���̋@��Ŏg�p���鎞�ɕ��ׂ��ǂꂭ�炢�Ŏ��d���͉��`�����̂��Ȃǂ��S���s���ł�����A��R�l���v�Z���邱�Ƃ��ł��܂����B �@�~�j�l��̃��[�^�[�ƌ����܂��Ă��A�^�~�������ł�����ނ������Ă��ꂼ�����d�����Ⴂ�܂��B �@�Ȃɂ�胂�[�^�[�͋�]�����邾���̎��ƁA���������蓮�������肷�鎞�ɂ����镉�ׂŏ���d�����傫���ς�܂�����A���̂ւ�̎������茳�ɂ��邩�����Őv���Ă���@�B�łȂ��ƑS�������킩��Ȃ��̂ł��B �@����ɁA�d�r�Q�œ������[�^�[(3V�d�l)���킴�킴�d�r�S�����6V�����R�œd���������Ďg�p����Ӗ����킩��܂���B �@���̐ڑ����ƒ�R�Ń��[�^�[�ŏ����̂Ɠ����d�͂�������ĔM�ɕς��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�d�r�̎��p���[���̂Ă邱�ƂɂȂ�A�d�r�Q�{�Ń��[�^�[�����̂܂܉̂Ɠ������Ԃ����������āA�d�r���S�{�g���Ă��܂�(�����Q�{�Ԃ�̓d�C�͎̂ĂĂ���)�Ƃ����ƂĂ����ʂȌq�����ɂȂ�̂ł����B�Ȃ����̂悤�Ȍq�����������̂����S���킩��܂���B �@�d�r�S�{(����)�ƒ�R�ȂǍl�����ɁA�f���ɓd�r�Q�{�œ������Ă��������B �@�܂��́A���[�^�[������ɂ��ēd�r�S�{��6V�œ������悤�ɂ��Ă��������B ���Ԏ� 2009/6/30
|
||||||||||||
| ���e |
�@���J�ȉ��肪�Ƃ��������܂��B �@���͎����A�ԈႦ�āA2��2����̓d�r�{�b�N�X�����Ƃ�����A4�{����ł����Ă��܂��āA��蒼���̂��ʓ|�������̂ŁA�Ȃ�Ƃ����̂܂܂ł��Ȃ����ƁA�l�������̂ł����B �@�ł��A�悭�l������A�d�r2�{���̃p���[�����ʂɂȂ�킯�ł�����A���������������Ȃ��ł��ˁB �@�V�����A2��2����̓d�r�{�b�N�X����邱�Ƃɂ��܂��B �@���A����ƁA���[�^�[2����������Ă݂��̂ł����A�Ȃ������܂���ł����B �@�����d�l�̃��[�^�[���g���܂������A�Ȃ��ł��傤���H1�̃��[�^�[�́A���܂����A����1�͉��ĂȂ��̂ɉ��܂���ł����B spark sheet �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d�r�{�b�N�X��g�ݑւ��ł���̂ł�����A�Q���Q����ɑg�ݑւ��āA�d�r�̃p���[��]�����Ȃ��g����悤�ɂ��Ă��������B �@����ŕЕ��̃��[�^�[�����Ȃ��̂́A���ׂ��Е������d���Ȃǃo�����X�������̂ł͂Ȃ��ł����H �@����Ŏg�p����ꍇ�͕��ׂ��ψ�ɂ�����悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B ���Ԏ� 2009/7/1
|
||||||||||||
| ���e |
�@������ɂ������[�^�[���Е��������Ȃ��̂́A���[�^�[�͔��d�@�ł����邩��ł��B �@�܂�A����Ă��郂�[�^�[�́A�������Ă���̂Ƃقړ����d�������Ă���̂ł��B �@���̂��߁A����Ă��Ȃ����[�^�[�ɂ́A�قƂ�Ǔd����������Ȃ��̂ʼn�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����킯�ł��B �@����́A�t���b�v�t���b�v�̂悤�ɓ����̂ŁA�Q�̃��[�^�[�ɓ������ׂ�^���Ă��A�ǂ��炩����������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �@�����āA����Ă�����̎����������Ď~�߂�A����Ă��Ȃ��������n�߂�Ƃ������Ƃł�����܂��B �@�ȏ�A�m�g�j����̍��Z��������̂���o���̈��p�ł����B ���� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[��A�u���d���Ă��邩��v�ł͐��������Ȃ��̂ł����E�E�E�B �@�Q�̃��[�^�[��ɂ������ɁA�}�u�`���[�^�[�̂悤��DC�R���R�C�����[�^�[�́u�P��]���łU���̈ʑ��ω��v������A���̑����Ƃɗ����d���̑召�ω�������Ɍq�������[�^�[���m�ō���Ȃ��ƃp���[���o�Ȃ��Ƃ����_�ƁA��]�������������[�^�[�̓C���s�[�_���X��������̂ł�����d���������A�X�ɉ�]����������_�E�����[�v�Ɋׂ��ĉ��Ȃ��Ȃ�Ƃ������[�^�[�̒��g���R�C���ł��鎖�ɋN������C���s�[�_���X�ω����v���Ƃ��đ傫���Ǝv���̂ł����B �@���Ԃ����鎞�ł���Ύ��ۂɎ������Ċe���[�^�[�̓d����R�C�����ʂ��ǂ��Ȃ��Ă���̂���������ׂ̃I�V���X�R�[�v�ł̊ϑ��f�[�^�Ȃǂ��f�ڂ��܂����A���͂���Ȃ��Ƃ����Ă���Ƒ��̕��ւ̉��i�܂Ȃ��Ȃ�܂��̂Ń��[�^�[�ɂ��Ă̂�����ɂ͂���ȏ�͂������ł��܂���B(����ɂ����͓d�r�ɂ��Ẵy�[�W�ł���) �@�����̂ɍ�����H�앨�ł́A���[�^�[�Q����ł����܂����̂Ŏg�p���郂�[�^�[�̌ŗL�����Ȃǂ��e������Ǝv���܂��B �@�������̘b��ɂ��ĉ������ꂽ��������������Ⴂ�܂�����A�������̃u���O�E�g�o�Ȃǂœd���d���̕ω���A�R�C���ɂ��e�g�`�Ȃǂ̃I�V���X�R�[�v�ʐ^�Ȃǂ�g�ݍ��킹�Ă킩��₷���������ʂ\���Ă��������B ���Ԏ� 2009/7/4
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �f�W�J���̊O���d�� | |||||||||||||
|
�@�����b�ɂȂ�܂��B �@���͌Â��f�W�^�������g���Ă��܂��āA�A�����J�ł��������o�b�e���[�͔����Ă��Ȃ����ߊO���o�b�e���[�����݂Ă���҂ł��B�����o�b�e���[��7.2V 2100mAh�ŃZ����4/5A�Ƃ������̂ł��B�ŏ��̓f�W�J����AC����R�[�h���q���A����ɂ����d�r�{�b�N�X+�G�l���[�v6�{�łǂ����낤�Ǝv�������܂������A���[�d��1���ڂ̓V���b�^�[����܂����A2���ڂ���͂���܂���B�����ŐF�X���אڐG��R�Ƃ��̂悤�ł��ˁB�����ł������߂̓d�r�{�b�N�X�͂���܂����H �@�����Đ\����܂��A�����W�R���o�b�e���[�ł�������ł��傤���H�Ⴆ���W�R���̃Z���͒P��ɋ߂��悤�ł����A���e�ʂł��G�l���[�v���ɔ�׃��W�R���̃Z���̕����L���Ȃ̂ł��傤���H�����������͐F�X�ƈႤ�ł��傤��..... �@�܂Ƃ܂�̂Ȃ����͐\����܂���B�X�������肢�v���܂��B ���� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�f�W�J����AC�v�Ƃ����̂���̉��Ȃ̂��T�b�p���킩��܂��A���ꂪ�O���d���[�q(AC�A�_�v�^�[�����q���[�q)���Ɖ��肵�Ęb��i�߂܂��B �@�����O���d���[�q�Ƀo�b�e���[�Ɠ����d����^����ΐ���ɓ����@��ł́A7.2V�o�b�e���[�̑����1.2V�[�d�r���U�{��7.2V(���[�d���͂���������)�̓d����^����A�f�W�ꂭ�炢�̏���d�͂Ȃ�]�T�ŋ쓮�ł���͂��ł��B �@����2100mAh�̃o�b�e���[�Ȃ�eneloop�łȂ���͏o�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�ŏ��̂P�������B��āA�����ɓd���s���ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B �@�������A�d�r�{�b�N�X�̋����q�����z�����x�̒�R�ł���Ȃɓ����Ȃ��Ȃ�悤�ȓd���h���b�v���N���邱�Ƃ��܂������ł��悤�B(�z����₷��ڑ��̈����Ƃ��A�ƂĂ��d�C�̏펯���鉽��������Ă���Εʂł����E�E�E) �@�d�r�œ����@��̑����́A�O���d���[�q�ɂ͓����̓d�r�E�o�b�e���[�d����荂���d����^���Ȃ��Ɠ����Ȃ��@��̂ق��������ł��B �@����͊O���d���[�q����͋@������ŕK�v�Ƃ���d����荂���d������͂��āA���ɒ�d����H�������Ă��ċ@����d���ɗ��Ƃ������݂ɂȂ��Ă��āA�O���̓d���A�_�v�^�[���̓d���ϓ��Ȃǂ��z������Ƌ��ɗ]�T�̗L��d���ŋ쓮������ړI�����˂Ă��܂��B �@�ł�����A7.2V�@��̏ꍇ�͊O���d���[�q�ɂ�10�`15V���x��AC�A�_�v�^�[��ڑ�������̂������A���̐��u�̍�����d����H�ɕK�v�ȃh���b�v�d���Ԃ�����]�T�̂���d�����K�v�Ƃ����킯�ł��B �@�܂��A���̋@�펩�̂������o�b�e���[�̏[�d�@�\��L���Ă���ꍇ�A�o�b�e���[�ɏ[�d����ɂ̓o�b�e���[�d����荂���d���d�����K�v�ł�����A�@��̊O���d�����͓d���̓o�b�e���[�d����萔�u�͍������Ă����Ȃ��Ə[�d�ł��܂���B���̂悤�ȋ@��ł͊O���d���[�q�͂�͂�o�b�e���[�d���Ɠ����ł͂Ȃ������Ȃ��Ă��܂��B �@�������������@��ɓ����o�b�e���[�Ɠ����d�����O���d���[�q�ɗ^���Ă��d���s���Ő���ɓ���͂��܂���B �@���Ƃ��Ώ[�d�����Ă�eneloop�̏ꍇ�͈�{��1.45V���x�A�U�{�����8.7V���炢�̓d��������܂�����A�O���d����9V�قǕK�v�ȋ@��łȂ�ŏ��̏��������͂Ȃ�Ƃ������āA�d�r�d���͂����ɉ������ĕK�v�[���ȓd����������Ă��܂��̂ŋ@��͓d�r��(�o�b�e���[��}�[�N���o��)�Ɣ��f���ē����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ł��傤�B �@�����Ă��̋@��ł͊O�����͒[�q�̉��ɁuxxV�v�Ƃ����d���\��������܂����A���������ꍇ�͋@��̎�舵����������ǂ�ŊO�����͒[�q�̓d�����m�F���A�K�v�ȓd����^���Ă��������B �@�����O���d���̎w��d�����킩��Ȃ��ꍇ�́A�w��d����荂���d����^����Ƌ@����댯������܂�����A�ނ�݂ɍ����d���Ȃǂ�^���Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������B�Ƃ������A�킩��Ȃ��ꍇ�͊O���Ƀ��[�J�[�w��ȊO�̃A�_�v�^�[��o�b�e���[�͌q���Ȃ��ł��������B ���Ԏ� 2009/6/30
|
||||||||||||
| ���e |
�@���̓x�͂��肪�Ƃ��������܂����B �@�ꉞAC�A�_�v�^�ɂ�output+7VDC/3.57A�Ə����Ă���܂����B �@���Z�����Ƃ��뎸�炵�܂����B�������������Ă݂܂��B �@���т��т����܂���B�悭�������d�r�{�b�N�X�̃X�v�����O���O���̎������n���H������ł���܂����B�������ꂾ�Ǝv���܂��B�{���ɂ����������܂����B�Ȃ�قNJO���[�q�Ɠ����o�b�e���[�ɂȂ��ꍇ�͒P���ɓd�������킹������Ƃ�����ł͂Ȃ���ł��ˁB���肪�Ƃ��������܂����B ���� �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����F�X�ƎQ�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��B �@�����o�b�e���[�Ƒ��������Z����4/5A�́A���̂̃y�[�W�Ŕ̔�����Ă��܂��B http://www.batteryspace.jp/shopdetail/003010000008/brandname/ �@�����Z������ɓ������A�O���d���Ƃ��l���Ȃ��Ă��A�ςނƎv���܂����A���ۂɏ����o�b�e���[�ɔ[�߂�ꍇ�A�X�y�[�X�I�ɗ]�T������A�����Z�������鎖�͂ł���̂ł����A�]�T�̂Ȃ��ꍇ�́A�X�|�b�g�n�ړ����g�p���Ȃ��ƁA���܂�ɂ����Ǝv���܂��B kita �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���傤�Ǘǂ��d�r�������Ă��܂��ˁB �@�����o�b�e���[�p�b�N�����Ē��̓d�r��������ւ�����ΊO����͂�����X�}�[�g�ɂł��܂��ˁB �@���̃o�b�e���[�p�b�N���J���Ē��g�����ւ���̂́u�k����v�Ə̂��Ăo�b�p�o�b�e���[�Ȃǂł悭����Ă�������ł��̂ŁA���H���@�Ȃǂ̓l�b�g�Ō�������ĐF�X�Ə����W�߂Ă݂���ƎQ�l�ɂȂ�ł��傤�B �@����AC�A�_�v�^�[��7V/3.57A�ł�����A�J�����̒��ɂ͒�d����H�͓����Ă��Ȃ��Ăقڃo�b�e���[�ƕ���(�v�Z�O�ؑ�)�ɂȂ��Ă��邾���̍\���̂悤�ł��ˁB �@����ł�����7.2V�̓d�r�p�b�N������Čq�������ʼn�����薳�������͂��ł����E�E�E�B  �@�����ׂɂȂ�ꂽ�悤�ɁA�d�r�{�b�N�X�E�d�r�z���_�[�ɂ͍�肪�ȑf�ł��̂Ԃ��ڐG��R���傫����d���p�r�ɂ͎g�p�ł��Ȃ���������܂��B
�@�����ׂɂȂ�ꂽ�悤�ɁA�d�r�{�b�N�X�E�d�r�z���_�[�ɂ͍�肪�ȑf�ł��̂Ԃ��ڐG��R���傫����d���p�r�ɂ͎g�p�ł��Ȃ���������܂��B�@AC�A�_�v�^�[��3.57A�Ȃ�đ傫�ȓd���p�ɂȂ��Ă���Ƃ������́A���̃J�����͎B�e��(�������[�������ݎ��H)�Ɏv�����ȏ�̑�d���������̂ł��傤���B �@�o�b�e���[��2100mAh�Ƃ������ƂłP�b�ȏ�̕��d�\�͂�K�v�Ƃ��Ă���悤�ł��ˁB �@��������ɑ��Ďʐ^�̍����E�����̂悤�ȃv�����ŁA�ړ_���ׂ��o�l�ɂȂ��Ă���d�r�{�b�N�X�E�d�r�z���_�[�ł̓v���X������}�C�i�X�o�l���A�����ĂȂɂ�����E�o�l��{�̂Ɏ~�߂Ă����u�n�g���v�Ƌ���ނƂ̊Ԃ̈������キ���ɐڐG��R��������i���ȓd�r�{�b�N�X�ƂȂ��Ă��܂��B �@�܂��[�q�^�̏ꍇ�A�n���_�Â������肾�ƔM�Ń{�b�N�X�̃v���X�`�b�N���n���Ē[�q����邭�Ȃ�����O��Ă��܂��Ƃ������_������܂��B �@�����̈����ȓd�r�{�b�N�X�ŏ����傫�ȓd���𗬂������ꍇ�́u�j�b�P�����f�[�d�r �P�Z�����d��̐����v�Ō��J���Ă��܂��悤�ȉ������K�v�ł��B �@���������v�����̓d�r�{�b�N�X�́A�u�d�r�œ��d�������悤�I�v�݂����ȓd�C�H��p�œd���͐��\mA�`���SmA���x�܂ŁA�܂��ڐG��R�ɂ�镉�S�ɂ��Ă͑S���C�ɂ��Ȃ��I�Ƃ����p�r�����ł��B �@��d���p�ł͕��d��Type-G�Ŏg�p���Ă���ʐ^�E��KEYSTONE�А��̓d�r�z���_�[�̂悤�ȑ�d���p�r�̂��̂��g���Ƃ����������܂��B �@�������K���[�W�X��l�ɂ��Љ����BULGIN�Ђ̓d�r�z���_�[ (BOX0035)�̂悤�ȓd�r�z���_�[���ǂ��ł��ˁB �@���������AC�A�_�v�^�[�̂悤�ɊO�����͒[�q��7V�ŗǂ��̂ł�����A���W�R���p��7.2V�o�b�e���[�p�b�N���g���̂��m���Ɏ�ł͂���܂��B �@�o�b�e���[�p�b�N�Ȃ璆�̃o�b�e���[�̓X�|�b�g�n�ڂŐڑ�����Ă��ă��X���قƂ�ǂ���܂��A�d�r�̗e�ʂ��傫���A�܂��d�r�̓�����R���P�O�^���͏������̂ő�d����v����@��̓d���ɂ͓K���Ă��܂��B �@�����o�b�e���[�Ə[�d��Ȃǂ�������Ƃ���Ȃ�ɗ\�Z��������̂Ŏ�����ł͂����߂ł��܂���B ���Ԏ� 2009/7/1
|
||||||||||||
| ���e |
�@���̌㌋�ʕł��B�C�̖����l�ŋ����Ē������L�[�X�g���̓d�r�{�b�N�X�ł��܂������܂����I��͂�ڐG�s�ǂ������悤�ł��B�������ł��Ă���݂܂��ˁB����ł��u�������艟�����Ă邺�v�Ƃ��������ł��������ł��B���肪�Ƃ��������܂����B���������B��邩�e�X�g���ł��B �@kita �l�@��肪�Ƃ��������܂��B���̓Z�������͂���Ă���܂��āA�Ȃ����̈����O���d�����Ɛ\���܂��ƃG�l���|�v�͂ǂ��ł������Ă܂����d�r�Ƃ��Ă��D��Ă���Ǝv��������ł��B����ƃX�g���{���G�l���[�v�ŋ쓮�����Ă���܂��̂ŋ��L�ł��郁���b�g������̂�...�B�{���͓����o�b�e���[�Ƀ��|�o�b�e���[���l�ߍ��݂����̂ł����A�܂������ɂ͋Z�p�I�ɂ͖����ł��B�i�j�b�͂����܂������̏����o�b�e���[�̓��[�J�[�Ŕ����ƂȂ�ƈ��㊯���i30,000�~�ł��B�݊��i��4000�~�i���j �@�F�l���肪�Ƃ��������܂����B ���� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�L�[�X�g�����̓d�r�z���_�[�́A���W�R���p�[�d��ŒP�O��[�d����ۂȂǂɂ悭�p�����Ă��āA���̋���̌ł�����D�܂�Ă��܂��B �@�����P�A�d�r�̘e�����ݍ��ދ�����������o���̂��߁A�d�r�̏o������̍ۂɓd�r�̔핢�������Ĕj���Ă��܂����Ƃ�����܂��B �@���i�̓v���X�ɂ��}�C�i�X�ɂ��ڑ�����Ă��Ȃ��̂ŃV���[�g�͂��Ȃ��Ǝv���܂����A�{�̋�����v���X���}�C�i�X�Ɍq����悤�Ȏg����(�Œ���@�H)������Ă���ꍇ�͒��ӂ��Ă��������B������ƃ��W�I�y���`�Ŋɂ߂Ă���ăr�j�[���e�[�v��\���Ă����ق����ǂ���������܂���B �@�O��̓d�ɕ����A�����g���Ă���Ə��X�ɐL���ꂽ�`�Ɂu����āv���܂��̂ŁA���ݍ��݂��ɂ��Ȃ����Ɗ�������y���`�ł�����ƒ��߂Ă�邱�Ƃ������߂��܂��B �@���N�g���Ă���Ƃ����������ɂ䂪�݂��o�Ă��܂����A�������������o�������Ƀy���`�ŏ����Ȃ��Ă�邾���Ō��ɖ߂�͕̂֗��ł��i�O�O�G ���Ԏ� 2009/7/4
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ipod nano�ɏ[�d����d�r��USB�A�_�v�^�̍����H | |||||||||||||
|
�@����ɂ��́B �@���́Aipod nano���悭�g���Ă��āA�O�o���Ȃǂł��A�j�b�P�����f�d�r�ȂǂŁA�[�d���ł���ƕ֗��Ȃ̂ł����A�ǂ����Ă��s�̂���Ă�����̂́A�����łȂ̂ŁA���삵�Ă݂�Ƃ����̂��l���Ă���̂ł����A�ǂ̂悤�ɂ���낵���ł��傤���H �@ipod�́A���������AUSB��4�{����R�[�h�̓��A�ǂ���[�d�Ɏg���Ă���̂������A����������炭���v���Ǝv���܂����A�ǂ��ł��傤���H spark sheet �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͂��߂ɁAipod�́u�ǂ���[�d�Ɏg���Ă���̂����킩��v�Ƃ����P���Ȑڑ��ł��[�d�ł��܂����B �@����ipod�����������Ă��Ȃ��̂Ŏ��؎����͍s���܂��A���̕��̏��ɂ��ƁuUSB�[�q�œd����^����v�ȊO�ɁuUSB�ʐM�[�q(+/-)�Ɉ��̓d��(���ړd���d���ł͖����A1/2Vcc���x)��^���Ȃ��Ɛڑ���F�������A�[�d�͊J�n����Ȃ��v�Ƃ������������ł��B �@DATA+��DATA-�M����1/2Vcc��^������������Ȃ̂ŁA�K���ɒ�R�ŕ������Ċe�M������1/2Vcc��^����ΔF������炵���ł��B������̍ۂ�DATA+��DATA-�ڌq���ł��܂��悤�Ȏ��͐�ɂ��Ȃ��ł��������BUSB DATA���C���͑o�����̒ʐM���ł�����A�ň��̏ꍇipod���܂��B �@���d�r�Ōg�ѓd�b�Ȃǂ��[�d�ł���USB�[�q�o�͌^�ً̋}�[�d��Ȃǂ͑����̔�����Ă��܂����A�P�ɓd���s���ɓd�����o�͂��Ă��邾���̋@�킪�قƂ�ǂŁAipod��iPhone����Apple���i�ɂ͏[�d�ł��Ȃ����������ł��ˁB�uApple���i�Ή��I�v�Ɨw���Ă��鏤�i������܂����A������10�`20�~���x�̕��i�����������łق��̏[�d���萔�S�~������������B �@Apple���i��Ή��[�d����������������Apple���i�ɂ��[�d�ł���悤�ɂȂ�̂ł����A����������ɒ������l�łȂ����~�X�����ď[�d���ipod���Ă��܂��\���������ł��B �@���̖��ɂ��Ẳ���ƁA�Ή�����u�P�O�d�r��ipod nano�Ή��[�d��̐���v�L�����d�g�V���Њ��w�d�q�H��}�K�W��No.2�x��52�y�[�W����̒O������D�搶�́u���o�C���@��ً̋}�d����[�d���\�ɁA�t�r�a�`���[�W���[�v�Ƃ����L���ŏڂ�����������Ă��܂��B����\�Z����2500�~�ł��B �@�d�q�H��}�K�W��No.2�͑��d�q�p�[�c�V���b�v�ł������Ă��܂����A���߂��̏��X�œX������Ɍ����Ď����邱�Ƃ��\�ł��B(Web�ʔ̂�����܂�) �@�܂��Ɂuipod nano��USB�œd�����q�������ł͏[�d�ł��Ȃ������I�A����́E�E�E�v�Ƃ����L���Ȃ̂ŁAspark sheet�l�̗~������܂�܍ڂ��Ă��܂���B ���Ԏ� 2009/6/26
|
||||||||||||
| ���e |
�@���肪�Ƃ��������܂����B �@�ȒP�ɂł���Ǝv���Ă����̂ł����A���\��������Ȃ̂ŁA����Ƃ������X�N�ɂ͎���o�����ɁAipod�ɑΉ������T�[�h�p�[�e�B�̂�����Ǝv���܂��B�l�i��2500�~���x�Ȃ̂ŁA����ƕς��܂���ˁi�j spark sheet �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�`��傫���ɍS��Ȃ��Ȃ玩�삵�Ă݂�̂��ʔ�����������܂��A�l�i�����܂�ς�Ȃ��Ȃ�s�̕i�̂ق������X�}�[�g�ł悢�ł��傤�ˁB �@�{���Ɍ`�ɂ�����炷�ɁA�d�r�{�b�N�X�����o���Ƃ�����S���b�c�ł����̂Ȃ�1000�~�ȓ��ł����E�E�E(�V���[�g������A�����Ă������̂ł���c) �@�s�̕i�̒l�i�ɂ͉�H������������Ă��āA�ǂ��P�[�X�ɑg�ݍ��܂�Ă���Ƃ����_���傫�ȃE�F�C�g���߂Ă��܂��B ���Ԏ� 2009/6/27
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| OLIGHT T25 Regular�Ŏg�p����d�r | |||||||||||||
|
�@���]�ԗp��OLIGHT T25 Regular�����̂ł����A�d�r�I�тŔY��ł���܂��B��ԃc�[�����O�̘A���_���œd�r���g����g�����Ȃ̂ł����A���̏ꍇ�G�l���[�v����2700mAh�N���X�̕������P�x�i90��190���[�����j�ł̃����^�C����L����̂ł��傤���H �@���d���������Ă����1.2�u�������^�C�~���O�ł͗��҂ɂ��܂荷���Ȃ��l�Ɏv���܂��B����ƋP�x�����������_�œd�r��������悤�Ȏg�����ł̓����^�C���͂����ς��Ȃ��C�����܂��B �@�����ł���Έ����₷���G�l���[�v�̕����������Ƃ��v���܂��B���������߂̓d�r������܂����狳���Ă��������B �Ђ�т� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@OLIGHT T25 Regular�̓���DC/DC�R���o�[�^�̐����ɂ����Ǝv���܂���(���͎����Ă��Ȃ��̂Œf��͂ł��܂���)�A2700mAh�̂ق��������Ԗ��邳���ێ��ł��܂��B �@1.2V��鎞�Ԃŗ��҂��r����Ă��܂����A���Ƃ���OLIGHT T25 Regular��1.2V�œ_�����Ȃ��Ȃ�̂ł�����������܂���(���Ȃ萫�\�̈������C�g�ł���)�A���������Ɠd����������܂ŖڂɌ����ĈÂ��͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂���B �@�I������|�C���g�Ƃ��āA��ԃc�[�����O�����邩�A�ꃖ���ȏ�Ԃ������Ă���ɂ��Ă�����O�̓��ɏ[�d�����̂ł���Ηe�ʂ̑傫�ȓd�r�̂ق����L���ł��B �@��x�c�[�����O�����ė����ɂł��d�r���[�d���A���Ɉꃖ���ȏ�g�킸�ɕ��u���āA����ɏ[�d�������c�[�����O�Ɏ����Ă䂭�悤���Y�{���Ȏg����������Ȃ�eneloop���͂��ߎ��ȕ��d�����Ȃ��^�C�v�̓d�r���ǂ��ł��傤�B �@�e�ʂɂ��g�p�ł��鎞�Ԃ͊m���ɏ��Ȃ��d�r�ł����A�ꃖ�����x�ł���Ώ]���^�̏[�d�r�̂悤�Ɏ��ȕ��d���C�ɂ����Ɏg���闘�_��I������Ƃ����킯�ł��B �@��{�I��eneloop�̂悤�ȓd�r�́u�d�r�̊Ǘ����ł��Ȃ��l�����v�Ȃ̂ŁA���������ǂ��������ӎ��œd�r���g���̂��f���ēd�r��I���Ɨǂ��ł��傤�B ���Ԏ� 2009/6/26
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@���̃��C�g��5�i�K�̋P�x�������t���Ă���܂��āA�d�r�̎c�ʂ��s�������1�i�K�����ʂ������čs���d�l�ɂȂ��Ă��܂��B�G�l���[�v�̏ꍇ�A�ő���ʂ�1����10���قLjێ��������5���Ԋu�Ō��ʂ����̃��x���ɗ����čs���Ƃ��������ł��B���̍ő���ʂ��ێ��ł��Ȃ��Ȃ������_�œd�r�����̗\��ł��B �@���ׂ͊o���Ă��܂��A�G�l���[�v��1����10����1.2�u�����荞��ł���f�[�^�������������̂ŁA���̕ӂ肪���������ɂȂ�̂��Ȃƍl���Ă��܂����B����ƍ��e�ʃ^�C�v���㔼�ŔS��������Ă��Ӗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɓc �@���������̃��C�g�ɂ͒�d����H���g�ݍ��܂�Ă���悤�Ȃ̂ŁA�d�r�̓d�����ቺ���Ă��撣���čő���ʂ��ێ����Ă����̂�������܂���ˁB �@���T���Ƀc�[�����O����\��ł��̂ŁA��e�ʃ^�C�v��O���ɏ[�d���Ď����čs�����Ǝv���܂��B�������A�}�ɕK�v�Ȏ������肻���ł�����\���ɃG�l���[�v���������������S�ł��ˁB�B �@2ch�́u�����d���E�ėp���C�g�����]�ԑO�Ɠ��Ɂv�X���̂܂Ƃ߂ł́u�����O�c�[�����O��AA2750�̈���v�Ƃ�����������܂��B������������̃e�X�g�ł͂�����Ɖ������ł��ˁB�T�����[������ł����A�A��e�ʃ^�C�v�̌����_�ł̂������߂͂���܂���ł��傤���H �Ђ�т� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d�r�̎c�ʂ�����ƁA�����I�Ƀ��[�h�𗎂Ƃ��@�\���u�@�\�Ƃ��āv���C�g�ɕt���Ă���̂͒������ł��ˁB �@����Ȃ炠����x�d�r����������J�N�b�ƈÂ��Ȃ�̂Ō��Ă��Ă͂�����킩��܂��ˁB �@�����A����ł��ǂꂭ�炢�ɓd���������������i���Ƃ��Ă����̂��͑��肵�Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��̂ŁA1.2V�Ƃ������ȓd���𐔎��ł͌����܂��A���̔���d���ɂ���Ă�eneloop�̂ق������̎��_�ɒB����̂��x���̂������̂��A����͎��ۂɃ��C�g�Ŏ��Ԃ��v���Ă݂Ȃ��Ƃ���ς�킩��܂���B �@�����܂Łu���Ȃ�Â��Ȃ���(���[�h�𗎂Ƃ���)�A���܂艓�����Ƃ点�Ȃ����x�̖��邳�v�ɂȂ�܂ł̎��Ԃł���A�e�ʂ������d�r�̂ق����L���ł��낤�Ƃ������炢�ł��ˁB �@����悤�Ɂu�Ȃ�ׂ����[�h�ɂ��킹�����邳��ۂ悤�ɂ���v��H���ڂ̂悤�ł�����A�A���J���d�r�Ȃǂ��g�p�����ۂł����܂�キ�Ȃ�Ȃ��悤�ɁA���Ȃ�d���������鎞�܂ł̓��[�h��ۂ悤�ɐv����Ă��āA�d�͒l���Z�ł��̃��[�h��ۂɂ͖����Ɣ��f�����Ƃ���ň�i���Ƃ��ď���d�������Ȃ����A�����ڂ̓d�r�d�����グ��(���ׂ��y���Ȃ��������ŁA�d�r������Ӗ��ł͂���܂���)�����ł�DC/DC�R���o�[�^�̌����̗ǂ�������ŏ����𑱂���悤�ɈӐ}����Ă���̂ł��傤�ˁB �@�����{���ɂ���������H�ł���A�Ō�ɍł��Â����[�h�ɂȂ鎞�ɂ̓A���J�����d�r�ł�������ł����A�j�b�P�����f�[�d�r�ł͉ߕ��d���Ă��܂��Ă��Ă��܂�d�r�ɗǂ��Ȃ��𑱂��Ă��邱�ƂɂȂ�ł��傤����A�����ڂɓd�r���������Ă��̂��d�r�ɂƂ��Ă͗ǂ����@�ł��B �@�ŋ߂͎��ȕ��d�̏��Ȃ��^�C�v�̓d�r���e�Ђ��甭������Ă��āA�e�X�g�p�ɂ����𒆐S�ɍw�����Ă��܂��̂�2500mAh�ȏ�̓d�r�͑S�������Ă��܂���B �@�c�O�Ȃ����e�ʓd�r�ł����߂ƌ����܂��Ă��A�����Ńe�X�g���Ă��Ȃ��̂ŊC�O�����܂߂č��͂ǂꂪ�ǂ����Ƃ��������������킹�Ă��܂���B �@�ȑO�L���ɍڂ���AA2750�������̎g�p�ŕ��ʂɗ��āA���Ȃ�O�Ɏ��������Č��������ނ��Ă��܂��B �@���ǂ��ꂽ�H�O�m2700�����N�ɓ����������肩��NC-M57�ŏ[�d����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA���݂͏�p����O���Ď��X�e�X�g�Ɏg�����x�ł��B(NC-M57�ŏ[�d�ł��Ȃ��Ă��AQEC-F20�Ȃ�S�R��薳���[�d�ł���̂ł����c) �@���ʂɎg���Ă������A�[�d�r�͎g���Ύg�����������ɋ߂Â��Đ��\�������Ă䂭���̂ł�����A�킸������ʼn���悤�ȕs�Ǖi�Ŗ���������͂���Ȃ�Ɏg���āA����Ȃ�Ƀw�^���Ă������ȁH�Ǝv���Δ���������悤�ɂ��āA���܂�ׂ����C���g���Ďg���悤�Ȃ��̂ł͖����Ǝv���܂���B �@�O�ɕʂ̂Ƃ���ł������Ă��܂����A�w�^���Ă��đ�d���p�r�ł͂����ɓd����������e�ʂ�����Ȃ��悤�ɂȂ����d�r�ł��A���d���p�r�ł͂��������g����������܂�����A���]�ԗp�Ȃ�C�eLED���g�����_�Ŏ��̔��F�t�����g���C�g�������S�̂��߂ɂƂ���āA������ɂ͌Â��Ȃ����d�r���u��������v������Ƃ������Ȏg���������āA��蒷���ԓd�r���g���|���Ƃ������Ƃ��ł��܂��̂ŁA�����������������ɂ͎̂ĂȂ��g�������l���Ďg���Ă��̂��d�r�ɗD�������T�C�t�ɂ��D�����g�����ɂȂ�Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/6/27
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �A�����t�@�X���z�d�r�͓d�C��R�H | |||||||||||||
|
�V���R���n�E�X�ŁA�����Ă����A�����t�@�X���z�d�r[R�w]/�@SC1025IDS (-) �ŁA�Q����Ɏg�p�Ǝv����ł����A���z�d�r�͓d�r�ɂȂ��ƁA��R�Ɠ����悤�ɁA�d�C��R�ɂȂ��Ă��܂��ƕ������̂Ŏ��₵�܂����B
3.14 �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ǂ�ȓd�r�ł��A�d�C�I�ɂ͓d�C��R�ɂȂ�܂��B �@�d�r�̒��ɂ͔��d����@�\�ƁA�d�C�𗬂��ɂ�������d�C��R�̗����̐����������Ă��邽�߁A�d�C��R�O�̓d�r�͂���܂���B �@�]���āA�d�r���Q�ȏ㒼��ɂ����ꍇ�͓d�r�̒��̓d�C��R�������u�����v�����邱�Ƃ�����܂��B �@�uSC1025IDS���Q����Łv���ɂ��g���ɂȂ�̂��͏�����Ă��܂��A�Z���d����6.5�ʂ`�������Ȃ��ƂĂ��ƂĂ��ア���z�d�r�ł�����A�t���d��̂悤���������ʂ̓d�C�œ�������p�̑��z�d�r�ł��B(���ʂ̃��[�^�[������A�[�d�r���[�d����悤�Ȏg�����ɂ͎g���܂���) �@�}�C�N���A���y�A���̔���d�����������Ȃ��ꍇ�ɂ͓d�r�̓�����R�̉e���������킸���ł�����A���̃p�l���ɓK�����p�r�Ŏg�p�������̓A�����t�@�X���z�d�r�̓�����R�͂قƂ�ǖ������Ă��ǂ����x�̂��̂ƍl�����܂��B �@�p�r�̂��w��₨�b���������̂ł���ȏ�͐����ł��܂���B���������������B ���Ԏ� 2009/6/24
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �T�C�o�[�V���b�g�̒P�l�d�r�̂����Ɏg����d�r�́H | |||||||||||||
|
SONY�̏[�d�r BC-CS2B�������Ă���܂��B�T�C�o�[�V���b�g�ɂ��Ă����̂ł����A�d�r(NH-AAA-2DA)�����߉ނɂȂ��Ă��܂��܂����B����̓d�r��T���Ă���̂ł����A���̏[�d�r�ŏ[�d���\�Ȃ��̂ł����߂͂���܂��ł��傤���H �䂤�䂤 �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�P�l�j�b�P�����f�[�d�r�Ȃ�Ȃ�ł������Ǝv���܂��B �@NH-AAA-2DA�͈�x�����L�������Ƃ��Ȃ��̂ŁA��������ȓ����̓d�r���ǂ����ȂǑS���ڍוs���ł��̂�(���[�J�[���p�i��ꗗ�ɍڂ��Ă��邾��)�A���[�J�[����������p�r�̓d�r�E�܂��͂��̏[�d�킪NH-AAA-2DA�ȊO�͏[�d�ł��Ȃ��ƃJ�����܂��͂��̓d�r�̐������ɏ����Ă��Ȃ�����A�e�ʂ����ʂ��Ă����ʓI�ȒP�l�j�b�P�����f�[�d�r�ŗǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@800mAh�̂悤�ł�����A�s�̂�800mAh�O��̃j�b�P�����f�[�d�r�ł���Ώ[�d����Ή����Ă���ł��傤�B �@�����T�C�o�[�V���b�g�ɂ��Ă������ł�����ASONY���̒P�l�j�b�P�����f�[�d�r���������[�J�[�i�Ƃ������Ƃōł����S�ł���̂ł͂Ȃ��ł����B �@�S�z�ł���A�\�j�[�̃T�[�r�X�����ɂ��₢���킹���������B �@�p�i��ɂȂ����d�r�̂�����SONY���d�r�������Ă���܂���B�܂��A���̓d�r��BC-CS2B�ŏ[�d�ł���̂��A���Ă������̂��ɂ��Ă��ڂ��������Ă����ł��傤�B ���Ԏ� 2009/6/21
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| YUASA�̃j�b�P�����f�d�r | |||||||||||||
|
�@YUASA�̃j�b�P�����f�d�r�i�������[�v�j http://item.rakuten.co.jp/rowajapan/10001470/ ���������\��͂���܂����H �@�ǂ̌������ǃG�l���[�v�̃p�N���A��Ԑ����ƌ����������̌��ʂɗ��������Ă��܂��Ă��܂�������ɂ͏������҂��Ă��܂� �@�܂��G�{���^�ɂ����҂��Ă����킯�ł����� �@���Ǝ��̓��W�R���Ŏg�p����̂ł�����{������̏d�ʂ��L�ڂ��Ă��������Ƃ��肪�����ł��A���{���g�p����̂ł������������ł܂� �A���X �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA���̂Ƃ���w�����Ă��܂���B�ߏ��Ŕ����Ă��Ȃ��̂ŁE�E�E�E �@GS-YUASA���̎��ȕ��d�}�~�^�C�v�d�r�ueNiTIME�v�Ȃ甃���Ă���̂ł����B �@���d�r�e�X�g�p�̕��d��������e�i���X���Ă��܂��̂ŁA�ēx�g�ݗ��Ă�܂ł͒P�O�d�r�̕��d�e�X�g�͓����͍s���\��͂���܂���B �@����Ƃ悭�V�^�C�v�d�r���u�G�l���[�v�̐^���v�Ƃ��������̎����������������Ⴂ�܂����A�G�l���[�v�����O����d�r�ƊE�ł͎��ȕ��d�̏��Ȃ��d�r�̑f�ށE�\���J�����e�Ђōs���Ă��āA�u���܂��܁v�G�l���[�v�̔��������������������ő��Ђ́u�G�l���[�v�̐^���������v�킯�ł͂���܂���B �@�G�l���[�v�̂s�u�R�}�[�V����������ŏ��߂ď[�d�ł��銣�d�r�^�d�r�̂��Ƃ�m�����l�̒��ɂ͏[�d���d�r��S�āu�~�~���[�v�v�ƌĂԂ悤�Ȃ����ւ�Q���킵��������A���Ԃ̐l�X�̓d�r�ɑ��Ă̔F���̒Ⴓ���߂����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/6/20
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| MHR-R7344��NC-MR58�Ɠ����ł����H | |||||||||||||
|
�@���߂܂��āB �@�ŋ߂�����̃y�[�W��m��A�m���K���ɖ𗧂����Ē����Ă���܂��B �@��������Ȃ̂ł����A�O�H�d�@�z�[���d�튔����А��́uMHR-R7344SET(�P3�^Ni-MH�[�d�r4�{�t)�v�̓G�l���[�v��N-MR58TGS�Ə[�d��̐��\�������Ȃ̂����m�肽���A���e�����Ē����܂����B �@�������ɂ́A �@�@���t���b�V���@�\ �@�@�[�d������1���ʒm �@�@���[�d�L�[�v�@�\�t �@�@�C�O�g�p�Ή�(AC100V�`240V) �Ə����Ă���A�قړ������̂Ǝv����̂ł����E�E�E �@�������ɂ���d�l�ɂ� �@�@���́FAC100V�`240V 12-17VA 50-60Hz �@�@�o�́F�P3�^�@�@�@�@�@�@565mA(*4) �@�@�@�@�@�P3�^(QUICK)�@�@1275mA(*2) �@�@�@�@�@�P4�^�@�@�@�@�@�@310mA(*2) �Ə����Ă���܂��B �@���[�J�[��HP�֍s���Ă����i�y�[�W��������Ȃ�(�I�H)�ƌ����������Ȃ̂�(��) �@�����X������킩��͈͂����ł������Ē�����Ǝv���܂��B �@���Z���������萔�ł͂������܂����A��낵�����肢�v���܂��B �@��Ȏg�p�p�r�̓~�j�l��(��)�ŁANi-CD�[�d�r(700�`1000mA)�̏[�d�Ɏg�p���悤�ƍl���Ă���܂��B �@���Ȃ݂ɍw���̓G�b�N�X�O�_�c�X�����1980�~�ƌ����j�i�l�ł���(��) �䂫�Ђ� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@MHR-R7344(�P�i)��MHR-R7344SET(�d�r�Z�b�g)���O�H�d�@�z�[���y�[�W�ɍڂ��Ă邱���ł��ˁB �@�uMHR-R7344�͎O�m�̏[�d��Ɠ����H�v�Ƃ���������Ɖ́A���傤�ǂP�N�O(�ƂQ���O)��������Ɍf�ڂ�����܂��B �@���Ȃ݂ɁA���Ќ������Y�i(OEM�i)�ł́u�d�r�`�F�b�J�[�@�\�������v�Ȃǎ���(�O�m)���i�Ƃ͍��ʉ����v���Ă��܂��̂ŁA�u�O�m��NC-MR58�Ɠ����ł����H�v�Ƃ���������ɂ́u���g���Ⴂ�܂��v�Ƃ��������Ȃ���Ȃ�܂���B�����ɂ́u�������������������v�Ƃ������ł͂���܂���B�@�\�I�ɂ͕ʐ��i�ł��B �@���̃G�l���[�v�Z�b�g�Ȃǂɕt���Ă���NC-MR58(�����ɂ�2700mAh�d�r�Ή��@��)�ł͖����A�P�O�̋@���NC-MR57(�����ɂ�2500mAh�d�r�Ή��@��)�Ƃقړ����̓��e���Ƃ��l�������̂��Ó����Ǝv���܂��B���^�@��ł����A�[�d����@�\�Ɋւ��Ă�MR58�ƕς�͂���܂���B(�ׂ��ȃv���O�����E����ʂł͐V�^�̂ق������P����Ă���\���͂���܂�) �@�P����O�̏[�d��ł����A�~�j�l��p�Ƀj�J�h�d�r���[�d����ɂ͉������͂���܂���̂ŁA���������Ă悩�����Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2009/6/19
|
||||||||||||
| ���e |
�@�f�������X�|���X�ƒ��J�ȉ�����肪�Ƃ��������܂��B �@�܂��A�ߋ��L���̌����Ƃ��ׂ̈��萔�����|�����Ă��܂��\����܂���ł����B �@�j�J�h�d�r�̏[�d���x�Ȃ���Ȃ������Ƃ̎��ŁA���S���܂����B �@�ꉞ�V�^�G�l���[�v���[�d����ۂ͂����ƎO�m���i���g���Ă�邱�Ƃɂ��܂�(��) �䂫�Ђ� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�J�[�ɂ���������Ȃ����x�̈Ⴂ�̓v���O�������ꂢ�Ă�����A�n�[�h�E�F�A��ŕ��i���������͂���ł��傤���A���m����Ă���Ή��d�r�E�e�ʂ̂��̂ł���قږ�薳���[�d�ł���͂��ł�����A���������Ă��܂��g���Ηǂ��ł��ˁB �@���Ƃ́E�E�E���ДO���MH-C9000���Ď����Ă݂Ă��������I(^^; ���Ԏ� 2009/6/20
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �G�l���[�v�́u���[�d�W���v�u�[���d�����W���v�́H | |||||||||||||
|
�@�͂��ߓ��e�����Ē����܂��B �@���S�҂Ȃ̂Ń|�C���g�����ꂽ����Ő\�������܂������₪�������܂��B �@���A�V�тő��z�����d�ŃG�l���[�v�̏[�d���l���Ă���܂��B �@�\�[���[�p�l���̑I��ɂĎQ�l���Ă���g�o�i�Ɨp�\�[���[�V�X�e���ł����j�ŁA�o�b�e���[�̖��[�d�W����[���d�����W�����̌��t���L�ڂ���Ă��܂��B �@�V�X�e�����傫���̉��~�d�r�Ȃǂ̌W���Ǝv���܂����A�G�l���[�v���̏[�d�r�ɂ����Ă͂܂�W���͂������܂����H �@���[�J�[�ɖ₢���킹�܂����Ƃ���A���̂悤�ȌW���͂Ȃ��A�[�d���@�݂̂��������Ă��������܂���ł����B �@�����Ⴂ�Ȃ����₩������܂���낵�����肢���܂��B fatman45 �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�j�b�P�����f�[�d�r�ɂ��u���[�d�W���v�u�[���d�����W���v�ɑ������鐫�\�l�͑��݂��܂��B �@�������A�u���[�d�W���v�͏[�d���@�E�[�d�d���ɂ��قȂ鐔�l�ł�����P���ɉ����ł��Ƃ����������͂��܂���̂ŁA�ʏ�́u���[�d�W���v�Ƃ����`�ł͐��l���o���܂���B�t�ɓd�r�ŗL�ł͂Ȃ��A�[�d���@�̋Z�p�I�Ȍv�Z���Ȃǂ̂ق��ɗR�����鐔�l�Ȃ̂œd�r���Ƃɂ͏�������\�����肵�Ȃ��̂����ʂł��B �@�u���z�d�r�ŏ[�d�v�ƌ����܂��Ă��[�d��H�E�����͗l�X�ł�����A���̂��g���ɂȂ�[�d��H�̐v�����d�q��H�̗��_�ƃj�b�P�����f�[�d�r�̓������n�m���������������ŎZ�o����K�v������܂��B �@�u�[���d�����W���v�ɂ��܂��Ă��A�j�b�P�����f�[�d�r�͏[�d���Ă����Ɏg���ꍇ�ƁA������x���u�����ꍇ�ł͎��ȕ��d�ŗe�ʂ��ς�d�r�ł�����A�P��́u�[���d�����W���v�Ƃ������l������킯�ł͂���܂���B �@���Ɂu�����t���[�d���āA����������g����p�r�v�ő��z���[�d����̂ł���A�ق�95�`99�����x�̐��l��������ł����悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�A���j�b�P�����f�[�d�r�̏ꍇ�����̐��l���[�d���Ɍv�Z���Ɋ|���ď[�d���Ԃ𑝂��ȂǂƂ������͐�ɂ��Ȃ��ł��������B�u�[�d�������Ǐ����ĂȂ��Ȃ�Ԃ���ŏ����瑽���[�d�����Ⴆ�I�v�Ȃ�Ă���Ă��A�d�r�ɗ��܂�e�ʂ͌��܂����T�C�Y��������܂���A����ȏ�l�ߍ������Ƃ��Ă��ߏ[�d�ɂȂ��ēd�r�Ƀ_���[�W��^���邾���ł��B �@�����čŌ�ɏd�v�ȓ_�ł����Aeneloop�Ȃǂ͒P���ȑ��z�����d�p�l���ƌq���ł̏펞(���X�A���ł�)�[�d�ɂ͓K�����Ȃ��d�r�ł��B �@�}���[�d�A�܂��͂�����x�̍����[�d�Ńs�[�N���o�ȂǂŖ��[�d�����o���ď[�d���~�߂āA����ȏ�͉ߏ[�d�����Ȃ��[�d���@�ł���ΐv�l�ʂ�̐��\�����܂����A���̂悤�ȃj�b�P�����f�[�d�r�ɂ������[�d���@�ȊO�ŁA���Ƀj�b�P�����f�[�d�r�p�ł͑S���������z�d�r�p�l���Ƃ̒��������ȂǂŖ������z�ɓ��ĂĂ���ƁA����I�ȉߏ[�d�ŒZ���Ԃɓd�r������Ă����ւ�������Z���Ȃ��Ă��܂��ł��傤�B �@�ꕔ���[�J�[�̕i�ł̓R���p�N�g�ȑ��z���[�d��ƒP�O�^�j�b�P�����f�[�d�r�̃Z�b�g�������Ă��܂����A�����ɂ́u�ߏ[�d�ɋ����A�펞�[�d�p����d�r�v���̗p����Ă��āA���ʂ̎s�̂̃j�b�P�����f�[�d�r�ł͓d�r��ɂ߂�Ƃ������ӏ���������Ă��܂��B �@���d�r�z���p�l���ŏ[�d���邵���݂ɂ��ĉ������Ă���g�o�Ȃǂ��Q�l�ɂ���Ă��邻���ł����A�j�b�P�����f�[�d�r�͉��d�r�Ƃ͓����E�[�d���@���S���Ⴄ�d�r�ł�����A�������������y�[�W�͂��܂�Q�l�ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂��B �@���z���p�l���ł̃j�b�P�����f�[�d�r�̓���I�ȏ[�d�ł́A���̋����ɂ���č��X�ƕς�d����Ԃł����肵�ăj�b�P�����f�[�d�r�ɏ[�d�d���𗬂����艻��H��A�j�b�P�����f�[�d�r���ߏ[�d�ɂȂ�Ȃ��悤�ȃR���s���[�^�V�X�e���ɂ��d�r�Ǘ��E�ی쑕�u�ł��J�����Čq���Ȃ�����A�u�[�d�͂ł��邪���d�r���Ă������[�d��v�ł����������Ƃ͂悭�L�����Ă����Đ���E�g�p���Ă��������B �@�u���������̃j�b�P�����f�[�d�r�[�d�����Ȃ����x�̓d���ɒ�d�����䂷��v�Ƃ����l����������A���̏ꍇ�͂��Ƃ���eneloop����min.1900mAh�̗e�ʂ�����܂����A�����1000�`1500mAh���x�����g��Ȃ��Ɗ�����ď[�d���䂷����@�ł��[�d��H��v�ł��܂��ˁB �@�����A���S�ɖ��[�d�ɂȂ�Ȃ����x�̏����Ⴂ�ڂ̓d���ł��A�������z���o�Ă���Ԃ̎��Ԃ͓d�����������ςȂ��ɂ���Ƃ������@�Ńj�b�P�����f�[�d�r�����Ȃ����ǂ����͎��̂ق��ł͎����������Ƃ�����܂���̂Ō��ʂ͕s���ł��B �@��ʓI�Ɂu�g���N���[�d�v�Ƃ������ɏ��Ȃ��d������ɗ����āA���������Ə[�d��������@�ŏ�ɓd�r�[�d�ɕۂ��@������܂����A�j�b�P�����f�[�d�r�̏ꍇ�͂���������ɓd���E�d����^��������ł͒Z�����ɗ��Ă��߂ɂȂ����Ƃ������|�[�g�͂��������Ă��܂��B������[�J�[�����������[�d�����͕s�K���Ǝ����Ă��܂��B �@�������Ƀj�b�P�����f�[�d�r�����z���p�l���Ŗ����ߏ[�d���Ă����Ȃ��̂ł���A�O�m�d�@�����́ueneloop�p���z�d�r�[�d��v�͒���Li-ion�[�d�r��������Ă��āA��U�����ɑ��z�����d�����d�C�𗭂߂Ă����āAeneloop�ɂ͂�������}���[�d��H��ʂ��Ă����Ə[�d�`�F�b�N�����Ȃ���[�d����Ƃ������Ȗʓ|�ȕ����͎��Ȃ��Ă��ǂ��͂��ł��B �@���z���p�l���ƁAeneloop���W�{���炢����d�r�{�b�N�X�œ����ɂW�{�قǍڂ��ē��ɓ��ĂĂ����A��ɂS�{�~�Q�Z�b�g�͏[�d�ł��Ă���I�Ƃ������ȑ��u�̂ق����C�U�Ƃ������ɖ��ɗ��������ł���ˁB�E�E�E�ł��Z�p�I�ɂ��������[�d��ł͂���܂���B �@������Ɠ�����������܂������A�v�́u�j�b�P�����f�[�d�r�͑��z�����d�Ȃǂœ���I�ɏ[�d����p�r�ɂ͕s�K�ȓd�r�Ȃ̂ŁA���������g�����͂��Ă̓_���v�Ƃ������ł��B �@�������A��p�̏[�d�V�X�e�����J�����ăj�b�P�����f�[�d�r�Ƀ_���[�W��^���Ȃ����������邩�A�����܂ŗV�тȂ̂��P�N��������eneloop�����Ă�������I���z�d�r�ŏ[�d�ł����炻��Ŗ����Ȍ��ʂ�����I�A�Ƃ������Ɋ�����Ďg����̂ł���A�Z�p�I�Ȗ��͖������Ē����č\���܂���B ���Ԏ� 2009/6/19
|
||||||||||||
| ���e 6/19 |
�@���A�L���������܂����B �@���J�Ȑ������܂��ă����������Ă������������o���܂����B �@������M�g�o���Q�l�ɂ����Ē��������H��Ƀg���C�������ƍl���܂��B �@�L���������܂����B fatman45 �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| TrustFire�̐V�^TR-001�H | |||||||||||||
|
�@TrustFire�̏[�d��ɐV�^���o�܂����H �@TrustFire Multifunctional Charger TR-001 http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2727 �@��̎ʐ^������ASONIX�@SN8P2711������Ȃ悤�ł��B http://www.kaidomain.com/UploadFiles/633565711372783750.jpg �@���̉�H���Ăǂ��v���܂����H kaido�z�� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@TrustFire TR-001�̌�p�@�ł��傤���B(�Ƃ������A�^�Ԃ�TR-001�̂܂܂ł��ˁc) �@�ʐ^����������TR-001�̂悤�ȃA�i���O��H�ɂ���d���E��d������̏[�d��H�ł͂Ȃ��AUltraFire WF-139(���^)�̂悤�ɒ�d��(�㔼�͔\�͕s���œd���͉�����H)�[�d��H�ŏ[�d�̏I������̓}�C�R���Ŕ��f���Ă���悤�Ɍ����܂��B �@SN8P2711�Ƃ����u�_�C�i�p���[ �p�[�t�F�N�g�`���[�W���[�v�ł��g�p����Ă����}�C�N���R���g���[���[�ł�����A�VTR-001������Ȃ�Ƀv���O�������䂳��Ă���̂ł��悤�B �@�����Akai�̊�ʐ^�͕s�N���ŁA���������̃p�^�[����ǂ������ł́u�����Ɖ�H�v���Ă�̂��ȁH�v�Ƃ����_�������܂��̂ŁA���������ĕ\���������Ɗm�F����܂ł͈��S�ł���[�d��Ƃ������f�͉����܂���B �@���̓}�C�R�����䂳��Ă���UltraFire WF-139���A�i���OCC/CV����ɕς��ď[�d���Ԃ����ɒ���������悤�ɂȂ�A�t�ɃA�i���OCC/CV���䂾����TR-001���}�C�R������ɕς����Ƃ����͉̂�������Ȃ��̂�����܂��ˁB �@���ۂɏ[�d�d�����ǂꂭ�炢�ɐݒ肳��Ă��āA�[�d���Ԃ������̂��ǂ����͍w�����ĕ������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂��A��قǒ�d���Ȑv�łȂ���ΈȑO��TR-001�Ɣ�ׂ�Ό��ƃX�b�|��(����)���炢�̍��͂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�P�����Ď����Ă݂����ł����E�E�E�EKai�̂��Ƃł�����A�w�������狌�^��TR-001���͂��I�Ƃ����\�����̂Ă���܂���̂ŕ|���Ē����ł��܂���(��) �@�Ȃɂ���Kai�ł�����A�O�̉�ꂽ�o�b�e���[���͂������ɂ��Ă̋��ɂ����܂��ɉ��̕Ԏ�������������܂���B���ꂪ������Kai�̃��[�U�[�T�|�[�g�̐��ł�����E�E�E ���Ԏ� 2009/6/16
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �j�b�P�����f�d�r�̊O���`���[�u | |||||||||||||
|
�@�[�d�r���D���ŁA�C�̖�������́A��ώQ�l�ɂȂ��Ă��܂��B �@�j�b�P�����f�d�r�̊O���`���[�u�ɂ��Ă��������܂��B �@���N�i�W�N�H�j������g�p���Ă��܂��ƁA�O���`���[�u���͂��ꂽ��A���t���āA�{�̂������Ă����肵�܂��B �@���[�J�[�̈ӌ����Q�l�ɂ��Ȃ���A���͈��S�ׁ̈A�傫���͂��ꂽ���̂́A�g�p���Ȃ��悤�ɂ��܂����B �@�ł������̏��ł���A���ȐӔC�Ŏg�p�������ł��i�L�E�ցE�M�j �@�{�̂̉����A�͂���Ă�����g�p���܂���B �@�Q�{�Z�b�g����@��ŁA�V���[�g���|������ł��B �@�����ƁA�}�C�i�X�[�q�߂��A�{�̉��̕��ł��A �@�d�C���ʂ����̂ŋ����܂����B�m��܂���ł����B �@�������A�}�C�i�X�[�q�܂�肪�A�͂���Ă�����x�̂��̂́A�g�p���Ă��������ł����A�[�q�̕�����ŁA�{�̂̉��������������肷����̂�����܂��B *�ǂ̒��x�͂��ꂽ��g�p���~�߂܂����B *�≏�e�[�v�͎g�p���Ȃ����������̂ł����B *�O���`���[�u�́A�ǂ̂悤�Ȗ�ڂ�����܂����B *�o�N�ŁA�[�d�r�{�̂̑̐ς́A�ό`���A�O���`���[�u���͂���₷���Ȃ�̂ł����B �@���v�ȂǁA�P�{�Ŏg�p����ꍇ�́A���̊O���`���[�u���A�ꕔ�͂���Ă��Ă��A�V���[�g����S�z�������ׁA�g�p�ł��܂����B *�Ⴄ����ł��B �@�j�b�P�����f�d�r���P�N�ȏ�A���͔O�̂��߂P�N���ɏ[�d���āA�����ԕۑ�����ꍇ�i�����R��������ɋ߂��g�p���܂ށj�́A�d�r�̗e�ʂ^���ɂ��邩�A�����ɂ��邩�A�ǂ��炪�����Ȃ��A�d�r�ɗD�����ł����B �@�����Ȃ�A���݂܂��A��낵�����肢���܂��B �����D�X�y�V���� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�O���`���[�u���j��āA�d�r�̋����{�f�B�������Ă�����͎̂g�p���Ȃ��ł��������B �@�����ȃL�Y��j��ł���A�Z���n���e�[�v��r�j���e�[�v���ŏ����ǂ��Ŏg�p���Ă����v�ł����A�e�[�v���@��̓d�r�{�b�N�X�����������������Ă��܂����肵���ꍇ�A���������\�����e�[�v�̈Ӗ��������Ȃ�V���[�g��j��̊댯��������܂�����A�ꉞ�͉��}�蓖���x�Ƀe�[�v�͎g�p�ł��܂����@���g�p�ɂ���Ă̓_���ȏꍇ������܂��B 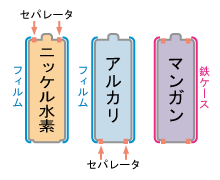 �@���^�̊��d�r�̌`�������j�b�P�����f�[�d�r�E�A���J�����d�r�E�}���K�����d�r�͊�{�I�ɂ͂��̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B
�@���^�̊��d�r�̌`�������j�b�P�����f�[�d�r�E�A���J�����d�r�E�}���K�����d�r�͊�{�I�ɂ͂��̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B�@�j�b�P�����f�[�d�r�̓{�f�B�̋����ʎ��̂��}�C�i�X�[�q�ɂȂ��Ă��܂��B�ł�����t�B�������������Ƃ����̓}�C�i�X�ɂł��B �@�A���J�����d�r�͋t�ŁA�{�f�B�̋����ʎ��̂̓v���X�[�q�ł��B�j���ƃv���X�ɂ������o���ɂȂ�܂��B �@�}���K�����d�r�͓���ŁA���̓d�r�̓d�ɂƂ͐≏���ꂽ�S���̃P�[�X��킹�Ă���܂��̂ł��ꂪ������邱�Ƃ������ł����A��{�I�ɂ͓S�P�[�X�̓v���X�ɂ��}�C�i�X�ɂ��q�����Ă��܂���ǂ��Ƃ��V���[�g�͂��܂���B �@�����t�B�����̔j�ꂽ�d�r���g�p����ƁA�@��̓d�r�{�b�N�X�����ɓd�C�z�����ʂ��Ă�����A�������̋���d�r�̉��܂ł���^�C�v�Ȃǂł̓t�B�����̔j��ڂƂ����ʓd��Ԃ̕������ڐG���ăV���[�g����댯��������܂��B �@�u�d�r����{�����g�p���Ȃ�����v�Ƃ��������ł͈��S�ł��܂���B�d�r�{�b�N�X���ɐj���̂悤�Ȕz�����ʂ��Ă���@��������A����ƐڐG����Ɠd�r��{�ł��V���[�g����ꍇ������܂��B �@�܂��t�B�����̔j�ꂽ�d�r���m���Q�{�ȏ���ׂ�ƁA�d�r���m���j��ڂŃV���[�g���Ă����ւ�댯�Ȃ��ƂɂȂ邩������܂���B �@�g�p����@��̒��Ŕj��ڂ̕������������d�C�I�ɑS���ڐG���Ȃ��\���ł�����j�ꂽ�܂܂̓d�r�����Ă��������̂��N���܂��A����ł��j�ꂽ�d�r���g�p����̂����ǂ��ʼn��ɐڐG���邩�킩��܂����̂ŋɗ͔����܂��傤�B �@�j�b�P�����f�[�d�r�E�A���J��/�}���K�����d�r�ł͌o�N�œd�r�������ăt�B�������j��邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B �@�ߓd���𗬂���(�܂��̓V���[�g������)�ُ픭�M���Ėc������ȂǁA�����������g�����������ꍇ�͕ό`���邱�Ƃ�����܂��B �@�ό`�����d�r�͒��g�Ɉُ���������Ă���\���������ł�����A�����Ɏg�p����߂Ĕp�����܂��傤�B �@�d�r�̕ۊǎ��ɏ[�d���Ă������ق����������ǂ����ɂ��ẮA�u�H���[�d��AMW1268�̒��g�́E�E�E�v�̃y�[�W�Ɂu���d�r�̕ۊǕ��@�i�Ǘ����@�j�v�Ƃ��Čf�ڂ��Ă��܂��̂ł������������B ���Ԏ� 2009/6/5
|
||||||||||||
| ���e |
�@���A���肪�Ƃ��������܂����B �@���ꂩ��[�d�r�́A���J�Ɏg�������Ǝv���܂��B ���o�N�œd�r�������ăt�B�������j��邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B �@�ǂ������i�L�́M�G�j �@�܂���������܂�����A���₵�����Ǝv���܂��B �@�}���K���d�r���A���܂ł��D���ɂȂ�܂����B �����D�X�y�V���� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@������͈̔͊O�ŁA�o�N���{�̂��c�����đ�ςȎ��ɂȂ�d�r�Ƃ������̂�����̂ł����A����̓d�r�Ƃ͈Ⴄ���߂ɏ��O���Ă��܂��B �@�ʔ����d�r�Ȃ̂ŋL�����\��ł����A�������N���炢�x��Ă��܂��B ���Ԏ� 2009/6/10
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d���H��̃T�[�}���v���e�N�^�[ | |||||||||||||
|
�@�d���H��̃T�[�}���v���e�N�^�[ �@�������Ƃ��͂����q�������Ă��������Ă܂��B �@���ɏ������Ă܂��B �@�d���H��̃o�b�e���[�p�b�N�̒��ɓ����Ă���T�[�}���v���e�N�^�[�����荢��ł��B �@���[�J�[�u�E�`���v�u�N���N�\���v�Ȃǂł��� �@�����i�ŏ������Ă��邩�A���͑�p���������̂��ėL��܂��ł��傤���B isamu �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�قƂ�Ǐ����肳��Ă��Ȃ����i�ł��ˁB �@�����o�b�e���[�̒��̃T�[�}���v���e�N�^�[����ꂽ�̂ł���A�H��̃��[�J�[�ɏC���ɏo�����ق��������Ǝv���܂��B �@���Ƃ��A�T�[���X�^�b�g�f�q��POWER MOS-FET��g�ݍ��킹���u�����J�b�g��H�v�Ȃǂ�g�ݓ���邱�Ƃ��l�����܂����A�H��̃o�b�e���[�̒��̃T�[�}���v���e�N�^�����x�œ����̂������܂��A�܂��ǂꂭ�炢�̓d���ʂɑΉ�����FET���g�p��������̂����H��̎�ނȂǂɂ���ĈႢ�܂�����ȒP�ɂ͉�H�}���o���āu�͂��A����Łv�Ƃ͂䂫�܂���B �@�܂��T�[�}���v���e�N�^�́u�傫�ȓd����������T�[���X�^�b�g�v�Ȃ����̒P���ȃX�C�b�`�ł����A����䂦�ɋɐ��������čH����g���u���d�v�̎����A�o�b�e���[���[�d����u�[�d�v�̎��ɂ������œ����܂��BFET���g������H�ł͕Е����ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@��̓I�ɍH��̋@���o�b�e���[�̎d�l�E�v�Ӑ}���킩��Ȃ�����A���[�J�[���ǂ̈Ӑ}�łƂ���Ă���̂������킩��Ȃ��̂œd�q��H�ȂǂŒu��������ɂ��Ă��ȒP�ɂ͂䂫�܂���B �@�u�P���ȃX�C�b�`�v�Ƃ͏����܂������A�T�[�}���v���e�N�^�ɂ́u���x�v�ȊO�Ɂu�d���v�ł̃J�b�g�@�\���t�������@�\�ȕ�������A�d�l�͗l�X�ł��B �@���Ƃ��������̉�Ђ̎�舵���T�[���X�^�b�g���i�����ł�����ȂɎ�ނ�����A�����́u�T�[�}���v���e�N�^�v�Ƃ��������L�[���[�h�ł̓q�b�g���܂���B �@�T�[���v���e�N�^�͂����܂ŃT�[���X�^�b�g�Ƃ����@�\�𗘗p�������i�̂����ꕔ�̌Ăі��ł�����A�T���͈͂��L���ē���i�̎g�p�ł��镔�i���ǂ����ɔ����Ă��Ȃ����T���Ă݂āA��������[�J�[�C���ɏo���Ă��������B (�T�[���X�^�b�g�Ō�������ƁA�d�q���i�X�ŎR�قǏo�Ă��܂�) ���Ԏ� 2009/5/30
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �f�W�g���i2SC3402�j�̓f�W�g���ł͖����H | |||||||||||||
|
�@�����Â��L���̂��ƂŐ\����܂���B �@Panasonic�̋}���[�d���BQ-390�̌ʏ[�d�\���������̌��ɂ��Ď��₵�����̂ł����A�����Ɏg���p�[�c�ł���A�f�W�g���i2SC3402�j���}���c�ŒT���Ă����Ƃ���A�����^�Ԃ̂��̂��A�g�����W�X�^�Ƃ������O�Ŕ����Ă��܂����B �@���炭����ł����Ǝv���܂����A�f�W�g���͂�������ƃf�W�^���g�����W�X�^�Ƃ������O�Ŕ����Ă����̂ŁA������Ƃ���ő��v�Ȃ̂��s���ɂȂ����̂ŁA���₳���Ă��������܂��B �@���Ȃ݂ɁA�f�W�^���g�����W�X�^�Ə�����Ă��鏤�i���ׂĂ��m�F���܂������A�^�Ԃ�2SC3402�̂��̂͑��݂��܂���ł����̂ŁA���Ԃ�g�����W�X�^�Ə�����Ă��Ă����v���Ǝv���܂����A�ǂ��ł��傤���H spark sheet �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�}���c�̌f�ڂ��Ԉ���Ă��܂��B �@�u�f�W�^���g�����W�X�^(�f�W�g��)�v�Ƃ́A�f�W�^����H�ɒ��ڌq���Ŏg�p�ł���A�u�o�C�A�X��R�����^�v�̃g�����W�X�^�̎�ޖ��ł��B �@�J������ROHM�Ђ�DATxxx��DTCxxx�V���[�Y�A������RNxxx�V���[�Y�Ȃǂ��L���ł��B �@2SC3402�Ȃǂ�SANYO�Ђ̐��i�́A�f�[�^�V�[�g����������������킩��Ǝv���܂����o�C�A�X��R��������Ă��āA���m�Ɂ@NPN Epitaxial Planar Silicon Transister (with Bias Resistance) �ƕ\�L����Ă��܂��B �@�������u(with Bias Resistance)�v�Ƃ����ӂ��Ɂu(�o�C�A�X��R���t����)�v�Ƃ������������̃g�����W�X�^�̓d�C�I�E�\���I�����̂����ꕔ�̕\�L�Ƃ��Ď�舵���Ă��āA2SA/2SC�Ȃǂ̏]���̃g�����W�X�^�̌^�Ԃ���ʓr�����邱�ƂȂ��ʏ�̃g�����W�X�^�̃V���[�Y���̈ꕔ�̕��i�Ƃ��Ď�舵���Ă��܂��B �@�]���āASANYO�Ђ̏��i���ނɂ́u�f�W�^���g�����W�X�^�v�Ƃ������i�͖����Ƃ����ӂ��Ɏ咣���Ă���悤�Ɍ����܂��̂ŁA������ʓI�Ƀf�W�^���g�����W�X�^�ƌĂ��g�����W�X�^������Ă��Ă��ASANYO�Ђ̎咣�����ݎ���2SC3402�Ȃǂ́u�f�W�^���g�����W�X�^�v�ł͂���܂���B�����܂Łw�o�C�A�X��R���g�����W�X�^�x�Ȃ̂ł��B(�Г��łǂ����������E�v�z���͒m��܂��A�f�W�^���g�����W�X�^�E�f�W�^�����o�^���W�ŁA���W�����l���ł��Ȃ������̂ŋ��͂Ɉӎ����Ă���Ƃ�����������܂���) �@������Ƙb�̓Y���܂����A���d�r�^�̃j�b�P�����f�[�d�r������Ă����āu�����̏��i��eneloop�ł��B���傻������̃j�b�P�����f�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�����܂�eneloop�Ƃ������ł��I�v�ƌ��������Ă���SANYO�̏�ԂɎ��Ă���Ǝv���܂��H�A���ꂪ�O�m�̎Е��Ƃ������̂ł��傤���B �@�}���c�̏��i���ނł̓��[�J�[�̎咣(�����܂�2SCxxx�̂����̈�ł���)�����ݓ���Ă�����̂Ǝv���܂��B �@���[�U�[�����i����������ۂɂ͂�����ƍ��������ɂȂ�܂��̂ŁA�}���c�̏��i���ނ͋���Ƃ���u������Ƃ���ő��v�Ȃ̂��H�v�Ǝv���Ă��܂��܂��ˁB �@�}���c��Web�ʔ̃T�|�[�g�S���ɒ�����i�����Ă݂Ă͂������ł��傤���B ���Ԏ� 2009/5/30
|
||||||||||||
| ���e |
�@�������������l���Ԉ���Ă�����̂Œ������E�E�B �@2SC3402�͂i�h�r�ł̌^�Ԃł��B �@�c�s�`�Ƃ��c�s�b�Ƃ��͎Г��^�Ԃł��B �@�Q�r�b�R�S�O�Q�Ƃ́A�Q�̐ڍ������������g�p�m�o�m�g�����W�X�^�łR�S�O�Q�Ԗڂɓo�^���ꂽ�����́E�E�ƌ����Ӗ��ł��B �@�i�h�r��ł̗p�r�̓X�C�b�`���O�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B �@�����Ɍ����A�h�b�̕��ނɓ���f�q�ł����o�^���Ƀ��[�J�[������́������ł���E�E�ƌ�������ɂȂ��Ă��܂��킯�ł��B �@�i�h�r�ł̓f�W�^���g�����W�X�^�ƌ������ڂ������̂ŁA�g�����W�X�^�Ő����ł��B �@�Г��^�Ԃł���Ύ��R�ł����A�������ҏ����ł�����B �@�}���c�͂Q�r�`�E�a�E�b�E�c�ŕ����Ă܂����A�c�s�b�͕ʂ̒I�ɓ����Ă܂����疳�����ƁE�E�E�������Ђł�����B azahatiouzi �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���݂܂���B�ǂ����Ԉ���Ă���Ƃ������w�E�Ȃ̂��悭�킩��܂���B �@azahatiouzi�l��5/30�̋L�q�ƑS����������������Ă���悤�Ɍ����܂��B �@�Ԉ���Ă�����e�����������Ȍ��ɂ������肦�܂��B �@����Ɓu�������l�v�E�E�E�ɂ��Ă͉��x�������Ă��܂��̂ō���x���m�F���������B ���Ԏ� 2009/6/2
|
||||||||||||
| ���e 6/3 |
�@�ԓ����肪�Ƃ��������܂��B �@�f�W�^���g�����W�X�^�͏��W��������ł��ˁB �@�}���c�ɖ����s���̂ŁA���������肢�������Ǝv���܂��B spark sheet �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �j�J�h�d�r�����[�^�[�����Ȃ��Ȃ�܂ŕ��d���Ă����ł����H | |||||||||||||
|
�@����������܂��i�Q�j�� �@�߂�������SANYO�̃J�h�j�J�d�r�i�V�O�O��Ah�j���\��ł��܂� �@�ō��Y��ł���͕̂��d�Ȃ�ł� �@�^�~���̃I�[�g�f�B�X�`���[�W�͐��Y��~�Ȃ̂ŁE�E�E�Ȃ�ł� �@�Ȃ̂Ń~�j�l��ȂǂłЂ����烂�[�^�[���܂킵�ă��[�^�[�������Ȃ��Ȃ�܂ŕ��d����������Ǝv������ł������낢��ȃy�[�W���݂���u�j�J�h�͊��S�ɂO�܂ŕ��d����Ɠd�r��ɂ߂�v�Ə����Ă������ł������[�^�[�������Ȃ��Ȃ�܂œd�r����d������d�r��ɂ߂�̂ł��傤���H �J���\ �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ɂ߂܂��ˁB �@�j�J�h���j�b�P�����f���A�u�I�~�d���v�Ƃ������d�������Ŏ~�߂�ׂ��d�����d�����Ⴍ�Ȃ�悤�ȁu�ߕ��d�v������Ɠd�r�̓����Ŏg�p����Ă��鉻�w�������{���̐��\���ێ��ł��Ȃ��Ȃ鉻�w�ω��𑁂��N��������������܂�����A�ߕ��d�����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��d�r�̎������g����悤�ɂ���K�{�����ł��B �@�����j�J�h�d�r�̓j�b�P�����f�[�d�r�Ɣ�ׂ�Ǝg�p�f�ނ��ߕ��d�ɑ��đ����͋�������������̂ŁA�̂���ߕ��d���݂̕��d�����Ă����d�킪�����̂������ł��B�Ă����[�^�[�����Ȃ��Ȃ�܂ŕ��d������Ƃق�0V�܂ŏd�x�̉ߕ��d�ɂȂ�܂�����A�d�r�̐��\������Ɋւ��Ă͉����N���Ă�����͌����Ȃ��ɂȂ�ł��傤�B �@�̂���A�ꕔ�̃j�J�h�d�r�p���d��ɂ�0V�܂ŕ��d����u�f�b�h�V���[�g�v�Ƃ������d�@���I�ׂ镨������A�u�j�J�h�d�r��0V���d����ƃp���`���o��v���Ƃ��������`�������W�R���E�ɂ͂���܂��B �@����������͌����I�ɂ͏����ɗǂ���Ԃ̓d�r���f�b�h�V���[�g��������ǂ���ԂɂȂ�킯�ł͂Ȃ��A�j�J�h�d�r�ɂ͔����Ă͒ʂ�Ȃ��u�������[�����v�̈��e���Œ��̉��w�����̐��\���ꎞ�I�ɉ������Ă��镨����d�ɂ�胊�t���b�V������ׂɁu0V�܂ŕ��d������A���̈��������S�����Ȃ��Ȃ��v���_�ōs�����̂ł��B �@��������f�b�h�V���[�g���d�r�̒��̉��w�����ɑ��ėǂ��Ȃ��̂͌����܂ł�����܂���B �@�������[���ʂ̈��e�����o�Ă��Ȃ��d�r�Ȃ炻��Ȏ������Ȃ��Ă��ǂ��A�܂��͂���������͖̂ڂɌ����Ă��܂��B �@�u�ǂ��Ȃ��̂ɂȂ�����́H�v�Ǝv����ł��傤�B �@�f�b�h�V���[�g���e�ʒቺ������Z�k�Ƃ������������ʂ������N�������ʁA�u�������[���ʂ��N�����Ēᐫ�\�������o�b�e���[�Ȃ�Ďg���Ă��Ȃ��I�v�Ƃ����X�s�[�h�Ƒϋv�͂����߂��郉�W�R�����E�ł́A�������k�����Ƃ����ڂ̑O�̃o�b�e���[�̓d���������ĕ��d�\�͂ɒ�����o�b�e���[���K�v�Ȃ킯�ŁA�f�b�h�V���[�g�Ŏ������k�߂��Z�����𖾂邭�R�₷�悤�Ȏg�������D�܂�Ă��܂����B �@�J���\�l�̕��͂��ƃj�J�h700mAh�o�b�e���[���~�j�l��Ȃǃ��W�R���W�Ŏg����݂����ł�����A�f�b�h�V���[�g�����Ăł��o�b�e���[�̗͂������o�������Ǝv����̂ł����烂�[�^�[�����Ȃ��Ȃ�܂œd�r���g���Ă������ł��傤�B �@�����A���W�R���E�ł����R�u�f�b�h�V���[�g��������o�b�e���[�����Ďg���Ȃ��Ȃ����v�Ƃ������|�[�g�����X����܂�����A�����Ƃ����܂Ƀo�b�e���[������Ďg�����ɂȂ�Ȃ�����\����������d���@���ƔF��������ōs���Ă��������B ���Ԏ� 2009/5/27
|
||||||||||||
| ���e |
�@�ԓ����肪�Ƃ�������܂����i�Q�j�� �@�ɂ߂܂����O�O�G �@�Ƃ肠���������g�������̂ł�����߂ĕ��d����Ă݂悤�Ǝv���܂��O�O�G �J���\ �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����d�r��ɂ߂��肵�Ȃ��̂ł���A��̂̃j�J�h�o�b�e���[����������������ɂł��u�I�[�g�J�b�g���d��v�Ƃ������i���킴�킴���W�R���p�ő�����������鎖�͖��������ł��傤�B �@���W�R��������Ă�����Ȃ烂�[�^�[�͎����Ă��܂�����A�o�b�e���[������Ɍq���ʼn��Ȃ��Ȃ�܂ŕ����Ă������������ł�����B �@���W�R���p�ł��~�j�l��p�ł��A���d�킪�킴�킴�I�[�g�J�b�g�@�\���t���Ă��鎖�����i�̃E������Ƃ��Ďg���Ă�����A���[�U�[�������K�v�Ƃ��Ă������l���Ă������Ɍ��ʂɂ��ǂ蒅���Ǝv���܂����E�E�E�B ���Ԏ� 2009/5/29
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| UltraFire��WF-139�`�E���C�I���d�r�p�}���[�d����܂��� | |||||||||||||
|
�@UltraFire��WF-139�Ƃ������`�E���C�I���d�r�p�}���[�d����܂����B �@����Ă����`�b�v�́A�\��Viper22A�A34063A�A����324�ł��B �@��͉����ł��B�����Ƀ`�b�v��R��i�ς݁{�ʂ̃`�b�v��R�{�`�b�v�R���c�t�����Ă��܂��B�}�C�i�X�ɗp�o�l�̃n�g���͓��̂܂ܔ��c�t������Ă��܂��B�O���y�ѓ����̎ʐ^�������肵�܂��B  N.F �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@UltraFire��WF-139�́u�C�OLi-ion�[�d����ׂĂ݂��v�ł��Љ�Ă��郊�`�E���C�I���p�[�d��ł��ˁB �@������̂ق��ł��u�����i�ɂȂ��Ă���v�Ƃ̂����������AWF-139�͂������߂ł́H�Ɖ\����Ă��܂����B �@����N.F�l���w�����ꂽWF-139�͂����������ł��ˁB �@�ʐ^�������蒸�����̂Ŋ���m�F���܂������A�m���ɉ�������Ă��ă}�C�R���ɂ��[�d�����H�͖����Ȃ��Ă��āATR-001�݂����Ȓ�d���E��d����H��LM324�œd�����m������LED��_�������邾���̒P���ȕ��ɕς��Ă��܂��B �@�u�}�C�R�������LED���_�ł��Ȃ��B���[�d�\�����ɂ�LED���ځ`���ƕς�B�[�d�Ɉُ�Ȃقǎ��Ԃ�������B�v�Ƃ��������̃}�C�R�����������WF-139�ł͂��肦�Ȃ��ᐫ�\�̏[�d��̗l���������Ă���������ŏؖ����ꂽ���ƂɂȂ�܂��B �@��́ATR-001�̂悤�ɓd�r����ꂽ�܂ܒ����ԕ��u�����ꍇ�ɓd�r�d����4.2V���z����ߏ[�d�[�d�킩�ǂ����Ƃ����_�����ꂩ��w���������̋^��ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�����ɂ͌���������܂���̂Ńe�X�g�ł��܂���A����N.F�l���d�r���[�d���Ă݂āA���[�d�\���ɂȂ������_�̒[�q�d����A���̌�����u�����ꍇ�ɂǂ��܂œd�����オ��̂��Ȃǂ𑪒肵�Ă�������Ƃ��ꂩ�甃������̎Q�l�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�������ɂȂ瑪�肵�Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/5/24
|
||||||||||||
| ���e |
�@���肵�悤�Ǝv���āA���}�n���Y�ɔ����ɍs���܂����B�d�r�͊O������ł����AWF-139�̓d���͓��ꂽ�܂܂ł����B�A���Ă�����A�Ԃ�LED�������Ƃ��`�J�`�J���Ă܂����B�d�����Ďb���u���Ă���ēx�d������ꂽ��ł����A����܂���B�o�͓d���𑪂��Ă݂��痐�������Ă܂����B �@�ǂ����A���Ă��܂����݂����ł��Borz �@����A�g�ݗ��Ē���������̐��퓮��ƍ����A��������A������ُ̈퓮��̓�����B��܂����B �@��낵��������A�����������B�܂��A�������C�t���̓_������܂����炨�����������B http://fujim.hp.infoseek.co.jp/WF-139NG.zip �@�d���������ςȂ��ɂ���Ɖ���[�d��Ȃ�ď��߂Ăł��B N.F �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d���������s����ɂȂ��Ĕ��U���Ă��܂��ˁB �@�g�pIC��MC34063A�Ȃ̂ŁAMC34063A�̓�����킩���Ă���l�Ȃ�e�X�^�[�œ������ĉ�ꂽ���������ł���ł��傤���A���܂�킩��Ȃ��ꍇ�͏C���ł��Ȃ��ł��傤�B �@�u�������Ă��܂��Ă���̂ŁA�Ȍア�����Ăǂ��Ȃ��Ă��ǂ��v�Ƃ�����߂����āA�S���̕��i�̑����n���_���Ȃ������̓������čӂ����@�ŏC�����Ă݂�ƒ��邩������܂���B �@������TR-001���d�r����ꂸ�ɓd�����������ƁA�_�ŋ@�\�Ȃ�Ė����͂��̐ԐFLED�������œ_�ł��鎞������܂�(��) �@����TR-001�̏ꍇ�̓R���Z���g���đ}�������ƒ���܂��B ���Ԏ� 2009/5/25
|
||||||||||||
| ���e 5/27 |
�@MC34063A�̓���͂����ς蕪����Ȃ��̂ŁA�������čӂ����@�ōs�����Ǝv���܂����A�����͎��Ԃ����Ȃ��ׁA�y���ɍĒ��킵�܂��B �@�Ƃ���Ŗl���������̂�DealExpreme�ŁAsku��1251�ł��B�Â����ł��B http://fujim.hp.infoseek.co.jp/WF-139paper.JPG N.F �l
|
||||||||||||
| ���e 6/1 |
�@�ڎ��ňُ�͌������Ȃ������c�t���̂�蒼���͎��M�Ȃ��B �@�ŁADC12V�������Ă݂���r���S�ł����BLED���ɂȂ�܂����B �@�������A����P�[�X�ɖ߂��ēd���𑪂낤�Ƃ�����LED����܂����B �@�������Ă݂��������̖��ȃW�����p�[���`�b�v��R�ƈꏏ�ɔ�����Ă��܂����B http://fujim.hp.infoseek.co.jp/WF-139broken.JPG �@�d���𑪂낤�ƃo�l��L�������Ɉ������������݂����ł��B �@�ŁA�����܂����B http://fujim.hp.infoseek.co.jp/WF-139repair.JPG �@�W�����p�̒��ɂ͔������Ă��܂����`�b�v��R�Ɠ���620���̒�R�������Ă����̂ŁAGND����������������ė��ăW�����p�ɓ����Ă�����R����č��E�̗̃A�m�[�h���Ɍ������܂����B �@�`�b�v��R�ƃW�����p�̒��̒�R�ɕ��U����Ă����d�����W�����p�̒��̒�R�ɏW�����܂��B �@�e�X�g�p���u�������������B http://fujim.hp.infoseek.co.jp/WF-139tester.JPG �@��ʉE���ɂ���d�r�{�b�N�X�Ɨ�LED�͓d�r�̕��d��H�ł��B �@�d�r��Protected�Ȃ̂ʼnߕ��d�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B �@���̑��u�ŗ��T�e�X�g���܂��B �@�������C�t���̓_������܂�����A�������������B N.F �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�O���������d��͎g�����ɂȂ�܂���ł����B �@24����LED�����������ɂ��Ă����d�o���܂���ł����B �@�ŁA60�����x�̒�R�����Ɍq���ł���ƕ��d�o���܂����B �@���������ALED�͒�R��Ɍq���Ȃ��Ɠd��������߂��ĉ���炵���̂ŁA���x����͒�R��t����l�ɂ��܂��B �@�g�����d�r�iProtected14500�j�́��ł��B http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3435 �@���d��̓d����2.7V�ł����BLow voltage cut off: 2.75V�������Ȃ̂�Protect��H���������Ǝv���܂��B �@�d����12V�̓p�\�R���̓d�����g���Ă܂��B�[�d����q������ԂŃW���X�g12.0V�ł��B �@�ŏ[�d�J�n�B�J�n���̓d����3.6V��6����20�����4.18V�܂ŏオ����LED�̐F���ɕς�[�d�I���ƂȂ�܂����B �@���d��ɉ����̂ł��傤���B���Ǝ��Ԃ��Z���l�Ɏv���܂��B �@�d�r���o���ēd���𑪂�����4.17V�ł����B �@�[�d���̓d���͑���܂���ł����B �@�[�d��̃}�C�i�X���ɒ���Ƀe�X�^�[��t������l�Ɏ��ƃA���~�z�C���œd�ɂ��������ł����A�����W��ς���ƒl���R���R���ƕς��Ă��܂��ĉ��𑪂��Ă�̂�������Ȃ��Ȃ�܂����B �@�����A���[�d��ɓd��������Ă��邱�Ƃ͊m�F���܂����B �@0.55�`0.58mA�ł����B���l�̓f�^���������m��Ȃ��ł��B �@�[�d��ɖ߂��č�3���Ԍo���܂��B�d����4.18V�܂ł����オ��܂���B �@�d�r�̓d����4.18V�܂ł����オ��܂���̂Ŗ��[�d�ł͂Ȃ��̂ł��傤�B �@�������A���̏�Ԃ��Ɓu���Ԃ͂����邪�댯�ł͂Ȃ��v�[�d�킩���B �@�d�����q���������ɂ��Ă܂����U����l���ƒ��댯�[�d��ł����B �@�ǂ����ɂ��攃��Ȃ������ǂ��[�d��ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��ł��B �@100V�̓d�����g���Έ�������ʂɂȂ��������m��܂���B �@�e�X�^�[�����Ȃ̂Ō덷������̂����m��܂���B �@�[�d��̌̍��������ł��傤�B�A�e�ɂȂ�Ȃ������ł��݂܂���B �@���̏[�d��A���̂Ƃ���͎g�����ł����A�t�@�������邳���Ĕn���f�J���p�\�R���p�d�������Ȃ̂ŁA�ʂ̂��܂��B �@������ł��B�����ł��B http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12162 N.F �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@4.18V�܂ł����オ��Ȃ��̂ł�����A�ߏ[�d�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ł��̂ŗǂ��ł��ˁB ���Ԏ� 2009/6/10
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d�����]�Ԃ̃o�b�e���[�̒��g������������G���[���o�܂� | |||||||||||||
|
�@�T�����[�d�����]�ԗp�o�b�e���[�b�x�|�o�d�R�O�ɕt���ċ����ĉ������B���̃o�b�e���[�����������̂ł����A���]�Ԃɑ�������Ɩ{�̎c�ʕ\�������v�Q���_�ł����ăA���[���ɂȂ葖��܂���B�B�[�d�͕t���̐�p��ŏ[�d�ł��܂����B���̃o�b�e���[�̒[�q�́{�Q�S�u�A�|�A�������x�T�[�~�X�^�P�O�j���A�Ɠ��������o�Ă���z���̌v�S�[�q�ɂȂ��Ă��܂��B�{�Q�S�u�A�|�[�q�̂Q�[�q����P�ƂŒ�R���ׂɂ͓d��������܂����A�e�ʂ��\�����邱�Ƃ��m�F���܂����B �@4�[�q�̓��A������ɂȂ����Ă���[�q���������o���Ă���[�q�Ȃ̂�������܂���B�킩��܂����狳���ĉ������B�V�i�̂b�x�|�o�d�R�O�o�b�e���[�����j���N���b�v�S�{�Ŏ��]�Ԗ{�̂ɐڑ����A���̓��̂��̒[�q1�{���O���Ă������悤�Ɏc�ʕ\�������v���Q�_�ł��ăA���[����ԂɂȂ�܂��B�@ ���������� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���]�ԗp�r�Ɍ��炸�A�u���̊�v�������Ă���o�b�e���[�p�b�N�̏ꍇ���̊�ɂ́u�o�b�e���[�Ǘ��`�b�v�v���ڂ��Ă���ꍇ���قƂ�ǂł��B �@�o�b�e���[�Ǘ��`�b�v�ɂ��F�X�����āA24V�p�b�N�̂悤�ɑ�R�̃Z����Ŏg�p���Ă���ꍇ�Ɂu����g�p�ɂ��ꕔ�Z���̑����̏�v�Ȃǂ����m����ׂɒ��̂������̃|�C���g�̓d�����v���ăp�b�N�́u����^�ُ�v���g�p�@��ɒm�点�镨��A�[�d���ɂ��������ُ�����m����悤�ȏ[���d���̊Ǘ����u�ł���ꍇ�B �@�܂��p�\�R���⃀�[�r�[�J�������Ŏg�p����Ă���u�C���t�H���`�E���o�b�e���[�p�b�N�v�̂悤�ɍ��x�ȃ}�C�R���`�b�v�������Ă��āA�o�b�e���[�p�b�N�̎g�p��c�e�ʁE�x�����m���Ďg�p�@��ƒʐM���Ă�����̂̏ꍇ�B (���`�E���Z���Ɍ��炸�A����{���������ꍇ�̓j�b�P�����f�Z���ł��Ǘ�����ꍇ������܂�) �@���낢��Ǝ�ނ������āA���̎��]�ԃo�b�e���[�̒��̊�����̓��������Ă�����̂��͂��`������������ł͔��f�����˂܂��B �@�d���͏o�Ă���Ƃ������ł��̂�(���̒��ԃ^�b�v���̔z�����ԈႦ�Đ��Ă��܂��Ă��Ȃ��Ƃ���)�A��҂̉��炩�̍��x�ȊǗ��@�\��L�����R���g���[���[��ŁA��x�ł��Z�����O���ēd�����O�ɂȂ�ƃ��Z�b�g����āu���Z�b�g���ꂽ�̂̓o�b�e���[���s�ǂɂȂ����؋��v�Ƃ��ĈȌ�͌̏�o�b�e���[�Ƃ����M�������o���Ȃ��Ȃ��Ď��]�Ԃł͎g�p�ł��Ȃ����Ă��܂����\��������܂��B �@���[�J�[�o���ɂ̓o�b�e���[��g�ݏグ�ēd�����������Ă����ԂŁA�ʐM�[�q����u����ƔF�����Ȃ����v�Ƃ����ʐM�f�[�^�𑗂��ē�����J�n�����Ă����Ƃ��������ŁA���d����艺��������O�u�ɂȂ�ƃA�E�g�I�Ƃ����u�d�|���v�ł��ˁB �@�������CY-PE30�����̒ʂ�́u�d�|���v�ɂȂ��Ă��邩�ǂ����͒m��܂���A���̒ʂ�R���g���[���[�`�b�v���̏���M���Ă���Ƃ����ۏ͂���܂���B �@�����܂ł��`���������������ɂ����z���ł��B ���Ԏ� 2009/5/17
|
||||||||||||
| ���e |
�@���Ԏ��L��������܂����B��ώQ�l�ɂȂ�܂����B��̕��A�������ׂĂ݂悤�Ǝv���܂��B�܂��A�X�������肢�������܂��B toshi �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d�����]�Ԃ̃o�b�e���[�𑼎Џ[�d��Ń��t���b�V�������� | |||||||||||||
|
�@���߂ē��e�������܂��B�����ł����[�d��ɂ��ċ����Ă��������B �@�d�����]�ԁi�^�C�K�Ёj�A�j�b�P�����f�d�r�Q�SV�o�b�e���[�Ő����R�{�o�Ă���^�C�v�Ȃ̂ł����A���ݎg�p���̏[�d��ɂ̓��t���b�V���@�\�����Ă��Ȃ��̂ŁA����(���}�n�j�̃��t���b�V���t�[�d��iMODEL�@�w�P�Q�|�O�O�j���g�p�������̂ł����A�g�p�ł��܂��ł��傤���A�g�p�o����ł�����z�����@�������肢�܂��ł��傤�� �J�i�g �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ǂ�����j�b�P�����f�[�d�r�ŁA20�{�g�p��24V�Ƃ������ł����قǗe�ʂ̈Ⴂ�Ȃǂ������ꍇ�͗ގ������[�d����g�p���邱�Ƃ͓d�C�I�ɂ͉\���Ǝv���܂��B �@�����A�ǂ���̃o�b�e���[�E�[�d����������Ƃ������̂ŁA��������Ȏ������Ă��đ��А��i�Ƒg�ݍ��킹��ƕs����N����Ƃ����\�����̂Ă���܂���̂ŁA�悭���ׂĂ��痬�p����悤�ɂ͂��Ă��������B �@���}�n�̏[�d��ɂ͒[�q���S�{����A�}�j���A���ɂ͗��[���{�Ɓ|�Ƃ���������Ă��܂����A�����̎c��Q�{�̒[�q�Ƀ��}�n��p�o�b�e���[�ɂ͉����z������Ă��āA���ꂪ�q����Ȃ��Ɛ������[�d���Ȃ��Ƃ��A�F�X�Ɓu�d�|���v�������Ƃ�����܂��B �@���������u�d�|���v��������A�{�Ɓ|�����q���Ώ[�d�ł���͂��ł��B �@���A�^�C�K�Ђ̃o�b�e���[�̂R���ɂ��Ă��A�{�Ɓ|�ȊO�̂�����{�͉ߋ��ɐ������Ă���T�[�~�X�^�[�q�̉\�����A����ȊO�̉�������Ȓ[�q�̉\��������܂�����A�������ĉ����q�����Ă��邩������Ȃǂ��āA���S�����悭�����ׂɂȂ��Ă��瑼�Џ[�d��Ɛڑ����Ă��������B �@�����o�b�e���[�A�܂��͏[�d�킪���Ă������܂Ŏ��ȐӔC�Ƃ������ł��B ���Ԏ� 2009/5/15
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����̉��肪�Ƃ��������܂��B �@�o�b�e���[�̐���1�{�̓T�[�~�X�^�[�Ɍq�����Ă���܂����B �@���}�n�̏[�d��́{�Ɓ|�����q���Ă��G���[�����v�H���_�����Ă��܂����B �@��͂�d�|���������Ė����Ȃ�ł��傤���E�E�E �@�������Ƀo�b�e���̃��t���b�V���̕��@�A���͋@��Ȃǖ����ł��傤����������������肦�Ȃ��ł��傤���B �J�i�g �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����ς艽���u�d�|���v�����肻���ł��ˁB �@�e�ЁE�e�d�l�łǂ̂悤�Ȏd�|�����͕������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��ł��傤����A���̂܂܂Ŏg�p���邱�Ƃ͕s�\�Ƃ��l�����������B �@24V�o�b�e���[�̃��t���b�V����Ƃ����͔̂����Ă��܂���A���Ƃ��u�d���H���p�o�b�e���[�̕��d���v�Œ����悤�ȕ��@�Łu24V�o�b�e���[�̎�����d��v�Ƃ��������̉�H��v�E���삳��āA�o�b�e���[�p�b�N�ɐڑ����ĕ��d���Ă�邵������܂���B �@�������A�u���d���͂����Ɩڂ𗣂����Ƀe�X�^�[�̕\������������v�Ƃ����E�ςƑ̗͂�������ł�����A100��/10W���x�̃Z�����g��R���{�Ɓ|�Ɍq����(���Ȃ蔭�M���܂��̂Ń��P�h�ɒ���)�A�e�X�^�[�̓d���\����18�`20V�ɂȂ�������d����߂�Ƃ������@�ł��\���܂���B �@�����r���ŐQ�Ă��܂�����A���u�����܂ܑ��̗p�������Ă���18V�����d���Ă��܂��Ɠd�r��ɂ߂܂��̂ŁA�{���ɔE�ς��K�v�ł��B ���Ԏ� 2009/5/17
|
||||||||||||
| ���e |
�@���x���\�������܂��A���L�̃��W�R���p�H�[���d����������̂ł����A���̏[�d��ł͓d�����]�Ԃ̃o�b�e���[�͖����Ȃ̂ł��傤���H ���i�� �@�[�d��(TAHMAZO) T30 v.2 �����œK���[�� �J�i�g �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@Ni-MH��30�Z���܂ŏ[���d�ł���̂ł��ˁB �@���ۂɎg�p�������������@��Ȃ̂ŁA���\�E�@�\�ɂ��Ă͐�`�̕��͂����̂܂ܐM���邵�������ł����A���̒ʂ�̐��\�ł���Ύg����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2009/5/19
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �ԂŁA�T�u�o�b�e���[��DC/AC�R���o�[�^�E�[�d��o�R�ŏ[�d | |||||||||||||
|
�@�ȑO�A�L�b�`���^�C�}�[�̌��ł͂����b�ɂȂ�܂����B �@�܂����k�����肢�������܂��B�ԂɃT�u�o�b�e���[��ς����Ǝv���Ă��܂����A�[�d���@�ɐF�X����悤�ł����A�����̍l�������@�̃A�h�o�C�X�����肢���܂��B���C���̃o�b�e���[����C���o�[�^�łP�O�OV�ɂ��[�d��ŃT�u���[�d������@�ł��B�[�d��̓g���N���ł��B�T�u�͓d���i�݂̂Ɏg���܂��B�����͂����Ȃ��Ǝv���܂����A�������ł��傤���䋳�����肢�������܂��B �S�T�Γd�q���N �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�T�u�o�b�e���[���u�[�d����v�Ƃ����Ӑ}�����ł���Εʂɍ\��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�[�d�킪�K�v�Ƃ���d��(�A���y�A��)�ɏ\���Ή�����DC/AC�R���o�[�^�ł���B �@�������ɂ��������ڑ�������ƃG�l���M�[�̕ϊ����������Ȃ舫���ł����ǁA����͐܍��ς݂Ƃ������ŕʂɍ\���܂���ˁB �@�ϊ������������Ԃ�A�G���W���������Ă��Ȃ��Ԃɂ��������ڑ��̂܂ܕ����Ă�������A�[�d�ׂ̈ɓd�C���R�g���ă��C���o�b�e���[���オ���Ă��܂���������܂��A������܍��ς݂Ƃ������ŁB �@������x�d�����̃o�b�e���[�d�������������珸���ł��Ȃ��悤�ȁA�i���̒Ⴂ�C���o�[�^���g���Ώ���Ɏ~�܂邩������܂���B�������́A���d���d���ȉ��ł͌x�����o���Ď����Ŏ~�܂�C���o�[�^�������Ă���̂��ȁH �@ACC�����肩��d��������āA��Ԓ��͏[�d�ł��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������ł��ˁB ���Ԏ� 2009/5/13
|
||||||||||||
| ���e 4/15 |
�@�����̂��A���肪�Ƃ��������܂����B
�@�\�z�ǂ�������������悤�ł��ˁB
�@�ł����A�͂����肵�܂����̂ŁA�ǂ������ł��B
�@�{���ɁA���肪�Ƃ��������܂����B
�S�T�Γd�q���N �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �f�W�J����Li-ion�o�b�e���[���G�l���[�v�ɂ����瓮���܂��� | |||||||||||||
|
�@�O���@�n�߂܂��āAWeb�y�[�W�͖��T�q�������Ē����A�Z�p�̍������������A�������Ē����Ă���܂��B�����ŁA�o�b�e���[�g�p���̎���ł��B�R���p�N�g�f�W�J�����O���d���i�[�d�r�O�m�G�l���[�v�j���g�p���Ďg�������v���o�b�e���[�p�b�N�����i�L���m������IXY�f�W�^���J�����A�o�b�e���[�p�b�N������ɂ��āA�O���d���[�q�d�l�ɉ������܂����B����p�̊����i���̔�����Ă��܂��B�����������ł��B�j���������āA�G�l���[�v��3�{����ڑ��i��4.02V�j���f�W�J���ɓd�����͂��܂������A�f�W�J�����Łh�o�b�e�����������Ă��������h�ƕ\�����܂��B�f�W�J�����̃o�b�e���[�p�b�N�̎d�l�́A�d��3.7V�A�d��850mA�ɂȂ��Ă�܂��B�����ŁA�G�l���[�v��1�{���₵��4�{����i��5.21V�j�ɂ��܂��ƁA�o�b�`���쓮���܂����B�Ȃ��ł��傤���H4.02V�ł̓_���Ȃ̂ł��傤���H�ܘ_�G�l���[�v�͐V�i�i�P�O�^1900mA�j3�{���[�d�ς݂ł��B���A���w�����肢���܂��B ���� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��AIXY�����ʼn��u�œd���x�����o���̂��ȂǁA�������삪�S���킩��Ȃ��̂Ŋm��I�Ȏ��͌����܂���B �@�����ALi-ion�o�b�e���[��3.7V�ƃG�l���[�v�R�{��3.6V(���[�d���͂�����������)�͑S���Ⴄ���̂Ȃ̂ŁA�������������������ꍇ�ɂǂ���������悤�ɓ����Ǝv�����͑�ԈႢ�ł��B �@�o�b�e���[�ɂ͕��d�������Ƃ������̂�����A��i�E�J�����d���������ł����ۂɕ��ׂ��q���œd�������o�����ꍇ�ɋN����d���~���̓o�b�e���[�̎�ނ�^�C�v�ɂ���ĈႢ�܂��B �@�ł�����A�f�W�^���J�����̒��œd���������ɂǂ̒��x�̕��ׂ������āA���̏�Ԃʼn��u�ɂȂ�����d���x�����o�����ȂǃJ�����ŗL��臒l������Ǝv���܂����ALi-ion�o�b�e���[�̂ق����j�b�P�����f�[�d�r�ł���G�l���[�v���d���~�������Ȃ��A���̏�Ԃɂ��킹�Č��m����Ă���ׂɃG�l���[�v�ł͓d���x�����o��\���͏\���ɍl�����܂��B �@�S�{�ŃJ���������Ȃ��̂ł�����̂܂��ȐӔC�Ŏg���Ă����\�ł����A�ǂ��l���Ă��K�i�O�ł̎g�p�ł����炢�J���������Ă��ǂ��Ƃ����S�\��(����A������߁H)�Ŏg�p���Ă��������B ���Ԏ� 2009/5/8
|
||||||||||||
| ���e 5/8 |
�@�O���@���Z�������A�����̂��L��������܂��B�o�b�e���[�̕��d�������̌��A��ϕ��ɂȂ�܂����B���͍�������G�l���[�v4�{�ڑ��ŎB�e���ăf�W�J�����̋@�\���g���A50�����̎ʐ^�������Đ��@�\���g����1���Ԓ��ق����炩���ɂ��܂������A���Ɉُ픭�M�E�G���[�\�����͂Ȃ��g�������ł��ˁB�i���ȐӔC�ł��ˁj������F�X�Q�l�ɂ����Ē����܂��̂ł�낵�����肢���܂��BPS�F3LED LAUNCHER LIGHT (�����`���[���C�g) No.13813�̋L�����Q�l�ɁAUV-LED�Ɍ�������UV���C�g���쐬���܂����B�ܘ_�A�o�b�e���[������R���Z�b�g�I�o�b�`���������܂����B�p�X�|�[�g�ɏƎ˂���ƁA��ʐ^�������яオ��܂��i�j�E�E�E�d����ł̎d�l�ɏ\�����܂����B�{���ɓd�q�H��͊y�����ł��ˁE�E�E
���� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| (R)���D�F�̃G�l���[�v | |||||||||||||
|
�@�Ǘ��l�l�͂��߂܂��āB�d�r�Ɋւ�������Q�l�ɂ����Ă��������Ă��܂��B �@eneloop-R�̘b�Ȃ�ł����A������eneloop-R�́���R�̃}�[�N��eneloop���S�Ɠ������^���b�N�ł������A�ŋ߂�eneloop-R�́���R�̃}�[�N�����̕����Ɠ������i�D�F�j�ɂȂ��Ă���悤�ł��B �@�܂�������ӏ��A�e�ʕ\�����ŋ߂̂��̂�Min.1900mAh�݂̂ƂȂ��Ă��āATyp.�\�����ȗ�����Ă��܂��B �@���̘b��͊��o�ł��傤���H �@�\���ȊO�̃X�y�b�N�̈Ⴂ������̂��ǂ����킩��܂��A���m�点�Ƃ��q�˂܂ŁB�Ȃ��A���o�ł�����A�킴�킴HP�Ɍf�ڂ��������K�v�͂���܂���B�����A�ǂ��̃y�[�W�Ɋ��o�������A���[���łł�����������������K���ł��B��낵�����肢�������܂��B Akihouse �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�O�m�d�@����P��E�P��T�C�Y��eneloop���������ꂽ���ɁA�P�O�E�P�l�T�C�Y���u�R�ۉ��H�v����܂����B �@���̎��ɍR�ێd�l�̃t�B�������g�p���������Ƌ�ʂ���ׂɈ����̃f�U�C���ύX���s���Ă��܂��B �@�R�ۉ��H�ɂ��Ă͎O�m�����T�C�g�́u�d�r�̊O���`���[�u�͍R�ۉ��H�B�ƒ�p�͂������A�����̐l���g���Ɩ��p�ɂ��Ή��B�v�������������B(�ʐ^�ɂ͊D�F�}�[�N�̓d�r���ʂ��Ă��܂�) �@�P�O�R��eneloop�������Ă��܂����A�d�C�I�ȓ��e�ɂ��Ă̓��b�g�̈Ⴂ�ɂ�鍷�ق��炢�����m�F���Ă��܂���̂ŁA���ɋL���Ƃ��Ď��グ��Ƃ��u�G�l���[�v���ς����I�v���Ƃ����~�ߕ��͂��Ă��܂���B ���Ԏ� 2009/5/4
|
||||||||||||
| ���e 5/5 |
�Ǘ��l�l �@�����̂����肪�Ƃ��������܂��B �@�����T�C�g�ɂ������̂ł��ˁB�m��܂���ł����B�����T�C�g���ăJ�^���O�I�ȏ���Ȃ��Ǝv������ł��Ă��܂茩�Ă��܂���ł����i�� �@�v���Ԃ�ɔ����Ă݂āA�A���H�F���Ⴄ�I�Ǝv���Ăт����肵�����̂ŁE�E�E�B�X�y�b�N�I�ɕς��Ȃ��̂ł�����A���܂łǂ�����S���āi�H�j�g���܂��B �@�ēx�A���肪�Ƃ��������܂����B akihouse �l
|
||||||||||||
| ���e 5/5 |
�@Typ.�l��min.�l�̕��L����min.�l�݂̂ɂȂ����̂́A�ȑO�Ɏ������������L��������܂��B �@�Ȃɂ�����̍R�ێd�l�ɂ��ύX�ł͂Ȃ��A�R�ۉ��ȑO���炠��܂����B �i�\�j���[�v����������min.�l�݂̂ɂȂ��Ă��܂����j �ڗ� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| NEXcell��NC-60FC�ŏ[�d�������BQ-330�ŏ[�d����H | |||||||||||||
|
�@�����́B���܂œd�r�ƈꌾ�ł������A���ɉ��[�����ɕ��ɂȂ�܂����B����������Ē��������Ǝv���܂��B�l�͊����ȕ��n�ł��āA���e���{�P�Ă��邩�����Ă܂��A���e�͊肢�����B �@�{��ł����A�J�������D���ő���g�p���Ă��܂����A���X�Â߂̈��t�@�ނł��ƁANi-Cd�͎g�p�̕�������ANi-Cd�g�p�̕��ɂ́A�p�i��1000mAh(�^��P-3GAV)���BNi-MH�g�p�̓G�{���^���B�ƕ��p���Ďg�p���Ă��܂��B�[�d��̓p�iBQ-330���g�p���Ă��܂������A���t���b�V���ƌ����L�[���[�h�����𗣂ꂸ�ANECcell�Ђ�NC-60FC�ƌ����}���[���d��Ȃ镨���w�����܂��Ďg�p���Ă���܂��B �@����ł͖������̂́A�C���������ɕ��d�{�^���������Ă��̂܂����I�ɋ}���[�d�B�ƌ���������J��Ԃ��Ă��܂����A���̂܂�NC-60FC�C���Ɏg�p���Ă����ׂ����HNC-60FC���[�d�I���̌�ABQ-330�ł������[�d�𑫂��Ă��ׂ��Ȃ̂��H �@�ςȊ����ł��݂܂��A�������肦����Ǝv���܂��B �@���A�����ʐ^�p�̃X�g���{�ł�Ni-Cd�͉� Mi-MH�s�̕����L��܂��B���[�J�[�̐�����ǂ݂܂��ƁA�K�X�̔������L�邽��Mi-MH�͕s�Ȃ̂������ł��B����ȂɈႤ�̂ł��傤���H �e�}�E���� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@NC-60FC�Ƃ�����NEXcell���̑��̒����[�d��ł��ˁB �@���̂ق��ł͕����E�e�X�g���Ă��Ȃ��̂Ő��\�ɂ��Ă͉������y�ł��܂���B �@��`����ʂ�̐��\���Ƃ���ƁA���d�@�\�E�[�d�@�\�ɂ��Ă͉������͖����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B(����A�����Ɛ�`�ɏ������[�J�[�͖����Ǝv���܂����c) �@��`����ʂ�̐��\���Ƃ���ƁA�C���t�������Ƀ��t���b�V��������x�̕p�x�Ŏg�p���Ă��Ă��������͖����Ǝv���܂��B �@�܂�NC-60FC�ŏ[�d�������BQ-330�ōēx�[�d����K�v������������܂���B �@NC-60FC�́|���u�����ŏ[�d���I������Ɛ�������Ă��܂��B��1000mA�[�d(�P�O)�Ə�����Ă��܂��̂ŁA����Ł|���u�����Ŗ��[�d���o���s���Ă���̂ł���A�d�r�͊��ɖ��[�d����Ă��܂��B �@�������̌�Œ�d���Ōp�������[�d�����Ă��A�̊��ł���قǂ̗ʂ̏[�d���ł���Ƃ͎v���܂���̂ŁA�قƂ�ǖ��Ӗ��ł��B �@�u�܂������Ȃ����H�v�Ƌ^�S�ËS�ɂȂ��Ă���̂ł�����A���S�̈��S�ׂ̈�BQ-330�Œǂ��[�d������Ă��\���܂��ABQ-330�͎����Œ�~�͂��܂���̂ʼnߏ[�d���ēd�r�̐��\�𗎂Ƃ��Ă��܂����肵�Ȃ��悤�����ӂ��������B �@�d�r���甭������K�X�̌��́A���܂łɉ��x�������Ă��܂����j�b�P�����f�[�d�r�͎g�p���ɉߕ��d������Ƒ�ʂɃK�X���������܂��B �@�u���C�g�Ŏg�p������A�X�C�b�`���̃S�����p���p���ɖc����v�u�d�r���o�����Ƃ�����L���b�v����������v�Ȃǂ̎��̗�͐��m�ꂸ�E�E�E�ł�����A�������C�g�E�����X�g���{�̂悤�Ȗ��@��ʼnߕ��d�����ꍇ�A�K�X�����@�\������܂���W���J���悤�Ƃ����r�[�ɒ��ɗ��܂��Ă����K�X���ŊW�≽���̕��i���������ŁA���ꂪ�ڂɓ����Ď�������댯��������܂��B �@�C�����̍����@��ł̓j�b�P�����f�[�d�r�̎g�p�͋֎~����Ă��܂��̂ŁA�K�����[�J�[�̎w���ɏ]���Ă��������B ���Ԏ� 2009/4/27
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��w��L���������܂��B �@�[�d�ЂƂ���Ă��������m���������܂܂��ƁA�}�C�i�X�ʂɓ]���Ă��鎖������̂ł��ˁB �@�K�X�̌�������v���܂����B �@BQ-330����A�\�j�[BCG-34HRMES�֔����ւ����l���Ă��܂��̂ŁANC-60FC�Ƃ̔�r�������Ȃ�ɂ��Ă݂����Ǝv���܂��B �@NC-60FC�́A���ƂȂ��M���o���Ȃ��l�ȋC�����āE�E�f�U�C���Ƃ��F�Ƃ��B �@���̓x�͂��肪�Ƃ��������܂��� F�}�E���� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@NC-60FC�͕Б��Q�X���b�g���ɂ�����ԕ\��LED���t���Ă��Ȃ��Ƃ��A�f�U�C���Ƃ��A�F�Ƃ��A�u�悵�I�������I�v�Ɠ���肪���Ȃ��_���E�E�E�B �@�����u�����ځv�Ɓu�d�C�I���\�v�͊W����܂���A�����������炷�������ǂ��[�d�킩������܂����I�H �@�g���Ă��ē��ɕs���R���Ȃ���A���t���b�V�����ł���悤�ł������i���g���Ă���Ă��������B ���Ԏ� 2009/4/29
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �P�O�d�r��ŕ��d�������̖�� | |||||||||||||
|
�@�d������P�O�̃j�b�P�����f�[�d�r���悭�g�p���܂��B �@���܂ň�x�����t���b�V�����������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�C�ɂȂ��ăT�C�g�������Ă�����ɎQ��܂����B �@���d��ɂ��Ă���قǏڂ����Љ��Ă���T�C�g�͂Ȃ��A��ϋ����[���ǂ܂��Ă��������܂����B �@����łł����A�P�O��8�{����d�r�{�b�N�X�Ƀj�b�P�����f�[�d�r�����A�Љ��Ă���p���[�Y�̃p�[�t�F�N�g�f�B�X�`���[�W���[�ɂȂ��Ŏg�p���Ă݂����ƍl���Ă��܂��B �@�p���[�Y�̃p�[�t�F�N�g�f�B�X�`���[�W���[�ɂ������Ǝv�����̂͋@�\���悳�����ȓ_�Ɖ��i�ł��B����ɕϊ��v���O�H������Ύg�p�ł��邩�ȂƎv���܂����B �@�����������g�p���@�͂ł��܂����H �@�܂��A�܂����_�͂���܂��ł��傤���H �@�܂����������Ė��m�Ő\����܂��A��낵�����肢�������܂��B �������� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����o���̒P�O�d�r�Ȃ�A��������Ȃ�u�ʕ��d�v���ł�����d��E�[�d����g�p���Ă��������B �@�p���[�Y�̃p�[�t�F�N�g�f�B�X�`���[�W���[�̓��W�R����d���K���p�́u�X�g���[�g�p�b�N�o�b�e���[�v����d���邽�߂ɗp�ӂ��ꂽ���d��ŁA�u�����ԂłȂ��ƕ��d�ł��Ȃ����i�p�v�̂��̂ł��B �@�p�[�t�F�N�g�f�B�X�`���[�W���[�łW�Z��������d�������ꍇ�A�I�~�d����6.4V(1�Z��������0.8V)�ł��B �@����͊e�Z�����ϓ��̃R���f�B�V�����ŁA�ϓ��ɕ��d�����ꍇ�ɂ͓K�x�ȓd���l�ŕ��d�����ۂ̏I�~�d���Ƃ��Ă͖��̖����l�ł��B �@�������W�{�̓d�r�̃R���f�B�V�����Ƀo����������A��Ԏ�肪������{����ɕ��d�I��(�e�ʂ��o����)�����ꍇ�͂ǂ��ł��傤���B �@��{������0V�܂œd�����������Ă��܂����Ƃ��Ă��A�c��̂V�{���܂���1.2V�̓d����ۂ��Ă�����A���d�d���͂V�~1.2��8.4V�B�܂��܂��J�b�g�d����荂���̂ŕ��d���p�����܂��B �@���̏�Ԃł͐�ɕ��d����0V�܂ʼn������Ă��܂����d�r(����A���̎��_�ł������댯�Ȃ̂ł����c)�ɑ��āA�c��̓d���̂���d�r�Ƃ̒����H�ɗ����d�����{���̃v���X�ƃ}�C�i�X�Ƃ͋t�����̓d����������A�t�����ɏ[�d����Ă��܂��܂��B���̂悤�ȋt�����̏[�d���s���Ɠd�r�̒��ł́u�]���v�Ƃ����d�r�ɂƂ��Ă����ւ��ɂȂ�_���[�W���傫���Ȃ�܂��B �@�����d�r�W�{�ŃJ�b�g�d��6.4V�ݒ�ł���A�����Q�{���]����ԂɂȂ��Ă����\���Ȃ��ɕ��d�𑱂���\��������ݒ�Ƃ������Ƃł��B �@����͐����Ԃ�1.2V(�O��)�ƕ��d�I���f����0.8�`0.9V�Ƃ����d���̍���{���Ԃ�|�������l���d�r��{�Ԃ��1.2V���z����悤�Ȓ�����d�ł͕K���N���肤��ŁA�d�r�̂��Ƃ��l����ł���Δ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł��B �@���������W�R���p�o�b�e���[�p�b�N�Ȃǂ̂悤�ɁA�o�b�e���[��ɐڑ�(������X�|�b�g�n�ڂ��Ă��܂�)���ăV�������N�p�b�N���Ă��܂��Ă��āA�������Ĉ�{���ʂɕ��d�ł��Ȃ��悤�Ȑ��i�̏ꍇ�͂��̂܂ܓd�C�R�l�N�^�ɐڑ����邾���ŕ��d�ł�����d����g�p���邱�ƂɂȂ�A�u�R���f�B�V���������ꂽ�o�b�e���[�́A����ȍ~��C�ɓd�r���Ă��܂��v�Ƃ��������e�F�����g����������l�B�����炱�����C�Ŏg�p���Ă��܂��B �@���ہA���W�R���p�o�b�e���[�p�b�N�̗Ǐ�ōł������̂����������g�����Œ��̃Z�����P�`�Q�}���ɗ��Ďg���Ȃ��Ȃ邱�Ƃł��B �@�������������l���u�W�{�̂������n�߂��d�r�͕��d�ʼnĂ��܂��Ă�������I�v�Ɗ�����čl�����Ă���̂ł�����A�P�O�d�r���W�{�������d�r�{�b�N�X�ɓ���ĂW�{�̒�����d������̂��l�̎��R�ł��B �@�p�[�t�F�N�g�f�B�X�`���[�W���[�Ȃ��S�Z��(4.0V)�ݒ������܂�����A�S�{����ŕ��d����Ȃ璆�̈�{���������d���I����Ă����̎��_�ŕ��d���~�܂��]���̐S�z�͂���܂���B(���ɉ��ׂ���d�s�\���̉\���͂���܂�) �@�P�O�d�r�S�{�p�̓d�r�{�b�N�X���g���ĂS�{�̒�����d���Q��ɕ����čs���Ƃ��A�p�[�t�F�N�g�f�B�X�`���[�W���[���Q�䔃���ĂS�{���d���ɂQ�g�s����悤�ɂ���Ƃ�����Ƒ����͎��Ԃ͉��P�ł��܂��B �@�����ǂ̏ł��A������d�����Ă������͓d�r��{��{�̓d���ׂĂ���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�ǂꂩ�������d���Ă��܂����d�r�̓d���������邱�ƂŁu�����ځv�̒����Ԃ̓d�����������āA���ꂪ�w��̓d���ɂȂ�������d���~�߂Ă��邾���ł��B �@�������d���I���d�r(����Ă���)�͂�苭�����d����čX�Ɏ��A�x���܂ŕ��d�������Ă���(���܂����Ă��Ȃ�)�d�r���K��̏I�~�d���܂ʼn�����O�ɕ��d���~�߂��Ă��܂��̂��I�~�d���܂Ő��������d���Ă��Ȃ�����ɂȂ�܂��B �@���������J�b�g�d���ݒ�̂�����d��Łu�I�~�d���܂ŕ��d���Ă�낤�v�Ǝv���ĕ��d���Ă���̂ɁA���͂����ƕ��d����Ă��Ȃ���������Ƃ����̂�������d��̗��Ƃ����ł��B �@����ł������Ƃ��l���̕��Ȃ璼����d������g�p�ɂȂ���Ɨǂ��Ƃ������܂��B �@���������ɁA�u�g���Ă��邤���Ƀp�b�N(�����Ɏg�p���Ă���d�r)�̒��ŃR���f�B�V���������J���Ă䂭���̓}�V�v�Ƃ����g�����ł��ˁB �@�ƒ�p�̒P�O�d�r�ł���ŏ�����o���Z����Ԃł�����A�ł���킴�킴�g��ł̒�����d�͔����āA�ʕ��d���ł�����d��ŕ��d�����ق����ǂ��Ǝv���܂���B �@�m���ɒl�i�͒���܂����A�ʂɕ��d�E�[�d���Ă����u���t���b�V���@�\���v�̉ƒ�p�[�d��(���Ƃ��ΎO�m��NC-MRxx�^�C�v)��������Ă����āA10�`20��̏[�d�Ɉ��̊���(�g�p�ɂ��)���炢�Ń��t���b�V�����Ă��A��蒷���d�r���g����ł��傤�B �@�������d�q�H�삪�ł�����Ȃ�u�j�b�P�����f�[�d�r �P�Z�����d��̐����v�̂悤�ȕ��d������A�W�{�����ł��Ȃ�ł��D���Ȃ悤�Ɉ��S�ɕ��d�ł��܂��B ���Ԏ� 2009/4/27
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d�����]�Ԃ̓d�r���������܂��� | |||||||||||||
|
�@�d�����]�Ԃ̓d�r���������܂��� �@�ȑO���₵�܂������A�d�����]�Ԃ̃_���ɂȂ肩�����d�r�����̓~�̊ԂɌ������܂����B �@���̓d�r�̓j�b�P�����f�d�r�S/�R�`�@�Q�D�WAH�ŁA�H������Ńj�b�P�����f�d�r18.0mm�~65.0mm�@�S�D�TAH�@20�{���Č������܂����B �@���ʂ́A�O���p���[�_�E���A�g�p���Ԃ��Z���Ɗ��҂ɔ��������ʂƂȂ�܂����B �@��͂�A�[�d�푤�ɖ�肪����̂ł��傤���B �@�S���̑f�l�Ȃ̂Ŕ��f�����܂���B �@�����A�ǂ��A�h�o�C�X��������肪�����ł��B fujisawa �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����́A���������d�r�̐��\�ɂ����̂��A�[�d��̖��Ȃ̂��A�������ڂ����������Ȃ��ƕ�������ł͑S���킩��܂���B �@�d�r�̑��Ɍ���������ꍇ�A���̌��������d�r�����ۂɂ��̂悤�ɕ\�L��菭�Ȃ��e�ʂ̓d�r��������A��r�I�傫�ȓd�������o���ɂ����^�C�v�̓d�r��������ƁA�d�r�����[�^�[�����p�r�ɂ͌����Ă��Ȃ��^�C�v�̐��i�ł���\��������܂��B �@�d�r�ɂ����i�Â�������܂�����A���̎��]�Ԃɓ��ڂ���Ă��������d�r�͑�d���g�p�����̓d���H���H�Ƌ@��p�d�r�B����ꂽ�̂͏��d�������Ԏg�p����@������̓d�r�������Ƃ��A�����܂Łu�\���v�����Ȃ炢����ł��l�����܂��B �@���Ƃ����[�^�[��͋����K�v�̂��郉�W�R���J�[���̏ꍇ�ł��A�o�b�e���[�͓����u�j�b�P�����f�ExxxmAh�v�Ƃ������ł����[�J�[�E�����E���b�g���ɂ��u���[�^�[���悭���v�u�キ�đ�������Ȃ��v�Ɨl�X�ł��B �@�[�d�푤�ɖ�肪����ꍇ�A���イ�Ԃ�ɏ[�d�ł��Ă��Ȃ��u�\���v������܂��ˁB �@�{����菭�Ȃ��e�ʂ��[�d�����Ƃ���łȂ����[�d��̔��f�Ŏ~�܂��Ă���Ƃ��A��������������������d�r�̒��ɕs�Ǖi���������Ă��āA���̕s�Ǖi�̂����œr���Ŏ~�܂��Ă��Ďg�p�ł��Ȃ��Ƃ��B �@�����܂Łu�\���v�Ȃ炢����ł����܂����A���g���̓d�r�E���]�Ԃʼn����N�����Ă���̂��͎��ɂ͔��f�ł����˂܂��B �@���[�J�[�����̃o�b�e���[�p�b�N�͂��̗p�r�E�@��ł����\�������ł���悤�I�����ꂽ�i�ł����A����𑼂̕i�Ɍ������ꂽ�ꍇ�͖{���̐��\���ł��Ȃ��ꍇ�����ʂɋN���蓾�܂��̂ŁA����̂悤�ɂ��Ȃ萫�\�������Ƃ������ł���Γd�r�̊e�Z�����ɂ�ł��Ȃ����A�s�Ǖi�͍������Ă��Ȃ����A�\�L�ʂ�̗e�ʂ͂���̂��H�A�Ȃǂ��������Ō����ł���@��𑵂��Ċm���߂鑼�Ɏ�͖����ł��B �@�ʂɗe�ʑ���ł���[�d��E���d��Ŋe�d�r�Z���̗ǔۂ肵�đ��v�ł�����A���]�ԂŎg�����Ă��玩�]�Ԃ̏[�d��ŏ[�d���A�[�d����~������̃o�b�e���[���o�����Ċe�Z���̗e�ʂ���d��ő��肷��Ȃǂ�����Γd�r�������̂��A�[�d��̂ق��Ŗ�肪�N���Ă����Ə[�d�ł��Ă��Ȃ����͔��f�ł��܂���ˁB �@���������������s���āA�ǂ��������Ȃ̂���˂��~�߂��炻����Ώ�������@���l���Ă��������B ���Ԏ� 2009/4/11
|
||||||||||||
| ���e 4/12 |
�@���J�Ȃ����肪�Ƃ��������܂��B �@�\��������Ԃ��Ă݂܂��B �@�d�r�̉��[���ɁA�����Ă��܂��B �@�ǂ������肪�Ƃ��������܂��B (������]) �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ����ƕ���̗����������Ďg�� | |||||||||||||
|
�@12V�̃o�b�e���[2�g�p�Ł@���ݕ����H���o�����ł��Ă����p�ԂɁ@24V�̗p�i���g�p�������̂Ł@�o�b�e���[�����̗p�i�ɂ����@����Ŏg�p�������Ǝv���Ă��܂��@�����H�ƕ����H�̕��p�͉\�ł���?�@�����I�Ȏ���Ł@�����܂���@��낵�����肢���܂��B �吼 �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ʂɍ\���܂��A����ɂ���o�b�e���[�����[�d���ɂ͊O���ĕʂ̏[�d��H�ŏ[�d����Ƃ��A�Ԃ���[�d����悤�ɂ���̂͂����ւ�ł��ˁB �@�܂����ʂɃo�b�e���[�Q�Œ���g�p���Ă���g���b�N���̏ꍇ�͂��̂Q�̃o�b�e���[�͎�����Ԃŏ[�d����d���s����̂ł��܂���͂���܂��A���������q�������Ɗe�o�b�e���[�̎c�ʂɂ��Ȃ�o�������o��̂Ńo�b�e���[������Ȃ��悤�Ɏg���̂͂��Ȃ�C���g���܂��ˁB �@��Ԃ�Ǘ��̖ʓ|���͂���܂����A�d�C�I�ɂ͂��������q�����ł̎g�p�͂ł��܂��̂ŁA�o�b�e���[���Ȃ��悤���ӂ��Ď��s���Ă��������B ���Ԏ� 2009/4/11
|
||||||||||||
| ���e |
�@���肪�Ƃ��������܂� �吼 �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�Ǘ��l�l�A�F�X�ƗL�v�ȏ��̔��M���肪�Ƃ��������܂��B �@�������Ă��������Ă��܂��B �吼�l �@���������Ď��₳�ꂽ�������̂́A �@�@�@12V�̒ʏ푕���i���g���Ȃ���A������24V�̗p�i���g�������̂� �@�@�@�o�b�e���[��ƁE����̕��p���������B �@�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł����H �@�Ǘ��l�l�̉� �@�@�@�����H�ƕ����H���u��ւ��āv���p���邱�Ƃ͉\�ł��B �Ƃ̓��e�ł��B �@�@�@�����H�ƕ����H���u�����Ɂv���p���邱�Ƃ͏o���܂���B �@�����Ӊ������B �܂肷 �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�₢�ʂɁA����12V�Ŏg���Ă��鏊�ɁA����24V�Ŏg�p���镔����t�������Ă��u�d�C�I�ɂ́v�S�R�\���܂����B�u�����ɕ��p�v�ł��܂��B �@���̘b�̏ꍇ�u����Ŏg���Ă���v�Ƃ��������͑S���W�����������č\���܂���B�K�v�Ȃ̂�12V�Ŏg�p���Ă����H�ɒ���Ƀo�b�e���[���q����24V�̋@����g���Ă��ǂ����Ƃ����_�����ł��B �@���������q�����������ꍇ�A����12V���ł��d���������̂ł�����ꂼ��̃o�b�e���[�ɗ����d���l�͈Ⴂ�܂�������Ղ���x�������ς��A�o�����X�������Ȃ�̂ŏ��Ղ��i�ނƍ���Ȃ��Ƃ������x�ł��ˁB�ߕ��d�ɂȂ�Ȃ��O�Ɏg�p����߂�̂ł���Γ��ɖ�肪����Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����B �@���ꂼ��̃o�b�e���[�Ɍʂɓd���v�����āu�Ǘ��v��ӂ�Ȃ��Ƃ��B �@�܂��lj������o�b�e���[�ɂ͂��̂܂܂ł̓I���^�l�[�^�[����͏[�d����܂���A�O���ď[�d����(�܂��͐ؑ։�H�̂悤�ȕ�������ăX�C�b�`�ő��삷��)��Ԃ���ς��Ȃ��Ƃ������ł��B �@����I�ɑ����Ă��鎮�Ɏg�p����̂ł͂Ȃ��A�L�����v�̓��̖�ȂǓ���̎��Ԃ���24V�@����g�p�������̂ł���Ώ\�����p�ɑς���Ƃ͎v���܂��B����Ɏg�p����lj��̃o�b�e���[�͉Ƃŏ[�d���Ă����āA�ԂŎg�p���鎞�͕��d�p�r�ɂ̂ݎg���o�b�e���[���ꂽ�炨���܂��B�Ƃ��B �@���ʂ̐l�Ȃ�24V���g���ׂɁA�Ԃ�12V�n�Ƃ͕ʂ�12V�o�b�e���[���Q�p�ӂ��Ē���ɂȂ��u24V��p�n�v�Ƃ��Ďg�p����̂����ʂł����A�吼�l�͊��Ɍ���12V�n�ł��o�b�e���[�����ɂ���ׂɂQ��(�ȏ�)�ς܂�Ă��ĎԂ���ςɏd���̂ł��傤�B �@�����ɍX�ɂQ�o�b�e���[��ςނƏd�����q��ł͂Ȃ��Ȃ�̂ň�̒lj��ōς܂����Ƃ����蔲���Ă��l�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���ׂ̈Ɍ���12V�n�Ƃ̒���ł̎g�p�͂ł��܂����A�L�����v�Ȃǒ�Ԓ��̎g�p�ŃA���o�����X�ȓd������Ō���12V�n�̃o�b�e���[�̂ق��ɕ��S���傫���Ȃ邱�Ƃ͊o��̏�ł̂��g�p�Ƃ������ł����\�Ȃ�u�d�C�I�ɂ́v�\�ł���B12V�n���u����v�ɂ���Ă���Ƃ������ŁA�����������S�ɂ��ς���悤�Ɏ��O�ɑ�e�ʉ�����Ă���̂�������܂���B ���Ԏ� 2009/4/12
|
||||||||||||
| ���e |
�@���݂܂���B �@�����n�R���ȕ��ł�����A�o�b�e���[��lj������� �@����ƒ���p���ꂽ���̂��ȁH�Ǝv������ł��܂����B �@�Ȃ̂ŁA �@�Q�̃o�b�e���[�ŕ���ƒ�����q�������Ďg�p(�����g�p�s��) ���� �@ ���� �@�@�@�@ 24�u �@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�� �@12�u�@�@�| �������@�@�� ���@���@�@�� �|�@�|�@�@�| �������@�@�� �Ȃ�n�j�ł����A ����E�����H �@ 12�u ����������24V �����@�� ���|�@�| ���������� ���@�@�@�� ���������� �@����͏o���܂���B�ƌ������������̂ł����B �@�}�ɂ���Ɩ��������Ă����ɔ���͂��ł����A������ڂ̑O�ɂ��āA�lj��̃P�[�u�����������Ă���ƁA���������Ă��܂��̂ł́H�ƐS�z�������܂��āB �@������吼�l���u�����I�Ȏ���v�Ə�����Ă�������Ƃ����āA����ł͌����т�߂��ł��ˁB��ώ��炵�܂����B �@������� �@�P�`�Q�̃o�b�e���[��lj����ĕ���E���p�i�����g�p�j 24�u �@�@�@ 24�u �@�@�@�@�@�@ 24�u �@���@�@�@�@�������@�@�@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@���@���@�@�@�@�@�@�@�� �@�|�@�@�@�@�|�@�|�@�@�@�@�@�@�@�� �@���@�@�@�@�������@�@�@ 12�u �@�| ������12�u�@������12�u�@�������@�� ���@���@�@�@���@���@�@�@���@���@�� �|�@�|�@�@�@�|�@�|�@�@�@�|�@�|�@�| �������@�@�@�������@�@�@���������� ����Ȃ�u�d�C�I�ɂ́v�n�j�ł��ˁB �@�Ǘ��E�^�p����ςȂ̂͊Ǘ��l�l�������ꂽ�Ƃ���ł��B �܂肷 �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@����Q�p���Ŏg���Ă���o�b�e���[���̂܂܂�24V�p�̋@��ɑ��Ă̂݃V���[�Y�ڑ��ɂ��Ďg���Ȃ����ƌ��������̂��Ǝv���܂��B �@���炭�Ǘ��l�l�̍l�������Ȃ�����Ȃ̂ňӐ}���`���Ȃ������̂ł͖����ł��傤���B (������]) �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�͂��Ȃ�قǁA�o�b�e���[�͂Q�̂܂܂ŁA12V�n�ɂ͕���ŁA24V�n�ɂ͒���Ōq�����Ă���悤�Ȕz���Ŏg�p�������Ƃ���������ł������H �@����̓P�[�u�����Ȃ��ł̐ڑ������ł��F���̖@���łł��܂����ˁB �@��������������E�����H�ŃP�[�u�����q���ł��܂�����A�q�����u�Ԃɔh��ɉΉԂ��U���ăP�[�u�����n���邩������܂��A�������̍l������H���Ԉ���Ă����Ɗw�K����ɂ͂��イ�Ԃ�Ȍo���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �� ��H�}����}����̂��ʓ|�������̂Œ[�܂����̂ŗ]�v�ɐ����s���ł������B�}���ڂ��Ă���Έ�ڗđR�ł����ˁB �@�N���A���Ȃ荋���ȓd�͉�H�����āA�`���[�W�|���v�݂����Ƀo�b�e���[�������g�ŐؑւȂ��璼��ƕ�����Ɏ��������H(�������[�d�E���d�ɗ��Ή�)�Ƃ���v���Ă݂���͖̂ʔ����̂ł́H �@��������Γ��������邩������܂����B ���Ԏ� 2009/4/12
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �p�^�XV�̒����͉\�� | |||||||||||||
|
�@�p�^�XV�̒����͉\��
(������]) �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�\�ł�����A�s�\�ł����� ���Ԏ� 2009/4/5
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���ł�impulse | |||||||||||||
|
�@2��ڂł����X�������肢���܂� �@����Ȃ�ł����ŋߓ��łłł�impulse�Ƃ����d�r���o���݂����Ȃ�ł������̐��\�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���H �@�����܂�����Ȃ�����ŁO�O�G �@�����悩������g���Ă݂悤���ȂƎv���Ă��܂� �J���\ �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���ł̢IMPULSE �C���p���X����}�N�Z���́u�{���e�[�W�v���w�����Ă��܂���B �@�����ւ�\�������܂��A�]���E���z�͂���܂���B �@�ʒi�g���Ȃ��d�r�ł͖����Ǝv���܂��̂ŁA�w������Ă͂������ł����H �@���ł̔��\�����������ɂ́A�u�C���p���X�v�ƌ����Γ��ł̃��C�o�����(?)�̃p�i�\�j�b�N�d�H�́u�A�����J���t�b�g�{�[�����y�C���p���X�z�v����Ȃ��̂��I�H�Ǝv�������炢�ł�(��) �@���ł��A���t�g�`�[���������Ă��܂�����A�Q�[���Œ��ڑΌ�����킯�ł͂���܂��킴�킴�G��ƃ`�[���̖��O�Ɠ������O�����i�ɕt����Ƃ́A���e�Ȃ̂�����Ƃ��E�E�E ���Ԏ� 2009/4/2
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| CGL3032�̂�����CR3032�͑�p�ł��܂����H | |||||||||||||
|
�@����ɂ��́Amorim�Ɛ\���܂��B �@CGL3032�Ƃ����{�^���d�r�ł����A���[�J�[�ł͂��łɐ��Y���~�Ƃ������ƂŁACR3032�ő�p�ł��Ȃ��̂��ȁH�ƍl���Ă��܂��B �@CGL���A3.7V�ɑ���CR��3V�Ƃ���܂����A���̏ꍇ��p�ł���̂ł��傤���H�܂��͑��ɑ�p���ꂽ���͂�������Ⴂ�܂����H �@����ǎ����Ă݂悤�Ƃ͎v���Ă���̂ł����A���̖������ɂ��ǂ�������₳���Ē����܂����B morim �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��ɂ�߂Ă��������I �@CGL3032�̓R�C���^�̃��`�E���C�I���[�d�r(�d�r)�ł��B �@���`�E���C�I���[�d�r�ł������i�d����3.7V�A���[�d�����4.2V����܂��B �@����CR3032�̓R�C���^�̃��`�E���ꎟ�d�r�ł��B�[�d�͂ł��܂����B �@�u���`�E���d�r�v�Ɓu���`�E���C�I���d�r�v�͓����u���`�E���v���ۂ��ł����S���̕ʕ��ł��B��������Ƃ����ւ�댯�ł��B �@CGL3032���g�p���Ă���@��Ƃ������Ƃ́A�[�d��H���@����ɓ�������Ă���͂��ł�����A���̂܂܂ܓd�r����CR3032�Ɍ��������ꍇ�͏[�d�ł��Ȃ��ꎟ�d�r�ɏ[�d�d���𗬂��āu�d�r�̔j��E���Ȃ��v�̎��̂Ɏ���܂��B �@�u�[�d�@�\�͎g��Ȃ��ŁA�d�r�����܂Ŏg���Ďg���̂Ă�v�̂ł�����g���Ȃ����Ƃ͖�����������܂��A���S�z�̂Ƃ��胊�`�E���d�r��3.0V�ł����烊�`�E���C�I���[�d�r�̕��d�I�~�d���Ƃقړ����ŁA�u�@�킪�d���s���œ��삵�Ȃ��v�u�d�r��Ƃ݂Ȃ��ď[�d��H�������A�ꎟ�d�r��j��E���������v�\��������܂��B �@Panasonic����́uVL�n���`�E���R�C���d�r�v�Ƃ��������̔�����Ă��܂����A����d�������`�E���C�I���[�d�r���Ⴍ���̂܂܃��`�E���C�I���[�d�r�̏[�d��H�ł͂�͂�d�r��j�Ă��܂��܂��̂Ō����͖����ł��B �@Panasonic���ł͂���܂��A���E�̊e�Ђ��R�C���^���`�E���C�I���[�d�r��LIR3032�����ł������̔�����Ă��܂��B �@�C�O�̖≮��V���b�v�Ȃǂ���w�����邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��̂ŁA�K�v�ł���Β��ׂĔ��������̂͂������ł��傤���B ���Ԏ� 2009/3/25
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����肪�Ƃ��������܂��B �@���ԂȂ����ԂȂ��ł��ˁB �@�����Ɏ��₵�ėǂ������ł��B �@LIR3032�Ƃ����̂������ł��ˁB �@���{�ł͊ȒP�Ɏ�ɂ͂���Ȃ����ł��ˁ`�B �@���肪�Ƃ��������܂����B morim �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@LIR2032�ł����ˁA�ԈႦ�Č������Ă܂����B �@���{�ł��w���ł������ł��ˁB �@���Ȃ݂ɁA3032��2032�ƃT�C�Y�̈Ⴂ������܂����A���̕ӂ͑��v�Ȃ�ł��傤���H �@��p����ꍇ�̒��ӓ_�͉��������ł��傤���H �@���������ł��݂܂���B morim �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���݂܂���A���������N���LIR3032�ł������̏�����������LIR2032�Ə����Ă��܂��Ă����悤�ł��B �@���̂܂܉����l�����Ɍ��������̂ł�����LIR3032�����g�p���������B �@�������E�I�ɂ�LIR3032���LIR2032�̂ق������萫���ǂ��̂ŁALIR3032������ł��Ȃ��ꍇ��LIR2032�ł��������������Α�p�͌����܂��B �@�R�C���^�d�r�̌^�Ԃ́u��ʁv-�u���a�v-�u���݁v�ł�����ALIR�́uLithium Ion Rechargeable(���`�E���C�I���[�d�r)�v��3032�́u���a30mm�~����3.2mm�v���Ӗ����܂��B �@2032�́u���a20mm�v��30mm�ɑ���20mm�Ɩ�10mm�������̂ŁA�\�P�b�g�ɂ��̂܂ܓ���ăK�N�K�N���Ȃ�����̂܂g���܂��B�g����E�g���Ȃ��͋@�푤�̖��ł��B �@�܂����a���������Ԃ�e�ʂ��������ł�����g���鎞�Ԃ��Z���Ȃ�܂����A�e�ʂ��������Ə[�d���̋��e�ő�d�����������Ȃ�܂�����3032�T�C�Y�ōő���̏[�d�d���𗬂��v�̏[�d��H�ł͉ߓd���œd�r��j�Ă��܂��\��������܂��B������g����g���Ȃ��͋@�푤�̖��ł��B �@���萫�̗ǂ��ł�2032�T�C�Y�̂ق����ȒP�Ɏ�ɓ���ł��傤���A�g�p�����@��̓����E��H�v���悭�����ׂɂȂ��Ă���LIR2032�͂��g�p���������B �@���A���̃��[�J�[�ł́A���Ƃ���Panasonic���uCGL�v�Ɠ��̕�����Ǝ��̕��ɕς��ď��i�����Ă���悤�ɁA���[�J�[�Ǝ��̓������Ō���2032�Ƃ��Ă���[�d���̃��`�E���C�I���d�r�͂܂��܂����E����T���Ό����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B �@������������ȒP�ɓ��{�ł�����ł��鏤�i�����邩������܂���̂ŁA���̂ւ�͒��ׂĂ݂Ă��������B(���ꂮ����ꎟ�d�r�Ɠd�r�͊Ԉ��Ȃ��悤��) ���Ԏ� 2009/3/26
|
||||||||||||
| ���e 3/27 |
�@�Ȃ�قǁA������₷���������肪�Ƃ��������܂��B �@���ɂȂ�܂��B �@�����������Ă݂܂����BPD3032����Ԏ�ɂ͓��肻���ł��ˁB �i����̓��`�E���C�I���d�r�@2���ł���ˁj �@���낢��Ƒ��k�Ƃ������A���ⓚ���Ē������肪�Ƃ��������܂����B morim �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �z���_�̃C���T�C�g�̃o�b�e���[���� | |||||||||||||
|
�@�z���_�̏����^�C���T�C�g�̃o�b�e���[���������悤�Ǝv���܂��B �@�E�B�L�y�f�B�A�ɂ��A�u1999�N�ɃC���T�C�g�ɍ̗p���ꂽ�~�d���u�̓R�X�g�̒Ⴂ�j�b�P�����f(Ni-MH)�d�r���uIMA�o�b�e���[�v�Ɩ��t�����̗p����Ă���B�d�r�͉~���`���W���[���ł���A�X�̃Z����20����ɐڑ������1�̃��j�b�g���\�����A3���ԕ��d����6.0Ah�̗e�ʂ������A�p�i�\�j�b�NEV�G�i�W�[���ł���B�v�Ƃ���܂��B�uIMA�o�b�e���[�v�͂��ł��O�����ԂɂȂ��Ă��܂��B�o�b�e���[�̑I��Ɠ���Ɋւ��Ă��m�b�����݂����������B�i�M�u���O�Ő��\�̍�������LEXEL��NMH�g�d�r�͓���\�ł����H�j mechaoyaji �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����̃n�C�u���b�h�����Ԃ̃o�b�e���[�ɂ̓j�b�P�����f�[�d�r���g�p����Ă����^�C�v������悤�ł���(���ł͏������`�E���C�I���[�d�r�Ɉڍs���ł�)�A�n�C�u���b�h�Ԃ̃o�b�e���[�����̓��[�J�[�̏����i�������p���������B �@�uIMA�o�b�e���[�v�����Ē��ɓ����Ă���Z�������Ċm���߂�A�����Ɏg�������ȑ��̃Z���͒T���Γ���ł���ł��傤���A�n�C�u���b�h�ԂŎg�p����Ă��镨�͑��s�łقږ��[�d�ɋ߂���ԂŎg�p��������[���d�ɓ����������ʂȐ��i�ł���\��������܂����A�o�b�e���[���j�b�g�Ƒg�Ŏg�p����[���d�R���g���[���[�Ƃ̑����ȂǂŎs�̂̕��ʂ̓d�r�E���i���g�p����ƕs�����������\��������܂��B [�Q�l] �z���_�́u�n�C�u���b�h�Ԃ����v�@�j�b�P�����f�d�r���ł���܂��v �@�V�F�[�o�[��d�C�h�����A�傫���Ă��d���A�V�X�g���]�Ԃ��炢�܂łł���u���ȐӔC�v�œd�r���������ĉ����@��Ƀg���u�����������Ă��@�킪��ꂽ�蓮���Ȃ��Ȃ���x�ōς݂܂����A�����Ԃ̏ꍇ�͓��͊W�Ńg���u�����N�����ꍇ�ɂ��ꂪ���Ŏ��̂��N�����āA���������P�K�����ꂽ�莀�S����Ԃ�ɂ͍\���܂��A���Ԃ⑼�l����������Ŏ��Ԃ��̂��Ȃ����̂ɂȂ����ꍇ�Ɂu���ȐӔC�v�Ƃ������t�ł͐ӔC����肫��Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���̂悤�ȋ@��E���u�œ��ɂ����Ŏ�������Ȃ��ƃ_���Ȃ悤�ȃ��x���̕��������g�Ńo�b�e���[����������鎖�͐�ɂ��Ȃ��ł��������B �@���Ƃ���͎��̕��s���Œm��������܂��A�d�������Ԃ̏ꍇ�̓o�b�e���[�܂Ŋ܂߂ĎԌ��̊��Z�K�Ȃǂ̔F������Ă���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���H (���ʂ̎����ԃo�b�e���[�̂悤�ɋK�i�������āA�K���i�Ȃ烆�[�U�[�����R�ɂǂ̃��[�J�[���i�ł��������ėǂ��Ƃ����i�ł͖����悤�ȋC������̂ł���) �@�����ł���A�o�b�e���[�����������ꍇ�́u�����ԁv�Ƃ��ĎԌ��ɒʂ�Ȃ��Ȃ�A���̏�Ԃŏ���Ă������@�����ŏ��������ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��ł����H ���Ԏ� 2009/3/25
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����̉A���肪�Ƃ��������܂����B �@�uIMA�o�b�e���[�v��PCU(�p���[�R���g���[�����j�b�g)����Đ��䂳��uIMA�o�b�e���[�v�̗��i�s����PCU�̑z��O�ɂȂ�ƁuIMA�ُ�v�ƂȂ�A���[�^�[�A�V�X�g�����f����A�����̃K�\�����G���W���ԂɂȂ�܂��B �@�����o�b�e���[�K�i�i�i�n�C�u���b�h�p�̗ʎY�ėp�i�j�Ɍ������邱�Ƃ͉����ł͖��������ł���ƍl���Ă��܂��B���K�i�i�̓�����@��m�肽�������̂ł����A�����ŒT���Ă݂܂��B mechaoyaji �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���K�i�́u�n�C�u���b�h�p�̗ʎY�ėp�i�v�ł����B�݂���Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/3/27
|
||||||||||||
| ���e |
�����̃n�C�u���b�h�����Ԃ̃o�b�e���[�ɂ̓j�b�P�����f�[�d�r���g�p����Ă����^�C�v������悤�ł���(���ł͏������`�E���C�I���[�d�r�Ɉڍs�� �Ə����Ă���܂������ݎs�̂���Ă���n�C�u���b�h�ԁi���Ȃ��Ƃ����{�ԁj�Ń��`�E���C�I���[�d�r���g�p����Ă���Ԃ͂Ȃ������͂��ł��B ���ׂăj�b�P�����f�d�r�ł��B (������]) �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@IMA�o�b�e���[���J���Ă݂܂����B �@���w�E�̒ʂ�K�`�K�`�̌���i�ŁA����U�{�̑g�d�r��20�Z�b�g�����Ă��܂����A���[�ɌŒ�p�˂����̂���[�q������A�����e�킪�X�|�b�g�n�ڂłȂ���Ă��܂����̂ŁA�����͒��߂܂����B �@���߂ă������[���ʉ����ɂƕ��d�I�~�d����6.0[V]�ɐݒ肵�Ďԍڗp�R���v���b�T�ɂ��20�{�̕��d��2.0[A](��0.3C)��8.0[V]�܂ŏ[�d���s���܂����B�W�N�ԂP�S���L���������̃o�b�e���[�ł����A�S�̂�1/3���u1�Z���v���̗A1/3���V�i���l�A�c���1/3�����̒��ԂƂ�������Ԃł����B �@�o�b�e���[�}�l�[�W�����g�̐i���ɂ��A���݂̎Ԃł͍͗X�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă�����̂ƍl���܂��B���đ������������Ă���g�d�r���������鎖�ɕ��j�]�����܂����B �@���t���������肪�Ƃ��������܂����B mechaoyaji �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�n�C�u���b�h�Ԃ̓d��(?)�̓��`�E���C�I���[�d�r�ւ̈ڍs��ƒ��ŁA�e�ЂŊJ�����i�߂��Ă��܂��B �@���̒m�l�ł���20�N���炢�^���[�J�[�łd�u��n�C�u���b�h�Ԃ̌����J�����s���Ă���j�����܂����A�ނƂ̐��Ԙb�̒��ł͂������`�E���C�I���d�r�̘b�����o�Ă��Ȃ����炢�ł��̂ŁA�ڍs���Ԓ��ƍl���Ă��������Ă��܂��B �@�j�b�P�����f�[�d�r�^�C�v�ł́A�N�X�d�r(�Z������)���V�����Ȃ��Ă��āA�u�n�C�u���b�h�p�̗ʎY�ėp�i�v�Ȃ�ĕ��͑��݂���͂����Ȃ��A�ޞH���u����Ȃ��������炱�������g��������I(��)�v�Ǝ��̍�ɂȂ��Ă��܂��B �@�Ȃɂ���l�b�g�̐��E�͍L���̂ŁAWiki�Ȃǂɂ��n�C�u���b�h�p�̗ʎY�ėp�i������Ə�����Ă����̂�������܂��E�E�E �@�������A�d�r���[�J�[�̒��ł́u�d�u�^�n�C�u���b�h�ԗp�v�Ƃ����J�e�S���ł̕i�킪����킯��(IMA�o�b�e���[�p�Z�������̒��̂P��)�A���ꂪ�������Ƃ������e�i���X�p�Ƃ��ŗ����[�g�ɗ���Ă�������������������\��������܂���ˁB�i�K�`�K�`�ɕi���Ǘ����Ă���i�ł��傤���ǁA�������͂��邩������Ȃ��킯�ŁE�E�E�j �@�ł���]�͎̂ĂȂ��ł��������B �@������̃n�C�u���b�h�ԗp���`�E���C�I���[�d�r�ł́u���E�W���d�l���v(ISO�ɂ��K��)�̓������i��ł��āA���E���Ŏg���܂킹��u�n�C�u���b�h�p�̗ʎY�ėp�i�v�ɂ��悤�Ƃ��������������c���i��ł��܂��B �@���́uISOxxxx�K�i�d�r�v�ɂȂ�A�n�C�u���b�h�Ԃ̃o�b�e���[�̓Z���P�ʂł͓���̂��̂��g�p�ł���悤�ɂȂ��\���ł��B(��c�͊e���̗��Q�W������œD���̗l���炵���ł����E�E�E) �@�����l�ŕ������Č���������A�Z�����̂��w���ł��邩�͍��Ƃ��܂�ς�Ȃ�(�X�|�b�g�n�ڂȂǂ̑g�ݗ��ĕ����ς�Ȃ�)�Ƃ͎v���܂����A���Ȃ��Ƃ��e�Ђŋ��ʂ̃Z�����g�p����ɂȂ���ꂱ���u�����[�g�v�ł̃Z���̔��������͊����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɓi�O�O�G �@���`�̃l�b�g�̔��T�C�g�ň����ɍw���ł�����(�ł����N�H���e�B�H)�A�����ł��l�b�g�I�[�N�V�����Łu�n�C�u���b�h�ԗp�A�g���Y�h���`�E���o�b�e���[����܂��v�Ȃ�ďo�i������ł�����E�E�E �@���[�J�[�̔ޞH���A�u�K�i�i���o�Ă��A���{�̃��[�J�[�͎��ЋK�i���D��������g��Ȃ����������B�����ł����Ђ̓Ǝ����i�̂ق������\���ǂ��Ɛ�`���������A���ۂ��������d�r���J�����邾�낤����B(�Ƃ��������ۊJ�����c)�v�B�����炠�܂���҂��Ȃ��ق��������̂�������܂��B �@��mechaoyaji�l�̃C���T�C�g�̃o�b�e���[�����͗e�Ղł͂���܂��A5�`10�N�キ�炢�Ɏ�����̃n�C�u���b�h�Ԃɔ����������鍠�ɂ͓d�r�������e�Ղȃo�b�e���[���j�b�g�ɂȂ��Ă��邩������܂���B ���Ԏ� 2009/4/5
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���d������܂��� | |||||||||||||
|
�����y�����q�������Ă��������Ă���܂��B �@�u�C�̖����v�l�̃y�[�W���Ɋ�������A�P�O�O�ςk�d�c���C�g�������Ă݂���A100�~�V�K�[���C�^�[�\�P�b�g�pDC-DC�_�E���R���o�[�^���Ă݂���ƁA��ʐl�ɂ͖��ʂƎv����悤�Ȏ��œ��X�y�����߂������Ē����Ă���܂��B ����u���d��v���쐬�����Ē����܂����̂ŁB�������Ă��������܂����B http://suika-lab.blogspot.com/2009/03/blog-post_22.html ������ �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u���ʂ̓��X�v�ɂ悤�����I �@����A���ۂ�100�~���C�g���R�����Ă����͎��p���Ƃ����_�ł́u���������̂Ɂc�v�Ƃ������ɂ����ɋC�t���ł��悤�ˁB �@���{�ɂ́u�`�����ς���ΎR�ƂȂ�v�Ƃ����̑�Ȋi��������A����100�~�V���b�v�i���x�c�Ǝv���Ă��Ă���R�����Čォ��v���u�Ȃ�ł���Ȃɖ��ʂȔ������������I�v�Ǝ��s�̔O�Ɋׂ�����E�E�E �@�E�E�E�����܂ŒB��������ʓ��̋Ɉӂ��ɂ߂���I(��) �@���X���i���Ă��������B �@100�~�V���b�v�̖��ʏ��i����ł�����������悤�A�g�����W�X�^��R���f���T�̓f�W�b�g�Ńe�[�v�i�̒��������i���Đߖ�͔̂��ɗL���ł��ˁB����͎��Ɉ����B �@�������ɒI�ɏ����Ă���^�Ԃ⏔���f�[�^���������āA������e�[�v�ɏ����ʂ��Ă������ꂪ���Ȃ̂��ԈႢ�܂��A�������̂��������Y�ꋎ���Ă��Ă����v�ł���i�O�O�G ���Ԏ� 2009/3/23
|
||||||||||||
| ���e 3/25 |
�@���������̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B���i�̂ق��͂قǂقǂɊ撣�肽���Ǝv���܂��A�A �@���A�A�����\��̃f�W�^�����x�v�������Ă��邵�A�A���N�͓d�����P�b�g���w�����ĉ�������\������ĂĂ���܂��B����Ƃ��y���݂ɂ��Ă���܂��B�ł͂�������悤 ������ �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| WF-138�̉��x | |||||||||||||
|
�@���������b�ɂȂ��Ă���܂��ASail�ł��B �@�ŋ߁AWF-138�[�d������g���͂��߂܂��ċC�ɂȂ����_������܂��B����͏[�d���̏[�d��{�̂̔��M�ł��B���ɓd����H�������Ă���̂œ��R�Ƃ͂����܂����ANi-MH�Ƃ͈ႢLi-Ion�[�d�r�ł͂��܂�M�ɂ͂悭�Ȃ��͂�(�ƁA��HP�Ŕq�������C�����܂�)�B �@�[�d��̗��ʂ��[�d���ɑ��肵���Ƃ���A�O�C��23�xC���ɏ[�d���40�xC�߂�����܂����B�����ēd�r�iUF16340�~2�j�̕\�ʉ��x��32�xC���x(���炭�͏[�d�킩��̔M�`��)�B���ꂪ�ďꂾ�Ƃ����炩�Ȃ�C�ɂȂ�܂��B �@�ꉞ�A�[�d��{�̗̂����ɔw�̍����S���������Ă݂͂܂������A�ʂ����Ăǂ��ł��傤��?�@���^�����[�^�[�ŏ[�d��{�̂̑��ʂƗ��ʂɃX���b�g�����A���M������邱�Ƃ�����ɂ���Ă��܂����A������Ɩ����Ă���܂��B���ꂪ���{���L�����[�J�[��Ni-MH�p�Ȃ炳�قNjC�ɂ��Ȃ��̂ł����A�Ȃ�Ƃ����Ă����ؐ��B�݂Ȃ��܂͂ǂ����v���ɂȂ���ł��傤��?�@��낵������ӌ��������������������B Sail �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ł��ˁB���x���C�ɂȂ�Ȃ猊���Ě���ٕ�������Ȃ��悤�Ƀ��b�V����\������A���^�̗�p�t�@��������ȂǐF�X�Ɖ������Ă݂�̂��ʔ����Ǝv���܂��B �@���̂Ƃ���ł�WF-138�͂ق�̂�g�����Ȃ�܂����A���`�E���C�I���[�d�r�̏[�d�����͉��x���z����悤�Ȋ����ł͂���܂���̂ŁA���ɉ������������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă��܂���B �@���ʂɊ��̏�ɒu���ď[�d���Ă��܂����C�ɂȂ������Ƃ͈�x������܂���B ���Ԏ� 2009/3/23
|
||||||||||||
| ���e 3/26 |
�@�����I�m�Ȃ��w�����肪�Ƃ��������܂��B �@�[�d��ւٕ̈������܂ł͋C�����܂���ł����B���b�V���ނ͊m���ɕK�v�ł��ˁB�ŋ߂͉��x�Ǘ��ɋC��z��悤�ɂȂ��Ă��ď����S�z���C���ł��BWF-138�͂��������l�q�����đ���u���悤�Ǝv���܂��B Sail �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �R�[�h���X�h�����̌����o�b�e���[����s�\ | |||||||||||||
|
�@�^�I�[�N�V�����Ə̂��鏊����R�[�h���X�h�����Z�b�g���w�������̂ł����o�b�e���[���Q�P�D�T�u�Ƃ��������ł͎�ɓ���邱�Ƃ�����o�b�e���[�ł��B�����������͂���܂����H�B����Ƃ��������ĕʂ̍��Y�̂m���b���i�H�j����ꂽ�����ǂ��̂ł��傤���B �@�����ĉ������B ��������� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��u�I�[�N�V������21.6V�h�����v�̔�Q�҂̕��ł����I�H �@��ɏo�Ă���w�d���h�����̃j�J�h�o�b�e���[�����ɂ����x�����ǂ݂��������B �@���̃h�����̃o�b�e���[��21.5V�Ƃ������ł����A�V��̏��i�ł��傤���B �@�Z���d������l���Ă���������21.6V�̂͂��Ȃ̂ł����A21.5V�Ə�����Ă���̂ł�����(�]����m���Ȃ��悤��)�l�b�g�Ō�������Ȃ��悤�ɂ킴�Ɛ��l��ς��ďo���Ă���Ƃ��H ���Ԏ� 2009/3/16
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���Ŏg���Ȃ��Ȃ���Li-ion�[�d�r | |||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�@����AWolf Eyes Defender Digital Cree R2 HO Li-Ion�[�d����Xenon 3.7V�o���u���w�����AXenon�o���u�Ɍ������Ė�Ԃ̎U���Ƀ��C�g��������܂Łi��1���ԁj�g�p���Ă܂����B �@���̌�18650�[�d�r�iWolf Eyes LRB-168A�v���e�N�g��H����)��t���̏[�d��iWolf Eyes���j�ŏ[�d��A�g�p����Ɠ_�����܂���B�[�d�s���������̂��Ǝv��������x�[�d��ɃZ�b�g���܂������A�����Ɋ��������v�ɕς��܂��i�ʂ̏[�d��WF-139�ł������j �@�ʂ�18650�[�d�r�iUltraFire�EMicroFire���j�ł͓_�����܂����B�o���u��Xenon����LED�ɂ��ǂ�����A�ʂ�18650�g�p���C�g�������܂��������߂ł����B�e�X�^�[�œd�����m�F���܂�����3.98V����܂����B���̓d�r��3.7�`4V�������̂œd���͖��Ȃ��悤�Ȃ̂ł����B�����͉����Ǝv����ł��傤���H takemiya �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@Li-ion�[�d�r���u�g�p�ł��Ȃ��Ȃ�v(�����Ƃ��̏�E�j���Ƃ�)�Ƃ�����Ԃɂ͂������̏Ǐ���܂��B �@����̂��b�ł͑����Z�����̏�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B �@�莝����Li-ion�[�d�r(���Z��)�ɂ������悤�Ɂu�J���d�����v��Ɩ�3.8V���邪�g���Ȃ��v��������܂��B �@������Ƃł����ׂ�������Əo�͓d���͂ق�0V���x�ɉ�����܂�����A�u�����ڐ���ł��e�ʂ��O�ɂȂ��Ă���v�悤�Ȍ̏�ł��ˁB �@����͐��Z���ł���A�v���e�N�g�t���d�r�̉�H�̏�Ȃǂ͌����ɂ͖����A������Li-ion�Z���{�̂Ŕ��ǂ��Ă��錻�ۂł��B �@���g���̓d�r���v���e�N�g��H���Ƃ������ƂŁA��H������炩�̌̏�����Ă���\��������܂����A�E�E�E���܂�l����Ǝv���܂��B �@���x���g���āu�����v�Ǝv����Z���͂قƂ�Ǐ[�d�ł��Ȃ��̂ł����A�[�d���Ă��ق�̏����̊Ԃł����ׂɓd���𗬂����炢�̗͎͂c���Ă��܂��B �@�����Ɨ������ꍇ�͊J���d�����قƂ�ǖ����Ȃ�A�[�d���ł��܂���B�N�����Ă��u���������܂����ȁv�Ƃ����悤�ȏ�Ԃ����܂��B �@�ŏ��̈��͂��܂��g���āA���ȍ~�͏[�d�ł��Ȃ��̂ł���A��͂��Z�����g�̌̏��̉\���������Ǝv���܂���B �@���̎g�p�ł����Ȃ����̂ł���A�����Ƃ������[�g(���X�̓X���Ȃ�)�ōw�����ă��C�g�ƈꏏ�Ƀ��V�[�g�E�ۏ؏��Ȃǂ�������[�J�[�ۏ��X�Ǝ��̕ۏ������Ǝv���܂��̂ŁA�̔��X�ɑ��k���Ă݂�Ɨǂ��ł��傤�B (�o�b�e���[�́u���Օi�v�Ƃ��ĕۏ؊O�̂��X�Ƃ������肻���ł����c) �@���ؒʔ̂Ȃǂōw�������ꍇ�́A�ۏ؏�������܂����ł̌̏���ؖ�����͓̂���̂ł��̂܂܋����Q����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/3/16
|
||||||||||||
| ���e 3/17 |
�@�Z�������A���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B�d��������ł��e�ʂO�̌̏�Ȃ�Ă����ł��ˁB �@�Ƃ肠�����w����ɕs��̃��[���𑗐M���Ă����܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����B takemiya �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���z�d�r�ƃ_�C�\�[�R���o�[�^�[�ŃG�l���[�v���[�d�ł��܂��� | |||||||||||||
|
�@�C�̖����T�C�g�Ǘ��җl�n�߂܂��āB �@�킽�����A���z�d�r�ƃ_�C�\�[�R���o�[�^�[�̑g�ݍ��킹�łt�r�a�i�T�{���g�j�[�d�V�X�e�������A���i����g����ЊQ�O�b�c�Ƃ����ʒu�Â��ŗV��ł��܂��B �@�g�ѓd�b�A�o�r�o�|�Q�O�O�O�A�c�r���C�g�̏[�d�͂��܂��o�����̂ł����A�G�l���[�v�̂t�r�a�[�d�킾�������܂������Ă���܂���B �@�[�d�͂���Ă���悤�Ȃ̂ł����A�₽�班�Ȃ��ʂ����[�d����Ă��Ȃ��B �@���܂��������ɂ͂ǂ�������ǂ����A�ǂ����m�b��݂��Ă��炦�܂���ł��傤���H �@�o����͈͂ő��肵���Ƃ���A���z�d�r�A�_�C�\�[�R���o�[�^�Ԃ̓d���� �@�@�@�o�r�o�|�Q�O�O�O�ł͂Q�T�O���`����� �@�@�@�G�l���[�v�t�r�a�[�d��ł͂P�O���`��������Ȃ� �@�Ƃ������Ƃ�������܂����B �@���̂��Ƃ��琄���ŃG�l���[�v�t�r�a�[�d�킪�d�����������肷���Ă���Ǝv���A���z�d�r�̓�������d���ɕω�������Ǝv�����肵���Ƃ���A �@�@�@�o�r�o�|�Q�O�O�O�ł͂V�D�R�T�{���g �@�@�@�G�l���[�v�t�r�a�[�d��ł͂P�P�D�Q�{���g �@�ƁA�\�z�ʂ�̌��ʂɂȂ�܂����B �@�����̍l������͈͂ł̓G�l���[�v�t�r�a�[�d���p�̃R���o�[�^�[����邵���l�����܂��A�ЊQ�O�b�c�Ƃ̈ʒu�Â����l����ƃR���o�[�^�[�͂ЂƂɂ������Ǝv���m�b��݂��Ă������������Ǝv���܂��B Jin �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�G�l���[�v�t�r�a�[�d�킪�d�����������肷���Ă���v�̂ł���A���ׂ��傫���̂ŏ�����d���������A�o�b�e���[�d����11.2V�Ȃ�č����d���͎������ɂ����Ə��Ȃ��d���������̂ł͂Ȃ��ł����H �@�u�������肷���v�Ƃ������͂��ꂾ���d��������Ă���͂��ł���ˁB �@���z�d�r���炽����10mA��������Ă��Ȃ��̂ł���A�S�R�d���͈��������Ă��܂����ˁB �@�u�G�l���[�v�̂t�r�a�[�d��v���ǂ��̉����킩��܂��A�P���ɂ��̏[�d����ɉ����d�q�I�Ȑ����H�������Ă��āA���̉�H�����肷�鐳��ȓd���d���͈͂ɃR���o�[�^�o�͂��������A�R���o�[�^�̏o�͐�����H�̓����ŏ[�d�킪�[�d�J�n���ɕK�v�Ƃ���d���������ł����ɓd���ቺ�����āA���̓d���ቺ���[�d����̓d�q��H�����肵�āu�[�d���Ȃ��v�悤�ɐ�ւ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł����H �@�Ƃɂ����A���́u�G�l���[�v�̂t�r�a�[�d��v������ɏ[�d��������鎞�̓d���d���͈͂ƁA���̎��ɏ����d���l�Ȃǂ��ڂ������ׂāA���̋K�i�Ƀ_�C�\�[�R���o�[�^���Ή����Ă��邩�����ׂĂ݂Ă��������B �@����Ƀ_�C�\�[�R���o�[�^�ƌ����Ă����Ђ��琔��ނ̕�����������Ă��āA��{�I�ȉ�H�}�͂قړ����ł����g�p����Ă��镔�i�ɂ���čő募���ł���d���l�����d���ɑ���o�͓d���̒ቺ������ꂼ��Ⴂ�܂��B��T�Ɂu�_�C�\�[�R���o�[�^�v�ƌ����Ă��܂����Ƃ͂ł��܂���̂ŁA�����g���̃R���o�[�^�̓����������ƒ��ׂĂ݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/3/8
|
||||||||||||
| ���e |
�@���₢���肪�Ƃ��������܂��B �@�d���̈������肪�����ł�����10mA�͂������Ȑ��l�ł��ˁB �@���Ƃ���Ƃ͂����p�������������ł����B �@�ʂ��Ă����G�l���[�v�̂t�r�a�[�d��̓T�����[�����́uNC-MDU01�v�ƁA�_�C�\�[�R���o�[�^�[�͋M�a�T�C�g�ł��Љ�Ă��鎩���ԗp�g�ѓd�b�[�d��(MC34063A)�ł��B �@NC-MDU01�̏���d���͒��ׂ��܂����A�R���o�[�^�[�����Ƃ͉����ǂ����ׂ��番����܂��F�X�����Ă��������Ǝv���܂��B �@�܂��A�G���L�W���b�N�Ƃ����G���𗧂��ǂ݂��Ă�����Ȉ�MPPT�Ƃ��ăg�����W�X�^�Ɣ��Œ��R�œ��͓d���̐��������Ă��܂����B �@�o����悤�Ȃ炱�̕ӂ�ɂ�����o���čs�����Ǝv���܂��B �@���Ƃ���̎���ɂ������Ă����������肪�Ƃ��������܂����B Jin �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����E�E�E������E�E�EMC34063A��IC�̌^�Ԃł����āAMC34063A�̊�{��H�}�����ɍ���Ă���R���o�[�^�ł��u���i���Ⴆ�ΐ��\���Ⴄ�v�Ə������킯�ł��B �@�_�C�\�[�Ŕ����Ă���12V��5V�g�я[�d��(315�~)�ł��`��������肵�āA���������̈Ⴂ��������Ⴄ���Ђ��炻�ꂼ��Ⴄ��E���i�萔�̕�����������Ă��܂���ˁB �@���Ƃ��A���鐻�i�ł͎g�p���Ă���R�C�����ׂ��đ傫�ȓd���𗬂��Ƃ����h���b�v���Ă��܂��Ƃ��A�d���������m�p��R�̒l���Ⴆ�Α傫�ȓd����K�v�Ƃ��ꂽ���̓��삪�ς��Ă���Ƃ��E�E�E�E�B �@������u�����ԗp�g�ѓd�b�[�d��(MC34063A)�ł��v���\�c�ꗍ���ɂ���Ă��܂��Ƃ́E�E�E�B������u���Ƃ���v�̈�ł����B �@��������DC�R���o�[�^���g��Ȃ��Ă��A���̕��@��MPPT������Ă������HP��u���O�Ȃǂ���R����悤�ł��̂ŁA�����[�����z�d�r�d���̌����͎v���������y���݂��������B ���Ԏ� 2009/3/8
|
||||||||||||
| ���e |
�@�͂��߂܂��āB �@usb�ɂ�4�̒[�q������ �@1��GND1��5v�c���2���M���p�̖�2.5v�̒[�q�Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă��܂�(�m���Ă��炷�݂܂���) �@������������Ƃ�����̂ŕ�����܂���psp�͐M���p�[�q���Ȃ��Ă������Ə[�d���Ă���܂��B�ł�iPod���Ƃ��̐M���p�[�q���Ȃ��Ƃ�������usb�ɂȂ����ĂȂ��ƔF�����[�d���Ă���܂���B �@����̃G�l���[�v�[�d��̏ꍇ��iPod�Ɠ����悤�ɁA�M���p�[�q�̓d��������Ă����Ȃ��ƑʖڂȂ̂ł͂Ȃ��̂ł��傤��? (������]) �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@������]�l�A�M�d�ȏ�肪�Ƃ��������܂��B �@USB�̐M�������u��2.5V�v�Ƃ����̂͏��߂Ēm��܂����B �@USB(2.0)�̐M������D+��D-�̂Q�{������AUSB Implementers Forum��USB�K�i�̋K��ł́uD+/D-�o�X��3.0V�`3.6V�̍����o�X�ł���A���[/�t���X�s�[�h�ʐM�����͔��f��VIH��2.0�`3.6V�AVIL��0.8V�ȉ��B�n�C�X�s�[�h��VHSSQ��100�`150mV�ȏ�B�v�ƒ�߂��Ă��܂��B�����d���ɂ��Ă̋K��ɁuDifferential Common Mode (VCM) 0.8�`2.5V�v�Ƃ������l�͏o�Ă��܂����A����̓o�X�d�����̂�2.5V�Ƃ������̂ł͂���܂����ˁB �@3.0V�n�ł���USB�o�X�̐M�����d�����u��2.5V�v�Ƃ����K��͂ǂ��ɂ��������Ԉ���Ă���̂ł����A����������܂���ʂ��Ă����Ԃ��Ƃ����炻��͂����ւ�߂������Ƃł��B �@�����uipod�͐M�����ɓd���������Ȃ��Ə[�d���n�܂�Ȃ��v�ƍŏ��ɏ������J�����l������������N�����uUSB�̐M�����͖�2.5V�v�Ȃ�ĊԈ�������������āA����������d�C�EUSB�̒m���������l�����̂܂܉L�ۂ݂ɂ��Ă݂�Ȃ����������ăR�s�[���y�[�X�g��ԂōL�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@������������A�f�W�^���ʐM���ł���USB��D+/D-�M�������ʂ̃e�X�^�[�œd�����v�����肵�āA�S�R��������2.5V���炢(�ŏ����t���t������H)��\�������̂Łu��2.5V�v�Ə����Ă���̂�������܂���B �@���łɁAiPod��iPhone��USB�[�d�P�[�u�������悤�ȋL���ŁA��R��5V���甼�����炢�̓d��������Ă�����uD+��D-���V���[�g�����Ă܂Ƃ߂Čq���v�Ƃ�����ϋ��낵���ڑ��𐄏����Ă���Ƃ��������̂Œ��ӂ��ĉ������B �@�K�i���USB�@�푤����̓z�X�g������v�������������f�[�^���M�͍s���Ȃ��͂��ł����A���Ƃ��uUSB�[�d����q�����u�ԁv�Ƃ��Ɂu�l�Ԃ̎�̓����ɂ��ڐG�s�ǁv�ŋ@��̓d��������肳��ĕs����ȏ�ԂɂȂ�������USB�R���g���[�����u���M�v��ԂɂȂ�Ȃ��Ƃ͌���܂���B(��{�I�ɂ�USB�̓z�b�g�v���O�Ή��Ȃ̂Ŕ�������OK�̂͂��ł����c) �@USB�o�X�͍����o�X�ł�����A�u�o�́v���ɂ�D+��D-�͂��݂��ɑ�������u���v�œ�����3.6V�d���܂���GND�Ɛڑ�����A�����O����D+��D-���V���[�g����Ă����USB�R���g���[������3.6V�d����H��GND�ƃV���[�g���ĉ��Ă��܂��܂��B �@�K�i��͂����������������悤�ɂȂ��Ă���͂�(����̋K�i�ȊO�ɂ��d�q��H��̕ی��H�Ƃ����c)�ł����A���̂悤�Ȏ��̂������N�����悤�Ȕz���ɂ��邱�Ƃ��u�����������ɐڑ����܂��傤�v�Ƒ��l�ɑE�߂�̂͂ǂ����Ǝv���܂��B �@�܂��A�uUSB�f�[�^���͖�2.5V�v���Ə������炢��USB�̒m���̕��Ȃ炻���܂œ����̎����m�炸�A�������Ă͂����Ȃ����Ȃ�Ă����m�����̂ł��傤���ǁB �@�[�d���J�n���邩�ǂ����̘b���ɖ߂��āAUSB�o�X�̓��삩�炷��Ɓu�z�X�g������D+/D-�ɉ��u���������Ă�����v�Ȃ�Ĕ���͂������Ȃ��ƂŁAUSB�@��̓z�X�g���Ɛڑ�������u�f�[�^�ʐM�����ăl�S�V�G�[�V����������������v���肪USB�z�X�g�ł���ƔF���E����J�n����̂ł���킩��̂ł����A�uUSB�o�X��D+/D-�ɉ����d�����������Ă�����v�����d���ƔF�߂ď[�d���J�n����ȂǂƂ����菇��USB�K�i�ɔ����Ă��܂��B �@�܂�D+/D-�ɂ�����x�̓d����������Ώ[�d���J�n����Ƃ���Apple���i(iPod��iPhone)�́uUSB�K�i�O�̎��ГƎ��K�i�i�v�ł���AUSB�z�X�g�ɂ͂Ȃ��ׂ����̂ł͂Ȃ�(USB�Ƃ��ĕs�K�i)�ƌ����Ă��܂��Ă��ǂ���������܂���B �@�upsp�͐M���p�[�q���Ȃ��Ă������Ə[�d���Ă���܂��v�Ƃ����̂����̃e�X�g���ʂ�\�j�[�̌������ƑS�������ł��ˁB �@USB�[�q���������v���C�X�e�[�V�����|�[�^�u��(2000�ԑ�)�Ńe�X�g�������ʁAUSB�[�q����̋��d�ł͑��肪USB�z�X�g�ł���psp�ƒʐM���������Ȃ��Ə[�d���[�h�ɂ͓���܂���ł����B�����USB�K�i�Ƃ��Đ������l�S�V�G�[�V�������s���Ă���Ǝv���܂��B �@�܂����Apsp�̏ꍇ�uUSB���d���v���O�ϊ��P�[�u���v�̂悤�ȕ����g�p���āupsp�͐M���p�[�q���Ȃ��Ă������Ə[�d���Ă���܂��v�Ȃ�ď�����Ă���̂ł͖����Ǝv���܂���(�f�[�^�[�q�̑S���W�����P�[�u���ł�����ˁc)�AUSB�[�q�o�R�Ńv���C�X�e�[�V�����|�[�^�u��(2000�ԑ�)��USB�z�X�g��������Ԃł��[�d�ł���悤�ȉ��ǂ��o�[�W�����ύX���������̂ł��傤���H �@�\�j�[��������USB�[�q����̏[�d�̓p�\�R����PS3��(�܂�USB�z�X�g)�Ɛڑ��������̂݉\�Ə�������Ă��܂�������A���ꂪ�ύX���ꂽ�̂ł����USB�P�[�u���ƌg�ѓd�b�[�d��Ȃǂŏ[�d�ł���̂ŕ֗��ɂȂ�܂����ˁB ���Ԏ� 2009/3/9
|
||||||||||||
| ���e |
�@�Q�l�܂ł� �@�莝���̎O�m�t�r�a��p�[�d��NC-MDC01�̓d���ʂɂ��[�d�������v��� �@�@�p�\�R���t�r�a�|�[�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�d���_�� �@�@�H���X�C�b�`���O�`�b�A�_�v�^�T�u�P�`�@�[�d���_�� �@�@�H���X�C�b�`���O�`�b�A�_�v�^�T�u�Q�`�@�[�d���_�� �@�@�H���c�b�c�b�R���o�[�^�T�u�P�D�T�`�@�@�[�d�ُ�_�� �@�c�b�v���O�Ƃt�r�a�̕ϊ��P�[�u���͎�����d���s�������ڑ����Ă��܂����B �@�c�b�c�b�R���o�[�^��HRD051R5E�œ��͂ɂ́A�|�[�^�u���d��SG-1000�̂P�Q�u�i���~�d�r�j�o�͂ł��B �@�ȏ�̌��ʂ���A �t�r�a�M�����͊W�Ȃ�
�@�ƌ������Ƃ������܂��B�@���Ƃc�b�c�b�R���o�[�^�ŒP�O�ƒP�l�ł͏[�d�ُ�_�ł̋�������ς��i�P�O�͂����ƈُ�_�ŁA�P�l�͊�{�ُ�_�ł��܂ɏ[�d���_�łɂȂ�܂��B�j �@�����ł����c�b�c�b�R���o�[�^���p���X�[�d�d���ɉ����ł��Ă��Ȃ������ł��B�i�m�M����܂���j ����炢�� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����炢�ӗl�A�ڂ������|�[�g���肪�Ƃ��������܂��B �@NC-MDC01��USB�M�����Ď����Ă��Ȃ��ėǂ������ł��ˁB > Jin �l �@�P���ɑ�Ȃ�ADC/DC�R���o�[�^�̏o�͂�10000��F���炢�̒�ESR�d���R���f���T(��������Ƒ�e�ʂ��K�v�H)��t���Ď����Č���Ƃ����肪�g���邩������܂���ˁB ���Ԏ� 2009/3/10
|
||||||||||||
| ���e 3/10 |
�@�Ǘ��l�l�A������]�l�A����炢�ӗl�A���X�y�ыM�d�ȏ�肪�Ƃ��������܂��B �@�����̓l�b�g������Ȃ��̂ł��Ԏ��x���Ȃ�\����܂���B �@�܂�������̏��Ƃ��āA �@NC-MDC01�̂t�r�a�̐M�����͊W�Ȃ����Ƃ͗��u�^���J���A�Ȃ����Ă��Ȃ����Ƃ͊m�F���Ă��܂����B �@�܂��APSP-2000�̏[�d�͂t�r�a=>�d���W���b�N�R�[�h�ŏ[�d���Ă��܂��B �@�Ƃ肠�������肵���f�[�^�[�V�[�g�X�y�[�W�̎Q�l�z�u�̒��Ɂu�O�D�P�v�Ȃ��̂�����A0.1��F�łȂ����Ƃɂ��ł���܂��B �@�Z���~�b�N�Ȃ炷���Ɏ�ɓ��肻���Ȃ̂ŁA�܂��͂��̕ӂ肩��͂��߂Č��܂��B �@�܂��A�I�v�V�����t�B���^�[�Ȃ���̂������Ă���̂ł����A�R�C���������ł��邩�ǂ����B �@��e�ʃR���f���T�͂��ꂩ��T���Ă݂܂��B �@�H��DCDC�R���o�[�^�[5V1.5A�Ƃ�HRD051R5E�ł��傤���H �@�ǂ����̃z�[���y�[�W�ł͂��܂�L���C�ȏo�͂ł͂Ȃ��ȂǂƏ�����Ă����悤�ȁB�����ɂ͈Ӗ��͕�����܂��A�����̎����Ă���_�C�\�[�g�я[�d�p�R���o�[�^�[���L���C�ȏo�͂łȂ��[�d����Ȃ��̂��ȁH�Ɛ������܂��B �@�����ł����n���ɂ���čs�������Ǝv���܂��B���A�������肪�Ƃ��������܂��B Jin �l
|
||||||||||||
|
�����y�����ǂ܂��Ē����Ă��܂��B �ߋ����O�����Ă��ċC�ɂȂ������Ƃ�����܂��̂œ��e���܂��B USB�[�q������[�d�ɂ��Ăł����AD+ �� D- ��Z������[�d��p�|�[�g(Dedicated Charging Port)�Ƃ����d�l������܂��B http://www.usb.org/developers/devclass_docs �� Battery Charging �K�i�ł�(���� v1.1)�B ���Q�l�܂łɁB �z�I�W�� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��肪�Ƃ��������܂��B �@�����Ō�ɏڂ����m�F����2005�N���ɂ͖����������(�K��)�ł��ˁB �@������USB�[�d��⏟��ɓƎ��K�i�����������̂ōQ�Ă�2007�N�ɋK�����悤�Ƃ����̂ł��傤���B �@���Ȃ݂ɁA�ǂ̋L���ŏ����Ă������ɑ��邨�b���킩��܂���ł����̂ŁA������Ɍf�ڂ����Ă��������܂����B ���Ԏ� 2010/3/2
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| THC-34RKC���t���b�V�� | |||||||||||||
|
�@����HP�������y�����q�������Ă��������Ă���܂��B �@���āA����\�Ă���Tiablo TL-1(AA�~1 or 14500�~1�d�l)���͂��܂����B����ɍ��킹�ď[�d��Evolta�ƃZ�b�g��BQ-391�[�d����w�������̂ł��B �@�Ƃ���ŁA���̏[�d��BQ-391�́u�������[�d�v�Ȃ�@�\�����ڂ���Ă��܂��B���́A�̍w���������Ő�Ni-MH��TH-3K(min 2300mA)������Ă��܂���(��N�Ԉȏ�����u���Ă����̂ł�!)�ABQ-391�̂������[�d���o���邩�������Ă݂��������̂ł��B���ʂƂ��Ă͗ǍD�B���̌Â�TH-3K(�~16�{)�͗]�����ɉ߂��������ł��B �@����BQ-391�Ɋւ��Ă͋C�̖����l�̋L���ɂ��G����Ă���̂Œ��ڂ��Ă����̂ł����A�c�O�Ȃ��ƂɃ��t���b�V���@�\������܂���B����ɂ��Ă��L���Ɍ�w�E������܂������A���t���b�V���@�\�̕⊮�Ƃ��ĂЂƂv�����܂����B���͍��܂Ŏg�p���Ă������Ő��̏[�d��THC-34RKC�̃��t���b�V���@�\���g���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�������ɂ��A����THC-34RKC��min 2000mA��TH-3LB�ɂ��Ή��Ƃ̂��ƁB����ƁA����Ni-MH�ŗe�ʂ�������HH-3MRS�ł����t���b�V���Ə[�d�͉\�ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����������ł��傤��?�@�������A�X�̓d�r�ɂ̓��[�J�[�����̏[�d����������͂��Ȃ̂ŕK�������œK�ȏ[�d�ɂ͂Ȃ�Ȃ������m��܂��A�ꃖ���Ɉ�x�Ƃ����X�p���Ń��t���b�V�����s���ꍇ�ɂ̓G�l���[�v��[�d���G�{���^�̃��t���b�V���p�ɓ��Ő��̏[�d�킪�g���Ȃ����ƍl���Ă���܂��B���܂��莝���̂��̂ŗ��p�ł���Ǝv���A���ӌ������������肦����K���ł��B �ǐL:�ȑO���e���܂���UF WF-138�[�d��͖����ɍw���ł��܂����B Sail �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@THC-34RKC�Ń��t���b�V���͂ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2009/3/5
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| IC���R�[�_�[�̓d�r���k | |||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�����Q�l�ɂ����Ă��������Ă��܂��B �@�C�ɂȂ镔���������Ă����������肪�Ƃ��������܂��B �@�����͌l�I�ɂǂ����Ă��C�ɂȂ��Ă��鎖�����₵�܂��B �@�����͎d���Ȃǂ�IC���R�[�_�[��������Ă��āA�g�p�p�x�����ɍ����l�ԂȂ̂ł����AIC���R�[�_�[�Ɏg���P4�d�r���ƁA�ǂ̏[�d�r���œK�Ȃ̂ł��傤���H �@�R�X�g�p�t�H�[�}���X�I��powerloop�Ȃǂ��������Ă܂����A���g���N�\�Ŏg���Ȃ���A�̐S�Ȏ��ɓd�r��A�Ȃ�čň��̏ꍇ�����낤���Ǝv���ƁA�Ȃ��Ȃ������܂���B �@���ƌ�����eneroop�͗e�ʂ����Ȃ��݂��������A�^�����Ԃ��Z���̂��C�����Ȃ��A�Ȃ�Ďv���A�����Ă��܂��B �@���Z�����Ƃ���\����܂��AIC���R�[�_�[�Ŗ�����������������^�����Ă���w�r�[���[�U�[�̎��ɁA�I�X�X���̒P4�d�d�r�������Ă��������܂���ł��傤���H �@����Ƃ��łɁA�[�d��͍��܂Ŏg���Ă������̂ł��ǂ����A����������Ă��������B �@���m��SONY�̃��t���b�V���@�\�t��BCG-34HRD�ł��B ��� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���������̋@��Ŏg�p����Ȃ�A�ʂ�eneloop�̂悤�Ɏ��ȕ��d��}�������^�C�v�̓d�r�łȂ��Ă��A�����[�d���Ď����ďo����������ł���ˁB �@����ł�����O�m�̒P�l�^�j�b�P�����f�[�d�r��1000mAh�^�C�v(HR-4UG)��l�N�Z����1000mAh�^�C�v�ȂǁA�e�ʏd���̓d�r���g���Ă͂������ł��傤���B �@�P�l�^�j�b�P�����f�[�d�r�͗e�ʂ����Ȃ��̂ŒP�O�^�ɂ���ׂĔ�r�I���ȕ��d�����Ȃ��A�������u���������ŗe�ʂ������Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ�����܂���B �@100�~�V���b�v��VOLCANO NZ(750mAh)�Ȃ�Đ��������u���Ă��Ă��S�R���ʂɎg���Ă��܂��B �@�P�N���x�Ƃ��A���̂��炢�����ԕ��u����Ȃ�eneloop��[�d���G�{���^�̂悤�Ȏ��ȕ��d�}���^���K�v�ł����A��r�I�g�p�p�x�������d�r�ꂪ�S�z�ł���Ύs�̕i�̒��ł���e�ʃ^�C�v�̏[�d�r��I�ꂽ�ق������S���Ǝv���܂��B�Q�g�����Č��݂Ɏg���Ă���(�Б������g���Â��āA�Б��͗\���̂܂܂ɂ���̂͂��@�x)�\��������d�r��̎��ɂ����������Ďg���܂���ˁB �@�P�l�d�r�̗e�ʂ͐̂����ׂ�Ɗi�i�ɑ�e�ʂɂȂ����Ƃ����킯�ł͂���܂���̂ŁA�[�d��͂��̂܂܂��g�������Ă����v���Ǝv���܂��B �@����̗p�r�ł́u�d�r�ꂪ�S�z�v�Ƃ����_���傫���Ǝv���܂��̂ŁA�������Z���ԈȊO�ŁA���ʂɁu�g�p�����v�Ǝv�������̓��̂����ɂ��̂܂[�d����悤�ȁu�p�������[�d�v���s���ĂȂ�ׂ����[�d��ԂŖ������������悤�ɂ��āA20��Ɉ�x���x�̓��t���b�V�����Ă��Γd�r�̃R���f�B�V�����������ɓn��ǂ���Ԃ��ۂĂ�ł��傤�B �@�قږ����g�p����̂ł�����A�P�����Ƃɓd�r�Q�g�����݂Ɏg���āA�ꃖ���Ɉ�x�����ς鎞�Ƀ��t���b�V������悤�ȏK��������悢�Ǝv���܂���B �@poweloop�̒P�l�͎g�p�������Ƃ�����܂���̂ŁA�ǂ̒��x�̕��u�ɑς�����̂��͒m��܂���̂ł���Ɋւ��܂��Ă͈ӌ��͍����T�������Ă��������܂��B ���Ԏ� 2009/3/1
|
||||||||||||
| ���e 3/1 |
�@�v���Ȃ��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@���ɏ�����܂����B �@�P3�ƒP4�ł́A�܂��������Ă��ł��ˁB �@��e�ʃ^�C�v�̂��̂��Ă݂܂��I �@���肪�Ƃ��������܂����B ��� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���`�E���C�I���d�r�̃v���e�N�g��H�̗��p | |||||||||||||
|
�@�����������Ē����Ă���܂��Bm(_ _)m �@���ă��`�E���C�I���d�r�̃v���e�N�g��H�ł����A���C�g���ɑg�ݍ��ގ��͉\�ł��傤���H �@�Ⴆ�v���e�N�g�t�̓d�r�ɓ�������Ă����Ղ��������āA�X�C�b�`���Ɏ��[����Ƃ��A���d�r�̃}�C�i�X���ɓ\��t����Ƃ��E�E �@�ߕ��d�h�~�����ł�������ł����E�E�E�B bao �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���`�E���C�I���d�r�̃v���e�N�g��H�́A�d�r����O���đ��ɗ��p���鎖���͉̂\���Ǝv���܂��B �@���̓d�r�ɓ\��t����(�A���d���z���Ȃǂ͂����Ƃ���)�g���̂��ł���ł��悤���A���C�g�ɑg�ݍ��ނ̂��ʔ������ł��ˁB �@�����A���C�g�̃e�[�����ɂ���X�C�b�`�̒��ɂ͓���ł��ˁB�d�������܂���B�w�b�h���ɓ���Ă����Ɠd��������Ďg���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/2/12
|
||||||||||||
| ���e |
�@���܂���C�t���܂����B �@���X���肪�Ƃ��������܂��B �@�����Ă݂܂��B bao �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����Ă݂āA�����ʔ����g�������ł����狳���Ă��������B ���Ԏ� 2009/4/8
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �j�b�P�����f�d�r�̔����ւ������A���� | |||||||||||||
|
�@�u�C�̖����v���炵���g�o�ł��ˁB �@�f�l�Ȃ���ɁA���̐�含�̍����ƌ����S�ɊS���Ă���܂��B �@�������łɁA�ǂ����ɉ�����Ǝv���܂����A�T���Ȃ������̂Ŏ��₳���Ă��������܂��B �@�j�b�P�����f�d�r�̔����ւ������Ƃ������H �@�����Ƃ������H�@���낻��p�����āA�V�����̂ɔ����ւ��邩�Ƃ������f�͂ǂ�����悢�̂ł����H �@������g����Ƃ����Ă��A�Ȃ�Đ����ĂȂ����E�E�B �@�Ǝv���Ă܂��B �@���́Aeneloop���ł�O�̌Â��j�b�P�����f�d�r�����{�������Ă���̂ł����A���T�C�N���ɏo�����̂��H�܂��A�g����������ƔY��ł��܂��B �@�܂��A�Â�eneloop�ƐV����eneloop�����Ďg���Ă����ɖ��Ȃ��ł����H �@���ƁA�J�[�o�b�e���[�ɂ��Ď��₵�Ă��悢�ł����H �@������A�������f�ł����E�E�B�o�b�e���[�t�̔�d�ȊO�ɊȒP�ɂ��낻��ւ����Ɣ��f������@�́A����܂��H �@�o�b�e���[�t�̔�d�͌v�������Ƃ͂���܂��E�E�B �@�������A�J�[�V���b�v�ɂ����A���肵�Ă����Ƃ́A�킩���Ă���̂ł����A�o����Δ��������Ȃ��̂ɁA���肾�����Ă��炤�̂ɁA�C���Ђ��܂��̂ŁB �@���݂܂���B�����I�Ȏ��₾�炯�ŁB�B kenken �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�j�b�P�����f�d�r������Ɓu500��v��u1000��v�ȂǂƌJ��Ԃ��g�p�\��������Ă��܂��ˁB �@�ł���������ۂɓd�r���g�p�ł�����̎��ł��A�����ւ������ł�����܂���B �@�ł͂��́u500��v�u1000��v���ĉ��H�A�ƂȂ�Ǝv���܂��B �@���̉́AJIS�������@�Œ�߂�ꂽ�d�r�̐��\�������s���āA���̋K��ɂ��e�ʂ�60%�܂Ō�������܂ł̌J��Ԃ��[�d�Łu500��ȏ�B���v��u1000��ȏ�B���v�Ƃ�������N���A�����d�r�ł���Ƃ����Ӗ��ł��B �@JIS�������@�ł́A�d�r��r���܂Ŏg���Čp�������[�d���J��Ԃ��A�r���Ŏ��X100%���d�����Ă��疞�[�d����A�����郊�t���b�V���̂悤�Ȏ�������Ƃ����z���50����P�Z�b�g�Ƃ��Ă��������B���ł��邩�œd�r���e�X�g���Ă��܂��B �@���킵���́w�G�l���[�v�̎g�p�͂ǂ��łP��H�@�g�����Ǝ����̊W�́H�x�Ő������Ă��܂��̂ł��ǂ݂��������B �@�ł́u������������̂��H�v�ł����A����͒N�ɂ��f���ł��܂���B �@�g�����ɂ���Ă�50�炢�ł��������s���邱�Ƃ�����܂����A�܂��ʂ̎g�����ł�1500�炢�͎g���邩������܂���B �@JIS�����ɂ��j�b�P�����f�[�d�r�̎����́u�e�ʂ�60%�������܂Łv�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B �@�܂�g���鎞�Ԃ��V�i�̎���60%���x���Z���Ȃ������ɂ́u����͎�������v��JIS�͒�߂Ă��܂��B �@�ł�����͂����܂ň��̊������Ă����Ȃ��ƁA�����Ɋe�d�r�̐��\��]���ł��Ȃ����炠��Ƃ���Ɋ��݂��Ă��邾���ŁA�e�ʂ�60%�ɂȂ����d�r���S���g���Ȃ��Ȃ����킯�ł͂���܂���B�܂�60%���g����̂ł��I �@�d�r�͐V�i���珙�X�Ɏ����ɋ߂Â��Ă䂭�ƁA�e�ʂ����邾���ł͂Ȃ����o����d���������������Ă䂫�܂��B�d����������Ɩ��[�d������ł����[�^�[���͂�C�g�����閾�邳��������̂Łu�p���[���キ�Ȃ����ȁv�Ɗ�����͂��ł��B�f�W�J���ł͐����B�e���������œd�r��}�[�N���o�邱�Ƃ�����܂��B �@�����ėe�ʒቺ�͎g�p���Ԃ̒Z���ő̊��ł��A�����I�Ɂu�キ�Ȃ����d�r�v�Ɗ�������͂��ł��B �@���ɂ��A���ȕ��d�̐��\��������A�[�d���Ă��炵�炭���u���Ă����Ɠd�C�������Ă��܂��䗦�������Ȃ�A������u�[�d�����̂Ɏg���Ȃ��Ȃ��v�Ƃ����g�p���ɂȂ���܂��B �@�ł��̂ŁAJIS�̋K��Ȃǂ͊W�Ȃ��A�d�r�̔����ւ���(�p�������ɂ��鎞��)�́A�����܂Ŏg�p��������g�p������Łu�g�p�ł��Ȃ��Ȃ������v�Ɗ��������ł����̂ł��B �@���Ƃ��A�����͂�K�v�Ƃ���@��(�f�W�J���Ȃ�)�ł͏[�d���Ă����g���Ă��キ�����g���Ȃ��u���Ȃ������d�r�v�ł��A���������d�C���g��Ȃ��@��(�~�jLED���C�g��W�I��)�ł͂܂��܂����C�ɁA����Ȃ�ɒ����Ԏg����������܂��B �@�������߂Â��đ傫�ȃp���[�����o���Ȃ��Ȃ��Ă��A�܂��ア�d�͂łȂ炻��Ȃ�ɓd�C�������������邱�Ƃ��ł���̂ł��B �@�ł�����A�[�d�r��������ȂƎv���Ă������ɂ͎̂Ă��ɁA�����ʂ̎ア�d�C�@��Ŏg�p�ł�����炭�͎g���Ă���āA�Ȃ�ׂ��p�������ɂ���ʂ����点��Ƃ����킯�ł��B �@�j�b�P�����f�[�d�r���̂Ă�ڈ��́A�@��Ŏg���Ȃ��Ɗ��������ƁA�u�[�d��ŏ[�d�ł��Ȃ��Ȃ������v�ɂ��܂��傤�B �@�e���[�J�[�̏����[�d��Ȃǂ��g�p���Ă��āA�G���[�\�����o�ď[�d�ł��Ȃ��Ȃ�������A�[�d�����������͂��Ȃ̂ɋ@��ɓ��ꂽ��ق�̏��������g�p�ł��Ȃ��������ɂ́A�������Ȃ�������s�������Ă��܂��̂ŁA�p�����Ă��܂��Ă��悢�ł��傤�ˁB �@�����A�[�d���d�r�̋����[�q������Ă��ď[�d�s�ǂɂȂ��Ă���Ƃ��A�ʂ̌����ŏ[�d�~�X�����Ă��܂��Ă��Ȃ����͂����Ɗm���߂Ă����܂��傤�B �@�d�r�͂܂��܂����C�Ȃ̂ɁA�[�q������Ă��������Ŏ����Ɗ��Ⴂ���Ď̂ĂĂ��܂��Ă͂��������Ȃ��ł�����ˁB �@���낢��Ɨ��Z�I�ȏ[�d�����āA���[�J�[�����[�d��ŃG���[���o��d�r���܂������Ďg���Â�����@������܂����A���������̂͗ǂ��m�����l�������s�������ł悢�ł��悤�B�m��Ȃ��l�͂���Ȃ�ɁE�E�E �@�����Ԃ̃o�b�e���[�������悤�Ȃ��̂ŁA�Z���X�^�[�^�[�������ǎキ�āu����Ⴞ�߂����H�v�Ǝv�����瑁���ڂɃ����e�i���X���Ă݂āA����ł����Ȃ��悤�Ȃ�V�i�Ɍ������܂��傤�B �@�o�b�e���[�̓ˑR���ňړ���ŎԂ������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂�����A�Ԃ̃o�b�e���[�͗]�T�������Č��������ق������S�ł���B ���Ԏ� 2009/2/11
|
||||||||||||
| ���e 2/12 |
�@��ς悭�킩��܂����B�����J�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�g���p�r�ŕς���Ă���Ƃ̎��ł��ˁB �@���Ƃ́A�����̊����ŁA�������g���悤���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B kenken �l
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����X���炵�܂��B >�J�[�o�b�e���[�̎��� �@�Ԃ̎g�p�p�x(�����̒ʋΓ��ł̎g�p�Ȃ̂��A�d���œ����̓t���ɑ��点�Ă���̂��A�͂��܂��T�������Ȃ̂�)��A����ꏊ(�a�������Ȃ�)�A�G�A�R���̎g�p�p�x�A�I�[�f�B�I���̓d���i���ǂ̒��x�ς�ł��邩�A���ɂ����̂ň�T�ɂ͌����Ȃ��̂ł����A�����Ԑ����W�̊Ԃł͈�ʓI��2�N���Ɍ����ƌ����Ă���A�����Ó����Ǝv���Ă��܂��B �@���[�h�T�[�r�X(JAF��ی���ЂȂ�)�ɉ������Ă���A���[�h�T�[�r�X���e�ՂɎ���X�����������Ă���̂Ȃ�M���M���܂Ŏ�������̂����肾�Ƃ͎v���܂����A�g�ѓd�b���Ȃ���Ȃ��悤�ȓc��(���ۍ��������ł��g�т��Ȃ���Ȃ��ꏊ������܂�)�ɏo������悤�Ȏ���������Α��ߌ����̂ق������S�ł��ˁB (�~�G�̖k���ł߂����ɎԂ��ʂ�Ȃ��悤�ȏꏊ�ŃG���W�����~�܂�悤�Ȏ��ɂȂ�Ɩ��ɂ������ꍇ���I) �@��Ԍ����_���Ŏ~�܂����ۂɃ��C�g���ɒ[�ɈÂ��Ȃ�A���C�g������ƃ��W�I��I�[�f�B�I�ɔ��d�@�̃m�C�Y(�q���[���Ƃ�����ɃG���W���̉�]���ɂ���ĉ����ς��悤�ȉ�)������悤�ɂȂ�A�������������̏Ǐ�ł��̂ŁA�����Ȃ����瑁�߂Ɍ��������ق����ǂ��Ǝv���܂��B �@�o�b�e���[������Ɣ��d�@�ւ̕��ׂ������A�R��ɉe�����鎖���l�����܂��B jr7cwk �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ڂ����lj���肪�Ƃ��������܂��B �@�E�E�E�E�����珑�����̂Ŗ���������̂��ȁB �@���́A�u�P�̃g�s�b�N�̓��e�ŁA�r����"�Ƃ����"�A���Řb���ς��ĂQ�ȏ�̓��e�̓��e�͂��������������B�v�Ƃ������e�̂��肢�ɑ��āA�����������e�����ꂽ����җl�͋��k����Ĕ���J�ł�����ɂ��A��������Ă��܂��B �@�ł��̂ŁA���͌�҂̎����Ԃ̃o�b�e���[�ɂ��Ă͂��̃g�s�b�N�ł͂��܂�G��Ȃ��悤�ɂ��A�T���b�Ɨ��������ɂ��Ď���җl�̂��C�����ɂ��������܂����B �@�܂��A���e��ǂ�O�҂̕����ڂ������b�����Ă����������̂Ȃ炠���܂Ŏ��R�ȗ��ꂾ�����Ƃ������ƂŁB ���Ԏ� 2009/2/14
|
||||||||||||
| ���e 2/15 |
�@jr7cwk����@���肪�Ƃ��������܂��B��ώQ�l�ɂȂ�܂����B �@�܂��A�u�C�̖����v�̃I�[�i�[�l�̊���Ȏ��v�炢�A���肪�Ƃ��������܂��B ������������ �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ���`�E���C�I���d�r���G�l���[�v�H | |||||||||||||
|
�@�G�l���[�v�Ƃ̓T�����[�̃j�b�P�����f�d�r�Ǝv������ł��܂������A�T�����[�ł̓��`�E���C�I���d�r���G�l���[�v�ƌĂ�ł��邱�ƂɍŋߋC�Â��܂����B�ǎ҂̊F�l�̒��ɂ����Ɠ��l�Ȏv�����݂����Ă����������̂ł́H Kin �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���m�ɂ́A�O�m�̓��`�E���C�I���[�d�r�P�̂�eneloop�Ƃ͌Ă�ł��܂���B �@eneloop�͍ŏ��͒P�O�E�P�l�^�̃j�b�P�����f�[�d�r�̖��O�Ƃ��Ďg���܂������A���̌�ɎO�m�̑S�Ђ��グ�Ă�(�܂��܂���)�c�Ə�ԉׂ̈̃X���[�K���uThink GAIA�\�z�v(�n�������l���悤�Ƃ����Ӗ�)�̌��A���͑匙���Ȍ��t�ł����O�m�́w�G�R�x���i���i�֘A�Łu�[�d���Ďg���镨�v�̂قƂ�ǂ͈Ȍ�weneloop�x�ƌĂԎ��ɂȂ�܂����B �@�weneloop���o�C���u�[�X�^�[�x�weneloop�J�C��/eneloop�A���J�x��weneloop�o�C�N(�d�����]��)�x�ȂǁAeneloop���E�����t�ł���u�J��Ԃ��g�����v���i�͎��X��eneloop�u�����h�Ƃ��Ĕ�������Ă��܂��B �@�����̋@��̒��ɂ́A�d���Ƀj�b�P�����f�[�d�r��eneloop�ł͂Ȃ��A���`�E���C�I���[�d�r���g�p������������܂����A���̃��`�E���C�I���[�d�r�ɂ��Ă͖��O�Ƃ��āueneloop�v�Ƃ͌Ă�ł��܂���B��������O���ŐF�̃��S��eneloop�ƃv�����g���ꂽ���`�E���C�I���o�b�e���[�Ȃ�ĕ�������܂���B(�������炻��͂���ő������܂�����/��) �@�����܂ő��u�E�@��E���i�̖��O���ueneloop�c�Ȃ�Ƃ��v�ł����āA���`�E���C�I���[�d�r�́ueneloop�v�Ƃ͌Ă�ł͂��܂��A�P�̂Łueneloop���`�E���C�I���d�r�v�͔����Ă��܂���̂ł��ԈႦ�̖����悤�ɁB ���Ԏ� 2009/2/10
|
||||||||||||
| ���e 2/11 |
�@��L�������܂����A�m���Ƀ��`�E���C�I���d�r���G�l���[�v�Ƃ͌Ă�ł��Ȃ��悤�ł��B �@�������u�V����̏[�d�r�Ƃ��āi�G�l���[�v�j�v���傫�Ȕ��������͎������Ǝv���Ă��܂��A������t��ɂƂ��ď���ȗ��������˂Č֑�i�g��j��`�͔@���ł��傤���H �@���ɂ͍ŋ߂̂����ȕs���\���Ɠ����Ɏv���ĂȂ�܂���B Kin �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d���h�����̃j�J�h�o�b�e���[�����ɂ��� | |||||||||||||
|
�@�����b�ɂȂ�܂��D �@�d���h�����̃o�b�e���[���g���Ȃ��Ȃ����̂Ŏ����Œ��g���������悤�Ǝv���Ă��܂��D �@���݂̃o�b�e���[�̓j�J�hC�Z��1.2V�i1200mAh�j�~18�{������i21.6V�j�ɂȂ��Ă��܂��D �@���̓d�r��P3�̃j�b�P�����f�d�r 1.2V�i1300mAh�j�~18�{�ɒu�������Ă����Ȃ��̂ł��傤��?�܂��C���̏ꍇ�C�[�d�͂ǂ̂悤�ɂ�������̂ł��傤���D ��낵���䋳���肢�܂��D ���� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�b�Z��(�P��^)��18�{�ł����I�H �@�ǂ�ȋ���ȃo�b�e���[�P�[�X�Ȃ�ł��傤�B����ȋ���ȓd���h�������Ď�Ɏ����Ďg�����ł����E�E�E�B �@�܂��A����͂��Ă����E�E�E �@�j�J�h�b�Z�����悭�����e�ʂ̃j�b�P�����f�[�d�r�ɒu��������ƁA�ꌩ����Ɠd�����e�ʂ��قړ����Ŗ�薳���g�p�ł���悤�ȋC�����܂����A�d�r�̓�����R�ɂ��Ă͂ǂ��ł��傤���H �@�j�J�h�d�r����������������̐��i�E�E�E�Ƃ����������邩������܂��A�j�b�P�����f�[�d�r�����܂�Ă�����d���H��ł̓j�J�h�[�d�r�������Ԏg���Ă��܂����B �@�����̃j�b�P�����f�[�d�r�͍����Ă�������Ǝg���Ȃ������Ƃ������������܂����A�d���H��ł��u�ԓI�ȑ�d�����K�v�ŁA��d���p�r�ł�(�H��p���ɐ�p�ɊJ�����ꂽ�^�C�v��)��p�j�J�h�[�d�r�̂ق����K���Ă����Ƃ������R������܂��B �@�����ɓd����e�ʂ����Ă��邩��Ƃ����ĒP�O�^�̃j�b�P�����f�[�d�r�����Ă��܂��ƁA��d�������o���p�ɍ��ꂽ��p�d�r�ł͖����ׂɓd�r�ɂƂ��Ă͉ߓd���ł̕��d�ƂȂ��ēd�r�̐��\�����������Ă��܂�����A���������Ă��܂��\�����l�����܂��B �@���W�R����H������Ō�����u�p���`�v�����邩�Ȃ����̈Ⴂ�ł��ˁB �@�d���H��ȂǁA�p���`���K�v�ȋ@��ł͂���Ȃ�ɓ�����R���Ⴍ�A��d���p�r�ɊJ�����ꂽ��p�^�C�v�̏[�d�r���g�p���邱�Ƃ��]�܂����ł��B �@���ł��b�Z��(�P��)�^�̃j�J�h�[�d�r�̓l�b�g�ʔ̂Ȃǂł������Ă��܂��̂ŁA�T���Ă݂��Ă͂������ł��傤���B �@���������ʔ̕i�ł��j�J�h��2500mAh�ȂǁA�̂̕i�ɔ�ׂ���e�ʂ͂Q�{���x�ɂȂ��Ă��镨�������悤�ł��B �@�[�d�킪���������[�d�����m����^�C�v�ł���A�e�ʂ������Ȃ��Ă��Ă�����قNJ댯�͖����[�d�ł��܂��B �@�e�ʂ��傫�ȓd�r�ɂ��ď[�d���Ԃ��{���炢�������Ă��܂��悤�ȏꍇ�́A�[�d�푤�̈��S�^�C�}�[�������ēr���ŏ[�d���X�g�b�v���邱�Ƃ��l�����܂��B �@�����́A�[�d��̎d�l�ɂ���Ă��ꂼ��Ⴂ�܂�����A�u�����g���̃h�����̏[�d��ł́v�Ƃ��������͂ł��܂���B�ł��܂����炲�����ł����ׂ��������B �@�܂��A�d���H��p�̏[�d��̏ꍇ�u30���[�d�v�Ȃǒ��}���[�d���s��������������܂��B �@�H������œd�r���ꂽ�ꍇ�A�����Ԃ��҂��Ă͂����Ȃ�����ł��B(���ʂ͗\���̓d�r�ƌ��݂ɏ[�d���Ȃ���g���܂�) �@���̂悤�Ȓ��}���[�d�̏ꍇ�A���̃j�J�h�Ɠ����e�ʂ̃j�b�P�����f�[�d�r�ɓ���ւ�����[�d�d�����������ēd�r��ɂ߂�A�ň��̏ꍇ�͔j����댯��������܂��B �@���̏[�d�d�������̓d�r�ɑ��Ĉ��S�Ȃ̂��ǂ������A�[�d��̎�ނ�g����d�r�̎d�l�ɂ���ėl�X�ł��̂ŁA�d�l���킩��Ȃ����b�Ȃ̂ł���ȏ�ڂ����͂��b���ł��܂���B �@�܂��j�J�h�p�ɐv����Ă���d���H��p�̏[�d��ł͌��o����|���u�l���[���A�j�b�P�����f�[�d�r�ł͉ߏ[�d�����邱�Ƃ����イ�Ԃ�ɍl�����܂��B �@�[�d�̍ۂɖ���o�b�e���[�p�b�N���o�����āA���̒P�O�j�b�P�����f�[�d�r���s�̂̒P�O�p�̋}���[�d��ŏ[�d����̂��x�X�g�ł����A�ʓ|�ł���ˁB �@�ł���A�����T�C�Y�œ����悤�ȗe�ʂ̃j�J�h�[�d�r��T����āA��������̂��ǂ��Ǝv���܂���B �@�ǂ����Ă������ł��镨�������ꍇ�̓j�b�P�����f�[�d�r�ɓ���ւ��Ă��u�h�����͓����v�ł��傤���ǁA��͂�h�����t���̏[�d��ł̏[�d�ɂ͐S�z���c��܂��B ���Ԏ� 2009/2/8
|
||||||||||||
| ���e |
�@���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B �@��͂�18�{�̒���͂������ł���ˁB�ł����ł������Ă��ł���B�I�[�N�V������21.6V�Ō�������Əo�Ă���h�����ނł��B���̏[�d�킪�Ђǂ��㕨�ŁA�ߏ[�d�ł����Ƀo�b�e���[���_���ɂȂ��Ă��܂���ł���B�����p�̃o�b�e���[�������Ă��Ȃ����߂ɁA���݂ł͎g�����ɂȂ�܂���B �@����ς�j�J�h�d�r�ɒu�������邵���Ȃ��ł����ˁB�������A18�{���w������Ɩ{�̂��������Ȃ��Ă��܂���ł���ˁBAC�A�_�v�^�[�ɒ������Ă݂悤���Ƃ��l���܂���������ȑ�d�����o����A�_�v�^�[�Ȃ�ĂȂ��̂ŁA������߂����Ă���Ƃ���ł��B���������Ă���������Ă������������ł����A�V���ɔ������ق��������ł����ˁB�@ ���� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����ڑ��ł̎g�p�́A�ŏ��͂����ł������̈�{�����n�߂���A���̈�{(�܂��͎�������{)�ɑ��Ďg�p���ɂ͉ߕ��d�œ]�ɂ����Ă��܂��Ȃǂ̖�肪����܂����A�[�d���ɂ͗e�ʂ������Ă��܂��Ă���Z���ɑ��ĉߏ[�d�ɂȂ�����A���������g���Ă��Ȃ���Ԃŏ[�d����ƁA�ł��e�ʂ��c���Ă������C�ȃZ���͂����ɖ��[�d�ɂȂ�̂ɑ��̑����̃Z�������[�d�ɂȂ�܂ł����Ə[�d���Â�����̂ő����ɂ߂Ă��܂�����A�u�S�Q�L���Ĉꗘ�����v�Ƃ��������ł��B �@18�{�Ƃ����ƁA���ʂ͂���Ȏg�����͂��Ȃ����낤�A�Ƃ������炢�̖{���ł�����ˁB �@�H��p�Ȃ畁�ʂ͌����p�o�b�e���[�������Ă���͂��ł����A���K�̍H��n�̘H�ł͂Ȃ��A�I�[�N�V�������Ŕ����Ă���悤�ȕ��̓��[�J�[�ɂ�������ۏȂǂ������o���G�e�B���i�����̂��̂ł��傤�ˁB �@�l�b�g���������Ă݂�ƁE�E�A�m���Ɂu�H��ł��̒l�i�͐�ɖ������낤�I�v�Ƃ��������ł��ˁB�v���̖ڂ��炵����I���`���̂悤�ł��B �@��{105�~��VOLCANO NZ��18�{�Ȃ�{�̂������ł����A��{150�`200�~�ȏシ��d�r�Ȃ�{�̂��Ȃ������ق��������ł��ˁB �@���������l�i�̍H��Ƃ킩��A�V�i�d�r���{�̂��Ȃ������ق������g�N���Ǝv���܂��B �@�h�����s�b�g�Ƃ��F�X�t���i���t���Ă��܂����A����قǕi���̗ǂ����ł͖����炵���̂ŁA�\����g���̂ėp�ɕt���i��������̂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�u�l�ŗV��ł݂����I�v�Ƃ������C�������傫���̂ł�����A�P�O�j�b�P�����f�[�d�r�~18�{�Ɍ�������̂��m���Ɏ�ł͂���܂��B �@���܂��䂯�A���̃j�b�J�h�d�r�̎��ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��p���[�Ŏg�p�ł��邩������܂���B �@�����܂Ŏ����̂���ʼn������Ă݂Ă͂������ł��傤���B (�A���A�h�����t���̏[�d��ł͂�͂肷���ɓd�r���Ă��܂��ł��悤) �@���̎�Ƃ��ẮA�uAC�A�_�v�^�[�g�p���l�����v�Ƃ������ŁA�H���P�[�u���������ĊO�Ƀo�b�e���[���q���ł������̂ł�����A���W�R���p�́u7.2V�o�b�e���[�p�b�N�v���R����Ɍq���ō��v21.6V�ɂ��Ďg���Ƃ����������܂��B �@�H����K���K���Ă��]�肠��p���[��������ł��傤�B �@�ڑ��ɂ̓��W�R���X���Ŕ����Ă����p�̃R�l�N�^���q���ŁA�o�b�e���[�p�b�N���ȒP�ɊO����悤�ɂ���A�[�d�ɂ̓��W�R���p�[�d�킪�g�p�ł��܂��B �@�����A7.2V�o�b�e���[�o�b�N�~�R�{�A���W�R���p�[�d����܂Ƃ߂Ĕ����ƁA�l�b�g���i(�ň��l��)2500�~���x�̂��̓d���h���������䔃���邩�E�E�E�Ƃ������l�i�ɂȂ�܂����ǂˁi�O�O�G ���Ԏ� 2009/2/9
|
||||||||||||
| ���e |
�@��������ł����[�B�m���ɂ����ł��ˁB�܂��A�����{�ʂŔ����Ă݂����Ȃ̂Őɂ����͂���܂��ǂˁB2000�~������Ƃł������B�ł�����͂����Ƃ��������܂��B �@�������A���W�R���̃o�b�e���[�R�{�����łł����[�B�������낻���ł��ˁB����Ă݂悤���ȁB �@�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂����A���肪�Ƃ��������܂����B ���� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u��������v�ŋC�����Q���ꂽ�̂ł����炲�߂�Ȃ����B �@�����ł��Ƃł̓z�[���Z���^�[��5000�~���炢�̏[�d�h�����E�h���C�o�[�Z�b�g�͎g���Ă��܂����A��͂�v���p�̍H��Ɣ�ׂ�Ƃ��Ȃ�`���`���̂ł��B �@�ŋߋ}�p�Ńz�[���Z���^�[�u�����h�i��3000�~���x�̕�(���͂��Ă��Ȃ�)���܂������A������5000�~�̂�肸���ƃ����ł��Ȃ�g��������ǂ�����܂���ł����B �@�v���p�H��ƂȂ�Ɩ{�́{�o�b�e���[�{�[�d�킾���łP���S��~���x�ȏ�ł����ƍ��������قƂ�ǂł����A��͂���ۂɎg���ƑS�R�Ⴂ�܂��B �@�h�����̎����A�P�i�ň�{1000�~�ȏ�Ŕ����Ă��镨�͑�ϗǂ��A�h�����{�̂Ǝ���10�{�Ƃ��A�X�Ƀh���C�o�[�s�b�g��Ȃɂ��܂őS��������3000�~���x�̊C�O���̓d���H��Z�b�g�ł́A�h�������̐��x�������ꖡ������Ȃ�E�E�E�Ȃ�ĕ������������Ă��܂����B(���ɂ͌����J�����Ȃ��h�������Ƃ��c) �@�l�b�g��2000�~���炢�Ŕ�����̂ł���A�u����Ȃ�v�̐��\�ł������j��H�ȂǂŎg������イ�Ԃ͎��Ă���Ǝv���܂��̂ŁA�������i���g���̂ł���Η\�Z�������lj����Ă���Ȃ�̕i���w�����Ă��܂��܂��傤�B�ł���Ό����p�o�b�e���[�������Ă���̂������ł��ˁB �@�������A�����������x�����������Ă��̏�ł́u�V�i�v���g���Ƃ������@���A���ł�����A�w������i�͊F�l���ꂼ��̗p�r��C���ɂ��킹�đI������̂������ł��ˁB ���Ԏ� 2009/2/10
|
||||||||||||
| ���e 2/16 |
�@�����X�����܂���B �@������Ǝv�������̂ł����A�y�����ԗp�̉��~�Q�������ł����H �@�d�ʂ͂��Ȃ�C�N�ł��傤���ϋv���͔��Q���Ƃ������܂���B ���� �l
|
||||||||||||
| ���e 4/23 |
�@���X���ł����A�ߏ[�d�h�~�Ƀ^�C�}�[���g���Ƃ悢�ł���B �@���͂��̎�̏[�d���䂪�������i�Ńo�b�e���[�������Ƃ����܂Ƀ_���ɂ������Ƃ�����܂��A��������{�̑�胁�[�J�i�ł��B�R���Ԃ���T���ԏ[�d�̏���Y��Ă��ĂP�O���Ԉȏ�[�d���Ă��܂����Ƃ����т��т���ߏ[�d�Ńo�b�e���[���_���ɂ����悤�ł��B �@�����Ń_�C�������^�C�}�[���g���ėe�ʂ�1.2�{���x�[�d���Ď~�߂�悤�ɂ��Ă��܂��B�o�b�e���[��1200mAh�ŏ[�d�d����500mA�̏ꍇ��1200mA��500mA�~1.2��2.88(��3����)�Ƃ��܂��B�܂����̕��@�ł͒Ǐ[�d�͍s���܂���g�����Ă���[�d���܂��A�Ȃ��Ȃ�c�e�ʂ�����Ȃ����߂ɉߏ[�d�����Ă��܂��\�������邽�߂ł��B �@�����I�[�N�V�����Ŏ�ɓ��ꂽ�����̓d���h������h���C�o�[�����̕��@�ŏ[�d���Ă��ĂR�N�قnjo���܂����o�b�e���[�͂܂��܂����C�ł��B hiro �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| UltraFire ICR123A(3.0V)��WF-139�łQ�{����[�d�I�H | |||||||||||||
|
�@�{���A�H�t��UltraFire C1�������ċC�ɓ���A�w�����܂����B �@UF ICR123A�̏[�d�r��3.0V�d�l�Ƃ������Ƃ�C1�ɍ��킹������ł����A�C�O���̏[�d���[�d�r�̒m�����R�������ߓX������ɒ������Ƃ���A�����[�J�[��WF-139��E�߂���܂܍w�����܂����B�������A���ƂŔ������̂����̓d�r�����Z���ł��邱�ƁB�������`�炷���WF-139��ICR123A��ŏ[�d�ł������Ȋ����ł͂���܂����A���ۂ̈��S�����C�ɂȂ��Ă��܂����B �@�����ŁA�������������̂����̏[�d�r�Ə[�d��̑g�ݍ��킹�A�����UF-C1���C�g�ł̎g�p�ɖ��͂Ȃ��̂ł��傤��?�@������������̂悤�ł����炲������낵�����肢�������܂��B �@�Ȃ��AICR123A��800mA�@3.0V�ƕ\�L����Ă��܂��B sail �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
 �@UltraFire C1�͂���ȃ��C�g�ł��ˁB
�@UltraFire C1�͂���ȃ��C�g�ł��ˁB(2008�N�̃V���[�Y)
�@����UltraFire���ł����A�ǂ��ƂȂ�SURE FIRE C2 �Z���`�����I���Ɏ��Ă���(��)�A�X�^�C���b�V���Ƃ����������������ATOOL�Ƃ��č��x���g�ɋ���ł����āA�S���S���Ԃ��Ȃ���g���Ă����ɗ��悤�ȃC���[�W�Ŏ�����{�����Ă��܂��B �@C2�Z���`�����I���͂Q���X��~�I�����܂����AUF-C1(R2)���������Q��Q�S�~�ł��ނ肪����(SureFire��1/10�ȉ�!!)�̂ň����Ďg���ׂ��ɂ͂����ł��ˁB �@���ʂ�UF-C1�ł���A�d�r�͓��ʂ�3.0V�d�l�ɂ���K�v�������A3.6V��RCR123/16340�ő��v�ł��B�A���Q�{�Ŏg�p�ł��邩�ǂ����͒��̃��W���[������ł��̂ŁA��ł��b�����܂��B �@���āA���C�g�͂����Ƃ��āAUF ICR123A(3.0V/���Z��)�ƃZ�b�g��WF-139��E�߂�ꂽ�Ƃ����͍̂����b�ł��ˁB �@�ڂ����́u�C�OLi-ion�[�d����ׂĂ݂��v�����ǂݒ������������Ǝv���܂����AWF-139��3.6V/3.7V��p�̏[�d��ŁA3.0V�Z���ɂ͑Ή����Ă��܂����B3.0V�Z�����[�d�������ꍇ�A�ň����ُ�ߔM�E���E�j��̊댯��������܂��B �@�ʔ̂Ōl�Ŕ����Ďg���̂ł��������ȐӔC�Łu�Ƃ��Ύ��ɂȂ��Ă����čς܂������I�v�Ƃ����C������������g�������Ă����\�ł����A���X�Ŕ���ꂽ�ꍇ�́u������ЂȂǂ��N�����ꍇ�́A�̔��X�̐ӔC�ő��Q���⏞������Ƃ����m��v�������ȏ����ł��̂��X���璸���Ă���g���܂��傤�ˁB (���̑g�ݍ��킹�ŁA����ȏ��ʂ��o�����X�͖����Ǝv���܂����c)
�@����ƁAWF-139��RCR123/16340�^�d�r���Q�{����ɓ����ƁA���̃}�C�R���`�b�v���ߓd���ʼn��Ďg�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�̂ŁA��ɓd�r���Q�{����ł͓���Ȃ��ł��������B �@�[�d�ł��Ȃ������ł͂Ȃ��A�[�d����Ă��܂��܂��B  �@�u3.0V�^�C�v�̃��`�E���C�I���[�d�r�v���[�d����ɂ́A�K��3.0V�ɑΉ������[�d�킪�K�v�ŁAUltraFire�����WF-138����������Ă��܂��B
�@�u3.0V�^�C�v�̃��`�E���C�I���[�d�r�v���[�d����ɂ́A�K��3.0V�ɑΉ������[�d�킪�K�v�ŁAUltraFire�����WF-138����������Ă��܂��B�@WF-138��3.0V/3.6V�̐ؑ����ł��A�ǂ���̃^�C�v�̏[�d�r�ɂ����S�ɏ[�d���ł��܂��B �@���X�ɍɂ�����̂ł�����AWF-139��ԕi����WF-138���w�����܂��悤�B �@�E�E�E��������WF-139����蔄�����ꂽ�̂�������܂��i�O�O�G �@�Ō�ɁA�uUF-C1�ł̎g�p�ɖ��͖������H�v�Ƃ�������ɑ��ẮA���̃h���b�v�C�����W���[������I�Ƃ����������͂ł��܂���B �@UltraFire�́uC1�v�Ƃ����̂́w�{�f�B�̖��O�x�ł����āA���C�g���̖̂��O��\������킷���̂ł͂���܂����B �@���ʓ��{���̃��C�g���ƌ^�����̂͂��̃��C�g�P�ŗL�̂��̂ŁA���O�����̃��C�g�̎d�l���킩��̂ł����AUltraFire�̂悤�ȊC�O�̃��C�g�ł̓{�f�B�̖���(����V���[�Y��)�ƃ��C�g�̐��\(�g�pLED���̌ŗL�����t���Ă���)�͗�����\�L���Ă͂��߂Ă��̃��C�g�̏������킩��܂��B �@���Ƃ���Ȃ�Ԃ������悤�ȕ��Łu�X�J�C���C���v�ƈꌾ�Ō����Ă�GTR��GTS�ł͐ς�ł���G���W�����Ԏ��̂̐��\���S���Ⴄ�ʂ̎ԁA�܂�����GTR�ł������N���ɂ���ĈႤ���ł���E�E�E�݂����Ȃ��̂ł��B  �@C1�{�f�B�ɂ͉E�̎ʐ^�̂悤��P60�T�C�Y�݊��̃h���b�v�C�����W���[���������Ă��āALED�̎�ނ▾�邳�A�������d���d���͈��͂����h���b�v�C�����W���[���̐��\�Ō��܂�܂��B
�@C1�{�f�B�ɂ͉E�̎ʐ^�̂悤��P60�T�C�Y�݊��̃h���b�v�C�����W���[���������Ă��āALED�̎�ނ▾�邳�A�������d���d���͈��͂����h���b�v�C�����W���[���̐��\�Ō��܂�܂��B�@���Ƃ��ADX�Ō��s�Ŕ̔�����Ă��� �� Ultrafire C1 Q5-WC 230-Lumen LED Flashlight with Clip (2*CR123A/1*18650)�@Price: $18.49 �ł�Accepted voltage input range: 3.7V~12V�̃��W���[���A �� Ultrafire C1 Cree R2-WC 5-Mode Memory LED Flashlight (2*CR123A/1*18650)�@Price: $22.81 �ł�Input voltage range: 3.0V~8.4V�̃��W���[���Ƃ����悤�ɁA�Q�~CR123A���`�E���ꎟ�d�r�A�܂��͂Q�~RCR123�[�d�r��6.0�`8.4V�ł���Ζ��͖����̂ł����A�ߋ��ɔ�������Ă���CREE P4����̃h���b�v�C�����W���[������ �� Ultrafire Alpha-C1 5-Mode 3W Cree Flashlight (18650)�@Price: $28.10 (�A�������C1�̑O�̌^)�ł�Powered by 1x18650 (do not use 2xCR123A)�̂悤��4.2V�܂������Ή����Ă��炸�A2�~CR123A�Ȃ�ē��ꂽ��LED���Ă��Ă��܂��悤�ȕ�������܂��B �@�����̂��X�Ŕ����Ă����i(C1)��CREE P5�ȍ~�̃h���b�v�C�����W���[���̂悤�ɁA8.4V�܂ł̑Ή��i�Ȃ�ICR123A�~�Q�{�ł����v�ł��傤���A�s�ǍɂŐ̂̕����c���Ă��āA���̃��W���[����4.2V���̕i�ł����2�~CR123���Ɗm���ɏĂ��܂��B �@�X�������ꏏ�ɔ����Ă��ꂽ�̂ł���A����8.4V�Ή��̃h���b�v�C�����W���[���������Ă��ēd�r�Q�{�����Ă����v�ȏ��i�Ȃ̂ł��悤�B �@�E�E�E��́A3.0V��ICR123�ƈꏏ��WF-139���Ă����悤�ȓX������̌��������ǂ��܂ŐM���邩�A�ł����ǁB ���Ԏ� 2009/2/7
|
||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@UF C1���w���������R�́A���͈ȑO����SureFire�t�@�����������߁AC1�Ɏ�����F�̃��f���ɓ���āA����Ɏ������̂��~�����������߂ł��B���Ȃ݂�SF�̐��i�͂��ׂĊ��d�r����C123A�Ŏg�p���Ă��܂����B�@���L1�AL2�AL5���ł��B �@UF C1�̏����͂��X�̏��ł�C123A�Ή��ƊO�`���@�y��Cree���ڂ�������܂���BCree�ɂ���ނ�����̂͑����Ă��܂����A�C���o�[�^�[�̎d�l�܂ł͊m�F�ł��܂���ł����B �@C1�����������Z���Ή���WF-138���g�p�\�ł���̂Ȃ�A��������������8�{��ICR123A�����p�邽�߂�WF-139�̕ԕi�Ə[�d��̔����Ȃ������������Ă݂����Ǝv���܂��B �@�Ȃ��AC1�̐��i�o�ׂ�2007�N1���̐V���f���Ƃ̂��ƁB�܂����[�h�ύX�͓��ڂ��Ă��炸�A�����i�ƂȂ��Ă��܂����B���ꂩ��d�r�̎g�p��CR123A�~1�݂̂̑Ή��B�����̔��Ə����ӂ݂�Ƌ����i�̕��o�i�̉\��������܂��B Sail �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�������A2007�N��C1�ł����I�H �@���Ƃ���Ǝ��̎����Ă���ʐ^�ɍڂ����u����C1�v�Ƃ͑S���Ⴄ���i�ł��ˁB �@�҂��҂��̃X�e�����X���ŁACR123�d�r��{��������Ȃ���������̂Ђ�ɂ����ۂ���܂�Z�����C�g�B �@����Ultrafire C1 3W Cree Stainless Steel Flashlight $26.64�ł��ˁB �@�uUltraFire C1 V2 Stainless Steel�v�Ƃ��uUltraFire C1 3W Cree Stainless Steel Flashlight�v�Ƃ��Ă�Ă������f���ł��ˁB �@�g�pLED��CREE�ł�P4�ŁA�d����CR123A 3.0V/3.6V�̗����ɑΉ��ł��B �@�A��3.6V�ŋ쓮����Ƃ����Ƀ{�f�B���M���Ȃ�Ƃ��̃��|�[�g�������������͂��B �@�܂����܂�2007�N�ł�C1 P4 �X�e�����X�̍ɂ��������Ƃ́I �@�d�r�͂��̂܂g���܂�����A�[�d�킾�����ւ��Ă��炢�܂��傤�B �@CR123����{�̃��C�g���ƁACR123A���`�E���ꎟ�d�r��RCR123/16340���`�E���[�d�r�ł�3.0V�^�C�v�̏ꍇ���Â��Ƃ����������݂��܂��BRCR123/16340��3.6V�^�C�v�ɂ��킹�Ă����āA�������Ȃ��^�C�v��LED�쓮��H�̏ꍇ�ł��B �@���̂悤�ȃ��C�g�ł͂��������߂ɂȂ�ꂽ3.0V�^�C�v��UF ICR123A�ł͑����Â���������܂���B �@C1 P4 �X�e�����X��������H�����ŁA3.0V�d�r�ł����邢���ǂ����͎����Ă��Ȃ��̂ł킩��܂���B����Bamboo!��takebeat�l������Ȃ�C1�X�e�����X�������Ă����͂��Ȃ̂ŏڂ������������m���Ǝv���܂��B (���̂�����́u���C�g�E�����v�E�k�d�c�v�̘b��ł����c) �@�u���Z���Ή��v�Ƃ����Ӗ����悭�킩��܂��A�v���e�N�g��H�����̐��Z����LED���C�g�Ŏg�p����ۂ́A�u�Â��Ȃ�n�߂�������v�Ƃ���������l�Ԃ��s��Ȃ���Ȃ炸�A�u���Z�������玩���I�Ɏ~�܂�v���Ƃ����e�ȃ��C�g�͂���܂���B �@SureFire���́u�t�B�������g�d���o���u�v�����C�g�̂悤�ɁA3.0V��CR123A�ꎟ�d�r�ł���n�j�����ǁA3.6V��RCR123/16340�[�d�r�����ߓd���Ńo���u�������Ă��Ă��܂��悤���s��������ׁA�����������C�g�ɂ�3.0V�^�C�v��RCR123/16340�[�d�r���g�p���Ȃ���Ȃ�܂���B���������Ӗ��Łu3.0V�Ή�/3.6V�Ή��v�͕K���m�F���܂����A�g�p�d�r�́u���Z�����A�v���e�N�g�t�����H�v�̓��C�g���̎d�l�Ƃ��Ă͕\�L���܂���B �@������H�������C�g�̏ꍇ�ACR123A�ꎟ�d�r���ł��Ō�̂ق��܂Ō��\���邭�����Ă���Ċ������̂ł����A�Â��Ȃ鍠�ɂ̓��`�E���C�I���[�d�r�ł͉ߕ��d�̈�܂œd�����������Ă��܂��Ƃ������Q������A������u���Z�����ƉĂ��܂��v�ƕ\������ꍇ������܂��B(������ƌ����Đ��Z���s�Ƃ͏����܂���) �@�v���e�N�g��H�����̃��`�E���C�I���[�d�r�ł���A�ߕ��d�ɂȂ�O�Ƀv���e�N�g�������Ď����I�ɕ��d���J�b�g���Ă����̂ŗǂ��̂ł����E�E�EC1 P4 �X�e�����X�̂悤�ȏ����ȃ��C�g�̏ꍇ�͓d�r�̒����������ē���Ȃ����A�����ƊW���܂�Ȃ��Ƃ������Q�����鎖������̂ŁA�S�Ẵ��C�g�Ƀv���e�N�g�t���̃o�b�e���[�������߂���킯�ɂ��䂫�܂���B(C1 P4 S�ɂ͓���̂��ȁH�A������takebeat����I(^_^; ) ���Ԏ� 2009/2/8
|
||||||||||||
| ���e |
�@�ȂĂꂽ�C����������(^_^;) �@�X�e�����X����Ultrafire C1�͏�����H�ɂȂ��Ă���̂�3.0V�̓d�r��OK�ł��B �@UltraFire ICR123A���ʏ��CR123A�Ƃقړ����T�C�Y�Ȃ̂łȂ̂Ŗ��Ȃ��g�p�ł��܂��B �@�Ƃ������3.6V(3.7V)��Li-ion�[�d�r�ł͂�葁�������ɂȂ�̂ł��̓_�ł�3.0V�̕����������߂ł��B �@ICR123A�͍~����H�������Ă��܂����v���e�N�g��H�������Ă��܂���B �@���������̂��ꉞ���Z���̕��ނɓ���܂��E�E�E��ˁH(^_^;) �@�[�d��͋C�̖�������̏����ꂽWF-138���x�X�g�ł��傤�ˁA���ɂ�3.0V�p�̏[�d��Ȃ�ǂ��̂ł����A�X�ɂǂꂪ�����H�ƕ����ꂽ��WF-138�ɂȂ�ł��傤�B takebeat �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���Җ��@�����I�i�O�O�G �@C1 P4 S��������H�����Ȃ�A3.0V��ICR123A�ň��S�ł��ˁB �@��͂�͂�Sail�l��3.0V�Ή��̏[�d�����肳��āA���S�ɏ[�d�ł���悤�ɂ���Έ�x�ɂW�{�������Ă��܂���ICR123A�����ʂɂȂ�܂���B �@Sail�l�A�v���e�N�g�����̐��Z�����g�p����ۂɂ́A���ꂮ����_�������܂ܖY��ĉߕ��d���Ă��܂�Ȃ��悤�ɁI ���Ԏ� 2009/2/8
|
||||||||||||
| ���e |
�@���낢��ƒT�����Ă��Ēx���Ȃ�܂���Sail�ł��B �@���̌�WF-138���H�t�����ŒT�����̂ł���������܂���ł����B�܂��AWF-139�͕ԕi�ł��Ȃ��Ƃ������Ă�������B��̂ǂ�ȏ����Ȃ̂ł��傤?�@�d���Ȃ�UF C2 Q5�{�̂Ɠ�����UF WF-502B�{�̂��w���������UF LC18650��3�Z�b�g�w�����Ă��܂����B �@C1 P4 S�Ɋւ��Ă�Soshine SC-S6�[�d���i�߂���܂܂ɍw���������̂́A�T�C�g��������Ɨ�ɂ���đ��А��i�̓T�|�[�g�O�ƂȂ��Ă���UF ICR123A���������(�������Ȃ���)�[�d�ł��邩�S�z�ł��B���Ȃ݂ɁADLG���̌����ڂ��ꏏ�̏[�d��������Ă܂�����������͎����܂���ł����B�Ȃ��ASC-S6�ɕt���̓d�r�͐��Z���炵���ł��B���̏[�d��Ńv���e�N�g�t�����g���邩�ǂ����̏��͌�������Ȃ������̂ł��̂܂܃e�X�g�s���悤���Ǝv���܂��B �@���ǁA���C�g�{��3�{(UF C6S���lj�)�Ɠd�r�A�[�d��̒lj��w���܂ł��Ă��܂��܂����B����ɂ��Ă��A����Ȃ�Li-ION�d�r�͕|���łˁB���Â��v���܂����B Sail �l
|
||||||||||||
| ���e |
�NjL�ł��B �@���ꂩ��Soshine SC-S6(RCR123 3.0/3.6V���Ή�)��UltraFile ICR123A 3.0V 800mA���[�d���Ă݂܂����B���ʁA���v4�{�[�d���Ă݂��Ƃ���A���[�d����̓d�r���ɂ̊J���d��(������)���ł͍Œ�3.89V�A�ō�4.21�ЂƂ������ʂɂȂ�܂����B����͖����ׂ����炻���Ȃ̂��͂킩��܂��ǂ����댯�ȓ��������܂��B���Ȃ݂ɑ���Ɏg�����͉̂��͂̋Ɩ��p�f�W�^���}���`���[�^�[�ł��B��͂肱�̏[�d��A��Ȃ��̂ł��傤��? �@���̓d�����炷��Ǝg�����Ƃ��Ă��郉�C�g(UF C1 or UF C6S)�ɂ͕��C�����ł����A�d�r�̕����S�z�ł��B Sail �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���킟�A�����X���̎v���c�{�E�E�E �@���̓X���͐S�̒��Łu����ɍv�����ĉ������Ă��肪�Ƃ��������܂��B�܂��ǂ����`�v�Ƃق�������ł���ł��傤�B �@���ꂾ���̃��C�g�{�̂ƃo�b�e���[���A�H�t���ł͂Ȃ��C�O�ʔ̂Ŕ�������\�Z�͖z���炢�Ŕ������ł��傤�ɁE�E�E�B �@�ł�����͎������̂悤�Ȓ����C�g����ɔ����Ă�g�̍l�����ȁB �@Sail�l�͌��XSureFire�����{�������Ă���悤�ł�����A����̒����C�g�Ɠd�r�E�[�d�킭�炢�̏o���Sure��{���炢�̒l�i�����Ȃ̂ŁA�uSure��{�̒l�i�ł���Ȃɑ�R���C�g��������v�Ǝv�����������������ł͂���܂����ˁB �@�F�X�Ƃ����������y���߂��_�͂������납������������܂���ˁB �@Soshine SC-S6(DX�Œʔ̂���Soshine CR123A Battery Charger $10.20)�̓X�y�b�N���3.0V/3.6V���p�ƂȂ��Ă��܂��B �@DX�Ƀ��[�U�[�����e���Ă���Soshine 3.0V CR123A Batteries (2-Pack) $6.67�d�r�̎ʐ^���������ASoshine��3.0V�d�r��3.6V��16340�o�b�e���[�Ƀ_�C�I�[�h��t���č~�����Ă��镨�ł��ˁB �@���`�E���C�I���[�d�r�ɂ�3.0V�Ƃ����Z���͑��݂��܂���A3.6V�d�r�Ƀ_�C�I�[�h(�܂��͍~����H)������0.6V������3.0V�ɂ��Ă��܂��B �@���̃Z���͖��[�d���ɂ͖�4.2V�ɂȂ�܂��̂ŁA���[�d��������d�����v��Ɩ�4V�O��̓d��������܂��B(�e�X�^�[���d���v�ł͓d�����قƂ�Ǘ���Ȃ��ׁA�_�C�I�[�h�ɂ��d���~���͂킸���Ȃ��߂ł�) �@�@��ɓ���āu����Ȃ�̕��ׂ�������v�ƁA�d���͖��[�d����3.6���x����A�����g����3.3�`3.0V�܂ʼn�����܂�����3.0V��CR123A�ꎟ�d�r���g�p����@��ł��g����Ƃ������̂ł��B �@3.6V�^�C�v�̃��`�E���C�I���[�d�r�ŁA���[�d����4.2V�Ŏg�����肵����@�킪���Ă��܂��I�Ƃ����ꍇ�Ɏg�p����ׂɍ~����H����ꂽ�u3.0V�@��Ή��v�̃��`�E���C�I���o�b�e���[�Ƃ����`�ł����A���̃Z����3.6V�d�r��3.0V�d�r������3.6V�Z�����g�p���Ă���Ƃ����_�͊o���Ă����Ă��������B �@�[�d��́u3.0V�Ή��v�Ƃ����\�L���\�ɂ��Ă���ɂ͂Q�̏ꍇ������܂��B �@��d����d��(CCCV)�����[�d�����Ă���[�d��ł́A�[�d��̏o�͂��ő�4.2V�ɐ������Ă��邽�߁A3.6V�d�r�A3.0V�d�r�̂ǂ�������Ă����v�ł��B�ߓd���œd�r��j����S�z�͂قƂ�ǂ���܂���B �@3.0V�d�r�̏ꍇ�͓d�r�̒��ɏ[�d���͒�����V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�������Ă��āA�[�d�������̏[�d�d��������Ȏ��ɂ͂ق��0.1�`0.2V���x�̓d���~���ōςނ悤�ɂȂ��Ă��āA�[�d�푤��4.2V�ł���Β��̃Z���ł�4.0�`4.1V���炢�̓d���܂ŏ[�d�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�ق�̋͂����Ȃ��ł����A�d�r�e�ʂƂ��Ă͂قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ����x�̍��ł��B �@Soshine 3.0V CR123A�̏ꍇ�͂��̂悤�ȓd�r�ł���A���̃��[�J�[�����̓d�r�p�ɏo���Ă���[�d��ł�CCCV����ŏ[�d���Ă���̂œd�r�Ɋ댯�������Ɨ\�z�ł��܂��B �@���A������P�Ȃ闝�_�ɂ�鐄���ł���A���؏[�d��ɂ͐��_���ʂ��Ȃ��e���i�����݂����͉̂ߋ��̋L���̒ʂ�ł��B���g���m�F���Ȃ�����́u�C�̖����v�Ƃ��Ắu����͈��S�Ɏg����v�Ƃ͐�Ɍ����܂���i�O�O�G �@���[�d��ɓd�����v������4.21V�ȂǁA�~����H����d�r�̂͂���4.2V���z���Ă���Ƃ������Ƃ́A�ߓd���������Ă��܂��Ă���댯�[�d��̉\���������ł��ˁB �@�����P�̏ꍇ�́AUltraFire WF-138/139������Ă����p���X�[�d�^�C�v�ŁA���̏ꍇ�͏[�d�d���𗬂��Ă��鎞�_�̓d�r�d�����v��̂ł͂Ȃ��A�p���X���~�߂Ă������̊J���d�����v���Ă���̂ŁA�����~���p�_�C�I�[�h������ɓ������d�r���v��ꍇ�ɂ͂��́u�_�C�I�[�h�~���Ԃ�̓d�����l���v���Ă��Ȃ��ƁA�_�C�I�[�h�̍~���d���Ԃ�O���猩����d�����Ⴂ�ɂ�������炸�u�܂�4.2V�ɂȂ��ĂȂ���ˁ��v�Ə[�d�𑱂���ƁA���̃Z�����Ƃ��̐̂�4.2V���z���Ă����ǂ����`��I�Ȃ�Ď��ɂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B �@���ׂ̈ɁA�O���Ɍ�����d���̔���l��ؑւ邽�߂�WF-138�ɂ́u3.0V/3.6V�ؑփX�C�b�`�v���t���Ă��܂��B �@WF-139�ɂ��ؑփX�C�b�`���t���Ă��܂������AWF-138�ɔ�ׂď[�d�d�����傫�Ȃ��߂ɏ[�d���͂�荂���d����������A�����ɂ���3.0V�^�C�v�̓d�r����ꂽ�ꍇ�͂��Ȃ苭��ɉߏ[�d���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B �@���ꂪ�ԕi�������߂������R�ł��B �@Soshine SC-S6�ł���A�������Ă��Ȃ��̂Œ��̍\���͂킩��܂��A���[�J�[������Soshine 3.0V CR123A���[�d����ɂ͂قڈ��S�ł͂Ȃ��ł��傤���B(�����d������������Ƃ�����������܂����c) �@UltraFire ICR123A�����͎����Ă��Ȃ��̂ŕ������Ċm���߂Ă͂��܂��ASoshine 3.0V CR123A�Ɠ����́u�_�C�I�[�h�Q�ɂ��~����H�v�������Ă���ł��P���ȃ^�C�v��3.0V����H����d�r�ł���ASoshine�����d�r�ł͂���܂��[�d���Ďg�p�͂ł���Ǝv���܂��B �@�����܂�������~����H�E�����̓d�r�ł���A����ɂ���ĕs����N����\��������܂��̂ŁA���[�J�[�ۏ؊O�̂��̂����ȐӔC�ł��g�����������B �@���Ƃ���Tenergy��3.0V���`�E���C�I���[�d�r�ł́A�d�q��H�ɂ��[�d����3.6V�d�r�Ƃ��ĐU�镑���A��u�ł����ׂ��������3.0V�d�r�ɐ�ւ���ȂǂƂ��������x�ȏ��������Ă���d�r�����邻���ł��B ���Ԏ� 2009/2/9
|
||||||||||||
| ���e |
�@�w�H�t���̓X�x�Ƃ����̂��C�ɂȂ��ē��e���܂��B �@�̂���H�t���ł� �w�X�i�ǂ��납�X���j���Ɋi��������x
�Ƃ����̂�����ł��B�@�����n��̓X�ł��A�݊��i���o���Ă����Ƃ���Əo���Ă���Ȃ��Ƃ��낪���X���������m�ł��B �@�ǂ�ȓX�ł����V�[�g�������čs���Ό����E�ԕi�ɉ����锤�ł��B �i����������X������܂����c�j �@����Ȏ�������A�H�t���ł́w�M������X����T���x�Ƃ����̂��A�l�̃m�E�n�E�Ƃ��Ē蒅���Ă��܂��B �@�����̓��C�g�֘A���i�́A�E���ł��Љ�Ă���O���e�Ŕ������ɂ��Ă��܂��B Thief �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ł��ˁB�̂���w�����n�̖ڂ��x�ƌ����Ă������]���̏����l�ƑΛ�����ɂ́A����Ȃ�̊o��Ɠx���ƒm�b�ƗE�C���K�v�ł��ˁB(�����Ⴄ�H) �@���̏ꍇ�͏H�t���ɂ͎��X�����s���܂��A����ł�20�N�ȏ�͒ʂ��Ă���킯�Łc�A�X�ɂ���Ă̑Ή��̈Ⴂ��A���q�����q�Ǝv���Ă��Ȃ��X���������Ă��܂����B �@��������I���W����l�ł���Ă�X�ł́A�����Ӗ�(?)�Łu�]�˂��q�C���v�Ƃ������A�܂ǂ�����������S�ҋq�̑Ή����ʓ|�Ƃ��������ŁA���ʂɓX���o���Ă���̂Ɂu�́H�f�l����̗���X����˂���I�v�݂����Ȃ�����ǂ�ȑΉ��̏�����R����܂����A��r�I�Ⴂ�X���̓X�ł́u�f�l�͂����J��������A�K���Ȏ��������č������i����Ă��܂����I�v�݂����Ȉ����X�����܂����B �@���X�X�Ȃ�ł͂́A�X�������m�����L�x�ł��q����̎���ɂ͓I�m�ɓ����A���߂Ă��镨���T�b�ƑE�߂Ă���邽���ւ�Ή��̗ǂ��X������܂��B �@����n��X�ł��X���̌l�̎��ɂ���đΉ����Ⴄ�Ƃ����̂����ӂł��ˁB �@�H�t������{���͒��N�ʂ��l�߂āA�X�̐�����X���̕��̑Ή����悭���āA�M���ł���Ƃ���Ŕ�����������@������Ȃ�Ƃ������ƂŊԈႢ�����Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/2/9
|
||||||||||||
| ���e |
�@���낢��Ƃ��߂ɂȂ邲���������肪�Ƃ��������܂����B �@����̔������̏ꍇ�A�킽���ɂƂ��Ă͐V���ȃ`�������W�ł����B���܂ł�Sure Fire�Ŏd���ɁALED Lenser��EDC���C�g���y����ł������ߏ[�d�����h�����Ă����̂ł����B(�P�O�^Ni-MH���x�͎g���܂�����) �@���ꂩ��A�H�t���̎���ɂ��Ă͂�����x�͑����Ă���܂��B���͂킽����20�N�ȏ㑱���Ă���HAM�ł��āA�d����PC�T�[�o�n�C���e�O���[�^�ł��B��ʼn�H�}�߂Ȃ������N������PIC����̑����������������Ă���̂ŁATr���ɑ�������p�ԂɂȂ��ĂČ݊��i��X���̃I���W����ɗ��ނƉ�����b�����ȖڂŌ����邱�Ƃ��悭����܂����B���܂��ɂ͌݊�Tr�̃s���z�قȂ��Ă����肵�čQ�Ă���B �@RCR-123A��3V�i�ɂ��Ă̏��͏����ł����B����̓V���b�g�L�[�œd�������Ă����̂ł��ˁB���ƁA���C�g�Ə[�d�r���Ɋւ��Ă͑f�l���R�̂��߁A����̔������͂��Ȃ�̖`���������悤�ł��B �@�܂��ALuxeon�ȍ~�̃��C�g�ł��������ؕ����ƂȂ�Ɩ��m�̐��E�ł�����A�Ȃ��Ȃ��N�b�L�[���Ă��悤�ɂ͂����܂���B�ǐm�����͖��̌��ł�������B(��) �@����UF CR123A�̏[�d�ɂ��Ă͂��������悭���ׂĎ������Ă݂悤���Ǝv���܂��BWF-138������ł���Ηǂ��̂ł����A�����l�q�����Ȃ�������Ă܂��肽���Ǝv���܂��B �@�܂��A���̃T�C�g�������܂Ȃ����Ēm�����z�����Ă܂��肽���Ǝv���܂��B sail �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@HAM��OM����Ȃ�H�t���ł̐킢��(��)�͂悭�����m�ł��ˁi�O�O�G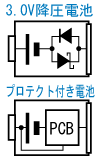 �@�Q�l�܂łɁA�ȈՂȍ\����3.0V���`�E���C�I���[�d�r�́A�E�}�̂���ɐ����p�V���R���_�C�I�[�h�ƃV���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h���Ό��ɕt�����Ă��܂��B
�@�Q�l�܂łɁA�ȈՂȍ\����3.0V���`�E���C�I���[�d�r�́A�E�}�̂���ɐ����p�V���R���_�C�I�[�h�ƃV���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h���Ό��ɕt�����Ă��܂��B�@���d���ɂ͐����p�_�C�I�[�h��Vf�Ԃ�d���������A�[�d���ɂ̓_�C�I�[�h�̉e�������Ȃ�����ׂ�Vf�̏����ȃV���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h��ʂ�܂��B �@Soshine 3.0V CR123�ł͐����p�V���R���_�C�I�[�h��Vf=1.1V(2A��)�Ƃ��������g�p����Ă��܂��B �@3.6V/3.7V�̃v���e�N�g��H���̓d�r�͐}�̉����̂悤�ɁA�v���e�N�g��H�������Ă��Ď��g�̓d���œ��삵�Ă��܂��B �@���ʂ��ߏ[�d(�ߓd��)�A�ߕ��d�A�ߓd���ɑ���ی��H�������Ă��܂��̂ŁA(�d�C�I��)���Ȃ藐�\�Ɏg���Ă����v�ł��B �@������������ł�����A���`�E���C�I���[�d�r�p�́u�v���e�N�g��HIC�v��u�v���e�N�g��H�p�����^FET�v�ȂǁA�ŐV�̃v���e�N�g�Z�p�̎��������{�̊e�Ђ�������\����Ă��܂�����A�l�b�g�����Ȃǂ����Ă݂Ă͂������ł��傤���B �@���ꂩ��́A������Ɓu�Z���v�ł����A���e�C�X�g�����y���݂��������B ���Ԏ� 2009/2/10
|
||||||||||||
| ���e |
�@���X�t�]�I�Ȕ��z���B �@����3.0V�~���d�r�̌������g���āAWF-139���R�u�Ή��ɉ��Ǐo���Ȃ��ł��傤���H �@�o����ΐ芷���X�C�b�`��t���āA�����̓d�r�Ή��Łc �@�����ɂ͏��X�n�[�h�����������Ȃ̂Łc�i���j �@���ԓI�ȗ]�T����������ŗǂ��̂ŁA�������@�������Ē����܂�����K���ł��B Thief �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�������g���āv�Ƃ����̂��A�ǂ̂悤�ȉ�H���l�����Ă���̂��킩��܂��A���Ȃ��ςȉ����ɂȂ�܂���B �@WF-139�����[�d�����m���Ă���̂́A�d�r�d����F9444��A/D�R���o�[�^���͂Ɂu���ځv����(�m�C�Y�h�~�̒�R�ƃR���f���T�͂���܂����c)���Ă�����f�W�^���l�ɂ��Ĕ��肵�Ă���̂ŁA���̂܂܂ł�F9444�����̃v���O�����ł����������Ȃ��Ǝ����ł��܂���B �@�����d�����͕����A�i���O�I�ɉ�������ƁA�u3.0V�d�r���J���d��3.6V�̎���F9444�ɂ�4.2V����͂���ׂ̉�H�v�Ƃ������ŁA�I�y�A���v���g�����d���ϊ���H�Ƃ��A���������F�X�ƕ��i��g�ݍ��킹����H�̑g�ݍ��݂Ɛ�ւ��X�C�b�`��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�ʓ|�ł��B �@�����Ă͂��܂��A�[�d�d���𗬂��Ă��鎞�̓d�������m���Ă��āA�����˔��I�ȉߓd���ŏ[�d���~������悤�Ȃ����݂��g�ݍ��܂�Ă�����A�P���ɓd�r�̒[�q�d����ϊ�����F9444�ɓ��͂��邾���ł͂Ȃ��A�[�d�d���𗬂��Ă��鎞�͓d���ϊ������A�J���d�����v���Ă��鎞�����d����������ȂǁA�[�d����ɓ������ēd��������p���ւ������x�ȉ�H���K�v�ɂȂ邩������܂���B �@�܂�380mA�Ƃ����[�d�d���A���ɏ[�d�����ɂ͓d���l�������Ă��ׂ����`�E���C�I���[�d�r�ɑ��Ăقڈ��̓d���𗬂�������WF-139���ƁA����16340�[�d�r�̏��e�ʃ^�C�v(���Ƃ���1000mAh�Ə����Ă�̂�300mAh���������Z���Ƃ��c)�ɂ͉ߓd���𗬂����ɂȂ�j�S�z�ł��B �@�����T�C�Y�̏�����16340/RCR123�����S���ď[�d����Ȃ�A��d����H�̒萔���ς��ēd�������Ȃ�����ׂ��ŁA���ׂ̈̐ؑ։�H�܂œ���đS�����X�C�b�`�Ő�ւ���ƂȂ�Ƃ����ւ�ȕ��ɂȂ�܂��ˁB �@�����܂ł���WF-139��3.0V��RCR123�ɑΉ����������Ƃ́u���́v�v���܂���̂ŁA�������������v�����ɂ͎c�O�Ȃ��炨�����ł��܂���B �@�u��R��X�C�b�`��t����ΏI���I�v���x�ŁA��������̎g�p�����S�Ȃ�l���邩������܂��A����͂����������ƂŁB ���Ԏ� 2009/2/13
|
||||||||||||
| ���e 2/13 |
�@�����܂ō��x�Ȏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��ˁB�����P���ɍl���߂��Ă����݂����ł��B �@�w�����X���ɂ�����ςȂ��͂��킢�����x�Ǝv�������̂Łc �@�\����܂���B Thief �l
|
||||||||||||
| ���e 3/4 |
�@UltraFire�@C1S�̂��̌�̂��ł��B �@UF ICR123A�ŕ��d�e�X�g���Ă����Ƃ���A��͂蔭�M����������3�����x���g�p���E�ł����B�Ƃ͂����A�L�[���C�g���o�Ŏg���ɂ͗ǂ������ł����B�܂��A���C�g�̐��i�Ȃ̂�����n�_����ڂɌ����Ė��邳��������A�����ɓd�r�����o�����Ƃ���J���[�d����2.74V�قǁB����͓d�r�̕��d�I�~�d���ɋ߂��̂Ő��Z�����g����ł͂ƂĂ�����₷�������܂����B�ł����A���邳�����牺����̃��C�g���Ɛ��Z���g�p�͑f�l�ɂ͂�����ƕ|���ł��ˁB �@���x��Tiablo�@TL1���w��(�\��)�����̂ł����ȓd�r�ƃ��C�g�̑g�ݍ��킹�Ŏ����Ă݂����Ǝv���܂��B Sail �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �^�~���j�J�h1000���j�b�P�����f�p�[�d��ŏ[�d�ł���H | |||||||||||||
|
�@���߂܂��ăJ���\�Ɛ\���܂� �@���̃y�[�W�̃A���J���d�r�̔�r���ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂����O�O �@�Ŏ���Ȃ�ł����j�b�P�����f�p�̏[�d��Ƀ^�~���̃j�J�h�d�r�i�~�j�l��j�̓d�r���[�d�͂ł���̂ł��傤���H �J���\ �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�j�b�P�����f�[�d�r�p�̏[�d��Ƃ����Ă��l�X�Ȃ��̂������Ă��܂��B �@���̒��Łu�j�J�h�d�r�Ή��v�Ə����ꂽ�[�d��ł���Ώ[�d�ł��܂��B �@�Ή��Ə�����Ă��Ȃ�������A�������́u�[�d���ԁv�̈ꗗ�\�Ńj�J�h�d�r�ɑ��Ă̏[�d���Ԃ�������Ă��Ȃ���Ί�{�I�ɂ͂��̏[�d��Ńj�J�h�d�r���[�d���Ă͂����܂���B �@�}���[�d��Ńj�J�h�[�d�r��j�b�P�����f�[�d�r�̏[�d������m��ׂ́|���u���o�ł́A�j�J�h�d�r�̂ق������d�����傫���A��菬���ȃ��d���Ŗ��������m����j�b�P�����f�Ή��[�d��ł͖��[�d�͐��������m�ł���ł��傤���A�����T�C�Y�̃j�b�P�����f�[�d�r�̓j�J�h�d�r���e�ʂ������A�}���[�d�̍ۂ̓d���l�͂��傫�ȓd���܂őΉ����Ă��܂��B�������j�J�h�d�r�͗e�ʂ����������߂Ƀj�b�P�����f�p�̑傫�ȓd���𗬂��Ɖߓd���œd�r��ɂ߂Ă��܂��\��������܂�����A�e�ЂƂ��Ƀj�b�P�����f�p�̏[�d��ő傫�ȓd���𗬂��^�C�v�̕��ł̓j�J�h�d�r�͏[�d���Ă͂����Ȃ��ƋL���Ă��܂��B �@�^�~�����甄���Ă���V�����u�����[�d��v(�^�~���P�O�j�J�h��{�p)�́A�O�m�d�@�̃j�b�P�����f�[�d�r��p�[�d��NC-MDR02�ŁA�{���̓j�J�h�[�d�r�͏[�d���Ă͂����Ȃ�(��Ή�)�Ƃ���Ă��܂����A�^�~������̔�����Ă��镨�ɂ��u�j�J�h�Ή��v�ƃV�[�����\���Ă��܂�����A���[�J�[�������L���Ă���Ȃ���v�ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2009/1/27
|
||||||||||||
| ���e |
�@�O�X����s�v�c�Ɏv���Ă����̂Ŏ��₳���Ă��������܂��B �@NI-MH/�j�b�J�h���p�[�d���NI-MH�ƃj�b�J�h���ǂ�����ċ�ʂ��Ă����ł��傤���H �@�j�b�J�h���[�d����̂ɂ��܂��ɐ�p�@�ɂ�������Ă��鎄�ł��B �䂸�ۂ� �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�[�d�푤�ł͕ʂɎ����ŔF�����Ă̋�ʂȂǂ͂��Ă��܂���A�C�ɂ��鎖�͂���܂���B �@���[�d����̃��u�̔���l���j�J�h�d�r�͂P�Z��-10mV�A�j�b�P�����f�d�r�͂P�Z��-5mV�ƁA�j�J�h��p�[�d��Ńj�b�P�����f�[�d�r���[�d����Ƃ�葽���ߏ[�d�����Ă��܂������ŁA�t�͉ł��B �@�A����ɏ����܂����悤�ɁA�j�J�h�d�r�̗e�ʂɑ��ăj�b�P�����f�[�d�r�̗e�ʂ����T�C�Y�̓d�r���m�ł͑傫���̂ŁA�j�b�P�����f�p�}���[�d��ł͏[�d�d�����������ăj�J�h�d�r��ɂ߂�ꍇ������܂�����A�j�J�h�d�r�^�j�b�P�����f�d�r���ɂ����ƑΉ������[�d��ŏ[�d���邱�Ƃ���ł��B ���Ԏ� 2009/1/31
|
||||||||||||
| ���e |
�@�ԓ��L��������܂����i�Q�j�� �@�Ȃ�قǓ�J�h�Ή�����Ȃ��ƑʖڂȂ�ł����O�O�G �@�����^�~���j�J�h�P�O�O�O���ǂ���琶�Y��~�ɂȂ����݂����Ȃ̂Ńj�b�������ւɂȂ�܂ő҂��Ă݂悤�Ǝv���܂��O�O�G �J���\ �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�҂��ɑ҂����j�b�P�����f���ւ������Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/2/4
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| ����o�b�e���[�`�F�b�J�[�̕s�ǁH | |||||||||||||
|
�@�O�ɃW�I���N�X�̌��ł����b�ɂȂ�܂������A����̓o�b�e���[�`�F�b�J�[�̂��Ƃł��������������܂��ł��傤���B �@100�~�V���b�v�Ŕ�����o�b�e���[�`�F�b�J�[�ł����A�J���A�����Ƃ��d��������Ȃ��̂��s���ŁA�ȒP�Ȏ���̃`�F�b�J�[���g���Ă��܂��B �@�Ƃ��낪��R�ŕ��ׂ�������ׂ̃^�N�g�X�C�b�`��g�ݍ���ł���̂ł����A���炭�g���Ă���ƃX�C�b�`�s�ǂɂȂ��Ă��܂��܂��B��惉�P�b�g�̋L����q�����A������2-300mA�̓d������i50mA���x�̃^�N�g�X�C�b�`�ɗ���Ă��邱�Ƃ��Ǝv���A��惉�P�b�g�̉��ǂɃq���g�āA2SC1815�g�����W�X�^���g��������H������x�[�X�d���̓��͕��Ƀ^�N�g�X�C�b�`�����܂����B �@�����Ŏ��ɂ͗����ł��Ȃ����Ƃ��N���܂����B �@��R���ׂ̃`�F�b�J�[���g�����W�X�^���ׂ̃`�F�b�J�[���d���͓d�r��+-�̗��[�ő����Ă���̂ł��������d�r���g���Ă������̓d�����g�����W�X�^���ׂ̃`�F�b�J�[�̂ق���0.2V���x�Ⴂ�l�������܂��B �@�d���𑪂��Č��Ă�20mA�ʂ�������Ă��܂���ł����B �@�d���𑪂�ꏊ���Ԉ���Ă���̂�����H�̍������Ԉ���Ă���̂��킩��܂���B���w������������K���ł��B �䂸�ۂ� �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@2SC1815����ő��i�R���N�^���d��150mA�̑f�q�ł��B200�`300mA�Ȃ�ė����Ȃ��ł��������B�^�N�g�X�C�b�`������̂Ɠ��l��2SC1815�����܂��B �@200�`300mA�Ŏg�������̂ł���A�Q�{�_�ōl���čő��i400�`600mA�ȏ�̃g�����W�X�^���g��Ȃ��Ƃ����܂���B�u�C�̖����v�ł̓p���[�����[��������x�̓d���̕��ׂ��쓮����Ȃǂ̏ꍇ��2SC2120(Max.800mA)�����g������H�}����Ă��܂��B �@�]�k�ɂȂ�܂����A���X�d�q�H��u���O(����PIC�n�ɑ���)�Œ�i�d�����z���镉��(20mA�ݒ��LED��20�ȏ�Ƃ��c)�Ȃ̂�2SC1815���g���Ă����H�}�����܂��B �@���������u���O�̐l�́u���l��(PIC��LED��_�ł�����)��H�}���Q�l�ɍ���Ă݂܂����v�݂����ȍ\�}�������̂ł����APIC�̃v���O�����ɂ��Ă͈ꐶ�����ɒ��ׂĎ���v���O����������Ă���̂ɁA�Ȃ�������2SC1815���g���Ă��đ��̗p�r�ł�����ꂪ�_���Ȏ��ɂ͋C�Â���Ȃ��悤�ł��B �@�R���N�^�d���̐v�l���ǂ�����Ă���̂��̏������A�x�[�X�d���̐v�l���������ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ʼn�mA�ɐݒ肳��x�[�X��R�̒l�������ɂ���Ă���̂��킩��܂��A�d�r���痬���d���̓x�[�X�d���Ԃ�����Z����܂���ˁB����͌v�Z�ɓ���Ă��܂����H (���ʂ͐�mA�Ȃ̂ʼne���͖����Ǝv���܂����c) �@�����A�x�[�X�d����2SC1815�̒�i�x�[�X�d�����z���Ȃ��悤�ɂ͂��Ă���Ǝv���܂����A���܂��R�����ƕ��d�d���ƍ��Z���ꂽ���ɂ������Ȑ��l�ɂȂ�܂���ˁB >�d���𑪂��Č��Ă�20mA�ʂ�������Ă��܂���ł����B �@�Ƃ������Ƃ́A���������d�r�ł͂Ȃ��̂ł����H �@��u�g�����W�X�^���g������H�ł́v�Ƃ������A�d�r���猩�����בS�̂̒�R�l(�����"�g�����W�X�^������H"���܂߂��S��)�̈Ⴂ�œd�r���痬���d�����������Ԃ�d���ቺ����̂ł́H �@�{����20mA���x�̍���0.2V��������Ƃ�����A�����\�͂̒Ⴂ�}���K���d�r�Ȃ�ł��傤���ǁB ���Ԏ� 2009/1/26
|
||||||||||||
| ���e 1/29 |
�@����o�b�e���[�`�F�b�J�[�s�ǂ̌��A�����̂��Ԏ���ς��肪�Ƃ��������܂����B �@�ǎ������Ă��邤���ɒ�R���׃`�F�b�J�[�̃n���_�s�ǂ��݂��܂��ĐF�X����Ă��邤���ɖ��^�N�g�X�C�b�`���s�ǂƂȂ�܂����B �@���ǂ��̒�R���׃`�F�b�J�[�͐M���ł��Ȃ��Ƃ̌��_�ɒB���܂��āA�j�����邱�Ƃɂ��܂����B���E�߂ɏ]��2SC2120����ɂ���A�g�����W�X�^���ׂ̃`�F�b�J�[������Ȃ����܂����B�x�[�X��R��1K���ŃR���N�^�ɂ͓d���v���p��1���̒�R������܂����B�J���d��1.48���̃I�L�V���C�h�d�r���g����������1����R�̗��[�d����120mV�܂�120mA������Ă��܂��B �@�����d����0.1���ቺ��1.37v�ɂȂ�܂����B����Ȃ�M���ł������ł����A�^�N�g�X�C�b�`�̕s�ǂɂ��Y�܂����Ȃ��Ă��݂����ł��B �@���e���Ȏ�������܂��Ă��p������������ł��B���ꂩ�����낵�����肢�������܂��B �䂸�ۂ� �l
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �d�����]�Ԃ̂m���l�g�̌� | |||||||||||||
|
�@���������Ȃ̂ŁA�����ЂƂ��t���������������B �@������ł��F�X�ǂ܂��Ă��������Ă����̂ł����A�d�����]�Ԃ̂m���l�g�̌��ł��B�S�N���x�g�p���[�d���Ă��Q�S����Q�T�u�܂ŗ����o�b�e���[���j�b�g�����S���������܂����B�h�i�[�͓���i�̂Q�N���x���u���ꂽ���g�p�m�[�g�o�b�e���[�ł��B�P��ڂ̏[�d�ł͓����x�̓d���ł��������t���b�V������ƋN�����炵���Q�V�u�ȏ�o�Ď��p���ł��B �@�O�������͍̂���20�{�����ԂȂ̂ŎQ�l�ł����e�Z���v�����܂����B��������1.3�u���Ő��{��1.29�u��Ƃ��������ł��B���j�b�g����O����26�u���x�o�Ă��܂��B �@�Z���̃o���c�L���Ă��̒��x�̍��Ȃ��̂ł��傤���H�܂����̓d�����āi�ψ�Ɂj���E�����ȕ��ł��傤���H0.1�u���x�Ⴂ�Z������������Η������邱�Ƃ�����Ǝv���܂����H�d����������Ƃ܂������̗l�ȋC�����ĂȂ�܂���B �@�[���d�̓��t���b�V���@�\�t�������[�d��݂̂Ŗ͌^�p�̏[�d�퓙�͎g�p���Ă��܂���B�e�X�^�[�œd���������Ă�������R��e�ʂ̗͔��f�ł��Ȃ��̂Ō����ɂ̓o�b�e���[�p�̌v���킪�K�v�ł��傤�ˁB���������ŃI�X�X���̂��̂͂���܂��ł��傤���H backup �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
>�Z���̃o���c�L���Ă��̒��x�̍��Ȃ��̂ł��傤���H �@0.01V�̍��Ȃ�Ė����ɓ������ł��B �@�قƂ�Ǒ����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��悤���B >�܂����̓d�����āi�ψ�Ɂj���E�����ȕ��ł��傤���H �@�����NiMH�[�d�r���ƁA�[�d�����1.35�`1.38V���x�͂���܂��B�A���[�d�������ɂ����܂��̂ň�T��1.35V�������ƕs�Ǖi�Ƃ͌����܂���B >0.1�u���x�Ⴂ�Z������������Η������邱�Ƃ�����Ǝv���܂����H �@���Ԃ�20�{�S���������ɋ߂Â��Ă���Ǝv���܂��̂ŁA���̔�r�I��Ԃ̈����������������Ă������ɑ��̃Z�������������܂��B �@�u�����v�Ƃ����Ӗ��ł͎b���͎g���Â��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂����A���{�I�ȉ��P�ɂ͂Ȃ�Ȃ����������ł��B �@20�{����g�p�ł�����A�ꕔ�̑���������Z�������ɒɂ߂��Ď���Ă���\���͂���A�������������p�b�N�S�̂Ƃ��Ă܂����炭�͎g�p�ł���\��������܂����A�����܂ʼn\���ł���S�ẴZ���̏�Ԃ𐳂�������E���肵�Ȃ��Ƃǂ�������Ԃ����͕��͂����邾���ł͔��f�͂ł��܂���B �@��{�I�ɁANiMH�[�d�r������d��(�J��H�d��)���������Ă��Z���̗�͂킩��܂���A�����d���̑����A�e�ʌ������s��Ȃ��Ǝ��ۂǂ̃Z�����s�ǂłǂ̃Z�����܂��g���邩�͔���ł��Ȃ��ł��悤�B �@���ׂ̈ɂ͐�p�̑�����A���W�R���p�ȂǂłP�Z���P�ʂŏ[���d���Č��ʂ��\�������[�d�킪�K�v�ŁA�����͂����Ă��͂P���~�ȏ�͂��܂��B�u�����Łv�ƌ�����Ɖ����Љ�ł��܂���B �@�u�j�b�P�����f�[�d�r�E�P�Z�����d��̐����v�̂悤�ȉ�H������āA�e�Z����P�̂ŕ��d�����ĕ��d���Ԃ��v��Ȃǂ��ėe�ʂ��m�F����̂��ǂ��ł��傤�B �@�������[���ʂ��N�����ăZ�����ꎞ�I�ȗ��N�����Ă��邾���ŁA�e�Z���������ƃ��t���b�V�����Ă��Α����͉��P���邱�Ƃ����邩������܂���B ���Ԏ� 2009/1/24
|
||||||||||||
| ���e |
�@���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B �@�Q�O�{�g�d�r�̏ꍇ���S�Ȗڈ��͂��悻�Q�V�u����Q�W�u���x�Ȃ̂ł��ˁB�O�̓d�r�͂ǂ����u�ψ�Ɂv�S���_���ɂȂ��Ă���\���������ł��ˁB��i�d���̂P�D�Q�u�͕��דd���Ŗ����ׂłP�D�R�u�O�゠���Ă����ۂ̉�H�d���͓�����R�̑��哙�łP�D�Q�u�o�Ă��Ȃ����Ċ����ł��傤���B �@���W�R�������Ȃ��̂ł悭�킩��܂��艿�Q�����x�̏[���d���1���t�I�N�łł������Č��悤�Ǝv���܂��B �@�@��t���̃��t���b�V����H��g�d�r��ԂŐ���s�����A��͂�P�Z���ŕ���ɂ��ď[���d����������ʂ������̂ł��傤���H �@�����ȏ[���d��̏ꍇ�Q�T�Z����R�O�Z�����x��Q�O�{�̏�ԂŌ��ʓI�ɏ[���d����@�\������悤�ł����A����ڑ��̂܂܊e�Z�����Ƃɉ������s����H���đ��݂���̂ł����H �@�C���[�W�ł��܂���ł����B backup �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�K���ɍ������d����ĐF�X�Ǝ����Ă݂���̂���ԕ��ɂȂ�ł��傤�ˁB �@�����A�P�Z���Ƀo�������d�r����悤�ɕ����u����[�d�v��u������d�v�͂��Ȃ��ق��������ł��ˁB�u����Ă݂����v�Ǝv���Ď��s�����͕̂��̂��߂ɂ͗ǂ���������܂��A���͂ǂ��Ȃ��Ă��m��܂���B �@����ڑ��̂܂܊e�Z�����Ƃɕ��d���s�����i�̓��W�R���p�̃p�b�N�^�o�b�e���[��p�ŗL��܂��B�ߋ��Ɂu���̐��i�͂ǂ��ł����H�v�݂����Ȋ����œ��e����Ă����Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/1/25
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �����ԃo�b�e���[�������̃o�b�N�A�b�v�c�[�� | |||||||||||||
|
�@���X�����Ē����Ă��܂��B �@�ŋ߂̎����Ԃ͓d���������o�b�e���[�������ɃV�K�[�\�P�b�g���œd����������o�b�N�A�b�v�c�[���Ȃ���̂����݂��܂��B�������������Ƃ͂Ȃ��̂ł����P�O���{��O�O�U�o���g�p����݂����ł��B �@�P�Q�u�ȉ��ł��������[�ێ��ł���Ƃ����v�z��������H�������Ă���̂��^��ł��B���d�r���ւ̋t���h�~�Ƀ_�C�I�[�h���x�͓����Ă��邩�ƁB���삵�Ă��������Ȏv���܂������킴�킴�_�C�I�[�h���B����قǕK�v�����Ȃ��̂ŁB �@�����Ŏ���ł����茳�ɂk�d�c�͂���̂ł����V�K�[�v���O�Ɗ��d�r�̊Ԃɓ���Ă����d�r�ی�ɂȂ�܂���ł��傤���H�̐S�̓d�����ቺ���ĈӖ������ł����H backup �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ԃo�b�e���[�������̃o�b�N�A�b�v�c�[���Ƃ��������������Ƃ������̂łȂ�Ƃ������܂��A�����ԃV�K�[���C�^�[�\�P�b�g�ɂ�����d���̒Ⴂ�d�r����P���Ɍq���Ύ����Ԃ���q�����d�r�ɋt�d��������Ă����ւ�댯�ł��B �@�K���_�C�I�[�h���ŋt���h�~�[�u���Ƃ��Ă��������B �@LED�͋t���h�~�_�C�I�[�h�ɂ͂Ȃ�܂����B �@�����p�̃_�C�I�[�h�͋t�����ψ������\�u�ȏ�ƍ����A���Ό����̓d���������Ă�(������Ȃ������)���Ȃ��̂ŋt���h�~�Ɏg�p�ł��܂����ALED�͋t�����d������T�u�ȏ�őf�q���j��ē��ʂ��܂��B������t���h�~�Ɏg�����̂ł͂���܂���B �@�܂��A�����Ԃ̃o�b�e���[�d���ƃV�K�[�\�P�b�g�Ɍq�����o�b�N�A�b�v�d�r�̓d�������������ċt�d���ʼn��Ȃ��Ă��A�o�b�e���[���O���ăo�b�N�A�b�v�d�����������鎞��LED�ɂ͑傫�ȓd���͗����܂���A�Ԃ̋@�푤�̃X�^���o�C�d���ɑ��Ă��イ�Ԃ�ȓd���������ł����ɁALED���Ă��铙�̕s����N����\�����傫���ł��B �@�o�b�N�A�b�v���K�v�ȓd����10�`20mA���x�ł���ALED�ł��d���𗬂���Ƃ͎v���܂����A�S�z����Ă���ʂ�LED��Vf�Ԃ�̓d���ቺ�͋N���܂�����@�푤���d���s���œ��삵�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��l�����܂��B �@LED���p�Ɏg�p���鎖�͂����߂��܂���B �@�����Ƃ��������p�_�C�I�[�h���g�p���Ă��������B ���Ԏ� 2009/1/24
|
||||||||||||
| ���e |
�@���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B �@�����̂��łɏH�t���Œ��B���܂��B >LED�͋t�����d������T�u�ȏ�őf�q���j��ē��ʂ��܂��B �@�������d���̒�i��12V�ȏ�̑f�q�ł���5V�Ƃ����Ӗ��ł��傤���H�܂�1�x�̐ڑ��~�X�Ń_���ɂȂ�\���������Ƃ������Ƃł��傤���H backup �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�������d���̒�i��12V�ȏ�̑f�q�v���ĂȂ�ł��傤���H �@����͊��ɂ��̐��E�ɑ��݂���LED�ł͖����Ǝv���܂���B �@LED�̏������d���͐ԐF��1.8�`2V���x�A���F��ΐF��2.2�`2.4V���x�A�F�┒�F��3.0�`3.4V���x�B �@���̒m��Ȃ������ŁALED�f�q��Vf��12V�ȏ�̕������݂���̂�������܂��A���������Ȃ炻�̐��i�̃f�[�^�V�[�g�������������B �@�ʏ��LED�̏펯���ʗp���Ȃ��ȏ�A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��ƂĂ��z�����ł��܂���̂ŁA������͉��������܂���B ���Ԏ� 2009/1/26
|
||||||||||||
| ���e |
�@�ڂ����͒m��܂������ԗp���C�g�Ɏg�p����Ă���k�d�c�͂P�Q�u�ȏォ�Ǝv���܂��B �@�f�q�ȑO�ɒ�d����H�ł��ׂĂQ�u�ȉ��ɂ��Ă���̂ł��傤���H �@���^�̎������Ƃ����̂悤�ȉ�H�X�y�[�X���������Ǝv���܂��B backup �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�u�����ԗp���C�g�Ɏg�p����Ă���k�d�c�v�ƌ����ƁA����́u�f�q�v�ł͖����u�d�q��H��������i�v�ł��ˁB �@���Ƃ��u12V�p�̐ԐFLED�o���u�v����Vf=1.8�`2.0V���ԐFLED���d�������p��R�������Ă��܂��B �@���F�̕�����Vf=3.0�`3.4V�����FLED���d�������p��R�������Ă��܂��B �@�d�������p��R�̑���ɒ�d���_�C�I�[�h�������Ă���ꍇ������܂��B >���^�̎������Ƃ����̂悤�ȉ�H�X�y�[�X���������Ǝv���܂��B �@���������A���^�̎������p�̓d���^LED���ł��d�������p��R�͓����Ă��܂���B �@�]���āA���̂悤��12V��LED��_��������ׂɉ��炩�̓d��������H�������Ă���uLED���i�v�ɂ�DC12V�����������_�Œ�߂�ꂽ�d����������܂���A����̓��e�̎�|�́u�����p�r�v�ɂ͂ƂĂ��g���܂���B ���Ԏ� 2009/1/27
|
||||||||||||
| ���e |
�@�͂��߂܂��āB���͂��������̂����L���Ă���܂��B �@�N���}�̃o�b�e���[�������ɗ��p�������Ƃ�����܂��B �@���̂悤�Ȑ��i���Ǝv���܂��B �@�o�b�e���[�������Ɏ��v�A���W�I�Ȃǂ̃o�b�N�A�b�v���ł���c�[���B�V�K�[�\�P�b�g�ɐڑ����Ďg���܂��B9V�A���J���d�r(�ʔ�) http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2001000001842 �@���Q�l�܂ŁB ezk �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�J�[�p�i�̉��i�Ƃ��čl����ƁA������H�Ȃ�ē����Ă������ɂ���܂���ˁB�d�r�X�i�b�v�̗��ɒP�Ƀ_�C�I�[�h����{�����Ă��邾���̂悤�ȁE�E�E ���Ԏ� 2009/2/28
|
||||||||||||
| ���y�[�W�擪�ɖ߂遣 | |||||||||||||
| �\�[���[���C�g�p�j�J�h�d�r | |||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�d�r�w���̍ۂ̎Q�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��B �@�ŋ߁A�z�[���Z���^�[�ɂāA�\�[���[���C�g�p�̒P�O�^�j�b�J�h�]�n�Ƃ������̂������Ă���A2�{��298�~�Ƃ��Ȃ�����̂ł����A���\�I�ɐS�z�łȂ��Ȃ������܂���B���\�e�X�g�����Ă��������܂���ł��傤���H�B (������]) �l
|
|||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�z�[���Z���^�[�Ń\�[���[�K�[�f�����C�g�p�Ɍ������i�Ƃ��ăj�b�J�h�d�r�͂����ƈȑO���甄���Ă��܂��B �@�l�i���Q�{��280�`380�~���炢�ƃj�J�h�d�r�Ƃ��Ă͒��قǂŁA����قǍ����͖����ł��ˁB �@���\�ƌ����Ă��\�[���[�K�[�f�����C�g�łP�N���x�g�p����Ȃ�ʂɖ��͂���܂���̂ŁA���S���čw�����Ă��������B �@�Q�{�p�b�N�Ȃǂł��A�Е��̂ق����e�ʂ������ĕЕ������Ȃ�(��i��菭�Ȃ�)�Ȃǂ̃o�������悭����܂��B �@���W�R���V���b�v�Ŕ����Ă��郉�W�R����p�j�J�h�d�r�̂悤�ɓ��ɑ�d�������ɐ��\��ς��Đ�������Ă���悤�ȓ���d�r�ł͂���܂���̂ŁA�K�[�f�����C�g�Ŏg�p����ȊO�ł���������ʂ̈����d�r���x���ł��B ���Ԏ� 2009/1/14
|
||||||||||||
| ���e |
�@���߂�Ȃ����B �@�͂�����g�p�p�r�������ׂ��ł����ˁB �@���͎g�p�p�r�I�ɂ̓\�[���[���C�g�̌����p�Ƃ��Ďg�p����킯�ł͂Ȃ��A�~�j�l��Ɏg�p���悤���Ǝv���Ă����̂ł��B �@�^�~���̃j�J�h�͂₽�獂���AGP�͈������ǁA���\�������A�H�t������{��������܂ő����^�Ȃ��Ǝ�ɓ���Ȃ��B����Ȋ����ŁA�ł̓\�[���[���C�g�p�̃j�J�h�͂ǂ̒��x���\���ǂ��̂��A�^�~���̃j�J�h�Ɣ�ׁA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�͗ǂ��̂��H�ȂǁA���������Ă��炢����������ł���B �@���݂܂���B����Ԃ���点������āB (������]) �l
|
||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�~�j�l��Łu���[�X�ɏ��������I�v�Ƃ����p�r�����ɂ̓K�[�f�����C�g�p�j�J�h�d�r�͂��܂�ǂ����̂͂���܂����B �@�t�Ɂu���߂��ă��[���`�F���W�ŃR�[�X�A�E�g���Ă��܂�����A�X�s�[�h�𗎂Ƃ��ׂ��K�[�f�����C�g�p�j�J�h�Ɍ������悤�I�v�Ȃ�ėp�r�Ɏg�p����邭�炢�ł��B �@����A���[�X�̌���ł͂��̂悤�ɃR�[�X�E�}�V���ɂ��킹�āu�œK��(��)�v�d�r�𑽐������Ă���̂����[�T�[�ɂƂ��Ă͕K���i��������܂��B �@�Ȃɂ��냉�W�R���̂悤�ɍ����\�o�b�e���[�ł��X���b�g������ł�����葖�点���镨�ł͂Ȃ��A�X�s�[�h���߂̓o�b�e���[�̐��\��[�d�E���d��Œ��߂��邵�������~�j�l��ł�����ˁB �@���K���s�ʼn��x�����x���g���ɂ͈����K�[�f�����C�g�p�j�J�h�Ŏg���ׂ��Ă��ǂ��悤�ɁB�������I�Ƃ������[�X�{�Ԃł͍����^�~��1000���g�����ł��ǂ��Ǝv���܂��B �@�����A���K���s�ł͂����Ƒ����Ă����̂ɁA�^�~��1000��ςƂ���ɃX�s�[�h�I�[�o�[�Ő������ł��܂��ė��I�I�Ȃ�Ď����悭����b�Ȃ̂ŁA�ł�����[�X�{�ԂƓ����R���f�B�V�����̓d�r�ŗ��K���s�E�Z�b�e�B���O���������ł���ˁB �@�����j�J�h�d�r���~�����I�Ƃ������ɂ́A�H�������{���ɏo�Ă��Ă��炤�K�v�͂���܂����A���N������̃Z�[���i��DLG�̃j�J�h(700mAh)���S�{180�~�I�Ƃ��������Ő�Γd���Ŕ����Ă��܂��B(���ʌ���A������ƁI���i) �@�S�{����v���X�`�b�N�̃P�[�X�t���ŁA�v���P�[�X��100�~�V���b�v�i�������ƍl����ƃj�J�h�d�r���S�{80�~�I(��) �@���傻����̃z�[���Z���^�[�̃K�[�f�����C�g�p�d�r���͂邩�Ɉ����ŃP�[�X�t���Ƃ��������Ԃ�ł��i�O�O�G ���Ԏ� 2009/1/24
|
||||||||||||
| ���e 4/27 |
�@����o���A��ɏH�t�Ɋ��܂������A��Γd���ŁA���X�ɂ���܂����P�O�J�h�j�J�d�rDLG�F�V����Ƃ������Ă���B�P�[�X�t���S�{��\�Q�Q�O�Ŕ̔����ł����B �i�H���łR�[�q����IC �g�s�V�V�T�O�`�@���̂��ł̏Փ������ł������B�B �@�A���Ă��猟��������R�D�RV�̂V�V�R�RA���~�����ƋC�Â�������̍Ղ�j �g���� �l
|
||||||||||||
|
(C) �u�C�̖����v�^Kansai-Event.com
�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������
| �N�`�R�~��� (�Ƃ��A�����ꌾ�Ƃ��c) |
|---|
�@�ق��A�d�r�Ɋւ��鉽���ꌾ��A���R�[�i�[�ɑ��邲�ӌ������z�Ȃǂ���܂�����ꌾ�ǂ����I
�ߋ����O
| �ڗ� �l | 2009/10/30 |
�Z�p�͂ł͒�]������̂ŁA����قǐS�z�͂��Ă��Ȃ��ł��ˁB
�܂��Aeneloop�̍��Y���ێ����Ă����A�����Ƃ��Ă�OK���ƁB
�ꕔ�̐l�́A�O�m����FDK�̕������S�ł���̂���Ȃ����ȁH(���)
�������l����ƁA�G�l���[�v1500�͎O�m���f���Ŏn�܂�AFDK���f���ւƕς��悤�ł��ˁB
�܂��R���N�V�����������邶��Ȃ����c�corz
���������A�t�W�͎O�mOEM�ŏ[�d�r���o���Ă܂�����ˁB(HR�g)
�������Y�Z��������������܂����ǁB(�P4��typ.900�N���X�Ŋm�F)
�����A�ǂ������������ȕ��d�}���^�̃K���^�o���Ă���Ȃ����Ȃ��c
�ʏ�T�C�Y��1000mAh���炢�܂Ō����Ă��\��Ȃ�����c�i���s��1400mAh�N���X�j
�����Ɍ����̃}�V���������c
| (������]) �l | 2009/10/29 |
http://jp.sanyo.com/news/2009/10/
28-1.pdf
http://www.fdk.co.jp/kessan-j/
fdk091028b.pdf
| �ʂ肷���� �l | 2009/10/28 |
�@eneloop�͏I�����܂����B���肪�Ƃ��������܂���www
http://osaka.yomiuri.co.jp/eco/
news/20091028-OYO8T00485.htm
| �ڗ� �l | 2009/10/2 |
���ɗL�p�ȃf�[�^�����肪�Ƃ��������܂��B
200mA���x�Ȃ�A�C�V���̌g�уQ�[���@���x�Ȃ炻��Ȃ�Ɏg�������ł��ˁB
���͕s���ɂȂ��ʂ����X���肻���ł����A�P�x�△���ȂǕ��ׂ������Ȃ���ً}�p�Ƃ��Ďg����͈�
���͂̋��e�d���H�ɂ����܂����A14500�^�̃��`�E���C�I���{�_�~�[�d�r���ƁA�Ȃ�Ƃ���������500mA�\�����m��܂���ˁB
➑̂����A�P�[�X���������d�ɕ������Ȃ�Ƃ�����ACR-V3(RCR-V3)�d�l�ɂ��Ă��������Ȃ��c�Ƃ��v�����肵�Ă��܂��B
�����O��Ȃ�A�j�b��3�{�d�l�ɂ���̂���ԗǂ���������܂���ˁB
�u�c���̂��̂Ƃ��Ă��A�p�[�c�Ƃ��Ă����Ȃ薣�͓I�Ȃ̂ł����c�c
�ߏ�Ō��Ȃ��̂Ō����_�ł͂ǂ����悤���Ȃ��ł�(��)
���Ƃ��Ƃ��V��̏o���̂��x�߂̏��Ȃ̂ŁA���i������Ȃ�ɑ����Ă����Ȃ�A����������ɂȂ肻���ł��c
| jr7cwk �l | 2009/10/1 |
�@�悤�₭�����𑪒肵�Ă݂܂����B
�@NiMH�d�r2�{���Ƒ�d�������̂̓L�c�������B
�@�ڍׂ͉��L�A�h���X���Q�Ɖ������B
http://samidare.jp/jr7cwk/
lavo.php?p=log&lid=151751
�ۂ肷������ �l
�@�f�[�^�V�[�g�͂��̒ʂ�ł��B(���̃T�C�g�ł̓f�[�^�V�[�g���̂��̃Y�o���̃A�h���X�͓���Ă��܂���B)
| �ۂ肷������ �l | 2009/9/30 |
�@����Ƃ��Ă��C�ɂȂ�܂����B�Ȃ�Ƃ��Q�b�g�������Ǝv������ł��B
�@�Ƃ��ɁA�u8530�v�̃f�[�^�V�[�g�ł����Ahttp://www.belling.com.cn/
upload/BL8530_en.pdf�ł��傤���H
| �������ւ� �l | 2009/9/17 |
�@�ȑO��57�~�ł������E�E
�@�ق�100�ς̔��z�Ƃ����킯�ł��B
�@���̂��̂Ƃ����Ɣ�r�������Ƃ͂���܂��A���ɖ��Ȃ������d�����Ŏg���Ă��܂��B�t�R��Ƃ�������܂���B
�@�������A���Ƒ卷�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�g���̂ėp�Ƃ��āA�����߂ł��B
| �g���C�A���A���J�������̋L�� |
| jr7cwk �l | 2009/9/17 |
�@�����������ƒ��ׂĂ݂܂����B���L�A�h���X���Q�Ɖ������B
http://samidare.jp/jr7cwk/
lavo.php?p=log&lid=151751
�@�����̒����͂܂��ł��B
| �K���ł����܂��� �l | 2009/9/13 |
PS�F�C�I���̃X�[�p�[�̓��W������ł����̂ŁA�킴�킴�W���X�R�̓d�C����܂ōs���Ă݂�ƁA88�~�̓d�r�������������ő����ꖜ�p�b�N�ȏ�͒�Ă��ċv���Ԃ�ɃY�S�����̂����܂����B
�����
| �K���ł����܂��� �l | 2009/9/10 |
| sail �l | 2009/9/7 |
�@�ߋ��L���̃��X�Ƃ������Ƃŋ��k�ł���WF-139�������ɂ��Ăł��B���̏������Ă���̂̓��C�Z���XNo.20072012353.2�ƕ\�L����Ă���A����ł��ċ��^�Ɠ���LED��������܂��B�v���e�N�g�t��UF18650���[�d�������o�ł͓����͋��^�Ƃ���F�Ȃ��Ǝv���܂��B���ꂪ�ߓn���̐��i�Ȃ̂��A����Ƃ������i���ʃ��[�g�����b�g���{���ɈႤ�̂��A����ł͔��ʂł��܂���B�{���ɍw�����ď[�d���A���g���m�F���Ȃ��ƂȂ�Ƃ������Ȃ��Ƃ�����Ԃ��Ǝv���܂��B
�@�ȏ�A�Ƃ肠�����͂��܂ŁB
| �ʂ肷���� �l | 2009/9/6 |
�@�ǂ����A�P1����O�O�U�o�܂ł��ׂč��Y�i�������ł����A���āA����J�ł��邪�A���\�͂ǂ��Ȃ낤���H�Ƌ^�₪�킭�̂��m���Șb�A�����g���C�ɂȂ��Ă���̂Ō����˂������܂��B
| �ЂႭ���� �l | 2009/8/27 |
| ���܁[��i�f�l�j �l | 2009/8/26 |
�@��قǂ̏��̒����ƕߑ��ł��B
�@NiMH�i�P�Ox2�j�t��USB�[�d��̉��i��360�~�ł����B�[�d�������Ă�LED�͏������Ȃ��^�C�v�̂悤�ł��BNiMH�̗e�ʂ�1300mAh�ł��B�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̓Z���A��VOLCANO2�{�{�[�d��Ɠ������炢�ł����ˁH
| �ʂ肷���� �l | 2009/8/24 |
�@���Ⴟ�ȓd�r�{�b�N�X�̍�肪��������D�D�D[URL]
�@\1,600�Ŕ������̂ɁE�E�E�D
| �ڗ� �l | 2009/8/24 |
��������ƁA�O�͉�����̏����o�Ă��܂����ˁc(;^_^A
�ǂ�����g�ѓd�b�p(����)�̃u�c�ƈႢ�A�c�u�V�̂����^�C�v�̂悤�ł��ˁB
��H�������V���v�������ł��ˁB
�f�ނƂ��Ă��ʔ������ł���ˁB
| jr7cwk �l | 2009/8/23 |
�@�l�b�g�Ō������Ă݂���ʐ^�t���ŏЉ��Ă��鏊������A����ƊO�ς̃C���[�W�͒͂߂܂����B(�������ɓ��e�̉�͌��ʂ܂ł͌�������܂���B)
�@�^�Ԃ́uEP-024CHA�v�̂悤�ł��B
�@���̌^�ԂŌ�������Ǝʐ^�t���ŏЉ��Ă���T�C�g���ꔭ�ň���������܂����B
�@���E�E�E�������t�I�N�ɏo�i����ׂ�������Ƃ����̂�����悤�ł��B�E�E�E�J�n��200�~�Ƃ��E�E�E
�@�������l������R���r�j�Ŕ����Ă���z�������ق���������E�E�E
| �ڗ� �l | 2009/8/21 |
�����[�����e�ł��ˁB
�G�R�v���X���i�Ƃ������ƂŁA�ߏ�̃Z���A�ł���舵���\�������肻���Ȃ̂ŁA���҂������Ƃ���ł��ˁB
���͂���mA�ʂ���̂�����������܂��ˁB
�܂��A�C�V���̌g�уQ�[���@�ɏ[���Ȃ��炢�Ȃ���Ȃ��Ƃ������ƂŁc(���)
���Ƃ́A�s�̂̌g�ѓd�b�����̃u�c�̂悤�ɁA�P�[�u����I�ԃ^�C�v�łȂ����Ƃ��F�肽���ł��ˁB
�@��GND���V�[���h�ɗ��Ƃ��Ă��Ȃ��ƁA���삵�Ȃ���ł���ˁc
�܂��A�G�R�v���X�̃u�c���Ƃ������ƂŁA���̂�����͂��܂�S�z���Ȃ��ł��ǂ������ł����c
�Ȃɂ͂Ƃ�����A100�~(105�~)�Ŕ�����̂͊������ł��ˁB
�ߏ�Ō��������甃�������낤�Ǝv���܂��B
�ܘ_�A1���������Ď蔲���P�[�u�����Q�Ń`�F�b�N���]�݂̃^�C�v�Ȃ甃����� �̃R�[�X�ł����B
| �O�͉� �l | 2009/8/19 |
| �ڗ� �l | 2009/8/19 |
�P4��6�{����ƁA�P3��8�{����ł��B
�G�{���^���ł͊����Ȑݒ�ł����A�G�l���[�v�Ɣ�ׂ�Ɣ����ȂƂ���ł��ˁB
�@����⍂�������ǁA�e�ʖʁi�P���E�v�j�ōl����Ɓc���Ċ����B
�P4��6�{�Ƃ����̂́ALED�܂���3�{�g�p���������炩�ȁc�Ƃ��v���܂����c�c
�p�i�̏[�d��ł�3�`4�{�[�d���o���Ȃ������͂��Ȃ̂ŁA�������ȑ��݂ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB
�܂��A�O�m������قǑ����Ȃ��A�u�}���v�͈̔͂ł�SONY��BCG-34HR�V���[�Y���炢���ȁH
���d�r���[�J�[�n�͈̔͂ŁB�Ë������My Charger View�����邯��
�������낻��A������Ə[�d������ǂ��ė~�����ł���ˁB���ɎO�m�ƃp�i�B
���ƁA���X��(���d�@�X)�ŃG�R�v���C�h���m�F�B
�P3��4�{�p�b�N�ƁA�P3�Ə[�d��̃Z�b�g�i�����ł������ǁB
�P4���������Ȃ������̂ŁA�w����������܂����B
| �������K���[�W�X��iJH3DBO�j �l | 2009/8/19 |
http://blog.zaq.ne.jp/igarage/
article/1692/
�@�T�C�N���G�i�W�[�̂ق����ǂ����ʂ��o�܂����B
| �Ȃ����� �l | 2009/8/10 |
| engel �l | 2009/8/10 |
| �K���ōl���܂����I �l | 2009/8/7 |
[URL]
| V36 �l | 2009/7/8 |
�@SoShine��SC-S1�Ƃ����̂��Ă݂悤�Ǝv���܂����A�]���������m�ł����狳���Ă��������B
| �邤�� �l | 2009/7/8 |
�@���āA����G�R�v���C�h�iECO PRIDE�j�Ƃ����[�d��t�d�r���������܂����B
�@�܂��A�f�ڂ���Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ł�����������E�E�E�Ǝv���o�Z�����Ă��������܂����B
�@���̏��i�ʔ̂ł͌������邱�Ƃ��ł��܂����A��Ќ���HP�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��p�ՁH�ȏ��i�ł��B�ł��A���M���͍ڂ��Ă����肵�܂��B
�@�܂��Attp://www.rinso-do.jp/info/pdf/news.pdf�Ȃ���̂������܂����B
�@�܂��A���f�����܂�
| ���Y �l | 2009/6/19 |
�@�����O�A�O�m2700���������Ƃ���A�ȑO�������Ă������̂Ƃ̑���_���A����ꂽ�̂ŁA���e�����Ă��������܂��B
�@��̓I�ɂ́ATyp.2700 Min.2500�̕\�����AMin.2500�̕\���݂̂ɂȂ������ƁA�O���t�B�����̐F�����A��ύX����Ă��܂��B
�@���Ȃ݂ɁA�������A�O�m2700�̃��b�g�́A09-02�ŁA��r�ɗp�������b�g�́A08-12�ł����B
�@���̘b�肪�A���ɏo�Ă��鎖�ł�����A�����ւ�\�������܂���B
| �g���� �l | 2009/6/5 |
�@���̕��i���B�͂ɂ������������ł��B
| �����D�X�y�V���� �l | 2009/6/5 |
�@�Ǘ�����ׂɁA�ʂɔԍ������Ă����Ƃ���A�Â������A�u1.2V 1300mAh�v�̕����̑傫�����A�傫�����ɋC�t���܂����B
�@������ύX�����̂��A�킩��܂��AVOLCANO�����ӂ�Ă��āA�Ǘ��������l�́A���Q�l�ɂȂ邩���B
�@����Ȃ��̂ŁA�Ԉ���Ă��邩������܂��B(�L�E�ցE)��
| �O�͉� �l | 2009/6/5 |
http://www.gaikokukaden.co.jp/
shoplist.html
�@�[�d�r�͋�����̃T�C�N���G�i�W�[(2300mAh��HR�̍���t)�ł����A�[�d��̓��t���b�V���@�\�ƌʏ[�d�Ή��A���s���i�ł��̂ł����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
| �ڗ� �l | 2009/5/20 |
�@�I�[���Ƃ������Ƃ���ADIY�X��Ɠd�ʔ̓X�ł��������₷���Ȃ邩�Ǝv���܂��B
�@�I�[��������������A�ǂ���OEM���C�ɂȂ�܂��ˁB
�@���،n�̉\�������ɍ������ǁc
�@�l�I�ɂ�Pisen��YoTuYo�����肶��Ȃ����ȁH�Ǝv���Ă܂��B
�@�܂��A�ߏ�Ō��������甃���\��ł����c�i����4�{�ÂƁA�����̔����̗\��j
�@���ɋC�ɂȂ����̂��A�G�R�v���C�hUSB�[�d��Z�b�g BT-JUUSB �ł��ˁB
�@�o�b�e���[�J�E�{�[�C�Ǝ��Ă�Ƃ��낪����܂��ˁB
�@�c���ADX��
Soshine 4-AAA USB Emergency Power Two-Way Charger with Flashlight
�Ƃ��Ĕ����Ă��郂�m�Ɠ�������ł��B
�@������ߏ�Ō���������~�����Ƃ���ł����ADX�Ŕ��������ǂ����ƓV���ɂ��������ł��B
| jr7cwk �l | 2009/5/6 |
�@USB�o�͌^��105�~�R���o�[�^���n���œ���\�ɂȂ�A���낢��g�������ł��B
�@�����_�̒������ʂ����̃T�C�g�ɒu���Ă܂��̂ŁA���Q�l�ɉ������B
| jr7cwk �l | 2009/4/28 |
�@�Z�u���C���u���Ŕ�����肿����ƈ��߂̉��i�ݒ�(�g������^�C�v��590�~�C�d�r�����^�C�v��890�~)��������Ƃ��ꂵ���ł��B
(���������ăZ�u���C���u���̔������u�Z�u���v���~�A���v�p�b�P�[�W�ύX�łɂȂ�̂��ȁH)
�@����ɂ��Ă����̎�̏[�d���[�d�P�[�u���A���낻��PDC�p�̐��Y�}���Ȃ��ƁA��ʂ̍ɂ��c�肻���ȋC������̂ł����B
(�_�C�\�[�̓X���ɂ����ʂ�PDC�p�[�d�P�[�u�������Ă����C�ɂȂ��Ă��܂��B)
| �g���� �l | 2009/4/28 |
| jr7cwk �l | 2009/4/26 |
�@�d�r����EVOLTA�ł͂���܂��A�[�d��͂悤�₭�F����ɒǂ����܂���(��)
�@BQ-390�ł͂�����Ă��܂��莝����2300mAh��NiMH�d�r������̂ł����A����ŏ[�d�ł���̂��E�E�E
(����Ȃ��ƁA�܂��H���̒�d���^�C�}�[���ɖ߂��Ă��܂��E�E�E)
�@�P�l�̏[�d���Ԃ�BQ-390���Z���̂�������Ɗ��ҁB
�@�Ȃ��ABQ-391�̃��b�g��1107�C�d�r��0709�ł����B
| worksmoon �l | 2009/4/25 |
�@�[�d��ƃZ�b�g�̂��̔����Ă��āA�P3�~2�{�Ə[�d��̃Z�b�g��1050�~�ł����B�[�d��͎���525�~�̂悤�ł��ˁB�[�d��͒P3�������͒P4����2�{�[�d����^�C�v�B����������������made in china.
�@�����A�[�d���Ԃ��P3�A�P4�ɂ�����炸12���ԂƂ���A�R���Z���g�v���O���܂肽���ݎ��ł͂Ȃ��S�̓I�ɍ��̓Z���A��100�~�[�d��̂ق����������肵�Ă��ĂȂ����v���O�̕��A������Ȃ��̂ł͂Ƃ�����ۂł��B
| �w�Ǘ��l�x | 2009/4/20 |
�@�Z���A�ȊO��100�~�V���b�v�ł�������悤�ɂȂ����悤�ł��ˁB
| worksmoon �l | 2009/4/17 |
http://ascii.jp/elem/000/000/409/
409120/
�@�C�̖�������̂Ƃ��ʼnߋ��ɂ�����e�X�g�Ƃ���|�����Ă܂����A���̓��W�L���̂��܂̂Ƃ���̌��ʂ������[���ł��ˁB�L�����̂͂܂������݂����ŁA������Ɗy���݂ł��B
| �Ɍ� �l | 2009/4/17 |
�@2�{�Z�b�g�́�525���i�ŁA�P3��1600mAh�ŒP4��800mAh�B
�@����o���ł����A�O���t�B�����̓I�����W�Ɣ����₾�����Ǝv���܂��B
�@�[�d��͌�������܂���ł����B
�@����Ƃ����炢����ŁA�ǂ�ȏ[�d��Ȃ̂��A���X�����Ȃ���������������Ă܂��c�c
| �R�� �l | 2009/3/21 |
�@���Y�N���́A��������̂ł���
�@�����I�ɂ́A�������Ɉ��œ���Ȃ��Ă������ł�蒼���@�\�t���B�ƗL�����̂ʼn��Ă��Ȃ��̂��ȁH�Ƃ��v���Ă��܂����B
�@���������̊������ƁA����BQ-391�́A��͂�̏���ۂ��ł��ˁB
�@����`�ʖڂȌ̂������Ă��܂��܂����B
�@�C���ɏo���悤�ɂ��܂��B
�@���肪�Ƃ��������܂����B
| �R�� �l | 2009/3/20 |
Sail �l
�@�F�l�̃R�����g���Ȃ�Q�l�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B
�@���ہA���ȊO�̐l���[�d���BQ-391��䂵�������Ă��Ȃ��ꍇ�A���̂悤�Ȍ��ۂ��������ꍇ�ɁA�ŏI�I�ɏ[�d���������Ă���̂ŁA���̌��ۂ͐���ƂȂ邩������܂���ˁB
�@������BQ-391�̃��b�g�́A0708�ł����i�[�d��̗��̌@�荞�݂��ȁH�j�����́A�p�i�Ƃ̃Z�b�g���i�ŗp�i�́A0806�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�����Ԃ�Â����̂ŁA�p�i���̂����߂Ă̏[�d�������̂Ŏ���Ă���i�قڕ��d����Ă���j��Ԃ������Ǝv���܂��B
�@������VOLCANO NZ�Ɋւ��ẮA�Z���A�ł̏��i�̓���ւ��͑����̂Ŕ�r�I�V�������̂Ǝv���܂����A�e�ʂ̖�肩�[�d�푤�ł͎���Ă���Ƃ̔��f��������܂���
�@�Ƃ肠�����䂪�Ƃł́A�[�d�d�r�̎g�p�����d���@�����Ȃ̂ŁA���̏[�d�͂Q�T�Ԍギ�炢�ɂȂ�Ǝv���܂����A�Ƃ肠�������̂܂g�p���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B
|
�@����͏[�d��͌�-�N�ł����A�d�r�̂ق��͔N-���ł�����Â��͂���܂���B �@�S������0708��0806�̑g�ݍ��킹��K-KJQ91M34C�Z�b�g�������Ă��܂����A�d�r�͂܂���x���g�킸�ɕۊǂ��Ă��č��v���Ă�1.2V��̓d��������ߕ��d�͂��Ă��܂���BBQ-391�ɓ���Ă���ԃ`�F�b�N�����̓_��(���b)���[�d���̒x���_�łƐ���ɏ[�d���J�n����܂������AVOLCANO�����܂ŐV�i�����Ȃ�g�p����������x���G���[�Œe�������Ƃ͂���܂���B �@�����������d�r�̓`�F�b�N���LED���������āA���̂܂ܕ��u���Ă��ēx�`�F�b�N�̓_�ł��n�܂邱�Ƃ͂���܂���B |
| Sail �l | 2009/3/19 |
| Sail �l | 2009/3/19 |
�@�킽���̏ꍇ�ł��Ǝ����AAA Ni-MH�̂Ƃ��Ɏ����悤�Ȋ����ł����B�_�łƏ����̌J��Ԃ����N����A���̂܂ܕ��u�ŏ[�d�����B���Ԃ͓d�r�̎����ɂ��Ǝv���܂��B�������A����Ă��Ȃ��d�r�͂������ʂɏ[�d�ł��܂��B�����Evolta�AEneloop�A���Ő��̂����l�B���Ȃ݂ɂ킽����BQ-391�̃��b�g�͓��Ƃ�1208�ł��B
| Thief �l | 2009/3/19 |
�@�F�X����Ni-MH�̑S�Ăł����Ȃ�܂��B
�@���݂ɗ����ɂ��鍏���
0808
1007
1107
| �R�� �l | 2009/3/17 |
�@���̂܂ܕ��u�����ꍇ�A�[�d����Ă���l�q�͂���܂����H
�@�Ƃ̎���ł����A���LED�����b�_�Ł������̌J��Ԃ��ƂȂ��Ă��܂��A�܂Ƃ��ɏ[�d���邱�Ƃ��o���Ȃ���ԂƋL�ڂ��܂������A���������x�i�ыʎ���ɂāj�������g�p��BQ-391�ɂď[�d���n�߂��Ƃ���A�܂�LED�����b�_�Ł������̌J��Ԃ��ł����B�p�i���[�d���n�߂���ALED�����b�_�Ł������̌J��Ԃ��ł����̂ŁA���́A�p�i�i�P�R�j���[�d���n�߂���ALED�����b�_�Ł������̌J��Ԃ��������̂ŁA����ς肱��́A�̏Ⴕ�Ă���Ǝv���܂������Q�`�R���ԕ��u������A�[�d�����ƂȂ�܂����B
�@���̌�VOLCANO NZ�i�P�R�j���A���������ĂƎv���[�d���n�߂���A������܂�LED�����b�_�Ł������̌J��Ԃ��ł������A�Q�`�R���Ԍ�ɏ[�d�������܂����B
�@����������BQ-391���Ă���Ȃ��́H
�@VOLCANO NZ��BQ-391�ɂď[�d���Ă���Ƃ̏������݂����܂����A�F��������̂悤�ɂȂ��Ă���̂��H�Ǝv���܂����B
| jr7cwk �l | 2009/3/16 |
�@���_�͖��Ȃ��悤�ł��B
�@3/11�̎��̏������݁A���ʓI�ɂ͌��ƂȂ��Ă��܂��\����܂���B
(���炭�g���ĂȂ������d�r�E�E�E���L�d�r1�E�E�E�Ȃ̂ŗe�ʖ����Ǝv������2�{��1�{�����\�c���Ă����悤�ł��B������Ԃ̊m�F�~�X�ł��B)
�@�����Ɏg�p�����d�r�͉��L3��ށB
�d�r1�F���Ł@Super HYDRIDE TH-3A
�d�r2�Fmaxcell HR-AA
�d�r3�FPowerBase�E�E�E(�m���Z���A�ōw���BVOLCANO������O�B)
�[�d���Ԃ�2�{�[�d��1���ԑO��Ƃ������Ƃ���ł��傤���B
�@���i�W�߂Ă������̂̐��삵�ĂȂ������u�C�̖����v�����d����}篐��삵�A����������d������BQ-390�ɂď[�d�A�����d��ŏ[�d��Ԃ��m�F�Ƃ����`�ōs���܂����B
(���d���̓d������܂ł͍s���Ă��܂���B)
�@�R���l�A
>LED�����b�_�Ł������̌J��Ԃ�
�Ƃ̎��ł����A���̂܂ܕ��u�����ꍇ�A�[�d����Ă���l�q�͂���܂����H
�@���̂ق���BQ-390�ł̃e�X�g�ł��̂āA���ꂪ���̂܂ܓ��Ă͂܂�Ȃ������m��܂��E�E�E
| �R�� �l | 2009/3/13 |
�@�䂪�Ƃɂ́A�d���𑪂�@�킪�����̂łȂ�Ƃ������܂��A�G���[���o��VOLCANO NZ�́A�p�\�R���̃}�E�X�Ŏg�p���̕��ŁA��Q�T�Ԃقǎg�p�������߁A�������낻��[�d���悤�Ǝv���[�d���܂����B
�@�}�E�X�ɂ͒P�O�Q�{���g�p���Ă���A�Q�{������BQ-391�ɂď[�d���悤�Ƃ��܂������ALED�����b�_�Ł������̌J��Ԃ��ƂȂ��Ă��܂��A�܂Ƃ��ɏ[�d���邱�Ƃ��o���Ȃ���ԂɂȂ�܂����B
�@�d�r�̏[�d�O�̏�Ԃ́A�����܂�����قǕ��d����Ă����Ԃł͖����Ǝv���܂��B�i�������炢�c���Ă��邩���H�j
�@�g�p���̓d�r�́A�[�d�́A�܂�10������Ă��܂���
�@����������ƁA����BQ-391�͌̏�Ȃ̂�������܂����
| jr7cwk �l | 2009/3/13 |
�@�O��̏������݂̒���������܂��B
�P�j�K���d�r�Ƃ��čڂ��Ă��钆�ŒP�O�ōł��e�ʂ����Ȃ�1700mAh�̓d�r�́AHHR-3EPS�ł͂Ȃ��AHHR-3GPS�ł����B
�Q�j�G���[�ɂȂ�
�@�u�G���[�v�Ə����܂������A����ȕ\��������͂����Ȃ��A�ŏ��̔���(��5���H)�o�ߌ�u���[�d�v�\��(LED�_��)�ƂȂ�܂��B
�{��
�@BQ-390�̏[�d�d��(�[�d���Ԃ��炷���391�������H)�ł����A�������Ƃ�����́u�ʏ[�d�\���������v�̋L�����炷��ƁA�d����2.2A�ŁA1�A2�{����duty50%(����1.1A),3�A4�{����duty25%(����0.55A)�ƂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂����A�����l�����1300mA�̓d�r�ł͏����I
�Ɍ������̂����m��܂���B
�@�Ȃ��s�m���ȏ��ł͐\����܂���̂ŁA�莝����1300mAh�d�r�e��ł��������������ēx���܂��B
| Thief �l | 2009/3/12 |
�@���A���ɃG���[���N���������͖����ł��˃F�B
�@�R�䂠��BQ-391�S�Ă����v�ł��B
�@��Ŏv�����̂��w�ɒ[�ɕ��d����VOLCANO�����x�Ƃ������ł��B
�@�P�`�`�̓d���������d���Ƃ��Ȃ炠�蓾�����ł��B
�@�Ⴕ���́w����Ȃ��Ȃ��Ă���b�����u�x�Ƃ��c
�@�l�Ŕ��ʂ���ɂ́A����Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�G���[�ɂȂ钼�O�̉���d���Ȃǂ�����Ηǂ��̂ł����c
| Sail �l | 2009/3/12 |
�@�R���l�̋��Ă���Volcano�̌��ł����A���Y�d�r�����L���Ă��Ȃ��̂łȂ�Ƃ��\���グ���܂���B�e�ʂ̏��Ȃ��d�r�ŃG���[�ɂȂ�Ƃ̂��b������܂����A�e�N�m�R�A�ňُ픭�M������Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA����͐����ɉ߂��܂��Ђ���Ƃ���ƌ��o���x���W����̂���?
| jr7cwk �l | 2009/3/11 |
�@�������_�E�����[�h���Ċm�F���Ă݂܂������A�K���d�r�Ƃ��čڂ��Ă��钆�ŒP�O�ōł��e�ʂ����Ȃ�HHR-3EPS��1700mAh�B
�@1300mAh�̒P�ONiMH�d�r�́u��Ή��v�����m��܂���B
�@���Ȃ݂Ɏ���BQ-390�ł����A(VOLCANO�ł͂���܂���)1300mAh�̒P�ONiMH�̓G���[�ɂȂ�܂��B
�@�Ȃ��P�l��VOLCANO�͖��Ȃ��[�d�o���Ă܂��B
| wagamiyoni �l | 2009/3/10 |
�e�N�m�R�A�ł͒P3VOLCANO���[�d����̂ɂ�1000���`�ȏヂ�[�h���ƈُ���M���Ă��Ă��܂��̂ŁA1000���`�ȉ��ݒ�ŏ[�d���Ă܂��B���̓d�r�Ə����������Ⴄ��ł��傤���H
�@���̑��ł͂g�q����̃L���m��2300���`�P3�i���ȕ��d���������^�C�v�ł��j���e�N�m�R�A�ł͂Ƃ�ł��Ȃ��M���ɂȂ�̂ła�p-321�ł̂�т�[�d���������Ă��܂��B
�@�e�N�m�R�A�̏[�d�Ή��\���X�V����Ȃ��Ȃ��ċv�����̂��炢���ł��B
| �R�� �l | 2009/3/9 |
�@�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�@�Q�l�ɂȂ�܂��B
�@�����ł����AVOLCANO NZ��BQ-391�ɂď[�d�����悤�Ƃ��܂����Ƃ���ALED�����b�_�Ł������̌J��Ԃ��ƂȂ��Ă��܂��A�܂Ƃ��ɏ[�d���邱�Ƃ��o���Ȃ����Ƃ�����܂��B
�@VOLCANO NZ��1300��A�ƒႢ���߂Ȃ̂��H����قǓd�����Ⴍ�Ȃ��Ă��Ȃ������̂��́A�悭�킩��܂��A���̌�A�[�d���ύX
�@NC-MDR02�ł͏[�d�ł���Ƃ������Ƃ��A�ŋ߂���܂����B
�@BQ-391�̐f�f�@�\�������\�߂���̂��H�悭�킩��Ȃ������ł��B
| �O�͉� �l | 2009/3/8 |
�@�p�i�P3�~2�{�p�b�N��390�Ƃ��A�[�d��(BQ-324)�p�i�P3�~2�{�t����990���R�R�I�ɂ��������ł��傤���B�g�їp�[�d��������i�����z�ɂȂ��Ă��܂����B
| Sail �l | 2009/3/7 |
| Sail �l | 2009/3/7 |
�@BQ-391�ɂ��Ă͋C�̖����l�����Ɍy���R�����g�ŐG����Ă��܂����A�킽�����Â����Ő�Ni-MH�Ŏ������Ƃ���A���Ɋ|�����Ă����d�r�������ł��܂���(��N�ȏ���u�̓d�r)�B�A���A�d�r�̐ړ_��ړ_�����ܓ��ł悭�����A���x�����g���C����K�v������ꍇ������܂��B�܂��A�����܂Ŏ�����d�r�͍���͐��\���t���ɔ����ł���Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA�p�ɂɓd�����`�F�b�N���ėl�q���݂��ق����ǂ������ł��B
| �R�� �l | 2009/3/4 |
�@����łȂ̂ł����ABQ-391�̒��J�[�d�ɂ��ẮA�R�����g��������Ȃ��������߁A�����w������Ă��܂�����A���r���[�̂ق���낵�����肢���܂��B
�@����Ə[�d��̃��t���b�V���@�\������A�p�������[�d�݂̂̎g�p�ƂŁA�ǂꂭ�炢�d�r�ɍ����o��̂���m�肽���ł�
| �R�� �l | 2009/3/4 |
�@���������O����A�Z���A�Ŕ����Ă���VOLCANO NZ���p�\�R���̃��C�A���X�@�L�[�{�[�h�A�}�E�X���Ɏg�p���Ă��܂��B�[�d�������܂ł̓Z���A�Ŕ����Ă���100�~�̏[�d����g�p���Ă��܂������A�Ȃɂ���[�d�Ɏ��Ԃ������邽�߁A�T�|�[�g�ΏۊO�ɂȂ�܂����A�}���[�d����w�����悤�Ǝv���A���낢�뒲�ׂ�����BQ-391���w�����܂����B�i���t���b�V���@�\���ɂ��邩�����܂������ABQ-391�̒��J�[�d���A�]���������̂Łj
�@�������AVOLCANO NZ�̃������[���ʂ̂ق����C�ɂȂ�܂�
�@���ہA���S�ɓd�r�����d����Ă����Ԃŏ[�d�����Ă��Ȃ��̂ŁA���t���b�V���@�\���̏[�d����w�������ق����悢�̂��A�������Ă��܂�
�@�p�������[�d�������̂ŁA�[�d������d�r���̂�ς����ق��������̂��H�A����VOLCANO NZ���[�d�i�p�������j����ꍇ�A�[�d���N-MR58��BQ-391�ł͂ǂ���̂ق����A�����ł��傤���H�ǂ����Q�l�ɂ������̂ŃR�����g�̂ق���낵�����肢���܂��B
| TEC �l | 2009/3/1 |
|
�@�C�ɂȂ�܂���˂��B �@�����������ɂ́A����ȏ��ɏo�Ă���u�O�H�A���J���v�ƁuLAWSON �u�k �A���J���v�Ƃ̔�r�L���Ȃ��Q�l�ɂ����Ɨǂ��̂ł͂Ȃ��ł��悤���B |
| �����T�� �l | 2009/2/15 |
| Sail �l | 2009/2/11 |
| Thief �l | 2009/2/10 |
�@���̊��d�r�A���Ƃe�c�j�̐��i�ł��B
�@������������g���g�͂p�p���d�r�Ɠ����h�����m��܂���B
�@���ۂɌv�����Ă݂��画��̂ł��傤���A�p�p���d�r�������X���ɂȂ��̂Łc�i���j
�@�����������͌v���@��������Ă܂���corz
| (������]) �l | 2009/2/8 |
http://www.7premium.jp/products/
list.php?category_id=21
�@���̓d�r�̓p�i�ȂLjꗬ���[�J�[�̓d�r���݂̐��\�������A�X�[�p�[�Ȃǂ̃v���C�x�[�g�u�����h�A���J�����̒l�i�Ƃ���搂�����ł��B
�P��@2P�@���i:348�~�@4P�@528�~
�P��@2P�@���i:248�~�@4P�@428�~
�P�O�@4P�@���i:348�~�@8P�@580�~
�P�l�@4P�@���i:348�~�@8P�@580�~
�@�����ɂ���
(���/�p�r)�@�P�ʁF����
�P��/�|�[�^�u���X�e���I�@�Z�u���F18.1�A�p�i�F16.6�A�����}�N�Z���F17.0�A�g�b�v�o�����F15.5
�P��/�|�[�^�u���X�e���I�@�Z�u���F12.9�A�p�i�F11.5�A�����}�N�Z���F12.5�A�g�b�v�o�����F10.7
�P�O/�t���b�V���t���J�����@�Z�u���F1.5�A�p�i�F1.5�A�����}�N�Z���F1.4�A�g�b�v�o�����F1.4
�P�O/�ߋ�@�Z�u���F7.7�A�p�i�F6.7�A�����}�N�Z���F6.9�A�g�b�v�o�����F6.9
�P�l/�t���b�V���t���J�����@�Z�u���F1.2�A�p�i�F1.2�A�����}�N�Z���F0.9�A�g�b�v�o�����F1.1
�@�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�e���[�J�[�d�r�̏ڍׂȌ^�Ԃ͂킩��܂��A�摜���������p�i�͋��p�iLR6XJ�A�����}�N�Z���@�A���J�����d�r�u�_�C�i�~�b�N�v�A�g�b�v�o�����́y�g�b�v�o�����z �A���J�����d�r�݂����ł��B
| Thief �l | 2009/1/31 |
http://www.march-rabbit.jp/index.php
?main_page=product_info&cPath=
36_44&products_id=3004
�@�P��\350�ł����w�c�w�Ƃ��̊C�O�ʔ̂͌��x�Ƃ����l�ɂƂ��Ă͂��肪�����ł��ˁB
�@�������N�G�X�g�����͓̂����ł��i�j
| �n���V �l | 2009/1/24 |
�@�C��0�x����|5�x�͈̔͂�3���Ԃ��������Ȃ��i����6���Ԃ��炢�����̂�����A���������߂���ƃp�i�\�j�b�N�ɓd�b���܂������A���̉��x�ł͓�����O�Ŏg�������Ԉ���Ă�ƌ����܂����B���̂悤�Ȏ�舵���������Ȃ��̂ɁA6���Ԏ��ĂΕ���͂Ȃ��ł���3���Ԃ͍���Ƃ����Ă�����Ȃ��̂ł������Ԏ�������܂���B
| backup �l | 2009/1/24 |
�@�V���n��t�H�[�N���t�g���ʂɏ��L�����ƂȂ班�X�����Ă��y�C���܂��ˁB
�@���ʂ�����ł����ǁB
http://www.sotolab.jp/products.html
| (������]) �l | 2009/1/20 |
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008081900057&genre=B1&
area=K00(���s�V��)
http://www.gs-yuasa.com/jp/news/
subject2.asp?CODE=127��PDF
http://www.dealextreme.com/details.dx
/sku.19277
���A�T�̐V�^���w���ł���悤�ł��B���r���[�l�^�Ƃ��Ă������ł��傤���H
|
�@�������ꂽ���ɒ������Ă��܂��B �@�����ɍw���������̏��i�̓��ׂ��x��Ă���̂ł܂���������Ă��܂��c |
| jr7cwk �l | 2009/1/5 |
�@PDC�p�̊ۂ�(UFO�^�H)�̕��ł��傤���H
�@���XPDC�p�̏[�d��͗v��Ȃ��̂ł����A���x006P�̃X�i�b�v���K�v�������̂Ŕ����Ă��Ă݂܂������E�E�E
�@�d�r+�`��R(10��)�`�����p�HD�`�d�b�@��
�@��R��D�̐ڑ��_����5.6V(����)�̃c�F�i�_�C�I�[�h��-���ɐڑ�
�@�Ƃ������A�ȈՌ^�ł����B
�@�����ׂœd���Ȃ���������300mA�ȏ���I�����Ƃ������ɂ��e���Ȃ�����̂̂悤�ł��B
�@����Ƃ͕ʕ��ł��傤���H
�@���Ȃ݂�5�N�ȏ�O�ɊJ�X�����Â��H�X�ŁA�V�����X�ł͂��̎�̏[�d��͌������Ȃ��悤�ł��B
| �J�i�w�r��D���I �l | 2009/1/5 |
�@�����A���̃C�I���ɂ����Ă��܂����B
�@��������R�K�ɃZ���A���o���Ă��܂����B
�@������I�I�Ǝv���A��������volcanoNZ�P�O��20�{�߂�����܂����B
�@�����āA�g�������Ȃ��̂�6�{�����܂����B
�@���A�N�C�b�N�G�R�ŏ[�d���ł��B
�@�߂��̐l�͍s���Č����炢����������܂���B
| jr7cwk �l | 2009/1/5 |
�@�ꏊ�͎R�`�s�암�̃C�I���n�V���b�s���O�Z���^�[�B
�@�����̂��Ȃ��E�E�E
| Kin �l | 2009/1/4 |
�@�_�C�\�[��006P���g�p����g�я[�d�킪����܂����A���e����͂��Ē����܂��H
�@�V���Y���M�����[�^�[�H�炵��IC���ڂ��Ă��܂��B
|
�@�_�C�\�[��006P�g�p�̌g�я[�d��͌������Ƃ�����܂���B �@���������n�߂��甃���Ă݂܂��B |
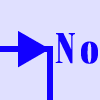
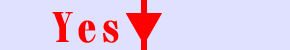
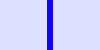

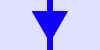
 �u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�
�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�