| ||||||||||
|
|
| ★★ 迷い箱 ★★の投書とお返事 |
電池・バッテリー・充電器
※ 記事ページに関する投稿は各記事ページに掲載しています ※
このページは「電池・充電器・ノウハウ (ログ)」セクションです
※ 投稿は「最近の投稿」ページからのみ受け付けています。
※ このページの話題(古い話題)へはレス・投稿しないでください。
※ 記事ページに関する投稿は各記事ページに掲載しています ※
このページは「電池・充電器・ノウハウ (ログ)」セクションです
|
※ このページの話題(古い話題)へはレス・投稿しないでください。
【一覧】
●最近の投稿 ページに掲載しています
|
■充電できない18650 ■容量ニッ水電池の早期劣化、原因は何なんでしょうね ■誰か、御願い致します ■複数の質問があります ■この記事を書いてる人は大丈夫かな? ■充電器を横にして使ってもいいですか? ■単三電池の良否を(測定器無しで)一発で見分ける方法 ■最近、こんな面白い充電器が出てました。 ■デジカメのDCカプラーにLi-ion充電池を繋いで動きますか? ■直列充電器で電池を個別に電圧をチェックする方法? ■車・ホッ〇イナズマ系商品は信用しますか? ■セリア USB Charger (その2) ■車の予備バッテリーは? ■電池がすく無くなる関数電卓 ■パナループのデザインが残念すぎる……orz ■雑談 |
|
●● バッテリー・機器を使用する ■パナかエネループか、急速・通常タイプか、どれがよいですか? ■エネループの使用回数はどこで1回? 使い方と寿命の関係は? ■「アルカリ電池専用/対応」と書かれた機器にエネループ? ■充電池使用禁止の玩具にエネループ ■エネループは乾電池の代わりに使用出来る? 出来ない? ■家庭でのリフレッシュ放電のしかたは? ■過放電についての質問です ■メモリー効果は可逆的なダメージでしょうか?過放電するくらいなら途中充電のほうが良いですか? ■過放電とはどのようにしたらなりますか? 直す方法はありますか? ■開放電圧何V程度で過放電? ■劣化すると自己放電も多くなりますか? ■ニッケル水素充電池の残量を調べる方法? ■バッテリーチェッカーの「充電池は使用出来ません」とは? ■Ni-MH電池を良好の状態で保管するために ■接点復活方法いろいろ ■充電エラーランプが点滅、急速充電は電池を痛める?(接点復活方法) ■充電池を並列にして保管すると電池残量は同じになる? ■リチウムイオン充電池の注意事項? ■リチウムイオン充電池の保管方法? ■リチウムイオン充電池の交換と保管 ■単三電池の容量は? ■充電電流、温度によって放電特性、充電容量は変化するのか ■電池をホルダーに入れたまま保管しても良いですか? ●● 充電する・充電器・互換性 ■エネループをパナのBQ-390で充電しても良いですか?(他社充電1) ■エネループをパナのBQ-390で充電しても良いですか?(他社充電2) ■エネループをパナのBQ-390で充電しても良いですか?(他社充電3) ■エネループを東芝THC-34-RHCで充電してもいいですか?(他社充電4) ■Cycle EnergyをFUJIFILMのDigi Chargeで充電しても良いですか?(他社充電5) ■充電中の電池の物凄い発熱 ■ニッケル水素充電池に対するトリクル充電 ■電気ドライバーの充電器に書いている「電流」の意味は? ■充電器の適合バッテリーについて ●● 機器のバッテリー交換 ■電動自転車のバッテリー交換 ■コードレス電話機の電池をニッケル水素と交換して大丈夫? ■コードレス電話機用の交換電池がNi-MHに変わっています ■シェーバーの中のニカド電池をニッケル水素電池と交換したい |
|
▽2012年の雑談・情報の過去ログ ■日本製が欲しい ■アンプにニッケル水素充電池を内蔵・充電する方法? ■なんでこんな使い方をするのでしょう? ■enelong superが出ました ■こんな使い方でいいのでしょうか?● ■100円ショップでLR44が4個入り ■電動歯ブラシの充電池を交換しました、大丈夫ですか?● ■いろいろ出るようです ■機器のニカド充電池をニッケル水素充電池と交換するのですが・・・ ■電動工具のバッテリーの比較を希望します ■新製品の改良版10000回再充電が可能な3000mAh高容量のリチウムイオン充電池 ■XTAR社製MP1充電器はどうですか?● ■今後の調査希望 ■エナジャイザーCH1HR-2でエネループは1時間充電できますか? ■スイッチをどちらに切り替えればいいですか?● ■ハブダイナモで昼間充電して夜ライトをつける回路 ■ニカド電池5本から安定した5Vでスマホを充電する回路図が見つかりません● ■モバイルブースター(系)のバリエーションが増えるようです ■放電器を作ってみました ■アルカリ乾電池充電回路がうまく動きません ■車のバッテリーから携帯などの充電用に三端子レギュレータでは何か問題がありますか? ■嫌だと言われている、鉛バッテリー・電動自転車の話をあえて投稿します!答えやがれ!● ■ニッケル水素電池をニッカド充電器で充電しても大丈夫? ■eneloopは長すぎで電池にキズが付きます● ■高いので安く済ませたい ■深夜電力利用のため、電動アシスト自転車用のLi-ionバッテリーを使いたい ■除雪機のバッテリーに充電できない ■docomo用でAU、又はその逆で充電しても問題は無い? ■IKEAのLADDAは?● ■このバッテリーはもうだめですか? ■パナのBQ-396という充電池で エボルタの単三充電池ならなんでも充電していいのでしょうか ■BQ-370改造しました ■Li-ionバッテリーをPnasonicの自転車充電器で充電したい ■ノートPCのボタン型ニッケル水素電池の交換について ■MW1268が故障し困っております ■エネループを1.7Vに昇圧するコンバータはありますか? |
|
▽2011年の雑談・情報の過去ログ ■ペンレコーダーの特殊な電池を交換したい ■バッテリー液を吸った物の処理業者はありますか? ■電池の取替えの時期ですか? ■電動アシスト自転車のバッテリーが充電できません ■電動アシスト自転車のバッテリーの中の基板は修理できますか? ■電動アシスト自転車の充電器は交流ですか、直流ですか?● ■似た性能で重さが1/2のバッテリーが欲しい ■電流が足りないのでDC/DCコンバータを並列で使いたい ■ワイヤレス充電器のつくりかた● ■カーステレオのバックアップ電源にはどれが省エネですか?● ■電池を3個以上奇数個使用を推奨てしいない理由?● ■コンビニで、USB充電器内蔵の単三電池が売られています● ■エネループ(単3,4)がパワーアップするとのこと ■バッテリーで動く溶接機の原理を教えて下さい ■アルカリ電池一本とマンガン電池二本ではどっちが電気の量が多い?● ■電動バイクにバッテリーとAC100Vインバータを積んで出先で充電する ■バラツキなくきっちりと個別に充電・放電する充電器● ■機能・求む。● ■マンガン電池、オキシライド電池、充電式電池は絶対に使用しないでください、と明記されています。なぜでしょうか?● ■Mag-LabのMMobile-5は電池が膨らむ● ■ドコモポケットチャージャー ■リチウムイオン充電池を、ニカド用充電器で充電していいですか? ■なぜリチウム電池だけ過放電した物には微弱充電するのでしょう? ■自作電動アシスト自転車にいいバッテリーは?● ■停電時 ソーラーになるリレーだけでいいのでしょうか?● ■充電式扇風機が熱くなります、大丈夫ですか?● ■リチウムイオンとリチウムポリマーの違い● ■販売してますか● ■海外用「変圧器」を通して充電する● ■電動自転車の為に、12Vバッテリーを24Vに昇圧する注意点 ■100Vなどの高い電圧のご質問にはお答えいたしません ■改造失敗しました、別の場所はどこですか? ■ソーラーバッテリーで携帯電話の充電器を作りたい● ■充電池を10本直列+2セット並列で使う ■油性ペン? ■パーフェクトチャージャーはどうですか? ■単2ニッケル充電池を10個同時充電を行いたい ■充電器の記事が最近無い● ■エネループは、どちらの方が近いものなのでしょうか?● ■ニッケル水素充電電池の重量について● ■ダイソーUSB充電器AU用使用時の必要電流・電圧はどれくらいでしょうか?● ■リチウムイオンとeneloopとどっちが有利ですか? ■UltraFireの3600mAhの18650を実験して下さい! ■天才!です● ■EOS-1D MarkIIの外部電源に鉛バッテリー ■廃バッテリーの廃棄・回収 ■送りますからこの充電器を評価してください! ■EVOLTAをCASIOのBC-K10NHで充電していいですか?● ■アルカリ乾電池の性能の比較実験を行ってください● ■三洋電機の乾電池はパナソニックになったらどうなるのでしょうか?● ■三洋電機の子会社化後に発売されたエボルタやサイクルエナジーのゴールド● ■ソニーのサイクルエナジーはエネループより高容量です! ■ダイソーの手動発電2LEDライトの改造 ■ケンコーのエネルグを調べてください● ■太陽電池と乾電池を切り替えてモーターを回す? ■USB充電BOXでLite系充電池は使用禁止? ■NC-TG1に個別LEDを付ける質問 ■WF-139の件● |
|
▽2010年の雑談・情報の過去ログ ■マッチモア、セルマスターレジェンドはどうですか?● ■BQ-CC05への個別充電LEDの付け方 ■昇圧した電池からは、流せるA数に決まった限界がある? ■がまんできません、すぐ答えてください! ■安物はやはり安物 ■リンク報告 ■セリアでニッケル水素電池を発見! ■ミニ四駆で勝つ方法 ■WF-188で3V電池の充電はできますか? ■単三2900mAhの電池● ■170mA消費する装置をソーラーチャージャーで補えますか? ■太陽光で電気二重層コンデンサにうまく充電できない ■セリア USB Charger ■携帯電話の電池の増幅 ■BATTERY ANALYZER ■たまにしか使わない鉛バッテリーが2年程度で使えなくなります ■ヤマハPASのバッテリ・・の話題、もう何件目?● ■単三エネループを手持ちのFUJIFILMの充電器で充電は可能ですか? ■本文を読んでも分かりません ■ACアダプター ■100円USB充電器で、iPhoneが充電できません ■おしえてください ■ソーラーガーデンライトの黒いセメント ■ニッケル水素充電池・単セル放電を・・・● ■がー!● ■定電流低電圧での充電であればダメなセル以外の充電が出来る?● ■エネループを1〜2日充電しても大丈夫ですか?● ■貴殿の記事を参考に何かやってみたくなりました ■掃除機の電池交換 ■太陽電池でヤマハのPASを走行充電 ■ACアダプターを変えてみた ■ORION EZチャージャーの情報はありませんか?● ■ニッケル水素充電池は「放射能電池」ですか? ■新電池を買ってきました ■UltraFireのLi-ion充電池で15A放電! ■充電できないニカド電池● ■Li-ion充電池の電圧が0Vです● ■マルハマのレーセンのバッテリー● ■自転車用LEDライトにリチウムポリマーバッテリー ■キムランタンQEC-F20の抵抗について ■5Vの電池はなぜ出来ない?● ■Li-ionを3本直列で充電する安くて良い方法 ■希望 ■電池2本の充電器と4本の充電器のどちらがいい? ■シールドバッテリーを2個、直列充電していいですか? ■100円で売ってるUSB充電器でどうでしょうか ■古いラジコン用の充電器● ■「注ぎ足し充電OK」と書いてある充電器● ■ニカド電池をハンダづけして使いたい ■1本だけ充電する充電器に2本重ねて充電できますか ■ノートパソコンのバッテリーの使用方法?● ■ヤマハ・パスの電池を交換したが動かない ■電池は冷蔵庫で冷やすと長持ち、暖めると復活する? ■GPの電池は変ったのか? ■アルカリに充電可能なのか、調査しませんか? ■Li-ione18650は単三電池と同じサイズ?● ■いろいろ ■GPからでているReCyko ■電池の種類と容量を教えてもらいたい● ■デュラセル ■オムロンの電動歯ブラシの電池は交換できますか? ■リチウムイオン充電池は回復しますか? ■電池はどうやって作られているんですか?● ■電池の使用時間が短くなった理由は? ■単三型と同じ形状のリチューム電池は有りますか?● |
|
▽2009年の雑談・情報の過去ログ ■オーム電機のエコプライド (2) ■オーム電機のエコプライド ■リポ電池に関する情報も、お願いします。 ■WF-138には色んな種類があるのでしょうか? ■TrustFireの新型TR-001? (2種類目) ■単一マンガンと単三アルカリはどちらが長く使えますか? ■魚群探知機で使用する充電池 ■ソーラーパネルの容量? ■USB充電ケーブルの違いによる充電容量 ■電池切れ携帯電話の充電がおかしい ■2本中1本がうまく充電されていない感じ ■対策済みのはずの三洋2700がすぐに死にました ■新型エネループ ■電池が熱くなり充電器をファンで冷やしています、大丈夫でしょうか? ■秋月電子の充電器キットを改造したら熱くなります ■電動工具の充電器を汎用の充電器として使ってみたい ■SONY液晶付急速充放電器で次世代DLG1300とかの海外製電池は充電できますか? ■Ni-MH 3.6V 240mAh用の充電器 ■チャイムにACアダプターを繋ぐ ■音波歯ブラシの電池交換 ■Ni-Cd AA400mAh 4.8V おもちゃ用電池が欲しい ■リチウム電池の汎用充電器は良品? ■3.0VタイプのRCR123Aを充電出来る充電器 ■MH-C9000とYZ-114SPはどちらがいいですか? ■ソーラーパネルの「直列接続禁止」? ■モーターの電流制限抵抗 ■デジカメの外部電源 ■ipod nanoに充電する電池式USBアダプタの作り方? ■OLIGHT T25 Regularで使用する電池 ■アモルファス太陽電池は電気抵抗? ■サイバーショットの単四電池のかわりに使える電池は? ■YUASAのニッケル水素電池 ■MHR-R7344はNC-MR58と同じですか? ■エネループの「満充電係数」「充放電損失係数」は? ■TrustFireの新型TR-001? ■ニッケル水素電池の外装チューブ ■電動工具のサーマルプロテクター ■デジトラ(2SC3402)はデジトラでは無い? ■ニカド電池をモーターが回らなくなるまで放電していいですか? ■UltraFireのWF-139チウムイオン電池用急速充電器を買いました ■電動自転車のバッテリーの中身を交換したらエラーが出ます ■電動自転車のバッテリーを他社充電器でリフレッシュしたい ■車で、サブバッテリーをDC/ACコンバータ・充電器経由で充電 ■デジカメのLi-ionバッテリーをエネループにしたら動きません ■(R)が灰色のエネループ ■NEXcellのNC-60FCで充電した後にBQ-330で充電する? ■単三電池を直列で放電した時の問題 ■電動自転車の電池を交換しました ■直列と並列の両方を混ぜて使う ■角型9Vの直結は可能か ■東芝のimpulse ■CGL3032のかわりにCR3032は代用できますか? ■ホンダのインサイトのバッテリー交換 ■コードレスドリルの交換バッテリー入手不能 ■一回で使えなくなったLi-ion充電池 ■太陽電池とダイソーコンバーターでエネループが充電できません ■THC-34RKCでリフレッシュ ■ICレコーダーの電池相談 ■リチウムイオン電池のプロテクト回路の流用 ■ニッケル水素電池の買い替え時期、寿命 ■リチウムイオン電池もエネループ? ■電動ドリルのニカドバッテリー交換について ■UltraFire ICR123A(3.0V)をWF-139で2本直列充電!? ■タミヤニカド1000をニッケル水素用充電器で充電できる? ■自作バッテリーチェッカーの不良? ■電動自転車のNiMHの件 ■自動車バッテリー交換時のバックアップツール ■ソーラーライト用ニカド電池 |
|
▽2008年の雑談・情報の過去ログ ■100均のメーカー品電池 ■パナソニックのBQ-391について ■電動工具専用バッテリーの放電器 ■クリップコンタクト型充電器 ■ソーラーパネルで鉛バッテリーを並列充電? ■ソーラーパネルの逆流防止回路? ■小型のスポット溶接機製作 ■電池パックを単三乾電池で代用する場合の問題点について ■サイバーギガゼロワンの新型 ■電池にハンダづけ ■006Pニッケル充電式電池を、急速に充電できる回路はありませんか ■LiFePO4,リチウムフェライト電池について ■富士フィルムニッケル水素充電池2300、2500についても ■充電式エボルタ発表 ■FDKによりOEM供給されている電池の見分け方を探す ■電動自転車のニッケル水素電池を交換 ■LMC555で昇圧しても電圧が1.43Vしかありません ■デシカメに入れるとすぐに電池切れ表示が出る ■時計の消費電力が低いため電池をギリギリまで使える? ■車載のサブバッテリーを12V30Aのリレー経由で充電したい。 ■高出力12W型LEDライトと電池 ■単二型の充電池はありませんか? ■CR123A電池の代用充電池 ■トップバリュ充電池について ■太陽電池でビデオカメラのバッテリー充電? ■ユニバーサル急速充放電器 ■12V、0.5Aで充電出来る様にするには24Ωの抵抗で良いですか? ■エボルタはテストしないのですか? ■電池に関する雑談 ■キムラタン、エレクトロニクス事業からの撤退 ■携帯充電器ネタ2題 ■航空機用::根本的に「過放電」という事に対する認識がまるで異なる ■サイクルエナジーグリーン ■VOLCANO NZに消費期限? ■ソニーの充電器(BCG-34HRME)について ■「充電王」の解析? ■困っています ■昇圧回路が入ったライトは放電器に最適? ■液漏れ等の危険度の違いを調査して欲しい ■電池の死に方 ■PSP? ■意を決して海外通販で中華電池を買いました‥‥_| ̄|○ ■「気の迷い」の放電についての説明の矛盾点について ■MaxussのAAA/1250mAh、AA/3000mAhのニッケル水素充電池 ■インタープランのFAD-701なる放電器 ■秋月の100円で2枚!の充電器基板 ■激安電池の比較 ■セリア充電器を満充電キープ用に改造可能? ■電池業界 ■キャン☆ドゥの100円DCコンバータ ■Cyber Giga 01を買っちゃいました(笑) ■1.4Vの太陽電池3つを使って水素電池二本が充電できる回路 |
|
▽2007年の雑談・情報の過去ログ ■バイオレッタ ■サンヨーの急速充電器NC-MDR02 ■アルカリ電池の外装の原材料? ■1年半以上前のeneloop ■気になりませんか?(笑) ■BQ-390で単一電池(min2800mAh)を充電できますか? ■秋月の太陽電池で6V鉛バッテリーを充電 ■赤いLEDのBQ−390 ■「e-keep」業界初の単1から単4・9V、1000回使える充電池 ■東芝THC-34RKCと三洋NC-TG1の基板 ■サンヨーN−MR58Sを購入しましたが… ■伸びる電池!? ■ソニーのBCG-34HREはどうですか? ■充電器を純正品に買い換えます ■セリア1300mAhがお亡くなりになりました ■単4のNiMHの都市伝説? ■三洋15分急速充電電池 ■単三型の富士フィルムのリチウム電池 ■3AAAのライトにLi-ion充電池 ■USB CELL ■パソコン制御ニッケル水素充放電器の製作 ■フランスの充電池事情 ■電池プロPowerSmartの性能、ほか電池の実験ページのご紹介 ■100円ショップの充電器に放電機能 ■psp用の外部電源を作ろうと思ったのですがうまくいきません ■海外のeneloopタイプ電池 (その2) ■LEXEL e-keep の宣伝 ■SG-1000のシールドバッテリー ■デジカメで使えないアルカリ電池 ■ニッケル水素電池用急速放電器の製作 ■eneloopを入れると壊れる石油ポンプ? ■海外のeneloopタイプ電池 ■三洋2700は交換してもらえますか? ■充電池の高い、安いの基準は? ■インテレクトのバッテリーのテストをお願いします ■wiiリモコンの消費電流テストはまだですか? ■セリアの100円や激安ニッ水充電池の性能比較実験やってください ■低温時のバッテリー性能比較を是非御願い致します ■使いはじめと使い終わりの内部抵抗? ■エネループのOEM? ■CR123Aサイズ互換のリチウムイオン充電池があります |
|
Section. ●● バッテリー・機器を使用する |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パナかエネループか、急速・通常タイプか、どれがよいですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
初めまして。子供のゲーム用にと充電電池の比較でググリこちらにたどり着きました。安易にパナかエネループかと口コミ比較しようと思っておりましたらこちらのあまりのすごさに、驚きました。 上記の様にその2社に絞っておりますが、充電器が急速タイプにしようか通常タイプにしようかと迷っております。4本単3充電タイプを購入しようと思うのですが、急速・通常タイプでは上記2社製品一般(絞込みの参考にしたいので)でおすすめはどちらですか? のん09 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
急速か、通常か、どちらを選ぶかはほとんど「趣味」の問題になると思います。 通常タイプの充電器を選ぶ理由は「急速充電は電池の寿命を縮める“らしい”から」という方が多いと思います。 1000回充電できるエネルーフを“いたわって充電して”1000回使いたいから、と通常タイプの充電器を使われるのもそれは良いことだと思いますので、通常タイプの充電器NC-TG1とエネループのセット品(N-TG1S)が良く売れていますね。 但し充電には7時間かかりますので、予備の電池と交換できる本数の電池を予め購入しておくか、7時間充電にかかっても問題の無い方向けです。 子供のゲーム機で使用する場合、エネループ等のニッケル水素電池は「突然電気が無くなってしまう」ように電池切れになりますので、電池が切れてゲームが中断され、そこから充電に7時間もかかっても良いのかどうか、予備電池を用意して対処するのか、はたまた「ほら、電池が切れたから今日のゲームはおしまい!」と子供からゲームを取り上げる理由に親が活用するのか(笑)、など使用シーンを考えて充電時間が妥当かを検討しなければなりません。 エネループは継ぎ足し充電に強い電池ですから、電池切れになる前にある程度使ったところで充電してしまえばそう簡単には電池切れまで使う事も無く、低速の充電器でも一回の充電時間は短くて済みますのでそういう使い方で長い時間かかる標準充電のデメリットを回避するという方法もあります。 「急速充電では電池の寿命を縮める」という噂話が先行していますが、サンヨーの公式回答として急速充電器(三洋純正品)でも「エネループの充電回数に関する性能は悪くなることはない」とのことでした。 従来の2本タイプ急速充電器セット(N-MDR02S)が発売されていたことからも、三洋の販売姿勢としては急速充電でもエネループの性能を損なう事は無いようです。 更に昨年末に4本タイプ急速充電器セット(N-M58TGS)が発売され、三洋の『倍速充電』でもエネループの品質をそれほど損なわないであろうことがセット商品の展開から推測できます。 但しここで「損なわないだろう」としか書けないのは、どこにも絶対に性能を損なわないと三洋も表記していないこと、また急速充電末期の発熱等で多少は電池の性能が落ちる可能性は否定できない技術的な問題が残ることなど、完全に何も損なわずに急速充電しても低速と同じだとはどこにも保証はありません。 NC-M58やNC-MR58等の倍速対応の4本タイプ充電器では、1〜2本だけ充電する時には『倍速充電』か『急速充電』かを選べるようになっていますし、3〜4本同時の場合は自動的に『急速充電』になって倍速にはなりません。 エネループと三洋4本タイプ充電器という組み合わせとなると、充電器はNC-TG1/NC-M58/NC-MR58ということになりますが、私のエネループを使用しての経験ではNC-M58が家庭で使用するには良いと思います。 上で書いたように1〜4本の場合約3時間40分で急速充電できますし、お急ぎの時は2本までなら倍速で約1時間40分で充電できます。満充電キープ機能も付いてますから、前の晩に充電を始めて翌朝使用する際にも常に充電したてのフレッシュな状態で使用できます。(保存性が良いエネループにはあまり意味が無いかもしれませんが) パナソニックのHR−3MPS(通称パナループ/緑パナ)の場合も基本的な話しは三洋エネループと変わりありません。 充電器セット品は4本タイプだとBQ−390とのセットかBQ−396とのセットになります。 パナソニックの場合、基本的には標準充電器は現在はニッケル水素電池用には販売していませんので、パナソニック製品で4本タイプでは急速充電器しか選択肢はありません。 またBQ−390もBQ−396も1〜2本だけ充電をする場合は自動的に三洋で言う『倍速充電』になり、1〜2本での「急速充電」はできません。 パナソニックの場合も『倍速充電』だからといって大幅に電池の性能を悪化させることは無いと考えて良いとは思いますが、「気にする」タイプの方はパナソニックの充電器より三洋の充電器のほうが自分の意思で『倍速』と「急速」を選べるので良いと思います。 このような理由で現時点の販売品種の中では、はじめてエネループ/HR−3MPSを購入される方への私のお勧めは「エネループと4本タイプ急速充電器セット(N-M58TGS)」という感じになります。 入門者向けに難しい機能や説明を省いたシンプルなエネループと標準充電器セット品(N-TG1S)よりは多少おねだんも高くなりますが、何十回〜何百回の充電使用で乾電池を使い捨てるのと比べれば確実にトータルコストは安くなりますので、ちょっとだけ高いですが急速タイプを購入されてみてはいかがでしょうか。 ちなみに「1000回充電できる」というのは、JIS規格の試験方法での充電/放電を繰り返した場合の規定の性能を満たす回数で、一般家庭での使用方法、市販の充電器での充電では1000回も使用できないと思っておいてください。 消耗するのは電池のほうだけですので、1〜2年に一回程度新しい電池と買い換えるくらいの予算で考えても、充電式の電池はどれも安いものだと思います。 お返事 2007/1/11
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
先日は素早い解答ありがとうございました。お礼と報告をしたく書き込ませていただきます。 迷いましたが気持ちはサンヨーに傾きつつ近所の他社メーカー製ユーザーに聞いてみると完了のランプあったほうがいいとの意見を頂き、こちらのサイトでNC-MR58の存在を知っていたのでセット商品ではなくNC−MR58とエネループを購入することにしました。 こちらのサイトを見て100円SHOPの電池も有用であることや充電電池について大変参考になりました。100円SHOPの白色LED比較を参考に購入しようとSHOPに行くと昨日は見当たりませんでしたが、又行ってみようと思います。タッチライトの2分間ランプにも挑戦しようと思います。 色々とありがとうございました。今後も楽しみにしています。 のん 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エネループの使用回数はどこで1回? 使い方と寿命の関係は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
充電電池の放電特性等、気になっていたことなので、面白く読ませていただきました。ところで、エネループの使用回数は、約1000回となっています。継ぎ足し充電や、キープ充電をする場合は、1回としてカウントすべきなのでしょうか? それとも、ある一定の電圧(例えば1V)を切らないうちに再充電をすれば、電池の寿命には影響がないのでしょうか? 1000回という数字自体は、メーカーがある条件で試験をしたものだと思うので、ユーザーが使う時には当てにならないとは思っています。使い方と寿命の関係がわかるとよいのですが。 げんこ 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
げんこ様はじめまして 電池メーカーの言う充電「500回」や「1000回」は、JIS規格の『密閉型ニッケル・水素蓄電池』の規格であるJIS-C8708(2004)に基づく試験の結果そう表記されています。 JIS-C8708(2004)ではまず電池の形状や基本性能(容量など)を規定していて、次にその基本性能に見合ったサイクル充電特性・放電特性の試験項目が規定されていて、それら全てを満足する商品のみJIS規格に沿ったものとして販売することができます。 この中でサイクル充電特性は「定格容量の60%未満になるまで」「規定の放電試験をおこう」ことで何回充電して使用できるかを測定しています。そしてこの回数が「500回以上でなければならない」と規定されています。 エネループはこの試験で1000回以上の成績を出しているものと考えられます。 試験方法は下記の50サイクルを1単位として行い、
なんだかややこしい数字が並んでいますのでこの表を見ただけではピンとこないと思います。 1) 最初に0.1C充電(標準充電)で16時間充電します。これはJIS規格試験での電池の満容量充電方法です。 2) 次に放電(電池を使用する)と充電を48回繰り返します。 放電は0.25C(つまり規定容量を4時間で放電終了する電流)で放電して、それを2時間20分で中途半端に放電を止めます。(だいたい58%くらい使ったことになる) 充電は0.25Cで3時間10分急速充電します(放電したぶん+αくらい)。ここでは満充電検出などは行わずにタイマーでのみ充電を止めます。 3) 49回目の放電では1.0Vの終止電圧まで完全に放電させます。(次の50回目で容量測定を行うため) 4) 50回目では0.1C充電(標準充電)で16時間充電し、0.2Cで0.1Vまで放電(規定容量試験と同じ)することでこの時点での電池の充電容量能力を測定します。 こういう手順の試験を最低10回はクリアしないとJIS規格に準拠した日本の充電池としては出荷できないわけです。 この試験の中では1〜48サイクルでは0.25Cで2時間20分という中途半端な放電終了と0.25Cで3時間10分という急速充電を繰り返しています。 これは家庭での使用で毎回終止電圧まで放電するのではなく、「電池が弱ってきたかな?」と思ったくらいで継ぎ足し充電をする状態を1放電サイクルとして実験しているということです。 家庭用機器では1.0Vの終止電圧を検知して自動的にバッテリー切れで電源を切る機器もあれば、懐中電灯のように高度な電源管理はしていなくて間違って放っておいたら過放電させてしまうような機器もあります。 珠玉混在の家庭内での使用では、ちゃんと1.0Vで停止するまで使ってから充電する用途より、「弱ってきたかな〜」程度で再充電してフルパワーで使いたいという感じの使い方を主にJIS規格では考えているという感じですね。 もう1つ、ニッケル水素電池の特性として「放電深度」というのもが寿命にたいへん大きな関わりがあり、放電深度が深い(終止電圧近くまで放電する)より浅い(途中で継ぎ足し充電をする)ほうが対数的にサイクル寿命が延びるということです。 毎回ずっと1.0Vの終止電圧まで使用してから充電するよりも、使い切る前に早めに充電したほうが電池の寿命が延びるということですので、電圧管理をされているデジカメなどでも電池を完全に使い切る前に充電したほうが良いということですね。 またJIS C8708(2004)の試験ても48サイクルは「途中での継ぎ足し充電」を行っていますので、もし毎回1.0Vまで放電して使用していたら、放電深度の関係で規定の「500回」(60%)まで使用できない可能性が高いです。 エネループの「1000回くりかえし使用できる」というのもこのJIS C7808(2004)試験上での数字ですので、実際の家庭での使用では1000回以上繰り返し使用できる使い方もあれば、そうでない使い方もあるということですね。 アルカリ電池にはまた別のJIS規格があります。 いずれこういった電池の規格やそれにまつわる性能話などもまとめたページを作成したいと思います。 お返事 2006/8/7
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
早速のご回答ありがとうございました。 ニッケル水素電池では、放電深度が浅い方がサイクル寿命が延びるとのことですが、ニッカド程ではないにしろ、ニッケル水素電池でもメモリー効果があるのではないですか? こんな使い方(どの位で継ぎ足し充電)をするとメモリー効果が起きにくい等の条件はあるのでしょうか? げんこ 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
残念ながら『どの位で継ぎ足し充電をするとメモリー効果が起きにくい』というのは一概には言えません。 各メーカーの発表では最新のニッケル水素電池では中身の改良が進み「メモリー効果の心配は無く、継ぎ足し充電OK」とされています。(詳しいデータは公開されていませんが) これを信じるのであれば、よほど極端な使用方法で無い限り、どのような中途半端な状態での継ぎ足し充電でも目に見えて「使えねー!」と思うような惨いメモリー効果は現われないということです。 実際に今まで使ってきたニッケル水素電池では(1700mAhなどの古い物を除いて)使用途中の継ぎ足し充電を繰り返してもニカド電池のようにはっきりとしたメモリー効果での性能低下は感じられませんでした。(厳密にテストをしてデータを取ったわけではありませんが) しかし完全にメモリー効果が無くなったわけではなく、その影響が非常に少なくなったものと考えられますので、JIS C7808(2004)のような継ぎ足し充電での使用テストで、メモリー効果のような極端な劣化が現われないことをテストしているのではないでしょうか。48回の継ぎ足し充電を行っても実使用上の性能に著しい低下が無いことを試験しているわけです。(厳密にはメモリー効果の試験ではありませんが) またJISC7808(2004)では50回に2回連続で1.0Vまでの放電と続く0.1Cで15時間充電を行っていますので、これは市販の充電器での「リフレッシュ」に相当するものです。 このテストをクリアしている国内メーカーの電池ではメモリー効果が心配であれば「半分くらい使っての継ぎ足し充電でも約50回使用程度に1〜2回程度リフレッシュしてやれば規定の能力を維持できる」性能であるということも読み取れます。 とはいえ、メモリー効果が本当に0%になったという事ではありませんので、継ぎ足し充電ではメモリー効果の「心配」が消えたわけではありません。 メモリー効果の心配が皆無なら、メーカー製の充電器にリフレッシュ機能付きのものが発売されることは無いですよね。 メーカーが各電池毎に「何%の継ぎ足し充電では何回使用したらどれだけメモリー効果での悪影響が出る」といったデータは公開されていませんし、「何%使用した」という点でも出力電流が大きかったか小さかったかで電池の消耗度も変わってきます。 一概に『どの位で継ぎ足し充電をするとメモリー効果が起きにくい』ということを言葉で言い表すのは難しいと思います。 それと同時に「継ぎ足し充電OK」と宣伝している製品では、普通に使用している範囲では実用上ハッキリと気になるほどのメモリー効果での性能劣化は起きないということを各メーカーは自信を持っているのでしょう。 これはあくまで単なる推測ですが、メーカー内部では「×0%(仮)の性能低下をした時点でメモリー効果の影響が大だとする。しかし本製品はテスト上は×0%(仮)の半分程度しか性能が低下しないのでメモリー効果の影響は少ないと告知できるものである。しかし×0%未満でも性能低下するのは事実なのでそれを回復させるリフレッシュ機能付きの充電器は発売しておこう。」みたいな何か色々とややこしいことがあるのだと思いますが・・・ ニッケル水素電池のメモリー効果実験はいつかは行ってみたいと思っていますが、「充電→(中途半端な)放電」をデータを採りながら数十回連続で繰り返さなければなりませんので、とうてい手作業では無理です。(しかも仕事をしている昼間にも連続で実行するとなると…) PICマイコンで制御する「自動充電放電試験機(自動記録機能付き)」を作って試すしかないので、暇な時に設計して作る気は満々です(笑)。電池を4本同時にテストする装置となると、結構な予算もかかりそうなので今スグに作るというのは無理ですが。 お返事 2006/8/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「アルカリ電池専用/対応」と書かれた機器にエネループ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
eneloopを買うか悩んでいたところ、ここの記事を拝見させていただき、とても納得しました!! やっぱり、eneloopは信用できるんですね!! エアーマスクに使用するため、さっそくeneloop-R購入したいと思います!! (アルカリ電池対応と書いてあったので、あきらめていました。) 電気機器が普及している現在、電池は必需品ですね。そういういみで、とても興味深いです。 これからも、実験大変楽しみにしています! モトイ 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
本ページでは、マンガン・アルカリ乾電池の代わりにエネループやほかのニッケル水素充電池が使えるか?につていは電気特性上は「おおむね使える」という説明をしています。 しかし「信用できるか」と言われると「信用」ってなに?ということになってしまいます。 世の中の電池式の機器にはマンガン・アルカリ電池用に設計されていて、充電池を使用しても電圧や電流の適正範囲内でトラブル無く動作するもののほかに、充電池(eneloopも含む)ではトラブルを起こすものがあります。「動かない」のではなく「充電池では動きすぎる」のが問題になる機器です。 たとえば、モーターや電球のような発熱する部品を使った機器では、アルカリ電池などで(内部抵抗や電気の供給能力の関係で)使用中には早い段階から電圧が下がってゆくことを見込んで「アルカリ電池専用」としている機器もあり、そこにeneloopだけでは無く放電電圧が長時間一定で大きな電流に耐えられるニッケル水素充電池を使用した場合、メーカーが想定していた以上に熱をもって部品が焼けたりプラスチックが変形してしまう事故の可能性もじゅうぶんに考えられます。 ニッケル水素電池の中でもeneloopは維持電圧がわずかに高い電池ですので、発熱に関する危険性ではほかの充電池より危険性が高いと言え、これは「信用できるか」という判断基準では信用してはいけない方向の要因になるでしょう。 電気特性ではニッケル水素充電池は本ページで説明していますようにアルカリ電池やマンガン電池の置き換えに多くの場面でじゅうぶん対応できる電池ですが、モーター・フィラメント・ヒーター部品などを利用している機器ではじゅうぶんに安全性を確かめた上で使用するようにしてください。 特に「アルカリ電池専用」と書かれた機器では、充電池を使用した際に発熱・発火・ヤケドなどの事故・ケガをした場合も全て自己責任になるという事は頭に置いて利用しましょう。 発熱事故以外にも、機器の寿命を極端に縮める場合があります。 大光量の専用豆電球を使用した強力ライト、またモーター(コイル)を使用した機器では、電球やコイルの特性で動作開始時に突入電流と呼ばれる大電流が流れ、普通のアルカリ電池では大電流特性があまり良く無いのでトラブルは起きませんが、充電池や最近のデジカメ用の「パルス放電に強い」強力なアルカリ電池にすると大電流を流せるので突入電流が機器の想定を超えた大電流になり、電球やモーターの寿命を縮めたり短期間で壊れて(切れて)しまう原因になる場合があります。 但し「アルカリ電池専用」と書かれた意味が「マンガン電池ではパワー不足なので、ハイパワーで長時間使用できるアルカリ電池専用(推奨)の機器です。」という意味なのか、「充電池では発熱や突入電流で機器を壊す(寿命を縮める)恐れがあるので、アルカリ電池専用です。[充電池使用禁止]」という意味なのか。 説明書に書かれた注意書きをよく読んで、メーカーの指示に従ってください。 どちらの意味でもメーカーが「アルカリ電池専用」とわざわざ書いているのなら、充電池の使用はあくまで自己責任で! お返事 2007/5/26
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電池使用禁止の玩具にエネループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
室内用の小型ラジコンヘリコプター(CCP製造:ハニービー・ハイパータンデム)にエネループを使っていましたが、注意事項に充電式乾電池を使うなとありました。 ラジコン機体にはリチウムイオンポリマー電池が使われています。 5,6回エネループでヘリに充電しましたが加熱等異常は一切見られませんでした。使い捨てのアルカリ電池を必ず使用しないといけないのでしょうか? ヘリラジミニ 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
ハニービー・ハイパータンデムの取扱説明書[PDF]には「コントローラーに充電式電池は使用しないでください。ショート、火災の原因になります。」と書かれています。 その文面を鵜呑みにするなら、充電池を入れた場合はショートしたり火災が発生する(可能性がある)そうです。 もしそれで火災になってもメーカーには責任は無く(禁止を明示している)、注意書きを無視して充電池を使用した使用者の責任になるという注意書きです。 充電池使用禁止の機器に充電池を使用した場合の危険性や注意事項は『「アルカリ電池専用/対応」と書かれた機器にエネループ?』で説明していますのでお読みになられていると思います。 その上で充電池を使用するのは自己責任で、何が起きてもご自分の責任と納得された上でご使用になられるのは自由です。 ハニービー・ハイパータンデムではLi-ion充電池にコントローラーの乾電池から充電する回路が入っているようですが、説明書にうるさいくらい書かれている万が一の充電回路やバッテリーの故障の場合、Li-ion充電池は激しく炎を吹き出して燃えますのですぐに消火できないと最悪の場合は部屋もろとも家が燃えてしまいます。 この玩具の充電回路中の保護回路がどのような仕組みになっているのかは分解した事がありませんので具体的に知りようがありませんが、上記「アルカリ電池・・・」の項でも書きましたように事故が発生した場合の過電流での危険性はアルカリ電池よりニッケル水素充電池のほうがはるかに大きいので、メーカーはアルカリ電池で使用できる装置(オモチャ)であればアルカリ電池を推奨しているはずです。 今は問題無く使えていても、たとえば将来に本体に内蔵のLi-ion充電池が劣化してきて正しく充電できなくなった場合、異常が発生した時に少しの被害で済むのか、大きく破損・発火してたいへんな事になるのかの境目が「充電池を使用していたから」という理由になる可能性は考えられなくは無いので、そういう点まで考慮した上でメーカーが禁止している機器で充電池を使用するかどうかは考えたほうが良いでしょう。 機器の中には乾電池を8本使って12Vを必要とする物では、充電池の1.2Vを8本では電圧不足でうまく働かないという物も存在しますが、そのラジコンの送信機はアルカリ乾電池6本では無くニッケル水素充電池6本にしたからといって動作不良や送信出力(赤外線)の大幅な低下をするとは説明書には書かれていませんので、メーカーが危惧する危険性はやはり万が一のバッテリー事故の場合の危険度の高さでそう注意書きに記しているのでしょう。 電圧不足での誤作動が無ければ、ニッケル水素充電池を使用してもコントロールは出来ますし、本体への充電も行えます。説明書に書いていないだけで、ニッケル水素充電池使用では電圧不足で正しくLi-ion充電池に充電できていない・・・とかなら話は別ですが、お使いになられていてちゃんと充電が完了しているのであれば大丈夫でしょう。 本体への充電異常やコントロール不良の症状が見られないのであればそのままお使いになられてもあくまで自己責任を認識されてご利用になるのでしたら結構だと思います。 ただその状態を長いこと続けられるうちに危険性を忘れてしまって、その頃に本体のLi-ionバッテリーが劣化して発火事故を起こすなんて事にならないように、常に注意は忘れない事をお勧めします。 お返事 2008/9/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
とても参考になりました。アルカリ電池ではヘリに10回くらい充電したら乾電池は捨てないといけないらしいので、アルカリ電池の使用は気が進まなかったので質問させていただきました。 難しいことは分からないですが、今のところ全く機体の発熱も感じられず、充電もビンビンで5分の飛行時間とありますが12分くらい連続で飛行できてます。 ラジコンの異常に気をつけながら、充電中は離れずに万が一の発火に備え、濡れた雑巾を用意しておきます。自己責任でエネループで行ってみます。 本当にありがとうございました。 ヘリラジミニ 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
異常事態が起きるのは何万ぶんの一程度の確率だとは思いますが、メーカーが「膨らんだり、臭いがしたり、煙が出たりしたらすぐ充電をやめる」と説明書でわざわざ注意している程ですから、充電する間はなるべく近くに居て、そのような兆候が無いか目を離さないようにしましょう。 Li-ion充電池の不良で膨らんだり発火したりする事故は、アルカリ電池を使っていても結局は起きますので、メーカー指定通りアルカリ電池を使用している時でも不具合の兆候には注意しましょうね。 お返事 2008/9/16
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エネループは乾電池の代わりに使用出来る? 出来ない? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
エネループはコードレスマウスには使用出来ないのでしょうか? メーカーはロジクールです。 一般人 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
よほど特殊な機器以外では、エネループやほかのニッケル水素電池は乾電池の代わりに使用できます。 (ここで言う「使用できる」は、長期保存や過放電で電池を痛めるかは関係なく、充電した充電池を入れて「機器が動作するか」についてです。) 知人の例ですが、ロジクールのワイヤレスマウス(型番は失念)でも使えています。 「エネループを入れたら動作しなかった!使えない!」という話を耳にします。 以前に「ロジクールのワイヤレスマウスに入れたが動かなかった。」という噂話も耳にしました。 それはなぜなのでしょう? ワイヤレスマウスだけではなく、色々な機器で「エネループは使えない?」には電気的な原因と、電池のサイズ的な原因の2つが考えられます。 原因がわかれば、電気的にどうしても使えない物以外ではエネループは普通に乾電池の代わりに使えます。 順を追って考えてみましょう。 ● 電圧の面から見た乾電池との互換性 (1.2Vでは動作しない?) ※ 具体的な放電特性は、本サイトの
各種電池放電実験記事をあわせてご覧下さい。 よく「乾電池は1.5V、充電池は1.2Vなので乾電池用の機器には充電池は使えない!」と言われる場合があります。 本当でしょうか? 乾電池の1.5V、充電池の1.2Vは「定格電圧」と呼ばれる電圧で、電池の中の化学物質の性質から「電池一個で起こせる電圧値」のことを言います。 これは作りたてで未使用の乾電池、またはちゃんと充電した充電池が起こせる電圧で、使用して電気を消費すればだんだん下がってゆきます。 厳密に言えば、作りたての乾電池や充電したての充電池では0.1〜0.2V程度定格電圧より高い電圧が出ています。(普通に使うぶんにはあまり気にしないでも良いです) 「使えば電圧が下がってゆく」のは全ての電池が同じ状態になるのではなく、電池の種類によって性格が違っています。 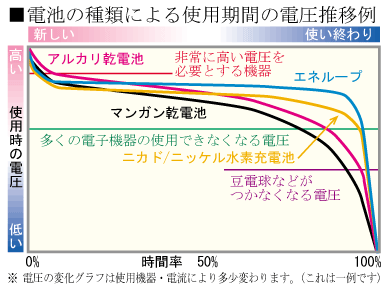 ※ 電池によって容量が違いますので、同じ機器でも使用時間は違います。
このグラフは使用時間は電池の使用開始から終了までの100%で表して 特性を比較するもので、各電池が同じ時間使えるという意味ではありません。 アルカリ乾電池、マンガン乾電池は確かに使用始めの電圧は約1.5Vありますが、少し使えばたちまち1.4…1.3…1.2Vと電圧が低下します。 その後もグラフのはじめから終わりまで徐々に電圧が下がり続け、中盤あたりでは充電池よりも電圧が下がってしまいます。 ニカド/ニッケル水素充電池(エネループも含む)は、使い始めは1.3〜1.4Vですが、少し使って1.2V前後に下がってからは使用期間中のほぼ大半をかけて非常にゆっくりと電圧が下がり、長期間同じくらいの電圧を維持し続けます。そして使い終わりが近づくと急に電圧が下がって充電した容量を使い果たします。 エネループは従来のニッケル水素電池よりも少し高い電圧を出し続けるように改良されていますので、グラフからも後半ではほかのどの電池より高い電圧を供給し続けられることがおわかりいただけると思います。 使用開始時は定格電圧の違いでマンガン/アルカリ電池のほうが電圧は高いですが、使ってゆくうちに放電特性(電池の性格)の違いにより「電圧の高い・低い」はニカド/ニッケル水素充電池と逆転してしまいます。 次に、グラフの中で「機器が使用できなくなる電圧」に注目してみましょう。 「多くの電子機器が使えなくなる電圧」は約1V前後の電圧で、この電圧まで電池の電圧が下がるまではマンガン/アルカリ乾電池もニカド/ニッケル水素充電(エネループ含む)も使い終わり近くの時間までじゅうぶんに長時間機器を使用できています。 デジカメや、電子回路の入った機器では中の電子回路が正常に働かなくなる前に電池の電圧を測って安全な電圧のうちに自動的に電源を切ったり、電池残量メーター表示で電池切れを知らせてくれますが、それがだいたいこの電圧です。 ”電源電圧の管理がされている”電子機器ではマンガン/アルカリ乾電池でもニカド/ニッケル水素充電池(エネループ含む)でもどちらでも問題無く使用できるはずです。(使用できる時間は電池の種類・容量によって異なりますが) 「豆電球がつかなくなる電圧」は電源管理がされていない機器の例で、懐中電灯やラジオ等の電源電圧に関係無く機器が非常に弱い動作状態になっても壊れたりしない機器で、電源を自動停止させないものの場合です。 こちらでもどの電池でもあまり変わらずにじゅうぶんに機器を使用できています。 但しニカド/ニッケル水素充電池は「終止電圧(約1.0V)」が決まっていて、終止電圧以下の電圧になるまで放電すると電池を痛めて性能が悪化しますので、このように自動停止しない機器での使用には注意が必要です。(このページの「過放電」に関する項目参照) 使用機器によっては本当に「1.5Vでは動作するが1.2Vでは動作しない」という機器も存在します。 しかしそれはあまりにも特殊な機器で、普通の家庭用機器やパソコン周辺機器ではまず見かけません。 そりかわり「かなり高い電圧でないと正常に動かない機器」という程度の物は少しだけ家庭用機器の中にもあるようで、もしそういう機器なら定格電圧が1.2Vの充電池は不利です。 グラフの中の「非常に高い電圧を必要とする機器」の線がそのような高電圧が必要な機器が動かなくなる電圧を表していますが、非常に高い電圧を必要とする機器でも乾電池の最初の1.5Vを「0.1Vでも下回ったら使用できなくなる」のではなく、少しは電圧が下がっても使用できるはすです。でないと「乾電池を入れて数分しか使えない」のでは全く実用的な機器ではないのですから。 そしてそのように高い電圧でないと動かない機器でも、「充電池では全く動かない」のではなく、充電したての満充電状態の充電池ではかなり乾電池に近い電圧がありますので、少しだけの時間なら動作させる事ができるはずです。 ここで注意して頂きたいのは、今まで書いてきた「電圧の違いがあっても同じように使える」という事は電池を1本使う場合や3〜4本程度直列で使う場合までの場合で、6本や8本以上直列で使用する場合は初期電圧の差が本数×0.2〜0.3Vとどんどん大きくなる為、多数の電池を使用する機器では1.2Vの充電池では動作しないものも少ない本数使用の機器よりは多くなる可能性があります。 もし電池1〜2本使用のワイヤレスマウスにエネループを入れて、少しだけ使ったらすぐに使えなくなるのでしたらこのような非常に高い電圧の間だけしか使えない、あまり良く無い機器だという可能性が考えられます。 満充電状態で、テスターやバッテリーチェッカーで計ってもじゅうぶんに電圧のあるエネループを入れても最初から全く動作しないのであれば別の原因が考えられます。 稀に、「個別表示ではない充電器」(エネループ専用のNC-TG1など)で充電して、どれか一本がちゃんと電池がソケットに差し込まれていなくて充電されず、それでも他の電池は正しくセットされて充電されたので充電完了ランプ(一個だけ)が点灯したので全部が充電できたと勘違いして「実は充電していない電池」を使おうとして「エネループでは動かない!」というふうに勘違いする方もいらっしゃるようです。 できれば個別表示機能のある充電器を使うのがベストですが、そこまでしなくても100円ショップの「バッテリーチェッカー」でもじゅうぶんに満充電されたか/充電失敗して電圧が低いかはテストできますので一個購入しておくと良いでしよう。 ● サイズの面から見た乾電池との互換性 (実は結構これが問題) エネループは従来のニカド/ニッケル水素充電池と違う問題点を抱えています。 それは「サイズが少し大きい」という事です。 電池のサイズは日本ではJIS規格で厳密に決められています。(世界でも規格があります) しかし「決められている」とは言ってもきっちり「このサイズで作りなさい」ではなく「このサイズ“以内で”作りなさい」という最大・最小のサイズに幅を持たせたもので、そのサイズの中では多少の大きさの違いは認められています。 従来の電池は「最大サイズより小さく、最小サイズよりは大きな、それなりに平均的なサイズ」で作られていましたが、エネループを作る際に容量を稼ぐ為にギリギリまで頑張ったのでしょう。ほぼ電池の大きさの最大限いっぱいのサイズで作られてしまいました。 その為に「平均的なサイズの電池では入るようにしていた」という機器ではエネループは大きすぎて入らない!という問題が各地・色々な機器で起こりました。 もちろん、電池のサイズ規格最大の物が作られて、それがちゃんと入るように電池ボックス側を設計するのが正しい機器メーカーの姿勢だとは思うのですが、それまでに発売されていた電池で機器の動作テストをしている時にちゃんと動けば良しとするような、きわめて適当な電池ボックスのサイズで機器を設計している所も多々あるのです。特に中華製品には・・・ (そのロジクールのマウスは Made in CHINA ではありませんか?) 電池が大きすぎて動かない・入らない例は海外ニッケル水素充電池の性能テストにも載せています。 最初から機器の電池ボックスに入らないのであれば、簡単に「入らないよ!」とわかるのですが、サイズ問題で最も陥りやすい動作不良に「逆挿し防止に引っかかる」があります。 機器に電池を逆向きに入れたら、中の回路には逆向きの電流が流れますのでICなどの+−の向きが決まっている(極性があると言います)電子部品が壊れてしまいます。 ※ 極性の無い豆電球などでは問題無いのですが・・・ そこで逆極性では壊れてしまうような機器では、「電子回路側に保護回路を入れる」「電池ボックスに逆挿入を防ぐ」の2つの保護方法のうちいずれか、または両方が取られています。 「電池ボックスに逆挿入を防ぐ」は電池の形状を利用したもので、電子部品を必要としない為に多くの機器で使用されている方法です。 具体的には「電池の+側は+電極が突起しているので、間違って逆向きで−側が来ても突起していないので接触しない」ようにするだけです。 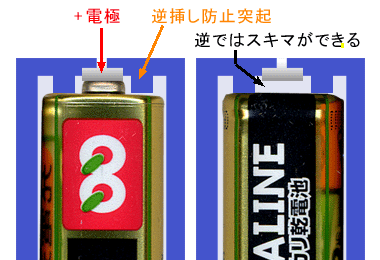 普通のニッケル水素電池でも同じで問題無く使用できますが、エネループはサイズがギリギリで製造されている為、全長は同じですがボディの肩が高くなっていて、結果的に+電極の突起高さが低くなっています。  ※ 突起の高さ(低い)によっては問題無く使用できる機器もあります。 今まで「エネループを入れたら全く動作しない。」という話の方の原因を調べたらほとんどがこの「肩の高さ問題」でした。 解決するには電池ボックス内の逆挿し防止突起をヤスリ等で削って高さを低くしてください。 (これも一応「改造」になりますので、メーカー保証は受けられなくなります。自己責任で!)  右のポータブル機器のように、電池ボックス内の+側が機器の中に隠れてしまっている機種では分解しないと逆挿し防止突起が削れないので加工がたいへんです。
右のポータブル機器のように、電池ボックス内の+側が機器の中に隠れてしまっている機種では分解しないと逆挿し防止突起が削れないので加工がたいへんです。エネループが使えない機器を買ってしまったと枕を涙で濡らしながら夜を迎えましょう。 朝になったら、別の充電池を買って使うのが幸せです。 ロジクールのワイヤレスマウスでもこのような接触しない問題が発生したと聞いていますが、正確なマウスの型番を聞いていないので確認の取りようが無いので、「ロジクールの特定の機種ではそういう事があったらしい」とあくまで噂程度の話と思ってください。 この「肩の高さ問題」は、リニューアルされた新型エネループでは多少改善されています。(単三型では確認、単四型は未確認ですが風の噂では単四も新型に変わったとか…) 詳細は新型eneloop、その名は「eneloop-R」ページに掲載しています。 お返事 2007/5/13
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭でのリフレッシュ放電のしかたは? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
エネループが250回で充電できなくなった記事を興味深く見させて頂きました。 私は去年9月に購入したデジイチK100Dで4本セットで使用しているのですが、先月から電池の持ちが1/3程度になってしまったのです。電池使用回数は100回、充電回数は50回程度です。 サンヨーにメールした所、『メモリー効果が発生しているか電池が不活性状態になっているので充放電を2〜3回繰り返してください』との返信がありました。 試しにK100Dで電池残量が0になった時の電圧を測定した所、4本とも1.2V程度でした。その電池を急速充電器NC-M58で充電した所、普段は3時間程度は掛かる充電が1時間で終了してしまうことに気がつきました。 記事を参考にして、リフレッシュで電池の性能を回復させて見たいのですが、どういう方法で何Vまで放電させれば良いのか教えてください。 今、考えているのは懐中電灯や毛玉取りで少しずつ放電させて、テスターで電圧をチェックして1Vになったら止めようと考えています。 ぬこ 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
デジカメ使用でeneloopの使用時間が短くなっているのですね。 いくつかの点にわけて説明したいので、少し長くなりますがご容赦ください。 ● なぜメモリー効果が起きるのか デジカメのように比較的大きな電流で使用し精密な回路を駆動する機器では、ニッケル水素充電池の終止電圧1本1.0Vまで使い切らずに残量0と表示するものもあり、たとえば1本1.1V程度の4本合計4.4Vで残量0とする機種もあります。(機種により色々あります) これはニッケル水素充電池が容量を全て使い切って空になる直前には急激に電圧が下がる傾向にあるので、撮影時(シャッターを押してからメモリーに記録が終るまで)の電子処理に電力を必要とする時に電池が急に切れてしまっては困るので、少し余裕を見た電圧がまだあるうちに電池警告を出して止まってしまうように設計されているからです。 その為ニッケル水素充電池を使用している場合には電池残量が0と表示されても完全に電池を使いきらずに継ぎ足し充電を繰り返す事になり、「メモリー効果」を生む原因になってしまいます。 もちろん電池残量0まで使わずに途中で継ぎ足し充電を繰り返してもメモリー効果は起きます。 ニッケル水素充電池はメモリー効果が非常に起きにくい電池とされていますが、完全に0になったわけでは無くやはりメモリー効果で性能が低下する場合があります。eneloopでも同じです。 お使いのデジカメがはたして何Vで電池残量を0としているのかは、デジカメから電池を取り出してテスターで電圧を測っても実は測定できません。 デジカメのようにまだ電池に余力がある時点で残量0と判断された場合は、電池はまだそこそこ元気ですから機器から取り外した(電源を切った)瞬間から電圧は回復して、実際に回路に電流を流していた時より高い電圧を示すようになります。 ですからテスターで電池の電圧を測っても1.2Vもありますが、デジカメは1.2Vで電池警告を出していたり残量0と表示しているわけではありません。 デジカメが本当に何Vで残量0と示しているのかは、デジカメを分解して中から配線を引き出すなどして実際に動作中の電圧を測定するしか無いのです。 これは、後の電池をリフレッシュの為に放電させる場合にも当てはまりますので覚えておくポイントです。 ● 不活性 デジカメに電池を入れたまましばらく使わずに放置する、または電池を取り出していても電池を使用せずに長期間いると「休眠」「不活性」という状態になり電池本来のパワーを発揮できなくなります。 「デジカメをしばらく使っていなくていざ使おうとしたら、電池残量警告が出て使えなかった、自己放電が酷い電池だ!」という声をたまに聞きますが、実は自己放電で電気が無くなってしまっているのではなく、不活性で電圧が出なくなっている場合があります。(うちではBPのAA2750が良くこうなります) 確かにデジカメが使えないのは同じなので悪い事なのですが、軽い不活性は少し使ってやると直ってまだ電池に入っている電気はじゅうぶん取り出せるようになります。電池警告が出ても自動電源OFFで切れない程度(または何度か電源を入れなおすうちに落ちなくなる)で、数枚〜十枚程度写真を撮るうちに電池警告が消えるようなら軽い不活性です。電池を使用する事で回復しましたのでそのまま使えます。 重度の不活性はやはりリフレッシュしてやらないと少し使う程度では回復しません。 普通の機器で使用する場合はこのような原因が複合的に働いて、充電池の状態を悪くしてしまう事があり、三洋の回答通りこのような一時的な状態不良から電池を回復させるのが「リフレッシュ」です。 ● リフレッシュするとどうなる? メモリー効果は、中途半端に継ぎ足し充電を繰り返すと電池の中で電気として使われなかった部分がずっと充電状態にあり、そのまま「固まってしまったように」化学物質がうまく働かなくなる事(*1)により容量の低下、内部抵抗の増大で大きな電流が流せなくなる(みかけ上電圧が低下する)などの不具合が起きるものと言われています。(完全には解明されていないそうです) 「不活性」はやはり長期間使用しない事で電池の中身全体が「固まってしまったように」うまく働けなくなる現象です。 *1 「固まる」はあくまで説明用の比喩で、実際は化学変化が起きています
人間でも同じ姿勢でずっと居ると身体が固まって凝ってしまいますよね。 この「固まってしまった」ものをマッサージでコリを揉み解すように柔らかくして、電池本来の性能に戻してやるのが「リフレッシュ」です。 数回電池の中身の全部を終止電圧まで放電してしまったり、満充電してやる事により電池全体を活発に動かしてやるとコリが解消されます。 身体全体を揉みほぐす「全身マッサージ」を行うようなものを想像してください。 1回で解消するのか、2〜3回リフレッシュしないと元に戻らないのかは電池の状態により違いますので、実際にリフレッシュしてみて試してください。 ● 家庭でのリフレッシュの方法 ではどうすればリフレッシュを行えるのでしょう。 自動的にリフレッシュ(放電→充電)を行ってくれる「リフレッシュ機能つき充電器」や私のページでも製作記事を掲載している「放電器」があれば、正しく電池の終止電圧で放電を終了して電池に「過放電」のダメージを与えないリフレッシュができるのですが、そういう機器を持っていない場合はやはり家庭によくある「懐中電灯」「電池式でモーターを回す物」(毛玉取り器はいいですね)を使用することになります。 懐中電灯(豆電球式)や毛玉取り器のような小型モーターの物で消費電流はだいたい250mA〜750mA程度です。(機器により異なります) これくらいの消費電流だと、満容量2000mAhのeneloopで約8時間〜2時間40分はライトを点灯またはモーターを回し続ける事ができます。 もろちんメモリー効果などで使用時間が1/3程度になっているのでしら、これら機器を駆動できる時間も1/3程度になっているでしよう。 (後で書きますが、放電を全部懐中電灯などで行うのはうまくないので、デジカメも併用します) 「時々テスターで電圧を計りながら、終わり時を見極める」との事ですが、この方法には大きな誤りがあります。 先にデジカメ使用の場合で説明しましたが、懐中電灯や毛玉取り器でも機器から電池を取り外してテスターで計るまでの間に、電池の電圧は回復して正確な機器使用時の電圧を測定することはできません。 やはり懐中電灯や毛玉取り器を分解して配線を出して、使用中の電圧をテスターで計りながら1Vになったら放電終了・・・とはなかなかできないでしょう。 そこで、あくまで「メモリー効果が出ている電池をリフレッシュさせる為」と割り切って次のようにしてください。 懐中電灯なら電球が暗くなるまで(完全に消える前)、毛玉取り器ならモーター音が弱って回転がかなり遅くなった時点で電池を取り出します。 すぐに電圧を測って、0.数V〜1.1Vの間であれば放電完了です。 放電中には少しだけ過放電になってしまうかもしれませんが短時間でしたら大きなダメージにはなりませんので、機器から外したときの「徐々に回復してゆく途中の、かなり放電中の電圧に近いもの」が1.1V以下なら放電中は終止電圧の1.0Vまでかそれ以下には下がっていただろうと判断します。 電球がうっすらとしか点灯していない、モーター音が弱く毛玉をカットする力は無いように思える、程度まで動作が弱ればじゅうぶん終止電圧かそれ以下程度まで放電しています。 もし灯りが消えたりモーターが止まった事に気付かなくても、少しだけなら大丈夫です。止まってから一晩中気付かない…とちょっと困りますが数分〜数十分なら過放電によるダメージも少ないので笑って済ませましょう。 放電が終れば充電器で満充電になるまで充電しましょう。 この時に充電完了までの時間を計れると良いですね。 (充電時間が長くても、使用時間は短いという劣化もあります)
そしてまた放電…を合計2〜3回繰り返せば、メモリー効果や不活性化はだいたい解消します。 リフレッシュの為の放電は最初(充電完了直後)から懐中電灯や毛玉取り器で行うと、電池のパワーが回復して長時間使用できるようになると何時間後に終るのかわからずに、知らないうちに終了していて過放電してしまうということになりかねませんので、放電はまずデジカメ等自動終了してくれる機器で電池残量0になるまで連続使用しましょう。 そしてデジカメではもう残量0で動作できないところまで残り少なくなってから、懐中電灯や毛玉取り器で人が見ていられる程度の短い時間最後まで放電するようにしましょう。 デジカメ使用→懐中電灯などでの放電は少しなら時間が空いても良く、絶対に時間的に連続して行うという必要はありません。 朝出かける前にデジカメをスライドショーモード(*2)にして残量0で自動的に電源OFFになるまで動作させておき、夜家に帰ってから残りの電気を懐中電灯で放電する、でも構いません。 *2 スライドショーでも時間で自動OFFになる場合は使えません。
「スライドショーだと消費電流が少ないのでリフレッシュ放電の 代わりになる」という説もありますが、デジカメによって異なり ますので全てのデジカメでという意味ではお勧めできません。 2〜3回リフレッシュしてみても使用可能時間があまり変わらないのであれば、メモリー効果などでは無く電池が劣化してしまっている可能性もあります。 またリフレッシュの際の2〜3回や、その後での使用でしばらくはデジカメで残量0になって電池を取り外した直後の各電池電圧を測って、どれか1本だけが痛んでいないか(特に電圧が低くないか)なども調べてみてください。「250回使ったエネループ」のようにどれか1本だけが劣化した場合でも機器使用中には急激に使用時間・充電時間が短くなる場合があります。 今回の方法では、テスターが無くても最悪は懐中電灯が消えるくらい暗くなるまで、毛玉取り器のモーターが止まる直前まで使用すればちょっと過放電にはなりますがリフレッシュ放電するという目的は達成できます。 ぬこ様は幸いテスターをお持ちですが一般家庭ではなかなかテスターが無いと思いますので、テスターが無い場合でもちょっと強引なリフレッシュ放電はできますので、もしメモリー効果っぽいとか、不活性っぽい症状でお困りの方は強引リフレッシュを行ってみてはいかがでしょうか。 ◇ ◇ ◇ 余談ですが、私の使っているコンパクト・デジカメ Fine Pix A800 にはメニューに「バッテリーリフレッシュモード」というのがあります。(他社でもあるのかな?) A800でも通常使用ではメモリー効果を起こす事をメーカー自身が認めているという事で、それの対処としてデジカメにリフレッシュ放電機能を内蔵してしまったという、ある意味スグレモノです(^^; 買ってから気付いて笑ってしまいましたよ。 お返事 2007/10/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
素早いお返事、どうも有難うございます。 早速、100円ショップで単3電池が4本入る懐中電灯を購入してきました。電球は4.8Vで0.5Aのクリプトン球です。 カメラの電池残量0の電池をセットし、2時間30分程度点灯させたら暗くなったので、テスターで電池を測定したところすべての電池が1.05Vまで放電完了しました。 その後、どの電池が劣化しているか特定し易いようにNC-M58で2本づつ倍速充電したところ、充電時間は取説の100分に近い90分程度でした。充電後の電池は4本とも1.53V程度になっていました。どれか1本が劣化しているという訳ではなかった感じです。 もう1回充放電を繰り返してカメラでの持ちを確認する予定です。 カメラで残量0にする方法が思いつかなかったのですが、スライドショーを利用する方法は素晴らしいアイデアですね。幸い、K100Dはオートパワーオフ機能をオフにする事が出来るのでこれで簡単に放電させる事が出来そうです。 リフレッシュの結果は、後日また報告したいと思います。 ぬこ 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
2時間も懐中電灯が点灯したという事はデジカメで残量0とされても電池にはまだタップリ電気が残っている、まさにメモリー効果で電圧が出ていなかったような症状ですね。 今回のリフレッシュ放電でしっかり放電して、充電時間を見ても正しく空まで放電している電池の容量ぶんを充電できたようですので、電池に充電できる容量自体はあまり減っていない(容量的には激しく劣化はしていない)ようです。 その調子だとあと一回くらい放電と充電を繰り返せば、普通に50回使用(充電)したくらいの少しだけ弱った状態に戻りそうです。 それなりに使用している電池ですので、リフレッシュしても新品同様とはゆかないかもしれませんが現状の1/3程度の時間しか使用できないかなり悪い状態からは脱出できると思います。 もし今回のリフレッシュで電池が元気に戻るようでしたら、K100Dで使用するなら充電10回に一度、または2ヶ月に一回程度の割合でリフレッシュしてやったほうが良さそうですね。 お返事 2007/10/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 過放電についての質問です | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
こんばんは 過放電についての質問です ニッケル水素電池の放電について教えてください。 例として、放電電流500mAで電圧が1Vになるまで放電したとします。 ここで放電電流を100mAにすれば、電池の放電電圧は、(電池が正常の場合)1V以上になりますよね(私の経験では)。 これ(1V以上をキープし電流を放電電流を下げて行く)繰り返すと、過放電になるのでしょうか。 要するに、ここまでは過放電でなく、ここからは過放電というような境目が、ニッケル水素電池には存在するのでしょうか? マツモト 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
過放電か過放電で無いかはニッケル水素充電池の終止電圧1.0Vを基準に考えてください。 というか、終止電圧を下回る程に放電する事を「過放電」と言いますので、ニッケル水素充電池では単セルの場合終止電圧は1.0Vと規定されていますから1.0Vより放電する状態を過放電と呼びます。 終止電圧は1.01Vならいくら使ってもセーフで、0.99Vなら突然電池が死んでしまうというものではありません。 電池内部の組成などから決められた「目安」であり、電子部品の最大定格と同じく「その値を越えてはいけないが、その値での連続使用を保証するものではない」という電気的な最大値の表現のひとつである事はご理解ください。 電流を制御して限りなく1.0Vに近い状態での放電を続けた場合過放電ではありませんが電池内部の化学物質の性質により、正極は還元されて減ってゆき、負極の水素吸蔵合金も腐食が進んで電解液の消費も早くなるとされています。 もちろん1.0Vを下回るとこの劣化反応がずっと急速に進むようになってそれを過放電と呼び、通常での使用に比べて短時間で電池の性能を低下させます。 終止電圧に近い状態をずっと続けることは正しく放電カットをして回復力により1.0Vより高い電圧に回復させてやる事で正極と負極の間に十分な電位差を置いて各極物質の劣化を抑制する使い方よりはずっと早く電池の劣化を進める事になります。 終止電圧近くでじわじわ放電する事は過放電とは呼びませんが電池の寿命を著しく短くする要因となりますので、ニッケル水素充電池は容量が減った状態・終止電圧近くでじわじわ長時間使うのではなく、じゅうぶん電圧のある状態で比較的大きな電流で使用して正しく終止電圧でカットオフ(開放)する、または終止電圧近くまで使用せずに継ぎ足し充電で放電深度の浅い状態で使用するのが好ましいです。(浅い使用ではメモリー効果はありますので時々リフレッシュが必要です) ニッケル水素充電池の放電カーブを見ればわかるように、電池電圧が1.0V近くまで下がるのはほぼ電池内の容量を使い果たしている状態です。その状態では電池内部の物質が電圧不足で劣化する状態になっていることがわかれば1.0V近くでの使用は電池に対して良いことか悪いことかが理解できるでしょう。 1.0Vを下回るのは赤信号。1.0V近くの低い電圧での使用は黄信号だと考えると良いでしょう。 お返事 2007/12/13
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
こんばんは 「過放電についての質問」に丁寧な解説ありがとうございます。 実は、1Vを下回らないような放電器を最近作ったのですが、いつまでもダラダラ放電して良いものか、心配になっていました。 (URL削除) 放電をカットする方法を考えるか、気をつけて電池を外すかすることにします。 マツモト 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
色々作られていますね、楽しそうです(^_^) お返事 2007/12/14
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 12/14 |
上記で紹介したURL間違ってました。 私作った放電器は、ここを参考(真似)にしました。http://mcalc.zapto.org/ 1V以下での切れが悪いようなので、調べなくてはなりません。 マツモト 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
メモリー効果は可逆的なダメージでしょうか? 過放電するくらいなら途中充電のほうが良いですか? |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
他の方の質問ですが、過放電について拝見しよくわかりました。 逆に、最後まで使い切らずに充電する使い方をするとメモリー効果で痛むと言われますが可逆的なダメージでしょうか? それとも序所にダメージが蓄積するのでしょうか?(たまにリフレッシュするとして) どこまで使ったら良いのか使い終わりの見極めが難しいです。 過放電するぐらいなら、ちょっと残った状態で止めた方が良い気はしますが。 kenta 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
同じような質問が過去に出ていますが、前には説明しきれていない部分もありますのでもう一度詳しく説明します。 確かに、過放電は不可逆的なダメージで電池の劣化は元には戻りません。 しかしメモリー効果と呼ばれているものの大半は一時的な性能劣化で、リフレッシュによって回復すると言われています。 メモリー効果の原因は電池の開発者・研究者の間でも「これ!」という1つの特定の原因は分っていません。 しかし色々な研究のうちに数種類の原因要素が考えられています。 そのうちの有力な1つが「充電物質の休眠化」です。 電池を充電・放電すると電池の中の化学物質が全部一斉に化学変化を起こすわけではなく、どちらかというと「端のほうから順番に」という感じになります。 従って、途中までの放電や充電を繰り返すと、端に近い部分の化学物質は化学変化を繰り返して常に充電されているか充電されていないかの状態に変化させられて活性化され安定します。 しかし途中までの充放電で化学変化をほとんど起こさない深い部分は、一定の状態(充電された状態)がずっと続くことになり、徐々に劣化してゆくということです。 劣化した化学物質は電気的な特性が悪くなりますので、そこが原因の内部抵抗の増加や電気を放出する能力の低下で見かけ上の電池電圧が下がったり容量に悪影響が出たるするのがメモリー効果の原因の大きな部分のようです。 さすがに私もニッケル水素電池を分解して試薬を垂らして反応を見るとか、
粒子がどれだけ劣化しているかを顕微鏡で見るようなテストはしていません。 この「充放電されなかった一部の化学物質の性能が落ちる」というのは、中途半端使用時のメモリー効果だけではなく、電池を長い間放置しておいたら放電しているだけでは無く充放電性能が一時的に落ちているといういわゆる「電池が寝ている」状態の原因にも通じる部分がありますね。 充電池をフルに使用しようと思ったら、中の化学物質を「寝かさない」ことです。 昔の電池では中身の「ニッケルカドミウム君」は非常にお寝坊さんで、少し放置するとすぐに寝てしまいました。 今の「ニッケル水素君」は優秀で、ちょっと放置したくらいでは眠ることが無く元気に働いてくれます。 ですので今の主流のニッケル水素電池では「継ぎ足し充電OK!」という中途半端使用をメーカーが認めた宣伝文句がついています。 しかし「寝グセ」が全く無くなったわけではなく、ニッケル水素電池でも、新タイプのエネループでも放置すると化学物質が一時的に劣化する事は完全になくなっていませんので、もし中途半端な使用を繰り返したのであれば適宜リフレッシュをしてやる必要があります。 これは私の各種電池の放電実験でも結果が出ています。 リフレッシュの必要があるはずなのに、なぜメーカーはリフレッシュ機能つき充電器とのセット品にしないのでしょう? 理由の1つは単純に「価格が高くなる」ので消費者に敬遠されるからですね(^^; そして2つ目はニッケル水素電池はリフレッシュしなくても昔のニカド電池のようにすぐに目に見えるようなメモリー効果が起きるような激しい劣化は起こさない電池だということです。実際に使用していて「メモリー効果が起きた!」と言っている人がほとんど居ないのがその証拠です。 そして3つ目の重要な理由。それはメーカーがニッケル水素電池の使用用途を「デジカメ等に!」と宣伝していること。 そうです。デジカメ等の「ちゃんと終止電圧まで放電してくれる機器で、電池切れサインまで使ってもらう使い方」であればメモリー効果は起きないじゃないですか(笑) 毎回最後まで使わなくて途中充電しても、10回に一回くらいは“うっかり”電池切れまで使ってくれれば、その一回でリフレッシュをしたのに近い状態になってくれるので、本当に何十回も途中充電を繰り返さない限りほとんどメモリー効果の劣化を体感できないほどの低劣化度なら実使用上では全く問題が無いと言ってもいいということなんです。 使う機器が変わって、メモリー効果に対して安全(?)な機器が多くなったということです。 もちろん懐中電灯のように自動OFF機能も電池残量メーターも付いていない原始的な機器も数多くあるのは確かですが。 では、そのような原始的な機器でニッケル水素電池を使用する際にはどうしたらよいのでしょう? まず最低限注意するのは「過放電させない事」です。 「過放電とはどのようにしたらなりますか?直す方法はありますか?」で説明したとおり、過放電させて与えたダメージは元には戻りません。 過放電させずに毎回最後(終止電圧)まで使うのが電池の中の化学物質を「隅から隅まで使い尽くす」ことになるのですが、普通の機器を使っている限りはそんな事は稀ですよね。 ということはやっぱり“どこかで”「中途充電」になってしまいます。 しかしそれでもよいのです。 何回か途中充電しただけで、メモリー効果でいきなり電池が使えなくなるとか、充電容量が半分になってしまうような激しい劣化では無いのですから、多分使用している本人はニッケル水素電池にメモリー効果が起きているとは気付かない程度でしょう。 果たしてメモリー効果による性能の変化か、使用回数による電池自身の劣化なのかす使用中にはらわからないはずです。 「デジカメの撮影枚数が減った“みたい”だけど?」と思った時点、またはそう思う前に一旦終止電圧まで放電してリフレッシュしてやって、回復すればそれはメモリー効果だった、回復しなければ充放電の繰り替えしによる劣化だったと。 ここで疑問に思うのは「少し使ったらすぐに毎回充電する」のが良いのか「少しづつ使って、ほぼ使い終わったと思ったら充電する」のか。 「少しづつ使う」の「少し」がどれくらいか、また使う時間がどれくらい開くのかの条件によって多少話は変わりますが、一般的な話としてはニッケル水素電池は「空になる前に余裕をもって充電しておく」ほうが良いと思います。 メモリー効果が非常に少ない、メモリー効果を感じたらリフレッシュすれば良い、という電池だと考えれば、終止電圧まで使い切らなくても継ぎ足し充電をして使っても良いということはわかりますよね。 メモリー効果に神経質になって「毎回終止電圧まで放電してから充電する」を繰り返すのは個人の自由なのですが、実はそれをするとメーカー発表のサイクル回数は使えないという恐ろしい特性もニッケル水素電池は持っているのです。 ニッケル水素電池の寿命に関する重要な性能条件として「放電深度によるサイクル寿命」というものがあります。 「放電深度」とは「どれだけ放電するか?」の事で、満充電を0%として終止電圧まで放電したら100%放電と表します。(過放電はその先…) 「サイクル寿命」は「何回充電できるか?」の回数で、よく「500回」「1000回」と書かれているアレです。これは電池が全く充電できなくなるまでの回数ではなく、JIS規格の試験と同じ条件で容量が60%以下になるまでの回数です。 放電深度とサイクル寿命の関係は「サイクル寿命は放電深度の二乗に反比例する」と言われていますので、放電深度が浅い(少し使って継ぎ足し充電する)ほうが放電深度が深い(沢山使ってから充電)よりサイクル寿命は何十倍・何百倍も延びるということです。 実際、松下のニッケル水素電池に関する資料 [PDF]ではある電池の場合、放電深度が100%では約300回、80%で1000回、60%で2000回、20〜40%では1万回近くも使用できることになっています。 もしここで回数を示している電池が市販のニッケル水素電池の基本的な性能とほぼ違わないとすると、「500回使用」と書かれている市販電池は約90%使用して継ぎ足し充電を繰り返した時の性能で、もし毎回100%終止電圧まで使用すると約300回程度しか使用できない物ということになります。(実はそうなんです。詳しくは後述します) という事はニッケル水素電池は「少し使っただけでも充電すると何千回も使える」という事のようです。 トータルで利用できるエネルギーのことを考えても、100%×200回=20,000%と、20%×10,000回=200,000%。なんと10倍も違いが出てきます。 10倍も使えるのなら、電池を20%使用した所で継ぎ足し充電をしたほうが、より経済的に充電池を繰り返し長く使えそうですね。 なんといっても1万回も使えるのですよ!(…一回20%ですけど) でも、電池の容量の20%だけ使って毎回継ぎ足し充電をするので、本当に家庭での使用の場合は実用的なのでしょうか? 夕方の犬の散歩に懐中電灯を使うのに、もし5日で電池切れ(終止電圧くらい)になるなら、毎日散歩から帰ったら電池を抜いて充電器にセット。 デジカメで使うなら、その電池で最大撮影できる枚数を一回調べておいて、その1/5の枚数で撮影をやめてカメラから電池を抜いて充電する。 電動ハブラシで使っているなら、何週間でモーターの回転が弱くなるからその1/5の日数で充電を・・・・・ ・・・・ああ、めんどくさい! よほどの電池マニア、充電マニアで充放電に命を架けてるような人でないと無理です! 日常生活でニッケル水素電池を使うには、「電池が切れる前にてきとーに充電する」で良いとは思いませんか? そして「20%使うごとに充電する」には落とし穴があります。 それは充電時の電池の発熱による劣化です。 ニッケル水素充電池は満充電になるあたりで発熱反応が激しくなります。充電時の化学物質の反応としては正しいのですが、この発熱の為に化学物質が自分で自分の首を絞めて劣化します。 そうです、1万回も満充電しようとすると、普通の急速や倍速の充電器では満充電になる時に発熱で電池の寿命を縮めて本当にグラフの通りに1万回も充電できないのです。 普通充電池は発熱による劣化も見込んでサイクル寿命500回とかの規格を満たすように余裕をもって設計されていますが、さすがにそれが数千回とかの無茶苦茶な回数になることは持たせている余裕では足りないでしょう。 では何回になるのか・・・私にはわかりません。 満充電時にどの程度発熱してどの程度劣化するのは電池により、また充電器により様々ですので一概に何回になるとは言えないのです。 しかし、発熱による劣化はどのニッケル水素充電池でも起きる反応ですから、なるべく充電回数を減らして満充電の際の発熱劣化を減らしたほうが寿命が延びるということも電池を長持ちさせる方法です。 ◆ 浅い放電深度で使ったほうがサイクル寿命が延びる ◆ 何度も充電すると満充電時の発熱で劣化する あらあら、同じ「寿命を延ばしてより多く使いたい」という希望に対して、相反する使用条件が出てきてしまいました。 あちらを立てればこちらが立たず・・・ ということで、今までわざと「極端な使い方」を書いてきましたが、そのように神経質にどちらかに偏った使い方をせず、「使い切る前にてきとーに充電する」で丁度良いのではないでしょうか。 ● 過放電はさせない ● 極端に少しだけ使って充電の繰り返しはしない ● メモリー効果はほとんど起きないが、気になっらリフレッシュ ※ ここで言う「気になった」は、実際に電圧低下等を感じた時、
または気分的にメモリー効果の心配が出た時のいずれかです。 電池に劣化が無くても、疑心暗鬼になっている心のリフレッシュができます。 ● しばらく使って無かったら寝ているので1〜3回リフレッシュ さあこれであなたのニッケル水素電池は、限りなく家庭使用での最高状態での使用ができるはずです。 と・こ・ろ・で・・・ 「満充電の際の発熱で電池の寿命が縮むから」とは書きましたが、世間には「充電末期に発熱させない充電器」というものが売られています。 満充電でも発熱しないのであれば、少し使って充電を繰り返しても満充電回数による電池へのダメージは少なくて充電回数は伸びるはずですよね? ではなぜ満充電で発熱しないのでしょうか? 実はその充電器は特殊な充電方法で満充電近くになって電池が発熱する前に充電を止めてしまっているのです。 厳密には「満充電」ではないのですが、それでも電池には満タンに近い電気が蓄えられているのでまぁよしとしよう。というアバウトな感性で充電しているようです。その結果普通は500回の電池を2500回は充電できると豪語しています。 その充電器をまだ購入して試していないので、その充電器に対しての評価はできないのですが、満充電させる前に充電を止めて発熱を少なく押さえているらしいという事で、熱による劣化を抑える効果は期待できそうです。 閑話休題。 ※ 「継ぎ足し充電OK!」「90%程度使用で500回」のワケ ※ 本文中で90%使用で500回、100%使用してしまうと300回くらいしか使えない、と書きましたがそれには理由があります。 電池のパッケージに書かれている「500回」や「1000回」は、JIS-C8708(2004)というJIS規格での充電池テスト方法による、一定の規格を満たしているかどうかの判断基準で合格したという意味です。 JIS-C8708(2004)では毎回の放電を約58%程度でやめてしまっています。 それを48回繰り返します。充電は一般的な「急速充電器で4本同時充電の約4時間充電」と同じ電流です。 そして2回の終止電圧までの放電と満充電(但し急速ではなく標準充電)、つまりリフレッシュを2回です。 60%(放電深度)程度の使用と急速充電器(倍速では無いですが)の使用を48回と、2回のリフレッシュで使用した場合に、規定の60%の容量まで下がるのに「500回」や「1000回」以上の性能を有している電池ですので、「終止電圧まで使わずに継ぎ足し充電でいいの?」という質問に対してはJIS規格が明確に答えを出しています。 「継ぎ足し充電でいいんです、しかもリフレッシュは50回中2回程度でOK」 ※ 厳密にはメモリー効果の測定はしていませんが
このJIS-C8708(2004)のテスト方法や、使い方と寿命の関係については既に迷い箱では回答があります。このページの下のほうの「エネループの使用回数はどこで1回? 使い方と寿命の関係は?」をお読みください。 どの電池メーカー(日本国内なら)も、JISの試験をギリギリ通る電池を商品化しているわけではないでしょう。 JIS規格を上回っている性能のものを商品化しているはずですので、実際は70〜90%の放電深度でもだいたい「500回」「1000回」の基準はクリアできるような実使用が可能なはずです。 松下の資料によれば90%で500回前後の位置にグラフがありますので、かなり余裕を持たせているようです。 しかしそれが100%の放電深度になるとやはり放電深度による劣化の進み方の比率から考えると、グラフの通り300回程度まで少なくなるのも間違いは無さそうです。 デジカメ等、終止電圧で停止する機器を使用していても、完全に電池切れで使えなくなってしまう前に、電池残量メーターが「残り少ない」を表示しているところで電池交換・充電をするのがニッケル漉磯電池の寿命を延ばす秘訣です。 そして時々は電池切れまで使ってリフレッシュしましょう。 お返事 2007/3/11
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 過放電とはどのようにしたらなりますか? 直す方法はありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
充電池の過放電についてお聞きしたいのですが 過放電とはどのようにしたらなりますか? ライトに入れっぱなしにしてたらなりますか? 又過放電してしまった電池はどのような状態になるのでしょうか 直す方法などあるのでしょうか よろしくお願いします (匿名希望) 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
ニッケル水素電池はマンガン・アルカリ乾電池のように0Vまで使用できるのではなく、まだ電圧があるけれども「これ以上放電してはいけない」という電圧があります。それを終止電圧と言い約1Vです。 ニッケル水素電池を使用中に1Vより電圧が下がるような放電をしてしまう事を過放電と言います。 但し電池の外側で計る電圧は電池の内部抵抗の関係で本来の電池内の化学反応で起きている電圧より少なくなりますので、使用中に電圧を計る場合は大きな電流を流している場合は少し低い電圧が計測値として出るのでそのぶんは補正する必要がありますが、普通の機器での使用の場合はほぼ外部で測定できる電圧を「電池の電圧」と見て良いでしょう。 過放電は電池の中にまだ多くの電気が蓄えられている時には起きません。 蓄えられた電気をほぼ放出した後、規定の所(1V)で放電を止めないでそのまま電気を取り出し続けると過放電になります。 懐中電灯等のように「電池の電圧が一定以下になったら自動的にスイッチを切る機能」が無い機器で電池一本の電圧が1V未満になってもスイッチを入れたままにしておくと過放電になります。 デジカメ等のように、内部回路への影響を考慮して「電池切れサインを出したり、自動的にOFFになる」機器ではほぼ終止電圧の1V前後より電圧が低くなると電源が入らないようになっています。こういう機器では過放電の心配は少ないです。(機器によっては心配が完全に0ではありません) 過放電してしまった電池はどうなるのでしょうか? 充電式電池は充電と放電を繰り返す事で徐々に性能が落ちてゆきます。これは中で使用されている+極と−極の特殊な金属が劣化したり、化学反応を起こす為に入れられている電解液と呼ばれる液体が減ってゆくことで起こるものです。 (ここでは使用されている物質名や化学反応式は割愛します、
ニッケル水素電池は約1Vまでの使用であれば、充電と放電の繰り返しで徐々に劣化が進行してゆきますがメーカーの言う「性能」をだいたい維持できると考えられます。興味のある方はネット検索をして調べてみてください) 過放電をしてしまうと、電池の中身が通常の使用とは違うたいへんな勢いで劣化が進行します。 1つめの原因は、+極と−極の間の電圧が1Vより下がってお互いの電位が近づくと、各極を作っている特殊な金属のそれぞれの構成が破壊されて充電・放電能力が無くなってゆくと言われています。 2つめの原因は、過放電が進むと電解液の一部がガス化して電池内圧が上がり、普通の充電・放電の際の安全ガス圧を超えると+極のところにある安全弁が開いて外部に放出されます。ガス化した物質を失う事で電解液の量が減り、充電・放電を行える容量が減ります。 もっと過放電が進んだり、電池を直列で使用する機器の中で「逆充電」をされると、内圧が上がり続けてガスだけではなく電解液自体が安全弁から吹き出してしまい、大量の電解液を失ってしまいます。 過放電により電池の内部では電極物質の劣化・破壊、電解液の質量減少という物理的な損失が進行するので、この損失は回復することはできません。 たとえ充電器のリフレッシュ機能を使用しても「直す」ことはできないのです。 過放電による劣化の進行は「1Vよりどれだけ低い電圧の状態」を「どれだけの時間続けているか」によって様々に変化します。 先の電圧が低い状態、すなわちスイッチを切らずに終止電圧を下回ってから「どのくらいの電圧まで放電を続けたのか」という電圧値。 これは消費電流の多い機器で使用すれば短時間で電圧が下がりますし、少ない機器では長い時間でも電圧の低下が少なくて電池に与えるダメージが少ない場合があります。 つぎに過放電を「どれだけの時間続けていたのか」の時間。 電池内部での化学反応や金属物質の疲労は、電圧が1Vを切った瞬間にパキッ!と金属物質が割れてしまっておしまい。というものではありません。 たとえば水に浸した鉄が時間をかけて錆びてゆくように、ある程度のスピードで徐々に壊れてゆきます。 この壊れてゆくスピードも電圧に関係がありますので、早く電圧が下がって低い電圧の状態を長時間続けた過酷な場合と、少し過放電した所で放電を止めて少しだけ内部にダメージを与える状態を続けた場合とでは全く劣化の進行が違うと思われます。 過放電でニッケル水素電池は一瞬にして壊れるのではなく、「電池にダメージを与え続けるる状態に置く」というイメージでとらえるのが良いでしょう。 ですのでもしライトに入れてスイッチを入れっぱなしにしている物を発見したら、すぐにスイッチを切り電池を取り出すことです。そして充電して過放電の状態で無くすようにしましょう。 放電深度、放置した時間、周囲の温度などで電池のダメージ度は様々に変わりますので、一概に「過放電を一回したら電池の寿命が何%縮まる」とは言えないのですが、確実に電池の寿命を縮めているのは確かです。 過去の経験では「ライトに入れて間違って一週間程度ONのまま放置したニッケル水素電池(Panasonic製)」でも、充電したら普通に充電出来ていますし、放電時間も実感ではあまり変化していません。 一応手持ちの機材で精密に測定すると、過放電させていない同じタイプの電池よりは電圧が多少低くなったり、充電容量がほんの少し減ってはいますが、すぐに目に見えて「痛んだ」という感じではありません。 多分このまま使用を続けていると、本来なら500回使用できるものが300回になっているなど、いますぐ目に見えるような痛みは(新品電池に近いほど余計に)表には見えず、家庭内での普通使用ではダメージを感じられない程度だと思います。 過放電での電池の劣化は、「実際には進んでいるけれども今は目には見えない病気」のようなものだと思っても良いでしょう。 人間でも、暴飲暴食や不摂生、栄養の偏りなどで内蔵や心臓に負担を強いても、精密検査をしない限りは通常生活を送れている人と同じです。 実際に身体が衰えて身体機能に障害が出たり、長くは生きられない身体になっているのかはまだ元気な時には外見からは判りません。 もちろん、人間でも食事を与えずに何日も放置すれば死んでしまいます。しかしこれも「人は食事抜きで何日目で死ぬ」とは一概には言えないので、電池を過放電のまま放置したら何日目で充電できないほどのダメージになるのかははっきりした日数では明言できません。 おかしなたとえですが、過放電とはこのような感じだと私は思っています。 劣化はあるのか?ないのか?と言われれば過放電での劣化はあります。 しかし一律に数値で表せないものなので、過放電させる状況や電池のメーカー・種類により様々な劣化の度合いであり、「これ!」という決まった劣化状態に関する答えは残念ながら用意できません。 お返事 2007/3/6
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放電圧何V程度で過放電? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
最近、パナループ4本組を購入しました。 初回満充電→デジカメで電池切れまで初回放電としたところ、数分放置後の開放電圧で、3本は約1.15Vあったのですが、1本は約0.95Vしかありませんでした。 セルのバラツキで、いきなり過放電? と心配です。 開放電圧何V程度で過放電となるのでしょうか? 高円寺マリオ 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
「開放電圧(開回路電圧)が何Vで過放電」という定義はありません。 数分放置後・・・という事で電圧の回復についてはご存知だと思いますが、改めて説明します。 『イーグル放電器 単4ニッケル水素用 AAA Active Mate の性能を調べる』のページの投書に対して以下のグラフを使い開放電圧の測定がほとんど意味が無い事を説明しています。 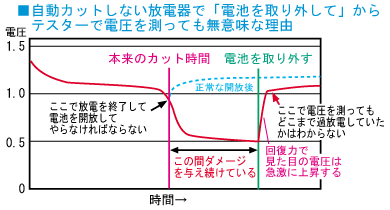 ただ唯一言えるのは回復中でも1.0Vを割っているのであれば、その電池は「使用中に確実に1.0V以下の過放電状態になっていたであろう」という事くらいですね。 そのデジカメが何Vで電池切れになるのか等がわからない限り細かな数値では語れませんが、電池4本を直列に使用してどれか一本が容量を使い果たして急に電圧が下がるタイミングの付近の時間で合計電圧がカメラの設定電圧の下限になって電池切れとなっているのでしょうが、そういう事はほとんどのデジカメで起きている事なので「電池切れになったら無理に何度もスイッチを入れなおしたりして、放電が終わった電池にそれ以上負担をかけない」という使い方しかありません。 いくら特性が揃った電池でも「数秒以内の誤差で全く同時に放電終止電圧を下回る」なんて事はありませんので、電池毎の個体差で終止電圧を割り込むタイミングは新品電池でも数十秒〜数分程度以内の誤差はあります。 その誤差の為に4本も直列で使っていたら中の一本が先に終わって過放電になる事なんて直列使用をしていればあたりまえです。 デジカメのように電池の使用本数にあわせて電池残量警告や電池切れを判定できる機器であれば、その程度のことは折込済みなのであまり気にしなくて良いでしょう。 どうしても気になるのであれば、電池切れになる前に電池の使用を終了して充電すると良いでしょう。(もちろん個別制御の充電器で) 継ぎ足し充電になりますので徐々にメモリー効果が発生して何十回の使用で電池本来の性能が得られなくなりますが、リフレッシュ機能付き充電器を使用するなどして10〜20回に一度程度リフレッシュしてやれば直りますし、過放電させる事もなく電池の寿命もほぼまっとうさせる事ができるのではないでしょうか。 既に何度も書いていますが、過放電のダメージは一回で電池がだめになってしまうのではなく徐々に電池の劣化を進めるものですから、電圧が低くなる事や、低い電圧になったままの時間を短時間でやめればいきなり寿命が縮んですぐに使えなくなるものではありません。 デジカメで自動的に電源が切れるほど使い切ったらすぐに充電してやる事を忘れなければ実用上気になるほど電池が痛むことは無いと思いますよ。 お返事 2008/3/18
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 劣化すると自己放電も多くなりますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
前回は充電器の質問について答えていただきありがとうございました。 また疑問が出てきたので質問させていただきます。 eneloopや充電式エボルタなど、自然放電が少ない充電池でも充放電を重ねると自然放電しやすくなりますか? というのも、去年買って使い込んだ3MPSと今年買ったあまり使っていない3MPSを交互にバッテリーエクステンダー2で使っていると、両方とも先週充電したものなのに去年買った方だとすぐ給電が止まってしまい使い物にならず、逆に新しい方だと充電したてとほぼ同じぐらい使用できます。 充放電をある程度重ねると従来のニッケル水素電池と同じように自然放電しやすくなってしまうのでしょうか?また、なぜそのようなことが起きてしまうのでしょうか? hirotake 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
「自己放電が少ない」という性質は従来のニッケル水素充電池の材料を改善して改良した点ですが、それら電池の中に入っている材料は使用と共に劣化してゆきます。それは新型電池もも従来型電池も変りありません。 使用回数が増えると容量が減ったり電圧が下がったりするのは「電気を電池の中に溜めておく力が弱くなる」と考えれば、充電してから自然と電気が抜けるのも「電池を溜めておく力が無くなってゆく」ので新品の時よりは使い込んだ電池は電気をガッチリ掴んでおけないのはあたりまえですよね。 うちでは発売当初に買っていろいろと使ってかなり古くなったHHR-3MPSは、ライトの中に入れておいても満充電から2ヶ月もするとほぼカラになっていて、スイッチを入れた瞬間一瞬だけついてすぐに消えるくらいになっています。 お返事 2009/7/5
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
ありがとうございます。なるほど、使い込むと全体的に特性が劣化してしまうのですね。 使い込んだ電池の自己放電特性のデータはありますか? そして、電池がどの位劣化しているか知る方法はありますか? hirotake 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
そういうデータは取っていないのでありません。(もう劣化した電池はそういう物として余生を送らせていますから) それと、日常的に機器で使用している電池は一部経過実験用を除いて正確にどういう使用状況で何回使ったかなどの記録がありませんので、それを測定しても「使った電池」としか書けません。 正確な使用回数などがわからない限り他の電池との比較データにはなりませんので、いくつかの使い込んだ電池のデータを取ってもそれらを並べて各メーカー・種類ごとの劣化データの比較とはゆかないので、発表すると混乱を招くだけだと思いますから正確な回数などを記録できた物以外はデータ公開しないことにしています。 電池がどのくらい劣化しているかは、正確に知るにはJIS試験と同じような定電流放電試験を行って時間を計ったりグラフを取るしか無いですね。その上で容量が60%を下回ればJIS試験で言うところの寿命です。 家庭では、同じ機器で使って新品電池で使用できる時間と比べて半分程度になるようでしたら寿命と判断するのでもいいでしょう。 そういう寿命の話は既に話題に出ていますので「ニッケル水素電池の買い替え時期、寿命」をお読みください。 ※ 実は、電池が劣化すると自己放電性能も落ちてくるとは「ニッケル水素電池の買い替え時期、寿命」に既にちょっと書いているのですが・・・ お返事 2009/7/5
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 7/6 |
お忙しい中回答してくださりありがとうございます。 参照してみます! hirotake 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニッケル水素充電池の残量を調べる方法? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
かなり楽しく読ませて頂いています。 初歩的な事になりますが、ご質問がありまして投稿させて頂きました。 ニッケル水素充電池の残量を調べる方法に関してお伺いします。 通常のテスターですと電池単体で電圧を測定しても正確では無いと思っていますがそれで宜しいでしょうか? そこで市販のバッティチェッカーを使う事を考えましたが、ニッケル水素充電池は対象外となっています。 今までのニッケル水素充電池ですと使用直前に充電すれば良かったのですが、eneloopだと放電しきらない為、使用する時に充電する必要が無く、しばらくほっておくと分からなくなってしまう事が多々あります(爆) また、デジカメが6本使用&フラッシュが5本使用という 中途半端な関係な事もあり、残容量を簡単に確認するにはどうしたら良いかなと思っています。 よろしくお願いします。 ありぽん 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
確かに、単純に電池電圧をテスターで測定しても電圧=残量ではありません。 後でも書きますがニッケル水素充電池の残容量を正確に計ることは技術的に困難ですので、「だいたいのめやす」程度を調べる方法について説明してゆきましょう。 あたりまえの話ですが、ニッケル水素充電池は充電直後は電圧が高く時間が経つと自己放電や不活性化で徐々に電圧が下がりますが、よほど放電してしまわない限りテスターで測っても定格電圧(1.2V台程度)に近い電圧を示しますので残量はよくわかりません。 もちろんテスターで測って1.1V程度(やそれ以下)まで下がっていたら即充電です! 電池だけでの開放電圧(開回路電圧)が高くても、実際に機器に入れて電流を流すとガクンと電圧が落ちる場合があります。 同じような開放電圧でも、この実際に使った時の電圧が低い電池は弱っていると判断できます。 それを測定するのが「電池チェッカー」で、説明書には「充電式電池は使用できません」と書いて有りますが、しくみを理解した上で使用するのであれば充電式電池にでも使用できます。 既にお読みだとは思いますが、『バッテリーチェッカーの「充電池は使用出来ません」とは?』で説明しています。(ここでは説明は省きます) まだ機器で使えるのか、充電したほうが良いのか?、の判断でしたらバッテリーチェッカーで十分に実用になります。 バッテリーチェッカーでは「機器で使用する際に、だいたいどの程度の電圧が出せるか」で電池の良し悪しを判断しますので、これも正確に電池の中の残りの容量を測定しているわけではありません。 たとえば「この電池の残り容量は75%です」なんて表示できる装置を開発すれば、それこそノーベル賞級(?)の大発明なのですよ。 電池メーカーでさえ、ニッケル水素充電池を外部から測定して残容量を表示するような機械は発明していません。 三洋の充電器(NC-MR58)に付いている「バッテリーチェック機能」も市販のバッテリーチェッカーとほぼ同じしくみで、容量を測定しているわけでは無いようです。 ラジコン用の特殊な充放電器では、途中で「xx%」なんて表示するものもありますが、充電式電池の特性を調べ尽くした上で標準的な数値をプログラムされていて、それにあわせて実際の電池の電流や電圧から計算した「おそらくこれくらい」という数値を表示していると思われます。 そのため充電(または放電)中に「99%」までは順調に数値が進んだのにいつまでたっても「100%」にならないで忘れた頃に充電完了表示になってたり、まだ「80%」程度の表示からいきなり「100%」に変わって充電が完了したりと、それは笑える表示をするような場合もあります。 ですので、eneloopをはじめ最近のニッケル水素充電池は「継ぎ足し充電OK」というメーカーの言い分を信じて、「しばらく置いていた場合は使用する前に充電する!」で良いと思います。 (…あれ? 従来型の使用前充電必要と変わり無いやん、と思っても口には出さない!) デジカメ等での家庭用機器では、本当に終止電圧まで使用してしまう事が少ないと思いますので、常に継ぎ足し充電で使っていたらたとえeneloopでもメモリー効果のような症状が出ることは家庭でのリフレッシュ放電のしかたは?で話に出ていますので、参考にして時々リフレッシュして使うと良いでしょう。 ◇ ◇ ◇
・・・と、ここまでの説明だと納得できない方の為に(笑) 基本的には市販の「バッテリーチェッカー」と同じ事をするのですが、こういうジグを作っておくと便利です。  右側は「電池ボックス」に「抵抗(3Ω/1W)」と「スイッチ」を繋いだものを簡単にテスターと接続できるようにミノムシクリップをつけたリード線をハンダづけしています。
右側は「電池ボックス」に「抵抗(3Ω/1W)」と「スイッチ」を繋いだものを簡単にテスターと接続できるようにミノムシクリップをつけたリード線をハンダづけしています。左側は100円ショップで売られている「電池チェッカー」を、右側と同じように電池チェッカー内の負荷抵抗をON/OFFできるように改造したものです。 ケース前面にスイッチがついています。 右側はテスターで電圧を数値で見れ、左側はメーターで簡易的に見れます。 ※ 撮影用に保護テープを剥いています
使い方は簡単で、電池の開放電圧を見る時は単に電池をセットするだけですね。 スイッチを押すと負荷時電圧が読み取れますので、「開放電圧は高くてまだ使えそうに見えるが、実は弱っている電池」などは簡単に見分けられます。 スイッチを入れたら極端に電圧が下がる電池は弱っていますので充電しなければなりませんし、充電した後でもテストしてみて大きく電圧が下がる電池は電池自体が痛んでいます。 充電後の開放電圧が何Vで、負荷をかけたら何Vになるのが正常かは、電池の種類や使用する充電器によって違いますのでここでは数値では書けません。ご自分の使用機材で実際に測定してみて傾向を調べる必要があります。 100円ショップ電池チェッカーを改造したものでは数値で電圧は読めませんが、針の示す位置の変化などで判断します。 このような物を使っても「電池の残容量」は結局は計れませんので、その電池が機器に入れた時に必要な電圧を出せるかどうか、開放電圧で見た目で騙される電池か?、がわかる程度です。 やはりニッケル水素充電池で大変なのは、少し使った(または自己放電した)電池と、半分くらいまで使った電池、そしてかなり使ったけどまだ少し使える電池では負荷時電圧はほぼ一定値を示しますので、残容量のめやすには全くならないという事です。 お返事 2007/10/25
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
ニッケル水素充電池の残量を調べる方法? で投稿させて頂きましたありぽんです。 回答ありがとうございます。 インターネットで調べてもニッケル水素用のチェッカーが無い理由を理解する事ができました。 電池毎に充電放電を管理するICとかが無いと無理そうですね。 コスト&サイズ的に無理な気がしますが・・・。 >しばらく置いていた場合は使用する前に充電する! エネループでも、必要な時には再充電をする事に致します。 ただ、ニッケル水素でも、負荷時時電圧の測定時に、抵抗(3Ω/1W)で良い事が分かりましたので、 私も自作をして電池毎の特性を統計だててみようかなと思います。 もう一点質問です。 バッテリーチェッカー M032 (秋月で400円) 1.5V電池は、負荷電流:50mA,100mAしか無いみたいです つまり、内部抵抗が30Ωと15Ωなのかと考えていますがこれでも、統計を取るぐらいは可能と考えて良いでしょうか? よろしくお願いします。 ありぽん 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
統計を取るくらいなら・・・使用できると思いますが、ニッケル水素充電池に対しての測定電流には少なすぎますね。 おおまかに、ニッケル水素充電池はマンガン・アルカリ乾電池よりは大きな電流を流すことができる性能がありますので、少ない電流を流しての測定では開放時とあまり電圧の差が見られない可能性があります。 それでもわずかですが電圧は下がりますので、それを調べてめやすにする事は可能です。 できれば豆電球式の懐中電灯程度の電流が流れる3Ω程度で測定される事をお勧めします。 お返事 2007/10/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 11/1 |
回答ありがとうございました。 週末にでも自作をしようと思います。 ちなみに家に有った100円均のチェッカーは3Ωより大きい抵抗がついていました。 今後ともよろしくお願いします。 ありぽん 様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
いつも楽しく読ませていただいております^^ ニッケル水素充電池の残量を調べる方法?のところに有りましたラジコン用のテスターについて先日メーカーに充電%放電中の%について聞いてみました。 メーカーでもその進捗については電池電圧で電池の内部抵抗等さまざまなデータから満充電のときの電圧を想定して%であらわしているらしいです。 そのため急にポンと%があがったりするらしいです。 %の分母を容量にすると劣化や条件で一定しないからですと・・・どうでしょうか??苦肉っぽいですね? 充電マニア見習い^^ 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
実際にそのメーカー(たぶんあそこ)の言っているとおりだと思いますよ。 充電中の電池を外側から計れるものは <充電中> ・通電時の電圧 ・通電時の電流 ・開放時の電圧 <放電中> ・放電時の電圧 ・放電時の電流 ・開放時の電圧 <あとは・・・> ・温度 温度は充電末期の検出や異常過熱の検出に利用する場合が多いので除外するとして、残るものは電圧と電流ですから、これらから電池の状態、内部抵抗などを計算して、更にはそれの「時間的変化量」で電池が今充電の初期段階にあるのか、末期であるのかなどを推測する計算を行っているのでしょう。 単純に電圧を測っただけで「今1.xxVだから充電78%!」とは言えませんから、ニッケル水素充電池の充電特性カーブを熟知した上で、変化量から今カーブのどのあたりのポイントに合致するかを計算するわけです。 しかし世の中の全ての電池が同一のカーブを描いているわけではありません。 基本的な特性は同じですが、電池によってカーブの描き方は少しずつ違っています(中にはかなりの変わり者も…)し、同一の電池でも使用が進んで劣化したものはやはりカーブの描き方が違ってきます。 ですのでラジコン充電器メーカーはいくつかのパターンまでは用意しているか、標準のパターンから計算して後は刻一刻と変化する実測データから補正(予測)して充電中の電池が今何%かを表示するようなプログラムを作っているものと考えられます。 「分母」の部分はそういう予測計算値の事で、「今充電しているのは多分2000mAhの電池で、今95%地点だから1900mAh入っている」と計算しているとして、実際の電池は2500mAhだった場合にはあと1000mAh充電した時点で充電器は「もう100%になっているはずだけど・・・でも満充電反応(−ΔV等)が見られないよ、これはまだ満充電じゃないから表示を100%にするといけない、98%くらいで止めておこう!」というプログラムでしばらくはずっと98%が続く場合があります。 逆に「2500mAhの電池だろう、今80%で2000mAh位だと思うからあと500mAh程度充電したら100%表示にしよう」という状態で、実は2000mAhの電池だった場合はあとほんの少しだけ充電しただけで−ΔV検出で満充電を検知して充電をストップ!、表示は80%からポンと100%になってしまったりするわけです。 しくみがわかっていればなんという事も無いのですが、単に表示だけ見ていると「全然信用できないじゃん!」とかユーザーに判断されてしまうわけです。 メーカーとしては本当に苦肉の策と受け止められしまうような、現状でニッケル水素充電池の容量を外部から正確には知り得ない状態でなんとか数値で表示させようという涙ぐましい努力がうかがえます。 同じように充電容量や放電容量から進捗状況を表示する機器としてソニーのBCG-34HRME通称「ソニーの液晶つき充電器」がありますが、これはうまくごまかしていて表示は電池マークのグラフィカルで3〜4段階しかありません。 数字で何%と表示してしまうと人間は残りの数値から時間などを予想してしまって、予想が外れると「故障だ!」「不良品だ!」と騒いでいまいますが、3〜4段階表示でしかも各段階が実際の数値で何%に相当するのかさえ公表されていないのですから「表示の電池マークグラフが進めばOK」程度にしか受け止めないので全然大丈夫です(笑) %表示を行っているラジコン用充電器と同じく98%からなかなか100%に進まないような事になっていても、ソニーの表示では最後の棒一本が表示されないままの状態が続いているので、ユーザーはその棒が表示されて満充電になるまでの間は実は1つ前の状態から予想より余分に時間がかかっていてもわからないので安心(心配する要素が無い)なのです。 ソニーの充電器は分解していないのでこれは想像でしかありませんが、どこのメーカーも本当に正しい充電池の容量を外部から測定できない以上、この程度の誤差・計算のズレはあるものと思って間違いはないでしょう。 「気の迷い」の電池放電実験や、掲載はしていませんが充電器の充電性能のチェックなどの際にはデータロガーの測定データをリアルタイムでPCの画面上にグラフ表示しています。 グラフを見ていると終了までの2/3から3/4程度まで進んだ時には「ああ、あと何分くらいで放電が終わるな」とかはグラフの線から見えてくるもので、%表示や3〜4段階表示を行っている充電器はそれと同じ事を中のマイコン・プログラムが行っているだけなのですが、確実に1分単位や1mA単位で正確に予測はできないものなのです。 お返事 2007/11/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリーチェッカーの「充電池は使用出来ません」とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
初めまして。エネループに興味を持っていろいろ調べていたらこちらに辿り着きました。 今まで触れたことの無い情報の理解に悪戦苦闘しながらも、興味深く読ませていただいています。 つい最近エネループを購入したのですが、ついでにバッテリーチェッカーも買おうとしたところ、多くの機種に「充電池は使用出来ません」と書かれていることがわかりました。これは何故なのでしょうか? 充電池対応のチェッカーもあるようですが、家電量販店や100円ショップなどで身近なところで安価に手に入る乾電池用のチェッカーでは測ってはまずいのでしょうか。 初歩的なのかもしれませんが、お答え頂ければ幸いです。 hide 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
電圧計と負荷抵抗が並列に繋がっていて、普通のテスターの電圧計とは違います。 電池の電圧は負荷(使用機器など)に電流を流している時と、何も繋いでいない時(無負荷)では違います。 何も繋いでいない時は見かけ上の電圧が高く、負荷に電流を流すと電池の電流供給能力に応じて電圧が下がります。 テスターで単に電池の電圧を測っただけでは、この無負荷状態の電圧を測ることになり、本当にその電池の電流供給能力を調べたことにはならないのです。 ですので「バッテリーチェッカー」では数オームの抵抗を負荷として電池に接続し、負荷に電流を流した時の電圧を測ることで実際に機器に入れて使用した時に「電池が使えるか?」を調べるようになっています。 ではなぜ「充電池は使えません」と書かれているのでしょうか。 単に電池から少しの電流を流しながら電圧を測っているだけなので、マンガン電池やアルカリ電池でもニカドやニッケル水素充電池でも変わりは無いように思えます。 事実、測定できる電圧(電流の供給能力)には違いはありません。 では、何が違うのでしょう? バッテリーチェッカーのメーターの目盛りには普通は「電圧」の数字は書いていません。(書いているものもあります) 目盛りの部分に赤・黄・緑の帯がつけられていて、それぞれ「緑=GOOD」「黄=LOW」「赤=交換」のように書かれています。 そうです。バッテリーチェッカーは正確な電圧を測る為のものではなく、電池が「まだ使えるか」「もう使えないか」などの「(おおまかな)残量」を知る為の装置なのです。 そしてこの赤・黄・緑の帯は「マンガン・アルカリ電池の特性にあわせた表示」であり、特性の違うニカド・ニッケル水素電池では正しくありません。 具体的には次のグラフを見てください。  ※ メーターの色分けや区切り位置は製品により様々です。
※ マンガン電池はアルカリ電池より電圧が下がる場合があります。
この図では特性を表す為に同一にしています。 バッテリーチェッカー内の負荷程度で計測できる「マンガン/アルカリ乾電池」と「ニカド/ニッケル水素充電池」の放電特性・測定電圧の違いです。 グラフ左側の時間率0%に近いほど電池は新品に近く、まだまだ電気がたくさん取り出せる状態です。 グラフの右側100%に近づくと使い果たして使用終了に近くほとんど電気を取り出せません。 マンガン/アルカリ乾電池ではゆるやかなカーブを描きながら徐々に電圧が下がってゆきますので、計測できる電圧値に応じて「新品」「使用中」「もうすぐおしまい」などがだいたい判別がつきます。グラフ下側に載せている「マンガン/アルカリ乾電池の表示」もほぼ使用時間に対して三等分した場所で色が変わりますのでだいたい色に合わせて「電池の残量」が読み取れます。 ニカド/ニッケル水素充電池の場合はどうでしょうか。 ニカド/ニッケル水素充電池は使い始めで少し電圧が下がったまま長期間だいたい同じ電圧を供給し続けます。そして使い終わり直前にガクッと電圧が下がります。マンガン/アルカリ乾電池とは大きく放電特性が違います。 そのため「ニカド/ニッケル水素充電池の表示」では、満充電時からほんの少し使ったくらいまでがGOOD、それから延々とLOW表示なにり、電池切れ直前でやっと要交換になります。 満充電から少し使った状態でも、もうすぐ電池切れに近づいたかなり放電した状態でも「使いかけ状態です。まだ使えますが心配な場合は交換したほうが良いですよ。」のLOW表示なので、本当にそろそろ交換(充電)したほうが良いのか、まだ少ししか使っていないのかの判別がメーターの針の振れ方からは非常に読み取り辛く、正しく判断ができません。 これでは「電池の残量」をメーターの針から読み取るのは簡単にどの色を指しているのかだけではわかりませんので、バッテリーチェッカーの主目的の「どれくらい使えるか?」を見るには不適です。 このような理由で、100円ショップや家電店で売られている単純に数Ωの負荷をかけた状態でメーターを振らせる「バッテリーチェッカー」では、ニカド/ニッケル水素充電池の「残量」は正確には知ることができないので、「充電池は使用不可」とされています。 電池の残量を知る機器としては、単三や単四電池対応のデジカメ等の「電池残量メーター」はバッテリーチェッカーの電圧チェック機能を高機能化したもので、「アルカリ電池モード」「充電池モード」など使用電池にあわせて特性パターンを切り替えて、“なるべく”正しく電池の残量を表示するように計算するものもあります。 簡易的なバッテリーチェッカーではニカド/ニッケル水素電池の「残量」は測れませんが、「もう電圧がほとんど無い(=要交換表示)電池」や「充電後にちゃんと充電されているか(=GOOD表示)」などの判定には使用できますし、2〜4本などを同時に使う機器の場合「機器の電源が早く落ちる(懐中電灯などでは暗くなる)ようになる」ような「あれ?電池が弱ってきたかな?」という時に、4本全てが同じように弱っているのか、どれか一本だけが痛んでいて他の電池の足を引っ張っているだけで、その一本を交換すればまだ他の電池は使えるのかなどを調べるには使えますので、あながち「充電池は使えません」とは言い切れないのです。 バッテリーチェッカーのメーカー・製品によって色の帯の割り振りは様々で、統一された規格は無いようですので、お買い求めになられたバッテリーチェッカーでは自分の持っている電池は満充電ではどれくらい針が振るのか、使い終わりではどのくらいの針の位置になるのか、を把握していれば結構使い物になりますよ。 お返事 2007/5/2
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
こんなに早く御返答頂けるとは思いませんでしたので、驚きながらも有難く読ませて頂きました。 とても丁寧でわかりやすく、抱いていた疑問がスッキリと氷解しました。 充電池に対してバッテリーチェッカーがまるで役に立たないわけでもなく、使うことによって何か危険性があるわけでも無さそうですね。 とても参考になりました、有難うございました。 hide 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
危険性といえば、長時間測りっぱなしにすると物によっては発熱して最悪は煙が出たりする事くらいですね。 これはニッケル水素充電池など充電池を測る時に限った事ではなく、アルカリ乾電池でもマンガン乾電池でも起こりうる危険です。 バッテリーチェッカーの中の数オーム(3Ωなど)の負荷抵抗に電池を接続していますが、新品のマンガンやアルカリ乾電池では負荷抵抗に電流を流しながら約1.4〜1.3V程度の電流が流れます。 満充電のニカド/ニッケル水素電池でも同じくらいでしょう。 多少減ったマンガン/アルカリ電池や、同じくグラフ中の水平期間のニカド/ニッケル水素電池では約1.2V程度の電圧です。 1.4Vの電圧を3Ωの抵抗にかければ電流は0.467A、抵抗で消費する電力は0.653Wです。 1.2Vの電圧を3Ωの抵抗にかければ電流は0.400A、抵抗で消費する電力は0.480Wです。 これに対して、バッテリーチェッカーの製品によっては、中の負荷抵抗に普通の1/4W(0.25W)品を使っているものがあるので、電力定格的には全然ダメです。 これはもちろん「チェッカーでバッテリーを測るのはほんの数秒」という使い方なので、発熱もほんの少しという前提の元に小さなW数の抵抗を使用しているのだと思います。 ですので、電力定格的に小さな抵抗に、定格以上の電流を流すようなバッテリーチェッカーでは、1分も電池を繋ぎっぱなしにしていると抵抗がかなり過熱してしまう場合もあります。 たとえ0.5W品などのW数の大きな抵抗が入っていても、発熱するのは同じです。 定格電力の大きな抵抗でも小さな抵抗でも、抵抗値と電流が同じなら発熱量は同じですのでどちらの抵抗も同じ熱量で発熱しますが、W数の小さな抵抗では体積や表面積が小さいので早く温度が上がります。早く高温になって煙が出たりするのもW数の小さな抵抗ですね。 元々数秒の接続でバッテリー残量を計る為のバッテリーチェッカーで、数分以上ずっと電池を繋ぎっぱなしにすることはしないようにしましょう。 「充電池は大電流を流せるのでチェッカーが焼けるから、バッテリーチェッカーでは充電池は使用不可」などというまことしやかな都市伝説が今でも流れている所もあるようですが、マンガン/アルカリ乾電池でもニカド/ニッケル水素充電池でも3オーム程度の負荷抵抗では同じような電圧をかけられますので、「充電池だけ危険」という事はありません。 お返事 2007/5/2
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ni-MH電池を良好の状態で保管するために | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
職場でeneloopを貰いました。 それも単3を12本、単4を10本もです。 単3は4本が06年6月製造の旧タイプ、8本が07年1月製造の『-R』です。 単4は4本が06ねん5月、6本が06年7月製造で、全て旧タイプでした。 『充電器が無いから』との理由で貰った筈なのですが、後になってからNC-MDR02が出て来たので、それも貰ってしまいました(笑) 自分は元々はPanasonic派なのですが、家にはeneloopが溢れております(汗) さてここからが本題なのですが、Ni-MH電池を良好の状態で保管するために気を付けなければならない点はありますでしょうか? 現在は半月に一度、全ての電池に追充電をしております。 Thief 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
まず、ニッケル水素充電池の保管に適した状態、(今回の質問にはありませんが)ニカド電池の保管に適した状態については『秋月充電器、MW1268の中身は・・・』の「迷い箱」お返事 2007/4/5で詳しく書いていますので、基本的な事はそちらをご覧下さい。 その上でまだ何か他に・・・というとほとんど無いと思います。 追い充電では自己放電によって終止電圧を割り込んで電極を破壊してしまうような極端な劣化は防げるでしょうが、上記ページで解説しましたように長期間使用しないことでの不活性(休眠状態)は回復しないと思われます。不活性化した電池は使用前の数回の深放電→充電サイクル(リフレッシュ作業)が必要になってしまいますのでサイクル寿命を結局は消費することにつながります。長期保管は「仕方なく」なら言葉通り仕方ないのですが、意図的にはしないほうが良いでしょう。 ニッケル水素充電池は長期間の保管・放置はせずに、適度に使ってやって使用によって自然と劣化したら新しい物(最新の良い状態の物)に買い換えるのが一番良い使い方です。 自己放電が少ないeneloopでも長期保管後は不活性状態になっているのは確認済みですから、「すぐ使える」「自己放電が少ない」というのは従来品と比べての効能であって、決して従来ニッケル水素充電池とは全く別物の「欠点の無い電池」では無い事は認識しておいたほうが良いでしょう。 お返事 2007/12/21
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 12/23 |
忙しい中、ご回答ありがとうございます。 やはり『買い溜め等は良く無い』と言う事ですね。わかりました。 なるべく早く家の乾電池をeneloopに置き換え、消費したいと思います。 その前に放電器を製作しないと…(汗) VOLCANOやパナループ、eneReadyもあるから大変だぁ…orz Thief 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点復活方法いろいろ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
接点復活方法で。(通りすがりで、すみません) 接点洗浄剤(中身はほぼ溶剤)で綺麗にしてから、表面に薄く接点復活剤を吹くなんてのが正攻法だと思うのですが、電池の頭や電池ボックス程度のものなんかは、CRC-556(CRC-226)なんかを綿棒につけて端子のみをしこしこ拭いてます。 (いったん綿棒につけてからやるのがミソで、直接吹くのは、つけすぎになるのでだめですが....プラスチックに対する影響も要注意.....カメラ、オーディオなんかの高級なものにはやめた方がいいです(笑)) サンハヤトのはそうでもないですが、昔よく使ってた「プレクリン」「クラモリン」・・(今はもう無いか?)などは結構高いですからね。 洗浄にトリクロロエタン(リキッドペーパー修正液の薄め液)なんてのを使ってみたりもした事がありました。(地球環境にとっても素敵なので、最近のは中身が違う?) ちなみにこんなのはどうでしょう。 (コンタクトZ) http://www3.coara.or.jp/~tomoyaz/higa0201.html#020113 これは、私も昔から(多方面で)愛用してます。(笑) ガッツ 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
多分「5-56」なんかは一家に一本くらいはあるのではないでしょうか。 私は「5-56」ではあまり良い記憶が無いのでガレージの片隅に放置していて使っていませんが、秋葉原や日本橋の専門店でなくてもどこでも(ホームセンター等)で買えるので非常用には便利ですね。 自転車や家の金具類にも使えますし(・・・ってそれが本来の使い方!) ちゃんと拭き取れば電気端子にも有効だと思います。拭き取らないと余計にホコリを吸って悪化します。(これが嫌い) サンハヤト等の電子機器・端子に特化した製品はそういう所がちゃんと考えられているので安心です。商品用途が元から違うので家庭用の汎用金属磨き剤とは単純には比較はし難いですね。 端子を磨く・接点を復活させるには、基本的には電気器具の「金具の汚れが落とせて、その後も保護できれば良い」という目的さえ達成できれば洗浄剤はなんでも良いのです。 家庭用(いや、業務用か?)で日本で一番有名な金属磨き剤「ピカール」なんかで磨けばどんな金属でもピカピカになります。お仏壇の輝きも素晴らしく!(笑) 昭和の家庭には必ず一本はあったと思います。(昭和と言えばトイレにサンポール…) 電子機器の端子を洗浄するというのは基本的にはオーディオマニアの人くらいしか一般的では無いと思います。 普通の家庭ではプラグやジャック、電池や電池ボックスの端子なんか一生磨いた事が無い人がほとんどではないでしょうか。 ちょっと磨くだけで性能UP!、雑音や接触不良が無くなってより長期間良い状態で機器を使用できるのに、端子部の劣化で動作が悪くなって「壊れた」と勘違いして捨てられる製品もあるかと思うと大変残念です。 端子の軽度の汚れなら専用の洗浄剤を使わなくても家庭用の中性洗剤を薄めてティッシュペーパーや綿棒に染み込ませた物で軽くこする(ちょっと力を入れると最適)だけでもかなり効果があります。 白いティッシュの表面に薄く茶色やグレーの汚れが付着するようなら汚れていた証拠。 家庭用洗剤よりは「アルコール入り・ウェットティッシュ」のほうがより金属端子向けですね。 オーディオ用の端子クリーナーの多くは洗浄成分は入っていないアルコール液が多いです。(テープデッキのヘッドクリーニング用の名残り) 水や一部の薬剤は金属を錆びさせるのであまり良くは無いですが、アルコールや有機溶剤は錆びさせませんので昔から接点洗浄に使われてきました。 家庭では専用の洗浄液や工業用アルコール(薬局で売っています)を買う事はあまり無いと思いますが、「アルコール入りティッシュ」ならコンビニでも手に入りますよね。 しかも別のティッシュや綿棒につけなくても最初から布に染み込ませているので、パックから引き出して使いたい大きさに折りたたんで使い、終わったらごみ箱にポイするだけの手軽さ。 ガッツ様情報にある「化粧品」の一部にもこういう用途に使える薬剤(溶剤など)を使用した物もあり、化粧品店ばかりか最近では100円ショップの化粧品売り場で105円で買えたりしますので、中身が分かっていると結構重宝します。100円ショップでなら男が化粧品をカゴに入れてレジに行っても恥ずかしくありません(^^; しかし溶剤・化学薬品系はガッツ様も書かれている通りプラスチックを侵すものもありますので、他の部分に付着しないよう綿棒等細いものでよく注意して使用する事や、残りの薬剤をしっかり拭き取るなど少しばかり気を使わなければなりません。 そして・・・禁断の大技、コンタクトZの登場ですか! 電気端子の洗浄では無く、使用時の接触抵抗の低減の為の薬剤として「ナノカーボン」という物が売られています。 名前の通りナノサイズ(本当かどうかは不明)のカーボン粒子(要は炭素の粒)が入っている物で、それを金属端子に塗ると接触面が炭素粒子で補完されて有効面積が増え、そのぶん抵抗値が下がって電流を多く流せるようになるという夢のような効果をうたう商品です。 高級品ではわずか数グラムも入っていないのに数千円もするようなものまで売られています。 それに対してコンタクトZは昭和の一般家庭ではどこにでもあり、一本10円程度と誰でもが手軽に使用できる接点改善材(?)でした。 「コンタクトZ−HBよりはコンタクトZ−Bのほうが効果がある!」など数々の都市伝説を生み出したまさに禁断の品です。 電池や充電器の端子を改善して性能UP!させるには今でもかなり有効だと思います。電池端子部をゴシゴシこすって軽く拭き取るだけで実測で数mΩの改善が見られました。 但し今では家庭に一本も無い場合もあるのでしないでしょうか。 「コンタクトZS(シャープ)」ならあるかもしれませんが、芯が細いので使いにくいですね。 コンタクト−Zの高級版として「紀州備長炭−Z」はどうか?と思い試してみましたが、効果はコンタクト−Zとあまり変わりませんでした(笑) お返事 2007/11/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
トイレにはサンポール。金属磨きにはピカール。 コンタクトZは丹精こめてナイフで・・・。 我が家を見たんか????(笑) 言われてみれば確かに昭和だ....。 (もう平成もずいぶん経つのに) ちなみに私の使ってるコンタクトZは2B(トゥービー)です。 (フォービーは汎用性に欠けてだめでした。(笑)) ガッツ 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
昭和の時代には様々なドラマがあります(笑) 接点復活剤が無い時には銅の端子を復活させるのに台所の「ソース」「しょうゆ」も活用したものです。
接点復活剤が無い時には銅の端子を復活させるのに台所の「ソース」「しょうゆ」も活用したものです。結局はソースやしょうゆの中の酸で銅の表面を腐食させて酸化膜や汚れまで全部剥ぎ取ってしまうという荒業ですが、結構効くのでTVのチャンネル切り替えのガチャガチャ回す「ロータリースイッチ」やなにやを分解して洗浄するのには効果的でした。 TVの映りが劇的に綺麗に! ガチャガチャ回すチャンネルなんて今の子供は知らないんだろうなぁ・・・ しかもそれをモーター(ソレノイド)で回す超音波リモコンがあったとか…左にしか回らなかったとか(笑) 昔話はさておき、今でも困るのはヘッドフォンやイヤホンで使われているようなプラグの酸化です。 1年程度放置しておくだけで銀色の端子が白っぽくなって接点復活剤でも完全には元に戻らずに接触不良が残る場合が多いですね。 家には無線機用のイヤホン等がごろごろしていますが、ちょっと使わずに忘れていて、酸化してガリガリ言いだすなんて日常茶飯事です。 そんな時には最後の手段。 紙ヤスリで金属表面を磨いて何もかも削ぎ落としてしまいましょう。 紙ヤスリと言っても荒いものだと本当に何もかも全部削ぎ落として傷だらけにしてしまいますので、「フィニッシュ用(仕上げ用)」として売られている「800〜1000番」のものが良いでしよう。私はいつも1000番を使っています。 1000番程度でしたら車の塗装の仕上げで塗装面を削ってもキズがつかない(逆に細かなキズ等を消す)細かさなので、プラグ等の表面の酸化膜だけ削ってその下の金属、特にメッキされているプラグ等でメッキを剥がさないので重宝します。 (いや、メッキごとほんの少し削り取ってはいますが) ガンコな汚れには、少し細かなキズが付きますが台所にある研磨剤「クリームクレンザー・ジフ」も結構使えますね。(水分が多いので要拭き取り) 「ジフ」を綿棒の先につけて端子をゴシゴシ磨くとかなりの威力があります。 ・・・・電子関係で使える薬剤はなぜか台所に多いようです。 以上、昭和の知恵袋のコーナーでした。 お返事 2007/11/6
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電エラーランプが点滅、急速充電は電池を痛める? (接点復活方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
はじめまして。 デジカメでの水中写真撮影用に充電器、充電池を所有しています。 充電器もいくつか持っているのですが、海外に居住しており、数年前に買った GP POWER BANK U-SMART という、超高速充電器を所有しています。 短時間で充電してくれるので、かなり重宝していたのですが、最近、表示ランプがチカチカ点等して、充電不可になることが多いのです。(新しい電池だと比較的充電可能で、電池のお尻と頭を拭いてやると充電可能になったりもします。) 超高速充電器は、電池によくないのでしょうか? この充電池で充電不可だったものを、別の充電器(VARTA MULTI COMFORT CHARGER)で充電してみると、充電できたりします。 短時間で充電できる充電器は、あまり日本にはないようなんですが、電池を傷める可能性があるからなのでしょうか? もし電池に悪影響を与えないようであれば、GPの充電池を使い続けたいんのですが、故障であれば、修理可能でしょうか? アドバイスお願いします。 ikan 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
GP POWER BANK U-SMARTは日本では見た事が無いのではじめて知りました。(どこか秋葉原の裏通りあたりだと売ってるかな?)
形も日本製品には無いスタイリッシュなデザインです。 さて、表示ランプが点滅してエラー表示、新しい電池だと端子を拭くと充電できる、という事は充電器の端子の金属が汚れているか表面が酸化して電気を通し難くなっている可能性が真っ先に思いつきます。 古い電池の端子も同じように薄い酸化膜が付いてしまっているかもしれません。 超急速充電器では普通の充電器より大きな電流を流します。 セットした電池と充電器の各端子が触れている場所ではどうしても「接触抵抗」が大きくなります。抵抗は電気を流し難くしますし、流す電流に比例してその部分で電位差が生まれます。 より大きな電流を流す超急速充電器では少しの抵抗でも充電中の電池電圧の検出に影響が大きくなりますので、他の充電器より不良電池の検出機能に悪影響が出やすいと考えられます。 充電器の端子が汚れていたり、電池の+−の電極が汚れている、また酸化している場合はアルコール系の洗浄剤で汚れなどを拭き取って、乾いた布で磨いて綺麗にしてやると回復します。 洗浄剤は電器店のオーディオコーナーの接続ケーブル等のアクセサリーを売っている場所で「オーディオクリーナー」等の名前でAV機器のコネクタやプラグを綺麗にする物が売られています。 海外ではどういう名前か分りませんが、秋葉原や日本橋の電気街では専門店で「接点復活剤」という製品が売られていて、汚れたり痛んだ金属接点を綺麗にして復活させるのに便利です。 まずは充電器と電池両方の端子・金属部を綺麗に清掃してみてください。 後は充電器の端子が弱くなっていて、じゅうぶんに電池を押さえられていないとか、やはり接触不良になっている部分が無いか確かめてください。 「新しい電池では…したら充電できる場合がある」という事は新しい電池でも充電出来ない時があるという事でしょうから、充電器側の端子が汚れているか弱っている可能性がかなり高いです。 清掃してみても改善されない場合は、充電器の内部的な故障の疑いもありますので、修理に出すしかないかもしれません。 ● 急速充電は電池をいためるか? については、ニッケル水素電池一般に言える部分と、各電池毎に言える事がありますので単純に「良い」「悪い」とは言えません。 ニッケル水素充電池の充電は普通は1C以下が望ましいとされています。 1Cとはその電池を1時間で充電できる電流の大きさで、2000mAhの電池なら2Aです。 「1時間充電器」くらいまでならおおまかに許容範囲内で、日本のメーカー製のものの多くは0.5C程度の電流で2時間くらいかけて充電するものが多いですね。 ここで間違ってはいけないのは「急速充電(但し許容電流以内)は電池に悪い」という事ではなく、急速充電でも低速充電でも電池へのダメージはあまり変わりません。 低速充電の場合は充電方法によっては「定格より寿命を延ばす事ができる場合」がありますので、急速と低速では電池の寿命に関しては違いが出ますが、「急速充電がダメージを与える」といった悪い面は基本的には持ち合わせていません。 急速充電時に問題が起きるのは、充電末期に電池が発熱して中の物質に悪影響が出るところで、これが設計上の許容範囲内であれば急速充電でも電池の設計上の性能を保てるように電池は作られています。 充電する電流が大きいほど、この充電末期に温度が上がる時間は短くなりますし、温度の上がり方も大きくなります。 急速充電器ではこのタイミングで正しく満充電を検知して、異常に充電を長引かせないような「満充電検知機能」がしっかりしていてるので、少し熱くはなりますが電池に異常なダメージを与えることはありません。 逆に言えば発熱がはじまる充電の最後のほうの時間までなら、かなりの大電流(もちろん電池の許容範囲内)で一気に充電してやっても電池にはダメージはほとんど無いという事です。 GPの30分超急速充電器ではこのあたりの満充電でのストップ制御を大電流充電でもうまく行えるように考えられているのでしょう。 日本・アメリカでは15分充電器・充電池という物が発売されていましたが、これは電池側に独自の機構を採用した特殊なもので、普通のニッケル水素充電池では2Cで30分程度までが許容範囲内と考えられます。 さてここから先は「電池毎」に違う点。 一言でニッケル水素充電池といっても様々な種類のものが売られています。 「大電流用」「高耐久型」など用途によって様々な電池が開発されていて、家庭用ではそのような性質のバランスの取れた商品が売られているのですが、そのような電池でも充電時の耐久性などはやはり各電池によって細かく違ってきます。 大電流充電への耐久性の弱い電池だと2C充電(30分充電)などをすると電池を痛める場合も考えられます。 ニカド電池の時代は電池本体にどの程度まで急速充電が可能(対応品)かが書かれていた物が多かったのですが、ニッケル水素充電池になってからはあまり見なくなりましたね。 これはある程度は一定の充電電流までは対応している事があたりまえになったのでわざわざ記載していないのでしょうが、詳しくは各電池メーカーの公表しているデータシートに書かれています。 データシートを公表していないメーカーも多いので困りますが。 市販品ではあまり無いとは思いますが、2C等の超急速充電に対応していない、または比較的弱い電池ではそのような大電流充電では電池を痛めることがありますので、不明な電池では超急速充電は行わないほうが良いです。 どの電池が対応していて、どの電池が非対応かをいちいちデータシートで調べて・・・なんて普通はできませんので、ここでは「その充電器を出しているメーカーの純正電池以外は使わないように」という感じにしかアドバイスできません。 GP POWER BANK U-SMARTでは、GP社製造の対応電池(これはメーカーがセットで売っているタイプの物など)以外を充電した場合には電池を痛める可能性はあるが、純正電池ならほぼ正常な状態で充電・使用できるでしょう。 (私の経験ではGP電池はそれほど素晴らしいわけでは無いので・・・以下省略) 「GP POWER BANK U-SMARTで充電できなくなった電池を他の充電器(超急速ではないVARTA MULTI COMFORT CHARGER)で充電したら充電できた」というのは、他の充電器が充電電流が少なめで、少し痛んだ電池でも超大電流充電器よりチェックが甘く(もちろん危険度も少ないのでそうなっている)適正に充電できると判定されたためでしょう。 もっと低速の充電器ではそのような不良電池の判定ロジックを持っていないものもありますので、判定なしに単純に充電電流を流すだけの充電器ならかなり劣化した電池にでも充電することができます。 もちろん痛んだ電池は充電できる容量も減っていますし出力電圧も弱くなっています。充電は出来ても新品のように使う事はできません。 お返事 2007/10/20
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
早速の詳しいご説明ありがとうございます!早速、明日、「接点復活剤」買いに行きます。 海の中では、電池交換ができないので、サンヨーの2700を何本か持っているんですが、今日、いろいろネットで調べていて初めて知ったのですが、充電池だけでなく充電器にもキャパがあるんですね。。GP U-Smart だと許容範囲(3200までOKと書いてありました)が、Varita の充電器だと、2100まででした。これだと、2700の電池でも最大2100までしか充電してくれないってことなんでしょうか?(すみません、超初心者で・・) 長期のダイビング旅行に出かけるので、サンヨー2700の電池と、同じサンヨーの対応充電器を新規に買おうと思います。GPも状態が改善すれば、持って行こうと思います。 2700は、「気の迷い」さまのサイトによると、ハズレがあるようですね。私も8本もっていて、ハズレ電池の可能性があるようです。 サンヨーのHPで製品紹介のサイトを見ていて思ったのですが、2700の充電池は、それ対応の普通の充電器とエネループ充填器、両方で充電できるようですが、良し悪しがあるのでしょうか? 「早い、薄い、軽い」の3拍子が超大好きな日本人なのに、なんでGP U-smartのような充電器を出さないのか不思議です。あったら、絶対に飛びつくと思うんですが。普通の急速充電器だと、単三4個充電すると、5〜6時間かかるんですよね。 長々と失礼しました。 ikan 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
「接点復活剤」は電子パーツ店の基板製作部品コーナー等にあります。瓶に入った液体タイプやスプレー式もあります。 普通の電器店にはなかなか無いのでご注意ください。 急速充電器には満充電を検知できなかったり、電池が満充電反応を起こさなかった時に過充電をしたり電池を破裂させてしまわない為の「安全タイマー」機能が入っています。 GP POWER BANK U-SMARTの説明で「4 x safety timer」と書かれているのがそれです。 具体的に何分で止まるのかはほとんど公表されていませんが、充電器によっては「最大xxxmAhまで充電対応」と書かれていますね。 どの時間で止めるのが安全なのかは電池の容量などによって違いますので一概に「何分」とは決められないのですが、その充電器が発売された時に同じく発売されている電池の最大容量+αに設定されいるはずです。 「2100mAhの電池まで」と書かれているのでしたら、+αで少し多い目まで充電できますが、多分2700mAhは満タンまで充電できません。 そのような場合は、手作業になりますが一度電池を外すか充電器の電源を切ってもう一度残りの充電をしてやれば満充電まで充電できます。 詳しくは『Panasonic充電器 BQ-390 個別充電表示化改造』ページに掲載しています「電源落としのテクニック」をご覧下さい。 三洋の2700mAhの充電池を充電する場合、エネループ専用のNC-TG1では充電できません。それ以外の急速充電器はエネループとセットで売っている物も2700mAh電池などとセット・または単体で売っている物は全て同じ製品ではから、違いはありません。 良し悪しも、早い・遅い・同時に充電できる本数、など充電器個別の性能の差があります。 GP POWER BANK U-SMARTのような充電器が発売されれば確かに買う人は多いと思います。 しかし電気製品の設計・製作現場では「最大定格の50%を市販商品の安全ラインと考える」という風習(自主安全基準など)があり、たとえ電池が2Cまで対応したものがあったとしても、それなら1C充電までが商品として世に出す物の制限いっぱい。「2CまでOK」というのは2Cまで対応はしていてもそれが最大なのでそれ以上は無理という事、つまり無理の直前で使い続けると品質の悪い物だと壊れてしまう可能性が大きい、なのでそんなギリギリ綱渡りは広く一般に販売する商品では危険すぎて売る事はできない・・・という事です。 電池業界の1つの提示である「ニッケル水素充電池は1C以下の充電が望ましい」という事であれば、その50%である0.5C程度までの充電電流に留めるというのが安全最優先を考える企業であればもっともな設計思想だと思います。 海外製品はよく壊れて、Made in JAPAN はあまり壊れないという日本製品神話もこういう安全設計に支えられている部分が大きいと思いますよ。 お返事 2007/10/21
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
電気屋さんでスプレー式「接点復活剤」をゲットしてきました。 GPの充電器ですが、改善しました。全てではないですが、エラー点滅が少なくなりました。 「接点復活剤」ですが、カメラバッテリーボックスの電池との接触部に使用しても問題ないのでしょうか? ikan 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
接点復活剤が入手できて良かったですね。 たとえば「こちらの商品」などではほとんど全ての電気製品の金属接点に使用できます。(リレー接点など一部は除く) 接点を復活させるだけではなく、そのまま保護剤にもなりますので、デジカメの電池ボックス内の接点にももちろん使用して大丈夫です。 軽くスプレーして、数分放置(薬剤が効く)してから乾いた布やティッシュペーパーで拭き取ってOKです。拭き取っても微量の薬剤が金属表面に残り保護効果が持続します。 本当は拭き取らなくても良い薬剤なのですが、ベタベタした薬剤が残ると電池の入れ替えの際に指や衣服を汚すといけませんし、余分なホコリを吸着して逆に接触不良の元になるといけないので、デジカメの電池ボックス・充電器の端子などでは軽く拭きとっておくほうが良いでしょう。 またごく稀にプラスチックを侵す場合がありますので、金属以外の部分についた薬剤は拭きとってしまったほうが良いでしょう。 長い間使っていた充電器の端子が汚れていたという事は、同じように電池の端子も汚れたり酸化していると思いますので、全部の電池の端子も接点復活剤で洗浄してやるともっとGP充電器でのエラーが減ると思います。 また一度の洗浄ではじゅうぶん復活しきれていない可能性もありますので、数日間隔をあけて2〜3度洗浄してみるのもよいかもしれませんね。 一ヶ月〜数ヶ月に一度程度、電池・充電器・デジカメの端子のクリーニングを行えばより長期に渡って良いコンディションで使用できますよ。 水中撮影で海に行かれるのでしたら、「接点復活剤」は他の電気機器のプラグや端子の洗浄・復活・保護にも役に立つと思います。 お返事 2007/10/22
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 10/24 |
詳しい情報、本当にありがとうございました。
ikan 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電池を並列にして保管すると電池残量は同じになる? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
いつも楽しく拝見しております。電池の取り扱いについて質問があります。 充電器によっては残量の違う電池はきちんと充電されないなどがありますが、並列につないで保管すれば電池の残量を合わすことは可能なものなのでしょうか? 可能な場合、このような方法は使用上問題ありますでしょうか? きし 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
たいていの急速充電器の場合は電池一本ずつをチェックして個別に管理しますので、容量(使用量)の違う電池を混ぜて充電しても大丈夫ですが、電池を直列で複数本充電するタイプの充電器では、満充電のチェックや充電の停止などを複数本単位でまとめてしか見ていないものがあります。 そういう直列充電式の充電器では、容量が違う電池を充電すると元の容量が大きかった電池が先に満充電を迎えて、容量が少なかった電池はまだ充電が必要ですからこの時点で充電終了すれば片方はまた満充電ではありませんし、充電を続ければ先の電池には過充電になりつつ続けて電流を流してしまい電池を痛めてしまいます。 満充電検知回路が入っている充電池では先に満充電になった電池の過充電反応を検知してじきに充電を止めるでしょうが(ちゃんと止まれば…ですが)、そのタイミングは正しく充電を止めなければならない時間より後になり少し過充電になりますし、もちろん中途半端で止められた残容量の少なかったほうの電池は満充電されません。 では、「電池を並列に繋いだら電圧の低い(容量の少ない)ほうの電池に電圧の高い(容量の多い)電池から電流が流れて、2つの電池の電圧(容量)が揃うのではないか?」という発想が出るのも当然ですね。 昔どこかで電池を並列に接続する電池ボックスやホルダーを「電池性能を整えるコンディショナー」と称して売っていたのを見たことがあります。 その理屈はある意味正しく、ある意味正しくありません。 まず第一に考えなければならないのは、ニッケル水素充電池の特性として『電圧と容量はイコールでは無い』という点が挙げられます。 電圧の値だけ見て電池の残容量がわかるのであれば、「ニッケル水素充電池の残容量を調べられませんか?」の質問に対して正確に残容量を表示するバッテリーチェッカーの回路などを示せたはずです。 しかしニッケル水素充電池は電圧の値ですぐに電池の中の容量を知る事ができません。極端に言えば「電圧が同じでも中の容量は違う」という性質を理解していれば、電池の電圧だけ揃えても容量が同じになる事は無いとわかり、並列で電圧を揃える事は中の容量を揃える事にならないとおわかりになるはずです。 その理論を確認する為の実験を行いました。 同じ銘柄・容量の電池A・B2本を用意し、どちらも満充電します。 そして電池Aは1/3になるまで放電、電池Bは2/3の容量の所まででストップさせておきます。 それぞれの実験用放電が終わってから6時間放置し、電圧を計ると電池Aは1.281V、電池Bは1.312Vと電圧だけ見ても電池Aのほうが少なくて電池Bが多いように見えます。 そこから電池AとBを並列に接続して12時間放置します。 なぜ12時間かと言うと、短時間では十分に二本の電池の電圧差が縮まらなかったので結果的に実験できるレベルまで縮まるのに12時間になりました。 電圧の高い電池Bから電圧の低い電池Aに流れる電流は繋いだ瞬間は数百mAありますが、あっというまに数十mA以下程度まで下がります。 つまり、2つの電池の容量の差にもよりますが電池を並列に繋いだ程度の電圧差では流れる電流はごくわずかで、充電器に入れる前の少しの時間程度では期待する効果が得られないという事です。 そして、12時間後では2つの電池の接続を切って別々に電圧を計っても0.001Vしか差が無い程度まで電圧は同じになっている事を確認して並列期間を終了。 もちろんそのままずーっと放置しておくと中の容量に差があればまた電圧差はじわじわと開いてゆくでしょうが、数分単位で見て0.001〜0.002V程度の開きなのでこの程度で実験用には十分だと判断しました。 そして放電器で各電池の残容量をチェックすると、下の図のように元の容量差とほとんど変わりが無いという結果が出ました。 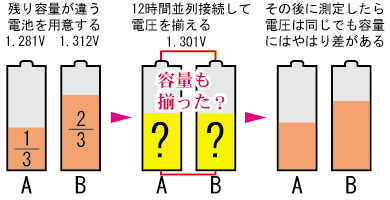 「並列にして電圧を揃えたら直列充電器でトラブル無く充電できる!」という説は間違いです。 先に「その理屈はある意味正しく、ある意味正しくありません。」と書きましたが、上記の実験でも2つの電池間で電流が流れて容量の多かったほうから少なかったほうに電荷が移動している事は間違いありません。 ただその量があまりにも少なく、「充電前に電池間の容量を揃えよう」という目的に対しては利用できない程度ですが、学術的には「並列接続した場合に2つの電池の容量はいずれ均衡する」という事で間違いは無いでしょう。 但しあくまで“学術的には”ですから、何週間〜何ヶ月間も電池を繋ぎっぱなしにしておいたら…という実用とはかけ離れた条件を考えなければなりませんね。しかも普通のニッケル水素充電池ならその保管期間中に自己放電して容量が減ってしまうでしょう。 実用的な時間内で平均化が終わるのは、2つの電池間の容量差などがごく小さくて、短時間に同じ電圧・容量になるくらいしか差が無かった時・・・しかしその程度の差だと直列充電でも充電時間に差は見られないでしょうから「やる必要なし」という事になりますね。 後は実用面では、同じように使用している電池でも個体差でわずかな性能差が生まれてきますから、たとえ充電前にきっちり容量をそろえたとしても充電中に同じ進行速度で充電されるとは限りません。 物によっては早く満充電反応が出たり、遅かったりと全く同じ電流値で充電しても個体差はありますから、2本や4本などの直列充電は電池にとっては基本的にあまり適した充電方法ではありません。 もし家庭用の単三や単四電池でこのことを考えているのであれば、個別に電池の状態を判別している充電器を買って使用するのがベストだと思いますよ。 お返事 2008/3/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リチウムイオン充電池の注意事項? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
はじめまして。いつも楽しく拝見させて頂いております。 リチウムイオン電池(プロテクト付き)について教えて下さい。 その明るさからRomisen RC-T5 4-Cree 3-Modeを自転車用に使用したいと思っています。 ただリチウムイオン電池(プロテクト付き)が初体験で迷っています。 ネットで調べるとリチウムイオン電池(プロテクト付き)は取り扱いが難しく、また自転車などの使用には不向き的(衝撃・ほこり・雨⇒発火・爆発)な記述もありました。 リチウムイオン電池(プロテクト付き)はUltraFire 18650 を考えています。 そこでお伺いしたいのですが、 Q1)リチウムイオン電池(プロテクト付き)の取り扱いでやってはいけないこと(充電時・使用時・放置時)はありますか? Q2)リチウムイオン電池(プロテクト付き)は自転車での使用は危険ですか? Q3)UltraFire 18650の通常使用で爆発などの事例はあるのでしょうか? 以上、お手数ですが、よろしくお願い致します。 taka 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
まず3つの質問に対しての回答、そしてその後に他の方への回答も含めて「リチウムイオン充電池の一般知識」に関する説明をします。 A1. 注意点 基本的に過充電・過放電は禁物です。 充電はその電池に対応した充電器で行い、正しく充電カットする充電器を使用しましょう。使用時には過放電しないよう注意しましょう。 「プロテクト付き」電池という事ですので、過充電や過放電はプロテクト回路が保護してくれますので使用中は特に気にする心配はありません。 放置時は、日常的にライトで使用して減ったら充電ならほぼ何も気にする事はありません。 メモリー効果が無いので継ぎ足し充電もOKです。 長期放置する場合、リチウムイオン充電池は「満容量充電状態では劣化が進みやすい」とされていますので、半分程度使用(または充電)した状態で保管するようにしましょう。 日常的にも毎日少し使っては継ぎ足し充電をして満充電にするよりは、数回に分けて使える容量と使用時間なら適度に使用と充電サイクルを計算して毎日充電して満タンにしっぱなしという使い方はしないほうが電池の寿命を延ばします。 携帯電話で、毎日家に帰ったらクレードルに載せて満充電にしている、という使い方は最も早くリチウムバッテリーを劣化させる使用方法ですね。 A2. 自転車での使用 衝撃に弱い電池ですので、電池にガタガタとショックが伝わるような場所での使用はお勧めしません。 ライトホルダーにクッションゴムが付いている(付けている)と良いのですが、硬くハンドルに固定するような場合は凸凹道を走ってライトの中の電池がガタガタ揺れたりすると後述する内部破壊でショート・発火の可能性があります。 RC-T5のボディ内径がわかりませんが、もし電池よりかなり余裕があってガタガタするなら電池に紙を巻くなどして隙間を埋めると共にクッションの代わりにしてやるのも良いでしよう。 マウンテンバイクで岩山でも走らない限りは普通の道路を走っている程度の衝撃ですぐに破損・発火するとは思えませんが、注意するに越したことはありません。 水・雨・ほこり、などは電池交換をコンディションの悪いオフロードで行わない限り、ライトに入れている間はほとんど心配は無いでしょう。ライトの中に水が入るようではそれはライト側の問題です。 A3. UltraFire16850 UltraFire 16850が爆発したという話は聞いていません。(私が知らないだけ?) 品質の悪い個体が多いとか、「表記より容量が少ない!」とかの苦情は良く聞きますが、まぁ中華電池ですし。そういう物としてつきあってゆくには何ら問題はありません。 私の手元のUltraFire 16850はプロテクト付き・無し共に特に不良や異常はありません。 「リチウムイオン充電池の一般知識」 ノートパソコン用バッテリーの発火・爆発事故(各国で複数件)や、中国で携帯電話用バッテリー爆発で人が死んだ?などの怪しげなニュースなど色々な報道からニセ情報まで様々な事がリチウムイオン充電池については言われています。 ではリチウムイオン充電池は常に爆発の危険性を危惧しながら使用しなければならないものなのでしようか。 だとすれば、皆さんが日常的に使用している「携帯電話」には大きく『爆発危険』と書かれていて、常に防火手袋をして手で持って、防爆ケースや耐火金庫に入れて持ち運んでいるのでしようか? もし発火・爆発したら・・・と考えると怖くて顔に近づけて使用するなんてもってのほか!ですよね。 でもそんな使い方をしている人は居ませんよね。 リチウムイオン充電池はほかのニッケル水素充電池・ニカド充電池と違って内部に使用している化学物質などが確かに発火性のある物を使用していますが、使い方さえ誤らなければほかの充電池とさほど取り扱いに違いはありません。 ● 電気的な取り扱い 電気的な、と言うと大きく2つに分けられます。「充電時」と「放電時(使用時)」ですね。 「充電時」には過充電してはいけません。 過充電すると活物質が金属リチウムに変化する化学反応が起こり、この金属リチウムは空気などと触れると激しく反応(燃える)するたいへん危険な物質なので、万が一発火すると燃え尽きるまでは簡単には火を消す事ができない物です。理系の方なら理科室の薬品棚にガラスビンに液体に沈めた状態でリチウムの個体を保管しているのを見た方も多いでしょう。私の通っていた学校(中学校の時か高校の時)では金属リチウムや金属ナトリウムが化学反応で激しく発火する実験などを実験実で行った記憶があります。 ちなみに、バッテリー内部で電極に使用している化合物の状態では簡単には発火したりはしない安定したものですので、通常のバッテリーは安全です。 「過充電」の状態になるのは2種類の原因が考えられます。 1つ目はその字の通り、満タンになっているのに充電をしてしまうこと。 電池に合った充電器で正しく満充電カットをしてやれば問題は無いですが、充電電圧を4.2V以上にしてしまうような充電器を使用する場合は要注意です。 2つ目は電池の許容量以上の電流値で充電してしまう事。 リチウムイオン充電池は1C以下の充電(0.5Cを推奨)とされていますので、多少はマージンがあるでしょうが大電流の急速充電器などでは充電電流値に注意して、電池の許容量以上の電流では絶対に充電しないようにしましょう。 許容量を超える電流で充電すると、活物質に吸収される量以上の電荷は受け入れられずに過充電状態が起こります。 「放電時」には過放電してはいけません。 単セル・リチウムイオン充電池は放電終止電圧は3.0Vまで、プロテクト回路の動作電圧は2.7V前後に設定されています。 ニッケル水素充電池と同じように、リチウムイオン充電池も中に蓄えられている電気を放出し尽くした時点で短時間で急激に電圧が下がります。 電圧がある一定の値を下回ると、電池内部で急激に悪い化学反応が起こって電池は回復不能なダメージを受け、この状態を「過放電」と言います。 リチウムイオン充電池の場合は0.6Vを下回ると内部で銅イオンが抽出されてしまい、これが次の充電時に化学反応の障害となったり、内部から電池のボディ缶を腐食させたり(最後には穴が開く)とかなりの悪影響を及ぼしてしまいます。 ラジコン用途などで「過放電させたリポ電池を充電していたら爆発した」などの事故が起きているのはこのような原因の為と考えられています。 「過放電」の場合は過放電させてしまっている状態の時に何かトラブルが起きるのではなく、次の充電時や使用中にトラブルが起きる「原因」を作ってしまっているのですぐに目に見えない怖さがあります。 ● 物理的な取り扱い 次に物理的な「取り扱い」について。 「衝撃を与えない」 リチウムイオン充電池に限った事では無いですが、バッテリーを硬い床に落としたり、何かケースの中に入れた状態でも激しい振動が加わる場所での使用は避けましょう。 バッテリーの中には薄い膜状の「正極」「セパレータ」「負極」「セパレータ」がミクロン単位の厚さでぐるぐる巻いた物が入っています。 このミクロン単位の物同士が並んでいる所に異常な圧力や衝撃が加わると一部が破損し、そこがショートして電池内部のプラスとマイナスの電気が一気に流れて発熱・過熱するトラブルが起き、その結果電池が爆発する事故につながります。 ノートパソコンの爆発事故では製造段階で電池内部にごく小さな金属片が混入し、このショート状態が発生して破裂・発火を起こしました。 ニッケル水素充電池やニカド電池でも同様の構造なので衝撃による破損・内部ショート・発熱トラブルはありますが電池が発火・爆発するまでの事はほとんどありませんが、リチウムイオン充電池の場合は使用している材質が異常時には激しく反応して燃焼してしまうところに危険性があります。 衝撃を与えた場合にも同様の事故の危険性がありますが、よほどの事が無い限りはその場ですぐに爆発するのではなく、衝撃を与えた時には内部に小さな「キズ」が発生し、そこが何度にも渡る使用で徐々に劣化していって最終的に限界を超えた時に急激なショートや発熱を起こすところにこれもすぐには分からないという怖さがあります。 「水に落としたり、高い湿度・結露する使い方はしない」 これは単純にショートするからですね。 ● 安全じゃないんですか? これだけ「痛む」「発火・爆発する」と書いてあると全然安全には見えませんが、それでは簡単に発火爆発するガソリンは発火するからといって自動車の燃料に使用しない事になっているでしょうか? 危険性を熟知した上で対策を施し、安全な範囲で使用するのであれば別段通常生活で使用するものでも特に触る毎に危険性に注意しておっかなびっくり取り扱う必要はありません。 自動車のエンジンを始動するたびに「今回は爆発しないだろうか?」とビクビクしながらキーを回す人は居ないと思います。 携帯電話やデジカメ・ノートパソコン、携帯用ゲーム機などでは専用バッテリーと言えばほとんどリチウムイオンバッテリーと、リチウムイオンバッテリーは世間ではものすごい数が使われています。 それらが安全に使用されているのはリチウムイオンバッテリーと共に専用の「保護回路」が機器に組み込まれているからです。 たいていの機器では機器にバッテリーを入れたまま充電するか、バッテリーを乗せる専用の充電器が用意されていますね。 それらの機器にはバッテリーの状態をチェックして「過充電させない保護」回路が入っています。 また「T端子」と呼ばれるサーミスタが接続された温度検出端子をバッテリーパックに用意し、充電中などに異常な発熱を感知すると即座に充電をストップする安全回路なども組み込まれています。 機器のほうには「バッテリー残量表示」がついている物が多く見た目でもバッテリーの残量を管理していることがわかりますが、その残量を計っている回路が正しく「過放電させない保護」回路として働いてバッテリーの電気を使いきった時に過放電させてしまう前に機器の電源を切ってしまってバッテリーを保護します。 ほかにも機器ではバッテリーの定格以上の電流を流してしまわないよう正しく計算されたバッテリーとの組み合わせで使っているとか過電流を感知して保護する回路が入っていたり、ノートパソコンのようにバッテリーパックの中で複数のセルが直列で繋がれているような場合には各セルの電圧を個別に計っていてセルバランスが崩れて一部のセルが過充電・過放電してしまうような時には使用停止処理をする(バッテリー管理専用チップがパック内に入っている)など、高度なセル管理と安全対策を施しています。 またバッテリーケースにも様々な工夫があり、18650のような裸のセルを扱う時とは違いプラスチックケースに入っているバッテリーパックの状態での対衝撃性や、機器に入れて使う時には機器やバッテリー蓋もガードするようになっているなど、機器に衝撃が与えられてもバッテリーは何重かのケース内にあって直接バッテリーの一部分に衝撃が加わって内部破損の原因にはなりにくい構造がとられています。 これら多くの安全対策が施されているからこそ、多くの家庭用機器・ポータブル機器ではリチウムイオン充電池を安全に「バッテリーパック」として使用できているので、そういう機器では特に「リチウムイオン充電池だからいつ爆発するかわからない」という心配をすること無く日常使用できるわけです。 もちろん、ノートパソコン発火爆発事故のようにメーカー製造時に不良品が混ざっていた!なんて不測の事態は例外です。 バッテリーパックを使用する機器ではメーカー純正品以外にサードパーティーから「互換バッテリー」などという名前で別のバッテリーパックが発売さていることがあります。 基本的に中身が同容量程度のリチウムイオンバッテリーであれば機器側の充電回路や過放電保護回路は問題無く働くと思いますので、普通に使用するぶんには技術的にはほぼ問題は無いと思いますが、容量がメーカー純正品と違ったり使用可能時間が違うなど、利用面での差やトラブルもありますので「そういう物」だと理解した上で使用するようにしましょう。 ● 単セル・裸バッテリーの場合は・・・ 18650型バッテリーのように、電池一個で裸(ビニールは被っていますよ)で売られている物は基本的には「一般用」では無いので、使用するにはそれなりの知識と自己責任が必要です。 電気店やスーパーマーケットで誰でも買えるマンガン・アルカリ一次電池やニカド・ニッケル水素二次電池とは段違いの様々な危険性や制約がある電池ですので、使い方を誤ると大きな事故に繋がります。 「プロテクト付き」電池では過充電や過放電、また過電流保護などの働きをする回路が入っていて充電・放電(使用)時にはかなりアバウトに使用可、それこそニカド・ニッケル水素充電池とあまり変わりない感覚で使用することができます。 充電器も専用の物を使えば電池を載せるだけで数時間後には完了していますし、使用時にはプロテクト回路が過放電を防止してくれるので懐中電灯等のように機器側に自動停止装置(過放電保護回路)が付いていない単純な機器での使用でも心配はありません。 プロテクト回路の存在はニカド・ニッケル水素充電池より便利な面もありますね。 「プロテクト無し(生セル)」の場合は保護回路などは全く無いので、使用者・機器のほうで過充電・過放電などの管理を行わなければなりません。 過充電は充電器が管理してくれるでしょうが、過放電に関しては使用する機器側で対応回路が無い場合は「過放電になる前に人間がスイッチを切る」以外に方法はありませんので、間違って過放電させてしまうとしばらくして発火・爆発などの危険性を内包した「いつ爆発するかわからない時限爆弾のような電池」を生んでしまいますので、そうならないようにかなり取り扱いに注意しなければなりません。 基本的に2本以上直列で使用する場合は、セルバランスが崩れると全体の電圧では正しく充電完了電圧や終止電圧の検出はできませんので、各セルの電圧を計る回路を用意するか、もしくは使用時はすべて「プロテクト付き」電池を使用することになります。 ニカド・ニッケル水素充電池でも同じですが、プロテクト付き/無しのどちらでも落としたり衝撃を与えてはいけません。 特に裸セル状態では衝撃が直接セル単体・また内部に伝わりますので内部の破損につながります。 落として缶の側面に凹みが出来た電池、などは使用しないようにしましょう。 海外通販で買うと、届いた時にはもう缶に派手な凹みがある電池が来る時があります(笑) お返事 2008/2/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リチウムイオン充電池の保管方法? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
リチウムイオン充電池の扱いで、過去記事を拝見しましたが、載っていない事項のようなので質問させていただきます。 プロテクト付リチウムイオン充電池なのですが、自転車用の懐中電灯に使用しております。冬場はほぼ毎日活躍しますが、春〜秋の半年くらいは使わなくなります。この場合、過放電にしないためにはどのように扱えばよいのでしょうか?よろしくお願い致します。 takahasi 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
2/1のお返事に
バッテリー機器メーカーベイサンのHPではリチウムイオン電池の基礎・13.リチウムイオン電池を上手に使う方法など一般の方にもわかりやすく説明されています。 ● できるだけ少ない容量充電で保管する ● できるだけ低温で保管する の2点を守ればリチウムイオン充電池の保管時の寿命は延びますが、少ない容量といっても0%に近い状態ではいくら自己放電の少ないリチウムイオン充電池でも長期保管中に電圧が下がってしまう事は避けられませんから、保管期間とその電池の個性(放電量)にあわせて適切な充電量で保管を開始してやれば良いのです。 しかし何%が適切か、というのはメーカー等で厳密な測定でも行わないと数値としては出てこないでしょうし、バッテリーの劣化度によっても異なります。更には一般家庭では保管時の温度なども様々ですから的確に「何ヶ月放置するなら何%が良い」とは言えません。 ですので「満充電では劣化を早めるので充電量を減らしておく」という理屈から各電池メーカーや機器メーカーによって「50%」や「30%」など各自の基準で『そう言っている』のです。 同じ理由で私も「半分程度(50%)」としか言えません。 低温で保管とは言っても凍らせたりしてはいけません。 冷蔵庫に入れるのも手ではありますが、メーカー各社が言うように結露の問題などがありますので家庭用の冷蔵庫で冷やしたり、そこから突然常温に取り出して使用などは絶対にしないでください。 夏場の保管では日当たりの良い場所や高温になる部屋に置くのではなく、冷暗所に保管したほうがより寿命が延びるでしょう。 正常なリチウムイオン充電池であれば、春〜秋の半年で50%の容量が0になる事はまず無いはずですが、心配でしたら一ヶ月に一回くらいは電圧を計って3Vを下回っていないか確認してください。 普通は充電後の保管開始時の電圧とほとんど変わっていないはずです。(というか激しく下がっていたら不良品かかなり劣化した電池です) お返事 2008/2/22
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リチウムイオン充電池の交換と保管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
秋月充電器、各社アルカリ乾電池/ニッケル水素電池比較記事を拝読して以来、その内容の深さ/情報の豊富さから、こちらの記事・投稿が更新されることを楽しみにしております。 私自身は電気等の知識はありませんが、ますます興味を持つようになりました。 今回、リチウムイオン充電池について教えていただきたく、投書させていただきました。いわゆる質問サイト等、ネット上の情報を読むと様々なことが書かれており、読めば読むほど混乱するばかりです。 現在使用中携帯電話のバッテリーパックを予備も含め3個持っています。 1個を携帯電話に入れて使用、残りは予備として保管し、数箇月使った後、これらをローテートさせたいと思っております。 (携帯電話使用→予備A→予備B→携帯電話使用→予備A→→) このとき、電池の性能劣化を最小限に抑える為には、 「どの程度の期間でもって、ローテートさせるべきか」 「予備保管にあたっての電池の充電状態はどうするべきか」 「その他、注意すべきこと」 を教えていただけたらと思っております。 携帯電話での使用のみならず、不要な携帯電話機はLi-ion充電器になるわけで、工夫すればいろいろと利用価値があるのではないかと思っております。 長い文章になってしまい恐縮ですが、教えていただければ嬉しいです。 先日、リチウムイオン充電池に関して質問させていただきました。 あの後、自分で再度、いろいろと検索をかけましたところ、 http://dennou.stakasaki.net/xiedai03_battery-j.html へ、たどり着きました。 私の疑問点、リチウムイオン充電池の保管法についても解説されています。これによると・・・ 「50%の充電率で保存し、半年に一度は追充電」ということで、私の場合、50%充電状態で保管し、3箇月ごとに電池入れ替えというのが妥当なところかなと思っております。 また、使わずに放置していたノートPCのバッテリーも早速、50%充電をいたしました。 気の迷い様としては、いかがでしょうか。 気の迷い様も、同様のご意見であれば、お忙しい中、私の愚問にわざわざご回答いただかずとも結構です。もちろん、サイト内容の充実のため、あるいは気の迷い様に別のお考えがあれば投書欄に掲載したいとの事であれば異論はございません。 これからも更新を楽しみにしております。近くにお住まいであれば助手として使っていただきたいくらいです。 SONY液晶付オーナー 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
既に自己解決されているようですので、特段追加する事はありません。 私も初期のノートパソコンのバッテリーを30回充電程度で潰したことがあります。 たまに持ち出して、ふだんは家で使うのにAC電源に繋ぎっぱなしで満充電状態(勝手にわずかな使用と充電の繰り返し)にしておいたら、「バッテリー劣化0%」「充電可能容量100%」との表示なのに突然「充電できません」となり、以後使用できなくなりました。 バッテリーパックを分解すると、いくつかのセルが死亡していて残りはまだ使えましたが、当時は今のようにネット通販で簡単に生セルが手に入る状況では無かったので、高いメーカー純正品を買い直したものです。 以後はノートパソコンのバッテリーは約80%程度の容量を残して本体から外しています。 携帯電話のバッテリーを数個ローテーションされるという事ですが、これは毎日の携帯電話の使用条件などがわかりませんので、特にアドバイスできることはありません。 適当にローテーションをして、各電池が性能低下する前のオイシイ所を3個ぶんの時間も使えばかなり長い間使えるのではないでしょうか。 私の今使っている携帯電話バッテリーは1年半でかなり使用時間が短くなってしまったので一個買って交換しました。弱ったバッテリーは使用していません。 あと少しで「DoCoMoは同じ電話機を2年使用したら、交換用バッテリー一個無料プレゼント!」期間になったのにと思うと少し残念です。でもあと少ししたら2年になるので無料でバッテリーを貰って予備用に置いておくつもりです。なんといってもタダ!で貰えるのですから(^^; お返事 2007/10/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 単三電池の容量は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
素朴な疑問なのですが、一般的な単3乾電池って何mAhなのでしょうか?
(匿名希望) 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
マンガン電池やアルカリ電池には決まった「XXXXmAh」という容量はありません。 充電池と違い、マンガン電池やアルカリ電池は消費する電流値によって取り出せる合計容量が大きく変わる為、一概にXXXXmAhというわけにはゆかないのです。 詳しくは「新・金パナ(赤金パナ) 性能評価試験」ページの“おまけ、アルカリ電池の容量”で既に書いていますのでそちらをご覧下さい。 1Ω負荷で使用した場合の単三アルカリ乾電池がどのくらいの容量なのかも測って結果を掲載しています。 お返事 2007/4/24
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電電流、温度によって放電特性、充電容量は変化するのか | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
こんにちは、いつも参考にさせていただいております。 さて早速ではありますがお聞きしたいことがあります。 それはニッケル水素電池の充電時の充電電流、温度によって放電特性、充電容量は変化するのかということです。 私はラジコン用にニッ水を使用しておりますが、その筋のHPや本を読むと高電流で充電したものは放電時にパンチ力(おそらく高電流)が実感できるとあります。 実際に私も単四バッテリーを約1.5Cほどで充電して使用してみたとこを加速力にあきらかな違いを感じることができました。 しかし、1.5Cで充電したものを数時間おいて使用したときには違いを感じることはありませんでした。 きちんとした測定器を使用しての情報ではないので測定器を使ってみれば違いがあったのかもしれませんが・・・。 そこで私なりに考えた結果、充電電流ではなくむしろ充電時、使用時の温度が関係しているのではないかと思いました。 また充電容量の変化というのは知人から聞いた充電方法を試してみようと思い新しく買ってきた電池を充電したときに表示されている容量が3300mAhだったのに4000mAh近くまで充電できたので関係があるのかとおもいまして・・・。 その充電方法は充電初期は1.5C〜1.8C程度で容量の70%くらい充電→0.4A程度で75%ほどまで→1C〜1.2C程度でオートカットがかかるまで、というものでした。 ちなみに買ってきて一度満充電後、2Aで放電しています。放電器は1セル0.75Vでオートカットがかかります。 これも温度が重要な気がします・・・。 よろしくお願いいたします。 たまお 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
電池に充電できる容量の最大値(電池が受け入れられる量)は充電方法や電流によって目に見えるほどは変わりません。(目に見えない程度、数値で測っても誤差の範囲程度は様々な要因で変わるでしょうが…) 定格で3300mAhの電池に4000mAhと「20%増し!」なんて事は物理的にはありえませんから、それは単に電池に蓄えられずに熱として逃げている電力ぶんまで含めた数値を表示しているものだと思います。 70%くらいの所で一旦充電電流を落としているのはその時点で充電による発熱や化学反応を遅くしていますよね。3300mAhの電池に対して0.1C程度まで充電電流を落としたら低速の標準充電になって電池はほとんど発熱せずに充電される状態になり、満充電時の熱などによる−ΔV反応がほとんど出ない状態になります。電池状態がそうなると同時に低レート充電では流した電流に対して実際に電池に蓄えられる電気の量は少なくなりますので、もしその期間に単純に流した電気量をカウントしているだけの容量表示だと実際の充電量より数字だけが多くなってしまい見た目だけは容量が増えたように錯覚させられてしまいます。 そしてその状態からまた1C程度の充電に切り替えると、充電せずに放置していたのとほとんど変わらない電池状態から最後の満充電までの充電を行いますので、1C程度で最初から充電していた時よりも−ΔV反応が出るのが遅くなる(電池が冷えている)ことも考えられますので、充電器が充電完了を感知するのが少し遅くなってその間に余計に電流を流し、この要因でも実際に電池に充電される電流量よりも多くの数値が表示されるという可能性も考えられます。 その充電器がどこのメーカーの何で、どのような計算をして数値を表示しているのかがわからないので一般的な話でしか想像はできませんが、3300mAhという表示の時が「実は満充電感知をミスしていて小容量で終了していた!」なんて事が無い限り、3300mAhのほうがその電池の正しい容量であれば4000mAhという表示はどう考えても充電ロスぶんを多く含んだ数値に思えます。 たとえば、正常な満充電容量が3300mAhの電池があったとして、満充電しておいて少し置いた物にまた追い充電をしたとしましょう。 1〜2C充電で追い充電した場合、−ΔVを検知して充電がストップするまで(充電器の種類などにもよりますが)数分〜10分かかります。−ΔV以外の別のアルゴリズムもあわせてプログラムされている充電器ならもう少し早く止まるかもしれませんが、ラジコン用の一般的な充電器ならセル数にあわせて計算した−ΔV値の反応を検知したら充電をストップします。追い充電などでは電池内部の反応がこの数値ぶんに至るまで通常は数分かかります。 1Cで10分追い充電できたとして、1Cの16.6%、3.3Aだと約550mAhぶんの電気が既に満タンになっている電池に更に充電できたかというとそうではありませんよね。 満タンの電池にはそれ以上は充電されませんから、流した電流約500mAhぶんのエネルギーのほとんどは熱として電池を暖めて放出されています。 でないと、もし追い充電で流した電流が全て電池に吸収されるとしたら、追い充電を2回・3回・4回…と繰り返せば永久に電池に容量を継ぎ足して行く事が出来ます。ノーベル賞をいくつももらえるくらいのまさに物理の法則を破る画期的な充電方法となるでしょう。 これらの事から考えても充電方法を変えたからといって10〜20%という大幅な容量アップは充電器に表示される数字上のマジックで、実際に電池にそれだけ充電されている事は無いでしょう。 条件が書かれていませんが、もしその3300mAh・4000mAhが「放電容量」(放電器で放電した時の容量)でしたら、3300mAhのほうが完全な満充電になる前に充電を止めてしまっている可能性が高いのでよく調べてみてください。 たとえばサブCセルの6セルパックをパックのまま充電していて、中の1〜3セルが早く充電が終わって−ΔV反応を示し(充電中にどんどん電圧低下し)、その為に6本全部がちゃんと充電される前に合計値での電圧が−ΔVの検出閾値を超えてしまうので途中で充電をストップさせているとか・・・ ニッケル水素充電池(ニカドもだいたい同じ)の放電性能(大きな電流が取り出せるか)については温度と大きく関係があります。 暖かいほど活性化して大きな電流が取り出しやすくなり、冷たいと大きな電流が取り出せません。 レース時などはバッテリーウォーマー等で電池を暖めておいて、走る直前にマシンに載せるという手法がよく使われていますね。 レース前に追い充電をするのは持ってくる前に充電した状態からほんのわずかでも自己放電している容量を補って本当にそれ以上は入らない程の満容量で電池を使いたいのと、実は「過充電させて電池が発熱する」事で電池温度が上がってより大電流がとりだしやすくするという理由のほうが大きかったりします。 後で書きますが一時的に電圧を上げてやることもできます。 満充電して持ってくるのか、何%で止めておいて持ってくるのか・・・などはレーサーの方によって様々な意見やノウハウがあるのだと思いますが、共通する事は追い充電ではチンチンになる程まで発熱しているほうがパンチがあるという事です。(やりすぎはいけませんよ…) ウォーマーで暖めるのではなく、過充電で電池自体か発熱する事を利用して電池を暖めているだけですが、容量もMAXにできる事とあわせればある意味合理的な方法ですね。 但し、必要以上に電流を流しているので電池を過熱させる以外に電池内部では過充電反応でガスが発生しています。 ニッケル水素充電池はある程度まではガスが発生しても電極に吸収還元するしくみになっていますが、これを無理に発生させる追い充電ではガスの吸収還元が追いつかずに安全弁から外部に放出させることにもつながります。 ガスとして放出される分子は電池内部で電気を蓄える為に使用されるもの(電極を構成するもの)ですから、それが逃げれば当然電池の容量は減ってしまいます。 「過充電で電池を痛めても(寿命が短くなっても)良いから、一時的なパンチが欲しい」・・・これが“そういう用途”で充電池を使うラジコン用途での特殊な使い方ですね。 ラジコン用でなくても、手元にある1980円くらいの充電式シェーバー(ニカド電池入り)も1時間急速充電が完了した直後のまだ暖かい時のほうが、満充電後時間を置いて使った時よりもパンチが実感できます(^^; 温度以外にもニッケル水素充電池・ニカド電池などは充電直後は充電器によって与えられていた高い電圧を維持てしいますので、そのぶん抵抗負荷やモーター等ではパワーがより強くなるという要因もあります。 充電時に大きな電流を流すには高い電圧をかけますので、ハイレートで追い充電をして電池により高い電圧を覚えさせる(一時的ですが…)のもモーターをより強く・速く回す為には良いと思いますので、ラジコンで追い充電をする(または満充電直後に使用する)のはまさに理に叶った使い方ですね。 たまお様が単四電池をハイレート充電(これも発熱が大きい)をしてパンチが出たが、しばらく置くと普通の電池になったという事の理屈は上記の説明でおわかりいただけるかと思います。 ご自身でも温度が関係しているのではないかと考えられていることは、非常に良い点に気づかれていると思います。 ラジコンの世界では「大電流で充電・放電を繰り返せばその電池は大電流用に育つ」とも言われていますが、これについては私のほうではまだその原理が特定できていませんし、そうなる事も確認していませんのでこの育成理論については理解できていません。 先にも書きましたが追い充電に関してもどれだけの容量まで準備しておいてレース直前に追い充電すると良い、また準備充電から追い充電までの時間は○○時間が良いなとはレーサーの方によって方法が異なるようですし、電池のメーカー・種類によってその容量や適正充電レートが違うなどと言われています。 聞いた話では同一メーカーの同一名称のバッテリーパックでもロットによってその適正時間やレートが全然違っていた!なんて事もあるそうですので、細かなノウハウについては皆さんがご自分の使用されている製品と環境で研究されて良い方法を見つけられるしかなさそうです(^^; お返事 2008/5/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
お返事ありがとうごさいます。 やはり放電時の温度は重要な要因だったのですね。 いま温度管理できる充電器をもっていないのでほしくなりました^^; 安全面を考慮しても購入したほうがいいですしね。 電流を変化させる充電方法で充電器に表示された容量が電池の定格容量を超えたことについても納得できました。 ところで充電方法の目的を書くのを忘れていましたね^^; 管理人様もおっしゃっていた高電流で充電すれば高電流で放電できるということを意識しているようです。 そのことを意識しつつ温度をあげすぎないようにと考えたもののようです。 このたびは本当にありがとうございました。 これからも参考にさせていただきますので調査、HP更新がんばってください。 たまお 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
幾種類かの充電器を買っていろいろな条件で試してみるのは面白いですよ。 ご自分の使い方で最も適した方法を見つけられると良いですね。 お返事 2008/5/12
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池をホルダーに入れたまま保管しても良いですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
いつも役立つお話をありがとうございます。 電池の保管方法に関して質問をさせていただきます。初歩的な事で恐縮です。 複数の電池を保管する場合、直列状態に繋げたまま保管しても問題はないでしょうか?先頭の+極と後尾の−極には何も接触させません。 回路を形成していないので問題無いとは思うのですが。 状況としまして、フラッシュライトにCR123Aを3本使うのですが、3本を直列でホルダーに入れ、ホルダーごとライト本体に入れて使用します。使わない期間が長く見込まれるときはライトからホルダーを抜き、電池はホルダーの中に入れたまま保管しているのですが、3本の電池が直列に接触したままで保管するのは電池にとってどうなのかなと思った次第です。 よろしくお願いいたします。 30M 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
基本的には、電池は電気を流す物ですから、電気的に回路を構成していなければ中の電気は消費されません。 ですから、ホルダーなりケースに入れた状態や、機器の中に入れて完全にスイッチが切れている状態であれば裸で保管している時と全く変わりなくその電池の保管期限までは保管できます。 ただし、私自身の経験からも「機器の中に入れておくと早く液漏れする場合がある」という事です。 今回ご質問のCR123Aリチウム電池では経験した事がありませんが(そもそもCR123Aの液漏れは聞いた事が無い)、マンガン電池・アルカリ電池などでは機器の電池ボックスに入れてスイッチを切っていたにも関わらず、外に出しておいた同じ時に買った電池は平気なのに機器内の電池は液漏れしていたという事が何度かありました。 もちろん放置していた電池は電気をあまり消費しておらず、機器内の電池は少しですが使って電気が減っていて寿命に近づいていて液漏れしやすくなっているという状況ではあります。しかし使用頻度もほとんど無い機器で、数回少しだけ使った程度という電池でそういう差が何度か見られましたので、やはり機器内での保管には電池を早く液漏れさせる作用がありそうです。 これは機器の電池ボックスがバネで電池の+か−の端子を押さえつける構造のため、常に力がかかってパッキン等の劣化や剥離を早く起こして中から電解液が漏れてしまうのではないかと考えられます。 従って、外部に取り出せる電池ケースのような場合はそのケースが電池ボックスのような構造でバネなどで電池を押さえている場合はできるだけそのケースからは電池を外しておいたほうが良いです。何も押さえずに単に筒の中に電池が並んで入っているだけの場合は裸で置いているのと同じようなものですからそのケース内に収めたままでもよいでしょう。 「長い間使わない場合は電池を取り出してください」という注意書きが機器の説明書にありますが、単に電池が液漏れする物であるという以外に、こういった電池ボックス内での液漏れ促進?効果の影響も危惧されているのだと思います。 CR123Aリチウム電池の液漏れは聞いたことがありませんが、念のためCR123Aでもなるべく機器の中での保管はせず、外に出して保管するほうが良いのではないでしょうか。 そして、仰られるような電気接点の無いケースであれば電気的にも圧力という点でも何も問題は無いのでそのまますぐ使えるようケースに電池を入れていても大丈夫です。 お返事 2009/6/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
早速のご回答をありがとうございます。 安心しました。 電池同士を直列で接触させての保管は、よくわかりませんが例えば電荷の移動?とかが発生して残容量が偏ってしまったりしないのかと思った次第です。 ライト専門店などでたまに見かけるのですが、元々バラのリチウム電池を店で数本の簡易パッケージにして売っているものがあり、接触する極間に紙を挟んであったので、そのような理由かなと気になりました。 ◇液漏れに関してはご指摘の通りの経験をしたばかりです。 テレビのリモコンにオキシライド電池を入れて(リモコンにオキシライドはいかがなものかと思いましたが手元にこれしかなかったので)使っていた所、わずか4ヶ月でリモコンが動作不能になり、電池を確認したところ、みごとに液漏れしていました。確かに電池ボックスのバネが非常にきつかったです。 ◇これで疑問に思っていたことが一掃されました。 ありがとうございました。 30M 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
電荷の移動とか、「静電気になって電気が逃げて行く」とか、都市伝説は沢山あります(^^; 電気回路が構成されていないのに、接触させておくだけで隣の電池に電気が移って行くとしたら、電池内部の電位差以外に地球上の何かの電気的な要素が電池に対して集中的に働かないとそんな事は起こりませんので、ピラミッドパワーが働く立体三角形の中に置くとか、飛行機や船が消滅するデルタゾーンの中で電池を保管するとかの科学的に解明できない特殊な状況にでも置かないと目で見れる程の異変は起こらないでしょう。 お返事 2009/7/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Section. ●● 充電する・充電器・互換性 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エネループをパナのBQ-390で充電しても良いですか?(他社充電1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
こんにちは。 エネループをパナソニックの充電器で充電しているようですが、問題ないのでしょうか。自己責任で行なっているのですか? 自分は、ソニーの充電器(BCG-34HRE)を持っていますが、CycleEnergy(まだ買ってません)だけでなく、エネループを充電しても大丈夫ということでしょうか。 mi84ta 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
分解、改造、充電池の他社充電器での充電は全て自己責任です。 「自己責任」って言葉で全て丸め込まれてしまうのはあまり好きではありませんが、「自己責任」以外に良い言葉が無いので「気の迷い」でも改造記事の場合は「自己責任で」と書かせて頂いています。 まず先にBCG-34HRMEでエネループを充電しても良いか?という点について。 CycleEnergyは三洋エネループのOEM品で、名前とデザインは違いますが中身はまんまエネループです。(こちらの購入実験でも充電・放電特性に差異はみられません、中身が同じなのであたりまえの事ですが…) ですので、ソニーの充電器で自社ブランド品としてCycleEnergyを出して充電しても良いということは、中身が全く同じエネループでも電気的な「問題」が起きる要因は考えられません。 と、ここまでは私の私見です。 実際には上記内容はメーカーが公式に発表しているものではなく、メーカーの言う通りエネループを他社充電器で充電することは公式には禁止です。 ここで言う「問題」とは、充電できない、著しく放電特性に支障が出る、充電中に燃える、などのどう考えても「事故」や「不良」と考えられるようなトラブルの事です。 トラブルが起きた場合、ひとつのメーカー製品内であればそのメーカーの責任として対処されますが、A社の電池をB社充電器で充電した場合はどちらの側に問題があるのかの特定や責任保障の取り扱いが非常に難しくなります。 難しくなるので「他社製品禁止」と書いてある以上、何か起きてもメーカーは「他社製品を使ったから」という理由でクレームを却下できます。(本当はある程度までは丁寧に対応してくれますけど) 電気的な面(技術的な面)ではどのメーカーの電池でもある一定の規格で統一されていて、商品により性能差はありますが規格差はほとんど無い為に同一規格の製品であれば、どのメーカーの電池をどのメーカーの充電器で充電しても大きな差や問題は無いものです。 これを技術の世界では「互換性」といいます。 また、同一メーカーの充電池・充電器であればその電池の性能を最大限に引き出せるように充電器は調整されていますが、他社製充電器で充電すると最大限の性能は発揮できずに少し劣るような可能性も考えられます。 自社製品はやはり最高のパフォーマンスで使用してもらいたいものですから、各メーカーの「他社製使用禁止」にはそういう意味もこめられています。 「互換性」の観点で見て問題無いものであれば電池も充電器も各社相互に利用できる物ですが、万が一の事故の場合の事を考えて、あまり電気や電池に詳しく無い方にはメーカーの言通り同一メーカー製品同士の使用をお勧めします。 なぜならそれは各メーカーが十分にテストをして安全性を確認した上で市販商品として販売しているもので、それ以上の安全・安心はありません。 まぁ改造やら怪しい内容を紹介するHPの管理者の言葉なので説得力には欠けますが(汗) ほかの情報は本ページに移動したいくつかの「エネループを××充電器で充電していいですか?」の返信をお読みください。 お返事 2006/12/7
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エネループをパナのBQ-390で充電しても良いですか?(他社充電2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
エネループの電池もパナのパナループ?の充電器でも使用できるらしいとメーカが行っていましたが、廉価版の充電器で4本充電タイプでたとえば3本充電しておいて、そのまま後から空になった電池を追加充電した場合、充電済みの電池は過充電にならないのでしょうか、1本管理ではないと思いますが、説明書にも詳細の記載なしですし、 さらに、15分充電タイプの充電器で充電すると寿命が短くなったり、メモリ効果を起こしやすくなるものでしょうか? ミークン 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
たいへん申し訳ございませんが、その「廉価版の充電器」のメーカー名と型番は何でしょうか? 型番も何も情報が無いので私としましては何も確定的なことをお話しすることはできません。 また後にも述べますが、充電器の機種別の動作に関しては自分で確認した機種以外では「一般的」な内容しかお答えできませんことをご了承ください。 一般的な話しとして、ほとんどの充電器の使用説明書には (1) 電池を充電器にセットする (2) 充電器をコンセントに差し込む (3) 充電が完了したらコンセントから抜く (4) 電池を取り外す という手順で充電するよう書かれていると思います。 ですので、一旦充電が終った(充電中でも)充電器に、たとえソケットに空きがあっても途中から電池を追加することはメーカーの定めた充電手順とは異なりますので、私としましてはお勧めできません。 メーカーもそういう充電方法では正常な充電を保証していないと思います。 (保証するなら説明書に書いているはずです)
一本ずつ「個別充電」方式の充電器でもそれは行わないほうが良いです。 たとえば三洋NC-M58では、その方法で後から電池を一本差し込むと、全てのソケットの電池の(充電器内部で記憶している)充電状態がリセットされ、充電完了している電池にも新たに充電が開始されます。(これは三洋電機にしては危険な要素を含んだロジックだと思います) 充電完了している電池は数分〜十数分で満充電が検知されてたいした過充電にはなりませんが、電池の種類によっては数十分以上の追加充電が行われて過充電になる場合もありえます。 三洋NC-M58のOEMの東芝・マクセル・フジほかの充電器も同じ動作だと思いますので、これらでは後から電池を足すのは良くありません。 松下BQ-390ではそのようなリセットは行われず、追加した電池にだけ充電が開始されます。この充電器では電池を追加してもほかの電池は再充電・過充電にはならない事を実験で確認していますが、説明書にはこのような使い方は書かれていませんのでメーカーの意図した使い方ではなく、やはり一消費者の立場では行うべきではありません。 (「気の迷い」に書いてあった、という理由ではメーカーは許さないです)
このように充電器のメーカー、機種により実際の動作は様々ですので、一概に「廉価版」や「個別充電」などという表現では充電器の挙動に関しての細部まではお答えすることはできません。 また上記二種類以外では内部を分解しての動作試験は行っていませんので、細かな挙動に関しては機種を指定されましてもお答えしかねますのでご了承ください。 「15分充電器」は専用の15分充電タイプの電池以外は自動的に識別されて、15分では充電できないとパッケージ・取説に書いて有ります。 15分充電器にエネループ等をセットしても通常の急速充電しか行われないようですので、劣化などは通常の急速充電器を使用した時と同じだと思います。 ほかの情報は本ページに移動したいくつかの「エネループを××充電器で充電していいですか?」の返信をお読みください。 お返事 2007/1/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エネループをパナのBQ-390で充電しても良いですか?(他社充電3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
エネループをパナのBQ-390で充電すると電池が痛んだり完全な充電が出来ないなどの現象は考えられるでしょうか? 手持ちがパナの充電器なのでエネループはやめておいた方がいいでしょうか。 キラリ☆ 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
同一種類の充電池で、基本的な性能が類似している電池同士であれば、技術面から言えばどのメーカーの電池・充電器の組み合わせでも問題はありません。 充電器の回路・動作の面からニッケル水素電池の2000〜2100mAhタイプに対応した充電器では、エネループやHR−3MPSを充電しても充電は正しく行われるはずです。(充電器の個別充電回路が正しく判定していれば) 上記の事はあくまで技術面から見た充電動作についてです。 痛めるかどうかについては、充電器の充電完了判定やその基準値によって満充電時の電池に与える影響は多少変わってくると思いますので「1000回充電できる」というエネループが800回しか充電できなくなるのかは実際に800回ほど充電してみないことにはわかりません。 (エネループが家庭使用で1000回使えるとはとても思えませんが…)
BQ-390が−ΔV方式なのに対して三洋充電器は三洋独自のピークカット方式と、充電完了を検知する方法やその際の満充電まで流す電流量はわずかに違います。 −ΔV方式のほうが原理的に満充電時により多くの時間電流を流して過充電させているようによく言われますが、実際に電流・充電時間を測定したところBQ-390もNC-M58もほとんど変わらない充電量でした。 充電池には満充電リザーブという過充電させない為の余裕が持たせてありますので、リザーブ範囲内であれば過充電で急激に電池の性能を損なうことはありませんので、この程度の差であれば「電池を痛める」という心配はしないで良さそうです。 充電末期の電池温度もほとんど変わらず、こういった測定面からはBQ-390でエネループを充電しても三洋の充電器とほとんど変わり無いとは思いますが、あくまで実験レベルで実用的かどうかは使われる方の判断にお任せします。 また「寿命を縮める」や「電池を痛める」と心配される方は、実際の電池の性能劣化よりも日常的な「心配」のほうがお体に悪いと思いますので、安心して使えるメーカー純正充電器の使用をお勧めします。 技術面・原理に於いて充電できる物でも、本ページでは「他社製品の使用はお勧めしません」ということにしておきます。 ここで私が「他社充電器で充電しても問題無いです」と書いて、それが原因で何か事故が起きた場合には責任が取れないからです。 PL法等の責任の所在についての問題がある為、メーカーは自社の充電器でしか充電を認めていません。 本ページに移動したいくつかの「エネループを××充電器で充電していいですか?」の返信をお読みください。 お返事 2007/1/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エネループを東芝THC-34-RHCで充電してもいいですか?(他社充電4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
エネループを東芝社充電器THC-34-RHCで充電してもいいですか?(無論、自己責任でメーカー保証が効かないことを覚悟の上で) また、この充電器はサンヨーのOEMでしょうか?サンヨーからもバッテリーチェックが追加されただけで同じ形の充電器があるので 区間快速急行 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
「エネループを●●で充電して良いですか?」に対しては、過去にも説明していますので既にお読みだと思いますので要点だけ。 (詳しくは他の投稿者の方の質問と回答もお読みください) 急速充電器の場合 ・ニッケル水素電池用充電器である事 ・ニッケル水素電池に対応した満充電検知機能が付いている事 ・安全タイマーがその充電器の充電電流でエネループの2000mAhを充電するのに必要な時間以上長い事、つまり2000mAh以上の電池に対応と表記されている充電器である事 ・特殊な充電器で、専用の電池以外の充電は禁止されていない事 これらの要件を満たしていれば「自己責任で」エネループを充電できます。 もし充電してみて異常な発熱・ガスが出る・充電器がエラー表示をするなどの異常が無く、満充電になってちゃんと使えれば大丈夫です。 不安な場合は最初の数回は充電中は充電器と電池から目を離さずに、満充電までじっくり観察しながら安全を確認してください。(かなり無理ですが) 以後「エネループを●●で充電していいですか?」というご質問をされたい方は、まずご自分でその●●充電器が上記の要件を満たしているか調べてエネループに充電して良いか判断してください。(質問しなくても良くなるはずです) 東芝のTHC-34RHCは2300mAhのニッケル水素充電池とのセットで販売されていますので、上記の要件を満たしています。 ですので「あくまで自己責任であれば、電気的にはエネループを充電するのに明確な不具合は無い」と思われます。 「サンヨーのOEMか?」については、◆SANYO充電器 NC−M58 個別充電表示化改造 ◆の2006/7/31の質問と回答に掲載していますのでお読みください。 OEM製品でたとえ中身が同じでも、充電はできますが三洋の保証は受けられませんし、エネループの「1000回充電」などの性能が確保・保証されるものではありません事はご理解の上でご使用ください。 お返事 2007/5/5
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle EnergyをFUJIFILMのDigi Chargeで充電しても良いですか?(他社充電5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
今まで、FUJIFILMの充電池を使ってきましたが、自然放電が多いと感じて、CYCLE ENEGRYを購入しました。 FUJIFILMのデジチャージミニNを今まで使用してきましたが、これをCYCLE ENEGRYにも使用できるでしょうか。 MIKE 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
色々とお調べさせて頂きましたが、たいへん申し訳ございませんがFUJIFILMの充電器・デジチャージシリーズの「ミニ+電池セット FWB MINI NH 320」(古い商品なので公式HPには載っていません)には末尾が「N」という型番は存在しませんでした。当時は充電器単品での販売も無かったようで、充電器本体の型番は不明です。 充電池セット品で末尾が D のものは2100mAhの電池セット。E は2300mAh、F は2500mAhとのセットとなっています。 メーカー公式の発表ではそのセットになっていた電池の容量までの対応となっています。(実際にどこまで充電できるのかは非公開です) またSONY の Cycle Energy充電池は現在「2500mAhのサイクルエナジーグリーン」と「2000mAhのサイクルエナジーブルー」の二種類が販売されていて単に「CycleEnergy」と言われましたらその両方が該当します。 「自然放電が多いと感じて」という事ですので、自己放電を抑えたタイプの「2000mAhのサイクルエナジーブルー」だと推測できますが、正しいでしょうか? もしご購入になられた電池が「2000mAhのサイクルエナジーブルー」でしたらデジチャージミニのどの型番でも容量の問題はありませんので充電できます。 もしご購入になられた電池が「2500mAhのサイクルエナジーグリーン」でしたら、上記の一覧より F タイプの充電器であれば問題無く充電できますが、 D または E タイプの場合は満充電できない場合があります。 お返事 2008/6/22
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電中の電池の物凄い発熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
いつも楽しく拝見させて頂いております。 いやぁ、楽しい実験の数々。こちらもワクワクしながら読んでおります。 さて、自分はVOLCANO NZをBQ-324で急速充電して使用しています。 先日、何気に充電中の電池に触れてみると、物凄い発熱に驚きました。 他の電池でもそうなのでしょうか? 是非、充電中の温度も比較して頂きたいと思います。 Thief 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
ご拝読ありがとうございます。 急速充電器を使うとどうしても電池が発熱してしまいます。 これはニッケル水素充電池の化学的な性質のためで、故障ではありません。 (稀に故障の場合もありますが・・・) ニッケル水素充電池を充電すると最初はほんのり暖かい程度なのですが、満充電が近づくと急に発熱するようになり温度もかなり高くなります。 そしてこの発熱・温度は電圧や電流が大きいほど多いものとなります。 また同じような電圧・電流で充電していても、容量の大きな電池では発熱も少なく、容量の小さな電池では発熱が多くなります。 ですのでたとえば2600mAhの電池と1300mAhのVOLCANO NZでは同じ充電器で同じように充電するとVOLCANO NZのほうが温度が高くなる率が大きいのは原理上はあたりまえなのです。 では、VOLCANO NZでは危険なほど高温になるのか?は後にグラフで確認しましょう。 ほかにも、劣化が進んで内部抵抗が大きくなっているような電池では、BQ-324等の定電流タイプの急速充電器では、一定の電流で充電する為の操作が行われて内部抵抗値の高い電池ほど高い電圧をかけて充電します。すると電圧が高いぶん発熱も多くなります。 おおまかには新品で内部抵抗も少なく容量も大きな電池ほど、同じ条件での充電では発熱も少ないというわけです。 電池メーカー(松下)の資料によるとニッケル水素充電池の充電時の電池温度は約0〜45℃と規定されています。(ちなみに機器での使用時は-10〜65℃です) 急速充電器では内部に温度センサー(サーミスタ)が入っていて、電池が異常に高温になった場合は充電を停止する安全機構があるのが一般的です。 充電末期に短時間だけ50℃超えになる程度であれば、特にすぐに電池の性能が落ちてしまうようなダメージは無いと考えられます。 今までの経験ではほとんどの電池が最高42〜48℃程度で、最大50℃台前半でした。高い温度を記録したのはほとんどが夏場の充電の場合です。 45℃というと江戸前の銭湯で常連オヤジさんが真っ赤に茹っているほどの高温です。(危険なので良い子はマネしちゃいけません!) 電池を素手で握ったら「あつっ!」と言って手放してしまうくらいの温度ですね。 はじめてこの温度になっている電池を触ってしまったら「過熱して危ないんじゃないの?」と思ってしまっても仕方有りません。 でも大丈夫、それで正常なのです。 下のグラフはいくつかの電池の充電時の温度を調べたものです。 松下のBQ-390で急速充電し、室内温度は20〜22℃の環境です。測定用センサーはLM35-DZで、いつものデータロガーに高感度入力端子を付けたもので記録しています。  同一の電池比較では正常なeneloop(2000mAh)が容量率的に見てほかの電池と同様の温度を示しているのに対して、劣化したeneloop(2000mAh)は「内部抵抗が増大している電池」らしく発熱も多く高温になっています。 ※ 今回測定に使った「劣化したeneloop」は250回使用でもまだ耐えていた2本のうちの片方です。最近かなり怪しくなってきましたのでそろそろ限界のようなので実使用から外して最後の性能テスト中です。このグラフからもわかるようにかなり劣化が進んでいます。 このグラフで注目して頂きたいのは、充電開始からほとんどの時間は約30〜37℃とほぼ人間の体温以下の温度なので触っても熱いと感じることはありません。ほんのりと暖かい程度です。 「電池を触ったら熱かった!」と仰る方のほとんどはふだん充電中の電池がどのような温度になっているのか知らず、たまたま偶然に満充電前後の高温になっている短い時間に電池に触れて、それまで知らなかった熱さに驚いて「電池が熱い!」とびっくりされているようです。 もしも電池がほとんど放電してしまっている状態から充電をはじめて、すぐに触れないような温度になってしまったらそれは電池が不良である可能性が高いですが、グラフのように充電終了前後に熱いのであれば正常です。 また今回室温20〜22℃の状態では松下BQ-390の急速充電(三洋なら倍速充電)でもほとんどの電池が最高45℃以下と、電池に対して高温でダメージを与えるような温度にはなっていません。メーカー規定通りです。 よく言われる「急速充電は過熱して電池を痛める」が実は都市伝説であることがおわかり頂けるのではないでしようか。 しかし室温が30℃を超える真夏では、電池の最高温度もこれより約10℃は高くなり55℃前後になる事があります。 満充電前後の短時間であればすぐに電池を壊すような事はありませんが、充電器内部の温度センサーが働いて充電を停止したりする事も確認していますので、真夏に急速充電をする場合は風通しの良い状態で行いましょう。 「充電した電池を触ったら電池が熱い!」については、それは人間が熱いと感じるだけで、電池にとっては異常では無いという事がおわかりいただければと思います。 ※ 故障や劣化で異常発熱する電池は除きます
お返事 2007/11/5
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
素早い回答を、しかもグラフ付きでしていただき、ありがとうございます。 充電末期にはこんなに発熱するものなのですねェ…初めて知りました。 これからはあまり気にしないで、存分に充電しようと思います。 どうもありがとうございました。 追伸 現在、VOLCANO NZと共に売られている充電器を放電器に改造中です。 中身を全て出せば、個別放電回路が入れられそうですので… では、これからも楽しい実験を心待ちにしております。 どうもありがとうございました。 Thief 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
電池が満充電近くで発熱する事を逆に利用して、個別充電表示機能の無い充電器で充電した場合に、一本だけ接触不良でちゃんと充電できていなくて冷たかった・・・、なんて確認方法もあります。 ただグラフからわかるように充電が終了して少し時間が経つだけですぐに冷めてしまいますから確認するタイミングが難しいですね。 夜寝ている間に充電…などでは触って確認もできませんし。 セリア充電器の改造はいろいろな方が行われているようで、こちらの方も「気の迷い」の放電器回路を見て改造されているそうです。検索で引っかかったブログです → http://blogs.yahoo.co.jp/cxtr554/14904934.html 皆さん工夫されていてすごいですね。 お返事 2007/11/6
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニッケル水素充電池に対するトリクル充電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
フル充電キープ充電器のこんな記事 http://oh1electronics.web.fc2.com/fullkeep/fullkeep.html ってどう思いますか? Mr.MAC 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
まずは、個人様のHPで製作された物に関しては、その方がそれで満足されているのでしたらそれで良いと思います。 そのHPの記事に関係なく『ニッケル水素充電池に対するトリクル充電』に関しての技術的な面からのお話などをしてみましょう。 Panasonicのニッケル水素充電池に関するドキュメントに詳しく書かれていますが、ニッケル水素充電池に対しては微弱電流を続けて流し続けるトリクル充電は推奨されていません。 簡単に要点をまとめると (1) 微弱電流の連続充電では過充電状態が続き、電池の寿命を縮める。 (2) かといって電流を少なくすると正しく充電できない。 (3) なので間欠充電やパルス充電で必要量のトリクル充電をするのが適している。 という事です。 たとえば、1/20C〜1/50Cで連続トリクル充電するとしましょう。 ものすごく大雑把な言い方をすると1/20Cなら「電池が空の状態から20時間で定格容量の充電ができる」(本当はもう少し時間がかかります)という充電電流ですから、「たった20時間で100%自己放電してしまう電池!」に最適(?)な充電電流といえます。 1/50Cなら50時間、約2日で自己放電してしまう電池用という感じです。 そんな電池は普通使いませんよね。 という事は、満充電後にそれくらいの電流を流し続けるという事は、満充電をキープしているというよりは過充電をキープしているという事になります。 1/20C〜1/50Cで連続トリクル充電をするような方法を推奨する技術データでは「電池の中で過充電反応が起きてガスが発生するが、それは再吸収される範囲なので大丈夫」という所をよりどころにしています。 確かにニッケル水素充電池の中では過充電時に出たガス(酸素)を水素吸蔵合金に再結合できるように余裕を持たせていますのである程度までは大丈夫です。 しかしそれは通常の充電時に満充電に達する時にちょっとだけ余っちゃうガスを吸収する程度の目的に用意されたもので、長期間ずっとガス発生と吸収をし続ける為には用意されていませんから、そんな事をするとどんどん電池が劣化してゆく事は容易に想像がつきます。 ですので連続電流でトリクル充電する技術の説明では「電池の寿命を縮めます」という注意書きもされていますね。 寿命は縮めますが数日のトリクル充電で電池が壊れてしまうという物でもありませんし、果たしてその状態を何日・何ヶ月続ければ電池の寿命がどれだけ短くなる(性能がどれだけ落ちる)のかはそれぞれの電池で個々に特性も違いますので、確かに寿命は縮めることにはなるかもしれませんがすぐに壊れないと思えば個人の自己責任の範疇でニッケル水素充電池に対して連続充電でのトリクル充電をするのもまぁ実験レベル・個人使用としては可ではないでしょうか。 松下の文献にも面白い例を出して解説しています。ここで同じようにたとえてみましょう。 2500mAhの充電池に対して1/50C(50mA)の連続トリクル充電をしたとして、その状態を一週間続けたとしたら50mA×24H×7日で8400mAhぶんの充電電流を流すことになります。 スタンバイ使用の機器で何ヶ月も流し続けるのではなく、一般家庭で使って一週間ほど後には電池を取り出して使うとしてこの程度です。もしこれを何ヶ月も流して何万mAhも…と考えるとちょっとゾッとしませんか? 一週間という期間はありますが2500mAhの電池に満充電後に8400mAhぶんの電気を更に流し続け、その電流は過充電の為の発熱(感じるような温度上昇はありませんが)とガス発生に使われているという事に対して気分的にはどうか・・・という事ですね。(いや本当は電気的に…ですけど) 但し数十mA程度の電流では電池内部の+−極に対してそれほどの電位差を増やすこともできず充電効率の面では非常に悪いことも分かっていますので、数十mA程度(但し連続)では本当に流したぶんの電流が充電されたり大量にガスが発生する事も無く何割かはロスされていると思います。 そう考えると数十mA程度の電流に設計されている個人製作のトリクル充電器は危惧するほど電池を痛めるものでも無い可能性が高いですね。 危険性や劣化させる事が0%になるわけではありませんが、短期間での使用では実用上はあまり気にする程度では無いという程度ではないでしょうか。 さてそこでニッケル水素充電池に適したトリクル充電の方法ですが、次の2つが上の技術資料では紹介されています。 (1) 間欠充電 (2) パルストリクル充電 (1)間欠充電は自己放電で放電してしまう量を正しく把握し、そのぶん一定量減ったところで同じ量を充電してやる方式。 但しこれは電池に特性などを厳密に把握する必要があるので、特定の電池しか使用しない電池組み込み式の機器(非常電源設備とか)でないと使用できないでしょう。 (2)パルストリクル充電は大手メーカーの市販充電器でも使用されている方法ですね。 小電流の連続充電では効率が悪くロスするエネルギーが多いため、充電効率に問題が無い大きさの電流を流します。但し電流を流す時間を細切れ(パルス)にしてトータルでの充電量は微弱な量にする方式です。 市販充電器は定電流充電回路とパルス式の制御ができるマイコンとスイッチング回路が内蔵されているものがほとんどなので、そのままの回路で急速充電とパルストリクル充電の両方式に対応できるのも利点だからでしょう。 たとえば三洋 NC-M58 を解析した時の内容では「1.7A×0.5秒を3分に一回で約4.7mAh」のパルストリクル充電を行っていました。 2500mAhの電池に対しては約1/530Cのトリクル充電という事になります。 (ニカド時代から言われている1/20〜1/50というレートとは大違い) 満充電キープ実験では2500mAh電池(一般的な自己放電率)に対してはちょっと少なかったようですが、eneloop等の電池に対してダメージを与えずに微弱な量を充電する方法としてはうまく働いている事がわかります。 ニッケル水素充電池に対して適した満充電キープ装置を作ろうと思うとやはりこのようなパルストリクル充電方式をとる事が理想的で、自作であればパルス幅や周期を可変にしてやって充電電流を使用する電池にあわせて最適にしてやれれば最もダメージ無く満充電キープをすることができるでしょう。 その為には定電流充電回路・パルス駆動回路等を設計して作る必要があるので、簡単にそのへんにある電源と抵抗だけで…とはゆきませんから敷居が高いですけどね。 ニカド電池には有効でしたがニッケル水素充電池に対しては特性の違いなどをよく理解して、「(劣化は進めるかもしれないが)すぐには壊さない程度で使える物」としては連続トリクル充電回路というのも安価に作れて良いのではないでしょうか。 そういえば、「セリアの100円充電器を使って満充電キープ充電器を作る」というお話が以前出ていたような・・・(どうなったのかな?) お返事 2008/7/15
[7/22 追記]セリア100円充電器での満充電キープ装置は作られて実験進行中だそうです。 少し上で「(劣化は進めるかもしれないが)すぐには壊さない程度で使える物」としては連続トリクル充電回路というのも安価に作れて良いのではないでしょうか。とは書きましたが、微弱電流を流しつづけたらニッケル水素充電池が壊れてしまったという実験結果もあったそうです。 短期間での使用では実用上はあまり気にする程度では無いという程度ではないでしょうか。と書きましたように、やはり長期間満充電をキープするような使い方ではなく、充電後数日程度を限度にしておいたほうが良いでしょうね。 元々ニッケル水素充電池には推奨されていない方式ですから、どこまでなら壊れないかを探るのも自己責任で行う個人工作なら面白そうですね(^^; |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
ふと思い出したのですが、コードレス電話の子機用の交換電池(車外品)でNiMH電池のもの市販されています。 機器がNiMH対応ならいいのですが・・・そうでない場合(機種未確認ですが)充電制御が正しく出来るのかな。とちょっと疑問になりました。 実は・・・こちらのサイトを知らない頃、24時間通電で使用する機器のバックアップ用に使用していたNiCd電池が寿命となった際、安易にNiMH電池に変えてしまい短期間のうちに寿命となる失敗をした経験があります。 (電流はかなり絞ったつもりだったのですが・・・) Mr.MAC 様ご紹介のサイト、電圧だけ計測してありますが・・・長時間経過後の(放電)容量が計られているわけではないようですね・・・ jr7cwk 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
「コードレス電話機の電池をニッケル水素と交換して大丈夫?」や「コードレス電話機用の交換電池がNi-MHに変わっています」で掲載していますように、市販のコードレス電話用として販売されている交換バッテリーのニッケル水素電池への置き換えは進んでいますね。 過去記事でも書きましたがニッケル水素充電池の中にも高い耐久性のほうに特性を振っている物があり、たとえば松下電池では「高耐久性タイプ(Hタイプ)」という分類の製品です。ちなみに乾電池互換タイプはBタイプ(BatteryのB?)だそうです。 充電方法の対応表を見るとHタイプは「トリクル充電可能」になっています。Bタイプは「トリクル充電不可」ですので一般的に市販されている乾電池タイプのニッケル水素充電池をニカドと同等の電流連続のトリクル充電してはいけない事は電池メーカーの資料からも明らかです。 そこで、何ヶ月もずっとバックアップ用途でトリクル充電するのではなく、「満充電キープの用途で少しの間だけトリクル充電をする」のなら個人の実験の範疇なら良いんじゃないかな・・・程度にお答えしています。 これらのメーカー資料からも「コードレス電話の子機用」等で売られているニッケル水素充電池はニカド電池用のトリクル充電対応の「専用品」ではないかと私は考えているわけです。 メーカーに直接問い合わせてみないと電池パックの中身のセルがどの種類なのかはわかりませんが。(そんな質問に回答が帰ってくれるかも謎) お返事 2008/7/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
ご回答ありがとうございます。 >トリクル充電対応の「専用品」 なるほどです。 ちなみに・・・私が失敗したというものですが、元が単4×3本の組電池でしたので、コードレス電話用の交換電池を流用しました。 (それが「トリクル充電対応」なのかどうかは不明ですが。) 電流のセッティングのまずさもあった(それ以上に元の電圧を電池電圧付近ギリギリまで下げる必要があったのかも?)のでしょうけど、24時間通電下でのトリクル充電はやはり条件的に厳しいようです。 まぁ「典型的な失敗例」だと思っています。 今だったら迷わず素直にNiCdの交換電池探します。 jr7cwk 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
もうほとんどの電話子機用交換電池はニッケル水素タイプに変わっていますので、今からニカドタイプの交換電池を探すのはかなり苦労しますね。 組電池になっていてケーブルと端子が付いている物なら。 ニカド電池単体ならまだ色々と売られているのでサイズが合えばまだなんとかなります。 お返事 2008/7/29
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気ドライバーの充電器に書いている「電流」の意味は? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
いつも大変面白く拝見させてもらってます。 質問ですが、充電器にある出力電流ですが、何を意味するんでしょうか? ちなみに電気ドライバーの充電器で、出力電圧DC12v、電流400mAです。電気ドライバーの種類によって電流の表示値がちがいますが、意味がわかりません。電気ドライバーの充電電池は、ニッカド蓄電池の1.2v 1000mAが、10個です。 電流値が違う充電器で充電すると、危険なのでしょうか? 是非返答お願いします。 ruru 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
充電器の出力電流はいくつかの意味を表す場合がありますが普通は「充電電流」です。(あ…あまりにあたりまえですか?) 充電池には容量やタイプに応じて「充電時に最大限流して良い電流」という決まりがあります。これを越えて充電してはいけません。 製品についている充電器はその製品に入っている電池に対応した安全な値に設計されていて、過充電で電池を壊してしまったり、異常発熱などのトラブルが起きないようにされています。 充電池の充電方法には二種類があり「標準充電」「急速充電」などと呼ばれています。 「標準充電」は少ない充電電流で電池が空の状態から約10〜16時間くらいかけて充電する方法です。 しかし自動的に満充電を検知して充電を停止する機能は無く、ほとんどは充電を停止しません。稀にタイマーが入っている物もあります。 この方法では時間はかかりますが電池への負担が少なく、多少は時間をオーバーしてしまってもすぐに電池が壊れるという事もなく、ほとんどの機器では「約×時間で充電器を外してください」と書かれています。 電動工具では使い勝手の向上を狙ってこの標準充電の電流量を増やして約3時間程度で満充電になる物も多く(厳密には標準充電ではありません)、電流量が増えているのに自動停止機構は無くて時間が過ぎたら早い目に充電器を外さないとかなり電池が熱くなるものもあります。 過充電に強い「ニカド電池」を使用した工具に多い方法ですね。 その12V 400mAの充電器だとだいたいこれにあたります。 もし充電器に自動的に充電を停止する回路が入っているのであれば、下の「急速充電」の項に該当しますのでそちらをご覧下さい。 もしこういう「標準充電」または「2〜3時間充電(自動停止なし)」工具に充電電流量の大きな充電器を使用した場合、「短い時間で満充電できる」という利点も生まれますが逆に「過電流や過充電で電池を痛める」危険性も発生しますので指定の充電器より大きな電圧や電流の充電器の使用はなるべく避けてください。 電池の定格を越えた充電を行うと電池が過熱・破裂する危険性があります。 「急速充電」は市販の単三型などの充電器で用いられているのと同じような原理で、約1〜2時間で満充電になるような大きな電流で充電をします。プロ用電動工具用では15分充電などという超急速充電器もあります。 急速充電では電池の状態を常に監視する回路が入っていて、満充電を検知したら充電をストップします。 「自動停止するのならどんな充電器、どんな充電電流のものを使っても安全なのでは?」と思われるかもしれませんが、急速充電では大きな電流で充電するというところが危険で、使用する電池の種類に応じた最大電流をオーバーした充電器で充電を行うと電池が過熱・破裂する危険性があります。 ですので急速タイプの充電器では特に使用電池に対応しているかどうかを確認し、安全なものだけ使用してください。 安全か判断する知識が無い場合はメーカーの指定する純正品以外は危険ですので使用しないでください。 一部の機器では、外部のACアダプター等は単にAC100Vから充電器に必要な電圧に下げるだけで、充電回路は機器の中に入っているという場合があります。 そのような場合は電流の制限などは充電回路が行いますので外部のACアダプターは同じ電圧値のものであれば電流値は大きなものでも構いません。 ここで言う電流値とはその電流値で充電するのではなく、ACアダプターが供給できる最大の電流を書いているので、本来のACアダプターより大きな電流値のものであれば余裕があるだけで不足は無いのでそのまま使用できます。(電圧は絶対に元の数値を越えてはいけません) ただしこの場合は充電電流を決める回路は機器側に入っていますので、電流値の大きなACアダプターを繋いでも充電は早くはなりません。 お使いの電気ドライバーは多分このタイプ(一部の機器)では無いと思いますので、知識として覚えておく程度にして、できる限り元の定格と違う充電器は使用しないでください。 【質問される皆様へ】 もしこういう質問をされる場合は、電圧・電流などの定格を今回のように詳しくお書き頂く以外に、できればメーカー名や型番などを書いて頂ければ検索してネットで調べられればより正確なお答えができますので宜しくお願いします。 お返事 2007/12/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
電気ドライバーの充電器について。 3.6Vの大陸製ドライバーの充電が大変時間かかる(付属のACアダプター(トランス式の小さいもの)使用で3時間)ので、5V1AのSWタイプのACアダプターで使う前に15分ぐらいの充電という使い方をしていました。(まあ大陸ものなので、寿命気にせず...) ところが、ある日、その状態で充電しながら居眠りしてしまい(1時間ぐらい)目覚めてみるとバッテリーの安全弁からすごいにおいの蒸気が....。 急いでアダプターから外したものの、数時間なかなか収まらず、メルトダウン寸前かと。(...まさに「逃げろ!」っという感じ) もし安全弁が固着していたらどうなっていたか・・・。 YouTubeによく載ってる爆発系の充電実験のようになってたかも。 とにかく当たり前の話ですが、何の制御もない充電は非常に危険だと思います。(つまり制御の設定が違う他社製の充電器も同じ事) ちなみに付属のACアダプターでは能力的(貧弱なアダプターなので)に2倍ぐらいオーバーな時間でやっても問題はありませんでした。(これとてつけっぱなしはヤバイと思われますが..) 単三単四のNi-MHやNi-Cdの充電器は大抵電池が充電器の設定の枠内だと思われるので、電池だけ他社製になってもそう問題は起こらないと思いますが(それでもメーカーでは保証できないので純正使用を明記してますが)工具なんかの組電池では、気の迷いさんの言うとおり純正をお勧めします。 P.S. 海外製Li-ion充電器の記事。大変参考になります。ありがとうございます。 いずれにしても生セルではリスク大きそうですね(Li-ionは破裂だけでなく炎上しますので)。特に私みたいなズボラなタイプには。 まあ、「〜Fire」という商品名に偽りは無しといわれればそれまでなんですが。(笑) ガッツ 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
ぜひメルトダウン直前の状態になるまでの過程をビデオに録っておいて欲しかったですね(^^; 実際に充電池を過充電した場合には中の化学物質が危険な状態になりますので、得体の知れない充電器や非対応の充電器で充電することは本当におやめください。> ALL P.S.部分のリチウムイオン充電池については本当に「電池がファイヤー! 部屋がファイヤー! 家がファイヤー!」になる可能性がある、取り扱いを間違えるとたいへん危険な電池なので特に気をつけて安全に充電しなければなりませんね。 お返事 2007/12/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電器の適合バッテリーについて | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
質問させてください。 オートクラフトのトリクル充電器(HC12-1)を所有しています。 この充電器の適合バッテリーが「12V 2.3〜28A(Ah/10HR)」とのことですが、「12V 1.5Ah」のシールバッテリーを充電しても大丈夫でしょうか? 他の充電器で適合バッテリーが「12V 0.8〜8Ah(20HR)」というのがあります、やはりこのような仕様の充電器を使用した方がよいのでしょうか? よろしくお願い致します。 かず 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
「大丈夫でしょうか?」という事ですが、それはお使いのバッテリーの性能によりますので一言で大丈夫ですなどとは言えません。 シールドタイプの鉛バッテリーは充電時に発生した水素ガスを内部で吸収するしくみになっていますが、密閉(シール)していますのでもしガスが吸収できる量を超えて発生すると破裂・爆発します。 ですので限界を超えてガスを発生させない為に充電時の最大電流値が厳密に決められています。 おおまかには容量の1/10ですが、バッテリーにより各メーカーの許容した「最大充電電流」があり、その電流値までなら流しても良いことになっています。 通常はバッテリー本体に「サイクル使用時」と「バックアップ使用時」のそれぞれの最大電圧・最大電流が記載されていますので、バッテリーに何と書かれているのかを読んでください。 ※ バッテリーに書かれていない場合はメーカーに電話するなりしてお問い合わせください。 次にオートクラフトのトリクル充電器(HC12-1)ですが、メーカーの告知によると「1A充電」のようですね。 定電圧・定電流充電機能、そして独自の100%充電機能と100%維持機能が内蔵されているようで、最大(バッテリーが空に近い状態の初期電流)では1A程度の電流を流すとされています。 従って、お使いの12V 1.5Ahのシールバッテリーのサイクル使用時の充電許容最大電流が1A以上であればその充電器で充電しても安全に充電できます。 もしバッテリーの側が1A未満の記載でしたら、破裂・爆発の危険性がありますので絶対にその充電器では充電しないでください。 おおまかに、一般的な規定値では容量の1/10ですがバッテリーによりその約2〜4倍までは最大充電電流として許容している物が多いようです。(バッテリーの性能により異なります) 1.5Ahのバッテリーの場合は多くても0.3〜0.6Aまでが安全な範囲だと思われますので、1Aの充電器では不適切でしょう。 できる限りは充電器とバッテリーの容量はそれぞれメーカーの用途・表記に合致したものをお使いください。 お返事 2008/7/29
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
ご丁寧な解説、ありがとうございます。 シールバッテリーは秋月電子で販売しいてる[WP1.5-12]というものです。 説明書には Cycle use: Charging Voltage 14.4 to 15.0V Maximum Charging Current:0.45A とありますので、HC12-1を使用しての充電は無理そうですね。 手元にある充電器で充電できればいいなぁと思った次第で、適切な電流で充電しなければならないことが良く分かりました。 素直に秋月電子で販売している充電キットを購入しようと思います。 ありがとうございました。 かず 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
秋月の充電器キットだと電流も可変で幅広いバッテリーに対応できるので良いですね。 今後違う容量のバッテリーが増えても対応できるので1つ作っておくと便利だと思います。 お返事 2008/8/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Section. ●● 機器のバッテリー交換 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動自転車のバッテリー交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
初めて投書いたします。 当方の電動自転車に利用しているバッテリーが寿命の為、買換えを考えましたが古い型で後継モデルがありません。 そこで、バッテリーボックスの中を見たところ単1サイズのセル20本がパック化されていました。整備諸元表では「ニッカド電池。容量(5時間率)1.2V×20(24V)、5Ah」(原文通り)と明記されています。 そこでお伺いしたいのが、市販・量販品の充電池を使って同等のパワーを引き出すバッテリーを自作(安価に)しようと思っておりますが、どの様な方法があるのでしょうか? また、当方が知識のない頭の中で考えたのが、市販品の単3充電池などに単1用のスペーサーを用いて20本分のスペースに収めて代替品が可能なのでしょうか。 その他、秋月電子の通販で「ニッケル水素電池 単3型1.2V 2500mAh(タブ付)」を20本使って代用なども可能なのでしょうか。 宜しくお願いします。 アシスト 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
まず最適な方法は、同じ1.2V 5000mAhの「ニカド電池」を探して交換してください。 たとえばメーカー不詳(品質不明)なこのような電池(タブ付き10本セットもあり)が通販で安価に売られています。値段は普通の価格ですがこちらの通販ではGP社や三洋製の有名メーカー製単一型ニカド電池が売られています。(機器組み込み用途のタブ付きです) 元の電池が普通の単一型で自転車の専用パックの中身を簡単に取り替えられるのでしたら単一型を、パックの中で電池同士が「金具」で繋がっているのでしたらタブ付きタイプを買ってご自分でハンダづけしてください。 タブの無い単一型電池の+や−端子をハンダづけするのは電池の中の部品を壊しますので厳禁です。 ニッケル水素充電池をニカド用充電器で充電するのは厳禁です。 既に何度も書いていますのでこのページの各投稿をお読み頂ければ不適切である事はご理解頂けるかと思います。 ニッケル水素電池は正しくニッケル水素電池の充電完了を検知できる「ニッケル水素対応充電器」で充電しないと、過熱・発煙・破裂などの原因になります。 またその自転車の専用充電器がどのような回路が存じませんが、正しく電子回路にて満充電を検知しているのなら良いのですが、タイマー式などで満充電や電池の異常を検知できない場合は元の電池と種類や容量の違う電池を入れた場合はやはり電池を痛めて破裂などの事故を起こす可能性があります。 使用する電池に対応した充電器でなければその自転車の電池パックを交換てしても元の専用充電器では充電してはいけません。 元の専用充電器で正しく充電するためにも、電池は元のものと同じ種類・容量の物を交換する必要があります。 電池スペーサーはあくまで臨時の代用品程度にお考えください。 元から単一型などの大型電池を使用する機器は「その電池が必要」として設計されています。 もし5000mAhの単一型ニカド電池の代わりに2500mAhの単三型ニッケル水素充電池を入れた場合、単に容量が少ないので使用時間が短くなるだけではなく、サイズが小さいせいで内部抵抗が大きくなり流せる電流が少なくなって電動アシストがじゅうぶんに働かなくなる、また電池が発熱して異常事態が起きるなどのトラブルも考えられます。 電池スペーサーを使用して小型電池を入れるのは、それほど電流を必要としない小電流機器程度にとどめておいたほうが良いでしょう。 お返事 2007/12/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 12/10 |
早速のご返答ありがとうございました。 当方の浅はかな知恵で投書をしてしまい、失礼しました。 ご教示ありがとうございました。 アシスト 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コードレス電話機の電池をニッケル水素と交換して大丈夫? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
家のコードレス電話がすぐにバッテリー切れになるため、家にあるニッケル水素電池で配線を移植して使用し始めました。大丈夫でしょうか? まさ 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
コードレス電話機に元から入っていた電池はニカド電池で、それをニッケル水素充電池に交換したというお話ですね。 既に質問の出ている「シェーバーの中のニカド電池をニッケル水素電池と交換したい」と同じ内容ですので、詳しくはそちらをご覧下さい。 ニカド電池とニッケル水素電池では充電時の挙動が異なり正しく充電できない・または電池を壊す場合があります。 またコードレス電話機のように長期間微弱電流でトリクル充電をする機器の場合、ニッケル水素充電池はニカド電池方式の微弱電流でのトリクル充電は適しませんので、早期に電池が弱る・故障する場合があります。 上記のような不具合が起きる事をご理解の上で、自己責任でニッケル水素充電池に入れ替える事は特に止めはしませんが、何が起きても良いという判断で行ってください。 コードレス電話用には各メーカー、また互換電池メーカーからほぼ全てのコードレス電話用の交換電池(ニカド電池パック)が発売されています。 電気量販店やホームセンターで販売されていますので、事故の無いようにできるだけ正しい交換電池を購入して使用してください。 お返事 2007/8/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コードレス電話機用の交換電池がNi-MHに変わっています | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
先週、ホームセンターに行ったらELPAのコードレス用交換電池が軒並みNiMHに変わっていてびっくりしました。 そう大きな問題は起きないでしょうけど、いいんですかねえ。 wagamiyoni 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
すぐ上の記事で「コードレス電話機にはNi-MH電池は不適切なので、専用の交換用ニカド電池を」と書いたばかりですが、事実世の中の充電池の多くはニカドからニッケル水素に変わってきています。 (用途によってはリチウムイオン・リチウムポリマー系電池にも) ホームセンターで売っている「ソーラーガーデンライト専用電池」も単3型のニカド電池からニッケル水素電池に変わり始めています。 交換用に単体でも売られていますが単3型で600mAhなんていう、普通の電池売り場ではお目にかかれない少容量のNi-MH電池が使用されていました。 従来のニカド電池の置き換え用に専用に作られているようで、ソーラーガーデンライトのように「過放電あたりまえ」、機種や日照条件によっては過充電になってしまう事もあるかもしれない機器用ですが、まだ買って試してはいませんがちゃんと適合してるのでしょう。 正当な理由として考えられるのは、ニッケル水素電池の中にも用途によってパワー重視の物や耐久性重視の物など何種類かのカテゴリに分けられた製品が製造されていますので、その中から「高耐久性タイプ」の物を使用した専用品である可能性が高いですね。 市販されている家庭用のニッケル水素充電池とは特性が違い、過充電や過放電に比較的強いタイプのセルを使用しているのであれば、ガーデンライトやコードレス電話機などの交換電池として使用する場合でもタフなので従来のニカド電池に近い耐久性で使用できることが考えられます。 ガーデンライト用の容量が600mAhという電池も容量などを犠牲にして耐久性を極限まで高めているのかもしれませんね。(実際のところはデータシートでも無いとわかりませんが) コードレス電話用交換電池もそういった高耐久性の専用品に順次置き換わっているのでしょう。 ヨーロッパの国などでは毒物であるカドミウムの有害物質指定でニカド電池の販売ができない国もあると聞いていますから、ニカドを使用していた機器ではニッケル水素タイプへの置き換えは進んでいるのだと思います。 そういうメーカーが動作試験をして許可・認定しているニッケル水素充電池であれば、従来のニカド電池使用機器への交換・置き換えは可能だと思います。 下で書いたように、通常売られているニッケル水素充電池は過充電や過放電にはあまり強くはありませんので、すぐに壊れる事はありませんがずっと微弱な充電をしっぱなしの機器などではニカド電池の置き換えには適していないのは間違いありませんので、メーカーの指定した交換電池(ニッケル水素があればそれで良い)への交換をお勧めする事には変わりはありません。 従来のニカド電池使用機器の内蔵電池を交換する時には注意しましょう。 お返事 2007/8/12
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ページ先頭に戻る▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シェーバーの中のニカド電池をニッケル水素電池と交換したい | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェーバーの充電池を交換したく分解した所、中に入っているのは、ニカド電池が直列2本で最近の電気屋さんでは見かけないものです。 ニッケル水素電池を代わりに使っても大きな問題はないでしょうか? ニッケル水素電池とニカド電池の充電特性などの違いを教えていただけるでしょうか? 標準充電時間は1時間となっています。 お聞きできそうな所が無くこちらで質問させていただきましたが、不適切な内容でしたら申し訳ありません。 金太郎 様
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
充電式シェーバーだと、今でもニカド電池が入っているものが多いですね。私の使っているSANYOの安物もニカドが一本入っています。 多分お使いのシェーバーは電池を少しだけ使って充電すれば充電時間も短く、回転が止まるくらいまで使って充電すれば約1時間かかるタイプだと思います。 そういう充電制御用回路が入っているシェーバーの場合、ニカド電池の代わりにニッケル水素電池を入れると故障や事故の原因になる可能性があります。 (電池がどんな状態でも1時間充電してしまうタイマー式だとまた別の話しになりますが…) ニカド電池とニッケル水素電池の充電特性の差で、問題となるのは満充電以後の電圧低下、つまり充電器(シェーバーの中の充電回路)が−ΔV方式等で満充電になったかどうかを判断する部分の電圧変化の量が違うという点です。 一般的にはニカド電池のほうが大きく、ニッケル水素電池のほうが小さいと言われています。 つまりニカド専用の充電回路では、ニッケル水素電池の満充電を検知しにくく(または検知できず)、満充電後も電流を流し続けて過充電で電池を痛めてしまう可能性が高いということです。 たとえ(ガスが噴出したり過熱して燃えたりせずに)充電ができても、過充電になっていて電池の性能が大きく劣化してゆく原因となり、普通に使える回数よりずっと少ない充電回数で電池がダメになってしまうことも予想できます。 単3や単4電池を充電するメーカー製の充電器では「ニカド/ニッケル水素両用」の為にセットされた電池がどのタイプかを判断する複雑なプログラムが入れられていたりと、性質の違うニカド電池とニッケル水素電池のどちらを充電しても事故が起こらないよう万全の対策が取られていますが、シェーバーのように特定の電池が内蔵されているタイプの機器ではその電池以外の物を使用する前提では設計されていないと思います。 ですので、専用の形で(ユーザーが交換できないように)ニカド電池の入っている機器にニッケル水素電池を入れるのはお勧めできません。 ニカド電池は単3型の700mAhタイプならまだ家電量販店やホームセンターで売っていますし、秋葉原や日本橋の電子部品店には様々なサイズの怪しい輸入品も販売されています。ネット通販などでも取り扱っている店がありますので探してみてはいかがでしょうか。 と、書いていると「迷い箱」へ次のような投書が届きました。 丁度ニカド電池の話題ですので続けて掲載したいと思います。 お返事 2006/12/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
まだ使い捨てタイプの単3x2本は買えておりません。 ヤマダでも最安値で900円を超えます。来店ポイントで差し引かれますが。年末は関東に行くのでその時にがんばってみます。 さて、秋葉原の千石電商では 単4で1100MAhのNiMHが出てます。130円/本です。 さらにいまどきニッカドが・・・ DLG DLG−DK070−2AH51−P4C 4AC6-LUDE 単3ニッカド 700mAh(4本+ケース付) 1.2V 公称700mAh 320円です・・・ 以上、ご存知かも知れませんが。 田舎在住 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
田舎在住様、あなたは超能力者ですか!? 金太郎様へのレスを書いている所になんとタイミングの良いニカド電池情報の投稿! こういうショップでまだニカド電池も入手できますので参考にしてみてください。 >>金太郎様 田舎在住様は年末に東京に行かれるそうですが、セブンイレブンを回ってみてください。609円充電器はセブンイレブンでは定番商品です。(売り切れを除いて) 私も年末は恒例行事で4日ほど東京に居ますが・・・ で、その単4ニッケル水素電池って、Typ.1000mAh/Min.950mAhだと、普通はTyp値を実性能として「1000mAh」って書くのが普通ですが、それを「1100mAh」としているあたりが実にうさん臭くて良いです(笑) その後者の電池[次世代]シリーズですが、ニッケル水素電池と充電器のセット品もあり、ドン.キホーテや一部の電気店・パソコンショップでも売っています。 なにより[次世代]ってでっかく書いてる中華なデザインがステキです(笑) どこがどう[次世代]なのか、一度買って性能を試してみたいのですが、すごく地雷っぽい雰囲気もあるのでいつも売り場の前で10分ほど悩んでは買わずに帰ってきてしまっています。 いつかは思い切って地雷を踏んでみたいです(^^; お返事 2006/12/27
* 踏みました (2007/4/10) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
ご丁寧にお返事ありがとうございます。 ホームセンターの電器製品売場のすみにコードレス電話の交換電池が有るのをみて、よく見るとニカド電池なのですね!これも使えそう...なんて今思案しています。 秋月電子で1000mAh 1本200円から売ってましたね。 田舎在住 様の投稿も参考にさせていただきます。 金太郎 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
なにやら 非常に良いタイミングでお知らせできた様で、良かったです。 セブンイレブンに寄って買いたいと思います。 さて、肝心な事を書き忘れておりました。 千石や秋月で売っているNiMH電池の実力や如何に? 秋月電子で売っておりますGP社製NiMH電池ですが、 GP社 単3型ニッケル水素電池 ■1.2V 2300mAh 実力はどのような物なのでしょうか? 値段的には、1本200円程度と比較的安価ですが。 Better Power BatteryとDLGともども興味が有ります。 Typ値ではない表示な辺りで、地雷の匂いは漂いますけれども。 それでは、色々な興味深いレポートを、今後も楽しみにしております。 田舎在住 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
GP等海外製のバッテリーも色々売られていますが、種類も多く実験の為だけに全種類買うわけにもゆかず、何かの用途が思いついた時に購入して「ついでに」テストすることもあるかと思います。 昨日ホームセンターコメリに行ったところ、庭園用品売り場で900mAhのニカド電池(Wintonic社製)が「ソーラーライト専用取替電池」として2本285円(税込)で売られているのを見つけました。 電池自体は中国Wintonic社からの輸入物ですが、パッケージはコメリのオリジナル商品となっています。説明も日本語です。 もし金太郎様のお住まいの近くにコメリがあれば探してみてはいかがでしょう。 お返事 2007/1/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
コメリですか・・・ ド田舎すぎて近くに無いんですよね。 ほぼ電池寿命としては終わっているシェーバーの電池どうしよう・・・ 淡い期待をもって近くにビーバートザンというホームセンターにいったのですが無かったです。 次はちょっと離れたカインズホームだ!! 金太郎 様
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| お返事 |
うちのシェーバーは安物で1980円なので、刃が痛んできたら替え刃を買うより本体を新しく買ったほうが安いんです(笑) 中の電池が寿命を迎えるより先に刃が痛むので電池を替える心配はありません。(ぉぃぉぃ…) コメリのニカド電池ですが、買って来て充放電テストを行ってみたところ一本はほぼ900mAhで正常、もう一本は約750mAh程度までしかいくら活性化させても充電できないというふうに少し大きなバラつきがありました。 元々の用途のガーデンライトやシェーバー等で使用するには問題は無いくらいのバラつき程度だと思います。 先日共立電子の2階で買ったバルク品(メーカー不明の黄色い奴)の700mAhのニカドの一本は、どう頑張っても300mAh程度しか充電できない不良品でした。 日本橋や秋葉原ではバルクで充電池が一本からバラで売られていますが、それなりに不良品が混じっている確率が高いので、どうしても!という場合を除いてあまり素人の方にはお勧めしてはいけない代物だと再確認しました(^^; お返事 2007/1/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
(C) 「気の迷い」/Kansai-Event.com
本記事の無断転載・転用などはご遠慮下さい
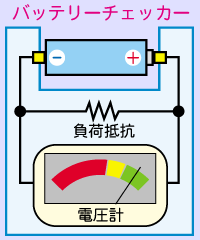
 「気の迷い」気になる実験・報告一覧ページに戻る
「気の迷い」気になる実験・報告一覧ページに戻る