| ||||||||||
|
|
| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |
��H�E�f���L�E����
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���� ���̃y�[�W��2008�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
|
�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |
�y�ꗗ�z
�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�
|
��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |
|
�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
���� ���̃y�[�W��2008�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
| �\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H | ||
|
�@�t�Z�_�b�N�@�\�[���[�뉀���E����@FC-505�ɉ\�ł����H �@�܂��w�����Ă܂��g�p�҂̕]��������ƁA�i�d���E����Ŏg�p�j �@���ʂɎg���ď[�d�ʂ�����Ȃ��悤�Ŗ�ԃo�b�e���[�g�p���ԒZ���Ȃ�悤�ł��A �i�V�C�A�ݒu�ꏊ�A�����A��̗ʁH�j���ŕς��ł��傤���A�z���ȏ�ɒZ���Ⴊ�o�Ă��܂��j �@�����Ń\�[���p�l�����݂Œ��ԏ[�d�ʑ��₵��ԃo�b�e���[�g�p���ԐL���Ȃ����ƍl���܂����B ���d�����F�\�[���[�p�l���S�u�^�P�U�O���`�@�@�@�g�p�k�d�c�F�F�k�d�c�i�U��p�j �d���d���F�T�O�O�u�^�S�O���`�@�@�@�g�p�[�d�r�F�j�b�P�����f�X�O�O���`�[�d�d�r�Q�� �@�[�d���ԂƓ_�����ԁF���V��W���ԏ[�d�Ŗ�U���ԓ_���i���P�x���F�k�d�c�뉀�����H�j �@�����Ƃ��Ă͊��{�̎��t���̃p�l�����͂����A �@�R�[�h2���ʂɉ������i������̗ǂ����փp�l���ړ�-�{�͉̂A�̕��j����Ƒ��ݕ���ڑ����悤�Ǝv���Ă���܂��A �@�d�l�ǂ���̐��V��W���ԏ[�d�Ŗ�U���ԁi�d���E����Ŏg�p�j�\�ɂ������A �@�p�l�����݁A��㕔�i�̌���,�[�d�d�r�e��UP�����A�������@�����ĉ������A �@�{�̓�����̖h�����m�ۂ���ׁA�p�l�����O����V�[�����O�������ł��B �@�d�r�̏[�d��ɂ��[�d�g�p�̓p�l���ɂ��t���[�g�p���ړI�Ȃ̂ōŏI��i�Ƃ��ĉ������B �@�����ς艹�s�̑f�l�ł��A �@��낵�����肢���܂��B z-a100 �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@FC-505�Ƃ����̂��������Ƃ������̂Ŏc�O�Ȃ���m��I�Ȏ��͐\���グ���܂���B �@�����܂ō��܂łɌ����u�\�[���[�E�K�[�f�����C�g�v�Ɠ��l�̕��Ƃ��Ă��b���܂��B �@���z�d�r�p�l���̑��݂͉\�ł����A���ꐫ�\�̂��̂ɂ��Ă��������B �@����FC-505���Q�䔃���āA�Е�����͑��z�d�r���������o���Ă����Е��ɑ��݂���悤�Ȏg�����ł��B �@�S���Ⴄ���\�̑��z�d�r�p�l��(���Ƃ��Βʔ̂Ŕ����Ƃ�)�݂���̂͂��܂肨���߂ł��܂���B �@���\������Ă����ꂼ��̑��z�d�r�p�l������_�C�I�[�h��ʂ��Đ��\�̈Ⴄ���z�d�r���m�ɋt�d��������Ȃ��悤�ɂ���Ȃǂ̉��H������Ȃ�g���܂����A���Ԃ�قǑ傫�Ȑ��\���̑��z�d�r�p�l�����q���Ȃ�����_�C�I�[�h�Ȃ��ł��t�d���Ńo�l�����j��鎖�������Ƃ͎v���܂����A�O�̂��ߕ����̑��z�d�r�p�l�������ɐڑ����鎞�͓��ꐫ�\�̓��ꐻ�i���q���ł��������B �@���܂Ō������̗L��\�[���[�E�K�[�f�����C�g�ł͂ƂĂ����Ԃ̂W���Ԓ��x�ł͓����[�d�r(400�`600mAh)�[�d�ɂ��鎖���ł����A���̏�Ԃł̖�Ԃ̓_�����Ԃ��ő�U���Ԓ��x�ł����B(�[�d��ŏ[�d�����12���Ԉȏ�͘A���_�����܂���) �@�܂�[�d�r�͓r���܂ł̏[�d�Ɖߕ��d���J��Ԃ��Ă����킯�ł��B �@FC-505��900mAh�̏[�d�r�����̃p�l���ꖇ�Œ��Ԃ̂W���ԂŖ��[�d����Ă����̂ł�����d�r�̗e�ʂ��A�b�v�����Ȃ��Ƒ��z�d�r�𑝂₷�Ӗ�������܂���ˁB �@�t�ɒ��ԂW���Ԃł͂ƂĂ����[�d����Ă��Ȃ��̂ł���A�d�r�̗e�ʂ͂��̂܂܂ŏ[�d�ʂ��ӂ₵�Ă��Ȃ��Ă��g�p�\���Ԃ𑝂₵�����Ƃ����v�]�͒B�������ł��傤�B �@���ۂɖ����d�r���J���ɂȂ�܂ŏ��Ղ�����ԂŁA���Ԃ̏[�d���Ԃłǂꂭ�炢�[�d����Ă���̂��͕��d�����Ȃǂ��s��Ȃ��Ƃ킩��܂���̂ŁA�ڂ����m�肽���ꍇ�͎������u�Ȃǂ�g�ݗ��Ă�K�v������܂��B �@�܂��͑��z�d�r�p�l���݂��Ă݂āA���ݑO�Ɣ�ׂė��p���Ԃ����т����ǂ������m���߂�̂������葁���ł��ˁB �@�������d�r�̗e�ʂ��A�b�v�����Ă����Ă��������͖����̂œd�r���������Ă��ǂ��ł��B �@�d���E�����[�h�łǂꂭ�炢�̓d���������̂��A�{���Ɍ����炠��900mAh�̓d�r�ň�Ӓ����삵��������̂��͑S���̓�ł��B �@������900mAh�̏[�d�r���ق��̏[�d��Ŗ��[�d���Ă݂āA��ɎE�����[�h�ʼn����ԘA���ғ�����̂��͊m���߂Ă������ق����ǂ��ł��傤�ˁB �@����ł����ƒ��܂œ��삷��Γ�����900mAh�̓d�r�͌������Ȃ��Ă�����[�d��������悤�ɑ��z�d�r�p�l���݂���Ηǂ������ł��B �@����900mAh�̓d�r�łЂƔӓ��삵�Ȃ�������E�E�E�d�r�����e�ʂ̂��̂Ɍ������āA�X�ɂ͂��̓d�r�[�d�������鑾�z�d�r�p�l���̔��d�e�ʂ��K�v�ɂȂ�܂��B �@���z�d�r�̔��d�ʃA�b�v�A�d�r�̗e�ʃA�b�v�ł������u��Ӓ����삳���Ă��]����x�̏[�d�ʂɂȂ�v�Ƃ��������ւ�����������ɂȂ����ꍇ�A����ǂ́u�d�r�̉ߏ[�d�v�̂ق��Ń}�C�i�X�_���o�ė��邩������܂���B �@�ЂƔӂœd�r�ɗ��܂����d�C���g�����Ă��Ȃ��̂ɁA���Ԃɂ͂���ȏ�̔��d�ʂŏ[�d���悤�Ƃ���B�d�r�����[�d�ɂȂ��Ă��܂������������Ă���Ԃ͂ǂ�ǂ�[�d�d���𗬂�������E�E�E �@�ߏ[�d�ŏ[�d�r������ł��܂��H �@����͎g�p���Ă��鑾�z�d�r�p�l���̐��\��q���d�r�̖{���ȂǗl�X�ȗv��������Ō��ʂ͈ꌾ�ł͔��f�ł��܂��A�\�[���[�E�K�[�f�����C�g�ɕt���Ă���悤�ȏ��^�̑��z�d�r�p�l���ł͑傫�ȏ[�d�d���𗬂����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA�ߏ[�d��Ԓ��ł��[�d�n�ɑ��Ĕj��I�ȓd���͗����܂���B �@���ێ茳�ɂ�����̂ł͂R�N�ق�(�����ƁH)�d������������ɖ������z���ɓ��Ă��ςȂ�(��)�łR�N�ԉߏ[�d�����[�d�r������܂����A���u���Ă����̂ŕs�����ɂ͂Ȃ��Ă��܂������d�r���̂�����ł���悤�Ȏ��͂���܂���ł����B���t���b�V��������(���S�ɐV�i�Ƃ͂䂫�܂���)���C�ɂȂ��Ă��܂��B �@���̂悤�ɖ������d�������ɂ����Ɖߏ[�d������悤�Ȏ��������A�������ʂɎg���Ă���̂ł���Ήߏ[�d�ł̌̏�Ƃ������̂͂��܂�l���Ȃ��Ă��ǂ��ł��傤�B�����܂ŕ��ʂ̃\�[���[�E�K�[�f�����C�g�I�Ȏg�p�̏ꍇ�ł��B �@�\�[���[�E�K�[�f�����C�g�̓d�r����������̂͂�͂蒩���ɂ͉ߕ��d���Ă��܂��Ă��鎖�̂ق����e�����傫�����ł��B ���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��
�@�������炩�Ȃ�]�k�ł��B �@�Ƃ���ŁA�u��̗ʁH�v�Ƃ����L�q������܂����A�����肽���̂ł����H �@���͍����̐��Ԃɂ��Ă͐��O�ł�����Ԉ���Ă��邩������܂��A���̒m�����u�����̏W����ɂ͂قƂ�ǂ̉�͏W�܂�܂����H�v�B �@��s���̒��̂�����̂悤�ȁu���ɏW�܂鐫��(������)�v�̂��钎�����т��悹�鎖���ł��܂����A�قƂ�ǂ̉�ɂ͂��̂悤�Ȑ����͖����̂œd���E����̐����ɂ͊���Ă��܂���B �@���ۂɖ�ɕ����̒��ɉ邪��э���ł������ɂ͌u�����Ȃǂ̖�����ɌQ����܂����A�����ɐN�������Ⴊ�V��̌u�����ɌQ�����Ă�����i�Ƃ����̂͌������Ƃ������ł���H�@����ɊW���������̒����t���t�����ł��܂���ˁB �@�����Ƃ������[�J�[�̓d���E����̐������ɂ́u�n�G�E��ɂ͌��ʂ�����܂����v�Ɩ��L����Ă��܂��B �� ��̒��Łu�C�G�J�v�͖�s���̈��ɏW�܂邻���ł��B �@�l�Ԃ̌����z�����X�̉�͐l�Ԃ̓f����_���Y�f�ƂȂɂ��畆�̕��啨�̏L���𗊂�ɔ��ł���(�l���ɑ_�����߂�)�����ł�����A�����낤�Ƃ���Ɠd���E���킩���_���Y�f����o�������݂��K�v�ł��B �@���ۂɁu��ɑΉ������A��_���Y�f�����@�\���̓d�����葕�u�v�Ƃ����̂��̔�����Ă��܂��ˁB(���ʂ̒��͒m��܂��c) �@�ʔ̂ȂǂŎ��X�u�����������W�߂��v�Ȃ�Đ�`��������Ă���̂��������܂����A�����܂Ŏ��l�̒m���ɂ��Ă͂߂�Ɓu����Ȏ������ł���I�v�Ǝv���Ă��܂��܂��B �@�u�����������W�߂��v�Ȃ�ԈႢ�ł͂���܂��A�u�n�G�E��ɂ͌����܂���v�݂����Ȓ��߂�����Ɛe�ł��ˁB �@���Ȃ݂ɉ�Ȃǂ͐F�̃X�y�N�g���̌��ɂ͗ǂ��������܂����A���g�����傫�����ꂽ���F�Ȃǂ̌��ɂ͔������܂���B �@���̖ڂɂ͐����͌����Ă����F�����͌����Ȃ�(�ア)�̂ł��ˁB �@�ł�����W�铔��d���E����ł͒��ɐ����𒆐S�ɕ����O���u�������g�ݍ��܂�Ă��܂��B �@���̐������t��ɂƂ��Ĕ���r�j�[���n�E�X�̏Ɩ����ł́u���F���A�����W�܂�Ȃ��u�����v�Ȃǂ����p����Ă��܂��B �@�d�C�̐��E�̐l���猩��Ƃ����������Ō�����m�肽���Ē��̐����͒��ׂĂ݂ė������Ă������Ȃ̂ł����A�Ԉ���Ă����炲�߂�Ȃ����B ���Ԏ� 2008/6/26
|
|
| ���C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H | ||
|
�@�ǂ����n�߂܂��āB�f�l�Ȃ���ɐF�X�l�������ʂ��������������炸�����Ă���܂��B �@�X�C�b�`��H�̎��Ȃ̂ł����@���d�r3��4.5V�Ɂ@LED�@CREE�̃_�C���N�g�h���C�u�@��1000mA�ő傫�߂̃X���C�h�X�C�b�`�Ŏg���Ă���̂ł����@�V�����������郉�C�g�ɂ́A�����d�l�ŃX�C�b�`������ύX���ă^�N�g�X�C�b�`�i�����Ă���Ƃ�����ON�@������OFF�j���g�p���ā@�I���^�l�[�g�i������ON��ێ��@������x������OFF)�@ON-OFF�݂̂̃X�C�b�`��H����肽���̂ł������܂�X�y�[�X���Ȃ��̂ŏ������Ȃ�悤�ȉ�H����₷�������Ă��������B �@PIC�͂ł��Ȃ��ł��B��낵�����˂������܂��B ������ �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@PIC���ƂW�s���^�C�v�̏��^PIC�ŊȒP�ɂł���̂ł����A�g�p�ł��Ȃ��ƂȂ�Ɣėp���W�b�NIC�őg�ݗ��Ă鎖�ɂȂ�܂��B �@16�s���^�C�v��IC���g�p���܂��̂ŁAPIC�łW�s���̏ꍇ�̔{�̃s�����ƖʐςɂȂ�܂����A�t���b�g�p�b�P�[�W�^�C�v���g�p����قƂ�Ǎ��͖����ł��傤�B ���d�q�I���^�l�[�g�X�C�b�`��H 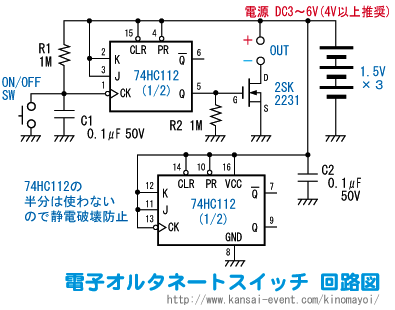 �@�M��������uON�v�ƁuOFF�v�����݂ɐ�ւ��ɂ́uJK-FF�v(�����������E�ӂ���Ղӂ����)�Ƃ����@�\��IC���g�p���܂��B �@JK-FF�̓s���̐ڑ��ŗl�X�ȓ��������̂ł����A�S����������ƒ����Ȃ�̂ł����ł͑��̗��p���@�̘b�͏ȗ����܂��B����̂悤��J��K�[�q��H�ɂ��Ă�����CK(�N���b�N)�[�q���������ŏo��(Q�܂���_Q�[�q)���O�̏�Ԃ��甽�]���܂��B �@�N���b�N���͂̓^�N�g�X�C�b�`��H����L�ɂ���Ηǂ��킯�ł����A�P���ɓd���ƃX�C�b�`���q���������ł��`���^�����O�ň�x�̉����ň�u�̂����ɐ���`���\����X�C�b�`�������ꂽ�悤�ȓd�C�M���ɂȂ�A�t���b�v�t���b�v�����̉���ON/OFF����čŏI�I�ɂǂ���Ŏ~�܂�̂��͂킩��܂���B�X�C�b�`�������Ă�ON�ɂȂ�̂�OFF�ɂȂ�̂��͉^����Ƃ����g�����ɂȂ�Ȃ���H�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@������R1��C1�ň��̎��萔���������`���^�����O�h�~��H���\�����Ă��܂��B �@�t���b�v�t���b�v�̏o�͂͂����̂悤�Ƀp���[MOS-FET��2SK2231���g�p���ďo�͓d�����X�C�b�`���O���܂��B �@CREE���1A���炢�Ȃ���M��t���Ȃ��Ă����v�ł��B(�C�ɂȂ�悤�Ȃ���M��t���Ă�������) �@H-CMOS IC�̓d���͈͂�2�`6V�ł����X�C�b�`���O��FET���g�p���܂��̂�FET���m����ON�ɂȂ�d���͈�4V�ȏ�(6V�ȉ�)�����̉�H�̐����d���͈͂ł��B�d�r��������3V���x�ɂȂ�܂�(�������CREE�ɗ����d����1A��肸���ƌ���܂�)��LED�_���p�ł͂قڐ���ɓ���͂��܂��B �@�Ȃ�ׂ����^�ɁA�Ƃ������ŏ��^��FET 2SK2231��I�����Ă��܂��B�t���b�g�p�b�P�[�W�i�ʼn����ǂ������������ł��\���܂���B�Œ�Q�[�g�d����3V���x�ŕK�v�d�����\���X�C�b�`���O�ł���FET�Ȃ�Ȃ�ł��ǂ��̂ő���FET�ł����D���ȕ������g�����������B �@�̐S��JK-FF IC�ł����AJK-FF�ł�����ނ͂���܂�����r�I���肵�₷��H-CMOS�^�C�v��TC74HC112AF��I��ł��܂��BAF��SOP�^�C�v�t���b�g�p�b�P�[�W�i�ŏ��^�ł��BAF������ł��Ȃ��ꍇ��AP�ł����\�ł���DIP�T�C�Y�Ȃ̂ő傫���ł���B �@74HC112������ł��Ȃ��ꍇ�͑���JK-FF IC�ł��\���܂���B���̏ꍇ�͎g�p�����IC�̃f�[�^�V�[�g���悭�ǂ�Ńs���z�u�Ȃǂ��m�F���Ă��������B�s���݊���IC�Ȃ�ǂ��ł������̉�H�}�ʂ�ł͖����\���������ł��B �@JK-FF�����荢��ȏꍇ�́A��H�}�̓K�����ƕς���Ă��܂��܂����u�o�C�i���E�J�E���^IC�v�Ȃǂ������悤�ɁuON/OFF�@�\�v�Ƃ��Ďg�p�ł��܂��B �@DIP/SOP�T�C�Y�Ȃ�TC74HC161AF���A�����ƒ����^�ɂ������Ȃ�TSSOP��VSSOP�Ƃ����قڎ�n���_�̌��E(��)�T�C�Y�̂��̂�����TC74VHC161F���ł��ǂ��ł��傤�B(��P�ʂōw���ł��邩�ǂ����́E�E�E) �@IC����L�̂ǂ���g���Ă��A�ҋ@�d�͂����ʂ`�ł�����X�C�b�`OFF���̓d������͋C�ɂȂ�܂���B �@�����ȃX�y�[�X��16�s��IC�����Ă��܂����Ǝv���ƃt���b�g�p�b�P�[�W�i���g�p���邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��̂ŁA�����Ȋ�����n���_�Â��Z�p�������̌�������܂��B �@���܂łɃt���b�g�p�b�P�[�WIC�̃n���_�Â���ƂȂǂ����ꂽ���Ȃ�IC��Ȃ̂Ŋy�ł��傤���A�͂��߂Ă̕����Ƌ�J�������ł��ˁB ���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��
�@���Z�Ƃ��āuON/OFF�@�\�̃\�t�g�X�C�b�`��pIC�v���\�ʎ�������Ă���uCare Free Talk�E�P�A�t���[�g�[�N�v����肵�āuIC�������g���v(����m�R�M���Ő��铙)�Ƃ����肪����܂�(��) �@ON/OFF�X�C�b�`��H���킸�����~���p�̊�œ���ł��܂��B �@������M���p��IC�������Ȃ̂œd�̓X�C�b�`�͂�͂�FET��ON/OFF���Ȃ���Ȃ�܂��AJK-FF IC�����g�����͂邩�ɏ��^(�Ȃɂ��K�v�ȉ�H���S��1�`�b�v���ɓ����Ă���)�ŁA���C�g�ɑg�ݍ��ނȂ�œK�ł��ˁB �@�A������́uCare Free Talk�E�P�A�t���[�g�[�N�v��105�~�œ���ł��鏊�ɂ��Z�܂��̕������ł��܂���A����͂��̉������p�ɂ��Ă͉�H�}�Ȃǂ͌f�ڂ��܂���B�����uCare Free Talk�E�P�A�t���[�g�[�N�v�����������g�����Ɏg�p�������͂������Œ��ׂĂ��������B ���Ԏ� 2008/6/18
|
|
| ���ʌ�����̂��肩���H | ||
|
�@��ЂŎg�p���Ă��铱�ʌ����p�̒��ԃP�[�u���ƃn�[�l�X���쐻�����������Ŏg�p����O�Ɍ������܂��B���̎��Ɏg�p���錟�����u����肽���̂ł����A��i�߂܂���B �@���茳�ɑ����ėL��p�[�c�̓X�C�b�`�A�V�[�P���T�[�i�����Q�����j�A�����[�A�_�C�A�����I���X�C�b�`(�I�������j�A�T�[�L�b�g�v���e�N�^�[�A�p���[�T�v���C�i��24v�j�ALED�����v6�R�ANG�AOK�p�����v�Q�ł��B �@�ŏ��͊ȒP�ɃC���[�W�����̂ł����A����ɍ\�z���o�Ă��܂���B �@��H�}�ɂď�L�̃A�C�e�����g�p���Ă̍\�z��F�X�����Ă��������B���肢���܂��B �@�s���̐��́A�R�{�ƂU�{�ł��B�P�[�u���iCVV�j���[�ɂ̓s���R�l�N�^�[�����܂��B�ՖʂɂQ��ނ̃��X���R�l�N�^�[�����t���܂��B �@�S�s��������ok�̎���LED�����v���S���_�����A�ʂɍ��i�����v����_�������܂��B �@����NG�̏ꍇ�͓��ʕs�ǂ̃��C����LED�����v�ɂĕ\���i�_�Łj�����ANG�����v��_���B �܂� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�܂��́u���ʃ`�F�b�J�[�v�ɂ��čl���܂��傤�B �@���ʂ́u���ʃ`�F�b�J�[�v�ƌ����Έ�{�̃P�[�u���ɑ��ē��ʂ��L�邩�������ׂ���̂ł��ˁB(�ƒ�p�e�X�^�[�Œ��ׂ�Ƃ�) �@�ł��̂œd���𗬂��āu���ʂ��Ă���v���ǂ����ׂČ��ʂ�\������悢���ƂɂȂ�܂��B �@����Ȃ�P���ɃP�[�u���̕Е��ɓd���������A���Α��ɓd�����o�Ă�������v�����悤�ɂ��Ă�邾���ł��ˁB �@�u�s�ǁv�\�����~�����̂Ȃ�d�C������Ă��Ȃ����Ɂu�s�ǃ����v�v���_������悤�Ƀ����[��t���邾���Œ��ׂ��܂��B �@���G�ȉ�H��u�͕K�v����܂���B �@�������A�����ň˗��җl���K�v�Ƃ��Ă���̂͂��̂悤�ȒP���ȁu��{�̃��[�h���v�p�̃e�X�^�[�ł͂���܂���ˁB �@�H�Ɛ��i�ȂǂŎg�p����u�����c�̃P�[�u���E�R�l�N�^�[(�n�[�l�X)�v���`�F�b�N����ׂ̑��u�ł�����A�P���ɑS���̐��ɓ����ɓd���𗬂��Ĕ��Α��ɒʂ��Ă��邩�ǂ��������ׂ邾���ł͕s�\���ł��B �@�Ȃ��Ȃ畡���c�̏ꍇ�́u���̐��ƃV���[�g���Ă���̏��v�����ׂȂ��ƁA�P�[�u���E�n�[�l�X�̊��������ɂ͂Ȃ�Ȃ�����ł��B �@�P�Ȃ�o���z���Ȃ烊�[�h���̓��ʂ��`�F�b�N���邾���ōς݂܂����A��ɃR�l�N�^��ڑ����Ă���ꍇ�̓R�l�N�^���Ńn���_�Â��∳���Ńs���Ɛڑ����Ă��܂����A�������H��s�ǂŃV���[�g������Ⴄ�s���Ɍq���ł��܂��Ă�����f�����Ă�����ƁA�F�X�Ȍ̏ጴ�����l�����܂����炻���𐳂����`�F�b�N�ł��Ȃ���u�d���Ŏg���v�Ƃ����p�r�ł͕s�\���ł��ˁB �@�K�v�ȏ����� �� �e�c���ʂɓ��ʂ̃`�F�b�N���s�� �� �l�X�ȃp�^�[���ł̃V���[�g�̃`�F�b�N���s�� �� ���ʂ�\������ 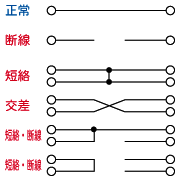 �@�e�X�g����P�[�u���E�n�[�l�X���Ŋe�c�̏�Ԃ͂����܂��ɂ͉E�}�̂悤�ɂȂ邱�Ƃ��l�����܂��B
�@�e�X�g����P�[�u���E�n�[�l�X���Ŋe�c�̏�Ԃ͂����܂��ɂ͉E�}�̂悤�ɂȂ邱�Ƃ��l�����܂��B�@�u�����v�ł���Ή��̖�������܂���B �@�P�Ȃ�u�f���v�̏ꍇ�����[�q�Ԃɒʓd����Ȃ������Ȃ̂Ń`�F�b�N���ȒP�ł����A�P�[�u���s�ǂƂ��Ă̈��e�����܂����Ȃ����̂ł��B �@�s�ǂ̒��ł���肪�傫���̂́u�Z���v(�V���[�g)�ł��B �@�s�ǃP�[�u�����@��ɑ}�����ꍇ�͍ň��͓d�����V���[�g���ċ@������蔭������Ɛr��Ȕ�Q���o�邱�Ƃ��\������܂��B �@�ł��̂ŕ����c�̃P�[�u���E�n�[�l�X����������ꍇ�͒f�����͒Z���̂ق��𐳂����`�F�b�N�ł��鑕�u���K�v�ł��B �@�u�Z���v��u�����v�ł͖{���d����������Ȃ��͂��̔z���Ɍ���ēd�����������Ă��邱�Ƃ����m�ł���Εs�ǂׂ��܂��B �@�܂�A�����c�p�̃P�[�u���`�F�b�J�[�ł͂ǂꂩ�̔z���Ɋւ��ē��ʂ��Ă��邩�ǂ����ׂ邾���ł͂Ȃ��A���ʂ̃`�F�b�N�����Ă���z���ȊO�̐c�ɂ��d�����������Ă��邩�ǂ����ׂ��H���K�v�ɂȂ�܂��B �@�菇�Ƃ��Ă� �� �e�c����{�������ʂɓ��ʂ̃`�F�b�N���s�� �� ���̍ۂɑ��̑S���̐c�ɂ͒Z���`�F�b�N���s�� ���̂悤�ȕ��G�Ȃ����݂̉�H���K�v�ł��B �@���ʂ�IC��g�����W�X�^�A�ŋ߂ł�PIC�}�C�R���̂悤�ȏ��K�̓R���s���[�^�𗘗p���đ唼���\�t�g�E�F�A�ōs���Ă��܂��̂���ʓI�ł����A����̂��˗��ł̓����[��V�[�P���T�Ȃǐ���p�̕��i���g���ĂƂ̎��Ȃ̂ł��̂悤�ȕ����g������H�Ƃ��Đv���Ă݂܂��傤�B �@�U�c�Ԃ�`�F�b�N���ꂽ�������ł����A���̂����P�c�Ԃ�̉�H�}�͂��̂悤�ɂȂ�܂��B ����H�}���N���b�N����Ɗg��\��
�@�����[�ȊO�ɐ��̃_�C�I�[�h�͎g�p���܂��B����͎��ȕێ���H��o�X�z��(���̃��j�b�g)����̋t���Ō�쓮���邱�Ƃ�h���ׂɕK�v�ł��B �@�����[�P(RY-1/�Q��H)�̓e�X�g�������c(�s���|�P�[�u���|�s��)���u���ʃe�X�g�ɑI������v�u��I����ԂŒZ���e�X�g��H�ɐڑ�����v�̐ؑւ��s���܂��B �@�o�H�I��[�q��DC24V��������Γ��ʃe�X�g���s���܂��B �@�����[�Q(RY-2)�̓P�[�u�����������Ă���Γ����āu���ʌ��ʕێ��v���ɁA�f�����Ă���u�f�����ʕێ����v�ɓd���o�͂��܂��B �@�u���ʌ��ʕێ��v�p�̃����[�S(RY-4)�Ɓu�f�����ʕێ����v�̃����[�R(RY-3)�͂��ꂼ��u���ȕێ���H�v�ƂȂ��Ă��āA��x�d����������ΈȌ�͓d������Ă������Ԃ�ۂ��܂��B �@�����ł�����Ƃ����Q�̉�H���Ⴄ�̂́A�u�f�����ʕێ����v�̃����[�R(RY-3)�̓d���͒���DC24V���瓾��̂ł͂Ȃ��A��U�u���ʌ��ʕێ��v�p�̃����[�S(RY-4)��N.C�[�q���o�R���Ă���Ƃ���ł��B �@�����[�͊�B���i�̂��߂ɓ���(�ړ_���ړ�)����̂Ɏ��Ԃ�������܂��B(�~���b�P�ʂł���) �@���ׁ̈A�̂���H�Ɍo�H�I��d�������������u�ԂɁu�f�����ʕێ����v�̃����[�R(RY-3)�ɂ͓d����������܂��̂ŃP�[�u���̏�ԂɊW�Ȃ����ȕێ���������܂��B �@���~���b�x��āu�����o�H�I���v�p�����[�P(RY-1)�����삵�ăP�[�u���̏�Ԃ肷�郊���[�Q(RY-2)�����삵�܂��̂ŁA�P�[�u�������ʂ��Ă����̂ł�����̃����[�Q�Ԃ�̎��Ԓx���̌�Ƀ����[�S(RY-4)�ɓd�����������āu���ʁv��Ԃ̃`�F�b�N���ʂ�ێ��܂��B �@���ʏ�Ԃł������ꍇ�ɂ͒f����Ԃ̌��ʂ�ێ�����Ă��Ă͍���܂�����A���ԓI�ɒx��ē��ʏ�Ԃ����m�����ꍇ�ɂ͑�������f����Ԃ̎��ȕێ���H�����Z�b�g���Ă��A���������ʂ��f�����̏�Ԃ��L�����܂��B �@�Ȃ����ȕێ��₱��������₱������H�ɂȂ��Ă��邩�ƌ����ƁA�u�o�H�I��������ă`�F�b�N���s���܂ł͂��̐c�ɑ��Ă͌��ʂ������\�����Ȃ��v�悤�ɂ���ׂł��B �@�e�X�g�����Ă��Ȃ��̂Ɍ��ʕ\�������v���u�f���v�Ƃ��u���ʁv�Ƃ��Ɍ����Ă���̂͂��������ł���B �@�u�Z�����ʕێ��v�̃����[�U(RY-6)�́u�����o�H�I���v�����[�P(RY-1)����I����Ԃ̏ꍇ�����ʃe�X�g���ȊO�̐c�Ɍq�����Ă��܂��̂ŁA�������̏�ԂŃs���ɓd����������u���̐c�ƃV���[�g���Ă���v�Ɣ��f�ł��܂��̂āA���̓d���Ŏ��ȕێ����܂��B �@�u���̐c����Z�����ēd���������v�Ƃ�����Ԃ̓_�C�I�[�h�Q(D2)��ʂ��āu�Z���ʒm�v�[�q�ɏo�͂���܂��B����͍��e�X�g���̑���H�ɒZ����ʒm���邵���݂ł��B �@�ʒm����鑤(�e�X�g���̐c)�́A�o�H�I��M����DC24V���������Ă��āu�Z���ʒm�Ǎ��v�p�����[�T(RY-5)�����삵�Ă��܂��̂Łu�Z���ʒm�v�[�q�ɑ���H����DC24V���o�͂����Ƃ��̓d���̓����[�T(RY-5)���o�R���āu�Z�����ʕێ��v�����[�U(RY-6)�삳���Ď��ȕێ����܂��B �@���̈�A�̓���Łu�Z���d���������v�Ɓu�Z���d���𗬂��Ă��錳�ɂȂ��Ă��鑤�v�̗����́u�Z�����ʕێ��v�����[�U(RY-6)�����삷�邱�ƂŒZ�����Ă��܂��Ă���c���ǂ�Ƃǂꂩ���L�����܂��B �@���ꂾ���̓����̉�H���P�c�Ԃ�̃��j�b�g�Ƃ��ĕK�v�Ȗ{���Ԃ�쐬���A���L�̂悤�ɐڑ����ē��ʃ`�F�b�J�[���������܂��B ����H�}���N���b�N����Ɗg��\��
�@�����[�`(RY-A)�͊e�c�̃`�F�b�N��H�ւ�DC24V�d�����J�b�g����ׂ̃����[�ł��B �@�J�b�g���邱�Ƃɂ���Ď��ȕێ���H�����Z�b�g���܂��B �@���[�^���[�X�C�b�`�܂��̓V�[�P���T�[�̓d���o�͂ŏ����b�g�P�`�U�܂łɁu�o�H�I���v�d����^���Ă��A���ꂼ��̐c�̏�Ԃ��`�F�b�N���Č��ʂ����ȕێ����܂��B �@�S�̂́u����v�u�s�ǁv�\����LED�̓d���̓��[�^���[�X�C�b�`�܂��̓V�[�P���T�[�̏o�͂��u�I���v�̏���DC24V���o�������_�œ_�����܂��B���Z�b�g����Ă���eCH�̃`�F�b�N���I���܂ł͏������Ă��܂��B �@�ǂ��炪���邩�́A�eCH����́u�s�ǒʒm�v�d�������邩�ǂ����Ō��܂�܂��B �@�r���Ɂu�����c���ؑփX�C�b�`(6CH/3CH)�v�����Ă���܂��̂ŁA�R�c�P�[�u���̏ꍇ�̓X�C�b�`���R�c���ɐ�ւ��Ă�����CH4�ʒu���e�X�g�I���ƂȂ�܂��B 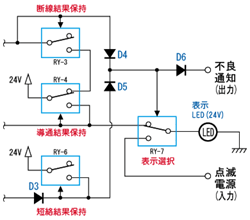 �@����̊e�c�p�̉�H�}�ł́u���ʁv�u�f���v�u�Z���v�̂R��LED�ŕ\������悤�ɏ����Ă��܂����A�˗��җl�̓����̂���]�̂悤��LED��Łu�_���v�u�_�Łv�ŕ\������Ȃ�E�}�̂悤�Ƀ����[�V(RY-7)�𑫂��Ă��Ηǂ��ł��傤�B
�@����̊e�c�p�̉�H�}�ł́u���ʁv�u�f���v�u�Z���v�̂R��LED�ŕ\������悤�ɏ����Ă��܂����A�˗��җl�̓����̂���]�̂悤��LED��Łu�_���v�u�_�Łv�ŕ\������Ȃ�E�}�̂悤�Ƀ����[�V(RY-7)�𑫂��Ă��Ηǂ��ł��傤�B�@���̔z���ł̓e�X�g���s���܂ł�LED�͏������Ă��āA���ʂ��u���ʁv�̏ꍇ�͓_���A�u�f���v���u�Z���v�������ꂩ�̃G���[�̏ꍇ�́u�_�œd���v�ɐ�ւ��܂��B �@�u�_�œd���v�ɂ͕ʓr�����f���I��DC24V�������ł����H���q���ł��������B �@���ƈ�_�A���̉�H�ł́u�Б��ʓd�v�Ƃ��Ă��邽�߂����ꕔ�̕s�ǃp�^�[���͐������\���ł��܂���B(�s�ǔ���͂��܂�) 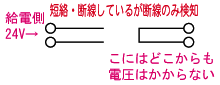
�@�E�}�̂悤�ȕs�ǂ̏ꍇ�́u�f���v�͔��f�ł��܂����A�E���̂Q�̒[�q(B��)�ɂ͂ǂ�������d���͂�����܂���̂Łu�Z���v���Ă��邱�Ƃ��킩��܂���B �@�u�f���v����͂��Ă���̂ŕs�Ǖi�Ƃ������ŕ����E�C������ł��傤����Z���~�X�����̎��ɂ݂��Ē����ł��傤���A�����Z���ɋC�Â����ɒf�������C�����Ă��ēx���ʃ`�F�b�J�[�ɂ��������ǂ͒Z�������m���܂����琻�i�����I�ɂ͖�肪�����Ƃ������ŁA����͕Б��ʓd�����ɂ��Ă��܂��B �@���ۂ̂Ƃ���A����ȕςȔz���~�X�͐����Ԃ�̈�̊m���ł��N����Ȃ��ł��傤�B �@���ꂪ�C�ɂȂ�悤�Ȃ�A���LED�\����������ɂ܂Ƃ߂Ă��܂���H�ɂ���u�f���v�Ȃ̂��u�Z���v�Ȃ̂��̌����̌��������ł��܂���l�Ԃ͋C�Â��܂���i�O�O�G �@�e�c�p�̉�H�Ń����[���U��(�܂��͂V��)�A�S�̂ł̓����[�R�W��(�܂��͂S�S��)�Ƃ������i�I�ɂ͂Ȃ��Ȃ��S�[�W���X�ȉ�H�ł��B �@�l�̎�ō����̂ł͂Ȃ��A��Ђ̂�����(!?)���̂ł�����S�̂����鐧��p�̃P�[�X�Ȃǂ̔�p���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B  �@�P�U�b�g�̃V�[�P���T���������������ł��̂ŁA�S�ăV�[�P���T���̃v���O�����ō��ΉE�̐}�̂悤�ȃV���v���ȉ�H�ōς݂܂��B
�@�P�U�b�g�̃V�[�P���T���������������ł��̂ŁA�S�ăV�[�P���T���̃v���O�����ō��ΉE�̐}�̂悤�ȃV���v���ȉ�H�ōς݂܂��B�@�����[�͎g���K�v�͂���܂���B (�V�[�P���T�̏o�͂��L�d���o�͂ł͖����ꍇ�̓����[���U�v��܂����ALED���z�����݂Ŏg�p) �@���ʂ�f���A�Z�����n�[�h�E�F�A�Ō��o����̂ł͂Ȃ��V�[�P���T�̃v���O�����Ō����Ɣ���E�\�����s���̂ŕ����I�ȍޗ��͋ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ�܂��B �� 16���o�͂ł͏�������܂���̂ŁA���̐}�ł��ʓd�����͕Е����ł��B
�o�͂��Q�{�]���Ă�̂Ń����[���U�lj����ďo�͂̈�{�œ������A ���E�̗��������ւ��ċ��d���ăe�X�g�ł���悤�ɂ͂Ȃ�܂��ˁB �@���̔��ʁA�V�[�P���T�̃v���O�����͐��I�Ȓm�����K�v�ŁA�v���O�����̒m���Ƃ����������ł͂Ȃ��v���O�����Ɏ���܂ł̓��ʃ`�F�b�J�[���u�̓��쌴���┻��̎�@�A�ǂ���H�ɑg�ݗ��Ă�Ηǂ��̂��̐v�Z�p�̑S�Ă������Ă��Ȃ��ƃv���O�����͍��܂���̂ŁA�܂���b�ƂȂ��H��������x�̒m����o����~�����Ă���łȂ��ƍ��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�H�Ɨp�V�[�P���T�[�͎����Ă��܂��A������x�͋K�i������Ă��܂����e���[�J�[�ɂ��u���v������܂��̂Łu�C�̖����v�ł̓v���O�����ɂ��Ă̓T�|�[�g���������˂܂��B �@�ł���Ύ���җl���������ŕ���i�߂��āA���̒��x�̊ȒP�ȃV�[�P���X���u�ł���������Ńv���O�����\�ɂȂ鎖�����F�肵�Ă��܂��B ���Ԏ� 2008/6/6
|
|
| ���e |
�@���̂��т́A���ɗL���������܂����B �@������������Ղ��Q�l�ɂȂ�܂����B �@�������g�\���ɍl��������ł������A�Ȃ�قǂƎv�킳��܂����B�܂��܂��삯�o���Ŗ��n�҂�ȂƒɊ���������ł��B�c��̓v���O�����ł��A���������Ă͏������J��Ԃ��Ă��܂��B���A�撣��܂��B �@�{���ɗL���������܂����B���A���₳���Ă��������܂��B �܂� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@��H�}���猴����������A���Ƃ͂�����u�V�[�P���X�}�v�ɓW�J���āA�V�[�P���X�}���ǂ��V�[�P���T�̃v���O��������ɒu�������邩������ǂ��ď����Ă䂭�����ł��B �@��x�ɑS�������悤�Ƃ͂����A�܂��͉�H�̈ꕔ�̋@�\�݂̂������Ă݂Ď��ۂɃV�[�P���T�ɓ]�����A������m�F�����Ƃ��J��Ԃ��čŏI�I�ɂ͑S�̂���������悤�ɒi�K�I�ɍ�Ƃ�i�߂Ă݂Ă��������B �@���̍�Ƃ�i�߂邤���ɏ��X�ɋZ�p���g�ɂ��ł��傤�B ���Ԏ� 2008/6/11
|
|
| �|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N | ||
|
�@����ɂ��́A�͂��߂܂��āB���̂悤�ȃy�[�W������Ƃ͋����Ȃ���ǂݐi�ނ����A���J�ȉƂ��̐^���Ȏ��g�݂Ɋ������Ă��܂��B �@����A�����I���Ǝv������e�ł����A���������������܂��ł��傤���B �@�g�ѓd�b�̃n���Y�t���[�̃}�C�N���C���z�����g���Ă���̂ł����A���l���̓d�b��c�Ȃǂł́A�}�C�N�͊O�̎G�����E�������ʼn�c�̎ז��ɂȂ�܂��B �@�����ŁA�g�т̃s���A�T�C���͒��ׂ�ꂽ�̂ł����A�R���f���T�}�C�N���~���[�g����̂ɁA�P�ɃO�����h�ɗ��Ƃ��ƃ|�b�v�m�C�Y�H�V���b�N�m�C�Y�H����������ƍl���܂����B �@���܂��ẮA�m�C�Y�̑����@�ɂ��Ă���������������K���ł��B��낵�����肢�������܂��B ���� �� �l |
||
| ���Ԏ� |
�@�������l�A�͂��߂܂��āB �@�����m���Ƃ͎v���܂����A�܂��̓G���N�g���b�g�R���f���T�}�C�N(�Ȍ�ECM�Əȗ�)�̃}�C�N��H�ɂ��Ă����炢�B �@ECM��ڑ�����}�C�N�[�q�̓}�C�N���͂ɂȂ��Ă���Ƌ��ɁAECM������u�d���v����������Ă���d���[�q(�d��:�u���傤���傤�v�Ɠǂ݂܂�)�ɂȂ��Ă��܂��B �@��ʓI��ECM��2�`3V���x��d���d���Ƃ��A���j�����x�̃o�C�A�X��R����ēd���������܂��BECM���̂������ʼn����ɂ��킹�ēd���́u�z�����ݗʁv�߂��Ē[�q�d����ϓ������邵���݂ł��ˁB �@���ꂪ�_�C�i�~�b�N�}�C�N���ł͖��d���E�d���o�ׂ͂̈Ɂu�����v�̎���0V�ł�����~���[�g���鎞�̓X�C�b�`�ŒP����GND�ɗ��Ƃ������ŗǂ��̂ł����AECM�ł͉����o�͒[�q�͏�Ƀo�C�A�X�d��������������ԂŖ�1�`2V���鎖�����ł��B �@�~���[�g�����悤�Ƃ��ăX�C�b�`���������q����GND�ɗ��Ƃ��Ɠd�C�M���I�ɂ́u������Ԃ̓d�������C�Ƀ}�C�i�X1�`2V�̐U���̉����M��(�p���X)�������I�v�Ƃ������ɂȂ�A�ʏ퉹���ł̓ʂu���x�̐U���̂Ƃ���ɂƂĂ��Ȃ�����ȉ������������ƂɂȂ��ăX�s�[�J�[����́u�{�R�b�v�Ƃ����|�b�v�m�C�Y���������Ă��܂��܂��B �@�Ƃ������̓o�C�A�X�d�����������̊�d���ł�����A�{���Ȃ�}�C�N���~���[�g�������ɂ͌��̃o�C�A�X�d�����ێ����Ă��ꂪ�����ŐU��Ȃ��悤�ɂ��Ă��̂������ł����A�g�ѓd�b�̋@���O���Ɍq���}�C�N�ɂ���Ĕ����Ƀ}�C�N�[�q�̖������̓d���͈Ⴂ�܂����A�~���[�g�������ɂ������̓d�����ʂu�P�ʂ̌덷�����ێ������H�Ȃ�č��͔̂��ɖʓ|�Ȃ̂ŁA�ʏ�̓}�C�N�[�q�̓d�����X�C�b�`��GND�ɗ��Ƃ��̂Ɠ������@�Ń~���[�g���Ă��܂��B �@���̍ۂɂ����Ȃ�GND�ɗ����āu�}���ȋ��剹�v�łȂ���Ηǂ������ł��̂ŁA�g�����W�X�^���g�p�����u�Ȃ��炩�ȃ~���[�g��H�v���쐬���Čq���u�{�R�b�I�v�Ƃ������ɂ͂Ȃ炸�A���ɕ������Ȃ����g���ȉ��̃X�s�[�h�Ń~���[�g�܂Ŏ����Ă䂯�܂��B�~���[�g�����̎��͂��̋t�ʼn��ɂȂ�Ȃ��d�C�M���ω��Ō��̓d�ʂ܂ʼn����Ă��悢�����ł��ˁB 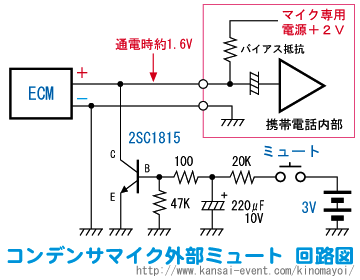 �@������̉�H�ł͖�0.3�`0.5�b���x�Ń~���[�g�^�������s���܂��B (����0.���b�ŏ�������߂����肵�܂����A�o�C�A�X�d���𑪒肵���ꍇ�͖�1�b���x�Ŋ��S�ɕω����������܂�) �@�~���[�g�X�C�b�`��ON�ɂ���ƃX�[���Ɖ����������Ȃ��Ă䂫�����ɂȂ�܂��BOFF�ɂ���Ƌt�ɃX�[���Ɖ����������Ă��܂��B �@�}�C�N��A���v�̌��ɂ���Ă̓X�C�b�`��ON�ɂ������ɂ����킸���ȃm�C�Y����������ꍇ������܂����A�X�C�b�`�Œ���ON/OFF�����H�̂悤�Ȏ����Ȃ��̂ł͂���܂���B �@���Ă��̉�H�A�g�ѓd�b�Ŏg�p����ꍇ�ɂ́u�V�[���h�v�ɂ��イ�Ԃӂ��đg�ݗ��ĂĂ��������B �@�g�ѓd�b�͒ʘb���ɂ͏��^�@��Ƃ��Ă͋���ȓd�g���o���Ă��܂��B �@���̓d�g���}�C�N�z��(�{��)���E���Ă��܂��Ɓu�u�[�v�Ƃ��u�u�u�u�u�u�u�c�v�Ƃ����s���ȃm�C�Y���Ƃ��ĕ������Ă��܂��܂��̂ŁA��H�͂�������V�[���h���ēd�g����荞�܂Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B ���Ԏ� 2008/6/4
��
|
|
| �ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H | ||
|
�@�������̕���͂Ǒf�l�ł����A���\�������L�肢���y�����q�������Ă��������Ă���܂��B�����ŏ��X���q�˂����������������܂����B �@�ȑO���f�W�J���̊O���d������肽���Ǝv���Ă���܂��āA���e�͒P�O�d�r�S�{���g�p��IN 4.8v OUT 3.4v�Ƃ����X�e�b�v�_�E���R���o�[�^�Ȃ̂ł����A�L���́w100�~�V�K�[���C�^�[�\�P�b�g�pDC-DC�_�E���R���o�[�^���A�b�v�R���o�[�^�ɉ������悤�I�x�����p�ł��邩�Ǝv����낤���Ǝv���Ă���܂��A �@�����ł��̉�H��IN��12v�`24���ɂȂ��Ă���܂���12���ȉ��ł͓��삵�Ȃ��̂ł��傤���H �@���������ł����4.2����3.4���ɂ����H�����������肦��Ǝv�����q�˂�v���܂��B ���O���O �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�܂����_�����ɁAMC34063A���g�p�����_�E���R���o�[�^�ł�4.8V��3.4V�̕ϊ��͂ł��܂���B �@�����MC34063A��12V�����œ����Ȃ�����ł͂Ȃ��A���̗��p���@�ł����͓d�����o�͓d���ɑ��ĒႷ���邩���ł��B �@MC34063A���g�p�����X�C�b�`���O�R���o�[�^��A�悭����O�[�q���M�����[�^�ł͒��ɓ����Ă���d�q��H�ŏo�͓d�������肳���܂����A���̍ۂɂ͏o�͂Ɠ��͂̓d���̍������イ�Ԃ�ɑ傫���Ȃ��ƈ��肵�ďo�͂ł��܂���B �@�����̉�H�ł͂����Ă��́u���o�͍��R�`�S�u�v���K�v�Ȃ��߁A3.4V�̏o�͂悤�Ƃ������6.4�`7.4V�ȏ��̓��͓d�����K�v�ł��B�d�r�S�{��4.8V�ł͑���܂����ˁB �@�ł��̂�MC34063A���g�p�����_�E���R���o�[�^�ł͂���]�̓d����H�͍��܂���B �@4.8V��3.4V�̍���1.4V�ł��̂ŁA�d����1.4V�ł��������M�����[�^���g�p����Γd����H�͍��܂��B �@3.3V�o�͂̒�h���b�v�^�O�[�q���M�����[�^TA48033F����PC2933���g�p����Ɨǂ��ł��傤�B �@�g�����͖{�y�[�W�́u100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p�������v�Ŋ��ɐ������Ă��܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ă��������B ���Ԏ� 2008/5/27
|
|
| ���e |
�@MC34063(�݊��i�܂�)���g�p����Ă��邢�����̌g�я[�d�pDC-DC(��5V�o��)�̓����𑪒肵�܂������A�@��ɂ���č���������̂̓d���d����8V�`9V�ȉ��ɂȂ�Əo�͓d�����ቺ���錻�ۂ��m�F���Ă��܂��B �@IC���̂̓���͈͂�3V�ȏ�ł���A�ŋ߉�������STEP UP�R���o�[�^��3V�O��ł̓�����m�F���Ă��܂��B �@�ȉ����S�Ҍ����̈��E���Ă��܂��܂����E�E�E �@���̍����ǂ�ȗ��R���甭������̂��A���߂čl���Ă݂܂����B (�����m���Ƃ͎v���܂����B) �@���̌���STEP DOWN��H�̏ꍇ�G�~�b�^�t�H���A�o�͂Ȃ̂ŁA�X�C�b�`���OTr�Ƃ��̃h���C�u��H�̊W�œ��쉺���d�����オ���Ă��܂��悤�ł��B �@�Œᓮ��d����������ɂ͂ǂ�����Ηǂ����l�����Ƃ���A�X�C�b�`���OTr��E(IC��2p)��GND�ɗ��Ƃ�����Ԃ���ԓ���d���������鎖�ɂȂ�悤�ł��B (����3V�ł����삷��STEP UP��H�������Ȃ��Ă��܂��ˁB) �@�����l����ƒႢ�d���œ��삳����ׂɈȉ��̂Q�̕��@�����肻���ł��B �@�P�ڂ̕��@�͂k���g�����X�ɕύX�����̈ꎟ����d���ƃX�C�b�`���OTr��C(IC��1p)�Ԃɐڑ�����B �@�Q�ڂ̕��@�̓X�C�b�`���O�g�����W�X�^�Ƃ���PNP�g�����W�X�^���O�t���AIC���X�C�b�`���OTr��C(IC��1p)���h���C�u����B �@���ꂪ���܂������̂ł���A�u�d�r�E�o�b�e���[�E�[�d��v�̖������Ɋ�ꂽ�u�o�r�o�H�v�̃^�C�g���̏������݂Řb��ɂȂ����A7.4V�o�b�e���[�����PSP�[�d/������\�����m��܂���B �@�Ƃ����onsemi�̃A�v���P�[�V����(AN920-D)�����Ă�����ASTEP UP��STEP DOWN�̓��삪����ɐ�ւ��H��H������̂ɋC�����܂����B(p18) �@�Ȃ�قǁA����Ȏg�������o����̂ł��ˁB �@����ɂ��Ă�����IC�ɂ����܂ł͂܂荞�ގ��ɂȂ�Ƃ́E�E�E jr7cwk �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@MC34063�̓����g�����W�X�^���g�p�����ɁA�O���Ƀg�����W�X�^��FET��t����܂��b�͈���Ă��܂��B �@�v��MC34063�̓R���p���[�^�Ɣ��U��H�Ƃ��Ă����g���킯�ł����A�����Ȃ�ƕʂɑ��̓d���pIC�ł��ǂ��킯�ŁAMC3463�ɂ������K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B ���Ԏ� 2008/5/31
|
|
| ���e |
�@�����̉L��������܂��B �@�d���������Ȃ��ꍇ�s�\�Ƃ������ŗ����������܂����B �@�Ⴆ��IN��d�r�W�{�łX�D�UV���x����ΐ���ɓ��삷��ƌ��������ŋX�����ł��傤���x�X���݂܂����낵�����肢�v���܂��B ���O���O �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�����ł��ˁB �@jr7cwk�l����������Ă���悤�ɁA5V�o�͎���8�`9V�������Ɛ��������삵�Ȃ��悤�ł��̂ŁA3.4V�o�͂ɑ���9.6V��������イ�Ԃ�ɓ��삵�܂��ˁB �@�d�r�̖{���������Ȃ�̂͂�����ƕs�ւ��Ǝv���܂����A��ō����̂ł����炻��ł��\�����Ǝv���܂��B �@�u��肽���I�v�Ǝv�������̂����ۂɎ�������̂͊y�����ł����為�Ѓ`�������W���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2008/6/4
|
|
| ���e |
�@���Ԏ��L��������܂��A�R�[�q���M�����[�^���g������H�ƂQ��ލ���Ă݂悤�Ǝv���܂��A�L��������܂����B ���O���O �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�����ƁA�d�q�H����y���܂�鎖�����F�肵�Ă��܂��B ���Ԏ� 2008/6/5
|
|
| �G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� | ||
|
�@�G�[�����H�Ƃ́u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ƌ������̂��w�������̂ł����A���̃��j�b�g�̎g�p�\�d����max��1,25A�B �@������Ԃ̃��[�������v�Ɏg�����ƍl���Ă���̂ł����A���[�������v�͑O��ɓ����A�����10mA��LED��10���قǎg�p���Ă��܂��B���[�������v��W���Ƃ����Ă��܂�������ʓI�Ȃ��̂ŁA����炷�ׂĂ����̃��j�b�g�ł܂��Ȃ�����̂Ȃ̂ł��傤��? ���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�u�Ԃ̃��[�������v�v�ƌ����Ă�����ނ̂v���̂��̂�����A��ʓI�ȁu�������Ƃ炷�v����(�V��)�Ɏg���Ă���d����12V/8W�̂��̂������ł��ˁB �@����12V/8W�̓d�����O��łQ�g�p����Ă���Ƃ����獇�v16W�ɂȂ�܂��̂ŁA�G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v���ő��i15W���Ă��܂��܂��B �@10mA��LED��10����12V/100mA�Ŗ�1.2W�Ōv�Z���Ă��������B �@�d���Q��(�����g���Ă���̂����ׂĂ�������)��LED����1.2W�𑫂���15W�ȓ��ł�����̃��j�b�g���g�p�ł��܂��B �@15W���Ă��܂��ꍇ�͎������̓d����6W���x�̓d�͂̏��Ȃ�����(�Â��Ȃ�܂�)�Ɏ��ւ��邩�ALED�d���̂悤�ȏ���d���̏��Ȃ����̂Ɍ�������Ηǂ��ł��傤�B �@�s�̂�LED���͏���d���͏��Ȃ��ŐV�Z�p�̔��FLED�g�p�Ƃ����_���E�P�ėǂ�����Ă��܂����A���邳�͑S�R�d���ɋy�Ȃ����������̂Ō������鎞�͂��܂���҂͂��Ȃ��ق����ǂ��ł��傤�ˁB �@�d���̂ق���ς����ɁA���̃��j�b�g��O��ʁX�ɂQ�Ƃ����Ƃ����S�[�W���X�ȕ��@������܂����E�E�E �@�G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�͓d����d������ł͂Ȃ�PWM����̂悤�ł��̂�LED�d���⎩���LED�Ɩ��ł��������u����`�v�Ɩ��邳��ς��邱�Ƃ��ł��܂��B ���Ԏ� 2008/5/20
|
|
| ���e |
�@���X�̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@�����A�O���Ē��ׂ���O��12V/8W�Ō�낪12V/10w�ł����B �@LED���悭�悭�l������11�E�E�E������ɂ��낾�߂ł��ˁB �@�A�h�o�C�X�̒ʂ�S�[�W���X�Ƀ_�u���ōs�������ƌ��ݍl���Ă��܂����ALED�̎�O�ɂ͎c�Ƃ����邽�߂̃R���f���T���t���Ă��܂��B �@���Ƃ��Ƃ̓G�[��������̏��Ԃ�̎c�Ƃ��������t���Ă������̂́A�ꊇ�őS���c�Ƃ����悤�Ɠ��ʂ�40,000�}�C�N���t�@���b�g���x�̃R���f���T�ɕt���ւ����̂ł��B �@�Ƃ͌����A����`���Ɠ_���̎���ɂ͏����ȊO�̎c�Ƃ̓_�����Ə�����Ă��Ă��ꂪ������ƐS�z�ł��B ���� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�S�[�W���X�ɂ䂭�Ȃ�A�O�E��̎������Ɋe�P���j�b�g�Ƃ���āALED�ɂ͂ǂ��炩�Е��̔z����ڑ�����Ηe�ʓI�ɂ͑S�R���v�ł��ˁB �@���̍ۂ�LED�̂Ƃ���ɂƂ���Ă���40000��F�̃R���f���T�͊O���Ă��܂��܂��傤�B �@�R���f���T�̓����v�̓d�����X�C�b�`�Ńp�`�b�Ɛꂽ���ɂ������̊Ԃ����d�C�𗭂߂Ă����ăR���f���T�����d����܂ł̊ԁu�ځ`�v���Ƃ���������������ׂł�����A�u����`���Ɠ_�����j�b�g�v��PWM����Ŗ��邳��ύX�����铭���ƂԂ����Ă��܂��܂��̂ŃR���f���T������Ɩ{���́u����`�v�ω��ʂ�ɂȂ��Ȃ��ꍇ������܂��B �@�d�q��H�̒m����������Ȃ�u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�̏o�͂ɍX�Ƀg�����W�X�^���p���[FET��lj�������j�b�g���őO�E��{LED�ł��]�T�Ńh���C�u�ł���悤�ɉ����͉\�Ȃ̂ł����A�����l�������܂łł����100�`200�~���炢�̒lj����i�ʼn������ł��܂��B(�ʂɂ��̃G�[�����̑��u�̉�H����͂����킯�ł͂���܂���̂ŁA�����܂ň�ʓI��PWM�o�͂̒������j�b�g����������ꍇ�ł�) �@�u�����͂�����ƁE�E�E�v�Ƃ����ꍇ�͂�͂胆�j�b�g���g���ă��[�J�[�w��̗e�ʓ��Ŗ������Ŏg����̂��V���[�g�┭�M�Ȃǂ̊댯���������S�ł悢�ł��ˁB ���Ԏ� 2008/5/21
|
|
| �Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� | ||
|
�@�͂��߂܂��� �@��H�̂��ƂׂĂ��Ă����ɂ��ǂ蒅���܂��� �@���܍l���Ă���̂́A�Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M���i�d���H�j���1�b�قǂ������肻�̂܂܂Œx�点�����̂ł��� �@�ǂ̂悤�ȕ��@�A��H������܂����B �^���N �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���x���̂��Ƃ�(���ׂč폜���܂���)�̌�A�@��̐������̐ڑ��}URL�������������Ă���Ǝ��̐^�����킩��܂����̂ʼn�H�̐v���ł���悤�ɂȂ�܂����B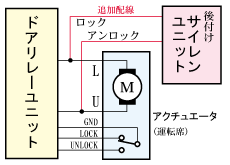 �@���ǁA�h�A�����[�̐���p�z���ł͂Ȃ��A�N�`���G�[�^�[�E���[�^�[�̋쓮�p�z�����番�Č�t���̃T�C�������j�b�g�Ɂu���[�^�[�����삵���v�Ƃ����M����`���Ă���Ƃ����̂��{���̔z���̂悤�ł��B
�@���ǁA�h�A�����[�̐���p�z���ł͂Ȃ��A�N�`���G�[�^�[�E���[�^�[�̋쓮�p�z�����番�Č�t���̃T�C�������j�b�g�Ɂu���[�^�[�����삵���v�Ƃ����M����`���Ă���Ƃ����̂��{���̔z���̂悤�ł��B�@���b�N�����ꍇ�ƃA�����b�N�����ꍇ�ŃT�C�����̖����Ⴄ�����ł��̂ŁA���ꂼ��̔z���͓Ɨ������܂܂ł���]�̕b���x������K�v�����肻���ł��B 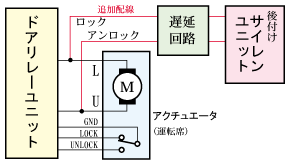 �@����̒lj��u�x����H�v�͉E�̐}�̂悤�ɁA���[�^�[�쓮�p�̓��͔z������T�C�������j�b�g�̊Ԃɋ��ނ悤�ɒlj����܂��B
�@����̒lj��u�x����H�v�͉E�̐}�̂悤�ɁA���[�^�[�쓮�p�̓��͔z������T�C�������j�b�g�̊Ԃɋ��ނ悤�ɒlj����܂��B�@���̐}�ł͓d���Ȃǂ̔z���͏ȗ����Ă��܂��B �@�M�����u�������肻�̂܂��v�Ƃ�������]�ł����A���[�^�[�쓮�p�̓��͂ɂ̓����[���j�b�g���̃����V���b�g�^�C�}�[��H�����莞��+12V�̓d�����o�͂���Ă��܂��B �@�x����H��v�����Łu�ǂ�ȐM��(�p���X�����ς�����艹���M����f�B�W�^���M���̂悤�ɐM���̕��⎞�Ԏ��̂ɉ����Ӗ��̂��镨)�����Ă������I�Ƀp���X����ǂݎ���āA������������肻�̂܂��o�͑��̃p���X���ɔ��f�����������肻�̂܂܉�H�v�Ƃ������S�S�����Ő����̋����������x�����u����낤�Ƃ���ƁA�f�B�W�^���f�B���C���̓���ȉ�H���i���g�����胍�W�b�N��H�Ƒ�e�ʃ������[���g�p�������́A�܂���PIC�}�C�R���̂悤�ȃ}�C�N���R���s�[�^���g�p���ăv���O�������쐬���đ��u�����ȂǑ�|����Ȑ��앨�ɂȂ�܂��B 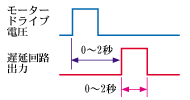 �@����̗p�r�ł͂����܂Ŏ�Ԃ����������G�ȉ�H���g�p�����ɁA�P���Ɂu�h�A���b�N�M�����������v���u�C�ӂ̎��Ԓx��������v���u�h�A���b�N�M���Ɏ����M�����o�͂���v�Ƃ��������̒x����H�ɂ��܂��B
�@����̗p�r�ł͂����܂Ŏ�Ԃ����������G�ȉ�H���g�p�����ɁA�P���Ɂu�h�A���b�N�M�����������v���u�C�ӂ̎��Ԓx��������v���u�h�A���b�N�M���Ɏ����M�����o�͂���v�Ƃ��������̒x����H�ɂ��܂��B�@�u�x�����ԁv�u�o�͂̃p���X��(����)�v�͂O�`�Q�b�̊ԂŔC�ӂɐݒ�ł��܂��B �@��H�}�ł��B ����H�}���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���̓J�v�� �@���[�^�[�쓮�d������̓��͂̓t�H�g�J�v��(TLP521)���g�p���ĎԂ�12V�n�Ɖ�H��5V�n���J�b�v�����O���Ă��܂��B �@�܂��t�H�g�J�v���ɐڑ�����z����ς��邾���āu�v���X�R���g���[���v�u�}�C�i�X�R���g���[���v�̂�����̎Ԏ�ł��g�p�ł��܂��B �� �x���^�C�}�[ �@TTL IC(H C-MOS)��74HC221���g�p���������V���b�g��H�ł��B �@74HC221�ɂ̓��m�}���`�o�C�u���[�^(�����V���b�g)���Q��H�����Ă��܂��̂ŁA�Е����u�x���^�C�}�[�v�ɁA�����Е����u�o�̓����V���b�g�v�Ɏg�p����ƕ֗��ł��B �@�x���^�C�}�[�͓���(_A)�[�q�̗�����œ�����J�n���A74HC221�ł̓��g���K(�ăg���K)��������܂��疜����̃`���^�����O�Ȃǂł��^�C�}�[���Ԃ͕ς��܂���B(���g���K�\�Ȃ��̂ɂ�74HC123������܂�) �@�x���^�C�}�[�ł͔��Œ��R(VR1 200K)�Œx�����Ԃ��O�`�Q�b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@�x�����쒆�́u�x��LED�v���_�����܂��B �� �o�̓����V���b�g �@�x���^�C�}�[���ݒ莞�Ԃœ���I������Ɠ�i�ڂ̏o�̓����V���b�g���̃^�C�}�[������J�n���܂��B �@����͒x���^�C�}�[�ƑS��������H�\��(�g�p���i������)�ɂ��Ă���܂��̂ŗ������₷���ł��傤�B���i���n���_�Â����鎞�ɂ��ԈႢ�ɂ������Ă��܂��B �@�o�̓����V���b�g�����Œ��R(VR2 200K)�ŏo�̓p���X���Ԃ��O�`�Q�b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@�o�͓��쒆�́u�o��LED�v���_�����܂��B �� �P�Q�u�o�� �@TTL IC��5V�n����Ԃ�12V�n�ւ̏o�͂̓g�����W�X�^��t�H�g�J�v���A�܂�FET�ȂǐF�X�ȕ��ō��܂����A�����p���̃T�C�������j�b�g�̉�H�}���s���ł��鎖(����d���ŗǂ��͂��ł���)�Ɖ�H�}�������l�����̎����ԗp�̉����̑��u�ɗ��p����邩������Ȃ��̂Ń����[�o�͂Ƃ��ă����[�����������I�ׂΐ��\�v���x�̕��ב��u�܂Ńh���C�u�ł���悤�ɂ��Ă��܂��B �@�܂������[�ړ_�����̔z����ς��邱�Ƃł�������u�v���X�R���g���[���v�u�}�C�i�X�R���g���[���v�̂�����̗p�r�ł��g�p�ł��܂��B �@��e�ʂ̓d���Ȃǂ��쓮���Ȃ��̂ł���Ώ����ȃ����[�ł��イ�Ԃ�ł��̂ŁAOMRON G5V-1 5V�����肪�ǂ��ł��傤�B �� 12V�ԂŎg���̂Ȃ烊���[�d����+12V�������āA�킴�킴7805�ō����5V�Ŗ����Ă��ǂ��̂ł����A��H�}������5V�n�����̕����ʼn����ɗ��p�����ꍇ������ƍl���Ă�����5V�n�����Ŋ��������Ă��܂��B �@�@���イ�Ԃ�ɒm����������+12V�Ń����[���쓮������(��^�����[�ȂǂłȂ�ׂ��R�C���d�������炵����)���͂ǂ��������R�ɁB �� �d�� �@�T�C�������j�b�g�ȂǂŎg�p���Ă�����̂Ɠ����u�펞+12V�v����d�������܂��B �@�d����H���͎̂O�[�q���M�����[�^7805���g�p������b�I�Ȃ��̂ł��B �� ����d�� �@�ҋ@���̏���d����1mA�ȉ��ł��B���̉�H���q��������Ƃ����ăo�b�e���[������ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B(���̃T�C�������j�b�g���ƕς��Ȃ����x�ł��傤) �@���b�N����E�A�����b�N��������ăp���X�o�͂�����Ԃ��������[�̃R�C���d���Ԃ���x������܂��B �@�����V���b�g�^�C�}�[��H�͍ł��|�s�����[�ȃ^�C�}�[IC 555�Ȃǂł����܂����A���b���x�܂łłQ��H�ȏ�̃^�C�}�[��g�ݍ��킹�ĉ�������肽�����ɂ�74HC221�܂���74HC123���g�p����ƌ��\�ȒP�Ɏ��萔�̌v�Z���ł���̂ł悭�g����H�ł��B �@�܂�74HC221�܂���74HC123�̏ꍇ�̓g���K�G�b�W�������オ��(B����)�ł�������(_A����)�ł��g���A�o�͂���(Q�o��)��(_Q�o��)�̗��ɐ�������Ă���̂ŋɐ������킸�ɃC���o�[�^(NOT��H)��lj�����Ȃ�ĉ�H�������Ȃ��Ă��ǂ��̂Ŕ��Ɏg���₷�������V���b�g�^�C�}�[IC�ł��B ���Ԏ� 2008/5/22
|
|
| ���e 5/22 |
�@���x���A����肵�Ă����������肪�Ƃ��������܂��B �@�����A���̋x�݂ɍ쐬���Ă݂����Ǝv���܂��B �@���肪�Ƃ��������܂��� �^���N �l
|
|
| �p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H | ||
|
�@�����Q�l�ɂ����Ă��������ēǂ܂��Ă�����Ă��܂��B �@�Ɩ��Ŏg����ނő��k�������܂��B �@�������Ƃōs���Ă����d�����ŋ߂̓p�\�R���̗��p�ŕ֗��ɂȂ�܂����B������ł����������ƕ֗��ɂ������̂ł��B�p�\�R������USB�|�[�g�Ő������͂֗̕��ȃf�o�C�X�����邱�Ƃ������܂��āA���̃e���L�[�{�h�̃G���^�[�L�[�𗘗p���Ė{�̂̕��ő��点�Ă���\�t�g�̊O�����͗p�L�[�ɗ��p�ł��Ȃ����H�̑��k�ł��B �@�ނ�݂Ƀf�o�C�X�̃L�[�{�[�h���甼�c�t���ŊO�֏o���Ă��悢�̂��H���o���Ŕ������o����H�����[�^�[���炢�܂ʼn�����OK���H�Ƃ��F�X�~���肪�ł܂����B �@�����������̃f�o�C�X�iELECOM�@TK-UEHBK)�͂ǂ�������H�ɂȂ��Ă���̂����������Ă��܂���A�����Ă��������B �����@�p�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@��Ɍ��_����B >�ނ�݂Ƀf�o�C�X�̃L�[�{�[�h���甼�c�t���ŊO�֏o���Ă��悢�̂��H �@10cm�`30cm���x�ł���Α��v�ł��傤���A����ȏ�����߂ł��B �� �m�C�Y�₻�̑������l������ƒ��ڊO���Ɉ����o�������̂ɖ�肪����܂�
�@�m���ɐ��i�ɂ���Ă͂P���[�g���ȏ�̉������ł��镨�������Ă��邩������܂��A�����P�[�u���ڃn���_�Â����Ďg�p�����Ȃ牺�L�́u�s��̉\���v���l��������Łu���삵�Ȃ��Ȃ��Ă��ւ������I�v�Ȃ璼�o���ł��\���܂���B �@�l�I�ȗV�тł͂Ȃ��A�Ɩ��Ŏg�p�����Ƃ������ł��̂ł��̂悤�ȕs����Ȍ�쓮�v�f���܂��̂��g�p�����Ƃǂ��Ȃ�̂��̐ӔC�͎��܂���̂Œ��o���͂����߂��邱�Ƃ��ł��܂���B �@��쓮�̐S�z�Ȃǂ��������肵�Ďg�p����̂ł�������ł��Љ��悤�ȊO���X�C�b�`�p�̒��p��H���Ƃ���Ă��������B ���@�@�@���@�@�@��
 �@PC�p�̊O�t���e���L�[�p�b�h�Ƃ����ƁA�����������̂悤�Ȍ`�����Ă��܂��ˁB
�@PC�p�̊O�t���e���L�[�p�b�h�Ƃ����ƁA�����������̂悤�Ȍ`�����Ă��܂��ˁB�@�ʐ^�́uELECOM TK-UEHBK�v�͎����Ă��܂������J�������͖����̂ł����A��{�I�ȃL�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�ɂ��Đ������܂��B �@�L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�̒��ɂ͏����Ȑ�pIC(�����Ă��̓v���O�����������ݍςݐ�p�}�C�R��)�������Ă��āA�o�b�Ƃ̒ʐM�ƃL�[�X�C�b�`�̓��͊Ď����s���Ă��܂��B 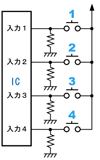 �@���^�}�C�R�����ƃL�[�X�C�b�`���q���ꍇ�A�X�C�b�`�̐������Ȃ��ƍ��}�̂悤�ɒ��ڃ}�C�R���̓��̓|�[�g�ɃX�C�b�`������ڑ����ă|�[�g�ɑ��Ĉ�Έ�̑Ή��œ��͏��������܂��B
�@���^�}�C�R�����ƃL�[�X�C�b�`���q���ꍇ�A�X�C�b�`�̐������Ȃ��ƍ��}�̂悤�ɒ��ڃ}�C�R���̓��̓|�[�g�ɃX�C�b�`������ڑ����ă|�[�g�ɑ��Ĉ�Έ�̑Ή��œ��͏��������܂��B�@���̂悤�ȉ�H�ł͐����[�g�����x�̉����͂قږ�肠��܂��A��H�E�d���E��������P�[�u���̎�ށE���͂̃m�C�Y�ɂ����܂���10���[�g�����x�܂ʼn�����ꍇ������܂��B �@�A�����̂悤�Ȉ�Έ�̐ڑ��̓X�C�b�`�������Ȃ��ꍇ�͊ȒP�ł悢�̂ł����A�����X�C�b�`�����\�`���S������ƁA���̓|�[�g�����\�`���S�|�[�g���K�v�łƂĂ����^�̃}�C�R���`�b�v�ł͂��̂悤�ȃs�����͗p�ӂł��܂���B �@�o�b�p�̃e���L�[�p�b�h�ł�20�L�[���炢�A�t���L�[�{�[�h�ł�80���L�[����ŋ߂ł�110�L�[������̂�����A�X�C�b�`�Ƀ|�[�g�����ł͂����ւ�Ȏ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�����ő�ʂ̃X�C�b�`���q���@��ł́u�}�g���b�N�X�ڑ��v�Ƃ������@�ŃX�C�b�`��Ԃ̖ڏ�ɔz�����ĕK�v�ȃ|�[�g�������炵�Ă��܂��B �@���Ƃ��A�u�O�`�e�v��16�̃L�[�X�C�b�`���q���ꍇ�͎��̉�H�̂悤�ɐڑ����܂��B(����͈��ŁA���ۂ̃L�[�p�b�h���i���Ƃ͈قȂ�܂�) 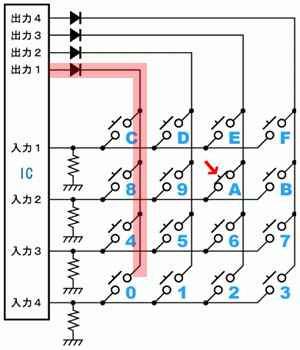 �@���̂悤�ȍs�E��ɕ����Đڑ������f�o�C�X��������������������u�_�C�i�~�b�N�����v�ƌ����A�L�[�X�L�����̂悤�ɓ��͂���ꍇ�́u�_�C�i�~�b�N�X�L�����v�ƌ����܂��B (�����悤��LED���}�g���b�N�X�ڑ����ĕ\������ꍇ�̓_�C�i�~�b�N�h���C�u�ƌĂт܂�) �@��̐}�ł́u�`�v�̃X�C�b�`�������Ă��܂��̂Łu�o�͂R�v��HI�̎��Ɂu���͂Q�v��HI�ɂȂ�܂��̂ŁA���̏�Ԃ����m���āu�`�̃L�[��������Ă���v�ƃ}�C�R���͔��f���܂��B �@�}�ł͂������o�͂��ւ��Ă��܂����A���ۂɂ͂P�b�Ԃɉ��\�����ւ����s���Ă��܂��B �@�u�}�g���b�N�X��H�Ń_�C�i�~�b�N�X�L��������Ă���X�C�b�`����{�I�ɂ͉����ł��܂����B�v �@10cm�`1m���x�ł���Ή����ł���ꍇ������܂����A�����܂ł���́u�ł���ꍇ������v�Ƃ������x����{�I�ɂ͌�쓮���܂��B �@�u�X�C�b�`���P�[�u���������ĉ�������v�Ə����ΒP�ɃX�C�b�`�܂ł̋����������Ȃ邾���œ��ɃX�C�b�`��ON/OFF�̏�Ԃ�d�C�I�ȓd����d���Ŏ����ɂ͕ς��͖����悤�Ɏv���邩������܂���B �@������Ɠd�C�̐����𗝉����Ă���l�Ȃ�u������(�z���̒�R��������)�d�C���͂��Ȃ��v�u�d�C������Ă��܂������H�v�Ƃ����S�z�Ȃ�o�ė���ł��傤�B �@�������������_������܂����A�_�C�i�~�b�N�X�L�����̏ꍇ�́u�M���̎��ԓI�x���v�Ƃ����S��������s��Ő������X�C�b�`��ON/OFF�����ʂł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@�z���������ăX�C�b�`�����t����ƁA���̔z���������d�C�I�ɂ́u��R�{�R���f���T�v�Ƃ��ē����܂��B �@��R�{�R���f���T������ƃR���f���T�̏[�d�E���d�œd���ω����Ȃ܂�A�M���`�B�ɒx�ꂪ�����܂��B 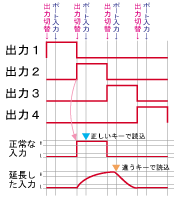
�@�E�}�̓_�C�i�~�b�N�X�L�������̊e�M���g�`�ł����A�L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�̊��ł͔z���͒Z���̂Ő������������L�[��ł��܂����A�z������������ƐM�����a��Ő}�̂悤�Ɂu�P�ׂ̃L�[���ƌ�F�������v���A�u�g�`�����イ�Ԃ�ɔ��f���x���܂ŕω������ɂǂ̃L�[��������Ȃ��v�Ƃ����s����N����\���������ł��B �@�����[�g����������딻�f����悤�ɂȂ�̂��A�Ȃǂ͎g�p����z���̑f�ށA���̃L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�̃X�L����������ǂݍ��݃v���O�����̍�莟��E�E�E�ł��̂Łu�����[�g���܂ʼn�����v�Ƃ͒f���ł��܂��A���\�Z���`�ȏ㉄���Ƃ��̂悤�Ȍ�쓮�̌����ɂȂ�ł��傤�B �� ��肢�v���O���}�����ƁA��쓮���ɂ����悤�^�C�~���O�����܂����Ă��鐻�i������ł��傤
 �@�����ŁA�_�C�i�~�b�N�X�L��������Ă���X�C�b�`�ډ�������̂ł͂Ȃ��A�u�O���̃X�C�b�`��ʉ�H�ɂ��ĉ��������v���@���Ƃ�܂��B
�@�����ŁA�_�C�i�~�b�N�X�L��������Ă���X�C�b�`�ډ�������̂ł͂Ȃ��A�u�O���̃X�C�b�`��ʉ�H�ɂ��ĉ��������v���@���Ƃ�܂��B�@�L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�̉����������X�C�b�`���t�H�g�J�v�����Ƃ���A�t�H�g�J�v�����h���C�u����d���������P�[�u���̐�̃X�C�b�`��ON/OFF���܂��B �@�t�H�g�J�v���삳����ׂ̃X�C�b�`�̓_�C�i�~�b�N�X�L�����Ƃ͑S�����W�ɁA�P���Ƀt�H�g�J�v������LED���u�X�C�b�`�������Ă���Ԃ����_��������v����������邽���ł�����A���\���[�g�������Ă����v�ł��B(�z����R��LED�����Ȃ��Ȃ�܂ŁB�K�v�Ȃ�300���̒�R�l��ύX����) �@���ۂɖ�50���[�g�����x��������������܂��B(�V�[���h�P�[�u���ł���) �@�L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�̐��i�ɂ���ăX�C�b�`�ɗ����Ă���d�C�M���̌���������̐}�Ƃ͋t�̏ꍇ������܂��̂ŁA���̏ꍇ�̓t�H�g�J�v��(�̌��g�����W�X�^��)�ƃL�[�p�b�h���̃X�C�b�`�Ԃ̔z�����t�ɂ��Ă��������B �@�܂��t�H�g�J�v����LED���d��(+5V)��GND���L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h��������̂ł͂Ȃ��A�X�C�b�`�삳����@��̑��������̂ł���o�b�Ƃ��̋@��Ԃ��d�C�I�ɐ≏�ł���̂ł����S�ł��ˁB �@�P����Enter�L�[���������āu�l�Ԃ������v�܂��͋@�B�̂ǂ����ɓ��ĂĂ����āu�@�B���������畨���I�ɉ������v�̂ł����炻�������S�z������܂���̂œd���̓L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h����������܂��ˁB �@�܂��A�X�C�b�`�����������ɊO���̓d�C�M����ON/OFF�����邾���Ȃ̂ŁA�t�H�g�J�v���Ŗ����Ă������[�ł��ǂ��킯�ł����E�E�E�B 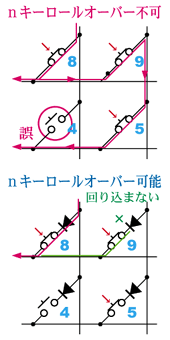 �@�L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�̃X�C�b�`���o�b�̊O�����͂Ƃ��Ďg�p����ꍇ�ɂ́u���L�[���[���I�[�o�[����v���l�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�̃X�C�b�`���o�b�̊O�����͂Ƃ��Ďg�p����ꍇ�ɂ́u���L�[���[���I�[�o�[����v���l�����Ȃ���Ȃ�܂���B�@���L�[���[���I�[�o�[�Ƃ́A�����̃L�[(���̃L�[)���ɉ������ꍇ�ɐ��������͂ł���̂��A�����łȂ����̎��Ő������L�[���͂ʂł�����̂����L�[���[���I�[�o�[�\�ƌ����܂��B�R�L�[���[���I�[�o�[�Ƃ��S�L�[���[���I�[�o�[�̂悤�ɔF���\�ȃL�[����������̂�����܂��B �@�������A�L�[�X�L����������}�C�R�����̃v���O���������������Ή����Ă���K�v������܂��B �@��ɏЉ���u�O�`�e�v�܂ł�16�̃L�[���}�g���b�N�X�ڑ������L�[�p�b�h�ł́A�E�̐}�̂悤�Ɂu�T�v�u�W�v�u�X�v�̂R�̃L�[���ɉ������ꍇ�A�u�W�v�̃L�[�̗X�L�������ꂽ���Ɂu�W�v�̃X�C�b�`����u�X�v�u�T�v�̃X�C�b�`���o�R���āu�T�v�̃X�C�b�`���q���������̓|�[�g�ɂ�HI�̐M�����`���A������Ă��Ȃ��͂��́u�S�v�̃L�[��������Ă����ƌ�F�����Ă��܂��܂��B �@�����h�~����ׂɐ������͉��̐}�̂悤�Ɋe�X�C�b�`���t���h�~�p�_�C�I�[�h�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@���������ׂẴX�C�b�`�Ƀ_�C�I�[�h������Ɛ����������オ���Đ��i���i�������Ȃ��Ă��܂��܂��̂ł����Ă��̃p�\�R���p�L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h�͋t���h�~�p�_�C�I�[�h�͓����Ă��܂���B �@�V�t�g�L�[���̂ق��̃L�[�Ɠ����ɉ����ꕔ�̃L�[�̂Ƃ��낾�������Ă�����̂�����܂��B �@�����Ō��āu�v���p�v�Ə����ꂽ���i�̍����L�[�{�[�h������܂����A�����������i�̓X�C�b�`���ɑϋv���̍������i���g���Ă���ȊO�ɂ��̋t���h�~�_�C�I�[�h���S�X�C�b�`�ɓ����Ă��āA�v���̃L�[�p���`���[���������X�s�[�h�ŃL�[�������ē�����ON�ɂȂ��Ă�����Ԃ������Ă����L�[���[���I�[�o�[���ňႤ�L�[�������ꂽ�ƌ딻�f���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@���Ă����ŃL�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h���o�b�̊O�����͋@��Ƃ��ăX�C�b�`���������ĉ����Ɍq�����ꍇ�E�E�E�E �@����̂悤�ɁuEnter�L�[������v�g���̂Ȃ牽����肪�N���Ȃ��ł��傤���A�����̎��ۂ��������̃L�[�Ɋ��蓖�ĂĕʁX�ɓ��͂��悤�Ƃ����ꍇ�A�����ŏЉ���悤�ɃL�[���R��(�ȏ�)�����ꂽ���ɕʂ̃L�[�������ꂽ�ƌ딻�f�����悤�ȃL�[�{�[�h�ł��̂悤�Ȕz��(�g���X�C�b�`�̑I��)�����Ă��܂����ꍇ�A���삵�Ă��Ȃ��@�킪���삵���悤�Ȍ�F�������Ă��܂��댯��������܂��B �@���L�[���ɑΉ��ς݂Ŗ����L�[�{�[�h�E�L�[�p�b�h���g�p���āA���ڃX�C�b�`��z�������ʼn������Ă��܂��A�܂������[�̂悤�ȋɐ��̖����ړ_�Œ��p����A�Ȃǂ̏ꍇ�͂��L�[��肪�N���܂��B �@��������P�[�u���ɋt���h�~�_�C�I�[�h�����Ă�邩�A����̃t�H�g�J�v���̂悤�ɋɐ��̂���f�q���g�����L�[���͉���ł��܂��B �@���ׂ̈ɂ�����̓t�H�g�J�v�����g�p�����������@�����Љ�Ă��܂��B �@�܂��AUSB�L�[�{�[�h�̂悤�Ɏ����œd���͎�������USB���d�œd�͂Ă���悤�ȑ��u�̏ꍇ�͏����ł��]���ȓd���͗��������Ȃ��ł����A�����[�̂悤�ȕ���菬�d���œ����t�H�g�J�v���͂��̂悤�ȗp�r�ł͕֗��ł��B ���Ԏ� 2008/4/23
|
|
| ���e |
�@ELECOM TK-UEHBK �ɂ��Ď��₵�܂������A���ۂɌ������Ď��������Ƃ��딽���͏[������܂����B���������Ď��@�̌��͂��ꂩ��ł������Ԃ�OK���Ǝv���܂��B �@��H�̕��͂͏o���܂��}�g���b�N�X�L�[�p�^�[���̉�H�R�l�N�^�[�P�P�{�̊Y�������Q�{�A����R�l�N�^�[�������璼�ڔ��c�t���ŊO���֏o���������ł��B���ꂪ���p�ł���Ȃ���ɕ֗��ł��B �@�����������Ă���\�t�g���^�[���œ��͂𑣂��Ă���ꍇ�݂̂ł����ǁB�d�C�I�ɕ��S���������Ė����������Ă���Ƃ��̕s��������܂����������ł��傤�H�����킪�����܂������A���������肢�������܂��B �����p�� �l
|
|
| ���e |
�@�����̏ڍׂȉ�������肪�Ƃ��������܂��B �@���o���͊�Ȃ������悭�����ł��܂����A�t�H�g�C���^�[�ɕύX���K�{�ł��ˁB �@���肪�Ƃ��������܂����B �����p�� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@��̐����ŏ����܂����悤�ɒZ���P�[�u���ł���g�قځh��薳�����삷�邱�Ƃ�����܂��B �@�������Ă݂ĉ����g���u�����N�����Ɏg����̂ł����炻��ł����\�ł��B �@�����g���u������������A�P�[�u��������悤�ȏꍇ�ɂ͉����p��H(�t�H�g�J�v���[)���g�p����Ηǂ��Ǝv���܂��B �@�ʂɖ�肪�����̂ł�����킴�킴���i���ė���J�͂₨���͂����Ȃ��Ă��ς݂܂�����ˁB ���Ԏ� 2008/4/24
|
|
| ���������|���v | ||
|
�@���O�̃^���N�Ɏ��������ł�����@���l���Ă���܂��B �@��H�́A���S�҂ł����l�b�g�ŐF�X�������Ă���܂��B �@�^���N�㕔�ƒᕔ�ɃZ���T�[��ݒu���ꕔ�̃Z���T�[���I���ɂȂ��ă|���v�쓮�����̏㕔�Z���T�[�ŃI�t���l���Ă���܂��B �@�Z���T�[�́A���[�h�X�C�b�`�|���v�̓o�X�|���v�𗘗p �@���A���������^���N�ŁA�����̃^���N�������Ȃ��Ȃ��Ă��|���v���I�t�ɂȂ��H�������Ă��������B���S�҂̏������݂œ��e���ǂ��܂Ƃ܂炸���݂܂���B��H���͋���������܂������S�҂ł��B �}���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@��H�}�͊��ɏ����Ă��܂����A���������₳���Ă��������B (Q1) ���ʃX�C�b�`�́H �@���[�h�X�C�b�`�Ə�����Ă��܂����A�u���ʏ㏸��ON�v�u���ʉ��~��ON�v�̂ǂ���̃^�C�v�ł��傤���H �@�܂��s�̂́u�t���[�g�X�C�b�`�v�𗘗p�����ق����y���Ǝv���̂ł����A�u���ʏ㏸��ON�v�u���ʉ��~��ON�v�̂Q�̃^�C�v�������Ă��܂��������̃^�C�v���w���\�ł����H �@����Ƃ��ǂ�����Е��̃^�C�v�����w���ł��܂��H �@��H�}�����J������Ɂu���̃X�C�b�`�͓���ł��܂���v�܂��́u���[�h�X�C�b�`�Ŏ��삵�悤�ƍl���Ă��܂������A���̕��@�̃X�C�b�`�͍�鎖���ł��܂���v�Ȃ�Ď��ɂȂ�Ɩʓ|�Ȃ̂Ő�ɋ����Ă��������B �@���ɐ��ʃX�C�b�`���u���ʏ㏸��ON�v�u���ʉ��~��ON�v�̂Q��ނƂ�����ł��鎖���t�F�C���Z�[�t�̍l�������獡��̂��˗��̉�H�ł͕K�v�Ȃ̂ł����A�ǂ����Ă��Е���������ł��Ȃ��ꍇ�̓X�C�b�`����ꂽ�ꍇ�Ɍ�쓮����\�����c�������H�ƂȂ��Ă��܂��܂��B (Q2) �o�X�|���v�̒�i�́H �@�o�X�|���v�͂����Ă�AC�A�_�v�^�[���Ɛ����|���v����������Ă���Ǝv���܂����AAC�A�_�v�^�[�̏o�͂͌𗬂ł����H�����ł����H �@�����ēd���͉��u�Ń��[�^�[�̏���d���͉��`�ł��傤���H (Q3) �d���́H �@�ŏ������H�p�̓d��(�g�����X��AC�A�_�v�^�[)��ʓr�p�ӂ��邨����ł����H �@����Ƃ���Ŏ��₵���o�X�|���v��AC�A�_�v�^�[�������̂܂ܗ��p���ēd�������܂����H �@�o�X�|���v�̔z�����J�b�g���č��삷���H���Ԃɋ��ނ悤�ȕ��@�œd���̓o�X�|���v��AC�A�_�v�^�[������Γd����H������Ԃ͏Ȃ��܂��������|���v����ꂽ���ɂ͕ʂ̃|���v�ƌ�������ۂɂ͌��̃|���v�Ɠ�����i�̏��i���܂�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�����H�p�̓d���͎��O�Ŏ����āA�o�X�|���v��AC�d���̋�����ON/OFF���邾���Ȃ�����|���v�����Ă��V�����|���v���Ă��Ė{�����H�̃R���Z���g�o�͂ɑ}�������ōς݂܂��B �@�����e�i���X���̎����l����Ό�҂ł����A�d������p�ӂ����肷��K�v������܂��B �@�����҂����Ă��܂��B ���Ԏ� 2008/4/10
|
|
| ���e |
�@���X�̂��Ԏ��L��������܂��B (Q1)�̓t���[�g�X�C�b�`(ON/OFF�j���[�h�X�C�b�`�ǂ�ł��w���\�ł��B���[�h�X�C�b�`���l�����̂́A���̓��e�ɏ������݂��������A��100�V���b�v�̖h�ƃZ���T�[�ň��オ��ɏo���邩�ȂƎv��������ł��B (O2)�͓d����AC100V���͗e��33VA�E�|���v��DC12V�A2���d��1.6A�̂��̂ł��B (Q3)�͓d����ʓr�p�ӂ��A�o�X�|���v��100V��ON�EOFF����ōl���Ă��܂����B �@�^���N�ł��������i��100ℓ�j����^���N�Ƌ������i��150ℓ�j�̃^���N��10M������Ă��܂��A���䂷��ꏊ�́A�������̃^���N�̏ꏊ��AC������l���Ă��܂��A���C�̎c���𗘗p����ׂł��B �@���ʃ��׃��Z���^�[�ƌ������̂�����̂ł����ƂĂ����z�ȈׁA�������Ȃ����ƍl�����̂��n�܂�ł��B �@�X�����A���������肢�������܂��B �}���� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@��H�̐���������O�Ɂu100�~�V���b�v�̑��p�h�ƃu�U�[���烊�[�h�X�C�b�`���v�ɂ��āB �@���̋L���ł͐Ζ��t�@���q�[�^�[�́w�t���[�g�X�C�b�`����ꂽ�̂��x�w����ł͑��p�u�U�[���烊�[�h�X�C�b�`�����o���܂���A�ʔ̂������p�̃��[�h�X�C�b�`������������ł����x�Ƃ����b���ł����āA�t���[�g�X�C�b�`�̑���ɖh�ƃu�U�[���g����Ƃ��A�t���[�g�X�C�b�`�����̂ɖh�ƃu�U�[�Ȃ�100�~�ōςނƂ����b�ł͂���܂����B �@�����h�ƃu�U�[����100�~�Ń��[�h�X�C�b�`�Ǝ������o�����Ƃ��āA�w�t���[�g�X�C�b�`�S�̖̂h���P�[�X�x�w����������t���[�g�x�Ȃǂ�S�����삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A�������v���X�`�b�N���o������ڒ�������A�h�����H�����肵�Ĉꂩ������͎s�̂̐��S�~���x�̃t���[�g�X�C�b�`���w�������ق����͂邩�Ɍo�ϓI���Ǝv���̂ł����E�E�E �@�����ǂ����Ă��u�t���[�g�X�C�b�`�����̂��ړI�ȂI�v�Ƃ����̂Ȃ�ʂɎ~�߂͂��܂��A�ړI�̑��u����邽�߂Ɋ����i�Ƃ킸���ȉ��i����100�~�V���b�v�i���畔�i�����o���āA�H�삷��̂ɉ����Ԃ������ĉ�������̂͂��܂�����I�Ƃ͎v���܂��B �@����ł͉�H�}�ł��B ����H�}���N���b�N����Ɗg��\��
�@�t���[�g�X�C�b�`�͒����^���N�p�ɂ́u���ʉ��~(����)��ON�^�C�v(���ʗL���OFF�^�C�v)�v���A�����^���N�p�ɂ́u���ʏ㏸(�L��)��ON�^�C�v(���ʖ�����OFF�^�C�v)�v���g�p���܂��B �@�t���[�g�X�C�b�`����ꂽ�ꍇ(�Ζ��t�@���q�[�^�[�̎���̂悤�ȉ���)�A�����^���N���́u�����ł���v�Ɣ��f���ă��[�^�[�������ςȂ��Ń^���N���琅������̂�h���܂��B �@�������͉�ꂽ�ꍇ�́u���������v�Ƃ��Ă�͂胂�[�^�[���܂���B �@�Z���T�[������(�ڐG���Ȃ��Ȃ�)�ƃ|���v�͓��삵�܂���̂ŃZ���T�[���������Ă��������B �� �����������f��H �@�����H�̐S������TTL IC��74HC00�ō���Ă���u�q�r�t���b�v�t���b�v�v�ƌĂԏ�ԕێ���H�ł��B �@SET(�Z�b�g=ON)���͂�RESET(���Z�b�g=OFF)���͂��������X�C�b�`�ێ���H�̂悤�Ȃ��̂ŁAON/OFF��Ԃ����ꂼ��̓��͂��������ق��ɐ�ւ��܂��B �@�������͏o�͂�OFF�ł��B �@�������琅�̗ʂ������Ė����X�C�b�`���u���ʌ��v���ɐ�ւ���Ă��q�r�t���b�v�t���b�v�ɂ͉����N����܂���B �@�����Ɛ��ʂ��������Ēᐅ�ʃX�C�b�`���u�ᐅ�ʁv���ɐ�ւ�����u�Ԃɂq�r�t���b�v�t���b�v��ON�ɂȂ�o�͑��̃g�����W�X�^�����܂��B �@�|���v�������Đ��ʂ��オ��A�ᐅ�ʃX�C�b�`���u���ʗL��v���ɐ�ւ���Ă��q�r�t���b�v�t���b�v�̏�Ԃ͂��̂܂܂Ń|���v�͓����Â��܂��B �@���ʂ������Əオ���Ė��^���ɂȂ薞���X�C�b�`���u�����v���ɐ�ւ�����u�Ԃɂq�r�t���b�v�t���b�v��OFF�ɂȂ�|���v�͒�~���܂��B �@�^���N�̐����g�����̃��[�v���J��Ԃ���܂��B �� �����̐��ꌟ�m �@�g�����W�X�^������O�̒i�K�ɋ����^���N�̐��ʂ�����Ȃ��������m����u�����ᐅ�ʃX�C�b�`�v��AND��H(���ۂ�NAND��H)�Őڑ����Ă��܂��̂ŁA�����ᐅ�ʃX�C�b�`���u����v��Ԃł͂q�r�t���b�v�t���b�v�̏�ԂɊւ�炸�g�����W�X�^����ON�ɂ͂��܂���̂Ń|���v�͋��肵�܂���B �@�������쒆�ɐ���ɂȂ������Ɂu�����ᐅ�ʃX�C�b�`�v���`���^�����O���N�����ƃ����[��������ON/OFF���Đړ_�ɉΉԂ����Ń����[��ɂ߂܂��̂ŁA�X�C�b�`���͕���R4��C3�Ń`���^�����O�h�~��H�����Ă��܂��B �� LED�\�� �@LED1�́u�v�����v�����v�͂q�r�t���b�v�t���b�v�����ʂ̌��������m����ON�ɂȂ��Ă�����ԓ_�����܂��B �@LED2�́u�������v�����v�͎��ۂɃ����[�����삵�ă|���v���Ă�����ԓ_�����܂��B �@���ʂ͗����������ɓ_�����܂����A�����ɐ��������ꍇ�́u�������v�����v�͓_�����܂���B �� �����[ �@�����[��DC5V�ŃR�C���d����500mA���x�ȉ��̂��̂��g�p���Ă��������B���ʂ�75�`100mA���x���Ǝv���܂����A�p���[�����[�̂悤��200�`300mA���炢����镨�ł��g�p�ł���悤�Ƀh���C�u�p�g�����W�X�^��2SA952(�ő��i700mA)�ɂ��Ă��܂��B �@�����[�̐ړ_�e�ʂ�AC125V��1�`2A�ȏ゠����g�p�ɂȂ�|���v�ł�����イ�Ԃ�Ή��ł��܂��B �@�]�T��������AC125V 3A���x(����ȏ�)�̂��̂��g�p�����Ɨǂ��ł��傤�B �@���ʂɑ傫�ȗe�ʂ̕��������ƃR�C���d�����傫���Ȃ�܂��̂œK���ȑ傫���ȓ��ŁB �@���i��̓t���[�g�X�C�b�`���������������1000�~���x�B �@�t���[�g�X�C�b�`��100�~�V���b�v�̖h�ƃu�U�[�ō��Ȃ�315�~�{���암�i��B���ʂɔ����t���[�g�X�C�b�`�͈���S�~�`��~��ł��ˁB �@��H�����͍���̂悤��TTL IC���g��Ȃ��Ă��g�����W�X�^��g�ݍ��킹����A���̕��@���l�����܂�������̓��W�b�N��H�̊�{��p�������̂ɂ��Ă݂܂����B ���Ԏ� 2008/4/11
|
|
| ���e |
�@��H�쐬�L��������܂����B �@�\�z�ȏ�ׂ̍��Ȑv�Ɋ��ӂł��B �i���́A�\�������v�̂��Ƃ��������ݖY��Ă��܂����B�j �@���[�h�X�C�b�`�̌��́A�A�N�����`���[�u�O���ɃP�[�u���Ƀ��[�h�X�C�b�`��ڑ��������̂����A�`���[�u�̒��ɔ��A�X�`���[���̂����Ɏ��������ȒP�ȕ����l���Ă���܂����B �@�����A�t���[�g�X�C�b�`���l���܂������A�t���[�g�X�C�b�`�����g�̓��[�h�X�C�b�`�ƒm���ĊȒP�ɏ�L�̂悤�ȕ�����낤�ƈ��Ղɍl���Ă܂����B �@������āA��H���쐬���܂��B �@���ʂ������Ă��������܂��A�F�X�L��������܂����B �}���� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�A�N�����`���[�u�ō�����t���[�g�X�C�b�`�Ȃǂ����܂��������為�Ўʐ^�Ȃǂ������ĉ������B �@�����^���N�����������Ƃ���ɂ���̂ŁA�e�X�C�b�`�̓����Ԃ�{�̑��ŕ\������LED���������ق����ǂ���������܂���ˁB ���Ԏ� 2008/4/12
|
|
| �����t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� | ||
|
�@����ɂ��́@��N�́w�\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H�x�ł����b�ɂȂ�܂����B�����������V�C�Ń\�[���[���d�͉ғ����Ă��莩���؊�����H���܂��܂������ɓ��삵�Ă���܂��B �@���āA�{���͂܂������ʂȘb�Ȃ̂ł����E�E�E��������������ɂȂ邱�Ƃ�����܂����狳���ĉ������B�Ζ��t�@���q�[�^�[���̏Ⴕ�Ă��܂��܂����B�Ǐ�͓����������Ă���̂ɋ��������v���_�����Ă��܂����삵�Ȃ��̂ł��B �@�������Ċm�F�����Ƃ�����ʃZ���T�[���̏Ⴕ�Ă��鎖���������܂����B �@�Z���T�[���O���ăt���[�g�i�����O��̎��������ɕt���Ă���j���㉺���Ē�R�l�𑪂�܂������܂��������������≏��Ԃł����B�t���[�g�Ɏ����t���Ă���̂ŏ㏸�������ɓd���������̂��Ǝv�������㉺�����Ă݂܂������d���͗���܂���ł����B�i�e�X�^�[�̃����W�͍ŏ��̃����W�Łj�̏Ⴕ�Ă��Ȃ������t�@���q�[�^�[�����������̂ŊY������Z���T�[�̒�R�l�𑪂�Ɓi�����͓�������ԂŁj��R�l�͖������ʏ�Ԃł����B �@�Ƃ肠�������̌��ʂ���̏Ⴕ���t�@���q�[�^�[�͒[�q��Z�����Ďg�p�\�ƂȂ�܂����B�i�����̌x��܂��j �@�����ŋ^��Ȃ̂ł������̃Z���T�[�͂��������ǂ������d�g�݂Ȃ̂ł��傤���H �@�t���[�g�̒��S�ɂ���Z���T�[�{�̂����o���Ă݂�ƃQ���}�j���[���_�C�I�[�h�݂����ȍ��ŃK���X�̓����ɍג��������̔����[����o�Ă���r���ł����Ȃ����悤�ȍ\���ł��B�@�\�Ƃ��Ă͖��ʂ�������ƃt���[�g���㏸���Ă��̃Z���T�[�Ə㉺�����ɏd�Ȃ�Ƃ������������܂��B�t���[�g�̎��͂��ǂ̂悤�ɂ��̑f�q�H�ɉe�����Ė��ʂ����o���Ă���̂ł��傤���H �@���͂����ł͕����肸�炢�Ǝv���܂��̂�yahoo�u���[�t�P�[�X�ɕ��i�̎ʐ^�����J���܂��B������낵������������肢�v���܂��B��[�ʐ^�y�[�W] (������]) �l
|
||
| ���Ԏ� |
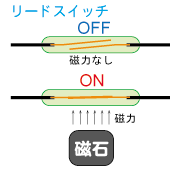 �@���̃Z���T�[�́u���[�h�X�C�b�`�v�Ƃ����ÓT�I�ȃX�C�b�`�f�q�ł��B
�@���̃Z���T�[�́u���[�h�X�C�b�`�v�Ƃ����ÓT�I�ȃX�C�b�`�f�q�ł��B�@�K���X�ǂ̒��̓d�ɂ��ӂ���͗���Ă��āA�����߂Â��Ǝ������Ă��݂����������ē��ʂ��܂��B �@���肵����������(�������Ă���)�ƃZ���T�[����ڐG������K�v������(���~�����x�J������)�̂Ŋe���ڐG�Z���T�[�Ɏg�p����Ă��܂����B �@�܂����[�h�X�C�b�`�ɃR�C�����������āA�R�C���ɗ�������ȓd���ŃX�C�b�`�������u���[�h�����[�v�Ƃ������i������܂��B �@�t�@���q�[�^�[�̓����Z���T�[�Ȃǖ��̃��x���𑪂鑕�u�ł́A���ʂ̃t���[�g�X�C�b�`���g���ƃX�C�b�`�ړ_��ON/OFF����ۂ̃X�p�[�N(�Ή�)�Ŗ�(�܂��͋C�����Ă�����K�X)�Ɉ����Ĕ������Ȃ��悤�ɂ��̂悤�Ȗ��^�̃X�C�b�`�f�q���g�p���Ă��܂��B(�X�Ƀv���X�`�b�N�P�[�X�ł��������Ă���ł��傤) �@�����Ƒ傫�ȃ^���N�ł͖h���^�̖��X�C�b�`���g�p����Ă���ł��傤���A���^�̋@��ł̓��[�h�X�C�b�`�͗��p���@�̕����L���֗��ȃX�C�b�`�f�q�ł��B �@���̌̏�̓��[�h�X�C�b�`�����ē��ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ł��̂ŁA���[�h�X�C�b�`���w�����Č������邾���Œ���ł��傤�B �@�ʔ̂ł��}���c�p�[�c�����n�j�h�́uSWORD211�v��uSWORD221�v���w���ł��܂��B(�T�C�Y�ׂč����ق���) �@ 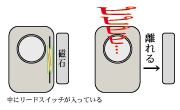 �@�܂��g�߂ȏ��ł�100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���u���p�h�ƃZ���T�[�E�u�U�[�v�̒��Ƀ��[�h�X�C�b�`�͓����Ă��܂��̂ŁA105�~�Ŕ����Ď��o���Ƃ��������ł��܂��B
�@�܂��g�߂ȏ��ł�100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���u���p�h�ƃZ���T�[�E�u�U�[�v�̒��Ƀ��[�h�X�C�b�`�͓����Ă��܂��̂ŁA105�~�Ŕ����Ď��o���Ƃ��������ł��܂��B�@�ŋ߂͂��܂茩�Ȃ��Ȃ�����315�~���i�ɂȂ��Ă���������܂����A���[�h�X�C�b�`��{�ʔ̑����̍��v������͈������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B �@����100�~�V���b�v�Ō������Ĕ�����Έ��オ��ł��B �@�������x���Z���T�[�Ȃǂ͓�d�O�d�Ɉ��S�Ȑv������Ă͂��߂Ďs�̐��i�Ƃ��Ĕ̔�����Ă��鏤�i�ł��̂ŁA���̕�����������C���E���H�����͈̂��S�ʂł͂��܂肨���߂ł��܂���B �@������Y�Ɋւ����S���ɉe�����镔�i�Ȃ̂Ń��[�J�[�ɏC���ɏo���ق����ǂ��ł��傤�B �@���ɕ�������Ă��܂��Ă���̂ŁE�E�E�E�������[�J�[�ۏ����������܂��B ���Ԏ� 2008/3/25
|
|
| ���e |
�@�����I�m�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B�����J�ȉ����đO��Ɠ��l�ɑz���ȏ�̂��ɂ܂��܂��������܂����B �@���S�ʂ̂��w�E�����������ʂ�ł��B���������̐��i�ŕ������Ă��܂������͒���Ȃ��Ǝv���܂��B �@���w���̎����烁�J���D���Ŏ��v�����Č��ɖ߂����e���ɂ����҂ǂ��{���܂����E�E�E���͌��݁A�^�����ԃ��[�J�[�ɋ߂Ă���Q�d�R�d�̈��S�A�t�F�C���Z�[�t�̍l�����͏[���F�����Ă���܂��B���S�ʂ��l�����Ăă��[�J�[�ɏC���ɏo�����A�����ŏC�����邩�͎��ȐӔC�̌����f�������܂��B �@�܂��܂��Y�݂��������܂���!!���肪�Ƃ��������܂����B (������]) �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�m���Ă���͈͂̎��������̂ł������ł��������ŁA�m��Ȃ������Ƃ������ɂ�����������͂ł��܂���i�O�O�G �@�Z�p�҂̑唼�͎q���̍��ɂ́u���v�������ł��傤����A�������畨�̍���d�g�݂��w��ő̂ɐ��ݕt���Ă��鎖�Ǝv���܂��B(�Ă��܂��o�����c) �@���̃y�[�W�͉�H��@�B�ɂ͉��̖������S�҂̕��������ǂ܂�Ă���悤�ł��̂ŁA�������������Ă���(�ǂ�����Δ������邩��)���ȐӔC�ŕ����E�����������Ȃ�ǂ��̂ł����A�Ȃ�ł�����ł��������ĉ�����C�������Ă��ǂ��Ǝ~�߂��Ă��܂��Ƒ�ςȎ��̂Ɍq����̂ňꉞ���ӂ͊��N���Ă��܂��B �@�j���[�X�𑛂������u�K�X�������@�Ŏ��S���́v�����ǂ͓������@�̈��S���u���~�߂Ă��܂������������ł������Ȑl�̖��������Ă��܂����킯�ŁE�E�E �@�u�Z�p�I�ɂ͉\�v�Ɓu��������ėǂ����H�v�͕ʕ��ł�����A���e�ɂ���Ă͂Ƃ�ł��Ȃ����ɂȂ邩������܂���ˁB ���Ԏ� 2008/3/27
|
|
| Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H | ||
|
�@�����y�����q�����Ă���܂��B �@���`�E���C�I���d�r18650���p�[�d��������ɓ͂��A���낢��H��ӗ~�������Ă��܂����i�j�B �@���āA18650��LED���C�g�������Ƃ��������Ȃ��̂ŁADC-DC�R���o�[�^�����܂��āAUSB5V�d������낤�Ǝv���Ă��܂��B �@�C�̖����l������Ă���悤�ɁA�g�ѓd�b�p�̊��d�r���[�d������p��3.7V��5V�̓���ɂ͐������܂������A���̎�̏[�d��́u�d�r���z���s�����v�̂�Non-Protect�^�C�v�̓d�r�͂�������ߕ��d�������ŕ|���Ďg���܂���B�iProtect�^�C�v�͂܂����v�ł��傤���j �@�����ŁA�ʏ�̎�|�Ƃ͋t�ł��傤���A���̓d�������荞���ɁA��H���Ւf����i���U���~������j�悤�ȉ�H��t�����邱�Ƃ͉\�ł��傤���H �@��낵��������������肢�������܂��B �݂��� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�u���̓d��������������ɉ�H���Ւf����v�Ƃ������������ł͐������o�b�e���[�̉ߕ��d�ی�E�v���e�N�g��H�Ƃ��Ă͓����܂���B �@�o�b�e���[�̓d�����Ď����āA���̓d��������������ɕ���H(���̏ꍇDC/DC�R���o�[�^)�̓�����~�߂邩�d���������J�b�g���Ă��A���̏u�Ԃɕ��ׂ������Ȃ����o�b�e���[�̒[�q�d�����オ��܂��̂ŁA�����u���̓d����艺�̏ꍇ�́v�Ƃ�����H�ł�����̏u�Ԃɂ܂��d�͂̋������ĊJ���āA���X�Ɓu�ؒf�v�u�ĊJ�v���J��Ԃ��Ĕ��U��ԂɂȂ邩�A��H�����ɂ���Ă͂��傤�ǒ�d����H�̂悤�ȓ��������ĕ��ׂɓd���𗬂��Ă���o�b�e���[�̒[�q�d�������ɂȂ�悤�ɕ��t��Ԃ�ۂ��āA�{���Ƀo�b�e���[�̓d�����K��d����艺�ɂȂ�܂œd�͂��z���s������H�ɂȂ�܂��B��҂̏ꍇ�͌����ڂ͋K��̓d���܂Ńo�b�e���[�̃G�l���M�[���z���o���悤�Ȃ̂Łu�֗��H�v�Ǝv���邩������܂��A�o�b�e���[�̏o�͓d���͋K��d����ۂ����܂��X�ɉ�H������R�Ƃ��ē����Ă��̒�R�l���傫���Ȃ�A���ׂɂ͓d���𗬂��Ȃ��Ȃ��Ă䂫�܂��̂Ŏ��ۂɂ͕��ב��̓���͐������s���Ȃ��Ȃ�ł��傤�B(�_�C�I�[�h�{��R�����̕��d��̂悤�Ȃ���) �@�o�b�e���[�̎g�p�𐳂������d�I�~�d���ŏI������ɂ́u�K��̓d���ɂȂ������H���A���̏�Ԃ�ێ������v�Ƃ��������݂��K�v�ł��B �@��x�o�b�e���[�̓d���ቺ�����m�������H���J�b�g���A���̃o�b�e���[���O�����(�܂��̓X�C�b�`���t���Ă��Ĉ�UOFF�ɂ����)�܂ł͂����ƃJ�b�g��Ԃ�ێ������H���K�v�ł��B �@�u���ȓd�������A�I�[�g�J�b�g�d���ρA�j�b�P�����f�[�d�r�E�P�Z�����d��̐����v�̉�H���̂܂܂ł�����Ȃ��́H�E�E�E�Ƃ����ӌ��̕�������������悤�ł����A���̉�H�ł̓X�C�b�`�͐l�Ԃ��蓮�œ���Ȃ��ƕ��ׂɓd��������܂���̂ŁA�@��̒��ɑg�ݍ���Ŏg���ɂ͕s�ւł��B �@���̉�H�ɕ��i�𑫂��ăI�[�gON�����H�ɕύX���邭�炢�Ȃ�A�ʓr��p�̉�H�}���������ق����ʔ����ł����A��������`�E���C�I���[�d�r�ł̎g�p��O��Ƃ�������IC��FET���g���܂��B���������ł�����IC��FET���g�p���ĐF�X�Ɖ��p�̗�����b��H�����܂��傤�B �@�������g�����W�X�^�����ł����܂��B �@�d�����m�Ɠ����ێ��ɂQ�A���ꂩ��X�C�b�`���O���łQ�`�R���g���Đ�قǏ������M���M���܂Œ�R�ɂȂ��ēd���𗬂�������悤�Ȍ�쓮�����Ȃ���H�}�������ƁE�E�E�E�قƂ�ǁu�^�~�����u�j�J�h�������d��v���\�A�b�v����I�H�v�̎s�̕��d��Ɠ����悤�ȉ�H�}�ɂȂ��Ă��܂����ׁA����ł͖ʔ���������܂���̂ŃI�[���g�����W�X�^�����̉�H�͍���͖����ɂ��܂��B �@IC��FET���g�p�������̂ƂقƂ�Ǖ��i�����ς��܂��B �@����ł͉�H�}�ł��B ����H�}���N���b�N����Ɗg��\��
�@�o�b�e���[�d�����RR1�ER2�ŕ��������d���ƁAZD1�ō������d������VR1���Đݒ肷���r��d�����R���p���[�^(OP AMP LM358)�Ŕ�r���āA�u�o�b�e���[�d������r��d����荂�����(�܂��������ėǂ����)�R���p���[�^�o�͂�Low�ɂ���v��H���S�����ł��B �@����ł��ł́u�o�͂��J�b�g���ăo�b�e���[�d�����オ����(����)�ꍇ�ɁA�܂��o�͂�ON�ɂȂ��Ă��܂��v�s����N���Ȃ��悤�ɁA�R���p���[�^�̏o��(Hi���x���d��)��D1��ʂ��ā{���͒[�q�ɋA�҂��A��r��d�����グ�Ă��܂����Ńo�b�e���[�d�����オ���Ă������Ĕ�r��d������ɂ͂Ȃ炸�A��x�Əo�͂�ON�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��܂��B �@�܂��A���̂܂܂ł̓o�b�e���[��ڑ������u�Ԃɒ�d�������m���Ă��܂��S���o�͂��o�܂���̂ŁAC1���[�d���鎞�Ԃ�����r��d�����オ��̂�x�点�A�o�b�e���[��ڑ������u�ԂɕK��ON�ɂȂ�悤�ɂ��܂��B �@�o�b�e���[���O����C1�͐��b�`10�b���x�ŕ��d���܂��B �@��U��d�������m���ďo�͂��J�b�g�����ꍇ�A�o�b�e���[���O���A�܂��͓��͑��ɃX�C�b�`��t���ăX�C�b�`��鎖��C1�����d���ĕێ���Ԃ̓��Z�b�g����܂��B �@���̉�H�͊ȈՓI�ȁu�ߕ��d�v���e�N�g��H�v�Ƃ��Đv���Ă��܂��̂ŁA���̂悤�ȍ��Ȃ̂ł��B �@���Ƃ��Έ˗��җl�̂悤��18650�̂悤��Li-ion�Z�����@��ɐڑ����Ďg�p����ꍇ���l�����܂����ANI-MH�[�d�r�~�S�{���g����4.0V�O��Ŏg�p���~�������ꍇ�A���Ƃ��u100�~�V���b�v�̎��]�ԃ��C�g�v��Ni-MH�[�d�r�����Ďg��(�d���͂��̂܂�)�悤�Ȏg�����̏ꍇ�̓��C�g�ɂ��̉�H������uNi-MH�[�d�r���ߕ��d�����Ȃ����C�g�v����鎖���ł��܂��B �@���C�g�̂悤�Ȏg�p�ł̓��C�g�{�̂̃X�C�b�`�Ƃ͕ʂɁu���ׂɓd���𗬂��n�߂�X�^�[�g�X�C�b�`�v�������āA����������Ȃ��Ɨ��p�ł��Ȃ��悤�ȍ��ł͕s�ւłȂ�܂���B���̉�H��d���Ƌ@��̓d���Ƃ̊Ԃɋ��ނ����ŋ@�푤�̃X�C�b�`�͉��������E���H�����Ɂu�@��̃X�C�b�`����ꂽ��ON�A����ł��ăI�[�g�J�b�g�v�̋@��ɂ��邱�Ƃ��ȒP�ɂł��܂��B �@�ꌩ�����LM358�̉E������2SC1815�͕K�v�Ȃ��A���̂܂܃R���p���[�^�o�͂�Hi/Low��FET�삳����ꂻ���Ɍ����܂����A�����ł̓R���p���[�^����ւ�邲������̏u�Ԃɏo�͓d�����A�i���O�I�ɕω����Ă��܂����ŁA���̏o�͂��璼��FET���R���g���[������Ɛ�q�̕s����ȓ�����N����������菜���ׂɂ��̂悤�ȍ\���Ƃ��Ă��܂�(���ɂ�LM358�̓����Ƃ��c)�B�܂��J�b�g�d����3.0V�ݒ�Ŏg���ƃJ�b�g�O�ɂ͂��イ�Ԃ��FET�̃Q�[�g�d����傫�����Ȃ��ꍇ������܂��̂Œ�d���܂ł������蓮�삳����ׂɃg�����W�X�^�ŃX�C�b�`���O���Ă��܂��B(R6�͂����Ƒ傫�Ȓl�ł��ǂ��ł����A�܂�����͂��ꂭ�炢��) �� �������@ �@�u�ϓd���d���v�������Ă��Ȃ����͎��̂悤�ɂ��Ă��������B (1) VR1���������ς��ɉĂ����܂��B (2) ���ׂɓd����LED�ȂǁA�d������������Ă��鎖���m�F�ł�����̂�ڑ����Ă��������B �@�@�ŏ������H��̏o�͕���LED�ƒ�R��t���Ă����̂��ǂ��ł��傤�B (3) ���イ�Ԃ�ɏ[�d���Ă���o�b�e���[��ڑ����܂��B �@�@���ׂɓd������������āA�d����LED������܂��B (3) VR1���������E�ɉāA�u����_�v�ŏo�͂��J�b�g����A�d����LED�������邱�Ƃ��m�F���܂��B �@�@��������t�ɉĂ���x�Ɠd����LED�͓_�����܂���B(�ێ�����Ă��܂�) (4) ��U�o�b�e���[���O���܂��B(���b�`10�b���x�����܂�) �@�@�܂�VR1���������ς��ɉĂ����܂��B (5) �܂��o�b�e���[��ڑ����܂��B(���ׂ͓_�����܂�) (6) VR1���������E�ɉāA��r�ݒ�d������]�̐ݒ�d���ɂȂ鏊�ɒ������܂��B �@�@���̎��_�ł͂܂��o�b�e���[�d���͂��イ�Ԃ�ɃJ�b�g�d����荂���̂ŁA�����ł͕��ׂ̓d����LED�͏����܂���B �����܂��B �@���ۂɂ́A�o�b�e���[�̕��d���i��œd����������ƁAZD1�ō���Ă����d�����킸������������܂��̂ŁA�d�����������ɒ���������r�ݒ�d�����͂ق�̏������̓d���ŃJ�b�g���삵�܂��B �@���������̍��͂킸���ł�����قږ��͖����͈͂ł��B �@�u�ϓd���d���v�������Ă�����͎��̂悤�ɂ��Ă��������B (1) VR1���������ς��ɉĂ����܂��B (2) ���ׂɓd����LED�ȂǁA�d������������Ă��鎖���m�F�ł�����̂�ڑ����Ă��������B �@�@�ŏ������H��̏o�͕���LED�ƒ�R��t���Ă����̂��ǂ��ł��傤�B (3) �o�b�e���[�̂����ɉϓd���d����ڑ����܂��B �@�@�d���d���̓J�b�g�������d���ɐݒ肵�܂��B (4) VR1���������E�ɉāA�o�͂��J�b�g�����_�Ŏ~�߂܂��B (5) VR1�����ɖ߂��Ă����ׂɂ͓d�����ēx����Ȃ���(�ێ�����)���m�F���܂��B (6) ��U�d����OFF�ɂ��܂��B(���b�`10�b���x�����܂�) (7) (1)�`(4)���ēx�s��((5)�͍s��Ȃ�)�AVR1���J�b�g�����_�Ŏ~�߂܂��B (8) ��U�d����OFF�ɂ��܂��B(���b�`10�b���x�����܂�) (9) �ϓd���d���̓d�����u�o�b�e���[�t���[�d�v�̎��̓d���ɐݒ肵�Ă���ēx�q��(�܂��͓d���X�C�b�`ON)���܂��B (10) �o�͂��o�Ă���(�d����LED���_������)���Ƃ��m�F���܂��B (11) �������Ɖϓd���d���̓d���������Ă䂫�A��]�̓d���ɂȂ�����o�͂��J�b�g����邩�m�F���܂��B (12) �ŏ��͑����̃Y��������Ǝv���܂��̂ŁAVR1���킸�������������āA(8)����J��Ԃ��Ċ�]�̓d���ŃJ�b�g�����_�܂Ŕ��������Ă��������B �����܂��B �@���̉�H�ł̓J�b�g��̕ێ������o�b�e���[����d�C������Ă��܂��B �@�ҋ@�d������菭�Ȃ�����ׂɕ�����R���d�����̒�R�l��傫�߂ɂ��Ă��܂����A����ł��ҋ@���͐�mA����܂��B �@�����Ƀo�b�e���[���ߕ��d�����Ă��܂��悤�ȓd���ʂł͂���܂��A�I�[�g�J�b�g����������Ȃ�ׂ������o�b�e���[�͏[�d���܂��傤�B �@���`�E���C�I���[�d�r�ɓ�������Ă���v���e�N�g��H�̂悤�ȃʂ`�I�[�_�[�̂قƂ�Ǔd�C������Ȃ���p�`�b�v�ɂ͂ǂ����Ă����Ȃ��܂���B ���Ԏ� 2008/3/20
|
|
| ���e |
�@�ߕ��d�h�~��H�ɂ����J�ȉ��肪�Ƃ��������܂��I �@�܂��߂ɂ�낤�Ƃ���Ƌ�Ƃ���A�P���ȉ�H�ł̓_���ł��ˁB �i�m���ɕ��ׂ��Ȃ��Ȃ����u�ԂɊJ���d���͏オ��܂����̂ˁj �@�p�������Ȃ���d�q��H�ȂNJw�Z���ƌ�v�����܂��߂ɓǂݍ���ł��Ȃ������̂ŁA�C�̖����l�̋L�����H�͂ƂĂ����ɂȂ�A�܂��A�̂̍H��~����݂������Ă��Ă��ꂵ���ł��B �@�������{���ɏo�����ăp�[�c���ɏo�����悤���ȂƎv���܂��� �݂��� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@����قǕ��G�ł͂Ȃ��A���i������ΐ����ԁ`���������������x�̉�H�ŖړI��B���ł��鎖��ڕW�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�d�q��H�̃v���Ŗ����Ă����i�̌��������ł��ăn���_�Â����ł�����x�ȏ�̕��Ȃ炨�y���ݒ�����悤�w�͂��Ă��܂��B �@���i�����������1000�~�ȓ��ōςނ��炢(�P�[�X�Ƃ��ŋÂ�����1000�~���܂���)�E�E�E�ƋC�y�Ɋy����Œ�������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2008/3/24
|
|
| �X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I | ||
|
�@�����[���A�y�����q�������Ē����Ă���܂��B �@���͐����p�̃n���f�B���C�g���i�m�l�̗v�]������j���s���낵�Ȃ���^���O�X�e�������甒�FLED�ւƕς��Ă���܂��B �@���͂R�v���̃��N�Z�m�����g���Ă��܂��i�_�C�I�[�h�P�A�P�R�d�r�R�����̃_�C���N�g�h���C�u�j���P�v�����R�ɂ��邽�߂ɃX�y�[�X�̊W��A�����Ȓ�d����H�����߂ĒT���Ă����Ƃ��낱����ł��炵���A�C�f�B�A��q�����i�g�ѓd�b�c�b-�c�b�R���j�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂��B �@���͂��̎��̃I�[�_�[�Łu�_�łł���悤�ɂ����ė~�����v�Ƃ���A�X�C�b�`������/�����Ȃ����̂ɉ����ǂ��g�ݍ��ނ��B �@����IC�ʼn�H���Ȃ���Ηǂ������ł����A�S�_��/��/�_��/��/����Ƃ��邽�߂ɂ̓X�C�b�`�̏�Ԃ�ێ�������̂��K�v�ɂȂ�̂ł��傤�ˁB �@�ʂʂ�...�ނ������������B ���낭�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���낭�ܗl�A���������������肪�Ƃ��������܂��B �@���C�g�̓d���p�X�C�b�`��Łu�n�e�e�v�u�S�_���v�u�_�Łv�u�n�e�e�v�Ƃ����p�^�[���R���g���[�����A����͌f�ڂ��܂���ł���������ȍ~�f�ڗ\��́u���]�ԗp�_�łk�d�c�����v(�ԐF)�v�̂h�b�������g����邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B �@�ȒP�ȉ������p�łł������(�����̕s�փA��)�ƁA������ƂЂƃq�l�����č�����(���Ȃ�֗�)�̓��ނ��l���t���܂����B(��҂͂�����Ǝ������Ă݂Ȃ��Ɩ{���ɓ��삷�邩�͓�ł���) �@���]�ԓ_�Ń��C�g�̂h�b�����g�p���Ă�������������H�͎��Ԃ�����Όf�ڂ������Ǝv���܂����A�N���N�n�͔��ɑ��Z�Ō��ݎ������I���Ă���L���̂v���������܂܂Ȃ�Ȃ���Ԃł��̂ŁA�������Ԃ��������Ă��ǂ��̂ł��������������Ă݂Č��ʂ��f�ڂ��܂��B ���Ԏ� 2006/12/4
|
|
| ���e |
�@�Ǘ��l���܃��X�|���X���肪�Ƃ��������܂��B �@�u���]�ԓ_�Ń����v�v���҂��Ă���܂��B�ǂ��������Ԃ̂���Ƃ��ɂ��肢���܂��ˁB����1�w�����l�����̂ł����]�݂�������Ȃ����̂œڍ����Ă���܂����B �@�҂��܂��Ƃ��I�ILINEAR�̃`���[�W�|���v�iLTC3424�A�傫�����Ēf�O�j���͂t�����邭�炢�Ȃ�...�@�i�����͂�����l���Ă����̂ł����g�я[�d��ʼn������܂����B�j �@���i�K�̌��O�����͓d���l�i1W������360mA,3W��700mA�Ƒ傫���j���炢�Ȃ̂ł���͕�����DC/DC�R���őΉ����܂��B �@100�~�V���b�v���Ēn���ɂ�����̂łƂĂ�������܂��B�H�t���܂ł̒��B����5000�~�������܂����́B ���낭�� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�ł́A�N���J���ď����ɂ��o����悤�ɂȂ�����������Ă݂܂��B �@�o�h�b�}�C�R�����g���ΐ����ȒP�ɂł���̂ł����A�����͂�͂�(PIC���g���Ȃ��l�������Ǝv���̂�)100�~�V���b�v���𗬗p���č���ƍl���Ă��܂��B �@�����͎��Ӄp�[�c�̒lj����K�v�ɂȂ�܂��̂ŁA�H�t���ɂ͈�x�͍s���Ē����Ȃ��Ƃ����Ȃ������H(�������i�����܂��Ă��܂���5000�~�̌�ʔ���͏H����800�~���炢�̑����{����̂ق��������ł����ǁc) ���Ԏ� 2006/12/9
|
|
| ���Ԏ� |
���낭�ܗl�ɒlj��A���ł��B �@���g�p�ɂȂ��鐅�����C�g�̃X�C�b�`�͓d�r�́u�v���X�v�u�}�C�i�X�v�̂ǂ������Ă��܂����H �@����Ƃ��̃X�C�b�`���o�R�����ɓd�r���璼�ړd�������z�������邱�Ƃ͏o���܂����H(�X�C�b�`�Ő藣���O�̒[�q�ɔz�����n���_�Â��ł��邩�H) �@�����̗v���ɂ���č���H�������ꒃ�ȒP�ɂȂ�����A���i�������Ȃ����肵�܂��B �@����ō��Ɓu�ǂ̉����d���łł��g����v�ėp�̂��̂ɂȂ�܂����t�ɕ��i�������ĕ��G�ȉ�H�ɂȂ��āA�����d���ɂ���Ă͒��̃X�y�[�X�Ɏ��܂�Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��Ă͈Ӗ�������܂��E�E�E �@�����ȒP�ɍ���ق��ł���A���낭�ܗl�̃��C�g�ł͂�����g���Ă�����āA�����P�ǂ̃��C�g�ł��g����ق��̉�H���������J����Γ��g�o�������Ă���ǂȂ��ł��g�p���邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA�ł���Η������J�͂������Ǝv���܂��B �@��������������ɂȂ�܂�����u�������v�܂œ��������肢���܂��B ���Ԏ� 2006/12/19
|
|
| ���e |
�@�x���Ȃ��Ă��݂܂���B�����̃R�����g���������Ă��܂����B �@�g�p���郉�C�g�͓���K-243�Ƃ������C�g�ŒP�Ox4�{����d�l�Ł@�d���ړ_ +-+-+-�i�����ɐ藣���X�C�b�`�j+-�d���ړ_�@�ł��B �@�d�r���璼�ړd�������z�������邱�Ƃ͏o����Ǝv���܂��B�z�����d�r�������Ɏז�������̂ŏ����H�v���K�v�ł����B �@���͂Ń��C�g�̊T�v�����`���ł��Ă��邩����܂���B�\����܂���B��낵�����肢���܂��B ���낭�� �l
|
|
| ���Ԏ� |
 �@����K-243�Ƃ����ƁA�E�̎ʐ^�̐������C�gDIVEMATE�Ɠ��`�̂��̂ł��ˁB
�@����K-243�Ƃ����ƁA�E�̎ʐ^�̐������C�gDIVEMATE�Ɠ��`�̂��̂ł��ˁB�@MADE IN CHINA �̃p�`�����̂悤�ł����A���͎���������n���Q�����Ɏ��ւ��đO����g���Ă����肵�܂��i�O�O�G �@�X�C�b�`�͓d�r�{�b�N�X�̌�둤�ɂ���A�{�f�B����]�����ăJ�`�J�`�Ƃn�m�^�n�e�e����^�C�v�Ȃ̂ŁA�d�r���璼�ړd�������������́A�d�����̂��n�m�^�n�e�e����ē��삷��ǂ̃��C�g�ł��g����ėp�̉�H�̂ق����ǂ������ł��ˁB �@���̃��C�g�̓��t���N�^�̗����Ɍ��Ԃ��^�b�v������̂ʼn�����H��DC-DC�R���o�[�^������̂��y�ŗǂ��ł��B �@���ɂR�v���F�k�d�c���ׂ̈�DC-DC�R���o�[�^�������Ă��āA�������炢�͌��Ԃ��g�p����Ă��܂��Ă�ł��傤���B �@�����̃��C�g���̉��������ċL���������Ă���Œ��ł��̂ŁA������ɂȂ�܂����������C�g�̓_�ʼn������L���ɂ������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2007/2/10
|
|
| ���e |
�@�Ǘ��l���܂���ɂ��� >�X�C�b�`�͓d�r�{�b�N�X�̌�둤�ɂ���A�{�f�B����]�����ăJ�`�J�`�Ƃn�m�^�n�e�e����^�C�v�Ȃ̂ŁA�d�r���璼�ړd�������������́A�d�����̂��n�m�^�n�e�e����ē��삷��ǂ̃��C�g�ł��g����ėp�̉�H�̂ق����ǂ������ł��ˁB �@������ς݂ł����@�ǂ������B�@�\���͂ł��`������̂ɂ��Ȃ�s���ł����̂ŁB >���̃��C�g�̓��t���N�^�̗����Ɍ��Ԃ��^�b�v������̂ʼn�����H��DC-DC�R���o�[�^������̂��y�ŗǂ��ł��B �@���������������l�����\�����ł��B���t���N�^�O�����܂��₷��ō�胊�t���N�^�̎��R�x�𑝂₵�Ă��炪�g������ǂ��݂����ł��B >���ɂR�v���F�k�d�c���ׂ̈�DC-DC�R���o�[�^�������Ă��āA�������炢�͌��Ԃ��g�p����Ă��܂��Ă�ł��傤���B �@���̓j�b�P�����f���S�̃_�C���N�g�Łi�t���h�~�_�C�I�[�h�P�̂݁j�������Ă��܂��̂ŃX�y�[�X�͂܂�����܂��B���M�p�Ɍ����T�o�̃A���~�~�Ղ����܂��Ă���̂ō����͂���قǂȂ��ł������... �@���R�ɂȂ�X�y�[�X���傫���̂ŃA�C�f�B�A����Ŗʔ������̂�����Ǝv���g���Ă��܂��B ���낭�� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�j�b�P�����f�~�S�ʼn^�p����Ă���̂Ȃ�D�s���ł��B �@���̏�Ԃłk�d�c�����Ă��Ă��A���̓d���̂܂܂ł��g�p�ł���_�Ł^�_���ؑ։�H�����܂��傤�B ���Ԏ� 2007/2/11
|
|
| ���Ԏ� |
�@�ŏ��̓��e����P�N�ȏ�o���Ă��܂��܂������A��H�}�ł��B �@�l�^(��H)�Ƃ��Ă͂قڊm�肵�Ă��܂������A���̋L���E������Ȃǂɉ�����č��܂Ōf�ڂ��x��Ă��܂��܂����B���݂܂���B 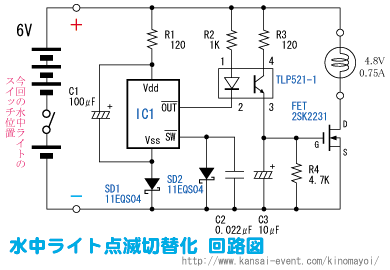 �@���]�ԓ_�Ń��C�g(�ԐF)�͊e�Ђ���o�Ă��܂����A��H�}�̂悤�Ȓ[�q�z��(�M������HI/LOW)�̂��̂Ȃ痬�p�ł��܂��B �@���]�ԓ_�Ń��C�g�̂ق��̕���(LED��)�͎g�p���܂���̂ŁA��𒆉���IC�t�߂����c���ăJ�b�g���Ă��܂��A�K�v�ȃp�^�[�������ɔz������̂��ǂ��ł��傤�B �@��H�̓���́u�d����OFF�ɂȂ��Ă��_��IC�����͂��炭���삵�Ă���v�Ƃ����ŋ߂��Љ�Ă���IC�o�b�N�A�b�v�����ŁA���̉�H�ł�IC��GND�����_�C�I�[�h�ŕ������Ă��܂��B �@����́u�X�C�b�`�[�q�v�����GND�Ɛڑ����Ă����܂����A�_�C�I�[�h��IC��GND�ƕ������邱�Ƃœd�r����̓d������������Ă���Ԃ̓_�C�I�[�h����ăX�C�b�`��ON(GND�ɗ�����)���܂����A�d�r��OFF�̎��ɂ�IC���猩��X�C�b�`��GND�Ɛڑ�����Ă��炸OFF�Ɍ�����悤�ɂȂ�܂��B �@����͎��]�ԓ_�Ń��C�g��IC���u�d��ON�̎��_�ŃX�C�b�`��GND�ɗ����Ă���ƍŏ��̃p�^�[���ɂȂ�v�u��ɃX�C�b�`��ON�ɂ��Ă��Ă����͖����v��H�ɂȂ��Ă��鎖�𗘗p�������̂ł��B �@�����ԓd������Ă�����Ԃ��烉�C�g�̃X�C�b�`������Ɠ_��IC�́u�ŏ��̓_��(�_��)���[�h�v�œ_�ł��͂��߂܂��B �@����IC�̏ꍇ�́u�ŏ��̓_��(�_��)���[�h�v�́w�펞�_���x�ł��̂Ń��C�g�͕��ʂɓ_�����܂��B �@�_�����Ɂu��u�����X�C�b�`����āA�܂������v���������ƁA�u���̓_��(�_��)���[�h�v�ɐ�ւ��܂��B �@���̐������C�g�̏ꍇ�A�d���X�C�b�`���u�e�[�������v���Ƃ�ON/OFF����^�C�v�Ȃ̂ŁA�N���N���Ď��X��ON/OFF�ł���̂ő��삪���ɃX���[�Y�ɂ䂫�܂��B �@���ʂ̉����d���̂悤�ȃv�b�V��ON/OFF�X�C�b�`�ł́uOFF�ׂ̈Ɉ��v�uON�ɖ߂��ׂɈ��v�̍��v�Q��X�C�b�`���K�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@���̐������C�g�͂܂�ł��̉���������ׂɂ���ȃX�C�b�`�\���ɂȂ��Ă���悤�Ȃ��̂ł�(��) �@�����_��IC�ɂ͂V�p�^�[���̓_�Ń��[�h��OFF�̍��v�W�̏�Ԃ�����AOFF�̍ۂɂ͓d���͏���܂���B�܂�����̒lj���H���������ɂ͓d��������܂���̂Łu�������[�h�v��I�������ꍇ�͂��̂܂܉����d���̓d���X�C�b�`��ON�ł��\��Ȃ��ł��傤�B �@�C���I�ɂ͒����Ԏg�p���Ȃ����ɂ͉����d�����̓d���X�C�b�`�͐�܂��傤�B �@�܂��V�p�^�[��������̂łǂꂩ�̓_�Ń��[�h�Ŏg�p���Ă����Ԃ���펞�_���ɐ�ւ��������ɂ͎��X�ƃp�^�[����i�߂Ă䂭�K�v������܂��B �@���ꂪ�ʓ|�ȏꍇ�͈�U�����d���̃X�C�b�`��OFF�ɂ��Ă���5�`10�b�҂��čēx�d�������Ă��������BIC�̃o�b�N�A�b�v����čŏ��̓_��(�_��)�p�^�[������͂��܂�܂��B �@���[�h�ؑւ̕��@��m��Ȃ��ꍇ�A���̉��������d���͑S�����ʂ̉����d���Ɠ�����������܂��̂ő���ɊԈႢ������܂���B �@����IC�ł͍ŏ��̓_��(�_��)�p�^�[�����u�펞�_���v�ł���������d���Ƃ��ĕ��ʂɎg�p�ł���킯�ł����A���А����]�ԓ_�Ń��C�g���ƍŏ��̃��[�h���u�_�Łv�̂��̂�����܂��B �@�ŏ����_�ł̏ꍇ�͉����d���̓d������ꂽ�ۂɓ_�łɂȂ��Ă��܂��A�_���Ŏg�������ꍇ�͂킴�킴���[�h��i�߂�K�v������̂ŕs�ւł��B�ł���ŏ��̓_�Ń��[�h���u�펞�_���v�̂��̂�I�т܂��傤�B �� ��H�I�Ȃ��� �@����g�p�������]�ԓ_�Ń��C�g��IC��3V���i�p�ŁA�ȑO�̎�����6V��������ƏĂ��Ă��܂��܂����̂ŁA����͓d��������R�����6V�̓d���Ɛڑ�������@������Ă��܂��B �@SD2��C2�͖����Ă������I�ɂ͖��͖����̂ł����A���܂ɕs����ɂȂ�悤�Ȃ̂œ���Ă��܂��B �@�����IC�̏o�͂���ϕ���H�ւ̓n�����t�H�g�J�v�����g�p���Ă��܂��B �@���Ђ̎��]�ԓ_�Ń��C�g�������܂������A�����d�C�I�Ȑ��\�̃o�������������̂ŁA�ǂ̃^�C�v�ł��قڊԈႢ�Ȃ����삷��悤�ɐԐFLED�̂����Ƀt�H�g�J�v���̒���LED�����点�邱�ƂŌ덷���z������Ӑ}�ł��B �@�t�H�g�J�v���ɐڑ�����IC��OUT�[�q�͂T��(�R��)����OUT�[�q�̂����^�̂��̂��ǂ��ł��傤�B�_�Ńp�^�[���������Ղł��B �@�d����FET(2SK2231)�Ńh���C�u���Ă��܂����A�Q�[�g�d���͓_��IC����o�Ă���M�����̂܂܂ł͂Ȃ��AC3�ER4�̐ϕ���H�ŏ������萔���Ƃ��Ă��܂��B �@���ɑ��̋L���ŏ����Ă��܂����A�����_��IC�̏o�͂́u�펞�_���v�̏ꍇ�͖{���Ɂu�펞�v�M����ON�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���̃p���X�o�͂ɂȂ��Ă��܂��B���̐��i�ł�LED�̓d��������R���Ȃ��펞ON�ł͉ߓd���ɂȂ�ׂɃp���X�_��������ׂł��B �@���̂܂܂̃p���X�œd�������点��Ɣ��ɈÂ��Ȃ�܂��B(�Â�����ׂ̃p���X�����炠����܂�) �@�ł�����A�p���X�������ď��ON�ɂȂ�悤���萔���v�Z���Đϕ����Ă��܂��B �@���i�ɂ���Ă͏펞�_�����[�h�̏ꍇ�p���X�_���ł͖������̂�����܂����B���̂悤�Ȑ��i�̏ꍇ�͐ϕ���H�͕K�v����܂��A�ʂɂǂ��̃��[�J�[�̂ǂ̓_�Ń��C�g�̏ꍇ�͂Ɖ���ł��܂���̂ŁA��ʓI�ȓ_�Ń��C�g�őS�Ďg�p�ł����H�Ƃ��Ă��܂��B �@FET�E�t�H�g�J�v���E�V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h���͐�ɂ�����g���K�v�͂���܂���A�݊��i�E�������\�̂��̂Ō��\�ł��BFET�͂قƂ�ǔ��M���܂���̂ŕ��M�Ȃǂ͕K�v����܂���B �@�A���~�d���R���f���T�̑ψ���10�`16V���x�AC2�͑ψ�50V�̃}�C���R���f���T�ŗǂ��ł��B �@���̎��]�ԓ_�Ń��C�g�ł͓��d�S����[�q�ɉ������Ă�X�C�b�`���g�p���Ă��܂����A����̉����d���ł̓X�C�b�`���͋�����ڐG������^�C�v�Ȃ̂�ON/OFF�̍ۂɃ`���^�����O�E�m�C�Y�����������悤�ł��B �@�����I�ɂ͒����d��OFF�̏�Ԃ���͂��߂�ON�ɂ������ɂ͍ŏ��̓_��(�_��)���[�h���I���͂��ł����A���܂ɂ����P��̃��[�h��AOFF�̃��[�h���I���ꍇ������܂��B �@���̂悤�Ȏ��ɂ̓��[�h��i�߂ĖړI�̃��[�h��I�����邩�A������x�d�������10�b���x��ɂ�����x�d�������Ă��������B(�펞�_�����[�h�ɂ������ꍇ�́A�ł�) �@���l�Ƀ��[�h���P�����i�߂����Ǝv�����d�����E���肵�������ł��Q��̃��[�h�ɐi�ނ悤�ȏꍇ������܂��B �@���̎��]�ԓ_�Ń��C�g�̐��i��Ԃł����̂悤�ȃ��[�h�����s����ȓ���͉��x���m�F����Ă��܂��̂ŁA�������i�ł͖����̂ł��̒��x�̕s���肳�͍ŏ����炠��Ƃ�����߂܂��傤�i�O�O�G �@�L�[�`�F�[���^LED���F���C�g�ŁA�X�C�b�`���������тɁuOFF���펞ON���_�Łv�̂Q���[�h�{OFF�̓�������鏤�i������܂��B���̏��i��IC���g���Ώ펞�_�����_�ł����I�ׂ܂���̂łV���[�h���K�v�������X�g���X������܂���B���������Ă���X�����Ȃ��̂ŋL���Ƃ��Ă͋�̓I�ɂ͌f�ڒv���܂���B ���Ԏ� 2008/3/17
|
|
| �ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) | ||
|
�@�ԏ゠�炵���Ɍ��ʓI�Ȗh��LED�t���b�V���̐�����l���Ă��܂��B �@�R���f���T�}�C�N���Z���T�[�Ɏg���Đl���Ȃǂ̕����Ɋ��m��LED�𐔕b�t���b�V��������P���ȉ�H�ł��B �@��̈Â��ԓ��ł̓ˑR�̌��̔����͖h�Ƃɂ�����Ƃ������ʂ�����Ǝv���܂��B �@����������ƁA�R���f���T�}�C�N�������E���ăA���vIC�ő��������̐M�����^�C�}�[IC�ȂǂŐ���LED�������邽���̂ł�����H�}�����܂��o���܂���B �@���������ȒP�Ɏv������H�͂���܂���ł��傤��? �@�ԏ゠�炵���ŋߑ����炵���̂ŁA�������炢�������O�b�Y�Ƃ��Ăǂ�����낵�����肢���܂��B �L�̐K�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���p�I���A���ʓI���E�E�E�ɂ��Ă͒u���Ă����Ƃ��āA���̂悤�ȉ�H���l�����܂��B ����H�}���N���b�N����Ɗg��\��
�@ECM(�G���N�g���b�g�E�R���f���T�E�}�C�N)�̔���ȓd�C�M����OP�A���v(�I�y�A���v)LM358�ő������܂��B(��H�}�̈�i�ځA��{�I�Ȕ��]������H) �@�s���A�I�[�f�B�I�p�̃}�C�N�A���v�Ȃ�4558�݊��̒�m�C�YOP�A���v�����g�p����̂ł����A����͉����ɂ͑S���S�炸�ɒP�Ɂu�����M�������������v�f���邾���ł��̂ł��̒��x�ő��v�ł��B �@�����x(�{��)�́u�����Q�C�������v�p�̔��Œ��R�ʼnςł��A100�{�`���{(���ۂ�OP�A���v�̌��E�̂P���{���x)�̊ԂŒ����ł��܂��B �@�{���u�̃}�C�N���x�����͂��́u�����Q�C�������v�p�̔��Œ��R���čs���܂��B �@LM358�̓�i�ڂ̓R���p���[�^�Ƃ��ē��삵�A��i�ڂő������ꂽ�����M����������̃��x���ȏ゠���������o��(7�ԃs��)���{�ɐU��܂��B �@���������m����Əo�͂��{�ɂȂ�A���̓d���ŃR���f���TC3���[�d���ă^�C�}�[�삳���܂��B �@���샂�j�^�[�p�ɐԐFLED��t���Ă��܂��̂ŁA�����������Ƀ}�C�N����̉��������m���x���ȏ�̎��ɂ͂��̐ԐFLED�������ɂ��킹�ē_�����܂��B �@���m����p�́u�X���b�V�����h���x�������v�p�̔��Œ��R����{�I�ɂ͐^���ɉĂ����Ă��������B �@�^�C�}�[����CR�ɂ����d���Ԃ𗊂�ɂ��Ă��܂��̂ŁA���m�Ȏ��Ԃ̃^�C�}�[��H���K�v�ł���{�d���Ńg���K�[�̂����郏���V���b�g��H���^�C�}�[IC�Ȃǂ��g���č��̂��ǂ��ł��ˁB �@��H�}�̒ʂ�ɍ��ƁA������������Ɩ�20�b���x�̎��Ԏ����_��LED���_�ł��܂��B �@�_�ł��������鎞�Ԃ�C3��10��F��K�X�ύX���邩�AR2��1M����ύX���܂��BR2��FET�̃Q�[�g�ی�����˂Ă��܂��̂Œ��ӂ��Ă��������B �@����̏o�͉�H�͍P���2SK2231�ɂ��X�C�b�`���O��H�Ƃ��܂����B �@555����IC��LED�_�ʼn�H������Ă��ǂ��̂ł����A����͌x������̂Ɂu�����_��LED�v���g�p���āA���U��H�Ȃǂ삷���Ԃ��Ȃ��܂��B �@�������A�������Ŕ��U��H�Ȃǂ�����Čq��������(�����Őv�ł����)�͂����R�ɉ�H��ύX���Ă��������B �@2SK2231�̓d�����e�ʈȓ��ł���u�U�[�ł��d���ł����D���Ȃ��̂�ڑ��ł��܂��B(���̂܂܂ł͉��̏o�镨���q���ƁA�i���ɓ��삵�����܂����c) �@����̓Z���T�[���̉�H�������������ړI�Ƃ��Ă��܂��B �� �������@ �@�u�X���b�V�����h���x�������v�p�̔��Œ��RVR1���^���ɂ��Ă����܂��B �@�u�����Q�C�������v�p�̔��Œ��RVR2���E�����ς��ɉƁA���͂̃m�C�Y���x�ł����j�^�[�p�ԐFLED���`���`���Ɩ��ł��ĉ��������m���x���ȏ�ł��鎖�������܂��B�������o�͂̎����_��LED�͓_�ł��܂��B �@�u�����Q�C�������v�p�̔��Œ��RVR2���������ƍ��ɉĂ䂭�ƁA�ǂ��������j�^�[�p�ԐFLED�����܂�_�����Ȃ��Ȃ�A�X�ɉƓ_�����Ȃ��Ȃ�ʒu������܂��B �@���̓_�����Ȃ��Ȃ�ʒu���ق�̏��������ɃZ�b�g���܂��B �@�������ς��ɉĂ��܂��`���`������ꍇ�́u�X���b�V�����h���x�������v�p�̔��Œ��RVR1���E�ɉĊ��m���锻�背�x�����グ�Ă݂Ă��������B �@�t�ɉE�����ς��̎��ł����܂蔽�����Ȃ��ꍇ�́u�X���b�V�����h���x�������v�p�̔��Œ��RVR1�����ɉĊ��m���锻�背�x����������Ă݂Ă��������B �@�e�X�g��H�ł́u�X���b�V�����h���x�������v�p�̔��Œ��RVR1�͐^���ŁA�u�����Q�C�������v�p�̔��Œ��RVR2�������ł��Ȃ�͈̔͂̉��ʂɑΉ��ł��܂����B �� ���x�A�Ȃ� �@�����ɖ{��H�ƃ}�C�N��u���A��P���[�g�����ꂽ���̑��K���X���u�R���v�ƒ@�����x�Ŕ������܂��B �@�������l�Ԃ�����������A�܂�����o���ƒ@���Ȃlj��炩�̉��������m����Ɣ�������LED���_�ł��܂��B �@���̒@�����A��H�Ŏg�p�����R���f���T�}�C�N�̕i��A���x�����߈ʒu�Ȃǂłǂ̒��x�̉��ʂœ��삷�邩�͕ς��܂��̂ŁA�����܂Ńe�X�g��H�ł̓��쎎�����ʒ��x�Ǝv���Ă��������B �� ���p�x�A�Ȃ� �@�����ԗp�i���[�J�[�Ȃǂ���Ȃ����������u�������������v�̃A���[�����u����������Ă��Ȃ��̂ł��傤���H �@����͉����������ƌ�쓮�������Ă��܂菤�i�Ƃ��Ă͎��p�I�ł͖�������ł��B �@�����Ԃ̎ԓ��ɒu�����Ƃ��āA���x���ǂ��ƎԊO�̂�����˔����ɔ������Ă��܂��A���͂��Â��Ȃ����͗ǂ��ł����߂��𑼂̎Ԃ��ʂ������̉���U���ŃA���[�������삵�Ă��܂����������ł��ˁB �@�����A���[����LED�_�ňȊO�Ɏ����Ԃ̃N���N�V������炷�h�Ƒ��u�̂悤�Ȑڑ��ɂȂ��Ă�����A�߂����Ԃ��ʂ�A�������ԏ�ɕʂ̎Ԃ��o���肷�邽�тɃN���N�V��������܂���ߏ����f�Ȗh�Ƒ��u�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�܂��𑼂̎����ԂȂǂ��ʍs���Ȃ��c�ɂ̈ꌬ���Ȃ炱���������͖����ł��傤�B �@�܂��ԓ��ʼn������E���Ƃ������ł�����A�O�𑼂̎Ԃ��ʂ������炢�ł͔������Ȃ����x�̊��x�ɂ��Ă����Ƒ��K���X�����Ȃ苭���@���Ȃǂ��Ȃ��Ɣ������Ȃ����}�k�P�Ȗh�Ƒ��u�ɂȂ�\���������ł��ˁB �@�ԏ�r�炵�����Ďԓ��F����ׂɂ���������x�̉��ł͉������������A�����u����Ă�낤�v�Ǝv���đ��K���X�����������̋����Ռ��ł͂��߂Ĕ������ē_�ł�����x�̓���ɂȂ邩������܂���B �@���K���X������������LED���_�ł��ċ����ĉ�����炸�ɓ����Ă䂭��������܂���ˁB(�K���X������p�͂V���~���x�ȏゾ�Ƃ��c) �@���̂悤�ɁA�Ԃ��~�߂Ă����ꏊ�̎��͂̉����Ȃǂɂ�芴�x�����������ւ�ʓ|�ȋ@����A�w���҂��N�ł��ȒP�ɖ������Ŏg�p�ł���̂��K�{�����̎s�̋@��Ƃ��Ĕ̔��ł��郁�[�J�[�͂قƂ�ǖ����ł��傤�B �@�l����̍H��Ő��삵�āA�����œ��쒲�������Ďg�p����ɂ͋@��̒����̓���Ȃǂ͒N���������͏o�Ȃ��ł�����A�������m���̃Z���T�[�x��@������Ă������̎ԂɂƂ����͖̂ʔ����Ǝv���܂��B �@�������x�����œK�ɒ������鎩��Ȃ�ł͂̊y���݂��E�E�E �@�ԗp�łȂ��Ă��A�Â��ȏꏊ�ʼn�������������ُ킾�Ɣ��f���Čx����o������A�Ɩ���������ƐF�X�Ɖ��p��������H�ł��̂ŁA�L����ǂ܂�Ă�����ł��ꂼ�ꉽ���ړI�Ɉ�v�����犈�p���Ă݂Ă��������B �@���e���������猩��ǂ��ł��������ƌ����ǂ��ł��������Ȃ̂ł����A���̃T�C�g�̖��O�́u�������v�ł͂���܂���B�ŋ߂̓��e�ɑ����̂ł����E�E�E �@�w�C�̖����x���������̂ł��B �@�u�������v�͓��e�𓊂������u���v�E������f�ڂ��Ă����R�[�i�[(�y�[�W)�̖��O�ł��̂Łu����������v�Ƃ������͂ǂ��ɂ���������Ⴂ�܂���B ���Ԏ� 2008/3/8
|
|
| ���e |
�C�̖����@�l �@�����́B�O��͂����O���Ԉ���ď������݂܂���ł����B �@�Ԉ���ČĂ��̂͂��܂�C���ǂ�����܂����ˁB���Ȃ��Ă܂��B �@��H�}���肪�Ƃ��������܂��B�u���b�h��ʼn�H���q���܂�����ƂĂ����܂����삵�Ă��܂��B�����ł��B �@���x���グ��Ɛ��������x�Ńr�b�N������قlj����̉��܂Ŕ������Ă��܂����B �@�ҋ@�d�͂�1.5mm�A���y�A�Ɨǂ������ł��B �@�ȑO�ALM386���g����2�i�A���v�Ŏ������̂ł������̂����܂��s���������Ă�����ɓ��e�����Ă����������̂ł��B �@��R�ƃR���f���T�̑g�ݍ��킹���ē���ł��ˁB �@�ԏ�r�炵��Ǝv���Ă��܂������A�Ƃ̒��ł��\���������ł��B �@�����ŐԊO���Z���T�[���ƃy�b�g�̌��L�ȂǓ����ɔ������܂���������͉��Z���T�[�Ȃ̂Ō�쓮����\�������Ȃ��Ȃ�C�����܂��B �@�����Ƃ����L�����𗧂Ă�̂Ō�쓮�͈ꏏ�ł����A�A�A �@�Z���T�[���͋C�̖�������̂������Ŋ����ł��̂ŁA���Ƃ�LED�̕�����x���_�łł͂Ȃ����������C���p�N�g�̂���f���t���b�V���ɂ��悤�Ǝv���Ă��܂��B �@�ŋ߁APIC�̕����n�߂�����ŁA�����Ă�`�������W�������Ǝv���܂��B �@�Z���T�[����̓��͂�����ƁA0.1�bLED���I������0.1�b�I�t�����10��J��Ԃ��B �@���ōl����̂͊ȒP�ł����A���ɂ̓v���O���������̂Ɏ��Ԃ��|���肻���ł��B �@���Ǝʂ��ł����̃X�g���{�𗬗p����Ƃ����ƈЊd�o�������ł��ˁB �@�Ƃ���Ń}�C�R�����g��Ȃ��Ă��A1�b�Ԓf���t���b�V���ȂNJȒP�ɏo�����ł��傤���H �@�T���ɂł��撣���Ė{�Ԃ삵�����Ǝv���܂��B �@�o���܂�����A�܂��A�������Ă��������܂��B �@�ˑR���Ă킪�܂܂ȏ������݂ɂ��A�e�ؒ��J�ɑΉ����Ă��������܂��� �@�{���ɂǂ������肪�Ƃ��������܂����B �L�̐K�� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�m���ɁA��i�ڂ�LM386�̂悤�ȉ����M���p�̃A���vIC���g���Ă����l�ȋ@�\�̉�H�͍���Ǝv���܂��B�悭����LM386�A���v���Ƒ����x��20�{��200�{�Ȃǂ��R���f���T��ς��邾���ŕύX�ł��܂����֗��ł���ˁB �@���̑��u�̃L���͂Q�i�ڂł��܂������̗L��/�����f�����邩�̕����ŁA���̕����ƃ}�C�N�A���v�������ݍ��݂ł��Ȃ�̕��������p(��H�}�̏�̂ق��̊�d���E�}�C�N�p�d��������Ă��镔��)���Ă��܂����őS�̂̕��i�_�������炷�H�v�����Ă��܂��B �@�}�C�N�A���v���A��r�X�C�b�`���O���ƕʁX��IC���H�ō���Ă����l�̋@�\�͎����ł��܂����A�����͂���u�C�̖����I�蔲����H�v�̎�@�łł��邾�������I(��)�ł���悤�ɂ��Ă��܂��B �@�ȒP�ȗ����̉�H�ł���Ԃ�A��q�̒ʂ�^�p�ʂł͂Ȃ��Ȃ��̋Ȏ҂������肵�܂��B �@�m���ɖ����̎����ł̖h�ƃZ���T�[�Ȃǂɂ��g���܂����A����L�̐��╨���ł��������Ă��܂��܂��ˁB�l�H�m�\���ڂœ����̖����ł͓��삹���A������l�̐��ɂ͌x����o�����u�Ȃ�ǂ��̂ł����E�E�E(����Ȃ̐��S�~�ł͂ł��܂���) �@�{���̖h�Ɖ�Ђ̃K���X����Z���T�[���ł͂���������p�̃Z���T�[���A�܂��͈��d�f�q�����}�C�N�̑���ɂ�����Łu�K���X�̊���鉹�E�q�r�����鉹�v�̎��g�������ɔ�������悤�ȃt�B���^�[��H�����Ă�����ƁA��H�͕��G�ɂȂ�܂�����쓮�Ȃǂ������悤�Ȃ������肵����H�ƂȂ��Ă��邻���ł��B���̉���U���E�K���X��@�����x(���̊J���߂�)�ł͔��������A�K���X������ꂽ�������x����o�����u�ł��ˁB �@�p�r�ɂ���Ă͂��̂悤�Ƀt�B���^�[������Ό�쓮�����Ȃ����邱�Ƃ��ł��܂��ˁB �@�h���I��LED�t���b�V����H��A�X�g���{������H�Ȃ͖ʔ����ł��ˁB �@�P�b�Ԋu(�ݒ�͎��R�ɉςł���)�Œf������M�������Ȃǂ͏�ł������܂������^�C�}�[IC 555�����Ƀ|�s�����[�ł��B �@������������g�̔��U��H����u���v���o�����x�̎��g��������H�A�܂��u�����V���b�g�^�C�}�[�v�Ƃ�����莞��ON�ɂȂ�^�C�}�[��H�ȂǗl�X�ȁu���ԁE������x�̕��̓d���M���v������IC�ł��B �@PIC���w�K�����̂�������̎���ɉ����Ă��Ă����ւ�ʔ����Ǝv���܂����A�^�C�}�[IC 555�͓d�q��H������ł͔����Ă͒ʂ�Ȃ���(��)���Ǝv���܂��̂ŁA��x�l�b�g�����łł����ׂĂ݂Ă��������B �@���̃y�[�W�́u�k�d�c���������_�ł��������B�v�ł�������Ɠ_�Ŏ����͒x���ł����g�p���Ă��܂��B ���Ԏ� 2008/3/11
|
|
| ���e |
�C�̖����@�l �@�T���Ɉ�ʂ�쐬���Ă݂܂����B �@PIC�̃v���O�����́A�܂��܂����ɂ͕~���������l�b�g�Ō������ԊO���Z���T�[�p�̃v���O�������g���܂����B �@LED��0.1�b�Ԋu�Ńt���b�V�����邱�Ƃɂ��āA�����M���������ꍇ�̓X���[�v���[�h�ɓ���A���ɔ��������INT���荞�݂�PIC�X�^�[�g�ł��B �@�S�̂̑ҋ@����d�͂�1.5mA�ȉ��œ��삵�Ă��܂��B �@����ƁA������CDS�̃Z���T�[��LED������Ȃ��l�ɂ��Ă��܂��B �@���Ԃ̊O���̌�쓮�������Ȃ����ď���d�͂��҂��ł��܂��B �@�g�p���������A��͂艹�Z���T�[�Ȃ̂Ō�쓮�͂�����x����܂����Ԃ̃K���X��@���Ռ��ȂǗǂ������ɍ쓮���Ă��܂��B �@�����ALED�ł͑傫�ȃC���p�N�g���Ȃ��̂ŃX�g���{�����Ȃǂ����č���A����Ȃ�h�ƌ��ʂ�ڎw���\��ł��܂��B �@����̉�H�ň�ԏd�v�ȓ_�́A�I�y�A���v�������ł����ł͂Ȃ��R���p���[�^���g���d���ϓ����m���ɔF�������邱�Ƃł����B �@���̒m����������Έ�l�ł͂��̓d�q�H��͏o���Ȃ������Ǝv���܂��B �@���̗l�ȁA�M�d�ȏ�����Ă��������{���ɂǂ������肪�Ƃ��������܂����B �@���ꂩ������낢��ȏ��y���݂ɂ��Ă��܂��B �L�̐K�� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@������쓮�͂���悤�ł����A�Ԃł������������ɗ����Ă���悤�ł��ˁB�悩�����ł��B �@����L�̐K���l���g�ݗ��ĂĂ���悤�ɁA�d�q��H�͂P�P�́u��b�@�\�v�̉�H��g�ݍ��킹��Ηl�X�ȕ������o�������ł��܂��B �@����̉�H�̉��Z���T�[�����ʂ̉�H�}�ł����܂����A�����v��_�ł����ĈЊd���镔����PIC���g������^�C�}�[IC���g������t���b�V���[���g������ƐF�X�ƍH�v���ł��܂��ˁB �@����̉�H�́u�����ԂŁv�Ƃ������œd���̓q���[�Y�{�b�N�X����12V����������O��ʼn�H�̓d����12V�Őv���Ă��܂��B(������d�r�p��5�`6V�p�ɕ��i�ύX���\�ł�) �@�Ԃ�12V�Ŏg�p����Ȃ�A���l�����Ă���u�X�g���{�t���b�V���v��t����ꍇ�͂��Ƃ�������ȃX�g���{�t���b�V���Ȃ��H�}���̎����_��LED�̕ς��ɂ���ƕt���ւ��邾���ňЊd���ʐ��̃X�g���{�ɕύX���鎖���ȒP�ɂł���悤�Ȑv�ɂ��Ă��܂��B �@�܂��_�Ń����v�ł͖����u�h�A�X�C�b�`�v�̔z����FET�̃h���C���ɐڑ�����Ɓu���������m������Ԃ̃��[�������v���_������v���u�ɂ��Ȃ�܂��B(���܂�G���œ_����������ƎԂ̃o�b�e���[������܂����c) �@�^�C�}�[IC�Ȃǂ�LED�_�ʼn�H����ꂸ��FET�̃X�C�b�`�����ɂ��Ă���̂͂������������l���Ă̐v�Ȃ̂ł���i�O�O�G ���Ԏ� 2008/3/24
|
|
| ���낢�� | ||
|
�@�I�[�g���C�g�ł����b�ɂȂ�܂����B����_�C�\�[�łR�P�T�~�̏��i�Ɠ����Ǝv����P�[�^�C�[�d��������܂����̂ł��ł��B�Ȃ�ƃP�[���[���Q�Őō��݂Q�X�W�~�ł����B����Ɋ�̌`�������`�ł��̂܂܁A�����d���ɓ���Ďg�������ł��B http://www.geocities.jp/osam_ka/judenki/ �@�R�C�����\��t���Ă��Ăh�b�̌^�Ԃ��s���Ȃ̂ƁA��R�����ׂă`�b�v�ɂȂ��Ă���̂ŁA�����͂��ɂ������ł��B����ŁA�d��������H��d��������H�ɉ������悤�Ǝv���܂�������肪����܂��B���ڂk�d�c��_��������̂ɂ͗ǂ��̂ł����A�s�̂̃T�C�N�����C�g�̓d���ɂ��悤�Ƃ���ƃX�C�b�`�����E��E�_�ł̐�ւ����d�q�X�C�b�`�ł��̂ŁA�܂��A�d�����������ł͋��オ��ւ��Ȃ��Ǝv���܂��s�B�ł͓d������ł͂ǂ����Ƃ����Ƒ���o���Ȃ��ƃX�C�b�`��������Ȃ��A�~�܂邽�тɃX�C�b�`�����A�ƂȂ肱��܂܂��s�ŁA��͂���_�ł͂�����߂邩�A�_�C�i���Ńj�b�P�����f�[�d�r���[�d�ł��Ȃ����Ƃ����l���ɂ�����܂����B �@�����Ŏ���ł����A#20071222�̍Ō�ɂ���w���s���Ɏ��]�ԃ_�C�i������j�b�P�����f�[�d�r�ɏ[�d���āA��Ԍ��10�b���x(��)���郉�C�g�x�̓d�q��H�͂��Ȃ������ł����A���݊��d�r�R�{�d�l�̂P�v�k�d�c�̃T�C�N�����C�g�Ƀj�b�P�����f�[�d�r�����Ďg�p���Ă܂����A������n�u�_�C�i���ŏ펞�[�d���A�d����������オ��J�b�g���A�ߕ��d�ɂȂ�Ȃ����x�܂ʼn���������[�d�J�n�����H������ƕ֗��Ɏv���܂����A��͂肩�Ȃ����ł��傤���H �@�܂��A���݂͂R�{�̏[�d�r���Q�{�p�̏[�d��i�Ƃ��ɃZ���A�S�Ϗ��i�j�łQ�{�ƂP�{�Ƃɕ����ĂQ��[�d���Ă܂����A��x�ɂR�{�[�d����ǂ����@�͂���܂��H�i����ɂȂ��ł����܂�Ȃ����ł��傤���H�j �@��قǂ̓��e�̎s�̃��C�g�̊�ʐ^�ł��B http://www.geocities.jp/osam_ka/autolight/autolight2.htm �@��͊i�[�������ڒ�����Ă���悤�ŁA�͂����܂���ł����̂ŁA�d�r�}���������猩���锼�c�t���ʂ����ł��B�d��������R�Ɠ�ƃR���f���T�[�A���Ƃ͋��E��E�_�ŃX�C�b�`�̎��ȕێ��ƃ^�C�}�[�p�ɂQ�s�x�Ə����Ă���h�b�H�i�p�P�j������Ǝv���܂����A�悭�킩��܂���B �@��H�����Ƃ͊W�Ȃ��ł����A���̃��C�g�̃z���_�̓}�}�`�����̃n���h���a��p�Ȃ̂��A�}�E���e���o�C�N�p��[�h�p�̖�Q�Umm�a�̃n���h���ɂ͏��������ē���܂���ł����̂ŁA�z���_�̓����̓ˋN���J�b�^�ō��A�~�߃l�W�����̂ɑւ��ĂȂ�Ƃ����t���܂����B�z���_�����L�����ڂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��ˁB(^_^;) i�i���j �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@��R�̎���������Ă��܂����A�ł���Όf�ډœ��e�̍ۂɂ͊Ȍ��ɂP�̎���ɂ��Ă��������B �@����]�́w�K��d���ȉ��̏ꍇ�ɏ[�d���J�n���A�K��d���ɂȂ�Ώ[�d���~�����H�x�����ꍇ�A�Œ���u�\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H�v�ȏ�̉�H�ƂȂ�܂��B �@�����������炠�̉�H�̔{�ȏ�̕��i�_���ɂȂ邩������܂���B �@���̍l���ł́A���̂悤�ȑ��u�͂������Ԃ₨���ɑ��āA�G�l���M�[�����̖ʂȂǂł͂��܂艿�l�̖������̂��Ƃ��v���܂��B �@�d�C���[�J�[�⎩�]�ԗp�i���[�J�[���������������݂̃��C�g�E�[�d���u�����Ȃ����R�͏\������Ǝv���܂��B �@�w���s���Ɏ��]�ԃ_�C�i������j�b�P�����f�[�d�r�ɏ[�d���āA��Ԍ��10�b���x(��)���郉�C�g�x�̐����Ɋւ��Ă��A������Ŋ��ɏ����Ă��܂�����̓I�ȉ�H�}����������͂���܂���̂Ō����E����̐����}�����ɗ��߁u��肽�����͂��̂悤�ȕ��@�ł������łǂ����v�Ƃ����X�^���X�ɗ��߂Ă��܂��B �@�Z���A�̏[�d��œd�r�����ɏ[�d���鎖�͓d�C�I�ɂ͉\�ł��B �@�P�O�����ɂ͖���(���M�E�ߔM�̌���)�ł����A�P�l�d�r���Q�`�R�{����ł���g�����X�̗e�ʓI�ɂ͏[�d��͉�ꂽ�肵�Ȃ��ł��傤�B �@�A���[�d�r�̃R���f�B�V�����������Ă��鎖�������ŁA�x��c�e�ʂ��o���o���̓d�r�����[�d�����ꍇ�ɂ͓d�r������A�ߏ[�d�E�[�d�s�����N����Ȃǂ̕s����N����܂��̂Ŏ��ȐӔC�ŊǗ����Ă��������B �@����������Ԃ��[�d���Ԃ����т܂�����A���[�d���m��H�̖����Z���A105�~�[�d��ł͂��d�r���O�����̊Ǘ����l�Ԃ̐ӔC�ł��܂����삵�Ă��������B �@������ǂ��̂͂�����105�~�̏[�d��ł�����A����������Ă���ق����͂邩�Ɋ��S�m�����Ǝv���܂��B �@1280�~�̎��]�ԃ��C�g���_�C�i������d�������������ꍇ�A�u��Ԃ���Ɠ_�����[�h�����Z�b�g����ď����Ă��܂��A���ɑ���o������������܂܂Ȃ̂ł܂��_�����삵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����̂͂܂��Ɂu�����������C�g���w�����ꂽ����d���Ȃ��v�ƌ����ׂ��ł��傤���B �@���d�r����LED���C�g���\�t�g�X�C�b�`����ON/OFF�A�܂���ON/�_��/OFF�Ȃǂ̃��C�g�̂قƂ�ǂ͓d�r���ƃX�C�b�`�I���̓��Z�b�g����܂��B�d�r���Ɛؑ։�H�̓d������āA���ɓd�r����ꂽ���ɂ̓��Z�b�g(OFF)��Ԃ���͂��܂邩��ł��B �@�����ȃt���b�V�����C�g(�����d��)�ł̓}�C�N���R���g���[��(�}�C�R��)�����Łu���[�h�������v�Ƃ����L���@�\������A�d������Ă��E�d�r���Ă����ɓd������ꂽ���ɂ͑O�ɑI���Ă��������[�h�œ_�����܂��B �@���]�ԃ_�C�i���̂悤�Ȏ~�܂�x�ɓd������Ă��܂��d�����g�p����ۂɂ́A���[�h�������̂�������d�������J�j�J���X�C�b�`���ŋL���������v��Ȃ��P���ȃX�C�b�`�g�p�̃��C�g���g���K�v������܂��B �@�܂����p���������C�g�̑I���Ɏ��s�����Ƃ����킯�ł��ˁB �@�\�t�g�X�C�b�`���̎��]�ԃ��C�g�̂����A�u�������v�̂��̂ł͂قƂ�ǂ̐��i�̓����́u���v�͓����ł��B �@����p�̓d�q��H(IC)������Ă��郁�[�J�[�����Ђłقړ��������E��H�̂��̂�����Ă���̂ł��傤�B���ʗp�̔��F���C�g���㕔�p�̃}�[�J�[(�ԐF�Ȃ�)���A�����Ď��]�ԗp�łȂ��Ă�100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���LED�̓_�ł���O�b�Y�����قړ��������̃\�t�g�X�C�b�`��H���̗p���Ă��܂��B �@���̂悤�ȁu������(?)�\�t�g�X�C�b�`IC��H�v���g�p�������̂̏ꍇ�A�u���[�h�������͖����̂ɁA�����������[�h������������悤�ɐU���킹���[�������������v���s�����Ƃ��ł��܂��B �@�����͊ȒP�ŁA��d������Ă��u�ؑ։�H�͓����Ă���v�悤�ɂ��邾���ł��B �@��d��(�d�r�E�_�C�i��)����̓d�������������Ȃ��Ă��A�ؑ։�H�ɂ͓d�������������܂܂ɂ��Ă��ΐؑ։�H�͓���𑱂��āA���[�h�����Z�b�g����鎖�͂���܂���B �@�E�E�E�E�N���l���Ă��u�d�����Ȃ��v�Ƃ������ł���ˁB�ȒP�Ȕ��z�ł��B �@�P���Ɂu�o�b�N�A�b�v�d���v��t���邾���ł��B �@�����Ă��̊ȒP�Ȕ��z���\�ɂ���̂��u�������̑g���_��IC�`�b�v�v�ŁA���C�g��H�Ɏg�p����Ă���ؑփ`�b�v�͏���d����������10�ʂ`���x�Ɠ��쒆���قƂ�Ǔd��������Ă��Ȃ��̂ƈꏏ�B���ꂾ���̏���d���ł���Α傫�ȓd�r�E�o�b�e���[�������Ă����Ȃ��R���f���T�E�L���p�V�^�����Ő����`�����Ԃ͓��삳�������邱�Ƃ��ł��܂��B �@���łɏ������������̑g���_��IC�`�b�v�̓��[�h���uOFF�v�̎��ɂ͓d�r�Ɍq�����ςȂ��ł��S���d��������܂���B�S���ƌ����ƊԈႢ��������܂��A�d���v�Ńʂ`�����W�ł�����s�\�ȓd���ʂł��B �@����(�_�����̏���d����쓮���e)���璆�g��C-MOS�\����IC���Ƃ͑z���ł��܂����A�e�Ђ���e���IC(�قƂ�ǂ͊�Ƀ_�C���N�g�ɕ\�ʎ���)���o�Ă��܂��̂ł����ł͂Ђ�����߂āu�������̑g���_��IC�`�b�v�v�ƌĂт܂��B �@���ɂ͂����݂⓮�삪�Ⴄ���̂�����A����̉������K�p�ł��Ȃ����̂�����ł��傤���A���̂ւ�͍���̋L���͌ʂ�IC�^�ԂȂǂŎw�肵�Ă��Ȃ��Ƃ������ł��e�͊肢�܂��B �@�������̑g���_��IC�`�b�v�ɂ͊�{�I�Ɏ��̂S�{�̑�(�ڑ��_)������܂��B �EVdd �c �d���{ �EVss �c �d���| �EOUT �c �o��(�I�[�v���h���C���o��) �ESW �c ���[�h�ؑփX�C�b�`(Low Active) �@�e�[�������v��A�N�Z�T���[�p�ł�OUT�[�q��2�`5�{����A�eLED�̓_�Ńp�^�[���ŏo�͂��ω����܂��B �@�����̗v�_�� �E��d������Ă��Ă�IC�ɂ͓d����������������(�o�b�N�A�b�v) �E�I�[�v���h���C���o�͂Ȃ̂ł��̑���H�̓d������Ă����͖��� �ƂȂ�A����͂������Q�̕��i�Ŏ����ł��܂��B 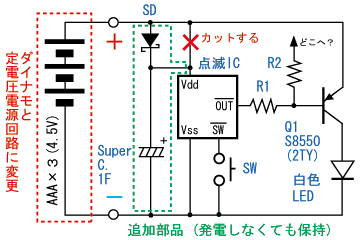 �� R2�͊�ʐ^�ł͂ǂ��ɐڑ�����Ă���̂��s���ׁ̈u�ǂ��ցH�v�ƋL�ڂ��Ă��܂�
�@IC��Vdd�[�q�Ɠd���{�Ɍq�����Ă���o�^�[�����J�b�g���A�V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�Ɠd�C��d�w�R���f���T(�X�[�p�[�L���p�V�^)�ō�����o�b�N�A�b�v�d�����q�������ł��B �@�d�C��d�w�R���f���T��1F/5.5V���g�p�����ꍇ�A24���Ԉȏ�(*1)�͕ێ����܂��B(IC����d����10��A�̏ꍇ�̎����l) �@�ʋΒʊw�ȂǂŖ������E�[�Ɏ��]�Ԃɏ��悤�ȏꍇ�͑I���������[�h��������ێ����Ă��āA������Ă��E�ǂꂾ���M���҂��Ŏ~�܂��Ă��A����ΕK���I�����Ă���_�����[�h�œ_�����܂��B �@�y���̋x���͎��]�Ԃɏ��Ȃ��Ȃ�A�P�����x�œd�C��d�w�R���f���T�͕��d���ĕێ��͂ł��Ȃ��Ȃ�A���ɑ��鎞�ɂ̓��C�g��OFF�ɂȂ��Ă��܂��B �@�����Ɉ�x���x���]�Ԃ𑖂点��p�r�ł��A�g�p���鎞�̍ŏ��̈�x�����X�C�b�`���삪�K�v�ł����M���҂����x�ł�OFF�ɂȂ�܂���̂ŕs�ւ��͖����ł��傤�B �@�d�C��d�w�R���f���T�ł͖������ʂ̃A���~�d���R���f���T���g�p�����ꍇ�A1000��F/10V����R�����x�͕ێ����܂����̂ŁA�M���҂��̊Ԃ����ێ�����悢�̂ł���Γd�C��d�w�R���f���T�łȂ��Ă�1/10���x�̉��i�̃A���~�d���R���f���T�ł��ǂ��ł��B �@���̕ێ������̏ꍇ�͂�������d��������LED�͏����܂��BLED���͂��̂܂�d���̓d���œ_�������Ă��܂��̂ł�����܂��ł��ˁB �@�܂������m��H�Ȃǂ͂���܂���̂Ń_�C�i������d�͂�������������͒��Ԃł��_�����܂��B �@LED�̎����͒����ł����A���̂������]�Ԃ����ԓ_���`���ɂȂ邩������܂�������m�Œ��Ԃ͏����K�v�������ł��傤�B �@�P�l�d�r���R�{�����X�y�[�X�Ƀ_�C�i������̌𗬂�4.5V�ɂ��鐮����H(��d����H)�Ƌ��Ƀo�b�N�A�b�v�d���̕��i�����Ă��]�T�œ���Ǝv���܂��B *1 �R���f���T�͉��x�ɂ��~�d���\���ቺ���܂��B�����ɂȂ�ꏊ�A
���˓����̓����钓�֏ꓙ�ɕ��u�����ꍇ�͕ێ����Ԃ��Z���Ȃ�܂��B ���Ԏ� 2008/3/3
|
|
| ���e |
�@�o�b�N�A�b�v���K�v�Ȃ����ł��̂ŁA�[�d�r���_�C�i���ŏ[�d����K�v�͖��������ł��ˁB �@�ڍׂȂ��Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B ���i���j �l
|
|
| ���e |
�@���낢�뎩���Ȃ�ɍl���Ĉȉ��̉�H�����������̐}���\�肵�č쐬���Ă݂܂����B http://www.geocities.jp/osam_ka/judenki/index.htm#kairo �@�c�b�R���o�[�^�[�o��5.33�u�ł����Ȃ��悤�Ɏv���܂����A���d�r�R�{�Ԃ�̓d��4.5V�ɋ߂����邽�߃_�C�I�[�h�Q�{����܂����B���͂̓_�C�i���̌𗬂�{�d���������P�Q�u�`�ɂ��Ă݂܂����B�茳�Ƀu���b�W������̂ł��̗��p�ł��BDC-DC�R���o�[�^�Ȃ�A�{�d���ɂ��Ȃ��Ă�������Ǝv���܂����A�ꉞ12�`24V�Ή��Ə����Ă���܂��̂ŁA�A�A �@�������ł��傤���H ���i���j �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@���̕��@�ł��Ѝ���Ď����Ă݂Ă��������B �@�����o���ƃL���������̂Ŋ������܂����A���C�g���ADC/DC�R���o�[�^���ƐF�X�Ɛ��\�ׂȂ��ƕs�K�ł���\��������܂����A�܂��ʂɉ��Ƃ�����������̂ł͖����̂ł���ō���Ă݂Ă��������B �@���ׂȂ��Ă����ꂼ��Ɉ��S�ȓ���������E���͗��z�I�Ȑ��\��L���Ă���Ƃ����\��������܂��̂ŁA���̂܂܂Ŗ�肪�����Ƃ����\��������܂��B �@�����s�K�ł������ɉ���Ƃ��ł͂Ȃ��A���炭����LED���������Ď������k�߂邭�炢�ł��傤�B ���Ԏ� 2008/3/7
|
|
| �k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ | ||
|
�@�����b�ɂȂ��Ă���܂��B���]�Ԃ̃_�C�i���i�U���A�Q�D�S���j���ێ�������Ђ́u�k�d�c��铔�@���v�i����Ő�������j���g���Ăk�d�c�����悤�Ǝv���܂��BLED�͂��̂܂ܕt���Ă�����̂��g�������̂ł��B��̂ǂ�����Ηǂ��ł��傤���H �ǂ��ǂ� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@LED��铔�ɂ̓u���b�W�ڑ����ꂽ�_�C�I�[�h���������Ă��ĕ��i����R���܂��ˁB �@�������ău���b�W�ڑ����ꂽ�_�C�I�[�h�S�{�ALED�A���ƒ�R���Ɏ�蕪���Ă��������B �@��́u���]�ԃ_�C�i�����d�@�Ŕ��F�k�d�c�������v�y�[�W�ɍڂ��Ă�����@�̒����炨�D���ȃ^�C�v�̉�H��I��ŁA�K�v�Ȓlj����i���w�����ăI���W�i���̃��C�g��g�ݗ��Ă���Ɨǂ��ł��傤�B �@100�~LED��铔�ɕt���Ă��锒�FLED�������_�������邾���Ȃ�A10mA��CRD���Q�����20mA��d���ɂ��Ďg�����炢�ł��ǂ��ł��ˁB(��d���ł͖��邭�͓���܂���) ���Ԏ� 2008/2/19
|
|
| ���e |
�@����A���]�Ԃ̃_�C�i�������v��LED�����܂����B �@�����ɕt���Ă����R���f���T�ƒ�R���O���A�����ɂS�O���̒�R��V���Ɏ��t���܂����BLED�̓X�[�p�[���C�g�R�k�d�c�̂k�d�c����Ղ��ƂƂ���܂����B���Ƃ��Ƃ��Ă����k�d�c�͂��̂܂܂��Ă����܂����B �@�ł�����ς�R�k�d�c����Â��̂łX�k�d�c�ɂ��܂��B �ǂ��ǂ� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@100�~�V���b�v��LED���R�t�������C�g�͂����ł�����܂��ˁB �@�lj����Ė��邢���C�g���ł���Ɨǂ��ł��ˁB ���Ԏ� 2008/2/27
|
|
| �ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� | ||
|
�@���₳���Ă��������܂��B �@�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_�������邱�Ƃ͂ł��܂����H �@�d�C��H�̒m���͑S���Ȃ��̂ł����A�ŋߋ����ŐF�X�Ƃ������Ă��܂��B �@�����ŃJ�[�i�r�̉����ē��ɂ��āA�����������Ƃ�����܂��B �@�J�[�i�r�̃~���[�g���J�[�X�e���I�ƌq���ʼn����ē��̂Ƃ��A�J�[�X�e���I�̉��ʂ��i�邱�Ƃ͈�ʓI�ł����A�ǂ������y�̕��͋C����Ă��܂��܂��B �@�����Ă��鉹�y�̕��͋C���Ȃ��悤�Ƀ~���[�g�M���i���[�M���j�𗘗p���āA�^�]�ȑ��̃X�s�[�J�[�������ʉ����āA������LED��_�����邱�Ƃ͏o���Ȃ����ƍl���Ă��܂��B �@���̕��@���g���Ă�����͂��܂��ł��傤���H �@���܂�����A��肩�����H�̐v�̎d���������� �@�������炠�肪�����ł��B BANROU �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�܂��A�~���[�g�p��Low�M����LED��_�������邾���ł����LED�ƒ�R���q�������ʼn\�ł��B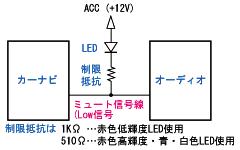
�@���̓J�[�i�r�������Ă��܂��A���[�J�[�̌��J�����ɂ��~���[�g�M���̓d�C�I��i�������Ă�����̂���������܂���ł����̂ŁA�~���[�g�M���[�q(Low�M��)�͈�ʓI�ȃI�[�v���R���N�^�o�͂��A12V VDD�œ����Ă���C-MOS���x����Low�o�͂Ɠ����ƍl���܂��B �@�J�[�i�r��Low�M���[�q(�z��)�̋z�����ݓd���̐��������\mA�͂���Ƃ���ƁA�}�̂悤��LED�ƒ�R��ڑ����邾���Ō���܂��B �@�z�����ݓd��������1mA�ȉ��Ƃ��A�Ƃ�ł��Ȃ��v�̃i�r�̏ꍇ�͂��̐ڑ��ŃI�[�f�B�I�̃~���[�g������ɓ����Ȃ�Ȃǂ̕s����������܂��B �@��胁�[�J�[���̃J�[�i�r�Ȃ���͖����Ǝv���܂����A���@�������Ă��܂��f�[�^�����\����Ă��Ȃ��̂łȂ�Ƃ������܂���B �@�~���[�g���ɕБ��̃X�s�[�J�[���������J�b�g����A�܂��͉��ʂ�����������ɂ͎��̂悤�ȉ�H�Ŏ����\�ł��B ����H�}���N���b�N����Ɗg��\��
�@�~���[�g�����ʌ���p��R4 20��(10W)�̓Z�����g��R�ł��B �@22�����ƃ~���[�g���ɂ��Ȃ菬���ȉ��ɂȂ�܂����A�I�[�f�B�I�A���v�̏o�́A���̎��̃{�����[���l�ɂ�肨�D�݂̉��ʂł͖����\��������܂��̂ŁA�K�X��R�l��ύX���Ă��D���ȉ��ʂɂȂ�悤�ɒ��߂��Ă��������B �@���������ɉ��ʉς̃{�����[����u�������ꍇ�͂��イ�Ԃ�ȃ��b�g���̃I�[�f�B�I�X�s�[�J�[�p�A�b�e�l�[�^�[���g�p���Ă��������B�����d�q��H�p�̏��^�{�����[�����g���Ɖ������Ă���\��������܂��B �@�������A�~���[�g���Ɋ��S�ɉ��ʂ�OFF�ɂ������ꍇ�͒�RR4�͖����Ō��\�ł��B�����q���܂���B �@�����[�͉�H�}���ł�OMRON �� G6B-2114P-US DC12V���g�p���Ă��܂����A����DC12V�����[�ŁuNC�[�q�̂�����́v(�ʏ�͐ړ_��ON�ŁA���쎞�ɐړ_OFF�ɂȂ�)�ł���Ύg�p�ł��܂��B �@�����傫�ȃ����[�ŃR�C���d����100mA�ȏ�ɂȂ�ꍇ�̓g�����W�X�^��2SA1015�ł͂Ȃ�2SA1296�ȂǃR���N�^�d���̑傫�Ȃ��̂��g�p���Ă��������B ���Ԏ� 2008/2/14
|
|
| USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H | ||
|
�@�ȑO��MAX641�̌��ł����b�ɂȂ�܂����B �@�����USB�ł�eneloop�[�d�����낤�Ǝv���Ă��܂��B �@������eneloop�p�́uN-MDU01S�v�Ƃ���USB����eneloop���[�d����[�d��������܂����̂ŁA������Q�l��2�{��eneloop��1.2V/500mA�ŏ[�d���悤�ƍl���Ă��܂��B �@���̏ꍇ�A2�{��eneloop�͒���A����ǂ���Őڑ���������̂ł��傤��? �@�[�d��H��LM317T���g����1.2V/500mA�̉�H�ɂ��悤�Ǝv���Ă��܂��B �@�܂��A���̐��i�͓��͂�5V/500mA�ɑ��ďo�͂�1.2V/850mA�ƂȂ��Ă��܂��B �@USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł͂Ȃ��ł��傤��? �@�ǂ��������d�g�݂�850mA�����o���Ă���̂ł���? �@��낵�����肢���܂��B sakichan �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�ȑO��MAX641��DC/DC�R���o�[�^�����ꂽ���ɂ�����x�͕�����Ă���Ƃ͎v���܂����A���̎��₪�o�Ă���Ƃ������̓R���o�[�^��M�����[�^�̓����ɂ��Ă͗�������Ă��Ȃ��Ƃ������ł��ˁB �@DC/DC�R���o�[�^�͂��̖��̒ʂ�u�ϊ��@�v�ł�����A���͂Əo�͂̊Ԃɂ͈��̗͗�(�G�l���M�[��)��ۂ��֊W������܂��B �@���z��H�ł́A���͂�5V/500mA���Ƃ��āA�o�͂�1.2V�Ȃ�ő�2.08A�̓d�������o���܂��B �@�d�C�G�l���M�[�ʂ͂v(���b�g)�ŕ\���܂��̂œ��͂�5V�~500mA��2.5W�A2.5W�̃G�l���M�[�ɑ��ēd��1.2V�̏ꍇ�d����2.08A�ƂȂ鎖�́u�ϊ��@�v�̓��엝�_���瓱����܂��B �@�A���A�ϊ��̍ۂ�100%�̌����ōs����d�q��H�͖����A�d�C��R�₻��ɔ������M�A�܂��ϊ��ɗp���镨���@����̑����ȂǗl�X�ȗv���ɂ�肷�ׂĂ̓��̓G�l���M�[���o�͂�����o������̂ł͂Ȃ��ADC/DC�R���o�[�^��H�ł͌������\���`90�����x�܂ł����p��H��̐���ƂȂ�܂��B �@����USB�[�d��ł�1.2V/850mA�̏o�͂�ɂ�1.02W�̃G�l���M�[���K�v�ł�����A����80����DC/DC�R���o�[�^���g�p���Ă���Ƃ���1.275W�̓��͂��K�v�ŁA5V�ł�0.255A�̓d�����������x�œ��삵�Ă���͂��ł��B5V/500mA�߂����ς��܂ŏ���Ă��Ȃ��ł��傤�B �@�������A�[�d�d���ȊO�ɏ[�d��̃R���g���[�������Ă����H�̏���d����USB�[�q�������Ă���̂ł������������Ȃ�܂��B �@���āAsakichan�l�������낤�Ƃ���Ă���LM317���g�p������d����H�́u�V���[�Y���M�����[�^�v�ƌĂ�钼��ڑ����́u���艻��H�v�Ȃ̂ŁADC/DC�R���o�[�^�̂悤�ɓd�͕ϊ��������H�ł͂Ȃ��A������H�͈꒼���ɒ���ɒ�R��(���ꂪLM317)�ƕ��ׂ��ڑ����ꂽ��H�ƂȂ�܂��B �@�ł��̂ł��̉�H�����ł͕K�v�ȓd���͕��ׂɗ����d����(�ق�)�������Ȃ�A�o�͂�1.2V��500mA�ł���Γ��͂̓d���ɂ�����炸(�����5V)500mA�͕K�v�ɂȂ�܂��B�������LM317������ɓ��삷��d���ȏ�ł̘b�ł��B �@�܂�LM317�́u��R�v�Ƃ��ē����܂�����A�����ɗ����500mA�̓d����LM317�̓��́E�o�͊ԓd���Ԃ�̓d�͔͂M�Ƃ���LM317�����M���܂��B���Ȃ�M���Ȃ�ł��傤�B �@LM317���g�p���Ē�d���[�d�����낤�Ƃ���ƁA�d�����m���ɂ͌Œ��R���g�p����LM317�̃��t�@�����X�[�q(ADJ)��1.25V�ɂȂ�悤�ɐݒ肷��K�v������܂��ˁB �@�[�d����j�b�P�����f��d�r�̓d���͏[�d���͂�������1.4�`1.6V���x�ł�����A����Ɍq���郊�t�@�����X�p��R�̗��[�d��1.25V�𑫂���2.65�`2.85V�ALM317�͓��͂Əo�͂̓d��������3V�ȏ�œ��삵�܂��̂ł��̓d����������5.65�`5.85V�ƂȂ�A�[�d��H�̓d���d���͍ŒႱ�̓d���ȏオ�K�v�ł��B �@USB�̓d���d��5.0V�ł͏�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�d�������Ȃ��ꍇ�͓��͏o�͍���2V���x�ł�����͂���Ƃ͎v���܂��̂łȂ�Ƃ��M���M���̏��œ���͂��邩������܂��A���܂肨���߂ł����H�ł͂���܂���ˁB �@�o��1.4�`1.6V�ŃM���M���ł�����ALM317���g�p����USB����P�O�[�d�r���Q�{����ŏo�͓d��2.8�`3.2V�ł̏[�d�Ȃǂ͏o���Ȃ����Ƃ͂킩��܂���ˁH �@�d�r���Q�{�[�d����ꍇ�͈�{���Ɉ��LM317���g�p���ēƗ������Q��H�̏[�d��H���K�v�ł��B �@���̏ꍇ�ɓ��͂�USB�ł�500mA�܂łƂ�������������܂�����A�Q�̉�H�ɓd���𗬂��Ƃ����炻�ꂼ�ꔼ����250mA���������Ȃ����ƂɂȂ�A�V���[�Y���M�����[�^���g������H�ł͏[�d�d��������250mA�ʼn�H�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@LM317�ɗ����d�����X�ɏ������Ȃ�܂��̂ŁA�M���M���̓d���ł�����Ȃ�ɓ���͂���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2008/2/9
|
|
| ���e |
�@�d����d���ł͂Ȃ��d�̘͂b�ɂȂ��ł��ˁB�����Ɖ�H�̕������Ă݂����̂ł����Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ��̂ƁA�ǂ�����ĕ���������̂��킩��܂���B �@���������b�͂ǂ�Ȗ{�ŕ����������ł��傤��? �@�o�͓d���ɊW�Ȃ��o�͓d����500mA�ł́AUSB�Ŏg�����Ƃ͂ł��܂���ˁB �@��������LM317�����삵�Ȃ���Θb�ɂȂ�Ȃ��ł��ˁc �@���Ƃ�����A����USB�[�d��͂ǂ̂悤�ȉ�H�Œ�d���ɂ��Ă���̂ł���? sakichan �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�Ō�̎���ɑ��Đ�ɁB �@���ɏ�̂��Ԏ��ŏ����Ă��܂����A����USB�[�d��́uDC/DC�R���o�[�^�v�œd���������Ă���̂ł��傤�B �@���ɓ����Ă���IC���ėp�i�Ȃ̂��A���̏[�d��ׂ̈ɐ�p�ɊJ�����ꂽ�����͎����Ă��܂��������Ă��Ȃ��̂Œm��܂��A��d�����������DC/DC�R���o�[�^��H�Ƃ����͉̂���ނ����@�͍l�����܂��̂ŁA�����ꂩ�̕����E��H�Œ�d���^DC/DC�R���o�[�^�ɂȂ��Ă��鎖�͗e�Ղɑz�������܂��B �@������LM317�������Ă�����̂ł͖����ł��傤�B �@�̂͌������Łu���W�I�̐���v�u�����̃��W�I�v�Ȃǂ̏��w�����炢����ǂ߂�d�q��H�E�A�}�`���A�����Z�p�̎G�������s����Ă��܂������A���ł̓p�\�R���G���͂���Ǔd�q��H��̏��w�������l�܂œǂ߂�G���͎c�O�Ȃ��猎�����s�͂���Ă��܂���B �@�]�k�ł����A�̂�NHK�̗[����TV�Łu�݂�Ȃ̉Ȋw�v�Ƃ����ԑg����������Ă��ėl�X�ȉȊw����������I�ɏЉ�A���̒��ŏT�Ɉ��u�y�����������v�Ƃ����T�u�^�C�g���ŋZ�p�I�ȓ��e���Ƃ肠�������A�X�Ɍ��Ɉ����x�͓d�q��H���P���グ�Č�����������܂ł��������ԑg������܂����B�܂�����Ɖƒ�p�r�f�I�f�b�L����������n�߂�����!?�ŁA�r�f�I�������Ă���ƒ�͏��Ȃ��K���ʼn�ʂɉf���H�}�������ʂ�����ANHK�ɗX�ւʼn�H�}�R�s�[�T�[�r�X��\�������̂ł��B �@���{��(���E���H)�́u�Î~�E�R�}���肪�ł���IVHS�f�b�L�v���������ꂽ���ɐe�ɂ˂����Ĕ����Ă�����āA��H�}�������ʂ��̂��y�ɂȂ�܂����B�ړI�̊��ɂ͐������z�ȓ����ł�(��) �������Ă݂�Ɓu�݂�Ȃ̉Ȋw�E���̂��������� - �z���o�̍L���v
�Ƃ����f���炵���T�C�g�l������܂����B�N��ʂɂ܂Ƃ߂��Ă��� �������e�̃���(�菑���I)��e�[�}���yMIDI�ɂ͗܂�U���܂��B �@���ł�(���₸���ƑO��)����Ȕԑg����������鎖�͖����Ȃ�܂������t�Ƀl�b�g�̔��B�ŕK�v�ȃf�[�^�V�[�g�̓��[�J�[�̃T�C�g����_�E�����[�h�ł���悤�ɂȂ�܂������A��b�I�ȕ������������(�l�܂�)�T�C�g�������m���������肷��̂͊y�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��发�Ђ̎�ނ⊧�s�����̂ɔ�ׂ�ΓV���̂悤�Ȋ��ł��B �@���ł��Z�p�Ҍ����̍��x�ȓ��e�̎G���Ȃ炢�������s����Ă��܂����A���S�҂̕����ǂ܂�Ă��قƂ�Ǔ��e�ɂ��Ă䂯�Ȃ��ł��傤���A�����u�g�����W�X�^�Z�p�v�͏��S�Ҍ����̊�b���������L���������d�q��H�̕�������l�Ȃ�K���ǂ�ł���ł��傤�B�����e�[�}���ς��܂�����A�u�g�����W�X�^�Z�p�v���Q�`�R�N��������w�ǂ��ēǂ�ł���Γd�q��H�̊�b�≞�p�͂��Ȃ�g�ɕt���ł��傤�B �@�܂��A�d����H�ɂ��Ēm�肽�������Ȃ�U�b�ƃl�b�g�������������ł����̂悤�Ȑ�发�Ђ��݂���܂��B(�ق�̈��ł�) ����{ ���g�����W�X�^��H�̐v�\FET �p���[MOS �X�C�b�`���O��H�������ʼn�� (�P�s�{) ���g�����W�X�^��H�̎��p�v�@�g�����W�X�^�^�e�d�s�^�_�C�I�[�h�̓��쌴�����{��H����C�d���^����g�^�����g��H�C�A�i���O�^�f�B�W�^���̎��p��H�܂� ���X�C�b�`���O�R���o�[�^��H���� �� �e���Д̔��y�[�W�̉��ɗގ����e�̏��Ђ̃����N������܂��̂ŁA�H����낢��Əo�Ă��܂��B �@�����܂Ńl�b�g�Œ��ׂďo�Ă������Ԃɂ������A�Ƃ������x�Ŏ��͂����̏��Ђ͎��ۂɌ������������̂ŁA�ǂ̒��x�̓��e�Ȃ̂��A�ǂ݂₷���̂��A�Ȃǂ͑S���킩��܂��A���ЂƂ������͓ǂސl�ɂ���Ăǂ̂悤�ȓ��e�E�\�L�̂��̂��K���Ă���̂��͌l��������܂�����A�ł���Α�菑�X�ɍs���Ď��ۂɎ�ɂƂ��Ē��g���m�F������ł����g���ǂ݂₷���Ǝv�����{���ċA����Ɨǂ��ł��傤�B �@��发�Ђ͂���Ȃ�̒l�i�Ȃ̂ŁA�����n�߂�Ƃ����Ƃ����܂ɐ����~�̏o��ɂȂ�܂����A����͎��g�̐g�ɂȂ镨�Ƃ��Č����Ė��ʂȓ����ł͖����͂��ł��B ���Ԏ� 2008/2/9
|
|
| ���e |
�@����ς�DC/DC�R���o�[�^�ł����B �@������̃T�C�g�ɂ�����MC34063�ł�������ł��傤���H �@���傤�ǎ����Ă���̂ŁA��x�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B �@�̂͑�ς�������ł���(��) �@���������܂ꂽ�Ƃ��ɂ͂��łɃr�f�I�f�b�L�͕��y���Ă��܂����B �@�ł��A��������Ď����œw�͂��ĕ���������ɗ����ł���ł��傤�ˁB �@�g�����W�X�^�Z�p�͕��������Ƃ͂���܂����A�ǂ��Ƃ͂Ȃ��̂ł��̋@��ɓǂ�ł݂悤�Ǝv���܂��B �@3���̖{���Q�l�ɕ����Ă݂����Ǝv���܂��B sakichan �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@MC34063�����t�@�����X���͂̓d����1.25V�ł���ˁB �@�o�͑��ŕK�v�Ƃ���d����LM317�ō�����ꍇ�Ɠ����ł��̂ŁA��͓��͑�����R�C���EMC34063�����̃X�C�b�`���O�g�����W�X�^��ʂ�o�H�ł̓d���~������2�`3V�ł����肷�邩�ł��ˁE�E�E�E �@����͂����ŏڂ����͏����Ȃ����ɂ��܂��̂ŁA���莝���̕��i�ʼn�H������Ď����Ă݂Ă��������B �@�P���ɓd�����o��R�Ȃǂ�1.25V��K�v�Ƃ���悤�ȊeIC�̊�{��H�}�ʂ�ɍ�邩�A�ʓrOP-AMP����lj��g�p���ēd�����o���̕K�v�d����0.��V���x�܂ʼn����ăX�C�b�`���O���̃h���b�v�d�����グ�Ă���Ĉ��艻�����邩�A�ق������������@�\���pIC���g�����ȂǁA������ł��l�����͂���܂��̂ŁA���������e����@�������Ă݂邽�߂ɂ���H�E����������Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2008/2/10
|
|
| RS232C�̂t�r�a�ڑ� | ||
|
�@�F�X�ȃT�C�g�����q�����ĉ�����Ƃ���A������͂ƂĂ��e�ɉ��Ă���������悤�Ȃ̂ŁA���e���Ă݂܂����B �@����̖��_�́A �@RS232�R�[�h��USB�ڑ��ɂ��A�O�����͏������s����PIC����PC���֗^������l���AC�����p���ĕϐ��֊i�[������@�@�ł��B �@�M���̊i�[���@�������炸�A�܂��AUSB�ڑ�������Ƃɂ���āAPC�ɗ^������l���ǂ̂悤�ɕω����邩������Ȃ����߁A�l�ꔪ�ꂵ�Ă����Ԃł��B �@������낵����A�����̕����肢�������܂��B �Ƃ���w�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�܂����_���Q�ɕ����čl���Ă��������B �� �V���A���f�[�^�̎�� �@�����ł́AUSB���ǂ����Ƃ��A�͑S���Y��Ă��������B �@�Ƃ���w������́ARS232C����̐M���̎��v���O�����͍��܂ʼn���ނقǍ���܂������H(����ɓ��삵�č��܂Ŏ��p�Ŏg�p���Ă��镨�ł�) �@�ʐM����̓p�\�R���ʐM�ȂǂŎg�p���郂�f�����œK�ł����A�����ꍇ��TXD��RXD�ACTS��RTS��ڑ������_�~�[�P�[�u����RS232C�R�l�N�^�ɐڑ����邾���ł��\���܂���B �@���f���A�܂��̓_�~�[�P�[�u���Ɍ������ĉ����f�[�^�𑗐M���A�����f�[�^���A���ė��邩(�A�����f���̏ꍇ��Echo��on�ɂ���)�AAT�R�}���h���Ń��f�����R���g���[���ł��邩�̃e�X�g���s������A���̃v���O������g��ł���̂ł�����USB�ڑ���RS232C�P�[�u���ł�����ς��͖����̂ŁA�f�[�^�̂��Ƃ��i�[�Ƃ����_�ł͉������͋N����Ȃ��͂��ł��B �@�����p�\�R���łb�����RS232C�|�[�g�𐧌䂷����@���킩��Ȃ��A�Ƃ������ł���A���g���̂b����̃}�j���A���A�܂�MS-DOS�p�̂b����ł����DOS/V��BIOS�o�R�ł�RS232C�|�[�g�̎g����������������ЁAWindows�p�̂b����ł����Windos�t�@���N�V�����̉���{��ǂ�ŁARS232C�|�[�g�̐ݒ���@�A�f�[�^�̑���M�̕��@�ɂ��Ċw��ł��������B �@DOS/V�ł�Windows�ł��u�|�[�g�����ݒ�(�{�[���[�g��STOP�r�b�g�A�p���e�B��)�v�u��M�f�[�^�̗L���̃`�F�b�N�v�u�o�C�g�ǂݍ��݁A�܂��̓f�[�^��ǂݍ��݁v�̊e�t�@���N�V�������o�R����RS232C�|�[�g���g���܂��B�����̎�@�͂ǂ̂悤��OS�ł��菇�͂قړ����ł��B �� USB��RS232C�A�_�v�^�[�̋��� �@USB�[�q�𗘗p����Ƃ������́A��{�I�ɂ�Windows��ł̗��p���Ɖ��肵�Ęb��i�߂܂��B �@�����Ă��̎s�̃P�[�u���ɂ�USB�h���C�o�\�t�g����������Ă��܂��B �@�h���C�o���C���X�g�[�������USB�ڑ������P�[�u����COMxx�Ƃ���Windows�ɂ͔F������܂�����AWindows��̃\�t�g�E�F�A�����USB�ł͖���RS232C�̃|�[�gxx(xx�͔ԍ�)�Ƃ��ăA�N�Z�X���鎖�ɂȂ�܂��B �@�ł��̂ŁAWindows��̃\�t�g�E�F�A�����RS232C�P�[�u���Őڑ������@��ƑS�������ɐ���ł��܂��̂ŁARS232C����̃v���O�������g�߂���Ȃ�USB�P�[�u�����g�p���Ă��鎖��S���ӎ����鎖�Ȃ��g�p���鎖���ł��܂��B �@�������A�uUSB�o�R������f�[�^�̉������ς��v�Ƃ����悤�ȐS�z������܂���B �� �@���Ɋ�{�I�Ȏ��ł����A����͉�������Ă��邩�Ƃ͎v���܂����O�̂��߁B �@�o�b��PIC����̃f�[�^�����v���O���������ꍇ�A�܂��e�X�g�p�ɂQ��̂o�b��p�ӂ��A�wRS232C���o�[�X�P�[�u���x���g���āu�o�b�Ƃo�b��ڑ��v���A�Е��𑗐M���A�Е�����M���ɂ��ăf�[�^����M�̃e�X�g���s���Ă��܂����H �@��������ɏ������悤�Ƀ_�~�[�P�[�u��������Ăo�b�P��Ńe�X�g����̂ł��ǂ��̂ł����A�����ʐM���鑕�u�����ꍇ�͂��ꂼ��̑��u�̓�����e�X�g����ׂɁu�ʐM����̃_�~�[���u������ē���e�X�g������v�Ƃ����͍̂H�Ɛ��i��v����ۂ̊�{��@�ł�����A�����Ȃ�^�[�Q�b�g�}�V�������̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̑��u�̊�b�Z�p��g�ݗ��Ă��ŗe�ՂɃe�X�g���ł���e�X�g���E���u������Č����E�J��������̂���{�ł��B �@���Ƃ���PIC����o�b�Ƀf�[�^�𑗂��ăf�[�^�L�^���鑕�u��������Ƃ��܂��傤�B �@�u����Čq���œ������Ă݂����ǃf�[�^���L�^�ł��Ȃ��I�v�Ƃ����g���u���Ɍ�����ꂽ���A���ꂪPIC���������̂��A�o�b���������̂����ǂ�����Ē��ׂ܂����H �@RS232C�e�X�^�[���������Ă��Ȃ����PIC���琳�����M�����o�͂���Ă��Ȃ��̂��A�o�b���̃\�t�g�ɖ�肪����̂��̌�������_�̒������ł��܂����ˁB �@�o�b���̃\�t�g�����܂����삵�Ȃ��ăf�[�^�������Ă���I�悤�Ɍ����Ă��A����PIC�̃v���O�����~�X�ő��M�{�[���[�g������Ă��ăf�[�^�������N���Ă���E�E�E�Ȃ�ă~�X���悭����b�ŁA����Ȏ��͂�����o�b���̃v���O�������f�o�b�O���Ă��Ă����͈ꐶ�������܂���B �@�\�t�g�E�F�A�݂̂ł���Γ������́u�f�o�b�K�v�ŐF�X�Ɠ���ׂȂ���f�o�b�O�ł��܂����A�n�[�h�E�F�A�̓e�X�^�[��Œ��ׂ���͈͂ɂ͌��肪����܂��B �@���삳���n�[�h�E�F�A�ɂ��킹�ăe�X�g�p�̑��u�E�_�~�[��H�Ȃǂ�����ĕ��������Ő���ɓ��삷��悤�ɑg�ݗ��Ă�̂̓\�t�g�̃T�u���[�`�����ɓ����������̂Ɏ��Ă��܂��B �@�uUSB�̃P�[�u�����g��������v�Ƃ����̂͂����܂ŏ̈ꕔ�ɂ����܂���B �@�u�ł͂��̕������Ȃ��āA�ʂ̕��@(����Ȃ炽����RS232C�P�[�u��)���g�����琳��ɓ��삵�Ă���̂��H�v�̃e�X�g���s���Đ���ɓ��삷��̂ł�����̕����̕s��܂��͑Ή��~�X�ł���A�����łȂ���v���O�����������܂����Ă��Ȃ��Ȃǂ̃o�O�ł���\���̂ق����^���ƁA�������Ɍ����Ă̌��������̌��ɂ߂��ł���悤�ɊJ���菇��\�����l���Đi�߂Ă݂܂��傤�B ���Ԏ� 2008/2/7
|
|
| ���e |
�@���Ԏ��̕��A���肪�Ƃ��������܂��I �@���́A����ƒʐM���ł���悤�ɂȂ�AC�ő啪�������悤�ɂȂ��Ă��܂����B �@�������A�܂�����肪�������Ă��܂��āA������낵����A���Ԏ��̕��x�X���k�ł����A��낵�����肢���܂��B �@����́A �@�A�����M����ہA �@�E���܂ɈӐ}���Ȃ�����(�m�C�Y�������H)��������B �@�E�����I�ɕ����������� �@���ƁA �@�s���̂قƂ�ǂ���͂Ɏg���Ă���̂ł����A �@�f�W�^���̓��͂��t����̂��s���ӂȃs���A �@�A�i���O���͂ɂȂ�Ȃ����@ ���AADCON1=0x07�ȊO�ŁA����悤�ł�����m�肽���ł��B �Ƃ���w�� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�A�����M���Ɂu�Ӑ}���Ȃ������v�Ƃ����̂� �E�f�[�^��������(�o�C�g���͐�����) �E�\��ɖ�������������(�o�C�g���������Ȃ�) �̂��A�܂�������������̂��ȂǏ�������܂���̂Ō����̓���͂ł��܂��A�����Ă��͎��̂悤�Ȗ��ł��B �� �{�[���[�g�������Ă��Ȃ� �@���M�Ǝ�M�̃{�[���[�g�W�F�l���[�^�̎��g�����킸���ɂ���Ă���ꍇ�A�A�����M����Ɠr������r�b�g������Đ������f�[�^���n���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@���ꂽ�ꍇ���f�[�^�̃r�b�g��̏ɂ��STOP�r�b�g��START�r�b�g�����ł��܂��Y�����z������ēr������܂��������f�[�^�ʐM�ł���悤�ɂ��Ȃ�A���̂܂ܑ�����܂��r������f�[�^�����������Ȃ铙�̏Ǐ�����܂��B �@�����ɂ̓{�[���[�g�W�F�l���[�^�̎��g���𐳂������̂ɂ��Ă��������B �@PIC�̃N���b�N���g�����������Ȃ��ꍇ������܂��B �@�ʐM���x�͒x���Ȃ�܂����A�{�[���[�g����i����i�K���Ƃ��Ă݂ăe�X�g�����Ă݂�̂��ǂ��ł��傤�B �� ��M���v���O�����̕s� �@��M�o�b�t�@�̎����A��舵�����ɕs�(�o�O)�������Đ������f�[�^���Q�Ƃ��Ă��Ȃ��A�������f�[�^���i�[�ł��Ă��Ȃ��B �@�o�O�������Ă��������B �@�����[�g����������RS232C�����_���_���L���Ă��铙�̔z����̕s�����Ȃ���A�d������ӂ̃m�C�Y�Ńf�[�^�������鎖�͂قƂ�ǂ���܂���B �@���ōH��@�B�̃��[�^�[���Ă���Ƃ��A�����������X�p�[�N�����Ă���@�B������Ƃ��A���������S�����Ŗ�����B �@PIC�̓��̓s�����A�i���O���͂Ŏg�����^�f�W�^�����o�͂Ŏg������ݒ肷����@��ADCON1���W�X�^���g��PIC�ƁAADSEL���W�X�^���g�p����PIC������܂����AADCON1���W�X�^���g�p����Ă���悤�Ȃ̂ł��̕��@�ȊO�ɂ͂���܂���B �@�u�s���Ӂv�Ƃ����̂������Ȃ̂��킩��܂���B �E�f�W�^���|�[�g�ɂȂ�Ȃ� �E���͂��Ă��邪H/L���s���� �ق��������̃g���u�����l�����܂����A�Ƃ���w���l���ǂ̂悤�ȃg���u���ɂȂ��Ă���̂�������Ȃ��̂ł�����I�m�ȉ͂ł��܂���B �@PIC���̖��ł͖����A�ڑ����Ă����H��H/L�����肵�Ă��Ȃ��Ƃ��A�v���A�b�v/�v���_�E�����������ł��Ă��Ȃ��Ƃ�(PIC�ɂ���Ă͓����Ńv���O��������)�A�n���_�s�ǂȂ�PIC�̃v���O������������ǂ������Ă��������Ȃ���肪�����Ƃ��������l�����܂��B �@ADCON1�ȊO�ɂ����o�͕�����ݒ肷��K�v������܂����APIC�ɂ���Ă͂��̐ݒ肪���܂����f����Ȃ����������Ď��X���܂����삵�Ȃ�����(�ݒ蕔���Q�`�R�d�ɂ���Ɖ���)������܂������A�ʂ����Ďg���Ă���PIC����(�^�ԁH)�łǂ̂悤�ȕs����N�����Ă���̂��s���Ȃ̂ł���ȏ�̃A�h�o�C�X�͂ł��܂���B �@���T�C�g�ł̃A�h�o�C�X�͂���܂łƂ����Ă��������܂��B�����g�Ŋ撣���Č������P���˂��l�߂Ă����ĉ������Ă��������B�����Ɖ����ł���ł��傤�B �@�܂��ʂ̃T�C�g�A�����āIgoo�ȂǂŎ��₳��Ă݂Ă͂������ł��傤���B �@�ʂ̃T�C�g�Ŏ��₳���ۂł��A�ǂ̌���(���[�J�[���E����\�t�g�̌ŗL��)�A�ǂ�PIC(�^��)�����̏d�v�ȏ��������Ȃ��܂��₳���ԓx�ł́A�N���I�m�ȉ͂ł��Ȃ��Ƃ͎v���܂��B���̓_�͂��ꂩ�瑼�̃T�C�g�l�ɍs����܂����璍�ӂ��Ă��������B �@���T�C�g���u�ƂĂ��e�ɉv�ƕ]�����Ē����܂������͂����ւ�������̂ł����A����҂̕����ǂ��܂ŏ����J�����ĉ҂ɓ�������������悤�ɂ��邩�����₷��ۂɂ͏d�v�ȗv���ł��̂ŁA���̎���p���`�T�C�g�������ɂȂ�킩��Ǝv���܂����A�I���˂Ȃ�����ł͋t�ɂ������w�E���ꂽ�莶��ꂽ�肵�ďI���ł��B ���Ԏ� 2008/2/10
|
|
| ���e |
�@�g�ѓd�b�[�d���DC-DC�R���o�[�^�ɂ��悤�ł͂����b�ɂȂ�܂����B�uRS232C�̂t�r�a�ڑ��v�̋L����ǂ�ł̂ӂƎv�������Ƃ��������݂܂��B �@���͌��݃~�c�g���̌v����f�[�^���p�\�R���Ɏ�荞�ދ@����l�I�ɐ��삵�Ă��܂��B �@�ڑ����@�͌v���큨�}�C�R����RS-232C�o�R�Ńp�\�R���ƂȂ�܂��B�����t���[�̃^�[�~�i���\�t�g�Ŏ�M���Ă����̂ł����A���Ȃ���M�ł��Ă��܂����B�������A�E�C���h�E�Y�t���̃n�C�p�[�^�[�~�i���ɂ���ƁA���܂ɕ����������č����Ă��܂����B�����̓}�C�R���̃N���b�N�ł����B�����N���b�N���g�p���Ă����̂ł����A���x�������{�[���[�g���C���Ȃǂ̉e���ł��ꂽ�肵�Ă����悤�ł��B�O���N���b�N�i�N���X�^���j�ɂ��ĕ����������Ȃ��Ȃ�܂����B�܂��A�V���A���ʐM�̃m�C�Y�Ɋւ��Č����A�P�N���b�N���Ƀf�[�^�擾��1��ł͂Ȃ��A������i3�炢���悢�H�j�ǂݍ��ݑ����ق����̗p����ƁA�m�C�Y�ϐ����悭�Ȃ�܂��B �@���ꂩ��A�g�ѓd�b�[�d���DC-DC�R���o�[�^�ł����A�ŋߍw������TOPLAND�̉������^�C�v�i�ȑO�̂��̂͏c�����H�j�ł́A�`���[�W�|���v�^�C�v�ɕύX���ꂽ�̂��R�C��������܂���B�܂��A��T�C�Y���������x�ɂȂ肩�Ȃ肷�����肵�Ă��܂��B���[�J���ׂ��邽�߂ɕK���ł��ˁB���^���ɂȂ�A������Ƃ��Ă͂��ꂵ���ł����I �A�b�L�[ �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@PIC�̓����N���b�N�̓N���X�^�����̈��萫�͖����̂ł���قǐM�p�ł��Ȃ����Ȃ̂ł����A�V���A���ʐM�p�Ɍ��p�����ꍇ�ɂ����܂ŃY����̂͂����ւ�ł��ˁB �@���ꂭ�炢�̈���x�̃V���A���ʐM����2400bps��4800bps���炢��(�m�C�Y�I�ɂ�)���S���ĒʐM�ł�����E�Ȃ̂ł����A�܂����F����ȏ�̃{�[���[�g�Ŏg�p����Ă���Ƃ��H �@����ƁA�ǂݍ��݂̉Ƃ��̘b�̓\�t�g�E�F�A�Ńr�b�g���ǂݍ���Ŕ��f����ꍇ�̍l�����ł���ˁB �@�p�\�R������ł͂��̂悤�ȓǂݍ��ݕ��̓n�[�h�E�F�A�I�ɂ͕s�\�ł����炿����ƈႢ�܂��B(�V���A���ʐM�̃f�[�^�s���͒��ړǂݏ����ł��܂���) �@�p�\�R����ł�USART LSI(���͊e��`�b�v�Z�b�g�ɓ����ς�)�Ƃ����V���A���ʐM�@�\�����������p�`�b�v��H���n�[�h�E�F�A�ŃV���A���f�[�^�̑��M�E��M���s���܂��B���̃`�b�v�����ł�16�{�N���b�N�ɂ�铮��͂��Ă��܂����A������T���v�����O���đ����������悤�ȉ�H(�n�[�h�E�F�A)�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���ˁB �@PIC�ł��V���A���ʐM�@�\��L�������ł͓����ɓ��l��USART��H���܂܂�Ă��܂��B(FIFO�o�b�t�@�������ȂNj@�\�I�ɒႢ�ł���) �@�����ĕ��ʂ�Windows��̃v���O������Windows�̒���API��ʂ��ăV���A���ʐM���s���܂��̂ŁA���ڒʐM�r�b�g�����Ă���悤�ȏ����̂悤��PIC�̃N���b�N��Xtal�ɂ��Ĉ��艻�������當���������Ȃ��Ȃ����A�Ƃ����Ǘ��Windwos�̍\����͑z�������������ʂł��ˁB �@�n�C�p�[�^�[�~�i���͌Â��\�t�g�ł����A�܂�������USART��I/O�Œ@���Ă���Ƃ��H �����ē����Ŏ����Ă���V���A�����������^�R��FIFO�o�b�t�@�̏��������܂��o���Ă��Ȃ��Ƃ��H �������Ƀn�C�p�[�^�[�~�i�����t�A�Z���Ē��ׂ�C�ɂ��Ȃ�܂���̂ŁA���̏Ǐ�ɑ��ċ�̓I�ɂǂ��������Ȃ̂��͂��Ȃ�s�v�c�ȏǏ�ł��ˁB(�̂̃v���O�����Ȃ̂�32�r�b�gOS�̃}���`�^�X�N�ɑΉ����Ă��Ȃ��̂ŏ�Q���o��̂��ȁH) �@�n�C�p�[�^�[�~�i����Windows95���炢�܂Ŏ��X�͎g���Ă��܂������A��{�I�ɂ͓�����KTX-Win�����C���Ƃ��E�E�E ���Ԏ� 2008/2/22
|
|
| �w�����b�g�_���C�g | ||
|
�@���̂g�o�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��ˁA�����k�d�c��H�����̓��ɓ��荞��ł��܂��܂����B �@���]�ԗp�̃w�����b�g�ɕt����y�ʂȓ_�Ń��C�g���~�����ȂƎv���A����ȕ������܂����B   (�ʐ^�{�̂͊O���ւ̃����N) (�ʐ^�{�̂͊O���ւ̃����N)�E100�ϐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g�̉�H�����̂܂g���Ă��܂��B �E�{�^���d�r�A�傫�ȃX�C�b�`�ALED�̂P��O�p�Ƃ��ĉ��F�ɕύX���Ă��܂��B �E�g���l���Ȃǂő���s�v�Ȃ悤�ɂb�c�r�Ŏ����_���ɂ��܂����B �i�S�̉摜�̏㑤�R�[�h�ALED�g�U�L���b�v�t���j �E�_����Ԃ������ł������悤�ALED�̂P�����^�̒�P�x�������ɂ��Ėڂɓ���ʒu�Ɏ��t���Ă��܂��B �@�O�p��Vf=3.0V�̐FLED���g�����肪�ACDS�̓��͂�2SC1815�ŃX�C�b�`���O������G�~�b�^�d����2.4V�ƒႭ�Ȃ�A�Â��Ďg���܂���ł����B �@���邢�ꏊ�ł͏������܂����A�d�����Y�ꂻ���ł��B�w�����b�g���O�������Ɏ���OFF����Z���T�������~�������ł��B �@�d�r�̎����͑���12���Ԓ��x�ł��傤���B���^�y�ʁi27g�j�̑㏞�ł����A�{�^���d�r2�`3���~�����Ďg���Ύ������ǂ��A��LED���y�ɓ_���ł��������B �@�C�̖�������Ȃ�ǂ���邩�C�ɂȂ鏊�ł��B �났�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�w�����b�g��LED��t���Ĉ��S�����m�ۂ��悤�Ƃ��������v�ł��ˁB�Ȃ��Ȃ��H�v�������ŗǂ��ł��ˁ`�i�O_�O�j �@�g�����W�X�^��CDS���g���āu���邢���ł͏�������v�悤�ɂ��Ă���̂́A��H�S�̂̓d�����R���g���[������ƃt���b�V���[����̂����Z�b�g����Ă��܂��Ė��邭�Ȃ�ƕK���������[�h�ɂȂ��Ă��܂��܂�����ALED�̃R�������g�����W�X�^��ON/OFF���Ă���̂ł��傤���B �� �G�~�b�^�d����2.4V�H �@�����Łu�G�~�b�^�d����2.4V�ƒႭ�Ȃ�v�Ƃ����g���u�����N���Ă���悤�ł����A�g�����W�X�^��NPN�^�C�v��2SC1815���g�p���āu�G�~�b�^�t�H�����v��LED�Ɛڑ����Ă��܂��H �@�G�~�b�^�t�H�����ł̓G�~�b�^�d���́u�d���d���|�g�����W�X�^��Vb-e�d���v�ɂȂ��Ă��܂��A�d�r��3V�����|0.6V�ł�������2.4V�ɂȂ��Ă��܂��܂��B 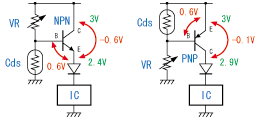 �@�g�����W�X�^��PNP�^�C�v��2SA1015�ȂǂɕύX�����R���N�^�t�H�����ڑ��ɂȂ�悤�ɂ���Ă͂������ł��傤���H
�@�g�����W�X�^��PNP�^�C�v��2SA1015�ȂǂɕύX�����R���N�^�t�H�����ڑ��ɂȂ�悤�ɂ���Ă͂������ł��傤���H�@�R���N�^�t�H�����E�E�E�Ƃ������g�����W�X�^�̕��ʂ̎g�����ł�Vc-e�ł̓d���~����0.1V���x�ł��݂܂��B �� �w�����b�g�����Ǝ���OFF �@�u����X�C�b�`�v�Ƃ����X�C�b�`���i������܂��B �@�K���X�ǂ̒��ɓd�C�ړ_�Ɓu����v�̉t�̂������Ă��āA���̌���(�����Ă��͏c�u��)�ɂ��Ă����Ɛ��₪��ɗ��܂��ēd�ɂʂ����܂��B �@�X������t���ɂȂ�Ɛ���͒Ⴂ�ق��ɗ���A�ړ_�̂����������Ɍ����Ă��܂��ƐڐG�����ɃX�C�b�`��OFF�ɂȂ�܂��B �@����X�C�b�`��d�r�ƃt���b�V���[��H�̊Ԃɓ���A�u�w�����b�g�����Ă��鎞��ON�ɂȂ�����v�ɂƂ������Ă��鎞�ɂ͓���\(�K�v�Ȏ��Ƀ{�^���X�C�b�`��������ON)�A�w�����b�g���O������u��x�t���ɂ���v���Ƃœd��OFF�A��x�d��OFF�ɂȂ����玟�ɂ�����x����Ă�(������ɂǂ����ɒu���Ă�)�t���b�V���[��H��OFF(�������[�h)�̂܂܂ł��������ē_�����Ă��܂����͂���܂���B �@���s���̐U�����ň�u����X�C�b�`��OFF�ɂȂ��Ă��t���b�V���[�����Z�b�g����Ȃ��悤�ɁA�t���b�V���[���̓d����100��F���x�̓d���R���f���T������K�v�͂���܂��B �@�����A����X�C�b�`���u����v�Ƃ����Ő��̂��镨���g�p���Ă�����ł͓��荢��ł��B �@�u�U���X�C�b�`�v��u�X�X�C�b�`�v�Ƃ������A�d�C�ړ_�Ƌ����ʂ�����������X�C�b�`�Ɏ����X�C�b�`���i�������Ă��܂����A�ړ_����������LED5�`6�̓_���d���ɂ͌����Ȃ����������ł��ˁB�����̐U���X�C�b�`�A�܂��͏��e�ʂ̐���X�C�b�`���g�p����ꍇ�̓g�����W�X�^���g�p���ăt���b�V���[��H�̓d����ON/OFF�����H���P�t���Ȃ�������܂���B �@���������Ɛ�(������)�̂悤�ȕ��Ńw�����b�g������ȕ����������Ă��鎞����ON�ɂȂ�悤�ȃX�C�b�`�����̂��肾�Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2008/2/3
|
|
| ���e |
�@�u�w�����b�g�_�Ń��C�g�v�̉�H��ύX���܂����B �EPNP��H�ɕύX�iLED�͉��̂܂܁j �E�X�X�C�b�`�ɂ�������lj� [ ��H�} ] �@�X�X�C�b�`�ɂ��w�����b�g���t���ɂ�������LED���������iIC�ւ͋����j�ҋ@��Ԃ�0.02mA�قǏ���Ă��܂����A�{�^�����삷�鎖�����g����悤�ɂȂ�܂����B �@�H���̌X�X�C�b�`�𗘗p���܂������A�X�C�b�`�̊��x�������̂œd���R���f���T�ŋt���ɂ��Ă�20�b�قǓ_���𑱂���悤�ɂ��Ă��܂��B�X�C�b�`��ON�ɂȂ鎞�͓d���R���f���T���V���[�g��ԂɂȂ�A��u�œ_�����܂��B �@�����ʼn�H���l���č�����̂͏��߂ĂȂ̂ŁA�g�����W�X�^�̑����ԈႦ����A�X�C�b�`��L���p�V�^������ꏊ�����s���낵����A�X�X�C�b�`��d���R���f���T�����t����ꏊ�������Ċ���ɋz�����Ă���A��Ղ̗����͂ƂĂ��l�Ɍ������Ȃ���ԂɂȂ��Ă܂��� �@�Ƃ肠�������삵�Ă��܂����A�����A�h�o�C�X�Ȃǂ����낵�����肢���܂��B �났�� �l
|
|
| ���Ԏ� |
�@�w�����b�g��E���ł��_�ŏ�Ԃ͕ێ����Ă���Ƃ������@�ł��ˁB �@���j�^�[�pLED������̂œd���̐�Y���Ԃł����ɔ��C�Â��܂��̂ł���ŗǂ��Ǝv���܂��B �@�͂��߂Ăł����܂ō�������\���ł��B �@���܂ɂ͌�z����v�~�X�ŕ��i�����肵�Ȃ���ł��A�������ʼn�H���l���ăe�X�g���Ă݂Ċ���������y���݂����ꂩ��������Ă����Ă��������B ���Ԏ� 2008/2/11
|
|
| �J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� | ||
|
�@���߂܂��āB �@�����y�����A�ǂ܂��Ă�����Ă܂��B �@�Ƃ���Ŏ��₪����̂ł����A�J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���̏Ⴕ�āA�`�ȉ~�`�Łi�Q�O�����w�S�O�����w�W�����@�W���P�v�j�K�i�̃X�s�[�J�[��������Ȃ��B�S���H�v������o�����̂Łi�`��͂قړ����j�A���t�������A�����ꂵ�܂��B �@�s�u�����̓{���[�������邱�Ƃʼn�������Ȃ������Ƃ��o���邪�A�J�[�i�r�̉����̓{���[��������@�\���Ȃ���������������܂��B�O���ɉ�H���ĉ�������Ȃ������Ƃ͉\�ł��傤���H�i���͏����������Ȃ��Ă����܂�Ȃ��ł��j �NjL�@�V�N�O�̃J�[�i�r�Ń��[�J�[����̕��i�̎�z���o���Ȃ��B �J�[�i�r �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����̓X�s�[�J�[�̃C���s�[�_���X���W������S���ɕς�����ׁA�A���v�̏o�͂���̓d���𑽂����������ĉߑ�ȓd��(����)�ŃX�s�[�J�[���쓮���ĉ�������N�����Ă���̂��Ǝv���܂��B �@�J�[�i�r����͘b�����܂����A�X�s�[�J�[�͕K���A���v�̎w��̃C���s�[�_���X�͈͂̕����g�p����K�v������A�I�[�f�B�I�p�̃A���v���ł́u�S���`16���v���ƃp�l���ɏ�����Ă��܂��ˁB �@���Ƃ��u�W���`16���v�Ə�����Ă���p���[�A���v�ɔ͈͊O�̂S���̃X�s�[�J�[���q�����ꍇ�A�ߓd���ŃA���v�̍ŏI�i���ߔM������ň��͏Ă����肵�܂��B�X�s�[�J�[������ꍇ������܂��B �@�J�[�i�r�̒��̏��^�A���v(�����A���v�pIC���)�̏ꍇ�͂����ɉ�ꂽ��Ă�����͂��Ȃ��Ǝv���܂����A���ۂɉ�����̂悤�ȕs����N���Ă���悤�ł��̂Ő������X�s�[�J�[��ڑ������ق����ǂ��ł��ˁB �@�W���̃X�s�[�J�[�������ĂS���̕����g�p����̂ł���A����ɂS��(1W���x)�̒�R���q���ŁA�A���v���猩���C���s�[�_���X���W���ɂ��Ă��Β�i�ʂ�̓d���𗬂����ɂȂ�A�A���v��ɂ߂邱�Ƃ͂���܂���B �@�A���X�s�[�J�[���h���C�u����d�͂͌��̐���ȏ�Ԃ̔����ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA���ʂ͏����������Ȃ�܂��B �@�Q��(1W)���x�̒�R�ƂS��(1W)�̒�R��p�ӂ��āA�܂��͂Q�����X�s�[�J�[�ƒ���ɐڑ����ĉ�������Ȃ��Ȃ���̒��x���ǂ���������܂���B����łn�j�Ȃ炠�܂艹�ʂ͕ς��܂���B �@�ʖڂȂ�S�����X�s�[�J�[�ƒ���ɐڑ����Ă݂Ă��������B �@��R�l��ς��ăe�X�g������ׂɁu��R�l��ς�����Ȃ�I�v�Ə��^�̉ϒ�R��(�{�����[��)���Ȃ��Ă͂����܂���B �@���^�̉ϒ�R��͓d�͗p�r�ɂ͎g�p�ł��Ȃ����d���p�ł�����A�X�s�[�J�[���ƒ���Ɍq���p�r�ł͎g�p�ł��܂���B �@��d�͗p�̃��I�X�^�b�g�Ȃ��e�X�g�͏o���܂�������~���܂����A��{10�`20�~���x�̏��^��R���Q�{�����l�i�Ƃ̍����傫�����܂��B ���Ԏ� 2008/2/1
��
|
|
|
����ȑO�̓����͂����灨 [2007�N�㔼�̉ߋ����O]
|
||
|
�T���₷���ړI�E��H�̃W�������ʈꗗ�͂����灨 [�W�������ʈꗗ]
�悭�g�����i�́u���̐}�v�͂����灨 [�悭�g�����i�́u���̐}�v]
|
||
|
(C) �u�C�̖����v�^Kansai-Event.com
�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������

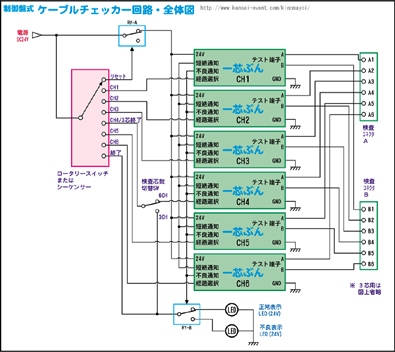

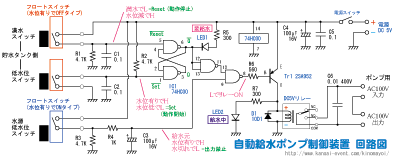
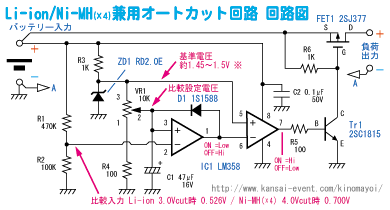
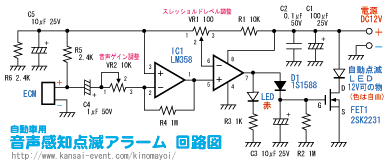
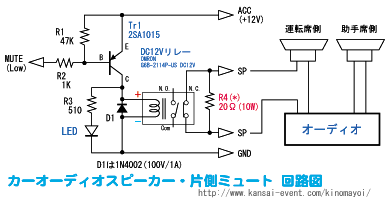
 �u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�
�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�