| ||||||||||
|
|
| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |
��H�E�f���L�E����
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���� ���̃y�[�W��2009�N�㔼�̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B
�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B
�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B
|
�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |
�y�ꗗ�z
�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�
|
��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |
|
�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
���� ���̃y�[�W��2009�N�㔼�̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
| ���]�ԗp�E�C���J�[ | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�u���̑O�͏ڂ����Ȃ��Ă��݂܂���ł����B�v �@���]�ԂɃE�C���J�[���t�������ƂƎv���̂ł����A�ǂ̂悤�ɂ�����悢�̂ł��傤���B �@�ȒP�ł����̂ł�낵�����肢���܂��B �r�c �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���]�ԂɃE�C���J�[�ƌ����܂��Ă��A�ǂ�ȃE�C���J�[�������̂�������Ȃ��̂œ���ł��ˁB �@�u�ȒP�ł����v�Ƃ������ł��̂ŁA�E�����œd�����_�ł��邾���̂��̂ł����̂ł��傤���B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�_�ŗp�̔��U��H�͂�����݂̃^�C�}�[IC555�ɂ�锭�U��H�ł��BVR1�œ_�Ŏ����߂ł��܂��B �@�X�C�b�`���E�����ȊO��OFF���I�ׂȂ��Ƃ����܂���A�u����OFF�v���ł���X�C�b�`���g�p���Ă��������B �@�d���̓o�C�N�p�ɔ����Ă���E�C���J�[���ŁA6V/6W(����d��1A)�ȉ��̂��̂��g�p���Ă��������B �@�d�����g�p����Ƃ����ɓd�r�������ĈÂ��Ȃ�A�܂����U���g�����オ���đ����_�ł��Ă��܂��悤�ɂȂ�̂ŁA�d�����g���ꍇ�͒P�j���P��̃A���J���d�r���g�p����悤�ɂ��āA�P�O�A���J�����d�r�̂悤�ȗe�ʂ̏��Ȃ����͎̂g��Ȃ��ق����ǂ��ł��傤�B �@�d���ł͂Ȃ�LED���g�p����̂ł���A�}�̂悤�ɉ��FLED���g�p���ĕK�v�Ȑ���LED��H������ĕ���ɐڑ��������̂��g�p����Ɨǂ��ł��傤�BLED���g�p����Ȃ�d�r�͒P�O�A���J�����d�r�ł����Ȃ蒷���Ԏg�p�ł���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/12/7
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 1/6 |
�@�g���T���Ɛ\���܂��B���͎��]�ԂɃE�C���J�[�����Ďg���Ă��܂��B�ŋ߂̓\�[���[�p�l���ƃn�u�_�C�i������̏[�d�����p�I�ɂȂ�A�قڊ����̈�ɓ���܂����̂ŏЉ�܂��B �@���̃z�[���y�[�W�ɉ�H�}���ڂ��Ă��܂��B�����̒i�K����̋L������ǂݐi�߂Ă����������ق����킩��₷���̂ŁA�܂��H��8�̃y�[�W�����ǂ݂��������B http://tonsan.boo.jp/tonsan/kosaku/kosaku8.html �@�ǂݐi�߂Ă��������ƍH��28�̃����_��H�}8���ŏI�łɂȂ�܂��B �g���T�� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�ǎ傳�b���ł��� �@�d�q�H��}�K�W��no5���܂��������A���]�ԓ_�Ń����v�̊�����H�����삵�܂������A���Z���T�[�����܂��s�������ウ�č�蒼���A�����܂������A�_�Ń����v�ɐڑ����Ă��_�����܂���{�Ɗ���X�y�[���ň�������Ă�����܂���n���_�t�����ԈႢ�Ȃ��悤�ł� �@���i���j���̂ł��傤�� ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d�q�H��}�K�W��No.5�́u100�~�V���b�v�����@�Â��Ȃ�Ǝ����I�ɓ_�ŊJ�n�I���]�ԗp�_�Ŏ����S���C�g�v�̐���ɂ� (1) 100�~���]�ԓ_�Ń����v��̉��� (2) ���Z���T�[��̐��� �̂Q�̍H�삪�K�v�ł��B �@���ꂼ��Ƀe�X�g���s���āA�ǂ��炪���܂������Ă��Ȃ��̂����m�F���Ă��������B (���ʂ̓s���ōׂ��ȃe�X�g�⌟�����@�͎G���ɂ͍ڂ����܂���) 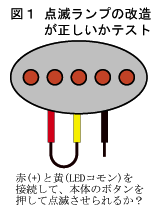 �@�}�P�̂悤�ɁA���]�ԓ_�Ń����v���������Ĉ����o�������[�h���̂�����(�v���X)����(LED A)��ڑ����܂��B
�@�}�P�̂悤�ɁA���]�ԓ_�Ń����v���������Ĉ����o�������[�h���̂�����(�v���X)����(LED A)��ڑ����܂��B�@���̎��_�ł͌��Z���T�[��͐ڑ����܂���B �@������������������������q���Ɖ����O�̏�ԂƓ����ɂȂ�܂��B �@�d�r�����Ė{�̂̃p�^�[���I���{�^���������A�������̏�ԂƓ����łV�̃p�^�[����I���ł���͂��ł��B �@�{�^���������Ă�LED���s�J�s�J�ƌ���Ȃ��ꍇ�́A�_�Ń����v��̉����Ɏ��s���Ă��܂��̂ł悭�m���߂Đ������������Ă��������B  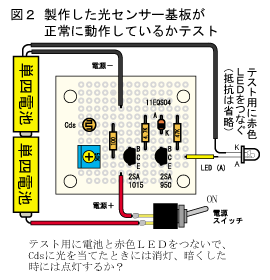 �@���Z���T�[����}�Q�̂悤�ɓd�r�Q�{(���ۂ͓d�r�{�b�N�X�ɓ���Ă�������)�ƃe�X�g�p�ɐԐFLED����Ȃ��Ńe�X�g���܂��B
�@���Z���T�[����}�Q�̂悤�ɓd�r�Q�{(���ۂ͓d�r�{�b�N�X�ɓ���Ă�������)�ƃe�X�g�p�ɐԐFLED����Ȃ��Ńe�X�g���܂��B�@�}�̒ʂ�ڑ����āA�d���X�C�b�`��ON�ɂ�����ACds�Ɍ����������Ă���Ƃ��ɂ̓e�X�g�pLED�͏����ACds����ŕ������肵�ĈÂ�������e�X�g�pLED���_�����܂��B �@���x�͔��Œ�VR���Ē��߂ł��܂��B �@���̌��ɑ��Ă̔�����������Ό��Z���T�[��̐���Ƀ~�X������܂��B�z����n���_�Â����m�F���Ă��������B �@�܂�����~�X�ŕ��i���Ă��܂��Ă���\��������܂��B �@���ƁACds�͕��i�\�ɍڂ��Ă�Ƃ��萳����80K���`200K���i���g���Ă��܂����H �@������30W�u�����̉���30K���������x�B���z�����ł͂����ƒႢ��R�l�B �@��ŕ������肵�ĈÂ������200K�`500K���ȏ�̒�R�l�ɂȂ���̂Őv���Ă��܂��B(���̏�Ԃŗ[���̉��O�̔��Â���œ_�����邭�炢�ł�) �@�s�̂�Cds�ɂ͐F�X�Ȏ�ނ�����܂����A�啝�ɂ��̐v��R�l����O��Ă��Ȃ���Ί��x���ߗpVR�ňႢ���z���ł���͂��Ȃ̂ł����B �@���]�ԓ_�Ń����v�A���Z���T�[��̗���������ł���A�Q���q���u�Â��Ȃ�Ǝ����I�ɓ_�ŊJ�n�I���]�ԗp�_�Ŏ����S���C�g�v���������܂��B ���Ԏ� 2009/12/7
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�ǎ�l���N����낵�����肢�������܂� �@����ƌ��Z���T�[����������܂����A�W�����o�[���̃n���_�t�����������Ǝv���܂��A�����Â��Ȃ�Ɠ_�Ń��C�g���_�����Ă��܂� �@���]�ԓ_�Ń��C�g�̔��FLED���Ƀ`�������W�������Ǝv���܂�������������ŁA���FLED3�@��2��t�������̂ł����A�����Z���T�[�Œ��ӂ�_�Ȃǂ����������肢�������܂� ���쏫�_ �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ʂɖ�薳���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/1/8
|
|||||||||||||||||||||||
| ���p�W���p�́A�l�����������������LED | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�����b�ɂȂ�܂��B �@�ȑO�A�Љ��Ă����uLED��d�����ɂ������_�ʼn�H�v�ɐԊO���Z���T�[�i������ȑO�Љ��Ă���NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�j��g�ݍ��݂����̂ł������������肢�ł��Ȃ��ł��傤���H �@���p�W���̌���Ŏg�p�������̂ł����A�l���ʂ��LED����b�قǂ������_�����ď�����Ƃ����Z���T�[���l���Ă��܂��B �@�ł���Έȉ��̍��ڂ����荞��ŋ����Ă��������Ȃ��ł��傤���B �E�g�p����LED�͔��FLED����B �E������H�̂��̂��Q�O�����ׂĎg�p����̂ŁA�d���͑S�Ĉꊇ���ĉƒ�p 100V������B �@���Z�������A���k�ł�������낵�����肢���܂��B (������]) �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�l���ʂ��LED������v�Ƃ����Ӑ}�͂킩��܂����A���L�̏����ɂ��Ă͂ǂ����l���Ȃ̂ł��傤���H �@�W�����̑O�ɃZ���T�[��LED�̑��u��u���Ƃ��āA�l�͕K����u�Œʂ�߂�����̂ł͂Ȃ��A�l�ɂ���Ă͋��������������ɗ�������A�l�ɂ���Ă͗����~�܂��Ă����ƓW�������ӏ܂���̂ł͂���܂��H �@LED�����_�����ď�������Ԃɗ�������̂ł�������̂ł����A���ʂ�LED���P�b���琔�b���x�_�����ď���������ɂ����u�̑O�ɗ����Ă��āA�l���Z���T�[�͐M����l�̋����ԂŒf���I�ɏo�͂��Â��Ă���Ǝv���̂ł����A���̍ۂ͂ǂ����ꂽ���̂ł��傤���H (A) ������Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B�l�������~�܂��Ă���Ԃ�(�Z���T�[�������Ɣ�������̂�)���x�ł�LED���s�J�s�J�ƌ����Ă��悢�B (B) ��x��������A�l����������(�ݒ�b���Ԑl�����Ȃ����m��H)�܂ł͎��̔����͂����Ȃ��B��l�ɂ��������B (C) ��x��������A���b�`���\�b�̓^�C�}�[�Ŕ��������Ȃ�����B�����^�C�}�[��ɂȂ������_�ł܂������l���O�ɗ����Ă��Ă��^�C�}�[��Ȃ̂�LED�͂܂�������^�C�}�[���ēx���삷��B �@�ق��ɂ��������̃p�^�[���͍l�����܂����A�ǂ̂悤�ɂ��ꂽ���̂����Ɏw�肪�������(A)�̂悤�ɐl��������艽�x���s�J�s�J�ƌ���A���p�W���Ȃ̂ɓW�������LED�̂ق����C�ɂȂ��Ă��܂��A���p��i�̍�҂̕��ɑ�ώ����LED���u�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������ł����H ���Ԏ� 2009/12/7
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@�������s�\���ł����f�����������܂����B �@�⑫�����Ă��������� �@���p��i�{�́i���̕��j��LED��20�d���݁A����ɘA������20�̊e�Z���T�[�����͍�i�̑���̐F�X�ȏ��ɐݒu���܂��B �@�ӏ҂���i�ɋ߂Â��ALED���_�����A����̎���������Ɏ����̓�����LED�̓_�����A�����Ă���̂��C�Â�����d�g�݂��ق����Ǝv���Ă��܂��B �@�Ȃ̂Ŋӏ҂��~�܂��Ă���ꍇ�́A����ɔ�������Z���T�[��LED�͓_�����J��Ԃ��Ƃ�����Ԃō\���܂���B �@�]���Ē�Ă��Ă����������ẮiA)�ł�낵�����Ǝv���܂��B �@��ϒ��J�Ɍ�A���Ă��Ă����������肪�Ƃ��������܂��B �@������낵�����肢���܂��B ������] �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�Ȃ�قǁA���p�i�̒��ɑg�ݍ���ŁA�l���߂Â�����(����ԉ��x��)�s�J�s�J�ƌ��鑕�u�ł�낵���킯�ł��ˁB ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �l���Z���T�[��M�� �@Panasonic�d�H��NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[���g�p���Đl���O�ɂ��邩�ǂ����ʂ��܂��B �@���[�V�����Z���T�[�́u�l�̓����v�ɉ����čׂ��ȃp���X�o�͂ł��̂ł��̂܂�LED�̓_�ʼn�H�����M���ɂ͕s�K�ł��B �@�ł��̂Ń����V���b�g�^�C�}�[��H�Ől�����m���Ă�����̎��Ԃ͏o�͐M�����o����H������ă��[�V�����Z���T�[�̔������Ԃ��������܂��B �@�^�C�}�[�Ƃ͌����Ă��^�C�}�[IC�Ȃǂ��g���̂ł͂Ȃ��A�R���f���T�̏[���d���Ԃ𗘗p�����ȈՌ^�ł��B�^�C�}�[�������Ԃ���2�b�`10�b��VR1�Œ��߂ł��܂��B �@LED1�̓e�X�g�p�Ń��[�V�����Z���T�[���������Ă���ԍׂ����s�J�s�J�ƌ���܂��BLED2�̓e�X�g�p�Ń^�C�}�[�������ɓ_���������܂��B �@�����̓e�X�g�p�Ȃ̂ŕ\�ɏo�����A�����܂Ŋ��ŃZ���T�[���������Ă�����̂��m�F���邽�߂ł��B�s�v�Ȃ�LED1��R2�͂Ƃ����K�v�͂���܂���B(������Ȃǂő�ʐ��Y����ꍇ�ȂǁA�̏�ł����Ȃ�����͐���ɓ����Ɗm�F�ł��Ă���ꍇ�Ȃ�) �� �_�Ő��䕔 �@���[�V�����Z���T�[�̉������ԐM���Œ��ڃ^�C�}�[IC 555�̔��U�𐧌�(ON/OFF)���Ă��ǂ��̂ł����A���̂܂܂ł���LED�̓_���T�C�N�����Ƀ^�C�}�[���Ԃ��ꂽ�ꍇ��LED���Z���Ԃŏ������Ă��܂��ꍇ������܂��B �@�������ł��u�^�C�}�[���ꂽ����LED�͂��̓r�[�ɏ����Ă�����܂��v�Ƃ����l�������ł��܂����A�ǂ������W�b�NIC���g�p���Ă��ăQ�[�g���]��̂�(�]����̂�p�ӂ��Ă���̂�)�A�f�W�^����H�炵���u�^�C�}�[����Ă��ALED���_�����͂��̓_���T�C�N�����I���܂ł͓r���ŏ������Ȃ��v�Ƃ����A������ƍ������̂����_�ŕ����Ɍ�����悤��H�����܂��B �@��̓I�ɂ̓^�C�}�[�ɂ��ON�M���ƁALED�_�����������^�C�}�[IC 555�̏o�͐M����OR���邾���ł��B����Ń^�C�}�[�M���ɂ��ʏ�̓_�łƁA�^�C�}�[����Ă�LED ON���́u���ȕێ��v����悤�ɂȂ�܂��B �� LED�_�ʼn�H �@�^�C�}�[IC 555�ɂ�锭�U��H�ŁA�����͈��̔���/��������2�`10�b�̎��Ԃ�������悤VR2�Œ��߂ł��܂��B �@555�̏o�͂͒�R�ƃR���f���T�ɂ��ϕ���H�ł������d���ω�����悤�v���Ă��܂��B���̂������d���𗘗p���ăg�����W�X�^2SC1815�ŖړI�̔��FLED���u�ڂ�`�v���Ɠ_��������������������肵�܂��B �@����̉�H�ł́u�ڂ�`�v���ƕω����鎞�Ԃ͌Œ�Ƃ��Ă��܂��B���FLED����P�b���x�ł������_���E����������l�ɂȂ��Ă��܂��B �� �d�� �@���̉�H��DC 5V�œ��삵�܂��B �@����d���͖�30mA���x�A20����Ă��S����600mA���炢�Ȃ̂ŁA5V/1A��AC�A�_�v�^�[���20���炢�͋쓮�ł��܂��B �@���d�r�S�{��6V�ł����삵�܂����A����ȏ�̓d���͐�ɂ����Ȃ��ł��������BNaPiOn���[�V�����Z���T�[�����܂��B �@�t�ɖ�3V���x�܂œd�����������Ă��Z���T�[�͓��삵�܂����A�^�C�}�[���Ԃ┭�U�����Ȃǂ��ς��܂��̂ł��܂芣�d�r�ł̎g�p�͂����߂ł��܂���B �@����̔��p�i�ւ̑g�ݍ��ݗp�r�łȂ��A�������̗p�r�ł��̉�H���g�p�����ꍇ�͂Ȃ�ׂ����肵��DC 5V�Ŏg�p����邩�A�j�b�P�����f�[�d�r���S�{�Œ����Ԃ�4.8V�O��̈��d�����ێ�����悤�ȓd���Ŏg�p���Ă��������B �� ���߂Ƃ� �@�����^�C�}�[���ԁALED�̓_�Ŏ����͂��ꂼ�ꔼ�Œ��R�Œ��߂ł��܂����A20�̊�ł��ꂼ�꒲�߂���ƌ��\�����ւ�ł��B �@�����S���̊����������������̂ł���A�܂��͈��������Ĕ��Œ��R�߂��A�����Ƃ��낪���܂����甼�Œ��R�����O���ăe�X�^�[�ł��̒�R�l���v��A���肳�ꂽ��R�l�ɋ߂��l�̌Œ��R���đS�Ă̊�œ�����R�l�̌Œ��R������Β��߂̕K�v�������Ȃ萻�삪�y�ɂȂ�܂��B �@���p�i�Ƃ������Ȃ̂ŁA20���ꂼ��œ_�Ŏ����Ȃǂ��Ⴄ�悤�ɂ����ق����ʔ������̂ɂȂ邩������܂���B �@���̏ꍇ�͉�H�}�ʂ蔼�Œ��R���g�������̂�20����āA�X�ɔ����Ƀ^�C�~���O�̈Ⴄ���̂�����đg�ݍ���l�̐ڋ߂ɑ��锽���Ƀo���G�[�V�����������āA���Ă��Ă�苻����������悤�ɂȂ邩������܂���ˁB ���Ԏ� 2009/12/10
|
|||||||||||||||||||||||
| �g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�����b�ɂȂ��Ă���܂��B���Z�����Ƃ��닰�k�ł������͓Y���X�������肢�������܂��B �@��̊��Ƀg�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~���ł��鑕�u�������������̂ł����ǂ̗l�ȉ�H�A���i���w��������X�����ł��傤���H �@������H�̓��͓d����11V������ϒ�R��15V�ɂ��������ł��B �@�~����H��19V���͓d�����ϒ�R��15V���������ł��B �@�d���͗����Ƃ�1A������Ɨǂ��ł��B �@���̂悤�ȑ��u����������̂ł��傤���H �@���z��������s���Ă��܂��B �@�Ǘ��l�l�̂����Ԃ̎���Ƃ��Ɍ��\�ł��̂ł������X�������肢�������܂��B ikikko �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�P��{�I�ȂƂ���Ŏ��₪����܂��B �@�X�C�b�`�Ő�ւ���Ƃ������ł����A (A) �����E�~���̓d�q��H�͂P�ŁA���̉�H���@�\���X�C�b�`�ŏ����p�ƍ~���p�ɐ�ւ���B (B) 11V��15V������H����A19V��15V�~����H����A���v�Q�̉�H���ʁX�ɓ����Ă��āA�P���ɃX�C�b�`�łǂ��炩��ւ���B �̂ǂ��������]�Ȃ̂ł��傤���H �@(B)�̂ق��Ȃ������͍l�����ɒN�ł��e�����E�~����H�̉�H�}������������܂���ˁB �@(A)�̂悤�ȉ�H���X�C�b�`�Ő�ւ��邱�Ƃ͂ł��܂����A��ւ��郖�������܂�ɑ����ĂƂĂ��g�O���X�C�b�`��Ő�ւ����ł���悤�ȑ㕨�ł͂���܂���B �@�����p�̉�H�ƍ~���p�̉�H�͎g�p���镔�i�͎��Ă��܂����A�z���E�ڑ��͑S���Ⴂ�܂����瑽���̕��i���q���ς��邱�ƂɂȂ�A�ʁX�ɂQ��H������ق�������ۂLj��S�m���Ȃ��̂ɂȂ�܂��B �@�܂��A11V�̓��͂Ƃ������̂�19V�̓��͂Ƃ������͕̂ʁX�ł����H �@����Ƃ���{�̓��͐���11V�̎���19V�̎�������Ƃ����Ӗ��ł��傤���B �@��̓I�Ȏg�p�Ⴊ�킩��܂���̂Ŏ���җl�̂����҂ɂ�����悤�ȉ��ł��܂���B �@���łǂ̂悤�Ȏg�p�`�Ԃ�z�肵�Ă���̂��A�܂�(A)��(B)�Ȃǂ̏����~����H�̗p�ӂ̎d���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����]�ɂȂ��Ă���̂������������������B ���Ԏ� 2009/12/7
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Z�����Ƃ��남���l�Ō�����܂��B �@���̎�������Ă���~����H�͎O�[�q���M�����^�[�ō�鎖���o���܂����B�M�d�Ȏ��Ԃ��₵�Ē������̂ɐ\���������܂���B �@����āA������H�݂̂���낤�Ǝv���܂��B �@�p�\�R���̓d��������܂��Ă�����Ԃ̓d����11V�`14.4V�܂ŕϓ�����̂ɍ��킹���d���ɂ������Ăǂ����Ă������d���ƁA�~���d���̂Q���ق����Ă��̗l�Ȉȗ������Ă��܂��܂����B �@������H�̍����̓l�b�g�Ŗڂɂ���̂ł����ǂ��̃V���b�v�̂ǂ̃p�[�c��������悢�̂�������܂��� �@�Ǘ��l�l�Q�l�ɂȂ��H�}�A���i�������Ē����܂���ł��傤���H �@�{���ɂ����̂Ƃ��날�肪�Ƃ�������܂��B���������X�������肢�\���グ�܂��B ikikko �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u���i�������Ē����܂���ł��傤���H�v�Ƃ悭������܂����A�ߋ��ɂ������Ă��܂��悤�Ɏ��͂��������ړI�ŏ����p�Ɏg����ǂ����i�Ƃ������������Ă��܂���B �@���ɃR�C�����d�v�Łu�ǂ��̉��Ƃ����R�C�����g�����������d���Ȃ炱�����������ł����ւ�ǂ��d�����ł��܂��v�Ƃ������Ɏ���������Ă��������邱�Ƃ͈�ł��܂���B �@DC/DC�R���o�[�^�ɂ�鏸���d���E�~���d���������ꍇ�ɂ͂����g�Ŏ���������āA���ǂ����i��T���Ē����K�v������܂��B �@�ǂ��ł����萫�̗ǂ�DC/DC�R���o�[�^�pIC�Ƃ��ẮA���ɉ��x�����グ�Ă���MC34063(A)������܂��B �@���ɂ������̓d���pIC�͂���܂����A�Â����炠��ǂ��̕��i�X�ł��w���ł���͕̂֗��ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�f�[�^�V�[�g�ɂ͏�}�̂悤�ȉ�H�}���f�ڂ���Ă��܂��B �@MC34063(A)�̓����X�C�b�`���O�g�����W�X�^�̗e�ʂ�1.5A�ł�����A�R�C���̌����Ȃǂ��l�����500mA�O��̏o�͓d���܂łȂ�IC������ŏ�����H���g�߂܂��B �@500mA�ȏ��̓d������낤�Ƃ����(����̂���]�̂悤��1A�Ƃ�)�A�����̃g�����W�X�^�ł͑���Ȃ��̂Ńf�[�^�V�[�g���d���u�[�X�g��H�̂ق����g�p����K�v������܂��B �@�O���X�C�b�`���O�p�̃g�����W�X�^�́A�K�v�ȏo�͓d���̂U�{�ȏ�̓d���𗬂���p���[�g�����W�X�^��I������K�v������܂��B �@�R�C���͏o�͓d���̂R�{�̓d���e�ʂ́A�d�͗p�̃g���C�_���R�C���ȂǁB�d�����o�p��R(Rsc)��0.33���s�[�N�d��(�o�͓d���~�R�{)���v�Z���A���M���܂��̂�0.3�~�s�[�N�d���v�̂Q�{�ȏ�̓d�͂̒�R��I�����܂��B �@���U���g����Ct�̗e�ʂŌ��߂܂����A���͂������H�}��1500pF����ɐ������Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���g���ɂȂ�R�C���E�d���l�Ȃǂɂ���ăR�C���̖O�a���Ԃ��ς��̂ŁA�O�a���Ԃɂ���ĕK�v�ȏ[�d���Ԃ�쓮���g�����ς��܂��B �@�܂�͂��g���ɂȂ�R�C���ɂ���Ă��̂�����̃R���f���T�e�ʂ��v�Z���Đ������l���o���Ē������A�J�b�g�A���h�g���C�ŗe�ʂ�ς��Ă݂čł��������ǂ��l��I�ԂȂǂ̎������K�v�ł��B �@���Ȃ݂ɁAMC34063(A)�̏ꍇ�͊e���i�̒萔�����߂�̂Ɏ��̂悤�Ȏ����f�[�^�V�[�g�ɋL����Ă��܂��B (�����I�ŐV�ł̃f�[�^�V�[�g�ɂ́A�����E�~���E���]�d��������C�A�E�g�ʐ^�����i�̍ڂ�����Ԃł̎ʐ^�܂ōڂ��Ă��܂��ˁB���S�҂ɂ����₷���Ȃ�܂������H) 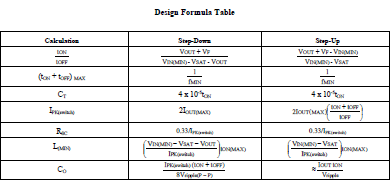 �@�f�[�^�V�[�g��̉�H�}�ł̓R�C���̃C���_�N�^���X��170��H�Ƃ����l��������Ă��܂����A���ۂɕ��i�X�ɍs������170��H�Ŏ����̊�]����d���e�ʂ̃R�C���������Ă��Ȃ��Ȃ�Ď����悭����Ǝv���܂��B �@����Ȏ��ɂ͕ʂ̃C���_�N�^���X�̃R�C�����w�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂����A���̃R�C���ɑ��ĉʂ����Č��̉�H�}�̒ʂ�̃R���f���T�e�ʁE��R�l�ŗǂ����ǂ����͍ēx�v�Z�����������A���ۂɑg�ݗ��Ăēd���E�d���𑪂��Č������v�Z���Ă݂���A�I�V���X�R�[�v�ŃR�C���܂��̔g�`���ϑ����ĉʂ����ēK������Ԃœ����Ă���̂����m�F������ƁA���n�����K�v�ł��ˁB �@�l�b�g��ȂǂŎ��ۂɑg�ݗ��Ă�ꂽ���̃��|�[�g�Ȃǂ������ɂȂ�ꂽ�Ǝv���܂����ADC/DC�R���o�[�^�̐v�Ɛ���Ƃ͂����������n�����̐ςݏd�˂ɂȂ�܂��B �@���ɁA�傫�ȓd������낤�Ƃ���ƃX�C�b�`���O�g�����W�X�^���ǂ����邩��AFET�������FET�̃Q�[�g�e��(�R���f���T�݂����ɂȂ�)�̂��߂ɍ����g�ł͐��퓮�삵�Ȃ��̂Ńg�����W�X�^��lj�����GND�Ɉ��������H��lj����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ��E�E�E�B �@�g�p���镔�i�ɂ���Ă��ꂼ��ׂ��ȃm�E�n�E������܂��̂ŁA�ȒP�ɉ�H�}�ƕ��i�̈ꗗ���ڂ���悤�ȋL���ɂ͂��ǂ蒅���܂���B ���@�@�@�@���@�@�@�@��
�@���Ƃ��A�K�����R�C���E�g�����W�X�^�Ȃǂ������Ă��āA������Ŏ��ۂ̉�H��g�ݗ��ĂĎ������ł���Ή�H�}�ɑS�Ă̒l�����Ă������ł��܂����A�c�O�Ȃ��玄�͂����������i�������Ă��Ȃ��̂ōׂ��Ȑ��l�╔�i�̌^�ԁA�ǂ��ōw������悢�̂��Ȃǂ��������ł��Ȃ����Ƃ����������������B �@���ꂩ�����A�����g�ɂƂ��Ă������������d����~���d����K�v�Ƃ��邱�Ƃ���������(���܂ł͈�x������܂���)�A����p�̕��i���l�b�g�ł̎���ɂ���������ׂ����ɔ����Ď���������X�g�b�N����\��͂���܂���̂ŁA����̂悤�ȃX�C�b�`���O�d���ɂ��Ă̂�����ɂ͏����I�ɂ��ׂ��ȕ��i�̑I����H�}�̐��l�ɂ��Ă͂��������������˂܂��B �@���X�ɍs���ƁADC/DC�R���o�[�^�̌�����������e��IC���g�p������H����E�����Ȃǐ��I�ȕ���܂Ő����������Ђ������Ă��܂��B �@DC/DC�R���o�[�^�����ł̓d����H�̍쐬�͂��̂悤�Ȗ{����������Ă��܂��قǁA�������悤�Ƃ���Ə��ʂ������Ȃ镪��Ȃ̂ŁA�����̂悤�Ȑ��S�����ł���������R�[�i�[�ł͐���������܂���B �@DC/DC�R���o�[�^�ŏ����E�~���d����H��g�ݗ��Ă悤�Ƃ������́A�����������ЂȂǂ��Q�l�ɂ���āA�������ł悢���i��T���Ă悢�d������������ł��ˁB ���Ԏ� 2009/12/9
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 12/10 |
�@�Ǘ��l�l�B�����l�ł��B �@�Ȃ�قǁA�ȒP�ɍ쐻�ł�����̂łȂ�����������܂����B �@��l���̓g���C�A���h�G���[�Ŋ����ւ��ǂ蒅���ꂽ�̂ł��ˁI �@�M�d�Ȏ��Ԃ��₵�Ē����܂��Ƃɂ��肪�Ƃ�������܂����B �@������X�������肢�\���グ�܂��B ikikko �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 12/17 |
�@�������炵�܂��B �@�Ԃ̃o�b�e���̓d���Ńp�\�R���삳�������A�Ƃ����̂���Ԃ̖ړI�ł��ˁB �@���������肽���Ďd���Ȃ��̂ł�(����DC-AC�C���o�[�^��AC�A�_�v�^�g�p)���ADC-DC�R���o�[�^�̐v�E���삪�l�b�N�Œf�O���Ă܂��B (�����g�p���Ă���p�\�R����19V����Ȃ̂ŏ�����H��i�ōςނ̂ł����E�E�E) �@���������p�\�R���̂悤�ɐ����ȓd����v������@��ɏ����^�~����ؑւ���K�v�̂���d���́A�둀�삵�����̔�Q���|���Ď��͎g�������Ƃ͎v���܂���B �@����̂悤��11V�`19V�̓��͓d���͈͂���15V�o�͂����A�Ƃ����ꍇ�̂悤�ɁA�d���d���̕ϓ��͈͂Əo�͓d�����߂��ꍇ�ł��A�Z�p�I�ɂ́ADC-DC��i�\���Ő؊��s�v�ȓd��������\�Ȃ͂��ł����A�������ɐv�o�����Ȃ��Ǝ��ۂɂ͍��̂͌��������B�������`�������W�������ۑ�̈�ł����A�����B jr7cwk �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@���߂ē��e�����Ē����܂��B �@�Ԃ̃z�[���i�S�`�~�Q�j���v�b�V���X�C�b�`���g���Q��u�v�b�v�b�v�Ɩ炷��H����낤�Ǝv���Ă��܂��B �@�uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�v���Q�l�ɍl���Ă݂��̂ł����A�m���̏��Ȃ����ɂ͉��p���ł��܂���B �@���Z��������ϋ��k�ł����������X�������肢�\���グ�܂��B �������� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�v�����ł͑��������ł��B �@�Ȃ��Ȃ�AON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�́u�C���^�[�o���^�C�}�[�v�ł���A�Ԍ���������X�ƌJ��Ԃ��^�C�}��H������ł��B �@�u�X�C�b�`�������Ă���ԁA�������v�b�v�b�v�b�v�b�c�Ɩ�Â���z�[���v����肽���̂Ȃ�K���Ă��܂����A����̗p�r�ɂ͕s�����ł��B �@�������A�����P��555���g���āu��莞�ԓ��삷�������V���b�g�^�C�}�[�v������āA���̈�莞�ԓ��Ɂu�v�b�v�b�v�b�v�b�c�v�Ɩ�Â����H�����A��莞�Ԃ̃^�C�}�[�����傤�ǁu�v�b�v�b�v�̂Q��鎞�ԂŐ��悤�ɒ��߂��Ă��ΖړI��B���ł��Ȃ����Ƃ͖����ł����A�����̂��ɂ����Ȃǂł��܂�ǂ��^�C�}�[��H�Ƃ͌����܂���B�����t�ɁA�v�b�v�b�v�b�ƂR��ɂ������Ƃ��̏ꍇ�̓^�C�}�[���Ԃ����������ŗǂ��̂ŕ֗��Ƃ����Ε֗��ł��B �@����́u�v�b�v�b�ƂQ��炷�v�Ƃ����ړI�ɂ͐�p�̉�H��������ق����G���K���g�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@������74HC221���g�p���������V���b�g�^�C�}�[��H���Q�g���܂��B�� ���ځE�j��ڂ�炷���߂̎��ԍ��^�C�}�[ �@74HC221�̒��̂P�ڂ̃^�C�}�[�́u���ڂ�炷���߂̐M�����v�Ƃ��Ďg�p�������A�u�j��ڂ�炷���߂̎��ԍ��^�C�}�[�v�Ƃ��Ďg�p���܂��B �@�{�^���������ƃ^�C�}�[�����삵�͂��߁A�P�ڂ̃^�C�}�[��H�̏o��Q��L��H�ƕω����A���]�o��~Q��H��L�ƕω����܂��B �@���̍ۂ�Q��L��H�ɕω�����M����������ĕω������u�Ԃ���H�ɂȂ�悤�p���X���������̂��u���ڂ�炷���߂̃g���K�[�p���X�v�ɂ��܂��B���̃g���K�[�p���X��D2��ʂ���74HC221�̂Q�ڂ̃^�C�}�[��H���X�^�[�g�����܂��B �@�ݒ莞�Ԃ��o�ƂP�ڂ̃^�C�}�[�͓�����I�����A�o��Q��H��L�ɖ߂�A���]�o��~Q��L��H�ɖ߂�܂��B �@���̍ۂ�~Q��L��H�ɕω�����M����������ĕω������u�Ԃ���H�ɂȂ�悤�p���X���������̂��u�j��ڂ�炷���߂̃g���K�[�p���X�v�ɂ��܂��B���̃g���K�[�p���X��D1��ʂ���74HC221�̂Q�ڂ̃^�C�}�[��H����ڂ̃X�^�[�g�����܂��B �@���ڂ̃v�b���Ɠ��ڂ̃v�b���̊Ԋu�����̂P�ڂ̃^�C�}�[�Ŏ��R�ɐݒ�ł��A�Ԋu��VR1�Ŗ�0�`1�b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B(0.7�b�O��ɒ��߂���Ƃ悢�ł��傤) �@���̃^�C�}�[�̓���m�F��LED1�Ŋm�F�ł��܂��B �� �z�[�������ۂɖ炷���߂̃^�C�}�[ �@74HC221�̒��̂Q�ڂ̃^�C�}�[�́u�z�[�������ۂɖ炷���߂̃^�C�}�[�v�Ƃ��Ďg�p���܂��B �@���ځE���ڂ̋N���M���p���X�����邽�тɁA�ݒ莞�Ԃ̊Ԃ����o�͂]�����ău�U�[��炵�܂��B �@�u�U�[�����Ԃ�VR2�Ŗ�0�`1�b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B(0.3�b�O��ɒ��߂���Ƃ悢�ł��傤) �@���̃^�C�}�[�̓���m�F��LED2�Ŋm�F�ł��܂��B �� �z�[���h���C�o �@�z�[����炷�X�C�b�`�̖�����MOS�p���[FET 2SK2232�ōs���܂��B �@�ő��i��60V/25A�Ȃ̂ŁA�ꎞ�I�ɖ炷�����̃z�[���p�̃X�C�b�`���O�p�r�ł�10A���x�̃z�[���܂łȂ���M�ȂǂȂ��Ő���ł��܂��B (��d���ŘA���g�p����悤�ȗp�r�ł͕��M�K�v�ł�) �� �p���[�I�����Z�b�g��H �@�d������ꂽ���Ƀ^�C�}�[����쓮���ăv�b�Ɩ��Ă��܂�Ȃ��悤�A�p���[�I�����Z�b�g��H�����Ă��܂��B �@�ł��̂ł��̉�H�̓d����Acc�ȂǃL�[���Ă��鎞����ON�ɂȂ�d���������Ă����v�ł��B �� �d����H �@���̉�H��5V�œ��삵�܂��B �@�Ԃ�12V����͎O�[�q���M�����[�^��5V�ɍ~�����Ďg�p���܂��B �@��H�̓d����5V�ł����AFET�Ő��䂷��z�[����12V�̎Ԃ̉�H�̂܂ܐڑ��ł��܂��B �@��H�}���̃s���N�̘g�Ɉ͂܂ꂽ�ڑ���̂悤�ɁA�]�����炠��n���h���̃z�[���X�C�b�`(�����ƃA�[�X�ɗ�����)�Ƃ��̉�H�̏o�͂����ɂ��ăz�[���Ɍq���ł����ƁA�n���h���̃z�[���X�C�b�`�ł͏]���ʂ�ɉ����Ă���Ԃ����z�[������A���̉�H��p�̃X�C�b�`(�ǂ����ʂɂ���)�����������ɂ̓v�b�v�b�ƂQ����悤�ɂȂ�܂��B �@�ŏ��ɏ����܂����悤�ɁA�C���^�[�o���^�C�}�[�ƃ����V���b�g�^�C�}�[�̑g�ݍ��킹�Łu��莞�Ԃ̊ԃv�b�v�b�v�b�v�b�Ɩ�v�z�[�������H���ʔ�����������܂���B������R�ɑI�ׂ�͍̂���̖ړI����O��܂����p�r�Ƃ��Ă͖ʔ������ł��ˁB �@����́u�Q��炷�v�Ƃ�������]�ł����̂ŁA���̗p�r�ł��u�{�^������������ŁA���Ԃ������ĂQ��쓮���鑕�u�v�Ƃ��ĐF�X���p���ł���悤�A74HC221���g�p�����Q��^�C�}�[�̉�H��I�����܂����B ���Ԏ� 2009/12/6
|
|||||||||||||||||||||||
| LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�n�߂܂��āB���߂Ẵl�b�g���k�ł��B��肽�����̂������ĕ����炸�����Ă��ĔY��ł��ăl�b�g�Ō������Č��܂�����A�M�a�̃z�[���y�[�W�ɂ��ǂ�t�����e���������Ă��炢�A���X�̎�������Ċ�������Ƌ��Ɍh�ӂ�\���܂��B���̑��k���e�̏d�������������Ƃł����k�ł��B�������߂����ł�����\����܂���B�ǂ��炩�ƌ����Ύ��̓A�i���O�h�ł��B �@�O�u�������Ȃ�܂������A����₳���Ē��������v���܂��B �@�k�d�c�̓_�ʼn�H�ł悢�̂ł����A�_�Ŏ��ԊԊu�������I�i���X�Ɂj�������ŏI�I�ɂ͘A���_���ɂ����H���������Ă��܂����A�ǂ̂悤�ɂ�����킩��܂���B�A���_���܂ł̎��Ԃ͂P�O�b����U�O�b�Ԃ��u�q�Œ����ł��āA�_�ŊԊu�͍ŏ��Q�b���x���珙�X�ɑ������ŏI�I�ɂ͘A���_�����������Ƃ̉�H�ł��B��̓I�ɂ͎��Ԃ������Ă���Ƃ̐M���Ƃ��Ďg�p�������ړI�ł��B�g�����W�X�^�̔����}���`�o�C�u���[�^���쐬���F�X�����Ă݂܂������A���̋Z�ʂł͂��߂ł����B���x�̓^�C�}�[IC�T�T�T�ŁA�����Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂����ȂɂԂ��b���Ȃ��̂ňʼn_�ɂ���Ă݂�ɂȂ��Ă��܂������ł��B �@�����A���m�b��q�؏o����K���ł��B mibayashiakira �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[��A555�ł��ł��Ȃ����Ƃ͖�����������܂��A555��łł����H�ł͖����Ǝv���܂��̂ŁA�ʂ̕��@�ōl���܂��傤�B �@�A�i���O�h�Ƃ������ł����A�Ȃ�ׂ��g��IC�̐��͏��Ȃ��������̂ŁA�����OP�A���vIC LM324����g�p���܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� LED�̔��U�����p�̉ώ��g���M�����������H �@�u���ԂƋ���LED�̓_�Ŏ����𑁂��������v�Ƃ�������]��������ɂ́w�u�b�n�x�Ƃ�����H���g�p���܂��B �@�u�b�n��Voltage Controlled Oscillator�̗��œ��{��ł́u�d�����䔭�U��H�v�ƂȂ�܂��B �@����d���̍���ɂ��킹�Ĕ��U������g�����ς��H�ł��B �@���ł��l�X�ȑ��u�ʼn��p����Ă��܂����A�̓d�q�y��́u�V���Z�T�C�U�[�v�����̐��ɂ͂��߂Ĕ������ꂽ���̉����̌��ɂȂ��Ă����H�ł�����܂��B�V���Z�T�C�U�[(�y��)�ł͐l�Ԃ̎��ɕ������鉹���Ŕ��U�����鑕�u���u�b�n�A���ɕω��������炷���ʗp�̒���g���U���u���k�e�n(Low Frequency Oscillator)�ƌĂ�ł��܂����B����쐬�����H��LED�̓_�ł��炢�̒Ⴂ���g���ł������k�e�n�ɂ�����܂��B �@�u�b�n�̓I�y�A���v�Q�ō����H�ł��̂ŁA����̑��u�̑��̕������I�y�A���v�ō��K�v������̂ŃI�y�A���v�S��H�����LM324���g�p������j(�c��̂Q��H�ŕK�v�ȉ�H������悤)�ʼn�H��v���܂��B �� �^�C�}�[���Ԕ�����H �@�^�C�}�[�̓R���f���T�ɏ[�d���鎞�ԂŌ��肷��悤�ɂ��܂��B �@���̓d���̓��Z�b�g����0V�ŁAVR1��R1��ʂ��ď��X�ɏ[�d����d�����オ��܂��B �@���̓d�����u�b�n�ɃR���g���[���d���Ƃ��ė^���邱�ƂŁALED�̓_�Ŏ������ŏ��͂������ŁA���Ԃ��o�ĂΑ����Ȃ�悤�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@�����A�R���f���T�̏[�d�d���͍ŏ��̏u�ԂɈ�C�ɍ����Ȃ�㔼�͏��X�ɂ������ɂȂ���������邽�߁A���̂܂܃R���g���[���d���Ƃ��Ďg�p����ƍŏ��̂킸���̎��Ԃň�C��LED�̓_�łΑ����Ȃ��Ă��܂��A�㔼�͑����܂܂قƂ�Ǖω���������ԂɂȂ��Ă��܂��^�C�}�[�̕\���Ƃ��Ă͕s�K�ł��B �@�����ŃI�y�A���v�̑�����H�ŏ[�d�d�����g�債�ė��p����悤�ɂ��āA�[�d�����̔�r�I�������̗ǂ��������������o���āA�قڈ��̑��x�œ_�Ŏ������Z���Ȃ��Ă䂭�悤������ƍH�v��g�ݍ��݂܂��B �@����̕��i�萔�ł́A�^�C�}�[���Ԃ�VR1����O�`�Q���̊ԂŒ��߂ł��܂��B (�I�y�A���v���g�p����̂ł���I�y�A���v�ƃR���f���T�Őϕ���H������Ē������̗ǂ��d���ω���H�����̂��悢�Ǝv���܂����A����͂���ł����イ�Ԃ���p�ɑς��܂��̂ł��̕��@�Łc) �� �I�������H �@���X�ɏオ��d����LED�̓_�Ŏ����𑁂����邾���̉�H�ł���A�Ō�͂ƂĂ������_�łɂ͂Ȃ�܂����^�C�}�[���Ԃ���������Ƃ����ē_�������ςȂ��ɂ͂Ȃ�܂���B���܂ł����Ă��_�ł����ςȂ��A�������͐l�Ԃ̖ڂł͓_�łɌ����Ȃ��{�[���Ƃ����_���ɂȂ�܂��B �@����ł͂��܂�u�^�C�}�[�v�Ƃ��Ċ������͂���܂���̂ŁA�͂�����ƃ^�C�}�[���Ԃ��������Ƃ��킩��悤�Ƀ^�C�}�[�I���Ɠ�����LED�����S�_���ɂ��ČŒ肵�܂��B �@���̂��߂ɃR���f���T�̏[�d�d��(�I�y�A���v�ɂ�葝�����ꂽ��̓d��)���Ď����āA�[�d�����d���ɒB�������Ƃ����m�����H�����܂��B �@�I�y�A���v���R���p���[�^(��r��)�Ƃ��Ďg�p���A�R���f���T�d��������p�̊�_�����z�������_�ŏo�͂�H�ɂ��܂��B �� LED�_����H �@�u�b�n�̔��U�M�����R���p���[�^�̏o�͂��_�C�I�[�hD2�ED3��OR���Ƃ��āA�^�C�}�[�i�s���̊��Ԃ͓_�ŁA�I�����肪�����ꂽ��A���_���ɂ��܂��B �@LED����_�����邾���ł���g�����W�X�^���g��Ȃ��Ă��悢�Ƃ͎v���܂����ALED���q������A�������̕����g���悤�ɉ��p�����������������邩������Ȃ��̂ňꉞ�g�����W�X�^�ɂ��o�b�t�@���s���Ă��܂��B �� �d�� �@���̉�H�͈��肵��5V�œ��삷��悤�v���Ă��܂��B �@AC100V�Ȃǂ���d�������ꍇ�́A5V��AC�A�_�v�^�[��O�[�q���M�����[�^�ň��肵��5V������ė^���Ă��������B �@���d�r�œ��삳����ꍇ�͒P�O���d�r�~�S�{��6V�œ��삳�����܂��B�j�b�P�����f�[�d�r�~�S�{��4.8V�ł����삵�܂��B(����d���͖�10mA���x�ł�) �@�d�r�g�p�̏ꍇ�͓d�r����������d���d����������܂����A���傤��4V�܂ł͐���ɓ��삵�܂��B4V�������ƏI�����肪�ł��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA���܂ł����Ă�LED�͓_�ł����܂܂ɂȂ�܂��B�����Ȃ�O�ɓd�r�������Ă��������B �� �G�� �@����Ē����̂��߂ɐF�X�Ǝ����Ă݂܂������A�m���ɍŏ���LED�̓_�ł��������Ō�ɂ͑����Ȃ�̂́u���Ԃ������Ă���v�Ƃ��������Ɏ��܂����A����̉�H�̂悤�Ƀ^�C�}�[�J�n����^�C�}�[�I���܂Ń��j�A�Ɏ������Z���Ȃ��Ă䂭�����ł͂��܂��@���Ƃ������A�I�����߂Â����͋C���������`���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B �@�l�Ԃ̊��o�Ƃ��āA�^�C�}�[�J�n���璆�ՁA���������3/4���x�̎��Ԃ܂ł͕\�����������_�ł��Ă��āA�u���Ə����̎��Ԃ������Ă����v���ɕ\���ɂ͂�����Ƃ킩��悤�ȕω��������炵�Ă�����ق����u���������I����v�Ɣ]�����m���܂��B 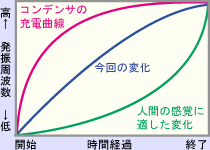 �@�E�}�̒ʂ�A����̉�H�ł͂قڒ����I�ɓ_�Ŏ�����Z�����Ă��܂����A�l�ԂɁu�c�莞�Ԃ������Ă��邼�v�Ƃ��܂��m�点��ɂ̓R���f���T�̏[�d�Ȑ��Ƌt�̑ΐ��Ȑ��̂悤�Ȏ����ω��������炷�K�v������܂��B
�@�E�}�̒ʂ�A����̉�H�ł͂قڒ����I�ɓ_�Ŏ�����Z�����Ă��܂����A�l�ԂɁu�c�莞�Ԃ������Ă��邼�v�Ƃ��܂��m�点��ɂ̓R���f���T�̏[�d�Ȑ��Ƌt�̑ΐ��Ȑ��̂悤�Ȏ����ω��������炷�K�v������܂��B�@�����Ă��̂悤�ȑΐ��Ȑ����o�͂����p�́u���O�A���v�v�Ƃ���IC�������Ă��܂��̂ŁA��������IC���w�����Ă��̓_�ʼn�H�ɓK�����ΐ��A���v�삷��̂��ʔ����ł��悤���A����R���f���T�d�������Ă���I�y�A���v�̕��������ǂ��āu�I�y�A���v�ɂ�郍�O�A���v��H�v������Ă݂�̂��ʔ�����������܂���B �@�����K�v�Ȃ�����ƐF�X�ƌ����E����������K�v������ł��悤�B����̂�����ւ̉ł͎��̂ق��ł͂����܂œ��ݍ��v�͒v���܂���̂ŁA��������������Ε����Đv���Ă݂Ă��������B (���̕��̂�����ȂǁA���Ԏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Č�����ʂɗ��܂��Ă��܂��̂ŁA����l�̕��ɂ������鎞�Ԃ̌��E�ł��B�ǂ������݂܂���) �@mibayashiakira�l�̓A�i���O�h���Ƃ������ƂŁA����̓A�i���O��H�̐^���Ƃ�������I�y�A���v�̉��p�ŕK�v�ȑS�Ă̋@�\���������Ă݂܂������A�I�y�A���v���g�p����ƃA�i���O�d���������̂Ŏ��ӂɒ�R����������K�v�ɂȂ�܂��ˁB 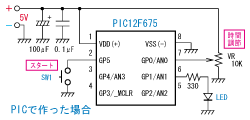 �@�����ł��������PIC�}�C�R���ō�����Ƃ�����A�E�}�̂悤�ȃV���v���ȉ�H�}�ɂȂ�܂��B
�@�����ł��������PIC�}�C�R���ō�����Ƃ�����A�E�}�̂悤�ȃV���v���ȉ�H�}�ɂȂ�܂��B�@���i�����������ĂƂĂ��J���^���ł���H �@�������v���O���������Ƃ�����Ԃ͕K�v�ł����A�A�i���O��H�ƃf�W�^����H(���Ƀv���O���������ŕK�v�����������ł���}�C�R��)�Ƃ̈Ⴂ�͂ǂ̒��x�Ȃ̂���c�����邽�߂ɎQ�l�ɉ�H�}���ڂ��Ă����܂��B �@PIC�̃v���O�����ł���A�l�Ԃ̊����ɓK�����ύX�Ԋu�œ_�Ŏ������R���g���[������̂��e�Ղł��B ���Ԏ� 2009/12/6
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 1/27 |
�����k�����������Ȃ��炲�Ԏ��x��Ă܂��Ƃɐ\����܂���ł����B �����Z���������̂Œ��X����ł����ɂ��܂������A��H���������삷�邱�Ƃ��o���Ċ����ł��B ���w�E�̒ʂ胊�j�A�Ɏ��ԊԊu���ω�����̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̊��o�ɓK�����ω��̂��w���͑S�����Ǝv���܂����B �������炪���ɂ͓��ł��B�{�����[���Ō����`�J�[�u�������ȕω��ł��ˁB �撣���Ă݂܂����A���߂ł�����܂������k�����Ă��������B ���肪�Ƃ�������܂����B mibayashiakira �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�������q�������Ă��������Ă���܂��B �@���͍�ƎԂ̃��[�������v���k�d�c���̉��������݂Ă���܂��B ���e�� �E�h�A�I�[�v�����͂n�m��1�����x�o�ƃW�����Ə��� �E�h�A�I�[�v�����n�m�A�h�A�N���[�Y���W�����Ə��� �E�G���W���n�m���W�����Ə��� �E�G���W���n�m����n�e�e���_���A�P�����x�o�ƃW�����Ə��� �ł��B �@��ƎԂȂ̂Ńn�b�`���J�����ςȂ��̎������X���邽�߁A�o�b�e���[�ւ̕��S�h�~�i�k�d�c���ƍl���Ȃ��Ă������̂����H�j��1�����x�łn�e�e�ɂ������̂ł��B �@��������낵�����肢�������܂��B ���������� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�h�A�ƃG���W���̗����̎��ۂŃ��[�������v���R���g���[���������Ƃ�������]�ł��ˁB �@�h�A�M���̓h�A�X�C�b�`���}�C�i�X�R���g���[���M��������܂��B �@�G���W���M���̓G���W�����������Ă��邩�ǂ�����d���o�͂��Ă����[�q�������������A�����ꍇ�̓L�[���Ă���Ԃ̓G���W���n�m���Ƃ݂Ȃ��Ă`�����[�q�Ȃǂ���A+12V���v���X�R���g���[���M��������܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���̓J�v�� �@�Ԃ̓d�C�M���n��+12V�n�M�����AIC��H��5V�n�ɓ��͂��邽�߂��t�H�g�J�v�� TLP521���g�p���܂��B �@�܂��A�v���X�R���g���[���M�����}�C�i�X�R���g���[���M���̗����������܂����A�t�H�g�J�v����LED��_�������镔���̉�H�����ꂼ��p�ɂ��킹�Ă�邾���ŁA�t�H�g�J�v���ȍ~�̐M���͐M���ɐ����C�ɂ��鎖�������Ȃ�܂��B �� ���۔������m��H �@�h�A�M���̓h�A���J����ON�A�����ăh�A���J���Ă���Ԃ�ON�����ςȂ��ł�����A����̗p�r�ł͂���ON�����ςȂ��̐M�����g�p����̂ł͂Ȃ��u�h�A���J�����u���v��h�A�X�C�b�`��OFF�ɂȂ����u�h�A���܂����u���v�����o�����H���K�v�ł��B �@�h�A�̏�ԐM�����������āu�h�A�J�v�p���X�M�������܂��B �@�܂��h�A�̏�ԐM����NOT(���ۂ�74HC02��NOR)��H�Ŕ��]�����������āu�h�A���v�p���X�M�������܂��B �@���ꂼ��̃p���X�̓h�A���J�����u�ԂƁA�h�A���܂����u�Ԃɔ������܂��B �@���l�ɃG���W���M�������������u�G���W���n���v�p���X�M���Ɓu�G���W����~�v�p���X�M�������܂��B �@�������ď�Ԃ̕ω������m����p���X�M�����o���܂�������A��͂�����^�C�}�[��H�𐧌�ł���悤�ɘ_����H�����܂��B �@����̘_���� �@�@�^�C�}�[�X�^�[�g�@���@�h�A�J or �G���W����~ �� �^�C�}�[�̓X�^�[�g�����P���Ŏ�����~
�@�@�^�C�}�[������~�@���@�h�A�� or �G���W���n���ɂȂ�̂ŁA74HC02��NOR��H��OR�����܂��B�o�͔͂��]����ăl�K�e�B�u�ɂȂ�̂ŁA�^�C�}�[IC 74HC221�̐���ɍD�s���ł��B �� �^�C�}�[��H �@����̂���]���P���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA0�`2���̊ԂŎ��R�Ɏ��Ԃ߂ł���^�C�}�[��H���^�C�}�[IC 74HC221�ō쐬���܂��B �@���[�������v���_�����Ă��鎞�Ԃ�VR1�Œ��߂��Ă��������B(�^�Ŗ�P���ł�) �@�^�C�}�[�X�^�[�g�p���X��74HC221�̃^�C�}�[�P���g���K����(~1A)�ɐڑ����ă^�C�}�[������X�^�[�g������M���ɂȂ�܂��B �@�^�C�}�[�N���p���X�̏�Ԃ�LED1�Ŋm�F�ł��܂��B�^�C�}�[�N���v������������ƈ�u�s�J�b�ƌ���܂��B �@�^�C�}�[��~�p���X��74HC221���N���A����(~1CLR)�ɐڑ����A�^�C�}�[���쒆�ł���Β��f���܂��B�����^�C�}�[���Ԃ��߂��ďo��OFF�ɂȂ��Ă�������ɐV���ȕω��͋N���܂���B �@�^�C�}�[��~�p���X�̏�Ԃ�LED2�Ŋm�F�ł��܂��B�^�C�}�[��~�v������������ƈ�u�s�J�b�ƌ���܂��B �@�^�C�}�[�̓����LED3�Ŋm�F�ł��܂��B �� ������������H �@���[�������v�_�����ɂ�ON�������u�Ŗ��邭�_�����܂��B �@�^�C�}�[��ON�M��(H���x��)��D2��ʂ��Ĉ�u��C8���[�d���AFET1 2SK2232�̃Q�[�g�ɖ�5V��������̂�FET��100%�ʓd���܂��B �@�^�C�}�[���ꂽ��74HC221��Q1��L�ɂȂ�܂����AC8�ɗ��܂����d�C��D2������̂�74HC221��Q1�ɂ͋z�����܂ꂸ�AVR2��R13��ʂ��Ă��������d���܂��B���̂��߃����v�̏������ɂ�FET�̃Q�[�g�d����������艺���邽�߂Ƀh���C���d����������茸�����A���[�������v�͂������������܂��B �@�������������鎞�Ԃ�VR2��0�`���b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@FET�̏o�͂̓��[�������v�p���}�C�i�X�R���g���[���M���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���[�������v�̃}�C�i�X���ɂ��̂܂ܐڑ��ł��܂��B �@���[�������v�ɓd�����g�p���Ă���Ƃ��ƁALED�ȂǏ���d���̏��Ȃ��f�q���g�p���Ă��鎞�ł͂�����������x�����������Ⴂ�܂��B(���̉�H�͓d���ELED�ǂ���ł��Ή����Ă��܂�) �@������������X�s�[�h�͂��D�݂ɂ��킹��VR2�Œ��߂��Ă��������B �� �d����H �@����̉�H��HC�^�C�v��CMOS IC���g�p����̂�5V�œ��삵�܂��B �@�����Ԃ�12V�d������O�[�q���M�����[�^7805��5V�����܂��B �@�G���W��OFF���ł��h�A�̊J�Ń��[�������v�̐�����s��Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA���̉�H�̓d���͏펞12V�̓d������^���Ă��������B �@���[�������vOFF���ɂ͂��̉�H�̓}�C�N���A���y�A�I�[�_�[�̓d����������܂���̂ŁA�ҋ@���̂��̉�H�̏���d���Ńo�b�e���[�オ��̐S�z�Ȃǂ͂���܂���B ���Ԏ� 2009/12/4
|
|||||||||||||||||||||||
| Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@���������b�ɂȂ��Ă��܂��B �@���x���ߊ�DC0mA-40mA���͐M���ɑ�SSR�ɂ�AC100V�̍쓮���s���ׁA���x���ߊ��SSR�ɂ��Ă͂��ꂼ��p�i�\�j�b�N KT4��AKT4113100�ƏH����SSR���g�p���Ă��܂����ASSRAC100V���ʓd�����A�쓮���܂���B �@���x���ߊ�KT4��SSR�Ɍq���Ȃ���Ԃł��̐M�������̓d���𑪂��DC10V����܂����ADDR�ɐڑ�������Ԃő����DC1V�ƂȂ��Ă��܂��܂��B �@�܂�SSR�ɂ��Ă͉�H�����͉�H�}�ʂ�ł����A�`�F�b�N����ׂ��_��������܂���B �y��ԁz (1)�H��SSR�͓��́iDC3-MAX24V_5-30mA)������ƃg���C�A�b�NT1-T2���ʓd����Ƃ���ŁA����ł�SSR�ɉ��x���ߖ��q�����Ƃ��ɓd����10->1V�ɂȂ�̂ŁA�ʓd���܂���B (2)SSR�͍Œ�3V�Ȃ��ƍ쓮���Ȃ��ׁA���͂P�OV->1V�ɂȂ��Ă��鎖�ō쓮���Ȃ��ƍl���Ă��܂��B �@�ȏ�܂��܂��āA �@�Ȃ�10->1V�ƂȂ��Ă��܂��̂ł��傤��? �d�q��H�ł͕��ʂ̂��ƂȂ̂ł��傤��? �i����Ƃ�KT4�̎d�l�ł���p�i�\�j�b�N�Ɋm�F���悤�ƍl���Ă��܂��j �A���ۂ�SSR���쓮������ׂɂ́A������H������K�v������܂���? ����Ƃ�SSR����������K�v������܂���? �̃A�h�o�C�X�������B �@�����A���ʂɃ����[�ʂ����g�������Ƃ����Ȃ��f�l�Ȃ̂ł����A��L�̎���ɑ���낵�����肢�v���܂��B ���݂� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��ȒP�ɓ��������B �@Panasonic�̉��x���ߊ�KT4��AKT4113100(�d���o��)�͏o�͒[�q�����������p�r(SSR/�����[��)�Ɍq�����߂̑��u�ł͖����̂ŁA���{�I�Ɏg�������Ԉ���Ă��܂��B �@�����o�͒[�q��SSR���g�������̂ł����SSR����p��AKT4112100(�d���o��)�^���g�p���Ă��������B �@AKT4112100�Ȃ�d���o�͒[�q(12V/40mA MAX)�ɒ���SSR��ڑ��ł��܂��B �@�w������i�����ԈႦ�ł͂���܂��H �@����b�B �@AKT411X100�ɂ͂R�̃^�C�v������܂��BX�̕����� 1 = �ړ_�o�� (3A 250V AC) 2 = ���ړ_�d���o�� (12V 40mA MAX) 3 = �d���o�� (DC 4mA-20mA 550��MAX) Type.1 �@�o�͒[�q�͓����̃����[�Ɍq�����Ă��܂��B �@�ݒ艷�x�Ń����[��ON�ɂł��܂��B �@AC250V/3A�܂�ON/OFF�ł��܂��B Type.2 �@�o�͒[�q�͓����Ńg�����W�X�^���o�R����12V�d���Ɍq�����Ă��܂��B �@�ő�40mA�܂Ŏ��o���܂��B �@�ߓd���ی��H��������Ă��܂��B �@SSR�ɒ��ڐڑ����邽�߂̏o�͂ł��B(�H��SSR�ɂ��q����܂�) Type.3 �@�o�͒[�q�́u�e�`�K�i�̓d���o���v�ł��B �@���艷�x�ɂ��킹��4mA�`20mA���d���o���Ƃ����A�i���O�l�ŕω����܂��B������d�����͂œ��삷��e�`�@���̐���p�[�q�ł��B �@���x�ɂ��킹�ă��j�A�Ƀq�[�^�[��t�@�����쓮����A����Ȑ����H���������p���[���䑕�u�ɉ��x����`�B���邽�߂����̃f�[�^�ʐM����ł�����A�����SSR/�����[�삹�邱�Ƃ͂ł��܂����B �@�c�O�Ȃ���u������H�v��uSSR�������v���x�̘b�ł͍ς݂܂���B �@�M�����鑤�ŁA���̓d���l�����o���ĖړI�̉��x�Ɣ��肵�ASSR�Ȃǂɓ���d����^����u���x�����H�v�����K�v������܂��B �@�������Ƃ͌����܂���̂ŁAAKT4113100(�d���o��)�̎g�p�͂�����߂�AKT4112100(�d���o��)���g�p���Ă��������B ���Ԏ� 2009/12/1
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����肪�Ƃ��������܂��B �@����TYPE1��TYPE3�������Ă��ă����[��H�t��TYEP1�̓J�`�J�`�����邱�Ƃ���ASSR�����p�o�����...�Ǝv��������ł��B �i�����[��H��10����������C������j �@�m����TYPE2�ɂ�SSR�p�Ə����Ă���ׁA���J�ȉ���ƕ����đ�ϕ��ƂȂ�܂����B ���������������TYPE3�͂ǂ̂悤�ȗp�r�Ɏg�p����̂ł��傤��? �@�u�T�[�������[��H�v�̂悤�ȕ������x�����H�Ƃ��Ēlj�����Ƃ������ł��傤��? �i�d���o�͂����낢�뒲�ׂĂ��܂����A�ڂ���Ƃ��������炸�A�܂����������Ⴂ�Ȃ̂��A�R�^�c�̉��x���������̂ɂ��Ƃ�����ƂȂ̂��A�܂��������������Ă��܂���j �@�Ƃ͌����A���L�̃T�[���Z���T�{SSR�ɂď\����p���o����̂ŁAPID�����I�[�g�`���[������߂�̂͏��X�c�O�ł������ɂĐ�����܂����B �@�d�˂Ă���\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B �ȏ� ���݂� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
>���������������TYPE3�͂ǂ̂悤�ȗp�r�Ɏg�p����̂ł��傤��? �@12/2�ɏ����܂����悤�Ɂu���x�ɂ��킹�ă��j�A�Ƀq�[�^�[��t�@�����쓮����A����Ȑ����H���������p���[���䑕�u�v�ɃZ���T�[�̉��x����`�B���邽�߂Ɏg���܂��B �@���̏ꍇ�AKT4���g�͉��x�ɂ��Ă̔�����͉����s���܂���u���x���ߊ��v�Ƃ��Ă͓������A�u�M�`�⑪����R�̂�d���E�d���o�͌^�Z���T�[�ȂǁA�Ȃ�ł��q����֗������x���d���o�͕ϊ��@�v�Ƃ��ē����܂��B �@���Ԃ݂��l��KT4���u�w�肵�����̉��x�ɕۂ悤�����[��ON/OFF������(������)���u�v���Ƃ��l���Ȃ̂ł��傤�B(PID����@�\�Ȃǂ����������@�\�Ȃ��̂ł����c) �@����������Ȃ�Type3�̓d���o�͋@�\��A�S�^�C�v�ɂ��Ă���RS485�ɂ��Modbus Protocol�ɂ��PLC�f�[�^�ʐM�@�\�ȂK�v�����킯�ŁA����炪�t���Ă���Ƃ������Ƃ�KT4���P�Ȃ鉷�x�X�C�b�`(���x���ߊ�)�ł͖����ėp���x�Z���T�[���u�Ƃ����ʒu�t���ł��B �@�P�̂Ŏg�p���đO�ʃp�l������Őݒ肵�����x�Ń����[��ON/OFF���邾���̎g�p���@�ł͂Ȃ��A�q�[�^�[�̃p���[���A�i���O�I��0%�`100%�܂Őݒ�ɂ��킹�Ď��݂Ɏ������߂��邤��ȋ@��ƔM�`�Z���T�[�Ƃ̊Ԃœd�C�M����ϊ����Ă���C���^�t�F�[�X�Ƃ��Ďg�p������A�R���s���[�^�ɂ���|�����FA���䑕�u�̃Z���T�[�[���Ƃ��ĔM�`�̊��m�������x���f�W�^���f�[�^��RS485�o�X�ŒʐM�����R���s���[�^�f�W�^���Z���T�[���j�b�g�Ƃ��ē������邱�Ƃ��ł��܂��B �@������KT4�֗̕��ȂƂ���́AFA�@��̕W���C���^�t�F�[�X�K�i�ł���d���o��(�J�����g���[�v)��Modbus�ʐM�ŐM�����o�͂��鑕�u�ł���_�ŁA�M�����鑤�ɂ��Ă݂�Γd�����͂�Modbus�Ńf�[�^�M������悤�v���Ă��������ŁA���x�����m����Z���T�[���M�`�Ȃ̂�������R��(��R�l���l�X)�Ȃ̂��A�͂��܂��d���o�͂ł��̓d���͈͂́H�Ȃ�Ĉ�؍l���Ȃ��Ă��������ł��B����牷�x�Z���T�[��������KT4���S�ĉB���Ă���āA�P����KT4���o�͂���W���C���^�t�F�[�X�K�i�̉��x��������FA����͂ł���킯�ł��B �@FA�@��ɂ͂��̂悤�ɉ��x�E���x�E���́E�K�X�Z�x�Eetc.���u���̐�ɉ�(�ǂ�ȃZ���T�[)���q�����Ă���̂����C�ɂ��鎖�����A�W���`���Ńf�[�^�݂̂𑗐M���鑕�u�v����������܂��B �@KT4�͏��i���͊m���Ɂu���x���ߊ��v�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����A���ۂ́u���ړI�R���s���[�^�������x�Z���T�[�C���^�t�F�[�X���u�v�ł��B ���Ԏ� 2009/12/2
|
|||||||||||||||||||||||
| �o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q | ||||||||||||||||||||||||
|
�g�ѓd�b�[�d���Li-ion�[�d��Ƃ��Ċ��p���鎞�̗]���[�q�̏������@�ɂ��ċ����ĉ������B���g���Ă���̂͌g�т𗧂ĂĒu�������ɒ[�q���Q����A�����ɐ����Ȃ��Ŋe�포�^Li-ion�d�r���[�d���Ă���A�ƂĂ��d�Ă��܂��i��i�o��150��A�j�B�ŋ�600��A�o�͂̋��^�[�d�����100�~�ōw�����܂������A4�[�q������A�s�Ƃr�̒[�q�ɉ��炩�̏��u�����Ȃ��Ɠ��삵�܂���B����IC��AN8167K(22�s��DIP�j�ł����f�[�^�V�[�g������o��������グ�ł��B���Ȃ݂ɂs�[�q�Ɓ{�[�q���q������A�r�[�q���|�Ɍq������A���ԓd�����������肵�܂��������삪�ςł��B����������Ƃr�[�q��100���ʂ���IC17�s���ɁA�s�[�q�͒�R2�ڑ�����Ă��āA4.7k���ʂ���16�s���A10k���H(1002�\���j�ʂ���18�s���ɐڑ�����Ă��܂��B���̏[�d��́uAC�}���[�d��D002 DoCoMo�A�����O�H�d�@�v�ƕ\������Ă��܂����ANTT��[�J�[�ɕ����킯�ɂ��������A���̒[�q�̓d�C�I���u���@�ɂ��Ă����������˂������܂��B �K�ێ܆� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�S�������b��(�[�d���T��S�[�q)���u�d�r�E�o�b�e���[�E�[�d���v�́w�d���H��̏[�d���ėp�̏[�d��Ƃ��Ďg���Ă݂����x�ɏo�Ă��܂��B �@�ڂ������e�͂���������ǂ݂��������B �@�Ȃ��A�T�[�~�X�^�[�q�ɂ͂��̏[�d�킪�ΏۂƂ��Ă���o�b�e���[�ɓ�������Ă���T�[�~�X�^�Ɠ�������ڑ����邩�A���̃T�[�~�X�^�����퉷�x�̍ۂɎ�����R�l�̒�R���q���Ώ[�d��͓��삵�܂��B(�O�H�d�@�̃o�b�e���[�p�b�N���ǂ̎�ނ̃T�[�~�X�^���g�p���Ă���̂����͒m��܂���B�ʂɂ����ׂ�������) �@S�[�q�͓��e��m��܂���̂ŁA�����q���Ηǂ��̂��̓A�h�o�C�X�ł��܂���B �@�[�d��̎��(���̐���IC�A�܂��̓}�C�R���̃v���O����)�ɂ��A�T�[�~�X�^�����퉷�x�������Ȃ��ƃo�b�e���[�ɏ[�d���Ȃ��[�d��͑����ł��B �@�ʏ�T�[�~�X�^��GND�Ƃ̊Ԃɐڑ����܂����A���[�J�[�E�@��ɂ���Ă�+V�Ƃ̊ԂƂ��A���̒[�q�̊�(�܂���S�[�q�H)�Ɍq���ꍇ�Ȃǂ��l�����܂��̂ŁA�[�d�����������ꍇ�͂����g�ł��������������B �@�T�[�~�X�^�[�q�Ƀ_�~�[�Œ�R�Ȃǂ�ڑ������ꍇ�A�[�d��ɂ���Ă̓o�b�e���[���O���Ă���Ԃ���ɖ��[�d�����v�̕\�����_��(�o�b�e���[������Ă���Ɗ��Ⴂ)����悤�ȕ�������܂��B�T�[�~�X�^�[�q�̒�R�l�Ńo�b�e���[���悹���Ă��邩�O����Ă��邩�����m���Ă���^�C�v���Ƃ����Ȃ�܂��̂ŁA�C���������ł��������������d�l�̏[�d��ł͎d���Ȃ��ł��B ���Ԏ� 2009/11/23
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 11/25 |
�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B�K�v���������g���C���Ă݂܂��B���܂����삷��悤�ɂȂ����Ƃ��͏��������܂��B �i�ǂ����Ă��_���ȂƂ��͂�����߂āA�ʓd�������삵�܂��j �K�ێ܆� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �d����������IC�H�H�H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@���������b�ɂȂ��Ă���܂��B �@����A�ӂƎv�������āA�l�X�ȃ��o�C���@��i�g�сAipod�Ȃǁj��1��ŏ[�d�ł���[�d��i�d���̓j�b�P�����f�d�r3�{�A�\�[���[�p�l���j��d�r2�{�œ����̌g�я[�d���Aipod�[�d����������č�낤�Ǝv�����̂ł����A�d�����A���J�����ƃ����j���O�R�X�g�������ɂȂ��Ă��܂��D�܂�������܂���B �@�����ŁA�j�b�P�����f�d�r3�{�̓d��3.6V���犣�d�r2�{���̓d��3V�܂ō~�������Ă�肽���i���_�㍷��0.6V�ł����A���ۂ͂����Ƃ���Ǝv���̂ŁE�E�E�j�̂ł����A��ʓI��3�[�q���M�����[�^�Ȃǂ͍���1.7V���x�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA���܂����p���邱�Ƃ��ł��܂���B �@�����ŁAIC���g���Ƃ��܂�������������Ȃ��ƗF�l���畷�����̂ł����A�ǂ̂悤�ɑg�߂����ł��傤���H spark sheet �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA������������͂��̗F�l�l�ɂ����̂��ߓ����Ǝv���̂ł����A�Ȃ����Ɏ��₳���̂ł��悤���H �@���͂��̂��F�l�l�ł͂���܂���̂ŁA�ǂ�IC���g���Ƃ��܂��䂭�̂���m��܂���B �@���������A���������֗���IC�����̐��ɑ��݂���̂�����A���͑����グ�܂���B �@���̗F�l�l�͂��̖ړI�ɓK����IC�������m�Ȃ̂ł��傤����A���Ђ������ɂȂ���IC�̌^�Ԃ�g�������o���āA���ɂ������Ē�����ƕ��ɂȂ�܂��B �@�܂��A��ʓI�ȎO�[�q���M�����[�^���uIC�v�̈��ł��B �@�X�ɁA��ʓI�ȎO�[�q���M�����[�^�̒��ɂ̓h���b�v�d����0.1V���炢�̕�����0.5V���炢�́u��h���b�v�^�C�v�v�̕�������܂�����A�������������uIC�v�ƌĂ�ł���Ƃ����\��������܂����A�킴�킴��ʓI�ȎO�[�q���M�����[�^�ƕ����čl���Ă���������悤�Ȃ̂ŎO�[�q���M�����[�^��IC�ƌĂ�Ă���̂ł͂Ȃ��悤�ł��ˁB(���܂肻���͌Ăт܂���) �@�X�C�b�`���O�R���o�[�^�pIC�Ǝ��ӂɂ��������i��t���č~���p�R���o�[�^�����Ƃ������Ƃ�����܂����A3.6V��3.0V�Ȃ�ĕ��ʂ�DC/DC�R���o�[�^�ō��܂����ˁE�E�E�B �@�܂��Ă�A3.0V��5.0V�ɏ�������DC/DC�R���o�[�^���쓮������̂ɁA�O�i��3.6V��3.0V�̍~���R���o�[�^��"���܂���"�Ȃ�ė��s�s�ł����ˁB �@�����X�C�b�`���O�R���o�[�^�pIC�̘b�ł͖����Ǝv���܂��B �@������Ɩʔ������Ȃ��b�ł�����A�ǂ��IC���g���Ɨǂ��Ƃ��F�l�l�������Ă���̂��A����ł����\�ł����炨�������������B ���Ԏ� 2009/11/23
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���肪�Ƃ��������܂��B �@���̂Ƃ��͗F�l�ɂ�����Ƃ����������Ă��炦�܂���ł������A����F�X�Ƙb���Ă݂�ƁA�ǂ����F�l�����̃T�C�g��m���Ă���悤�ł��āA���̒��̃����N���http://www.kansai-event.com/kinomayoi/koneta/dcdc2.html���Q�l�ɂ��Ă݂�Ƃ����ƌ����Ă���܂����B �@�F�l�ɂ͂���3.6V����3V���傤�ǂ̓d������肽���Ƃ��������Ă��Ȃ������̂ŁA�̂��ɏ[�d�킪���5V�܂ŏ�������Ƃ͎v���ĂȂ������悤�ł��B�����g���[�d�킪�������邱�Ƃ��l�����Ă��܂���ł����B �@����ƁA�����g��������x�悭�l���Ă݂�ƁA�g�ѓd�b�̏[�d����������A��������5V����悤�ɂ��AUSB�d�l�ɂ��Ă��܂��ΐF�X�ȋ@�킪�ڑ��ł��Č�X�y�ɂȂ邩�Ǝv���A�������邱�Ƃɂ��܂����B spark sheet �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@IC�Ƃ�MC34063�̂��Ƃł������B �@�m���ɒP���Ɂu3.6��3.0V�ɂ����H�v�Ƃ��������̘b��Ȃ�MC34063�̂悤��DC/DC�R���o�[�^IC�����ɏオ�邱�Ƃ͂���Ǝv���܂��B �@���������ۂ͍���́u�d�����u(����)�v�������߂ɂ܂��u�d�����u(�~��)�v������������Ƃ�����x��ԁA�ϊ����X���Q�����ēd�r�̓d�͂�r���Ŏ̂Ă��ʂ��Q�������Ƃ����A�ƂĂ��d����H�����ɂ͓K���Ă��Ȃ����̂ɂȂ�Ƃ͗F�l�l���v���Ă͂��Ȃ������ł��傤�ˁB �@�A���J�����d�r�Q�{3.0V�œ������u�Ƀj�b�P�����f�[�d�r�R�{3.6V(4.2V)����������Ȃ�AIC��H��O�[�q���M�����[�^�����g�p���Ȃ��Ă��u�����p�_�C�I�[�h�P�{�`�Q�{�v�ōςނƎv���̂ł����B �@�P���Ɂu�d���𗎂Ƃ��Ďg�����������v�Ȃ琮���p�_�C�I�[�h��ɓ���邾���ŁA��{�Ŗ�0.6V�����܂���ˁB�������[�d��4.2V�̍ۂ��|���̂Ȃ�Q�{����Ă����������ŁE�E�E�B �@IC���g����DC�R���o�[�^��H��O�[�q���M�����[�^�̂悤�Ɂu���͓d�����ړI��荂���ꍇ�ɂ́A�~���������d���ɕۂ��v�ׂ̍��x�Ȉ��艻��H�Ȃ�ĕK�v�����g�p�ړI�ł�����A�P���ɓd�r�d��(3.6V)�����0.6V������3.0V�ɂȂ��āA�d�r�����Ղ��ēd����������Ɠ��R�d�r�d������0.6V�������d�����o�͂����̂ő��u�ɋ�������d���͉�����܂����A����̓A���J�����d�r�������ēd����������̂Ƃ������ĕς�Ȃ��̂ʼn�����͋N���Ȃ��͂��B ���Ԏ� 2009/11/28
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B �@�_�C�I�[�h���͂���ł��܂��Ƃ����肪����܂������B�_�C�I�[�h�͐����Ȃǂɂ������i�g���Ă��Ȃ������̂ŁA����A���̂悤�Ȏg���������Ă������֗��ɂȂ邩������܂���ˁB �@�F�l�ɂ����̂��Ƃ��Љ�Ă��낢����ɗ��ĂĂ��炢�܂��B spark sheet �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d�q��H�ɂ͂P�̕��@�����ł͂Ȃ��F�X�ȕ��@������܂��̂ŁA�����L���Č��������Ɩʔ����Ǝv���܂��B �@�����̚����Ƃ��āE�E�E �@3V��5V��DC/DC�R���o�[�^�̏ꍇ�A���͂�3.6V�ł�4.2V�ł���薳�����C�ɓ��삵�Ă��܂����̂��قƂ�ǂ��Ǝv���܂��i�O�O�G �@���������͓d�����o�͓d���ɋ߂��Ȃ�̂ŁA��������̂Ƀp���[��K�v�Ƃ��Ȃ��̂Ń��X�����Ȃ��Ȃ��ĕϊ��������A�b�v���A�d�r�̓d�͂����ǂ�5V�ɕϊ����ďo�͂ł���悤�ɂȂ���������܂��B �@��O�Ƃ��āA�g�p����Ă��镔�i�����͓d�����オ�邱�Ƃʼnߓd���E�ߓd��������ĉ��Ă��܂��A�܂��͉ߔM���Ă悭�Ȃ���ԂɂȂ鐻�i����ؖ����Ƃ͌�����܂���B �@��H����͂��Ĉ��S�Ȃ��̂Ȃ̂��댯�Ȃ��̂Ȃ̂��ʂł���Z�\���������̕��ł���A���g�����ĒP���ɓd�r�R�{�ɕς��Ă��ǂ����킩����̂悤�ɓd�r�R�{�����ł������ł��ˁB �@�u�悭�킩��Ȃ����ǁA�Ƃ肠�����d�r�R�{�����Ă݂��B�E�E�E�E�����o�ăR���o�[�^���Ă��Ă��܂����I�v�Ȃ�Ď��ɂȂ��Ă����͐ӔC�����܂����(��) ���Ԏ� 2009/12/2
|
|||||||||||||||||||||||
| DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H | ||||||||||||||||||||||||
|
DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H
GATT �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�uLi-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H�v�ŁA��r�d����1.05V�ł��g�����������B ���Ԏ� 2009/11/21
|
|||||||||||||||||||||||
| 12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H | ||||||||||||||||||||||||
|
��b���w��łȂ����S�҂ł��B����悤�ȓ��e�Ȃ̂�������܂������Ă������������̂ł��B �d���d�����P�Q�u�Ń��W�b�N�h�b�̂S�O�Q�W�i�p�O����p�X�܂ł̂P�O�{�̏o�͂̂����A���͂a�b�c�R�[�h�ɑΉ������o�͂� �g�g�h ���x���ɂȂ�A����ȊO�̏o�͂͂��ׂ� �g�k�h ���x���ɂȂ�j�ƃg�����W�X�^�A���C�̂U�Q�O�W�S���g���Ċ�p�~�j�����[�𐧌䂵�悤�ƍl���Ă��܂��B�P�Q�u�p�̃����[���g���̂Ȃ牽�����Ȃ��Ǝv���̂ł����A�T�u�p�̃����[�̔����u��������̂ł�������g���Ȃ����ƍl���܂����B�R�[�q���M�����[�^�łT�u������ă����[�̐��ɂɂȂ��A�����[�̕��ɂ��U�Q�O�W�S�́g�k�h����Ƃ����̂ł����̂ł��傤���H���ꂾ�Ƃm�o�m�^�̃g�����W�X�^��e�d�s�Łg�k�h���䂳������ΈقȂ�d���̉�H�����݂��Ă��n�j�ɂȂ��Ă��܂������ʼn����Ԉ���Ă���悤�ȋC������̂ł����悭�킩��܂���B�m���ɂP�Q�u��H�łT�u�����[���g������A�t�ɂT�u��H�łP�Q�u�����[���g������H��͌����L��������܂���B�T�u�����[�̂������̂Ȃ琳�����͂���ȉ�H���K�v�ł���B�݂����Ȑ���������������Ώ�����܂��B��낵�����肢���܂��B �Ƃ����� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ׂɁA5V�̉�H��12V�ȏ�̑��u�����̂��\���܂��A12V�̉�H��5V�̑��u�����Ă����\�ł��B �@�������ʂ̎g�����ł��B �@�P���ɁA�P�̉�H�����Ȃ�S���̕��i���d���d���œ������̂ōς܂��A�d����H(���u)���P���ɂ����ق������̂��y�ł���H �@������Ƃ�����H�Ȃ̂ɕ����d����p�ӂ���ق�������ۂǂ߂�ǂ������̂ŁA���ʂ��P��d���œ����悤�ɂ��Ă��̂���ʓI�Ƃ��������ł��B �@�ق��ɂ��A�d���d���̈Ⴄ���i���q���ۂɁu����͌q���ł������̂��A���̉�H�ʼn��Ȃ����H�v�Ȃǂ��l���Đv���Ȃ�������Ȃ��̂ŁA�펯�I�ɂ͐v���ʓ|������킴�킴�d���̈Ⴄ���i��g�ݍ��킹����͂��Ȃ��ł��B �@������u�ǂ����Ă��d���̈Ⴄ���i(��u)���쓮���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ɂ̓g�����W�X�^��x���V�t�^IC�A�����[�Ȃǂ��g���ĕʂ̓d���n�̉�H���m��ڑ����܂��B �@�Ƃ�����l�̏ꍇ�͂킴�킴����H��12V�Ƃ͕ʂɎO�[�q���M�����[�^��5V�̓d�������Ƃ����u�ʓ|�Ȏ��v�������Ƃ������ł�����A�������ł��̓���I���Ȃ�ʂɂ���ł����Ǝv���܂��B �@TD62084������킯�ł��Ȃ��̂ŁA���̂܂܂ǂ����B ���Ԏ� 2009/11/11
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 11/12 |
���Z�������̑����A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�������V�������E���J�����悤�ȋC���ł��B�قȂ�d���̉�H�����݂����āg�k�h�Ő��䂷�邱�Ƃ��ł���B�Ƃ����͎̂��ɂ���ΎY�Ɗv���ɕC�G�������ł��B����܂Ŗ��ʂɍ����ȃt�H�g�����[���g������A�����[�𑽗p���Ă��܂����肵�Ă��܂�������B����Ƃ���낵�����肢���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B �Ƃ����� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �x���A���R���Z���g����肽�� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@���߂܂��Ă����b�ɂȂ�܂��B�x���A���R���Z���g����낤�Ǝv���Ă���̂ł����A�d�����o�̎d�g�݁i��H�j���킩��܂���B �@�x����H�ɂ��܂��Ă͎Ԃ̃��[�������v�c�Ɖ�H�ƃ����[�ʼn��p���悤�Ǝv���Ă��܂��B�i����́A�莝����8�قǂ��邽�߁j����ł͂�낵�����肢�������܂��B �� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@AC100V�̓d���R�[�h�ɗ���Ă����d�������o������@�ɂ��܂��ẮA���t���߂��Ƃ���ł́u�ȈՃf�W�^���\������d�͌v�v�̍��ŏڂ����������Ă��܂��̂ł��ǂ݂��������B �@�{���Ɂu�Ȃ��d�����o���ł���̂��H�A�R�C���͂ǂ����������g�p��������̂��v�ȂǓd�����o�̏ڂ��������́uAC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF�v�̍��Ő}�����Ő������Ă��܂��B �@�܂�����̂���]�Ɠ������́uAC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF�v���܂��ɂ��̒ʂ�ł͂���܂��H �@��������d����5A�`10A�ł͂Ȃ��A1A�������x�ł���������悤�ɒ��߂��Ă��A�����ׂɂȂ�ꂽ��AC100V���C���ɓd�������ꂽ��A�ʉ�H��ON�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@��H�}�̓d����5V�Őv���Ă��܂����A�Ԃ̃��[�������v�p�̒x�����u�����g���ɂȂ���̂ł�����d����12V�Ƃ��āA�P�����H�}��R1=510�AR2=1K�AR4=1K�AC6�͑ψ�25V�A�����[��DC12V�����[�ɒu�������Ă��������B ���Ԏ� 2009/10/25
|
|||||||||||||||||||||||
| 100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@100�ς̖��ÃZ���T�[�����Ă����铔���������Č��ւ̊O���ɑg�ݍ��݈Â��Ȃ����玩���œ_�����A���������邭�Ȃ�Ə�������悤�Ȃ��̂��o���Ȃ����l���Ă��܂��B �@�����d�C�n�̒m�������܂�Ȃ���H�}�̌������ǂ�������܂��쐬�\�ł��悤���H sinori �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ւ�\�������܂��A�����ł́u��H�}���ǂ߂Ȃ��v�Ƃ������̏ꍇ�͉������@����邱�Ƃ͒v���Ă���܂���B �@������ɉ����ĉ�H�}����āA��͂������Ő��삵�Ē����������Ƃ��Ă��܂��̂ŁA��H�}���ǂ߂Ȃ��ƕ��i���W�߂���E�����̐ڑ����������ōl���Đ��삷�邱�Ƃ��ł��܂���B �@��H�}�̓ǂ߂Ȃ����ł��������s�����Ƃ͉\�ł����A���̂悤�ȏꍇ�͏��S�Ҍ����̏��ЂɌf�ڂ��Ă���悤�ȁu���̔z���}�v���ڂ��āA�G�̒ʂ�ɔz������Αg�ݗ��Ăł���悤�ȋL���ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�c�O�Ȃ��炱���͂����܂Őe�ɂ��鏊�ł͂���܂���̂ŁA100�~�̃Z���T�[�����v���������ĂƂ����H��͂����ƕ�������āA�������ʼn�H�}��ǂ߂ĕ��i���W�߂���悤�ɂȂ��Ă���ɂ��Ă������ق����悢�ł��傤�B �@���֓��̎����_��/�����ɂ͕��ʂ́uEE�X�C�b�`�v�ƌĂ��d�C�z���p���i���g���܂��B �@Panasonic�d�H��EE8113K�Ȃǂ���ʓI�ŁA�z�[���Z���^�[�̓d�C�z���p�i������1000�~���炢�Ŕ����Ă��܂��B �@�ŐV���́u�d�q��EE�X�C�b�`�v��1000�~�O��ŋ����d�q�̓X��(3F���W�̉�������)�Ŕ����Ă��܂����A������ƌ^�Ԃ��o���Ă��Ȃ��̂Œl�i�ׂĂ݂܂����������ł��o�Ă��܂���B �@200�`300�~����Ȃ���_�����I�A1000�~�Ȃ�ďo���Ȃ���I�A�ƌ���Ȃ���Α�胁�[�J�[�̐�p�i���Ďg��ꂽ�ق����ǂ��Ǝv���܂���B �@���֓��̒��ɑg�ݍ��ނƂ������ŁA�@��̉����ɂȂ�̂ō���͊Y�����܂��A�ꉞ�������Ă����܂��Ɖƒ���̓d�C�z����������������H�����肷��̂́u�d�C�H���m�v�̎��i���K�v�ł��B�����i�H���͂��Ă͂����܂���B �@�ƒ��AC100V�̔z����������ɂ́A����Ȃ�̒m���Ɛ������Z�p�������ƃV���[�g��R�d�ȂǓd�C���̂̌��ƂȂ�A�ň��͔z����s����N�����Ƃ��낪�ߔM�E���M���Ĕ��Ύ��̂��N�����A���̂܂܉Ƃ܂ŏĂ��Ă��܂��Ƃ����悤�ȔߎS�Ȍ��ʂɌq���邱�Ƃ�����܂��B �@�@��̒��ʼn������s���ꍇ�͓d�C�H���ɂ͊Y�����܂��A����ł�AC100V�ڂ���������ɂȂ�܂�����A��ɉ����肵�Ȃ��悤AC100V�̋��낵���𗝉����A�������z���m����g�ɕt���āA���̂̋N����Ȃ����S�ȍH���Ƃ��s�����M��g�ɕt���Ă���s���Ă��������B ���Ԏ� 2009/10/25
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���X�ɂ����������L��������܂����B�A�h�o�C�X�����������l�Ɋ����̐��i���Ȃ����ēx���ׂĂ݂܂��B�ǂ����L��������܂����B sinori �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���ꂩ��̃V�[�Y���A�N���X�}�X�̓d�����Ԃ����_��������ׂ�AC�����P�[�u���݂����Ȍ`�̖��邳�Z���T�[�X�C�b�`���z�[���Z���^�[���̓d�����݃R�[�i�[�Ŕ����܂�����A��������������������Ă݂Ă͂������ł��傤���B ���Ԏ� 2009/10/27
|
|||||||||||||||||||||||
| USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@���߂ē��e�����Ă��������܂��B �@���ݎ莝����USB�ڑ��̃J�����𐔑䏊�L���Ă��܂��B �@������r�f�I�i�q�e�M���j���͑Ή��̃r�f�I�f�b�L����繫���Ŗh�ƃJ�����Ƃ��Ďg�������̂ł����A�����ǂ����@�͂���ł��傤���H�B �@�t�r�a�J�����̏o�͂̓f�W�^�����邱�Ƃ͗������Ă��܂����A�ԂɐM���ϊ��̋@�킪�K�v�ɂȂ邾�낤�Ǝv���Ă��܂��B �@����ȂǂőΉ��o���Ȃ��ł��傤���H �@�X�������肢���܂��B �������� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�������ܗl�A�͂��߂܂��āB �@USB�J�����ɂ��F�X����܂����A�悭�o�b�V���b�v��Ɠd�ʔ̓X�Ŕ����Ă���悤��1980�~�`5000�~���炢�̕i���ƁA����CCD/C-MOS�B���̃h���C�u��H���݂�USB�ʐM�����pLSI������Ă��āA�J�����̒��ł�NTSC�f���M��(���{�ȂǂŎg�p����Ă���f���M���̋K�i)�̕����͂���܂���B �@���̂悤�ȃJ��������s�u�ɉf���悤��NTSC�f���M������낤�Ƃ���ƁAUSB�[�q������o����f�W�^���ʐM�f�[�^������āANTSC�f���M���ɕϊ����鑕�u���K�v�ł��ˁB (1) USB�K�i�ŒʐM�ł���}�C�R���E�n�[�h�E�F�A (2) ���̃}�C�R����œ���OS(�܂��͑S������) (3) �e�Ђ�USB�ʐM�f�[�^�̃t�H�[�}�b�g��ʐM�p�����[�^��m���Ă��鎖 (4) USB�ʐM����640�~480dot���̃t���J���[CG�ɕϊ��ł���Z�p (5) �r�f�I�R���g���[��(��pLSI)����RGB�r�f�I���������������r�f�I�o�b�t�@�̃n�[�h�E�G�A (6) ���̃r�f�I�p�n�[�h�E�G�A�𐧌䂷��Z�p (7) �r�f�I������(�R���g���[��)����A/D�R���o�[�^��ʂ��ďo�͂����RGB�r�f�I�M����NTSC�r�f�I�M���ɕϊ�����n�[�h�E�F�A(����͏H���̃L�b�g�Ȃǂ��L��) (8) NTSC�r�f�I�M����RF�M���ɕϊ�����n�[�h�E�F�A(������r�f�I���M�@���̋@���L�b�g���L��) �@�Ƃ܂��A��G�c�ɏ����Ă��ꂾ���̃n�[�h�E�F�A�ƃ\�t�g�E�F�A�����Ȃ������g�ő�������u����v�͂ł��܂��B �@���ɓ���̂́A�}�C�R������USB�ʐM������t�@�[���E�F�A�Ƃ��̃J�����̒ʐM�t�H�[�}�b�g�p�̒ʐM�h���C�o�������Ƃ���ƁA�����͂��܂茩�����Ȃ��r�f�I�R���g���[����LSI���ǂ��i��߂����ē��肷�邩�B �@�g�p�}�C�R����PIC�̂悤�ȏ��K�͗p�̕��ł͂��߂�H8�V���[�Y���x�͕K�v�ł��傤�ˁB(�ŋ߂͂����ƐF�X����܂����炨�D���ȕ���) �@�Ȃɂ���r�f�I�������[�Ƃ��F�X��I/O�ő�ʂɌq���Ȃ���Ȃ�܂��A�r�f�I�R���g���[���̐���(�����ݒ�)�Ȃǂł��S��I/O�ڑ��ŃK�V�K�V���䂷��K�v������܂��B �@�r�f�I�������[����A/D�R���o�[�^��ʂ���NTSC�^�C�~���O��RGB�f���M�����o���܂ł̉�H�}�̓r�f�I�R���g���[���̋Z�p�����ɍڂ��Ă���Q�l��H�}�����č����������͍���Ǝv���܂��B �@���[��A�f���o�͂̌`����q�����͏����Ⴂ�܂����A���N��NEC�̂W�r�b�g�}�C�R���uPC-8801�v����䂭�炢����ł���Z�p�͂̂��邨���Ȃ�AUSB�J�����ƒʐM���ĉf���M����NTSC�ŏo�����u�͍���Ƃ����������ł��B �@CPU������[�Ƃ��������i�̐��\��PC-8801�̍�����l����Ɣ���I�ɗǂ�������ɓ���܂����A�r�f�I�M���܂��Ȃǂ͋t�ɍ��ł͏H�t���ȂǂŊȒP�Ɏ�ɓ��镔�i�ł͍��ɂ����Ȃ��Ă��܂��ˁB �@�͓̂������̃r�f�I�R���g���[���[LSI�ƍ����\�̃f���A���|�[�gSRAM(�����N���m��Ȃ�����)�Ȃ��Ă��āA�����Ńp�\�R��(�����̓}�C�R��)�ɒlj�����u�t���O���t�B�b�N�r�f�I�{�[�h�v�Ȃ����삵�����̂ł��B �@�t�ɍ��ł�DOS/V�p�\�R���ɑ}���u�O���t�B�b�N�{�[�h�v��p�ӂ��āA����̃o�X�ڑ����@�⒆�̃R���g���[���`�b�v�̐���R�}���h���̋Z�p�����������āA�����H8���̃}�C�R���{�[�h�ƌq�����ق����r�f�I�M���̏o�͂܂��͂�������������邩������܂���ˁB�O���t�B�b�N�{�[�h�ɂ�NTSC�r�f�I�M�����o�͂ł���^�C�v�������ł����B �@�Ƃ������ŁA���ꂾ����ςȊJ�����������ōs���C�͂ƗE�C�ƁA�����̋Z�p�͂�������ł����為�Ѓ`�������W���Ă��������B �@�u����Ȃ̖����I�v�ł��ʂɒp�����������Ȃ�Ƃ��Ȃ��ł���B����]�̕i�͂��ꂭ�炢�̘J�͂������Ȃ��ƍ��Ȃ����ł�����B �@�����|���t����USB�J�����̐M����NTSC/PAL�o�͂ł��郏���`�b�vLSI�Ȃ������Ă���Ȃ�A�����m�̕��͏���������������ܗl���e�Ղɂ���]���������邩������܂���B �@�����₻�̑���LSI�s��ɏڂ������Ȃ�A��������LSI�̑��݂�l�ł̓�����@(���݂��Ă����ꂪ����c)���������肦��Ə�����܂��B �@������������LSI������A�^����ɏH���d�q�ʏ����L�b�g�����Ĕ����Ă������ł����ǁi�O�O�G ���Ԏ� 2009/10/16
|
|||||||||||||||||||||||
| ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB �@555�^�C�}�ƃ����[�i12�`���x�j���g�p���āAON��1���i�Œ�ł��j�EOFF���ϒ�R���g�p��3���`6���̒������\�ȉ�H���l���Ă���̂ł������S�҂ׁ̈A�ǂ̂悤�ȃp�[�c�i�R���f���T���R�j���ǂ̂悤�ɔz�đg�グ��Ηǂ��̂��킩��܂���B �@�g�p����d���͂c�b12�u�ł��B �@�X������Ή�H�}���܂߁A�������肢�܂��B �@�X�������肢�v���܂��B ���肷�� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�^�C�}�[IC 555���g�p������H��́uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�v�Ōf�ڂ��Ă��܂����A��������Ē��ׂčl���ĉ��p����E�E�E�Ƃ����̂̓_���������Ƃ������ł��傤���B �@��H�̐����́uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�v�̂ق��ł��Ă��܂��̂ŁA�K�v�ł�����ǂ݂��������B �@���̉�H�}�̒ʂ�ɑg�ݗ��āAVR1��VR2�ł��ꂼ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ����D���Ȏ��Ԃɒ��߂��Ă��������B �@�����[��OMRON��LY1 DC12V�ł��̂ŁA�R�C���d����75mA��555�Œ��ڃh���C�u�ł��܂��B�ړ_��DC12V�Ȃ�ő�15A�܂Ŏg�p�ł��܂��B12A���x�Ƃ����ړI�Ȃ���v�Ȃ͂��ł��B �@���x�������Ă��܂����A���i�̕��ו�(��̍���)�Ȃǂ͂�����ł͂��������Ȃ����ɂ��Ă��܂��̂ŁA���͂ŕ����Ă��������B ���Ԏ� 2009/12/7
|
|||||||||||||||||||||||
| �@�����L���� ���A����܂��B | ||||||||||||||||||||||||
| ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�R�ł̌F�悯�p�̑剹�ʂ̊Ԍ��u�U�[����낤�ƍl���Ă���܂��B5�`10�b�ԂɈ��s�b�Ɩ炵�l�Ԃ̑��݂��F�ɒm�点����̂ł��B �@��ɓ���₷�����i�ł̉�H���l���Ă��܂����A�^�C�}�[IC�ł̂��̂悤�ȃC���^�[�o���ł̓����H�����܂����B���������肢���܂��B masa �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ł��|�s�����[���^�C�}�[IC 555�̃A�v���P�[�V������ɁA���̂悤�ȖړI�́uON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ���U��H�v�Ƃ������̂�����܂��B �@���ʂ͏[�d�ƕ��d�͓�����RR2��ʂ��čs���̂ł���(���ۂ͏[�d�̎���R1���ʂ�)�A�����Ƀ_�C�I�[�h�ƒ�R(����͔��Œ��R)��lj����ď[�d���鎞�ƕ��d���鎞�ŕʁX�̒�R��ʂ�悤�ɂ��A�ʁX�̒�R�̒l��ς��邱�Ƃŏ[�d����(��ON����)�ƕ��d����(��OFF����)�����ꂼ��ʂɐݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B �@���̉�H�}�ł�ON��������0�`1�b�B���ɂ���Ɓu�s�b�v���u�s�[�v���炢�̒����Ńu�U�[��炷���Ƃ��ł��܂��B �@OFF��������0�`10�b�ŁA�u5�`10�b�ԂɈ��s�b�Ɩ炷�v�Ƃ����ړI�ɍ����悤�ɂ��Ă��܂��B �@LED�œ�����m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B �@����́u�^�C�}�[IC�ł̂��̂悤�ȃC���^�[�o���ł̓����H�����܂����v�Ƃ���������ł����̂ŁA�u�U�[���͍��Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂����̂ŁA�f���p�̔��U��H�����̒Ƃ����Ă��������܂��B �@�u�U�[�͎s�̂̓d�q�u�U�[(200mA�ȉ�)���g�p���邩�A�^�C�}�[IC 555��������g���ēd�q�u�U�[�������Ƃ悢�Ǝv���܂��B555�œd�q�u�U�[�������ꍇ�́A���̒f����H�̏o�͂U��H��555�̃��Z�b�g�[�q(�S�ԃs��)�ɐڑ����Ĕ���/�����𐧌䂵�܂��B555���g�p�����u�U�[��H�́u�����e�̓I����肽���v�ɍڂ��Ă��܂��̂ł����X������ΎQ�l�ɂ��Ă��������B �@�Ȃ��AON���Ԃ�OFF���Ԃ�ς��Ȃ������̃u�U�[�f���p�̔��U��H�́u�u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j�v�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B ���Ԏ� 2009/10/7
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̉��ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�����͂T�T�T�̃I�t���Ԃ������H���l���t���܂���ł����B��������Ă݂܂��B masa �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@555�Ȃ�ǂ��ł���ɓ���܂����A����555�ŕ��ʂɃ^�C�}�[��H�Ȃǂ��e�X�g���ꂽ���Ƃ�����Ε��i�����茳�ɗ]���Ă��邩������܂���B �@�u��ɓ���₷�����i�Łv�Ƃ��������ł͂���قǓK�������i�͂ق��ɂ���܂���A���Ђ��������������B �@�܂��A�u��ɓ���₷�����i�Łv�Ƃ������b�ɉ����ĉ�H�}���ڂ��Ă����A���̗p�r�ʼn�H�}��T���Ă���悤�ȕ��̎Q�l�ɂ��Ȃ�₷���Ǝv���܂��B����̂�����͗ǂ��e�[�}���Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2009/10/16
|
|||||||||||||||||||||||
| �@�����L���� ���A����܂��B | ||||||||||||||||||||||||
| 5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�����������Ē����Ă���܂��B �@�����ł���cds�Z�����g�������u����낤�Ǝv���܂��B �@�ŁA�u���̉�H��ς��Ďg�������v�Ɓu5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H�v���Q�l�ɂ����Ē����Ă���̂ł��� �@�u5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H�v��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ē����܂���ł��傤���H �@�܂��A���̍ۃ����[�͂ǂ̗l�ȕ����]�܂����ł��傤���H�^�������ĉ������B �@��ς����Z�̒��s�^�Ȃ��肢�ł������܂����������X�������肢�\���グ�܂��B ������ �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�͂��E�E�E�E�A�܂�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̐����ł͑S���킩��Ȃ������Ƃ������ł����B �@���݂܂���B �@���݂܂���B �@���݂܂���B �@���̐������킩��ɂ��������̂ł��ˁB �@�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̃����N��̉�H�}���q���ɂ͂��̂悤�ɂ��܂��B  �@��₱�����b��ǂ݂������͂��̒������ǂ݂��������B �@�ǂ݂����Ȃ����͓ǂݔ���ĉ��܂ł��i�݂��������B
�@�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̃����N��̉�H�}�̂Ƃ���A10K���̒�R�������Ă��Ȃ�Ƃ������Ƃ͎v���܂����A�v���A�b�v��R�͓���Ă������ق�������ł��B
�@�v���A�b�v��R�������ꍇ�A�g�����W�X�^�������Ă��Ȃ����ɂ�74HC123�̓��͂�LED��LED�̓d�������p��R�o�R�Ńv���A�b�v����Ă����ԂŁALED(�ԐF)��Vf�Ԃ�d���~���������Ė�3.8V(����)�����^�����܂���B�����ΐF��F��LED���g�p����������Ɠd����������ł��傤�B �@�f�[�^�V�[�g���A74HC123�̃V���~�b�g���͂ł���A�EB���͓͂d��4.5V�̏ꍇ3.15V�ȏ��A�d��6.0V�̏ꍇ4.2V�ȏ��Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�d��5V����3.8V�ł͂��肬�肵����i�����Ă��܂���B �@���̂܂܂ł��Ȃ�Ƃ������Ƃ͎v���܂����Aikikko�l������ē����Ă���悤�Ȃ̂Łu���l�l�̏����ꂽ��H�}�����A�������Ȃ��Ă��܂��������v�Ǝv���Ă��܂������A���̉�H�ƌq���̂ł���ΐ������v���A�b�v������Ԃ����肵�������Ŏg���Ă������������Ǝv���܂��B �@���łɁA�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̃����N��̉�H�}�ł͈Ӗ��s���ȂƂ���Ƀ_�C�I�[�h�����Ă��܂��B���Ă����Ȃ��Ă�����͕ς��܂���B(�Ƃ������s�v�ȏꏊ�ɂ��Ă���) �@74HC123/221���g�p����ꍇ�A�^�C�~���O�p�R���f���T�̗e�ʂ��傫���Ɠd��OFF���ɗ��܂����d�ׂʼn�H���Ă��܂��\�������邽�߁A���d�p�o�H�����ׂ̃_�C�I�[�h������悤��������Ă��܂��B(�����܂ł�����̗e�ʈȏ�̏ꍇ�ł�) �@���̏ꍇ�̓R���f���T�ɗ��܂����d�ׂ��u�d�����C���ɕ��d���ē������v���߂ɃR���f���T�́{����Vcc�̊ԂɃ_�C�I�[�h������̂ł����A�Ȃ����s�v�c�ȂƂ���Ƀ_�C�I�[�h�������Ă��܂��ˁB�S�����ɗ����Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�u�d���R���f���T�ɋt�d����������̂�h�~����_�C�I�[�h�H�v�Ƃ��v���Ă��܂��̂ł����A�܂������ɂ��郊���[�̃R�C�������������t�d���X�p�C�N���z������_�C�I�[�h�̂悤�ɓd���R���f���T���t�d����������A���̉�H�}�ŋt�d�����������ăR���f���T���p���N������悤�Ȃ��Ƃ͖����Ǝv���̂ł����A�Ȃ��Ȃ��ɓ�ȉ�H�}�ł��B �@����A�M�҂̕����Ԉ���Ă���̂��Ƃ͎v���܂����A���̓d�q�ƊE�ł͈Ќ��̗L���b�p�o�Ŏ��̔��s���ЂŃv���A�b�v�������Əo���ċ��Ȃ�������A74HC123/221�̕ی�_�C�I�[�h���ςȂƂ���ɂ��Ă����H�}���f�ڂ��Ă���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��̂ł����E�E�E�B �@������������A�킴�ƃv���A�b�v�d����Ⴍ����74HC123/221�̃g���K�[��������ɂ������鎖��Cds�̌����������E�܂ň������Ă�Ƃ��A���̃_�C�I�[�h��74HC123/221�̃f�[�^�V�[�g�ɂ������Ă��Ȃ����ʂȈӖ�������̂�������܂���̂ŁA���������m�̕��͂��������������B �@�u�����[�v�̑I�ʂɂ��ẮA���͂����ߗl�����̖ړI�łǂ�ȑ��u�ɂǂ�ȓd���łǂ�ȓd���𗬂��ׂɃ����[�����g���ɂȂ�̂��S��������܂���B �@�����P����������̂́A�F���ǂ̂悤�ȃ����[���g���̂��킩��Ȃ��̂����̉�H�}�ł̓g�����W�X�^��2SC2120�ɂ��ēd���e�ʂɗ]�T���������Ă��܂��̂ŁA�R�C���d����500mA�߂��܂ł̒��^���炢�܂ł̃����[���g�p�\�ł��B�u���̉�H��ς��Ďg�������v�̃����N��̉�H�}�̂悤��2SC1815���g�p���Ă�ꍇ�̓R�C���d����100mA�ȉ��̏��^�����[�����g�p�ł��܂���B �@�ړI�ɉ����ă����[��I�肷��ۂɃh���C�u��H�̓d���e�ʂ��l���āA�e�ʂ��z���Ȃ��R�C���d���̃����[�����g�p���������B ���Ԏ� 2009/10/6
|
|||||||||||||||||||||||
| �ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�Ǘ��l�l�A���͓Y���������������������݂����Ă��������܂��B �@�o�C�N�̃E�B���J�[�X�C�b�`���I���^�l�C�g�������V���b�g(ON-OFF-ON)�ɕύX�������ƍl���Ă��܂��B �@����Ƃ��܂��ẮA���͉͂E�Ȃ����͍��������V���b�g�œ��͂��A�L�����Z���͂�����x������������͂���B �@�Б��̃E�B���J�[���쒆�ɔ��Α�����͂����ꍇ�͂������L���ɂ���B �@�Ƃ���������ł��B ��B �@�E��ON���E�E�B���J�[���쁨�E��������xON�ŃL�����Z�� �@�E��ON���E�E�B���J�[���쁨��ON�����E�B���J�[���쁨��ON�ŃL�����Z�� �@�����Ńt���t���ōl���Ă݂��̂ł������܂����Ă��܂Ƃ܂�܂���ł����B���Z��������ϋ��k�ł����������X�������肢�\���グ�܂��B �܂��� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����A�Б��̃X�C�b�`���삾���l����u�Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂����v�Ōf�ڂ��Ă����H�}�ōς݂܂��B �@�t���b�v�t���b�v���g���āu��x�X�C�b�`����������ON�v�u������x��������OFF�v�ɂȂ��g�O�������������邱�Ƃ́A�t���b�v�t���b�v�̓��삪�킩����ɂ͊ȒP�ł��ˁBD-FF��JK-FF���g������H�}�̓t���b�v�t���b�v�̋��{��z�[���y�[�W�ɂ悭�Љ��Ă��܂��B �@�Ƃ��낪����́u���E�ŕʁX�̉�H�v������A���ꂼ��P�Ƃł͂Ȃ��u���Α������䂵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���̂ł��B �@�ꌩ��₱�����悤�Ɍ����܂����A���͂ƂĂ��J���^���Ȃ̂ł��B �@�u�Б��̃E�B���J�[���쒆�ɔ��Α�����͂����ꍇ���������L���ɂ����v�Ƃ��������ł����A�X�C�b�`������������L���ɂ����ƍl����ƂƂĂ�����̂ł��B �@�����ōl����(������)��ς��āu�����Е��̃{�^���������ꂽ��(ON�ׂ̈ł�OFF�ׂ̈ł�)�v�u���Α��̃E�C���J�[�͐�(�������Α���OFF�ł���Ƃ�������ł悢)�v�Ƃ��܂��B �� �X��u�{�^���������v�Ə����Ă��܂����A���ۂ́u�E�C���J�[�X�C�b�`�̃��o�[��|��(�X���C�h������H)�v�ł��B���̉�H�͑��̗p�r�ł��g���܂�����悭�g���{�^������������Ő������Ă��܂��B �@�Е��̃{�^���������ƁA������̃E�C���J�[��ON�܂���OFF�̐�ւ���������܂����A���Α��͕K����Ȃ���Ȃ�܂���B���ʂ�ON�ɂ��鎞�Ɂu�������Α���ON�Ȃ�����{�^�����������ق���D��ɂ����v�Ƃ����_����H���l���܂����A�E�C���J�[��OFF�ɂ���ׂɃ{�^���������Ă����Α���OFF�ɂ��铮��������Ă��������͂���܂���(���ʂ͔��Α��͏����Ă��܂���)�B �@�����l����ƁA ���{�^�������� �@�@�@����> �����瑤�̃t���b�v�t���b�v�]������ (���ʂ̉�H) �@�@�@����> ���Α��̃t���b�v�t���b�v���N���A���� �Ƃ�����H�������������ŁA���͕��ʂ̃g�O������̃t���b�v�t���b�v�ɔz������{�lj����āu���Α��̃t���b�v�t���b�v���N���A�����v�����ł����̂ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@��H�}�͂��̒ʂ�A���ʂ̃g�O������̃t���b�v�t���b�v��H�����E�̃E�C���J�[�p�ɂQ�g�p�ӂ��āA���ꂼ����{�^������(FF�̃N���b�N����)�Α����N���A�[�q�ɐڑ����邾���ŁA�Е���FF�]������X�C�b�`���͂�����Δ��Α���FF�̓N���A����āA����ON�Ȃ�OFF�ɁAOFF�Ȃ炻�̂܂ܕς炸OFF�̏�ԂƂȂ�܂��B �@���̉�H�ł͊eFF�̃N���A�[�q���p���[�I�����Z�b�g��H�͕t���Ă��܂��A���̓{�^�����͕����ɂ��Ă����`���^�����O�h�~��H���p���[�I�����Z�b�g��H�ƑS�������\���̂��߁A�d������ꂽ�ŏ��̈��ڂ̓d���R���f���T���[�d�����܂ł̎��Ԃ����Α���FF�̃��Z�b�g�Ɏg�p����A���ʓI�ɗ�����FF�͓d��ON�Ɠ����ɃN���A����ăp���[�I�����Z�b�g�Ɠ�����������܂��B �@���i���팸�E�E�E�Ƃ������P�̉�H���Q�̗p�r�ɓ����Ƃ����ƂĂ��g���b�L�[�ȉ�H�ł������낢�ł���H �@�f�W�^����H��v���鎞�ɂ́A�ړI�̑��u�̓����𐳖ʂ��琳�U�@�ōl����ȊO�ɁA�u������p�]���Ă݂�v�Ȃǃf�W�^����H�Ȃ�ł͂̃C���o�[�^�I���_�ōl���Ă݂�ƈӊO�ƃA�b�T���Ɖ������邱�Ƃ������ł���B �@����ƁA�t���b�v�t���b�v�������ł����A�J�E���^��V�t�g���W�X�^�Ȃlj��炩�̕��G�ȋ@�\��������IC���g�p����ꍇ�͂���IC�ɕt���Ă���e�[�q�̂悤�����悭���Ċώ@���邱�Ƃł��B���Z�b�g�[�q�Ȃǂ������̋@�\���������[�q�����Ă���͂��ł�����A�u���̒[�q�͉����낤�H�v�u�����ɐM��������Ƃǂ������̂��ȁH�v�ƍl���Ă݂�ƁA���{���H�}�̍ڂ����z�[���y�[�W�̓���̎g�����ȊO�ɂ���IC�̎g�������킩���Ă������ʼn�H�}���l���鎞�ɂ����ւ���ɗ����܂���B ���Ԏ� 2009/9/23
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 9/28 |
�@�Ǘ��l�l �@���������肪�Ƃ��������܂��B���ɋC�t���̂��x��Ă��܂��\����܂���B �@���ꂩ���H��ǂݎ�藝�����������ō쐬�������Ǝv���܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����B asami �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���̉�H��ς��Ďg������ | ||||||||||||||||||||||||
|
�Ǘ��l�l�A���������������Ă���܂��B �@���̐߂͑�ς����b�ɂȂ肠�肪�Ƃ��������܂����B �܂��搶�̂��͓Y���������������������݂��Ă܂��B ���̃T�C�g�́uhttp://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/37/37281/37281_7SYO .pdf�v��ԉ��́u�Ռ��Z���T�[�̐���v�̉�H���h�������������h�����莞�ԃ����[�삳����l�ɉ�������ɂ͂ǂ̗l�ɂ�����X�����ł��傤���H ���Z��������ϋ��k�ł����������X�������肢�\���グ�܂��B ikikko �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@(�`)�_��74HC123�̂Q�ԃs����藣���B �@�Q�ԃs����Vcc�ɐڑ�����B �@�P�ԃs����GND�ɐڑ�����Ă���̂�藣���B �@(�`)�_��74HC123�̂P�ԃs����ڑ�����B �@�����74HC123�̃g���K���삪�t�ɂȂ�܂��B �@�ȏ�ł��B ���Ԏ� 2009/9/19
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 9/19 |
�@����ɂ��́I�I �@�Ǘ��l�l�A���d�����������ăr�b�N�����Ă��܂��B �@������T�C�g�̉�H�ɏƂ炵���킹�Ċ����ڎw���܂��I�I �@���̓x�̂������S���炨��\���グ�܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����A����v���܂��B ikikko �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 10/5 |
�@�Ǘ��l�l �@�����l�ŏ�肭���삳���鎖���o���܂����B �@���ꂵ���ł��I�I�I �@���肪�Ƃ��������܂����B�B ikikko �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� | ||||||||||||||||||||||||
|
���݁A�H���̂R�f���Z���N�^�[�L�b�g���g�p���Ă܂����A�g�p�@��𑝂₵�����̂őΉ��ł���U�f���Z���N�^�[�������������Ǝv���܂��B�H���L�b�g�������P��lj����āA�Q����X�C�b�`�Őؑւ悤���A�ł��邱�ƂȂ�莝����TC9135P(�U�ґ���X�C�b�`�h�b)�Ń~�j�����[�U�Őؑւ���R���p�N�g�Ɏ��܂�̂����Ȃǂƍl���Ă���̂ł����A�f���M���̎戵���ɂ͂ǂ���75���̒�R��10��F�̃R���f���T�[�̑g�ݍ��킹��H�������K�v�Ȃ悤�ŁA���͕��̓L�b�g�Ɠ�����H�ɂ���Ƃ��ďo�͕��ł͂ǂ̂悤�ɑg�ݍ��߂����̂��������Ă��������������e���܂����B���掿��Nj����Ă���̂ł͂Ȃ��A���̒m��Ȃ��f���M���̎戵���ɂ����邨���݂����Ȃ̂����肻���Ȃ̂ŁA�Œ���̎�@�����͉������Ă������j�^�[�������Ȃ��Ƃ̋C�����ł��B�����Ɨǂ����@������̂Ȃ玄�̎v���t���ɂ͌Ŏ����܂���B�f���M���̎戵���������͉�H�}���������ł��B�m���ɖR�������S�҂ł����ǂ�����낵�����肢���܂��B �Ƃ����� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͂��߂ɊȒP�Ȃق��̌��_�����B �@TC9135P�����^�����[���U�g���āu�f���U�I����v�����̂ł�����A�f���M���̓���b�͑S�������ō\���܂���B �@75���̒�R��10��F�̓d���R���f���T�͑S���K�v�Ȃ��A�f�����͂P��H���ƂɃ����[���P���āATC9135P�łǂꂩ��̃����[���������悤�Ɍq���ł����ꂾ���ŏ\���ł��B �@����́A�d�C�X��Q�[���V���b�v�̓X���Ŕ����Ă���d�r�s�v�̃K�`���K�`���ƃX�C�b�`���ւ��ĉf���E�������͂��R���炢����I�ԁuAV�Z���N�^�[�v�Ɠ����\���ŁA���g�͂����̋����ړ_�����̃X�C�b�`���������Ă��Ȃ����̂ł��B �@�����I�ɂ͔z�����������ĕ����̋@����q���ς���̂Ɠ����ŁA���̔z���ɂ�75���̒�R��d���R���f���T�͓����Ă��܂����ˁB�����Ă���͉̂f�������@��(�s�u)�̒������ł��B �@�ł�����TC9135P�����^�����[�ŒP�Ȃ�z���ؑփX�C�b�`������āA�f���M���͔z���ؑփX�C�b�`�Ő�ւ��邾���Ȃ������Ƃ͂܂������l���Ȃ��Ă����v�Ƃ����킯�ł��B �@�ł́A���͓���b���B �@�H���́u�R�f���Z���N�^�[�v��A�Ɠd�X�Ŕ����Ă���d���̂���AV�Z���N�^�[�ɂ͒��Ɂu�d�q��H�ɂ��X�C�b�`�v�������Ă��܂��B�H���̃L�b�g�ł͐�ւ��@�\��IC���g���Ă��܂��B �@���������d�q��H�ň�U�f���M�����āA���œd�C�M���̂��Ƃ�������ꍇ�ɂ͉f���ؑ։�H���̂��u�f���M������M�����H�v�Ƃ��ē����A���̏ꍇ���f���M����d�C�I�ɓ`�B����ۂ̍��ۓI�Ȏ�茈���Ɋ�Â����菇�E��H�œd�C�M������舵��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�܂���U�d�q��H�Ŏ�����f���M�������H(�Z���N�^�ł͐ؑւ݂̂ł����c)�Ȃǂ�������ق��̉f���@��ɑ��M�����ꍇ���f���M����d�C�I�ɓ`�B����ۂ̍��ۓI�Ȏ�茈���Ɋ�Â����菇�E��H�E�M���̌`�ő��M����K�v������܂��B �@�����ʼnf���M���̒��g�ɂ��Ă͐[���͐G��܂��A���{���̗p���Ă���f���M����NTSC�����ƌĂ��f�������ŁA�P�b�Ԃɖ�R�O��(�����ɂ͂Q�{��60��)�̉摜�𑗂��ē������ʂɉf�������݂ł��B �@�f���M���̓d������P�u�ŁA���̒��ɗl�X�ȏ�ڂ���ꂽ�����ւ����d�C�M���ɂȂ��Ă��܂��B �@�����Ă������Ȃ̂́A������P�u�Ƃ����d���͕K�����Ȃ���Ȃ炸�A������0.5V��Q�{��2V�ȂɂȂ�Ǝ�M���̉f���@��ł͂����Ƃ����f���M���Ƃ��Ď�舵���Ȃ��Ȃ�A�摜���f��܂���B �@���̂��߂ɉf���M���Ƃ����d�C�M�����@��Ԃő��M�E��M���邽�߂̂Ƃ肫�߂��ׂ������߂��Ă��܂��B �@���̒��̂P���d�C�z���́u�C���s�[�_���X(�Ӗ��͌𗬒�R)�v�ł��B �@�����M����f���M���A�܂��d�g�Ɏ���܂œd�C�M���ɐU��������u���v�̐������������d�C�̏ꍇ�͂����`����d���̓����Ǝ��d�q��H���𗬒�R�l�ɑ傫�ȉe�����A���̒�R�l���ł����肵�Ă��̓d�C�M����`�B��������悤�ɒ��߂���Ă��Ȃ����������c�����������Đ������`�ŐM����`�����Ȃ��Ȃ�܂��B �@�f���M���Ɍ�����c�݂���������ƁA���ꂱ����ʂ��c��{��������܂Ƃ��ȉ�ʂł͌���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B �@�����ʼnf���M���ł́u�C���s�[�_���X75���œ`�������v�ƌ��߂��Ă��āA�f���𑗂鑤����鑤���S�ăC���s�[�_���X75���ʼn�H�����삷��悤�ɐv���܂��B �@�f������鑤�ł́A�u�f���M���͕K��75���̒�R�ŃA�[�X�Ƃ̊Ԃ̒�R�l(�C���s�[�_���X)��75���ɂ����v�ƌ��߂��Ă��܂��̂ŁA�����Ă��̋@��͂��������v�ɂ��܂��B �@�������A����ȓd�q��H�̋@��ł͂��̂悤�Ȍ��܂�ɏ]���Ă��Ȃ��ꍇ������܂��̂�100���������ł͂���܂��A���ʂ�75���̒�R���t���Ă��܂��B�H���́u�R�f���Z���N�^�[�v�������ł͂���܂��H �@10��F�̓d���R���f���T�͓��͕����̓d�q��H�Ƃ̊Ԃ̃J�b�v�����O�p�ŁA�d�q��H�̐v�ɂ��0.1��F�̎��������100��F�̎�������A�K������10��F�̓d���R���f���T�Ɛ��E���Ō��܂��Ă���킯�ł͂���܂���B����͌X�̋@�펟��ł��B �@�f���M�����鑤�ł͍Œ���͂��̂悤�ȃC���s�[�_���X�����̎葱��������Ă��܂��B �@����ǂ͓d�q��H����f���M���𑼂̋@��ɑ��M����o�͉�H�̏ꍇ�A�u�f���A���v�v�Ƃ�����H���g�����W�X�^�ō�������p���f���A���vIC���g���Đ�ɐ����������ۊ�̓d����C���s�[�_���X�ő��M�ł���悤�ȓd�C�M�������܂��B �@�����ł̓C���s�[�_���X75���̓`���o�H�ɓK�����d�C�������������A�c�݂Ȃǂ̕s����ł����Ȃ��Ȃ�悤�Ȓ��ӂ����v�ɂ��܂��B �@��H�̎�ނ�IC�̎�ނ͖L�x�ɂ���܂��̂ŁA��������Ő��삳���ꍇ�͊eIC�̃f�[�^�V�[�g�Ȃǂ������ɂȂ��āA���������i�����Đ������f���A���v������悤�ɂ��Ă��������BIC�̎�ނ��������Ĉꌾ�őS�������ł���悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B �@�d�q��H�ʼnf���M������M������A���M�����肷��ɂ͓���u��@�v������A�f���M���̎d�g�݂��茈�߂��悭���ׂė���������ʼn�H�v������K�v������܂��B �@���������d�q��H�ʼnf���M������舵��Ȃ��ꍇ�A��̃����[�Ő�ւ���ȂǒP�Ȃ�z���ؑւ̏ꍇ�͂��܂����l���邱�Ƃ͖����A�P���ɃX�C�b�`�Ń|���Ɛ�ւ��邾���ł��\���܂���B �@�s���A�I�[�f�B�I�⒴���掿�f���}�j�A�A�܂��s�u�ǂ̂悤�ȃv���̃��x���ł́A�f�����ւ���ׂ̒P�Ȃ�X�C�b�`�ł��������C���s�[�_���X75���Ŗ�������s�����������ĐM���ɘc�݂ތ����ɂȂ�̂ŁA�f���`���P�[�u���̓r���ɂ���ȕ������ނ����ł������Ȃ����ɂȂ�̂ł����A��ʉƒ�(����͎Ԃ̒�)�łs�u�̑O�ɉf���Z���N�^�[�Ƃ��ăX�C�b�`�����邭�炢�ł͖{�l�����e����Ȃ�ʂɖ��ɂ͂Ȃ�܂���B �@���́A�v���̐��E�ɂ̓C���s�[�_���X75���̌o�H�ɓK�������Ɩ��p�́u�f���M����ւ��p�����[�v�Ȃ�Đ����������݂��܂��B���ꕔ�i�Ȃ̂ŕ��ʂ̓p�[�c�X�Ȃǂł͔����Ă��܂���B �@�ŏ��ɏ������悤�ɁA����̖ړI�ł͕֗���TC9135P�����ɂ������̂悤�ł����A���ʂ̏��^�����[�Ő�ւ��鑕�u�������̂��ȒP�ł悢�ł��ˁB ���Ԏ� 2009/9/19
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
���Z�������̉A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B ���̊�]���P�Ȃ�z���ؑւȂ̂œ���l���Ȃ��Ă��悢���Ƃ��킩��܂����B��������ɂ��Ă͂܂��܂������ł��܂������������Ď����̗͗ʂɍ�������H�Ŋy���݂����Ǝv���܂��B����ň��S����TC9135P�̐����H�ɖv���ł��܂��B��ԑ�ȉf���ؑւɂ��Ă��s�����������̂ŁA��Ԃł������₷���Ɩ��t�Z���N�g�E�X�C�b�`���Ƃ��A�o�b�N�M���Ńo�b�N�J�����Ɏ����ؑւƂ����낢��ȕt����H�ɐi�ނ��Ƃ��ł�����X�Ƃ��Ă���܂����B���ӂ��猳�C�n�c���c�łƂ肩���肽���Ǝv���܂��B����Ƃ���낵�����肢�������܂��B���肪�Ƃ��������܂����B �Ƃ����� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�o�b�N�M���Ƃ����@�\�ŁA�F�X�y�������ȍH��ɂȂ肻���ł��ˁB �@�撣���Ă��������I ���Ԏ� 2009/9/19
|
|||||||||||||||||||||||
| 5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�����m���̔q�������Ē����Ă�҂ł��B�����b�ɂȂ�܂��B �@�����ł����B �@�u5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H�v���̋L�����ȑf���ɏo���Ȃ����Ǝv���������݂����Ē����Ă܂��B �@5V�̓d�C��������0.5�`1�b�Ԃ����k�d�c�_�������鑕�u����肽���̂ł��������ς܂�����@�����Ē����܂���ł��傤���H �@���Z�������\�������܂��ǂ����X�������肢�������܂��B �C�ɂȂ�l �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ς܂���Ƃ������ŁA�g���[�h�I�t�Ƃ��āu��@�\�v�ɂȂ鎖�͂������Ƃ��������������B �@������@�\�ɂȂ�̂��͏���ǂ��Đ������܂��B  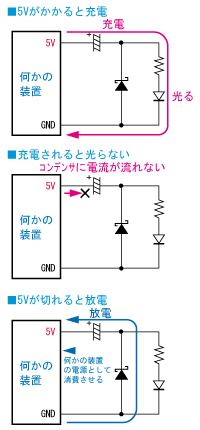 �@5V�Ƃ����̂́A�����̑��u�̓d����5V������Ɖ��肵�܂��B
�@5V�Ƃ����̂́A�����̑��u�̓d����5V������Ɖ��肵�܂��B(����ȊO�͌�Ő������܂�) �@�����̑��u�̓d��������ƁA�{��H�̓d���R���f���T���[�d����͂��߂܂��B �@���̎��[�d�d���͒�R���o�R����(�d�����������)�k�d�c�ɗ����k�d�c������܂��B �@�ŏ��͓d���R���f���T�̒��̓d�C�͋�Ȃ̂ł�������d��������A�[�d���i��ŏ��X�ɓd�����オ��Ɠd��������Ȃ��Ȃ��Ă䂫�܂��B �@���̂����k�d�c�͍ŏ��̏u�Ԃ͔��ɖ��邭����A���X�ɈÂ��Ȃ��Ă䂫�܂��B �@�^�C�}�[IC��g�����W�X�^��H�Ȃǂ��g���Ă��������ON��OFF���ւ����H�ł͂Ȃ��ȑf����H�Ȃ̂ŁA���̏��X�ɈÂ��Ȃ�̂͂�����߂Ă��������B �@���X�ɂƌ����Ă��킸��0.5�`1�b���x�ł��̂Łu�s�J�b�I�X�[�c�v�ŏI���܂��B �@�d���R���f���T�����S�ɏ[�d�������k�d�c�͊��S�ɏ��������܂܂ɂȂ�܂��B �@�����̑��u�̓d�������ƁA�d���R���f���T���V���b�g�L�[�_�C�I�[�h(SD)�o�R�ŕ��d���܂��B �@���̕��d�������̑��u�̓d�����ɓd���R���f���T�ɒ��߂��d�C�𗬂��Ă��܂����Ƃōs���܂��B �@�ł���������{��H�ɋ�������Ă���5V���d����H�ƌq������5V�ł͖����ꍇ�A���Ƃ��Ή�����IC�̏o�͂Ƃ��̏ꍇ�ɂ͒��ӂ��K�v�ŁA�d���̋z�����݂��o���Ȃ���(�I�[�v���ɂȂ�)�Ɍq���ł�����d���R���f���T�͕��d�ł��܂��玟��5V�ɂȂ鎞��LED�͓_�����܂���B���̏ꍇ�̓I�v�V�����̒�R1K�����Ƃ���ĕ��d�����Ă��K�v������܂��B 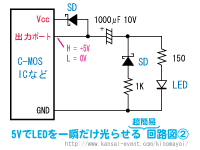 �@C-MOS IC�̏o�͂̂悤��H���x���̎���+5V�ɂȂ�L���x���̎���GND�Ɍq����悤�ȕ�������5V������Ă���ꍇ�AL���x���ɂȂ��ēd�����t������ۂɑ傫�ȓd���������IC���Ă��܂��\��������܂��B���̂悤�ȏꍇ���V���b�g�L�[�_�C�I�[�h(SD)�ƒ����1K�����x�̒�R���q���K�v������܂��B
�@C-MOS IC�̏o�͂̂悤��H���x���̎���+5V�ɂȂ�L���x���̎���GND�Ɍq����悤�ȕ�������5V������Ă���ꍇ�AL���x���ɂȂ��ēd�����t������ۂɑ傫�ȓd���������IC���Ă��܂��\��������܂��B���̂悤�ȏꍇ���V���b�g�L�[�_�C�I�[�h(SD)�ƒ����1K�����x�̒�R���q���K�v������܂��B�@�����IC�̏o�͂Ɍq�����ꍇ��IC�̓d�����ꂽ�Ƃ��ɓd���R���f���T����o�̓|�[�g�ɓd������������IC���Ă��܂��ꍇ������܂��̂ŁA�d�����ꂽ�ۂɂ͓d���R���f���T��d�����ɕ��d�����邽�߂̃_�C�I�[�h���K�v�ł��B(���i�������܂��ˁ`) �@�����́u�Ȃ����ɂ���ĕK�v�Ȓ�R���Ⴄ�v���ɂ��Ă��ȑf����H�Ȃ̂Ŕ[�����Ă��������B �@�I�v�V�����̑S���̒�R��_�C�I�[�h�����Ă����Ă��\���܂��A��͂��ȑf���������Ƃ�������]�ł�����A�P�ł����i�͏��Ȃ�����ق����悢�ł��傤�B �@���Ɏg����̂��ړI��������Ă��܂��A�P���Ɂu5V�œ������Ă���@��̓d������ꂽ���Ɉ�u����LED�����点�����v�Ƃ����ړI�̏ꍇ�̓I�v�V������R�Ȃǂ��Ƃ�����ɍς݂܂��̂ŁA�ł��ȑf��������H�ƂȂ�܂��B �@LED�����鎞�Ԃ́A�d���R���f���T��1000��F�̏ꍇ����P�b�ł��B470��F�̏ꍇ����0.5�b�ł�����A���D���Ȏ��Ԃ��R���f���T�̗e�ʂőI��ł��������B �@�^�C�}�[����g�����W�X�^���g�p������H�̂悤�Ƀ{�����[���Ŏ��R�ɒ��߂ł��Ȃ��̂��ȑf����H�Ȃ̂ŁB �@����LED���Â��Ȃ��Ă������I�Ƌ���̂ł�����A150���̒�R�ƒ����100�`500�����炢�̔��Œ��R���q���ŁALED�ɗ����d���𐧌������R�l���ςɂ��Ă��Ώ[�d���Ԃ��ς��܂�����{�����[���Ŏ��Ԃ̒��߂͂ł���悤�ɂȂ�ł��傤�B �@�A���ALED�ɗ����d���𐧌�����Ƃ�������LED���Â��Ȃ�Ƃ������ł�����A���ꂪ�K�}���ł���͈͂��ǂ����͔��Œ��R���Ȃ��ł݂Ă������̖ڂŊm���߂Ďg���Ă݂Ă��������B�u���b�h�{�[�h�ȂǂŃe�X�g��H��g�ݗ��ĂėV��ł݂�ƃ{�����[�����ω����m�F�ł��Ėʔ����ł��傤�B �@���̉�H�̏ꍇ�A��U5V����Ă���d���R���f���T�����S�ɕ��d����܂Ő��b������܂��B(�����̉�H���̕��ׂɂ����܂�) �@5V����Ă����ɂ܂�5V���������ꍇ�ɂ͓d���R���f���T���܂��\���ɕ��d����Ă��Ȃ��Ə��������[�d�d��������܂��瓖�RLED�͈Â��A�܂��[�d���Ԃ��Z���̂ŒZ���Ԃ�������܂���B �@������ȑf����H�Ȃ̂ŁE�E�E(�����������āH) �@IC��g�����W�X�^���g�����^�C�}�[��H�ł�LED��ON/OFF����������Əo������A�^�C�}�[���Ԃ��ǂ̃^�C�~���O��5V�����Ă���������ƌ��܂������Ԃ���ON�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����A���i�������������Ȃ��Ă��܂��܂��B �@����́u�ȑf���v������]�Ȃ̂ʼn�H���o�������P���ɁA�ȑf�ɂ��Ă��܂����炻��ɔ�������̊ȒP���ɋN�����邩�Ȃ�A�i���O�I�ȓ���́u�����������v�Ɣ[�����Ďg���Ă���������������܂���B �@�u�������������������肵������ɂȂ�܂��H�v�Ƃ��l���ɂȂ��������������Ⴂ�܂�����A�f���Ɂu5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H�v�̂悤�ȃ^�C�}�[��H�����g�p���������B(�ق��ɂ�555���g�����^�C�}�[��H�ȂǐF�X�Ɖߋ��Ɍf�ڂ��Ă��܂�) �@�{��H�Ƀg�����W�X�^�Ȃǂ�lj���������������Ɛ��m�ȉ�H�ɕς���ƁA���ǂ�IC���g������Ƃ������ĕ��i�����ς�Ȃ��悤�ɂȂ��āA�c�O�Ȃ���ȑf���̈Ӗ��������Ȃ��Ă��܂��܂��B ���Ԏ� 2009/9/18
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�Ǘ��l�l�B �@���Z�������A�����̉��ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@������₷�������A���ʁA�ق�Ƃ�������������܂��B �@�����ŁA�ǂ�ȕ��Ɏg�����������Ē��������Ǝv���܂��B �@IC���R�[�_�[�ƌg�ѓd�b���g���ă��W�I�ԑg�̃^�C�}�[�^�����u����낤�Ǝv���Ă��܂��B �@�ŁAIC���R�[�_�[�̃^�N�g�X�C�b�`�̒[�q�ɓ����c�t�����Čg�ѓd�b�̃o�C�u���[�^�[�p���[�^�[�̒[�q����̏o�͓d���𗘗p����IC���R�[�_�[�̃^�N�g�X�C�b�`�ړ_���q�������o���Ȃ�������Ă���̂ł����A���Ŏv���Ă�l�ɊȒP�ɂ͏o���܂���A�A�A �@���́A�^�N�g�X�C�b�`�̖�ڂ͓d���Ƙ^���̗����������Ă���2�b�����œd���AON-OFF 0.5�b�����Ř^���̊J�n�A�ꎞ��~�ƂȂ��Ă܂��B �@������e���炻��Ă��܂��܂������i�ŏ����炱�̂悤�ɏ����Ă�Ηǂ������ł��A�\�������܂���B�j �@�Ǘ��l�l�B�@�^�N�g�X�C�b�`�̐ړ_���q���ɂ̓����[���g���ȊO�����Ȏ��ł��傤���H �@�����f���|���������܂����A�����������t������������Δ��ɏ�����܂��B�ǂ����X�������肢�\�������܂��B �@��������v���܂����B �C�ɂȂ�l �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�@ �B�@�B �@ / �^ ( �D ) �@���������܂ł��炭������܂��B ���Ԏ� 2009/9/19
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Z�������x�X����v���܂��B �@�Ǘ��l�l�@�u5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H�v������̉�H�͐�Γ��͓d����5V�łȂ��Ɠ��삵�Ȃ��̂ł��傤���H �@2.8V�ʂł͓��삵�܂��H �@�����ă����[�͂ǂ̗l�ȕ��������߂ł��傤���H �@�X����������ʔ̃T�C�g�̏��i�������Ē����܂���ł��傤���H �@�����Ƃ����f�A���萔���|���������܂������t�������̒��X�������肢�\���グ�܂��B �C�ɂȂ�l �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���݂܂��A����ɂ��������������B �@IC���R�[�_�[�̓d���͓�����ςȂ��ɂł���̂ł��傤���H �@����Ƃ��I�[�g�I�t�@�\�Ȃǂ����蒷���ԓd����ON�ɂ����ςȂ��ɂ͂ł��Ȃ��̂ŁA�^�C�}�[���쎞�ɕK���u2�b�����v(�d��ON)�����ď����҂��āu0.5�b�����v(�^���J�n)�ƂQ�̓�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���H (a) �d���͓�����ςȂ��ŁA�g�т��u���u��������u0.5�b�v�����X�C�b�`�𑀍삷���H�ŗǂ� (b) �d���͓����Ă��Ȃ��̂Łu2�b�v�u0.5�b�v�ƕ��G�ȓ��삪�K�v �̂�����̑��u����낤�Ƃ���Ă���̂ł��傤���B �@�܂��A�^���I���͎������삷��̂ł����H (c) �Q��ڂ̃u���u���Łu0.5�b�v�Ɓu2�b�v�̑��������B (d) �Q��ڂ̃u���u���Łu0.5�b�v�����Ĉꎞ��~���邾���ł悢�B �̂���������l���ł����B �@(b)(d)�̂悤�ȏꍇ�͌��\��ςȉ�H�����Ȃ��Ƃ����܂���ˁB�u�ȑf���v������]�Ƃ̂��Ƃł������A�ƂĂ��ȗ����ł���悤�ȓ��e�ł͖����Ǝv���܂��B �@(a)(c)�̂悤�ȕ��ł悢(�d���͓�����ςȂ�)�Ȃ�A���Ȃ�ȑf���ł��܂��ˁB �@�܂��A�g�ѓd�b�̃��[�^�[�̓^�C�}�[�œ������ɂ͍쓮���Ԓ��͂����ƃu���u���Ɖ�葱���Ă��܂����H �@����Ƃ��A�u���u���E�E�E�E�u���u���E�E�E�̂悤�ɒf���I�ɓ����ēr���ɓd�����o�Ȃ����Ԃ͂���܂����H �@��҂̏ꍇ�͒f�����邲�Ƃ�IC���R�[�_�[�𑀍삷��p���X������Ă�����A�u���u���̉����{�^���������ĉʂ����Ċ��Ŏ~�܂��Ă����Ō�͘^����ԂɂȂ�ł��傤���A������Ŏ~�܂�ƈꎞ��~��ԂŏI����Ă��܂��܂��ˁB �@�����f���U���Ȃ炻��ɑΉ������H���K�v�ɂȂ�܂����A���̂�����ɂ��Ă͂ǂ̂悤�Ȃ��l���ł��傤���B ���Ԏ� 2009/10/2
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�Ǘ��l�l�B���Z�������{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@�ł��Ba�̉�H����]���܂��B �@�^���I���͒����Ԙ^���ł���̂ŗ����Ɏ蓮��~���܂��B �@�������Ȃ��肢�Ő\�������܂���B �@�������Ȃ���Ȃ��ʼn������ˁI �C�ɂȂ�l �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[��B�����͔��������ł����B �@�K�v�ȏ�����o����܂ʼn��x�����x�����x�����x�����x�����x�����x��������J��Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂ƂĂ��ʓ|�ł����A�L�������ʂɉ��т邾���ŒN�ɂ������b�g�͂���܂���̂ł����炩��̎���͂����܂łƂ����Ē����āA���܂łɏo�Ă�����ɑ��Ă����ōl��������̂���Ă��̎���ւ̉͏I���Ƃ����Ă��������܂��B  �@��{�̓����͊��ɏ����Ă���ʂ�ł��B �@�g�ѓd�b�̃o�C�u���[�^�̃��[�^���A���ʼn��̂��A�f�����ĉ��̂��ɑ��ĉ�����܂���̂ŁA�ǂ���ł���쓮���Ȃ��悤�ɕ��i�𑝂₵�Ă��܂��B �@�ʏ�̌g�ѓd�b�̃o�C�u���[�^�[�ł���A�ǂ�ȐU���̂������̕��ł������ł��傤�B �@�g�����W�X�^���g���Ƃ��A�����Ɗȑf���ƒቿ�i�����������邱�Ƃ��ł��܂����AIC���R�[�_�̃X�C�b�`�����̉�H�}���킩��܂��A���Ɍq����Ă����삷��悤��(�A���t�H�g�J�v���̒�i�ȓ�)�Ȃ��Ă��܂��B�t�H�g�J�v���Ő≏���Ă��܂��̂ŁA�����Ă��̓d�q�@��̃X�C�b�`���ƌq�����Ƃ��ł��܂��B �@�ȏ�ŏI���ł��B �@���肪�Ƃ��������܂����B ���Ԏ� 2009/10/6
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 10/7 |
�@�Ǘ��l�l�A��ς����f�������������܂����B �@�e�ɋ����ĉ�����^�ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �C�ɂȂ�l �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �d���̎��₪�Q���ق� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@��PWM������g������H����낤���Ǝv���Ă���̂ł����A9V�̓d�r��3V�̃��[�^���g�p����\��Ȃ�ł����A9V����3V�ɕϊ��������H��������܂���B �@��H��������������Ă��������܂��H ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||
|
�@�����W�R����40�s��PIC���g���APWM��������悤���Ǝv���Ă��܂��B�O�ւɂ�3V���[�^�ō��E�̃^�C���̐�ւ��A��ւɂ͉���������ׂ�3V�̃��[�^�ōs�������Ǝv���Ă��܂��B �@�ł���PWM�����H�̃��[�^���Vcc�Ƃ����������ǂ̂悤�ɂȂ��̂���킵�Ă��܂��B �@������������Ă��������܂��H ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���ڂ�Ȃ��Ԃɂ܂�������������܂�Ă��܂����̂ŁA�Q���܂Ƃ߂Čf�ڂ����Ă��������܂��B �@9V�̓d����3V�̃��[�^�[���Ƃ����̂��O�[�q���M�����[�^�ł͂��߂ł����H �@���`�������Ȃ��Ƃ����Ȃ���^�̃��[�^�[�łȂ���A�͌^�p��3V���[�^�[(�}�u�`���[�^�[�Ƃ�)���炢�Ȃ�P�`�p�̎O�[�q���M�����[�^�ō~��������Γd���͏\���Ȃ͂��ł��B �@�ŋ߂ł�3V�o�̓^�C�v�̎O�[�q���M�����[�^ (�����3.3V)���̔�����Ă��܂����A1.2V�`37V�d���ώ��̎O�[�q���M�����[�^ LM317�ł������̍D���ȓd���ɐݒ肷��̂��ǂ��Ǝv���܂��B (�����ȊO�ɂ���������̎�ނ������Ă��܂�) �@�O�[�q���M�����[�^���ǂ��g���̂��́A�����̋L���ł����x���o�Ă��܂��̂œǂ�ł݂Ă��������B �@��̃����N��̏H���d�q�Ŕ����A�e�Ɏg���������������������Ă��܂����炻���ǂނ̂ł������ł��B �@�uVcc��������Ȃ��v�Ƃ����̂́u��H�}�̓ǂݕ����킩��Ȃ��v�Ƃ��������̏��S�҂̕��ł��ˁB �@�uVcc�v�̓g�����W�X�^��H�̃R���N�^�d�ʂ̓d���Ƃ����Ӗ��ŁA���ʂ��v���X�̓d���ł��B��H�̒��̃v���X�̓d���̂��Ƃ������܂��B �@���������Ӗ��s���̋L���╶������������o�ė���ł��悤����APWM����݂����ȍ��x�Ȃ��Ƃ��͂��߂�O�ɁA���Гd�q��H��d�q���i�̓��发���ĂЂƂƂ���͓ǂ�ł������ق��������Ǝv���܂���B �@�����A�ʂ��Ă����w�̐}���قɂ���������u���Ă���ł��傤����A�킴�킴�������Ĕ���Ȃ��Ă������œǂނ��Ƃ��ł���̂ł́H ���Ԏ� 2009/9/17
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 9/19 |
�@�ԓ����肪�Ƃ��������܂��B �@���e��������₷�������ł��܂����B �@�ȏ�̂��Ƃ��Q�l�ɂ��낢��T���Ă݂����Ǝv���܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| 100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g | ||||||||||||||||||||||||
|
�@���߂܂��Č��֑O�̖h�Ɨp�Ƀ_�C�\�[�ŐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g�ƃZ���T�[���C�gDX���w�����܂������A�S���̏��S�҂ł����ꂩ����������܂��B�Â��Ȃ����玩���_���������̂ł��B �@�Z���T�[���C�g��AC100V�p�ł����Acds��H�����̂܂ܐԐF�_�Ń��C�g�̉�H�̃}�C�i�X�q���ŋX�����ł��傤���A�h�o�C�X���肢�������܂��B ���쏫�_ �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA���ꂾ���ł͂�����̗v�_���킩��܂���B (a) AC100V�̃R���Z���g�ɃZ���T�[���C�g�������āA������z�����āu�Â��Ȃ�Ǝ����Łv�ԐF���]�ԃ��C�g�ɓd����^�������B (b) �d���͐ԐF���]�ԃ��C�g�̓d�r�Q�{�ŁA�Z���T�[���C�g�́u���邳�Z���T�[�v�Ƃ��Ă����g�������B �@�̂ǂ���ł��傤���H �@�ŁA�ǂ���ɂ��Ă��u���̂܂܌q���v�����ł͓����܂���B �@����Ȃ�ɉ������Ȃ��Ƃ��߂ł��B ���Ԏ� 2009/9/13
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Z�����Ƃ���A�����s���ł����܂���A�������ib�j�Z���T�[���C�g��CDS�̊������O���āA�ԐF���]�ԃ��C�g�ցu���邳�Z���T�[�v�Ƃ��Čq�����@�������Ă��������B ���쏫�_ �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��ł������܂������A�Z���T�[�i�C�g���C�g��AC100V�p�̉�H�Ȃ̂Łu���̂܂܂ǂ�������z�������q���ŁA���]�ԓ_�Ń��C�g�̃X�C�b�`�ɂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B�v �@�i�C�g���C�g�̊�����āACds��SCR�������O���ė��p���邱�ƂɂȂ�܂��B���i���O������͕s�v�ɂȂ�܂��B(�c�������i�͉����Ɂc)  �@Cds�͖��邢��ԂŒ�R�l2�`3K��(�܂��͂���ȉ�)�A�Â���Ԃ�5�`10K��(�܂��͂���ȏ�)�Ƃ����i���t���Ă��܂����̂ŁA���Œ��R�̒l�͂���ɂ��킹�Ă��܂��B �@��L�̉�H�}�̒ʂ�ɑg�ݗ��ĂāA�u���]�ԓ_�Ń����v�v���d�r�[�q�Ɍq���܂��B �@���d�r�Q�{�͕ʓr�d�r�{�b�N�X�ɓ���邩�A�u���]�ԓ_�Ń����v�v�̊��Ńp�^�[���J�b�g����Ȃ肵�Č��̓d��������f���ĕʓr�z�����Ă��������B��҂̏ꍇ�͊���H�Ȃǂ̋Z�p���K�v�ł��B �@�u���]�ԓ_�Ń����v�v���X�C�b�`�[�q(���d�S����������悤�ɂȂ��Ă���)�̕����̓��[�h���ȂǂŃW�����p�[���ď펞�X�C�b�`�������ꂽ��Ԃɂ��܂��B �@�����Ă��́u���]�ԓ_�Ń����v�v�́A�X�C�b�`���������ςȂ��ɂ��ēd�r������Ɓu�ŏ��̃p�^�[���œ_�ł����v�悤�ɐv����Ă��܂��B �@���̃W�����p�[���������邱�ƂŁA�p�^�[���͑I�ׂȂ��Ȃ�܂����d�����������ŏ��̃p�^�[���œ_�ł���u�P�p�^�[���_�Ń����v�v�ɉ������邱�Ƃ��ł��܂��B �@���ӂ��K�v�Ȃ̂́A�u�ŏ��̃p�^�[�����_�łł͂Ȃ��펞�_���v����^�C�v�̏��i������܂��̂ŁA�K���ŏ��̃p�^�[�����_�ł̂��̂����I�т��������B(�_�C�\�[�̏��i�͍ŏ����_�ł̕��������Ă��܂���) �@��H��g�ݗ��Ăēd�r������ACds����ŕ����Ȃǂ��ĈÂ������LED���_�ł��͂��߂܂��B����ǂ��Ė��邭�����LED�͏������܂��B �@���̊��x���߂�10K���̔��Œ��R�Œ��߂��܂��B���ۂɂ��g�p�ɂȂ閾�邳�ł�����ON/OFF�ł���悤�ɂ��܂����߂��Ă��������B �@SCR(�T�C���X�^)�̓_�C�\�[��LED�^�C�v�̃Z���T�[�i�C�g���C�g(315�~���i)�ɂ�PCR606J���g���Ă��܂������A�������b�g�ɂ���ĈႤSCR���g�p����Ă��邩������܂���B �@�Ⴄ�i���g�p����Ă���ꍇ�̓l�b�g�Ńf�[�^�V�[�g��T���Ȃ肵�Đڑ����Ԉ��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@�Q�l�܂łɓ��{�����Ŕ̔�����Ă���ł��|�s�����[��SCR SF0R3G41�̃s���z�u���ڂ��Ă����܂��B�ˁA�Ⴄ�ł���B �@SCR(�T�C���X�^)�͎�����Ŏg���X�C�b�`���O�f�q�ŁA�Q�[�g�d�����������xON�ɂȂ�ƃQ�[�g�d���������Ă�A��K�Ԃɓd��������Ă������X�C�b�`��ON�ɂȂ���ςȂ��ɂȂ��u�X�C�b�`��Ԃ��L������v�f�q�ł��B �@��UON�ɂȂ���SCR��OFF�ɂ���ɂ�A��K�Ԃ̓d�����J�b�g(������)�����K�v������A�ʓrOFF�ɂ����H���K�v�ł��B �@�ł�����A��K�Ԃɗ����d������(���ۂɂ͕Г������疬��)��������A�𗬂͓d�����u����v�Ɓu�Ȃ��v�����݂ɌJ��Ԃ���Ă���̂ł��́u�Ȃ��v���Ԃ�A��K�Ԃɓd��������Ȃ��Ȃ����ƂɂȂ�̂ŁASCR��OFF�ɂ���̂ɕ֗��Ɏg���܂��B �@SCR�Ō𗬂��X�C�b�`���O����ꍇ�́A���T�C�N�����Ƃ�OFF�ɂȂ�^�C�~���O������̂ŃQ�[�g�ɓd���������Ă���Ԃ�ON�A�Q�[�g�ɓd���������Ȃ��ꍇ��OFF�ƂƂĂ����܂��𗬓d�����X�C�b�`�ł���̂ł��B (�ق��ɂ��A�������Q�[�g�d����0V�߂��ɗ��Ƃ��Ă��܂��Ƃ������̎��) �@����������͊��d�r�d���Ƃ��������d���Ŏg�p���܂�����A���̉�H�}�̒ʂ�ɍ���āu���]�ԓ_�Ń����v�v�̂����ɓ��d���₽����LED(�펞�_��)���q���ƁA�Â��Ȃ��Ĉ�x�_���������x�Ə������Ȃ��Ƃ����s�ւȃ����v���o���オ���Ă��܂��܂��B �@����܂��ˁE�E�E�E�B �@�ł�����͂��̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��A�����Ɩ��邭�Ȃ�Ə������܂��B �@���̃J���N���́u���]�ԓ_�Ń����v�v���_�Ń��[�h�Ŏg�p���Ă��邩��ł��B �@�_�Ń��[�h�Ŏg�p����ƁALED���������Ă�����Ԃɂ��قƂ�Ǔd��������܂����B���̓d��������Ȃ����Ԃ�SCR��A��K�Ԃɓd��������Ȃ��Ƃ������ɂȂ���SCR��OFF�ɂł���̂ł��I �@���ɔ���ȓd���œ_�ʼn�H�삳���Ă���u���]�ԓ_�Ń����v�v�Ȃ�ł͂̋@�\�����p�����A�C�f�A��H�ƂȂ��Ă��܂��B �@���̑g�ݍ��킹�ł͂Ȃ��A���d����LED�_�ʼn�H�ł��������Ԃɂ��������傫�ȓd���������d�q��H�ł͂��̉�H�}�ʂ�Ɍq���ł��Â��Ȃ��Ĉ�x�_���������x�Ə������Ȃ��s�ւȂ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂�����悭���ӂ��Ă��������B �@����̉�H�ł́A���Ԃ̖��邢�����ɂ�Cds�̒�R�l���Ⴍ�Ă����ɓd���𗬂����Ƃ�SCR�������Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B �@���邢���̑ҋ@�d����1mA�`��mA�ł��B �@���邢�Ԃ������킸���ɓd�r�����Ղ��Ă��܂��̂ŁALED�������Ă��邩��Ƃ����Ċ��S�ɓd�r���g���Ă��Ȃ��킯�ł͂���܂���B���Ԃ��Z���T�[��H�͓d�C���g���ē����Ă��܂��B �@����̎g�p���@�ł̓Z���T�[�i�C�g���C�g�̑��͕��i����������͑S�R���ɗ����Ă��܂��ACds��SCR��d�q���i�X�Ŕ����ƍ��v100�~�ʂ�100�~�ȏサ�܂��̂ŁA100�~���i(�i�c�����^�C�v)�̃Z���T�[�i�C�g���C�g�Ȃ炻����̂ق��������Ă����ł����A315�~���i(LED�^�C�v)���Ƃ�����Ɗ�����������܂���B �@LED�^�C�v���Ɣ��FLED����p�_�C�I�[�h�Ȃǂ��������܂�����A�����������i������Ǝv����315�~�ł��[�������E�E�E�H �@���ɍ���̂���]�̂悤�ɃZ���T�[�i�C�g���C�g���畔�i����炸�A�d�q���i�X��Cds��g�����W�X�^���w������Ȃ�u���p�^�[���̂�������D���ȃp�^�[����I��ł����A�Â��Ȃ����炻�̃p�^�[���œ_�ł��鎩���_�Ń����v�v�Ƃ����̂���ꂻ���ł��ˁB �@����́u�ŏ��̂P�p�^�[���ڂŌŒ�v���͎��R�x�������܂��B �@���̉�H�}�́A����l���ĕʂ̋@��ɔ��\�ł�����Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/9/18
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�A�h�o�C�X�L�������܂����B �@�w���������]�ԓ_�Ń����v�̓N���A�����Y�łk�d�c���T�t���Ă���X�C�b�`�������Ɓu�ŏ��̃p�^�[�����_�łłȂ��펞�_���v����^�C�v�ł��A���������̃_�C�\�[���s���Ă݂܂������A��H�}�ɍڂ��Ă���k�d�c�R�t���Ă��鎩�]�ԓ_�Ń����v�͗L��܂���ł����B �@�Z���T�[���C�gDX�́u�T�C���X�^�v��MCR 100-6P86���g���Ă��܂��B����͐��ɐ\����L��܂��f�O�v���܂��B �@�Ǘ��l�̃A�h�o�C�X�̓d�q���i�X�ŐV����cds��g�����W�^���w�����č���H�}��������đ҂��Ă���܂��B ���쏫�_ �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ł��ˁB���̎����_�C�\�[�Ŕ����Ă���u���]��-151�v(5��)���u���S-No.1�v(5��)���{�^���������čŏ����u�펞�_���v�ł��ˁB �@�ʂɍ��쏫�_�l���u�_�ł��郉���v�v�ɍS��Ȃ���A�u�ԐF���]�ԓ_�Ń��C�g�̔��F�k�d�c���v�ŏ����܂����悤�Ƀ_�C�\�[�́u���]��-151�v(�u���S-No.1�v��)�͏펞�_���Ɍ��������Ď��̓p���X�_���œ_�ł��Ă��܂�����A��������T�C���X�^�g�p�̉�H�ł����ƈÂ��Ȃ�Γ_���^���邭�Ȃ�Ώ������܂��B �@�ŏ��̓��e�ł͕ʂɓ_�ł�����K�v���͏�����Ă��܂���ł����̂ŁA���w�����ꂽ�u���]��-151�v���Â��Ȃ�����_��(�_�ł͂��܂���)���Ė�Ԃ̌x�����Ƃ��Ė��ɗ��Ȃ炻�̂܂g���Ē����Č��\�ł���B 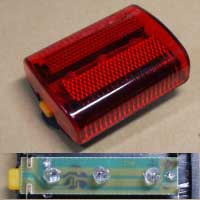 �@�_�C�\�[�ȊO��100�~�V���b�v�Ŕ����Ă��鎩�]�ԗp�ԐF�_�Ń����v�͂��̖��O�̒ʂ�Ɂu�ŏ��͓_�Łv�Ȃ̂ł����E�E�E�B
�@�_�C�\�[�ȊO��100�~�V���b�v�Ŕ����Ă��鎩�]�ԗp�ԐF�_�Ń����v�͂��̖��O�̒ʂ�Ɂu�ŏ��͓_�Łv�Ȃ̂ł����E�E�E�B�@���߂��Ƀ_�C�\�[���������n��Ȃ�����_���ł����A�_�C�\�[�ȊO��100�~�V���b�v�������āA��n���i�ȊO�̎��]�ԗp�ԐF�_�Ń����v�������Ă�������ł��ˁB �@�܂����܂Ŕ��������]�ԗp�̐ԐF�_�Ń����v�̒��ɂ͍ŏ����펞�_���ŁA���_�C�\�[�́u���]��-151�v�̂悤�ȃp���X�쓮�ł͂Ȃ����S�ɏ펞�_���̃^�C�v���E�̎ʐ^�̕��ƂقƂ�Ǔ����`�����Ă��܂������A�u�����ēd�r�����Ă��瓖���肩�n�Y���͎����Ŋm�F���ׂ��I�v�Ƃ����M�����u���̂悤�Ȃ��̂ł����ǁB ���Ԏ� 2009/9/23
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�ʂ̋@��Ɂv�Ƃ���������Ă��܂������A���͗\�肪�����Ă��āuCds��g�����W�^���w�����č��v��H�́A11��17��(��)�����́w�d�q�H��}�K�W�� No.5�x��100�~�V���b�v�i�̉����L���Ƃ��Čf�ڗ\��Řb���i��ł��܂��B �@����̓��e�œ����悤�ȕ����o���̂ł�����Əł�܂������A���e�������Ⴄ�̂ʼn����L���̂ق��͗\��ʂ�No.5�Ɍ����Ă̋L���Ƃ����Ă��������܂��B ���Ԏ� 2009/10/2
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@9/23 10/2 �̏ڍׂȐ����L�������܂��� �@�uCds��g�����W�X�^���g���Ẳ�H�v�̋L����d�q�H��}�K�W���ɍڂ��邻���ł��ˁA11��17�����y���݂ł��A���@�X�������肢�������܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�\�z���Ă����Ƃ���A100�~�_�Ŋ���̉��H�ȂǁA�H�삵�Ē��������������̂Łu�������v�ł̂������Ƃ��Čf�ڂł���͈͂��z���Ă��܂��܂����B �@�d�q�H��}�K�W��No.5�Ɍf�ڂ�����v���܂����̂ŁA���������҂����������B ���Ԏ� 2009/10/30
|
|||||||||||||||||||||||
| ���x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v | ||||||||||||||||||||||||
|
�@���̔��N�قǎ���������ɂ͂܂��Ă܂��āA�K�X�R�����ł͂Ȃ������̃j�N�������q�[�^�[�R�������g���č����@�ɕς��悤�Ǝv���Ă��܂��B http://item.rakuten.co.jp/wich/kckl103/ �@�������A�j�N�������q�[�^�[�R�����̓d���̓r���Ɂ����̃T�[���X�^�b�g��10cm�قǂ̓S�����Ďg����OFF�ɂȂ��Ă���̕��A�����̂��������Ԃ������Ďv���悤�������o���܂���B�B�B http://www.rakuten.co.jp/denshi/173948/1805550/ �@��������ɃT�[���X�^�b�g�𒈂Ԃ���ɂ��Ďg���Ă���ł����A���x���Ȃ��Ȃ�������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B �@����̃e�X�g�́����̃X���[�J�[�ɍX�ɑ傫�ȃS�~�o�P�c�����Ԃ��ĕ����Ă��܂�����Ԃł���Ă܂����B http://item.rakuten.co.jp/e-camper/10000400/ �@������邩��]�v�ɉ��x��������ɂ����̂��Ǝv���܂��B �@8,000�~���炢�o���Ă܂Ƃ��ȃT�[���X�^�b�g�������̂����m��܂��A�o����Έ����Ɏ���ł����炢���ȂƎv���܂��āE�E�E �@AC�A�_�v�^���g���ȂǕʓd�����K�v�ł������̂ŁA60�`70�����炢��AC100V��ON-OFF�o�����H�������Ă��������܂��H �@�Z�����Ƃ͎v���܂�����낵�����肢�v���܂��I ����� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��������������ł����B �@�������u�j�N�������R�����v�Ƃ͂܂��������������E�E�E�i�O�O�G �@���x�����o����AC100V���R���g���[������͓̂d�q��H�̓��ӕ���(?)�ł��̂ŁA��H�͔�r�I�ȒP�ɂł��܂����A�u���x�v�\���v�܂ŕt����ƕ��i�オ�����Ȃ�̂ł܂��͕\���̖�����H�ł��B �@�f�W�^���\���Ȃǂ͖����̂ŁA���߂⓮��m�F�̓e�X�^�[���K�v�ł��B �� �T�[�������[ ��H�} (�����`100���T�[�������[) ���N���b�N����Ɗg��\��
IE�ł͏k����Ԃŕ\�������ꍇ������܂��B�g�呀�삵�Ă��������B
�� ���x�Z���T�[ �@���x�Z���T�[�ɂ͔����̉��x�Z���T�[�̒��Ń|�s�����[�ȁuLM35DZ�v���g�p���܂��B �@LM35DZ�͂R�{���̃g�����W�X�^�̂悤�ȏ�����TO-92�p�b�P�[�W��IC�ŁA���Ɂu���x�Z���T�[�v�Ɓu���x���d���ϊ���H�v�A�����č����x�Z���T�[�ɕK�v�ȁu���x�⏞��H�v�������Ă�����ɍ��@�\�ȉ��x�Z���T�[IC�ł��B �@�d���͈͂�4�`30V�Ɣ��ɍL�������OP�A���v��H�ɓK�����͈͂ƂȂ��Ă��āA�o�͓d����+10mV/��(-55���`+150��)�Ƃ��̂܂܃f�W�^���d���v�Ȃǂ��Ȃ������ł��u�ێ������v���o���邽���ւ�֗��ȓd���ŏo�͂���܂��B(�}�C�i�X�����v��ꍇ�̓}�C�i�X�d����H���K�v�ł�) �@���Ƃ��u20������200mV�v�u50������500mV�v�Ƃ��������Ɂu1.0V�̎���100���v�Ƃ����悤�Ȕ��ɒ����I�Ȉ�����v�Z���ł���o�͓����������Ă��܂��B �� �d�������A���v �@OP�A���vLM358�̔���(�P��H)���g����LM35DZ�̏o�͓d�����R�{�����H������āA100���̎���3V�ɂȂ�悤�ɂ��Ă��܂��B �@����E�E�E���̂܂�100���̎���1V�ł������̂ł����A��ɉ��x���r���鎞�ɂȂ�ׂ�����LM358�̓���d���͈�(5V��)��3.5V�����ς��߂��܂Ńt���Ɏg��������������ł��B�ł��邾���m�C�Y�ɋ�������Ƃ��E�E�E �� �R���p���[�^(��r��) �@LM358�̎c�蔼��(OP�A���v���)���g���āALM35DZ�ő��肵�����x�ɑ���d���ƁA���Œ��RVR1�Ō��߂��u���쉷�x�v�ɑ���d�����r���āA���艷�x����]�̉��x�ɒB�������B���Ă��Ȃ����肵�܂��B �@LM35DZ�ő��肵�����x�ɑ���d�����R�{����Ă��܂����AVR1�Őݒ肷��u���쉷�x�v��10mV/���̂R�{��30mV/���ƂȂ�܂��B �@���̃R���p���[�^�́u�o�͂�L�̎������t�B�[�h�o�b�N��������v�悤�ɂ��ăq�X�e���V�X���������Ă��܂��B �@���x���オ����VR1�Őݒ肵�����쉷�x�ɒB����Ɓu�M���Ȃ����̂�OFF�ɂ��Ȃ���I�v�ƃR���p���[�^�̏o�͂�L�ɂȂ�AD1�EVR2�ER4���o�R���Ĕ�r�d���������������A���ɉ��x���������Ă����쉷�x�ł̓R���p���[�^�o�͂͂�L�ɂ͂Ȃ炸�A���Ə������̉��x(���̍������A���x���ƌĂт܂�)�ɂȂ������ɂ͂��߂āu��߂��̂�ON�ɂ��Ȃ���I�v�Ɣ��f���ďo�͂�H�ɂ��܂��B �@���x���������ďo�͂�H�ɖ߂�Ɣ�r�d����VR1�Ō��߂����쉷�x�ɖ߂�܂��̂ŁA�܂����A���x���Ԃ��Ȃ������쉷�x�ɒB���Ȃ��ƍēxOFF�ɂ͂Ȃ�܂���B �@���̂悤��ON�ɂȂ鎞��OFF�ɂȂ鎞�ɉ��x�������Ă����Ă��Ȃ��ƁA�P��̉��x������ON/OFF������Ƃ��̉��x���傤�ǂ̎��ɏo�͂�ON��OFF�Ɍ�������ւ�A���̂����Ń����[�̐ړ_���Ă�����ڑ������@�킪��ꂽ��F�X�ȕs����������܂��B �� �o�̓����[ �@�d����DC 5V�Ȃ̂Ńg�����W�X�^2SC2120��5V�����[�����Ă��܂��B �@�����[���ړ_����NO(A)��NC(B)�̗����̐ړ_������^�C�v���g���u���x�����ɏオ��܂�ON�y���M�z�v�Ɓu���x�����ȏ�ɂȂ�����ON�y��p�z�v�̂Q��ނ̓��삩��ړI��I�ׂ܂��̂ŕ֗��ł��B �@�����[�̃R�C���d����DC5V��500mA���x�܂ŁB �@�ړ_���͎g����@��ɉ����āA����Ȃ�AC100V/600W�̓d�M��ł�����AAC125V/10A���x��10A�ȏ�̃����[���g�p���Ă��������B �@��ʓI�ȓd�͗p�����[�̂����Ɉ����ȁu�H���d�q��SSR�L�b�g (250�~)�v�ł��\���܂���B �@SSR�L�b�g�g�p�̏ꍇ��2SC1210�͕s�v�ŁALM358�̂V�ԃs�������̂܂�SSR���(+V)���͂ցA���(GND)�͉�H��GND�ɐڑ����邾���Ō��\�ł��B �@���̐ڑ��ł�SSR�g�p�ł́u���x�����ɏオ��܂�ON�y���M�z�v�Őړ_�����삵�܂��B �� ���ߕ��@ �@�܂���TP1�̓d�����v���āA������LM35DZ���牷�x�ɉ������d�����o�͂���Ă��邩�m�F���Ă��������B �@10mV/���ł�����A���Ƃ��Ύ�����20���Ńe�X�g�����200mV(�O��)�̏o�͂ł��B �@VR1���E�����ς�(��100��)�ɁAVR2�͍������ς�(���A���x�͍ł��Ⴂ)�ɉ܂��B �@��������쉷�x�͖�100���̐ݒ�̂͂��ł�����A���ʂ̎����ł���u��]�̉��x���Ⴂ���I�v�Ɣ��f�����LED1�͓_���A�����[��ON�̂͂��ł��B �@VR1�����X�ɍ��ɉĂ䂭(����ݒ艷�x��������)�ƁA�r����LED1���p�b�Ə������ă����[���J�`����OFF�ɂȂ�_������͂��ł��B �@�������ς�(�O���ݒ�)�܂ʼnĂ����삵�Ȃ��ꍇ�͑g�ݗ��ă~�X�ł�����A�~�X�̌���T���Ē����Ă��������B �@LED1�����������_����܂�����VR1���E�ɉĂ䂭(�ݒ艷�x���グ��)�ƁA������LED1���_�����āu�ݒ艷�x��茻�݉��x���Ⴂ�v�Ɣ��f����܂��B �@VR1�����ɉĂ����āA�����Ă���LED1���p�b�Ɠ_������ʒu��TP2�̓d�����v������݂̉��x�~30mV��菭�������d���ɂȂ��Ă���Δ�r�d��������H������ł��B �@��́A���݂̉��x����]�̐ݒ艷�x���Ⴂ���(LED���_�����Ă���)�ŁATP2�̓d�����v��Ȃ�����]�̓��쉷�x�~30mV�ɂȂ�悤�ɒ��߂��܂��B����Ŋ�]�����쉷�x�ɒB�����烊���[��OFF�ɂȂ钲�߂��I���ł��B �@�������A���x���̒��߂ł����A�Z���T�[�܂��̉��x�����쉷�x�ȏ�ɂ��āALED1���������Ă��鎞��TP2�̓d����VR2�Œ��߂���̂ł����A����̂���]���x�������ꍇ�͂Ȃ��Ȃ������ɂ��Ă��璲�߂Ƃ����̂�����̂ŁA���̈ꗗ�\���Q�l��VR2��K���Ȉʒu�ɉĂ������x�ł����v���Ǝv���܂��B
�� �Z���T�[�P�[�u���ɂ��� �@LM35DZ�̏o�͓d����mV�P�ʂƂ��������ȓd���ł��̂ŁA���܂�P�[�u�����L���ƃm�C�Y�Ȃǂ̉e���Ő��������x���v��Ȃ��Ȃ�܂��B �@�ʏ��20�`30cm�܂ŁB��������Ƃ��Ă�50cm���x�܂łɂ��Ă��������B (����ȏ�̋����̏ꍇ�́A�v���A���v��H��g�ݍ��o�b�t�@������o�͓d������������Ȃǂ��Ē����z���ɑΉ�������H�ɂ��܂�) �@�����������̉��x���v��悤�ȏꍇ�A���͂̋�C�ł͂Ȃ��������̗e�킪70���ȏ�ɂȂ�\��������܂��̂ŁA�P�[�u���͕K���u�ϔM�d��(140�����炢�ȏ�)�v���g�p���A�ł���u�ϔM�V���R���`���[�u�v��킹�Ă���v�ȏ�ԂŎg�p���Ă��������B �@�Z���T�[�ւ̔z�����n���ăV���[�g���Ă͂��܂�܂���B ���Ԏ� 2009/9/11
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�d�q�T�[���X�^�b�g�̉�H�}�����肪�Ƃ��������܂����B �@�莝���̍ޗ��������Ă݂��Ƃ���A330���̒�R��LM35DZ�����g���镨������܂���ł���(^^;) �@�Z���T�[�P�[�u�������������g�����肪�ǂ������Ȃ�ł����A�u�v���A���v��H��g�ݍ��o�b�t�@������o�͓d������������v�Ƃ����͉̂�H����₱�����Ȃ��ł��傤���H �@�܂��A�ǂꂮ�炢�̒����܂ŐL���܂����H �@2m���炢�܂ő��v�Ȃ炻�̕����g���₷���̂ŁB�B�B �@�ł��A�{�����[����LED��������ʼn����Ă��Ζ{�͉̂��x�̑��蕔�Ƌ߂��ɒu���Ζ��Ȃ��̂��ȁH �@���ƁA��������̉��x�𑪂�̂ɂ�LM35DZ�͂��̂܂ܒ��Ԃ���ɂ��Ďg�����������̂ł��傤���H �@����Ƃ������ȂǂɌŒ肵�����������̂ł��傤���H �@�Ƃ肠�����͋ߓ����Ƀp�[�c���Ă��܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����I ����� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����@(�d�M�q�[�^�[�܂�)�ɃZ���T�[�����āA���̐^���̃q�[�^�[��AC100V���R���g���[�����鑕�u�ł͂Ȃ��̂ł����H �@2m�������ł����E�E�E�E�B �@���̂悤��OP�A���v�̊�d�����͕��Ȃǂ̓��̓C���s�[�_���X�����������̃{�����[�����P�[�u���ʼn������ꂽ�肵���炽�܂�܂���B �@�d������������m�C�Y�Ō�쓮���肷�鑕�u�ɂȂ�����A���p�I�ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ���������邭�炢�Ȃ��x�������̂����ς���ق����}�V�ł��ˁB �@�������L���܂����B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�������ߕ��@�ȂǂX�Ə����Ă��܂��̂ŁA������悤��(�e���̓d�����ς�)�o�b�t�@�A���v�̑��݂͎��̕��͂�������Ԃ��c��ɂȂ�̂ŁA���̂܂܂Q��H�ɕ����Ă��܂��B �@�s�{�ӂȕ���������܂����A����ō���Ă݂Ă��������B �@���A�������Ȃ���H�͎����Ńe�X�g���Ă��܂����A���̉��������H�͑S���e�X�g���Ă��܂���B �@����ƁALM35DZ�ɋ���������̂́A�����ړI��������ł����H �@������̒��̋�C�̉��x�𑪂��Đ��䂵�����̂ł͂Ȃ��A���̋������̊��̕\�ʉ��x�Ń����[��ON/OFF������̂ł��傤���B���̂ւ�͎���������������Ă��Ȃ��̂Ŏg�������킩��܂���B �@�����̔M�`�����Ƒ̐ςʼn��x���`��闦�͌v�Z�ł���Ǝv���܂����A���x�Z���T�[�ɋ���������̂����x(�������x)���������ȊO�̖ړI�ɂ͎g��Ȃ��Ǝv���̂ŁA�u������蔽�����������v�u�ׂ��ȉ��x�ω��ɂ͔������������Ȃ��v�u���x���������Ă������Ƀq�[�^�[��ON�ɂȂ炸�A���܂�Ȃ����������肽���I�v���Ƃ�������]�łȂ������t��������̂ł����E�E�E�B  �@�d�q���i�X��o�b�p�[�c�V���b�v�Ŏʐ^�̂悤�ȉ��x�v�������Ă��܂��B
�@�d�q���i�X��o�b�p�[�c�V���b�v�Ŏʐ^�̂悤�ȉ��x�v�������Ă��܂��B�@���̓t�B�����^�̃T�[�~�X�^�������o���ŁA�E�͋����P�[�X�̒��ɉB��Ă��܂��B �@�C���̕ω���o�b�����̉��x�A�܂��[�d���̓d�r�̕\�ʉ��x�Ȃǂׂ悤�Ƃ���ƍ��̃T�[�~�X�^�̉��x���m���������o���̉��x�v�͖ʔ����قǂɑf�������x�ω��ɔ������ĕ\�����l���ς�܂��B �@����ɑ��ĉE�̋����P�[�X�ɃT�[�~�X�^�������Ă��镨�ł͂܂������P�[�X�����܂������߂��肷��̂Ɏ��Ԃ�������A���x�ω��������Ɍ����܂����Ȃ�̒x�����o�ă��A���^�C���ł͂���܂���B �@�E���̂͑����h���Ȃ̂��ȁH�Ƃ͎v���܂����A���ꂼ��ǂ�����������Ǝv���܂��̂ʼn��x�Z���T�[�������P�[�X�ɓ��ꂽ�艽�������ȂǕʂ̕��ɐG�ꂳ���āu���̋����̕��̉��x���v�肽���v�ȂǗp�r�ɂ��킹�Ďg�������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/9/17
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���݂܂���A�֏�łЂƂ��₳���Ă��������B �@�ԁA�o�C�N�ɗ��p���悤�Ƃ��A12V INPUT�̏ꍇ�ASSR �����[��12V�����[�Ƃ���ȊO�ł��̑��̕ύX�͂ǂ̂悤�ɂȂ�܂��ł��傤��? �@���Z���������萔�ł͂���܂����A��낵�����肢���܂��B ���݂� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̉�H��12V�d���̒��ړ��͂ł͎g�p�ł��܂���B �@�K����H�}�ʂ��5V�d���Ŏg�p���Ă��������B �@12V����Ȃ�O�[�q���M�����[�^�����g�p���āA5V�̓d���d����������������Ă��������B �@12V�̓d�����g�p���āA�������O�[�q���M�����[�^����5V�̓d���͍�邯��ǂ��A�莝����12V�����[���Ɏg�������I�悤�ȓ���ȏꍇ�́A�����[�̃R�C���́{��������12V�Ɍq���Œ����Ă����\�ł��B �@�������A���̉�H��S��12V�œ������悤�ɏ���������͉̂\�ł��B �@������R�l�̕ύX�����ӏ�������A�܂����A���x���̐��l���ς��Ă��܂��̂ł����������ς�����ƕʕ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�u12V�ŋ쓮����A28���ȏ�ɂȂ�Ɨ�p�t�@�������n�߂��H�������ĉ������B�v�Ƃ������e�����Ă��܂����������҂������Ă����Ԃł��B �@������ւ̉ł͓d���d����12V�œ��삷���H�}���f�ڂ��܂����A�����Ԃ̎ԓ���12V�Ŏg�p�����ꍇ�A12V�Ƃ͌����Ă�10�`15V���炢�͈̔͂œd�����ϓ�����̂ł��̉�H�}�̂܂ܒ�R�l�����ς���12V�p�ɂ���ƁA�d���d���̕ϓ��Ŋ�d�����ς��Ă��܂��ĉ��x�ݒ肪���`���N�`���ɂȂ��̂ł��܂肱�̂܂ܒ�R�l�����ς���̂͂����߂ł��܂���B�˗��җl�̈ӌ��ʂ肠���܂�AC�A�_�v�^�[����5V�d�������肵�Ă����Ƃ����O��Őv���Ă��܂��B �@�Ԃ̒��ł��̉�H���g�p�����ꍇ�́A��ɏ������悤�ɕK��12V(10�`15V)�������肵��5V�������ɂȂ��Ďg�p���Ă��������B ���Ԏ� 2009/11/25
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Ή����肪�Ƃ��������܂��B �@�m���ɓd���ϓ����l��5V�����[�ɂāA5V���̂܂܂Ŏg�p�����Ē��������v���܂��B �@�ŋ߂�12��5V�̃R���o�[�^����y�ɓ���ł��܂����A���͂Ȃ������ł��B �@�v���Ȃ��Ԏ��A���肪�Ƃ��������܂����B ��D1�̂Ƃ���́u1S2096A�v�ɂ��ĒT���Ă���܂����킩��܂���ł����B��ʏ펯�ł���Α�ϐ\����Ȃ��̂ł����A�{�i�͑����i�Ƃ��đ�p���o������̂Ȃ̂ł��傤��? ��HP��q���������A��ς��Z�����Ǝ@���܂��B����H�}���Q�l�Ɏ��ȐӔC�ɂĐ��삳���Ē����܂��̂ŁA���Ԏ��͂������Ȃ���Ȃ��ł��������B �@�d�˂ĂɂȂ�܂����A���Ή����肪�Ƃ��������܂����B ���݂� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �@�����L���� ���A����܂��B | ||||||||||||||||||||||||
| �Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH | ||||||||||||||||||||||||
|
�@MT�ԗ�����o�͂���Ă���A�i���O�g�`�iSIN�g)�ł����A�p���X�i��`�g)�o�͂ɂ������ƒ������Ă��܂��B �@��H�͈�ʓI�Ȑ����_�C�I�[�h��74HC14���g�p���đ��x�Z���T�[����o�͂����SIN�g��g�`���`���A74HC393�ɂĕ������s���A2SC1815�ɂăI�[�v���R���N�^�o�͂ɂāA�e��̑��x��K�v�Ƃ���v��ɐM�����S�p���X�œn�������ƍl���Ă���܂��B���L�̂悤�ȉ�H�Ŗ��Ȃ��ł��傤���H �@�@�@�@5V �@�@�@ |R=4.8K SIN�g--|<-----74HC14----74HC393---2CS1815---�I�[�v���R���N�^�n�� �I�f �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�uMT�ԗ�����o�͂���Ă���A�i���O�g�`�iSIN�g)�v�Ƃ͔������͂Ȃ�ł��傤���H �@�R�C���Ǝ��ŎԎ���]�����������Ă���H �@����Ƃ������̃Z���T�[�Ɣg�`������H�������������Ă���H �@�܂�A���̂��l���̉�H��GND���x���ɑ��āu�}�C�i�X�d�ʁv�����͂����悤�����Ȃ̂��AGND�d�ʂɑ��ăv���X���ɂ����d�����o�Ă��Ȃ��������Ƃ������ł��ˁB �@�������ł���A���l���̉�H�}�ł�74HC14�̓��͉�H�Ƀ_�C�I�[�h��ʂ��ă}�C�i�X�̓d����������IC��j�Ă��܂��ł��傤�ˁB �@�����Ƃ����J�b�v�����O��H�����Ȃ�������܂��A���́u�A�i���O�g�`�iSIN�g)�v�̓d���͉��u���炢�ł����H �@���s���x�ɑ��Ĉ��̓d����SIN�g���ϑ��ł���̂��A������葖�鎞�ɂ͓d�����Ⴍ�A��������Ɠd�����オ��܂����H �@���̓d���o�͂̂Q�{�̐����Ԃ̃A�[�X�ƓƗ�(�ڑ��ꂳ�Ă��Ȃ�)�ŁA��H��GND����͐藣����Ă��Ď��R�Ɉ�����̂��A�ǂ����ŃA�[�X����Ă���GND���x���ɑ������Ȃ̂����������ׂĂ��������������B �@�u�ԑ��Z���T�[�v�ƈ���Ɍ����܂��Ă��u�f�W�^���M����JIS�K�i�ŐM���o�͂��Ă�����́v�ȊO�̃R�C�����₻�̑��Z���T�[���ŐM�����A�i���O(SIN�g�Ȃ�)�ŏo�͂������̂͊e�Ђ̓Ǝ��K�i����Œ��g�ɂ��Ă͎����Ă���l�E���������l�łȂ��Ƃ킩��܂���B �@�����ւ�\�������܂��A�d�����킩��Ȃ��A�ʑ����킩��Ȃ��܂܂ł́u�C�̖����v�ł͉����l�����܂���B ���Ԏ� 2009/8/30
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���ɐ\����܂���A�����Ɏ��Ԃ��������ĕԓ����x��Ă��܂��܂����B �@�M���͌��ABS�Ɏg�p���Ă��鑬�x�p���X�ł��B���ԂɃZ���T���ߐڂ����Ă���A�Z���T�d���o�͂�GND���͎Ԃ̃A�[�X�Ƌ��ʂƂȂ��Ă���܂��BABS�Ɏg�p���Ă���M���̂��ߑ��x�p���X����JIS�ɋK�肳��Ă���p���X���ł͂���܂���B�v�����ʂ͎Ԏ��P��]�łP�U�p���X�ł����B�iJIS��4,8,12�E�E�E�j �@�����ł����A�I�V���X�R�[�v�Ŋm�F�����Ƃ���A�z�[���f�q����̔g�`�Ǝv���܂��B�ȉ����g�`�̃C���[�W�ł��B �@�@�@��1.5V �@�@�@ | �@�@�@ |____�g���l��0.3V GND---- ---- �@�@�@�@�@�@| �@�@�@�@�@�@| �@�@�@�@�@�@ ���\1.5V �@��`�����͖�0.3�u�ŁA�����オ��G�b�W��1.5�u���x�̔����g�`�ɋ߂�������肪����0.3V�Ő��ڂ��}�s�ɗ���������A����������G�b�W�ł͓��l�Ɂ\1.5V�܂ŋ}�s�ɓd����������܂��B���s���̔g���l�ł����}�s�ɗ����オ�藧��������ω�����+1.5�`-1.5V�d���͏�ɓ������x���ł��B�i�}�s�ɗ������+1.5�`-1.5V�̓d���J�ڎ��Ԃ��ς��܂���ł����j �@���A�m�F�̂��߃G���W�����n�����Ȃ��ŁAACC���I���̂܂܃^�C������ŋ�]�����Ă��g���l�y�ь`�͕ς��܂���ł����B �@���w�E�̂悤�ɁA�}�C�i�X������-0.7V���邽��IC�j��ɂȂ���Ǝv���D2��lj����A�{����������ϊ�����ȉ��̉�H��0-5V�ɕϊ��o���邱�Ƃ͊m�F�v���܂������A�Z���T�y��ABS-CU�ɉe�����Ȃ��������Ă��炦�Ȃ��ł��傤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@5V �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��R=4.8K �@�@�@�@R=300�@�@ D1�@�@| �M��---��--------|<------74HC14-----(��i��PIC�ŕ�����JIS�ɋK�肳��Ă���S�p���X�ȏ�ɕϊ�) �@�@�@�@�@�@ |�@�@�@�@| �@�@�@�@�@�@ |�@�@�@�@�\ �@�@�@�@�@�@ |�@�@�@�@���_�C�I�[�hD2 �@�@�@�@�@�@�\�@�@�@�@ | �@�@�@�@�@�@�\C0.001u�@GND �@�@�@�@�@�@ | �@�@�@�@�@�@ | �@�@�@�@�@�@GND ��R300��C0.001�̓I���^�m�C�Y�����p�ł��B �@�����܂���A�����Y��܂����B �@�l���Ă����H��0-5V�̐M���Ŏ����ƍl���Ă���܂��B �@�܂�GND�͐藣�����A���ʂƍl���Ă���܂��B �I�f �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ڍׂȑ��茋�ʂ������蒸���Ă��玞�Ԃ��o���Ă��܂����݂܂���B �@�Z���T�[���z�[���f�q�炵���Ƃ������ŁA������̂��l���̉�H�}�̂悤�Ɂu�ʉ�H�Ŏg�p����Ă���z�[���f�q�ɁA������d���𗬂��Ă��������̂��I�H�v�Ƃ����_�ɂ��āA���ۂ̃z�[���f�q�Ŏ��������Ă��炨�������悤�Ǝv���Ă����̂ł����A�茳�̃z�[���f�q���ǂ����ɍs���Ă��܂��Ĕ����ł��Ȃ��̂łƂ肠�������������ōl���Ă��Ԏ����܂��B �@��H�͐V������H�}�̂��̂ō쐬����ăp���X�͎�ꂽ�悤�ł����A�u�Z���T�y��ABS-CU�ɉe�����Ȃ��������Ă��炦�Ȃ��ł��傤���v�Ƃ����_���S�z�ł��ˁB �@�����������Ɂu�d����������v�f�q�ł���z�[���f�q�̓d���o�͂ɑ��āA����������H�����o�C�A�X�d���𗬂��`�œd�����������ꍇ�ɁA�{���ɐ������ԍ�ABS-CU�������Ă��邩�ǂ����������^��ł��B �@�����g�p����Ă���z�[���f�q�����͂O�̎��ɂ͒�R�l���قږ�����ԂŁA���͂Ă��Ă���Ƃ��ɒ�R�l�������Ȃ��đ���ɓd��������悤�ȓ�����������̂Ȃ���͖����̂ł����A�z�[���f�q�ɂ���R������(�����Ə��d���������Ă��鑤�������ւ�Ȃ��ƂɁc)�����ɊO������d���𗬂��Ƃ������Ƃ̓z�[���f�q�̏o�͒[�q�Ԃɓ�����R�ɉ������d�������������Ă��܂��H �@�܂����͂��������Ă��Ȃ��̂ɁA�������Ă��鎞�Ɠ���������ȏ�̓d�ʍ����������Ă����Ƃ������͂���܂��H �@���������Ȃ��Ă���̂ł�����AABS-CU�̓^�C���̉�]�����m���鎖���ł��܂���̂ŁAABS�͐���ɓ��삵�Ȃ��Ǝv���܂��B �@�����A���̉�����Ԃő����Ă��ē��Ɉُ�\�����o���A�u���[�L����ABS�����삵�Ď����Ń|���s���O���Ȃ��̂ł���AABS�̓^�C���̉�]�����m���Ă������ɂȂ�܂��̂ŁA�z�[���f�q�ɉ�����o�C�A�X�d���������Ă�����(?)�ɉ�]�͌��m���Ă���Ƃ������ɂȂ�܂���ˁB �@�z�[���f�q�̔���ȏo�͓d�������̂܂ܓd����r��A�I�f�l�̍l����ꂽ��H�̂悤�Ȃ��̂Ō��m���Ă���̂ł͂Ȃ��A��U�I�y�A���v���ő���������ŒP����r�ł͂Ȃ�������H�ȂǂŃp���X���m�����Ă���̂��Ƃ�����A�����Z���T�[�̂Ƃ���œd�����Ԃ��ς��Ă��ω��_�����͑����ă^�C���̉�]���Ă���̂�������܂���B �@�ł��A���͎��͂��������Ă��Ȃ����ɂ�0.3V��菭�����̓d���ɂȂ��Ă��āA�M���M��ABS-CU���Z���T�[���������Ɗ��m���Ă��邾���ŁA�z�[���f�q�����x�ɂ���ē������ω�������o�N�Œ�R�l�������ɕς������A�����̔��q�ɒ[�q�ԓd��������l���Ă��܂��āA���ꂪ���s����ABS-CU�ɑ��ă^�C����~�ƌ딻�f������ُ�M���ɂȂ�\�����̂Ă���܂���B �@����͂������̃Z���T�[�������A�ǂ��̉��Ƃ������i����˂��~�߂āA�X��ABS-CU�̒��̉�H�}�܂ŏ����Ē��ׂȂ��ƒf��͂ł��܂���B �@�����A�����܂��Ɍ�����̂͂��̏�ԂŖ{����ABC-CU�������E�����Ɛ���ɓ��삵�������邩�ǂ����͉�H��͂����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B �@�d�q��H�̗�����v�p�^�[���ɏƂ炵���킹��������čs���ׂ��ł͖��������ł����B�Ƃ����������͌����܂��B �@���͈ꌩ����ɓ��삵�Ă���悤�Ɍ����Ă��A���ԑ��̉�H��Z���T�[���Ă��܂��āA���ꂪ���s���̑厖�̂Ɍq����댯��������̂��\�������Ȃ�(���S�����o���Ă��Ȃ�)����A���̂悤�ȉ�����H�͂����Ɏ��O���ׂ��ł��B �@�������̂悤���z�[���f�q�炵������ȓd���o�͂̐M��������p���X�����ꍇ�́A�Z���T�[��H���ɉe�����y�ڂ��Ȃ��I�y�A���v�ɂ��n�C�C���s�[�_���X���͉�H����Ă�����̎�M��H��ڑ����ׂ��ł��B  �@0.3V�قǂ̔���ȓd�������邩�������肷�邾���Ȃ�A�I�y�A���v�ő������Ȃ��Ă��������n�C�C���s�[�_���X���͂̃R���p���[�^(���Ƃ���LM393)����ł��A0.15V���炢��臒l�ɂ���HI/LOW����������Ă��̌�̓��W�b�NIC��g�����W�X�^�APIC�Ɍq�����Ƃ��ł��܂��ˁB
�@0.3V�قǂ̔���ȓd�������邩�������肷�邾���Ȃ�A�I�y�A���v�ő������Ȃ��Ă��������n�C�C���s�[�_���X���͂̃R���p���[�^(���Ƃ���LM393)����ł��A0.15V���炢��臒l�ɂ���HI/LOW����������Ă��̌�̓��W�b�NIC��g�����W�X�^�APIC�Ɍq�����Ƃ��ł��܂��ˁB�@��H�}�͈��ł��A�������ŐF�X�Ɖ�H�v���ł���悤�ȕ��Ȃ̂ŁA���̕��@�ɂƂ���ꂸ�ɑ��̕��@�������Ă݂���Ɩʔ������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/10/26
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�ڍׂȕԓ����肪�Ƃ��������܂��B �@���x��܂������A�����A��H��g�ݏグ�A���[�X�Ɋ��p�����Ē����Ă���܂��B �@���[�X�ԗ��͊C�O���i�̂��߁A�Ȃ��Ȃ����{�Ɏg������̂��Ȃ��̂ő�Ϗ�����܂����B �@���ꂩ������邱�Ƃ����F��v���܂��B �I�f �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�������삵�ĂȂɂ��ł��B �@���[�X�Ԃł��g�p�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA���Ȃ�X�s�[�h���o����Ă��鎞�Ƀu���[�L���O�������ɉ����d�C�I�ȃg���u���Ńu���[�L���䂪���������Ȃ��āA���Ɋւ��悤�Ȏ��̂Ɍq����Ȃ��悤�ɂ��F�肵�Ă��܂��B ���Ԏ� 2009/11/3
|
|||||||||||||||||||||||
| �ȈՃf�W�^���\������d�͌v | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�����y�����q�������Ē����Ă���܂��Alevitron �Ɛ\���܂��B �@�g�p���̋@��̏���d�͂��펞�\������d�͌v���A�ȒP�ɐ��삷�鎖�͏o���܂���ł��傤���B �@�g�p���̋@��̓d�͏���ʂ������������ł��̂ŁA������x�̐��x�Ŗ�肠��܂���B �@AC100V 1~1500W �̋@���ڑ��������ƍl���Ă���܂��B �@PC�E�e���r�E�G�A�R���E�d�M�� �Ȃǂ��ڑ��̑Ώۂł��B �@7�Z�O4���ɔ瑊�d�͂�\�����镨���ق����ł��B �@���͖{��Ő\���������܂���B�f�l�ɂ͓���ł��傤���B �@�ǂ����A�X�������肢�������܂��B �@���L�̎ʐ^�̂悤�Ȃ��̂����z�ł��B http://blog.livedoor.jp/cpiblog00520/archives/51437003.html levitron �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ŋ߂̃G�R�Ɠd�Ȃǂ̓W���ł͓d�͒l��\�����Ă���X�������܂����ˁB �@���Љ���܂����d�C�X�l�̃u���O�̂悤�ɁA���[�J�[������ꂽ�d�͕\�����u���Ă���Ƃ�����悭�������A���q����ɂƂ��Ă̓J�^���O���l�Ō�����͉����f�W�^���\�����Ă�ق������킩��₷�������͂�����悤�ł��B �@���āA����̂���]�́u1�`1500W�v(����x�ɕ\��)�Ƃ����̂͂�������ґ�ł͂���܂��H �@�����̐��E�ł�1��1500�{�������W�ň������Ƃ���Ƃ��Ȃ萸���ȑ����H���K�v�ŁA�ŏ��l����ő�l�̊Ԃŋώ��Ȑ��x�����߂悤�Ƃ���Ƃ��Ȃ��ςȑ��u�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�\���݂̂̓d�͌v�Ȃ�u1�`200W���x�v�Ɓu10�`1500W�v���x�������W�������āA���̒��ōŏ�����\��ۏ���悤�Ȃ��̂����܂����A����]�̕��ɂ͂���قǍׂ��Ȓ��ߋZ�\����ȑ������������ł͂Ȃ������ł��̂ŁA�u�ł�����������(���i�������Ȃ�)�v�u�ȒP�ɑg�ݗ��Ăł����v�Ƃ��������ʼn�H��v���܂��B �@���̂����u���x�͂���Ȃ��v�u10W�����͌v��Ȃ�(�\���͂��邪���x�Ȃ�)�v�Ƃ���10�`1000W(1000W�ȏ�͏������x����)�\���v�Ƃ��܂��B �@����A10�`1500W���S���j�A�\������H�I�ɂ͉\�ł����A10�`8000W�܂őΉ��̓d���Z���T�[CTL-10-CLS���������l�b�g�ʔ̂ɂ͗L��̂��X���ɂ͒u���Ă��Ȃ��Ƃ����Ă����炭�ł����̂ŁA�X���Ŕ�����P�����N����CTL-6-S32-8F-CL���g�p���܂��B��������10�`1500W�܂ł͉�H�I�ɂ͑���ł��܂����Z���T�[�̓������ő�1000W�ȏ�ł͒������������������\���͍s���܂���B(���ۂɎg�p�����炠�܂�C�ɂȂ�Ȃ����x�ł�����) �@RL��10���ɂ��āA��H������p�ɍ��킹���1500W���͒��������ۂĂ�炵���ł������x�͔����d����ł̏o�͓d�������Ȃ�Ⴍ�Ĉ���x�������Ȃ肻���ŁA����͂�����o�����X�ǂ��o�͂�����RL=100���Őv���Ă��܂��B �@�X�C�b�`�����ă����W�ؑւł���悤�ɂ����1�`199W��10�`1000W��100�`1500W�݂����ɔ͈͕ʂɐ��x��ۂ��Ƃ��ł��܂����A���߂��ʓ|�Ȃ̂ō���͊������܂��B �@�ŋ߂̃G�R�u�[���Łu�ҋ@�d���v���C�ɂȂ����������������܂��A�Ȃɂ���u1500W�܂Łv�Ƃ��������ȑҋ@�d�͂ɑ��Ĕ���Ȓl�������Ɍv�肽���Ƃ�������]���炻��͊��킸�A10W�ȉ��̔����d�͂͑���Ȃ��Ă��A�ڑ�����PC��Ɠd�����쒆�d���Ƃ����傫�Ȓl�̂ق��̂���]�����������Ǝv���܂��B �@�ҋ@�d�͂𑪂肽���ꍇ�́A�ҋ@�d�͐�p��0.1W�`10W���x�ɖڕW���i�����������דd�͌v��v���ꂽ�ق��������ł��傤�B���̏ꍇ�̓N�����v�Z���T�[���g�p�����ɁA���ڒ�R�ȂǂŒʉߓd�����v��悤�ɂ����ق��������ł��傤�ˁB �@�ꉞ�A����̉�H�Ńe�X�g�܂ł͍s���܂����ҋ@�d�͑���p�̉�H�͍���̖ړI�ł͖����̂ŏڂ����͌f�ڂ��܂���B �@�܂��Alevitron�l�͑��̓d�͌v�̐���L���T�C�g�����ĈӖ��s���ō��܂��ꂽ�����ł����A���������̉�H�̐������Ӗ��s�����Ǝv���܂��B �@�{�L���ł͈Ӗ����킩��Ȃ������͓ǂݔ���āA��H�}�ƒ������@�����ǂ�Œ����č\���܂���B����Ő���͂ł��܂��B �@���ۂɃe�X�g�����\���摜�͌��Ă��ē��e���킩�邩�Ǝv���܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ă��������B �@�����āc�Ō�̂ق��̂�����Ƃ������ӊW�͓ǂ�ł��������B�d�v�Ȃ��Ƃ������Ă���܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
IE�ł͏k����Ԃŕ\�������ꍇ������܂��B�g�呀�삵�Ă��������B
 �� �J�����g�Z���T�[
�� �J�����g�Z���T�[�@�𗬓d���Z���T�[�ɂ�CTL-6-S32-8F-CL���g�p���ĉ�H��v���܂����B �@RL=100���Ŏg�p����ꍇ�A1W�`900W���͒��������m�ۂł������ł��B900�`1500W���͑���͂ł��܂����������������A���ۂ̓d����菭�����Ȃ��\������悤�ɂȂ�܂��B �@�Z���T�[�̐��\�́u1W�`�v�Ƃ͂Ȃ��Ă��܂����A����͑����H�̂ق��̔����d�����̓����ȂǂŎ��ۂɈ��肵�ēd�͂��v���̂�10W���x�����ł��B �@���̃Z���T�[�͎ʐ^�̂悤�ɓS�S���������p�J�b�ƊO��Ĕ푪��P�[�u���ɊȒP�ɋ��ނ��Ƃ��ł��܂��B �@�d�͌v�̒������Ŏg�p����Ȃ�ʂɊ���Ȃ��Č������Ă���Z���T�[�ł������ł���(�z���̂ق���ʂ�)�A�Z���T�[�𑪒�킩��o���Ċ����̓d�C�z��������ő��肷��悤�Ȍ`�ł��ȒP�ɔ푪��P�[�u���ɋ��߂�̂ŕ֗��ł��B �@RL=100���Ŏg�p����̂ł����A�J�b�v�����O���ł�51���~�Q�{�ŎĂ��܂��B �@����͌��OP�A���v�ɂ�锼�g������H���ő�}1.7V(�ł���Ό��E�l�t�߂͎g�������Ȃ�)�̌𗬂������Ȃ��̂ŁA�������̂܂�RL=100���ŃJ�b�v�����O�����1500W�̎��ɂ͌�1.4V�Ńs�[�N�́�Q�{�Ł}2V���炢�ɂȂ��Ă��܂��A���͔͈͂��z���Ă��܂��܂��B �@���̒l�ł�1000W���x���z����d�͂������Ƒ���Ȃ��̂ŁA�Z���T�[�̏o�͓d�����ɂ��Ă����܂��B �@����E�E�EOP�A���v�������ƍ����d���ŋ쓮����Ƃ��AOP�A���v�̐������g�����Ƃ��ā{�|���d���ŋ��ȏ��ʂ�́uOP�A���v�炵����H�v�������ꂭ�炢�̏����ȓd���Ȃ牽�̖��������̂ł����A����́{�|�̗��d�����g���ēd�����ɂ�����������悤�Ȃ��Ƃ͂����A�g�p����f�W�^���d���v���K�v�Ƃ����{5V�݂̂̓d����OP�A���v��H�܂őS���������Ă�낤�Ƃ����n�R��H�v�Ȃ̂ł��������u������݁v�����܂�Ă��܂��B �@�Ȃɂ���A�J�����g�Z���T�[���1500�~�ȏ������̂ł�����A���̕����ŕn�������Ȃ��Ɓu���x�͋��߂Ȃ��A�f�l�ł����邩�H�v�Ƃ����ړI�̂��̂ɋ@��S�̂ʼn���~�������Ă����Ȃ��ł���H �� �S�g������H �@OP�A���v�ɂ��S�g������H�ł��B �@OP�A���v�̑S�g������H�́{�|�̗��d���łȂ��Ɠ��삵�܂���(�}�C�i�X���̓d�ʂ��g���̂Łc)�A�����ł́{5V�̓d�������R�ŕ������āu���zGND�v�����A�����𒆐S�Ƃ���OP�A���v�����삷��悤�ɂ��܂��B �@���zGND�͓d��GND���猩��+1.75V�ɂ��܂��B�͂āA�u5V�̔�����2.5V����Ȃ��́H�v�ƕ��ʂ͎v����ł��悤�B �@�������g�p����OP�A���vLM662CN�̓��͕��ɂ͖�1.5V�̃w�b�h���[��(�g���Ȃ�����)������A5V�Ŏg�p����Ɠ��͔͈͂�0�`3.5V�ł��B�]���ĉ��zGND�͂��̔�����1.75V�ƂȂ�킯�ł��B(LMC662CN�o�͂̓��[��to���[����0�`Vcc���t���ɑΉ����Ă��܂�) �@�������E�E�EOP�A���v���{�|���d���Ŏg���Ă������Ȍv�Z�����Ȃ��ėǂ��̂ł����E�E�E�B �@�����ł̓Z���T�[�������������d��(�̎��ۂ�1/2)�𗼔g�������邾���ő����x�͂P�ł��B�d���͑������܂���B �� ������H �@��R�ƃR���f���T�ɂ�镽����H�ł��B �@�����őS�g�������ꂽ��(����)���ɂ��܂��B �@�_�C�I�[�h�̖����P��������H�ł��̂Ŗ����̑S�G�l���M�[�����R�����ꂽ�����d���ƂȂ�A����͌𗬂Ō����Ƃ���́u�����l(RMS)�v�ƂȂ�A���ꂩ�狁�߂��������d���Ɠd���̌𗬓d�����|���Z����Ƃ��m��ɂȂ肽���u�瑊�d���v(�����l�ɂ��d��)�����߂��܂��B �@�������A�{��H���ȈՔ��ł��̂œd���d���𑪒肷���H�͂���܂���B �@�]���Đ������d���d���ϓ��ɒǐ����ĕ\�����v�Z����鐳�m�ȓd�͌v�͍��܂���B �@�����܂Łu�d����AC100V���v�Ƃ��u���₤���̃R���Z���g�͂���AC102V���v�Ƃ������̒l����Ƃ��ēd�͂����߁A���̊����u��ɓd���d���͈��v�Ɖ��肵�Ă̓d�͕\���Ƃ��܂��B �@�d���ɐ������ǐ������H�܂œ����ƂƂĂ������ւ�ł��B �@�e�X�g�|�C���gTP1�̓d�����v��ƁACTL-6-S32-8F-CL�̃f�[�^�V�[�g���o�͓d���O���t(RL=100��)��1/2�̓d�����ϑ��ł��܂��B���ꂪ�ϑ��ł���ΑS�g������H�͐��������삵�Ă��܂��B �� �o�b�t�@�@���@�Q�{���� ��H �@������H�̃R���f���T����d�������o���ēd�����v���H�ɂ���ƁA�R���f���T�̓d���͂���ʼn������Ă��܂��̂ł��܂����������܂���B(���₻��̐��l�Ōv�Z����悤�ɂ�������̂ł���) �@�����ł�OP�A���v�̓��͓͂d�����قƂ�Ǘ����Ȃ��Ƃ��������𗘗p�����o�b�t�@���͂Ƃ���Ƌ��ɁA�]������H�œd�����Q�{�ɂ��܂��B �@�d�����Q�{�ɂ���̂́AOP�A���v�̃w�b�h���[���̊W��1/2�ɂ��Ă����Z���T�[�d�������ɖ߂��ׂł��B �@�����Ȃ�RMS�l�ɂȂ��Ă���̂�1.7V���z���邱�Ƃ͖����̂ŁA�Ȃ�ƂȂ����̐��l�ɖ߂��Ă������ق����F�X�ƌv�Z���₷���̂ŁB �� �I�t�Z�b�g���߉�H �@�Ō�͓d���v�œd����\��������Ηǂ������ł����A�����ō���͕̂��������ꂽ�d�������zGND����̓d���ł���A�d���v�ő��肷���d��GND�����+1.75V�قǍ����d���ł��B �@���̂܂ܕ\������Ɛ������d�͕͂\���ł��܂���B �@�Ƃ������A�������{�|���d����OP�A���v��H��v���Ă�����A����GND��0V�Ȃ̂ł��̂܂ܓd�����v�邾���ł悢�̂ł����E�E�E�B �@�ł��A�{�|���d���ō���Ă��Ă��u�I�t�Z�b�g�����v�͕K�v�Ȃ̂œ����悤�ȉ�H������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�����̎�Ԃ͂��܂�ς�܂���ˁB �@�����ł�OP�A���v�ɂ��u����������H�v�Ƃ�����H������d���������zGND�Ԃ�̓d���و����Z���܂��B �@���̂܂����zGND�d���ڈ����Z����悢�悤�Ɏv���܂����AOP�A���v���I�t�Z�b�g�d������ł킸�������d��������Ă���̂ŁA��������邽�߂ɂ������Z����d���͉ςɂ��Ă���߂ł���悤�ɂ��Ă��܂��B  �� �f�W�^���\����
�� �f�W�^���\�����@�u����Ȋ�����7�Z�O4���\���v(�����N��u���O�Q��)�Ƃ�������]�ł����̂ŁA����ɍł��߂��H���d�q�́u�k�d�c�f�W�^���p�l�����[�^ �R�E�P�^�Q���i1999�\���j�m�T�u���́A�����햳�n�v���g�p���܂��B �@����`�A�����ڂقڈꏏ�ł���(��) (�����Ɏg���邩�Ɣ����Ă����Đ���) �@���̃f�W�^���d���v�́u�����}200mV�v(�Œ�)�ł��̂ŁA�I�t�Z�b�g��H�̏o��(��0�`1.5V)��1/10�{�ɂ��ē��͂��Ă��K�v������܂��B �@�Z���T�[�̏o�͂�1000W=1.0V�ƃs�b�^����������P����1/10������������ł����A������ƈႤ(�f�[�^�V�[�g�̃O���t�Q��)�̂ł��̂ւ�̐��l���߂ƁA���͂��̃f�W�^���d���v�͂��Ȃ萸�x������(�܂�1000�~�̈����ł�����)�̂ł��̌덷�C���̈Ӗ������˂�VR2�ł�����x�͈̔͂Œ��߂ł���悤�ɂ��Ă��܂��B �@���Ȃ݂ɁA���x�̍����u�{���v�̃p�l�����[�^�[���ƈ��5000�~�`�ꖜ�~�͂��܂��B(�H�Ɨp���Ƃ����Əォ�ȁ`) �� ���ߕ��@ �@�\�����鐔�l�́A���m�̂v���̋@�����q���ŁA���̂v���ɕ\���������悤�ɒ��߂��܂��B �@�ł��̂�����ɂ͕K���u�𗬓d���̌v���e�X�^�[�v�܂��́u�𗬓d���p�N�����v���[�^�[�v���K�v�ł��B �@��������H���̓d�����v��̂Ɂu���ʂ̃e�X�^�[�v���K�v�ł�����A���ʂ̃e�X�^�[�ł��𗬓d�����v���^�C�v�̂��̂�����Έ��ōς݂܂��B �@�����𗬓d�����v���e�X�^�[�Ȃǂ��������Ŗ����ꍇ�́A�����ւ�ʓ|�ł���CTL-6-S32-8F-CL���f�[�^�V�[�g�̃O���t����d����ǂݎ���āATP1�̓d���l(1/2�ɂȂ��Ă��܂�)���ʂ����ĉ��`�̓d���̎����ׂĂ��������B����Ŏ��ۂɗ���Ă���d���������܂��ɒm�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�܂��AVR1�͉E�����ς��AVR2���E�����ς��ɉĂ����܂��B �@���߂��I���܂ł͂V�Z�O�f�W�^���\����̐��l�̓f�^�����ł����C�ɂ��Ȃ��ł��������B �@�d�������ĕ��ׂɉ����@��(50�`100W���x���]�܂���)���Ȃ��ATP1�̓d�����e�X�^�[�Ōv��100W�@��̏ꍇ��0.052V���ł��邱�Ƃ��m�F���܂��B����100W�@��ȊO�ő��肵�Ă���ꍇ��100W�Ƃ��̓d�͒l�̔�Ōv�Z���Ă��������B �@���ꂪ��������Z���T�[���畽����H�܂ł͐���ɓ��삵�Ă��܂��B �@�������ׂɂ͉����q�����ɁI�ATP2�̓d�����e�X�^�[�Ōv��܂��B�܂��O�v�\���̒��߂����܂��B �@�ŏ���100mV�ȏ�������Ă���͂��ł��B �@��������VR1�����ɉĂ䂭��TP2�d����������͂��߂܂��B �@���̂܂܉čŒ�̐��l�ɂȂ鏊�Ŏ~�߂܂��B��6mV���x�ł��B �@�Œ�ɂȂ��Ă�������炭�͍Œ�l��ۂ��A�܂��Â���Ƃ܂��d���������オ��͂��߂܂��B�ł����Œ��ۂ��Ă���͈͂ł������Z�͍s���Ă���̂ŏo�͓d���͐����������͈͂ɂȂĂ��܂��̂ŁA�K���Œ�̒l�ɂȂ�u�ԂŎ~�߂Ă��������B �@����ŃI�t�Z�b�g���߂͈�U�I���ł��B �@���ɕ\���l�̒��߂ł��B �@50�`100W���炢�̕��ׂ̓d�����Ƀe�X�^�[�Ōv���Ă����܂��B �@�d�����v��Ȃ��ꍇ�͕��ׂɌq����TP1�̓d�������f�[�^�V�[�g�̃O���t�ɏ]���ċt�Ɍv�Z���܂��B(���ۂ͂�����ƌ덷������ł��傤) �@���Ƃ��A100W�d���ɗ����d�����v�肻�ꂪ��0.9A�������Ƃ��܂��B �@����ǂ͂��̓d����{���u�̕��ׂɌq���ŁA�f�W�^���\�����u90W�v�Əo��悤��VR2�߂��܂��B �@�������R���Z���g�̓d���͏��100V�Ƃ͌���܂���A�R���Z���g�̓d�����v���Ă���102V��������A102V�~0.9A��91.8W�ł�����A�\����92W���炢�ɂȂ�悤�ɂ��Ȃ���ΐ��������b�g����\�����Ă��邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂���B �@���̂�����͓d���d�������m���Ċ|���Z�����H�������Ȃ��ȈՔł̎ア�Ƃ���ł��B �@�����āA�u�I�t�Z�b�g���߂̍ēx�������v(�ق�̏�������VR1���Ē���)�Ɓu�\���l�̔���߁v(�ق�̏�������VR2���Ē���)�𐔉�J��Ԃ��Ă�萳�����l��\���ł���悤�ǂ�����ł䂫�܂��B �@���̒ǂ����ݍ�Ƃ��{���u�̐��x�����E���邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA���T�d�ɁA��萳�m�ɍs���Ă��������B �@�܂��ǂ����ݍ�Ƃ��s������ɁA�e��̏���d�͂̈Ⴄ�@����Ȃ��Ō��ăo�������傫���ꍇ�ɂ́A�����傫�ȏ���d�͋@���ڑ�������ԂŒǂ����ݒ��������Ă��������B �@�ǂ����Ă����̏H���̃f�W�^���d���v�����x�������A�e�X�^�[�ƕ��ׂē����d����\�������Ă��Ă�ňႤ���l��\�������肷���������`�����ł��B �@�{��H�̒ǂ����ݍ�Ƃ��u�����܂ł��̏H���̃f�W�^���d���v�ŋɗ͌����ڂ͐��������b�g����\�����邽���v�Ǝv���Ă���Ă��������B �@���̃f�W�^���d���v�ƃe�X�^�[�����Ɍq���Ńe�X�^�[�̓d�������Ȃ������Ă���Ɠ����o�������Ȃ�܂�(���)�B �@��H��P�d���œ��삳���Ă��邽�߁A�I�t�Z�b�g���߂��s���Ă��Œ�6mV�قǂ̓d�����c�芮�S��0V�ɂ͂Ȃ�܂���B �@������f�W�^���d���v�ŕ\������Ɓu�d�C���g���Ă��Ȃ��̂ɂU�v�v�ƕ\�����܂��B����͌̏�ł͂���܂���B�P�d���ɂ��Ă��邽�߂����������x�ł��B �@�C�ɂȂ���́{�|���d���̉�H��v���Ă��������B �@�Ƃ��낪�ł��A�������x�������H���̃f�W�^���d���v�́A�����̎茳�̕��͓��͒[�q��GND�ƃV���[�g����0V�ɂ��Ă������A����s�v�c�u-014�v���x�̃}�C�i�X���l��\�����܂��B �@�Ƃ������ƂŁA+0.6mV�̃I�t�Z�b�g(6mV��1/10���Ă���)��-1.4mV�̃f�W�^���d���v�̕\���덷�ŁA�d�͂O���b�g�̎��ɂ́u-007�v�`�u-005�v������ŕ\�����t���t�������Ԃɗ��������܂���(��) �@�I�t�Z�b�g�l�������グ�Ă��Ɓu000�v�\���ɂȂ�܂��B����͂����Ŏg���Ă��܂��B �@�����ēd�����オ��ΐ^�̓d���ƕ\���d���Ƃ̌덷�͏��Ȃ��Ȃ��Ă䂫�܂��B(�{���͗��̔��Œ��R�Œ��߂ł��܂�) �@����̓f�W�^���d���v�����x�̈������痈�Ă��邱�ƂȂ̂ŁA�F���w�������f�W�^���d���v���K��-1.4mV�̌덷�������Ă���Ƃ͌���܂���B �@�܂��H���ł̔������ł�����A�^��V�ɔC���܂��傤�I �@�Ƃ������ƂŁA�����ƒ��߂����{���u���ǂ̒��x�̑���\���ɂȂ�̂������Ă݂܂����B �@�U�X�u���x�������v�Ə����Â��Ă��܂������A�o���̈����q�ɂ͈����q�Ȃ�ɂ����Ƃ�����̂ق�����o�͓d�������킹�Ă��������Ȋ����ɁE�E�E�B
�@���̉�H�̐��x�ƏH���f�W�^���d���v�̐��x���炷��ƁA��ԉ��̌��͎Q�l���x�ɍl����ׂ��ł����A�T�v�܂łقڐ������\���ł����̂͂�͂荡��g�p�����d���Z���T�[CTL-6-S32-8F-CL�̊��x�Ɛ��x�̗ǂ��̂������ł��傤�B �@�uPC�E�e���r�E�G�A�R���E�d�M�� �Ȃǂ��ڑ��̑Ώۂł��v�u������x�̐��x�Ŗ�肠��܂����v�Ƃ�������]�ł����A�����ƒ��߂��Ă��ꂭ�炢�̐��x���o��܂����p��͖�薳���Ǝv���܂��B �@���łɁA�J�����g�Z���T�[��RL��1K���ɕύX���A���ꂾ���ł̓_���Ȃ̂Œ��ߍς�(�ǂ����ݍς�)�����H�ɍ������o�͓d���ɂȂ�悤�ɃZ���T�[�d�������킹�镔�i�����Ď����Ă݂��Ƃ���E�E�E
�@���x��10�{�Ŏg���Ɓu�ҋ@�d���v���炢�̏��Ȃ��d���ł��v�ꂻ���ł��ˁB �@�����A�����x�E�����ו\���ɂ���Ƃ�萳�m�Ȓ��߂�v���A���m�ɒ��߂��Ȃ��Ɛ��������l��\������̂ŁA����͂�����̂ق��͌f�ڂ����ɕK�v�Ȃ�F���������ʼn����E���ǂ���邱�Ƃɂ��܂��傤�B �@�����W�ؑփX�C�b�`�����āu1�`199.9W�v�Ɓu10�`1500W�v�̗������v���悤�ɂ���̂������ł��ˁB �@���ɐ��\�̗ǂ��d���Z���T�[CTL-6-S32-8F-CL�̂������ł��Ȃ蕝�L���d�͒l�ł���Ȃ�ɐ��������l��\��������u�d�͌v�v����邱�Ƃ��ł��܂����B �@�����A���i���W�߂ĉ�H�}�ʂ�|���ƍ��Ί����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�u�����v�Ƃ������̂��ǂꂾ�����m�Ȑ��l��\�����邩�͒��߂���l�Ԃ̘r�O�ɂ������Ă��܂��̂ŁA���ДO����ɒ��߂��ď�L�̊m�F�ʐ^���x�̐��x�ŕ\������g����Ȃ�Ɋ������d�͌v�h�삵�Ă��������B �@�e��d�͌v�̒��ӏ����ɂ�����Ǝv���܂����A�𗬔g�`������������Ă���ꍇ�ɂ͕\�����l�����ۂ̓d�͂ƈقȂ�ꍇ������܂��B �@�܂��U������(�R�C���E���[�^�[��)�̏ꍇ�͈ʑ��Y���ɂ�閳���d�͂̔����Ŏ��ۂɏ�����d�͂Ɠd���d�����狁�߂���d�͂Ƃ̊ԂɈႢ���������܂��B �@�{��H�ł͒P���ɐ����E�������Ă��܂��̂łقځu�G�l���M�[�̕��ρv�����Ă���͂��ł�����A��قǐ����g����ɂȂ��Ă�����̈ȊO�͂قڐ��m�Ɍv���ł��傤���A�ꉞ�𗬂̌����I�Ȗ��ł��������g���u�����L�肤��Ƃ������͂��������������B ���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��
�@�d���Z���T�[���1500�~�ȏ�A�V�Z�O�̃f�W�^���d���v�����1000�~�A����ȊO�̕��i�A�d���pAC�A�_�v�^�[�܂��̓X�C�b�`���O�d�����j�b�g�A1500W�����S�ɒʂ��Ƃ���Ɠd�͔z���p�̃R���Z���g��(���̂ւ���܂������I)�A�S�Ă�g�ݍ��ރP�[�X�E�E�E�ȂǂȂǂ�S�����킹���5000�`6000�~�ȏ�͗\�Z���K�v�ł��B �@�s�̕i�ŗL����ELPA�́u�G�R���b�g�v�����2980�~�Ŕ����܂��B �@�����ȃ{�f�B�Łu�d��(���b�g)�v�����ł͂Ȃ��u�ώZ�g�p�ʁv��u�d�C��v�܂ʼnt���\�����Ă���܂��B �@�����5000�~���炢�����āu�d��(���b�g)�v���������\�����Ȃ����u�������́A�s�̂̐��i�����ق�����荂�@�\�ŃR���p�N�g�Ƃ����u����͈������I�v�Ƃ������z�ɂ͔������H�ł���B �@�Z�p�͂̂�����Ȃ�1000�~�̃f�W�^���d���v���l�i��PIC�}�C�R���Ɖt���\���p�l�����āA�����Ń}�C�R�����d���v������Ă��łɃv���O�����Łu�ώZ�d�́v�u�d�C��v�Ȃǂ��v�Z���鎩�ȗ��̓d�͕\�������邱�Ƃ��\�ł��B �@�����ɂ�������\���ł���t���p�l���Ŗ����Ă��A�V�Z�OLED���S�ł��̃f�W�^���d���v�Ɠ����悤�ȕ\�����ɂ��āA�X�C�b�`���삩�����ŕ\�����ւ���̂ł������ł��ˁB�u�V�Z�OLED�̕\�����v�Ƃ�����]���������@�\�ȓd�͕\������}�C�R���v���O������g�ނƗe�Ղɍ쐬�ł��܂��B �@�u�j�Ȃ�Ԃ�����V�Z�O�͐��`�I���̃��}������炸���ĉ��Ƃ���I�H�v�Ƃ�������]�Ȃ�ǂ��̂ł����A�����łȂ���Βǂ����ݒ��߂Ȃǂ��Ȃ�X�L����v�����H�ł��̂Łu�f�l�ɂ�����v�Ƃ����_�Ɋւ��Ă͂�����x�̋Z�ʂ⒲�ߋZ�p���K�v�ȁA������Ƃ����~���̍�����H�ł��B �@�v���Ē��Ă����ăi�j�ł����A�u�d�q��H����Ƃ��Ă��āA����āA�Ȃɂ�蒲�߂���̂��y�����I�v�Ƃ������łȂ��ƁA����Ă��璲�߂ō��܂���邩������܂���B(�ʐ^���ڂ������̐��x�����߂Ȃ���܂�����Ȃ�ɁE�E�E) ���Ԏ� 2009/9/5
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@��H�}���v���v���܂����̂ɁA�����قǐv���ɉ����܂��Đ^�ɗL�������܂��B �@��̓I�Ȏ������ʂ̌f�ځA�L�������܂����B �@���x������̂�10w�`�Ƃ̎��ł����A���̗p�r�ł͕K�v�\���łƂĂ����肪�����ł��B �@���b�ɂ���܂����G�R���b�g �ł́A�d�͗ʂ̕\�������ł��Ȃ��̂ŕs���ł����B �i���b�g�`�F�b�J�[���w�����ׂ��ł����B������Ă��܂��B�j �@����ɁA��������̎��F�����~������7�Z�O���ǂ���ł��I �@�L�������܂����B��������v���܂��B levitron �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���ꂭ�炢�̑傫���̂V�Z�OLED�\������g���Ă���A���ʂ̕����̒��Ȃ�ǂ�����ł����b�g�����m�F�ł��܂����A�钆�ł��������ǂ߂܂��B �@�s�̂̃��b�g�`�F�b�J�[���ƈ������̂�6000�~���x���܂�����A���̉�H�Ɠ������炢�ł��傤���B���@�\�ŃG�R���b�g�ȏ�ɐF�X�v��܂����牿�l�͂���Ǝv���܂��B�c�O�Ȃ���ƒ�p�Ɏs�̂���Ă�����̂ɂ͂V�Z�OLED�^�C�v�͂���܂���ˁB �@�d�͂����A���^�C���Ō����ƁA�G�A�R���Ȃǂ��ŏ��̓t���ғ��ő傫�ȓd�͂��g���Ă��āA����������300�`400W�Ȃǔ�r�I���Ȃ��d�͂ʼn^�]����Ă���̂����Ď��Ėʔ����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/9/7
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�H���d�q�̃p�l�����[�^�[�@�o�l�|�P�Q�X�a�́A�d����ʂɋ������Ȃ��Ɛ��������삵�܂���B�`�b�A�_�v�^��d�r�ŒP�Ƃɋ�������Ɛ��m�ɓ��삵�܂��B �@�ȑO�H���d�q�̒S���҂ɑ���O�����h�Ɠd���O�����h�̋��ʂ͏o���Ȃ��̂������Ŋm�F���Ă��炢�܂����B���̌�h������O�����h�Ɠd���O�����h�����ʂɂł��܂��B�h�̕\�L�͏������̂ł����A�܂��ŋߕ\�L�����悤�ɂȂ�܂����B�ŋ߂̕��̓���m�F�͎��͂��Ă��܂���B tama �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�M�d�ȏ������肪�Ƃ��������܂��B �@������PM-129B(������Ȃ�)�͌��\�Â��ق����Ǝv���܂��B �@�H���d�q�̂����P��LED�p�l�����[�^�[PM-129E(���������)�̂ق��́u������O�����h�Ɠd���̃O�����h�͋��ʂɂł��܂���B�ʐ^�̐������������������v�ƍŋ�(�ʔ̃T�C�g���ύX�ɂȂ���������)�͐Ԏ��Ōx������Ă��܂����APM-129B(������Ȃ�)�̂ق��́u������O�����h�Ɠd���O�����h�����ʂɂł��܂��B�v���̂��珑���ꂽ�܂܂ł��ˁB �@�����H���̓X���ōw���������Ɂu������(PM-129B)��GND���ʂɂł��܂����H�v�ƓX�����ɕ����ƁA�͂�����Ɓu�ł��܂��I�v�Ɠ����Ă���܂���(��) �@�d�����ʂɂ���ƕ\�����t��������A�덷���傫���Ȃ�͎̂��ۂɎg���Ă킩���Ă��܂����A�X�����������āu�ł��܂��I�v�Ƒ��۔��������Ă���Ĕ��������i�ł�����AGND���ʂł̎g�������P���Ƃ��Ďg���Ă��܂��i�O�O�G �@���������Ď����Ă��܂��̂ŁA��������PM-129B��PM-129E�����������̑����H�ł��낤���͐����ł��܂����A�����悤�Ɍ덷���o���ł����ǂˁB �@���d�r�ŒP�Ɠd����^����Ƃ����ƂO�u�͂�������o�܂����\���̐k��������܂���B(�ł����肳���d���̕\���덷�͗����̃g���}�[�߂��Ă����\����܂����) �@�H���̃f�W�^�����[�^�[���g��Ȃ��̂ł���A��͂萔��~�͂��鍂���ȃp�l�����[�^�[���g�p���邩�A500�`1000�~���炢�œ����肳��Ă��钆�����̃f�W�^���e�X�^�[��\���p�Ɍq�������Ȃ��ł��ˁB ���Ԏ� 2009/10/21
|
|||||||||||||||||||||||
| �ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�������̂������̃y�[�W��q�����Ă���܂��B �@����A�����k���������Ƃ́A�Ԃ̉�H�ɂ��Ăł��B �@���̓��[���C���~�l�[�V������LED�ō�肽���ƍl���Ă��܂����P���Ƀ����[��Ԃ���ON/OFF���䂪�o���Ȃ��č����Ă���܂��B �@���m�b��q�ł���Ə�����܂��B �@���������Ƃ� �@�h�A�I�[�v���M����LED�̖��邳��� �A�h�A�N���[�Y���X���[���A����LED�̖��邳�� �B���ԁi�X���[��OFF���j���h�A�N���[�Y��LED�̖��邳OFF �@�ŁA�����Ŗ��Ȃ̂ł����A�A�B�̏�ԂŁA���[�������v��OFF���䂪�A�ǂ���PWM����ƂȂ��Ă���炵���A�����[���Ő��䂵�܂���ON/OFF���J��Ԃ��A���M��������Ƃ������ƁB �@�܂��A�}�C�i�X�R���g���[���Ƃ������ƂŁA���[�������v����̐M���]����K�v�����肻���Ƃ������B �@�ŁA�ǂ̐M�����g���K�[�Ƃ���A��肭���삷��̂ł��傤���H �@PWM�ł�LED��H�́A���̔ł��������Ă��������Ă���܂���PWM��PWM�����o���Ƃ����A�Ȃɂ��{���]�|�Ȃ������܂����������肦��Ə�����܂��B �@���Z�����Ƃ͑����܂����A��낵�����肢���܂��B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ŋ߂̎Ԃ͒lj��Łu����`���Ə������H�v��lj����ĂȂ��Ă��A�W�������̂��̂������Ȃ��Ă���悤�ł��ˁB �@�̂̓R���f���T��lj�������A�d�q��H�ō������Ƃ��낢�뗬�s�������̂ł����A�ŋ߂͂��������y���݂��E�E�E�B �@���������̔��ʁA���Ɨl�̂悤�Ƀ��[�������v�̓d�C�M�����牽���ʂ̕��������Ƃ��Ă����܂��䂩�Ȃ��p�^�[��������悤�ł��B �@�ŏ��̓��e�ł͈Ӗ����킩��Ȃ��������������̂ŁA���[���Ŗ₢���킹�čׂ��ȕ����������������������Ƃ���A���̂悤�ȕ����K�v�Ƃ������̂悤�ł��B
�@�Ƃ��������ŁA�ƂĂ������[���x�̊ȈՂȉ�H�őΉ��ł������ȑ㕨�ł͂���܂���B �@�܂��͂��́u����`�v���Ə�����Ԃ�PWM���䂳��Ă������ȏ�Ԃ����m�����H���K�v�ł��B �@�����Ă��́u����`�v�ȊO�Ɂu���S�_���v�u���S�����v�Ȃ̂��ǂ����̌��o���s����H���K�v�ł��B �@�����̏�Ԃ����m�ł�����A��́u�X���[���̏�ԁv���|�����킹�āu����]�̃C���~�_����Ԃ����o����H�v�����K�v������܂��B �@�ƂĂ��ʓ|�ȉ�H�ł����A�@�\���ƂɊe�������P���������Ɠ��삷��ł��傤�B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �����v�M�����o��H �@����̐���ň�Ԃ̊̂ł���A���́u�Ԏ�ɂ���Ă����Ɠ������ǂ����킩��Ȃ��v�Ƃ����^����������킹����H�ł��B �@�����鎞�ɁuPWM�Œ�������Ă���炵���v�Ƃ̏���ŁA�ʂ�����PWM���g���͂����炩�Ƃ��������܂���̂ŁA�𗬓I�ȓd�C�M������舵���̂ɂ��̎��g�����킩��Ȃ����Ƃ��v���I�ł��B �@�ꉞ�A�e�X�g��H�ł����SHz�`��KHz��PWM�M���Ńe�X�g�͂��Ă����Ɗ��m���Ă���̂ő��v���Ƃ͎v���܂����A���������Ȃ�(�����Ɗ��m���Ȃ�)�ꍇ�͂��̂ւ�i��ς���Ȃǂ��Ē��߂��Ă݂Ă��������B �@�uPWM�������v�����m���邽�߂ɂ́A�R���f���T�́u�𗬂͒ʂ��������͒ʂ��Ȃ��v�Ƃ��������𗘗p���A�R���f���TC1�Ń��[�������v�M�����p���X����������Ƃ��݂̂��̃p���X��ʂ��ăg�����W�X�^Tr1�삳�����H�ɂ��Ă��܂��B �@�g�����W�X�^Tr1�����삷���C2���[�d����AC2�̓d�����f�W�^�����x����H�ɂȂ�A��ɐڑ����Ă���C-MOS���W�b�NIC�ɏ�`�B����܂��B �@�p���X�M���������Ȃ��(�������邩�A�_�������ςȂ��ɂȂ邩)�AC2�͏[�d����܂���̂�R5��ʂ��ĕ��d����d����L���x���ɂȂ�܂��B �@�قƂ�ǎ�����H���g�����W�X�^Tr2���ɂ�����܂����A������̓R���f���T�ŃJ�b�v�����O���Ă��Ȃ��̂ł��̂܂ܒ����I�ɓ��삵�܂��B �@PWM���䒆�ł͂Ȃ��A�u��Ƀ��[�������v���_�����v�܂��́u��ɏ������v�����o�����H�ł��B �@�����������瑤��PWM�����������邢�͈��ł́u�_�����v�Ɣ��肵�Ă��܂��܂��̂�(������܂��ł���)�A��̃��W�b�N��H�ł��̂ւ�����܂��蕪���܂��B �@�����ł́u�X���[�������v�v�̏�Ԃ͌��o���Ă��܂���B��ɕʂ̉�H�ōs���܂��B �� �����v�M����Ԕ����H �@��́u�����v�M�����o��H�v�����o�����uPWM�������v�u��ɓ_����(���̎��ɂ���ɏ������Ƃ����Ӗ�)�v�̐M������ �@�@(a) PWM������ �@�@(b) PWM�������Ă��Ȃ������Ƀ��[�������v����ɓ_���� �@�@(c) PWM�������Ă��Ȃ������Ƀ��[�������v����ɏ����� �Ƃ����R�̐�������Ԕ��f���f�W�^��IC�̃��W�b�N��H��p���čs���܂��B�����Ă��̌�ɃC���~�o�͂��R���g���[������M�����쐬���܂��B �@�����ł�NAND�Q�[�g C-MOS���W�b�NIC�� 4011B ���Q�g�p���܂��B �@�d���d����3�`18V�ƎԂ�DC 12V(�ő�15V���炢)�ł��̂܂g�p�ł��܂��B(�m�C�Y��͕K�v) �@��ɓ_����������s�����ꍇ�́A���̏o�͐M����L���x�������̂܂g�p���āu�o�͂Q�v�p��FET2 (2SJ334)���h���C�u���܂��B �@������ɓ_�����M���͒����ł�����A�C���~�͒������ꂸ�Ƀt���������܂��B �@��ɏ�������PWM�������́A����]�́u�C���~�𖾂邳���Ō��点�����v���Ԃł�����A�����̐M���ƁuPWM2��H�ō�������邳���ɂ���PWM�M���v��AND(���ۂɂ�NAND)����邱�ƂŁA���̂Q�̏�Ԃ̎��ɂ����D�݂̖��邳��PWM�p���X�M����FET2���h���C�u���A���̐�Ɍq�����Ă���C���~�͒������ꂽ��ԂŌ���܂��B �@����H �@���̎��_�܂łŁu�X���[�������v���_�����Ă��鎞�����v�Ƃ������肪���W�b�N��H�ōs���Ă��܂���ˁB �@���́A�f�W�^����H���ɂ��̔���@�\��g�ݍ���ł��܂��Ă��\��Ȃ������̂ł����A���ꂾ��IC����������̂ł�����Ɠ����q�l���ĕ��i�������炵�Ă݂܂����B �� �X���[���M�����o��H �@�X���[�������v�̓���M�����v���X�R���g���[����DC 12V������͂��ł�����A�����D3�܂��̓��͉�H�����荞��ŁA�C���~�̖��邳�߂���PWM�M��������Ă���u�^�C�}�[IC 555�����Z�b�g�[�q�v�ɉ����Ă��܂��B �@�^�C�}�[IC 555�̃��Z�b�g�[�q��L�Ń��Z�b�g�AH�œ���ł�����A�����ɃX���[�������v�����H�M���������Ă��鎞����PWM�M������锭�U���삪�s���A�X���[�������v�������Ă���Ԃ�PWM�M�����o���܂���B �@���Ȃ킿�A�u���邳���v������H���X���[�������v�ƘA�������āA�X���[���������Ă��鎞�ɂ́u���邳�����v�ɂ��Ă��܂����ƂŁA�f�W�^���_����H���ł̓X���[����ON/OFF��Ԃ��C�ɂ���K�v�����Ă��܂����킯�ł��B �� �u�ʂ̃C���~���w����`�����r���x�������点�����v��H �@�Ȃ��r������~���ėN������H�ł����A�ʂɓ���͖����̂Œlj����Ă��܂��B �@���̂���]�́uPWM�������������点�����v�Ƃ����V���v���ȕ��Ȃ̂ŁA��H���P����PWM�������M����FET1�삳���邾���ł��B �@�����A���̂��܂��o�͂́uPWM�Œ����������̂��ǂ����H�v���킩��Ȃ��̂ŁA�ꉞ�X�C�b�`������PWM�����ł��t�������ł����D���Ȃق���I�ׂ�悤�ɂ��Ă��܂��B �@�����Ɨ~�����āu���܂��o��(�o�͂P)�̓��C���̏o��(�o�͂Q)�Ƃ͕ʂ̖��邳��PWM�����������I�v�Ȃ�Ă������Ȏd�l�ɂ��ꂽ���ꍇ�́A�^�C�}�[IC 555�ō���Ă���PWM�����H�������P����āAIC2��13�ԃs���ɂ���555�̏o��(3�ԃs��)��ڑ����Ă��A�ʓr���邳���߂��ł���悤�ɂȂ�܂��B �@��H�}���ɂ��ڂ��Ă��܂����A�{��H�̓�����܂Ƃ߂�Ƃ��̕\�̂悤�ɂȂ�܂��B 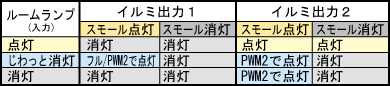 �@���̉�H����{�I�ɂ̓f�W�^�����Ȃǂ͐v��͌�쓮�͂��Ȃ��͂��ł����A�ԂŎg�p�������Ԃ�������m�C�Y��d���̕s����Ȃǂ��v���̌�쓮���N����\��������܂��B �@��쓮����ꍇ�ɂ͊eIC�ɂ����ƃm�C�Y���p�̃R���f���T���t�����Ă��邩�A�d���̔z���͖��ʂȈ��������Ă��Ȃ����ȂǁA�z���ԈႢ�Ɣz����̃m�C�Y�����Ƃ���Ă��邩�̗����̎��_�Ń`�F�b�N���Ă��������B �@�ŏ��ɏ����܂����悤�ɁA���̎Ԃ�PWM�����̎��g�����킩��Ȃ��̂ňꉞ�͍L�����ł����삷��悤�Ɍ��o��H�͐v���Ă��܂����A�����ꂻ�̂�����̑����Ƃ����_���g���u�������Ƃ��Ă͎̂Ă������̂ŁA�����C���~���u�����ςȂ��v�u�������ςȂ��v�Ȃ�PWM���Ԃ����܂����o���Ă��Ȃ��悤�Ȃ��Ԃ�̏ꍇ�́A���o��H���������쓮�̌����Ƃ��Ē������Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/8/31
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�Ǘ��l�l �@�ڂ�����H��������L��������܂��B �@PWM�̎��g�����I�V���Ŋm�F�ł���悤�A100V���Ԃ܂ň��������Ċm�F�������Ǝv���܂��B �@�܂��A�~�����H���A���������ł��̂ō쐬�������Ǝv���܂��B �@���Z�������A�����������L��������܂��B �@���}���A����܂ŁB ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�Ԃ܂ŃI�V���������Ă䂩���̂ł����I�H �@����͑�ςł��傤�E�E�E�E�B�撣���Ă��������B �@�����A�e�X�g�ł͂��Ȃ�̕��ő��v�ł����̂œ����Ƃ͎v���܂����A����PWM���肳�������Ɠ����Ό�̕����͐F�X�Ƃ��D�݂ɂ��킹�ĉ����ł��܂�����A�u�~����ȏo�͂PPWM��H�v�Ȃǂ��D�݂ɂ��킹�ăA�����W���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/9/2
|
|||||||||||||||||||||||
| �ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�u12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H�v���A���i�����Ȃ����܂��ł��傤���H �@12V�A11V�A10V�A9V�A8V��5��LED�ŊY������d����LED������_�����������ł��B �@��͂肱����A�Ⴆ��12.0V����11.0V�ɓ_������ւ�鋫�ڂ��A���킶����Ɠ_���̖��ɂȂ�܂���ˁB �@����RN�̃f�W�^���g���W�X�^�ł�2SC1815���̓L�b�`���_���ɋ߂Â�����̂ł��傤���H �@�������d�q�m���͎������킹�Ă��܂��A���i�����Ȃ��L�b�`���_���ɋ߂Â����A�d�����m�点��H���ł��Ȃ����Ɗ���Ă���܂��B �@�X�������肢�v���܂��B �Ȃ�Ƃ� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d����LED��\�������H�������O�ɁA�u�f�W�^���g�����W�X�^�v�ɂ��ĊԈ�����F��������Ă���̂Œ������Ă����܂��B �@�u�f�W�^���g�����W�X�^�v�́w�O���ɒ�R�Ȃǂ�����K�v�����A�f�W�^����H�ɂ��̂܂܌q�������g�����W�X�^�x�ł���A�w�f�W�^����H���������g�����W�X�^�x�w�f�W�^���I�ȓ��������g�����W�X�^�x�ł͂���܂���B �@���ʂ̓g�����W�X�^�ɂ̓o�C�A�X��R��d��������R�Ƃ������g�����W�X�^�̓����ɂ��킹�Ē�R�����ĉ�H��g�ݗ��Ă܂����A�g�����W�X�^���f�W�^��IC�̏o�͂Ɍq���ʼn����𐧌�(ON/OFF)����悤�ȗp�r�̏ꍇ�A�f�W�^����H�ł͓d����IC�̏o�͓d�������܂��Ă��邽�߂���ɂ��킹����R���g�����W�X�^�ɓ��������Ă��܂��A���������O����R�����Ȃ��Ă��e�ՂɃf�W�^��IC�ƃg�����W�X�^��ڑ��ł���悤�ɂ������̂��u�f�W�^���g�����W�X�^�v�ł��B �@�f�W�^�����A�i���O��H�̐����e�Ղɂ��A���i�_�������点��Ƃ��������b�g������܂��B �@�ł��̂Łu�f�W�^���g�����W�X�^�v�ƕ����ăf�W�^���I�ɓ��삷��g�����W�X�^���Ǝv���̂͊ԈႢ�ł��B �@���āA�Ȃ�Ƃ�l�͉ߋ��Ɍf�ڂ��Ă���u�~�~�u�ɂȂ�����LED���_���v�Ƃ�����H���R���ׂ�12V,11V,�c�Ȃǂł��ꂼ���LED���_�������H�����삳�ꂽ�����ł����A����ł͊e��H���Ƃɂ���VR�̒������ʓ|�ł����A�ߋ��Ɍf�ڂ��Ă����H�}�͂��ꂼ��̓d���ɂ��킹�Đv���Ă���̂Őv�d����荂���d���œ��삳����Ɓu�ڂ�`�v���ƕς�d���͈͂��L���Ȃ��āA����������r�I�J�`�b�Ɛ�ւ�悤�ɐv���Ă����H�ł������ς��Ă��܂������ƂŁu�ڂ�`�v���ƕς��H�ɂȂ��Ă��܂����肵�܂��B�����������ō���ꂽ�悤�ł��ˁB �@����̂���]�̂悤�ɑ�R��LED�����ꂼ��̎w��d���œ_��/����������ꍇ�́A�e�d�����ƂɃg�����W�X�^�Ȃǂœd�������H���R���ׂ�Ƃ�����(�͋Z)������܂����A���ʂ͉�H�̋K�͂��傫���Ȃ肻���ȏꍇ�͂Ȃ�ׂ����Ȃ����i�ŋψ�ȕi���Ŋe�i�����삷��悤�ɐv���܂��B �@�v�i�K�Ŕ���d�������߂镔���Ȃǂ���������v�Z���Ă����A�w��̒�R�l�Ȃǂ��Ԉ�킸�ɑg�ݗ��Ă�Δ��ɐ��x�̍������̂���邱�Ƃ��ł�(�������ŗǂ�)�A���ʂ͍H�Ɛ��i�ł͂��������v�����܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
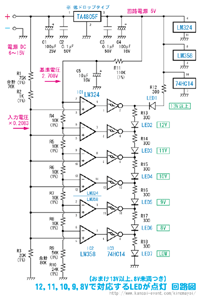 �@�d���̔���̓I�y�A���v(OP-AMP)���R���p���[�^(��r��)�Ƃ��Ďg�p���A�e�I�y�A���v�ɂ͊�d��(2.7V)���番�������e����d���p�Ɍ��߂�ꂽ�d����^���A���̊e�i�̊�d���ɑ��ē��͓d��(�d���d������������)�Ƃ��ׂĂ������͓d������r��d���������Ă�����o�͂�HI�ɂ��܂��B
�@�d���̔���̓I�y�A���v(OP-AMP)���R���p���[�^(��r��)�Ƃ��Ďg�p���A�e�I�y�A���v�ɂ͊�d��(2.7V)���番�������e����d���p�Ɍ��߂�ꂽ�d����^���A���̊e�i�̊�d���ɑ��ē��͓d��(�d���d������������)�Ƃ��ׂĂ������͓d������r��d���������Ă�����o�͂�HI�ɂ��܂��B�@��r��d����12V�p��2.500V�A11V�p��2.2917V�A10V�p��2.0833V�E�E�E�Ƃ����悤�ɐݒ肵�Ă��܂��̂ŁA����Ɠ������Ȃ�悤�ɔ��肵�����d���ł�����͓d����0.20833�{�ɂȂ�悤��R�ŕ������Ċe�R���p���[�^�ɓ����l����͂��܂��B �@�I�y�A���v�̓A�i���OIC�Ȃ̂ŁA��͂��r�d���Ɠ��͓d�����������Ȃ邲���킸���ȓd���͈͂ł̓A�i���O��������܂��B���̂܂�LED���q���Ɓu�ۂ�`�v���Ƃ����Ȋ���܂��B �@�����ŃA�i���O�d���ω��ł��Ȃ�ׂ�������������LED�̓_���Ə������ւ���ׂ��V���~�b�g���͂�NOT�Q�[�gIC 74HC14���g����LED�_���p�̃f�W�^���M���ɕϊ����܂��B �@���Ȃ�L�b�`����ւ�܂����A�I�y�A���v���A�i���O��������Ă���Œ��̂��������͈͂ł͂�͂葽�����͓d�������ԓ_�Ńt���t�����܂��̂ŁA�����́u�ڂ�`�v���Ƃ����Ԃ͎c��܂��B��������̓I�y�A���v�̏o�͂ł��̂܂�LED��_���������Ƃ��ɑ��Ă����킸���Ȕ͈͂ł��̂ŁA���̒��x�͋��e���Ē����Ȃ��ƍ���܂��B �@�������A�����Ƃ�������Ɩ{���ɃJ�`�J�`�Ǝ���悭��ւ��H�͍��܂����A�u���i�����Ȃ��v�Ƃ�������]����͊O��đ�R�̕��i���g���č����ȉ�H�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA����͂���������H�͖����ɂ��܂��B �@�u12V,11V,10V,9V,8V�v�Ɣ��肷��d�����T����Ȃ̂ŁA�I�y�A���v�͂S��H�����LM324����ƁA�Q��H�����LM358����g�p���܂��B �@�ԂŎg���Ȃ�9V�������Ă�����ߕ��d�ł��傤�ɁB���肪�S����Ȃ�LM324��ōς̂ɁE�E�E�Ƌ�s���Ă��Ă��d���Ȃ��̂ŁA�I���^�l�[�^������Ă��鎞�ɂ͕��ʂ̓o�b�e���[�ɂ�14V�ȏォ�����Ă���͂��Ȃ̂łP�]��R���p���[�^�Łu13V�ȏ��v�ƃI�}�P�łP�i�\���𑝂₵�Ă����܂����B �@LED�̕\����H��74HC14�̏o�͂��畁�ʂɓd��Vcc��GND�Ɍq���̂ł͂Ȃ��A������ƕς����ڑ������܂��B �@����́u�Y������d����LED������_�����������v�Ƃ�������]�������邽�߂ŁA���̂悤�ɐڑ�����Ɗe�i�̃C���o�[�^(NOT��H)�̏o�͂��uH��L�̋��ɂȂ��Ă���_�v����LED�ɐ������d���������肻�̂P��LED���_�����܂��B �@����ȊO��LED�̗��[�ɂ�H��H�܂���L��L�̐M�����^�����ēd������0V�Ȃ̂œ_�����܂���B �@���̂悤�Ȑڑ��ł͊Ԉ����LED��A����L�AK����H�ɂ��Ă��܂��Ƌt�d������������LED��j���˂܂��A����̃R���p���[�^��H�ł͂��̂悤�ȐM���ɂ͂Ȃ�܂���̂ň��S�ł��B �@�d�����O�[�q���M�����[�^�͕K���u��h���b�v�^�C�v�v��5V�p���M�����[�^���g�p���Ă��������B �@������Œ�������u8V�v�Ƃ����ݒ�̂��߁A���ʂ�7805�̂悤�ȃh���b�v�d������3V���x����O�[�q���M�����[�^���Ɠd���d����8V�����荞�ނƉ�H�d�����s����ɂȂ�A��H�d���������Ă����d���������܂�����\�����삪�������ł��Ȃ��Ȃ�\��������܂��B �@TA4805F���ƃh���b�v�d������0.5V(0.5A��)�ƒႭ�A�o�b�e���[�d����5.5V���x�܂ŗ������ނ܂ł͐���ɓ��삵�܂��B �@�ʂ�TA4805F�łȂ��Ă������[�J�[�̒�h���b�v�^�C�v��5V�O�[�q���M�����[�^�ł����v�ł��BLED�͈�����_�������Ȃ���H�Ȃ̂ŏ���d���͐��\mA�ȉ��ł�����A100mA���x�̗e�ʂ̏��^�̃��M�����[�^�ł����삷��ł��傤�B �@�g���Ă��Ȃ���Ԃ���d������ꂽ�u�Ԃ́A��d�������肳����d���R���f���TC5���[�d�����܂Ő��b�Ԃ͊�d�����Ⴂ����(���͓d���������Ɣ��肵��)�u13V�ȏ�v��LED���_�����A�������\���܂ŏ��Ԃɉ������Ă䂫�܂��B �@�̏�ł͂���܂���̂ł����ӂ��������B �@��{�I�ɒ������̖�����H�}�ł��̂ŁA���i�Ƒg�ݗ��Ă����Ԉ��Ȃ�������x�œ��삵�܂��B �@��H�}���Łu�P���v�Ǝw�肵�Ă����R�͌덷�P���i���g�p���Ă��������B��d������͓d���̕����Ɏg�p����{��H�̗v�ƂȂ��R�ł�����A���̒�R�l�͓��ɉ�H�}�ɏ����Ă���ʂ�̕����g�p���邱�Ƃ������߂��܂��B ���Ԏ� 2009/8/28
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�Ǘ��l �l �@���肪�Ƃ��������܂��B �@13V�ȏ�ALOW�̂��܂��t���ŏ��Ȃ����i�v�ɋC���g���Ă�������ƂĂ��������ł��B�������m���ƌo����������Z�Ɗ��S�������܂����B����ȂɃV���v���ɂł���Ȃ�āI���̍�����͋Z�����p���������ł��B�f�W�^���ɂ��Ă�I�y�A���v�̏ڂ������������ɂȂ�܂����B�����A���i�������č쐬���y���݂ł��B �@�ȑO�����Ē����������[���ȕێ���H�͊������āA�t�H�O�����v��SW���`�����Ɖ����x��ON/OFF�o����悤�ɂȂ�܂����B�d�˂Ă����\���グ�܂��B �@�m����9V�ȉ��͉ߕ��d�ł��B�d�͏�������オ��x�ɕ�[�d�����Ă���̂Ŏ���������������Ǝv��9V�ȉ����t���܂����B �@���������w�E����čl���������̂ł����ALM358�����w4�_���x+�w13V�ȏ�x�ɂ��āA���܂����q���g�Ɂw13V�ȏ�A12V�A11V�A10V�A9V�ȉ��x�_���ł�����A����ɕ��i�����炷���Ƃ͉\�ł��傤���H���萔�����|���������܂����A��H�}�������Ă��������B �@�X�������肢�v���܂��B �Ȃ�Ƃ� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
���N���b�N����Ɗg��\��
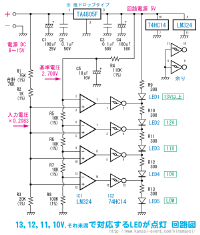 �@��x��H�}�������Ɂu����ǂ́������~�����v�ȂǂƂ����͔̂����ł��B
�@��x��H�}�������Ɂu����ǂ́������~�����v�ȂǂƂ����͔̂����ł��B�@�o������H�}��������ƕς�����x�ŕύX�ł�����e�͓d�C�E�d�q��H�ɋ������������ɂȂ��Ă����Ŏ��₳�����Ȃ��������ł����R�ɂǂ����Ƃ����̂��u�C�̖����v�̃X�^���X�ł��B �@���ꂪ�ł���悤�ɁA��H�̂����݁A���쌴�����ڂ���������Ă��܂��B �@�܂�A�������Ԃ������ĉ�H��v������A���������������肵���͖̂��ʂ������Ƃ������ł��ˁB ���Ԏ� 2009/9/1
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�f�I�ȉ�H�}�ɊǗ��l��������́w���������L�������x�����������h���I�Ŋy�����q�����Ă܂��B��D���ł���`��i�L���C�Ō��\�ł��B�C���������I�O�O�j�����J�ȉ���Ɋ��Ӓv���܂��B���肪�Ƃ��������܂���O���炿����ƌ��Ă�LED���s�J�b�Ɠ_�����āA�o�b�e���[�c�ʂ���ڂŕ�����[�d�̃^�C�~���O�̓o�b�`����T���̃o�b�e���[�オ���h�~�ł��Ċ������Ł[���B �@�K�\��������������E�E�E�ȈՃf�W�^���\������d�͌v�E�E�E���ĉ��l�̐l�����ӂ��Ă��邱�Ƃł��傤�i�j���Ԃl1�l�����ł݂Ȃ���99.9����炸�X���[�ł��傤�i���j�f�l�ɂ͎n�߂�����Ȃ��}�j�A�b�N�Ȏ���d�q�Z�t�̖����������������͎̂��Ԃ̖��ʂł��ˁB �@�Ƃ�悪��̉�H�v�����ڗ����A�������̈אl�̈בf�l�ɂ�������₷�����p�I�ȉ�H�Ɂw�����x�Ɓw�m�F�x�Ɓw�p�r�ɍ��킹�ăJ�X�^���x�ł���悤�Ɏ��₵�Ă������Ƃ͂��C�t�����Ǝv���܂��B�����1-2�}�ł��̂܂g���̂��悵�B��r���Ċm�F���ė������J�X�^�������̂��悵�B���\�l�͉{�����āw���ہx�ɍ��A�w���p�I�Ȏ��Ɖ���x�ɐÂ��Ɋ��ӂ��Ă���ł��傤�O�O/�B�y���E���Ɍ��J����z�Ƃ������͂����������Ƃ��l���Ȃ��Ă͂����܂���˖�������B�悩�����ł��ˁi�j �@�܂��A�f�t�H���g�Łu���J���Ă��ǂ��v�Ƀ`�F�b�N�����Ƃ������������ł���B�u�����̂݁v�Ƀ`�F�b�N������ƂԂ������傽��郁�[������������͂��܂�����i�j�Ԃ�������Ȃ��Ă������悤�ɈӖ��������u�����̂݁v�������悢�B �@���������ꂩ����������Ă���܂������� �Ȃ�Ƃ� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̈אl�̈בf�l�ɂ�������₷�����p�I�ȉ�H�Ɂw�����x�Ɓw�m�F�x�Ɓw�p�r�ɍ��킹�ăJ�X�^���x�ł���悤�Ɏ��₵�Ă������Ƃ���������Ă���̂ł�����A���Ђ���Ȃ�����Ȃ��g�o�Ŏ���������̂ł͂Ȃ��A�������œd�q�̐��E���L���Љ��g�o��u���O������āA����ȑf���炵�����𐢊E�ɔ��M���Ă��������I �@�u�ȈՃf�W�^���\������d�͌v�v�Ȃǂ��A�����ƊȒP�ɁA�����ƕ��L���g����f�l�ł������H�����J���Ă������邱�Ƃł��悤�B �@�Ȃ�Ƃ�l�̂g�o���ł����URL���������肦��A�����ŊF�l�ɂ��Љ�Ď��̐�����肻��������ǂ݂��������悤�ɗU�����������܂���B �@��������A��������Y�܂��鐔�����Ԃ̖��ʂ������đ叕����ł��B ���Ԏ� 2009/9/17
|
|||||||||||||||||||||||
| ���ē� |
�@���̉�H�ɂ́u���̑��E��ʂ̘b��(2011�N)�v�y�[�W�Ɏ����@�\�� 12V���o�b�e���[�pLED�o�[�d���v
(LM3914�g�p�E10V�`14V/0.5V�P�ʕ\��) �̉�H�}���f�ڂ��Ă��܂��B �@�g�p���i�����Ȃ��A�\���𑜓x�������̂ł����߂ł��B |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�������y�����q�������Ē����Ă��܂��B �@�����ł����A�[�d�d�r�̎c�ʂ�LED�Ŋm�F�����H�������Ē����܂���ł��傤���B �@�d�r�́A1.5V���3V�ł��B3V�`2V�܂ł́A�ΐF��LED���_�����A2V�ȉ��ɂȂ�����A�ΐF��LED���������A�ԐF��LED���_������l�ɂ������ł��B�O���d�������ŁA���܂���ł��傤���H �@�d���͈͂́A���������̂Ƃ���ŗǂ��ł��B2V�`�́A���R�����ŗǂ��ł��B���X�����Ă��݂܂��A�X�������肢�v���܂��B JVX �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�����ڂ͈����v�ł����A�ȉ��̉�H�ŖړI�͒B���ł��܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@���̓d��(���̏ꍇ2.1V)�ȉ��肵���ԐFLED��_���������H�ƁA����ȊO(�ԏ���)�̎��ɂ��ΐFLED��_���������H�̂Q�g�̓_����H��g�ݍ��킹�Ă��܂��B �@���ꂾ���ł�2V�t�߂ł͂��Ȃ�J�b�`��������������ւ�܂����A���܂ł��Љ���g�����W�X�^���̓d������LED�_����H�ł͂ǂ����Ă��g�����W�X�^�̑������ʂׂ̈ɐؑ֓_�ł͑����͂ڂ���Ɛ�ւ����������A����ɑ��āu���������ւ�Ȃ��I�v���̋����܂��B �@����ɂ͌��J���Ă����H�}���������D�݂ɏ���ɑΉ��d����ύX�����肵����Łu�d����ς����炫�����蓮���Ȃ��Ȃ����I�v�Ȃǂ̂��A��������A�u����E�E�E����͐v���珟��ɒ�R�l�Ȃ�ύX���Ă���̂�����A���������Ȃ��Ă�������܂��ł���I�v�Ƃ����ƂĂ����������Ԃɂ��Ȃ��Ă��܂��B �@���̉�H�}�̏ꍇ�A�㔼�̗�LED��_���������H�̕������u���p�v����D1��R3�Ńt�B�[�h�o�b�N�������āA�d�����蕔���V���~�b�g���������ɂ��Ă�蔽�����x���グ��Ƌ��ɁALED�̓_���E��������d���ɍ���ׂ��Ĉ�x��ւ�����d�����߂��Ă�LED�\�������ɖ߂�܂ł̉����������Đؑ֓_���傤�ǂ̓d���œd���������ϓ����Ă��p���p����LED���_�ł����肵�Ȃ��悤�ꖡ�H�v�������Ă��܂��B �@���̂�������܂߂Ċe��R�l�͍���̂��w��̓���d��2�`3V�Ő��������삷��悤�ɐv���Ă��܂��̂ŁA����Ɂu�d�r�S�{��4V�œ��삳�������A�d���d�����Q�{�������R�͑S���Q�{�̒l�ɂ����瓮�����낤�v�Ƃ��̃g�����W�X�^�̓���v�Z�Ȃǂ�S�������������������āA���̏�Łu�����Ɠ����Ȃ����I�v�Ȃ�Č����������肵�Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B > �ǎҊe�� �@�b�������Ɉ��܂������A�{��ɖ߂������̉�H�}�ł͒������͂���܂����B �@���̂܂܍�����2V(�����l�ł�2.1V)�ȉ��̓d���ɂȂ��LED�����������ɐ�ւ�܂��B �@���̍ہA��LED��OFF�ɂ��悤�Ƃ���g�����W�X�^�̓�����(�Ȃ�ׂ��J�`�b�Ɛ�ւ�悤�ɂ͂��Ă��܂����c)�A�Ȃɂ���LED�̕K�v�d����2.2�`2.4V�ł�����2V�t���ł��d���s������LED�͔��ڂ���Ƃ�������܂���B �@�������ɐ�ւ�����ɓd�r�d��������(���ׂ��y���Ȃ��āH)�ꍇ�A�d����2.2V�ȏ�ɂȂ�����������ɖ߂�܂��B �@���\���̂܂ܓd��������ɉ��������ꍇ�A�ԐFLED�̓���d���ł�����1.8�`1.5V���x�܂ł͔��ڂ���ƌ���܂����A����������Ǝ��R�ɏ����܂��B �@�ŏ��Ɂu�����ڂ͈����v�Ə������̂́A�܂�����]��2V�܂ŗ�LED���_���Ƃ��������ł���ł͗�LED�̕K�v�d����������Ă��邽�ߐԂɐ�ւ�O�ɂǂ����Ă���LED�����ڂ���ɂȂ��Ă��܂����ꂪ�����ڂ������B������LED�̓��삻�̂��̂ł����Ȃ��Ă���̂ł͂��邪�A�܂�ʼn�H�������Đؑւ��u�p�b�v�Ɛ�ւ�Ȃ��ʂ邢��H�ɂȂ��Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��Ƃ������ł��B �@���̂�����̂���]�d������LED�ɂƂ��Ă͍ň��̏����ł���_�͓��܂��āA��L��H�Ńg�����W�X�^�ɂ���V���~�b�g��H���\�����Ă���̂ł���A�������̂����V���~�b�g���͂̃f�W�^��IC���g���ċ@�\�͓����ŕ��i�������炻���Ƃ��������̉�H�}��������ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�g�����W�X�^���R�Ƃ��������i���������薳���Ȃ��āA�g�����W�X�^���14�s����IC����A���Ƃ͂킸���̒�R�Ȃǂō��ĕ��i���͌������Ă��܂��B �@�g�p�����V���~�b�g������NOT�Q�[�gIC 74HC14�͓d���d��2�`6V�œ��삵�܂��B �@����̂���]������2V�ł��̂ŃM���M������͈͓��ŁA������d���������������\���̂܂ܓd�r�d����������Â��Ă��A���������ԐFLED�������Ă��܂���1.6V���x�܂ł���i�O�ł������삵�Â��܂��B �@������̉�H�ł́A�ؑ֓d����VR1�����ɂ��Ă��܂��B �@���̉�H�ɕ\�����ւ������d����^���āAVR1���ĕ\������ւ�_��T���Ă����R�ɐݒ肵�Ă��������B �@�V���~�b�g�����^�C�v�̃Q�[�g���g�p���Ă��܂��̂ŁA��ւ�ۂɂ́u�p�`�b�I�v�ƋC�����悭��ւ�܂��B (�A��2V�ł͗�LED�͔��Â��͕̂ς肠��܂���) �@74HC14�̓���d����2�`6V�̂��߁A�u�j�b�P�����f�[�d�r�⊣�d�r�S�{�ōő�6V�A�x���d����4V�v�uLi-ion�o�b�e���P�{�ōő�4.2V�A�x���d��3V�v�Ƃ����p�r�ł��قڂ��̂܂g���邽�߁A���p���₷���悤�Ɍx���d���̐ݒ�͎��R�ɂł���悤�ȍ\���ɂ��Ă��܂��B �@�A���A�d���d����LED����ւ�d�����オ��Γ��RLED�̓d��������R���ς��Ȃ���Ȃ�܂���B �@��H�}���ɂ͓d����6V�Őؑ֓d����4V�̏ꍇ�̒�R�l���L�����Ă����܂����̂ŁA6V�Ŏg�p�����ꍇ�͂��̒l�ɕύX���Ă��������BLi-ion�o�b�e���[�Ŏg�p�����ꍇ�͂���6V�ݒ�̒�R�l�ł��\���܂���B�܂��������Ōv�Z����ĕύX�����̂��悢�ł��傤�B ���Ԏ� 2009/8/27
|
|||||||||||||||||||||||
| �u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�u�}�O�l�b�g�X�C�b�`�t�u�U�[�v�̃��[�h�X�C�b�`�����O���ăe�X�^�[�Łi��Ղ̃��[�h�X�C�b�`��t�ԁj�d���𑪒肵�Ă݂��̂ł����A�����W��DC 0.25mA�ɂ��Ă�����ł��܂���ł����B �@�����Łu�}�O�l�b�g�X�C�b�`�t �k�d�c���C�g�v��u�}�O�l�b�g�X�C�b�`�t�u�U�[�v�ȂǂɎg���Ă���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŊJ����ON�ɂȂ��v��H�͂ǂ��Ȃ��Ă�̂��m�肽���̂ł����A������낵����Ή�H�̒ʏ̖�����������Ă��������܂��H�i�������Ă݂��̂ł����A��H�̒ʏ̂����̂��m��Ȃ��̂ł���炵���������ʂ��ł܂���E�E�E�j �@����ǂ��A�����A���傤�͋C�����C�C���I�Ƃ��A���̉�H�͉��ɂ܂�����I�Ƃ��A�܂��͂��̑��̂����R�ɂ��d�q�H�쏉�S�Ҍ����ȒP���ň����ȉ�H�������Ă���������Ȃ�Ή�H�}�����肢�������̂ł����N�����Z���Ƃ͏��m�v���Ă���܂����Ȃ�Ƃ���낵�����肢�v���܂��B P.S.�u�C�̖����v���܂̃T�C�g�A�ʔ������L�p���Ǝv���Ă���܂��B���ꂪ���ɂ͏o���Ȃ������̌��ʂ�𗧂����^�_�œǂ߂Ċ������Ă���܂��B����͋��k�����₳���Ă��������Ă���܂����A���z�ł�����t�Ȃǂ������Ă������������v���ł��B�iLED�����d���̋L����d�r�̋L���ɂĖ��ʂȏo���������]�̕����w���ł��܂����B�j�@���F��t�Ƃ����Ă��{���ɏ��z�ł��̂ŃK�b�J�����Ȃ��ł��������B �K���ōl���܂��� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����������H��m�肽����u�f�����m��H�v��u�f���X�C�b�`�v�ȂǂŒ��ׂ�Ƒ�R�o�ė���Ǝv���܂��B �@����Չ�H�̐��E�ł́u�a�ړ_�v�Ƃ��E�E�E�B �@�X�C�b�`���ɒ��ڂ��ē��������ƁA�u�X�C�b�`���ꂽ���H�͓��삷���v�Ƃ����X�C�b�`��ON/OFF�Ɖ�H�̓���͔��ɂȂ�̂Ńf�W�^���̐��E�ł́u���]��H�v(NOT��H)�ȂǂƂ���������������ꍇ������܂��B �@�X�C�b�`�̂Ƃ���œd�����v���Ă��قƂ�Ǔd���͌v��Ȃ������̂́A���p�̖h�Ɓu�}�O�l�b�g�X�C�b�`���u�U�[�v�Ȃǂ̒��ɂ́uIC��H�v�������Ă��āA����IC��H��C-MOS�\���Ƃ���FET����b�\���ɂ����d�q��H�őg�ݗ��Ă��Ă���̂ŁA�u�قƂ�Ǔd��������Ȃ��v(����d�����قƂ�ǖ���)�Ƃ����A�����ȓd�r�Œ����Ԃ����Ǝg�p����@��Ƃ��Ă͗��z�I�ȓd�q��H�ɂȂ��Ă��܂��B �@�u�f�����m��H�v�̌����ɂ��Đ������܂��B �@�u�f�����m��H���X�C�b�`�������Ă���Ɖ�H�삳���Ȃ��v��H�ł��ˁB �@�Ƃ������́A�u�X�C�b�`����Ă��鎞�ɂ͓��삷���H�v�Ƃ����̂��܂���ɂ���A���̉�H���X�C�b�`�Łu���삳���Ȃ��悤�ɂ����v�ƖړI���B���ł��܂��B �@�̂��������[���g�����W�X�^�ō���Ă��܂����B 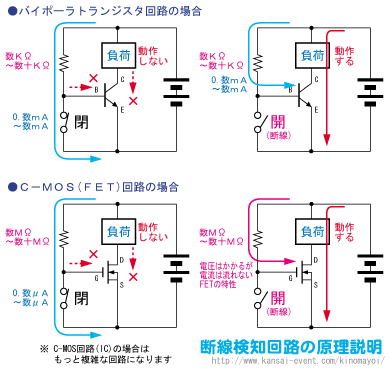 �@�w�X�C�b�`����Ă��鎞�x�ɂ́A�g�����W�X�^�̃x�[�X��R�ɗ����d���́u�X�C�b�`�v�ɂ��o�C�p�X�����GND�ɗ��Ƃ����̂ŁA�g�����W�X�^�͓��삹������(�u�U�[����v��)�ɂ��d��������܂�������͂��܂���B �@���̎��Ɂu�X�C�b�`�v�ɗ����d�����d���d������R�l�ŁA��R�̒l���g�����W�X�^�����イ�Ԃ�ɓ��삷���R�l(���j��)�ɂ��Ă���Ɛ����`���x�̓d��������܂��B �@������̂悤�ȃg�����W�X�^��̊ȒP�ȉ�H�ł͂Ȃ��A�����������G�Ŋ��x�̗ǂ���H�ɂ�����̒�R�l�͂����Ƒ傫���ł��A�u�X�C�b�`�v�ɗ����d���������Ə��Ȃ��͂ł��܂����A�����ł͌��������Ƃ������Ő��j���̒�R�œd���͐����`�Ƃ������ɂ��Ă����܂��B �@�w�X�C�b�`���J�������x�ɂ́A��R��ʂ����d���̓g�����W�X�^�̃x�[�X�ɗ���܂��̂Ńg�����W�X�^�͓��삵�āA�R���N�^�ɐڑ�����Ă��镉�ׂɂ��d������������삵�܂��B �@�u�X�C�b�`�v��h�ƖړI�Ń}�O�l�b�g�X�C�b�`�ȂǕ��펞�ɂ͕��Ă��āA�ُ펞�ɂ̓}�O�l�b�g���痣��Đړ_���J���悤�ɂ��Ă���A���̂悤�Ȓf�����m��H���q���ł������ƂŁu�f���������Ƃ����o�����v�u�U�[��炵���胉���v��_���������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B �@���̌����͐̂���u�x�u�v��u���S���u�v�ōL���g�p����Ă�������ŁA�x�����悤�Ȏ��Ԃ��������Ȃ��Ă��������ꂽ�X�C�b�`���܂ł̔z�����f��������A�ӂ���͓��삵���ςȂ��̂͂��̃X�C�b�`�����ĐڐG�s�ǂȂǂ��N���������ɂ��u�ُ킾�I�v�Ƃ��ĉ�H���������ău�U�[����v�삳���Ĉُ��m�点�Ă���A�̏�����m�ł��܂��B �@���ʂɁu�X�C�b�`����������ON�v�Ƃ�����H�ł́A�����f�����Ă�����X�C�b�`�����Ă��Ă��ӂ����OFF�̂܂܂ŁA�������펖�ԂŃX�C�b�`��ON�ɂ�������ł����ۂ͉��Ă��Čx�o�Ȃ������I�Ȃ�Ă��ƂɂȂ����炽���ւ�ł���H �@�ł�����A�x�����S���u�Ƃ������A�u���̋@�펩�̂����Ă�����A�E�g�ȋ@��v�ł͂��̂悤�Ȓf�����m�����̃X�C�b�`�@�\��`�B�@�\���g�p����Ă��܂��B �@���Ă���ł͐}�̉��̂ق��́uC-MOS (FET)��H�v�ɂ��āB �@��{�I�ɂ̓o�C�|�[���g�����W�X�^���g�p������H�ƍl�����͓����ŁA�w�X�C�b�`����Ă��鎞�x�ɂ�FET�̃Q�[�g�d���́u�X�C�b�`�v��GND�ɗ��Ƃ���Ă���̂�FET�͓��삵�܂���BFET�����삵�Ȃ������ׂ����삵�܂����B �@�w�X�C�b�`���J�������x�ɂ͓d���d������R��ʂ���FET�̃Q�[�g�Ɉ�������̂�FET�͓��삵�āA���ׂɂ͓d���������̂����ׂ͓��삵�܂��B �@�����Ńo�C�|�[���g�����W�X�^�̏ꍇ�ƈႤ�̂́A�uFET�̃Q�[�g�ɂ͓d���͗���Ȃ��v�Ƃ���FET�͓d������f�q�ł���Ƃ���FET�̓��쌴���ŁA���ʂ̃g�����W�X�^�̂悤�Ƀx�[�X�ɐ�mA���x�̓d���𗬂��Ă��Ȃ��Ƃ��イ�Ԃ�R���N�^�d�������Ȃ��g�����W�X�^�ƈႢ�d���𗬂��K�v�������d���������邾���Ȃ̂ŃQ�[�g��R�͂��Ȃ�傫�Ȓl����邱�Ƃ��ł��A�������́u�X�C�b�`�v�̂悤�Ȍ`�ŃQ�[�g��R����GND�ɓd���𗬂��悤�Ȑڑ������Ă��u�X�C�b�`�v�ɗ����d���͐��ʂ`(���ۂ̋@��ł͂���ȉ�)�Ɣ��ɂ킸���ŁA���ʂ̃e�X�^�[�Ȃǂł͑�����ł��܂��A�Ȃɂ��{�^���d�r�̂悤�ȏ��e�ʓd�r���g���Ă��Ă��u�ҋ@���͂قƂ�Ǔd��������Ȃ��v���u�������ł��܂��B �@�@��ɓ����Ă���IC�̒��ł͂����FET����Ƃ�����H�ł͂Ȃ������������G�ȉ�H�ɂȂ��Ă��܂����A�����ł͂����܂œ��쌴���̐����Ɓu�Ȃ��e�X�^�[�œd�����v��Ȃ������̂��v�ɑ���Ƃ��čł��ȒP�ȉ�H�Ő������Ă��܂��B �@���Ȃ݂ɁAFET��C-MOS IC�͔��ɍ����x�Ȃ̂ł���ȊȒP�ȉ�H�ł͊O������̃m�C�Y�Ō�쓮�����肵�܂��B�����ƒf���X�C�b�`��H�����ꍇ�͂����������i�𑝂₵�Č�쓮���Ȃ���H�ɂ���K�v������܂��B �@�܂��A���̊��x��������u�}�O�l�b�g�X�C�b�`���u�U�[�v�̂悤�ɉ�H�ƃX�C�b�`�������߂��ɂ���悤�ȋ@��ł͎g�p�ł��܂����A�z���������ĉ����ɃX�C�b�`����u���x�u�̂悤�ȉ�H�ł́A�z���m�C�Y�̑�̂��߂��̂悤�ȍ����x��H�͎g�p�ł����A������x�͓d���𗬂��ăm�C�Y�Ȃǂ̉e�������Ȃ����S�ȉ�H��v����K�v������܂��B �@��ɂ������܂������A�����ł̐����}�͂����܂Ō�����������Ă��邾���ŁA���̂܂ܑg�ݗ��ĂĂ��܂������ۏ͂���܂���B P.S. �@����t�ȂǁA���z���͂��肪�����̂ł����A���C�������������Ă����܂��B �@�u���y�v�ł���Ă��邾���̃T�C�g�ł�����A(���Ƃ�����t�₨�C�����Ƃ����`�ł�)������Ⴄ�ƑΉ��ɑ���ӔC���������Ėʔ�������܂���̂ŁB �@���̂Ԃ�A��������Ă��܂Ŋ������܂���̂ŁA�������ȏエ�҂�������ꍇ�⎿��җl�̂����҂Ƃ���̉����Ԃ����Ȃ��ꍇ������܂��B ���Ԏ� 2009/8/19
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 8/23 |
�@�E�I�[�I�d�q��H�̈̂��l�I�C�̖������܁I���肪�Ƃ��������܂����[���I�u�f�����m��H�v����܂������I �@�C�̖������܂���悤�ɁA�ȑO�L�����[�J�[�̓d�q���u�U�[�i�X�C�b�`�܂łP�T�����炢�̕��s���Őڑ��j�����Ō�쓮�������Ƃ�����܂��āA�R�����ĐM�������܂荂���Ȃ��ȁ`�Ǝv���Ă���܂����B�܂��S�ς̖h�ƃu�U�[�̓��[�h�X�C�b�`�����O���āA����܂��S�ςׂ̍����������[�v�ɂ��đ��̊O�ɂ͂킹�āA�f�������������悤�ɂ��Ă���܂��B�ŁA������͍��̂Ƃ����쓮�͖����̂ł����A�C�ɂȂ��Ă���܂����B�i����ɖh�ƃu�U�[�̔��c�t�����G�Ȃ̂ŕ��i����U�S���O���Ĕ��c��蒼���������ʼn��ē����Ȃ��Ȃ����̂ŁA�i�����̂���܂�悭�Ȃ��̂��Ǝv���Ă���܂����j�����ŁA�M�����̍����i���Ƃ��Ō�쓮���Ȃ��j��H�������炦�悤�Ƃ����̂ł����A�����[���g������H�͏���d�͂��������Ċ��d�r�ł͒����^�p�͖����ł����B�d�q���i���g���ł���̂��ȁ`�Ƃ͎v�����̂ł����A�ҋ@�d�͂��قƂ�ǃ[���̉�H�Ȃǂ����ς茩�������܂���ł����B �@�uFET�̉�H�v�����Ă݂܂��I�i�J�`�b�I�d�q��H���S�҂̃X�C�b�`����܂������I�j �@�ǂ������肪�Ƃ��������܂����I P.S.��t�̌�����v���܂����B���ꂪ�������E���a�̂��߂ɂ����܂��I�ƌ����Ă��������Ǝv������A�݂Ȃ��܂ɂ����f�����������Ȃ��悤�ɋC�����܂��I �K���ōl���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �����e�̓I����肽�� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�ԊO���Ŕ��������H �@����ɂ��́@ �@�Q�O�N���炢�O�Ƀg�~�[�i���݂̓^�J���g�~�[�j����w�T�C�o�[�V���b�g�x�Ƃ����A�ԊO���𗘗p�����V���[�e�B���O�Q�[���p�̃I���`��������܂����B�Ȃ������̏e��������A���̎�����������Ȃ����Ɩ͍��v�Ē��ł��B �@��͂�ԊO���ƈꌾ�Ō����Ă��A���g���͂����ł���ˁH �@�ԊO���˂���e����ǂ�Ȏ��g�����łĂ���̂��킩��Ȃ��ƍ��܂��H �@���ɂ��̏e�����Ŕ���������̂����łȂ��Ă��ǂ��ł��B�g�߂ɂ��郊���R���Ŕ������Ă��悢�ł��B �@���Z�����悤�Ȃ̂ł��ɂɂȂ�����Ō��\�ł��B �@��낵�����肢���܂��B �ЂႭ���낤 �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̏��i�A�w�T�C�o�[�V���b�g�x�ł͂Ȃ��w�T�o�C�o�[�V���b�g�x�ł��B�T�C�o�[�V���b�g�ƌ�����SONY�̃f�W�^���J�����ł��ˁi�O�O�G �@�́w�W���I���x(�X�g���{����)�������Ă��܂������w�T�o�C�o�[�V���b�g�x(�ԊO�������R������)���������o��������܂��B �@���͊��ɂǂ�����茳�ɂ͖����A���@�Ŋm�F�ł��Ȃ��ł��������̃f�[�^���炨�b�����܂��B �@�܂��̓T�o�C�o�[�V���b�g�ɊW�Ȃ��A�ԊO���́u���g���v�Ƃ����̂ɂ͐F�X�ƈӖ�������܂��̂ł�������B �� ���̎��g���H �@�d�g����������g���Ƃ����ƁA���̓d���g����g���̂́u�U�����v�ł���u�P�b�Ԃɉ���U�����邩�v�ł��B���Ƃ��Α�G�c�ɐԊO���Ƃ����͈͂��g������780nm�ȏ���x(���͈̔͂œd�g�̑O�܂�)�ƌ����Ă��܂��B �@�ԊO�������R���ȂǂŎg�p����u�ԊO��LED�v�ɂ͔�����ԊO���́u���S���g���v�������f�[�^�Ƃ��ĕ\����Ă��āA���Ƃ��u940nm��LED�v�Ȃǂł��B����͎��g���ɂ����3.19�~10��14��Hz�ƂȂ�A���ʂɂ悭�g��MHz��GHz�Ȃǂ��͂邩�ɏ�̎��g���ł��B �@�u���̎��g���v�͂��܂�ɂ��傫�Ȑ����̎��g���̂��ߎ��g��(Hz)�ŕ\���Ɛ����傫�Ȑ��l�ɂȂ��Ă��܂��āA���܂���p�I�ł͂���܂���B�ł�����u���v�̏ꍇ�͎��g���ł͂Ȃ��u�g���v�Œ������Z�����A�ǂ̒��x�̌��Ȃ̂���\���܂��B �@�ԊO������LED�ɌŗL�̔g������������A���̔g���̌����ł������A��������g�����Y����ƌ��͔g���������قǎキ�Ȃ�܂��B �@�ʏ�̐ԊO��LED�ł͓���̔g���̂��������͈͂̐ԊO�����Ă��܂��B �@�ԊO���������f�q�ɂ������悤�Ȏ��g������(�g������)������A�uXXXnm�v�ƌ��߂�ꂽ����f�q�ł͂��̔g���̌��ɑ��Ă͔��Ɋ��x���ǂ��ł����A�����Y����Ƌɒ[�Ɋ��x�������Ă��܂��Ď�M��H�͔������Ȃ��Ȃ�܂��B �@�ł�����A�ԊO���ʐM�Ȃǂ��s�����u�����ꍇ�A���M���̔����f�q(LED)�Ǝ�M���̎���f�q(�t�H�g�g�����W�X�^���p��M���W���[��)�̔g�������͍��킹�Ȃ���Ȃ�܂���B �@�K�i�s���̐ԊO��LED�������Ă�����̔g�����ʂ����ĉ�nm�Ȃ̂��H�ׂ�ɂ́A��w���匤���@�ւɂ���悤�ȕ������������g�p���Ȃ��ƂƂĂ���ʉƒ�⒬�̓d�C������ł͖����ł��B �@�K�i�s���̐ԊO��LED�̒��S�g������nm���ׂ�̂͂�����߂Ă��������B �@��ɏ����܂����悤�ɁA����������������u������x�̕��v�͂���܂��̂ŁA���̕��̒��Ɏ��܂��Ă���Ί��x�E���B�����͒Z���Ȃ�܂������������͔������܂��B �� �f�[�^�����g�̎��g�� �@�ԊO�������R���ł́A�P���ɐԊO��LED�����点������点�Ȃ������肵�ă����R���M��(�f�W�^���M��)��1��0�𑗐M���Ă���킯�ł͂���܂���B �@�ԊO���͎��R�E�ɂ����݂��A���z������M������̂����ɑ�ʂɕ��o����Ă��܂��B �@�����̎��R�ȐԊO���ɂ��S�Ĕ������Ă����烊���R���̎�M���͂��܂������̂ł͂���܂���A�����R���M���ɂ͂������̎��g���Ŕ��U�������p���X�g�Ŕ�������ԊO�����g���܂��B����ȃp���X�g�͎��R�E�ɂ͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��ł��悤�B �@��M���ł͂��̃p���X�g������ʂ��t�B���^�[��H�Ȃǂ��g���āA�ق��̐ԊO���Ƌ�ʂ��đ��M�@���瑗�M���ꂽ�f�[�^���������o���܂��B �@���̓�����g���Ŕ��U�������d�C�M���́u�����g�v�ƌĂ�A����ɂ����ON/OFF���ăf�W�^���M�����Ӗ�����ԊO���ʐM�M��������ă����R���̔��������甭���E���M���܂��B �@���Ƃ��ΐ���ނ̕ʁX�̃����R�����������Ƃ��āA���ꂼ�ꂪ�ʁX�́u�����g�v�̎��g�����g���Ă���A�g�p����@��ɂ���Ď�������M���ׂ������g���g�������߂��Ă��܂�����ʂ̋@��̃����R�����M�@���������ԊO���M���ł͔������Ȃ��͂��ł��B �@�����g���g����ς��邱�Ƃʼn���ނ��̃����R������邱�Ƃ��ł��܂��B �@�������A���ۂɂ͉Ɠd���i�ł͔����g���g����ς��ă��[�J�[���Ƃ̃����R����������肷�邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���Ă��炸�A�ƊE���ʂ̔����g���g�����g���āu�^�ԃf�W�^���f�[�^�̒��g��ID������U��v�Ƃ������@�Ŋe���[�J�[�E�e�@�킲�Ƃ̃����R������ʂ���悤�ɂ��Ă��܂��B �@�N���ǂ����߂��̂��͏ڂ����͒m��܂��A����͑��M�@�E��M�@�Ƃ��ɓ����K�i�̉�H�╔�i���g����̂Ő����H����̋��ʉ����v���A���i��Ȃǂ������ς܂�����Ƃ���ɋƊE�c�̗̂��Q����v�����̂ł��傤�B �@�����Đ���ނ́u�f�W�^���f�[�^�̒ʐM���@�v���K�i�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă��āA���́u���@�̎��(�`��)�v�Ɓu���Ɋ܂܂ꂽID�R�[�h�v�ŗl�X�ȑ��u�p�̐ԊO�������R�������i������Ă��܂��B �� ���{�ł�NEC������SONY�����̂Q���嗬�ł� �@����ȊO�ɑS���K�i�ɉ����Ă��Ȃ��Ǝ����i��A����i������܂����E�E�E�B �@�K�i��͔����g�̎��g����33KHz/36KHz/38KHz/40KHz/56KHz�Ȃǂ����߂��Ă��܂����A�ł��悭�g���Ă���̂�38KHz�ł��B �@�ԊO������f�q�Ƒ�����H�A�����g�t�B���^�[��o�̓o�b�t�@�Ȃǂ��P�̃p�b�P�[�W�ɓ������u�ԊO�������R������f�q�v�ƌĂ��d�q���i����y�Ɏ�ɓ���i�ł͂���38KHz�p���ł��|�s�����[�ł��B �@���������g���g�p�����ԊO�������R����ގ����u�̔�����ԊO������M���ĉ����������Ƃ���Ȃ�A���̔����g���g�����Ⴄ������i���g���ƑS���������܂��璍�ӂ��Ă��������B �@�����g���g���̓t�H�g�g�����W�X�^�Ȃǂ̐ԊO������f�q���g���Č�����d�C�M���ɕϊ�����A��͎��g���J�E���^��I�V���X�R�[�v�Ȃǂň�ʉƒ�ł�����͉\�ł��B �� �ԊO�������R���`�F�b�J�[(�ԊO���`�F�b�J�[) �@�w�T�o�C�o�[�V���b�g�̓I�x�����O�ɁA�ԊO�������R��������e����ԊO�����������Ă���̂��ǂ������`�F�b�N�����H�̉�H����܂��B �w�ԊO���M���`�F�b�J�[�E��H�}�x  �@�u�ϒ��Ȃ��v�̂ق��̉�H�́A�P���ɐԊO���t�H�g�g�����W�X�^(TPS615)���g�p���āA�u�t�H�g�g�����W�X�^�ɉ���������������LED���_�������H�v�ł��B �@TPS615�͒��S�g��800nm�ƐԊO�����͉������ŁA���x�����L���Ēʏ�̉����ł���������̂Ŋe����Z���T�[�p�Ɏg�p�ł���t�H�g�g�����W�X�^�ł��B �@�ł�����ԊO�������R���ł��A�����d���ł��A���̉�H�ł͋������Ă��LED������܂��B �@�t�Ɋ��x�͔��ɒႢ��H�ł�����A�ԊO�������R���Ȃǂ̓t�H�g�g�����W�X�^��萔�Z���`�قǂ̋����܂ŋ߂Â��Ȃ��Ɣ������܂���B �@���̋����ł͌����e�̓I�ɂ͂��̂܂܂ł͎g���܂���B�����܂ŐԊO�������R���̓���e�X�g�Ȃǁu�g��������g���g���Ȃǂ��Ȃ�ł������A�����Ă���Δ�������`�F�b�J�[�v�ł��B �@�u38KHz�ϒ�(�����R��)�p�v�́A������ɁuIRM3638NS�ԊO�������R����M���W���[���v���g�p���āA������W���[���̏o�͂��o���LED�����点���H�ł��B �@�������38KHz�̃����R���M���݂̂ɔ������܂��B �@�܂������R��������W���[���̒��ɂ͑�����H�������Ă��Ĕ���ȐԊO���ɂ��������A���ʂ̐ԊO�������R���ł���ΐ����[�g���`�\�����[�g���̋����ł��������܂��B �@�����e��38KHz�̃����R���M�����g�p���Ă�����̂悤�ȃ����R���p�ԊO��������W���[���𗘗p���邱�ƂŁA���G�Ȏ�M�A���v������g�t�B���^�[�Ȃǂ����Ȃ��Ă��ς݂܂��B �@�P����Ă����ƁA�u�Ƃ̃����R���łs�u������ł��Ȃ��Ȃ������ǁH�v�Ƃ������ɁA�܂��͓d�r���������Ă��炻��ł������Ȃ��ꍇ�͂s�u(��M��)�������̂��A�����R��(���M��)�����ĐԊO�����Ă��Ȃ��̂������ׂ��܂��B �@���āA����ł��̎�M�`�F�b�J�[�ɉ����I�ɓ�����������≹���o����H��t����Ύ���җl�̂���]�́u�T�o�C�o�[�V���b�g�̓I�v�����܂��ˁI�E�E�E�Ƃ������ɂł������ł����A���͂�����ƍ��������Ƃ�����̂ł܂��͐ԊO���`�F�b�J�[�̉�H�}�̂f�ڂ����̂ł��B �@�u�ԊO�������R���Ō����e����낤�I�v�Ƃ������ł�����̉�H�ɕ\���@�\��t����n�j�ł��B �@�ł�����̂����k�́u�T�o�C�o�[�V���b�g�v�Ȃ̂ł��B �� �T�o�C�o�[�V���b�g�͑��@�\ �@�T�o�C�o�[�V���b�g�͒P���ɏe�u�T�C�R�u���X�^�[�v�̑����ԊO���Ō�����(�����g�Ȃ�)�A�I�u�T�C�R�R���o�[�^�[�v�̂ق��͐ԊO��������u���������I�v�Ɣ�������悤�ȒP���Ȍ����e�ł͂���܂���B �@����́u�I�v�����̂ɏd�v�ȗv�f�͂��̂Q�ł��傤�B �E�`�[�������@�\ (�G/�������ʋ@�\) �E���b�N�I���@�\ �@�u�`�[�������@�\�v�Ƃ́A�吨�Ń`�[���ΐ�����鎞�Ɂu�����ɂ���ˁv�ɂ���e�������߂ɏe���甭����ԊO���M���Ɂu�`�[��ID�v���������āA�����̃`�[��ID�̐ԊO�����Ă���e�������Ƃɂ͂��Ȃ��悤�ȃV�X�e���̂悤�ł��B �@�u�̂悤�ł��v�Ƃ��������Ȃ��̂́A�͎̂����Ă��܂��������͖����̂łǂ̂悤�ȐM�����ڂ��Ă���̂��m�F�ł��Ȃ��̂ŁA�����̋L���ƃ��[�J�[�̍L����̐����ł��B �@�܂�A�T�o�C�o�[�V���b�g�͐ԊO�������R���̂悤�Ƀf�W�^���f�[�^�𑗐M���Ă���ԊO�����M�@�ł��낤�Ƃ������ł��B �@���ꂪ38KHz�̔����g���g�p���Ă���̂ł�������肵�₷��38KHz�p�̐ԊO�������R��������W���[���Ŏ���������ċ����������Ȕ͈͂Ŕ������܂���������e�̓I�Ƃ��Ă͂��Ȃ�ǂ����̂����܂��B �@�����s�̂ł͓��荢��Ȏ��g���̔����g���g�p���Ă���ƁE�E�E���삷��̂͂����ւ�ʓ|�ł��B(�u�C�̖����v�́u�������v�ł͑Ή������˂܂�) �@�ł��A������38KHz�ȊO�̔����g�ł��u�P���Ƀp���X�ԊO������M�����甽������I�v�����A��p���g���̎�����W���[�����g��Ȃ��Ă��ǂ������Ȃ̂œI�͍�ꂻ���ł��ˁB �@�����������͖≮�������Ȃ��̂��T�o�C�o�[�V���b�g�Ȃ̂ł��B �@�u���b�N�I���@�\�v�Ƃ́A�u�G�̏e��������_���Ă���(�I�ɂ���Ă���)�v��Ԃ����m���ăT�C�R�R���o�[�^�[���U������@�\�ł��B �@�u�������I�v�Ƃ������|�����킦�A���u������I�v�Ƃ����U���M���ōQ�Ăđ̂����̂Ō������炷��ƂȂ��Ȃ�����Ɍ����Ă��Ȃ�������āA�����e�ɂ��肪���ȁu��������X�i�C�p�[�Ɍ�����āA�����N�������̂��킩��Ȃ������ɏI���`�v�Ƃ����܂�Ȃ��V�`���G�[�V�������Ȃ����ăQ�[�����y�������܂��B �@���āA�Q�[�����ł̋@�\�͂����������Ǝv���܂����A�������b�N�I���@�\����������Ƃ���Ɖ����K�v�ł��傤���H �@�����A������������ł��ˁH �@�T�o�C�o�[�V���b�g�ł́u�e�̈������������Ēe��(����)�������Ă��Ȃ����ɂ��A��ɐԊO���M�����o�Ă���I�v�Ƃ������ł��B �@�펞�u���b�N�I���M���v�Ƃ����f�W�^���f�[�^���ԊO�����M����Ă��āA���̃��b�N�I���M������M���ɓ�����Ɓu���b�N�I�����ꂽ�I�v�Ɣ������邵���݂ł��ˁB �@���̂܂܈������������ƃf�[�^���u�ˌ��M���v�ɕς��āA���˂�������`���܂��B(�ˌ��M���͈�u�����o�Ă܂����b�N�I���M���ɖ߂�) �@�X�Ƀ`�[�������@�\�ɂ���āu�`�[���`�̃��b�N�I���M���v�u�`�[���`�̎ˌ��M���v�u�`�[���a�̃��b�N�I���M���v�u�`�[���a�̎ˌ��M���v�Ƃ������ɍŒ�S��ނ̃f�W�^���f�[�^�����M����Ă�����̂Ǝv���܂��B �@���Ȃ݂ɁA�������s�����A�~���[�Y�����g�{�ݓ��ő����̐l���Ō����������ł��鍂�x�ȁu�����e�o�g���Z���^�[�v(�����Ȗ��͖̂Y��܂���)�ł͏e�P�P�Ɍʂ�ID������U���Ă��āA���N�Ɍ����ꂽ�̂��E��n�����j�����̂͒N���H�̃f�[�^���W�v���Đ���(�|�C���g)�����܂�A�Q�[���I����Ƀv�����g�A�E�g���Ă��炦��悤�ȋ@�\������܂����B��������̃T�o�C�o�[�V���b�g�ɂ��̌�ID�@�\��lj����悤�Ƃ����v���W�F�N�g�������������ōs���Ă��܂����ˁi�O�O�G �@�������̐�������������A�T�o�C�o�[�V���b�g�ł́u�ԊO����������ƒe�ۂ����������v�Ƃ����P���ȕW�I��H�ł̓Q�[���ɂȂ�Ȃ��̂ł��B �@�������������Ȃ��Ă��A�e�������āu������v�͈͂Ɍ����������Ŕ������Ă��܂��̂ł�����B �@�T�o�C�o�[�V���b�g�̓I�������ƍ��ɂ́A�u�ԊO���f�W�^���M������M���āA�������ˌ��f�[�^�݂̂ɔ������ē��삷��A�}�C�R������̕W�I�V�X�e���v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �@���ׂ̈ɂ̓T�o�C�o�[�V���b�g���ǂ̂悤�Ȍ`����f�[�^�ł����̏��ʐM���s���Ă���̂��̉�͂��K�v�ŁA�����������ɂ��Ăo�h�b�}�C�R���Ȃǂ̃v���O�����̍쐬�A�}�C�R���g�ݍ��݂̕W�I��H�̐v�Ȃǂ����ւ�ȍ�Ƃ��K�v�ł��B �@�����������G�ȕW�I�V�X�e���̐v�͂��́u�������v�ł̎���t���ł͑Ή����Ă��܂���B(�ʓ|�ł�����I) �@�T�o�C�o�[�V���b�g�ɂ��u�o�[�W�����v������A�����^�ɂ́u�`�[�������@�\�v�u���b�N�I���@�\�v�����������Ǝv���܂��B �@�������@���ꂽ�T�C�R�u���X�^�[�������^�ŁA�����^�͏�Ƀ��b�N�I���M���M���Ă��Ȃ��Ďˌ��M���̂�38KHz�����R���M���ő��M����Ă���̂ł�����A������H�}�̃����R��������W���[�����g�p����^�C�v�ň���������������u������������͂��ł�����A�܂��W�I��P���ȓd�q��H�݂̂ō쐬�ł��܂��B �@����W�I��H�}���o�����Ƀ`�F�b�J�[��H�}���������̂͂��������e�X�g���s���Ē�����������ł��B �@���������������悤�ȏ����^�ŁA�ԊO���M�������ˎ������o��^�C�v�ł������ȍ~�ɕW�I��H���l���܂��B �@�z�������ʂ�ɏ�ɐԊO���M�����o�Ă���^�C�v�ł�����A������߂Ă��������B(���̃^�C�v�������Ƃ������͂ł�����m�点��������) �@�����_����������A���̂����d�q�H��}�K�W�����Ɂu�����e�Q�[������낤�I�v�Ƃ��������̐���L���𑗂낤���ƈȑO����v�����͗����Ă���̂ŁA�����L�����ڂ�����T�C�R�u���X�^�[�����̌����e�ɉ������Ċ��p���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/8/10
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@���������Ƃ���A�w�T�C�o�[�E�E�x�ł͂Ȃ��A�w�T�o�C�o�[�E�E�x�ł��i�j �@�������Ǘ��l�l�̒m���̐[���ɂ͐�債�܂����B �@�T�o�C�o�[�V���b�g�ɂ��o�[�W����������Ȃ�Ēm��܂���ł����B�����������Ă���̂͏����^�̕��y�ł̂ق��ŁA���b�N�I���ȂǂƂ������̂͏o���܂���B�w���̂܂ɂ�����Ă����x�o�[�W�����ł��B �@���Ԏ���ǂތ���ł́A�W�I������\��������ق��̃T�o�C�o�[���Ǝv���܂��B �@�����A�W�I��ʎY�ł����珬�w���̑��q�̗F�B��吨�Ă�ŁA�ԊO���S�������݂����Ȃ��̂��������Ȃ��A�Ƃ�������������ꂻ���ł��B �ЂႭ���낤 �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����̂��̂��ꔭ�����ԊO���˂��Ă���̂��A����̓����R���M���p�̎�M���W���[���Ŏ�M�ł���̂��A���Ђ��m���߂��������B ���Ԏ� 2009/8/10
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 8/11 |
�@�ԊO��LED�̓_���ł����A�f�W�J��or�r�f�I�J�������ŎB�e����ƌ�����Ǝv���܂��B �@���g���̔��ʂ�f�[�^�̓��e�܂ł͂킩��܂��A�_������̂���u�Ȃ̂��A�A���Ȃ̂��ʂ͔��ʂł���Ǝv���܂��̂ŁA���i�K�̃`�F�b�N�Ƃ��Ă������ł��傤���B �@����ɂ��Ă������́u��������v�͔��ɍ��x�ł��ˁB jr7cwk �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 8/12 |
�@jr7cwk�l�@���������肪�Ƃ��������܂��B �@�Ǘ��l�l�����p�ӂ��Ă���܂����w�ԊO�������R���`�F�b�J�[��H�}�x���Ȃ��������̂o�b�ł͌���Ȃ��m�F�����܂���ł��܂����B �@���ʁA���������w�����������������x�ł����B �ЂႭ���낤 �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�Ǘ��l�l�@�ԊO�������R���`�F�b�J�[��H�}�����悤�ɂȂ�܂����B�n�r���S����O�̂��ߕs�s���Ȃ��Ƃ������A�����炭��������̂����ł͂Ȃ��ł��傤���H �@38KHz�ϒ��̃`�F�b�J�[���쐻���܂����B�f�W�J���Ŋm�F�ł����Ƃ���A���������������������_���ł��B �ЂႭ���낤 �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@38KHz�`�F�b�J�[�Ŕ���������A���S���܂����B �@�����e�̎d�l�ɕs���_��������������e�ł����̂ŁA(���₵�悤�ɂ����[���A�h���X���L���̖₢���킹��̖������e�ł������c)���̕��̉�H�}�˗��ւ̉���Ɏ�����e���f�ڂ��A�s���_��o���܂����̂ł��ꂩ��q���p�́u�I�v��v�ł��܂��B �@���̕��̉�H�}�쐬�����Ȃ藭�܂��Ă��܂��̂ŁA�f�ڂ͂��Ȃ��ɂȂ�Ǝv���܂����A�C���ɂ��҂����������B �@�摜�������Ȃ��������ł����A�u�C�̖����v�Ŏg�p���Ă���C�O�̃����^���T�[�o�[���A���X�摜��o�^���Ă������Ɍ����Ȃ���������܂��B(�L���b�V���̊W�H) �@�x�����ɂ͔������炢����ƌ�����悤�ɂȂ�̂ŁA�摜�������Ȃ����ɂ͂P�����x���x���m�F���Ă��������B �@�܂��A�ȑO�͂����ƌ����Ă����͂����A���������t�@�C���������Ȃ��Ă��邱�Ƃ���������܂��B�Â��L���̉�H�}��ʐ^�������Ă���ꍇ������̂ł����������������ꂽ���͂��m�点���������B(�����T�[�o��Ђ�����Ă������o�b�N�A�b�v�̍ۂɉ���������悤�ł��c) ���Ԏ� 2009/8/19
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 8/24 |
�@�Ǘ��l�l �@�A�h���X�̌��A���݂܂���ł����B �@���C���Ɏg���Ă�����̂��l�r�m���������̂ŁE�E�E�B �@�摜������Ȃ������̂̓T�[�o�[�������H�������̂ł��ˁB������ƈ��S���܂����B �@�W�I�̉�H�}�͋C���ɑ҂��܂��B�҂Ă܂��B �@�܂��w�C�̖����x��ǔj���Ă��܂���̂Łi�j�B �@���Ԃ�����̂Ŋ�{��H�������Ȃ�ɃA�����W�i�ƁA�����Ă��k�d�c��h��Ɍ��点����x�����ł��܂��i�܁j�j���Ă݂܂��B �ЂႭ���낤 �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�w�����e�̓I�x�̉�H�}�ł��B �@����͓��������̃J�E���g�ȂǁA�T�o�C�o�[�V���b�g�Ɍ����炠��悤�ȍ��@�\�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�P���Ɍ����������������莞�ԓd�q����炵�č��P�xLED���s�J�s�J�Ɠ_�ł����鑕�u�ł��B �@������������Ɓu�s�s�s�s�s�I�v��u�v�[�A�v�[�A�v�[�v�Ȃǂ��D�݂̉����ƊԊu�A�܂����쎞�Ԃ����R�ɐݒ�ł��܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �ԊO����M(�Z���T�[)�� �@�e�X�g��H�Ŏg���Ē�����IRM3638NS���g����38KHz�ԊO���M������M���܂��B �@��M�����ꍇ�͂��̐ԊO���M���̃p���X���Ԃ����o�͂�L�ɂȂ�܂��B �� �����V���b�g�^�C�}�[ �@�ԊO���M������M����ƁA��莞�ԓ��삷��悤�Ƀ^�C�}�[�����܂��B �@�^�C�}�[IC 555�������V���b�g���[�h�œ��삳�����H�ŁA���萔��VR1�ʼnςł���2.5�`15�b�ł��B �@555�̓^�C�}�[���쒆�ɍăg���K�[�͂�����܂���(�ʋL���Q��)�̂ŁA�������������Ė����ɍēx�������������Ă����삷��̂�VR1�Őݒ肵�����Ԃ݂̂ł��B �� �u�U�[�f���������U��H �@�u�U�[����P�Ɂu�u�[�[�[�[�v�ƒP���Ŗ炷���A�u�r�E�r�E�r�E�r�E�r�E�r�v�Ȃǒf�����ɂ����ق����킩��₷���̂ŁA�����Œf������d�q�M��������Č�̃u�U�[��H��f���I�ɖ炵�܂��B �@�f�����g���͖�12�`2.7Hz(�������`����)��VR2�ʼnςł��܂��B �@���ł�(��)�A���̒f���M���ŐԐF���P�xLED��_�ł����邱�ƂŁu���������I�v�Ƃ����̂����o�I�ɂ��悭�킩��悤�\���ł��܂��B �� �����\���t���b�V���[ �@���P�x�ԐFLED���S���炢�g���āA�P�[�X�̂ǂ̕���������悭������悤�ɖ����\����_�ł����܂��傤�B �@LED���P�ł����ꍇ�͕\����H(LED�ƒ�R)�͂P��H�݂̂ł��\���܂��A5�`6��H�قǂ܂łȂ琔�𑝂₵�Ă��\���܂���B(����ȏ�͑��₳�Ȃ��悤��) �� �u�U�[�������p���U��H �@�d�q�u�U�[�́u�v�[�v��u�s�[�v�Ƃ����w���x�������锭�U��H�ł��B�u�U�[�̎��g���͖�570�`1600Hz���x(�v�[����s�[�܂�)��VR3�ʼnςł��܂��B �@�u�U�[�f���������U��H�ō�����f�������M���ʼn����o�����o���Ȃ����𐧌䂵�Ă��܂��̂ŁA�f���I�Ɂu�u�u�u�u�u�u�c�v��u�s�s�s�s�s�s�c�v�A�܂��͎������������ɂ���u�|�[�A�|�[�A�|�[�A�|�[�c�v�݂����ȉ��ɂ�����Ǝ��R���݂ł��B �@���̂�����͂��q�l�ɍD���Ȃ悤�ɒ��߂����Ă�����Ɗ�Ԃ�������܂���B �@555�͂��̂܂܂ŏ��^�̃X�s�[�J�[���쓮�ł��邭�炢�̏o�͂����o���܂��̂ŁA470��F�̓d���R���f���T�ŃJ�b�v�����O���āA�C���s�[�_���X�W���Œ��a�����Z���`(�P�[�X�ɓ���傫����)�̃_�C�i�~�b�N�X�s�[�J�[��ڑ����Ă��܂��܂��B���\�傫�ȉ������܂��B �� �܂Ƃ� �@������^�C�}�[IC 555�̊�{�@�\�́u�����V���b�g�^�C�}�[��H�v�Ɓu���U��H�v�̂Q�̊�{�p�^�[����g�ݍ��킹�ĖړI�̋@�\���������Ă݂܂����B �@555�Ȃ甼���̃��[�J�[�e�Ђ���o�Ă��āA�����Ă��̓d�q���i�X�ōw���ł��܂����畔�i����ɓ��炸�ɍ��Ȃ��I�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��͂��ł��B �@��H���@�\�u���b�N(���555�̂܂��)���Ƃɍ�����قǓ�����̂ł͂���܂���B �@���ӂ���͓̂d���܂��ɓ���Ă���m�C�Y���p�̃R���f���T�ŁA���ꂼ��w��̏ꏊ�ɂ����ƂƂ���Ȃ��ƃX�s�[�J�[���特��炵�Ă���Ԃ͂���Ȃ�ɑ�d��������Ă��ēd��������ɔ����ĕs����ɂȂ�A���̉e�����Ċe555����쓮���N�����Ă��܂����Ƃ�����܂��B �@���Ƃ��A�����V���b�g�^�C�}�[������쓮���ă^�C�}�[���삪�I������̂ɏ���Ƀ^�C�}�[���쓮���āA�����ڂɂ̓^�C�}�[�������Ɠ����Ă����ԂɂȂ��ĉ����~�܂�Ȃ��Ȃ�����E�E�E�B �@���������������Ǐo���ꍇ�ɂ͓d���܂��̃R���f���T���������w��̏ꏊ�ɂƂ�����Ă��Ȃ������܂��^���Ă��������B �@��H��g�ݗ��Ă���Ɠd�r�A�X�s�[�J�[�A�ԊO���Z���T�[��100�~�V���b�v�̃^�b�p�[�Ȃǂɓ���Ă��܂��āA�ȒP�ȃx���g�ő̂ɂ�����悤�ɂ���u�����e�S�������v�Ɏg���܂��ˁB �@�̂̑O�ʂȂǂ̃P�[�X�𒅂���悤�Ȍ`���ƑO�ʂ��炵��������������܂���A���̏��X�q�̂Ă���Ɏ�M����u���Ȃlj����H�v�����Ă��L�͈͂���_����悤�ɂ����ق����y������������܂���B �@���ۂ̑g�ݗ��āE�^�p�ő�R�H�v������]�n�����肻���ȃI���`���ł�����A���������H������q�l�ƈꏏ�Ɋy���ނ̂��ǂ������ł��ˁB ���Ԏ� 2009/8/29
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�Ǘ��l�l �@�����̂����肪�Ƃ��������܂����B�Ƃ������A�ƂĂ������ċ����Ă��܂��B �@���ꂩ��̏H�ɖ钷�Ɂw�C�̖����x���n�ǂ��悤�Ƃ��Ă������ɏo���オ��̃��[���B �@���邩��͒�������H���R���p�N�g���A�w�C�̖����x�ɒp���Ȃ��悤�ɃJ�b�R���N���߂���悤�ɉ�H�}�Ƃɂ�߂������܂��B �@�����ďo���オ�����W�I�̃{�f�B�[�ɂ͑傫���ڗ��悤�ɁwPRODUCED by �C�̖����x�ƕ`���܂��ˁB�����I�H���R�H�@�ł���ˁi�j�B �@�Ǘ��l�l�@����̌��A�{���Ɋ��ӂ��Ă��܂��B�������`���Ă������������ɂȂ肻���ł��B���i���莝���̂��̂�3���炢�͏o�������Ȃ̂ŁA�����ɂł��q�������ƗV�ׂ����ł��B���肪�Ƃ��������܂����B �@�@ �@�Ō�ɍő�̖�肪����܂��B �@�������S�ɂȂ������A�e����ɓ����f���q���B��ǂ������Ă��đ��v�Ȃ̂��ƁE�E�E�B �ЂႭ���낤 �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���܂�ڗ��悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ł��������B���̂g�o�͂Ђ�����ƁA�ׁX�Ƃ���Ă���̂ŁE�E�E�B �@����Ɂu�C�̖����v�Ȃ�ĉ��N�̈����P��������Ă���ƁA�q�����s�R�����܂���B �@���q�͗c�q���q�̒J�ɗ��Ƃ��Ēb����Ƃ����܂��B�S�ɂȂ�����S���S�ɂ��Đ���Ă��������B ���Ԏ� 2009/8/30
|
|||||||||||||||||||||||
| �d�삪�����Ő���H�������ĉ����� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āI �@�ŋ߂����������ē��e�̔Z���ɋ����܂����B �@�����ŊF�l�ɂ��q�˂��������Ƃ�����܂��B �@��ʓI�ɔ̔�����Ă���d��ŁA�����ԑ��삵�Ȃ��Ɠd���������ŗ�����悤�ɂȂ��Ă��܂����A���̋@�\�͂ǂ̂悤�ȕ��Ő��䂵�Ă��āA��̓I�ɂǂ̂悤�ȓd��(����)��H�������Ă��������B�ґ�������A��H�}�����ڂ��ċ����Ă���������Ɗ���������ł��B �@�C���^�[�l�b�g�ł��Ȃ茟�����������̂ł����A��̓I�ȃy�[�W����������Ȃ������̂ŊF�l�̂��͂����݂����������B�X�������肢�������܂��B �F�ꎁ �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�F�ꎁ�l�͂��߂܂��āB �@�d��̕��Ƃ��ĒT���Ă���̓I�ȃy�[�W�́E�E�E�E�܂������ł��傤�B �@�u�d��́v�ƌ��肵�Ă��b������ƁA���̋@�\�͓d��̐S�����̃J�X�^��LSI(��p�̏W�ω�H)�̒��ɑg�ݍ��܂�Ă���@�\�ŁA�������ɓd�q���i�ŃX�C�b�`��H���Ƃ���Ă�����̂ł͂���܂���B �@��pLSI�₻�������@��ɑg�ݍ��ރ}�C�R���`�b�v�ɂ́u�X���[�v���[�h�v�u�X�^���o�C���[�h�v�ƌ����āA��v�ȋ@�\�삵�Ȃ����ď���d�͂��قڂO�ɂ���@�\��IC�̒��ɐv�i�K����d���܂�Ă��܂��B �@�X���[�v��(�d��Ȃ�d��OFF��)�͓d���X�C�b�`(�d��Ȃ�ON�{�^��)�Ɍq�����Ă��邲���ꕔ�ɂ����d�r����d������������Ă��āA�l�Ԃ��d���{�^�����������炻������m���ē����̑S�̂̉�H�������͂��߂܂��B �@���쒆�ɐl�Ԃ��������������Ɠ������ꂽ�^�C�}�[�����Z�b�g����Ĉ�莞�Ԃ͓d����OFF�ɂ͂��܂���B �@�������삵�Ȃ���Ԃ���莞�ԑ����ƃ^�C�}�[���K��J�E���g�ɒB���āA�����̃X���[�v�@�\�ʼn�H���x�܂���@�\�Ƀg���K�[���������ċ@�\���~(�x�~)���܂��B �@�܂��d���{�^�����������܂ŋx�~��Ԃ͑����܂��B �@���̂悤�ɁA�d��Ȃǂ̑��u�ł͂��̑��u���`����Ă����pLSI�����Ɂu�x�ވׂ̋@�\�v���g�ݍ��܂�Ă���̂ŁA��莞�Ԍo�Ǝ����I�ɓd�����ꂽ�悤�Ɍ�����킯�ł��B �@���Ď��͈�ʓI�Șb�ł��B �@�u��H�}���v�Ƃ������ł����A�s�̂̓d�q���i�ʼn�H������ă^�C�}�[�œ��삷��d��ON/OFF��H�Ƃ������̂͗e�Ղł����A���Ɏg����̂��H�A�d���͉���ON/OFF�����H�͂ǂ̂悤�ȕ��ŁA�u��莞�Ԉȓ��ɑ��삵����A���삵���Ƃ����M�����o�͂���悤�ȋ@�\������̂��H�v(�����Ȃ�������]�̂悤�ȃ^�C�}�[�͍��܂�����)�ȂǁA���p�̓d����H�Ȃ̂���������Ȃ��Ɛv�Ȃ�Ăł��܂���B �@�܂��u�d���X�C�b�`�v�̂悤�ɓƗ������X�C�b�`��ON���ł��A����͂��̉�H�̑��̋@�\�ɂ͋��L���Ă��Ȃ��̂�(�d��Ȃ�CE�L�[�ƈꏏ�ɂȂ��Ă���Ƃ�)�Ȃǂɂ���Ă���H�̍l�������ς��Ă��܂���B �@���Ɂu���Ɏg���v�Ƃ����Ӑ}�͖����A�P�Ɂu�d�g�݂�m�肽���v�Ƃ��������̂����₾�Ǝv���̂ŁA�ꉞ�T�v�����킩����x�̉�H�}����܂��B  �@�d������Ă��鎞�ɂ͓d��������ɂ́u�d���X�C�b�`�v��������������܂���B �@���̉�H�ɂ͓d������������Ă��Ȃ��̂Łu�d�������H�v�͓������ɂ������Ȃ��̂ł�����B �@�u�d���X�C�b�`�v���������g�����W�X�^�P��ON�ɂȂ蒆�̉�H�ɓd������������܂��ˁB �@���̉�H�������͂��߂���u�d�������H�v���������g�����W�X�^�Q��ON�ɂ����d������M���̓d�����o�͂���悤�Ɂu�d�������H�v��v���܂��B �@�u�d�������H�v���ێ��M�����M���d�����o�������Ă������A�u�d���X�C�b�`�v����w������Ă��Q�̃g�����W�X�^��ON���Ă��܂������H�͓���𑱂��܂��B �@���̂悤�ɁA�u���̉�H���������������ŃX�C�b�`�������Â���悤�Ȃ͂��炫�v�̂��Ƃ��w���ȕێ��x�ƌ����܂��B�ǂ�Ŏ��̔@���A���̂܂�܂ł��B �@���Ƃ��u�d�������H�v�Ƀ^�C�}�[��v���đg�ݍ���ł���Ƃ��A���̉�H������̓����������u�d�������H�v�ɒm�点��Ƃ��A���炩�̗v���Łu�d�������H�v������ێ��M�����M���d�������悤�ɐv���Ă����A�^�C�}�[��≽�炩�̐v�������g�����W�X�^�Q��OFF�ɂȂ�A����ɔ����g�����W�X�^�P��OFF�ɂȂ�����H�ɋ��������d���͐₽��܂��B �@�������ĉ�H�����̉��炩�̗v���Ŏ����I�ɓd�������A��H�����͓��삵�Ȃ��Ȃ�̂Œ�����ēx�d��������(�ێ��M�����M���d�����o��)���Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA��U�d�����ꂽ�玟�ɓ���J�n������ɂ͐l�Ԃ��u�d���X�C�b�`�v��������������܂���B �@�����ł̓g�����W�X�^��d��ON/OFF�Ɏg����H�}�ŗ�������܂������A�Â�����̓����[���g��������Ղ̐v�ȂǁA�����čŐV�Z�p�ł́u�������[�v����LSI�̒��̓d�q��H�Ȃǂ���Ƃ�����u�d�C�I�ɏ�Ԃ�ۑ��E�ێ��E�L�������v�Ƃ�����b�Z�p�̂P�����ȕێ��ł��B �@�����Ă���(���ȕێ���H)���̂�d�����ɉ��p����ƁA�ێ��Ƃ���������t�ɓǂނƁu�����Ŏ����̓d������Ă��܂��v��H�̏o���オ��ł��B ���Ԏ� 2009/7/30
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e 8/3 |
�@�Ǘ��l�l�A���Z���߂����̒��A����肪�Ƃ��������܂��B �@��͂�d��̓d������ON/OFF��H�ׂĂ�������Ȃ��̂ł���...�x���ꑁ���ꂱ����̃T�C�g�������邱�Ƃ��o���ėǂ������ł��B �@�d��́u�X���[�v���[�h�v�Ȃǎ��ԂŎ����d��OFF�ɂȂ��H�́A�{�X�v���O���~���O���ꂢ�Ĉ�ʂ̐l���ȒP�ɐG��Ȃ��悤�Ȃ��̂�������ł��ˁB�ʂ�Œ��ׂĂ��Ȃ��Ȃ���H�}��������Ȃ��킯�ł��B �@���������������������̂́A�d����ON/OFF����̎d�g�݂�m�肽�������̂ŁA����̏ڍׂ��s�\���������̂ɉ�H�}�܂ŋL�ڂ��Ă��������Ĕ��ɕ�����₷�������ł��B�S���犴�ӂ��Ă��܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �F�ꎁ �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �t���b�V���[��������肽���H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��� �@�����ʔ����������肪�Ƃ��������܂� �@�ŋ߂k�d�c�ɋÂ��Ă��܂� �@�o�C�N�A�Ԃ̂k�d�c���ŁA�e�[���A�E�C���J�[�ȂNJy����ł��܂� �@���http://www.audio-q.com/carkit.htm�̎����J��Ԃ�8���_�����i�Z�b�g�����܂������A�����������Ŏ����悤�ȕ����o����ƁA���肢����������ł� �@�k�d�c�E�C���J�[���g���b�N�̗l�ɗ����E�C���J�[�ɂ������̂ʼn����ǂ��Ă�����܂����炨�肢���܂� �@�o����Δz���}�A�g�p�p�[�c�̏ڍׁi��R�l�A�R���f���T�[�e�ʂȂǁj�����肢���܂��B �@����ɂ���A�����y������肪�Ƃ��������܂��A�������x���e�����Ă��������܂����u�����E�C���J�[�v�ɂ��Ăł����A������̉�H����ǂł���Έ����ō�ꂻ���ȁH�i�f�l�ϑz�ł����A�A�A�j���Ԃ���܂������x���Ă��������A�X�������肢���܂� �@ http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g75457152 �K���K�� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̃L�b�g�ō����Ɗ������Ă���̂ł�����A���̃L�b�g�̔z���}�����ɕ��i�������W�߂��1/2�`1/3�̒l�i�ŕ��͍�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�܂����ɂ����������t���b�V���[�̉�H�}�̓l�b�g�ł��������J����Ă��܂��̂ŁA���������g�o�����Q�l�ɍ����̂��ǂ��Ǝv���܂��B �@����lj����ꂽYahoo�I�[�N�V�����Ŕ����Ă��邻�̏��i����͂���̂͂����Ƃ��āA�ʐ^���Ɍ������ɒ��ڃ��[���h����Ă���_�Ő���IC�͎s�̕i�ł͂Ȃ��A���̊��(������IC������͕ʂ̒��ؐ��i�̒��g�����o������������ɗ��p���Ă���悤)���������̐�p�i�ŁA�����V���ɔ�������Ȃ琔��`�����𒆍��̃��[�J�[�ɔ������Ȃ��Ɠ���ł��܂���A�ʂ����ăK���K���l���l�ōw���ł�����z���ЂƂ��Ă̌_���s�ł��邩�ǂ����E�E�E�B �@�u�K���K���d�q������Ёv�݂����ȃt���b�V���[������Ђ�ݗ�����āA�s�̗p�ɐ���P�ʂō����Ȃ炽�Ԃ�IC�P������̉��i�͂����������Ȃ�܂���I �@�����A�����̉�H�}�̃t���b�V���[���Ɗ�{�I�ɂ͍��E�̃E�C���J�[�ɂ��ꂼ��P��H��t���Ȃ���Ȃ炸�A�K�v�ȕ��i�Ɨ\�Z�͂Q�{�ł��ˁB �@�t���b�V����H�͂P��H�����ŁA���̑��ɕ��i��lj����č��E�̃t���b�V���͓��p�^�[���œ_�ł����鎖���\�ł����A���������g�����̓L�b�g�̔��y�[�W�╁�ʂɁu�t���b�V���[�����܂����v�Ƃ�������Ă���l�l�̂g�o�ɂ͏�����Ă��܂���̂ł����ōl���Č��J���邵������܂���B �@����ƁA�����̉�H�}�͍��E�ɕʁX�ɉ�H�����Ďg�p����ꍇ�ɂ́u���E�̓����v�ɂ��đS���l������Ă��܂���̂ŁA��H�̕����E�ꍇ�ɂ���Ă̓n�U�[�h�����v���̂悤�����E�����̕����w�����_�ł����Ă��鎞�A���E�̃t���b�V���[���ʁX�̌�������������������������ȂǁA���p��̖��_�ɋC�t���Ă��Ȃ����A�C�t���Ă��Ă����J���Ă��Ȃ��ꍇ�������ł��B �@���̂Q��H�g���������������������́A (A) �E�C���J�[�_���������ʌ^(�����^)�ł͂Ȃ��E�C���J�[�P���A���^(�d���f���^)�ŁA�����J��Ԃ��łȂ��t���_���ɂȂ���������Ȃ���H�ɂ���B (B) �E�C���J�[�_���������ʌ^(�����^)�ł͂Ȃ��E�C���J�[�P���A���^(�d���f���^)�ŁA�����J��Ԃ��ł��P��̃E�C���J�[�_�ł̓_�����Ԓ��ɂP���t���b�V�����Ȃ����x�̎������蓮�Œ��߂���(���\�ʓ|)�B �Ȃǂ̏��u�ʼn���͂ł��܂����A(B)�^�C�v�͂��܂肨���߂��܂���B �@���������u�E�C���J�[���t���b�V���^�ɂ������v�Ƃ�������]�͂��܂�ɂ��B���ł��B (C) �E�C���J�[�_�ł̓_������(���̓d���������Ă��鎞�ԓ�)�����t���b�V�������������(�d�����P�����ԂɂP���t���b�V�����Ď~�܂�A�܂��͓d�����P����鎞�Ԓ��ɍ����Ńp�p�p�p�Ɖ��x���t���b�V����������)�A�d���������Ă��鎞�Ԃ̓t���b�V���������Ă���B �̂ŗǂ��̂��A (D) �E�C���J�[�_�ł��������m��H��ʂ��ĕ��R��ON���Ԃɕϊ�����(�E�C���J�[�X�C�b�`�������Ă��邩�ǂ�����m��)�t���b�V���[��H�̓d����ON�ɂ��āA���X�t���Ă���Ԃ̃E�C���J�[�����[��ON/OFF����Ƃ͑S���ʂɃt���b�V���[��H�̂ق��Ńs�J�s�J�_�ł�������E�X�s�[�h�E�_���ێ����ԁE�����ێ����ԂȂǂ�ݒ肵�Ă��̒ʂ�Ƀt���b�V���[�����点��B�A���A�E�C���J�[����Ă��_�Ŋ��Ԃ̏����P�Ə����̎��Ԃ̓t���b�V���[�̓t���b�V����������(�����ɂ͏����Ȃ�)�B �Ƃ����d�q��H�ł̃t���b�V���[�{���̓�������������̂��B �@�܂��͂ǂ̂悤�ȃt���b�V���[�̓��삪�~�����̂��l���ă��X���Ă��������B �@���܂���҂��ė~�����Ȃ��̂́A�ŏ��ɂ������܂������L�b�g�Ő琔�S�~�̂��̂�������������Ă���~��邭�炢�Ɉ����Ȃ邾���ł��B ���Ԏ� 2009/7/21
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@����ɂ��� �@���Z�����Ƃ�����肪�Ƃ��������܂� �@�l�̎�Ŋy����ł���̂Œ��������ʍw������قǁA�A �@�܂��Ắu�K���K���d�q������Ёv�͐�ɖ�������(^_^;) �@�X�N�[�^�[�Ȃ̂Ńn�U�[�h�͎g��Ȃ�����ł��̂� �@���ʁA�s�̂̃L�b�g���Ċy�������ǂ������ł��� �@�ڍׂȐ����܂ł��Ă����������ӂ������܂� �@�܂���������Y�肵���Ƃ��ɂ͋X�������肢���܂��B �K���K�� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�p�r�͎Ԃł͂Ȃ��X�N�[�^�[�ł����B �@����ł����獶�E�̘A���⓯�����Ȃ��Ă������ڂł͖�肠��܂���ˁB �@���삷��Ɗ����i��L�b�g���͈����͂Ȃ�܂����A���̂Ԃ��ŕ��i���W�߂���A��p�v�����g��������Ԃ�S�������Ŋ��̔z�����l���ăn���_�Â����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���S�҂̕��ɂ͕~���������ł��B �@�����������Ď��삷��̂��d�q�H��̊y���݂Ȃ̂ł����A�d�q�H���ړI�ɂ���̂��A����@���~�����Ƃ����~������Ȃ̂��A�Ŋ��S���삩�L�b�g�⊮���i�̂悤�ȗp�ӂ��ꂽ�������A�ǂ���̂ق������ǂ��v�������̂����ς���Ă���Ǝv���܂��B �@��������̃X�N�[�^�[�ł̎g�p�ł���A�L�b�g���Q�����đg�ݗ��Ăč��E�ɂ����ق����y���Ǝv���܂��B �@�Ȃɂ��L�b�g�Ȃ畔�i���S���Əڂ������������t���Ă��āA�������ɂ����đg�ݗ��Ă���������ł��̂ŏ��S�҂̕��ł��y�Ɋ��������鎖���ł��܂��B �@������x�Ȃ畔�i���W�߂�̂ƃL�b�g�ł͂˂�������܂�ς�Ȃ��̂ŁA���������Ӗ��ł��L�b�g�ŗǂ��Ǝv���܂��B�����ēd�q�H��̘r���āA�����ƕʂ̎s�̕i�ɂ͖����悤�ȕ�����]�ɂȂ����玩�삳���Ɨǂ��ł��傤�B ���Ԏ� 2009/7/24
|
|||||||||||||||||||||||
| ���|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H | ||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��� �@�uLi-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H�v�ɂ��Ď��₳���Ă��������B �@���̉�H�͊�{�Ƃ���1Cell��Li-ion��4Cell��Ni-MH��ی삷����̂Ǝv���܂����A���W�R���̌Â��A���v��d���K���p�Ɏg�p�������̂�2�`4Cell��Li-po�ɑΉ�������͉̂\�ł����H �@�g�p�d���͑傫���قǗǂ��ł���20�`70A���炢�Ŏg������ꂵ���ł��B �@�\�ȏꍇ�A�ǂ̕��i���ǂ̂悤�Ȃ��̂ƕύX����K�v������܂����H �@����Ȏ���Ƃ͎v���܂����A���̖R�����m���ł͂���グ�ł����̂ł�낵�����肢���܂��B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���Z�̂��߁A��Q�����ȏエ�҂����v���܂����B�\�������܂���B �@���āA�Z�����𑝂₷�����Ȃ�uLi-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H�v�̉�H�ňꕔ�̒�R�l�Ȃǂ�ς��邾���łقڂ��̂܂g����̂ł����A�u20�`70A�܂Ŏg�������v�Ƃ�������]��70A�Ƃ͂܂��r���������d���l�ł�����A�uLi-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H�v�ł͈ꕔ�ȗ����ׂ̈Ɏg�p���Ă���P-ch�p���[MOS FET���g�����Ƃ���ƁA��ł���ȑ�d���𗬂��鐻�i�����ʂ̓d�q���i�X�ł͂�������Ǝ�ɓ���܂���B(���p���ɂ��Ă������̂ł����E�E�E) �@N-ch�p���[MOS FET�ł���Α�d����������ON��R�����ɒႢ���i������\�ł�����A���̂ւ�ɍ��킹�ĉ�H�}���ύX����K�v������܂��B �@����͕ύX���łɃg�����W�X�^�Ő֑ؑ��x���グ����@�ł͂Ȃ��A�R���p���[�^IC���Q��H����̂��̂���S��H����̂��̂ɕύX���āA�R���p���[�^���i�ł̍����ؑ։�H�ɂ��Ă݂܂��傤�B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@��{�̍\���́uLi-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H�v�ƕς�͂���܂���B �@�d���d����R1��R2�ŕ�������ăR���p���[�^(1�i��)�́|���͂ɓ��͂���܂��B �@��H�̓����ł̓c�F�i�[�_�C�I�[�hZD1����3V�̊�d�����쐬���A����Œ��RVR1�Œ������ăJ�b�g���肷���r�p�d�����R���p���[�^�́{���͂ɗ^���܂��B �@�����ɂ�C4������A�d������������킸���Ȏ��ԓd�����オ��̂�x�点�āA�d���𓊓��������ɂ͕K���o�͂�ON�ɂȂ�X�C�b�`�̖������������܂��B �@���͓d������d����荂���ƃR���p���[�^�̏o�͂�Low(��0V)�ł��B���̏�Ԃł͍ŏI�I�ȏo�̓X�C�b�`��FET��ON�ɂ��Ă��܂��B �@���͓d������d����艺����ƃR���p���[�^�̏o�͂�Hi(��d���d��-1.5V)�ɂȂ�A�ŏI�i��FET��OFF�ɂȂ�܂��B �@����Ƌ��ɁA�_�C�I�[�hD1��R7��ʂ��Ĕ�r�p�d���������グ�A��U�o�͂�OFF�ɂ�����d�r�d�����������č����Ȃ��Ă���ɒB���Ȃ��悤�ɂ��ĉߕ��d�ی��Ԃ����b�N���܂��B �@����́u�J�b�g�\��LED�v�����Ă��܂��̂ŁA�{��H���o�͂��J�b�g����LED(�ԐF)���_�����܂��B(�A����R�l��12V���x�p�ɍ��킹�Ă���܂��̂ŁA6V�Ŏg�p����ƈÂ��ł��B��R�l�͓K�X�ύX���Ă��������B) �@���āu70A�g�������v�Ƃ������v�]�����Ȃ��邽�߁A�����IRF3703�Ƃ���N-ch�p���[MOS FET���g�p���܂��B �@IRF3703�͍ő��iDC30V�A210A�AON��R�Œ�0.0028���Ƃ�����d���p�̃p���[MOS FET�ł��B(�����d�q��525�~�ł�) �@����ON��R�i�ł����A70A�������Ȃ炿���ƕ��M��t���Ďg�p���Ă��������B �� �������@ �@���Œ��RVR1�͍������ς��ɉĂ����܂��B �@�\���ɏ[�d���Ă���o�b�e���[��ڑ����Ă��������B �@���ׂɂ͓d���Ȃǒʓd��Ԃ��킩����̂�ڑ����Ă��������B��H������ł���Βʓd���ēd���Ȃ����܂��B �@�܂��A�u�J�b�g�\���v��LED�͌���܂���B �@VR1�̂Q�Ԓ[�q�̓d�����e�X�^�[�Ōv��Ȃ���VR1���������E�ɉ܂��B �@�@�@2Cell (6V�J�b�g)�@= 1.053V �@�@�@3Cell (9V�J�b�g)�@= 1.579V �@�@�@4Cell (12V�J�b�g) = 2.105V �ɂȂ�悤�ɒ��߂��܂��B �@���ӂ��K�v�Ȃ̂́A���̓d���͂����܂Łu�ʓd���v�̓d���ŁA�J�b�g���̓_�C�I�[�hD1��ʂ��ăo�C�A�X�d�����������Ă����͖�3V�ȏ�ɂȂ�܂��B���߂͕K���ʓd���ɍs���Ă��������B �@�܂��A�c�F�i�[�_�C�I�[�h���g�p������d����H�̓����ŁA�d���d��(�d�r�d��)�������ꍇ�ƒႢ�ꍇ�ł͍�����d���������ς��Ă��܂��܂��B �@�o�b�e���[�����[�d�̎��ɂ��̊�d������������ƁA���ۂɓd�C���g�p���ăo�b�e���[�d�����������Ă䂭�ƁA��d���������킸���ɉ������Ă䂫�A�ݒ肵���J�b�g�d����菭���Ⴂ�d���ɂȂ�Ȃ��ƃJ�b�g����Ȃ��Ȃ�܂��B �@���̍��͂킸��0.1�`0.2V���x�ł�������p��͖�肠��܂��A���ۂɃo�b�e���[�̕ی��H�Ƃ��Ďg�p����Ȃ�1�Z��3.0V�ł͂Ȃ�2.7V���x�Ŏ~�߂Ă��������炢�ł�����A���̓d���ቺ�ɂ���d���ቺ���S����肪�����͈͓��ł��B �@�u1�Z��3.0V�͌����B2.7V�ŃJ�b�g����悤�ɂ������I�v�Ƃ������́A��]�d���~0.1754385����d���ƂȂ�悤�Ɍv�Z���Đݒ肵�Ă��������B �@�����̓d����������ŃJ�b�g����ׂɂ́A�ʓd���̃o�b�e���[�d���̓J�b�g�d����育���킸�������������(�܂�J�b�g����钼�O�̓d��)�Œ��߂���ƁA�o�b�e���[�d���ቺ�̉e�����Ȃ�(�ቺ������Ԃ�����)�{���ɂ�������ƖړI�d���ŃJ�b�g�ł���悤�ɂȂ�܂��B �@�A���A���̉�H���Q�Z���ȏ��Ŏg�p���Ă��������B �@�P�Z���ł͓d��������Ȃ���IRF3703��ON��R�������R��ԂɂȂ�Ȃ��ꍇ������AON��R��������Ԃő�d���𗬂����Ƃ����FET�������ւM���܂��B�ň��͉��Ă��܂���������܂���A100A�߂������������̂ł���ΐ������Q�Z���ȏ�Ŏg�p���Ă��������B �@����ƁA���̉�H�͏o�͂��J�b�g���������H���̂��킸���Ȃ���d��������Ă��܂��B �@�J�b�g���̏���d���͂����킸���ł����A�����LED��_��������������Ă��܂��̂ŃJ�b�g������ɒ����ԃo�b�e���[��ڑ������܂܂ɂ͂����A�K�����������ɓd���X�C�b�`��邩�o�b�e���[���O���Ă��������B ���Ԏ� 2009/7/14
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Z���������肪�Ƃ��������܂����B �@���Ԏ����x���Ȃ��Đ\����܂���B �@���̉�H���g���Ĉ��S��Li-po���C�t���y�������Ǝv���܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||
| �{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@������ŏЉ��Ă����u�ڂ��[�ނ����Ձ^�ڂ��[�ނ���Ձv�A�����w�����ďd�Ă��܂��B �@�ł����ĊO����d�͂������A�d�r�������ɂ������Ă��܂��܂��B �@�P�O���g����Α叕����Ȃ̂ł����A��y�ɉ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł��傤�� �@�X�������肢�������܂� P �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�X�������肢�������܂��ƌ����܂��Ă��E�E�E�B �@�v���X�`�b�N���H�Z�p�̏�肢���ł���A�{�����[���A���v�̃P�[�X�̒����d�r�z���_�[�ɂȂ��Ă��镔����S����������炿�傤�ǒP�O�d�r���Q�{���錄�Ԃ��ł���T�C�Y�̂悤�ł���B���݂����傤�ǒP�O�d�r�����肻���ł��B(�{�f�B���Œ肷��l�W����{�g���Ȃ��Ȃ�܂����c) �@��H�Ɍq�����Ă���d������͂��̂܂ܗ��p���āA�d�r���m���q�����͌��̕��ł͒P�O�d�r�̕��ł͂�����ƒZ�������ł�����V�K�ɍ쐬���邩���������ʼn�������K�v�����肻���ł��B �@�������P�[�X�ɂ͑傫�Ȍ����̂Ō����炠��W�͎g�p�ł��܂���A�������Ńv���X�`�b�N�𐮌`����Ȃ肵�ĊW��p�ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B���̊W�������炠��悤�Ƀp�`�b�ƃ��b�N�ł���悤�Ȋ����ȕ��ɂ���ɂ́A�v�����f�����t���X�N���b�`�ł���ʂ̗��̋Z�p�҂����f���[�łȂ��Ɩ�����������܂���B�v�����Z���n���e�[�v�Ŏ~�߂�悤�ȕ��Ȃ�N�ł��o���܂��ˁB �@�{�̂�(�\�������)�����ڂȂ킸�ɁA����y�ɉ�������Ƃ����炻��Ȋ����ł��傤���B �@�v���X�`�b�N�̉��H���ł��Ȃ����Ȃ�E�E�E�f���ɒP�O�d�r�z���_�[���{�����[���A���v�ɓ\��t����(�J�b�R����)���A�����ʂ̃P�[�X�ɒ��g���ڂ����������ł��ˁB ���Ԏ� 2009/7/5
|
|||||||||||||||||||||||
| �Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� | ||||||||||||||||||||||||
|
�@���́B���߂܂��ăt�@���R���Ƃ����܂��B �@�ł͑����ł����A���k��VU���[�^�ɂ��Ăł��B�Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�A��H��T���Ă���̂ł����A���܂����҂�Ƃ��܂���E�E�E�Ȃɂ�������H�Ȃǂ�����܂�����Љ�Ă��������Ȃ��ł��傤���H �@�ł͂�낵�����肢���܂��B �t�@���R�� �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@VU���[�^�[�ƌ����܂��Ă��F�X����A�A�i���O�̐j�����[�^�[��f�W�^�����[�^�[�ȂǗl�X�ł��B �@���ɂ��w�肪�����̂ŃA�i���O�̐j���̂��͉̂�H�}�Ȃǂ̒萔�������܂���̂ł��������������B �@�A�i���O���ł͐�p�́uVU���[�^�[�v�Ƃ����p�l�����[�^�[���g�p���܂��B �@�u���ʂ̓d���v��d���v���Ⴞ�߂Ȃ́H�v�Ǝv����ł��傤���AVU���[�^�[�̕\����db(�f�V�x��)�ł���A�d����d���̂悤�ȃ��j�A�ł͂Ȃ��ΐ��\���ɂ���K�v������A�����p�̃��[�^�[���l���p�l���Ɉ������Ă���uVU���[�^�[�v���g���K�v������܂��B �@�����d���v��d���v�ő�p����ƂȂ�ƁA���[�^�[�p�l����db�\���ɏ����������p�l�������삵�Ȃ���Ȃ�܂���B�p�\�R���ƃv�����^�[���A�����ăO���t�B�b�N�`��\�t�g���g��������p�l������邱�Ƃ͋Z�p�̂�����Ȃ�ł���ł��傤���Adb�P�ʂ̖ڐ���Ԋu�Ȃǂ͊��d���@���Ȃ���ЂƖڐ��薈�̊p�x���v�Z���Ă�������ۂ̃p�l����̖ڐ���ʒu�ɔ��f������ȂǁA�ƂĂ��f�l�̕���������ƃp�\�R���ŁI�ƍ�����̂ł͂���܂���B �@�Z�p�ƍ����̂�����ɂ��������߂ł��܂���̂ŁA���l�I�ȐE�l�������������ʂ̕��͑f���Ɏs�̂���Ă���VU���[�^�[���܂��傤�B �@db�ڐ����VU���[�^�[���w������A��̓I�[�f�B�I�M����VU���[�^�[��U�点���H�����悢�����ł��B �@���A������Ƒ҂��Ă��������B �@�u�s�̂�VU���[�^�[�v�Ƃ������_�ŁA���Ƀ��[�^�[�ւ̓��͐M���Ő�����VU�l(db�l)��\������悤�ɂȂ��Ă�����H���芮���i��VU���[�^�[������܂��B �@�����āu�P�ɖڐ��肪db�\���ɂȂ��Ă��邾���̓d���v�v(���Ƃ�����Ȃ���)�Ƃ���VU���[�^�[�����݂��܂��B������̂ق��͉��炩�̋@��ɑg�ݍ��ވׂ̕��ŁA���������l�ŕ\�����邽�߂ɂ̓A���v��H�Ń��[�^�[�ɗ^����d��(�d��)�߂��Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�O�҂͉��i������(����~)�A��҂͈���(���S�~�`)�̂œ��肵�₷���ł��B �@�����ł͌�҂��w������Ƃ��Ęb��i�߂܂��B �@VU���[�^�[�ƌ����ǂ����g�͒������[�^�[(�d���v)�ł�����A�I�[�f�B�I�M���̌𗬓d���𗬂��Ă��j�͐G��܂���B�𗬃I�[�f�B�I�M�����ɕϊ����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B 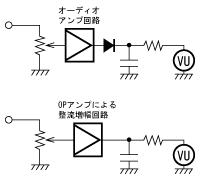 �@�𗬃I�[�f�B�I�M�����ɂ����H�͒P���Ƀ_�C�I�[�h�Ő������Ă����@�A�܂��̓I�y�A���v��H�Ő���������H������Ă����@�Ȃǂ������̕���������܂��B
�@�𗬃I�[�f�B�I�M�����ɂ����H�͒P���Ƀ_�C�I�[�h�Ő������Ă����@�A�܂��̓I�y�A���v��H�Ő���������H������Ă����@�Ȃǂ������̕���������܂��B�@����͓��ɍׂ��Ȏw�肪�����̂Łi�ǂ�ȃA�i���O���[�^�[���g����̂��킩��Ȃ��̂Łj��H�}�╔�i�萔�͒��܂��A�������ł��g�p�ɂȂ�VU���[�^�[�ɂ��킹����H��I�����Ă��������B �@�l�b�g�Ō������������ł��o�ė���Ǝv���܂��B �@���āA�f�W�^��VU���[�^�[�����ꍇ�́A��p��IC���g�p�����ق����y�ł��ˁB �@�I�y�A���v��\���i���������ׂ�LED�����H���������ł����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��ł����A�e�i��db�l�̌��o�l�̐ݒ�Ȃǂ����d���Ў�ɗ܂𗬂��Ȃ����R�l���v�Z���Ă��K�v������A�����I�ł͂���܂���B �@�����d�q�ł̓f�W�^�����ň����ȁu�R���p�N�g���x�����[�^�[�L�b�g�v(1000�~)�������Ă��āA�����ȗ����Ȃ�̐l�C���i�������ł��B  �@�g�ݗ��Ă�Ƃ���Ȋ����ł��B
�@�g�ݗ��Ă�Ƃ���Ȋ����ł��B�@�g�pIC��LM3915N�ŁA10�_LED�ڃh���C�u�ł��郌�x�����[�^�[IC�ł��B �@���̃V���[�Y��IC�ɂ͂R��ނ���A �� LM3914N = ���j�A�^�C�v �� LM3915N = ���O(�ΐ�)�^�C�v �� LM3916N = VU�^�C�v �ƂȂ��Ă��܂��B �@�����̃L�b�g�ł́u���O(�ΐ�)�^�C�v�v���g�p����Ă��܂��̂ŁA�L�b�g�����̂܂ܔ����ƃ��O�\���̃��x�����[�^�[�ɂȂ��Ă��܂��܂�����AVU���[�^�[����肽���̂ł����LM3915��P�̂Ŕ����ĉ�H��g�ݗ��Ă�K�v������܂��B �@�K�������̓X���ł͂��̃L�b�g�́u��̂݁v�������Ă��܂��̂ŁA��݂̂�LM3915�A������A-Bright��10�_LED�Ɛ��̕��i���o���Ŕ����f�W�^��VU���[�^�[���ȒP�ɍ��܂��B �@LM3914N/LM3915N/LM3916N��LED�̕\�����ǂ��Ⴄ�̂�������ׂɍw���������̂�����A��r���[�r�[������Ă���܂��̂ł���������ɓ���܂��傤�B(�Z�œ_�ŎB�e�ł��Ȃ��f�W�J���̂��߃{�P�Ă��܂��c) �@���ʂ������ȕ����ł͂قƂ�ǐU��Ă��܂��A���ۂɌ𗬓d���𑪒肷��Ƃ���Ȋ����ł��B �@���O�^�C�v��LM3915N�͂����ւ�悭�U��Ă��܂��B �@�ΐ��\���Ȃ̂œ��͐M�������������͑傫���\�����A���͐M�����傫���Ȃ���Ɉ��k���ĕ\������܂����珬���ȐM���ł���R��LED������܂��B �@�u���ɂ��킹�ăs�J�s�J�����Ċ������v�Ƃ����A���Αf�l�x���I�ȃ��x�����[�^�[�ł��ˁB �@�����l�Ԃ̎��ɂ́A�����ȉ��̍��͂͂����芴���܂����A�傫�ȉ��ɂȂ�Ƒ傫�ȉ����m�̍��͓݊��ł��܂�悭�킩��Ȃ��A�Ƃ�������������A�����ȉ��̓r���r�����������đ傫�ȉ��ɂ͏��������Ƃ����ΐ��\���́u�������Ă��鉹�̑傫���v�Ɏ��������������̂Ŏ��ۂ�db�l�Ȃǂ�m��Ȃ��l�ɂ͂��ꂪ�ł��u���ɕ������鉹�ʁv�ɋ߂��\���ƂȂ�܂��B �@������L�b�g�ł̓��O�^�C�v��IC��I��ł���̂ł��傤�B �@������VU�^�C�v��LM3916N�ł́A�قڃ��j�A�^�C�v�Ɠ����\���ł��B �@�����̃R���p���[�^�̒萔���킸���ɈႤ�����ŁA�A�i���O���[�^�[�����j�A�Ƀh���C�u����db�ڐ���Ō���̂Ɠ������x�ł����Ǝv���킴�킴VU�Ή���LM3916N���g��Ȃ��Ă������悤�ȋC�����܂��B���̃V���[�Y���ł�LM3916N���������ł����B �@������VU�^�C�v�̕\���ł͂�͂萳����db�ڐ����LED��_�������Ă��邽�߁A�����ȉ��̎��ɂ͂قƂ��LED������܂���B�uLED���s�J�s�J���郌�x�����[�^�[���~�����I�v�Ƃ������ɂ́u������VU���[�^�[�v�ł͕�����Ȃ��ł��傤�B  �@���̋����̃L�b�g�ɂ͂P���_������A�uVU���[�^�[�p�̂Q�FLED��������t�����Ő������\���ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����ƂĂ��A���r���[�o�{�[�I�Ȏd�l�ł��B
�@���̋����̃L�b�g�ɂ͂P���_������A�uVU���[�^�[�p�̂Q�FLED��������t�����Ő������\���ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����ƂĂ��A���r���[�o�{�[�I�Ȏd�l�ł��B�@���̂܂�2�FLED������Ǝʐ^�̂悤�ɒ�x�����ŐԐF�ɓ_�����Ă��܂��Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ����x�����[�^�[�ɁB �@�����ƒ�x������ɂ��āA0db�ȏ��Ԃɂ��悤�Ƃ���ƉE���̎ʐ^�̂悤�Ɋ�̗�����LED���n���_�Â����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�����m�炸�ɕ\���Ƀn���_�Â�������ŋC�t������A�����Ȃ���20�����̃n���_���z�������LED���O�����ƂɂȂ�̂Œ��ӂ��Ă��������B �@���͎��O�ɏ����Ă����̂ŁA�e�X�g��ɂ͗��\������IC�\�P�b�g�����Ăǂ���̖ʂɂ�LED��t������悤�ɂ��������{�[�h�ɂ��Ďʐ^���B�e���Ă��܂��B�������IC���\�P�b�g�łR��ނ�IC�̕]�������̃{�[�h�ꖇ�ōs���Ă��܂��B �@�u2�FLED���g�p����ꍇ�́A��̗��ɂ��邩�A���[�h���ʼn�������LED�͕ʕt���ɂ��ĉ������v�������ł��B (�܂��A���̃L�b�g����IC�̕]���p�{�[�h�Ƃ����ʒu�t���Ȃ̂ł�����ł����ǁc) �@���̑��Z�����߂����炱��LM391xN�V���[�Y���g�������x�����[�^�[�L�b�g�̉��p�ȂǂŁu���l�^�W�v�̐V�L�����P�������Ǝv���Ă��܂������A���[�r�[�Ȃǂ����J���Ă��܂����̂ŋL���y�[�W�͖����ɂ��܂��傤�B �@�b�͉����Ɉ��܂������A�����k���uVU���[�^�[������v�Ƃ������Ȃ̂łP�S�z������܂��B �@����́wVU���[�^�[�Ƃ́A+4dBm�̐����g(1KHz)���������ꍇ��0VU���w���x�Ƃ������܂肪����A��������Ƃ���db�l�Ŗڐ��肪�U���Ă��Ȃ���VU���[�^�[�Ƃ͌Ăׂ܂����B(�����ƐF�X�Ɠ���K�肪����܂�) �@�ʂ����āA���[�^�[����肽���l���u0VU���߁v���ł��邾���̌v����E�g�`���U�@�Ȃǂ̃I�[�f�B�I�����@����������ł��邩�Ƃ������ł��B �@���ꂾ���͊ȒP�ȃe�X�^�[���������̒��x�ł͉����ł��܂���B(����Ȃ��db�l���v���e�X�^�[�Ƃ��Ȃ炢���̂ł���) �@�����u0VU���߁v���ł��Ȃ��̂ł���A��������[�^�[�͐�����VU���l�������Ă���̂ł͂Ȃ��u���l�͊Ԉ���Ă��ĒP���ɉ��̑傫���ɂ��킹�Đj���G���(�܂���LED���_������)�����̃��[�^�[�v�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�����������[�^�[��VU���[�^�[�ł͂Ȃ��u���x�����[�^�[�v�ƌĂт܂��B �@���x�����[�^�[�ł���A���ʂȂǂ̃��x����\�����邾���ł���Adb�l�Ȃǂ̍��ۓI�Ɍ��܂��Ă��鐔�l��\�����Ă���K�v���͂���܂���B�����܂ł���@��ɂ����Ă̐M�����x����傫�������������A��_���x���̐M�����H�Ȃǂ�\���E�m�F�ł���Ηǂ��̂ł��B �@��ŏ������A�i���O���[�^�[�p�ɓd�q��H(�A���v)������ă��[�^�[��U�点��ꍇ���A��҂�LED�����̏ꍇ�����͒i�ɔ��Œ��R���t���Ă��ē��͐M���ɑ��ĕ\�����ǂ����邩�̒��߂��ł��܂��B �@�u�ł��܂��v�Ə����Ɨǂ��悤�Ɍ����܂����A�t�Ɂu���̑����Ȃǂ��g���Ĕ��Œ��R���ǂꂾ���ΐ������\���ɂȂ�̂��v�Ƃ����������ł��Ȃ�������VU���[�^�[�ł͂Ȃ������̃��x�����[�^�[�ł��B �@�u�Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�v�Ƃ������_�ł����܂ł̌v�����Ȃɂ���������ł͖��������ł��̂ŁA����]��VU���[�^�[������y�ɍ��̂͂�����߂Ă����������ق����ǂ����Ǝv���܂��B �@���������x�����[�^�[�ł���A�L�b�g��ȒP�ȉ�H�ƃA�i���O���[�^�[�ō�邱�Ƃ͂ł��܂��̂ŁA�����������[�^�[���u�����ꂽ��ŐF�X�ƌ�������āA�����Ȃǂ��������Ă����{����VU���[�^�[�̐���ƌ����Ɏ��g�܂�Ă͂������ł��傤���B �@�P�ɕ\�����郌�x���ȊO�ɂ��A�������x��Ȃɂ���VU���[�^�[�ɂ͍��ۓI�Ȍ��܂肪��R����A���삷��͖̂{���ɑ�ςł���B �@�u�Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�v�Ƃ�������]���A����VU���[�^�[�Ƃ͂������������Ȏd�l�̕����Ƃ͒m�炸�A�I�[�f�B�I�p�̃��x�����[�^�[�̂��Ƃ�S���uVU���[�^�[�v�ƌĂ�ł��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B �@����Ȃ�K���Ƀ��[�^�[�ƃA���v�Ɛ������i�ł��A�L�b�g��LED���ł��Ȃ�ł��\���܂���ˁB ���Ԏ� 2009/7/2
|
|||||||||||||||||||||||
| �ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ | ||||||||||||||||||||||||
|
�����b�ɂȂ�܂��B�C�O���̃t���b�v�_�E�����j�^�[�t���̂k�d�c���[�������v�̉����̌��ł��B�h�A�A�����v���X�P�Q�u�ł̐v�ƂȂ��Ă��镨���}�C�i�X�ɂē��삳�������̂ł����A�ǂ����ǂ̗l�Ɍ���������ǂ����������炸�䑊�k�����Ă��������܂����B�ʐ^�̌f�ڕ��@������Ȃ����߁A���t�[�t�H�g�ɂ̂��܂����̂ł�������m�F���Ă��������Ȃ��ł��傤���Hhttp://photos.yahoo.co.jp/***** ��낵�����肢�������܂��B nao �l
|
||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�c�O�Ȃ��烄�t�[�t�H�g�ɂ́u���̃A���o���ɂ͌��݁A���������Ă��܂���B�v�Ƃ������Ŏʐ^�͌���܂��A�ʐ^�����Ȃ��Ă������Ԃ̓d�C��H�ł͊�b�I�Ȏ��ł悭���鎿��ł�������v�ł��B �@�����Ԃ̓d���i�ɂ�+12V�̓d����^���邱�Ƃœ��삷��u�v���X�R���g���[���v�ƁA�A�[�X�ɗ��Ƃ����Ƃœ��삷��u�}�C�i�X�R���g���[���v�̂Q��ނ�����܂��B �@�����������Ƃ���A�X�C�b�`�Ȃǂ�ʂ���+12V�Ɍq�����A�[�X�Ɍq�����̂ǂ��炩�œ��삵�āA�X�C�b�`OFF�ʼn����q���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��悤�ȍ��ɂȂ��Ă��܂��B �@�ł�����A�v���X�R���g���[���ƃ}�C�i�X�R���g���[�����t�]������ɂ́A�u+12V�Ɍq��������ԁv�Ɓu�A�[�X�Ɍq��������ԁv��ϊ����Ă��悭�A�l�X�ȓd�q��H�ȂǂŎ����ł��܂������m�����d�q��H�H��̋Z�p�������Ă��N�ł��ł����u�����[����g������H�v�����Љ�܂��B �@�܂��A���������p�r�Ɏg�p���邽�߂������ԗp�i�Ƃ����G�[��������u�����ԗp�����[���i�v���J�[�p�i�X�ȂǂŔ̔�����Ă��܂��B����g�p����S�Ƀ����[���ƈ��950�~���炢�ł��B �@�d�q���i�X�Ń����[���������ň��ň��50�~���炢�Ŕz���ނ܂Ŕ����Ă�200�`300�~�ōς݂܂����A�d�q���i�X�Ő��\��ޔ����Ă��郊���[�̒�����K��������I�яo������A�����[�ɂ���Ă͂ǂ̒[�q���ǂ̓���������̂������Ă��Ȃ�(�����Œ��ׂȂ���Ȃ�Ȃ�)�i�������̂őf�l�̕��ɂ͂����ߒv���܂���B �@�d�q���i�̒m���̖������̓G�[�����̎����ԗp�����[(�S�ɂ܂��͂T��)�����g�p���������B 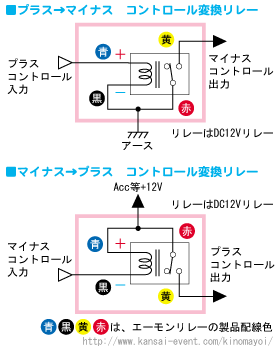 �@�u�v���X���}�C�i�X�v��+12V�̓��͂Ń����[�̃R�C���삳���A�ړ_���ŏo�͂��A�[�X�ɗ��Ƃ���H�ł��B
�@�u�v���X���}�C�i�X�v��+12V�̓��͂Ń����[�̃R�C���삳���A�ړ_���ŏo�͂��A�[�X�ɗ��Ƃ���H�ł��B�@�u�}�C�i�X���v���X�v�͓��͂��A�[�X�ɗ��������Ƀ����[�̃R�C���삳���A�ړ_����+12V���o�͂������H�ł��B �@����~�����̂͌�҂́u�}�C�i�X���v���X�v�ł�����A���̂悤�ɔz������Ί����ł��B �@�����u�G�[�����̂T�Ƀ����[�v���w�����ꂽ�甒���z��������܂����A����͎g�p���܂���̂Ŗ������Ă��������B(�ǂ����ɃV���[�g���Ȃ��悤�ɔz���̐�̓e�[�v�ōǂ��ł����܂��傤) ���Ԏ� 2009/7/1
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
���X�̂��ԓ��Ȃ�тɂ����A��ς��肪�Ƃ��������܂����B���t�[�t�H�g�g�������ƂȂ��A����J���������ߌ��鎖���ł��Ȃ������l�Ŏ��炢�����܂����B�����Ɍ��J�v���܂����̂ŁA�m�F�ł���Ǝv���܂��B�o����X�C�b�`����܂�Ȃǂ��猻�݂̕��𗘗p�������ƍl���Ă������̂ł����B ���ƂȂ��ł����A�k�d�c�̊�̉������ł������ȋC�����āA�A�B ����Ɠ������j�^�[�Ȃ̂ł����A�X�C�b�`�����邽�тɁw�v�b�x�Ƃ��w�v�`�b�x�Ƃ����m�C�Y������̂́A���P�̕��@�Ȃǂ�����̂Ȃ̂ł��傤���H �肪�����Ō��\�ł��̂ŁA�܂����m�b������ł��܂���ł��傤���H nao �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����������p�����ł���A�ŏ����炻�̂悤�ɂ����������Ȃ���ŏ��̕��͂��Ɓu���������v�Ƃ������ŁA�ԂƑ��u�̊Ԃ̌������ǂ��ύX������}�C�i�X�R���g���[���œ����悤�ɂȂ�̂��̂�����Ƃ������܂���B �@���u�̒��g���ǂ���������Ƃ������b�ɂ͌����܂���ł����̂ŁA�ʐ^�������Ȃ��Ă��ǂ̎Ԃł��A�ǂ̑��u�ł��Ώ��ł��鎩���Ԃ��d�C�����̊�{�̂��b�Ƃ��Ď~�߂ĉ����Ă��������܂����B �@�ʐ^����������A���̐��i�̉�H�v��ňꕔ�D�ɗ����Ȃ�����������܂����A�������茳�ɖ����ׂɑ�����ł�������͂��������v���Ɗ��肫���āA�ł��ȒP�ɏo�������ȉ�����i�����`�����܂��B 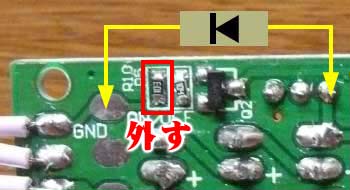 �@��͂Q������܂��̂ł��ꂼ��ɉ��H���K�v�ł��B �@���X��4013 D-FF�Ŋ��̃v�b�V���X�C�b�`�ɂ��ON/OFF����ƁA�O������̃v���X�R���g���[����LED�h���C�o�p�̃g�����W�X�^��ON/OFF���Ă����H�ł����A���̃g�����W�X�^�ɗ��炸�ɊO���X�C�b�`�Œ���(�Ƃ͂����_�C�I�[�h��ʂ���)LED��GND�ɗ��Ƃ��܂��B �@�����͂��ꂾ���ł��B �@�{���͂��̎ʐ^�̐^������̃v���X�R���g���[���Ő��䂵�Ă���g�����W�X�^�܂��������肽�����ł����A�`�b�v���i�̂Ƃ�͂�����n���_�Â��Ȃǂ͓����������܂���̂ŁA�n���_�Â������₷�����ȏꏊ�ւ̃_�C�I�[�h������邾���ɗ��߂Ă����܂��B �@���A�ʐ^��LED����݂̂ł����̂łR�{�̔z���̂����R���g���[����(���F)���ǂ��ɂǂ̂悤�Ɍq�����Ă��邩�s���ł��̂ŁA���ꂪ�h�A�X�C�b�`�Ƃ����q�����Ă���Ƃ����O��ł̉����ł��B�������̉����Ɍq�����Ă����肵���Ƃ��̓���̕ۏ͂���܂���B���̉����ŋ@�킪�̏Ⴕ�Ă��ӔC�͕������˂܂��B �@�X�s�[�J�[���u�u�c�b�v�Ɩ錏�ł����A�P��d���^�A���v���g�p�����@��ł͂悭���邱�ƂŁA�A���v��H���̂������������ʼn������Ȃ��Ɩ����ł��B �@�{�����[�����O�ɍi���Ă��Ă����j�^�[�d����ON�Łu�u�c�b�v�Ɩ�Ǝv���܂��B �@��̎ʐ^�������Ă���������x�ł͑Ώ��ł��܂���̂ŁA���̑Ή��͒v�����˂܂��B ���Ԏ� 2009/7/2
|
|||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�A�h�o�C�X��ς��肪�Ƃ��������܂����B�����s���������ւ炢�����܂����B �@�͂��߂ɐԍ����̐����Ȃ���Ă���ق���NO.1�Ƃ��āA�c���NO.2�ƌĂ��Ă��������܂��B �@�A�h�o�C�X�����Ƃɂk�d�c�H��Ɏg�p���悤�ƍw�����Ă��������_�C�I�[�h�w1N4007�x��NO.1�ANO.2���ɒlj��������ʂł����A�Ԑ����v���X�ցA�������}�C�i�X�ڑ����܂��Ɨ����_�����X�C�b�`�������Ă��������܂���B���̏�Ԃɉ��F�����}�C�i�X�ɐڑ����܂���NO.1�͂��̂܂ܓ_�����X�C�b�`�������܂��ANO.2�͏������܂����A�X�C�b�`�œ��ł���l�ɂȂ�܂����B �@��]�͐Ԑ����v���X�ցA�������}�C�i�X�ڑ��������ɃX�C�b�`�ł��ꂼ�ꂪ�P�Ƃœ����ł��A�������}�C�i�X�ɐڑ��������ɓ_������l�ɂ������ƍl���Ă���܂��B �@���t�[�t�H�g�̎ʐ^�̓_�u���N���b�N�Ŋg�債�ĕ��i���H�����ʏo����悤�ɍ��𑜓x�Ōf�ڂ��Ă���܂��B �@�ʐ^�ŕ�����ɂ����\���k�d�c���̃g�����W�X�^�́w�r�W�T�T�O�x�ł��B�����̂P�S�{�̑������镔�i�́w�g�d�e�S�O�P�R�a�s�A�k�W�`�T�r�O�P�Q�A�t���f�O�W�P�V�V�A�m�w�o�x�ł��B �@�����̓}�C�i�X�R���g���[���̃h�A�X�C�b�`�Ƃ����q���悤�Ƃ��Ă���܂��B �@�Z�p�I�ɂ́A�ԗ���̃`�b�v�k�d�c�w2012�x�̎��O���A��t�̌o��������܂��B �@�H��W�͑唼����܂��B �@�X�C�b�`���u�u�c�b�v�Ɩ錏�ł����A�m���Ƀ{�����[�����O�ɍi���Ă��Ă����j�^�[�d����ON�Łu�u�c�b�v�Ɩ�܂��B �@�A�i���O�s�u�������ɉ��x�����Ȃ�A���̓s�x��C�ɂȂ邽�ߑ��k�����Ă��������܂����B���Ȃ��ςȕ��̂悤�ł��̂ł�����߂܂��B �@�ȂɂԂ�A���k��낵�����肢�������܂��B nao �l
|
|||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����ł́A�����R10(10K)�����O���Ă��������B �@�d������ꂽ���ɓ_�������ςȂ��ɂȂ�̂́A�lj������_�C�I�[�h���o�R���ĊO�����͂]������g�����W�X�^(�\�ʎ���)�������Ă��܂��Ă���悤�ł��B �@�Q�̃��j�b�g�œ��삪�قȂ�͕̂s�v�c�ł��BR10���O���Ă������N����悤�ł����炨�m�点���������B �@�ڂ��Ă���IC��4013�ł��邱��(���̂܂܌^�Ԃ������܂�)��A�傫�ȃg�����W�X�^��S8550�ł��낤��(����EBC�z�u��PNP���ƒ��́c)�͎ʐ^�����Ă킩���Ă��܂��B �@���𑜓x�̎ʐ^���f�ڂ��Ē����Ă��肪�Ƃ��������܂��B ���Ԏ� 2009/7/4
|
|||||||||||||||||||||||
|
����ȑO�̓����͂����灨 [2009�N�O���̉ߋ����O]
|
||||||||||||||||||||||||
|
�T���₷���ړI�E��H�̃W�������ʈꗗ�͂����灨 [�W�������ʈꗗ]
�悭�g�����i�́u���̐}�v�͂����灨 [�悭�g�����i�́u���̐}�v]
|
||||||||||||||||||||||||
|
(C) �u�C�̖����v�^Kansai-Event.com
�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������
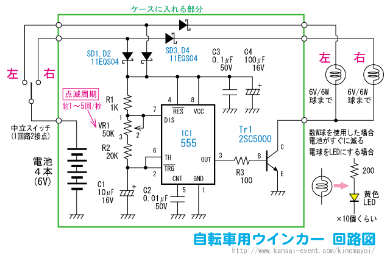
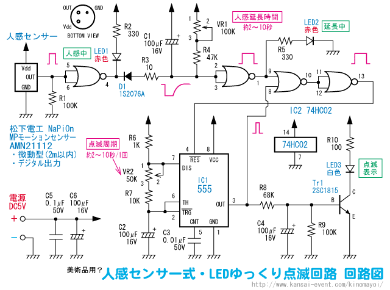
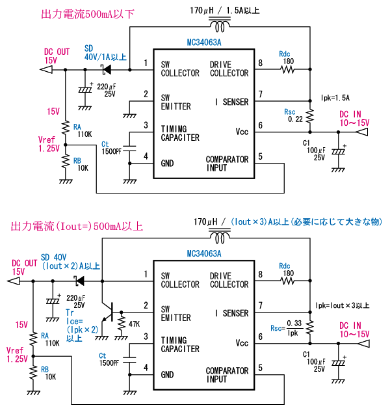
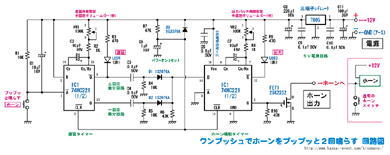

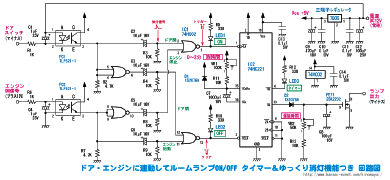

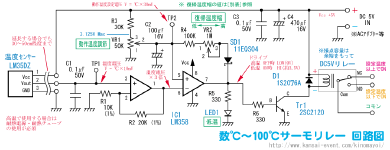
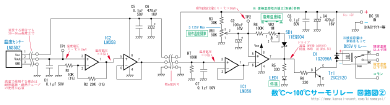
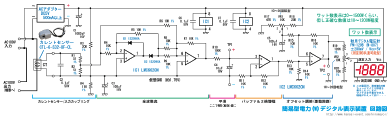










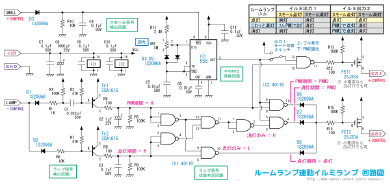
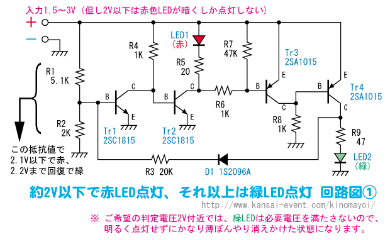
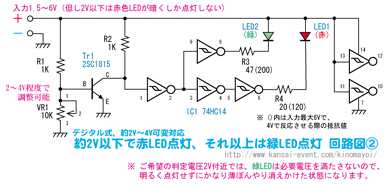
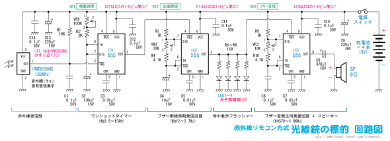
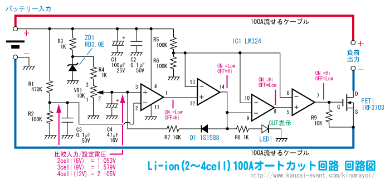
 �u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�
�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�