| ||||||||||
|
|
| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |
��H�E�f���L�E����
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���� ���̃y�[�W��2013�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B
�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B
�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B
|
�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |
�y�ꗗ�z
�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�
|
��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |
|
�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
���� ���̃y�[�W��2013�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
| �艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H | |||
|
�o�C���^���X�C�b�`�쓮�m�F��H ���������b�ɂȂ�܂��B �d���Ŋ��m��̍쓮�_���i���h�ݔ��_���j�����Ă����ł����A�艷�����m��́A�o�C���^���X�C�b�`�ɂȂ��Ă��āA�쓮����܂Ŏ��Ԃ�������܂��B������i�g�j�|�R)�ŁA���悻�P�T�b����S�O�b�قǁB�}���V�����Ȃǂ̋����ւ�����܂���ƁA�쓮����Ɗ��m��̐ԐF�k�d�c���_������̂ł����A������ŕ�����ׁA���A���m�킩�玎������O���Ċm�F���K�v�ŁA�����҂���s�Ǖi�ł����H�Ȃ�Ď��₳��邱�Ƃ���������܂��B���������Â��ł���A���m��̃o�C���^���X�C�b�`�������ƁA�w�J�`�b�x�Ɖ������āA��������O���Ȃ��Ă��i�ԐF�k�d�c�_�������Ȃ��Ă��j�쓮�������Ƃ��m�F�ł����ł����A�܂�肪���邳���ꍇ�Ȃǂ́A�w�J�`�b�x�̉����������܂���B�}���V�����Ɍ��炸�A�������̋@�B���ȂǁB�Â����m��ł́A�ԐF�k�d�c���Ȃ����̂�����A�쓮�m�F����ςł��B �����łȂ�ł����A������Ɏ�t�āA�o�C���^���X�C�b�`�̍쓮���w�J�`�b�x���E���A�����̎茳�ŕ\���ł��鑕�u����肽���̂ł����A�v�����܂���B�}�C�N�ł́A���̉����E���Ă��܂����A�ȑO���₳���Ē������������P�O�O�~���C�^�[�̓d���g�̊�����g����Ȃ�Ă��l�����̂ł����A�o�C���^���̍쓮�ł́A�d���g�Ȃ�ďo�ĂȂ��Ǝv���܂����A����������H������܂�����X�������肢�v���܂��B ��� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
(1) �U���Z���T�[�����m��ɓ\��t���� �@�u�U���Z���T�[�v�͎��]�ԃ����v�p�̃o�l���݂����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u���K���X��ǂȂǂɓ\��t���āA����ȐU�������m�����v�悤�ȍ����x�Z���T�[�ŁB �@�����āA�Z���T�[���U�����E�������ǂ������茳�̓d�q��H�Ŕ��ʂ��āALED��_��������Ȃ�u�U�[��炷�Ȃ�B �@�A���A�Z���T�[��\��t���銴�m���ӂ́A�����@�̃J�b�v�̒���100�����炢�܂ł͉��x���オ�������A�u����ȍ�����Ԃł����Ȃ��U���Z���T�[�v���w�����Ďg�����������ł��ˁB �@�c�O�Ȃ���A�����������i�͋�̓I�Ɍ^�ԂȂǂ͒m��܂��A������Ǝ莝���ɂ͖����̂ł�����ʼn�H�̐v����ۂɓ����̂��̃e�X�g���ł��܂���B (2) �}�C�N�����m��ɓ\��t���� �@�O�̑��������܂�e�����Ȃ��悤�A�}�C�N�����m��ɓ\��t���āA���ꂩ�玎���@�̃J�b�v�ŕ����ΊO�̑�������͂�����x�Ւf����܂�����A�o�C���^���́u�J�`�b�v�Ƃ������̓}�C�N�ŏE�����Ȃ��ł����H �@�u�O�̉������܂����Ȃ��v�u�o�C���^���̉��͂������肵�Ă����v�̂ł���A�u�ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m)�v�ł����Ǝv���̂ł����A�������ł����H �@�����A��������m��ɓ\��t����}�C�N�������ł����Ȃ��^�C�v���K�v�ŁA�G���N�g���b�g�R���f���T�}�C�N�̒��ɂ�70�`80�����x�܂łȂ�ς����鍂���^������悤�Ȃ̂ŁA�����������i���g������\��������܂���B �@�ʏ�̐������ł̑������炢�Ȃ�A������g�t�B���^�[�Ȃǂ�����ĂȂ�ׂ����ʂ̉��ɂ͔������ɂ�������Ƃ��E�E�E�B �@�ł��H��̋@�B���Ȃ�ăo�C���^���̓��쉹�Ɠ����V���b�N������ł�����A�t�B���^�[�ł��܂����ˁB �@�c�O�Ȃ���A�����Ή��̃}�C�N�Ƃ��E�E�E�����������i�͂�����Ǝ莝���ɂ͖����̂ŁA������ʼn�H�̐v����ۂɓ����̂��̃e�X�g���ł��܂���B (3) �}�C�N���J�b�v�̊O�ɓ\��t���A���ŕ����I �@�ύ����^�̃}�C�N�łȂ��Ă��悳�����ł����A�܂��ł���Αύ����^�̃}�C�N���J�b�v�ɓ\��t���āA���̃}�C�N�́u100�~�V���b�v�́w�ڂ��[�ނ����Ձx�v�ɂȂ��A���̏o�͂��C���z���ŕ��������ł��ˁB �� �ڂ��[�ނ����Ղɒ��ڃ}�C�N���q�������͂���܂��A����͈ٗl�ɑ������������̂ł��̂܂܃}�C�N���x���̉��ł����イ�Ԃ�C���z���ŕ������鉹�ʂɑ������Ă����Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤�ˁH �@�u�����r���t�B���^�[�v�u�o�C���^�����̓���@�\�v���l�Ԃ̎��Ɣ]�ɔC�������ƂŁA�d�q��H�͓��ɂȂɂ�������Ƃ͍s�Ȃ��܂���B �@�����ӂ��m��̉����Ȃ�Ă���l�Ԃł���A�J�b�v�ɓ\��t�����}�C�N�̏E���u�J�b�v�̒��̃J�`�b�Ƃ������v�͈ꔭ�ŕ�����������Ǝv���܂���B (4) ���m��̃R�[�h���O���āA�u���m�킪�������\�����鑕�u�v�Ɍq�� �@���m��̒��̐ڑ��R�l�N�^�́A�e���[�J�[���i���ł͋��ʂł��傤����A����ɂ��킹�āu�o�C���^���X�C�b�`��ON������u�U�[���邾���̑��u�v�Ƃ���p�ӂ��āA�V�䂩�痈�Ă���R�[�h���O���Ă���Ɛڑ����Ċ��m��͓V��ɉ��u�����A�����@�Œg�߂�ł��J���^���ŁA�m���Ɂu���m�������H�v�ׂ���Ǝv���̂ł����E�E�E�B �@�����������W�Ȃ��B ���Ԏ� 2013/5/13
|
||
| ���e 5/14 |
�����̉��肪�Ƃ��������܂��B �P�`�S�܂ł��낢��l���Ē����܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B �����I�ɂ́A�Q�Ԃ̈Ăł����邩�ȂƂ������܂����B�}���V�����̋����ł́A�@�B���قǂ��邳���Ȃ��̂ŁA�b�����A�s�u���Ȃǂ��Ȃ���Ȃ�Ƃ��Ȃ肻���Ȋ����ł��B���̍āA�@�B���g�p�́A���Ȃ����Ƃɂ��܂��B �u�ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m)�v���������Ă���肽���Ǝv���܂��B �����̉��肪�Ƃ��������܂����B ��� �l
|
||
| �e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� | |||
|
�d�q�H��o���͉�H�}�����Ȃ��猈�߂�ꂽ���i���đg�ݗ��Ă���x�ł��B�������̑�^�̐����\���@���쐬�������ł��B�������Ƃ����������ł��B��낵�����肢���܂��B �V���C�z���C�g �l
|
|||
| ���e |
������e�����Ă��������܂����B������^�\���@�̌��ł��B �d��24V�i�D�̓d���j�C�����Q�P�^�C�P�����̑傫�����O�T���悩�猩����傫���ł��BLED�C7�Z�O��H���ȈՂȂق��������ł��B�{�g�o�̃��[���𗝉����ĂȂ��Ă��݂܂���B��̃e���L�[�œ��\���ł�����̂��ق����ł��B�D�̃u���b�W����D��ɂ���l�֓��̐�����`������̂ŁC�������𐔕b�����`������̂ŁC2��ڂ̓��͎��e���L�[�������ƂP��ڂɓ��͂������l�̓N���A�����Ƃ����ł��B��ʂŔ̔������Ă�����̂�����܂���B ��낵�����肢�܂��B���s���ȓ_������܂�����C�������E��H�}�쐬�O�ɕs���_�������Ă���������Ǝv���܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���Ԏ� |
>�P�����̑傫�����O�T���悩�猩����傫���ł��B �@�E�E�E�Ƌ��܂��Ă��A�T���悩�猩����͖̂ڂ̗ǂ��l�Ȃ�킸�����Z���`�̕\���@�ł����ʂł���ł��傤���A�ڂ̈����l�Ȃ琔�\�Z���`�����炢�̑�^�\���@���K�v�ɂȂ�܂���ˁH �@��̓I�ɁA�ǂꂭ�炢�̑傫���̕\���@�����l���ɂȂ��Ă���̂ł��傤�H �@�����P���̍������Z���`���[�g���ł���������������Ƃ��肪�����ł��B �@���Ȃ݂ɁA�s�̕i�̂V�Z�OLED�ł� �E�u��^�ԐF�V�Z�O�v������2.54cm �d�d [�H����] �E�u����^�ԐF16�Z�O�v������5.68cm �d�d [�H����] ���炢�Ȃ�A�ǂ��ł������Ă���Ǝv���܂��B �@���f�W�b�g�̓X���ňٍʂ�����Ă��邪������� �E�u�ቿ�i�I��^7�Z�O�����gLED�v������12.7cm �d�d [�f�W�b�g�u���O] ��������12.7cm������̂ŁA���Ԃ�T���[�g�����炢����Ă��N�ł�������Ǝv���܂��B (������������A�������Ă���i�͂��̃u���O�L���̕i����X�ɐV�����Ȃ��Ă��邩���H) �@���ɂ��T���A12.7cm(�T�C���`�^)���炢�ł����瑼�i����l�b�g�ʔ̂Ȃǂł݂��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B��������]�̕i������Ύw�肵�Ă���������A����LED�p�ɂł��܂����A�w�肪������f�W�b�g��12.7cm�^������ł̐v�ɂȂ�܂����B �@�܂��A�u���삷��ꏊ�v�Ɓu�\���@��u���ꏊ�v���ǂ̂��炢����Ă���̂��H �@�����܂ň�̌^�ŁA�\���@�̗������炢�Ƀe���L�[���t���Ă��āA��H�������������P�[�X���Ɏ��܂��Ă���̂��B �@��H�͕\���@�̒��ɓ����Ă��āA�e���L�[�������\�Z���`�ȓ����炢�ŃP�[�u���Őڑ�����Ă���̂��B �@��H�ƃe���L�[�͂P�̃P�[�X�ɓ����Ă��āA�\���@���������[�g�����炢�͗��ꂽ�ʂ̂Ƃ���ɒu�������̂��H �@�ȂǁA�ڒn���@�₻�̋����ɂ���ẮA�ʓ|�Ȏ��ɂȂ�ꍇ���l�����܂��B >�������𐔕b�����`������̂� �@�Ƃ������́A���Ȃ葁���y�[�X��������ς����K�v�����鑕�u�̂悤�ł����A������ƂĂ������_���Ȑ��l�Ȃ̂ł����H �@�u�Q�T�v�c�u�Q�Q�v�c�u�P�X�v�c�u�P�T�v�c�u�P�Q�v�c �@�݂����ȁH �@�悭����ȈՌ^�̃f�W�^�������\���@�E�����̎����̃X�R�A�\���@�݂����ɁuUP�v�uDOWN�v�{�^�����C�ӂ̃^�C�~���O���������P���グ��������悤�Ȏg�����ł͂��܂��䂩�Ȃ��g�����Ȃ̂ł��傤���H �@��̓I�ɁA�D�̏�łǂ��������V�`���G�[�V�����Ŏg�����̂Ȃ̂����A�킩��Ɛv���₷���Ȃ�܂��B >2��ڂ̓��͎��e���L�[�������ƂP��ڂɓ��͂������l�̓N���A�����Ƃ����ł� �@�Ƃ����̂́A���Ƃ��ΐ�Ɂu�Q�T�v�Ƃ����\�����o�Ă������Ɏ��Ɂu�P�W�v��\�������悤�Ƃ���Ƃ��ɂ́A �@�u�Q�T�v��[�P]�L�[���������u�Q�P�v�ɂȂ�A������[�W]�L�[���������u�P�W�v�ɂȂ�A�Ƃ����菇�ł����H �� �u�Q�v�͂��̌��͖��\���ł� �@����Ƃ��A�u�Q�T�v��[�P]�L�[���������U�\���͏����āu�Q�Q�v�ɂȂ�A������[�W]�L�[���������p�b�ƂQ���̕\���u�P�W�v�ɂȂ�B �@�Ƃ������ɁA��U��������悤�Ȍ`�ł����H �@�O�҂ł����҂ł���A�P�������̐�����\���������Ǝv�������̑���ɂ͍���܂��H �@�P���̐��l��\�����鎞�ɂ�[�O][�S]�݂����ɕK���\�̈ʂɁu�O�v�������Ƃ������[���H �@����Ƃ��A�P�������̏ꍇ��[�S][����]�݂����ɁA�����Ƃ͕ʂɁu�����v�L�[��p�ӂ��Ă����āA�u�������͂͏I������̂ŁA���ɃL�[�������ꂽ���ɂ͂���͎��̐��l���ƔF���������v�Ƃ����ӂ��ȏ����������̂ł����H �@���܂̂Ƃ���A�����܂��Ɂu�e���L�[�������ĂQ���̐�����\�����鑕�u����肽���v�Ƃ������v�]�����͓`����Ă��Ă��܂����A�ʂ����Ă�����u�ǂ��^�p(����)����̂��H�v�̃j���A���X���`����Ă��܂���B �@�\�������܂��A�����܂łɏo������ɂ������肦�܂��H �@����ƁA���̂��v�]�ł͂���Ȃ��IC���������Ȃ�A���܂ŐF�X�Ɖ�H�}����Ă��܂������A���̌�Ɂu���܂����I�v�u�������܂����I�v�Ƃ���������ؖ����Ȃ�p�[�^���̉�H�E���i���̋K�͂��Ǝv���܂��B (�܂��܂��Q���Ȃ̂ŕ��i�͏��Ȃ��ق��ł��傤�A���ꂪ�W���Ƃ�����ꂽ��A�z���Ƃ��n���_�Â��Ƃ��Ŋm���Ɏ��˂܂��B�����������Ɓu�����}�C�R���ł���ĉ������v�Ƃ������x���ł�) >�d�q�H��o���͉�H�}�����Ȃ��猈�߂�ꂽ���i���đg�ݗ��Ă���x�ł��B �@�Ƃ̎��ł��̂ŁA�����s�����N���Ă��܂����A���v�ł��傤���H ���Ԏ� 2013/5/3
|
||
| ���e |
�������肪�Ƃ��������܂��B�܂��C�{�g�o�Ɏ����̕��ʂ��f�ڂ��ꊴ�����܂����B���������ł͉�H���l�����Ȃ��̂Ŗ{�g�o�̉�H�����̂܂ܗ��p�����Ă��������Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂��B�������������܂���������ɂ��Ăł��B�f�l�Ȃ�Ɋ�]�������܂����B��낵�����肢�������܂��B >�w�肪������f�W�b�g��12.7cm�^������ł̐v�ɂȂ�܂����B �u�ቿ�i�I��^7�Z�O�����gLED�v������12.7cm [�f�W�b�g�u���O]�ł��肢���܂��B >�u���삷��ꏊ�v�Ɓu�\���@��u���ꏊ�v���ǂ̂��炢����Ă���̂��H ��H�ƃe���L�[�͈�̃P�[�X�ɓ����Ă��ĕ\���@�����P�����炢���ꂽ�ʂ̂Ƃ���ɒu�������ł��B >����͂ƂĂ������_���Ȑ��l�Ȃ̂ł����H �����_���ł��B�{�\���@�͊C��i�D���j�Ŏg�������āC�u�C��̃|�C���g���v�C�u���[�v���̓`�B���Ɠ��e�ɂ���ĐF�X�Ȏg���������܂��B���̐������u���v���u���[�v���܂ł͕\������K�v�͂���܂���B�V�`���G�[�V�����ł����C����ꏊ�͑D�u���b�W���ŁC�D�̐�[�ɂ���l�֓��̐�����`���������̂ł��B�\���@�̓u���b�W�̃t�����g�K���X���ʂőD��Ɍ����Đݒu���܂��B����҂ɂ͕\�����ꂽ���l������Ȃ������C�����Ɖ���ł��܂��e���L�[���_�C�������e���L�[���i���݂���̂��H�ł����j�ő���҂ɂ����l�����������ق��������ł��B��o�����[���ᔽ�ł��݂܂���B�D�ɂ̓}�C�N�E�X�s�[�J�[������܂����C�����ԈႢ�������邱�Ƃ������̂ł��B >2��ڂ̓��͎��e���L�[�������ƂP��ڂɓ��͂������l�̓N���A�����Ƃ����ł��B ����҂���\���@�ɕ\�����ꂽ���l�͌��������l���m�F�ł��Ȃ������C����͖h�~�̂��߂Ǝv���A�N���A�����ق��������̂��Ǝv���܂������C�O�q�̂悤�ɉ����Ɖ���ł��܂��e���L�[���_�C�������e���L�[�ɂ�葀��҂����l���m�F�ł�����́u�N���A�v�͕K�v����܂���B����ł��܂��e���L�[��_�C�������e���L�[�͎��݂���̂��킩�Ȃ��̂ł����B����͖h�~�ŕ��i�������Ȃ���H����]���܂��B �f�l�̂����ɐF�X�Ɨv�]�������čς݂܂���B�ǂ�����낵�����肢�������܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���e |
���т��т��݂܂���B����̒NjL�ł��B ���l���̂��߁C���ރe���L�[��_�C�������e���L�[�i���݂��邩�킩��܂��j���ꌅ�Ɉ�̌v�Q���������Ă���������Ǝg�������������܂��B��낵�����肢�������܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���������肪�Ƃ��������܂��B�ǂ��łǂ̂悤�Ɏg���̂��͂��������킩��܂����B >���ރe���L�[��_�C�������e���L�[ �@���ރe���L�[�Ƃ����͎̂��݂���Ζʔ����p�[�c���Ǝv���܂����A���������p�[�c�͑��݂��܂���B �@�ǂꂩ�L�[�����������O�ɉ����ĉ���ł����L�[�g�b�v�����ɖ߂��̂ɂ́A�@�B�I�ȃ��b�N�E�����@�\���K�v�Ȃ̂ŁA���ꂪ10��(�ȏ�)������ł��������Ȃ�ʓ|�ȋ@�B�ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�܂��A�d��ȂǓd�q�v�Z�@�����������O�́A�@�B���v�Z�@��W�X�^�[�ɂ͂������������������������{�^����������������ł����킯�ł����E�E�E�B �@�_�C�������e���L�[�Ƃ����̂��A����̖ړI�Ŏg�������ȕ��ł͂�����Ƃ��������p�[�c�͌�����������܂���B �@�u�Đ�����ݒ�ł���X�C�b�`�v�͊m���ɁA���邱�Ƃ͂����ł��B 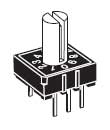 �@���Ƃ��A�I�������́u���[�^���[�E�f�B�b�v�X�C�b�`�v�V���[�Y�B
�@���Ƃ��A�I�������́u���[�^���[�E�f�B�b�v�X�C�b�`�v�V���[�Y�B�@�E�}�̂悤�ɃX�C�b�`�{�̂���]���̃c�}�~���t���ĂāA��0�`9(�܂���0�`F��16�i��)�̔C�ӂ̐������Q�i���R�[�h�Őړ_��ON�܂���OFF���܂��B �@�X�C�b�`����P���ɑΉ�����̂ŁA�����ڂ�������킩��₷���ł��B �@�����E�E�E�X�C�b�`�̃T�C�Y���Pcm�p���炢�ƒ����^�ł��B �@����͌��X����������イ������ς���p�r�ł͖����A���Ȃǂɂ����������ݒ�ȂǁA��U�ݒ肵����ӂ���͕ύX���Ȃ��g�����̃X�C�b�`�ł��B  �@�܂��A�u�T�����[�^���[�X�C�b�`�v(�T���͐����̈Ӗ�)�Ƃ����A���삷��l�ԂɂƂ��ĂƂĂ��킩��₷�������ݒ�X�C�b�`������܂��B
�@�܂��A�u�T�����[�^���[�X�C�b�`�v(�T���͐����̈Ӗ�)�Ƃ����A���삷��l�ԂɂƂ��ĂƂĂ��킩��₷�������ݒ�X�C�b�`������܂��B�@���Ƃ����I�������́u�T�����[�^���X�C�b�` �v�V���[�Y�ȂǁB �@�����̑��̒��ɐ������\������Ă��āA�㉺�́u�{�v�u�|�v�{�^���������ƒ��̉�]����]���Đ������ς��܂��B �@�ړ_�͂�͂��Q�i���̐ړ_�Œ��ڐ��l�f�[�^��ؑ�/�o�͂ł��܂��B �@�T�����[�^���[�X�C�b�`���P���ň�̕��i�ŁA�ʐ^�̂悤�ɂS���Ŏg���ɂ��p�`���I�Ƃ͂ߍ���ŘA�����Ďg���܂��B�ʐ^�̒ʂ荶�E�̒[�ɂ͂߂鉻�ϔ�(�p�l������̔����h�~�p)������܂��B �@�����E�E�E������X�C�b�`�̃T�C�Y���c�Rcm���炢�Ə��^�ł��B �@������@��̃p�l���ɂƂ���āA���l��ݒ肵�āA�ő��ɕύX�͂��Ȃ��p�r�Ŏg�p������̂ł��B �@�ꉞ�A�Rcm���炢�Ȃ̂Ŏw�ő��삷��̂͗e�ՂȂ��߁A�����ė��������Đ��̃I�y���[�^�[���茳�̑���Ղő��삷��̂ŗǂ��̂Ȃ�A���̃}�C�R����p�\�R�������ɂȂ�O�́ATV�̃N�C�Y�ԑg�̓��_�\�����V�Z�O�̐����ݒ�p�Ȃǂɂ��g���Ă��܂��B �@����̂���]�̑��u�ɂƂĂ��ǂ����Ă��܂��ˁB �@�ł����Ԃ�A�D�̃u���b�W�Łu�����_���Ȑ������A���b�������v�Ƃ����g�����ł́A�����̕ύX���ώG�ɂȂ�܂����A�������đ��삵�h���Ǝv���܂��B �@����ŁE�E�E�A�h���D�̃u���b�W�ŁA�����Ă���l�����삵�Ă��A�m���ɐ�����I�ׂ�A��]���̃X�C�b�`�ƂȂ�ƁA�ƂĂ���ʓI�ȁu���[�^���[�X�C�b�`�v�ɗ��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H  �@���Ƃ��A�H���Ŕ����Ă��郍�[�^���[�X�C�b�`���̂����u�P��H12�ړ_���[�^���[�X�C�b�`�v(�E�ʐ^)�̂悤�Ȃ��̂ł��B
�@���Ƃ��A�H���Ŕ����Ă��郍�[�^���[�X�C�b�`���̂����u�P��H12�ړ_���[�^���[�X�C�b�`�v(�E�ʐ^)�̂悤�Ȃ��̂ł��B�@������]������(���̃X�C�b�`�̏ꍇ��)12�̐ړ_���ւ���X�C�b�`�ɂȂ�܂��B �@����K�v�Ȑ�����0�`9��10�E10�ړ_�ł����A�X�C�b�`�̂ق���12�ړ_�Ȃ̂łQ�ړ_�]��܂����A�u0�v��]���Ɋ��蓖�ĂĂ����Ƃ��u0FF(���\��)�v�ȂǂɊ��蓖�Ă邱�Ƃ��ł��܂��B �@�܂��A��̐����ɂȂ�܂����AIC�Ȃǂ��g�킸�Ɂu�_�C�I�[�h�}�g���N�X�v�ŕ\�����������߂��H�������@�ɂ����ꍇ�A���̗]�����Q�ړ_���g�����}�C�i�X�L����A�A���t�@�x�b�g�Ȃlj����C�ӂ̂Q������\�������邱�Ƃ��ł���悤�ȋ@�\���g�ݍ��߂܂��B �@���Ƃ��A�u��ƏI���v���Ӗ�����A���t�@�x�b�g�́u�d�v�Ƃ��E�E�E�B �@����͓��ɕK�v�ł͖����Ƌ��Ă���u�|�C���gNo.�v�u���[�v�Ȃlj��炩�̃A���t�@�x�b�g��L���ŕ\�����邽�߂̌��������P���₵�Ă݂�̂��ʔ�����������܂���B(����͓��ɂ����������͖̂����̕����ł����Ǝv���܂�) �@�H���Ŕ����邻�̏��i�́A�w�ő��삵�₷��(�܂݂₷������)�c�}�~���Z�b�g�ɂȂ��Ă��܂�����A�h���D��ł��m���ɑ��삪�ł���Ǝv���܂��B �@���āA�����ł�����Ƙb��ς��āE�E�E >����҂���\���@�ɕ\�����ꂽ���l�͌��������l���m�F�ł��Ȃ����� �@�Ƌ��Ă��܂����A����Ȏg���ɂ������u�̉�H�}�͒������Ȃ��̂ŁA�ŏ������茳�ɑ����(�e���L�[)�A�\���Ղ͊O�����Ƃ����������ʂ̊O�̐l�Ɍ������\���@������]���Ɗm�F�ł���A���R�u�茳�̑���Ղɂ��V�Z�OLED�������āA���쒆�ł������͊m�F�ł����v��H�������ɂ���܂���B �@�����́u�e���L�[���v�u�傫�ȂV�Z�OLED�Q�����v�Ƃ������v�]���� 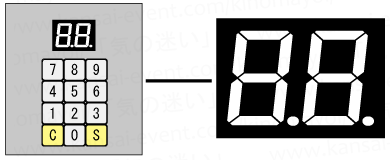 �@�lj��̂��v�]�Łu(�X�C�b�`��)�ꌅ�Ɉ�̌v�Q���v�Ƃ����V��o�܂����̂ŁA�\�����������āE�E�E�B �w���[�^���[�X�C�b�`���Q�g���āA�_�C���N�g(�@�B��)�ɐ��l��I�ԕ����x 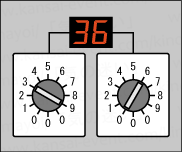 �@���̂悤�ȑ���Ղ͂������ł��傤���H
�@���̂悤�ȑ���Ղ͂������ł��傤���H�@�����̑I���͂ǂȂ��ł������I�ɍs�Ȃ��A�ԈႢ������܂���B �@�܂��A���[�^���[�X�C�b�`���g���ꍇ�ɂ͐�ɂ������ӂ�܂������A���W�b�NIC�͈���g�킸�A(��ʂ�)�_�C�I�[�h�����ōς��Ƃ�������قǓ�Փx�̍����Ȃ���H�ł��݂܂��B �@��ʂ̃_�C�I�[�h���g�����@���ƁA������0�`9�ȊO�ɂ��ȒP�ȃA���t�@�x�b�g�Ȃǂ��\�����邱�Ƃ��ł��܂��B(�]��Q�̐ړ_�𗘗p) �� �������A�_�C�I�[�h�͐��\�K�v�ł��̂ŁA�n���_�Â�����ӏ��͌��\����܂��B �@�܂��A��ʂ̃_�C�I�[�h�͎g�킸�ɁA���W�b�NIC���ŃX�C�b�`����V�Z�OLED�̊Ԃ̉�H������Ƃ������@���I�ׂ܂��B >����͖h�~�ŕ��i�������Ȃ���H����]���܂��B �@�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�ڂ̑O�ʼn�]�_�C�����̈ʒu�Ō����ڂ̂܂�܂̐����ɂȂ�����͖͂���������@�Ƃ��ẮA���[�^���[�X�C�b�`���g���ăK�`���K�`���ƃc�}�~����]�����Đ�����I�Ԃ̂��ł��K���Ă���Ǝv���܂��B �@���̕��@�̌��_�́A���[�^���[�X�C�b�`�̒��͋@�B���̐ړ_�ł����Ƃ������Œ����Ԏg���Ă�����ړ_�����Ղ����ڐG�s�ǂ��N����\���������Ƃ������ƁA�c�}�~���Œ肵�Ă���l�W���ɂ�Ńc�}�~���Y�����c�}�~�̎w���Ă���ԍ���LED�ɏo�鐔�����H������Ă��܂��\��������Ƃ������ł��B �@�Ȃɂ���A�@�B���ł�����@�B�Ȃ�̌��_�͂���܂��B �@����ŁA�e���L�[���Q���Ԃ���ׂ��ƁE�E�E�B �w�e���L�[���Q�g�g���āA���l��I�ԕ����x 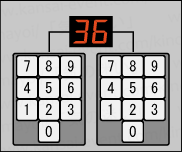 �@���̂悤�ȑ���ՃC���[�W�ɂȂ�܂��B
�@���̂悤�ȑ���ՃC���[�W�ɂȂ�܂��B�@������@�͌����܂�܂ŁA���ꂼ��̌��p�̃e���L�[�̒�����D���Ȑ����������ƁA���̐������V�Z�OLED�ɕ\������܂��B �@�g�p���i�́A�e�������W�b�NIC���₻�̑����ӕ��i�Ȃǂ��K�v�ł��B �@�����̂���]�́u2��ڂ̓��͎��e���L�[�������ƂP��ڂɓ��͂������l�̓N���A������v�Ƃ����̂́A�e���L�[���Q�g�ɂ��Ă���̂Ŗ����ł��B �@�e���̃L�[�������ƁA���̏u�Ԃɂ��̌��̂V�Z�OLED�̕\���͕ω����܂��B �@���̂悤�ȃe���L�[�ƃ��W�b�N��H���g�p���������̏ꍇ�A�����ȊO�͕\���ł��܂����B �� �Ƃ��Ă����G�ȉ�H�ɂ���Ƃ��A�}�C�R�����g���Θb�͕ʂł� �@����ŁA�e���L�[���g�����ꍇ�Ɂu�����Ɖ���ł��܂��e���L�[�v�ł͂���܂��A�H��̐���ՂȂǂł͂悭�g���悤�Ȍ`�ŁA�S�ʏƌ��^�v�b�V���X�C�b�`���g�����̂悤�Ȃ��̂��ł��܂��B �w�e���L�[���Q�g�g���āA���l��I�ԕ����B�S�ʏƌ��L�[�ʼn������L�[������I�x 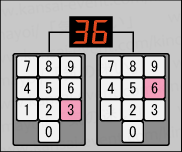
�@�E�}�̂悤�ɁA�������L�[���Ԃ�(�Ƃ�������܂�)����܂��̂ŁA�ǂ̃L�[���������̂���ڗđR�ł��B �@��H�͏���w�e���L�[���Q�g�g���āA���l��I�ԕ����x�ɁA�e�L�[�����点�邽�߂̃��W�b�NIC��lj����A�e�L�[��(�p�l�����t���p)�ƌ����v�b�V���X�C�b�`���S�ʏƌ��^�^�N�g�X�C�b�`(������������)���g���悤�ɂ��邾���ł��B �@�܂�����ՂɂV�Z�OLED���t���Ă���̂�����A����ȋ@�\�K�v�Ȃ��Ƃ͎v���̂ł����A�ꉞ��������������낤�Ǝv�������Ƃ����`�����͒m���Ă����Ă��������B �@�t�ɁA�V�Z�OLED�͖����ŁA�L�[�����邾���ł������ł����ǁE�E�E�B�ǂ��炩�Ƃ����Ɓu�\���p�l���ɕ\������Ă���V�Z�O�\���Ɠ����`�̂��̂�����Ղł������Ă����v�ق����A�����I�ŗǂ��Ǝv���܂��B �@���Ă���ł́A��{�I�ɂ� �� �e�����ƂɁA���[�^���[�X�C�b�`���g�� �@�@�@���̏ꍇIC�����̃J���^���ȉ�H�AIC�ō���H�̑I�������� �� �e�����ƂɁA�e���L�[���g�� �@�@�@�L�[������͍̂���͖��� �̂ǂ��炩�̕��@�ŗ����������悤�ƍl���Ă��܂����A�ǂ��炪��낵���ł����H �@����ƁE�E�E�u�D�̃u���b�W����O�ɋ���l�ɐ��b�����ɐ�����`����v���āA�܂�ŋ��T�ł����Ȃ��甽���̏o�Ă��鐅�[��`�����悤�Ȋ����Ɍ�����̂ł����A���̑��u���������Ŏ�͈̔͂Ŏg����(�����̑D�ɕt���邾��)�̂ł���ˁH �@���i������Ĕ̔�����̂ł͖����ł���ˁH �@�Ȃɂ���A(���i���ł��ł�������)����Ȃ�̑��u�̉�H�}����������₵�Ă���̂����[���A�h���X�̋L���������A�������l������̂�����ł�����A�ŋ߂��������f�]�ځ������̂��̔����݂����ɁA���p����l�����H�Ǝv���Ă��܂��܂��̂ŁB����ł����O�̂��߁B ���Ԏ� 2013/5/4
|
||
| ���e |
�������肪�Ƃ��������܂��B �f�l�ɂ��킩��₷���悤�Ɏʐ^�����}�����Ă����������肪�Ƃ��������܂��B >���i������Ĕ̔�����̂ł͖����ł���ˁH �����Ă��̂悤�Ȏ���Ȃ��Ƃ͂��܂���B���f�]�ځ������̂��̔����������Ă��܂���B���������̂ł͂���܂���B �����C�l�I�Ɉ��S�ʂƌ����ʂ����コ���Ă����Ƃ����v�]�����ł��B �F�X�Ƃ��������Ă����������肪�Ƃ��������܂��B��ϋ��k���Ă���܂��B >����҂���\���@�ɕ\�����ꂽ���l�͌��������l���m�F�ł��Ȃ����� >�Ƌ��Ă��܂����A����Ȏg���ɂ������u�̉�H�}�͒������Ȃ��̂� ���炵�܂����B���݂܂���B ���������܂����u���Ԏ��v���������Ă��������Ȃ���P���Ԉȏ�l���Ă����̂œ��e���x���Ȃ��Ă��܂��܂����B ���������������܂����R�Ă̂����w�e���L�[���Q�g�g���āA���l��I�ԕ����x�͉�H�����G�����őf�l�ɂƂ��Ă͍ł���Փx�������C�D���ł̐U���╨�̓]�|�ɂ�����͂������₷���̂��ȂƎv���܂����B �c���w���[�^���[�X�C�b�`���Q�g���āA�_�C���N�g(�@�B��)�ɐ��l��I�ԕ����x�́u���W�b�NIC�����̃J���^���ȉ�H�v�A�u���W�b�NIC�ō���H�v�̂����ǂ��炩��I���������Ǝv���̂ł����C���L�̂Q�_���������Ă��������B �E�u���W�b�NIC�����̃J���^���ȉ�H�v�́u�_�C�I�[�h���\�v��50�Ƃ�60�ɂ��y�Ԃ̂ł��傤���H �E�u���W�b�NIC�ō���H�v�̕������i���͏��Ȃ��ł���̂ł��傤���H�ėp���̂��郍�W�b�NIC�ł��傤���H ��Ȃ�����ł��݂܂���B �ėp���̂�����̂ŁC�ł�����蕔�i�������Ȃ��ȒP�ɍ쐬�ł��C���R���p�N�g�����z�ł��B�f�l�̂킪�܂܂ł����������Ă��������Ȃ��ł��傤���H �܊p�̉�H�}�����Ēf�O�������Ȃ��̂ł�낵�����肢���܂��B ���ꂩ��C�u���Ԏ��v���ʒ��̉�H�}�����}���₷���ĂƂĂ��Z���X�������Ǝv���̂ł����C�ǂ������\�t�g�ō쐬����Ă��܂����H�{��Ƃ͊W�Ȃ����Ƃ܂ł��݂܂���B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�^���Đ\�������܂���B �@���v�Z���܂������A�w���[�^���[�X�C�b�`���Q�g���āA�_�C���N�g(�@�B��)�ɐ��l��I�ԕ����x���_�C�I�[�h�}�g���N�X��g�ꍇ�A������0�`9��\��������̂��P���Ԃ�Ń_�C�I�[�h�����傤�ǂT�O�K�v�ɂȂ�܂��B�Q���Ԃ�ł҂�����100�I�ł��B �@���̂����AIC��g�����W�X�^�ȂǍH�삪��₱�������ȕ��i�͈����܂���B(��R14�{�͕K�v�ł�) �@�����uIC���g���v�ق��őg�ޏꍇ�A�u�ėp���̂��郍�W�b�NIC�v�̒�`���B���ł��������h���̂ł����A���ʂɔ����Ă���IC�����g���܂���B �@����m���ɑ�̂���̒���Ԓ��̒�Ԃ́u�V�Z�OLED�_���pIC�v�Ȃ̂ŁA�ŋ߂̃}�C�R���嗬�̉�H�ȊO�łV�Z�OLED���g���Ȃ��K���i��IC�ł��B �@������́E�E�E���Ԃ�̂���A����p�r���炢�ɂ����g��Ȃ��̂Œm��Ȃ��l�̂ق��������H�Ǝv����f�R�[�h�^�G���R�[�h�pIC�ł��B(�ł��l�i��50�`100�~���炢�ňꉞ�͂��������p�r�ł����) �@���Ƃ͔ėp���W�b�N�Q�[�gIC�Ƃ��A�g�����W�X�^�A���C�Ƃ��A���܂ł̉�H�}�ł��悭�o�Ă���悤�Ȉ�ʓI�Ȃ��̂ł���ˁB �@�P���ɂ�IC�R���炢(������Ɩ���)�A�g�����W�X�^�A���C�P�B��͂V�Z�OLED(����E��)�ƒ�R(24�`30�{�H)�E�E�E�ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�ǂ��炪�����̂��A��������l���Ă݂Ă��������B (�Ƃ������A�����Q�Ƃ��������ق����Ă��Ƃ葁���H) �@����ŗ]�k�̌��ł����A���̃y�[�W�Ŏg�p���Ă���}�ł̍쐬�ɂ́uAdobe Illustrator (�A�h�r�E�C���X�g���[�^�[)�v�ƁuAdobe Photoshp(�A�h�r�E�t�H�g�V���b�v)�v���g�p���Ă��܂��B �@�u�C���X�g���[�^�[�v�͌l����Ɩ��p�܂ŕ��L���}�ŁE���S�}�[�N�E�C���X�g�쐬�ȂǂɎg�p����Ă���Q�c(��)�b�f�E�C���X�g����p�\�t�g�ł��B�o�ŋƊE��b�f�f�U�C�i�[�A�C���X�g���[�^�[(���d���̖��O)�ł͎嗬�ł��B �@�{�Ƃ̊e��h�L�������g(����)�̐}��f�U�C���쐬�A�G���̋L�����������̌��e�̓��e�p�ȂǁA�l�X�ȋƖ��Ŏg�p���Ă��܂��B(�Ƃ͂����A�v���̃C���X�g���[�^�[���猩����A�{���Ɋ�{�̋@�\�����g���Ă��܂���) �@�����E�E�E����ʼn�H�}�������l�͏��Ȃ��ł��傤�i�O�O�G �@�t�Ɍ��������Ōf�ڂ��Ă����H�}�Ȃǂ́u�G���p�[�c�v�͑S�Ď��̃I���W�i���Ȃ̂ŁA���f�ŃR�s�[���Ďg�p���Ă����肵����ꔭ�Ńo���܂�(��) �@�u�t�H�g�V���b�v�v�̂ق��͖��O�͂����m���Ǝv���܂����A�ʐ^�̉��H�₠����b�f�����Ȃǃp�\�R���łb�f�摜���������ɂ͖����Ă͂Ȃ�Ȃ��\�t�g�ł��B(����A���А��i�ł�������ł����ǂ�) ���Ԏ� 2013/5/4
|
||
| ���e |
���͂悤�������܂��B�������肪�Ƃ��������܂��B �[��x���܂ł��肪�Ƃ��������܂��B >�ǂ��炪�����̂��A��������l���Ă݂Ă��������B >(�Ƃ������A�����Q�Ƃ��������ق����Ă��Ƃ葁���H) ��������l���Ă݂܂����B�܊p�̂��肪���������t�ɊÂ������Ă��������C��Ƃ������Ăق����ł��B �w���[�^���[�X�C�b�`���Q�g���āA�_�C���N�g(�@�B��)�ɐ��l��I�ԕ����x�Ƀ`�������W�������Ǝv���̂ł����C�܊p�Ȃ̂ŁuIC���g���v��������������̂ŗ����łǂ��炪�R���p�N�g�ɂł��邩�������Ȃ�ɍl���Ă݂����ł��B ����Ȃɐe�ɂ��Ă��������Ă��肪�Ƃ��������܂��B �����܂ł��Ă���������̂��L���Ȃ̂��ȂƂ����s�����łĂ��܂��B �]�k�̌������肪�Ƃ��������܂����B ��낵�����肢�������܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����܂ł��������ł��B (�܂����̂����A���̃S�[���f���E�C�[�N�͖����Ȃ��Ă��邾���ł�) �@��H�}�͗����~�����Ƃ������ŁA�܂��̓J���^���Ȃق����u�_�C�I�[�h�}�g���N�X�v���g����H�̂ق�����B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�@ �@�����̂悤�ɁA�ƂĂ��P���ɁA�_�C�I�[�h�Ń}�g���N�X��g��ł��邾���ł��B �@IC��g�����W�X�^�͈���g���Ă��܂���B �@���[�^���[�X�C�b�`�Ŏw�肵�����l(����)���A���ۂɂV�Z�OLED��_��������\���p�^�[�����ϊ�����̂Ƀ_�C�I�[�h���g���܂��B �@�_�C�I�[�h���g�킸�ɒP�ɏc���̔z�����V���[�g���邾�����ƁA���̐����I���s�̃V���[�g�n�_���o�R���đS���̑I���p�[�^�����V���[�g������ԂɂȂ�A�X�C�b�`���ǂ��ɉĂ��S�_��(�W�̎�)�ɂȂ��Ă��܂��܂�����A�_�C�I�[�h�ŋt���h�~�����Ă��K�v������܂��B �@�u���吔���\���v�̂V�Z�OLED�Ǝ茳�́u����Ձv�̂V�Z�OLED�́A�ǂ�����d���d����DC 24V�Ō��点��悤��R�l���v�Z���܂��B �@�����A�����Ŏw�肵�Ă���^�Ԃ̂V�Z�OLED�ȊO���g����̂ł�����A��R�l���v�Z�������Đ�������R�ł��g�p���������B �@�܂��A�_�C�I�[�h��1N4001(50V/1A)���w�肵�Ă��܂����A��H�}���̂悤�ȂV�Z�OLED���������g��Ȃ��̂ł�������Ɠd���l�̏����ȃ_�C�I�[�h�ł��\���܂���B �@��H�}�ł�1A�߂��܂Ŏg����̂ŁA����\���̂ق��́u�d�����v��ŋߗ��s�́uLED�e�[�v�v�ȂǁA�\�肵�Ă���V�Z�OLED�������Ɠd���������Ė��邢�\�����i���g�����Ƃ��ł��܂��B �@�����u���W�b�NIC�v���g����H�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�@IC���g���Ƃ͂����A�ׂ������ȕ��i�͎g���Ă��Ȃ��̂ŁA��H�}���V���v���ł��B �@�u���[�^���[�X�C�b�`��10�ړ_����A�V�Z�OLED�̓_���p�^�[���ɕϊ����Ă����֗���IC�v�Ƃ����̂����݂���ƂĂ��ǂ������̂ł����A�������ɂ���ȓs���̗ǂ�IC�͒ʏ��74�V���[�Y��4000�V���[�Y�ɂ͑��݂��Ȃ��̂ŁA�l�X�ȋ@�\��IC��g�ݍ��킹�ĖړI�̋@�\���ʂ�����H�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�܂���Ɂu�V�Z�OLED��_����������IC�v�ɂ��āB �@���ꂪ�����Ƙb�ɂȂ�܂���B �@���W�b�NIC��H�Łu������\���̂ɂV�Z�OLED��_���������v�E�E�E�Ƃ����A74�V���[�Y���������ꂽ��������N�����u7447�I�v�Ɠ�����قǃ|�s�����[�����ɗނ����Ȃ���Ԓ��̒�Ԃ�IC�ł��B �@���ɂ�7446�₻�̑��������@�\���Ⴄ�V�Z�O�\���pIC�����������݂��܂����A���ۂɍł������g���Ă��č��ł��̔�����Ă���̂�7447(74LS47)�ł��傤�B �� C-MOS 4000�V���[�Y�ɂ��V�Z�O�\���pIC�͂���܂����A�����74�V���[�Y�Řb������̂Ŋ��� �@74LS47 [PDF]���A�m�[�h�R�����^�̂V�Z�OLED�ړ_����������悤�A�o�͂����_��(�_���̎�L)�ł��B �@���ʂ̂V�Z�OLED��Ȃ璼�ڐڑ��ł��܂�(��R�͕K�v�A�܂��o�͑ψ���15V)���A����̂悤�ɕ\���Ƒ���Ղŕ����̂V�Z�OLED��_��������ɂ̓g�����W�X�^�Ȃǂ��O���ɐڑ����Ă����Ɠd���𗬂���悤�ɂ��Ă��Ȃ��Ƃ����܂���B �@�܂��A����g�p�����f�W�b�g�̑�^�V�Z�OLED�̓Z�O�����g�d����13.4V�ƁA���˗��̑D�̓d��24V�d���œ_��������̂��Ó��ȂV�Z�OLED�̂��߁A74LS47�̏o�͑ψ�15V���Ă��܂����߁A�K���g�����W�X�^�Ȃǂ��K�v�ɂȂ�܂��B �@����ŁA�V�Z�O�_���p���g�����W�X�^�A���C(�����TD62384APG [PDF])���g�������d���ɑΉ��������d���ɑΉ��̗������������܂��B �@74LS47�̓��͂�BCD�R�[�h(�j�i��10�i��)�ł��B�_�������_���ł��B �@�S�r�b�g�̓�i���̂����O�`�X�܂ł��g�p���܂��B �@���Ȃ݂ɁA��i���ł`(10)�`�d(14)�̐��l����͂�����Ƃ�ł��Ȃ����������݂����ȕ\���ɂȂ�܂��B(�f�[�^�V�[�g�����Ă�������) �@�e(15)����͂���ƁA�S�Z�O�����g�����p�^�[���ƂȂ�̂ŁA�V�Z�O�����������������ɂ��g���܂��B����͂�������܂����p���Ă��܂��B �@���Ɂu���[�^���[�X�C�b�`�̓��͂��A�V�Z�OLED�_���p��74LS47���쓮����BCD�R�[�h�ɕϊ�����IC�v�ɂ��āB �@����ɂ́A�ӂ���͂��܂�g���܂�����̂悤�ȁu10�{(�܂ł�)�o���̓��͂̏�Ԃ��ABCD�R�[�h�ŏo�͂����v�Ƃ����u10��BCD �G���R�[�_IC�v������܂��B �@74HC147 [PDF]�ł��B �@74HC147�̓��͂��P�`�X�̂X�{(10�{�ł͖���)����A�ǂꂩ�̓��͂�L�ɂȂ����炻�̓��͔ԍ���BCD�R�[�h�ŏo�͂��܂��B �@����̓��[�^���[�X�C�b�`��ڑ�����̂ŒP����͂���L�ɂ͂Ȃ�܂��A�ʂ̃X�C�b�`�≽���̃Z���T�[���������� �Ԃ牺�����悤�ȏꍇ�������ɕ����̓��͂�L�ɂȂ��Ƃ������Ƃ��������܂����A74HC147�ł́u��ʗD���v�Ȃ̂ł�萔���̑傫�Ȃق��̓��͂�BCD�R�[�h���o�͂��܂��B �@�܂����͂́u�P�`�X�v�̂X�{�ŁA�ǂ�����͂������ꍇ�́u�O�v��BCD�R�[�h���o�͂��܂��B �@��������Ȃ̂�74HC147�̏o�͂����_����BCD�R�[�h��H/L���t�̐M�����o�͂���܂��B �@���̂܂܂ł�74LS47�����_�������Ɍq���ł�������������\���ł��Ȃ��̂ŁA�Ԃ��_�����t�](H/L�t�])���Ă��K�v������܂��B �@�����ŁA���W�b�NIC�́u�C���o�[�^�^NOT��H(���]��H) IC�v�ł���74HC04������̏o�ԂȂ̂ł����A74HC04�ł͒��̂U�Q�[�g���Q�Q�[�g�]���Ă��܂��]��Q�[�g�����Ƃ������Ȃ��Ƃ����܂���B �@����Ȃ�ƁABCD�R�[�h�̂S�r�b�g�]������Ȃ�uNAND�Q�[�g�v�S��H�����74HC00 [PDF]���g����BCD�R�[�h�̘_���]������Ƌ��ɁA�Q���͂̂����Б����uL�ɂ����BCD(�Q�[�g)�o�͂������I�ɑS��H�ɂ��Ă��܂���H(74LS47�̃R�[�hF�őS�����@�\�����p)�v�Ƃ��Ďg�p���邱�ƂŁA�u���[�^���[�X�C�b�`�̂P�̐ړ_�Ɛڑ����āwOFF(����)�x�@�\�����������v���Ƃɂ��܂����B �� �����74LS47�ɂ��Ă���(�d��Ȃǂ̕\���̂悤��)��ʌ��̂O�\���������I�ɏ����u�[���T�v���X�@�\�v�͎g���Ă��܂���B �@��L�̐v�ŁA���W�b�NIC�R�A�g�����W�X�^�A���C�P�A��R�K�X���u���W�b�NIC�v���g����H�͊����ł��B �@IC��74HC�V���[�Y���g���܂����̂ŁA�d����DC 5V�ƂȂ�܂�����A�D�̓d����DC 24V������O�[�q���M�����[�^(7805/�ψ�35V)�ō~�����Ďg���܂��B �@�Q���\��������ɂ́A5V�d���ȊO�͑S�ĂQ��H�K�v�ɂȂ�܂��B �@���āE�E�E�u�_�C�I�[�h�}�g���N�X�v���g����H�ł��u���W�b�NIC�v���g����H�ł��n���_�Â�������͂��܂�ς��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�ǂ��炪���R���p�N�g�ɂȂ邩�H�ɂ��ẮA�u�_�C�I�[�h�}�g���N�X�v�������W���i�z�u�łт�����g�ݗ��Ă����Ƃ��ł���l�ł���A������̂ق��������Ə������Ȃ�܂��B �@�����łȂ��āA���ʂɊ�Ƀ_�C�I�[�h����ׂĂ䂭�Ȃ�A�ǂ�����������Ċ�ł́u�ʐρv�ł͓������炢�ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���D���Ȃق������I�т��������B ���Ԏ� 2013/5/6
|
||
| ���e |
���̂��т͂��Z�������C��ς��肪�Ƃ��������܂����B �܊p�̂f�v���]���ɂȂ��Ă��܂����݂܂���ł����B �܂��C�Q��ނ���H�}���쐬���Ă����������������ꂵ���ł��B ��H�}����͂�Z���X�����ł��ˁB �܂��̓I�X�X���̃_�C�I�[�h�T�P�̕����畔�i�B���č���Ă݂����Ǝv���܂��B���̌�u���W�b�NIC�v���g����H�ɂ��`�������W���Ă݂����Ǝv���܂��B�L���ݏZ�̂��߁C���X���i���B������̂ŁC�i�_�C�I�[�h�T�O�{�u���Ă�X������܂���B�����̂͒�R�Ə������V�Z�O���炢�������炢�ł��B�j�܂��̓l�b�g�ŏH���Ƌ������畔�i�B���悤�Ǝv���܂��B�f�W�b�g�i����^�V�Z�O�j�́u��������_�~�[�����ōw���\�v�Ƃ����܂����B ����ȑf�l��ɂ��Ă��������C�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�����ڎw���Ċ撣��܂��B�܂����܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���e |
���т��т��݂܂���B >�u�_�C�I�[�h�}�g���N�X�v���g����H >�@���A��Ɂu�_�C�I�[�h�͂��傤�ǂT�O�I�v�Ə����܂������A�悭������T�P�ł����B���݂܂���B������ł��B �z���}cad�ŏ����Ă�����C�Â��܂����B�_�C�I�[�h�T�O�ł����B�u�V�v�̓_�C�I�[�h�S�ŁC�V�|���̃_�C�I�[�h�Ȃ��ł����ł���ˁB �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@��ϐ\�������܂���B �@���w�E�̒ʂ�A7-g�̃_�C�I�[�h�͕s�v�ł����B�����Y�ꂾ�Ǝv���܂��B �@��H�}�̂ق��͏C�����Ă����܂����B �@���A�����肪�Ƃ��������܂��B �@���i�ɂ��ẮA����̉�H�}�ɍڂ��Ă�����̂͑S�Ēʔ̉̂��̂�I��ł��܂��B(���O�ɍŐV���͒��ׂĂ���ڂ��܂���) �@�����ׂɂȂ�ꂽ�悤�ɁA�H���Ƌ���(�ꕔ�̓_�~�[������)�œ���\�ł��B �@��ʂɕK�v�ȃ_�C�I�[�h�ł����A�����ł͑�ʍw��������100�{�Ȃ�800�~(�X���ł�100�{�e�[�v�i�������Ă��悤�ȁE�E�E)�B�H���ł�1N4001�͖����ł�������Ɏg����1N4007(1000V/1A)��20�{100�~�Ȃ̂ŁA�T�p�b�N������100�{500�~�ł��B �@���[�^���[�X�C�b�`���H���Ŕ����Ă��镨�����Љ���̂ŁA�ǂ�����̑�����������Ȃ���V�Z�OLED A-551SRD���H���̃l�b�g�ʔ̂ŏo�Ă��鏤�i��I�����Ă��܂��B �@�V�Z�OLED�Ȃ͒n���̂��X�ł������邻���Ȃ̂ŁA�킴�킴�ʔ̂Ŕ����K�v�������ł����A�Ȃ�ƂȂ��u�������Ȃ�K�v�Ȃ��͈̂ꏏ�ɂ܂Ƃ߂čw���v�Ƃ����n�R�����������Ă��܂��܂��i�O�O�G ���Ԏ� 2013/5/6
|
||
| ���e 5/7 |
�F�X�Ƃ��肪�Ƃ��������܂����B�e�ȕ�������������Ȃ��Ɗ��S���܂����B�܂��C��낵�����肢���܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���e |
�����_�C�I�[�h���g�p���������������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B��������IC���g�p���������쐬�g�p�Ǝv�����̂ł���TD68384������܂���B����܂œ����ɏo�����Ă����̂ŏH�t���̓d�C������ɍs�����̂ł�������܂���ł����B�^���Â��Ēu���ĂȂ��ƌ����܂����B�����i�̌^�ԋ����Ă��������Ȃ��ł��傤���B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@TD68384�E�E�E�ł͎��݂��܂���B�^�Ԃ��ԈႦ�ĒT���Ă���̂ł͂Ȃ��ł����H �@������H�}�ɍڂ����͓̂��ł̃g�����W�X�^�A���C TD62384APG�ł��B �@�m���ɋߔN���ł͂��܂�g���Ȃ��Ȃ����g�����W�X�^��p���[�f�o�C�X���玟�X�ƓP�ނ��Ă��āA���ɑ唼�̂��̂悤�Ȕ����̐��i���p�i���ƂȂ��Ă��܂����ATD62xxx�V���[�Y�Ȃ͂܂��܂��s��ɂ��c���Ă���Ƃ���ł͔̔����Ă���Ǝv���܂��B �@���Ȃ݂ɁA�����H�}�ɍڂ��Ă���TD62384APG��(�����̗p�r��)��N�����炢�ɓ��{���Ŕ����Ă����o��������܂��B(���̎��Ɏg��Ȃ������]�肪���i���ɐ��c���Ă��܂���) �@��������ȍ~�ɕi���ƂȂ��āA���ł̓l�b�g�ʔ̂����Ă��Ȃ��̂ł�����A���{���̓d�q���i�X�ł�����͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�H�t���̂ق��������������i�̍ɂ͑��������Ă������Ȋ����Ȃ�ł����ǂˁE�E�E�B�l�b�g�ʔ̂͂��Ă��܂��A�G���r���̒��ɂ���G�R��IC�Ƃ�����ׂĂ���A���₶�����l�ł�����肵�Ă�ƂĂ��������X�Ƃ��B(�ǂ����ɂ��Ȃ��Ȃ邩�A���₶�����ނ��ēX����ނ��ǂ������������E�E�E�Ƃ����ʂ̓X�ł����ǁB����ȑO�Ƀr�����Ƃ�Ŗ����Ȃ��ēX�����ł���p�^�[���̂ق������̏H�t���ł͑����ł���) �@TD62384APG�ł��[����搶�Ō������Ă݂���A�܂��̔����Ă���Ƃ���݂͂���Ǝv���܂��B �@�u�����i�v�ƌ����܂��Ă��ATD62384APG�̂悤�ȁu�Wch�������[�A�N�e�B�u�^�ENPN�g�����W�X�^�A���C�v�͑���T���Ă����݂��܂���B���ꂾ�����Ǝv���܂��B �@��H���͌���܂����u�Sch�����v�ŗǂ�����Sch�������[�A�N�e�B�u�^�ENPN�g�����W�X�^�A���C TD62308APG(APG) [�H�� �Q����/200�~] ���Q�g���Γ����悤�Ƀ��[���͂łV�Z�OLED��_�������邱�Ƃ��ł��܂��B �@�g�����W�X�^�A���C���Q�ɂȂ�܂�����A�u�R���p�N�g���v�Ƃ�������]����͗���Ă䂫�܂��B �@�u�n�C�A�N�e�B�u�^�ENPN�g�����W�X�^�A���C�v�ł���A���А��i�ł����А��i�ł����Ȃ肽������̕i�킪����܂��B�܂��l�b�g�ʔ̂ł������̔�����Ă��܂��B�E�E�E�ł������͍���̉�H�ł͂��̂܂g�p�͂ł��܂���B �@�����āA�V�Z�O�h���C�o��74LS47�����[�o���ł�����ˁB����ɑ��ăg�����W�X�^�A���C�����[���͌^���q���Ȃ��Ƃ����܂���A�R���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂�ɂ͎���TD62384APG���������킯�ŁE�E�E�B �@���Ȃ݂ɁA�������Ɂu74LS47���g���ĂV�Z�OLED�ɐ������o���v�Ȃ�Ă�����H���A�������N�ǂ��납�\�N�ȏ�͐V���ɂ͌��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �@�u74LS90�̂悤��BCD�J�E���^�[IC���g���Đ������J�E���g���A74LS47�łV�Z�O�\���v�Ȃ�����a�̎���ɂ͂���������܂��̋Z�p�E��H�������̂��APIC�}�C�R���̂悤�ȏ��K�̓}�C�R���̑䓪�ɂ����Ɂu���W�b�NIC��g�ݍ��킹�č���v�Ƃ������@�ł͍���Ȃ��Ȃ�������ł��B �@�E�E�E�E���a���āA�������N�O�Ȃ�ł��傤�ˁH �@�}�C�R���g�p�Ɏ��オ�ς���Ă��A�}�C�R���̏o�̓s���͓d�������Ȃ��A������傫��LED�������胂�[�^�[���ɂ͊O���Ƀo�b�t�@���K�v�Ƃ����p�r�ł́A���ł��g�����W�X�^�A���C��FET�A���C�̏o�Ԃ͂���܂�����A�}�C�R���̏o�͂ȂǂŐ��䂵�₷���n�C�A�N�e�B�u�^�����̃g�����W�X�^�A���C�ł���A�܂��s��ɂ͖L�x�ő����̓X�ɒu���Ă���Ǝv���܂��B �@���Ƃ��A�H���Ȃǂł������Ă����Wch�����n�C�A�N�e�B�u�^�ENPN�g�����W�X�^�A���C TD62083APG [PDF] [�H�� �Q����/100�~][���� �P��/136�~] �̂悤�Ȃ��́B �@�ł��A��ɏ������悤�ɂ�����n�C�A�N�e�B�u�^�ł�����A74LS47�̏o�͂Ɍq���ɂ��M���]�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁANOT�Q�[�g(INV)���W��H���K�v�I�ɂȂ�܂���ˁB �@���Ƃ����āA�悭�g����悤��NOT�Q�[�g(INV)���U��H������74HC04 [PDF]���Q�g���āE�E�E�Ƃ����̂�IC���������Ă����ւ�ł��B �@�����ŁA�P��IC��NOT�Q�[�g(INV)���W��H�������u�R�X�e�[�g�^/INV/�o�X�E�o�b�t�@�v�ł��� 74HC540 [PDF] [�H�� 20��/200�~][[���� �P��/115�~] ���g����INV��IC���͈�Ɍ��点�܂��B �@�ƂĂ����������ƂɁA�g�����W�X�^�A���CTD62083APG�Ɠ����悤��IC�̗����ɓ��͑��E�o�͑����Y��ɕ�����ĕ���ł����̂ŁA���ł̔z�����ƂĂ����N�`��(����)�ł��B �@���ǂ̓g�����W�X�^�A���CTD62308APG���Q�g�����AINV�o�X�o�b�t�@74HC540����ƃg�����W�X�^�A���CTD62083APG����g�����E�E�E�E�B �@������ɂ���TD62384APG�̑�ֈĂƂȂ��IC�Q�Ԃ�̖ʐς͋킯�Łu�R���p�N�g�v���Ɍ����܂����A���Ƃ��Ă͔z�����y��74HC540�{TD62083APG�̂ق����y�ɑg�ݗ��Ă���̂ŗǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@�܂������܂ŁATD62384APG�����S�ɓ���ł��Ȃ���E�E�E�E�̕i�͂ł����ǁB �@�܂��ʂ̃v�����Ƃ��ẮA�n�C�E�A�N�e�B�u�^�̃g�����W�X�^�A���C��������ł��Ȃ��̂ł���A�n�C�E�A�N�e�B�u�^��BCD-�V�Z�O�h���C�oIC���g���ΊԂ�INV�Q�[�g�����܂Ȃ��Ă������ł���ˁH �@�m���AC-MOS 4000/4500�V���[�Y�̒����n�C�E�A�N�e�B�u�^��BCD-�V�Z�O�h���C�oIC�͑��݂����Ǝv���܂��̂�(����o��)�A���������̂�T����Ďg���Ă݂�Ƃ����̂���ł��ˁB �@�������A���͖ő��Ɏg���鎖�̖���4000/4500�V���[�Y�̒��̂V�Z�OLED�h���C�o�Ȃ�āA�����Ă���E�E�E�̖�肪�ő�̓�ւɂȂ邩�Ǝv���܂����B �@��������Ȃɒ����F�X�Ə����Ĕ��܂����̂ŁA�����܂Œ��ׂđS�������̂͂�߂Ă����܂��B �@�����K�v�Ȃ炲�����ł����ׂ��������B ���Ԏ� 2013/5/16
|
||
| ���e |
�F�X�Ƃ��肪�Ƃ��������܂����B�H�t���̎G���r�����̓X�𐔌�������̂ł���TD62384APG�͂���܂���ł����B�߂������ɑ��o���Ȃ̂œ��{���ł��T���Ă݂܂� �B�������낵�����肢���܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�V���̏H�t���ł��������Ƃ������́A���{�ł͂�����ɓ���Ȃ���������܂���ˁB �@�ȑO���������̂ł����A���������ŏ��i�╔�i���Љ��ƁA������ɂ͔���ꂽ����������Ȃ����肵���������x������܂��B �@TD62384APG���A���Y�͏I����Ă���̂œX����͖����Ȃ莟�抮�S�ɓ���s�\�ɂȂ�ł��傤����A�T���Ƃ�������߂ɁB �@�u����Ȏ��͖������낤�v�Ƃ��v���̕��́A�Â��b�ł����wNo.2007_0210�x�݂����ɁA����܂ł����ƕs�ǍɂŒI�Ńz�R�������Ԃ��Ă����̂ɁA�����ŏ������r�[�����T�ɂ͉e���`�������Ȃ��Ă��I�Ƃ������b������܂����A���͂��ꂪ�����Ă��炠�܂�b��ɂ͂��Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ł����A���{���Ō������ʔ������ȕ��i��W�����N�A�������ʂɔ����Ă��镔�i�ł��X���ɍɐ������Ȃ��������̂Ȃǂ���͂肱���ōڂ��Ă��炷���ɕi��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͉��x������܂��B �@�u����Ȃɂ݂�Ȃ����Ō�����������A��H�}���ڂ����������肵�Ă�͂��͖������ǁE�E�E�v�Ǝv���悤�ȕ��܂œ˔@�Ƃ��ď��i�I��������Ă����肷��̂ŁA�s�v�c�ł��B �@�܂����x���͂����ŏ��������������l���A�l�b�g�̓�������f���ŏ��]�ڂ��āA����������l�����l�������ɗ����Ƃ����p�^�[�����������Ƃ��B��œX������ɋ����Ă�����ď������Ƃ�����܂����B �@TD62384APG�Ȃ͏H�t���ɂ����������ƒm�����C���Ǝ҂̐l�Ȃ��u���̂����ɔ����Ă����Ȃ��ƁI�v�ƍ��T��������ɔ�������ɗ��邩������܂���ˁi�O�O�G ���Ԏ� 2013/5/17
|
||
| ���e |
����ɂ��́u�ቿ�i�I��^7�Z�O�����gLED�v������12.7cm�i�ԐF�j�ō쐬�����̂ł����C�f�W�b�g�u���O�悭���Ă݂�Ɓu�ቿ�i�I��^7�Z�O�����gLED�v������12.7cm�i�F�j�Ƃ����̂����葁�����܂����B�������f�[�^�V�[�g���Ȃ��������d���⏇�����d�����킩��܂���B�����u�ቿ�i�I��^7�Z�O�����gLED�v������12.7cm�i�ԐF�j�����C��薾�邢���������Ǝv���C15��17V�������Ƃ���LED�����܂����B��i13.4V�ł��B�����߂����J��Ԃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���āC�f�W�b�g�ɓd�b�Ŋm�F�����Ƃ���C�u�킩��܂���B16V�܂ł͓_�����܂���B�v�Ƃ����ŎQ�l�ɂ��Ȃ�܂���ł����B���쒼���d���œd�������Ȃ��班�����d���������Ă����m�F�����̂ł����C20V��7mA�܂ł�������ł��܂���ł����B�����d���ő�20V�܂ŁB�������d���C�d���ׂ�̂͏����Âd�����グ�Ă����C�d��15mA�`20mA���x�ɂȂ�d�����������d���B�Ƃ��������Œ��ׂ邵���Ȃ��̂ł��傤���H���̓d���ł͂���ȏ�m�F�ł��Ȃ��̂ŁC24V�̃A�_�v�^�ƒ�R�Ŋm�F���邵���Ȃ��̂ł��傤���H�������d����15mA�`20mA�Ə���ɐݒ肷��̂��댯�Ȋ���������̂ł����ǂ��ł��傤���H����Ȏ���܂ł��Ă���낵���̂ł��傤���H������낵��������Ă���������Ɣ��ɏ�����܂��B��낵�����肢���܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁE�E�E����LED�̏������d��(If)�ɂ��ẮA���[�J�[�̏��E�f�[�^�V�[�g�����Ȃ��Ɖ����킩��܂���B �@�����܂ŐԐF�^�C�v��15mA�Ə�����Ă�������Ƃ����āA�F�^�C�v��15mA�Ȃ̂��ǂ����́A���[�J�[�łȂ��Ƃ킩��܂����ˁH �@�������́A�u���̐F�p�l���̒��Ɏg���Ă���LED�̌`��傫��(�V���O���`�b�v�Ȃ̂������`�b�v�Ȃ̂��H)��A�p�l�������Œ���E����ɂǂ��ڑ�����Ă���̂��H���p�l�������Ď����̖ڂŊm���߂��Ȃǂ̉���v�����Ȃ��ƁA�������������͌�����l�͋��Ȃ��ł��傤�B �@�ԐF�^�C�v�̃p�l���́A�e�Z�O�����g�̒�i�d��/�d��13.4V/15mA(�f�[�^�V�[�g�͖����A�f�W�b�g�ł̎����l)�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA�p�l�����ł́u1.9V/15mA�̐ԐFLED���V�����v�ɂȂ��Ă���悤�Ȋ����ł��鎖�͒N�ł��z�������Ǝv���܂��B �@����ɑ��Ă�����d�����グ��LED���2.1�`2.4V����������E�E�E�E����̓J���^����LED���Ă���ĉ��Ă��܂��܂�����E�E�E�B �@���������j��s���͂�߂Ă������ق����ǂ��Ǝv���܂��B �@�u�d�����グ���v�Ƌ��܂����ALED�͓d���f�q�Ȃ̂œ�������߂�͓̂d���Ŏw��͂��܂��A���点�邽�߂̎w����w����u�d�������u���v�Ƃ������ł͍s�Ȃ��܂����B(��i���ŁA�d���ɑ��ēd�����ǂ��ω�����̂��̐��\�ׂ���A�O���t�Ŏ����ۂɂ͓d����p���܂�) >�������d���C�d���ׂ�̂͏����Âd�����グ�Ă����C�d��15mA�`20mA���x�ɂȂ�d�����������d���B�Ƃ��������Œ��ׂ邵���Ȃ��̂ł��傤���H �@�͂��A�����ł��B �@�d���l���Ď����A�d����ω������Ăǂ̒��x�̓d���ł���Β�i�͈͓��̓d���������̂��ׂ܂��B �@�����A�f�[�^�V�[�g�Œ�i�d�����킩���Ă���A�u��d���d�����u�v�ŏo�͓d�������̒l�ɂ���LED�Ɂ{�Ɓ|���q���ł��A��u�œd�����킩��܂��B(���ʂ͂������肵�܂�) �@�����܂őz���̐����o�܂��A�f�W�b�g�̐l���u16V���x�܂ł͓_�����܂����v�Ƃ����M�d�ȏ����^���Ă��������Ă���Ȃ�A�܂��͂�����قڂ��̃p�l���̑f���͂킩���������R�ł���ˁH �@�FLED�Ȃ�W���I��Vf��3.0�`3.6V���x�̊Ԃł�����A16V�܂ł͓_�����Ȃ��Ȃ�Œ���ڂ���ł��_������d����2.5�`3.0V�Ŋ����LED�̒��͐����ł���̂ŁA�����܂��ɂT�`�U�{���x�͓����Œ����ڑ��͂���Ă������ł��B �@���̃p�l���̂悤�ɂR�{����~�Q����̂悤�ȁA12V���x�̓d���̒Ⴂ�d���œ_������p�l���ł͖����Ƃ������ł��傤�B �@�ԐF�p�l���ƐF�p�l�������̊���S�������ŁA�P�ɍڂ���LED��ς��Ă��邾���Ƃ����m�͑S������܂��A����������𗬗p���������̕ʌ^�Ԃ̐��i�ł���A�ԐF�^�C�v��LED�U�`�V����ł��낤Vf�Ő������_�������邱�Ƃ��ł��Ă���Ȃ�A�F�^�C�v����̗L�p�ȏ��Ƃ��킹�ē����悤�Ɂu�FLED���U�`�V����ł����v�ƍl����̂����R�ł́H �@�������H�Ɛ��i�ł�����ALED�̐F������Ă��Ȃ�ׂ�����̓d���d���œ_������悤�ɂƁA����Vf�̍����F�E���FLED�̏ꍇ��LED�̒���{�������炵�����ʂȐ��i�ɂ���(���̂Ԃ���͑��₵�ď���d����������)�Ƃ����v�ō��ꍇ���l�����܂��̂ŁA�Ȃ�ł�����ł��u�ԐF�p�l���Ɠ������낤�v�ƍl����̂͂����ւ�댯�ł��B �@���j���f�W�b�g�X���Ŕ����Ă��镨�����܂������A�u�ΐF�v�u���F�v�^�C�v�͐ԐF����i�d��(�f�W�b�g����l)���ԐF�^�C�v���킸���ɍ����l��������Ă����̂ŁA�u�ΐF�v�u���F�v�^�C�v�͐ԐF�Ɠ�������g�����F�Ⴂ���i�ł͂Ȃ����Ǝ����̔̔�����Ă��镨�����Ċm�F���܂����B �@�c�O�Ȃ���u�F�v�^�C�v�͒u���Ă��Ȃ������̂ŁA�f�W�b�g�̂ق��łǂ������Ĕ����Ă���̂��킩��܂���B(�������̐F���l�����ł͖����A�F�������ʂɃJ�E���^�[�̓��̏�ɒ݂��Ă����Ȃ猩�Ă��܂���) (�f�W�b�g�u���O�ł��Y���L���݂͂����܂���ł����E�E�E) �@�����܂�16V�܂ł͓_�����Ȃ��Ƃ����������炻��ȏ�̓d�����K�v�Ȗ{������ڑ�����Ă���Ȃ�A����Ɂu���Ɏg���Ă���^�Ԃ��s���ȐFLED����iIf��15mA�ł����v�Ƃ����ƂĂ���G�c�ʼn��̊m���������_�����ɗ����Čv�Z����A�F�^�C�v���i�Ō��点��ɂ͓d����18�`24V���x�͕K�v�Ǝv���܂��B >20V��7mA�܂ł�������ł��܂���ł����B �@�Ǝ��n�ő��肳�ꂽ���ʂ����Ă���̂ŁA��͂�ԐF�Ɠ��l�ɂV���炢�͓����Ă��āA��i�d���𗬂��ɂ�24V�ȏ���x�͕K�v�Ȃ̂�������܂���B �@�܂�24V�ƌ����Ă��A����͓d���f�q��LED�ł�����A�d���������������ɒP���ɒ���24V����������܂��Ă���ďI����Ă��܂����Ƃ��l�����܂�����A�d���������I�ɐ�������悤�ȁu��d����H�v�����Ďg���Ȃǂ̕ی��͎{���Ă������ق��������ł��傤�ˁB �@�ł��ȒP�Ȓ�d�����i�Łu��d���_�C�I�[�h(CRD)�v������܂����A15mA�^�C�v��CRD��LED�ƒ���ɓ���ALED�̒�i�d���{�T�u�ȏ����炢�̓d����������Ύ�����LED�p�l���̕K�v�d�����p�l���[�q�Ɍ���܂��B���̍ۂ̓d����30�`35V�͕K�v�ł��ˁB �@30V���x�̓d���ł��A100�~�V���b�v��006P���d�r(9V)���R�`�S�������������Ȃ̂ŁA�������d�����u�͕K�v�����ł����B �@��d����H��CRD���g�킸�A30V���x�̓d���Łu����LED�p�l����Vf��xxV������A�d��15mA�Ŏg���ɂ͒�R�lxx���v�ƌv�Z���āA�v�Z�����l�̒�R��30V���炢�̓d�����q���ł��ʂɍ\���܂����B �@�\���菭�Ȃ��d����������Ȃ��v�̒�R�l���珇�ɒ��ׂĂ䂯�A���̂����ɐ�������R�l��LED�p�l�����K�v�ȓd�����m���Ǝv���܂��B �@�v�Z���Ԉ������A�\�������Ƃ܂��p�l�����܂����B ���Ԏ� 2013/6/12
|
||
| ���e 6/18 |
����ɂ��͂������čς݂܂���B�������肪�Ƃ��������܂��B �f�W�b�g�̑�^�V�Z�O�ł����C���ێ������Ƃ���C�������ƂT������Ă��\���������̂ł����C ���ꂽ���ɑD�̃u���b�W���ɒu���D�猩���Ƃ��딖���Č����܂���ł����B�i�������ア�����j ���ǁC�F�X�K�\�����X�^���h���̋��z�\����LED�����Q�l�ɂ���5mm��LED70�i1��35�j�𗘗p���č��܂����B ���O�Ŏg�p����ꍇ�͍��P�xLED�ނ��o���̕����K���Ă���悤�ł��B �܂��C�ڑ��P�[�u����16c�P�[�u���œd���͋��ʂɂ���DSUB15�P�[�u�����g�p���܂����B�������C�w��������ʓI�ȃf�B�X�v���C�p�Ƃ��Ĕ̔�����Ă���DSUB15�P�[�u���̓s����15�ł����P�[�u���̐S����15c�ł͂Ȃ�12c�ł��莸�s���Ă��܂��܂����B ���ǃl�b�g��DSUB15�s���̃X�g���[�g�S�����Ƃ����P�[�u���𒍕����܂����B ����́C�F�X�ƕ��ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�������낵�����肢���܂��B �V���C�z���C�g �l
|
||
| �d���̎��� | |||
|
����͊��d��̓d�r����ɂ��ċ����Ē������肪�Ƃ��������܂����B ���݁A�d�C�߂����p�ɂRV�`�P�QV���x�̉ςłTA�`�VA���x�̈��艻�d������肽���Ǝv���Ă��܂��B �̖̂����G����������ƂP�WV���x�̏\���d��������傫�ȃg�����X�ɓd��IC�̂V�Q�R��QN�R�O�T�T��p�������艻�d���L�b�g��p����̂��퓹�̂悤�ł����A���̃g�����X�̑���Ƀp�\�R���̓d���Ɏg����悤�ȃX�C�b�`���O�d����p����͖̂�肠��ł��傤���B �܂��A�g�����X�̑���ɃX�C�b�`���O���M�����[�^��p���Ă���ɂV�Q�R�̑���ɂ�����i�d���ς�DC-DC�R���o�[�^�œd����������Ƃ����͖̂��ʂł��傤���B ��낵�����肢���܂��B aka �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�g�����X�H�̂����ɂo�b�̓d���Ƃ����̂́A�u�g�����X�{�����u���b�W�{�����p�d���R���f���T�v�ō��DC�d���̂����ɁA�o�b�p�̓d�����j�b�g��p����E�E�E�Ƃ������߂ł�낵���ł���ˁH �@�����p�u���b�W�Ȃǂ͂��̂܂܂ŁA���i�Ƃ��Ắu�g�����X�v�����o�b�d���ɒu��������̂ł����H(���ꂾ�Ƃ�����ƕs�v�c�ł���) �@�ʂɁA�K�v�ȓd���ƁA�K�v�ȓd���e��������o�b�d���ł���A�u�g�����X�{�����u���b�W�{�����p�d���R���f���T�v�̕������܂邲�ƒu�������Ă��s�s���͖����̂ł͂Ȃ��ł����H �@�㔼�A�u���i�K���̕ʁX�̒�d����H��ɂȂ��v�Ƃ����̂ł���A����͂������@���̖���ł�����A���D���Ȃ悤�ɂ��Ă��������B �@�莝���̕��i��Ȃɂ₪�A�V�����P�̓d�����u�����ɂ͑���Ȃ����ǁA�K���Ɋ��Ɏ����Ă���d�����u�𑽒i����Ύg���邾�낤�E�E�E�Ƃ������ŁA�������������ɂ�肽���I���̗��R�Ȃ炻��͂���ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@����������̖�肪�E�E�E�Ƃ��A���i���̂��ƂŁE�E�E�Ƃ��A�����������ł̕s�s����s�o�ϐ��͂��邩������܂��A�����͓̂����ł��傤����A�ʂɏ��i�����Ĕ�����̂ł��Ȃ��A�������̎�Ŏg�����̂Ȃ�{���Ɏ��R�ɑg�ݍ��킹�Ďg�������������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2013/5/3
|
||
| ���e 5/7 |
�����̂����肪�Ƃ��������܂��B ���@���̒ʂ�傫�ȃg�����X�������ł��邽�ߑ�p�Ƃ��ăX�C�b�`���O�d�����Ƃ����l���ł����B(���w�E�̒ʂ�u���b�W����p�ł�) �܂��A�X�C�b�`���O�d����傫�Ȕ͈͂œd���ς���������̕~��������������ꂽ�̂ŃV���[�Y���M�����[�^��ɂȂ����Ƃ��l���܂����B �W�����N�̈��艻�d���̃g�����X��u���b�W�𗬗p����ȂǕʂ̕��@�����߂Č������Ă݂܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B aka �l
|
||
| �f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� | |||
|
��������p����http://eleshop.jp/shop/g/g96I412/ ���x�v����肽���̂ł����A�ǂ�������H�ɂȂ�܂����ˁH�d���͂ǂ������炢���ł����H ������ �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���̃f�W�b�g�́u�U�nju���\���@�L�b�g�v�̓d���d���́A�������ɂ���DC 18V�`24V�炵���̂ŁA�f�W�b�g��DC18�`24V��AC�A�_�v�^�[���L�b�g�ƈꏏ�ɍw������̂��ǂ��Ǝv���܂��B �@�f�W�b�g�̓X������͐e�ł�����A���̃L�b�g���w�����鎞�Ɂu����Ɏg����AC�A�_�v�^�[���~�����v�Ɠ`����A�g������̂��o���Ă����ł��傤�B �@��H�ɂ��āA���̃L�b�g�́E�E�E �� �U���_�C�i�~�b�N�h���C�u �� �e���́ETTL���x��(5V)���� �� �Z�O�����g��a�`g��dp��-�ō��v�X�{ (���_��) �� ���I����G1�`G6�̍��v�U�{ (���_��) �ɂȂ��Ă���悤�ł��̂ŁA�R���g���[����TTL���x��(5V)�o�͂�PIC/AVR�ȂƂ̃}�C�R�����AArduino���̃}�C�R���{�[�h����s�Ȃ��܂��B  �@�P�ɂ��ꂾ���ł��ǂ����̌��ɂP������\�����������Ƃ����ł��܂���A������l�̖ڂɎ~�܂�ʑ����ŁA�������Ō��ƕ\���������ւ��Ă���A���Ȃ킿�u�_�C�i�~�b�N�h���C�u�v���Ă��K�v������܂��B(���̃L�b�g���̂��u�_�C�i�~�b�N�_���^�v�ł������) �@�}�C�R���̃v���O�������^�C�}�[���荞���Ȃǂ��g���āA�|�[�g�ɐڑ����ꂽ���̕\����ɔC�ӂ̕\�����ł���悤�ȁu�_�C�i�~�b�N�_���v���O�����v�������Ă��������B �@���x�Z���T�[�́A�}�C�R���̓��o��(�o����)�|�[�g�ɒ��ڌq�����Ƃ��ł���u�f�W�^���^�^�V���A���ʐM�^�v�ƌĂ�钼�ڃf�W�^���f�[�^�ʼn��x���o�͂���^�C�v���ǂ��ł��傤�B �@�}�C�R���Ɖ��x�Z���T�[�Ԃ́u�o�����ʐM�v�ŁA�}�C�R������̓R�}���h�𑗂�A����ɑ��ĉ��x�Z���T�[������͉��x�f�[�^��Ԃ��悤�Ȃ��Ƃ肪�K�v�ł��B���g���ɂȂ��鉷�x�Z���T�[IC�̎d�l���^�������ɏڂ��������Ă���܂��̂ł悭�m�F���ăv���O������g��ł��������B �@�u�U�nju���\���@��v�̓d����DC18V(�`24V)�Ȃ̂ŁA�u���\����̓d���[�q(CN2)�͂��̓d���ɑΉ������d�����u��ڑ����܂��B �@�}�C�R����H�̓d���́A���̌u���NJ�p�ɗp�ӂ���18V�d������A���^��DC/DC�R���o�[�^���W���[����DC+5V������ċ������Ă���OK�ł��B�}�C�R�����͂قƂ�Ǔd��������܂���A���e�ʂ�DC/DC�R���o�[�^���W���[���ŗǂ��ł��傤�ˁB �@������A�f�W�b�g�̓X����(AC�A�_�v�^�[���o���Ă��������)�u����AC�A�_�v�^�[�̏o�͂���A�}�C�R���p��5V����肽������ǁA�g����DC/DC�R���o�[�^�͂���܂����H�v�ƓX������ɐq�˂Ă��������B �@���̂悤�ȁu���x�v�v���}�C�R�����g�킸�ɑS�����W�b�NIC��A�i���O���i�ō��Ƃ����ւ�ȕ��i���ɂȂ�̂ŁA�����ł͂��̉�H�}�͏����Ă��Љ�邱�Ƃ͂ł��܂���B �@������}�C�R�����ɐڑ����Ďg�p����ړI�Őv����Ă��܂��̂ŁA��H�\�������������R���Z�v�g�ł��g���ɂȂ�̂�������ł��B �@�������A�u�V�Z�OLED���_�C�i�~�b�N�_�����Ă��鉷�x�v��H�v�����ɂ����Ă����u��������Ƃ��A�uBCD�R�[�h�����ʼn��x�����o�͂��鉽�炩�̍H�Ɨp���x�v�����u�v��BCD�o������Ƃ��Ȃ�E�E�E�����������i���g���Đڑ��p�̉�H��g��ł�����ɐڑ����Ďg���邩������܂���B ���Ԏ� 2013/5/2
|
||
| ���e |
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-02912/ �}�C�R�����g�킸�ɂ����g�ݍ��킹����ł��܂����H ������p�p �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@��������́E�E�E�Q�������������A�ʔ��������Ȃ��Ǝv���č���̐������珜�O�������̂ł��ˁB �@���̓d���vIC�łR����S���̂��̂�����u�f�W�b�g�̃L�b�g�͂U������̂ŁA�����Q�������g��Ȃ��悤�Ȏ₵�����͂��Ȃ��ōς��v�Ƃ悩�����̂ł����AJRC�ɂ͂��̂Q���̂������������̂ł��Ȃ�܂�Ȃ��Ǝv�����O���܂����B �@�̂�(���̃��[�J�[���ł���)�R�E1/2���̓d���vIC�Ƃ��A�F�X�����Ă����̂ł����ǁB �@����ŁA�������̃L�b�g�Ŏg�p���Ă���NJU9252A(�܂���P)���g���Ȃ�A �� �Z�O�����g�o�����o�`���l���|�I�[�v���h���C���o���łł��� �� ���Z���N�g�o�����m�`���l���|�I�[�v���h���C���o���ł��� �Ƃ������Ȃ̂��Z�O�����g�o�͂͂��̂܂܁u���_���v�Ŏg�p�ł��܂��B �@���Z���N�g�o�͂͂m�`���l���ł�����u���_���v�ƂȂ��̂ŁA�Ȃ�炩�����]��H�Ř_�����]���Ču���NJ�ɓ���Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁATTL(74HC�V���[�Y��)���W�b�NIC�̃C���o�[�^�Q�[�g�Ŕ��]�����Ă�邩�A�g�����W�X�^�Ŕ��]��H��g���K�v������܂��B �@�܂��Q�r�b�g�����Ȃ̂ŁA�g�����W�X�^�ł��������ȁE�E�E�ƁB 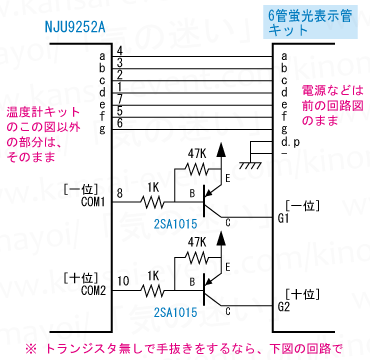 �@����ŁANJU9252A���Q�������̏o���Ɍ������b�ŁA���ANJU9252A�̃f�[�^�V�[�g�Ń^�C�~���O�}���������COM1��COM2�����S�Ɍ��݂ɐ�ւ���悤�ŁA�ؑւ̊Ԃɉ������̏�ԂɂȂ���Ԃ������̂œ��ʂɃg�����W�X�^��������Ȃ��Ă����M���𑊌݂ɑ���̋t���M���Ƃ��đ��������ƂŁA�g�����W�X�^�Ȃǂ͏ȗ����Ďg�����Ƃ��ł��܂��B 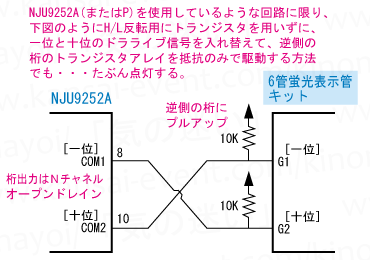 ���Ԏ� 2013/5/3
|
||
| �ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� | |||
|
�����d�q��H�y�ѐ���n�ɂ��Ƃ����̂ł��B ���ԏC���s�\�@�B���X�s�[�h���[�^�[�y�у^�R���[�^�[�u�����A���[�^�[�쓮���[�^�[���j�b�g�̐�����������̂ł����X�������肢���܂��B �ȉ��K�v�Ǝv��������L���܂��B �Ώێԗ�:�p���ԁ@1960�N�ȑO��4�T�C�N������6�C�����ڎԗ��S�ʁ@ �G���W���F4�T�C�N������6�C���@ �d���F�_�C�i�����d�@12V�o�b�e���[_���d���i10V����15V)�v���X�O�����h�@ �_�Ε����G�V���O���R�C���@�f�X�g���r���[�^�[�@�@�B���R���^�N�g�u���[�J�[���i�|�C���g�j ���상�[�^�[�v��_ ���[�^�[�F�v�ɗ͏��^�@�Q�Ɨ�X�e�b�s���O���[�^�[�̏ꍇ/COPAL SG20-1332�� �X�e�b�v�p/�X�e�b�s���O���[�^�[�̏ꍇ�F1-2�x ���[�^�[�d�l/�X�s�[�h���[�^�[�F�X�P�[��/0����140Mile/H�@�U��p/270�x�@���߈ʒu/70Mile/H�@7��30���ʒu/0Mile/H�@��]����/���v��� ���[�^�[�d�l/�^�R���[�^�[�F�X�P�[��/0����6000rpm�@�U��p/270�x�@���߈ʒu/3000rpm�@4��30���ʒu/0rpm�@��]����/�����v��� ���͐M��/�X�s�[�h���[�^�[�F�@�Z���T�[/�I�[�v���R���N�^�[�A���v�����z�[���Z���T�[�@�����d��/5-15V�@�Z���T�[�o�́i�g�`�j/0-�d���d���i�d���d����ׁj�@�p���X��/10520.7952�p���X1mile�� ���͐M��/�^�R���[�^�[�F�C�O�j�b�V�����ꎟ�R�C���M��/0-�d���d���̒f���œ�����M���@�M�����d���͖��v���@�@�B���R���^�N�g�u���[�J�[�ׁ̈A�v�m�C�Y��@�p���X��/3�p���X�G���W����]�� ��H�}�̍쐬�Ȃ�тɃv���O�����ɑ��鏕�������������܂����炠�肪�����ł��B Tomo �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͂��߂ɁA���̎茳�ɂ��̔N���E�����̎ԂƂ������̂������̂ŁA��H�}�ɂ��Ă͂����܂ŗ����̏�Ƃ��A�z���̏�ł̘b���ƂȂ�܂��B���������������B �@�X�s�[�h���[�^�[�̃Z���T�[�́A�z�[���Z���T���Łu�I�[�v���R���N�^�o���v�Ƃ̎��ł�����A�I�[�v���R���N�^�ړ_�̏�Ԃ�m�邽�߂̉�H�ł����̂ŁA���ɓ���͖����Ǝv���܂��B �� �u�v���X�A�[�X�ԁv�Ƃ̎��ł����A�I�[�v���R���N�^�o�͎͂Ԃ̃o�b�e���[�́{�ɂ��|�ɂ��q�����Ă��Ȃ��A���R����I�[�v���R���N�^�́u�ړ_�v�ł��鎖�������ł��B �@�^�R���[�^�[�̂ق��́A�M�������C�O�j�b�V�����R�C���̗��[������������Ă���Ƃ������ŁA12V�M�����|�C���g�ړ_��ON/OFF����Ă����Ԃ̃R�C���[�ł�����ړ_OFF���ɂ����ɑ傫�ȋt�d������������Ǝv���܂��B �@�ł��̂ŁA�t�d��������Ȃ��悤�����������͂ŁA�|�C���gON��12V��(������������̓p���X�I�ȍ��d���m�C�Y������)�ɔ����A�|�C���gOFF�Ŗ��d�����t�d���̎��ɂ͖������ȓ��̓J�b�v�����O��H���������Ƃ����b�ł��ˁB �@����ŁA���[�^�[�̐j�����̂�COPAL SPG20-1332(�H���Ŕ̔�)�̂悤�ȁu�Q�����j�|�[���E�X�e�b�s���O���[�^�v�ł���ƁB �@����́APIC��AVR���̃}�C�R���Ă悭�Ă��鏬�^�X�e�b�s���O���[�^�[�Ȃ̂ŁA�̂ɂ̓n�[�h�I�ɂ��\�t�g�I�ɂ����ɓ���Ƃ���͖����Ǝv���܂��B �@�Q�l��H�͂��̂悤�Ȋ����ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@���x�Z���T���̓��͉�H�́A��قǂ̎��ł���������A�������Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B �@�z�[���Z���T�̏o�͂��I�[�v���R���N�^�o�͂ŁA��{�I�ɂ��o�b�e���[�́{�Ƃ��|�Ƃ��ڑ�����Ă��Ȃ����A�����Б����ڑ�����Ă���̂ł�����G�~�b�^�����}�C�i�X�ڒn����Ă���^�C�v���g���܂��B �@�Ԃ��v���X�A�[�X(�v���X�ڒn)�̂悤�ł����A�z�[���Z���T�̉�H�ɗ^����d���z���͎ԑ̃A�[�X�Ƃ͓Ɨ���12V��^���Ă���Ζ��͂���܂���B �� �������ł��g���̃z�[���Z���T���j�b�g�̐������܂��͉�H�}�ł悭���m���߂��������B������ł͎����ł͊m�F�������ł��܂���B �@�t�H�g�J�v����12V�n��5V�n�̃J�b�v�����O��������A�}�C�R���̓��̓|�[�g�ɐڑ����܂��B �@�Ԏ��̉�]�Ƌ��ɐ������p���X��Ԃɂ��̏o�͂�0V/5V�ɐG��Ă��邩�A�p���X�`��͐��������A�Ȃǂ̓I�V���X�R�[�v��ڑ�����Ȃǂ��Ă��m�F���������B �@��]��(�_�ΐ�)�̓��͉�H�́A�C�O�j�b�V�����R�C���ꎟ���d�����V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�Ő���(�t�d���h�~)������A���d���ł̃m�C�Y�����i���o�ăt�H�g�J�v����LED�����点�܂��B �@�����̃C�O�j�b�V�����R�C��(�Ԃɍڂ�����Ԃœ��삵�Ă������)���茳�ɖ����̂ŁA�ʂ����Ăǂꂭ�炢�̋t�d���p���X���������Ă���̂��s���ł����A�ϓd��100V�̃V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h���R�����300V�܂ł͂قږ��Ȃ�����(�j�~)�ł���͂��ł��B �@�����������Ă����ƍ����t�d�����������Ă���A�K�v�{������ɑ��₵�Ă����Ǝv���܂��B �@���ꂾ���́A�{���Ɏ茳�ő�����������ł��܂���A�{���ɖ��Ȃ��g����̂��H(�����Ԏg�������̑ϋv���́H)�͒��ׂ��܂���B �� �ł�����A�ߋ��ɂ��C�O�j�b�V�����R�C������d����������ĉ�]���p���X�����Ƃ��������₪�o�����ɂ͂��f�肵�Ă��܂����B �@�X�e�b�s���O���[�^�̋쓮��H�́A������{�I�ȃp���[MOS-FET�ɂ��S�R�C���ʂ̃��j�|�[���쓮��H�ł��B �@MOS-FET�ɂ͒P�̂̂��̂��S���ׂĂ��ǂ��ł����A�K���H���ł͂��������p�r�p���p���[MOS-FET���W���[��������ޔ����Ă��܂��̂ŁA���̒����珬�^�̂��̂��g���Ă݂܂��傤�B �@�}�C�R���̏o�̓|�[�g��H�ɂ���R�C���̓d��������܂��B �@�v���O�����ɂ����́A���̃R�[�i�[�ł͏ڂ����͂��������Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��̂ŁA�ƂĂ������܂��ȃA�E�g���C�������B �@�X�s�[�h�^��]��������ɂ��Ă��A���ꂪ�ǂ̂��炢�̒l�Ȃ̂������̓p���X�̊Ԋu�E�����𑪒肵�ċt�������߂܂��B �@��̓I�ɂ́A���̓|�[�g�́u���荞���v�@�\�œ����n�[�h�E�F�A���荞�݃v���O�����������A�}�C�R�������̃^�C�}�[�@�\���g���ăp���X�ƃp���X�̊Ԋu�𑪒肵�܂��B �@���̊Ԋu���ԂƁA���̃p���X����������̏���(���]���x�Ƃ��c)�Ȃǂ���v�Z����A�X�s�[�h(Km/h)���]��(rpm)�͓����܂��ˁB �@��́A���荞�݂Ƃ͕ʂɏ펞���[�v���Ă��郁�C�����[�`���̂ق��Łu����̐j�̈ʒu�ɃX�e�b�s���O���[�^���^�܂��͍��̈ʒu�ɐÎ~�������v�����𐏎��s�Ȃ��A���x���]���ɉ����ďu���Ƀ��[�^�[�̐j�������܂��B �@��H�}�ɂ͈ꉞ���~�b�g�Z���T�[��t������悤�ɂ��Ă���܂����A�d������ꂽ���̐j�̈ʒu���s��ȏꍇ�Ȃǂ��l�����āA���[�^�[�̂O�ʒu���o�p�ɃZ���T�[�����Ă������ق����ǂ��Ǝv���܂��B �@�����ݒ菈���Łu�O�ʒu�̊m�F�v��u���[�^�[�쓮�e�X�g�v�Ȃǂ��s�Ȃ����ɂ͂O�ʒu�Z���T�[�������ƕs�ւł��B �@���������ł���̂͂����܂łł��B >�����d�q��H�y�ѐ���n�ɂ��Ƃ����̂ł��B �E�E�E�Ƌ��Ă���̂ŁA�v�ɂȂ鎩��\�t�g�E�F�A�̂ق��͂��������̘r�O�Ȃ̂ł��傤�ˁB(���܂��������K�v�͖����������Ȃ�) �@�X�e�b�s���O���[�^�[���Ȃǂ̎Q�l�ɂȂ肻���ȃy�[�W���l�b�g�ł݂���Ǝv���܂��B �@������Đ��삵�Ă��������I ���Ԏ� 2013/5/2
|
||
| ���e 5/14 |
���ԓ����肪�Ƃ��������܂��B ������ƁA������Ă݂܂��B Tomo �l
|
||
| LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H | |||
|
���߂܂��ēd�C�̂��Ƃʼn���Ȃ��̂ŋ����Ă��������܂���ł��傤���H�H�H LED�d�����t���Ă����v���X�}�C�i�X�[�q����d��5V�������̂�5V�̓��d����_���悤�Ƃ��܂������_���܂���B ���̂ł��傤���H�H ���Ƃ��_������ɂ͂ǂ�������悢�̂ł��傤���H�H ���Z�����Ƃ��낷�݂܂��B�B ���������������܂�����K���ł��B ��낵���@���肢�������܂��B masakoba �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����A�����͂P���Ǝv���܂����A�z�����Ԉ���Ă����炢���Ȃ��̂Ŏ���ł��B (1) ����͉��ł����H �@���̑��u�E�@���LED�d�������Ă��āA�Ȃ�������O�����Ƃ����̂ł����H (2) �uLED�d���v���āH �@�uLED�d���v�ƌ����A�Ƃ̓V��̏Ɩ����ɂƂ����A�u�]���̓d���Ɠ����`�������d���^��LED����v��u�����d���Ȃǂ̓��d���̒u�������p�́A���d���Ɠ����`������LED�Ɩ��d���v�̂��Ƃ������܂����A���Ȃ���(�����O����)�d���𑪒肵���ꏊ���āA���������˂����ݎ��̓d���\�P�b�g�̋���E�[�q�̕����̃v���X�ƃ}�C�i�X�Ȃ̂ł����H �@����Ƃ��A���̉��߂͊ԈႢ�ŁALED�d���Ə�����Ă���̂́u�d�q���i��LED�f�q�v�̂��Ƃł����H�@�P�ɑ�(�d��)����{�����Ă��钼�a5mm���x�̓����ȁB �@���̋@��̂ǂ̕�������ǂ�Ȍ`���傫����LED�d�����O�����̂��B �@������ڂ��������Ē����Ȃ��ƁA�Ԉ���������Ă��܂��Ă͐\�����̂ŁA�ڂ������������������B ���Ԏ� 2013/4/30
|
||
| ���e |
���Z�����������̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B HC-1000�Ƃ����E�G�u�J�����̏Ɩ��ł��Ċ�Ղ��璼�ڑ���{��LED�����Ă���܂��B ���������̒��ɋ�����{�����������������Ă���܂��B ���̎����������R�[�h���͂t�����ēd���ɂȂ��܂����B 5V����܂������_���܂���B�B�d��������Ȃ��̂ł��傤���H�H �Ɩ����Â��悭�����Ȃ��̂Ŗ��邭���悤�Ƃ����̂ł����A�A�A ���@����܂����炨�����������܂��B ���݂܂��@�X�������肢�v���܂��B�B�B masakoba �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���i���ƁA�ǂ����ǂ������̂����������������܂��āA���肪�Ƃ��������܂��B �@�����ւ炩�Ƒ����܂����E�E�E�C�e�^LED���āA����������ă��[�h(��)���o���ɂ��āA�����Ƀ��[�h�����q���œd�C����낤�Ƃ����l�͏��߂Ăł��I �@���d�����_���Ȃ����R�͑z�������Ƃ���ł������A�܂�������������������Ă����Ƃ́E�E�E�B �@���߂Ċ����n���_��n������LED�̑����āA�����Ƀ��[�h���ł��n���_�Â����ē��d�����q���ł����̂��Ǝv�����̂ł����B �@�ŁA���_������ɏ����ƁA���R�̂��ƂȂ���A���̂悤�ȕ��@�ł͓��d���͌���܂����B >���߂܂��ēd�C�̂��Ƃʼn���Ȃ��̂� �@�Ƃ͏�����Ă��܂����A�uLED�Ƃ͉����H�v��uLED��_���������H�̍����v���͕�����܂������H �@����͓��d�������悤�Ƃ��ꂽ�悤�Ȃ̂ŁA�uLED��_��������v�Ƃ����b�͕ʖ��Ǝv���Ă���̂�������܂��A���X������LED���t���Ă���̂ł�����A���R�uLED��p�̓_����H���g�ݍ��܂�Ă����v�uLED�Ƃ͓��d���Ƃ͈Ⴂ����ȓd�q���i�ł����v�Ƃ����F�����炢�͎����āA����ɂ��Ē��ׂĂ݂�Ǝv���̂ł����A�ǂ�����܂������H �@LED�̓g�����W�X�^�ȂǂƓ����������ł��B �@�d�C�I�ɂƂĂ���������i������A���͈̔͂�菭�Ȃ��d���E�d���ł͌���܂��A�ߑ�ȓd���E�d����^����Ƃ����Ƃ����܂ɔj��Ă��܂��܂��B �@����ꂽ(���ꂽ)�̂�5mm�C�e�^�̔��FLED�ŁA�W���I�Ȑ��i�ł�����������������d��(Vf)��3.0�`3.3V���x�A�������d��(If)��20mA�ȉ��Ƃ����l�����Ȃ��ƁA����Ȃ����Ă��ĉ��܂��B �@�ł�����A������H�d���d����DC 5V�ł���A�����Ă����d��������R�����āALED�ɂ�����d���E�����d������i�ʂ�ɂȂ�悤�ɂ�����H���v����đg�ݍ��܂�Ă��܂��B �� ���̉�H����������܂����A���܂�g���Ȃ��̂ł����ł͐����͏ȗ����܂� �@�d��������R�̒�R�l�͉��}�̒ʂ�̌v�Z���ŋ��߂��܂��B 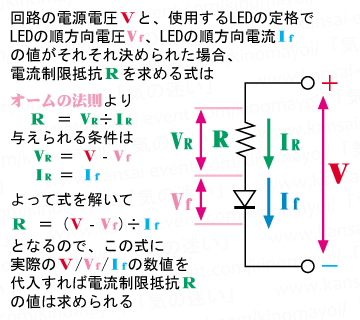 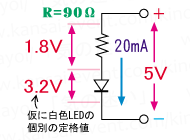 �@����ŁA����ꂽ(���ꂽ)���̂͑����E�}�̂悤�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��B
�@����ŁA����ꂽ(���ꂽ)���̂͑����E�}�̂悤�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��B�@�����������Ă��Ȃ��̂Ő��l�͂��������悭������̂Ƃ��Ă��܂����A�Ɩ��p�̔��FLED��Vf=3.2V�EIf=20mA�Ƃ��āA�d���d����V=5V�B �@������d��������R��90���ƌv�Z�ł��܂��B �� ���ۂ̒�R�ɂ�90���i�͖����̂�91���Ƃ�100���Ƃ����g�p����܂�  �@���������������i��LED����(�O����)�����̓d�����e�X�^�[�ő������ꍇ�A�E�}�̂悤���e�X�^�[�̕\����5V�������܂��B
�@���������������i��LED����(�O����)�����̓d�����e�X�^�[�ő������ꍇ�A�E�}�̂悤���e�X�^�[�̕\����5V�������܂��B�@LED���O���Ă��܂��āA�����Ƀe�X�^�[���d���v�����W�Őڑ������ꍇ�A�d���v�̓�����R�͔��ɍ����̂ŁA���̓d��������R�ƃe�X�^�[�̓�����R(���ɍ���)���������Ō��߂����e�X�^�[�̗��[�ɂ�����d���́A�قړd���d���Ɠ��������ƂɂȂ�A�\����5V�ł��B �@�t�Ɍ����A���̉�H�����m�̓d���d���͑���5V�ł��낤�Ƃ������_�������o����������ʂł��B 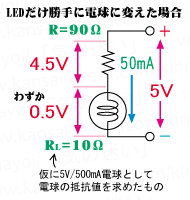 �@�����āA����LED�_����H����LED���O���ē��d�����q���ǂ��Ȃ邩�E�E�E�B
�@�����āA����LED�_����H����LED���O���ē��d�����q���ǂ��Ȃ邩�E�E�E�B�@���ɁA��i 5V/500mA �̓��d�����q�����Ƃ���ƁA���d����LED�̂悤�Ȕ����̂ł͖����P�Ȃ��R�Ƃ��Čv�Z�ł����̂ŁA5V/500mA�Ƃ�����i����(����)���d���̓�����R��10���ƂȂ�A��R�l10���̓��d�����قǂ�LED�_����H�ɐڑ�����ƉE�}�̒ʂ��d��������R�̒l�Ɠ��d���̓�����R�̒l������ۂɓ��d���ɂ�����d���E�����d�����v�Z�ł��A���d���ɂ͂�����0.5V���������炸�d����50mA��������܂����B����ł͌���܂����ˁE�E�E�B �@�d�C�̊�b�I�Ȍv�Z������������o����悤�ɁA���RLED�_����H�̒�����LED���������āA�����ɓ��d�����q���ł�����킯�������킯�ŁA����s�Ȃ�ꂽ�悤�Ȃ������������͖��Ӗ��ł��B �@�����u�P��(�펞�_�����Ă���)LED�̂����ɓ��d�����������v�Ƃ�������]�ł�����A�d�������p��R��ʂ�Ȃ��A������5V�d���̂Ƃ���Ƀ��[�h�����Ȃ��ŁA5V�̓��d�����Ȃ������ł���ˁB �@���������ɂ́A���u�̊�p�^�[������͂��āA�ǂ������������d�����ǂ����A�܂������Ɂu����Ȃ��̂��q���ł��܂��Ă������̂��H�v���悭�m�F���Ă���������܂��傤�ˁB �@���́E�d�q��H�v�̒m���ƋZ�p���K�v�ł��B �@����ŁE�E�E��舵���������ɂ��ƁA����HC-1000�J�����ɂ́u�Ɩ�LED�����u�n����ON/OFF�ł���@�\���t���Ă���v�悤�Ɍ�����̂ł����H �@�Ƃ������́A����LED�̓_����H�́A��̐}�Ő��������悤�ɒP����5V�̓d���Ɍq�����Ă���̂ł͂Ȃ��I�Ƃ������ł���ˁB �@�u�����[�g���삵�Ă���l����Ɩ�ON/OFF�ł���悤�A��������Ă���R���s���[�^�`�b�v���琧�䂳��Ă����v�͖̂����ł���A�����Ȃ���}�C�R���`�b�v��I/O�[�q����LED�ɓd�����o�͂���Ă���A�������͉��炩�̃g�����W�X�^�Ȃǂ����ON/OFF����Ă����͂��ł��B �@�����A�}�C�R���`�b�v��I/O�[�q����d�����o�Ă���Ƃ���ƁA����ȂƂ���ɓ��d���Ȃq������}�C�R���`�b�v��j��Web�J�������̂��I�V���J�ɂȂ�I�Ƃ����������ɍ����\���Ƃ��čl�����܂����A�����g�����W�X�^����������ē_�������Ă����Ƃ��Ă��A���i�̗l�q���������(�v�ʂ�)����LED��_��������̂����傤�ǂ��炢�̃g�����W�X�^���g���Ă��āA�����ɓ��d���Ȃq�������g�����W�X�^�����ʁI�Ƃ��������l�����܂��B �@�܂�A���������āu�Ɩ�LED���ǂ����䂵�Ă���̂��H�v�ׂāA����ɍ������u���d���_����H�v��v���Đڑ����Ă��Ȃ��ƁA���Ղɓ��d���Ȃq�����Ƃ����瑽���{�̂��Ă��܂��āA�J�����Ƃ��Ďg�����ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��\���������ł���B �@�����ւ�\�������܂��A�����܂łɐ������Ă����l�X�Ȍv�Z���◝�����킩��Ȃ����炢���d�C�̎����킩��Ȃ����ł���A���Ƃ������]��ł��uLED���O���Ă������瓤�d�����������I�v�Ƃ������ȉ����ɂ͎���o���Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B �@�������Ȃ����d�q�H��̌o��������A�d�q�p�[�c���Ă��Ă������ōH�삪�ł����̂ł���A�g�����W�X�^�Ȃǂ��g�������d���̋쓮(�_��)��H�Ƃ������̂�g�ݗ��ĂĐڑ���������̂�������܂��A���d������炢�Ȃ�ő�1A�܂ň�����u�t�H�gMOS-FET�v������ł�������������܂���B �@�u���C�����X�`���C����LED�ő��̋@����������v�ł��Љ�Ă���t�H�gMOS-FET(G3VM-61B1)�����ł����Ǝv���܂��B �@����ƍŌ�ɁA���̃J���������������ꂽ�܂܂̖{�̈ȊO�ɁA���d���Ȃq���ł�_����������قǂ̗]�T���������d���������Ă���̂ł����H �@�d����H�̉���ł����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ǝv���܂����A�e�ʂ�����Ȃ��d����H�ɉߕ��ׂɂȂ铤�d���Ȃq���ƁA���Ԃ��d�����Ă��āA�J����������ł��܂��܂����B �@�܂��A�u�������Ă݂ăJ���������Ă��܂��Ă��\��Ȃ����`�v�Ƃ����]�T�̗L����Ȃ炢���̂ł����A�J�����������Ȃ����Ȃ炻�̃J�����ɒ��ړ��d�����q���ŁA�J�����̓d���ɉߑ�ȕ��S�������Ȃ��ق��������ł��傤�ˁB �@���d���p�̓d�����ʂɗp�ӂ��āA����œ��d�������点����悤�ȉ�H��g�ݗ��ĂȂ���Ȃ�܂����ˁB�E�E�E�����B ���Ԏ� 2013/5/8
|
||
| ���e 5/9 |
���Z���������̂悤�ȂǑf�l�ɂ����J�Ȃ��Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B ���C�����X�`���C����...�����Ă݂܂��ďo���Ȃ����Ȃ���߂܂��B �{���ɗL���������܂����B�B�B masakoba �l
|
||
| �ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H | |||
|
���߂܂��āA�ȑO���Q�l�ɂ����Ē����Ă���܂��B �ԓ��̎���LED�C���~�̓_�����^�N�gSW�ɂēd����I�����A�X���[�������v�A��ON�^�L�[�iAcc)�A��ON�^OFF�ɐ�ւ������A�Q�l�ƂȂ��H�i�}���`�v���N�T��H�ƌ����̂ł��傤���H�j��T���A���L�̋L�������t���܂����B http://okwave.jp/qa/q5584624.html �M�T�C�g�́u�Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H���c�v���Q�l�Ƀt���b�v�t���b�v��H����낤�Ƃ����ہA4027B������o����4013BP�̉�H�����A�\���Ƃ��čw������4013BP���]���Ă���܂��̂��A������g�������o���čD�s���Ȃ̂ł����A��L��H��OFF�i���͂Ȃ��j�̎d��������܂���B �܂��A4066�Ȃ�IC�iuPD�H ��PD�H TC�H�j�̃f�[�^�V�[�g�����������čő��i��13V�ł�������20V�ł�������ŎԂŎg�p�ł���̂��c�A�I����R��100��������̂�12V�d����LED�C���~��ON/OFF�o����̂��c�A�ǂ�����܂���B ��LED�C���~�̏���d���͐�10mA�i2����LED�����ꂼ��15mA�œ_���j�Ȃ̂ŁA��H�̏��^���̂��߂ɏo��������[���g�킸�ɍς܂������Ǝv���Ă��܂��B �������A4013BP���g�p���Ȃ���H�ł��\���܂���̂ŁA�h�v�b�V��SW�Ń��[�^���[SW�̗l�ɐڑ����ւ����H�h����������ƗL������܂��B ��]��H�̎d�l�F ��H�̓d����Acc�i11�`15V�j�A��H���̂�5V�i���M�����[�^�[�g�p�j�ł�OK�B ���͂�A�i�X���[���j�AB�iAcc�j�AC�iOFF�j��3�ړ_�ŁA�o�͂�Acc�����i11�`15V�j��50mA�����OK�B �L�[ON�i�����ݒ�j��A�ɐڑ��A�X�C�b�`����������A��B��C��A���J��Ԃ��B �o����ATC4013BP���g�p�B �o����A�����[���g�p���Ȃ��B �����_�ł�3�ړ_�̓��͂��l���Ă���܂����A�X�C�b�`IC�ɋ�����iIC��lj����Ȃ��čςށj�ꍇ�́A�h�A�����v�A��ON��펞�d����ON�i��H�̓d�����o�b�e���[������܂��j�ɔ����A�ړ_��lj�������@��������������Ƒ����܂��B �X�������肢�v���܂��B ���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
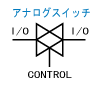 �@���[�ƁE�E�E�E�A4066B [PDF]�́u�A�i���O�^�f�W�^���M���p�̑o�����X�C�b�`���O�Q�[�g�vIC�ł���B
�@���[�ƁE�E�E�E�A4066B [PDF]�́u�A�i���O�^�f�W�^���M���p�̑o�����X�C�b�`���O�Q�[�g�vIC�ł���B�@�_����H�I���Q�[�g��H�E�f�q�Ȃ̂ŁA���[�^���[�X�C�b�`�̂悤���d�C�𗬂����ǂ�����ւ���d�C�ړ_�Ƃ��Ă͎g���܂���(�g���܂���)�B �@�����C���s�[�_���X�������A�ϓd���������Ȃ��̂ŁA�����M���E�f���M���E�Z���T�[�M���̂悤�Ȕ���M�����ւ���p�r�Ɏg�p���A�܂�ON��R(�C���s�[�_���X)�������̂ŏo�͂ɂ��I�y�A���v���̍��C���s�[�_���X���͉�H��ڑ�������A�g�����W�X�^�̃x�[�X�d�����̔����ȓd���œ��삷���H���q���Ďg�p���܂��B �@�Q�l�ɂ��ꂽ�����̃y�[�W�ł��u�����M���̐ؑ։�H�v�̎���Ɖł���A�d���̗�����H(����)���ւ����Ƃ������ȍ�i�ł͂Ȃ��ł���H �@�A�i���O�X�C�b�`�́A���ʂ�Hi��Low�̂Q�l���������Ȃ��f�W�^�����W�b�N��H�ŁAHi�ł�Low�ł��������̊Ԃ̃A�i���O�d����`����^�`���Ȃ��̐��䂪�ł������ȁu�Q�[�g�v(�u�X�C�b�`�v�ł͖����u�Q�[�g�v)�Ȃ̂ŁA�������d�C��ʂ����ǂ�����ւ������߂́u�X�C�b�`�v�u�����[�v�Ƃ͑S����������i�ł�����A����̂��]�݂̗p�r�ɂ͓K���܂���B �@����̂���]���킸�����\mA�ł��̂ŁA�m���ɂȂ�Ƃ�4066B����ꂸ�ɍςޔ͈͓��H��������܂��A��H�v�エ���߂ł��Ȃ����̂ł����炻��͎g���܂���B �� �����H�ɁA�d�q��H���ʼn�H�̈ꕔ�́u�d���v���ւ���̂ɃA�i���O�X�C�b�`���g�p���Ă�����̂����݂͂��܂��B�A�����̏ꍇ�͏n���̏�Őv����Ă��āA���̉�H�}�������悭�m��Ȃ��l�����̗p�r�Łu�����A�d���X�C�b�`�Ɏg����I�v�Ɗ��Ⴂ����̂������̂ŁA��̓I�ȗᎦ�͔����Ă����܂��B �@�A�i���O�X�C�b�`�͎g�킸�ɁA�g�����W�X�^��FET���g�����X�C�b�`���O��H�ōl�����ق����ǂ��Ǝv���܂����A�������ł��傤�B �@���ɁA >��L��H��OFF�i���͂Ȃ��j�̎d��������܂���B �Ƃ��������ł����A������܂���H�̂����݁E����ɑ��ĕs�\�Ȃ���]������Ă����܂��B 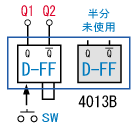 �@�u�Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂����v�Œ��Ă����H�́w�s�|�e�e(�g�O���E�t���b�v�t���b�v)�x�ł��B
�@�u�Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂����v�Œ��Ă����H�́w�s�|�e�e(�g�O���E�t���b�v�t���b�v)�x�ł��B�@���̂p���`�y�[�W�Ŏ�����Ă���̂�4013B���g�p�����g�O���t���b�v�t���b�v�ł��B �@�g�O���t���b�v�t���b�v�́u�g�O������������t���b�v�t���b�v�v�ł��B �@�g�O�������Ƃ́uON���^OFF���v���Q�̏�Ԃ̂��������ꂩ�Е��̏�ԂɂȂ铮��ł��B �@�u�Ԃ̎�������O�ƌォ��c�v�̉�H��A���̂p���`�Ŏ�����Ă����H�ł��P�̃g�O���t���b�v�t���b�v(JK-FF�܂���D-FF��T-FF�Ƃ��ē�����H�Ƃ��Đڑ�)���g���A�����o�͂p�����]�o��^�p���Q�̑��������Ԃ��o�͉\��D-FF�܂���JK-FF IC���g���Ă���̂ŁA���݂ɔ��̏�ԂɂȂ�o�͒[�q��p���Q�o�͂ł������Ƃ��g�p���Ă��Q��Ԑؑ։�H�ł��B �@���̂悤�ɁA�g�O���t���b�v�t���b�v�P�������ƁuON��OFF���̂P�o��(Q)���������Ȃ��v�u���]�o��(^Q)�[�q���L��ꍇ�͐����o�͂ɑ��Ĕ��]�����o�͂�������v�Ƃ����g���������ł����A���]�o�͂𗘗p����ƂQ�ڂ̏o�͂������o�͂̋t�̐M�������o�Ă��܂���B �@����b��������܂��A���������킯�Ńg�O���t���b�v�t���b�v�P�����Ɓu�o�͂P=ON�^[���]����]�o�͂Q=OFF�v�܂��́u�o�͂P=OFF�^[���]����]�o�͂Q=ON�v�������ꂩ�̏�Ԃ������܂�������A���Ȃ��������]�݂́u�o�͂P=OFF�^[���]����]�o�͂Q=OFF�v�Ƃ��������̏o�͂�OFF�̏���͍��܂����B �@����͂����܂Ńg�O���t���b�v�t���b�v�P�����ł̘b���ŁA�O���ɂ����ƐF�X�ƃQ�[�g��lj����Ă�₱������H��g�݁A�o�͐M���𐧌䂷��悤�Ȃ߂�ǂ�������������A�g�O���t���b�v�t���b�v�P�����ɒlj���H�ł�����͎����ł��܂��B �@�������A����͂��܂�X�}�[�g�ł͂Ȃ��A���p�I�ł�����܂���B �@�X�C�b�`���������тɁu�P���Q���R���P�c�v�Ə��ɐ�ւ���čŌ�܂ōs������܂��ŏ��ɖ߂�悤�ȉ�H��d�q��H�ł́u������H�v�ƌĂт܂��B �@������H�̍����͂��낢�날��܂����AD-FF IC�ł���4013B���g���Ă����܂��B 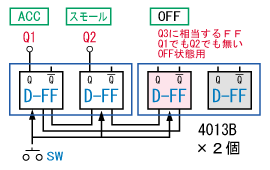 �@�u�\���Ƃ��čw������4013BP���]���Ă���܂��̂��v�Ƃ������ł����A�����]���Ă���̂ł��傤���H �@�Q�]���Ă���̂ł���A���Ȃ��̎茳��4013B�����ʼn�H�����܂����A����Ȃ��Ƃ܂��������ƂɂȂ�܂��B �@D-FF���g����������H�ł́A�N���b�N�M��������(�X�C�b�`���������)���тɂP�ׂ�D-FF�̏�Ԃ�����D-FF�Ɏn����A���ꂪ�S����D-FF�ŃN���b�N�M�����������u�ԂɈ�ĂɋN����̂ŁA�S�Ă̏o�͂̏�Ԃ��P���ɃY���܂��B �@D-FF���g�������̉�H�̏ꍇ�A�ׂɏo�͂������ON�ɂȂ��Ă���Ƃ����K�R�����Ȃ��A�C�ӂ̕����̏o�͂�ON�ɂ��Ă����āA���ꂪ�P�N���b�N���Ƃɉ��ɃY���Ă䂭�Ƃ������Ȏg�������ł��܂��̂ŁA���Ƃ��ΊŔ̂܂��ɂ����Ɠd����������������d���ŔŁA���̓d�������������_�������p�^�[���������邮��ƊŔ̎�������Ƃ����A���Ȃ��݂̓d���Ŕ̒��̉�H�Ƃ��Ă��L���ł��B �@��̐}�ł͐������ȗ������邽�߂ɂ����ď����Ă��܂��A����̂���]�œ��삷�邽�߂ɂ́u���Z�b�g���ꂽ���ɂ͏o�͂P�݂̂�ON�A����OFF�v�ɂȂ�z�����K�v�ł��B�z���͕K�v�ł������ɒlj���IC���͗v��Ȃ��̂Ő}�����Ă��܂���B �@�����āA���������u�ׂ̃f�[�^���P�N���b�N�łP�ׂɈڂ���鏇����H�v�́u�V�t�g���W�X�^�v�Ƃ���IC��H�ŁAS���W�b�NIC��4000�ԃV���[�Y��74xx�V���[�Y�Ȃǂł͒�Ԓ��̒�Ԃł��B �@���낢��ȃr�b�g���⓮��̃V�t�g���W�X�^IC�����݂��܂��B �@���āA�b��߂��āu�o����ATC4013BP���g�p�B�v�Ƃ�������]�ɉ����āA����]�̌㔼�́u�T�����v�ɂ����ꍇ�͂��̂悤�ɂȂ�E�E�E 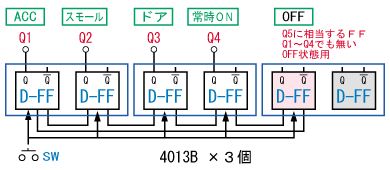 �@�I���\�Ȓ[�q��(�o�̓r�b�g��)�𑝂₹�A���R���̃r�b�g������D-FF�̐���������̂ŁAIC���͂ǂ�ǂ��Ă䂫�܂��B �@����ł́u��H�̏��^���̂��߂ɏo��������[���g�킸�ɍς܂������v�Ƃ�������]�ɔ����Ă��܂��܂��H �@�u�o����ATC4013BP���g�p�B�v��D�悷��ƁA���X��4013B�������āA�ꏊ���ǂ�ǂ�Ђǂ���H�Ƃ������̂��d�オ��܂����A�R���p�N�g�������莝���ŗ]���Ă���IC���g�������I�̂ق���D�悷�ׂ����A�����܂łǂ̏����ɂ��u�o������v�Ə�����Ă�̂łǂꂩ�͎̂ĂĂ����������ق����A�����I�ɂ͂�育��]�ɉ��������̂��ł���Ǝv���܂��B �@�����Y�o���A4013B���g�������Ƃ�������]�̓X�p�b�Ǝ̂ĂĂ��������āA�ʂ�IC(�V�t�g���W�X�^�Ƃ��c)���g����IC���͌������܂��̂ŁB �@���Ƃ��A�d�q��H�̊�{�I�ȍl�����ŁA�u�J�E���^�[IC�ƃf�R�[�_�[IC�̑g�ݍ��킹�ŁA�C�ӂ̏o�͐��ɏ�����ւ���H�v�Ƃ������@���g���̂��P�̎�ł��B 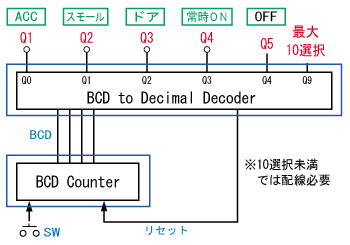 �@10�̏o�͂�S���g����10�o�͂����邮��̂Ŗ�����A�s�v�ƂȂ�o�͂���J�E���gIC�Ƀ��Z�b�g�M����Ԃ��Ă��ΔC�ӂ̏o�͐������邮����[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ȓ��������܂��B (���̕����͑I�ŁA�u�X�C�b�`�v�ɂ����镔���͂܂���) �@�܂�������Ɖ����Ɉ��܂����A����͎g��Ȃ��Ƃ��Ă���A�i���O�X�C�b�`���g���悤�ȏꍇ�A���Ƃ��r�f�I�M���E�I�[�f�B�I�M�������Ԃɐ�ւ���u�`�u�Z���N�^�[�^�V�[�P���T�[�v(���Ԃɐ�ւ�邾��)�݂����ȕ������Ƃ����ꍇ�A��}�̂悤�Ɉ�UBCD to Decimal decoder IC���킴�킴�o�͑I��������z�����o���ŏo���āA�ʂ̃A�i���O�X�C�b�`��ON/OFF�����悤�Ȏ������Ȃ��āA�uBCD���͂�4/8/16���́E�P�o���̃A�i���O�X�C�b�`IC(�}���`�v���N�T)�v������̂ŁA���}�̂悤�ȉ�H��IC�������Ȃ����Ď������邱�Ƃ��ł��܂��B 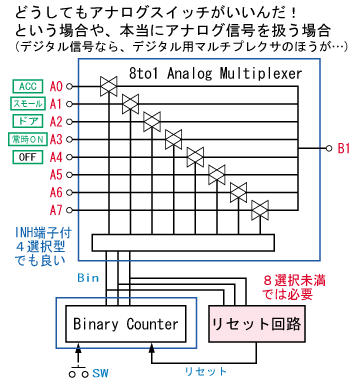 �� �f�W�^���p��4000�V���[�Y�ɖ����̂ŁA12V�ŎԂł��̂܂g�p�����H�͂ł����A74�V���[�Y��5V�̉�H�̂� �@���āA���Ȃ艡���Ɉ�ꂽ�̂ł��낻��{��ɖ߂�Ƃ��܂��傤�B �@���X�̕��j�Łu4013B���Əo��(�I��)���𑝂₷��IC�����ǂ�ǂ����v�̂��悭����܂���ł����̂ŁA�u�V�t�g���W�X�^�����g����IC�������Ȃ������v�̂��ǂ��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B �@�V�t�g���W�X�^���g���AIC���𑝂₹��������ł��o��(�I��)���𑝂₷���Ƃ��ł��܂��B �@�ł�����̂���]�ł͍ŏ����R�I���A���݊�]�ł��T�I�����炢�A�X�ɂȂɂ��~�������Ă����ƂQ�`�R�I�����炢�����邭�炢�ł��傤���B �@���Ƃ�����E�E�E�E�����̂���IC������������ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�������̃R�[�i�[��������H���̍H��ł͂��Ȃ����́@Decade Counter with 10 Decoded Output IC �E�E�E4017B [PDF]���������10�o�͂܂Ŏ��R�ɗ~���������̏����o�͂�����@�\�������̂ł�����B 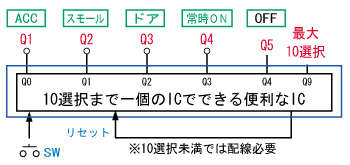 (�܂�����̂���]�ł͂��̔��������g���܂���) �@����ŁA�C�ӂ̐��̏o�͒[�q���A�X�C�b�`���������тɂP������Ă䂭�I��M���̐ؑ։�H��4017B������ō�邱�Ƃɂ����ق����A����̂���]�́u��H�̏��^���̂��߂ɏo��������[���g�킸�ɍς܂������v�Ƃ��������ɑ��āA�����[�̘b�Ƃ͈Ⴂ�܂����I��M������镔����IC�����Ɍ�(���)�܂Ō��炷�Ƃ����ړI�ɂ͍��v���Ă���Ǝv���̂ł����E�E�E�B �@��́A�A�i���O�X�C�b�`���g�킸�ɁA�C�ӂ̓��͂̏�Ԃ�LED�C���~��_��/�������������������W�b�NIC�ƃg�����W�X�^��FET�ō���Ă��Ηǂ��̂ł����A�ʂ����Ă��̂悤�ȕ������Řb��i�߂Ă����̂��A���������͂��ݗl�̂��ӌ����Ă���i�߂邱�Ƃɂ��܂��傤�B ���Ԏ� 2013/4/28
|
||
| ���e |
���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B �Ɠd�ł̓v�b�V��SW�ł�ON/OFF��@�\�ؑւ�������O�ł����A���앨�ł̓X���C�hSW��V�[�\�[SW����ł����̂ŁA�����FF��H�ɂ��ON/OFF���V�N�ŁA�Ȃɂ�菬���ȃ^�N�gSW���g���邽�߁A�_�b�V���{�[�h�Ɍ��J�����H���Ȃ��Ă��ς݂����i���ʃe�[�v�ŏ[���j�Ƃ̎v���Ŏ��₳���Ē����܂����B 4013B��2������1�g���܂����̂ŁA�]���1�����ł��B 1��H��2���͂̑I���A2��H����Ȃ̂ŁA4���́i3���́{OFF�j���\�ł́H�Ǝv���Ă��܂��܂������A1���͂̑I����1��H���K�v�Ȃ̂ł��ˁB 4066�́u�g���������Ȃ��i�v�Ɨ\�����Ă���܂������A��͂��H�̐�ւ��ɂ͌����Ȃ��Ɨ������܂����B �ɂ�4013B�̓u���b�h�{�[�h�p�Ƃ��č���̕��Ɏg���܂��̂ŁA4017B�ł̉�H�����肢���܂��B ������H�ƌ����͉̂��x���ڂɂ�����������̂ł����A�p�r��LED�̏����_���i�o�́j�ŁA��H�I���i���́j�ɗp���鎖��A�z�o���܂���ł����B �Ȃ�قǁATR��FET�ɏo�͂���A�����i���[�^���[�H�j�X�C�b�`���O���o�����ł��ˁB ��H�\���͗����o���܂������A��̓I�Ȕz����CR�����߂�X�L��������܂���̂ŁA���������A�����������肢�v���܂��B ���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�Ƃ��ŁA�P�d�v�ȏ���������Ȃ̂Ŏ��₳���Ă��������B �@�ǂ̓��͂ɐ�ւ���Ă��邩�̕\�������v(LED)�͕K�v�ł����H �@�K�v�����Ȃ�o�C�i���J�E���^�{�f�[�^�Z���N�^���̑g�ݍ��킹�̂ق���IC���E���i�������Ȃ��ςނƎv���܂����A���̕����Ɂu���̓Z���N�g�\���v�����悤�Ƃ�����ABCD to Decimal�f�R�[�_����IC���H���ʓr�K�v�ɂȂ��Č��Ǖ��i���������܂���ˁB �@�ŏ�����Z���N�g�\���͕K�v�Ȃ̂ł�����A��͂�4017�����g���ē��͑I��M�����o���ŏo�Ă����ق����ALED��_��������ɂ͍D�s���ł��B �@�I�𐔂ɂ���Ă͓��͑I���̉�H�ŕ��i���������邩������܂��B ���Ԏ� 2013/5/1
|
||
| ���e |
�����b�ɂȂ��Ă���܂��B �u�o�C�i���J�E���^�{�f�[�^�Z���N�^���̑g�ݍ��킹�v�Ƃ́A�����̂��Ԏ��ł��������������uBCD���͂�4/8/16���́E�P�o�͂̃A�i���O�X�C�b�`IC(�}���`�v���N�T)�v�̉�H�ł��傤���H ���ɂƂ��ẮA�h�A�i���O�X�C�b�`IC�h�Ƃ����u���b�N�{�b�N�X�����A�h�V�t�g���W�X�^�[�h�i�܂��A����������ɂƂ��Ă̓u���b�N�{�b�N�X�ł͂���̂ł����c�j�ɂ�鏇����ւ���H�̕����������Ղ����ł��B �����_�ł͕\�������v�͕s�v�ł����AIC���E���i�������Ȃ��čςޕ����D�s���Ȃ̂ł����A����̉��p�̂��߂ɂ��u4017�����g���ē��͑I��M�����o���ŏo�Ă���v�ق��ł��肢�v���܂��B ��o������Ő\����܂��A�����̊�]�d�l�Łu�L�[ON��A�ɐڑ��v�Ƃ��܂������A�u�O��̐ڑ����ێ��v���֗��ȋC�����ė��܂����B �ȒP�ȉ�H�̕ύX�i�u�p���[ON���Z�b�g���Ȃ��āA�Z���Ɍq���v�Ȃǁj�ōςނ悤�ł�����A�����Ă�����������ƗL������܂��B ���ڑ��i�I���j���ێ����邽�߂�IC��H��ʓr�݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�́A���̎���͂����̂ĉ������B ���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
>�u�o�C�i���J�E���^�{�f�[�^�Z���N�^���̑g�ݍ��킹�v�Ƃ́A�����̂��Ԏ��ł��������������uBCD���͂�4/8/16���́E�P�o�͂̃A�i���O�X�C�b�`IC(�}���`�v���N�T)�v�̉�H�ł��傤���H �@����E�E�E�E�A�A�i���O�X�C�b�`�͎g��Ȃ��A����������H�}�͏����Ȃ��ƌ���������Ȃ��ł����B �@�u�f�W�^���M���Ȃ�A�f�W�^���p�}���`�v���N�T�̂ق����E�E�E�v�Ə������ʂ�A�����̂̓f�W�^����H�ł����獡�܂ł��Љ�Ă��Ȃ��f�W�^���E���W�b�N�M���p�̃}���`�v���N�TIC�ł��B �@�ł��A���������̂ł͂Ȃ��u4017���g�����ق����~�����v�Ƃ�������]�ł��̂ŁA����ʼn�H�}�͂����قƂ�Ǐ����グ�Ă��܂��B �@����ŁA�Ō�Ɏ���ł����A���X�̂���]�� �� �d����Acc���� �� �� (�h�A�ڑ����̊g���ĂƂ���)��H�̓d�����o�b�e���[���� �Ƃ����Q�̕��@��������Ă��܂����A��́u�d����Acc�����v�̏ꍇ�A�uAcc��OFF�ŃX���[�������v�͓_�����Ă��鎞�v�́H �@��������d����Acc�����Ȃ̂ŁAAcc��OFF�ł�����C���~�͓_�����܂����ˁB �@�ł��A�g���Ă��d���͏펞�d�������ɂ����ꍇ�A��H�̓d���͏�ɓ����Ă���̂������X���[���A���ŃX���[�������v��ON���ƁA�ŏ���Acc�d���̏ꍇ�ƈႢ�AAcc��OFF�ł��X���[���ɂ͘A�����ăC���~���_�����Ă��܂��Ƃ��������ɂȂ�A�X���[���A�����̉�H�̓����������̂���]�Ƃ͈���Ă��܂������B �@����ɂ��ẮA�ǂ̂悤�ɂ��l���ł����H �@�ŏ�����g���v�����ł̉�H�}���������Ǝv���Ă��܂����A���ꂾ�Ə��Ă��d����Acc����Ȃ̂ŁA�C���~��Acc(�L�[)ON�̎�����(�����ɘA������)�_�������Ȃ��Ƃ������[���ɔ����Ă��܂��܂��B �@�g����]�̂ق��̉�H�ł́u�X���[���A���̎����A�d�����펞�d������Ȃ̂�Acc�ɊW�Ȃ��_�����Ă��ǂ��v�̂��A�u�X���[���A���̎��ɂ́A�����̊�]�ʂ�wAcc�ƃX���[��������ON�x�̏ꍇ�̂݃C���~�_���Ƃ����_����H���lj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�̂��A��������������ȊO�̓������~�����Ƃ����ӌ������ꂩ��o��̂��E�E�E�B �@�悭�킩��܂���̂ŁA���w�������肢�������܂��B ���Ԏ� 2013/5/4
|
||
| ���e 5/5 |
�����̎��₪���Ă��钆�A���萔�����|�����Đ\����܂���B ��]�̉�H�́A�L�[OFF�̎��̓X���[���_���ɘA�����Ȃ��č\���܂����̂ŁAAcc�d����OFF���܂�3�ړ_�i�I���j�̃X�C�b�`��H�ł��B �������Ȃ���A�L�[OFF�ŃX�C�b�`��H�̓d������Ă����ԂŃX���[���i���邢�͕ʂ́j���͂ɓd�����|����Ɖ�H�Ɉ��e��������ꍇ�͏펞�d���Ƃ��ĉ������B ���̍ۂ́A�u�wAcc�ƃX���[��������ON�x�̏ꍇ�̂݃C���~�_���Ƃ����_����H�v�̒lj��͕K�v����܂���B �ړ_��lj�������@��������������A���������ł͂Ȃ��A�{�L�����Q�l�ɂ�����ɂ��֗��ł��낤�Ǝv���Ċg���̉\�����L���܂������A�펞�d���ł�ON�̏ꍇ�́u�X�C�b�`��H�̓d�����o�b�e���[������Ȃ��ƃL�[OFF�ł͓����܂����v�Ƃ̂��w�E�̎�Ԃ��Ȃ����߁A�u�펞�d����ON�v�̕⑫�Ƃ��āu��H�̓d�����o�b�e���[�v�ƋL��������ł����B �������Ĕς킵�����Ă��܂��A�\����܂���ł����B ���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����ł́A�����ǂݏI��������ǂȂ��ł���H������悤�ɁA��b����������܂��傤�B �@�܂���������H���`������u10�i�W�����\���J�E���^�vIC 4017B [PDF]�̎g�����ł��B �� ����IC�ł����܂����A(����]�ł�����悤�ł���)����͂���Ő������܂��B�܂��A4017���g������H�}��������ߋ��ɉ��x���f�ڂ��Ă��܂����E�E�E  �@4017B��10�{�̏o�͒[�q�����u10�i�W�����\���J�E���^�v�ŁA�o�͒[�q��Q0(�O�Ԗ�)�`Q9(�X�Ԗ�)�܂ł̖��O���t���Ă��܂��B
�@4017B��10�{�̏o�͒[�q�����u10�i�W�����\���J�E���^�v�ŁA�o�͒[�q��Q0(�O�Ԗ�)�`Q9(�X�Ԗ�)�܂ł̖��O���t���Ă��܂��B�@�u���Z�b�g�v����������10�i�J�E���^�̒l�͂O�ƂȂ�AQ0��H�A���̑�(Q1�`Q9)��L�ƂȂ�܂��B �@�o�͂�����10�i�J�E���^�̒l�ɑΉ������A�����ꂩ�P������H�A���͑S��L�ƂȂ��H�ł��B �@10�i�J�E���^���N���b�N����(CLOCK�[�q)�������オ��G�b�W�ŃJ�E���g���P�i�߂܂��B �@0��1��2�c�ƃJ�E���g�A�b�v���Ă䂫�A10�i�J�E���^�Ȃ̂�9�̎���0�ɖ߂�܂��B �@�]���āA���ɉ�����₱�����ڑ������Ȃ���A4017B���N���b�N���������邽�тɃJ�E���g�A�b�v���āA�X�܂Ői�ނƂO�ɖ߂�u�P�O�܂Ő������v�������J��Ԃ��܂��B �@�u�P�O�̃����v�������_�����������I�v��u�P�O�̓��͂�������ւ������I�v�Ƃ����ӂ��ɁA�Ώە��̐����P�O�̏ꍇ�͂��̂܂g���Ε֗��ł��B �@�������A�����Ŗ����ꍇ�̂ق��������Ǝv���܂��B �@����Łu�C�ӂ̐�(�J�E���g)�Ŏg���v�ꍇ�ɂ��Ă��������܂��B 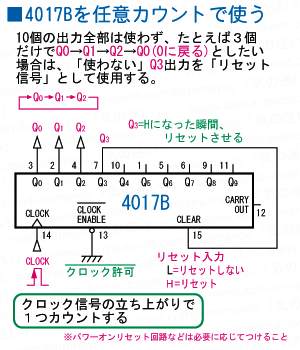 �@���Ƃ��u�R�̑I�����J��Ԃ��v�Ƃ����p�r�̏ꍇ�B
�@���Ƃ��u�R�̑I�����J��Ԃ��v�Ƃ����p�r�̏ꍇ�B�@�K�v�ȏo�͂�Q0�`Q2���R�{�����ł��B �@�S�Ԗڂ̏o�͂�Q3�͎g���܂���̂ŁA�J�E���g�A�b�v���Ă����āA�g��Ȃ������܂ł�����O�Ƀ��Z�b�g���Ă���Ƃ�����������H�ɂ�������A�u�C�ӂ̐�(n)�܂ŃJ�E���g���J��Ԃ��v����ɂȂ�܂��B �@4017B�̏o�͒[�q�͒��̃J�E���^�̐��l�ɑΉ������o��Qn��H�ɂȂ�u���_���v�o�͂ł��B �@�܂�4017B�����Z�b�g����(CLEAR�[�q)�́uH�����Z�b�g�v�uL�ŔZ�b�g(�ʏ퓮���)�v�Ƃ����u���_���v���͂ł�����A4017B�����Z�b�g���������ꍇ�ɂ͂�����H�ɂ���悭�A���܂��uQn�o�͂�H�ɂȂ������Ƀ��Z�b�g���������v�Ƃ����v���ɍ��v���܂��B �� ���R���v�����̂ł͂Ȃ��A������u���������ڑ��Ŏg�����߁v�̐v�ł��B �@����������������A�u���i�J�E���^�Ƃ��Ďg���v�ꍇ�́uQn�����Z�b�g�����Ɛڑ�����v�����ʼn�H���������܂��B �@����y�ł��ˁB �@�{���́A����ȊO�Ɂu�p���[�I�����Z�b�g��H�v�Ȃǂ����Z�b�g�����[�q�ɂ͌q���ł����Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A�����ł͊�{�I�ȃJ�E���^�[����̐����Ɛڑ����@�ɂ��Ă����q�ׂ܂��B �@4017B�ɂ��u�K�v�ȏo�͂�I������M��Q1�`Q(n-1)������v�Ƃ��������܂ł͏�L��OK�ł�����A���Ɂu�I�������C�ӂ̓��͂̏�Ԃׂ��v�Ƃ�����H�ɂ��Ăł��B �@�������{�����o�C�i���J�E���^�{�f�[�^�Z���N�^�ō�����ق��������Ɗy�Ȃ�ł����A����̂���]�ł́u4017B���g������H�Łv�Ƃ������ŁA���̂܂ܘb��i�߂܂��B �@4017B�̏o��Q1�`Q(n-1)�Łu�ǂ̓��͂̏�Ԃׂ�̂��H�v���w�肷��u�I��M���v�͍���܂����̂ŁA�����I��M���Ɓu���̐M���őI�������X�̓��͐M��(�C�ӂ̓���)�v����A���͏�Ԃ����������H��v���܂��B �� �����ł͊����C�ӂ̓����̐M�������_���́u�f�W�^���M���v������Ă�����̂Ƃ��܂��B�Ԃ́u�v���X�R���g���[���v�u�}�C�i�X�R���g���[���v���͊W�Ȃ��uON�Ɣ��f������͂̏ꍇ��H�v�ł��B �@�X���C�ӂ̓�����Ԃ���u���̐M�����������邱�Ƃ��L���ł���A�������̐M����ON�ł���Ό�̐���(�����v��_������A�u�U�[���Ȃ炸�ȂǔC�ӂ̉���)��ON�ɂ����v�Ƃ����_�������炩�̉�H�Ŏ������Ă��悭�A����͈��AND�Q�[�g�Ŏ����ł��܂��B 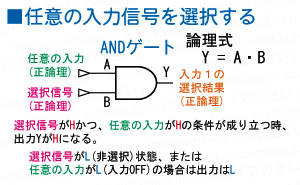 �@�E�}�̒ʂ�A���W�b�NIC��AND�Q�[�g�́A���̓���(A�EB)���S����H�̏ꍇ�̂ݏo��Y��H�ɂ���_����H�ł��B
�@�E�}�̒ʂ�A���W�b�NIC��AND�Q�[�g�́A���̓���(A�EB)���S����H�̏ꍇ�̂ݏo��Y��H�ɂ���_����H�ł��B�@�_������ Y = A�EB
�ł��B�@A���́EB���͂��ꂼ��Ɂu�C�ӂ̓����v�u�I��M���v��ڑ����Ă��ƁA����́u�I��M����H�őI������Ă����H�́A�C�ӂ̓�����H�̏ꍇ�̂݁A�o��Y��H�ɂȂ�v�Ƃ������ɂȂ�܂��B �@�����u�I��M����L�����̉�H�͑I������Ă��Ȃ��v�ꍇ��A�u�I��M����H�ł��̉�H���I������Ă������A�C�ӂ̓�����L�Ȃ̂��o�͂�ON�ɂ͂��Ȃ��v�ꍇ�Ȃǂ́AAND�Q�[�g�̏o�͂�H�ɂ͂Ȃ�܂���B �@���������I�����ꂽ���͂̏�Ԃׂ�A���ʂ��o�͂����Ƃ�����H���A�K�v�ȓ��͐��Ԃ�͗p�ӂ���K�v������܂��B �@�������A���ꂾ���ł͓��͐��Ԃ�̕ʁX�́u�I�������ɍ��v�������͂�ON�������̂��H�v�Ƃ��������H�����Ԃ����ł�����A���̂܂܃����v��u�U�[�̐�����s�Ȃ��킯�ɂ͂䂫�܂���B �@�ł��̂ŁA�u�X�̓��͂������������ʂ���A�o�͂𐧌䂷���H�v�����Ȃ��Ƃ����܂���B �@�����ōl����̂������̓��͔����H������ł��鎞�́A���ꂼ��̉�H�̓���Ƒ������đS�̂̓����ł��B �@�ǂꂩ�̓��͔����H�̏o�͂́u���ꂪ�I������Ă��āA�����͂�ON�̏ꍇ�͉�H�̏o�͂�ON�v�ŁA�X�Ɂu�I��M���͂ǂꂩ�P�̉�H�����I��ł��Ȃ��v�Ƃ��������܂Ŋ܂߂đS�̂��l����ƁA�u���͔����H�̏o��(�ǂꂩ��AND�Q�[�g��Y)�́A���͏�Ԃɂ��ǂꂩ�P����H�ɂȂ��v�u�I�����ꂽ���͂�OFF�̏ꍇ�́A�S�Ă�AND�Q�[�g��Y��L�ł����v�Ƃ�������ł��B �@�����Ő�ΓI�ȏ����Ƃ��Č���̂́u�I������Ă��Ȃ��̂ɁA�������Ȏ���H�ɂȂ�AND�Q�[�g�͖����͂��v�Ƃ������ŁA���̏�����������Ă���̂ł���A�ŏI�I�ɂ́u�ǂꂩ(�P�ł�)AND�Q�[�g�̏o�͂�H�ɂȂ��Ă���ꍇ�A�ŏI�I�Ȑ���o�͂�H�ɂ����v�u�S����AND�Q�[�g�̏o�͂�L��������A�ŏI�I�Ȑ���o�͂�L�v�Ƃ����_����H�ŁA�o�͐�����s�Ȃ��Ηǂ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@�u�����̓��͂̂��������ꂩ�P�ł�H�̏ꍇ�A�o�͂�H�v�u�P��H�������S���͂�L�̏ꍇ���o�͂�L�v�Ƃ�����������W�b�N�Q�[�g�̊�{����̂����̂P�ŁAOR�Q�[�g������ɂ�����܂��B 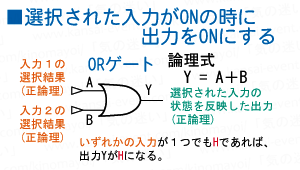 �@OR�Q�[�g�̂Q�̓���A�EB�ɂ��ꂼ��
�u���͂P�̑I�������v�u���͂Q�̑I�������v��ڑ�����ƁAOR�Q�[�g�̏o�͂́u���͂P�̑I�������܂������͂Q�̑I�������������ꂩ�Е��ł�H�Ȃ�A�o�͂�H�Ƃ����Ƃ��������ɂȂ�A���ʁu�I�����ꂽ�����̏�Ԃ�ON�ł������ꍇ�A�o�͂�H�v�u�I�����ꂽ�����̏�Ԃ�OFF�ł������ꍇ�AL�v�Ƃ����ړI�̉�H���������܂��B
�@OR�Q�[�g�̂Q�̓���A�EB�ɂ��ꂼ��
�u���͂P�̑I�������v�u���͂Q�̑I�������v��ڑ�����ƁAOR�Q�[�g�̏o�͂́u���͂P�̑I�������܂������͂Q�̑I�������������ꂩ�Е��ł�H�Ȃ�A�o�͂�H�Ƃ����Ƃ��������ɂȂ�A���ʁu�I�����ꂽ�����̏�Ԃ�ON�ł������ꍇ�A�o�͂�H�v�u�I�����ꂽ�����̏�Ԃ�OFF�ł������ꍇ�AL�v�Ƃ����ړI�̉�H���������܂��B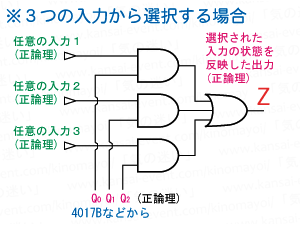 �@����̖ړI�̂悤�Ɂu���͂P�v�u���͂Q�v�̂Q������I������Ȃ��̐����ŏ������悤���Q����OR�Q�[�g IC���g�������ł����A���ꂪ�����R���͂���I�������Ȃ�A�E�}�̂悤���R����OR�Q�[�g IC�����g���܂����A�����Ɠ��͐��̑���������OR�Q�[�g IC�����݂��܂��B
�@����̖ړI�̂悤�Ɂu���͂P�v�u���͂Q�v�̂Q������I������Ȃ��̐����ŏ������悤���Q����OR�Q�[�g IC���g�������ł����A���ꂪ�����R���͂���I�������Ȃ�A�E�}�̂悤���R����OR�Q�[�g IC�����g���܂����A�����Ɠ��͐��̑���������OR�Q�[�g IC�����݂��܂��B�@�܂��AOR�Q�[�g�́uOR�Q�[�g�̏o�͂����i��OR�Q�[�g�̓��͂ɐڑ����āA�����̓��͂�OR�Q�[�g�Ƃ݂Ȃ��v�Ƃ������Ȏg�������ł��܂�����A�����莝�����Q����OR�Q�[�g IC�������ė��p���������Ȃǂɂ́A�����������炻��Ŏg���邩������܂���B �@�����̂Ƃ���͂����܂ŁB �@�����������̂͋��ȏ��I�ȁu��b�I�ȍl�����v�ŁA���ۂ̉�H�}�ł́u�����͓���������ǂ��A���̐}�Ƃ͈Ⴄ���i�E�Ⴄ�z���̉�H�v��p���邱�Ƃ����X����܂��B (�Â�) ���Ԏ� 2013/5/10
|
||
| ���Ԏ� |
�@���Ď��ɁA�d�����ǂ����邩��A�e���͒[�q�ƃ��W�b�NIC�̓��͂��q���b���ł��B �@�u�ԂŎg���v�ł�����A�d����Acc�����肽���I�Ƃ�������]�̂��̂������ł��ˁB �@�����A���̏ꍇ�́uAcc�̓L�[��Acc-ON�ȏ�ɉĂ����Ȃ���+12V����������Ȃ��v�Ƃ���������܂��Ƃ���������܂��̘b�ł����A����ɑ��č���q�������Ƃ����b���o�Ă������[�������v���X���[�������v(�|�W�V������)���L�[��}���Ă��悤�����܂����A���ł�(����p��)�X�C�b�`ON�œ_�����铔�ł����Ƃ������������ł��B �@�܂�A�uAcc��OFF�ʼn�H�̓d���������Ă��Ȃ��̂��A���͒[�q�ɐڑ����ꂽ�X���[�������v(�|�W�V������)�Ȃǂ̉�H����(�O������)�d�����������Ă��܂��I�v�Ƃ����g���u�����N����܂��B �@�����S�������[���g���č��Ȃ�A����ȐS�z������K�v�͖����̂ł����A���W�b�NIC���g���č���̂ł�������W�b�NIC�̎g�����E��i���֎~�����͓��R�m���Ă��āAIC���Ȃ��v�����Ȃ���Ȃ�܂���B 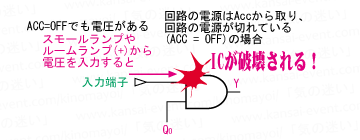 �@�ň��̏ꍇ�AIC���j������܂��B �� �ꉞ�A�����Ă���IC�̓����ɓ��͕ی��H�������Ă��܂����A����͂����܂ŃC���M�����[�ȏꍇ�ɏ�������IC����邽�߂̂��̂ŁA��Ɉُ�ȓd����������悤�Ȑv�Ŏg���Ă��ǂ��Ƃ������̂ł͂���܂���B�C���M�����[�𑱂���Ɠ��RIC�͉��܂��B�ň��Ȃ̂́A���̈��IC�����邾���ł͖����A��H���Ōq�����Ă�ق���IC�����ُ�d�����������Ĕj�Ă��܂����Ƃł��B �@��ʓI��IC�̓��͓d���́AGND�`Vcc(Vss�`Vdd)�͈̔͂ƌ��߂��Ă��܂��B(����ȕi�͏���) �@�d���d����^����IC�삳���Ă���ꍇ�A���͒[�q�ɂ͂��̓d���d���ȏ�������Ă͂����Ȃ��Ƃ������܂�ł��B �@�������A(�����IC��������)�}�C�i�X�d������ɋ֎~�ł��B �@�����̒�i������āA�ُ�ȓd����������Ȃ��悤��H�v������K�v������܂��B �@���Ƃ��A�u�g�����W�X�^���g���āA���[�������v��X���[�������v����̓d�����A���ڂ�IC�ɂ����Ȃ��悤�ɂ����H�v�Ȃǂ��Ԃɋ��݁AIC�ɂ͊O������̓d�������ڂ͂�����Ȃ����̂�p�ӂ��Ă��܂��B 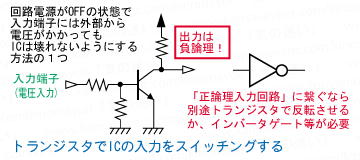 �@�����A���̂悤��NPN�g�����W�X�^��̏ꍇ���R���N�^���œ�����M���d���́A���͂Ƌt���ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����������W�b�N��H�ł͖��ɂȂ�ꍇ������܂��B �@���͂��u�d��(12V)�������ON�v�Ƃ��Ă���̂ɁA�R���N�^���̓d�ʂ́u���͂����������ɂ�0V�v�ƂȂ��f�W�^���I�ɂ�L�ƂȂ�u���_���v�o���ɂȂ邩��ł��ˁB �@���X�̃��W�b�N��H�̂ق����u���_�������v�œ����悤�ɐv����Ă���A������͂���܂���B�����������͉�H���g�����ŏ�����킩���Ă�����A������������悤���I�����ꂽ���͐M���̔����H�̂ق����ŏ�����u���_�������v�Ƃ��đS���ʂ̉�H�}�ŏ��������ł��B (�ʓ|�Ȃ̂ŁA���̉�H�}�͂����ł͐������܂���) �@�����A���������g�����W�X�^�ŊO�������12V���ăX�C�b�`���O����������p�����ꍇ�A�u���_���v�o�͂Ƃ������̂ł���A�����P�g�����W�X�^�𑫂��ĐM���]�������H�ɂ������A���̃��W�b�NICC�̐��_�����͂Ƃ̊ԂɁuNOT�Q�[�g/�C���o�[�^�Q�[�g�v(���]��H)�������ŐM���]���������E�E�E�B �@������ɂ���ʓ|�ł��B �@�����ł�����Ƙb��ς��āA���͂ɐڑ����鑊�肪ON�̎��ɂ͓d��(+12V)���o�͂����u�v���X�R���g���[���v�ł͖����AON�̎��ɂ̓A�[�X�Ɛڑ�������ړ_�o���́u�}�C�i�X�R���g���[���v�̏ꍇ�͂ǂ���Ηǂ��̂ł��傤�H 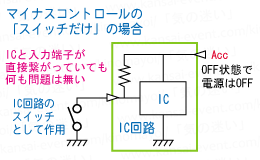 �@�O������d���͂����炸�A����̓A�[�X�Ƃ̊Ԃ̃X�C�b�`�������Ƃ���ƁAIC���O������j��悤�ȓd���͂�����Ȃ��͂��ł��B
�@�O������d���͂����炸�A����̓A�[�X�Ƃ̊Ԃ̃X�C�b�`�������Ƃ���ƁAIC���O������j��悤�ȓd���͂�����Ȃ��͂��ł��B�@�P���ɁAIC��H�̈ꕔ�Ƃ��ẴX�C�b�`�Ƃ��ĎԂ̂ǂ����̃X�C�b�`���g�������Ȃ���v�ł���ˁB 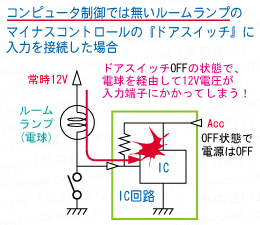 �@�ł��E�E�E����ς����͒[�q�ɂ�(Acc-OFF�̊Ԃ�)�O������12V���������Ă��܂��I�Ƃ����p�^�[����z�肵����H��v���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�ł��E�E�E����ς����͒[�q�ɂ�(Acc-OFF�̊Ԃ�)�O������12V���������Ă��܂��I�Ƃ����p�^�[����z�肵����H��v���Ȃ���Ȃ�܂���B�@�E�}�̂Ƃ���A�u�}�C�i�X�R���g���[���̃��[�������v�X�C�b�`�v�ɐڑ��������[�������v�ɘA�������E�E�E�Ȃ��悤�Ƃ���ƁA�̂Ȃ�����d�����̃��[�������v���A�h�A�X�C�b�`�ƒ�������Ă����H�ł���A�h�A����Ԃł��X�C�b�`��OFF�ŁA���̏ꍇ�펞�d������d����ʂ���+12V��IC�̓��͂ɂ�����I�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@�ƂȂ�ƁE�E�E��͂�IC�ɂƂ��Đ������Ȃ��ڑ��ƂȂ�̂ŁA����ł͂����܂���B �@�K���A�}�C�i�X�R���g���[���̏ꍇ��IC��H�̂ق��Ńv���A�b�v���Ă���̂ŁA��������X�C�b�`�����֓d��������邾���ɂ��Ă���āA�t�ɊO������d�������������肵�Ȃ��悤�ɂ����IC��H�͕ی�ł��܂��B 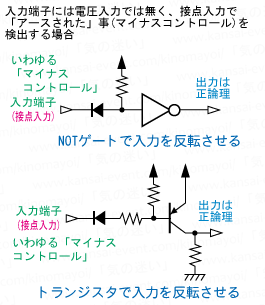 �@�t���̖h�~�ɂ������p�_�C�I�[�h����{�g�������̂ŁA���ɍl����̂́u�}�C�i�X�R���g���[���̏ꍇ�AON�̎��ɂ�GND�Ɍq�����ē��͂�L�ƂȂ�(�����_��)�v�Ƃ����_�ŁA��͂�u���_���v���͂̉�H�Ɍq���ɂ��_���]���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�t���̖h�~�ɂ������p�_�C�I�[�h����{�g�������̂ŁA���ɍl����̂́u�}�C�i�X�R���g���[���̏ꍇ�AON�̎��ɂ�GND�Ɍq�����ē��͂�L�ƂȂ�(�����_��)�v�Ƃ����_�ŁA��͂�u���_���v���͂̉�H�Ɍq���ɂ��_���]���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B�@��ɐ��������悤�ɁANOT�Q�[�g(�C���o�[�^�Q�[�g)��ʂ��Ĕ��]����A�܂��̓g�����W�X�^�Ŕ��]������A�Ȃǂ̕��@�����܂��B �@��͂肱�����ɏ����܂����悤�ɁA�ŏ����畉�_�����͂��Ƃ킩���Ă���A���̌�̔����H�Ȃǂ�����p�ɐv���܂����ǁE�E�E�B �@����ŁA���������悤�Ɂu�����d������Ă���ԂɊO��������͒[�q�ɓd���������������v�Ƃ��u�v���X�R���g���[�����������v�u�}�C�i�X�R���g���[�����������v�ł��Ȃ�Ⴄ��H�}�ɂȂ��Ă��܂��ƁA�v����̂��ʓ|�ł����A�g�����W�X�^�Ȃ��g�������R�l�̌v�Z�Ȃǂŏ\���Ȓm���������Ƃ��܂���H�����܂���B(��R�l����̉�H�}�������Ă����āA���ꂳ���g�������Ƃ����b�ł����E�E�E�B�u�l�b�g�Ō������ĂȂ�Ƃ����悤�v�Ȃ�Ď����l���Ă�l�ɂ͂���ŏ\���ł���ˁE�E�E) �@��H�}���ȒP�łǂ̐ڑ�����E�ڑ��p�[�^���ł��A�v���X�R���g���[���^�}�C�i�X�R���g���[���ɊW�Ȃ��g�����H�E�E�E�Ƃ������܂��b������A�݂�Ȃ�����g�����ق������N�`��(����)�ł��傤�B 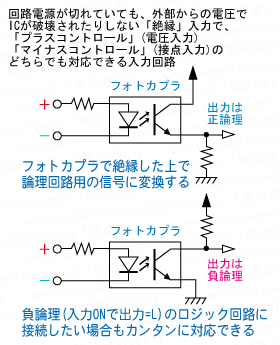 �@�����Ő����ł���̂��u�t�H�g�J�v���v���g�������͂̃}�b�`���O��H�ł��B
�@�����Ő����ł���̂��u�t�H�g�J�v���v���g�������͂̃}�b�`���O��H�ł��B�@�t�H�g�J�v�����g���A�t�H�g�J�v���̓��͂Əo�͂����S�ɐ≏����Ă��܂�����A�u��H�̓d��OFF�̎��ɊO����IC�̓��͂ɓd��������������E�E�E�v�Ȃ�Ă����S�z�͑S���Ȃ��Ȃ�܂��B �@�܂��t�H�g�J�v���̃t�H�g�g�����W�X�^�����v���A�b�v�Ŏg���^�v���_�E���Ŏg���̈Ⴂ�����ŏo�͂����_���ɂ����_���ɂ��g���܂��B �@��R�l���P�������͓d���Ő�����LED��_���������Ƃ��v���A�b�v�^�v���_�E���������炢�Ȃ̂ŁA�v�Z���y�ł���ˁB  �@�܂��A���͑����Ԃ��v���X�R���g���[���^�}�C�i�X�R���g���[��������̉�H�Ɛڑ�����̂����݂ł��B
�@�܂��A���͑����Ԃ��v���X�R���g���[���^�}�C�i�X�R���g���[��������̉�H�Ɛڑ�����̂����݂ł��B�@�v���X�R���g���[���Ȃ�u�O�����狟�������+12V���t�H�g�J�v����LED����������v�ł����A�}�C�i�X�R���g���[���Ȃ�u�O���̃X�C�b�`�ŃA�[�X�����ړ_�ɓd��������鎞���t�H�g�J�v����LED������悤�ɓd���Ɛڑ����Ă����v�Ƃ������ɁALED�C���~�Ȃǂ��Ԃɐڑ��������Ƃ̂�����Ȃ�N�ł��ڑ��ł�����@���t�H�g�J�v����LED����z�����Ă�邾���ł��ˁB �@���܂Ŏ������������̉�H�E�ڑ���́A�����E�����E���@�����������̂��߂̂��̂ŁA���イ�Ԃ�ȕی��H�Ȃǂ͐}�ɂ͓���Ă��܂���B �@���ۂ̉�H�����i���x��(�d���Őv����)�Ƃ��čl����Ȃ�A�m�C�Y���t�ڑ��E�ߓd���ȂǂŌ̏Ⴕ�Ȃ��悤���ی��H���K�b�`���Ƃ���Ƃ���ł����A�����ŏЉ�Ă���̂͂����܂��l�Ŋy���ޓd�q�H�����x���ɂ��Ă��܂��̂ŁA���܂�K�b�`�������ی��H�܂ł͂��Ȃ��Ă��ǂ��ł��傤�B �@���̕��@�E�l�����̉���ȊO�́A���̂�����ɑ�����ۂ̉�H�}�ł������̕ی��H�͓���܂����A�d���ō����̂�Ɩ��Ŏg�p������̂Ƃ��Ă͂��̂܂g��Ȃ��ł��������B (�Â�) ���Ԏ� 2013/5/11
|
||
| ���Ԏ� |
�@����ł͂��҂������܂����B��H�}�ł��B �@�E�E�E�����܂Ő������Ă�������A���������炩���H�}�����K�v��������������܂���(^^; ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�@��{������4017B [PDF]����g���āu�{�^�����������тɂ`���a���b���`��(�R�ړ_��)��ւ���v��H�ł��B �@Q3(�S�Ԗ�)�̏o�͂����Z�b�g�[�q�Ƀt�B�[�h�o�b�N���āA�S�Ԗڂɐi��O�Ԗڂɖ߂��܂��B �@�p���[�I�����Z�b�g��H�́A���ꂪ�����Ɓu4017B�̒��̃J�E���^�́A�d�������������ɂǂ�Ȑ����ɂȂ��Ă��邩�킩��Ȃ��v�̂ŁA���]�݂̓���ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂Ő�ɓ���Ă����܂��B �@�����ƁA�����d������ꂽ�����������S�ɂȂ��Ă�����A�������]�̂R�ړ_�̂ǂꂩ�͑I������Ȃ����肩�A�X�C�b�`�������Ă��T���U���V���W���X���O�Ɖ��X���������Ă���ƂO�ɂȂ��Ƃ�������ɂȂ�A�d��ON�ʼn��̐����ɂȂ��Ă��邩�킩��Ȃ��ꍇ���ʂ����ĉ���X�C�b�`����������O(�ŏ��̑I��)�ɂȂ�̂�����S���킩��Ȃ��Ƃ�ł��Ȃ���H�ɂȂ�܂���ˁH �@����m�F�p��LED1�ELED2�́u�ʂɗv��Ȃ��v�u�t�������Ȃ��v�Ƃ����̂Ȃ�A�ʂɂ��Ȃ��Ă������ł��B �@�u�����͏��S�҂�����g�ݗ��ĂĂ����Ɠ����Ă�̂��m���߂����v�Ƃ��u�X�C�b�`�������āA�`���^�����O��m�C�Y�ł̌�쓮���Ȃ������ƃ����v�b�V���łP���i��ł�̂��H�v�u�p���[�I�����Z�b�g��H�͂����Ɠ����Ă�́H�v�Ȃǂ��m�F���������͂��܂��傤�B �@���͏�Ԃ�I�������H�ł́A��̐����ŏo����AND�Q�[�g�ł͂Ȃ�NAND�Q�[�g���g�p���Ă��܂��B�o�͂����]���Ă���ȊO�͍l�����͓����ł��ˁB �@����ƁA���͉�H�Ƀt�H�g�J�v�����g�����A�i���O��H��ڑ�������̂ł�����A�������V���~�b�g��H������V���~�b�gNAND�Q�[�g 4093B [PDF]���g�p���܂��B �@����̂悤�ȑ��u�ł���A�o�͂ɂ̓����v���x�����q���Ȃ��̂ŃV���~�b�g��H�ł�������ƃf�W�^�������Ȃ��Ă��ʂɍ\��Ȃ���ł����ǁB �@OR�Q�[�g���g�킸���_�C�I�[�hOR��H�ő�p���܂��B(��������肽����ł���ˁH) �@���͂́A�uAcc�d���������v�Ƃ������ł�����A�uAcc-OFF�̏�Ԃ��X���[�������v����d�����������v�Ƃ��������l�����܂��̂ŁA�t�H�g�J�v�� TLP521-1 [PDF]�Ő≏���Ă����܂��B �@�o�͂��p���[MOS-FET 2SJ377 [PDF]���g�����n�C�T�C�h�X�C�b�`�Ƃ��܂��B �@�Ԃ̓��Ηނ�_��������ɂ́u�v���X�R���g���[���v�Őڑ����������������ł��傤����B �@����ŁAAND�Q�[�g�͎g�킸��NAND�Q�[�g���g�p���Ă��܂��B �@�d���͎Ԃł�����AAcc�Ȃǂ��璼��12V������Ďg���܂��B �@�O�[�q���M�����[�^�Ȃǂ͕s�v�ł��B �@Acc�ł͂Ȃ��A�펞�d��������������[��H���͖����Ă��Ō�̏�Ԃ��o�b�e���[����Ȃ�������i���ɋL�����Ă��܂��ˁB �@�����ď펞�d������Ƃ�E�E�E��H�̓d���͐�Ă���̂ɓ��͒[�q����IC�ɓd�����������Ƃ������������Ȃ�̂ŁA���͂̃t�H�g�J�v���͖����ł����ƃJ���^���ȓ��͕ی��H�ł��悭�Ȃ�ꍇ������܂��B �@�ł��܂��A���������펞�d���������Ă���E�E�E�͂��Ƃ�����H�}�������Ă��A�g�ݗ��ĂāA�e�X�g����Ԃւ̑g�ݍ��ݒ��ɖ�����d���̔z���͌q�����ɓ��͂����q�����Ă���ň��̏���ȂǂƂ����̂��e�Ղɑz���ł��邽�߁A�����ł͂����������̂͒��Ȃ��ł����܂��傤�B �@��H�̐v���@��S���������Ă���̂ŁA���͂��S���͂ɑ����悤���T���͂ɂȂ낤���A�K�v�ɉ����ē����悤�ȓ��͉�H�𑝂₷�����Ȃ̂ŃJ���^���ł���ˁH �@����ďI���ł��B ���Ԏ� 2013/5/13
|
||
| ���e |
�ڂ�������Ɖ�H�̂����肪�Ƃ��������܂����B �Ǘ��l�l�́u�펞�d���ł̃o�C�i���J�E���^�{�f�[�^�Z���N�^��H�̕����K���i�ȒP�H�j�v�Ƃ��l�����Ƒ����܂����A�����uAcc�d���ł̃V�t�g���W�X�^�[��H�v��I���������߁A��ςȂ���ԂƂ����Ԃ��₵�ĉ����������ɐ[�Ӓv���܂��B �|�|�|�|�|�@�ꕔ�ȗ��@�|�|�|�|�| �����̂��Ԏ��ŁA������H�ɂ��d���̐�ւ��Ƃ́ALED�����_����H��LED�̑���ɓd���I�����i�X���[����Acc���j�̃��C�����\�[�X�Ɍq����FET����ׂ���H��z�����Ă��܂������A���ꂼ��̃��C����d���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�M���Ƃ��ē��͂��A���ׁi�C���~�j��H�̓d����ON/OFF����Ƃ͎v�������т܂���ł����B ���̑z�����Ă�����H�ł͓d���I�����̐������p���[FET�����сA�I�����������ꍇ�͊���傫���Ȃ�܂��̂ŁA�M���Ƃ��Ĉ����������X�}�[�g�ł��ˁB�@�ƌ������A�I��d���ȊO�̃��C���i�s����̂Ȃ��d���j���eFET�Ɉ���ꑱ���鎖�����Ȃ̂����m��܂���B �܂��A�o�͂��v���X�R���g���[���i�n�C�T�C�h�X�C�b�`�j�Ƃ��邽�߁ANAND�Q�[�g���g�����������ł͎v���t�����A��ϕ��ɂȂ�܂����B �߂����Ƀp�[�c����肵�A�܂��̓u���b�h�{�[�h��őg�݁A����Ȃ���������A�܂����₳���Ē��������m��܂���̂ŁA�X�������肢�v���܂��B ��i�C���~��H���ƐV������蒼���\��ł��j���������܂�����A���߂Ă��v���܂����A�܂��͂���܂ŁB ���� �l
|
||
| ���e |
�O���e�̏ȗ������ɂ́AAcc�d������]�����o�܂��L���܂������A�������������z���Ă��܂������ߏȗ��v���܂����B �ȗ�������lj����e�v���܂����A�ȑO�̓��e�ɂ�Acc�d���̊�]�͕\���ς݂ł��̂ŁA�f�ځi�}���j�^�폜�͂��C���v���܂��B �|�|�|�@��������@�|�|�| ����C���~�Ƃ́w���y�ɍ��킹�ē_�ł���LED�x�ŁA�Ǘ��l�l���w�ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_��������x�Ŏ�����Ă����H�ł͂���܂��A�l�b�g�Ō��J����Ă������l�ȉ�H�ł��B �����I�[�f�B�I���ЊO�̃I�[���C�������i�r�Ɋ��������ہA�A�_�v�^�[�p�l���i�i�r��t�g�j�̍��E�ɕ�1cm���̃X�y�[�X������A�����ɐ�LED�i���E1�Âj�ߍ��݁A��H��͏����ȃP�[�X�Ɏ��߂āA�_�b�V���{�[�h���̃i�r�{�̂ɗ��ʃe�[�v�œ\��t���܂����B ��Ԃ̉^�]�ł͓_�ł���LED�����E�ɓ����Ĕς킵�����߁A��R�ɂēd�����i���ĈÂ߂ɓ_�������܂����̂ŁA�����͖w�ǖڗ��������ʂɓ_�����Ă����d���Ȃ��ƁA�d�����X���[��������܂����B ���A�_�v�^�[�p�l���̃X�y�[�X���������߁A�d���X�C�b�`�݂͐��܂���ł����B ���X���[��ON�ɘA�����āA������������ɂ��������ǂ�������������܂���B(^^�U �������A����i�_�Łj�̊m�F��Ȃ̃m���ɂ���Ă͓������_��������������A�t�ɖ�Ԃ̓_�ł��ς킵����������A���[�^���[�X�C�b�`�ɂ��X���[���A���i��Ԃ̂ݓ_���j�^Acc�A���i�����_���j�^OFF�i��ԏ����j���l���܂������A�A�_�v�^�[�p�l���Ƀ��[�^���[�X�C�b�`�����t����X�y�[�X���Ȃ��A���^�̃v�b�V���X�C�b�`�i�^�N�g�X�C�b�`�j�ɂ���ւ��Ȃ�A�_�b�V���{�[�h�Ɍ��J�����H���ă��[�^���[�X�C�b�`�����t������A������߂��P�[�X�Ƀ��[�^���[�X�C�b�`�����t���ă_�b�V���{�[�h�ɌŒ肷��K�v���Ȃ��ƍl��������ł��B �]���āA�I�[�f�B�I�i�i�r�j��OFF�i�L�[OFF�j�̎��ɓ_�������鎖�͂Ȃ��A��H�̓d����Acc������o�b�e���[�オ��̃��X�N�����Ȃ��ƍl���i�d�����펞�d���Ƃ��Ă��s���쎞�̏���d���͔��X������̂Ƃ͎v���܂����c�j�AAcc�d������]���܂����B �|�|�|�@�����܂Ł@�|�|�| ���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�u�R���p�N�g���v�Ƃ���������Nj�����Ȃ�A���͏�Ԃ肵�Ă���AND�Q�[�g�͖����ɂ��āA�t�H�g�J�v����AND�@�\�܂Ŏ������Ă��܂��悤�Ȏg�����ł������Ǝv���܂��B �@���肩���A���̔����H�̏o�͂̓n�C�E�A�N�e�B�u�ł����炻�̂܂܂ł�P-ch�p���[MOS-FET�͋쓮�ł��Ȃ��̂ŁA�R���p�N�g�ɁE���i�������Ȃ��Ƃ������z��ǂ����߂��ꍇ��N-ch�p���[MOS-FET���쓮�����}�C�i�X�R���g���[���ɂȂ�܂��B �@�����ǂ����Ă��v���X�R���g���[�����ǂ��Ƃ����̂ł���A�g�����W�X�^�P��������]��H����g��ł������ł����A������Ɠ����q�l�����t�H�g�J�v�����g�������]��H�ɂ��Ă݂�̂������ł��ˁB���͉�H�Ńt�H�g�J�v�����g���Ă���̂ŁA�܂Ƃ߂Ĕ����Έ����Ƃ��Ȃ畔�i����g�����W�X�^�Ɠ������炢�ɂȂ邩������܂���B 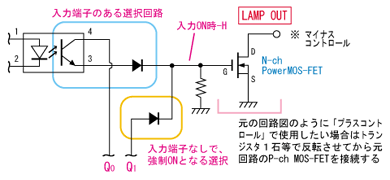 ���Ԏ� 2013/5/14
|
||
| ���e 5/21 |
���j���ɕ��i�B���A�u���b�h�{�[�h�ɑg��ł݂܂����B 2SJ377������o�����A�茳��2SK2961������܂����̂ŁA�Ō�ɂ�������������4093B���Ȃ����}�C�i�X�R���g���[���i���[�T�C�h�X�C�b�`�j��H�Ƃ��܂����B �C���~��H�i������ɍ\���\��j��LED�ő�p���A�X���[��ON�̓t�H�g�J�v���Ɂ{12V�̓����ōČ����āA��]�ʂ�̓�����m�F���܂����B OFF�I�����̏���d����0.00mA�ł����̂ŁA��H�d�����펞�d��������A�L�[OFF����I�����ێ�����������������Ă݂܂��B �����̕����g�����肪�ǂ������Ȃ̂ŁA2��H����̃t�H�g�J�v���������Ă����܂����B(^^�U �C���~��H�ɂ��M�~�b�N��lj����悤�ƍl���Ă���܂��̂ŁA������͂܂���ƂȂ�܂����A���̓x�͑�ς����b�ɂȂ�A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B ���� �l
|
||
| �t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H | |||
|
�t�F���V���O�A�R���@�A��H�}�ł����ɂ��ǂ蒅���܂����B �܂����A�R���@�̉�H�}��WEB�ɍڂ��Ă���l������Ƃ͎v���܂���ł����B�́A�d�q�H��̖{��ǂ݂A�ꐶ�����R���@��������v���o���c�B �i�̂̓E���\���~��������ł����A���̓E�����~�Ŕ������ł���ˁ[�j �������A�I�����s�b�N�����Ă���ƁA�Ȃ�ƃ��C�����X���Ⴑ�����܂����B�i�R���@�ƑI��Ԃ̃P�[�u�����Ȃ��B�j �~�����Ǝv���A�l�����̂ł����A�����Ȃ��B �ǁ[����āA�����蔻�������낤�B �i���ƃW���P�b�g�ɂ͉��炩�̃��W���[���͕t���Ă錩�����ł����c�j �G�y�Ȃ�A�ȒP�����Ȃ�ł����ǂˁ`�B �ʕ������܂���B�������Ă�����Č��\�ł��B ��ƂȂ����B�ł�������ƕs�v�c���Ǝv���܂���H �ȒP�H���������قȂ����H �� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�ߋ����O�́u�t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I�v�u�t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H�v�L���ɂ͎��X�t�F���V���O�W�̌����Ŕ��ŗ����Ă����������������悤�ŁA���삵�����ƍl�����Ă������������������������悤�ł��ˁB �@���l���������ł����݂��l�����č��ꂽ�Ƃ́I �@�������ł��B �@TV���Ō��Ă��ŋ߂̌��������̓d�C�R��������C�����X������Ă��āA�I��͎ז����K��(�����P�[�u��)�����Ȃ��Ă��ǂ��Ȃ��Ă��܂��ˁB �@���������������@�͂������l�����܂��̂ŁA�{�����ǂ̂悤�ȕ��@�E��H�ɂȂ��Ă���̂͂��������������Ƃ������̂Ŋm�͓����܂��A���̑z�������r�I�ȒP�Ɏ���������@�Ő������Ă݂܂��傤�B �@�u�t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I�v�Œ�����H�͂����܂��K��(�P�[�u��)���q���ŁA�����d���œd�C�I�Ȑڑ����m�������悤�ȕ��@�ł��B �@��b�������d�r�ƃ��[�h���ƌ��ƃW���P�b�g�Ɠ��d����Ɍq�����A���d�����_�����邩�ǂ����E�E�E�E���炢��z�����Ă���������Γd�C�̏��S�҂̕��ɂ��킩��悤�Ȍ��m��H�ł��B �@����ɁA������ƕ��G�ȃ��W�b�NIC���g�����u14/1000�b�������ĂĂ��邩�H�v��u�������L���͈͂�˂��Ă��邩�H�v�̔����H���q���Ă�����̂ł��B �@���āA���̑��u�����C�����X������ƁA�ǂ�������Ȃ�ł��傤���H �@�I�肪���郏�C�����X���u(����������q�@�ƌĂт܂�)���̂́A�I��̍��̂�����Ƀx���g�ŌŒ�A�܂��̓��^���W���P�b�g�̔w�������ɐ�p�̃|�P�b�g�ł�����ē���Ă��܂��A�����̑̂ƌ��E�܂��̓��^���W���P�b�g�̋����Ȃ烊�[�h���Ŕz���ł��܂��B �@�u����˂������H(���̒��̃X�C�b�`)�v�ɂ��ẮA�I��Ǝ����̌��̓��C�����X�ł͖������[�h���Ōq������Ǝv���܂��B�ł�����]���ʂ�����n�I�ȃX�C�b�`���̓d�C�ړ_�ł����Ǝv���܂��B �@���ɂȂ�̂́u����I��̗L����(���^���W���P�b�g)�Ɍ��悪���������H�v�̔��ʉ�H�ł���ˁB �@�Ȃɂ���A���C�����X�����Ă��܂��Ă͂��Љ����H�}�̂悤�ɑ���̃��^���W���P�b�g�ƃ��[�h���œd�C��H��ڑ����邱�Ƃ͂ł��܂����B �@�ł͂������ǂ����邩�Ƃ����ƁE�E�E�E�B �@���m���d�C��H�Ȃ����ɁA�d�C�̐��E�ł́u����ƃ��[�h���Œ��ڐڑ����Ă��Ȃ��Ă��A�d�C�I�ɂ͌q�����Ă���悤�ȏ�Ԃ͐��������v�Ƃ����ƂĂ��֗��Ȑ������g����킯�ł��B �@�{��ɓ���O�ɁA�܂��̓J���^���ɑz�����Ă��������B �@�u�e���r��W�I���āA�����ǂƓd���Ōq�����Ă���킯�ł͖����̂ɁA�A���e�i�𗧂Ă�Γd�g�ʼn�����f�����`�����Ă��܂��v�E�E�E��� �H �@����͊F����悭�����m�́u�d�g�v�̐����𗘗p�������u�Ɠd�C�M���̓`�����@�ł��B �@�܂�A�d���Œ��ڌq�����Ă��Ȃ��@�B���m�ŁA�Ȃ�炩�̓d�C�̗���͑��݂ł����Ƃ������Ƃ��F����͂����g�߂ɗ��p���Ă���킯�ł��B �@�����A�d�g�ł��Ƌ�C�����r�����r�������ł��܂��āA�t�B�[���h�ɗ����Ă��闼�I��̊Ԃ��炢�̊Ԋu�ł���ɓd�C�I�Ɍq�����Ă��܂��I��������܂���B �@���C�����X�q�@�ƐR����(�e�@)�̊Ԃ́A�܂��ɓd�g���r�����r�������ŏ��������Ă���킯�ł����ˁi�O�O�G �@�����ŁA�����Ɣ�Ȃ��d�g�H(������ƃ`�K�E)���g���A���[�h���Ōq�����Ă��Ȃ�����ł��u����˂������ۂɑ���ɐG��Ă��鎞�����A�d�C�M�����������H���`���ł����v�̂ŁA�����������@���g���܂��B �@�u���b�N�}������������B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�u����I�葤(���̐}�ł͐ԃT�C�h)�v��H�́A���U��H�Ŕ����������𗬓d�����M���̕Б������^���W���P�b�g�Ƀ��[�h���Őڑ��Ă����܂��B�@���̌𗬓d���͓d�g�قǂ̍������g���ł͂Ȃ��A��KHz�`���\KHz�̂��̂ł��イ�Ԃ�ł��B �@�������邾���Ȃ�A�悭�g���^�C�}�[IC 555�Ŕ��U��������`�g�̏o�͂ł����v�ł��B �@�����{���́A��쓮�Ȃǂ������悤���x��v�������̂ŁA�Z���~�b�N���U�q�␅�����U�q�Ȃǂ�p���������x�Ȕ��U��H���g���Ă��邩������܂���B �@���葤�A���Ȃ킿�u���M���v�͂��������ꂾ���ł��B �@����ʼn����ł��邩�ƌ����ƁA������x�ȏ�̎��g���̌𗬓d���́A�K���������[�h�����Œ��ړd�C�������d���o�H���q���ł��Ȃ��Ă��A��Ԃ��܂����œd����������Ƃ��������𗘗p���āA���^���W���P�b�g�ƌ��悪�����I�ɐڐG���邾���ŁA������𗬐M���̗L���Œ��ׂ邱�Ƃ��ł���I�Ƃ����A������Ɩ��@�̂悤�Ȗʔ�����H�����Ă��܂��킯�ł��B �@�����Ɋւ��Ắu�U���v�Ƃ��F�X�Ɠ���v�Z���̓l�b�g�Œ��ׂ���Ǝv���܂��̂ŁA�����ł͐����͏ȗ����܂��B �@�𗬓d���̕Б��̌o�H�u���^���W���P�b�g�`�����v�͕����I�ȓd�C��H�ŁA���̐ڐG�������Ɠd���͗���Ȃ��A���Ȃ킿�u�ڐG�������H�v��d�C�I�Ɍ��o���邱�Ƃ��ł���B �@�����Б��u���M�����U��H�̃A�[�X�`��M����H�̃A�[�X�v�͋�Ԃ�`����āA�Ƃ������ɂȂ�܂��B(���ۂ̓A���e�i�ɂȂ���������Ԃ�Ԃ牺���Ă����ƈ��肵�ē��삵�܂�) �@�u�������̑I��(���̐}�ł͗T�C�h)�v��H�͂�����ƕ��G�ɂȂ�܂��B �@����˂��Ă��Ȃ����ɂ͌������̓d�ɂ̓��[�N(ON)��ԂŌ���p�̔z���̓t�H�C����(GND)�ƌq�����Ă��āA�u�˂��Ă��Ȃ��v��ԂɂȂ�Ƌ��ɁA�𗬐M�����o��H�̓��͂�GND�ɗ��Ƃ��ĉ������͂���Ă��Ȃ���Ԃ����܂��B �@���ʼn�����˂��ƁA�ړ_�̓u���[�N(OFF)�ɂȂ�̂Ō���ւ̔z����GND�ɗ��Ƃ��ꂸ�A��d������苟�������DC�o�C�A�X�œd�����������āu(�����Ă��邩�ǂ����͕ʂƂ���)����˂����v��Ԃ����o���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�ƁA���̏�ԂŐ���������̗L����(���^���W���P�b�g)�ɓ����Ă��Ȃ��ꍇ�A�𗬓d���͗���Ă��Ȃ��̂Ō𗬂����o�����H�͓��삹���u�����v�Ɣ���ł��܂��B �@���悪����̃��^���W���P�b�g�ɐڐG�����ꍇ�A���U��H�̌𗬐M��������̒[�q����`����Ă���̂ŁA������𗬌��o��H�Ō��o���A����̐M��(����̔��U�M��)�����o�������̂݁u�L���ʂ�˂��Ă����v�Ɣ��ʂ����܂��B �@�𗬌��o��H�́u�𗬂̓d�C�M���Ȃ�Ȃ�ł��ǂ��v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B �@���̉�H�̂悤�ɕБ��̔z�����ڑ�����Ă��炸�u�U���v�̌����ŐM�������ꍇ�A�������͐M���͂ƂĂ������łق��ɂ���Ԃ��ь����Ă��邠����d�C�I�ȃm�C�Y�ƍ������Ă��܂��āA�P���������𗬂̐M�������͂���Ă���H�Ƃ������ׂ���A�m�C�Y�܂őS�āu�L���ŁI�v�ƐR�����Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B �@����ł͍���܂���ˁE�E�E�B �@�����Ŏ�M���ł͑��M��������o��������̎��g���̐M���̂��o�������߂̃t�B���^�[��H�Ȃǂ��K�v�ƂȂ�܂��B �@���̓���̎��g�������o�����H�́A���̂ق��ɂ��u�����Ƒ���Ŏ��g����ς��Ă����v���ƂŁA�����̉�H���ō���Ă��鑗�M�p���U��H����̈��e��(���M)����菜�����Ƃɂ��L���ł��ˁB �@�܂��A�����ł͌����̐����̂��߂Ɏ�M���̌𗬌��o��H�͂P�����`���Ă��܂����A������Q�̎��g���Ԃ�Q��H�p�ӂ��Ă����āA����(�s�X�g)�d�ɂ���O�̎��g���̐M���𗬂��Ă����u���ʂ�˂����ꍇ�ɂ́A�����łƂ͔��肵�Ȃ��v�Ƃ������胋�[���������ł������ł��B �@�{�������̂悤�ȕ������H�ɂȂ��Ă��邩�ǂ����͕ʂƂ��āA���[�h���Œ��ڌq�����Ă��Ȃ���l�̊ԂŁu�L���Łv�u�����Łv�肷����@�͓d�C�E�d�q�̊�b���_�����p���čl�������قǓ���������@�Ŏ����ł�������͂ł������Ǝv���܂��B �@�����̃��C�����X�R����ł́A�q�@�͐e�@�Ƃ̒ʐM�@�\�����킹�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ׂɁA���Z��(���[���ɉ�����)�̏�Ԕ���܂Ŋ܂߂Ă�₱���������̓}�C�R���`�b�v�ŏ��������Ă���ł��傤�B ���Ԏ� 2013/4/23
|
||
| ���e |
�����̂����肪�Ƃ��������܂��B ���̒��̂�����₪����܂����B �Ȃ�قǁA���^���W���P�b�g��s�X�g�𑗐M���c���̔��z���Ȃ������i�O�O�G�B �ǁ[���Ă��A�s�X�g�Ȃ�Đڒn����Ă�����̂ƍl���āc�B �F��Ȏ��g�������藐��Ă�X�|�[�c���đf�G���ȂƉ��߂ăt�F���V���O���D���ɂȂ�܂����B �Ȃ�̂�������B�O�O�B �܂���������܂����珑�����݂����Ƃ������̂ł�낵�����肢�v���܂� �� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�ǂ����Ŗ{���̃��C�����X���̐R����ł����݂����Ă݂�@�����A�ǂ�����Ă���̂����ׂĂ݂Ă��������B ���Ԏ� 2013/4/25
|
||
| �@�����L���� ���A����܂��B | |||
| �X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B | |||
|
�͂��߂܂��āB ���݁A����������쐬���Ă��܂������܂��������A���������߂Ă�����܂ł���Ă��܂����B�ǂ�����낵�����肢�������܂��B ��H�̎d�l�p�r�E�ړI�F�X�}�[�g�t�H���E�^�u���b�g�[���̃}�C�N�W���b�N�֓��͂��鉹���M���̔��U��H�ł��B �v���O�C���p���[�����ŁA��Ɉ��̋�`�g�i���Ƃ���1Khz�j���������A�X�C�b�`�i���̓X�C�b�`�Fhttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04002/�j���q���邱�ƂŁA���g�����ω��i���Ƃ���2Khz�j�����H�����߂Ă���܂��B ��낵�����肢�v���܂��B �܂� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@����́E�E�E���Ɏg���̂ł����H �@�ǂ�Ȏ����Ɏg���̂��A�ڂ��������Ă��������B �@���ƁA�u���̓X�C�b�`���q������v�Ƃ������ł����A���̃����N��̈��̓X�C�b�`��ON�ɂȂ��Ă��ڐG��Ԃɂ�萔�SK���`2K�����x�̊ԂŒ�R�l�͕s���ɂȂ�悤�ł����A (A) �ق�̏����ł��ڐG����A���g���͈�C��2KHz(��)�ɕς��u�f�W�^���I�ɕω��v�����H���~���� (B) ��R�l�����Ȃ����ɂ͎��g�������������ς��Ȃ��A���͂������\���ɐڐG�������ɂ͍ő��2KHz(��)�ɕω�����Ƃ����A�u�A�i���O�I�ω��v�����H���~���� �́A������ł��傤���H �@���Ȃ݂ɁA(B)�́u�A�i���O�I�ω��v�����H�ł���A�����茳�Ńu���b�h�{�[�h��œ����Ă��܂��B �@OPEN��: ��1KHz �@10K����: ��2KHz (2K�����͂����ƍ������g��) �� ���̃e�X�g��H�ł��AIC�̓���d���d���͈͊O�ňꉞ�͓��삵�Ă���̂��m�F���Ă��邾���ŁA���S�ɂǂ��̂ǂ̂悤�Ȋ��ł������ۏł�����̂ł͂���܂���B �@(A)�́u�f�W�^���I�ɕω��v�����H���~�����ƂȂ�ƁA���Ȃ��̗v������Ă����ڑ��@��Ȃǂ̎d�l�E�K�i�̌��ˍ����ŁA����������H�͍��Ȃ��\���������̂ʼn͂��f�肷��\���������ł��B �@�ƂĂ���ʂ̓d�q���i�X�̓X���Ŕ����Ȃ��悤�ȓ����IC�ȂǁA�ꉞ�̓��[�J�[�̌��J���Ă��鐻�i�ꗗ�ł͌��鎖�͂ł�����̂́A�܂����ʂɌl��������悤�ȕ��i�X�Ŏ�舵���Ă��Ȃ��悤�ȕ��i�ʼn�H�}�������E�E�E�Ȃ�Ƃ��Ȃ邩������܂��A����ł͎��ۂɕ��i���đg�ݗ��ĂĎg�p���邱�Ƃ��ł��܂��ˁB �@�d�l�E�K�i�Ƃ́A���������������u��v����ɂ�������ɂ����ׂɂȂ��Ă킩���Ă���������Ƃ͎v���܂����A�g�сE�X�}�z�EPC���̃}�C�N�[�q�̓d���́u�j�����E�G���N�g���b�g�R���f���T�}�C�N(ECM)�v�������߂̓d����^���邽�߂̓d���o�͂ł���A�G���N�g���b�g�R���f���T�}�C�N���K�v�Ƃ������ȓd���E�d�����������ł��Ȃ����l�ƂȂ��Ă����Ƃ����_���ł����ƂȂ�Ƃ���ł��B �@�u�d���v(�v���O�C���p���[)�Ƃ͖�����ŁA���ۂ��o�C�A�X�d���������Ă��邾���Ȃ̂ŁE�E�E�B �@���Ԃł悭�����u�t�r�a�o�X�p���[�v�݂������o�ŃG���N�g���b�g�R���f���T�}�C�N�́u�v���O�C���p���[�v�Ƃ����p��`��݂����ɍl���A���U��H��f�W�^�����W�b�N��H�E�I�y�A���v���̉��炩�̒�R�l�ɂ�锻���H���������̓d���ɂȂ邾�낤�E�E�E�Ȃ�čl����̂͑�ԈႢ���Ƃ������́E�E�E�E���ɂ������̂��ƂƂ͎v���܂����A�O�̂��߁B ���Ԏ� 2013/4/4
|
||
| ���e |
���X�̉���\���グ�܂��B �E�����͕��̂����ʂɗ��������A���������u�Ԃ�����悤�ɁA���̃^�C�~���O�����Œm�点��H�v���l���Ă��܂��B �E�����l���Ă����̂͂��掦���������������yB�z�ɑ������܂��B ���������������܂��ƍK���ł��B �܂� �l
|
||
| ���e |
�NjL�����Ă��������B ��OPEN��: ��1KHz �@10K����: ��2KHz (2K�����͂����ƍ������g��) �f�G�ł��B ���z�͂����ł����A���݂̏����ł͋�̉��ł��܂���̂ŃA�h�o�C�X�����������܂��B ������ȓd���E�d�����������ł��Ȃ����l �����ł��Ă��܂��B �����d����1.8V�ŁA�d�������ゾ�Ǝv���܂��B ������ɔ��U��H�֓��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B �ǂ�����낵�����肢�v���܂��B �܂� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@(B)�̂ق��̉�H�ł���A���Ȃ����i�Ŏ����ł������ł��B �@�ł��E�E�E�E�}�C�N�[�q�̓d����1.8V�ł����I�H �@�W���I�ȃR���f���T�}�C�N�p��H��2.2V�͖����̂ł��傤���B �@����1.8V���Ƃ���ƁA�d���C���s�[�_���X�͉�K���̉�H�ł����H �@�d���d��2.2V�ŃC���s�[�_���X1�`2K�����x�̕W���I�ȃ}�C�N�[�q�ł���Γ���\�ł����A�C���s�[�_���X�������ł�����d�����Ⴂ�Ɠ��삵�Ȃ���������܂���ˁB >�����ł��Ă��܂��B �@�Ƌ��Ă���̂ł��܂�ڂ��������Ȃǂ͂��Ȃ��Ă����v�̂悤�Ȃ̂ň��S�ł����A�}�C�N�[�q��d���Ƃ��Ďg�����������Ďg��(����d�������偁�}�C�N�[�q�̃C���s�[�_���X�ł͖���)�Ȃ�Ăقږ������Ƃ��������A�����I�ɂ��킩�肾�Ǝv���܂��B �@�����A�������������ōl����ƁA�����s�\�ł͂Ȃ����ƁB �@�\���Ƃ��Ắu��ɖ����v�Ƃ������͖����Ƃ͎v���܂����A�܂���{�I��������H�̉�H�}�͂��̃R�[�i�[�ł͈���Ȃ��Ƃ�����{�H��������܂����A�������Ďg����̂��H�Ƃ����_�ɂ��Ă̓e�X�g���l�@�����Ȃ����Ƃɂ����Ă��������܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@������œ��삵�Ă���̂͏�L�̉�H�ł��B�@�ʂɓ�����͍l�����A�P���Ɂu2.2V/�C���s�[�_���X1�`2K���̃o�C�A�X�d������d�C�����v�u0.7�`0.8V���x�ł����U����d�q���v���g�����������Ȃ̂ŁE�E�E�B �@C-MOS�^�C�}�[IC��LMC555 [PDF]�͒�i(���[�J�[�ۏؒl)�ł�1.5V�ȏ��œ���Ƃ���Ă��܂����A�傫�ȕ��ׂ��������Ȃ������0.7�`0.8V���x�ł����삷�邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B �@C-MOS�\���Ȃ̂ŏ���d�͂����ɏ��Ȃ����߁A�C���s�[�_���X�̍�����d���d������ł����낤������0.7�`0.8V���x������Γ��삵�܂��B �@�����A�����܂Ń��[�J�[�̕ۏ؊O�ł̎g�����ɂȂ�A�d����H�̓����E�����\�͂Ȃǂɂ��傫�����E�����M���M���̂Ƃ���œ������Ă��܂�����A�S�ẴR���f���T�}�C�N�[�q�œ��삷��ۏ͂���܂���B �@�u�j�����R���f���T�}�C�N�v�̔z���ɂ̓}�C�N�M��(�����M��)�ƃo�C�A�X�d�����d��(���傤���傤)����Ă��܂�����A���̉�H�ł����̂悤�ɂ��܂��B �@�}�C�N���C�����特���M���̌𗬐�������菜����IC��H�ɓd����^���A�t�ɉ����M��(�𗬐M��)�̓J�b�v�����O�R���f���T��ʂ��ă��C���ɑ���܂��B �@�����M���̃��x����VR1�Œ��߂ł��܂���(���S�ɉ��ʂO�ɂ͂ł��Ȃ��d�l�ł�)�A�}�C�N���͉�H���̃C���s�[�_���X�ɂ���Ă͉��ʂ�傫������ƕ��ׂ������肷���ēd���d����������E����������肵�āA����̂悤�ȃ}�C�N�d���ł͕s����ƂȂ�ꍇ������܂��B �@�H���d�q�Ŕ����Ă��鈳�̓Z���T�[�͎����Ă��Ȃ��̂Ŏ����ł͎����Ă��܂��A��R�ő�p���ē��ɖ��Ȃ����U���g�����ς��A����d���ł����U���~�܂�����͂��Ȃ����͊m�F���Ă��܂��B ���Ԏ� 2013/4/5
|
||
| ���e 4/9 |
�q���v���܂����B ��H�}�A�������ɂ��肪�Ƃ��������܂����B ��Ϗ�����܂��I�I�I�I �茳��LMC555������܂���̂ŁA���B������쐬�v���܂��B �܂� �l
|
||
| �O���u���V���X���[�^�[���� | |||
|
�O���u���V���XDC���[�^�[�̑��x��ϑ��ł����H�������Ă��������B �X�C�b�`�f�q�́AFET���g���\��ł��B ��H�}�ƁA�p�[�c���X�g�������Ă��������B ���肢���܂��B ������ �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����ւ�\�������܂��A�u�A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H�v�ŏ����܂����Ƃ���A�茳�ɎO���u���V���XDC���[�^�[�������̂ŁA�ʒu�Z���T�[��H�̎����ł��܂���A���̉�H���������͂ł��܂���B �@������ł̓n�[�h�f�B�X�N�̃��[�^�[���Ă݂܂������A����җl�̂�������e�ɉ������e�X�g�p�̊ȈՉ�H�ŁA�E�����ĂƂĂ��g�����ɂ͂Ȃ�Ȃ���H�łȂ�ڂ��Ă��܂��B �@�l�b�g����������A���삳���̂ɎQ�l�ɂȂ肻���ȁA�����ƈʒu�Z���T�[��H���݂̃u���V���X���[�^�[�̋쓮��H��͌��\��R�o�Ă���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2013/3/26
|
||
| ���e |
�w�A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���x���ǂ݂܂������A���������O���u���V���X���[�^�[�́A�Z���T�[���X�Ń��[�^�[����̒[�q���O�����łł��炸�A�R�C����R�́A�ǂ��𑪂��Ă������Ȃ̂ŁA�R�����́A�Ȃ��^�C�v���Ǝv���܂��B �����O���u���V���X���[�^�[�́ACD�h���C�u������o�������[�^�[�ł��B�Z���T�[�́A�����Ă��܂���ł����B ��H�}�ƁA�g�p���i�������Ă��������B ������ �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@������x�����܂��B�茳�ɎO���u���V���XDC���[�^�[�������̂��A���̂悤�ȉ�H�͍��܂���B �@�������ł����A���������Ă�Z���T�[���؎����́A�z�[���Z���T�[���ɂ��Ă��A�Z���T�[���X���[�^�[�̈ʒu���o��H�ɂ��Ă��A�ǂ���ł��u�ʒu��m�邽�߂��Z���T�[��H�v�ł��B �@�����������̂ɁA��������A���Ă��锽���d����g�`�E�^�C�~���O�����������Ȃ���̊J����e�X�g���ł���킯�͖����Ǝv���܂��B �@�����āA���Ȃ��l�̕ԐM�̌�ɂ�����ƃl�b�g�Ō������Ă݂܂������A���Ȃ��l�̂������̎O�����̃Z���T�[���X���[�^�[���}�C�R�����͎g�킸�Ƀf�B�X�N���[�g���i�����ŃX�s�[�h��ς���������Ȃ�����H�}�A�������FET���g�������́E�E�E���f�ڂ��Ă���T�C�g��}�ʂ�������������̂ł����E�E�E�B �@�ǂ������������Ƃ�����Q�l�ɐ��삵�Ă݂Ă��������B�����ł͂��������Ȃ��ł��������B ���Ԏ� 2013/3/26
|
||
| ���e |
������肽���̂́A�O�����u���V���X���[�^�[�����ƂŁA�E���Ă������̂ŁA������̂ł��B �ǂ��T�C�g������A�Љ�Ă��������B ���肢���܂��B (���O���L���œ��e���ꂽ ������) �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�������������āA����ς�͂����菑���Ă����Ȃ��Ƃ��߂Ȑl�������ł��ˁB �@�O��Ō�Ɂu��������Ηe�Ղɏo�Ă���̂ŁA�������Ō������Ă����������B��������H�}������܂�����A���̒��ł������̎�₨�莝���̕��i�ɂ��������̂�I���̂��ǂ��Ǝv���܂��B���̂ق��ł͌������ʂȂǂ͒��܂���B�v�Ə����Ă������ǂ��������܂������A�ꉞ�͂���������|�̕��Œ��߂������Ă����܂����̂ő��v���Ǝv���Ă܂����B >�ǂ������������Ƃ�����Q�l�ɐ��삵�Ă݂Ă��������B�����ł͂��������Ȃ��ł��������B �@�Ə����Ă���̂ɁA����ȏ��������Ă���l�͕��ʂ͋��Ȃ��Ǝv�����̂ł����E�E�E�B �@�܂��A�͂����菑���Ă����܂��B �@���̂ق����炠�Ȃ��ɒ���Q�l�y�[�W��URL�̒͂���܂���B �@�Ȃ����͍��̂��Ȃ��ɂ͂킩��Ȃ���������܂��A�킩��Ȃ��Ȃ�킩��Ȃ��ł����ł��B��x�Ƃ����Ŏ����ʂ̘b��ł����e�͂��Ȃ��ł������邾���Ō��\�ł��B ���Ԏ� 2013/3/27
|
||
| �d�����u������Ă���̂ł��� | |||
|
�d�����u������Ă���̂ł����A������̕����R���f���T��18000uF�Ƒ傫���̂œ˓��d���h�~���������Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B �h�~���@�Ƃ��ẮA��R��ɓ������@���ł��ȒP�ł������M���������͂��ł��B(5A�̓d���Ȃ̂�) �����ŁA�ŏ��̐��b�͒�R��ɓ���ă����[�Ō�͒Z��������A�Ƃ������@����肽���Ǝv���Ă��܂��B ���b�V���J�����g�h�~��H���Ȃ�ׂ����i�_�������Ȃ����Ă����H�������ė~�����ł��B �X�������肢���܂��B �Ƃ����[ �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�Ƃ����[�l�͍��܂ʼn��x�����e����Ă��āA�����̓��e���[���͂��킩��Ǝv���܂��̂ŁB �@�d�����u�̓d���₻�̑����͑S��������Ă��Ȃ��̂ŁA������Ƃ��Ă����m�ȉ�H���������Ƃ��ł��܂���B �@�ł��̂Œl���͈�ؖ����́u���Ԃ�E�E�E�����ƍ���������Ȃ��́H�v���炢�̉�H�����������ɂ��܂��B 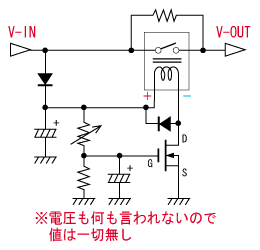 �@����Łu�Ȃ�ׂ����i�_�������Ȃ������v�Ƃ�������]�ł����A�g�p�d�����킩���Ă��������ō������ǂ������f���āA����̔������炢�̕��i���ł����ƊȒP����邱�Ƃ��ł����H�E�����Ƃ����̂�����̂ł����A����͂�����Ƃ��������̂͏o���܂���ˁB (�d���Ȃǂ̓s���ō���Ȃ��A���̕��@�œK�����镔�i�������ꍇ�͕��i�������炵���ʂ̉�H�͎g���܂���) ���Ԏ� 2013/3/11
|
||
| ���e |
�������肪�Ƃ��������܂��B�ƂĂ��Q�l�ɂȂ��Ă��܂��B
�d����20V�A�d���͈ꉞ10A�܂ł̕��ɂ������̂ł��B
�ꉞ�Ƃ����̂��A������5A���x�܂ł����g���܂����X10A���g�p���邱�Ƃ����邩��ł��B
���ƁA����̓u���b�W�_�C�I�[�h�ƕ����R���f���T�̊Ԃɋ���Ŏg�p�����ł���ˁH
�Ƃ����[ �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@��������A��H�}����o������ł́A�d���Ƃ��͕����ĂȂ��̂ŏ����Ȃ��Ă����\�ł��B �@�������̎g����d���Ȃǂł����Ɠ�����H�}����Ȃ��Ő���ɓ������i�ŁA�������̗p�r�ɂ��킹�Đv���č���Ă���������B �@���ޏꏊ�͂����ł����ł��B ���Ԏ� 2013/3/12
|
||
| ���e |
���b�V���J�����g�h�~�p��R�́A�ǂ̈ʂ̒l�̕��������ł����H �Ƃ肠�����茳��7w�A1���̒�R������̂ł����A����ł����ł��傤���H �����ė~�����ł��B �Ƃ����[ �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����́u�����[��t�������A�Ȃ�ׂ����Ȃ����i�Łv�Ƃ������v�]�ɑ��Ă���������Ƃ������e�Ŗ{�����f�ڂ��Ă��܂��B �@��R�l�Ȃǂ͊��Ɍ��߂��Ă��邩�A�K�Ȃ��̂��������őI�����̂ƁB �@�m���A�ŏ��ɒ�R�l�͂ǂ�������ǂ��̂���A�d���d�����ǂ��ŕ��ׂɂ͉����q���̂Ƃ��̂����������������܂���ł������B �@�����[������H�ȊO�̂�����͖����Ƃ������ŗ������Ă��܂��B �@���鎿������Ă����āA�������o����u���̎���ł��E�E�E�v�Ƃ����̂͂��������������ƁA�O�X���猾���Ă邱�ƂȂ̂ł����B �@���������Ă��������Ȃ������Ƃ������́A���̎���ɓ�������܂����̎��₪�o�Ă���\��������܂���ˁB �@���̃��b�V���J�����g�h�~���u�Ɋւ�邨�b��A������͍����؎t���܂���B ���Ԏ� 2013/3/17
|
||
| �o�l�Q�D�T����킪��肽�� | |||
|
�o�l�Q�D�T����킪��肽�� �Ȃ�ׂ��ȒP�ȉ�H�� �l�b�g�ʼn�H�}�����ďH���ŕ��i���ĕ��˔\�����͍�����̂ŏH���Ŏ�ɓ��镔�i�� (������]) �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@��ϐ\�������܂���B �@�H���łƂ��E�E�E�d�q���i�X�ŁuPM2.5�Z���T�[�v�Ƃ����ӂ��Ȕ����q�Z���T�[(���i�E�L�b�g������)�͂�����ƌ������Ƃ�����܂���B �@�l�X�Ȍ��Z���T�[�≷�x�E���x�E�K�X���̃Z���T�[�͓d�q���i�ł��낢��o�Ă��܂����A���b���PM2.5�݂̂����o�ł���悤�Ȕ����q�Z���T�[�ƂȂ�ƁA������Ɠ���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2013/3/7
|
||
| ���e |
�{���ɖ����̂��H ���˔\�����̏ꍇ�������˔\�𑪒肷�镔�i�ł͖����_�C�I�[�h����˔\����Ɏg����Ƃ������ŊS�������� �o�l�Q�D�T�����̏ꍇ�o�l�Q�D�T�𑪒肷���啔�i�Ŗ����Ă��g���镨�͔����Ă��邾�낤�ƍl���Ă��� (������]) �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����Ă܂���B ���Ԏ� 2013/3/11
|
||
| ���e |
�����X���炵�܂��B PM2.5�̑���͊�{�I�ɂ͍H�ꉌ�˂̔r�o�_�X�g��r�C�K�X�𑪂�u�_�X�g���j�^�v�Ɠ����d�g�݂ł��B �F�X�ȕ���������܂����ȈՓI�ɂ́u�|���@�v���������ă����u�����t�B���^�ɔ푪��Ώۋ�C��ʂ��t�B���^�[�̋l�܂���������@�ł�����̂ł́B�B���N�O�ɖ^�s�m�����f�B�[�[���̔r�C�K�X�����҂Ɏd���ďグ���Ƃ��ɓo�ꂵ�Ă����ۂ���������ł��B �d�q�H��̕��ނł͂Ȃ��A�@�B�H��̕��ނł��B �d�q�H��n�̑�����@������܂����f�l�ł͒���������Ȃ��ł��傤�H arii �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����ł��ˁB������ƃl�b�g��������A��C���̔����q�ʂ𑪂鑕�u�̋�̗�͏o�Ă��܂���ˁB �@�����́u�t�B���^�[�v�ɏW�߂����q�̗ʂ�ʂ��Ă���̂ł����E�E�E�B �@�d�q���i�����ŁE�E�E�E�ƂȂ�Ɩ����ꒃ����͖����ł����B �@�d�q���i�����łƂ͌����Ă��A��͂肻��Ɏ��Ԃ�������ʂ̑�C��ʂ����߂̋@�B�I�Ȏd�g�݂�A�����̕����I�t�B���^�[�͗p�ӂ��Ă��K�v���o��Ǝv���̂ł����B �@�����A������]�̕��̂��v�]�̂悤�ȁu�H���d�q�Ŕ�����悤�ȕ��i������(�f�l�ł��e�Ղ�)�g�ݗ��Ă�v�Ƃ����͖̂������Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2013/3/12
|
||
| ���Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 | |||
|
�V�S�g�b�S�O�P�V�̃N���b�N�i�b�q�j�ɂV�S�g�b�P�R�Q�ŃN���b�N�p���X���P�b�����ő���X�̂k�d�c�����Ԃɓ_�ł�������J��Ԃ��P���ȉ�H�������Ă��܂��B������������ĂX�ڂ̂k�d�c�ɗ������ɂ��炭��~�i�O�`�U�O�b���炢�ϒ�R��Œ����j���A���̎��i��~���j�ʉ�H�̂h�b�i�Q�X�O�S�c�j�̓d�����Ւf�i�����[�ł͂Ȃ��A�g�����W�X�^�������̂Łj�����H����肽���ł��B ���낢��l���܂��������܂������܂���B�悫�A�h�o�C�X���������I �`�j�a �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@74HC4017 [PDF](C-MOS���W�b�NIC 4017B [PDF]��HC��)�́u10�i�E�f�R�[�h�J�E���^(Decade Counter)�v�ŁA����10�i�J�E���^�Əo�͕��ɂ͓����̓���ȃJ�E���^�r�b�g�f�[�^���u0�`9�v�ɉ�����10�̏o�̓s���Ɋ���U��f�R�[�h��H���������J�E���^IC�ł��B �@���̂܂܂ł̓N���b�N���͂��Ƃɐ������u0�`9�v�܂Ő�����9�܂ōs�����玟�́u0�ɖ߂��v���J��Ԃ��u����10�܂Ő�����IC�v�ł����ARESET(CLEAR)�s���ɂ����ꂩ�̏o�̓s����ڑ����邱�ƂŁu�C�ӂ̐��ɂȂ����烊�Z�b�g����0�ɖ߂��v�����́u���i�J�E���^�v�Ƃ������R�Ȑ����܂ł̃J�E���^�Ƃ��Ďg�p�ł��܂��B �@����җl�̉�H�� >�X�̂k�d�c�����Ԃɓ_�ł�������J��Ԃ� �Ƃ������ł�����A10�i�S�����g���Ă���̂ł͂Ȃ��A�uLED�͂X�����q���Ȃ��̂ŁA10�Ԗ�(Q9)�ɂȂ����烊�Z�b�g�����v�Ƃ����g����������Ă���̂ł��傤�B �@�����P�̋@�\�Ƃ���^CLOCK ENABLE(L=�N���b�N����)(C-MOS���W�b�N�łł�CLOCK INHIBIT(H=�N���b�N�֎~))�s�����g���āu�N���b�N�ɏ]���Đi���v�u�N���b�N�������Ă���~�����܂܂ɂ����v�Ƃ������삪�s�Ȃ���̂ŁA�u0�`9�v�̔C�ӂ̏o�͂�^CLOCK ENABLE��ڑ����邱�ƂŁu�C�ӂ̐����܂Ő������炻���ł����ƒ�~�����v0�ɖ߂�Ȃ��^�C�v�̃J�E���^�Ƃ��Ă��g�p���邱�Ƃ��ł��܂��B �@���������@�\���g���č���̂悤�Ɂu�ꎞ�I�ɒ�~�������v�Ȃ�^CLOCK ENABLE�s�����R���g���[�������̂���ʓI���Ƃ͎v���܂����A�������ꂾ��������Ƃ����s�s���������̂ŁA�����č���͕ʂ������ƖړI���ʂ�����H���l���܂��B >�X�ڂ̂k�d�c�ɗ������ɂ��炭��~�i�O�`�U�O�b���炢 �@�Ƃ����@�\���ʂ����ɂ́u�X�ڂ̂k�d�c�ɗ������v�Ɂu�U�O�b���炢�̃^�C�}�[���쓮�������v�Ƃ�����H��p�ӂ���̂͒N�ł��v�������Ƃ��Ǝv���܂��B �@����͂���͑S����薳���̂ŁA�����̃����V���b�g�^�C�}�[IC��74HC221 [PDF]���g�����^�C�}�[���g�p���܂��B �@����ŁA��قǏ������u������Ƃ����s�s���v��������邽�߁A�u���炭��~�v������ɂ́u�N���b�N���~�߂��v���@���Ƃ�܂��B �@�N���b�N���~�߂��Ƃ����Ă��N���b�N��H����̓��͂�4017���N���b�N�M���Ƃ��ē���Ȃ��悤�ɂ��邾���̉�H���ł��܂����A����ł�^CLOCK ENABLE�[�q���R���g���[�����ăN���b�N���֎~�����̂Ɠ����Ȃ����I�Ȃ̂ŋp���ł��B �@����́u�N���b�N���U���̂��~�߂��v�K�v������܂��B �@�����ւ�s���悭 >�V�S�g�b�P�R�Q�ŃN���b�N�p���X���P�b�����ő��� �Ƃ������ŁA�N���b�N���U��H�ɂ�NAND�Q�[�g��74HC132 [PDF]���g���Ă���̂ŁA�uNAND�Q�[�g�ō�������U��H�́A���̓s������������o�������U��ON/OFF���ł����v�̂ł����ꕔ�̕ύX�����őΉ����\�ł��傤�B �@�����N���b�N���U��H��NOT�Q�[�g��74HC14 [PDF]�Ȃ��g���č���Ă�����A������Ƃ���IC�͊O���Ă�����āA�V�K��74HC132�Ŕ��U��H������Ă��������ƌ����Ƃ���ł����i�O�O�G �@�Ƃ������Ƃ� �� �X�Ԗڂɂ������莞�Ԓ�~�����邽�߂̃^�C�}�[���N�� �� �^�C�}�[���̓N���b�N���~���� �Ƃ����ړI����H�}�ɂ���Ƃ����Ȃ�܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�܂��e���̖ړI�⓭���͏�Ő��������Ƃ���ł��B >��~���A�ʉ�H�̂h�b�i�Q�X�O�S�c�j�̓d�����Ւf �@�Ƃ����ړI�ɂ́A�u�X�Ԗڂ̏o�͂�ON(Q8 = H)�̊��AFET��OFF�ɂ���OP-AMP�ւ̓d�����Ւf����v�u�X�ȊO�̎�(Q8 = L)�ɂ�FET�������d���͋���������v�Ƃ������_�œd���X�C�b�`�̂����ƂȂ�FET�����������̂ŁAP-ch�^�C�v�̃p���[MOS-FET���g�����������킩��܂��B �@�ʂ�FET�łȂ��Ă������W�X�^(�ƃx�[�X��R�Ƃ����K�v)�ł��\��Ȃ��ƌ��������Ȃ�ł����E�E�E�A�Ȃ�ׂ�74HC4017�̑��̗p�r�̔z�����q�����Ă����{�̃s������g�����W�X�^�̃x�[�X�d���܂ŗ��������͖����Ȃ��E�E�Ƃ��������z�ł��ˁB �@����OP-AMP(2904D)���̉�H���ǂ��������̂��S���������Ă��Ȃ��̂ŁA���Ԃ�P����OP-AMP���ȓ��������炢�̉�H�Ȃ琔�\�`���SmA������������̂ŏ��d���p�g�����W�X�^�ł��悩�����̂ł����A����������Ă��Ȃ��̂�5A�܂ŗ�����2SJ377 [PDF]�ɂ��Ă���܂��B �@�ʂɍ������i�ł͖����̂ŁA���̒ʂ�ɂ���肭�������B �@���āA�Ō�Ɂu������Ƃ����s�s���v�ɂ��Ăł��B �@�i�s���~�߂�����^CLOCK ENABLE(L=�N���b�N����)�[�q��H�ɂ��Ă�邱�ƂŊm����4017�̃J�E���g�͐i�݂܂��A���̊Ԃ��N���b�N���U�͔��U�����������̂ŁE�E�E�u��~�p�^�C�}�[���I���������_��^CLOCK ENABLE�[�q��L�ɖ߂������A�N���b�N���͂�H�̏�Ԃ������ꍇ�A����́w���̃N���b�N�������I�x�Ƃ����J�E���g���P�i��ł��܂��܂��v�B �@�u��~����^�C�}�[���������ꂽ����A���̏u�ԂɎ��ɐi�ނ̂ł����̂ł́H�v �@�Ƃ������Ɏv���邩������܂���B �@�������A�������܂����悤�Ɂu�N���b�N���͂�H�ɂȂ��Ă����v�悤�ȏ�Ԃ��u�P�b���Ƃ�LED�����ɐi�߂�v�Ƃ������ԒP�ʂ̂ǂ����r���ɂ�����A���̎��_��LED���P�i�߂�Ƃ������́u�N���b�N��H���Ԓ��Ƀ^�C�}�[����Ă�ނȂ��i����LED�\���́A�{�����ꂪ�_�����鎞��(���ɂP�b)�̓r������_���������ƂɂȂ�A�K���LED����_�����鎞��(���ɂP�b)�������_���������Z�����ԂŎ��ɐi��ł��܂��v�Ƃ����A������Ǝc�O�ȓ�������Ă��܂��܂��B �@�N���b�N��J�E���^�[���i�ޘ_�����悭�������Ă��Ȃ��ƁA���͂����ǂ�ł��Ȃ��Ȃ������������܂��A�u�P�ڂ�LED���_�����鎞�Ԃ��K��ʂ�ɂȂ�Ȃ�(�ꍇ������)�v�Ƃ����_�����킩���Ă��炦�����ł����ł��B �@����ɑ��āu�N���b�N���U���̂��~�߂Ă��܂��v����̉�H�ł́A�^�C�}�[���Ԓ��̓N���b�N���U���~�߂ăN���b�N�M����H(�J�E���^���X�Ԗڂɐi�ނ���ɓ��������̏��)�ɂȂ����܂ܒ�~�����A�^�C�}�[���ԏI����ɂ������������̂��^�C�}�[�������ɏ���ɃJ�E���g���P�i��ł��܂��Ƃ������Ƃ�����܂����B �@�J�E���g���i�ނ̂́u�^�C�}�[���I�����N���b�N���~������̂���������A�N���b�N���U���ĊJ���ꂽ���̃N���b�N�M����H�ɂȂ鎞�_�v�ɂȂ�A���̂悤�����ʂɃN���b�N���U��H�����U���Ă����Ԃł̃J�E���g���P�i�߂�ʏ�̃^�C�~���O�ŃJ�E���^�̓J�E���g��i�߂�̂ŁA���ɓ_������LED���_�����鎞�Ԃ͂����������ʂ�LED����_������P�P�ʂԂ��_�����܂��B �@�ˁH �@���̉�H���Ɖ�����肪�����ł���B �@�����P��肪����Ƃ���ƃ^�C�}�[���Ԃ��I�����āA�e�X�g�p�ɂ��Ă���u�^�C�}�[�m�F�vLED���������Ă����P�N���b�N�x��Ď��̃N���b�N�����オ���LED���X�Ԗڂ��玟(�P�Ԗ�)�ɐi�ށE�E�E�悤�Ɍ������Ƃ������Ƃ��炢�ł��傤���B �@�u�^�C�}�[�m�F�vLED�����Ă���ƁA���삪�ĊJ�����̂�������ƒx��銴�������܂��B �@�u�^�C�}�[�m�F�vLED�͂����܂��^�C�}�[��H�̍H�삪�Ԉ���ĂȂ��A���������삷�邩�H���m���߂邽�߂̂����Ƃ��ĕt���Ă���̂ŁA�u���ۂɂX�ԖڂŎ~�܂鎞�Ԃ̒��߂́A�X�Ԗڂ�LED���~�܂��Ă��鎞�Ԃ����Ē��߂����v(������܂��Ƃ���������܂��ł����E�E�E)�Ƃ������@�Œ��߂��Ă��������B �@�u�X�Ԗڂɗ�����ꎞ��~������^�C�}�[������v�u�^�C�}�[�����쒆�̓J�E���g���i�ނ̂��~�߂��H�E�z���ɂ���v�Ƃ�������̖ړI��B������̂ɁA�g�����i�Ɣz���͏��Ȃ��Ă����������Ƃ͂���܂��A�����̑g�ݍ��킹��ǂ̕������R���g���[������Ɗ�]�ʂ�ɐ�����������H�ɂȂ邩�̐v�́A����Ȋ����ł�����IC�̓��������[���������Ă��Ȃ��Ƃ��܂����Ȃ���������܂���B �@���ꂩ��̍H��̎Q�l�ɂ��Ă��������B ���Ԏ� 2013/3/3
|
||
| ���e |
���ł́A����v�����Ȃ������ȉ�H���l���Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B���̉�H�����ƂɁA�������삵�Ă݂܂��B�܂��A���������ł����炻�̎��͂�낵�����肢���܂��I �`�j�a �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�͂��A�撣���č���Ă݂Ă��������B �@����ŁE�E�E���̃R�[�i�[�̂��肢���Ƃ���
�@�I�y�A���v�̓d������ĉ��������H�Ȃ̂��H�A����łǂ�ȑ��u������Ă���̂����������肦�܂��H �@���������Łu�S���������Ă��Ȃ��̂��v�̂悤�Ȍ������g���Ă��鎞�ɂ́A�ÂɁu(�ԐM��)���Ȃ��ɂ��̂��̏��������Ă��炢�����v�ƌ������Ă����⊮����鎖�����肢���Ă���̂ł����E�E�E�B ���Ԏ� 2013/3/6
|
||
|
|
|||
| �Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I | |||
|
�͂��߂܂��āB 30�N�O��APPLE�U�R�s�[�i�̃n���_�t������������Ƃ����邾���ŁA��H�v�͑S���̑f�l�ł��B ��̍�����ԍ̏W�łSW�u���b�N���C�g���g�p���Ă��܂����A�d�r�̏��Ղ��傫��LED�����������Ǝv���T���Ă�����u�C�̖����l�v�̃T�C�g�����t���܂����B �C�O�Ŗ�Ԑݒu����Ɠ��܂�邱�Ƃ��������߁A�ł��邾���S�ςŒT���悤�ɂ��Ă��܂����A�����̏��i�Љ�ƌ����ȉ�������Љ��Ă���̂ɂ͊������܂����B �����ŁA�M�T�C�g�ŏЉ��Ă���A�u�^�b�`���C�g�u���b�N�v(�_�C�\�[TS090601�j��UV-LED�����āA���ÃZ���T�[�Ŗ邾���_������悤�ɉ��������݂܂������A���܂��s���܂���ł����B �u���邳�ɘA������LED�v���Ó_���ɕύX���鎖�ƁA�u�Â��Ȃ�Ɠ_������LED�炢���v���Q�l�ɂ����Ē����Acds�i100K-200K����10LX/��10M���j��2SC2120Y��100K����VR2���g���ăg���C���܂������AON-OFF�������ł��܂���B�M�R�����g�ł́u�^�b�`���C�g�u���b�N�v�̓d���͂�130-90mA�Ȃ̂ŁA�P�[�X�Ɏ��߂邽��2SC2120�����̎g�p�Ƃ������̂ł����A�u�Â��Ȃ�Ɠ_���炢�Ɓv��2SC1815�_�[�����g���������܂������ʖڂł����B �ߋ����O�Ɋ֘A���鎿��Ő\����܂��A�A�h�o�C�X����K���ł��B ��낵�����肢���܂��B ���{ ���V �l
| |||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁE�E�E�u�A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED�v�ł��u�Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł��v�̂�����̉�H���g���Ă��_���������Ƃ������́E�E�E�A���{�I�ɉ�H�}�Ƃ��ȑO�̖�肪����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�g�����W�X�^�̑����Ԉ���Ă����Ƃ��z���܂��͉�H�v���ԈႦ�ĕ��i���Ă��܂����I�Ƃ��B �@���Ƃ͓d�q��H�ȑO�̖��Ƃ��āA�^�b�`���C�g�u���b�N��LED�����O��LED�ƌ������ꂽ���ɂ́A�܂��͂��ꂾ���Ő���ɓ_������̂͊m���߂��܂�����ˁH �@���̎��̏���d���͉�mA�ł������H >�u�^�b�`���C�g�u���b�N�v�̓d���͂�130-90mA�Ȃ̂� �@�Ƃ����̂́u�����܂ŏ��i�ɕt���Ă��锒�FLED(�̒�i�̏ꍇ)�ɗ����d���v�ł���ALED�����������炻���̐��l���ʕ��ɕς���̂͂������̏�ʼn������ꂽ��ł���ˁH �@LED���Ă��Ă��܂��悤�Ȉُ�ȓd���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���ł�����ˁH �� UV-LED�Ȃ甒�FLED�Ƃ������ĕς��Ȃ��Ǝv���܂����A�O�̂��� �@���̏�Łu����ɓ��삵�Ȃ��v�Ƃ����͈̂�̂ǂ̂悤�ȏǏ�Ȃ̂ł��傤���H �@�uLED���S���_���v���Ȃ��̂ƁuLED�������ςȂ��ɂȂ��v�̂Ƃł́A�����ӏ��̓���ɓ��铹���ς���Ă���Ǝv���̂ł����E�E�E�B �@���Ƃ܂����A�u���邳�ɉ����āE�E�v�̉�H���u�Â��Ȃ�����v�ɕύX����ۂ�Cds���}�C�i�X���Ɉړ����āA�v���X���͔��Œ�VR�����ɂ��Ĕ��Œ�VR�̃c�}�~�����������Ȃ���g�����W�X�^��H�Ƃ��Đ�ɂ���Ă͂����Ȃ������Ȃ͂��Ė����ł���ˁE�E�E�H �@�g�����W�X�^���Ȃ��Œ���̓d��������R(���ʂ͌Œ��R�ŕt����)��������ԂŔ��Œ�VR�����ɂ��āA�c�}�~���O���ɂȂ�ʒu�ɉȂ�ċ��낵������������A�x�[�X�ɉߓd��������ăg�����W�X�^����u�ŏĂ��Ă��܂��܂���˂��B �@���������j��H���������ł��Ă��Ȃ��Ƃ��āA����ł�����ɓ��삵�Ȃ��ƂȂ�Ɓu�g��ꂽCds�ɑ��Ĕ��Œ��R�̒l�������������v�Ȃǂ��l�����܂����A100K���ł������Ă͂����Ɣ�������͂��ŁE�E�E�B �@�{���Ɂu��H�}���������������ɉ�H�̒m���������̂ʼn����ԈႦ�Ă�̂ł́H�v�Ƃ��v���܂������u�Â��Ȃ�Ɠ_���炢�Ƃ�2SC1815�_�[�����g���������܂������ʖڂł����v�Ƃ�����̂ŁA����ɓ��삷��͂��̉�H�}�̒ʂ�ɑg�ݗ��ĂĂ��_���Ƃ������Ƃ́E�E�E��͂��g�ݗ��āE�z���̃~�X�̉\���̂ق��������Ǝv���̂ł����A�������ł��傤���H (1) �^�b�`���C�g�u���b�N���Ɠd�q��H���͐藣�� (2) �^�b�`���C�g�u���b�N��������UV-LED�͓_������H �@�J�\�[�h���͌��̊����藣���ăg�����W�X�^�ɍs���Ă����Ǝv���̂ŁA���̔z���̓g�����W�X�^��H�ɑ����Ă����d���̃}�C�i�X�z���Ɛڑ�����AUV-LED�͌���܂���ˁE�E�E�B (3) �d�q��H���͐���ɓ��삷��H �@�d�q��H����g�ݗ��ĂĂ����ɓd�������z�����A�^�b�`���C�g�u���b�N�̂������ԐFLED������ԐFLED�ɓK�����d��������R���Ȃ��ŁA�d�q��H������ɓ��삷�邩���炢�͊m���߂��܂���ˁB �@����ŐԐFLED���u�Â��Ȃ�����_�� (���邢�Ԃ͏������Ă���)�v���Ȃ��ꍇ�́A�g�����W�X�^�܂��̔z���~�X���A���i���Ă��Ă��܂��Ă����Ō���Ȃ킯�ŁE�E�E�B �@�u�Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł��v�ŏo�Ă����H�}�̌Œ��R�Œ��R�ɕύX������H�}�͂����������̂ł����A������ł̃e�X�g�ł͂���łƂĂ��ǂ��������Ă��܂��B(�Ƃ������A��H��ł͓����Ȃ����R�������I�Ƃ����ʂɒP���ȉ�H) ���N���b�N����Ɗg��\��
�@���̕��@�ł̓g�����W�X�^���_�[�����g���ڑ����Ă��܂��̂Ńg�����W�X�^�̑������͉҂��܂����A���ʁA�_�[�����g���\���̌�����ǂ��撣���Ă�Vce����0.7V�ɂ��Ȃ��Ă��܂����߁ALED�ɂ�������d�����d�r�d���|0.7V�����Ȃ茸���Ă��܂��̂ł�����l������LED�̓d��������R�̒l��v���Ă��Ȃ��ƁALED���Â��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������_������܂��B >�P�[�X�Ɏ��߂邽��2SC2120�����̎g�p�Ƃ������̂ł��� �@�Ƃ̂���]�ł�����܂����A���̉�H�}�̃_�[�����g�������g�����W�X�^������ɂ��Ă�����ɓ����܂����A���̏ꍇ��Cds�Ŗ��邳�����o���镔���̓���͈͂ƃg�����W�X�^��ɗ����x�[�X�d���ƃg�����W�X�^(2SC2120)��hfe�̊W(��₱����)�ŁALED3�ɕK�v���イ�Ԃ�ȓd���𗬂���قǃg�����W�X�^�͓d���𗬂����ɁA�����d�������������炢�ɂ��������Ȃ��̂�LED�͑����Â��Ȃ��Ƃ������_�ɂȂ�܂��B �@���Ƃ��ẮA���{�l���ǂ����Ԉ���āu���삵�Ȃ��v���ƂɂȂ��Ă���̂��A�����ƌ����������Ă��茳�̍�i�œ�������ɂ��ė~�����Ƃ���ł����A����Ƃ͕ʂɍŌ�ɂP�̃v�������Ă����Ă��������܂��B �@�u��ōς܂������I�v�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA2SC2120���̃g�����W�X�^��ł�Cds�܂��̒�R�l�Ɠd���������̊W�ő傫�ȓd���𗬂����g�����W�X�^�����S�ɃX�C�b�`�Ƃ��Ă͂n�m�̏�Ԃɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������_�͐�قǏ������ʂ�ł����A�����͓d�������f�q�̃g�����W�X�^����߂ēd������f�q��FET�ɂ��Ă��܂��قƂ�lj������܂��B 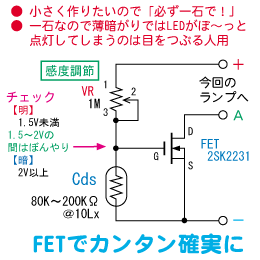 �@�E�}�̒ʂ�AFET��ŁACds��VR�ɂ�镪���d����FET��Vg-s�����S�ɒ��������ɂ͏\���ɑ傫�ȓd���𗬂����Ƃ��ł��܂��B
�@�E�}�̒ʂ�AFET��ŁACds��VR�ɂ�镪���d����FET��Vg-s�����S�ɒ��������ɂ͏\���ɑ傫�ȓd���𗬂����Ƃ��ł��܂��B�@������FET�Ȃ̂�Vg-s�͊��d�r���{���炢�̓d���Ȃ璼�ڂ����Ă����Ȃ��Ƃ�����������A�g�����W�X�^��H�ł̓x�[�X�d���̍Œ�ی�p�ɓ���Ă����Œ��R(1K��)���K�v�Ȃ��Ȃ�A���i�����P���Ȃ��Ȃ�܂��B �@�g�����W�X�^������g�p�̎��Ɠ����悤�ɁA�����Â����́u���S�ɓd�����Ւf�����ԁv�Ɓu���S�ɓd���𗬂���ԁv�̊Ԃł�LED�͂ځ`���Ɠ_�����Ă��܂��Ƃ������_�́A��͂���ł���Ă���ȏ�d���Ȃ��Ƃ��Ėڂ��Ԃ邵������܂���B �@�u����Â��ɂȂ�����p�b�I�Ɠ_������^���閾�邳�ɂȂ�����p�b�I�Ə��������v�悤�Ȍ����ڂɑu�₩�ȓ����(�g�����W�X�^�ō��Ȃ�)���͕K�v�ł��B ���Ԏ� 2013/3/2
|
||
| ���e 3/24 |
��T�܂ŊC�O�ɏo�����Ă������߂��Ԏ����x���Ȃ�\����܂���B �f�l�̎���ɑ��A�����J���ڍׂȉ����Ē������肪�Ƃ��������܂��B ���܂����삵�Ȃ��Ƃ����̂́AVR��ύX���Ă݂��疾�ÃZ���T�[�Ƃ��Ă͓��삷�邪�ALED���{�������Ƃ����_�����Ȃ��A�Ƃ������ł������A�g�����W�X�^�ł͗�����d���Ɍ��E������Ƃ������Ƃ��悭����܂����B ����FET��p������@�������Ă݂����Ǝv���܂��B ���炭���Ԃ��|���邩������܂��A���ʂ��o������߂Ă��Ԏ������Ē����܂��B �ڍׂȉ�������Ē����A��ϕ��ɂȂ�܂����B ���肪�Ƃ��������܂����B ���{�@���V �l
|
||
| ���e |
�Q�l�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ�������܂����B (���O���L���œ��e���ꂽ ������) �l
|
||
| �ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H | |||
|
�@�Ԃ̃i�r�̃{�����[����UP/DOWN�̃{�^�����ő��쐫���C�}�C�`�Ȃ̂ŁA�N���b�N���̂����]���̃{�����[���ɂ������Ǝv���Ă��܂��B �@���͉����Ȃ��ł��Ȃ��X�e�A�����O�X�C�b�`�p�̒[�q������̂ł�����𗘗p�ł��Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B �@���̒[�q��1K������ăA�[�X�ɗ��Ƃ���(�T�u���R�D�P�u�j�{�����[��UP�A3K������ė��Ƃ��i�T�u���S�u�j�ƃ{�����[��DOWN�Ƃ�������ŁA���ʂ̃X�e�A�����O�X�C�b�`�̂悤�ɉ����{�^��SW��2�g���̂ł���ΊȒP�ł��B��������]���̓s���̂����X�C�b�`�ȂǂȂ������Ȃ̂ŁA���ƂȂ�ƃ��[�^���[�G���R�[�_�[���g������H�ɂȂ�Ǝv���܂����悭�킩��܂���B �@�����������i�͂悭����̂ɂ��̂܂g�������ȉ�H�}��������Ȃ��̂ŁA�ȒP�ȉ�H�������Ă���������Ƒ�Ϗ�����܂��B ��낵�����肢�������܂��B (������]) �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���₪����܂��B �@���̃i�r�̃����[�g�X�C�b�`�́A�������A�ł��Ă��������܂����H �@�ƂĂ��Z���`�����Ɖ����Ă��������܂����H �@�X�C�b�`���������ςȂ��ɂ�����A�������ŏ��̈���P�X�e�b�v�Ԃ�{�����[�����オ��^�����邾���ł����A����Ƃ������Ă���Ԃ��イ�̓{�����[���������Əオ��^�����铮������܂����H �@�����A�ł��Ă������������ꍇ�Ȃǂ́A���[�^���[�G���R�[�_�[���Ă��i�r�����ǂ������ɁA���슴���������̂ɂȂ��Ă������Ƃ��A�������������͑��v�ł����H (�i�r���̔�������ł�����) �@�}�C�R���Ȃǂ��g���A���[�^���[�G���R�[�_�[��������ƈ�C�ɑ����Ă��A������L�����Ă����ăi�r���̔������x�ɂ��킹�Ă����ƒǐ����锽�����������H�Ȃǂ����܂����A�����̃��W�b�NIC�Ȃǂł��������͖̂�����������܂���B �@�E�E�E�E�����܂ŁA�i�r���̔������x��A�A�������������̓��쎟��ł����ǁA�A�i���O��H�̕��p�ŁA������Ƒ�ʂɉ����������ƒǐ�����悤�ȕ�������ꍇ������܂��B �@�S�Ă̓i�r����ł�����A�������������������������B �� ���ԓ����������܂��Ă��A���݂͑��̕��ւ̉�H�}�̒Ȃǂ����܂��Ă��܂��̂ŁA�����ɉ�H�}���������Ƃ��ł��܂���B�\�߂��������������B ���Ԏ� 2013/1/10
|
||
| ���e |
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@�X�C�b�`�͉������ςȂ����Ƃ����Əオ��^�����铮������܂��B���m�ɃJ�E���g�ł��Ă��܂���1�b�łP�O�X�e�b�v���炢�ς��܂��B �@�V���[�e�B���O�Q�[�����݂̘A�ŁA�`�����������������Ă���܂��������{�^��SW�ł̘b�Ȃ̂ŁA����ȏ�̃X�s�[�h�œd�����ω�����Ƃǂ��Ȃ邩�͔���܂���B �@���͂��̒[�q��SEEK UP/DOWN�̑���������Ă��āA�OV�ɂ����SEEK UP�A1.75V��SEEK DOWN�ɂȂ�܂��B�P���ɉ����{�^��SW�����ɂ������ł����̂łP��ڂ̓��e�ɂ͏����Ă��Ȃ������̂ł����A�����œd�����ω�����Ƃ��̂�����̌�쓮�̉\�����肦��̂ł͂Ǝv���Ă��܂����B���₭���[�^���[�G���R�[�_�[���Q�O�X�e�b�v�������ĂP�O�X�e�b�v���炢�������ʂ��ω����Ȃ��̂͋C�ɂ��܂��A�Ⴄ�ȂɂȂ��Ă��܂�����A�{�����[��UP����Ń{�����[��DOWN����͔̂��������ł��B �@���~��sec�Ŕ�������̂ƕ�����Ă����ɂ͑���܂���̂ŁA�듮�얳���Ńn�C���X�|���X�̗����͓�����ł��ˁB�n�m�E�n�e�e�̔䗦���T�O���łT�u�̂R�u�������ŌJ��Ԃ��ƂS�u�Ɣ��肳���\�������肻���ł����A�n�m���Ԃ��Œ�łn�e�e���Ԃ����ω��A�������쎞�͂����Ƃn�m�ɂȂ��H�ł���Έ��肵�ē��삵�����ł������G�ȉ�H�ɂȂ��Ă��܂��܂���ˁB �@���܂����Ȃ���H�A���܂��쓮���Ȃ��A���������̃��X�|���X�ŁA���������͂��C�����܂��̂ŋX�������肢���܂��B�@ (������]) �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�`���������ł��A�łł��������A�A�������̏ꍇ�͉����Ă���ԘA������UP/DOWN����̂ł�낵���̂ł��ˁB �@�P��]24step���炢�̃��[�^���[�G���R�[�_�[�ł��A�c�}�~���w�ł�����Ƒf��������]��������x�ň�u��10�`12�p���X�͏o�͂��܂��B �@����͎w�łł���A�ł��͂邩�ɒ�����X�s�[�h�ł��B(�������l�ł������ȑ���/��) �@���S�z����Ă���悤�ȁA���r���[�ȓd���Ƒ������邩������܂���B�����܂Ńi�r�E�I�[�f�B�I�@�푤�̉�H��X�L�������@�ɂ����܂����ǁA����͎茳�ɂ��̋@�킪�����̂œK���Ɂu�����Ȃ�Ƃ����Ȃ��v���x�ɓ��ōl���邵������܂���B �@��͂��Ԑ������̂́A�u���[�^���[�G���R�[�_�[�̉�]���p���X���J�E���g���ĉ��Z�����H�v�u���Z��ɐ���������Ԃ̓i�r����쓮���Ȃ��͈͂̂������p���X�������o�͂��A���Z��̐��������Z���Ă䂭��H�v�u��]�����ʁE�L�����ďo�̓p���X���o����H��I�������H�v�Ȃǂ�g�ݍ��킹��̂���Ɍ�쓮�Ȃǂ��N�����Ȃ��ƁA�s��ɋC�ɕa�݂Ȃ�����Ȃ��ōςނ̂ň��S�ł��B �@�ł����ꂾ�Ɖ�H�����Ȃ�ʓ|�ɂȂ�܂����A���i���������č��̂���ςł��傤�B �@���̍l�����́APIC�Ȃǂ̃}�C�R���ō��ɂ͓K���Ă��܂��B�S�@�\�͂W�s����PIC��ł��݂܂���(^^; �@�l�ԑ��̌��܂��Ƃ��āu�c�}�~�͂�����肵���Ȃ��v�ƌ��߂Ă��܂��A���P���ɉ�]�����̌��o�ƁA1step�ɂ�1�p���X���o�͂��邾���̉�H�E�E�E�ōςނƎv���܂��B �@�^�C�}�[���ԂƓ��̓p���X�̑�������A������̉�]�����߂�����o�͂̓p���X�ł͂Ȃ��A���g�`�ɂȂ�܂���ˁB����̋@��́u�������ςȂ����ƘA������UP/DOWN����v�悤�Ȃ̂ŁA�ʂɑ������Ƃ��ɘA��������ԂɂȂ��Ă���쓮�͋N�����Ȃ��͂��ł��B �@��H��g�ݗ��Ă��ōł��ȒP�ŕ��i�������Ȃ��̂͂���������H�ł��B �@�����A�A�i���O��@�Łu����]step���ɉ����āA�������p���X��K�v�o�͂���v�悤�ɂ��̂�������Ƃ�����A���S�Ƀf�W�^����H�őS�č����͕��i�������Ȃ��Ă��݂����ł��B �@�����E�E�E������1step�ɂ�1�p���X�o�邩�ǂ����Ƃ����ƁE�E�E�E�����܂Ō����������߂�Ȃ�S�f�W�^���ō���蕔�i�������������ł��ˁB(�����q���Ȃ�) �@������x�A�o�E�g�āA�b�q�̏[���d�̓����Ńc�}�~��]�ƃ{�����[����UP/DOWM�p���X�͓������͂Ȃ�Ȃ��Ă������u�Ȃ���ĉ�H�v�Ȃ�A�i���O�ƃf�W�^���̑g�ݍ��킹�ł���ꂻ���ł��B �@���݂̂Ƃ���ł̓W�]�͂��������Ƃ���ł��傤���B �@�����������̂Ŋm���߂悤������܂��ASEEK���쎞�̓d��(�����d��)��VOL���쎞���Ⴂ���̂ł�����A�X�C�b�`�������Ƃ݂Ȃ��p���X����莞�Ԉȏ�ɂ��Ă����A�p���X���A�������Ƃ����VOL����d����艺����͂��������Ƃ������Ɏ��ɂ͌�����̂ł����E�E�E�E�B �@����ł́A��Ɏ��₳��Ă��鑼�̕��ւ̉��ςݎ�����|���点�Ă��������܂��B ���Ԏ� 2013/1/12
|
||
| ���Ԏ� |
�@��H�}���o���܂����̌f�ڂ��܂��B �@�ł��E�E�E���̑O�ɁA���ʂɃ}�C�R�����g�����ꍇ�̉�H�͂ǂ��Ȃ邩�Ƃ������͌��Ă����܂��傤�B 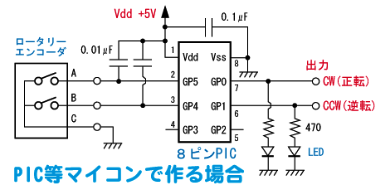 �@����]�̃����R���M���p�̒�R���ւ��镔���͏����Ă��܂��A�P�Ɂu���[�^���[�G���R�[�_�[�̐ړ_�̍������삩���A��]�����Ɠ�����������m���A�����UP/DOWN�����ʂɃf�W�^���M���ŏo�͂����v�Ƃ�����H�Ȃ炽�������ꂾ���̕��i�ł��B �@�u�N���b�N���鑬���ɉ����ĉ�]�ɉ������Z���Ńp���X���o�͂���v��u�P�N���b�N���ƂɈ�蕝�p���X���v��u�N���b�N���𐔂��āA�o�͑��͈��̑��x�Ńc�}�~���ꂽ�������������Ɛ��m�Ƀp���X���o�͂���v�Ȃǂ�l�X�ȕ������}�C�R���̃v���O���������Ńn�[�h�E�F�A�͑S���������̂Ŏ����ł��܂��B �@��������W�b�NIC�Ȃǂőg�ݗ��Ă�Ƃǂ��Ȃ邩�Ƃ����̂����Љ���H�}�ł��ˁB  �@�܂�����g�p����u���[�^���[�G���R�[�_�v�ɂ��āB
�@�܂�����g�p����u���[�^���[�G���R�[�_�v�ɂ��āB�@���[�^���[�G���R�[�_�����[�^���[(��]��)�ɐړ_�E�Z���T�[�����t�����Ă��āA���̉�]�ɂ��킹��ON/OFF�R�[�h�M�����o��(�G���R�[�h)���镔�i�ł��B �@�o�͂���M���̌`�Ԃɂ�肨���܂��ɕ����� �� �`���a���̂Q�̏o��(�ړ_)�������A���̂Q�̏o�͂��݂���90�x�ʑ������ꂽ�M�����o�͂���u�C���N�������^���^�v �� ���{�̃f�[�^���������A��]���̈ʒu�ɑ����Βl���R�[�h�����ďo�͂���u�A�u�\�����[�g�^�v �̓��ނ����݂��܂��B �@����g�p����͎̂ʐ^�̂悤�ȕ��i�ŁA�����Ă��̕��i�X�Ŕ����Ă��ăJ���^���Ɏ�ɓ���A�O�{���́u�C���N�������^���^�v�ł��B �@�܂��A�傫�����ʐ^�̂悤�ȏ��^�ʼn��ʒ��߂ȂǂɎg���{�����[���ȂǂƂقړ������炢�̃T�C�Y�̕��ł��B���i��100�~(����)�`500�~���炢�B �@���[�^���[�G���R�[�_�ɂ͂���ȊO�ɂ��H�ꓙ�̋@�B�̉�]�����m���邽�߂̋���ȕ��i(����~�`���~��)�����݂��܂��B �@�O�{���̃��[�^���[�G���R�[�_�̒��ɂ��X�C�b�`���Q�����Ă��܂��B �@���ꂪ�u�Е����E��]�̎��Ƀp���X���ON�v�u�Е�������]�̎��Ƀp���X���ON�v�E�E�E�Ƃ������ɉ�]�����ʂɊe�ړ_���v�`�v�`��ON/OFF���Ă����Α�ψ����₷��(?)�̂ł����A�c�O�Ȃ��炻���ł͂���܂���B 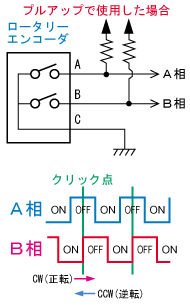 �@�����C���N�������^���^�̃��[�^���[�G���R�[�_�̐ړ_�́u�ʑ����o���v�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�����C���N�������^���^�̃��[�^���[�G���R�[�_�̐ړ_�́u�ʑ����o���v�ɂȂ��Ă��܂��B�@�E�}�̂悤���P�N���b�N������]����Ԃ��`���E�a���̐ړ_�����ꂼ����ON���܂��B �@�P�N���b�N����Ԃ��P������360�x�Ƃ��ĕ\���ƁA�e�w��ON���Ԃ�180�x�A�����Ċe�w�̏��(�ʑ�)�́u90�x����Ă����v�ƌ����܂��B �@��������360�x�Ƃ́A�����P��]����360�x�ł͂Ȃ��A�����܂łP�N���b�N�Ԃ��������E�d�C�̗��_�ŕ\���ꍇ�̌������E�l�����ł���A���ۂ��P��]12�N���b�N�^�ł͎���360�x�Ԃɂ��̂P�N���b�N������12�����܂��B�P�N���b�N�����͎��̊p�x�ł͂P������30�x�ł��B �@�ʐ^�̂悤�ȁu�l�Ԃ��c�}�~�����́v�����N���b�N��������~�܂�ꏊ(�f�e���g)���t�����Ă��Ă��̓_�ʼn�]���~�܂�悤�ɂȂ��Ă��܂����A���[�^�[���̉�]���̃Z���T�[�Ƃ��Ďg���悤�ȃ��[�^���[�G���R�[�_�[�ɂ̓N���b�N����_�͖���360�x���ׂĂɊ��炩�ɉ�]���܂��B �@�����O�܂ł悭�g���Ă����p�\�R���p�́u�{�[�����}�E�X�v�̒�̃{�[���̉�]�����o���Ă����̂����[�^���[�G���R�[�_�[�̈��(���w�X���b�g��)�ł��B 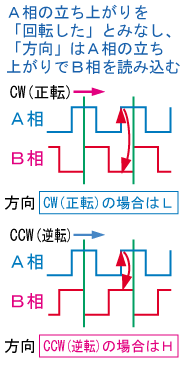 �@����ł́A�`���E�a���̂Q�̏o�͏�Ԃ���u��]�����̂��H�v�Ɓu�ǂ���̕����ɉ��̂��H�v��m��ɂ͂ǂ�����悢�̂ł��傤���H
�@����ł́A�`���E�a���̂Q�̏o�͏�Ԃ���u��]�����̂��H�v�Ɓu�ǂ���̕����ɉ��̂��H�v��m��ɂ͂ǂ�����悢�̂ł��傤���H�@�P�����̊ԂɊe�w�̐M���͈��ω����܂��B �@�Ƃ������Ƃ́A�����ꂩ�̑��̐M�����u�ω������v�Ƃ�������߂炦��u��]�����̂��H�v�̓J���^���ɒm�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�����\����������`���́u���]�E�t�]�̂ǂ���̏ꍇ���A�P�����̂قڐ^�ň��ON�ɂȂ��v�̂Ŏg���₷�����ł��B �@�ł́A�u�`����ON�ɂȂ�����v�܂��́u�`����OFF�ɂȂ�����v�̂����ꂩ���ω��_�������āu��]�����v�Ɣ��肷�邱�Ƃɂ��܂��B �@�����̐����ł͌�Ɏ��ۂɎg�p����IC�̎d�l����u�`����OFF�ɂȂ�����(���f�W�^���M����H�ɂȂ�����)�v�̂ق����g�p���邱�Ƃɂ��܂��B �@���Ɂu�ǂ���̕����ɉ��̂��H�v��m��ɂ́A�u�`���E�a���̐M����90�x����Ă����v�Ƃ����d�l��p���Ď��̂悤�Ɍ��o�ł��܂��B �@�`���̕ω��_(ON/OFF�_)�̂����ꂩ���u���������o����^�C�~���O�v�Ƃ����ꍇ�A�����^�C�~���O�ł��a���̐M���́A�Е��̕����̏ꍇ���K��H�A���Ε����̏ꍇ���K��L�ł��B �@�����`���̗����オ�������o�_�Ƃ���Ɛ��]�̏ꍇ���K��L�A�t�]�̏ꍇ���K��H�ł��B �@�u�ǂ���̕����ɉ��̂��H�v��d�q��H�Œm��ɂ́A���̗��_����H�ɒu��������悭�A�w�`���̗����オ�����u�����a���̐M�����ǂݍ���Ń������[�����H�x�����悢���ƂɂȂ�܂��B �@����ŁA�u�ǂݍ��ݐM��(�N���b�N)�̗����オ��ŁA�f�[�^�M��(����)�̏�Ԃ��L�������H�v�E�E�E�Ƃ����͕̂ʂɕ��G�ȉ�H��g�܂Ȃ��Ă�IC���������(����A����)�łł��Ă��܂��܂���ˁB �@�f�[�^�̋L���E�ێ���H�Ƃ��Ă悭���p�����D-FF(�f�B�[�E�t���b�v�t���b�v)���g�������ł��B �@�����āA�����ōX�ɍl�������J���^���ɂ��āA�u��]�����̂��H�v�����o�����ꍇ�Ɂu��]������p���X������o���v�Ƃ����@�\�́A�P�N���b�N������r���ŕK���N����u�`����ON�ɂȂ��Ă���Ԃ�(��]�����ɉ������ق���)�o��ON�v�Ƃ��Ă��A�ʓ|�ȃ^�C�}�[�Ȃǖ������P�N���b�N�ɂ����̏o�͐M��(�p���X)�������܂��B �� �A���c�}�~�𑁂��ƃp���X�������Ȃ�A�p���X�����Z���Ȃ�܂��B 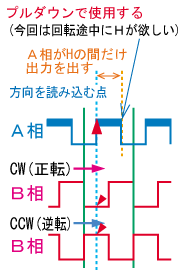 �@�܂Ƃ߂��
�@�܂Ƃ߂���� ��]�������`���E�a���̑��֊W����D-FF�ɋL�� �� �o�̓p���X���`����ON�ɂȂ��Ă�����o�͂��� �� ���̍ۂ��ǂ���̕������H��D-FF�ɋL�����ꂽ���ɏ]�� �@�Ƃ����v��}�ɂ������̂��E�}�ł��B �@���ۂɎg�p����IC�̎d�l�̊W��A���[�^���[�G���R�[�_���v���_�E���Ŏg�p����悤�ɂ����̂ŁA���܂ł̐����}�Ƃ̓��W�b�N(H/L)�����]���Ă��܂��B �@�ł��`���E�a�����ɔ��]���Ă���̂ŁA�ǂݍ�����]�����̏���͓����ł��B(��₱����) �@�g�ݗ��Ă����_�����W�b�NIC�Ŏ�������Ƃ����Ȃ�܂��B 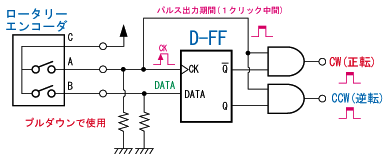 �@�E�E�E�E����H �@�Ȃ�PIC�}�C�R���ō�鎞�̗�ɏo������H�}�Ƃ������ĕς��Ȃ��V���v�����ł��ˁi�O�O�G �@�����Ȃ�ł��A�u���[�^���[�G���R�[�_�����]�����ʂɂ��ꂼ���]�p���X��~�����I�v���ėv�����������H�́A���͂��������ꂾ���łł����ł��B (�����܂ŁA������������邾���̉�H�}�ł�����) �@�����A����ȃV���u���ȉ�H���u�Ȃ����������̂��H�v�́A���܂Œ��X�Ə����Ă����u���[�^���[�G���R�[�_�Ƃ͉����H�v��u�ʑ����o�͂����]�����H���]�����H��m��ɂ��v�Ƃ�����ʂ̏���m���������Ɨ����ł��Ȃ��킯�ŁA�����Ȃ肱�̉�H�}����邾���ł�����ɂ͉�����ꂽ�̂ł����A�ꉞ�́u�C�̖����v���ɗ����⌴����������Ă���Ƃ���Ȃɒ����Ȃ��Ă��܂��܂����B �@���S�ɗ]�k�ɂȂ�܂����A�N���b�N����ʒu�������Ď��̑S���ɓn���ăX���[�Y�ɉ��^�C�v�̏ꍇ�A�u�����łP�J�E���g�v�Ƃ����_�̓N���b�N�_�ɂ��Ȃ��̂ł`���E�a���̐M���̕ω��_�̂ǂ�����ɂ��Ă��ǂ����ƂɂȂ�܂��B �@������������悤�ɂǂ��炩�̑��̗����オ�肩������̂����ꂩ�̈�_�Ƃ���̂��ǂ��ł����A�}�C�R�����œǂݍ��ނ̂Ȃ��n�[�h�E�F�A�͂��̂܂��ɏ����̓v���O�����̂ق��Ŏ��̂œ�����G�Ȕ��f�ł��e�Ղɑg�ݍ��ނ��Ƃ��ł��邽�߁A�u�`/�a�������̑��́A�����オ��ł�������ł��ǂ�ł��g�ω������h�_��S�����f�_�Ƃ��āg�ω�����O�Ɣ�r����h���ƂŁA�ǂ̂悤�Ȉʒu�łǂ̕����ɕω������̂��H���g�p�^�[������h���Ă�邱�ƂłS�{�̐��x�ʼn�]��ł���B�v�Ƃ����������s���܂��B �@���ہA�}�E�X�̃{�[���̉�]�Z���T�[�Ȃǂł͂��̂悤�ȏ����ŁA�����I�ɃZ���T�[���Ɏd���߂�@�B�I�ȁu�P�p���X�Ԃ�v�̉𑜓x�̂S�{�̉𑜓x�ʼn�]�����o����Z�p���g���Ă��܂��B �@���āA�]�k�͂��ꂭ�炢�ɂ��āA����̌����݂̂̉�H�}�����ۂɎg����悤�ȉ�H�}�ɂ���ƈȉ��̒ʂ�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�@�ԂŎg�p�����Ƃ������ł��̂ŁA12V�d���ł��̂܂ܓ����悤IC��C-MOS���W�b�NIC��4000�ԃV���[�Y���g�p���܂��B �@D-FF�ɂ�4013B [PDF]�����(�Q��H����Ȃ̂Ŕ����͎g�p���Ȃ�)�AAND�@�\���~�����̂�NAND�Q�[�g��4011B [PDF]����g�p���܂��B �@���W�b�N������]�����p���X��������A�J�[�I�[�f�B�I�̃{�����[�������R���p�ɂ��g�����W�X�^�Œ�R��GND�ɗ��Ƃ���H�Ń{�����[����UP/DOWN���ꂼ��̒�R�l�������[�g�[�q�ɐڑ����܂��B �@�E�E�E����ŁA���[�^���[�G���R�[�_�̃c�}�~�����肭��ƉƁA��]�ɉ����ăI�[�f�B�I�̃����R���[�q����{�����[�������R�ɃR���g���[���ł���͂��E�E�E�Ȃ̂ł����A�����u���ȏ㑁������A�p���X�����Z���Ȃ肷���Ē�R�l�𐳂����ǂݎ��Ȃ��v�悤�ȏǏo��ꍇ�A��葬�x�ȏ�ł̓p���X�ŏo���̂͂�߂āA�A��������Ԃɂ����H���K�v�ɂȂ��Ă��邩������܂���B �@�����ŁA�u���̃p���X�����^�C�}�[�ň��ɂ��āA���ꂪ�A�����Ă��܂������ł͏o�͂͏o���ςȂ��ɂ���v�悤�ȉ�H�͈ȉ��̒ʂ�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�@���̉�H�ł͏�̉�H�������V���b�g�^�C�}�[IC��4538B [PDF]���g�p���܂��B �� ����͂`����Hi���Ԃ��o�͊��ԂƂ݂Ȃ��K�v�������̂ŁA�悭�o�Ă��郍�[�^���[�G���R�[�_�̎d�l���ʂ�Ƀv���A�b�v�Ŏg�p���Ă��܂��B�P�N���b�N�̏I���_�߂��ŏo�̓p���X�̃g���K�[��������܂��B �@4538B�łP�N���b�N���ƂɈ��A��蕝�̃p���X���o�͂��āA�����N���b�N�Ԋu���^�C�}�[�Ő�������p���X�����Z���Ȃ��(4538B�̃^�C�}�[�̓��g���K�u���̂���)�o�͂̓p���X�ł͖������̑��x�ʼn�]����H�ɂȂ���ςȂ��ƂȂ�܂��B�g�����W�X�^��H�̒�R��ON�ɂȂ���ςȂ��Łu�A�������v��Ԃł��B �@���̏o�̓p���X����VR1�Œ��߂ł��܂��̂ŁA�`�����Ɖ������Ɛ��������肳���ȏ�̃p���X���ɐݒ肵�Ă��������B���������ƒx���ڂ̉�]�ł������ɘA��������ԂɂȂ�܂��B �@�{���͂���ł��A�������ɂȂ��菭���x����Ԃł͍����ŏo�͂����p���X�̒��ŏo�͂�L�̏�Ԃ����ɒZ�����ԂɂȂ�̂ŁA�����ɂ͒Z������p���X�ɑ��Ă̊��S�Ȗh���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B �@�����������i��lj����Ă����ƍׂ����^�C�~���O�����o���āA�u�p���X�Ԋu�������Z���Ȃ����炻����葁���ꍇ�͘A���ɐ�ւ����H�v�̂悤�Ȋ����̂��̂�t�������Ȃ���Ȃ�܂���B �@�����܂ŕ��i���𑝂₷�Ɓu�ȒP�ȉ�H�������Ă���������Ƒ�Ϗ�����܂��v�Ƃ����u�ȒP�ȉ�H�v�͈̔͂��Ă��܂��܂��̂ŁA����͂����܂ł͍l���Ȃ����ɂ��܂��B �@���Ԃ�E�E�E�^�C�}�[�����̂ق��̉�H�ł��\���ɂ��܂����삷��Ƃ͎v���܂����A�Ȃɂ����̃I�[�f�B�I�̌������茳�ɖ����̂ł�����ł͊m���߂悤������܂���B �@�u��������p���X�Ԋu���Z���Ȃ��āE�E�E�v�Ƃ������Ƃ��뜜����̂ł���A���[�^���[�G���R�[�_�̂ق����u�P��]12�p���X�^�v�̂悤�Ƀp���X���̏��Ȃ�����I�ԂƂ����������܂��B�悭�����Ă���̂́u�P��]24�p���X�^�v�Ȃ̂Ń}�C�R�����Ɍq���ʼn����̐ݒ萔�l��ύX���鑀��c�}�~�ɂ͏��Ȃ���]�Ő��������ς�����ق����D�܂��̂ł����A����̗p�r�ł͂P��]12�p���X���x�̃^�C�v���g���₷���Ǝv���܂��B �@���̉�H�}�����ɁA������ŐF�X�Ǝ����Ă݂āA���܂��Ƃ���ŗ�������T���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2013/2/26
|
||
| AVR/Arduino�ؑ֊� | |||
|
�ȒP�Ɍ����Ɛؑ@����낤�Ƃ��Ă��܂��B�Ⴆ�Aarduino���T�䂠�����Ƃ���AVRISPmkII�P��Ńv���O�����𗬂�����ŏ��������Ă��܂��B�����[�g����s���Ă���̂�AVRISPmkII�̍������݂�ʂ�arduino�ɍ����ւ����܂���B���̐�ւ����̂������[�g����s�������ƍl���Ă��܂��BAVRISPmkII��6�̃s����IO�͌Œ�ł��B�܂��A�T���arduino��digital(8pin��)/Analog(6pin��) �̃s���̐ڑ�����o��������[�g�����ւ������Ǝv���܂��BI/O�s���̓v���O������Output��Input���`�ł���̂Ő�ւ��͑o�����ɑΉ��ł�����̂Ő��삵�����Ǝv���܂��B ���͏��S�҂Ȃ̂ő�ʂ̃����[�ōs�����Ƃ��炢�����v�����܂���B����ł́A���������Ȃ肩�����Ă��܂��܂��BAVRISPmkII����ʂɔ����ƍ��z�ɂȂ��Ă��܂��܂��BTCP�ł�UDP�ł��ǂ��̂ł����A�����[�g�����ւ��R���g���[���o����ؑ@�����オ��ɓd�q��H�ŏo���Ȃ��ł��傤���H�o����Ƃ���ǂ̂悤�ȉ�H�ɂȂ邩�����Ă��������B�ǂ�����낵�����˂����������܂��B arduino �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA���X����AVR�͂���Ă��Ȃ��̂�AVR�Ɋւ��邲����ɂ͂قړ����Ă��܂��A��N2012�N11��18����AVR�Ɋւ��鎿����̌��ȗ�����AVR�ɊW����b��ɂ͐G��Ȃ����ɂ��Ă��܂��B �@����ł��E�E�E���₷��ƌ�����̂ł���A�ꉞ�͂��������Ă����܂��B �@�A���A����AVR��Arduino���A���̃��C�^�[�������Ă��܂������炱����Ő��������삷�邩�̃e�X�g�������ł��܂���B �@�����P�Ɂu�d�q��H�����`�A�����ł͑���������Ȃ��́H�v�Ƃ������x�̎����������܂���̂ŁA���������������B �@�O���́uAVRISPmkII�ŕ�����AVR���ւ��ďĂ������v�ɂ��āAAVRISPmkII��ISP�Ŕz������AVR�Ƀv���O�������������ރ��C�^�[�ł���悤�Ȃ̂ŁA�����Ŏg�p����ISP�p�̔z�����ւ��ă^�[�Q�b�g��I�ԁu�Z���N�^�[�v�����Ηǂ��������ƍl���܂��B �@AVR��ISP�[�q�́u�z�X�g���^�[�Q�b�g�̃f�W�^���M�������R�{(SCK/MOSI/^RESET)�v�u�^�[�Q�b�g���z�X�g�̃f�W�^���M�������P�{(MISO)�v�̌v�S�{�ŁA��͓d���Ȃ̂ŁA���̌v�S�{�̃f�W�^���M�������Ȃ�����^�藣���������邾���ŗǂ������ł��B �@�m���ɁA�����[�ŃK�`���b�Ƌ@�B�I�ɐڑ�������藣���̂������葁���Ƃ͎v���܂��B(����ł�������Ȃ����ȁ`) �@�f�W�^����H�ŐM����(�̏o��)���q������Ԃ�J������(�藣����)��Ԃɂ����H�E�f�q�́u�R�X�e�[�g�Q�[�g��H�v�ƌĂ����̂�����܂��B �@�u�R�X�e�[�g�v�Ƃ́u�R�̏�ԁv�Ƃ����Ӗ��ŁA���ʂɃf�W�^���M���́uH(�n�C)�v�uL(���[)�v�̂ق��ɁuZ(�ǂ���ł������J������Ă���)�v�Ƃ�����Ԃ��Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B �@����̐M���z���ɕ����̉�H�E�f�q��ڑ����A���̒��̂ǂꂩ�P���炾���M�����ɏ����悹��(�o�͂���)�Ƃ����g��������ŁA�R���s���[�^�����ł͏��̃��C�����H�ł���u�o�X�z���v�ɑ��Đڑ�����Ă���CPU/�������[/IO�f�o�C�X�ȂǁA�قڑS�Ă̑f�q�ƃo�X��ڑ����镔���Ŏg���Ă��܂��B(�������AVR�̃`�b�v�̒��̃f�W�^��I/O�s���̓������R�X�e�[�g��H�ł�) �@�ŁA����̖ړI�ł́u���C�^����̐M�����^�[�Q�b�gAVR��ISP�[�q�ɂȂ��^�藣���v�u�ǂꂩ�P��(�I��)�^�[�Q�b�gAVR�̏o�͐M�������C�^�[���ɓ��͂�����v�ړI�łR�X�e�[�g�o�b�t�@IC���g�p����A�J���^���ɖ��͉�������͂��ł��B �@�����܂ŁE�E�E�u�͂��v�ł���̂́A��ɏ������Ƃ���A������Ŏ����ł��Ȃ��̂Ŋ���̋�_�ł��邱�Ƃ͈������炸�B 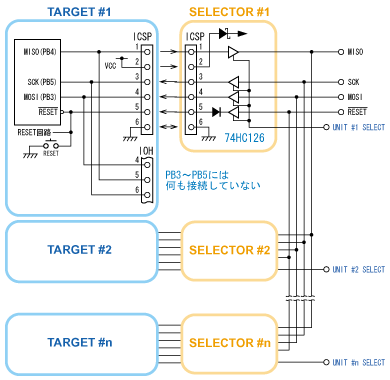 �@UNIT SELECT�[�q�́A���Ȃ��������ɂȂ�u�^�[�Q�b�g��I�����鑕�u�v�Ő��䂵�AH�őI���AL�Ŕ�I���ł��B �@�Ԉ���Ă��A�����ɕ�����UNIT��I�����邱�Ƃ������悤�ɁA�ԈႢ�̖����悤�ɑI�����鑕�u������Ă��������B �@�ԈႢ�����Ȏ��ɂ́A�o�C�i��to�f�V�}���f�R�[�_�[IC���ŁA�u��ɂǂꂩ�P�����I������Ȃ��v�悤�ȉ�H�̍H�v�Ȃǂ��K�v��������܂���B����͎��R�����ۑ�Ƃ������ƂŁB �@�ŏ��ɏ����܂����Ƃ���A����̂�����́uAVR�Ɋւ��邨�b�v�Ȃ̂ŁA���@(Arduino)�œ������ǂ����́A�������Ō������Ă��������B������ł͎���ɂ��������邱�Ƃ͂ł��܂���B(�����ɏ��������ȊO�ɖ{���Ɋ֘A���邻�̑��̎�������l��) �@����ŁA�㔼�́uAVR��I/O�|�[�g�ɕ����̑�����q���ւ������v�ɂ��ẮA�܂����������ŁB �@���̉�H�ł����AAVR�̃f�W�^��I/O�s���̓��o�͂͂������v���O������`�œ��͂ɂ��o�͂ɂ��ݒ�ł��܂����A�ڑ���̋@����Ȃ����_�Ŋe�@��̎d�l(�e�s���̗p�r�E�@�\)�ɂ���Č��܂��Ă��܂��܂���ˁH �@�ؑ։�H�͂��ꂼ��̐ڑ��@��ɑ��āA�n�[�h�E�F�A�I�ɓ��͂Əo�͂��Œ��̂��̂̍����ł����̂ł����H �@����Ƃ��A�u�ڑ���̋@��ł������Əꍇ�ɂ���ĕt���ւ��邩���A�W�{�̃f�W�^���|�[�g�͓��́^�o�͂������[�g���玩�R�ɐݒ肵�����v�Ƃ��������K�}�}�Ȃ���]�ł����H �@�C���������炨�Ԏ����������B ���Ԏ� 2013/1/10
|
||
| ���e |
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�������ς��肪�Ƃ��������܂��B �܂��́A���͎g�p�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A����Ắu�R�X�e�[�g�Q�[�g��H�v���g���Ď������Ă݂܂��B���R�����ۑ�̃^�[�Q�b�g���P�̂ݑI������d�g�݂̓\�t�g�ōs���܂��B ���̐��I/O�̐�ւ��́A���̂��Ƃ̘b�ł��ˁB (�m���ɐڑ��@��ɑ��āA�n�[�h�E�F�A�I�ɓ��͂Əo�͂��Œ�̂��̂ɂȂ�Ƃ͎v���܂����A�ύX����������܂��̂ŁA�ł���@�B�I�Ƀ����[�Ő�ւ���̂Ɠ����悤�Ȋ��o�Ŏg�p�ł����H�����҂��Ă��܂��B)�Ƃ肠�����A������̂��������ɃA�b�v����Ă��������Ă����Ȃ��̂ł܂�74HC126�����鎞�Ԃ��������B ����̂��͔��ɂ��肪�������e�ł����B �ƂĂ����ɂȂ�܂��B�i���������(���Ԃ͂�����Ƃ������܂���)�܂����|�[�g�����Ă��������܂��B �ǂ�����낵�����肢�������܂��B arduino �l
|
||
| ���e |
���т��ѐ\�������܂���B Selector#1��'ICSP'�̉E���̃_�C�I�[�h�Ɏ����L���́A�c�F�i�[�_�C�I�[�h�ł��傤���H �o���܂�����^�Ԃ������Ă��������܂����H ���萔�ł�����낵�����肢�������܂��B arduino �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�c�F�i�[�_�C�I�[�h�Ƃ͋L�����Ⴄ�Ǝv����ł��B �@������H�}�ɍڂ��Ă���u�V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h�v�ł����ǁE�E�E�B �@���������āA�����̉ߋ��̋L�����H�}��S���ǂ�Ŗ����l�Ȃ�ł��傤���H �@�悭�g���^�ԂƂ��A�ڂ��Ă�Ǝv����ł����ǂˁE�E�E�B �@11EQS04�Ƃ�1S4�Ƃ��A����قǑ傫�����������g���Ă��������B �@����ƁAAVR/Arduino��ISP���C�^���^�[�Q�b�g�{�[�h����d�������(�����ɂ͓d���͎����Ă��Ȃ�)�Ƃ�������炵���̂ł킴�킴SD����ēd��������Ă��܂����A�������E�E�E���Ȃ��l��������AVR/Arduino����q���Ŏg���ۂɁu���u�n�ɒu���ă����[�g�ň����̂œ��R�S���d�����������܂܂����A���C�^�[���ɂ�5V�d���͕ʂɎ����Ă邵�`�v�Ƃ����낢��Ƃ�������K�v�������ꍇ��5V���C���͐ڑ����Ȃ��Ă�������ł����ǁB �@�܂��A�������ʓI��AVR/Arduino��ISP���C�^�I�ȉ�H�Ƃ��ď����Ă��邾���ŁA�s�v�Ȃ�q���Ȃ��Ƃ��A�����ƕʂ̕��@���Ƃ�Ƃ��A�F�X�ƑΏ��̂��悤������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2013/1/17
|
||
| ���e |
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B�ߋ��̋L����S���ǂ�łȂ��킯�ł��Ȃ��̂ł����A�����̂���Ƃ��낾���E���ǂ݂����Ă��������Ă܂��B�V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h�Ƃ̂����肪�Ƃ��������܂��B�Ƃ肠�����펞5v�Ƃ��Ƃ���P��������Ƃ邱�Ƃɂ��܂��B �ł͕��i�𒍕������ۂɐ�ւ����邩�m�F���Ă݂܂��B ��낵�����˂����������܂��B arduino �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�ɂ�����E�E�E�ł����̂ŁA���̋L�����ǂ�ł���������ƁA�����ł͂���܂����m���̑����ɂȂ邩�Ǝv���܂��B �@��H�̃e�X�g�Ƃ��A��������Arduino���AVRISPmkII���Ȃ��悤�A�\���ɂ����ӂ��������B ���Ԏ� 2013/1/17
|
||
| ���e 2/13 |
����ǂ��Ď������悤�Ƃ��Ă��܂��B �܂��́A�u���b�h�{�[�h�o�R�� 1arduino:1AVRISPmkII �����Ȃ��R�l�N�V�����ł��邩�`�F�b�N���Ă݂܂����B�����OK�ł��B (�s���w�b�_�̃G�N�X�e���_��������̂Ń`�F�b�N���܂���) ���̌�74HC126���P�g�p���A�P��arduino��AVRISPmkII�̐ڑ�/�藣�����ł��邩�m�F���Ă݂܂����B �M���P�P��74HC126���o�R����悤�Ɏ�������ƁAMISO,SCK,MOSI�܂ł͖��Ȃ��ڑ�/�藣�����ł����Ǝv���܂��B�X�P�b�`�̏������݃e�X�g��OK�ł��B DESELECT�ŏ������݃G���[�ɂ����ƂȂ�܂��B �ł����A/RESET��74HC126�o�R�ɂ����NG�ł��B AVRISPmkII�̓I�����W�̓_�ł��n�߂܂��B/RESET�Ŏg�p�����_�C�I�[�h�͐����p��1N4007���g�p���Ă��܂����A���ꂪ�����Ȃ��̂ł��傤���H /RESET�����܂������A2arduino:1AVRISPmkII�̃e�X�g���s�������Ǝv���܂��B����悤�ł��������������܂�����͂胊���[�ŋ@�B���ɐ�ւ��܂��B �����A�����Ԃ�����Ƃ�������A�ʓ|�łȂ���A����A�h�o�C�X���������B�ǂ�����낵�����肢�������܂��B arduino �l
|
||
| ���e 2/13 |
��قǁA�����Y��Ă������Ƃ�����܂��̂ŁA�lj����܂��B /RESET�̐M�����`����Ă��Ȃ�(LOW�Ɉ����ς��ĂȂ��H)�����ł����̂ŁA�_�C�I�[�h���O�����ڐڑ����������ƁA/RESET�̃Q�[�g�̌�����ς��Ă݂����ƁA���̗����͂���Ă݂܂����B�ł����A���ʂ͓����ł����B ���ƈ���̂Ƃ���ɂ��銴���ŁA���Ȃ�������ł��B ���t���炸�Ő\�������܂���낵�����肢�v���܂��B arduino �l
|
||
| ���e 2/17 |
�i�W������܂����̂ŁA�A�������Ă��������܂��B/RESET�̓v���A�b�v�ŃG���[LED�\�����Ȃ��Ȃ�A�v���O�����̏������݂����Ȃ��ł��܂����B�����A�ʏ�Arduino�{�[�h�̓v���O�����������݂Ɠ����ɑ���n�߂܂����A���̐ؑ@�ɐ�قǂ̃v���A�b�v���������̂ł́A�v���O�����������㑖��n�߂܂���ł����B(DESELECT���Ă��_��)�{�[�h���I�ɐ藣���Α���n�߂܂����B���܂�A���t���������������̂��C�������Ă��܂����̂ŁA�ʂ�IC�ōēx���킵�Ă݂܂��B���Ԃ�o���銴�������Ă��܂��B�����_���Ȃ炨�ƂȂ��������[�Ő�ւ��܂��B ���낢�남���Ԃ�����Ă����������肪�Ƃ��������܂����B �ł́A����v���܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B arduino �l
|
||
| ���e 2/17 |
��قǂ͎��炵�܂����B ���̃u���b�h�{�[�h�̐ڐG�s�Ǔ��������قǂ̕��ʂ���������Ă��������B ��قǂ̑����ł����A/RESET�̃v���A�b�v�����ŁA�v���O������������^�[�Q�b�g�{�[�h��RUN���܂����B ���̌�A1mkII:2Arduino�̃e�X�g���s�����Ȃ���Ί������ăP�[�X�ɓ����\��ł��B���낢�낲���f�����������Đ\����܂���ł����B �ł́A���炵�܂��I�I arduino �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�F�X�ƃg���C����āA�Ȃ�Ƃ�����]�̂��̂ɋ߂Â����悤�ł��ˁB �@Arduino����ɂ̓v���A�b�v��R�������Ă��܂��̂ŁA�v���A�b�v��R��t���Ȃ��ƃ��Z�b�g����������ςȂ��Ƃ����͓̂�ł����A�܂�����œ����Ă���Ȃ炻��ł����̂ł��傤�B �@�������悭�P�[�X�ɓ���āA���܂��S���ɑ��ď������݂��ؑւł���Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2013/2/22
|
||
| ���e 2/26 |
�ł��܂����I�I(�ǂ����Ă��A���������ď����Ă��܂�) �u���b�h�{�[�h���1mkII:2Arduino��ւ��o�b�`���ł��B �����A�R��H�A�S��H�ł��������Ƃł��B ���Ƃ�nRF24L01�o�R�Ő�ւ��M���𑗂��Đ�ւ��܂��B ���肪�Ƃ��������܂����I�I�Ƃ��Ă�������܂����B���ɂ��Ȃ�܂����B PS.����Arduino�́A�H���̌݊��{�[�h�ł��B�ēx�m�F���܂������A�v���A�b�v�͂ǂ����Ă����Ȃ��ƃ_���ł����B arduino �l
|
||
| �\�[���[���C�g���S����H�H�H | |||
|
�����Z���T�[�\�[���[���C�g���S�w�����A�\�[���[�p�l���S��Z�߁A�Z���T�[���C�g�S��ɐڑ��ł��܂����B�]�|���܂��������������B
�n�j �l
|
|||
| ���Ԏ� |
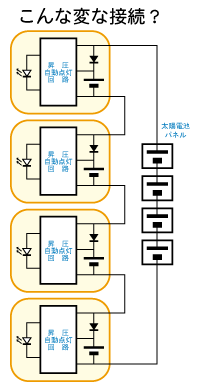 �@���[�ƁE�E�E�B�E�}�̂悤�Ȋ����ł��傤���H
�@���[�ƁE�E�E�B�E�}�̂悤�Ȋ����ł��傤���H�@����͈�́H�H�H �@���̖ړI�ł��̂悤�Ȑڑ������ꂽ���̂��A�����ɋꂵ�݂܂��B �@�\�[���[�p�l���ƃZ���T�[���C�g�{�̂̋����𗣂������Ƃ��H �@�ł����̏ꍇ������Ȓ���ł͂Ȃ��A���ʂ͕���ɂ��܂�����E�E�E�B �@����ɂ�����A�e���C�g�̓����Ԃ�[�d�r�̎c��e�ʂɂ���ăo�������o�āA���܂��낵������������N���邱�Ƃ��l�����܂����A�܂��A�u�_�����邩���Ȃ����H�v�ƕ������u���Ԃ�A�ꉞ�́A�_������ł��傤�v�Ƃ��������邵������܂����B �@�������������ڑ��ɂ�������Ƃ����āA����Â��Ȃ��ē_���������S������Ăɓ_�������݂����ȘA������킯�ł͂���܂��A�{���ɁA�܂����ʂ͂���Ȕz���͂��܂���B ���Ԏ� 2013/1/6
|
||
|
����ȑO�̓����͂����灨 [2012�N�㔼�̉ߋ����O]
|
|||
|
�T���₷���ړI�E��H�̃W�������ʈꗗ�͂����灨 [�W�������ʈꗗ]
�悭�g�����i�́u���̐}�v�͂����灨 [�悭�g�����i�́u���̐}�v]
|
|||
|
(C) �u�C�̖����v�^Kansai-Event.com
�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������
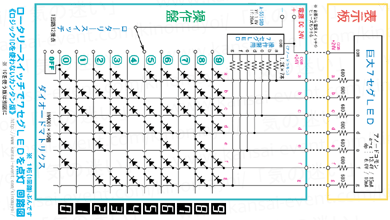
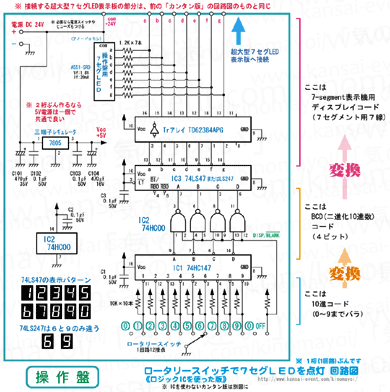
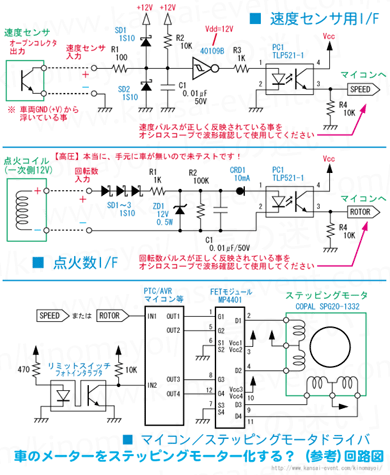

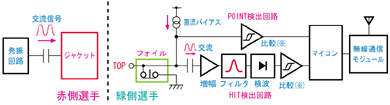
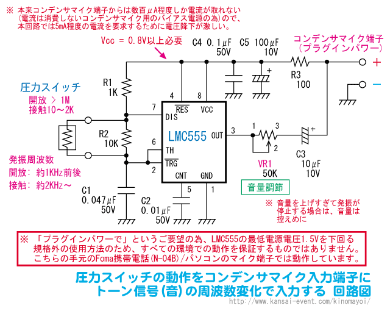
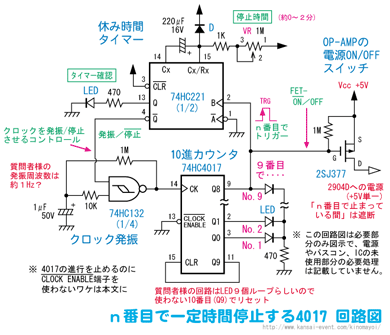
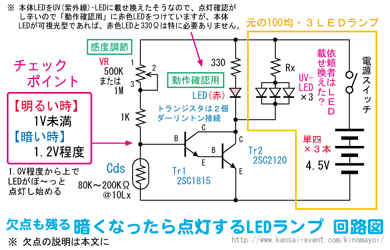
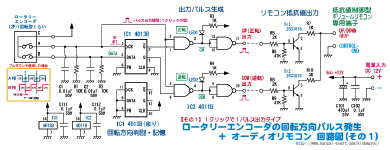

 �u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�
�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�