| ||||||||||
|
|
| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |
��H�E�f���L�E����
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���� ���̃y�[�W��2010�N�㔼�̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B
�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B
�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B
|
�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |
�y�ꗗ�z
�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�
|
��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |
|
�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
���� ���̃y�[�W��2010�N�㔼�̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
| 2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H | |||
|
�����y�����q�����Ď������ɖ𗧂����Ē����Ă��܂� 08/10/17�@�́i�C�ӓd���Ōx��LED�_���j��H�ł����Z���T�[���C�g�i�UV�d�l�j�O�ɓ��ڂ��Ĕ��ɋ�悭���S���Ďg�p���Ă��܂����ALED�i�ԁj�̓v�����^�[�̃C���N�J�[�g���b�W�̌�K���� ��������SMD��Ձi8�~���p�j���ƃe�[�v�Œ���t���Ă��܂��A�z����IC�̃{���f�C���O���C���[���ǂ��ɋɍא����n���_���Ă��܂� ����@��̍X�V�ŐV�^�Z���T�[���C�g�v�������̂ł����d�����P�O�~3�{�d�l�ƂȂ荡�܂ł̌x��LED�ł͍쓮���܂��� �F�X���s����̖����ł��������͊J���̌��E�������܂��� ���Z�������ƂƂ͎v���܂���3.6V�d�l�A2.4���d�l�̉�H�}�����������肢���܂� �G�S������ �l>
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���ɉߋ����O�Ɉړ����Ă���L���ɑ��āu�d����ς�����H�}����Ă��������v�Ƃ�����������͊�{�I�Ɏt���Ă��܂���B �@����́A���̃R�[�i�[�͈�x������H�ɂ͐��������Ă��܂����A�Q�l�ɂȂ��H�}�����ɂ���u����������R�ɉ��ς��āA�������̖ړI�ɂ��킹����������Ă��������v�Ƃ����X�^���X������ł��B �@�d�q��H�ʼn����~�������̂������ꍇ�́A�Q�l�ɂȂ鎑�������Ă������ł�������p����̂����ʂ̂������ƁB �@���x�������悤�ȉ�H��g�ݗ��ĂāA�������Ă����H�}��(HP�Ō��J�ł���悤��CG��)�����A�܂������悤�ȋL���������ق��̐g�ɂȂ��Ă��������B (���������Z�ł��Ԏ��ł����˂�Ƃ����ɏ������Ă��鎞�ɁA���������ӂ��ɐ_�o���t���ł���悤�ȓ��e�����ꂽ��������_�I�ɎQ���Ă��܂��܂���) �@xxV�ɂȂ�����LED���_������Ƃ���������Ƃ����n���̂�����ɓ�����̂͂��ꂪ�Ō�ɂ������Ǝv���܂��B  �@����������H�͂����������ڂ��Đ������Ă��܂��̂ŁA����͏ڂ��������͖����Ƃ����Ă��������܂��B �@���̉�H�ւ̎���A���ӌ��Ȃǂ̃��X�E���e�����܂���B ���Ԏ� 2010/11/27
|
||
| ���e 12/2 |
���Z���������ɂ������������܂��ėL��������܂��� ��������Ɏ��|���肽���Ǝv���܂� �ډ��A�Z���T�[���C�g�������߂����ĕ\�ʎ����^�i�f�W�^���A�A�i���O�j�̎��쒆�ł���܂� �H���̃v���g�^�C�vSMD��Ղ͎��Ɏg���₷���ł� �\���x��܂��������͂UZP1�A�UC6,�UD6�A�W�O�V���̐^��ǐ���� �d�g���N�̂Ȃ�̂͂ĂŌ�����܂� �Q���}�A�V���R�����悭�������ʂ܂܋����������Ă��܂��� �T�O�N�Ԃ�Ƀn���_�̏L�����v���o�����Ă��ꂽ�u�C�̖����v�l�ɐ[�������Ɗ��ӂ��o���܂��� ���ꂩ�����������L�������҂��Ă���܂� �{���ɗL��������܂��� �G�S������ �l
|
||
| AC100V�h�����̉�]���𐧌䂵���� | |||
|
�͂��߂܂��āA�X�������肢�������܂��B �P�O�O�u�n���h�h�����Ɋւ��Ď���Ȃ̂ł����g�p���Ă���h�����̓X�s�[�h�R���g���[�����t���Ă��Ȃ����̂ł��B �쓮��(ON)�Ƀh�����̉�]�����傶��ɏオ��悤�ɂ������̂ł����ǂ̂悤�ɂ���悢�ł��傤���A7�b�Ԃ�MAX�ɂȂ�悤�ɂ������̂ł��B ���������������A���肢�������܂��B ������������52 �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����ւ�\�������܂��A���ߕ����悭���ǂ݂ɂȂ��Ă���������Ȃ��悤�ł��̂ŁA���߂Ă����ɏ������Ă��������܂��B
�@���̒ʂ�A�������ł����˂܂��̂ł��������������B �@�܂�����]����������s�̕i���d�C�X�Ȃǂł͔����Ă��܂���B �@���̃g�s�b�N�͈����Ԍo�ߌ�ɍ폜�������܂��B ���Ԏ� 2010/11/26
|
||
| �ԁE�R���v�̕\�������킹����� | |||
|
�͂��߂܂��ā@���₳���Ă��������B �I�[�g�o�C�̔R�����[�^�[�ɂ��Ă��������������B 30�N�قǑO�̃I�[�g�o�C�̔R���v�ł� ���[�^�[�𑽋@��̂��̂Ɍ������܂��� �\�����ƃZ���T�[���̃}�b�`���O�����܂��� 12�{���g�����[�^�[���ɓ��肻������Z���T�[�ւ�5�{���g����������Ă��܂��B �Z���T�[�̓t���[�g���g�����ϒ�R�Œ�R�l�������łP�R�I�[������P�R�O�I�[���܂ł͈̔͂ŏ㉺�������܂��B �o�͂����d���͂O�{���g�`�R.�U�{���g�@����������l�ł� �ǂ����A���̏o�͓d�����O.�R�`�O.�T�{���g�قnj�������ƂقړK���ȓd���ɂȂ�悤�Ȃ̂ł������̌������@���킩��܂���B �����܂������̑f�l�Ȃ̂ŁA�Ȃ�ׂ��f�l�ɂ��킩��悤�ɂ����������Ə�����܂��B �p�J�X�P �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@��R�l�̕ς��R���Z���T�[�Ƃ����ƁA��ʂ�t���[�g�̕t�����ϒ�R�̂��̂��Ԃ�o�C�N�ł͂悭�g���Ă���悤�ł��B �@���͔R���^���N���o���������͖����̂Ŏ������������Ƃ͖����̂ł����A�l�b�g�Œ��ׂ�Ǝʐ^�Ȃǂ������̂łƂĂ��P���ȍ\���ł��邱�Ƃ��킩��܂��B �@����ɑ��āA���g���̃��[�^�[���j�b�g�͓����d���d����5V�n�œ��삵�Ă��āA�R���Z���T�[�̒�R�l�̕ω������Ă���悤�Ȃ̂Œ�R�l�ƃ��[�^�[�̕\�������킹��ɂ̓Z���T�[�̒�R�l��ς���̂��ł������������ł����A�Z���T�[��������������킯�ɂ��䂩�Ȃ��ł��傤����O�t���̕��i�łȂ�Ƃ��߂��l�ɂȂ�悤�ɂ��Ă݂܂��傤�B 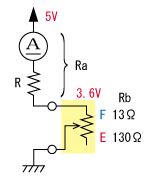 �@�ԁE�o�C�N�̔R�����[�^�[�̉�H�E�ڑ��͑�G�c�ɏ����ĉE�}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�ԁE�o�C�N�̔R�����[�^�[�̉�H�E�ڑ��͑�G�c�ɏ����ĉE�}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�@�}����130����13���͍��m�点��������R�l�ŁA�ŋ߂̎Ԏ�ł͎g���Ă��Ȃ���R�l�̔R���Z���T�[�̂悤�ł��B �@�o�b�e���[��12V�d���A�܂��͍��g�p�̃��[�^�[�̂悤�Ƀ��[�^�[�̒��ɒ�d���d����H�������Ă��ăo�b�e���[�d���̕ϓ��ɉe�����Ȃ������d������̓d�����A�d���v(���[�^�[)�Ɠd��������R(R)��g�ݍ��킹���u�d�������H�v�����C���̃��[�^�[��H�ŁA���̉�H�ɒ���Ɂu�R���Z���T�[�v���q������H�ɗ����d���l��R���̎c�ʂƂ��ĕ\�����܂��B �@�^���N���̔R�������Ȃ��ƃZ���T�[�̒�R�l���傫���d��������ɂ����A�c�ʂ������ƒ�R�l���������Ȃ��ēd������������܂��B �@�u�o�͂����d���́v�u�قړK���ȓd���v�Ȃǂ��d���ɒ��ڂ���Ă���悤�ł����A�R���̗ʂ͓d���ł͂Ȃ��d���Ŋ��m����V�X�e���ł��B �@�ł��A����̖��ł͓d���l�Ȃǂ��v���Ē����͖̂ʓ|�Ȃ̂ŁA�Z���T�[�̒�R�l�Ƃ����̓d���l�������������������Ńf�[�^�͏o�����܂�������A��������ɂǂ�����������������S�Ă킩��܂��B �� �R�����[�^�[�̓�����R��m�� �@�܂��ŏ��ɁA���̔R���v�̓d���v�Ɠd��������R�̍��v��R�l��m��Ȃ��Ɖ����v�Z���ł��܂���B �@�����ł��������������R�����[�^�[�̓�����RRa�����߂܂��B 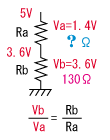 �@�d���d����5V�ŁA�Z���T�[�̒�R�l(Rb)��130���̎��ɃZ���T�[�[�q�̓d����3.6V�ɂȂ�ꍇ�A�E�}�̂悤�ȉ�H�ƂȂ�A�e��R�̒�R�l�E�d���̊W��
�@�d���d����5V�ŁA�Z���T�[�̒�R�l(Rb)��130���̎��ɃZ���T�[�[�q�̓d����3.6V�ɂȂ�ꍇ�A�E�}�̂悤�ȉ�H�ƂȂ�A�e��R�̒�R�l�E�d���̊W��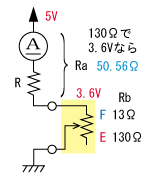 �ɂȂ�܂��̂ŁA�R�����[�^�[�̓�����R�͖�50.56���Ɠ�����܂��B
�ɂȂ�܂��̂ŁA�R�����[�^�[�̓�����R�͖�50.56���Ɠ�����܂��B�@���ꂪ�킩������ɗ����d���l������Ƃ͕ς��āA�������c�ʂ�\������悤�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@���A���̌v�Z�͂����܂ŔR�����[�^�[���]�����炠��悤�ȓd���v�����̂��̂ŁA�R���c�ʃZ���T�[�̒�R�l�ړd���𗬂��Čv������P���ȕ��@�̏ꍇ�݂̂ł��B �@�ŋ߂̃f�W�^�����[�^�[�ł������悤�ȓ�����H�Œ�R�l���v�镨������܂����AA/D�ϊ���H�ɂ����ƕ��G�ȕϊ���H���g���Ă���ꍇ�ɂ͂��̂悤�ɒP���ɓ�����R���v�Z�ł��Ȃ����́A������R�Ƃ����T�O�ł͍l�����Ȃ����̂�����܂��B �� �R���Z���T�[�̕�l��m�� �@���āA����́u�Z���T�[�[�q�̓d����0.3�`0.5V�قlj�����Ɛ������\���ɂȂ��v�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA��������ɂ͉����ǂ̂悤�ɂ��邩�l���Ă䂫�܂��B 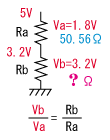 �@�R�����[�^�[�̓�����R�͖�50.56���Ƃ킩��܂����̂ŁA����ǂ��c�ʂO(EMPTY)�ƕ\�����鎞�ɒ[�q�d���͂���]��3.6V - (0.3�`0.6V)�ɂȂ�Z���T�[��R�l�����߂邱�Ƃɂ��܂��B
�@�R�����[�^�[�̓�����R�͖�50.56���Ƃ킩��܂����̂ŁA����ǂ��c�ʂO(EMPTY)�ƕ\�����鎞�ɒ[�q�d���͂���]��3.6V - (0.3�`0.6V)�ɂȂ�Z���T�[��R�l�����߂邱�Ƃɂ��܂��B�@�E�}�̋��߂�����RRb���ɂ͎��� �@��90���ł����A��90�`100���ŔR�����J���ƕ\������Ƃ������Ƃ́E�E�E����w���ɂȂ�ꂽ�R�����[�^�[�́u100���^�C�v�v�ƌĂ��K�i�i�ł͂Ȃ��ł����H �� �R���Z���T�[������������@�E�l��m�� �@�v�Z���瓱�������l�ɂ��킹��Ӗ��ł��A100���^�C�v�̃��[�^�[�ɍ��킹��Ӗ��ł��A�ǂ���ł��u�R���Z���T�[�̒�R�l��(�ő�)130����90���ɕύX(����)�����v�Ƃ����������j������ƌł܂�܂����B �@�Z���T�[�̒�R�l��Ⴍ����ɂ́A��R�����ɂȂ��ō�����R�l��Ⴍ���܂��B 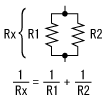 �@��R�����ɂȂ����Ƃ��̍�����RRx�͉E�}�̂悤�Ȍv�Z���ŕ\����܂��B
�@��R�����ɂȂ����Ƃ��̍�����RRx�͉E�}�̂悤�Ȍv�Z���ŕ\����܂��B�@����͂Q�̒�R�l����Rx�����߂�̂ł͂Ȃ��A�����̈�̒�R(R2)�ɐV�K�ɒ�R(R1)���������Ē�R�l������������ɂ͐V�K�̒�R(R1)�͉������K�v�����v�Z���邱�ƂɂȂ�܂��B �@����R1�����߂邽�߂� 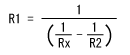 �ƕό`���āA �ƕό`���āA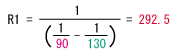 �ɂȂ� �ɂȂ��@290���Y�o���̒�R�͖����̂ŁA�s�̂̌Œ��R��270����300����R���Z���T�[�ƕ���ɂƂ����ΖړI�̕\���ɋ߂Â��邱�Ƃ��ł��܂��B �@270���{20���̒����290���ł������ł����A�{����290���ł��傤�ǂ����̂��͕s���ł��B �� �ύX�l���ς����A���R�ɒ��߂ł���悤�ɂ��� 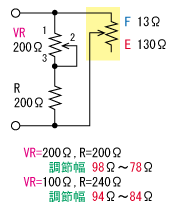 �@�Œ��R���g�p�����A���Œ��R(�{�����[��)�Œ�R�l���ςł���悤�ɂ���Ύ��R�ɒ��߂ł���悤�ɂȂ�܂��̂ŁA�E�}�̂悤��200���̔��Œ��R��200���̒�R��200���`400���̊Ԃʼnςł���悤�ɂ���ΔR���Z���T�[�ƕ����98�`78���̊ԂŒ��߂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B
�@�Œ��R���g�p�����A���Œ��R(�{�����[��)�Œ�R�l���ςł���悤�ɂ���Ύ��R�ɒ��߂ł���悤�ɂȂ�܂��̂ŁA�E�}�̂悤��200���̔��Œ��R��200���̒�R��200���`400���̊Ԃʼnςł���悤�ɂ���ΔR���Z���T�[�ƕ����98�`78���̊ԂŒ��߂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�@���Œ��R���قڐ^�ɉ���ԂŁA����]�̕\���ɂ�����߂����邱�Ƃ��ł���͂��ł��B �@200���̔��Œ��R������ł��Ȃ��ꍇ��100���ł������ł����A���̏ꍇ�͌Œ��R�̂ق���240���Ƃ��鎖�ł�͂�c�}�~�𒆉��ɉ��Ƃ��낪�قڍœK�l�ɂȂ�܂��B �@�����̒�R�l�ł���Δ��Œ��R�E�Œ��R�ɗ����d���l�����Ȃ��̂ŏ��^��1/4W�i�ő��v�ł��B �@30�N�قǑO�̃o�C�N�Ƃ������ŁA���̔R�����[�^�[�̋K�i�i�ł͂Ȃ��e�Ђ�e�o�C�N�œƎ��i���g���Ă����̂ł��傤���B �@�ő�130���Ƃ����͍̂��̋K�i���[�^�[(100/250/510���Ƃ�)�ł͂ǂ�ł��Y��������̂������ł��ˁB ���Ԏ� 2010/11/24
|
||
| ���e 11/26 |
�ԁE�R���v�̕\�������킹����� �����₵���p�J�X�P�ł� �M�d�Ȃ����Ԃ������Ē����Ẳ܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B ���X���肵�����Ǝv���܂��B �d���ł͂Ȃ��d�����݂Ă��ł��ˁ@��ϕ��ɂȂ�܂��B �܂�����k������Ē����܂��B �p�J�X�P �l
|
||
| �ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H | |||
|
�w�ȈՃn�C���[�R���o�[�^�����x�Ɋւ��Ď���Ȃ̂ł����A8���̒�R�����镔���̓X�s�[�J�[��4���̏ꍇ4�I�[���̒�R������̂��悢�̂ł��傤���H�܂��A�ȈՃn�C���[�R���o�[�^�Ƃ̑薼�ł����A�ǎ��̃n�C���[�R���o�[�^�͍쐻�\�Ȃ̂ł��傤���H ���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�A���v�̏o�͂Ƀn�C���[�R���o�[�^��t����ꍇ�A�X�s�[�J�[�͌q���܂����ˁH �A���v �� �n�C���[�R���o�[�^ �� �����I�[�f�B�I�@���LINE����
�@�Ƃ������ɔz������Ǝv���̂ł����A�����Ɂu�X�s�[�J�[�v�͑��݂��܂���B �@�]���āu�X�s�[�J�[���S���̏ꍇ�v�Ƃ��������͂ǂ��ɂ��W���Ă��Ȃ��̂ŁA���������b�͐��藧���܂���B �@�܂����A�A���v�ɃX�s�[�J�[���q�����܂�܂Ńn�C���[�R���o�[�^�[���X�s�[�J�[�ɕ���ɂȂ��ŁA���̃X�s�[�J�[���S���̏ꍇ�Ƀn�C���[�R���o�[�^�̒��ɂS���̒�R������悤�ȋ��낵�����͍l���Ă��Ȃ��ł���ˁH �@�A���v���R���܂���I (�ی��H�������Ă���A���v�Ȃ�ی삪�����ďo�͂���邾���ł���) �@���A�ƂĂ��ƂĂ����̗ǂ����ŁA�n�C���[�R���o�[�^��ڑ�����O�Ɍq���ł����X�s�[�J�[���W���̎��ƂS���̎��ʼn����Ⴂ�A�������̓X�s�[�J�[�̐����̈Ⴂ�ł͂Ȃ����׃C���s�[�_���X���S���̎��ƂW���̎����A���v���o�͂��鉹�ɈႢ���o��I�ƕ�����������悤�Ȓ��������������ł�����A���Ѓn�C���[�R���o�[�^���ɒ�R�����Ă��ꂪ�S���̎��ƂW���̎��łǂ��Ⴄ���ɂȂ�̂����������ɂȂ���Ɨǂ��Ǝv���܂��B �@�������̍D�݂̉����o��ق��ɂ��Ă���������A����ł悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�ȈՔł̃n�C���[�R���o�[�^�ł͂Ȃ��A�lj����̃n�C���[�R���o�[�^�̐�����\�ƌ����Ή\�ł��B �@�����M���p�̃g�����X��ST-71�ȊO�ɂ���R�����Ă��܂��B �@�܂����C���g�����X�ȊO�ɂ��X�s�[�J�[��炷�ׂ�1K��:8���̂悤���A�E�g�v�b�g�g�����X������܂�����A������t�Ɏg���ĂW�������A���v�̏o�͂ɃX�s�[�J�[�̂����Ɍq���ł݂���ǂ��Ȃ邩���̎��������Ă݂āA������g�����X�̒�����ł������̗ǂ����̂�T���o���Ƃ������@��������������܂���ˁB �@�P�ɃA�E�g�v�b�g�g�����X�̂W�������u�W��������v�ƃA���v�ɂȂ��ŁA�{�����[�����グ��ƃg�����X���Ă��Ă��܂��܂�����A���ʂɒ��ӂ���Ƃ��A�����Ƒ��ɉ����H�v������Ƃ��A�F�X�ƌ����̗]�n�͂���܂���B(���C���g�����X�̂悤�ɃC���s�[�_���X�������R�C�����ƏĂ��Ȃ��̂ł��̂܂܂Ȃ��ő��v�Ȃ̂ŕ��ʂ͂��������g�����X���g���̂ł���) �@�ǂ����̃g�����X�ɂ߂��荇���܂łɉ���~�A�����~�����邩�킩��܂��A����Nj�����Ȃ炻���������@������܂��B �@ST-71�̂悤���ėp�̈����ȃ��C���g�����X���g���̂ł͂Ȃ��A��p�̃g�����X�������Ŏ芪���ō���Ĕ[���̂䂭�܂ʼn��x�ł��R�C�������������Ƃ��A�g�����X�̐������[�J�[�ɔ������ĂƂĂ������̗ǂ��g�����X�����Ă��炦�悢�̂ł��B���������\������Ȃ�̔ėp�g�����X�ł͉������C�ɓ���Ȃ���������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�����Ŏ芪�����鎞�ł��R�A(�S�S)��d���ɂ͂������A�~�~�|���g�����R�A�Ŏ������ǂ��Ƃ��A�������̓d�����g�����̂œd�C��R���ǂ��Ƃ��A����ʼn���������I�ɃA�b�v�����I���ƍ����I�[�f�B�I�}�j�A�̊F���悭�P�[�u�����Ɋւ��Č���Ă���������悤�ɁA�f�ނ����I���Ē������ȃg�����X�����A���ꂪ����S�~�̃g�����X�ł͏o���Ȃ��悤�ȉ��ł���Ɣ[�����Ă�������Ό��\�ł��B �@�m���A�s�̂̃n�C���[�R���o�[�^�ł����������g�����X�����g�p���Ă��鎖�蕶��ɂ��Ă��镨���������悤�ȁE�E�E�B �@�������A����Ŏg��LINE�[�q�������b�L��RCA�[�q�ł���I �@���C���g�����X���g��Ȃ��ꍇ�A�X�s�[�J�[�M���������d�q��H�Ŏ�A/D�R���o�[�^�łP�r�b�g�f�W�^���M���Ȃǂɂ��āA�≏�g�����X��≏���̃f�[�^�ʐM�f�q�Ȃǂ���ďo�͑��Ƀf�W�^���M�����n���A��������P�r�b�gD/A�I�[�f�B�I�A���v�ŃA�i���O�����M���ɕϊ�����悤�Ȓ��w���̍����ȃf�W�^�����n�C���[�R���o�[�^�Ȃ�Ă̂��l�����܂��ˁB�ŋ߂̂P�r�b�g�f�W�^���I�[�f�B�I�}�j�A�̕��Ȃ炱���������u��(�����Ƃ��������������щz���āc)����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���ڌq���ƃ_����BTL����LINE�ɕϊ��������Ƃ��A�O�����h���[�v�m�C�Y���Ȃ��������Ƃ��A�����������R�̂��߂ɂ͂��܂�ɂ��ُ�Ȃقǂ̕��i���Ɛ����x�ł����A�ƂĂ��ƂĂ����ɂ������I�[�f�B�I�}�j�A�̕��Ȃ炱�ꂭ�炢�̍\���̒��f�W�^���E�n�C���[�R���o�[�^�Ȃ�Ă̂��u�A���v��������܂���B �@���Ԃ�g�����X���Ȃ�Ƃ����Ȃ��Ɓu�ǎ��v�Ƃ������t�̎����Ƃ��낪�u�����v�Ȃ���i�ɂ͗ǂ��͂Ȃ�Ȃ��ł��傤���A�P�[�X�ɃX�C�b�`��t���ē����̕��ג�R���u�Ȃ��^�S���^�W���v�ƑI���ł���悤�ȋ@�\���t���Ă���Ƃ��AST-71���g������H�ł͏o�͑����g�����X�̂S�ԂƂT�Ԃ̂ǂ���̒[�q�����邩�Łu�m�[�}���^�u�[�X�g�v���̕\�L�̃X�C�b�`�ɂ��Ă��܂��A�Ȃ�Ɓw����(���@�\)�n�C���[�R���o�[�^�x�̂悤�Ɍ�����ł��傤���I �@�u�u�[�X�g�v�̂悤�ɁA�l�̐S���������閼�O�ɂ���Ƃ��낪�|�C���g�ł��I(��) ���Ԏ� 2010/11/23
|
||
| �ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H | |||
|
�����́A���߂܂��āB �p���X�̑����ׂĂ���A���ǂ蒅���܂����B ���A�o�C�N�̃^�R���[�^�[���������Ă���̂ł��� ���t����ԗ��̓N�����N2��]��2�p���X ���[�^�[�̓N�����N2��]��1�p���X�̂悤�� �\�������ۂ̔����ƂȂ��Ă��܂��܂��B �u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v��q�����܂������A�P����]����̂őΉ��ł��邩�킩�炸�A ���e�����Ă��������܂����B ���Ђ��m�b�����݂����������܂���ł��傤���H�X�������肢�������܂��B ���b�V �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�������t�ł͂Ȃ��ł����H �ԗ��̓N�����N2��]��2�p���X �� 1��]1�p���X ���[�^�[�̓N�����N2��]��1�p���X �� 2��]1�p���X �@2��]1�p���X�̃��[�^�[��1��]1�p���X�̐M������ꂽ��A�\���͂Q�{�ɂȂ��Ă��܂��A�u�\�������ۂ̔����ƂȂ��Ă��܂��܂��v�Ƃ͐H���Ⴄ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�����܂ŁA�ړI���u�p���X�����Q�{�ɂ������v�������Ƃ��Đ����𑱂��܂��B �@�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�̏ꍇ�A�o�̓p��������0.01�`0.1msec�ɉςł��A�ł��Z��0.01msec�ɐݒ肵���ꍇ�ɂ͏o�͂P�p���X�Ԃ��0.02msec�A�Q���{��H�����p���X���K�v�Ȃ��߂ɂP��̃J�E���g����(����)�ɂ͍Œ��0.04msec�K�v�ł��B �@�P����0.04msec�̃p���X���A�����ē��͂���鎞�̎��g����25,000Hz�A������P��]�P�p���X�̍ۂ�rpm�ɂ����150����](rpm)�̓��͂�300����](rpm)�ɕϊ�����Ƃ���܂ł͑Ή����Ă��܂��B �@�o�̓p���X����0.1msec�ɂ��Ă�15����](rpm)�̓��͂�30����](rpm)�ɕϊ�����@�\�͂���܂��B (�Q�{�A�S�{�p���X�d�l�̏ꍇ�͊e1/2�A1/4�ɍl���Ă�������) �@��]���͂����܂őΉ����Ă��܂����A����ɓ������ǂ����́u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�̂ق��ŏ����Ă���ʂ�A���̉�H�̏o�͂���p���X��(0.01�`0.1msec)�Ń��[�^�[���̎�M��H���������p���X�Ƃ��Ď�M�ł��邩�ǂ����ƁA�Q��A�����ăp���X���o�����0.02�`0.2msec�̊Ԋu�Ő������u�Q�p���X�v�ƃJ�E���g���Ă����\�͂����邩�ǂ����B �@�����čł��d�v�Ȃ̂͂��̉�H��OMRON�̃f�W�^���^�R���[�^�[(�H�Ƌ@��p�̃J�E���^�ŁA�ԓ��̃��[�^�[�\���p�ł͖���)�p�ɐv���Ă�����̂ŁAOMRON�̃^�R���[�^�[�͎Ԃ�o�C�N�̃^�R���[�^�[�Ƃ͈Ⴄ���i�̂��߂ɁA���Ȃ������g���ɂȂ�Ԃ�o�C�N�̃^�R���[�^�[�����������`���̂Q���{�M���ɑΉ����Ă��邩�ǂ����Ƃ�����������ł��B �@���̂�����͂��g���ɂȂ��郁�[�^�[���ǂ̂悤�Ȏd�l�ŁA�ŏ��p���X���͂ǂꂭ�炢�ɑΉ����Ă���̂���A�Ԃ̃^�R���[�^�[�p�M���̂悤�ȉ�]���͋ϓ��ȃp���X�łȂ��ƌ�쓮����悤�ȃJ�E���g�`�����Ƃ��Ă��Ȃ������イ�Ԃ�Ɋm�F���Ă��炲�g�p���������B ���Ԏ� 2010/11/23
|
||
| �N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� | |||
|
���߂Ă��ւ肳���Ă��������܂��B���s�e����431si�Ƃ����i�r���o�C�N�Ŏg�p���Ă��܂��B�������W���b�N������o���Ă���̂ł������������������߃L�b�g�̃A���v���g���Ă����̂ł����A�m�C�Y�Ƃ������@�Ƃ��ɕ��Q���o�����߂��낢��T���Ă����Ƃ����N���A�[�{�C�X�̋L���������܂����B840�~�Ŏ�ɓ���W���b�N�Ȃǂ����t���o�C�N�Ŏg����悤�ɂ����̂ł����L�[���Ƃ����m�C�Y�H���o�ċC�ɂȂ�܂��B���������ጸ������@�������Ă��炦��Ǝv�����e�����đՂ��܂����B�X�������肢�v���܂��B ���M �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�Ԃ�o�C�N�ŁA���W�I��I�[�f�B�I�ȂǂɁu�L�[���v�Ƃ��u�q���[���v�Ƃ��������̌��ȉ�(�m�C�Y)������̂͂悭���鎖�ł��B �@�G���W���̓_�Όn��ŋ߂̎Ԃł̓G���W���R���g���[���p�R���s���[�^�Ȃǂ���o��m�C�Y�I�ȓd�C�M�������ځA�܂��͓d�����C���̓d���ɕs����ȕϓ���^���邱�Ƃʼn����o�����u�ł͂��̉e���ʼn��Ɂu�L�[���v�Ƃ����m�C�Y���������Ă��܂��܂��B �@���ʂ̓J�[�I�[�f�B�I���ł͂قƂ�NjC�ɂȂ�Ȃ����x���Ȃ̂ł����A���Ƀm�C�Y���x�����傫���Ȃ�Ƃ��Ȃ�͂����蕷�����鉹�ɂȂ��Ă��܂��ĕs���ɂȂ�܂��B �@��������ɂ� �� �m�C�Y���������� �� �m�C�Y���`���o�H���� �� �m�C�Y���Ă����� �̂R��ނ̕��@���l�����܂����A�Ȃ��Ȃ���ؓ�ł͂䂫�܂���B �@����Ԃł��鏊����m�C�Y���o�Ă���Ƃ킩���āA����ɑΏ����鏈�u�����ăm�C�Y���y�������Ƃ��āA�ق��̎Ԃł͓����m�C�Y����`�B�o�H�ł͂Ȃ��ē����Ώ����@�ł͑S�R�����Ȃ��Ƃ������Ƃ����X����ƂĂ���������Ȗ��Ȃ̂ł��B �� �m�C�Y���������� �@����͂قƂ�ǖ����ł��ˁB �@�_�Όn��R���s���[�^�̓��[�J�[�ɂ�芮�������`�Œ���Ă��āA����Ɏ�������ăm�C�Y��ጸ������悤�ȉ����͂��܂芩�߂�����@�ł͂���܂���B �@�Ԃ�����Ɋ���Ă��āA�_�Όn�Ȃǂ��������������������E�E�E���������Ԃ̉����Ɋ��ꂽ���Ȃ�킩��͈͂ʼn��ǂ��Ă��������B �� �m�C�Y���`���o�H���� �@�ǂ����Ŕ��������m�C�Y���ԑ̂≽���̓d���P�[�u����`����Ă܂��ɔ��U����̂�}���邽�߁A�A�[�X������������d���P�[�u���Ƀm�C�Y���p�̃t�F���C�g�R�A�Ȃǂ�킹�Ă��Ȃǂ̑l�����܂��B �@�Ԃł͑����̏ꍇ�o�b�e���[�̃}�C�i�X���͎ԑ̂̂Ƃ��ēd�C�P�[�u���̂����Ɏg���Ă���̂ŁA�ԑ̂̋�����R�Ȃǂœd�C��������H�ɓd�ʍ������܂�A���ꂪ�����Ŏԑ̂ɓd��������鎞�ɓd���g�Ƃ��ăm�C�Y�����o����邱�Ƃ�����܂��B �@�������������ɂ̓o�b�e���[�̃}�C�i�X�ɂƁA�Ԃ̒��œd�C���g���ꏊ(�@��)�Ƃ̊Ԃ��ԑ̂ł͂Ȃ����ڃP�[�u���Ōq���悤�ɂ��ēd�C��R�����炵����A�ԑ̂̊e�����p�[�c�Ԃ��P�[�u���Ōq���Ŏԑ̑S�̂œd�ʍ����N���Ȃ��悤�ɂ���u�{���f�B���O�v�Ƃ�����@���悭�p�����܂��B �@�u������A�[�X���͌q�����Ă���̂ɁA�������A�[�X��lj��z�����邾���ʼn��P����́H�v�Ǝv���邩������܂��A�����@�Ɂu�L�[���v�����ڂ��Ď���肾�����ԂŁA�h�A�ƃ{�f�B�ԂɃ{���f�B���O���C���[���q���������Łu�L�[���v�����قƂ�Ǖ������Ȃ��Ȃ����Ƃ���������邭�炢�ł��B �@�傫�������ŕ����Ă���ԂłȂ��Ă��A�o�C�N�ł��ԑ̂̋��������炩�̃m�C�Y���U����o�H�ɂȂ��Ă���\���͂���܂��̂ŁA�A�[�X�^�{���f�B���O��������Ă݂鉿�l�͂���Ǝv���܂��B �� �m�C�Y���Ă����� �@������o�Ă���m�C�Y�����������ʼn��P���Ă��܂��C�ɂȂ���x�́u�L�[���v������������ꍇ�́A�I�[�f�B�I�@�푤�ʼn���������邵������܂���B �@�����̏ꍇ�͓d���z������m�C�Y���I�[�f�B�I��H���ɓ��荞��ŁA���ꂪ��������Ď��ɕ������鉹�̃��x���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�d�����C���Ƀm�C�Y�t�B���^��H���Ƃ���ăm�C�Y��ጸ���邱�ƂɂȂ�܂��B �@�d�q���i�X�ł��������p�r�̃m�C�Y�t�B���^�������Ă��܂��̂ł����������i�����A�����ŃR�C���ƃR���f���T�Ńm�C�Y�t�B���^�������DC12V�̓��͂�A�A���v��H�̒��̓d�����̏o�͂ɓ���邱�ƂŃm�C�Y�����Ȃ����邱�Ƃ͂ł��܂��B 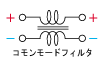 �@�d���g�I�ȕ��˂��d�����Ȃǂɉe����^���ăv���X�ƃ}�C�i�X�̗����̔z���ɓ����ʑ��̓d������������m�C�Y�̏ꍇ�͂P�̃R�A�ɂQ�����������m�C�Y�����p�R�C��(�R�������[�h�t�B���^�[)��d�����͂ɂƂ���܂��B
�@�d���g�I�ȕ��˂��d�����Ȃǂɉe����^���ăv���X�ƃ}�C�i�X�̗����̔z���ɓ����ʑ��̓d������������m�C�Y�̏ꍇ�͂P�̃R�A�ɂQ�����������m�C�Y�����p�R�C��(�R�������[�h�t�B���^�[)��d�����͂ɂƂ���܂��B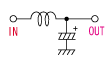 �@�m�C�Y���d���ϓ��Ɍ����悤�ȏꍇ�́A�v���X�������ł��R�C����ʂ��Ď��g���̍����d�C�ϓ���ʂ��Ȃ��悤�ɂ��āA���̏o�͂�d���R���f���T�ŕ������ăm�C�Y��ጸ�����܂��B
�@�m�C�Y���d���ϓ��Ɍ����悤�ȏꍇ�́A�v���X�������ł��R�C����ʂ��Ď��g���̍����d�C�ϓ���ʂ��Ȃ��悤�ɂ��āA���̏o�͂�d���R���f���T�ŕ������ăm�C�Y��ጸ�����܂��B�@�������v���X���Б��ł͂Ȃ������ɃR�C���̓������m�C�Y�����p�̃R�C��(�R�������[�h�t�B���^�[)���g���Ă����܂��܂���B �@�ǂ̒��x�̃R�C�����g�����Ȃǂ͏ɂ��l�X�ł����A�d�q�p�[�c�V���b�v�̓X���œX������Ɏ����������āA���̓X�Ŕ����Ă���R�C���̒��łǂꂪ�����̂��I��ł��炤�Ɨǂ��ł��傤�B �@�ق��ɂ́A�A���v�̓d����H�Ɋe��e�ʂ̈Ⴄ�R���f���T���Ȃ����@�Ńm�C�Y���y������ꍇ������܂��B �@�d���o�R�Ńm�C�Y������Ă���ꍇ�A�d����H���ɃR���f���T��������ē�����H����邱�Ƃł��܂����̃m�C�Y���g���Ɠ������邱�Ƃ��ł���m�C�Y�͂��Ȃ�����܂��B �@�������̕��@�͓d����H��@������̃C���s�[�_���X�ƃR���f���T�̗e�ʂŃt�B���^�[�ł�����g�������܂邽�߁A�P���Ɂuxx��F�̃R���f���T��t���Ă��������v�Ƃ͌����Ȃ��̂���_�ł��B �@���g���̋@��̃C���s�[�_���X�ɂ��ǂ�ȃR���f���T��t�����炤�܂��䂭�̂��A�܂����̕��@�ł͂قƂ�lj��P����Ȃ��̂��͐獷���ʁA�F�X�ȃR���f���T���ĂȂ��ł݂ăe�X�g���Ă݂Ă��������Ƃ��������܂���B �� �d����H���̂�ς��Ă��܂� �@�����܂œd������m�C�Y������Ă���ꍇ�ł����A�N���A�[�{�C�X�̓d����H����蕥���ĕʂ̓d����H�ɕς��Ă��܂��m�C�Y���ጸ�����邩������܂���B (����Ȃɖҗ�Ƀm�C�Y��ʂ��Ă��܂���H�ɂ͌����܂���) �@�O�[�q���M�����[�^��9�`12V���x�̓d��������Č������Ă݂�Ƃ��A�m�C�Y�t�B���^�[�Œጸ�ł��Ȃ��Ȃ炻��������H�ύX�������Č��鉿�l�͂��邩������܂���B �@�{���Ƀm�C�Y���͓d�����C���ŁA�������͂Ɂu�L�[���v�ƃm�C�Y������Ă���̂ł͖����ꍇ�ł���B �� �Ō�̎�i �@�ԁE�o�C�N���̃A�[�X��A�I�[�f�B�I��H�̓d���m�C�Y��ł��܂������ȁu�L�[���v����������ꍇ�́A�J�[�i�r����A���v�ɐڑ����镔�����A���v�̓����Ɂu���[�p�X�t�B���^�[�v��H�����č������g���̉��������Ă��܂����ƂőΏ����邵������܂���B �@�������A���[�p�X�t�B���^�[������ƍ����������Ă��܂��̂ʼn��y��W�I���悤�ȃI�[�f�B�I�ɂ͂����߂ł��܂���B�������������Ȃ��ƂƂĂ������������������ɂȂ��Ă��܂�����ł��B �@�����܂ŁA�J�[�i�r�̈ē��������Đ�����X�s�[�J�[�p�E�E�E�ł���Α��������������Ȃ��Ă��A���������Ă��邩���킩������̂ŁA�{���ɍŌ�̎�i�ł��B �@�܂��A���[�p�X�t�B���^�[������ƃJ�b�g���Ȃ����g���̉������x�����������Ă��܂��̂ŁA�N���A�[�{�C�X�̃A���v�����ł͂��イ�Ԃ�ɑ傫�ȉ��������Ȃ��A���[�p�X�t�B���^�[�Ƌ��ɂ�����i�A���v�����Ȃ��Ƃ����Ȃ���������܂���B�Ȃ���Ԃł���ˁB �@�Ȃɂɂ��Ă��A�Ԃ�o�C�N�Łu�L�[���v�Ƃ����m�C�Y�����錴���Ƃ���ɑ��鐳���������@�͂��̎ԁE�o�C�N�ɂ���ėl�X�ɈႤ�̂ŁA�������Ńm�C�Y�����ǂ��Ȃ̂��A�ǂ����o�R���ē����Ă���̂����m���߂Ȃ���Ȃ��Ȃ��J���^���ɂ͂�����������Ƃ͂ł��܂���B ���Ԏ� 2010/11/23
|
||
| ���e 11/26 |
���J�Ȃ��ԓ����肪�Ƃ��������܂����B�Ǒf�l�Ȏ҂Ȃ̂Ŏ��ɂƂ��ē����͏o�����˂܂��̂Ń{���f�B���O���̊ȒP�Ȃ��̂���g���C���Ă݂悤�Ǝv���܂��B�͂Ȃ͂��ȒP�ȕ��͂ő�ϐ\�������܂���B�������A�S�̒��͊��ӂ̋C�����ň�t�ł������܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B ���M �l
|
||
| ���e 12/5 |
�����̌o�����牡���X���炵�܂��B �P�̂ł̓m�C�Y���������Ȃ��̂ɁA�A���v���O�t���ڑ��������Ƀm�C�Y������̂́A2�̋@��̃A�[�X�̓d�ʂɍ������鎖�������̂悤�ł��B (�m�C�Y��������d������2�̋@��ɕʁX�ɓd��������鎖�ƁA���ꂼ��̋@������̃A�[�X�Ɠd�����̃A�[�X�Ԃ̒�R���قȂ鎖����A�@��Ԃ̃A�[�X�d�ʂɍ���������B) �z����ڑ��ő���@(��)������̂ł����A���S�҂ɂ͂�����Ɠ���Ǝv���܂��B �@��̊ԂɃg�����X�����鎖�ł��̓d�ʍ��̉e�����瓦���鎖���o���܂��B���ꂪ�ł��ȒP���Ǝv���܂��B ���z����ڑ��ő���@ �P�D2�̋@��͂Ȃ�ׂ������d���C�A�[�X����ڑ����A����_����̃P�[�u�����ŒZ�ɐڑ�����B(�\�Ȃ�2�̋@��̃A�[�X�Ԃ����ōŒZ�Őڑ�) �Q�D�A���v�̓��͉�H�̃A�[�X���A�M���̃\�[�X(���̏ꍇ�̓i�r)�����瓾����@�B �u�R���|�`���v�̃J�[�I�[�f�B�I�̋@��Ԃ����̂悤�Ȑڑ�������Ă���悤�ł��B ���Q�l�ɂȂ�K���ł��B jr7cwk �l
|
||
| ���e 2/17 |
jr7cwk�l�����X���肪�Ƃ��������܂����B�b�����̃y�[�W��K�₵�Ă��Ȃ��ăA�h�o�C�X���L��̂�m��܂���ł����B ���Ɠ����悤�Ȏg����������Ă���������ĕt���̃V�K�[�v���O�R�[�h�Ɍ������L�����悤�Ȃ��Ƃ��ڂ��Ă����y�[�W������A���������V�K�[�v���O���w�����A���t���Ă݂��Ƃ���m�C�Y�͌y������܂����B�܂��s���͎c���Ă��܂����B �m�����Ȃ����ߋZ�p�I�Ȃ��Ƃ��ȒP�Ȏ������Ή��ł��܂���̂ŁB ���낢��ƃA�h�o�C�X�����肪�Ƃ��������܂����B ���M �l
|
||
| ���d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� | |||
|
����ݏZ�̍ŋߓd�q�H��Ƀn�}���Ă���I�W�T���ł��B�X�������肢���܂��B �{��ɓ���܂����A100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���u���p�h�ƃu�U�[�v�ɓ����Ă���R�C���ɂ��ċ����ĉ������B ���d�X�s�[�J�[��剹�ʂŖ炵�������߁A�h�ƃu�U�[�ɓ����Ă���R�C���ƈ��d�X�s�[�J�[�����A�^�C�}IC555�̔��U��H�ɐڑ������g��1�`5kHz�Ŏ������̂ł����A�傫�ȉ��͏o�܂���ł����B �u�J�~��x��u�U�[�v�Ɍ��J����Ă����H���݂��Ƃ���A�g�����W�X�^�̂Ƃ���ɃR���f���T������܂����A����Ȃ̂ł��傤���B���������ł�����A�R���f���T�̗e�ʁi�����ł��ǂ��ł��j�������ĉ������B �����w �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�傫�ȉ��Ŗ�܂���ł������H �@�������100�~�V���b�v�̌x��u�U�[����R�C�����āA555�̔��U��H�ɂȂ��ł݂܂����������ׂꂻ���ɂȂ邭�炢�̑傫�ȉ����o�܂�����B (�����I�ɂ͑剹���ɂȂ�Ȃ��͂��͖����̂ł���) 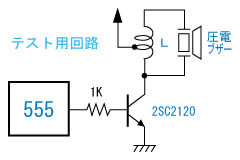 �@�E�}�̂Ƃ���A555�Ŕ��U������1.5�`3KHz���x�̋�`�g�p���X�Ńg�����W�X�^���쓮���A�R�C���d�����/�����č��d���������Ĉ��d�u�U�[��剹�ʂŖ炵�܂��B
�@�E�}�̂Ƃ���A555�Ŕ��U������1.5�`3KHz���x�̋�`�g�p���X�Ńg�����W�X�^���쓮���A�R�C���d�����/�����č��d���������Ĉ��d�u�U�[��剹�ʂŖ炵�܂��B�@100�~�V���b�v�̌x��u�U�[�̉�H�Ƃ܂������������̂ł��B �@�T�E���h�̔��U�����x���H�p��IC����555�ɕς�������炢�ŁA��H�}��̈Ⴂ�͂���܂���B �@�܂��A�R���f���T�����Ȃ��Ƒ傫�ȉ��ɂȂ�Ȃ��Ƃ������͂���܂���B(�����Ŗ��Ă��܂��A����Ă���܂����c) �@���Ă����ł�����ő傫�ȉ����o�Ȃ������ł����E�E�E �� ��{�I�ɉ����ڑ����Ԉ���Ă��� �@�R�C���̑����ԈႦ���Ƃ��A�g�p���Ă���g�����W�X�^�̑����Ԉ���Ă���Ƃ��E�E�E�H �@���������P���~�X�ł͂���܂��H �@���100�~�V���b�v�̌x��u�U�[�Ŏg�p����Ă���g�����W�X�^��S8050�ł����A���{�ł悭�g����2SC1815�Ȃǂƃs���z�u���Ⴄ�̂ŊԈႤ�Ɠ��삵�܂���B �� �g�����W�X�^���g���Ă��Ȃ� �@�u�R�C���ƈ��d�X�s�[�J�[�����v�Ƃ͏�����Ă��܂����A�u�g�����W�X�^�����v�Ƃ͏�����Ă��Ȃ��̂ŐS�z�ł��B �@�`���b�p�^�̃R�C�������̌����͂悭�����m���Ƃ͎v���܂����A�R�C���ɓd���𗬂��ė㎥���Ď��̓G�l���M�[�𗭂߁A�d��������������̎��̓G�l���M�[���������R�C���ɍ����d���̃p���X�����������ƂŌ��̓d�����͂邩�ɍ����d���܂��B �@�R�C���Ƃ͌����Ă��܂����A����̂悤�ȃR�C���́u�����g�����X�v�̈��ł��B �@����g�p����100�~�V���b�v�i�̒��̃R�C�����ƈ��d�u�U�[��ڑ�������Ԃŏo�͂͂�������50�`60V���x�������܂��B �@���Ă����ŋC�ɂȂ�̂́A�����ƃg�����W�X�^���g�����`���b�p��H�ɂȂ��Ă��܂����H �@���Ƃ��A�g�����W�X�^�͎g�킸��555�̏o�͒[�q�����̂܂܃R�C���ɂȂ��ł��܂��Ă���Ƃ��̊Ԉ������H�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����ˁH �@555�̏o�͂͒P�Ȃ�g�����W�X�^�o�͂ł͂Ȃ��v�b�V���v���ł�����AH����L�����ǂ�����o�͎��Ƀg�����W�X�^�ŏ㉺�Ɉ��������܂��B �@��������ȃv�b�V���v���o�͂��R�C���Ɍq������A�R�C���ɓd���𗬂��Ď��͂𗭂߂邱�Ƃ͂ł��܂����A�R�C���d������č��d���������������ɂ͔��Α��̃g�����W�X�^�̓����ŃR�C�����V���[�g������悤�ȉ�H�ɂȂ��āA�R�C���ɗ��߂����͂͂��̂܂�����Ă��܂��̂ō��d���������邱�Ƃ͂ł��܂���B �@���d���͔������Ȃ��̂ŁA555�Œ��ڈ��d�u�U�[��炷�̂Ƃ������ĕς��Ȃ����ʂł�����Ȃ��ł��傤�B �� �ق��E�E�E �@���ɉ�������ł��傤���H �@������Ǝv�����܂���B �@�����ɂȂ�ꂽ��H��������x�悭�������āA�ǂ����Ԉ���Ă��邩�����ׂ��������B ���Ԏ� 2010/11/22
|
||
| ���e 11/27 |
�g�����ł��B ���d�u�U��傫�ȉ��Ŗ炷���߂ɂ� ���U��Ƃ����鏬�����i�`�����o�[�j�̋�Ԃ� �K�v�ł��B \100�V���b�v�h�ƃu�U�ł��������\����݂��� ����܂��B �Q�l�i�x�m�d�@�A���d�f�q�����j http://www.fdk.co.jp/cyber-j/pdf/BZ-TEJ001.pdf �Q�P�łɋ��U��̐v�ɂ��Ă���܂��B ���d�u�U�̐U���ł��P�[�X����O�������ƂŁA������ �\�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�������Ǝv���܂��B ���������Ȃ��悤�ɃP�[�X���珬�������Ǝ��o���� �ڐA���ꂽ��ǂ��Ǝv���܂��B �g���� �l
|
||
| ���e |
�����w�ł��B �V�Q�҂̎��Ɍ�ԓ������A��ϊ��ӂ��Ă��܂��B �g�����l�́u���U��v�ɂ��ẮA���d�X�s�[�J�����o���ۂɊ��ɉĂ���A�����Ɏ������Ƃ͂ł��Ȃ��ł����A���̋@��ɂ͍l���������Ǝv���܂��B ���̎�������H�́A���̉�H�������Ă���A�Ⴂ�̓g�����W�X�^��2SC1815���炢�ł��B�d����AC�A�_�v�^(5V, 500mA)���g�p�B ����A2SC2120�Ŏ����܂������ω�����܂���ł����B ���݂ɁA���d�X�s�[�J�̐ڑ�����H�}�̂悤�ɃR�C���̗��[�ł͂Ȃ��A�^�ƃg�����W�X�^���ɐڑ����������Q�{�قlj����傫���ł��B �R�C���̗��[�ŁA���܂������ł��Ă��Ȃ��̂ł��傤���H �����w �l
|
||
| ���Ԏ� |
�E�R�C���̑����Ԉ���Ă��� �E�R�C�����O�����ɉĂ��� �Ȃǂł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2010/12/2
|
||
| ���e |
�����w�ł��B ���w�E�̂Ƃ���A�R�C�������Ă��܂����B ���[�̑����e�X�^�Ō��������Ƃ���ʓd���Ă��܂���B �����s���ł����A�������ɉ��悤�ł��B �ēx�A�h�ƃu�U�[���ɍs���܂������ߏ��̃_�C�\�[�ł͔����Ă������߁A�T���̂ɋ�J����������������Ă��܂��Ԏ����x���Ȃ��Ă��܂��܂����B ����Ȃ�Ƃ���ɓ���A���Ԏ��̉�H�Ŏ������Ƃ���A�ƂĂ��傫�ȉ��Ŗ��Ă���܂����B �ڕW��B������ϊ��ӂ��Ă��܂��B �R�C���͊ȒP�ɂ͉��Ȃ��Ǝv������ł��܂������C���g��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��ˁB ���P�ɂȂ�܂����B���낢��Ƃ��肪�Ƃ��������܂����B �����w �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�������Ă悩�����ł��ˁB �@���̂悤�ȃR�C���Ɏg���Ă���u�t�F���C�g�R�A�v�͂ƂĂ����낭�āA�����͂�������������Ń|�����Ɗ���Ă��܂��܂��B �@�����Ȃ���ۂȂǂɑ��̍��������W�I�y���`���ŌŒ肵�āA�������ɗ͂�������悤�ȕ��@�ŋȂ��L�����Ȃ��ƁA�{�̂������đ������Ȃ����肵����Ă��߂�ɉ��܂��B �@���̍����̌Œ肪����Ă��܂��ƁA���̃G�i�������͂ƂĂ��ׂ��̂łق�̏������������������Ńv�c�b�Ƃ�����Ă��܂��ł��傤�B �@�~�j�`���A�R�C���E�C���_�N�^�̏ꍇ�̓R�A�Ƃ͕ʂɃv���X�`�b�N���́u����v�����Ă�����̂͂��Ȃ藐�\�Ɉ����Ă����v�ł����A�\�����P���ł��������Œ��̕t���Ă��Ȃ��R�C�����ƍאS�̒��ӂ��K�v�ł��B �@����ƁA100�~�V���b�v�i�������ɗ��p�E���p���悤�Ƃ���ꍇ�͓����ɂQ�`�R�����Ă����ׂ��ł��ˁB �@���Ƃł�����g����������105�~�̂��߂ɓX�܂ōs����Ԃ�A����̂悤�ɓX���ɖ����ĒT�����̂͂��܂�ɔ߂�����Ƃł��B ���Ԏ� 2011/1/4
|
||
| �e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ | |||
|
�e�j�X���y����ł��܂����N�̂������J�E���g��Y��Ă��܂����Ƃ����X����܂��B�����ŃX�R�A�J�E���^�[�����Ȃ����Ƃ��낢�뎎�삵�܂������ǂ����Ă��傫�����i���������̂ł��B�r�Ɋ����t���Ďg�������̂ŃJ�E���^�[�͂Ȃ�ׂ��������y���A���������z�ł��B�e�j�X�͂P�|�C���g���邲�ƂɃt�B�t�e�[���A�T�[�e�B�[�A�t�H�[�e�B�[�Ɛ����A�t�H�[�e�B�[�I�[���Ńf���[�X�ƂȂ�܂��B�J�E���^�[�̎d�l��LED���R�A�v�b�V��SW���P�����ƂɂP���_�����A�R�܂œ_�����A�S��ڂɃ��Z�b�g�Ƃ������̂ł��BIC��H�ō��ł������Ȃ̂ł����A�������A�����A�y���ƂȂ�Ɠ���Ƃ͎v���܂����A�ł��邾������ɋ߂Â��悤�ȕ��i���̏��Ȃ���H���������肢�����̂ł�낵�����肢���܂��B river2924 �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�r�Ɋ����t���Ďg���E�E�E�ł����B �@��H�̐����Ƃ����������b���A��ɂ��̂�����ܘb���B �@(�傫�ڂ�)�r���v���炢�̑傫���Ɏ��܂���X�g�o���h�ɕt���Ă��������Čy���Ă����ł��ˁB �@�ł��A���ꂭ�炢�̑傫���ɂ���ɂ�IC���g���Ă�IC����炢�ōς܂��āA�d�r�̓��`�E���R�C���d�r�A�Ƃɂ�������������Ȃ�IC�͕��ʂ�DIP�^�C�v�ł͂Ȃ��\�ʎ����p�̃t���b�g�^�C�v���g�p����LED���R�Ȃǂ��`�b�v���i���g���ȂǁA�l�Ő���ł���͈͂ł͂���܂����ƂĂ����x�ȕ\�ʎ����Z�p���������l�łȂ��ƒ����^���͓���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�n���_�Â��Ȃǂ̍H�삪�\�ʎ������i�قǓ���͂Ȃ��ALED���R�����ʂ̑傫���̕��i���g���H��̓J���^���ł����傫���͂���Ȃ�̂��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B��̓}�b�`�����Q���ׂ����炢�ł��傤���B �@������H�}�ł��g�����i���ǂ��I�Ԃ��A�ǂ̂悤�Ȏ����������Ƃ邩�ő傫���͂��Ȃ����Ă��܂��B �@����ł��^�o�R�̔����͂����Ə����Ȃ��́A���܂����Όg�ѓd�b�̔������炢�̑傫���ɂ͂ł���ł��傤����A�W���M���O�p�ȂǂŌg�ѓd�b���̘r�ɂƂ����O�ʂ������r�j�[���ɂȂ����u�g�уz���_�[�v���ɓ���Ă��܂��e�j�X�̂悤�Ɍ������r�������ł������ƕێ����Ă�����Ƃ͎v���܂��B �@�g�ѓd�b�̔������炢�̑傫���Ȃ烊�X�g�o���h�ɌŒ肷��̂��Ȃ�Ƃ��ł���͈͂��ȂƁB �@�܂��A�Ō�ɎQ�l���Ƃ��čڂ��Ă����܂����A���W�b�NIC�ʼn�H����炸��PIC�}�C�R�����g���W�s���̏�����IC(PIC�}�C�R��)��ōς�ł��܂��܂��B �@PIC�}�C�R���łȂ���ɕ\�ʎ����p�̃t���b�g�^�C�v���g�킸��DIP�^�C�v�ł�(���݂͂���܂���)�r���v���炢�̑傫���Ɏ��܂�܂��ˁB ���N���b�N����Ɗg��\��
�@���W�b�NIC�ō��ƍŒႱ�ꂭ�炢�̕��i���ł��B �@�X�R�A���J�E���g���镔�����V�t�g���W�X�^�Ƃ����@�\��IC���g���܂��B�����C-MOS 74HC�V���[�Y�� 74HC164���g�p���܂��B �@�V�t�g���W�X�^�͓��͒[�q�ƁA���Ƀf�[�^�����Ă����L����H����������ł��āA�u�N���b�N�v�[�q�ɓ��͂����N���b�N�M���̃^�C�~���O�Œ��ɋL�����Ă���f�[�^���P�Âׂ̋L����Ƀo�P�c�����[�̂悤�Ȋ����Ŏn���Ă䂭��H�ł��B �@��������͂ɋ߂��[�̋L����H�̓N���b�N�M���̃^�C�~���O�ŊO������̓��͐M�����L�����܂��B �@�܂��A���Z�b�g�M���őS���̋L����H�̒��g�����Z�b�g����L�ɂ��܂��B �@�ł�����A���Z�b�g�������ɂ͑S���̏o�͂�L��LED�͓_�������A���͒[�q��H�ɂ��Ă������ƂŃN���b�N�M���������������[�̋L����H��H���ǂݍ��܂ꂻ�̏o��(QA)��H�ɂȂ�̂�LED����_���B���ɃN���b�N�M�������͂������ꂪ�P�ׂɎn����Q�ڂ�LED���_������Ƌ��ɓ��͒[�q��H�̂܂܂Ȃ̂Œ[��LED�͂�͂�_���ō��vLED���Q�_���A�����悤�ɂ������N���b�N�M���������LED���R�_������悤�ɂ��܂��B �@�����āA�S��ڂ̃N���b�N�M��������S�ڂ̏o��(QD)��H�ɂȂ鎖�𗘗p���Ă�������Z�b�g�M���ɂ��ăV�t�g���W�X�^�����Z�b�g���Ă��u�S��ڂ̃X�C�b�`����Ń��Z�b�g�v�Ƃ�����H�ɂȂ�܂��B �@�c�O�Ȃ���74HC164�̃��Z�b�g�[�q��Low �A�N�e�B�u�Ȃ̂�L�M���Ń��Z�b�g����邽�߁AQD�̏o��H�Ń��Z�b�g����ɂ��_�����]�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�ŏ���IC�������炷���߂Ƀg�����W�X�^��łƂ��l���܂������A74HC164�̃N���b�N���͒[�q���ϓ�����M���Ɏア���ߐM���𐮌`���Ă��Ȃ��ƌ�������쓮���邽�߁A�X�C�b�`���͕����V���~�b�g�Q�[�g���K�v�ɂȂ����̂ł����"���ł�"���p���邱�Ƃɂ��ăV���~�b�gNAND�Q�[�gIC�� 74HC132�̃Q�[�g�̂����̂P���g�p���Ĕ��]�����܂��B �@�ŁA�������܂����悤��74HC164�̃N���b�N�[�q�͂Ȃ��炩�ȓd���ω��ł͌�쓮���Ĉ�u�ŃJ�E���g�����x���J��Ԃ��Ă��܂��̂ŁA�X�C�b�`���������M���̓R���f���T�ƒ�R�̃`���^�����O�h�~��H��74HC132�̃V���~�b�g�Q�[�g���o���Y��ȃf�W�^���M���ɐ��`���Ă���74HC164�̃N���b�N�ɗ^���āu�J�E���g�����i�߂Ȃ����v�Ƃ����M���Ƃ��܂��B �@�{���Ȃ�V�t�g���W�X�^IC��������ōς܂����������̂ł����A�X�C�b�`�����������̕s����ȓd�C�M���Ő��m�ɃJ�E���g��������悤�ȉ�H�ł͂��̂悤�ȓ��͐M���̔g�`���`��H�͂����̂Ȃ̂ŁA�����IC���Q�g�p���Ă��܂��܂��B �@�d���͏��^�����邽�߂ɃR�C���^���`�E���d�r��CR2016�܂���CR2032�����3V�ł��B������CR2016/2032�p�̓d�r�z���_�[���d�q���i�X�ł͔����Ă��܂��B �@�g�pIC��74HC�n�͓d���d����2V�`6V�œ��삷�邽�߁A���`�E���R�C���d�r���3V�ł�����ɓ��삵�܂��B �@LED��S�������Ă���ꍇ�A74HC�V���[�Y��C-MOS IC���Q�Ȃ琔�\�}�C�N���A���y�A���x�����d��������܂���̂ŁA�d���X�C�b�`�͗v��Ȃ����炢�ł��B�ł��ꉞ�͉�H�}���ɂ͕t���Ă����܂����B �@���ʂ�DIP�T�C�Y��IC���g���č��Ɗ�T�C�Y��2.5cm�~4cm���炢�ł��傤�B(�d�r�{�b�N�X�͊���ʑ���) �@�\�ʎ������i���g����2cm�~3cm�ȉ����x�ɂł��邩������܂���B�r���v���炢�̑傫���Ɏ��܂�܂����`�b�v���i�ȂǓ���ȕ��i���g���̂őg�ݗ��ċZ�p�����̂�������ƂɂȂ�܂��B �@�`���ŏ������悤�ɁAPIC�}�C�R���ō��Ή��̉�H�}�ɂ悤�ɂW�s���̃}�C�R����ōς݂܂��B  �@�������\�ʎ����p�̃t���b�g�p�b�P�[�W��PIC�}�C�R�����g���X�ɔ������炢�ɂ͏��^���ł��܂����E�E�E�B �@PIC�}�C�R�������g�p����ꍇ�ɂ͕����I�ȕ��i�̐���K�͂������ւ����ł��܂����A���̔��ʂ���]�̓�����v���O�������Ȃ���Ή��������܂���B �@������̃R�[�i�[�ł�PIC�}�C�R���̃v���O�����Ȃǂ͒��Ȃ����j�Ȃ̂ł��������܂Œ����^�����ꂽ���ꍇ�ɂ̓}�C�R���v���O�����̕������Ă��������B �@�ŋ߂̓��W�b�NIC�ʼn�H�������e��̏��^�}�C�R���`�b�v���g���ĖړI����������ق����������E�����ł���ꍇ�̂ق��������ł���B ���Ԏ� 2010/11/21
|
||
| ���e 11/26 |
�������Ԏ��������������肪�Ƃ��������܂��B�Ȃ�Ƃ�����ł������ł��B�������APIC�Ȃ���̂��g���ƕ��i�������ɂȂ�̂ł��ˁB�����ł��B����ɁA�������v���O�������K�v�Ƃ̂��ƁB���͓I�ł͂���܂����A�n�[�h�����������B�ꂩ�������ƂȂ�Ǝ��Ԃ��B��x�{���Ă���l���܂��B����������A���e�����Ă��������܂��B�ł́A������Ă݂܂��B river2924 �l
|
||
| ���~���^�̓d����H | |||
|
�܂������b�ɂȂ�܂��B �Ԃ�DC12V�o�b�e���[�������I��DC12V�����H�������Ă��������B �����ł̓o�b�e���[�d���́A10.4�u�`14.4�u�Ƃ��Ȃ蕝������܂��B �o�͓d����5A�A���Ŏ��o�������ł��B �����A�������~�����ł����H���K�v�Ǝv���܂��B �ł��邾���d�C�ʂɂ������Ȃ��̂ŁA�����̗ǂ���H����]�������܂��B ��낵�����肢���܂��B ���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���̗p���ł͏��~���^��DC/DC�R���o�[�^���K�v�ł��ˁB
�@5A������R�C�����������킹������܂��B �@�ȑO�̂�����̍ۂɁA���̒������̂����ǂ��f�o�C�X�Ȃǂ����T���ɂȂ�ꂽ���т̂�����ł����A���~���^��DC/DC�R���o�[�^�pIC�Ȃǂ��ǂ��i�������Ă���������p�ɂȂ��鎖�͉\�ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2010/11/12
|
||
| ���e 11/18 |
�������܊Ǘ��l�l�����玸�炵�܂��B�g�����Ɛ\���܂��B ���Ȃ��݂�DC�R��IC�ł���MC34063�̃A�v���P�[�V�����m�[�gAN954�ɏ��~���^�̉��p�v������܂��B 7.5�`14.5V�����͂ŁA10V/120mA�̏o�͂ł��B 2�X�C�b�`�����̏��~���^�C�v�ŁA���[�X�C�b�`��IC������Tr�ŒS���Ă��܂��B ������Q�l�Ƀn�C�T�C�h��PNP�A���[�T�C�h��NPN�Ƃ��O�t����15A���̃g�����W�X�^���g�p���ăR�C����10A���̕���p�ӂ��Đv����Ƃł������ł����B �`�������W���Ă݂Ă��������B AN954��MOTOROLA�Ō�������ƎG���g�����W�X�^�Z�p2007�N11�����̘A�ڋL�����q�b�g���܂��BWEB���{�Ō����̂�2�y�[�W�݂̂Ȃ̂Ő}���ق�����Ŏc������ׂ�ƎQ�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B �g���� �l
|
||
| ���e 11/20 |
�����X�����܂���B �����Ԃ̃o�b�e��������肵��12V��ׂ̓d�����ǂ���낤���A�U�X�Y��������܂����B �g���� �l���Љ��AN954�̏��~���^�̉�H�ɂ͋C���t���Ă��܂������E�E�E ����ȃg���b�L�[�ȉ�H���Ȃ��Ă��A�����^��H��L��1��2�ʂ̃g�����X�ɒu������������̂ł́E�E�E�Ƃ����\�z�����͕`���Ă����Ƃ���ł����B (���ۂɐ���ɂ͎����Ă��܂���B���܂��߂ɐv����ƂȂ�����A�g�����X�̓R�C���ȏ�ɖ����Ŏ�ɕ����܂���(��) �P�Ȃ鈫�Y���x���Ȃ��ꂽ�X�C�b�`���O�d���̃g�����X���������āE�E�E�ȂǂƂ��v���Ă͂���̂ł����E�E�E) jr7cwk �l
|
||
| �Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H | |||
|
��낵�����肢�������܂��B ���̓d���i�Ⴆ�T�X�j���펞�ʓd���Ă����H������A���̉�H�Ɉ��ȏ�̓d�����ʓd�����ꍇ�ɃX�C�b�`ON�ɂȂ��H����肽���̂ł�����w�����������B �f�̑f�l �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���܂�ɂ��������ς����āA���ł��܂���B �@���̓��e������]�̐��l�Ȃǂł��w�肭�������B (1) ���͓d���͖{����5V�Ȃ̂��H �@�u�Ⴆ�T�X�v(V[�{���g]�ł͂Ȃ��X[�t�@�C�u]�Ȃ͉̂����Ӗ�������̂ł��傤���H)�Ə�����Ă��܂����A����͂����܂Łu���Ƃ��v�ł���A�ォ��u����12V�ł������������v�Ƃ��u3�`20V�Ŏ��R�ɒ��߂������v�ȂǁA������H�}�ł͑Ή��ł��Ȃ��悤�ȓd���l�������o���Ƃ������͂���܂��H �@�{���͉�V�œ��삷��̂��������Ɣ��f�������̂ł����H (2) �d���͉��H �@���̌��m��H�̓d���͂��́u���Ƃ���5V�v�������Ă����̂��A�ʂɒP�Ƃɓd����p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����H �@���̓_�ł��ォ��u����12V�ł����v�Ȃ�Č����o�����Ƃ����ւ�̂ŁA��ɐ������d���̎����Ɠd���d�������߂Ă��������B (3) ���d���ȏ�Ƃ́H �@���d���Ƃ͉ʂ����Ăǂ̂��炢�ł��傤���H �@�u���Ƃ���5V�v�ƌ�����ƁA�{�PV��6V���炢�ł����̂��A�{�TV��10V���炢�܂ł͌��o�������̂��E�E�E�B �@����͂ǂ̒��x�̕ϓ��܂ł����Ƃ��āA���m�����d���ȏ�ōő�͉�V���x�܂ł̓d����������̂����悭�l���ċ����Ă��������B (4) �X�C�b�`ON�Ƃ́H �@�u�X�C�b�`�v�Ƃ����̂́A�ǂ�Ŏ��̒ʂ�u�X�C�b�`�v�Ȃ̂ł����H �@�܂胊���[�̂悤�ȕ����g���Đړ_�o�͂ɂ������Ƃ����Ӗ��ł����H �@���̏ꍇ�ɐړ_�e�ʂ́H �@���̐ړ_�ʼn��𑀍삵�����̂ł����H �@����Ƃ��A�d�q�I�Ƀg�����W�X�^�̃I�[�v���R���N�^�o�͂̂悤�Ȍ`������]�ł����H �@�Œ�ł���L��(1)�`(4)�̓��e���킩��Ȃ��ƁA�������邱�Ƃ��ł��܂���B �@�t�ɉ�������Ȃ��܂܁A0�`30V���x�łǂ�ȓd���ł����삷���H�͂������ł����H �@�������d���͂��́u�Ⴆ�T�X�v�Ƃ������͂𗬗p����̂ł͂Ȃ��A���蓮��̂��߂ɕʓr�d����H��K�v�Ƃ���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/10/27
|
||
| ���e |
�O�������ςȎ���Ő\���������܂���ł����B �@�A�P�Q�{���g�o�b�e���[��ɂQ�Ȃ����o�͂Q�S�{���g�d���ł��B�g���b�N�ԗ� �B������e�F�h�A�J���x�������v������h�A���J���Ă��鎞��2.5�{���g�œ_���@�h�A�����Ă��鎞��24�{���g�œ_������x�������v��H������܂��B �B��L�̓d�����𗘗p���ĉ����u�U�[�i�x�����j���������H����肽���Ǝv���Ă���܂��B�i24�{���g�������j �X�������肢���܂��B �f�̑f�l �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����ς�E�E�E�S�R5V�Ƃ͊W�����ł���ˁB �@����5V�p�̉�H����Ă�����A24V�ł͎g���܂���S�����Ӗ��Ȃ��̂ɂȂ��Ă����ł��傤�B �E�h�A���J���Ă��鎞��2.5�{���g�œ_�� �E�h�A�����Ă��鎞��24�{���g�œ_�� �@�Ƃ���܂����A�ǂ���ł��_���Ȃ�ł����H �@����́A�����̓_����H�̓��͒[�q�̓d���ł����āA�����v�ɂ�����d���ł͖����Ƃ������Ƃł����H �E24�{���g�������A�����u�U�[��炷 �@�Ƃ����̂ł���A�P����24V��DC24V�����[�����ă����[�ړ_��ON/OFF����悤�Ȃ��̂ł͂����Ȃ��̂ł��傤���H �@���Ƃ��́A����2.5V/24V����ւ��M���������炩�̃f�W�^����H�̐M���d���ŁA�����[�̃R�C���Ȃǂ��쓮���邾���̓d�������Ȃ��Ƃ����悤�ȐM�����Ȃ̂ł��傤���H �@������d���肷��d�q��H���K�v�ŁA�d�q��H����ă����[���쓮���Ȃ��Ƃ���2.5V/24V���o�͂��Ă����H������Ƃ��H �@���̂�������ڂ������������������B �@�ʓ|�ȓd�q��H�ȂK�v�Ȃ��ꏊ�ɓd�q��H����Ă����_�ł���ˁB�{���ɕK�v�Ȃ�d�q��H�ō��Ȃ���Ȃ�܂��A�s�v�Ȃ炻��ɉz�������Ƃ͂���܂���B ���Ԏ� 2010/11/9
|
||
| ���e |
���Ԏ��L��������܂��B�����v�̉�H�ŏ\���ȓd��������悤�ł��̂ŁA24�������[�ŖړI�B���������Ǝv���܂��B�����f�W�^����H�Ȃǂœd�������Ȃ��ꍇ�͂ǂ̂悤�ȕ��@���l������̂ł��傤���H�B�X�������肢���܂��B �f�̑f�l �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����A24V�̃f�W�^����H�Ȃ�Ă��肦�Ȃ��̂ŁA���݂��Ȃ����̂ɑ��ĉ�H�}����Ă��E�E�E�Ƃ�������������ł������A���̖Z���������ɂ���������������܂����E�E�E�B �@�������Ȃ������g���̋@�킪������������ȑ��u�ŁA��Ƀ����[�Ȃǂł͉��Ă��܂��悤�ȑ��u�Ȃ�ǂ��̃��[�J�[�̉��Ƃ����@��Ȃ̂��A���ꂪ�ǂ������d�l�Ȃ̂��������������������킯�ł����A�����������͖����ł����B  �@�f���āA�����[��ŗǂ������̉�H�̂悤�Ȃ̂ł���������߂����킯�ł����A�Ȃ�Ƃ��Ă��d�q��H�̉�H�}��m��Ȃ��Ɓc�Ƃ����̂��ړI�̕��Ȃ̂ŁA����ȏ�ׂ͍��Ȑ��������Ă����_�ł��ˁB
�@�f���āA�����[��ŗǂ������̉�H�̂悤�Ȃ̂ł���������߂����킯�ł����A�Ȃ�Ƃ��Ă��d�q��H�̉�H�}��m��Ȃ��Ɓc�Ƃ����̂��ړI�̕��Ȃ̂ŁA����ȏ�ׂ͍��Ȑ��������Ă����_�ł��ˁB�@�͂��A���ꂪ��H�}�ł��B ���Ԏ� 2010/11/27
|
||
| ���e 12/9 |
���L��������܂��B �����Z���̒��I�O��Ȏ���Ő\�������܂���ł����B ����Ƃ��X�������肢�������܂��B �f�̑f�l �l
|
||
| ���W�I�ɊO�����͂����� | |||
|
�����y�����q�����Ă��܂��B �܂��A�����VVVF�p���[�p�b�N�̌��ŃA�h�o�C�X�������������肪�Ƃ��������܂����B��킵�Ă��܂����������v���O������g�ݎn�߂Ă��܂��B ���āA����͑S���ʂ̘b��ł����A����80�N��̎Ԃɏ���Ă��܂���FM���W�I�������Ă��܂���B�ȑO��MD�����Ă����̂ł����f�U�C�������킸�ɊO���Ă��܂��܂����B�ŋ߂�FM�g�����X�~�b�^�[������ނ��g���Ă݂܂������������Ȃ舫����߂܂����B���������Ƃ���FM���W�I���������ĊO�����͂�t������Ƃ����������̂ł����A�l�b�g�������炳�����Ă����@�܂Ō�����܂���BFM���W�I�̂ǂ��ɂǂ�ȉ�H��t����Ɖ������͂ł���̂��A�A�h�o�C�X���������܂���?���W�I�̕����ƃA���v�̊Ԃɂ����Ηǂ��̂ł��傤����������̂�������ł��B��͂�v���Ɉ˗����邵���Ȃ��̂ł��傤���c�B �悵���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@����́E�E�E�A�����m���Ă���l�ł�����܂�ɂ�����܂������Ă��������L���ɂ������������肷��悤�Ȏ��ł͖����ł�����A�l�b�g��T���Ă��o�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���ꂩ�A�����悤�Ȏ������ăl�b�g�ɋL�^���ڂ��Ă��Ă��uFM���W�I�ɊO�����͂�t����v�̂悤�Ȓ��ړI�ȒP��ł͒N�������Ă��Ȃ����̂ǂ��炩�ł��傤�ˁB >���W�I�̕����ƃA���v�̊Ԃɂ����Ηǂ��̂ł��傤����������̂�������ł� �@���ꂪ�������Ă���A�ȒP�Șb�Ȃ̂ł��B �@���t�ł́u���W�I�̕����ƃA���v�̊ԂɁv�Ɨ����ł��Ă���̂ɁA�����̃��W�I�̒��łǂ���G�����炢���̂����킩��Ȃ��Ƃ������ł��ˁB �@�d�q���N�ł���A�����Ă��́u�`�l�E�S��(�g�����W�X�^)���W�I�L�b�g�v�̂悤�ȃ��W�I��g�ݗ��Ă���������A���W�I�̂����݂�W�I�̒��ʼn�H���ǂ��Ȃ��Ă���̂��A�܂����ʒ��߂̂����݂��܂߂ĉ����M�����ǂ��`����Ă���̂������W�I�̑g�ݗ��ĂȂǂŊw�K���Ă���͂��ł��B �@���W�I�łȂ��Ă��A�A���v�≽�炩�̉��̏o���H��g�ݗ��ĂĂ��Ă������悤�Ȃ��̂ł��ˁB �@�e���r��W�I�ɂ��Ă���u�{�����[���v���ƂȂ����ʂ��ς�邩���l�������Ƃ͂���ł��傤���H �@�{�����[���̓c�}�~������A���ɂ���Ă̓X���C�h��������Ɛl�Ԃ��������ƒ�R�l�̕ς���R�ł��ˁB �@��R�l��ς���Ɠd�C�̗�������ς��̂ŁA�d�C�𗬂�ɂ�������Ɖ��ʂ��������Ȃ�A�d�C�����������悤�ɂ���Ɖ��ʂ��傫���Ȃ�ƍl�����܂��B �@�����ł悭���S�҂̕����ԈႤ�̂́A�u�{�����[���̓A���v�̏o�͂ƃX�s�[�J�[�̊Ԃɓ����Ă����v�ƍl���Ă��܂��̂ł��B �@�X�s�[�J�[�ɗ����d�C���{�����[���Œ���(����)���Ă���ƁB �@�m���ɃI�[�f�B�I�̐��E�ɂ́u�A�b�e�l�[�^�[�v�Ƃ����X�s�[�J�[�̒��ɓ����{�����[�������݂��܂��B �@�ł��A�X�s�[�J�[��炷���߂̓d�C�͂��Ȃ�傫���A������R�Ő������悤�Ƃ���Ƃ��̒�R�̕����ł̔��M�Ȃǂ������Ȃ�A��d�͂ɑς�����悤�ȑ�^�̉ϒ�R���K�v�ɂȂ�܂��B���ꂪ�I�[�f�B�I�p�ł̓A�b�e�l�[�^�[�ƌĂ�镔�i�ł��B �@�܂��A�X�s�[�J�[�̕����ɒ�R�𑫂��ĉ�������������ɂ́A�A���v�̓X�s�[�J�[�ƒ�R�̗����ɓd���𗬂����������Ȃ���Ȃ炸�A���ʂȓd�͂�����Ă��܂��Ƌ��ɑ傫�ȃp���[�A���v�ł͔��M���H�ւ̕��S���傫���Ȃ�������Z���Ȃ�܂��B �@���S�҂̕��͈�炢�̓A���v�ƃX�s�[�J�[�̊ԂɃ{�����[��(���ʂ�10K���Ƃ�)��ɓ���āA�u�{�����[����������Ɖ����őS�������o�Ȃ��Ȃ�I�v�Ƃ����g���u�����N���������Ƃ�����Ǝv���܂��B(�ߋ��̎��Ⓤ�e�ɂ�����܂�����) �@�C���s�[�_���X(��R�l)���S�`16�����x�̕��ʂ̃X�s�[�J�[�ƒ����10K���Ȃ�đ傫�Ȓ�R����ꂽ��d�����قƂ�Ǘ���Ȃ��Ȃ��āA�X�s�[�J�[���特���o�Ȃ��Ȃ�̂͂�����܂��ł���ˁB�ł����ꂪ������܂��ƋC�Â��ɂ͈�x���炢���s���Ă���łȂ��ƁE�E�E�B 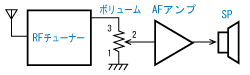 �@���āA�O�u���������Ȃ�܂������A���ۂ̃��W�I��e��I�[�f�B�I�ł́u�{�����[���v�̓X�s�[�J�[��炷���߂������A���v(AF�A���v)�̓����ɂ��Ă��܂��B
�@���āA�O�u���������Ȃ�܂������A���ۂ̃��W�I��e��I�[�f�B�I�ł́u�{�����[���v�̓X�s�[�J�[��炷���߂������A���v(AF�A���v)�̓����ɂ��Ă��܂��B�@�������A���͂ɒ���ɒ�R������̂ł͂Ȃ��A�}�̂悤�Ƀ��W�I�Ȃ�`���[�i�[��H�̉����M���o�͂��{�����[���̒�R���������ĉ����A���v�ւ̓��͓d���߂��邵���݂ł��B �@�{�����[�����E(3��)�ɉƃ`���[�i�[���̉�H�̉����o�͓d���ɋ߂��傫�ȓd�C�M�����A���v�̓��͂ɓ���A�A���v�̏o�͂͑傫���Ȃ��ăX�s�[�J�[��傫�ȉ��Ŗ炵�܂��B �@�t�Ƀ{�����[������(1��)�ɉƃA���v�ɓ��͂���鉹���M���d���̓{�����[���̒�R���������ꂽ�����ȓd���ƂȂ�A�A���v�̏o�͓d�����������Ȃ��ăX�s�[�J�[����o�鉹�͏������Ȃ�܂��B������(1��)�ɉ����Ă��܂���GND�d��(0V)�ɂȂ�A�����M���͂܂������`���܂���̂ŃX�s�[�J�[������S�������o�Ȃ��Ȃ�܂��B �@�����`���[�i�[���̉����o�͂ƃA���v�̓��͊Ԃ������Ƀ{�����[�������邾�����ƁA�{�����[���̒�R�l���������傫�����Ă����Ȃ��d���ł����K���d���͗����̂Ń{�����[�����������ς��ɉĂ����ʂ͂O�ɂ͂Ȃ炸�ɁA��ɉ��ŏo������Ƃ������ʒ��߂Ƃ��Ă͂��܂�悭�Ȃ����̂ɂȂ�ł��傤�B�����番�����Ďg�p����̂ł��B �� �A���v�̓��͂Ƀ{�����[���͂��Ă��� �� �{�����[���ɓ����d�����A���̉����M���ł��� �@�Ƃ����������m���Ă���A�ǂ�ȃA���v�ł����̃{�����[���̓��͂ɂȂ�����ς��邾���ł��̃A���v�ɓ��͂��������M���ŃX�s�[�J�[���特���o�����Ƃ͂ł��܂��B 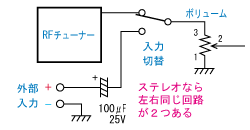 �@���ꂳ���m���Ă���A�{�����[�������Ă��郉�W�I�ł��e���r�ł��A���ꂱ���I�[�f�B�I�p�̃A���v���̂��̂ł��A�{�����[���̈ʒu�������ׂ�����̓��͂ɃX�C�b�`�Ȃ�Ȃ�Ȃ��lj����āA�ʂ̓��͒[�q�E�z���ƂȂ��ł��Εʂ̋@�킩��̉������X�s�[�J�[����炷���Ƃ��ł��܂��B
�@���ꂳ���m���Ă���A�{�����[�������Ă��郉�W�I�ł��e���r�ł��A���ꂱ���I�[�f�B�I�p�̃A���v���̂��̂ł��A�{�����[���̈ʒu�������ׂ�����̓��͂ɃX�C�b�`�Ȃ�Ȃ�Ȃ��lj����āA�ʂ̓��͒[�q�E�z���ƂȂ��ł��Εʂ̋@�킩��̉������X�s�[�J�[����炷���Ƃ��ł��܂��B�@�I�[�f�B�I�p�A���v(AF�A���v)�Ƒ��̐M�������Ȃ����ɂ͓d�C�I�Ȗ��Łu�J�b�v�����O(����)�p�R���f���T�v�Ƃ����p�r�œd���R���f���T���P���݂܂��B �@���ʂ̓A���v��H�̂ق��ɓ����Ă���̂ŕʓr�p�ӂ���K�v�������͂��Ȃ̂ł����A���W�I�Ȃǂ̒��̉�H�ł̓`���[�i�[���̉�H���ɂ��������@�\���ʂ������i�������Ă��āA�A���v���ɂ͓����Ă��Ȃ��ꍇ���l������̂œd���R���f���T�����(�X�e���I�Ȃ�L/R�łQ��)����Ă����ƈ��S�ł��B �� �d���R���f���T�̋ɐ�(+/-)���A�A���v��H�̎��ۂ̉�H�ɂ���ċt�̏ꍇ������܂��B�S�z�ȕ��̓I�[�f�B�I�p�u���ɐ��d���R���f���T�v���g�p���Ă��������B �@������O�����͒[�q�������āA������X�C�b�`�ŕ�����ւ���悤�ɓ��݂͂���悤�ȏꍇ�ɂ̓R���f���T��lj�����K�v�͂���܂���B�O�����͒[�q������Ƃ������͌���������ɂ��Ă���̂ł�����B �@80�N��̎ԂŁA����ɂ��Ă������W�I�Ȃ�{�����[�����c�}�~�������ĉ�]�܂��̓X���C�h�����ĉ��ʒ��߂�����̂ł��傤����A����̍l�����ʼn����ł���͂��ł��B �@�ŋ߂̃I�[�f�B�I�ł͉��ʂ�UP/DOWN�{�^���������Ē��߂���悤�ȁu�d�q�{�����[���v�̂��̂������A���������{�����[�����d�q������Ă�����̂ł͂��̒ʂ�̕��i�Ƃ��Ắu�{�����[���v��T���Ẳ����͂ł��܂���B �@�{�����[�����̂�IC��LSI�̒��ɉB��Ă��܂��Ă��܂��̂ŁA�����M���̗���Ă����H�ׂĂǂ�����Ăǂ��Ɍq�������̂�����͂ł�����m���̂���l�łȂ��Ƃ��Ȃ����ł��傤�B �@�ƂĂ����x��IC�ELSI�����ꂽ�I�[�f�B�I(���ɍŋ߂̃f�W�^���I�[�f�B�I�@��)�ł͂قڑS����IC�ELSI�̒��ɓ����Ă��܂��Ă��āA�A���v�܂œ������ꂽ��pIC�ELSI���ŃA�i���O�M���ŊO���ɏo�Ă��Ȃ��悤�ȏꍇ������܂��B �@����̎�@���g����͉̂�]����X���C�h���̋@�B�I�ȃ{�����[�����g�p�����A�A�i���O�I�ȉ�H�\���̃I�[�f�B�I���u�݂̂ł��B �@�܂��A�{�����ł͐G��܂���ł������A�{�����[���̓��͐M���̓d���́u�������C��(LINE)�M���v�ƌĂ�邠����x���܂����d���͈݂͂̂ł��B �@�}�C�N���͂Ȃǂł͓d�����ƂĂ��������̂ł���ɂ��킹�����͓d���ɂ���K�v��A�t�Ƀ}�C�N�ʂ̃A���v�ɐڑ�����Ȃ�u�}�C�N�A���v�v�ƌĂ��}�C�N�̔����ȐM�������C��(LINE)�M�����x���ɑ�������A���v���ʓr�K�v�ɂȂ�܂��B �@mp3�v���[���[�Ȃǂ́u�w�b�h�t�H���o�́v�̐M���d���̓��C��(LINE)���x���ɋ߂��̂ł��̂܂܂Ȃ��ł��قڑ��v�ł��B �� ���̘b�͑S�Ĉ�ʓI�ȃ��W�I�E�I�[�f�B�I���u�̏ꍇ�ŁA����ȉ�H�E�\���ɂȂ��Ă��鐻�i�͏����܂� ���Ԏ� 2010/10/7
|
||
| ���e |
�����������Ă�����Ă܂��B �Ԃł͂Ȃ��̂ł����q�����g���Ă��郉�W�J�Z�ŊO�����͂��Ȃ���������������߂����Ƃ�����܂����B���̂Ƃ��ɂ��̏��������Ă���E�E�E(^_^;) >�� �d���R���f���T�̋ɐ�(+/-)���A�A���v��H�̎��ۂ̉�H�ɂ���ċt�̏ꍇ������܂��B�S�z�ȕ��̓I�[�f�B�I�p�u���ɐ��d���R���f���T�v���g�p���Ă��������B �����̕��������m�F�����Ă��������B�ʏ�̓d���R���f���T��2�t�ɐڑ�����Ɩ��ɐ��R���f���T�Ƃ��Ďg����Ɖ������Ō����C������̂ł����A����ő��v�ł��傤���H�e�ʂ͔����ɂȂ��Ă��܂��܂����ǁE�E�E ���܁[��i�f�l�j �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�͂��A�ʂɕ��ʂ̗L�ɐ��d���R���f���T���Q�A�ɐ����t�����ɒ���ɂȂ��ł����܂��܂���B �@�L�ɐ��R���f���T�ɐ��Ŏg�����߂ɃR���f���T�Q�A�X�e���I�ł͂S�g���Ȃ�A�ŋ߂ł͕ʂɓ��荢��⍂�����i�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���̂Ŗ��ɐ��R���f���T�̂ق����lj����J���^���ŗǂ����Ǝv���܂��āB �@���ʂ͓��͒[�q�ɐڑ�����I�[�f�B�I�Đ��@�푤�̃w�b�h�t�H���[�q�̒��ɂ��d���R���f���T�͓����Ă���͂��Ȃ̂ŁA�{���ɉ����̎��̂��߂̗\���Ƃ����������ł��B ���Ԏ� 2010/10/9
|
||
| ���e 10/13 |
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �ŋ߂͕��ʂɎ�ɓ���̂ł��ˁB���炵�܂����B�܂��͎茳�ɂ���p�[�c�łȂ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����ȁH�Ǝv���Ċm�F�����Ă��������܂����B(^^�U �i�������ɐ��f���鎩�M���Ȃ��Ƃ����̂��傫�ȗv���ł����E�E�E�j �O�o�̃��W�J�Z���ŋ߂߂����Ɏg���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���悤�Ȃ̂ŁA�N���N�n�Ƃ��܂Ƃ܂��Ď��Ԃ̎���Ƃ��ɂ�����ē��͒[�q�����t���Ă݂܂��B(^^�� ���܁[��i�f�l�j �l
|
||
| ���e 11/5 |
�悵�����ł��B���Ԏ����x���Ȃ�܂��Đ\�������܂���B�������M�̃��[�������������Ă����̂ł����A�u���e�m�F���[���v���Ɗ��Ⴂ���A���Ԏ���҂��Ă����̂ł����A��قǃ��[�����悭������u���J���܂����v�Ə����Ă������̂ŃA�N�Z�X���Ă݂�Ɓc�B�܂�������Ȃɑ���������������Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂ł��݂܂���ł����B ���āA���W�I�ɊO�����͂�t���錏�A��Ϗڂ���������Ă����������肪�Ƃ��������܂����B�f�l�̎��ł��\�������ł�����e�ł����B�{���E���̈ʒu�Ȃ�ȒP�Ɍ�������Ǝv���܂��B���Ƃ͂��̒[�q�����ăX�e���I���E�f���Čq�����߂Ηǂ��ƌ������Ƃł���ˁB��ϕ��ɂȂ�܂����B �Ђ���Ƃ�����ŋ߂̓d�q�{���E���̃I�[�f�B�I�����̎�@�Łc�Ɨ~���������̂ł����A�����܂ł����J�ɉ�����Ă��������Ċ����ł��B�����������W�I����������o���ăg���C���Ă݂����Ǝv���܂��B���������̂悤�ȊȒP�Ȍ����Ȃ̂ɋƎ҂ɂ��肢����Ɛ����~�����Ƃ́c�B������ɂ��Ă��{���ɎQ�l�ɂȂ�܂����B�Ȃ�Ƃ����\���グ�ėǂ��̂�������܂��A��������̂悤�Ȋ����𑱂��Ă���������Ƒ�ς��ꂵ���ł��B �悵���� �l
|
||
| ���p�ݑ�\�������v | |||
|
�͂��߂܂��āB���̍Ȃ͎��ƂŐg���̉������Ă���܂��āA�ݑ�ƕs�݂��P�K����Q�K�։���LED�ł��m�点�ł�����̂��Ȃ�������H�Ƃ����ƍȂ̗v�]�ŒT���Ă�����A������̃z�[���y�[�W�ɏo��܂����B ���[�����^���X�C�b�`���u�ݑ�v�Ɓu�s�݁v�p�ɂQ�ݒu���āA�ݑ�̎��ɂP�K�ʼn����{�^���������ƁA�u�|�[���ƒႢ�����P���Ɠ����ɁA�ԐF�_������F�_�Łi0.5�b�Ԋu�j�ɕς��Q��s�J�s�J�Ɠ_�Ō�ɐF�_���v���ĊO�o���鎞�ɕs�ݗp�����{�^���������ƁA�u�P���Ɠ����ɁA�F�_������ԐF�_�łɕς��3��_�Ō�ɐԐF�_���v����B �Q�FLED���g���A�_�ő��x�̓{�����[���Œ����B���̓C���[�W�I�ɔ�s�@�̋@���ē��̑O�ɂȂ�|�[���Ƃ����Ⴂ���ɋ߂��Ɗ������ł��B �{�̂͂Q�K�̕����ɒu���ēd���͂P�Q�u�P�`�X�C�b�`���O�d���i�莝���Ōy���̂Łj���P�O���[�g�����ꂽ�P�K����Q�K�����ɂ������v���܂��B �ǂ̂悤�ȉ�H���l�����܂����H�����Ă��������B�X�������肢�v���܂��B �O���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���������₳���Ă��������B (1) �g�pLED�́H �@�u�ԂƐ̂Q�FLED�v�Ƃ���܂����A�A�m�[�h�R�����ł����H �@����Ƃ��J�\�[�h�R�����ł����H �@�t���ƑS���قȂ�̂ŁA���g���ɂȂ���LED����̓I�ɂǂ��炩���w�肵�Ă��������B (2) �����Ԃւ̍Đݒ�͉\�^�s�\�̂ǂ���H �@���ɁA��x�u�v�̃{�^���������āu�v�̏�ԂɂĂ����鎞�ɁA������x�u�v�̃{�^������������ �@�@(A) �����������Ȃ� �@�@(B) �`���C��������LED���_�ł��� �̂ǂ��炪����]�ł����H �@�u�v�ł��u�ԁv�ł����l�ł����A���K�ɂ�LED�\��������܂���̂ŁA�u�{�^�������������ȁH�v�ƕs���ɂȂ����ꍇ�ɂ܂��{�^���������āA���̎��Ƀ`���C���Ȃǂ����������ق����ǂ��̂��A�����������Ȃ��̂��ǂ��̂���I��ł��������B �@�������A���K�ɂ�LED�\��������u���������ȁH�v�Ƃ������ȕs�����ԈႢ�������ł����A����̂���]�ł͉��K�ɂ̓X�C�b�`���������悤�ł����B �@���K�̃X�C�b�`���v�b�V���X�C�b�`�ł͂Ȃ��g�O���X�C�b�`�ɂ���A���o�[�̓|��Ă�������łǂ���̃��[�h�ɂȂ��Ă��邩�͈�ڗđR�ŊԈႢ�͖����Ǝv���܂����A�v�b�V���X�C�b�`�ł�����LED�\���������Ƃ����Ɖ����Y��ɂ��ԈႢ���������܂���B ���Ԏ� 2010/9/28
|
||
| ���e |
���Ԏ��ɂ���Ă����肪�Ƃ��������܂��B�ȂƋ��Ɋ��ł���܂��B �i�P�j�ɂ��āA�Q�FLED�̓J�\�[�h�R�����@VF:2.0V�i�ԁj,3.4V�i�j@20mA�ł��B �i�Q�j�ɂ��āA�g�O���X�C�b�`�ɕύX�ƃX�C�b�`���Ɋm�F�p�Q�FLED�ƂQ�K�̕\���p�Q�FLED�͂R�ӏ��ɕύX�ŃX�s�[�J�[�̃{�����[�����lj��ł��肢�v���܂��B �Q�K�̕\��LED�͕����̂R���ɒu������Ǝv���A�\�z�̓x�b�g�㕔�̒I�Ɂu�{�̊�Ձ{�X�s�[�J�[�{�\���p�Q�FLED�v�A�{�@�𒆐S�ɍ��E2.5�����ꂽ�Ƃ���ɕ\���p�Q�FLED���P�Âz�u�B �X�s�[�J�[�͎莝���̓d�q�����f�B�[�ɂ悭�g���Ă���A�C���s�[�_���X:8�� ����:1W �������x��:90�}3dB/0.1W ���U���g��:520Hz�}20%@1.0V ���g�������W:f0Hz�`20KHz �T�C�Y:���a��28mm�~������6.3mm��\�肵�Ă܂��B ���̂���Ă������܂����琥���Ă��������B ����������낵�����肢�v���܂��B �O���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�g�O���X�C�b�`��I�ꂽ���ƂŁA���b�`��H���K�v�Ȃ��Ȃ�̂ŏ������i������܂��B �@�X�s�[�J�[�̃{�����[���͍ŏ�������������̂ł��̂ł����S���������B �@LED�����ӏ��ɒu����悤�ɂ��܂��B �@����͎��ۂ̐���ɂ͊W������������܂��A�ƊE�ł͉����Q�Ҍ����̑��u�ł͂Q�FLED�͂��܂�g��Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��B �@�M���@�����Ă���������킩��Ǝv���܂����A�M���@���P����2�F(��/��)��3�F(��/��/��)�ɐF���ς����̂ł��M���F��\������Ƃ����ړI�ɂ����Ă͖��͂���܂���B �@�ł��A�F���F�ӁA���͂̎ア���ɂ͂P���ł͉��F�ɂȂ��Ă���̂��悭�킩��܂���B�܂��X�H�̖�����ɂ܂���Ă��ꂪ�M���Ȃ̂����̏Ɩ���L���Ŕ̌���Ȃ̂�����ʂ����ɂ����Ȃ�܂��B �@�ł�����A�N�����Ă��u�����v���������\�����ŐM���@�ł���`���F���ł��A�����Ă���ʒu�ł��\����Ԃ�F���ł���v�Ƃ����̂��M���@�Ȃǂ�P�ɐF���ς�铔�ł͂Ȃ��A�Ӗ��̈Ⴄ�ʁX�̓������̈Ӗ��������ɓ_������Ƃ������ɍ�闝�R�ł��B �@��ʐM���@�ȊO�ł��H��̋@�B�̏�ԕ\�������v��x���v�A�I�[�f�B�I�@��Ȃǂ̃p�C���b�g�����v�ł��P�ɐF���ς����̂��͌ʂɈӖ��̂��郉���v��ʁX�ɕ��ׂ邱�Ƃ̂ق��������ł��ˁB �@�������Q�F��R�F�ɐF���ς��^�C�v�̕\�������v��X�C�b�`�����̒��ɂ͑�������A���������^�C�v�͂ǂ��炩�Ƃ����ƈ�����P�̂Ŏg���̂ł͂Ȃ��A����ՂȂǂœ����̑���őΏۋ@�킪�����������̃X�C�b�`����ׂĂ��Ă��̂����ǂꂪON�Ȃ̂�OFF�Ȃ̂���A�S���������F(�Ƃ�)�œ_�����Ă����琳��Œ��ɂۂ�ƐF���Ⴄ(�ԂƂ�)�̂��������炻��ُ͈��\���Ă���ƂЂƖڂł킩��悤�ȃX�C�b�`/�����v�z�u�ɂ���ꍇ�Ȃǂɑ����g���܂��B �@�|�[�^�u���@��łP��LED�Łu�[�d���͐ԁv�u�[�d��������Ɨv�Ƃ��������v���悭���܂����A���͐F�ӂɑ����Ƃ���Ă���u�ԗΐF�Ӂv�̕��ɂ͐ԂȂ̂��Ȃ̂������ʂł��Ȃ����߂ɕs�]������������܂��B �@����̂���]�ł͉����Ă��������邲�Ƒ��̕��̖ڂ������͂Ȃ��A�E�Ԃ̐F��e�ՂɎ��ʂł���悤�Ȃ̂ň˗��҂̕��̂��ƒ���ł͂Q�FLED�ł��ǂ��Ƃ͎v���܂����A�������̕��������Q�҂̕��p�̑��u�������ꍇ�ɂ͂Q�FLED���͕ʁX��LED����ׂāA�p�b�ƌ����ڂłǂ���̕\�����_���Ă���̂��킩�����ق��������S�E�e�ł���B �@�����]�k�ɂ���Ă��܂��܂������A��H�}���ł�������܂�����f�ڂ��܂��B���炭���҂����������B ���Ԏ� 2010/9/29
|
||
| ���e |
���e�ɕ\�������v�̐��������肪�Ƃ��������܂��B�M������Ë@��̃����v���ʂɂ���܂����B �g���̉��ŐF�ӂ�㎋�͍��͋C�ɂȂ�܂���ł������A�Q�F�\�����ʕ\���Ȃ�u�ݑ�v�u�s�݁v���x��������܂����m���Ɍ��₷���Ǝv���܂����B �C�����ʏ������w�E���������Ċ������ł��B�u�ݑ�v�u�s�݁v�ʁX��2��LED���g���d�l�ɕύX�����Ă��������B ��낵�����肢�������܂��B �O���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�u�J�\�[�h�R�����v�p�ɉ�H�}�͏����܂��̂ŁA�J�\�[�h�R�����^�C�v�̂Q�FLED���g���邩�A�Q�F�ʁX��LED�����邩�͐���җl�̍H�쎟��ł��B �@�g���ꏊ�〈�Ղ����l���āA�K�X�ǂ���ɂ��邩�͂����R�ɂ����߂��������B �@���T���͔��ɑ��Z�Ȃ̂ŁA��H�}���������肷��̂͗��T�ɂȂ�܂��B���炭���҂����������B ���Ԏ� 2010/10/1
|
||
| ���e 10/5 |
����ɂ��́B���Z���������e�ɑΉ����Ē����܂��Ċ��ӂ��Ă���܂��B �m�l�������悤�Ȋ��Ȃ̂łQ�g����ł��B �O���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@10����葽�Z�ł����ւ҂����������܂����B �@������̉�H�}�ɂȂ�܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�� �X�C�b�`���͂̔���E�ω����o��H �@��K�ɒu�����X�C�b�`����̓��͂́AD1,D2,R5�̕ی��H��ʂ���R6,C5�Ń`���^�����O�������������IC1 74HC86�Ńf�W�^���M���ɐ��`���܂��B �@���`���ꂽ�f�W�^���M���͌����[�s��]����[�ݑ�]��I������M���Ƃ��Ďg�p����ق��A�X�C�b�`��ԕω����o��H�Łu�X�C�b�`����ւ���ꂽ�v���Ƃ����m���܂��B���̐�ւ���ꂽ���Ƃ����m�����M��(�p���X)�̓����v�̓_�ł��J�n����M���ƍ��m����炷�M���Ƃ��Ďg�p���܂��B �� �_�ŗp�N���b�N���U��H �@�����v�̓_�ŃX�s�[�h�����肷�锭�U��H�ł��B �@���Ȃ��݂��^�C�}�[IC 555���g�p���܂��B �@�_�ŃX�s�[�h��VR1�Œ��߂ł��܂��B �@�N���b�N���U�̗l�q��LED1�Ŋm�F�ł��܂��B �@�A���A�N���b�N���U�́u�_�Œ��v�������U���Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ŁA�_�ł��I����ă����v���_�������ςȂ��ɂȂ���Ԃɂ�LED1�͏������܂��BLED1�����ăN���b�N���U��H�����삵�Ă��邩�ǂ�����_�ő��x�߂���͕̂K���X�C�b�`��������ă����v���_�ł��Ă�����Ԃɂ��Ă��������B �@�����ŃN���b�N���U��_�Œ��ȊO�̊��Ԃ͒�~�����Ă����Ȃ��ƁA���U�����ςȂ����ƃX�C�b�`�𑀍삳��ē_�Ŋ��Ԃɓ������Ƃ��̍ŏ��̈�_�ł̓r���ɂȂ邽�߁A�ŏ��̈��̓_�Ŏ��Ԃ�����S������Ă��܂��܂��B�قƂ�Ǔ_�łɌ������Ƀp�b�ƂQ��ڂɐi��ł��܂���������܂���A����ł͂��܂�ɕs�i�D�ł��B �@�����ɂ�555�̔��U�͒�~��Ԃ���J�n�����ꍇ�͍ŏ��̈���ق�̏��������Ȃ�̂ŁA�ƂĂ��ƂĂ������ɔ��U���Ԃ��������E�g�������Ƃ������ɂ͕s�����ȉ�H�ł����A����̗p�r�̂悤�Ƀ����v��_�ł����邽�߂Ȃ�ŏ��̈��͐F����ւ�����u�ԂȂ̂ł킸���Ȏ��Ԃ̈Ⴂ�ɂ͋C�Â��Ȃ����x�ł��傤�B(�X�Ɍ����Ή������Ă͂��߂ă����v�����邭�炢�ŁA�ŏ��̏u�Ԃ͑��u�����Ă��Ȃ����̂ق��������ł��傤����E�E�E) �� �_�ʼn����H �@��[�s��]����[�ݑ�]�̃����v��C�ӂ̉_�ł����A�_�ł��I�������_�������ςȂ��ɂ��邽�߂̉�H�ł��B �@IC2 74HC4017�ŃN���b�N�p���X�̉��J�E���g�^�f�R�[�h���܂��B �@���̏o�͂̂����C�ӂ̉̏o����I�����[�s��]����[�ݑ�]�ł��ꂼ������Ŏ~�߂�̂��𐧌䂵�܂��B �@��H�}�ł͂���]����[�s��]�͂R������[�ݑ�]�͂S���Ƃ��Ă��܂����A�ʂ̉ł��A�ԁE���ɓ����ɐڑ����Ă����܂��܂���B �@��[�s��]�܂�����[�ݑ�]���I�����ꂽ�ɒB�����Ƃ��ɃJ�E���^�[�ƃN���b�N���U��H���~��Ԃɂ��܂��B�܂���~��ԂɂȂ�ƃ����v���_�������ςȂ��Ƃ���M�����o���܂��B �@��x��~��ԂɂȂ�ƁA�X�C�b�`�𑀍삵�ă��Z�b�g�p���X����������܂ł͂��̂܂܂ł��B �@���Z�b�g�����ƃJ�E���g�͂܂��O����J�n����A�w��̒�~�J�E���g�܂ʼn��܂��B �� �ԁE�_�������H �@���ۂɂǂ���̐F�̃����v��_��������̂��A�_�łȂ̂��_�������ςȂ��Ȃ̂��Ȃǂ̏�Ԑ���������H�ł��B �@���͂Ő�������͖̂ʓ|�Ȃ̂ŁA��H�}���̐��䃍�W�b�N�̒��߂��������������B �� LED�h���C�o �@�����LED���E�ʁX�̏ꏊ�œ_�����������Ƃ̎��ł��̂ŁA�g�����W�X�^���g����100mA���x�܂łȂ痬����LED�h���C�o�Ƃ��Ă��܂��BLED2�`5���x�܂œ_���ł��܂��B �� ��s�@�̂悤�ȁu�|�[����v�T�E���h������H �@�莝���̕��i�E�����ɓ���\�ȕ��i�Ŋ��S�ɂ��̉����Č�����͓̂�����߁A�u�����Ȃ��̉��v�̍Č��͒f�O���܂����B �@�����ƐF�X�ƕ��i�𑝂₵����A�����I���i�ł�����s�\�ɂȂ邩�킩��Ȃ�����IC�Ȃǂ��g���Ί����ȍČ����ł���̂ł����A���ꂾ�Ƃ����͍��Ȃ��Ȃ����蕔�i���������Đ������Ԃ������Ȃ�̂ŁA����͂�����x�������Łu�����̃f�W�^�����̂悤�ȋ@�B�I�ȉ��ł͖���������Ƃ����G���K���g�Ȋ��������鉹�v�ł��e�͂��������B �@��s�@�̒��ɔE�э���Łu���̉��v�̉�H�ɃA�N�Z�X���邱�Ƃ͂ł��܂���̂ŁA���܂łɕ���������(�̋L��)��A�f��ȂǂŎg�p����Ă�����ʉ����璲�ׂ�Ɓu���̉��v����500Hz�̃T�C���g(�����g)�ŁA�����G���x���[�v�͖�P�b���O�p�g�ł��B �@�q��@������Ђɂ��Ⴂ���A���ʉ����쌳�̍�҂̈Ⴂ���ɂ����10Hz���x�̃Y���͂���܂��B �@�T�C���g(�����g)�Ȃ̂łƂĂ��������肪�悭�A�Y��ȉ��ɕ������܂��B �@�������O�p�g�ŃX�[���Ə����Ă䂭�����ł��B �@���ۂɕ����Ə����r�u���[�g�����������悤�ɂ��������܂��̂ŁA���̎�̉��Ɍ��݂ƃG���K���g����^���邽�߂ɂق�̏������g���̃Y�������������Ęa���ɂ��Ă���̂�������܂���B (����A�����������邾���Ŗ{���͒P�����������E�E�E) �@�����Ńp�\�R���Łu���̉��v���Ǝv���鉹���M���삵�Ă݂܂����B �@500Hz��SIN�g�ɂ�炬�p��50Hz���������Ă��܂��B �@�ŁA���̉����Y�o���o���H���������̂ł����A��q�̂悤�ɖʓ|�Ȃ̂ł���Ȃ�Ɏ������̏o���H�ł��B �@�c�C���s�^�̈�Δ��i��H���Y���SIN�g�`�U�����܂��B �@���̂܂܂ł͐U�����������̂ň�A���v�ő������Č�Ŏg���₷�����炢�̐M�����x���ɂ��܂��B �@���U���g��(����)��VR2�Œ��߂ł��܂��B �@�����Tr2 2SC1815�Ń~���[�g���Ă���āu�|�[����v�Ƃ��������ɋ߂��`�ɂ��Ă��킯�ŁA���̌����̂��߂̎O�p�g�̓I�y�A���v LM358�́u�m�R�M���g��H�v�Ő������܂��B �@�c��(���Ă���)���Ԃ�VR3�Œ��߂ł��܂��B �@�X�C�b�`����ւ���ꂽ���Ƃ����m�����p���X�M���Ń~���[�g����������A���̃p���X�͈�u�ŏ�����̂ł�������m�R�M���g�Ƃ��ăG���x���[�v�g�`����������܂��B���̓G���x���[�v�M���̓d�����オ��Ə������Ȃ�܂��B(�A��Tr2�̃x�[�X�d��0.6V�t�߂ł̕ω�) �@���i�������Ȃ����Ă���̂ŁA�u�|�[���v�́u�|�v�̕������������������A�Ō�ɃX�[���Ə�����悤�Ȋ����ɕ������܂��B �@��`�g�̌ł������̃f�W�^�����ł͂Ȃ�SIN�g�ŁA���������u�u�[�v�ƃu�c�b�Ə�����̂ł͂Ȃ��X�[���Ə����Ă䂭�̂ňꉞ�́E�E�E����Ȃ�ɁE�E�E�_�炩�������̉��͏o��̂ł����A���S�ɔ�s�@�́u���̉��v�����҂����̂ł���������ƕʂ̉�H�ō��ꂽ�ق��������ł��ˁB �� �����o�̓A���v �@���Ȃ��݂̉����A���vIC LM386N���g�p���ăX�s�[�J�[��炵�܂��B �@����̉�H�ł͋��������d���d����12V�ł��̂ŁA�A���v�̓d���͂����������Ă��傫�ȉ��܂Řc�܂��ɖ炷���Ƃ��ł���悤�ɂ��܂��傤�B �@���ʂ�VR4�Œ��߂ł��܂��B �@C17 1000��F�͕K��LM386�̓d���s���̂��ɕt���Ă��������B �� �d����H �@���W�b�N����5V�œ��삳���܂��̂ŁA���������12V����O�[�q���M�����[�^��5V�����܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@��[�s��]����[�ݑ�]�œ_�ʼn�ʁX�ɂ�������A��s�@�́u���̉��v�̂悤�ȉ�������]�ȂǁA���ꂼ��̂���]�������邽�߂ɂ��Ȃ蕔�i���������Ă��܂��B �@����ɂ͂��イ�Ԃӂ��āA�z���~�X�Ȃǂ������悤�ɂ��Ă��������B �@�g�ݗ��Ăēd��������ƁA�u�|�[����v�Ƃ������Ƌ��Ƀ����v���_�ł��܂��B �@�_�ł��郉���v�̓X�C�b�`�őI�����Ă��鑤�̐F�ŁA�͓d������ꂽ���ɂ̓��Z�b�g���Ă��Ȃ��̂ŕs��(10��ȓ�)�ł��B�����A���X�ɂ���74HC4017�͓d���������ɂ̓��Z�b�g��ԂɂȂ�悤�ŁA�ݒ肵�Ă���_�ł���Ǝ~�܂�悤�ł��B �@�X�C�b�`���ւ����LED2(�ω��m�F)����u�����_�����܂��B �@����Ɠ����Ƀ����v���w��̉_�ł��A���̌�ɓ_���ɕς��܂��B �@�����v���_�ł��Ă���Ԃ�LED1(CLOCK�m�F)���_�ł��Ă��܂��B �@���������v���_�ł��Ȃ��ꍇ�̓N���b�N���U�͍s���Ă��邩��A�����H���ӂ̔z���~�X���������m���߂Ă��������B �@�N���b�N�\�����w��̉_�ł��ď�����̂ɐԁE�̃����v���_�ł��Ȃ��ꍇ�͓_�������H����LED�h���C�o�A������LED�܂��̉�H���m�F���Ă��������B �@�X�C�b�`���ւ���LED2(�ω��m�F)����u�����_��������A�u�|�[����v�ƃT�E���h����܂��B �@������Ȃ�������A�����W�̂ǂ������Ԉ���Ă��܂��B �@���Ƃ��ATr2�̃R���N�^�z����藣���A�~���[�g�͂�����܂���̂ł����ƃX�s�[�J�[����u�|�[�v�Ƃ��������Ŕ��U��������ςȂ��ɂȂ�܂��B �@Tr2�̃R���N�^�z������Ă������o�Ȃ��ꍇ��SIN�g���U��H�����H�A�����A���v�̂ǂ������Ԉ���Ă��܂��B �@�R���N�^�z���������X�s�[�J�[���特���o�āA�ł��X�C�b�`����ł́u�|�[����v�Ɩ�Ȃ��ꍇ�̓I�y�A���v�܂��̔z���~�X�ł��B �@����ɓ��삵���Ȃ�A�eVR�߂��Ă������̂��D�݂̓_�ő��x�≹�ɂ��Ċ��������Ă��������B ���Ԏ� 2010/11/20
|
||
| ���e |
���ݑ�\����H������Ă��������܂��āA���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�|�[���̉����Č��ł������łƂĂ��������ł��B�_�ʼn�C�ӂɐݒ�ł���悤�ɂ��Ă�����������A���o������g�����肪�֗��ɂȂ�悤�l���Ă�����������A���ߍׂ₩�Ȑ����Ȃǂ��C�g���Ɋ��ӂ������܂��B ��H�̕��G���Ɉ��|���Ă���܂����A���i�����X�g�A�b�v���Ĉ���ǂ��Ȃ��琧�쏀����i�߂Ă���Œ��ł��B �������グ�Ă��������C�����ł����ς��ł��B ���쒆�ɕ�����Ȃ������o�Ă��邩�Ǝv���܂��̂ŁA�܂����̎��͋����Ă��������B��낵�����肢�������܂��B �O���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����]���F�X�ƍׂ����̂ŁA�������������ɂ͂���Ȃ�ɕ��i���������A�g�ݗ��Ă���Ԃ���������̂ƂȂ��Ă��܂��B �@�܂��A�������A��������ƍ������Ɗ�������͂��ł�����A�Q�Ă��ɂ悭�m�F���Ȃ����Ƃ�i�߂Ă��������B ���Ԏ� 2010/12/15
|
||
| �J�~��x��u�U�[ | |||
|
�����e�ؒ��J�ȉ���ŕ������Ă��������Ă���܂��B �ŋ߂͓ˑR�̉J�Ȃǂ�����A������̐����݂ō��������Ƃ�����܂����B������100�~�V���b�v�Ŕ����Ă��鑋�̖h�ƃZ���T�[�i���������ƌx��������������j���������ĉJ�Z���T�[�ɂł��Ȃ����ȁH�ƍl���Ă���܂����ȒP�ɉ����ł�����@�͂Ȃ��ł��傤���B�����Ƃ��ẮA ���J�̂�����Z���T�����̓A���~��2���𗼖ʃe�[�v�Ŗh�ƃZ���T�{�̂ɕt����B �����ʂ�ς�����B ���h�ƃZ���T�ɕt���Ă���{�^���d�r3��d���Ƃ���B ���ł���Αҋ@��Ԃ����N���炢�����Ăق����B �h�ƃZ���T�͂����Ȏ�ނ��o�Ă��܂����A���Ɏw��͂���܂���B�i�����炪�������̂�T���܂��B�j ���萔�ł�����낵�����肢���܂��B tenten �l
|
|||
| ���Ԏ� |
 �@�h�ƌx��@�́A100�~�V���b�v�_�C�\�[�Ŕ����Ă���ʐ^�̂��̂��g�p���܂��B
�@�h�ƌx��@�́A100�~�V���b�v�_�C�\�[�Ŕ����Ă���ʐ^�̂��̂��g�p���܂��B�@�F�͔���ʐ^�̃x�[�W���A�ق������邩������܂����̊�E��H�������Ȃ�g�p�ł��܂��B �@��p�^�[���Ɣz���͉��L�̂Ƃ���ł��B 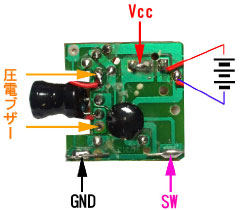
�@100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���u���p�h�ƃu�U�[�v�͎�ނ͂����Ă����삷�錴���͓����ŁA�u�U�[��甭�U��H(���[���h���ꂽIC�̒��ɓ����Ă��܂�)����/�������Ȃ����u���[�h�X�C�b�`�v�Ƃ������̓X�C�b�`�ŃR���g���[�����܂��B �@���a3mm���x�̃K���X�ǂɓ��������[�h�X�C�b�`����ɂƂ�����Ă��镨(����̐��i�͂���)��A���[�h�X�C�b�`�̒��̋����ړ_�������ނ��o���Ŋ�ɂƂ�����Ă�����̂�����悤�ł��B�����ځE�`�͕ς���Ă������͓����ł��B �@���[�h�X�C�b�`�͎��͂�^����ƒ��̋����ړ_���������ēd�C�𗬂��܂��B���͂������Ɛړ_�͗���Ă��ēd�C�͗���܂���B �@���p�h�ƃu�U�[�ł͑����܂��Ă���Ɩ{�̂ɑ��g�ɂƂ�����������߂Â������[�h�X�C�b�`��ON�ɂȂ�����Ԃł̓u�U�[�͖�܂���B�����J�������������������[�h�X�C�b�`��OFF�ɂȂ��ău�U�[����܂��B �@�Ƃ������ŁA���p�h�ƃu�U�[���J�~��œ��삳����ɂ́A���[�h�X�C�b�`�̂����Ɂu����Ă�����ON�v�u�J���~������OFF�v�Ƃ����X�C�b�`��H���Ȃ��Ηǂ����ƂɂȂ�܂��B �@����Ă��邩�J���~���Ă��邩�����m����ɂ́A�ӂ��́u�J�~��Z���T�[�v�Ƃ����Z���T�[�����܂��B �@�ɋ����̃p�^�[���������̂ŁA����Ă��鎞�ɂ͂Q�̋����p�^�[���͗���Ă��Ă���̂œd�C��ʂ����A�J���~��ƂQ�̋����p�^�[���̊ԂɉJ�Ԃ��������Ɛ��������Ȃ̂Ńp�^�[���Ԃɓd�C�������悤�ɂȂ�܂��B�d�C�������Ƃ͂����Ă����̂܂܃X�C�b�`�ɂł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u���̒�R�l�v�Ő������ꂽ����ȓd�C���������x�ł��B �@�ł�����A�u�J�~��Z���T�[�v�����ł͑��̕����H��ON/OFF���邱�Ƃ͓���̂ŁA�ӂ��̓g�����W�X�^�Ȃǂ��g���ăX�C�b�`���O���s���܂��B �@���������悤�ɁA�u����=OFF�v�u�J=ON�v�Ȃ̂ŁA����̌x��u�U�[�����[�h�X�C�b�`�삳���邽�߂́u����=ON�v�u�J=OFF�v�Ƃ����X�C�b�`����Ƃ͋t�ł�����A��������]�������K�v������܂��B �@�܂��A�g�����W�X�^���g������H�ł͒ʏ�̓o�C�A�X�d������ɂ�����x�͗���Ă���̂ŁA�ҋ@����������x�͓d�r�����Ղ��܂��B �@�u�{�^���d�r�Ŕ��N�͓��삳�������v�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA���̌x��u�U�[��H���l�ɉJ�U��Z���T�[��H���ҋ@���͓d�͂�����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ͕��ʂ̃g�����W�X�^��H�ł͂��߂ŁA��Ԃ��ω����鎞�ȊO�ɂ͓d��������Ȃ�FET���g�p������H���������Ƃɂ��܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�g�p����x��u�U�[��́A��̉�H�}�̂悤�Ɂu���[�h�X�C�b�`�̕Б���GND�ɐڑ�����Ă���^�C�v�v�ł��BVcc���ɐڑ�����Ă���^�C�v��AIC�̒��Œ����ȉ�H�ɐڑ�����Ă�������ł͂��̉�H�}�̒ʂ�ɍ���Ă����삵�܂���B �� ���ʒ��� �@500K���̔��Œ��R�܂��̓{�����[�������d�u�U�[�ƒ���ɐڑ����܂��B �@�u�U�[�����d�u�U�[�Ȃ̂ł��̂悤�ȍ�����R�l�̒�R��ɓ���邱�Ƃʼn��ʒ��߂��ł��܂��B �@���ʂ�4�`32�����x�̃}�O�l�`�b�N�X�s�[�J�[���g�p�����u�U�[��W�I�̂悤�ȃI�[�f�B�I�p�X�s�[�J�[��H�ł͒�R��ɓ������@�͂Ƃ�܂���B �@���̕��@�ł̓{�����[�����i���Ă����ʂ͂O(����)�ɂ͂Ȃ�܂���A�����ȉ��͕������܂��B �@�����܂Łu�x���v���u�Ȃ̂ŁA�x���o�Ȃ�����͈̂Ӗ�������܂���A���ʒ��߂ł͍Œ�ł��x����������悤�ɂ��Ă����܂��B �@�炵�����Ȃ����ɂ͓d���X�C�b�`����Ă��������B �� �J�~��Z���T�[��H �@�J�~������m����Z���T�[�{�[�h�̒�R�l�̕ω��u����=OFF�v�u�J=���̒�R�l�Ԃ�̒�R�v�ɂ���āA�x�U�[��ON/OFF�����邽�߂ɍ����x��FET�ŃX�C�b�`���O���܂��B �@����Ă����FET��G(�Q�[�g)�[�q��5�`10M��(�l�͓K�X�I��ł�������)�̒�R��ʂ���Vcc�̓d�����������Ă��܂��B �@���̏�Ԃł�FET��D-S�Ԃ�ON��ԂƂȂ�A���������[�h�X�C�b�`�ɐڑ����Ă����u����=ON�v�ƂȂ��ău�U�[�͖�܂���B �@���AFET��G-S�ɂ͓d���ω����ȊO�ɂ͓d���͗���܂���̂ŁA�ӂ���̑ҋ@���ɂ�5�`10M���̒�R�ɂ͂܂������d�������ꂸ�A�J�~��Z���T�[���ł͓d�͂�����邱�Ƃ͂���܂���B �@�J���~���ăZ���T�[�{�[�h�ɉJ�Ԃ����ƁA�Z���T�[�{�[�h�͉J�Ԃ̒�R�l(5�`10M����肸���Ə����Ȓ�R�l)�œ��ʂ���̂�Vcc����5�`10M����ʂ��ė����d����GND�ɗ���Ă��܂��܂��B�]����FET��G(�Q�[�g)�[�q�ɂ͓d����������Ȃ��Ȃ�AFET��D-S�Ԃ�OFF��ԂƂȂ�u�J=OFF�v�Ōx��u�U�[����܂��B �@�Z���T�[�{�[�h�ɐ��H�����Ƃ��̒�R�l�{5�`10M���̒�R���o�R���ēd��������܂����A5�`10M���Ƃ����傫�Ȓ�R�l�o�R����̂Ŏ��ۂ̓d���l�͂����킸���ł����B �@������A���H�����Čx��u�U�[�����Ă���Ƃ��̃u�U�[�̏���d���͂��Ȃ�̂��̂ŁA����Ɣ�ׂ������͑S���d��������Ă��Ȃ��ƌ����Ă��������炢�ł��B �� ���́u���p�v�X�C�b�`�Ƃ̋��p�ł����ƕ֗��ɁI �@�˗��җl�̂���]�ł͂��̑��u�𑋂̓����ɒu���Ă����āA�u�J���~�荞��v�x��u�U�[����悤�ɂ��l���Ȃ̂ŁA���ɂ��̉��p�����Ȃ��Ă��ǂ��̂ł����A���ʂ̉J�~��Z���T�[�̂悤�Ɂu�Z���T�[�{�[�h�𑋂̊O�ɏo���āA�J�̍~��͂��ߒ��x�Ŋ��m���Ă��m�点�����v�Ƃ����p�r�Ŏg�����ꍇ�ɂ́A�u�J���~�荞��v�Ƃ����̂�m�肽���Ȃ�u����߂Ă���Όx���炷�Ӗ��������v���ƂɂȂ�A�Z���T�[�{�[�h�𑋂̊O�ɏo������ԂŃX�C�b�`�����Ă���Α���߂Ă��ĉJ�����������ސS�z�������̂ɉJ���~��ƌx�������邳���I�����ƂȂ��Ă��܂��܂��B �@����߂邽�тɃX�C�b�`���̂ł͂��܂�ɖʓ|�ŁA�����J�����̂ɃX�C�b�`�����Y��Ă��ĉJ���~�荞�̂Ɍx��Ȃ������I�Ƃ������s���l�����܂��B �@�����ŁA�u�Z���T�[�{�[�h�͑��̊O�̐ݒu���ĉJ�̍~��o����f�������m����I�v�u�����J���Ă��鎞���������ʼnJ�~��x����o���I�v�Ƃ��������̑f�������ԈႢ�̖����x�u�ɂ�����@�����Љ�܂��傤�B �@����̉J�~��Z���T�[��H�́u�����J�������ǂ����v�肷�郊�[�h�X�C�b�`�̓����ɂ��̂܂܌݊������������Ă���܂��B �@�ł�����A(�����g��Ȃ����OFF�Ȃ̂�)�������[�h�X�C�b�`�����O���K�v�͂���܂��A���[�h�X�C�b�`�͌��̂܂܂̏�ԂŁu�J�~��Z���T�[��H�v������ɂȂ����x��u�U�[�ƃ}�O�l�b�g�𑋂ɂƂ���đ����J������x�鎞�Ɠ����悤�ɃZ�b�e�B���O���Ă����A�u�����J�������[�h�X�C�b�`��OFF�v���u�J���~����FET��OFF�v�̗����̏��������藧�����Ƃ��ɂ����x��u�U�[����u�����܂��Ă��鎞�ɉJ���~���Ă��x��u�U�[�͖�Ȃ��v�֗��@�\���̉J�~�肨�m�点�u�U�[�ɂȂ�܂��B �@���̏ꍇ�͉J�~������m����Z���T�[�{�[�h�͌x��u�U�[�{�̂��班���P�[�u���ŗ����đ��̊O���ɂƂ���邱�ƂɂȂ�܂����A���̎���5�`10M���̒�R���傫���ƐÓd�C��O���d�C�m�C�Y�Ō�쓮����\��������܂��̂ŁA������쓮����Ȃ�1�`5M�����x�̊ԂŌ�쓮���Ȃ���R�l��T���Ă݂Ă��������B �@���͂��́u���p�h�ƃu�U�[���p�E�J�~�肨�m�点�u�U�[�v�͉J���U��o�����炨������̂��������悤�ɒm�点��u�U�[�p�r�ȂǂŁA�d�q�H��}�K�W����100�~�V���b�v��������I�����̋L���p�ɒg�߂Ă����l�^�ł��B �@����Ŏ��ʂł̔��\�͖����Ȃ��Ă��܂��܂����̂ŁA�܂������ʂ̃l�^��T�����Ƃɂ��܂��傤�i�O�O�G ���Ԏ� 2010/9/27
|
||
| ���e |
���肪�Ƃ��������܂����B ����ł����畔�i�S�ăP�[�X�Ɏ��܂肻���ł��B200�~���炢�łƂĂ��֗��Ȃ��̂��o���オ��̂łƂĂ����ꂵ���ł��B �X�C�b�`��������lj����ĉJ�u�U�[�Ɩh�ƃu�U�[���ւ��邱�Ƃ��\�ł��ˁB �d�������ON�ł悯��Γd���X�C�b�`�����p�^�[���J�b�g�����ĉJ�u�U�[�A�h�ƃu�U�[��ւ��X�C�b�`�ɂ��Ă��ǂ��ł��ˁB PS:�l�^���ꑫ��Ɍ��J���Ă��܂��\����܂���ł����B �g������Ă������������ƂɊ��ӂł��B�i�L���ɂ��Ă��������Ă��S����肠��܂���B�j tenten �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�ǂ������Ă���̂��́u�����݁v���킩��Α��̗p�r�Ȃǂɂ����p�������Ǝv���܂��̂ŁA���ꂼ����ǂ������Ėʔ����g�������l���Ă��������B �@���Ђɂ͈�x�l�b�g�Ō��J������H�Ȃǂ͊�e���Ȃ���(�������[��)�ɂ��Ă��܂��̂ŁA���̃l�^�͂����{�c�ł��i�O�O�G �@�������e�̕��Ō��e�������悤�o�ŎЂ̕�����˗���������͂����������d���Ȃ̂ŕʂł����A���Ƀl�b�g�Ŕ��\���Ă��܂������̂����Ƃ���ɑ��ĐF�X�Ɨǂ��v��Ȃ��l���當�傪����̂ŁA�����Ńl�^���l���ĕҏW����Ǝϋl�߂ĉ��\���邩�̏ꍇ�����炩��o�����͖̂����\�̂��݂̂̂ƌ��߂Ă��܂��B �@�o�ŎЂ̂ق�����́u����(���J��)�̕��ł������ł����A�ł���Ζ����\�̂ق����ǂ��v�Ƃ������Ă��܂����B �@���ЂŌ��J����L�����ʂɏ�菑�Ђ����l���ǂ�ł��̂����̉��l���͍���Ă����ł��傤���A�l�b�g�Ō��J����Ό����ȂǂŖړI�̂��̂�T���Ă���l�̖ڂɎ~�܂�₷�������b�g������܂����A�ǂ���Ō��J���Ă��N�����g���Ă����Ȃ炻��ł悢�̂ł��B �@���Ђ��Ƃ���Ȃ�̌��e���������܂����A�l�b�g���J���ƕ����I�ɂ͉��������Ȃ���������܂���B����ł��l�b�g�Ŏ���ɓ����Ă���̂́A����җl���u���ɗ������v�ƕԐM���Ă����������Ŗ������Ă��邩��ł��B ���Ԏ� 2010/9/28
|
||
| GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H | |||
|
GND��������͉�H �f�[�^���K�[���w���������ƍl���Ă���܂��BA&D�Ɉ����ēs���̗ǂ����̂��������̂ł����A���͂̂Q��H�Ƃ�GND�����ʂɂȂ��Ă��܂��B�����̌v���Ώە���GND�ɓd�ʍ�������A���ʉ��ł��܂���B�����������ꍇ�A������H��O�i�ɕt�����邱�ƂŁA�Q�`�����l���Ԃ�GND���ł��܂���ł��傤���B ���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���ʂ́A�I�V���ł��f�[�^���K�[�ł������`�����l���Ή��ł�����GND�͂P�ł���ˁB �@�u�v���Ώە���GND�ɓd�ʍ�������v�Ƃ������ł����A�ǂ��d�ʍ��������̂����킩��Ȃ��ƑS���Ή��ł��܂���B �@����A�����̂悤�ɐݔ��Ƃ����������đΉ�������@���Ƃ�A�ǂ�Ȏ��ԂɂȂ��Ă��Ă��Ή��͂ł���̂ł��傤���A�����Ŏ���������Ƃ������͉�H�����Ƃ��ė\�Z�͐��S�~���x�̊ȈՂȂ��̂łł��Ȃ����H�A�Ƃ���������݂ł���ˁH �@����GND�d�ʍ����N���錴���͉��ł��傤���H (1) �S���ʁX�̋@��𑪒肵�悤�Ƃ����Ƃ���A�@��Ԃ�GND�d�ʍ��������āAGND���Ȃ��ł��܂��ƃV���[�g����Ă��܂��B (2) �P�̋@��E��H�������AGND�d���̉e���łQ�_�Ԃ�GND���m�ɓd�ʍ��������Ă���B (3) ���̑��A�Ȃɂ��M�����Ȃ��悤�Ȍ���������B ���̂����̂ǂꂩ�A�܂������ƕʂ̌����Ȃ̂��A���ꂭ�炢�͂��������������B �@����ƁA���肵�����d���͉��u�Ȃ̂ł��傤���H �@�ő�d��(�����W)�Ƃ��A�𗬂Ȃ̂������Ȃ̂��A�������������킩��Ȃ��Ƃǂ��������őΉ��ł���̂��ӌ��������o���悤������܂���B �@�����Ȃ�AC 6600V�Ƃ�����Ȃ��ł��������ˁB �@�d���̏�ł͊m���ɓd�����Ƃ�ϓd�����Ƃ�GND�͂��Ȃ荷���o��ł��傤���E�E�E�A���̂ւ�̓d�q���i������Ŕ����Ă��镔�i�ł͂ƂĂ��Ώ��ł��܂���i�O�O�G ���Ԏ� 2010/9/22
|
||
| ���e |
�����s���Ő\����܂���B ���肵������H ��̗�F���z�����d�p�̃`���[�W�R���g���[���[�̓��͓d���Əo�͓d�����ɑ��肵�����B ���ہFGND�Ԃɂ͐��SmV�̓d�ʍ�������B���������ƃ`���[�W�R���g���[���[�͓��삵�Ȃ��B���炭�A������H�ɓd���v���p�̃V�����g��R��GND�ɐڑ�����Ă���B ���̉�H�ł���A�Ⴆ��R1,R2,R3������ɐڑ����ꂽ��H�ŁAR1��R3�̓d�����ɑ��肵�����ꍇ�AGND���ʂł͌v��Ȃ��Ǝv���܂��B ����d���F0-20V�ȓ��ł��B �f�[�^���K�[��T&D��VR-71���l���Ă���܂��B�i���Q��C/P) �A�C�\���[�V�����A���v�Ȃ���̂�}������A�v���ł���悤�ł����A�ȒP�ɐ���ł�����̂��������A������������Ǝv���܂��B ���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�Ȃ�قǁA�u���肵�����ꏊ�̕Е��̃}�C�i�X����GND�ł͖����v�̂ŃA�C�\���[�V�����A���v���~�����킯�ł��ˁB �@�A�C�\���[�V�����A���v�Ƃ́A�A�C�\���[�V����(�≏)���ꂽ�A���v�Ƃ������ŁA���͑��Əo�͑����d�C�I�ɂ͐ڑ�����Ă��Ȃ�������H�ł��B
�@�A�C�\���[�V�����A���v�Ƃ́A�A�C�\���[�V����(�≏)���ꂽ�A���v�Ƃ������ŁA���͑��Əo�͑����d�C�I�ɂ͐ڑ�����Ă��Ȃ�������H�ł��B�@�E�}�̂悤�ɁA�A���v���u�̒��œ��͑��̉�H�Əo�͑��̉�H���g�����X���Ŋ��S�ɐ≏����Ă��āA�d���͏o�͑�����X�C�b�`���O�d���Ȃǂœ��͑����쓮����悤�≏����Ă��āA�M���͓��͑��Ńp���X���ϒ�����g���ϒ��Ȃǂ������p���X�M���ɒu�������ăp���X�g�����X�Ő≏���ē`���A������o�͑����������ēd���M���ɒu��������Ƃ������Ȃ蕡�G�ȉ�H��g�ݍ����u�ɂȂ��Ă��܂��B �@���̐}�E�����͈��ŁA���[�J�[��i�ɂ���ėl�X�ȉ�H�������̗p����Ă��܂��B �@���ʂ͂��������������u���A��g�ݍ��ݗp�̃��W���[���A�܂��͏��^������IC�����ꂽ���̂��g�p����̂ł����A����Ȃ�̒��g�Ȃ̂ł��l�i�������Ȃ��̂ɂȂ�܂��B �@���č���̂���]�̂悤�ɁA�P�̑��u�̒��Łu���镔�i�ɂ�����Ǐ��d���𑪂肽���v�Ƃ����ꍇ�A����Ȃ���w�ȑ��u�⍂��IC���g��Ȃ��Ă��A�����g���Ă���P��100�~�ȉ����I�y�A���vIC�ƒ�R�������ōς�ł��܂��܂��B 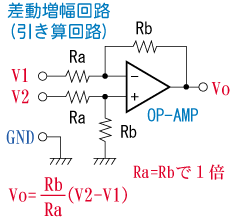 �@�������O����H�}�̒��ɏo�Ă����I�y�A���v�ɂ�鍷��������H(�����Z��H)������ł��B
�@�������O����H�}�̒��ɏo�Ă����I�y�A���v�ɂ�鍷��������H(�����Z��H)������ł��B�@����������H�ɂ�V1��V2�̂Q�̓d�����͂�����A�o�͓d����Vo��(Rb/Ra)(V2-V1)�ŋ��߂��܂��B �@������Ra��Rb�Ƃ���Ƒ��������P�{�ƂȂ�A�o�͓͂���V2��V1�������̂����ƂȂ�A��H���̔C�ӂ̓_�̓d�������ꂼ��V1��V2�ɗ^���Ă����C�ӂ̂Q�_�Ԃ̓d����GND����̓d���Ă��ďo�͂��邱�Ƃ��ł��܂��B �@�I�[�f�B�I��r�f�I��H�p�r�ł̓O�����h���[�v���ȂǂŐM��GND�̓d�ʍ��m�C�Y����菜�����߂ɍ����A���v���g�p�����H�̂��Ƃ��u�A�C�\���[�V�����A���v�v�ƌĂ�ł���ꍇ������悤�ł����E�E�E�B���ʂ͂��̉�H�̂��Ƃ͍���������H�E�����A���v(�f�B�t�@�����V�����A���v)�E�����Z��H�ȂǂƌĂсA�≏���u�ł���A�C�\���[�V�����A���v�Ƃ͋�ʂ��܂��B �@�܂��A���͑��Əo�͑���{���ɐ≏���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȗp�r�A���Ƃ��Γ��͑��Əo�͑������\V�`���SV�̓d�ʍ�������Ƃ��E�E�E���������{�i�I�ɐ≏���K�v�ȏꍇ�͐�ɃA�C�\���[�V�����A���v��≏���u���K�v�ł��B �@����������H�͂����܂œ��͓d���͈͂��g�p����I�y�A���v�̓d���d�����x�̒�d���Ɏ��܂��Ă���Ƃ������������ɂȂ�܂��B >�Ⴆ��R1,R2,R3������ɐڑ����ꂽ��H�ŁAR1��R3�̓d�����ɑ��肵�����ꍇ�AGND���ʂł͌v��Ȃ��Ǝv���܂��B �@���̂悤�ȑ�����s���ꍇ�͉��}�̂悤�ɐڑ�����Α���܂��B 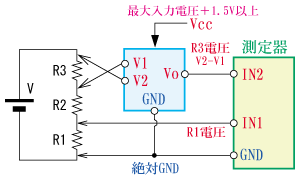 �@R1�̓d���͂��̂܂ܑ����ɓ��͂ł��܂��B
�@R1�̓d���͂��̂܂ܑ����ɓ��͂ł��܂��B�@R3�̓d��������������H�̓���V1��V2��}�̂悤��(�����Z����̂�V2����V1���d��������)�ڑ�����ƁA�o��Vo�ɂ�R3�̗��[�d����GND����̓d���Ƃ��Č���܂�����A���̂܂ܑ����̓��͂ɂȂ���R3�̓d�����v���ł��܂��B �@�����uR2�̓d����R3�̓d���𑪂肽���v�Ƃ����̂ł���A����������H���Q��H����Ă��ꂼ��̓��͂�R2��R3�̊e���[�ɐڑ����Ă��Α���ł��܂��B �@���̏ꍇ������������H��GND�͕K�����GND�Ɛڑ����Ă����Ȃ��Ɛ���ɓ��삵�܂���B �@�e�X�^�[�̑���_�̊��o�ŒP����V1��V2�Ɋ��d�r���Ȃ��E�E�E�݂����ȑ���͂ł��܂���BV1��V2�͕K��GND����̓d����^����K�v������A���̍����H�ł��B �@�ʏ�̃I�y�A���v�̓��́E�o�͂̓d���͈͂�GND�`Vcc-1.5V(�P��d���g�p��)�ł��B(���[��to���[���^�C�v���g�p����ꍇ��Vcc�܂�) �@DC20V�܂ő��肽���̂ł���AVcc��21.5V�ȏ�K�v�ŁA�悭�g��LM358�̏ꍇ��Vcc�̍ő��i��+32V(�P��d���g�p��)�ł����炲��]�̓d���͈͂͑���ł��܂��B �@Ra�ERb�̒l�͂��܂菬��������Ɣ푪���H����d�������ꍞ��ʼn�H�ɂ���Ă͓���ɉe�����y�ڂ��\��������܂��̂ŁA100K���ȏ�`1M�����x�܂łœK�X�v���Ă��������B �@�o�b�e���[�[�d��̓d������ł����100K���ȏ゠��Α��v���Ǝv���܂����A�ʂ̉�H�Ŕ��ɃC���s�[�_���X�̍�����H�̑���̏ꍇ�͓��͒[�q�̑O�ɃI�y�A���v�Ń{���e�[�W�t�H����(�o�b�t�@)���P�i����āA�����H���̃C���s�[�_���X����������K�v�����邩�Ǝv���܂��B(�ʂ̉�H������̂Ō�q���܂�) �@����������H�͌v���p�r�̉�H�ł͗l�X�ȕ���Ŏg�p����Ă��܂��B �@���Ƃ��Ώ[�d��̒�d����H�œd�����m�p��R���d���������ɂ���ꍇ�Ƃ��ALED�̋쓮��H�̓d�����m��R����͂�GND���ȊO�ɂ��鎞�Ƃ��B �@����̂���]�̂悤�ɁA�[�d��œd�����m��R��GND���ɂ���A�o�b�e���[�̓d����GND��蕂���Ă���ۂ̃o�b�e���[�d������Ȃǂɂ͏[�d��̒��ɂ���������H�Ƃ��đg�ݍ��܂�Ă���ꍇ�������ł��ˁB 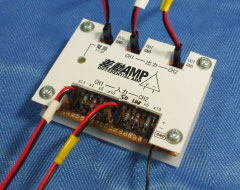 �@�d�����m�p�r�ł͔{�����P�{�ł͂Ȃ�10�{�E100�{�ȂǃV�����g��R�Ɍ��������ȓd�������đ��肷��K�v������A����������H�̑�������10�{�E100�{�Ȃǂɐݒ肵�Ă��������ȓd�����v����ő����d���͈͂܂ő������܂��B
�@�d�����m�p�r�ł͔{�����P�{�ł͂Ȃ�10�{�E100�{�ȂǃV�����g��R�Ɍ��������ȓd�������đ��肷��K�v������A����������H�̑�������10�{�E100�{�Ȃǂɐݒ肵�Ă��������ȓd�����v����ő����d���͈͂܂ő������܂��B�@�����ł͎ʐ^�̂悤�Ȑ���ނ̔{���œd����������I���ł���悤�ɂ������������������Ă��āA�K�v�ɉ����ăf�[�^���K�[�̓��͒i�̑O�ɐڑ����ď[�d��Ȃǂ̑���Ɏg�p���Ă��܂��B (�������킹�łĂ��Ɓ[�ɍ�����̂Ō��J�ł���`�̉�H�}�͂���܂���c) �@����̂����l�̖ړI�ł���Όv����Œ��ڑ����d���͈͂Ȃ̂Ŕ{���͂P�{�݂̂Ŗ��͖����ł����A�ق��̗p�r�ʼn��p�����ꍇ�͂������̗p�r�ɂ��킹�Ĕ{����ݒ肵����H������Ċ��p���Ă݂Ă��������B �@����͐������Ă��܂��A�I�y�A���v�̍���������H�̈��Łu�C���X�c�������e�[�V�����A���v�v�Ƃ�����H������܂��B �@�������i���������܂����A���̓C���s�[�_���X���I�y�A���v�̓��̓C���s�[�_���X�Ɠ������Ȃ�푪���H�ɉe����^���Ȃ��̂ƁA����������R��{�ŕύX�ł���̂Ń{�����[����ő��������ςł���ȂǁA���Ȃ�֗��Ɏg�����H�ł��B �@�����\�ȍ���������H���K�v�ȏꍇ�ɂ͍����ׂĊ��p�����Ƃ悢�Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/9/23
|
||
| ���W�R���E�����|���v������~���u | |||
|
�͂��߂܂��āB ���͔��c�t��������Ƃł�����x�̏��S�҂œd�q��H�ɂ��ڂ����Ȃ��̂ł����A���W�R����s�@�̔R���^���N�ɊO���̓d���|���v�ŋ������͔�������Ƃ��s���ۂɖ��^�����͋�^���N�ɂȂ����玩����~���鑕�u����肽���Ǝv���Ă��܂��B �@�̂ɐ��ʃZ���T�[�����t���邱�Ƃ̓X�y�[�X�I�ɖ��������邽�߁A�|���v�̃��[�^�[�̓d�����͓d���̕ϓ������m���ēd�����d�q��H���ɂł���A�Ǝv�����[�������グ�܂����B �|���v�̃��[�^�[�����d����12V7Ah���̃o�b�e���[�ŁA4���b�^�[�̔R���ʂ���z���グ�ċ@�̂̃^���N�ւƃ`���[�u(���H)��ʂ��đ��荞�݂܂��B �@�̂̃^���N�����^���ɂȂ�ƃI�[�o�[�t���[�����R�����߂�p�̃`���[�u(���H)�𗬂�ĔR���ʂɉ�������z�ǂɂȂ��Ă��܂��B�������ɉ��H�݂̂ɗ���Ă���Ƃ��ɑ��āA���^���ƂȂ蕜�H�ɂ�����o���ƃ��[�^�[���ׂ����܂�쓮�����ς��܂����A���̂Ƃ��d����1V���x������d����80mA���x�オ��܂��B ���A�R��������莞�ɂ̓��[�^�[���t�]�����邱�Ƃŋt��������悤�ɂȂ��Ă��܂����A������芮�����|���v����]����Ƃ܂������ς��d���E�d�����ϓ����Ă�����̂Ǝv���܂��B�����̕ω������m�������̂ł����A�o�b�e���[�̏[�d��ԓ�������̃t���C�g�̊Ԃɕω����Ă���悤�Ȃ̂ň��̓d����d���l�Ɍ��߂Č��m������@�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �����ŁA�������ɃZ�b�g�{�^�����������Ƃł��̂Ƃ��̓d���l���L�����ꂻ�̒l�ɑ��đ��債���ꍇ�ɓd�����悤�ɂ��Ă͂ǂ����ƍl���܂����B�t��]�Ŕ������̏ꍇ�����l�ɃZ�b�g���ꂽ�d���l�ɑ��Č��������ꍇ�ɓd�����d�g�݂ł��B ���[�^�[�̐��E�t��̕v�X�ɂ��ĔC�ӂɃZ�b�g���ꂽ�d�����͓d���l�ɑ��鑝�������m���d������H�ł��B �����i�C���[�W�Ƃ��ẮABOX�Ɋ��x�����c�}�~�ƃZ�b�g�{�^���̃v�b�V��SW�A�Z�b�g���ꂽ�ƕ\������LED���t���Ă���12V�d�����͂ƃ��[�^�[�ւ̏o�͒[�q������Ƃ����`�ł��B�����킩�炸�v�]�̂ݕ��ׂ܂��đ�ϋ��k�ł����A�ǂ����X�������肢�v���܂��B ubebe �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����|���v�̕��ׂ̑����ŁA�������̃o�b�e���[�d�����ω����������d�����ω����邱�Ƃ������ׂɂȂ�A����Ŏ����I�Ƀ|���v���~�������H���v�����ꂽ�̂͂Ȃ��Ȃ����炵�����z�ł��ˁB �E����(���])����1V���x�d����������(���ׂ��d���Ȃ�)�������o���� �E�r��(�t�])����xV���x�d�����オ��(���ׂ��d���Ȃ�)�������o���� �E�o�b�e���[�̏��Տ�Ԃ��ς���Ă��A�����œK�X�Ή��ł��� �Ƃ�����H�ōl���܂��傤�B �@�d���E�d���̂ǂ���ׂĂ��悢�̂ł����A����̓��[�^�[������Ă��鎞�̓d���l��������Ă��܂���ł����̂œd�����m��H�����̃��[�^�[�ɓK�������l�Őv�ł��܂���A�d���d����12V���ω�����l�q�𑨂��ĕω������m������@�Ƃ��܂��B �@12V/7A�̉��o�b�e���[�ʼn^�p����Ă����ԂȂ炻�̃o�b�e���[�̐��\�ŁA���[�^�[���ׂ��ς��Γd���������ς��(����m�F���ꂽ�d���l���炢��)���ۂ��N����̂Ŗ��͂���܂��A�����Ɨe�ʂ̑傫�ȃo�b�e���[���g�p������A�e�ʂ̑傫�Ȉ��艻�d�����g�p�����ꍇ�ɂ͂��܂�d���d���ɂ͕ω�������ꂸ�A���̉�H�ł͓K���Ȃ��ꍇ������܂��B �@�ǂ�ȓd���ł��قڑΉ��ł���悤�ɂ���ɂ͂�͂�d���l�̕ω��𑨂���̂��ǂ��ł����A����̉�H�͂����܂œ��e���e�ɉ����ă��W�R����s�@�����O�Ŕ����鎞�ɁA�|�[�^�u���d���Ƃ���12V/7A�̉��o�b�e���[�����g���ɂȂ���Ƃ����p�r�����̉�H�ł��B �@�K�v�Ȃ��̂� �E�����]���Ă��鎞�̓d�����u�L���v�����H �E�u�L���v�����d���Ɓu���v�̓d�����r���Đ��l�������H �E��r���ʂ��u�C�ӂ̐ݒ�l�v�Ɣ�ׁA�ݒ�l�����玩����~�������H �E���[�^�[���R���g���[�������H �ȂǂɂȂ�܂��B �@���ꂼ��̓I�y�A���v���g�p���ĊȒP�Ɏ����\�ł�����A��H�̋K�͂�����قǑ傫���͂Ȃ�܂���B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�� �d����H �@�|���v�����o�b�e���[����{��H�̓d�������炢�܂��B �@�|���v�̕��ׂ̕ϓ��Ńo�b�e���[�d���͕ω����܂�����A���̂܂ܓ����Ŕ�r�p�̓d�������ƃo�b�e���[�d���̕ϓ��ɍ��E����Ă��܂��܂��̂ŁA��U�O�[�q���M�����[�^�ň����5V������āA����ʼn�H�d�����d���Ɏg���܂��B �� �T���v���A���h�z�[���h��H �@�u����ɋ���/�r�����Ă����Ԃ̎��̓d���v���u�L���v������K�v������܂��̂ŁA�A�i���O�d���̋L����H�ł���w�T���v���E�A���h�E�z�[���h��H�x�ŔC�ӂ̎��_�̓d�����L�����܂��B �@�g�p����I�y�A���v�͂��Ȃ��݂�LM358�ł��B �@LM358��5V�d���Ŏg�p���Ă��܂��̂ŁA����/�o�͂ł���d����0V�`��3.5V�ɂȂ�܂��B�ł�����o�b�e���[�d����12V�ړ��͂ł��܂���̂ŁAR1�ER2�ŕ�������1/5�̓d���ɂ��܂��B���͓d����12V�̎��ɂ̓I�y�A���v�̓��͂�2.4V�ɂȂ�܂��B �@���͂��ꂽ�d���͉�H�}�㑤�̃I�y�A���v�Ńo�b�t�@������A�o�b�e���[�d���̍��̏���`����u���d���v�ƁA�C�ӂ̎��ԂɁu�L���v�������u�z�[���h�d���v�̂Q�̏o�͂��ł���悤�ɂ��܂��B �@�u�z�[���h�d���v�����̂��T���v���A���h�z�[���h��H�ŁA��H�}�̉����̃I�y�A���v�Ɠd���R���f���TC2��SW1-1���T���v���A���h�z�[���h��H�ł��B �@���̉�H�ł�SW1-1��ON�̎��ɂ͉�H�����͑��Ɛڑ�����AC1�̓d���͓��͓d��(���d��)�Ɠ������Ȃ�܂��B �@SW1-1��ON�ɂ��Ă���Ԃ͓��͓d�����ω����Ă�C1�̓d���͂���ɂ��킹�ĕω����A���͂�ǂݍ��ށu�T���v�����O�v����ɂȂ�܂��B �@SW1-1��OFF�ɂ���ƁAC1�͓��͉�H����藣����邽�ߓ��͓d���ɊW�Ȃ��[�d���ꂽ�d�����ێ����܂��B���ꂪ�u�z�[���h�v����ł��B �@�I�y�A���v�̓��͒[�q�͔��ɃC���s�[�_���X�������A�d�������ꍞ�݂܂���̂ŗe�ʂ̑傫�ȓd���R���f���T�Ȃ��U���߂��d�C�͂��炭�̊Ԃ͕��d���ꂸ���̓d����ۂ��܂��B���̃R���f���T�d�����I�y�A���v��ʂ��ďo�͂��邱�ƂŁA�d����������H�ɂ��R���f���T�̓d����`���邱�Ƃ��ł��܂��B �@SW1-1��ON�Łu�T���v���v�AOFF�Łu�z�[���h�v������X�C�b�`�ł��B �� �d���̌���/�������o��H �@�o�b�e���[�d�����ǂꂭ�炢�u�L���v���Ă���d������ω������̂��A���́u��(�ω���)�����o�����H�v�Ɓu���͐ݒ�l���z�����̂��ʂ����H�v�Ń|���v���~�߂邽�߂̐M�������܂��B �@�ǂꂾ���d�����オ�����̂�/���������̂��́u���d���v�Ɓu�z�[���h�d���v�������Z����킩��܂��B �@�d���̈����Z��H�̓I�y�A���v�Łu����������H(�����Z��H)�v������Ă��悢�̂ŁA�I�y�A���vLM324���g���ĉ�H��g�ݗ��Ă܂��B�u�����p��H�v�u�r���p��H�v�łQ�����悤�ȉ�H���K�v�ɂȂ�A�I�y�A���v�����v�S�K�v�ɂȂ�܂��̂łS��H�����LM324���g�p���܂��B�ʂɎ茳��LM358����R���܂��Ă����(��l�b�g�ʔ̂�LM358�~5����Ȃǂ����)�Ȃ�LM324�̂�����LM358�~�Q�ł����܂��܂���B��������H�}�̃s���ԍ��͕ς��܂����炲�����œǂݑւ��Ă��������B �@����v��������������H�ł́A�������́~�T�{�Ƃ��ē��͓d�����̒l���T�{�ɂ��Ă��܂��B �@�ŏ��̃T���v���A���h�z�[���h��H�̓��͒l��1/5�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�����ō����T�{�ɂ���Ώo�͂�������d���͂��̂܂ܐ������d��(1V�Ȃ�1V)�ƂȂ�A�e�X�g���̌v���₱�̌�́u�ω��ʂ̌����v�ł̓_�C���N�g�ɓd���l��������̂ŕ֗��ł��B �@�������A�ω��ʂƂ��ē��e�җl�̂���]��1V���x�̕ω��Ƃ������Ȃ̂ŁA�ω��ʂ̐ݒ�l��0�`3.5V�ȓ��ɂ��Ă��S�R���܂�Ȃ��Ƃ����O��ł̘b���ł��B �@����������H�ŋ��߂��d���̕ω��ʂ��u�ݒ肵���l�����v���ǂ����肷���H�̓I�y�A���v���u�R���p���[�^(��r��)�v�Ƃ��Ďg�p���Ĕ��ʂ��܂��B �@����p�̐ݒ�d����VR1(�����p)/VR2(�r���p)�ł��ꂼ��ݒ肵�܂��B �@0V�`��2V�̊ԂŐݒ�ł��܂��̂ŁA����̂���]�̗p�r�ł͑��v�ł��傤�B �@�o�b�e���[�d���̍���VR1/VR2�Őݒ肵���d���ȏ�̕ω��ɂȂ����ꍇ�ALED1(���d�����o)�ELED2(���d�����o)��_�������Ă��m�点���܂��B �@�������A�������ɕ��ׂ��d���Ȃ��Ĕ�������o�b�e���[�d���̒ቺ���ۂ́A�|���v���~�߂�ƃo�b�e���[�d����(���ׂ������Ȃ���)�オ���Ă��܂��̂Ń|���v��������~������Ɣ����H���u�d���͉������Ė����v�Ɣ�����Ă��܂�LED1(���d�����o)�͌��m������u�ŏ������Ă��܂��܂��B �@�܂��A�|���v�͎����Ŏ~�܂�܂����ʂɓ����̖��͖����̂ł����A����e�X�g���ȂǂɁu�m�C�Y�ȂǂŌ�쓮���Ď~�܂��Ă��܂����̂��H�v�u���ׂ��d���Ȃ������߂ɐ���Ɏ�����~�@�\���������̂��H�v�̔��ʂ����ɂ������߁A�������̉�H�ɂ͈�u��LED1(���d�����o)�������Ă��܂�Ȃ��悤�Ƀt���b�v�t���b�v�����ĕ\����ێ������Ă��܂��B �@�C�����̖�肾���Ȃ̂ł����E�E�E�B �@����ɁA�ǂ���74HC132�̔������]��̂ŁA���ʂɖ��g�p�ɂ��Ă������͉����Ɏg�����ق��������ł���H �@�r�����̓|���v���y���Ȃ��Ď�����~������A���[�^�[�͐��Ă����ƕ��ׂ͌y���Ȃ�̂Łu�y���Ȃ����v��Ԃ͑����̂�LED2(���d�����o)�͎�����~��������ςȂ��ɂȂ�܂��B�ł�����t���b�v�t���b�v�Ȃǂ͕K�v����܂���B �� ���쐧���H �@�V���~�b�gNAND�Q�[�gIC 74HC132���g�p����R-S�t���b�v�t���b�v�Łu�|���v���^�~�߂��v�̏�Ԃ��Ǘ������H�����܂��B �@�d������ꂽ���ɂ��p���[�I���E���Z�b�g��H�������ăt���b�v�t���b�v�����Z�b�g���܂��B�o�͂�L�ɂȂ�FET��OFF�ɂ��܂��̂Ń��[�^�[�͉��܂���B �@SW1-2��ON�ɂ����SET���ɐ�ւ��A�o�͂�H�ɂȂ�FET��ON�ɂă��[�^�[���܂��B �@SW1-2��SW1-1�ƘA��(��̃X�C�b�`�����̕ʐړ_)�ł�����A�����ڂP��SW1��ON���ɐ�ւ�������[�^�[�����͂��߂��Ƌ������̎��_�ł̃o�b�e���[�d�����u�L���v�����̂ŁA�L������̂���SW1���K���Q�`�R�b��ON�ɂ��Ă���AOFF�ʒu�ɖ߂��Ă��������B �@ON�ʒu�̂܂܂ɂ��Ă����ƁA������~�@�\�͓��������[�^�[�͂����Ɖ�����܂��ɂȂ�܂��B �@������~�@�\���g�킸�Ƀ|���v����������ꍇ�ɂ�ON�ɂ����ςȂ��ł��悢�ł��傤�B �@�܂��A�|���v�����͂��߂��ŏ��̂����̓��[�^�[�̓��삪�s����ŁA������x����/�r�����i��Ԃ��u�L���v���������ꍇ�ɂ��A���̏�ԂɂȂ�܂�SW1��ON�ɂ����܂܂ł��āA�u�L���v���������^�C�~���O��OFF�ɂ������ȍ~�Ŏw��̓d���ω����������ꍇ�ɂ͎�����~���܂��B �@����]�̃v�b�V���X�C�b�`(�Q��H�E�P�ړ_)�ɂ���ƁA�u�N���{�^���v�̂悤�ȉ����{�^���X�C�b�`�ɂȂ�܂����A����10�`20�b�قǕs����Ȋ��Ԃ�����Ƃ����Ɖ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�ł���g�O���X�C�b�`(�Q��H�E�P�ړ_)�Ȃǂɂ��Ă������ق����g������͂悢�Ǝv���܂��B �@��U�����ON�ɂ��Ă��܂��A�|���v���쒆�͂��ł�SW1��ON�ɂ��ēd���́u�ċL���v���\�ł�����A���쒆�Ɂu���̓d�����L�������āA����������ω����������玩����~����悤�ɂ������v�ꍇ�͂��ł�SW1��ON�ɂ���2�`3�b���OFF�ɖ߂��Ă��������B �� ���[�^�[�h���C�o��H �@FET 2SK2232�œd����12V���X�C�b�`���O���ă��[�^�[(�|���v)��ON/OFF���s���܂��B �@SW2-1�ESW2-2�Ń��[�^�[�̉�]�������u���](����)�v�u�t�](�r��)�v�̐�ւ������܂��B �@������SW2-3�Ŏ�����~�p�̐M�����Ƃ��āu�d���������o��H�v���u�d���������o��H�v���̂ǂ�����g�p���邩����ւ��܂��B �@SW2���R��H�E�Q�ړ_�X�C�b�`���g�p���܂��B �@�����ڂ͂P��SW2�ŁA���ɂ�SW2-1�ESW2-2�ESW2-3�ɂ�����R�̐ړ_�������Ă��܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@�g�ݗ��Ă���A�z���ԈႢ�Ȃǂ��������ǂ������m���߂Ă��������B �@�܂��́A�|���v�͂Ȃ����ɖ{��H�݂̂Ńe�X�g���s���܂��B �@VR1/VR2�͉E�������ς�(��2V)�ɉĂ����܂��B �E�T���v���A���h�z�[���h��H�̊m�F �@�d�������ATP1�̓d��(���d��)���o�b�e���[�d����1/5�ł��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@���̎��_�ł�TP2�̓d��(�z�[���h�d��)�͂܂��s��ł��B(���Ԃ�mV�`���\mV) �@SW1��ON�ɂ����TP2�̓d��(�z�[���h�d��)��TP1�̓d��(���d��)�Ɠ����ɂȂ�܂��B��������mV���x�̌덷�͂���܂��B �@SW1��OFF�ɂ��Ă��ATP2�̓d��(�z�[���h�d��)�͂قƂ�Ǖω����Ȃ����Ƃ��m���߂Ă��������B �@���g�p�ɂȂ���d���R���f���T�̐��\�ɂ����܂����A���\�b���x�o�Ƃق�̏�������(��mV�`���\mV���x)�d�����ω�����ꍇ������܂��B�|���v�ł̋���/�r���ɐ��\����������悤�ȏꍇ�͑������ł����A�����ȓ��ł�����̒��x�̔����ȃz�[���h�d���ω��͖�肠��܂���B �E���쐧���H�̊m�F �@�d������ꂽ���ɂ�LED1(���d�����o)��LED4(���[�^�[����)���������Ă��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@�d��ON����LED2(���d�����o)���_�����Ă��Ă����܂��܂���B(��ŋL������ŏ����܂�) �@SW1��ON�ɂ����LED3(�L����)���_����������LED4(���[�^�[����)���_�����܂��B �@LED1(���d�����o)��LED2(���d�����o)�͏������܂��B �@SW1��OFF�ɂ����LED3(�L����)�͏������܂����ALED4(���[�^�[����)�͓_�������܂܂ŁA(���͂Ȃ��ł��܂���)�|���v�͓����Ԃ��ێ����܂��B �� LED3�́u�L�����v�ƕ\�L���Ă��܂����A�u���̉�H���d�����L�����Ă���Ƃ������(�܂�L�����Ĕ�r������s���Ă���)�v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�u�L���������ƒ�(�ǂݍ��ݒ�)�v�̈ӂł��B �@���̓|���v��ڑ����Ă��܂���̂ŁA�o�b�e���[�d���ɕω��͋N���Ȃ��̂ł��̏�Ԃ���͉����ς��܂���B �E�d������/�������o��H�̊m�F�ƁA�ݒ�{�����[���̒��� �@�d������Ė{��H�Ƀ|���v���Ȃ��܂��B �@SW2���u�����v���ɐ�ւ��܂��B �@�d�������Ă��������B �@�|���v�͒�~���Ă���͂��ł����A����ɉ�肾���Ȃ����m�F���Ă��������B �@SW1��ON�ɂ���ƃ|���v�����͂��߂܂��B �@���̂Ƃ��A�t�]���Ă��Ȃ������m�F���Ă��������B�t�]���Ă�����SW2�̕����]���p�ړ_�܂��̃~�X�ł��B(����A�|���v���t�ɂȂ��Ȃ��������ł������ł����c) �@SW1��2�`3�b��ON�ɂ��Ă���OFF�ɖ߂��Ă��|���v�͂��̂܂ܓ���𑱂��܂��B �@VR1���E�����ς�(2V)�ɉĂ��܂��̂ŁA�o�b�e���[�d�����L��������2V�ȏ㉺����Ȃ��Ǝ�����~�͂��܂���B �@�^���N����K�\���������ӂ�āA�|���v�̕��ׂ����܂��ăo�b�e���[�d�����������Ă�������~�͂��܂��A�����Ȃ邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@�K�\���������ӂ�ċt���z�[�X��`���Ă���ԂɁAVR1��������荶�ɉ��䂫�A���鎞�_��LED1(���d�����o)���_�����ă|���v����~���܂��B �@����VR1�̈ʒu��菭�������u�������Ɏ�����~������̂ɓK�����ݒ�d���ʒu�v�ł��B �@�]�T���݂ď��������ɐݒ肵�܂��B �@���^������TP3�̓d�����e�X�^�[�Ōv���āAVR1�Ō��߂�ݒ�d���������菭�������Ȓl�ɂ���̂ł����܂��܂���B �@���A�|���v�͒�~���Ă��܂���ˁH �@���ɁASW2���u�r���v���ɐ�ւ��܂��B �@SW1��ON�ɂ���ƃ|���v���u�r���v�����ɉ��͂��߂܂��B �@���̂Ƃ��A�t�]���Ă��Ȃ������m�F���Ă��������B�t�]���Ă�����{�i�I��SW2�̕����]���p�ړ_�܂��̃~�X�ł��B �@�܂�VR2���E�����ς�(2V)�ɉĂ��܂��̂ŁA�o�b�e���[�d�����L��������2V�ȏ�オ��Ȃ��Ǝ�����~�͂��܂���B �@�^���N����ɂȂ��āA�|���v�̕��ׂ���܂��ăo�b�e���[�d�����オ���Ă�������~�͂��܂��A�����Ȃ邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@�|���v����]���Ă���ԂɁAVR2��������荶�ɉ��䂫�A���鎞�_��LED2(���d�����o)���_�����ă|���v����~���܂��B �@����VR2�̈ʒu��菭�������u�r�����Ɏ�����~������̂ɓK�����ݒ�d���ʒu�v�ł��B �@�]�T���݂ď��������ɐݒ肵�܂��B �@��]����TP5�̓d�����e�X�^�[�Ōv���āAVR2�Ō��߂�ݒ�d���������菭�������Ȓl�ɂ���̂ł����܂��܂���B �@VR1�EVR2���ɂ��܂荶�ɉ�����ƌ��m�d�����������Ȃ��āA�ق�̏����̃|���v�̕��ׂ̕ω��ł��r���Ŏ~�܂��Ă��܂���������܂���A����e�X�g�ƒ������J��Ԃ��čœK�Ȑݒ�ʒu��T���Ă݂Ă��������B �@���ʂ͏�L�̒��߂����Ă��܂��o�b�e���[��Ԃ��ω����Ă��Ă��قڔ���͈͓��Ő��퓮��͂���͂��ł����A�ɂ���Ă̓o�b�e���[�����[�d�̎�(�����d������������)�Ə��Ղ��Ă��鎞(�����d�������傫��)�ł͐ݒ�l�𑽏��͒��߂��Ȃ����Ȃ��ƌ딻�肷�邩������܂���B �@���ۂɎg���Ă݂āA�o�b�e���[�̎c�e�ʂ̈Ⴂ�Ō딻�肷��悤�ł�����u���[�d�̍ۂ̈ʒu�v�u��ɋ߂����̈ʒu�v�̂悤�Ƀ{�����[���܂݂̈ʒu�ɂ��邵�����ĉ^�p���Ă݂Ă��������B �@���ۂɂǂ̂��炢�̍��ɂȂ�̂��͂��̃|���v�Ƃ��g���ɂȂ��Ă���o�b�e���[�̑g�ݍ��킹�Ŏ������Ă݂Ȃ��Ɛ��l���킩��܂���B �@�����Ă��̏ꍇ�A���[�d�œd���ω������Ȃ����ɒ��߂��Ă����A�e�ʂ������ēd���ω����傫���Ȃ��Ă����܂������͂���Ǝv���܂����A�ω�����ʂ��傫���ꍇ�ɂ͂܂�����Ƀ��[�^�[������Ă���Ԃł������ȃK�\������/���ׂ̕ω��ł̓d���ϓ����A�ł��q���ɐݒ肵�Ă���ݒ�l���Ă��܂��ēr���Œ�~���Ă��܂����Ƃ����邩������܂���B �@���̏ꍇ�͐ݒ�l��ς���̂ł͂Ȃ��A����/�r�����Ɂu�ċL���v�����āA����ƏI�����ɋ߂����̓d�����L���d���Ƃ��Ďg�p����A���쒆�̕s����ȕϓ��̉e���͎ɂ����Ȃ�܂��B �@�{��H�ɂ́u�ً}��~�X�C�b�`�v�͂��Ă��܂���̂ŁA���쒆�ɒ�~���������ꍇ�́u�d���v�X�C�b�`����Ă��������B ���Ԏ� 2010/9/20
|
||
| ���e |
�����b�ɂȂ�܂��B ��ϑf���炵����H��v���������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂����B��������̏����Ƃ��Ď��ۂ̊��̑f�q�̔z��E�z�����܂��l�������Ǝv���܂��B���͓d�q�I�Ȓm�����قƂ�ǂ���܂��A�ڂ�����������ǂ�ʼn�H�̍\���E�d�g�݂���܂��ɂ͗����ł����悤�Ɏv���܂��B�d���������d���l���m�����̕����d���̈���x�����ɂ�����炸���m���₷���Ƃ̂��Ƃł������A��H�������12V7Ah������^�̎����ԗp�o�b�e���[�œd���ϓ�������菬�����ꍇ�ɂǂ��Ȃ邩�������Ă݂����Ǝv���܂��B ���̓x�͂ǂ������肪�Ƃ��������܂����B ubebe �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͂��̉�H�Ŏ���E�e�X�g���s���Ă݂Ă��������B �@�o�b�e���[���ς�������ɂ��܂������Ȃ��ꍇ�́A�ꕔ�̕ύX�œd�����m�����ɉ����ł��܂��B �@���̍ۂɂ͒ʏ퓮�쎞�̃|���v���[�^�[�̏���d�����킩��Ȃ��ƓK������H���v�ł��܂���̂ŁA�d���l���Y���Ă��m�点���������B �@�ق��ɂ��A����̂悤�ɒʏ퓮�쎞�̓d��(�܂��͓d��)���L����������@�ȊO�ɁA�u�ˑR�d��(�܂��͓d���c�̂ق����]�܂���)���ω������������m����v�Ƃ������@������A���̏ꍇ�͋������͂��߂ăK�\�����ʂ������邤���ɏ��������ׂ��ω����ēd��(�d��)�����X�ɕω�����ꍇ�̋L���������̂Ƃ́u���v���傫���Ȃ��āA�ݒ�d�������������Ă����ĕq���ɂȂ��Ă��鎞�Ɍ�쓮����m�����Ⴍ�Ȃ�܂��B �@�A���d���܂��͓d���̕ω��ʂ�������x�ȏ�傫���Ȃ��Ɛ��������肵�ɂ����̂ŁA�꒷��Z�ł��B �@�܂��́E�E�E���̉�H�ł��܂��䂭���Ƃ����F�肵�Ă��܂��B ���Ԏ� 2010/9/20
|
||
| NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� | |||
|
�����ɂȂ�܂��B�{�y�[�W�q�������X�̌����ȉɊ��Q���Ă���܂��B �����k�����Ē����������Ƃ�����܂��ē��e���܂����B ���͓d�C�ɂ��Ăقڑf�l�ƌ����Ă����قǂȂ̂ł����A����ɂ�NaPiOn�̐l���Z���T�[��p�����ȈՂȖh�ƃu�U�[���撣���Đ��쒆�ł���܂��āA2SC1815�ɂăZ���T�[�̏o�͂ŃX�C�b�`���O���u�U�[��炷��H���쐬�v���܂����B(�P3�~4��6V�ɂāB) �����Z���T�[�ɔ������u�U�[���镨�͏o�����̂ł����A�����ōX�ɃZ���T�[�̏o�͐M����p���ĊO���o�͂̐ړ_�����o���d�l�ɂ���׃����[�����܂������Ǝv���AOMRON��G6A-274P���_�[�����g���ɂč\�����A��L�̃u�U�[��H�ƕ���ɂ���(�Z���T�[�o�͂̎��̃x�[�X��R�����B)�쐬���Ă݂��̂ł����A�����[������Ƃ�����Ƃ����킸�E�E�E�B�d�����v�������烊���[�ɂ�2.3�u�������Ă��炸�B�B�B�ʂ����Đv������ł����̂����番����Ȃ��A�������Ă��鎟��ł��B ��H�̏����Ƃ��� �@�@�@ 6V �@�@�A NaPiOn�g�p �@�@�B �����[��OMRON��G6A-274P���g������(�莝���̈�)�A �ł��B ������������ƗL��ł��B ������ �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@����́E�E�E�E�����Ȃ��Ǝv���܂��B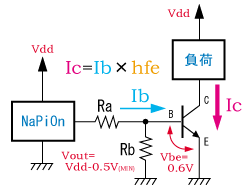 �@���ʁA���炩�̐M���o�͂Ńg�����W�X�^���g�p���ĕ���(�����v�E�u�U�[�E�����[�Ȃ�)���쓮����ꍇ�A�E�}�̂悤�Ȍv�Z���Ńx�[�X��RRa�̒l�����߂܂���ˁB
�@���ʁA���炩�̐M���o�͂Ńg�����W�X�^���g�p���ĕ���(�����v�E�u�U�[�E�����[�Ȃ�)���쓮����ꍇ�A�E�}�̂悤�Ȍv�Z���Ńx�[�X��RRa�̒l�����߂܂���ˁB�@�g�����W�X�^�̃x�[�X��R�́A���̃g�����W�X�^�̐��\�E��i�ɂ��킹�Čv�Z���Ă��Ă�����̂ŁA�ڑ�����g�����W�X�^���ς�����R�l�͌v�Z���Ȃ����ł��B �@���ɓd���d��Vdd=6V�Ƃ��āANaPiOn�̏o�͒[�q����ő�l��100��A�����o���悤�ɂ���Ƃ�������ARa = (6-0.5-0.6)/100�� = 49,000�ƂȂ�A49K���ȏ�(�ɂ��イ�Ԃ�傫��)��R���g����NaPiOn���Ȃ��͈��Ŏg�p�ł��܂��B �� NaPiOn�����g�p����ۂɂ̓x�[�X�J�����Ɍ�쓮���Ȃ��悤��Rb���K�v�A�A����̌v�Z�ł͊ȕւȐ����ɂ��邽��Rb�͖�����ԂŌv�Z���Ă��܂��B �� NaPiOn�̏o�͓d����Vdd-0.5V�܂ō~�����Ȃ��ꍇ�͂��������d���l�͑�����̂ŁA��R�l�͂����܂ōl������Ɨǂ��B �@�����āA��������100��A�̃x�[�X�d����2SC1815�ɗ��������ɂ�(�R���N�^�d���E�d���Ƃ����x�Ƃ��F�X�ƊW���鐔�l�͂���܂����A�����܂��Ɍv�Z���āc)hfe=150�Ƃ���Ic=15mA�����ׂɗ�����d���l�̍ő�l�ƂȂ�A�uLED������炢�v�Ȃ�Ȃ�Ƃ��쓮�ł�����x�ł����g�p�ł��܂���B �@�����������x�[�X��R�l�Ńu�U�[�̋쓮��H������Ă���Ƃ�����A�ƂĂ����d���̃u�U�[����A����Ɩ点����x�ł��傤�B �@�����Ń����[��������x�̑傫�ȓd����������X�C�b�`�Ƃ��āu�g�����W�X�^�̃_�[�����g���ڑ��v�܂Ŏv�����ꂽ�̂͗ǂ����Ƃł��B �@�ł������Ŗ�肪�B >�Z���T�[�o�͂̎��̃x�[�X��R����� �ƁA�������ȏ�����_�[�����g���g�����W�X�^�p�̃x�[�X�d�������o���Ă͂��܂��H �@��ŏ������Ƃ���A�g�����W�X�^�̃x�[�X��R�������ɂȂ��g�����W�X�^�̒�i�Ȃǂɉ����Čv�Z������̂ł��B �@�p���[�A���v�̍ŏI�i�A�����ꕔ�̓d����H�Ȃǂł̓g�����W�X�^������ɂ��ăp���[���҂��悤�Ȏg���������܂����A���̏ꍇ�͂���p�Ɍv�Z�����x�[�X��R���g���܂����A����ڑ�����p���[�g�����W�X�^�͑S�Ă����\�E�i�������S�ɑ����������g�p���A�������\���Ⴄ�g�����W�X�^���������肵���痬���d���l�Ƀo�����������āA�R���N�^�d�����ꕔ�ɕ��ĉߓd���Ȃ�g�����W�X�^��j�܂��B �@����������Ă���u�Z���T�[�o�͂̎��̃x�[�X��R�����v�_�[�����g���g�����W�X�^�Ƀx�[�X�d��������Ă���Ȃ�A���̉�H�}�̂悤�ɂȂ��Ă���͂��ł��B  �@�ŏ��ɍ���Ă���u�U�[�p�̉�H�ƌ�ō���������[�p�̉�H�͑S���ʁX�̃g�����W�X�^��H�ł�����A���ꂼ��ɐ������v�Z�Œl�����߂��x�[�X��R���Ƃ���A�܂��Q�̃g�����W�X�^��H�ɗ����x�[�X�d���̍��v��100��A���Ȃ��悤�ɂ��v�Z���Ȃ���Ȃ�܂���B 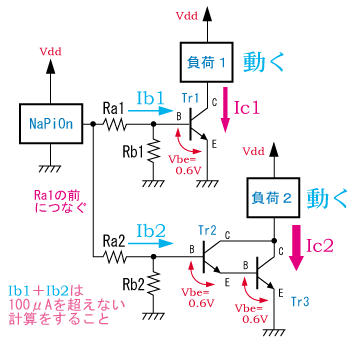 �@�ŏ��̃u�U�[�̑����_�[�����g���g�����W�X�^�\���ɂ��āA�u�U�[�ɂ������[�ɂ����ꂼ�ꂶ�イ�Ԃ�ȓd����������悤�ɐv�ύX���܂����H �@���́E�E�E�ENaPiOn�̏o�͂Ńg�����W�X�^�����Ă���l���߂��������Ȃ��Ǝv���܂��B �@�u����ȓd���o�͂Ńg�����W�X�^�����āA�傫�ȕ��ׂ�����������v�ɂ͂����Ă��̉ۑ肩������܂��A�o��100��A�ł̓g�����W�X�^���g���ĉ��������ɂ͑�������������܂��B �@�g�����W�X�^�A���v���Q�i�ȏ�ɂ���Ƃ��A�_�[�����g���ڑ��Ŏg�p����Ƃ��A�E�E�E�ł��Ȃ����͖����̂ł�肽�����ׂ͂ɂ����̂ł����B �@������NaPiOn�ɂ��Ă����炢�����Ă݂܂��傤�B �@�u�œd�^ MP���[�V�����Z���T �i�s�I�� NaPiOn�v�͒����^�ŒP�d���E�ȓd�́E�m���ȃZ���T�[����(�f�W�^���o��)�ƁA�l���Z���T�[���p�@��삷��ɂ͂ƂĂ��ׂ��ȏ��i�ł��B �@NaPiOn�f�W�^���o�̓^�C�v�̏o�͂� �E���o�� �� HI���x��(������100��A / Vout��Vdd-0.5V) �E�o �� �I�[�v�� �ɂȂ��Ă��܂��B �@�o�͓d����������100��A�܂��ƂȂ��Ă���̂́A������IC��H�̏o�͒i�����̒��x�̓d���܂ł��������Ȃ��d�l(�f�W�^��HI���x�����ێ��ł��Ȃ������ŁA����̂͂���������)�Ȃ̂ł����A���̎d�l��NaPiOn���uC-MOS���͂ȂǁA�d����K�v�Ƃ��Ȃ����͒[�q��������IC�ELSI�ȂǂƐڑ��������߂̂����v�ł��鎖������킵�Ă��܂��B �@�M����LOW�̎��ɏo�͂��I�[�v���ɂȂ�܂�����AC-MOS IC��FET���͂̏ꍇ���v���_�E����R���Ƃ���Ȃ��ƊJ���ł̓m�C�Y��Ód�C�ȂǂŌ�쓮���Ă��܂��܂��B �@���̂��߂ɂ���u�v���_�E����R�ɏo�͂�HI�̍ۂɗ����d����100��A�ȉ��ɂȂ�悤�Ȑv�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��̍ő��i�ł�����܂��B����ȏ�v���_�E����R�ɓd�������o���Ă��܂��ƁA�o�͓d�����h���b�v���ăf�W�^���M����HI�d���������A����ɓ��삵�Ȃ��Ȃ邩��ł��ˁB �@�ł�����E�E�ENaPiOn�ɂ͕��ʂ͐���ɓ��삷�邽�߂��v���_�E����R�ƁA����Ő������f�W�^���M���������o�͂����d���œ��͂ł���uC-MOS�^�}�C�R���`�b�v�v�uC-MOS ���W�b�NIC�v�uFET�v�Ȃǂ�ڑ����܂��B (�悭�l�b�g�Ō��J����Ă����H�}�������Ȃ��Ă���͂��ł��c) 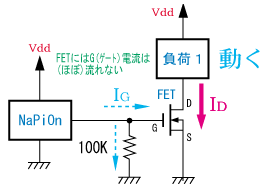 �@NaPiOn�̏o�͂ŒP�Ƀu�U�[����[���������ꍇ�AMOS �p���[ FET�Ȃǂ�FET���g�p���ĕ��ׂ��X�C�b�`���O����̂���ʓI�ł��B
�@NaPiOn�̏o�͂ŒP�Ƀu�U�[����[���������ꍇ�AMOS �p���[ FET�Ȃǂ�FET���g�p���ĕ��ׂ��X�C�b�`���O����̂���ʓI�ł��B�@�E�}�̉�H�}��FET��2SK2961���g���Ε��ׂ͍ő�2A(���S�������1A�ȉ�)�܂ł̋@�킪�g�p�ł��܂��B����2SK2231�Ȃ�ő�5A�A2SK2232�Ȃ�ő�25A�ȂǁA�ׂ�FET���u�U�[�p�ƃ����[�p�ȂǕ�������ׂȂ��Ă��A�P��FET�����ŕ����̕��ׂ���x�ɂȂ��ł����イ�Ԃ�ȓd���𗬂����Ƃ��ł��܂��B �� ��d���Ŏg�p����Ȃ���M�Ȃǂ̒��ӂ��K�v�ł��B �� �R�C���ȂǗU�����ׂ̏ꍇ�͓˓��d���l���悭���ׂĒ�i���Ŏg�p���Ă��������B �@2SK2961���g�p���Ă��A��2SC1815�ł��イ�Ԃ���Ă���u�U�[�ƁAOMRON G6A-274P�����ɂȂ��ł��S���]�T�ŗ������삵�܂��ˁB 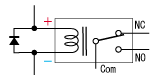 �@��̉�H�}�ł͐l�ɂ���ĕ��ׂɉ����Ȃ����ς��Ǝv���܂��̂ŒP�Ɂu�����v�Ə����Ă��܂����A�R�C�������U�������̏ꍇ�͕K���t�N�d�͂ɂ���Q�̖h�~�p�ɃR�C���ƕ���Ƀ_�C�I�[�h���Ƃ���Ă��������B
�@��̉�H�}�ł͐l�ɂ���ĕ��ׂɉ����Ȃ����ς��Ǝv���܂��̂ŒP�Ɂu�����v�Ə����Ă��܂����A�R�C�������U�������̏ꍇ�͕K���t�N�d�͂ɂ���Q�̖h�~�p�ɃR�C���ƕ���Ƀ_�C�I�[�h���Ƃ���Ă��������B�@�R�C���ɓd��������Ȃ��Ȃ鎞�ɔ�������t�d���p���X�Ńg�����W�X�^��FET�Ȃǂ��t�d���j��鎖������܂��B ���Ԏ� 2010/9/3
|
||
| ���e |
�����肪�Ƃ��������܂��B���i�B���ł��ĕԎ����x���Ȃ�܂������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B FET�̒m���ɑa�����̂ŁA����Ă̒ʂ�2SK2961���w�����}�̂悤�ɍ\�����Ă݂܂����B(Vdd-�h���C���ԂɃu�U�[�ƃ����[�����ɐڑ�) ����������A�u�U�[�͖������̂̃����[�����삹���E�E�E�B�����[��+-�d���𑪒肵����6V�͗��Ă����̂ŁA�d���l������Ȃ����̂Ɣ��f���ėǂ��̂ł��傤���H ���P��Ƃ��čl�����̂��A �@NaPiOn�̏o�͂�������FET��2�q���e�X�ɕ��ׂ�ڑ�����B �A�v���_�E����R�l��ς���B(C1815�̂悤�ȃx�[�X��R�����߂�Ԋu?) �Ȃ̂ł����E�E�E�B���m�ł��p���������ł�����w���Ղ��܂��Ə�����܂��B��낵�����肢�v���܂��B ������ �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�ƂĂ���{�I�ȕ����̎���ł��݂܂��A�����[�͂����Ɠ������e�X�g���Ă���g���Ă��܂����H �@�܂�AOMRON��G6A-274P�̂P�s���ɓd���́{�A16�s���Ɂ|�ڂȂ��Ń����[���u�J�`�J�`�v�Ɖ����o���ē��삵�Ă��鎖�͊m�F���Ă��܂����H �@�����āA���́{�Ɓ|���Ԉ�킸��Vdd��FET��D�ɐڑ����Ă��܂����H �@G6A/G6B��DC�^�C�v�ɂ̓����[�̃R�C���ɋɐ�������܂��B�{�Ɓ|���t�ɂȂ������삵�܂����B �@���Ȃ݂�G5V��DC�^�C�v�ɂ�DC�ł����R�C���ɋɐ��͂���܂���A�{�Ɓ|���ǂ���ɂȂ��ł����삵�܂��B �@�u�莝���̈��v�Ƃ���������Ă���̂ŁA�ȑO�����Ɏg����G6A�̐������g�����ɂ��Ă͂����m���Ƃ͎v���܂����A�ꉞ�m�F���Ă��������B 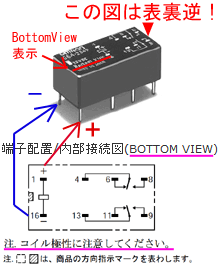 �@���S�҂̕����悭�Ԉ����_�ɁAOMRON��HP���f�[�^�V�[�g�ł̓s���z�u���uBOTTOM VIEW(�ꂩ�猩���})�v�Ƃ��ď�����Ă���_�ł��B�����TOP VIEW(�ォ�猩���})�Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��ƁA�P�s����16�s���͂܂������t�ɂȂ�܂�����A�{�Ɓ|�̐ڑ����Ԉ���ă����[�͓��삵�܂���B
�@���S�҂̕����悭�Ԉ����_�ɁAOMRON��HP���f�[�^�V�[�g�ł̓s���z�u���uBOTTOM VIEW(�ꂩ�猩���})�v�Ƃ��ď�����Ă���_�ł��B�����TOP VIEW(�ォ�猩���})�Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��ƁA�P�s����16�s���͂܂������t�ɂȂ�܂�����A�{�Ɓ|�̐ڑ����Ԉ���ă����[�͓��삵�܂���B�@�����J��G6A/G6B�^�C�v�����[�̏�ʂɂ̓s���z�u�}���v�����g����Ă��āA����BOTTOM VIEW�Ƃ͂����菑����Ă��܂���BOTTOM VIEW�̈Ӗ���m��Ȃ��l�́u�ォ�猩�Ă��̐}�̒ʂ�ɔz������Γ����v�����Ⴂ���ăR�C���̋ɐ����t�ɂȂ��ł��܂��āu�����[�������Ȃ��I�v�Ƒ�Q�Ă���ꍇ�������ł��B �@IC�Ȃǂ̃s���z�u�͕��ʂ�TOP VIEW(�ォ�猩���})�ŏ�����Ă��܂��B �@�ł�����z�����鎞�����i��u���Ă�����ォ�猩���ʂ�Ƀs���z�u���l���Ĕz����������̂ł����A�����[�Ɋւ��Ă�BOTTOM VIEW(�����猩���})�Ńs���z�u�}�������̂���ʓI�ł��B �@����͐̂���u����Ձv�Ȃǂ̑傫�Ȕz���Ղő�^�̐���p��d�͗p�̃����[���g���ꍇ�A�z�����������猩��(������)�s���̂���ʓI�Ȃ��߁A���̍ۂɍ�Ƃ����₷���悤�Ɂu�������猩���}�v�Ŏ����ق����ԈႢ�������Ƃ���Ă������߂ƍl�����܂��B (�����[�ł��l�W���ߔz�����̃\�P�b�g���g���ꍇ�͗����ł͖����\�����猩��̂ł܂����肪�Ⴄ�̂ł����E�E�E) �@NaPiOn��FET(2SK2961)�łȂ�G6A-274P 6V (33.3mA)��10�`20����ɂȂ��ł��]�T�Ńh���C�u�ł��܂�����A2SC1815�Ŗ点�Ă���(���d���Ŗ�)�u�U�[�ƕ���ł�������ł͂���܂���B �@���̒m�����ł́A�����[�̋ɐ����ԈႦ�Ă���ȊO�ɓ��삵�Ȃ������͍l�����܂���̂ŁA��x�����[�̔z���E�ɐ����m�F���Ă��������B ���Ԏ� 2010/9/10
|
||
| ���e |
���}�Ȃ����肪�Ƃ��������܂��B ���p�����������ƂɁA��ʂ�{�Ɓ|�̌�z���ɂ����̂ł����B�B�B �����u�U�[�ƃ����[���쓮�����邱�Ƃ��o���܂����B ����͂ƂĂ��I�m�Ȍ�w�����肪�Ƃ��������܂����B���s�����g�ɐ��݂��̂ŁA���ꂩ���H�̕��ɐ��i���čs�������Ǝv���܂��B ������ �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����ĂȂɂ��ł��B �@��������āE�E�E�E�F�X�g���u����̌����Ēm�����g�ɂ��Ă䂭�̂ŁA�܂������ʔ����Ǝv�������̂�g�ݗ��ĂėV��ł݂Ă��������B ���Ԏ� 2010/9/16
|
||
| �Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� | |||
|
�@�n�߂܂��āB���~�̑O������ǂ��������̂������ĕ����炸�����Ă��ĔY��ł��ăl�b�g�Ō������Č��܂�����A�M�a�̃z�[���y�[�W�ɂ��ǂ�t�����e��q�������Ă��炢�A���X�̉Ɋ��Q�������ł��B���̑��k���e�̏d�������������Ǝv���̂ł����A�������߂����ł�����\����܂���B �@���݁A�和�̕\�D��LED�ɂďƖ������Ă���܂��BCDS�̖��ÃZ���T�[�ƃ^�C�}�[(�Â��ɂ��_����APIC�g�p��1���ԒP�ʂ̐ݒ�ŏ������ł��܂�)�̕��p�ł��B�Ƃ��낪�_���Ǝv���鎞�Ԃ���ݒ�̎��Ԃŏ������Ă���܂���B�l�e��A�Ԃ̃��C�g���ŗ\��O�̓_���A����������悤�ł��B�_���̃^�C�~���O�����Ă݂��̂ł������܂��䂫�܂���B�ϕ���H�A�x����H�A���g�������ȋC������̂ł����A�Ȃ��Ȃ������ł����܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂���B��莞�ԓ�����Ԃ�������(�������ω�����)�ꍇ�̂ݓ���(���E��)�����H������������������K���ł��B�Ȃ��APIC���g�p���Ȃ���2�`10���Ԉʂ̃^�C�}�[�����܂��ł��傤���H�������́APIC�̎g�p�Ŗ��ÃZ���T�[���ƃ^�C�}�[�����ꏏ�ɂ��邱�Ƃ��\�ł��傤���H �����\�ł��������̂ق�������������������K���ł��B ��)�^�C�}�[��H�Q�� http://www.zea.jp/audio/tim/pica_01.htm��L��AC�A�_�v�^�[5V�œ��삳���Ă��܂��B 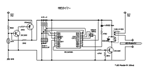 ��H�}�͂�����ł�
��H�}�͂�����ł��� �N���b�N����Ɗg��\�� �C�b�`���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@��ɗ]�k����E�E�E�B �@���݂��g���̉�H�}�ŁACds�̂Ƃ����50K���Ƃ�����R��������Ă��܂����A1%������R�ł���������50K���Ƃ�����R�͔����Ă��Ȃ��͂��BE-24�n��̒�R����51K���ł���ˁB �@�悭����Cds���g�������邳�Z���T�[�̉�H�}�ŁA�����ɂ�50K���̔��Œ��R���g���Ă��邱�Ƃ������̂ł����A���������Ĕ��Œ��R�ƌŒ��R���Ԉ���Ă���Ƃ��H �@�����[�̂Ƃ���ɓ�̕��i�����Ă��܂��ˁB �@2SD2076���Ăǂ�ȃg�����W�X�^�Ȃ�ł��傤�H �@���ʂ����ɂ͋t�d���ی�p�Ƀ_�C�I�[�h������̂ŁA1S2076A�Ƃ��̏����ԈႢ��(����HP�ł�10D1�ł���)�A����ł��}�L�����V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�݂����Ɍ�����̂ŁA1S2076A���̒ʏ�̃_�C�I�[�h�ł͂Ȃ�����ς�2SD2076�Ƃ����܂�Ńg�����W�X�^�̂悤�Ȍ^�Ԃ̃V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h���ǂ����Ŕ����Ă���̂��E�E�E�B �@����LED��100mA���x�̏���d���Ȃ�A�킴�킴�����[���g��Ȃ��Ă�PIC�Ő��䂵�Ă���g�����W�X�^�Œ��ړ_���ł���̂ɁE�E�E�Ƃ��B �@�͂��B�]�k�͂����܂ŁB �@�u�_���Ǝv���鎞�Ԃ���ݒ�̎��Ԃŏ������Ă���܂����v�Ƃ����̂́A���̉�H�ł͂�����܂��ɋN���肤�錻�ۂ��Ǝv���܂��B �@���̉�H�̓�����悭�l���Ă݂܂��傤�B �� Cds�Z���T�[��H �@Cds�ƃg�����W�X�^�ō\�������Z���T�[��H�́A�u���邢�Ɠd���o��OFF�v�u�Â��Ɠd���o��ON�v�Ƃ�����H�ł��ˁB �@�����ɓ��Ɏ��萔��H(�^�C�}�[)�͖����̂ŁA���ԂɈ�u�����ŃZ���T�[���Â��Ȃ�Ƃ��A��ԂɈ�u�Ԃ̃��C�g��������Ƃ��ł��o�͕͂ω����܂��B �� PIC�ɂ��^�C�}�[��H �@PIC�̃v���O�����łP���ԒP�ʂ̃^�C�}�[���\�����Ă��܂����A�u�d��ON����xx���Ԃ���ON�v(xx�̓X�C�b�`�Őݒ�)�Ƃ����^�C�}�[�ł��ˁB �@����HP�̉�H�}��AC�d��ON�ň�莞�ԓ��삳����^�C�}�[�ŁA�^�C�}�[���Ԃ��߂��ăX�C�b�`�����A�������g�̓d�������Ă��܂��đҋ@�d�͂O�ɂ����Ƃ����G�R�v�̃^�C�}�[�ł��B �@���̂߂��Ɂu�d�������������ɏo�͂�ON�v�u���Ԍv���͓d���������������炷���͂��߂��v�Ƃ����v���O�����ɂȂ��Ă��܂��B �� �s������H �@���̃^�C�}�[�pPIC��H���ACds�ɂ�閾�邳�Z���T�[�Łu�Â��Ԃ͓_���v�u��莞�Ԃ�����������v�Ƃ������ɂ����悤�Ƒg�ݗ��Ă�ꂽ�悤�ł����E�E�E�E�B �s�������ԂɁA��u�Z���T�[�̑O��l�������ĉA�ɂȂ������t �@�A�ɂȂ����u�Ԃ�Cds�Z���T�[��H�������APIC�^�C�}�[�ɓd������������܂��B �@LED�����v���_�����܂��B �@�ł��A�l���ʂ�߂��Ă܂����邭�Ȃ�����A���̏u�Ԃɓd�������̂�LED�͏������Ă��܂��܂��B �@�������PIC�̃^�C�}�[���d�����ꂽ�炻��ȏ�͓������Ƃ͂ł��܂���B �@�A�ɂȂ������Ԃ���LED���_�����Ă��܂��܂����A���i�g���u���Ƃ������ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �s������ԂɁA��u�Z���T�[�ɎԂ̃��C�g���������Ă��܂������t �@��ԁACds�Z���T�[�����Â��ĉ�H�̓d��������APIC�^�C�}�[�������w���xx���ԂɂȂ�܂�LED�����v��ON�ɂȂ��Ă�����ԁB �@�Ȃɂ��Ƃ���������̂܂�xx���Ԍo�ߌ�Ƀ^�C�}�[�����LED���������܂��ˁB �@���ꂩ�Axx���Ԃ�葁���������Ď��͂����邭�Ȃ�ACds�Z���T�[��H���d�������LED���������܂��B �@�ł������ACds�Z���T�[���ɎԂ̃��C�g�������̌�����u�ł�����������H �@�Z���T�[�́u�������������̂��H�v�ƌ��ɔ������ĉ�H�̓d������Ă��܂��܂��B �@�����ĎԂ̃��C�g���ʂ�߂���Ƃ܂��^���ÂɂȂ�A�Z���T�[�́u�����邩�H�A�Z�����������ȁc�v�Ɖ�H�̓d������Ă܂�LED�����v��_�������܂��B �@�����H �@�����钆�ɂ��̂悤�ȎԂ̃��C�g���������Ĉ�u���ԂɂȂ����Ɗ��Ⴂ����^�C�~���O�����������ꍇ�APIC�^�C�}�[�͈�x��~���A�ēx�d�����������u�Ԃ���܂�������������������xx������LED�����v��_���������悤�Ɠ����܂��B �@�܂肱�̉�H�́u�钆�A�Ƃ̑O���Ԃ��ʂ�����A��������xx���ԃ����v��_��������(���Ԃ�����������)��H�v�Ƃ��������ȃ^�C�}�[��H�ɂȂ��Ă���킯�ł��ˁB �@�������������ɂ́E�E�E Cds�Z���T�[���������ɓ���āA
��Ɍ����Ēn��̌�������Ȃ��悤�ɂ���I �@�Ƃ����̂͂ǂ��ł��傤���H�i�O�O�G �@�J������Ȃ��悤�ɓ����Ȗh���̃t�^�����āE�E�E�B �@����ς肾�߂ł����H �@�P��UFO���^������쓮�����Ⴂ�܂���ˁE�E�E�B �@�J���^���ȉ��P���@�Ƃ��āACds�ɑ�e�ʂ̓d���R���f���T��������āACds�̒�R�l�ω����}���ł��g�����W�X�^�̃x�[�X�d���������ɕς��Ȃ��悤�ɂ���E�E�E�Ƃ����ƂĂ������Ĉ��Ղɂł�����@���l�����܂��B �@�����A���̕��@���Ƃ�����Cds�Z���T�[��H���g�����W�X�^�Q�ŃV���~�b�g��H���`�����Ă���Ƃ͂����ACds�̔������u�ڂ�`�v���Ɠd���ω����Ă��܂����߁APIC��H�ւ̏o�͓d�����u�ڂ�`�v���ƕω����ăp�`�b��ON/OFF���Ȃ��Ȃ�܂��B �@PIC�̐ݒ�Ȃǂɂ����܂����A������������ӂ�ȓd����PIC�삳����̂���쓮�̌��ł��B �@����āA2SA1015���璼��PIC��H�֓d�����������Ă��܂����A2AS1015�Ń����[����������A���̃����[��PIC��H�ւ̓d����ON/OFF����ȂǃJ�b�`���Ɠd����ON/OFF�ł����H�ɉ��P����K�v���o�Ă��܂��B �@�������́A�����ƃg�����W�X�^�𑝂₵�Ă�������ON/OFF����X�C�b�`���O��H����邩�E�E�E�B �@Cds�Ŗ��邳�����m���āA�Ȃ�ƂȂ�LED�Ɩ���_��/����������悤�ȉ�H�Ȃ�Cds�ɓd���R���f���T��������邾���ł��u��u�̖��邳�ω��ɂ͔������Ȃ��v���̂��ł��܂����APIC��H�Ȃǂ̓d���𑀍삷��ɂ͂��̉�H�}�ɕ��i���������������ł͂�����Ɩ���������܂��B �@�ł́A��͂��܂����Ɂu��u�̕ω��ł͔������Ȃ��v�u��莞�ԏ�Ԃ��p�������ꍇ�������������v��H������āACds�Z���T�[�̔������^�C�}�[����쓮���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B 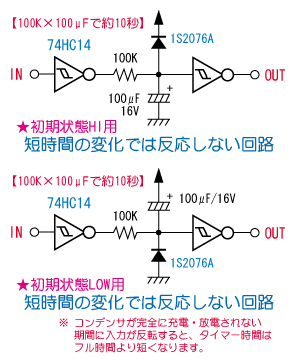 �@�E�}���u��u�̕ω��ł͔������Ȃ��v�u��莞�ԏ�Ԃ��p�������ꍇ�������������v��H�ł��B
�@�E�}���u��u�̕ω��ł͔������Ȃ��v�u��莞�ԏ�Ԃ��p�������ꍇ�������������v��H�ł��B�@�ǂ���̉�H����U����ԂɂȂ��Ă��܂��Γ���͓����Ȃ̂ł����A�ŏ��ɓd������ꂽ�Ƃ��ɓ���(�o��)��H�̂�L�Ȃ̂��ʼn�H�͂Q��ނ���܂��B �@�u�K��ɖ����Ȃ��v�Ɣ��肷�鎞�Ԃ́A100K���~100��F����10�b�ł��B �@���̎��Ԗ����̕ω��ł͏o�͕͂ς��܂���B �@�A���A�V���~�b�g�Q�[�g��臒l�̊W�ŁA���Ƃ���H�ɂȂ����Ɣ��肷��d���͂܂��d���d���Ɠ������͖����A���ꂩ�����d���R���f���T�͓d���d���Ɠ������Ȃ�܂ŏ[�d���ꑱ���܂��B �@�]���āA臒l�����u�Ԃ���t�����ɕ��d���͂��߂��ꍇ�A����L�Ɣ��肷��܂ł̎��Ԃ͊��S�ɏ[�d���ꂽ��Ԃ�����d���J�n�������Z���Ȃ�܂��B �@H��L���t�̏ꍇ�������ł��B �@����ȂɃo�^�o�^�Ə�Ԃ��ς��悤�ȓ��͐M�����ƁA��莞�Ԍp�������Ɣ��肷�鎞�Ԃ͐v�l�̖����炢�ɂȂ�܂����璍�ӂ��K�v�ł��B �@������������Ԃ������A���X��u������Ԃ���ւ���Ă��܂��悤�ȏꍇ(����̂���]�̂悤��)��r������悤�Ȏg�����Ȃ�v���Ԓʂ�ɓ����܂��B �@���̎��萔��H��Cds�Z���T�[��H��PIC�^�C�}�[��H�̊Ԃɓ����ꍇ�A���̂悤�ȉ�H�ɂȂ�܂��B(50K��R�Ȃǂ͌��̉�H�}�ʂ�ɂ��Ă��܂�) ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�Ԃ̃��C�g�������鎞�Ԃ���10�b�ȉ��Ȃ炱��őΏ��ł���͂��ł��B �@���p�I�ȃ��x�����l����A�^�C�}�[���Ԃ͂������������ق����ǂ��Ǝv���܂��̂ŁA��R��470K�����x�ɂ��ĕی쎞�Ԃ��Ƃ����ق����ǂ��ł��傤�B �@���āA���̉�H�͍���̂����k�̉�H�ł͕K�v�͂���܂��A�����ƍ��x�Ȕ������W�b�N��g�ݍ���ŁA�u�K���E���̎��Ԉȏ�H�܂���L�̏�Ԃ������Ȃ��ƁA�o�͂���ւ��Ȃ���H�v�Ƃ������łȂ��̂ł��B �@��L�̉�H�ŃV���~�b�g�Q�[�g�̓����ŁA���S�ɃR���f���T���[�d�E���d���Ă��Ȃ���Ԃœ��͏�Ԃ��ς��ƃ^�C�}�[����(���莞��)���Z���Ȃ�Ƃ������_������܂����B �@��������S�Ɏ�菜���āAH�܂���L�̏�Ԃ��ݒ莞�Ԃ��z���Ȃ���ΐ�ɏo�ٕ͂ω������Ȃ��悤�ɂ�����H�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�uH���K�莞�Ԉȏ㑱�������H�v�uL���K�莞�Ԉȏ㑱�������H�v�̔����ʁX�̉�H�œƎ��ɍs���A�e��H�́u�p�����łȂ���^�C�}�[�p�R���f���T�͑����d�v�����邱�ƂŃ^�C�}�[���Ԃ��O�ɂ��܂��B����Ŋ��S�ɁuH/L�̏�Ԃ��K��ȏ㑱�����ꍇ�̂��v�A�����H�̏o�͂�L�ɂ��܂��B �@�����H�̏o�͂͂��̌��RS-FF�ɓ��͂���A��莞�Ԉȏ㑱�������̏�Ԃ�ێ����܂��B �@RS-FF�͓d��ON���ɏo�͏�Ԃ��s��(���ɂȂ邩�킩��Ȃ�)�Ȃ̂ŁA�p���[�I�����Z�b�g��H�����Ă��܂��B �@�����܂ŋ��łȔ����H��K�v�Ƃ��鑕�u�E���i�Ƃ����̂͂��܂薳���Ǝv���܂����A�ꉞ��H��Ƃ��Ă����Ă����܂��B �@�����čŌ�ɁAPIC���g�����^�C�}�[��H�ł͂���ȓd�q���i��lj����ă^�C�}�[�����H�����Ȃ��Ă��K�v�ȋ@�\�͑S���v���O�����Řd���Ă��܂���̂ŁA�\�[�X�����������ăv���O�����ł���l�Ȃ�lj����i�͒�R��{�I�A�\�Z�T�~���炢�ōς݂܂��B 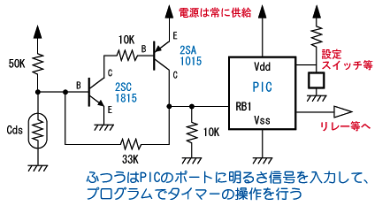 (PIC�̏���d�����c�A�Ƃ��C�ɂȂ�̂ł�����PIC��SLEEP���[�h���w�K���Ă�������) �@Cds�Z���T�[��H��2SA1015�̏o�͓d����PIC�̓��̓|�[�g(���ɗ]���Ă���RB1)�ɐڑ����܂��B(�v���_�E����R�̒lj����K�v�ł�) �@�v���O�����̕ύX�� �� ���������A�o�̓|�[�gRB3��ON�ɂ��Ȃ��I �@���̃v���O�����ł͓d��ON�ő��o�͂�ON�ł�����A����������RB3��ON�ɂ��Ă��܂��B �@�ł��A�����łł́u�Â��Ȃ�v�܂ł͏o�͂�ON�ɂ͂��Ȃ��̂ŁA���������ɂ͏o�͂�OFF�ɂ��Ă����܂��B �� ��������A�܂��́u�Â��Ȃ��v�̂�҂I �@�����Ɂu�X�C�b�`�̓ǂݍ��݁v�u�P���ԑ҂v�^�C�}�[�ɐi�ނ̂ł͂Ȃ��A�܂���RB1�̏�Ԃ�ǂݍ���Łu�Â��Ȃ������H�v�肷��v���O������lj����܂��B �@�������P���ɁuRB1 = H�ɂȂ�����Â��Ȃ����I�v�Ɣ��ʂ���̂ł͂Ȃ��A�w�p������^�C�}�[�x�Ƃ����ϐ�(����T1)������āA�uRB1 = H�Ȃ�T1�J�E���g�A�b�v�v�uT1��30�b�ȏ�ɂȂ�����A�Â��Ȃ����Ɣ��ʁv�u����RB1 = L���Ɩ��邢�̂�T1�̓��Z�b�g�v�Ƃ����v���O�����ɂ��܂��B �@�����Łu30�b�ȏ�Â���Ԃ������v�Ƃ�����Ԃ����m���Ȃ�����A�����ƃ��[�v���ĈÂ��Ȃ�̂�҂��܂��B �@�u30�b�ȏ�Â���Ԃ��������I�v���ɂ́A���[�v���āu�X�C�b�`�̓ǂݍ��݁v�u�P���ԑ҂v�^�C�}�[�ɐi�݂܂��B �� �Â��Ԃ��u���邭�Ȃ��v�̂���ɒ��ׂ�I �@���̃v���O�����ł́u�P���ԁv�����ɋK��̃^�C�}�[���ԂɂȂ��������肵�A�K�莞�ԂȂ�o�͂�OFF�ɂ��Ă��܂����A���̂P���Ԃ�҂^�C�}�[���ł��u���邭�Ȃ��āA�^�C�}�[�𒆒f����LED����������ׂ���ԂɂȂ��Ă��Ȃ����H�v����������K�v������܂��B �@RB1 = L�łȂ�������Ɍ������A����RB1 = L�Ȃ�u���邢�v��Ԃ��Ɣ��ʂ��܂����A�������ŏ��Ɂu�Â��v�Ɣ��肵�����̂悤�Ɂw�p������^�C�}�[�x�Ƃ����T�O���g�p���āA�����莞��(���Ƃ���30�b)��RB1 = L�����������ǂ����ʂ��Ȃ��ƁA�Ԃ̃w�b�h���C�g����u�������������ł��������Ă��܂��āA���ǂ͍ŏ��̃g���u���Ɠ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�u���邢��Ԃ�xx�b�������v�Ƃ�����Ԃ肵����A�o�͂�OFF�ɂ��āA�v���O�����͍ŏ��́u�Â��Ȃ�̂�҂v���[�`���ɃW�����v���܂��B �@�u�P���Ԍo�������H�v�Ƃ����^�C�}�[�����Ɠ����ɁuRB1 = L��xx�b�ȏ�p���������H�v�Ƃ����������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�v���O�������S�҂̕��ɂ͂��Ȃ�����������܂���B (���荞�݂��g���āA��L�̋��łȔ����H�Ɠ��������o�b�N�O���E���h�ŏ��������A���C���̃^�C�}�[�v���O�������ł͂��̌��ʂ����ĒP��H��L���ʂ��邾���E�E�E�Ƃ������@������܂����A���G�Ȃ̂ŕK�v�Ȃ炲�����ŕ����Ă�������) �@PIC�Ȃǂŋ@�B�����ɂ́A�����������s���ĕ����̏��������Ȃ��悤�v���O���������Ȃ���ΖړI�̑��u���ł��Ȃ����͓��풃�ю��Ƃ����Ă����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁAPIC�̃v���O�����őΏ������ꍇ�͂��������v���O�����̗��V�����Ѓ}�X�^�[���Ă��������B �@������̃R�[�i�[�ł�PIC�̃v���O�����̋�̓I�ȃR�[�h�Ȃǂ͂��������Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��̂ŁA�v���O�����͂������ŏK���E���ǂ��Ă��������B ���Ԏ� 2010/8/22
|
||
| ���e |
�����̂��L��������܂��B �]�k�̂Ƃ���ł̂��w�E�\����܂���B���w�E�ʂ�ł��B �_���^�C�~���O�̒�����A��H�}���C�����Ă��Ȃ������̂ŁA�A�b�v�O�ɂ���ĂďC�����ԈႦ�Ă��܂��܂����B�g�����W�X�^�� "1S2076A" �����ł��B�N���̂�鎖�Ƃ��������������B (�����̎v���Ƃ�)�듮��̉���͗����ł��܂����B �u�������ԂɁA��u�Z���T�[�̑O��l�������ĉA�ɂȂ������v�͖������āA�u������ԂɁA��u�Z���T�[�ɎԂ̃��C�g���������Ă��܂������v�����l����悢�Ƃ������Ƃɂ��āA�u�������LOW�p�E�Z���Ԃ̕ω��ł͔������Ȃ���H�v�Ɏ��g�݂����Ǝv���܂��B���� "74HC14" ���ɍs���܂��B ��Ԗ��͂̂���u�\�Z5�~�v��PIC�}�C�R���̃v���O�����ύX�́A���ݕ����ŁA�����ɂƂ͂��������ɂ���܂��A�߂����ɒ��킵�����Ǝv���܂��B�L��������܂����B(8/22) �C�b�`���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���Ԃ�A�ꕔ�������Ă���悤�Ɏv���܂����A >�u�������ԂɁA��u�Z���T�[�̑O��l�������ĉA�ɂȂ������v�͖������� �@��������K�v�͂���܂��E�E�E�B �@�u�������xxx�p�E�Z���Ԃ̕ω��ł͔������Ȃ���H�v������������d������ꂽ���̂��Ƃł�����A��x�����o���Ă��̑��u�̈�莞�Ԉȏ�̈����ԂɂȂ�ALOW����HI�ɂȂ�̂ł��AHI����LOW�ɂȂ�̂ł��A�ǂ���ł���莞�Ԃ̌o�߂肵�܂��B �@�ϕ���H�̋ɐ��Łu�d������ꂽ���ɂ�LOW��ԂƓ�����Ԃł����H�v�Ȃ̂��u�d������ꂽ���ɂ�HI��ԂƓ�����Ԃł����H�v�Ȃ̂��ɈႢ������A�d������ꂽ���ɃZ���T�[��LOW�Ȃ珉�����LOW�̉�H�A�d������ꂽ���ɃZ���T�[��HI�Ȃ珉�����HI�̉�H���g��Ȃ��ƁA�d������ꂽ���ɃZ���T�[�͓����Ă��Ȃ��̂ɂ��̌��m��H��������M�����o�͂��āA�@�B����쓮��������x��A���[����炵�����ƕs����N����ł���H �i�P������莞�ԃZ���T�[�������H���悢��ł��j �@����̂����k�̉�H�́u�Â��Ȃ����烉���v������v�����Ȃ̂āA������Ԃ��ǂ���̉�H���g���Ă����܂��܂���B �@������Ԃ���H�̓d��������u�Ԃ̃Z���T�[��ԂƋt�Ȃ�A�ŏ���xx�b��(xx�b�͐ݒ�ɂ��)������쓮���邽���ł��B �@�����������ԂɂȂ�A��́u���ԂɈ�u�A�ɂȂ�v�ꍇ�ł��u��ԂɈ�u���邭�Ȃ�ꍇ�v�ł��A�ǂ���ł���莞�Ԃ̓��͕ω������m���Ȃ�����͏o�͕͂ω����܂����B ���Ԏ� 2010/8/26
|
||
| ��莞�ԃZ���T�[�������H | |||
|
����̉����Z���T��ԊO���Z���T�Ȃǂ̓d���������ɓ��삳���Ȃ����@�������ĉ������B�d���������ɃZ���T�ނ���������LED����[���ғ����Ă��܂��ƕs�ւȂ̂ŁA�d���������ɂ̓Z���T���ғ����Ȃ��l�ɂ������̂ł��B�R���f���T�Ȃǂœd�����͎��̏Ռ��H���ɂ₩�ɂ��Ă݂��肵���̂ł����ǂ��ɂ������܂���B��낵�����肢���܂��B Hco �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�ǂ�ȃZ���T(���i)��ǂ�ȉ�H���g���Ă���̂���؏�����Ă��Ȃ��̂ŁA���Ȃ������g���̃Z���T��H�ƍ������ǂ����킩��܂��A��ʓI�ȉ����p�ӂ��܂����B �@NaPiOn�œd�^�l�̌��o�ԊO���Z���T�ȂǁA�d������ꂽ�ۂɓ��������肷��܂Ő��\�b���x�o�͂��o���ςȂ��ɂȂ�悤�ȃZ���T�[�͂�������܂��B �@�������g���ꍇ�͓d������ꂽ�Ƃ��ɔ����E���삵�Ă��ʂɂ����������ł͖����悤�ȋ@��(�P�ɓd�����_������Ƃ�)�Ŏg�p���邩�A�@�푤�ł���������������Ă���肪�����悤�ȕی��H��g�ݍ��݂܂��B (�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�����Ɠd�����Ȃ��p�r�̋@��Ɏg�p����ق��������ł���) �@�d��ON���̔�������������Ȃ�A�u�������鎞�Ԃ̃^�C�}�[�v��AND<���Ƃ邾���ōς݂܂�����A��H���J���^���ł��ˁBbr>  �@�b�E�q�ō\������ϕ���H���[�d�����܂ł̊ԁAAND��H�̕Б���L�̂܂܂Ȃ̂ł����Б��̓��͏�Ԃ�H/L�ǂ���ł��W�Ȃ��o�͂�L�ł��B �@���Ԃ��o���ď[�d����A�_����H�ɂȂ�����Е��̓��͂�AND���Ƃ����o�͂������܂��B74�V���[�Y�ɃV���~�b�g�Q�[�gAND�͖����̂ŃV���~�b�g�Q�[�gNAND���g�p���Ă��܂�����A�o�͘_���͔��]���܂��B �@�^�C�}�[���Ԃ�100K���~100��F�Ŗ�10�b�ł��B �@�������̕K�v�Ȏ��Ԃŕ��i�萔�͕ς��Ă��������B �@���Ɏw�肪����܂���ł����̂ŁA�Z���T�[�Ȃǂ̉�H��TTL/C-MOS���x���o�͂̃f�W�^����H�Ƃ��Ă��������܂����B �@����TTL/C-MOS�d�l�ł͂Ȃ��A�i���O��H�Ȃǂ̏ꍇ�́A������Q�l�ɂ������ʼn�H��v���Ă��������B ���Ԏ� 2010/8/22
|
||
| ���e |
�x��܂������f�l�H��Ŏ����Ԃ̖h�ƃu�U�[������Ă��܂��B �Z���T�͏H���̌Â��ԊO���Z���T�ƁA�ȒP�ȉ����Z���T�ł��B������ԓ��ɉғ�����ƃu�U�[����E�E�l��AND��H��NOT��H�ō���Ă���̂ł����Ԃ����鎞�X�C�b�`�����ău�U�[����ƒp�����܂��̂ŁA�X�C�b�`�����Ċi�D�ǂ������Ă������������̂ł���܂��B���������܂ŗL��������܂��B Hco �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���̗p�r�Ȃ�A10�`30�b���x�̒x���^�C�}�[���炢�ł悳�����ł��ˁB �@�����p�r�I�ɁA�x���^�C�}�[�������āu�Z���T�[�̏�Ԃ����f������ԂɂȂ����v�Ƃ���LED������������ƁA�ԊO���猩�Čx�����@�\���Ă��邩�킩���Ă�����������܂���ˁB �@�d�������Ă܂��^�C�}�[���́u�܂����S�v�Ƃ��ėΐF���FLED���_�����āA�x���ɓ���ƐԐFLED���_�ł���Ƃ��B ���Ԏ� 2010/8/26
|
||
| ���e |
���肪�Ƃ��������܂����B�{����������Ă݂܂������A�d�������Ɖғ��iLED�_���j���Ă��܂��܂��B���[�A�N�e�B�u�^�ŏH���Z���T�o�͂���555�^�C�}�[��2�ԃs���Ɍq���ł���ӏ��ɉ�H���q���ł��܂��B�ŏI�I��555�̏o�͂���Tr�o�R�ŃI�����WLED��_�������Ă��܂��B �d�������Ɠ_�����^�C�}�[�I����A��������̓R���f���T�i��H����100��16F��200�ʂɕς��Ă��܂��j�ɓd�C���[�d�����܂ŁiC�̃v���X������d���v�Ō����2.8V�ʂɂȂ�܂Łj�͔������Ȃ��ł���̂Ő���ғ����Ă���̂��Ǝv���܂����A�d��������̓����h���܂���B �q���ꏊ�������̂ł��傤���H Hco �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����́A�^�C�}�[IC 555�̓����ł��B �@�����Ƃ������E�E�E�E�u�����N�Z�v�̂ق����\���͐������ł��ˁB �@���Ԃ�A���̏�ʼn�H��g�ݗ��ĂāA�����Ńe�X�g������Ă���Ǝv���܂��B �@�����āE�E�E�d������Ă����������̊Ԃ�u�����������ɓd�������āA���̎��ɏ���Ƀ^�C�}�[�����삵�Ă��܂��H (�d������ĉ��������Ԃ��o���Ă��炾�ƌ�쓮���Ȃ��͂��ł����E�E�E) �@�������̏ǏƁA�u�d������������ł��A��H���̃R���f���T�����d���I���܂ł͓d������������Ă���555�͓������ŁA���̊ԂɃg���K�[�[�q��LOW�ɂȂ�Ɠ�����FF���Z�b�g�����̂ŁA���̏�Ԃ����d���X�C�b�`��ON�ɂ��ēd������������Ƒ����Ƀ^�C�}�[�����삵�͂��߂��v�Ƃ����g���u���ł��B �@�H���̃L�b�g�̂܂܂Ȃ�5V�d���̓d���R���f���T��10��F�Ə����ȗe�ʂł����A��������֎~��H�̓d���R���f���T���d��OFF���ɂ̓_�C�I�[�h��ʂ��ēd���ɕ��d���邵����(�������Ȃ���IC����)�Ȃ̂ŁA�^�C�}�[�p�d���R���f���T�̗e�ʂ�傫�����Ă���Ȃ�Ȃ�����d���X�C�b�`����Ă��܂��R���f���T�̓d�C��555�̓������������Ă��鎞�Ԃ͒����Ȃ�܂��B �@�H���̃L�b�g�ȊO�ɉ������q���ł��邩�Ƃ��A�g���Ă����H��C-MOS�f�o�C�X�ŏ���d�����قƂ�ǖ����Ƃ��܂��͗L��Ƃ��E�E�E�A�ɂ��ς��܂������\�b�`�����̓R���f���T�̎c�d����555�܂�肪���삵�����܂��B �@�H���̃L�b�g�̂悤��555�̃����V���b�g�^�C�}�[�̊�{��H�ł́A���Z�b�g�[�q(4)��Vcc�ɂȂ����ςȂ��ɂ��Ă����āA���ɊO�����疾���I�Ƀ��Z�b�g�������Ȃ���H�Ŏg�p���Ă���̂�����ł��B �@�����A���Z�b�g�[�q�ɊO���ɕ��i�����ēd���d����������x�ȉ��ɂȂ����狭���I�Ƀ��Z�b�g����Ȃǂ̉�H(�܂��̓��Z�b�gIC��)��t�������̂��ʓ|�ł��B (555�̓����ɂ��d��ON���̎������Z�b�g��H�͂���܂����A���S�ɓd������Ȃ��Ɠ��삵�܂���) �@�����ŁA���������ꍇ���퓅��i�Ƃ��ėp����̂́u�d���Ƀu���[�_�[��R�������v�Ƃ������@�ł��B �@�d������d���ɑ��ĕ��d����\���̓d���R���f���T�ɗ��܂��Ă���d�C�ŗ\��O�̌�쓮���N�����̂ŁA�g��Ȃ����ɂ͗��܂��Ă���d�C����d�����Ă��܂������̂ł��B �@��̓I�ɂ́A��H���̓d���́{�Ɓ|��1K���`10K���̒�R���q���܂��B�d���p�̓d���R���f���T�́{�Ɓ|�Ɍq���`�������ڂ��������Ƃ킩���Ă����ł��ˁB �@����ŁA�d����OFF�̎��ɓd���R���f���T����d�����đf����0V�ɂ��܂��B�d��OFF���炾���������b���x�Ō�쓮���Ȃ��d���܂ʼn�����܂��B �@�d���d����5V�̏ꍇ�A�d��ON����1K����5mA�A10K����0.5mA�قǗ]�v�ɓd��������܂����A���ꂪ�o�b�e���[�����������Ղ���Ƃ������s�����������͍ł��J���^���ŗL���ł��B �@�d���Ƀu���[�_�[��R�����Ȃ��Ă�������������ȏ�d������Ă����Ȃ�d�������Ă���쓮�͂��Ȃ��͂��ł��B �@���ʂɎԂɏ���āA���Ԃ��鎞�ɑ��u�̓d�������邾���Ȃ���ǂ��Ȃ��Ă���쓮���Ȃ��g�p�ł��܂��B �@�ł��A���u���Z�b�g���Ă���Y�ꕨ�������ŎԂɖ߂�A��x�d�������(���̍ۂɂ͐l���Z���T�[�Ȃǂ����삵�Ă��܂�)�A�����ɂ܂��X�C�b�`����ꂽ���ɂ͌�쓮���Ă��܂��ł��傤����A����ł͂Ȃ���͎{�����ق����ǂ��ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2010/8/30
|
||
| ���e |
�L��������܂��B >�E�E�E�d������Ă��牽�����̊Ԃ�u�����ɂ����ɓd�������āA���̎��ɏ���Ƀ^�C�}�[�����삵�Ă��܂��H �d��OFF����̍ēd���������͋t�ɒx���^�C�}�[�����퓮�삵�Ă��܂��B �܂�A�d�������Ă�LED���_�����Ȃ���Ԃł��B �������Ԃ������āi�T���ʁj�d�������������LED���_���Ă��܂��܂��B �ł��̂ł����������������Ƃ͈Ⴄ�l�ȋC�����܂��B ���̌�A�x����H���n�C�A�N�e�B�u�^�ɕύX���A555�̏o�͂�LED�쓮��Tr�̃x�[�X��R�Ƃ̊Ԃɕt���Ă݂܂������A�d����������LED�_���͌���ꂸ�A�x���^�C�}�[�̉ғ��ɂ��������Ĉ�莞�Ԍ㔽�����܂��B �f�l�l���ł����A�˓��d���Ƃ��������d�C�ɕq����IC�̗ނɉe�����đ@�ׂȃg���K�[�M���z���ĉғ����Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �{��555��HC123�̗l�ȃg���K�[�M���ʼnғ����铮�삷��IC���́A�d������ꂽ���ɔ�������Ռ��g�i�˓��d���H�j���e�����ăg���K�[�M�����������Ȃ��Ă��o�͉ғ����Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H Hco �l
|
||
| ���e |
�E�E�E�����܂����ł��B�j ���݂ɐԊO���Z���T�̃Z���T�������O������A�����Z���T�ŃR���f���T�}�C�N��t���Ȃ���Ԃœd���������Ă݂��LED���_�����܂��B����͋ɒ[�Ɍ�����555���̃g���K�[���͂ɉ����ڑ����Ȃ���Ԃł��d����������Δۉ��Ȃ���IC�����삵�Ă��܂����̂Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H ���̓˓��d���H�݂����ȕ���a�炰����IC�ɉe�������Ȃ����͏o���Ȃ��̂ł��傤���H �f�l�����Ő\����܂��A�����������������ł��傤���B Hco �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�u�H���̃L�b�g���g�p���Ă���v�Ƃ����b���o�����_�Łw�x���֎~��H�́A�H���̃L�b�g(555�̏o��)�̏o�͂ɂ��Ă��������B�H���̃L�b�g��555�����܂Ŋ܂߂āu�P�̃Z���T�[���u�v�ł�����A���̓�����������Ȃ�I�V���X�R�[�v���Ŋϑ����Ċm���ɓ��삷�鎎�����s���Ă��������ˁB�x�Ƃ������͂������āA�ł��ǂ������ʂ�555�̏o�͂Ɍq�����̂�����A�����܂ōׂ����w�����Ȃ��Ă����v�ł��傤�ƍ폜���܂����B �@����ɁA555�̃g���K�[�̓��͂ɍ���̒x���֎~��H���q���ł��A��쓮����v���͉�����������Ȃ��̂ŁA�ǂ��ɂȂ��ł�(�ړI�ɑ���)���ʂ͈ꏏ�̂͂��ł��B �@�ŋ߂́A�ׂ��Șb�������Ƃ���ɑ��ĕʂ̈ӌ����L������C�`�����������闈��悤�ł�����A�ʓ|�Șb�͔��������̂ŁB �@���ꂪ���ڂɏo�܂������H �@���Ȃ݂ɁA�H���̃L�b�g�͎����Ă��܂��A�O��̂��Ԏ����������_�ŏH���̉�H�}�̂悤�ɐԊO���Z���T�[����555�^�C�}�[���ɂ킯�āA555�̃g���K�[���͂ɓd�����s����Ȃ�����LOW�M��������ƃ^�C�}�[�������Ă��܂��Ǐ�͊m�F���Ă��܂����A���S�ɓd���������(����LOW���͂���������)����͋N����Ȃ������m�F���Ă��܂��B >�d��OFF����̍ēd���������͋t�ɒx���^�C�}�[�����퓮�삵�Ă��܂��B >�������Ԃ������āi�T���ʁj�d�������������LED���_���Ă��܂��܂��B �@����́A555�̓��͂ɑ��ĉ���LOW�M���������Ă��邩�I�V���X�R�[�v�������Ŋm�F���ꂽ���ۂł��傤���B �@555�̓��͂ɒx���֎~��H���q�����ꍇ�A�R���f���T�����d����Ă���Γd������ꂽ����Ƃ����ĉ����m�C�Y�̂悤�ȃp���X�͔������܂���B���W�b�N��H�̘_���I�ɂ������ł����A���Ƃ��I�V���X�R�[�v���q���ňꔭ�ł��u�ԓI�ȃp���X����������Όv���ł��郂�[�h�ő��肵�Ă��A�����N���Ȃ����Ƃ��m�F�ł��܂��B �@�ł�����A�T�����o�߂���R���f���T�͕��d����Ă��܂�����A�����œd������ꂽ����Ƃ����Ă���ɏo�͐M���͏o���Ȃ��̂ł��B �@�t�ɁA�d���ؒf����ɂ܂��d������ꂽ�ꍇ�́A��ɏ����܂����悤�ɂ܂�555�̒���FF�͐����Ă��āA���x���֎~��H�̃R���f���T�ɂ��܂��d�C���c���Ă����ԂȂ�Z���T�[�̔����M���͂����ł�����A�d������ꂽ�r�[�ɔ������錻�ۂ͋N���܂��B �@�������ꂪ�t���Ƃ���ƁA����������őz�肵�Ă����H�}�Ƃ͈Ⴄ���̂�����Ă��܂��H >�f�l�l���ł����A�˓��d���Ƃ��������d�C�ɕq����IC�̗ނɉe�����đ@�ׂȃg���K�[�M���z���ĉғ����Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@����������悤�Ƃ��Ă݂܂������A��H�}�ʂ�ɑg�ݗ��ĂĂ���A�����N���܂���B �@�H���̉�H�̂悤�Ȃ��̈ȊO�ɁA555�Ƃ���IC�P�̂ł̊�{�@�\�̊m�F�e�X�g���s���܂������A��Ɏ����������d���s���蒆�Ƀg���K�[������悤�ȓ���ȊO�ɂ́A�u555�𐳂����g���Ă���v�d���˓��ŏ���ɓ��삵�͂��߂�悤�Ȏ��͂܂������N����܂���ł����B(������܂��Ƃ���������܂��E�E�E) �@�Ȃ��A�H���̐l���Z���T�[�L�b�g�́u���邢�Ԃ͓��삳���Ȃ��v�悤�Ƀ��Z�b�g�[�q��Cds�����Ă��܂����A���̋@�\�͕K�v�Ȃ��̂ł��Ă��܂���B��R�ECds�E�_�C�I�[�h�͖����Œ���Vcc�ɐڑ����܂��B >���݂ɐԊO���Z���T�̃Z���T�������O������A�����Z���T�ŃR���f���T�}�C�N��t���Ȃ���Ԃœd���������Ă݂��LED���_�����܂��B����͋ɒ[�Ɍ�����555���̃g���K�[���͂ɉ����ڑ����Ȃ���Ԃł��d����������Δۉ��Ȃ���IC�����삵�Ă��܂����̂Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�܂����Ƃ͎v���܂����E�E�E�E�u�Z���T�������O���v�Ƃ�555�̓��͂Ɍq�����Ă���d�q��H��S���O���Ă��܂��Ă͂��܂��H �@555�̓��͒[�q�̓I�[�v���Ŏg�p�͐�ɋ֎~�ł��B �@�K�v�ȐM�����̓��x��LOW/HI��^���邩�A�M�����͂Ƃ��Ďg�p���Ȃ��ꍇ��Vcc�܂���GND�ɐڑ����Ďg�p���Ȃ���Ȃ�܂���B �@���Ƃ��g���K�[���͒[�q�ɉ����Ȃ��Ȃ��Ƃ��A���Z�b�g�[�q���J���̂܂g�p����̂͐�ɂ��Ă͂����܂���B �@�����l���Z���T�[��H�̐l���Z���T�[���i�����O���A�}�C�N�A���v����R���f���T�}�C�N�����O���Ȃǂ������ꍇ�A���̉�H�}�ɂ���Ă͓d��ON�������ԂɂȂ�܂Œ��̓d���R���f���T�Ȃǂɏ[�d���āA�u���肵���v�Ƃ����d�C��Ԃ����܂ł̊Ԃ͏o�͂�ON�ɂ����ςȂ��ɂ����H������܂��B �@���g���̉�H�E���i�̓��쌴���𗝉����A���̃Z���T�[��H�����������u�d��ON�ŏo�͂��o���v�d�l���ǂ����͂悭���m���߂��������B �@���A���̂悤�ȃZ���T�[��H�ł����Ă��A�����֎~��H�͐������Z���T�[�M����d��ON�����莞�Ԃ͋֎~���܂�����A�d������ꂽ���ɏ����555�^�C�}�[��ON�ɂȂ鎖�͂���܂���B �@����͂�����ł����Ȃ�̉̃e�X�g���s���Ċm�F���Ă��܂��B �@��������ɊԈႢ����������A�ڑ�������Ă��Ȃ����Ȃǂ��ēx�m�F���Ă��������B ���Ԏ� 2010/9/3
|
||
| ���e |
���ԓ��L��������܂��B >555�̓��͂ɑ��ĉ���LOW�M���������Ă��邩�I�V���X�R�[�v�������Ŋm�F���ꂽ���ۂł��傤���B �������A���퓮�삵�Ă���Ƃ����͓̂d��OFF����̍ēd�������ł�LED���_�������A��莞�Ԍ�ɂ͐ԊO���Z���T�ɔ�������LED���_������̂ŁA�ēd����������͒x���^�C�}�[�����퓮�삵�Ă���Ǝv���܂����B >�܂����Ƃ͎v���܂����E�E�E�E�u�Z���T�������O���v�Ƃ�555�̓��͂Ɍq�����Ă���d�q��H��S���O���Ă��܂��Ă͂��܂��H �@555�̓��͒[�q�̓I�[�v���Ŏg�p�͐�ɋ֎~�ł��B �f�l�Ƃ͋��낵�����m�ŁA555�̓��͕������O���Γd�C���ʂ��Ă��Ȃ��̂Ń}�C�i�X���낤�ƍl���Ă��܂����B���߂ĉ����Z���T�̂T�T�T���͕�����Vcc���q���Ɠd���������Ă�LED�_�����܂���ł����BGND�Ɍq���Ɠ_�����܂����B �������A���[�A�N�e�B�u�x���^�C�}�[����͕��Ɍq���Ɠ_�����Ă��܂��܂��B Hco �l
|
||
| ���e |
�E�E�����ł�) �����ē��l�̎����ŁA�ԊO���Z���T��555�ł͓��͕���Vcc�ł�GND�ł��d��������LED���_���Ă��܂��܂��B����́u��ɋ֎~�v������j�������߂ɉ��Ă��܂����̂ł��傤���H �ԊO�Z���T�̂T�T�T�ɂ́A�ȑO�������HP�ŏЉ�ꂽ�u������H�v��CDS����t���Ă��܂��B >���A���̂悤�ȃZ���T�[��H�ł����Ă��A�����֎~��H�͐������Z���T�[�M����d��ON�����莞�Ԃ͋֎~���܂�����A�d������ꂽ���ɏ����555�^�C�}�[��ON�ɂȂ鎖�͂���܂���B����͂�����ł����Ȃ�̉̃e�X�g���s���Ċm�F���Ă��܂��B �����ł��ˁB��l�����鎖�́A�Z���T��T�T�T�ɂ͒�R�ȂǑ����̃`�b�v���i���g���Ă��܂��̂Ń��b�g���̖���R�d�H�����d���H�������Ƃ��čl������̂ł��傤���H Hco �l
|
||
| ���e |
�����܂����ɂȂ�܂��j ���l�̎����ŁA�ԊO���Z���T��555�ł͓��͕���Vcc�ł�GND�ł��d��������LED���_���Ă��܂��܂��B����́u��ɋ֎~�v������j�������߂ɉ��Ă��܂����̂ł��傤���H �ԊO�Z���T�̂T�T�T�ɂ́A�ȑO�������HP�ŏЉ�ꂽ�u������H�v��CDS����t���Ă��܂��B >���A���̂悤�ȃZ���T�[��H�ł����Ă��A�����֎~��H�͐������Z���T�[�M����d��ON�����莞�Ԃ͋֎~���܂�����A�d������ꂽ���ɏ����555�^�C�}�[��ON�ɂȂ鎖�͂���܂���B����͂�����ł����Ȃ�̉̃e�X�g���s���Ċm�F���Ă��܂��B �����ł��ˁB��l�����鎖�́A�Z���T��T�T�T�ɂ͒�R�ȂǑ����̃`�b�v���i���g���Ă��܂��̂Ń��b�g���̖���R�d�H�����d���H�������Ƃ��čl������̂ł��傤���H Hco �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@555�͉��Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B���ʂ��ꂭ�炢�ł͉��܂��A�g�p����Ă���555��C-MOS�^�C�v���Ƃ���ʼn�ꂽ�Ƃ����\��������܂��ˁB �@�ƂĂ���b�I�����āA���₷��̂��\����Ȃ��̂ł����A�P���₳���Ă��������B �@74HC132�̃p�X�R���͉����ǂ�����Ă��܂����H ���Ԏ� 2010/9/6
|
||
| ���e |
>74HC132�̃p�X�R���͉����ǂ�����Ă��܂����H �ŏ��͉����t���Ă��Ȃ������̂ł����AIC�ɂ͂��܂��Ȃ��̗l�ɃR���f���T��t����ƌ����̂��v���o���āAVcc��GND�̊Ԃ�0,1��F�̃`�b�v�R���f���T��t���Ă��܂��B Hco �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����Ȃ���S�ł��ˁB �@���āA�ŏ��̓��e�̎��ɂǂ̂悤�ȉ�H�Ŏg���̂���؏����Ȃ�������A9/6�̓��e�ł͂��߂�555�ɂ́u������H�v���t���Ă���ƌ����o������E�E�E�E�B �@���Ԃ�A�܂��������ɂ͒m�蓾�Ă��Ȃ��閧����������̂ł��傤�B �@�����������ł͉��Ă��u���͂����ł͂Ȃ��A�����Ȃ��Ă��܂��v�̌J��Ԃ��ɂȂ�A�����ɂ��ǂ蒅���ɂ͂܂��܂����Ԃ������肻���ł����A�{���́u�Z���T�[����莞�ԋ֎~����v�Ƃ�����H����b���O��܂����̂ŁA���̘b��͂���ɂďI���Ƃ����Ă��������܂��B ���Ԏ� 2010/9/8
|
||
| �ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� | |||
|
�Q�O�O�W�N�㔼�̃��O�Ɂu�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H�v�����܂����B���e�҂̊�]���琔��ނ̉�H�}���t�o����Ă��܂����A���̒��Ń��g�C�[�W�[����H�����삵�悤�ƍl���Ă��܂��������[�Q�����e�d�s�ɒu���������Ȃ��ł��傤���H�܂��c�P�A�c�Q�̃_�C�I�[�h�͂c�R�Ɠ����_�C�I�[�h�łn�j�ł����H �d�C���S�� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����[���Q�Ƃ�FET�ɒu�����������ł����H �@���C�g��ON/OFF���Ă��郊���[�P�͂��ꎩ�̂����ȕێ���H���\�����Ă���̂ŁA�P��FET��ƒu��������͖̂���(�ʓr�g�����W�X�^���K�v)�ł����A�G���W��OFF���ɉ�H��邽�߂Ɏg�p���Ă��郊���[�Q�͂킴�킴FET�ɒu�������Ȃ��Ă����ʂ̈����g�����W�X�^�ł����̂ł����E�E�E�B �@�����[���g���Ă��邩�炱�����Ȃ����i�ō\���ł��Ă���̂ł����A�����̂ɂ���ƕ��i�����₽��Ƒ����܂���B����ł������̂ł����H ���N���b�N����Ɗg��\��
�@���ꂭ�炢�ł��B �@�ǂ����Ă������[���Q�g�����ق����J���^���ɍ��āA�M���x�������Ǝv���̂ł����A�ǂ����Ă������̂ō�肽���Ƃ��������Ȃ�ǂ�������������H�ł����肭������ �@���A�I���^�l�[�^�������Ă���G���W����]���d���M���́A�����܂Ń��M�����[�^�^���N�`�t�@�C�A������ɓ��삷����̂Ƃ��āA���15V���x�̌��E�ȏ�̍��d���p���X�͗��Ȃ����̂Ƃ��Ă��܂��B �@�������M�����[�^�^���N�`�t�@�C�A���̏Ⴗ��A�܂��͌��X�����Ƃ��������ɂȂ��Ă��Ȃ����ŁA�W�F�l���[�^�R�C���������鍂�d���p���X�����̉�H�ɂ�����ƃg�����W�X�^�Q���j��܂��̂ł��C�������������B �@�����܂Ő��퓮�삷��o�C�N�Ŏg�p�����O��ŁA��H�}�ł͈��S���i�͏ȗ����Ă��܂��B �@�܂��A�ߋ��̃����[���g�p������H�}�ł́AD1�`D3�͑S��1N4001�Ȃǂ̐����p�_�C�I�[�h���g�p���܂��B �@���̉�H�}�̂悤��D1,D2�ɏ��M���p�_�C�I�[�h1S2076A�Ȃǂ��g�����̂ł͂���܂���B ���Ԏ� 2010/8/21
|
||
| ���e |
���J�Ȑ������肪�Ƃ��������܂��B �����[�Q�����ȃX�y�[�X�����\�Ȃ�Ǝv�����e�����Ē����܂����B�������Ȃ���M�����A���S���̊ϓ_���猳�̃����[�Ŏ��삵�悤�Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B �d�C���S�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����[���o�J�ɂ��Ă͂����܂����B(�o�J�ɂ��Ă���킯�ł͖����ł��傤���E�E�E) �@�����[�͂��܂��g���Δ����̐��Ԃ�̉�H�������[��Ő���ł��閂�@�̓���Ȃ̂ł��B �@�����������̂̂悤�Ƀm�C�Y��ُ�p���X�Ō̏Ⴗ�闦�̒Ⴓ���֗��ł��B �@���ʁA�R�C���ł�����x�̏���d�͂��g���Ă��܂����Ƃ�A(�����̂ɔ�ׂ�)�X�C�b�`���O�X�s�[�h���x���Ƃ����_�Ȃǂ�����܂��B �@�����A�����̂���r�I�ȒP�ɐ����H�����邱�ƁA����p�̃��W�b�N�Ƒ�d����ON/OFF������ړ_�������Ɉ�����ȂǕ֗��ȓ_�������̂ŁA�p�r�ɂ���Ă̓����[���g������H�̂ق����K���Ă�����̂���������܂��B ���Ԏ� 2010/8/26
|
||
| �@�����L���� ���A����܂��B | |||
| �ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H | |||
|
����ɂ���@�����y���݂ɔq�����Ă��܂��B �@�Ԃ̃C���~�l�[�V�����Ȃ̂ł����A�d��on�Ńt�������A�C���~on�ł�����ƌ����A�C���~off�ł�����ƃt�������������H�͂ǂ̂悤�ȉ�H���l�����܂����B �@LED��5���x�g�������ƍl���Ă��܂��B �@��낵�����肢�v���܂��B �݂͂� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@��H�}�͈ȉ��̒ʂ�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �O�p�g������H �@�I�y�A���vLM324���g�p���āA��1400Hz�̎O�p�g�������܂��B �@LED��PWM�Œ����������M���ɂȂ�܂��B (�ߋ��ɉ��x���悹����H�ƑS���ꏏ�ł�) �� ���͉�H �@�O�������+12V�M�����A�����p�̊�d�����쐬���܂��B �@��d���͓��͂��ꂽ+12V�d����VR1��0�`12V�̊ԂŒ��߂��܂��B �@0V�ł͌����Ȃ��A12V�ŏ����ɂȂ�܂��B �@�O������+12V�d����������Ȃ��ꍇ�A�����̓d����0V�ł����猸���Ȃ��Ńt�������ł��B �@��R�ŕ������ēd��������Ă���̂ŁA��ŃR���f���T�̏[�d�E���d�Ɏg�����߂ɃI�y�A���v�̃{���e�[�W�t�H�����Ńo�b�t�@�����O���Ă����܂��B �� PWM������H �@1400Hz�̎O�p�g�Ɠ��͉�H�ō������d�����r���āAPWM�g�`���쐬���܂��B �� �o�̓h���C�o �@FET 2SJ334��12V�d�����X�C�b�`���O���ďo�͂��܂��B �@���S���݂Ė�15A�܂ł̎g�p�ɂ��Ă��������B �@���A���`�ȏ�Ŏg�p����ꍇ�͕��M�����Ă��������B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@�u�x���ݒ�v�p��VR2���܂�0���ɂ��Ēx���͂��Ȃ��悤�ɂ��Ă����܂��B �@�d�����q���ƊO�����͂ɉ����q���ł��Ȃ���Ԃł̓t���������܂��B �@�t���������Ȃ��ꍇ�͍H��~�X�̉\��������܂��B �@�O�����͂�+12V���Ȃ��ŁA�u�����ݒ�v�p��VR1���܂킷�Əo�͂ɂȂ���LED�̖��邳���ς��܂��B �@����]�̖��邳�ɐݒ肵�Ă��������B �@�O�����͂���LED�̓t�������ɖ߂�܂��B �@�����܂Ő���ł�����A���́u�x���ݒ�v�p��VR2��K���Ȉʒu�ɉāA�O�����͂���ꂽ������肵�Ă��������B �@VR2�̈ʒu�ɂ���Ăڂ�`���Ɩ��邳���ω����鎞�Ԃ����߂ł��܂��B(�ő��10�b���x) �@�d���R���f���T�̏[���d�Ŗ��邳���������ω������Ă��邽�߁A�Â��Ȃ鎞�ɂ͂������ŁA���邭�Ȃ鎞�ɂ͏��������ڂɌ����܂��B ���@�@�@�@���@�@�@�@��
�@���āA���낻��u�Ԃ̃C���~���E�E�E�v�ȂǂɑΉ�������H�������̃p�^�[������܂������A��������ȏ�͎���͏o�Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�K�v�ȉ�H�E�\���͂�������ڂ��Ă��܂��̂ŁA�Ȍ�͎ԊW�Ŏ�����������͉ߋ��̍����Q�l�ɁA�������ł������̕K�v�ɂ��킹�ĉ�H������Ă��������܂��B ���Ԏ� 2010/8/21
|
||
| �ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H | |||
|
�͂��߂܂��āB�F�X�T���Ă��ǂ蒅���܂����B �^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�ɒʂ���̂�������܂��A�����Ă��������B 3�C���̎Ԃ�4�C���p�̃^�R���[�^�����t�������̂ł����A4�C���̏ꍇ�G���W���R���s���[�^(ECU)����̃^�R�p���X��2��/��](4��/2��])�Ȃ̂ɑ��āA3�C����1.5��/��](3��/2��])�Ȃ̂ŁA���̂܂܂Ȃ��Ǝ��ۂ̉�]���Ⴍ�\������Ă��܂��܂�(3/4��]�ɂȂ��Ă��܂�)�B ������ECU����̃p���X��IC��PIC���𗘗p���Ĉ�����4/3�{�ɏo���Ȃ����ƍl���Ă��܂��B �Ȃ��AECU����̃^�R�p���X��5V���x�̏o�͂ŁA�G���W����]����0�`9000rpm�Ƃ���Ǝ��g����0�`225Hz���x�ł��傤���B �ǂ̂悤�ȉ�H��g�߂悢���A�h�o�C�X�����܂���ł��傤���B �g�b�| �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@��]���p���X�̐���3/4�{�ɂ���ɂ́A�P���Ɂu�p���X���R����P��lj����ĂS��ɂ����v�Ƃ�����H��g�߂悢�̂ł��B �@�������A�g�p����^�R���[�^�[��������]�����̒Z���p���X�ɂ��イ�Ԃ�ɑΉ������@��ł���Ƃ������������ł��B�����Ă��̃f�W�^����H���̃^�R���[�^�[�ł͑��v�̂͂��ł��B(�K�i�O�̏ꍇ�͂��߂ł�) �@�ő�225Hz���x�܂łƂ������ŁA��H��͍ő�300Hz���炢�܂őΉ�����悤�v���܂��B 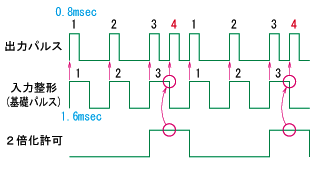 �@���͂�����]���p���X�̕����s���Ȃ̂ŁA��U�����V���b�g��H��300Hz�̔����̎��ԁA��1.6msec�̊�b�p���X�ɕϊ����܂��B
�@���͂�����]���p���X�̕����s���Ȃ̂ŁA��U�����V���b�g��H��300Hz�̔����̎��ԁA��1.6msec�̊�b�p���X�ɕϊ����܂��B�@�ʏ�̉�]���p���X��`�B���邽�߁A��b�p���X�̗����オ��ŏo�̓p���X�������A�o�̓p���X���͊�b�p���X�̔����̖�0.8msec�ł��B �@���̓p���X���J�E���^��H�ŃJ�E���g���āu�R����v�̂Ƃ�������b�p���X�̗�����^�C�~���O���������o�̓p���X�����āA�S��ڂ̃p���X���o�����Ƃ�3/4�{�����܂��B �@����Ń^�R���[�^�[�ɂ�3/4�{�̐��̃p���X�����͂���A��������]����\�����܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���̓J�b�v�����O��H �@ECU����̏o�͓d�����u��5V�v�Ƃ������ŁA������TTL���x����5V���ǂ����s���ł�����A�����ߓd���Ȃǂł�����̉�H���Ƃ����Ȃ��̂Ńt�H�g�J�v���ŃJ�b�v�����O���܂��B �@�g�p����t�H�g�J�v���͂�����TLP-521-1(�P��H����)�ł��B �� ��b�p���X������H �@�t�H�g�J�v���œ��͌��m����ECU����̉�]���p���X�ɉ����āA�{��H���Ŏg�p������Ղ�̃p���X�̊�b�ƂȂ�^�C�~���O�p���X�������V���b�g�^�C�}�[�Ő������܂��B �@�g�p����IC��74HC221�ł��B �@�Q��H����Ȃ̂ŁA�c��͌�ŏo�̓p���X�����p�Ɏg�p���܂��B �� 3/4�{���^�C�~���O������H �@��b�p���X���u�R�i�J�E���^�v�ŃJ�E���g���A�R��Ɉ�x�����u�Q�{���v�̓��������^�C�~���O�����܂��B �@�R�i�J�E���^��D-FF IC��74HC74��NAND���W�b�N��74HC00�őg�ݗ��Ă܂��B �@�R�i�J�E���^�ō�����R��Ɉ�x�̃J�E���g�ƁA��b�p���X��^Q�o�͂�AND������āA�S��ڂ̃p���X�����^�C�~���O�Ƃ��܂��B �� �o�̓p���X������H �@��b�p���X�̗����オ��ƁA�S�x�ڂ̃p���X������^�C�~���O�M���A���ꂼ��������H�ŏo�̓p���X�����p�̃g���K�[�M���Ƃ��A�_�C�I�[�hOR���Ƃ��Ăǂ���̃g���K�[�̎��ł��o�̓p���X�������V���b�g��H�Ŕ���������̂��o�̓p���X������H�̓����ł��B �@�o�͂�TTL���x��(C-MOS�o��)��5V�ł��B �@�g�p����^�R���[�^�[��TTL���x���̓��͉�H�ł���K�v������܂��B (ECU��5V�M���œ����Ă���Ȃ���Ȃ��͂��ł�) �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@�{��H�ɂ͒�������ӏ��͂���܂���B �@�����V���b�g�^�C�}�[�̓��쎞�Ԃ͌v�Z��̎��Ԃœ��삷��悤��R�l�E�R���f���T�̒l�����߂Ă��܂��̂ŁAVR�ȂǂŒ��߂���K�v�͂���܂���B �@�g�ݗ��ĂɊԈႢ��������AECU�Ɍq���ŃG���W�����ƁA���]���ł͓��͐M���Ő���������b�p���X�ɉ�����LED1���p���p���Ɠ_�ł��܂��B �@�قړ����^�C�~���O�ŁA�����Â��o�͕\����LED3���_�ł��܂��B (�{����4/3�{������Ă��܂����A�l�Ԃ̖ڂŌ��Ă�����͊m�F�ł��܂���) �@�S�Ԗڂ̃p���X������^�C�~���O������LED2��LED1���R��_�ł���̂ɑ��ĂP��̊����œ_��(�_��)���܂��B �@��]�����オ��Ɛl�Ԃ̖ڂŌ��ē_�łƂ킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��̂ŁA�m�F�̓A�C�h�����O��Ԃōs���Ă��������B �� PIC�ō��ꍇ �@����PIC�ō����Ȃ�A8�s����PIC 12F629���������g�������ł悭�A��H���ƂĂ��ȒP�ł��B(5V�d�����͏ȗ����Ă��܂�) 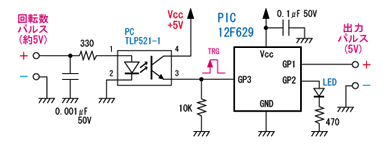 �@���i�͏��Ȃ��ł����A�����S���\�t�g�E�F�A�ōs�킹��̂ŁA�v���O�����̒m����������ł����琻��\�Ƃ������ŁA�����łȂ����IC���R�E�R���f���T������ׂď�̉�H�}�ʂ�ɍ�邱�ƂɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/8/21
|
||
| ���e |
�f�ڂ��y���݂ɂ��Ă���܂����B���Z�����̂ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �^�R���[�^�̒��g���悭�킩���Ă��Ȃ��̂ł����AF/V�݂����Ȃ��̂��Ƃ���ƁA�s���s�b�`�œ���Ă����v�Ȃ�ł��傤����(�j���s�N�s�N�Ƃ����܂���)�H�d�q�H��͕s����́A�������Ԃ������邩������܂��A�����Ă�����������H��g��Ŏ����Ă݂܂��B �g�b�| �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�j�ł����I�H �@�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�����������ɏo����Ă��܂����̂ŁA�Ă�����f�W�^�������\�����f�W�^���o�[�O���t�̃^�R���[�^�[���Ǝv���Ă��܂������E�E�E�A�j�ł����H �@�j���ƃ^�R���[�^�[�̒��g���}�C�R�����ŁA�p���X���J�E���g���Ă���^�C�v�Ȃ炱�̉�H�Ő������\������͂��ł��B�f�W�^�����������ƃJ�E���g���@���ς��Ȃ�����ł��B �@F/V�����ŃA�i���O���������Ă���ꍇ�����͖��Ȃ��͂��ł����A���܂��\������Ȃ��\��������܂��B�ΏۊO�Ƃ����Ă��������܂��B �@��{�I�ɂ́AF/V��H���悭����u�p���X�E�ϕ������v�Ȃ炱�̕��@�ł��S�����F�Ȃ��������\��������͂��ł��B �@���͂�����]���p���X�̃f���[�e�B��Ȃǂɂ͊W�Ȃ��A���͂����p���X�̗����オ��ň�蕝�̊�p���X������āA������ϕ����ēd���o�͂���̂�F/V��H�̊�{�I�ȉ�H�ł�����A���ꎩ�̂́u�p���X�����Ԋu���ǂ����v�Ȃ�đS�����Ă��Ȃ��āA�����P�Ɂu�P�ʎ��ԓ��ɓ��͂��ꂽ�p���X�����������Ȃ����v�Ƃ��������������o�͓d�������E����v���ł�����A10Hz�ȏ���x�̃p���X�����͂���Ă���S���ڂ̃p���X�𑫂��Ă��邩�ǂ����Ȃ�Đϕ���H�̃R���f���T�ŕ�������Ă��܂��āA���[�^�[�̐G��Ɍ���邱�Ƃ͖����Ǝv���܂��B �@�����܂ŕq���ɓ��̓p���X�ɓK�����ă��[�^�[�̐j������Ȃ�A����]�Ɍ�����G���W����]���̂킸���Ȃ���Ń��[�^�[�̓u���܂���ł���B �@�����ƕʂ̕����APLL�������Ŏ��g���ɓ��������ĉ����̐M�����E���悤�ȕ��@�Ȃ�A�s�K���ȃp���X���ƕs�s�����o�邩������܂���ˁB �@�����͂��Ђ��g���̃^�R���[�^�[�ɕs�K���ȐM�����킴�Ɠ�����H�Ȃǂ�v���āA���ۂɂǂ������s�K���p���X�Ȃ�\���������̂������������̂��ʔ����ł��傤�B �@�����ǂ����Ă��u���Ԋu�̃p���X���~�����I�v�Ƃ������ł�����A���ꂱ�����̉�]���p���X��F/V��H�œd�������āA���̓d����V/F��H(VCO)�Ō���4/3�ɂȂ�悤�Ȏ��g���������Ă�邵�������ł���ˁB �@F/V�pIC���茳�ɖ����̂�(�}���c�ł����̂������Ă�炵���ł���)�����ł͐v����H�}�̒��ł��܂���̂ŁA�������������A�i���O�I�ȉ�H���K�v�ł�����IC�̃f�[�^�V�[�g�ł����Ă������ō���Ă݂Ă��������B �@��͂艞�p�̗���PIC�ɂ��āA�u�P�b�Ԃ̃p���X�����v�����Ď��̂P�b�͂���4/3�p���X�ɂȂ���g���̏o�̓p���X���o���v�Ƃ����������P�b�Y���ōs���A����ł����Ԋu��4/3�{���p���X�������܂��B �@�����^�R���[�^�[�̕\���ɂP�b�̒x�ꂪ�o�܂����B ���Ԏ� 2010/8/21
|
||
| ���e |
�X�~�}�Z���A�A�i���O(�j)���[�^�ł��B �܊p�Ȃ�Ōo�܂��B ���̎�(3�C��)�ɂ̓^�R���[�^���Ȃ������̂ŁA�����Ԏ�̃^�R���[�^�t���[�^(4�C���Ԃɂ����ݒ�Ȃ�)�����܂����B ���ʁA3�C���Ή��̌�t�����[�^�����܂����A�X�����Ȃ�̂ŏ������[�^���~���������̂ł��B �f�l�l���ŁA3����������1���Ԃ��悤�ȉ�H�ł܂�1/3�{���A����1�������4���Ԃ���H�Ǝv���A�l�b�g���T�������ɖ������̒��{��H�ɂ��ǂ蒅���܂����B F/V�͌X�̃p���X�����オ��̎��ԊԊu����s�x���g�����o���āA���g���ɉ������d�����o���Ă���̂��Ǝv���Ă��܂����B �P�ʎ��ԓ��ɓ��͂��ꂽ�p���X���ɉ������d�����o���Ă���Ƃ���A�s���s�b�`�ł����Ă����v�ł��ˁB �d�q�H��͕~���������w�ǂ�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�ߏ��Ƀ}���c������܂��̂ŁA�p�[�c���W�߂ĉ�H�������Ă݂܂��B �܂��A���炻����PIC�ȂǂƏ����܂������A�{��ǂݎn�߂����x�̏��w�҂ł��B������ɂȂ�܂����A������������Ă���g��ł݂܂��B �������A���������ʂ� F/V �� V/F ��������V���v���ŊȒP�Ȃ̂�������܂���ˁB �g�b�| �l
|
||
| ���Ԏ� |
>3����������1���Ԃ��悤�ȉ�H�� �@���肪�f�W�^���J�E���g��(�ώZ��)�̃^�R���[�^�[�Ȃ炻��ł��\����4/3�����l�ŕ\�������ł��傤�B �@�����A���̃p���X�R��Ɉ�x�����o�̓p���X���o���Ȃ��ƁA�A�i���O���̃��[�^�[�Ȃǂł͂��̈�u��������]�A����ȊO�̎��Ԃ͒��]�ƌ��m����̂ŁA���S�z�́u�s�N�s�N�v�������Ɍ����\���������ł��ˁB >F/V�͌X�̃p���X�����オ��̎��ԊԊu����s�x���g�����o���� �@���Ԃ�A����̋K�͈ȏ��CPU��R���s���[�^��H���茩���Ă�����Ȃ炻���������@���v�����Ǝv���܂��B �@�ł����ۂ�F/V�pIC�́u���R����A�i���O��H�v�ō���Ă��܂��B �@���Ƃ��u�ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v�v�̓��e�҂̕����g���Ă���TA8029S(�}���c�Ŕ̔�)�̂悤��IC�ł��B �@�ق��ɂ��L�������̃��[�J�[�e�Ђ�������Ƃ�����(?)IC���e��̔�����Ă��܂����A�قƂ�ǂ͒��g�̊�{�ƂȂ�F/V��H�͓��l�ɃA�i���O���ɏ[�d�E���d����ϕ���H���g���Ă��܂��B �@�����āA���������ϕ���H���g�����A�i���O������F/V�R���o�[�^�ł���A��������f�W�^����H�Ńp���X����4/3�������H�̏o�͂ł��A�u�P�p���X����P�p���X�Ԃ�̓d�����[�d����A�����͂��Ɠd���͉�����v�u���̓d���̓R���f���T�ŕ����������v�Ƃ����A�i���O��H�̓���ŁA�p���X�̊Ԋu�ɂ͂قƂ�Ǎ��E���ꂸ�������p���X�Ԃ�ɉ�����F/V�o�͓d���𐳂�������Ă����͂��ł��B �@���Ƃ��ƃf�W�^����H�̂悤�Ɉ�莞�Ԃ��Ƃɋ���ăf�[�^���v�Z�����肷����̂ł͂Ȃ��A�u��ɕϓ�����p���X�ɂ����ĕ��C�őΉ������Ⴂ�܂��I�v�Ƃ����̂��A�i���O��H�̓��ӕ���ł�����A���̓p���X�ɒǐ�����\�͍͂����A�����ׂ�������ϓ��̓R���f���T�̏[�d�E���d�v���Z�X���t�B���^�[�ɂȂ��ċz�����Ă��܂��Ƃ������肪�����@�\������Ă���̂ł��B �@�j�Ƃ͂����Ă��A�A�i���O��H��F/V�ϊ����āu�d���v�v�̐j�ړ������Ă�����̂ƁA���g���}�C�R���ƃX�e�b�s���O���[�^�[�ŁA�}�C�R�����p���X�����v�����Đ��l�����A���̐��l�ɍ����悤�X�e�b�s���O���[�^�[�����j�̈ʒu���ړ������Ă����v�悤�ȃf�W�^�����������J�������Ă��镨������܂��B �@�ԗp�ŁA���\�������^�C�v�Ȃ炱�����������g���Ă���\���������ł��ˁB �@���̏ꍇ�͒��̃}�C�R�����p���X�����v��Ȃ��烊�A���^�C���ɉ�]���̐��l���v�Z���Ă�ł��傤���A�P��ŏ������悤�Ɂu�����v�����v���O����������Ă���Ȃ��v����̉�H��������悤�ɂR��Ɉ�x�Q�{�̃p���X�����͂��ꂽ���x�ł͐j�̓s�N�s�N�����ɂقڈ��肵�Ă���͂��ł��B �@�����łȂ���E�E�E�E�����̃��[�J�[�̐��i�ɂ͂�����Ƌ^���������Ȃ���Ȃ�܂���B �@���������̃^�R���[�^�[�����[�X�p�Ȃǂ̓���i�ŁA�s�N�s�N���Ăł��������班���ł����̃f�[�^�ɋ߂��\���ɂ��邱�Ƃ�ړI�ɐ������ꂽ�A���������\�����ق����l�����Ȃ炵��������܂��B ���Ԏ� 2010/8/26
|
||
| ���e |
���ԕł��B�s����䂦���Ȃ��J���č��グ�܂������A�������łǂ����Ԉ�����炵�����܂������܂���ł����B���Ƃ��ԈႢ�������čēxtry���܂��B �g�b�| �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���͒i�t�߂��猩�����āA���X�ɏo�͒i�܂Ńp���X�M�����`����Ă��邩(LED�̓_���Ȃǂ�)���ׂĂ݂Ă��������B ���Ԏ� 2010/9/19
|
||
| �ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� | |||
|
�@���߂܂��āA�����b�ɂȂ�܂��B�L���ꗗ�ɎQ�l������Ɩڂ��Ƃ��Ă݂܂�����������܂���ł����̂ŁA��������Ă��܂������v�����ē��e���邱�Ƃɂ��܂����B��낵�����肢���܂��B �@���փ`���C���ł����A���ݓ��g�����X�ŏo��AC�WV���g�p���ăs���|����1���܂��B�莝����DC�UV�`�P�QV�œ��삷�郁���f�B�[�`���C�����L��u���b�W�_�C�I�[�h�Ɠd���R���f���T��DC�ϊ����܂�������u������܂���B�ꉟ���Ń����f�B�[�`���C�����T�`�U�b���삷����@������Ή�H�}�A���i�ȂNj����Ă��������B �A���v�X �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[��A�^�C�}�[IC 555���g������H�}�Ȃǂ�����ł����̗p�r�Ɏg�����H�}�͍ڂ��Ă���Ǝv���̂ł����E�E�E�B �@���̂�����Ń_���Ȃ�A�����ƕ��i�����炵�āA�����͓���Ɉ���x������(�^�C�}�[���Ԃ�����ӂ�)���̂ł��A���̂��y�ŃJ���^���Ȃ��̂������ł��ˁB �@����AC100V����DC�ɕϊ�����d����H�͍���Ă���悤�ł�����A�����ɏ����������i�𑫂��āu5�`6�b��v�悤�ɂ��܂��B  �@�lj����镔�i��OMRON��DC12V�����[�uG5V-1 DC12V�v����ƁA4700��F�̓d���R���f���T������ł��B �@�I���S�[���̓����[�̐ړ_��ON/OFF����悤�ɂ��āA�����[�̃R�C���ɓd���R���f���T�����ɂȂ��ŁA���փX�C�b�`�������Βʓd���ă����[��ON�ɂ���Ƌ��ɓd���R���f���T�ɏ[�d�A���փX�C�b�`�𗣂������_����͓d���R���f���T�ɒ��߂��d�C�ł��炭�̓����[��ON�������܂��B �@G5V-1 DC12V��4700��F�̑g�ݍ��킹�Ŗ�5�`6�b�ł��B �@�������A���փX�C�b�`���������ςȂ��ɂ���Ƃ����ƒʓd���Ă��܂�����I���S�[���͖葱���܂���B �@�ق��̃����[���g���ƃ����[�̃R�C���̏���d�����Ⴂ�܂����玞�Ԃ��ς���Ă��܂��܂��B �@����͕��i�������炵�ĊȒP�ɍ����H�ŁA�d�q��H�ɂ��^�C�}�[�ł͖����̂Ń{�����[���ȂǂŊȒP�Ɏ��Ԃ߂��邱�Ƃ͂ł��܂���B �@G5V-1 DC12V���g���ꍇ�ł��A4700��F�ȊO�ɂ�2200��F��1000��F�ȂǗe�ʂ̈Ⴄ�d���R���f���T��p�ӂ��āA�ǂ���g�����₢��������Ɍq���ŗe�ʂ�傫�������肵�Ď��Ԃ�ς����܂��̂ŁA�K�v�Ȃ�e��̓d���R���f���T�������Ď��ۂɂȂ��Ō��Ă������̂��D�݂̎��ԂɂȂ�g�ݍ��킹�������Ă��������B ���Ԏ� 2010/8/19
|
||
| ���e |
�@���e�ȗ������̂悤�ɂ��Ԏ����y���݂ɑ҂��Ă��܂����B���Ԏ���҂��Ȃ��玩���Ȃ�ɂQ���ԃ����v���̑��̉�H�}���Q�l�Ɏ����Ȃ�ɉ��t�����č���Ă݂܂����B���Ԏ���������������H�}�ɋ߂����̂��ł��܂��������������܂������܂���ł����B�v�̓I�������̃����[���g�����Ƃł����B�lj����i�̃����[��R���f���T���͈�̑O�ɃA���v�ȂǕ������ĕۑ����Ă��������Õi�ł��ׂĊԂɍ��������Ȃ̂ō��ӂɂł��������������Ǝv���܂��B���Z�����{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���̎��ł܂������b�ɂȂ邩������܂���낵���肢�܂��B �A���v�X �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���~�O��ƔN���N�n�́u�C�̖����v�ɂ�����鎞�Ԃ����܂薳���̂ŁA���҂������Ă��܂��܂��B���݂܂���B �@�Q���ԃ����v�̂悤��FET���g������H�A�^�C�}�[IC 555���g�����^�C�}�[��H�A���낢��ȕ��@�œ����悤�ɐ��b�ԓ�����H�͍��܂��B �@����̃����[�ƃR���f���T���g������H���ł����i�������Ȃ��ĊȒP�ɍ��܂�����A���莝���̕��i���g���ē�����m�F������A�R���f���T�̗e�ʂ�ς�����Ǝ��������Ă݂ĉ�H�̓�����������Ă݂Ă��������B �@�܂��A�����[�̐ړ_�ŃJ�`�b�I�ƃI���S�[����ON/OFF����̂ł͂Ȃ��A�����[���g�킸�ɃI���S�[���̓d�����R���f���T�ɒ��߂��d�C�œ��������牽�b���炢��̂���A�R���f���T�����d������ˑR�I���S�[������~�ނ̂��A���X�ɉ����������Ȃ��čŌ�ɖ�~�ނ̂��Ȃǂ��������Ă݂�̂��ʔ����Ǝv���܂��B �@���̌��ʁA�܂��ʂ̉�H����鎞�̍l�����́u���̒��̈����o���v��������Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2010/8/19
|
||
| ���e |
�����y�����q�������Ă��������Ă��܂� ����ӂƎv�������Ƃł��� �����[�ɃX�i�C�p�p�_�C�I�[�h����ꂽ�����R���f���T�ɕ��S���Ȃ��Ǝv���̂ł����`�`�@���ł��傤���H �܂������������[���쓮����̂łȂ���ΕK�v�Ȃ��̂��ȁH gokichan �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�S�E�E�E�S���S�P�R�ɑ_���Ă܂����I�H �@�X�i�C�p(�_����)�ł͖����X�i�o(���d���z����H)�ł���ˁB �@�Ƃ���ŁA�X�i�o��H�E�X�i�o�p�_�C�I�[�h�͂ǂ�Ȏ��ɓ���镨�ł��傤���B �@�����[���R�C�����g�p�������̂ɓd���𗬂��Ď��͂������A���̓d�����}���ɐ��������R�C���ɒ��߂�ꂽ���͂��d�͂ɖ߂��āA�^�����Ă����d���Ƌt�����ɍ��d�����������Ƃ����R�C���̐����ɂ���ċN�����p���X��̍��d��(�������t�d��)�������̂Ȃǂ̉ߓd����t�d���Ɏア�j�~��j�Ă��܂�Ȃ��悤�A�R�C���ɋt�d�����z������f�q(��Ƀ_�C�I�[�h�Ȃ�)�������H���u�X�i�o��H�v��u�X�i�o�z����H�v�ȂǂƌĂт܂��B �@�R�C�����ł͂Ȃ����d�����d����ON/OFF����ړ_���ł��A�d����ON/OFF�̍ۂɋN����p���X�E�m�C�Y���z������悤�ȉ�H���������X�i�o��H�ƌĂт܂��B �@�����[�̏ꍇ�A�g�����W�X�^�ȂǂŃ����[�����āu�J�`�b�I�v�ƓˑROFF�ɂ���悤�ȏꍇ�ɂ͍��d���p���X����������̂ŁA�ڑ�����Ă���g�����W�X�^�Ȃǂ�ی삷��K�v������܂��B �@�ł́A����̉�H�́H �@�����[��ON�ɂ��鎞�ɂ͓��ɖ��͂���܂���B �@�ł̓����[��OFF�ɂ��鎞�Ƀ����[�̃R�C�������d����������u�u�ԓI�ȓd��OFF�v�̏͋N����̂ł��傤���H �@�X�C�b�`����Ă������[�ɂ͓d���R���f���T����d������������A���̓d���͕��d�ɂ���ď��X�ɒቺ���Ă䂫�܂��B(��H�}�ʂ�̕��i�萔�ł�)���S���d�܂ł�10�b�ȏ���x������ł��傤�B �@�������ƃR�C���ɂ�����d����������̂ŁA�R�C���ɔ������Ă��鎥�͂�����ɂ�Ă������キ�Ȃ��Ă䂫�A�Ō�ɓd�����O�u�ɂȂ鎞�_�Ŏ��͂��O�ɂȂ�܂��B �@�d����������r���Ń����[�̐ړ_��OFF�ɂȂ�܂����A����̓R�C�����ɂ͉���W�Ȃ��A�ړ_������������Ƃ����ăp���X�d������������悤�ȍ\���ł͂���܂����ˁH �@�����[�̃R�C���ɗ����d�����u�J�`�b�I�v�Ɛ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A������艽�b�������ēd����������̂ŃX�i�o��H���K�v�ɂȂ�悤�ȋt�����̍��d���p���X�ȂS�������܂����B �@�X�i�o�������K�v�ȃp���X�Ȃ������Ȃ��̂ŁA�R���f���T�Ɉ��e�����y�Ԃ��Ƃ��Ȃ��A�X�i�o�����p�̃_�C�I�[�h��t����K�v������܂���B �@��͂�ǂ����炩�X�i�C�p�[�ɑ_���Ă��āA�u�Y�M���[���I�v�ƃp���X�d�����������܂�Ă��܂��̂ł��傤���H ���Ԏ� 2010/8/20
|
||
| ���e |
�d�q�I���S�[���̏���d���ɂ����܂����A�����[���g�p���Ȃ��Ă��v�b�V���X�C�b�`�̌�ɓd�q�I���S�[���ɓd���R���f���T��������邾���ł������ł���悤�ȋC�����܂����H (������]) �l
|
||
| ���Ԏ� |
>�@�܂��A�����[�̐ړ_�ŃJ�`�b�I�ƃI���S�[����ON/OFF����̂ł͂Ȃ��A�����[���g�킸�ɃI���S�[���̓d�����R���f���T�ɒ��߂��d�C�œ��������牽�b���炢��̂���A�R���f���T�����d������ˑR�I���S�[������~�ނ̂��A���X�ɉ����������Ȃ��čŌ�ɖ�~�ނ̂��Ȃǂ��������Ă݂�̂��ʔ����Ǝv���܂��B �@�ƁA�����Ă������̂ł����A���ǂ݂ɂȂ��Ă��܂��H �@���̒m�����A�I���S�[��IC���g�����d�q�I���S�[���ł͓d��������͈͂�艺���ƁA�u���������������Ȃ�v�u�e���|�����������Ȃ�v���̂������A�I���S�[���Ƃ��ĕ����Ă���Ƃ܂�ʼn�ꂽ�悤�ȉ��ɂȂ��ă����f�B�[�������Ă䂭���̂��قƂ�ǂł��B �@�����[���g�킸�ɃR���f���T�����ŃI���S�[����炵���ꍇ�A���������s���ȉ��ɂȂ�̂����O���Ă��������Ă���̂ł����E�E�E�B �@�R���f���T�̓d�����������āA���̂Ƃ���Ńs�^�b�I�ƃ����f�B����~�ނ悤�ȗD�G��IC���g���Ă���d�q�I���S�[�����ƃR���f���T��ł��݂܂��ˁB ���Ԏ� 2010/8/20
|
||
| ���e |
�@������Ԏ������������Ė鑁���쐬�����܂����B�u���b�W�_�C�I�[�h�p�ɂ͂P�O�O�O��F���g�p���A�����[�p�͂P�O�O�O�A�P�T�O�O�A�Q�Q�O�O�A�S�V�O�O��F�ƃe�X�g���܂����������̗��z�Ƃ��ĂQ�Q�O�O��F�łS�b�`�T�b���x�Ō��肵�����������������܂����B�F�X�Ȃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂��B�Ȃ��R���f���T�����d����Ō�ɂ̓u�[���Ə����������o�܂������ɋC�ɂȂ�܂���̂łƂ肠�����悵�Ƃ��܂����B���肪�Ƃ��������܂����B �A���v�X �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���傤�ǎg����(�W�����N)���i���茳�ɂ����Ă悩�����ł��ˁB �@�Ō�Ƀu�[���Ƃ��������I���S�[���̃X�s�[�J�[����o��̂��Ƃ�����A���g���̃����[�����͂��キ�Ȃ��ă����[�̐ړ_�����Ƃ��Ɂu�ڐG�s�ǁv���x�̐ڐG�͂ɂȂ��Ă�����悤�ȕ���������܂���B �@�C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ炢���̂ł����A�g���Ă��Ăǂ����Ă��C�ɂȂ�Ȃ�ʂ̃����[����肵�����Ɏ����Ă݂邩�A�R���f���T�Ń����[��x�点���H�ł͂Ȃ�����Ƃ����^�C�}�[��H���������g���悤�ɉ��ǂ��Ȃ���Ȃ�܂���ˁB �@�܂��������ɂȎ��ɂł��A�ʂ̃����[�Ŏ����Ă݂�Ƃ��A�I���S�[���̓d���{�Ɓ|��10�`100��F���炢�̓d���R���f���T�����ɂȂ��ł݂�Ƃ��A�܂��܂������̗]�n�͂���܂��ˁB ���Ԏ� 2010/8/20
|
||
| ���e 8/21 |
>�X�i�C�p�[�ɑ_���Ă��� �M�N�I�I >���d���p���X�ȂS�������܂��� �������܂����A���낢��ƕ��ɂȂ�܂� ���ꂩ�����낵�����肢���܂� gokichan �l
|
||
| ���e 8/21 |
>�@�ƁA�����Ă������̂ł����A���ǂ݂ɂȂ��Ă��܂��H ���ɐ\����܂���ł����B �\����܂���ł��� �l
|
||
| ���e 8/22 |
�@�F�X���ӌ����肪�Ƃ��������܂��B���ꂩ�珔����ɂ��Z�����Ȃ�܂��̂ŗ]�T���ł����烊���[�E�R���f���T���Ńe�X�g���Ă݂܂��B �A���v�X �l
|
||
| ���x�ʼn�]����������@ | |||
|
����Ȃ��Ƃ����₵�Ă����̂��킩��Ȃ������̂ł����A���₳���Ă��������܂��B �j�����Ă����܂��܂���B ���R�����ŁA���x�ʼn�]����������@����낤�Ǝv���Ă��܂��B ���ׂĂ݂āA�T�[���X�^�b�g���g���Ăł���ƒm�����̂ł����A���̑��ɕK�v�ȕ��i��A��H�}���A������T���Ă��킩��܂���B �����f�ł����炷�݂܂���B ��H�}�́A�����ł�������v�ł��B ���͂�݂��Ă���������Ƃ��ꂵ���ł��B ��낵�����肢���܂��B (������]) �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�ƂĂ��c�O�ł����A�u�T�[���X�^�b�g�v�ł͖����ł��B �@�u�T�[���X�^�b�g�v�����x�X�C�b�`�ŁA�u�~�~���ȏ��ON(�܂���OFF)�v�݂�����ON��OFF���̂Q�̏�Ԃ��ւ���g�����ɂ͎g���܂����A���x��d����d���̑召�̒l�ŕԂ��Z���T�[�ł͖����̂Łu���x�ɉ����ĉ�]����ς���v�悤�Ȏg�����ɂ͎g���܂���B �@�������u30�����z�����獂��]�A30�������ł͒��]�v�݂����ȂQ�̏�Ԃ��ւ��邾���Ȃ牞�p���邱�Ƃ��ł���ł��傤�B �@���ʂɍl���āA���x�ɉ����ĉ�]����ς���ɂ� �E���x��d�����d���Ȃǂ̓d�C�M���ɕς���Z���T�[ �E�d�����d���̒l�ɂ����AC100V�̓d�͂���`���̊ԂŒ��߂����H ���v��܂���ˁB �@���x�Z���T�[�͐��x�̍��������ȍH�Ɨp�̂��̂���A100�~���Ȃ��T�[�~�X�^�̂悤�ȑf�q�܂ł��낢�날��܂��B �@���������Z���T�[�Ŋ��m�������x�M��(�d����d��)���I�y�A���v���̑�����H�Ō�̉�H�ŕK�v�ȓd���M���ɕϊ����܂��B �@���x�M�����d���œ�����A����ǂ͂��̓d����AC100V�̓d�͂��R���g���[�������H�Ɍq���悢�̂ł����A�O���d����AC100V�𐧌䂷���H�͂قƂ�lj�H�}�Ƃ��Ă͌��J����Ă��Ȃ��ł��傤�B �@�H�Ɨp�̐��i�Ȃ琔��~�`�����~�͂��܂������������i������܂��B �@�u�C�̖����v�ł͓d�q�H��ɒ��������łȂ����AC100V�ɊW����H��͊댯������̂ŁA�����ł͉�H�}������͌��J���Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��B �@���x�ɉ����ăp���[�̕ς���@�Ƃ����̂͂����ւ�ʔ����H�삾�Ǝv���܂����A�ċx�݂̎��R�����̍H��ł͂�����Ɩ���������ۑ肾�Ǝv���܂��B �@���d�r�ƃ��[�^�[�ō��I���`���̐�@���炢�Ȃ�d�q�H��ʼn��x�ŃX�s�[�h�R���g���[������̂��\�ł��ˁB �@����ł��u�����Ńt���p���[�ɂ���̂��v��u�����Œ�~(�܂��͍ł��ア��]��)����̂��v�ȂǁA���p�I�ȋ@�\��S�Đ��荞�ނƂ��Ȃ蕡�G�ȉ�H�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/8/17
|
||
| ���e |
�����J�Ȑ������肪�Ƃ��������܂��B �Ȃ�Ƃ��A����Ă݂悤�Ǝv���܂��B �܂��A���₷�邩������Ȃ��̂ŁA���̎��́A��낵�����肢���܂��B kitajima �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���x�Z���T�[�ƃI�y�A���v���g���āA���x��d���l�ɕϊ������H�Ȃǂ͂����ɉ�H�}������������܂��̂ŁA�������������Q�l�ɂ���]�̌`�ɋ߂Â��Ă䂩���Ɨǂ��Ǝv���܂��B �@���Њ撣���Ă��������I ���Ԏ� 2010/8/18
|
||
| �p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H | |||
|
���߂܂��āB�����A�d�q�H�쏉�S�҂ł��B �}�C�N�̃~���[�g�X�C�b�`�ɂ��Ď���ł��B �p�\�R���ŃC���z���}�C�N���g�p���Ă���܂����A�P�����̎��ȂǁA�����Ƀ}�C�N���~���[�g�����̂ł����A�O�o�́u�|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N�v�����̂܂g�p�ł��܂����H �C���z���}�C�N�̃I�X�[�q�́A�R�Ɂi�Ƃ����̂ł��傤���H�j�ɂȂ��Ă���悤�ł��B ��H�}�͓ǂ߂܂��A�ȒP�ȓd�q�L�b�g�̍H��͉��x���o�����܂����̂ŁA�����V���b�v�ʼn�H�}�������ĕ��i�����낦�A���c�t�����邱�Ƃ͉\���Ǝv���܂��B �l�b�g�ŎU�X�������܂������A���̃T�C�g�ȏ�ɐ�������Ă��鎖�Ⴊ������܂���B �ǂ����A���m�b�������ĉ������܂��B ��낵�����肢�������܂��B ��� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���_�����ɏ����ƁA�|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N�ł��̂܂g���܂��B �@�p�\�R���̃}�C�N�[�q��3.5mm�X�e���I(�R��)�[�q�ɂȂ��Ă��܂����A�u�R�����R���f���T�}�C�N�v���Ȃ��[�q�ł͂Ȃ��A�u�Q�����R���f���T�}�C�N�v���u�X�e���I�̂k�E�q�̂Q���v�Ȃ�����悤�R�ɃX�e���I�z���ɂȂ��Ă��܂��B �@�v�̓w�b�h�t�H���[�q�Ɠ����悤�ɁuGND�v�uR-CH�v�uL-CH�v�̂R�{�̐������Ă��邾���ł��B �@�p�\�R���ŃX�e���I�Ή��}�C�N���g���鉹�����͉�H(��T�E���h�J�[�h)�𓋍ڂ��Ă��镨�͋H�ŁA���ʂ̓��m�����p�Ƃ���L-CH(���}�C�N)�̂ݎg�p���܂��B �@�R�Ƀv���O�ł� ����[(�`�b�v)�� L-CH(���}�C�N) ������(�����O)�� R-CH(�E�}�C�N) ������(�X���[�u)�� GND(�A�[�X�E���E����) �ƂȂ��Ă��܂��B �@�������|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N�̉�H���Ȃ��A�������~���[�g�E�����������̃}�C�N�ɂȂ�܂��B �@��H�}�E�g�p���i�͂܂����������ł��B ���Ԏ� 2010/8/17
|
||
| ���e |
�����玸�炵�܂��B �ȑO�p�\�R���̃}�C�N�[�q�ɂ��Ē��ׂ����Ƃ�����̂ł����A���̎��ɂ͒��[�i�����O�j��+5V��Bias���������Ă���炵���ƌ����Ƃ���܂ł���������܂���ł����B http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html ����̂��Ԏ��������̗����Ƃ͈قȂ��Ă����̂ŁA�ł�����������ڂ���������Ă���������Ƃ��肪�����ł��B ���܁[��i�f�l�j �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����E�E�E�����̃y�[�W�ɃR���f���T�}�C�N�̃v���O�ɂ�����o�C�A�X�̘b�͂�����p�^�[���ɂ��ďڂ���������Ă��܂�����A������ǂ܂�����������������Ǝv���̂ł����E�E�E�B �@�ȒP�ɏ����ƁA�����O��+5V���������Ă���̂́ACreative�Ђ̃T�E���h�u���X�^�[(���Ȃ苌��)�ƁA���̌݊��T�E���h�J�[�h(�܂��͎����č���Ă������)�����ł��B(�����ɂ����������Ă���܂����) �@���������Â����łȂ��A���݂̎嗬���P�s���ւ̒��ڃo�C�A�X�ł��B �@�����ɂ���f�X�N�g�b�v�p�\�R������(MB�͊e�Зl�X)�̂����A�P��������Ă��̃^�C�v�ł��B 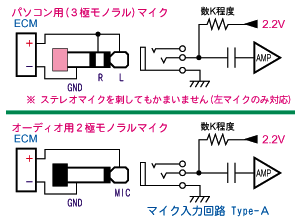
�@�}�C�N�[�q�͂R�ɃX�e���I�W���b�N�ł����A���z����L-CH(�`�b�v)��GND(�X���[�u)�݂̂����q�����Ă��܂���B �@�`�b�v�ɂ̓R���f���T�}�C�N�p�̐�p�d��(2.2V)����o�C�A�X��R���o�R���ēd������������Ă��܂��B �@�����łP�o���Ă����Ă������������̂́A�u���m�����}�C�N�v�ł��p�\�R���p�̂R�Ƀv���O���}�C�N�̓I�[�f�B�I�p�}�C�N�Ƃ͈Ⴂ�u�`�b�v�ƃX���[�u���ڑ�����Ă����v�Ƃ������ł��B �@�p�\�R���p�w�b�h�Z�b�g�Ȃǂ��v���X�`�b�N�����s���N�F�̂R�Ƀv���O������ł��B �@����́A��q����uCreative�Ђ̃T�E���h�u���X�^�[(���Ȃ苌��)�ƁA���̌݊��T�E���h�J�[�h�v�ł��g����悤�ɂ��邽�߂ł��B �@�P�s���o�C�A�X���̃W���b�N�ł���A�p�\�R����p�̃}�C�N�łȂ��Ă��I�[�f�B�I�p�̂Q�Ƀv���O���̃��m�����E�R���f���T�}�C�N���g�p�ł��܂��B �@�܂��A�I�[�f�B�I�p�̂R�Ƀv���O���̃X�e���I�E�R���f���T�}�C�N����CH�݂̂ł����g�p�ł��܂��B �@�܂肱�̕����� �E�p�\�R����p�̃R���f���T�}�C�N(�s���N�F�v���O) �E�I�[�f�B�I�p���m�����R���f���T�}�C�N �E�I�[�f�B�I�p�X�e���I�R���f���T�}�C�N(�A�����̂݃��m�����g�p) �E(�ق��A�_�C�i�~�b�N�}�C�N�����ꕔ�g�p�\) �ƁA�s�̂���Ă��鑽���̃}�C�N���g�p���邱�Ƃ��ł��܂��B �@���Ɂu���Ȃ��v�Ƃ͏����܂��������ۂɂ͎��݂���̂ŁE�E�E�B�����ł�Acer�̃l�b�g�u�b�N�^�p�\�R���Ɛ������s����PCI�T�E���h�J�[�h������ɂ�����܂��B 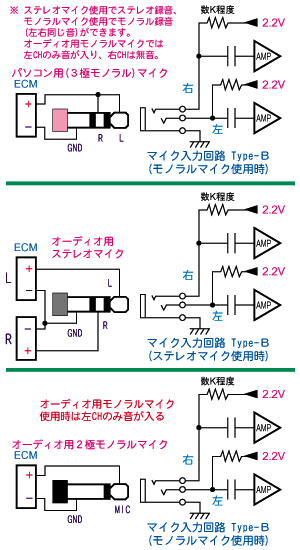
�@�P�s���o�C�A�X���ł����A�����ƃX�e���I�Ή��œ��͉�H���Q�����Ă��܂��B �@�������s���N�F�v���O�̃p�\�R���p���m�����}�C�N���h���ƁA�v���O�̒���L-CH��R-CH���ڑ�����Ă��܂�����A�p�\�R���ɂ͍��E�����̃`�����l���ɓ�����������A���m�����M���Ƃ��ĉ������͂ł��܂��B �@�I�[�f�B�I�p���R�ɃX�e���I�}�C�N���h���A���̂܂܍��E�Ɨ��������������͂ł��܂��̂ŁA���͂̂���X�e���I�^�����ł��܂��B �@�I�[�f�B�I�p���Q�Ƀ��m�����}�C�N���h���AL-CH�̓}�C�N���q����AR-CH��GND�ɐڑ�����܂��̂Ńm�C�Y�̖����������͂ƂȂ�܂��B �@�X�e���I�^���ł͂Ȃ��A���m�����Ř^������{�C�X���R�[�_�[�\�t�g�Ȃǂł͂���ł����Ȃ��^���ł��܂��B �@�͂��A�ŌオCreative�Ђ̃T�E���h�u���X�^�[(���Ȃ苌��)�ƁA���̌݊��T�E���h�J�[�h�����ŁA�����ł�IBM���̃f�X�N�g�b�v�p�\�R�����������̕����ł����B 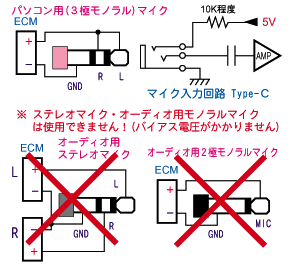 �@�`�b�v�̓}�C�N�A���v�ւ̓��͂ɂ̂q�����Ă��āA�R���f���T�}�C�N�p�̓d���o�C�A�X�͂���܂���B
�@�`�b�v�̓}�C�N�A���v�ւ̓��͂ɂ̂q�����Ă��āA�R���f���T�}�C�N�p�̓d���o�C�A�X�͂���܂���B�@���̂����A�����O��+5V�d�������R��ʂ��ăo�C�A�X�d�����ڑ�����Ă��܂��B �@�������s���N�F�v���O�̃p�\�R���p���m�����}�C�N���h���ƁA�s���N�F�v���O�̃p�\�R���p���m�����}�C�N�ł͓����Ń`�b�v�ƃ����O���ڑ�����Ă��܂�����A�R���f���T�}�C�N�ɂ̓o�C�A�X�d�����������Đ���ɓ��삵�܂��B �@�������A�R�ɃX�e���I�}�C�N���Q�Ƀ��m�����}�C�N�ł͐������o�C�A�X��������Ȃ��̂���؎g�p�ł��܂����B �@�p�\�R����p�}�C�N�łȂ��Ǝg���Ȃ��̂́A�ƂĂ��s�ւł��ˁB �@�ł��t�ɁA���ɐ�������u�R�ɃR���f���T�}�C�N�v��u�_�C�i�~�b�N�}�C�N�v�̂悤�ɁA���ł̓p�\�R���p�ɂ͂قƂ�ǔ����Ă��Ȃ������I�A�C�e���͌q�����Ƃ��ł��܂�����A20�N�ȏ�O�̂��������}�C�N�������Ă���l�����p����ɂ͗ǂ���������܂���i�O�O�G �@����Creative�Ђ̃T�E���h�u���X�^�[(���Ȃ苌��)�ƁA���̌݊��T�E���h�J�[�h�������g���Ă���p�\�R���͂�����������ꂽ�@�킾���ł͂Ȃ��ł��傤���B �@����Creative�����i�ł��ŋ߂̃T�E���h�J�[�h���P�s���ւ̒��ڃo�C�A�X�ɂȂ��Ă��邻���ł��B �@SB16����̐��i���Ȃ����̂悤�Ƀo�C�A�X��ʂɂ��Ă��邩�Ƃ����ƁA�T�E���h�u���X�^�[(SB16)���J�����ꂽPC/AT�@���ʎY���͂��߂�ꂽ��(�܂�Windows�ł͂Ȃ�DOS/V����ł��c)�A�}�C�N�͂܂��Q����(�Q��)�R���f���T�}�C�N�嗬�ł͂Ȃ��A�d�����Ɖ����M�������ʁX�ȁu�R�����R���f���T�}�C�N�v�������g���Ă������ƁA�܂��d����^�����Ɏ����Ŕ��d����u�_�C�i�~�b�N�}�C�N�v�����������̂ŁA���̃^�C�v�̓��͉�H�ł͂R�����R���f���T�}�C�N�͂��̂܂܂R���S�����Ȃ���A�_�C�i�~�b�N�}�C�N���q���ƃo�C�A�X�������ă_�C�i�~�b�N�}�C�N�̃R�C�������ڃ}�C�N�A���v���͂Ɍq���邾���̐v�Ƃ������Ȃ̂ł��B �@���ł́A�_�C�i�~�b�N�}�C�N�̓I�[�f�B�I�p�̃}�C�N�ł͂܂����p����Ă��܂����A�p�\�R���p��|�[�^�u���I�[�f�B�I�p�ł͂قƂ�ǎg�p����Ă��܂���B �@�R���f���T�}�C�N���R�����͂����قƂ�ǎg���Ă��܂���B���^�̂Q�����R���f���T�}�C�N���嗬�ł�����A�p�\�R����|�[�^�u���I�[�f�B�I�̃}�C�N���͉�H�͂قƂ�ǑS�Ă��R���f���T�}�C�N�p�Ƀ}�C�N�[�q���̂Ƀo�C�A�X�d����������Q�����̐v�ɂ��Ă��܂��B �@�����āA�s���N�F�v���O�̃p�\�R���p���m�����}�C�N�ł̓`�b�v�ƃ����O������Őڑ����邱�ƁA�܂��p�\�R���������������v���O���h���鎖�ɑΉ������s���ڑ��ɂ��邱�Ƃ��s���N�F�v���O�̃p�\�R���p���m�����}�C�N�ł� �E�T�E���h�u���X�^�[���ł̓o�C�A�X�ƃ}�C�N���q�� �E�P�s���o�C�A�X�E���m�������͎��ł͓��ɖ����������� �E�X�e���I�Ή����͎��ɂ́A���E�ɓ���������͂ł��� �Ƃ����A�ǂ̓��͉�H�ɑ��Ă��Ή��������Ƀ}���`���[�X�ȃR�l�N�^�ɂȂ��Ă��܂��B 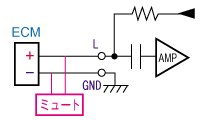 �@�����܂ł𗝉�������ŁA����җl�̂��g�p�̃C���z���}�C�N�̃}�C�N�[�q���p�\�R���p�R�Ƀv���O�Ƃ̎��ŁA���Ƃ��p�\�R���{�̂��ǂ̉�H�����ł����Ă��v���O���������Ƃ��ɂ͉E�}�̉�H�����藧���܂��B
�@�����܂ł𗝉�������ŁA����җl�̂��g�p�̃C���z���}�C�N�̃}�C�N�[�q���p�\�R���p�R�Ƀv���O�Ƃ̎��ŁA���Ƃ��p�\�R���{�̂��ǂ̉�H�����ł����Ă��v���O���������Ƃ��ɂ͉E�}�̉�H�����藧���܂��B(�C���z���}�C�N�ŁA�X�e���I�}�C�N�Ƃ������͂܂������ł��傤�E�E�E) �@���m�����}�C�N��L-CH�ɐڑ�����A�����ł�L-CH��R-CH���ڑ�(�V���[�g)����Ă���͂��ł����A���ꂪ�v���O���ŃV���[�g���Ă���̂��X�e���I�P�[�u���̐�Ń}�C�N���t����������̒��ŃV���[�g�z������Ă���̂��͐��i�ɂ���ĈقȂ�̂Ŏ���җl�̃C���z���}�C�N���ǂ��z������Ă���̂��͎��ɂ͑z���s�\�ł�����A�ǂ���̏ꍇ�ł��uL-CH���̃}�C�N�z���v�ɑ��ă~���[�g��H���Ȃ��͖ړI���B���ł��鎖�����͂��`���ł��܂��B �@�����āASB16����̋����ȃ}�C�N���͒[�q���g�����p�\�R���͂����H�Ɍ��邾���ŁA�ŋ߂̋@��͂قڑS�Ă��Q��(�Q��)���̃R���f���T�}�C�N�p��H�ɂȂ��Ă��āA�X�e���I�Ή��܂��͕Ѓ`�����l���̂ݔz���̂��̂������Ȃ��Ă��܂����炻�������Ă���̂ł����A����ʼn�����肪����ł��傤���B ���Ԏ� 2010/8/18
|
||
| ���e |
�����̂��L��������܂��B ���~�x�݂��J����̂�S�҂��ɂ��Ă���܂���(��) ��������ɁA�ǂ�ȕ��i���K�v�Ȃ̂��A�����i�̎p���z�����A�����l���Ă��疳��������ɂɑ��k�ɍs���܂��B �l�C���ł���Ԃɂ���������A�ʔ��݂������ł����̂ˁB �L��������܂����I ��� �l
|
||
| ���e |
�֏掿��ɂ�������炸���J�ɐ������Ē����L��������܂����B �T�E���h�{�[�h�ƃ}�C�N�̂��낢��ȑg�ݍ��킹��A���݂̎嗬�ł���P�s���ւ̒��ڃo�C�A�X�i����͑S���m��܂���ł����j�ɂ��Ẳ�������Ă��������Ă���Ɨ��������邱�Ƃ��ł��܂����B �����I�t�B�X�⎩��Ŏg���Ă���PC���T�[�o�^�C�v�̂��̂������ČÂ��T�E���h�J�[�h���g���܂킵�Ă�����̂ł�����A�ŏ��̂��Ԏ������ă����O�̓d�����`�F�b�N���ď��ǂ��c���ł��Ȃ��Ȃ�}篎��₳���Ă��������܂����B<(_ _)> PC�ɐڑ������w�b�h�Z�b�g�i�s���N�̃��m�����^�C�v�j�ł悭�d�b��c�ɎQ������̂ő������̃~���[�g��H�����p�����Ē��������Ǝv���܂��B(^^�U ���܁[��i�f�l�j �l
|
||
| ���e |
SB16�����FMV�t���}�C�N�ASB16�łȂ����f���̃}�C�N�[�q�q���Ǝ���Ɏw�����������̂͂���ȗ��R���������̂ł��ˁB HD�I�[�f�B�I�K�i�Ń��C�����͂����˂邽�߂ł��傤���A���N������NEC�̃m�[�gPC�͒P�s���o�C�A�X�̃X�e���I���͂ł����B (������]) �l
|
||
| ���Ԏ� |
>��� �l �@���S�ɕ��i���������p�ӂ���Ă���u�L�b�g�v���J���^���ɂ͂䂫�܂��A���i�������Ȃ��̂Ŗ���������̓X������Ƙb���Ȃ��畔�i�B�����A�����Ŋe���i�ɂ��ẴA�h�o�C�X�����Ă���������Ǝv���܂��B �@�l�b�g�ʔ̂ƈႢ�A���X�ł̑Ζʔ̔��ł͓X������̂��m�b�����肵�āA�킩��Ȃ��Ƃ���͂����ł����ɕ�����̂������ł��ˁB 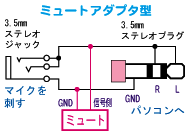 �@�����łP�A�h�o�C�X�ł����A���莝���̃C���z���}�C�N��(�z������āH)���ă~���[�g��H��t����̂ł͂Ȃ��A�E�}�̂悤�ɂR�ɂ̃v���O�E�W���b�N��p�ӂ��ă~���[�g��H�����������P�[�X�ɓ����A�u�p�\�R���}�C�N�p�~���[�g�A�_�v�^�[�v���ł�������܂��̂ŁA�C���z���E�}�C�N���͉̂������Ȃ��Ă����݂܂��B
�@�����łP�A�h�o�C�X�ł����A���莝���̃C���z���}�C�N��(�z������āH)���ă~���[�g��H��t����̂ł͂Ȃ��A�E�}�̂悤�ɂR�ɂ̃v���O�E�W���b�N��p�ӂ��ă~���[�g��H�����������P�[�X�ɓ����A�u�p�\�R���}�C�N�p�~���[�g�A�_�v�^�[�v���ł�������܂��̂ŁA�C���z���E�}�C�N���͉̂������Ȃ��Ă����݂܂��B�@�����C���z���E�}�C�N���������Ƃ��ɂ��V�����}�C�N�ł��~���[�g�@�\���g����悤�ɂȂ�܂���B >���܁[��i�f�l�j �l �@��ɏ�����IBM�̃r�W�l�X�p�@��SB16�d�l�ł������A�ق��ɂ��r�W�l�X�p�@�ł͂܂��Â��K�i�̃}�C�N�[�q�ɂȂ��Ă��镨�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�ӂ���g���Ă��Ȃ��x�m�ʂ̌Â�FM/V(�������ʋ@�ł͂Ȃ��r�W�l�X�@)�ɓd�������Ď����Ă݂܂������ASB16�d�l�̃��m�������͂ł����B >(������]) �l �@���Ԃ�ALINE���͒[�q�̖����m�[�g�p�\�R���ȂǂŃX�e���I���͂��ł���悤�ɂ���p�r�Ƃ����ړI�͋����̂ł��傤�ˁB �@�������Â��m�[�g�p�\�R���̓��m����(�P�s���o�C�A�X)�ł����V�����m�[�g�̓}�C�N�[�q���X�e���I���͂ɑΉ����Ă��܂��B ���Ԏ� 2010/8/20
|
||
| ���e 8/26 |
���e�ɒlj��̃A�h�o�C�X�L��������܂��I ���܂肨��Ԃ��|���Ă͂����Ȃ��Ǝv���ŏ����̎���������̂ł����A ����͊�]���銮���`���̂��̂ł��i��j �����Ɏ��M�����������������n�b�L�����܂����B �d�˂Ă���\���グ�܂��I ��� �l
|
||
| �ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� | |||
|
DVD���R�[�_�̃����R���̌����{�̂ɓ͂��ɂ������ߑ��삵�Â炢�B�P�j�����R���̓d�r���A�P�S�w2�{����P5�w3�{�ɂ�����������Ȃ邩�H��H�����߂邩�H�Q�j�ق��ɁA��������������@�́H�R�j���ԊO���M�������Ĕ�������s�̕i�����������A�P�O���~�ȏ�̍����ł����B�����Ȑ��i�A�܂��́A����Z���Ԃłł����H�����Ă��������B �����Ă��܂� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����R���̓d�r�̓d�������Ղɏグ��ƁA��H(IC)�����Ă��܂��ł��傤�B �@���ɂ͓d�r�Q�{����d�r�R�{�ɂ��Ă����Ȃ������R�������݂͂��邩������܂���B���������R�����������ŁA���̒��̂P���炢�͉��Ďg�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă��������悤�Ȋ��̕��Ȃ�A�d�r�̖{���𑝂₵�ĉ��Ȃ��������Ă݂�̂��ʔ�����������܂���ˁB �@�ق��Ɍ�������������@�͂�����ł�����܂����A���莝���̃����R���̉�H����͂��āALED�܂��̐��䂪�ǂ̂悤�ȕ����ɂȂ��Ă��邩�𗝉����āA����ɂ��킹���lj���H��g�ݗ��Ă�����ɂ��������R�����������邱�Ƃ͂ł��܂���B �@��{�I�ȉ�H�͂قƂ�Ǔ����ŁA�n�C�T�C�h�����[�T�C�h���̈Ⴂ���炢�łQ��ނ̉�H�}����I��ŁA��͏����萔�����̃����R���ɂ��킹�邾���ł����A�܂������Ŏ�����o�����炢�̕��ł͉�͂ƒ��߂͖����ł��傤����A�����R���{�̂̉����͂�����߂Ă��������B �@�������A�����R���̉��������Ȃ�100�`200�~���x�ƂƂĂ������ς݂܂��B(�������Ń����R������́E�����������͎��ȐӔC�łǂ���) �@�����R���{�͉̂����������Ȃ��Ė����ŁA�����R���̐�ɕʂ̉�H�Ɠd�r�����ĐԊO��������Ƃ������@������܂����A�����R�����d���Ȃ�܂����lj������H����ꂽ�P�[�X�Ȃǂ��[�ɂƂ���ău�T�C�N�ɂȂ�̂ł��܂肨���߂͂��܂���B �@���āA�u�ԊO��(IR)�����R�����s�[�^�[(���p��)�v�Ƃ����@�B���I�[�f�B�I�r�W���A���n�̏��i�Ƃ��Ĕ����Ă���悤�ł����A������X���Ō������Ƃ͂���܂��A���l�i������~�`�P���~�ȏ�͂���悤�ł��ˁB �@�d�q��H�n�̃V���b�v�ł����ꂻ�̂��̂̑g�ݗ��ăL�b�g�͔�������Ă��Ȃ��悤�ł��B �@IC����炢�łł�����̂Ȃ̂ŁA���삵�Ă��܂��̂��悢�ł��傤�B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �ԊO����M��H �@�ԊO���̎�M��H�͐�p�́u�ԊO�������R������f�q�vIRM3638N3���g�p���܂��B �@�L�����A���g��38KHz�̈�ʓI�ȐԊO�������R���̎�M��H���������ꂽ���W���[���ŁA��M���������R���M����(���_����)�f�W�^���M���ŏo�͂��܂��B �@���̐ԊO�������R��������W���[�����g�p���Ă����\�ł��B���_���o�̓^�C�v�̃��W���[���ł�����̂܂g���܂��B �@IRM3638N3�̏o�͕͂��_���ł�����A�����R���M����H�̊��Ԃɂ͏o�͂�L�ł��B �@���̔��U��H�̐�����͂�H�Łu����v�ƂȂ�܂��̂ŁANAND�Q�[�g(NOT)��ŐM���]�����܂��B �@NAND�Q�[�g(NOT)�͐M�����]�ƂƂ��ɁA��M�m�F�pLED1��_��������������ʂ����Ă��܂��B(�ԊO�������R��������W���[���̏o�͎͂キ���ڂ�LED��_���ł��܂���) �@38KHz�ϒ��^�C�v�̐ԊO�������R���M������M����ƁA�����R���̃f�W�^���M���ɂ��킹�ă`���`����LED1���_�����܂��̂ŗe�ՂɎ�M���Ă��邩�ǂ����̊m�F���ł��܂��B �� 38KHz���U��H �@��M���������R���R�[�h(�f�W�^���M��)�����̂܂ܐԊO��LED�Ŕ��������Ă������R���M���ɂ͂Ȃ�܂���B �@�����R���M���𑗐M����ɂ́A�����R���M����H�̊��Ԃ�����킷38KHz�Ŕ��U���Ă���p���X�M�����K�v�ŁA���̔����g�̂��߂̃L�����A�M��38KHz�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�����ł�(�ق��̗p�r�ł�NAND�Q�[�g���g�p����̂�)�V���~�b�gNAND�Q�[�gIC 74HC132���g�p���Ĕ��U��H�����܂��B �@���U���g����VR1�Ŗ�33�`41KHz�̊ԂŒ��߂ł��܂��B(38KHz�Ŏg�p���Ă�������) �@���̔��U��H�͐ԊO����M�M��(�����R���̃f�W�^���M��)��ON/OFF�̐��������Ă��āA�����R���M������M���ă����R���f�[�^������Ă���Ԃ������U���삵�܂��B �� �ԊO�����M �@���U���Ő��������u�����R���M��H�̊��Ԃ�38KHz�p���X�M���v���g�����W�X�^�ŃX�C�b�`���O���āAIC�ł͒��ڋ쓮�ł��Ȃ��傫�ȓd���ŐԊO��LED3���p���X�_�������܂��B �@�ԊO���͖ڂɌ����܂���A�ԊO��LED�ƈꏏ�Ɋm�F�p��LED2���_�������܂��B �@LED2�͑��M���郊���R���M����38KHz�Ńp���X��������ԂŌ���܂�����A��M�m�F�p��LED1�Ɠ����Ɍ���ALED1���͏����Â������܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@IC����Ƃ܂��ɏ����̕��i�ł�����A�g�ݗ��Ă͂���قǓ�����̂ł͂���܂��A�g�ݗ��Ă���ɓd��������O�ɂ͂��イ�Ԃ�z���Ƀ~�X���������m���߂Ă��������B �@�ŏ���SW2�u�e�X�g�v�X�C�b�`�́u�ʏ��v���ɐ�ւ��Ă����Ă��������B �@VR1�͐^������(37KHz)�ɉĂ����Ă��������B �@�d�r�����ēd���X�C�b�`(SW1)��ON�ɂ���ƁA�eLED����u����܂�(������W���[���̏�����Ԃň�u����)�B���̌�͊eLED�͏������܂܂ɂȂ�܂��B �@LED��������ςȂ��ɂȂ�悤�ȏꍇ�A�z���~�X������܂�����A�����ɓd������Ĕz���ׂȂ����Ă��������B �@���̏�ԂŃ����R����������W���[���Ɍ����ĉ����{�^���������ƁA�`���`����LED1�ELED2�������Ɍ���܂��B �@LED������Ȃ��悤�ȏꍇ�A�܂�������ςȂ��ɂȂ�悤�ȏꍇ�A�z���~�X������܂����炷���ɓd������Ĕz���ׂȂ����Ă��������B �@��x�����R���̃{�^�����������炸����LED��������ςȂ��ɂȂ�悤�ȏꍇ�A�����̑��M�o�͂���M���W���[�����ĉi�v���[�v�ɂȂ��Ă���悤�ȉ\��������܂��B �@�����̐ԊO��LED�̌��͎����̎�����ɓ���Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@�u���p��v�ł�����A���M�p�̐ԊO��LED�̓P�[�u���ŐL���ĉ����ɒu�����A��M���E���M�����P�̃P�[�X�ɓ���Ă��܂��ꍇ�ɂ̓P�[�X�̕\�Ɨ��ɂȂ�悤�Ȕz�u�ŌŒ肷��Ƃ͎v���܂����E�E�E�B �@���̂܂܂ł��������̂܂g�p�ł��܂��B �@�ԊO��LED3�𐧌䂵�����@��̂ق��Ɍ����A�����R���̐ԊO���͋@��ɒ��ړ`���Ȃ�������ꏊ�ɒu���Ė{��H�̎�����ɂ����`���悤�ɂ��A�����R���̃{�^���������Ƌ@�킪�������ē��삷�邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@�ԊO��LED�ɍL�p�^�C�v(���ʂ̃����R���Ɏg�p����Ă���^�C�v)���g�p�����ꍇ�ɂ́A�ԊO��LED�𑽏��@�킩�炸�炵�������Ɍ����Ă��Ă���������ł��傤�B�ԊO��LED�͋@��ɑ��Đ��ʂ������悤�ݒu����̂����z�I�ł��B �@���p�^�C�v���g�p�����ꍇ�A���B�����͒����Ȃ�܂����@��ɑ��ĐԊO��LED���^���ʂ������悤�ɐݒu���Ȃ��Ɣ������Ȃ��ꍇ������܂��B �@�ł��@��Ɋ��x�悭��M�����悤�ɁA���M�L�����A���g���𐳂���38KHz�ɒ��߂��܂��B �@���g���J�E���^��A���g�����v���f�W�^���e�X�^�[���������̕��͔��U��H�̔��U���g�����v��Ȃ��璲�߂���ςނ��Ƃł����A���ʂ͎����Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�ق��ɐ���L�������J����Ă�����Ȃǂ́u���ۂɃ����R�����삵�Ȃ��璲�߂��āA�ł��@�킪�悭��������悤�Ɂc�v�ȂǂƂƂ������@���Ƃ��Ă���ꍇ������Ǝv���܂����A����ł����߂͂ł��܂��B �@�ł��A���ۂɃ����R���{�^���������Ȃ���E�E�E�Ƃ����̂�������Ɩʓ|�ł��B �@�����ŁA�N�ł��J���^���ɍł��ǂ���ԂŎg����悤�A�{��H�ɂ́u�e�X�g���[�h�v�����Ă��܂��B �@SW2�u�e�X�g�v�X�C�b�`���u�e�X�g�v���ɐ�ւ��Ă��������B �@����Ŕ��U��H�͎�M��H����藣����A��ɔ��U���Ă����ԂɂȂ�܂��B �@��ɔ��U���Ă��܂�����A�ԊO��LED3�Ƒ��M�m�F�pLED2�����U�M���Ō�����ςȂ��ɂȂ�܂��B �@���̃e�X�g������ԂŐԊO��LED3(�P�[�u���̐�ɂƂ���Ă���ꍇ)��{�@�̐ԊO��������W���[���Ɍ����Ă��ƁA�����Ŕ��������M������M���Ď�M�m�F�p�ԊO��LED1���_�����܂��B �@�����P�[�X�̕\���ɂȂ�悤�z�u����ꍇ�ł��A���߂��ςނ܂ł͐ԊO��LED�͏��������P�[�u���łȂ��ł����āA���R�Ɍ����⋗����ς�����悤�ɂ��Ă����ƒ��߂����₷���ĕ֗��ł��B �@�ԊO��LED3�Ǝ�����W���[���͏��������������Ă����AVR1�����E�ɉĎ�M����ׂ͈͂܂��B �@��M����͈͂̒����ɒ��߂��Ă��������B������38KHz�ł��B �@�ԊO��LED�Ǝ���������܂�߂��Ő^���ʂɌ��������ƁA���Ȃ���g�����Y���Ă��������Ă��܂��܂��̂ŁA10�Z���`�ȏ�͋����������A�������ʓ��m�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�Ȋp�x�Œ��߂����VR1�̒��ߔ͈͂������Ȃ�A���Ȃ萳�m��38KHz�_�����ɂ߂邱�Ƃ��ł��܂��B �@������d�v�ł����A�{��H�̔��U���g���͓d���d���ɂ��ω����܂��B �@�V�i���d�r��6V���Ɏ��g�����߂�����ƁA�d�r��������4V���x�ɂȂ������ɂ͂��Ȃ���g��������ċ@�킪�������ԊO���R�[�h��F�����Ȃ��Ȃ邩������܂���B �@�d���d��5V�Œ��߂��Ă����ƁA6V�Ɠd���������Ƃ��ł��A4V�Ɠd�����Ⴂ�Ƃ��ł��A�قږ��Ȃ��@��͐ԊO���M����F�����܂��B �@���d�r�Ŏg�p����ꍇ�͂ł���Γd��5V�Ŏ��g�����߂����Ă��������B�܂��́A�V�i6V�Œ��߂���ꍇ�ɂ�6V���ōł����m��38KHz�Ǝv����ʒu��菭���������g���������Ȃ�ʒu��VR1�߂��Ă��������B �@�{��H�̑ҋ@���̏���d���͖�1mA�ł��B �@�����̃����R���̎g�p�p�x�ɂ����܂����A�P�O�A���J�����d�r��A�P�Oeneloop����2000mAh���x�̏[�d�r�Ŗ�P�`�Q�������x�͎g�p�ł���ł��傤�B �@�d�r��������4V���x�ȉ��ɂȂ�ƁA���g��������Ă��܂����A�Ȃɂ��ԊO��LED�����������������Ȃ��Ȃ�܂�����ԊO��LED���牓���̋@��Ȃǂ͑���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�d�r��4V���x�܂Ō�������d�r�������Ă��������B �@�����A����I�ɏ�ɓd���͓��ꂽ�܂܂ɂ��Ă���悤�ȕ��Ȃ̂ŁA�ł���Γd�r�ł̎g�p����AC�A�_�v�^�[�ȂǂŃR���Z���g����d�����Ƃ�悤�ɂ����ق����g������͂悢�Ǝv���܂��B �@���̍ۂ͓d��DC5V(�܂���DC6V)�œd����100mA�ȏ��AC�A�_�v�^�[���g�p���Ă��������B�܂��K�����艻��H�����œd���͈��艻���ꂽ���̂��g�p���Ă��������B �@AC�A�_�v�^�[���g�p���Ă���A�d�r�̂悤�Ɍ����ēd���͕ω����܂�����g�����ς�炸���肵�Ă����Ǝg�p�ł��܂��B ���Ԏ� 2010/7/19
|
||
| ���e |
�ڍׂȉ����L��������܂��B���g���ϒ����Ă���Ƃ͒m��܂���ł����B�lj��̎��₪���܂�܂����B�P�j���M�p��LED�̒�R�l��ς��Č��������ł��܂����H�ǂꂭ�炢�܂ŕς��Ă����܂��H�Q�j�܂��͑����p�ɂP�[�Q����ɒlj��\�ł��傤���H�����Ă��������B �����Ă��܂� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@��R�l�͐�ɕς��Ȃ��ł��������B(����A��R�l��傫�����ďo�͂��キ����̂͂����R��) �@�����LED�ɂ͖�60mA(peak)�����v�ł��B �@����́u�ԊO�������R���̃p���X��ԁv�ł�����LED��_�������A����o�͂��A�������k�߂Ȃ��ł������̗ǂ���ԂŐv���Ă��܂�����A��R�l�������Ă������d���𗬂����Ƃ����LED�̎����͂��������ۏł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@LED�����ɁE�E�E�Ƃ������ł����A����ǂ̓g�����W�X�^2SA1015�̓d����i�̈��S�͈͂��܂��̂ŁA���̂܂܂�LED�����ɂ���Ƃ���ǂ̓g�����W�X�^�̎�����ۏł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@�g�����W�X�^��2SA950���ɒu���������2�`3����܂łȂ�_���ł��܂�����A�K�v�ɉ����ăg�����W�X�^���ς��Ďg���Ă݂Ă��������B �@���ʂɎ����Ŏg�������LED�����ɂ�����A�d����傫������K�v�͖����Ǝv���܂����E�E�E���X�Ɏ��ۂɑg�ݗ��Ă��ďo�͂�����Ȃ������̂ł��傤���H ���Ԏ� 2010/7/22
|
||
| ���e |
��H�̏����A�����������܂����B �����Ă��܂� �l
|
||
| ���e |
���������b�ɂȂ��Ă���܂��B�Ɠ��̎ԁi7�N�قǑO�̃��S���q�j�̃L�[���X�����R�����ԊO�����Ȃ̂ł����A��������ꂽ�ʒu���瑀�삵�Ȃ��Ɣ������Ȃ��ĕs�ւɎv���Ă���܂����B���̉�H�̎���f�q���A�O�㍶�E4�R�ɂ��Ē��˓�����������ʒu�ɐݒu����ΑS����������K�ɔ�������悤�ɂȂ�̂ł͂Ǝv�����̂ł����E�E�E�B�i�L�[���X�����R���̎��g���������ł���Ƃ����ꍇ�Ɂj�P���ɕ����̎���f�q��OUT���h�b1��12,13�s���ɂ܂Ƃ߂Đڑ������̂ł悢�̂ł��傤���H�������̂قǂ�낵�����肢���܂��B �Ƃ����� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�܂��u�Ԃ̐ԊO�������R������38KHz�ł��������H�v�Ƃ����^�₪�c��܂����A�����ɂ͂������������R���������̂Ŏg���镨�Ƃ��ĉ����Ă��������܂��B �@�ԊO��������W���[���݂����ȏW�ω�H(IC)�̏o�͂��A�����P�ɑ��˂��炢�����Ƃ��v���ɂȂ��鍪���͂Ȃ�ł��傤�H �@���ʂ́uIC�̏o�͕͂����Ȃ�����AH��L���V���[�g����IC�̏o�͉�H�������v�ƍl����̂ł����A��������IC�ŕ��������Ɍq����悤�ȉ�H�ł��ߋ��ɂ����ł����H �@���Ƃ��Ώo�͂��u�I�[�v���R���N�^�v�Ȃ��Ă��āA�v���A�b�v���Ďg���ĕ��������Ɍq���悤�ȗp�r�ɂ��g����悤�v�E��������Ă���IC�Ȃ炻�������g�������ł��܂����A���ʂ̃��W�b�N�o�͂�IC���Ƃ܂��ԈႢ�Ȃ����܂��B �@���̎���f�q��A�H���d�q�ȂǂŔ����Ă���ق��̃��[�J�[�E�^�Ԃ̎���f�q�̃f�[�^�V�[�g�������������ɂ킩��Ǝv���܂����A�ǂ��ɂ��I�[�v���R���N�^�Ƃ͏�����Ă��܂��A�u���b�N�}�����Ă����������\�����Ƃ͋L�ڂ���Ă��܂���B �@�ǂ����Ă����W�b�N�o�͂ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
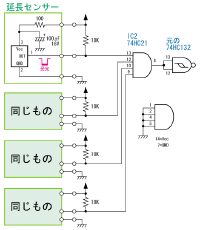 �@���W�b�N�o�͂���������ɂ́A�u�_�C�I�[�hOR�v���Ƃ邩�u���W�b�NIC��OR�܂���AND����v���ǂ��炩�ō�������K�v������܂��B
�@���W�b�N�o�͂���������ɂ́A�u�_�C�I�[�hOR�v���Ƃ邩�u���W�b�NIC��OR�܂���AND����v���ǂ��炩�ō�������K�v������܂��B�@����̂���]�����[�A�N�e�B�u�̂S��H�̍����ł�����A�S���͂�AND�Q�[�gIC 74HC21���g�������ł��܂��B �@�ԊO������f�q�̃p���X����ɂ�铮��s������������邽�߂̓d���t�B���^�[�́A�e�f�q�̋߂��ɒu���K�v������܂��̂ŁA�f�q�����P�[�u����L���̂ł͂Ȃ��A�t�B���^�[��H���ƐL���܂��B �@���̉�H�}�ł́A�ʂɂǂ̎���f�q�������������̕\��LED�͕t���Ă��܂���A�����M����������ςȂ��ɂȂ�悤�Ȍ�쓮��A�������Ȃ��Z���T�[���������ꍇ�̓Z���T�[���P���q���ŕςȓ��삷��ӏ���T���Ȃǂ̕K�v������܂��B ���Ԏ� 2010/7/26
|
||
| ���e |
�����Ȃ��璚�J�Ȃ��������肪�Ƃ��������܂��B�����̃o�J���ɋC�t�����Ă��܂��܂����B�܂��܂��Ȏ����ł������ꂩ�����낵�����肢���܂��B �Ƃ����� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���ʂ́A�Ƃ肠�����v�����ʂ�ɂ���Ă݂āA���𐁂��Ă���u�����A����͂��߂������v�Ɛg�������Ēm�邱�ƂɂȂ�̂ł����A�ŋ߂̓l�b�g�����B���ĉ����o�����ɋ����Ă��炦��悤�ɂȂ��āA�֗��Ȑ��̒��ɂȂ�܂����i�O�O�G ���Ԏ� 2010/7/29
|
||
| �ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� | |||
|
�P���E�b�h��CD�`�F���W���[�P�R�s���R�l�N�^�[�P�[�u�����iCA�|C�QAX�j�̃R�[�h���l�ɉ��H�������R���g�p�ł���悤�ɂ������ł� ���ł��o������͎̂��삵�����̂� naokazu �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@Kenwood�̃J�[�I�[�f�B�I���ACD�`�����W���[�ڑ��P�[�u��CA-C2AX�������Ă��܂���A�ǂ��ɂǂ̔z�����q�����͂������ł��܂���B �@�l�b�g��CA-C2AX�̎ʐ^������ƃJ�[�I�[�f�B�I����DIN 13pin�v���O�ł�����A�v���O�͓d�q���i�X�Ŕ����Ă��܂��B �@�u�P���E�b�h��CD�`�F���W���[�P�R�s���R�l�N�^�[�P�[�u�����v�Ƃ������ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ́A�P�[�u���͂��łɂ������ŃI�[�f�B�I���̃v���O�̕t���ւ������ōς܂������ԂȂ̂ł��傤���B �@CA-C2AX����2,3,6,8,9,12pin�Ƀs���������Ă��܂��̂ŁA�O�����͂Ƃ��Ďg�����ł����̂U�s���ɂ͉������A�T�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł��ˁB �@�����M����GND��L�ER�œ���邾���Ȃ�S�s���ōςނ͂��ł����A�U�s������Ƃ������͂ǂꂩ�̃s�����m�̓R�l�N�^�̒��Őڑ�����Ă��āA���̃s�����m�܂���GND�Ȃǂ�(�z���͂������O������͕s���ł�)�q���Ȃ��ƊO�����͂��ڑ�����Ă���ƔF�����ꂸ�A�����R�l�N�^���h�������ł͊O�����͂��g���Ȃ��悤�Ȃ����݂ɂȂ��Ă���\���͍����ł��B �@�J�[�I�[�f�B�I�̎������������̂悤�ł�����A�������Ă݂�DIN�R�l�N�^�̊e�s�������łǂ�Ȕz���ɂȂ��Ă���̂�����͂��Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B(������x�͓d�q��H�E��z���̒m���͕K�v�ł�) �@���낿���DIN�R�l�N�^���Ă��Ďh���āA�ǂꂩ�̃s���ɉ�������ꂽ�特���o�邩�ǂ��������n�Ŏ����Ă݂�̂������Ƃ��Ă͂����ł��ˁB �@�����A���̒[�q�͒P�Ȃ�O�����͒[�q�ł͂Ȃ��ACD�`�F���W���[�̃R���g���[���[�q�ł������ǂꂩ�̃s���̓f�[�^�ʐM�p�̐M�����o�Ă��āA�����ɕςȔz����������J�[�I�[�f�B�I�̃R���g���[���[�����Ă��܂��ē�x�Ǝg���Ȃ��Ȃ��\��������܂��B �@�J�[�I�[�f�B�I���Ă������Ƃ��v���ł�����e�[�q�ɒ��ډ����M�����q���Ȃǂ̃`�������W�����Ă݂�̂��A�d�C��H�̕�(���ʂ͒ɂ����̂ɂȂ邩���H)�Ƃ��Ă͖ʔ����Ǝv���܂��B������Ȃ��̋����Ɣ��f�ōs�����ŁA���͈�̐ӔC�͎����܂���B �@�����łȂ���A2000�~�ʂŃ��[�J�[�����̃P�[�u�����Ă��Ďg���ق������S�֗��Ŋm���ł��B ���Ԏ� 2010/7/12
|
||
| �ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v | |||
|
���������b�ɂȂ�܂��B�ԍڗp�̃A�N�Z�T���[�p�r�ł̉����x�\���@�H����肽�����₳���Ă��������܂��B�A�N�Z�����x�^���݂������ɂ͐Ԃk�d�c��3�_���B�ʏ�̔��i���x�̉������ɂ͐Ԃk�d�c��1�_���B���̒��Ԓ��x�̉����ł͐Ԃk�d�c��2�_���B�}�u���[�L���ɂ͐k�d�c��3�_���B�������Ǝ~�܂錸�����ɂ͐k�d�c��1�_���B���̒��Ԓ��x�̌����ł͐k�d�c��2�_���B�قڈ�葬�x�ł̑��s���̂Ƃ��ɂ͗k�d�c��1�_���B�M���҂��Ȃǒ�Ԓ��͑O�q�̗k�d�c���������Ɠ_�ŁB�Ƃ����ӂ���7�̂k�d�c��ԐԐԗΐƔz�u���ĉ����x���x�����[�^�[�Ɏd�グ�����̂ł��B���݁A�i�r�p�̎ԑ��p���X�M������e�u�R���o�[�^�h�b�𗘗p���Ď���100�L���̂Ƃ���1�u�̓d������������悤�ɒ���������H�����삵�Ă���܂��̂ŁA���Ƃ���0.5�b�O�̎ԑ��d���ƌ��݂̎ԑ��d���Ƃ��r���邱�Ƃɂ�肻�̓d�������v���X�A�}�C�i�X�e3�i�K�A�������܂߂Čv7�i�K�ɂĕ\�����������ƍl���Ă���܂��B0.5�b�O�̎ԑ��d���ƌ��݂̎ԑ��d���Ƃ��r������@�Ƃ��Ă�0.5�b�T�C�N���ŃR���f���T����d�A�[�d�A��r��3�H�����J��Ԃ���H��3�Z�b�g���A1�H�������炵�Č��ݓd���Ɣ�r���邱�Ƃɂ���ď��0.5�b�O�̎ԑ��d���ƌ��݂̎ԑ��d���Ƃ̔�r�l��0.5�b�ԕ\������Đ�ւ���Ă����̂ł͂ƍl���Ă���܂��B�Ƃ��낪��ɕϓ�����d�������ǂ̂悤�ɂ��Ēi�K���������炢�����̂����̕��@���v�����܂���B�ǂ�������100�L���̂Ƃ���1�u�̓d�������������H����7�̂k�d�c�𗘗p���������x���x�����[�^�[�������@�ɂ��Ă��������������܂��悤��낵�����肢���܂��B �Ƃ����� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���������u�d�����L������v��H�́u�T���v���E�A���h�E�z�[���h��H�v�܂��́u�T���v���E�z�[���h��H�v�Ƃ����āA�R���f���T�Ɠd�q�X�C�b�`�ƃI�y�A���v���ō��̂���ʓI�ł��B �@�l�b�g��Ō�������Ύ����͏o�Ă���ł��傤���A�����Ă��̃I�y�A���v�̃f�[�^�V�[�g�ɂ̓T���v����H�}���ڂ��Ă��܂��B �@�ԑ����r����Ȃ�R�g���p�ӂ��Ȃ��Ă��A (1) ���݂̎ԑ���ۑ����� (2) �ߋ��̎ԑ���ۑ����� 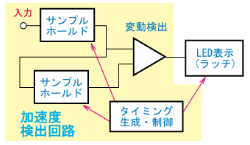 �̂Q�̃T���v���z�[���h��H��p�ӂ��āA����r������(1)�̏���(2)�ɃR�s�[���Ă����������ł��B
�̂Q�̃T���v���z�[���h��H��p�ӂ��āA����r������(1)�̏���(2)�ɃR�s�[���Ă����������ł��B�@���f�[�^(�d��)��ǂݍ��ނ̂��̐����A��r�����f�[�^��LED�̕\���p�^�[���ɕς��Ă�������̔�r���܂ŕۑ����Ă�����H�₻�̐���ȂǁA�f�W�^����H�ɂ�鐧�䕔�ƃA�i���O��H�ɂ��d���ۑ�(�z�[���h)���r��H�̑g�ݍ��킹�őS�̂���邱�ƂɂȂ�܂��B �@�܂��A�����d�q���i�ł͂Ȃ�PIC�Ȃǂ̃}�C�R���Ő��삷��ꍇ�������悤�Ȋ����ŁA���鎞�_�ł̎ԑ��d����A/D�R���o�[�^�œǂݍ���ŁA���̑O�̂��鎞�_�ł̓d���f�[�^�Ɣ�r���Ă��̍��̐��l�̑傫�������(�{���|��)�ŏ�Ԃʂ���v���O������g�ނ��ƂɂȂ�܂��B �@��x��r����LED�̓_�����s������A���ǂݍ��ŐV�̃f�[�^���P�O�̃f�[�^�Ƃ��ċL�����Ă����āA���̉�̔�r�ɔ����܂��B �@PIC�̘b�͂܂��]�k���Ƃ��āA����̂���]�ʂ�ɃT���v���z�[���h��H���Q�ƃf�W�^�������H��g�ݗ��Ă�ƂȂ�Ƃ����������i���������Ȃ�A��������\��ςɂȂ�܂��B �@�����łP��ĂȂ̂ł����A�������̃T���v���z�[���h��H�ƃf�W�^�����䕔�ō��u�����x�����o�����H�v(��̐}�̉��F�������ALED�\�����͏����܂�)���������P��IC�ō���Ȃ�ǂ��ł��傤���H �@��������pIC�ł͂Ȃ��A�ǂ��ɂł������Ă��鐔�\�~�̃I�y�A���vIC��ƁA��R�E�R���f���T�ȂLj������i���łł��B �� ���ۂ̓m�C�Y��Ȃǂł��Ɛ����i�������܂����E�E�E 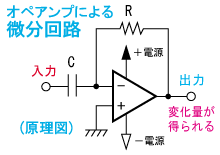 �@�E�}�̓I�y�A���v��ō��u������H�v�ł��B
�@�E�}�̓I�y�A���v��ō��u������H�v�ł��B�@�u������H�v�Ƃ������t���̂͂悭�����ł��o�Ă���̂ŕ��������͂���Ǝv���܂��B �@�I�y�A���v�ɂ�����]������H�̓��͕�����R�����R���f���T�ɕς�������̂ŁA�R���f���T�̓����ɂ��𗬂ȂǓ��͓d�����ω����鎞�������I�y�A���v�̓��͂̓d�����ω�������̂ł��B �@���͓d�����ω����鎞�����o�͓d���̕ω��Ƃ��Č��ʂ�����܂��̂ŁA�ԑ��d������͂��Ă��u�������Ďԑ��d�����オ�����������v�u�������Ďԑ��d�������������������v�I�y�A���v�̏o�͒[�q�Ɏԑ��̕ω��̑傫���ɉ������d��������܂��B������肵�������E�����Ȃ�Ⴂ�d���A�}���ȉ����E�����Ȃ獂���d���ł��B �@���������������Ă��Ȃ����ɂ͏o�͂͂O�u(�E�}�̏ꍇ)�ŕω��͂���܂���B �@�������A�A�i���O��H�ł����珈���̓��A���^�C���ł��I �@0.5�b�����ɕ\�����p���p���ς��Ȃǂ̃J�N�J�N���������͑S������܂���B �@�ω��ʂ����o���邽�߂̃R���f���T�̏[���d���Ԃ̂Ԃ�0.1�`0.2�b���x�͒x��ĕ\�����邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂����A�\�����̂̓A�i���O�����ŏ�ɕω��𑱂��Ă��܂��̂ŎԂ̉��������قڑ̊��ʂ�ɕ\���ł��܂��B [ ���[�r�[������ (11MB) ] (�ʃE�C���h�E�ŊJ���܂�)
�� �f�W�J�������[�r�[���[�h�ł̓}�N���B�e�ł��Ȃ��̂ŁA�ʏ틗���ŎB�e�������̂��g�債�Ă��܂��̂ʼn掿�͂��̂����������ł��B���������������B �� �e�X�g��H�̂��߁A�}0�\���͗ł͂Ȃ��s���NLED�A��Ԍ��o�͐Ԃł͂Ȃ���LED���g�p���Ă����܂��B �� ���[�r�[�͍폜���܂����B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�� ������H �@����̉�H�̗v�ł��B �@���͒[�q�ɓ��ꂽ�ԑ��d��(1V=100Km/h)��������āA�ω��ʂ�d���o�͂��܂��B �@���x��VR1�Œ��߂ł��܂��B �@�������ӂ��K�v�Ȃ̂́A�I�y�A���v�Ŕ�����H�����Ɗ�b�����]������H�Ȃ̂ŁA���͓d�����オ��(����)�Əo�͓d���̓}�C�i�X���A���͓d����������(����)�Əo�͓d���̓v���X���ω����܂��̂ŁA�\�����͂���ɑΉ������\���ɂȂ�悤�ɂ���K�v������܂��B �@�����ʂ̗p�r�E��H�Ŏg���ꍇ�Ɂu���͓d�����オ������o�͓d�����v���X���~�����v�Ƃ����悤�ȏꍇ�́A������i���]������H�������Ĉʑ��]�����Ă������ł��傤�B �@���A�����(�����E�E�E)�I�y�A���v���v���X�E�}�C�i�X�̗��d���Ŏg�p�����Ɂ{�T�u�̒P��d���Ŏg����H�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�K���d����GND�ł͂Ȃ��ʂ̕����ō����1/2Vcc(2.5V)��^���Ă��܂��B �@�ł�����o�͂��u�������Ȃ���2.5V�v�u������2.5V���Ⴂ�d���v�u������2.5V��荂���d���v�ƂȂ�܂��B �@LM358�̓����ɂ��A�o�͓d���͍ő��Vcc-1.5V (3.5V)�܂ł����オ��܂���B���LED�\���p�̓d����r���ł͂��͈͓̔��̓d���œ��삷��悤�v���Ȃ���Ȃ�܂���B �@�ʂ̗p�r(�A�i���O���[�^�[�ʼn����x�\��������Ƃ��c)�Ńt����5V�܂ŗ~�����ꍇ�́A������ƍ����ł������[��to���[���^�C�v�̃I�y�A���v���g�p���Ă��������B����͂��̕K�v�͂���܂���B �� LED�\����H �@������H�̏o�͓d����LED��_���������H�ł��B �@R12�`R19�Ŕ�r�p�d�������A���ꂼ���LED����r�p�d���Ɠ��͓d��(������H�̏o��)�̊W�ŕ\��������������������LED��_�������܂��B �@�u�������Ȃ��v�̗�LED�́A�w�u�������v���u�������v���_�����Ă��Ȃ��x���ɂ����_�����܂��B �@�X�ɓd���́u�Î~�p���U��H�v���������āA��Ԓ��͓_�ŁA�����łȂ���(���s��)�͌p���_���Ƃ����\���`�����I��܂��B �� �Î~���o��H �@�ԑ��d�������d���ȉ��̏ꍇ���u�Î~(���)�v�Ɣ��f����d����r��H�ł��B �@�Î~�Ɣ��f����X�s�[�h��VR2��0�`10Km/h�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@�Î~�Ɣ��肵���ꍇ�̏o�͂�R9�EC7�̐ϕ���H��2�`3�b�قǒx�点�܂��B �@�t�ɐÎ~��Ԃ��瑖�s��Ԃɕω�����ꍇ��D1�o�R��C7�������ɕ��d�����Ĉ�u�ő��s����ɂ��܂��B �@�Î~�����m���Ă��邩��LED1�̓_����Ԃł킩��܂����A�ϕ���H�̏o�͏�Ԃł͂���܂���B �@�����܂ŃX�s�[�h���������ĐÎ~��ԂƔ��肵�Ă��邩�ǂ����ł��B �@���ALED1�̓e�X�g�p�E�����p�ł���A����]�ɂ͂���܂���̂Ńp�l���\�ʂɏo���K�v�͂���܂���B �� �Î~�p���U��H �@�Î~��Ԃ̎��Ɂu�������Ȃ��v�̗�LED��_�ł����邽�߂̔��U��H�ł��B �@�_�ŃX�s�[�h��VR3�Œ��߂ł��܂��B �@�Î~��Ԃ����o����Ɣ��U���܂��B �@���̔��U��H�����U��������Ƃ����āA���ꂾ���ł͗�LED�͓_�ł��܂���B �@���������o��H�������⌸�������m�����A�u���������Ă��Ȃ������LED�_���v�Ɣ��肵�����ɂ�����LED�͓_�ł��܂��B �@���s���͔��U���~���āA�o�͂͗�LED�ɓd�������������ςȂ��ɂȂ�܂��B���̏�Ԃʼn������Ȃ��ŗ�LED��_��������Ɠ_�ł͂����ɘA���_�����܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� 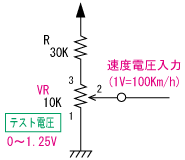 �@�g�ݗ��Ă���A�e�X�g�͎ԂɌq�����ɍs���܂��B
�@�g�ݗ��Ă���A�e�X�g�͎ԂɌq�����ɍs���܂��B�@�ԑ����͒[�q�ɁA��R30K����10K�����x�̉ϒ�R(���삵�₷���悤�Ƀ{�����[�����ǂ�)��}�̒ʂ�q���܂��B �@����Ń{�����[�����Ή��z�I��0Km/h�`125Km/h�܂ł̎ԑ��d������͂ł��܂��B (FV�ϊ���H�����삳��Ă���悤�ȕ��ɂ͐������v��Ȃ��Ǝv���܂����c) �@�����������e�X�g��H�̃��[�r�[�͂������ă{�����[�����ăe�X�g���Ă��܂��B�f�W�^���X�s�[�h���[�^�[�͂�������̓d����\�����Ă���e�X�^�[�ł��i�O�O�G �� �e�X�g�J�n �@VR1�AVR2�AVR3�͑S�Đ^�ɍ��킹�Ă����Ă��������B �@���̏�ԂŃe�X�g�pVR���������ς��ɉĎԑ��d����0V�ɂ��A��H�̓d�������܂��B �@�ŏ���LED���p���p���Ɠ_�����Đ��b��ɏ��X�ɏ����܂��B �@����͉�H���̊e�R���f���T���K��̓d���ɂȂ�܂ŁA�������ł�����LED���_�����Ă��܂����߂ŋC�ɂ��Ȃ��ł��������B �@����̊ԈႢ���Ȃ���A�u�������Ȃ��v�̗�LED�Ɓu�Î~���o�v�̐�LED���_�����܂��B �@�u�������Ȃ��v�̗�LED�͒�Ԃ��Ӗ�����_�ł��͂��߂܂��B �@��LED�̓_�ő��x��VR3�Œ��߂ł��܂��B �@���D�݂ɂ��킹�Ē��߂��Ă��������B �� �����x���o�̃e�X�g�B �@�e�X�g�ԑ��{�����[�����E�ɉāA���x���グ�鑀�������Ɖ������̐ԐFLED���{�����[�����X�s�[�h�ɉ����ĂP����R�̊Ԃœ_�����܂��B �@�ǂ����Ŏ~�߂�Ɖ��������Ă��Ȃ���ԂȂ̂ʼn������̐ԐFLED�͏����āu�������Ȃ��v�̗�LED���_�����܂��B �@�e�X�g�ԑ��{�����[�������ɉāA���x�������鑀�������ƌ������̐FLED���{�����[�����X�s�[�h�ɉ����ĂP����R�̊Ԃœ_�����܂��B �@�e�X�g�ԑ��{�����[�������낢��ȑ��x�ł��肮�荶�E�ɉāALED�̓_���E�ω��E�����̂悤���� �@�����܂Ńe�X�g�ł�����A���x���ߗp��VR1�����ɉƊ��x�������ăX�s�[�h�̕ω��������Ȃ���LED���R�_�����Ȃ����ƁA�E�ɉĊ��x���グ��Ə����̕ω��ł�LED���R�_�����邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@���x���߂��ύX�ł���Ή��������ʂ�LED�_����H�͐��������삵�Ă��܂��B �@VR1��^������ɖ߂��āA���Ԃɐڑ����Ă̒��߂�҂��܂��B �� �Î~���o�̒��߁B �@�e�X�g�ԑ��{�����[�����E�ɉđ��x���グ�鑀��������10Km/h�O��Łu�Î~���o�v�̐�LED(LED1)���������A���ɉ�0Km/h���炢�܂ŗ������LED1���������܂��B �@VR2���Ȃ�ׂ����ɉāA��L�̑��s����LED1�����A��Ԃ����LED1�_������ʒu���Ȃ�ׂ������Ō����Ƃ���܂ʼn����܂��B �@VR2���������ς��ɉĂ��܂��ƁA��Ԃ��Ă�LED1���_�����Ȃ��Ȃ�܂�����A���܂����߂��Ă��������B �� ���Ԃł̊��x���� �@�����܂Œ��߂ł�����A��͎��Ԃɍڂ��Ė{���̑��x�d���M����ڑ����āA�u�}�����E�}�u���[�L���x��LED���R�_������悤�v���ۂɑ�����LED�̓_����Ԃ��m���߂Ȃ���VR1�Ŋ��x���߂����܂��B �@�����A���肢�ł�����^�]�҈�l���^�]���Ȃ���̒����͐�ɂ��Ȃ��ł��������B �@����Ȃɏ���̕����悹�Ă��̕���VR1���Ă��炤�Ƃ��A��l�^�]�̏ꍇ��VR1�̒��߂͕K����Ԓ��ɍs���ȂǂƂ��A��ɑ��s���ɉ^�]�҂̕������߂��s�����Ƃ͂��������������B �@������x�@���ɂ݂������ꍇ�A�^�]����(�g�ѓd�b�₻�̑����u��)�킫������Ƃ��Č��������\��������܂��B �@�Ō�ɁA������낵����Ύԑ��p���X����ԑ��d���ւ�FV�ϊ���H�̉�H�}���ǂ����Ō��J���Ă��������܂��H �@���̋L�����Q�l�Ɏ����̎Ԃɂ������Ƃ��l���ɂȂ�������������邩������܂���B �@�������������̐S�̃X�s�[�h�����Ԃ��瓾���Ȃ������炱�̉�H�͈Ӗ��𐬂��܂���̂ŁA�����ł���Ό��J���ĒN�ł�����悤�����������Ă��������Ă��������B ���Ԏ� 2010/7/4
|
||
| ���e |
���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�ԑ��p���X�̂e�^�u�ϊ��ɂ��� �g�`���`�� �u�ԑ��p���X�M���͂��ꂢ�ȐM���ł͂Ȃ���GND�ȉ��ɗ����Ă��镔����1V�ȏ゠������A��Ԏ���DC�I�t�Z�b�g��1V���x��������A�o�͔g�`�����SmV�P�ʂłӂ���Ă����肷��̂ŁA���ꂢ�ȐM���邽�߂ɁA�_�C�I�[�h��GND�ȉ��̓d�ʂ�12V�ȏ�̓d�ʂ�����������A�M���Ɋ܂܂��m�C�Y��Ƃ��ăR���p���[�^��4.7���Ƃ������Ȃ�傫�ȃq�X�e���V�X�����������������d����^���Č��M�����U�b�N���Ɛ��`�B�I�[�v���R���N�^�o�͂�+5V�Ńv���A�b�v���čŌ�̎d�グ��74HC14��ʉ߂����Ĕg�`���`�����v�Ƃ����������l�b�g�Œm�������܂����B�i�������d���`�F�b�N�p�ɂk�d�c�𗘗p�B�S���_�ł��Ȃ��d������`���`�����n�߂�d���܂ʼn�������ɏ��������ă`���`�����͂����肵���Ƃ���ŌŒ�B�j����ł��ꂢ�Ȏԑ��p���X�M�������o�����͂��ł��B TA8029S�� �[�q1�F�f�[�^�V�[�g�̉��p��H��ƈ���Ă��܂��B���̂e�^�u�ϊ��h�b�̉��p��H��Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ď��s����̌���4.7KΩ��0.47��F�����̂悤�ɐڑ����܂��������_�͑S���킩��܂���B �[�q2�F6800pF��100km/h�̂Ƃ�1�u�o�͂ɐݒ肷�邽�߂ɒ[�q3�̌Œ�22KΩ+���Œ�10KΩ�Ƃ̑g�ݍ��킹�őI�l�ł��B �[�q3�F22��F�̓f�W�^���\���l�ƎԂ̃��[�^�[�̓����������悤�ɂƑI�l�ł��B �[�q4,6�ƒ[�q7,8�F�������l�t�߂Ŗ\��Ȃ��悤�ɑ傫�ȃq�X�e���V�X��74HC14�p�B�x�����ȂǕʉ�H�p��35�`143km/h�ԂŐݒ肵�Ĕ��ʐM���������������Ǝv���Ă��܂��B TA8029S�̏o�͏����� �{���e�[�W�t�H����+���Z��H�Œ������āA�����ɂȂ�قnjv�Z�l���o�͓d�����Ⴍ�Ȃ錻�ۂ����P�B ���Z��������ƍ����ɂȂ�قnjv�Z�l���o�͓d���������Ȃ�̂ł��傤�ǂ����Ƃ����T���܂��B �ԍڃe�X�g������̂��Ȃ��Ȃ�����̂ł����A�Ԃ̃��[�^�[��60km/h�̂قڒ葬���s���������̏o�͓d����0.6�u�ɒ���������ԂŎԑ��p���X�̑����32Hz�̃e�X�g�M������͂����0.46�`0.47�u�ƂȂ����̂�32Hz��128Hz�̃e�X�g�M���Ŗ�0.47�u�Ɩ�1.88V�ɂȂ�悤�ɒ������Ă��܂��B ���̔z���}�͑��x�v�Ɖ�]�v�̃y�A�ɂȂ��Ă��܂����A�p���X���̈Ⴂ�ɑΉ����������œ������̂ł��B ��ς킩��ɂ����}���Ƃ͎v���܂����ǂ�����낵�����肢���܂��B �Ƃ����� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����肢��������Excel�̃V�[�g���摜�ɂ��Čf�ڂ������܂����B �@F/V�ϊ��̓d�����ᑬ�ƍ����ŋ����Ƃ������Ƃł����A�f�[�^�V�[�g�ł��Y��Ȓ����ɂȂ�͂��Ȃ̂ŁA�R���f���T�̑I���ق������ŋ�������������̂�������܂���B �@�������A�p���X�ɉ����ď[�d�E���d���ďo�͓d��������H�ł�����A�Ⴂ���g��(��Hz���x�`)�قǕs����ɂȂ�͎̂d���Ȃ��̂ł��܂�Ⴂ�d���ɑ��Ċ��҂������Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B �@TA8029S�̓��͒[�q�̓f�[�^�V�[�g�̃u���b�N�}������킩��悤�ɃV���~�b�g���͂ɂȂ��Ă��܂�����A74HC14�͕s�v�ł����Ȃ���0.47��F�����������ɂ��Ă��܂����A�������Ȃ��Ɠ����Ȃ������̂ł��傤���B���Ƃ�����s�v�c�ł��B �@���̓R���p���[�^�̊m�F�̂��߂�LED���������̂�74HC14�����Ă���Ƃ��������Ȃ�74HC14���g���Ă���͕̂ʂɂ��܂��܂���B�ł����̂܂�TA8029S�̓��͒[�q�Ɍq���ł����Ɠ��삵�Ȃ��̂ł���Ζ�肠��ł��ˁB �@���̎��������ꂩ��������̎Q�l�ɂȂ�Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2010/7/13
|
||
|
����ȑO�̓����͂����灨 [2010�N�O���̉ߋ����O]
|
|||
|
�T���₷���ړI�E��H�̃W�������ʈꗗ�͂����灨 [�W�������ʈꗗ]
�悭�g�����i�́u���̐}�v�͂����灨 [�悭�g�����i�́u���̐}�v]
|
|||
|
(C) �u�C�̖����v�^Kansai-Event.com
�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������
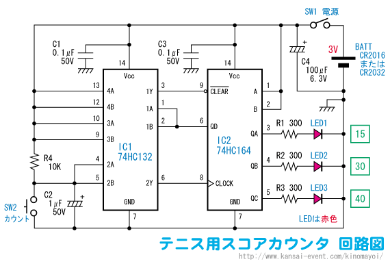
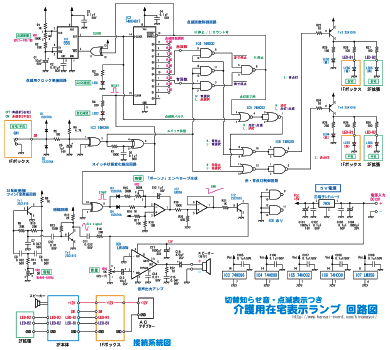
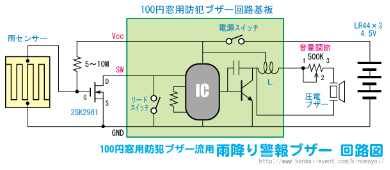
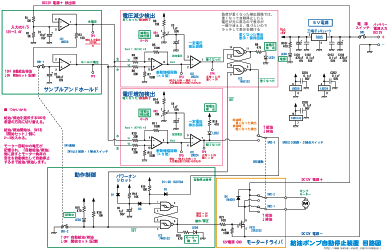
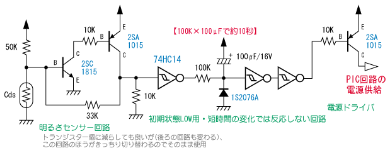
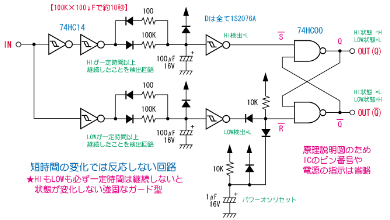
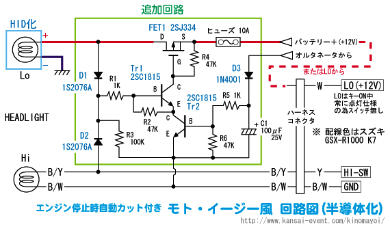
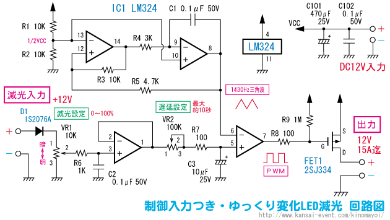
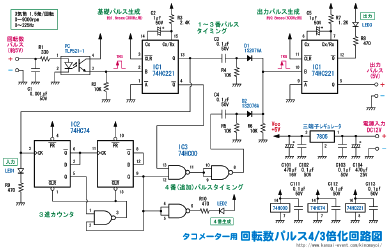
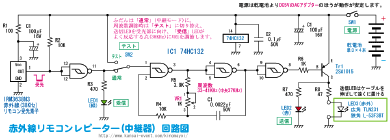
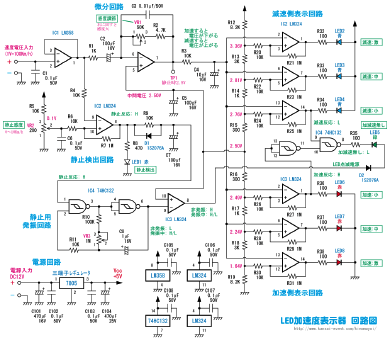
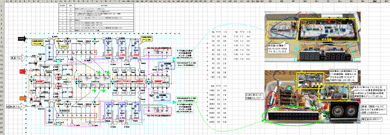
 �u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�
�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�