| ||||||||||
|
|
| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |
��H�E�f���L�E����
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���� ���̃y�[�W��2012�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B
�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B
�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B
|
�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |
�y�ꗗ�z
�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�
|
��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |
|
�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
���� ���̃y�[�W��2012�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
| �p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ | |||
|
�����b�ɂȂ�܂��B �u�p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v�v�������������p���Ă��܂��B ���āA�܂��A�s���l�܂�܂����̂ł������̂قǂ��肢���܂��B �{�^���d�r�ʼnғ����鏬���̖������o�鏬���̂������Ⴊ����̂ł����A�{�̂��V�����Ēu���̑̂𐬂��Ȃ��Ȃ����̂ŁA�d�q�I���S�[�������o���čė��p�������Ǝv���܂��B ���̔������i�́A���ɔ������Ė�̂ł����A�d�r����ꂽ���ɂ��P���܂��B�����ŁA��������̖��Ái�d���̓����j�Ŗ�悤�ɂ��悤�Ǝv���܂��B �u�ς��ƈÂ��Ȃ�������v�̂́A�u�p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v�v�̕��ׂ����̃I���S�[���ɂ���A���̂܂܊����ɂȂ�Ǝv���܂��B�܂��A�u�ς��Ɩ��邭�Ȃ�������v�̂��ACds�̈ʒu��ς���Ύ����ł���Ǝv���܂��B �ł́A�ς��ƈÂ��Ȃ����Ƃ������邭�Ȃ����Ƃ������悤�ɂ���ɂ́E�E�E�H Cds���Q�g���āA�u�����Áv�Ɓu�Á����v�̃Z���T�[�������AOR��H��555�̃g���K�[�ɂ���Ή\���ȂƎv���̂ł����ACds�P�ŁA�u�ς��ƈÂ��Ȃ��Ă����邭�Ȃ��Ă��v�g���K�[�ɂȂ��H���A�i���O��H�Ŏ������邱�Ƃ͉\�ł��傤���H ��ʉ�����ƁA�d����������Ƃ��ƁA�オ��Ƃ��ɂ��ꂼ��g���K�[��������ɂ́A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���H �����\�ł���A�g���K�[�܂ł̉�H�̍l����������������������K���ł��B �X�~ �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���Ԃ�E�E�ECds���Q�A�g�����W�X�^���Q�E�E�E�݂����ȁu�p�b�Ɩ��邭�Ȃ����v�u�p�b�ƈÂ��Ȃ����v�̂Q�̉�H������ă_�C�I�[�hOR�����Ε��i�������Ȃ��ăJ���^�����Ǝv���܂����A�܂��߂ɍ��Ƃ���Ȋ����ɂȂ�܂��B �@���i���Ō����ƁE�E�E�������炢���ȁi�O�O�G ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ������H and ���x���� �@�I�y�A���v LM324 ���g����������H�ł��B �@������H�Ƃ͓��͐M��������������̂�(������܂����c)�A�d�C�M�����������Ƃ������Ԃ�����̕ω��������o���܂��B �@�܂�ACds�ƒ�R�ō�����u���邳�ɑ�������d���v����͂��Ă��ƁA�u���邳�ɕω���������A�o�͓d���͖���(0V)�v�u���邳�ɕω�������A���̕ω��ʂɉ������o�͓d�����o���v�Ƃ������������܂�����A�u�p�b�Ɩ��邭�Ȃ����v�u�p�b�ƈÂ��Ȃ����v�悤�ȏꍇ�ɂ��o�͓d���̐U���͂��傫��(���ۂ́{���Ɓ|���̗����ɐU��)�Ȃ�A�������Ƃ������邳�̕ω��ł͏o�͓d���͂قƂ�Ǖς��Ȃ��Ƃ����A���邳�̕ω��̌������E�ʂm�ɑ���ł���o�͂������܂��B �@������H�̓I�y�A���v�����]������H�̉��p�ł��̂ŁA�t�B�[�h�o�b�N�ʂ߂��Ă�����������ς������̂ŁAVR1�Łu���x�v�߂ł���悤�ɂ��܂��B �@�E�ɉΊ��x�͑��������̕ω��ɂ��q���ɔ������܂��B���ɉΊ��x�͗�����̂ő傫�ȕω��łȂ��Ɣ������Ȃ��Ȃ�܂��B �@������Ƃ����]�k�ł����A���̔�����H�ł͂�����ȏ�́u�����g�v�͊��m(����)���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B �@���Ɋ܂܂��m�C�Y��O���m�C�Y���������Ă��܂��Č�쓮����悤�Ȏ���h���ړI�ƁA�ŋ߂�LED�Ɩ��ł̌�쓮��h�����߂ł��B �@LED�Ɩ��̒��ɂ������@�\(���邳��F��ς�����)�̂�����������A�����͂����Ă���PWM�����Ŗ��邳��F��ς��Ă��܂��B �@PWM�ł͂�����x�ȏ�̎��g���Ŕ��U�����p���X��LED��_�������u�l�Ԃ̖ڂɂ͖��邳���ς��悤�Ɍ�����v�悤�ɂ������@�ł����A�����������Z���T�[�ɂƂ��Ă͋Ȏ҂ŁA�Ɩ����p���X��ɓ_�ł��Ă����̂ł��̃p���X���u�p�b�ƕω����Ă����v�ƌ��m���Ă��܂��Ă͏Ɩ���_�����Ă���Ԓ������Ɣ��������ςȂ��ɂȂ�܂��B �@�����Ȃ�Ȃ��悤�A�����Ƃ��������ł́u���͂̕ω��ʂ𒊏o���铮��v�Ƃ������ɂȂ�̂ł����A�I�y�A���v�ɂ�������H�ł͒��ɓ��삪�������ϕ���H�̗v�f���g�ݍ���Łu�������g���̓m�C�Y�̌��Ȃ̂Œʂ��Ȃ��I�v�Ƃ��������݂�����̂ŁA������u�������g���œ_�ł��Ă���LED�Ɩ���PWM�_�łɂ͔������Ȃ��I�v�����ɗ��p����悤�v���Ă��܂��B �@���́A�����ɂ�PWM�Œ��������肷�鍂����LED�Ɩ��͖����̂ŁA�e�X�g�́uPWM�������Ă���LED���C�g�v����ނōs���Ă��܂��B �@���Ԃ�A���ۂ�LED�Ɩ��ł����v���Ǝv���܂����A�����ƒ�p��LED�Ɩ��̕����ł����Ɣ��������ςȂ��ɂȂ�悤�Ȃ�ꕔ���i�萔�̕ύX���K�v��������܂���B �@�̂́A����ȐS�z���Ȃ��Ă��ǂ������̂ɁI(��) �� �E�C���h�E�R���p���[�^�[ �@������H�Ō��o�������邳�̕ω��ʂ��u�p�b�Ɩ��邭�^�Â��Ȃ������H�v(�K��̔����������H)�̔��ʂ����邽�߂̃R���p���[�^�[(��r��)�ł��B �@��ŏ����܂����Ƃ���A������H�̏o�͂���d��(���̉�H�ł��[��GND)���v���X�^�}�C�i�X�ɐU��U���ƂȂ�܂�����A�R���p���[�^�̂ق����u���d���̕�����(��E����)���H�v�ʂ��邽�߂̏���^�����ɑ��ăR���p���[�^�����ꂼ�����p�������̂ɂȂ�܂��B �@����̐v�ł́A��d�������}0.23V�͈͈̔ȏ�̐U�������m������o�͂�ON�ɂ��܂��B �@���m������LED1�u�����v���p�b�ƈ�u�_�����܂��B �@��u�_�����鎞�Ԃ́A���邳�̕ω��ʂ�ω����Ԃɂ���đ����قȂ�܂����A����̌��m��H�̖ړI�́u���m������^�C�}�[���J�n����g���K�[�p���X���������v�ł����炱��ŏ\���ł��B �� �g���K�[�o�͉�H �@����]�́u�^�C�}�[IC 555�̃g���K�[���������v�Ƃ������ł��̂ŁA���肵�ĊO���g���K�[���o�͂ł���悤�g�����W�X�^��Ńg���K�[�M�����o����H�ɂ��Ă��܂��B �@�^�C�}�[IC 555�̃g���K�[�[�q(�Q�ԃs��)�ɐڑ�����A�^�C�}�[���J�n�ł��܂��B �� �^�C�}�[��H �@���邳�̕ω������m�����H��LM324�̂S�̃I�y�A���v�̂����R�����g���Ă��܂���B �@�����g��Ȃ��Ȃ�u���g�p(�]��)�v�Ƃ��Č�쓮�h�~���������ďI���ł����A���������I�y�A���v���P��H����̂ł�����A�킴�킴�ʓr�^�C�}�[IC 555���g��Ȃ��Ă�����LM324�����Ń^�C�}�[�܂ō���Ă��܂����̂ŁA����p�ӂ��Ă���LM324��Ń^�C�}�[�����˂Ă��܂��āA�قږړI�̉�H�͑S�����ꂾ���Ŋ���������悤�ɂ��܂��傤�B �@�������A�u���Ƀ^�C�}�[IC 555���g�����u������Ă��Ă���ɐڑ�����Z���T�[�������K�v�Ȃv�Ƃ��uPIC�}�C�R���̓��͗p�Ɏg���v�Ȃǂ̏ꍇ�ɂ͂��̃^�C�}�[��H�͐�ɕK�v�Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂ŁA���Ȃ��Ă������ł��B �@���̏ꍇ�̓I�y�A���v��͖��g�p�����������Ƃ��Ă��������B �@�^�C�}�[�̓��͂̓E�C���h�E�R���p���[�^�̏o�́uSENS�v�M��������炢�܂��B �@�uSENS�v�M���ŃR���f���T���[�d���A���ꂪ���d����܂ł̎��Ԃ��^�C�}�[���ԂƂ��܂��B �@�^�C�}�[���Ԃ�VR2�u���Ԑݒ��v����1�b�`��3��30�b�܂ł̊ԂŐݒ�ł��܂��B �@�^�C�}�[���쒆��LED2�u�^�C�}�[�v���_�����܂��B �@�^�C�}�[�̏o�͂̓p���[MOS-FET 2SJ377�o�R�ŕ��ׂɓd���������ł��܂��B(�ő��1A���x�܂�) �� �d�� �@�Z���T�[��H�Ȃ̂ŁA�Ȃ�ׂ��ϓ��̖������肵���d�����g�p���Ă��������B �@���d�r�S�{�g�p��5�`6V���x�œ��삵�܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@IC��Ǝ��ӂɕ��i�������Ȃ̂ŁA����قǓ���͖����Ǝv���܂��B �@�g�ݗ��Ă���AVR1�u���x�v���ő�(�E�����ς�)�ɁAVR2�u���Ԑݒ��v���������ς�(��P�b)�ɂ��A�ʏ�̕����̖�����̒���Cds�Ɏ���������ĉA�ɂ��Ă݂�LED1�u�����v���p�b�ƈ�u�_�����A������LED2�u�^�C�}�[�v��P�b�ԓ_������Ή�H�̑g�ݗ��Ă͂قڑ��v�ł��B �� LED2���_������̂̓^�C�}�[��H������Ă���ꍇ �@�O���Ƀ^�C�}�[IC 555�Ȃǂ�ڑ����Ă���ꍇ���ALED1�u�����v���p�b�ƈ�u�_�������Ƃ��Ƀg���K�[���������āA�O���̃^�C�}�[�����삷�邱�Ƃ��m�F���܂��B �@Cds���A�ɂ����薾�邭�����肵���u�Ԃɔ������^�C�}�[�͔�������ݒ莞�ԓ��삷�邱�Ƃ��m�F������A���D�݂̊��x�E�^�C�}�[���Ԃɒ��߂��Ă��g�����������B ���@���@���@���@���@�ȉ��]�k�@���@���@���@���@��
�@���������u���邳�ω��Z���T�[�v�͐̂���g���Ă���A������u(���w��)���[�V�����Z���T�[�v�ƌĂ�Ă���悤�ȃZ���T�[���u�̒��g�ł��B �@Cds�Ȃǂ��g�����u�l�����m����Z���T�[�v�ƂĂ��͌��ĂĂ����Č�����Cds�̊Ԃ�l���ʂ��ĎՂ�����u�Â��Ȃ����v�����m����悤�ȁw�Ռ��Z���T�[�x���L���ł����v�������ԂƎv���܂����A����̉�H�̂悤�ȁu�}���Ȗ��邳�̕ω������������v�Ƃ������@������܂��B �@�������A���[�V�����Z���T�[�ł�Cds�Ɍ������璼�ڌ��ĂĂ�����Ղ�̂ł͂Ȃ�(����c����ł����삷��ł��傤����)�ACds�ƃ����Y�Ƃ�g�ݍ��킹���J�����̂悤�ɉ����̏��(����_�̖��邳)��Cds�ɑ������������@�����܂��B �@�ʘH�̏�̂ق����牺�Ɍ����āA�܂�ŊĎ��J�����̂悤�Ȋ����̏����Ȕ��ɏ����ȃ����Y���t���Ă���悤�ȁu���[�V�����Z���T�[�v���x���p�ɂ����Ă���̂��������Ƃ������������������ł��傤�B(�ԊO���Z���T�[�ł͂Ȃ���) �@���z�������E���E��ƕω�������A�ꎞ�I�ɉ_�ɉB���悤�Ȃ������Ƃ������邳�̕ω��ł͔��������A�u�l���ʂ����I�v���炢�̋}���ȕω��̂ݒ��o���邵���݂ŗp���܂��B �@�����A���̕��@���Ɓu���邢�ꏊ�ɁA���̏ꏊ�Ƃ͈Ⴄ���邳�Ɍ����镞�𒅂��l(�܂��͕�)���ʂ��v�Ƃ����������K�v�Ȃ̂ŁA���͂̎��R���ɉe�����ɂ����悤�ԊO�������@�Ƒg�ݍ��킹�ĐԊO���Ŋ��m����悤�ȕ��@�����܂����A���ł͂����ƕʂ��l�̑̉�(�ŕω�������˔M)�����m����u�ԊO���œd�Z���T�[�v�Ȃǂ��ΐl�Z���T�[�Ƃ��Ďg����̂���ʓI�ŁA���w���̃��[�V�����Z���T�[�͎p����������܂��B �@�ق��ɂ��A���^��CCD�J�����Ɛ�p�d�q��H��g�ݍ��킹�ĉf���ŕ��̓��������m����ŐV�̃Z���T�[�Ƃ��B �@����Cds��p�������[�V�����Z���T�[�̂�����Ɩʔ����g�����Ƃ��ẮA�r���Ȃǂɕt�����Ă����Ď��J�����ŐN���҂����m�����Z���T�[���ƂĂ����n�I�ȑ��u�Ƃ��Ă��g��ꂽ���Ƃ�����܂��B �@���Ȃ�(�Ƃ��������Ȃ�̂ł�)�J�������瑗���Ă���u�r�f�I�M���v�̒���d�C�I�ɒ��ׂ�d�q��H�ł���Ă��܂��悤�Ȏ��ł����A��̂ɂ͂���Cds�ɂ�郂�[�V�����Z���T�[������āu�Ď��p�e���r��ʂ́A�Ď��������|�C���g��Cds�������Ɠ\��t����I�v�Ƃ����܂�ŏ�k�̂悤�ȕ��@�ŐN����(�ʉ߂���l�╨)���Ď�����悤�ȑ��u�����݂��܂����B �@�l�╨���ʂ�ƁA�Ď��J�����̉�ʂ̂��̃|�C���g�̖��邳���ς��̂Łu���邳���}�ɕω������I�v�����o����킯�ł��ˁB �@���Ԃ�A�����Ƃ��Ă̓r�f�I�M������ُ�����o����悤�ȑ��u�͂܂����G�ō������������߁A�����ɍ���Cds���̂悤�ȕ��ł��{�C�ŋƖ��p�Ɏg���Ă����悤�ł��B �@�܂��������ɁA����Ȃ�Ď��J�����Ɖf�����j�^�[��ʂ̂ق��͂ǂ��̃��[�J�[�̉��ɂł��|���Ǝ��t���ł���킯�ł����A��ʂ���Cds���|�����Ɨ�������x�������Ă��܂�(��)�Ƃ�����̌��_�����������̂́A�ėp���͍������u�ł��ˁi�O�O�G ���Ԏ� 2012/6/6
|
||
| ���e |
�����̂��������肪�Ƃ��������܂��B ���ɂ́A���o���l�����y�Ȃ�PWM���䂷��Ɩ��̉e����[�V�����Z���T�[�Ƃ��Ă̗��j�̘b��ȂǁA�ƂĂ������[���L���ɂ��Ă������������ƂɊ��ӂ������܂��B ���ɂ����̕ω��ɂ������Ė��o���Ƃ������\���A���ȏ������ł������ł��i�j�B ���̂��߂ɂ͏펞�ʓd��ԂŁA���̕ω��ł�������d����OFF�ɂ��A���̌�ON�ɖ߂���H���l����Ƃ����V�����e�[�}���ł��܂����B �ŏ�����A�u�ω������Ƃ��Ɉ�uOFF�ɂ���ɂ��v�Ƒ��k���Ă���A�������o�Ă��܂��Ă����ł��傤���A���ꂼ��̕��ʂł̓d���ω��̌����܂Ŏ�����Ă��܂�����i�����s������̂������Ɍh���������܂��j�A����͎��͂ʼn����������Ǝv���܂��B ��ʓI�ɂ́A�ω����������Ƃ���ON�ƂȂ�������R�ł��̂ŁA����̐ݒ�͊Ԉ���Ă͂��Ȃ������Ǝv���܂��B ���A�I�y�A���v���g���Ẵ^�C�}�[�����ɂȂ�܂����B �Ƃ肠�����A�I�y�A���v����肵�āA�u���b�h�{�[�h��ŃE�C���h�E�R���p���[�^�[�܂ł̓���̊w�K����n�߂܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B �X�~ �l
|
||
| ���Ԏ� |
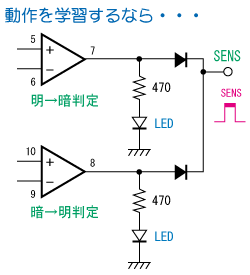 �@�u���b�h�{�[�h�œ�����m�F����Ȃ�A�ω����o���m���߂�LED�́u�����Áv�Ɓu�Á����v�̂Q�ɕ������ق����A��藝�����₷���ł��傤�B
�@�u���b�h�{�[�h�œ�����m�F����Ȃ�A�ω����o���m���߂�LED�́u�����Áv�Ɓu�Á����v�̂Q�ɕ������ق����A��藝�����₷���ł��傤�B�@�u�ω������Ƃ��Ɉ�uOFF�ɂ���ɂ��v�ɕύX����̂̓J���^���ł��ˁB �@������ƃq���g���������ƁA�^�C�}�[��H�̃A���ƃA�����i�j����Ƃ��A�A�����i�j�ɕς���Ƃ��A���@�͂���������܂����A����قǓ���͖����̂ł������Ń`�������W���Ă݂Ă��������B �@��uOFF�ɂ��邾�ƃ^�C�}�[���Ԃ͍ő�R�����v��Ȃ��̂ŁAC4��1��F(�ő��4.5�b)���炢�ł����ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2012/6/9
|
||
| ���e |
�u���b�h�{�[�h��ł̎���i�������܂����B ���[��A�����ȓ���I �����ACds���R�[�h�ʼn������A�e���r��ʂɕt���Ă݂܂����i�j�B ��ʂ̕ω��ɍ��킹�āALED���_�ł���̂͂Ȃ�Ƃ������ł��B ��ՂɈڐA����Ί����ł����A�F�X�Ǝ������Ă݂������߁A���炭���̂܂܂̏�ԂŊy���݂܂��B �u�p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v�v�́A�������肢�������̂ł͂���܂��A���̋L���ɐG������A�������炱�̌��w�����[�V�����Z���T�[�܂Ŕ��W���Ă��܂����B Cds�ALED�A������H�i�����V���b�g��H�j�A555�^�C�}�[IC�A�g�����W�X�^�AFET�ɂ��X�C�b�`���O�A�����đ��@�\�ȃI�y�A���v�̎g�������X�B �����̂��Ƃ��w�K�����Ă��������܂����B ���j�d�q�H��}�j�A�i�̏��S�ҁj�Ƃ��ẮA���e�L��]�鋳�ށi�����������p�i�j�ƂȂ�܂����B ���p��������{�I�e�N�j�b�N���ڂł��̂ŁA��A�̋L�����T�C�g�g�b�v�̂Q���ԃ����v�ɒlj����ăg�b�v�L���ɏ��i�����Ă������̂ł́A�Ǝv�����炢�ł��B ���i���^�c���Ă����������Ƃ�����Ă��܂��B �i�Ƃ���ŁA�Q��ڂ̉̉E���̉摜�g�H���\������Ȃ��̂́H�A�h��H�j �X�~ �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�e�X�g�����܂��������悤�ł��ˁB �@Cds��TV��ʂɓ\��t����e�X�g(���V�сH)�܂ł���āA����̊m�F�Ɖ��p�̊w�K�Ȃǂ܂ł��ꂽ�悤�ŁB�����ɗ��ĂČ��h�ł��B �@�摜���\���ł��Ȃ��̂́E�E�E�A���܂Ƀt�@�C���X�V���̓��������܂��䂩�Ȃ���������A�]�������͂��̃t�@�C�������������肷�邱�Ƃ�����A������ŏ��ɍX�V�������ɂ̓t�@�C�����������̂ł����A���̌�ɑ��̕��ւ̕ԐM���ڂ����肵�����Ɍ����Ȃ��Ȃ���(�t�@�C���������Ȃ���)�悤�ł��B �@������x�A�����I�ɓ]�����Ă����܂����B �@���݂܂���ł����B �@�ق��ɂ��A������ł͉������Ă��Ȃ��̂ɁA�T�[�o��Б��ʼn������Ă���̂ł��傤���A���X�Â��L���̉�H�}�Ȃǂ̉摜���������Ă��邱�Ƃ�����܂��B ���Ԏ� 2012/6/16
|
||
| �@�����L���� ���A����܂��B | |||
| �ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ | |||
|
�C�̖����l �����y�����q�������Ă��������A���傱���傱�Ɛ���������Ă��������Ă���҂ł����A�w�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�x�ɂ��Ă��������Ă�������Ǝv���A�ԊW�͂��x�ݏ�ԁH�����m�œ��e�������܂����B ���̉�H���Ԃɂ��g����Ǝv�����삵�܂����B�g�p���@�́A�X���[���_�����Ɂu�E�C���J�[�̃|�W�V�������@�\�v��ړI�ŁA+12V�d����ACC�d���ɕύX�ʼn��L�̂P���Q���R���Ńe�X�g���܂����B
�T�O�̎�o�� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�͂��E�E�E�A�m���Ƀo�C�N�ŃG���W��ON���͏펞�|�W�V�������Ƃ��āu�����_���v�����������H�ŁA�d������ꂽ��Ԃł̃E�C���J�[���͂����鎖�͍l���ɓ���Ă��܂���B �@��������p�̓d���ȊO�ɕʓrAcc��|�W�V�������d�������̉����X�C�b�`�o�R��ON/OFF�����M���ɘA��������Ȃ�A�A�������H���֎~�����H�Ƃ���������̂����݂�������Ă���͂��ł��B �@����������H�̓d�����̂�ON/OFF����ƁA������ő��肳�ꂽ�Ƃ���d������Ă�C2�ɓd�ׂ��c���Ă���Ԃ�PWM�p�̊���U��H�͓��삵�����܂����AC5�EC7�ɂ��d�ׂ��c���Ă���̂Łu�����_���v�����铭���͑������܂��B �@�������A��H�̓d�������Ă����Ƃ������́A���̎��ɃE�C���J�[�M���������Ă��Ȃ��ق��̃E�C���J�[���ɂ�C2�ɗ��܂��Ă���d�ׂ�FET��ʂ��ċ���������̂ŁA��u��C2�����d���ēd�C�̋������ł��Ȃ��Ȃ�̂Ŕ��Α��̃E�C���J�[���͈�u�����_�����Ă���悤�Ɍ����܂��B �@�E�E�E�Ƃ����ӂ��ɊȒP�ȗ��R�����Ȃ炢���̂ł����A���ɂ��d��Ȗ�肪����܂��B �@��H�̓d���������Ԃł͓��R�d������͂��̉�H�삳������A������Ԃœ_��������E�C���J�[���ւ̓d�C�̋����͖����͂��ł����A�c�O�Ȃ����ʂ̂Ƃ��납��d��������������̂Ŗ{��H�͓��삵�Ă��܂��A�E�C���J�[�̓_�łɂ��킹�Ĕ��Α��̃E�C���J�[�����_��(�A��������)���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B 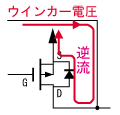 �@���܂łɉ��x�������Ă��܂����A�p���[MOS-FET�̓����ɂ���H�}�ɂ͏����Ă��Ȃ��ی�p�̃_�C�I�[�h�������Ă��܂��B
�@���܂łɉ��x�������Ă��܂����A�p���[MOS-FET�̓����ɂ���H�}�ɂ͏����Ă��Ȃ��ی�p�̃_�C�I�[�h�������Ă��܂��B�@���ꂪ���K��D-S�ԓd���Ƃ͋t�����ɓd���������������ɂ�FET��ی삷�邽�߂��d���𗬂���FET�ɂ�����d�����قږ������悤�ɓ����܂�����A���Ό����̓d���̓_�_�R���ɂȂ�̂��p���[MOS-FET�̏h���ł��B �@�ł�����A����̉�H�ł͓d��OFF���ł��E�C���J�[�����[����E�B���J�[����_�������邽�߂ɋ��������d����FET�̒����t�����ĉ�H���d���d����^���Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�E�E�C���J�[���痈���d���Ŗ{��H�̓d���͓����āA���E�C���J�[���͉E�̃E�C���J�[�_�łƓ�������������Ԃœ_������Ǝv���̂ł����E�E�E�B �@�d�����E�C���J�[�_�łɂ��킹��ON/OFF����̂ŁAC5�EC7��(�ڂ�`���Ɠ_�������铭���̂���)�K��̓d���ɒB���Ȃ��Ĕ��Â������_�����Ă��Ȃ��ċC�Â��Ȃ�������������܂���B (������̏ꍇ�͍��E�͔��]�œ�������) �@�t���ɂ��ẮA�o�C�N�Ȃ̂ŁA�{��H�̓E�C���J�[�E�|�W�V�����_��������ꍇ�͏�ɓd���͓����Ă��邩��A���������t�����Ȃ�������ŕs��͂����Ȃ��Ƃ����v���R����ʂɉ������͖�����H�ł��B 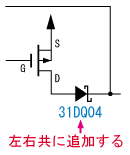 �@����ł͓d������Ă��Ă��E�C���J�[�_�����ɂ̓|�W�V�������������Ƃ��������ł��܂���A�����t�������Ȃ������K�v���o�Ă��܂��B
�@����ł͓d������Ă��Ă��E�C���J�[�_�����ɂ̓|�W�V�������������Ƃ��������ł��܂���A�����t�������Ȃ������K�v���o�Ă��܂��B�@�t������o�H�����Ă��܂������̂ŁAFET�ƃE�C���J�[�����[���痈��d���̊ԂɃ_�C�I�[�h�����ċt�����~�߂܂��B �@��H�̓d���̓o�b�e���[�����ŁA�����_����Acc�܂��̓|�W�V�������p�̓d���Ȃǂ��琧�䂷���H��lj����Ă������ł����A�_�C�I�[�h�ŋt����h�~����ق������i�������Ȃ��ł����A���ɉ�H������Ă���Ȃ�����ӏ������Ȃ��Ċy�ł��傤�B 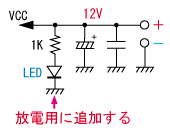 �@��́A�قƂ�ǖ��͂���܂��{��H�̓d����OFF�ɂ�������C2�̓d�ׂ���d���Ă��܂��āA�����ɉ������삵�Ȃ��悤�ɂ���̂ɂӂ���͂��Ă��Ȃ��u�d���p�C���b�g�����v�v�����Ă��������B
�@��́A�قƂ�ǖ��͂���܂��{��H�̓d����OFF�ɂ�������C2�̓d�ׂ���d���Ă��܂��āA�����ɉ������삵�Ȃ��悤�ɂ���̂ɂӂ���͂��Ă��Ȃ��u�d���p�C���b�g�����v�v�����Ă��������B�@���ɎԂ�o�C�N�̕��͓d���\���̃p�C���b�g�����v�����Ă���Ɓu�o�b�e���[���オ��̂ł́H�v�Ƃ����S�z�������̂ŁA�ӂ���͂Ȃ�ׂ��p�C���b�g�����v�͂��Ȃ������ɂ��Ă��܂��B �@�d�������ΐ��b�ʼn������삵�Ȃ��Ȃ�͂��ł��B �@��́E�E�E�Ԃł̓o�C�N�ƈ���ă|�W�V�������̐���F�ɂ��Ă̋K�肪�������ł�����A��@�ɂȂ�Ȃ��悤�����ӂ��Ă����p���������B ���Ԏ� 2012/6/1
|
||
| ���e |
�C�̖��� �l ���Z�������A�f���������肪�Ƃ��������܂��B ���������܂ŗǍD�ȓ���ƂȂ�܂����B �傽�錴����C2�R���f���T�]�X�ł͂Ȃ��A�p���[MOS-FET�����̕ی�_�C�I�[�h�̋t���ɂ��d����������Ă������Ƃł��ˁB �g�����W�X�^�̗l�Ƀo�C�A�X�Ȃ����͋t���Ȃ��Ɠ����悤�Ɏv���Ă��܂����A���̋L���ł�����������Ă�����߂ĕ��������܂����B �Ȃ��A�Ԃւ̎��t�����͊��݃|�W�V�������̎��O�����A��@�ƂȂ�Ȃ��悤�ɏ��u����\��ł��B ���ꂩ����ʔ������Ȃ�L�����y���݂ɂ��Ă���܂��B �T�O�̎�o�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���A�����ύX����܂������B �@����]�ʂ�ɓ����ĂȂɂ��ł��B �@�d�q���i�ɂ͂��낢����N�Z��������̂������̂ŁA�v��ʂƂ���ɗ��Ƃ������������肵�܂��i�O�O�G �@��@�ɂȂ�Ȃ��悤�ɐT�d�ɂ���鎖�������������������肪�Ƃ��������܂��B �@����ł́A���ꂩ������ԂƎ���H������y���݂��������B ���Ԏ� 2012/6/4
|
||
| �ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ | |||
|
�͂��߂܂��āB �����ł����A�d�C��������� �L���`���E���L�b�h��earth�m�[�}�b�g�Ȃǂ̉ƒ�p100v�̐��i���A�Ԃ�12V�Ŏg����l�ɉ����������ł��B �L�����s���O�J�[�̃o�b�e���[�ʼn^�p�������̂ŃC���o�[�^�[�Ȃǂ��g���ƌ�������邭�d�C��H���Ǝv���܂��̂ŁA���Ŏg�p�o����悤�ɂ������̂ł����A�������ȃ��m�ł��傤���H ��낵�����肢���܂��B ���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�w�o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn����x�Ǝ����悤�Ȃ����k�ł��ˁE�E�E�B �@�Ƃɂ��鐔��ނ�AC100V�p�̉������������A���̃q�[�^�[��AC100V�p�̃q�[�^�[�������Ă���̂ŁA��܂�����������ɂ͂��̃q�[�^�[��AC100V�������邵������܂����B �@���ɂ̓X�C�b�`�ƈ��S�̂��߂ɉ��x�q���[�Y�������Ă��邭�炢�ł��B �@�܂�AAC100V���Ȃ��Ɠ����Ȃ����i���������Ă��Ȃ��̂ŁA����������������Ďg���Ȃ�Q�̕��@������܂��B (1) ������H����� �@DC12V����AC100V�ɕϊ����鏸����H������ăq�[�^�[��AC100V��������B �@�Ƃ͂����Ă��A��H�̕��i��傫������l���Ė{�̃P�[�X�̒��ɂ͓���Ȃ��ł��傤����A�O�t���̔��ɓ���邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B �@����H �@DC12V����AC100V����锠�E�E�E�H �@������āA�C���o�[�^�Ƃ������O�̔��ł���ˁB �@�܂�E�E�E���Ȃ��̍����Ă���DC12V��AC100V�̃C���o�[�^�ŕϊ�����AC100V�œ��삳�����Ƃ������̂ɂȂ�A����͏��O�ł���ˁH (2) �q�[�^�[��DC12V�p�ɉ������� �@���̑傫���ł��傤�Ǔ���ւ�����q�[�^�[�Ƃ������͂܂������Ă��Ȃ��Ǝv���܂�����A�������Ńj�N���������������Ă�����܂�����������̂ɍœK�ȉ��x�E�M�ʂ�^������q�[�^�[������Č�����������Ƃ�����ł��B �@�ʂ�����AC100V�p�̏�Ԃłǂ̂��炢�̉��x�ɂȂ�̂��A�q�[�^�[�ʒu�Ɩ�܂��c�̋����łǂ̒��x�̉��M���s���Ă���̂��A�Ȃǂ������Ō������ADC12V���̉��M�������u�����삷��Ƃ����H���ł��B �@�����A���x��M�ʊW�̑������������ŁA�����i����M�����Ȃǂ𑪂�m�邱�Ƃ��ł���̂ł���ADC12V�œ����悤�ȔM�����̃q�[�^�[������Ă݂�̂��ʔ�����������܂���B �@�P��12V�p�q�[�^�[�ɂ��邾���ł�����A�C���o�[�^�ł̃��X�Ȃǂ������{���ɉ��M�Ɏg���G�l���M�[�ȊO�͎g���܂���B �@�ƂĂ����z�I�ł����A����q�[�^�[�̐���ɂ͎��Ԃ����������Ȃ�K�v�ł́H �@�Ƃ����ӂ��ɁA�ǂ���̃P�[�X�ɂ��Ă����Ȃ��ςȂ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����܂��A�����܂ł��ĉ�������܂����H �@�f���ɁA�C���o�[�^��AC100V������Ă����p�ɂȂ邩�A���d�r���̃|�[�^�u���̉����(�����͉�͋ߊ�点�Ȃ������ŎE���Ȃ��c)�̂��g�p�������߂��܂��B ���Ԏ� 2012/5/17
|
||
| �L�^ |
����J�ŕԐM������܂����B�@(�Ȃ�����J�Ȃ̂��킩��܂��E�E�E) |
||
| �ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� | |||
|
�͂��߂܂��āA��Ԃɏ��̂ɃG���W���L�[����ꂽ���̂ł����Â��Č����ɂ����̂ł����݃��[�����C�g�ƘA���łk�d�c�����Ă���̂ł������̂��鎞�͂���Ȃ��ł��A�邾���P�����炢�ŗǂ��̂łk�d�c��_�����H�������ĉ��������肢���܂� �������� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���݂܂��A�F�X�ȈӖ��ɂƂ�邨���t�ŏ�����Ă���̂ŁA�d�l���܂Ƃ܂�܂���B �@�~�����@�\�����肵�Ă��炦�܂��H �@�u�P�����炢�ŗǂ��̂��v�Ƃ����̂́A �� �����܂ňÂ����� (1) ���[�������v���P���ȓ��ɏ��������ꍇ �@�@�@�� (A) ���[�������v�Ƌ��Ɍ����pLED���������� �@�@�@�� (B) �����pLED�͂P�����x�͓_���������� �@�@�@�@�@���̏ꍇ �@�@�@�@�@�@�@(B1) �^�C�}�[�̓��[�������v���_�������u������P�� �@�@�@�@�@�@�@(B2) �^�C�}�[�̓��[�������v�����������u������P�� (2) ���[�������v���P���ȏ�_�����������ꍇ �@�@�@�� (A) �����pLED�͍ŏ��̂P���ŏ������� �@�@�@�� (B) ���[�������v�Ƌ��Ɍ����pLED���_���𑱂��� �@�@�@�@�@���̏ꍇ �@�@�@�@�@�@�@(B1) ���[�������v���������献���pLED�������ɏ������� �@�@�@�@�@�@�@(B2) �����pLED�����[�������v�������Ă���P����ɏ������� �@�Ȃǂ̓��삪�l�����܂����A�ǂ̂悤�Ȃ��̂����]�݂Ȃ̂ł����H �@��{�I�ɂ� (1-A)�{(2-A) �@�ŏ��̂P���ȓ�����A���[�������v�������ԓ_�����Ă��Ă������pLED�͂P���ŏ�����A���[�������v���P���ȓ��ŏ�����Γ����ɏ����� (1-A)�{(2-B1) �@����͂����̘A��(�����g���̒ʂ�) (1-A)�{(2-B2) �@�u���[�������v���P���ȓ��ɏ��������ꍇ�͓����ɏ����v �@�u���[�������v���P���ȏ�A�������ꍇ�̂݁A�����pLED�̓��[�������v�̏�������P�����������v �@�Ƃ������d�s�v�c�ȓ�������� (1-B1)�{(2-A) �@���[�������v���_�������u�Ԃ���A�����pLED�����[�������v�̏����^�C�~���O�ɊW�Ȃ��K���P���_�����ď����� �@�@�� �A�����̏ꍇ�A�����pLED�_�����Ƀ��[�������v����x�������Ă܂��_�������ꍇ�A �@�@�@�@(�b) �����pLED�̃^�C�}�[�͉������ꂸ�A�_���J�n���[��K���P���ŏ����� �@�@�@�@(��) �����pLED�̃^�C�}�[�͉�������A���[�������v�̍ē_������܂��P���Ԃ͓_������ (1-B1)�{(2-B1/B2) �@�������������ɂȂ�̂Ŗ��� (1-B2)�{(2-A) �@�������������ɂȂ�̂Ŗ��� (1-B2)�{(2-B1) �@�u���[�������v���P���ȓ��ɏ���������A�����pLED�͂��̏u�Ԃ���P�������v �@�u���[�������v���P���ȏ�_��������A�����pLED�̓��[�������v�����Ɠ����ɏ�������v �@�Ƃ������d�s�v�c�ȓ�������� (1-B2)�{(2-B2) �@���[�������v�̓_�����ԂɊւ�炸�A���[�������v���������Ă��献���pLED�͂P���ԓ_���������� �@�@�� �A�����̏ꍇ�A�����pLED�_�����Ƀ��[�������v����x�������Ă܂��_���A���̌�ɏ��������ꍇ�A �@�@�@�@(�b) �����pLED�̃^�C�}�[�͉������ꂸ�A�_���J�n���[��K���P���ŏ����� �@�@�@�@(��) �����pLED�̃^�C�}�[�͉�������A���[�������v�̍ď�������܂��P���Ԃ͓_������ �@�Ƃ����p�^�[�����l�����邲�˗����ł��B �@���āA�ǂ̃p�^�[���E�@�\������]�ł����H ���Ԏ� 2012/5/16
|
||
| ���e |
�x���Ȃ��Ă��݂܂���A���[�������v���_���Ɠ����Ɍ����p�k�d�c���_�����܂��A���[�������v�������̏u�Ԃ���P���㌮���p�k�d�c���������܂��A�����������Ă��߂�Ȃ��� naka �l
|
||
| ���Ԏ� |
�� �Â����A���[�������v�_���Ɠ����悤�Ɍ����pLED�͓_�� �� �Â����A���[�������v���������Ă��P���Ԃ͌����pLED�͓_���������� �� ���邢���͌����pLED�͓_�����Ȃ� �@�ł�낵���ł��ˁH �@����ŁA�u���邢���ɂ͓_�����Ȃ��v�ɂ��F�X�����āA����������Ă���Ƃ܂����Ԃ������肻���Ȃ̂ŁA������ŏ���Ɍ��߂����Ă��������܂��B �� �u���[�������v�ƘA���A������^�C�}�[�v�͖��邳�ɊW�Ȃ����� �� �����pLED���_�����邩�ǂ����́A��L�̓_�����Ԓ��Ɂu�Â��v�ꍇ�͓_���A�u���邢�v�Ə��� �� �܂�A�_�����Ԓ��ɖ��邳���ς��Ɠ_����Ԃ��ς�� �@�Ƃ����d�l�ŁB ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�� ���[�������v�M�����̓J�v���[ �@������A���ɂ����炩��͕����܂���ł������A�]���̎Ԃ̂悤�Ƀh�A�X�C�b�`�Ȃǂ��}�C�i�X�R���g���[���Ń��[�������v�̓d���Ɍq�����Ă���悤�ȎԂȂ̂��A�ŋ߂̃R���s���[�^���ꊇ���ă����v�ނ��Ǘ����Ă����v���X�R���g���[���Ń��[�������v�����郊���[�������̃X�C�b�`�ɂȂ��Ă���̂��A�ŋ߂͎Ԃɂ���ĈႢ������̂ŁA�ǂ��炩�����ČŒ�ō����͂����Ȃ�ł������̂Ń��[�������v�ƕ���Ɍq���Γ��͐M���Ƃ݂Ȃ��悤�Ƀt�H�g�J�v��( TLP-521 )�œ��͂��܂��B �� �P���^�C�}�[ �@�t�H�g�J�v���ɓ��͂������C2�ɏ[�d���A�^�C�}�[���N�����܂��B �@���͂����葱�������C2�͖��[�d���ꂽ�܂܂ł�����^�C�}�[�̓X�^�[�g��Ԃ̂܂܁A���͂������Ȃ�VR1��R2��ʂ��ď��X�ɕ��d���ēd�����V���~�b�g�g���K�^�C�v��NAND�Q�[�gIC 4093B���V���~�b�g���͂̉���臒l��艺���ƃ^�C�}�[����܂��B �@�^�C�}�[���Ԃ�VR1��0�`��R���̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@���[�������v�_�����A�Ȃ�тɏ�����Ƀ^�C�}�[�������Ă���Ԃ�LED1�u�^�C�}�[�v���_�����܂��B �@���̃^�C�}�[�͖��邳�ɊW�Ȃ��A���[�������v�̓_����Ԃł̂ݍ쓮���܂��B �� ���邳�Z���T�[ �@���Z���T�[��Cds(�����80K�`200K����10Lx�^�C�v)���g�p���܂��B �@�������閾�邳��VR2�Œ��߂ł��܂��B �@���������u���邢�v�Ǝv���閾�邳�ł�LED2�u�Ô������v�������A�u�Â��v�Ǝv���閾�邳�ł́u�Ô������v���_������ʒu�ɒ��߂��܂��B �� �o�͐���E�o�̓X�C�b�` �@�u�^�C�}�[���Ԓ��v�Ɓu�Â��v�Ƃ��������������������̂����pLED��_�������邽�߁ANAND�Q�[�g�ŏ�����v���A���̏o�͂�FET(2SJ377)�𐧌䂵�ĕ��חp�o��(�x�������v�o��)��ON/OFF���܂��B �@���חp�o��(�x�������v�o��)���v���X�R���g���[���ŁA�ő�d����2�`3A���x(12V/30W���x)�܂ł̕��ׂ𐧌�ł��܂��B�����pLED�����v�ł���ΑS�R�]�T���Ǝv���܂����A�ǂ̂悤��LED�����g���Ăǂ̂��炢�̏���d�������킩��Ȃ��̂ŁALED�p�Ƃ��Ă͂��Ȃ�傫�ȕ��܂Őڑ��ł���悤�Ȏd�l�Ƃ��Ă��܂��B �� �d�� �@�d���͑��u�̐�����A�펞12V�d���������Ă��������B ���Ԏ� 2012/5/26
|
||
| ��p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� | |||
|
���₪���łɏI������Ă���L���ɂ��Ď��₷�邱�Ƃ����������������B http://www.kansai-event.com/kinomayoi/cycle_light/CL.html#SECTION_4 �����ł��Љ��Ă����H������Ă݂����Ǝv���̂ł����A ���i���B�ɋ�J���Ă��܂��B ����2SC4685�Ɏ����Ă͌�������܂���B ��������ƂȂ�g�����W�X�^���Љ�Ă��������Ȃ��ł��傤���B �����Ȃ�Ő\����܂���낵�����肢���܂��B zodo �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���A��������܂��H �@�m���ɐ���������g�����W�X�^�̒��ł͑�������p�r�����ŁA�X���ɒu���Ă���X�����Ȃ��ł����E�E�E���[����搶�Ō�������ƂS�ڂɂ͓d�q���i�̔̔��ł͘V�܂̓X�̃l�b�g�V���b�v�Œʔ̂���Ă��鏊���o�Ă��܂����ǁE�E�E�B���������Ă��X�ɖ₢���킹��Ɓu�i��v�ł����H �@�u���^��hfe(������)�������v(���ʂȂ�_�[�����g���g�����W�X�^���K�v�ɂȂ�Vbe�������Ȃ��Ă��܂��Ƃ��낪����͂����ł͖���)�Ƃ����̂�2SC4685�̗ǂ��Ƃ���ŁA���\�D���Ŏg���Ă���̂ł����E�E�E�B �@�ŁA�S�R����p�r�ł͖����u�g�����W�X�^�Q�̒�d����H�v�ł���A�ʂ�2SC4685�ł���K�v�������A���̂ւ�ł�����ł������Ă����p���[�g�����W�X�^�ő�p�������܂��B���A��������H�v(��R�l)�̂ق����ς���Ă��܂��܂����ǁB �@�w�j�b�P�����f�[�d�r �P�Z�����d��̐����x�̃y�[�W�ɂ�����10��ނقǑ�p�ł���g�����W�X�^�̈ꗗ���ڂ��Ă��܂�����A���̒��̂ǂ�ł����܂��܂���B �@�A���A���̃g�����W�X�^�ł�hfe���Ⴂ�̂ŁA���]�ԗp�y�[�W��2SC4685���g�p������H�}���x�[�X��R(�}�ł�10K��)�����������āA��葽���x�[�X�d���𗬂��Ă��Ȃ��Ə\���ȃR���N�^�d������ꂸ�ɁA���ʓI�ɒ�d����H�ɂ͂Ȃ炸��LED�͈Â�������A���邳���ς�����肷��ł��傤�B �@���������ꗗ�\�̂ق��̃g�����W�X�^���g���Ȃ�A�x�[�X��R��1K���`3K�����x�̊ԂŒ��߂��Ă��������B �@�܂��A1K���ł�2SC1815���p���[�g�����W�X�^�����͂��Ȃ��Ǝv���܂�����A���߂�v�Z���ʓ|�ȕ���1K���ł����\�ł��B ���Ԏ� 2012/5/15
|
||
| �Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� | |||
|
�͂��߂܂��āB �d���̂Ȃ��Ƃ���ŗe�ʂ̑傫�ȑ�^�����ԗp��12V�o�b�e���[��d���Ƃ��Ė��ÁA�l���Z���T�[���g���ďƖ����R���g���[���������Ǝv���AAC100V��150W�n���Q���Z���T�[���C�g�̃n���Q�����C�g����DC12V�����͂����Ɠ_������LED�ɕύX���č쓮���������A�l�b�g��ŐF�X�ƒT���Ă�����ʼnߋ��Ɍf�ڂ��ꂽ�uAC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI �v�Ƃ����L���ɂ��ǂ蒅���܂����B ������̃y�[�W�ł͂��̕ύX���e�ƕK�v���A�ύX�̕K�v���Ȃ����̂̐������ڂ����������Ă��������Ă���A�Q�l�ɂȂ�ƂƂ��ɗǂ����ɂȂ�܂����B ��H���S���������͖̂����̂ł����Z���T�[���C�g�𐔎�ޓ��肵�A�d�����̉�H�̓e�X�^�[�ŗ�����m�F�����肵�đ�̗̂��ꂪ�킩��܂����̂ʼn�H�̕ύX�����݂܂����B ��������������H��12V�ɐڑ�����Ɛڑ�����̓����[������12V���o��̂ł�����莞�Ԍo�ߌ�i�����ݒ肳��Ă��鎞�ԁj�����[���J���Ă���̓Z���T�[���Ɏ�ĂĔ��������Ă������[����u���ĊJ���A�܂���u���ĊJ���Ƃ������삪���X�����Ă��܂��܂��B ���[�J�[������Ă��d�����̍\���͓����悤��DC24V�ɕύX���Ă���Z���T�[���ɂ͂���Ɍ������ċ�������Ă���̂ł����Z���T�[���Ɋւ��Ă͐F�X���͈�����̂ł������ʂ͓����ł����B �d�C�̂��ƂɊւ��Ă͊w�Z�ŏK�����ʂʼn�H�}�͒��ׂȂ��牽�Ƃ��ǂ߂���x�ł����������Ƃ͉����������Ē��ׂȂ��Əo���Ȃ��Ǝv���܂��B�i���G�ȃZ���T�[���͐����ȂƂ���H�������ς��ŁA�g�����W�X�^�ŃR���g���[�����Ă���ʂ����E�E�E�j ����ȏ��̎{���悤���Ȃ��A���Z�����Ƃ��닰�k�Ȃ̂ł���������������������Ǝv�����e�����Ă��������܂����B ����Ɋւ��܂��Ċ�Ղ̎ʐ^���𑗂点�Ă������������̂ł������ɂ��K�v�Ȏ�������܂�����w�����Ă��������܂��ł��傤���B ��낵�����肢���܂��B �邬 �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�s�̂�(��r�I����)�Z���T�[���C�g���ƁA�ǂ�����g�͎����悤�Ȋ������Ǝv���܂��B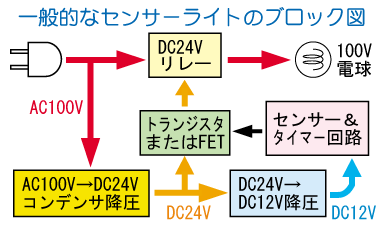 �@�d����H�́u��R�{�c�F�i�[�_�C�I�[�h�v�̕����̏ꍇ������A�u�O�[�q���M�����[�^�v�Ȃǂ������Ă���ꍇ������܂��B �@�����ŁuAC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI �v�����{�I�ɈႤ�̂́A�Z���T�[�E�^�C�}�[��H�̓d���d���͑����̏ꍇ12V(���܂�5V�`6V���x�̏ꍇ��)�ł���APT50D�^�C�}�[�̂悤���t���\���^�C�}�[�p����������1.5V���x�̒�d���ł͖����Ƃ����_�ł��B �@���̈Ⴂ�͔F������Ă��܂����H �@PT50D�^�C�}�[��12V�������ł͈ꎟ�d����DC24V�������̂܂�DC12V�ƍ����ւ��āA�����[��DC12V�i�Ɋ��������œ����܂������A�Z���T�[���C�g�̏ꍇ�͂��Ԃ�ł͐���ɓ����܂����B �@�����āE�E�E�d����H�̏o�͂�DC12V�Ȃ̂ɁA���̓d����H��DC12V����ꂽ���d���s�����Z���T�[�E�^�C�}�[��H�ɂ͐���ɓd�����^�����Ȃ�����A����ȓ���͖]�߂܂����ˁH �@�����Z���T�[�E�^�C�}�[��H�̓d����5V�`6V�̉�H�Ȃ�A�P��DC24V�n�̕�����DC12V�n�Ɍ������Ă��܂��Ă��ADC5V�n�̍~���d����H�̓d���d���Ƃ��Ă͏\���Ȃ̂ł����Ɠ����Ǝv���܂��B �@�ł�PT50D�^�C�}�[�Ɠ������������Ă��܂������Ȃ��̂ł���A�Z���T�[�E�^�C�}�[�n��DC12V�n�œ�����H�ŁA���̓d���̑O�Ƀo�b�e���[��DC12V�����悤�Ƃ͂��Ă��܂��H �@�����A��H�E�\�����悭���ׂĊ��ɓd���̐��DC12V�����āA����œ��삪���������Ȃ��Ă���̂ł����炱�߂�Ȃ����B �@�Z���T�[�E�^�C�}�[��H��DC12V�œ��삵�Ă���̂ł���A�d�����������Ă��̂܂�DC12V�n�̉�H�Ƀo�b�e���[��DC12V���������Ă��ΐ���ɓ����E�E�E�Ƃ�������������܂��̘b�ł���ˁH �@���̂��߂ɂ́A�d����H������̕��i�E�z�����悭���ׂāA�����O����(�ǂ�����)�����̂��A�ǂ���DC12V���������Ă������̂��E�E�E�ׂĉ������Ă��������B �@�������E�E�E�A�d���̋����ɖ�肪�����̂ɂ��܂����삵�Ȃ��ꍇ�A�Z���T�[��H���^�C�}�[��H(���Ԃ�^�C�}�[��H)�̂ǂ����ɕs�s��������܂��B 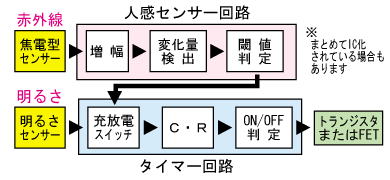 �@�悭�����H�ł�LM324�̂悤�ȃI�y�A���v�łقƂ�ǂ̉�H������Ă��܂��B �@�ŋ߂ł͐�p��IC�ɕς���Ă�����̂�����܂��B(��pIC���Ɠd���͐���ł���̕s�ǁE�E�E�Ƃ������͖����Ǝv���܂�����) �@�u�l���Z���T�[��H�v�́A�u�œd�^�E�ԊO���Z���T�[�v�ƌĂ���l�����˂��Ă���ԊO���ɔ�������Z���T�[���g���A���̔���ȏo�͓d�������āu��Ԃ��ω��������H�v�ׂ܂��B �@�ԊO���Z���T�[�͑��z���ȂǂɊ܂܂��ԊO��(�l�̂����˂��Ă���̂Ɠ����g���̕���)�ɂ��킸���ɔ������Ă��܂��܂��̂ŁA���E���̖��邳�̕ω��ȂǂŌ�쓮���Ȃ��悤�A�u�l���O�ɗ����I�v�u�������I�v�u�o�Ă������I�v�Ȃǂ̂�����x�}���ȕω��݂̂𒊏o���Ĕ�������悤�A�ω��ʂ�������̗�(臒l)�����ꍇ�ɂ̂݁u�ω������I�v�Əo�͂��o���悤�ɂ��Ă��܂��B �@������A�l���Z���T�[�̑O���ƂĂ��ƂĂ��������ƈړ�������A�Z���T�[�͔������܂���i�O�O�G �@�Z���T�[��H����������ƁA�^�C�}�[��H�Ƀg���K�[��������A���ʂ͂b�E�q��H�ō��^�C�}�[��H���[�d(�܂��͕��d)���ă^�C�}�[���N�����܂��B �@�����Ă��̃Z���T�[���C�g�ł́u���邢�Ƃ��ɂ͓��삵�Ȃ��v�悤�Ɂu���邳�Z���T�[�v(Cds�Ȃ�)���g�ݍ��܂�Ă��āA���邢���ɂ̓^�C�}�[���N�����Ȃ��悤�ɐڑ�������Ă��܂��B �@�u�����[�����삷�鎞�Ԃ����������v�ꍇ�͂��̃^�C�}�[��H�̂b�E�q�̏[�d�܂��͕��d�����������̂ŁA���̂�������悭���ׂĂ��������B �@��H�}�������āA�������̏ꍇ�̐���ȏ�Ԃł̓d���͂ǂ��Ȃ��Ă���̂���A�l�����m������ǂ̂悤�ȓd���ɕω�����̂��A���ꂪ���ԂƂƂ��ɂǂ��Ȃ�̂��E�E�E�B �@������ɓ����悤�ɓd���̏�ԂׁA�����������̂ł�����ꂪ�u�[�d(�܂��͕��d)������X�C�b�`���O��H�ɕs�������̂��H�v�u�X�C�b�`���O�ł͖������̌�Ɏ��Ԃ������ĕ��d(�܂��͏[�d)�����H�E�o�H�ɖ�肪����̂��H�v�u���������[�d(�܂��͕��d)�X�C�b�`���O��H�̓d���͐������d�����������Ă��āA�����̓d�����̓R���f���T�̏[�d�ɏ\���ȓd����Z���Ԃɋ����ł��Ă���̂��H�v�ȂǂȂǁE�E�E�E�A���ׂ�Ƃ���͂�����ł�����܂����A��H�}�������Ăǂ̂悤�ȓ���̉�H���ׂȂ��猴����ǂ��Ă䂯�A�ǂ��Ɍ���������̂��ǂ��l�߂Ă䂯��ł��傤�B ���Ԏ� 2012/5/9
|
||
| ���e 5/11 |
���Z�������A�����Œ��J�ɂ��Ԏ������������肪�Ƃ��������܂��B �����������̕����悭���ׂĔ�r���Ă��̌��ʂƐi�����܂������Ă��������܂��B �邬 �l
|
||
| �ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� | |||
|
����ɂ��́B ������������Q�l�ɕ����Ă�҂ł��B �����Ē��������̂ł����AIC��4584N���l�b�g�ŒT���Ă���̂ł���������܂������ɂȂ镨�������Ă��������X�������肢�������܂��B ���Ȃ݂ɂ�����̕�����낤�Ǝv���܂��B http://minkara.carview.co.jp/****(�폜) �ЂƂ� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�܂��ŏ��ɁA�ЂƂ�l�͂����ւJ�ȕ��͂ŗ�V���킫�܂������ł���A��H�����삷��ӗ~��������Łu�C�̖����v�I�ɂ͑劽�}�ł��B �@�������Ȃ�����������Ă�����ƂĂ��h煂Ȃ��̂ɂȂ�A�ǂݕԂ��ƂƂĂ����J�ł�����̂ł͖����Ȃ�܂����B �� ���̐l�̉�H�}�̕\�L�͊ԈႢ���炯 �� �ǂ����Ԉ���Ă���̂� �� �Ȃ��Ԉ���Ă���̂� �� �����炻���̎���R�����g���������ĕԎ��������Ă��Ȃ� �� �������Ȃ��悤�Ȓm���ʼn�H�}���ڂ��Ă�Ƃ˂��E�E�E �� ���i�̌^�ԂȂǂ̕t������Ӗ��A��H�}���������́u��@�v�Ȃm��Ȃ��ł���Ă�悤�ɂ��������Ȃ� �� ����ɂ��Ă̏ڂ������� �� �p�\�R���̉�H�}�G�f�B�^��p�^�[���G�f�B�^���g���ĉ�H�}���̕��i�z�u���ڂ��Ă��邪�A��{���u�m���̃R�s�y�v�������Ă��Ȃ��̂ŁA�����M���Ă������Ă��Ȃ���` �@�݂����ȓ��e�ŁA�ƂĂ����������̂ł��B �� �݂�J���͎ԊW�̐��u���O�����A�l���u�u���O�v�Ƃ��ď����Ă��邾��������A�d�q��H�̒m�����������\���Ă��Ă��ʂɂ����ꏊ �� ��������A������݂�J���̒��̂����ł���ĂĂ������� �� �u�C�̖����v�Ɏ����ė��Ȃ��ł�������
�@�Ƃ������e�ł������A���͂����܂����̓I���h煂������̂ŁA����͑S���폜���Ĉꗗ�������������܂����B �@�{���Ƃ��ẮA�ȉ��́u��l�̑Ή��v�ɏ��������Čf�ڂ��Ă����܂��B �y��l�̑Ή��z �@4584N�Ƃ���IC�͑��݂��܂���B (����A�ꉞ�͎��݂͂���̂ł����A�ƂĂ�����ł�) �@��H�}���������AC-MOS IC��4500�ԃV���[�Y��4584B���Ǝv���܂��B �@4584B�Ȃ�ƂĂ��|�s�����[��IC�Ȃ̂ŁA�����Ă��̓d�q���i�X�ōw���ł��܂��B[���Ƃ�����(���63�~)] �@4584B�́u�݊��i�v�Ƃ��Ďg������̂�40106B������܂��B�������߂��̃V���b�v��4584B������ł��Ȃ����40106B�ł������ł��B �@���̐l�̉�H�}�ɂ͑��ɂ��ԈႢ������܂����A����R�����g��������Ă��܂����������ĕԎ��������Ă��Ȃ̂́A����قǓd�q��H�̒m���̖������Ȃ̂ł��傤�B �@�ߋ��ɂ��݂�J���Ō�����H�}�͊ԈႢ���������̂����Ȃ�̊m���ł�������A�݂�J���ň�ʂ̕��������čڂ��Ă����H�}�͂�قǐT�d�Ɍ��Ȃ��Ǝ��s���܂���B ���Ԏ� 2012/5/5
|
||
| ���e |
�����X���炵�܂��B �ЂƂ�l�A ���������Q&A�T�C�g�ɂ��Ȃ���Ă���悤�ł����E�E�E Q&A�T�C�g�̉��u���Ȃ�v������(��������)�ł����璍�ӂ����ق��������ł��ˁB �Ƃ����̂����̉�H�A�P�Ȃ�NOT(�C���o�[�^)����Ȃ��A�u�V���~�b�g�v�^�C�v�̃C���o�[�^����Ȃ��Ɠ����Ȃ��͂��Ȃ̂ŁA�u�V���~�b�g����Ȃ��v7404�Ȃ���(�萔�ς����Ƃ��Ă�)�ǂ�����ς��Ă������܂���B jr7cwk �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@5/5�ɉ������Ĉȍ~�A����10�����o���܂������������������Ƃ��������ƁA���������͌��Ă��Ȃ��̂ł��傤�B �@���t������ƁA������̂ق��Ɏ�����������̂͂����̉����Ă���̂悤�ł����B �@������̉ɂ͕s�����������A�������邱�Ƃ�I��Ă���悤�ł��B ���Ԏ� 2012/5/16
|
||
| ���e 6/1 |
����f���ł͈��]������ėlj}�[�N��t���Ă���悤���� �����ł͓����i�����[�����H�j��������Ă�����Ă����u�ł������Iwww �}�W���������ȓz������A���������̓z�ɂ͉��Ă��Ȃ��Ă�����Ȃ��ł����H �����ƁI ���������[������Iw ����ȓ��e�͖������܂����H�Ǘ��l�T�� ������ƒʂ�܂��� �l
|
||
| �G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H | |||
|
�͂��߂܂��āA���x���q�������Ă��������Ă���܂��B �@�B�n�G���W�j�A�ł����d�q�H��ɂ��Ă͂ƂĂ����Ȏ҂ł��B ����؉H�l�܂����A�ǂ����Ă���肽����H�����蓊�e�����Ă��������܂��B ���݁A�^�C�ɍݏZ���Ă���܂��B ���̂��߂ɁA�G�A�R����C�ӂ̉��x�Ŏ����I���I�t���鑕�u���쐬�������̂ł��B �A�p�[�g����Đ������Ă���̂ł����G�A�R���̉��x���ߋ@�\���悭�Ȃ��AON�ɂ���Ɗ�������̂ŁA�M�і�̒��A�P���Ԃ����ɋN���ă����R���𑀍삵�Ȃ�������܂���B �Ȃ������n���ł����g�̓I�Ɍ������悤�ŁA���u�����������m�ۂ������Ǝv���܂����B �܂��͎s�̕i�łȂ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����ƍl���܂������������������i���ł����A�������m���̖R�������ɂ͍l�Ă��邱�Ƃ��ł����r���ɕ��Ă���܂��B ���Ђ����͂��������܂��ƍK���ł��B ���|�C���g��
omori �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���x���m�₻��Ɩ{�̓d����Ή����������������m���ĕK�v�ɉ����ă����R���́u�d���v�{�^�����O�����牟�����悤�ɂ����H�͓��ɖ��Ȃ�����̂ł����A����������Ɠ������ɂ́u�{�̂̓d���������Ă��邩�H�v����H���Ō��o�ł���K�v������܂��B >�{�̓d�������ƕ��A����OFF��� �@�Ƃ�������]���A�u�{�̂̓d���������Ă��邩�H(��Ă��邩�H)�v����H���Œm��Ȃ��Ǝ����ł��܂����ˁH (�����āA�ꂽ���Ƃ�m��Ȃ��Ɓu���A���Ɂv�Ȃ�Ăǂ����肵�ėǂ��̂��E�E�E) �@�����m����@�͂�����Ŏ����\�Ȃ̂ł��傤���H (1) �G�A�R���{�̂�LED�\�������v������d��������Č��m �@�G�A�R����LED�\�������������āA�u�d���v�\�������d��ON����m���悤�Ȕz���E��H�͂Ȃ��邱�Ƃ͂ł��܂����H (2) �G�A�R���{�̂̓d���R�[�h�Ɂu�d�����m��H�v���Ȃ��Ō��m �@�uAC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF�v�܂��́u�ȈՃf�W�^���\������d�͌v�v�݂����ȓd���Z���T�[��H������āA�G�A�R���̓d���R�[�h�ɓd��������Ă��邩�ŃG�A�R����ON��OFF����m��E�E�E�Ƃ��������Ȃ�ʓ|�ȑ��u������ĂȂ��܂����H (3) �����R�����t�����ȂǂŁA�ǂ�����ON(�t����ON���̕\�����o��)���ƒm��M�����o�Ă��邩����H �@�����������Ƃ͎v���܂����A�����R���̂ق��ɉ���ON����m��M���͏o�Ă��܂����H �@�ȏ��(1)�`(3)�̕��@�A�܂��͂�����ʼn����v�������ʂ̕��@�Łu�G�A�R���̓d����ON�ł���^OFF�ł���v��m����@���g����A������x�͐�ɐi�߂܂��B �@�����������ł܂��P��肪�I >�{�̓d�������ƕ��A����OFF��� �@���Ď��́A�u�l�Ԃ̑���œd��������̂��H�v�u�������x���߂ł��̉�H���d��������̂��H�v�Ƃ������ʂ͂ǂ��ł���̂ł��傤�H �@�G�A�R���̓d���\����d���R�[�h����d����ON/OFF��Ԃ�m�ꂽ�Ƃ��āA�u�l�Ԃ��{�^���������ēd��������^���ꂽ�v�����ʂ���悤�ȍ��x�ȉ�H�����Ȃ��ƁA�u�{�̓d�������ƕ��A����OFF����v�Ƃ����̂����ʂ��邱�Ƃ��ł��܂���B �@�����݂Ƃ��ẮA���x�����m���Ă��̉�H��ON/OFF������Ԃ���A���̉�H���������Ă��Ȃ��̂��G�A�R���̓d�����������^�ꂽ�H�Ƃ������肷��悤�ȉ�H��v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł���ˁB �@���Ă��Ăǂ��������̂��H �@�����������G�ȏ�������R���M���������Ȃ�PIC�}�C�R�����Ńv���O������g��ō��̂��ł��X�}�[�g�Ȃ̂ł����E�E�E�B �@����͂����͂����܂����˂��B >�{�̓d�������ƕ��A����OFF��� �@�Ƃ�������]�������邽�߂ɁA�P�����������������Ă��܂��̂�e�F����������A��H����@�͂��Ȃ�ȒP�ɂȂ�܂��B �@����́E�E�E�w�G�A�R���{�̂̓d�����(�{���ɓd���������ēd��������Ă��邩)�����m���Ȃ��Ă������x�Ƃ��������ōs���Ƃ������@�ł��B �@�܂�A�����܂������R�����g���̂�����A�����R���̌������G�A�R���̂ق��������Ă��Ȃ��āA�ԊO���M�����͂����Ɏ����̈ӎv�̑��삪�G�A�R���ɓ`����Ă��Ȃ��Ă��A�G�A�R���͂�����̈ӎv�ʂ�ɓ����Ă����Ƃ݂Ȃ��Ă��܂��Ƃ������ł��B �@�������������O��Ń����R������������Ȃ�A�u�d���v�{�^���������R���{�̂̂��̂͑��삹�����A���x���m��H�����uON/OFF�v�Ƃ����{�^����t���Ă���𑀍삷��A�u�G�A�R�����g���Ă���^���Ȃ��v�u����ON�ɂ������ɂ͎����@�\��OFF(�{�̓d�������ƕ��A����OFF���)�v�Ƃ������͉\�ɂȂ�܂��B �@���x���m��H���́uON/OFF�v�X�C�b�`�ŃG�A�R���̓d��������Ƃ܂��͎������[�hOFF�œd��������A�u��������J�n�v�{�^���������������Ή��x�ɂ���Ď����I�ɃG�A�R����ON/OFF���܂��B����͉��x���m��H���́uON/OFF�v�X�C�b�`�œd����邩�A�u��������I���v�{�^���Ŏ����@�\���܂ő����܂��B �@�u��������J�n�v�u��������I���v�{�^������ōς܂��āu��������ON/OFF�v�{�^���ł������ł����A�d������Ă���Ƃ݂Ȃ�����Ԃ���͉��x���m��H���́uON/OFF�v�X�C�b�`�ȊO�ɂ��u��������J�n�v�܂��́u��������ON/OFF�v�{�^�������������ł��ŏ����玩�����[�h�ŃG�A�R�����N�������悤�ȋ@�\���g�ݍ��߂܂��ˁB �@�ȏ�̂悤�Ȑ���@�\�́A�F�X�ƃf�W�^�����W�b�NIC���Ă�����āA��H�����\���G�ɂȂ�܂����E�E�E�B �@���������l�����Ă��邲��]�ɂȂ�ׂ��߂��Ȃ�悤�ɍl����ƁA��L�̂悤�Ȑv���j�̂����̂ǂꂩ�ɂȂ�܂��B �@�����āE�E�E >�{�̓d�������ƕ��A����OFF��� �Ƃ����l�������������������āA�w�����܂ŃG�A�R���̓d���͓����Ă���Ɖ��肵���A���x�ɂ���ăG�A�R���̓���(����͓d���ł͖���)�𐧌䂷���H�x�Ƃ����A�����݂͊ȒP�ʼn�H���P���A�������{�̓d�������ƕ��A����OFF����Ȃ�ċ@�\�͖����ŁA���̉�H�̓d���X�C�b�`����Ă��Ȃ��ƁA�G�A�R���̓d������Ă��Ă���ɉ��x���m���ăG�A�R����/�x�~�����悤�Ɠ����̂ŁA�����R���̓d�r�̌��肪�����Ȃ��Ă��܂��܂��B �@�d�r�̌�����́A�ŏ��ɏ������G�A�R���̓d���������Ă���̂����m�����H�������ł���̂ł���A����ƘA�������Ă��̉��x���m��H��ON/OFF�����Ă����������ł����A���̍l�����̍ŏ��ɐ�̂Ă��{�̓d�������ƕ��A����OFF����Ƃ����̂��\�ɂȂ�܂��ˁB �@���̎蔲�����@�ł́A�G�A�R���{�̑��̓���(�^�]�^�x�~[����͓d���͓����Ă��邪��p���Ă��Ȃ�])��ԂɊW�Ȃ��A�w�����R������ݒ艷�x����������A���Ⴍ���ăG�A�R����ON/OFF���[���I�ɑ��삷��x�Ƃ����S���o�J������������锭�z�ł��B �@�悭���郊���R���́u�d���v�{�^���ł���A��~���Ɉ����ON�A���쒆�Ɉ����OFF�ɂȂ��g�O�������Ȃ̂ŁA�P���Ƀ����R�����ł��G�A�R���{�̂��{���ɓd���������Ă���̂��H�^�����Ă��Ȃ��̂��H��m��p�͂���܂����B �@��������ɂ��A���ꂪ�S������������ɂȂ�_�ł��B �@�����R���̕\�����d��ON�ł����������삵�Ă���悤�ɂȂ��Ă��Ă��A���͐ԊO�����͂��ĂȂ��ăG�A�R�������삵�Ă��Ȃ��Ƃ������Ԃ�����킯�ŁE�E�E�B �@�����������鎖��A���x�Ő��䂷�鎞�ɃG�A�R���������܂��d���𑀍삷��@�\�œ���������~�߂��肷���ɂ́A�{�̂̉^�]��Ԃ������ƒm��K�v���o�Ă���̂͊��ɏ������ʂ�ł��B �@�ł́A�����܂Łu�d���v�{�^���ɂ͉����G�炸(���삹��)�A����ł��ăG�A�R����C�ӂɓ���^�x�~������ɂ͉���������������ƍl����ƁA�u�G�A�R���̉��x�ݒ�ɂ��^�]���邩���Ȃ����̒��ߋ@�\���A�ɒ[�ɍ������x��Ⴂ���x�ɕς��Ă����A�G�A�R���͗�p������x�~�����肷�邶��Ȃ����I�v�Ƃ����A�܂���q���������R���ŗV��ł���悤�ȑ���(���x���߃{�^����K�v�A�ł�����/��)��d�q��H�ł���Ă��Ɗ�]�ɋ߂����̂���������̂ł́H�Ƃ������Ȃ�ς�������z�ł��B �@�����A����ɂ����͂����āE�E�E���̉�H�ŃG�A�R�����^�]�^�x�~��������ɂ́A�����R���̉��x�ݒ肪�ނ��Ⴍ����(�����������)�ɂȂ��Ă���Ƃ����_�ł��ˁB �@�����{���ɂ�₱�������Ƃ͉����l�����ɁE�E�w�w�艷�x�������A�w�艷�x��艺��������A�����R���̓d���{�^������莞�ԉ�����H(TC622EPA��555�����Ő���)�x�Ȃ�Ă����蔲�����ł��܂��B �@��������̓G�A�R���{�̂̓���ɂ͊W�Ȃ����삵�܂�����A���̉�H�p�̓d���X�C�b�`���v��܂����A���̉�H��ON/OFF����Ȃ炱�̉�H�삳����O�ɃG�A�R���͊��ɂ��̉�H�Ŕ��ʂ��Ă��铮���ԂɂȂ��Ă���K�v������܂��B �@�������Ɏ蔲�������āA���܂���p�I�ł͖����ł���ˁB �@�������l��������Ă݂܂������A�ǂꂪ�����ł����H �@�������A��̂ق��̓d����Ԃ�Ȃɂ������m���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȕ��@���ƁA�ǂꂪ�g����̂������Ƃ��Ă��������������B �@����͑Ή��͈͊O�ł����A�G�A�R���̃����R���ł́uON/OFF�v(�{�^�����������H)�Ƃ����g�O���M���ł͂Ȃ��A�����Ă̓����R�����ɉt�������Ă��āA������ON�\���ɂȂ�Ɩ{�̂ɂ��u�^�]��ʏ��E���x�ݒ���E�^�C�}�[���v�Ȃǂ𑗐M���A�t����OFF�ɂȂ�悤�ɑ��삷��ƃ����R���́u�d��OFF�v�M���𑗐M����悤�Ȃ��̂������ł��B �@�G�A�R���{�̑��͓d��OFF�̏�ԂŁu�^�]��ʏ��E���x�ݒ���E�^�C�}�[���v����M����Ƃ��̐ݒ�œ�����J�n���܂����A�d��ON���Ɂu�^�]��ʏ��E���x�ݒ���E�^�C�}�[���v����M����Ɖ����ݒ肪�ς�����H�Ƃ��ē���ύX���邩�ǂ����̔�������܂��B�܂��d��ON���Ɂu�d��OFF�v�M������M����Ƃ������d������܂��B�d��ON���Ɂu�d��OFF�v�M������M���Ă��E�E�E�������܂���B �@�Ȃ̂ŁAPIC�}�C�R�������g���ăG�A�R���̃����R���M�����̂��쐬���ĐԊO�����M�����H�ƃv���O����������Ă��܂��A���샊���R�����ŔC�ӂ̉��x�����o���ė�p�^�x�~(�����H)���ւ�����A���샊���R���̓d����ON�ɂ��������ł͎���I�[�g�͋@�\OFF�ɂ��Đݒ艷�x�̔���̓G�A�R���{�̂̂��Ƃ��炠��@�\�ɔC���Ă��܂��Ƃ��A���Ȃ育��]�ʂ�̂��̂��ł���̂ł����E�E�E�B(�ǂ��̃��[�J�[�̃����R���R�[�h�Ȃ̂��͂����ƒ��ׂē��e��m���Ă����K�v�͂���܂�) �@�܂��A�����܂ŗ]�k�Ƃ������ƂɂȂ�܂���ˁB �@TC622EPA�͎����Ă��܂���ł������A����̉��x�W�̉�H����ɂ����p�ł������Ȃ̂��H���d�q�ɒʔ̂Œ������܂����B ���Ԏ� 2012/5/4
|
||
| ���e |
�A�t���J�Ő������Ă��鎞�ɉ��x���߉�H�̉�ꂽ�①�ɂ̏C���𗊂܂ꂽ��������܂��B�����������ŁA�����S�L�����ꂽ���ɏo���������ł������낢��l�������A�P���Ƀ^�C�}�[��ON,OFF���J��Ԃ���H�����A�d���ɑ}�����郂�m�����F�l�̏��ɑ���܂����B���p��͖��Ȃ��A�Q�N�ԃ^�C�}�[�ݒ�̕ύX�ŏ������悤�ł��B �i�F�l���Q���ԂɈ��R���Z���g�̔������������Ă����悤�ł��j �C�̖������܂́u�p���[��H�G��Ȃ��v�Ƃ�����|�ɔ����A���̓��e�T�C�g�̕i�ʂ𗎂Ƃ������ꒃ��H�ł����A�d�l���m�肵�Ȃ��ȏケ�̂悤�ȍr�Z���K�v���ƁB ��H���g�͌��n�ŃI�[���f�C�^�C�}�[����ɓ���Ȃ炻����R���v���b�T�[�Ɋ��܂��A���x�ݒ�͍Œ�ɂ��킹�邾���ŊȒP�ɂł��܂��ˁB�B�B�����Ƀ^�C�}�[���������߂Ύ茳�Őݒ���ύX�ł��܂����A�����^�]���ł��܂��B �ň����n�̓d�C���ł�����Ǝv���܂��B�i�A�t���J�ł͂��ꂷ�����������̂Łj arii �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����A�����������@���A�����Ǝv���܂��B �@�����A�u�d�����̂�ON/OFF����v�Ƃ��u�R���v���b�T�[��ON/OFF����Ƃ������ȍr�Î�(��)�v�͑I��������O���Ă��܂��B �@���e�҂̕����@�B�n�G���W�j�A���Ƃ������ŁA�������������Ȃ猾���Ώo����Ƃ͎v���܂������Aarii�l�̂��w�E�̂悤�Ɂu�d�l���m�肵�Ȃ��ȏ��v�ǂ����������A���b�ɂȂ�܂���B �@���Ƃ��Aarii�l�̃^�C�}�[�lj������①���ł́u�F�l���Q���ԂɈ���R���Z���g�̔������������Ă����悤�ł��v�Ƃ��������G�A�R���̂悤�ɓd�q(�}�C�R��)����ł͖����A�܂��ɓd�C(���@�B)����̗�p�@�ł���A�P�����d�C��ʂ����瓮���A�d�����J�b�g���Ă܂���œd����ʂ������p���삷��Ƃ������Ȃ��̂ł���ˁB �@�������e�җl���^�C�Ŏg���Ă���G�A�R���������܂Ō��n�I(�ԊO�������R���Ȃ��R�t���Ă��Ȃ�)�Ȃ�d�����C�����̂�ON/OFF�����ł������ł��܂��B �@�ł��A�P���ɃG�A�R���{�̂̓d����ʓd���������ł��ҋ@����ɂȂ��āA�����R������ON�M���������Ȃ��Ɨ�[������J�n���Ȃ��悤�ȕ�(�����R�����t���Ă���^�C�v�Ȃ�قƂ�ǂ�����)�ł�����P�ɓd�����C������ON/OFF���Ă������ŁA�����R����M�M����M���Ă�邩arii�l�̒�Ă���Ă���悤���R���v���b�T�[�̓d�������Ԃ������Ă��(��)�Ƃ������ɂ̑I���Ȃǂ����邵������܂���B �@���n�I�ȃG�A�R���ł���R���v���b�T�[�������Ă����v�ł����A�d�q�����H���t���Ă��鍡�̃G�A�R���ł̓R���v���b�T�[������Ɓu���O�@�ُ��v�Ɣ��肵�ăG���[�\���ƂȂ�A�G�A�R�����̂��~�܂��Ă��܂��Ď��ɃR���v���b�T�[���q���ł����삵�Ȃ��Ƃ��E�E�E���̃G�A�R���ł̓R���v���b�T�[���悤�ȉ����̓^�u�[�Ȃ̂ŁA���͒��Ă����͈͂��Ƃ͔��f���܂���ł����B  �@�ƂĂ��������P�ɓd�����C����ON/OFF���邾���ł����^�C�v�^�R���v���b�T�[����ON/OFF���Ă��G���[�ɂȂ�Ȃ��^�C�v�ł���w�z����̎������x���ߊ��x�ł��Љ���悤�ȁu���x�R���g���[���[�v���Ă��āA�Ԃ��p���[�����[�ł�����ŃG�A�R���̓d��(�܂��̓R���v���b�T�[)��ON/OFF���Ă����������ŁE�E�E�E�B
�@�ƂĂ��������P�ɓd�����C����ON/OFF���邾���ł����^�C�v�^�R���v���b�T�[����ON/OFF���Ă��G���[�ɂȂ�Ȃ��^�C�v�ł���w�z����̎������x���ߊ��x�ł��Љ���悤�ȁu���x�R���g���[���[�v���Ă��āA�Ԃ��p���[�����[�ł�����ŃG�A�R���̓d��(�܂��̓R���v���b�T�[)��ON/OFF���Ă����������ŁE�E�E�E�B�@���n�Ŕ����Ă��Ȃ��Ă��A�ʐ^�̐��i��DX�Ŕ����Ȃ�Worldwide�����Ȃ̂ł�قǕƒn�Ŗ�������́A�X�ւ��͂��������������Ŕz�B���Ă���܂��B �@�܂��A�ԊO�������R�����t���Ă��Ď�d����ʂ��Ă��ҋ@����ɂ����Ȃ�Ȃ������̃G�A�R���ł��A��L�̉��x�R���g���[���[(�܂��͂��莝����TC622EPA���g���ĉ��x�X�C�b�`�����)�Ńp���[�����[�����Ď�d����ON/OFF����Ƌ��ɁA�u��d�����J�ʂ�����A���b��Ɉ��|���ƐԊO�������R���̓d���{�^���������Ă���H(����͂��莝����555���ō��)�v�����삵�Ă��A���x�������Ȃ��ăG�A�R�����K�v�ɂȂ�Ύ�d���J�ʂƐ��b��ɉ^�]�w�߂������R������o���B���x�������Ȃ��ăG�A�R���̕K�v�������Ȃ�Ύ�d������ė�[�͂��Ȃ��Ȃ�E�E�E�݂����ȕ������܂��B �s�����܂ŎQ�l���x�̗]�k�t �@�u��d����ʂ��Ă��ҋ@����ɂ����Ȃ�Ȃ������̃G�A�R���v�ł��A���ʃp�l�����J���Ē��́u�T�[�r�X�X�C�b�`�v�܂��́u���^�]�X�C�b�`�v��ON�ɂ���A�����R���ɊW�Ȃ��P�Ɏ�d�����ʂ���Ή^�]����@�\�����镨�������ł��B��������A�O�������d���̋�����ON/OFF���邾���ł������[�gON/OFF�͉\�ł��B �@����̓T�[�r�X�}�����C���Ȃǂ̍ۂɉ^�]�e�X�g�����鎞��A�����R�������ăV���b�v������Ă��炤�܂ł̊ԂɈꎞ�I�Ɏg�������ꍇ�Ȃǂً̋}���ɑΏ�������̂ł�(�ً}�^�]�̏ꍇ�͉��x�ݒ�͒��ɍŌ�ɋL���������̂܂܂̕�������)�B���ʂ͏�p������̂ł͂���܂���B �s�����܂ŎQ�l���x�̗]�k�A�����܂Łt �@�ł��A��قNj����̃G�A�R���Ŗ�������͂����Ȃ�O�������d�����J�b�g����̂͂����߂ł��܂���B �@���[�o�[���J�����܂~�߂�Ƃ��́A���܂�l�����Ă��Ȃ��̂ŁE�E�E�B (�ً}�^�]�X�C�b�`�Ȃǂ�����ꍇ�́A����������[������ON/OFF����Ƃ�������l�����܂����A�����܂ŋ@��ɂ��܂�) �@���������ꍇ�́A�ȑO�������������ȋ@�\�����Љ�܂������A�u�^�C�}�[ON�̎��ɂ͐�Ɏ�d�������āA�����x��ă����R���̓d���{�^���������^�^�C�}�[OFF�̎��ɂ͐�Ƀ����R���̓d���{�^���������āA�����x��Ă����d�����J�b�g�����v�݂�����ON��OFF�ƂňႤ���������x����H��g��ł������̂ł��B �@�܂��ʂ̍l�����Ƃ��āA��d���ł��R���v���b�T�[�ł��A�O������^�C�}�[��ON/OFF������Ƃ���arii�l�̂���Ẵp�^�[��(���x���߉�H�͍��Ȃ��Ƃ����O��ł����܂Ń^�C�}�[����)�ł���A�s�̂̃^�C�}�[(�m���ɔ��W�r�㍑�ł���ɓ���)���͊��ɂ��莝���̃^�C�}�[IC555���g���āA�ߋ��ɂ��Љ�Ă���悤�ȁu�f���[�e�B������R�ɕς����锭�U��H�v�̕����ŁA���̃^�C�}�[����(���Ƃ���30��)�̂����ɃG�A�R�������삷�鎞�Ԃ��c�}�~�P�Ŏ��R�ɒ��߂ł���^�C�}�[�E�E�E�Ƃ�����H�����A��]�̉��x��Ԃɒ��߂���̂��ƂĂ��y�`��(����)�ɂȂ�܂��B �@����������ẮA����̓U�b�N���Ɣr�����Ă�5/4�̂��Ԏ��Ȃ̂ł����E�E�E�B �@�Ȃɂ���Aarii�l�̂��S�z�ʂ荡��́u�d�l���m�肵�Ȃ��ȏ��v�ǂ�ȉ�H��������K�Ȃ̂����킩��܂���B �@�l������S�Ă̕��@���L������A���Ɖ��{�قǕ��͂������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ邩�E�E�E �@���ɁA�����̃g�s�b�N�������ǂނ̂����ɂȂ邭�炢���͂��肪�����Ă��܂��H �@���Ƃ��ẮA���e�җl�̓��̒��ɂ́uTC622EPA�Ƃ������x�X�C�b�`���i�������Ă���(�g����Ǝv���Ċ�]������Ĕ������̂ɁE�E�E)�B�ł����������p���č�鉽�炩�̕��@�������Ă��炢�����I�v�Ƃ�������]�����Ȃ苭���Ǝv���A�Ȃ�ׂ������������������Ɏ����čs���Ă��������ƍl���Ă�5/4�̉Ȃ̂ł����B ���Ԏ� 2012/5/5
|
||
| ���e |
�����������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B���̎���ʕ��͂ŁA���̎v��ʒ�����ł��܂��\����܂���B �Ǘ��l�l��Arii�l�����������悤�ɐ^����Ɏ�d���𑀍삷�鑕�u�őΉ����悤�Ƃ����̂ł����A��d�������Ă��ҋ@��Ԃɂ����Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����R���̉����Ɏ���o��������ł��B �F�X���l���������������̂ł����A�ł��ȒP�ȊǗ��l�l���蔲���Ƃ�������鑕�u�w�w�艷�x�������A�w�艷�x��艺��������A�����R���̓d���{�^������莞�ԉ�����H(TC622EPA��555�����Ő���)�x�ł��肢�������Ǝv���܂��B ��낵�����肢�������܂��B omori �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@����ł́A����]�̎d�l�ł̉�H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�� ���x�Z���T�[ �@Microchip�Ђ�TC622EPA [PDF] ���g�p���܂��B�i�H���ň��120�~�j (���ł��f�W�b�g�ɂ����ׂ��������ł� 2012/9/6�A���180�~)
�@TC622EPA�͂W�s����DIP IC�Ɠ����`�����Ă��āA-40���`85���̐������x�ɑΉ����A���ɂQ���̃q�X�e���V�X���������R���p���[�^���������ON/OFF�̃f�W�^���o�̓^�C�v�̉��x�Z���T�[�ł��B �@���x�Z���T�[�Ƃ������́E�E�E���x�X�C�b�`�Ȃ̂Ŏ�舵�����ȒP�Ȕ��ʁA����Łu���x���v��(�����Œm��)�v�Ƃ����p�r�ɂ͎g���܂���B �@�d���d����4.5V�`18V�ƍL���A���d�r����Ԃ̃o�b�e���[�ł̒��ڎg�p���x�܂ł��̂܂g���܂��B �@�܂��^�C�}�[IC 555��4.5V�`16V�Ƃقړ����Ȃ̂ŁA555�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł͊��d�r����Ԃ̃o�b�e���[�ł̒��ڎg�p���x�܂łɂ��K�����܂��B �@���������鉷�x�̐ݒ����R��{�ōςނ̂łƂĂ��ȒP�ȉ�H�ɂȂ�܂��B �@�ݒ��R�l�� �@����̉�H�ł�R1 100K����VR1 20K����ɂ���100K������10���`120K������35������g�[�̉��x���ߗp�Ɏg���鉷�x�͈͂Ƃ��Ă��܂��B �@����Ƃ͕ʂ̉��x�͈͂Ŏg�p���ꂽ�����́A�������œK�Ȓ�R�l���v�Z���Ă����p���������B �@VR1�Œ��߂����ݒ艷�x��荂�����x�����o�����LED1�u�g�n�s�v���Ԃ��_�����܂��B(LED2�͏���) �@TC622EPA�̃q�X�e���V�X���Q���Ȃ̂ŁAVR1�Œ��߂����ݒ艷�x����Q�x�Ⴂ���x�����o�����LED2�u�b�n�k�c�v�����_�����܂��B(LED1�͏���) �@�ݒ艷�x��莺���������̂��Ⴂ�̂��A�G�A�R���삳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�����ڂł킩��܂��B �@�J���^���Ɏg���Ă������������x�X�C�b�`IC TC622EPA�Ȃ̂ł����P���_������܂��B �@����́uIC���̂��Z���T�[����r��H�E�o�͉�H�v�Ȃ��߁A�ق��̃Z���T�[IC�����ƕʓr��r��H�����ꍇ�ł́u�Z���T�[�͖{�̂��烊�[�h���ŊO�ɏo���čD���ȏꏊ�̉��x�𑪂�v�Ƃ����g����������Ȃ�܂��B �@TC622EPA�Ɛݒ艷�x�����߂��R���ڂ�������̂��u���x�������镔���v�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�d�r��TC622EPA�Ƃق��o�͗p��H���P�[�X�ɓ���Ă��܂��ꍇ�́A�P�[�X�ɒʕ��E���J���Ă܂��̋�C�̉��x���ǂ�TC622EPA�ɓ`���悤�ȍ��ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�܂��A�������M���镔�i�ƈꏏ�̊�ɍڂ���ƁE�E�E���������̉�H���̔��M�ł����Ɖ��x������܂����ˁE�E�E�B �� �g���K�[(����)��H �@TC622EPA�̏o�́AOUT��^OUT�[�q�͂��ꂼ��OUT���ݒ艷�x��荂����H�^�ݒ艷�x���Ⴂ��L�A���]�o��^OUT���ݒ艷�x��荂����L�^�ݒ艷�x���Ⴂ��H�ɂȂ��̉�H�����o�͂��~�����̂����o�͂��~�����̂��A�ǂ���ł��D���Ȃق���I��Ŏg����̂ŕ֗��ł��B �@�{��H�ł́u�b�n�k�c�v�Ɓu�g�n�s�v��LED��_��������̂ŗ����𗘗p���Ă��܂��B �@�܂��A����̖ړI�́u�������ݒ艷�x�����Ƃ��v�u�������ݒ艷�x����������Ƃ��v�̂Q�̏�ԕω���m�邽�߂ɂ��AOUT��^OUT�[�q�̗������g���܂��B �@��Ɍq����^�C�}�[IC 555�̃g���K�[���͂��������ł�����AOUT��^OUT�[�q����(L)�ɂȂ�u�ԂɃg���K�[�p���X���������H�Ƃ��܂��B �@���ۂ̉�H�ł��b�q�ɂ�������H��OUT��^OUT�����ꂼ��L�ɂȂ�u�Ԃ���L�ɂȂ�p���X�������A����_�C�I�[�h�n�q�ŗ����̃p���X�̂��������ꂪ�������Ă�555�Ƀg���K�[��������悤�ɂ��܂��B �@����Łu^OUT(�ݒ艷�x���Ⴂ)��L�ɂȂ����������ݒ艷�x�����v�uOUT(�ݒ艷�x��荂��)��L�ɂȂ����������ݒ艷�x����������v�Ɣ��肵���p���X����u555�̃g���K�[�ɂ�����܂��B �� �����V���b�g��H �@�悭���郊���[�ʼn����̋@�������H�ƈႢ�A����̖ړI�́u�����R���̃|�^���������v�Ȃ̂Ń^�C�}�[IC 555�ł��̉������Ԃ���莞�Ԃ̃p���X�������܂��B �@�܂��A���܂����ΐ�̃g���K�[�p�̔�����H������ŏ����������Ԃ̃p���X������Ă��Ȃ�Ƃ��Ȃ�͂��Ȃ̂ł����A���ꂾ�ƌ��ǂ��̌�ɂ܂Ƃ��ɏo�͗p�g�����W�X�^��FET���h���C�u�����o�b�t�@��H���K�v�ɂ��Ȃ�̂� �A�����͈�ʓI�ȃ^�C�}�[IC 555���g���������V���b�g�^�C�}�[�ŏo�͂���莞��ON�ɂ����H�Ƃ��܂��B �@�����R���̃{�^�����������Ԃ͍���͌Œ����0.5�b�ł��B �@�����̂悤��VR�����ĉςɂ��Ă������ł����A�����R���̃{�^���������Ƃ����ړI����ʂɉςɂ���K�v�������������܂���B �@�u�������ݒ艷�x�����Ƃ��v�u�������ݒ艷�x����������Ƃ��v�̃g���K�[�p���X������ƁA�^�C�}�[IC 555�͖�0.5�b��ON�ɂȂ�܂��B �@���̊�LED3�u�o�t�r�g�v������܂��̂œ�����m�F�ł��܂��B �� �o��(�����R���̃{�^��������)��H �@�^�C�}�[IC 555�̏o�͂Ńg�����W�X�^(Tr3) 2SC1815���쓮���ăX�C�b�`���O���s���܂��B �@�I�[�v���R���N�^�o�͂ɂ��Ă��܂��̂ŁATr3�̃R���N�^(C)�ƃG�~�b�^(E)�������R���̒��́u�d���v�X�C�b�`�̕����ɐڑ����܂��B �@�ɐ�������̂Œ��ӂ��Ă��������B�t�ɐڑ�����Ɠ��삵�܂���B �� �{��H�ƃ����R���̓d�����C��(GND)�����S�ɕ����������ꍇ�́A���̕������t�H�g�J�v�����g�p������H�ɕύX����܂̂������ł��ˁB �� �d�� �@����̂��˗��ł͓d���͒P�O�d�r�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA�P�O�d�r���S�{�g�����U�u�ŋ쓮���܂��B �@TC622EPA�A555���ɍŒ�d����4.5V�ł�����A�d�r�d����4.5V�������܂ł͓��삵�܂��B �@�d���d����6V���A����d������15mA�Ȃ̂ŁA����X���Ԃ��炢(�A�Q���̂�)�g�p����Ƃ��ĒP�O�A���J�����d�r�ł��������Q�T�Ԓ��x�g�p�ł��錩���݂ł��B �@����d���̑����́u�b�n�k�c�v�Ɓu�g�n�s�v��LED�Ȃ̂ŁA���̂Q��LED���펞���Ȃ���Ή�H�݂̂ł̏���d������3mA���x�ł��B �@���x�̔���\���p�ƁA�d���������Ă���Ƃ����p�C���b�g�����v�����p�ł��̂Q��LED�͂��Ă���̂ŁA���ɕK�v�������Ǝv����(���d�r�̎��������������I)�Ȃ炱�̂Q��LED�͂��Ȃ��Ƃ��A�v�b�V���X�C�b�`�ł��t���ĕK�v�Ȏ��������点��Ƃ��E�E�E�B �@�����d���̐ԂƐ́u�����_��LED�v�ɂ���(�d��������R�͊O��)�A����d��������������Ƃ����������܂��B �� ����m�F�ƒ��� �@��H��g�ݗ��ĂāA�d�r�Ɖ�H�̊ԂɃe�X�^�[���uDC�d���v(Max25�`100mA���x�����W)�v�ɂ��ē���A�d��������Ɠd���͖�15mA���x�����̂��m�F�ł���͂��ł��B �@�܂����̎��ɂ́u�b�n�k�c�v�܂��́u�g�n�s�v��LED�̂����ꂩ�P���_�����܂��B �@�ُ�ȓd���������ALED���_�����Ȃ��ALED�������_������E�E�E�Ȃǂ̏ꍇ�͂ǂ����Ƀ~�X������܂����炷���ɓd������Ċm�F���Ă��������B �@�����܂Ő���ł�����A����VR1���������ς�(10��)�ɉāu�g�n�s�v���_���A�u�b�n�k�c�v���������邩�m�F�B �@VR1���E�����ς�(35��)�ɉāu�b�n�k�c�v���_���A�u�g�n�s�v���������邩���m�F���܂��B �� ���̃e�X�g�͎�����10���`35���̊Ԃł���K�v������܂��B�^�~��10����������Ă���A�܂��͐^�Ă�35���������Ă��鎺���ł͏�ɂ����ꂩ�Ή�����LED�������ςȂ��ł��B �@VR1���u���݂̎����v�̂�������㉺�ɒʉ߂��邠�����LED�̓_������ւ��ΐ���ł��B �@�u�b�n�k�c�v�Ɓu�g�n�s�v����ւ�����u���A�u�o�t�r�g�v����0.5�b����܂��B �@�����܂Ŋm�F�ł�����A�g�����W�X�^(Tr3)�ƃ����R���̃X�C�b�`��ڑ����AVR1���āu�o�t�r�g�v���������Ƃ��ɁA�����R����ON/OFF���ւ��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@�ȏ�܂ł�����ł���A��H�̑g�ݗ��ĂƓ���͐���ł��B �@VR1�̃c�}�~�̂܂��ɒ�R�l����v�Z�������x�̑Ή��̖ڐ�����L������Ǝg���₷���Ȃ�܂��B �@�G�A�R����������ON/OFF���������x�Ƀc�}�~�����킹�Ă��g�p���������B �@���ۂɂ́A�G�A�R�����g�p���Ȃ���̊����x�ł��傤�ǂ������t�߂�ON/OFF����悤�A���X�̎g�p���Ƀc�}�~�����������K�v�͂���Ǝv���܂��B �� ���S�ɗ]�k �@TC622EPA�̃f�[�^�V�[�g��ǂ�ł��o�͒[�qOUT��^OUT����ő��i�������Ă��Ȃ��悤�ł��B(�����Ƃ��H) �@�o�͒�i�\���������AH�o�͂�Vdd��80%�����荞�ޓd���܂ʼn�����̂�500��A�AL�o�͂�Vdd��35%�ȏ�̓d���ɂȂ�̂�1mA�ƂȂ��Ă���̂ŁATC622EPA���o�͓d���͂قƂ�ǎ��܂����B(����̓Z���T�[�n�`�b�v�ł͂悭���鎖) �@�܂����̏o�͓d���́u���肪�f�W�^��IC�̏ꍇ�̐����H/L�ʂ���d���͈̔͂���E���Ȃ��v�Ƃ������܂������͈͂̂��ƂȂ̂ŁA������Ă������Ȃ琔mA���x�܂łł���Ύg���Ă������ɉ���Ƃ������̂Ă͖����Ƃ͎v���܂��B �@�ł��A�Q�l�܂łɃl�b�g��TC622EPA���g������ȂǂׂĂ݂�ƁE�E�E���͈̔͂��Ďg���Ă�悤�ȉ�H�}���U������܂��i�O�O�G �@���������āA���ʂ�TTL IC��C-MOS���W�b�NIC�A�}�C�N���`�b�v���i�Ȃ̂�PIC�}�C�R���̏o�̓|�[�g�Ɠ������Ǝv���Ă�l�������̂��Ȃ��E�E�E�B �@�����ڂ��W�s����IC�Ɠ����ł����˂��B ���Ԏ� 2012/5/8
|
||
| ���e |
�Ǘ��l����A���ӂ́B ���x�Z���T�[TC622EPA �ɕt���Ă͑S�����m�ł����A�ݒ艷�x�̌v�Z���͊Ԉ���Ă���l�ȋC�����܂��B �����炭�A��Ή��x�ɕϊ�����̂ł��傤���� "237.15"�ł͂Ȃ��A "273.15"���Ǝv���܂��B �������ł����B ����̂�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�͂��A���̒ʂ�ł��B �@�L�[�{�[�h�̑ł��ԈႢ�ł��B �@�摜�͒����������܂����B �@�܂��A�摜�Ȃ�тɖ{�����ł́uTC622EPA�͐�Ή��x(��Η�x����̐��l)�Őݒ�Ȃ̂Őێ�(��)����͐��l�����킹��v�Z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v���̕��͂́A�����܂ŏ����K�v�͖������낤�ƍ폜�������̂Ȃ̂ŁA�폜���鎖���̂��ԈႢ�������悤�ł��B �@���w�E���肪�Ƃ��������܂��B ���Ԏ� 2012/5/10
|
||
| ���e 5/11 |
��ς킩��₷������������������肪�Ƃ��������܂��B ���������p�[�c�𑵂��č쐬�ɒ��݂����Ǝv���܂��B omori �l
|
||
| ���e |
** ����J���e ** |
||
| ���Ԏ� |
�@�ʂɁu����I�v�ɂ͎v���܂���ł������A���l���������Ƌ��ɋL���쐬���Ɏv�������Ƃ����߂ď����������ł��B �@�����ӏ������Ă������������ɁA�{���Ɋ��ӂ��Ă��܂��B ���Ԏ� 2012/5/12
|
||
| �Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� | |||
|
����ɂ��́B ����A�s�`�Q�O�Q�O�̎����Ԃł̎g�p�̉ۂɂ��Ď��₳���Ă������������̂ł��B���̌�A���ۂɑ����E�g�p���Ă��܂����A���[�p�X�t�B���^�[�Ȃǂ̑��ݖ����ł��\���Ɏ��p�ɂȂ邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B����t�B���^��lj����ċ͂��ɔ������Ă���m�C�Y�������Ă������Ǝv���Ă��܂��B���肪�Ƃ��������܂����B �Ƃ���Ŏ���Ȃ̂ł����A �Ԃ̓d�����琳���d���i�{�|�P�T�u���炢�j�����ǂ����@�͂���܂��ł��傤���H�o����Α�d���i�P�`���炢�j�ƈ��萫�A�N���[���������˔������d�����~�����̂ł��B����v���A���v�⏫���I�ɂ͏��o�͂̃f�B�X�N���[�g��H�̂`���p���[�A���v���ԓ��Ŏg�p���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B ���ׂ����A�P�d�����琳���d�������h�b�Ƃ��āA�k�s�P�X�S�T���݂���܂����B�܂��A�k�s�b�R�U�U�Q�Ƃ��������h�b���m�F���Ă��܂��B����ŏ������āA�I�y�A���v��[���X�v���b�^�Ő����d�������̂����肩�ȂƎv���Ă��܂��B �����A�l�̖]�ސ��\�ɂȂ邩�͊m�M�����ĂȂ��̂ƁA����������������ƊȒP�ȕ��@�Ŏ����ł���̂��ȁH�Ƃ��v���A���e�����Ă��������܂����B�o�b�e���[���Q��ςނƂ����悤�ȑ�|����ȕ��@�͖����ŁA�Ⴆ�ΎԂ̃V�K�[�\�P�b�g���琳���P�T�u�A�ő�P�`�i�v���A���v�Ȃ�P�O�O���`����Ώ\���ł��傤���A���^�p���[�A���v��z�肷��Ȃ�j�����o���ǂ��A�C�f�B�A�͂���܂��ł��傤���H �A�h�o�C�X��낵�����˂������܂��B (������]) �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA
�@�u�l�̖]�ސ��\�ɂȂ邩�͊m�M�����ĂȂ��v�Ƌ��Ă��܂����A�ړI�̓I�[�f�B�I�p�r�̂悤�ł��������b�v���m�C�Y���ǂ̒��x�o�ĉ��ɉe�����o�邩�ǂ�������S�z����Ă���Ǝv���̂ł����A���͂��������I�[�f�B�I�͍���Ă��܂��A�Ȃɂ�肻��Ȍ^�Ԃ�IC�͎g�������������̂łǂ̒��x�̃m�C�Y���o��̂��A�܂����ǂ͎g���R�C�����ɂ���Ă����������m�C�Y���\���ς���Ă���̂ŁA��ɏ����Ă���ʂ�w����Ȃ̂��Ȃ��̎g�����i�ŕς��ł���H�x�Ƃ��������悤�������̂ŁA�ƂĂ��₽�������ł��܂��A�������ł��D���ȕ��i���đg�ݗ��ĂāA���ʂ��������̗v���ɍ������ǂ������m�F���������B �@��������IC�ׂĒT����Ƃ������́A�S�������m�炸�ɒP�Ɂu�����ĉ������v�ƕ����l���͂����ƒm���͂�����ł��傤����A�����������Ď��n�Ŏ������Ă݂���܂��䂭�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�u�����ƊȒP�ȕ��@�v�ōl������̂́A�f���Ɂ}15V�̓d�����u���Ƃ����̂������葁���ł��B �@���Ƃ��A�d���ł͗L���ȃ��[�J�[�R�[�Z���́uMGW301215 IN:DC12V(DC9�`18V) - OUT:DC�}15V/1A (�W���������i 3,500�~)�v�̂悤�ȁ}15V�o��DC/DC�R���o�[�^���g���A�����g�ݗ��ĂȂ��Ă������ł��ˁB �@���������������d�����i�͊e��ی��H�������Ă��܂�����A����ŒP����DC/DC��H����邾���łȂ��A�ی��H�܂ŐF�X�ƒlj����ĉ�H�������͎�Ԃ������炸�A���\���l����Βl�i�I�ɂ����育��ł��B �@���А��i�ł��T���ΐF�X�Əo�Ă��܂�����A�T���Ă݂ċC�ɓ��镨������Ύ���ł͂Ȃ������i�ōς܂��̂��u�����ƊȒP�ȕ��@�v���Ǝv���܂��B �@�������A���������d�����u�́u���������߂�s���A�I�[�f�B�I��p�ɊJ������܂����v�Ȃ�Ă����I�[�f�B�I��p�d���ł͂Ȃ��A�����̔ėp�d���ł�����ʂ����āu�l�̖]�ސ��\�ɂȂ邩�v�ɂ��Ă͑S���z�������܂���B(�Ȃɂ���]�ނ��̂�������Ȃ̂����킩��Ȃ�) �@���������m�C�Y������ċC�ɓ���Ȃ��̂ł���ADC/DC�����삷�鎞�ł������Őv���Ēlj�����m�C�Y���H�E���i��������������̂ŁA���̂�����͉���IC�œd����H�����삳��悤�Ƃ���Ă������Ȃ�l�����͓����Ȃ̂ő��v���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2012/5/4
|
||
| ���e |
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �����̂��鎿������Ă��܂��Đ\����܂���B ���A�ƂĂ��L���ȉ������������Ǝv���Ă܂��B ��̓I�ȉ�H��m�肽�������킯�ł͂Ȃ��A�d�q�H��̈�ʘ_�Ƃ��Ėl�̍l���Ă���������ő��v���A�����Ƃ��Ă�����@�͂Ȃ����A�m�F�����������̂ł��B �Љ�Ă����������R�[�Z���̃p�[�c�͒m��Ȃ������̂ő�ώQ�l�ɂȂ�܂����B���̂܂g�����瓮���ł��傤���爫���Ȃ������ł��ˁB�����[�������̂́A�J�^���O�œ��e������ƁA�C���o�[�^�[���g�����X�@�Ƃ������ɂ���A��x�𗬂ɕϊ����Ă��琳���d�������o���Ă���Ǝv����_�ł��B �����A�����������ׂ��̂Ŏ���ɒ��킵�Ă݂悤�Ƃ����C�����������̂ŁA�_���Ȃ�R�[�Z���ɗ���Ƃ��āA��x����킷��̂������Ȃ������ł��ˁB�����d�������ɂ͑僁�[�J�[�ł������������@���̂�Ƃ������Ƃ�������Q�l�ɂȂ�܂����B ���肪�Ƃ��������܂����B (������]) �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���������̋@��Ȃ̂Ŏ��삳���̂������Ǝv���܂��B �@����ɓK���Ă���͉̂ߋ��ɂ����x���Ƃ肠����100�~�V���b�v��DC/DC�R���o�[�^�ł��g���Ă���MC34063A�Ȃ̂�(����������)�A���������ėpIC�Ŏ������Ă݂�̂��������l�b�g�Ŏ���H��������āA���������Ă����ׂ₷���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�f�[�^�V�[�g��ǂ߂u�}�C�i�X�o�͓d���̉�H�}�v���ڂ��Ă��āA�}�ǂ���̏o�͂̉�H������֗���IC�ł����B �@����ƁA�R�[�Z���̂��̓d�����u���́u�X�C�b�`���O�d���v�Ȃ̂ł���������H��������܂��ł��B �@���ԂȂ������g���̂قƂ�ǂ̉Ɠd���i�A�p�\�R���̓d�����j�b�g�A�g�ѓd�b�p�ȂǏ��^�̃X�C�b�`���O�^��AC/DC�A�_�v�^�[�ȂǁA�d�����u�̂قƂ�ǂ�(AC�d����)�ꎟ��DC�d�����C���o�[�^(���U)���䁨�t���C�o�b�N�g�����X���ړI�̓�DC�o�͂̏��ɂȂ������u�X�C�b�`���O�d���v�ł��B �@�����ɏЉ�����i���≏�^(���͂Əo�͂̃A�[�X�͌q�����Ă��Ȃ�)�^�C�v�ł��B �@�≏�^�͓d����ς���ȊO�����d���Ȃ��悤�댯��AC100V�Ɛl���G���d���@��������ړI�ŊԂɃg�����X������ԂŁA�d�C�I�ɂ͓��͑��Əo�͑������ڐڑ�����Ă��Ȃ��悤�ɂ��܂��B �@�����A�P��AC100V�ƕ�������Ƃ����ړI�ł͂Ȃ��A�]���̕������������ǂ����M�����Ȃ��Ƃ������_�����邽�߁ADC��DC�̓d���ϊ��ł������̏ꍇ�ɗp�����܂��B �@�܂�DC��DC�ϊ��ł��u�A�[�X���������v�Ƃ����l�����K�v�ȏꍇ�ɑ����p�����܂��B �@���Ƃ��A������]�l�����g���ɂȂ���悤�ȎԂł̃I�[�f�B�I�@��̏ꍇ�A�����M�����̃A�[�X���C���̓d�ʍ��ŋN����u�O�����h���[�v�v���痈��m�C�Y�������A�������C���Ƀ��C���g�����X��n�C�E���[�R���o�[�^�����ăA�[�X��ڑ������ɉ����M�������`����Ƃ��������@�������������Ǝv���܂��B �@���̏ꍇ�X�ɃI�[�f�B�I�@��́u�d���v���̂��Ԃ̃v���X12V��A�[�X���番�����āA�ԑ̂ɗ���Ă���m�C�Y�����̓d�C�M�����A���v���ɓ��ꂽ���Ȃ��I�悤�ȏꍇ�ɂ͂��������≏�^�̓d�����u�œd�C�I�Ȑڑ����J�b�g���Ă��A�Ԏ��̂̃m�C�Y�Ƃ͖��W�ȗǂ������ʼn��y���y���߂��悤�ɁE�E�E�E�Ȃ邩������܂���B(�����܂Ō��I�ȕω������邩�ǂ���/��) �@�X�C�b�`���O�d���ł��A��≏�^(���͂Əo�͂̃A�[�X�͌q�����Ă���A�P�̓d�q��H���ȂǂňႤ�d���̓d�����K�v�ȏꍇ�Ɏg��)���̂�����̂ŁA���i��I�ԍۂɂ͖ړI�ɂ��킹�Ē��ӂ��K�v�ł��B �@�������܂ł��z�����Ă���DC/DC�R���o�[�^�̓`���b�p���̏���/�~����H�̂ق����Ǝv���܂����A����͉����̋@��̒��œd����ύX���Ďg���悤�ȗp�r�̏ꍇ�̈ꕔ�̕����Ƃ��ėp��������̂ŁA�u�d�����u�v�Ƃ��Ă̍l�����ł͎嗬�̓C���o�[�^�{�t���C�o�b�N�g�����X�̃X�C�b�`���O�����ł��B ���Ԏ� 2012/5/5
|
||
| ���e 5/7 |
�d����ł������ȕ��@������ʔ����ł��ˁB���ɂȂ�܂��B ���������ʂ�A�l�̒��ׂĂ����h�b�̓`���b�p���̏����̂悤�ł��B���^�@��̒��ɑg�ݍ���œd�����グ����̂Ȃ�ł��ˁB���̋@��̓o�b�e���[�쓮�̃P�[�X�������̂œd���͔�r�I���肵�Ă���A�`���b�p���̏��������̃m�C�Y���P�A����Ηǂ��ƁB�h�b�ɂ���Ă̓X�C�b�`���O���g���m�����Ă�����̂������āA�t�B���^�������Ղ��悤�ɂȂ��Ă���悤�ł��ˁB �≏���͒m��Ȃ������̂ł��낢�댟�����ł��B�≏���E�E�E�Ȃ��Ȃ����͓I�ȋ����ł��B���ہA�ԍڃI�[�f�B�I�̓d���Ƃ��Ďg���Ȃ�A�Ԃ���藣���ꂽ��ԂɂȂ�A���̐≏���̃X�C�b�`���O�����̃m�C�Y������Ώ�����Ηǂ��̂ł���ˁH���Ƃ���Ζ��͓I�����B���ׂ����QW���x�̏��o�͂ł����IC�Ƀg�����X�����܂œ����������̂�����悤�ł��B�܂��A�O�t���̃g�����X���̗p����^�C�v�Ȃ���������o�͂��҂������B�o�͓I��DAC�ƃv���A���v�ł�����������ł����A�R�X�g���l�b�N�����ł��ˁB���ꂱ���A�R�[�Z�����Ă��܂����ق��������������ł��B �����������̂ŁA�����������ׂĂ݂܂��B (������]) �l
|
||
| �ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ | |||
|
���������������B �Ԃł��B �o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON�������B 12V�ł��B ���͐M���̓����V���b�g�ł͂Ȃ��A�A���M���B ���͂�����ƁA2��̓_�ŐM�����o�͂������B �o�͂�G5V���̃����[���쓮�������B 1��ڂ̏o�͓͂��͂Ɠ����ɍs�������B 1���ON��0.3�b��OFF��0.3�b��2���ON��0.3�b�����̌�OFF�B ���͂�OFF�ɂȂ�A�ēx���͂����m�����瓯������B �ɗ͊ȈՂȉ�H�A���肪�e�Ղȕ��i�ōs�������B 555��2�g���A1�i�ڃ^�C�}�[��H�A2�i�ړ_�ʼn�H�őg��ł݂܂������A�^�C�~���O�����܂���ꂸ�A�o�͉Ƀo���c�L�������Ă��܂��܂����B �c�ɂ̓`���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[��A���̖ړI�ł���w�ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H�x�ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@�ړI�̃^�C�~���O�Ƃ����삷�钷���Ƃ��s�b�^�����Ǝv���܂����ǂ��ł��傤���H >�ɗ͊ȈՂȉ�H�A���肪�e�Ղȕ��i�ōs�������B �@�Ƃ������ł��̂ŁAIC����ł����ƂĂ��J���^���ł���H �@���͂��v�b�V���X�C�b�`����o�b�N�M��(�v���X�R���g���[��)�ɕς���̂ŁA���L�̉�H�ɕύX����ςނ����ł��B 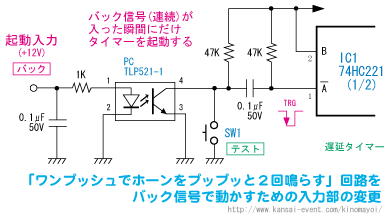 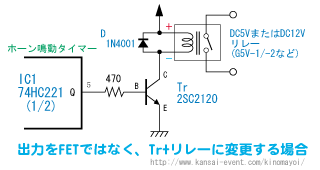 �@����ŁA�����o�͗p��FET�ł��Ȃ��̂��D�݂̃����[�삳����̂����������Ȃ��̂ł���A�g�����W�X�^�œ������Ă������킯�ł����E�E�E�B
�@����ŁA�����o�͗p��FET�ł��Ȃ��̂��D�݂̃����[�삳����̂����������Ȃ��̂ł���A�g�����W�X�^�œ������Ă������킯�ł����E�E�E�B>555��2�g���A1�i�ڃ^�C�}�[��H�A2�i�ړ_�ʼn�H�őg��ł݂܂����� 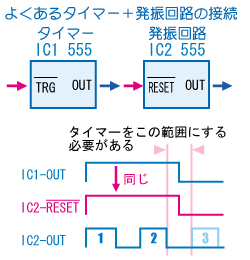 �@�Ƃ������ł����A�悭�����H�}�̂悤�ɂ��̂悤�Ȑڑ��ɂ���Ă��܂��H
�@�Ƃ������ł����A�悭�����H�}�̂悤�ɂ��̂悤�Ȑڑ��ɂ���Ă��܂��H�@����͂܂�555�̊�b�I�Ȑڑ����@�Ƃ��Ăǂ��ɂł�������Ă��܂����A���e�I�ɂ́u���\����������ȓ���ł�����H�v�Ƃ������̂ł��B �@����̖ړI�̂悤�Ɂu�Q��ON�A���������̎��Ԃ͂Q��Ƃ��������蓮�삵�ė~�����v�Ƃ����ړI�ł���A�^�C�}�[��OFF�ɂȂ�^�C�~���O�͂Q��ڂ̏o�͂��I��������Ԃ���R��ڂ�ON�ɂȂ�Ԃ̂ƂĂ��Z�����ԂłȂ��Ƃ��܂����삵�Ȃ��Ƃ����A�ƂĂ����߂����ɂ����A������ƃY�����炤�܂��ړI��B�����ɂ������̂ł��B 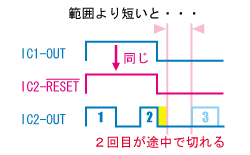 �@��̓I�ɂǂ��Ȃ�̂��}�Ŏ����ƁA����IC1�̃^�C�}�[���Ԃ��Q��ڂ�ON���Ԃ̏I�������Z���Ȃ�ƁAIC2�̃��Z�b�g�[�q��Lo�ɂȂ��ă��Z�b�g����A�Q��ڂ̏o�͂͊�]���Ă������Ԃ��Z�����ԂŐ�Ă��܂��܂��B
�@��̓I�ɂǂ��Ȃ�̂��}�Ŏ����ƁA����IC1�̃^�C�}�[���Ԃ��Q��ڂ�ON���Ԃ̏I�������Z���Ȃ�ƁAIC2�̃��Z�b�g�[�q��Lo�ɂȂ��ă��Z�b�g����A�Q��ڂ̏o�͂͊�]���Ă������Ԃ��Z�����ԂŐ�Ă��܂��܂��B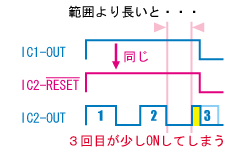 �@�܂��AIC1�̃^�C�}�[���Ԃ��Q��ڂ�OFF���玟�̂R��ڂ�ON�܂ł̊Ԃ̎��Ԃ��߂��Ă��܂��悤�ɒ����Ȃ��Ă��܂��ƁA�R��ڂ�ON�M�����o�͂����̂ŁA������܂���]�Ƃ͈Ⴄ�������ȂR��ڂ̓��삪�N���Ă��܂��܂��B
�@�܂��AIC1�̃^�C�}�[���Ԃ��Q��ڂ�OFF���玟�̂R��ڂ�ON�܂ł̊Ԃ̎��Ԃ��߂��Ă��܂��悤�ɒ����Ȃ��Ă��܂��ƁA�R��ڂ�ON�M�����o�͂����̂ŁA������܂���]�Ƃ͈Ⴄ�������ȂR��ڂ̓��삪�N���Ă��܂��܂��B�@�^�C�}�[�M���Əo�͐M���̃��j�^�[�pLED�������ƕt���Ă���A����LED�̓_�Ń^�C�~���O�����Ȃ������������Ȃ�Ƃ���̂����Ƃ���ɒ��߂ł��邩������܂��A0.3�b���炢���Ɗ���Ă��Ȃ��ƂȂ��Ȃ������������܂���B �@�����Łu555���g���Ă��Ă��A�o�͂̃p���X���Ԃ���̉�H�̂悤�ɕςɒZ���Ȃ�����A���̃p���X��������Əo���肵�Ȃ���H�v������Ă��A���͂قƂ�lj������܂��B �@�Ƃ͌����Ă��A��������ȉ�H�ō��{�I�ɉ��ς��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A��}�̂������ʂ�555���Q�g����H���ꕔ������ύX���Ă�邾���ʼn������Ă��܂��̂ł��B 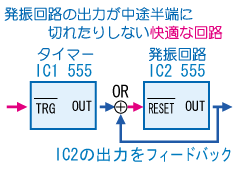 �@�܂�E�E�E�u����ڂ̏o�͂��o�Ă���Ԃ́AIC2�̃��Z�b�g�͂����Ȃ��I�v�Ƃ����ӂ��ɁAIC2�Ɏ��ȕێ�������t�B�[�h�o�b�N�ڑ���lj������Ƃ����l����K�p���܂��B
�@�܂�E�E�E�u����ڂ̏o�͂��o�Ă���Ԃ́AIC2�̃��Z�b�g�͂����Ȃ��I�v�Ƃ����ӂ��ɁAIC2�Ɏ��ȕێ�������t�B�[�h�o�b�N�ڑ���lj������Ƃ����l����K�p���܂��B�@�����IC2�̏o�͎��Ԃ͒Z�����������Ȃ�Ȃ��Ȃ�A������̒�������ON���܂��B �� ����ƌ����Ă��A���U��H�̏ꍇ��555�̓����ōŏ��̈���͏��������Ȃ�܂��B����͈ȑO���ς݁B �@�o�͎��Ԃ������ŕςȎ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂������A�u�^�C�}�[���Ԃ������ƂR��ڂɓ����Ă��܂��v�Ƃ������ɂ͕ς��͂���܂���B �@�������A�^�C�}�[�͏o�͂�OFF���Ԓ��ɂ��킹�Ȃ��Ƃ������ȓ���������Ƃ������߂̂��h���͂قږ����Ȃ�܂����B 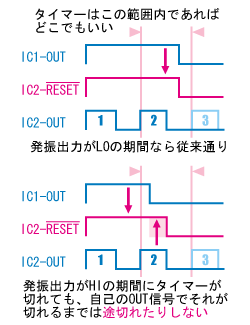 �@�}�Ŋm�F����ƁA�^�C�}�[����鎞�Ԃ́u�Q��ڂ̃p���X���o�n�߂�Ƃ��납��A�R��ڂ̃p���X���o�n�߂�܂ł̊ԂȂ�ǂ��ł������v�Ƃ������ƂŁA���ȕێ��̃t�B�[�h�o�b�N�������Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂĖ�Q�{�͈̔͂ƂȂ�A�������^�C�~���O���Y������o�͂��Z���Ȃ�����R��ڂ�������Əo����Ƃ����������ȓ�������ăX�g���X�������邱�Ƃ�����܂���B
�@�}�Ŋm�F����ƁA�^�C�}�[����鎞�Ԃ́u�Q��ڂ̃p���X���o�n�߂�Ƃ��납��A�R��ڂ̃p���X���o�n�߂�܂ł̊ԂȂ�ǂ��ł������v�Ƃ������ƂŁA���ȕێ��̃t�B�[�h�o�b�N�������Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂĖ�Q�{�͈̔͂ƂȂ�A�������^�C�~���O���Y������o�͂��Z���Ȃ�����R��ڂ�������Əo����Ƃ����������ȓ�������ăX�g���X�������邱�Ƃ�����܂���B�@�u����o�͂��o�������̂��H�v�����߂�^�C�}�[�̎��Ԓ��ߗpVR�����ƂŁA�K������̏o�͂��o�邱�Ƃ�I�ׂ�悤�ɂȂ�̂Œ��߂͂ƂĂ��y�ł��B 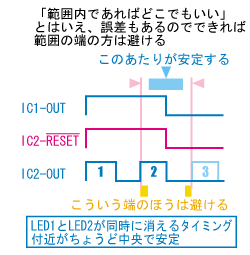 �@�Ƃ͂����A����ڂ̏o�͂��o��u�Ԃ�����Ƃ��A���{�P��ڂ̏o�͂��o�钼�O�Ƃ��A�����܂�^�C�~���O�̋��ڂ��肬���ɂ͒��߂��Ă����Ȃ��ق����ǂ��Ǝv���܂��B
�@�Ƃ͂����A����ڂ̏o�͂��o��u�Ԃ�����Ƃ��A���{�P��ڂ̏o�͂��o�钼�O�Ƃ��A�����܂�^�C�~���O�̋��ڂ��肬���ɂ͒��߂��Ă����Ȃ��ق����ǂ��Ǝv���܂��B�@�����̔��q��(���x�Ƃ��A�d���ϓ��Ƃ��AVR��������ƃY����Ƃ��c)�����ɉ�H�̓��삪�ς���������ŁA�w�肵�Ă����Ƃ͈������(�}�P��)�ɂȂ��Ă��܂��̂���낵������܂���B �@�E�}�̐��F�͈̔͂�����ɒ��߂��Ă����A������Ƃ₻���Ƃ̕ϓ��ł͓���ɕω��͖����ł��傤�B �@��H�}�ɂ���Ƃ������������ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�@�}�ɂ������܂������A���߂̃|�C���g�Ƃ��Ă̓^�C�}�[�����LED1�Əo�͊m�F�p��LED2�������ɏ�����悤��VR1�߂��܂��B �@�S�̂̓��쒲�����@�Ƃ��ẮAVR1���E�����ς��ɉă^�C�}�[���Ԃ��Œ��ɂ��Ă����A���̓e�X�g�X�C�b�`�������ĉ�H�삳���AVR2���Ă���]�̏o��ON/OFF���Ԃ߂��܂��B �@�o��ON/OFF���Ԃ����܂�����AVR1�����ɉĂ����āA����]�̉ڂ�LED2�̏����Ɠ�����LED1��������_�ɂ��킹��ƁA�ł�����ɂȂ�܂��B �@����������H�����ꍇ�A�u��H�̓���E�^�C�~���O�̊W�Ƃ��̈Ӗ��v���悭�������A����m�F�ƒ������ɂ��̈Ӗ��⓮�삪�������Ă��邩���m�F���₷���v���邱�Ƃ��|�C���g�ł��B �@555���Q�q���ŁA���Ƃ����ȕێ��t�B�[�h�o�b�N�������Ă��Ȃ��Ă��A�^�C�~���O�̈Ӗ��𗝉����Ă���LED1�ELED2�ɑ�������LED�����ă^�C�}�[�Ɣ��U��H�̓���m�F��ڂŌ��āA���傤�Ǘǂ��^�C�~���O(0.3�b�ł���)�ɑ_�������Ď��Ԓ��߂ł���悤�ɐv�E�g�ݗ��ĂĂ���A���߂�������Ƒ�ςȂ����ł����������肵�ē��삷���H�Ɏd�オ���Ă����Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2012/4/25
|
||
| �ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� | |||
|
����ɂ��́B���炭�������̂��̂������k�������܂��B ���ȏ��L��50CC�o�C�N�̃z�[���͂킸���UV�̃o�b�e���[�ō쓮����̂Ŏ������܂��Ȃ��������Ȃ����炢�n��ł��B�����ōl���Ă����̂��z�[���ƃo�b�e�[���̊ԂɂȂ����d�r���������u�̊ȒP�ȉ�H�͂Ȃ��̂��H�Ƃ��������Ƃł��B�܂��A�ʈĂƂ��Ďq�ǂ����h�ƃu�U�[���������ăX�C�b�`�������č쓮����悤�ɂł��Ȃ����ƁH�剹�ʂœd�r�̏���͂�������ł����A�[�d���̊��d�r���������ƂŖ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B�ǂ��ł��傤���H�g�ݍ��ݎ��̑������u�̓w�b�h�z���A���v�̂悤�ɂ���A���ȉ��ɑg�ݍ��ނ��ƂŎg�����͂���̂��ƁB �Ȃ݂ւ� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
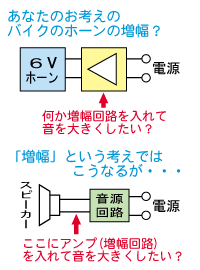 �@�u�z�[���ƃo�b�e�[���̊ԂɂȂ����d�r���������u�v�Ƃ����ƁA�E�̐}�̂悤�Ȑڑ������v�����Ȃ��̂ł����A�����������ł����H
�@�u�z�[���ƃo�b�e�[���̊ԂɂȂ����d�r���������u�v�Ƃ����ƁA�E�̐}�̂悤�Ȑڑ������v�����Ȃ��̂ł����A�����������ł����H�@�����������Ƃ�����E�E�E�u�U�u�ԗp�̃z�[���͂U�u�œ����悤�ɏo���Ă����v�̂��U�u�ȏ�̓d��(�����H)��������ƏĂ���Ă��܂��Ƃ������͂���������Ă��܂����H �@�u�g�ݍ��ݎ��̑������u�̓w�b�h�z���A���v�̂悤�ɂ�����v�Ƃ������͂���E�}�̂悤���A���v�������悤�ȕ��@���l���Ă���������̂�������܂��A���Ȃ��Ƃ����̒m�����ł͂U�u�̌��t�o�C�N�ȂɎg�����̕n��ȃz�[���ł��̂悤�ȓd�q������(�����A���v��)�X�s�[�J�[�łł����z�[���Ƃ������̂͌������Ƃ͂���܂���B �@�����c���g���悤�ȁA�h��ȉ��y����u�����f�B�z�[���v(��������@�i)�Ȃǂł͓d�q�����ƃA���v�ƃX�s�[�J�[�ō\�����ꂽ�������݂��܂����A�����������ł͂���܂����ˁH 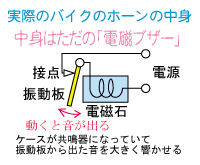 �@���ʂ̎ԁE�o�C�N�p�̃z�[��(�d�C��)�̒��g�́A�E�}�̂悤�������̓d���u�U�[�ł��B
�@���ʂ̎ԁE�o�C�N�p�̃z�[��(�d�C��)�̒��g�́A�E�}�̂悤�������̓d���u�U�[�ł��B�@�d�����ɓd�C���������U�������z�����A������x�z��������ړ_������ēd�C������Ȃ��Ȃ�܂��B �@�d�C������Ȃ��Ȃ�Ǝ��͂������Ȃ�̂ŐU���ł͌��̈ʒu�ɖ߂낤�Ƃ��āA���̈ʒu�ɋ߂��Ȃ�Ƃ܂��ړ_���ڐG����̂œd���ɓd�C�������悤�ɂȂ�z�����͂��߂܂��B �@�d���������Ă���Ԃ͂��ꂪ���X�ƌJ��Ԃ���A�U������u�u�[�v�Ƃ��������������܂��B �@�ԗp�ł́A�Q�̎��g���̈قȂ�z�[�����ɖ炵�A�u�t�@�[�v�݂����ȓƓ��̏_�炩�������o���܂��B �@�d���ɂ�����d����傫������ƁA���͂��傫���Ȃ��đ����͉����傫���Ȃ�܂����A�R�C���ɂ͒�i������A�v���傫�ȓd���E�d����������Ɣ��M���ďĂ��Ă��܂����i�Ȃ̂ŁA�v����Ă���ʂ�̎g�����������Ă͂���܂���B �@������u�z�[���ƃo�b�e�[���̊ԂɂȂ����d�r���������u�v�Ȃt���āA�����X�u���P�Q�u�Ƃ����������d���������Ă��A�ꎞ�I�ɂ͏����傫�ȉ����o�Ă��A�����ɏĂ���Č̏Ⴕ�Ă��܂��ł��傤�B �@�Ă��Ă��܂��ƁA�ۈ����u�Ƃ��Ă̈Ӗ��������Ȃ�̂Ŋ댯�ł��B(�����s�ǂŐؕ�����鎖�ɂ��E�E�E) 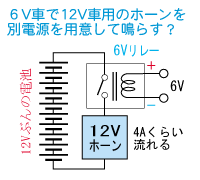 �@�����u���d�r�������ŕʓd����p�ӂ����v�̂ł���A12V�o�C�N�p��12V�z�[�����Ă��āA�����[���Ԃɋ���Ŗ点���Ȃ�傫�ȉ����o�܂���ˁB
�@�����u���d�r�������ŕʓd����p�ӂ����v�̂ł���A12V�o�C�N�p��12V�z�[�����Ă��āA�����[���Ԃɋ���Ŗ点���Ȃ�傫�ȉ����o�܂���ˁB�@�����A�Ԃ�o�C�N�p��12V�d�l�̃z�[���́A�傫�ȉ����o�邩���ɓd�������Ȃ�A�傫�ȉ��̂��̂ł��S�`���x���d��������܂��̂ŁA�P�O�A���J�����d�r�Ȃǂł͕͗s���ł��イ�Ԃ�ɖ点�Ȃ��ł��傤�B �@�P�O�^�̃j�b�P�����f�[�d�r��10�{����ɂ��Ă��A�A���Ŗ炷�̂͂�߂Ă������ق��������Ǝv���܂��B �@�z�[���Ƃ����p�r�ł����畁�ʂ͘A���Ŗ炳���A�u�v�b�v�[�v���x�Ɏ��X�炷�̂ł���A�j�b�P�����f�[�d�r�ł����v�ł��傤�B �@�o�C�N�p�ŏ���d���P�`���x�܂ł̕����g���̂�����Ǝv���܂��B 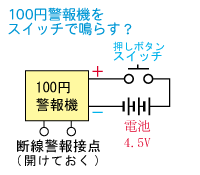 �@�z�[���̘b�Ƃ͕ʂ̂��b���Ƃ��ād�d�A100�~�V���b�v�́u�h�ƃu�U�[�v���X�C�b�`�Ŗ炷�̂͂ƂĂ��J���^���Ȏ��ŁA�P���ɓd����ON/OFF���Ă����������ł��B
�@�z�[���̘b�Ƃ͕ʂ̂��b���Ƃ��ād�d�A100�~�V���b�v�́u�h�ƃu�U�[�v���X�C�b�`�Ŗ炷�̂͂ƂĂ��J���^���Ȏ��ŁA�P���ɓd����ON/OFF���Ă����������ł��B�@�u�h�ƃu�U�[�v�͎q���p�́u�g�іh�ƃu�U�[�v�Ȃ�q���̕t�����v���O�����������Ă����Ζ�܂����A�u���p�h�ƃu�U�[�v�ł���Α��ɕt����u���v�����ɒu���Ȃ��ł������������ł���ˁB �@�v�͒����f�������m����ړ_���J���Ă����Ɩ�u�U�[�Ȃ̂ŁA�������Ă����Ό�͓d����ON�ɂ���Ζ�܂��B �@�A���E�E�E�A�u�h�ƃu�U�[�v�͂����܂��ԁE�o�C�N�p�̃z�[���ł͖����Ƃ������ŁA�����Ⴂ�܂������ʂ͎Ԃ�o�C�N�ł̑��Ԃ�ʍs�l�ɑ��Ďg���x���@�₻�̉��Ƃ��Ă͎g�p�ł��Ȃ��Ƃ�����肪�c��܂����A����ł�������ł����H �@��@�s��(�����s��)�ɂȂ�܂���B �@50cc�o�C�N���ƃz�[���̐ݒu�≹�F�ɂ��Ắw���H�^���ԗ��@�E��44��7���i�����@�t���]�Ԃ̍\���y�ё��u�j�x�Ŏ����Ԃ̂���Ɠ�������K�p�����Ƃ���Ă��āA�w���H�^���ԗ��@�E�ۈ����43���i�x����j�x�ɂĉ��ʂ≹�F����߂��Ă���A�u���F�A���ʓ��Ɋւ������Œ�߂��ɓK��������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ���Ă��܂�����A100�~�x��@�Ȃǂ̓z�[��(�x���@)�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl�����܂��B �@�x����̋Z�p��ɂ́u�x�������u�́A�A�����Ĉ��̌x�����A���̉����X�y�N�g���́A�쓮���Ɏ����I�ɕω����Ȃ����̂Ƃ����B�v�ƒ�߂��Ă��܂�����A100�~�x��@�̂悤�Ɂu�L���[���L���[���v�����g��(�X�y�N�g��)���ω����鉹�́E�E�E�E�K�����܂����ˁH �@�܂�́A�u�����������̂ւ�ɂ��鉹�̏o�鑕�u������ɎԁE�o�C�N�̃z�[���Ƃ��Ďg�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����@���ɂȂ��Ă��܂�����A������������Ƃ��Ă������ƎԁE�o�C�N�p�ɔ����Ă���@���ɓK���������i���g��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�悭�킩��Ȃ��ꍇ�́A�f�B�[���[�܂��͎ԁE�o�C�N�p�i�X�ɂ����k���������B ���Ԏ� 2012/4/23
|
||
| ���e |
�����b�ɂȂ�܂��B�ڂ������������肪�Ƃ��������܂��B�ŏ��Ɂw���F�A���ʓ��Ɋւ������Œ�߂��ɓK��������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��x�����͑�ł��ˁB�Ƃ������ƂŖh�ƃu�U�[�̌��͂Ȃ��ł��ˁB �b��߂����Ē����܂����A�܂��͂UV�d�l�́i�����j�z�[�����Ȃ��i�͈͂ł̓d�����펞�m�ۂ��������ƁA�UV�̃o�b�e���[���[�d���Ă��z�[����点�Ȃ����e�ʂ��w�ǖ������Ƃɂ���܂��B �܂�e�ʂ��ǂ߂Ȃ��o�b�e���[�Ƃ̊Ԃɑg�ݍ��ނ����A�z�[���Ɠd�r�����āi�z�[���ƃo�b�e���[��ʉ�H�j6V���m�ۂ��Ă��悢�i�j�b�P�����f�d�rX5�H�j�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���H �����A�n���h���̃u�U�[�X�C�b�`������ł���̂łł���Ί�����H��ON/OFF���\�ɂ��đg�ݍ��ނ̂��ǂ��̂ł͂ƍl���Ă��܂��B�[�d��������͐V�i��off�Ŏg���āA���炩�ɃE�C���J�[���u�U�[���������Ȃ����炢������Ƃ��ɂ�on�ɂ��Ă̂悤�ȁE�E�E�f�l�l���ő�ς������킯�������܂���B �Ȃ݂ւ� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�u������H��ON/OFF���\�ɂ��đg�ݍ����v�̂ł���A��L��12V�z�[����炷��H��6V�d���Ɗ�����6V�z�[����p����悤�ɂ��āA������X�C�b�`�Ŋ����̃z�[����H�Ɛ�ւ���悤�ɂ��邾���ł����̂ł́H �@�n���h���܂��͉��ς����ɁA�z�[���̋߂������ōς݂܂���B �@���ɂ���������H�͎����Ă���̂ŁA(�d����12V��6V���̈Ⴂ��������)����ł����Ǝv���̂ł����B �@�����[���g������A�X�C�b�`���g���Ă킴�킴�l�͂�ON/OFF�����肵�Ȃ��Ƃ��A�_�C�I�[�h���g�������������I�ɁA�o�b�e���[�̓d�����Ⴂ�������d�r����d�����������ăz�[����点���悤�ɂȂ�܂����A���������������͂��߂ł��傤���H 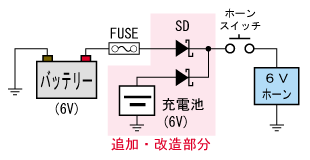 �@�g���_�C�I�[�h�͂Ȃ�ׂ��h���b�v�d�����Ⴂ�ق��������̂ŁA�V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h���g���A�d��40V�ȏ�A�d���́E�E�E���Ȃ��̂��g���̃z�[���ɗ����d����2�`5�{�ȏ�̗e�ʂ̂��̂����g�����������B (���̓d���́A���͂��Ȃ��̃o�C�N�͎����Ă��Ȃ��̂łǂ�ȃz�[�����t���Ă���̂��킩��܂���B�������ő��肵�Ă�������) ���Ԏ� 2012/4/26
|
||
| ���e 4/26 |
�@�V�����o�b�e���[�ɔ����ς�������b �@�z�[�����܂Ƃ��ɖ�Ȃ��Ȃ�E�C���J�[���܂Ƃ��ɓ_�ł��Ȃ����� �@�E�C���J�[�̓_�ʼn��@�߂Ō��߂��ĂĂ܂Ƃ��ɓ_�ł��Ȃ��ƈᔽ�ɂȂ鎖�ʒm���Ă��ȁH �@�܂�����@��Ԃŏ���Ă�o�C�N�̈�@�s�ׂ�������ɛ����悤���č��_���ᖳ����ȁH �@���������Ȃ��Ə��ĐÊς��Ă���肾���������ꂾ���͌������Ȃ� (������]) �l
|
||
| ���e 4/26 |
����̃��x���̘b�͂Ƃ������A�UV�n�̃o�C�N�͏[�d�@�\��������Ȃ̂Ńo�b�e���[���ւ��Ă��]��͕ς��܂���B������ƃr���e�[�W���ƃZ����������ŏ[�d�Ȃ̂ŃA�C�h�����O�ł͏[�d�����A������Ƒ���Ƃ����ߏ[�d�ɂȂ�܂��B�������V�[���h�o�b�e���[�͎g���܂���B�i�ł��ǂ����邵������������ł��j �P�QV�����鎞�����Ă���̂�������܂���B�Ȃ�Ƃ����Ă��UV�n�̓o���u�W�𒆐S�ɓd���p�[�c�̋��������o���Ȃ��Ă܂��B arii �l
|
||
| 12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H | |||
|
12V�̓d���h���C�o�[�p�j�J�h�o�b�e���[�̏[�d��������ԗp��12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H (������]) �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����͂ł��܂��B �@�A���A�H��p�̏[�d�킪�u�}���[�d�^�C�v�v�u���[�d�Ŏ����I�ɒ�~����v�^�C�v�̏ꍇ�A�j�J�h�p�̏[�d�����H�Ɖ��o�b�e���[�p�̏[�d��H���S���Ⴄ�̂ŁA�P�Ƀj�J�h�p�[�d��H�̒��̕��i�������������������炢�ł͑Ή��͂ł��Ȃ����߁A���������̂������Ƌ��Ă���̂ł����������ł��B �@��{�I�ɂ��ł����ƌ����Ă��A���̃j�J�h�p�[�d��������̒�d���d���Ƃ��Ă��炢�ɂ����g�킸�A������12V�o�b�e���[��ɂ߂Ȃ����S�ȓd���̒�d���d���ɉ������āA��͒�R������(����������d�q��H�ł�����)������d���[�d��H���o�b�e���[�Ƃ̊Ԃɋ���ŁA�o�������o�b�e���[�̏[�d���@�ɏ��������[�d���ɂȂ�悤�ȉ������{�������̂ł��B �@�����̕�������ɍ����g���̃j�J�h�p�[�d��̎d�l�Ƃ����̉�H�}�Ƃ��̒������̂ŁA�����������������ł��܂��Q�l�ɂ��Ă��������B ���Ԏ� 2012/4/22
|
||
| �ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H | |||
|
�ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������̂ł����A�ǂ̂悤�ɉ�H������悢�ł��傤���H �W���Ńh�A�I�[�v����h�A�A�����b�N�ł͂��܂� ��Ȃ� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁE�E�E�w�ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������x�ł͂��߂Ȃ�ł��傤���H ���Ԏ� 2012/4/22
|
||
| ���e 4/22 |
�����܂���A�������₪����̂������Ƃ��Ă��܂����B ���肪�Ƃ��������܂��� ��Ȃ� �l
|
||
| �����₷�����{��\���̉t���������Ă������� | |||
|
�����y�����q�����Ă��܂��A ���ɂ킩��₷�������Ɖ�H�}�ŏ��S�ҁA���K�҂��܂����悤�ȂƂ���ׂ̍₩�ȃt�H���[���ƂĂ����ɂȂ��Ă��܂��B ���āA��ʼnt���ɓ��t�Ƃ��̓��̖����݂����Ȃ̂�\�����ABGM�ʼn��y���Đ���������̂肽���Ǝv���Ă��܂��B �e�L�X�g�≹�y��SD�J�[�h����ǂݍ��݁A�t���ɕ\���������Ǝv���܂��Barduino�Ȃ�SD�V�[���h��mp3�V�[���h������̂ł��₷���̂��Ǝv�����̂ł����A�t���̕\�����Ȃ��Ȃ��~���������ĔY��ł���܂��B�f�W�b�g�Ń^�b�`�p�l���Ή��̉t�����Ă����̂ł����ǂ���������ł��B ����ŁA�����₷�����{��Ή��t������{��\�����@�̃A�h�o�C�X�����������Ȃ����Ǝv�����e���܂����B �Ԏ��͋}���܂���̂ł����Ԃ̂��鎞�ɉ�����낵�����肢���܂� jm3atn �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�u�����₷�����{��Ή��t���v�ł����A���܂Ō������Ɏg��������������Ό������Ƃ������̂�(�������������p�L�����N�^�t���ł��ˁc)�A�Ă��Ɓ[�Ƀl�b�g������������s�̕i�ł悳�����ȕ�������܂����̂ł��m�点���܂��B �@������ЃG���E�A���h�E�G�t�́wLF59 ���{��\���Ή��t���\�����j�b�g [PDF]�x�Ƃ������i�ł��B �@120�~52�h�b�g�E���m�N���t���ɑS�p10�����~�S�s�̕\�����\�ŁA�����̕\�����V���A���ʐM��JIS�R�[�h��]�����邾���̂悤�ł��B (�����������Ă��Ȃ��̂ŁA�u�悤�ł��v�Ƃ��������܂�) �@����Ȃ�Arduino�̃V���A���ʐM�@�\�Őڑ����Ďg����A�ƂĂ��J���^���ȗ��p���@�Ŋ��p�ł���Ǝv���܂��B �@���̂ł�13,500�~�ƁA���̂悤�ȓ��e�̐��i�Ƃ��Ă͍w�����₷���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�����A���ɐ����I�����Ă���̂ŁA�Ɍ���ƂȂ��Ă���̂��S�z�ł��B �@�����t�H���g�����^�̉t���p�l�������t���R���g���[���[�͔����̃��[�J�[�e�Ђ��o���Ă��āA���Ȃ�̎�ނ�����̂ł��������g�ݍ��u���{��t�H���g�����v�̉t���p�l���Ƃ������i�́A�Ȃ��Ȃ�������܂���B �@�����������i�̂قƂ�ǂ��s�̗p�ł͂Ȃ��A�J�X�^�����C�h�̐�p�i������ł��B �@�ꉞ�A�����̃y�[�W�ɏo�Ă���uNEC 8 bit�}�C�R���ɂ��Ă͊����q�n�l�����ڂ���Ă��܂��B�v�Ƃ������i�Ȃ�����t�H���g�ɂ����{��\�����\�̂悤�ł�����A�����K�v�ł���Δ̔��X�ɂ��₢���킹���������B �@�����u�����ŃO���t�B�b�N�t���Ɋ�����\���������v�Ƃ����v���O���������̂ł���E�E�E�A��b���̊�b�Ƃ��āu�t���p�l����CPU�̊Ԃ̃f�[�^�ʐM�v���������Ńv���O��������K�v������܂��B �@�܂��͂��ꂪ�ł��Ȃ��Ɖ����͂��܂�܂���B �@Arduino�Ȃ�ARM�R�A�ł�����AARM CPU�̃p�������|�[�g�Ɖt���p�l����z�����āA�u�R���g���[�����E�f�[�^���̈������v�A�u�f�[�^�������݁E�ǂݏo���̃r�b�g����v�A�u�r�W�[WAIT��^�C�~���O�v�Ȃǂɂ��ďn�m������Ńv���O�����������Ȃ���Ȃ�܂���B �@�uCPU�Ɖt���p�l�����Ȃ��v�Ɓu���߁E�f�[�^�𑗂�/�ǂݏo���v���ł���悤�ɂȂ�A���͉���������摜(�͗l)��\�����邽�߂ɁE�E�E �� �t���R���g���[�������������� �� �\���������ʒu�����߂� �� �\������������(�܂��͖͗l)���������� �Ȃǂ̑��삪�ł���v���O����(���E�T�u���[�`��)�����܂��B �@�����ŁA�w�����ꂽ�t���p�l�����f�W�b�g�́w�����i�^�b�`�p�l��LCD��2��ނ��Љ�����܂��B�x�̂悤�ȃO���t�B�b�N�t���ł���A�����t�H���g�͒��Ɏ����Ă��Ȃ��̂��S���v���O�������ŗp�ӂ��Ă���K�v������܂��B �@���ʂ͔��p�t�H���gROM�^����ROM�ɑ�������t�H���g�f�[�^�������������́u����ROM�v(JIS��ꐅ���E���)�Ȃ��g���̂ł����A�ŋ߂ł͂�����������ROM���̂قƂ�Ǔ���ł��܂��A�Ȃɂ�蕁�ʂ����́u�p�������E�o�X�p��ROM�v�Ȃ̂�ARM��PIC�̂悤�ȃ}�C�N���R���g���[���[�ƌq���ɂ͂���܂�I/F��H����ςɂȂ�܂��B �@�Ȃ̂ŁA�q���₷���V���A��EEP-ROM�ɕK�v�ɉ����ăp�\�R���ŕ����t�H���g���Ă����u���������̃I���W�i������ROM�v�݂����Ȃ��̂����삵����H�ɑg�ݍ��ނ̂��ł��g���₷���ł��傤�B (�T���Ă��Ȃ��̂Œm��܂��A�V���A���^�C�v�˔����Ă��邩������܂����) �@��̓v���O�������ł͕\�������������t�H���g���P���������슿��ROM����ǂݏo���ĉt���p�l���ɖ͗l�Ƃ��ē]�����邾���ł��B �@�E�E�E�Ƃ܂��A�̂���p�\�R��(�̂̓}�C�R��)�̃O���t�B�b�N��ʂɖ͗l��}�`��V-RAM(�摜�\���p�������[)�ɏ�������Ő}��\��������A�Q�[����������肵�Ă�������ɂ͑��肪�t���p�l���ɕς���������ł�鎖�͓����ACPU���}�C�N���R���g���[���[�ɕς���������Ńv���O����������b����Ƃ�����Ɏ�����p����ň����₷���Ƃ��E�E�E�A�Ƃɂ����n�[�h�E�F�A��@���Ă܂Ƃ��ɂ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������̐l�Ȃ炻��قǓ���͖����悤�ȍ�Ƃ�v���O�����ł����A�ŋ߂́u�n�[�h�E�F�A�͍������ނ����v�u�v���O�����͕K�v�ȃ��C�u�������p�ӂ���Ă��āA������Ăяo�����@��m����������v�݂����Ȃ���y�J���^���R���s���[�e�B���O�̎���ł́A������ƕς��������(�W���i�ł͖���)���q�����Ǝv���ƂЂƋ�J�ł��B �@�����p����ROM��p�ӂ����肵�Ȃ��Ă��A�ǂ���SD�J�[�h�Ɋi����mp3�T�E���h�Ȃǂ��L�������Ă��܂���̂ł���A�u�ŏ�����t���ɕ\�����銿���t�H���g���A�����̃O���t�B�b�N�f�[�^�Ƃ��ăx�^�ȃf�[�^�ŗp�ӂ��āAArduino���͂�����x�^�ɉt���ɓ]�����邾���I�v�Ȃ�Ď蔲����������ق����ǂꂾ���y���I(��) �@�������̂��߂ɂ́APC��Ō��̊i���f�[�^����u�h�b�g�G�v��Ԃ̊����t�H���g�ɒu��������u�R���o�[�^�\�t�g�v�͎��삵�Ȃ���Ȃ�܂���B �@�p�\�R����œ����\�t�g������A���������������̘b�ɂȂ�܂����ǁB ���Ԏ� 2012/4/22
|
||
| ���e 4/30 |
���낢��Ƃ����������������肪�Ƃ��������܂��B �����ł��ˁB�R�U�T�����̉摜�t�@�C����p�ӂł�����̂ق����y��������܂���ˁB ���肪�Ƃ��������܂����B jm3atn �l
|
||
| �_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� | |||
|
����ɂ��́B�ȑO�u���V���X���[�^�쓮��H�ł����b�ɂȂ����҂ł��B ���q�˂��������e�� �u�_�C�I�[�h�̊����ɂe�d�s���g�p���Ēᑹ���ȋt���h�~��H��v���Ē��������v�ƌ������k�ł��B �g�p�p�r�� ����d�C�����ԋ��Z�u�G�R�f���v�ɓ��ڂ��Ă���c�b�c�b�R���o�[�^�̏o�͂ɒ���ɐڑ����Ă���t���h�~�p�_�C�I�[�h�̊����ł��B �G�R�f���̓��e�� 12�u�̉��~�d�r����g���A50�v�̃u���V���X���[�^�[�͂Ƃ��A����̎Ԃő��s�������������Z�ł��B �c�b�c�b�R���o�[�^���ǂ̗l�ɂɎg���Ă��邩�Ɛ\���܂��� �C�ӂ̃^�C�~���O�ŏo�͂��グ��ʏ́u��悹�u�[�X�g�v�@�\�Ɏg�p���Ă��܂��B(�ʏ��12�u�ő��s���܂�) 12�u�̉��~�d�r�ɁA����12�u�@�o��3.3�u�̂c�b�c�b�R���o�[�^�̏o�͂�Ɍq��15.5�u�̓d���Ƃ��Ďg���܂��B ����ȋ@�\�͌����������Ӗ��������悤�Ɏv���邩���m��܂��A���[�X�����̕��̉e���Ȃǂŏ���d�͂��ς���Ă���̂� ���[�X�㔼�̔C�ӂ̃^�C�~���O�Ń��X�g�X�p�[�g���o����Ԃ��L���ł��B �g�p�c�b�c�b�R���o�[�^�� �C�[�^�d�@�@�^���@NVD3.3SC12-U1 �ł��B ���̂c�b�c�b�R���o�[�^�͎���Ɂu�����A����ڑ��^�]�s�v�Ƃ���܂����B�������������̏�ʃ`�[�����̗p�����т�����܂����B �s�v�c�Ɏv���A�e�N�j�J���T�|�[�g�̋L����ǂ��A�_�C�I�[�h��ڑ����������ǂ��Ɗ����܂����B ���̔��f�Ɏ��M�����������̂Ń��[�J�[�ɑ��k�������A�u�c�b�c�b�R���o�[�^�̏o�͂ɋt���h�~�p�ɒ���Ƀ_�C�I�[�h��ڑ��A�N���s�ǂ�h�~����ׂɕ���Ƀ_�C�I�[�h��ڑ����āv�Ɖ�Ⴂ�܂����B ���܂ŏH���Ŕ̔����Ă���i�S�T�u�R�O�`�j�l�a�q�R�O�S�T�e�b�s���g�p���Ă��܂������A�c�b�c�b�R���o�[�^�ɒ���ɐڑ�����Ă���_�C�I�[�h�̓d���~�����C�ɂȂ育���k���܂����B ��H�ɂ��肢���������Ƃ�4����܂��B �@�t���h�~��H�̓d���d����12�u�ł��肢���܂��B (���[����12�u���~�d�r�������ڂł��Ȃ���) �A��i�d���͘A��3�`�A�Z����8�`(2����1��̃y�[�X��10�b��)�̑Ή������肢���܂��B �B�o���邾���ᑹ���ł��肢���܂��B �C�e�d�s���h�q�e�R�V�O�R���g�p���ė~�����B (���̗p�r�ɍ���Ȃ��A�������ɖ�����������܂�����A���̇C�͖������Ă�������) ���͎w�肠��܂���B ���Z�������\����܂��A��낵�����肢�v���܂��B �n�X�e���C �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�܂����C�́u�e�d�s���h�q�e�R�V�O�R���g�p���ė~�����v���炢���܂��傤�B �@�Ȃ�IRF3703���g�������̂���ł��B �@100���炢�����Ă��ė]�点�Ă���Ƃ��H �@�N���ɑE�߂�ꂽ�Ƃ��H �@�܂��A���Ȃ�̓d���𗬂���H�ł͂悭�g����p���[MOS-FET�ł͂���܂����A���Ȃ��̂���]�̉�H�ɂ͕s�K�ł��B �@�����IRF3703���A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�u�قƂ�ǂ̃p���[MOS-FET�͂��̗p�r�ɂ͎g���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B 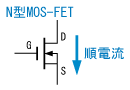 �@�p���[MOS-FET�́A�����̂̍\�������H�}�ł͂悭�E�}�̂悤�ɏ����L���Ă��܂��B
�@�p���[MOS-FET�́A�����̂̍\�������H�}�ł͂悭�E�}�̂悤�ɏ����L���Ă��܂��B�@�g�����W�X�^�̈��ł���MOS-FET�ł�����A�m�^�̏ꍇ�͓d�����c���r�����Ɉ���ʍs�ŗ���A������f�d���ŃR���g���[�����܂��B �@�ƁA�����܂łȂ�u�d���͈���ʍs������A���ɂ͗���Ȃ��v�u�܂萮��(�t���h�~)�Ɏg����I�v�ƒP���ɍl���Ă��܂������ł����A�����͖≮�������܂���B �@��H�}�ł͊m���ɓ��쌴�����炻���}�ɏ����Ă��܂����A�����̃p���[MOS-FET�͒��g�������Ⴂ�܂��I 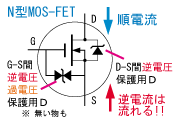 �@FET�Ƃ����f�q�͂ƂĂ��q���Ȕ����̂ŁA�ߓd����t�d���ŊȒP�ɉ��Ă��܂��܂��B
�@FET�Ƃ����f�q�͂ƂĂ��q���Ȕ����̂ŁA�ߓd����t�d���ŊȒP�ɉ��Ă��܂��܂��B�@�ł��̂ŁA�p���[MOS-FET�ɂ͑f�q���̂�ی삷�邽�߂ɒ��ɉE�}�̂悤���ی�p�_�C�I�[�h���g�ݍ��܂�Ă��܂��B (��������i���Ŏg�����Ƃ�t�d���Ȃ����Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł����A���(�d�C�I�ɂ͋���)�o�C�|�[���^�p���[�g�����W�X�^�̂悤�Ɏ�舵�����ȒP�ɂ��邽�߂ł�) �@���āA�}�ł킩��悤���c-�r���ɂ��t�d���ی�p�_�C�I�[�h�������Ă��܂�����A�����{���Ƃ͋t�����̓d���������������t�d���͉ؗ�ɃX���[����āA�t���h�~�ɂȂg���܂����B �@���Ȃ݂ɁAIRF3703�̒��̋t�d���ی�_�C�I�[�h��Vr = Typ 0.8V�Ȃ̂ŁA0.8V�ȏ�Ńp�X���܂��B �@����ŁuON��R���Ⴂ�p���[MOS-FET���g���A�_�C�I�[�h�������Ɨǂ��t���h�~��H�����邾�낤�I�v�Ƃ������͖��c�ɑł��ӂ��ꂽ�킯�ł��B �@�Ƃ������ŁA����]�̂悤�ȋt���h�~��H�����ƂȂ�ƃX�C�b�`���O�ɂ̓p���[�g�����W�X�^���g�����A�����ƕʂ̔����̂��g���Ă���𐧌䂷���H����邩�E�E�E�B �@�ł��A����͌��\�ʓ|�Ȃ̂�(���͂܂����\���Z�Ȃ̂Łc)�A����͂Ƃ��Ă��������i�����Љ�܂��傤�B �@����́u�N�[���o�C�p�X�X�C�b�`�v�Ƃ������i�ŁA�w�����p�ɃV���b�g�L�[�_�C�I�[�h�̂����ɒu�������Ďg���A�t���h�~�E�X�C�b�`���O�p�Ƀp���[FET���g���āA�����ʂ̃_�C�I�[�h���͂邩�Ɍ��炵�������f�q(���g��IC)�x�E�E�E�Ƃ����A�܂�Ŗ��̂悤�ȑf�q�ŁA���傤�Ǎ��n�X�e���C�l������]����Ă���v�f�����̂܂�܈�̕��i�̒��ɓ����Ă��܂�(��) �@����������H�}���l����K�v������܂���B 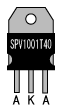 �@�r�s�}�C�N������SPV1001T40�uCool bypass swtch�v������ł��B
�@�r�s�}�C�N������SPV1001T40�uCool bypass swtch�v������ł��B�@TO-220�p�b�P�[�W�̃p���[�g�����W�X�^�Ɠ����`�����Ă��܂��B �@���̒��ɁA�X�C�b�`���O�p�̃p���[MOS-FET�Ƌ쓮�p��H�A�쓮�p��H�������߂�DC/DC�R���o�[�^�܂œ����Ă���Ƃ������Ȃ�~�����IC�ł��B �EIF=16A,VR=40V (Max) �EVF=230mV @IF=16A �EVF=120mV @IF=8A �ƁA����̂���]�̎g�p�d���ł͂��イ�Ԃ�ł��B �@���i�̏Љ�Ɣ̔��́u�����d�q�̃u���O�v�ɍڂ��Ă��܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ă��������B(�Q�l���� 600�~) ���Ԏ� 2012/4/13
|
||
| ���e |
����ɂ��́B���Z�������f�����ԓ����肪�Ƃ��������܂��B �u�N�[���o�C�p�X�X�C�b�`�v���̂悤�ȕ����������̂ł��ˁB �ꉞ�A���O�ɍ���̗p�r�Ɏg���镔�i�����������ׂ��̂ł����C���t���܂���ł����B ���������������Ă݂悤�Ǝv���܂��B ���͍���̗p�r�Ɏg�����H���l�b�g�Ō������Ă������[�O�m�_�C�I�[�h�ƌ������i�������܂��������ʓ��肪�o���܂���ł����B http://www.nnp-denshi.co.jp/pdf/xexno_diode.pdf �f�[�^�V�[�g�̃u���b�N�}������Ǝ茳�ɂ������h�q�e3703�ƃf�B�X�N���[�g���i�ōČ��o����̂��ȂƎv���܂������A���̗͗ʂł͖����������̂ŊǗ��l�l�ɑ��k���܂��������ʗǂ����i�ɂ߂��荇�����̂Ŋ��ӂ��Ă��܂��B �n�X�e���C �l
|
||
| ���e |
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/active_rectifier/report.htm ���̕��@�łh�q�e3703�����܂���H ������悢 �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@������悢�l�A���̕��@�Ŏ�������Ă����������������̂ł��ˁB �@�����I�ɂ͂��̕��̏�����Ă���ʂ�AMOS-FET�͗����ɓd���������͂��E�E�E�Ȃ̂ŁA��20���N�قǑO(�̂����c)��FET�̕����������ɂ����������������Ă݂����͂���̂ł����A���̍ۂ̎����ł́u�t�����ł͎v�����ق�ON��R���Ⴍ�͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ʂ��o�܂����B �@�ł�����AMOS-FET�̋t�������p�������I�ɂ͉\�����A���z�I�ȃ_�C�I�[�h�p�r�ł͖����������Ƃ������_�ɒB���Ă��č��Ɏ���܂��B �@�����A30�N�߂��O�̎��Ȃ̂Ŏg����FET(�܂��R���ԍ��ɂȂ������肩�Ȃ�)�ɂ���肪�������̂�������܂���B �@�������Ă���MOS-FET���t�d���ł��\���ɐ������Ɠ������炢ON��R���Ⴍ�Ȃ�Ȃ�g���܂��ˁB �@���̎茳�ɂ�IRF3703�͖����̂Ŏ��ۂɎg����̂���A�g���Ă݂����z�͏����Ȃ��̂ŁA������낵����Ή�����悢�l�̂ق��Ŏ������Ď����f�[�^���n�X�e���C�l�ɋ����č����グ��Ȃǂ�������������܂���ˁB �@���[�X�ɏ����߂ɂ́A���Ƃ���mV�ł����X�͏��Ȃ��ق����ǂ��Ɍ��܂��Ă��܂��B �@�������̉�H�ł͖ړI�d���Ƌt�����̓d����p�ӂ���̂��ʓ|��������A�d�����m��H(OP�A���v)���������Ǝ�Ԃƕ��i����������̂ŁA���ǂ͂���������H���P�̃p�b�P�[�W�Ɏ��܂��Ă���u�N�[���o�C�p�X�X�C�b�`<�v���g���̂��ȒP�ŕ֗��ł���B(����̓d���l�Ȃ�K�i���ł���) �@�t�d���Ȃ̓p�b�P�[�W�i��DC/DC�R���o�[�^�Ȃ��H���Ȃǂň��������Ă��܂����AOP�A���v���FET���Ȃɂ��ƑS�������ƁA���ǂ̓o���őg�ݗ��Ă�ƍ������Ă��܂��܂����B ���Ԏ� 2012/4/21
|
||
| �A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H | |||
|
HDD�h���C�u�����ă��[�^�[�����o���܂����B����������̂ł������̋쓮��H�����ׂăA�i���OIC�ŋ����Ă������������̂ł��B �������ɂ̓n�[�t�u���b�W��H�Ƃ������̂��K�v�Ƃ������ƂŃl�b�g�Œ���Tr2sc1815���U�{�g���u���b�h�{�[�h��ō\�����܂��������܂������܂���BPIC�Ȃǂ͎g���܂���̂Ńp���X�o�́i�����d�������H�j��H��HC04��HC4017B���g���Ă��܂��B ���[�^�[�͎O�����[�^�[�Ƃ������̂��Ǝv���܂��B���[�^�[����S�{�̒[�q���o�Ă��܂��B�TV�{�|�ړ�{�̃��C���ɐ��ɓ��ĂĂ݂�ƃr�N�b�Ɠ����܂��̂ʼn��Ă͂��Ȃ��Ǝv���܂��B ���܂� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@HC04��HC4017B�Ȃǂ̃f�W�^����H�ł��܂������Ȃ�����u�쓮��H�����ׂăA�i���OIC���v�Ƃ������b���ł����E�E�E�B �@�O�����[�^�[�Ȃ�A���ʂ̓f�W�^����H�ŎO���̃p���X������ăh���C�u����̂ł����A������A�i���OIC(�I�y�A���v��R���p���[�^��)�ō��̂͂ƂĂ��ʓ|�ł��ˁB �@�A�i���O�łƂ������˗��ł����A��������̂͂�����Ƒ�ςł����A������e�X�g����O�����[�^�[�̎������킹�������̂ŁA���̂��˗��ɂ͂��������邱�Ƃ��ł��܂���B �@�A�i���O��H�̊�b����w�ׂ鏑�ЂȂǂŕ����āA�A�i���O��������H�Ȃǂ������@���l���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2012/4/13
|
||
| ���e |
�S�����m�ł��݂܂���B�킽���̓f�W�^����H�Ƃ����̂�PIC�̎����Ǝv���Ă���܂����BHC04��HC4017B���f�W�^����H�Ȃ̂ł��ˁB �Ӎ߂��������߁A���ߍēx���₳���Ē����܂��AHC04��HC4017B���g���ĎO�����[�^���������@�������Ē����܂��H ���݁ATr2sc1815�̂U�{��ύX���AMOSFET�iPC��Ղ���̕��i���i�j��3�g���A�h���C�����ɂTVDC�ƎO�����[�^�̃��C�����q���ŁA4017�̃p���X���Q�[�g�Ɍq�܂����B�i4017�͂S���ڂŃN���A����܂��B�j �ł��������܂���B���C��1�iFET��1�ځj��4017�̃p���X������ƃh���C���ƃ\�[�X�ɓd��������A���[�^�[�̃��C��1�ɂ̓}�C�i�X�̐M��������Ă���͂��ŁAFET�Q�ɂ�4017�̃Q�[�g�M�����Ȃ��̂Ńh���C���ɂ̓v���X�M��������āA���[�^���Ƀv���X�M��������Ă���͂��ł��B ���ہALED�ł̃e�X�g�ł�FET�P�ƂQ�̃h���C�����Ƀv���X�A�}�C�i�X���q���ł݂�Ɠ_���A�_�ł��܂��A�ł������[�^�[�ł͓����܂���ł����B���������Ȃ̂ł��傤���B�����Ē�����K���ł��B ���܂� �l
|
||
| ���e |
�����b�ɂȂ�܂��B���̌��Ɋւ��Ă����Ԏ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A�����J�����Ă���悤�Ŋ��ӂ������܂��B 2SC1815�ł͓����Ă��܂���B���������Ȃ�iTr�������邽��Ɓj�s���Ɏv��MOSFET��C144�ȂǕʂ�Tr�ɂău���b�h�{�[�h��ł���ł݂܂��������������܂���B�l�����ł����쓮�͎O�{�ň�{�͒����ׂ̈̐M�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��E�E���̂��Ƃ����ƃ��C���ɒ��ړd���̃v���X�}�C�i�X��t���Ă݂ăr�N�b�Ɠ����Ȃ�����������{����܂����̂ŁA���ۋ쓮�Ɏg�p����͎̂O�{�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B������f�l�̉����ɉ߂��܂��B�B�B HDD�̃��[�^�[�͖{���ɔ������ł��B�g���N�X�̃l�W���]���̖����グ��ꂽ�������̓W�����N�Ƃ��đ��苎��͔̂��ɂ��������Ȃ��ł��B ��������Ƃ�����������������A����A���ɔ��������ẴI�u�W�F�N�g������Ǝv���Ă��܂��B������X�~���肢�������܂��B ���܂� �l
|
||
| ���Ԏ� |
5/6�Ɂu���m�点�v�Ɍf�ڂ�������
�@�e�X�g��H�͂�����̒ʂ����m�|�[���쓮(���j�|�[���쓮)�ŁA74HC14�̔��U��H��74HC4017�ł̏�����H�A������2SK2231�Ń��[�^�[�̎O���ɏ����d���𗬂����̂ł��B �@������Ŏg�p�������̂́u�l�����ł����쓮�͎O�{�ň�{�͒����ׂ̈̐M�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��v�Ƃ������ȕς�����l�������̃��[�^�[�ł͂Ȃ��A�����Ƃ����x�z�����l�����̂��̂ł��B��������[�^�[�������Ǝv�����m�|�[���쓮�ł����͉̂��͂��ł��B �@���Ȃ݂ɁA�n�[�h�f�B�X�N��̋쓮��H�͂��܂��l�̂���]�̃��m�|�[���쓮�ł͂Ȃ��A�����ƈʒu���o���̃o�C�|�[���쓮��H�ł����B�S�{�ڂ̐��̓��[�^�[�쓮�p�ł͂Ȃ��A�ʒu���o�p�̔z���Ƃ��Ďg�p����Ă��܂��B �@�Ȃ̂ŁA���̎茳�̃n�[�h�f�B�X�N�ł́u�l�����ł����쓮�͎O�{�ň�{�͒����ׂ̈̐M�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��v�Ƃ��������Ӗ������ł͓����炸�������炶�ł��B�������u�r�N�b�Ɠ����Ȃ�����������{����܂����v�Ȃ�Ă��Ƃ͖����A�����Ǝl�{�Ƃ����x�z���̌����ʂ��ɐڑ�����Ă��āA�x�z���p�̓d���𗬂����[�^�[�͓����܂��B �@���������ĉ�������ȃ��[�^�[���������ł����H �@�ŁA����̂�����̊j�S�́A���̈ʒu���o�����Ȃ��ŒP���ɎO���d����^���郂�m�|�[���쓮�ł́E�E�E�܂����������͑z���ʂ�ł����B �@�O�����[�^�[�̍\���̒ʂ�A�R�̃R�C���ɏ����d���𗬂��ƁA��]���鎥�͓d�������ꂽ�R�C���ɂЂ�������̂œ����͂��܂��B �@�������A�O�����[�^�[�́u�X�e�b�s���O���[�^�[�v�Ƃ͈Ⴂ�A�e���Ŏ��E��]������~����@�\�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����߁A�������܂��Ď��̑��ȏ�̂Ƃ���܂œ]�����Ă����Ă��܂�����A�s�߂��Ă܂��߂��Ė߂肷���Ă݂���E�E�E�A�����ƂĂ�����Ɂu�O���ɓd���𗬂��Ƃ��̑��̈ʒu�܂ňړ�����v�Ȃ�Ă����悭�{�ɏ����Ă���悤�Ȃ܂��߂ȓ����͂��܂���B �@�ŏ��Ɏ���������Ɂu�����Ȃ��Ȃ��E�E�E�v�Ƃ͎v���A���̍l���ł́u�Ƃ肠�����A�d����ON�����璴�ᑬ�œ������͂��߂āA�������Ǝ��g�����グ�Ă䂯������Ȃ�ɒǏ]���ĉ�]�����オ��A�ꉞ�͉��̂ł͂Ȃ��̂��H�v�Ƃ������@�Ŏn���͂��Ă݂܂������A�����Ɂu�E��(�����͂���)�v���N�����ĉ��Ȃ��Ȃ�A��́u�u�[���v�Ƃ��Ȃ��Ă��邾���ł��B �@�����A�P���ɂ�����x�̍����ʼn����g���̔��U��74HC4017���Ă��邾���̉�H����n�[�h�f�B�X�N�̃��[�^�[�ɋ쓮�d���𗬂���A�c�O�Ȃ��炻�ꂱ���u�u�[���v�Ƃ��Ȃ邾���Ő�ɉ��͂�������܂���B �@��]���O����̎n����H�͎����Ă݂܂������H �@���W�R���p���[�^�[�APC�̗�p�p�t�@���̒��̃��[�^�[�Ȃǂł��ŋ߂͎嗬�ɂȂ�����u���V���X���[�^�[(�O��DC���[�^�[)���ɂ́A���ʂ���]�ʒu���o��H(�z�[���f�q�̂��̂�R�C�����d�����m������̂Ȃ�)����]�ʒu�Ǐ]�^�̋ɐ���ւ���H(�܂�f�W�^����H�ƃn�[�t�u���b�W�~�R��H)���g���āu�u���V(�ɐ���ւ���)�������Ԃ�d�q��H�ŋɐ����ւ��Ă��v���@�ʼn̂���ʓI�ł��B �@����̓��[�^�[�̌��݂̉�]����d�����ł͋C�ɂ��邱�ƂȂ��A�u�O��DC���[�^�[�{��p�쓮��H�v�łP��DC���[�^�[�̂悤�Ɍ��������邵���݂ŁA�d��ON�̉�]���O����n�����āA�^���Ă���d���ƕ��ׂ̏d���ʼn�]�������肷��܂ŁA��]�����ς���Ă���]���ɂǂ̃R�C���ɂǂ̃^�C�~���O�œd���𗬂��̂��������I�ɒ���������̂ł��B �@�ʏ��DC���[�^�[(�u���V����)�́A��]���̉�]�ʒu�ɂ���u���V�E�R�~���e�[�^�[(�����q)���e�R�C���ɓK�ȃ^�C�~���O�œd�����ւ����Ƃ������Ƃ��@�B�I�ɂ���Ă���̂͂����m���Ǝv���܂��B �@���̋@�B�I�ȑ��u�̑�p��S���d�q��H�ł���Ă��܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���\��ςȂ킯�ł��B �@������ň��������܂Ƃ��������H������ăe�X�g���Ă������ł����A�n�[�h�f�B�X�N�̃��[�^�[�ɂ͈ʒu���o�p�̃z�[���f�q���t���Ă��Ȃ����߂ɃR�C���̋N�d�͂����o����ʒu���m��H���K�v�ł��B �@�����Ƃ��킹�Ĉʑ������H�܂ō���ă��[�^�[���������s���̂́A���̎��Ԃ����܂���Ȃ���Ԃł͂قږ����ɋ߂��̂ŁA���̌��͂܂���قǎ��Ԃ̂��鎞�ɂ���Ă݂邱�Ƃɂ��āA����͎����I���Ƃ����Ă��������܂��B >��������Ƃ�������������������A����A���ɔ��������ẴI�u�W�F�N�g������Ǝv���Ă��܂��B �@���[�ƁE�E�E�A������쓮���@�ɂ��Ēm�肽���̂ł���A�����ŕ�������A2SC1815���g���悤�Ȃ��Ƃ������Ă���u���O�����Ēm������A�����Ƃ������̂�����܂����E�E�E�B �@���Ƃ������������Ёw���^DC���[�^�̊�b�E���p�x�Ń��[�^�[�̂����݂Ƌ쓮�ɕK�v�Ȃ��͉̂����H������܂��傤�B �@���Ȃ��������n�[�h�f�B�X�N�̃��[�^�[�Ȃ�u��4�́@�Z���T���XDC���[�^�̋쓮�@�v������ɏڂ����ڂ��Ă��܂��B �@�n�[�h�f�B�X�N�̃��[�^�[�͂��̂��̃Y�o���A�z�[���f�q�Ȃǂ̉�]�ʒu�Z���T�[�̖����u�Z���T���XDC���[�^�[�v�Ȃ̂ł�����B �@���m�ɁA�u�E���v�����ɁA���[�^�[���ɂ͂܂��u��4�́v�̓��e�͎��H�ł���悤�ɂ��āA���̏�Łu���[�^�[�̉�]����ς���v�ɂ͂P�O�́u��3�́v�́uPWM�쓮�ɂ�郂�[�^�����H�̏ȓd�͉��v�Ȃǂ̓��e�Ƒg�ݍ��킹�����[�^�[�쓮��H�������Ȃ�ǂ����̂��ł���͂��ł��B �� ���̖{�͎����Ă��Ȃ��̂ŁA���e�ɂ��Ă͕ۏ����˂܂��B ���Ԏ� 2012/5/12
|
||
| ���e |
�����Ȍ��ؔz������L��������܂��B HDD������o�������[�^�[�ł�������ȃ��[�^�[���ǂ���������܂��� ������̎���͂��Ă���܂���B �v�����^�[������o�������[�^�[�͉��܂����B �������A��]���͏オ�炸�ŏ��͎�ʼnȂ��Ɖ��܂���B �����A�v�����^�[������o�������[�^�[�͔���������܂���B���͂���܂���B H�cD�̃��[�^�[�͔������A���̂܂ܓ����X�J�C�c���[�̖͌^�œW�]��̉�]����C���~�l�[�V�����Ɏg����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂����B ���ʁA�����̂悤�ł��ˁB �Ō�ɁA�����X������Ό��ؒ�������H�������Ē����܂��H ���������Ǝl�{�Ƃ��ɂx�z���̌����ʂ�ɐڑ�����Ă��āA�x�z���p�̓d���𗬂����[�^�[�͓����܂��B ���܂� �l
|
||
| ���Ԏ� |
>������̎���͂��Ă���܂���B �@���āE�E�E�B �@�ŏ��Ƀ��[�^�[�̑f���ׂĂ��Ȃ��̂ł����H �@�����{���Ɂu�O�����[�^�[�v�Ŏl����DC�u���V���X���[�^�[�Ŗ����Ȃ�A���Ȃ��̍ŏ��̃��[�^�[�̌����ĂƉ�H�ł͓����Ȃ��Ǝv���܂���B �@�������A���̍�����e�X�g��H�ł������Ȃ��ł��傤�B �@�{���ɍŏ��̍ŏ��ɂ��̃��[�^�[���������Ƃ��A�d�����q���Ńr�N���Ɠ����̂͂������t�E�u�E�v���̃R�C��(�l�����ƌ����Ă��邩��ɂ��R�����[�q����̌o�H���܂߂ĂS�{�S��)�ɓd��������āA�����̃R�C���̈ʒu�Ɍ����ĉ�]�����r�N�b�ƈړ����Ă�̂��m�F���Ă�̂ł���ˁH �@�R�C����R�͑��肵�Ă݂܂������H �@�l�����x�z�����[�^�[�ł������A���̂P�̃R�C���̒�����R���q�Ƃ���ƁA
�t�|�u�� �� �Q�q,�@�@�t�|Common�� �� �q
�̎������藧�̂ŁA�e�[�q�Ԃ̒�R�l�𑪒肷��Ζ{���Ɏl�����x�z�����[�^�[�ł���̂��A�܂��S�̒[�q�̂ǂꂪ�ǂ�ł���̂��͈�ڗđR�ł��傤�B�u�|�v�� �� �Q�q,�@�@�u�|Common�� �� �q �v�|�t�� �� �Q�q,�@�@�v�|Common�� �� �q >�v�����^�[������o�������[�^�[�͉��܂����B �@�Ƃ������ł�����A�v�����^�[������o�������[�^�[�������������ɂ����Ǝl�����x�z�����[�^�[���Ɗm�F���ĉĂ��Ȃ��Ƃ��������ł���ˁH �@����Ƃ��A�v�����^�̃��[�^�[�ɂ͒[�q�Ɂu�t/�u/�v/�b�v�̃}�[�N�ł��t���Ă����̂ł��傤���B����Ȃ�[�����ł��܂��B �@�����A�v�����^�[�̒��ɂ͂���ȂɃu���u���悤�ȃ��[�^�[�͓����Ă��Ȃ��̂ł́H �@���ʂ͈ʑ�����ʼnȂ�A�w�b�h�⎆����̈ʒu���߂����邽�߂́u�X�e�b�s���O���[�^�[�v�Ȃ�����Ă���Ǝv���̂ł����B �@�܂����̃��[�^�[�͉���Ă���̂ł�����A����ł����̂ł��傤�B �@�u�A�i���O��H�v�Ɓu�f�W�^����H�v�̒�`����������m��Ȃ������Ƃ��Ă��A�d�q��H�̌�����eIC�̑f���𗝉����Ă�����������74HC14��74HC4017���g�����O��������H��v������A�h���C�o���茳��FET���ɕς��Ď����Ă݂邾�����v�Z�p���������̕��Ȃ�A�O�����[�^�[�̒��g��z�����Ĉꉞ�m���߂Ă݂�Ȃǂ͂���قǓ�����Ƃł͖����Ǝv���̂ł����E�E�E�B �@����ł����x�z���̎l�����ł͂Ȃ��A���z���̎O�����ɉ����Z���T�[�p�̂S�{�ڂ̐��H���t���Ă��郂�[�^�[�Ȃ��R�l�̑��肾���ł����ɂ킩��܂���ˁB���z���Ȃ�R�C���Ɍq�����Ă���[�q�̓��z���̌����ʂ�̒�R�l�ɂȂ�͂��ł����B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�@�O��DC���[�^�[(�Z���T�[���X)�Ŏl�����x�z���̕��ł���A���̉�H�œ���e�X�g�͂ł��܂��B �@���ۂɉĂ���l�q�B �@������x�̃X�s�[�h�ɂȂ�������ʂ���E�����܂����A���̒ʂ���E���j�|�[���쓮�ł��x�z���l�������[�^�[�Ȃ�A�n�����x����������Ɠr���ŒE�����Ȃ��悤���ӂ��ăX�s�[�h���グ��A����Ȃ�̑��x�܂ł͂����Ɖ��܂��B ���Ԏ� 2012/5/16
|
||
| ���e |
�����X���炵�܂��B ���܂��l�A �֑��ł����A���W�R����s�@�p�̃u���V���X���[�^�A���v���g���܂��B 3�@���4�����̂g�c�c���[�^���Ă݂܂������A2�@�͓���������N�������ɉ^�]�ł��܂����B ����1�@�����܂Ƃ��ɉ�]���܂���ł����B �R�C���̌����ڂ͂x�����ƃR�����̕��ʂ�4�����Ɍ������̂ł�����R�𑪂�ƈႤ�悤�ł����B �C�ɂȂ����̂ŃR�C���������Ē��ׂ悤�Ǝv�����̂ł����������ׂ������Ōł߂Ă����̂Ő��Ă��܂��悭������܂���ł����B �����܂œǂ�Œ������̂ɔ����ȃI�`�ł��݂܂���B �����\���͕��ʂ̃u���V���X���[�^�������̂ŃR�C���������Ŋ����������疳����]���܂����B �u����u���V���X���[�^�[�v�Ō�������Ƃb�c-�q�n�l�X�s���h�����[�^���������ă��W�R����s�@�ɓ��ڂ��Ă���T�C�g������̂ŎQ�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B (������������g�c�c���[�^�Ƃb�c-�q�n�l���[�^�͓����\���ł���) �����̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B �n�X�e���C �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����܂��E�E�EESC(�A���v)�ɂ̓t���h���C�o�ƈʒu�Z���T�[��H���S�������Ă܂�����˂��i�O�O�G �@�������������q���ʼn̂������ł����A�����ESC���o�����Ă݂Ē��g�����ĉ�������ɖ𗧂Ă�̂������ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2012/5/16
|
||
| ���e |
��H�}��q�����đ����A����ɋ߂������莝���̕��i�ō��܂����B �N���b�N���M�͎��}���A�O�ɍ��������i�𗬗p���܂����B FET ��2SK2231�̃��[�^�[�h���C�u�p�������̂ŁAPC��ՂȂǂ�����O����FDS7764A��FDS6680A���g���܂����B �V���b�g�L�[�o���A��3.�HV�p�����莝���ɂȂ������̂Ŏ�芸�����i�V�Ō������Ă݂܂����B ���͓d���͉�H�p�ƌ��p�Ƃ��܂����B �i���͂Ɖ�H�̋����d����ʂɂ��āA�O�����h�����ʂɂ��Ă��ǂ��̂ł��傤���H���m�䂦�A������ƕ|���Ȃ�܂����̂ŁE�E�j �u�R�C����R�͑��肵�Ă݂܂������H�v �����ď��߂đ��肵�Ă݂܂����B����g�ݍ��킹����10�I�[���A���̑���̐���ʂ��Ƃǂ���V�D�S�I�[���Əo���̂ł��ꂪcommon�ł��鎖������܂����B �����ĖႤ�܂ŃR�C���̒�R�l�𑪒肷�鎖�͉���܂���ł����B ���̏�Ԃ�5V�d�������E�E�E���ʁE�E�m�F�p��LED��t����Ɖ��܂���ł����B �͂�����U,V,W�����Œʓd����ƍŏ��u���u���k���Ă��܂������A�������ƃ{�����[�����Ƃ��鎞�_�ʼn��܂����B�E�E�E�����ł��B�L��������܂����B ���܂� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@3.�HV�p�̃V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�H�H�H �@����E�E�E����ȕ������ł����H �@���������āA3.�HV���c�F�i�[�_�C�I�[�h�Ɗ��Ⴂ���Ă��܂��H �@�V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h�Ȃ畁�ʂ̃V���R���_�C�I�[�h��Vf=0.6V�����Ⴂ�d���Ȃ̂������̂͂��ł����B �@�܂��A����͌q���Ȃ��Ă�FET�����Ȃ�������̂ŁA�����R�ɁB >�O�����h�����ʂɂ��Ă��ǂ��̂ł��傤���H �@����́E�E�E�AGND���q���Ȃ���FET�����삵�Ȃ��ł���H �@GND���q���Ȃ��ŁA�ǂ�����ăQ�[�g�d��(G-S�ԓd��)����������̂��A��x��������ƍl���Ă݂܂��傤�B �@�܂���́A�܂��˂����ݏ��͂���܂����A������̂Ȃ炻��ł悵�Ƃ��܂��傤�B ���Ԏ� 2012/5/17
|
||
| ���e |
���Ⴂ�ł����B�c�F�i�[�_�C�I�[�h�ł����B ���炵�܂����B ���@����́E�E�E�AGND���q���Ȃ���FET�����삵�Ȃ��ł���H GND���Ȃ��Ȃ��Ɠd�C���ʂ�Ȃ��Ƃ����̂͏��w��������������Ă��܂��B ����̎�|�́AFET�̃\�[�X����GND�ƃ��[�^�[���͓d����GND�����ʂɂ��Ă��悢�̂��Ƃ������ł����E�E�B���Ƃ��V�[���h�o�b�e���[�Ȃǂ����H�p�̂TV�p���������A�TV��DC�R���o�[�^�[���烂�[�^�[�֓d�����������悤�Ƃ����ꍇ�AFET�̃\�[�X�̓��[�^�[�d����GND�q���i�����[�̂悤�Ȋ����j�ɂ�������ǂ��̂��A��H�p��GND�Ƀ��[�^�[�p�̓d���̃}�C�i�X���q���ł��ǂ��̂��Ƃ������Ƃł��B ���̎�̎��⎩�̂����w�����ł�������ӂ�Ȃ܂܂����܂Ő����Ă��܂����B �n�X�e���C �l ���肪�Ƃ��������܂����B�T�C�g�����ĎQ�l�ɂ��܂��B (������]) �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@������]�̕��ցB �@���܂��l�Ƃ͂����O���Ⴂ�܂����A�ڑ�AP���g�pPC���Ⴂ�܂�����A�{���ɂ��{�l�l���ԓ�����Ă���̂��m�F���Ƃ�܂���B �@�ł��̂ŁA�_�C�I�[�h�̎�ނ��Ԉ���Ă����Ȃǂ̏��ʂ����Ă��{�l�l�̂��ƂȂ̂��A�ʐl������ɂ��{�l�l�ɂȂ肷�܂��Ĕډ�����Ă���̂����킩��܂���A����͓��e�ɂ��Ă͉������������Ȃ����Ƃ����Ă��������܂��B �@���A���{�l�l�ɘA���ł��B �@�g�����W�X�^��FET�̓���(�����Čq����)�ɂ��Ă̕��ɂ͂ǂ̂���ȏ��Ђ��Ċw�K���܂������H �@�����Ă��̏��Ђł��x�[�X���ƃR���N�^���ɕʁX�̓d�r�E�d���̊G���`���Ă����āA�x�[�X�d���E�R���N�^�d���̗�����ɂ��Đ������Ă���͂��ł��B �@�������������ǂ�ł���AGND�����ʂɂ��Ă����̂��H�Ƃ����^�⎩�̂��قڐ��܂�Ă��Ȃ��͂��Ȃ̂ł����A�ǂ̂悤�ȕ����@���Ƃ��Ă���̂ł��傤���B �@���A����ɂ��Ă͂��������Ă��������K�v�͂���܂���B �@����I�Ȉӌ��̒����ŁA�ԓ��͗v��܂���B �@�������̋^��������ɂ́A�܂��͓��发�������������āA����������b��������ꂽ�ق��������Ǝv���܂��B �@�O���牽�x�������Ă��܂��悤�ɁA�����Ńg�����W�X�^������J������͂���܂���A���₳��Ă��������͒v���܂���B ���Ԏ� 2012/5/20
|
||
| �l�R���������d����H�������ĉ����� | |||
|
�L���r�r�点���H�������ĉ������B ���S�~������ł��O�̃S�~���ɓ���Ă����ƁA��ǔL���L����k��������|���A�S�~�܂�j��A���S�~���U�������A���̓����Ƃ�ł������Ƃ���ɐH���U�炩���Ă���܂��B �߂܂��Ă��d�u�������Ă�肽���̂ł����A�߂܂������͂���܂łɈ�x���Ȃ��A���������ɁA�}�ɑ������ׂ������荘�ɂȂ�����������܂��B �G�A�[�K�����Ă݂悤�Ǝv���܂������ߏ�����ʕ�鋰�������̂ł�߂Ă����܂����B �l���������������A�l�b�g�Ŏg���̂ăJ�������g����������H�Ƃ�����������d�r��{�Ōu�������_�����炢�̓d���������o����Ƃ�������m��܂����B ���ꂪ����C�m�V�V�����Ȃǂ̑傰���ȓd�q�S��Ԃ����Ȃ��ŔL�悯���o����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B �d�r��{�����{���炢�ŁA������H��100�{���g�ȏ�ɏ������A���̉�H�ɐڑ��������̉a��H�炤���Ɋ��d���āA�L���Ђ�����Ԃ�悤�ȉ�H�������ĉ������B �����������ĔL���E���Ȃ��悤�ɂ��肢���܂��B�L�͉����ďo�܂��B �L�ɂƂ��Đg�ɗ]�鋰�|�𖡉�킹�Ă��̂��ړI�ł��B��x�Ƃ��̉Ƃ̉a�͐H��Ȃ��E�E�E�Ƃ����B ��ǕS�� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�u�� AC100V�ȂǁA�����d���̉�H�����v�͎�舵���܂���ƃy�[�W�㕔�̒��ӏ����ŏ����Ă��܂��悤�ɁA���̂悤�ȉ�H�̉�H�}�Ȃǂ͂����ł͂������������Ă���܂���B �@�u�d�q�u�����v��u�d�q�т����蔠�v�Ńl�b�g��������ƁA���d�r1�`2�{��100V�ȏ���������H�}���������݂���܂��B �@�������Q�l�ɁA�������Ă݂Ă��������B �@���ɂ́A�ǂꂭ�炢�̓d����d���Ńl�R�������̂��킩��܂��A�u���i�v�̓d�C�I�\���������ƍ��Ȃ��Ɗ��d�͂��Ȃ��̂ŁA�������������̌������܂߂đ�ςł��ˁB �@����ł́B ���Ԏ� 2012/4/12
|
||
| ���e 4/13 |
���b�N���S�~���ʼn������܂���B toms �l
|
||
| �t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B | |||
|
�ȑO�̎��⎞�ɂ͐e�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B ���č���A�ˑR��ʃ_�E�������t���f�B�X�v���C�i�O�H�j�̏C�������悤�Ǝv�����g���݂ĊY������ꏊ���������̂ł����A���̔����̂̏ڍׂ��c���ł��܂���A�o���܂�����A�h�o�C�X���肢���܂��B �Y�����锼���̂͂Rpin�^�AW:2.9�o�AH:2.5�`2.8�o�At�͑���ł����B������Ղ���͂����Ă͂��܂���A��荇�����m�M�X�ő��肷������܂œ͂����T�����@�ł��B �㑤�ɂPpin�A���ɂQpin�A�e�ɂc�ƃv�����g��ɕ\�L����B �L�ڂ���Ă���L����A1RB�A���̘e�ɍ���90�x��]���ꂽ33�̕\�LA1RB�̕\�L�̏�ɉ��o�[�i�n�C�t���j�̕\�L����B �����Ȃ�ɐF�X���ׂ����ʁApanasonic�i���O�m�j�̃_�C�I�[�h�ŁASC-59A�n��̃c�F�i�[��SBD�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B �ʎ����^�̔����̂ɏ����ꂽ�L�����璆�g�����ʂł���ΏC���ɒe�݂������ȂƎv���Ă��܂��B �]�k�ł����g�p���ɉ����ł��̂ŋ}���ŃP�[�u�����O���A������g��`���ĕό`�����`�b�v����������ł��B ������H�̉�͍͂s���Ă���܂���A�ό`�����`�b�v�����������̂��A���͑��̕��i�����Ă��̕��i���Ă����̂��͂��ꂩ��̉�͂ɂ��܂��B �������[�y���g���ĉ�͂��Ȃ���Ζ����ȋɋ��Ȋ�Ղł��B �����܂ŏo���邩���M���Ȃ��̂ł�����荇�����ό`�����`�b�v���������Ē�������b�L�[���ȂƊÂ����҂����Ă���܂��B ��낵�����肢���܂��B �c�ɂ̃I���W �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@��낵�����肢���܂��E�E�E�Ƃ����܂��Ă��E�E�E�B �@���������SC-59A�ł͖����Ǝv���܂��B �@���̕\�L����͒��ׂĂ��Y�����镔�i�͌�����܂���B �@�_�C�I�[�h�ɂ͊ԈႢ�����Ƃ͎v���܂����A�R�s���^�̃`�b�v�_�C�I�[�h���ƒ��g�̃_�C�I�[�h�̕����Ȃǂʼn���ނ��̃p�^�[��������܂�����A�P���ɂǂ��Ƃ͌����Ȃ����i�ł���ˁB �@��͂�A���ӂ܂őS����H����͂��āA�{���t���Ă���ׂ��������łǂ�ȋK�i�̂��̂��K�v�Ȃ̂��������ׂɂȂ��āA�K�ȕ��i�ƌ������Ă��������B �@������S�z�̂悤�ɁA���̃_�C�I�[�h���̏�̌����ł͂Ȃ��A���̕����ňُ�d��������ă_�C�I�[�h���Ă����Ƃ����p�^�[���̂ق��������Ƃ��Ă͊m���������Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2012/4/11
|
||
| ���e 4/21 |
�A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂��B ��͂薳���ł���ˁB �C�̖����I�[�i�[����͎d�����F�X�Ȕ����̂����Ă���Ǝv���܂��̂ň�ʐl������ł��Ȃ��悤�Ȏ����������������ȂƊÂ����҂����Ă��܂��܂����B ����������d�q��H�ɕt���Ă͏ڂ����Ȃ��̂ʼn�͎͂��Ԃ�������Ǝv���܂����A���̎��͖��A�h�o�C�X�����肢���܂��B �c�ɂ̃I���W �l
|
||
| ��������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ | |||
|
�������q�������Ē�����ϖ��ɂ����Ă��܂��B �X�g���{�����p�R���g���[����f�l�Ȃ��琻�삵�Ă��܂��B �P�O��]�ʼn�闃��NF�̔��M���IC���g���ăg���K�p���X�P�OHz����藃���Î~���Ă����Ԃ͍�鎖���o���Ă��܂��B �܂��A360�x�ɕ������ĔC�ӂ̈ʒu�ɐÎ~�����鎖���o���Ă��܂��BIC��74192,7474���g�p���Ă��܂��B�����ŁA���q�˂ł����A�g���K�[�p���X�̊Ԋu����肩�炷�������x�炷�Ȃ�A���߂ĂĐÎ~���Ă��闃����������]���������̂ł����A�g���K�[ �p���X�����܂��R���g���[���ł�����@��������������Ƃ��肪�����ł��B�܂��ATTL��IC���őg��ł��܂��̂ŁA�n�[�h�I�Ȃ��̂ŏo����ƂȂ����肪�����̂ł����B �V��
�V�� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���݂̂��̂́A���̂O�x�ʒu�����o���āA����������̎��Ԍ�ɃX�g���{�����点�ĔC�ӂ̈ʒu�Ɏ~�܂��Ă���悤�Ɍ����鑕�u�Ȃ̂ł���ˁB �@�����ŁA�u�O�x�ʒu���玞�ԂƋ��ɏ��X�Ƀ^�C�~���O���x���(���܂�)��H�v�Ƃ����̂��f�W�^��IC�ō��ƂȂ�ƁA�P��]���ƂɃJ�E���^�[��i�߂āA���̃J�E���^�[�l�Ԃ�̎��Ԃ��v�����ăX�g���{�������O�x�ʒu����x�点���H�Ƃ��E�E�E���������̂ɂȂ�܂����A���͂��ꂾ�Ƃ�����Ƃ�����肪����܂��B �@���Ƃ́E�E�E�u���J�E���^�[�����Z�b�g����̂��H�v�Ƃ������ŁA�������x�����Ă�������ŏI�I�ɂ͂P��]�Ԃ�̎��Ԃ܂ʼn��тĂ��܂��A�O�x�ʒu���z���Ď��̎���ɓ����Ă��܂��܂��B �@�܂��ʂɐ������炢�Ȃ炻�̂܂܂ł������ł����A���ꂱ��������ł�����x��ɂȂ��Ă������Ɖ���Ă���悤�Ɍ����܂����炻��ł������̂ł����E�E�E�A��͂肢���̓J�E���^�[�̌v�Z�ł��錅�����鎞�ɂO�Ƀ��Z�b�g����܂��B �@���̏u�ԁA�x�����Ԃłǂ����̈ʒu�Ɍ����Ă��������A�r�����ƕʂ̈ʒu�A�܂�O�x�ʒu�ɕς���Ă��܂��̂ł�����ƌ����ڂ���낵���͂���܂���B �@������͂܂��}�V�Ȃ̂́A�u��������������o���ăJ�E���^�[���O�Ƀ��Z�b�g�������v���@���Ƃ邱�ƂŁA���O�ʒu���z���ă^�C�}�[���삪�n�܂��Ă���^�C�}�[���Ԉȓ��Ɏ��̂O�ʒu�M��������Ɓu�P�������I�v�Ɣ��肵�ăJ�E���^�[���O�Ƀ��Z�b�g���A�����̂��̎���̔����M�����o���Ƃ����悤�ȕ��@�ł��B �@���̕��@���ƁA��قǑ�����]�Ɍ�����悤�ȏꍇ�������āA����������Ă���悤�Ɍ������ԂȂ�A���Z�b�g���ꂽ�̂��{���Ɍ�����ʒu���O�x�ʒu�Əd�Ȃ����̂��͖ڂŌ��Ĕ��f�͂ł��Ȃ��ł��傤�B�������ă��Z�b�g�����Ă��قڃJ�N�J�N�͂��܂���B �@���ǁA���ƂɎ��Ԃ������J�E���^�[��H�A���̃J�E���^�[��ǂݍ���Œx�����Ԃ�����f�W�^���^�C�}�[��H����]�X�s�[�h�߂���N���b�N���U��H�A���������������o�����������Z�b�g��H�E�E�E�Ȃǂ�g�ݍ��킹�����̂ɂȂ�܂��B �@���[��A���i�����������Ȃ�ʓ|�ł��B �@�V��l�́u���̉�]�Ɠ������ăg���K�v�Ƃ����Ƃ��납�甭�z���L�����Ă��܂����A�S���ʂ̍l�����ɂ����IC�͂�������ōς݂܂��i�O�O�G �@���̉�]�̓��[�^�[�Ȃǂň��̉�]���ʼn���Ă��āA����͑傫���͕ϓ����Ȃ����̂Ƃ��܂��B �@�Ƃ���ƁA���̗��ɃX�g���{�Ă��������Ɖ�]���Ă���悤�Ɍ������悤�ɂ���ɂ͕��ʂ́u���Ȃ�̌����v�𗘗p���܂��B �@���Ȃ�̌����Ƃ́A�Q�̎��g���̔g����������ƁA���̍��̎��g���́u���Ȃ��v�̔g����Ƃ������̂ŁA�����͊ȒP�� fo �� f1 �| f2
�ƂȂ�܂��B�@�܂�A10Hz�̑��̔g(���̉�])��9Hz(�܂���11Hz)�̑��̔g�̃X�g���{���Ă�ƁA���ʓI�ɂ�1Hz��������]���Ă���悤�Ɍ������Ƃ������ɂȂ�̂ł��B(�����̓X�g���{�̎��g����10Hz����̑召�Ō��܂�܂�) �@�ł�����A����H�͒��J���^���I �@���ɐF�X�ƕ��i���g���ĉ�H������Ă���悤�ł��̂ʼn�H�}�������͕̂s�v�ł��傤�B �@�^�C�}�[IC 555 �������ŁA��10Hz�̔��U��H�����A���̎��g����VR�ł�����Ƃ����������������H���������̂ł��B �@������͉̂����K�v����܂���B �@VR���Ɨ��̉�]����l�q���O�O�[���ƕς��̂Ŗʔ����Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2012/4/11
|
||
| ���e |
�@���Z�������A������L��������܂��B �@�u���̉�]�Ɠ�������g���K�[�v���肪���ɂ���Ȃ�Ƃ��ʑ������炷���@���ƐF�X�ȃf�W�^����H�̖{��������������܂����B �@���b�́A���Ȃ�̌������v�����܂���ł����B �@�����A���g�����������炵�ē��Ă���A�����ɃX���[�Y�ɗ�����]���܂����B �@���������肪�Ƃ��������܂����B�܂��A���̐�����w���X�������肢�������܂��B �V�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����A�e�X�g�������̂������ł��ˁi�O�O�G �@�����Ƃ���������Ă���悤�Ɍ����܂������B �@���̌����́A�e���r��f��̃V�[���ŖڂɌ����Ȃ��قǂ̍����ʼn�]���Ă���͂��̃w���R�v�^�[�̗����A�J�����̎B�e�����Ɠ�������Ƃقڎ~�܂��Ă���悤�Ɍ�����������قǂ������Ɖ�]���Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃ��A����ȑ��u�����Ȃ��Ă���ʉƒ�̊F����ł��������Ƃ����邩������܂���B ���Ԏ� 2012/4/13
|
||
| ����͓����܂����H | |||
|
�u40�`45���œ��삷���H�v�Ɓu100�~�V���b�v�����v�����A�Q���ԃ����v�̐���v�̉�H��g�ݍ��킹�Ă����艷�x�ɒB����ƃX�C�b�`������A���̌�w�艷�x��������������莞�ԃX�C�b�`���z�[���h�����H���ł������Ȃ̂ł����A�Ԉ���ĂȂ����������肢�܂��B �u40�`45���œ��삷���H�v�̌��m�g�����W�X�^��PNP�ɂ��āA�R���N�^��FET�̃Q�[�g�A�R���f���T�A��R��ڑ�����Ηǂ��̂ł��傤���H �߂�ǂ������ł��傤���A��낵�����肢���܂��B ���I�}�C�͂����ԑO�Ɂu�C�̖����v����Ƃ��̓��e�Łu�d�q��H�̕����܂��I�v�Ɛ錾�����̂�����A�y���肹���Ɏ����Ŏv�l���낵�Ȃ����I�Ƃ������ԓ����A���ŁA���v�ł��B �K���ōl���܂��� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���Ԃ��Ǝv���܂��B �@�ǂ������y���݂��������B ���Ԏ� 2012/3/11
|
||
| �ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� | |||
|
���K�V�[�̎����hῃ~���[�̓d�r�쓮���`�b�b�d�������邽�߂ɁA�c�b�|�c�b�R���o�[�^�[���������Ă��Ă��ǂ蒅���A�����ԗp�̌g�я[�d��̉σR���o�[�^�[�����q�������Ē����A���삵�Ă݂܂����B��肭�c�b�R�u�o�͂̃R���o�[�^�[���������āA�����hῃ~���[����肭���삷��̂ł����A�hῃ~���[�̓��쎞�i�R���o�[�^�[�̕����H�j�Ƀm�C�Y���������܂��B �i�r�̉����͎ԗ��{�̂̃I�[�f�B�I�ւ̂e�l����Ȃ̂ł����A��L�̓��쎞�ɎG��������܂��B�d�r�쓮�ł͎G��������Ȃ��̂ŃR���o�[�^�[���쎞�Ǝv���܂��B �hῃ~���[�̕��חe�ʂ͕�����܂��A�ݒu�A�ڑ����@�Ȃǂɖ�肪����̂ł��傤���H ������͈͂ŃR�����g���肢���܂��B MicMori �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���̃m�C�Y�������hῃ~���[�̉�H�̂ق��Ŕ������Ă���̂��ADC/DC�R���o�[�^�̉�H���甭�����Ă���̂��킩��܂��AFM�̎�M���Ƀm�C�Y��������Ƃ������Ƃł��傤���H �@FM��M�����Ă��Ȃ��āACD���Ă��鎞�Ȃǂɂ��I�[�f�B�I�����Ƀm�C�Y���������ĕ�������̂ł��傤���B �@�O�҂�FM���������Ńm�C�Y����������Ȃ�ADC/DC�R���o�[�^�̔��U���g�������܂���FM�d�g�ɉe����^������g���œ����Ă��āA���ꂪ�d�g�Ƃ��ĕ��˂���Ă��鎖�ʼn����Ƀm�C�Y�Ƃ��ĕ������Ă���\��������܂��B �@DC/DC�R���o�[�^�̔��U���g����ς��Ă݂�Ƃ��AMC34063���g�p���Ă���Ȃ甭�U���g���ݒ�p�̃R���f���T�̒l��ς�����������Ă݂�Ɨǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@MC34063�Ȃǂ̓����PFM�Ȃ̂ŁA�d���𑽂������Ă��鎞�Ə��Ȃ����ł͔��U���g�����قȂ�܂��B���铮�쎞�ɂ��傤��FM���W�I�ɉe��������g���ɂȂ�̂��\���Ƃ��čl�����܂��B �@���ɁA�����hῃ~���[��H�ADC/DC�R���o�[�^�̂����ꂩ�ʼn��炩�̔��U���N���Ă��āA�d���̏���d�����p���X��ɏ����Ă��ꂪ�m�C�Y���ƂȂ�AFM�d�g�Ƀm�C�Y����邩�d�����C����ʂ��ă��W�I�Ƀm�C�Y����荞��ł���Ƃ����\��������܂��B �@�܂��A�����hῃ~���[�̐����H��t��(?)���삳�����H�����U���Ƀm�C�Y������悤�ɂȂ��Ă��āA���͊��d�r�Ȃ̂ŎԂƂ͉�H�I�Ɍq�����Ă��Ȃ��̂Ŗ�肪�������x���̃m�C�Y�ł������̂��ADC/DC�R���o�[�^���o�R���ĎԂƐڑ����邱�ƂŃm�C�Y���Ԃɂ܂ʼn���Ă��܂��悤�Ȑڑ����m�����Ă��܂����Ƃ����\�������藧���܂��B �@DC/DC�R���o�[�^�̓d�����Ԃ̓d���Ɛڑ������A�ʂ�12V�o�b�e���[�E�d�r�Ȃǂƌq���œ��삳����ƎԂ�FM���W�I����̓m�C�Y���������Ȃ��Ȃ�悤�ȏꍇ�́A�d�����C���̃m�C�Y����������������\��������܂��B �@����12V�d�r��o�b�e���[�������Ă���ꍇ�̓e�X�g���Ă݂Ă��������B �@�d�����C���̃m�C�Y��ł́ADC/DC�R���o�[�^�̓��͑���o�͑��ɐ���pF�`0.1��F���x�̃Z���~�b�N�R���f���T�����Ă݂�Ƃ��A���͑��Ƀm�C�Y���p�̃R�������[�h�`���[�N�R�C�������Ă݂�Ƃ��̎��������Ă݂Ă��������B �@�ق��ɁADC/DC�R���o�[�^�̏o�͕����p�d���R���f���T�̗e�ʕs�����i���ő�o�͎��ɓd�����s����ɂȂ肻�ꂪ�m�C�Y�Ƃ��ēd�����C������`���悤�Ȏ�������܂�����A�o�͕����d���R���f���T��1000�`4700��F���x�̑傫�Ȃ��̂ŁA��C���s�[�_���X�^(��ESR�^)�̂��̂����Ă݂�Ȃǂ��d���̐��\�A�b�v�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2012/3/10
|
||
| ���e |
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B �A�h�o�C�X�Ɋ�Â��e�X�g���Ă݂܂����B �ԗ��̂b�c�v���[���[�Ȃǂł͉����Ƀm�C�Y�͓���܂���B �`�l���W�I�ł������ł����B �e�l�̂V�U�D�W�l�g���`���悭�g���A�i�r�̂e�l����͂V�V�D�V�l�g�����g�p���Ă��ĂX�O�l�g����ł��m�C�Y������܂��B �i�r�̂e�l�o�͎��g���ݒ�͂V�U�D�O�`�V�W�D�S�l�g���܂ł͈̔͂ł����ݒ�o���Ȃ��̂ł����A�V�U�D�O�l�g�����ƃm�C�Y�̓��肪���Ȃ��Ȃ�܂����B�i�r�̎g�p�͓��ʂV�U�D�O�l�g����ݒ肵�܂����A�e�l���������܂ɕ����̂ŁA���삵���R���o�[�^�̔��U���g����ς���Ȃǂ̕K�v������l�ł��B �A�h�o�C�X�ɏ]���e�X�g���Ă݂܂��B MicMori �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���̗l�q���ƁA��͂�d�g�̂ق��Ƀm�C�Y������Ă��܂��ˁB �@�����pIC�܂���������̂Ɠ����ɁA�ꉞ�͓d���܂��̃m�C�Y���p�R���f���T�̒lj��Ȃǂ̎����Ă݂Ă��������B �@������������Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2012/3/13
|
||
| 10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H | |||
|
�F�X�Ȏ���ɓ����Ă����������肪�Ƃ��������܂��B�̒��ɐԊO���ɔ������閾����Z���T�[�̌��͌������̂ł����A�ԊO���ł͂Ȃ��ԐFLED���_�������Ƃ��Ƀ����[���쓮�����閾����Z���T�[�̉�H�������Ă������������������܂��B�ԐF��LED���_�������甽�����ău�U�[���Ȃ炵�����Ă������̂���肽���̂ł��BLED�܂ł̋�����10�����ȓ��ɃZ���T�[��u�����肪���邭�Ă��ԐF�݂̂ɔ���������́B�d���͓d�r2�{3V�ō쓮�B��낵�����肢���܂��B ��� �l
�� ���͂��ꂽ���[���A�h���X�ł̓G���[�ƂȂ胁�[�������͂��ł��܂���ł����̂ŁA�����[���̖��O�F�Ƃ����Ă��������܂����B |
|||
| ���Ԏ� |
�@�ŋ߁E�E�E3V�ŃZ���T�[�Ƃ��A1.5V�Ń��[�^�[�̉�]������Ƃ��A�����Șb�������ė���l�������܂����ˁB �@�����ǂ����ŗ��s���Ă���̂ł��傤���H �@���ʁE�E�E�܂Ƃ��ȃZ���T�[��H�����ɂ̓I�y�A���v��e��Z���T�[IC�����g���A������3V�ł͓����Ȃ��̂ł����A���������̂�3V�œ����������Ƃ������ȃg�����h���Ƃł����ɂ���̂�������܂���B �@�ŁA�S�R�p�r�������Ă��Ȃ��̂Ŏ���ł��B �@10cm�܂ł̋������āA����͍ő��10cm���ꂽ���ɐԐFLED�ƌ��Z���T�[��Ό����Đݒu����Ƃ����Ӗ��ł����H �@�܂�������0cm(�قږ���)����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�K���Ԃɋ�Ԃ�u���āA����Ō����Ă��邩�ǂ����ׂ鑕�u�H �@���܂łɍڂ��Ă���悤�ȁu�Ԃɉ������Ղ�ƁA�����Ă��Ȃ��v�Ɣ��f����悤���ʉ߃Z���T�[�������ł���ˁH �@�����ԊO���ł͂Ȃ������̐ԐFLED�ō�肽���Ƃ�������]���ƂƂ炦�Ă�낵���ł����B �@�܂����Ƃ͎v���܂����A�����̑��u�̃p�C���b�g�����v���ԐFLED�ŁA���ꂪ�_�����Ă��邩�������Ă��邩�����ꂽ�������璲�ׂ����Ȃ�Ă��Ȃ薳���Ȃ���]�ł͖����ł���ˁB������3V�ŁB �@�p�C���b�g�����v�̓_���ׂ�ɂ��Ă��A���̃p�C���b�g�����v�������P�x�ԐFLED���炢���g�p���Ă���Ă��āA�ő�10cm���炢�̋����ɒu�����Z���T�[�����\���ɐԐF�ɏƂ炵�o�������̌��ʂ��o�Ă�����̂ł��傤���B �@�{���ɁE�E�E�܂����Â��|�b�ƌ�����x�̕\���p��LED���_�����Ă��邩�ǂ������A�܂�肪���邢�̂ɍő�10cm���̋����Ō��m�������Ƃ��E�E�E���������������ł͖������Ƃ��F���Ă��܂��B �@�����ɖ���������̂ł���A���肪���邭�Ă��A3V�d���ł�����قǓ���͖����ł��傤���ǁE�E�B�p�r���s���Ȃ̂ʼn�����̓I�ȉ�H�͍l�����܂���B ���Ԏ� 2012/3/9
|
||
| ���e |
�A�����x���Ȃ肷�݂܂���B���w�E�̒ʂ�ł��i�����̑��u�̃p�C���b�g�����v���ԐFLED�ŁA���ꂪ�_�����Ă��邩�������Ă��邩�𗣂ꂽ�������璲�ׂ����B�܂����Â��|�b�ƌ�����x�̕\���p��LED���_�����Ă��邩�ǂ������A�܂�肪���邢�̂ɍő�10cm���̋����Ō��m�������B�j�d���͏������܂��̂�3V�������ł�����\�ȓd���ŁB�\�������܂����̂قǂ��肢���܂��B ��� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���������p�C���b�g�����v�̌�(���Ƃ������A�{���Ɍ����ĐF���ς�������ǂ������x�̔��ׂȕω�)�𗣂ꂽ�Ƃ��납�猟�m����ɂ́A��H�̐v�����Z���T�[�̌��w�n�̐v�ƍH��̂ق��������ւ�ɂȂ�܂��B �@�����Y�őΏە��ɏœ_�����킹�āA�Z���T�[���̒��̌��Z���T�[�ɑ���������ȂǁA�ʐ^�@�Ȃǂ̌����Łu10cm���x��܂ł̑Ώە����B�e����J�����v������肢���������ƂɂȂ�Ǝv���܂����A���̂�����̐v��H��͑��v�ł����H �@�������ɓd�q��H�ɂ͂�����Ȃ��̂ŁA�����Ń����Y�̎�ނ�ȗ�(?)�Ȃǂɂ��Ă͐v�����������ł��܂���̂ŁA���̕������������łȂ�Ƃ��Ȃ�Ȃ�A�ԐF�������o����ON��OFF���f�����H�E�E�E���炢�Ȃ�ł��܂��B �@�A���A���̉�H�}���������Ƃ����āA������ō������w�n�̐v�ł����Ɠ��삷��̂��ȂǁA�s�m��v�f�������̂ʼnʂ����Ă��܂��䂭���ǂ����E�E�E�B �@�����������ł�����A�����u�܂����E�E�E�v�Ǝv�����Ƃ���A�P���ɉ�H�}���������Ċ������邤��Ȃ��̂ł͖����̂ŁA�����ւ�\�������܂������ł͉�H�}�Ȃǂ��������Ƃ��ł��܂����B �@�{���ɁA�d�q��H���ǂ��Ƃ��������A���������p�C���b�g�����v���炢�̌��𗣂ꂽ�Ƃ��납�猟�m������āA�摜��͂̕���ł���ˁE�E�E�B �@���Ȃ�@�ނ������Ȃ��Ă��܂�����A���Ẫm�[�g�p�\�R����USB�J�����ł������āA�v���O���~���O�Ƀ`�������W����Ă݂Ă͂������ł����H �@USB�J�����ł��̋@������A���^�C���ŎB�e���āA�摜���̓���̏ꏊ�����[�U�[���w�肵�Ă��A���̃|�C���g�̉�f(����f�̕��ρH)���Ԃ����Ԃ��Ȃ�����RGB�l����ǂݎ���Ĕ���ł��܂��B �@����Ȃ�A�P��1�`2���~���炢�̈����ȍޗ��ŊȒP�ȉ摜���ʃV�X�e�����ł��܂���B �@�̂͐��\���~���炢�����Ȃ��Ƃł��Ȃ��������̂��A�Ȃ�Ƃ���y�ɁI(��) �@�������ło�b�v���O�����̐��E�Ƀ`�������W����Ƃ�������ɂ��Ȃ��āA�ʔ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2012/3/13
|
||
| ���e 3/13 |
���肪�Ƃ��������܂����B������߂܂��B ��� �l
|
||
| �֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I | |||
|
���߂ē��e�����Ē����܂��B��낵�����肢���܂��B ���Ɍf�ڂ���Ă���u�ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵�����v�̉�H�łe�^�u�ϊ���̓d���͈͂��O�`�R�u�Őv����Ă��܂����O�`�T�u�ɂ���ɂ͉�H�̂ǂ����ǂ̗l�ɕύX������悢�����������Ȃ��ł��傤���H�I�y�A���v�̌�i�ɐڑ�����Ă���k�d�c�o�[���[�^�[�͎g�킸�A�`�^�c�ϊ����Ďg�������Ǝv���܂��B �ȏ��낵�����肢���܂��B �����݂� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁE�E�E�ߋ����O�y�[�W��
�Ƃ����B���h���Ă���̂ł����A�E�E�E�E���������Ă��Ȃ��̂��g���̃p�\�R���E�[���ł͂��̕��͂��\������Ă��Ȃ��̂ł��傤���H �@������ł͂킴�킴�ߋ����O�̉�H��������x�g�ݗ��ĂẮu�ύX�̂��˗��̎��n���v�͍s����������܂��A���̂��߉�H�}�̒E���i�̕ύX�̒Ȃǂ͂������܂���B �@������Őv�ł���悤�P�����q���g���B �@F/V�ϊ��̐ϕ���H�͔��]������p�Ȃ̂ŁA�����o�͂����邽�߂̍���������H���x�P�Őv���Ă��܂�����A�����3V��5V�ɂȂ�悤�ȑ����x�Őv����Ă݂Ă͂������ł��傤���B �@LM358�̂悤�Ƀw�b�h���[����1.5V������悤�ȃI�y�A���v�ł͂Ȃ��A�t���X�C���O�^�C�v���g�p���Ă���̂ʼn�H�}��啝�ɕς����肹���Ƃ��\�Ȃ͂��ł��B ���Ԏ� 2012/3/4
|
||
| AC�A�_�v�^�[���������܂��� | |||
|
AC�A�_�v�^�[�����ăe�X�^�[�̃��[�h�ĂĂ݂��畔�i���������܂����B100V�̕����ɕЕ��̃��[�h�Ă������ŃV���[�g�����Ă͖����Ǝv���̂ł����A�����ԈႦ�܂����ł��傤���H�ǂ����������������܂��B �������� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�܂����ʂɍl���āA�e�X�g���[�h����{�����ǂ����ɓ��Ă������ŕ��i����������悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B �@�\���Ƃ��ẮA�������ł͈�ӏ��ɓ��Ă�����ł��A���[�h�̐悪�Y���ĂQ�ӏ����V���[�g���A�ُ�ȓd�������ꂽ�Ƃ���̕��i���j���̂ł��傤�B �@�������茳�ɖ����̂Ō��Ċm���߂�킯�ɂ��䂫�܂���A����ȏ�͏ڂ����ǂ����V���[�g�����̂łǂ���ꂽ���̔��f�␄���͑S���ł��܂���B �@��ꂽAC�A�_�v�^�[���g�����X���Ȃ̂��A�X�C�b�`���O�d�����Ȃ̂��ł��̏Ⴓ���������Ɖ�ꂽ���i�͂��Ȃ�ς���Ă���Ǝv���܂����A�e�X�g���[�h�Ă����Ɉُ�d�������ꂽ�Ղ��c���Ă��Ȃ������悭���ׁA����AC�A�_�v�^�[�̉�H�}�������ĉ�ꂽ���i���j������悤�ȓd���̗��ꂪ���ă~�X���N�������ꏊ�����ꂽ���i�ɗ���邩���悭�����Ă݂Ă��������B(�����������m�肽����E�E�E�ł�����) �@���ʂ͋@��̃`�F�b�N�����鎞�ɂ̓e�X�^�[�̃��[�h(�e�X�g�_)�͂Q�{����Ɏ����đ���ӏ��ɉ������Ă܂����A���̎��Ɏ�悪��������A�������Ă����ɔ푪�葤(��Ȃ�)�������Ă��܂��ė\��O�̕����ɂ��G��Ă��܂����Ƃ͂悭����܂��B  �@�������������������悤�A���Ȃǂ̓e�X�^�[�_����Ŏ����Ē��ړ��Ă�Ƃ������Ƃ͂����A�E�̂悤�Ȑ悪�uIC�N���b�v�v�u�~�m���V�N���b�v�v�ɂȂ����Œ肵�Ă�����e�X�g���[�h��A�d���v���v���[�u�Ȃǂ��ꂼ�ꑪ�肷�鑊���V�[���ɂ��킹�Ďg�������������đ�������܂��B
�@�������������������悤�A���Ȃǂ̓e�X�^�[�_����Ŏ����Ē��ړ��Ă�Ƃ������Ƃ͂����A�E�̂悤�Ȑ悪�uIC�N���b�v�v�u�~�m���V�N���b�v�v�ɂȂ����Œ肵�Ă�����e�X�g���[�h��A�d���v���v���[�u�Ȃǂ��ꂼ�ꑪ�肷�鑊���V�[���ɂ��킹�Ďg�������������đ�������܂��B�@�قƂ�ǂ̏ꍇ���e�X�^�[�Ȃǂ̑����𐔑�Ȃ��ő�����s���̂ŁA�Q�{�̎�ł͂ƂĂ�����Ȃ��Ƃ����̂��傫�ȗ��R�ł�����܂����B �@�ʐ^�̂悤�Ȏ���e�X�g���[�h�ȊO�ł��A�ڂ����v���⎞�Ԃ̗���ł̏�Ԃ̕ω��Ȃǂ𑪒肷��ꍇ�A�푪��|�C���g�Ƀe�X�g�p�Ƀ��[�h�����n���_�Â����āA���[�h���̐���ق��̕����ƃV���[�g���Ȃ��悤�ȌŒ�{�[�h�ɌŒ肵�A���̐�Ƀe�X�^�[��I�V���X�R�[�v�̃v���[�u��ڑ�����悤�ɂ��āA�@��̃e�X�g�E���\�����Ȃǂ��s���Ă��܂��B �@�e�X�^�[������܂��W���ŕt���Ă���e�X�g�_�̐���āA���̕\�ʎ������i���炯�̋ɏ��z���v�����g��Ȃǂł͖_�������ėׂ̃p�^�[����G���ăV���[�g�����Ă��܂��Ȃ�Ă����U���ɋN���Ă��܂��܂����A�����������l�����Ă�ꂽ�悤��AC100V�̃p�^�[���Ȃǂ́A�����V���[�g�������d��������đ�ςȂ��ƂɂȂ��悤�Ȃ��Ƃ��z��ł��܂�����A���܂���ƂŃe�X�g�_�Ă�悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ق������S���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2012/3/2
|
||
| ���e 3/4 |
���肪�Ƃ��������܂����B AC100V�ɂ͐G��Ă͂����Ȃ����̐�������ƕ������̂ŊW���邩�ƕs���ł������A�����茳�������ăV���[�g�������̂ł��ˁB ����̓~�m���V�N���b�v�Ȃǎg���Ď��s���Ȃ��l�ɋC�����܂��B �������� �l
|
||
| �X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H | |||
|
���Z�������������܂��B�d�C��H�͏��S�҂ł��B ���o�ł����炷�݂܂���B �|�P�b�g���W�I�Ȃǂɂ��Ă���X�C�b�`�t���{�����[���� �g���Ă��邤���ɐڐG�������Ȃ�₷���̂��o���o������������ ������ƉƋ}�ɉ����傫���Ȃ����肵�Ă��܂��܂��B ���̓x�Ƀ��W�I�����ăp�[�c���Ă��܂��B �X�C�b�`�ƃ{�����[�������ēƗ����������̂ł����A���������������������L����q���������Ƃ�����܂���B�ȒP�ɏo�������Ɏv���̂ł�����H��ǂ��������ɔz�u������ǂ��̂��킩��܂���B�����ǂ��Ⴊ����܂����狳���Ă��������B��낵�����肢���܂��B �R�b�y��3�� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����������L�����������Ƃ������E�E�E�Ƃ̎��ł����A�������������L���͐��̒��ɂ͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�����āA�Ȃ�̂��߂ɋL��������̂��A�������������������l�������Ƃ��Ă�(���̒��ɂ͑吨����ł��傤����)�킴�킴�L����u���O�ɍڂ���悤�Ȃ���������Ƃł��Ȃ�ł��Ȃ�����ł��ˁB �@�u�X�C�b�`�t���{�����[���v�́A���X�͕ʁX�̕��i�ł���u�X�C�b�`�v�Ɓu�{�����[���v���X��E�g�����ɂ���Ă͎g���₷��������̉������������̕��i�ł���ˁB �@���W�I�Ȃ�A�u���ʂ�������������d�������ƃc�}�~���P�ōςނ̂ŕ֗��v�Ƃ������R����X�C�b�`�t���{�����[���ɂ���ꍇ�������ł��B �@�̂̃e���r�Ȃǂ������ł������A�ŋ߂̍l�����ł͓d���X�C�b�`�ƃ{�����[���͕ʁX�ɓƗ����Ă���ق����u���ʂ̐ݒ�͑O�Ɍ��߂��l�̂܂܂̂ق����֗��v�Ƃ����l�����ɃV�t�g���Ă��܂��B 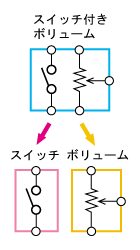 �@���X�͕ʁX�́u�X�C�b�`�v�Ɓu�{�����[���v�̂Q�̕��i�����̂����������́u�X�C�b�`�t���{�����[���v�ł�����A�ʂɂ��ꂼ��ʁX�́u�X�C�b�`�v�Ɓu�{�����[���v�̃o���̕��i�ɒu�������Ă����ʂ͉��̖�������܂���B
�@���X�͕ʁX�́u�X�C�b�`�v�Ɓu�{�����[���v�̂Q�̕��i�����̂����������́u�X�C�b�`�t���{�����[���v�ł�����A�ʂɂ��ꂼ��ʁX�́u�X�C�b�`�v�Ɓu�{�����[���v�̃o���̕��i�ɒu�������Ă����ʂ͉��̖�������܂���B�@��H�̐v��̖��œd�C�I�Ɂu�d����ON/OFF����ۂɂ̓{�����[���ʒu���K���O�łȂ��ƁA���u���̏Ⴕ���范��������Ől�ɊQ��^�����v�Ƃ����悤�Ȋ댯�ɍۂ��Ă����S���u�Ƃ��ăX�C�b�`�t���{�����[�����g���ꍇ������܂����A���W�I�Ȃ�u�X�C�b�`����ꂽ���Ƀ{�����[�����ő�ɂȂ��Ă��āA�傫�ȉ����o�Ăт����肷���v���x�̔�Q�ł��傤����A�X�C�b�`�ƃ{�����[����ʁX�ɂ��Ă�����قǂ̏�Q�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �� ��o�͂̃p���[�A���v���ł́A�X�s�[�J�[��j�Ă��܂����Ƃ�����܂� �@�����������Q�̖����@��ł�����A�ǂ��������R�ɃX�C�b�`�E�{�����[���̕ʁX�̕��i�Ɋ����Ă��������Ă��A�ʂɗǂ��Ǝv���܂��B �@�����m���Ƃ͎v���܂����A�u�{�����[���v�ɂ͉�]�p�x�ɉ����ĕω������R�l�̊������`�J�[�u�^�a�J�[�u�^�b�J�[�u�̂R��ނ̃^�C�v������܂��B �@���ʗp�{�����[���Ȃ炽���Ă��͂`�J�[�u�ł��傤����A�Ԉ�킸�ɓ�����R�l�ƃJ�[�v�̃^�C�v�̕i�ƌ�������A���̒ʂ�ɓ��삵�܂��B ���Ԏ� 2012/2/25
|
||
| ���e |
�����̂����肪�Ƃ��������܂����B �������āA�Ȃ�̂��߂ɋL��������̂��A�i�����j�킴�킴�L����u���O�ɍڂ���悤�Ȃ���������Ƃł��Ȃ�ł��Ȃ�����ł��ˁB ���͌����Ăӂ������C�����Ŏ��₵���̂ł͂���܂���B �u���O��l�́u���S�҂̂����ɂ悭�����������ӂ��������Ƃ��Ă���B�{�P�I�J�X�I�v�ƌ����Ă���悤�ȕ��͂ɂ͐����߂����Ȃ�܂����B���Z�������ɂ���Ȃ�����Ȃ���������ꂽ�̂ł����瑽�����ɗ����̂�������܂��A�p�����̂�Ŏ��₵���̂ł�������������D�������t�ł����Ăق��������ł��B �@���L����SONY��ICF-SW11�̓X�C�b�`�ƃ{�����[�����ʁX��12�N�O�ɍw�����܂������A�����Ƀo���o������ڐG�s�ǂ��N�����Ă��܂���B�ŋߔ������|�P�b�g���W�I�i�x�ߐ��j�͂R�������炸�ł����o���o�����ɔY�܂���Ă��܂��B �R�b�y��3�� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���C�����Q����Ă���悤�ł����A���͎���ɃX�g���[�g�ɂ��������������ł��B �@�����������L�����������Ƃ������E�E�E�Ƃ��������ɑ��āA����͂����ł���A�����ā������Ƃ������R�ł�����B�Ƃ����̉Ɠ����悤�ɗ��R�����������Ă��܂��B �@���̎���Ɖ�ǂ܂�Ă��Ȃ��̂ł��傤���B���������ԓ������Ă���͂�������܂���B �@�̓��e�Ɋւ��ẮA���₳��Ă���̂ł���Ɏ���������������̂������ł̎��̃X�^���X�ł��B �@����ŁA�����P�̎���B�ȒP�ɏo�������Ɏv���̂ł����E�E�E�ɑ��Ă͐}�܂œY���Ă��������Ă���̂ł����A����ł����s���Ƃ������ł��ˁB �@���̎茳�ɂ���X�C�b�`�t���{�����[�����g���Ă��鉹���@��ł͏��a�̐��i�ł��K�������Ă��Ȃ��������ʂɂ���܂����A���������������I�[�f�B�I�̃��C���{�����[�����K�����Ă镨������܂��B �@�u�X�C�b�`�t���{�����[��������A�i���������v�Ȃ�āA�X�C�b�`�t�����Ƃǂ̂悤�ȗ��R�ŕi���������Ȃ�̂��A�d�C�̃v���łȂ��Ă��\���╨�̍��ɂ��čl����X�C�b�`�̗L���ŕi�����ς��Ƃ͍l����Ƃ����̂͂ǂȂ��ł������邱�Ƃł��傤�B �@�X�C�b�`�t���{�����[���ł��A����\�~�̕�������1000�~�ȏシ��悤�ȕ��܂ŁA�O���[�h���Ⴄ���̂�������ł�����܂��B �@�����Ȃ�i���͂���Ȃ�őϋv���������A��������20�`30�N�o���Ă��قƂ�Ǘ��Ȃ��i������܂��B �@���Ȃ��������Ă����Ɉ����Ȃ����Ƃ������i�ɂ́A�������������őϋv���̗ǂ����i���g���Ă���̂ł��傤���H �@�������ŁE�E�E���āA�������Ɍ����̈�[�͕������Ă邶�Ⴀ��܂��B �@�������ăp�[�c�����悤�Ȏ��܂łł�������Ƃ������āA���ꂭ�炢�������Ȃ炲�����̖ڂŌ��ĕ��̗ǂ������A���̗ǂ������͔F���ł��Ă���Ǝv���Ă����̂ł����E�E�E�B �@�u���S�҂͉������Ă��A���������Ă��������B��җD��Љ�v�Ǝv���Ă���̂ł����Ă�A�ǂ���Yahoo�m�b�܂�����Ŏ�������Ă��������B ���Ԏ� 2012/2/27
|
||
| 1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H | |||
|
���[�^���̃��[���b�g�̉�H���킩��܂���B �͂��߂܂��āA��낵�����肢�������܂��B���[���b�g���e�`�|�P�R�O�ŃX���[�X�^�[�g�������̂ł����A��H���킩��܂���B�d���̓G�l���[�v�i�P�D�Q�u�j�P�{�ʼn����{�^�����������ςȂ��łR�`�T�b��ɑS����]�ɂȂ艟���{�^���𗣂����Ƃ��ɂ����ɒ�~�����H�ł��B�i��~���͂��͂łȂ߂炩�Ɏ~�܂�\��j�ǂ����A���͂����݂����������܂��I �`�j�a �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����ł��B �@�d�����d�r��{�ł́A�g�����W�X�^�ɂ��d��������H���炢�����ł��܂��A����ł������X�ɓd���𑝂₷��H����ꂽ�Ƃ��Ă��ADC���[�^�[�ɂ͓d�������X�ɏグ�Ă�������̂Ƃ���ŋ}�ɉ�肾������������̂ŁA�K�N���Ɖ��͂��߂邾���ł�������������悤�ȓ����ɂ͂Ȃ�܂����B �@�d���d����5V���x�͂���APWM�����ł̉�]�������\�ɂȂ�̂ŁA�������z������Ă���悤�ȁu�������ƃ��[���b�g�����͂��߁A���Ă���Ԃɉ������čō����x�ɒB����v�Ƃ����ʔ�����]�������ł���̂ł����E�E�E�B �@�܂����d�r��{��1.5V���x�̓d���ŁA�ׂ��ȉ�]�����X���[�Y�ȉ����E�����Ȃǂ̌����ڂ��ǂ��悤�ȉ�H�͓d�q��H�̌�����DC���[�^�[�̐�������͖������Ƃ��l�����������B �@���d�r����@�́A�c�}�~���Ă�����x�̃X�s�[�h�R���g���[�����ł���E�E�E���炢�Ȃ�1.5V�ł��ł��܂��ˁB �@�܂��E�E�E���������čl����A���d�r��{����DC/DC�R���o�[�^���g���ď������ēd����5V���x�ɂ��āAPWM��H�����Ƃ��E�E�E�E�B���������ʓ|�Ȃ��̂ł������̂�����H ���Ԏ� 2012/2/25
|
||
| ���e |
���A���肪�Ƃ��������܂��I LED�ŏ��X�ɖ��邭�Ȃ��H���������Ƃ�����̂Ń��[�^�[�ł��A�������Ƃ��ł���Ǝv������ł��܂����B ���ɂȂ�܂����B ���Ԏ��ɂ���܂����A�c�}�~���Ă�����x�̃X�s�[�h�R���g���[���̉�H�������Ă��������B �d���́A�P�D�Q�u�ŁA�Ȃ�ׂ����i�����Ȃ߂ł��˂������܂��B �i�c�}�~���̃��[���b�g�ɕύX�\��ł��j ��낵�����肢�������܂��B akb �l
|
||
| ���e |
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��I �����𓊍e���܂������A���e����Ă��Ȃ������݂����Ȃ̂ł�����x���e���܂��B �P�D�Q�u�̓d���Ń��[�^�[�̉�]���R���g���[�����邱�Ƃ͓�����Ƃ͗������܂����B �P�D�Q�u�Ńc�}�~���Ă�����x�̃X�s�[�h�R���g���[���ł���ȒP�ȉ�H�������Ă���������Ƃ��肪�����ł��B ��낵�����肢�������܂��I AKB �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�Ȃ����e�ł��Ȃ������Ɣ��f�ł����̂���ł����A���Ȃ�G�X�p�[�\�͂̂�����̕��Ȃ̂�������܂���B �@�������[�^�[�̓d������ł͎g�����[�^�[�ɂ���ē����̓o���o���Ȃ̂ŁA������ƒv���܂��Ă͎茳�ɖ���FA-130���[�^�[���w�����Ď��n�œ����ɂ��킹��K�v���L��킯�ŁA���[�^�[���ɂ䂭��Ԃ┃���ɂ䂭�ɂȎ��Ԃ�������̂���ςȂ̂ł����A����������Ԃ������Ă���Ƃ����̂����̓����G�X�p�[�\�͂Ō�������Ă���̂ł���ˁB �@���e���ꂽ�ۂɂ́u��H�}��K�v�Ƃ���ԓ��ɂ́A���Ԃ�������v�Ƃ�����������\�����Ă��܂����A����ł��G�X�p�[�\�͂ŐF�X�ƌ�������Ă���ƁE�E�E�B 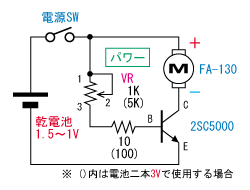 �@��H�}�͒��܂��̂ŁA���[�^�[���ǂ̂���ȋ����������̂���A�u������x�̋@�\�ł̓��[���b�g�Ƃ��Ă͂ǂ���H�v�Ƃ����悤�ȓ_�ɂ́A�G�X�p�[�\�͂ŗ������Ă��������B ���Ԏ� 2012/3/1
|
||
| ���e 3/4 |
�킴�킴�A���n�܂ł��Ă����������̂ł����I ���肪�Ƃ��������܂����B �u�q�̕ӂ���������Ȃ�ɉ������ĉ��Ƃ��͈͂̋����R���g���[���Ŋ������܂����B ���ӂł��I�܂���낵�����肢�������܂��B AKB �l
|
||
| 2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H | |||
|
�u���ȓd�������A�I�[�g�J�b�g�d���ρ@�j�b�P�����f�[�d�r�E�P�Z�����d��̐����v��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���B�ǂ�ȗ��R�ł��傤���B �m�������Ȃ��Ă��݂܂���B 2SC(D)���ƁA�ϒ�R���番������ăx�[�X�ɗ���āA�����悤�Ɏ��ȕێ��������Ȋ��������܂����B �͂��悤�����낤 �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�����ւ�\�������܂��A���d��̋L���ŏ����܂����悤�ɂ����Łu�g�����W�X�^����v�̂悤�ȃg�����W�X�^�̎g�����u�����������͑S������܂���̂ŁA�g�����W�X�^�����g���̉�H��v������@��ڂ������l�v�ɂ��܂��Ă͂������ł����˂܂��B �@���̏�ŁE�E�E�������ʼn����ł���悤�ɂ���q���g�����B �@2SA/B�^�C�v��PNP�g�����W�X�^��2SC/D�^�C�v��NPN�g�����W�X�^���ɐ����t�Ȃ̂ŁA���̂܂ܒu�������Ă��d���͗���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂���������Ă����ł̂��̔��z�ł��傤���H �@����Ƃ��E�E�E���ꂭ�炢�̒���{�͓��R�̎��Ƃ��Ă���������Ă��āA���������g�����W�X�^�̋ɐ����t�ɐڑ��������E�E�E�Ƃ������z�H �@���̏ꍇ��2SC/D�^�C�v���G�~�b�^�t�H�����ł̎g�p�ƂȂ�̂ŁA�ǂ̂悤�ȓd�����K�v�ɂȂ�̂��͍l���Ă݂��܂������H �@�{���ɓd�r��{�̓d���œ��삳�������H�����܂����H �@�܂��A�������������ڑ��ɂ����ꍇ�A(������g�����Ƃ���)�J�b�g��̊e���̓d����d�����ǂ��Ȃ邩�͍l���Ă݂܂������H �@�u�t�B�[�h�o�b�N�v�͂�����܂����H �@��������Łu�j�b�P�����f�[�d�p�v�u�I�[�g�J�b�g�������x�Ə���ɂ͕��d�͊J�n���Ȃ��v�Ƃ����������������d��ɂȂ�Ȃ�A���̉�H�}�Ɠ��샍�W�b�N���������肦��Ǝv���܂��B �@���Ȃ��̑z��������H���������ǂ����������}�ʂ������Č����Ă݂���A���ۂɉ�H��g�ݗ��Ăē��삷�邩�e�X�g���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2012/2/23
|
||
| ���e 2/25 |
���肪�Ƃ��������܂��B NPN��PNP�̎g�����Ƃ��āAPIC�ȂǂŒ�R���ăX�C�b�`�Ƃ��Ă̎g�����݂̂ŁA�ڍׂɓ��삳����d���ȂǍl�����������Ȃ��猩���ڂŎ�������܂����B �Œ��R�Ɍ������ēd���𗬂��Ăǂ��Ȃ�́H �Œ��R�̓d���l���g�����W�X�^�̃x�[�X�ɗ^���ăX�C�b�`�����Ă����܂������̂ł́H�Ǝv�����̂��A����Ȃ���]�����J�j�Y���ł����B �ق�����ɑ��A�����肪�Ƃ��������܂��B �������q���g�ɂččl�������܂��B �܂��A�Ȃɂ��^��_������܂����玿�₳���ĉ������B �͂��悤�����낤 �l
|
||
| �ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ | |||
|
�ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��]��H�̍ۂɂ����b�ɂȂ�܂���kk�ł��B ���A���܂ʼn��x���n���_�t���Ŏ��s���Ȃ�������S����܂ł��ǂ蒅���܂����B���肪�Ƃ��������܂��B ���x�́u�ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[�v�̉�H�v�ŔY��ł���܂��B �z���}�ihttp://gazailabo.web.fc2.com/img/p44-2.gif�j �ɂ��ƁA�����[�~2�ƃg�����W�X�^�~2�ŊȒP�ɏo�������Ȃ̂ł����A�悭����ƉE���̃g�����W�X�^�ɂ����C�O�j�V�����I���z�������Ă��܂���B�i�����͌q�����Ė����Ă������̂��ȁH�j ����Ƃ��A���������ă����[�ƃg�����W�X�^�ł͂Ȃ��A��̌^�̕��i�Ȃ̂ł��傤���H �O��g�����W�X�^�ł͕s���Ȃ̂Ńp���[MOS FET���g�p���܂������A�����FET���g�����ق����ǂ��̂ł��傤���H �E�d��12V �E�q���[�Y15A �E�q�[�^�[�i�d�M���j��R�͑����Ă܂��Б�32W�`50W�ʂ��Ǝv���܂��B ���Z�������ƂƂ͎v���܂����A��H�}�A�g�p��R���킩��Ղ�����������������ƍK���ł��B kk �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���O���炷��ƂȂ���w�ȕ��̂悤�ł����E�E�E�����́u�}�C�i�X�R���g���[�����v���X�R���g���[�������[�v�ł͂Ȃ��ł����B �@�z���}���ʼn����Б��ɂ���Acc���C�����q�����Ă��Ȃ��Ƃ������ł����A���̃R���g���[�����j�b�g�������}�́u�u���b�N�}�v�ł��肻���Ɏ�����Ă���̂���H�}���z���}�ł͂���܂���B �@����T�v�}���炢�̂��̂ł��B �@�u�����[�o�͂ƃX�C�b�`��H�̓d���͕ʂł����v�u�g�����W�X�^��H���g���Ă��܂����v�u����Ń����[��ON/OFF���Ă��܂����v�Ƃ������g�̍\���������Ă��邾���ŁA�{���ɒ��ɓ����Ă����H�̃g�����W�X�^���R��`���Ă���킯�ł͂���܂���B�K�v�ȕ��i���U�b�N���ƕ`����Ă��炸�u���g���ڍׂɂ͌��J���Ȃ��v�Ӑ}�ŕ`����Ă��܂��B �@����͎Ԃ������e�i���X����ۂɎg���}�ʂŁA�R���g���[�����j�b�g�́u���������@�\�̔��v�Ƃ��Ă�������Ȃ��̂ł���ł����ł���ˁB �@���삷��l�̂��߂ɃR���g���[�����j�b�g�̒��̉�H�}�������Ă�����I�Ƃ������߂̐}�ʂł͖����ł����B �@������A���̐}�̂܂܂Ɍ��ăg�����W�X�^��ƃ����[���Ȃ�����E�E�E�܂��g�����W�X�^���Ă��ďI���ł��B �@�u��̌^�̕��i�v�Ƃ����͓̂����炸�Ƃ������炸�ł����A���ۂɂ͒��ɂ͐F�X�ƕ��i�̓������d�q��H�������Ă��܂����A����������̎l�p���L���ŕ\���Ă��邾���A�u��̌^�̕��i�v�ł͂Ȃ��āu��H���l�܂�����v�����ɓ����Ă���Ƃ����Ӗ��ł��B �@�d�q��H�̐��E�ł͂ƂĂ�������܂��ŁAIC�̃f�[�^�V�[�g�Ȃǂ����Ă�IC�̒��̉�H���i��S�ď�������H�}���ڂ��Ă�����̂͏��Ȃ��AIC�̒��łǂ̂悤�ȋ@�\����������H���ǂ��g�ݍ��킳���Ă��āA�ǂ̒[�q�ɂǂ�ȐM������͂���Ƃǂ�ȐM�����o�͂���邩�̐}�E�E�܂��u���b�N�}���K��������Ă��܂��B �@�܂��A�u���b�N�}�͏ڍׂȉ�H�}�ł͖����̂ŁA�`����Ă��Ȃ��z���������̂�������܂��B����̂悤�ɒ��ɂQ�̋@�\��H�������Ă���ꍇ�ɂ͕Б��ɂ��������Ă��������Б��͏ȗ����Ă��Ӗ���������悤�Ȕz���́A�}�������Ⴒ����ɂȂ�ꍇ�͏ȗ������̂���}����@�ł��B �@����ŁA���̃R���g���[�����j�b�g(���������Ȗ��O�E�E�E)�����삵�����̂ł���A �� Acc�d����ON�̂Ƃ����������[������ �� ��Ȃ̃X�C�b�`(�}�C�i�X�R���g���[��)��ON�ɂ����Ƃ����������[������ �@�Ƃ���������s�������̂ŁA�����������[�P��(���E�łQ��)�����ł������ł��ˁB �@���ԂłȂ�Ńg�����W�X�^��H����̃����[���j�b�g���g���Ă���̂��A�{���̗��R�̓��[�J�[�̐v�҂ɂł������Ȃ��Ƃ킩��܂��A�����̃��[�J�[�ł͂��������}�C�i�X�R���g���[���p�X�C�b�`�œd�͕��i��ON/OFF����ۂɂ͋��ʂŎg����g�����W�X�^��H�t�������[�̃��j�b�g���ėp�̋K�i�i�Ƃ��ėp�ӂ���Ă���̂ł��傤�B �@�g�����W�X�^��H�������[�ɂ���ƁA�X�C�b�`�z���ɗ����d����}������̂ŁA���e�ʂ̃X�C�b�`��z�����g���܂��B �@�����[�ڃX�C�b�`��ON/OFF���Ă��R�C���d���͂킸���ł�����A���ʂ̔z���E�X�C�b�`�Ȃ牽�̖��������͂��ł����A�������������d�q�X�C�b�`�I�Ȃ��̂ɂ������Ӑ}�◬�s������̂ł��傤�ˁB �@�ŋ߂̎Ԃ̓��C�g�ނȂǂ��R���s���[�^�����(�R���s���[�^�Ɍq������)ON/OFF���Ă���ꍇ�������悤�ł�����A�R���s���[�^��I/O�|�[�g�̔����d���e�ʂł������[�������߂̃o�b�t�@�Ƃ��ăg�����W�X�^��H����̔ėp�i��p�ӂ��Ă��āA������ǂ��ł��g�����Ⴄ�Ƃ������ŕ��i�̎�ނ����炷�u�����e�i���X���̌����v���_���Ă���̂�������܂���B �@������ƍl����A�o�b�e���[����12V�n�ł��A�R���s���[�^��5V�n�ł��A�ǂ���ɐڑ����Ă����삷��g�����W�X�^����̃����[�E�E�E�Ƃ����v�ł��܂����B �@����̂���]�ł͂���ȕ��܂ł͗p�ӂ��Ȃ��Ă������̂ŁA�P���ɏ�L�̂Q�̏������������ɏo�͂�ON�ɂȂ郊���[�����悢�����ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �����[�̂ݎg�p �@���̕ϓN�������A�����[��̃}�C�i�X�R���g�[�����v���X�R���g���[���̒��p(�ϊ�)�����[�ł��B �@���Ƃ��Ύԗp�ł悭�g���Ă����G�[�����̂S�Ƀ����[���g�����ꍇ�A�R�C���d������110�`120mA���x����܂��B �@������X�C�b�`��r���̔z�����������Α��v�ł��B �@���ʂ̎Ԃ̔z����A�p�l���ɂ��Ă�X�C�b�`�ł���Ή��̖��������͂��ł��B �@����(�q�[�^�[)���Б�50W���x�炵���̂ŁA�d����5A�ȉ����Ɖ��肷��ƃ����[�̓G�[�����S�Ɍ^�̂悤��20A���̗e�ʂ̕K�v�͂Ȃ��AOMROM G6C-1117P-US DC12V(�ړ_�e��10A)���g���R�C���d����16.7mA @ DC12V�Ɖ��L�̃g�����W�X�^�g�p��FET��H�Ƃ��܂�ς��܂���B �@(�X�ɂ����܂��� )���l�i���G�[�����S�Ƀ����[�̔������x�ł��B �� �g�����W�X�^�{�����[�g�p �@�����[�̃R�C�����g�����W�X�^�����ON/OFF���܂��B �@�X�C�b�`�ɂ��ő��15mA���������܂���A��قǍׂ��z���⏬���ȃX�C�b�`�ł����v�ł��B �@�����^�̃��[�h�X�C�b�`��X�X�C�b�`�A����X�C�b�`�Ȃǂ̂ƂĂ��ア�d�����������Ȃ��悤�ȃX�C�b�`�ł������[�ő�d����ON/OFF�ł��܂��B �� �t�H�g�J�v���{�e�d�s�g�p �@FET���g�p����ꍇ�AFET���͕̂��n�̓d��(�o�b�e���[)�Ɛڑ�����Ă��邽�߁A���̂܂܃X�C�b�`�n���Ɣz�����邱�Ƃ��ł��܂���B(�����܂ō���̖ړI��Acc���ɘA��������ꍇ) �@�g�����W�X�^�Ȃǂ��g����Acc���d����FET���R���g���[�������H������Ă������̂ł����A�����͊ȒP�ɐ≏�ł���t�H�g�J�v���Ńo�b�e���[�d���n�Ɛ藣���āA�R���g���[�����͂�Acc�d���n�ŃX�C�b�`�Ɛڑ����܂��B �@�X�C�b�`�ɂ��ő��15mA���������܂���A�g�����W�X�^���Ɠ��l�ɏ��d���p�̃X�C�b�`�Ȃǂ�ڑ��ł��܂��B �@�܂��A�Ȃ�Ƃ������E�E�E�A�ԊW�̐l���ƁuFET���g�������I�v�Ƃ��g�����W�X�^��FET�ȂǓd�q���i�ɖ��������Ă���l�������̂ŁE�E�E�B �@��d���p�̃X�C�b�`�Ƀg�����W�X�^��FET���g���@�B�I�Ȑړ_�������̂Őړ_�����X�ɏĂ��ĐڐG�������Ȃ�Ȃǂ̗͏��Ȃ��ł����AON��R���O�ł͖����̂��傫�ȓd���𗬂������̔��M���傫���Ȃ��Ƃ��������̂ɂ����̂̌��_���������킹�Ă���̂ŁA������ł����߂�����̂ł͂���܂���B (�����[���ړ_��R�͂O�ł͖����ł����A��i���g�p�Ȃ���ɑ傫�ȕ��M�Ȃǂ͂��Ȃ��Ă��ǂ�) �@�����[�̂悤�ɃR�C���d����100mA��(�G�[�����S�Ƀ����[�̏ꍇ)�قǁu���ʂɎv�������d���v�������͖̂��͂ł����A����̗p�r�̂悤�ɕ��ׂ�4�`5A�قǏ����̂ɁA�����Ń����[��0.1A���x���팸�������I�Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ��Ƃ����C�����܂��B �@���ׂ����\mA��������Ȃ��̂ɁA�����[�̂ق���100mA���H���I�Ȃ�ĉ�H�ł������d�������d�r�Ƃ��Ȃ�A�����[���g�����Ԃ�̃��_�͍팸�������ł����A��d�����ׂ�ON/OFF�������I�Ƃ����g�p�ړI�ł͂킴�킴���M����FET���g���Ă܂ŃR�C���d���Ԃ���팸����Ӗ�������̂��A�悭�l���Ďg�p��H�����͑I�Ԃׂ����Ǝv���܂��B �@����̖ړI�Ɍ����ẮAG6C-1117P-US DC12V�܂��̓G�[�����S�Ƀ����[���Q�p�ӂ��邾���ŁE�E�E�\���ȋC�����܂����������H ���Ԏ� 2012/2/21
|
||
| ���e |
���Z�������A���S�҂ɂ�������₷������̂��Ԏ����܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B ��H�}�Ǝv������ł����͎̂��̓u���b�N�}�ŁA�ȗ�����̂���}�̍�@�Ƃ́c���ɂȂ�܂��B ����3����v�}��`���Ē������k�ł��B ��ʂ�u�d�q���i�ɖ��������Ă���v��������܂���B ���������Ȃ̂�2��ڂ́u�g�����W�X�^�{�����[�g�p�v��OMROM G6C-1117P-US DC12V(�ړ_�e��10A)���g���Ē��킵�悤�Ǝv���܂��B �����[�Q���g�p������H�}����`�����Ă݂܂����B http://gazailabo.web.fc2.com/img/img001.jpg ����Ȋ����ŕ��i�B���Đ��삵�悤�Ǝv���܂��B ���Ȃ݂ɏ��������[�R�l�N�^�Ƀ|���t���o����悤�ɁA http://gazailabo.web.fc2.com/img/relay1.jpg �Ɠ����̑傫���A7�ړ_�Ɏd�グ�����ƍl���Ă܂��B ���� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�K���R�l�N�^���������ł�����A�H����y�ł��ˁB �@����A�e�X�g�I�ȉ����͍H��̊y���݂ł�����A�ǂ������y���݂��������B ���Ԏ� 2012/2/23
|
||
| ���e 2/24 |
���A���܂ŁA�{���H�t���ŕK�v���i��S�đ����邱�Ƃ��ł��܂����B ���ꂩ�炶�����胊���[����Ɏ��g�݂����Ǝv���܂��B ���܂���������A�܂����������܂��ˁB���肪�Ƃ��������܂����B kk �l
|
||
| ���e |
�������Ƀ����[�������������܂����̂ŕ��܂��i�O�|�O�j ���������[�̃P�[�X�𗬗p���Ċ�Ղ̑傫�������߁A����������7�[�q�ɐڑ��B������e�X�^�[�œ_������ƁA�n���_�t�������܂������ĂȂ�����2�ӏ�����A���J�ɕ�C���܂����B �����邨����ԂɎ��t���ē���m�F����Ɓc ���ʁc�听���I�ł��B ����Ō㕔���Ȃɍ��邱�ǂ������ɂ��A���N�̊����~�������Ă��炦�܂��B ����3�N�O����Y�ݑ����Ă������̃����[�ł����A���̓x���{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B ps.�A�L�o�ł̕��i���B�̍ہA�u�悭�킩��d�q��H�̊�b�̊�b�v���ꏏ�ɍw�������̂ŁA�����͎����Őv�ł���悤���������܂��B �Ƃ����A�܂�������Ȃ����Ƃ�����܂����炨���b�ɂȂ邩�Ǝv���܂��̂ŁA����Ƃ���낵�����肢�������܂��B kk �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@���́[�A�ʂɂǂ��ł������^��Ȃ�ł����A������ă��A�V�[�g�ɂ̓q�[�^�[���ŏ���������Ă��āA�����[�̂݃I�v�V����(��H�}�ɂ̓I�v�V�����Ə����Ă���)�����ŁA�Ԃ̃O���[�h�ɂ���Ă̓����[���t���Ă���t���ĂȂ������肷��̂ł����H (����Ń����[��������đ}������q�[�^�[���g�����) �@�����[�������̂Ƀ��A�V�[�g�̃p�l���ɂ̓q�[�^�[��ON/OFF�X�C�b�`�͑S�ԕt���Ă�̂ł����H �@�ŏ�����q�[�^�[�Ȃ��̎Ԃɂ̓����[�͂��Ƃ��V�[�g�q�[�^�[���p�l���X�C�b�`�������t���ĂȂ���Ȃ��āH �@�����������Ƃ�����A�����[�����ʉ��i�ŃI�v�V�������肷�邭�炢�Ȃ�A�S�O���[�h�ɍŏ�����t���Ă��������̂ɁE�E�E�B ���Ԏ� 2012/2/27
|
||
| ���e |
�^��Ɏv�킹�Ă��܂����݂܂���ł����B �������ŏ����烊�A�q�[�^�[�����ł��B�i�t�����g�͏��������j �����炭�����ɂ̓��A�q�[�^�[�I�v�V�������t���Ă�Ԃ͖����Ǝv���܂��B�i�����[�ł����A�X�E�F�[�f���ȊO�̍��ł͂قƂ�ǎ��v�������悤�ŁA���ʂ��Ă܂���B�j �u���b�N�}�Ƀ��A�̃I�v�V�������ݒ肳��Ă����̂ŁADIY�ŏo�����Ȃ����Ǝv���A����܂ŃR�c�R�c�ƃq�[�^�[�d�M���A���E�V�[�g�X�C�b�`�A�n�[�l�X�𗬗p���H���삵�܂����B �Ō�̗v�̕����������[�������Ƃ�����ł��B kk �l
|
||
| ���e |
���т��т��݂܂���B �Q�l�܂łɁc�O��ƍ���̍�Ƃ̐����蒠�ł��B ���A�V�[�g�q�[�^�[�͂���Ȋ����ʼn��H���t�����܂����B �T���o�C�U�[���j�^�C���X�g�[�� ���A�V�[�g�q�[�^�[�C���X�g�[�� ���A�V�[�g�q�[�^�[Part2 ���A�V�[�g�q�[�^�[�t�@�C�i�� ���A�r���[���j�^���C kk �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�Ȃ�قǁA�����������P�������̂ł��ˁB �@�{���{�̖k�������Ԃɂ������A�V�[�g�q�[�^�[�̐ݒ肪�����Ƃ����̂����߂Ēm��܂����B �@�t�����g�V�[�g�̃q�[�^�[�Ƃ����肵�āA����̔����(!?)�ڐA����ȂǑ�ςȍ�Ƃ��o�Ă���̂ł��ˁB �@�z���}�ɐF�X�Ə������܂�Ă�����A�Ԑ��������Ċm�F����Ă���悤�Ȃ��̂��ʂ��Ă��܂����A��������Ǝ菇��ōH�삳��Ă��邨�p�ɂ͊������܂��B �@�Ԃ��āA��x�G��n�߂��玟�X�Ɓu�����������v�Ƃ����~�]���N���Ă��܂�����ˁ`�i�O�O�G ���Ԏ� 2012/2/28
|
||
| �ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g | |||
|
�͂��߂܂��āA�����d�q��H���쎞�ɂ��傭���傭�����b�ɂȂ��Ă܂��B �����ł����A����A�C�x���g��p��(�o�^�����ς�)�ւ́u���������z�[���v(�z�[���{�^���𗣂��������珙�X�ɉ��ʂ�������A3�b��ɉ��ʃ[��)�̐���ɁA������̃y�[�W�ɂďЉ��Ă錸����H�̗��p�Ń`�������W���Ă݂��̂ł����c �z�[���Ɏg�p�ƂȂ�ƃA���y�A����40�A���y�A�������̂ŁA�����̉�H�ł͗e�ʕs�����Ɗ����܂����B �����Ȃ�ɉ�H�͍l���Ă݂��̂ł����A�Ȃ��Ȃ����܂������܂���B �ǂ̂悤�ȉ�H��g�߂����̂��A�悩������m�������肵�������₳���Ē����܂����B��낵�����肢���܂��B ���Ȃ݂�12V�p�̃z�[���ł��B �킽����� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@40A���g���z�[���ł����I�H �@�C�x���g�p�Ƃ������ŁA���̂������傫�ȃz�[���Ȃ̂ł��傤�ˁB �@���ʂ̎ԗp�̃z�[���Ȃ炽���Ă���4A�O��^�C�v�ł���ˁB�ԂȂ炻����Q��8A���x�Ŗ炵�Ă��܂��B �@�ŁA40A���������̉�H�Ŗ炵�����̂ł���A�h���C�o�Ŏg�p���Ă���FET���d���^�ɂ��邾���ł������̂ł́H �@�ȑO�ڂ��Ă���IRF3703�Ȃ���210A(25����)�܂ŗ����܂��B �@�����AFET�̃Q�[�g�d���œd����������悤�ȏꍇ�A�d���������Ԃɂ�FET�ł̑������S���M�ɕς��܂�����A�����ȑ傫���̕��M�����邱�Ƃ�Y��Ȃ��ł��������B �@12V��40A����镉�ׂ��q���œd�����������ꍇ�A���M�����ł͈ꔭ�ŏĂ��Ă��܂��ł��傤�B �@�قƂ�ǔ��M���Ȃ�PWM���䂪�����̂ł����ǂˁB(����ł�40A���ׂ��ƕ��M�͕K�v) �@���̂�����͉ߋ��̉�H�}���Q�l�ɐF�X�Ǝ����Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2012/2/19
|
||
| ���e 2/19 |
�����̉��肪�Ƃ��������܂��B �c�悭�悭�l������40A���āc�i�j �悭���Ă݂���A4.0�́u.�v���C��ď����Ă܂����B�B�B ������40A���Ɗ��Ⴂ���ĉ�H�\���l���Ă����̂ł����A4A�Ȃ炢�������ł��I PWM����Ȃ�A�o�����ĂȂ̂ł��傢�������ł����ǃ`�������W���Ă݂܂��I ���肪�Ƃ��������܂����B �킽����� �l
|
||
| �t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� | |||
|
�͂��߂܂��āA�����₨�����������B �����̂g�o�X�S�C�ł��I ���Ȃ�Q�l�ɂ����Ē����Ă���܂��B �������������̂́A���x�v�Ȃ̂ł����H���d�q�Ŕ̔����Ă��鐻�i�Ȃ̂ł����A�����o����̂��Ǝv���܂��āc ���i��� http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-01745/ ���̉��x�v���g���Ă�̂ł����A�t���\���Ȃ̂ł����D�̃G���W���̉��x�Ȃǂ��ȈՓI�ɏ펞�\�������Ă���̂ł�����ԂȂǂ������d�C���Ƃ炵����Ɩ��𒅂����肵�Ċm�F���Ă���̂ł����A������k�d�c�\���ɂ��鎖�͉\�Ȃ̂ł��傤���H �k�d�c�V�Z�O��� http://akizukidenshi.com/catalog/c/c7seg/ �܂��A���x�Ɩ����ڐG�s�ǂʼnt�����\���s�\�i�S�̂������ƕ\������B�j �Ȃǂ����茋�\�s�ւȎg���������Ă��܂��B ���݂́A�k�d�c�ŏƖ������m�F���Ă��Ԃł��B ���Ƃ������o���Ȃ������Ɓc �ȒP�Ȓm��������Ȃǂ͂��Ă���̂ł������i�̍\���Ȃǂ�������Ȃ�����ł��B �d���́A1.5�u�Ȃ̂łT�u��1.5�u���Q�l�ɓd�����ƍl���Ă���܂��B �����Ȃ�܂�������낵�����肢�v���܂��B yamanbo �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁE�E�E����LR44�~1�ŋ쓮���Ă�t�����x�v�ł���ˁB �@����̒��g���t���\����p�̉��x�vIC�`�b�v(��������d���^)�Ȃ̂ŁA���ʂ���������LED�����ł��܂����B �@�u���ʂ��v�Ə������̂́A�n���l�̉p�m�����W���A�Ő�[�Ȋw�����p��������d�q��H��v���A���̉��x�v�̉��{���̑傫���̉�H���g�ݗ��āA�܂�Ŏ��Ȗ����̉�̂悤�ȑ��u������B�����܂ł̘J�͂������Ă܂ō�肽���̂ł���A���͎~�߂͂��܂��A�������Ō������ĉ�H�����������������ŗp�ӂ��Ă��������܂��B �@�������t���\����LED�\����ɒu�������������Ă���]�ɂ́A�����R�N�O�́u�t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g�v�Ń^�b�v���ƌl���x��������ȉ�H�E����������͖̂������������Đ������āA�����ł���������H���ڂ���̂͂��f�肵�Ă����ł�����B (�������ǂ݂łȂ���A���Ј�x�ǂ�ł����Ă��������B) �@���g���Ă���t�����x�v����������Ƃ����ړI�͂�����߂āA�f����LED�\���̉��x�v�������Ǝv���܂��B  �@���Ƃ��X�g���x���[���i�b�N�X���́u2�`�����l��LED���x�v�L�b�g�y�ԐF�z\3,465�v�u2�`�����l��LED���x�v�L�b�g�y�ΐF�z\3,465�v�Ȃ�āA�Ȃ��Ȃ��ǂ����ł���B�Q�`�����l���̉��x���肪�ł��܂����A�Z���T�[����100m����܂ʼn�����̂����܂葼�ł͖����@�\�ł��B
�@���Ƃ��X�g���x���[���i�b�N�X���́u2�`�����l��LED���x�v�L�b�g�y�ԐF�z\3,465�v�u2�`�����l��LED���x�v�L�b�g�y�ΐF�z\3,465�v�Ȃ�āA�Ȃ��Ȃ��ǂ����ł���B�Q�`�����l���̉��x���肪�ł��܂����A�Z���T�[����100m����܂ʼn�����̂����܂葼�ł͖����@�\�ł��B�@�̂͏H���d�q����ł��uLED�\���̉��x�v�L�b�g�v���Ă����̂ł����A���͏��i�ꗗ��������Ă܂����˂��B >�ȒP�Ȓm��������Ȃǂ͂��Ă���̂ł��� �@�Ƃ������ł����A����̂���]���d�q��H�̉����ł����炠����x�̃n���_�Â����͂ł���Ƃ�����E�E�E��������LED�\���̉��x�v������Ă͂������ł��傤���H �@������ō��܂ʼn��x�W(xx���ɂȂ���ON�Ƃ�)�̉�H�Ƃ����ƃI�y�A���v���g�����肵�Ă�����ƕ��i���������Ȃ�悤�Ȃ��̂����������ł����A�����P��LED�\���̉��x�v����邾���Ȃ�A�H���d�q�Ŕ����Ă��邢�����̕��i��g�ݍ��킹�邾���ŁA���S�҂ɂ��ȒP�ɑg�ݗ��Ă邱�Ƃ��ł��܂��B�������ʓ|�ȁu�����ӏ��Ȃ��I�v�Ő��m�ȉ��x���v���̂ł�����A�����s������ł��B �@�g�����i�͂��������ꂾ���B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@LED�̃f�W�^���\�����͏H���d�q�̒��LED�p�l�����[�^�[�u�k�d�c�f�W�^���p�l�����[�^�[�R�E�P�^�Q���m�P�X�X�X�\���E����������n�o�l�|�P�Q�X�d (750�~)�v���g�p���܂��B �@PM-129E�͗��̊�̂������̃W�����p�[�ӏ�(�p�b�h)���n���_�V���[�g���āA�D�݂̐ݒ�Ŏg�p���܂��B �@����́uDC �}2V �����W�v�u�d����5V�v�u10mV/1���ʼn��x�v�Ƃ��ĕ\�������v�Ŏg�p���邽�߁B �E�d���I���� 5V �p�b�h���V���[�g �E�����W�I���� DC �� 2V �̓�ӏ����V���[�g �E������R�ڂ̏����_��_��������ׂ� P3 ���V���[�g ���Ďg�p���܂��B �@���x�Z���T�[�͂�������x�W�̍H��ł͒�Ԃ́u�����x�h�b���x�Z���T�@�k�l�R�T�c�y�@�O�`�P�O�O�� (100�~)�v���g�p���܂��B �@LM35DZ��0�`100���͈̔͂�10mV/1���̓d�������j�A�ɏo�͂��邽�߁A���̏o�͓d�������̂܂܃f�W�^���d���v�ŕ\�����邾���Ńf�W�^�����x�v���������܂��B �@����͂��̂܂ܒP���Ɏg���Ă��悩�����̂ł����ADZ�ł͂Ȃ���{��LM35�͑��艷�x�͈͂�-55���`150���ƍL���A�}�C�i�X�̉��x���v��܂��B �@�ŁALM35DZ�͖{���Ƀ}�C�i�X���x���v��Ȃ����Ƃ����ƁE�E�E���[�J�[�͔͈͊O�Ƃ��Ă��܂������ۂɂ�LM35���l�Ƀ}�C�i�X�̉��x������ł����Ⴂ�܂��i�O�O�G �@�����ŁA�����LED���x�v��H�ł́uPM-129E�̓}�C�i�X�d���̕\�����ł����ˁ`�v�uLM35DZ�̓}�C�i�X���x��(��i�O������)����ł����ˁ`�v�u���͓~�����A�X�_���̉��x���v���ƂȂɂ��ƕ֗���������ˁ`�v�Ƃ��������̚����ɂ��A�}�C�i�X���x�܂Ōv����H�Ƃ��܂����B �@LM35�n�Ń}�C�i�X���x�𑪒肷��ɂ́u�}�C�i�X�d���v���K�v�ł��B �@�ł�������̉�H�͓d����+5V�̒P�d���œ����������̂ŁA��H���ŕK�v�ȃ}�C�i�X�d��(-5V)��DC/DC�R���o�[�^�ō���Ă�����ƂɂȂ�܂��B �@�uDC/DC�R���o�[�^���ƁA���̂��ʓ|�Ȃ�Ȃ��H�v���Ă��ƂɂȂ�܂����A�K���ɂ��Ă��������p�r�Ɏg���������^�Ƀ��W���[�������ꂽDC/DC�R���o�[�^�������Ă��܂��̂ŁA�����������i���g���Ώ��S�҂̕��ł��ȒP�Ƀ}�C�i�X�d����H���g�����Ƃ��ł��܂��B �@�X�ɁE�E�E�H���d�q�ł�PM-129E�̏��i������ > �����̃f�W�^���p�l�����[�^�[�͓d���̃}�C�i�X�[�q�Ƒ���[�q�̂f�m�c�����ʂ��Ă��܂��B > �@�i�R�����O�����h�j�B�e�X�^�[�œ��ʃ`�F�b�N���Ċm�F�ł��܂��B [2012/2/14����] �@�Ə����Ă��܂����A�ߋ������w���������ɂ� > ������O�����h�Ɠd���̃O�����h�͋��ʂɂł��܂���B �Ə�����Ă��āA�H���̒ʔ̃y�[�W�ł͂��́u�ł��܂��v�u�ł��܂���v������ւ��Ƃ�������ۂ��Ђ�ς�ɋN���Ă��܂��B �@�ŁA�茳��PM-129E�Œ��ׂ�ƁAGND�����ʂɂ���ƕ\�����ł����(�덷��)�ɂȂ�܂��B �@�d���n�Ƒ���n��GND�����Ă��ƁA�\���͂��Ȃ萳�m�Ȓl�������܂��B �@�Ƃ������ŁA�u�����������獡�����Ă���PM-129E�͒��g���ς���Ă���GND���ʂœ�����������Ȃ����ǁE�E�E�v�S�z�Ȃ̂�GND���ʂɂł��Ȃ��^�C�v��PM-219E�������Ă���l�ł�����ɓ��삷���H�Ƃ��āA���[�^�[�d����LM35DZ�̉��x����n�d���͕ʁX�̂��̂ɕ�������K�v������ƍl���܂��B �@�Ƃ������Ƃ́E�E�E+5V�̂ق���������ʂ�5V�d�����Ȃ����A���ꂩ�����ʂ�5V�d�����g�����A�Ƃ������ɂȂ�܂����A���������J���^���Ȃ��Ƃɐ�قǃ}�C�i�X�d�����K�v������DC/DC�R���o�[�^���g���Ƃ������j�𗧂ĂĂ���̂ŁA�u��������}�̗��d�������o����DC/DC�R���o�[�^���g�������I�v�uDC/DC�R���o�[�^���W���[���ɂ͓��͂Əo�͂��������Ă���w�≏�^�x������̂��I�v�Ƃ�������y�J���^���ɂł�����@�ɂ��ǂ���킯�ŁA�K���Ȃ��ƂɏH���d�q�Ŏ�舵���Ă���DC/DC�R���o�[�^���W���[���ɂ܂��ɂ҂�����̏��i�����݂���̂ł��B (�Ƃ������A�ʔ������Ȃ̂Ŕ����Ď茳�ɃX�g�b�N���Ă���킯�ł����c) �@����g��DC/DC�R���o�[�^���W���[���́u�P�v���≏�^�c�b�|�c�b�R���o�[�^�[�i�}�T�u�P�O�O���`�j�l�`�t�P�O�U (450�~)�v�Ō���ł��B �@���Ƃ́A�d�����̕����p�d���R���f���T�Ƃ��A�d���\��LED�Ƃ��A������Ƃ����d�q���i��g�ݍ��킹�邾���ł��B �@�����A�d���\���p��LED�ƒ�R(���}�Q�g)�́u�ǂ����P�[�X�̒��ɓ���邩��A�d���\��LED�Ȃv��Ȃ���I�v�ƍ폜���Ȃ��ł��������B �@����g�p����DC/DC�R���o�[�^MAU106�������ׂ��Əo�͓d�������ˏオ���Ƃ����댯�ȓ������������킹�Ă���̂ŁA���S�Ɏg���ɂ͏o�͂ɂ͔���ȓd���𗬂��Ă��K�v������܂��B �@�Ȃɂ���A���ۂɕ��ׂƂ��Čq�����Ă���̂��A�قƂ�Ǔd����H��Ȃ�LM35DZ�����ł�����B �@���̂��߂�LED�����点��d���ŏo�͈��艻��LED���_�����Ă����Ɠ��삵�Ă���Ƃ킩�鎖����Γ�_���Ă����̂ŁA��ɊO���Ȃ��ł��������B �@��H����P�[�X�̒��ɓ���Ă��܂���LED�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�K�����ɂ͉�H�}�ʂ��LED�͒u���Ă����Ă��������B (�܂��ALED��t�������Ȃ��Ȃ炩����500���O��̒�R��{�ɂ��Ă������ł����ǁc)  �@���ۂɂǂꂭ�炢�̐��x���Ƃ����ƁE�E�E
�@���ۂɂǂꂭ�炢�̐��x���Ƃ����ƁE�E�E�@LM35DZ�͂ƂĂ����x�̍������x�Z���T�[�Ȃ̂Ő����������x�B �@�ǂ��炩�Ƃ�����PM-129E�̕\�����x�ɍ��E�����Ǝv���܂��B �@�������x�\���̌덷���C�ɂȂ�����ALM35DZ�̏o�͓d�����҂�����ɕ\������悤�APM-129E�̗��̒����pVR�Ŕ��������Ă݂Ă��������B �@�H���d�q�ł́u�����ς݂Ȃ̂ŐG��Ȃ��悤�Ɂv�Ə����Ă��܂����A�����������Y���Ă������̂��߂ɁB �@��ɂ������Ă��܂����u�ۏ؊O�v�ł����}�C�i�X���x������ł��܂��B �@�①�ɂ̗Ⓚ����LM35DZ��˂�����ł݂��Ƃ���A�����Ɨ①�ɂ̃p�l���ɕ\������Ă���̂Ɠ����}�C�i�X���x������LED���x�v�ł��\�����܂����B �@�������Ɍ��E��-55���܂ŗ₽���͖����ł����ǁB ���Ԏ� 2012/2/14
|
||
| ���e |
�F�X�Ƃ��肪�Ƃ�������܂����B �ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��B �t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g�C���t���܂���ł����B �\����܂���Bm(-_-)m �����A�H���d�q�ŏT���ɂł����i���B���č���Č������Ǝv���܂��B �X�g���x���[���i�b�N�X�����ǂ������ł��ˁB �Z���T�[�������P�O�O���܂ŐL����̂����͂ł��B �Z���T�[�����̐��ł����A�ŒZ�ł��R���`�S���ʗ~�����̂ł�����������Ƃǂ̒��x�̌덷���ł�̂ł��傤���H ���ۍ���Ċm�F���Ă݂悤���Ǝv���Ă���܂����c(^^; ���Ȃ݂ɂł����A�H���d�q�̉��x�v���R�����������Ďg���Ă���܂������قNj����͖����ł��B �i�x�����ʼn����j ���i�\��������Ȃ��悤�ł��̂ł�����Ă݂܂��B �I���W�i�����Ėʔ����ł��ˁ` �{���ɂ��肪�Ƃ�������܂����B yamanbo �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@LM35DZ�͉�m���L�����肵�Ȃ��ł��������ˁB �@���̉t�����x�v�́u�T�[�~�X�^���v�Łu10K���^�C�v�v�̃T�[�~�X�^���g�p���Ă��܂�����A�z����R�ɑ��ăT�[�~�X�^�̒�R�l�������̂ł�����x�͐L���Ă��덷���قƂ�ǖ����ł����A������@���d���E�d���̌��o�ł͂Ȃ��T�[�~�X�^�̒�R�l�Ɉˑ�����d���Őϕ������Ō��m�����H�̂����O���m�C�Y�ɂ�������x�͋������ł��B �@�ł�����x���P�[�u���̂悤�ȃm�C�Y�ɖ��h���ȊȈՂȔz���ł�������x�͐L���܂��B (������̎��тł�15m���x�L�������Ƃ�����܂�) �@����ɑ���LM35DZ�̏o�͂́u�d���o�́v�ł�����A�v����(���̏ꍇLED�p�l�����[�^�[)�̓��̓C���s�[�_���X�������̂ŊO���m�C�Y�ɂ͎ア�ł����A���������H�ł̓P�[�u�����L�����Ƃ͍l�����Ă��Ȃ��̂ł���ɑΉ������镔�i�������Ă��܂���B �@�����L���Ƃ�����A�p�l�����[�^�[�̓��͂Ƒ���GND�̊Ԃ�10K���̒�R��10��F���x�̓d���R���f���T�����ɂ���B �@�ߋ�LM35DZ���g�������x�W�̋L���ł������Ă���悤�ɁA�K���Q�c�V�[���h���̂悤�ȃV�[���h�����g�p���ĊO���m�C�Y��h�삷��A�Ȃǂ̑�͕K�{�ł��B �@����Ŕz����R�������ȉ��ł���A�덷��0.1���o�邩�o�Ȃ������x�Ɏ��܂�܂��B �@�����A�{���ɉ����[�g�����L���悤�ȗp�r�ł���Ή��u�Z���T�[���ɂ��d�q��H�����ăo�b�t�@�����O������A�z���C���s�[�_���X�̉e�����ɂ����`�����@���Ƃ�ȂǁA���{�I�ɈႤ��H�ɂȂ�܂��B �@�X�g���x���[���i�b�N�X�̉��x�v�́A�Z���T�[���Ɂu�f�W�^���o�́v�^�C�v�̉��x�Z���T�[���g�p���Ă��邽�߁A�f�W�^���M�������Ȃ�����͂ƂĂ������z����L�����Ƃ��ł��邽�߁A��100m���̒������ł��Z���T�[���̓Z���T�[IC����P�[�u���ŐL�������ł��݂܂��B �@������Ă����H�}�́A���Ȃ��̓��e�ɏ�����Ă����ʂ�A���̉t�����x�v�̐��i��̂܂܂Ɂu�{�̂���L�тĂ���Z���T�[����1m�`1.5m�̏��i�v���Ƃ��ăJ���^���ɑ�ւł���ړI�Őv���Ă��܂��B �@�u�Z���T�[����Đ����[�g���ɐL���Ă���v�Ƃ������͂ǂ��ɂ�������Ă��܂���ł����̂ŁB ���Ԏ� 2012/2/15
|
||
| AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ | |||
|
���߂܂��āA�����y���݂Ɍ��Ă��鏉�S�҂ł��B �w���[�x�b�N�X �f�W�^���v���O�����^�C�}�[�U PT50D�x�����悤���^���ō���Ă݂܂����B ���e�̓����[��G5V-1 DC5�Ɍ�������DC7V���͂Ń^�C�}���[�쓮����ƃ����[��ʂ��ĂR�[�q���M�����[�^�[�V�W�O�T����DC5V���o�͗\��ł��B �d��DC7V���w���A�_�ɓ��͂�B�_��GND�ɔz�����ēd�C�������̂ł����A�����[�́{�Ɓ|�̏��̓d�����v���1.7V�������Ȃ������[�������Ă���܂���B �����[���������܂œd�����グ���DC11.7V�Ń����[�́{�Ɓ|�̏��̓d����3V�ŃJ�b�`���Ɖ������Ēʓd���܂����B �iPT50D�ɂ͐��o�[�W�������݂���悤�ł��j�Ƃ̎��Ȃ̂Ŋo��͂��Ă��܂������A�������������̂͊�Ղ̔z�����f�ڂ���Ă��镨�Ǝ�Ⴄ�悤�ł����B �ʐ^��O�̈B���Ƃ��܂����B DC7V���͂Ń^�C�}�[���������̂ŁA���̔z���̎d�����Ԉ���Ă���̂��A���ɉ������O���Ȃ��Ƃ����Ȃ̂��A�������̒��X�������肢�v���܂��B ������q�r���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�uAC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI�v�̋L���̂��Ƃ��Ǝv���܂����A���Ȃ�O�̋L���ւ̘b��ł��ˁE�E�E�i�O�O�G �@�ŁA�����DC7V(�����[��5V�p)�œ��������Ƃ����킯�ł����E�E�E����͓����܂�����B �@�Ȃɂ���APT50D�Ɏg���Ă���FET�͂���ȑ傫�ȓd���𗬂��镔�i�ł͂Ȃ��̂ł�����B �@FET�̌^�Ԃ͍���Ă��ĉ����g���Ă���̂��������Ă͂��܂��A�̑��肵���l�ł͂��̂܂܂̏�Ԃ�20mA���x�܂łł��������ς��B��i��10mA�O��̐v�̂悤�ł��B �@�Q�[�g�o�C�A�X��R��10M���ƂƂĂ��傫���̂ł���������������班�����炢�͒�d�����ł�������d���������邩������܂���(FET�͓d���f�q�Ȃ̂ł��������ω��͖]�߂܂��c)�A��������ƃ����[OFF���Ƀ^�C�}�[��̂ق��Ɉ������ޓd����������̂ł���ǂ̓^�C�}�[��̂ق��̋��e�l���ǂꂭ�炢�Ȃ̂��A�^�C�}�[����IC�͊��S�Ƀu���b�N�{�b�N�X�ł�����킩��܂��s���ł��B �@�ł�����PT50D�̊��̒�R�����������琫�\���ǂ��Ȃ�I�Ƃ����l�����͎g���܂���B �@��������E�E�E�uFET����������H�v�Ƃ����ȒP�Ȍ��_�ɒB���܂��B �@��������ő��v���Ǝv���܂��B �@������ł͉������ăe�X�g���邽�߂�PT50D�͂���܂���̂ŁA�������̕��@�ł���Ă݂�I�Ƃ����̂ł���ǂ����������Ńg���C���Ă݂Ă��������B �@��������͉ߋ��̒������ʂ̋L�^�Ɋ�Â����b�ł��B �@PT50D�̓d�����̓R���f���T�~�����̂��ߑ傫�ȓd���͋����ł��܂���B �@�ł������菭�Ȃ��d���ŋ쓮�ł���悤�����[�p�d���̓d���͍����v�ɂ���K�v������APT50D�ł�24V�̃����[���g�p���Ă��܂��B����̃R�C���d����10mA���x�ł��B �@�l���Z���T�[���C�g�Ȃǂł������悤�ȗ��R�Ń����[���g�����͎̂��������Ń����[�p�ɓd����24V�ɂ�����̂������ł��B �@�����^�ԁE�V���[�Y�ł���A�����[�͓d���d���������ق����R�C����R��������菭�Ȃ��d���ŋ쓮���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�d���̒Ⴂ�����[���g���ƁA�����[�̋쓮�p�̓d���͑傫���Ȃ�܂��B �@�����[�����^�ɂȂ�쓮�d�������Ȃ��ꍇ�������̂ł����A���^��G5V-1�ł�DC 5V�^�C�v�̓R�C����R167���œd����30mA����܂��B �@����30mA�Ƃ����d����PT50D��FET�ŋ쓮�ł�����E���y�������Ă��܂��B �@DC 5V�`7V���x�Ŏg�p������쓮�s�\�ł�����Ōv�����ꂽ�d���l���炢�ɂȂ�ł��傤�B �@�uAC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI�v�̉����̏ꍇ�A���ւ��郊���[��DC12V�i�Ȃ̂ŁA��قǑ傫�ȃp���[�����[�Ɍ����ł����Ȃ�����A�قړ����傫���E���\��DC12V�����[�Ɋ����邾���Ȃ�R�C���d����20mA���x�ƁAPT50D��FET�ł��Ȃ�Ƃ��쓮�ł���͈͂ł��B �@������A������̉����ł�PT50D���͕��i�����Ȃǂ��Ȃ��Ă����������ł��B �@���������Ȃ��̍���̂���]��PT50D�̊��̕��i���\���y�������Ă��܂��B �@�Ƃ������Ƃ́APT50D�̊��̕��i���������đΏ�����(��LFET����)���@���APT50D���͂����炸�ɊO���Ƀ����[�쓮��H��lj�����������̂Q�ɂP�ƂȂ�܂��B �@FET�������X�}�[�g���Ƃ͎v���܂����A���ꂪ�ł��Ȃ��ꍇ�͊O���Ƀg�����W�X�^�ɂ�郊���[�쓮��H�����A�u���̋쓮��H�𐧌䂷��M������PT50D������炤�v�Ƃ������@������PT50D��H�ɂ͕��S��������܂��A�F�X�ȃ����[�E�����v�h���C�o�Ȃǂɂ��Ή��ł��܂��B 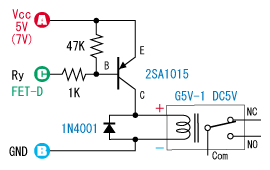 �@�E�}�̂悤�Ƀg�����W�X�^�P�Ń����[�쓮��H�����A�g�����W�X�^�̃x�[�X�d��(6�`7mA)����PT50D��FET�ɗ����Ή��̖����Ȃ����삵�܂��B
�@�E�}�̂悤�Ƀg�����W�X�^�P�Ń����[�쓮��H�����A�g�����W�X�^�̃x�[�X�d��(6�`7mA)����PT50D��FET�ɗ����Ή��̖����Ȃ����삵�܂��B�@5V�p��G5V-1��7V�Ŏg�p����ƁA�R�C���d����42mA���x�����v�Z�ł����A�g�����W�X�^�ŋ쓮����Ȃ���v�ł��B �@���̕��@�͉ߋ���5V�łȂ�e�X�g���Ă��܂��B �@�uFET����������v���@�Ȃ�g�����i�͂�������Ȃ̂ł������̂ق����ȒP�Ȃ̂͗\�z�����܂����A������ł̓e�X�g�������������̂�FET�����������̂ł���܂��͂������Ńe�X�g���Ă��������B �@������ł͂���ł����̂��ǂ����͑z�����邾�������ł��܂���B �@���ƁA�E�E�E�܂��{�肩��͊O��܂����A���M�����[�^IC 7805�������d����3V�ł���B �@�܂��i�Ƃ��ĕۏ���Ă�����͓d����8V�ȏ��ł���A���Ȃ��̂���]��7V�͒�i�����������5V�̏o�͂��Ȃ��\��������܂��B �@�\�����E�E�E�Ƃ����̂��A������H�̂����݂��班�Ȃ��d���Ŏg�p����Ȃ�5V�̏o�͂�������Ƃ͎v���܂����A�傫�ȓd������낤�Ƃ���Ɣ\�͕s���ɂȂ�5V���o�Ȃ��Ȃ�܂��B (�Ȃɂ���7805��7V�łȂg�������������̂Łc) �@��i�ł́u7805��8V�ȏ�Ŏg��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����̂��d�q��H�����l�Ȃ��{�I�ɒm���Ă���͂��̒m���Ȃ̂ŁA�g���O�ɂ͕��i�̑f���ׂĂ���g���悤�ɂ����ق����ǂ��Ǝv���܂��B �@7V����5V����肽���ꍇ�́u�ᑹ���^�C�v�̎O�[�q���M�����[�^�v���g��Ȃ��Ƃ����܂���B �@���Ƃ���TA4805S�Ƃ��B ���Ԏ� 2012/2/14
|
||
| ���e 2/15 |
�����b�ɂȂ�܂��B ���Ȃ�O�̋L���Ő\�������܂���B ������������g��ł݂܂����B 1K�I�[�������������̂Œ�R���q���ċ��c�q�ɂ��đg��ł݂܂����B �ŏ���2SA1015�̌�����f���\�݂Ȃ��炵���̂ł����t�ɑg��œ����Ă���܂���ł����������Ƀ����[�������Ă���܂����B ���M�����[�^IC 7805�͍��l����Ƃ��p�����������ł��BTA4805S��1�����Ȃ��]���Ă����̂Ŏg���Ă��܂����B ���������ʂ�5V�o�Ă��܂���ł����B ���S�҂ŕ��i�̑f�����Ă��`���v���J���v���Ŏ��₵�Ă���̂Ő\�������܂���B FET�̌^�Ԃł��������������������ł����iMPSA42)���Ǝv���܂��B ���Z�������������܂��Ė{���ɏ�����܂����B �������Ċ��ӂƂ��炪���������ď������݂������Ē����܂����B ���x��12V�����܂��B ���肪�Ƃ������܂��܂����B ������q�r���� �l
|
||
| �}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) | |||
|
2008�N�㔼�Ɂu�}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H�v�Ƃ������̂�����܂������A���̉�H�ɒlj��ŘA�˃X�s�[�h�̒���������ɂ́A�ǂ̂悤�ȉ�H��g�߂����̂ł��傤���E�E�E�B �v���A�b�v�A�v���_�E���A�ǂ����������Ă�������Ə�����܂��B BLUE�����w�� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@������ł͂Ȃ�ׂ������ȒP�ɍ��A�}�E�X�̃{�f�B�̒��ɂ��ȒP�Ɏ��߂Ă��܂��邾���̏������c�̂��߂�LED�_��IC���g����p��H����܂������ALED�_��IC�͔��U���g���Œ���ύX�⒲�߂͂ł��܂����B �@�ł�����u���̉�H�ɒlj��ŘA�˃X�s�[�h�̒����������v�Ƃ����̂��s�\�ł��B �@���x�ςɂ���Ȃ�A�P���ł����^�C�}�[IC 555�Ȃǂ̔��U��H��g�ݗ��Ă�K�v������܂��B �@���g�p�ɂȂ�}�E�X�̒��̋X�y�[�X�̍L����A���l�̍H��Z�p�ɂ����܂����A�}�E�X�̒��ɑg�ݍ���ł��܂��ăX�}�[�g�Ɋ����ł��邩�ǂ����͂��܂���҂��Ȃ��ق��������ł��傤�B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@��H�}�ł��B �@��d����3V�^�̃}�E�X�ł����삷��悤�A�^�C�}�[IC 555��C-MOS�� LMC555���g�������U��H�ƁA�}�E�X�ւ̐ڑ����@�ł��B �@�v���A�b�v�^�A�v���_�E���^�A������̐ڑ��ł����삵�܂��B �@�A�˃{�^���������Ă����LED���_�ł��܂��̂ŁA����m�F�����₷���A�{�^�������������̎���������܂��B �@�A�˃X�s�[�h��VR1�Ŗ��b��6�`30����x�͈̔͂Œ��߂ł��܂��B ���Ԏ� 2012/2/13
|
||
| �Ԃ̓d��������m�����H | |||
|
�Ԃ̓d��������m�����H�}�������ĉ������B ���͏��S�҂ł��A�ł���ΊȒP�ȕ��@�ł��肢���܂��B �T���� �l
�� ���͂��ꂽ���[���A�h���X�ł̓G���[�ƂȂ胁�[�������͂��ł��܂���ł����̂ŁA�����[���̖��O�F�Ƃ����Ă��������܂����B |
|||
| ���Ԏ� |
�@�Ԃ̓d���̋�������o������@�͉���ނ�����܂����A�u�ȒP�ȕ��@���v�łƂ������ł��̂Ŋ����Ȍ��o�ł͂Ȃ��A�s���S�ł�����H���ȒP�ɂȂ�����Ő������܂��B �@���̕��j�ł́u�����v��OFF�̊��v������������o�ł��܂���B �@�Ԃ��~�߂Ă��鎞��A�L�[��}���ēd����ON�ɂ�������ǂ������v�ނ̃X�C�b�`�͂܂�OFF�̏�ԂȂǂł��B �@�u�X�C�b�`�����ă����v�_����Ԓ�(�{���͐�ē_�����Ė����Ă��c)�v�����ꌟ�o�͂ł��܂����B �@�ŋ߂̂قƂ�ǂ̎Ԃł́A�����v�_���������o�ł����H���̗p����Ă��܂��B �@���Ƃ��X���[�������v(�ԕ���)�Ȃǂł���ԓ_�����ɋ��ꂵ���ꍇ�ł����o�ł��܂��B �@�A���A��H�����G�ɂȂ�̂Łu�ȒP�ȕ��@���v�Ƃ�������]�ɔ�����̂ł����ł͐�������H�}�̒����Ȃ����Ƃɂ��܂��B �@�\�߂��������������B �@�]�k�ł����A�̂̎Ԃɂ͍��Ƃ͋t�Ɂu�����v�X�C�b�`ON�œ_��������Ԃ������o�ł��鑕�u�v�Ƃ����̂�����܂����ˁB �@�d�q���i���g�킸�ɂقƂ�Ǖ������u�Ŏ�������Ă����A�ƂĂ��A�C�f�A���̂ł������ǁE�E�E�B �@�{��ɖ߂��āA�u�����vOFF���ɋ�������o�����v�ɂ́A�d���Ɍ����p�̃o�C�A�X�d���������ē��ʂ��`�F�b�N������H���ƂĂ��ȒP�Ŋm���ɓ��삵�܂��B 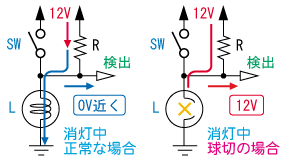 �@�E�}�̂悤�ɁA��R�Ŕ���ȓd����d���ɗ�����H�����c
�@�E�}�̂悤�ɁA��R�Ŕ���ȓd����d���ɗ�����H�����c�� �����Ȃ猟�o�_�̓d���͓d���ŃA�[�X(GND)�ɗ��Ƃ������0V�ɂȂ� �� �����Ȃ�d���ɓd��������Ȃ��̂Ō��o�_�̓d������12V�ɂȂ� �Ƃ������ۂ����m����悢���ƂɂȂ�܂��B �@���̎��ɓd���ɗ��������p�̓d���͐�mA���x�ƂƂĂ����Ȃ��A�d�������邱�Ƃ͂���܂���B �@�������Ȃ��炱�̌��o���@�ł̓X�C�b�`������ƌ����͂ł��Ȃ��Ȃ�܂��B 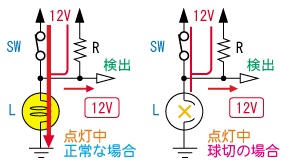 �@�E�}�̂Ƃ���ɁA�X�C�b�`��ON�ɂ���ƌ��o�_�ɃX�C�b�`����12V��^���邱�ƂɂȂ�̂ŁA����ȏꍇ������̏ꍇ�ł��ǂ���ł����o�_�d����12V�ƂȂ�A����̓X�C�b�`OFF���́u12V�������v��ԂƓ����ł��B
�@�E�}�̂Ƃ���ɁA�X�C�b�`��ON�ɂ���ƌ��o�_�ɃX�C�b�`����12V��^���邱�ƂɂȂ�̂ŁA����ȏꍇ������̏ꍇ�ł��ǂ���ł����o�_�d����12V�ƂȂ�A����̓X�C�b�`OFF���́u12V�������v��ԂƓ����ł��B�@�ł�����A�����v�X�C�b�`ON���ɂ��Ԉ���ċ���\�����o���Ȃ��悤���A�����𒆎~����悤�ȉ�H�̂����݂��K�v�ł��B �@�g�����W�X�^�ō��ƁA�d����̌����̂��߂Ƀg�����W�X�^�Q�ƒ�R�����A���ƃ_�C�I�[�h��LED���K�v�ɂȂ�܂��B �@�����d���̐��������ׂ�ΎԂŎg����킯�ł����A���ꂾ�ƕ��i�������\�����Ȃ�̂ŁA�u�ȒP�ȕ��@���v�Ƃ�������]�ɉ����悤��IC�������ŕ��i�����팸���ĊȒP�ɂȂ���@��T��܂��B (1) �����_�̓d�����u0V(L)�������v�u12V(H)�������v�Ɣ��� (2) �X�C�b�`OFF�ŋ��d0V(L)�̎��ɂ����������A�X�C�b�`��ON����Ă��ċ��d12V(H)�̎��ɂ��������֎~���� �@�Ƃ����Q�̏���������H���K�v�Ȃ̂ŁE�E�E 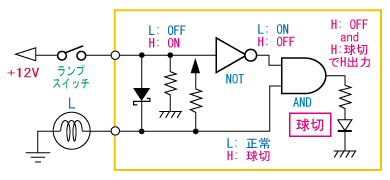 �@NAND�Q�[�g���g����NOT�ɂ�AND�ɂ��g���܂�����IC�̎�ނ�NAND�Q�[�gIC���ނł��݂܂����A�����̃Q�[�g���g�p����̂ł��܂蕔�i���̍팸�ɂ͂Ȃ�܂���B �@�ƁA����������������������ƁE�E�E 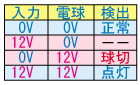 �@�����v�̓_����H�͂��̐}�̂悤�ȂS�̏�Ԃ��Ƃ肤�邱�Ƃ��킩��܂��B
�@�����v�̓_����H�͂��̐}�̂悤�ȂS�̏�Ԃ��Ƃ肤�邱�Ƃ��킩��܂��B�@�Q�ڂ̓d��ON�ł����o�_�̓d����0V�Ƃ����̂́A�z�����������ڑ�����Ă���N���肦�Ȃ��̂ōl���Ȃ��Ă������̂ł����A�ꉞ��X�̂��߂ɂ�����Ă����܂��B �@���̐}����������������o�_(�d��)�̓d�����u�����ł���ΐ���ɏ����A�܂��͐���ɓ_�����v�u�Ⴆ�Έُ�(����)�v�Ɣ��f���邱�Ƃŋ�������o�ł���Ƃ������Ƃ��킩��܂��B �@�u�Q�̓��͐M�����Ⴄ���Ƃ����o�����H�v�����悢�Ƃ������ŁA�ׂ��ȓd���̍������o����̂ł͂Ȃ��u0V��12V���v�����W�b�N�M���Ƃ��Ď�舵���鍡��̏ꍇ�ł́A�������������̃��W�b�N�Q�[�g��������̂܂g����Ƃ������ł��B �@�ŁE�E�E���������u�s���̗ǂ����i�v�����邩�ƌ����ƁE�E�E�A�Y�o�����̒ʂ�ɓ������W�b�N������܂��B 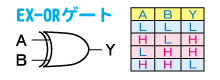 �@���ʂ̂n�q�Q�[�g�̂悤�Ɂu�`�E�a�����ꂩ�̓��͂�H�̏ꍇ�͏o�͂x��H�v�Ƃ��������̂ق��A���ʂ̂n�q�Q�[�g�Ȃ�u�`�E�a�����̓��͂�H�̏ꍇ��(�����ꂩ�Ƃ��������ɂ͍��v����̂�)�o�͂x��H�v�Ƃ������������܂���EX-OR�́u�r���I�v�Ȃ̂Łu�`�E�a�����̓��͂�H�̏ꍇ�͏o�͂x��L�v�Ƃ�����������������܂��B �@����Łu�Q�̓��͐M�����Ⴄ�����v�����o����Əo�͂x��H�ɂȂ�̂Łu�Ⴂ�����o�����v�p�r�Ɏg�p�ł��܂��B �@EX-OR�Q�[�g���g���ĉ�H�}�����������ƁE�E�E 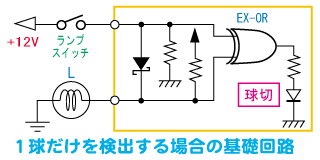 �@C-MOS EX-OR�Q�[�gIC 4030B�܂���4070B�ł�IC��ɂS��H��EX-OR�Q�[�g�������Ă��܂�����A���IC�ŋ��ꌟ�o��H�͂S��H�܂ł����ǂɍ�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�ł��E�E�E�Ԃ��ēd���͈�ł͂Ȃ��đ�R�t���Ă��܂���ˁH �@�Ԃɕt���Ă���d���̐��������ꌟ�o��H����ׂ�Ƃ��̂��������ƂɂȂ�܂��B �@���ۂ̎Ԃł�����Ȃ��Ƃ͂��Ă��܂���B �@�Ԃ̓��Ηނł́u�u���[�L�����v�͍��E�p�̂Q�������ɓ_������v�Ƃ��u�E�C���J�[�͕Б��őO�p�E���p�̂Q�y�A�v�Ƃ��قƂ�ǂ̓����u�Q���Z�b�g�v�ɂȂ��Ă��܂��B �@�����Ă����Q���Z�b�g�������q���ł�����ꌟ�o��H�͈�ōςނ̂ł����A�c�O�Ȃ��Ƃɒ���ł͓d������ꂽ�����Œ���Ɍq�����Ă���S���������Ă��܂��̂ň��S���肪����A���ꂼ��̓d���������Őڑ�����Ă��܂��B �@����ڑ����ꂽ�܂܂ł͕Е�����Ă������Е��͓_������̂ŁA���S��͂����ւ�ǂ��̂ł�������̌��o��H�͂��̂܂g���܂���B �@�����Ă��̎Ԃł͂����Ƌ��ꌟ�o���ł���悤�A�X�C�b�`�{�b�N�X�̂Ƃ���܂ł͊e�d���ʂ̔z�������������Ă��āA�d�����ɋ��ꌟ�o��H�����邱�Ƃ��ł���悤�Ȑv�ɂȂ��Ă���͂��ł��B(��قǂ̋�����ςȕ��������āc) �@����ŁA�Ԃ̓��Ηނ��Q���Z�b�g�ŋ��ꌟ�o���s���āA���Ƃ��u�|�W�V��������v�݂����Ȍx�������v����_��������ɂ́A��L�̂P���p�̋��ꌟ�o��H���Q����ďo�͂����������Ƃ������@�ł��\���܂��A�����ł��u�ȒP�ȕ��@���v�Ƃ�������]�ɉ����Ă����ƒm�b�����ĂȂ�Ƃ��ł��Ȃ����l���Ă݂܂��B 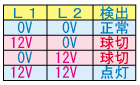 �@�Q���Z�b�g�̏ꍇ�A�d����ԂƋ��ꂩ�����łȂ����̏��(���o�_�̓d��)�͂��̐}�̂悤�ȂS��ނ̏�Ԃ��l�����܂��B
�@�Q���Z�b�g�̏ꍇ�A�d����ԂƋ��ꂩ�����łȂ����̏��(���o�_�̓d��)�͂��̐}�̂悤�ȂS��ނ̏�Ԃ��l�����܂��B�@���[���Ƃ悭���Ă��A����ȂɌ����قnj��Ȃ��Ă��A���̕\�͏�̂P�������̏ꍇ�̓d���ƌ��o�_�̑��֕\�Ɠ������u�Q�̓��͐M�����Ⴄ�����v�����o����Ƃ���́u�����v���Ɣ��肷�邱�Ƃ��ł���킯�ł��B �@���ӂ���_�́A���������̓d���������ɋ�����N�������ꍇ�A�������ɓ�������ɂȂ�̂Ő������͋��ꂪ���o�ł��Ȃ��_�ł��B �@�������Ȃ���A�{���̎Ԃɐς܂�Ă��錋�\�����Ȍ��o��H�ł��A�Б��̋���͌��o���邪���������̏ꍇ�����f�ƂȂ��H���ς܂�Ă���I�Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂��̂ŁA���̓_�͎���җl�́u�ԗp���v�Ƃ��������ɂ͍��v���Ă���Ƃ������ō���͖�莋�͂��܂���B �@�P���ɂ́u���ꌟ�o���W�b�N��H���Q�p�ӂ��āA���̏o�͂��������邽�߂̉����Q�[�g��������p�ӂ��āc�v�Ƃ����R���炢�̓��W�b�N�Q�[�g���K�v�ȉ�H���E�E�E 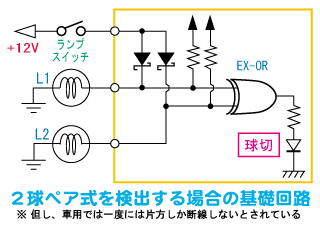 �@����Łu�����v�X�C�b�`��OFF�̊ԁA�ǂ��炩�Е��̓d�����ꂽ��x������_���������v�Ƃ����@�\���ԗp�̋����H�̗��_�͊����ł��B �@�u�ȒP�ȕ��@���v�Ƃ�������]�ɁA����ȏ�ȒP�ɂ͂ł��Ȃ����炢�܂ŕ��i�����팸�ł��܂����B �@���Ă���͂��̗��_�Ŏ��ۂ̉�H�}�������グ�邾���ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�ꌩ����Ƃ����Ⴒ���Ⴕ�Ă��ĕ��G�Ɍ����邩������܂��A�������̂��S��H����ł��邾���Ȃ̂ō��̂͂���قǓ���͂���܂���B �@�S��H�K�v�łȂ���Εs�v�ȕ����͍��Ȃ��Ă��ǂ��̂ŁA���̏ꍇ�̓Q�[�g�̓��͂͐}�̂悤��GND�ɗ��Ƃ��Ă����Ă������B�����q�����ɊJ�������܂܂��ƐÓd�C�Ȃǂ�C-MOS IC��j�����錴���ƂȂ�܂��B �@�S��H�ł͑���Ȃ��ꍇ�́AIC�𑫂��ē����悤�ɕK�v�ȉ�H�������g�ݗ��Ă�Ηǂ��ł��B �@�d���̓o�b�e���[����(�q���[�Y�͌o�R)�̏펞�d�����]�܂����ł����AACC�d���̂悤�ɃL�[ON�̎������d��������d���ł����\�ł��B �@�A���AACC�̂悤�ȏ�����d����������ꍇ�A��H�̓d����OFF�ł��X���[�������v��u���[�L���ȂǃX�C�b�`�������������v�͓_�������H�Ɛڑ�����Ă��܂��̂ŁA�uIC�d����OFF�Ȃ̂ɓ��͒[�q�ɓd�����������v�悤�ȏ�ԂɂȂ邱�Ƃ��l�����A�����Ȃ��IC���j��Ă��܂��̂ł����Ȃ�Ȃ��悤�e���͒[�q����d���Ɍ����ă_�C�I�[�h�œ��͓d���𗬂��ĉ�H�̓d���ɂ��Ȃ�悤�ɂ��Ă��܂��B �@���̉�H�Ō����ł��郉���v�́u�d���E21V/25W�v�܂łł��B (�����v�d����ʂ�SD���e�ʂ̂��̂ɕς�������Ƒ傫�Ȃv������)
�@LED���͌��o�ł��܂���B�@�w�b�h���C�g�̂悤�ȑ�d���𗬂������v�̏ꍇ�́A�_���p�d���͉�H���̃_�C�I�[�h�o�R�ł͂Ȃ��A�����ɕʓr�����[�Ȃǂ���Ĕz������K�v������܂��B ���Ԏ� 2012/2/13
|
||
| ���e 2/15 |
2/15 ���̓x�͂��ʓ|�Ȃ��Ƃ��肢�v���܂����B �d�q��H�͖��n�Ȃ��̂ŊȒP�ȉ�H�����肢���܂����B �ڍׂȐ����͑�ώQ�l�ɂȂ�܂����A�����p�[�c�𑵂��쐬�������Ǝv���Ă��܂��B ���ɗL���������܂����B (������]) �l
|
||
| ���̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H | |||
|
�����y�����q�������Ă��������Ă܂��B 20�`30�x�����m���ăt�@����12V�ʼn�H�Ȃǂ��Q�Ƃ��Ă����̂ł����A�����悤�ȖړI�E�����ŁA��ʼn�H��g�܂Ȃ��Ă��A110V/13W�t�@���Ɖ��x30�x��ON����110V/1A��i�̃o�C���^�����T�[���X�^�b�g�ő�p�\�ł��傤���H�����͏H�t�ł݂������i�����ł��B��i�Ȃǂ���g���邩�ȁH�Ǝv�������̂�K���ɋL�ڂ��Ă��܂��B �f�l�Ȃ���Ɏv�������Ԑڑ����@�Ƃ��ẮA�ǃR���Z���g����v���O�ɐڑ������R�[�h�ɁA�T�[���X�^�b�g��100V�t�@����Ɍq�������Ȃ̂ł����B ������������100V�������̂ɒ�R�͂���܂����A�A�_�v�^�[���g��Ȃ�/��H�����Ȃ��ł��Ȃ�X�b�L���������Ȃ̂Ŏv�����܂����B �p�r�Ƃ��ẮA�Ȃ��悭�d�q�����W���I�[�u���ŗ��������邽�߁A���ɃI�[�u���g�p���Ɏ��ӂ����\�M���Ȃ��Ă���A�ׂɂ���①�ɂɂ��_���[�W�������Ȃ����A�Ƃ����s���ɑ���Ώ����������̂ł����B �Ȃ����L�Y�����e�ł��݂܂���A��������������K���ł��B �ǂ� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�T�[���X�^�b�g�Ƃ������̂́A���X���������g�����p�ɔ������ꂽ���x�X�C�b�`�ł�����A���g���ɂȂ���T�[���X�^�b�g�̒�i�����ׂ����イ�Ԃ���S��ON/OFF�ł��鐻�i�Ȃ���v�ł��B �@���̎ʐ^�̂悤�ȁA���Ȃ�̑�d�͑Ή��ŁA���x�ݒ���_�C�����������Ŏ��R�ɉςł��邤��ȃT�[���X�^�b�g���ƈ��S�ł��B
�@���̎ʐ^�̂悤�ȁA���Ȃ�̑�d�͑Ή��ŁA���x�ݒ���_�C�����������Ŏ��R�ɉςł��邤��ȃT�[���X�^�b�g���ƈ��S�ł��B�@�p���[�g�����W�X�^�Ɠ����`��TO-220�^�ŁA���x��50���ȏ�Ŋe��Œ�l�̈����Ďg���₷�����^�T�[���X�^�b�g�Ȃǂ������Ă��܂��B (���̃V���[�Y�ɂ�30���ȂǒႢ���x�̕��͂���܂���) �@���������Ƃ͖����ł����A�H�t��������d�M��30���Œ�̃T�[���X�^�b�g (110V/1A)�������Ă��āA�H�t���Ŕ����Ȃ猋�\��Ԃ̂悤�ł��ˁB �@�������Ă݂�ƁuF-1�T�[���X�^�b�g(BF130L)�v���Ďg���Ă������HP������A�ʐ^���ʼn��H�Ⴊ�Љ��Ă��܂��B �@http://kura3.web.fc2.com/thermo2.html �@���Ȃ�̑f�l�̕��ł������ł������ȃR���Z���g�����P�[�u���ɓ���邾���̉���Ȃ̂ŁA�t�@���̃P�[�u���̂ق�����ɉ������Ȃ��Ă��A���������u�T�[���X�^�b�g�t�������P�[�u���v�����ΕK�v�ɉ����Ă�������ނ����ł��݂܂��ˁB �@�����܂ŁA�ݒ艷�x�͌Œ��Ŏ��R�ɕύX�͂ł��܂��ǁB ���Ԏ� 2012/2/7
|
||
| ���e |
�����̉��肪�Ƃ��������܂��I �܂��Ƀ����N��\���Ă�����������ŏЉ��Ă��鉄���P�[�u�������ł������ł��B �����A���d�r�Ȃ�DC���{���g�̉�H�H��ƈ���āAAC100V���������Ƃő����r�r���Ă���܂��B���ꂾ������AC�A�_�v�^�ʼn�H��g�߂A�ƂȂ�܂����A����̓V���v���ɍs�������̂ŁB �����N��ł̓J�v�����g�p���Ă���܂����A��͂肱�������������[�q���x�X�g�Ȃ�ł��傤���HAC�̂��ꂼ��̐����m�̐≏�����������肵�Ă�Ζ��Ȃ��悤�Ɏv���܂����A�������S�Ď��ȐӔC�Ȃ̂͏��m�̏�ł����A�ڑ�������ΉԂ��U���ĉΎ��ɁE�E�E�͔��������B�B�B ���݂܂���A���������������܂��ł��傤���B �ǂ� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����A������O�����肵��������M�{�V�[�q�������������Ǝv���܂��B �@�ʂɁE�E�E��ɃR�l�N�^��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����@��������܂���A�R�[�h����Đ�����킹�Ă˂����ăn���_�Â����āA�≏�e�[�v(�r�j���e�[�v��)�����邮�銪���Đ≏�������Ă��Ε��ʂ̉ƒ���ł̎g�p�Ȃ���͖����͂��ł��B �@�S�z�ł���A�≏�e�[�v������������������ƌ����ڂɁA���邮��̉𑝂₵�Ă��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�M�{�V�[�q��R�l�N�^�����āA�O�������̃R�l�N�^�p�̂��̂��g���Ό����ڂ̓X�}�[�g�ł��ˁB ���Ԏ� 2012/2/7
|
||
| �H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I | |||
|
�H���̃g���C�A�b�N�������75�����炢���������o���Ȃ��̂ł��������͉����ɂ���̂ł��傤�� ���܂��� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�u�g���C�A�b�N���\������L�b�g�v�ł���A���������ς���Ă��Ȃ�����A�������́u�g���C�A�b�N�������H�̐����v���C�̍��ڂ̂Ƃ����Ɂu�R���g���[�����ɂ����ꍇ�ɂ́c�v�ƁA�������@�������Ă���܂��B �@��H�E���i�̖��ł���A����ɏ]���ĉ����ł���͂��ł��B �@���i���������Ă����P����Ȃ��ꍇ�A�������̏H���d�q�ɂ��₢���킹���������B �@�������̌����Ŗ����ꍇ�́A�L�b�g�������`���ɏ�����Ă���悤�Ȏg�p���@(�Ή�����@��)�ł͖����A�������Ȃ��g�p���@������Ă���Ƃ��E�E�E�B ���Ԏ� 2012/1/27
|
||
| �ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� | |||
|
�������܃o�C�N�̉������ł��B �W���ŕt���Ă���A�i���O�^�C�v�̔R���v�����O���āA�R���������Ă����烉���v���_������u�x�����v�ɕύX�������ƍl���Ă��܂��B �R���^���N�ɂ��Ă���Z���T�[�ׂĂ݂��Ƃ���A�R������t�̂Ƃ��ɂ�10���A�R���^���N����ɂȂ��100���ɂȂ邱�Ƃ�������܂����B �ʏ�͏������Ă��āA��R�l��90���ȏ�ɂȂ�����_�������H����肽���Ǝv���܂��B �Ȃ��d����12�{���g�Ŏg�p����C���W�P�[�^�[��12�{���g�œ_������^�C�v�̂��̂ł��B �ǂ̂悤�ȉ�H�����悢�������Ă��������Ȃ��ł��傤���H�X�������肢���܂��B �c����Y �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@���̏��ł��ƁA�g���Ă���R���ʃZ���T�[�͈�ʓI�ȁu100���^�C�v�v�̂悤�ł��ˁB �@�R���ʃZ���T�[�����̂悤�Ȓ�R���̏ꍇ�A�����̓d���𗬂��Ē�R���[�Ɍ����d���𑪂�Β�R�l�̑召��m�邱�Ƃ��ł��܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�����ŁA�Z���T�[�Ɏア�d���𗬂���H�ƁA�����P�\���͑S�������ŃZ���T�[�̂����ɔ��Œ��R���q���Ŏ蓮�œd����ݒ�ł����H�����A���ꂼ��̏o�͓d�����r���Ă�邱�ƂŃZ���T�[�̏o�͓d�����ݒ�d����荂�����Ⴂ���ʂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@�Q�̓d���̔�r�E����ɂ̓I�y�A���vIC LM358���g�p���܂��B �@�d����r��H�ɂ�R6�Ńt�B�[�h�o�b�N�������A����l�Ƀq�X�e���V�X���������邱�ƂŎc�ʒl�Ő������x�͈̔͂ł͎c�ʌx�������v���o�^���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B �@��́ALM358�̒��̃I�y�A���v���P�]��̂Ń{���e�[�W�t�H�����ɂ���LED�_������v�h���C�o���쓮����ׂɎg�p���܂��B �@�R���ʂ����Œ��RVR1�Őݒ肵���ʂ�菭�Ȃ��Ȃ��LED1���_�����܂��B �@�����v�h���C�o��H������Ă���ADC12V�̓d���Ȃ�LED��������d���̑傫�ȃ����v��_�������邱�Ƃ��ł��܂��B �� ���g�p�̃����v�����������܂���ł����̂ŁA�����v�h���C�o�̕����͕s�v�Ȃ���Ȃ��Ă��悢�ł� �@�x������_��������ݒ�l��VR1�Œ��߂ł��܂����A��H�}�ʂ�ɍ��������ς��ɉ�100���ŃZ���T�[��100���u���v�ɑΉ��A�E�����ς��ɉ�0��(���Ȃ��̎Ԏ�ł�10���ł��������ł͒[��0���܂őΉ�)�ŃZ���T�[��0���u���^���v�ɑΉ����܂��̂ŁA90�����炢�̎c�ʂŌx������_��������ɂ͍�����10%���x���Ƃ���ɒ��߂��Ă��������B �@�X��(�ق��̕�������ĕʂ̗p�r�Ŏg�p����ꍇ�̂��Ƃ��l����)�AVR1�Ŏc�ʂO���疞�^���܂ł̊Ԃł��D���ȂƂ���ɒ��߂ł���悤�ɂ��Ă��܂��B �@�����u�ςɂ��Ȃ��Ă��A90���̂Ƃ���Œ�ŗǂ��v�Ƃ����̂ł���AVR1�͔��Œ��R�ł͂Ȃ����ʂ̌Œ��R��90��(�A��90���Ƃ������͔����Ă��Ȃ��̂�30�����R�{����Ȃ�)�ɕς��Ă��ǂ��ł��B ���Ԏ� 2012/1/25
|
||
| ���e 1/26 |
��H�}�y�і��m�Ȃ������A�ǂ������肪�Ƃ��������܂��B ��R���Q�A�R�̉�H�Ŏ����ł���̂��ȁH�ƁA���R�ƍl���Ă��܂������A���ۂɂ͂��̗l�Ȃ��̂��K�v�Ȃ̂��Ƌ����Ă��܂��B ����قǂ̂��̂������Ƃ����Ԃɂ��������������ƂɁA�����Ƌ����Ă��܂����B �Ƃ͂����A�Ȃ�Ƃ�����ł������ȋC�����܂��̂ŁA���N���U��ɔ��c���Ă������Ă݂����Ǝv���܂��B �{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �c����Y �l
|
||
| ���[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� | |||
|
���߂܂��āB�Z���T�[�^�C�v�̃u���V���X���[�^�̋쓮��H�������Ē����܂���ł��傤���H�i�Ԃ̃A�N�Z���̂悤�Ƀ{�����[���Ŗ���]����ō���]�܂ŘA���I�ɕϑ��o���镨�j �g�p�p�r�̓G�R�f���ƌ�������d�C�����ԋ��Z�ł��B �G�R�f���̓��e��12�u3�`���̉��~�d�r����g��40���̊Ԃ� �̏d60�����̃h���C�o�[���^�]����d�C�����Ԃ��ǂ̈ʑ��s�ł��邩���������e�ł��B�i���15�����ʑ��s�ł��܂��j �g�p�u���V���X���[�^��12�u50�v�@���[�^�[�ʒu���o�p�z�[���h�b�͏o��5�u�ł����B�i��ʓI�ȃZ���T�[�^�C�v�̂q�b�J�[�̃u���V���X���[�^�[�Ɠ����ł��j �쓮��H�ɂ��肢������������5����܂��B �@�쓮��H�̓���d����6�u�`20�u�ł��肢���܂��B �A��i�d���͘A��20�`�܂ł̑Ή������肢���܂��B �B�o���邾�������d�͂ł��肢���܂��B(���[�^���Ȃ���Ԃ�30���`���炢) �C120�x�ʓd�ł��肢���܂��B �D���Ȃ��d�͂��ő���Ɏg�����߂ɓ��������ƉσL�����A�����������Ē��������B �l����镨�̉�H�ƌ��������S�O����邩������܂��A�G�R�f���J�[�͍ō�����22�����ʂ̒ᑬ�ł��̂ň��S�ł��B ���̑��ɋ��͂ȃf�B�X�N�u���[�L��2��A�@�B�I�Ƀ��[�^�̎������b�N����@�\�A����~�X�C�b�`��3�d�Z�[�t�e�B�[������Ă��܂��B �����Z�̒��A�s�^�Ȃ��肢�Ő\���������܂���B���܂Ŏg�p���Ă����R���g���[���͏���d�͂��������т��ǂ�����܂���ł����̂ŁA�ǂ��ɂ������Ŕj�ł��Ȃ����̂��Ǝv���܂��Ă����k�����ĖႢ�܂����B �ȏ�A��낵�����肢�v���܂��B �n�X�e���C �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�n�X�e���C�l�͂��߂܂��āB �@�����ւ�ڂ����������ŁA�K�v�Ȃ��̂������ɑz�������܂����A���̎茳�ɂ̓u���V���X���[�^�[������܂���B �@�������Ƀe�X�g���ł��Ȃ��̂ŁA�������Ɖ�H�}�������āA�e�X�g���āA�f�ڂ���Ƃ������Ƃ���y�ɂł��܂���̂ŁA���̂��˗��ɂ͂��������邱�Ƃ��ł��܂���B �@�\�������܂���B �@�܂��A���̂��˗����e���ƃf�B�X�N���[�g���i��g�ݍ��킹�邾���ł͕s�\�A�܂��͂����ւi���������Ȃ�A���^�}�C�R���̂悤�Ȑ��䑕�u���g���đg�ݗ��Ă�̂���ʓI�ł��B �@PIC�}�C�R�����̃v���O�����͂�����̃R�[�i�[�ł͎�t�͈͊O�Ƃ����Ă��������Ă��܂��̂ŁA�c�O�Ȃ��炱����ł��ł�����e�ł͂������܂���B �@�����āA�u���������ƉσL�����A�����������Ē��������v�Ȃǂƍ��x�ȃv���O��������(�܂������s���ɉ������钲�ߗp�{�����[�����킯�ł͖����ł��傤�c)���K�v�ȓ��e�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����������e�ł������H�v����v���O�����܂ŁA�����u�ł̎��������킹�Ďd�l���ϋl�߂Ă䂭���d���Ƃ��Ď����Ă��������悤�ȓ��e�ł��ˁB �@���͐���n�̈ꂩ��̐v�E�e�X�g�y�ъJ���ƂȂ�܂��ƁA���\���~�`(���e�ɂ���Ă����S���~)�̊J����Ղ���悤�Ȃ��d���ƂȂ�܂��̂ŁA���ꂾ���̗\�Z�ƊJ�����Ԃ����p�Ӓ�����Ȃ�����Ă���������������܂���B �@�����A���N���瑱���Ă���d���̊W�ō��N�����\�Z�����A����������|����Ȃ��d����ʌn���Ŏł��邩�Ƃ����ƁE�E�E���Ȃ�X�P�W���[���I�ɂ�����̂ł����B ���Ԏ� 2012/1/21
|
||
| ���e 1/21 |
����ɂ��́B �f�����ԓ��A�L��������܂��B ���̋��߂鐫�\�̃R���g���[���삷��̂ɂǂ̈ʂ̘J�͂Ǝ��ԂƎ������K�v�������ł��܂����B �R���g���[���̖��͕ʂ̃A�v���[�`�ʼn������Ă����܂��B ���̑��ɉ��P���ׂ�������������݂�̂ł��������ׂ��Ă����A�\����̏��ڎw���܂��B �܂��������������Ƃ����鎞�͑��k�����Ē����܂��B ���̎��͂�낵�����肢�v���܂��B �n�X�e���C �l
|
||
| �r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� | |||
|
�r�N�^�[�r�f�I�f�b�L�iHR-F9�j��UV�`���[�i�[�uQAU0086-002�v���s�ǂȂ̂ŁA�o���邾�������ȕ��@�ɂē��肵�����B �ܘ_�A�䂪�Ƃ̓f�W�A�i�ϊ��ɂăA�i���OTV�Ō��Ă���܂��B ���[�J�[�́A�S�C725�~�ōɂ͂���炵���̂ł����c�B ��낵�����肢���܂��B ���Ȃ���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@10�N�قǐ̂̓r�f�I�f�b�L�^TV�p�̃`���[�i�[���j�b�g�Ȃ�H�t������{���̃W�����N����100�`500�~���x�Ŕ��������̂ł����A�����������N�͕��i�Ƃ��Ĕ����Ă���̂�������������܂���B �@���[�J�[�ł����낻���C���i�̕ۑ�����(�����I������8�`10�N���x)�����X�ƏI����Ă���̂ŁA�T�[�r�X���܂������Ă���Ȃ炻����̂�������ł��傤�B���[�J�[�ł������Ȃ�O�ɁI �@���̑��A������@�Ƃ��Ă̓l�b�g�I�[�N�V�������Ń��J������ꂽ���^�r�f�I�f�b�L��100�`500�~���炢�ŏo�i���ꂽ���ɔ����āA�����Ă���`���[�i�[���ĈڐA����Ƃ��H (�����͈ꕔ�̃r�f�I�f�b�L�Ƃ��A�b�r�`���[�i�[����ꂽ���ɂ̓I�[�N�V�����ŕ��i���p�ɃW�����N���ďC�����Ă��܂�) �@�ŏ��ɏ������悤�ȕ��i���x���Ŕ̔�����Ă����`���[�i�[���ƁA�������H�t�������{���Ńz�R���������`���[�i�[���j�b�g���@��o���Ĕ������Ƃ��Ă��A���^�Ԃ̑S�������i����ɓ��鎖�͂܂������ł��傤����A���������Č`���[�q�`����Ⴄ���̂������ʼn�͂��Ĕz������K�v������܂����A�`�����l����I�Ԑ���d�������Ԃ�Ⴄ�ł��傤���炻����ϊ������H�Ȃ��v���Ȃ��ƁA�P���ɍ����ւ��邾���Ŏg����悤�Ȃ������͎̂�ɓ���Ƃ͎v���܂��B ���Ԏ� 2012/1/20
|
||
| ���������R���łq�b�T�[�{������H | |||
|
������RC�T�[�{���X�O�x�������R���p�N�g�ŁA�o����ΊȒP�ŁA����ɂł���Έ�����H�������Ă��������B �d�l�Ƃ��ẮA�T�[�{����H�̓d�������āA�����R����A�̃X�C�b�`������90�x��]�BB�̃X�C�b�`��������90�x�t��]���Č��ɖ߂�B �����̕����́A10M���炢���ł���āA�������ɂ������̂���]�ł��B �T�C�Y�̓����R�����L�������������x�i�d�r�܂ށj�A�T�[�{�����g�C���b�g�y�[�p�[�̐c���x�i�d�r�����j�B �R�X�g�͂ł���ޗ���5000�~�ȓ��i�T�[�{�㏜���j�B �p�r�F���u����̂ł��郍�b�N�@�\ ���Z���A�������̎҂ł����ǂ�����낵�����肢���܂� ���� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�ȑO������]���o�Ă����u�������̃����R���v�Ɠ������A315MHz�їp���������W���[�����g�p����A�������͔��ɃR���p�N�g�ɂȂ�܂��B �@���M���͂��������ꂾ���ł��B 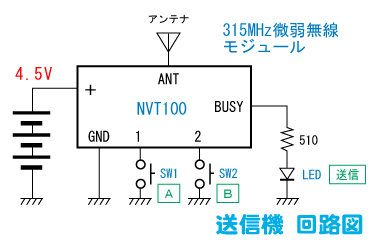 �@��ȕ��i�͖������W���[��(NVT100)��������܂���B �@����ɃX�C�b�`�Ƒ��M����\��LED(�ƒ�R)�����邾���ł��B �@�d�r���݂ł��L�����������ɗ]�T�Ŏ��܂�܂��B �@�ŁA��M�����u�R���p�N�g�ŁA�o����ΊȒP�ŁA����ɂł���Έ�����H�v�ɂ���ƂȂ��PIC�}�C�R�����g���E�E�E 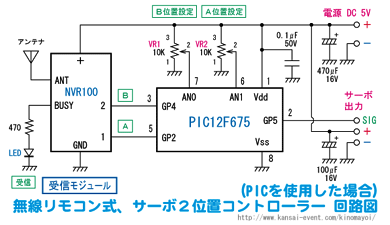 �@PIC�̃v���O�����́w���W�R���T�[�{�u�Q�ʒu�v�R���g���[���x�Ō��J���Ă�����̂��������������Ďg���Ă��������B �@�P�L�[���͂̃v���O�������A�Q�L�[���͂ŏ�ԕێ�����悤�ɏ��������邾���Ȃ̂ŁAPIC�v���O������������Ȃ�J���^���ȕύX�ł��B(������ł͕ύX���@�Ȃǂ͂������������܂���) �@PIC�̃v���O�����Ȃǂ��ł��Ȃ����Ȃ�A�f�B�X�N���[�g���i��g�ݍ��킹�ēd�q��H�ŖړI�̉�H�삷�邱�ƂɂȂ�܂��B �@PIC�g�p�̂悤�ȕ��i���̏��Ȃ��Ƃ͂䂫�܂��A��r�I���Ȃ����i�ō�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�g�C���b�g�y�[�p�[�̐c���炢�̑傫���ɂ͗]�T�œ���܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�� ��M���W���[�� �@315MHz�і��������R�����W���[�� MVR100���g�p���đ��M�@����̓d�g����M���A�o�͐M���܂��B �@��p���W���[�����g�p���܂��̂ŁA�����ӏ��Ȃǂ͂���܂���B �� �I�����b�`��H �@�����ő��삳�ꂽ�M�������ɁA�u�`�ʒu�v�u�a�ʒu�v�̂ǂ���̈ʒu���w�����邩�̑I�����L�����郁�����[��H�ł��B �@NAND�Q�[�gIC 74HC00���g�p����RS�t���b�v�t���b�v�ł��B �@�d���������ɂ͏�Ԃ��s��(�ǂ����I������邩���܂��Ă��Ȃ�)�Ȃ̂ŁA�p���[�I�����Z�b�g��H�œd���������ɂ��a��(��������ʂƂ���)��I�����܂��B �@�ǂ��炪�I��Ă��邩��LED2�ELED3�Ŋm�F�ł��܂��B �� �ʒu�p���X�쐬��H �@�T�[�{�̈ʒu���w�肷��T�[�{�M���������H�ł��B �@�T�[�{�M����20mSec���ƂɈʒu���M����p���X�M���Ȃ̂ŁA�܂����^�C�}�[IC 555�Ŗ�50Hz(20mSec��)�̃^�C�~���O�p���X�����܂��B �@����20mSec�^�C�~���O���ƂɁAC-MOS�����V���b�gIC 74HC221�ŃT�[�{�ʒu�M�������܂��B �@�T�[�{�̈ʒu���߂ɂ�1.5mSec���𒆐S�Ƃ����}1mSec(180�x�̏ꍇ)�̃p���X�M���A���Ȃ킿0.5mSec�`2.5mSec�̃p���X����������̂ŁA��R�E�R���f���T�̒萔�͂��͈̔͂̐M��������l�Ƃ��A����͏��������L���ڂɖ�0.35mSec�`3mSec�̊Ԃ̐M�����ł��܂��B (�T�[�{�͋@�B�I�Ȍ��E�ȏ�ɂ͉��܂���̂Œ��ӂ��Ă�������) �@�`���E�a�����ꂼ��VR2�EVR1�ňʒu�߂ł��܂��B �@����74HC221�̃����V���b�g��H�͑I�����b�`��H�̏o�͂ɂ���`���܂��͂a���̂����ꂩ����̂ݍ쓮���A���Α��̓��Z�b�g���ꂽ��Ԃœ��삵�܂����B �@�Q�̃^�C�~���O�p���X�o�͂�SD1�ESD2�Ń_�C�I�[�hOR����A���ۂɃp���X�o�͂���Ă���ق��̐M�����T�[�{�ɏo�͂���܂��B �� �d����H �@���ɓd���̎w��(�d�r���g���Ƃ�)�������������߁A�T�[�{��74HC�n��IC�����삷��d��4.5�`6V�̒����d����ڑ����Ă��������B �@�S�̂Ƃ��Ă͕��i�������Ȃ��A�u�g�C���b�g�y�[�p�[�̐c�v���炢�̃T�C�Y�ɂ͗]�T�Ŏ��܂�͂��ł��B ���Ԏ� 2012/1/12
|
||
| ���e 1/13 |
�����Z�̒��A ��H�}�A�b�v���Ă��������A���ɗL���������܂��B<(_ _)> ��������H�}���ő����������悤�����܂��B ���� �l
|
||
| �lj� ���� |
�@�������W���[��NVT100�ENVR100�͊��ɐ��Y�I���i(��Ў��̑��݂��Ȃ�)�̂��ߌ��݂͓���ł��܂���B �@��ւƂ��čŋ߂̃��{�b�g�E�}�C�R���E�v���p�����ʐM�Z�p�Ȃǂł悭�g���������^ZigBee�������W���[�� TWE-Lite(�g���C���C�g)�Ȃǂ͂������ł��傤���H �@�����ɂ����܂����ő�PKm�I�H���d�g����т܂����A�㋉�҂Ȃ疳�����W���[�����̂Ƀv���O�������������ނ��ƂŎ��ӂɃ}�C�R����Ȃǂ�ڑ������ɒP�Ƃŗl�X�ȗp�r�ɓW�J���邱�Ƃ��\�ł��B �@�d�q�H��p�r�ł���ADIP�T�C�Y��ɕK�v�Ȃ��̂���������Ă��ăJ���^���Ɉ�����TWE-Lite DIP�͂������ʂ̓d�q���i���o�Ŏg���ĕ֗��ł��B 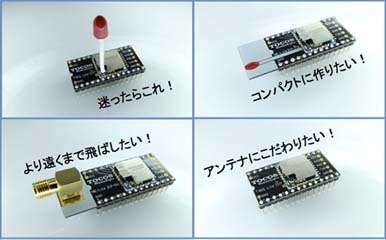 |
||
| ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I | |||
|
���̓x�A���߂ēd�q�H������܂����B EK-Japan ��PS-3242����(10�ȏ�)�ݒu�����ׂĂ̒ʉߎ҂̍��v���A��PS-3245�ŕ\�����������̂ł��B PS-3242�̂��ׂẴI�[�v���R���N�^�[�o�͂���PS-3245��CY-IN�ɐڑ�����ƁA�i���������J�E���g���Ă���悤�œ����2��݂̂̃J�E���g�����ł��܂���B �P��ł̐ڑ��ł́A������ƃJ�E���g�����Ă��܂����B �Q����Ȃ��ł̐i�����������m������̂��������ɋL�ڂ�����܂������A�L�ڂ��ꂽ�z���͂��Ă���܂���B �P���ɂ��ׂẴI�[�v���R���N�^�[�o�͂���PS-3245��CY-IN��G�ɐڑ����܂����B �ePS-3242�ɂ́A�����[�o�͂�����A�����[�͂��ׂĂ̂��̂Ő���ɍ쓮���Ă���悤�ŁA�J�`�J�`�Ɣ������Ă��܂��B ������͂���܂����H yamaturi �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@����ELEKIT�̐v�҂ł��̔��҂ł������̂ŁA�����̃L�b�g�̓��́E�o�͂̉�H���ǂ��Ȃ��Ă���̂��m��܂���B �@��H�}���������Ɂu�ǂ��ł��傤�H�v�I�Ȏ��������l�ɂ́A�ǂ����ǂ��ŁA�����ǂ���������̂��̉͂ł��܂���B �@���ʂ́A�I�[�v���R���N�^�̏o�͂Ȃ炽���������Ɍq���ł����C�ł���ˁH �@�����v���ĕ���Ɍq����Ă���̂��Ǝv���܂��B �@����łQ�ȏ�ڑ������ꍇ�ɐ���ɃJ�E���g���Ȃ��̂ł���A�ǂ��炩�̃L�b�g���ُ�Ȃ̂ł��傤�B �@�ł��A��H�}�������A�����������̂Ɏ��ɂ́u�����̕��i���~�~�ɕς��āA��H�}�͂����ŁE�E�E�v�Ȃ�Ď����悤������܂���B �@����ł́A�J�E���^�̓��͕��̓d���́A���������W�b�N�l�Ƃ���H��L�ʂł���d���͈͂ɂȂ��Ă���̂ł��傤���H �@���̂�������e�X�^�[�ő����Ē��ׂĂ݂Ă��������B �@���Z���T�[����P�䂩�牽����q�������ꂼ��̏�Ԃ̂Ƃ��A�܂�����ɃJ�E���g���鎞�Ƃ��Ȃ����Ƃ��A�����̓d���l�����퉻�ǂ������ׂ���A�������牽�������Ă��܂��H �@������������A��������P����������l���Ă݂Ă��������B �@�Ă��Ƃ葁���A�I�[�v���R���N�^�o�͂����ɂ���̂ł͂Ȃ��A�������������[���t���Ă���̂ł����烊���[�ړ_�����ɂ��ăJ�E���^�̃X�C�b�`���͂ɂȂ��ł��܂��̂ł������̂ł́H �@�����[���J�`�J�`���Ă�̂Ȃ���ɂ͔������Ă���͂��A�����Ă��̐ړ_�����Ɍq���Ȃ牽100�q���ł��A�ǂꂩ����������J�E���^�͌v������͂��A�E�E�E�S�Ắu�͂��͂��v�ł����A����ňُ킪�N���錴���͑z���ł��܂���B �@���ꂱ���A�J�E���^�[�L�b�g�̓��͕�����������ȓ��͂ŁA���������ӂ��ɐړ_���R�Ȃ��Ɖ����s����N����悤�ȉ�H�}�ɂȂ��Ă���Ƃ��ł��Ȃ���B ���Ԏ� 2012/1/10
|
||
| HT7750A�̏o�͓d���ύX | |||
|
HT7750A�̏o�͓d���ύX�ɂ��āB �l�b�g�Ō������Ă�����AHT77xx�̏o�͓d����ύX������@���������Љ��Ă���̂ɖڂ����܂�܂��B 2�̕��@��������܂����A����͎���̂�����@�ł����̂ŁA���������������@���l���A��H��g�ݓ����𑪒肵�Ă݂܂����B �܂������ȓ����������Ă��܂��A���Q�l�ɂȂ�K���ł��B http://samidare.jp/jr7cwk/lavo.php?p=log&lid=263510 jr7cwk �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@HT77xx�͕֗��ł��ˁB �@LED�����v�̉����p�ɑg�ݍ���ł���l�������悤�ł����A�������̉����̔��W��2�`3������g�p�p�̒�d���h���C�u��H�Ȃ�����Ɩʔ�����������܂���ˁi�O�O�G ���Ԏ� 2012/1/9
|
||
| �d���v���R�v�ɂ���H | |||
|
�d���v���R�v�ɂ���ɂ͂ǂ�������悢�ł����H���x�͂���Ȃɗv��Ȃ��ł��B�����ɂ��邽�߂�100�~�V���b�v�̓d�r�`�F�b�J�[�̓d���v�𗘗p���悤�ƍl���Ă��܂��B �Ƃ����[ �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@��R�v�ȂǂɎg�p���郁�[�^�[�͓d���v�ł͂���܂���B�d���v���g�p���܂��B �@100�~�V���b�v�̓d�r�`�F�b�J�[���烁�[�^�[�����o���Ďg���ꍇ�͒��ӂ��Ă��������B �@����͓��ɐ��x�����߂��A�uxxx���Ƃ�����R�l��m�肽���v�Ƃ����g�����ł͂Ȃ��A��R���L�邩��������A��R���傫���������������x��������Ȃ��Ă��ǂ������Ȃ��˗��ł�����A�����ɐ��l�𑪂��悤�Ȓ�R�v�Ŗ����Ă������ł��ˁB 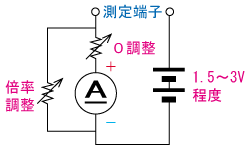 �� �e���Œ��R�͒�R�l�O�ɉđ���[�q���V���[�g����ƏĂ��܂��B���������Ƃ���̕ی��H�͂Ȃ��̉�H�}�ł��B �@���g���ɂȂ��郁�[�^�[���ʂ����ĉ���A�t���X�P�[���̕i���A�܂�������R�������̕i���ȂǁA��S������܂���̂ŏڂ�����R�l�����������邱�Ƃ͂ł��܂���B �@���茳�̃��[�^�[�ɂ��킹�āA�K���ɐ��S���`���\�j�����x�̔��Œ��R��g�ݍ��킹�āA�������̑��肽����R�l�͈̔͂ł������̂��D�݂Ń��[�^�[�̐j���U��悤�ɁA�������ŃJ�b�g�A���h�g���C���Ă��������B �@���A100�~�V���b�v�̓d�r�`�F�b�J�[�Ɏg���Ă��郁�[�^�[�ɂ́A������x�̓d���܂ł͑S�R�j���������A����_�ŋ}�Ƀr�����Ƒ傫���U��āA�܂����̏����悩��͂��܂蓮���Ȃ��Ƃ����A�d���E�d���E��R�̂ǂꂩ�ł����肷��p�r�ɂ͂قƂ�ǎg�����ɂȂ�Ȃ����[�^�[�������Ă��鏤�i������܂�������A100�~�V���b�v�Ŏ�ɓ��郁�[�^�[�͂��܂�M�p���Ȃ��ق��������ł���B ���Ԏ� 2012/1/5
|
||
| �S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) | |||
|
N�Q�[�W(�S���͌^)�̋쓮�p���[�^�[����{���̓S���ȂǂɎg���Ă���VVVF�C���o�[�^�[���ۂ������o����H�������Ă������� �o����Ώ��c�}�d�S�̂P�O�O�O�n�̂悤�ȉ����o��悤�ȉ�H�������Ă������� (������]) �l
|
|||
| ���Ԏ� |
�@�ߋ��ɑS���������e�̓��e�����Ă��܂��̂ŁA�u�S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@�v���������������B ���Ԏ� 2012/1/5
|
||
| �͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H | |||
|
�d�Ԗ͌^���ďo��������̂ɔY��ł��܂��B �P��d���P�Q�u�ŐؑփX�C�b�`�͓��{�J��v�s�|�Q�W�`�s�i���n�m���n�e�e���n�m���j�Q�ɑo���U�[�q�^�C�v)���g�p���A�d���̃v���X�}�C�i�X��ؑւ��邱�ƂŃ��[�^�𐳓]�i�O�i�j�^�t�]�i��i�j�����������Ă��܂��B�������Q�̉w�̊Ԃ��s�������������̂ł����A�w�ɂ͂��ꂼ�ꓞ�����o�X�C�b�`�i�I�������r�g�k�|�v�Q�T�T�j��ݒu���A�d�����Ւf���d�Ԃ��~�߂��̂ł����ŏ��̓����ł͓d�Ԃ��~�܂�܂����A���̌�X�C�b�`��ؑւ��Ă������܂���B�d�����Ւf���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���̂ōďo���ł��܂���B���b�`���O�����[�Ȃǎg���Γd�����A�ł������ł����A�����̓����d�Ԃ��������ɂȂ��Ă��܂��܂����B�A�h�o�C�X�����肢���܂��B �� �l
|
|||
| ���Ԏ� |
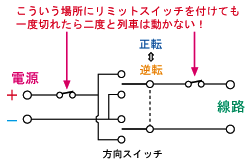 �@���������āE�E�E�w�ɐݒu�������~�b�g�X�C�b�`(SHL-W255)��12V�̓d���܂��͗�Ԃւ̋����o�H���̂���Ă��܂��Ă���̂ł���ˁB
�@���������āE�E�E�w�ɐݒu�������~�b�g�X�C�b�`(SHL-W255)��12V�̓d���܂��͗�Ԃւ̋����o�H���̂���Ă��܂��Ă���̂ł���ˁB�@���ꂾ�ƈ�U�ǂ��炩�̉w�ŗ�Ԃ̓����ŃX�C�b�`���ꂽ��A��Ԃ����̈ʒu�Ɏ~�܂��Ă������͓d�����i�v�ɐꂽ�܂܂Ŕ������ɂ��Ȃ��ł���ˁB �� �z���ɂ���ẮA�}�Ƃ͍��E���t(�d�����Ɛ��H�����t)�̏ꍇ������܂� �@����ł͑��s�����̃X�C�b�`�Ό����ɏo�������悤�Ɛ�ւ��Ă��s�N���Ƃ������܂���B �@����ƁE�E�E�܂��]�k�ł����u���b�`���O�����[�v�Ƃ������P�ꂪ�o�Ă��܂����A�����������玗����H��p�r�łǂ����ł����������i���g����Ƃ����o�Ă��āA������Q�l�ɂ��Ă݂�����ǂ����܂��䂩�Ȃ������Ƃ��H �� ���H�͒P���ŁA���[�̂`�|�a�w�Ԃ������^�]�������� �@�@�@(�~�`�̃��[�������邮����̂ł͖��� �� �����d�v) �� �I�[�w�ɒ�������(�X�C�b�`�̈ʒu��)�����Ŏ~�܂� �� ��Ԃ̑��s�����X�C�b�`�ɂ�����A���Ԃł��� �Ƃ����@�\�������ł�������̂ŁA���������̃X�C�b�`�R�����ŁA�z����ς��邾���łł��܂��B �@���́A���s�������ւ���X�C�b�`�����J��WT-28AT�݂����ȃI���^�l�[�g(�|���ƃ��b�N����)�^�C�v�ł͂Ȃ��A��𗣂��ƒ����ɖ߂��Ă��܂��悤�ȃ������^���[�^�C�v���Ɖ��炩�̃��b�`�@�\�ł����Ȃ��ƁA�X�C�b�`����œ|���Ă���Ԃ�����Ԃ͑���Ȃ��̂Ŗʓ|�ł����A����g���Ă���X�C�b�`�͕��ʂɁu�Б��ɓ|������A��Œ����ɖ߂��܂ł͓|�ꂽ�܂��v�̂悤�Ȃ̂ő������H���J���^���ł��ˁB 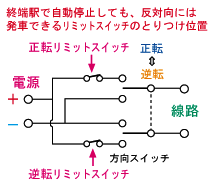 �@�ړI��B������̂Ɏg�������́A�i�s�������ւ���X�C�b�`�̏��ŁA�i�s�������ƂɈႤ�d�C�̌o�H�����~�b�g�X�C�b�`�ŕK�v�����������Ƃ������@�ł��B
�@�ړI��B������̂Ɏg�������́A�i�s�������ւ���X�C�b�`�̏��ŁA�i�s�������ƂɈႤ�d�C�̌o�H�����~�b�g�X�C�b�`�ŕK�v�����������Ƃ������@�ł��B�@�E�}�̂悤�ɁA�����X�C�b�`�ɂ���đI��������H�̒��ŁA���]�̂Ƃ�������ւ����鑤�����]�̂Ƃ�������ւ����鑤�̊e�z���ɂ����A���̕����ւ̗�Ԃ̑��s���~�߂郊�~�b�g�X�C�b�`���Ƃ���܂��B �� �z���ɂ���ẮA�}�Ƃ͍��E���t(�d�����Ɛ��H�����t)�̏ꍇ������܂� �@����ŁA���]�̎��ɂ͐��]�����̉w�ɂƂ�������~�b�g�X�C�b�`�Ŏ�����~�E���Ό����ɋt�]���Ԃ��鎞�ɂ͓d���͗�����A�t�]�̎��ɂ͋t�]�����̉w�ɂƂ�������~�b�g�X�C�b�`�Ŏ�����~�E���Ό����ɐ��]���Ԃ��鎞�ɂ͓d���͗�����悤�ɂȂ�܂��B �@���̂悤�ȃX�C�b�`��H�́A��Ԃ̉��������ł͂Ȃ��A���[�^�[�ƃM�A�[�œ��������ݐ�̃o�[�Ƃ��݂����ɁA�X�C�b�`�œ���������ς��Ă���n�_�Ń��[�^�[��������~������悤�ȋ@�B�ɂ悭�g���܂��B �@�܂��A���ݐ�̏ꍇ�͓��JWT-28AT�݂����ȃX�C�b�`�ł͂Ȃ��u��Ԃ̐ڋ߂œ��������[�v�œ���������ւ���̂ł����B �@�悭�������u�̘b�ł́u���~�b�^�[���A���[�^�[�����H�v�ł���舵���Ă��܂����A������ł͎���҂̕�����ׂ��Ȑ����͖��������ł����g�O���X�C�b�`�ł��u�������^���[�X�C�b�`�v�ł��낤�Ƃ������ŁA�f�W�^����H�Ń��b�`��H������đΉ����Ă��܂��B �@IC�������g���ĉ�H�����G�ł����A����̂������̂悤�ȁu�I���^�l�[�g�^�C�v�v�̃X�C�b�`���Ƃق��ɓd�q��H���K�v�Ȃ��ĂƂĂ��J���^���ł����ł��ˁi�O�O�G ���Ԏ� 2012/1/2
|
||
| ���e |
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B �����Ȃ������͂��w�E�̒ʂ�ł����B ���X�ɕύX���Ă݂܂��B �܂���������܂����瑊�k�ɏ���ĉ������B ���肪�Ƃ��������܂����B �� �l
|
||
| ���Ԏ� |
�@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B �@���i�̒lj���A��H�̐���̕K�v�������̂ŁA�y�ɕύX�͂ł���Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2012/1/6
|
||
| �������T���Ă��܂� | |||
|
������Ƃ䂤�d�����i�ō����Ă��܂��B �l�b�g�ŏ���T���Ă��ăR�`���̃T�C�g�ɂ��ǂ���܂����B ���m�b�����݂�����������Ǝv�����e�������܂����B �Q�T�N���x�o�߂�������@�Ńn�[�l�X�Ɏg���Ă���������Ƃ䂤���i���p���N���Ă��܂��܂����B ���[�J�[�͎O�H�_�@�iOEM�Ńt�W�C�R�[�|���[�V���������j��MSR701�Ƃ䂤�@��ł��B �̔��X�ɕ⋋���i��₢���킹��������u���̍��̃��m�̕��i�́A���łɋ������Ă��܂���B�v�Ƃ̉ł����B ���̐����킪�Ȃ��ƃG���W���Ŕ��d���ꂽ�𗬓d�����ɕϊ����ăo�b�e���[�ɏ[�d�ł��Ȃ��̂ŕ��d���J��Ԃ������Ńo�b�e���[���オ���Ă��܂��܂��B �o�b�e���[�́A12V�ł��B�p���N����������́uED 0010�v�Ƃ���A ���̒���M�̃}�[�N�i��Ђ̃��S�H�j��������Ă��ĕʂɁu661�v�Ə�����Ă��܂��B �������i�̓���́A�s��������Ȃ��ł����A�����i�Ȃnj��݂ł�����͉\�ł��傤���H ���Z�����Ƃ��닰�k�ł����A���m�b��q�ł���Ǝv���܂��B ���肢�������܂��B kuroken �l
�� ���͂��ꂽ���[���A�h���X�ł̓G���[�ƂȂ胁�[�������͂��ł��܂���ł����̂ŁA�����[���̖��O�F�Ƃ����Ă��������܂����B |
|||
| ���Ԏ� |
�@������Ƃ��̌^�Ԃ炵���������̏��ł́A�Y�����镔�i���݂���܂���B �@��ʓI�Ȑ�����Ȃ獡��ɓ���̂́u�����p�V���R���_�C�I�[�h�v��u�_�C�I�[�h�u���b�W�v�ł��B �@���̐�����̒[�q���Q�{�Ȃ畁�ʂɐ����p�_�C�I�[�h�ő�ւł��܂����A�S�{�Ȃ�_�C�I�[�h���������ɓ����đg�ݍ��킳�������i�̃_�C�I�[�h�u���b�W���g�p���܂��B �@���^�̔_�k�p�G���W������o�b�e���[�̏[�d�p�Ȃ炻��قǑ�d���p�̂��̂łȂ��Ă��\��Ȃ��Ǝv���̂ŁA�]�T�������đ傫�߂̂��̂ł������������i(300V[max1000V]/50A)�������������i(400V/25A)�őΉ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�����Ə��d���p�ł������Ȃ�����������������i(600V/4A)�������������i(600V/2A)������܂����A���̕��i���ǂ������K�i�̂��̂���A���̏���@�Ɏg���Ă��锭�d�p�R�C���̒�i�E��H�}�Ȃǂ������̂ŋ�̓I���ǂ̕��i�Ɍ�������ΐ�ɑ��v�Ƃ̓l�b�g�Ō��t(����)�����œ`����ꂽ���͓���ł��܂���B �@������������A�����Ə����ȕ��i�ł��悩������������܂��A�܂���͏������˂�Ƃ������ŁB �@�G���W�����i�̏ꍇ�u���N�`�t�@�C���[�v����{��Łu������v�ƕ\�L����ꍇ�����邻���ł��B �@���N�`�t�@�C���[�͊m���ɃG���W�����d�@�Ŕ��d�����𗬂��ɐ������镔�i�ŁA���Ƀ_�C�I�[�h���U�{�����Ă��܂��B(�R���R�C���p�Ȃ�) �@�����K�v�ȕ��i�����N�`�t�@�C���[�Ȃ�A���̔_�k�@�B�G���W���p�̃��N�`�t�@�C���[���g���邩������܂���B �@��i�Ȃǂ��s���ł����A�����傫���̃G���W���̂��̂�T���̂��肩������܂���B ���Ԏ� 2012/1/2
|
||
| ���e 1/4 |
���Z�����̂ɂ��₢���X���肪�Ƃ��������܂��B �����Ă����������p�[�c�A���������Ă݂܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@kuroken kuroken �l
|
||
|
����ȑO�̓����͂����灨 [2011�N�㔼�̉ߋ����O]
|
|||
|
�T���₷���ړI�E��H�̃W�������ʈꗗ�͂����灨 [�W�������ʈꗗ]
�悭�g�����i�́u���̐}�v�͂����灨 [�悭�g�����i�́u���̐}�v]
|
|||
|
(C) �u�C�̖����v�^Kansai-Event.com
�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������
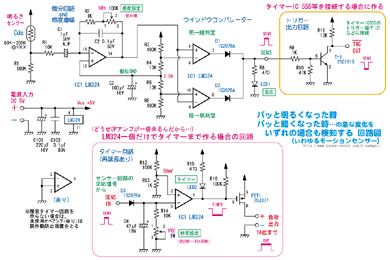
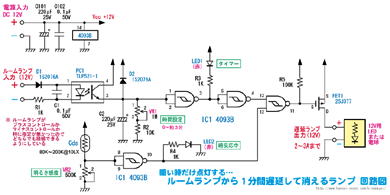
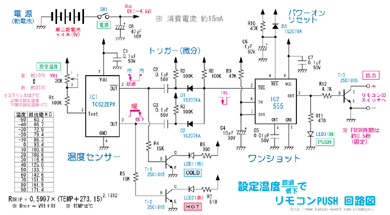
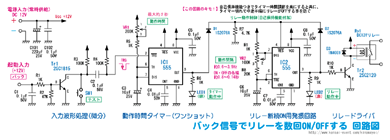
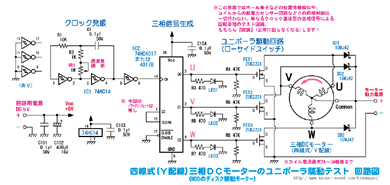

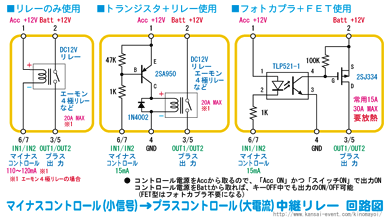
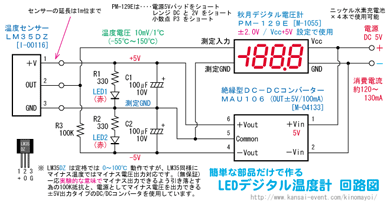
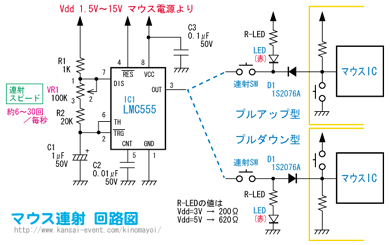
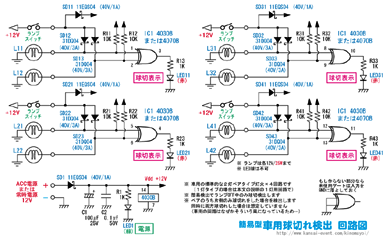
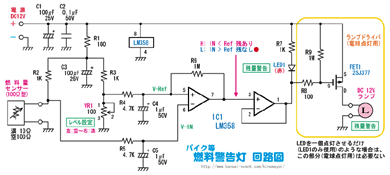
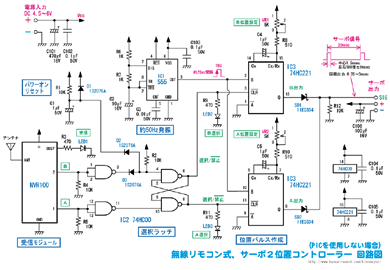
 �u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�
�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�