| ||||||||||
|
|
| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |
��H�E�f���L�E����
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���� ���̃y�[�W��2010�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B
�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B
�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B
|
�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |
�y�ꗗ�z
�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�
|
��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |
|
�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
���� ���̃y�[�W��2010�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
| �ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���߂܂��āA�����������Ă�������܂����B �o�b�e���[���X�̌��`�����ɁAHID �����v�����t���悤�ƁA�i�����Ă��܂��B���]�ł́A�X�g���{�����A����]�ȏ�ł́A���픭�����܂��B�d���́A�e��]��14.4V�`14.7V�L��܂��B�o���X�g�̓���d����9V�`16V�ƕ\������Ă܂��B�ԗ��́AHONDA CRM50N�ł��BR.R�́A�V�d��SH542-12�@3.3�ƕ\������Ă܂��B�����Ŏ���Ȃ̂ł����A3A���x�̃o�b�e���[���L���p�V�^�H�̂悤�ɗ��p�������̂ł����A���YR.R�ɁA�o�b�e���[���Ȃ���AC,G�ɋt�����Ċ댯�Ƃ���܂����̂ŁAR.R�̏o�͑��{�Ƃ̊Ԃ�10A�ʂ̃_�C�I�[�h����ăo�b�e���[��ڑ�����A�ǂ��̂ł́H�ƍl���܂������A���܂�ɂ��P�������āA�������Ƃ���������̂�����������ł��B���̕��@�ʼn����ł��邩�A�������������B�i��肠��̏ꍇ�́ASH686-12�ӂ��p�ӂ��ăo�b�e���[�L�̓d���ɉ������܂��j�ǂ�����낵�����肢���܂��B �Ԃ��Ȃ��\�H �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̃o�C�N�̃��C�g�R�C���̔��d�ʂƁA���M�����[�^�E���N�`�t�@�C��SH542-12�̒��g(��H�\���Ƃ���i�d���Ƃ�)���悭�킩��܂���̂Œf��͂ł��܂��A�_�C�I�[�h�Œlj��o�b�e���[�ȍ~�����Ă��͕̂ʂɓd�C�I�ɂ͖��͖����Ǝv���܂��B �@SH542-12�̏o�͓d���͌��X�ԗ��ł̉��o�b�e���[�[�d�p�d���ɐ�������Ă���悤�ł����A�u�o�b�e���[���Ȃ��ȁv�I�Ȓ��ӏ����͌����邱�Ƃ��ł��܂���ł����������������ӏ���������Ƃ���Ɖ��������ŋt�����Ă��܂��悤�ȕs�s��������̂ł��傤�B�_�C�I�[�h�ŋt�����Ȃ��悤�ɂ���Ζ��͖����͂��Ă��B �@���C�gOFF�̏�Ԃő����Ă���Ԃɉ��o�b�e���[���[�d���Ă����āA���C�g�n�m���ɃG���W�����]�̍ۂ̔��d�ʕs��(�`���`���ƌ�����x�̃p���X��ɂ������d���Ȃ�)�����o�b�e���[�ŕ₤���Ƃ͂ł���Ǝv���܂��B �@���C�g�R�C���̔��d�ʂ����Ȃ��āA���o�b�e���[�����Ă�(�{���t���Ă��郉�C�g�����)��H����HID���C�g�n�m�ő��s����Ƃ����ɉ��o�b�e���[�����d���Ă��܂��ĉߕ��d�ɂȂ��ĉ��o�b�e���[���ɂނƂ��A���������s�s���͂��邩������܂���B �@���C�g�R�C���Ɠ_�R�C��������ɂȂ��Ă��āA���C�g�o�͂ő傫�ȓd�������Ɠ_�R�C���o�͂̓d�����������ĔR�Ăɕs����o��Ƃ��A�����������������邩������܂���B �@���̂�����̓o�C�N�ʂ̖��Ȃ̂ŁA�����������Ă��Ȃ��̂Ŏ��͑���������ł��܂���B �@��������HID�̏���d�͂����̃��C�g���Ƃ��܂�ς��Ȃ��̂ł���A�d�́E����d���ɂ��s��Ȃǂ��قƂ�ǖ����Ƃ͎v���܂��B �@�_�C�I�[�h�E���o�b�e���[��ڑ����邱�ƂŃ��C�g�R�C���^R.R�������ɉĂ��܂����͖����Ƃ͎v���܂����A�lj������サ�炭�͒��ӂ��Ȃ��瑖�s���Ă݂Ă��������B �@SH542-12�̓�����H�}���i�ɂ��ď�����Ă���HP�Ȃǂ������m�̕��͊Ԃ��Ȃ��\�H�l�ɋ����Ă����Ă��������B ���Ԏ� 2010/6/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 7/11 |
���Ԏ��������肪�Ƃ��������܂����B�_���܂ł́A�s���܂����B ���p��ɂ́A�����n�����Ԃ��K�v�ł��B�F�X�M��|�����Ǝv���܂��B�b���y���߂����ł��B�������L��������܂����B �܂������b�ɂȂ�Ǝv���܂��̂ł�낵�����肢���܂��B �Ԃ��Ȃ��\�H �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����ɂ��́A�����b�ɂȂ�܂��B �ȑO��莩���̎v���悤�ȉ�H�͂Ȃ����Ɓi�����ł͍��Ȃ��j�T���Ă��܂��������炸�A�����Ɏ����Ă��܂��B ����͎E�ۗp�̃{�b�N�X�ł����A���i�͂Q���̔����܂��Ă��āA����ł������J���Ă��E�ۓ��͓_���܂��A�����܂�ΎE�ۓ����t���ĂP�O���`�R�O���i�ω\�Ɂj�ŏ������A�܂��J���Ă������̂܂܂ŕ���ƌ��߂����ԓ_������̌J��Ԃ��ł��B�_�����ɔ����J����A��������B ������o���邾���������P���ɏo���Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�i��̕K�v�����j����ł��傤���H ���� �`�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��H���������őg�ݗ��Ăł��Ȃ��Ƃ������Łu��̕K�v�Ȃ��v�Ƃ̂���]�Ƃ������A�ꉞ�g�������ȕ��i�͂���܂��B �@���������p�r�ł́u�e�`�@��v(FA���t�@�N�g���B�E�I�[�g���[�V����)�Ƃ����H�Ɨp�E����p�̓d�C���i���g���ꍇ�������A�d�q���i�Ŏ��삷��̂ł͂Ȃ��ŏ�����e��̋@�\���������^�C�}�[���p�̑��u���w�����Ĕz���E�g�ݗ��Ă��ċ@�B�����܂��B �@�������A�d�q���i�Ŏ��삷���1000�~��������Ȃ���H�E�ړI�̕i�ł��AFA�@��p�̊����i���Ε��i�������~������̂͊o�債�Ă����Ă��������B�Ȃɂ������z�R���܂݂�ŐU���⍂����������܂��̍H��̒��ł����Ȃ����łȓ��ꕔ�i�Ȃ̂ł�����B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�E�ۓ��̓d���d����������Ă��Ȃ��̂ʼn������g���Ȃ̂��͂킩��܂��A���ʂ�AC100V�Ŏ��O������_��������E�ۓ������g���ł��傤����A��H��AC100V�ł��̂܂ܓ������̂Ƃ��܂��B �� �h�A�X�C�b�` �@�����܂��Ă��邩�ǂ����ʂ���̂́u�}�C�N���X�C�b�`�v���g�p���܂��B �@�}�C�N���X�C�b�`�ƌ����Ă��d�q��H��ɍڂ��鐔mm�p�̒����^�X�C�b�`�̂��Ƃł͂Ȃ��A�H���H�Ƌ@�B�ɕt����l�̂��Ԃ���ȏ゠��傫�ȃX�C�b�`���͏����������̗͂œ����X�C�b�`�Ƃ����Ӗ��Ŗ��t����ꂽ�A�H�Ɨp�̃X�C�b�`�ł��B�傫����3�Z���`�قǂ���܂��B �@�}�C�N���X�C�b�`�̉����{�^�������͏������Čy���͂ʼn������߁A�@�B�̓�����h�A�̊J�ŃX�C�b�`�������ł��B �@���ɋ������́u���o�[�v���t���Ă��镨���h�A�̊J�ő��삵�₷���̂ł������������g�p�����ق����E�ۃ{�b�N�X�̃h�A���ɃX�C�b�`���Ƃ����H�삪�y�ł��傤�B �@��H�}�ł�OMRON���h�A�p���^�d���X�C�b�`�ł���DT2�^�}�C�N���X�C�b�`(�J�^���OPDF)���g�p���镗�ɏ����Ă��܂��B �@�ʂɑ��Ђ̕ʐ��i�ł��A�E�ۓ��̏���d�����傫�ȓd���e�ʂ̃}�C�N���X�C�b�`�ł���Ȃ�ł��\���܂���B �@�X�C�b�`���e���Ɉ���A�Q�����ɐڑ����邱�ƂŁu�������܂��Ă����Ԃł̂ݓd��ON�v�ɂ��܂��B �@�ǂ��炩�Е��A�܂��͗����̔����J����Ɠd����OFF�ɂȂ�܂��B �@�����Q�������Ă��Ȃ��ƗL�Q�ȎE�ۓ��̎��O�������v�͌���Ȃ��d�|���ł��B �� �^�C�}�[�����[ �@�u10���`30���Ŏ����I��OFF�v�̂���]��������̂�OMRON���\���b�h�X�e�[�g�E�^�C�} H3Y�^(�J�^���OPDF)�ł��B �@�u�d��ON�����莞�Ԍ�Ƀ����[����ւ��v�@�\�̒P�ꎞ�ԃ^�C�}�[�ł��B���Ԃ�60���^�̏ꍇ��2���`60���̊ԂŔC�ӂ̎��Ԃ��Z�b�g���Ă������Ƃ��ł��܂��B �@H3Y�͓d��������ƃ����[�͂܂��������A�w��̎��Ԃ��o�߂���ƃ����[���J�`���Ɛ�ւ�܂��B��ւ�����d�������܂ł��̂܂܂ł��B �@�d�������ƃ��Z�b�g����܂��B�܂����ɓd��������ƃ^�C�}�[�����삵�Ĉ�莞�Ԍ�Ƀ����[����ւ�܂��B �@�܂�A�u�h�A��߂����d��ON�v�ɂȂ�����E�ۓ��̓d�������āAH3Y�^�C�}�[���쓮���Ĉ�莞�Ԍo�����烊���[�ŎE�ۓ�����H�ɂ���悢�����ł��B �@�����[��N.C.�ړ_(�ʏ��ON�ړ_)�ŎE�ۓ��Ɠd�����q���ł����A�^�C�}�[��������N.C.�ړ_���ꂽ��E�ۓ���������悤�Ȑڑ��ɂ��܂��B �@�g�����i�͂������R�B �@���������d�q���i�̃n���_�Â���g�ݗ��Ă͕K�v����܂���B �@�}�C�N���X�C�b�`�ƃ^�C�}�[�����[�̊e�[�q�ɕK�v�Ȕz�����n���_�Â����邾���ł��B �@�e�[�q�͂ǂ��Ȃ̂��͐��i��PDF�������悭���ĊԈ��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@�Ȃɂ���AC100V���g�p�����H�ł�����A�Ԉ���ăV���[�g����z���ɂ��Ă��܂�������܂��B ���Ԏ� 2010/6/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���X�̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B�����ł��B ���܂ŔY��ł����̂��A����Ȃɂ����ɉ�������Ƃ́I �ł�����ȕ��i���L���ł��ˁA���X�ɒT���č��܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B ���Ȃ݂ɂ����d�q��H�ɂ�����Ȃ蕡�G�ł��傤���H �S�̃{�b�N�X���L��܂��̂ŁA�P�ʂ͍���Ă��ǂ������I �����@�`�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�d�q��H�ō��A�^�C�}�[�pIC��Ƃ��̎��ӕ��i�����A�����[�ƃh���C�o��H�A���Ƃ͂����������i���K�v��������܂��A�������̕��i��������1000�~�O��ł��ˁB �@�d����AC100V�Ȃ̂�5V��12V���x��AC�A�_�v�^�[�������Ƃ���600�`1000�~���炢�B�P�[�X�ɓ����Ƃ����h����ǂ�����Ȃ琔�S�~�̃P�[�X���̂�������������܂���B �@�}�C�N���X�C�b�`�͂��̂܂ܓ��������Ďg���̂ŃX�C�b�`���̂˂���͕ς��܂��A�^�C�}�[��OMRON�̊����i�����͈����Ȃ�܂��B �@�^�C�}�[�W�͉ߋ��ɂ��������H�}������܂�����A����Ȋ����̉�H�}�����Ă������ŕ��i���đg�ݗ��ĂɃ`�������W�����̂ł����炨�\���t�����������B ���Ԏ� 2010/6/29
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����b�ɂȂ�܂��B��͂�P�x����Ă݂悤�Ǝv���܂��B �Q�N�قǑO�ɒx���A���R���Z���g�i�؍H�W��HP���j�����܂����B���̒��x�ł���Ή�H�͉���Ǝv���܂��B�������G�ł�����������������Ă���肽���Ǝv���܂��B��낵�����肢�������܂��B ���� �`�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����ł́A����͈ꉞ����]�ʂ�̉�H�}�͒��Ă��܂��̂ŁA�}�����Ɏ��ɉɂɂȂ������ɍl���Čf�ڂ����Ē����܂��B ���Ԏ� 2010/6/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̕��̗D�揇�ʂ�������܂����̂ŁA��ɂ�������B �@OMRON��H3Y�ƑS�������[�q���E�@�\�̉�H�Łu�d��ON�����莞�Ԍ�Ƀ����[���쓮�����H�v���P�l���܂������A�Ȃɂ������܂őS�������������Ȃ��Ă��ړI��B���ł�������̂ŁA������̃^�C�}�[��H�̂ق������i�������Ȃ��ςނ̂ł�����̂ق����f�ڂ��܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�^�C�}�[�����͂����̂悤���^�C�}�[IC 555�Ń����V���b�g�^�C�}�[�����܂��B�@�悭����555�^�C�}�[��H�ƈႤ�̂́u���͂���������^�C�}�[����v(�����܂ł͓���)�u���͂��ꂽ��^�C�}�[�𒆒f�����v�Ƃ������f�@�\���K�v�ȓ_�ł��B �@���ʂ�555�Ń^�C�}�[���������A��x�^�C�}�[������͂��߂��玞�Ԃ�����܂œr���Ŏ~�߂�Ƃ����g�����͂��܂肵�܂���RESET�[�q��Vcc�ɂȂ����ςȂ��̉�H�������ł��B �@����������͓r���ł����Z�b�g���K�v�Ȃ̂Ńh�A�X�C�b�`���͂��u���Z�b�g�������v�ق��ɏd���������āA�h�A���J���Ă��鎞(��̏�E�f�������ꍇ)�ɂ̓��Z�b�g���ďo�͂���ON�ɂ͂��Ȃ��Ƃ������S���u�I�ȉ�H�ɂ��Ă��܂��B �@�ł��A555�̓h�A��߂āu���Z�b�g�������v���������ł̓^�C�}�[�͓��삵�܂���B �@�g���K�[�q�Ƀg���K�M�������Ă��Ȃ�����̓^�C�}�[�͑ҋ@�����܂܂Ȃ̂ŏo�͑��u�������Ƃ͂ł��܂���B �@�����ŁA�u(�h�A��������)���Z�b�g���������ꂽ��A��莞�Ԃ̊ԃg���K�[�p���X����͂����H�v�Ƃ������̂�����ăg���K����������悤�ɂ��܂��B �@���̂����肪�g�����W�X�^(2SC1815)�ō���Ă��������H������ł��B �@����Ńh�A�������u�Ԃ�555�^�C�}�[���N�����āA�ړI�̎��Ԃ����^�C�}�[����������邱�Ƃ��ł��܂��B �@�^�C�}�[���Ԃ�VR1�ōő���40�����x�܂Œ��߂ł��܂��B(�d���R���f���T�̌덷�Ȃǂő����͈Ⴂ�܂�) �@555�̏o�͂ɂ͏H���d�q�́u�\���b�h�E�X�e�[�g�E�����[�i�r�r�q�j�L�b�g �Q�T�`�i�Q�O�`�j�^�C�v [K-00203]�v���q����AC100V�̃X�C�b�`���O���s���܂��B �@�ʂɕ��ʂ̃����[�ł������̂ł����A���̃\���b�h�X�e�[�g�����[�̓X�i�o���X�v�ƌ�����AC100V��ON/OFF���ɔ�������m�C�Y���������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��Ă܂��Ƀm�C�Y�ň��e�����o�Ȃ��̂��ǂ��ł��B�Ȃɂ������ł����i�O�O�G �@���Ă���� �E�h�A���������莞�ԃ^�C�}�[�������E�ۓ��_�� �E�ݒ莞�Ԃ��߂�����E�ۓ����� �E�r���Ńh�A���J������E�ۓ��͏����A�^�C�}�[�����Z�b�g �E���Ƀh�A���J������܂��^�C�}�[���� �Ƃ�������]�̃h�A�X�C�b�`���̓_���^�C�}�[�ɂȂ�܂����B �@��H�̓d����DC 5V�ł��̂ŁAAC100V�����AC�A�_�v�^�[����5V�ɂ��Ă��������B�H���̒ʔ̂ł�600�~���x�ł��A���X�ɂ���Ă̓W�����N�i���ł͂����ƈ����@��o�������L�邩������܂���B ���Ԏ� 2010/7/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�D��I�ɂ��Ԏ����������A���k�������܂��B �܂����J�ɓ���������܂߂�����ł��肪�Ƃ��������܂��B �����������̓��j���ɂł��A���{���ɍs���Ă��܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B ���� �`�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���{���ŕ��i���B����Ȃ�A�\���b�h�X�e�[�g�����[��Panasonic��OMRON�̊������i���w������Ƃ悢�ł��傤�B �@���ɂ��Z�܂��̕��͏H���d�q�̃L�b�g�͏H���d�q�̒ʔ̂������œ��肵�Ȃ���Ȃ炸�A�����{������萔����800�~������܂����炢��������L�b�g�ł��������̉��i�������ڂ̑��Ŕ����Ă��镁�ʂ̕��i�����ق��������ꍇ������܂��B �@����(7/2)�����d�q�́u�V���R���n�E�X�����v�u�e�N�m�x�[�X�����v���ʃr���Ɉړ]���ă��j���[�A���I�[�v�����܂��̂ŁA�d�q���i����ꂪ���K�ɂȂ�̂������_�ł͂킩��܂��A������ňȉ��̕��i���w�������Ƃ悢��������܂���B �EOMRON �\���b�h�X�e�[�g�����[ G3MB-202P DC5V [ZC�@�\] 495�~ �@�@�@�@����AC125V 2A (200W)�܂� �EOMRON �\���b�h�X�e�[�g�����[ G3MC-201P DC5V [ZC�@�\] 395�~ �@�@�@�@����AC125V 1A (100W)�܂� �� �A���u�����E���[�^�[�̂悤�ɋN�����ɑ傫�ȓd��������镨�͋@��̏���d���\���̐��{�̗e�ʂ̃����[���K�v�ł� �@���Ȃ݂ɁAOMRON��H3Y AC100V 60s�^�C�v��OMRON�ʔ̂łȂ��Ă������d�q�̃l�b�g�ʔ̓X�Ŏ�舵��(���� 3780�~)������܂����B �@���ꕔ�i�Ȃ̂œX���ɂ͖����Ǝv���܂����A�ق��ɂ����{���Ő���@����Ă�����X�ȂǂœX���ł̎�舵��������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/7/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���肪�Ƃ��������܂��B �������ɗǂ������m�ŁA�{�����q���i����܂����j�V���R���n�E�X�ɍs���܂����B�����f�W�b�g���V���R���n�E�X�Ǝv���Ă��܂��B�\���b�h�X�e�[�g�����[�ł����A�E�ۓ��i�Q�OW�Q�{�j�̋N�����̓d����OMRON�̂QA�i�Q�O�OW)�ő��v�ł��傤���H �t�H�g�T�C���X�^�ƃg���C�A�b�N�ō�낤�Ǝv���Ă��܂������E�E �������������m���Ə��͂ł��ˁA��������������Ԃ邱�ƂȂ� ���J�����S�Ɋ����������܂����B ���� �`�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����A�ړ]OPEN�����V���R���n�E�X�ɍs���Ă��܂����B �@�������ɔ����z�u���ς��Ɣ������ɂ��ЂƋ�J�ł��i�O�O�G �@SSR�̊����i��L�b�g��Ȃ��Ă��A�t�H�g�g�T�C���X�^�ƃg���C�A�b�N�̑g�ݍ��킹�Ŏ��삳���͖̂��͖����ł���B �@���ǁA�������Ă��邩�A�����ŕ��i���đg�ݗ��Ă邩�̈Ⴂ�ł��B �@�u�C�̖����v�ł͏H���̃L�b�g��[�J�[�i�������߂��Ă���̂́A���̃y�[�W�㕔�ɏ����Ă���ʂ�uAC100V�Ɋւ���H��͊댯�Ȃ̂œd�q���i���g���č��悤�Ȃ��͈̂���Ȃ��v�Ƃ������[���ɂ��Ă��邩��ł��B �@�^�C�}�[��H�Œ�d���p��FET���g�����X�C�b�`��H�ł����AFET�̑��̔z�����ԈႦ�āu�����܂����v�Ƃ�������J�̎��₪���x����������ł��܂��B �@�����Ă悭�悭�����o���ƕ��i�̑����ԈႦ�Ĕz���~�X�A�n���_�s�ǁA���قƂ�ǂł��B �@�����������S�҂̕����ǂ܂�Ă���l�b�g�̃y�[�W�ŁAAC100V�W�������ŕ��i��g�ݍ��킹�ĉ��������H�Ȃڂ������ɂ́E�E�E���o�܂����A�������܂����A�ǂ����Ă�����ł����H�E�E�Ȃ�Č��t����R�A���ė���͖̂ڂɌ����Ă��܂��B �@�ł�����A�Œ��AC100V�̏ꍇ�͂���������ׂ���������Ă��郊���[�Ƃ��A�H���̃L�b�g�Ȃǁu���̃��[�J�[�̎w���̌��A�������ʂ�Ɍq�������v�̕��i�E���i�������Љ�Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��B �@���̕��i���g���ĉ������s�����Ȃ�A���̕����́u�C�̖����v�̐ӔC�ł͂Ȃ����̕��i�������[�J�[�Ǝ��삵���l�̊Ԃ̐ӔC���ɂȂ邩��ł��B �@�ł�����A���̒����H�}�ł͏H����SSR�L�b�g��A���ʂ̃����[���g���Ă���悤�ȉ�H���u�������̈ӎu�ƒm���ƋZ�p�́I(�ƐӔC)�v�Ńt�H�g�T�C���X�^�ƃg���C�A�b�N���g����SSR�����삷������ɕύX�����͉̂�����͂���܂���B(�L�b�g�E�����i��SSR�̒��g�ƈꏏ�ł�) �@����������H�}�̓l�b�g�ɂ��낲��]�����Ă���ł��傤�B �@����ɑ��āu�ύX���Ă��\���܂��H�v�ƕ��������x�܂ł͂����ł����A�u�ς�����(���s����)�����Ȃ��Ȃ�܂����v�Ƃ��������g�̐ӔC�͈͂����ɉ����t����悤�Ȏ������Ȃ���Α��v�ł��B �@�u�����̌��ł����A20W�̌u�����Ȃ�˓���(�u�Ԃł���)���`�͗���܂��B�Q�{���Ƃ��̂Q�{�B �@OMRON �\���b�h�X�e�[�g�����[ G3MB-202P�̏ꍇ�A��i�Łu�����d�� 30A (60Hz�A1�T�C�N��)�v�Ə�����Ă��܂��̂ŁA���[�^�[��u�����ȂǂŒʏ�^�]����2A�܂łŁA�˓��d�������̐��{���x�̋@��ł���Η]�T�őΉ��ł��܂��B20W�u�������Q�{�Ȃ�͈͓��ł��B �@�S�z�ł�����A��͂�H����SSR�L�b�g��ʕ��i��SSR�����삳��āA�ʏ�d����20A���x�A�˓���100A�ȏ�����e����SSR���g����̂��S���I�ɉ��₩�ɂ�������悤�ɂȂ�̂ł�������ق���������������܂���ˁB �@�����g����@��ł�����A�u���������Ȃ��̂��H�v�ƐS�z���Ȃ���g�����A�u���Ȃ��悤�ɍ�����I�v�Ƃ������M�ň��S���Ďg����ق��������ł��傤�B ���Ԏ� 2010/7/3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����牽�܂ł��肪�Ƃ��������܂����B W�̒Ⴂ�i�UW�Q�{�j�̂͊����i�ŁA�Q�OW�͎���ł���Ă݂܂��B ���ǂ��ׂĉ�H�ō�邱�Ƃɂ��܂����A���ꂾ�����������������ƍ��Ȃ��ƂˁI�܂��쐬�ɂ͏\�����ӂ��A�`�F�b�N���܂��̂ŁB �Ō��SSR�iomuron)�̑ϗp�N���͒�i���g�p�i���M�͏�����j�łǂ̂��炢�ł��傤���H ���x�����肪�Ƃ��������܂����A�܂���낵�����肢�������܂��B ���� �`�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��i���g�p�Łu���M�͏������v�Ƃ����̂͂ǂ������g�����ł��傤���H �@����̎g�����ł͂Ȃ��A�����ʂ̗p�r�Ŕ��M����悤�ȓd���l�Ŏg�p����Ƃ������ł��ˁB �@���M������Ȃ炻�̒��x�ɂ���Ď����͏k�݂܂��B �@�����ɔ��M������Ɖ����ԏk�ނȂǂ̃f�[�^�͂���܂���A24���ԏ펞�g�p�Ő��N�ȓ��ɗ̒���������x�ł��傤���B �@�̒��x�����̔��M��d���ʂɂ���ėl�X�ł�����A�����ǂ̒��x�Ɋ�������̂��͎g�p����ł��B �@�����̂͒�i�̔���(2A�i�Ȃ�1A�ȉ�)�Ŏg�p�����ꍇ�A�����͂قڔ��i�v�I�ł��B �@���i�v�I�Ə����Ɖ���N�E�����N�g����Ɗ��Ⴂ�����Ƃ����܂���A���ʂɎg���Ă�������10�`20�N�̘A���^�g�p�ɑς�����x�̎����͂���ł��傤�B �@SSR�����삳���Ƃ������ŁASSR���g�p���鎖�Ɋւ���댯�E���ӎ����Ȃǂ̊�{�����͊��ɕ�����Ă���Ƃ͎v���܂����A���߂ă��[�J�[�����Ă���SSR���i�̒��ӎ����u�\���b�h�X�e�[�g�����[�̋��ʂ̒��ӎ����v�͓ǂ�ł��玩�삳��鎖�������߂��܂��B �@�������A�u�悭���ׂāA����Ȏ��\���n�m������Ŏ��삷���ł��v�Ƃ��������Ƃ͎v���܂��B�߉ނɐ��@�ɂȂ�܂����玸��v���܂����B �@��i���Ŏg���Ă������ASSR��������A���~�d���R���f���T�����Ďg���Ȃ��Ȃ�ق��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�A���~�d���R���f���T�͕W���i�̏ꍇ��10�N�ŗe�ʂ��������镨�܂ł́u��i�v�ƔF�߂��Ă��܂��B �@������g�����ɂ��܂����A�킸�����N�Ńp���N�E�j�Ă��܂����̂���A�����ڂ͕ς�炸�ɗe�ʂ������ē����Ȃ��Ȃ���́A�܂��t��20�`30�N�o���Ă��قƂ�Ǘe�ʂ��ς��Ȃ����̂�g����������܂��B �@10�N�ʌo���ă^�C�}�[���Ԃ������悤�ł�����d���R���f���T���ł��������ł����A�u�����̓_�����������ȏꍇ��SSR���i�̗��^���ĕ��i�������Ă��������B ���Ԏ� 2010/7/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���݂܂���A���t���炸�ł����B �g�p�͕��ʂɎE�ۓ��Ƃ��Ă̗��p�ł����A���^�Ȃ̂ŁA�g���C�A�b�N�͂��Ȃ�M���o��悤�Ȃ̂ŁA����łǂ����Ȏv���܂��āI ���炢�����܂����B ���� �`�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@20W�~2�{��_��������̂ɂ���Ȃɔ��M���܂����H �@�����œ����x�̕������Ă��܂��������M���Ă��܂��E�E�E�E�B �@���S�v���̃��[�^�[��q�[�^�[�����Ȃ�����A���M�����Ȃ��Ă����C�Ȃ��炢�̔��M���Ǝv���̂ł����A����ȂɔM���Ȃ�܂����B(���������Ȃ��c) �@�����̒��ŁA�u�����̔��M�̂ق��������̋C�����㏸�����v���ɂȂ��Ă��܂��H �@�����āA���Ɏ�������Ȃ��悤�ȍ����łȂ���A�C���ɂ��g���C�A�b�N�̗͖����Ǝv���̂ł����B ���Ԏ� 2010/7/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����AFET�Ń����[�쓮�o���܂����H�Ŏ��₳���Ē�����T.Y�ł��B �Q���ԃ����v�̉�H�ł܂��A���₳���Ă��炢�܂��B ���̉�H�ł́AHi���͂�MOS-FET��x��OFF�����Ă��܂����ALo���͂Œx��OFF������ꍇ�͂ǂ̂悤�ɉ�H���ύX�ɂȂ�܂����H �G���W��OFF�Œx��OFF���������Ǝv���̂Łc�B ��낵�����肢���܂��B T.Y �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@Hi���͂ł͂Ȃ�Lo���͂Łu�[�d�v�A�uLo���͂��ꂽ�炻�������莞�Ԓx���v���������Ƃ���������ł����H �@�O��̕��͂ƁuLo���͂Œx��OFF������ꍇ�v�Ƃ������Ȃ̂ł���ł����Ǝv���̂ł����ALo���͂Ƃ͎Ԃɑ����u�}�C�i�X�R���g���[���v�̎��ł���ˁB �� �G���W�����������Ă���Ԃ�Lo����(�}�C�i�X�R���g���[��)����Ă���B �� ���̊Ԃ͂����ƃ����v(�o��)�͓_��(ON)���Ă��� �� �G���W�������ƃ}�C�i�X�R���g���[�����J��(0V�ł�12V�ł�����)����� �� �G���W�����ꂽ�������莞�Ԍ�Ƀ����v(�o��)��������(OFF�ɂȂ�) �@�����������S�R�Ⴄ��H�ɂȂ�̂Ŋm�F�ł��B ���Ԏ� 2010/6/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����b�ɂȂ�܂��B �����s���Ő\����Ȃ��ł��B �G���W�����ꂽ���ƁA�x��OFF��H���R�O�b���x���삷��Ƃ������̂ł��B �ł���A�G���W�����|�����Ă���Ԃ̓����v��OFF�i������j��Ԃɂ������B �G���W������Ă��鎞�͊J����Ԃł��B �G���W�����|�����Ă���Ԃ�Hi���́B �����ł��l���Ă��������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂������̂Łc�B T.Y �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
>�G���W�����|�����Ă���Ԃ�Hi���́B �@�����Acc�d�����ǂ�������+12V�����Ă���̂ł��ˁB >�G���W�����|�����Ă���Ԃ̓����v��OFF >�G���W�����ꂽ���ƁA�x��OFF��H���R�O�b���x���� �@�G���W��ON����OFF�ŁA�ꂽ�烉���v��ON�ɂȂ��āA�^�C�}�[����ł��炭���OFF�B �@�����^�C�}�[����œ_�����ɂ܂��G���W��������������OFF����B �@�Ƃ����u�G���W������ĎԂ��~���܂ł̊ԂɃ����v��_�����������v�݂����Ȏg�����ł���ˁH �@������āE�E�E�ߋ��L���́u���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������v�ƑS���������e�ł͂���܂��H �@���������Ⴄ�Ƃ��낪������������������B ���Ԏ� 2010/6/29
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 7/5 |
�ǂ����Ԏ��x���Ȃ�܂����B ���̉�H�Ɠ����ł��ˁB ����܂����B �ǂ������肪�Ƃ��������܂��B T.Y �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���������b�ɂȂ�܂��B 660nm������LED���g���ĐA���琬���삵�悤�Ǝv���܂��B ���z�d�r�œ_�����������̂ŁA�d����DC12V�ɂȂ�܂��B ���āA���ʂ�LED�͍��P�x�^�C�v��20-30mA�̂��̂������ł����A������100���炢�g����6W���x�̃����v�����̂ƁA350mA��1W�^�C�vLED��6�g���̂ł́A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤���B 1W�^�C�v��LED�͕K�����M�킪�K�v�̂悤�ł����A�t�ɓd��������PWM���̃R���g���[���[���̔�����Ă���A��ʓI�Ȓ�R�����������ǂ��悤�ȋC�����܂��B30mA�N���X�Ȃ畁�ʂ͕��M��͗v��܂����ˁBLED�̓X�y�b�N�V�[�g�ɔ���������������Ă��Ȃ��̂ŁA����ǂ�������܂���B ���A�l���Ă���p�[�c�́A http://www.temkon.com/led/led-3/led-3.htm�̂b�s�|�P�k�`�q�b�ƁA http://www.temkon.com/led/led-2/led-2.htm�̂r�c�k�|�T�m�R�j�q�ł��B ���Ȃ݂ɁA30mA�̓d�������ɒ�R����g���̂ƁA��d���_�C�I�[�h���g���̂ł́A����d�͂ɍ����o�܂����H�i���������m��܂��j �܂��ڂ���������������K���ł��B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�c�O�Ȃ���A���ɂ͂��̂Q�̂ǂ���̂ق������邢�̂��T�b�p���킩��܂���B �@�C�e�^LED�̂ق��ɂ̓��[�����l�Ȃǁu����(����)�v�Ɋւ����o�Ă��܂���A�ʂ����ĉ��v�̓d�͂�H�킹�Ăǂꂾ���̃G�l���M�[�����o�����̂��A�S�R�f�[�^��������Ԃł͔�r�͂ł��܂���B �@�J���f���l�͏o�Ă��܂����A�S���ʂ̔z���p�^�[���O���t�����琸���Ɍv�Z���Ȃ��ƁALED����o�Ă���S�̂̌��ʁE�G�l���M�[�ʂ͋��߂��܂����ˁB �@1W�Ȃǂ̃p���[LED�p�́uPWM���̃R���g���[���[�v�Ƃ����̂��悭�킩��܂���B �@DC/DC�R���o�[�^�pIC���g���āAPFM��(�܂�PWM�ł����c)�ɍ~�����Ē�R�����̂悤�ȃ��X�Ԃ��M�ɕς��Ă��܂�������胀�_�̖�����H�Ƃ����̂͗L�邩������܂��A����ł��C�eLED����������܂Ƃ߂����ɑ��ē����悤��DC/DC�R���o�[�^�œd���������Ă����������ł����A�C�e�^LED������Ƃ����ĕK����R���g��Ȃ�������Ȃ��Ƃ��A��d���_�C�I�[�h�Ő������Ȃ�������Ȃ��Ƃ��̌��܂�͖����ł���B �@�uPWM���̃R���g���[���[�v���āA���������āu���邳�߂ł���PWM�����̒����R���g���[���[�v�������Ɗ��Ⴂ������Ă���Ƃ������͖����ł���ˁB �@�d����12V�ŁA�ԐFLED�̒�iVf��2V���x�Ȃ�d�����m����0.6V���x�H���V���v����(�M�͏o��)��d����H����LED 5�{����~20�g�A20�g�~30mA(�{����30mA�������́H)��600mA�̒�d����H���q�����������ł���ˁB �@���M���X���قƂ�ǖ��������߂�Vref��1.25V��DC/DC�R���o�[�^�Œ�d����H�����Ƃ���ƁALED 4�{����~25�g�A25�g�~30mA��750mA��DC/DC�R���o�[�^���q���قƂ�ǃ��X�Ȃ���d���쓮�͂ł��܂��B �@����������H��́u���]�ԃ_�C�i�����d�@�Ŕ��F�k�d�c�������v��DC/DC�R���o�[�^���g�p������d����H�̍������Č������Ă��������B �@�u20�g�Ƃ�25�g�Ƃ�(���₽�Ƃ�2�g�ł�)�����Ōq���̂͐�Ɍ��I�v�Ƃ����@���ɓ����Ă�����A�܂�������c�l�̈⌾�ŁuLED�͐�ɕ���Ɍq������Ȃ�˂����I�v�Ƃ������������Ɏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȉƌP��������́A�d���Ȃ��̂�LED 3�{����{��d���_�C�I�[�h(�܂��͒�R)�̑g��33�g���ALED 5�{�{��R�̑g��20�g�ɂ��Ă����d���ɕ���Ɍq���Ƃ����ł��ˁB���150�~���炢��30mA��d���_�C�I�[�h��33�Ƃ����Ƃ��Ȃ��ґ�ȕ��ʍ��ƂȂ�܂����A�܂����z�{�Ǝv������ł��ǂ�������ꂻ���ł��B�܂�����c�l�ɂ��ʖڂ������܂��ˁB �@��R����d���_�C�I�[�h���A�ǂ��炪�������Ƃ����̂���������ł��B �@�����܂œd���d�����ϓ����Ȃ�12V���Ƃ���ƁA�d���������R�ɂ��Ă����ĂP�g�ɂ�LED���T�{�A�c���2V�Ԃ���R�œd�������p�Ɏg���ƌv�Z����ł���R�ł̃��X�͏��Ȃ��Ȃ�܂��B �@�Ԃ̃o�b�e���[�̂悤���d���d�����ϓ�����12V(10�`15V�̊Ԃ��炢)�Ŏg���̂ł���A2V�Ԃ�̐ݒ�Œ�R�l���v�Z����Ɠd���ϓ��ɂ���R�ɂ�����d���̕ω����傫���A����ɂ���Đ����d���l���傫���ω����Ă��܂��̂ŁA�ł���Β�R�Ԃ�d����5�`6V�Ƃ��Čv�Z�����ق���LED�̖��邳���d���ϓ��ɂ��܂�e�����Ȃ��Ȃ�܂��B��������ƈ��������ɒ�R�Ń��X���锭�M�Ԃ�̃��_�G�l���M�[�͑�����̂ŖړI�ɂ��Ƃ������Ƃ���ł��B �@��d���_�C�I�[�h���g�p����ꍇ�́A��d���_�C�I�[�h�������ƕ\�L�ʂ�̓d���l�������悤�Ɏg�����Ƃ���ƁA��d���_�C�I�[�h�̒[�q�ԓd�����T�u���x�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B���܂�m���Ă��܂�����d���_�C�I�[�h�͂ǂ�ȏ����ł����̓d���𗬂��Ă���闝�z�I�ȃ_�C�I�[�h�ł͖����̂ŁA�f�[�^�V�[�g�����Ē[�q�ԓd���ɂ���ĉʂ����Ė{���͉�mA�����_�C�I�[�h�Ȃ̂����v�Z���Ďg���Ȃ�2�`3V���x�ȏォ��g���܂����A���ꂭ�炢�̒[�q�d���ł��\�L�̓d����菭�Ȃ��d�����������܂����B �@�Ƃ������ŁA12V���炢��2�`3V/20�`30mA�̖C�eLED��Ɍq���ł���ɒ�R����d���_�C�I�[�h���q���ꍇ�A�d���ϓ��ɉe������ɂ��������v�����Ȃ��R�ł�5V���x�̃��X��H�킹��K�v������A��d���_�C�I�[�h��5V���x�̒[�q�d���Ő������g���Ȃ��R����d���_�C�I�[�h���ǂ���������Ń��X����G�l���M�[�͖�5V�~�d���l�ł���������͓����ł��B �@�d���d���ɕϓ��������K��12V�ŌŒ肳��Ă���Ȃ�A��R���g���Ē�R�[�q�Ԃ�2V���x�̓d���܂ŏ��Ȃ�����ƒ���LED���͑��₹�܂�����A��R�����̃��X�������ĂP�g�ł�LED�����������Ԃ�S�̂̑g���������đ����I�ȏ���d�������邱�ƂɂȂ�A���Ȃ�G�l���M�[�����͗ǂ��Ȃ�܂��B �@���āA���̂ւ�łǂ̕��@�A�ǂ̖{����I��邩�͂����g�Ō��肵�Ă��������B �@����1W LED���U�{��5mm�C�eLED��100�{�̂ǂ��炪���邢���́E�E�E�E�{���ɔ����č���ĂQ����ׂĂ݂Ȃ��Ƃǂ��炪�ǂ����͂킩��܂���B �@�ʔ����̂łQ����ĖڂŌ��Ĕ�ׂĂ݂Ă��������B �@�N���Ɍ�����̂Ȃ�1W LED���U�{���A5mm�C�eLED��100���t���Ă���ق����u�Ȃ����������u�v�Ɍ�����ł��傤��(��) �@�A���ɂȂ�ׂ��܂�ׂ�Ȃ����Ă�̂ɂ��A�U������100�����L�����ׂ��ق��������悤�ȁH �� ���C�g�E�����v�E�k�d�c�����̘b��ł����A�����ɓ��e����܂����̂ł����ʼn����Ē����܂����B ���Ԏ� 2010/6/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āB�����y�����q�������Ă��������Ă���܂��B ����ŝ��a�@����낤�Ƃ��Ă���܂��B���[�^�[�ƃh���C�o�[�͗ǂ����̂��������̂ł�����]�v�����t���悤�Ƃ����Ƃ��냂�[�^�[�h���C�o�[����̉�]�p���X�͈��]�R�O�p���X�Ȃ̂ł�����]�v�͈��]�U�O�p���X�̂��̂������t����ꂸ�����Ă��܂��B�h���C�o�[�̐M���̓I�[�v���R���N�^��30V,10mA�ʼn�]�v�̓I��������H7ER-NV1�ł��B���[�^�[�̉�]����MAX��2300rpm�ł��B �����ǂ����@�͂���ł��傤���B�p���X�𑝂₷�ɂ͒��{����Ɨǂ��ƕ����܂������B��낵�����肢�������܂��B �邿��� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�m���ɁA���g�����Q�{�ɂ����H�́u���{(�Ă���)��H�v�Ƃ������̂��g�p���܂��B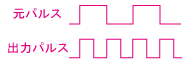 �@���̃p���X�����Q�{�ɂ������킯�ł�����A�E�}�̂悤�ȊW�ŏo�̓p���X������悢�킯�ł��B
�@���̃p���X�����Q�{�ɂ������킯�ł�����A�E�}�̂悤�ȊW�ŏo�̓p���X������悢�킯�ł��B�@�ȒP�����ł��ˁB �@�A�i���O�Ŏ���d�g�ʂ̍����g�������ꍇ�͍����g(�������g���ɏo�镛�Y��)�̒�����K�v�Ȕ{���̎��g���̂��̂����Ď��o�����肷���H�������ł��ˁB �@����̉�]���v���x�̒Ⴂ���g���ł͂قƂ�ǎg��(��)�܂���B �@�f�W�^���ł́uPLL��H�v���g�����{�̎��g���̐M������邱�Ƃ��ł��܂����A����PLL��H���Ɠ����ł�����g���͈͂�����قǍL���͎�ꂸ�A�x�����̉�]���p���X�̖��b���`���\���x�̃p���X����A�������̖��b1000���x�܂łɓ���������悤��PLL�͉ʂ����č���̂��H�Ƃ��������ɂȂ�܂��B �@����̂悤�Ȃ���]�œ���̂́A���̃p���X���g���͈̔͂��L�����̍L�����ɑ��ē��삷��悤�ȕ������̂͑�ς��Ƃ������ł��B �@�ƂĂ��ƂĂ����G�ȓd�q��H�œ��͂��ꂽ�p���X�����v��A���̔����̃p���X���łQ��p���X���o���Ƃ������_�͊ȒP�Ɏv�����܂����A���̃p���X�����J�E���g������A�����̃p���X������悤�ȃf�W�^���J�E���^��H��IC���������Ȃ�܂����A�����u�^�R���[�^�[�̕\�����Q�{�ɂ������v�Ƃ����ړI�̂��߂ɍ��ɂ͑傰�������܂��B �@���ꂱ�����Ԍv���₻�̔����̎��Ԃ̃p���X���Q��o���悤�ȃf�W�^��������PIC�}�C�R���̂悤�ȁu�v�Z�@�v�̓��ӂƂ��镪��ł��B �@�ł��A�����ł�PIC�}�C�R���͎g��Ȃ����@�łȂ�Ƃ��Ȃ邩�l���܂��傤�B �@����g�p�����^�R���[�^�[�u�I������ H7ER-NV1�v�͎����ɂ��Ɓw�P�b�J�E���g���̃f�W�^���J�E���^�x�ł��邻���ł��B �@�P�b�Ԃ̓��̓p���X�����J�E���g���Ă�����t���ɕ\�����܂��B �@60�p���X/��]�^�G���R�[�_�g�p���ōő�10000�J�E���g�ŁA���͍ő���g����10KHz�A�p���X����0.05msec�ƋK�肳��Ă��܂��B �@�Ƃ������́A0.05msec�ȏ�̃p���X���̐M���ł���Γǂݎ���Ă����Ƃ������Ȃ̂ŁA�ŏ�0.05msec�̃p���X�����[�^�[��30�p���X/��]�^�G���R�[�_�̏o�͂���쐬���ĂP�p���X�ɂ��Q�p���X�o�͂ł���AH7ER-NV1�͂����̃f�W�^���J�E���^�Ȃ̂Ńp���X�Ԋu�Ȃǂɂ͊W�Ȃ��������p���X�̐����������ĕ\�����Ă�����͂��E�E�E�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B 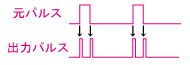 �@�Ȃ�b�͊ȒP�ŁA���[�^�[�̉�]���p���X����u�ω����o��H�v�Ńp���X�̗����オ��_�Ɨ�����_�̓�ӏ������o���āA���ꂼ���0.05msec�̃p���X��������Α���H7ER-NV1�^�R���[�^�[�͓ǂݎ���Ă����ł��傤�B
�@�Ȃ�b�͊ȒP�ŁA���[�^�[�̉�]���p���X����u�ω����o��H�v�Ńp���X�̗����オ��_�Ɨ�����_�̓�ӏ������o���āA���ꂼ���0.05msec�̃p���X��������Α���H7ER-NV1�^�R���[�^�[�͓ǂݎ���Ă����ł��傤�B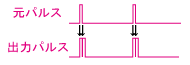 �@���������Ŗ�肪�B
�@���������Ŗ�肪�B�@���g���̃��[�^�[�̉�]���p���X�����o����Z���T�[�^�G���R�[�_���ǂ̒��x�̃f���[�e�B��Ńp���X���o�͂��Ă���̂��킩��Ȃ��̂ŁA�����P��̃p���X�����ƂĂ��Z����0.05msec�����̏ꍇ�A�}�̂悤�Ƀp���X�̗����オ��Ɨ�����̊Ԃ�0.05msec�������Əo�͂���Q�̃p���X�ɊԂ������Ȃ��āA�Ȃ����ĂP�̃p���X�ɂȂ��Ă��܂��̂łQ�{�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@�����܂ŋɒ[�Ƀq�Q�̂悤�ȒZ���p���X���o�͂��Ă���Ƃ͎v���܂��A�ꉞ�͂��̒��x�ł��Ή��ł���悤�ɂ͍l���܂��傤�B �@�܂��A�����܂Ŋ�]�I�ϑ��Ƃ��āu30�J�E���g/��]�v�Ƃ�����������A����́u60�J�E���g/��]�̃Z���T�[�������Ă��āA���̃Z���T�[������FF��1/2�ɂ��ăf���[�e�B50���̂ƂĂ��Y��ȃp���X�ŏo�͂��Ă����e�ȑ��u�v�ł͂Ȃ����Ɨ\�z���Ă݂邱�Ƃ��ł��܂��B �@�ʂɂ��������[���l���Őv���ꂽ���u�ł͂Ȃ��A����30�p���X/��]�ɂȂ�悤�ɍ��ꂽ�����̃Z���T�[�������Ă��邾����������܂��B 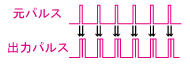 �@�܂��������ŁA��]�����オ��Ύ����ƃp���X���̎��Ԃ͒Z���Ȃ�܂��̂ŁA����]�̍ۂɂ��P�p���X��0.05msec�ɖ����Ȃ��ꍇ�͂Q�{�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�܂��������ŁA��]�����オ��Ύ����ƃp���X���̎��Ԃ͒Z���Ȃ�܂��̂ŁA����]�̍ۂɂ��P�p���X��0.05msec�ɖ����Ȃ��ꍇ�͂Q�{�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�@���[�^�[�̉�]�����グ�čs���āA����_����}�ɉ�]���\�����K�N���Ɨ����Ĕ������炢�ɂȂ�����A���̂悤�ȃp���X���̌��E�����Ƃ������ɂȂ�܂��B �@����̂���]�̍ő�2300rpm�~30�^�b��H7ER-NV1�Ɍq���Ƃ����ړI�ł���قږ�薳����H��v���܂����B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���͕� �@���[�^�[�̉�]���p���X�o�͂��I�[�v���R���N�^�炵���̂ŁA���d���ړ_�p�̓��͉�H�ɂ��܂��B �@���̓p���X�������Ă���Ԃ�LED1���_�����܂��B �@���ۂ̓p���X�ł�����_�ł��Ă��܂����A�ڂɌ�����_�ő��x�ł͂���܂���̂Ń��[�^�[�̉�]���͘A�����ē_�����Ă���悤�Ɍ����܂��B �@�����A���[�^�[���~�܂��Ă����Ԃŏo�͂�ON�ɂȂ�悤�ȏꏊ�Ŏ~�܂�����ALED�͓_�������ςȂ��ɂȂ邩������܂���B �� �ω����o�E�p���X������H �@�ω����o��EX-OR IC 74HC86���g�p���܂��B �@�ω����o�̌����́u�Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF�v�Ő������Ă��܂��̂ł���������ǂ݂��������B �@����́u�ω������m������o�͂���p���X�v�̎��Ԃ���0.01�`0.1msec�ł��B �@�p���X����VR1�Œ��߂ł��܂��BVR�𒆉��ɂ��킹��Ɩ�0.05msec�ɂȂ�A����̎g�p�ł͂��̒����ő��v�Ȃ͂��ł��B �@�o�̓p���X�����Ă���Ԃ�LED2���_�����܂��B �@�����A0.05msec�ƂƂĂ��Z���p���X�̂���LED�͔����ڂ���ƌ�����x�ł��B���邭�͌���܂���̂Ŗ��邢���ł͊m�F���ɂ����ł��傤�B �� �o�͕� �@H7ER-NV1���d�������̂��߁A�L�d���o���Ƃ��܂��B �@�Q�{������ďo�͂��ꂽ�p���X��5V��ON/OFF���܂��BH7ER-NV1��4.5V�ȏ��H�ƔF������炵���̂ő��v�ł��傤�B �� �e�X�g�p�X�C�b�` �@SW1�Łu�Q�{�����ꂽ�p���X�v�Ɓu���͂��ꂽ�p���X�v�̂ǂ�����o�͂��邩���ւ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@�g�ݗ��ăe�X�g�ƒ����Ŏg�p���܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@�g�ݗ��ĂɊԈႢ��������A���͂ƃ��[�^�[�̃p���X�o�͂��q���Ń��[�^�[����LED1���_�����܂��B �@���[�^�[���~�߂�Ɠ��̓p���X�������Ȃ���LED1�͏�����͂��ł����A�Z���T�[��ON�̈ʒu�ɂȂ�ꏊ�Ń��[�^�[���~�܂�悤�Ȃ���̏ꍇ�́ALED�������ςȂ��Ŏ~�܂邩������܂���B �@���[�^�[����ł������Ă݂�LED1���p���p���ƖڂɌ�������x�̑����œ_�ł��邩�����̂ł������ł��B �@���͂�ON/OFF����ւ�u�ԂɂQ�{���p�̃p���X�����܂�����A��Ń��[�^�[��������蓮���������x�Ȃ�LED1��������������肷��u�Ԃ�LED2���p�b�ƈ�u�����_������̂��m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B �@���[�^�[�ʂɉ��ꍇ��LED2�͂�������Ɠ_�����܂��B �@VR1�����ɉ�LED2�̖��邳���Â��Ȃ�A�E�ɉƏ������邭�Ȃ�܂��B �@���̖��邳���ς�Ώo�̓p���X����0.01�`0.1msec�ɕω������鎖�ɂ��������Ă��܂��B(�{����0.01�`0.1msec���͂��ꂾ���ł͂킩��܂���) �@�e�X�g���I���AVR1�͊�{�͒����ɉĂ����Ă��������B �@�����܂ł̃e�X�g���I���A�o�͂�H7ER-NV1���Ȃ����[�^�[�̉�]����\�����܂��B �@�����\�����Ȃ��ꍇ�͏o�͗p�g�����W�X�^�܂����悭���ׂĂ��������B �@�\�����o��ASW1�Łu�Q�{�����ꂽ�p���X�v��I�ׂΖ{���̃��[�^�[�̉�]���A�u���͂��ꂽ�p���X�v��I�ׂ��̔����̉�]����\�����邩�m�F���Ă��������B �@���̕\�����������Q�{�̒l��\���ł��Ă���n�j�ł��B �@������]���ɂȂ�ƂQ�{�ł͂Ȃ����̃p���X��(�{���̉�]���̔���)�����\�����Ȃ��Ȃ�ꍇ��VR1�����ɉăp���X����Z�����Ă݂Ă��������B �@H7ER-NV1�����e�������̓p���X����Z�����邱�Ƃ��ł��A���̓p���X�����ɒ[�ɒZ���悤�ȏꍇ�ɂ�������x�͒������đΉ����邱�Ƃ��ł��܂��B �@VR1�𒆉����E�ɉĂ��A�ō���]�̎��ɉ�]�����������\�������悤�ł���A�������E�ŕ\�������Ȃ��͈͓��łȂ�ׂ��E���ɉĂ������ق����A�o�̓p���X�����L���Ȃ���H7ER-NV1�̍ŒZ�p���X�����L���ڂŌ�쓮�Ȃǂ����Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��BH7ER-NV1�̓��͂ɂ͗]�T������͂��Ȃ̂Œ����ł����͋N���Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�����E�ɉĂ����v�Ȃ班���E�Ŏg�p���Ă��������B �@���̓p���X���Y��ȏꍇ(�f���[�e�B��50%�ɋ߂�)�AVR1���������ς��ɉďo�̓p���X�����ł��Z������ƍō�16000rpm���炢�܂ł͂Q�{���ł��܂��BH7ER-NV1�͍ō�10000rpm�܂łł����炱�̉�H�̐��\�͍���̖ړI�̂��߂ɂ͗]�T�̂͂��ł��B �@���̃��[�^�[�h���C�o���茳�ɖ����̂łǂ̒��x�̏�ԂŃp���X���o�͂����̂��H �@H7ER-NV1�͍ō��ǂ̒��x�̃p���X���܂ŋ��e�����̂��H �@�Ȃǂ��m�F�ł��܂���̂ŁA����͂��̒��x�̉�H�����ł��܂���B �@�����A���[�^�[����̏o�̓p���X�������̂������Z���āAVR1���ǂ��̈ʒu�ɉĂ��Q�{������Ȃ��悤�ȏꍇ�́A���͕��Ƀ^�C�}�[��H�����ăp���X���Ԃ������đΏ�����ȂǁA���������������K�v������܂��B �@��������Ȃɋɒ[�ȃp���X�̏ꍇ�A�Ȃ���]���v�ɂ���Ă͎t���Ȃ��������\���������Ȃ������肷�镨���łĂ���ł��傤����A���������܂ō����p���X���o�͂͂��Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A�͂����āH ���Ԏ� 2010/6/11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����肪�Ƃ��������܂����I�������i���W�߂č�낤�Ǝv���܂��B���[�^�[�ƃh���C�o�[�ł������{�d�Y��FY8S25-D3��FYD825PD3�ł��B�ƂĂ����^�ň����ł��B�܂��ϑ����[�^�[�Ƃ��Ă͂ƂĂ��g���₷�����낢��Ǝg�������ł��B��]�p���X�̓I�[�v���R���N�^�Ńp���X����0.45ms�Œ�Ńp���X�Ԋu����]���ɂ���ĕω����邻���ł��B�������܂�����܂����A�����܂��B����͂��肪�Ƃ��������܂����B �邿��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@0.45msec�̃p���X�Ȃ畝�I�ɂ͗]�T�ł��ˁB �@�u���V���X���[�^�[���R���g���[���[�ʼnĂ���Ȃ�A�u��ʼnāv���p���X�͔������Ȃ��ł��傤�����ʼnĊm�F�͂ł��܂��A�t�ɃZ���T�[���̌��o�@�ŕςȏ��Ŏ~�܂��ē��̓p���X�������オ����ςȂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂Ō����ڂ��X�}�[�g�ŗǂ��ł��B �@�H��@�B�p�Ƀu���V���X���[�^�[�^�R���g���[���[�����Ȃ����������悤�ɂȂ��Ă���̂ł��ˁB ���Ԏ� 2010/6/12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p)�̂Ƃ��͊��荞�ݎ��炢�����܂����B �������܃m�C�Y�����ɕ������ł��B ����͕ʂ̌v��Ŏ��₵�����Ǝv���܂��B ���e�́A�P���̂������܂������Ԃɖ�Q�b�Ԃ����n�m�����H�ł��B���܂������ԂƂ����̂͂`�l8�F00�Ƃo�l4�F00���炢���l���Ă���܂��B�������@���3�u0.1�`���x�ł��B tekku �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u����(����̂���)�~���~���Ɂv�Ƃ������ł��Ɛ��m�Ȏ��v���K�v�ŁA���W�b�NIC�Ŏ��v�����ƌ��\�ʓ|�Ȃ̂ł��̕�����100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���u�t���A���[���N���b�N�v���g�p���ďȗ͉�(�蔲��)���܂��傤�B �@����͈���ɂQ��A�ʁX�̎��Ԃɓ��삳����Ƃ������ŃA���[���N���b�N�͂Q�g���Ă��ꂼ��̎�����ݒ肵�܂��B �@�A���[���N���b�N�𑝂₹�Ή���ł����쎞���𑝂₹�܂����A���܂莞�v������`���ƕ��Ԃ̂��ٗl�Ȍ��i�ł�����A���2�`3��̌ʐݒ����ꍇ�́uAC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI�v�ʼn������@���ڂ��Ă���PT50D(14�v���O����)���g��ꂽ�ق����y�ł����V���v���ɂȂ�܂��B 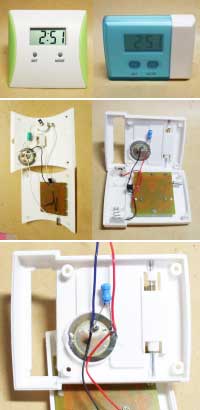 �@����e�X�g�����A���[���N���b�N�́A100�~�V���b�v�L�����E�h�D�ōw�������ʐ^�̂Q��ށB(�O���甃���Ă�����)
�@����e�X�g�����A���[���N���b�N�́A100�~�V���b�v�L�����E�h�D�ōw�������ʐ^�̂Q��ށB(�O���甃���Ă�����)�@��������d���͓d�r���1.5V�B�E�̎l�p���ق��͒P�l�d�r���g�p����̂œd�r�����Ȃ��Œ����Ԃ̎g�p���ł������ł��B �@�u�s�s�s�c�v�Ɩ�u�U�[�ɂ́w���d�u�U�[�x���g�p����Ă��āA1.5V�ł͂ƂĂ������ȉ��ł�����Ȃ��̂��R�C�������ɕ������Ă��āA�g�����W�X�^�ŃR�C���ɓd���𗬂��ď[�d���Ă���d�����Ւf�������̗U���N�d�͂ŋN���鍂�d���p���X�ň��d�u�U�[�ɏ\�������d���������āA�傫�ȉ���炷�����݂ł��B �@����͂�������^�C�}�[�Łu���Ԃ������v�Ƃ����M�������o���܂��B �@���d�u�U�[�ƕ���ɕ��ׂ��Ȃ��̂ŁA�u�s�s�s�c�v�Ƃ������͂��Ȃ菬�����Ȃ�܂��B �@�u�ڊo�܂��v�Ƃ��Ďg���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�Â��Ȏ����Ŏ��v�̋߂��ɋ��Ă���ƕ���������x�̉��ʂ͋t�ɋC�ɂȂ�Ȃ����x�ł悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@����ł��u���͕s�v�v�Ƃ����ꍇ�͈��d�u�U�[�͊O���Ă��܂��Ă��������B�R�C���͊O���Ȃ��悤�ɁI �@�ʐ^�̃A���[���N���b�N�ȊO�ł��A�u�U�[�Ɉ��d�u�U�[���g�p���Ă��āA����Ɠ��l�ɃR�C���ŏ������Ă���^�C�v�ł���ǂ�ł��g�p�ł��܂��B �@�}�O�l�`�b�N�X�s�[�J�[���g�p���Ă���^�C�v�́A���茳�ɖ����̂Ńe�X�g�ł��܂���ł����B���삷�邩�͕s���Ƃ������ŁA�����}�O�l�`�b�N�X�s�[�J�[�g�p�^�C�v�̎��v���g�p�����ꍇ�͊e���Ŏ������Ă��������B�����I�ɂ͓��삷��Ǝv���܂����A���삵�Ȃ��Ă��m��܂����i�O�O�G �@��H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���̓J�v���[ �@���d�u�U�[���p�̃p���X�d���́A�t�H�g�J�v��TLP521-2�Ŏ܂��B �@TLP521�̓����̐ԊOLED�͖�1V���x�Ō���܂��̂ŁA���͂�1V���x�ȏ゠��Δ������邱�ƂɂȂ�܂��B �@�R�C���ŏ������Ă���M���Ȃ̂ł�����傫�ȓd���ł�����K�X��R�����ēd�������͂��Ă��܂����A�R�C���������Ă��Ȃ��^�C�v�̎��v�ł���1V�O��̓d�����X�s�[�J�[�ɂ�����قڔ������܂��B �@���ʂł���Β���Ƀ_�C�I�[�h�����ċt�d����h�~���܂����A���̎��v��1.5V�O��œ����Ă���̂Œ���Ƀ_�C�I�[�h�������Vf�Ԃ�̃h���b�v�d���Ńt�H�g�J�v���ɂ�������d����������̂����������Ȃ��̂ŁA����_�C�I�[�h�͖����ŕ���ɋt�d�������_�C�I�[�h�����ĕی�Ƃ��Ă��܂��B �@�R�C���Ŕ��������t�d���͒�R�ƃ_�C�I�[�h�œ�������Ă��܂����ߑ傫�ȉ��͏o�Ȃ��Ȃ�܂����A����̖ړI�ł͂��̂ق������v�̓d�r�����Ȃ茸���Ă���������̂ŗǂ��ł��傤�B �@����͂���]���u����Q��v�Ȃ̂Ŏ��v���Q�ڑ�����\��ŁA�Q��H�����TLP521-2�Ő}�����Ă��܂����A�P��H�����TLP521-1���Q�ʁX�Ɏg���̂ł����\�ł��B �@�܂��A�R��H�A�S��H�Ƒ��₵�����̂ł����TLP521-1��K�v��H�Ԃ�p�ӂ��邩�ATLP521-4�ȂǍX�ɑ����̉�H���P�̃p�b�P�[�W�ɓ������i���g���̂ł��\���܂���B �� �f���� �� �A�����^�C�}�[ �@�A���[�����́u�s�s�s�c�s�s�s�c�v�Ƃ��������̒f�����ł��B �@�P���ɂ��̉����M�����u�L�邩�^�������v�������肷��Ɓu�s�v���ƂɃX�C�b�`�������Ă��܂����܂�����܂���B �@�����Ń����V���b�g�^�C�}�[IC 74HC123(�̂�������)���g�p���āA�u�s�v�Ń^�C�}�[���N�����Ă��������莞�Ԃ́u�A���[�������Ă����v�Ƃ����M����A������ON�ɂ��܂��B �@���́u�A���[�������Ă����v�Ƃ����M�����Ԃ��u�s�s�s�c�s�s�s�c�v�́u�c�v(�x��)�̕����ȏ�̒����ɐݒ肵�Ă����A�u�s�s�s�c�s�s�s�c�v�Ɩ��Ă���Ԃ͂����Ɓu�A���[�������Ă����v�Ɗ֒m���Ė葱���Ă���Ԃ͐M�����o�������邱�Ƃ��ł��܂��B �@���̎��Ԃ�VR1����0�`10�b�Œ��߂ł��܂��B �@���ۂɂ�0.5�b�ȏキ�炢�ɐݒ肵�Ă����Ζ��͂���܂��A���肵�ē��삳���邽�߂�1�b�ȏ���x�ɂ��Ă������ق��������ł��傤�B �@�u�A���[�������Ă����v�Ɣ��肵�Ă���Ԃ�LED1���_�����܂��B �@����̂���]�ɂ͂���܂��A���́u�A���[�������Ă����v�M���ŊO���̋@��삳���郂�[�h���p�ӂ��܂����B �@�A���[�������Ă���Ԃ����Ɖ����@��삳������A�^�C�}�[���Ԃ����邱�ƂŖ�~��������ԋ@��삵���������邱�Ƃ��ł��܂��B �� �֒m�����莞�Ԃ����o�͂��o���^�C�}�[ �@�u�A���[�������Ă����v�Ƃ��������֒m������A���̏u�Ԃ����莞�Ԃ����o�͂�ON�ɂ���ׂ̃^�C�}�[�ł��B �@���Ԃ�VR2����0�`10�b�Œ��߂ł��܂��B �@�^�C�}�[�����삵�Ă���Ԃ�LED2���_�����܂��B �@�u�@����Q�b�������삳�������v�Ƃ����ꍇ�͂Q�b�ɐݒ肵�܂��B �@�����ƒ������ԓ����������ꍇ�A�d���R���f���T��100��F����1000��F�ɕς���Ǝ��Ԃ�10�{��100�b�ɁAVR��100K������1M���ɕς���Ƃ�͂莞�Ԃ�10�{��100�b�ɁA�����ς����100�{�̖�16���܂Œ������邱�Ƃ��ł��܂��B �� ���[�h�ؑփX�C�b�` �@�㑤�ɐ�ւ��Ă������y�Z����z�Ƃ��āA�A���[�����J�n�̏u�Ԃ���VR2�Őݒ肵�����Ԃ����o�͂�ON�ɂ��܂��B(����̂���]�̏ꍇ������̃��[�h) �@�����ɐ�ւ��Ă������y������z�Ƃ��āA�A���[�������Ă���Ԃ͂����Əo�͂�ON�ɂ��A��~��ł���VR1�Őݒ肵�����Ԃ��o�߂�����o�͂�OFF�ɂȂ�܂��B �� ����ON/OFF�X�C�b�` �@�A���[���N���b�N�ŋ@��������ǂ�����ON/OFF�ł���X�C�b�`�ł��B �@�^�C�}�[�ŋ@��삳�������Ȃ�����OFF�ɂ��܂��B�ӂ����ON�ɂ��ă^�C�}�[�ŋ@��삳���܂��B �@�����Ă��̃A���[���N���b�N�ł́A���v�̃{�^�����������Ɓu�s�b�v�Ɗm�F�����o�܂��B �@���̊m�F���ł��{��H�̓A���[�����������Ɣ������Ă��܂��܂�����A���v���킹���s������Ȃǂ����鎞�ɂ͂��̉��ŋ@�킪�����Ă��܂�Ȃ��悤�A�o�͂��J�b�g���Ă��������B �� �蓮ON�X�C�b�` �@�^�C�}�[���ԂɊW�Ȃ��A�@������������ɉ����Ɠd�����o�͂����蓮�X�C�b�`�ł��B �@���ɂ��������K�v�������ꍇ�͂��Ȃ��Ă��\���܂���B �� �o�̓g�����W�X�^ �@�o�͂̋@��͏��d���炵���̂ŁA�g�����W�X�^2SC2120�ŃX�C�b�`���O���܂��B �@3V��200�`300mA���x�܂łȂ���v�ł��B(�ő�500mA���x�܂ŁA�A���d�������d�r�ł́E�E�E) �@�傫�ȕ��ׂ�ڑ�����ꍇ��AAC100V�@������ꍇ�̓����[(DC 3V)��SSR���q���ł��������B �� �d�� �@����]�̕��ׂ�3V 0.1A�Ƃ������ŁA��H�̓d�������d�r�Q�{��3V�Ƃ��Ă��܂��B �@�o��OFF�̏ꍇ�A���̉�H�̏���d������60��A���x�Ɣ��ɏ��d����������܂���B���ׂ�����Q��Q�b�ԂƂقƂ�Lj���������Ă��Ȃ��̂ŁA���d�r�ł������������삵�����܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@�g�ݗ��Ă���A���@��͌q���Ȃ����u����ON/OFF�v�X�C�b�`�������Ԃœ���e�X�g���܂��B �@VR1��VR2�̗������������ɉĂ����܂��B �@���̏�Ԃł́u�A���[�������Ă����v�Ɣ��肷��^�C�}�[�͈�u�Ȃ̂ŁA�u�s�v�������Ă���u�ԂɑΉ�����LED1���_�ł��܂��B����Ƃقړ�����Ԃ�LED2���_�ł��܂��B �@���ۂɃA���[���N���b�N�̃A���[����ݒ肵�āA�^�C�}�[���ԂɂȂ��Ĉ��d�u�U�[�������ȉ��Łu�s�s�s�c�v�Ɩ�����A����ɓ�������LED1���_�ł���Ɠ��͕��Ɓu�A���[�������Ă����v��H�͓��삵�Ă��܂��B �@VR1���E�ɉĂ䂭�ƁALED1���_�����鎞�Ԃ����X�ɒ����Ȃ��Ă䂫�A0.5�b�ݒ肠���肩���́u�s�s�s�c�v�Ɩ��Ă���Ԃ����Ɠ_�������ςȂ��ƂȂ�܂��B �@���̎��Ԃ�����ƁA�A���[������~��ł����炭��LED1���_���������āA�x��ď�������悤�ɂȂ�܂��B �@�P�b���x�ȏ�ɐݒ肵�Ă��������B �@���ɁA�A���[�����������āA�A���[�����葱���Ă���Ԃ�LED1���_�����������ԂŁALED1���_���J�n����u�Ԃɓ�����LED2���_�����A������(��u��)�����鎖���m�F���Ă��������B �@VR2���E�ɉĂ䂭�ƁALED2���_�����鎞�Ԃ����X�ɒ����Ȃ�A�E�������ς��Ŗ�10�b���x�ɂȂ邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@�m�F�ł�����A���D�݂̎��Ԃɐݒ肵�Ă��������B �@�^�C�}�[����̊m�F�Ƃ��D�݂̎��Ԃ̐ݒ肪�ł���A���ׂɖړI�̋@����q���Ń^�C�}�[����ł����Ɠ������m�F���Ă��������B �@�A���[�����ƘA�����Ẵe�X�g�̍ہA����̎ʐ^�̃A���[���N���b�N�Q�@��ł́u�{�^���Q���ɉ����ƃe�X�g���[�h�ɂȂ�A�����Ă���ԉt�����S�\���ɂȂ�Ƌ��ɃA���[�������o������v�Ƃ������Ƃ��킩��܂����B �@���������^�C�}�[��ݒ肵�āA���̎����ɂȂ�܂ő҂��Ȃ��Ă������̂łƂĂ��֗��ł��I�i�O�O�G  �@100�~�ł͍ς݂܂��A�ʐ^�̂���ȁu�d�g���v�v���z�[���Z���^�[����980�~���x�Ŕ����Ă��܂��B
�@100�~�ł͍ς݂܂��A�ʐ^�̂���ȁu�d�g���v�v���z�[���Z���^�[����980�~���x�Ŕ����Ă��܂��B(�d�r���ꂽ�̂ŕ\�����o�Ă��܂���E�E�E) �@100�~�V���b�v�̃A���[���N���b�N���ƌ��������\�b�ȏ�����鐻�i�������A�������g���Ă���Ǝ��v�̋������C�ɂȂ��Ď������킹�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂���B �@������̑��u�̗p�r�����v���������x�����Ă��Ă���薳���p�r�ł����100�~���v�ł������̂ł����A����������x�͎��v�̋������C�ɂ���p�r�ł���Έ����d�g���v���g���̂���ł��ˁB �@�p�r��������Ă��܂��A����Q��Œ��Ɨ[���ƂȂ�ƁE�E�E�u�Ϗ܋��̐����̎����a��葕�u�v�̃��[�^�[���p�r�̂悤�ȕ���������܂���B����L�p�ɂ������������u������悤�ł��ˁB �@���������p�r�ł���A���v���������炢�����Ă��Ă��S�R��薳���ł��ˁB �@�e�X�g���Ă��ċC�t�����̂ł����A���v���u����u�U�[�n�m�v�ɂ��Ă����ƁA�����O���Ɂu�s�b�v�Ɩ�M�����Ă��̉�H�������܂��B �@�����O��(�܂��͎��v�����炵�Ă����ĔC�ӂ̖���XX��)�ɉ����̑��u��������A�����f�B��H�Ƒg�ݍ��킹�Ď���̂����ɓd�q�I���S�[����炵����A�u�P���ԂɈ��������v�̂ɂ��g�������ł��B ���Ԏ� 2010/6/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�Ȃ�قǁI�I100�ς̎��v�ł����A����͎v�����܂���ł����B ����Ȃ玞�v�Q���n�q�����b�`�Œ����ԃ^�C�}�[�����܂��ˁB �������炵���A�C�f�A�Ƃ��̑����ɂ́A����������������ł��B�ŏ����C�ɂȂ����̂ł������̉�H�A���v�̃A���[�����R�O�b���炢�葱����Ƃ��̊Ԃ��g���K�[���|����R�O�b�ȏ㓮�삷��悤�ȁE�E�E�Ԉ���Ă����炷�݂܂���A����������������ƍK���ł��B tekku �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�� ����J�Ƃ̂��w��ł������A���e�����e�����Ɍ��J�ʼn����Ē����܂� >���v�̃A���[�����R�O�b���炢�葱����Ƃ��̊Ԃ��g���K�[���|����R�O�b�ȏ㓮�삷�� �@���[�ƁA�u�����V���b�g�^�C�}�[�v�̓�����悭����������Ă��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B �@��H�}�̒��ɂ���� �@����́u�G�b�W�����v(�������Ȃ̂Ő��_���̃G�b�W����)��\�����̂ł��B �@�u�G�b�W�v�Ƃ͂��̂܂܁u�[�v�̈Ӗ��ŁA���̏ꍇ�͓��̘͂_��(�l)����(L)���琳(H)���ς�����u�������̉�H�ɂƂ��ĈӖ��𐬂����Ƃ�����킵�A���̌ジ���Ɛ��_��(H)�ɂȂ���ςȂ��ł�������Ӗ��𐬂��܂����B �@�^�C�}�[�Ō����u�N���b�N��H�ɂȂ����u�ԂɃX�^�[�g�A���H�ɂȂ���ςȂ��ł��^�C�}�[�ɂ͉e�����Ȃ��B�v�Ƃ������ł��B �@�t���b�v�t���b�v��b�`�Ō����A�u�N���b�N(�X�g���[�u)��H�ɂȂ����u�ԂɁA���͒[�q�ɓ��͂���Ă����_��(�l)��ǂݍ���ŁA����ȍ~�͓��͂̒l���ǂ�Ȃɕς��Ă��o�͂͊��ɓǂݍ��f�[�^���o�͂���Â��ĕς��Ȃ��A���͂̕ω��͉e�����Ȃ��B�v�Ƃ�������ɂȂ�܂��B �@����ɑ��āA�G�b�W�^�ł͂Ȃ�������ON/OFF�ɂȂ�u�C�l�[�u��(����)�^�v�̐�����͂ł́A���͂����_���̏ꍇ�͓��͂̒l���o�͂��ʂ��ɂȂ�A���͂����_������s���_���ɕς�����Ō�̏u���̃f�[�^���z�[���h����܂��B �@�ȑO�̓��e��74HC595���������Ă�����Ƌ��Ă��܂������A74HC595���g�p���鎞�ɂ��K�v�ȍl�����ł����A�߂��ԍ���IC�Łu�W�r�b�g�̃f�[�^��ێ�����v�Ƃ����ړI�͓�����74HC577��74HC580������܂����A���ꂼ�ꒆ�g��D-FF�ŏo���Ă���̂ƃ��b�`�ŏo���Ă��镨�ŁA�܂��ɂ��̈Ⴂ�Ō����ڂ͂قƂ�Ǔ���IC�ł������ɂ͑傫�ȈႢ������܂��B �@����̓t���b�v�t���b�v��b�`�𐧌䂷��ɉ������ւ�d�v�Ș_���ŁA����𗝉����Ă��Ȃ��Ƒ����̘_����H�̐v�͂ł��܂���B 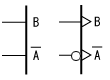 �@��H�}����IC�̕��������W�b�N�@�\�ŕ\���ꍇ�́u�G�b�W�v��u���_���v�Ȃǂ��ꂼ��u���v�u���v�ŕ\���K�v������܂����A����̉�H�}�̂悤�Ɂu�����̔z���}�v�Ƃ��ď����ꍇ��IC�͂����̎l�p�����ŁA�s���ԍ����������Ă�������Ƃ������܂�ɂȂ��Ă��܂��B���̈Ӗ��̃s�������������K�v�͂���܂��A���͉��̈Ӗ��̃s�������炢�͕�����悤�ɐM�����͏�������Ă��܂��B
�@��H�}����IC�̕��������W�b�N�@�\�ŕ\���ꍇ�́u�G�b�W�v��u���_���v�Ȃǂ��ꂼ��u���v�u���v�ŕ\���K�v������܂����A����̉�H�}�̂悤�Ɂu�����̔z���}�v�Ƃ��ď����ꍇ��IC�͂����̎l�p�����ŁA�s���ԍ����������Ă�������Ƃ������܂�ɂȂ��Ă��܂��B���̈Ӗ��̃s�������������K�v�͂���܂��A���͉��̈Ӗ��̃s�������炢�͕�����悤�ɐM�����͏�������Ă��܂��B�@�u�G�b�W����v�ɂ��Ă��������Ē�����A���̃^�C�}�[�����]�݂̏o���� >���v�̃A���[�����R�O�b���炢�葱����Ƃ��̊Ԃ��g���K�[���|����R�O�b�ȏ㓮�삷�� �@�Ƃ������͖����Ƃ������͗����ł��܂����H �@�u�f�� �� �A�����v�p�̃^�C�}�[(����TIMER-1)�͂��Ȃ��̍l����ʂ�Ƀs�s�s�Ɩ��Ă���Ԃ͂������f������p���X��̃g���K�[�M���Ő��_���̃g���K�[�����\��E���S��Ƃ����葱���u�ĉ����v����A���Ă���Ԃ͂�����ON�ł��B(�����74HC123���ăg���K�\�ȃ����V���b�g�^�C�}�[�ł���@�\�𗘗p���Ă��܂�) �@����ɑ��āu�Q�b�Ԃ����@����������v�Ƃ����ړI�́u��莞�Ԃ����o�͂�ON�ɂ���^�C�}�[�v(����TIMER-2)�́ATIMER-1�̏o�͂��g���K�[���͂Ɏg���Ă����̂ŁATIMER-1�������Â��Ă���Ԃɂ́A���������Â��Ă����Ƃ����͑S�����Ӗ��ŁA�����͂��߂�ŏ��̂��������(��u)�����g���K�[��������Ȃ��͂��Ȃ̂ł��B �@�_����}�ɂ���Ƃ����Ȃ�܂��B 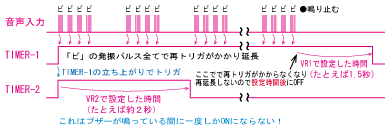 �@���[�h�ؑփX�C�b�`��
�@��H��g�ݗ��ĂāA�������@�̂Ƃ����VR�߂��ĊeLED�̓_���ȂǓ����ڂŌ��Ċm���߂�A���������s�����o�Ȃ��Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/6/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���݂܂���A�ăg���K�̓��삪�����Ă��܂���ł����B 555�^�C�}�[����Ȃ�74HC123���g���Ă��鎞�_�ŋC�Â��ׂ��ł����B �������i�̎�z�Ɋ|���낤�Ǝv���܂��B �����I�Ȏ���Ő\����܂���ł����B tekku �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�S�������s���z�u�E�@�\�\����74HC123��74HC221�ł̓��g���K�u�����ǂ����̋@�\���Ⴄ�ȂǁA��H�}��@�\�}�̌����ڂł͔��f�ł��Ȃ�IC�̋@�\�̈Ⴂ�����X����܂�����A���̂�����͂悭���ӂ��Ă��������B ���Ԏ� 2010/6/11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�c�b�P�Q�u���͂̂k�d�c�i3.5V 20mA)�Q���E�k�d�c��(2.4V 70mA)�T���̃V�O�i���c���[�삵�����̂ł����A�i�P��������̂k�d�c���͂S���ɂȂ�܂��j �N���̓v�b�V���{�^���i�����߂�^�ŁA�Q�n���K�v�ł��j �P�n���E�_���J�n�i��A�̃V�[�P���X�X�^�[�g�j �Q�n���E���~�i�V�[�P���X�쓮���݂̂ŁA�M�����͎��ɑS�\���n�e�e�j �V�[�P���X�ł����A�쓮�������ۂ̎��̐�������ɂȂ�܂� �i�\���͖ڕW�̐����ɑ���|�E�{�b�ŏ������Ă��������܂��j�ł����玞�v�i�d�g���v���j�ƘA�������ĕ\���������̂ł����A��O�Ŏg�p����̂ŁA�g�ݍ��߂���̂�����̂��A���̕ӂ͕��s���ŕ�����܂���B�i�����I�ɂ͌��ݎ��ԁi�b�܂Łj���k�d�c�\���ł���悤�Ȋg���������������Ǝv���Ă��܂��j �Ȃ̂ŁA�V�[�P���T�[�g�p���l�����̂ł����A����̊g�������l����ƌ������i��ԂȂ̂̓V�[�P���T�[�ɓd�g���v���g�ݍ��܂�Ă�����̂Ȃ̂ł��傤���E�E�E�E�E�j���ȁA�Ƃ������܂��āB �쓮�\���� �P�E-30sec�`�ԂS�������_�� �Q�E-15sec�`�ԂR�������_�� �R�E-10sec�`�ԂQ�������_�� �S�E-5sec�`�ԂP���_������0sec�܂ŁA1sec���ɐԂP����_�� �i-1sec�ŐԂT���S�_���ɂȂ�܂��j �T�E0sec�ŐԑS�����{�Q���_���i�Γ_���́{20sec�܂œ_���j �U�Eomron�̌��d�ǂ��g�p���Đԕ\���쓮�V�[�P���X���Ɍ��d�Ǎ쓮���͐ԑS���_�ŕ\���i�t���C���O�j�i�Γ_���Ƃ͕ʂɂȂ�܂��A�͓_���ŁA�ԑS���_�ŕ\���ɂȂ�܂��j�����̍ۂ͍쓮�n�e�e�X�C�b�`�A���ł� �R�����炢�̎d�l�ŕ�����܂��ł��傤���H ��낵�����肢�������܂� �����̂��� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���݂܂���A���������₪����܂��B [��D�P] �@�`���́u�c�b�P�Q�u���͂̂k�d�c�c�v�Ƃ����̂́A�u�P�Q�u�œ_������k�d�c���L��̂ł�����g���A�A���eLED�͓����ł�xxV xxmA�̒�i�炵���v�Ƃ����Ӗ��ł��傤���H �@����Ƃ��A�u��H�̓d���͂P�Q�u�v�u�k�d�c�͒�i3.5V 20mA���S�{�Ń����v�P���A������Q���g�p�v�u�k�d�c�Ԃ͒�i2.4V 70mA���S�{�Ń����v�P���A������T���g�p�v�Ƃ��������ɁA�u�c�b�P�Q�u���͂́v�u���v�Ƃ����̂͌�̕��͑S���ɂ������Ă��āA��Ǔ_�������Ă�����x�Ƃ����Ӗ��ł��傤���H [��D�Q] �@�V�[�P���X�͉��̕\�̒ʂ�ł�낵���ł����H
(�����v�̕��ו��͉��Ɉ��ɂ��Ă��܂�)
[��D�R] �@�^�C����00�ɂȂ��āA�Ε\���ɂȂ��Ă����(00�`19�b)�ɁuOFF�X�C�b�`�v�������ėΕ\���������@�\�͕K�v�ł����H �@20�b�����Ď����ŏ�����܂ł͑�����t���Ȃ��ق����悢�ł����H [��D�S] �@�ҋ@���ɃX�^�[�g�X�C�b�`�������ꂽ���A�b�j��-30�b���z���Ă����ꍇ(���ɐԂ�_��������悤�Ȏ��ԂɐH������ł���)�A�{�^�����������Ƃ������͋L�����Ă�����(�{�^���̂Ƃ���ɂ͉����ꂽ�Ƃ���LED�\��������)�A���̕���-30�b�ɂȂ�����ԕ\�����J�n����̂��H �@����Ƃ��A�ҋ@���ŃX�^�[�g�s�̎��ԑтɂ̓{�^��������t���Ȃ��̂��B [��D�T] �@���������A���̃V�O�i���c���[�͂ǂ̂悤�ȋ��Z�Ɏg�p�����̂ł����H �@���܂蕷�������������_���p�^�[���ł����c�B �@����ƁA�d�g���v�ɍ��킹�Ă܂ł�������00���ɃX�^�[�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ����[���Ƃ́A�ǂ�ȋ��Z�Ȃ̂ł��傤���H [��D�U] �@����������A�����`�Ǝ��ۂɎg�p����Ă��錻��̎ʐ^(�f�W�J���ʐ^)�������肢�������܂����H �@���܂ł������V�O�i���̉�H�}�������܂������A���ۂɎg���Ă���Ƃ���������Ă��ꂽ���͂�������Ⴂ�܂���B �@�ȒP�ȉ�H�Ȃ�ʂɂ����̂ł����A���\���G�ȃV�[�P���X�̉�H�}�����������ł͂��ꂪ���h�ɓ����Ă���Ƃ�������Ă݂����̂ł����B �@��������͊��S�ɗ]�k�ł����A���ꂭ�炢�̕��G�ȃp�^�[���ɂȂ��PIC���̃}�C�R���ō�����ق��������ƃX�}�[�g�ł���ˁi�O�O�G �@�d�g���v�ƘA���ɂ�������A�d�g���v�̋@�\���̂��̂����̃V�O�i���𐧌䂷��}�C�R���̃v���O�����ō������E�E�E�B �@PIC���̃}�C�R���̃v���O�������o���Ȃ��ƈӖ������ł����ǁB �@����͂�����W�b�NIC����Őv����\��ł��B ���Ԏ� 2010/6/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
��l���̎Q������}���\�����Z�ȂǂőS�������ɃX�^�[�g���C���ʉ߂��o���Ȃ����ւ̔z������A���l���̕����O���[�v�ɕ����Ė������ɃX�^�[�g������Ƃ����p�r�ł́H�c�Ɛ����B �t���C���O������t�^�[�����čŏI�O���[�v�ōăX�^�[�g�Ƃ��A�S�[���^�C���͓d�g���v�Œ��ڋL�^���A�X�^�[�g�̑g�~�������������Ό����i�H�j�L�^�̏o���オ��B �w�Z�̉^�����L�^��Ȃ�L�蓾��c�Ǝv�������т܂������B �����X���h �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���Ȃ�A�˗����e���ȑf���������悤�ł��̂ŁA���l�т������܂� ���T�E�d�g���v�ƘA��������K�v������ƌ����̂́A�����ԋ��Z�Ŏg�p�i�����[�t�B�[���h�j������̂�����ł��B ��O�g�p�O��́i�ꍇ�ɂ��J�V�ł��g�p���܂��̂ŁA���萫�����߂��܂��j���ł��B �P�O���̂P�b�܂Ōv������ꍇ������̂ŁA�i�X�^�[�g�ƃS�[���Ԃ̌v����͘A�����Ȃ����߁j�d�g���v�ŊǗ�����K�v������ƁA���f���Ă��邩��ł��B�X�^�[�g�͐����ɂȂ�܂��̂ŁA�t���C���O���Ȃ���Ζ��Ȃ��i��[���B�h���̗v�̂ł��ˁj�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �_���V�[�P���X�͂���ŁA��肠��܂���i���Z�^�c�K��ɉ��������e�ł��̂ŁA���ɃJ�E���g�_�E���������Ⴂ�܂��ƁA�I�肪�������Ă��܂��܂��B�t���C���O�����\���͎��R�ٗʂɂȂ�܂��j ����������������i��H�}�͕ʂł����j�g�p�����J�������܂��I �����̂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
>�����X���h �l �@�s�s�}���\���̂悤�Ȋ����ł����B �@�s�s�}���\���̂悤�ɉ���l�E�����l���Q������Ƒ�ςł��ˁB �@�X�^�[�g���Ԃ̓X�^�[�g�s�X�g�����������u�Ԃ����ʼn���l�ł��S������ĂɃX�^�[�g������@���ƁA�O���X�^�C���Ōv������ƑO�̂ق��̐l�ƌ��̂ق��̐l�̍��͕��ʒu�ŕ������ς��܂��ˁB �@�傫�ȑ��̂悤��IC�`�b�v��S���Ɏ������āA����Œʉ߃^�C��(�l�b�g�^�C��)���v�������̂ł����A���������ݔ����g����������Ȃ��ł��傤�B �@���\�l�`���S�l�̃O���[�v�ɕ����ăX�^�[�g���Ԃ����炷�킯�ł��ˁB �@�w�Z�Ȃǂł��L�^���Ȃ炻���������ɂ��āA�����O���[�v��l���ƂɃX�^�[�g���Ԃ���̂̓A�����Ǝv���܂��B >�����̂��� �l �@����̗p�r�̓����[�ł����B �@�����[�̃V�O�i�������������_�����������Ƃ͒m��܂���ł����B���s���Ő\�������܂���B �@�m���ɁA�X�^�[�g�n�_�ƃS�[��(�܂��͒ʉ߃`�F�b�N)�n�_�����L��������Ă���̂ŁA���m�Ƀ^�C�����v��ɂ͎��O�ɂ��킹������v���A���킹��K�v�̖����d�g���v���K�v�ł��ˁB �@�u�X�^�[�g�͐����v�Ƃ������́A����O���[�v�͈��̐����V�O�i���őS�Ԉ�ĂɃX�^�[�g���A���̃O���[�v�̃X�^�[�g�͂P���Ԍ�Ƃ��A������X�^�[�g����ꍇ�͂������������łP���Ԃقǂ̒����Ԃ̊Ԃ��J���Ƃ������ł����B �@�����t���C���O��������Ȃ����H�A�ׂ̈ɐ����ȊO�ł����ł������ɃX�^�[�g�ł���悤�ɁA�{�^�������������̐����ŃX�^�[�g����悤�ɐԃV�O�i�����_������悢�ƁB �@�Ƃ肠�����A�g�������ȓd�g���v(�H���̓d�g���v�L�b�g Ver2)�͑��݂��܂��������ł͎����Ă��Ȃ��̂ŁA���ɓd�g���v�̑���ɂȂ�(�[���I��)���b�E�����M�����������H�������āA�V�O�i���S�̂̐v�ɐi�܂Ȃ��Ƃ����܂���B �@���G�ȉ�H�Ȃ̂ő����̂����Ԃ��܂��B�����C���ɂ��҂����������B �@������ƃl�b�g�Œ��ׂ��Ƃ���2008�N��JAF�̎����ɍڂ��Ă��郉���[�V�O�i���̎d�l�ƈႢ�܂����A�{���ɂ�����ł���ˁH �@JAF�̎����ł͒Z���Ȃ��Ă������ԃV�O�i���Ɣ��Α�����T�b�O�̐Ԃ��L�тĂ��Ă��܂��B �@�����͂T�b�O����P�b���Ƃ̐ԃV�O�i����00�b�ł̗V�O�i���ɐ�ւ�A����ȑO��-30�b-15�b-10�b�͂ǂ��炩��������Ă����Ă������Ƃ��A���ɂ��̕����ɂ͌����̋K��͖����Ƃ��ł����H �@-30�b-15�b-10�b�̕\�������������̂T�b�J�E���g�̃V�O�i���̐��i�������݂���܂��B �@���ɂ��̃p�^�[���ł����Ƃ������ł��A���̕��������ꍇ��(����̂��H)JAF�̎����̂Ƃ���̏��Ԃɓ_�����������Ƃ�������]�����邩������܂���̂ŁA������Ɖ�H�̕��j��ύX���Ăǂ���̃p�^�[���ɂ��Ή��ł���悤�ɂ��Ă����܂��傤���B �@�ǂ���̃p�^�[���ɂ��Ή��Ƃ͌����Ă��A�X�C�b�`�P�Ńp�`���ƃp�^�[����ς�����̂ł͂Ȃ��A���ŕ��i��z�����鎞�ɂǂ��炩�̃p�^�[���őg�ݗ��ĂĂ��܂��Ƃ������@�ł����B �@����̃p�^�[���ŌŒ�̃��W�b�N��H�Őv���Ĕ��\���āA�ʂ̕�����uJAF�p�^�[���Ŏg�������̂Őv�������Ă��������v�Ȃ�Ă���]���o����A���̂ق����ʓ|�ł�����i�O�O�G ���Ԏ� 2010/6/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�c�^�ł����ł��\���܂���B �v�́A�ԃV�O�i��������������Ɠ_���V�[�P���X�����ǂ�Ζ�肠��܂����B�_�����Ɋւ��ẮA�z����őΏ�����\��ł��i���䕔�������j�b�g�ɂ��Ė�����̎��Ƀ��j�b�g�����őΏ�����悤�ɂ��܂��j�B �����Ƃ͂P�����ɂP��̃X�^�[�g�ɂȂ�܂��̂ŁA���͎�t���t���[�ʼn\�ɂȂ��Ă��܂��Ə�����܂��B�i���Z�Ԃ��w�莞�Ԃɒx��Ă����ꍇ�Ƃ��́A�����Ƃ��Ԋu���܂����j �����̂��̂͏c�^�ȃX�y�[�X�^�ł��B�i���E�I�茠�Ƃ��͌��ݎ��ԁi�b�܂Łj�\�����̉��^�ɂȂ�܂��j �i�`�e�K��͐Ԃ̕����i�b�ł̓_�����̂݁j�̋K�肪����݂̂ŁA�_���i�ォ�����Ƃ��j�����ׂ͍����K��͂Ȃ��̂ł��B �ł��̂ŁA�����I�Ɍ��ݎ��ԕ\���̂V�Z�O�k�d�c�̎��v���g���ł���悤�ɂ������ƍl���Ă���킯�ł��B �����̂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����N���c�Ƃ����Ƃ��͘_���Ă��Ȃ��킯�ł����E�E�E�B �@���Ȃ��̂���]���玄���������ď������V�[�P���X�}������ŁA
�@�ق�A�����ڂ��S�R�Ⴄ�ł���H �� �A���A�ΐF����Ƃ���Ƃ��A�ԐF�ɑ��Ăǂ��瑤�ɗL��Ƃ��͂��̍ۖ��Ӗ��ł��B�u�͏�ɒu������v�Ƃ������o�����ƍ���܂��B �@(���̉�ʂł͉������ł����A�ʂɌ���ł͏c�ł������ňӖ��I��)�����������ו���A
�@���Ȃ��̂���]�ł�-30�b����ԐF�����ɏ����Ă����āA����-5�b����̂P�b���ɑ����Ă䂭�p�^�[���ɕύX�ɂȂ�ۂɁA�����Ďc�����P�������̂܂ܓ_�����Ă������瑝���Ă䂭�̂��AJAF�̕\���̂悤�����Α��̂P���ɐ�ւ����A�����炩�珇�ɑ����Ă���̂��A�u�����v�Ȃǂɂ��Ă͑S���G����Ă��Ȃ��̂ŁA���ꂪ���Z��K���Ƃ��Ē�`����Ă���̂ł���A���Z�҂̕��X�͋K���ʂ�̃V�O�i���Ɋ���Ă��āA�����T�b�O����̃V�O�i��������Ă�����̂Ɣ��Α�����j���L�b�ƐL�яo������˘f���̂ł͖������H(�������X�^�[�g���O�ْ̋����Ă��鎞�ɁE�E�E)�Ƃ����_���m�F�����킯�ł��B >�i�`�e�K��͐Ԃ̕����i�b�ł̓_�����̂݁j�̋K�肪����݂̂ŁA�_���i�ォ�����Ƃ��j�����ׂ͍����K��͂Ȃ��̂ł��B �@�Ƃ������t��M���āA-30�b���猸���Ă����������v���Ō�Ɏc����������܂����ɖ߂�A���������V�[�P���X�Œ�(JAF�̕\�����@�ɂ͉����ł��Ȃ�)�̉�H�}�ŕʂɖ��͖����Ɗm�M���Ă�낵���̂ł��傤���B �@�P�Ɍ��t�Łu�T�b�O���珇�ɂP�����ԐF���_�����Ă䂫�A00�b�ŗɕς��v�ƕ����ŏ�����Ă��邾��(�łǂ̂悤�Ȕz�u�ł�����)�Ȃ̂ł��ˁB �@-30�b-15�b-10�b�̕\�����A�T�b�O����̓_�������v�ɑ��Ăǂ̕�������_���E�����Ƃ͋��Z��K���ł͌��߂��Ă��Ȃ����AJAF�̃��[�X�ł̓_���������悭���[�X�Ō����Ă����f�t�@�N�g�X�^���_�[�h�ɂȂ��Ă���Ƃ������������A���[�X��Î҂܂��̓V�O�i������҂̂ق��Ŏ��R�ɍ���č\��Ȃ��̂ł��ˁB �@����Ȃ���S���܂����B �@����]�̓_���V�[�P���X�����̉�H�����̂ق����y�Ȃ炻�����܂����A�����̂����l������JAF�����̂ǂ���ł��D���ɑg�ݗ��Ăł�������̂ق������i����z�����y�Ȃ炻����Ŕ��\���܂��B ���Ԏ� 2010/6/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�V�O�i���c���[�g�p���͊e�C�x���g�̓��ʋK���œ_���������L�ڂ��Ă���n�j�Ƃ����A�i�`�e�K��ł��B �Ȃ̂ŁA�����ŋL�ڂ����������d�v�Ȃ̂ŁA�_�����͖{���L�ڂ̒ʂ�Ō��\�ł��B ��낵�����肢�������܂� �����̂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�킩��܂����B �@���T�͂��܂莞�Ԃ����Ȃ��̂ŁA���Ə������҂����������B ���Ԏ� 2010/6/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���҂����v���܂����B��H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�� �d�g���v �@�d�g���v�ɂ́A�H���ʏ��́u�o�h�b�P�U�e�W�V�R�g�p �d�g���v�L�b�g�@�u�����D�Q [K-00559]�v���g�p���Ă��������B �@���̃L�b�g�ɂ͓d�g���v�̊�{�@�\��^�C�}�[�@�\�̂ق��ɁA�{��H�ɕK�v�ȁu���b�v�u�����v�̐M�����I�[�v���R���N�^�Ŏ��o���܂��B �� �g�ݗ��āE�M���̎��o�����̓L�b�g�̐����������ǂ݂��������B �� �d�g���v����̐M�� �� �^�C�~���O�M���ϊ� ��H �@�d�g���v����o�͂����u���b�v�u�����v�M�������ɁA�{��H���ł��P�������̎��v��H�������܂��B �@�A���P�����v�Ƃ����Ă�60�b�̂P�b�Ԋu���v�ł͂Ȃ��A����̂���]�̏�Ԑ��ڂ��T�b�����̂��ߓ������v���T�b���Ƃ̎��v�Ƃ��܂��B BCD(10�i)�J�E���^IC 74HC390���g�p���āu���b�v���͂�1/5�ɕ������ĂT�b�Ԋu���v�̊�N���b�N�����A��������S�r�b�g�́u�T�b�Ԋu���v�v�M�����o�͂��܂��B �@�ƁA�����Ɂu�T�b�̂����O�b�v�M�������A��ł���Ɓu���b�v�M����AND���āu�T�b�Ԃ̂͂��߂�100mSec�̏u�Ԃ����o�̓p���X���o��v��̊eLED�����H������ƂȂ�N���b�N�M�����쐬���܂��B �@74HC390�ō����4�r�b�g�́u�T�b���Ǝ��v�v�M����4to16�f�R�[�_IC 74HC154�Ńo�C�i������P�r�b�g�̏o�͂ɒu�������܂��B�o�C�i����Ԃ��͒P�r�b�g�ɂȂ��Ă���ق����F�X�g���̂ɕ֗��ł��B �@�����āA�F�X�g����H�̐���������O�ɁA��Ɂu�X�^�[�g�\��v��u�ԓ_���v�����H�ɂ��Đ������܂��B �� �X�^�[�g�����H �@�X�^�[�g����Ƃ����Ă��A���ۂɃX�^�[�g������̂́u-30�b�M���v�ŁA�����͐������́u�X�^�[�g�\���H�v�ł��B �@D-FF IC�� 74HC74���g�p���āASW1�u�X�^�[�g�\���v�X�C�b�`�������ꂽ���ǂ������L�����܂��B �@�X�C�b�`���������FF���Z�b�g������LED1�u�\���v�����v���_�����܂��B �@��ɏ����܂����A�O���Ɂu�\��E�����s�ԃX�^���o�C(STAND-BY)�v�����v��ݒu�����ꍇ�ɂ͂��̃����v���_�����Ď����s�Ԃ̃h���C�o�[���Ԃ��Ȃ������ɃX�^�[�g�̍��}���o�邱�Ƃ��m�F�ł��܂��B �@SW1�u�X�^�[�g�\���v�X�C�b�`���t���C���O�\�����ȊO�ł�����ł������܂��B�Ԃ�̃V�O�i�����i�s���ō��X�^�[�g�ʒu�ɋ���Ԃɑ��ẴV�O�i�����쒆�ł��A���̎Ԃ̃X�^�[�g�\��Ƃ��ĉ����Η\��@�\�������܂��B �@�X�^�[�g�\���Ɂu-30�b�v�p���X������ƁA�ԓ���FF���Z�b�g�����ԃV�O�i���̓��삪�J�n����܂��B �@�ԃV�O�i���̓��삪�J�n�����ƁA�X�^�[�g�\��FF�̓��Z�b�g����\��͉�������܂��B(�\��͎��s���ꂽ�̂ł����炠����܂��ł��c) �@�����u-30�b�v�p���X�����Ă��A�X�^�[�g�\��Ă��Ȃ���Ή����N����܂���B �@�X�^�[�g�\���SW2�u���~�E���Z�b�g�v�X�C�b�`���������Ƃł��ł��\��L�����Z�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�܂����̃X�C�b�`�œ_�����̐ԁE�̃V�O�i���𒆎~���邱�Ƃ�A�t���C���O���m��Ԃ̃��Z�b�g���s���܂��B �� �ԃp�^�[��������H (1) �@�ԃp�^�[��������H (1)�ł́A-30�b�`-5�b�܂ł�
�@-30�b�ɂȂ������_�ŗ\��Ă���A�ԓ���M����H�ɂȂ�܂��B �@����Ɠ����Ɂu-30�b�v�p���X�����܂��̂ŁAAND���Ƃ��ăV�t�g���W�X�^�̃N���b�N�[�q�Ƀp���X�����Ă��V�t�g���W�X�^�͂P��Ԃ�̓�������܂��B �@�����Ŏg�p����74HC195�͂S�r�b�g�̃V�t�g���W�X�^�ŁA�p���������͒[�q������Ă��܂��B �@�u���Z�b�g��Ԃł͑S�o��=L�v�u����J�n���ɂ͑S�o��=H�v�u�Ȍ�P�N���b�N���Ƃɒ[���珇��L�ɂȂ�v�Ƃ����_���p�^�[�������ɂ́A���ʂ̃V���A�����͂����̃V�t�g���W�X�^�ł͂��߂ŁA�p���������͋@�\�̂���V�t�g���W�X�^���g���ē���J�n���̏�Ԃ��p���������͂���ǂݍ��܂���K�v������܂��B �@�V�t�g���W�X�^�ɑ��āu�p���������͂���ǂݍ��߁v�Ƃ����M���[�q���������(���^)������܂����A����74HC195�̓p�������ǂݍ��ݓ�����N���b�N�M���ɓ������čs�������^�̂��ߊȒP�Ȕz���ł͂䂩���A�N���b�N���͂��������Ƃ��Ɂu�V�t�g��������邩�H�^�p���������͂���f�[�^��ǂݍ��ނ��H�v��I������M���𑀍삵�Ă��K�v������܂��B �@�����Ŏv�����_���́u���Z�b�g��Ԃł͊e�o�͂�L�v�u������Ԃł͊e�f�[�^��H(�ɂȂ�͂�)�v�Ȃ̂ŁA�o�̓f�[�^�̂��������ꂩ��I����͒[�q�ɓ���Ă��u���Z�b�g����Ă��ďo�͂�L�̎��ɂ̓f�[�^�ǂݍ��ݓ�����������v�ƃV�t�g���W�X�^�������Ŏ����ɖ��߂���悤�Ȃ����݂��������܂��B �@���ۂɂ��N���b�N����̑O��Ő���[�q��ω������Ă͂����Ȃ�����(���Ȃ��ƌ�쓮����)�Ƃ������̂��K�肳��Ă���̂ŁACR�ɂ��x����H�łق�̏��������x�������Đ��������삷��悤�ɂ��Ă��܂��B �@����Ń��Z�b�g��Ԃł͑S�o�͂�OFF�ŁA�\��Ă����Ԃ�-30�b�ɂȂ�����ŏ��̃��[�h���������������ɁA���̌�-15,-10�b�̊e�p���X�ł��[���珇�ɏ���(L�f�[�^���V���A�����͂���ǂݍ���ŏ���L�ɂ��Ă䂭)���삪�����ł��܂��B �@���̉�H�ł́A�������̂܂��X�ƃN���b�N�����͂����ƁA�Ō�ɑS���̏o�͂�L�ɂȂ��Ă��܂�����E�E�E����̓��Z�b�g��ԂƓ����Ȃ̂����̎��̃N���b�N�ł܂��f�[�^���p���������͂���ǂݍ��ރt�F�[�Y������Ȃ����ɂȂ�܂��B �@LED��S��(����IC�̏ꍇ�S��)�_�������A�����������āA�S������������܂��S���_��������E�E�E�Ȃ�Ă����C���~���[�V�����Ɏg�����H�ł����A�����-10�b����ɂ̓N���b�N�M���͓����Ă��܂���̂����������̏�Ԃ������������ւ͕ω����܂���B �@���ɉ����ω�����̂́u-5�b�v�p���X���N���A�[�q�ɓ��͂��ꂽ���ŁA-5�b�ɂ̓��Z�b�g��������������Ԃɖ߂�܂��B �@�ق��A���̉�H���_�����ł��蓮��SW2�u���~�E���Z�b�g�v�X�C�b�`�������ƃ��Z�b�g�ł��܂��B �� �ԃp�^�[��������H (2) �@�ԃp�^�[��������H (2)�ł́A-5�b�`00�b�܂ł�
�@�ԃp�^�[��������H (1)�Ǝ��Ă��܂����A������́u���Z�b�g��Ԃł͑S�o��=L�v�u�N���b�N�����邲�Ƃɒ[����H�ɂ��Ă䂭�v�Ƃ����P���ȓ���̂��߁A�V���A�����́E�p�������o�̓^�C�v�̍\���̊ȒP�ȃV�t�g���W�X�^IC 74HC164���g�p���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�ԓ���FF���Z�b�g����Ă����ԂŁu-5�b�v�p���X������ƁA���ڂ̃N���b�N�M�������ăV�t�g����������A�f�[�^���͂���H�M������荞��Œ[����P��H�ɂ��܂��B �@���̌�u-4�b�v�u-3�b�v�u-2�b�v�u-1�b�v�ƂP�b���ƂɃN���b�N�M������������̂ł����A���v�����T�b���ƂɐM�����������H�Ƃ��Ă��邽�߂ɂ��̂悤��-4�`-1�b�̐M���͑��݂��܂���B �@�����ł��̃V�t�g���W�X�^�����쒆�ɂ́u���b�v�p���X�ł��N���b�N�����삷��悤�Ɏ������g�̂P�Ԗڂ̏o�͐M�����C�l�[�u���M���Ƃ݂Ȃ��āA�u�������o��(����)���͂P�b���ƂɂP��N���b�N���삷���v�Ƃ�����H�ɂ��ĂP�b���Ƃɓ_�����郉���v���P�������Ă䂭������������܂��B �@���āA���̉�H�ɂ����ꍇ����74HC195�͂W�r�b�g�̃V�t�g���W�X�^�ŁA��x�\�����͂��߂���W�b��ɑS���̏o�͂�H�ɂȂ����炻��ȏ�͉����ω����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B �@�������\���Ɏg���Ă���̂͂T�r�b�g�Ԃ�ł�����A�ԃ����v���T�_��������Ȍ�͂��̂܂ܐԂ��S���_�������܂܂ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�ł�����A�u00�b�v�p���X�ŃV�t�g���W�X�^�����Z�b�g����00�b�Őԕ\����S�������Ă��܂��B �@���̉�H���_�����ł��蓮��SW2�u���~�E���Z�b�g�v�X�C�b�`�������ƃ��Z�b�g�ł��܂��B �� �E�����H �@�̐���̏ꍇ�A�ԂƂ͈Ⴂ�p�^�[���͕ω����܂���̂ŒP����D-FF�Łu��_�������邩�ǂ����v�𐧌䂵�܂��B �@�ԓ���FF���Z�b�g����Ă����ԂŁu00�b�v�p���X������ƁA�u�Γ_��(GO!)�v�Ƃ݂Ȃ���D-FF�̓Z�b�g����܂��B �@�u20�b�v�p���X�������D-FF�̓��Z�b�g����A�V�O�i���͏������܂��B �@�V�O�i�����_�����ł��蓮��SW2�u���~�E���Z�b�g�v�X�C�b�`�������ƃ��Z�b�g�ł��܂��B �� �t���C���O���� �@�ԓ���FF���Z�b�g����Ă�����(�܂�Ԃ̃V�O�i�����i�s���̏ꍇ�̂�)�ŁA�O���Ɍq�����ʉ߃Z���T�[�̐ړ_��ON�ɂȂ���t���C���O���o�p��D-FF���Z�b�g����܂��B �@�������Γ_������A�V�O�i�����o���Ă��Ȃ��ҋ@���ɂ̓t���C���OD-FF�͓��삵�܂���B �@�t���C���OD-FF�������I�ɂ͉�������܂����B �@�K���蓮��SW2�u���~�E���Z�b�g�v�X�C�b�`�������ă��Z�b�g���Ȃ���A�t���C���O�\���̂܂܂ł��B �@�t���C���O��Ԃł̓V�O�i�����t���C���O�\���ɂ���ׁA�f�[�^�Z���N�^IC 74HC157�Œʏ�̐ԁE�̃V�O�i����H����t���C���O��Ԃ̕\����H�ɐ�ւ��܂��B �@�t���C���O�\�����̐ԃV�O�i���S���̓_�ł̓^�C�}�[IC 555�Ŕ��U�������M���œ_�ł����܂��B �@�_�ł̑�����VR1�Ŗ�2�`6Hz���x�̊ԂŒ��߂ł��܂��B4Hz(���b�S��)���炢�����Ă��Ă��悤�Ǘǂ��X�s�[�h���Ǝv���܂��B �@�t���C���O�����o�����ꍇ�A�Ԃ�̓_����H�͑S�ă��Z�b�g���܂��B �@�܂��\��FF�����Z�b�g���āA�����\��X�C�b�`��������ė\�����Ă��Ă���USW2�u���~�E���Z�b�g�v�X�C�b�`�������܂ł͗\�邱�Ƃ͂ł��܂���B �� �����v�h���C�o���V�O�i���c���[ �@�����v�h���C�o�ɂ̓g�����W�X�^�A���C�� TD62083���g�p���܂��B �@�eCH�ő�500mA�܂ŗ����܂��B �@�����40�`70mA���x�Ə��Ȃ��̂őS�R���͖����ł����A���������v���𑝂₵����A�����v���LED���𑝂₷�Ȃǂ������ɑΉ��ł���悤�ɂ��Ă����܂��B 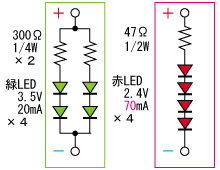 �@LED�����v�͓d���d����12V�œ_�������邱�ƂƂ��A�E�}�̂悤�ȍ\���ɂȂ�܂��B
�@LED�����v�͓d���d����12V�œ_�������邱�ƂƂ��A�E�}�̂悤�ȍ\���ɂȂ�܂��B�@����]�̒ʂ��3.5V/20mA���S�{�A�Ԃ�2.4V/70mA���S�{�ł��B �� �d����H �@74HCxx�V���[�Y�̓d���d����2�`6V�ł�����ATTL�W����5V�Ŏg���܂��B �@�O�[�q���M�����[�^��5V������ĉ�H�p�̓d���ɂ��܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@�����Ƃ����Ă��A�t���C���O�\���̓_�ŃX�s�[�h�����߂�VR1���炢��������܂���B �@VR1����LED12�̓_�ŃX�s�[�h�����D�݂̃t���C���O�\���̓_�ŃX�s�[�h�ɒ��߂��Ă��������B �@��́A�H���̓d�g���v�L�b�g�̑g�ݗ��Ă��ԈႢ��������A�d�g���v����o�͂����u�����v�u���b�v�p���X�ɏ]����LED1,LED2���s�J�b�c�s�J�b�c�Ɠ_�����܂��B �@SW1�u�X�^�[�g�\���v�X�C�b�`��������LED3���_�����܂��B �@�u�\��v��t������Ă��āALED3���_�����Ă����ԂŁu-30�b�v�ɂȂ�ΐԃV�O�i������������͂��߂�͂��ł��B �@���̂܂܃V�O�i�����i��Łu00�b�v�ɂȂ�ƗV�O�i���A�u20�b�v�ɂȂ�ƗΏ����Ɛi�߂n�j�ł��B �@�ԃV�O�i�����삪�͂��܂�Ɨ\���Ԃ���������鎖��A�ԓ_�����Ƀt���C���O���͂�����t���C���O�\���ɐ�ւ邱�Ƃ��m�F���Ă݂Ă��������B �@�Ȃɂ��듮�삪���G�ŁA���i����z�����������̂ŊԈႢ�₷���Ƃ���͂�������܂��B �@�t���C���O�\���p�̔��U��H�ȊO�͑S�ăf�W�^����H�ł�����A�z���~�X����������ΊԈႢ�Ȃ����삷��͂��ł��B �@�Ԃ�̃V�O�i�����������Ƃ���͑O�̓����H���玟�̓����H�ւƓ���������p���̂ł͂Ȃ��A��(1)�E��(2)�E�Ƃ��ꂼ�ꂪ�P�ƂŁu���ԃp���X�v�ɂ���ē_�����J�n���A�܂����ԃp���X�ɂ���ă��Z�b�g�����\�����Ƃ��Ă��邽�߁A�e�����v�̕\��������������Ίe�\���p�̉�H�̒��ł̔z���~�X�ɂȂ�܂��B �@�������A��ƂȂ�T�b�������v�����~�X���Ă���ƁE�E�E�E���삪�ނ��Ⴍ����ɂȂ�ł��傤�B �@�Ō�ɁA����͓��ɕK�v�͖����Ǝv���܂����A�p�^�[���I��p�̔z����ς���ΐԃV�O�i���̓_���E�������鏇�Ԃ����E(�}�ł͍��E�ł��A�V�O�i�����c�ɒu���Ώ㉺�ł�)����ւ��邱�Ƃ��ł��܂��B ���Ԏ� 2010/6/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
>����������������i��H�}�͕ʂł����j�g�p�����J�������܂��I ���܂łɔ���J�œ��e�������͘A���������̂ł��傤���B ���̌オ�C�ɂȂ��Ă��܂��B toms �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���J�E����J������ł��A���A���͂��������Ă��܂���B �@�ߋ��̗���Ƃ��Ă��A�u�ԁv�W�Ŏ�����������͉��ڂ����炻�������ŁA���Ԏ������A�������������Ȃ�l�������̂ŁA��������������l�ł͖������ƁB �@�������A���Ԏ�������A�������Q�l�ɉ�H������Ď��p�ɂ���Ă�����������Ƃ͎v���̂ł����A�����܂Łu�ԁv�W�̐l�̂��܂肤�ꂵ���Ȃ��Ή��������ƁA���낻���ԊW�̂�����ɂ͂����������f�肵�悤���ƍl���Ă���Ƃ���ł��B ���Ԏ� 2010/7/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���[�ށA�c�O�ł��ˁc�B �܂��Y�ꂽ����ɂЂ�����蓊�e������������悤�ł����O�O�G �ȑO���������Ȃ��i�H�j�ƒQ����Ă������A�ԓ����߂P�������Œ��ׂ����Ƃ�����܂��B(�ԂɌ��炸�Œ������܂�����) ���̍ۂ͓������ςȂ��̖������̓��C�g�E�����v�E�k�d�c�f���ȊO�ł���������悻�������炢�ł����B �Ȃ������C�g�̂��\�ԓ��������������ƋL�����Ă��܂��B�i���R�H�j �P���Ƃ��Ȃ炠����x�������ł��܂����A ���̐l�����₵�Ă����Ė��������Ă̂��Ȃ��ȁ[�Ǝv�����L��������܂��B toms �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���C�g�W�́A���C�g���D���ŋ^������������玿�₵���l����������ł͂Ȃ��ł��傤���B �@������������Ă��̌�͉��������ō��Ƃ����H���������A�m������Ƃ��Ēm�邱�Ƃ��ł���Ί����Ƃ����b�������Ǝv���܂��B �@�d�C��H�̏ꍇ�A��H�}������玟�͂�������Ȃ���Ȃ�܂���B �@�u�����͍���Ă���̂ł����A�����͂킩��܂���v�Ƃ����l�̏ꍇ�A�����̉�H�}�����u�킩��܂����I�v�Ƃ���������ɂȂ���p�^�[���͑����ł��傤�B �@�������H�}���ǂ߂邵�A������x�͐�����o������Ă���̂ł����Œ�����ł��イ�Ԃ�ȕ��ł��B �@����ɑ��āu�ԂŁ~�~�������v�Ȃǂ̎�����������́A�d�q��H��g�ݗ��Ă����Ƃ��疳�������䗦�Ō����Α����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@��H�}�͒��ꂽ���A�ǂ�ȕ��i�������̂��킩�炸���i���W�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ��A���i���Ă����ۂɊ�̏�łǂ����ׂĂǂ��z����������̂�������Ȃ��̂ŕ��u�����Ƃ��B �@�u����Ă݂͂����Ǔ����Ȃ������v�Ƃ����A�d�q�H��ł͕K���ʂ铻�œڍ����Ă���l�������Ǝv���܂��B �@IC��4�`5�ȏキ�炢�̉�H�ɂȂ�ƁA�������̂���]����鑕�u�̓��e�Ƃ���ɕK�v�ȕ��i�����H�K�͂����₳��鎞�_�ł͑z���ł��Ă��Ȃ��āA������H�}�������u�Ȃ��̕��G�ȕ��́I�A�f�l�ɂ���ȕ�������킯��������A�ӂ�����ȁI�v�Ƃ������Ɏv��������吨���������邱�Ƃł��傤�B �@����҂��{�l�l�łȂ��Ă��A�����������ӌ��œ˂��������Ă���ꂽ�ʂ肪����̕�����������Ⴂ�܂�����ˁB �@���Ԏ��̖������̔������炢�͒�����H�����Ȃ��������A���������́u����Ă����Ȃ��Ă��Ԏ�������Ƃ�����V��m��Ȃ��悤�Ȑl�v���Ǝv���Ă��܂��B �@��͂ƂĂ��H�ɂł������[���A�h���X�𖢋L���̕��ŁA���₵�ĂP�����x�ʼn��f�ڂ���Ȃ���������u�{�c�ɂȂ����v�Ǝv���āA���ꂩ��ꃖ���ȏ�͌��ɗ��Ă����Ȃ������A��Ō��ĉ���Ă��Ăт����肵���B�Ȃ�Đl�����܂����B �@��H�}�����߂�ꂽ�ꍇ�A�����烁�[���ł��m�点���Ă���̂ł����A���̎�������ꂽ�������[���͎���Ă���ł��傤���ԓ��������Ƃ������͕Ԏ����������Ȃ�����������̂ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2010/8/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�A�����x���Ȃ�\����܂��� ���̂Ƃ���C�x���g����������A������̕��ɂ͎��t�����Ȃ������̂ŁE�E�E�E�E�E�E ���悢�敔�i�̍w�����ς݂܂��āB ���ꂩ�玎��P���@�̒���ɂ�����Ƃ���ł��B ��̈悩��Ȃ̂ŁA�{�Ƃ̍��Ԃɍ�邱�ƂɂȂ�܂����A����L�̕��́A������x�`�ɂȂ�������J���܂��B ���͂܂����i���ł��̂ŁB�B�B�B �撣���č��܂��I �p�[�c�W�ł����A������H�}���݂���u���E�E�E�E�\�Z����˂��E�E�E�E�v�ƂȂ�܂��āA���т��тP���@�p�̃p�[�c���W�߂Ă����̂��^���ł����i���낢�뉯�����Ă悤�ł����j ���͂�������ǂ݂���H�}�������}�ɕϊ����Ă���Ƃ���ł��B �i�v�������T�C�Y���f�J����������܂��āj ��쐬�ɂ����������_����u���O�ɃA�b�v���悤���ȂƎv���Ă��܂�URL�݂͂�J���́@http://minkara.carview.co.jp/userid/505320/ �ɂȂ�܂����A�u�����蒠�v�ɃA�b�v���Ă����\��ɂ��Ă���܂��B��낵�����肢�������܂� �����̂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[���ŋߋ������q�˂�����A��L�̂��Ԏ����e�����������܂����B �@��͂��H�����G�Ȃ̂łȂ��Ȃ����삪�i��ł����Ȃ��悤�ł��ˁB �@������x�`�ɂȂ�������J����邲�\��́A����L���F����y���݂ɂ��Ă��܂���I ���Ԏ� 2010/8/26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���łP�Q�u�̓d���t�@�������̂ł����T�u�����[�Ƃ��ŒP����ł��傤���H ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����͂��Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B �@�Ԃ̃R���s���[�^�[���āA�C���ɐ����~�ȏ�̏o��ɂȂ���܂��B �@�ꉞ�A�Ԃ̃R���s���[�^�[�M���ł͎g�p���Ă͂����Ȃ���H�}�ł����A�P����5V��12V�@���(USB����5V��12V�d����)ON/OFF�����悤�ȃ����[���g�p�����H�}�̗�������Ă���������܂��B �@�uUSB�A���R���Z���g�v���ɂ����p�ł��܂����A���̏ꍇ��USB 5V���e�@�̓d���ɘA������ON/OFF�����ꍇ�����ł��B�ŋ߂̃p�\�R���̂悤�ɁuUSB�d���͏o�͂����ςȂ��v�̂悤�ȏꍇ�ɂ̓p�\�R���̓d���ɘA������ON/OFF�͂ł��܂���B �y5V�M����12V��ON/OFF�z (�����[�g�p/USB 5V��12V��ON/OFF�Ȃ�)  �@�����f�W�^���M���̔z���Ƀ����[�����Ȃ��ł��܂�����E�E�E�E�R���s���[�^���i�����Ă��܂��܂��B �@�f�W�^���M����5V�Ń����[�������ꍇ�ɂ͕K���u�X�C�b�`���O��H�v�u�����[�h���C�u��H�v�Ȃǂ̑�d���𗬂�����̂ɐM����ϊ������H���K�v�ł��B �@���ʂ̓g�����W�X�^�ƕ����̕��i��g�ݍ��킹�č��܂����A��p�̓d�q���i�������Ă��܂��B �@�Ԃ̒���12V�t�@�������x�ł���A�����[�������Ă��g�����W�X�^��FET���g�����X�C�b�`���O��H�����Ńt�@�������Ƃ��ł��܂�����A����̂���]�ł���p���[MOS FET�Ńo�b�t�@��H�����̂��y�ł��B �y5V�M����12V��ON/OFF�z (FET 2SK2232/�}�C�i�X�R���g���[����) 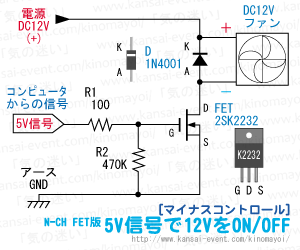 (�����Ƒ�d���p��FET�ɂ�������b�ł����A�Ԃ̐l�̓����[�����D���ȕ��������̂�) ���Ԏ� 2010/6/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���������̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B���̉�H�}���Q�l�Ɋ撣���Ă݂܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����[��̂悤�ɊȒP�ɂ͂䂫�܂��A���i���ł�����Ȃ��������Ԉ��Ȃ���Ίe���ɓ��삵�܂��B �@�`�������W���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2010/6/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���肪�Ƃ��������܂��B�����A�������������Ă݂��̂ł����A�P�Q�u�̓d������ꂽ�����łT�u�̐M�������Ȃ��Ă��P�P�C�Q�u���炢����Ă����܂��̂ł����A�����Ԉ���Ă�̂ł��傤���H ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@FET�̑����ԈႦ�Ă��܂��H �@2SK2232�̏ꍇ�A�������ǂ߂��Ԃō�����G(�Q�[�g)�ED(�h���C��)�ES(�\�[�X)�ł��B �@D��S���t�ɂȂ��ƁAFET�̒��ɓ����Ă���t�ڔj��h�~�p�̕ی�_�C�I�[�h�ɓd��������āAFET��S��D�����ɓd���𗬂����ςȂ��ɂȂ�܂�����A�X�C�b�`�͓�����ςȂ��ɂȂ�܂��B �@���������ԈႦ�Ă��Ȃ��̂ł�����A�e�X�^�[��G(�e�X�^�[�̃v���X��)��S(�e�X�^�[�̃}�C�i�X��)�̊Ԃ̓d�����v���Ă݂Ă��������B �@5V�̐M�������q���ł��Ȃ���Ԃł���ق��O�u�ł��B �@�����d�����������Ă���Ƃ��������ł��B ���Ԏ� 2010/6/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���x�����肪�Ƃ��������܂��B�������܂����B�����A��H���쓮�����サ�炭�A�t�@���ɍs���P�Q�u�̓d���ɂO�C�Q�u�قǎc��̂ł����A���e�͈͂ł��傤���H ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�{����0.2V���c��܂����I�H �@���Ƃ��A�f�W�^���\���̃e�X�^�[�Ōv���Ă��āA�{����12V����0V�ɂȂ��Ă���̂ɁA�e�X�^�[�̓��삪�x����0.2V���炢����0V�ɂȂ�܂ł͂��炭�p���p���Ɛ������o�Ă��܂��悤�Ȏ���������Ă���Ƃ��͖����ł���ˁH �@�e�X�^�[��P����12V�ɂȂ���12V�\���ɂ��āA�e�X�g�_�𗣂������ɂ͈�u�œd�����O�ɂȂ�܂����H�A����Ƃ��p���p���Ƃ��炭���Ԃ������ĂO�ɖ߂�܂����H �@�Ƃ肠�����A������Ōv��������ł́A���̉�H��5V�M��������u��1mV�ȉ��܂ʼn�����܂����炶�イ�Ԃ��FET�Ő藣����Ă��܂��B �@���ꂩ�A���g����12V�t�@���̒����m�C�Y�h�~�p�̃R���f���T�������Ă��āA���̃R���f���T�����d����Ȃ��̂ł��炭�d�����c��Ƃ��̗��R�ł͂���܂��H �@�t�@���͌q�����ɁA���̉�H�̏o�͂Ƀe�X�^�[�Ă������̏�Ԃœd�����v���Ă��A��͂�0.2V���x�����炭�c��܂����H �@�܂��A�t�@����12V�d���Ɍq���ŁA���̐ڑ���藣�������Ƀt�@���́{�Ɓ|�̐��̓d����(���̃R���f���T����)0.2V�̓d�����t�@�����炵�炭�͔������Ă����Ƃ������Ƃ͂���܂��H �@�܂����Ƃ͎v���܂����A5V�M���̂ق������S��0V�ɂȂ炸�ɁA���炭�͏��������d�����c���Ă���Ƃ������I�`�ł͂Ȃ��ł���ˁH �@�ǂ̎������A�������g���̃e�X�^�[�����Ȃ�������ƂO�u�ɖ߂�^�C�v���ƁA�d�C���ꂽ�u�Ԃ��炵�炭�͐������O�u�𑪒�͂ł��Ȃ��킯�ł����E�E�E�B �@���炭(���b�`���\�b)��0.2V���炢�c���Ă��A0.2V�Ńt�@�������킯�ł��Ȃ��A�ʂɖ��͖����̂ł����E�E�E�B �@�J�����̐Ód�C�ی�E��쓮�ی�̂��߂ɓ���Ă���470K��100K��47K�܂ŏ���������FET��GS�Ԏc�e�ʂ����Ȃ�����悤�����Ă݂�Ƃ�(5V�M��������ȏꍇ��470K�ł��イ�ł퓮�삵�܂����c)�A������0.01V�ł��d�����o��̂͌��I�Ƃ������炢�̌��ȏǂ̕��ł�����A���̉�H�}�̃t�@���̂Ƃ����12V�����[�����āA�����[�̐ړ_�Ńt�@����ON/OFF����悤�ɂȂ��0.001V�ł��R��d���͂Ȃ��Ȃ�܂��ˁB ���Ԏ� 2010/6/11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�����ł��B����ŁA���Ȃ�`���[�j���O�̃n�o���L����܂��B���ƍŌ�Ɏ���Ȃ�ł����A���̉�H�͌��\�����Ԃ̘A���g�p�ł����v�ł��傤���H
���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@FET�����M���Ă��Ȃ�����A�����`���\�����Ԓ��x�͘A���Ŏg�p���Ă��������܂���B �@�g�p����FET�ɐG���Ă݂āA�M���Ȃ�����̂܂܂ł����v�ł����A�M���Ȃ��Ă���قǂ̑�d���𗬂��Ă���Ȃ�K�X���M�����ĉ��x�������Ă��������B �@�G��Ȃ��قǔM���Ȃ��Ă���������͂����Ƃ����܂ɏk�܂�܂��B �@����ƁA�P����Ȃ̂ł����A�Ԃ̃R���s���[�^����o�Ă���M�����Ńt�@�����p�r�Ƃ́A�R���s���[�^����ǂ̂悤�ȐM�����o�Ă���̂ł����H �@�ŋ߂̎ԍڃR���s���[�^�͎Ԃ̗l�X�ȏ�Ԃ����m���ĕ��G�ȏ��������Ă���悤�ł����A�ǂ����̉��x�𑪂��Ĉ�艷�x���z�����5V�M�����o��悤�ȋ@�\������Ԏ�Ȃ̂ł��傤���B5V�M���Ƃ������́A���������̃I�v�V�����������Ɍq����p�r�ŃR�l�N�^���o�Ă���Ƃ��ł��傤���B �@��w�ׂ̈ɁA��낵����ǂ�ȏɂȂ�����M�����o��悤�ȃV�X�e���Ńt�@�����q���ł��g���Ȃ̂����������������B ���Ԏ� 2010/6/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�͂��B�l�̏ꍇ�́A�����̃��C���R���s���[�^�[�ł͂Ȃ��A�T�u�R���ŁA�R���g���[�����܂��B���̃T�u�R�����A�����������āA�o�̓|�[�g�����n���������āA�P�Q�u�ŏo��o�͂�����̂ł����A�T�u�ł����o���Ȃ��|�[�g�������āA�l�̏ꍇ�P�Q�u�̏o�̓|�[�g���g�������Ă��܂��A�ǂ����Ă��A�T�u�o�͂��g�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����k�����Ē����܂����B���ڂ̉��x�Z���T�[�ȂǂŁA�R���g���[�����邱�Ƃ��ł���̂ł����A���ꂱ��A�o���o���Ő��䂷����A�T�u�R���ŊǗ��ł�������X�}�[�g�Ńg���u���V���[�g�����₷�����ƁB�|�[�g�Ɋւ��ẮA�قڎ����̏o�͂���������I�ׂ܂��B���̉�H�̂������ŁA���Ȃ�A�͂��A�L����{���ɏ�����܂����B�܂��X�������肢�v���܂��B
���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�F�X�Ȑݒ肪�ł��鍂�@�\�ȃT�u�R���݂��Ă���̂ł��ˁB �@�|�[�g���g�����Ă���Ƃ́E�E�E�E���Ȃ�̃`���[��������Ă���̂ł��ˁA�Ȃ��Ȃ����������ł��i�O�O�G ���Ԏ� 2010/6/21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���낢�남���b�ɐ����Ă���܂��B����ł������̉�H��2�r�i334�ō�鎖���o���܂����H�A���Ƃ�����ǂ��z������Ώo����ł��傤���H��낵�����肢���܂��B ���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̂܂�FET��ς��Ă����߂Ȃ̂ŁA�g�����W�X�^�ňʑ����t�]�����܂��B �y5V�d����12V��ON/OFF�z (FET 2SJ334/�v���X�R���g���[����)  ���Ԏ� 2010/6/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 6/29 |
���肪�Ƃ��������܂����A�����ւ���܂����A�܂���낵�����肢�������܂��B ���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����M��OFF����x�������SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āA�����b�ɂȂ�܂��B �x��Đ���H�������Ă��������B �{��H����⏕��H�ւ�DC�d������(6V�`8V)�����𗘗p���āA�ʂ̋@��̓d��(100V)��A�����������ƍl���܂����B �⏕��H�͕�����LED���_�������̉�H�ł��B �����ŁASSR�L�b�g�𗘗p����100V�̓d�����쓮�����悤�ƍl���܂����B �⏕��H�ւ̓d�����������āA������SSR�L�b�g��lj����邱�ƂŎ����ł��܂����B �������������@�@�@�@�@�@������������ �� �{��H �����������������⏕��H�� ���@�@�@�@�����������������@�@�@�@����������LED���_�������H �������������@�@�����@�@������������ �@�@�@�@�@�@�@�@���� �@�@�@�@�@�@�@�������� �@�@�@�@�@�@�@��SSR �� �@AC100V���������@�@���������ʂ̋@�� �@�@�@�@�@�@�@�������� �Ƃ��낪�A�{��H�͕⏕��H�ɏ펞�d�����������Ă����łȂ��������߁A�ʂ̋@��̓d�����p�ɂɓ�����悤�ɂȂ�܂����B �����ŁA�{��H����⏕��H�ւ̓d��(6V�`8V)��ON�ƂȂ�A���̌セ�̓d����OFF�ɂȂ��Ă��ASSR�L�b�g�ɂ�5�`10���Ԃ͓d�������������悤�ɂ������̂ł����A���̂悤�ȉ�H��g�߂����̂ł��傤���H ����A�����������܂��Ƃ����ł��B��낵�����肢�v���܂��B �L �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�⏕��H�ւ̓d����������Ă��A�{��H�̂ق��̓d�����������܂܂ŁA���̓d���ŐV�K�ɍ쐬����x����H�������̂ł���ΊȒP�ȃ^�C�}�[��H�ōς݂܂��B �@�₢���킹���܂�����A�{��H�����DC 5V�̓d��������悤�ł��̂ŁA�^�C�}�[������6�`8V�Ŏ��Ԃ����߂��H�ɂ��āA�V���~�b�g��H��SSR�̐���͏펞�d�����K�v�ł�����{�@������炤DC 5V�œ����悤�ɂ��đS�̂��ȑf�����܂��傤�B �@����قǐ��x���K�v�ȖړI�ł͖��������ł����A�^�C�}�[IC���g�����@������܂��������CR��p������@�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �^�C�}�[���� �@�O������p�̓d��(6�`8V)��������āAC1���[�d���܂��B �@�O������p�̓d�����o�Ă���Ԃ�C1�͖��[�d������ςȂ��ł��B �@�O������p�̓d�����o�Ă���Ԃ�LED1���_�����܂��B �@�O������p�̓d�������ƁAC1�ɗ��܂����d�ׂ�R2��VR1��ʂ��ĕ��d���܂��B �@���d�ɂ����鎞�Ԃ�VR1�Œ��߂ł��A�ő����15��(6V)/��18��(8V)���x�܂Œx���ł��܂��B �@����̃^�C�}�[���Ԃ��O������p�̓d���Ɉˑ����܂��B �@�d�����ς�ƃ^�C�}�[���Ԃ��ς��܂��̂ł����ӂ��������B �@�R���f���TC1�̓d����FET1�̃Q�[�g�d���Ƃ��ė^�����A��1V���x�܂ʼn�����܂�FET��ON�ɂ��܂��B �� �V���~�b�g�Q�[�g��SSR��ON/OFF �@R3�Ńv���A�b�v����Ă���FET1�̃h���C��(D)�d���́AFET��ON�̎���0V�AFET��OFF�̎���5V�ɕω�����̂ł����A�Q�[�g�d������1V���x��ʉ߂���ۂɂ�FET�̑�����p�ŃQ�[�g�d���̓A�i���O�I��0V��5V�ƕω����܂��B �@�^�C�}�[���Ԃ��Z���A���̒ʉߎ��Ԃ��Z���ꍇ�͂��܂���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł����A����̂悤�ɐ����`15�����̃^�C�}�[��H�ɂ���Ɩ�1V���x��ʉ߂���̂ɐ��\�b�قǂ�����A�h���C���d�������ԓI�ȓd���̊��Ԃ����Ȃ蒷���Ȃ�܂��B �@�ł��̂ō���̃^�C�}�[��H�ł�FET�̏o�͂Œ���SSR�̃t�H�g�J�v��(�t�H�g�g���C�A�b�N)�삳�����ON/OFF�̕ω����ɕs����ɂȂ�A�ڑ������@��Ƀ_���[�W��^����\��������̂ŁAFET�̏o�͂��V���~�b�g�Q�[�g���g�p���Ă��������ON��OFF�̏�Ԃɐ�ւ��܂��B �@���ׂ̈Ɏg�p����̂��V���~�b�gNAND�Q�[�gIC 74HC14�ł��B �@�V���~�b�g�Q�[�g��ʂ�����̃f�W�^���M���͂������肵��ON/OFF�M���ɂȂ�܂�����A�����SSR�삳����AC100V�@��̓d����ON/OFF���܂��B �@SSR��ON�ɂ��Ă���Ԃ�LED2���_�����܂��B �� �O�����䂪�o���ςȂ��Ɍ�����ꍇ �@���̉�H���q���ŁA�O������d������Ă���(�O���ɂ��Ă���LED�_�����Ă��Ȃ�)�͂��Ȃ̂�LED1���_�������ςȂ��̏ꍇ�A�O������d����6�`8V�̃v���X����ON/OFF���Ă���d���o�͂ł͂Ȃ��A�}�C�i�X����ON/OFF���Ă���\��������܂��B�@��̒���NPN�g�����W�X�^����ON/OFF�����Ă���ꍇ�Ȃǂ�����ł��B �@�}�C�i�X�����J�b�g���Ă���ꍇ�ɂ́A���̉�H�̓��͂͏펞�v���X��(6�`8V)�Ɍq���邱�ƂɂȂ�̂ŁA�@��̓d���������Ă���Ԃ͏�Ɂu���쒆�v�Ƃ݂Ȃ��Ă��܂��܂��B �@�ҋ@��(�s�u�������R�����œd��������悤�ȏ�ԂŁA�@����̈ꕔ�����삵�Ă���)���@��d��(5V)�͏o�Ă��邻���Ȃ̂ŁA�����ҋ@���ɂ��O������d���p�̓d����H�������Ă���Ȃ�@��d�����������ł��펞�^�C�}�[��ON�ɂȂ���ςȂ��ɂȂ�܂��B �@���������Ȃ�E�E�E�E�A���͂��t�H�g�J�v���ɂ��ăv���X���E�}�C�i�X���ǂ�����J�b�g����Ă��Ă���薳���悤�ɂ��āA���łɃ^�C�}�[���^�C�}�[IC�ō��ʂ̉�H�ɂ����ق����悳�����ł��B �@������A�@��̓d����(�����ڂ�)���Ă�LED1���_�������ςȂ��̏ꍇ�͍ēx���A�����������B ���Ԏ� 2010/6/5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�f�������A���ɗL��������܂��B �����A����Ɏ��|����܂��B �����ɓ�����m�F�����Ƃ���ŁA���������Ǝv���܂��B �L �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�e�X�g����̂�R1��ELD1�����ł����̂ŁA���̕��i�͔���Ȃ��Ă������ł��B �@�����ʂ̉�H�ɕς���Ƃ���ƁA���̉�H�̕��i�����ʂɂȂ�܂�����AR1��LED1�����ŊO������d�����v���X����ON/OFF����Ă���̂����ׂ��ق������_�������Ă悢�Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/6/6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�L��������܂��B�����A�e�X�g��H�ɂĎ����Ă݂܂����B ���ʂł����A���@���̒ʂ�A�{��H�̓d������Ă�LED1�͓_�������ςȂ��ƂȂ�܂����B �e�X�g��H�̒���R1��LED1�����ŁA�@��d��+5V�ɂ͉����ڑ����Ă��܂���B �O������d������(+6�`8V)�Ƌ@��d���̃}�C�i�X���̐ڑ��ł��B �x�X�\�������܂��A��낵�����肢�v���܂��B �L �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�͂��E�E�E�BGND�����^�C�v�ł����B(��x��Ԃł��ˁE�E�E) �@����ł͂�����̉�H�ŁB ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�O������p�̓d���̓t�H�g�J�v��TLP521-1�Ŏ܂��B���̌�ɃV���~�b�gNAND�Q�[�gIC 74HC132�Ŕg�`���`���܂��B �@�d�����͂̓v���X�E�}�C�i�X�̂ǂ���Ő��Ă��Ă������ł����A�{��GND���番�����Ă��܂�����S���ʂ̋@��E�d���ł��\���܂���B �@�u�ԂŎg�������v�悤�Ȏ��v�����邩������܂���A12V���͂ł�R1��1K���ɂ��Ă��������B(��������H�̓d���͎O�[�q���M�����[�^����5V�������) �@�O������p�̓d�������邤���͂�������m����SSR��ON�ɂ��܂��B �@�O������p�̓d���œ��삵�Ă���Ԃ�LED1���_�����܂��B �@�O������p�̓d���������Ȃ�ƁA74HC123�̃����V���b�g�^�C�}�[��������J�n���āA�^�C�}�[���쒆��SSR��ON�͑����܂��B �@�^�C�}�[�œ��삵�Ă���Ԃ�LED2���_�����܂��B �@���Ԃ�VR1����10�b�`20���̊ԂŐݒ�ł��܂��B �@�^�C�}�[���쒆�ɂ܂��O������p�̓d��������Ƃ���������m�������R��SSR��ON���Ă��鎖�Ƃ�LED1���_�����܂��B�^�C�}�[�����쒆�ł�LED2�͏������܂��B �@�^�C�}�[���쒆���O������p�̓d���������āA�܂��Z���Ԃɐ�Ă����̏u���Ƀ^�C�}�[�͍ĉ�������܂�����A�O������p�̓d�����ꂽ�u�ԂɃ^�C�}�[�̓��Z�b�g�E�X�^�[�g���ĕK���ݒ莞�Ԃ�SSR��ON�������ĊO���Ɍq�����@��͈�莞�ԓ��삵�܂��B ���Ԏ� 2010/6/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����b�ɂȂ��Ă���܂��B > �͂��E�E�E�BGND�����^�C�v�ł����B(��x��Ԃł��ˁE�E�E) �ق��Ƃ��ɐ\�������܂���B�����Ǝ��O�ɒ��ׂ�ׂ��ł����B ������₷������ł������L���ł��B�ǂ�ł��邾���Ŋy�����Ȃ��Ă��܂��܂��B �����ł����A�p�[�c���W�߂Đ���Ɏ��|���肽���Ǝv���܂��B ���萔�����������܂����B�L��������܂����B �L �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�P�Ɂu�d�����o�Ă���v�Ƃ����Ă����̉�H�͗l�X�ł�����E�E�E�B �@�����O���@�킪�s�ӂɎ~�܂炸�ɁA����������Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2010/6/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 6/12 |
���ʂ�����Ē����܂��B �����Ɉ��肵�ē��삵�Ă��܂��B�z�肵������ɂȂ�A�������������ł��B ���̓x�́A�ق�Ƃ��ɗL��������܂����B �L �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���߂܂��āA�d�C���S�҂Ȃ̂ŎQ�l�ɂ����Ă�����Ă���܂��B AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI �����ԗp�̋�C����@�i�P�QV�RW�j���v���O�����^�C�}�[�ō쓮�ł��Ȃ����̂��ƍl���Ă��܂��B DC�^�C�}�[��T���Ă��܂������A�����Ȃ��̂�➑̂̂Ȃ����̂������AAC100V�^�C�}�[�iREVEX��PT50D��ON/OFF��14�v���O�����łP�S�O�O�~�O��j�ƂP�QV�����[���g���ē�������̂ł́H�B �ƍl���܂����B �������̒��A�X�������肢���܂��B ���쎛 �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���悭���ݍ��߂Ȃ��̂ŁA�Q�̃p�^�[���ɕ����čl���܂��B (1) �g�p����AC100V�ŁI �@��C����@��DC12V�����A�g���Ă���ꏊ�͉Ƃ̒��ȂǂŁAAC100V����AC�A�_�v�^�[�����g�p���ē������Ă���B �@���̂܂܃^�C�}�[��AC�A�_�v�^��ON/OFF������������ł���ˁE�E�E�B �@����Ȏ���͏o���܂����ˁH (2) �g�p����DC12V�ŁI �@�Ԃ̒��ȂǁADC12V�d�����������ꏊ�Ŏg���Ă���B �@100V�p�^�C�}�[�̒��g�������������I�H �@�����A���̃^�C�}�[������100V�p�̓d����H��藣���āA��H�̒�i�d��(�s���ł���12V�Ɠ�����12V���͒Ⴂ�ł��傤)�̓d����DC12V����^���Ă��^�C�}�[�͓��삵�܂��B �@AC�o�͂�15A����݂����ł�����A�����̂ɂ��\���b�h�X�e�[�g�����[�ɂȂ��Ă��邩�A�p���[�����[�������Ă���ł��傤����A�p���[�����[�Ȃ炻�̂܂g����DC12V��ON/OFF�ł���ł��傤���A�\���b�h�X�e�[�g�����[�ɂȂ��Ă�����̐���M������O����DC12V�����[���������[�h���C�o�����삵�Ă����DC12V��ON/OFF�ł��܂��ˁB �� �A���^�C�}�[���u��AC���������ŃR���Z���g��50/60Hz����Ɏ��Ԃ��v�����Ă���ꍇ�́AAC�d���œ��삳���Ȃ��ƃ^�C�}�[�����삵�܂��� �@�������������͂������ł��̃^�C�}�[���u�����āA��̃p�^�[�������H�}�������Ăǂ̂悤�ȉ�H�ɂȂ��Ă���̂��A�ǂ����ǂ���������ΖړI�̂悤�ȓ������������̂��A����S�Ă������ʼn�́E�v�E�����ł�����łȂ��Ǝ��s�ł��܂���B �@�������PT50D�������Ă��܂���ǂ����ǂ�������������Ƃ͂������ł��܂���B �@���������������o���Ȃ����͎s�̂̋@����Ă��đg�ݍ��킹�ĖړI��B�����邵����͂���܂���B �@PT50D�^�C�}�[�ȊO�ɁADC12V����AC100V�������ł���悤�ɂ���uDC/AC�C���o�[�^�[�v(�J�[�p�i�V���b�v�Ŕ����Ă��܂�)�A�����ă^�C�}�[��AC100V�o�͂œ����uAC100V�����[(���Ƃ�����)�v�̂Q��lj��w�����Ă��������B�����[���^�C�}�[�ɂȂ����߂�AC100V�p�R���Z���g�v���O���v��܂��ˁA���v�R�̒lj��ł����B �@DC12V �� [DC/AC�C���o�[�^] �� [PT50D�^�C�}�[] �� [AC100V�����[] �̏��ɐڑ����AAC100V�����[�̐ړ_��DC12V�@��(��C����@)��ON/OFF���܂��B �@DC/AC�C���o�[�^�̓^�C�}�[�ƃ����[���������������̂ŁA�Ԃ̃V�K�[�\�P�b�g�Ɏh���^�C�v�̃v���O�^�̏��^�̂��̒��x�ł��イ�Ԃ�ł��B100W�Ƃ���d�͂�����傫�ȕ��łȂ��Ă������̂ŁA��������I�т܂��傤�B �� �A��PT50D�^�C�}�[��DC/AC�C���o�[�^�̋�`�g��[�������g�𗬂Ő���ɓ��삷��ۏ͂���܂���B���ȐӔC�Ŏ������Ă��������B �@�g�p�����S��������Ă��Ȃ��̂ŁA�K���ɑz�����Ă��������܂����B �@���������̏Ƃ͈Ⴄ�A�Ȃ��Ȃ��z��������ł��g���ł�����܂����m�点���������B ���Ԏ� 2010/5/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����J�ɐ�ւ����܂����̂Ń��[���ł��Ƃ�v���܂������A���ǂ��{�l�l�̎�ɂ͕����Ȃ������悤�ŁE�E�E�E�B �@�ʂ̗p���Ń��h�o�V�J�����ɗ����������A���[�x�b�N�X �f�W�^���v���O�����^�C�}�[�U PT50D (REVEX PT50DW/PT50DG)��1680�~(�|�C���g10%)�Ŕ����Ă����̂ŁA�ƂŖ��邳�Z���T�[�A���ɂ��Ă��錺�֓����^�C�}�[���ɂ���̂ɂ������`�Ǝv���P�����Ă݂܂����B  �@�]�����甄���Ă����u���[�x�b�N�X �f�W�^���v���O�����^�C�}�[�v���2/3���x�ɏ��^������A�R���Z���g�ɑ}���Ă����܂�C�ɂȂ�Ȃ��T�C�Y�ɂȂ��Ă��܂��ˁB
�@�]�����甄���Ă����u���[�x�b�N�X �f�W�^���v���O�����^�C�}�[�v���2/3���x�ɏ��^������A�R���Z���g�ɑ}���Ă����܂�C�ɂȂ�Ȃ��T�C�Y�ɂȂ��Ă��܂��ˁB�@AC100V��ON/OFF�̓����[���ŁA���쎞�Ɂu�J�`�b�v�Ɖ������܂��B �@�\�ʐ^���ɂ��錊�̒��ɐFLED�����Ă��āA���쎞�ɂ͂��Ȃ薾�邭����܂��B �@�]�k�ł����A���k�җl���w�����ꂽ���̊�ʐ^�𑗂��Ē����܂������A�����w����������LED�̐�����R���Q�{�قǒ�R�l���Ⴂ�܂����B �@���̂ق�����R�l�����Ȃ��A���̂ԂM����̂Ń��b�g���̑傫�Ȓ�R���g���Ă��܂��B �@���̔������̂͂܂Ԃ����قǂɐFLED������܂����A��R�l�̑傫�Ȍ̂͂���قǂ܂Ԃ����͖�����������܂���B �@�������ɍw���ŁA����̂̔ԍ��͓����ł������E�E�E�B �@�l�W���O���ăt�^���J����ƁA���́u�d���E�����[����v�Ɓu�^�C�}�[����v�ɕ�����܂��B �@�Q�̊�Ԃ͂R�s���̃s���w�b�_�[�E�R�l�N�^�[�Őڑ�����Ă��āA�t�^���J����Ƃ��̃R�l�N�^�[�������ĊO��܂��B���̃R�l�N�^�[����d������������Ă���^�C�}�[��ւ̓d�����₽��܂�����A�Z�b�g�����^�C�}�[���ԂȂǂ͑S�����ł��Ă��܂��܂��B �@�l�b�g�Ō������Č����������ʐ^�ł͂��̕������t���b�g�P�[�u���Őڑ�����Ă��āA�������Ă��d������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B �@�����̕��i�Ⴂ�A�z�����@�̈Ⴂ�Ȃǂ�PT50D�ɂ͐��o�[�W�������݂���悤�ł��B(��H���͈̂��Ȃ��Ǝv���܂����c) �@�d�����͂悭����R���f���T�~�������̃g�����X���X�B�G��Ɗ��d���܂�(��) �@�����[���Ȃ�ׂ����Ȃ��d���œ����������̂��A����������H�ł͔�r�I�d���������ڂ�DC24V�����[���g���Ă��܂��B �@�ł��A�^�C�}�[��̂ق���1.2V(1.5V)����̂悤�ł��B �@�{�^���d�r��œ����t���f�W�^�����v��L�b�`���^�C�}�[���Ɠ������A��d������̐�pIC���g�p����Ă��ĂقƂ�Ǔd�C���g��Ȃ����炢�̏��d�͂œ����܂��B �@���̎��v��{�@���R���Z���g���甲���Ă���Ԃ����삵���������A���v���~�܂炸�^�C�}�[�̃������[����������Ȃ��悤�ɁA�d����ɂ�1.2V 400mAh��Ni-MH�[�d�r����ڂ��Ă��܂��B�[�d�͕��G�ȏ[�d��H�Ƃ����悤�ȕ��͖����A���[�d��ߏ[�d�ɂȂ�Ȃ��d���ł̃t���[�g�[�d�ł��B �@�����������ɓ����@��̒���24V���K�v�Ȍn����1.2V���K�v�Ȍn���̂Q�n���̉�H�������Ă���̂ŁAAC100V�����UDC25V�ɍ~��������ɁA������i�~���d����H�����ă^�C�}�[�p��1.2V������Ă��܂��B 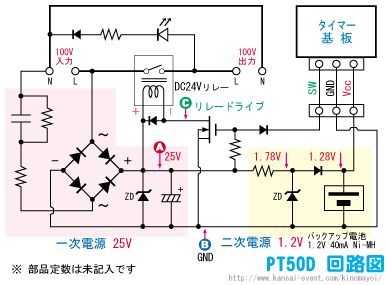 �@���ɏ������悤�ɁA�d����AC100V��DC25V�̈ꎟ�d���ADC25V��DC1.2V�̓d���̂Q�ł��B �@DC24V�����[�͏��^��MOS FET�Ńh���C�u���Ă��܂��B �@�ӂ���(�^�C�}�[OFF��)�̓^�C�}�[��̏o�͂�L��FET�̓�����֎~�AON����H��FET�̓o�C�A�X��R����̓d���œ��삵�܂��B �@���āA���̉�H��DC12V�œ����������Ƃ���ƁE�E�E�B �@�����[�̌����ȊO�ɂ͉��������͕K�v�����ł��ˁB (�X�C�b�`���삾���łȂ�LED�����点�����Ȃ�LED�̔z���ς��͕K�v) �@���̈ꎟ�d����DC25V�ɐv����Ă���̂̓����[��DC24V�i������ł����āA����DC12V�̃����[���g���Ȃ炱�̑��u�̓d����DC12V�ł����̂ł��B����5V�����[���g���Ȃ�d����5V�łn�j�B �@DC12V���y�`�z�_�ɒ��ړ˂�����ł��Ή������͂���܂���B �@AC100V����̍~����H�ɂ��_�C�I�[�h�u���b�W�������Ă���̂ŁA�����ɓ˂�����DC12V��AC100V���̕��i�ɋt�����邱�Ƃ������ł����A�킴�킴AC100V�n�̕��i���O���K�v�������ł��ˁB �@�d���͐e�d��(�ꎟ�d��)��DC25V�łȂ��Ă��ADC12V�ł�DC5V�ł���薳���ł��BDC1.2V(��������������܂�)����������̂ŁA�e�d��������ȏ�̓d������������̂œ����������H����K�v�͂���܂���B �@���ɁA�������郊���[�����̊�ɂ��Ă��郊���[�ƑS�������[�J�[�̓��`���œ���d��������DC24V����DC12V�ɕς�邾���Ȃ�A��ɂ��Ă��郊���[���O���Ă�����DC12V�����[���ꏊ�ɍڂ�����������ł����E�E�E�E����ȓs���̗ǂ������[�������Ă����蔃����Ƃ́A�_�l�������܂ŃT�[�r�X�͂��Ă���Ȃ��ł��傤�B �@�������郊���[��PT50D�̊O�ɒu�����A���̊��̃����[�����O���ĊJ�����X�y�[�X�ɋl�ߍ���(�u������)���Ƃɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��̂ŁA���̃����[�̎�舵���ɂ͒��ӂ��܂��傤�B �@�ʂɂ��̂܂܂ł������ł����A���̂܂܂ɂ��Ă�����DC12V�����[�ƕ����DC24V�����[���q�������܂܂ɂȂ�̂ŁADC24V�����[�͓��삵�Ȃ��̂ɃR�C���ɓd�������͗�����ԂɂȂ�A���_�ɓd�͂�����܂�����Ȃ�ׂ������[�͎��O���Ă��܂��܂��傤�B �@�����[�Ɗ�̊Ԃɂ̓n���_�Ă���Ȃ̂ŁA���̃n���_���z������Ď�菜���̂��ʓ|�ł���A�����[�͎��O�����ɃR�C���z�������p�^�[���J�b�g���ēd��������Ȃ����邾���ł������ł��B �@�����[�̌����B�܂��͊O�t���ȊO�͌��̊�̕K�v�ȃ����Ƀ��[�h�����n���_�Â����邾���ł��B 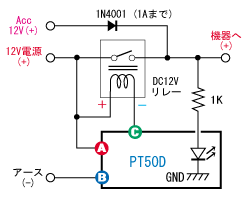 �@DC12V�����[���O�t������Ƃ��āA�z���͉E�̐}�̒ʂ�ł��B
�@DC12V�����[���O�t������Ƃ��āA�z���͉E�̐}�̒ʂ�ł��B�@�u�Ԃ̃L�[��ON�ɂ��ēd�������Ă���Ԃ͏�ɋ@��͓����v������]�̂悤�ł��̂ŁA�_�C�I�[�h����{�����Acc����@��ɓd�����������܂��B �@�_�C�I�[�h����{����A�Ԃ̓d����OFF�̊Ԃ̃^�C�}�[���쒆�ɋ@�푤����Acc���ւ̋t���͂���܂���B �@�A���g�p�����_�C�I�[�h�̗e�ʂɂ��g����d���͐�������܂��BAcc����d�������̂ʼn��S���b�g���̑�d�͑��u�͌q�����Ƃ͂ł��܂��A1�`3A���x�̃_�C�I�[�h���g�������Ă��̏��^�@��ɂȂ��薳���d���������ł���͂��ł��B �@1N4001(�܂��͌�q��1N4007)��1A�܂ŁA10W���x�܂ł̏��^�@��Ȃ���v�ł��B �@�����Ƒ�d�͂̋@���Acc�A���œ����������̂ł���A�������������ʂ�ԉ����悭�g�������[���g����Acc�A���t���h�~�����[�œd���������Ă���Ă��������B �@�����A�G���W������Ē�Ԓ��̎ԓ��Ń^�C�}�[�ŋ@����������Ƃ������ł�����A���܂�傫�ȓd���������ƃo�b�e���[���オ���Ă��܂��ł��傤�B����̂���]�͐��v�Ȃ̂ő��v�ł����E�E�E�B �@�_�C�I�[�h���킴�킴����Ȃ��Ă��A�d�����Ńu���b�W������Ă���S�{�̐����p�_�C�I�[�h(1N4007)��ALED�_���p�ɒ���ɓ����Ă��鐮���p�_�C�I�[�h(1N4007)�͕s�v�ɂȂ�܂�����A�������{�O���ė��p���Ă��܂��O�~�ł��B �@�{�̂�LED��AC100V�œ_���������H�ɂȂ��Ă��܂�����A���̂܂܂ł�DC12V��������S������܂���B �@����LED���K�v�ł�����A�lj��E��������DC12V�����[��ON�ɂȂ������Ɍ���悤�ɂ��Ă��������B1K���̒�R�͒lj��w������K�v������܂��B �@���A�{�̓���AC100V�R���Z���g�ɂȂ��Ă���p�[�c�Ȃǂ͕s�v�ł�����O���Ă��܂��āA�R���Z���g���̂Ƃ��납�烊�[�h�����O�ɏo���Ȃǂ���{�f�B�ɗ]�v�Ȍ������ɔz���ł��܂��ˁB �@����w�������o�[�W�����ł̉���(?)�|�C���g�ł��B 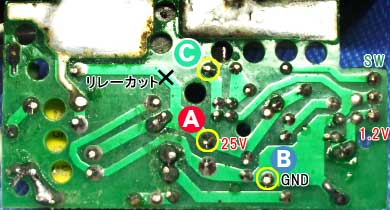 �@�����o�[�W�����Ⴂ�̕i���ĉ����������ꍇ�́A�������ʼn�H�E����悭���ׂĂǂ����ǂ������炢���̂������ׂ��������B �@���A�s�̕i�̉����ɂ������Ă͑S�Ď��ȐӔC�ŁA�����Ɏ��s���Ă��A���Ă��A���̂��N���Ă��S�Ă������ŐӔC������āA���čς܂�������ȊO�͉����ɂ͎���o���Ȃ��ł��������B �@DC12V����DC5V���Ȃǒ�d�����ł͔�r�I���S�ł���(����ł��V���[�g����Ɣ��Ȃǂ̊댯���͂���܂�)�A���̐��i�͌��X��AC100V�d�l�ł�����100V�̂܂܂Ŏg�p����ꍇ�͊댯�ł������ɉ������Ȃ��ł��������B ���Ԏ� 2010/6/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���A���肪�Ƃ��������܂��B �d�C���S�҂̎��ɂƂ��āA����������������ł��B �ǂ����Ă��Ԃ̏ꍇ���l����ƁA�w�b�h���C�g��N���N�V�����Ńo�b�e���[�̋߂��ɐݒu����悤�ȃ����[���g���āA�t���h�~���l���Ă��܂��̂ł����A���d���̏ꍇ�Ƀ_�C�I�[�h�Ő���ł���̂ł��ˁB �����Ȃ�ɁA�e�X�^�[�ĂĂ݂���A���Ȃ���H��`���Ă݂��肵���̂ł����A�_�C�I�[�h�̃u���b�W�őS�g��������Ă����̂ł����E�E�E�B���F�����������������炸�ɂ��܂������A�~�������R���f���T�������̂ł����A�G��Ȃ��ėǂ������Ǝv���Ă��܂��B�܂��A�����i�Ԃ̃^�C�}�[�ł��A���\�Ⴄ�Ƃ��낪����̂ł��ˁB�܂��A�P�[�X�̐F���w���������́A�\�ʁi���j�w�ʁi�_�[�N�O���[�j�B���~�������̃R���f���T�[����������t�����BLED�̒�R���A�������ȂǁB���������A�P�QV�����[�ƒ�R���Ă��āA���H���Ă݂܂��B����ƁA�P�O�OV�̎��Ƀ����[�N���́{�|�ԂɃ_�C�I�[�h������܂����A�P�QV�̏ꍇ�ɂ��t���Ă��������ǂ��̂ł��傤���B ���쎛 �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����[�̃R�C���̂Ƃ���ɂ��Ă���T�[�W�z���p�_�C�I�[�h�́A��̎菇�ʂ�ɉ�������Ƃ��̂܂܂����܂܂ɂȂ�܂��B�O���Ȃ��ł��������B �@�����Ɍf�ڂ��Ă���ق��̉�H�}�ŁA�g�����W�X�^��FET�Ń����[�����Ă��镨�ɂ͑S�ăT�[�W�z���p�_�C�I�[�h�����Ă��܂��B �@�R�C���͓d�C�𗬂��Ǝ��͂����܂����A�����ɓd�͂����͂ɕς����G�l���M�[�͎��͂�����Ԃ͂��̎��͂̂Ԃ��ێ����Ă��܂��B �@�d��������u�Ԃ��d���U���ł��̒~�����Ă������̓G�l���M�[���d�C�ɖ߂�����C�ɋt�����܂��B �@���̎��Ԃ͂��܂�ɒZ�����߁A���̓d�����͂邩�ɍ��������p���X����������̂ł����A����ȍ����p���X�����̂܂ܒ�d���p�̃g�����W�X�^��FET���̓d�q���i�ɗ����Ɠd�q���i�͔j��Ă��܂��܂��B(�p���[�p�r��FET�ɂ͓����ɋt�d���������߂̕ی�_�C�I�[�h�������Ă��镨�������ł��A�R�C���ɂ���_�C�I�[�h�Ƃ͂܂��ʂ̂��̂ł�) �@�ł��̂ŁA�d����������ɃR�C���ɔ�������t�����̍��d���p���X�����Ă��܂�(�V���[�g�����č����d���͔����ł��Ȃ����Ă��܂�)���߂ɁA�d�q���i�œd����f������R�C���ɂ͕K���ی�p�ɋt�����Ƀ_�C�I�[�h�����Ă����K�v������܂��B �@����͓d�q��H�ŃR�C�����g����ł̐�̂��ł��B �@�Ԃ�Acc�A�������[���g���悤�ȏꍇ�͓��Ƀ_�C�I�[�h�͂��Ȃ����Ƃ������Ǝv���܂��B �@�����Acc�A�������[�̃R�C����ON/OFF����̂�Acc�X�C�b�`��z���Փ��̃����[�ړ_�Ȃ��d�q���i�Ŗ�������ŁA���̃X�C�b�`�E�����[�̐ړ_�̓p���X�ʼn��Ȃ�����ł��B �@�������Ȃ���A�ŋ߂̎Ԃ̓��C���̃R���s���[�^���͂��߃I�[�f�B�I�₻�̑�LED�n�̃����v�A�N�Z�T���[�܂ŁA�d�q���i�̉�Ɖ����Ă��܂��B �@����d�q�̗v�ǂł��B �@�����[�̃R�C�������ڂ��������d�q��H�ƂȂ����Ă��Ȃ��Ă��A�d�����C�����烊���[�̍����p���X���m�C�Y�Ƃ��đ��̉�H�ɉ�肱��ň���������ꍇ������܂�����A�ŋ߂̎ԗp�ɔ����Ă��郊���[�͒��ɕی�p�_�C�I�[�h�������Ă��鏤�i������悤�ł��B �@����ŎԂɃ����[���Ƃ����ꍇ���A���������m�C�Y��Ƃ��ăR�C���̒[�q�Ԃɂ͓���d���Ƃ͋t�����Ƀ_�C�I�[�h����ꂽ�ق����x�^�[�ł��B �@�X��0.1�`0.01��F�̃Z���~�b�N�R���f���T�ł�����ɂ��Ă��ƃm�C�Y��Ƃ��Ă͋��͂ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/6/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āA�������낢��ƕ������Ă�������Ă��܂��B ���̂��сA�ȒP��DC �̓d���v�̍쐬���l���Ă��܂��B �\���Ƃ��ẮA�j�b�P�����f�d�r�̓d����6V�A����ɂȂ��镉��MAX 1A ������A�[�d�ɑ��z�d�r�𗘗p���Ă��܂��B ���̎��A�d�r����̏[���d��LED���g���āA�[�d���ł���ΐ��A���d���ł���ΐ��Ɠ���������������d���v��H���ȒP�ɍ쐬�ł��邩�Ƃ������̂Ȃ̂ł����A ��ʓI�ȃA�i���O�Ȃ牽�̂��Ƃ͂Ȃ������̂ł����A��r�I�ȒP���f�W�^������DC �d���v����邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł��傤���B �\�ł���A���^���ł���Ɗ������ł��B ���Z�����Ǝv���܂����A���m�b��q���������e�������܂����B PIKA1 �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@PIKA1�l�͂��߂܂��āB �@���v�]�̒��́uLED���g�����f�W�^�����̓d���v�v�Ƃ������̂��A���̂��̃Y�o���I�V�Z�OLED���R�`�S���g���Đ����œd����\������f�W�^���e�X�^�[�̂悤�Ȃ��̂Ő����\�����̐F���ƐԂɕς����̂Ȃ̂�(�H�Ɨp�̐���ՊW�̑��u�ɂ͂V�Z�O�̐F���ς�镨�������ł���)�A�P�Ɂu�[�d���v�u���d���v�̂ǂ��炩�̏�Ԃ�m�邱�Ƃ��ł���悤�ɐƐԂ�LED��������点������̂��E�E�E�B��ł��B �@���́u�E�Ԃ̂Q�F�Ŕ�����������V�Z�OLED�\����v�Ƃ������͂����ɂ��ƕ��i������Ō������Ƃ�����܂���B �@�����ɂ́u���E�Ԃ̂Q�F�Ŕ�����������V�Z�OLED�\����v�͔����Ă���̂ŁA������g����PIC�ȂǂŃR���g���[������Ώ[�d���ƕ��d���łQ�F�ɐF���ς��f�W�^���d���v�Ƃ����������Ȃ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B �@�H�Ɛ��i�ł̓J���[�t�����g���Ă��邩�A���ߌ^���m�N���t���̃o�b�N���C�g�̐F��ς�����@�ŐԂƗȂǂɕ����̐F��ς��Ă�����̂������悤�ł��B�܂����l�i�������~�`���\���~������悤�ȓ���p�r�̑��u�ł�����A���낢����ґ�ȕ��i���g���Ă��܂��B �@�����E�E�E���̃R�[�i�[�ł�PIC���g�������u�̃v���O�����̊J���͂��������Ă��܂���̂ŁA�����������u������]�̏ꍇ�͂ق������Ă��������B �@�o���̕��i���g���āA�V�Z�OLED�܂��͐E�Ԃ�LED����ׂēd�q��H�ł����ɓd���l��\������d���v��H�Ƃ������̂��A�ƂĂ���H�K�͂��傫���Ȃ�܂��̂ł��̃R�[�i�[�ł͎�舵���͂ł��܂���B �@�ׂ��Ȃ���]���s���ŁA�������[���A�h���X�����L���̖₢���킹��s���̕�����̓��e�ł��̂ŁA�f�ڂ܂ŏ������Ԃ��܂��������̊ԂɃ��[���ł��₢���킹���鎖���ł��܂���ł����B(��������f�ڂ����������m�点����u�f�ڂ��m�点���[���v��������ł��Ȃ��킯�ŁE�E�E���[���A�h���X���L�����Ă��Ȃ����͑������Ă��܂���) �@����͂U�`12V�̃o�b�e���[�Ŏg�p�ł���ȈՌ^�́u�P���ɏ[�d���Ă��邩���d���Ă��邩��LED(�P��)�ł��m�点�����H�v�̒ɗ��߂����Ǝv���܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �֒m�d���l���ω\�ɂ�����H�}�����̂ق��ɂ���܂��@�o�b�e���[���[�d����Ă���̂��A���d���Ă���̂��͓d�����o�p�̔�����R���o�b�e���[�ɒ���ɐڑ����āA���̗��[�d���𑪒肷��Β��ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B�d���v�̌������̂��̂ł��B �@�d�����o�p��R�̗��[�d�����o�b�e���[�����傫���Ȃ��Ԃł͓d���̓o�b�e���[���畉�ׂ̕����ɗ���o�Ă��܂��̂ŁA���d�Ɣ��f���܂��B �@�t���d�����o�p��R�̗��[�d�������ׁE���z�d�r�����傫���Ȃ��Ԃł͓d���͑��z�d�r����o�b�e���[�̕����ɗ��ꍞ��ł��܂��̂ŁA�[�d�Ɣ��f���܂��B �@�d�����o�p��R�̗��[�d�����u�������v�ꍇ�A�ǂ���ɂ��d��������Ă��Ȃ��j���[�g�����̏�ԂƔ��f�ł��܂��B �@�d����r�̓I�y�A���v LM324 �ōs���Ƃ��āA�d�����o�p��R�܂��͂�����ƍl���Ȃ��Ƃ����܂���B �@LM324�ɂ̓N�Z������A���͓d���͓d���d���t�߂̍����d���ł͎g�p�ł��܂���B �@�]���āA���肵�����o�b�e���[�ł��̉�H�����삷��悤�ɂ����ꍇ�ɂ́A�d�����o�p��R�̗��[�d��(����ɓd���d��)���v��Ȃ��̂ň�U��R�ŕ������Ĕ����̓d���ɗ��Ƃ��Ă����r���܂��B �@����ł�0.1���̒�R�̗��[�ŕ\���d�ʍ��͔���Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���̂܂܃I�y�A���v�Ŕ�r���Ă��d��������Ă��Ȃ����ɂ́u�����d���v�ɂȂ�̂ł���������Ԃ́u�d��������Ă��Ȃ��v�Ɣ��f���A������x�̓d�ʍ��ȏ�ɂȂ�Ȃ��Ɓu�d��������Ă���v���f�������H���K�v�ƂȂ�܂��B �@�ӂ���̓d����r�Ȃ�u�q�X�e���V�X���������Ă�����x�ȏ�ɂȂ�Ȃ���ON�Ƃ͔��f���Ȃ���H�v�����̂ł����A�q�X�e���V�X���̔�r��H�̏ꍇ�͕����d���̐v�������ȂƂ���ŁA����̂悤�Ȕ�r�ł͂��܂��d�������O�d���ɋ߂��Ƃ���ŕ������Ă����悤�v�Z����̂͂�����Ɩʓ|�ł��B �@�����Ŏv�������̂́u���̔�r�d�����̂��A�d��������Ă��Ȃ����ɂ̓I�y�A���v�̓��́{�Ɓ|�ŏ��������d�ʍ�(�I�t�Z�b�g)���������Ă���v�Ƃ������@�ł��B �@������R�̐^�ɏ��Ȃ���R�l�̒�R�����݁A���̏㑤�Ɖ����̓d�����𗘗p���ĕ��ׂɓd��������Ă��Ȃ����ɂ͔�r��H�ɂ͏��������}�C�i�X�Ɣ��肳���d����^���ĂO�u���߂ł̌�쓮��}���A�܂����A���ɂ��d���������Ȃ��(�����}�C�i�X�Ɣ��f����̂�)�m���Ɂu�d���͗���Ă��Ȃ��v�Ɣ��肷�邱�Ƃ��ł��܂��B �@������ƃg���b�N���ۂ�(�H)�I�t�Z�b�g���d��������H���g�p���邨�����ŁA�I�y�A���v�ɂ��d����r���͂ƂĂ��V���v���ȉ�H�ł��݂܂����B �@�]�k�ł����A�傫�ȉ�ЂŐv�����Ă���Ƃ���Ȋ����̃A�C�f�A���o����S�������\���p������������܂�(��) �@�{���̊J���̎d�����A�����������ނ�d�l���������Ă��鎞�Ԃ̂ق��������͍̂��������̂ł��B �@����̎v�������A���ɒN��(�ǂ����̉�ЁH)�������������Ă��邩������܂���ˁB �@�d��������Ă��Ȃ���Ԃł̕s�����������܂����̂ŁA�I�y�A���v�œd����r��H���Q�g�p�ӂ��Ă��ꂼ��u�[�d�v�u���d�v�����o�����H�A������LED��_�������H�Ƃ��܂��B �@���肷�銴�x�͂�������100�`150mA���x�����Ɓu�d��������Ă���v�Ɣ��肵LED��_�����܂��B(�ő�1A���x����镨�̂悤�Ȃ̂ŁA���̒��x�ő��v�ł��傤) �@��������100K����R�ɐ��x�̍��������g�p���A51�����������������Ȓl�ɕς���ΐ��\mA�ł̔�����\���Ƃ͎v���܂����A�Q�g�̕�����R�̒�R�l�̌덷���@���ɔ��萸�x�ɉe�����y�ڂ��܂��̂ŁA�������ł��̂�������������Ċy���܂��̂��������Ƃ͎v���܂����A���܂�ڂ����������͉�H�}�̐��l�̂܂܂Ő��삳��邱�Ƃ������߂��܂��B�����̕��i�덷�������Ă���쓮���Ȃ��قڃM���M���̐��x�܂Œǂ�����ł���܂��B �@�{��H�̏���d���́A�[�d�����d�����Ă��Ȃ���LED���������Ă���ꍇ��60��A(6V��)�ƂقƂ�ǃo�b�e���[�̓d�C������邱�Ƃ͂���܂���BLED�_������10�`20mA���x�ł��B �@����ς�f�W�^���\���Ő����������f�W�^���d���v���~�����I�Ƃ������́A�H���d�q�ʏ��ȂǂŔ����Ă���f�W�^���\���̓d���v�Ɏg����p�l�����[�^�[���w�����Đ����͂���ŕ\��������ȂǁE�E�E���܂����͂��߂ł����H �@�f�W�^���\���̓d���v�̉��ɁA�{��H�̕\��LED������u�[�d�v�u���d�v�̓p�b�ƌ����ڂ̐F�Ŕ��f�ł��A�ڂ���������m�肽����p�l�����[�^�[�̃f�W�^���\��������ƁB �@�t���^�C�v�̃p�l�����[�^�[��d���v�L�b�g�����H���āALED���o�b�N���C�g���Ɏd����Ńo�b�N���C�g�̐F��ς�����悤�ɂ���ƁA������ۂ������ł������ȋC�����܂����E�E�E�͂����āB ���Ԏ� 2010/5/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����犄�荞��ł��݂܂���B �d�������o�������ꏊ�̃V�����g��R�̓d�ʂ��A���o��H�̓d���d���t�߂Ƃ��������̏ꍇ�ɍ����Ă܂����B ����ȕ��@����������ł��ˁB���̂������Q�l�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B ���W�I�y���` �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���܂ł������ڂ��Ă���u�d�����~�~�ɂȂ�����LED�_���v��u�ߕ��d�h�~��H�v�Ȃǂ��A�d�������̓d���������Ă���ꍇ�͌��o�������d�����I�y�A���v�̓d���d�����̂��̂��߂�
�̂߂��ɂ��̂܂ܓ��͂��邱�Ƃ͂ł��܂���B(�w�b�h���[���̖����I�y�A���v�̏ꍇ�͓d���d���܂Ŏg�p�ł��܂�) �@�ł������R�ŕ������ăI�y�A���v�̓��͉\�d���͈̔͂ɂ��Ă��܂��B �@���̍l�����̓I�y�A���v���g�p�����ł̊�b�ŁA�ق��̗l�X�Ȏg�p�p�r�ɉ��p�ł��܂�����m���Ă����Ί��p�ł��܂��ˁB ���Ԏ� 2010/5/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���L�肪�Ƃ��������܂��B���Ԏ��x��܂��Ă��݂܂���B ���̂悤�ȍl����������Ƃ́A���������z�Ńr�b�N�����܂����B �܂��AMail�A�h���X�̖��L�����݂܂���ł����B ���̉�H�̍l�������ɂ��g���Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B ���J�Ȑ}�܂ŃA�b�v���Ă����������肪�Ƃ��������܂����B PIKA1 �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�f�W�^���\���łȂ��Ă����v�ł������H �@���̂悤�ȏ�Ԃ����̕\���ł������ɗ��Ă�̂ł�����ǂ������ł��B �@���Ȃ݂ɁA�u�֒m�d���ύX���v�ł̉�H�}�͂�����ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@VR1,VR2��LED��_��������d���l��ݒ�ł��܂��B �� ���ߕ��@ �@�[�d�����d�����Ă��Ȃ����(�d�r�����Ȃ��A���ב��͊J��)VR1,VR2�����ɉ����LED���_�������ςȂ��ɂȂ�܂�����A��������E�ɉĂ䂫�ALED��������_�����m��H���d���O�Ɣ��肷��_�ł��B �@���̓_�Ŋ��x�͖�1mA���x(�����̌덷�͂���܂�)�ōō����x�ł����A���̓_�ł͊��S�ɂO�_�Ȃ̂��d�������ꂽ��ɓd�����O�ɖ߂����Ƃ�LED���_�������܂܂ɂȂ���������܂���A�O�_�Ŏg�p����ꍇ�͂ق�̏����E�ɉĂ��������B �@�����ƉE�ɉƁA�ő��100�`150mA���x�œ_������悤�ɐݒ�ł��܂��B �@1mA�͂������ɂO�ɖ߂������ɕs����Ȃ̂Ŗ�5�`10mA���x�ȏオ���p�I���Ǝv���܂��B �@LED����_��������x�̓d���l�Ŕ������܂�����A���Ȃ�����ȕ��ׂ܂��͏[�d�d���ł��֒m���܂��B ���Ԏ� 2010/5/31
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���W�R���̎�M�@��3CH4CH��LED�����v��ON�EOFF�������B �v���|���ɂăX���b�g�����X�e�A�����O���̐ؑւ��o����̂ŁA�ϓ�����0.3V�قǂ̓d���̕ϓ������m����LED��ON/OFF�������̂ł����\�ł��傤���H ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
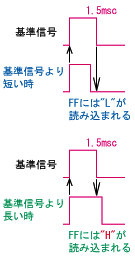 �@���[�ƁA���܂ŃT�[�{�W�̋L���ŏ����Ă��Ă���̂ł����A���W�R����M�@�ȂǂŎg���Ă����T�[�{�M���̓p���X���ϒ��̋�`�g(�f�W�^��)�M���ŁA�����Ă���悤��0.3V�قǂ̃A�i���O�M���ł͂���܂���B
�@���[�ƁA���܂ŃT�[�{�W�̋L���ŏ����Ă��Ă���̂ł����A���W�R����M�@�ȂǂŎg���Ă����T�[�{�M���̓p���X���ϒ��̋�`�g(�f�W�^��)�M���ŁA�����Ă���悤��0.3V�قǂ̃A�i���O�M���ł͂���܂���B�@���Ԃ�T�[�{�M���̂Ƃ���Ƀe�X�^�[�Ăēd�����v���Ă݂āu0.3V�ʂ��v�Ǝv���Ă���̂ł��傤���ǁE�E�E�B �@�T�[�{�M����20msec���Ɉꔭ�̃p���X���A�����Ď��X�Ƒ��o����Ă��āA���̃p���X����1.5msec�𒆐S�Ɂ}0.5msec(90�x�T�[�{�̏ꍇ)�ƌ��߂��Ă��܂��B�j���[�g������1.5msec�̃p���X���ŁA�X���b�g����n���h�����ƃ}�C�i�X����1msec�܂ŁA�v���X����2msec�܂ŕω����܂��B �@���̃p���X���������o����(�X�e�A�����O�E�X���b�g����)�u����ʒu���}�C�i�X�̏ꍇ�͏o��OFF�v�u����ʒu���v���X�̏ꍇ�͏o��ON�v�Ƃ�����H��g�߂T�[�{�M�����牽�炩�̃X�C�b�`�����܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�g�p����IC�̊W�łQ�`�����l���Ԃ�̉�H�ɂȂ�܂��B �@�u3CH,4CH���g�p�������v�Ƃ�������]�Ȃ̂ŁA���̂܂܊e�`�����l���M������͂��ĂQ�n����LED�Ȃǂ�����ł��܂��B �@���͂��ꂽ�T�[�{�M���̗����オ���74HC221�̃����V���b�g�^�C�}�[���N�����āA1.5msec�̊�M�����쐬���܂��B �@��M���̎��Ԃ�VR1,VR2�Œ��߂ł��AVR�𒆉��Ŗ�1.5msec�A�������ς��Ŗ�1msec�A�E�����ς��Ŗ�2msec�Ƃقڃv���|�̃X�e�A�����O�ȂǂƓ����悤�Ȋ����Œ��߂ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@���D���Ȉʒu�ɒ��߂��Ă��������B(���ʂ͒��S�ł�) �@�T�[�{�M�������͂�����LED1,LED3���_�����܂��B����͊�M���p���X�Ɠ������Ŋ�M�����������Ă�����Ԃ����_�����܂��̂ŁA�����Â��ł��B �@��M�����I���������_�ł̃T�[�{�M���̏��(����)��D-FF IC 74HC74�ɓǂݍ��܂�܂��B �@���͂��ꂽ�T�[�{�M������M����蒷����LED2,LED4���_�����A�����Ƀg�����W�X�^��ON�ɂ��ĊO���Ɍq����LED�Ȃǂ�5V���������܂��B �@�O����LED�ɂ�5V�� �������_������悤�d��������R�����邩�A���W�R���p�̎�M�@�d����5V����_��������悤�ȏ��i���g�p���Ă��������B �@����͊�{���암���݂̂̐����Ƃ��āA�p���[�I�����Z�b�g��H�͐}�����Ă��܂���B �@�d����������T�[�{�M������M����܂ł̊ԁA�o�͕͂s��ł��B �@�K��OFF�ɂ������ꍇ��FF�Ƀp���[�I�����Z�b�g��H���Ƃ���Ă��������B ���Ԏ� 2010/5/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/28 |
�����������肪�Ƃ��������܂��B �x�f�l�̎���ŁA��ϐ\����܂���ł����B �����A����ɂ����肽���Ǝv���܂��B ���̓x�́A���肪�Ƃ��������܂����B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�ߔM�h�~�k�d�c���x�v�Ƃk�d�c�R���c�ʌv�ł́A�����b�ɂȂ�܂����B �@��ϕ֗��ŁA�ʎY�H�ƌ����Ă����ł����A�v�悵�Ă��܂��B �@�V���ɂ��肢���������Ƃ�����܂��B �@�D�O�@�����L���Ă��܂��B2�T�C�N��2�C���ł��B �@�R��̗ǂ���]�����L�[�v���邽�߂ɁALED�Ń^�R���[�^�[����肽���ł����A�v�����肢�ł��܂��ł��傤���H �@�N�����N�V���t�g1��]��2��_�ł��B4�T�C�N����4�C���Ɠ����ł��B �@�C�Ŏg�����߁A�Ԃ�o�C�N�p�̓P�[�X�������Ƀ{���{���ɂȂ�A�������H���Ă��܂��܂��B�܂��U���Őj���悭�����܂��B �@�t���^�C�v���g���Ă݂܂������A�D�ɉ����������̂ł悭�����Ȃ����A�t�����悭���܂��B �@���R�A�D���p�ł͂Ȃ��̂ŁA����͎̂d�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B �@�D���p�͍����ł����A�ŋ߂�LED�͖��邭�F���L�x�Ȃ̂ő��s���ł����₷���A���Ă������ŏC���ł�����Ǝv�����e�����Ă��������܂����B �@8000rpm���炢�܂ŁA500rpm���Ƃ�LED���_������^�C�v������Ε֗����ƂƎv���܂��B �@��H�����G�ŕ��i�������ɂȂ�悤�ł�����A1000rpm���Ƃ�LED���_������^�C�v�ł��������Ǝv���܂��B �@�o�b�e���[�͎ԗp��12V�ł��B���s���͓d�����オ��܂��B �@��낵�����˂������܂��B punta �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��H�Ƃ������ (1) ��]���Z���T�[�͉��������܂����H (2) �h����͑��v�ł����H �Ƃ����Q�̋^�₪����܂��B �@���̑D�O�@�ɂ͉�]���Z���T�[�̗ނ͌�����t���Ă��܂����B�����5V�`12V���x�̓d�q��H�p�̓d���o�͂��A���d���ړ_�o�͂��œd�q�I�ȃ^�R���[�^�[���q���p�ӂ͂���܂����B �@����Ƃ��ߋ��Ɍq���������̓d�q�^�R���[�^�[�̓d�q�I��]���Z���T�[�����ɕt�����܂ܕ��u����Ă���Ƃ��A������]���Z���T�[�����������Ƃ�����u����v���邵���Ȃ��̂ŁA�������������G���W����(�V���t�g�Ƃ��̘e)�ɂƂ���邱�Ƃ��ł���̂��B �� �G���W����]������Ƃ��āu�v���O�̓_�Γd��(�A���ꎟ���̒�d��)���v��v�Ƃ������@����ʓI�ɂ���܂����A�����͂��̑D�O�@���������Ă��܂���̂Ŏ��@�œd�������g�`����Ȃǂ��ł��܂���B�]���ē_�Ή�H����_�^�C�~�i�O����@�ł͉�H��v�ł��܂���̂ŁA�\�߂��������������B �@���E�E�E��������d�C�M�������o���āA���S�ɓd�q��H�ƌq�����Ƃ��ł���Z���T�[��H�����ɂƂ�����Ă���Ȃ炻����g���܂���B����Ȃ�d�l�����������������B �@LED�\���̃^�R���[�^�[��d�q��H�ō�����Ƃ��āA�h���P�[�X�Ȃǂ̂��p�ӂ͂ł��܂����B(�䏊�p�̃^�b�p�[���ł����ł���) �@����ƁA�����������ʼn�]���Z���T�[�Ȃǂ��G���W�������Ɏ��t����Ƃ��āA�����͖h���ł����A����Ƃ����͓��邪�������Ŗh�����������邱�Ƃ͂ł��܂����B �@�Ƃ肠�����A����炪�킩��Ȃ��Ɛv���ł��܂���̂ŁA���������������B �@���ƁAPIC�}�C�R���Ȃǂ��g���ăp���X���Ԍv���␔�l�v�Z���ł����H�Ȃ�Ԃ�LED�^�R���[�^�[�̂悤�ɂقڃ^�C�����O�Ȃ��ɉ�]���\�����X�V����܂����A���W�b�NIC�ʼn�]�����v������悤�ȃf�W�^����H�������ƃ��[�^�[�̍X�V�͂P�b�ԂɂP�`�Q����x�ł��B �@�X���b�g���������ăG���W�����ӂ����Ă��A�O�[���ƃ^�R���[�^�[���ω�����̂ł͂Ȃ��A�P�b�ɂP�`�Q��̍X�V�Ńp�b�c�p�b�c�ƕ\������ւ�悤�Ȋ����ł���B �@�v�͂���ł������Ȃ�E�E�E�Ƃ������ɂȂ�܂����A�������ł��傤���B ���Ԏ� 2010/5/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��ԓ����肪�Ƃ��������܂��B �@��]���Z���T�[�ł����A�ЊO�i�̊O�t���́A�_�R�C���̈ꎟ��������o���Ă��܂����B �@�_�R�C���́ACDI����Ȃ���Ă��܂��B �@�I���W�i���́A�����}�j���A�������Č������ʁA�t���C�z�C�[�����̃��C�e�B���O�R�C��1����^�R���[�^�[�p�̔z�����o�Ă��܂����B �@���̃^�R���[�^�[�p�̔z�����o�Ă��郉�C�e�B���O�R�C��1�́A���N�`�t�@�C���[���M�����[�^�[�ɂȂ���Ă���̂Ńo�b�e���[�[�d�p�ł����A2�{�����z�������������F�Ȃ̂ŁA�P���̂悤�ł��B�^�R���[�^�[�p�̔z���͂���1�{����҂ɂȂ��Ă��܂��B �@����2�R�C��������܂����A������CDI�ɂȂ����Ă��܂��B �@���̃��C�e�B���O�R�C���́A�[�d��p�Ǝv���Ă��ǂ��悤�ł��B �@��]�����m����Ƃ�����A���ꂵ���Ȃ��悤�ł����A��낵���ł��傤���H �@�G���W���̉�]�𑪒肷��e�X�^�[�͎����Ă��܂��̂ŁA�����߂͂�����łł���Ǝv���܂��B �@�h�����H�ł����A�g��Ȃ��Ȃ����J�����p�̐����n�E�W���O������܂����A�A�N���������H�A�ϑw���āA���h���̗ǂ����̂���낤���Ƃ��l���Ă��܂��B �@�z����O�����O�������Ă���J�v���[�Ȃǂ�����̂ŁA���Ȃ��Ǝv���܂��B �@����ł͂�낵�����˂������܂��B punta �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�^�R���[�^�[�p�ɂƔ��d�R�C������z�����o�Ă���̂Ȃ炻�ꂪ���̂܂g���܂��ˁB (�T�[�r�X�}�j���A����I�[�i�[�Y�}�j���A���Ŕz���}���������̕��͘b�������ď�����܂�) �@�����ł���A���̃^�R���[�^�[�p�̔z����GND�̊ԂŖ�12V�̌𗬂��o�Ă��邩�ǂ����A�e�X�^�[�̌𗬓d�������W�Ōv���Ă݂Ă��������B �@�����Ă����E�E�E���g���̃e�X�^�[���c�l�l(�f�W�^���e�X�^�[)�ŁA�u���g���v����@�\��������̔z������o�Ă���𗬓d���̎��g�����v���Ă݂Ă��������B �@�t���C�z�C�[���̉�]���Ō𗬈��Ԃ�̔��d�����Ă���Ȃ�A1000rpm��16.667Hz�̎��g���ɂȂ�܂��B(2000rpm�Ȃ�33.333�Ɣ��) �@���g������@�\�̃e�X�^�[���������łȂ��ꍇ�͑��������Ȃ��Ă����\�ł����A��{�I�ɂ͂����������]���P�����̔��d�R�C������̓d���Ƃ��Ă���𐔂����H��v���܂��B �@���T���͏����Z�����̂ŏT���J�������j�E�Ηj�ȍ~�Ɏ��|����܂��̂ŁA�������������Ĉ��]�łQ�x�𗬔g�`���o��悤�Ȕ��d�@�𓋍ڂ��Ă���Ƃ��A�v�ɍ��{�I�Ɋւ�鉽���������ł�������߂ɂ��������������B ���Ԏ� 2010/5/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Z�����Ƃ���A�����b�������܂��B �@���傤�Ǎ��N�ɓ����Ĕ������f�W�^���e�X�^�[�ɁA���g������@�\���t���Ă����̂Ŏg���Ă݂܂����B �@�G���W�����Â��̂��A�e�X�^�[�̊��x���ǂ�����̂��A�Ȃ��Ȃ����肹���A���m�Ȏ��g���͌v���ł��܂���ł������A�ȉ��̂Ƃ���ł��B�}30Hz�ȏ�̕ϓ�������܂��B �@�^�R���[�^�[�p�̔z����GND�̊Ԃ̎��g���́A2000rpm��100Hz�O��A4000rpm��200Hz�O��ł����B �@�d����4000rpm��6V�O��ł����B �@���Ȃ݂ɁA���C�e�B���O�R�C������o�Ă���z���Q�{�Ԃ́A2000rpm��50Hz�O��A4000rpm��100Hz�O��ł����B �@�d����4000rpm��12V�O��ł����B �@���C�e�B���O�R�C���́A������h�b�N�{�[���X�^�C���ŁA�R�C�������Ɍ����Ă���^�C�v�ł��B �@�t���C�z�C�[�����̉i�v���́A4�t���Ă��܂��B �@����ł́A��낵�����˂������܂��B punta �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@2000rpm��100Hz�ł����E�E�E�B����Ŏ��S�H �@���R�Ȃ�[���ł��鐔���ł����A���̃G���W���̃t���C�z�C�[���̓G���W����]�Ƃ͕ʂɉ����M���ʼn�]����ς��Ă���Ƃ��A������������ȕ��Ȃ̂ł��傤���B �@�_�Όn��CDI�炵���̂ŁA(�_�^�C�~���O�͕ʂ̎��̃J���������œ�����H�̂�)�ʂɔ��d�@�̃T�C�N�����G���W����]�Ɠ������Ă���K�v�͖����ł����A���������G���W��������Ƃ������Ƃł��ˁB �@�Ȃɂ���D�O�@�p�̃G���W���Ƃ������͌������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�D���W�͕��ʂ̎Ԃ�H��@�B�p�Ƃ͂܂��Ⴄ�����݂�����̂ł��ˁB �@�Ƃ肠�����A���R�Ɠ��������łP��]�łR���A2000rpm��100Hz�Ƃ������Őv��i�߂܂��B ���Ԏ� 2010/5/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����b�����܂��B �@�e�X�^�[�Ōv�����A���g���́A100Hz�����ɁA70�`130Hz���s�����藈���肵�Ă��܂����B �@�����v���ɁA���ۂ́A2000rpm��33.333�~����4��133.332Hz�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@������2�T�C�N���̌Â��G���W���Ȃ̂ŁA��]�������肹���A���̌v���l�́A���Ȃ��܂����Ǝv���܂��B �@���ہA��]�v�i�f�W�^���j�̐��������肵�Ă��܂���ł����B �@�����́A�R�C����1�A����4�Ȃ̂ŁA1��]��4���ł����Ǝv���܂����ǂ��ł��傤���H �@�G���W���͂ƂĂ��V���v���ŁA2�T�C�N��2�C���̃I�[�g�o�C�ƍl���Ă�����Ă������Ƃ��v���܂��B �@�����A�r�C�ʂ��o�C�N�Ɣ�ׂ�Ƒ傫���̂Łi�W�O�O�b�b�j�����ׂł͉�]�����肵�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B punta �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����ł́A���S�łP��]�łS���A2000rpm��133.33Hz�Ƃ������Őv��i�߂܂��B �@���P�A�Q�A�S���炢�̐�ւ��͂ł���悤�ɂ͂������Ǝv���܂��B(�R�͖ʓ|�Ȃ̂ō���͑Ή����Ȃ�������) ���Ԏ� 2010/5/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�y���݂ɂ��Ă��܂��I punta �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����Ǝ��Ԃ����܂����̂ō���Ă݂܂����B �E LED16�_��500/1000/1500�c7000/7500/8000rpm�\�� �E �p���X���͂́~�P/�~�Q/�~�S/�~�W/�~16�ɑΉ� �E ���b�R��X�V (�U��ɕύX��) �ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�� IC�����炵��"�ŐV��"��H�}�����̂ق��ɂ���܂� �� �N���b�N���U��H �@�����̂悤���^�C�}�[IC 555��666.666Hz�̃N���b�N�M�����쐬���܂��B �@���̃N���b�N�������Ă���Ɛ������\���ɂȂ�܂���ATP1�Ɏ��g���J�E���^�^���g���̌v���f�W�^���e�X�^�[���ĂĐ��m��666.666Hz�ɒ��߂��Ă��������B �@���g���J�E���^�^���g���̌v���f�W�^���e�X�^�[�����������łȂ�����VR1���قڒ����ɉĂ����Ă��������B �@VR1�ł�������630�`690Hz���x�͈̔͂Œ��߂ł��܂��B �@�ǂ����Ă��d���R���f���T�̗e�ʂ̃o����(�ő��20��)�ȂǂŕK��VR1�̒����ł҂�����666.666Hz�ƂȂ�Ȃ��ꍇ������܂��B�������炢�Y���Ă��Ă�������G���W����]����������x�͈̔͂Ńt�������肵�Ă���̂ŁA���p��͂��܂���͖����Ǝv���܂��B �� �N���b�N��ւ��W�����p�[ �@JP1(333Hz)��JP2(666Hz)�̂Q�̃W�����p�[������܂����A�ʏ��JP1(333Hz)�̂ق����W�����p�[�s���Őڑ����Ă����܂��B �@��q�̖��b�U��X�V�^�ɕύX����ꍇ�ɐ�ւ��܂��B �� ��ւ����肵�Ȃ��ꍇ�́A�ŏ�����W�����p�[�����ŕK�v�Ȃق������z�����Ă��������B �� �V�X�e������ �@�����ł͊e����E�\����H�ŕK�v�ȃ^�C�~���O�M�������܂��B �@��{�^�C�~���O(�N���b�N)�M�����͍Œ�𑜓x�ł���500rpm�����o����̂ɕK�v�Ȏ��Ԃł��B �@500rpm�Ńp���X�����͂��ꂽ�ꍇ�A�p���X���g����8.333Hz�Ńp���X�Ԋu��0.12�b�ł��B �@����̉�H�ł͂�����u�Q�����ꍇ�ɍŒ���̃p���X���͂������v�Ƃ݂Ȃ����߁A�Q�{��0.24�b�����̑��莞�ԂɂȂ�A�^�C�~���O�M��������H�ł͂W�X���b�g�ň��̑���Ƃ��邽�߂ɃN���b�N�M����0.24�b �� �W�� 0.03�b/pulse�A���g���ł�33.333Hz���K�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@�N���b�N��555�����U��������10�iBCD�J�E���^IC 74HC390��1/20�ɕ�������̂ŁA555���ł�666.666Hz�̐M���U�����Ă��܂��B �@33.333Hz�̓���N���b�N�M����10�i�W�����\���J�E���^IC 74HC4017��Q0�`Q9�o�͂����X�Ɛ�ւ��đI�����邱�ƂŁA�����H�ELED�\����H�ɕK�v�Ȑ���M�������܂��B
�@����m�F�p��LED1��Q8�ɂ��Ă��܂��B(��H�̓���ɂ͉e�����܂���) �@LED1�͈��̑��蓮��ň��p�b��(0.03�b)����܂��B�p�b�ƌ�������(���ۂ͏�������)��]��������LED�\�����X�V����܂��B �� ���̓p���X�ϊ� �@��]�����m�p�̃p���X�d���M������M���āA�{��H�̃f�W�^����H���ɓ`���܂��B �@�p���X�d����3�`15V���x�̃p���X�A�܂��͌𗬓d���ɑΉ����܂��B �@�^�R���[�^�[�p�M�����A�܂��͔��d�@�̔��d�d��(��)���g�p�ł��܂��B �@�p���X�̓��͂����邩�ǂ�����LED2�Ŋm�F�ł��܂��B �@���͓d��������ꍇ�͓��͏�Ԃɉ����ē_�����܂��B �@�G���W����]���x�����ɂ̓p���p���Ɠ_�ł��Ă���悤�Ɍ����A������]�����オ��ƂقژA���_�����Ă���悤�Ɍ�����ł��傤�B �� �v���X�P�[�� �@��]���p���X�����]�ň��ł͂Ȃ��A���]�łQ�p���X�A�S�p���X�ȂǃZ���T�[�̔������������ꍇ�͂����ŕ������Ĉ��]�Ɉ���̃p���X�ɂ��܂��B �@�~�Q�A�~�S�Ȃǃp���X���������قǕ��������ŕ��ω������̂ŁA�덷��m�C�Y�ɑ��ėǍD�ɂȂ�܂��B �@SW1�Ńp���X���̕����l��I���ł��܂��B���g�p�̃Z���T�[�E�p���X�o�͂̎d�l�ɂ��킹�ăX�C�b�`���ւ��Ă��������B �� �ŏ�����Œ�Ŏg����ւ����肵�Ȃ��ꍇ�́A�X�C�b�`�����ŕK�v�Ȕz���������Ă��������B �� 500rpm���p���X���� �@�v���X�P�[���ň��]���ƂɂP�p���X�ɐ��`���ꂽ��]���p���X���u�Q�p���X��500rpm�Ƃ���LED���P�_��������M���������v�悤�ɂ��āA���ꖢ���̃p���X���ł�LED��_�������Ȃ��悤�ɂ��܂��B �@����̃J�E���g�\����H�����̓p���X�Ɣ��Ōv�����邽�߁A�������Ă����Ȃ��Ƃ����u0.12�b�̊ԂɂP��ł��p���X�������500rpm�J�E���g�A�b�v�v�Ɣ��肳����ƁA500rpm�����̉�]���̏ꍇ�ɂ��p���X���E���̂Ńp���p����500rpmLED���_�ł��܂��B �@�܂�����͉�H���ȈՔł̂��߁A500rpm�ȏ�̉�]���̏ꍇ�ł��G���W���̉�]��������LED�̕\�����ɋ߂��ꍇ�A�J�E���g�̊W�łP����LED���p���p���Ɠ_�ł���ꍇ������܂��B���̂悤�ȕ\���̏ꍇ�͎��ۂ̉�]�����Q�̕\���̒��Ԃ��炢�̉�]���ɂ���Ƃ��l�����������B �@500rpm COUNT UP �M���͈��̌v������0.24�b�̊ԂɁA��]����500rpm���x�ł���P��A1000rpm���x�ł͂Q��Ƃ����ӂ��ɉ�]���ɔ�Ⴕ�����̃p���X�����܂��B �� LED�o�[�O���t�_����H �@�o�[�O���t��\�����邽�߁ALED�̌�����ɑ�������f�W�^���M�������̂ɃV�t�g���W�X�^IC 74HC164���g�p���܂��B��łW�r�b�g�Ȃ̂łQ�J�X�P�[�h�ڑ������ĂP�U�r�b�g�Ԃ�p�ӂ��܂��B �@�V�X�e������M����RESET�M���ŃV�t�g���W�X�^�̊e���W�X�^�̓��Z�b�g����o�͂͑S��L�ɂȂ�܂��B �@�X���b�g���P�`�W�ɐi�ފԂ̓��Z�b�g����������Ă��āA500rpm���p���X������H�����LED�_���M�������邽�тɂP�r�b�g����̌��ɃV�t�g���܂��B �@�����̃��W�X�^�̓��͂�H�ɐڑ����Ă��܂��̂ŁA���Z�b�g��Ԃł͑S�Ẵr�b�g��L�A���V�t�g�N���b�N�p���X������ƈ�ԉ��̃r�b�g�ɂ͓��͂��ǂݍ��܂��H���Z�b�g����A�ȍ~�V�t�g�N���b�N�p���X�����邽�тɏ��Ԃ�H�ɂȂ��Ă���o�͂���ɑ����Ă䂭�d�|���ł��B �@�����Ă����ƑS���̃r�b�g��H�ɂȂ��Ă���ȍ~�͉����ω�������(���ۂɂ̓f�[�^�̓V�t�g����Ă��邪�A�S��H�Ȃ̂Ō����ڂ͑S�R�ς��Ȃ�)��ԂɂȂ�܂����A�����ɗ��鎟��RESET�M���Ń��Z�b�g����Ă��܂��̂ŃI�[�o�[�t���[�����牽�����m������Ή������H�͖����Ă��Ȃ����͂���܂���B �@�������̂܂܁A�V�t�g���W�X�^�̏o�̓r�b�g��LED��_���������(�d���e�ʂ�����Ȃ��̂ł��߂ł���)�A0.33�b���Ƃ�LED���������ւƃj���L�j���L�L�тĂ䂭�ʔ����\���ɂȂ�܂��B �@�ł��A����ł͍ő�ǂ��܂ŐL�т��̂���0.33�b���Ƃɏ����Ė����Ȃ�̂ŁA�^�R���[�^�[�̕\���Ƃ��Ă͎��p�ɂȂ�܂���B �@������0.24�b�̌v�����Ԃ��o������A���̎��_�ł̃V�t�g���W�X�^�̏o�͏�Ԃ����b�`IC 74HC574�ɓǂݍ��܂��ċL�����A�L�������f�[�^��LED�����点�܂��B(�����IC�̏o�͂ɑS��LED�͌q�����Ƃ͂ł��܂���) �@���̓ǂݍ��݁E�L���̓V�X�e������M����LOAD�M���̗����オ��(�̏u��)�ōs���܂��B �@��x�ǂݍ��܂ꂽ��A����ȍ~�܂��V�t�g���W�X�^�̃r�b�g���ړ����Ă��\���ɂ͊W�����̂ŁA�V�t�g���W�X�^���̓��Z�b�g�����܂ŕ��u���Ă��܂��B �@�{���͓ǂݍ��ݑO��̈����Ԃ͓��͂�ω������Ă͂����Ȃ��̂ŁA�ǂݍ��ޒ��O�Ƀp���X�J�E���g���~�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A�ǂݍ��݃^�C�~���O�̏u��(����Ԃ�̈�b���炢)�ɃV�t�g���W�X�^�̃f�[�^�������Ă��A���̕ω������P�r�b�g�̕\�����������Ȃ������x�̍��Ȃ̂œ��ʂɂ�IC�̃^�C�~���O�K��Ƃ���̕ی��͎���Ă��܂���B �@C-MOS IC�ɐ����x�ł����LED��(��R�͂���)�Ȃ��œ_�������邱�Ƃ͂ł��܂����A����̂悤��IC��ɂW����LED���q���悤�ȏꍇ���ʓrLED�h���C�o��p�ӂ��Ă��K�v������܂��B �@����̓g�����W�X�^�A���C�� TD62083AP���g�p���܂��B �@LED�\�����͂���Ȋ����ł��B �@�]�k�ɂȂ�܂����A[�V�t�g���W�X�^] �� [���b�`] �� [�d���h���C�o] �ƁA�v�����ĕ\��LED��_�������邾���łR��ނ�IC�E�A���C���K�v�Ȃ̂ŕ��i���������Ȃ�܂��B �@���������g�����͂悭������̂Ȃ̂Łu��p�Ń����`�b�v�ɓ����Ă��܂��Ă���IC�͖����̂��H�v�ƒT�����Ƃ���A�H���d�q�Ɂu�W�r�b�g�V���A���|�p�������ϊ��h�b NJU3711�v(12�r�b�g�� NJU3714)�Ƃ��������ւ�֗�������IC�������Ă��܂����B(���U�ł������܂Ƃ߂čw�����܂���) �@�������E�E�E����̉�H�Ƃقړ������e�Ȃ̂ł���NJU3711/NJU3714�ɂ��V�t�g���W�X�^���Ƀ��Z�b�g���͂�����܂����B���Z�b�g�������̂̓V�t�g���W�X�^�̂ق��Ń��b�`�ł͂���܂���B �@�c�O�Ȃ���R��IC����ł܂Ƃ߂Ă��܂����ɂ͎g���܂���B�m���ɁA�}�C�R���̊O��I/O�̊g���p�Ȃ烉�b�`�����Z�b�g���邱�Ƃ͂����Ă��A�V�t�g���W�X�g�ɂ̓}�C�R�������ɐV�����f�[�^���V�t�g���Ă��烉�b�`������̂ŁA�킴�킴�V�t�g���W�X�^�������Z�b�g����K�v�Ȃ����킯�ŁE�E�E�B�p�r���Ⴄ�̂Ŏd������܂���B �@�ق����ɉ���[�V�t�g���W�X�^�^���b�`�^�d���h���C�o]���܂Ƃ߂ĂP�ɓ�����IC�������āA�ȒP�ɍw���ł��đ�p�\�ł���A�����������������m�̕��͂ǂ����֗��ȕ����g���Ă��������B �� 74HC595������\���Ƃ킩��܂����̂ŁAHC595���g�p����IC�����炵����H�}�����̂ق��ɒlj��f�ڂ��܂����B �� �d�� �@����̉�H��5V�œ��삵�܂��B �@�O�[�q���M�����[�^��5V������ė��p���܂��B �@555�̔��U���g�������肳����ׂł�����܂��̂ŁA�d�����t�������Ƃ̂Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ă��������B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@���\���i�����z���������̂ŁA�Ԉ��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@�f�W�^����H�ł�����A�z�������Ԉ���Ă��Ȃ��āA�Ƃ�ł��Ȃ��m�C�Y���̋߂��œ��삳����ȂǔߎS�Ȋ��łȂ���A�g�ݗ��ĂɊԈႢ������������Ɠ��삵�܂��B �@�d��������ƁALED1���P�b�ԂɂR��A�p�b�p�b�Ɠ_�ł��܂��B(���鎞�Ԃ�0.03�b�ƂƂĂ��Z���ł�) �@TP1�Ɏ��g���J�E���^�^���g���̌v���f�W�^���e�X�^�[���ĂĐ��m��666.666Hz�ɒ��߂��Ă��������B �@���g���J�E���^�^���g���̌v���f�W�^���e�X�^�[�����������łȂ�����VR1���قڒ����ɉĂ����Ă��������B �@�W�����p�[��JP1(333Hz)��ڑ��A�u�p���X���^��] �I���X�C�b�`�v���~16�ɐ�ւ����āATP1����]���p���X�����[�q�����[�h���������łȂ��܂��B �@����ʼn�]���p���X�Ƃ���666.666Hz���^����ꂽ���ƂɂȂ�A�~16���[�h�Ȃ̂�2500rpm�����̐M���Ƃ��Čv������ALED�o�[�O���t��2500rpm�������͂��ł��B(�����̓`���`������ꍇ������܂�) �@�X�C�b�`���ւ����~�W���[�h�ɂ����5000rpm��\�����܂��B �@�~�S���[�h�ȉ��ɐ�ւ���ƁA10000rpm�ȏ�ɂȂ�̂őS����LED���_������8000rpm�ȏ�̕\���ƂȂ�܂��B �@�����܂Ő���ɓ����A��H�̑g�ݗ��Ă͊����ł��B �@TP1�ɂȂ����e�X�g�p�̃��[�h�����O���A�X�C�b�`�͎��ۂ̓��̓p���X���̐ݒ�ɂ��Ă��������B �@�G���W���̉�]���p���X�M��������]���p���X������ڑ����A�G���W�����ƃp���X�̓��͂ɉ�����LED2���`���`����������A�قژA�����ē_�����Ă���悤�Ɍ����܂��B �@�Ɠ����ɁALED�o�[�O���t����]���ɉ����ĐL�т�͂��ł��B �@TP2�Ɏ��g���J�E���^�^���g���̌v���f�W�^���e�X�^�[���Ă�A���͂���Ă���p���X�̎��g���𑪒�ł��A���ۂ̃G���W����]�Ƃ̊Ԃő傫�ȈႢ���Ȃ���Α��v�ł��B �@�����e�i���X�p�̃G���W����]���v���������̂悤�Ȃ̂ŁA������̕\���ƌ���ׂāA������VR1�Ŕ��������Ȃ���͂Ȃ�Ȃ���������܂���B �@�p���X�J�E���g�̂����݂̊W��G���W���܂�肩��p���X�M���ɏ��m�C�Y�Ȃǂŏ��������ڂɃJ�E���g���āA�\����LED�P���炢�͑����ڂɕ\�����邩������܂���B�K�XVR1�߂��Ă݂Ă��������B �� �p���X���̑����Z���T�[�̏ꍇ�̉��p (�{�����[�h) �@���]�Ɉ���̃p���X�ł͂Ȃ��A���]�łQ,�S,�W,16�p���X�ȂǏo�̓p���X�������^�C�v�̃Z���T�[�E�o�͓d�������g�p�̏ꍇ�́A�V�X�e���N���b�N��333.333Hz�ł͂Ȃ�666.666Hz�ɕύX���邱�ƂŁA�X�V�������P�b�ԂɂR��U��ɑ��₷���Ƃ��ł��܂��B �@�P�b�ԂɂR��̍X�V�ł͏����x���Ɗ�����悤�ł���A�W�����p�[��JP1(333Hz)�͊J���AJP2(666Hz)��ڑ��ɐ�ւ��Ă��������B �@�{�����[�h(666Hz)�̏ꍇ�A�p���X���^��] �I���X�C�b�`�͈�i�ׂ̐ړ_�ƂȂ�܂��B(��H�}���̋L�q�ɒ���) �@�{�����[�h�ł͕\�������Ȃ芊�炩�ɂȂ�A���₷���Ȃ�ł��悤�B ���Ԏ� 2010/5/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/28 |
�@���Z�����Ƃ���A���肪�Ƃ��������܂����B �@��������ɂ����肽���Ǝv���܂��B punta �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�ˑR���݂܂���B �����o�[�O���t�\���̃^�R�ɒ��킵�Ă��܂����B ���A���낢�뒲�ׂĂ��݂Ȃ���}�C�R���d�l�Ń��W�b�N�őg��ł�����������邱�Ƃ��o���܂���ł����B �Ȃ̂ł��̉�H�͖ڂ���ł��B �����ŏ�������Ȃ̂ł������̉�H�Ńv���O�R�[�h�Ɋ������ĐM������邱�Ƃ͉\�ł����H�i�G���W����2�T�C�N��50cc�ł��j ���Ȃ݂�74HC595�i�V�t�g���W�X�^+���b�`�j������̂Ŏg�p�ł�����肪�����̂ł����B tekku �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@74HC595���������ł����B �@�茳��TTl-IC�K�i�\�Ɂu�~���ז����v�ƋL�����Ă���̂ŁA�ȑO�X�ɔ����ɍs�������ɕi��Ŕ����Ȃ��������ł����B�u���ז����v�u�p�i��(���͍ɂ͂����Ă������Ȃ�������������Ȃ��Ȃ�c)�v�ƋL������IC�͂Ȃ�ׂ��g��Ȃ��悤�ɂ��Ă���̂ŁA����̐v�̎������荢��i�Ƃ��Đv����r������IC�ł��B(���̓l�b�g�ʔ̂ł������܂��ˁc) ���N���b�N����Ɗg��\��
�� IE�Ȃǂł̓N���b�N���Ă��k���\������܂��B�g�呀������Ă�������
�@IC���Q����̂ŏ������삪�y�ɂȂ�܂��B �@�v���O�R�[�h�Ɋ������ĐM����������Ƃ͓d�C�I�ɂ͉\�ł����A���̐M�������̉�H�ɓ���ē������ǂ����͂킩��܂���B �@�Ȃɂ���A���̓G���W���������Ă��Ȃ��̂ŁA�ʂ����ăv���O�̍������ɃR�[�h�����������ʼn��u���x�̓d����������̂��A�_�p���X�̃p���X���ł��イ�Ԃ�J�E���g�p���X�Ƃ��ĔF������̂��̃e�X�g�͂ł��܂���B �@�d�������イ�Ԃ�Ă����(3�`12V���x)���̉�H�ɂ��̂܂ܓ���Ă��Γ��삷�邩������܂��A����Ȃ���I�y�A���v�Ȃǂő��������H��lj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �@���̂�����́A���ۂɃG���W�����������̕��̌v���Ǝ���ɂ��C���������܂��B �@���l�̗��R�Ŏ����̃G���W���E�ԂŌ����ł��Ȃ����߁A����̋L�����ł́w�G���W����]������Ƃ��āu�v���O�̓_�Γd��(�A���ꎟ���̒�d��)���v��v�Ƃ������@����ʓI�ɂ���܂����A�����͂��̑D�O�@���������Ă��܂���̂Ŏ��@�œd�������g�`����Ȃǂ��ł��܂���B�]���ē_�Ή�H����_�^�C�~�i�O����@�ł͉�H��v�ł��܂���̂ŁA�\�߂��������������B�x�Ƃ��Ă��܂��B �@�����Ԃ�o�C�N�A�D�������Ă��Ȃ��̂������̂ł����A���e�͂��������B ���Ԏ� 2010/5/31
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����̂����肪�Ƃ��������܂��B �Ƃ肠�����p���X�ϊ���H�܂ł�����ăI�V���ő����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B74HC595�g�����ł���^^ ���̓x�͉����玸�炵�܂����B tekku �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�I�V�����������Ƃ͗��������I �@�ǂ����ʂ��o���為�Ћ����ĉ������ˁB ���Ԏ� 2010/6/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
[LED�Ń^�R���[�^�[]�̉�H�͑f���炵���ł���!!����Ȃ̂ł���74HC595��5�A�����o�[�O���tLED[10�A]��4�q��8000rpm�܂ŕ\�����������̂ł������ꂾ��LED1������200rpm�ŕ\�������鎖�ɂȂ�̂ł������U��H�܂���74HC393���ǂ̗l�ɕύX����Ηǂ��ł��傤��?�ǂ����X�������肢�������܂��B �r�[���}�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�Œ�𑜓x��500rpm����200rpm�ɂȂ�ƁA�Œ�𑜓x���ɂP��LED��_�������邾���ŃJ�E���^(�V�t�g���W�X�^)�����Z�b�g������^�C�~���O��500/200��2.5�{�ɂȂ�A�v���Ԋu��0.24�b �~ 2.5 �� 0.6�b�ƂȂ�܂��B �@�ł��ȒP�ɕύX�ł���̂̓^�C�}�[IC 555�̔��U���g���ŁA���݂�666.666Hz���U��266.666Hz���U�ɂ��邾���ł��B �@VR1��500���ɁAR2��2K���ɕύX���邱�ƂŁA���U���g������240�`262Hz�ɁBVR��200���̓_(������菭�����Ȃ���)�ŖړI��266.666Hz�ł��B �� VR���g�p�����ɁAR2��2.2K���Ƃ��邱�ƂłЂ�����266.66Hz�̔��U��H�ɂȂ�܂����A�R���f���T���̌덷�ōő�10%���x�̎��g���덷���������܂��B �@�X�V������0.6�b�Ə��������ڂɂȂ�܂����A���̉�H�̖ړI���D�O�@�ł̎g�p�Ȃ�قƂ�ǖ��͖����ł��傤�B(����Ȃɋ}���ɉ�]����ς��鑕�u�ł͖����ł�����) �@�������̓p���X���~�Q�ȏ�̃��[�g�ł���A��������̒ʂ�Ɍv�����x���Q�{���ɕύX(JP2���g�p)����A���̎��g�������ł�0.3�b���Ƃ̍X�V�ɂȂ�̂Ō��̍X�V����0.24�b�Ƒ卷�Ȃ��\�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�~�S�ȏ�Ȃ�A�v���X�P�[���ŕ������镪����𗎂Ƃ��āA�X�V���g�����グ�邱�ƂōX�ɍX�V������Z�����邱�Ƃ��ł���̂ł����A�ʂ����Ăǂ̂悤�ȓ��̓p���X��Ȃ̂��킩��܂���A���̂�����͊�{��H�}�ʂ�ō��̂��ǂ��ł��傤�B ���Ԏ� 2012/6/20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�f�W�^���^�R���[�^�[�̎���ł̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B ���������Ȃ̂ł���2�Ă��{��H�ɂē��̓p���X��{�ɂ���(���݈��]2�p���X)1��]4�p���X�Ƃ���1��]1�p���X�̂Ƃ���ɓ��͂��đO���Ă���������266.666Hz�̔��U���g����533.333Hz�Ƃ���X�V���Ԃ�0.15�b�ƂȂ�y���ȃ^�R���[�^�[�ƂȂ�Ǝv���̂ł����ԈႢ����܂���ł��傤��?�ԈႢ�Ȃ��Ƃ���533Hz��555�@IC�Ŕ��U������ꍇ�͒�R�l�͂ǂ̗l�ɕύX����Ηǂ����̂ł��傤��?�X������w�����肢�������܂��B �r�[���}�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�ߋ����O�ւ̎���ɑ��Ă͕Ԏ��͂��Ȃ��v�Ƃ������܂��j���ĉ��������o�J�ł����B �@�}�ɏ���čX�Ɏ���𑱂��ė���Ƃ́E�E�E�B �@������x�Ɛe�ؐS���N�����Č��܂��j������͂��܂���B �@�ǂ��������ʼn������Ă��������B ���Ԏ� 2012/6/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āA���낢�뒲�הY������������ւ��ǂ���܂����B �ȈՌ^����d�d������肽���Ǝv���Ă��܂��B �d���̂Ƃ����O�Ř^���@�ނ��g�p���鎖�������̂ł����A�ԗp�o�b�e���[�Q�����ԂɁA�����Ȃ肵�������̓s�x�o�b�e���[�����ւ��Ďg���Ă��܂��B�܂������Ȃǂ�AC���g���鎞�ɂ͂��ꂼ���AC�A�_�v�^�[���Ȃ������Ďg���܂��B ���̍�Ƃ��ʓ|�������̂ƁA�o�b�e���[�̉ߕ��d���S�z�ŁA�o���鎖�Ȃ玩���I�Ƀo�b�e���[�̐�ւ��ƁAAC���g����Ƃ��͊ȒP�ȏ[�d���o���āA���s����� AC (�[�l���[�^�[�Ȃ�) �̎g�p���ɂƂ��� AC �������Ă��A����d�Ńo�b�e���[�ɐ�ւ��悤�ȃV�X�e�����l���Ă݂܂����B �ߕ��d�ی�Ɠd�C��d�w�R���f���T�Ń����[��ւ����̏u�Ԓ�d�⏞�łȂ�Ƃ������Ȃ����ȂƎv���A�}�ʂ�����Ă݂��̂ł����A�ȂɂԂ�f�l�œd�C�ɋ����m�荇�����������M���Ȃ��̂ŁA�A�h�o�C�X�������Ǝv���Ă��܂��B �o�b�e���[�͂T���ԗ�40Ah���x���g�p���āA�g�p����^���@��̓d���l�̍��v�� 5,6A ���x�ł��B AC �g�p���̏[�d�d�����R�� 1A ���x (�����Ȃ�)�Ɏg�p�Ǝv���Ă��܂��B �Ȃ�ׂ������d�� (AC������)�Ƃ������̂ł����A�p���[�����[���g�����@�����v�����܂���ł����B AC �͊C�O�ł��g�p���鎖���L�邽�߁A���j�o�[�T���d���Ƃ������Ǝv���̂ł����A100-240V��AC�����[��������Ȃ������̂ŁA�ȓd�͂�100-240VAC�A�_�v�^�[���炵�Ďg�����ƍl���Ă��܂��B DC-DC���g�����R�Ƃ��ẮA���d�ɂ��d���~���������肵��12V���������邽�߂ł��B �܂��ADC-DC�̗e�ʂ�5A���������ׁA�d�v�ȋ@�ވȊO��DC-DC�̑O���狟�����悤�Ǝv���Ă��܂��B �F�}�� (PDF) �ȏ��낵�����肢�v���܂��B martan �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��ւ���H�͂����ނ˖�薳���Ǝv���܂��B �@�d�C��d�w�R���f���T���S���ł����A�ψ���2.5V�ł��S����10V�����Ȃ��A�o�b�e���[�̍ő�d����13.5V���炢�A���펞�ł�12V����Ήߓd���ŃR���f���T���j��܂��B �@�ł����5V�i�~�R���ȏ�ɂ��邩�A2.5V�i�ł͂U���Ŏg�p���Ă��������B �@�[�d��R�̓o�b�e���[��10V�ŏ[�d�J�n�Ƃ��āAAC/DC�̏o�͂�13.5V�ɐݒ肵�Ă����3.5V�ŁA�ő厞1A�ŏ[�d����Ȃ�3.5��/5W���炢�̃Z�����g��R�ł悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@100��/3.5W�̉ϒ�R�ŁA�d���v�����Ȃ��璲�����邨���肾�Ǝv���܂����A1A�����ɂ�3.5���ł�����قƂ��0�����ɉȂ��Ƃ����Ȃ��̂Œ��߂�����Ǝv���܂��B �@1A�ƌ��ߌ��������ɁA���ۂɎg�p���Ă݂āu���������d�����ւ炻���v�Ȃǂƍl�������ɑΉ��ł���悤�ɉϒ�R���g���Ă���̂�������܂���B �@�������������Ԉ����0���ɂ����AC/DC�̔\�͂ɂ����܂����ߑ�ȓd��������邩������܂���A�ł���Ήϒ�R�ƒ����2�`3��/10W���炢�̃Z�����g��R��ɓ���Ă������ق����A�둀���A�����Œm��Ȃ������ɉϒ�R������Ă��܂��Ă������̔j���ɑ���ی�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/5/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �܂��ŏ��ɂ��w�E�̃R���f���T�̑ψ��ł����A����͐}�ʂ̕\�L�~�X�ł��B5.5V1F���g�p���Ă��܂��B���݂܂���B ��͂�K���ɍl�������������đ傫�ȗ��Ƃ���������܂����B �̐S�̃o�b�e���[��ւ����ɏu�₪����܂����B����͍����e��1F�ł͑���Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H ��������������������1F�Ƃ����l�ɂ�����ł͂Ȃ��A��̓I�Ȍv�Z���킩�炸�ɁA���̂��炢�łǂ����낤�H�Ƃ�������̂��e���Ȑݒ�l�Ȃ̂ł��B �����܂Ō����ڂł̔��f�Ȃ�ł����A���ׂ̒l�����������Ă��i200mA���x�j�R���f���T�S�̂��O���Ă��u��̎��Ԃ͕ς��Ȃ��悤�Ɍ����܂����B AC�̏[�d�ł���͂育�w�E�̖�肪����A�Ώ��ɔY��ł������ł��B ���������Ă������������@�������Ă݂����Ǝv���܂��B �����Ȃ�ɂ���Ă݂܂������A����d�Ƃ����ڕW���N���A�o���ĂȂ��̂Ŏc�O�łȂ�܂���B ���Z�����Ƒ����܂����A���̉����ɂނ��Ă��w�������������炠�肪�����Ǝv���Ă��܂��B martan �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂���ɃR���f���T�ŏu�f(�u��)�̕⏞���ł��邩�ɂ��āB �@1F�Ƃ����e�ʂ́u1A�̓d����1�b�ԗ������Ƃ��ł���e���v�ƒ�߂��Ă��܂��B �@�ł��̂ŁA���Ƃ���(����̗p�r�̂悤��)���ׂ�5A�̓d���������g�����̏ꍇ�A�u�T�Ԃ�̈�ɂȂ��āA0.2�b�Ԃ�1A�̓d���𗬂����Ƃ��ł����v�E�E�E�Ƃ����P���Ȃ��̂ł͂���܂���B 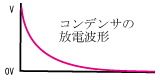 �@�R���f���T�̕��d�J�[�u�͉E�}�̂悤�Ȍ`�ŁA���d���𐅕��ɕۂ��Ă���X�g���Ɨ�����悤�ȗ��z�I�ȓd�r�݂����ȕ��d�ł͂Ȃ��A�Œ��R�l�ɋ߂����ׂ��ƕ����I�G�l���M�[�̕��o�����Ɋ�Â����J�[�u��`���̂����d�J�n����Z���ԂŃX�g���Ɠd���������āA��C�ɓd��������������ɂ͂��킶��ƒ����ԕ��d�������Ƃ������܂���������������ɂȂ��Ă��܂��B
�@�R���f���T�̕��d�J�[�u�͉E�}�̂悤�Ȍ`�ŁA���d���𐅕��ɕۂ��Ă���X�g���Ɨ�����悤�ȗ��z�I�ȓd�r�݂����ȕ��d�ł͂Ȃ��A�Œ��R�l�ɋ߂����ׂ��ƕ����I�G�l���M�[�̕��o�����Ɋ�Â����J�[�u��`���̂����d�J�n����Z���ԂŃX�g���Ɠd���������āA��C�ɓd��������������ɂ͂��킶��ƒ����ԕ��d�������Ƃ������܂���������������ɂȂ��Ă��܂��B�@1F�Ő�A�������悤�ȕ��ׂ��q�����Ă�����A���ꂱ����u�œd�����������ċ@��͓����܂���B �@�X�ɍl���Ē��������̂́A�o�b�e���[�d�����������ĉߕ��d�ɂȂ�O�̒i�K�ŃJ�b�g���悤�Ƃ���d���Ńo�b�e���[��藣���킯�ł�����A���̎��_�ł̓R���f���T�ɂ̓o�b�e���[��O�̒Ⴂ�d�������~�����Ă��܂���B �@����12V�������Ɖ������10V�ɋ߂��d���ɐݒ肳��Ă���Ǝv���܂����A����ȒႢ�d�������~���Ă��Ȃ��R���f���T�������狋�d����ƁA���d�J�n�d���͂����w���w���B�����Ă��������C�ɓd����������̂Ŗ{���Ɉ�u�����@��𐳏�ɓ��삳������d�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ���������܂���B �@�����[����ւ�Ԃ̒Z�����̕⏞�p�Ƃ��čl�����1F���x�ł����イ�ԂƎv���܂������A����܂��B �@���ʂ͋@��̓d����H�ɂ͓d���R���f���T(�d�C��d�w�R���f���T��肸���Ə������e�ʂł�)�Ȃǂ������Ă��āA�ق�̈�u�����[����ւ���x�̎��Ԃł���Ώu�f���Ă��@��̓d���͗����Ȃ��͂��ł��B �@���g�p�̋@�킪��قǓd���ɗ]�T�������̂��A�ق��ɉ�������������̂��킩��܂��A�����[�̐�ւ�Ԃ��炢�̎��Ԃ̒�d�ł��߂Ȃ͖̂��ł��ˁB �@������H�}�ŋC�ɂȂ�̂́A�ߕ��d�h�~�p�̃����[(����BAT1 low V cut�p��RY-1,BAT2�p��RY-2�Ƃ���)�������āA���̃����[�̐ړ_�Ńo�b�e���[��ւ�<�p�̃����[(RY-3�Ƃ���)���ւ���悤�ɓ�i�K�ɂȂ��Ă���_�ƁARY-3�̓d���̓R���f���T�ɂȂ��Ă���_�B �@���n��ōl����ƁA�����o�b�e���[�P�ʼnғ����Ă��ăo�b�e���[��d���ɂȂ����ꍇ�A�܂�RY-1�����[�N�ړ_���ɐ�ւ����o�b�e���[����̓d�͋����������Ȃ��Ă���(RY-1�̂����P�g�̐ړ_��)RY-3�ɃR���f���T�̓d�͂��������ăR�C���������Ƃ����Ƃ������Ԃł���̂ŁA�܂��P�ڂ͂��̎��_�łǂ���̃o�b�e���[������d�͋������Ă��Ȃ����Ԃ����܂�Ă����Ƃ�����_�B�Q�ڂɂ�RY-3�̃R�C�������d�͂��A�ŏ�����キ�Ă��������ׂɓd�͂��z������Ȃ����C�ɓd�������������R���f���T���狟�������̂ŁA�R�C���ɂ��イ�Ԃ�Ȏ��͂�������ꂸ��RY-3�̓��삪�x���Ȃ�(�ň��͐�ւ�Ȃ�)�Ƃ����s����������Ă���\���������̂ł��B �@�o�b�e���[�Q�ʼnғ����Ă��ăo�b�e���[��d���ɂȂ����ꍇ�ɂ́A��͂�RY-2�������Ă���RY-3����ւ�܂ň�i�K�̃^�C�����O�͂���܂����A������̏ꍇ��RY-3�̃R�C���̓d�����J�b�g���邾���Ȃ̂ŁA�R���f���T�̓d��������Ȃ��Ă������[�͂����ɐ�ւ�܂����A�d���s���Ő�ւ�Ȃ��Ƃ��������Ȃ��ł��ˁB �@�����܂Ń����[����ւ���x�̊ԂȂ�(�R���f���T������Ă��邵)�@�킪�ۂ��Ă���邾�낤�Ɨ\�����Ă����̂��Â������悤�ł��̂ŁA�����͂���������d�ɂȂ�悤�Ȃ����݂����Ȃ���Ȃ�܂���B �@��u�ł��d�����ꂸ������d�œ��삷��ɂ́A���̂悤�Ɂu�o�b�e���[���J�b�g����v���u�o�b�e���[��ւ��郊���[���ւ���v�Ƃ����菇�ŊԂɓd���f�̎��Ԃ����̂ł͂Ȃ��A�u�o�b�e���[����֒m����v���u�����̃o�b�e���[����d�͋�������v���u��d���ɂȂ����o�b�e���[�̂ق���藣���v�Ƃ����菇�ŁA��ւ��̉ߓn���ɂ͗��������̂ł͂Ȃ��������q�����Ă����Ԃ����܂��B �@�F�X�ƕ��@�͍l�����܂����A����͍������H�ɉ����ċ߂���H�ōςނ悤�ȕ��@�ŁA���Ǖ������������Ă݂܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@RY-1,RY-2�̂�����������X�C�b�`�p��RY-11,RY-21��lj����܂��BRY-1,RY-2�̐ړ_�Ő��Ă����������͂�����̃����[�̐ړ_��ʂ��܂��B�@���킹�āARY-3�Ő�ւ��Ă����o�b�e���[��ւ��͂�͂�RY-3�̐ړ_�ł͒��ڍs���܂���BRY-3�͒lj������V�����[�̂ǂ�������邩�̐�ւ��ɂȂ�܂��B �@�����Ń|�C���g�́ARY-11,RY-21�̃R�C���ɂ͓d���R���f���T������ɐڑ�����Ă��āA�J�b�g����Ă��ق�̏���������ON�ɂȂ����܂܁A���̂��x�����܂��B����Ńo�b�e���[����ւ��u(���b�H)�̊������̃o�b�e���[���ڑ����ꂽ��ԂɂȂ�u�f�͋N����܂����B �@�������{���̓V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h������ł��܂��̂ŁA�d���̍������̃o�b�e���[���炵���d���͗���܂��B �@�ʂ����ĉ��b�قǒx������̂��̓����[�̏���d���Ɠd���R���f���T�̗e�ʂŌ��܂�܂��̂ŁA������ł͂ǂ�ȃ����[�����g�����킩��܂���̂ʼn��b���͂����ł͏����܂���B �@���ۂɍ���Ă݂āA���Ԃ��Z����R���f���T�̗e�ʂ𑝂₵�Ă݂Ă��������B�P�b��������イ�Ԃ���p�I���Ǝv���܂��B �@�}�ł́u�����vLED��lj����Ă��܂��̂ŁA�o�b�e���[����ւ鎞�ɒx�����Ԃ̊Ԃ��������̋���LED���_�����܂��B�x���̓����ڂŊm�F�ł��܂��B �@���̒x�������[�̂�����������d��H�ƂȂ�d�͋������r�₦�邱�Ƃ͂���܂���̂ŁA�d�C��d�w�R���f���T�͕s�v�ɂȂ�܂��B �@�ʂɂ��Ă��Ă��s���ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���ɍw������đg�ݍ��܂�Ă���Ȃ炻�̂܂܂ɂ��Ă����Ă������ł��ˁB �@���ƁA�����������ł͂���܂��A���̉�H(���̉�H�ł�)�̏ꍇ�̓o�b�e���[�P���J�b�g�����d���Ńo�b�e���[�Q�͎g�����Ԃœd���X�C�b�`����ꂽ�ꍇ(AC100V�͖���)�A�ǂ��������Ă�RY-3�̃R�C�������d���͗^�����Ȃ��̂ŁA���������o�b�e���[�Q�ɓd���������Ă��d�͉͂i�v�ɋ����ł��܂���B�o�b�e���[�P�����イ�Ԃ�ɏ[�d���������AAC100V���Ȃ����E�E�E�B �@���A�������o�b�e���[�P�ƃo�b�e���[�Q����������N���ł���悤�ɂȂ�܂����A����Ȗʓ|�Ȏ��͂���Ă��Ȃ��Ǝv���̂ŁA�o�b�e���[�P���J�b�g�d���Ńo�b�e���[�Q�ɂ����d�C���������ł��V�X�e�����N���ł���悤�ɁARY-3�̂����ɃX�C�b�`��RY-21�ɑI��M���Q�𗬂���悤�ɂ��Ă��܂��傤�B �@���ׂ̈ɂ��Ă���̂��u�o�b�e���[�Q����N���v�X�C�b�`�ł��B �@�X�C�b�`������̂̓u�T�C�N���ƍl����ꍇ�ARY-3�����Ă���ړ_�Q�̏���12V����������̂��o�͓_������̂ł͂Ȃ��A�o�b�e���[�P�ƃo�b�e���[�Q���炻�ꂼ��_�C�I�[�h���o�R���Ă����ɓd������������悤�ɂ���ƁA�X�C�b�`�s�v�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/5/1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/2 |
�����̉��肪�Ƃ��������܂����B ���ׂ��傫���Ƃ��̃R���f���T�̐U�镑���悭����܂����B ���w�E�̒ʂ�A�Ȃ�Ƃ��������Ȃ����H�Ƃ����l�����܂��ɊÂ������̂��Ǝv���܂��B ����d�̉������@�̂����肪�Ƃ��������܂����B ����ɍ��L������̉�H���x�[�X�ɍl���Ă��������ċ��k�ł��B ����Ȃ珉�߂����蒼�����ړI��B���o�������ł��B ���낢��ƕ��@�͍l������ƗL��܂������A�Ǘ��l���܂�����������ƃX�}�[�g�ȉ�H���\�z�����ł��傤�ˁB ����������ƕ����܂��B ����͖{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B martan �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���������܂Ŗ����H�Ȃ�Ƃ��ł��܂����B ������p����Ȃ��̂ł����A���낢��h�肪�c��܂����B �Ⴆ�A���X�ɖ����Ȃ��Ȃ��ăo�b�e���[�R�[�h���͂��������ւ��Ȃ��Ƃ��A�ߕ��d�ی�̕��A�d����ݒ�o���Ȃ��Ƃ��A�o�b�e���[�̒[�q�d������ɊĎ��������̂ɁA�@����̓d���v�̃I�t�Z�b�g�߂��Ă����̎��X�̕��ׂ̗ʂɉ����ēd���l���ω����Ă��܂����ȂǁA���ۂɍ���Ă݂Ȃ���Ή���Ȃ���肪�����ĕ��ɂȂ�܂����B ���ǔł���鎞�܂������k�����Ă��炢�����Ǝv���܂��B ���肪�Ƃ��������܂����B martan �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�o�b�e���[�������Ȃ����玩���Ő�ւ�Ƃ�����|�̑��u�ł����̂Łu�܂��o�b�e���[�����邤���Ɉ��������v�Ƃ����͎̂��ۂɂ��邩������܂��E�E�E�z��O�ł��B �@���ǂ��̏ꍇ�́A��d�������m���Đ�ւ�����������悤�Ƃ����p�����[��RY-1,RY-2�̃R�C���d�����A���̎������g�̃o�b�e���[����d����������ē��삷��悤�ȉ�H�̂��߁A�o�b�e���[������������RY-1,RY-2�͓��삷��͂��������̂ŁA�����I�ɐ�ւ��H�͓����܂����ˁB �@��ɏ����܂����悤�ɁA >�X�C�b�`������̂̓u�T�C�N���ƍl����ꍇ�ARY-3�����Ă���ړ_�Q�̏���12V����������̂��o�͓_������̂ł͂Ȃ��A�o�b�e���[�P�ƃo�b�e���[�Q���炻�ꂼ��_�C�I�[�h���o�R���Ă����ɓd������������悤�ɂ���ƁA�X�C�b�`�s�v�ɂȂ�܂��B �Ƃ����l�����ŁA��d���̊Ď���H��A�����[�����d�������ꂼ��ʁX�̃o�b�e���[����X�Ɏ��̂ł͂Ȃ��A�ǂ�Ȏ��ł��d��������A�d�q��H�����ׂ̓d��(�V�X�e���d��)�Ƃ����l���œd����H��g�ݍ��܂Ȃ��ƁA�������̃o�b�e���[����d�������Ƃ������@�ł͂��̃o�b�e���[���ꂽ���ɓd������������Ȃ��Ȃ�s�s�����N����܂��B �@�q���g�͏o���Ă������̂ŁA���������������ɑg�ւ������h�����c�����킯�ł��̂ŁA�����ł͉�H�}�͕����Ă����܂��B �@���������ꍇ�̓N���b�N���ĉ��lj�H�}���J���Ă��������B �@�܂��������̃o�b�e���[�����������ۂɂ́A����o�b�e���[���O���X�C�b�`�𑀍삵�āA�o�b�e���[�����͂������Ƃ�ʒm���ĕʂ̃o�b�e���[�ɐ�ւ��A���̌�Ƀo�b�e���[�����O���Γd������邱�Ƃ͂���܂����ˁB �@���A�d���̒��߉\�ɂ�����@���ɓ���Ă��܂��B �@�d���v�̖��́A�o�b�e���[�Ƃ͂��̂悤�ɕ��ׂɓd���𗬂��Γd���~�����N�������Ȃ̂ŁA�u�o�b�e���[�̓d�����v��v�Ƃ����Ӗ��ł͂���Ő���ł��B �@�g�p���ɊJ���d�����v�肽���̂ł���A��͂��o�b�e���[���O���X�C�b�`�𑀍삵�ĕʃo�b�e���[�ɐ�ւ��āA�d���������Ȃ��Ȃ����o�b�e���[�̓d�����v��悤�ɂ��邵���Ȃ��ł��ˁB ���Ԏ� 2010/5/7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �p�Y���������Ȃ��ĉ䖝�o�������������Ă��܂��悤�Ȕs�k���������Ȃ���@�s ���Ƃ�����������H �t�@�����Ă��܂��܂����D�D�D ���ߑ������Ȃ���Ȃ̐v�i����Ă��Ċy�����j�̖��n����Ɋ����܂����B �������F�X�����Ă��������ĂȂ�Ƃ����p�̈�ɒB���܂����̂ŁA����͂���ł���Ă݂悤�Ǝv���܂��B�i���͂��łɊC�O�ɔ������Ă��܂��܂����B�j ���T����^�C�̃W�����O���̎B�e����łQ�����ԂŎg���Ă݂܂��B �������Ȃ�������o�ߕ������Ǝv���܂��B ���v���Ȃ��D�D�D martan �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�^�C�̃W�����O���ł����B�o�b�e���[���K�{�ł��ˁi�O�O�G �@�����Ă�����Ⴂ�I �@�E�E�E�Ă������A���ꂩ�炾�ƉJ�G�̃W�����O���I�H ���Ԏ� 2010/5/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�u���邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[�v�̐܂͑�ς����b�ɐ���܂����A���ł͐F�X�ȕ��ɂ����p���đ�ϖ𗧂��Ă���܂��A���肪�Ƃ��������܂����B ����܂����肢�ɏオ�����̂́A���u�n�̋@��̓d�����j�^�[�̎��Ȃ�ł����A���u�n�ɂ���쐶���������̓d��̃o�b�e���[�̏��Ղ����Ȃ����邽�߂ɒf�����̃X�C�b�`�ɂ��āA���������ɐG��Z���T�[�̐����f���������ɓd��̃X�C�b�`������悤�ɂ��܂����B ���̍쓮���j�^�[�Ƃ��ē��菬�d�̓g�����V�[�o�[���g���A�d��̓d��������ƃg�����V�[�o�[�̓d���Ƃo�s�s�X�C�b�`���쓮���R�b�ԓd�g�𑗐M���A�Ƃɂ���g�����V�[�o�[�̎�M���j�^�[�k�d�c�ɃZ���T�[��t���ă��b�`��H�łk�d�c���_�ł������鑕�u�ɂ��܂������A��N�����`�����l�����g���d�g���o�Ă���悤�Ō�쓮�����т��т��܂����B �����ō��N�̓g�[�������āE�E�E�Ƒf�l�l���ł��n�߂�L567CP�Ƃ����h�b�H�����肵�܂������A�I�V���X�R�[�v����������Ă����܂łœڍ����Ă��܂��܂����B�o���܂����瑗�M�@�̃}�C�N�[�q�ɓ����g�[�����M�@�ƁA��M�@�̃C���z�[���[�q����̃g�[������̓��͂ō쓮����X�C�b�`�̉�H���L��܂����狳���Ă��������Ȃ��ł��傤���H�A�܂����ɗǂ��Ă�����܂����狳���Ă��������ATC4584BP�ATC4011UBP�A74HC14�A74HC132�A���茳�ɗL��܂����g���Ȃ��ł��傤���H�A���݂܂���낵�����肢���܂��B ���܂��� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�F�X�ƍ���Ă��܂��ˁB �@��������̕i�ł͂Ȃ��A���p�i�Ƃ������Ŋ����������܂��B �@NE567�͐̂��炽���ւ�悭�g���Ă���g�[�����o�pIC�ŁA�Z�J���h�\�[�X��LM567�ANJM567(���{��PDF)�ȂNJe�Ђ��琻�i������Ă��܂��B �@���̃R���f���T�ƒ�R�����邾���ŁA�������͂̒����������P�̃g�[�������o���邱�Ƃ��ł��܂��B �@����̂���]�̂悤�Ƀ����R���M���Ƃ��ăg�[�������g�����ꂽ���ƗL���E�����Ō���ʼn�����ON/OFF������A�J�Z�b�g�e�[�v�ɘ^�����ꂽ�N�ǂȂǂ̓r���Ƀg�[�������Ă��̃g�[�������o����ƃX���C�h���̏�f�����̉�ʂɐi�߂鑕�u�A�o�X�̒��ŗ���鎟�̒◯���ē��̃e�[�v�Ƀg�[�������Ă����ė����\����i�K�l�グ�����鑕�u�A�����ēS���t�@���̊Ԃł͓S��������M�����́u����M���L�����Z���[�v�Ɏg������A�̂��畝�L���g���Ă��܂����B �@���ɖ����Ƃ̊Ԃł́u����M���L�����Z���[�v�̂悤�ɖ����@�E��M�@�Ɍq���Ńg�[�������o�����H�͂��Ȃ�L���ŁA�F�X��HP�l�Ő�����@�����J����Ă��܂��B �@NE567�͂��Ȃ�f����IC�ŁA�f�[�^�V�[�g�ʂ�̌v�Z���Ōv�Z���Ē�R�l�E�R���f���T�e�ʂ����߂�قƂ�NJԈႢ�Ȃ����삵�܂��B �@���������v�Z���ł��Ȃ��Ă��E�E�E�E����̉�H�}�ʂ�ɑg�ݗ��Ă�قڊm���ɓ��삵�܂��B �@�����@�Ńg�[���M���𑗐M����ɂ́A�u�}�C�N�[�q�Ƀ}�C�N���x���̃g�[���M�������Ă��A�g�[�������d�g�ɏ���đ��M������v�ƒP���ɂ͂䂫�܂���B �� ���͂ǂ������PTT�������Ă���̂ł��傤�B���������ĉ����Ăăe�[�v�ł��邮�銪���ɂ��Ă���Ƃ��E�E�E�B����A�����ƊO���}�C�N�[�q�ɐ�������H���q���ő��M���Ă��������ł����ǁB �@���菬�d�̓g�����V�[�o�[�����g���Ƃ̎��Ȃ̂ŁA�A�}�`���A�����̌Œ�@�̂悤�Ȑ獷���ʂȊO���}�C�N�[�q�ł͖����̂̓z�b�Ƃ��Ă��܂����A�n���f�B�����@�Łu�O���}�C�N���g���ĉ����M������͂��A���M������(PTT����������)�v�ɂ����̍�@������A�e�Ђ̃}�C�N�[�q�EPTT�[�q���ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�𗝉����Ă��Ȃ��Ɖ�H�����܂���B �@�傫�������ĂQ��ނ���܂��̂ŁA�ǂ���̋@������g�����킩��܂���̂Ŗ����@�ւ̐ڑ��}�͂Q��ޗp�ӂ��܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���M���E�g�[�����U �� �g�[�����U��H �@�V���~�b�gNOT�Q�[�gIC��74HC14���g�p������`�g���U��H�Ńg�[���M�������܂��B �@���U���g������2KHz�ŁAVR1�Ŗ�1.8�`2.38KHz�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@�g�[���M���Ƃ��ċ�`�g�͌ł��Ă�����ƋC�����ǂ������E�E�E��͂�SIN�g�������I�Ƃ����������������邩������܂��A��`�g�ł�NE567�͂����ƌ��o���Ă����̂ŁA���삪�y�ȋ�`�g���U��H���g�p���܂��B �� �}�C�N�[�q�ւ̃J�b�v�����O��H �@TTL���x��(5V)�Ŕ��U������`�g�M�����R�Ń}�C�N���x��(���\mV)�܂ŗ��Ƃ��āA�d���R���f���T�ŃJ�b�v�����O���Ė����@�̊O���}�C�N�[�q�Ɛڑ����܂��B �@�����@�̊O���}�C�N�[�q���G���N�g���b�g�E�R���f���T�E�}�C�N�p�Ƀo�C�A�X����Ă��܂��B �@VR2�Ńg�[���M���̑傫��(�}�C�N����)�߂ł��܂��B �� �o�s�s��H �@�P���E�b�h(KENWOOD)�̖����@�̏ꍇ�APTT�M�����͓Ɨ����Ă��܂��̂ŁA�P����PTT�M������GND�ɗ��Ƃ����������M��ԂɂȂ�܂��B �@�����P���E�b�h�@�ł�GND���C���z��/�O���X�s�[�J�[�q�ł���2.5mm�v���O���ɂ��������̂ŁA�}�C�N�֘A�̔z��(3.5mm��)���g�����Ƃ���ƃC���z������2.5mm�v���O���K�v�ɂȂ�܂��B �@�܂��A�C�R����(ICOM/YAESU/STANDARD/ALINCO�c�ق�)�p�Ȃǂ̓}�C�N�z����PTT�M���������p���Ă��āA�u�I�[�v�����AGND�Ɠd�C�I�Ɍq���邩�v�ŊO��PTT�������ꂽ���ǂ����̔�����s���܂��B �@�ł����瑗�M���Ȃ����ɂ̓I�[�v��(�����q���Ȃ�)�A���M���鎞�ɂ͒�R��GND�ɗ��Ƃ��A�Ƃ�����ւ����K�v�ł��B �� YAESU��STANDARD�͍��͍�������Vertex Standard�ɂȂ��Ă��܂�
�@�ǂ���̋@��̏ꍇ���A��H�}���ɂ͂��ꂼ���PTT�V�X�e���𗝉����邽�߂�PTT�X�C�b�`���L�����Ă��܂����A����̂���]�ł͑��M���������ɂ͂R�b�Ԃ����d���������H�����ɂ����ł��̂ŁA������̑��M��H�ł�PTT�𑀍삷��K�v�͖����A���PTT��ON�ƍl���ăX�C�b�`�͖������Ă��̂܂ܒ����Ō��\�ł��B �@�{��H��ڑ�����ꍇ�A���������@�{�̂�PTT�X�C�b�`���Œ肵�ĉ����Ă���̂ł���A���������d�|���͕s�v�ł��B(����t�ɖ{�̑��͂Ȃɂ����Ȃ��ł�������) �� �d����H �@74HC14�̔��U��H���d���d���ɂ�蔭�U���g�����ς�܂��B �@�K���A�O�[�q���M�����[�^�Ȃǂň��艻������5V���g�p���Ă��������B �� ��M���E�g�[�����o �� �����@���特�����͂� �@�{��H�����������[�q�ɁA�����@�̊O���X�s�[�J�[/�C���z���[�q�����M������͂��܂��B �@����������@�̃��[�J�[���Ƃɔz�����Ⴂ�܂��B��H�}�ł͏ȗ����Ă��܂����A���M���̐}���Q�l���C���z��/�O���X�s�[�J�[�ւ̐M����GND�����ꂼ��ڑ����Ă��������B �@�������̓��x�����ߗp�̃{�����[���͂���܂���B�����@�{�̂̃{�����[���ʼn��ʂ͒��߂��܂��B �� �g�[�����o��H �@NE567���g�p�����P��g�[���̌��o��H�ł��B �@���o���g������2KHz�ŁAVR1�Ŗ�1.9�`2.26KHz�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@����̐M�������o�����ꍇ�A�o�͒[�q��L�ɂȂ�܂��B(�I�[�v���R���N�^) �@�m�C�Y�A���̖����@����̍��M�Ō�쓮���ɂ������邽�߁A�������Ԃ͖�0.2�b���x�A�����ē���g�[�������o���Ȃ��Ɗm�肵�Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B �� LED�\����H �@NAND�Q�[�gIC��74HC00��RS�t���b�v�t���b�v�����A�g�[�������o�������Ƃ��L������LED��_�������܂��B �@����g�[�������o�����LED�͓_�����A�g�[���������Ă�LED�͓_���������܂��B �@���Z�b�g�X�C�b�`�������Ə������܂��B �@��H�}�ł�NAND�Q�[�g���Q�]���Ă��܂��̂ŁA�����LED�̓_�ʼn�H�����Ƃ��ڗ����܂��ˁB �@4011B���������̂悤�ł��̂ŁA���̕�����4011B�ɒu�������Ă������ł��B4011B�̓s���z�u���Ⴂ�܂��̂ł��ꂮ��������ӂ��������B �� �d����H �@������̎�M��H��NE567�̔��U���g��������ɕۂ��߁A�K���O�[�q���M�����[�^�Ȃǂň��艻������5V���g�p���Ă��������B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �� ���M���̒��� �@�I�V���X�R�[�v����g���J�E���^������Γ����e�Ղɑ���ł��܂����A�����ꍇ�͒��ږ����@�Ɛڑ����ē���m�F���s���܂��B �@���M�������@(�`)�Ɛڑ����ēd��������ƁAPTT��ON�̏�ԂɂȂ����M���J�n���܂��B �@��M�������@(�a)�̓`�����l�������킹�ēd�g����M�ł����Ԃɂ��A�X�s�[�J�[����u�s�[�v�Ƃ������U������������Ή�H�͐���ɓ��삵�Ă��܂��B �@VR1���āu�s�[�v���̉������ω����邱�Ƃ��m���߂Ă��������B �@VR2���āA���������Ȃق�����傫�Ȃق��ɉ��ʂ��グ�Ă����āA�����������Ȃ��_�Ŏ~�߂܂��B �� ��M���̒��� �@�����@�Ɍq���Ńe�X�g�����Ă������̂ł����A�܂��͊��̉�H�̓�����e�X�g���܂��B �@���M��H�����M�������@(�`)�Ƃ̐ڑ��͊O���Ă����č\���܂���B(�q���ł����Ă������ł����E�E�E) �@���M��H��TEST OUT�Ǝ�M��H����������(+)��ڑ����܂��B �@���M��H�Ǝ�M��H��GND���m���ڑ����Ă��������B �@����Ŗ����@�Ȃ��ŁA���M�Ǝ�M�̃g�[�����g�������킹�钲�߂��ł���悤�ɂȂ�܂��B �@���M��H�E��M��H�̗�����VR1�������ɉ܂��B(���M���͂ق�̏��������̂ق������g�����������Ȃ�܂�) �@����ŗ����̉�H�̎��g������2KHz�ɂȂ�܂��̂ŁA��M�����g�[�������v�������Ƃ����o����LED1�u���o�v���_������͂��ł��B �@�_�����Ȃ��ꍇ�́A�܂��͑��M����VR1�����E�ɉĂ݂Ă��������B�ǂ����Ŏ��g����������LED���_������͂��ł��B����ł��_�����Ȃ��ꍇ�͂���ǂ͎�M����VR1���܂߂Ă��낢��Ȉʒu�W�ɂȂ�悤�ăe�X�g���Ă݂Ă��������B �@LED1�u���o�v���_������Ɠ�����LED2�u�����v���_�����܂��B �� �d��ON���Ɉ�u����NE567�̏o�͂�ON�ɂȂ�܂��̂ŁALED2�u����v���_�������܂ܕێ����܂��B��Ƀ��Z�b�g�X�C�b�`�������ď����Ă����Ă��������B �@���M���E��M����VR1���Ă݂āA�ʒu���ς�ƃg�[�����g�����ς���LED1�u���o�v���������邱�Ƃ��m�F���Ă��������B �@�����܂ł�����ł�����ANE567�͐���Ƀg�[�����o���s���Ă��܂��B �@�Ȃ�ׂ�������VR1�������ɋ߂��ʒu�ŁA���g����������LED���_������ʒu������߂Ē��߂��Ă��������B �� �����@�Ɛڑ����Ă̒��� �@�e�X�g�p�Ɍq����TEST OUT�Ǝ�M��H����������(+)�̔z���AGND���m�̔z���͊O���܂��B �@���M����H�����M�������@(�`)�A��M����H����M�������@(�a)�A���ꂼ����ۂ̎g�p��ԂŐڑ����܂��B �@��M�������@(�a)�̃{�����[���͍ő�ɂ��Ă����܂��B �@���ꂼ��d�������āA���M�������@(�`)�����M���J�n���A��M�������@(�a)�͂��̓d�g����M������ԂɂȂ�E�E�ELED1�u���o�v���_������͂��ł��B �@�����_�����Ȃ��ꍇ�A��M�������@(�a)�ɑ}���Ă���C���z��/�O���X�s�[�J�[�p�̃v���O���āA�{�̃X�s�[�J�[����u�s�[�v�����������Ă��邩�m���߂Ă��������B �@�ڑ�������Ԃ���M�������@(�a)�̃{�����[�����ĉ��ʂ�ς��Ă݂āA�������Ȃ����m�F���Ă݂Ă��������B �@�܂��A��M��H�����������[�q�ɕ����8�`16�����x�̃X�s�[�J�[�A�܂��̓C���z���E�w�b�h�z���Ȃǂ�ڑ����āA�����Ɖ������Ă��邩�m���߂Ă݂���@���Ƃ��Ă݂Ă��������B �@�������Ă���̂�LED1�u���o�v���_�����Ȃ��ꍇ�́A���M����VR1���������E�ɓ������Ă݂āA���U���g����ς��Ă݂Ă��������B��������Ŕ�������A��������͈͂̒����ɂ��킹�Ă��������B �@�d���d���̕ϓ��A���������x�ϓ��Ȃǂ�������Δ��U���g���͂قƂ�ǃY���܂���A���肵�ē��삵�܂��B �@���̉�H�ł�NE567�̌��m�͈͂Ƃ��āA�w��̎��g��������}50Hz�͈̔͂ł���Ό��m����PLL���b�N���܂��B �� ��M�������@�̐ݒ� �@���M�����u�̓d����ON�ɂȂ鎞�Ԃ��R�b�Ƃ������ƂŁA�{���u���g�[�������o����x�����Ԃ��l������Ɓu��M�������@(�a)�̃p���[�Z�[�u�@�\�v�͕K��OFF�Ŏg�p���Ă��������B �@�p���[�Z�[�u�@�\��ON����M�������@(�a)�����Ԋu�ł�����M���Ă��Ȃ��ꍇ�A�^�C�~���O�ɂ���Ă͑��M�J�n����̒Z���Ԃ͋x��ł��Ď�M�ł����A���ʓI�ɂ͂R�b�̑��M�̂����Ō�̂ق��̏�������������M�ł��Ȃ��ꍇ������܂��B �@���������Z���Ԃ�����M�ł��Ȃ���Ԃ����������ꍇ�A�g�[���𐳂������m�ł����ɏI����Ă��܂��\��������܂��B �@�p���[�Z�[�u���g��Ȃ����A�������͑��M���̓d���^�C�}�[��ύX����10�b���x�͑��M��������悤�ɂ���Ƃ����肵�����삪���҂ł��܂��B �� �g���Ƃ� �@��ɂ������܂����悤�ɁA�]���Ă���NAND�Q�[�g��LED�̓_�ʼn�H�����Γ���m�F�pLED���s�J�s�J�_�ł����邱�Ƃ��ł��܂��B �@���������[�q�ɕ���ɃX�s�[�J�[��ڑ����Ă����A���������đ��u�����삵�����ɃX�s�[�J�[����u�s�[�v�������āA���ł�������m�F�ł��܂��B �@�������̏ꍇ�͖����@�́u�O���[�v�@�\�v���g���ē���̃O���[�v�ԍ����m�̉������o���Ȃ��ݒ�ɂ��Ă����Ȃ��ƁA���̌�쓮�̌����ɂȂ��Ă���ʂ̐l���g���Ă���ʘb�̉����ہX�������Ă��܂��ĕs�ւł��ˁB �@�����o���̂ɑ��ɂ�NE567�̏o�̓s����L�ɂȂ�M������d�q�u�U�[��H�����悤�ɉ�H�����ANE567���g�[�����o�������������u�U�[�����̉����������Ƃ��ł���ł��傤�B �@���̉�H�������(������VR1�̒�R�l�̊g���ύX�͕K�v)�A���M�@�P��1.8KHz�A���M�@�Q��2.0KHz�A���M�@�R��2.2KHz�A�ƕʁX�̃g�[���M���𑗐M(�����̃`�����l���͓���)����悤�ɂ��A��M���͖����@�͈���NE567�ɂ��g�[�����o��LED�_����H��1.8KHz�p�A2.0KHz�p�A2.2KHz�p�ƂR��H���ׂ�A�R�����̕ʁX�̓����Z���T�[�E�����������u�̓�����ʂ�LED�\�����邱�Ƃ��ł��܂��ˁB(�S�������ɃZ���T�[�͔������Ȃ��Ƃ��������͂���܂����A�ʁX�̏ꏊ�Ɏd�|���ē�������ł͂܂��������M�͖����ł��傤) ���Ԏ� 2010/4/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��A�����@�͂h�b�n�l���ł��B�o�s�s�͖����@���Œ肵�ă����[�ƃv�b�V���\���m�C�h���g���Ė����@�̓d���n�m�̌�\���m�C�h���o�s�s���R�b�ԉ����ēd��������H�ł��B�����Ă�����������H���ƃ\���m�C�h���g��Ȃ��Ă��O���}�C�N�[�q���g���ă����[�ło�s�s�X�C�b�`�͍��܂��ˁI���M���P�O�b���x�ɐL���܂��A�F�X���肪�Ƃ��������܂��A�������삵�Č��܂��B ���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�\���m�C�h�ŁE�E�E�E����͗͋Z�ł��ˁB �@�O���}�C�N�[�q���g����PTT��ON/OFF���d�q��H�ő���ł��܂�����A�����@���Œ肵����\���m�C�h�ʼn������肷��@�B�\���͖����Ȃ�̂ŁA�̏�����Ȃ��Ȃ�ł��傤�B ���Ԏ� 2010/4/30
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���삵�Ď��������܂����A���������w���̒ʂ�ɂ����炷�ׂĊ����ł��I�I���肪�Ƃ��������܂����A���ꂵ���Ă��܂�܂���B �\���m�C�h�̓��O����㩂̃g���K�[�Ɏg�����c�肪�L�����̂Ŏg���܂������A��x�g���Đ�������Ɠ����悤�ȕ��������̂ł��ːl�Ԃ́i�j�B�k�d�c�͌��̂悤�ɓ_�łɂ��܂����A�����o��Ɛ^�钆���ƍ���܂�����A�u�U�[�͖h�Ɨp�̒ʕ�@�ɂ���Ȃ�ǂ��ł��ˁB��������炵�����m�b��q�ł��ĐS��芴�ӂ��܂��A���肪�Ƃ��������܂����B ���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���������d�C��ɃX�Y���o�`�����d���A���O����㩁E�E�E�������u����R����_����z�����Ă��܂��܂��i�O�O�G �@���������_�ƌ����̍H����܂Ƃ߂ďЉ��HP�Ȃǂ�����Ă͂������ł����B������A�C�f�A����{���イ�ŕK�v�Ƃ���Ă���Ǝv���܂��B �@�j���[�X�ł����Δ_�앨�̓�����Ȃǂ����Ă��錙�Ȑ��̒��ł����A��ԂȂǂ̓���h�~�x�u�Ƃ��Ēf���Z���T�[��l�֒m�Z���T�[�Ƒg�ݍ��킹�āA����ł͌x���炵���胉�C�g�����A�����ʼnƂɒʕ�V�X�e���Ȃǂɉ��p����Ɩ�ł����S���ĐQ�Ă����邩������܂���ˁB ���Ԏ� 2010/5/2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/2 |
�F�X�ȑ��u�̓d�q��H�̓I���W�i��������܂����A���̂g�o�𑽐��Q�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��A�d�q�H����y���݂Ȃ�����ɗ��������Ă��ꂵ���ł��B �h�Ƃ�h��ɖ𗧂��������ɍ��ĕ��y����Ηǂ��ł��ˁA���̍���������Q�l�ɂ��Ă���������悤�Ȃg�o���ǂ������m��܂���H�l���Č��܂��I���邩���m��܂������̃A�C�f�A�Ɍq���邩���m��܂���ˁB �F�X�Ƃ��肪�Ƃ��������܂����B ���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AC12V(50/60Hz)10W�d�l�̕����|���v��DC12V�ŋ쓮�������̂ł����A�^�������g�ŋ쓮�ł����H�����������������B ����A��`�g�œ��삳���Ă��܂����A�ǂ�������d�͂��傫���A���[�^�[�̐U�����傫���]��ǂ���ԂłȂ��悤�ł��B�K���ȃ��[�^�[�쓮�pIC��T���Ă݂��̂ł��������悤�ł��B��������AC12V�d�l�̃��[�^�[����ʓI�łȂ��悤�ł����ADC�d�l�̃|���v�Ɋr�חy���ɒ������̂悤�ł��B�i���܂ł�AC�A�_�v�^�[�ŋ쓮�A����̓\�[���[�ƘA�����������j ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@AC���[�^�[�́ADC���[�^�[�̂悤�ȃu���V�E�R�~���e�[�^���̋@�B�I�ȐڐG�E���C���i�������̂ŁA�@�B�I�ɂ͎��̖��ՈȊO�ɕ��i�ړ_�����Ղ��Ȃ��̂��������ŗ��_�ł��B �@���̔��ʁu�𗬂�^���Ȃ��Ɖ��Ȃ��v�̂Ńo�b�e���[���ł͒��ډ��Ƃ͂ł����A���ʂ�AC100V�̃R���Z���g�Ȃǂ���𗬓d��������@��Ŏg�p����܂��B �@��������AC���[�^�[��DC�d���ʼn��Ƃ���Ɓu�������𗬂ɕϊ�����C���o�[�^�v���K�v�ɂȂ�A�A�i���O�E�f�W�^�������ŐF�X�ȃC���o�[�^��H������܂��B �@���ɐ��삳��Ă����`�g�ŋ쓮����Ƃ������́A�f�W�^�����U��H��50Hz�̏��p���g���Ŕ��U�����H������āA����Łu�g�u���b�W�v�Ȃǂ̃��[�^�[�쓮��H��DC�d���̋ɐ����ւ����[����������Ďg���Ă���������̂��Ǝv���܂��B �@�m���ɋ�`�g�ł�AC���[�^�[�͉�邩������܂��A�d����0�`100%�̊ԂŐ����g�ŕω�����AC�d���ɂ���ׂ�ƁA���100%�̓d���𗬂����Ƃ����`�g�ł͖��ʂɓd�͂����Ղ���ł��傤���A���̃f�W�^���p���X�̐�ւ�_�ł����Ȃ�ɐ����]�����Ă��܂��̂��m�C�Y�E�U���̌��ɂȂ�܂��B �@�����Ń��[�^�[�E�R�C���Ȃǂ��g����AC�@���Â��Ɏg���A�܂��Ȃ�ׂ��������g�p����ɂ̓C���o�[�^�̏o�͔g�`��ʏ�̌𗬂Ɠ������u�����g(SIN�g)�v�ŕω�����悤�ɂ��Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�Ƃ��낪�A�C���o�[�^�̔g�`�𐳌��g�ŕω��������H�͂����ȒP�ɂ䂭���̂ł͂Ȃ��A�����Ă��̃C���o�[�^�́u�[�������g�v�Ƃ����f�W�^���M���̋�`�g�������g���������̂����܂����Ă����̂���ʓI�ł��B 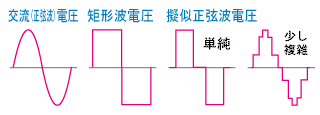 �@�����������G�ȉ�H���g���[�������g�ł͐}�̂悤�ɋ�`�g�̃f�W�^���M�������Ԏ��Ő��i�K�ɕ����āA���ꂼ��ɐ����g�ɋ߂��d�����������邱�ƂŁA�f�W�^���g�`�ł��������g�ɋ߂��d���̕ω�����悤�ɂ������̂ł��B �@�悭��������s�̋@��ł́A�Ԃ�DC12V����AC100V�����C���o�[�^�Ȃǂł��̋Z�p�͐g�߂Ɏg���Ă��āA���������@��ł͏o�������͒P���ȋ[�������g(����S�R�����g�ɋ߂��͖����ł����c)����A�ŋ߂̐��i�ł̓}�C�R�������10�`16�i�K���x�̒i�K�����������Ȃ芊�炩�Ȃ��̂܂ł���悤�ł��B �@�������A�o�v�l�Z�p�Ȃǂ��g���������Ƃ��������g���o�͂ł���C���o�[�^����������Ă��܂��ˁB �@����ł�PIC�}�C�R���Ȃǂō���Ă��܂����Ȃ芊�炩�ȕ������܂��������͂��������R�[�i�[�ł͂���܂���̂ŁA��͂���肪�e�Ղȃf�W�^�����i�Ȃǂ��g���Đ��삷����j�ōl���܂��B �@�P�ɋ�`�g��100%�̓d���d�����ւ��邽���ł͂Ȃ��A������ƍ������g�`�̓d�����������ɂ��𗬓d��������̂ɏo�͓d�������R�ɕω����������g�����W�X�^��FET�łł����u���[�^�[�h���C�o�v���K�v�ł��B �@�������o���o���Ƀg�����W�X�^�Ȃǂ��W�߂č�邱�Ƃ��ł��܂����A���������p�r�p�̕��i�������Ă��܂��̂ł�����g�����ɂ��܂��B �@�E�E�E�Ƃ������A���������֗��ȃ��[�^�[�h���C�o�����݂���Ƃ����O��ʼn�H��v���܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �N���b�N���U��H �@�����̂悤���^�C�}�[IC 555�Ŕ��U��H�����܂��B �@�ړI�̔��U���g����1000Hz�܂���1200Hz�ł��B �@����͍ŏI�I�Ȍ𗬂̏o�͎��g���ł���50Hz�܂���60Hz��20�{�̎��g���ł��B(��ŕ������Ďg���̂�) �@VR1����900�`1600Hz[�o�͖͂�45Hz�`80Hz]�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@VR1�𒆉��ɂ��Ă����ƁA��������1100Hz�ŏo�͂�55Hz�ƂȂ�܂��̂ŁA�ʏ��50Hz/60Hz�p���[�^�[�Ȃ��薳�����͂��ł��B �� �[�������g������H �@����̉�H���S�����ł��I�i�O�O�G �@10�i�f�R�[�_���J�E���^�[IC 4017B���g�p���āA�����o�͂���ւ�@�\���u�V�[�P���X��H�v�Ƃ��Ďg���A�e�o�͒[�q�ɒ�R�ŕ��������H(D/A�R���o�[�^)���q���ł��̒�R�l���o�͒[�q���Ƃɕς��邱�ƂŎ��Ԏ��ɑ��ď����d�����ς�u�[�������g�v�����܂��B �@4017�̏o�͂�10�i�K�ł��̂ŁA�����g�̔�����(�Е��̔g)�����Ԏ���10���������e���_�̓d�������ꂼ��̏o�̓s���Ɋ��蓖�Ă܂��B �@�A�������g�͑O���ƌ㔼�͓����`�Ȃ̂Œ�R�Ȃǂ̉�H�͑O�����������Ԃ����A�㔼�͊��ɑO���ō���Ă��铯���d��������H�ɐڑ����܂��B���̍ۂɑO���M���ƌ㔼�M���̓_�C�I�[�hOR�����܂��B(�łȂ���H�o�͂�L��͂��V���[�g���܂����) �@���Ă����4017���O�`�X�܂ŃJ�E���g����ԂɁA���������g�ɑ�������d�������邱�Ƃ��ł��A���̓d������Ƀ��[�^�[�ɗ^�����[�������g���`��鐧��d���ɂȂ�܂��B �� �ϕ���H �@���̂܂�4017�ō�����[�������g�Ō𗬓d��������Ă��A���Ԃ�10�����ō���Ă���̂ł��Ȃ�𗬔g�`�ɋ߂����ɂȂ��Ă��ă��[�^�[�����肷��̂ɂ͂��イ�Ԃ�ł��B �@����A������ƍ������Ă��イ�Ԃ��邩������܂���B �@�ł��A���̊K�i��̃f�W�^���M���Ō𗬂����̂܂܍��̂ł͂Ȃ��A�X�ɂ�����ƔP���Ă������������g�ɋ߂��g�`�ɂ��Ă����܂��傤�B 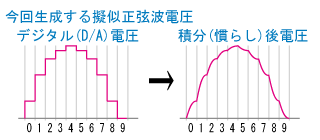 �@�����Ȑ����g�ɂȂ�͂��͂���܂��A�J�N�J�N�����Ă��Ȃ芊�炩�Ȑ����g�ɋ߂��Ȃ�܂��B �@���̐M���ŖړI�̌𗬂̓d���ω������܂��B �� �ɐ����]�M��������H �@��́u�[�������g������H�v�ō�����[�������g�͔����������ł��B �@�[�������g������H����͔������̎R�`�d���̔g�`���J��Ԃ��o�͂���邾���ł��B �@�𗬂̓v���X���ƃ}�C�i�X���ɎR�^���d�������݂ɏo�͂�������̂ł�����A�o�͂͂����������ɓd�����o��悤�ɂ���K�v������܂��B �@������4017��CARRY OUT�M��(���オ��M��)���g�p���āA�u�P��̎R���I������v���Ƃ�m�邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA���̈��̎R���Ƃ��o�͂̈ʑ��]��������H��p�ӂ��܂��B �@D-FF(�c�E�t���b�v�t���b�v)IC�ł���4013B���g�p���܂��B �@4013�ɂQ�����Ă��邤���̂P��D-FF���u���]FF(T-FF)�v�Ƃ��Ďg�p���A���̓��̓p���X(4017�����CO�M��)���Ƃ�D-FF�̏o�͂����]����悤�ɂ��܂��B �@D-FF�ɂ͏o�̓s�����u���E�o��(Q)�v�Ɓu���]�o��(^Q)�v�̂Q����AQ��H�̏ꍇ��^Q��L�AQ��L�̏ꍇ��^Q��H�Ƃ��ꂼ�ꔽ�̏o�͏�ԂɂȂ�܂��̂ŁA������u�𗬏o�͂̃v���X�E�}�C�i�X���ւ����v�M���Ƃ��Ďg�p���܂��B �� ���[�^�[�h���C�o��H �@��̉�H�ō�����u�[�������g�M���v�u�ʑ�����M���v����A���ۂɃ��[�^�[�ɗ^����𗬓d�������܂��B �@�����Ŏg���̂� TA7291P �Ƃ������[�^�[�h���C�o�ł��B �@ �� �L���f�ڎ�(2010�N)�ɂ͗��ʍɂ�����ł������A
2019�N���݂ł��������~�i�̂��ߓ��荢�������܂���B ��ւɎg����H �� TA7288P �@���[�^�[�𐳓]�E���]�̗������ɉׂ��g�u���b�W��H�������Ă��āA�����d���Ń��[�^�[�ɐ������E�t�����̗����̓d���������鐧�䂪�ł��܂��B (�ق��ɍ���͎g���܂��u���[�L����Ƃ�) �@�����ĕ��ʂ̃��[�^�[�h���C�o�ɂ͂��܂薳��TA7291�ɂ������ʂȋ@�\�Ƃ��āA�u�d������s���ɗ^����d���ŁA�o�͓d���𐧌䂷�邱�Ƃ��ł����v�Ƃ����ϓd���@�\�������Ă��܂��B �@�g�u���b�W���̃��[�^�[�h���C�o�͕��ʂ̓}�C�R������Ŏg�p���āA���[�^�[�̃X�s�[�h��ς���ꍇ�ɂ͂o�v�l����ȂǂŃp���X���������̂���ʓI�ł��B�g�p���郂�[�^�[������������[�^�[�ł��B �@�ł��A�u�d���̕����𐳁E�t�ɐ�ւ��ł����v�u�d�����A�i���O�Ŏ��R�ɃR���g���[���ł����v�Ƃ����Q�̋@�\������������IC�͍���̖ړI�ł���u�𗬂�����v�Ƃ�����H�ɂ͎��ɂ҂�����Ȃ̂ł��B �@����IC��������Ε����̃p���[�g�����W�X�^�⑼�̕��i�Ō𗬃h���C�o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA����̂��˗��ɂ͊ȒP�ɂ͂������ł��Ȃ������ł��傤�B �@TA7291��Vref�[�q(�o�͓d������p�[�q)�ɂ́u�[�������g�M���v����͂��āA�o�͓d���𐳌��g���ۂ��ς��܂��B �@TA7291��IN1,IN2�[�q(�o�͕�������p�[�q)�ɂ́u�ʑ�����M���v����͂��܂��B �@IN1=H,IN2=L�̏ꍇ�������ɁAIN1=L,IN2=H�̏ꍇ�t�����Ɍ𗬓d�����o��悤�ɂȂ�܂��B �@����TA7291�̕���������͂�IN1��IN2���t�ɂȂ�Q���̐M����K�v�Ƃ��邽�߁A�ʑ�����M���̔����ɂ�4013�̂悤�Ȑ��E���]�o�͂�������FF���ƂĂ��K���Ă����Ƃ����킯�ł��B �@TA7291�͕���(�ʏ�)���ő�1A�܂��̓d���Ŏg�p�ł��܂��B��������AC12V/12W�ȉ��̕���(���[�^�[)���g�p���Ă��������B�s�[�N��2A�ł��̂Ń��[�^�[�N�����̓˓��d���Ȃǂɂ�������x�͑Ή��ł��܂��B �@���x�ی��H�������Ă��܂��̂ňُ�ߔM�����ꍇ�ɂ��ی��H�������ďo�͂��J�b�g���Ă����E�E�E�͂��ł��B �@�o�͓d���̐�����o�v�l�̂悤�ȃp���X����ł͂Ȃ��AVref�[�q�𗘗p�����d������ɂ����ꍇ�A�d���������Ă�����Ԃ�TA7291�����̃g�����W�X�^����R�Ƃ��ē����ēd�����i���ēd����������悤�ɓ����܂��̂ŁATA7291�����̍��̓d�͂�����ĔM�ɕϊ����܂�����A���M���܂��B �@�K���ȑ傫���̕��M�����Ă��Ȃ��ƁATA7291�ɕt���Ă�����M�t�B�������ł͕��M���ǂ����Ȃ���������܂���B �@���M���傫���A�ł����M�Ȃǂ�����̂����E�E�E�Ƃ����ꍇ�ɂ́A�[�������g�̐����̐}�ɍڂ��Ă���u�P���v�^�C�v�̋[�������g�ł��̉�H���쓮������@�ɕύX���邱�Ƃ��\�ł��B 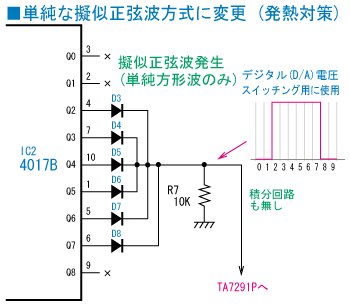 �@TA7291���ł̒�R�͂����킸���ɂȂ�̂Ŕ��M�͏��Ȃ��Ȃ�܂����A��͂�g�`�����\�Ȃ��߂Ƀ��[�^�[�̃m�C�Y��U���Ȃǂ͏����}��������x�ɂȂ�܂��B �@�_�C�I�[�h�ŏo�̓^�C�~���O��I�����镔����ς��āA���������o�͕���Z������Ƃ��A���D�݂ɂ��킹�ĕύX���\�ł��B �@�{���͂��������P���g�`�łg�u���b�W�𐧌䂷��Ȃ�AVref�[�q�ɗ^����d���Ő��䂷��̂ł͂Ȃ��AIN1,IN2�[�q�ɗ^������ݐM�������̎��Ԏ��̒P���g�`�p����M����AND���Ƃ��ė^����̂����U�@�ł����E�E�E�A����̏ꍇ��TA7291���g�p���Ă���̂�Vref�[�q�ł̃R���g���[�����\�ł����A�Ȃɂ��AND��H��IC����lj����Ȃ��Ă������̂ŕ��i���팸�ł��܂��i�O�O�G �� �d����H �@����g�p���Ă���555��4013/4017�͂��̂܂�DC12V�œ��삵�܂��̂ŁA�d�������͕����p�E�m�C�Y�����p�̃R���f���T�݂̂ł��B �@�g�p���郂�[�^�[��AC���[�^�[�Ȃ̂Ńm�C�Y���قƂ�Ǐo���Ȃ��̂Ń��[�^�[�m�C�Y�ł��̉�H����쓮����\���͒Ⴂ�Ǝv���܂��B �@�����m�C�Y�Ō�쓮����ꍇ�͓d�����Ƀm�C�Y�t�B���^�[��lj�����ȂǁA�K�v�ɉ����ĉ��ǂ��Ă��������B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@��������VR1�̈�ӏ������ł��B �@�g�ݗ��ĂɊԈႢ���������VR1�𒆉��ɉĂ����ƁA�o�͂͂�������55Hz�ƂȂ�܂��B �@555�̔��U���g������1KHz�O��ƁA���샂�j�^�[�p��LED�����Ă��l�Ԃ̖ڂŌ��ē_�ł��Ă��邩�ǂ����͐�Ɍ����܂���̂ŁA����m�F�p��LED�Ȃǂ͂��Ă��܂���B �@�𗬏o�͂�LED�����Ă��A��͂�50�`60Hz�ł͓_�ł��Ă���悤�Ɍ����܂���̂ŏo�͂ɂ����Ă��܂���B �@�𗬏o�͂Ƀe�X�^�[���q���ŁA�𗬓d�������W�ő��肵�Ă����ƌ�12V������ł���Α��v�ł��B �@�ŋ߂̃f�W�^���e�X�^�[�ɂ́u���g������@�\�v�����Ă��镨�������̂ŁA���������e�X�^�[�Ōv���555�̃N���b�N���U��A4017��4013�����삵�Ă��邩������ł��܂��B �@����̉�H�͋[�������g������H�Ƃ��Ă͂��Ȃ�{���̐����g�ɋ߂��g�`��������̂̂����ɓ���Ǝv���܂��B �@�ŏ�����A�i���O���U��H�Ő����g������āA�������烂�[�^�[�h���C�o�𑀍�ł���R���g���[����H�����Ƃ������@������܂����A�����܂ł��Ȃ��Ă����萫�̗ǂ��|�s�����[��C-MOS IC���g�����f�W�^����H�ŋ[�������g������Ă����ꂭ�炢�͂ł���Ƃ����P�[�X�Ƃ��čl���Ă݂܂����B ���Ԏ� 2010/4/26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����肪�Ƃ��������܂��B �ȑO�A���ł�TA�V���[�Y���g������������܂����o�C�|�[���̂��ߏ���d�͂��傫���悤�ł����BMOS�\����BD6222HFP��TA7291�ɋ߂��Ǝv���܂����A��։\�ł��傤���H �܂��A�����X�e�b�v�����������ׂ������鎖�͉\�ł��傤���H ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@BD6222HFP�͕֗������ł����A�ߏ��̓X�Ŕ����Ă��Ȃ��̂ł�����ł͎g�������Ƃ�����܂���B �@�f�[�^�V�[�g��������قړ����悤�Ɏg�������ł����APWM�Ńp���[�R���g���[��������̂ƁA�𗬔g�`�̂����Ɏg���̂Ƃł͑����̈Ⴂ������܂�����A���S�ɓ����悤�Ɏg���邩�ǂ�����BD6222HFP���������ł�������ۂɍ���Ă��m���߂��������B �@10�i�K���z���ĕ���\���ׂ�������̂̓��W�b�NIC�ŕ��G�ȉ�H�����Ή\�ł����A��̓I�ɂǂ̒��x�̕���\������]�Ȃ̂ł��傤���H �@�i�ƂĂ��ȒP��4017��������ō���10�i�K�Ƃ͈Ⴂ�A11�i�K�ȏ�ł͕��i�������Ȃ葝���܂����A���ꑊ���̌��ʂ�������Ƃ͎v���Ȃ��̂�10�i�K�ȓ��ɍl���Ă��܂��j ���Ԏ� 2010/4/26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����肪�Ƃ��������܂��B���Ӓv���܂��B �������̉�H�ɂāA��_�����C�ɂȂ�̂��ATA7291��Vref��ς��ă��[�^�[�d�����A�i���O�I�ɕς��Ă��镔���ł��BB���A���v�Ɠ����Ń��X�������Ǝv���܂��B �����̎���̈Ӗ��́A���z�d�r�ŋ쓮������d�͂����炵�����Ӑ}������܂��B�d����ω�������̂ł͂Ȃ��A�p���X�쓮�ʼn��Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��H�ƍl���Ă���܂����B ���[�^�[�pIC�ł͂Ȃ��A�p���[MOS�A���C��MP4212���g���A�n�C�T�C�h�̋쓮��H���s�v�ɂȂ�A�������̉�H�������ς��邾���ŊȒP�ɂł������ɂ��v���܂����c�B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@MP4212�����܂�Ă��̂����E�E�E���������Ƃ������̂ŁA�茳�Ńe�X�g�͂ł��܂���B �@��������{�I�Ȃg�u���b�W�f�q�Ȃ̂ŁA�g�p���@�͊ȒP�ō���̂悤�ȗp�r�ɂ͓K���Ă���Ǝv���܂��B(BD6222HFP�̂悤�ȃn�[�t�s�b�`�ł�����܂���) >�������̉�H�������ς��邾���ŊȒP�ɂł������ɂ��v���܂����c �@�Ƃ����̂́A���Ƀ��W�b�N��H�Ȃǂ��g����MP4212�̋쓮���@�ɂ͎v�������Ă���Ƃ������b�ł�낵���ł��傤���H (�����MP4212�͖�薳�����Ƃ���������) �@MP4212�̐���͂g�u���b�W�̊�{�ł�����A����قǓ���͖����Ǝv���܂��B �@������_�����A�{��H�̈ʑ�����M��(�Q�{)�Ɓu�P���ȋ[�������g�����ɕύX�v�̃f�W�^���p���X�M���g�`��AND���Ƃ���MP4212��FET�̃Q�[�g�ɗ^���邾��(�n�C�T�C�h�ƃ��[�T�C�h�̕������䂪����)�ł͂����܂���ˁB �@�ʑ��M��=�S��L = FET1(6)=L, FET2(8)=L, FET3(2)=L, FET4(4)=L �@��������ƃp���X��OFF�ŋ[���𗬔g�`��0V�ɂ��������Ԃɂ͂g�u���b�W�̋@�\�́u�u���[�L�v��������A0V���Ԃ̓��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���Ƃ�ł��Ȃ����[�^�[�쓮�����ɂȂ�܂��B �@MP4212���g�p����Ȃ� 0V = FET1(6)=H, FET2(8)=H, FET3(2)=L, FET4(4)=L (�SFET�J��) �{ = FET1(6)=L, FET2(8)=H, FET3(2)=L, FET4(4)=H (�d��1��4) �| = FET1(6)=H, FET2(8)=L, FET3(2)=H, FET4(4)=L (�d��2��3) �̂R�̈ʑ����ւ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@0V�ŋx�~���ɂ�H/H/L/L���ʂƂ��A�{���d���ɂ��������ɂ�FET1��FET4�̐���M���]�A�|���d���ɂ��������ɂ�FET2��FET3�̐���M���]�B �@�Ƃ܂����������g�u���b�W�̕����]���Ƌx�~���ł����b��H�����W�b�NIC�őg�ނ����Ȃ̂ŁA���̒��x�̃��W�b�N��H�̒lj��v���u�ȒP�ɂł������v�ƍl�����Ă���̂ł�������v�ł��ˁB �@�������̂悤�ɂg�u���b�W�𐳍U�@�Ő��䂷��ꍇ�A�u�n�C�T�C�h�̋쓮��H���s�v�ɂȂ��v�Ƃ������ɂ͂Ȃ炸�A�n�C�T�C�h�E���[�T�C�h���ɍ��������悤�ȕ�������̂��߂ɌʂɐM����^���Ă��K�v������̂ŁE�E�E�n�C�T�C�h���𐧌䂵�Ȃ��Ă������Ƃ������z�͂ǂ�������H�����l���Ȃ̂�������Ƃ킩��܂���B (1) 4013����o�͂����ʑ��M��[�P]�ƁA4017�Łu�P���ȋ[�������g�����ɕύX�v�����ŏo�͂����p���X������M��[�Q]��AND���Ƃ�A���ۂɓd���o�͂�����{���ԂƁ|���Ԃɂ���H�ɂȂ�ON���Ԉʑ�����M��[�R]�����B (2) ����ON���Ԉʑ�����M��[�R]����A�g�u���b�W�̂S��FET�𐳂����쓮���邽�߂̃��W�b�N�M��[�S]�����B �@�Ƃ����菇�ōl�����Ă͂���Ǝv���܂��̂ŁA���䃍�W�b�N���Ԉ��Ȃ��悤�ɐ��삵�Ă݂Ă��������B �@�u�P���ȋ[�������g�����ɕύX�v�����ł��Ƃ��܂�U����Ȃǂɂ͂Ȃ�Ȃ���������܂��A���̂�����̓_�C�I�[�h�őI�����Ă���o�̓p���X����ς��Ă݂�Ȃǂ��āA�ł������Â��ł����[�^�[�̃p���[�����܂茸��Ȃ��_��T���o���̂��y������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B(���̂����肪����̑�햡�I) �@�~�������A�O���̉�H��SIN�g�̃A�i���O�g�`������āA�u�d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����)�v�Ȃǂł��Љ�Ă���PWM�g�`�̐�����H��ʂ���SIN�g��PWM�p���X�ɕϊ����A�����AND������MP4212�ł�BD6222HFP�Ɠ����悤��PWM��SIN�g�`�ł̌𗬐M�������܂��ˁB �@PWM���g����KHz�`���\KHz�ɏグ�Ă����܂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�܂��A��͂�d����PWM�Ő��䂷��(�܂��߂�SIN�g�`���o��)���@�͂�����߂āA555��4017�Łu�P���ȋ[�������g�����ɕύX�v�̂悤�ȃf�W�^���p���X�����ꍇ�A������I�y�A���v��PWM�g�`������H��100/120Hz���x�ɔ��U�����Ă��̎������ł�ON���Ԃ�VR�ŃA�i���O�I�ɕω���������悤�ȉ�H�ɂ���A��ɏ������悤�Ƀp���X���߂��ă��[�^�[�ɍœK�ɍ��킹��̂Ƀ_�C�I�[�h�̑g�ݍ��킹�ȂύX���Ȃ��Ă��AVR�������ŏo�̓f���[�e�B������R�ɒ��߂ł��܂�����A�\�[���[�d������̓d���l�ƃ��[�^�[�p���[������ׂȂ���VR���Ă��œK�ȃ��[�^�[�쓮�䂪������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�������p���X�쓮�ł�����A�C�ɂ���Ă��郂�[�^�[�h���C�o�ł̔M�����Ȃǂ�����܂���B �@�ȂǂȂǁA��H�̑g�ݍ��킹�≞�p�͍l������肪����܂���B �@�ʂɍ��������H�}�̂܂܍����K�v�͂ǂ��ɂ�����܂���B �@���[�^�[�h���C�o�p�f�q�ȂǁA�ŋ߂̐��i�ŗǂ������Ȃ��̂�T���Ă����ĉ�H�}�����l���ɂȂ��Ă���悤�ł��̂ŁA�����������ŏo�Ă���ߋ��̉�H�}���Q�l�ɁA��育�����̖ړI�ɍ��������̂�����肭�������B ���Ԏ� 2010/4/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@4/28�̂��Ԏ����f�ڂ��Ă���A������Y�݂܂����B �@���̌��ʁA���肪�P����AC���[�^�[�ł���t�N�d�͂�d�͔͂������Ȃ��ƒf�肷��A���[�^�[�h���C�o���u���[�L��������Ă����[�^�[�ɂ͒�~�͔͂������Ȃ��̂ŁA�ʓ|�ȃu���[�L�����p���W�b�N��H��g�܂Ȃ��Ă��u���[�L�L��ō���āA�n�C�T�C�h���̐�������[�T�C�h���Ɠ��������ɂ��Ă���Ă������̂ł͂Ȃ����ƌ��_�Â��܂����B �@�茳�ɂ����������[�^�[�h���C�o��g�u���b�W�͂���܂��A��������12V��AC���[�^�[���������킹�Ă��Ȃ��̂ŁA����������H�ɂ����ꍇ�Ƀ��[�^�[�����ǂ̂悤�ȋ����ɂȂ�̂�����ł��܂���B �@�����l����������AC���[�^�[�̓����܂őS�ďn���̏�Łu�ȒP�ɂł������v�Ƌ��Ă����̂ł���A�������̏o�開�ł͂���܂���ˁB �@���ɉ�H���j�����l���̏�ł̂������Ƃ����v���܂��̂ŁA���Ђ��̉�H�Ő��삳��āA�ł��܂����烂�[�^�[�̋����Ȃǎ��ۂ̑��茋�ʂ��������肦��ƕ��ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/4/29
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���낢��Ɛe�g�ɍl���Ē������肪�Ƃ��������܂��B �ʑ��̔��]����2�̋�`�g��TLP250��MP4212�Ō��݂�AC���[�^�[���쓮���Ă���܂��B����MP4212���̔��M�������A�P�Ƀ��[�^�[�̐U���Ə���d�͂������̂��C�ɂȂ��Ă��܂��B�u���[�L�̘b�͗]��l���Ȃ��Ƃ��ǂ��悤�ȋC�����܂��B �A�x���ɋ��́u�O���̉�H��SIN�g�̃A�i���O�g�`������āA�u�d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����)�v��PWM�g�`�̐�����H��ʂ���SIN�g��PWM�p���X�ɕϊ����A�����AND�����PWM��SIN�g�`�ł̌𗬐M�������BPWM���g�����グ�Ă��B�v���Q�l�ɂč��܂����Ƃ���A��肭���삵�Ă���܂��B�i���X��H�����G�ł������j���[�^�[�����炩�ɓ����Ă���悤�ł��B ���낢��ƃA�h�o�C�X�������肪�Ƃ��������܂����B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@SIN��PWM�̕ϊ���H���쐬���Ď����ꂽ�̂ł��ˁB �@����ł��܂������Ă���Ȃ�(���쌴���̎����͑��v�������Ƃ�������)�APWM����̕����͎��삵�Ȃ��Ă�BD6222HFP���g���Ε��i���������ėǂ������ł��ˁB �@�����e�X�g�̌��ʂ����������������܂��Ė{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@���i���������Ȃ�_�́A�����̉�H�ō��Ȃ�A�ʑ������PWM�g�`�̔�������PIC�}�C�R���Ȃǂ��g���ăv���O�����ŏ�������AIC��ōς݂܂��ˁB �@����PIC�Ȃǂ̊J�������������ł�����A������ꂽ�n�[�h�E�F�A���}�C�R���ō쐬���Ă݂���̂��ʔ����ł��ˁB ���Ԏ� 2010/5/7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�����ԗp�̂d�k�������[�^�[�p�l���ɂ��Ăł��B �C���o�[�^�[�̂c�b�P�Q�u�d�����͂��Q�r�c�̂s�q�Ő��䂵�Ă��܂��B ���[�������v��������`�Ɠ_���M�����Q�r�`�̂s�q�ŏE���āA�d�k�p�l��������`�Ə�����Ƃ���܂ł͏o���Ă���܂��B ����A�G���W���X�^�[�g���̃C�x���g�Ƃ��āA�Q�b���x�ŏ�������t�������܂ł���`�Ɠ_�������āA�܂��A����`�Ə������������Ǝv���Ă��܂��B �R���f���T�[�ƒ�R�̉�H�ł́A�p�b�Ɠ_���Ă��܂��悤�ł��B PWM��H�͂T�T�T�̂h�b���ō��邱�Ƃ͔������̂ł����A�ǂ̂悤�ȉ�H�ɂ������`�Ɠ_�������āA�܂��A����`�Ə���������PWM��H���o����ł��傤���H ���w���̒��A��낵�����肢�������܂��B �q�����e�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[��AEL�p�C���o�[�^�𑼂̃����v�́u����`�v�d������A��������̂ɂǂ����ăg�����W�X�^���K�v�Ȃ̂��悭�킩��܂��A����łb�q��H�ł͈�u�œ_����������Ă��܂��̂́A�g�����W�X�^�̑�����p�łb�q�̓d���E�d���̕ω��̂��������ꕔ�̋��E�_��ʂ鎞�ԂɃT�N�b�Ə�Ԃ��ς邾���ł��傤�B�����������Ƃ������ɂ���E�E�E�ƌ����Ă��E�E�E�E���ꂾ���ł͂Q�b�œ_�����Ă܂��Q�b�ŏ����Ƃ͂䂫�܂���ˁB �@�ԂɌ�������Ă���u����`�v�Ə����郉���v�ƌq���ŁA����łd�k�p�l��������`�Ɩ��邳���ς�̂ł���A�Ԃ̂���`����͂o�v�l�ōs���Ă���̂ł��傤�ˁB�d�������ł͂b�q���g�����ꍇ�Ɠ����œˑR�p�b�Ə����Ă��܂��ł��悤�B �@�^�C�}�[IC 555�ł�PWM(PPM)����Ȃǂ͂ł��܂���(�ߋ��ɉ�H�}���ڂ��Ă��܂�)�A555�͉�H���̔��Œ��R��{�����[���Ŗ��邳�߂���ɂ͎g���܂����A�O������̐M���Ŗ��邳��ς���ɂ͖ʓ|�ȉ�H��F�X�ƒlj����Ă��Ȃ�Ȃ�Ȃ��̂�(555��H���̂�PPM��H�Ƃ��č��)�A����̂���]�̂悤�Ɏ��ԂŎ����I�ɕω�������悤�Ȍ����ł͂��܂�g���܂���B �@�I�y�A���v��PWM�����H��^�C�}�[��H�����ΖړI�͒B���ł��܂����A����̖ړI�̉�H�ł͎g��IC��������ōςނ̂őg�ݗ��ĂȂǂ��y�`��(����)�ł��B �@�Ȃ�ׂ��g�����i�͏��Ȃ����āA������y�ɂ��܂��傤�B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �^�C�}�[��H �@�d��ON����[�d�����b�q��H(�ϕ���H)�̃R���f���T(C2)�ɏ[�d�����d�����I�y�A���vLM324�ň��d��(����͓d���d����1/2)�Ɣ�r���āA���̓d���ɒB����܂ł̎��Ԃ��v��^�C�}�[��H���쐬���܂��B �@C2�̓d����0V����1/2Vcc�܂ŏオ��ԁA�o�͂�H���x���ɂȂ�A��̒x���p�̐ϕ���H�̃R���f���T(C3)���[�d���܂��B �@C2�̓d����1/2Vcc�ɒB������A�o�͂�L���x���ɂȂ�A��̒x���p�̐ϕ���H�̃R���f���T(C3)�����d���܂��B �@C2�̓d���͍ŏI�I�ɂ�Vcc�̓d���܂ŏ[�d����܂��B��r���Ă���1/2Vcc��肸���ƍ����ł����A����͂��イ�Ԃ̂���d���ɂ��邱�Ƃœd���̕ϓ���m�C�Y�Ȃǂɂ���쓮��h�~���邽�߂ł��B �@VR1�ŏ[�d�d���߂ł��A�^�C�}�[���Ԃ���P�`�T�b�ł��D���Ȃ悤�ɒ��߂ł��܂��B �@�������A����́u����`�v�Ɠ_�����鎞��(�ω�������ׂ̎���)�ł͂���܂���B �@�u����`�v�Ɠ_�����鎞�Ԃ͌�q�̒x����H�̂ق��ō쐬���܂��B �@VR1�Œ��߂ł��鎞�Ԃ́u����`�Ɠ_�����鎞�ԁv�v���X�u���̌㎞�Ԃ������Ă���`�Ə������͂��߂�܂ł̎����v�̍��v���Ԃł��B �@VR1�Őݒ肵�����ԓ��Ɂu����`�v�Ɠ_������ω����Ԃ������Ȃ��ꍇ�A�t�������܂ł䂩���ɓr���ł���`�ƈÂ��Ȃ�ꍇ������܂��B �� �x��(����`)��H �@���ۂɂ���`�Ɩ��邳��ω�������M�������̂͂��̕����ł��B �@�^�C�}�[��H�̃I�y�A���v�̓���ŏ������悤�ɁAC3�͓d��ON�Ɠ����ɏ[�d���J�n����A�^�C�}�[��ɂȂ�ƕ��d���J�n����܂��B �@���̕ω����鑬�x(����)��VR2�ʼnςł��A��O�`�T�b�̊ԂŐݒ�\�ł��B �@�����x������(����`����)���T�b�ɐݒ肵�āA�^�C�}�[���Ԃ��Q�b�ɂ�����A�T�b�������Ė��邭�Ȃ�O�ɂQ�b�ڂňÂ��Ȃ�n�߂܂����璍�ӂ��K�v�ł��B �@�^�C�}�[���Q�b�E�x�����Ԃ��Q�b�Ȃǂقړ������Ԃ��A�^�C�}�[���T�b�E�x�����Ԃ��Q�b�ȂǕK���^�C�}�[���Ԃ̂ق���x�����Ԃ�蒷���ݒ肵�Ă����Ȃ��ƁA�t�������������邭�Ȃ�܂���B �@�^�C�}�[���Ԃƒx�����Ԃ����ꂼ��ʁX�ɒ����ł���悤�ȉ�H�ɂ��Ă���̂́E�E�E�E���삳���l�̂��D�݂ŐF�X�Ǝ��Ԃ�䗦�����߂ł��Ȃ��ƁA��ӂɌ��߂Ă��܂��Ƃ�������̕ύX�E���p�E�����͖ʓ|�ɂȂ邩��ł��B �� �o�v�l�����H �@�x����H�̃R���f���T(C3)�̓d���ŁA�o�v�l�̃f���[�e�B����R���g���[�����܂��B �@�O�p�g������H�ō������1KHz�`1.5KHz���x�̎O�p�g�ƁA�R���f���T(C3)�̓d�����r���ăR���f���T(C3)�̓d���̂ق��������ꍇ�͏o�͂�H�ɁA�����łȂ��ꍇ��L�ɂ��鎖�Ŏ��g���͈��Ńf���[�e�B�䂪�R���f���T(C3)�̓d���ɂ��ω�����o�v�l�g�`�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�o�v�l���g���͌Œ�ł��B(�ς��Ă��l�Ԃ̖ڂɌ����Ȃ�����E�E�E) �� �o�͉�H �@���������o�v�l�M���Ńp���[MOS-FET(2SK2232)���R���g���[�����āA�k�d�c�E�d���Ȃǂ̃����v������`�Ɠ_������������܂��B �@�o�͂�GND�ɗ��Ƃ��u�}�C�i�X�R���g���[���v�ł��B �@���[�������v�ȂǂƓ����ł�����A���̏o�͂����[�������v���œ��삵�Ă���@��ɂȂ��ł����̋@��̌��ʂ��R���g���[���ł��܂��B �� �d����H �@LM324��3�`32V�͈̔͂Ŏg�p�ł��܂�����A�Ԃ�12V�d��(10�`15V)�Ŗ�薳�����삵�܂��B �@���ɎO�[�q���M�����[�^�Ȃǂ����č~�������d����p�ӂ��Ȃ��Ă����v�ł��B �@�����Ԃ̒��ɂ������m�C�Y���������쓮����悤�ł�����A�����̃m�C�Y��͕K�v��������܂���B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@��H�}�Ƃ���ɊԈႢ�������g�ݗ��Ă���AVR1��VR2�����ꂼ��^���炢�ɒ��߂��ēd��(12V)��ڑ����܂��B �@���̍ۂ܂��o�͂ɂd�k�Ȃǂ͌q���Ȃ��ł����ł��A��݂̂̃e�X�g�ł��B �@�^�C�}�[�����\��LED1���_�����A�قړ�����LED2������`�Ɠ_�����͂��߂܂��B �@LED2��2�`3�b�Ńt�������ɂȂ�܂��B �@�J�n����T�b�قǂ����LED1���������ALED2������`�ƈÂ��Ȃ�͂��߁A��͂�2�`3�b�ł������������܂��B �@���̊m�F���ł��AVR1���^�C�}�[���Ԃ��AVR2������[�ƕω����鎞�Ԃ��ς��Ί����ł��B �@���A�d�����ƃ^�C�}�[�̓��Z�b�g����܂����A�^�C�}�[�p�Ȃǂ̃R���f���T�̕��d�ׂ̈Ɋ��S�Ƀ��Z�b�g�����܂Ő��b�`���\�b������܂��B �@���ۂɎԂ̒���ACC�d���ȂǂɌq�����ꍇ�͑���ACC�d���ɐڑ�����Ă���@��Ȃǂ��d��OFF�Ɠ����ɓd���z���̓d���������Ă����̂ŁA���̉�H�̃��Z�b�g������(�قڈ�u�ōς�)�ł��B �@���̊�P�̂�DC12V�d�������q���Ńe�X�g������ꍇ�ɂ́A�d������Ă������ɂ̓R���f���T�����d���ꂸ�A���\�b�ȓ��Ɏ��ɓd������ꂽ���ɂ̓^�C�}�[���Ԃ������Z���Ȃ�ȂǁA�������͎��ԂɌ덷��������ꍇ������܂��B �@���ꂪ���ȏꍇ�ɂ́A�e�X�g���͂��̊�ƕ���ɉ���12V�̓d���Ȃǂ��q���œd�����ꂽ���ɃR���f���T�̓d��������Ă����悤�ɂ��Ă݂Ă��������B �@��P�̂Ẵe�X�g���I������A�o�͂Ɏ��ۂ̂k�d�c�����v�E�d���Ȃǂ��q����LED2�Ƃقړ������Ė��邳���ω�����͂��ł��B �@�d���Ȃǂ��_�����Ȃ��ꍇ��A�_�������ςȂ��ɂȂ�ꍇ�̓p���[MOS FET�܂��ׂĂ��������B �� �d�k�̃C���o�[�^�̏ꍇ �@�d�k�p�l���������鍂�d����������C���o�[�^�͂��ꎩ�̂����U��H�ɂȂ��Ă���ׂɁA�^����d�����o�v�l�Ő��䂵�Ă����Ғʂ�̖��邳���߂��ł��Ȃ����Ƃ��l�����܂��B �@�ꉞ�A�ԂɌ�������Ă��邶��`�ƈÂ��Ȃ��H�Ɍq���łd�k������`�Ə����Ă���悤�Ȃ̂ő������̉�H���q���ł�����͂���Ǝv���܂����A�d�k�̌����������̂ł�����ł̓e�X�g���ł��܂���B (�ʏ�̓d����k�d�c�ł̓e�X�g�����Ă��܂�) �@�Ђƌ��ɂd�k�̃C���o�[�^�ƌ����Ă���H�̐v�E���ۂ̓���͎��G���Ȃ̂ŁA�����ɂȂ��ł݂Ȃ��Ɩ��邳���߂ł��邩�͊m��ł��܂���̂ŁA�\�߂��������������B ���Ԏ� 2010/4/25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
����[�A�f�������Əڂ�����H�������肪�Ƃ��������܂����B PWM��H���Ăo�h�b�Ńv���O�����Ƃ��~������������I�ƁA�v���Ă��܂������A�k�l�R�Q�S�A�P�ł�����Ȏ��܂ŏo�����Ⴄ��ł��ˁB�����ƁA���G�ȉ�H�ɂȂ��Ă��܂��̂��Ȃ��H�Ƒz�����Ă��܂����B ���̉�H�ւ̎���ł����A �P�DPWM�M���͂k�l�R�Q�S�̂V�ԃs���ցA�{�P�Q�u�ƂO�u�̃p���X�M���B �Q�D�Q�r�j�Q�Q�R�Q�͕��M�����������肷��c�b�Q�T�`�܂ŃR���g���[���ł���B �Ƃ́A�����ł�낵���ł��傤���H �������i���B���ăe�X�g���Ă݂����Ǝv���܂��B �d�k���[�^�[��A��������̂ɂs�q���g���Ă��邩�H�ł����A ���[�������v�ł͂��ׂẴh�A�̊J�ɔ������Ă��܂��܂��B�^�]�Ȃ̃h�A�I�[�v�������ɘA��������ɁA�L�[�C���~�ɖڂ�t�����̂ł����A����͏����ȓ��������ł����B �ŋ߂̎����Ԃł̓L�[�C���~���̃W���b�Ɠ_����H�����ׂĎԍڃR���s���[�^�[�Ɍq�����Ă��邻���ŁA�ւ��Ȃ��Ƃ�����ƁA�����~�I�[�_�[�ŎԍڃR���s���[�^�[�����߉ނɂȂ�܂��B �L�[�C���~�łǂꂾ���d�������邩�H����Ȃ����߁A�ԗ��̊�����H�Ƀ_���[�W�������Ȃ��悤�ɁA�o���邾�����Ȃ��d���ŐM������낤�ƍl�������߂ł��B �q�����e�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@PWM�M����LM324��(7)�s������o�Ă��܂��B�U���͖�GND-Vcc�Ԃ�12V�U���Ă��܂��B �@2SK2232�������ōő�25A(�p���X�ōő�100A)�A�A������(���M)��35W�ȓ��Ŏg�p�����ꍇ�ł��B �@�����PWM�ł̃X�C�b�`���O�ł�ON���ɂ�D-S�ԓd����1V�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ͂���܂��APWN�ŃR���g���[�����Ă���Ԃ�ON/OFF�̐�ւ����ɔ��ɒZ�����Ԃ�0V�`12V�̒��ԏ�ԂɂȂ�̂ł��̊Ԃ͔��M���܂��B �@���̓_���l�����Ă����M�ʂ�35W���z���邱�Ƃ͖����͂��ł��̂ŁA�K�X���M���Ă��Β�i�����ς��܂ł͈͓̔��ł���Ύg�p�ł��܂��B �@�ƁA�����Ƃ����ƃ��[�J�[�Őv����Ă��������u�����̂┭�M���镔�i�́A��i��1/2�ȉ��Ŏg�p����̂��܂Ƃ��ȍl�����A��i�����ς��܂Ŏg����ƍl����̂͑f�l�̍l���v�Ƃ����˂����݂�����ł��傤�B �@�ł��̂ŁA���Ɛ��i(�Ɠd���i)�̂悤�Ɍ̏Ⴕ���ꍇ�̃��[�J�[�ӔC��������A���\�N�͉�ꂸ�ɓ������u�Ƃ��Đ��삷��ꍇ�ɂ͒�i�̔����ȉ�(12A�ȉ����炢�܂�)�Ŏg�p����悤�ɐS�����Ă��������B �@�Ԃ̃L�[���������琔�b�Ԃ����������āA���ꂪ����̂�������ȓ��A�Ƃ������Ȃ��̉�H�̖ړI�ʂ�̎g�����ł���A�������M���Ă������ɉ���悤�ȉ��x�ɂ͒B���܂���A���M��t���Ă����100�N�ȏ�͎g����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B(�������ɎԂ̂ق��������ɂȂ�Ǝv���܂�) �@�L�[�C���~�͉^�]�Ȃ̃h�A�J�ɂ����A�����Č���̂ł����B �@����͕��ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B �@�L�[�C���~���t���Ă���悤�ȎԂɂ͏�������Ƃ������̂Łi�O�O�G �@�ŋ߂̎Ԃ̓h�A�X�C�b�`���烉���v�ɒ�������Ă��镨�������āA�����̃R���s���[�^���j�b�g�ɂ݂�Ȍq����悤�ɂȂ��Ă���Ԏ킪�����Ă���悤�ł��ˁB �@�����܂ł��Ȃ��Ă������Ǝv���̂ł����A�Œቿ�i�т̕��y�Ԏ�ł����[�������v�̂���`�Ə����@�\�Ȃǂ���ʓI�ɂȂ��Ăǂ̎Ԏ�ł����ʂ̃R���s���[�^���j�b�g�ɂ����ق����A���ǂ͗ʎY���ʂň������̂ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2010/4/26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ߔM�h�~�k�d�c���x�v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�k�d�c�R���c�ʌv�̐v���肪�Ƃ��������܂����B �@LM339�̒l�i�ׂ���A�U����łP�O�O�~�I �@���傤�ǂS���炢���\�肾�����̂ł����A���܂�ɂ������̂ŁA���łɉ����w�����悤�Ǝv���A�ē��e�����Ă��������B �@�����̍�Ƌ@�B�ɂ͐����v���t���Ă��܂������A�V���ɕt���Ă��Ȋ��Ȃ̂ł����ɉ��邵�A�����Ĉ����Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA���͖�����Ԃł��B �@�V�����_�[�w�b�h�̏㕔�ɂ́A�W�O�x�ȏ�ɂȂ�ƃ����v���t���V�O�x�ȉ��ɂȂ�Ə�����d�g�݂́A�I�[�o�[�q�[�g�x���̉��x�Z���T�[���t���Ă��܂��B���V���ō�Ƃ̂Ƃ��ɂ́A���܂Ɍx�������v���t���Ă��܂��A��Ƃ����f���Ă��܂��܂��B �@�����ŁA�W�O�x�_�ɁA�R�`�S�̂k�d�c�Œi�K�I�ɉ��x�㏸��m�点�Ă����ȒP�ȉ�H�͂ł��Ȃ��ł��傤���H�@���m�ȉ��x�\���������Ă��A���������̉��x��Ԃ��킩��A�d���̔z����y�[�X���R���g�[���ł���悤�ɂȂ�܂��B �@���Z�����Ǝv���܂�����낵�����肢���܂��B ���������� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u���ł��v�Ƃ������ɂ͂�����ƐS�Ɉ�����������̂�����܂����A�k�d�c�R���c�ʌv�̉�H�ƂقƂ�Ǖς炸�����x�v�͂ł��܂��̂ʼn�H�}�������܂��B �@�R���v�Ɗ�{�͕ς�܂���A������̉�H�ł͏ڂ��������͏ȗ����܂��B (���̉�H�}�͎������i�Ńe�X�g�͍s���Ă��܂���) ���N���b�N����Ɗg��\��
�@����Ă���̂̓Z���T�[�Ɂu�T�[�~�X�^�v���g�p����_�ƁA�e�R���p���[�^�ɂ̓q�X�e���V�X���������邽�߂̃t�B�[�h�o�b�N��R�������Ă��܂��B�@�R���v�ł̓X�C�b�`�̓���Œ�R�l�����������ւ�܂����̂ŁA��r����d���Ƀq�X�e���V�X����������K�v�͂���܂̂���ł������A���x�v�ł̓T�[�~�X�^�̒�R�l�����x�ɂ�胊�j�A�ɕω����܂����A�o�͓d����������胊�j�A�ɕω�����Ԃ�臒l���肬��̍ۂ�LED���ځ`���Ɠ_���܂��͏�������̂ł��ꂪ�C���������Ǝv���邩������܂���B�ł��̂Ńq�X�e���V�X���������ĂȂ�ׂ���������_���E��������悤�ɂ��Ă��܂��B �@�T�[�~�X�^���Β˓d�q�́uJT�T�[�~�X�^�v10K���^�C�v (-50�`90��)���g�p������̂Ƃ��ĉ�H�̒萔���v�Z���Ă��܂��B(�u�Β� 103JT�v�܂��́u103JT-025�v�ȂǂŌ�������ƃl�b�g�ʔ̓X����������o�Ă��܂�) �@�M���Ƃ���ɃT�[�~�X�^��u���K�v������̂ŁA���[�h���́u�ϔM�d���v�Ȃǂ𗘗p���ĔM�Ŕ핢�̃r�j�[�����n���ăV���[�g�����肵�Ȃ��悤�A���イ�Ԃ�ɒ��ӂ��Ă��������B �@�u�f���x���v�͖����ɂ��āA���x���S�i�K��LED�\���Ƃ��Ă��܂��B �@�����������̒��x�̕\��������A�@�B(�̃G���W��)���ߔM����O��60�`70���̊ԂŃy�[�X�𗎂Ƃ��ȂǁA��Ƃ��~�߂Ȃ��悤�ɋC�����邱�Ƃ͂ł���Ǝv���܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@���̉�H�ɂ͒������͂���܂���B �@�g�ݗ��ĂɊԈႢ���Ȃ�������Ɠ��삵�܂��B �@��Ƌ@�B�ɂƂ�����Ɋ��̏�œ���e�X�g������ꍇ�ɂ́A�T�[�~�X�^�Ƀh���C���[�̉����Ă�Ȃǂ��ĉ��M���Ă݂āA���x���オ���LED�������_�����邩�m���߂Ă��������B �@�T�[�~�X�^�̂����ɂT�`10K���̃{�����[�������Œ��R���Ȃ��ŁA�c�}�~���Ē�R�l��ς��Ă��e�X�g�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�T�[�~�X�^�ɑ��А��i�A�܂��͐Β˂̐��i�ł̕ʃV���[�Y�̕��Ȃǂ��g�����ꍇ�A��H�}���̉��x�敪�ł͐�����LED���_�����Ȃ��ꍇ������܂��B �@���А��i�Ȃǂ��g�p�����ꍇ��A���̉�H�}�����x�敪��ς��Ďg�������ȂǁA���̒ʂ�ȊO�̎g���������ꂽ�����́A�������ŕ�����R�l���v�Z����Ȃǂ��Ă���]�̃T�[�~�X�^�E���x�敪�ȂǂɕύX���Ă��g�����������B �@���̉�H�}���k�d�c�R���c�ʌv���I�}�P���x�ɍl�������̂ŁA�u���b�h�{�[�h��Ŏ����삵�ăe�X�g�����Ă��܂��A���܂�d����u���Ă��܂���B���̉�H�}�𗬗p���悤�Ǝv���������Ⴄ�g����������������ǂ��u��R�l���v�Z�� ���܂���v�Ȃǂ̂�����͂��������������B ���Ԏ� 2010/4/23
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 4/24 |
�@�����ALM339�ō���̂́A������܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����B punta �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �k�d�c�R���c�ʌv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�����y�����q�������Ă��������Ă��܂��B �@���́A��Ƌ@�B�̔R���v�����삵�����̂ł��������������B�R���Z���T�[�͖_��ŁA�R�̃t���[�g�X�C�b�`���t���Ă��܂��B�t���[�g����͂Q�{�̐����o�Ă��āA �@�@�@���^���i�R�S���̃t���[�g���n�m�j���ƂP���A �@�@�@�c�ʂ��R/�S�ȉ��i������Q�̃t���[�g���n�m�j���ƂP�O�O���A �@�@�@�����ȉ��i������P�̃t���[�g���n�m�j���ƂR�O�Q���A �@�@�@�P/�S�ȉ��i�R�S���̃t���[�g���n�e�e�j���ƂU�X�Q�� �̒�R�l������܂��B �@�ȒP�ȉ�H���g���k�d�c�Ŏc�ʂ����������̂ł����A�������肦�܂����H �@�d���͎ԂƓ����ŁA�[�d���͂P�R�u�ȏ�ɂȂ�܂��B ���������� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�t���[�g�X�C�b�`�Œ�R���ւ���^�C�v�̉t�ʃZ���T�[(�������������i)�ł��ˁB �@�X�C�b�`���R�����Ă��āA���ꂼ��� �@�@�@�@�ŏ㕔�@�P�O�O�� �@�@�@�@���ԕ��@�Q�O�O�� �@�@�@�@�ʼn����@�R�X�O���@(�S�O�O���͖����̂ŋ߂���) �ƁA��R�l���{�X�ɂȂ�悤�Ȓ�R���t���Ă��āA�t�ʂɂ��O���^100���^300���^700(690)���ɂȂ�悤�Ȑv���Ǝv���܂��B �@�S�X�C�b�`�����������̂P����X�C�b�`OFF���̂Q�����x�̍��͂͐ڐG��R�⑪��덷���ƁB �@����ʼn��炩�̕\�����s���ɂ́A���̒�R�l���v������̂ŁA�d���𗬂��Ăǂ������d���ɂȂ邩�ׂ�����킯�ł��B �@�t���[�g�X�C�b�`������ȓd�C�M����ON/OFF�������[�h�X�C�b�`���g���Ă��܂����A���ɓ�����Ă����R������d���p�̂��̂��g���Ă���ł��傤�B �@�ł��̂ł��������t�ʃZ���T�[�ɂ͑傫�ȓd���𗬂��܂���A���\mA���x�܂ł̏��d���𗬂��Čv�������H�ɂ���K�v������܂��B �@�����ŁA12V(�O��)�̓d������g�p����Ƃ��āA����10mA���炢�̓d���Ōv������ׂ�1K���œd����������Ƃǂ��Ȃ邩�v�Z���܂��B (���̒�R�l�ł����܂����A����ތv�Z���Ă݂�1K���K���Ă���悤�Ȃ̂Łc)
�@12V��1K�����o�R����Ƃ������������ɉt�ʂɉ�������O�u�^�P�u�^�R�u�^�T�u���炢�ŋ��̂��������̓d��������ꂻ���ł��B �@�����������̂����d����������Ƃ������Ƃ́A���ʂɎg��臒l�����̂����d���A0.5V�^2V�^4V���炢�Őv�ł���̂łƂĂ��v�Z���y�ł��i�O�O�G �� �{���͓d���d���ϓ��^�Ȃ̂Łu���u�v�ł͖����d���́u�����v�Ƃ����l�����Ȃ̂ł����E�E�E ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ��r��H �@�d���d�������R�ŕ������č����臒l�ƁA1K����ʂ��ēd���𗬂��������t�ʃZ���T�[�̗��[�d�����e�R���p���[�^(��r��)�Ŕ�r���āA�Z���T�[�d�����Ⴂ�ꍇ�ɂ���LED��_�������܂��B �@�R���p���[�^�͂S��H�����LM339����g�p���܂��B �@�d���d����2�`35V�œ��삵�܂��̂ŁA�����12V�O��ł̎g�p�ɖ��͂���܂���B �@�܂�����̗p�r�ł́A�Œ�̊�d��������ăZ���T�[���͓d�����v��悤�ȉ�H�ł͂Ȃ��A��d�����Z���T�[(�t�ʃX�C�b�`)�ɗ^����d���������d���d������ɕ������邾���ł��̂ŁA�d���d���̕ϓ��͂��̂܂ܔ�r����d����ɂ�����̔䗦�ʼne����^���邽�߁A�d����������ϓ����Ă����茋�ʂɂ͉�����͂���܂���B �@�����̂悤�ɓd����H�ɎO�[�q���M�����[�^���g�p���č~�����Ĉ��艻������悤�ȕK�v���Ȃ��A�H��@�B�̃o�b�e���[�d�����ϓ����Ă����v�ł��B �@LED�̓d��������R�̒l�̊W�ŁA��H�}���ł͓d���d����9�`15V�ƌ���͂��Ă��܂��B �� �t�ʂ�LED�\�� �@LED1�`LED3�́A�t�ʃZ���T�[���̊e�X�C�b�`�ɑΉ����Ă��āA �@�@�@�@LED1�͍ŏ㕔�X�C�b�`(�܂őS��)��ON�̏ꍇ�_���@[�t��3/4�ȏ�] �@�@�@�@LED2�͒������X�C�b�`�܂łQ��ON�̏ꍇ�_���@[�t��1/2�ȏ�] �@�@�@�@LED3�͍ʼn����X�C�b�`�݂̂�ON�̏ꍇ�_���@[�t��1/4�ȏ�] ���܂��̂ŁALED���R���ׂ���_�O���t�̂悤�ɉt�ʂɉ����ĘA�����ē_�����܂��B �@�t�ʂ�1/4�����̏ꍇ�ALED1�`LED3���S���������Ă��܂��̂ŁA��������m���ĎԂ̔R���v�̂悤�Ɂu�����v�T�C���̐ԐFLED�ł��_�������悤���Ƃ��v���܂���������͂���͂����A�u1/4�����v�����̕\���͓d���������Ă����Ԃł͏�ɓ_������ԐFLED��ōς܂��܂��B �@1/4����LED�ł���LED4�݂̂̕\���ɂȂ�����A�R����ԋ߂ł����狋�����Ă��������B �� �f���\�� �@�����T�C���̕\�������Ȃ������ɁA�t�ʃZ���T�[�̂R�̃X�C�b�`��Ԃׂ邾���Ȃ�LM339�̒��̃R���p���[�^����]��܂��B �@�]�点�����g�p���������Ă������̂ł����A������������Ȃ牽���Ɏg���Ȃ����Ǝv�Ă������ʁE�E�E�u�f���x���v�����v��݂��邱�Ƃɂ��܂����B �@����̉�H�ł́A�t�ʃZ���T�[����ꂽ��A�z�����f�����Ă��܂����ꍇ�ɂ͓��͓d����12V(�d���d��)�ƂȂ�A�\����LED1�`LED3���S���������Ă��܂��̂ŁA�R����������^���N�ɓ����Ă��Ă��\����1/4�����̂܂܂ł��B �@�������u�Z���T�[����ꂽ�v�u�f�������v�Ƃ����̏�Ȃ̂ʼnt�ʂ�\�����Ȃ��Ȃ�̂͂���ł����̂ł����E�E�E�B �@�����ŃZ���T�[���͓d�����ő�ł�4.9V���x�܂łƂ����𗘗p���āA����ȏ�(��H���ł�6V�ȏ�)�̓��͂̏ꍇ�́u�f�������v�Ɣ��f���āu�f���x���v�����vLED5��_�������܂��B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@���̉�H�ɂ͒������͂���܂���B �@�g�ݗ��ĂɊԈႢ���Ȃ�������Ɠ��삵�܂��B �@�t�ʃZ���T�[���Ȃ����Ƀe�X�g����ꍇ�A�t�ʃZ���T�[�̂�����1K���̃{�����[�������Œ��R�����āA�Ă݂Ă��������B��R�l���ς��LED�̓_����Ԃ��ς�܂��B �@�Q�l�}��LED�z�u�̂悤��LED����ׂĂ���ƁA�_�O���t��x�����[�^�[�̂悤��LED������܂��B �@�Z���T�[��{�����[�����q���Ȃ��ʼn����ڑ����Ȃ��ƁE�E�E�f���x�������v���_�����܂��B ���Ԏ� 2010/4/23
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 4/23 |
�@�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �@��������ɂ�����܂��I punta �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�g�ѓd�b�̓d���r�v�̂悤�ɁA�ݒ肵�����ԁi���b�j���������Ȃ���ON�܂���OFF�ɂȂ�Ȃ���H�������Ă��������B ��x��������ON�ɂȂ��H�͊������܂����A��u�̉����ԈႢ��ON/OFF�����獢��̂ŁA���p�҂��Ӑ}�I�ɐ��b�ԃ{�^���������������瓮�삷��悤�ɂ������̂ł��B�iTTL���x���œ��삷���H���]�܂����BPIC���\�t�g�E�F�A�͕s�ł��j ��܂��� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�g�ѓd�b�⑽���̓d�q�@��͒��̃}�C�R���ȂǂŃX�C�b�`�������ԉ����ꂽ���ǂ����ׂāA����ON�Ɣ��肷�邩���v���O�����Ō��߂Ă��܂��B �@�����ĕʂɂ��������}�C�R���Ȃǂ������Ă��d�q���i���œ����悤�ȋ@�\�͎����ł��܂��B 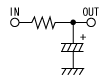 �@�f�W�^����H�����Ԃ�x�点���ɂ͒�R�ƃR���f���T���g�p�����ϕ���H�œd�C�M���̕ω���x�点�܂��B
�@�f�W�^����H�����Ԃ�x�点���ɂ͒�R�ƃR���f���T���g�p�����ϕ���H�œd�C�M���̕ω���x�点�܂��B�@���Ƃ��ŋ߂̉�H��ł́u���邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[�v�̒��Ɍf�ڂ����u�^�C���E���~�b�^�[��H�v�̂悤�ɁA��莞�ԐM���������Ƃ���肵�Ē�߂�ꂽ���������悤�ɂ�������̂ł��B �@�ق��ɂ��ߋ��̉�H��ł͂�������̐ϕ���H���o�ꂵ�Ă��܂��B �@����̖ړI�ł���A���삷��X�C�b�`��ON/OFF�����d����������ƕό`�������ϕ���H�Œx��������ƖړI�̂��̂��ł��܂��B  �@���펞�A�X�C�b�`������Ă������ł͓d���R���f���T�͏[�d����Ă��Ȃ��ׂ�0V�ł��B 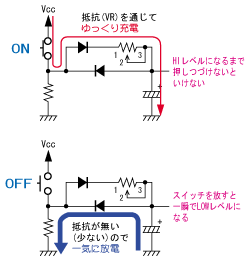 �@�X�C�b�`�������ƁAVcc�d�����_�C�I�[�h�Ɣ��Œ��R(VR)��ʂ��ăR���f���T�ɗ���[�d���܂��B
�@�X�C�b�`�������ƁAVcc�d�����_�C�I�[�h�Ɣ��Œ��R(VR)��ʂ��ăR���f���T�ɗ���[�d���܂��B�@���̍ۂɂ͔��Œ��R�̒�R�l�Ԃ�d������������܂��̂��������[�d����A�d���R���f���T�̓d�����������㏸���A���̓d�����V���~�b�g�Q�[�g��HI����d���܂ŏオ��Əo�͕͂ω�(74HC14�Ȃ�LOW��)���܂��B �@���̂܂܃X�C�b�`�������Â���ƁA�o�͂͂��̂܂܂̏�Ԃ������܂��B �@�X�C�b�`������ƁA��R�l�̏��Ȃ��v���_�E����R��ʂ�����C�ɕ��d����̂ŁA�����ɃV���~�b�g�Q�[�g��LOW�d���ȉ��܂ʼn�����̂ŏo�͕͂ω�(74HC14�Ȃ�HI��)���܂��B �@��x�X�C�b�`��������玟�ɂ܂�ON�ɂ���ɂ̓X�C�b�`���K�莞�ԉ����Ȃ�������܂���B �@�������A�K�莞�ԂɂȂ�O�ɓr���ŃX�C�b�`������Ă��܂����ꍇ�����Ԃ̓��Z�b�g����܂��̂ŁA���ɉ��������ɂ͋K�莞�Ԃ̊ԉ����Â��Ȃ��Ƃ����܂���B �@�R���f���T�̏[�d�E���d���ɓd�����A�i���O�I�ɕω����A�r���Œʏ�̃��W�b�N��HI/LOW����d���̒��Ԃ�ʂ�܂��̂ŁA���̉�H�̌�Ɍq�����W�b�NIC�͕K���V���~�b�g���̓^�C�v�̂��̂��g�p���Ă��������B (�V���~�b�g���͂łȂ��Ă������ɓ����Ă����ꍇ������܂����c) �@VR = 1M���AC = 1��F �̑g�ݍ��킹�������������͍ő�Ŗ�P�b���ł��B(�����74HC14���g�p�����ꍇ) �@���������Ԃ������ƒ����������ꍇ�� C = 4.7��F ���x�ɕύX����Ɛ��b�܂ł͉����܂��B �@���̉�H�}�́u�������X�C�b�`�v�̕��������ł�����A�K�v�ɉ����Ă��̌��ɃX�C�b�`����ɉ����ēd�q��H��ON/OFF����f�W�^����H�Ȃǂ�ڑ����Ďg�p���Ă��������B ���Ԏ� 2010/4/21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �X�p�[�N�L���[�̔j���́H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�X�p�[�N�L���[�̔j���́H �Ⓚ�@��̐���Ղ�200V�����[�ړ_�ی�ɃX�p�[�N�L���[�����t���ėL��A������̕��i���j���𐁂��ُL���Y���s����������܂����B17�N�O�̋@��ł��鎖����X�p�[�N�L���[�̗ƍl���܂��ĐV�������i�Ǝ�ւ��܂������A1����ɂ܂��j�Ă��܂��܂����B�Ƃ肠�����X�p�[�N�L���[���O�����ݖ��Ȃ������Ă���܂��B�X�p�[�N�L���[���j��v���͂ǂ̗l�Ȏ����l������ł��傤���B�A�h�o�C�X�X�������肢�v���܂��B �������� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����m���Ƃ͎v���܂����A�X�p�[�N�L���[�͓d�C�ړ_�Ȃǂ�ی삷�邽�߂ɂƂ����A���g�̓R���f���T�ƒ�R������ɂȂ������i�ł��B �@���[�^�[�Ȃǂ̗U�����ׂƓd����ڑ�����ꍇ�A�X�C�b�`�����ēd���𗬂��͂��߂鎞�ɂ͂����ւ�傫�ȓ˓��d��������܂����A�X�C�b�`��������ɂ͂܂��d�������ꑱ���悤�Ƃ��鐫���̂��߂̃A�[�N���d���N������A�R�C���ɋt�N�d�͂��������Ă��ꂪ��荞��Ɨl�X�Ȍ����ŃX�C�b�`����[�̐ړ_�����߂邱�ƂɂȂ�܂��B �@����������������X�C�b�`����[�̐ړ_�����̂��X�p�[�N�L���[�̎d���ŁA�ړ_�ƕ���ɂȂ��ŃX�C�b�`��ON/OFF�̏u�Ԃɐړ_�ԂɃX�p�[�N(���d�E�Ή�)�����ł��̍����Őړ_�����߂Ă��܂킢�Ȃ悤�ɃX�p�[�N�L���[���ŏu�ԓI�ɓd�����o�C�p�X�����铭�������܂��B �@�U���N�d�͂����H��ی삷��ꍇ�͕��ׂ̗��[�ɂȂ��g����������܂����A����͐���Փ��Ƃ̎��Ȃ̂ŏ�L�̃X�C�b�`�܂��̓����[�̐ړ_�ی�p�Ɏg���Ă���Ǝv���܂��B �@�m����17�N���g���Ă�����X�p�[�N�L���[�̗�(��ɃR���f���T�̗�)�Ƃ��������z���ł��܂����A�V�i�ɕς��Ă������ɏĂ��Ă��܂����Ƃ������̓X�p�[�N�L���[�������ł͖����悤�ł��ˁB �@�ł́A�ق��ɍl�����錴���́E�E�E�E�Ⓚ�@��̕s�����Ǝv���܂��B �@�Ⓚ�@��Ƃ������́A��ȓd�͏���u���R���v���b�T�[�ł���A�R���v���b�T�[�͋��͂ȃ��[�^�[�A���Ȃ킿�傫�ȓd���𗬂��R�C���łł��Ă��܂��B �@�R���v���b�T�[�����āu���삪�d���v�Ȃ�ƃ��[�^�[�ɉߑ�ȕ��ׂ�������d�C�I�ɂ��ߑ�ȓd���������悤�ɂȂ�A�˓��d���Ȃ�(�^�]���̏���d�����H)���ƂĂ��傫���Ȃ��Ă���\��������܂��B �@���̉ߑ啉�ׂɂ��p���X�d���Ȃǂ��X�p�[�N�L���[�̒�i���z���Ă��܂��ƁA�X�p�[�N�L���[�͉ߔM�E�j�������ł��傤�B �@�X�p�[�N�L���[���O���Ă��܂��Ă��X�C�b�`��ON/OFF�ł��܂����Ⓚ�@��͓��삵�Ă���Ƃ͎v���܂����A���������̂悤�ɗⓀ�@�푤�ɂ���ꍇ�͂����Ƀ����[�̐ړ_���Ă��ē��삵�Ȃ��Ȃ�����ON�̂܂~�܂�Ȃ��Ȃ�����A���X�j���[�X�ɏo�Ă���u���s��̗①�ɂ���o�A�s���S���v�݂����ȑ厖���ɔ��W����\��������܂��B �@����Ղ̃X�C�b�`�E�����[�̐ړ_�����Ĉُ�Ȓf�����N���āA���ꂪ�����ŃR���v���b�T�[�Ɉُ�d��������ă����[�ړ_�ɉߕ��ׂ��������Ă���Ƃ����\�����ʂ����܂���B �@�X�p�[�N�L���[���Ă����̂͂��������厖�̗̂\���ƂƂ炦�āA�����ڂɗⓀ�@�탁�[�J�[�Ƃ����̐���Ղ̐����𐿂��������d�C�H����ЂɘA�����āA�����ƃ����e�i���X�������ق��������ł��傤�ˁB �@���ꂮ����A�u�X�p�[�N�L���[���O�����܂܂œ����Ă��邩�炢����I�v��u������i�̑傫�ȃX�p�[�N�L���[�Ɍ���������Ă��Ȃ����낤�v�݂����ȏ��u�͍s��Ȃ��ł��������ˁi�O�O�G ���Ԏ� 2010/4/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԁE�f���x�������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ǂȂ��������Ă��������B�P�V�n�N���E���̃n�C�}�E���g�X�g�b�v�����v��LED�Ɍ������܂������A�f���x�������_���܂����������@�������Ē����܂��H �V�Q�L �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�f���x���́A�d������ēd��������Ȃ��Ȃ������Ƃ����m���ē_��������̂ł��B �@LED�͓d���ɂ���ׂĂ����킸�������d���𗬂��Ȃ����ł�����A�f���x����H�́u�d�����ꂽ�v�Ɣ��f���܂��B �@���̂܂܂Ŏx�Ⴊ�����̂ł�����A���̂܂ܑ��s����Ă͂������ł��傤���H �@���́u�{���̃u���[�L���v���d���ł��̓d�����ꂽ�Ƃ��Ɍ��m�ł��Ȃ��Ȃ��č���̂ł���ALED�ƕ����12V/5W���x�̓d�����ԉ��n�p��Ō����u�B�����v�Ƃ��Ăǂ����ɓ���Ă��܂��Όx�����͏����܂��B �@�d���ȊO�ɂ�30��/10W���炢�̃Z�����g��R���g���Ă��\���܂��A�d���ɂ���Z�����g��R�ɂ���5W���x�̔��M������̂ŁA�R���Ȃ��悤�ȏ��������Ĉ��S�ȂƂ����(�B����)����Ȃ��ƎԂ��ۏĂ��ɂȂ��Ă��܂��Ă͂��܂�܂���ˁB �@���A�uLED�͏ȓd�͂�����v�Ƃ������R�Ō������ꂽ�̂ł�����A�f���x���������ׂɉB�����Ȃǂ����Č��ǂ͓_�����ɓd�͂�������Ȃ��ƌx�������_�����Ă��܂��̂ŁA�S�R�ȓd�͉��ɂ͂Ȃ�܂���B ���Ԏ� 2010/4/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 4/11 |
���Z�����Ȃ��A�I�m�Ȃ������A���ɎQ�l�ɎQ�l�ɂȂ�܂����B�L�������܂����B �V�Q�L �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����̎��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�����y�������N���N����L���A�L���q�����Ă���܂��B�iNiMH���d��Ȃǃo���o�����Ă��܂����j �d�r���̏����I�Șb��Ȃ̂ł����A����������H�ƌ����Ή�H�H�Ƃ������f�ŁA������֓��e�����Ă������������c�B �C�����������ɂ��Ԏ����������܂��ƍK���ł��B ���� ���݁A�V���N��100�~�u�P�O�Q�{��USB5V�o�͋@�v���A�Ƃɗ]���Ă���18650Li-ion�Z��(max4.2V-typ3.7V)�ʼn^�p���Ă���܂��B ���ׂ���̗v����500mA�߂��Ȃ��Ă�������5V�o�͂��ێ��ł��Ă���A���̓_�͑傢�ɖ����A���z�I�Ɏg�p�ł��Ă��܂��B ����ŁA�ꕔ�@��ɂĎg�p�����ۂɁu�ړI�̂U���قǂœd����18650���͐s���Ă��܂��v�Ƃ���������܂��B ����̃P�[�X�ɂ͂܂��X�y�[�X������A���傤��18650��������{���邩�ȁ`�Ƃ������~�ł��āA�d���Ƃ���18650���Q�{����ŋ쓮���A�����^�C���������ł���Ζ��X�Ȃ̂ł����A�A�A �������� ���̏ꍇ�A�P����18650�����ɑg�ݍ���ŗǂ����̂Ȃ̂ł��傤���H �Ɛ\���܂��̂��A�Q�{�̃Z���́u�Ȃ�ׂ��r�́E���v�͂̋߂����́v��p�������ƍl���Ă���܂����̂́A�ǂ����Ă��d���̍��ق���g�ݑ���̃Z���ɓd��������Ă��܂��A�̑��i�E�肪��������̂ł́H �ƋC�ɂ�������ł��B �����������邽�߁A�u���ꂼ��̃Z���ɓd���~���̂Ȃ�ׂ����Ȃ��_�C�I�[�h���y�A�ɂ��Ă����ĕی삷�ׂ��v�Ȃ̂��A���邢�́A�u����ł̓_�C�I�[�h�ł̓d���~�����̃��X���t�ɑ傢�ɖ��ʂƂȂ�̂ŁA�C�ɂ������̂܂ܕ���v���x�^�[�Ȃ̂��A�͂��܂��A�u����͂�߂Ē���Q�{��d���ɁA��100�~�V�K�\�P�R���o�[�^��5V�֍~�������Ďg���̂��g�v�Ȃ̂��A���₢��A�u��������̂��펯�I�v�u���ꂪ��낵���I�v�Ƃ�������܂�����A�����������������Bm(_,_)m cholera �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�ړI�̂U���قǂœd����18650���͐s���Ă��܂��v�Ƃ����̂́A�ړI�̋@���18650��{�ł͏[�d�ł��Ȃ��Ƃ������ł��傤���B �@����Ȃ�P����18650�����ɂ��邾���ł��ˁB �@��������ʂ�ɐ��\��[�d��Ԃ̑������Q�{�����ɁB �@���Ƃ��A�m�[�g�p�\�R���̃o�b�e���[�p�b�N�̒��ł͑�����Li-ion�[�d�r������{����ɑg�ݍ��킳���Ă��āA�u����g�p�͂�����܂��v�Ƃ����g����������Ă��܂��B �@����ɂ���ƕЕ������\�������Ă����Е������\���Ⴂ�ꍇ�E�E�E�Ƃ����S�z�͂���Ǝv���܂����A�ʂ����ĉ��u�̓d�ʍ������܂ꂽ���ɉ��`�̓d�����d�r����d�r�ɗ���邩�����m�ł��傤���H �@�������̒l�������m�̕��Ȃ�d�r�����Ɍq�������ɉ����N����̂��͑z�������Ǝv���܂��B�����Ă��̋N�����u�����v���ǂ̒��x�d�r�ɑ��ėL�Q�����Q�����B �@����͎��ۂ̋@���Li-ion�[�d�r������Ŏg�p����Ă��鎖��������z���͂ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�u����Ŏg�����v�u����ō~���R���o�[�^���g�����v�ǂ��炪�ǂ��̂��́A�g�p����邻�ꂼ��̃R���o�[�^�̌������ǂ��炪�ǂ����ɂ���Č��܂�ł��傤�B �@DC/DC�R���o�[�^�̕ϊ������͓d���d������o�������d���l�ő傫���ς�܂�����A���Ƃ����i�𖼎w������Ă���������łǂ��g�����ł��̏ꂻ�̏�Łu�ǂ��炪�ǂ��v���͌��ꎟ�悾�Ǝv���܂��B �@�ɒ[�ɂ����ꂩ�̑��u�̐��\�E�������ƂĂ������āu����Ȑ��i�ŕϊ�������قƂ�ǂ����X�Ŏ̂Ă��Ă��܂��I�v�Ƃ����悤�ȏꍇ�������āA���ʂ����ϊ���ł͖ړI�ɂ��킹�Ď��ۂɕϊ������𑪒肵�Ă݂Ȃ����Ƃɂ͂ǂ��炪�ǂ��Ƃ͑z�������ł͔��ʂł��܂���B ���Ԏ� 2010/3/26
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����̂��Ԏ������������A���肪�Ƃ��������܂��I �Ȃ�قǁA�s�̂̐����@��(�m�[�gPC��)�ł�����g�p�Ő��̒������|���Ă���Ƃ�������A�傢�ɔ[���ł��B �����āu���ꂪ�펯�I�v�Ƃ����̂Ȃ�A�u�����̐v�����@��ŁA�]�ތ��ʂɍł��߂����̂�������^�C�v���A�����E�v�����Č��ɂ߂�̂��펯�I�v�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B ���̍ې܊p�Ȃ̂ŁA����(�~��)�^�C�v�������Ċy����ł݂����Ǝv���܂��` �d�ˏd�ˁA�A�h�o�C�X�����������肪�Ƃ��������܂������I cholera �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��i���͂����肵�Ă��鐻�i�Ƃ��A���i�P�ʂŃf�[�^�V�[�g������ΐ��\���킩��i�Ȃ炻�̏��ł�����x�͔��f�ł���ł��傤���A�����i�Ŕ̔�����Ă��Ē��g�ɂ��Ă̐��\�����Ɍ��\����Ă��Ȃ����̂��ׂ�Ȃ�A��͂���ۂɎg���Ă݂��葪�肵�Ă͂��߂ėǂ�������K���Ă��邩�ǂ����͕�������̂ł��B �@100�~�V���b�v�̐��i�Ȃ�����̂ŋC�y�Ɏg���Ă݂āA���߂��Ƃł����T�C�t�ւ̃_���[�W�����Ȃ��̂ł��낢��ƗV��ł݂Ă��������B ���Ԏ� 2010/3/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����ɂ��́B�������p�����Ă��������Ă���܂��B ������ւ̓��e�ŋX�����̂�����܂����₳���Ē����܂��B �\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\���ɂ��ĊǗ��l�l�̐��������������肢�������܂��B �ǂ����ĂQ�̓d���œ��삷��̂��ƂĂ��s�v�c�ł��B ����IC�Ȃ����Ă�̂ł��傤���H �����Ԃ̋������ɂ��Ԏ�������ƍK���ł��B �F �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ʂɕ��G�ȋ@�\�͓����Ă��Ȃ��ł���B �@�m���ɁuIC�v�̒��̉�H�ł͂���܂����E�E�E�B 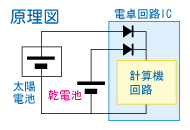 �@�ʁX�̓d������_�C�I�[�h������ʂ��āA�d���̍����ق�����d��������������悤�Ɍq�����Ă��邾���ł��B
�@�ʁX�̓d������_�C�I�[�h������ʂ��āA�d���̍����ق�����d��������������悤�Ɍq�����Ă��邾���ł��B�@���Ăđ��z�d�r�����̊��d�r��荂���d���������Ă���Ԃ́A���z�d�r����_�C�I�[�h��ʂ���IC�ɓd�������������܂����A���̍ۂɊ��d�r�d����IC�̒��̓d���d�����Ⴂ�̂Ŋ��d�r���̃_�C�I�[�h�ɁuIC�̒������d�r�v�̕����ɋt�����ɓd��������悤�Ƃ���̂ŁA�_�C�I�[�h�̓����œd���͗��ꂸ�Ɋ��d�r�͏�����[�d(?)������܂���B �@�����������Ă��Ȃ����ɂ͋t�ŁA���d�r�̓d�������z�d�r�̔��d�d����荂���̂Ŋ��d�r����IC�֓d���͗���܂����A���z�d�r�ւ͋t�����������܂���B �@���ۂ�IC�̒��ł̓_�C�I�[�h�͎s�̂̌ʂ̕��i�̂悤��0.6V���������d��������悤�ȕ��ł͂Ȃ��AIC�̓d�q��H������Ă���V���R����H��ɓd�ʍ��������킸���ȓd���ōςނ悤�ȕ��i�Ƃ��Č`������Ă��܂��B �@�łȂ��Ɗ��d�r��{��1.5V�œ����悤�ȓd�삾�ƁA�_�C�I�[�h��0.6V���d�����������Ă��܂�����ƂĂ����̓d�q��H�������܂���ˁB ���Ԏ� 2010/3/20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 3/20 |
�Ǘ��l�l
���Z�������ł̂��Ԏ����ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�ƂĂ��킩��₷�������A��H�}
�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
������X�������肢�������܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�F �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���������b�ɂȂ��Ă���܂��B�Ԃ̃o�b�e���[�����̔��f�ޗ��Ƃ��āA�����G���W���n���O�̃o�b�e���[�d�����A�N�Z�T���[�̓d���v�Ŋm�F���Ă���G���W�����n���������Ǝv���Ă���̂ł����A�m�F����̂��悭�Y��Ă��܂��܂��B�����Ŏn������T�`�P�O�b�Ԃ��炢�����ŃG���W���n���O�̃o�b�e���[�d����\�����������Ǝv���A�L�[���Ɠ����Ƀ����V���b�g�E�^�C�}�[�ƃ����[��100�ʂe�̃R���f���T�[���o�b�e���[����藣���ăR���f���T�[�̓d����\��������悤�ɂ����̂ł����A�����ɓd�����������Ă��܂��Ċm�F�p�Ƃ��Ă͖��ɂ����܂���ł����B�莝���ɑ�e�ʂ̃R���f���T�[���Ȃ��̂ő�e�ʉ������͂��Ă��܂���B�G���W���n���O�̃o�b�e���[�d����\�������邢�����@����������Ă��������B��낵�����肢���܂��B �Ƃ����� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�g���Ă���d���v�̓f�W�^�������ł����H �@�f�W�^���d���v�Ȃ���̓C���s�[�_���X�������A100��F���x�ł�10�b�قǂȂ�0.1V��������Ȃ��̂Ŗڎ��œd�����m�F���邾���Ȃ���͖����Ǝv���܂��B �@�����A�i���O�d���v�ł���Ȃ�ɃR�C���d���������悤�ȕ��Ȃ�A�R���f���T�̓d�ׂ���������邷���Ɠd����������ł��傤�B �@������ɂ���A10�b���x�ł����̂ł���R���f���T�̗e�ʂ𑝂₵�Č���ł̓d���v�̏���d�����x�ł͂����ɓd���������Ȃ��悤�ɂ��鎖���ł���y�ň��オ��ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�d�q��H�ʼn����E�E�Ƃ����Ă����̓d�q��H�����d�����Ԃ̃o�b�e���[�������Ă���̂ŁA�L�[����ON�ɂ������ɂ̓G���W�����܂�����Ă��Ȃ��̂ŃL�[���O���Ⴍ�Ȃ��āA����ȓd���d���ł͓d���d���ȏ�̓d�����o�͂��邱�Ƃ��ł����A�g�p����Ă���d���v���ԗp��10�`15V��\��������̂Ȃ�ƂĂ�����ȓd���ŕ\�����邱�Ƃ͂ł��܂���B(�G���W����������Γd���͏オ��ł��傤���ǁE�E�E) �@���ʂ͓d�q��H�ʼn����g�ނȂ�A�N���O�̓d����ێ����Ă���R���f���T�̓d���͓d���d����1/2���x�ɂ��Ă����āA�N����ɋ����ꂳ��d�����������Ă����̓d���d�������̐M������舵���悤�ɂ�����̂ł����A�����������Ă��d���v��10�`15V���͂̕��ł͂�͂���ɗ����܂���B�u�����̓d������͂��Ă������Q�{�̓d���l��\������d���v�v�Ȃ�ĕ֗��ȕ��������Ă����炻���������̂��g�������̂ł����APIC�Ŏ��삷��Ƃ��Ȃ炷�����܂����Ȃ��Ȃ��s�̕i�ł͎�ɓ���܂����ˁB �@���̂�������������ɂ́A���Ƃ��Γd���v�ɏo�͂���d����1/10�ɂ��ĒႢ�d���d���̎��ł��o�͓d���ɓd���̉e���������悤�ɂ��Ă����āA�d���v��1�`1.5V�𐳂����\���ł������(�ړI��1/10�̓d���p)���g���ă��[�^�[�̕\����10�{�ɓǂݑւ����(�����W�ς̃f�W�^���p�l�����[�^�[�Ȃ班���_�̓_���ʒu��ς��邾���Ƃ��c)�A�����Ԃ͋N���O�̓d�������ɕ\����������悤�ȉ�H���ł���ł��傤���A����͍����g���̓d���v�̏�������܂��A���ɂ���ȉ�H������đΏ�����K�v�������Ǝv���܂��B �@����̖ړI�ł���A4700��F�Ƃ��c���̑O��̑�e�ʂȓd���R���f���T�ɕύX���邾���ő������͉������܂���B ���Ԏ� 2010/3/20
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ő�100LED�E�����t���b�V���[��H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���������b�ɂȂ��Ă���܂��B ������������m�b��q�������������f�������ĉ������B TC4040BP�����g���ĂQ�O�A���ȏ�̑���LED����肽���̂ł��B �̃g���b�N��Y�̃f�R�g���ɂ������d�������郂�m���q���̃v�����f���g���b�N�ɕt���Ă�낤�Ǝv���A�`�b�vLED�Ǝ莝���̃J�E���^�f�R�[�_HC4017�ƐV���ɍw�������o�C�i���J�E���^TC4040BP�ō�낤�Ǝv���̂ł����A4017��10��A4040�͏o�͂�12�L��̂łP�Q��̏��������ł��܂���B�S�O�P�V���g���Ă��ꏄ����Ǝ��̂S�O�P�V����_���ƌ������Ƃ����o���Ȃ��悤�ł��B���Ƃ��P�Q�A���ȏ�̑���d������鎖�͏o���Ȃ��ł��傤���H 40�߂��̏��S�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͂��߂ɁA4017��4040�͑S���@�\�̈ႤIC�Ȃ̂ł����A������������čl�����Ă���悤�Ȃ̂ł��̓_�����B �@4017�͂T�X�e�[�W(5bit)�́u10�i�J�E���^�v�@�\�ƁA���̏o�͂���Q0�`Q9��10�{��10�i�ʏo����ON/OFF����u10�i�f�R�[�_�v�@�\�̂Q�̋@�\��������IC�ł��B �@�u10�i�f�R�[�_�v�@�\�̂������ŁA���̃J�E���^�Ő�����0�`9�̐��l�̌��ʂ�Q0�`Q9�̂ǂꂩ��{�̏o�̓s����H�ɂȂ�悤�ɏo�͂��܂�����ALED���q�����ǂꂩ���LED���_���������ƂɂȂ�܂��B �@4040��12�X�e�[�W(12bit)�́u�o�C�i��(2�i)�J�E���^�v�@�\�݂̂�IC�Ȃ̂ŁA�J�E���g�ł��鐔�l��0�`4095�܂ł�4096�J�E���g�A�o�͂͂Q�i���\�L(�o�C�i��)�ŃJ�E���g���l���o�͂���܂�����A������LED���q���ƃo�C�i���\�L�̊e�r�b�g�ɑΉ�����LED���_�����āA�f�l�ڂɂ͂Ȃɂ��Ȃ��킩��Ȃ��\���ɂȂ�܂���B �@�ƂĂ��u4040�͏o�͂�12�L��̂łP�Q��̏����v�Ȃ�ē����͂��Ȃ��̂ł����E�E�E�B �@����4040�̏o��(0�`4095)��LED����_�����������̂ł���A�u�o�C�i�����K�vLED�{���̃f�R�[�_��H�v��4040�Ƃ͕ʂɕK�v�ŁA�g�p����LED�{���ɑΉ������ʓ|�ȉ�H��v���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B �@����Ȏ������Ă���ƁA�������Ȃ��ɁuLED20�p�̉�H�}�v���������Ƃ��āA�ォ��ʂ̕�����u30�ɑ��₵������ł����A�ǂ������炢���ł����H�v�Ƃ����������Ń��W�b�N��H�������Ȃ��l����̎���Ȃǂ��o����܂��ꂩ��f�R�[�_��H�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂łƂĂ��ʓ|�Ȏ����N����\��������܂��B �@����Ɏg�p����IC�̐������Ȃ葝���āA���ꂾ���ł��ƂĂ��ʓ|�ł��B �@�������A�p�r�ɂ���������̂ق����K���Ă���ꍇ������܂����A����̃��W�R���̓d���p���炢�Ȃ炻���܂�IC�̐��𑝂₵�Ėʓ|�ȉ�H�����K�v�͖����ł��傤�B �@4017���Q�g�������オ���ɂ܂ōl���������Ă���̂ł���A���̂܂܂�LED�\�����}�g���b�N�X�����邾���ōςޖ��Ȃ̂ł����������j�ʼn�H��v���܂��B �@�}�g���b�N�X��H�͑����̑f�q��X�C�b�`���N���X����I��z���ŏc���ɐڑ����āA�z���������Ȃ�����Z�p�ł��B�p�\�R���̃L�[�{�[�h�̂悤�ɑ����̃X�C�b�`�����Ȃ��|�[�g�ŃX�L����������A�t���f�B�X�v���C�̖c��Ȑ��̃h�b�g���c���ɔz�����ꂽ�}�g���b�N�X��H�Ő��䂳��Ă��܂��B �@����4017���Q�g�����c10�~��10���ő�100LED���̐��̗����t���b�V���[�����܂��B�������LED�͏c���ɕ��ׂ�̂ł͂Ȃ��A���ɕ��ׂ�20��30�c100��LED�ɑ����P�̌��̓_������čs���悤�ɐݒu���܂��B �@�A���A��{������4017�ō���āA������g�������H�Ȃ̂ő��₹��LED��10�P�ʂł��B�u16�Ń��[�v����悤�ɂ������v���͎t���܂���̂ŔO�̂��߁B(���W�b�N��������郊�Z�b�g��H��lj�����Ή\�ł��A�K�v�ȕ��͂������Őv���Ă�������) ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �N���b�N���U��H �@�����̂悤���^�C�}�[IC 555�Ŕ��U��H�����܂��B �@���U���g����VR1����6�`46Hz�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@LED1�ŃN���b�N���U�̂悤�����m�F�ł��܂��B �� �J�E���^�ELED�h���C�o��H �@555�Ŕ����������N���b�N�M���ł܂�IC2��4017���J�E���g�A�b�v�����܂��B �@�����10��LED�������_�������Ă䂭��{�����ł��B �@IC2��CARRY OUT (���グ) �M����IC3�̃N���b�N���͂ɐڑ����āAIC3��IC2��10�J�E���g�I������0�ɖ߂������ɂP�J�E���g�A�b�v����悤�����オ�������܂��B �@����10�J�E���g���ƂɂP�オ��J�E���g���\�̌��ł�����ALED����̌��̂Ԃ�10�łP�O���[�v�Ƃ������̂�IC2�̏o�͂Ɍq���ł����āA�������R���������\�̌��̃J�E���g�œd��(�����GND)�Ɍq����O���[�v���P������ւ��Ă��A�S�Ă�LED�̒������̌��Ə\�̌��őI�ꂽ�P�������_�����܂��B �@����f�ڂ��Ă����H�}�ł͏\�̌�����h���C�o���Q�g�ɂ��č��v20LED�̗����t���b�V���[�Ƃ��Ă��܂��B �@��̌���4017��10��LED���ւ���d�l�ł�����A�P��ɂ�10��LED����𑝂₵�Ă䂯�A30LED�c40LED�c50LED�c�A��10�P�ʂōő��100LED�܂ő��₹�܂��B �@��𑝂₷�ꍇ��IC3���烊�Z�b�g��H�ɐڑ�����Qx�͎��ۂɎg�p����Qn���P���������̏o�͂�Q(n+1)��ڑ����܂��B �@100LED�̏ꍇ�͓r���Ń��Z�b�g����K�v�͖����̂�IC3���烊�Z�b�g��H�ւ̏o�͉͂����ڑ����܂���B �@�����Ⴄ�g�p���@�Ƃ��āA���Z�b�g�M����Q(n+1)�ł͂Ȃ��X�ɐ��Q(n+2)��Q(n+3)����ڑ������ꍇ�A���ڑ��ɂ���Q(n+1)���i��X��Q(n+2)���j�ɂ�LED������悤�ɏ\�̌��J�E���^�͐U�����܂������ۂ�LED�͑��݂��Ȃ����߁A�����ڂł͑S�Ă�LED���_�����I�������͂��炭�͑S�Ă�LED���������Ă���悤�Ɍ����܂��B��x�Ō�܂Ō������ꂽ��A��H�Ŗ��ڑ��ɂ��Ă���10��LED�Ԃ�͋x�e���Ă���܂�LED00����_�����n�܂�悤�ɏ����x�݂������������t���b�V���[�Ƃ��Ă��g�p�ł��܂��B �� �d�� �@���̉�H�}��5V�p�ł��B �@�e��R�l�Ȃǂ�5V�p�ɐv���Ă��܂��B �@���������Ԃ̓d��12V�ȂǂŎg�p�����ꍇ�́A��H�}���ɏ����Ă���悤�ɓd���R���f���T�̑ψ���e��R�l��ύX����A����ȊO�͂��̂܂܂Ŏg�p�ł��܂��B �@����IC��74HC4017�͍ő�6V�܂ł����g�p�ł��܂���A18V�܂Ŏg�p�ł���4017B��K���g�p���Ă��������B �@���ɍw������Ă���̂�74HC4017�̂悤�ł�����d����5V�Ő��삵�Ă��������B �@���̕��������Ԃ�12V�d���ł��g�p�������Ƃ�������]���o��\���������̂ňꉞ���ӏ����͓���Ă����܂������A�����Ԃ̏ꍇ�͉ߋ��̗�ł������Ԃ���������m�C�Y��IC����쓮���Đ���ɓ����Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA�ł���ΎO�[�q���M�����[�^�Ȃǂœd����5V�ɂ��āA���̂܂܂̉�H�}�̂܂g�p����邱�Ƃ������߂��܂��B ���Ԏ� 2010/3/11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�������ϗL��������܂��B����ɂ��Ă��f�l�̑����_�ł悭���ׂ�������TC4040BP�𑽗ʍw�����Ă��܂����ʑK���g���Ă��܂��܂����E�E�E�B ����TC4040BP�ō��郂�m��T���Ȃ��ƁE�E�E�B �u�}�g���b�N�X��H�v�͕����������������̂ł����ǂ�ȃ��m������܂���ł����B�����đՂ��������鎖���o���܂����B�E�B���ƁA�N���b�N���U�͂T�T�T�������ꍇHC�O�S���ł������̂ł��傤���H 40�߂��̏��S�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�N���b�N���U��H�͂��D���ȕ��łǂ����B �@����̓N���b�N���������䂵����A�~�߂��肷��K�v�͂���܂���B ���Ԏ� 2010/3/12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�L��������܂����B����䋳��������������H����{�ɗ����������o����Ǝv���܂��̂ŃA�����W���čH�v���Ă݂����Ǝv���܂��B��������PIC�̂悤�ɗ����_��������A�S�_���E�_�ł͏o���Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E�B����Ƃ��X�~���肢�������܂��B 40�߂��̏��S�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����������G�Ȃ��Ƃ����ꂽ���̂ł���APIC�}�C�R���̂悤�ȕ����g��ꂽ�ق��������ł��ˁB �@IC�𑝂₹����]�͊����Ǝv���܂����A��H����K�͂ɂȂ銄�ɂ͌��ʂ�����قǂ̉�H������Ă܂Ŏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł͖��������ł����B ���Ԏ� 2010/3/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�����b�ɂȂ�܂��B �@���������ʂň��|����A�����u�b�N�}�[�N�����Ă��������܂����B �@�S�Ă�q�����Ă��炸�A�����I�Ȏ���ł������������������B �@����̓��e�ł����A�I�[�g�o�C�Ŗ������s�����߂�2SC1815���g�p�����}�C�N�A���v�ɃR���f���T�[�}�C�N�Ńw�b�h�Z�b�g�삵�܂����B �@�}�C�N�����؉�����ɋ����E����M�Ɏx�Ⴊ����̂ŁA���[�J�b�g�t�B���^�[��lj����悤�ƌ������Ă���܂����A�悭����܂���B �@���݂̃}�C�N�A���v�̎d�l���́AVcc��3.3V�ŁA�R���N�^��R��1K���A�G�~�b�^��R��200�����Œ�A�x�[�X��R��100K���ŁA�R���f���T�[�}�C�N��Vcc����2.2K���̒�R�o�R�œd�����Ƃ�A�ƃA���v�Ԃ�1�ʂ̓d���R���f���T�[�����Đ��삵�Ă���܂��B �@�J�b�g�I�t���g����300Hz�Őv�������ƍl���Ă���܂��B �@RC�t�B���^�[��H�Ƃ������t�܂ł͒��ׂ܂������A�ǂ̂悤�ɐv���ׂ������悭����܂���B �@�X�����������肢�܂��B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
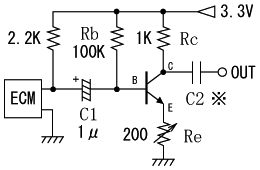 �@���ݎg���Ă���}�C�N�A���v�̉�H�͂��̂悤�Ȃ��̂ł��傤���H
�@���ݎg���Ă���}�C�N�A���v�̉�H�͂��̂悤�Ȃ��̂ł��傤���H�@�g�����W�X�^�ɂ���Œ�o�C�A�X������H���d���A�ґ�����H�̑��̎q�݂����Ȓ�������H�ł��ˁi�O�O�G �@�d���A�ґ�����H�̌����ŃG�~�b�^��RRe��ω������ăQ�C��(������)��ς��ĉ��ʃ{�����[���ɂ��悤�Ƃ��Ă���悤�ł����A��������ł�����Ƃ������ɁE�E�E�B �@����͂Ƃ肠������ɒu���Ă����āE�E�E�B �@���؉������Ȃ��������u���[�J�b�g�t�B���^�[�v������ɂ́A�m����CR�ɂ��u�n�C�p�X�t�B���^�[�v��H���g�p���܂��B �@�d�q��H�̐��E�ł͂��܂�u���[�J�b�g�t�B���^�[�v�Ƃ����������͂����A�u�n�C�p�X�t�B���^�[�v��t�̓����́u���[�p�X�t�B���^�[�v�̂悤�ɒʂ��ق��̐M���ɂ��Ă̖��O�ŌĂт܂��B 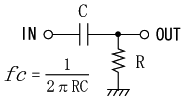 �@���ꂪCR���g�p�����n�C�p�X�t�B���^�[�̉�H�ŁA�J�b�g�I�t���g���� fc = 1/(2��RC) �ŋ��߂��܂��B
�@���ꂪCR���g�p�����n�C�p�X�t�B���^�[�̉�H�ŁA�J�b�g�I�t���g���� fc = 1/(2��RC) �ŋ��߂��܂��B�@CR�ɂ��n�C�p�X�t�B���^�[�̌����́A�R���f���T�͌𗬂�ʂ������͒ʂ��Ȃ�����������܂�����A�o�͑��ɂ�����R�̃C���s�[�_���X�ƃR���f���T�̓������g�ݍ��킳��Ƃ�����̎��g���ȏ�̌𗬐M���ɑ��Ă͂قƂ�ǒ�R�l�̖�����ԂŐM�����ʉ߂��A������g���ȉ��̌𗬐M���ɂ͎��g�����Ⴂ�قǒʉ߂��ɂ����Ȃ�t�B���^�[�Ƃ��ē����悤�ɂȂ�܂��B �@�A���v�̏o�͂ƐM�����鑤�̋@��(�����@)�̊Ԃɂ��������n�C�p�X�t�B���^�[��H�����Ă������̂ł����A�����͊ȒP�ɂ͂䂫�܂���B �@���̂܂܂̃R���f���T�ƒ�R���A���v�Ɩ����@�̊Ԃɓ����Ȃ�A�����@���̓��̓C���s�[�_���X���������Ă��Ȃ���ΐv���ł��Ȃ��̂ł��B �@����CR��H���@�Ɍq���ƁA��RR�Ɩ����@�����ɑ��݂����RRx������Ɍq���邱�ƂɂȂ�A���̒l��m���Ă��ĕ����R�̌v�Z�����Ă��ΖړI�̎��g���ŃJ�b�g����t�B���^�[�ɂȂ�悤�ɓI�m�ȃR���f���T�e�ʂ��v�Z�ł��܂����A�����@���̒�R�l�Ȃǂ��������Ȃ��ƌv�Z�ł��܂���B �@CR�t�B���^�[�̌�ɍX�ɃR���f���T��lj�����Ƃ��A�����@���̃}�C�N���͉�H�ɃR���f���T���^����ɂ���Ƃ��A�F�X�Ɖ\���͂���܂�������͂��̃}�C�N�A���v�̏o�͑��ɒP����CR�t�B���^�[��lj�������@�͎g��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B �@�����Ŏ��Ɂu�g�����W�X�^��̃n�C�p�X�t�B���^�[��H�v�ɍl����i�߂܂��B �@�I�y�A���v���g�����n�C�p�X�t�B���^�[��H�ȂǓd�q��H�ł͐F�X�Ƒ��̕��@�ł����܂����A����̓g�����W�X�^��ō���n�C�p�X�t�B���^�[�ɘb��i�߂܂��B 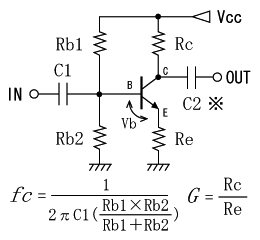 �@�E�̉�H�}�̂悤�Ƀg�����W�X�^��ɐ��̕��i�œd���A�Ҍ^�̃A���v���\�����A���͂ɃR���f���T�����鎖�Ŋ�{�I��CR���g�p�����n�C�p�X�t�B���^�[���l�A�R���f���T�̎��g�������𗘗p���ē���̎��g���ȉ��͌���������A���v�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�E�̉�H�}�̂悤�Ƀg�����W�X�^��ɐ��̕��i�œd���A�Ҍ^�̃A���v���\�����A���͂ɃR���f���T�����鎖�Ŋ�{�I��CR���g�p�����n�C�p�X�t�B���^�[���l�A�R���f���T�̎��g�������𗘗p���ē���̎��g���ȉ��͌���������A���v�ɂȂ��Ă��܂��B�@��{�I��CR�ɂ��n�C�p�X�t�B���^�[�Ƃ͏����Ⴂ�A�C���s�[�_���X����R��Rb1��Rb2�̍�����R�l�ɂȂ�_�ƁA�g�����W�X�^�̃x�[�X�d�����G�~�b�^�ɗ����_���C���s�[�_���X�ɉe������_���Ⴂ�܂����A�x�[�X�d���Ԃ�͔����Ȃ̂Ŗ�������Ƃ��ĉE�}�̂悤�Ȍv�Z���Őv���܂��B �@�A�����̉�H�ɂ�����̂�����ɓ��Ă͂߂��邩�ǂ����̋^�₪�N���Ă��܂��B �@���̃t�B���^�[��H���d���A�ґ�����H����{�Ƃ��Ă��āA�x�[�X�ւ̃o�C�A�X�d����Rb1��Rb2���d���d�������ăV���R���g�����W�X�^������_��0.6V�ɂȂ�悤�ɐv���܂��B �@�����d�������ĕK�v�ȓd���Ă����Ƃ����_�����ŁA�u�d���d����������x�����v�āA���u�d���d�������܂�ϓ����Ȃ��v�Ƃ����������K�v�ɂȂ�܂��B������Ɠd���d�����ω����������œK�ȓ���_���O��A�g�����W�X�^�̑����@�\�������Ȃ��Ȃ�܂��B �@���Ƃ��Ί��d�r�Q�{�p��3V�œ��삷��悤�ɐv����ƁA�d�r��������2.5V���x�܂ʼn�����Ƃ������삵�Ȃ��Ȃ�A�t��2�`2.5V���x�œ��삷��悤�ɐv����Ɩ�3V�ł͑S�����삵�܂���B �@�]���č���̂��b�́u�d����3.3V�v�Ƃ����̂������ƍ����d������3.3V�̎O�[�q���M�����[�^���������g���Ĉ��肵��3.3V����������Ă���Ȃ炱�̉�H�}�Őv���Ă��ΓK�ȉ�H�����܂����A���̏�����̂ł����������ƍ��͂�����߂܂��傤�B(���d�r�Q�{�g�p�ł͎g���Ȃ�����) �@���Ȃ݂ɁA�ŏ��̃}�C�N�A���v�̉�H���Œ�o�C�A�X������H�̂��߁A�d���d����1V���x�܂ʼn������Ă��g�����W�X�^�͑������������悤�Ȍ������g���Ă���(�ׂ��������͏ȗ����܂���)�A��Ɋ��d�r�P�`�Q�{�Ȃǂ̒Ⴂ�d���ŁA���d�r����������d���������肻�̍������\�傫�Ȃ��̂ɂȂ�悤�ȕs����ȋ@��Ŏ�Ɏg�p������̂ł��B 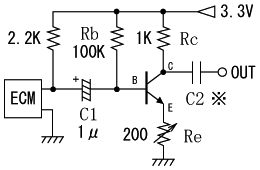 �@���Ă����ōŏ��̌��ݎg�p���̃}�C�N�A���v�̉�H�}��������x���Ă��������B
�@���Ă����ōŏ��̌��ݎg�p���̃}�C�N�A���v�̉�H�}��������x���Ă��������B�@��̃n�C�p�X�t�B���^�[��H���قƂ�Ǔ����Ɍ����܂��H �@�x�[�X��R���Œ�o�C�A�X������H�̂���Rb��ł����A�g�����W�X�^�̃x�[�X�d��������邽�߂ɂ���͂��̉�H�ł͖����ł��Ȃ��t�@�N�^�[�ƂȂ�A���̂�������܂߂Č𗬐M�����ʂ�ʂ蓹�Ɋւ��Ă̓n�C�p�X�t�B���^�[��H�ƂȂ��Ă��܂��B �@�{��C1�̓G���N�g���b�g�R���f���T�}�C�N�̏o�͓d��(����͒�����2.4V���炢)�ƃg�����W�X�^�̃x�[�X�d���̊Ԃ̍�����菜���A�����M���ł���𗬐M�������ʂ������������J�b�v�����O�R���f���T�̓�����������ׂɂƂ�����Ă���̂ł����A��H�}��͂��̓����Ɠ����Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B �@�Q�C�����ߗp��VR Re���ǂ̂ւ�ɉĂ��邩(�܂��g�����W�X�^�̃����N��)�Ńx�[�X�d���ɂ�������C���s�[�_���X���ω�����̂Ńo�V�b�Ɛ��l�����߂Čv�Z�ł��Ȃ��̂�������Ǝc�O�Ȃ̂ł����A��H�}�̒ʂ�ɍ���Ă����(������)�������300�`500Hz������ŃJ�b�g�I�t����n�C�p�X�t�B���^�[�ɂȂ��Ă��܂���I �@����������300�`500Hz�ȏ�(3KHz�܂ő���)�Ńt���b�g�B150Hz�ł�-6db�قnj������Ă��܂�������A�{�R�{�R�Ƃ��������̕��؉����Ƃ����ƒႢ���g���Ȃ̂ł��Ȃ茸�����Ă���͂��ł��B �@�ł��̂ŁA�u�J�b�g�I�t���g��300Hz�̃��[�J�b�g�t�B���^�[��t�������I�v�Ƃ�������̂���]�͊��Ɋ������Ă���Ƃ������Ȃ̂ł����E�E�E�i�O�O�G �@���������Ȃ肱�̓������������Ă��Ӗ����킩��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���A�^���������Ă���CR�t�B���^�[��H�̐����Ȃǂ��ǂ��ǂƏ���ǂ��Đ������Ă��܂������A�Ȃ���Ȃɂ����Ȃ��Ă������Ƃ����Ɏ�����������͂���܂łŏ��߂Ăł���(��) �@�����ƒ���g���J�b�g�������̂ł���A�R���f���T��1��F����0.47��F��0.22��F�A0.1��F���x�܂Ō������Ă݂Ăǂ̂悤�ɂȂ邩�������Ă݂���Ƃ悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B(����ȏ㏬������������Ɖ����ш�ł������������ĉ����������Ȃ��Ă��܂��܂�) �@���ꂼ��J�b�g�I�t���g���͍����Ȃ�܂����A����ȏ�Ɏ��ŕ������o�I�ɂ͒���g������ʂ��Ȃ��Ȃ鐫���͍����Ȃ�܂��̂ŁA���D�݂̌��ʂ������邩������܂���B �@�t�Ɍ����ƁE�E�E��ʓI�ȃ}�C�N�A���v���Ƃ��̃R���f���T�͒ቹ�����܂�J�b�g���Ȃ��悤��10��F��������g���Ă���̂����ʂȂ̂ł����i�O�O�G �@�ŏ�����n�C�p�X�t�B���^�[��(���R�ɂ�)�������}�C�N�A���v���g�p���Ă��ĕ��؉��������ȏꍇ�́A�}�C�N�����h�̂ق������܂����H���ꂽ�ق������P����邩������܂���ˁB �@���ɕ��h�͕t�����Ă���Ƃ͎v���܂����A�X�|���W�̗ʂ�傫���𑝂₵�Ă݂�Ƃ��A���ڕ�����������ɂ̓J�o�[�������ăX�|���W���ɕ�����ʂɐ������܂Ȃ��悤�ɂ���Ƃ��A�d�q��H���Œጸ����悤�ɍl������m�C�Y�����Ȃ�ׂ��キ������ǂ��ꏏ�Ɍ������Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2010/3/3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��������肪�Ƃ��������܂��B �@��H�}�̓\��t���̂̎d�������炸���萔�����������܂����B �@�����̉�H��1�Ԗڂ̐}�̂Ƃ���ł��B�i�uC2���v��10��F�ł��B�j �@�܂��ɓ������Y��ł���t�߂̉�����肪�Ƃ��������܂��B �@�n�C�p�X�t�B���^�[�̒�R��3�Ԗڂ̐}�̂悤��C1����O�����h�ɗ��Ƃ����̂Ɨ������Ă���A�����ł���Ƃ����ꍇ�ɂ́A�x�[�X��RRb1�Ƃ̍�����R�n���v�Z���ARb2�����肵����ŁA�ufc=1/(2��RC)�v��fc=300��������C1�̒l�����߂�Ηǂ��̂��E�E�ƍl���Y��ł���܂����B �@�}�P�̉�H�ł�Rb2���Ȃ��̂Ńt�B���^�[���ʂ��Ȃ����̂Ɨ������Ă���܂������Ƃ���ώQ�l�ɂȂ�܂����B �@��H�̌����͈�U�ۗ����A�����������������Ƃ���R���f���T��1��F����0.47��F�`0.1��F�Ō������Ď����Ă݂Ȃ���A�}�C�N�̃m�C�Y�����̓_�C�i�~�b�N�}�C�N�ł������Ă݂����Ǝv���܂��B �@��ς����J�ɂ��������������������Ă���܂��B �@�܂��u�������v���ɂ͂����k�������܂��̂ŁA�X�������t���������������B�i�j �@�{�����^���Y���Ŗc��ȉ�����Ă������̂悤�ł��B �@�����ł��̂悤�ȏ��ɐG��邱�Ƃ��ł���ς��炵���Əd�˂Ă���\���グ�܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����̂悤�ɉ�H�́u�C���s�[�_���X�v�Ƃ��������W���Ă���ꍇ�A��{�̗��_�}�̂悤��GND�Ɛڑ������H�������Y��������̂ł͂Ȃ��A�d���������Ƃ���S�Ăɒ�R�l(�C���s�[�_���X)�������ƍl����A���̓d�C�M�����d���̃v���X���ɂ�(����H)�����ꍇ�������ɃC���s�[�_���X����������ƍl���Čv�Z����Ƃ������ł��B �@�܂���ɏ����܂����ʂ�A�g�����W�X�^�̃x�[�X�|�G�~�b�^�Ԃł��d������������͐M�������猩��Β�R�l������o�H�Ɍ�����킯�ł��B �@�܂��A���������ׂ��Ȏ��͒u���Ă����āA����̉�H�ł͓��͕��̃J�b�v�����O�R���f���T��ς��邾���ŐF�X�Ǝ�����̂�(�蔲���݂����ł���)�I�C�V�C�ł��ˁi�O�O�G �@�g�����W�X�^�ő�����H��������肷��Ƃ��ɂ́A�e��R�l�����߂�̂ɑ�R�v�Z����K�v������̂œ����g���̂ł��܂�D���ł͂���܂���(��) �@�I�[�f�B�I��H�͂ӂ���̎d���ł��قƂ�Lj���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��ŁA������͒��قǂɂ��肢���܂��i�O�O�G �@���d��̋L���̎��ɂ������܂������u�g�����W�X�^����v�݂����Ȍv�Z��v�m�E�n�E���̘b��A����̘b�肩�甭�W���āu�t�B���^�[��H�̏�肢�v�v�݂����Șb�ɂȂ�ƁA���ꂱ�������̌��Ȃ́u�{����������Ă��܂��v�悤�ȑ�ʂō��ݓ������b�ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA�����̂悤�Ȉ��ꓚ�ʼn�H�������ċ^��ɂ���������悤�ȃR�[�i�[�ł͂ƂĂ���舵���Ȃ����x���̘b�ɂȂ��Ă��܂��܂��B ���Ԏ� 2010/3/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āA�F�X�ȕ�����鎞���̂g�o���Q�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��A��ς��߂ɂȂ芴�ӂ��Ă���܂��B �����ł����A��œ��{�~�c�o�`�������Ă���܂��A��N�H��X�Y���o�`�ɑ����P���ĉ�œI�ȑŌ����Ă��܂��܂����B �h��Ƃ��Ď����Ԃ̃C�O�i�C�^�ƃt�H�g�g�����W�X�^TPS601A(F)��LED���g�����Ռ��Z���T�ŃI�I�X�Y���o�`���~�c�o�`�̃Q�[�g�t�߂ɋ߂Â��ƃX�p�[�N���Č��ނ��镨�����ݒu���Ă���Ȃ�ɐ��ʂ��������̂ł����A�@������f�l�ɖт̐��������炢�̓d�C�I�m�������Ȃ��Z���T�[�̌�쓮�i���z���ɂ��j�X�C�b�`������Ȃ��������т��їL�����悤�ł��B �����ŃZ���T�[�̓������܂�L���Ȃ��Ă�������쓮�̏��Ȃ��Ռ��Z���T�������Ă������������Ǝv�����e���܂����A��낵�����肢���܂��B ���܂��� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�t�H�g�g�����W�X�^TPS601A��������Ɏg�p���āACds�ƃg�����W�X�^���ō��悤�Ȉ�ʓI�ȎՌ��Z���T�[��H��������Ƃ������ł��ˁB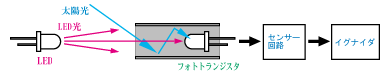 �@����ł����˂Ȃǂœ�����̗ʂ������̂łȂ��Ȃ���J����Ǝv���܂��B �@���ʁA���O�ȂǂŎg�p������Z���T�[�͒P���ɃZ���T�[�ɓ�������̖��邳�����o����̂ł͂Ȃ��A���Ă�����̂ɓ���̎��g�����������Ă����������ł��t�B���^�����O���āA����̑��M�@���甭�����ꂽ�������ɔ��������Z���T�[��H��p����̂���ʓI�ł��B �@�����́A���W�I��e���r��z�����Ă݂Ă��������B �@��C���ɂ͗l�X�ȑ��M�����瑗�M���ꂽ�d�g��������܂��ɔ�ь����Ă��܂��B�e���r�E���W�I�����ł͂Ȃ��e��̖�����g�ѓd�b�ȂNj��낵���قǂ̐��̓d�g����x�ɑ��M����Ă��āA��͓d�g�ɖ������Ă��܂��B �@�������e���r��W�I�̓`�����l�������킷�Ɠ���̕����ǂ̓d�g��������M���Ĕԑg���������邱�Ƃ��ł��܂���ˁB �@����͊e�ǂ̑��M����d�g�̎��g�����������̎��g���Ɍ��߂��Ă��āA���W�I��e���r�̎�M��H�ɂ́u������H�v�Ƃ�����H�������āA�l�Ԃ��`�����l����I�ԑ���Ŏ��͂��̓�����H�ɂ�����̎��g�����w�����邱�ƂŁA��M��H�͂����g���̐M�����������o�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@���Z���T�[�ł�����̎��g���̌��������g���Ύ������Ƃ��ł��܂����A���̎��g���Ƃ����̂͂ƂĂ������Ă����ȒP�ɓd�q��H�ő��삷�邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�����Łu�ԐF�̌��������g���v�Ƃ��u�ԊO���������g���v�Ƃ������@�ł���A�ԐFLED�ƐԐF�����ɔ���������Z���T�[�A�ԊO��LED�ƐԊO���t�H�g�g�����W�X�^�ȂǁA����́u���̔g���v������������f�q�Ƃ���ɂ��������������f�q���g���Ύ������Ƃ͂ł���ł��傤�B �@�����ł͏Ɩ��Ȃǂ͉������͈̔͂̌����o���Ă��āA�ԊO���͂��܂薳���̂��ԊO�����g�p���邱�Ƃ������ł��B�e���r�̃����R���Ƃ��͂قƂ�ǂ��ԊO�������ł��ˁB �@�����A���̕��@���Ɖ��O�Ŏg���Ƒ��z���ɂ͐ԊO�����率�O���܂łقڑS�Ă̔g���̌����܂܂�Ă��邽�߁A��͂葾�z����������Ƃ��̖��邳�ŖW�Q����Ă��܂��ď�Ɍ�����������ςȂ��ƌ딻�f���Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B �@�����ł������瑾�z�����������݂܂�����A���z�����̐ԊO�������͖������邱�Ƃ��ł��܂���B �@�Ƃ������ŁA�����g�����Z���T�[��H�ł������̂��̂̎��g���Ɋւ��Č��o����̂ł͂Ȃ��A�X�����̌��ɕϒ��������ē���̓d�C�M����������Ƃ����̓d�C�M�������o�������@���Ƃ��ĐM�����o���m���Ȃ��̂ɂ��܂��B �@�����ԊO�����g���Ƃ��āA���̐ԊO�������̎��g���ŕϒ�(�_��)���Ă��ƁA��Ԃɗl�X�Ȕ�ь����Ă���ԊO���̒����炻�̓���̕ϒ������������ԊO���M���݂̂𒊏o���āA���̐M�����L�邩�������̔��ʂ��ł��܂��B �@�ϒ�������g���͂Ȃ�ł��悭�A���ɕ������邭�炢�̒���g����A�ԊO��LED��t�H�g�g�����W�X�^���������邬�肬��̍����g�܂ł̊ԂōD���Ȓl��I��ŁA���̎��g���ɂ��킹�����U��H�Ɠ�����H������Ă����������ł��B �@���������ł��E�E�E�ƌ����Ă����͓�����H�����ƂȂ�ƌ��\���G�ȉ�H���K�v�ɂȂ�A���i�����������߂��ʓ|�Ȃ̂Łu������������H���S�������Ă��镔�i�v�Ƃ����ƂĂ��X�o���V�C�����g�p���邱�Ƃɂ��܂��B �@����́A���܂ʼn��x���o�Ă���u�ԊO�������R��������W���[���v�ł��B �@�ԊO���̃����R���M���́A�P���ɐԊO��LED���f�W�^���M���œ_�ł����Ă��邾���ł͂���܂���B �@���͐ԊO��LED��_����������Ԃɂ�38KHz(*)�ŕϒ����Ă��āA��M����38KHz�ŕϒ����ꂽ�ԊO���M���݂̂����o�������݂ɂȂ��Ă��܂��B �@�������ԊO�������R��������W���[�����ɂ͐M�������ʂ�����ɁA�����38KHz�̔��U�M������菜�����Y��ȃf�W�^���M���Ƃ��ďo�͂��邽�߂Ƀf�W�^����H�łƂĂ��g���₷���Ȃ�܂��B �� 38KHz�͋K�i�̂����̂P�ŁA�ق��̎��g���̕�������܂��B
�@�Ƃ������ŁA�ԊO���t�H�g�g�����W�X�^��38KHz�̃t�B���^�����O�E������H�A�f�W�^���o�͉�H���S���P�̃p�b�P�[�W�ɓ����Ă���u�ԊO�������R��������W���[���v���g�����Ŗʓ|�Ȏ�M��H�̂قƂ�ǂ̕��������i��Ŋ������Ă��܂��B���38KHz�ŕϒ����ꂽ�ԊO���M���𑗐M���鑗�M���������������ƂȂ�܂��B �@���ۂ͎�M���͂����������IC����lj����āA�������Ռ��Z���T�[�Ƃ��ē��삷��悤�ɂ���K�v�͂���܂����E�E�E�B �@��H�}�͂�����ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���M�� �@�V���~�b�g�^��NOT��H��C-MOS IC 74HC14���g�������U��H��38KHz�̃f�W�^���M�������܂��B �@VR1����30�`46KHz�̊ԂŔ��U���g���߂ł��܂��B �@VR1���قڒ����ɂ���Ɩ�38KHz�Ŕ��U���܂����A��̒��ߕ��@�̍��łȂ�ׂ����������߂��܂��B �@LED1���ԊO��LED�ł��B(�e�X�g�Ŏg�p��������L-53F3BT 21�~) �@�d�q���i�X�Ŕ����Ă���u�ԊO�������R���p�v�Ɏg����ԊO��LED�Ȃ炽���Ă��̂��̂��g���܂��B �@�ԊO��LED�̓P�[�u���������Ďg�p���܂��B �� ��M�� �@�ԊO�������R��������W���[����IRM-3638N3���g�p���܂��B �@�H���d�q�ȂǂŔ����Ă���ԊO�������R��������W���[���ł����v�ł��B(�A��������̏o�͂�L�̂���) �@��p�̎�����W���[�����g�p���܂����A�����������˓�������������������̐ԊO���ȂǂŖO�a���Đ���ɓ��삵�܂���A�u���v�܂��́u���v�͕t���Ē��ڑ��z����������Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@����قǒ������͕̂K�v�����A���˓������Z���T�[�ɓ�����Ȃ������{�����x�Ō��\�ł��B �@�ݒu�ꏊ���H�v���āA�Ȃ�ׂ����z�̑��ɃZ���T�[��u���đ��z��w���ɂł���ق��������ł��ˁB �@�ԊO�������R��������W���[���̏o�͎͂ア����74HC14�̃Q�[�g�Ńo�b�t�@�����O���AC3�ER7�̐ϕ���H�Ńm�C�Y�ł̌�쓮��h���܂��B �@LED2�͎�����j�^�[�p�ŁA38KHz�̐M����������͌���܂��B�����Ղ�Ə����܂��B �@OUT�[�q�́u�Ռ�����H�v�ł�����A�g�A�N�e�B�u�œ��삷��@���ڑ��ł��܂��B �@�C�O�i�C�_�[���쓮(ON/OFF)���Ă����H���ǂ��Ƃ��͂��b���̒��ɏo�Ă��܂���̂�OUT�[�q�����͂������Őv���Ă��������B �@���Z���T�[��H�����삳��Ă���̂ł�����A���̂�����͑��v�ł��傤�B �� �d�� �@�ԊO�������R��������W���[����74HC14���d����5V�Ȃ̂�5V���������Ă���Ă��������B �� ���� �@�������������A���M�p�̐ԊO��LED��ԊO�������R��������W���[���̋߂��̐��ʂɒu���AVR1���قڒ����ɂ��ēd���������LED2���_������͂��ł��B �@��ȂǂŌ����Ղ��LED2�͏������܂��B �@�����܂ł̓�����m�F������AVR1�����E�����ɉĂ݂āALED2��������p�x���m�F���܂��B �@�p�x���m�F�ł�����A���ɔ�������p�x�͈̔͂̂قڒ����ɖ߂��܂��B �@���ۂɐݒu����ۂɂ́A�ԊO���͖ڂɌ����܂���ԊO��LED�̌��������Ɛ��ʂɌ����Ă��āA������W���[���ɏƎˌ��̒��S�����Ă��邩�ǂ������m�F���邽�߂�LED2�̓_�������Ȃ���ʒu���킹�����Ă��������B �� ���p�͈� �@�ԊO��LED�ƐԊO�������R��������W���[���̊Ԃ̋����͖�P���[�g�����x�܂łł��B �@����ȏ�̋����ł͎g���܂���B �@�e���r�Ȃǂ̐ԊO�������R���͐����[�g�����x�̋����Ŏg���܂����A�ǂ����IRM-3638N3�̓����̃t�B���^�E������H�̓����Łu��(38KHz)���A�������Ԃł͊��x���݂�v�Ƃ�����ԂɂȂ�悤�ł��B�i���̃��[�J�[�̐ԊO�������R��������W���[�����Ƒ����̈Ⴂ�͂���Ǝv���܂��j �@����̎Ռ��Z���T�[�ł�38KHz�����͏o���ςȂ��ł����A�����R���Ȃǂł̓f�W�^���M���œ_�ł����Ă���̂ł��������M�����Ƃ����ƒʐM�������L�т܂��B �@��������������f�[�^���ɓ_�ł������H�܂őg�ݍ���ł��܂��������������͐L�т�ł��傤���A�������̎Ռ��Z���T�[������قNj�����L���Ďg�p���Ă��Ȃ����낤�Ɣ��f���ĊȈՔłŕ��i�������Ȃ����Ă��܂��B ���Ԏ� 2010/2/21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �h�b�������W���[���Ȃǎ莝��������܂���̂ő����w�����Đ��삵�Ă݂܂��A���ʂ������܂��B���Ȃ݂ɎՌ��Z���T�[�̋�����30�����ł��B ���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@30cm���炢�Ȃ���v�ł��ˁB �@���������為�Ћ����Ă��������B ���Ԏ� 2010/2/22
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
����͂��肪�Ƃ��������܂����A�Ռ��Z���T�[���i�����܂����̂ő������삵�Ă݂܂����B �i��H�}����74HC14��GND��8�Ɍ����܂���7�s���ŗǂ������ł���ˁB�j �����܂����I�B�����O�Ŏ��������Č��܂��������ʂ͗ǍD�ł��B ������x���z��������悤�ɐF�X������ς��Ď��������̂ł��������Ɠ����܂����A�����I�����ł��I�B ����t���Ȃ��ł��傤�ǃX�Y���o�`�̑傫���ȏ�ō쓮���܂��A�~�c�o�`�̑傫���ł͍쓮���܂���p�[�t�F�N�g�ł��B ��͂k�d�c�̋ʐ�Ƃ��Z���T�[�ɉ������|����Ƃ��̕s��ɂ��A���I�ɍ쓮���Ȃ��悤�Ɂu��莞�Ԉȏ�̃g���K�[���m�����[�v���Q�l�ɂ����Ă�����ăL���X�C�b�`��t���悤�Ǝv���Ă��܂��B �����쓮�����2���{���g�ȏ�̓d�����A�����ďo�܂��̂ň��S���u�ł��B ��N�͂��ݎE����ă~�c�o�`�̎��[�̎R���o���܂������A���N�͂�����x����Ă���Ǝv���܂��B ����ɖI���������肵�����C�����ł��A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B ���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@74HC14��GND��7�ԃs���ł��B�Ԉ���Ă��܂����̂Œ������܂����B �@LED��≽���������������ēd�����o���ςȂ��ɂȂ�̂�h�~����ɂ́A�^�C�}�[IC555�܂���74HC221���g���������V���b�g�^�C�}�[�ȂǂŁA�Ռ����ꂽ���莞�Ԃ����C�O�i�C�_�[���쓮��������@�����邩�Ǝv���܂��B �@�����u��莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H�v���C�O�i�C�_�[��12V�d���n�Ɍq���ŁA��莞�ԓd����ON�ɂȂ���ςȂ��ɂȂ�����OFF�ɂȂ郊���[�Ƃ��Ďg�p����̂ł���A���������Z���T�[��H��IC��H�œ��삵�Ă���̂ł�����AIC���g�����u�^�C���E���~�b�^�[��H�v��lj�����Ă͂������ł��傤���B  �@���Œ��R�Ő������Ԃ���0�`12�b�ŔC�ӂ̎��Ԃɐݒ�ł��܂��B �@�o�͂��������Ԃ��z����ON�ɂȂ���ςȂ��ɂȂ낤�Ƃ���ƁA���~�b�^�[�������ďo�͂�OFF�ɂ��܂��B �@��U�Ռ��Z���T�[��OFF�ɂȂ���~�b�^�[����������āA�܂����ɎՌ����ꂽ��o�͂�ON�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@LED�͈ꉞ�p���X�_���Œ�i���Ŏg�p���Ă��܂����A����30cm�Ƌߋ����Ŏg�p���Ă��Ă���قNj��͂ɓ_�����Ȃ��Ă��悢�̂ł���AR4 100�������������傫�Ȓl(200�����炢�H)�ɂ��ēd���l�����Ȃ�����A��蒷�����Ŏg�p�ł��܂��B �@�����キ����Ƒ��z���̉e�����₷���Ȃ�܂�����A���̂ւ�͎��n�Ńe�X�g���Ă݂Ď��p�ׂ͈͂ĕύX���Ă݂���Ƃ悢�ł��傤�B �@���̑��u�Ń~�c�o�`�̑����ɓ��荞�����Ƃ���X�Y���o�`���ނɌ��ʂ��オ��Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2010/2/25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 2/26 |
�d�ˏd�˂����������������肪�Ƃ��������܂��B ���Z�b�g�������Ƃ������Ƃł܂����S�ʂƃZ�L�����e�B�[�̖ʂł����������܂��A�������삵�Ă݂܂��B �����ł����A���d���ɂ����̂̓Q�[�g�̍������L�����鎖�ƃQ�[�g���O�ŃV���b�N��^���鎖���o����ׂł��B ���Ȃ݂ɃI�I�X�Y���o�`�͒Z���Ԃ̓d���ł͎��_�͂��܂����߂����Ɏ��ɂ܂���A�Ƃɂ����Q�[�g��蒆�ɓ����Ă��ꂳ�����Ȃ���~�c�o�`�̔�Q�͍ŏ����ōς݂܂��B ���R�E�ł̓X�Y���o�`���厖�Ȗ�ڂ����Ă��܂��A�K�v�ȏ�ɎE���Ȃ������Ǝv���܂��B �F�X�Ƃ��肪�Ƃ��������܂����B����Ƃ���낵�����肢���܂��B ���܂��� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āA�_�ʼn�H�ł������Ă܂�����M�T�C�g�ɂ��ǂ蒅�������[���q�������Ă��������Ă���܂��B��H�}�����Ȃ��烉�W�I�Ȃǂ̂j�h�s��g�ݗ��Ă郌�x���ł�����낵�����肢���܂��B ����A�X���̂o�n�o�Ƃ��ė��p�o���Ȃ����ƏH���d�q�ʏ��Œ��f�J�d�k�����p�l���E��p�C���o�[�^�Z�b�g�𐔃Z�b�g�w�����܂������t�����Ă���C���o�[�^�[�͂X�u�̓d�r���g���ď펞�_���Ȃ̂ł��B ������P�Q�u�̓d�����g���ē_�ł���C���o�[�^�[����肽���Ǝv���Ă��܂��B �d�k�V�[�g�̓J�b�g���ĂP�O�O�����Z���`�قǂŎg���Ă���܂��B �Ђ�ڂ� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�H���́u���f�J�d�k�����p�l���E��p�C���o�[�^�Z�b�g(��)(��)(��)�v�Ƃ������i�͔��������Ƃ������̂ŁA�ڂ������͂킩��܂��A����d���͂ǂꂭ�炢�ł����H �@�d�k�p�l���̖ʐρA�d���d���ɂ���ď���d���͑傫���ς�Ǝv���܂��A100�����Z���`�œd���d����6V�̎��̏���d���������Ē�����Ί������̂ł����A�킩��Ȃ��ꍇ�͉��Ɏ�����H�}�̂܂܂Ō��\�ł��B �@�d�k�Z�b�g�̏��i�����ɂ� ����p�C���o�[�^�t�i�c�b�T�u�`�U�u�ł��g�p���������j ���t���̂O�O�U�o�d�r�͓_�������p�ł��i�X�u�ł����d�r�̓�����R���傫���̂œ_��������ƂU�u���炢�܂Œቺ���܂��j �Ƃ���܂����A���������悤�Ɂu�X�u�̓d�r���g���ď펞�_���v�Ə�����܂��ƁA�H���̒��ӏ�����m�炸�ɂ��ꂾ�������ƂX�u�Ŏg�p�ł�����̂Ǝ��܂��B �@����Ƃ��A�H���̐����̂悤�ɃC���o�[�^��5�`6V�d���Ŏg�p�������Ƃ�������]�Ȃ̂��悭�킩��܂���B �@�H���̒ʔ̃y�[�W�ł́u�S�`�Q�T�u�i�ő�T�`�j�σX�C�b�`���O��d���d���L�b�g (K-02190)�v�̎g�p�𐄏����Ă���悤�ł�����A������g�p�����̂��ǂ��ł��傤�ˁB �@�d�k�̏���d�����킸���ł���A����Ȃɂ��������ȓd�����j�b�g�͕K�v�Ƃ��������Ƃ�������邱�Ƃ��ł��܂����A���͂��̏��i�������Ă��܂���̂Ŋm�F���ł��܂���A�N������Ă��ԈႢ�������悤�ɏH���̐�������d�����j�b�g���g�p���čl���邱�Ƃɂ��܂��傤�B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���U��H �@���U��H�͂�����݂��^�C�}�[IC 555���g�p���܂��B �@���U���g������0.6�`2.5Hz�Œ��߂ł��܂��B �� �_�Ő���p�X�C�b�` �@�X�C�b�`���i�ɂ̓p���[MOS FET��2SK2232���g�p���Ă��܂��B �@�d�����W���[�����ő�T�`�炵���̂ŁA���ꂭ�炢�d��������Ă����v�Ȃ悤�ɂ��Ȃ�傫�ȓd���e�ʂ�FET���g�p���Ă��܂��B �� �H���̏��i �@�u���f�J�d�k�����p�l���E��p�C���o�[�^�Z�b�g�v�Ɓu�S�`�Q�T�u�i�ő�T�`�j�σX�C�b�`���O��d���d���L�b�g�v�͏H���̏��i�ł�����A�g�ݗ��Ă�g�p���@�͕t������������ɏ]���Ă��������B �@�u�S�`�Q�T�u�i�ő�T�`�j�σX�C�b�`���O��d���d���L�b�g�v�̏o�͓d�����߃{�����[�����ďo�͂�4�`6V���x�̊ԂŒ��߂���A�d�k�̖��邳�߂ł��܂��B �@�d�k�̏���d���̍��v���R�`�������x�܂łł���A�����H�Ɓu�S�`�Q�T�u�i�ő�T�`�j�σX�C�b�`���O��d���d���L�b�g�v�͂P�g�ŁA�d�k�Z�b�g�𐔃Z�b�g����ɓ_���ł���Ǝv���܂��B �@���삷��d�q��H�����͕��i�������Ȃ��A�z����g�ݗ��Ă�����قǓ�����̂ł͂���܂���̂ŁA���������������ԈႢ���������m�F����g���u�����������ł��傤�B ���Ԏ� 2010/2/13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���Z�������A�����ɕԓ����Ă����������肪�Ƃ��������܂��B �d���͂��w�E�̒ʂ�U�u�̎d�l�ŁA�O�O�U�o�d�r���g��Ȃ��łP�Q�u�̓d�����g�������ƌ����Ӗ��ł����B ����d���͂V�O���`�قǂł����A����d�k�V�[�g�̃T�C�Y��ύX���Ă��g����ق��������̂ŁA��������H�}�Ő��삵�Ă݂����Ǝv���܂��B �s�i�C���������r��钆�A����ŏ����ł����オ��鎖���F���Đ��삵�܂� �Ђ�ڂ� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@70mA���ł����炩�Ȃ��R�q���ł����v�ł��ˁB �@�ڗ��f�B�X�v���C�ɂ��āA�����ł����オ�オ��Ƃ����ł��ˁI ���Ԏ� 2010/2/14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 3/6 |
����͂��肪�Ƃ��������܂����B�����I�Ɋm��\���Ƃ����Q�s���ɂȂ鍠�ɂȂ��Ă��܂��쐬���x��܂������{������ƃu���b�h�{�[�h��ł����_�ł����鎖���ł��܂����B �_�ŃX�s�[�h���C�ӂɌ��߂���̂Ŋ������Ă܂��B �o�n�o�̑n��ӗ~���킢�Ă����̂ŁA�X�Ɋ����肽���Ǝv���܂��B �{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��� �Ђ�ڂ� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��� ���́A���Ɨp�Ԃ�PC�iWindows�@�j���ԍڂ��Ă��܂����Ɩژ_��ł��܂��āA�P�QV�P��d��PC�₻�̑��̋@�ނ͑������̂ł����A�B��d���ɂ��ė��p�ł��镨���A��������Ȃ��̂ŔY��ł��܂��B �d�����̂��̂ɂ��ẮA�Ԃ̃o�b�N�A�b�v�d���Ɍq���ŁAPC���̂̃I���A�I�t�́APC�̓d���X�C�b�`���瑀��o����Ηǂ��̂ł����E�E�EPC�{�̂̓V�[�g���ɐݒu���܂��̂ŁAPC�{�̂̓d���X�C�b�`�ɂ͎肪�͂��܂���B ����ł́APC�̓d���X�C�b�`�ƕ��s�ɔz���͊O���Ɉ����o���č݂�܂��̂ŁA�A�N�Z�T���d�������鎞�Ɉ�u�i�P�b���j����ON�B �܂��A�A�N�Z�T���d������鎞�ɂ܂��P�b��ON�ɂȂ�l�ȉ�H������APC�d���̐�Y�ꓙ���h�~�ł���̂ŁA�ǂ��Ǝv���̂ł����A�g�߂ɗ��p�ł���悤�ȉ�H������܂���B�����͒�����Ǝv���A���e�������܂����B�܂��A�����s���ȓ_������Ǝv���܂����A��낵�����肢�������܂��B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u������ON�ɂȂ����������o����v�u����������OFF�ɂȂ����������o����v�Ƃ�����H�͎��͂��̂������P���ȃ��W�b�N��H�Ŏ����ł��܂��B �@�����Ă��̉�H�̌����セ�̓����̓^�C�}�[��H�����˔����Ă���̂ŁA����̂���]�̂悤�ȁu�����̐M����ON�܂���OFF�ɓ]�������ɁA��莞�ԏo�͂�ON�ɂ���^�C�}�[�v�Ƃ��������͂ƂĂ��V���v���ȉ�H�ɂȂ�܂��B �@���̉�H�Ŏg�p����IC�ő��̕����̉�H���g��ł��܂���悤�ɍl�����IC��ōς݂܂����B �@������Ԃɐς��DC12V�œ��삷���H�Ƃ��A�o�͂͂o�b�̓d���X�C�b�`(�����ATX�d�����Ɠ��������[�g�p�H)�𑀍�ł�������̂ł���p�ɐv���܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �d���Ɠ��̓J�v���[ �@����̉�H��74HC�n��C-MOS���W�b�NIC���g�p���鎖�Ƃ��A�d����5V�œ��삵�܂��B �@�Ԃ̏펞�d��(�����PC���Ɏg�p���Ă���o�b�N�A�b�v�d��)����12V��������āA�O�[�q���M�����[�^��5V�ɗ��Ƃ��Ďg�p���܂��B �@5V�ɗ��Ƃ��Ďg�p����̂̓m�C�Y���������Ԃ̒��ł��̉�H�����肵�ē��삳����ړI�����˂Ă��܂��B �@�{��H��5V�n�œ��삷�邽�߁AACC�d�����猟�m����12V���͂̓t�H�g�J�v��(TLP-521-1)�ŃJ�b�v�����O���܂��B �� ACC���͂̃m�C�Y�� �@ACC���͂ɍׂ��ȃm�C�Y������Ă����ꍇ�A����ɉߕq�ɔ������Ă͂o�b�̓d�����o�`�o�`��ON/OFF���J��Ԃ��Ă����ւ�Ȏ��ɂȂ�܂��B �@�����Ŗ�0.1�b���x������ACC�̓d���ω��ł͔������Ȃ��悤�ɁA��R(R3)�{�R���f���T(C1)�̐ϕ���H�Ńm�C�Y����菜���܂��B �@���̃m�C�Y������H�̓��쎞�Ԃ̊W�ŁA�o�b�̃X�C�b�`��ON/OFF����o�͎͂��ۂ�ACC��ON/OFF�����u�Ԃ����0.1�b���x�x��܂����A���p��͖��͂���܂���B �� ACC�ω����m���^�C�}�[��H �@ACC��ON����OFF�A�܂�OFF����ON�ɂȂ����������o����A�{��H�̃L���͂��̕����ł��B �@�����ł�EX-OR(�G�N�X�N���[�V�u�E�I�A�^�r���I�n�q)�Ƃ����_����H���g�p���܂��BIC��74HC86�ł��B �@EX-OR�Q�[�g�͒ʏ��OR�Q�[�g�Ɠ������u���͒[�q�̂����ꂩ�P�ł�H�ɂȂ�Ώo�͂�H�ɂ����v�Ƃ���OR�Q�[�g�Ƃ��Ă̓�������{�Ƃ��āA�u�r���I�v�Ƃ�������ȋ@�\��������Ă��āu���͂̂ǂ��炩�Е�������H�̏ꍇ�����o�͂�H�ɂ����v�Ƃ��������ɂȂ�܂��B �@����������Ɓu�Q�̓��͏�Ԃ������ꍇ�͏o�͂�L�v�u�Q�̓��͏�Ԃ��Ⴄ�ꍇ�͏o�͂�H�v�ƂȂ�܂��B 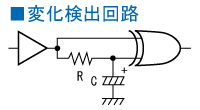 �@����EX-OR�̂Q�̓��͒[�q�ɁA�Е��͓��͐M�������̂܂��A�����Е��ɂ͓��͐M����CR�̒x����H�Œx�点���M������͂��Ă��A���͐M�����ω������������o�͂�H�ɂȂ��Ƃ����ω��_�̌��o��H���o���オ��܂��B
�@����EX-OR�̂Q�̓��͒[�q�ɁA�Е��͓��͐M�������̂܂��A�����Е��ɂ͓��͐M����CR�̒x����H�Œx�点���M������͂��Ă��A���͐M�����ω������������o�͂�H�ɂȂ��Ƃ����ω��_�̌��o��H���o���オ��܂��B�@�����x����H�̎��萔�����̂܂܁u�o�̓p���X�̎����v�ƂȂ�܂�����A���Œ��RVR1�Ńp���X���Ԃ��0�`2�b�̊ԂŒ��߂ł���悤�ɂ��Ă������ƂŁA����]�́u��P�b�v�O��Œ��߂��Ă��������܂��B �� �o�b�̓d���𑀍삷���H �@���ʂ�ATX�d���ł���A�u�d���X�C�b�`�R���g���[����(�ΐF)�v��GND�ɗ��Ƃ����ŃX�C�b�`������������d�����u�����̃��W�b�N�ɓ`����̂ŁA���̏ꍇ�̓g�����W�X�^�ŃX�C�b�`���v�b�V������̂Ɠ����悤�Ƀ`������GND�ɗ��Ƃ��o�b�̓d������ꂽ�������ł��܂��B �@���g���̂o�b���u12V�P�d���œ��삷��v�Ƃ������ŁA���͂��������d���œ����o�b���������Ƃ������̂ŁA�X�C�b�`��GND�ɗ��Ƃ��^�C�v�ł͖����\��������܂��̂Ńt�H�g�J�v���ɂ��≏�����āA�ɐ����ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��Ă��{�Ɓ|�����q���Ԉ��Ȃ�������[�g���삪�ł���悤�ɂ��Ă����܂��B �@�t�H�g�J�v�����g�p�����X�C�b�`�ł��̂Ő��\mA���x�̔���ȐM�������R���g���[���ł��܂���B���ʂ�ATX�d���Ȃǂ̃����[�g�X�C�b�`�[�q�ł���Ζ��͖����͂��ł����A�����傫�ȓd���𗬂��Ă���X�C�b�`�ł���Ζ�肪�o�܂��̂ł��������������B �� �����ƒ��ӓ_ �@�g�ݗ��ĂɊԈႢ��������AACC�d����ON������OFF�����肷��Əo�͂�VR1�Œ����������Ԃ���ON���܂��B �@LED1������܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ȃ���VR1�Ŏ��Ԓ��߂��Ă��������B �@���ӓ_�Ƃ��ẮA�^�C�}�[���쒆(�o�͂�ON�ɂ��Ă��鎞�Ԓ�)��ACC���܂��ω������ꍇ�A�x�����̐M���Ɠ��͐M�������v���܂��̂ŏo�͂͑�OFF�ɂȂ�܂��B�K�v�Ȏ��Ԃ����o�͂�ON�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂���B �@�܂��x����H��CR�ɂ��ϕ���H�ŁA���W�b�NIC��臒l�̊W�Ń^�C�}�[�o�͂�ON�܂���OFF�ɂȂ�������܂��[�d�E���d���s���Ă��܂��B�������̊�(���b���x)�ɂ܂�ACC����ւ����ꍇ�ɂ͂�͂�o�̓p���X���ݒ莞�Ԃ����ς��ŏo�Ȃ��ꍇ������܂��B �@�o�͂����肵�ē��삳���邽�߂ɂ́AACC�̑���͂T�b�ȏ�J���čs���Ă��������B �@�o�`�o�`��ACC��ON/OFF����悤�ɃL�[���K�`���K�`���Ƃ͉Ȃ��ł��������B ���Ԏ� 2010/2/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����̉L���������܂��B �������������܂�����H�E�E�E�u�Y�o���I�v�ȉł��B �܂��A�ꏏ�ɉ�H�̐��������Ē����A��ϔ���Ղ��q���������܂����B �����ɂ��Ō�ɍ�����̂��A�uZ80�̃����{�[�h�}�C�R���v�̎���ŁA����ȍ~���������Ă��܂����̂ŁA�܂���y���݂��������C���ł��B �����A���i�̎�z���������܂����̂ŁA�܂�����Ȃ������݂�܂�����A��낵�����肢�������܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����]�ɓY������{�̓���͂���Ǝv���܂��B �@��ŏ������悤�ɃL�[���K�`���K�`�������ȂǂɁA�Z���p���X�����o�Ȃ�������A�{���͂Q��p���X���o���Ăo�b�̓d����ON���Ă�����OFF���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ȏ��ɂP��̃p���X�����o�Ă��Ȃ��Ăo�b��������ςȂ��ɂȂ�����ƁA�Z���ԂŃK�`���K�`������Ǝ蓮�X�C�b�`�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂȂ邩������܂���B (���ʂ̓K�`���K�`�����Ȃ��ł��傤���A�O�̂���) �@�����L�[�̃K�`���K�`���ł������ɑΉ�������ɂ́APIC�}�C�R���Ő��䂵�āA�o�b�̓d����Ԃ����m���Ă��������l�Ԃ����f���đ��삵�Ă���悤�ȓ��������C���e���W�F���g��ACC�A���}�C�R���X�C�b�`���������̂ł����E�E�E�B �@�����I��PIC�}�C�R���Ȃǂ̍��@�\�ȃf�W�^��IC���g���@�B������A�����������������Ă݂�̂��ʔ�����������܂����i�O�O�G ���Ԏ� 2010/2/11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āBRon�Ɛ\���܂��B ������ϊy�����q�����Ă���܂��B Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H�����]�ԃ��C�g�ɑg�ݍ��������ƍl���Ă���܂����ˑR�J�b�g�I�t�����̂��|���̂Ŏ��O�Ɍx���̂���LED�i�ԁj���_������Ƃ��ꂵ���̂ł����ȒP�ɒlj��ł��܂��ł��傤���B ���������肢���܂��B Li-ion�ߕ��d�h�~��H�ւ̌x��LED�lj��ɂ��Ă��肢�������܂������������s�����Ă��鎖�ɋC�Â��܂����B �x�����̓_���d���ł����ߋ��̋L����q�����܂��Ɛ��f�j�b�P���d�r�ŃZ��������1.1v�A���`�E���C�I���d�r�ł���3.5v�����肩��}���ɓd���ቺ���������悤�ł��̂ł��̂�����ł̓_������悤�ɂ��肢�������Ǝv���܂��B2�x��Ԃ����������\����܂���B Ron �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�悭�u�ȒP�ɒlj��ł��܂��ł��傤���v�Ə��������������Ă��܂����A�ǂ̒��x���u�ȒP�v�Ȃ̂ł��傤���H �@�܂������ł����ǁE�E�E�B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�x��LED�����������d����VR2�Œ��߂��Ă��������B �@������̓q�X�e���V�X���������Ă��܂��̂ŁALED�͔�r�I�p�b�Ƃ�����������肵�܂��B �@�J�b�g���̉�H�������ďo�͂��J�b�g�����ꍇ�A�A�������x��LED�͂����ςȂ��ƂȂ�܂��B �@�J�b�g���ēd�r�̓d�����x���d�������Ă�LED�͓_�������܂܂ł��B����̓J�b�g�������Ƃ�\������ׂɂ������Ă��܂����A����������LED�������������ꍇ��D2�����Ă��������B �@��́uLi-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H�v�̐����̂Ƃ���ł��B �@������̋L�����͂��߂ēǂ܂����́A�d�����߂̕��@�Ȃǂ͌Â��L���ɏڂ��������Ă��܂����炠�킹�Ă��ǂ݂��������B ���Ԏ� 2010/1/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 1/28 |
�����̂������L��Ƃ������������B �������삵�Ă݂����Ǝv���܂��B �܂��͌��܂� �q���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���߂܂��āA��ς��߂ɂȂ������Ŗ��ɗ����Ă��܂��B 100V�܂���200V�����ꂽ�������o�������̂ł��B OMRON���̃^�C�}�[���o�R���č쓮���Ă���d���فE�����[����ON���Ԃ��A���L���Ă���H���d����Dr.DAQ�ő��肵�����̂ł����A�ǂ����@�����������������B Dr.DAQ�̓d�����背���W��0�`5V�ƂȂ��Ă��܂��̂ł��̕������g����Ǝv���Ă��܂��B �wAC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF�x��q�������̂ł����A�g�p�d�������Ȃ��ׁA�g����̂��s���ł��B �o����A���G�ȉ�H���g�p���Ȃ����@��������肢�v���܂��B Kay �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�P���Ɂu100V(�܂���200V)�̋@�킪���삵�������𑪂肽���v�Ƃ��������ł����H �@����Ȃ炻�̋@��ɕ����100V(�܂���200V)�����[���q���ŁA�����[��5V��ON/OFF����Dr.DAQ�̓��͂Ɍq�������ł͂����߂Ȃ̂ł����H �@���G�ȃZ���T�[�����H�Ȃǂ�S���g�p����K�v�͖����Ǝv���̂ł����B �@�ׂɁuAC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF�v�̑����x���グ�Ă���Ă������ł����A���������ȓd���ɂ��Ή������u�ȈՃf�W�^���\������d�͌v�v�̑����x���グ�Ă������ł��ˁB �@�d���ق͂Ƃ������A�����[���đ����ƂĂ����Ȃ��d�͂œ��삵�Ă��܂�����A�����[������������Ă���悤�Ȕz���ɃJ�����g�Z���T�[�̂悤�ȕ��ĂĒ��ׂ�ɂ́A����d�͌v�̉�H�̂悤�Ȕ���d�������肵�đ���ł����H��g�܂Ȃ��Ɛ���������ł��Ȃ��\���͍����ł��B �@�ŏ��ɏ������悤�ɂ��̃����[�ɕ���ɓd���������Ă��邩�ǂ����ׂ邽�߂̃����[����q���Ή����ǂ��Ȃ��Ă��Ă����m�Ƀ����[ON�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA���ɃZ���T�[��H���q���ŋ�J������͊y���Ĉ����ς܂�����̂ł͂Ȃ��ł����H ���Ԏ� 2010/1/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����̉��肪�Ƃ��������܂��B �P���Ƀ����[�ł悩������ł��ˁB ����l�������Ă܂����B �茳�̃����[(MY�~�j�p���[�����[)�̃J�^���O���Q�Ƃ����Ƃ���A�������Ԃ�20��S�ȉ��ƁA��]�̑��x���(1/10)�H�x�߂ł����̂ŁASSR�ŒT���Ă݂܂��B ���Z�������A���肪�Ƃ��������܂����B kay �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���҂��Ă��鉞�����x��2msec���x�ł����H �@���̎��Ԃ��v�낤�Ƃ���Ă���̂��͏�����Ă��܂��A�I�������̃^�C�}�[�����[�Ƃ�������������p�@��͂�����~���b�P�ʂł͓����܂��A���R�̂��ƂȂ���^�[�Q�b�g�ɂ���Ă��郊���[��d���ق��~���b�P�ʂœ��삷��Ƃ��v���܂���B �@����~���b�P�ʂœ��쎞�Ԃ��v��Ȃ��Ɗ댯�ȋ@������̒��ɂ͑��݂��܂�����A��T�ɐ��x�����߂Ȃ��ł����Ƃ����킯�ł͂���܂���ˁB �@���Ƃ��ΉF�����P�b�g�̃u�[�X�^�[(���P�b�g�G���W��)�̕��ˎ��ԂȂ�āA�P�~���b�Ⴆ�ΖړI�n�ւ̓��B���x�������L���قǕς��Ă��܂���������܂���B(AC100V�Ő��䂵�Ȃ��ł��傤���ǁE�E�E) �@���������A���p�d���̌�100V�̑��u�𑪒肷��ƍl����A50Hz�n��łP����20msec�A60Hz�n��łP����16.6msec�ł�����A�����^�C�}�[�����[�Ȃǂ��[���N���X�^�C�v��SSR���g�p���Ă����炻��ȏ�̉𑜓x�œ��삵�Ă���킯���Ȃ��A�P���ȓd�������[�ŃR���g���[������Ă���̂ł��𗬂̌������炵�ĊȒP�ȉ�H��u�ł͂���ȏ�(��10�{�H)�̉𑜓x�œd�������ꂽ���ǂ������ɑ��肷��̂͂��Ȃ��ςł���ˁB �@�I�������̃^�C�}�[�����[�{�����[�Ƃ������b�ł�����A�u�~�b�v�Ƃ��u�~���v�Ƃ����X�p���ōŒ�𑜓x��0.1�b���x��������イ�Ԃ�ȓ��쎞�Ԃ��v�낤�Ƃ���Ă���̂��Ǝv���܂������A�~���b�P�ʂł�����������������@�B���i(�{���ɉF���p�̋@��Ƃ��H)�̓��쎞�Ԃ��v��ړI�������̂ł��ˁB �@�����ւ�\�������܂��A�uAC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF�v�Ȃǂ̉�H�ł̓Z���T�[�Ŋ��m�����𗬂��������邱�Ƃň��肵���d���o�͂��H�Ȃ̂ŁA�������x�͐��~���b�Ȃ�Ē������ł͂���܂���B �@������H������50Hz/60Hz�̌𗬔g�`�����̂܂�5V�U�����炢�ɑ������Ă��A��������̂܂�Dr.DAQ�ɓ��͂��Ă��A��������]���𗬔g�`�̂܂���Ŕg�`�̓r������ON���ꂽ��OFF����Ă���悤�Ȕg�`�Ǝ��Ԃ܂ő���ł���ł��傤�B �@�m���ɁA���~���b�œ��삷�钴���������[���g���A�𗬔g�`�̓r���ł����m�Ɏ��Ԃ𑪒�ł��邩������܂���B �@���ʂ̌𗬃����[���Ƃ�͂菤�p�d���ɂ��킹�ĉ������Ԃ�16�`20msec���x�Ƃ������������Ǝv���܂��B���G�ȉ�H���g�p���Ȃ��Ă��������x����������������g����Ǝv���܂��̂ŁA�������������[���݂���Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2010/1/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 1/29 |
�ڂ�������{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B 50Hz��1����20msec�Ƃ����̂����߂ė������܂����B �����甽�����x��20msec�Ȃ�ł��ˁA20msec���Ă���ȂɒZ�����Ԃ�������ł��ˁB ���i�A���~���b�Ƃ��ӎ����Ȃ��ł�����ˁB �ŏ��ɗp�r��������Ɛ��������ɁA�����Ē������Ƃ��Ă����܂���ł����B �p�r�̓^�C�}�[�̎Г��L�����u���[�V�����ł��B �ݒ莞�Ԃ�0.5sec�Ō덷1���ȓ��Ƃ����Г��K�肪����ׁA5msec�̐��x���~�����ƒP���Ɏv���Ă��܂����̂ł��B�ʏ�͊e��ݔ��̃^�C�}�[(�����`�\�����Ԃ̐ݒ�)���X�g�b�v�E�H�b�`�ő��肵�Ă�̂ł����A0.5sec�Ȃ�ē��ꖳ���ł�����A��������肵�āA���܂��ܐ��������������̂��L�����Ă܂����B �ȑO�A�O�����͕t���̃X�g�b�v�E�H�b�`�I�Ȃ��̂�T�����̂ł��������炸�ł����B ���ۂ�1���덷�Ȃ�ĕK�v�Ȃ��̂ł����A�K��サ�傤���Ȃ�����Ă���̂ł��B �ŋ߁A�ʗp�r��Dr.DAQ���w�������̂ł��܂��g����0.5sec�̃^�C�}�[�̍Z�����w�{���Ɂx�o���邩�H�Ǝv���A���̂��߂ɂ��A�����k�����Ē����܂����B kay �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 1/30 |
�NjL�ł� �{���̓^�C�}�[�P�̂ɂ��ĕ��ב��Œ��ڐڑ�����悢�̂ł��傤���A10�{�ʂ̐����ڑ�����Ă��肷��̂Ŗʓ|�Ȃ̂ŁA���ׂƕ���ő���ł���Ǝv���܂����B ���ʂ̎��ԑ���ł̓����[���g���悢���Ƃ�������܂����̂ŁA���肪�Ƃ��������܂����B kay �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������J�����̉f����d�g�Ŕ������ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
������J�����̉f����d�g�Ŕ���Ď�M��������ł����A�\�ł��傤���H �s�`�o�t �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�r�f�I�g�����X�~�b�^�v�Ō������Ă݂Ă��������B �@������ł������Ă��܂��B ���Ԏ� 2010/1/27
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2���ԃ����v�삵�đ�ϕ֗��Ɏg�p���Ă��܂��B �lj��̋@�\�Ƃ��ăp�b�ƈÂ��Ȃ������̂݁i�Ⴆ�Ε����̓d�C�����������j�ɓ_��������ɂ́A�ǂ̂悤�ȉ�H��lj�������ǂ��ł��傤���B���Z�����Ƃ���A��낵�����肢�v���܂��B �݂͂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�p�b�ƈÂ��Ȃ����瓮���v�Ƃ������́u�������Â��Ȃ����瓮�삵�Ă͂����Ȃ��v�Ƃ������ł��ˁB �@������u�Q���ԃ����v�v�ɒlj�����ƂȂ�ƁE�E�E �E���邳�����m����Z���T�[��H �E�}�����Â��Ȃ�����������I�������H �E�I���o�͂��o�����ɁA�Q���ԃ����v��H�̃R���f���T�����イ�Ԃ�[�d����ׂ̈�莞�Ԃ̃p���X�������H �E�[�d�p���X����[�d�����[�d�X�C�b�`���O��H ���K�v�ɂȂ�܂��B �@����������ĂQ���ԃ����v�ɐڑ����Ă��\��Ȃ��̂ł����A�lj��ō���[�d�p�p���X������H�̓^�C�}�[��H�Ȃ̂ŁA��������̂܂������v��_��������^�C�}�[�Ɏg���Ă��A�Q���ԃ����v�̉�H�̂ق����K�v�Ȃ��Ȃ�܂��B�킴�킴�ڑ�����͓̂�x��Ԃŕ��i�����_�ł��B �@�Ƃ������ŁA�Q���ԃ����v�ɐڑ����邱�ƂȂ��A���̂܂܂Ńp�b�ƈÂ��Ȃ������莞�ԓ_�������H�Őv���܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���邳�Z���T�[��H �@�Z���T�[�ɂ�Cds(��R�l80k���`200k���^�C�v)���g�p���āA�g�����W�X�^�ŃX�C�b�`���O���܂��B �@VR1�Ŋ��x�߂��܂����A���邢����TP1�̓d����Hi�ɂȂ�A�Â������Low�ɂȂ�悤���߂��܂��B �� �u�p�b�ƈÂ��Ȃ�v���Ƃ𒊏o�����H �@C1�܂���������H�ŋ}���ȓd���̕ω����������𒊏o���܂��B �@�u�p�b�ƈÂ��Ȃ�v�Əo�͂�Low�ɂȂ�܂����A�u�������Â��Ȃ�v�Əo�͂͂킸�������d���������炸��555�̃g���K�[�������Ȃ��d���͈͓��Ŏ��܂蓮�삵�܂���B �@�����̓d�C����������A�Z���T�[����ŕ������肷����x�̃X�s�[�h�ňÂ��Ȃ�Ɠ��삵�A���R�ɑ��z�����ޒ��x�̕ω��ł͓���܂���B(�}�ɉ_�������邭�炢�ł͓��삵�܂�) �� �^�C�}�[��H �@�}���Ȗ��邳�̕ω������o�����������A�^�C�}�[�삳���܂��B �@�^�C�}�[�͍ł��|�s�����[�ȃ^�C�}�[IC LMC555 (C-MOS�^�C�v)���g�p���ă����V���b�g�^�C�}�[��H�Ƃ��Ďg�p���܂��B �@�����_�������ł͂Ȃ��A���̂Q���ԃ����v�̂悤�Ɏ蓮�ŃX�^�[�g������X�C�b�`�����݂��܂��B �� �����v�h���C�o �@�����v�h���C�o�́A���̂Q���ԃ����v�ɂ��킹��MOS�p���[FET 2SK2231���g�p���ē��d����_�������܂��B �@LMC555�̏o�͂ł��̂܂ܓ_�������Ă��܂��̂ŁA��������ۂɂ̓p�b�Ə����܂��B �@������Ə��������悤�ȏꍇ�ɂ́A�_�C�I�[�h���R�E�d���R���f���T��g�ݍ��킹�ĉߋ��ɏo�Ă���悤�Ȋ����ł�����Ə��������H�ɂ��Ă������ł��傤�B �@���̂ւ�͂��D�݂ɂ��킹�āA�������������R�ɐ��삵�Ă��������B �� �������{���Ɍ��̂Q���ԃ����v�ɐڑ�����ɂ� �@�^�C�}�[�̓��쎞�Ԃ����b���x(VR2���g�킸�ɌŒ�ł悢)�ō���āALMC555�̏o�͂Ō��̉�H�}�̓d���R���f���T���[�d����悤�ɐ��\���̒�R�ƃ_�C�I�[�h���o�R���Đڑ����Ă��������B �@�܂��A���̂܂܂̉�H�}�œ��삷��̂ŁA�킴�킴���i�𑫂��Č��̂Q���ԃ����v�ɐڑ�����K�v�������Ǝv���܂��B �� �d�r���Ȃ��Ȃ�܂���I �@�Q���ԃ����v���ҋ@�d�͂O�ł�������A�_�����鎞�ȊO�ɂ͓d�r�͏��Ղ��܂���̂Œ����Ԃ������ɒu�����ςȂ��ɂ��Ă��d�r�͂��Ȃ蒷�����Ԃ��̂ł����A���̉�H�ł͖��邳�Z���T�[��H�ŏ�ɐ�mA���x�̓d��������Ă��܂�����A�P�O�d�r�̂悤�ȏ��e�ʓd�r�ł͂���قǒ������ԓd�r�͂����܂���B(�ڈ��Ƃ��Ĉꃖ�����炢�H) �@�Â��Ȃ�����d�r����������p�x���オ��܂��̂ŁA�d�r�����̉����炷���߂ɂ͒P���P��d�r�̂悤�ȑ�e�ʓd�r���g�p���邩�AAC�A�_�v�^�[���g�p����Ȃǂ����ق��������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2010/1/25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 1/27 |
���Z�����Ƃ�����肪�Ƃ��������܂����B �d�r�̖��́A�l�q�����Ȃ���l���Č������Ǝv���܂��B �݂͂� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����b�ɂȂ�܂��B �u�p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v�v��֗��Ɏg���Ă���̂ł����A���Â��J��Ԃ����ƁA�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B ��ꂽ���Ǝv���A���i���`�F�b�N�����Ƃ���A�@�\���������܂��B ���s���낵����A�ǂ���������H�̃R���f���T�����[�d�̂܂܂ɂȂ��Ă��܂����삵�Ȃ��Ȃ�悤�Ȋ����ł��B�R���f���T����d������ƁA���̌㐔�삵�܂��B ���邭�Ȃ�����A���炩�̕��@�ŃR���f���T����d������K�v�͂Ȃ��ł��傤���H �X�~ �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u���Â��J��Ԃ����Ɣ������Ȃ��v�Ƃ����̂��悭�킩��܂���B �@�P����(���x�̊�)�ɉ�������Â��J��Ԃ����Ɖ����N����̂ł��傤���H >�ǂ���������H�̃R���f���T�����[�d�̂܂܂ɂȂ��Ă��܂� �@�R���f���T���[�d�����̂̓g�����W�X�^�������āu�Â��v�Ɣ��f���Ă��鎞�ł��B >���邭�Ȃ�����A���炩�̕��@�ŃR���f���T����d������K�v�͂Ȃ��ł��傤���H �@���邭�Ȃ�����A�[�d�p�̃g�����W�X�^�������Ȃ��Ȃ��A�R���f���T�̗��[�ɂȂ����Ă����R��ʂ��ăR���f���T�͕��d����܂��B �@���x���߂�VR�̒��߃~�X�ł͂���܂��H �@��H�}���ɂ���悤�ɁATP1�̓d���́u���邢������U�u(�d�r�̓d��)�v�u�Â�������mV�`���\mV�v�ɂȂ��Ă��܂����H �@�Z���Ԃɖ��Â��J��Ԃ����Ƃ��̓d���̊Ԃōs�����藈���肵�āA���̊Ԃ͓��R�p�b�ƈÂ��Ȃ锽���͂��܂���B�^�C�}�[�ň�莞�ԓ_�����郉���v�ł�����A���̃^�C�}�[���Ԓ�(��Q�����炢�H)�͕ʂɎ���̔��������Ȃ��Ă��_�����Ă���͂��ł�����B �@���邢��Ԃ���莞�ԑ����ƁA�R���f���T�͕��d����Ď���̃p�b�ƕω��������̂��߂̑ҋ@��Ԃɖ߂�܂��B �@������ >���邭�Ȃ�����A���炩�̕��@�ŃR���f���T����d������K�v�͂Ȃ��ł��傤���H �ƌ����Ă���̂��Ƃ�����A���邭�Ȃ��Ă��R���f���T�͕��d����Ă��Ȃ��悤�ł��̂ŁA���̌����� (1) VR�̒��߃~�X�ŁA���邢�����g�����W�X�^�������Ă��āATP1�̓d�����d���d���܂ŏオ��Ȃ���Ԃɂ��Ă��܂��Ă���B (2) �R���f���T�܂��̃n���_�Â��~�X�ȂǂŁA��R���������ڑ�����Ă��Ȃ��B(���d�ɐ����`���\���ȏォ����) �̂悤�Ȃ��Ƃ��l�����܂��B �@�܂��͖��邢��(���Ƃ��A���Â��Ȃ��Ă��܂��u�Â��v�Ɣ��f�����Ȃ����邳�̎��ł�)�ɖ{����TP1���U�u�ł��邩�m�F���Ă��������B �@���Ȃ����u���邢�v�Ǝv�����邳�̎��A�������U�u�ł���Ζ��邢���ɂ̓R���f���T�ɓd�����c�邱�Ƃ͂���܂���B ���Ԏ� 2010/5/22
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�]��ɂ��f�������X�ŁA���ӂ������܂��B������̍Č����ǂ����Ȃ����炢�ł��i�� �u���b�h�{�[�h�ōČ����A�e�[�q�̓d���𑪂��Ă݂܂����B TP1�̓d���ω��͊��Ғʂ�ɕω����Ă��܂��B �R���f���T�́{���̓d���́A�����Á����ɕς��ƁA��C�ɓd���d����1.5�{�߂��d���ɂȂ�̂͐���ł��傤���H ���̂܂܂��ƁA���̓d�������X�ɉ�����܂����A����(2)�̗��R�ŁA���d�ɋɒ[�Ɏ��Ԃ��������Ă���̂��ȂƐ�������܂����B ������C���������Ƃ́A���C�g��������A�R���f���T�̕��d���������Ă��Ȃ��Ԃ͎��̔������N����Ȃ��킯�ł����A�����Ŕ������Ȃ�����ƁACds�ɖ��Â��s���ƁA�����ڂɂ͕�����Ȃ��̂����ǁA�R���f���T���Ăя[�d�����Ă��܂��Ă��邱�Ƃł��B����������_�̌����̂悤�ł��B �A�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B �����I�Ȏ���ŋ��k�ł����A�R���f���T�̕��d�ł����AR2(10k)��R3(100k)�̉�H�ŒZ�������ĕ��d���Ă���ƌ��������ł�낵���ł��傤���H �X�~ �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���́u(2)�̗��R�ŁA���d�ɋɒ[�Ɏ��Ԃ��������Ă���̂����v�Ƃ����l���͑S���̓��ĈႢ�ł��B �@�R���f���T�̃}�C�i�X���ƃv���X���Ɍq�����Ă����R�̒l�̊W�ŁA����GND�ƃR���f���T�̃v���X�ɂɃe�X�^�[�Ăēd�����v�������E�E�E�����ڂ̓d���͊m���ɂ����Ȃ�܂����A�ʂɂ��̓d�����̂��̂��R���f���T�ɒ��߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�R���f���T�ɂ͓d���d���Ԃ�̓d���������߂��Ȃ��̂ł��������v����������獂���d���Ɍ�����̂͂�����܂��ŁA���d�Ɏ��Ԃ�������Ȃ�Ă����̂͑S�����_��͂��肦�Ȃ��b�ł��B �@���݂܂��A��ɂ������܂����悤�ɂ��̉�H�̓���ł́u���邢��Ԃ���莞�ԑ����ƁA�R���f���T�͕��d����Ď���̃p�b�ƕω��������̂��߂̑ҋ@��Ԃɖ߂�܂��B�v�Ƃ�������̕����́u���邢��Ԃ���莞�ԑ������v�̕����A������������Ă��Ȃ��������A������F�����������������悤�ł��ˁB �@�d���R���f���T�̕��d�ɂ���10�b���x���Ԃ�������v�ɂȂ��Ă��܂��B �@����͕��d��x������Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�p�b�ƕω������Ƃ��ɂȂ�ׂ������������������A�������ω��������̌�쓮��}������A���R�̑��z���������_�ł����Ɩ��邳���ω����鎞�Ȃǂɂ͑S����쓮���Ȃ�����ׂɓ����o�����K�Ȏ��Ԃł��B �@�Z���T�[���Â���Ԃ��֒m����ƁA���邢��Ԃɖ߂��Ă���10�b�͔������Ȃ��u�K�[�h�^�C���v��݂��Ă��܂��B �@�u���邢��Ԃ���莞�ԑ����ƁA�R���f���T�͕��d������v�Ƃ����v�ł�����A�u������C���������Ƃ��v�ŏ�����Ă��锽���͐v�ʂ�ł��B �@�����v�������Ă���Ԃł�����I�������ł��A�u�Â��v�Ɣ��f������R���f���T�͕��d���܂�����A�u�Â��v��Ԃ������Ԉȏ㖳���Ȃ��E�E�E�܂�u���邢�v��Ԃ���莞�ԑ����Ƃ�����Ԃ��B���ł��Ȃ���A�r���ňÂ��Ȃ�����K�[�h�^�C���̃^�C�}�[(�R���f���T)�����Z�b�g����܂��B �@�v�ł͈Â���Ԃ��疾�邢��ԂɂȂ��Ă��A��10�b�̓K�[�h�^�C���Ƃ��Ĕ����͂��܂���B���R�E�ł͂���ȒZ���Ԃő��z�̖��邳���߂��Ă܂�������Ȃ�Ă��Ƃ͖����͂��ł��B �@�_�̗���Ȃǂł̌�쓮���N���邩������܂��A�K�[�h�^�C����Z������ɂ�100K����10K�����x�܂ŏ��������Ă��������B�K�[�h�^�C����3�`4�b�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/5/25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/30 |
�����I�Ȏ���ɂ������������肪�Ƃ��������܂��B ����ɁA�K�[�h�^�C���Z�k�̉�܂ŋ����Ă����������ӂ��܂��B �����A��R�l�������Ă݂��Ƃ���A�����̃j�[�Y�ɂ҂�����̃��C�g�ɂȂ�A�������Ă��܂��B �X�~ �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�����L���� ���A����܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āA ����A�m���x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v�n���Q�l�ɁA�y���`�F�f�q���g�����A�艷�ۉ��ɂ��쐬���܂����B ��ώQ�l�ɂȂ�A���肪�Ƃ��������܂����B ���āA�s�̕i�̃p�[�\�i���≷�ɂł́A�����悤�Ƀy���`�F�f�q�̓d�Ɂ{�|�������[�ɂ�����ւ��āA��p����@�\������܂��B ���̗≷�ɂɎg���Ă����H��8bit�}�C�R�����g���Đ��䂵�Ă���̂ł����A�}�C�R�����j�������ꍇ�ɁA���i�������ł��Ȃ����߁A�≷�ɂ������邵����͂Ȃ��̂ł��B �����ŁA�m���x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v�n�̂悤�ɁA�I�y�A���v�ō\�����ꂽ�y���`�F�f�q�ɂ��≷�T�[���X�^�b�g��H���l���Ă��������Ȃ��ł��傤���H ���x�Z���T�[��LM35DZ�@�P�����p���A�I�y�A���v��LM358���Q�A�����[���Q�ɂ�����A���Ƃ��A�ݒ艷�x�Q�W���Ƃ��āA�Q�V�ȉ��ł͉��M�A�Q�X�x�ȏ�ł͗�p���̉�H���\�ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A�������ł��傤���H ��]�̉��x����͈͂͂S���`�T�O���ł��B ��낵�����肢�������܂��B Nory* �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@Nory* �l�͂��߂܂��āB �@�u���x�Z���T�[��LM35DZ�@�P�����p���A�I�y�A���v��LM358���Q�A�����[���Q�ɂ�����v�܂ōl�����Ă���̂ł���A����Ŋ����ł͂���܂��H �@�ʒi�����Ŏ��₳��Ȃ��Ă��A���̂܂܍��������Ǝv���̂ł����B �@�Q�l�܂łɁA�����������ꍇ�ɂ́E�E�E�Ƃ����`�������Ă����܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@���x����̕����́A�����P���������H�ō������̔�������܂��B�@�I�y�A���v�܂��̉�H�͑S�������Łu�������艷�x��荂���ꍇ��OFF�v�ɂȂ��H�ł��B �@���삹�鉷�x�́A�Ⴂ���������A�������������Ƃ��ĕʁX�ɐݒ肵�܂��B �@�����AVR�ɂ��ݒ艷�x�͂P����(���Ƃ���28��)�ŁA��������}�����̕�(�����Őݒ�͂��Ă���)�Ŏ����I�ɐ��䂳���悤�ȉ�H�͑S���̕ʐv�ƂȂ�܂�����A���ɂȂ��Ă����H�}�ł͖����ł��B �@�����[���h���C�u����g�����W�X�^��NOT��H������ā~����荂���ꍇ�̓����[��ON�ɂ���悤�ɂ��܂��B �@������A���̂܂܂Ńg�����W�X�^��Ł~�����Ⴂ�ꍇ�̓����[��ON�ł��S�R�\���܂���B�����[�̐ړ_���t�Ɏg�����������̘b�Ȃ̂ŁB �@�����A�C�����������炱�����Ă��܂��B���i���20�~���炢�P�`�肽���ꍇ��A�����[���Q������ON�ɂȂ��Ă����Ԃ��������Ė��ʂɓd�C��H���Ă���Ƃ����C����������Ԃ��������Ă��Ă��ʂɋC�ɂ��Ȃ��Ȃ�킴�킴�g�����W�X�^��ɂ���K�v�͂���܂���B���̂܂܌��̉�H�̂܂g���Ă��������B �@�y���`�F�f�q���g�u���b�W�Ő��䂵�܂��B �@�P�ɉ��x���ʕ����Q�ɑ��₵�āA�����[���Q�ɑ��₵�Ăg�u���b�W�Ő��䂷��A�y���`�F�f�q�̎��d�������̋t�]�ʼn��M�ɂ���p�ɂ��g���鐫�������̂܂܈����o�����Ƃ͂ł��܂��̂ŁA�ʂɓ�����Ƃ��l���Ȃ��Ă������ł���B ���Ԏ� 2010/1/23
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B �g�����W�X�^�ɂ��NOT��H�����ɕ����т܂���ł����B ���x���ߗp�̃{�����[�����Q�A�̂��̂ɂ���悢�̂��ȁH�ƍl���Ă��܂��B ���������܂ŁA�Ă͒艷��p�ɂƂ��Ďg�p�ł������ł��B ���肪�Ƃ��������܂����B Nory* �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�u�Ă͒艷��p�ɂƂ��Ďg�p�v���邾��(�~�͕ۉ���)�ł���A�킴�킴�I�y�A���v��lj����Ă��Ȃ��Ă������ł���ˁH �@�s�̂��≷���́u�①(��p)�v�u�ۉ�(���M)�v���ؑփX�C�b�`���t���Ă��āA���x�ݒ�_�C����(�܂��̓f�W�^�����x�\��)�͂P���ł��B �@�����āA�u���x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v�v�ɂ͌����炻�̋@�\�͕t���Ă��܂�����A�����[�́u�ݒ艷�x�ȏ��ON�v�[�q�Ɓu�ݒ艷�x�ȉ���ON�v�[�q���g���ăy���`�F�f�q�ɂȂ�������(�①/�ۉ��ؑփX�C�b�`���lj�)�A��ʓI�Ȏs�̂��≷���Ɠ����ɂȂ�܂���ˁB 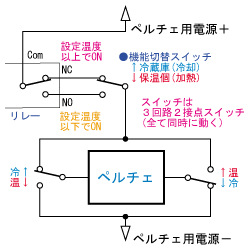 �@�����炠��u�w�艷�x�͈͈ȏ�ɂȂ�����ON�v�̋@�\�̒[�q�Ɓu�w�艷�x�͈͂����������ON�v�̊e�o�͂̂ǂ�����g�p���邩��I������u�①/�ۉ��ؑփX�C�b�`�v������A�d�q�T�[���X�^�b�g��H�͒g�ߗp�ɂ���p�p�ɂ��ǂ���ɂł��g���܂��B
�@�����炠��u�w�艷�x�͈͈ȏ�ɂȂ�����ON�v�̋@�\�̒[�q�Ɓu�w�艷�x�͈͂����������ON�v�̊e�o�͂̂ǂ�����g�p���邩��I������u�①/�ۉ��ؑփX�C�b�`�v������A�d�q�T�[���X�^�b�g��H�͒g�ߗp�ɂ���p�p�ɂ��ǂ���ɂł��g���܂��B�@�����āu�①/�ۉ��ؑփX�C�b�`�v�œ����Ƀy���`�F�f�q�̓d���������t�]������悤�ɂ���A�d�q�T�[���X�^�b�g��H�����������Ƀy���`�F�f�q�͔��M����̂��z�M����̂����ւ����܂�����A���v�R�̃X�C�b�`���ɐ�ւ��ł����R��H�Q�ړ_�X�C�b�`���g���Ε��ʂ̗≷�ɂ̂悤�Ȋ����ɐ�ւ����ł��܂��B >�x���ߗp�̃{�����[�����Q�A�̂��̂ɂ���悢�̂��ȁH�ƍl���Ă��܂� �@�Ƃ������ł����A���ꂾ���I�y�A���v���Q�ɂ����Ӗ����Ȃ��Ȃ�܂���ˁH �@�Q�A�{�����[���łǂ���̃I�y�A���v�ɂ�������d����������̂ł�����A�Q��H�p�ӂ����Ӗ�������܂���B �@�Q��H�p�ӂ����̂́A����E���������x�ł͂Ȃ��ʁX�̉��x�ɐݒ�ł����悤�ɂ��āA���D�݂̉��x�ł��ꂼ��ɕ��A���x���ςł���悤�ɂ���悤�A������H���Q�p�ӂ������̂ł��B �@�ǂ���̉�H�ɂ��Q�A�{�����[���œ�����d������������A�Q�Ƃ��������x�œ��삵�Ă��܂��S�R�Ӗ�������܂����B �@��p���x����(������)�ɂ͍�����d����^���A���M���x����(�Ⴂ��)�ɂ͒Ⴂ�d����^���Ȃ��ƁE�E�E�B �@�Q�A�{�����[���̊e�����ɕʁX�Ƀo�C�A�X�d����ύX�����R�܂��͔��Œ��R���㉺�ɂ����肵�Ĕ����ɓd������ׂ���ȂǁA���\�ʓ|�ȉ������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��H �@������A�I�y�A���v�̒lj��Ȃ�Ă��Ȃ��Ă����̃X�C�b�`��lj����邾���̉�H�ŁA�d�q�T�[���X�^�b�g�̉��x�ݒ�����Ƃ��u����29���A���A27���v�ɒ��߂��Ă����A�u��p�Ŏg�p����ꍇ��29���ɂȂ������p�J�n�A27���܂ʼn����������~�v�u�ۉ��Ŏg�p����ꍇ��27���ɂȂ�������M�J�n�A29���܂ŏオ�������~�v�Ƃ����≷�ɂ̋@�\�������ł��܂��B �@�����ĕ��A���x���̐ݒ�͕��ʂ͊����������ɍD�݂ɒ��߂��Č�͕ύX���Ȃ��͂��ł�����A���̔��Œ��R�ɂ��Ă����Ăӂ���͈�ؐG��܂����ˁB �@���x���߂�100����20���݂����ȋɒ[�Ȕ͈͂ŕύX����Ȃ畜�A���x�̕������Ȃ�ς�܂����A����I�Ɏg��28����15�����x�̊Ԃł�����܂�ς�܂���B����Ɖ����̉��x���͉��x�ݒ�Ɋւ�薳���قړ����ƍl���Ă悢�͂��ł��B(����ȑO�ɐl�Ԃɉʂ����ĂP�����x�̌덷���킩��̂��ǂ����E�E�E) �@�u����v�Ɓu���A�v�Ƃ����T�O�ő�����ƕЕ��������ɂ����g���Ȃ��悤�Ɏ��ꂪ�����Ǝv���܂����A����͂����܂Ŋ�d���̐ݒ�Ɋւ����Ƃ肫���Ȃ̂ŁA���Ƃ��Δ��̊O�Ƀ{�����[���̎����o���ăc�}�~���Ƃ����̂ł���A�����ɉ��x�ݒ�\���������ۂɂ��Ƃ������A���x�����Q�����x�ɓ����Őݒ肵�Ă�������A�c�}�~�̂܂��ɏ������x�\�����{���̐ݒ艷�x�d���Ō��܂鉷�x�{�P���������Ă����Ƃ���s�v�c�A�u��p�̏ꍇ�̓c�}�~���Ē��߂������x�{�P�x�ŗ�p���J�n�A�ݒ艷�x�|�P���Œ�~�v�u�ۉ��̏ꍇ�̓c�}�~���Ē��߂������x�|�P�x�ʼn��M���J�n�A�ݒ艷�x�{�P���Œ�~�v�Ƃ����������ɒ����I�ȑ������\�Ȃ̂ł���B �@����܂��A��₵�������g�߂������Łu�①/�ۉ��ؑփX�C�b�`�v�̑���͕K�v�ł����B �@�������A�I�y�A���v���Q�ŕʁX�ɉ��x�Ǘ����ł����H�ł���u�①/�ۉ��ؑփX�C�b�`�v�͖����ŔN�����ł��X�C�b�`�ʒu���C�ɂ����Ɏg����̂ō��@�\�ȗ≷�ɂł͂���܂��B �@�������x�ݒ�c�}�~���P�ɂ��邽�߂ɂQ�A�{�����[�����g�����Ƃ���ƁA������Ɩʓ|�ȃo�C�A�X��H��lj��Őv���Ȃ��Ƃ��������I�y�A���v�𑝂₵���Ӗ�������܂����E�E�E�B �@�܂��������œw�͂�����āA�Q�A�{�����[���ł��܂��䂭�悤�ȉ����������̂�����̖ʔ������Ǝv���܂��̂ŁA��������Ċ����x�̍�������v����A�����g���̂��̂��O���[�h�A�b�v������̂��y�������ł��ˁB ���Ԏ� 2010/1/25
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�䖳�������Ă��܂��B �ȑO�A�u�y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H�v�Ŗ₢���킹�����Ē�����Nory*�ł��B�{���A�����������������R��H�Q�ړ_�X�C�b�`���g������H�ɉ��C���A���q�悭���삵�Ă��܂��B ��ϖ��ɗ����܂����B���肪�Ƃ��������܂����B Nory* �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�����y�����q�������Ă��������Ă���܂��B �����ł����A���肢�������܂��B �K�[�f���\�[���[���C�g�i���z�d�r�œd�r���[�d���āA�Â��Ȃ�ƁALED���P�_�����镨�ŁACDS�͂Ȃ����ł��j�B����LED���P�O�O�~�V���b�v�̂V�F�ɕς��LED�ɑւ��Ă݂��̂ł����A���܂��ϐF���܂���B�������@�����������肢���܂��B �S�U�Γd�q���N �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����͕�����H�������Ă��Ȃ�������H���g�p�����\�[���[���C�g������ł͂Ȃ��ł����H �@���FLED��_�������邾���ł���A�������ŏ����p���X�����̂ق����d�������������ڂ����邢�̂ŕ�����H�����̃\�[���[���C�g�͑����ł��B �@����ɑ��āA���C���{�[LED�⎩���_��LED�͒��ɓ_�ŗp��IC�������Ă��܂�����A��������Ă��Ȃ��p���X�d���ł͐���ɓ��삷��͂����Ȃ��E�E�E�B �@�܂��́A���g���̃\�[���[���C�g�̉�H�}�������āA������H�������Ă��邩�ǂ����m�F���A���������Ă��Ȃ��̂ł����畽����H��g�ݍ���ł��������B �@�ߋ��̓��e�ŁuLMC555�ŏ������Ă��d����1.43V��������܂����v�����肪�Q�l�ɂȂ�ł��傤�B �@�܂��A�\�[���[���C�g�̂悤�ȒP���ȏ�����H�ł̓��C���{�[LED�⎩���_��LED���_�����Ȃ����Ƃ́u�\�[���[�p�l���̗e�ʁH�v�ɏ����Ă��܂��B ���Ԏ� 2010/1/23
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �s���N�m�C�Y������H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����p�Ƃ܂ł͐��x���V�r�A�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ��̂ł����A�s���N�m�Y���M�����낤�Ǝv���A���낢�댟�����Ă���Ƃ����̃y�[�W������܂����B ���S�҂ł��A�ł������ȉ�H�}���Ă������܂��ł��傤���H ��낵�����肢�v���܂��B �䂫�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�s���N�m�C�Y�̓z���C�g�m�C�Y�����g���ɂ�茸�������Đ������܂��B �@�z���C�g�m�C�Y�͑S���g���ш�ɂ����ē������x���Ńm�C�Y�����Ă�����̂ł��ˁB �@�ȒP�Ȑ�����H�̓c�F�i�[�_�C�I�[�h�̔�����m�C�Y�����ē��邱�Ƃ��ł��A�c�F�i�[�_�C�I�[�h�ƃg�����W�X�^�܂��̓I�y�A���v���̑�����H�ŊȒP�ɍ�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�s���N�m�C�Y�����ɂ͂�������č�����z���C�g�m�C�Y���A3db/oct(�P�I�N�^�[�u�ɂ�3db)�̌����t�B���^�[��ʂ��ł��܂��̂ŁA����̂��˗��̃L���͂��̌����t�B���^�[��v����Ƃ���ɂ���܂��B �@�I�y�A���v���g�������[�p�X�t�B���^�[�̉��p�Őv�͂ł���̂ł����A�u�C�̖����v�ł͐v������H�͑S�Ď��ۂɑg�ݗ��Ăē����x���m�F���Ă�����J���Ă��܂��̂ŁA�����ш�p�̃t�B���^�[��H�ł�����̑S�ш�ɂ����Č��������𑪒肵�āA���ʂ̃O���t�Ƌ��Ɍ��J����Ȃǂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�Ƃ��낪�E�E�E���͂����̑���ɕK�v���X�y�A�i(�X�y�N�g�����E�A�i���C�U�[�����g���ш�ɂ��Ẵ��x�����������I�ɑ���E�\������v����)�����L���Ă��܂���̂ŁA��p�����ɂ�鑪��͖����Ȃ̂Ńs���N�m�C�Y������H�̎��g��������(���������ł�)�������������Ă���̂����ׂ�p������܂���B �@����A�p�������킯�ł͂Ȃ��A�S���g���ш�̔C�ӂ̎��g���������锭�U��H��ʓr�p�ӂ��āA20Hz���炢����40KHz���炢�܂ŏ��Ƀt�B���^�[��H�ɓ��͂��Ă���āA���̎��̏o�̓��x�����I�V���X�R�[�v�ő����ĖڂŌ��Ď��Ƃ�Excel�������ɓ��͂��Č�ŃO���t����������̂ł��B��w�̍��̎����ł�Excel�Ȃ�Ė��������̂ŃO���t���܂ł����ƂŃO���t�p���ɏ����Ă����킯�ł����E�E�E�B �@���A�����܂ő�ςȍ�Ƃ�����ł͂�肽���Ȃ��̂�����ł��B �@�ł��̂ʼn�H��v���Ă����ꂪ(���������ł�)���������ł��������̊m�F������Č��J�ł��܂���̂ŁA������Ō��J���邱�Ƃ͍���ł��B �@�����ւ�\�������܂��A���̂ق��Őv������H�����������邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA���̕����g�o�Ō��J����Ă����H�}���Q�l�ɂ��Ă��������B �@�l�b�g���s���N�m�C�Y������H�ɂ��Č������܂��ƁA���������l�́w�����ȏ��i���X�x�Ƃ����g�o��������܂��B �@���̕��̂g�o�̏��ʂ͕������A�d�q��H�ɋ�����������Ă�����ɂ͂����ւ�L�p�ȃy�[�W�ł͂Ȃ��ł��傤���B �@������̃��j���[��[�d�]�H�쎺]��[analog circuit]��[1- 5. Pink noise generator(�s���N�m�C�Y������H) ]�Ɛi�߂ΒN�ł��ȒP�ɍ��郌�x���̉�H�}�ƁA�����𑪒肵���O���t���f�ڂ���Ă��܂��B (�s���N�m�C�Y������H���f�ڂ���ꍇ�A���������O���t���K�v�ł�����c) �@�l�b�g�Ō�����������Ƒ��ɂ��o�Ă���ł��傤����A���₷�������Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2010/1/23
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B�����ЂƂA�h�o�C�X�����肢�v���܂��B ���e���ꂽ�uout�v�Ɋւ��ĂĂł����A���̐�̓v���A���v���Ȃ��悢�̂ł��傤���H ���̂܂܃X�s�[�J�[�ł悢�̂ł��傤���H �����܂����낵�����肢�v���܂��B �䂫�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�������e���ꂽ�̂��悭�킩��܂��E�E�E�E�B �@�}�����j����̉�H�}��out�ł���A���̂悤��OP�A���v�ɂ��t�B���^�[��H�����ڃX�s�[�J�[���쓮�ł���͂��͖����̂ŁA�v���A���v�Ȃ�X�s�[�J�[�h���C�u�A���v�Ȃ�A�Ȃ�炩�̑������ʂ��ăX�s�[�J�[��炵�Ă��������B ���Ԏ� 2010/1/28
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 1/30 |
��ϕ��ɂȂ�܂����B ���肪�Ƃ��������܂����B �䂫�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���݂P�̃X�C�b�`���t���Ă���z���𗘗p���āA�X�C�b�`���R�ɑ��₵�ă����[������s�������B �@���݂P�v�b�V���X�C�b�`���t���Ă���z���ɁA�lj��Ńv�b�V���{�^���Q���x���t���A��R�l�ω��ȂǂŁA���̔z�����g���e�{�^�����������Ƃ��Ɋe�����[���쓮�����H���l���Ă���̂ł����A�ǂ��Ă���܂����炨�����������B �@�z���̒lj����o���Ȃ����Ɍ��̔z���𗘗p���đ����lj��������ƍl���Ă���܂��B���̃X�C�b�`��H�͉����ƃ}�C�i�X�ɐڑ�����Ă��܂��B�@�B�̓d����12V�ł��B�}�C�R�������g��Ȃ���H�ł��肢���܂��B �@�������t�������Đ\����܂���B fUkUtEk �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�z�����lj��ł��Ȃ��Ƃ���ɃX�C�b�`�ނ�lj�����ꍇ�A�ŋ߂ł�PIC�}�C�R���ȂǂŃV���A���ʐM�������đ�R�̃{�^����lj��ł���悤�ȉ�H���嗬�ł��ˁB �@���������̂悤�ȃ}�C�R���̃v���O�������J�������Ƀ{�^����lj�����ƂȂ�ƁA�Â����炠����R�l�̈Ⴂ�����o������@���A�i���O��H�ō�邱�ƂɂȂ�ł��傤�B (����̉�H���A�i���O�ł͂Ȃ�PIC�}�C�R���ō���Ă��AA/D���͋@�\�̂���W�s���̃}�C�R����ōςނ̂ł����c) 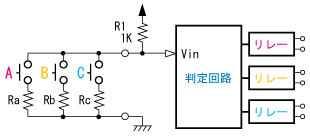 �@�E�̐}�̂悤�ɂR�̃X�C�b�`�ɂ��ꂼ���R���Ƃ���A�{�^���������ƃX�C�b�`�o�H�̒�R�l���ς�悤�ȃX�C�b�`���ɂ��āA���̃X�C�b�`����ŕς�Vin�̓d�����H�Ŕ��ʂ��ĉ����ꂽ�{�^���ɊY�����郊���[��ON�ɂ��܂��B
�@�E�̐}�̂悤�ɂR�̃X�C�b�`�ɂ��ꂼ���R���Ƃ���A�{�^���������ƃX�C�b�`�o�H�̒�R�l���ς�悤�ȃX�C�b�`���ɂ��āA���̃X�C�b�`����ŕς�Vin�̓d�����H�Ŕ��ʂ��ĉ����ꂽ�{�^���ɊY�����郊���[��ON�ɂ��܂��B�@���̏ꍇ�A�{�^�����P�����������Ƃ��̃{�^���Ɍq��������R�l���X�C�b�`��H�̒�R�l�ɂȂ�̂ł����A�������{�^���������ɉ����ꂽ�ꍇ�ɂ͒�R�l�͉����ꂽ�{�^���̒�R�����ɐڑ���������������R�ɂȂ�܂��̂ŁA����ł���쓮�͂��Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�{���ł����[A�̂�][B�̂�][C�̂�][A+B����][A+C����][B+C����][A+B+C����]���S���łV���(OFF���܂߂�ƂW���)�̏�Ԃ����o���Ă��Ȃ���Ȃ炸�A�d�������H�����ꂾ���K�v�ʼn�H�������ւG�ɂȂ�̂ō���́u���������̏ꍇ�̕����{�^���͔��ʂ��Ȃ���������Ă��钆�ŁA�D�揇�ʂ̍����ǂꂩ�P�̂ݏo�͂����v�Ƃ��������ɂ��ĉ�H�͊ȗ������܂��B �@�R�̃{�^�������ꂼ�ꉟ���ꂽ�Ƃ��ɁAVin�Ɍ����d�������傤��Vcc���S�����������ꂼ��͈͓̔��Ɏ��܂�悤�ɂ���A��̔��肪���₷���Ȃ�܂��B 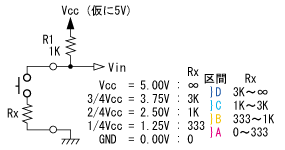 �@���ɓd������̃o�C�A�X��RR1�̒l��1K��(�X�C�b�`�z���ɗ����d���͍ő�5mA)�ɂ����ꍇ�ɂ́ARa�ERb�ERc�̊e��R�Ɋ��蓖�Ă���l�͉E�}�̂悤��Ra=0�`333���ERb=333�`1K���ERc=1K�`3K���̊Ԃ̒�R�l�ƂȂ�܂��B
�@���ɓd������̃o�C�A�X��RR1�̒l��1K��(�X�C�b�`�z���ɗ����d���͍ő�5mA)�ɂ����ꍇ�ɂ́ARa�ERb�ERc�̊e��R�Ɋ��蓖�Ă���l�͉E�}�̂悤��Ra=0�`333���ERb=333�`1K���ERc=1K�`3K���̊Ԃ̒�R�l�ƂȂ�܂��B�@���Ƃ����b���(2.5V�`3.75V)�̒��S�d����3.125V�Ȃ̂�Rc��Vin�����̓d���ɂȂ��R�l������Ă����R���p���[�^�Ŕ��ʂ��鎞�ɍł��Z�p���[�V�����̗ǂ��d�����o�͂��邱�Ƃ��ł���ƍl������̂ŁA���̏ꍇ��Rc��1.67K��(1K�`3K���͈͓̔�)�ƂȂ�܂��B �@���l��Rb��600���ARa��143���ƂȂ�܂����ARa�Ɋւ��Ă͕ʂ�0�`1.25V�̊Ԃ̓d�������Ȃ��Ă��A�ɒ[�Șb0V�̂ق������̓d���Ƃ̍����ł��傫���Ă����̂�0���ɂ��܂��B����́u�D�揇�ʂ��������̈��ON�ɂ����v�Ƃ�������̃��[�������邩��g�����ŁA�����R�̃{�^���̑S�V��ނ̑g�ݍ��킹�ʂ���Ȃ�0���ɂ͂ł�����143��������̒�R�l���������Ȃ���Ȃ�܂���B �@�ȏ�̌v�Z��̒�R�l���琻�i�Ƃ��Ď��݂����R�l��I�сA�e�{�^�������������̓d���̃p�^�[�����ꗗ�\�ɂ���Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
(�{���͂���������ƕ���Ēǂ����݂����ł����A����̓p�X) �@Ra��0���ɂ��Ă���̂ŁA�X�C�b�`�`�Ƒ��̃X�C�b�`�̓��������̏ꍇ�͑S�Ē�R�l��0���œd����0V�ɂȂ�킩��₷���悤�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B �@��R�l�̌v�Z�Ɏ��Ԃ������܂������A����̉�H�ł͂��̒�R�l�̌v�Z���v��Ƃ�90%���炢���߂Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B �@�X�C�b�`��Ԃ����肵�Ĕ���ł����R�l�����܂�A��͂�����R���p���[�^�܂��̓I�y�A���v���g�p���Ĕ��ʂ��āA�����[�������H�}�����������ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �X�C�b�`�� �@�X�C�b�`�������Ə�Ōv�Z������R�l�ɂȂ�悤�ȃ����[�g�X�C�b�`�ł��B �@�D�揇�ʂ��` > �a > �b�Ȃ̂ŁA�ڑ�����@��̓{�^���̓������������ꂽ�ꍇ�ɂ��̂悤�ȏ��ʂłǂꂩ�P��ON�ɂȂ��ėǂ��悤�Ȑڑ���I�т܂��B �� �d�����ʕ� �@�I�y�A���vIC LM324���P�g�p���܂��B �@LM324�ɂ̓I�y�A���v��H���S�����Ă��܂����A���̂����̂R���g�p���ĂP�͗]��܂��B �@�d���d�����S��1K���ŕ�������1.25V/2.50V/3.75V�̂R��臒l�����A���͓d����������ォ�����łR�̃R���p���[�^��H����������܂��B �@�e�R���p���[�^��H�̏o�͂́u���͂���l��荂����L���x��(0V)�v�u���͂���l���Ⴂ��H���x��(��3.5V)�v�ƂȂ�܂��B �@���͓d���̒l�ɂ��S���łS�̏o�͏�ԂɂȂ�܂����A�R���p���[�^��H�̏o�͂Ń����[�ړ������������̃����[��ON���Ă��܂��Ƃ����ړI�̏o�͂ɂ͂Ȃ�܂���̂ŁA�u�d���l�ɉ����āA�Ή������P�̃����[������ON�ɂȂ��v�Ƃ����_����H������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�ʏ���f�W�^��IC�Ȃǂ��g���ă��W�b�N��H�Ŕ��ʉ�H��������肵�܂����A������t�H�g�J�v�� TL521-1���g�p���ď�̃R���p���[�^�o�͂Ɖ��̃R���p���[�^�o�͂̏�Ԃ��u�オH�ʼn���L�̈ʒu(�܂肻���ɑ���d���͈͂�����)�v�����t�H�g�J�v������LED�ɓd��������ăg�����W�X�^��ON���锻���H���g�p���܂��B �� TLP521-1���R�ł͂Ȃ��A�S��H�����TLP521-4���g���Ă��\���܂��� �� �����[�E�h���C�o �@�g�p���郊���[��OMRON G5V-1 DC5V�ȂǃR�C���d��100mA�ȉ��̏��^�����[�ł��B �@�h���C�o�p��2SC1815�̃x�[�X��1��F�̓d���R���f���T�����Ă��܂����A�O���m�C�Y�ȂǂŃ����[��ON�ɂȂ��Ă��܂�Ȃ��悤�킸�������������x�𗎂Ƃ��Ă��܂��B������ł͒x��͑S���������Ȃ����x�ł��B �� �d�� �@�@�B�̓d����12V�������ł����A�s����ȏꍇ������܂��̂ŎO�[�q���M�����[�^��5V�ɗ��Ƃ��Ĉ��艻���Ďg�p���܂��B �@�X�C�b�`�Ƃ͂����d���͈̔͂����o����ȂLj��̃Z���T�[��H�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���肵���d���œ��삳���܂��B �� �����Ȃ� �@���̉�H�ɂ͑g�ݗ��Ă�������ߌ��͂���܂����B �@�g�ݗ��ĂɊԈႢ����������̂܂܂œ��삵�܂��B �@���������Ȃ��ꍇ�́A�e�����̓d���Ȃǂ���H�}���̒l�Ɣ�ׂĂ݂āA�g�ݗ��ĊԈႢ�̂������T���Ă��������B �@�I�y�A���vIC��LM324���g�p���Ă��܂��̂ŁA�I�y�A���v���P��H�]���Ă��܂��B�Ȃ����������Ȃ��悤�ȋC�����܂��i�O�O�G �@�����P��H�R���p���[�^��H�𑝂₵�Ĕ��ʂ��T�i�K�ɂ��Ă��ƁA�o�͂͂S�̃X�C�b�`�܂Ŕ���ł���悤�ɂȂ�܂��ˁB �@�܂�����̉�H�̂悤�Ɂu�����̃X�C�b�`��������Ă��ǂꂩ�����[�������ON�v�Ƃ�����H�ł͂Ȃ��A�u�����ꂽ�X�C�b�`�ɑΉ����������[�������ł������ƑΉ�����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ����̂��R���p���[�^�ɂ��d������������ƍׂ������đS�Ă̒�R�l�p�^�[���ɑΉ��ł���悤�ɂ��āA���̏o�͂���Ή����������[��ON�ɂ����H�����Ă��Ύ����ł��܂��B �@��������̉�H�������ƍ��x�ȃX�C�b�`��H���K�v�ȕ��́A����̋L�����ɏ����܂����v���@��ǂ܂�čX�ɕ����āA�������Ŏv���悤�ȃX�C�b�`��H��v���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2010/1/21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
��́@4013���g�p���āA �@1.�X�C�b�`���`���C�i�Z���ԁj��������Əo�͂�on �@�@����1��X�C�b�`���`���C��������Əo�͂�off �@�@�X�C�b�`�������x�ɏo�͔��] �@2.�X�C�b�`�����ԉ����ƁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�on�ɂȂ� ����ȉ�H���������L��������܂����A����Ȃ����Ƃ��Ă���́H (������]) �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���ꂾ���ł͏����ݒ肪����ӂ�ŏ����܂��E�E�E�B �@�������ԉ������ꍇ�A(�X�C�b�`�͉���������)���̏�Ԃ����]���Ă��ǂ��Ȃ�b�͊ȒP�ł��B �@�����u����OFF�ŁA�������ԉ�������FF��ON�ɂ͂Ȃ炸�ɁA�o�͂����X�C�b�`�������Ă���Ԃ�ON�ɂȂ�A���������猳��OFF�̂܂܁B�v�Ȃ�Ă���������삾������4013������������ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��悤���B �@�`�����ƒZ���ԉ��������������]�p�̃N���b�N���o�͂���悤�Ȕ��ʃ^�C�}�[��H���K�v�ɂȂ�܂���ˁH �E�`�����Ɖ�������o�͂����]���� �E�����ԉ����Ă���Ԃ͏o�͂�FF�̏�ԂɊW�Ȃ�ON�ɂȂ���ςȂ� �Ƃ��������ł���A�_�C�I�[�hOR����邾���ʼn\�ł��B 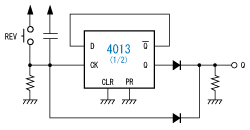 �@4013��D-FF�ō�������]FF(T-FF)�̏o�͂ƁA�{�^���������Ă����H�ɂȂ�CK���͂̐M�����_�C�I�[�h��OR���Ƃ�A���]FF�̏o��Q�̏�ԂƋ��Ɂu�X�C�b�`�������Ă���Ԃ�Q=H�v�ɂȂ�܂��B
�@4013��D-FF�ō�������]FF(T-FF)�̏o�͂ƁA�{�^���������Ă����H�ɂȂ�CK���͂̐M�����_�C�I�[�h��OR���Ƃ�A���]FF�̏o��Q�̏�ԂƋ��Ɂu�X�C�b�`�������Ă���Ԃ�Q=H�v�ɂȂ�܂��B�@�X�C�b�`���`������������A���ʂɏo�͂�ON��OFF��OFF��ON���J��Ԃ��܂��B �@OFF�̎��ɒ���������ƁAFF�̏o�͂�ON�ɂȂ�܂�����o��Q��H�ŏo�͂�H�ɂȂ�܂�����A���������Ă��Ă������Ɏ������Ă��������(�o��=H)�ł��B �@ON�̎��ɒ���������ƁAFF�̏o�͂�OFF�ɂȂ�܂�����o��Q��L�ɂȂ�܂����A�X�C�b�`�������Ă���Ԃ̓X�C�b�`�o�R�ŏo�͂�H�ɕۂ���܂�����������܂ŏo�͂�H�̂܂܂ł��B�u���������Ă���Ԃ�ON�v�Ƃ������������܂��B ���Ԏ� 2010/1/15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
���₳���Ă����������҂ł��B �����̂����肪�Ƃ��������܂����B �����܂Ƃߒ����܂����B �P�D�o�͂�off�̂Ƃ��� �@�X�C�b�`�̃`���C����(0,5�b�ȉ��j�ł́A�o�͂�on���܂��B �Q�D�o�͂�off�̂Ƃ��� �@�X�C�b�`�����ԁi0.5�b�ȏ�j�����ƁA �@�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�on�ɂȂ�܂��B �R�D�P�ŏo�͂�on�ɂȂ������ �@����1��X�C�b�`�������ƁA �@�`���C�����ł��������ԉ�������ł� �@�X�C�b�`�𗣂����u�Ԃɏo�͂�off���܂��B ���̎���́A��30�N�O�́@CQ Ham Radio�ɁA�g�X�}�[�g��PTT��H�h�Ƃ��āA�f�ڂ���Ă����ƋL�����Ă��܂����A�ǂ����Ă��v���o�����ɂ��܂��B ����ӂ�ȋL���ł����A �P�D�X�C�b�`�i���́j�́AL�ŃA�N�e�B�u �Q�D��H�́A�o�̓X�C�b�`�p�̃g�����W�X�^�ȊO�� �@�@4013�Ɛ��̃R���f���T�E��R�݂̂��g�p���Ă��܂����B �R�D�o��Q�́A�g�����W�X�^�� �@�@���]�o��Q��CR�̒x����H��ʂ�D���͂ɐڑ����Ă��܂����H�B (������]) �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@�uPTT�p�̉�H�v�ł���A������������Ŏg�����Ƃ����������Ȃ��ŏ��ɂ����������Ȃ��̂���ϕs�v�c�ł��B �@�u�X�C�b�`�k�ŃA�N�e�B�u�v�Ƃ��������ł���A4013��H�G�b�W�g���K�^�ł�����u�X�C�b�`����������ɏo�͏������ς��v�Ƃ�����H�ɂȂ�܂��B �@����l���Ă����H�ƍ��{�I�ɍl�������Ⴂ�܂��̂ŁA�܂��ꂩ����Ȃ����ł��ˁB������̉�H�̂ق����_�C�I�[�hOR���g�킸�ɍς�ŕ��i�������Ȃ��Ă��X�}�[�g�ȉ�H�Ȃ̂�������܂���B �@�v�����Ȃ����܂��̂ł����ԂՂ������Ǝv���܂��B �@��̉ł������܂����ʂ�A�����u����OFF�ŁA�������ԉ�������FF��ON�ɂ͂Ȃ炸�ɁA�o�͂����X�C�b�`�������Ă���Ԃ�ON�ɂȂ�A���������猳��OFF�̂܂܁B�v�Ȃ�Ă�����H�Ƃ����̂�����̐����ł���ˁH �@������̒��ł͓��ɂ��������w��͖��������̂ʼn��珜�O���Ă��܂����B �@�������������H�ł���]�̋@�\����������̂ł���A�R���f���T�ƒ�R����lj����邾���ł�����������ɂȂ�܂��B 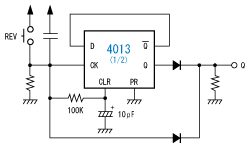 �@�u�X�C�b�`��(0.5�b�ȏ�)�����������ꍇ�AFF��OFF�ɂ���B�v�Ƃ�������������������̂ŁA�X�C�b�`ON�̎��Ԃ����ȏ㒷���ꍇ�́A���̃X�C�b�`�����̏u�Ԃ�FF��ON�ɂ��Ă��Ă�OFF�ɂ��Ă��Ă��W����FF�����Z�b�g���Ă����������ł�����A�X�C�b�`�M����H����ϕ����Ĉ�莞�Ԓx���������M����FF��CLR�[�q��H���x���ɂ��܂��B
�@�u�X�C�b�`��(0.5�b�ȏ�)�����������ꍇ�AFF��OFF�ɂ���B�v�Ƃ�������������������̂ŁA�X�C�b�`ON�̎��Ԃ����ȏ㒷���ꍇ�́A���̃X�C�b�`�����̏u�Ԃ�FF��ON�ɂ��Ă��Ă�OFF�ɂ��Ă��Ă��W����FF�����Z�b�g���Ă����������ł�����A�X�C�b�`�M����H����ϕ����Ĉ�莞�Ԓx���������M����FF��CLR�[�q��H���x���ɂ��܂��B�@�`���������ł͐ϕ���H�̓d���͏\���ɏオ��܂���̂ŁA�P��CK�[�q��H�G�b�W��FF�]�����邾���ł��B �@����������ƁA���������Ă���Œ��ɐϕ���H��������FF�����Z�b�g���܂�����A�X�C�b�`������O��FF��OFF�ɂȂ��Ă��ăX�C�b�`����������_�ł͕K���o�͂�OFF�ł��B �@�����@�Ɛڑ�����W�ŁA�O��PTT�X�C�b�`�̂킩���PTT�[�q��L�ɗ��Ƃ������̂Ńg�����W�X�^�����Ă����̂ł��傤���A����̉�H�}�ł�4013���̓���������邾���ł��̂Ńg�����W�X�^�͋L�����Ă��܂���B�������炸���������������B ���Ԏ� 2010/1/18
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���߂܂��āB �Ԃ̓d���Ɋւ��Ă̎���Ȃ�ł����A���[�������v�ƃ}�b�v�����v��A������悤�ɔz�����l���Ă��܂��B �}�b�v�����v�P�̂ł��g�p�\���邽�߂ɁA�}�b�v�����v�e��ON-OFF-ON�X�C�b�`�ŘA��-OFF-��A���̐�ւ������悤�Ǝv���܂��B ��肪�A ���[�������v�Ɍq����z�����番����l���ē��ʃ`�F�b�J�[�Ŋm�F�����ہA�h�A�N���[�Y���`�F�b�J�[�_���A�h�A�I�[�v�����`�F�b�J�[�����ɂȂ�܂��B ���̎��A�h�A�I�[�v���Ł{12V������悤�ɂ���z���������ĉ������B �����̓d�C�A�d�q�m���͂���܂��B �X�������肢�v���܂��B ������ �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA���̏��������ƃh�A�X�C�b�`���烋�[�������v�Ɍq�����Ă�����Ɂu�h�A��=�d�C(+12V)�����Ă����v�u�h�A�J=�d�C���r����v�Ƃ������ȑ��茋�ʂƂȂ��Ă��āA�u�h�A���J��������(�����v��_��������̂�)�d�C(+12V)���~�����v�Ƃ������̂悤�ɗ����ł��܂����A����Ő������ł����H �@�������̒ʂ�̑��茋�ʂ��Ƃ�����A����͎ԂƂ��Ă��������z���ł��B (����A�ŏ������ԈႢ���Ƃ͌����Ă��܂��E�E�E) �@��������C�W�����ȏ������ɂȂ�܂����A�ߋ��ɂ�������ł̓��[�������v�ɂ��Ẳ�H�������������Ă��܂����A�Ԃ̓d���n�ł͊�{���̊�{�ł���u���[�������v���}�C�i�X�R���g���[���ł���I�v�Ƃ����_��������������Ă���A���d��ő��肵�Ă݂����ʂ͐��������Ƃ����킩��ɂȂ�܂���ˁB �@�����āA�}�b�v�����v���v���X�R���g���[���œ_�������Ă���悤�Ȃ̂ŁA�u�}�C�i�X�R���g���[�����v���X�R���g���[���̕ϊ����s���Ηǂ��v�Ƃ������͂����ɓ����o����Ǝv���܂��B �@�����ł܂������������Ă���̂́A�ԗp�����d��(�G�[�����̃A�C�e��No.A49�����g�p�������ł�)�Ōv�����u�����v�u����Ȃ��v�́A���̂܂܁u�����v��_��������悤�ȓd���Ƃ����d�C(+12V)�����Ă����v�u���Ă��Ȃ��v�ɂ��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ������ł��B 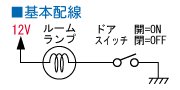 �@�Ԃ̃��[�������v�̔z���͉E�̐}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�Ԃ̃��[�������v�̔z���͉E�̐}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B(�����v��ON-OFF-AUTO�X�C�b�`��A�����̃h�A�X�C�b�`���͏ȗ����Ă��܂�) �@�ق��̃����v���̔z���ƈႢ�A�����v��+12V���Ɍq�����Ă��āA�X�C�b�`���A�[�X�Ɍq�����Ă��܂��B �@����́A�����̃h�A����v���̃X�C�b�`�ł��ꂼ��ǂ��łł�ON�ɂȂ�悤�ɂ���ׂ̍�ŁA�e�h�A�ɂ킴�킴+12V�̓d�����ăX�C�b�`���o�R���ė���ɂ͂Q�{�̘H���K�v�ł����A�h�A���̃X�C�b�`�̐�̓A�[�X�ɂ��Ă���h�A�̋������ɗ��Ƃ������ōςނ̂Ŕz������{����܂��B���������u�蔲���v������ׂɃ��[�������v�̃X�C�b�`���}�C�i�X�R���g���[���ɂȂ��Ă��܂��B  �@�������l�̌v��ꂽ�悤���͉E�}�̂悤�Ȋ����ł��B
�@�������l�̌v��ꂽ�悤���͉E�}�̂悤�Ȋ����ł��B�@�h�A���������ă��[�������v�������Ă������ɂ́A�h�A�X�C�b�`���n�e�e�Ȃ̂ʼn�H�ɓd���͗���Ă��܂��A�r���̔z���Ɍ��d��ĂĂ����̂�+12V���烋�[�������v����ʂ������d��ɓd��������Ă��܂��A���d���LED������܂��B �@��H��OFF�Ȃ̂ɓr���̔z���ɂ��X�C�b�`����d�������ɉ�������p��12V���������Ă����悤�Ɍ����Ă��܂��܂��B �@�t�Ƀh�A���J�������[�������v���_�����Ă��鎞�ɂ́A�r���̔z���������h�A�X�C�b�`��ON�ŃA�[�X�ɗ����Ă��邽�߂Ɍ��d��ɂ͓d���������炸�ALED�͏�������̂ňꌩ������d�����������Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��B �@�����Ɂu�d�����������Ă��邩�H�v�Ƃ����_�ł�LED�̓_��/������ԂŐ������̂ł����A���ۂɂ͂�������ɂ��̓d���������čs���ă����v��_��������悤�ȓd���ł͂Ȃ��A�d����ʂ���+12V�����R��ė����d�����A�����̓d���ł�����LED�̓����Ō���ĕ\�����Ă���̂ɂ����܂���B �@�������ׂ�ꂽ�Ԃ����̒ʂ�̉�H�ɂȂ��Ă��āA�}�C�i�X�R���g���[���ł���̂ł���Ύ��̂悤�ȊȒP�ȕ��i�̒lj������ōς݂܂��B 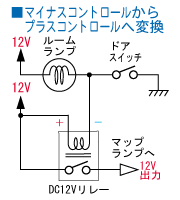 �@�E�}�̂悤�Ƀ����[�������邾���Ńh�A�I�[�v������+12V���}�b�v�����v�ɋ������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�E�}�̂悤�Ƀ����[�������邾���Ńh�A�I�[�v������+12V���}�b�v�����v�ɋ������邱�Ƃ��ł��܂��B�@����{���ɁA���������ꂾ���ł��B �@���́A�}�b�v�����v���}�C�i�X�R���g���[���ɉ���(�z����ς���)���Ă��܂��ƁA�����[�ȂȂ��ɂ��̂܂܂��̔z�����q�������Ń��[�������v�ƘA�������Ă��܂���̂ł����A�����́u�����̓d�C�A�d�q�m���͂���܂��B�v�Ƌ�����Ȃ炱���ʼn�H�}�������Ȃ��Ă����v�ł���ˁB �@DC12V�����[�͏H�t���Ȃǂ̓d�q���i�X�ň������Ȃ���50�`100�~���炢(����͑�d���p�ł͖����̂ŏ��^�ł��イ�Ԃ�)�B�J�[�p�i�X��z�[���Z���^�[�̎ԗp�i�����ł悭�����Ă���G�[�����̃����[��900�`1000�~���炢�ł��B �@�����݂����킩���Ă��܂��A�����[�̂Ƃ�����@���͂������l�ɂ͂��o���ɂȂ�ł��傤����A�z������������ǂ����Ԃ̗��ɒʂ����肷��H�����܂߂Ă��P���Ԃ��炢�łł��Ă��܂��ł��悤�ˁB ���Ԏ� 2010/1/14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 2/8 |
���������܂ŁA���܂��o���܂����B ���肪�Ƃ��������܂����B ������ �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ�������ł����c �p�b�ƌ����āA3�b���炢�_�������܂܂ŁA�p�b�Ə����Ă܂��p�b�Ɠ_������悤�ɂ������̂ł����c �o���܂����H�@�@�����o����悤�Ȃ��낵�����肢���܂��B ���R �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA����͖@�I�ɃA�E�g�Ȃ̂ł́H �@�Ԍ��ɒʂ�܂��A��@�����Ɋւ��Ă͂�����ł͂��������Ă��܂���B ���Ԏ� 2010/1/14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�ǂ����B�Ԏ��A�x���Ȃ��Ă����܂���B �@�I�ɂ̓A�E�g�ł����A��ւ��X�C�b�`�ȂǂŐ�ւ����ɂ��邱�Ƃ͖����ł��傤��? �ԉ�����ɕ������Ƃ���ɂ��ƁA��ւ��ł���Ȃ���Ȃ��炵���Ɓc�B�@���ł��傤���H�@��͂薳���ł��傤���H ���R �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���Ԃ����������Ƃ������Ƃ́A�F�X�ȂƂ���ɖ₢���킹����A�ԊW�̊e��@�����߂������ׂɂȂ��Ă����̂ł��傤�ˁB �@���̎ԉ�����Ƃ����̂́A�\��������Ɂu�E�E�Ȃ���v�v�ƌ����ĕs�@���������Ă���悤�Ȃ��X�ł����H(�܂�������Ȃ����炳�܂Ȃ��X�͂Ȃ��Ȃ������Ǝv���܂����c) �@�܂Ƃ��Ȃ��X�ł͂��̂悤�Ȃ��Ԏ��͂ł��Ȃ��͂��Ȃ̂ł����E�E�E�E�B �@���Ƃ��A�ߔN�̖@�K���ŃG���W����]���͏펞�_�����`���t����ꂽ�o�C�N�̃w�b�h���C�g�Ɂu�ӂ���͂����ςȂ��ɂ���B�@���̋y�Ȃ����L�n���ł̂ݏ����������̂ŃX�C�b�`��t�������B�����𑖂�ۂɂ̓X�C�b�`�͕K��ON�ɂ��Ă����Ɩ��邩��B�v�Ƃ��������Ƃ��炵�����R�Ń��C�g��������X�C�b�`�������ꍇ�A�u�X�C�b�`���t���Ă��邾���ň�@�v�Ɖ��߂����킯�ł����A����Ɠ����Łu���̓_�ő��x����߂��Ă���E�C���J�[�ɁA�ӂ���͂����Ƃ����_�ł�������A����̏������ł݈̂�@�_�łɂ͂Ȃ邪�ӂ���̓X�C�b�`����Ă���������v�B�v�ƌ����ăX�C�b�`�������ꍇ�A���炩�̌x�@�ɂ�錟����A���R�̂��ƂȂ���Ԍ��Œʂ邱�Ƃ͂���܂����ˁB �� �ŋ߂�LED�C���~�Ɩ�(�قƂ�ǂ���@�i)�̕��y�ŁA�Ԍ��̏ꍇ�ɉ��炩�̒lj��@���z���Ɏ肪�������Ă���ꍇ�A���̕����̌����͓��ɔO����ɍs���Ēlj�(����)��H�Ȃǂ̏ꍇ�͂���삹�ĕs���Ȃ��̂łȂ������Ȃ茵�����`�F�b�N����Ă��邻���ł���B �@�����ԉ��������Ƃ��āu�X�C�b�`��t����Α��v�v�ƌ����Ă���̂ł�����A���̎ԉ����珑��(�����ɉ�Ж���Ј����ꂽ����)�Łu�X�C�b�`��t���ăE�C���J�[����@�ȃX�s�[�h�ɐ�ւ�������s���͖̂@�I�Ȗ�肪���������Ȃ̂ŁA���Ђ̐ӔC���������s���܂�(�s�킹�܂�)�v�Ƃ����悤�ȏ���(�O��)��������Ă��Ă��������܂��B �@����ł��̉�ЂƁA�m�荇���̌x�@���Ȃǂɖ₢���킹�ĉ��������v�Ȃ�A���m�Ȏ��̎v���Ⴂ�������ƎӍ߂����܂����A��H�}�����������܂��B ���Ԏ� 2010/2/4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 3/13 |
���܂��܁C������ƍ���Ă݂�����H�������āC������̃z�[���y�[�W�����܂����D ���낢��ȃA�C�f�B�A����H�}�Ƃ��ċ����Ă��ė��h���Ȃ��Ǝv��������ł����C����ɁC���̂悤�ȑΏ�������Ă��鎖�ɂ̓r�b�N���D��@�͂����܂����ˁD �Ƃ肠�����̊��z�ł��D �Ȃɂ��C���f�����鎖�����邩���m��܂��C���̐߂͂�낵�����肢�������܂��D shoji �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�^�C�}�[IC���g������H����肽���ƍl���Ă��܂��B �@���ݓd�r2��(3V)�ŐU�����[�^���쓮�����g�p���Ă��܂����A���s���ł킩��Ȃ��̂ŁA�����Ă��������B 1)3�A10�A60�b�ŐU�����~ 2)3�A10�A60�b�Ō������Ȃ����~ �@���p�^�[�����K�v���Ǝv���̂Ńu���b�h�{�[�h�Œ�R�E�R���f���T��ς��Ȃ���g�p�������ƍl���Ă܂��B stsm �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �^�C�}�[ �@�^�C�}�[���͂�����ʓI���^�C�}�[IC 555�ɂ�郏���V���b�g�^�C�}�[�ł��B �@�A���A���d�r��{�Ŏg�p���邽�߂ɁA��d�����삪�\��C-MOS�^�C�v��LMC555���g�p���܂��B �@���Ԃ͔��Œ��R�ʼnςł��A����]�̂R��ނ̎��ԗp��VR1(0�`12�b)�EVR2(0�`25�b)�EVR3(0�`120�b)�̂R��p�ӂ��A�X�C�b�`�Ő�ւ��Ďg�p���܂��B(�ׂɃu���b�h�{�[�h��ŕ��i���������Ă��\���܂���c) �� ���[�^�[�쓮��H �@LMC555�ł̓��[�^�[�͒��ډ܂���A�g�����W�X�^�ɂ�郂�[�^�[�h���C�o��H���K�v�ł��B �@�P�Ƀ^�C�}�[ON���Ƀ��[�^�[�������Ȃ�g�����W�X�^��ōς݂܂����A����́u�������Ȃ����~�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�R���f���T�̕��d�ɂ��x����H�Ƃ��܂��B �@�X���[OFF�X�C�b�`�����Ă����Ԃł͖�Q�b�O��(���[�^�[�ɂ��)�ŃX���[�_�E�����܂��B �@�X���[OFF�X�C�b�`����Ă���^�C�}�[OFF�Ń��[�^�[�͑����ɒ�~���܂��B �@������X�C�b�`�������ɁA�u���b�h�{�[�h��Ŕz�����q����������肵�Ē����Ă��S�R�\���܂���B �� �m�C�Y�� �@�e���ɓ����Ă���m�C�Y���p�̃R���f���T�Ȃǂ͕K���t���Ă��������B �@�u���V�����DC���[�^�[�͉�]���͂��Ȃ�̃m�C�Y���ƂȂ�܂��B �@�m�C�Y��555����쓮���ă^�C�}�[�����X�Ɛ�Ȃ�������A�ꂽ�u�Ԃɂ������쓮���Ď��Ԃ��Q�{�₻��ȏ�ON���Ă��܂��Ȃǂ̌�쓮���N����ꍇ�̓��[�^�[�m�C�Y��d���ϓ��ɂ��g���u���ł��B ���Ԏ� 2010/1/14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�����A��X�� �p���`�ɂ������̂���ہA���S������Ɣq�������Ă��������Ă���܂��B����A�L���l�Ɏ��������e����̂ŁA�h�L�h�L���܂��B �@���āA���̉Ƃł̓��r���O�̓V��ɃT�[�L�����[�^�����t���ĉāE�~�A�̊����x�œ_������������肵�Ă��܂����A���Ƃ������ʼn������䂵�����Ǝv���A�䑊�k�ł��B �V��ɉ��x�Z���T�[ TH�P�A���ʕt�߂ɃZ���T�[ TH�Q��ݒu���āA �m�����T�n���̉��x��(��F�R�� -��)�����m����ƁA�T�[�L�����[�^(�Ȍ� �l)�� ON����悤�ɂ������B �@�Ȃ����A �m�����U�nTH�Q������̉��x(��F�P�T�� -��)�����m����܂ł�ON�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ������̂ł��B �@�ړI�́A�~�G�ɑΗ����̒g�[�����g�����Ƃ��ɁA�V��t�߂ɂ�����x�g�C�����܂��Ă�����A�l���X�^�[�g�����A�Ȍ㎩���^�]���������̂ł��B�@�ċG�������^�]�ɂ��h�J�r���ʂ͈ӊO�Ȃ��̂�����܂��B �@�T�[�L�����[�^�́AAC 100V 20W���炢�ł��B���x�ݒ�͂�������Ō��肢�����܂��B�����H�ɂ��ĉ��Ƃ��䋳����������ƁA�܂��Ƃɏ�����܂��̂ŁA������낵�����肢�������܂��B ���������i���������܂����j �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�^�Ăɂ����Ⓒ�������̂ɁA����ȓ~��܂ʼn��x���Ȃ�܂��Đ\�������܂���B �@�V�䕔�Ə��ʋ߂�(�l�Ԃ̋���ʒu)�ʼn��x������s���A����]�̏����œ��삷���H�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���x�Z���T�[ �@���x�Z���T�[�ɂ́A������LM35DZ���g�p���܂��B �@�����x�ő��艷�x��d���o�͂���IC�ł��B �@�o�͓d����1���ɂ�10mV�ł��B �@�}�C�i�X�d����p�ӂ����0���ȉ��̃}�C�i�X���x������܂����A�����5V�̒P�d���Ŏg�p����̂�0���ȏ�ŁA��H�v�ƃI�y�A���v�̋K�i�̊W�Ŗ�0�`85���܂ł�����̉�H�̑���͈͂Ƃ��܂��B �@LM35DZ�̏o�͓d���̓I�y�A���vLMC662�łS�{�ɑ������āA1���ɂ�40mV�ɂ��Č�̔�r��H�ȂǂŎg�p���܂��B �@�V��ɐݒu���鉷�x�Z���T�[�Ə��ɋ߂��{�̂Ƃ̊Ԃ͋���(2m���x)������܂��̂ŁA�V�䕔�ɂ͉��x�Z���T�[LM35DZ������u���̂ł͂Ȃ��A�v���A���v�����ēd�����グ�ď��������m�C�Y�Ȃǂɋ������Ă����܂��B �@�z�����Q�`�R���̃V�[���h�����g�p���ĊO���̓d�C�I�ȃm�C�Y�ɋ������Ă��������B(�Q���̏ꍇ��GND�̓V�[���h�Ԑ��ő�p) �� ���x�����H �@�u���ʂ̉��x��xx���ȏ���v�̏����肷���H��LMC662�ɂ���R���p���[�^��H�Ŕ��肵�܂��B �@��r�d����VR1�Ŏ��R�ɐݒ�ł��A��0���`85���͈̔͂�I���ł��܂��B �@���������͈݂̔͂̂Ŏg�p�����ꍇ(����̂���])�́AR3��30K���ɕύX����Ɖϔ͈͂���0���`31���ɂȂ�A�{�����[���̓����͈͂�����������g�[�̐ݒ�͈͂ɋ߂��Ȃ�܂��̂ŁB���ݒ肪�y�ɂȂ�܂��B �@���̉�H�}�����đ��̗p�r�Ɏg�p�����������������邩������܂���̂ŁA��{�̉�H�}���ł͍���̉�H�Őݒ�\�ȍő�͈͂�0���`85���ŏ����Ă��܂��B �@����(�{�̂�u���Ă���ʒu)�̉��x���ݒ艷�x��荂���Ȃ��LED1���_�����܂��B �� ���x"��"�����H �@�u�{�̉��x�Z���T�[�v�Ɓu�V�䉷�x�Z���T�[�v�̉��x����LMC662�ɂ�������A���v�Ō��o���܂��B �@�Q�̃Z���T�[�o�͓d�����u�����Z�v�����H�ō������߁A���̍ۂɏ����ȓd��������Ŕ��肵�₷������ׂ�10�{�̓d���ɑ������܂��B �@�����A���v�̏o�͂͂Q�̃Z���T�[�����x�� (S2-S1) �~ 400mV�ƂȂ�܂��B �@�����u�R���ȏ�̍����J������(�V�䑤�̂ق�������)�v�Ƃ���������s�������ꍇ�́A�R���~400mV��1.2V�ȏ�ł��鎖�ʂ���悢�̂ŁA���x���d����LMC662�ɂ���R���p���[�^��H�Ŕ��ʂ��܂��B �@���ʂ��鉷�x����VR2�Ŏ��R�ɐݒ�ł��A��0�`6���͈̔͂�I���ł��܂��B �@����]��̂R���̏ꍇ��VR2���قڒ����ɂ��킹�����]�̉��x�������m����悤�ɂȂ�܂��B �@�Q�̃Z���T�[�̉��x�����ݒ荷�ȏ�ɂȂ��LED2���_�����܂��B �� �o�͉�H �@�u���x�����H�v�Ɓu���x�����H�v"��"�̏o��(�A���쑤)���_�C�I�[�hD1��D2��OR���Ƃ��āA�u���x���Ⴂ���v�܂��́u���x�������������v�̂����ꂩ�̏ꍇ�́u�o�͂삳���Ă͂����Ȃ��v�������������܂��̂�Tr1��ON�ɂ��ďo�͗pTr2��OFF�ɂ��܂��B �@�u���x���������v���u���x�����傫�����v�̂֎~��������������A�o�͂�ON�ɂȂ�܂��B �@AC100V��ON/OFF����̂̓����[�ł��悢�̂ł����AON/OFF���̃m�C�Y�̂قƂ�ǖ���SSR(�\���b�h�X�e�[�g�����[/�����̃����[)���g�p���܂��B �@�����SSR�͕��i���o���ŏW�߂č��̂ł͂Ȃ��A�H���d���Ŕ����Ă���SSR�L�b�g(25/20A�^�C�v 250�~)���g�p���܂��B����͈����Ċ����x�������̂ŏd�܂��i�O�O�G �� �d�� �@�d����DC 5V�ł��B �@AC�A�_�v�^�[�Ȃǂ����艻���ꂽ5V���g�p���Ă��������B �@���x�≷�x���肷�镔���ł͓d���d�����番�����Ċ�d��(����d��)������Ă��܂��̂ŁA�s����ȓd�����g�p����Ɠ��삪�s����ɂȂ�܂��B �� �V���~�b�g��H �@���x����Ɖ��x�������H�ł̓V���~�b�g����������Ă��܂��B �@��x�ݒ艷�x�ɂȂ���ON�ɂȂ�ƁA���x���킸����(����)������܂ł�OFF�ɂ͂Ȃ�܂���B �@����͐ݒ艷�x���肬��̂Ƃ���ʼn��x���t�������Ƃ��Ƀ����[�o�͂��o�^���̂�h�����߂ł��B �@���l�ɉ��x�������H�ł������킸����(0.����)�������Ȃ�܂ł�OFF�ɂ͂Ȃ�܂���B �@���̕��A�܂ł̉��x�̕��͍���͂��܂�ςɂ���K�v�����Ⴂ�ƍl���ČŒ�ɂ��Ă��܂��B �@�����ςɂ��ꂽ���ꍇ��R4��R15��100K�`1M�����x�ʼnςł���悤�ɌŒ��R(100K)�{���Œ��R(1M)�̂悤�Ȋ����ɂ��Ă��������B �� ���� �@��{�I�ɁA���삳����ׂ̒��߂Ƃ����K�v�͂���܂���B �@�u���x����v�Ɓu���x������v�̔��Œ��R(�܂��̓{�����[��)���Ă���]�̉��x�ɐݒ肷�邾���ł��B �@���삪���������ꍇ�A�e�e�X�g�|�C���g(TP)�̓d�����v��A���ۂ̉��x�ɂ��킹�Đ������d���ɂȂ��Ă��邩�ǂ����ׂĂ݂Ă��������B �@LED�\���́A�u���x����v��LED1�Ɓu���x������v��LED2�̗������_���������Ɂu����v��LED3���_�����ďo�͂�ON�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/1/12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@��A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@�s���Ȏ҂��A��J���Ēm����g�ɂ������ɂ�������Ă₷�₷�Ɓu�����v�������ʂ����Ă�������悤�Őg�̂����ގv���ł��B �@�悸���̉�H���ꐶ�����ǂݍ���ŁA����ƌ����s���Ă݂܂��B �@����A�K������������܂��B�����b�ɂȂ�܂����B �@���l�сF���k�����A�m�����U�n�̂s�g�Q�͂s�g�P�̊ԈႢ�ł����B ���������i���������܂����j �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�S�̂Ƃ��Ă͑������G�ȉ�H�ł��A�e�����X�X�ɕ����čl����������ē�����͎g���Ă��Ȃ��̂ŁA�������邱�Ƃ�A�������삵�Ȃ��������ł�����(�z���~�X��n���_�s��)�̉𖾂͗e�Ղ��Ǝv���܂��B �@�����Q���Ԉ���Ă����Ƃ������ł����A��H�}�������ɂȂ��Ă����������肾�Ƃ͎v���܂����A�u�V��̉��x��xx���ȏ���v�ɕύX����ɂ́AIC1���U�ԃs��(��r����)��TP2�̂Ƃ�������ʉ��x�d���ł͂Ȃ��ATP4�̂Ƃ낱���V�䉷�x�d���ɐڑ����Ă��������B ���Ԏ� 2010/1/13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�����L���� ���A����܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�����y�����q�ǂ��Ă��܂��B��Ă���Ă��邢�����̉�H�����^���ō쐬���A���p�ɂ������Ă��܂��B �@���āA�Q���ԃ��C�g�ƌg�я[�d����g�����A�b�v�R���o�[�^�����p�����Ă��������Ă��܂����A�����g�ݍ��킹�Ċ��d�r�Q�{�ŗ��p�ł���k�d�c�����������^���̂Q���ԃ��C�g�������݂܂����B �@�ŏ��A�ȒP�ɑg�ݍ��킹��ł��邾�낤�ƍl���Ă����Ƃ���A�g�уR���o�[�^�̃X�C�b�`�ƂȂ�`�E�b�ڑ����I���E�I�t����̂ɂ́A�ʉ�H���K�v�ɂȂ�̂ł́c�Ƃ������ƂŁA����͔\�͓I�ɒf�O���A�d���Ȃ��A�`�E�b�Ԃ͏펞�ڑ��ŁA�A�b�v�R���o�[�^�͓d���I���̂܂܂Ƃ��܂����B�ҋ@���̓d�����e�X�^�[�ő������Ƃ���A�P�D�U�ʂ`�Ƌ͂��ł����B�iau�p���^�R���o�[�^���p�j �����Ŏ���Ƃ��肢�E�E�E ����F������ǂ����̋L�����ɂ������Ǝv���܂������A���ꂭ�炢�̓d���l�Ȃ�A���قǓd�r�����ɂ��e���͏��Ȃ��̂��ȂƎv���̂ł����A�������ł��傤���H ���肢�F����ԂłȂ���A�Q���ԃ^�C�}�[�̃I�t�ŁA�d���������̃A�b�v�R���o�[�^�̓d�����I�t�ɂ�����@������������������Ƃ��肢���܂��B �@�Ȃ��A�d�r�������t�R�ꂪ�|�����߁A�}���K�����d�r���g�p�������ł��B �X�~ �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u100�~�V���b�v�����v���� �Q���ԃ����v�̐����v�ł͊��d�r�S�{�^�C�v��100�~�����v���x�[�X�ɂ��܂������A����͕��G�ȃ^�C�}�[��H���g�킸��MOS�p���[FET�̃Q�[�g�d�����R���f���T�Œx�������邾���̒P���ȃX�C�b�`��H���g�p���邽�߂ł����B �@MOS�p���[FET�̃Q�[�g�d���͍Œ�2.5V���x�͕K�v�Ȃ̂ŁA�R���f���T�����d���ēd�����������Ă䂭�Ԃ����イ�Ԃ�ɂ��̓d���ȏ���ێ����邽�߂ɂ͓d���d����4�`5V�ȏ�͕K�v�ł��B �@�������d�r�Q�{��3V(�d�r�������Ă�����2V���x�܂�)��d���Ƃ���ƑS���������A�������d�r�Q�{�p�ō��Ȃ��d���œ��삷��g�����W�X�^����g�ݍ��킹�đS���Ⴄ�^�C�}�[��H�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@100�~�̃����v�̉����ɂ���Ȃɕ��i�𑝂₵�Ă�����������͖̂��Ӗ��ƍl���āAMOS�p���[FET�̃X�C�b�`��H�����ōς܂���������Ȃ��̂�I��ł���킯�ł��B �@�X�~�l�͂��̓d�����Ɋ��d�r�Q�{����4.6V(�`5V)�ɏ�������u�g�ѓd�b�[�d���DC-DC�R���o�[�^�ɂ��悤�I�v��DC�R���o�[�^����g�p���ꂽ�����ł����A�m����DC/DC�R���o�[�^���̂̓d����ON/OFF�����悤�Ƃ���Ƃ��낢��ʓ|�Ȏ��ɂȂ�A����(�����v��)�������d��������Ȃ��ꍇ��DC/DC�R���o�[�^�͂قƂ�Njx��ł���̂œ��i�ɃX�C�b�`������K�v��������������܂���B �@�ҋ@���̏���d�������}�C�N���A���y�A���x�ł���A�������قǓd�r�������ςȂ��ɂ��Ă����Ă����d�r�����R�Ɏ���葽�������d�r�������Ă��܂����炢�ŁA���p��͂قƂ�ǖ��ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B �@����Ɉ��ȏド���v��_��������悤�Ȏg�������ƁA�ҋ@�d�͂̓����v�_���d�͂ɑ��Ă��܂�ɏ������̂łقƂ�ǖ������Ă��ǂ����x���ł��B �@����ł����}�C�N���A���y�A�ł��d��������Ă���̂͋C�ɓ���Ȃ��I�Ƃ������ł�����A�ꉞ�d�q��H��DC/DC�R���o�[�^�̓d����邱�Ƃ͂ł��܂��B  �@�}�C�i�X���𑀍삵�Ă���W�ŁA�^�C�}�[�̋N���X�C�b�`��DC/DC�R���o�[�^�̃}�C�i�X���𑀍�ł���悤�ɂ��āA�d������Ă����ԂŋN���X�C�b�`��������DC/DC�R���o�[�^�ɓd��������ď���������J�n����悤�Ȑڑ��ƂȂ�܂��B �@�܂��N���X�C�b�`�������Ă���Ԃ̓^�C�}�[�p�̃R���f���T�ɏ[�d���Ȃ���Ȃ�܂���A�N���X�C�b�`���}�C�i�X���ɍs���Ă��܂����̂ŃX�C�b�`�ŏ[�d�d���𗬂����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�g�����W�X�^����lj����ċN���X�C�b�`��������Ă���Ԃ̓g�����W�X�^�����삵�ăR���f���T�ɏ[�d����悤�ɕ��i��lj����Ȃ���Ȃ�܂���B �@����ŋN���X�C�b�`��������DC/DC�R���o�[�^�����삵�ď������J�n���A�����ɃR���f���T�ɏ[�d���ă^�C�}�[���쓮���܂��B �@�^�C�}�[���쓮���͂��߂���A�N���X�C�b�`����w�𗣂��Ă�MOS�p���[FET�����삵�ă����v��_��������Ɠ����ɁADC/DC�R���o�[�^��GND���}�C�i�X���ɗ��Ƃ��Ă���Ă���̂Ń^�C�}�[���Ԃ����܂ʼn�H�͓��삵�Â��܂��B �@���Ԓ��߂͔C�ӂ̎��Ԃɉςł���悤��VR��lj����Ă��܂��B �@�ł������Ŗ�肪�B �@�g�ѓd�b�[�d���DC/DC�R���o�[�^��������\�͂�����قǗǂ����̂ł͖����̂ŁA�����v��4.8V/500mA�̓��d�����g���Ă���ƁA���ׂ��d�����ċN���X�C�b�`�������Ă�3V�������x�܂ł����o�͂��オ�炸�Ƀ����v�͂قƂ�Ǔ_�����܂��A�R���f���T�̓d�������イ�Ԃ�ɏオ��Ȃ��̂�MOS�p���[FET�����삹���ɋN���X�C�b�`������Ƃ����Ƀ����v���������Ă��܂��܂��B �@�F�X�Ǝ����܂������A�L�����̌g�ѓd�b�[�d���DC/DC�R���o�[�^��𗬗p����Ȃ�o�͓d����200mA���x�ȉ��Ŏg�p���Ȃ��Ɛ������N���ƕێ������܂���B �@���d����4.8V/200mA���x���Â��d���ɕς����{���]�|�̃����v�ɂ��邩�A���d���̎g�p�͂�����߂����FLED��10�ȓ����炢�ŏ���d��200mA�����ł����������邢LED�d���ɂ����ȂǁA�����v�������イ�Ԃ�ɋᖡ����K�v������܂��B �@�܂�4.0�`4.2V/250mA�̕��דd�������o�����ꍇ�A�d�����̓j�b�P�����f�[�d�r�g�p��2.4V/680mA�`700mA���d��������܂��̂ŁA�d�r�͂��イ�Ԃ�ɑ�d���g�p�\�ȃA���J�����d�r���j�b�P�����f�[�d�r���g�p���Ȃ��ƁA�}���K���d�r�ł͂����ɓd�r�����Ղ��Ă��܂���������܂���B�܂��d�͕s���ł��イ�Ԃ�ɏo�͓d�����オ�炸�ɐ���ɓ��삵�Ȃ����Ƃ��l�����܂��B �@���ȕێ���H���q�����ɁA�g�ѓd�bDC/DC�R���o�[�^�������4.8V/500mA���d����_���������ꍇ�A���͂ł�2.4V/1300mA�ȏ�Ƃ����ƂĂ��Ȃ���d��������܂�������A�펞ON�X�C�b�`����ꂽ��ԂȂǍł��d�������������̏ꍇ�ɂ͌��̂Q���ԃ����v�Ɠ������d���ł̓}���K�����d�r�ł͂ƂĂ����������܂���i�O�O�G ���Ԏ� 2010/1/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 1/10 |
�@���������������ӂ��܂��B �@��͂�A�Ɨ͂ł͖������������ƂƁA���ɁA���̑ҋ@�d�͂Ȃ疳���ł��邱�Ƃ��������āA���₵���b�オ����܂����B �@���C�g���́A�d���͎�菜���A100�~3LED���C�g��LED���𗬗p���āA������R�v�Z�@�ŎZ�o����������R�����Ďg�p���Ă��܂��̂ŁA�_�����d���́A60mA���x���Ǝv���܂��B �@�����A�A�Q���ɂP��i�P���ԂɒZ�k�j���x�g�p���Ă��܂��B���݂̓d���́A100�~���C�g�ɓ����Ă����{�^���d�r��d���ɂ��Ă��܂����A��Â��Ȃ��Ă����悤�ł����A���łɂQ�������炢�����Ă��܂��B�i����قǂ̖��邳��K�v�Ƃ��Ă��܂���B�j �@���ʁA���̂܂g�p�������ł��B������������������H�́A�X�e�b�v�A�b�v�̂��߂̏h��Ƃ��܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����B �X�~ �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�͂��߂܂��āB�����ł����ɒH�蒅���܂����B���܂�̏��̑����ɖڂ܂����������₳���Ă��������܂��B �Ζ���̘b���ł����A3�K���Ă̊K�i�����Ɍu�����i30W�~2�{�j�����Ă��܂��B���̌u�����͊e�K�̕ǂɐݒu���ꂽ�X�C�b�`���g����ON/OFF����悤�ɂȂ��Ă��܂��B3�K�ɍX�ߎ�B������A3�K�Œ��ւ��ċA���ۂɏ����Y�ꂪ���\�����č����Ă��܂��B�����ŏ����Y��h�~�̂��߂ɁA�X�C�b�`����ꂽ���莞�ԁi��5���j�_��������Ɏ����������������i�X�C�b�`�̂܂܂ł͓���悤�Ȃ�v�b�V���{�^���Ɍ����ł������j�ƍl�����̂ł����m�����s�����Ă���A�ǂ�������炢���̂����F�ڌ��������܂���B �C�̖��� ���� ���l�^�W �����Ɍf�ڂ���Ă���u100�~�V���b�v�����v�����A�Q���ԃ����v�̐���v���ƂĂ��߂��悤�Ɏv���̂ł����A�����E�𗬂̈Ⴂ�������Ă���グ�ł��B �ǂ�������炢���̂ł��傤���H yanz �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@yanz�l�͂��߂܂��āB �@�����������u����邱�Ƃ͉\�ł����A����͂������ł��܂���B �@�K�i�̌u������5V��12V���x�̓d���͈͂́u�����[�g�R���g���[���[�q�v�ł��t���Ă���Εʂł���(���ʂ͖����ł��c)�A�������ʂɓV��(���ǂ̈ꕔ)�Ɍu���������Ă��āA�L���̕ǂ̂Ƃ���ɃX�C�b�`���t���Ă���悤�ȏꍇ�͂��̔z���E�X�C�b�`��ύX����ꍇ�ɂ��d�C�H���m�̎��i���������l���������邱�Ƃ��ł��܂����B�z���̕ύX�E���݁E�X�C�b�`��R���Z���g�Ȃǂ̕��i�̎�ւ����d�C�H���ɂ�����A����ł����Ă��ǂ��Ƃ������̂ł͂���܂���B �@yanz�l�̂悤�Ɂu�ǂ�������悢���킩��Ȃ��v�Ƃ����悤�ȕ���100V�̔z�������������ꍇ�A�R�d�E���Ȃǂ̎��̂ɂȂ��鋰�ꂪ����܂�����A���S�̂��ߍ��͂����������������z���������邱�Ƃ͋֎~���Ă��܂��B �@�܂��u�C�̖����v�ł����l�̍l���ŁA���̒���r���ɃA�_�v�^�[�̌`�Ő���ł���AC100V�@��p��H(���Ƃ��Ή��x��ON/OFF���鑕�u�Ȃ�)�ł���������������܂����A�d�C�H���̔��e�ɂȂ���́A�܂�24V���z���Ă��̐����z���Ɋ댯���������̂Ɋւ��ẮA�����Ŏ��₳�����̒m���E�Z�p�ł͈��S�ɐ������H���s���Ē�����\�����Ⴍ�A���̂̐ӔC��������ɋ��߂���̂����ł����炨�������Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��B �@�����ւ�\�������܂��A����̂��˗����e�ł͎���͂�����߂ēd�C�X�E�d�C�H���X�ɂ����k���������B �@�^�C�}�[�Ŏ����Ő�āA�����K�i�X�C�b�`���L�̏�̊K�ł����̊K�ł��ǂ��炩����X�C�b�`���삪�ł���悤�ȕ��͎s�̂̔z�d���i�ł͂���܂���A���������̑��u�ɂȂ��čH����݂ł��̂��������i�ɂȂ邩������܂���B �@�q���g���āE�E�E�B�������ɂ���X�C�b�`�E�z���ɂP�����X�C�b�`���������āA1-2�K�̊K�i�u������2-3�K�̊K�i�u�������܂Ƃ߂ĂP�̌u�����Ƃ݂Ȃ��āA�����1�K�E2�K�E3�K�̊e�K�̃X�C�b�`�ň�x��ON/OFF�ł���悤�ȉ����Ȃ�d�C�H���m�̕��ɗ��߂����ɂł��܂��ˁB �@1�K����2�K�ɍs������1�K�ŃX�C�b�`����ꂽ���ɂ̓��_��2-3�K�̊K�i�̓d�C�����܂����A3�K�Œ��ւ��ċA�鎞�ɂ�3�K(�ł��ǂ��ł�)�ŃX�C�b�`�����邾����1-2�E2-3�K�K�i�����S�����ĉ��܂ō~���܂����A1�K�ŃX�C�b�`�����������őS�K�̌u������������̂ł����ŏ�����������Ώ����Y��͂���܂���B �@���G�ȃ^�C�}�[���u��d�C�H����Ђ̕����Ƃ���Ă�������Ȃ�ǂ��̂ł����A���������������u�������Ȃ炷������{�I�ȓd�C�H���̋��{�ɏo�Ă��邱�������K�i�̌u�����܂Ƃ߂ăh���I(�Ə���ɖ���)�X�C�b�`�ɔz����ς��Ă��炤�����ŏ����Y��͖h����Ǝv���̂ł����E�E�E�B ���Ԏ� 2010/1/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��A���肪�Ƃ��������܂����B �@���Ԏ��̓��e�͗���v���܂����B�����������ʂ肾�Ǝv���܂��B �@�܂��́A�q���g�̌��ł����A��H�͂��łɂ����Ȃ��Ă��܂��B�u�����͂͂ǂ�����̃X�C�b�`����ł���܂����A������悤�ɂȂ��Ă���܂��B���O�͒m��܂��A���݂̏�Ԃ�NOT����X�C�b�`�ɂȂ��Ă��܂��B �@����ł������Y��邩�獢���Ă���܂��B �@���t���炸�Ő\����Ȃ������̂ł����A���ۂ̍H����������������͂���܂���ł����B��Ђɂ��d�C�H���̎��i���������҂�����A���̎҂ɘb�����Ƃ���A�ȒP�ɂł��邢���Ă��o�Ă��Ȃ������̂ł����k��������ł��B����Ձ{�V�[�P���T�[�ʼn�H��g�߂Ύ����\�ł��傤���A������Ƃ����@�B�ݔ���������Ă���̂ł���͂ł��܂��B�����A�����������悤�ɑ�ȑ��u�ŕ��i�ゾ���ł����z�ɂȂ�܂��B�����ƊȒP�ɂł��Ȃ����Ƃ������Ƃł����B �@���Ƃ����܂��Đߖ��������A�����Ă��������Ȃ��Ƃ������Ƃ��d�v������邨�����A���t���邾���Ōu�����̎��������������ł��鐻�i�������Ă����������Ȃ��Ǝv�����̂ł����A�Ȃ��Ȃ��Ȃ����̂ł��ˁB yanz �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�m���ɃG�R�Ƃ��ȓd�͂ƌ����Ă銄�ɂ́A�z���ݔ��ł͂��������������Ȃ��ł��ˁB �@�s�̂̕��ł͉ƒ���g�p�ł́u�œd�Z���T�[���̐l�̃Z���T�[�X�C�b�`�v�����̖�����S���Ă���Ǝv���܂��B �@Panasonic�d�H����́u�����ĂɃX�C�b�`(�M���Z���T���X�C�b�`)�v�Ƃ���������������Ă��āA���̒����K�i�E�L���p�ł͂P��̐e�@�Ɏq����Q��܂ő��݂ł��܂��̂ŁA�P�K�E�Q�K�E�R�K�ɂ��ꂼ��l���Z���T�[�����Ƃ���āA1-2�K�K�i����2-3�K�K�i�����Ɏ����I�ɓ_�������A�l�����Ȃ��Ȃ�����w��̎��Ԍ�Ɏ����ŏ��������邱�Ƃ��ł��܂��B �@�d�C�H���m�̕�������������Ȃ�A�������������̔z�d�p���u���g����Ǝ����H�����Ȃ��Ă���{�I�ȓd�C�H�������ōς܂����܂��B �@�����Ă������̓d�C�H���m�̕����d�q���i��H��ɂ������Ă�����Ȃ�A�ŏ��̂���]�̒��ɂ���悤�Ɂu�e�K�̃X�C�b�`�͉����{�^���ɕύX����v���Ƃɂ��āA�^�C�}�[���u���u������ON/OFF�p�ɂǂ����ɐݒu����Ă������ł��܂��B �@���Ƃ��AON/OFF����ɂ�Panasonic�d�H�́u�ꎞ����X�C�b�`/�x���~�X�C�b�`�i���̂���g�C���p�j�v���u�p�^�[���Q�v�̈��X�C�b�`�����������莞�Ԃ���ON����p�r�Ŏg���A��������ăX�C�b�`���̔z�����e�K�̉����{�^���X�C�b�`�ɉ������܂��B �@���X�̓g�C���̊��C��p�̐��i�ŁA�ړ_�e�ʂ͏�������(1.5W�`60W)���d�͂̕������q���ł͂����܂��A30W�~2�{���x�ł�����肬��Z�[�t�̂悤�ł��B(�˓��d���Ȃǂ��s���Ȃ烊���[�����Ƃ��c) �@��������舵���������ɂ́u�Ɩ��E�����[���ɂ͐ڑ����Ȃ��ʼn������B���C���p�ł��B�v�Ƃ�������ƓB���h����Ă��܂��̂ŁA���̂ւ�͂悭�����ׂĖ�肪�����悤�Ȃ痬�p����ȂǁA�����܂Ōl�̐��앨�Ƃ��Ắu���ȐӔC�v�̊Ǘ������Ȃ���Ȃ�܂���B �@�����ꃖ���ȏエ���Ԃ��Ă��ǂ��̂ł�����A���݂̔z���͂��̂܂܂Ɍu�������̓���(�܂��͓V�䗠������H)�ɑg�ݍ���ł��܂��u��莞�Ԉȏ�͓_�����Ȃ��^�C�}�[�v�̉�H�}�͒ł���Ǝv���܂����A���݂��������҂������Ă�����ŋ��N�̂W���ɓ��e���ꂽ������ւ̉��܂����f�ڂł��B �@���͂����ōςނƎv��������������Ɍf�ڒv���܂������A��H�}�̒ƂȂ�Ƒ��ɂ��҂������Ă�����̌�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ȃ肨�҂��������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B �@���ꂾ���҂��Ă��ǂ��Ƌ���Ȃ�Ȍ�̑҂����ɓ���܂��̂ŁA�{�L���Ƀ��X����`�ł��m�点���������B ���Ԏ� 2010/1/12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20�`30���œ��삷���H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12V�ŋ쓮����A28���ȏ�ɂȂ�Ɨ�p�t�@�������n�߂��H�������ĉ������B��p�t�@���̒�i���͂�12V 0.08A�ł��B�ł���A���x��20�`30���͈̔͂ʼnϒ�R�ȂǂŐݒ�ł���悤�ɂ������ł��B�}�C�R���Ȃǂ͎g��Ȃ���H�ł��肢���܂��B (������]) �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�w�艷�x�œ��삷�郊���[�Ȃǂ͂������x���f�ڂ��Ă��܂����A����͕��i�������Ȃ����Ċȕւȉ�H�ɂ��Ă݂܂��B �@�������A�I�y�A���v���g�p�������x���m�����[�̂悤�ɉ��x�œ��삷�邩�͓d���Ȃǒ��ړI�Ȑ��l�ł͐ݒ�ł��܂���B���x�ݒ�p�̔��Œ��R(�{�����[��)���čD�݂̉��x�̎��ɓ��삷��悤���߂���K�v������܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���x�Z���T�[ �@���x�Z���T�[�́u�T�[�~�X�^�v(TH)���g�p���܂��B �@�T�[�~�X�^�͉��x�ɂ���Ē�R�l���ς�f�q�ł��B �@����g�p������̂͒�i�u10K���^�C�v�v�̂��̂ł��B���̒�R�l�̂��͎̂g�p���Ȃ��ł��������B �� ���x�����H �@���x���ݒ艷�x���Ⴂ��VR1�{R1�̒�R�l�ƃT�[�~�X�^TH1�ŕ������ꂽ�d�����g�����W�X�^Tr1�̓���d���ȏ�ƂȂ��Ă��āATr1�͓��삵�Ă��܂��B �@Tr1�����삵�Ă����Tr2�̃x�[�X�d����0V�ɗ��Ƃ���Ă���Tr2�͓������A�����[�����삵�Ȃ��̂Ńt�@���͉��܂���B �@���x�������Ȃ�ƃT�[�~�X�^(TH1)�̒�R�l��������A�g�����W�X�^Tr1�̃x�[�X�d������������Tr1��OFF�ɂȂ�܂��B �@Tr1��OFF�ɂȂ��Tr2�ɂ�R2��ʂ��ăx�[�X�d���������̂�Tr2�͓��삵�A�����[�̃R�C���ɓd��������ă����[��ON�ɂȂ�t�@�������܂��B �� �q�X�e���V�X�@�\ �@�ߋ��Ɍf�ڂ�����H�}�ł̓g�����W�X�^��I�y�A���v�Ȃǂ�臒l���蕔���Ƀq�X�e���V�X����������臒l���肬��̂Ƃ���Ń����[���o�^�����肵�Ȃ��悤�ȓd�q��H�ɂ��V���~�b�g��H������Ă��܂������A����̉�H�ɂ͂��̂悤�Ȃ��̂͂���܂���B �@�V���~�b�g��H�E�@�\��������臒l���傤�ǂ�����̉��x�̂Ƃ���ʼn��x������炷��ƃ����[���o�^�������ł����A�����͂Ȃ�܂���B �@���́A����̉�H�ł́u�����[�̃R�C���Ɖ��������q�X�e���V�X�����v�ŃV���~�b�g��H�Ɠ����悤�ȓ�����������Ă��܂��B �@�����[�͊�{�I�ɂ͂�����̓d���ȏ�̓d����������ƒ��̃R�C�����ړ_�����S�Ђ��������ăJ�`�b�Ɛړ_���ւ�����̂ł����A�����ɂ͂��̉���������(ON)���鎞�̓d���ƊJ��(OFF)����鎞�̓d���ɂ͍�������܂��B �@ON�ɂȂ鎞�ɂ̓R�C���ƓS�Ђ̋���������Ă��邽�߂ɂ��鎥�͈ȏ�ɂȂ�Ȃ��ƓS�Ђ����������ē��������Ƃ��ł��܂���B �@�Ƃ��낪��x���������Đړ_�����ƁA�R�C���ƓS�Ђ̋����̓[���ɂȂ�̂ōŏ��ɓ����������̎��͂��ア�͂ł��̈ʒu���ێ����Ă������Ƃ��ł��āA�������ɂ͈������������ア���͂܂Ŏ�߂Ȃ��ƓS�Ђ͗���܂���B �@���̍��͔��ɏ����Ȃ��̂ł����A�R�C���ɗ����d���ƃ����[�̓���ɂ��イ�Ԃ�ȃq�X�e���V�X���\���������邱�Ƃ��ł��܂��B �@�ł�����A����̉�H�ł͂���ݒ艷�x�ɒB������J�`�b�ƃ����[�������A�ݒ艷�x��菭���������x��������Ȃ��ƃ����[�͐�Ȃ��̂ŁA���x���ݒ艷�x���x�̂Ƃ���Ńt���t����0.�������x�t�����Ă������[���o�`�o�`�Ɩ\��邱�Ƃ͂���܂���B �@�������A�q�X�e���V�X�͈̔͂��z���鉷�x�ŕω������ꍇ�͕ϊ����킹�ă����[��ON/OFF���܂��B �� ���x�̈��艻 �@����̗p�r�ł͓d����DC12V�炵���̂ŁA���x�Z���T�[��H�̓d���͎O�[�q���M�����[�^78L05���g�p����5V�œ��삳���܂��B �@����]�̎g�p�t�@���͏���d�������Ȃ��̂ő������v���Ƃ͎v���܂����A���x�Z���T�[��H�̓d�������̂܂�12V�œ��삳����ƁA�t�@����ON/OFF�œd���d�����ϓ�������A�܂����̉�H�}�����Ď����ԂȂǂ�12V�d���̏ꏊ�Ŏg�p���鉽���ɗ��p����悤�Ǝv����������������邩�Ǝv���A�����Ԃ̂悤�ɖ�10�`15V�̊Ԃœd���d�����ϓ�����悤�ȏꏊ�Œ��ړd��������ăZ���T�[��H�삹��ƁA�d���̕ϓ��œ���̊�d�����ς��Ă��܂��Đ��������x���肪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��̂ŁA�Z���T�[��H���͈��艻�������d����p�ӂ��ĊO���̓d���d���̕ϓ��ł͉��x���肪����Ȃ��悤�ɂ��܂��B �� ���쉷�x�̐ݒ� �@��H�}�̒ʂ�̒�R�l�Ő��삷��AVR1�����ƂŖ�20���`30���̊Ԃœ��쉷�x��ݒ�ł��܂��B �@�����ɉƖ�20���A�����Ŗ�25���A�E�����ς��ɉƖ�30���ł��B �@���͈͈̔ȊO�̉��x�͈͂Ŏg�p���ꂽ�����́AVR1�{R1�̒l�����͈̔͂ɂȂ�悤�ȕ��i��I�肵�āA�������̊�]�͈̔͂Ŏg�p�ł���悤�ɂ��Ă��������B
���Ԏ� 2010/1/9
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�����L���� ���A����܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�����y�����q�����Ă���܂��B �@�����ł����A�ŋߓS���͌^�̐��E�ł�PIC��PWM���g�����p���[�p�b�N�������������Ă���悤�ł��B����͖^�G�������グ�Ă��瑝���n�߂��C�����܂��BN�Q�[�W�̃��[�^�[���̂���VVVF�Ȃǂ̑��s����������Ƃ������̂ł��B �@�Q�l��HEX�t�@�C���̃_�E�����[�h�y�[�W��\���Ēu���܂��B http://www.radiolife.com/RL-Online/support/dl/DL.html �@�ŋ߂͊e�y�[�W�Ŏ��グ���Ă��܂����A�����C�ɂȂ�y�[�W��\���Ēu���܂��B http://kodawaritrain.blogspot.com/ �@����PIC�̏��S�҂ł��A����ƃv���O������������悤�ɂȂ��Ă������x���ł��BPIC��PWM�����N�Q�[�W�̃��[�^�[���特���o���Ă݂����Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł����A�ǂ�ȃv���O�����������Ή����o��̂������ς蕪���炸�A�Ƃ肠�����͖^�G���̃t�@���R���g���[���[������Ă݂��܂łł��B �@�������甭�W�����Ă��������̂ł����A�ǂ������特����Ƃ��q���g�݂����Ȃ̂������m�ł�����f�ڂ��Ă���������Ə�����܂��B����������������ŁA�����Ԃ���������ł����c�B �@�ł͍���Ƃ��Q�l�ɂȂ�L�����y���݂ɂ��Ă���܂��B �悵���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͂��߂ɁAPWM�ł�VVVF�̂悤�ȁu�E�B�`���A�u�C�`���A�M���C�`���c�v�Ƃ������ȉ��͏o�܂���B �@�������������o����̂�PFM�ł��B �@����͑O���œd�Ԃ��特���o���ׂ̊�b�Z�p�ɂ��āA�㔼�ł͂�����ƃn�[�h���������ł������{�����ۂ�����ɂ͂ǂ̂悤�Ȏ�i���K�v����������܂��B �@�܂�PIC�̃v���O�������͂��߂�ꂽ����̕��Ƃ������ł��̂ŁA�O�������������邾���ł���ς�������܂��A�㔼�́u�܂��{�����ۂ�����̂͑�ςȂȂ��v���x�ɂ��ǂ݂��������B 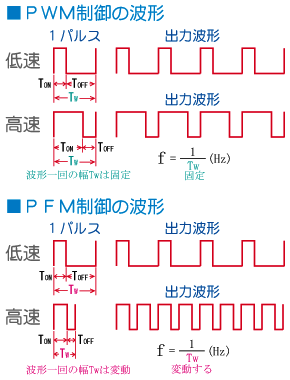 �@PWM��Pulse Width Modulation�̗��Łu�p���X���ϒ��v�ƌĂ��p���X��������ł��B
�@PWM��Pulse Width Modulation�̗��Łu�p���X���ϒ��v�ƌĂ��p���X��������ł��B�@�������̋�`�g�p���X������A���̒���ON���Ԃ�OFF���Ԃ�ω������Ĉ��̃p���X���ł�ON-OFF���Ԕ���f���[�e�B��Ƃ��ĕ\�����ƂŁA���[�^�[�Ȃǂ̃p���[�����̃f���[�e�B��Ԃ�̗͂Ő��䂷�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�}�ł͈��̃p���X��Tw�͈��ŁAON���Ԃ�Ton��OFF���Ԃ�Toff�̃o�����X���ω����A���U���g���� f = 1/Tw (Hz)�ƂȂ�Tw�͕ς�Ȃ��̂�f�����ł��B �@�܂�PWM�ł́A�������U���g��f���l�Ԃ̎��ɕ���������g�����Ƃ��Ă��A�d�Ԃ̃X�s�[�h��ς��Ă������������������܂����B �@PFM��Pulse Frequency Modulation�̗��Łu�p���X���g���ϒ��v�ƌĂ��p���X��������ŁA�m���Ƀp���X�̕���ω������ăp���[�R���g���[�����s�����Ƃɂ�PWM�ƈႢ�͂���܂��APWM�ƈႤ�̂��p���X��ON���Ԃ͕ς����Ɉ��̃p���X��(�܂�OFF����)��ς������@���Ƃ������Ƃł��B �@�}�ł�Ton�̎��Ԃ͈��ŁA�p���[��ω�������ɂ�Toff�̎��Ԃ�ω������Ĉ��̃p���X�̃f���[�e�B���ς���l�q���������邩�Ǝv���܂��B �@PFM�ł͈��̃p���X��Tw�� Tw = Ton + Toff �ŁA���̂���Toff�͕ω����܂����猋�ʓI�ɂ�Tw���ω����A���U���g�� f = 1/Tw (Hz)�͏o�̓f���[�e�B���ω��������Ԃ�ω�����Ƃ������ɂȂ�܂��B �@PFM�ł͏o�͂��ア���ɂ͎��g�����Ⴍ���ɂ���ƒႢ���ɂȂ�A�o�͂��������ɂ͎��g���������������ɕ������܂��B�A�����U���g�����l�Ԃ̎��ɕ���������͈͂̏ꍇ�ł��B������O���Ɖ��Ƃ��ĕ������܂���B �@��������PFM�Ńp���X���䂵�Ă��A������葖���Ă��鎞�ɂ͓d�Ԃ���u���[�v���炢�̒Ⴂ�����������A���������Ă��鎞�ɂ́u�r�[�v���炢�̉�����������悤�ȃR���g���[�����\�ɂȂ邩������܂���B �@�Ⴂ����50�`100Hz�A��������700�`800Hz���x�ɂȂ�悤��PFM�̊e�p�����[�^�߂��Ă��AVVVF�̃��[�^�[���͈̔͂��炢�̉��ɕ�������ł��傤�B �@�����܂ł́A�p���[�p�b�N�œd�Ԃ��特��炸�Z�p�̊�b�҂ł��B �@�����Ă��������͉��p�ҁB�Ƃ��������Ȃ�n�[�h���̍������b���ł��B �@������b�҂̒ʂ��PFM�Ńp���[�𐧌�ł����H��PIC�ō�����Ƃ��܂��傤�B �@�������A�d�Ԃ̓��͌���DC12V��0%�`100%�̊Ԃ̃f���[�e�B��(�p���[)�ŃR���g���[���ł���悤�ɂ��āA�p���[�p�b�N�́u�X�s�[�h�܂݁v(���g�̓{�����[����PIC��A/D���͂Ɍq�����Ă���)��0%����100%�̊Ԃʼn��Ƃ��ɂ��̉�]�p�ɂ��킹�ăp���[�R���g���[�����邾���́u���ʂ̃p���[�p�b�N���̃X�s�[�h�����v�ɂ���ƁA�m���ɑ��x���x�����ɂ͒Ⴂ�����A���x���������ɂ͍����������܂����A�x�������瑁�����܂ň��Ԃ�̒ቹ�`�����̊Ԃ̕ω����y���߂邾���ŁA�{����VVVF�̂悤�ȃE�B�`���A�u�C�`���A�M���C�`���c�Ƃ��������̓r���œr��ČJ��Ԃ����i�K�̃p�^�[�����ɂ͂Ȃ�܂���I (�{���̓d�Ԃɂ̓h���~���K�ɂȂ�悤�ݒ肳�ꂽ�V������VVVF���u������܂���) �@���́A�P����PFM�Ő��䂷�邾���ł�VVVF�̂���VF(��딼��)�����s���Ă��Ȃ��̂ł��B �@VVVF�Ƃ�Variable Voltage Variable Frequency�̗��Łu�ϓd���E�ώ��g�������v�ƕ\���܂��B �@���̌�딼����Variable Frequency�̕��������̂܂܃Y�o���ώ��g����PWM�̂��ƂȂ̂ł��B �@�ł͑O����Variable Voltage�̕����A�ϓd���ł����[�^�[�𐧌䂵�Ă���̂ŁA���ۂ̓��[�^�[�ɂ�����d�����ω�������PFM�ɂ��p���X����ł��ׂ����d�Ԃ̃p���[���R���g���[�����Ă���̂ł��B �@���Ԏ��ɂ͂܂��d����Ⴍ�ݒ肵(�����d���P�Ɖ��ɌĂт܂�)�APFM�Ńf���[�e�B��0%���珙�X�Ƀp���[�������Ă䂫100%�t�߂܂Ńp���[�A�b�v���܂��B�������ēd���P�Ńf���[�e�B100%�A�܂�d���P�̃t���p���[�܂ŏオ�����炱��ǂ͓d�������̃X�e�b�v�̓d���Q�ɏグ��PFM�f���[�e�B��0%�ɗ��Ƃ��Ă܂��������珙�X��100%�Ɍ����ďグ�Ă䂫�܂��B �@�������ēd���P�̒���0%��100%�A�d���Q�̒���0%��100%�A�d���R�̒���0%��100%�̂悤�ɂ����d����PFM���g����ς��Ȃ��琧�䂵�Ă䂭VVVF�����̍ۂɕ�������̂��A����ɓn��0%�`100%�̊Ԃŕω�����E�B�`���A�u�C�`���A�M���C�`���c�Ƃ������̐��̂ł��B �@���������ԖƋ����������̕��Ȃ�A�}�j���A���ԂŃV�t�g�A�b�v���Ȃ���������Ă䂭�̂��C���[�W����Ƃ킩��₷���ł��傤�B(�Ƌ��̖������͂��߂�Ȃ���) �� �{���̓d�Ԃł́A���[�^�[�͎O���𗬗U���@�Ƃ����𗬃��[�^�[�ŁA����������ƕ��G�Ȃ����݂ɂȂ��Ă��܂��B �@�܂�A�S���͌^�̃p���[�p�b�N�Ō����ɓd�Ԃ���E�B�`���A�u�C�`���A�M���C�`���c�Ƃ���VVVF����炵�����̂Ȃ�A�����ɂ��킹�ĂR�`�S�i�K�̓d���d�����ւ��鍂�x�ȓd�q��H���A���Ȃ蒲��������ł���PFM��ON���Ԃ�ς��āA��b�g���N��ύX�������Ƃœd����ς����悤�Ȋ����̏�Ԃ����A�{���̃p���[0%�`100%�̊Ԃ𐔒i�K�ɕ��f���Ă��ꂼ��̋敪���Ńf���[�e�B��%�`100%�̃R���g���[�����s���悤�ȍ��x�ȃv���O���������A�قږ{���̓d�Ԃɋ߂�VVVF�����y���߂܂��B �@�������낻��u�����ɂ̓_�������`�v�Ǝv���Ă��邩������܂��A�X�ɐ[���b�����ďI���ɂ��܂��傤�B �@��ɏ������悤�ȁu��]�c�}�~�̉�]�p�����̂܂܃X�s�[�h�ɂȂ�v�悤�ȒP���ȃR���g���[���[���ƁA�K���d�Ԃ��t���X�s�[�h�܂ŏグ�Ă��܂��Ȃ甭�Ԏ��ɂ�VVVF���̂悤�ɕ������čŌ�̓f���[�e�B100%�Ȃ̂Ńp���X����ł͂Ȃ��Ȃ蒼���ɂȂ邩��S���������Ȃ��Ȃ�܂����A�S���͌^�̏ꍇ�̓c�}�~�������ς��ɉĂ��܂��ăt���X�s�[�h�ő��点�邱�Ƃ͋H�ł���ˁB �@�����Ă��̓t���X�s�[�h�ł͂Ȃ��X�P�[���X�s�[�h�Ŗ{���̓d�ԂɌ�������x�̃X�s�[�h�ő��点�Ă���͂��ł�����A���x0Km/h���炻�̒��x�̃X�s�[�h�܂ł̊Ԃ�VVVF������������̂��œK�ł��B �@�Ƃ������́APIC�Ɍq�����Ă���{�����[���̊p�x0�`�K���Ȉʒu�܂łł͐l�Ԃ̕�������͈͂̉��ɂȂ���g����PFM���䂵�āA��������z�����炻��ȏ�͐l�Ԃ̎��ɕ������Ȃ��������g����PFM��PWM���������悤�ɐ�ւ���v���O�����ɂ���Ƃ��A���x�Ȑ�����K�v�ɂȂ��Ă��邩������܂���B �@�łȂ��ƁA���Ԃ��炢�̑��x�ŌŒ肵�đ��点�Ă���ƁA���̂��������イ�����Ɓu���`�v�Ƃ��d�Ԃ�����ςȂ��ɂȂ�܂���B �@�����Ă���͖{���Ƀv���O�����Z�p���g�ɕt������Ƃ��A�d�Ԃ̓��͐���ɂ��킵���Ȃ������������̂ł����A�{���̓d�Ԃ̂悤�Ɂu�m�b�`����v���ł���悤�Ƀv���O���������āA�����⌸���̎�����VVVF�����o���āA�m�b�`OFF�̏�ԂőĐ��^�]���Ă��鎞�ɂ͉��͑S���o�����ɁA�ł������ƃp���X�͗^���ēd�Ԃ����̑��x�ő��点��(���ۂ͑Đ���\�����邽�߂ɏ��X�ɃX�s�[�h�͗��Ƃ�)�悤�ȃv���O�����ɂ���A�{���̓d�Ԃ��^�]���Ă���悤�Ȋ����œS���͌^���y���߂܂���I �@PIC�Ńp���X���䂷��悤�ȕ��ł͂Ȃ��A�d�����A�i���O���䂷��悤�ȋ����ȕ��@�̎��ォ��A�S���͌^����胊�A���ɑ��点��m�b�`����^�C�v�̃p���[�p�b�N�͐̂���悭����Ă��܂����B �@���������܂Ŏ���ł���悤�ɂȂ�ɂ́A�v���O�����̋Z�p��[�^�[����Z�p�A�{���̓d�Ԃ��ǂ̂悤�ɐ��䂳��Ă��Ă����͌^�ŃV�~�����[�V��������ɂ͂ǂ�����̂���[���������Ă��������K�v������܂����A����PIC�ł̃X�s�[�h���䂪���܂���������A���̐�ɂ��������{�����ۂ����E���҂��Ă���Ƃ������x�Ɋo���Ă����Ē��������ł����\�ł��B �@�܂��͑����Ƃ��āA�d�Ԃ��特���o��PFM�����PIC�ō���Ă݂܂��傤�I ���Ԏ� 2010/1/6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 1/7 |
�@�����X���炵�܂��B �@�̍�����y�[�W�Ń����e�����ĂȂ��̂œ˂����ݏ����ڂł����A�����̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B �@�u�u�u�e�C���o�[�^�Z�p��� http://www2.jan.ne.jp/~jr7cwk/rail/vvvf/vvvf1.html �@�C���o�[�^�d�Ԃ̃T�E���h�������� http://www2.jan.ne.jp/~jr7cwk/rail/vvvf/vvvf_syn.html jr7cwk �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�ڍׂȉ�����肪�Ƃ��������܂����B �@�ƂĂ����ɂȂ�܂��B���̔��������������ł��܂����B �@PWM�ł͂Ȃ�PFM�Ƃ�������ɂȂ�Ƃ͏��߂Ēm��܂����B �@�����͗����ł��܂����������PIC�Ńv���O��������͓̂�����ł��ˁB��H�͏o���Ă��܂��̂ł܂���VVVF��VF���������Ŏԗ����������邩�����Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B �@���ꂪ�ł���p���[�p�b�N�̃{���E���Œi�K�I�ȓd�Ԃ̉������ł��邩�ȁA�Ǝv���܂��B �@���̂�͒������ł����撣���Ă݂܂��B�ڂ���������肪�Ƃ��������܂���!! �悵���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�n�[�h�E�F�A�Ŋ��ɂł��Ă���̂ł���A��̓\�t�g�E�F�A�����ւ��Ȃ��玎�s���낵�Ă䂭�����ł�����A����قlj����Ȃ������ɂ�VVVF���̉����o���Ȃ���ڂ̑O�œd�Ԃ�����悤�ɂȂ�Ǝv���܂���B �@�撣���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2010/1/12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����ȑO�̓����͂����灨 [2009�N�㔼�̉ߋ����O]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�T���₷���ړI�E��H�̃W�������ʈꗗ�͂����灨 [�W�������ʈꗗ]
�悭�g�����i�́u���̐}�v�͂����灨 [�悭�g�����i�́u���̐}�v]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(C) �u�C�̖����v�^Kansai-Event.com
�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������
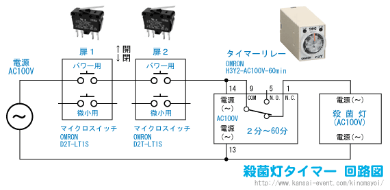
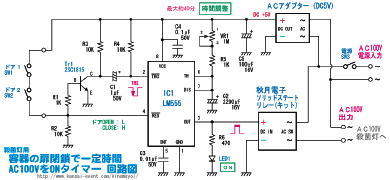
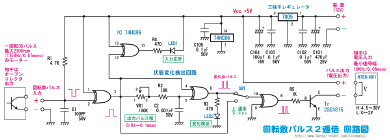
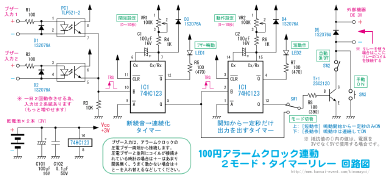
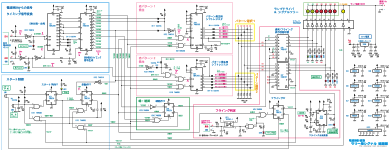
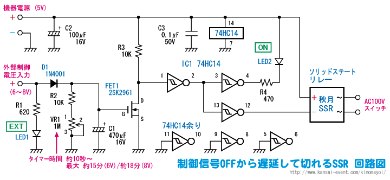
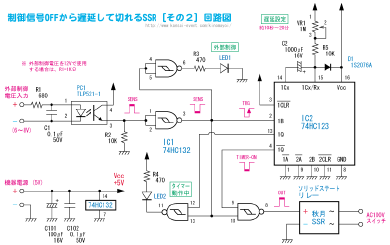
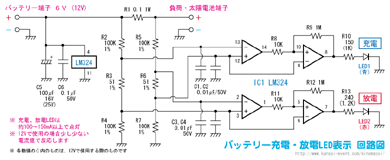
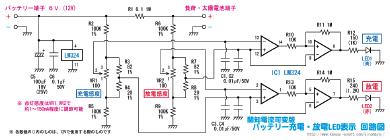
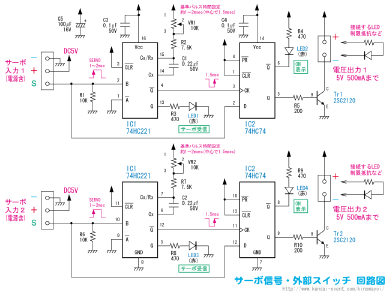
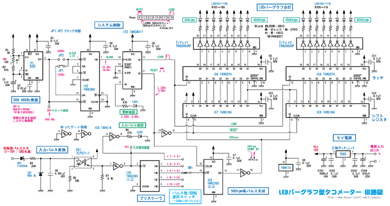
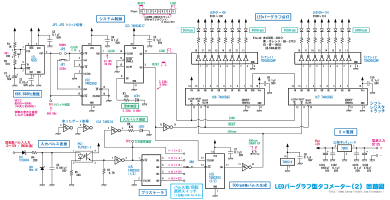
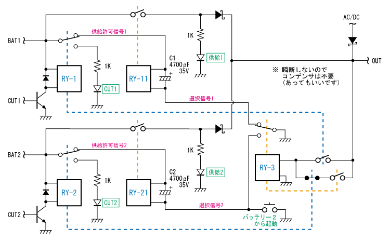
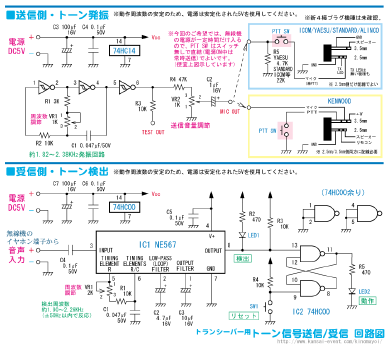
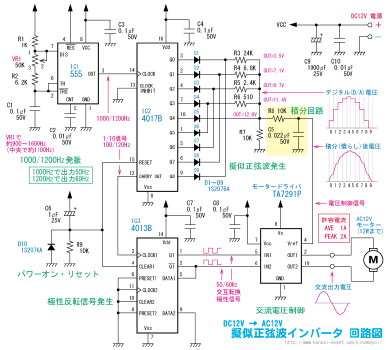
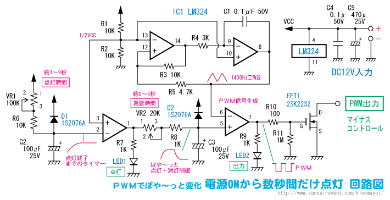
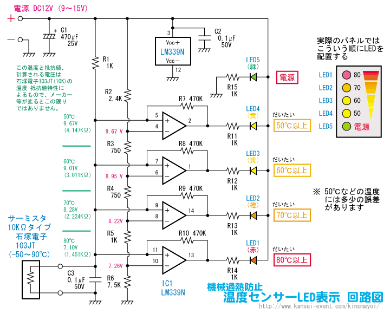

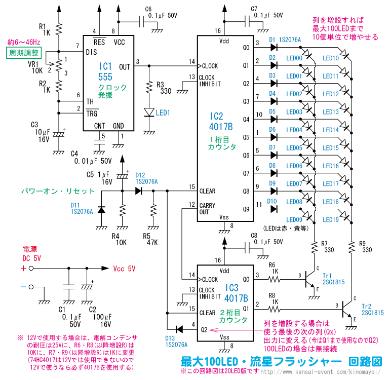
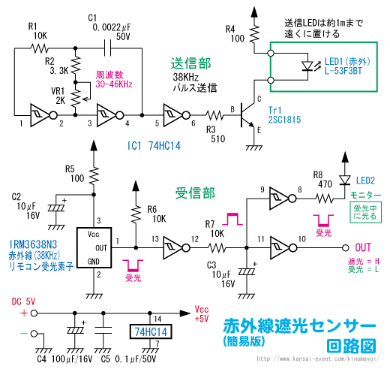
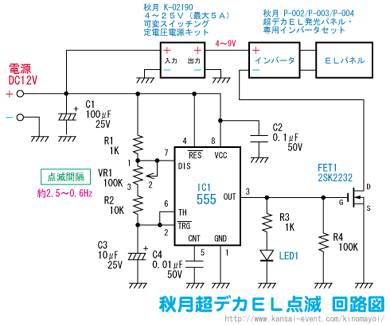
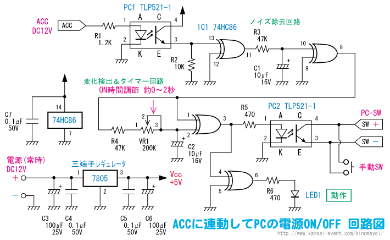
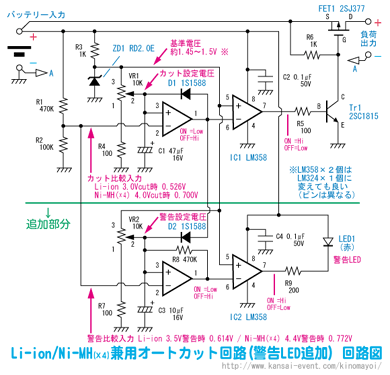
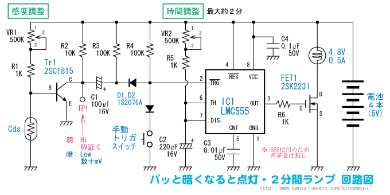
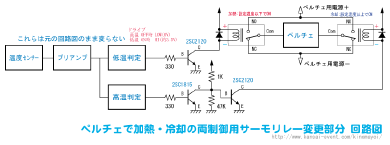
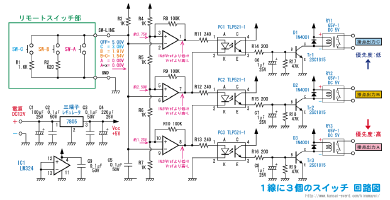
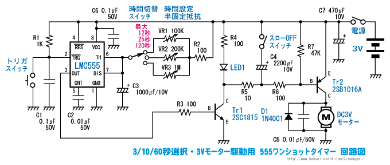
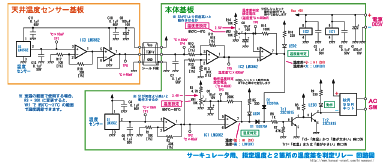
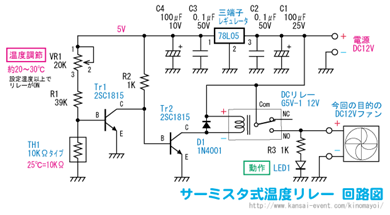
 �u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�
�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�