| ||||||||||
|
|
| ���� ������ �����̓����Ƃ��Ԏ� |
��H�E�f���L�E����
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
�� �L���y�[�W�Ɋւ��铊�e�͊e�L���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă��܂� ��
���� ���̃y�[�W��2009�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�� ������ ��������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
�@��ŏ����Ă���u�V�K���e�v�Ƃ͐V�����b��̓��e�̂��Ƃł��B
�@���̉ߋ����O�y�[�W�Ɉړ��E�f�ڂ��Ă���L���ɑ��āu�d����ς��ē��삳�������̂ł����c�v�uON��OFF�ɂ������̂ł����c�v���̂�����E��H�}�̒Ȃǂ̂��˗��͎t���Ă��܂���B
�@�����Ɍf�ڂ��Ă�����̂Ǝ������̂������ꍇ�͊F�l�����g�ł����R�ɉ�H�}�����ς��āA����]�̂��̂�����肭�������B
|
�@�ߋ����O�́u�W�������ʈꗗ�v���ł��܂����B �@�����ɂȂ�ɂ́d��������N���b�N�I |
�y�ꗗ�z
�������N���b�N�Œ��ڋL���Ɉړ��ł��܂�
|
��1.8V��FET�œd����ON/OFF�������H �� �����܂��ŐV�̃y�[�W(�X�V��)�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �������艺���N�x�ʂ̉ߋ����O�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B |
|
�� 2016�N ���t�F���V���O�̓d�C�R����̃I�v�V������H���~�����I ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g(���̂Q) ����ꂽ�d���H����肽�� ���m�Q�[�W�̗�Ԓʉ߃Z���T�[�͈ȑO�̑��̉�H�œ��삵�܂����H �����d�T�E���_(���d�u�U�[)�����d�r�Ŗ炵���� ���q���[�Y�̐������g�����������ĉ����� ���`���C����LED�ő��̋@���������(���̂R) ���u���[�J�[���ꂽ��x���炷��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2014�N ��3�b�u�U�[�̉�H�H ���X���b�g�J�[�p�̒ʉ߃Z���T�[�̐��� ���Ԃ̖h�ƃZ���T�[���������疳����200m���ꂽ���Œm�肽���I ��Cds�ɂ��� ��74HC123���v�ʂ�̎��Ԃœ����܂��� �����ۂɍH�삵����������Ȃ��ƂȂ��Ȃ��g�ɂ��܂��H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�㔼 �����z�����d�̑����d�ʌv���L�b�g����肽���I �����@�\�ȃ��[�g�`�F�b�J�[����肽���I ���g�p�p�r�s���̈˗� ���f�W�܂߃J�E���^�[�����]�Ԃł��܂������܂��� ���`�b�v�d���R���f���T��σZ���ő�p�H ��NJU9252A(P)���g����LD8035E�u���\���ǁ~2�ŕ\���������� ���Â��Ȃ�����A�d������삳�������I ���悻���܂̃L�b�g�̎g�������킩��܂��� ���悻���܂̃L�b�g��LD�ɕϒ����������� ���^�C�}�[IC 555�ŕς�������̌x��炵�����I �����b�g���[�^�[�t���e�[�u���^�b�v���S���I ���v���Z�b�g�I�ǂ̂ł��郉�W�I�����W�b�NIC�ō�肽�� ���^�C�}�[IC 555���Q���݁^�܂��͂�������q���ŏ������삳�����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2013�N�O�� ���艷���M���m��̃o�C���^���̓�����O������m��!?��H�H ���e���L�[�������ĂV�Z�O�\���@�ɐ�����\�����鑕�u����肽�� ���d���̎��� ���f�W�b�g�E�U�nju���\���@�L�b�g�ʼn��x�v����肽�� ���ԁE�X�e�b�s���O���[�^�[���̃X�s�[�h���[�^�[�^�^�R���[�^�[����肽�� ��LED�d���d���Ɋ����������_�����Ȃ��H ���ԁE�v�b�V���X�C�b�`�Ń��[�^���[�X�C�b�`�̂悤�ɐ�ւ���H ���t�F���V���O�̓d�C�R����B���C�����X�̂́H ���X�}�z�̃}�C�N�[�q�Ɍq����`�g�g�[��������H�B���̓X�C�b�`�Ŏ��g���ω��B ���O���u���V���X���[�^�[���� ���d�����u������Ă���̂ł��� ���o�l�Q�D�T����킪��肽�� �����Ԗڂň�莞�Ԓ�~����4017 ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃ����܂����܂���I ���ԁE�i�r�̃{�����[�������[�^���[�G���R�[�_��UP/DOWN�������H ��AVR/Arduino�ؑ֊� ���\�[���[���C�g���S����H�H�H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�㔼 ���ԁEACC����Ă����炭�h���C�u���R�[�_�[�����Ă����x���d�� ��FOMA�g�ѓd�b�̒��M�ŕ��ʂ̓d�b�̃x����炷�x���M������肽���H ��FOMA�g�ѓd�b(USB�[�q)�ʼn��u�n�̑��u�ƒʐM�������H ���ԁE������HID�w�b�h���C�g�o���X�g�̒x���p���[���߉� ���ԁE�o�C�N�̃E�C���J�[�p�Ɂu�����Ă������ԉ��������^�C�}�[�v���~�����H �������M���̗L���ŃA���v�̓d����ON/OFF������ ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_�����������c����쓮���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�܂��H ���ϒ�R��(VR)�͂ǂ���g���̂ł����H ���X�s�[�J�[����^���p�̏o�͒[�q���o�������H ��DVD�̉f���M����AV�P�[�u���łQ���z����ȒP�ȕ��@�H ��LM338T/LM350T/LM317T�A�d���ϓd�������������ł��I ���ԁE�I�[�f�B�I(����)�ɘA������LED�C���~��_�������� ���ԁE�t�H�g�C���^���v�^�Ń����[��ON/OFF�����H �����C�����X�`���C����LED�ő��̋@��������� ���ߋ����O�ɑ��Ă��ӌ��\���グ�� ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H���A�z�[���X�C�b�`�ő��삵�āA�z�[���X�C�b�`�������Ă���Ԃ͖葱�����������I ���ԁELM317��GPS������LM317���M���Ȃ��ēd����������g���Ȃ� ���t�F���V���O�̓d�C�R�������肽���I ���t�F���V���O�̌��̃`�F�b�N��H ���X�u�̊��d�r�����E�܂Ŏg�����肽���H ���d�C��̓d�C��H��m�肽�� ���A���v�Ɍq���ŃX�s�[�J�[����u�u�[�v�Ƃ��������o�����u����肽�� ���U�����m�ŁA���]�ԑ��s�������f�o�r������H ������d�@���V���b�g�L�[�E�o���A�E�_�C�I�[�h���g���ď���������@ ��PLC�Ńn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽���H �����ʂ̑傫�����փ`���C������肽�� ���ԁE�E�C���J�[��LED�������瓮�삵�܂��� �����ɒЂ��Ȃ��Ód�e�ʎ����ʌv���~�����I ���ԁEADDZEST��ZK-6020A-B�̔z���������ĉ����� ���ԁE�A�C�h�����O�X�g�b�v�Ńi�r���������H ���ӌ��E���e ���ԁE�A���v��ON/OFF���郊���[�����܂����������@�H ���ԁE�^�C�}�[IC 555 ����쓮����H ���u�ߋ����O�ւ̎����v�ɑ��Ă̌��J�� ���A�i���O�I�ɁA���邳�ɘA������LED ��1.5V�œ����^�C�}�[��H ���ԁE�R�X�e�[�g�M����(�h�A���b�N)���[�^�[���� �����[�U�[�n�o���@�̃p���X���ɔ��������M��H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉��i���̂Q�j |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2012�N�O�� ���p�b�ƈÂ��Ȃ����^���邭�Ȃ������A�����������閾�邳�ω��Z���T�[ ���ԁE�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v���ԂŎg������ ���ԁEAC100V�p�̓d�C����������������DC12V�Ŏg������ ���ԁE�邾���P�����炢���[�������v�ɘA������LED�������� ����p�ɂȂ�g�����W�X�^�������ĉ����� ���Z���T�[���C�g�̉��������܂��䂫�܂��� ���ԁE4584N��������܂������ɂȂ镨�������Ă������� ���G�A�R���̃����R�������x��ON/OFF�����H ���Ԃ̃o�b�e���[����}15V����肽�� ���ԁE�o�b�N�M�������m�������ɁA�����[���Q��ON������ ���ԁE50cc�o�C�N�̃z�[���̉����������̂ő��������� ��12V�̃j�J�h�o�b�e���[�̏[�d���12V���o�b�e���[�̏[�d��ɉ����o���܂����H ���ԂŃ��[�������v���G���W���I�t������_�����������H �������₷�����{��\���̉t���������Ă������� ���_�C�I�[�h�̑����FET���g�����ᑹ���̉�H��v���ĉ����� ���A�i���OIC�ŎO�����[�^�[���H ���l�R���������d����H�������ĉ����� ���t���f�B�X�v���C�̕��i���Ă��܂����A��낵�����肢���܂��B ����������Ă���悤�Ɍ�����X�g���{ ������͓����܂����H ���ԁEDC/DC�R���o�[�^���g����FM���W�I����m�C�Y���������܂� ��10cm���ꂽ��������ԐFLED�̌��������o���鑕�u�H ���֎~����Ă���A�u�ߋ����O�ւ̑Ή��v�����Ă��������I ��AC�A�_�v�^�[���������܂��� ���X�C�b�`�t���{�����[���̓X�C�b�`�ƃ{�����[���Ɍ����o���܂����H ��1.5V�œ������[�^���̃��[���b�g�̉�H�H ��2SA�g�����W�X�^��2SC(D)�g�����W�X�^�ł͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H ���ԁE�q�[�e�b�h���A�V�[�g�����[ ���ԁE40�A���y�A�������z�[������������悤�ɂ���q���g ���t���\�����x�v��LED�\�����x�v�ɉ��������� ��AC100V�p�uPT50D�v��DC7V�Ŏg������ ���}�E�X�̘A�ˉ�H(�܂��ߔ�) ���Ԃ̓d��������m�����H �����̃T�[���X�^�b�g��AC100V�Ŏg���܂����H ���H���d�q�̃g���C�A�b�N������ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���ԁE�o�C�N�̔R���x��������肽�� �����[�X�ɏ��ׂ̃��[�^�[�����H��v���ĉ����� ���r�f�I�f�b�L��UV�`���[�i�[�������Ɏ�ɓ��ꂽ�� �����������R���łq�b�T�[�{������H ��ELEKIT�̃L�b�g�̃T�|�[�g�����Ă��������I ��HT7750A�̏o�͓d���ύX ���d���v���R�v�ɂ���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@(���̂Q) ���͌^�d�Ԃ𗼒[�̂`�|�a�w�Ŏ����Ŏ~�߁A�ďo���������H ���������T���Ă��܂� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�㔼 ���ڂ��̂�������H�}�������Ă��������I ���X�g�b�v�E�H�b�`�̉��u����H �����~�b�^�[���A���[�^�[�����H ���ڂ��̂�������]�v ���ڂ��̂������\�[���[�d�� ���^�C�}�[IC 555���ُ퓮�삵�܂� ��Android�^�u���b�g100�����x�ɓd���������H�H ���l�I���T�C���̓_�ő��u������Ĕ̔����ĉ����� ���ԁE�X�g���[�g�}�t���[�ɐ�ւ����H ���X�C�b�`�����������Ĉ�莞�Ԃ������[�^�[���A�������甽�ɉ�H�H ���S���́u��]���ϊ���v���ƒ�Ŏg�p���� ���P�P�^�̃A���J�����d�r���������ĂP�O�O���͏o���܂����H ��Panasonic�̃^�C�}�[�̎g�����H ���ԁE�G���L�b�g�j�o�r�|�R�Q�Q�U(�^�C�}�[IC 555)��12V�Ŏg�p�������I ���ԁE���Ԑ����������[(�����Y��h�~) ��DC�t�@���̌Œ�(�Z��)�� ���ʐ^�B�e�p�̘I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H�I�o�v�͏��^�ŃV���v���ȍ\���ō��܂����H �����Ԃ̔��d���A�c�b����`�b�ɕϊ��H ��AC���[�^�[�̉_����� �����d��̍����������Ă������� ���e�X�^�[��250V�����W��50V-MAX�ɕς����� ���ԁE�i�r�̉����M�������m���āA�J�[�I�[�f�B�I�̃~���[�g�p2.5V�M��������H �����W�I�ŕ��˔\�𑪒肷�鑕�u�H ��Panasonic�d���R�[�h�p�b�N(EZ9090)�������ł��ȃC�J�H ���ԁE�C���r���C�U�[�̏o�͂f���ĂR�̏o�͂ɕ����� ��40�`45���œ��삷���H ���l�̏o������������m�����H ���ԁE�h�A�X�C�b�`�̓��� ���I���f�B���C�E�I�t�f�B���C��H �����]�Ԃ�LED�o���u���C�g�𑖍s���͕K�����悤�ɂ����� ���ԁE�o�C�N�̓d�� ��14��LED�����ɓ_���������H�AIC�P���Q�ŁI �����̂悤�ȃf�W�^�����v����肽���ł��I ��DC/DC�R���o�[�^��(���˔\������)����Ɏg���Ă����H ���ԁE�C�O�j�b�V�����R�C�����V�O�i���\�[�X�ɂ�����@ ���L�[�{�[�h�A���v�̌̏�ɂ��� ���ȈՌ^�E�t�@���^����AB�t�@���^���d���ϊ��� ���r�C�t�@����ON�ŘA�����鋋�C�t�@���A�ӂ���͎�^�] ���d�����ꂽ��ʂ̉�H(�d��)�ɓd���𗬂� ���h�Ж�����I����M�����H�H ���ԁE�펞ON�̃V�K�[�\�P�b�g���L�[�ƘA���������� ���T�[�W�z�����i�̑I��H ���ԁEDC12V�̃I�[�f�B�I���Ԃɍڂ���ی��H�H ���ԁEPWM�������ꂽ���[�������v�Ńl�I����A��������Ɓc ��AC100V ���d�����[ ���z����̎������x���ߊ� �����W�R���̒�R���ł��܂����A�������ƌ������Ă����ł����H ������V���A�������ʐM���W���[����38KHz�̐ԊO�������R���M����ʂ��ă����R�������� ���ԁE�L�[���X�Q��v�b�V����ON�ɂȂ�s�v�c�ȃ����R�� ���ȒP�Ȕ��M�@�̉�H�������Ă������� �������@�̉�H�������Ă������� ����R�v��d���v�E�d���v�ɂ���H ���p�\�R���ɂڂ��[�ނ����ՁI��LED������(���₷)�H ���Â��Ȃ�Ɠ_������k�d�c�炢�Ƃɂ��Ď���ł� ���������𗬂ɕς����H�H ���ԁE���g���ƃf���[�e�B�������ςł���PWM LED������H ���v���A�b�v�E�v���_�E���ɂ��Ă̎��� ���Ǖi��Ԃ�ǂݍ��ރn�[�l�X�`�F�b�J�[����肽�� ��LED����������T�m�@�����삵���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2011�N�O�� �����x���P���オ�鎞�Ԃ��v�鑕�u ���ό^3�[�q�@317���g�p�����@��d����H��m�肽�� ��LM3914/LM3915/LM3916�̓d���ݒ�A�v�Z���@ ���t�r�a�}�E�X�̐�����Čq���ł����ł����H �����₪�R�_ �����[�^�[�̃m�C�Y�Ō�쓮���܂� ���ԁELED����莞�Ԃŏ���(�����Y��h�~) ���S�̔��Ɏ��t�����G���Ɩ����鑕�u ���V�Z�O�k�d�c�̃R�����̓���� ��TTL�p���X�����鎞��"1"���o����H ���I�[�g�d���L���@�\�͊ȒP�ɍ쐬�ł���ł��傤���H ���ԁE�Z�L�����e�B�ɍD�݂̃^�C�}�[���q������ ���t��TV�������܂��� ���ϑ��I�ȉ�H�̃\�[���[�K�[�f�����C�g�̓��쌴�� ��12V/400W���̃o�C�N�p�A���v���g������ ���v���X�e�̃X�s�[�J�[�Ɏ����_��LED�H ����������������H ���ԁE�����@�\��EL�p�C���o�[�^ �������U�����{�b�g ���u�J�b�g������v�̒��g���Ⴂ�܂� ��100Pin��100Pin�̓��ʃ`�F�b�J�[�̂��肩�� ���o�b�e���[���P�O����Ŏg�� ���Q��AC100V���ւ��郊���[ ���ԁE�o�C�N�p��LED�^�R���[�^�[�����삵���� ���ԁE�E�C���J�[�����[�̐����������ĉ����� ����ʓI�ȃX�C�b�`���O�d�����d��������LED�����点�� ��12V����}1V���炢�㉺�ɒ�����ƃ����[ON��H ���t��AQUOS���Ԃ̃o�b�e���[�œ��������� ���K�C�K�[�J�E���^�[�̉�H�}�������ĉ����� ���H���d�q��LED�f�W�^���p�l�����[�^�ɂ��ăT�|�[�g���Ă��������I ���h�A���J���Ă��߂Ă��Q���ԃ����v ��AC�A�_�v�^�[�ɒ�R��ɓ���Ďg������ �����]�Ԃ̃_�C�i���Ōg�ѓd�b���[�d������ ���ԁE�d�������[�̌̏�\�� ���ԁE�d������x�_�������A���������Ă�����x�_�����������H ���R���f���T�̑�� �������N���Ă������ł����H ���Z���A��Softbank3G(FOMA)��p�ʐM�P�[�u���͂Ȃ��[�d�ł����̂ł��傤�H ���Ԃ̃o�b�e���[�オ��~����Ǝ��̃T�[�W�A�u�\�[�o�[�ɂ��� ����ɂȂ�ƂR�b�Ԋu��LED���_�ł��郉�C�g ��PM-129B�Œ����̓d�́E�d���v ���ԁEAutomotive LED timing light ���ԁE���[�h�X�C�b�`�̔��] ���ԁE�c�Ƃƒ�����H�̎���ł� �����d�r�����ɂ���Ǝ������Ԃ͂Q�{�ɂȂ�܂����H ���S���͌^�p�ɉ��̏o�鑕�u ��15�����x�Â���Ԃ����������Ƀg���K�[�����������H�̍l�@ �������ȍ~��Z���T�[�̎��� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�㔼 ��2V�ɂȂ�����A3V�ɂȂ�����LED���_�������H ���ԁE�R���v�̕\�������킹����� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�ɓ�����R�́H�^�����i�̐���H ���ԁE�u�^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H�v�͂P����]���Ă��g���܂����H ���N���A�[�{�C�X�Ƀm�C�Y�����܂� �����d�X�s�[�J�[���R�C���ő剹�ʂŖ�܂��� ���e�j�X�p�X�R�A�J�E���^�[ �����~���^�̓d����H ���Ⴆ�T�X�����d���ŃX�C�b�`�������H �����W�I�ɊO�����͂����� �����p�ݑ�\�������v ���J�~��x��u�U�[ ��GND�d�ʍ��̂��镨��P��GND�̌v����Ōv��H �����W�R���E�����|���v������~���u ��NaPiOn�Ń����[���������Ȃ� ���Â��Ȃ������莞�ԓ_�������H�����܂������܂��� ����莞�ԃZ���T�[�������H ���ԁE���g�C�[�W�[����H���̉� ���ԁE�O������ON�ł�����ƌ�������LED��H ���ԁE�^�R���[�^�[�E��]���p���X4/3�{����H ���ꉟ����5�`6�b�錺�փ`���C�� �����x�ʼn�]����������@ ���p�\�R���̃}�C�N�̃~���[�g��H�A�O�o�̕����g���܂����H ���ԊO�������R���̌��������ɓ͂������� ���ԁE�J�[�I�[�f�B�I��mp3�v���[���[���Ȃ����� ���ԁELED�\���̃��A���^�C�������x�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2010�N�O�� ���ԁE�o�b�e���[���X�̌��`������HID�����v��t���� ���E�ۓ��̃^�C�}�[�X�C�b�`��d�q��H�����ŁI(�L���) ���ԁE�Q���ԃ����v��Hi���͂���Lo���͂ɕς�����@�H ��LED�A�ǂ���̕��������ǂ��������o����̂ł��傤�� ���^�R���[�^�[�E��]���p���X�̂Q���{��H ��100�~�A���[���N���b�N�A���A�Q���[�h�E�^�C�}�[�����[ ���ԁE�d�g���v�ɓ��������V�O�i���c���[ ���Ԃ̃R���s���[�^�[����̂T�u�̐M���Ń����[�����܂����H ������M��OFF����x�����Đ��SSR ��AC100V�^�C�}�[��DC12V�^�C�}�[�ɁI ���o�b�e���[�[�d�E���d��Ԃk�d�c�\���� ���T�[�{�M����LED�Ȃǂ�ON/OFF���鑕�u ��LED�Ń^�R���[�^�[(�D�O�@�E�@�B�p) ���^���@��p�ȈՌ^����d�d���ɂ��Ď��� �������@�ʼn��u�����R���A�g�[�����M�@/�g�[�����o���u ��DC12V��AC12V�A�[�������g�C���o�[�^ ���d��ON���琔�b�Ԃ����_�������H(����`�Ɠ_��/����) ���ߔM�h�~�k�d�c���x�v ���k�d�c�R���c�ʌv ���u�������v���Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��X�C�b�` ���X�p�[�N�L���[�̔j���́H ���ԁE�f���x�������� �������̎��� ���\�[���[�d�r�ƒP�O�d�r�̗����Ŏg����d��̍\�� ���R���f���T�ɒ��߂��d�����v�� ���ő�100LED�E�����t���b�V���[��H ���}�C�N�A���v�Ƀn�C�p�X�t�B���^�[�@�\ �����邢�ꏊ�ł����삷��Ռ��Z���T�[ ���H�����f�J�d�k�����p�l���̓_�ʼn�H ���Ԃ�ACC�ɘA�����ăp�\�R���̓d����ON/OFF ��Li-ion�ߕ��d�h�~��H�Ɍx��LED��lj����� ���d���فE�����[����ON���Ԃ𑪂�H ��������J�����̉f����d�g�Ŕ������ ���p�b�ƈÂ��Ȃ������̂ݓ_�����郉���v(�Q���ԃ����v�����H) ���y���`�F�f�q�ň��̉��x�ɕۂ�H ���K�[�f���\�[���[���C�g�łV�F�ɕς��LED���_�����Ȃ� ���s���N�m�C�Y������H ���P�{�̔z���ɂR�̃X�C�b�` ��4013�̔��]FF�ŁA�X�C�b�`�������Ă���ԏo�͂�ON�ɂȂ�H ���Ԃ̃}�b�v�����v�����[�������v�ɘA�������������c�H ���Ԃ̃E�C���J�[�����[���������ɂ���H ��3�A10�A60�b�ԁA�U�����[�^�[����H �����̉��x�ƁA���x�������m����Ɠ��삷�郊���[ ���Q���ԃ����v��DC/DC�R���o�[�^������H ���K�i�̌u�����������v�b�V���ň�莞�Ԃ����_���������� ��20�`30���œ��삷���H ���S���͌^�ŁAVVVF���̉����o��p���[�p�b�N�̐�����@ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�㔼 �����]�ԗp�E�C���J�[ ���d�q�H��}�K�W��No.5�̎��]�ԓ_�Ń����v�������܂��� �����p�W���p�́A�l�����������������LED ���g�O���X�C�b�`�ŏ����ƍ~�����ւ����H�H ���ԁE�����v�b�V���ŁA�z�[�����v�b�v�b�ƂQ��炷��H ��LED�_�ł������Ȃ�^�C�}�[ ���ԁE�h�A�E�G���W���ɘA�����ă��[�������vON/OFF��H ��Panasonic�̉��x���ߊ��SSR�����܂����삵�܂��� ���o�b�e���[��T�ES���S�̒[�q ���d����������IC�H�H�H ��DC12V�ʂ���6V�ɒቺ����Ɠd�����Ւf����ȒP�ȉ�H ��12V�̉�H��5V�̃����[�����̂͂��������H ���x���A���R���Z���g����肽�� ��100�ς̃Z���T�[�����v�ňÂ��Ȃ����猺�֓���_���������� ��USB�J�����̃r�f�I�M���o�͉� ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�}�Q(�����[) ��ON���Ԃ�OFF���Ԃ̈Ⴄ�C���^�[�o���^�C�} ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H��cds�Z��������Ƀ����[ON����l�ɉ�H��t�������Ă������� ���ԁE�v�b�V�����E�C���J�[�X�C�b�` �����̉�H��ς��Ďg������ ���ԍڂ̂U�f���Z���N�^�[����肽�� ��5V��0.5�b�`1�bLED�_�����A�ȑf���� ���d���̎��₪�Q���ق� ��100V�p�Z���T�[���C�g�ƐԐF���]�ԓ_�Ń��C�g �����x��AC100V��ON/OFF����u�d�q�T�[���X�^�b�g�v ���Ԃ�SIN�g����`�g�p���X�ɁH ���ȈՃf�W�^���\������d�͌v ���ԁE����`���Ə����郋�[�������v�ɘA��(�Ή�)����C���~PWM������H ���ԁE12V�Ԃ�12V-8V��5�i�K�d�����m�点��H ��3V�`2V�܂ł͗ΐFLED���_���A2V�ȉ��ɂȂ�����ΐF�����A�ԐF�_�������H ���u�ʏ�̓X�C�b�`�ړ_�����Ă��ďo��OFF�ŁA�J����ON�ɂȂ��H�v�Ƃ́H �������e�̓I����肽�� ���d�삪�����Ő���H�������ĉ����� ���t���b�V���[��������肽���H �����|/Li-ion�p�A2�`4�Z���A70A�Ή��ߕ��d�h�~��H ���{�����[���A�b�v�I��P�O�d�l�� ���Ȃ�VU���[�^����肽���Ȃ�܂��� ���ԁE�}�C�i�X�R���g���[���̃v���X�R���g���[���ϊ������[ |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2009�N�O�� ���Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� ��CCD�J�����ɓd�����d���H�́H ���W���C���ŃT�[�{������� ��LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H ���l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u ���ԍڗp�c�u�c�̉����������I ���u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j ���P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H ���ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r ��TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ ����莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H ��DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� ���ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� ���}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����H ��24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H ���d�C��H�̖�� �����͑����̐��� ��24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� ��12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H ���Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� ���ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ �����d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� ��USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� �����������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� ���X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g ���Ԃ̓d����15V�ɏ����������H �����W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H �������R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H ��5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H ���ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� ��FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH ���ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H ���ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ ���u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H ���d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H ���~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� �������g������̂����� ���g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H �����A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v ��LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) ��555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ ��PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� ���H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H ���t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g ���u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I ��Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�㔼 ���ԁE�o�C�N�̑O�Ɠ����G���W��ON�������_�������H ��F-1���X�^�[�g�V�O�i���̐��� ���ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐��� ���r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g ��CENTURY���u�A�|�����T�v�̉�H�ׂĂ݂܂��� ��USB�n�u�̎��� ����d���Ɍ��郉�C�g �����f�B�A�v���C���[�̎��� �����]�ԂɐF�X�t������ ��555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�� ���u�����̃v���X�C�b�`�̑��ݕ��@ ���P���ȃX�C�b�`�ł͖����J�[�e�V�X�C�b�`���烉���v�̔z�� ���Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H ���V�K�[���C�^�[�p�R���o�[�^�Ńo�b�e���[���オ��H ��10�`15V�ɕϓ�����o�b�e���[����12V ��12��24V �ő�7A�̏����R���o�[�^�͍��܂����H �������v(�����v)�ŎԂ̃g���b�v���[�^�[������H ���d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H ���A�˃p�b�h�ƃ}�E�X���q���H ��AC100V�A5A�`10A���O���Ō��o���ă����[ON/OFF �����胉�P�b�g��Ŏg���̂ăJ�����̃L�Z�m���ǂ�A������ ���}�E�X�̘A�˃N���b�N�ɑ�p��H ���Ԃ� �o�b�e���[(11.5v �` 12.7v)���� 13.7V�ʂ� �����������ł��B ����@�̉�H�} �����Œ��R ��5V/1A�̉ߕ��d�ی�t���X�C�b�`���O���M�����[�^ ���ԁE�G���W���N���㐔�b����P�O�b���x�͂��鑕�u���~�������H �����d�@���v���ɉĂ�LED�����点��ɂ́H �����艻�d���̓d����ύX������ �����X���[�X�s�[�J�[�p�ɐ�@�̃��[�^�[�̉�]������ ��3V��12V�̃t�@����������H�͍��܂����H ���o�b�p�P�Q�u�t�@�����R�u�ʼn��� ���d�q�A�d�C��H�̐}�ʋL���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����܂����H |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2008�N�O�� ���\�[���[�뉀���E����Ƀ\�[���p�l�����݂͉\�ł����H �����C�g�pON/OFF�X�C�b�`��H �����ʌ�����̂��肩���H ���|�b�v�m�C�Y�̏o�Ȃ��g�ѓd�b�~���[�g�}�C�N ���ߋ��L����DC�R���o�[�^��4.8��3.4V�̕ϊ��͂ł���H ���G�[�����u����`���Ɠ_�����j�b�g�v�ɂ��Ď��� ���Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点���� ���p�\�R���̃L�[�̃{�^���͉����ł���H �����������|���v �������t�@���q�[�^�[�̃Z���T�[�̏� ��Li-ion�[�d�r�̉ߕ��d�h�~��H ���X�C�b�`����/�����Ȃ��������C�g�̓_�ʼn������L������]�I ���ԏ゠�炵�h�~�A�h��LED�t���b�V��(���q���������m) �����낢�� ���k�d�c��铔�����]�Ԃɕt������ ���ԁE�J�[�i�r�̉����ē��̍ۂ�LED��_���A�Б�����SP���ʂ������� ��USB�̋K�i��5V/500mA�Ȃ̂�850mA�����o�����Ƃ͖����ł́H ��RS232C�̂t�r�a�ڑ� ���w�����b�g�_�Ń��C�g ���J�[�i�r�̃X�s�[�J�[���� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�㔼 �����d�X�s�[�J�[�ʼn��� ���C�J�����O �����]�Ԃ��~�߂Ă����炭���郉�C�g�H ���Z���T�i�C�g���C�g�̉��� ���J���ǂ����u �����d��̐���Łu�ϓd���d���v���~���� ���d���E�����P�b�g�ׂĂ������� ��PIC��CF�J�[�h�Ȃǂ��g���ăp�\�R���Ƀf�[�^��]���o���܂����H ��100�~�L�b�`���^�C�}�[�Ń����[��������(���������[) ���~�j�b�c�̂O�P��Ղ�s8430AFD13�H�H�H ���I���{�[�h�J�����p��4.8V��9V�̃R���o�[�^ ���l�`�w�U�S�P�ɂ��� ��DC-DC�R���o�[�^���g���|�����߂� ���k�l�R�P�V�s�̒�d���E��d��(�ϓd���ϓd��)��H�}�ɂ��� ���k�d�c���������_�ł��������B �����y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H �����z�d�r�p�ɗǂ��ȓd�̓��[�^�͂���܂����H ��NJM2360M�̊O�t���g�����W�X�^��FET�ɁH ���ԁE���[�������v���L�[�I�t���ɐ��\�b�ԓ_���������� |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
|
�� 2007�N�O�� �����z�d�r��Ni-MH�[�d�r���[�d�H ���f�W�^���I�V�� STN? TFT? ���\�[���[�p�l�����o�b�e���[�p �m�[�g�o�b�����d����ւ���H ���{�����[�������܂��t�����Ȃ� ����d��DC�R���o�[�^���k�d�c�p�ɒ�d��DC�R���o�[�^�ɂ����� ��100�~�V���b�v�̎��]�ԐԐF�_�œ���12V�Ŏg�p������ ���[�d�r���Ƃ����ɂ��Ȃ��Ȃ�u�����̉��� ���k�d�c�i�c�����̉��� ���A�b�v�R���o�[�^�� 12V 250mA �͍��܂����H ���H���̏[�d���]�����Ă������� ���e�X�^�[�œd�������܂�����܂��� ���g�я[�d���DC�R���A�v���ς�����̂�����Ƃ���H��������H ������Ƃł��܂����B���邢�k�d�c�_�C�i�����C�g���I�I ���L�������h�D�̂k�d�c���C�g�A��R�������Ă���̂Ɠ����Ė����̂ƁH ��MAX879�ɏ[�d���E�[�d�I����LED�����t������ ��100�~�̃Z���T�[�i�C�g���C�g���k�d�c�����Ă݂܂��� ���[�d��̉�H�ɂ��āu�Ȃ�ł���ȉ�H�ɂ���˂�v |
| �����Ղ��u�W�������ʈꗗ�v�ŒT���b�u�L�[���[�h�v�Ō������� |
���� ���̃y�[�W��2009�N�O���̃��O�ł� ����
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
������̌Â��L���ɂ͓��e�E���X�ł��܂���B
( �V�K���e��[������]�Ŏt���Ă��܂� )
| �Ԃ̂ق����H�ُ̈퓮�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB �@����܂�LED���Ƀn�}���Ă��܂��l�b�g�Œ��ׂĂ����Ƃ�����R�ɂ����ǂ蒅���܂����B �@100�ςł��낢��Ƃł�����Ă��ƂɊ������܂����B �@���āA���₳���Ă��������̂̓z�^���̂悤�Ɍ���X���[�������v�����܂������A�G���W����������Ɛ���ɓ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ĂƂ���ł��B �@�܂��́A����ł��B http://tinyurl.com/m8vd7b �@���ێ��t���ăG���W���I�t�̏�Ԃ� http://tinyurl.com/ox5a2j �@���ɃG���W����������� http://tinyurl.com/nfa8v5 �@�_�ł��ُ�ɑ����Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��B �@�l�b�g�Œ��ׂ��Ƃ��듯���悤�Ȃ��Ƃ�����Ă�l������ http://tinyurl.com/rd9b62 �@�����悤�ɃZ���R���A�P�~�R�����͂���ł݂܂��������ʂȂ��ł����B �@�������A220��F�����S���炢�͂��Ƃ����_�ł��x���Ȃ�܂����B �@�܂��A����Ƃ͕ʂɃ����[�̂悤�ȈӖ��Ńg�����W�X�^��g�ݍ���H����ꂽ�Ƃ��� http://tinyurl.com/mxs7cn �@�_�ł̓G���W���I�t�Ɠ������炢�ɂȂ�܂������A����������Ă��܂��܂��B http://tinyurl.com/mvfh34 �@���Ȃ݂ɉƂŒ�d���̂P�T�u�A�_�v�^�[�i�����P�`�����ĂP�S�D�S�u���炢�ɂ��Ă܂��j�œ���m�F�����Ă����̂ŁA�G���W�����������Ƃ��̓d���Ɠ������炢�ɂ͂Ȃ��Ă���̂ɂȂ����_�ł������Ȃ��Ă��܂��̂͂Ȃ��ł��傤�D�D�D �@���Ƃ��Ƃ���[�ƂȂ̂Ŏ�l�܂�ȏ�Ԃł��B �@���͂�����ł���ƂĂ����肪�����̂ł����D�D�D �@���Z�����Ƃ��닰�����܂�����낵�����肢�������܂��B �v�Q�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@������œ�����H������ĎԂ̃V�K�[���C�^�[�\�P�b�g����d��������ē������Ă݂܂������A���삪�����Ȃ邱�Ƃ͂���܂���ł����B�S������ɓ��삵�܂��B �@�܂��d���d�����F�X�ƕϓ������Ă݂܂������A�����Ȃ�͂��܂���ł����B �@�Ԏ�ɂ��d���m�C�Y�������̂ł��傤���A�܂��g�����W�X�^�Q�̖�����}���`�o�C�u���[�^�͓d���̃m�C�Y�ő����Ȃ��H�ł͂���܂���̂ŁA���̕���(�g�ݗ��Ă�n���_�Â��̋Z�ʁA���i���������������Ȃ��Ă��铙)�ɖ�肪����̂�������܂���B �@�Ȃɂ��낱����łُ͈�͋N����܂���ł����̂Ō����̓���͂ł��܂���B �@�P���Ɂu�m�C�Y���낤�v���x�ł̉��P�������܂��Ƃ����������������B �@���ɂ�����̑��k��ł��b�ɏo�Ă��܂����A�O�[�q���M�����[�^�œd�������艻�����Ă��������B �@�������A���ɂ��Ώ����@������ޕ����т܂������A�O�[�q���M�����[�^���g�p������@��������Č������ǂ��Ǝv���܂��B �@���A�O�[�q���M�����[�^�̓d����H�͂��̉�H�S�̂̓d���ɑ��ē����̂ł͂Ȃ��A���U��H�ɑ��Ă̂ݓ���ĉ������B�łȂ���LED�d���܂ʼn����Ă��܂��܂�����B 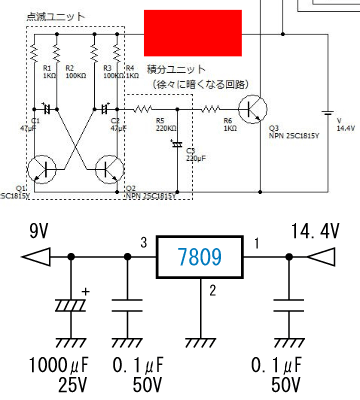 �@���A�V�k�S�Ȃ��炲�����\���グ�܂��B �@���ݍH�삳��đg�ݍ��܂�Ă��܂��ق����H����@�ł��B �@�w���H�^���ԗ��̕ۈ���E��42���^���̑��̓��Γ��̐����x�v�Ɂu�A��R�Q�������S�P���܂ł̓��Α��u���������A�_�ł��铔�������͌��x���������铔������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肳��Ă��āA�W���I�ȎԂ̑����̓��Η�(������@)�ȊO�Ɂu���x���������铔���v���Ƃ���邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�܂�|�W�V���������ɂƂ�����Ă���u�ق���LED�v�͂��̈�@���ɂ�����܂��B�Ԍ����ʂ�Ȃ��Ȃ�܂���B(�ԊO�Ɍ����ĕt�����ɁA�ԓ��̃C���~�l�[�V�������x�ɂ����Ηǂ��̂ł���) �@LED�����ꂽ��A�Ԃ̃p�[�c�ɑg�ݍ��ލ�ƂȂǂ��������̗͍�̂悤�ł����A��@�ɂȂ�܂��̂ō��������O�����Ƃ������߂��܂��B �@�ق����H���g�킸�ɁA�|�W�V�������ƘA�����Č��邽���̔��FLED�ł���A��قLjُ�ȕ��Ŗ�������̓|�W�V�������̔��e�Ƃ݂Ȃ����ł��傤����A�f�B�[���[�̕��Ƒ��k�����Ȃǂ��č��@�͈͓̔��Ŏg�p���Ă��������B �@���A�U���͈�@�����o�ŋ������Ԃł��B ���Ԏ� 2009/6/19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���J�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B �@��������3�[�q���M�����[�^�����܂�����E�}�������܂����B �@�����Ԃ�����₵�Ă������̂��������肵�܂����B �@��ϊ��ӂł��B �@���Ȃ݂ɁA���i�̓X�C�b�`�ŃI�t���Ă����܂��ˁB�ᔽ�ł����炗 (������]) �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���Ȃ݂ɁA�X�C�b�`OFF�ł�����������H���q�����Ă���ƈᔽ�ł��B �@�X�C�b�`OFF�ł��u�������������݂̓��v�Ƃ݂Ȃ���܂���B �@�������Ԍ����ɃX�C�b�`OFF�ł��A�u��H�A����LED��lj����Ă���ȁA���̔z���͂ǂ��ɂȂ����Ă���̂��낤�H�v�ƒ��ׂ��܂�����A�X�C�b�`OFF�ł��u���̉�H�͉��ł����H�A����ȕ����t���Ă�����Ԍ��ł��܂����B�O���Đ���ȏ�Ԃɂ��Ă�������������Ԍ��ɏo���Ă��������B�Ƃ������ɂȂ��āA�ƂĂ���Ԃ�������܂��B �@��@�����͂�߂܂��傤�B ���Ԏ� 2009/6/21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD�J�����ɓd�����d���H�́H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@CCD�J�����ɓd�����d���H�́H k.matumi �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�r�f�I�P�[�u��(�����P�[�u��)�ɓd���d��ꍇ�̉�H�\���͎��̒ʂ�ł��B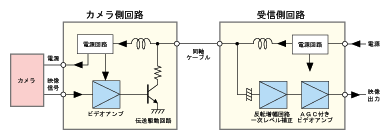 �@��}�����ɂ������Őv����鎖�������߂��܂��B �@�Q�l���Ƃ��ẮANTSC�r�f�I�M���͌����ɓd���Ȃǂ����߂��Ă��āA���͈̔͂��O���Ɖf���M���Ƃ��Đ������@�ʼnf�����ł��܂���B �@���ׂ̈ɓd���d�����őS�����̉f���M���Ƃ͈Ⴄ�d���Ȃǂɕς��Ă��܂������̂��A������NTSC�M���ɖ߂���ƁE��H�̕��������Ȃ�ʓ|�ȕ��ɂȂ�܂��B �@���܂������Q�C������(AGC)�@�\�t���̃r�f�I�A���vIC������ł���Ή�H�͊ȒP�ɂȂ�Ǝv���܂����A����ł��Ȃ��ꍇ�͕��G�ȉ�H�ɂȂ�Ǝv���܂��B �@���炩�̐M�����ɓd�����d��Z�p�̓R�C�����œd����DC�����͓d����H�ɒʂ��āA�M���͍������g���ɕϊ����ăR���f���T�ŕ�������Ȃǂ���ʓI�ł����ANTSC�r�f�I�M���͂��̂܂ܒ�C���s�[�_���X�p�̃h���C�u��H��v���ē����P�[�u���̓d���d����ϒ����Ă��Ό��\�y�ɒʂ������ł��܂��B �@�����M�������킹�Ēʂ����Ƃ���Ɣ����g�������FM�ϒ�����Ȃljf���M���Ɗ����Ȃ����@�����Ȃ��Ƃ����܂��A����͓��Ɂu�������v�Ƃ�������]�ł͖��������ł������H�͊ȗ����ł��܂��ˁB  �@�́A�f���@��W�̉�ЂŎd�������Ă������ɂ͂��������`�����u�����܂������A�ŋ߂͉f���M���͈���Ȃ��d���Ȃ̂ŕ��i�̎莝�������i�������������Ƃ����������������B
�@�́A�f���@��W�̉�ЂŎd�������Ă������ɂ͂��������`�����u�����܂������A�ŋ߂͉f���M���͈���Ȃ��d���Ȃ̂ŕ��i�̎莝�������i�������������Ƃ����������������B�@��قǕ��i�������Ȃ����āA�掿�͂��������ŗǂ��̂ł�����2000�`3000�~���炢�ō���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���掿�A�������`������]�����̂ł������͂薜�~�P�ʂ̉�H�ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�u����Ȃ��H�������͊����i���ق��������̂ł́H�v�ƁA�v�������鐻�i�̒l�i���m�F���܂����B �@�E�̎ʐ^�́uCCD�J�����p�d���E�M���`������M�A�_�v�^�[�v���i�ŁA������1980�~�ł��B(�V���R���n�E�X����1F) �@�g�p����P�[�u���͓����P�[�u���ł͂Ȃ��s�̂̂k�`�m�P�[�u���ŁA���i���Ă��Ȃ��̂Œ��g�����Ă͌��Ă��܂��k�`�m�P�[�u���̕����̐��ɂ��ꂼ��d����M��������U���āA�d��͂��Ă��Ȃ��Ǝv���܂������̂Ԃ�d�q��H�͓����Ă���́H�Ǝv�����炢�̏��^�ň����Ȑ��i�ƂȂ��Ă��܂��B �@���ۂɓX�ł�100���[�g���̂k�`�m�P�[�u���Ƀr�f�I�M����ʂ��Ď������Ă݂āA�Y��ɓ`���ł����̂͊m�F���Ă��邻���ł��B(�X�����k) �@�P��CCD�J�����������ɒu���āA��{�̃P�[�u���œd�������肽���I�Ƃ�������]�ł���A�������������Ȑ��i��ꂽ�ق������G�ȓd���d��^�̃r�f�I�M���`����H��g�ݗ��Ă���͊y�ł��������ď��^�ōς݂܂���B ���Ԏ� 2009/6/12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 7/4 |
�@���Ԏ��x���Ȃ莸�炢�����܂����B
�@����̓A�h�o�C�X�����������A�����i���w�����Ďg�p���Ă݂悤�Ƃ������Ă���܂��B
�@���J�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����B
k.matumi �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �W���C���ŃT�[�{��������H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�u���W�R���T�[�{"�ᑬ�ω�"�R���g���[���v���Q�l�ɂ����Ă�����Ă��܂��B �@PIC12FC675��7�s���Ɍq���ł��鑬�x�����p�̃A�i���O���͂ɁA�W���C����H�̏o�́iVcc/2�}1.5V�j���q���ŃW���C���W���C�����䂳�ꂽ�T�[�{�ɂ������̂ł����A�A�h�o�C�X������A���������������B �@��{�I�ɂ́A�W���C���o�͂̓d���Ńp���X�����������悤�ɂ���Ή\���ƍl���Ă��܂��B�W���C���o�͂ɂ͒����pVR�Ŕ�����H����������ł��B �@���W�R���T�[�{�̑��x�����łȂ��A�p�x�i�p���X���j�����ɕύX�������̂ł��B���łɁA�u���W�R���T�[�{"�ᑬ�ω�"�R���g���[���v�̉�H��g��Ń\�[�X�����낢����ǂ��Ă��܂��B�������A��{�I�ȉ�H����͂��Ă��܂����A�W���C���iENC03RC)�ł̊p�x������܂������܂���B takuo �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�W���C�����䂳�ꂽ�T�[�{�v�̈Ӗ����킩��܂���B �@���ʁA�W���C���ƃT�[�{���q���p�r�̏ꍇ�ɂ́A�u�W���C�����o�p�ɉ����ăT�[�{����(������)�v�Ƃ������u���l���܂����A����ł͂Ȃ��Ƃ������ł����H �@�u�ʂ̃T�[�{����M�������ɂ���A����ɑ��ăW���C�����o�p�ŏ�Z�������v�Ƃ�������]�ł����H(���Ɏg���̂��z���ł��܂���c) �@��̓I�ɉ����ǂ����ꂽ���̂����������������B�B ���Ԏ� 2009/6/6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@������ɂ����Đ\����܂���B�p�r�́A�Q�����s�̃T�[�{�Ɍ��݂�GWS����GP-03���ڂ��Ă��܂����A���x�����ŕϓ�������̂œ����̂悢�W���C���Z���T�[�Ŏ���݂悤�ƍl���Ă��܂��B �@GWS����GP-03�̎d�l�́A�T�[�{�M������͂��ăW���C����H�Ńp���X��(1.5msec�}0.6msec�͈͓̔�)�������T�[�{�M�����o�͂���B�u�ʂ̃T�[�{����M�������ɂ���A����ɑ��ăW���C�����o�p�����Z�������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B takuo �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�s�̂̃W���C���Z���T�[�͂��܂�悭�m��Ȃ��̂�GWS��GP-03�Ō������Ă݂܂�����A�K���_������R�o�Ă��܂��ˁB �@�u�Ȃ�قǁA�K���_���͊m���ɓ��s���{�b�g�����ȁE�E�E�BGP-03:�f���h���r�E���͂��̋��啺����w���킹��Ƃ�����Ƃ₻���Ƃ̓��s�V�X�e���ł͕����Ȃ���Ȃ����H�A�����������̕����͉F����ԗp�ŏd�͂̂���n��ł͎g��Ȃ�����ʂɂ����̂��H�v�Ƃ����S���Ă��܂������A����������GWS�А���RC�p�W���C���R���g���[���[�ł�PG-03�̊ԈႢ�ł͂Ȃ��ł����H �@[��M�@]��[PG-03]��[�T�[�{]�A�Ɛڑ������ł���ˁH �@����Ɠ�������PIC�ō��ꍇ�A�u���W�R���T�[�{"�ᑬ�ω�"�R���g���[���v�̂������ω��p�v���O�����͂�������O���Ă��܂��āA����� DO_COUNT = LOOP_COUNT + (ANALOG_0H - 127)
�Ƃ����v�Z���ɂ��邾���ŗǂ��̂ł����B �@LOOP_COUNT�͓��͂��ꂽ�p���X���B����ɑ���1/2Vcc�Œ��_�ƂȂ�A�i���O�d���Łu���Z�v����Ȃ�A���_��A/D�f�[�^127�𒆓_���l(=0)�Ƃ��ăv���X/�}�C�i�X�́u�U��v�ɕ�������l�����Z���邾���ł���ˁH �@�W���C���Z���T�[��1/2Vcc�}1.5V�̏o�͂ł���Ύ�蓾��d���͈͂����S��2.5V�ʼnϕ���1�`4V�AA/D���l�͖�51�`204(���S��127.5)�ŁA127�𒆓_�Ƃ�����|76�`�{77�͈̔͂Łu���Z�v����邱�ƂɂȂ�܂��B (�ꉞ�A�����܂ł��������Ǝv���܂����A0�`255�͈̔͂��z���Ȃ��������f�����͕K�v�ł���) �@�W���C���̌X���ɂ���l���[�����ςɂ���ꍇ�́A�W���C����PIC��A/D���͂̊ԂɒP����(���y�{�����[���̂悤��)�ϒ�R�����Ă͂����܂���B �@�P�ɉϒ�R�œd���������邾�����ƁA�P����A/D�ϊ������d���l���������Đ��l���S�̓I��0�ɋ߂Â������ŁA���_��127�ł͖����Ȃ��Ă��܂��܂�����W���C������ɌX������ԂɂȂ��Ă��܂��A���{�b�g���ƕ��t���o�������ē|��Ă��܂��ł��傤�B �@�������ς���ɂ̓I�y�A���v���g����1/2Vcc�𒆐S�ɑ��������ςł���悤�ȓ���ȓd�q��H��v���邩�APIC�̒��Ő��l�v�Z�ōς܂��邩�A�ł���Ό�҂̂ق����n�[�h�E�F�A�̒lj������Ȃ�(���Œ��R�����)���{�b�g�ɓ��ڂ������ɂ��ꏊ�����Ȃ��Ă����ł��ˁB �@�v���O�����ōς܂��ꍇ�̔䗦�̌v�Z���@�Ȃǂ͂������ōl���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/6/7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���J�ɁA�������������Ӓv���܂��BPG-03���Ԉ���Ă��Đ\����܂���B �@���݁A���낢��ƌ������ĊȒP�ȃe�X�g�����Ă��܂����A�Ȃ�Əo�������ł��B��l�̐[�����ςɂ���ꍇ�܂ŁA�������Ē����L�������܂��B�ς̌���PIC�Ń\�t�g�I�ɉ��Z�����������ł��B���͔g�`�����ł���A���͔g�`����ꂸ��PIC�Ŕ��������邾���ł��o�������Ȃ̂ŁA���̕����������������ł��B �@�������������Ӓv���܂��B���ꂩ����撣���Ă��������B takuo �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���{�b�g�͉����̐���P�Ƃ��Ă��l�X�ȋZ�p�̍��̋Z�ŏo���Ă��܂�����A�F�X�ȕ���g�ݍ��킹�邱�Ƃ��H�v����Ƃ�莩���炵�����{�b�g���o���Ėʔ����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/6/10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED���X�g���{�݂����Ƀs�J�b�s�J�b�Ɠ_�ł������H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�����b�ɂȂ�܂��B �@�ȑO�o�b�e���[�̓d���������������ɂk�d�c���_�ł����H�ő�ς����b�ɂȂ�܂����B �@���̉�H�œ_�ł̊Ԋu�̒������o����̂ł����A�X�g���{�݂����Ƀs�J�b�@�s�J�b�Ɠ_�ł����鎖���o����ł��傤���X�������肢�v���܂��B su �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H�v�ł̓^�C�}�[IC 555(LMC555)�Ŕ��U��H�������LED�̓g�����W�X�^2SC2120�Ńh���C�u���Ă��܂�����A555�̏o�͂������H�Ŕ�������Εω������������Z���ԃg�����W�X�^�삳���邱�Ƃ��ł��܂��B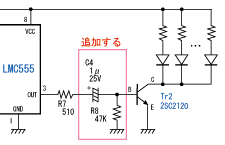 �@�E�}�̂悤��C4 1��F��R8 47K��lj����Ă��������B
�@�E�}�̂悤��C4 1��F��R8 47K��lj����Ă��������B�@���ꂾ����555�̏o�͂�H�ɂȂ����u�Ԃ����s�J�b�ƌ���܂��B �@���ۂɂ͂ƂĂ��Z�����Ԉ�u���邭����A�ق�̏����c�����c���Ȃ�������܂��B�c���͔��ɒZ�����ԂȂ̂Ől�Ԃ̖ڂł͂قƂ�nj����܂���B ���Ԏ� 2009/5/28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/28 |
�@�Z�������A���Ԏ��L�������܂��B �@�������삵�Ă݂܂��B su �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �l�����Ȃ��Ȃ����玩���I�ɐ��s�u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�����b�ɂȂ�܂��B �@sony�̃u���r�A���l���Z���T�[���g����ʂ������@�\��t���Ă��܂����B �@�䂪�Ƃ͂܂��n�f�W�Ή������Ă���܂�����Ƃ����̋@�\�����삵�����ƍl���Ă���܂��B �@��H�}�A�w�����i�ȂNj����Ă��������Ȃ��ł��傤���H �ړ_���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@SONY�̃u���r�A�͎����Ă��Ȃ��̂ł悭�킩��܂��A���̋@�\�͏�������͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H (�ꉞ�ATV�̃R�}�[�V�����ł��̋@�\�𓋍ڂ����Ƃ�����`�͌��Ă��܂�) (A) �l���߂��Ă�����A���̃`�����l���E���ʂŏ���ɂs�u�����B (B) ��U�����Őꂽ��A���͐l�Ԃ������R�������ON�ɂ��Ȃ��Ǝ�����ON�ɂ͖߂�Ȃ��B �@�����āA�ړ_�����l�̎g���Ă���s�u�ɂ͉����O�������[�g�p�[�q�͂���܂����H �@�[�q������ꍇ�͂��̒[�q�̗L�d���E���d���E�ړ_�H�Ȃǂ̏����A�����ꍇ�̓R���Z���g��ON/OFF�����[�������ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�R���Z���g�̃����[�ɂ����ꍇ�A���g���̂s�u�͓d��ON�Ŏ������ɃR���Z���g�̃v���O�����������ēd��������ꍇ�A���̌�ɂ͂ǂ̂悤�ȓ�������܂����H (���Ȃ݂ɁA�R���Z���g��茳�œd�����悤�Ȏg�����̓��[�J�[�͐������Ă��܂���) �@�ēx�R���Z���g����������A���̃`�����l���E���ʂłs�u�͂��܂����H �@����Ƃ��s�u�̓d��(��d���ł͂Ȃ������R���Ȃǂő��삳��Ă���\�t�g�d��)�͐ꂽ��ԂɂȂ�܂����H �@�����P�A�d����������(�������d����ON�ŁA�\�t�g�d����OFF�̏��)�ŃR���Z���g����v���O�����������āA�ēx�v���O���������猳�̂܂�OFF�ł����A����Ƃ������ON�ɂȂ��Ăs�u�����Ă��܂����肵�܂����H �@�����ďd�v�ł����A�����̏����������Đړ_�����l�͂ǂ̂悤�ȓ���̑��u������]�Ȃ̂ł��傤���H �@�u�l���߂��Ă��Ă������Őꂽ�s�u��OFF�̂܂܁B����OFF���u�̂Ƃ���ɕ����Ă����āA�����{�^���������Ȃ��Ɠ�x�Ƃs�u�͌���Ȃ��B�v�Ƃ������u�ł���Β��ȒP�ł��ˁB(���܂�~�����Ǝv���l�͋��Ȃ��Ǝv���܂��c) �@�P�Ɂu�l�����Ȃ��Ȃ�������v��������O���ŃR���Z���g�̓d�����J�b�g����̂���ԂĂ��Ƃ葁���ł����A���̌�̕������@�₻�̎��̂s�u�̓��삪�킩��Ȃ��Ɖ����v�͂ł��܂���B �@�ڂ������e�����������������B �@���A��L�̎���͂����܂łs�u�̊O���ɓd����ON/OFF���鑕�u��t����ꍇ�ŁA�s�u�̓������瓮�쒆�肷��d��������ꍇ��AON/OFF���R���g���[��������͂ɒ��ډ�H���Ƃ����悤�ȕ��̐v�ړI�ł͂���܂���B �@�܂��A�O���œd����ON/OFF���鑕�u��������ꍇ�ɁA�u��xAC100V��OFF�ɂ�����A�l���߂��Ă�AC100V��OFF�̂܂܂ŁA�s�u�̃����R���œd���X�C�b�`�������ꂽ��͂��߂�AC100V��ON�ɂ���v�̂悤�Ȑ����PIC�}�C�R���łł����Ȃ��Ɩ����ł����炻��������]�͖����ɂ��Ă��������B �@�ȈՔłŁA�s�u�̃����R���̂ǂ̃{�^���������Ăł���������AC100V��ON�ɂȂ�Ƃ��A�����̒��ŃG�A�R����I�[�f�B�I�̃����R���ȂǐԊO�������R���ł���ǂ�ł��{�^���������s�u��AC100V�d��������̂ł������̂Ȃ�A�����R���A���^�ɂ��ł��܂��B ���Ԏ� 2009/5/20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����玸��v���܂��B �@�����R����������A�ƌ����`�ł͑ʖڂȂ�ł��傤���H �@�ЊO�i�̃����R�������Ă��Đl���Z���T�[�t���ɉ������Ă��܂��̂������葁�����Ȃ��Ǝv�����̂ł����B �@��͂��ȑf�l�l���ł�����A�ǂ����ǂݎ̂Ăĉ������B waganiyoni �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����͂ƂĂ��ȒP�ȍH��Ȃ̂ł����A���p��͖�肪����̂Ŏg���܂����ˁB �@�l���Z���T�[�ƃ^�C�}�[�ƐԊO�������R����g�ݍ��킹�āu�l�����Ȃ��Ȃ���10���o�����玩���Ń����R���̓d���{�^���������v�Ƃ������u��������Ƃ��܂��傤�B �@�ꌩ����Ƃ��ꂾ���ŗǂ������ł����A���̂悤�ȏꍇ�͂ǂ��ł��傤�H �@���̑��u��u���Ă��镔���Łu�茳�̃����R���łs�u�������āA�l�͑��̕����ɍs���Ă��܂��B�v�Ƃ�����������ӂꂽ���i�ł��B �@�l�����Ȃ��Ȃ��Ė�10����A�^�C�}�[�������Ď����Ń����R���̓d���{�^�����������u�������āE�E�E�N�����Ȃ������ŏ���ɂs�u�����Ă��܂��܂��B �@�H��e���r�̂ł�������I �@�s�u�̓d����ԂƘA�������H�̖����A�����̐l���Z���T�[�ƃ^�C�}�[�����̃����R���X�C�b�`�ł͂���ȊO�ɂ��l�X�ȃV�[���ŕs����l�����܂��B �@�����������ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�^�C�}�[�œd�����Ƃ��ɂ͊m���Ɂu�d��OFF�v�ɂł���悤��AC100V���J�b�g���Ă��܂��̂��Ă��Ƃ葁���̂ł��B �@�����āA��̎���ŏo���Ă��܂����A�s�u�̓����Ԃ��O�����犴�m���邱�Ƃ��ł���A�^�C�}�[���u���u�d���������Ă��鎞�����d�����]������s���v�Ƃ����������ł���̂ŁAAC100V���Ȃ��Ă��ԊO�������R���ł��Ȃ�ł����@�͂���܂��B �@�������̕��@�����ɂ͂��g���ɂȂ��Ă���s�u�ɂ���������Ԃ��O���ɒm�点��M���[�q�����Ă���̂��ANTSC�r�f�I�o�͂͂���̂��A�����o�͂��������̂��A�s�u�����Ăǂ�������d���o�͂�����l�Ȃ̂��A�Ȃǂ̏��������Ȃ��Ƃ����킯�ł��B �@�s�u���R���g���[������ɂ��Ă��A�s�u�̃\�t�g�d���{�^�����O������ON�ł���Ă��Ƃ葁���ł����A���ꂪ�o���Ȃ���ΐԊO�������R�����g�����@��AC100V���J�b�g������@�ȂǁA���ɂ��킹�čœK�Ȃ��̂�I�ڂ��Ƃ��Ă���̂ŁA�����]�����Ȃ̂����킩��Ȃ��Ɖ�H���@�͎R�قǂ��肷���āu�������������̉�H�v�Ƃ����̂͂����ɒł��܂����A���ꂪ���ۂɂ��g���̂s�u�ł���]�̓����ł���̂��͓�ł��B ���Ԏ� 2009/5/21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����[�����b�ł��ˁB �@�d����on/off��Ԕc���͔ėp�I�ɂ͉�����Ȃǂ̗��p���ł��Ȃ����Ƃ����낢��l���Ă��܂��܂��B �@�ƁA���̑O�ɐl�̌��o���ǂ����邩���C�ɂȂ�܂��B �@�䂪�Ƃł̓g�C���ɐl�̃Z���T�t�d����u���Ă܂����A���[�V�����Z���T�Ȃ̂Ńg�C���ɗ����ėp�𑫂��Ă���i�����Ƃ��Ă���j�ԂɁu���l�v�Ɣ��肳��Č������n�߂Ă��܂��̂Ŕ����ɓ����Ȃ���p�𑫂��Ƃ����Ԕ����ȏ�Ԃł��i�ߓd�̂��ߓ_���ێ����Ԃ��Z���̂Łc�j �@���i���Ŏ�ɓ��镔�i�����������ł�NaPion�Ȃǂ�����܂�������������[�V�����Z���T�ł��̂Ńe���r�����Ă���Ƃ��ɂ����Ƃ��Ă���Ɓu���l�v�Ɣ��肳�ꂻ���ȋC�����܂��B �@�u���r�A���l�̋@�\��Nanao��PC���j�^�ō̗p���Ă���A���Əڂ�������������܂����B �@����͋����Ƃ�������邻���Ȃ̂łǂ��Ȃ��Ă���̂������[���Ƃ���ł��ˁB http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0904/21/news060.html mojo �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�s�u��ON/OFF�̔c���ɂ́A�ȑO�����ł����Љ���u�J�����g�Z���T�[�v���g����TV��AC100V�d���ɓd��������Ă��邩�ǂ����H�ׂ�ΊO�����o�͂Ȃǂ���ؖ����s�u�ł����m�ł���̂ł͂Ȃ���(����Ȃ�ԊO�������R���ł�ON/OFF���ł���)�E�E�E�Ƃ��A�{���ɂ�����ł����p�ł������Ȃ��̂͂���܂��B �@�l���Z���T�[�Ɋւ��ẮA�Z���T�[�f�q���̂̓A�i���O�o�͂ʼn��x�������Ă��镨��������ԊO�����Ă��̃��x�����o�͂��܂�����A�u���̖����v����̎�����A���̃p�\�R���p���j�^�[�̂悤�Ɂu�l�������߂��ɋ���v�Ȃǂ̌��肳�ꂽ�łȂ�ȒP�ȉ�H�Ől����ɋ��邩�ǂ����Ȃǂ͌��o�ł���ł��傤�B �@������������ɂ��킹���Z���T�[��������ꍇ�A�����������������镔���Ȃǂɒu���Ɠ����̐ԊO����l�Ɗ��Ⴂ���ď�ɐl�������ԂƔ��f���Ă��܂��܂�����A�����Ă��̐l���Z���T�[�́u�ω��ʔ�r��H�v��p���ĐԊO���ʂ��傫���ω����������u�l������(�������E�������E�o��)�v�Ɗ��m���ďo�͂Ƀp���X���o���܂��B���̕ω��ʌ��m�����Ȃ�����p�I�ɂ������ƕω����鑾�z���̓��˂���ԊO���ʂ̑������O�ɃZ���T�[��ݒu�����ꍇ���A���R�E�̐ԊO���ω����ƂĂ��ۗ����ĕω�����l�⓮���̓����ɔ����ԊO���ʂ̕ω��Ȃ�ԈႢ�Ȃ������������A���R�����̌�쓮��h���܂��̂łقƂ�ǂ̐l���Z���T�[�͂��̕����ł��ˁB �@�]�k�ł����A�ԊO���l���Z���T�[�̑O���u�ǂꂾ���������ʂ����甽�����Ȃ����H�v�Ƃ����������������Ƃ͂���܂��H �@���嗬�̐ԊO�����Ă��̗ʂ𑪂�^�C�v�̃Z���T�[���A�ԊO�����Ǝ˂��Ă��̔��˗ʂ𑪂�Z���T�[���A������̏ꍇ���u�ω��ʁv�����Ă����H�̏ꍇ�͂ƂĂ��������ƑO��ʂ�Δ������Ȃ����͐l�̎����Ŋm�F���Ă��܂�(��) �@���˗ʃZ���T�[�ȂǂŁA�ӂ���͋�ԂɏƎ˂��Ă��邾���Ŕ��˂��Ă��Ȃ��āA�l�╨���Z���T�[�͈͂ɓ���ƈ��ȏ�̔��ˌ������o����悤�ȃ^�C�v�ł͂ǂ�Ȃɂ�����蓮���Ă��Z���T�[�͈͂ɓ���Ɣ������Ă��܂��܂��B�j�q�g�C���̐���Z���T�[�̂悤�ȁE�E�E�B �@�]���āA�A�N�e�B�u�Z���T�[�ƃp�b�V�u�Z���T�[�Ȃǐ���ނ̃Z���T�[��g�ݍ���ŁA����͕��G�ȃR���s���[�^����Łu�l���O�ɋ���̂��H����Ƃ����R�E�̕ω��Ȃ̂��H�v�肷��悤�ȍ��x�ȃV�X�e����v����Ȃ炻�̃p�\�R�����j�^�[�̂悤�ȍ��x�ȁu�l�͋���H�v������s���V�X�e���������ł��܂����A�����ł͂Ȃ�����̂��˗��Ȃǂł͎s�̂̐l���m�Z���T�[���W���[�����g�p���邱�ƂɂȂ�̂Łu�g�C���Ɩ��̐l���Z���T�[�v�Ɠ������s�u�̑O�ł����ƍ����Ăs�u�����Ă���Ɓu�l�͋��Ȃ��v�Ɣ��肳��ă^�C�}�[�œd������Ă��܂��܂��B �@����҂̕������x�ȃR���s���[�^����Z�p�҂̕��Ȃ�u�l�������Ă��邩�H�v�ɂ��ẴZ���T�[�����̐v��v���O��������͂����g�ɂ��C�����܂����A�����łȂ��ꍇ�͎s�̂̐l���Z���T�[���W���[�����g�p���܂��̂ŁA�������܂܂ł͎��Ԃ��o������d������A�����h�~����ɂ́u���O�Ɍx������炷�v���Ƃł��̎��_�Ől���O�ɋ���Ȃ���U���Ă��炤�Ȃǂ��ăZ���T�[�������A���Ԃ��������Ă��炤�����Ȃ��ł��傤�B �@�u�g�C���Ɩ��̐l���Z���T�[�v(���ۂɕs�ւɊ����鎖������܂��ˁc)�Ɠ����ł��B �@���āA����҂̕�����̃��X�|���X��������Ԃő��̕��̊��荞�݂��������Ă��܂����A���������b�����Ă���Ǝ���҂̕��������ɂ����Ȃ�܂��H �@���悤�ɂ��u��������b������āA�����ɂ͂킩��Ȃ��������������I�v�Ƃ�������ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă��܂��B �@����҂̕��������������̂ł����A���̂܂܉������ꍇ�͈����Ԃ�������ɂ��̎��⎩�̂��폜�������܂��B ���Ԏ� 2009/5/23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�Ǘ��l���܁A�ړ_�������܁@���̓x�͎��炵�܂����B �@�m���Ɏ���҂��܂��ԐM������O�ɏ�����b���n�߂Ă��܂��Ə������ݓ�Ȃ��Ă��܂��܂��ˁB �@��ϋ����[�����ł����̂Ŕ��˓I�ɔ�ѕt���Ă��܂��܂����B�Ȍ�C��t�������Ǝv���܂��B �@�Z���T�[���ɂ��Ă̐����A��ώQ�l�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂��B �@�����ԊO���Z���T�[�ł�������������W�b�N�ɂ���ĐF�X�Ȏg����������̂ł��ˁB �@�ω��ʃ^�C�v�̐l�̎����͎������܂����B���Ӗ��ɕs���т�T������i�� mojo �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ԊO���Z���T�[�ŗV�Ԃ͖̂ʔ����̂ł����A�V�т�ʂ��ăZ���T�[�̓����𗝉�����̂͗l�X�ȃZ���T�[�Z�p�ւ̗�����[�߂�ǂ����@�ł�����܂��B �@�Z���T�[�𗘗p����ɂ͂��̃Z���T�[�̐��i��������悭�������Ȃ���ΐ��������p���@�Ŏg���܂���B �@���������Ӗ��ł͐ԊO���Z���T�[���ǂ��g�����̎��₪�o��̂����R�Ƃ�����ł��傤�B �@�����A�����̂���l���ǂ߂ƂĂ��ʔ������e��b���Ă���Ƃ͎v���̂ł����A�����̖����l��܂������ɖR�����l�ɂ͗���s�\�̘b�ɐi��ł��āA�ʔ����Ȃ���������܂���B �@����̖ړI�ł���u�l�����Ȃ��Ȃ�����v�Ƃ����̂����m������@�ɂ��Ă͂��Ȃ�i�荞���܂Řb���i��ł��܂�����A��͎���҂̕����ǂ̂悤�ȋ@�\�𗘗p���ꂽ���̂��Őv���j���ł܂�܂��B �@��������������o���ꂽ�̂ł�����A���Ђ���]�������ė~�����Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/5/28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Ԏ��x���Ȃ莸�炢�����܂����B �@�䂪�Ƃ̃e���r�ɂ͊O�������[�g�p�[�q������܂��������Ƀv���O���ēx�����ƌ��̃`�����l���A�����ł��܂��B �@�d���������Ԃōēx��������������ƌ��̂܂�OFF�ł��B �@���Ƃ��Ă͐؎��Ȃ̂ł����Ɠ����r�f�I�����I�������A�r�f�I�̓d����OFF�ɂ���̂ł����e���r�̓d����OFF�ɂ���̂�Y��邱�Ƃ��܂܂���U���Ԓ��e���r�̓d����������ςȂ��ƂȂ�܂��B �@�d�C�̖��ʌ����ł����e���r�ɂ��ǂ������Ǝv���܂��B �@SONY�̃u���r�A�͂܂������䂪�Ƃׂ̈̑��u��t���Ă����ȂƎv���܂����B �@�Ƃ肠�������̃e���r�őΉ��ł��鑕�u���쐬�ł���Ɠ��e�����Ă��������܂����B �ړ_���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�e���r�̓���������������������肪�Ƃ��������܂��B �@�O���łs�u�����Ă��邩�ǂ����ׂ���[�q�͖����Ƃ������ł��ˁB(�f���o�͒[�q�Ȃǂ���������) �@�Ƃ������Ƃ́A�w�s�u�����삵�Ă��鎞�̂݁A�l�����Ȃ��Ȃ�Ɠd������x�Ƃ����u���r�A�̂悤�ȑ��u�͒P���ȉ�H�ł͕s�\�Ƃ������ł��ˁB �@�w�s�u�����삵�Ă��Ă��A���Ă��Ȃ��Ă��A�l�����Ȃ��Ȃ�Ɠd��(AC100V)�������I��OFF�ɂ����x�Ƃ������u�ł�낵���ł����H �@����Ƃ��A������H�����āw�O������s�u�����삵�Ă��邱�Ƃ����m���āA�����R���łs�u��OFF�ɂ����x�Ƃ������@�\�ł������ł����H �@���@�\�łł́A�l�����Ȃ��Ȃ�Ƃs�u��OFF�ɂ��܂����AAC100V���킯�ł͂���܂���̂Ŏ���s�u�����������ɂ̓u���r�A���Ɠ��l�Ƀ����R���𑀍삷�邾���ōς݂܂��B �@�O����H�łs�u�̓�������m���Ȃ��ꍇ�̒�@�\�ʼn�H�̏ꍇ�A�l�����Ȃ��Ȃ���AC100V�������ɂ܂��l���������̓�������w�肭�������B (A) �l�����m�����玩���I�ɍēxAC100V��ON�ɂ���B �@�� ���g���̂s�u�Ȃ�ēx�d��������܂��B�Ō��VTR������VTR����Ă���Ȃ�^��������ʂ̂܂܂ł��ˁB (B) �J�b�g���u�́u�d���ē����v�{�^���������Ȃ��Ƃs�u��AC100V�͕������Ȃ��B �@�� �钆�ȂǂŐl�����Ȃ��Ȃ��Ď����Őꂽ��A���ɂs�u������ۂɂ͕K�����̃J�b�g���u�́u�d���ē����v�{�^���������Ȃ���Ȃ�܂���B (C) �����̒��łs�u��r�f�I�̐ԊO�������R���������ꂽ��AC100V��ON�ɂ���B �@�s�u�����悤�Ƃ��ă����R���𑀍삷��ƁA�J�b�g���u�������R����������m����AC100V��ON�ɂ��܂��B �� �G�A�R���̃����R���ł��Ȃ�ł����삵�܂��̂ŁA�s�u�̃����R���݂̂�r�f�I�̃����R���݂̂Ƃ����w��͂ł��܂���B(PIC���g���Ώo���܂����������Ő��삵�Ē����܂�) �@���̂ق��A��������ȊO�ɂ���]�̂��̂�������������������B �@�������́A �E���@�\�Ł|TV�g�p������AC100V�J�����g�Z���T�[�Ō��m �E���@�\�Ł|TV�g�p�����͉f���o�͐M���Ō��m �E���@�\�Ł|TV�g�p�����͑��̉���(���w�肭������)���g�p �E��@�\�Ł|(A) �l������Ƌ����I�ɂ�ON �E��@�\�Ł|(B) �d���ē����{�^�������� �E��@�\�Ł|(C) �Ȃ�ł������̂Ń����R���ɔ�������ON �̂����̂ǂꂩ��I���A�܂��͕ʂ̂���]�͂ł��肢���܂��B ���Ԏ� 2009/5/30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@������x���Ȏ�������������Ă��܂����̂����[�̗l�Ő��ɐ\����܂���ł����B �@�u�H��e���r�v�̉���̂������ł���ȂɃV���v���ɂ͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ����ɂ��悭�킩��܂����B�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �NjL �@�ԐM���x���Ȃ�\�������܂���B�{�肪�����Ԃ�i��ł���悤�ł��̂ŁA���̋L���̗����W����l�ł����炱�̂܂ܓǂݎ̂Ăĉ������B����v���܂����B wagamiyoni �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@����A���Ԏ��Ƃ��s���S�ȓ_�������\�������܂���B �u��@�\�Ł|(B) �d���ē����{�^���������v�ŏ\���ł��B �@�钆�֏��ɋN�������ɂ��傤�Ǘ\��^�悪�n�܂��^���Âȋ��Ԃ���̐��������������ɂ͂т����肵�܂����B �@�Ɠ����e���r�̓d����鎖��Y��Ȃ���ςގ��Ȃ̂ł���...�B �@��낵�����肢�������܂��B �ړ_���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
wagamiyoni�l �@�ړ_�����l���߂��āA�b���i��ł��܂��̂ł��C�ɂȂ��炸�ɁB �ړ_�����l �@�ł́A�u��@�\�Ł|(B) �d���ē����{�^���������v�ʼn�H��v���܂��B �@���ق��̕������҂������Ă��܂��̂ŁA�\�������܂����������Ԃ��܂��B ���Ԏ� 2009/6/1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����ւ҂����v���܂����B��H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �l���Z���T�[������  �@�l���Z���T�[�ɂ�Panasonic�d�H�́uNaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�v���g�p���܂��B
�@�l���Z���T�[�ɂ�Panasonic�d�H�́uNaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�v���g�p���܂��B�@10�~�ʂ�菬���Ȓ����^�ŁA�����ɂ��œd�Z���T�[�`�b�v�Ɗ��m��H�E�o�͉�H�������Ă���Ƃ����X�O�����m�ł��B �@NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�ɂ͂��낢��ȃ^�C�v������A����̗p�r�ł́u�f�W�^���o�͌^�v�ł��鎖�͕K�{�ł��B �@���x��Ή������ɂ�����ނ�����܂����A�����p�ɂ�TV�̑O�ł����Ƃ��Ă���l�Ԃ̂�����Ƃ̓����ł����������������߂Ɂu�����^ (2m)�v���g�p���Ă��܂��B�莝���̂��̂Ńe�X�g���Ă��܂��̂ŁE�E�E�B �@������2m�ł͍L�����r���O���ł�2m�ȏ㗣���TV�����邱�Ƃ�����ł��傤����A�L��������TV������ꍇ�́u�W�����o�^ (5m)�v�Ȃǂ��ǂ��ł��傤�B(���������͈����Ȃ�܂�) �@NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�E�f�W�^���o�͌^�̏o�͐M�������_���ŃZ���T�[��������������H�ɂȂ�܂��B �@�Ƃ��낪������ƃN�Z������AH�ɂȂ�Ƃ����Ă��d���͍ő�100��A�������Ȃ��Ƃ�����������ȏo�͂ł���Ƃ������ƁA������L�̏ꍇ���I�[�v���ɂȂ�Ƃ���P�^�̃I�[�v���h���C���o�͂��Ƃ������Ƃł��B �@�Ƃ������ƂŁu�v���_�E����R���K�v�v�A�u�o�͂̓g�����W�X�^���œd���������Ă�邩�A�d��������Ȃ�C-MOS IC���g�p����v�Ƃ��������ɂȂ�܂��B �@�v���_�E����R������ɂ��Ă��A�悭����5V�n��TTL���W�b�N�p��4.7K���Ȃ�Ēl����H�o�͂̎���1mA���x�������Ă��܂��̂ŁA�ő��i��100��A���y���z���Ă��܂��̂ł��̂ւ�͒��ӂ��Ē�R�l��I�����܂��B�����C-MOS���͂Ƃ���̂�50��A���������イ�Ԃ�ł��傤����100K���Ƃ��܂��B �@LED1�͐l���Z���T�[���l�́u���������m�v�������Ԃ����s�J�s�J�ƌ���܂��B �@�悭�Ԉ����̂ł����A�œd�^�̐l���Z���T�[�́u�l������̂����m�����v�̂ł͂Ȃ��u�l��������(�ω�����)���Ƃ����m�����v�Z���T�[�ł��B �@�ł�����œd�^�Z���T�[�̑O�ł����Ƃ��Ă��Ă��Z���T�[�͔������܂���B �@�Z���T�[�̃G���A���ɃG���A�O����l�������ė���B�����G���A���œ����B�G���A������G���A�O�ɏo�Ă䂭�B�Ƃ����ω��ɑ��ďœd�^�Z���T�[�́u�����ω�����������I�A�������������炵����I�v�Ƃ����M�����o���̂ł��B �@���̐�����u�Z���p���X���v�̏o�͐M���ɂȂ�̂ŁA���m���Ă�������ԉ����̋@��삳����ɂ́A�ʓr�^�C�}�[��H���K�v�ɂȂ�܂��B �@NaPiOn MP���[�V�����Z���T�[�̔���ȏo�͐M����⋭����Ӗ��ƁA��Ƀ^�C�}�[��H�Ƀg���K�[�M����^���邽�߂�C-MOS���W�b�NIC��74HC04�Ŕ��]�o�͂Ɛ��o�͂̂Q��ނ̏o�͐M���ɕϊ����܂��B �@���]�o�͂́u�Z���T�[���������Ă�����Ԃ̂�H�v�Ƃ����M���ɂȂ�A���̐M������́u�^�C�}�[ON���v�Ƃ����M�������鎞�̂ݒʂ��Q�[�g��H����āu�����M���v���쐬���܂��B �@�u�����M���v�͂��̖��̒ʂ�Z���T�[�����m������^�C�}�[���������邽�߂̐M���ł��B �@�Ȃ��u�^�C�}�[ON���v�̐M���Ɗ|�����킹�Ă��邩�Ƃ����ƁA�����|�����킹�Ȃ�����^�C�}�[OFF���ł��A�Z���T�[������������TV�̓d��(��d��)�������ON�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ�������ɂȂ��Ă��܂��A�˗��җl�́u�ċN���͎�ŃX�C�b�`�������̂ł����v�Ƃ������˗��ɔ����Ă��܂��܂��B �@���̐v�̏ꍇ�A��x�^�C�}�[���ꂽ��TV�̑O�Ől�������Ă��d���͓���܂���B �@TV�̓d��(��d��)�����Ȃ����ɂ͖{��H��SW1�́u�蓮�N���v�{�^���������K�v������܂��B �@�����ATV�̓d���͂����Ǝ蓮�Ő��Ă��Ă��A�{��H�ł�TV�Ƃ̘A���@�\�͂���܂���l�����Ȃ��Ȃ�����K��������TV�̓d��(��d��)�͐�Ă��܂��܂��B �@�u�����蓮�Ő�Y�ꂽ��E�E�E�v�Ƃ�����������~�X��Ƃ������ɂ͎����Ő�Ă���āA���̓��ɂ͎蓮�Ń{�^���������čēx��d�������Ȃ����̂������ł��傤�B �@�����������Ă��̓��ɂ͐�Y��邱�Ƃ͖����A�����R����TV�̃X�C�b�`����Ă���͂��Ȃ̂Ŏ���TV���������Ƃ��ɂ͂����ʂ��TV�̃����R���̓d���{�^����������TV�����Ă��ꂽ�ق����y�ł���ˁB �@���������ꍇ�ASW2��ON�ɂ��Ă����u�N���v���E�l�̊��m�v�@�\�������A�^�C�}�[�Ŏ�����OFF�ɂȂ��Ă���TV�̎�d����TV�̑O�ɐl�������Ǝ����I��ON�ɂȂ�܂��B �@���̎��ɁA�O��ɂ����ƃ����R����TV����Ă����(�˗��җl��tv�̓���m�F�ł�)TV���͎̂�d�������邾���Ŏ����d���͓���Ȃ������Ȃ̂ŁA���̎蓮�Ń����R����TV�������Ԃɖ߂邾���ŏ����TV��������͂��܂���B �@��������TV�������ςȂ��ɂ��Ă��ă^�C�}�[�Őꂽ�̂ł�����A�l��TV�̑O�ɗ������d��������Ɠ�����TV�͍��̏�ԂɎ����I�ɕ��A����̂Ŏ����d���������č�錩�Ă����`�����l�����f��ł��傤�B �@���ꂪ�u�킸��킵���v�Ɗ�����Ȃ�u�N���v���E�l�̊��m�v�@�\��OFF�Ŏg�p���Ă��������B �� �ԊO�������R�������� (���܂�) �@�˗��җl�̂��w��ł͂���܂��A����ƕ֗��Ȃ̂Łu���܂��v�Ƃ��ĉ�H�}�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B �@�s�v�Ǝv��ꂽ�Ȃ�s���N�̔j���ň͂��Ă����H�͐��삷��K�v�͂���܂���B �@�ԊO�������R����M���W���[��(IRM3638NS)�𗘗p���āA�u�ԊO�������R�����g��ꂽ�甽�������v��H�ł��B �@���̉�H���o�͂͂Q�n���p�ӂ��Ă��āA�P�̓����R�������������H�ɂȂ�M���ŁA������͐l���M���Ɠ��l���^�C�}�[�̉����Ɏg���܂��B �@TV�̓d����ON�̊ԂɐԊO�������R�����g����ƁA�u�����R�����g���� �� �����ɐl�������v�Ɣ��f���ă^�C�}�[���������܂��B �@SW3��ON�ɂ��Ă���Ɓu�N���v���E�����R�����m�v�@�\�������悤�ɂȂ�A�^�C�}�[�����TV�̎�d����OFF�ɂȂ��Ă��鎞�A�킴�킴�{���u�̂Ƃ���܂ōs���āu�蓮�N���v�{�^����������TV�̎�d�������Ȃ��Ă��悢�̂ł��B �@�^�C�}�[����Ă��Ă��A�����̂悤��TV�̃����R���̓d���{�^�������������Ŗ{�@��ON�ɂȂ�A�����Ő�Ă���TV�͉��Ă��̂܂܃����R���̓d���{�^���M������M����TV���f��ł��傤�B �@�O��ɏ����Y��Ď����Ő�Ă�����ATV�̃����R���{�^���������ēd�����ē������ꂽ���_�ʼnf��n�߁A���̂܂܃����R���̓d���M�����Ĉ�U�����Ă��܂���������܂���B���̂悤�ȏꍇ�͑O���Y��Ă����������Ȃ̂ŁA���߂ă����R���̓d���{�^���������Ȃ������������ł��B �@�A���A���̐ԊO�������R����M���͓���TV�̃����R���̓d���{�^�������ʂ���}�C�R������ł͂Ȃ��A�P���ɕ����̒��ʼn����ԊO�������R�����g��ꂽ�炻��ɔ������܂��̂ŁA���N����TV�͌������Ȃ����ǃG�A�R���̓d���̓����R���œ��ꂽ�c�Ƃ����悤�ȏꍇ�ł�TV�̎�d���͓���܂��̂ŁA���ꂾ���ł͑O�邤����������Y��Ė��������TV�͉f��܂��A�G�A�R���̃����R���Ŏ�d�������邾���ł������I�Ƃ����悤�ȏꍇ�͂��̃X�C�b�`����Ă������A���̂��܂���H���̂����Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B �@�����R���g�p�����m���Ă̎��������@�\��TV�����Ă��鎞�Ƀ����R�����茳�ɂ���A�^�C�}�[�������邽�߂Ɏ��U������̂�������ƕ����̒��ł������ȋ���(�H)�����Ȃ��Ă��茳�Ƀ����R���������Ă���u���ʁv�{�^���ł��Ȃ�ł��`�����Ɖ��������ł����̂ŕ֗������ł͂���̂ł����E�E�E�E�����g�p���͐l�ɂ���ėl�X�ł��̂ł��̂��܂���H����ɕ֗��Ƃ͌�������܂���B �� �^�C�}�[��H �@�{�@�̃^�C�}�[��H�́u�Q�i�K�����v�ɂ��Ă��܂��B �@��i�K�ڂ́u�^�C�}�[�P�v�͒ʏ��TV�̓d���������Ă��鎞�������߂�ړI�̃^�C�}�[�ł��B �@��X���`25���̊Ԃ�VR1�Ŏ��Ԃ�ݒ�ł��܂��B �@�^�C�}�[�P���쒆��LED2���ΐF�Ɍ���A�ʏ�́u�d��ON�v�����m�点���܂��B �@�^�C�}�[�P��74HC123�́u�ăg���K�\�v�@�\�ɂ��A�^�C�}�[���쒆�ɍēx�Z���T�[�����������ăg���K��������^�C�}�[���Ԃ͐ݒ肵�����Ԃ܂ōēx��������܂��B �@�ł�����TV�����Ă��鎞�Ɏ��U��E�̂���(�܂����蓮�����{�^��������)�Ȃǂ��Đl�����邱�Ƃ�{�@�ɓ`����A���̎��_����^�C�}�[�͉�������܂��B �@�ԊO�������R��������H������Ă���ꍇ�͐ԊO�������R���̎g�p�ł���������܂��B �@�^�C�}�[�P�̐ݒ莞�Ԃ����ă^�C�}�[���ꂽ�ꍇ�A������TV��OFF�ɂȂ�̂ł͂Ȃ���i�K�ڂ́u�^�C�}�[�Q�v��������J�n���܂��B���Ԃ�VR2�Ŗ�10�`30�b�ɐݒ�ł��܂��B �@�^�C�}�[�Q�́u�^�C�}�[��x���p�v�ŁA�^�C�}�[���Ԃ��ꂽ���Ƃ�l�Ԃɒm�点��ׂ�LED3���F�ɓ_�ł�������Ԃ̎��Ԃ����܂��B�u�U�[��H������Ă���u�U�[����܂��B �@�^�C�}�[�P���^�C�}�[�Q�̏o�͂�D4�ED6��OR������Ă���̂ŁATV�͂ǂ��炩�Е��̃^�C�}�[��ON�̊��Ԃ͓d��������悤�ɂȂ��Ă���A�x�����Ԓ��������͂��܂���B �@����TV�����Ă��Čx�������v����F�œ_�ł��͂��߂���A�x�����ԓ��Ɏ��U��E�̂���(�܂����蓮�����{�^��������)�A�ԊO�������R��������H������Ă���ΐԊO�������R���𑀍삷��Ȃǂ̂����ꂩ�̓��������^�C�}�[�͏�����Ԃɖ߂��^�C�}�[�P�̒ʏ�̃^�C�}�[���ԂɂȂ�܂��B �� �x���u�U�[��H �@�ꉞ�u�x���u�U�[�v��H���f�ڂ��Ă��܂����ATV�����Ă��鎞�ɂ����Ƃ��Ă��Ē����ԃZ���T�[�����m�Ń^�C�}�[��ɂȂ鎞�ɂ�LED�̓_�łƋ��Ɂu�s�s�s�s�s�c�v�Ɩ��Ă��m�点���Ă����͕̂֗��Ȃ̂ł����ATV�����I����Ė�Q�鎞�ɂ�TV�A���ł͖����ׂ��^�C�}�[�̎��Ԃ������珟��Ɂu�s�s�s�s�s�c�v�Ɩ��Ă��������������͂��߂��̂ɋN������Ă��܂���������܂���B �@���d�u�U�[�̉��͏������Ă��܂艓���܂ł͕������܂��A�{���Ɂu�ꉞ�v�ڂ��Ă݂������ł��̂ō���Ă݂āu�����W�Q�v�����Ǝv��ꂽ�ꍇ��SW4�͐��Ă������ق���������������܂���B �@��H�}���d�グ�Ă��獡���̕��͂������Ă��Ďv�������̂ł����A���̃u�U�[��H�̕����Ɂu���邳�Z���T�[�v��g�ݍ���ŁA�������Â����ďA�Q���Ă��鎞�ɂ̓u�U�[�͖炳���ɁA���邢�������u�l�͋N���Ă��邾�낤�v�Ɣ��肵�ău�U�[��炷�Ƃ����̂�������������܂���B �@�F�X�������������E���ǂ��ł��܂�����A�������̖ړI����ɂ��킹�Đv��ς��Ă݂���̂��ʔ����ł��傤�B �� �\���b�h�X�e�[�g�����[ �@AC100V��ON/OFF����̂ɁA����͒ʏ�̃����[(�d�������[)�ł͂Ȃ��\���b�h�X�e�[�g�����[(SSR)(�����̃����[)���g�p���܂��B �@�@�B���̃����[�ł͐ړ_��ON/OFF�Ńm�C�Y���o����A�ړ_������Ɠd����ʂ��ɂ����Ȃ��Č̏�̌����ɂ��Ȃ�܂����ASSR���Ɛړ_�̗͂���܂��u�[���N���X�^�C�v�v�u�X�i�o���X�^�C�v�v�Ȃǃm�C�Y���o���Ȃ��悤�ȓ���Ȑ��\��L�������̂��g���m�C�Y���X�œd�q��H�̌�쓮�̌����ɂȂ邱�Ƃ����܂肠��܂���B �@SSR�͓d�q���i���[�J�[�A�d�H���[�J�[����e��̔�����Ă��܂������l�i�������������܂��̂ŁA����͈����ȁu�H���d�q��SSR�L�b�g (250�~)�v���g�p���܂��B �@����ޔ̔�����Ă��܂��̂ŁA���g���ɂȂ���TV�̂v���ɉ����ė]�T�̂���d���l�̂��̂��w�����Ă��������B(�K�v�Ȃ���M����Y�ꂸ��) �@�������A�H���̃L�b�g�łȂ��Ă����[�J�[���̂������肵��SSR(DC��5V�쓮�^�C�v)���g���Ă����\�ł��B ���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��
 �@�g���v�����Ƃ��ẮA�b��ɏo�Ă����p�\�R���p�̃��j�^�[�Ŏg�p����ׂɁu�����Z���T�[�v(GP2Y0A21YK)���g���āu�l��??cm�ȓ��ɋ��鎞�ɂ͓d��ON���p���v�Ƃ����̂��ʔ����Ǝv���܂��B
�@�g���v�����Ƃ��ẮA�b��ɏo�Ă����p�\�R���p�̃��j�^�[�Ŏg�p����ׂɁu�����Z���T�[�v(GP2Y0A21YK)���g���āu�l��??cm�ȓ��ɋ��鎞�ɂ͓d��ON���p���v�Ƃ����̂��ʔ����Ǝv���܂��B�@���̂悤�ȐԊO�������Z���T�[�́A�ŋ߂͓d�q���i�V���b�v�ł́u���{�b�g�p�v�Ƃ��Ĕ����Ă��܂���(����{�������ł����c)�A�F����̐g�߂ȂƂ���ł���������g�C���Ŏg���Ă��܂��B �@�j���p�g�C���Ȃ�A�T�K�I�̑O�ɗ�������Z���T�[����LED���Ԃ��_�����A������������LED�������Đ����W���[�Ɨ����A���ł��B���O�g�C���ł͗m���֍��ł����̕ǂɃZ���T�[���������āA�l�������Ă���(�Z���T�[�O�ɕ��̂�����H)���Ƃ����m����LED���Ԃ�����A��͂�l����������Ɠ����ɐ����W���[�Ɨ���܂��ˁB �@���̍����v���X�`�b�N�ɕ���ꂽ�Z���T�[�����悭����ƁA���ɂ��̂悤�ȁu�������v�u������v���Z�b�g�ɂȂ��������Z���T�[���d���܂�Ă���̂����Ď��܂��B �@GP2Y0A21YK�̏ꍇ��80cm�`10cm�܂łŃA�i���O�d�����o�͂��܂��̂ŁA���̓d�����v���ă��j�^�[�O60cm���x�ȓ��Ƃ�������������A�^�C�}�[���ăg���K�[���������H(���̏ꍇ�A�Z���T�[�o�͂̒�������ł͂��߁A�p���X������H)�����ΊȒP�Ɏ����ł��܂��ˁB ���Ԏ� 2009/9/3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@��ς��萔�����|�������悤�Ő\�������܂���B �@���̃X�L���ł͂��Ȃ�̑��ɂȂ�悤�ł����Ō�܂Œ��߂��ɍ�肠�������Ǝv���܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����B �ړ_���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���������Ă��܂����A���G�����Ɍ�����d�q��H�ł��������̃u���b�N�ɕʂ�Ă��܂��̂ŁA���ꂼ��̃u���b�N�������Ɠ��삵�Ă��邩�m�F����Ƃ�i�߂���ΕK���������܂��B �@�����S������Ă����Ɠ����Ȃ��Ă��A�u���b�N���Ƃɓ���m�F��z���~�X�̃`�F�b�N���������قǓ���͂���܂���B �@�}�����A�������m���ɑg�ݗ��ĂĂ݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/9/4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԍڗp�c�u�c�̉����������I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�����ԂɂP�QV�p������DVD��t�����̂ł����A����d�������邽�щ��ʂ������Ȃ��Ɓ@�����������ĕ������܂���B�����Ԃւ̓g���^�����O�����͒[�q���特���A�f�������Ă��܂��B �@������DVD�ɉ����H�Ƃ��A�Ԃɉ���������Ɠd�������邽�щ��ʒ������Ȃ��Ă��ǂ����@�Ȃǂ���܂����H �@�d�q��H�͂܂����Ȃ̂ł����A���ꂢ������Ă�����H��������������Ă��������B �x���J �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���ʂ��ςł���Ƃ������́A�u�w�b�h�t�H���[�q�v���特���M�������o���ăJ�[�I�[�f�B�I�ɐڑ�����Ă�̂ł����H �@���ʂ͉f���o�͒[�q�ƕ���ł���u�����o��(���C���o��)�v�Ƃ������ʂ�ύX�ł��Ȃ��[�q���特�������A���C���[�q�ł͑��̃I�[�f�B�I�@��Ɛڑ�����̂ɓK�����M���d�����o�Ă���͂��Ȃ̂Łu���ʂ��������v�Ƃ������������͂��ł��B �@���������g���̒�����DVD�v���[���[�Ƀ��C���o�͒[�q�������Ƃ��A�Ȃ������C���o�͒[�q���w�b�h�t�H���o�͒[�q�ɂȂ��Ă��ăw�b�h�t�H�����x��(���C���x����菬����)�Ȃ̂ʼn��ʂ��������Ƃ��Ȃ�O���ɕʓr�v���A���v���q���ł���ĉ��ʂ��グ�Ă��������B �@�d�q��H�͂܂����Ƃ������ł��̂ŁA�����ʼn�H�}����Ă������ŕ��i���W�߂đg�ݗ��Ă�͓̂����������܂���A�s�̂̃L�b�g�ŗ��p�ł������ȕ������Љ�܂��B �@�L�b�g�ł���Αg�ݗ��ĕ���ڑ��̕��@�Ȃǂ͑g�ݗ��Đ������ɏڂ���������Ă��܂�����A������������K�v������܂���i�O�O�G �@�����d�q�̒ʔ̂ł́u380�A���v (���661�~)�v�Ƃ��Ĕ����Ă���A�A���vIC LM380���g�p���������A���v�L�b�g�ł��B �@�{���̓��C�����x�����x�̓��͂ŃX�s�[�J�[��炷�ׂ̃p���[�A���v�L�b�g�ł����A���̓{�����[���̒��߂œ��͂����C�����x�����x�ŏo�͂����C�����x�����x�ł̎g�p���ł��܂��B �@�d���d����8�`22V�ł�����A�����Ԃ�12V�ł��̂܂g���܂��B �@���̃L�b�g�̓��m�����p�ł�����A�X�e���I�Ŏg�p����ɂ͂Q�����ĉE�E���̃`�����l���ɂ��ꂼ��Ƃ���܂��B �@�A���vIC LM380��ALM386���g�p�����L�b�g�͊e�Ђ���F�X�o�Ă��܂��̂ŁA�������߂��̓d�q�p�[�c�V���b�v�Ŕ����Ă��������g�p�����Ɨǂ��ł��傤�B �@�����d�q�Œʔ̂�����Ă���LM380���g�p�����i��661�~�Ɣ�r�I�����̂ł����߈Ղ��Ǝv���܂��B �@�K�v�ȃp�[�c���������Ŕ����đg�ݗ��Ă�Ζz�ō쐬�ł��܂��B�{�y�[�W�̂ق��̋L������LM386���g�p�����A���v��H�̉�H�}�͌f�ڂ��Ă��܂��̂ŎQ�l�ɂ������ō����̂��ʔ����ł��傤�B ���Ԏ� 2009/5/17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �u�U�[�f����H�}�iLED�_�ʼn�H�ɂ��j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB �@���d�u�U�[�i���㎮�j��p�����u�U�[��H����肽���̂ł�����H�}�������Ē����Ȃ��ł��傤���H �@�u�s�b�s�b�s�b�s�b�v��u�s�[�s�[�s�[�s�[�v�Ȃǂ̂悤�Ƀu�U�[��炷������C�ӂɕύX�ł���悤�ɂ������ł��B �@�����ԕ��i�Ȃ̂œd���͂P�PV�`�P�TV�ł��B ���w�����i�ȂǍׂ��������Ē�������肪�����ł��B �@��낵�����肢�v���܂��B ���낦�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�炷�Ώۂ����d�u�U�[�̂悤�ł��̂ŁA���ɑ�d���̃h���C�o��H�����Ȃ�555���U��H�ōς݂܂��B �@555�͊e�Ђ���LM555��NE555�Ȃǂ���������Ă��܂�����A���X�Łu�^�C�}�[IC��555�������v�ƌ������̂��X�Ŕ����Ă���i���o�Ă��܂��B �@���U���g����VR1�Ŗ�0.6Hz�����12Hz�̊ԂŔC�ӂɒ��߂ł��܂��B �@���Œ��R���Ĕ��U�������ς�̂̓u�U�[�̉��ł킩��܂����A�ꉞ����m�F�ׂ̈�LED(�ԐF)�����Ă��܂��B �@�u�U�[�̂�����LED�𐔌`�\�܂Œ��x�ł���A�K�v�ȓd��������R������555�̏o�͂Œ��ړ_�ł������邱�Ƃ��ł��܂��B �@��R��R���f���T���A�d�q�p�[�c�X�ɍs���ĉ�H�}���v�����^�[�ň����������X������Ɍ�����ǂ�������̂��������Ă���܂��B (�p�[�c�V���b�v�͊�{�I�ɃZ���t�T�[�r�X�ł��A�����ŒT���Ȃ��ꍇ�̂ݓX������ɐq�˂Ă�������) �@���X�ɍs���Ȃ��Ńl�b�g�V���b�s���O�ȂǂŃp�[�c���ꍇ�́A�u�C�̖����v�̊e����L���y�[�W(���i�ʐ^��)�Ȃǂ��Q�l�ɕ��i��I�Ԃ悤�ɂ��Ă��������B �@�O�ɂ������Ă��܂����A�u�������v�ł͉�H�}�̒͂��܂����ׂ��ȕ��i�ɂ��Ă͐��������A�������ōw�����Ē����Ƃ����X�^���X�ł��B ���Ԏ� 2009/5/6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���������b�ɂȂ�܂��B�������O�Q�P�O�ł������܂��B �@�k�d�c�Ԋu�œ_�ł��������Ă��̉�H�̂b�S���Q�Q�O�ʂɂ����̂ł����A�d�������������_�����Ԃ���Q�T�b�E�����P�U�b�ɂȂ�Q��ڈȍ~�͓_����P�U�b�E������P�U�b�̌J�Ԃ��ƂȂ�܂����B �@�ŏ������R���f���T�[�ɗ��߂�̂ɗ]���Ȏ��Ԃ��K�v�ƌ������Ȃ̂ł��傤���B �@�ŏ�����Q��ڈȍ~�Ɠ����b���ɂ�����@�͂���܂��ł��傤���B �@�܂��A���łƂ����Ă͂Ȃ�Ȃ̂ł����T�T�T�̂Q�Ԃ��f�m�c�ɗ��Ƃ��g���K�Ƃ���^�C�}���悭�g���Ă���̂ł����A����ŕs��͂Ȃ��̂ɁA�Ԃɓ��ڂ���Ǝ���̃m�C�Y���E���̂��d���������^�C�}������ɃX�^�[�g���Ă��܂��������X����܂��B�ʓd��͉��x����Ă�����Ƀg���K�Ń^�C�}�Ƃ��ċ@�\���܂��B �@�����g�p�̓��A�S���ُ�����Ȃ���������܂����A�������镨���d������������ł͂Ȃ��A���X�Ȃ̂ŗ]�v�C�ɂȂ�܂��B �@�d�����C��100�ʁE0.1�ʂT�Ԃ�0.01�ʓ��͕t���Ă͂���̂ł����B �@�����ǂ����@�͂Ȃ��ł��傤���B �@�����I�Ȏ������Ő\����Ȃ��̂ł����X�������肢���܂��B �������O�Q�P�O �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ŏ��������Ԃ������̂��^�C�}�[IC555�̎d�l�ʂ�̓����ł��̂ŁA�̏��v�~�X�ł͂���܂���B �@�^�C�}�[IC 555���f�[�^�V�[�g�͂����ɂȂ�ꂽ���͂���Ǝv���܂����A�g�p�ɂ������ăC���^�[�l�b�g����555�̔��U��H�̐v���@�⌴�����Љ�����Ă���y�[�W�������ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@����(���Ƀf�[�^�V�[�g�ł�)��555�̓���ɂ��Đ�������Ă���̂ŁA�����Ă����������������Ə����Ȃ��Ă��ǂ����Ǝv��������ł͉�����Ă��܂��A555���g�p���钍�ӂƂ��Ă͂ƂĂ���{�I�ȓ��e�ł��̂ŁA���������m�Ȃ��̂ł�����o���Ă����Ă��������B �w�^�C�}�[IC 555�̔��U�̏��x���Ȃ錴���̐����x 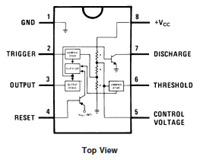 �@555�̓R���f���T�̏[�d�E���d���P�T�C�N���Ƃ��Ĕ��U���܂����A���̃R���g���[���̓g���K�[(���_���E�����ESET)���͂ƃX���b�V�����h����(���_���E����ERESET)�̂Q�̓d�����͂�臒l���R���f���T�d�����z���邩�ǂ����Œ��̐���p�t���b�v�t���b�v���Z�b�g�E���Z�b�g���܂��B
�@555�̓R���f���T�̏[�d�E���d���P�T�C�N���Ƃ��Ĕ��U���܂����A���̃R���g���[���̓g���K�[(���_���E�����ESET)���͂ƃX���b�V�����h����(���_���E����ERESET)�̂Q�̓d�����͂�臒l���R���f���T�d�����z���邩�ǂ����Œ��̐���p�t���b�v�t���b�v���Z�b�g�E���Z�b�g���܂��B�@�g���K�[�[�q�ƃX���b�V�����h�[�q��IC�����ŃR���p���[�^�̃A�i���O���͂ƂȂ��Ă��āA�e�R���p���[�^�͓����̕�����R��1/3Vcc��2/3Vcc����d���Ƃ��ė^�����Ă��܂��B �@���U��H�̉�H�}�ʂ�ɕ��i��t�����ꍇ�A�t���b�v�t���b�v��1/3Vcc�ȉ��ŃZ�b�g����A2/3Vcc�ȏ�Ń��Z�b�g����܂��B 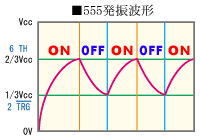 �@�]���āA�d��ON�������ŏ��̏�Ԃł̓R���f���T��0V�ł�����1/3Vcc�ȉ��Ńt���b�v�t���b�v�̓Z�b�g����A���d�g�����W�X�^��OFF�ŃR���f���T�ɂ�Vcc���R1+R2(+VR1)����ď[�d���J�n����܂��B���̓d����2/3Vcc�܂ŏ㏸����܂ł̎��Ԃ�����̏[�d�T�C�N���̎��Ԃł��B
�@�]���āA�d��ON�������ŏ��̏�Ԃł̓R���f���T��0V�ł�����1/3Vcc�ȉ��Ńt���b�v�t���b�v�̓Z�b�g����A���d�g�����W�X�^��OFF�ŃR���f���T�ɂ�Vcc���R1+R2(+VR1)����ď[�d���J�n����܂��B���̓d����2/3Vcc�܂ŏ㏸����܂ł̎��Ԃ�����̏[�d�T�C�N���̎��Ԃł��B�@�R���f���T�d����2/3Vcc�܂ŏ㏸����ƃX���b�V�����h�[�q�̔���d��2/3Vcc���z����̂Ńt���b�v�t���b�v�̓��Z�b�g����A���̕��d�g�����W�X�^��ON�ɂȂ�R���f���T��R2(+VR1)���o�R���ĕ��d����܂��B���̓d����1/3Vcc�܂ō~������܂ł̎��Ԃ����d�T�C�N���̎��Ԃł��B �@1/3Vcc�܂ʼn���������g���K�[�[�q��臒l���z���܂��̂Ńt���b�v�t���b�v�̓Z�b�g������d�͏I���AR1+R2(+VR1)��ʂ��Ă̏[�d�T�C�N���ɐ�ւ��܂��B�Q��ڈȍ~�̏[�d�T�C�N���̎��Ԃ�1/3Vcc����2/3Vcc�ɏ㏸����܂ł̊ԂŁA�����0V����2/3Vcc�ɏ㏸����܂ł̎��Ԃ��Z���Ȃ�܂��B �@���̂悤�ɁA555�̓���ł͏���̏[�d�̂�0V����2/3Vcc�܂ŏ[�d����ׁA�Q��ڈȍ~��1/3Vcc����2/3Vcc�܂ŏ[�d���鎞�Ԃ��͒����Ȃ�܂��B �@������u���瓯�����Ԃɂ������v�Ƃ����v���́A���ʂ�555���g�������U��H�����l�͍l���܂���B�u�������������IC�v�Ȃ̂ł�����B �@���瓯�����Ԃ��~�����ꍇ�́A���瓯�����Ԃ̃^�C�}�[��H�₻������IC��T���Ďg�����̂ł��B(�ǂ�ȉ�H��IC���L��̂��͂����ŐG��܂���) �@�����u�ǂ����Ă�555�ŏ��玞�Ԃ��ɂ������v�Ƃ����̂ł���A555�̎g�p���@�Ƃ��Ă͎ד��ł������̂悤�ȓ��엝�_���l�����܂��B �@�g���K�[���x����1/3Vcc����ς����Ȃ��̂ŁA�R���f���T��1/3Vcc�ł͂Ȃ�0V�t�߂܂ŕ��d�������Ƀg���K�[�[�q�ɂ�1/3Vcc��������悤��555���x����H��lj����Ă��B ���T�ԃs���̃R���g���[���{���e�[�W�̕ύX�Ŋ�d���͕ς����邪�A�X���b�V�����h���ς�̂łT�ԃs����ύX������@�͎��Ȃ��B �@���āA���̕��@�łQ�ԃs���ւ̓d�����R��lj������떂���������ƁA�m���ɃR���f���T�d����0V�t�߂܂ŕ��d������g���K�[��������悤�ɂȂ�܂������A���x���ʂ̖�����������܂��B �@����́A�Q�ԃs���̓d�����떂�����ׂ�Vcc�ƃR���f���T�d�����R�ŕ������Ă��̂ł����A����������R��lj����鎖�ŏ[�d���ɂ͂��̒�R���o�R���ăR���f���T�ɂ�葽���[�d�d��������A���d���ɂ�Vcc���炻�̒�R��R2(+VR1)�ŕ��������d���܂ł����d����������Ȃ�(���d�̑������j�~�����)�̂ŁA���d�Ɏ��Ԃ�������悤�ɂȂ�����A���d���������Ȃ��悤�ɂȂ�܂��B���d���������Ȃ��̂͒lj��̒�R�l�߂���Ύx��͂Ȃ��Ȃ�܂����A���̒�R��lj�����Ƃ��������Ō��̔��U��H�ł́u555�̓����̂P�ł���[�d���ƕ��d���̒�R�o�H���Ⴄ�ׁA�f���[�e�B���50%�ɂ��鎖���s�\�ł���B�v�Ƃ�����_����茻��Ȃ����Ă���(�[�d���ƕ��d���̒�R�l�̍����������������Ă���)�Ƃ������z�I�Ȑv�������A�[�d(ON)���Ԃƕ��d(OFF)���Ԃɂ��Ȃ�̍�������邱�ƂɂȂ�܂��B �@�u����ƂQ��ڈȍ~�̎��Ԃ��ɂ������v�Ƃ������z��������ƁA�u�f���[�e�B�䂪50%����傫��������v�Ƃ��������ɂ��Ȃ�̂ł����A����������H������]�ł��傤���H �@�^�C�}�[IC 555���g�p���Ă������A�����ƃg�����W�X�^��IC����lj����Ȃ��ƌ��X�̐v�̃f���[�e�B��50%�ɋ߂����z�I�Ȕ��U��H���c���A�ŏ����玞�Ԃ�S�ē����ɂ���Ƃ����̂͂��Ȃ����Ǝv���܂��B �@����Ȏ������邭�炢�Ȃ�A555���g��Ȃ��ʂ̉�H�������ŖړI�̉�H��������ق����X�g���[�g���Ǝv���܂��H (�����ł͉�H�͒��܂���) �@���ł̌��ɂ��ẮA���͂����ł͂Ȃ����������Ǐo��̂��킩��܂���̂ŁA�ȒP�Ȓlj���H�Ƃ��ăp���[�I�����Z�b�g��H���Ƃ���Ă݂Ă͂������ł��傤���H �@��H�}�͉ߋ��ɑ����o�Ă��܂��̂ŎQ�l�ɂ��ăe�X�g�E�g�ݍ��݂��Ă��������B ���Ԏ� 2009/5/19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/20 |
�@���������b�ɂȂ�܂��B �@�{���ɏ����̎���ł���Ԃ���点���݂܂���ł����B �@���������ʂ葼�Ɏg����IC�͂�����ł�����̂�����555�ɍS��K�v�Ȃ�Ăǂ��ɂ������ł���ˁB �@���X�ł����{���ɃA�z�Ȏ���ł��݂܂���ł����B �@���ł̌�����C�ER�E�_�C�I�[�h�ʼn�H��g�݃e�X�g���Ă݂܂��B �@����������ǂ������肪�Ƃ��������܂����B max0210 �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�P4�d�r�œ����f�W�^���I�[�f�B�I���Ԃ̂P�Q�u�œ�������悤�ɂ͂ǂ���������ł����H �V�I �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���ɓd�r�{����������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂P�{�Ƃ݂Ȃ��Ă�낵���ł��ˁH �@�u���y�v���[���[�p��1.5V�̓d���͍��܂����H�v�ʼn��Ă��܂��B �@�܂��u�ԂŁA1.5V�̋@����g���d���̐����v�Ƃ��������⒆�ł��L�b�g���g�p���ē��l�̂��Ƃ��ł��邩�ǂ����ɂ��Čf�ڂ��Ă��܂����A�ǂ܂�Ă��܂��H �@����1.5V�Ŗ����Ă��A��L�̓��e�Ōf�ڂ��Ă���d���͓d���ςł����炽�Ƃ��d�r�Q�{��3V���K�v�ł����̂܂g���܂��B �@����������O�ɂ͕K�����l�̕����f�ڂ���Ă��Ȃ����m�F�����肢���܂��B ���Ԏ� 2009/5/5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԁE�o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�|�[�^�u���J�[�i�r���o�C�N�Ɏ��t�������̂ł����Ԃł��ƃV�K���b�g����ȒP�ɓd�������܂����o�C�N�̏ꍇ�͎��鏊����܂���B �@�P�Q�u����T�u�ɕψ��ł����H���o���܂����B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�V�K�[�\�P�b�g�͖����ł����A�t�����g�p�l������Β��Ɋe��z���̃n�[�l�X������܂�����A�����̒�����K�v�Ȑ���I���12V�͎��o���܂���ˁB �@�d�C�̊�b�m�����炢������������Ńo�C�N������12V�����o����͂��ł��B �@�����ł��Ȃ��Ƃ��A�������Ă��ǂ̔z�������ׂ��Ȃ��ȂǁA�d�C�����E�H�삪�ł��Ȃ����͖��������ăo�C�N�����悤�Ƃ��Ȃ��ł��������B�i�r���o�b�e���[�^�C�v���g�p���Ă��������B �@12V�����o������́A�u�C�̖����v�ʼn��x���L����b�ɏo�Ă���DC/DC�R���o�[�^�E���i��O�[�q���M�����[�^���g�p�����d����H�Ȃǂ�����ĂƂ����Ηǂ������ł��B �@�|�[�^�u���i�r�̏���d����400mA���x�܂łł����105�`315�~�Ŕ����Ă���V�K�[���C�^�[�p�̃R���o�[�^�𗬗p����悢�ł����A1A���x�K�v�Ȑ��i�Ȃ�1000mA�Ή��̏��i�������ԗp�i�X�Ȃǂōw�����Ďg�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������H�t���Ȃǂɒ��ڍs����̂ł�����d����Ȃǂi�X�ŒT���Ĕ�����Ύ����ԗp�i�X�̂悤�ɓd�C�W���i�͂Ȃ�ł������X�Ŕ������͂����ƈ����ł��܂����A�����������ŕi��T���̂��Z�p�E�m���̂����ł�����A�����ł͂Ȃ��l�͑��������Ă���ʐl�����̓X�ŕK�v�ȏ��i���Ďg�����ق������s�����Ȃ��ł��傤�ˁB ���Ԏ� 2009/4/3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����͎��ۂɎ��t���Ă��܂��̂ŎQ�l�܂ŁB �@�z�[���̒[�q����{�̓d�������A�R�[�q���M�����[�^�[�œd���𐧌䂵�Ă��܂��B �@�}�C�i�X���͂��̂܂܃{�f�B�[�A�[�X�ł��B �@����ŕs�����^�p���Ă��܂����B �@�Ȃ��A�g���Ă�i�r��Mio C323�ł��B Thief �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���߂ē��e���܂��z�[���y�[�W�h���������p�h�̊Ǘ��l�ł��B �@�����u�C�̖����v���y���݂ɔq��,�Q�l�ɂ����đՂ��Ă��܂��B �@�����l����o�C�N�Ń|�[�^�u���J�[�i�r�̂���������āA���Q�l�ɂȂ�Ǝv�����e�����đՂ��܂��B �@���͑�p�̑�k�ɒ��݂��Ă��܂����A�c�h�x�X�����Ȃ��A�d�q�H��̎����`���āA�ȒP�ȓd�q�H��̉��������Ă��܂��B �@���̂g�o�ł��Q�l�ɂȂ�K���ł��B ���������p �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�o�C�N�̂ǂ̏ꏊ����d�������邩�v�Ȃǂ́u�C�̖����v�̎�|�E���e�ł͂���܂���̂ŁA�o�C�N�E�Ԃ̎���T�C�g��R�~���j�e�B�Ŏ�������ꂽ�ق��������Ǝv���܂��B �@���܂ł̎ԊW�̂���������ꂽ���̓��e�L���������ɂȂ���킩��Ǝv���܂����A�e�ɕԓ������Ă��������ʂ�Ԃ��Ȃ��l���������܂���ˁB �@���������āA�Ȍ�͎ԁE�o�C�N�W�̂�����͂������肢�������炢�ł��B(���̃R�~���j�e�B�T�C�g�Ƃ�������ł��傤�ɁE�E�E) �@������ɂ͂����ւJ�ȕ�����������Ⴂ�܂�����A�ԁE�o�C�N��̕��S�̂������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��͕̂������Ă��܂��B �@�������ߋ��̗�����Ă���Ƃ��܂�ɂ��u�l�Ɏ��₵�Ă����āE�E�E�v�Ƃ��������������܂��ˁB �@������ԁE�o�C�N�W�ł����₳���������܂�Ɂu�ǂ����̓����Őg����Ȍf���Ɗ��Ⴂ���Ă���H(�l�b�g�Ƃ͂����������Ǝv���Ă���)�v�u������l�ɕ���q�˂��V��m��Ȃ��l����v���Ǝv����悤�ȓ��e�������ꍇ�ɂ́A�Ȍ�ԁE�o�C�N�W�̂�����͈�؎t���Ȃ����Ƃɂ��邩������܂���B �@���āA���������p�l�B���d���ő�p���ݒ��ł����A����J�l�ł��B �@�d�q���i���[�J�[�͗L���ǂ���ő�p�̉�Ђ������ł����A�c�h�x�X�E�p�[�c�X�͔�r�I���Ȃ��̂ł����B(�n��ɂ����Ǝv���܂���) �@����ł��镔�i�����{�Ƃ͈Ⴂ�A�����n��̐��i���قƂ�ǂȂ̂ł��傤�ˁB�t�ɓ��{�ł͎�ɓ���ɂ������A����������������邩������܂���ˁB �@�Ƃ���ŁA���̃����N��ɏ�����Ă���u�f�o�r���̓��`�E���d�r�����ڂ���Ă��܂��̂ŁA���`�E���d�r�� �@�[�d���鎞�ɂ͈��S�̂��߁A���`�E���d�r���[�d�o����@�\���������d�����K�v�ɂȂ鎖��������܂����B�v�Ƃ������e�͊Ԉ���Ă��܂��B �@�g�p����Ă���@���USB�[�q���狋�d���邻���ł����A���Ƃ�����p�\�R������USB�d�����q�����ꍇ�ɂ̓p�\�R���ɂ́u���`�E���C�I���o�b�e���[�̏[�d�@�\�v�Ȃ�ĕt���Ă��܂���A���̃i�r��j�Ă��܂����ƂɂȂ�܂���ˁB �@���݂̌g�ѓd�b���͂��߃��`�E���C�I���[�d�r��������Ă��āA�O�������d���d��(USB������)�ŏ[�d�ł���@��ɂ��@��̒��Ƀ��`�E���C�I���[�d�����H�������Ă��܂��̂ŁA�O���̓d���͎O�[�q���M�����[�^�̂悤�ɒP���ɂT�u�����������H�ŗǂ��̂ł��B �@��̂̃A�i���O����̌g�ѓd�b��AUSB�[�q�̌`�����Ă��Ă����͐�p�[�d�킵���q���ł͂����Ȃ����u(�������Ɩ����ł����c)�Ȃ�ڑ�����d�������̋@��Ŏg�p���Ă���d�r��p�[�d��H�𓋍ڂ����u�[�d���v�łȂ�������܂��A�ėp��AC�A�_�v�^�[��USB�[�q�ł̋��d������@��͊O���ɂ͏[�d��H�͎����܂���B �@�������g���̃i�r���uUSB�[�q�̌`�����Ă���̂ɁA��p�̏[�d�킵���q������_���v�ȋ@��ł���A�ł���u���̂f�o�r�́v�ł͂Ȃ����[�J�[�E�^�ԂL���Ă����Ă��������B �@�łȂ��ƃ��`�E���C�I���o�b�e���[�g�p�@��S�̂��u���`�E���C�I���Ή��̓d���v���g��Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�ȑ傫�Ȍ����^���Ă��܂��܂��B ���Ԏ� 2009/5/5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�Ǘ��l�l�@�����̂��w�E�L���������܂��B �@�u�C�̖����v�Q�O�O�W�N�Q���P���̃��`�E���C�I���[�d�r�̕ۊǕ��@�H�̂��Ԏ��ɁA�����ӎ����Ƃ��ďڍׂɋL�q����Ă��܂����̂ŁA�������`�E���d�r�̏[�d�͋C������K�v������Ƃ̌�������Ă��܂��܂����B�Ȃ��A�@��͂l����(GPS)�R�P�O�ƌg�ѓd�b(PG1900)�̗����ɂɂ���܂��t�r�a�R�l�N�^�[�ɐڑ����ď[�d���Ă��܂��B�{�̑��ɂ͏[�d�����H������͂��ł�����A���w�E�̒ʂ�ł��ˁB �@�g�o����������đՂ��܂��B ���������p �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���L��������܂��B �@��ӌ����Q�l�ɒ��킵�Ă݂܂��B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�|�[�^�u���i�r�Ŏg�p����Ă���̂�MIO�V���[�Y�������悤�ł��ˁB �@�����l�͂ł�����߂��Ƀo�C�N������̏�肢���F�B���A�������������ȒP�ɑ��k�ł���s���t���̃o�C�N�V���b�v���L��(�܂��͎��Ԃ������č��)�Ƃ悢�ł��ˁB ���Ԏ� 2009/5/5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV�̃R�}�[�V�����̑剹�ʂ������ʼn������H�̎������@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�ŋ߂̃e���r�̓R�}�[�V�������ɁA�}�ɑ剹�ʂɂȂ�̂������Ő��䂵�Ă���邻���ł����A�Â��e���r�p�ɊO�t���A���v�ł���ȉ�H�������o���܂���ł��傤���H
�}�[�u�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���������@�\�̂���s�u�������Ă���̂ł����H�A�m��܂���ł����B���s���ł��݂܂���B �@���������@�\�̂��Ƃ��`�f�b�ƌ����܂��BAuro Gain Control�̂��Ƃœ��{��ł́u�������������v�ƌ����܂��B �@������������傫�������肷����͐M�����A�����I�Ɉ��̍œK�ȃ��x���ɑ��������H�ŁA���͐M���������Ŕ��f���đ����x��ς��ďo�͂����ɂ��܂��B �@�����A�X�s�[�J�[�̉����̏ꍇ�́u�����ŏ����ȕ���傫������v����������Ɩ{���͏����ȉ��̂͂��Ȃ̂ɏ���ɑ傫�ȉ��ɂ��Ă��܂��āA�����Ƃ����e���r��W�I�̉����ɂ͕������Ȃ��Ȃ�܂��B �@�ł��̂��`�f�b�̋@�\�̒��ł��u�傫�ȐM���͏���������v�@�\�������g�p�����H������A������u�R���v���b�T�[�v�ƌ����܂��B �@�Â�����A�}�`���A�����̐��E�ł͑��M�p�}�C�N�̃��x�������ȏ�ɏグ�Ȃ��u�}�C�N�R���v���b�T�[�v�Ƃ�����H�����삷��l�������A�u�}�C�N�R���v���b�T�[�v�Ō�������Α�R�̐l�̃��|�[�g��������ł��傤�B �@�ȈՂȉ�H�ł͉������x�����������f����̂ł͂Ȃ��A�P���Ɉ��ȏ�̃��x���ɂȂ�Ȃ��悤�ɓd�����J�b�g���Ă���悤�ȏꓖ����I�ȕ�(�A�����i���͏��Ȃ�)����A�����Ń��x�����m�����đ�������ς���悤�Ȃ������肵�����܂ŗl�X�ł��B �@�悭�g����IC��������TA2011S��(�T����)���ł�����\�ł�����A��������IC�ʼn�H��v����Ă͂������ł��傤���H (���������̓��x���̓}�C�N���x���Ȃ̂ŁA�K���Ƀ��x���_�E�����ē��͂��Ă��K�v�͂���܂�) �@�l�b�g�Œ��ׂĂ݂�ƁA�܂��Ƀ}�[�u���l�̕K�v�Ƃ���Ă���@�\���X�s�[�J�[�쓮��H�܂őS��������LSI��������܂����B �@����(Panasonic)��AN12945N�ŁA�g�ѓd�b��m�[�g�p�\�R���Ȃǂʼn����o�͂����ȏ�̃��x���ɂ͂��Ȃ��X�s�[�J�[�ی�p���`�f�b��H�����̃A���v�̂悤�ł��B �@�����A�@��g�ݍ��ݗp��LSI�ŏH�t���Ȃǂł��ʏ�̔��͂���Ă��Ȃ��ł��傤����A�l�ł̓���͕s�\�ł��ˁB �@�ŋ߂̍��@�\�ȉt���s�u�Ȃǂł͂�����������@�\���̃A���v��X�s�[�J�[�h���C�o�[�����g�p���āA�ق��ɂ��{�̂b�o�t�̃v���O������@�\�Łu�R�}�[�V�����̉�������������v�Ƃ����悤�ȋ@�\�𓋍ڂ��Ă���̂ł��傤���B �@�����l�b�g������ǂ����ɉ�H�}���o�Ă���Ǝv���܂����A�����M���p�̃R���v���b�T�[��H�̓g�����W�X�^��I�y�A���v��g�ݍ��킹�č�邱�Ƃ��������ł��܂��B �@����́u�����\���H�v�Ƃ���������ł��̂Ŏ������@�̂������܂łƂ����Ē����܂����A�o���o���̓d�q�p�[�c���W�߂č��l�I�ȕ��@����A���[�J�[�̍H�ꐶ�Y�Z�p����g������p�`�b�v�܂ŁA�F�X�ȕ��@�Ŏ������ł���Ƃ����������킩�肢��������Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/5/2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�́A�����̎G���Ńr�f�I�f�b�L��TV�̉������d��X�e���I������\������LED�̐M���𗘗p���āA���]�݂̋@�\������������������悤�ȋL��������܂��B �@���̓f�W�^��������������A�f�b�L��TV�ɂ������LED���̂������I���X�N���[���\���ɂȂ����肵�Ă���̂ł��܂茻���I�ł͂Ȃ������m��܂���ˁB�A�i���O����������1�N������ƂŏI�����Ă��܂��܂����B �@�ŋ߂̃f�W�^���Ή�TV���f��Ƃ��̔ԑg�Ɍ������@�\�ł���A�����ʼn������d�M�������m���Ă���̂����m��܂���B�����ɉ������x���Ŕ��f���Ă��邱�Ƃ�����Ƃ͎v���܂����B �O�͉� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�������d�v�������n�܂������ɂ悭�����āA���ł͂����قƂ�ǎg���Ă��Ȃ����@�ł��ˁB �@�����O�ɔ������u�g�r�r�f�I�f�b�L�ɂ��܂��u�b�l�J�b�g�v�@�\���t���Ă��܂����B �@�̂̉������d���n�܂��������̂悤�Ɂu���y�ԑg�����X�e���I�����v�u�C�O�f��͓�������v�Łw�b�l�̓��m���������x����������ɂ͉��y�ԑg��f��͂����Ƃb�l�J�b�g�ł��܂������A���̂悤�ɂb�l�����ʂ̔ԑg���قƂ�ǃX�e���I�����ł͑S���b�l�J�b�g�ł��܂���B �@�B��u�C�O�f��̓�������v�����́u������������^�悷��v�Ƃ����@�\���r�f�I�f�b�L�ɂ���Ύg���܂��ˁB(���R�b�l�̓X�e���I���������̂Ń��m�������m�@�\�����ł͖���) �@�u�b�l�������v�u�ԑg�{�ҕ������v�M���𗬂��Ă���I�Ƃ͗ǂ�����ꂽ���̂ł��i�O�O�G �@���Љ��TA2011S�ŃX�s�[�J�[�p�R���v���b�T�[��H�łł���ł��傤���A�X�s�[�J�[�o�͂��u�X�e���I�v�̏ꍇ�͍��E�̃A���v�ɕʁX�ɃR���v���b�T�[������ƈ��k�������E�ň���Ă��܂��ƃo�����X�������Ȃ�܂��ˁB �@�u�Â��s�u�v�Ƃ������ƂŃ��m�����o�͂Ȃ�悢�̂ł����A�X�e���I�o�͂ŃX�s�[�J�[���X�e���I�Ŗ炻���Ƃ��Ă���̂ł�����A����ς��p�̉�H��v���č��E�ǂ���̃��x���ł����������o���āA���E�����̃`�����l���𐳂������k�ł����H���K�v�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2009/5/8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@����ƃu���b�h�{�[�h�őg�ݗ��Ă܂����B �@��H�͂܂�܁��ł��B http://members.jcom.home.ne.jp/dvc/m-amp/tw141.jpg �@���ʁA�剹�ʃJ�b�g�Ƃ��������A�����ʎ��ɑ������悤�Ƃ��āA�Â��ȃV�[���Łu�T�[�m�C�Y�v���������Ⴂ�܂����B �@�萔�������Ă݂܂��B �@�܂����m�őg�����ł����A�X�e���I���̓������@���v�����܂���B �@�A�h�o�C�X����������Ƃ��肪�����ł��B �@��낵�����肢�v���܂��B �}�[�u�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@5/8�ɏ����܂����悤�ɁATA2011S�̓}�C�N�R���v���b�T�p�ɊJ�����ꂽ�P�`�����l��������HIC�ł�����A�X�e���I�ɂ͑Ή����Ă��܂���B �@�茳�Ɍ����������̂ƁA�f�[�^�V�[�g�ɂ�(������Ɖ�����)�u���b�N�}���ڂ��Ă��邾���ŏڂ���������H�}�������̂ŊȒP�ɂǂ����ǂ�����X�e���I�A�������ł���̂��Ƃ��A�ł��Ȃ��ƒf�����Ă��`�����邱�Ƃ͂ł��܂���B �@���ʂ����o���ă^�C�}�[���삳����ׂ̕��i�͊O���ɂb�q���o�Ă��܂��̂ŁA���̂��������ł��Ȃ����ǂ����Ƃ��ׂĂ݂���Ɨǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���ʂɃX�e���I��H�ō��ƃI�y�A���v���R���p���[�^��牽���ō���āA���x�����߂��P��̔���LED�����Ȃ��璲�߂���Ƃ������܂胆�[�U�[�t�����h���[�ł͖�����H�ɂȂ�܂����A�ʂ̕����g���Ă����ƒ��߂��y�œ���̊m�F���e�Ղȉ�H�E���u�Ƃ����̂����������ōl�Ă��܂����B �@�A���{���Ɏ��p�ɂȂ�̂��ǂ����͌����Ŋm���߂Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂��獡�͌f�ڂ��܂��A����Ɏg�����i���w�����ăe�X�g���ł����(�����Ď��p�ɂȂ��)��H�}�Ȃǂ��f�ڂ������Ǝv���܂��B �@�����茳�ɖ��������g�����߁A���镔�i�ꎮ���w��������Ɨ\��O�̂�����������̂ŁA�����ɍw�����ăe�X�g���邩�ǂ����͖���ł��B�����̂͂��݂ł�����@�������łɃe�X�g������Ƃ��������ł��傤���B �@�������A���p�ɂȂ�Ȃ������ꍇ�͌f�ڂ��������܂���B���̓A�C�f�A�����Ȃ̂ł��܂���҂��Ȃ��ł��������B ���Ԏ� 2009/5/20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
>�Â��ȃV�[���Łu�T�[�m�C�Y�v���������Ⴂ�܂����B �@TA2011S��6P��10��F��47��F�ɑւ�����A�����オ�肪��邭�Ȃ��ăT�[�m�C�Y����J������܂����B �@��ɃX�e���I�őg���PC�X�s�[�J�[�ɋl�ߍ��݂܂����B �@���k�������E�ň���Ă�ł��傤���A����ȂɋC�ɂȂ�܂���(^^) �@�摜UP���܂���|�ʐ^�P|�ʐ^�Q|�ʐ^�R| �A�h�o�C�X�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �������낵�����肢�v���܂��B �}�[�u�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�Ȃ�Ƃ��m�C�Y����J������ĂȂɂ��ł��B �@������͐V�����ʼn�H�����邩�ǂ����̕��i�͍w�����܂������A����ǂ͂��̐�Ɏg�p����VCA���Ȃ��Ȃ�����ł����ɓڍ����Ă��܂��B �@�̂Ȃ�LM3080�Ȃ��ǂ��łł��w���ł����̂ł������ɔp�i��œ��荢��B�T���Č���ƃ��[�J�[���s���i�ł������͂���悤�ł����A�ǂ�������{���̕��i�X�ɂ͒u���Ă��܂���B �@���ɂ͂W�s��IC�ŁAIN-CONTROL-OUT�~2CH�Ɠd��2pin�Ƃ����A�V���v��������̖ړI�ȂǂɍœK�Ȑ�����̂ł����A�����T���v���œ���ł��Ă����ʂɓX���Ŕ����Ă��Ȃ������ʼn�H������Ă��F�����Ȃ��Ƃ����Ӗ��̖������ɂȂ�܂����ˁB �@���i���������ĂƂĂ��ʓ|�ɂȂ�܂����A��͂�I�y�A���v���ŃX�e���IVCA��H�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��傤���B �@�}�C�R�������琧�䂷��u�f�W�^���d�q�{�����[��IC�v�͔����Ă���̂ŁAPIC�}�C�R�����ʼn��ʂ����m���ăR�}�[�V�����ɂȂ�����f�W�^�����䂷��A�Ƃ��������u�Ȃ���{���ŕ��ʂɔ����Ă���p�[�c�ł����ɂł������ł������ł��B �@�����u�������v�ł�PIC�}�C�R���̃v���O��������Ɋւ��Ă͎�t�͈͊O�ɂ��Ă���̂ŁA�����ł��Ԏ��̔��e�ō��Ƃ����킯�ɂ͂䂫�܂���̂ō���̓f�W�^���d�q�{�����[��IC�͍w�����܂���ł����B �@�}�[�u���l�̍��E�Ɨ��̉�H�œ��Ɂu���Ɋ�����v�قǂ̃X�e���I���̑����Ȃǂ����������ł����̂ł����E�E�E�B ���Ԏ� 2009/5/26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ��莞�Ԉȏ�g���K�[���͂��������������[����ON�ɂ����H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂ē��e���܂��B�����d�q��H����������x�̃I���W�ł��B�u�C�̖����v�l�̃y�[�W�͔��ɂ��߂ɂȂ邵���S���邱�Ƃ���ł��B �@����ł����A�T�T�T�^�C�}�[IC�Ȃǂň�莞�ԁi�Q�b�`�T�b�j�ȏ�g���K�[���͂��������������[�����AON�������H����肽����ł��B555�^�C�}�[IC�ɂ�������Ă���킯�ł͂���܂���B�ǂ�ȉ�H���K���������������������肪�����ł��B��낵�����肢���܂��B shou1 �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�悭�u�����[�����n�m�������v�Ƃ�������]������܂����A����Ȃǂ̏ꍇ�� (A) �����ɂ��A�����[��0.01�b���x��ON�ł��ǂ� �̂��A (B) �����[��ON���ĕێ��A�ʓr���Z�b�g�X�C�b�`���������Ȃ̂� �w�肪�����̂ʼn�H�͍��܂���B �@���͒ʂ�P���Ɂu��莞�Ԉȏ�g���K�[���L�����ꍇ�v�f���ă����[��ON���āA���̈��ȏ�̃g���K�[�������Ȃ����烊���[��OFF�ɂ���悤��(A)�̂悤�ȉ�H�̏ꍇ�́A�g���K�[���莞�ԁ{0.01�b�̃g���K�[�M���̏ꍇ�̓����[��ON���Ԃ�0.01�b���ƂȂ�A�����[�Ƃ��Ă͂قƂ�ǖ��Ӗ���ON�ƂȂ邱�Ƃ͗e�Ղɍl�����܂��B �@��莞�Ԉȏ�̃g���K�[�肵�����Ƃ������Ȃ̂ŁA���ۂɃg���K�[�M���̎��Ԃ͕s��ŁA���̂悤��0.01�b���������Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ��L��Ƃ������ł���ˁB �@����ɑ���(b)�̂悤�Ƀg���K�[����������烊���[��ON���Ȃ���ςȂ��ɂȂ�̂ł���A�g���K�[���Ԃ̔�������邾���ōςނ̂ł����A����ǂ͐l�Ԃ������[��OFF�ɂ���X�C�b�`���������Ƃ��A���b�ɂ͏o�Ă��Ȃ���莞�Ԃ̌�Ƀ����[��OFF�ɂ���ʂ̃^�C�}�[��H���K�v�Ƃ��A���������w��������̂ʼn�������ėǂ��̂��킩��Ȃ��̂ł�͂��H�͍��܂���B �@���������ڂ����A���Ɏg�����łǂ������p�@�����鑕�u����肽���̂��A�������肦�܂��H ���Ԏ� 2009/5/2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/3 |
�@���ԓ����肪�Ƃ��������܂������s���Ő\�������܂���ł����B �@�p�r�̓��x��SW�̌x���H�ł����u�U�[���邾���ł��̂ŁA���̃��x���t�߂Ńu�U�[���`���^�����O�݂�����̂ōl���Ă܂��B �P�@���x��SW����̓��͖͂�{�R�`�TV�ł��B �Q�@�����[�͈�莞�Ԉȏ���͂��L�鎞�̂�ON�ƃ��Z�b�gSW�Ń��Z�b�g���闼���l���Ă܂��B �@�X�������肢���܂��B shou1 �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����[�̓�������������Ƃ��A�~����Ȏd�l�ł��ˁB ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���̓J�v���[ �@���͂��u3�`5V�v�ƕs����܂��͕s��̂悤�ł��̂ŁA�t�H�g�J�v��(TLP521-1)�ŃJ�b�v�����O���܂��B �� �^�C�}�[��H �@�g�����W�X�^�Ƃb�q�Ń^�C�}�[��H���쐬���܂��B �@�ҋ@����Tr1(2SC1815)�����삵��C1�͕��d���ꑱ���d���͂ق�0V�ł��B �@�g���K�[���͂�ON�ɂȂ��Tr1��OFF�ɂȂ�AVR1�ER4��ʂ���C1�͏[�d����A���d���܂œd�����オ���Tr2(2SC1815)��ON���܂��B �@�g���K�[�����������Ԃ����m���钲�߂�VR1�Ŗ�P�`�V�b�̊ԂŔC�ӂɐݒ�ł��܂��B �@�ݒ莞�Ԃ܂ł��g���K�[��OFF�ɂȂ�A���̏u�Ԃ�Tr1�ɂ��C1�͕��d����܂��̂ŁA���m�^�C�}�[�̓��Z�b�g����܂����̃g���K�[�M���̗����オ�肩��^�C�}�[�J�E���g���J�n���܂��B �� ���ȕێ���H �@Tr3(2SA1015)�̏o�͂�Tr4(2SC1815)�삳���邱�ƂŁA�o�͂�ON�ɂȂ�����Tr3��ON�ɂȂ���ςȂ��ɂ���t�B�[�h�o�b�N�������Ď��ȕێ����܂��B �@���ȕێ�����SW2���������ƂŎ��ȕێ������Z�b�g�ł��܂��B �@���ASW1�Ŏ��ȕێ��@�\���g�p���邩���Ȃ�����ؑւł���悤�ɂ��Ă��܂����A�ŏ����玩�ȕێ��@�\���s�v�̏ꍇ�͎��ȕێ���H���̂����K�v�͂���܂���B �@�^�C�}�[IC 555���g�p�����Ƀg�����W�X�^�݂̂Őv���܂������A���555�łȂ��ƃ_�����I�Ƃ���������������A���̉�H�ō쐬���邱�Ƃ������߂��܂��B ���Ԏ� 2009/5/5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/17 |
�@�����肪�Ƃ��������܂����B �@��]�ʂ�̓��e�ő�ς��ꂵ���v���܂��B �@���������܂������]�ǂ���ł��܂������܂��� �@�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B shou1 �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC/DC�R���o�[�^��H�̃C���_�N�^��̑I�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���߂܂��āA�d�q��H���S�҂Ȏ҂�DC-DC�R���o�[�^�H�ɂ��ċ����ĉ������B �@����v�����[���̃��C�g��LED�œ_�����������̂ł����A1.5V�œ_��������L�b�g��������܂�������Ń`�������W�������Ǝv���Ă��܂��B �@�F�X�ƒ��ׂĂ��������ɃC���_�N�^�AIC�A�R���f���T�����K�v�Ȃ͉̂���܂������A�C���_�N�^��Ƃ��Ă��d���l��e�ʓ��A��ނ����肷���Ă���Ղ�Ղ�Ȃ�ł��B �@�f�l�Ő\���������܂����������肢�v���܂��B nikku �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�{�y�[�W�́uDC/DC�R���o�[�^ICHT7750�ŗV���v�͊��ɂ��ǂ݂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A����IC�ł��R�C����ς�����ǂ̂悤�ȕω����N����̂��̈��͎����Ă��܂��B �@������HT7750�̃y�[�W�ł��e�X�g�Ɏg�p�����ΐF�̕��Ȃǂ����U��H�p�ŃR�C�����������ׂ���R�l�������ׂɕs�K�ŁA�d���E�d�͗p�ł͂���܂����B �@�d����H�Ŏg�p����Ȃ�^���g���C�_���R�A�^�C�v�̓d�͗p�R�C���A�܂��͉E�̊�ʐ^�Ŏg�p����Ă���悤�ȏ�����H�p�ɐv���ꂽ���^���{�r�������^�̒��R�R�C�����K�v�ł��B �@HT7750�̃y�[�W�ł��Љ�Ă���悤�ɁA�u�����܂Ŕ��FLED��1�`2�_���������H�v�̂悤�ɁA�d�͕ϊ������₻�̑�DC/DC�R���o�[�^�Ƃ��Ă̐��\��˂��l�߂Ȃ��g�r�ł�����̂悤�ȃR�C�����g�p���邱�Ƃ͂ł��܂��B�����܂Łu�l�Ŏg�p���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ����������x��DC/DC�R���o�[�^�̐v���������ɂ����߂ł�����̂ł͂���܂���B �@�����Ɛv������̂ł���ΕK���d���E�d�͗p�̃R�C��(�C���_�N�^)�����g�p���������B �@HT7750�ŗV�ڂ��Ƃ������ɂ͂܂����܂�X���ł͔����Ȃ��������̂ł����A���ł̓`�b�v�^�̏�����H�p�R�C��������������܂��̂悤�ɓ���ł���悤�ɂȂ�܂����B �@ ��Γd���̃l�b�g�ʔ��ł��`�b�v�p���[�C���_�N�^�����ꂭ�炢�̎�ގ�ɓ���܂��B�i�X���ŕ��i�I�߂Ȃ���u���ꂪ����A����R����A����A��������Ȃ��c�v�ƃ��_���𐂂炵�Ă��܂������ł����j �@���A�e��(H:�w�����[)�͂��g�p�ɂȂ�DC/DC�R���o�[�^IC���f�[�^�V�[�g�Ŏw�肳��Ă�����̂����g�p���������B �@�܂��f�[�^�V�[�g�̎Q�l��H�}�ɍڂ��Ă���e�ʂƁA���ۂɑg�ݗ��Ă��ꍇ�̍œK�e�ʂ��قȂ�ꍇ�������̂ŁA���̂ւ��DC/DC�R���o�[�^�̐v�����ň���̖{��������قǂł��̂ł����ł͊��������Ă��������܂��B(���X�ɍs���Ύ��ۂ�DC/DC�R���o�[�^�̐v�̖{����R�o�Ă��܂�) �@������H�}�ł��ϊ�������D�悷�邩�E�������\��D�悷�邩�A�܂����U���g����t���R���f���T�ŕύX�ł���悤�ȉ�H�ł͗e�ʂ�ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��x�����͌����ł��ˁB �@�d���e�ʂ͏o�͓d���̒l�ł͂Ȃ��A�[�d���̓˓��d���̒l�����イ�Ԃ�ɋ��e����d���l�̃R�C�����g�p���邱�Ƃ��]�܂����ł��B �@�R�C���̒�R�l��X�C�b�`���O�f�q(FET�Ȃ�)��ON��R�A�����ēd���d����X�C�b�`���O���g���Ȃǂ���K�v�Ȓl�͌v�Z����܂��B �@�v�Z�ł��Ȃ��ꍇ�͏o�͓d���̐��{�̗e�ʂ����R�C�����g���Ă����Εs��͏��Ȃ��ł��傤�B �@�{�E�Ŏd���Őv������̂łȂ���A�����܂ő�G�c�œK���ȃR�C�����g���Ă��Ă���H�͓���͂���Ǝv���܂��̂ŁA�ꉞ�̓f�[�^�V�[�g�Ɏ����ꂽ�T���v����H�ƕ��i�̒萔������đg�ݗ��Ă�Ηǂ��Ǝv���܂��B ���Ԏ� 2009/4/25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ȈՃn�C���[�R���o�[�^�̐��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�������\�Z�Ŏ��삵�ĎԂŃJ�Z�b�g�������I �@�͂��߂܂��āA�Ƃ�����ł��B �@�r�o�o�͒[�q�����Ȃ��J�Z�b�g�E�f�b�L���k�h�m�d�ڑ�������@�ׂĂ����n�C/���[ �R���o�[�^�[�Ȃ���̂��g�p��������Ƃ������Ƃ��킩�����̂ł����A���鐻�i�̒��g�̎ʐ^�ł́A���i�������Ȃ����h�ȃP�[�X�������Έ�������ł������Ɍ����܂��i��H�}������̘b�ł����j�B �@���ɍ������̂������ȃg�����X�H�ł��B�Ƃ肠���������ڂ��������̂�T���Ă݂͂����݂̂̂��炸�A��ނ������K�i�����܂��܂Œm���̂Ȃ����ɑI���ł�����̂ł͂���܂���ł����B���i�̃J�^���O�l�͓��̓C���s�[�_���X�F4���`8���A�o�̓C���s�[�_���X�F10k���A�ő���́F20W�~2�A���͓d���F0�`30V�A�o�͓d���F0�`15V�A���͊��x�F0dB�ƂȂ��Ă���܂��B �@������x�̎��s����͊o�債�Ă���܂��B�ǂ������͓Y������������H�}�╔�i�̑I��ɂ��ċ����Ă��������B��낵�����肢�������܂��B �Ƃ����� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��g�����X�͌����ڂœ������������Ă��A�`�E�F�E�傫���������Œ��g���Ⴄ�����R�قǍ���Ă��܂������ՓI�ɋ��R�����������o���Ȃ��Ƃ��܂��䂩�Ȃ��ł��傤�B �@�u�n�C/���[�R���o�[�^�v�����ꂽ���Ƃ������ł����A�n�C/���[�R���o�[�^�̓X�s�[�J�[���̍����d���̉����o�͂��烉�C�����x���̒Ⴂ�d����(���Ԃ�̈��)���Ƃ����ƁA�X�s�[�J�[�[�q���������̃g�����X�����ŐV�̂a�s�k�ڑ��̂悤�ɂ��̂܂܃O�����h���ʂł͐M�������o���ɂ����ꍇ�A���ƃI�[�f�B�I�̐��E�Ō�����u�O�����h���[�v�v�ł̃m�C�Y�����ׂ́u�A�C�\���[�^�v(�≏��)�Ƃ��Ďg�p����镨�ł��B �@�����݂̓J���^���ŁA�≏���g�����X�ŐM����≏���Ă��邾���ł��B �@���x���ϊ�(������)���{�����[���������邾���ł��B(�{�����[���{�Œ��R�̉�H�ł������ł�) �@�Ѓ`�����l���Ԃ�̈��H(���})�ň������Ε��i���500�~���炢�łł��܂��B�����P�[�X���̂ق��������������H �� �Ō�ɁA�������i����lj����܂���
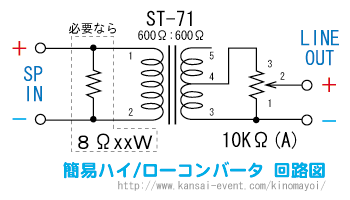 �@�T���X�C���̂͊��ɓP�ނ��Ă��āA���ł͌���p�������{�d�C�̃g�����X��A�u�݊��i�v���e�Ђ���o�Ă��܂��B(300�`500�~��) �@ST-71�͏o�͑��Ɂu�Z���^�[�^�b�v�v(���ԓ_)���o�Ă��܂��̂ł�������o�͂����A�܂����̒i�K�œ��͐M���̔����̓d���ɂ��܂��B �@���̌��10K���̃{�����[���ŏo�͂����R�ɒ��߂ł���悤�ɂ��܂��B �@���āA���͑��ɂ��Ă���u�K�v�Ȃ��v�Ə����ꂽ�W���̒�R�ł����A���ʂɃX�s�[�J�[�[�q����M�������炤�̂ł�����̂W���͐�ɕK�v�Ƃ������̂ł͂���܂���B �@�g�����X�̈ꎟ���A���̓C���s�[�_���X��600���̉�H�ɂ��イ�Ԃ�ȓd���͗����̂Ő����������M���͎��܂��B�قƂ�ǂ̃A���v�̓X�s�[�J�[�̂�����600�����x�̕��ׂ��q���ł��Y��ȉ����M�������o���܂��B �@�����A�w���ɍS��l�x�����̐��i�ł́u�X�s�[�J�[���ڑ�����Ă����ԂƓ�����Ԃ����A�A���v�o�͂��X�s�[�J�[��炵�Ă��鎞�Ɠ����s���A�ȉ����M�����o�͂ł���悤�ɂ��A���Č��������߂Ă��܂��B�v�ȂǂƂ������R�ł��̂悤�ɃX�s�[�J�[�̑���ɂȂ��R�����Ă��镨������悤�ł��B �@�����w���ɍS��l�x�ł���A�X�s�[�J�[�o�͂̃A���v�̃��b�g���~�Q�{�̃��b�g���̂W���̃Z�����g��R�Ȃǂ�t���Ă��������B���b�g�����傫���Ƃ��Ȃ�T�C�Y���傫���Ȃ�܂����A���̃{�����[�����グ�Ă���Ɣ��M�����܂��B (�������̃{�����[���͂��܂�グ�Ȃ��Ŏg���ł��傤����A�{���̓��b�g���͏������Ă������ł����c) �� 8�����x�̒�R�͔����Ă��Ȃ��̂Ŏ��ۂ�8.2���ł�
�@�X�s�[�J�[�o�͂������ɂ���ꍇ�͂��̉�H�ŏo�͗p�{�����[�����E�����ς��ɉĂ����ƁA�o�͓d���͓��͓d���̖����x�ɂȂ茳�̉����̃{�����[���������`�������炢�Ő��������C���M���d�����炢�ɂȂ�̂ŃJ�[�I�[�f�B�I���ł͓K���ŕ�����͂��ł��B �@�|�[�^�u��mp3�v���[���[��g�ѓd�b�Ȃǂ́u�C���z����p�@��v�̃C���z���E�w�b�h�t�H���[�q����M����Ⴄ�ꍇ�͌�����̓d�����Ⴂ�̂ŁAST-71�̓��̓Z���^�[�^�b�v�ł͂Ȃ��[�̒[�q(5��)����o�͂��Ȃ��ƃ��x���s���ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�����ŏ�����Z���^�[�^�b�v�����炸�ɒ[(5��)�������Ă����Ă�10K���̃{�����[���ʼn��ʒ��߂ł��܂����炻�̂悤�ɍ���Ă����\�ł��B �@����]�̕������͓d���Əo�͓d���̔䂪2:1�̂悤�ł����̂ŃZ���^�[�^�b�v���g����H�Ŏ����Ă��܂��B �@�o�͂��S�Ԃ����邩�T�Ԃ����邩�̐ؑփX�C�b�`�����Ă����Ɓu�n�C���x���o�́E���[���x���o�֑͂̐ؑΉ��I�v�݂����Ȑ�`���傪������A������Ƒ��А��i��萫�\�̗ǂ������@�����o�ł����肵�܂�(��) �@���\�`���S�v�Ƃ����X�s�[�J�[�o�͂Ɍq���悤�Ȃ��Ƃ͖����Ǝv���܂����A��o�̓A���v�Ɍq�����悤�ȏꍇ�̓g�����X�̈ꎟ���ƒ���ɐ��S���̒�R�����ăg�����X��ی삳�ꂽ�ق���������������܂���B �@���̂�����͎g����@��ɉ����Ă��D�݂̉�H�Ɏd�グ�Ă��������B ���Ԏ� 2009/4/24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�Ƃ�����ł��B����Ȃɑ��������������{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B����Ă������e�Ŋ����ł��B �@���̍ہA���o�����k�h�m�d�o�͂Ńi�V���Z�~��LM3915���g�����k�d�c���x�����[�^�[������Ă݂悤���Ȃǂƃ��N���N���Ă��܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �Ƃ����� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@LM3915�̃��x�����[�^�[�͖ʔ����ł��ˁB �@����Ȃ�ł͂֗̕��Ŗʔ������u���o����Ɨǂ��ł��ˁB ���Ԏ� 2009/4/25
[�lj���� 2012/1/5] �@ �@2012�N�ɂ��Љ�Ă����C�O�ʔ̏��i�́A���ݏI���ƂȂ�w���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B 2018�N�E�Č��݂͈ȉ��̏��i�Ȃǂ��̔�����Ă��܂��B  [�lj���� 2018/7/22]
[�lj���� 2018/7/22]�@DX(�����̒ʔ�)�ʼnE�̎ʐ^�́u12V Universal RCA Line Car Stero Radio Converter Speaker High To Low Vehicle Amplifier Audio Impedance Converter Car DIY Multi�v��������US$ 1.73(�������ݖ�195�~)�ł��B �� �l�i��2018/7/22��
�\�����i�ƈבփ��[�g �@�X�e���I�Ԃ�Q��H�����Ă��āA�g�����X�Ƃ������W�߂Ď��삷��������E�E�E�B  [�lj���� 2018/7/22]
[�lj���� 2018/7/22]�@DX(�����̒ʔ�)�ʼnE�̎ʐ^�́uCar Speaker To RCA Level Adaptor High To Low Sockets Auto Line Out Audio Converter Sound Subwoofer Amplifier Adjustable Dark Grey�v��������US$ 2.59(�������ݖ�291�~)�ł��B �� �l�i��2018/7/22��
�\�����i�ƈבփ��[�g �@�X�e���I�Ԃ�Q��H�����Ă��āA�g�����X�Ƃ������W�߂Ď��삷��������E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�P��I�ȋM�Z�̒m���[�֊����Ɍh�ӂ������A���̉��b�ɂ�������Q�l�ɂ����đՂ��Ă���܂���l�ł��B �@�s�^�ł������A���C�����X�}�E�X�����p���Ă���A�g��������悭�d�Ă���܂����A�B���ʃX�N���[�����߂̃��[�^���[�G���R�_�[�������@�B���ړ_�ŁA�悭���Ղ�����s�ǂɂȂ�A���x���ڐA�����肵�ĉ������Ă܂���܂��������Ղɂ������������Ă���܂��B �@���̕�����ėp��IC�̋�`�g���M�@�ƃ����[�ȂǂŒu�������邱�Ƃ͏o���Ȃ��ł��傤���B�ܘ_�ǂ�ȉ�H�ł����\�Ȃ̂ł������S�҂Ȃ̂ŊȒP�ȉ�H�ɉz�������Ƃ͖����Ƌ𗶒v���Ă���܂��B �@���Z�����Ƃ��닰�k�ł����������Ղ���K�r�ɑ����܂��B�ǂ��āA���Q�l�ɂ͂Ȃ疳�������m��܂��A�}�E�X��MPL�Ƃ�����А��炵��MPL-8040�ƂȂ��Ă���A������PAN201,BSI-20,33H2500LC�Ə�����IC���P������Ă���܂��B ��E���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�^���[�G���R�[�_�������uIC���U��H�v�Ȃǂɒu�����������A�Ƃ������e�ł����A�R���R���Ǝw�ʼnz�C�[�������āA�Q�̉����{�^���X�C�b�`�Łu��v�u���v�݂����ɂ��̃{�^�����������甭�U�M���ŃX�N���[��������悤�ȉ�H�ł�낵���̂ł����H �@�}�E�X�̒��ɑg�ݍ���ł��܂��ƂȂ�ƁA�ėp�̃��W�b�NIC���g�p�����悤�ȕ��ł������^�̃t���b�g�p�b�P�[�WIC���g�p���čH�삵�Ȃ��Ɠ���Ȃ��Ǝv���܂��B �@�}�E�X�̒��ɂ���炪����]�T����������̂ł����B �@�܂��͏�L�́u�����{�^�����v�ɉ������ꂽ���̂��A����ȊO�̈Ӑ}�Ȃ̂������������������B �@���������p�r�Ń��[�^���G���R�[�_�p�́u�ʑ����M���v��������IC���͂���܂���̂ŁA�ėp���W�b�NIC���ʼn�H���\�����邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B(�Ȃ̂Ń}�E�X�̒��ɓ��邩�͔����c) �@������E����l��PIC�̃v���O�������쐬�ł���Z�p�Ɛݔ����������ł�����A�W�s����PIC��ōςޘb�Ȃ̂ł����E�E�E�B �@�H�t�����Ő��S�~�Ŕ����Ă���}�E�X(�K���t���ł��Ȃ�ł�)�̒�������w���̃G���R�[�_�[���g�����z�C�[���̕���T���āA�z�C�[���܂����ڐA����Ƃ����Ď�͂��߂ł����H �@�����̓v���X�`�b�N�̉��H��^�Z�p�͗v��܂����B ���Ԏ� 2009/4/22
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�O���A�}�E�X�̋@�B���z�C�[���̉����̌��A���������̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@�����ł���2�̉����tSW�̍\���Ō��\�ł��B �@����PIC�ɑ�ϋ����͎����Ă���̂ł������݃v���O�����̋Z�p������܂���B �@�Ō�Ɍ��w���G���R�_�[�̃}�E�X�͍w�����Ă݂��̂ł����A�莝���̃}�E�X�̖��̈ړ��ʒn�̌��o�i���w���j�Ƌ@�B���G���R�_�[��ON,OFF�M���̓��͂Ƃ����̖����o�͂�1����IC�Ŏ����Ă��܂��̂ŁA�G���R�[�_�[���͕������ǂ̈ʂ̃��x���̐M�������e�͈͂Ȃ̂��悭���炸�A���Ƃ��Ɠ��͂��@�B���G���R�[�_�[��ON,OFF�M���������̂ŁA��`�g���M�@�ƃ����[���Œu�������]�X�Ɛ\���グ������ł��B�ł�����@�B���G���R�_�[������������z�C���ւ̂������͂���܂���B����PIC�͔����Ēʂ�Ȃ���˂Ȃ̂ŁA�����\�Ȃ�PIC�̉�H�����L���Ă���������Α�ς�������ł��B�܂��͎��}�����Ԏ��܂ŁA���X�B ��E���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�@�B���́u�����[�v�͑S���g������͂���܂���A�K�����̃}�E�X�� �� �d���d�� �� �@�B���G���R�[�_�[�̌q�����Ă�����͒[�q�̓��̓��x�� �� �G���R�[�_�[�̏o�͌`��(�ʑ����H) �͂��m�点�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@���Ƃ�PIC�ō��ɂ��Ă��A����IC�̓��͂ɐ������ڑ��ł��邩�A�܂����������삳�����邩�͂��ꂹ�̏�����Ɗm��ł��܂���B �@�����[���g���āA�{�^���������ăX�N���[�������Ă���Ԃ��イ�A�����̒��Ɂu�u�[�v�Ƃ��u�K�[�v�Ƃ��̃����[�̔��U���쉹�������n���Ă���������e����A�}�E�X�̒��ɓ���قǏ����ȃ����[���Q�������ł��炻����g���Ƃ��������ōl���Ă�������������܂���B �@�܂��A�@�B���G���R�[�_�[�͂����ƈʑ������͌^�ʼn�]���������m���Ă���̂��A�܂������]�Ƌt�]�Ńp���X���o���ړ_�̂悤�Ȃ��̂ł͖����̂������ׂĂ��������������B �@�u��`�g���U�v�Ə�����Ă���̂����ɋC�ɂȂ�܂��B �@�ʏ�̃��[�^���G���R�[�_�͂Q�r�b�g�̈ʑ����M���ʼn�]���Ɖ�]���������m���܂��B�ł������ɏ������悤�ɒP���ɔ��U��H�����`�g������Δ�������悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B �@�܂����A�{���ɂ܂����ł����A���]�Ƌt�]�̂��ꂼ��ɓ��͂��P�r�b�g����A���]�̎��ɂ͐��]���͒[�q�Ƀp���X������ƂP�p���X�P��Ɛ����ăX�N���[��������悤�ȉ�H���g���Ă���}�E�X�Ȃ̂ł����H �@�����l���Ă���͕̂��ʂɈʑ������͂̏ꍇ�ɂ��Ăł��B�ł������������Ⴄ�Ɖ�H��v���Ă��S���g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂��B �@���������ɐi�ޑO�ɂ͕K�����̓_�ɂ��Ă����ׂĂ��������������B �@����ƁA�@�B�ړ_��ON/OFF����͂��Ă���̂ő����v���A�b�v���v���_�E����R���t���Ă���Ǝv���܂����A���̒�R�̓v���A�b�v�Ȃ̂��v���_�E���Ȃ̂������ׂĉ������B�����v���A�b�v�܂��̓v���_�E����R���t���Ă��Ȃ��̂ł�����A�}�E�XIC�̓����Ńv���A�b�v���v���_�E������Ă���Ǝv���܂��̂ŁA�ړ_���J������Ă��鎞�ɂ͂ǂ���̃��x���ɂȂ��Ă��邩�����ׂĂ��������B������̔��Α��̓d�ʂɐړ_���q�����Ă���Ǝv���܂����A������m�F���Ă��������B �@��{�I�ɂ����w���ʑ����Z���T�[���t���Ă���z�C�[���́A���̂܂܋@�B���̈ʑ����ړ_�̃z�C�[���ƌ����ł��܂��I �@�@�B�ړ_�ƈ���ăt�H�g�g�����W�X�^�ɋɐ�������܂�����A�ǂ���̒[�q���ǂ��q���̂����v���A�b�v�^�v���_�E����Ԃ�IC�̓��̓|�[�g�̓����ׂȂ���Ȃ�܂���B �@�lj���H�I�ɂ̓t�H�g�C���^���v�^�삳����ׂ�LED�̓d����^�����R���K�v�ɂȂ邭�炢�ł��B �@����ƁA��{�I�Ȏ��ł����m�F���Ă��������Ǝv���܂��B�lj���H�̓}�E�X�̒��ɑS�������Ă��܂��T�C�Y�ō����̂ł���ˁH �@���C�����X�}�E�X�Ȃ̂ŊO���Ɋ��u���ăP�[�u���Ōq�����Ă���Ƃ��A���C�����X�}�E�X�̗������Q���Ă܂ŊO���ɉ�H��u���悤�Ȏg�����͍l�����Ă͂��܂����ˁH ���Ԏ� 2009/4/23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�x�X�\������܂���A�d���d���̓G�l���[�v2�{��2.4V�ł��B�G���R�[�_�[�̌q�����Ă�����͒[�q����͐ړ_�J������1.56V���o�Ă��܂����i����10M���Ƃ������Ă��܂������A�e�X�^�[�ł̌v���ł��H�j�B�ܘ_�ړ_�Z������0V�ł��B �@�܂��G���R�[�_�[�̏o�͔g�`�i�ʑ����j�͋ߎ��I��90���i���i�x���j�̂悤�ł��i�ړ_�̃u���V�l�����̈ʒu�W�W����̐����j�B �@�����[�͌��݂̃G���R�[�_�[�ړ_�ƑS��������ON,OFF������Ƃ����P���Ȕ��z����ł����A���w�E�̒ʂ胊���[�͘_�O���Ǝv���܂��B �@�G���R�[�_�[�͑O�q�v���܂����悤�ȗ��R�ňʑ����^�Ǝv���܂��B �@��`�g�]�X�Ɛ\���グ�܂����̂͋@�B�I�ړ_�ł��邱�Ƃ���A�P���Ɉʑ��̂��ꂽ��̋�`�g�ƌ����Ӗ��ł��i�㑫�炸�Ŏ��炵�܂����j�B �@IC���܂߂ĉ�H���[���������Ă��܂��A�P���Ɉʑ����Ő��]�t�]��F�����Ă���悤�ł��B �@�v���A�b�v�i�_�E���j�́A�ړ_�J�����d�����o�܂��̂Ńv���A�b�v����Ă���悤�ł��B�������v���A�b�v��R��IC�����ɂ������Ă��Ȃ��̂ł͂Ǝv���܂��B����́A����z�C���̉�]�ʒu�i���]�t�]�̐ړ_�����ɊJ����ԂɂȂ�ʒu�H�Ǝv���̂ł����j�Ń}�E�X�|�C���^�[���������Ďg���h���̂ŁA�G���R�[�_�[�̐ړ_�ƃO�����h�Ԃ�100K��������Ƒ������肷�邩��ł��B�܂��A�i�e�X�^�[�łł����j�ړ_�I�[�v�������͑������ɍ���R�l�ł��B �@�����A�O�t���H�̌��́A�t����H�͓�����O��ōl���Ă���܂��B �@�F�X���ς킹�v���܂�������ɋ��k�ł����A���e�����̔\�͂��Ă���悤�Ɋ������܂��̂ŁA�t�H�g�C���^�[���v�^�ƃz�C���̉�H�\���ōēx�����S�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B����ł܂��s���l�܂����Ƃ��ɂ͍ēx��������������l���肢�v���܂��B �@����܂ő���Ȏ��ʂ�������������A�����J�Ȃ��Ή����肪�Ƃ��������܂����B�m���s���ő�ώ���v���܂����B ��E���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����A���w���̃z�C�[�����i�ƌ����ł���̂ł�����ꂾ���ʼn�������Ǝv���܂��B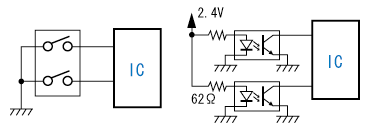 �@���́u�s����ɂȂ�v�Ƃ����Ǐ�̎��A�Ȃ�GND�Ƃ̊Ԃ�100K������̂��킩��܂���B���ʂ̓v���A�b�v���Ă��ׂɓd���{�Ƃ̊Ԃɐ��\�`100K���x��������̂��Ǝv���܂��B�����t�H�g�C���^���v�^�Ɍ������ĕs����ł���ΕK���d���{�Ƃ̊Ԃɒ�R�����ĉ������B �@���W�b�NIC�őg�ނƑ���IC��3�`4���x�ɂȂ�A��R��R���f���T���܂߂�ƃt���b�g�p�b�P�[�W�ł�IC���g�p�����Ƃ��Ă��ɏ���ŕ\�ʎ����Z�p����g���č��Ȃ��Ƒ����}�E�X�̒��ɂ͓���Ȃ��Ǝv���܂��B �@����͑�������Ƒg�ݍ��݂͖����Ƃ������ŁA��H�}�͒��Ȃ��܂܂ɂ��Ă����܂��B 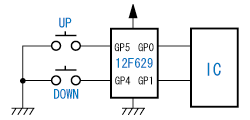 �@UP/DOWN�{�^�������ɉ�������Ƃ��āAPIC���g�����ꂾ���̉�H�ōς݂܂��B
�@UP/DOWN�{�^�������ɉ�������Ƃ��āAPIC���g�����ꂾ���̉�H�ōς݂܂��B�@�X�C�b�`�̃v���A�b�v�͂������PIC�̃|�[�g���ɂ��̋@�\������܂�����O���ɒ�R�͕K�v����܂���B �@���̒��x�ł����DIP�p�b�P�[�W�̂W�s��PIC���}�E�X�̒��ɓ���邭�炢�̌��Ԃ͂���ł��傤�B �@PIC���Œ�2V���瓮��͂��܂��̂ŁA�d�r������܂Ő���ɓ��삷��͂��ł��B �@���̂����ɁA�v���O�����̊J���Z�p���g�ɂ����炱�����������ɂ��`�������W���Ă݂�Ɨǂ��ł��傤�B���W�b�NIC����IC���R�g��Ȃ���Ȃ�Ȃ���H��PIC���ƃ}�C�R��IC��ōςޏꍇ�������ł��B ���Ԏ� 2009/4/24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 4/25 |
�@�O���A��̓I�ȃA�h�o�C�X���肪�Ƃ��������܂����A����̓t�H�g�C���^�[���v�^�[�ƃX���b�g�t���z�C���Ŏ������悤�Ǝv���܂��B �@�ł����A���ɋ߂������A�ꕔ���ՓI�ړI��IC�ȊO�̃f�W�^��IC��PIC�ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɏv���܂��̂ŁA�v���O�����̊J���Z�p�ɂ͒��킹���ɂ͍ς܂���Ȃ��Ǝv���܂��B��ς����b�ɂȂ�܂����A����Ƃ���낵�����肢�v���܂��B���X�B ��E���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V��12V(13.8V)�̃R���o�[�^�����9V�`12V�ɂł��܂����H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�F�l����_���v�p�̓���24V�@�o��12V(13.8V)10A��DC/DC�X�C�b�`���O��H�����R���o�[�^������܂����B �@�����B�O�o���Ɏg�p����|�[�^�u�������@�̊O���~�d�r�d���ቺ���p�ɂ�������9V�`12V�@�o��13.8V5A���x�ɉ����������̂ł����ł���ł��傤���B �@���̂悤�ȃ^�C�v�̋@��͎͐̂s�̂���Ă��܂��������͍�邵���Ȃ��悤�ł��B�ꂩ��������������ق����ȒP�ɑ̍ق悭�Ȃ�̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B���_�A�֘A�L������������������ ���K�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����Ɓ����K�Ƃƌ����āA�̂���@��ɖ��ʂȂ������������ɂ��܂�(����)�ړI��B������B�l�ƌ���ꂽ���̂ł��B �@����́u�X�C�b�`���O�����v�Ƃ킩���Ă��܂��̂ŁA�����ł���\���̂��镨�Ƃ��Ęb��i�߂܂��B �@�u24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂����v�ŏo�Ă����悤�ȃV���[�Y���M�����[�^��H�ɂ��~���d���ł͂���ȉ����͂ł��܂���̂ŔO�̂��߁B �@���āADC/DC�R���o�[�^�́u�����̓d������A�����̓d���ɕϊ����镨�v�ł����A�u������H�v�Ɓu�~����H�v�ł����g���S���Ⴂ�܂��B �@�u���ĈقȂ镨�v�ƌ������ق����������̂ł����A�l�����Ƃ��Ắu�Ⴄ���v�Ƃ��Ă������ق����ǂ��ł��傤�B �@�������������i�̑��u�������āA������u�~���������ɉ����v��u�������~���ɉ����v�͒��̊�����āw���i�����p�ł��邱���x���킩��Ή\�ł��B �@�t�Ɍ������S�������\�����镔�i�����p�ł��Ȃ���A�ꕔ�̕��i�����o���đS���ꂩ�����H�ɗ��p�ł��邩�ȁE�E�E���x�ł��B �@�������u���K�v�ƌ����Ă����S�ɂO�~�ł͂Ȃ��A������x�͕��i���Ă��Č�����lj�����K�v������Ƃ͎v���܂��B����ł��V�i�d�����u�����͂����ƈ����ς݂܂��ˁB �@�ȒP�Ɂu���Ƀq�~�c�̃X�C�b�`�������Đ�ւ����珸���ƍ~������ւ��v�Ƃ��u���̓d���ݒ�p�{�����[��������A�����ɂ��~���ɂ��ǂ���ɂ��Ȃ�v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B(�n�i���炱��ȏ��S�ғI�ȗ��z�͕����Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A�ق��̓ǎ҂̕��ׂ̈Ɉꉞ�����Ă����܂�) �@���l�i�͂���Ȃ�ɂ��܂����A�T���u���~���^�C�v�v�Ƃ������͓d���������Ă��Ⴍ�Ă��ړI�̓d�������o����d����H�E���u�͂���܂����A����̕��͂��������֗��ȕ��ł͖��������ł��ˁB �@���̕��i�����p�ł��邩�ǂ����ł����A�X�C�b�`���O����DC/DC�R���o�[�^�ł͎�ȕ��i�� �� DC/DC�R���o�[�^����pIC �� �p���[�g�����W�X�^�A�܂��̓p���[�e�d�s�@(IC�ɓ����̏ꍇ������) �� �R�C�� �� �V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h �� �d���R���f���T �� ���d���ɂ���ׂ̃t�B�[�h�o�b�N��H������R �ł��ˁB �@�X�C�b�`���O�����̏�����H�ƍ~����H�̊�b�͎��̒ʂ�ł��B 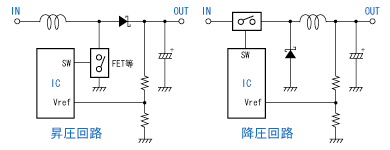 �@�ł��d�v�Ȃ̂́w����pIC�͏���/�~�������̉�H�Ɏg����IC���H�x�ł���A���ꂪ�g���Ȃ��Ƃ��������u�����v�Ƃ������x���ł͂��݂܂���B �@����/�~���̂ǂ���̉�H���v�ł���IC�Ȃ�A�f�[�^�V�[�g�����ēd���d���͈͂���ӂ̉�H�̏ڍׂׂĖړI�̉�H�}��v���܂��B �@��̊�b��H�}�ɂ͂���܂��AIC���ɔ��U���g�������߂�ׂ̃R���f���T��A�ق��ɂ��t�����i���K�v�ȕ��ł͂����̃p�[�c�������ƍ~���̏ꍇ�ł͈Ⴄ�����g�p����ꍇ������Ǝv���܂��B�f�[�^�V�[�g���悭���Đv���Ă��������B �@�p���[�g�����W�X�^��p���[FET�������p�ł���Ηǂ��̂ł����A������H�̏ꍇ�ƍ~����H�̏ꍇ��NPN��PNP���Ⴄ�Ȃǂł��̂܂ܗ��p�ł��Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA�悭IC�w��̎Q�l��H�}�����ă`�F�b�N���܂��B �@�R�C����V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h���͂قƂ�ǂ��̂܂ܗ��p�ł���ł��傤���A�d���e�ʂȂǂ��Ή����Ă���̂��͊e���i�̒��ɓ����Ă��镨�ɂ��Ⴄ�ł��傤���畔�i�̒�i�ׂĂ���g�����A�g���Ă݂āu�������߂��`�v�ƂȂ邩�E�E�E �@�{���ɕϊ������̗ǂ�DC/DC�R���o�[�^�삷��Ȃ�S�Ă̕��i���ᖡ���ėǂ�����I�Ȃ���Ȃ�܂��A���ɂ��镨���������ė��p����̂ł���Ό�����t���Ă��镔�i�̐��\��������H���K�v�Ƃ���X�y�b�N�����Ă��邩�ǂ����Ŋ�����̐��\�͑傫���ς�ł��傤�B �@�����܂Łu���K�v�ړI�ł���A�����̐��\�̈����͐܍��ς݂ł���ˁi�O�O�G �@DC�R���o�[�^�̉����L���́w100�~�V�K�[���C�^�[�\�P�b�g�pDC-DC�_�E���R���o�[�^���A�b�v�R���o�[�^�ɉ������悤�I�x�ɂ���܂��̂ł����������B(����A��ɓǂ܂�Ă��܂���ˁc) ���Ԏ� 2009/4/20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �d�C��H�̖�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�d�C��H�i�ċN���h�~��H�j�̖�肪�킩��Ȃ������Ă��������Ȃ��ł��傤���H �@���肢���܂��B �@���́@�{�^���uA�v�ƃ{�^���uB�v���������烊���[�uCR1�v��ON����B*�������A�uA�v�܂��́uB�v���K������OFF�����m�F����ꂽ�ꍇ�̂݁A�uCR1�v��ON���邱�ƁB �@�ł��B���Ȃ�l�����̂ł����킩��܂���B��Ⴂ��������܂���낵�����肢���܂��B ���S�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�w�Z�̓d�C��H�̉ۑ肾�Ǝv���܂��̂ŁA�Y�o����H�}�����̂ł͂Ȃ��u�l�����Ƙ_���v��������܂��B �@���̖��̏ꍇ�A�v�_�͂Q�ɕ������܂��B [�v�_�P] �@�����̃X�C�b�`��ON�Ń����[��ON����B(�����ł͖����A��������) [�v�_�Q] �@�����̃X�C�b�`��OFF(���������m�F)�Ń����[��ON����B �@���̏ꍇ�A���͏d�v�Ȃ̂�[�v�_�Q]�̂ق��Ȃ̂ł��B �@[�v�_�P]�����������ꍇ�ɂ́u�܂��v�����[��ON�ɂ��Ȃ��̂ł���ˁH �@�Ȃ̂Łu[�v�_�Q]�������������_��[�v�_�P]�̏�������ɐ������Ă��邩���f�����v�Ƃ����_����H���K�v�ł���A��������̂����̖��̉��ł��B �@���̉�����[�v�_�R]�Ƃ��܂��B �@�Ƃ���� [�v�_�P]�́A�X�C�b�`�P AND �X�C�b�`�Q �� �p�P (�A�����ȕێ���H) [�v�_�Q]�́ANOT�i�X�C�b�`�P OR �X�C�b�`�Q�j �� �p�Q [�v�_�R]�́A�p�P AND �p�Q �� �p�R (�A�����ȕێ���H) �Ƃ����_�����ɂȂ�A�������H�}�ɂ���Ζ��̉ƂȂ�܂��B �� [�v�_�P]�ɂ��Ă͖��ł́uA�EB�ʁX�ɉ����Ă��ǂ��v�Ƃ͏����Ă��Ȃ��̂ŁA�uA��B�͓����ɉ����Ə��������v�Ɖ��߂��܂��B �@[�v�_�R]�̏o�͎͂��ȕێ���H�Ƃ��邱�ƂŁA��x�S�Ă̏���������������̏o�͂ɐڑ����ꂽ�����[(CR1)��ON�����ςȂ��ƂȂ�A�ēx�����ꂩ�̃{�^����������Ă�OFF�ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���B �@���ł́u���Z�b�g�v�̊T�O��u�ǂ������OFF�ɂł���̂��H�v�ɂ��đS���G����Ă��܂���̂ŁA�e���ȕێ���H�͓d���������Ƀ��Z�b�g����Ă�����̂Ƃ��܂��B�������Z�b�g��H��Z�b�g�{�^�����K�v�ł���ΓK�X��H�}�ɕt������Ɨǂ��ł��傤�B �@�]�k�ɂȂ�܂����A����̉�H�ł�[�v�_�P]�́u�����̃X�C�b�`��ON�ɂȂ����v�Ƃ�����Ԃ��L�����Ă������ȕێ���H�ɂ��Ă��܂��B �@�u�X�C�b�`������������Ă��Ȃ��v�u�����ꂩ�Е����������ꂽ�v�Ƃ�����Ԃł�OFF�̂܂܉����ς炸�A�u�����̃X�C�b�`�������ꂽ�v�Ƃ��������������������Ɂu����������I�v�Ƃ������(����)��ۊǂ��Ă����������[��H�Ƃ��Ďg�p���܂��B �@����������Ԃ̕ۊǂ��u�t���O�Ǘ��v�ƌ����A���̃������[���e��d�C�I�ȐM���Ȃǂ̂��āu�t���O�v�ƌĂт܂��B �@�u�t���O�v�Ƃ͉p����t���b�O=�u���v�̂��ƂŁA�������ۂ������������Ɋ��𗧂ĂĒm�点��l�q���炱���Ăт܂��B �@�p�\�R�����̃Q�[���ʼn����������������Đ�ɐi�߂�悤�ɂȂ������Ɂu�t���O���������v�Ƃ���������������̂�����Ɠ����ł��B �@�ǂ����ŕ��݂��āu���v����ɓ���Ă��Ȃ��ƁA��������̑O�ɗ��Ă������J�������ł��Ȃ��悤�Ȃ��̂ł��B �@�����[�v�_�Q]�́u�X�C�b�`������OFF�v�Ƃ����A�S���������삵�Ă��Ȃ����ƁA�����̃X�C�b�`����������ɗ������������̂ǂ���̏�Ԃł��N���肤������ɂȂ��Ă��܂����A�X�C�b�`������OFF�ł����̑O�Ɂu�����������v�Ƃ����t���O�������Ă������́u������������ɗ����������v�Ƃ�����������������킯�ŁA����̖��̓t���O�Ǘ��̊T�O�������Ɖł��Ȃ����ł��B ���Ԏ� 2009/4/20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����s���ƕ��͉���Ŗ{���ɐ\����܂���ł����B �@A�EB�{�^�����ɉ����ƁiCR1�j��ON���܂��B�Е��ł�������OFF�ɂȂ�܂��B�����̃{�^���������Ȃ���iCR1�j��ON���܂��� �@�����Ĉ�xON��ԂɂȂ����ꍇ�����̃{�^����OFF���m�F����Ȃ��Ǝ��ɓ�����N�����Ă��iCR1�j��ON�ɂȂ�Ȃ� �ł��B �@�@�@�Е��̃{�^��1�ł͐�ɍ쓮���Ă͂����Ȃ� �@�@�@�Е��̃{�^������쓮�i������ςȂ��j���N�����Ă���������xOFF�ɂȂ�Ȃ��Ɠ��삵�Ȃ��悤�ɂ��� �@�����{�^���X�C�b�`2�ƃ����[3�`4�Ő���Ղ����Ȃ����Ɩ����o���ꂽ���̂ł��B �@�f�ً@���̋@�B�ɂ��鐧��ƕ����܂����B �@����������Ȃ��\����܂���B ���S�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�f�ً@���̋@�B�ɂ��鐧��v�Ƃ����g�r(�������͏o��Ӑ})���������Ă���̂ł���A�ŏ����炻�������Ă���������Ȃ��̕��͂̒������������ɋC�t���A�ڂ��������������ƂŖ��ʂɎ��ԂƘJ�͂�Q��邱�Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B �@�u���葀�쎮���S���u�v�ƌ����A�H��ْ̍f�@��v���X�@�ȂǁA�l�������Z�b�g���đ傫�ȗ͂ʼn��H������@��ɕt�����Ă�����S���u�ŁA�H��������ō��E�ɂ���X�C�b�`���ɉ����Ȃ��Ƌ@�B�����삵�Ȃ��悤�ɂ���X�C�b�`�@�\�ł��B �@�u����œ����ɉ����v�̂͋@�B�̒��Ɏ����ꂽ�܂܍ْf����v���X��������Ȃ��悤�ɁB�܂���x���������S��OFF�ɂȂ�Ȃ��Ǝ��̓�������Ȃ��̂͏�����Ă���ʂ�X�C�b�`�̌̏��ON�ɂȂ���ςȂ��ɂȂ��Ă��āA���S���u�Ƃ��ē��삵�Ă��Ȃ��������m���邽�߂ł��B �@���āA���͊��ɑ��̕��̂�����̉�Ƃ����Ă��鏊�ō��邠�Ȃ��l�̎���Ɏg���鎞�Ԃ͎g���Ă��܂��Ă��܂��̂ŁA�����ȍ~���Ԃ��o�������ɒlj������͉����Ă��������܂��B ���Ԏ� 2009/4/20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��ӂ���l���Ċ��������̂ʼn�H�}���f�ڂ��悤�Ƃ��܂������A���̑O�Ɂu���̒m�点�v�Ƃ������u�_�̂������v�Ƃ������A�C�ɂȂ鎖(�{���̉Ɋւ��Ăł͖����ʂ̋^��)���o�����̂ł������̌������[�h�ł�����ƌ������Ă݂�ƁE�E�E �@�uYahoo!�m�b���v��2009/4/21 09:12:59�̎���Łu�d�C��H�}�i�f�ً@�j�̉�H�}���������Ă������� (rinopjp����)�v�Ƃ������₪�o����Ă��āA�ǂ����Ԃ���Ă��܂��ˁB �@�u�����{�^���������ꂽ��CR1��ON�B���ɂ͗����������ꂽ�����m�F���Ȃ��ƍēxON�ɂ͂����Ȃ��B�v�Ƃ�����蕶�Ɏ����ꂽ����ʂ�̎菇���G���K���g�ɃV�[�P���X��H�ɒu�������Ă��܂��B �@������̉ł͂܂��{�^�������������ꂽ�̂����m���Ăf�n���o���ق����D�悳��Ă��܂���(��ŗ��������ꂽ���Ƃ����m���Ă���)�A�����l�������ł͂܂������̃{�^����������Ă��Ȃ���ԂŁu�̏Ⴕ�Ă��Ȃ������Ɍ��m����v���@�ł����B �@�ْf�@�Ȃǂ̈��S���u�Ƃ��Ďg�p������̂ł�����A���S��̂ق����D��(�̏Ⴕ�Ă���ꍇ�͓����Ă͂����Ȃ�)���Ǝv���܂������A�܂��ŏ��̈�x���炢�͌̏Ⴕ�Ă��Ă����삵������Ă����̂��ȁE�E�E �@�����[�S�ō\������Ƃ������ł����ɍ������ł��ˁB(�X�C�b�`�ɉ����g�p����̂����ł͐G����Ă��܂��A���̈��̉ł͈�ړ_�X�C�b�`���g�p���鎖�Ƃ��ă����[���P�]���ɕK�v�ł��B) �@����ՊW�̋��ȏ��ɂ͂��̉�H(�܂��͎�����)���ڂ��Ă���̂�������܂���B �@��蕶�ʂ�̃V�[�P���X��H�������Ƃ����ݖ�ł���p�[�t�F�N�g�Ȑ����ł��ˁB �@�o�肳�ꂽ���������l������Ɉ��S�Ǘ��ɋC���g������H�����߂Ă���̂��A����Ƃ�������ŏo����Ă���̂悤�Ɏ菇��ł̃V�[�P���X�����̐v(�Ɛ���)���ł���l�ނ��ǂ���(�܂����S�܂ŋC�����Ȃ��͓̂��Ђ����Ă̐V�l�Ȃ�d���Ȃ��ƗP�\��^���Ă���Ă���)�f����ړI�Ȃ̂��ŁA���̉�H���o�������̕]�����������Ƃ��낾�Ǝv���܂��B �@������������A��Ђʼnۑ���o����ĉ�����21�����������̂�������܂���B �@�������L��悤�ȏꍇ�͊�����������������A�����͑��̕����D�悵�đΏ����ł���ł��悤���A���ɉ��̎w��������ꍇ�͊F�l���炨���蒸��������Ȃǂɏ��ԂɑΉ��������܂��B����̂悤�Ɍ�t���ŏ������ς�悤�ȏꍇ�́A�܂����������Ɏ��Ԃ��o�������ɏ����Ή�����̂ŏ��ԑ҂��ɂȂ鎖�������ł��B �@Yahoo!�ł͎��╶�̓��e�₻�̒������e�܂ł�����Ŏ��₳��Ă�����e�ƑS�������ł��̂ŁA���R�Ⴄ�������������Ă���Ƃ͎v���܂���B �@���ɗ����Ă���Ƃ������͂������ɂ͊��҂���Ă��Ȃ��悤�ł��̂ŁA���̂�����ɂ͉��Ȃ��Ă��ǂ��̂ł��傤�ˁB �@�M�d�Ȏ��Ԃ�����Ē����Ă��肪�Ƃ��������܂����B ���Ԏ� 2009/4/22
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���͑����̐��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�O��̓X���b�g�J�[�̃��C�g�̌����肪�Ƃ��������܂����B �@����̓X���b�g�J�[�̎��̋����𑪂肽���Ǝv���A���R���̃e�X�����[�^�[�ƌ����������Ǝv�����̂ł����A�̔��I�����Ă��܂����B�o�����肽���̂ł����A��H�}�������Ă��������B���肢���܂��B noris �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�e�X�����[�^�[(�K�E�X���[�^�[)�Ȃ烈�R���̐��i�łȂ��Ă����ʂɌv���탁�[�J�[�����R�����Ă��܂��B �@���R���̕����艿�����炾�������m��܂��A���育��ȃn���f�B�^�C�v��1��5000�~����2���~���x�Ŕ��������ł��܂��B �@���R���̕����̔��I�����Ă��Ă�����͗e�Ղł���B �@�����āA���������Ƃ�������d�q��H�ō��Ƃ�����OP-AMP���g������F�X���Č��\�ʓ|�ȉ�H�����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�u�����[�̑��̐ڑ����킩��Ȃ��v�Ƌ��Ă������炢�̏��S�҂̕��ɍ��邩�ǂ����E�E�E���Ȃ肨�E�߂ł��܂���̂ŁA�����ł͊ȈՓI�Ȃ��̂����Љ�܂��B  �@���͂̋����𑪂�ɂ́u�z�[���Z���T�v(�z�[���f�q)�Ƃ��������g���܂��B
�@���͂̋����𑪂�ɂ́u�z�[���Z���T�v(�z�[���f�q)�Ƃ��������g���܂��B�@�d�C������Ă��镨���Ɏ��͐��Ă�Ǝ��͂̓����ʼn������ɓd�q�̗��ꂪ�N���錴���𗘗p���āA�����̂ɓd���𗬂��Ă����Ă����̉������̓d�������m����Z���T�[�ł��B �@����g�p����͓̂��ł�THS123�Ƃ����f���`���z�[���f�q�ŁA�ʐ^�̂悤�ɔ��ɏ����ȑf�q�ł��̂Ŏ�舵���ɂ͂��イ�Ԃӂ��Ă��������B (�s���ԍ��͍�����1�E2�E3�E4)
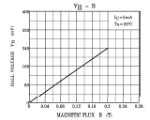 �@��i�d��10mA�ŋ쓮�����ꍇ�A0.1�e�X���̎��͐����ʂ��240mV�̋N�d�����������܂��B
�@��i�d��10mA�ŋ쓮�����ꍇ�A0.1�e�X���̎��͐����ʂ��240mV�̋N�d�����������܂��B�@���͐��̋���-�N�d�͂̊W�̓��j�A�Ŕ��ɗǂ������̑f�q�ł��B�܂��o�C�A�X�d��-�N�d�͂̔�����j�A�ł�����o�C�A�X�l���������茈�߂�Ώo�͓d�����玥�͒l�̋t�Z���e�Ղł��B �@THS123�ł�10mA�쓮�ł͍ő�0.1�e�X��(240mV)�܂Ő��m�Ɍv��܂��B(���ۂɂ�0.3�`0.4T���炢�܂ł͓d�����o�܂����B�K�i�O�Ȃ̂Ő��x�͐M���ł��܂���) �@THS123�̓V���R���n�E�X�����̓X���ň��73�~�B(�Ƃ������莝���̕i) �@�A�����[�J�[�p�i��ł��̂łق��ł͓��荢�������܂���B���̃z�[���f�q���g�p�����ꍇ�͂��̑f�q�̃f�[�^�V�[�g�������ɂȂ��ăo�C�A�X�d����o�͓d���ׂāA�K�v�ł���Ή�H�}��ύX���Ă��������B (��Γd���̃l�b�g�ʔ��ł�THS119/THS130(���50�~)���͔����Ă��܂��B��i�E���l���Ⴂ�܂�) �� �L���f�ڐ�����Ɍ�����V���R���n�E�X�����ł��ɂ�THS130�݂̂ɂȂ��Ă��܂����B �@����̉�H�}�ł��B 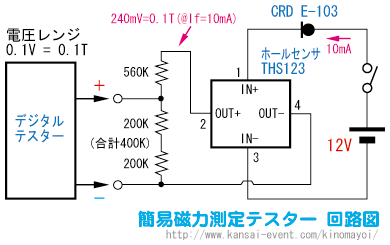 �@�o�C�A�X�d����10mA�ŁA��d���_�C�I�[�h(CRD)��E-103���g�p���Ă�������H���ȗ������܂��B �@���̂Ԃ�d���d����12V�K�v�ł��B �@12V�ȏ�Ȃ�ǂ��̂ŁA9V�̓d�r(006P)���Q�����18V�ł��\���܂���B �@THS123�̏o�͂�240mV/0.1T�ł�����A�o�͓d����100/240�{�ɂ��Ă���0.1V��0.1T�ƂȂ�d���v�Œ��lj\�Ȑ��l�ƂȂ�܂��B �@��R�ŕ�������100/240�ɂ���̂ł����A�s�̂̒�R�ł�560K:400K���ł��䗦�Ƃ��Ă͋߂��Ȃ�܂��̂ł��̒�R�l�ɂ��܂��B�A��400K�̒�R��E-24�n��ɂ͖����̂�200K���Q�{�����400K�Ƃ��܂��B �@�ł���Β�R�͌덷1%�i���g�p���Ă��������B(���������̐��l��ǂނ����Ȃ�덷5%�i�ł������ł�) �@���肷��d���v�́u�f�W�^���e�X�^�[�v���g�p���܂��B �@�F���������Ǝv���܂��B �@�����Œ��ӂ��K�v�ŁA�K���u��r�I�����ȃf�W�^���e�X�^�[(�I�[�g�����W�̕�)�v���g�p���Ă��������B �@�z�[���f�q�̏o�͔͂���Ȃ��߁A�����̐j���[�^�[���̃e�X�^�[��A�f�W�^���e�X�^�[�ł��j���[�^�[���Ɠ����������W�c�}�~���ăK�`���K�`���ƒ��̒�R���ւ��Ă��镨�͂��߂ł��B �@�K���I�[�g�����W�ŁA�e�X�^�[���̃C���s�[�_���X�����l���ȏ�̂��̂��g�p���Ă��������B �@�C���s�[�_���X�̓e�X�^�[�̐������ɏ�����Ă��܂��̂ł��m���߂��������B �@�܂��A���̉�H�}�̓d��12V�𗘗p���ăf�W�^���d���v(��p�ӂ���)�����āA���̓d���v�œd����\��������Ƃ������@�����߂ł��B �@�����d������q���ꂽ�d���v�ƌq���ƃz�[���f�q�̃o�C�A�XGND�Əo��GND���V���[�g���Đ������d�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@�ł��̂œ���d����H�ő��肷��ꍇ�͍����A���v��H�Ȃǂ��g���ăz�[���f�q�̏o�͂ɉe����^���Ȃ���H���q���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂Ŗʓ|�Ȃ̂ł��B �@����͂����܂Łu���[�^�[�̎��͂𑪂肽���v�Ƃ������炢�̗p�r�Ŏg�p����ȈՂȑ����E����A�_�v�^�[�̐���Ƃ������ƂŁA�K����H�}�ʂ�Ƀf�W�^���e�X�^�[��ڑ����Ă��������B ���Ԏ� 2009/4/19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���肪�Ƃ��������܂��B �@�O��A�̃u���[�L�����v�쐬�Ɏ��|����O�ɓd�C��H���S�҂̓���̖{���Q���ǂ݂��Ԃ����炢�̖{��ǂݎn�߂Ă��܂��B �@�������ł��m�������Ă��ꂩ��������܂��B�܂��܂������b�ɂȂ邩�Ǝv���܂����A���ꂩ�����낵�����肢���܂��B noris �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�撣���č���Ă݂Ă��������B �@�X���b�g�J�[�̃��[�^�[�̎����ǂ̒��x�̋��������m�ł����A�������̉�H�̊��x�̂܂܂Ŋ��x���ǂ����Ăǂ��𑪂��Ă�0.1V�ȏ゠��Ƃ��Ȃ�A�o�C�A�X�d���𗎂Ƃ��ׂ�CRD��10mA��菬���ȓd���̂��̂ɕς��Ă݂Ă��������B���̎��̎��͒l�̓o�C�A�X�d�������炵���䗦�Ōv�Z���܂��B ���Ԏ� 2009/4/19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
���� �NjL ����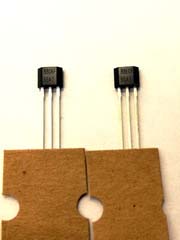 �@�O�[�q(�R�s��)�����j�A�o��(���́|�o�͓d�����A�i���O�Œ����I)�Ŏg���₷���u�z�[��IC�v���V���R���n�E�X�̏��i�ɑ����܂����B
�@�O�[�q(�R�s��)�����j�A�o��(���́|�o�͓d�����A�i���O�Œ����I)�Ŏg���₷���u�z�[��IC�v���V���R���n�E�X�̏��i�ɑ����܂����B�@�w�}�C�R���Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ҂�����ȃz�[��IC�����ׁI�x ��DRV5055A2QLPGM �E�d���d���F3�`3.63V/4.5�`5.5V �E���x�FVcc3.3V�� 30mV/mT�@Vcc5V�� 50mV/mT �E��d���FVcc3.3V�� 1.65V�@Vcc5V�� 2.5V �E�v���͈́FVcc3.3V�� �}44mT�@Vcc5V�� �}42mT ��DRV5055A3QLPGM �E�d���d���F3�`3.63V/4.5�`5.5V �E���x�FVcc3.3V�� 15mV/mT�@Vcc5V�� 25mV/mT �E��d���FVcc3.3V�� 1.65V�@Vcc5V�� 2.5V �E�v���͈́FVcc3.3V�� �}88mT�@Vcc5V�� �}85mT [DRV5055�V���[�Y�E�f�[�^�V�[�g�͂�����] �@�ǂ���� �u���͂��O���Əo�͓d����1/2 Vcc�v �u �u���͂�S/N�͏o�͓d����1/2 Vcc���瑝���邩���邩�ł킩��v �Ƃ����P���Ȃ��̂Ȃ̂ŁA1/2 Vcc���(0V�Ƃ���)�Ɂ{�|�̓d���ō��E�ɐj���U���d���v���q���A�i���O�I�Ɏ��̗͂L���E�ω�������܂����AArduino��PIC/AVR�}�C�R���Ȃ����g�����z�[��IC�̏o�͓d����A/D�ϊ����ăf�W�^�����l�ŕ\������̂������ł��ˁB 2020/4/12 �NjL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V��12V(13.8V)�R���o�[�^�������܂��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āA�c�b�|�c�b�R���o�[�^�ɂ��ċ����Ă��������B �@24������13.8���ɍ~������R���o�[�^�[���������ł����A�����@�����t���ēd������ꂽ���~�������ɁA�����@�̃R���f���T�[���p���N�����Ă��܂��܂����B������24�������̂܂o�Ă��܂����B�R���o�[�^�[�̕��i�ׂ�ƁA�g�����W�X�^�[���r�c845�P���Ă����̂Ō������e�X�^�[�ő������Ƃ���A11.9�������o�͂��܂���B�X�ɖ����@���Ȃ��œd���������4���ʂ܂ŗ����܂��A�ǂ��̕s����l������ł��傤���H�����Ă��������B�X�������肢�������܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�Ђƌ���24V��12V(13.8V)��DC/DC�R���o�[�^�ƌ����Ă��A�X�C�b�`���O��H�����Ȃ̂��V���[�Y���M�����[�^�����Ȃ̂��ʼn�H��̏���͈���Ă���Ǝv���܂��B �@�X�C�b�`���O�����ł���g�����W�X�^/�e�d�s�̂ق��ɍ~����ɃR�C���̃G�l���M�[����o����ׂ̃V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h������܂�����A���̂�������^�킵���ł����A�d����H�ł�����ǂ̂悤�ȉ�H�����ł��o�͕����p�̑�e�ʂ̓d���R���f���T�̗e�ʔ������^���܂��B �@�g�����W�X�^���Ă��Ă����������o�͂̃V���[�g���ɂ��ߓd���ɂ����̂Ȃ̂��A���i�̗ɂ����̂��Ō̏��������Ă���Ǝv���܂����A���ʂ̓V���[�g�Ȃǂɑ��Ă͕ی��H���t���Ă���Ǝv���܂����炻��ł��g�����W�X�^���Ă����ꍇ�͕ی��H���d����H�̕s����l���ɓ���Ȃ���Ȃ�܂���B�܂�d����H�S���̕��i�ɋ^����������킯�ł��ˁB �@�����������ŁA�����_�𐄎@���Ȃ��畔�i���P���e�X�^�[�œ�����Ȃ�A�������Ē��ׂ�Ȃ肵�Č̏������肵�Ă��������B �@���A�悭�������₪�w�������E�����^���̑��E��ʂ̘b���x�́uNo.2009_0415�v�ɏo�Ă��܂��B�Q�l�܂łɂ��ǂ݂��������B ���Ԏ� 2009/4/18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�Q�S�u�����P�Q�u�̃R���o�[�^�[�A�ԃp�[�c�̓X�Ŕ����Ă�����̂Ȃ�A�g�^���W�X�^�̃R���N�^�E�x�[�X�Ԃɓ����Ă����R����������Β���Ǝv���܂��B �@�r�c845�P�E�E�Ƃ���܂����A�����̂Q�r�c�W�S�T�̓��P�E�E���Ǝv���܂��B �@���^�Ԃ̃g�����W�X�^�ł͂Ȃ��A�݊��i��H�ɑւ���ꂽ�Ǝv���܂����@���ł��傤���B �@���̗l�ȏ��i�́A�p���[�g�����W�X�^������ɕ������ׂĂ���A�������a�E�b�E�d�܂ł������ڔz�����ꂽ���̂��w�ǂł��B �@���̗l�ȉ�H�\���́A�ア���̂��玀��ōs���܂�����C�����łɉ���������������ł��B �@�o�͓d���͂P�O�`�Q�O�`���Ǝv���܂����A���Ƃ��P�O�`�Ƃ��āA�p���[�g�����W�X�^�[���Q����ł���A�P������T�`�B �@�G�~�b�^�[�̔z�����A�ʂɂO�D�Q�I�[���P�O�������܂��B �@�Q�r�c�W�S�T�͂u�a�d���P�D�T�u�ł�����A�V�D�T�`���炢�œd���������|����܂��B �@�R���N�^�[�E�x�[�X�ɓ����Ă����R�́A�������P�O�O�Ƃ��āi�T�T�`�P�U�O�j�Q�S�|�P�T���X�u�i�c�F�i�[�_�C�I�[�h�͂P�T�u�łP�T�|�P�D�T�u�łP�R�D�T�u�j�h�a�͂T�O���`�ȏ㗬�������̂Łi�h�b���T�`�j�P�W�O���B �@�Q���ƂX�O���A�V�T���W�Q���ŗǂ����Ǝv���܂��B �@�ŏ��Ɍ����Ƃ��A����ȉ�H�ŗǂ��́H�H�ƁE�E�E�B �������q �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�������q�l�̋��Ă�̂�Tr��ZD�̓d���ύt�𗘗p�����d����H�ł��ˁB�ȈՂȓd�����u�ł͂悭�g���Ă��܂��B �@�܂��A2SD845�̂悤�Ȓ���g�����p(�I�[�f�B�I�p)�g�����W�X�^�̓A���v�̓d�͑����i�ȂǂłT�p�����x�Ŏg���悤�Ȏ���������܂��ɍs���Ă��܂��B �@����җl�̎g���Ă���d�����u�������ԗp�̂��������ȈՂȕ����A�����@�p�̂����ƕ��G�ȓd����H�̕����킩��܂���̂ŁA���͂��̂܂܉������y���Ȃ��ł����܂��B ���Ԏ� 2009/4/19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̌�ԓ��A�Ȃ�тɎ������q�l�̌䓊�e���肪�Ƃ��������܂��B�������q�l�̋�Ƃ���Ԃ̃p�[�c�X�̔��̂��̂ł��B �@�����A�C�����Ă݂܂��B���肪�Ƃ��������܂����B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̃^�C�v���ƁA�C���Ƃ������p�[�c�S�����ł��ˁE�E�E�B ���Ԏ� 2009/4/20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12�`30Hz�̐M����PWM(50�`10%)�ɕϊ������H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���������b�ɂȂ�܂��B���Ђ������������������̂ł����A�Ȃ�ƌĂԂ̂�����Ȃ��̂ŗ~�����̂��L�q�������܂��B �@�����Z���T�[�ŁA��P�Q�`�R�O�w���c�i�ρj�Ńp���X���o���Ă���܂��B���̃p���X�𗘗p���ăf���[�e�C��i�T�O������P�O�����x�܂Łj���ł�������̉�H�Ȃǂ�����܂��ł��傤���H���͂悢��H�����������������܂���ł��傤���B �@�ǂ����X������肢���܂��B �l�R�q�̃p�p �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�������������̉�H�͖����Ǝv���܂��B �@��H�}���쐬����Ƃ��Ă����m�̒萔������������܂���B �E�d���͉�V�Ȃ̂� �E���͂̓f�W�^���p���X�Ȃ̂��A�i���O�M���Ȃ̂� �E���͓d���U���͉�V�Ȃ̂� �E���邳��12�`30Hz�̊Ԃŕς�̂� �E12Hz�̎���50%�ŁA30Hz�̎���10%�ƃ��x�����t�ł����̂��H �E�o�͂�PWM���g���́H �E�o�͂�TTL���x���A�I�[�v���R���N�^�A����Ƃ����炩�̓d���o�́H �@���Ȃ��Ƃ������̏�����������Ȃ��Ɖ����v�ł��܂���̂ł��������������B �@����OP-AMP�Ƃ��̑��̑g�ݍ��킹�Őv�ł���Ǝv���܂����AF-V�ϊ�IC�����g�����ق����ǂ��Ɣ��f�����ꍇ�͓K����IC���w������܂Őv�ł��Ȃ������l�����܂��B�\�߂��������������B �@�����閧�ɂ���Ă�����e���Ƃ͎v���܂����A�����\�Ȃ牽�Ɏg�����Ȃ̂����������肦��ƁA�v�����œK���������ǂ����̔��f���ł���Ǝv���܂��B �@������������ʼn�H�̗p�r��g�p�ꏊ��閧�ɂ������������ł����A��H�}���ڂ��Ă���u���ꂾ�͈Ⴂ�܂��v�Ƃ������Ă����邾���ł��̂ŁA����������ꍇ�ɂ͉��Ɏg���Ăǂ̂悤�ȖړI�̉�H�ł��邩�m�ɂ��Ă��������B�łȂ��Ƃ���]�ɓY��Ȃ��ʂ̂��̂���邱�Ƃ�����A���ɂƂ��Ă�����җl�ɂƂ��Ă����ʂȎ��ԂƘJ�͂����������ʼn����ǂ����Ƃ͂���܂���B [�NjL] �@���v�Z���܂������APWM�ł͂Ȃ�PFM�Ŏ��g���͓��͂ɓ����ŗǂ��Ȃ�A�p���X�̕ϊ��̓V���O���V���b�gIC������12Hz�`60Hz�ɑ���64%�`10%(�܂���36%�`90%)�Ńf���[�e�B���Ή��������܂��B �@���́E�o�͂̓d���E��ނȂǂɂ�镔���͂��ꂼ��ɑΉ����K�v�ł��傤���AF-V�ϊ������Ă���PWM�ϒ������H�̂悤�ȕ��G���͂Ȃ��u�f���[�e�B��ς�����(�����ɂ͎��g���Œ�Ƃ����v�]�͖���)�v�Ƃ����ړI�͒B���ł��܂��B ���Ԏ� 2009/4/17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��Ԏ������肪�Ƃ��������܂��B���������������̂ɔ��[�Ȏ���̎d�������Ă��܂��܂����B�\����܂���B�g�p�ړI��LED�̏Ɩ��Ɏg���܂��B���݂̓X���b�g�Ђ�p�����t�H�g�Z���T�[�łT���̃I�[�v���R���N�^�[�p���X��14011B�Ő��`������AFET�œ_�ŗp�d�����i��XV�j�o�͂��ė��p���Ă���܂��B �@�f���[�e�B����������͔̂�ʑ̂̏Ɩ����Ԃł��B���R���Â�����܂����A��ʑ̂̐Î~���Ԃƌ���l�̓��̎��͂̊W���H�ł��傤���u���Č����Ȃ����x�ŁA�o���邾�����邭�Ɩ����Ă䂫�A�ŏ�̔�������ŋ��߂����̂ł��B�����������悤�Ɏ��g���̌Œ�͂���܂���A��ʑ̂ƃV���N���������Z���T�[������܂��̂ő��ΓI�ȓ����ƂȂ��Ă���܂��B �l�R�q�̃p�p �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����A���̍l���Ă������Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�����~�����̂ł��낤�Ƃ����������͌����_�ł킩��܂����B �@�u���Z���T�[�Ō��m�������邳��12�`30Hz�̎��g���M���ŕ\���Ă���f�[�^�𗘗p���āA�����g�Ńp���X�ϒ�����50�`10%�̐M��(�����̖��邳�߂���)�����v�Ƃ������邳���߉�H�ł͖����悤�ł��ˁB �@�u��ʑ̂ƃV���N���������Z���T�[�v�Ƃ����̂�12�`30Hz�̐M�����o�����Z���T�[�ŁA����12�`30Hz�̃p���X�Ɂu�����v����50�`10%�̃p���X���K�v�Ƃ������ł����H �@����50�`10%�Ƃ����p���X���̓Z���T�[�����������邳�̓x�����ł͂Ȃ��A12�`30Hz�ŏo�͂���Ă���p���X���X�Ƀ{�����[���������Ŏ��݂ɕύX�ł���50�`10%�̊����ŕ�������Ƃ������ł����H �@���܂̂Ƃ��뎄�ɂ͑S�������ł��Ă��Ȃ��悤�ł��B �@����͂�����Ȃ��Đ\�������܂���B �@���������킩��悤�ɕʂ̊p�x���炲�����肦�܂���ł��傤���B ���Ԏ� 2009/4/18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�ǂ����A�X�g���{�Ɩ��̗l�ȕ����Ǝv���܂��B �@�P���Ƀp���X�̃f���[�e�B�[��ω�������Ȃ�T�T�T�����g���������V���b�g�}���`�őΉ��ł���ł͂Ȃ��ł��傤���H�B �������q �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���т��ѐ����s���ł��݂܂���B �@�~�Տ�ɓ������������̕��i������A�j���[�V�����j���Œ肵�Ă����܂��B�����K���ȑ����A���ݖ�U�O�������قǂʼn�]�����܂��B���̕��������u�����͔C�ӂł���12����18���x�A����ɓ������ďƖ�����ƃI�u�W�F�͂����������̏�Œ�~���Č����A�I�u�W�F�̕ό`���y���߂�̂ł��B �@����𗧑̃]�[�g���[�v�ƌĂт܂��B �@���̓��j�A�[�ɓ����Ă��邽�ߎ��o�I�ɒ�~����̂͏Ɩ����Ԃ����ł����A�Z������Ɠ��R�Â��Ȃ�A�͔C���ɗʂ𑝂₵�Ė��邷��t���b�V�����ʂŊώ@�҂ɕ��S�������肷���̌��O������܂��B�ǂ��Ƃ����T���o���ɂ͉�]�X�s�[�h�A�����I�u�W�F�̐��A�Ɩ����ԂƂ��̏Ɠx�ł��傤���B �l�R�q�̃p�p �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�]�[�g���[�v(�X���b�g�A�j���[�V����)�ł����B����Ȃ炻���ƍŏ��ɏ����Ē�����Ή����Ԉ��Ȃ������Ǝv���܂��B �@�u���Z���T�[��12�`30Hz�̐M�����o���v���u�������p�e�����[�^�`�����u�v �@�u���̃p���X��50�`10%�̃p���X�v���u�����ė����f�[�^(�A�i���O�l�����g���ɒu���������Ă���)���ŏI�I�Ɍ��̃A�i���O�d���܂��͓d�͒l�ɕϊ�����ׂ�PWM���u�v �Ƃ����A�������A�i���O�`�����u������Ă���̂��Ǝv���܂����B �@����́u���Z���T�[�Łv�Ƃ������ł������A���⒴���g�Ȃǂ̃Z���T�[�Ń_�����̐��ʂ𑪒肵�āA�A�i���O�d���̂܂܂ł͒������̓d���̒�R�œd���������萳�����`���ł��Ȃ��̂ŁA��������g���ϊ����ĉ��L���`���\�L�������ꂽ����Z���^�[�܂ŃA�i���O��(�̂̕��ʂ̓d��)�œ`���āA����Z���^�[�ł͎��g�����猳�̃A�i���O�l�ɖ߂��Đj���̃��[�^�[��U�点��悤�ȁA���y��ʏȂ̊ϑ��V�X�e���̂悤�ȕ����ƁB �@����A�Ȓ����x���łȂ��Ă����ꂽ���̃A�i���O�l���v��������\���������{�\���Ȃ̂ł����E�E�E�B �@��x�ڂ̓��e�Łu�Ɩ��v�Ƃ����P�ꂪ�o�Ă��܂����̂ł����ł͖����Ƃ킩��܂������A����ł�12�`30Hz�̐M�����ʂ����ĉ����́u�ʁv(�u���R���Â�����܂����v�Ƃ������t����A���Ƃ��Δ�ʑ̖̂��邳�𑪒肵��Lux�l)��\���A�i���O�l�����g���ϊ��������̂ł��낤�Ƃ����\�L�ɂ����ƌ˘f���Ă��܂����B �@�����́u�����X�g���{(�݂����ȕ�)�v�Ȃ玚�����q�l�̋�ʂ胏���V���b�g�ō��܂��B�ŏ��ɏ������V���O���V���b�g�����ō���H�ł��B �@555���g���������V���b�g�ŗǂ��̂ł���A�����d�q�ȂŔ����Ă���ėp�́u555�^�C�}�[���(150�~�ʁH)�v(������ŕ��i�͕t���܂���)���Ă��Ď����ŕ��i���ڂ���Ί����ł��B �@�u5V�M����4011�Ő��`�v�uFET��9V��ON/OFF�v�ɂ��킹��555�̃^�C�}�[��H�������Ă݂܂����A�����ėp�̃^�C�}�[���L�b�g���w������č����̂ł����炻��̂ق��������葁����������܂���B ���Ԏ� 2009/4/18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 4/19 |
�@�܂������u�����X�g���{�v�ł��B�u5V�M����4011�Ő��`�v�uFET��9V��ON/OFF�v�ɂ��킹��555�̃^�C�}�[��H�������Ă݂܂��E�E�E�E���ʓ|�����������܂����A���肢���܂��B�f���[�e�C��ɂ��ẮA��H�������Ď������Ă݂܂��B �l�R�R�̃p�p �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�P���ȃ^�C�}�[IC 555���g�p���������V���b�g�^�C�}�[�ŁA��1�`50msec�̃p���X���o�͂��܂��B �@�v������Ă���p���X���̍Œ���12Hz�̏ꍇ��50%��41.67msec�A�ŒZ��30Hz��10%��3.33msec�ł�����A��1�`50msec�͈̔͂ʼnςł���ΖړI�͒B���邱�Ƃ��ł���͂��ł��B �@���̉�H�ł�4011B��NAND��H��ŃI�[�v���R���N�^�o�͂̌��Z���T�[�̔���Lo���x���]����Hi���x���ɂ���FET���쓮���Ă���̂��Ǝv���܂����A555�̃g���K���͂�Lo�A�N�e�B�u�ł����甽�]����ׂɂ������NAND�Q�[�g��Inverter(NOT)�Ƃ��Ďg�p���܂��B �@�܂�555�̃g���K���͂̓G�b�W����ł͂���܂���̂ŁA���Z���T�[�̏o�͂�ON�̊Ԃ̓^�C�}�[�ݒ肪������Z���Ă��o�͂�ON�ɂȂ��Ă��܂����߁A�g���K�[�p���X��������ē��͂��܂��B �@����Ɋւ��Ă͓��ɓ�����͖����Ǝv���܂��̂ŁA�����Ȃ��I�Ƃ������͖����͂��ł��B ���Ԏ� 2009/4/21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Ԃ̎�������O�ƌォ�瑀�삷���H������Ă������܂��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āA���ケ�Ƌg�V�Ɛ\���܂��B �@�~�j�o���̎������̃X�C�b�`��O�ƌォ��ON-OFF���������ĒT���Ă�����A���L�̂�HP�ɂ��ǂ���܂����B http://www.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx (��: URL�͔�f�ڂƂ����Ē����܂�) �@�������i�B���č���Ă݂��̂ł����A���������삵�܂���B �@�悭�悭�ǂ�ł݂�ƃm�C�Y�������ŕs����Ə����Ă���܂����B�����A��H�}�͉��Ƃ��ǂ߂���x�̏��S�҂ł��̂ŁA�ǂ̂悤�ɂ��ē��삳���邱�Ƃ��o����̂��A�S���킩��܂���B �@�ǂ������͓Y���̂قNjX�������肢�v���܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̐���L�����ڂ��Ă���T�C�g��ǂ܂��Ē����܂������A�u�{�������̂ǂ�������̃R�s�[�ł���o���v�u�����͓d�C�̒m���͂��܂薳���v�Ƃ�����H�}�ŁA��������̂܂܍���Ă�����ɓ��삷��̂�������Ǝv���܂��B �@�m�C�Y��s����v�f�̑S�R�������̏�łȂ��ꉞ��������������܂��A�Ԃɐς肵�Ă̐��퓮��͂܂������߂܂���B �@�ʏ�ł���A�w�N���l�̂g�o�Ō��J����Ă����H�ɂ��Ăł���A���̐l�Ɏ��₵�Ă��������B�����͒N���l�̃T�|�[�g�Z���^�[�ł͂���܂���B�x�Ƃ��f�肷��悤�ȓ��e�ł����A���̒N���l�ɕ����Ă����������������͕Ԃ��Ă��Ȃ��ł��傤���獡���͒N���l�̐v���ꂽ��H�ɂ��Ă��������������Ǝv���܂��B 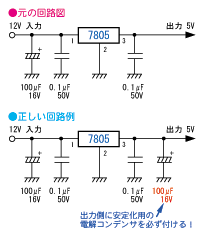 �@�d����H�ɂ��Ăł����A��{�I�ȎO�[�q���M�����[�^7805���g�p������H�}�ł����A�K�v�ȕ��������Ă��܂��B
�@�d����H�ɂ��Ăł����A��{�I�ȎO�[�q���M�����[�^7805���g�p������H�}�ł����A�K�v�ȕ��������Ă��܂��B�@�O�[�q���M�����[�^�͏o�͂̓d�������ɕۂ����͂���܂����A�d����(���̏ꍇ��12V��)����o�͂��v������d���ʂɉ����āu�����̎����v�悤�Ȋ����Łu�����̉��ɒu�����o�P�c�̐��ʁE����(���ꂪ�d��)�����ɂ���ׂɐ��𗬂��ʂ߂��铭���v�����܂��B �@�����R�g���ăo�P�c���琅����R����o�Ă������R�̐����������āA�����قƂ�ǎg���Ă��Ȃ���o�P�c�ɐ�������K�v�������̂Ŏ����i��܂��B �@�o�P�c���傫����Ώ������炢�}���ɑ�ʂ̐�������Ă����ʂ͉�����܂��A�o�P�c��������������R�b�v���炢�̑傫���ł���A�R�b�v��t�Ԃ�̐�������邾���Ő��͖����Ȃ��Ă��܂��A���Ɏ����J���Đ������܂łɎ��Ԃ��������Ă��̊Ԃ͂��イ�Ԃ�Ȑ��ʂ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B �@���ꂪ�d�C�̏ꍇ�͓d���̓d��������������H������ɓ��삵�Ȃ��Ȃ錴���ƂȂ�܂��B �@�ł�������ł���O�[�q���M�����[�^�̌�ɂ͕K���o�P�c�ɑ�������傫�ȓd���R���f���T��t���Ă����Ȃ����S�R���艻�d���Ƃ��Ė��ɗ����Ȃ��킯�ŁA7805���̏ꍇ�͐��\�`����ʂe�̓d���R���f���T�����܂��B�e�ʂ͕��ׂ̕K�v�d����ϓ��ʂɂ���Č��߂܂����A�����IC����x�̉�H�ł͐��\�`100�ʂe���x�ŏ\���ł��B �@�uIC��Ȃ����d���͂قڂO�ɋ߂����A0.1�ʂe���t���Ă�̂ŏ\������Ȃ����I�v�ƌ����邩������܂��A0.1�ʂe�̃R���f���T�́u�O�[�q���M�����[�^�̔��U�Ȃnj�쓮�h�~�p�v�ł���A�o�͓d���̈��艻�p�ł͂���܂���B �@�m����IC����x�ł���Ώ���d���̕ω����قƂ�ǖ����āA�d���R���f���T�����Ȃ��Ă��u�����ځv�͐�����5V����������܂����A���ꂾ���ł͉�H���삪�s����ɂȂ������ɂ�������E���邾���́u�]�T�v�������̂ł��߂ł��B �@�X�C�b�`�p��H�{���ɂ��Ăł����A�c�b�R�~�����ڂłǂ�����������ėǂ��̂��Y�ނ��炢�ł��i�O�O�G 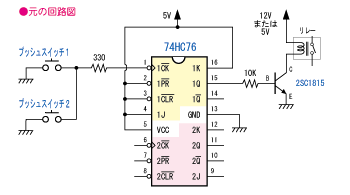 ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�܂��́u�X�C�b�`�Ɠ��͉�H�v�ł����A�S���̃f�^�����ł��B �@�f�W�^��IC�̓��͒[�q�ɂ́uHi�v�uLo�v�̓��ނ̃��x��(�d��)�̂��������ꂩ����͂��Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B �@IC�̒����ł͂ǂ���̃��x���ɂ��Ȃ��Ă��܂���̂ŁA�O�����炻�̂����ꂩ�̓d����^���Ă��Ȃ���Ȃ�܂����B �@����Ȃ̂ɁA�X�C�b�`�������Ă��Ȃ���(�ӂ���̏��)�ł͓��͒[�q(1CK)��330���̒�R�͌q�����Ă�����̂́A���̐�͉��̓d���ɂ��f�m�c�ɂ��q�����Ă��炸�I�[�v���ɂȂ��Ă��܂��B �@����ł����͒[�q�͕s�����Ńm�C�Y��U���Ȃǂɂ��O���d���̉e���ɎアC-MOS IC�ł͓��Ɍ�쓮�̌����ɂȂ�܂��B��쓮�Ƃ���������ɓ��삷��悤�ɍ���Ă��Ȃ��̂ł��B �@���������삳����ɂ́A�����ƃX�C�b�`��ON/OFF��Hi/Lo�̓d���ɐ�ւ���H��t���Ă��Ȃ���Ȃ炸�A����̏ꍇ�́u�X�C�b�`ON��Lo�ɂȂ�v�悤�ɂӂ����Hi���x���ɂȂ�悤�Ɂu�v���A�b�v��H(��R���)�v���K�v�ł��B �@�܂��u���͂̓V���~�b�g���͂ɂȂ��Ă��邩��A�`���^�����O�h�~��H�͕s�v�v�Ƃ������Ă��܂���������ԈႢ�B (�f�[�^�V�[�g�Œ��ׂ���A74HC76�̓��͉�H�̓V���~�b�g���͂ł͂���܂���B��������H��ł̓V���~�b�gNOT�Q�[�g��74HC14��lj����ăV���~�b�g���͂ɂ��܂��B) �@��ʓI�ȃV���~�b�g���͉�H�ɂ��Đ������܂��B �@�`���^�����O�Ƃ����̂́A�X�C�b�`�����p�`�b��ON�ɂ�������ł��A���ۂɂ͐ړ_�̓�����d�C�̓`�����̐����̂������ł����Z���Ԃ̊Ԃ�ON��OFF�����x���J��Ԃ��ꂽ�悤�ȓd�C�M���ɂȂ��Ă��܂����ۂł��B �@�ł�����`���^�����O��h�~���Ă����Ȃ��ƁA�X�C�b�`����������Ă��Ȃ�����ł�IC�ɂ͉��x���X�C�b�`���������悤�ȏ�ԂɂȂ�A���́u���x���v�Ƃ����̓}�`�}�`�Ȃ̂����ʂ͂ǂ��Ȃ邩�킩��܂����B �@����̃X�C�b�`��H�ł́u�X�C�b�`������������Ȃ̂ɁAIC�ɂ�2�������Ƃ��ē`����đS�R�X�C�b�`������Ȃ��I�v�Ȃ�Ď�(��쓮)�͂�����܂��ɋN����̂ł��B �@�V���~�b�g��H�ł̓��x������ɍ���݂��ĂȂ�ׂ����͂̕s���肳�ɑΏ��ł���悤�ɂ͂��Ă��܂����A�X�C�b�`�̐ړ_�̂悤���V���~�b�g���͂̔��背�x�������Ă��܂��`���^�����O�m�C�Y������ꍇ�͕K���`���^�����O�h�~��H(�R���f���T�Ȃ�)���Ƃ����K�v������A���̃R���f���T�ɂ���Ă��₩�ȓd���ω��ɂȂ���͓d���̓f�W�^���l�ł͖����Ȃ�̂ŃV���~�b�g���͉�H�Ő������A�܂���쓮����Hi/Lo�肳����̂ł��B�ł����炱�������ꍇ�̃V���~�b�g��H�Ƃ����̂̓`���^�����O�h�~��H�ƃy�A��g��ł͂��߂ėL���Ȃ킯�ŁA�u�V���~�b�g���͉�H������`���^�����O�͖h�~�ł����v�Ȃ�Ă��Ƃ͖����̂ł��B �@���Ď��Ɂu74HC76�̎g���Ă��Ȃ���H�v�ɂ��Ăł��B �@74HC76�ɂ�JK-FF���Q��H�����Ă��܂��B���̂�������͂P��H�݂̂��g�p���Ă��Ă����Е��͎g�p���Ă��܂���B �@�u�����P��H�]���Ă���̂ŁA�����P��H���܂��v�Ȃǂƌ����Ă��܂����A�����P��H����̂ɂ͊ԈႢ�͂���܂��A�u�g���Ă��Ȃ��Ȃ琳�������g�p�������s���v�Ƃ����l�����o�b�T���Ɣ��������Ă��܂��B �@C-MOS IC�̓��͒[�q�͔��ɕq���ŁA��ɏ����܂����悤�ɓ����ł�Hi/Lo�̂ǂ���ɂ��ڑ�����Ă��Ȃ���ԂŊO���m�C�Y�Ȃǂ���ƕq���ɔ������܂��B �@�u�Ȃɂ��q���ł��Ȃ����͒[�q�̋߂��Ɏ���߂Â��������Ńr���r���Ɣ��������v���炢�̕s���肳�ł�����A���g�p�̒[�q�����̉�H�}�̂悤�ɉ����Ȃ����ɂ����ƁA��̂܂��̕��̏�Ԃ�Ód�C�Ȃǂ̑�C���̓d�C�I�v�f�̉e���������ɎāAIC�̒��ł͂����ւ���m�C�Y�E�p���X�E�ߌ��ȓ������N�����Ă��܂��܂��B �@�O���d�ʂ�m�C�Y�����ł͂Ȃ��AIC�����̓���Ŕ�����������̓d�C�I�ȕω��ɂ��ߕq�ɔ������ē�����H����쓮���N�������Ƃ�����A���̌�쓮�͐������z�����Ă���͂��̂P��H�ڂ̓���ɂ��e����^���ĂP��H�ڂ�����ɓ��삵�Ȃ��Ƃ��������悭����܂��B��H�}��͂Q�̕ʁX�̉�H�������Ă���悤�ɏ�����Ă��Ă��A���ۂ��P��IC�̒��g���S����쓮�����Ǝv���Ă��������B �@�ł�����C-MOS IC�ł͓��Ɂu�g���Ă��Ȃ��Ȃ琳�������g�p�������s���v���Ƃ��K�v�ŁA���g�p��H�́u����ɓ��삵�Ȃ��v�悤�ȃs���ڑ��ɂ��Ă��܂��B �@���̉�H�}�̂܂܂ł́u��쓮������I�v�ȉ�H�����Ǝw�����Ă���悤�Ȃ��̂ł��B �@����IC�̓d���[�q�̂����߂��ɂ́u�o�C�p�X�R���f���T�v�����܂��B �@0.1��F�̐ϑw�Z���~�b�N�R���f���T����ʓI�ł����A�����IC�ɓd�����痈��m�C�Y��h�~����̂ƁAIC���g�̃f�W�^�������IC�̓d�����s����ɂȂ��Č�쓮����̂�h�~���铭��������܂��B �@�d���̎O�[�q���M�����[�^�ɂ��锭�U�h�~�p��0.1�ʂe��A��������IC�̓d���ɂ���p�C�p�X�R���f���T�͌�쓮�h�~�Ƃ����Ӗ��ł͔��ɗL���ŁA���́u���܂��Ȃ��R���f���T�v�ƌĂ�ł��܂�����H����쓮�����Ȃ��ׂɁu�����Ɠ����܂��悤�Ɂv�Ƃ��F�肵�Ȃ�������ƌ�쓮��h���ł���邠�肪���[���R���f���T�ł��B �@�Ō�Ɂu�����[�h���C�u��H�v�ł��B �@�܂��N���l���u��R�l�Ȃǂ͓K���ł��v�ƌ����Ă��܂����A�{���ɓK���ł��ˁB �@�x�[�X��R��10K�ł͂��Ȃ菬�^�̃����[�ŁA�R�C���d�������d���ȕ��łȂ��Ɠ����Ȃ��ł��悤�ˁB �@�K�������������^�����[���g���Ă��ĒN���l�̂��茳�ł͓��삵�Ă���̂ł��傤�B �@2SC1815���g�p����Ȃ�R���N�^�d������p��75�`100mA���x�܂ŗ����܂�����A�x�[�X��R��1K�����x�ɂ��Ă����Ώ\���ɃR���N�^�d���͖O�a�����邱�Ƃ��ł��A2SC1815�Ńh���C�u�ł���͈͂̕��ׂł���ő���܂ł͍쓮�������܂��B �@���������[��5V�^�C�v���ɂ��ăR�C���d����150mA�Ƃ��K�v�ȓd���������ꍇ�́A2SC1815�ł͂Ȃ�2SC2120�����傫�ȓd����������g�����W�X�^�ɕύX���A�x�[�X��R��510�����x�Ƃ������傫�ȓd���𗬂��ݒ�ɕύX���܂��B �@�܂��A�����[�̃R�C�����̂悤�ȁu�U�������v���g�����W�X�^��ON/OFF����ꍇ�́uOFF���̓d���U���ɂ��X�p�C�N���d���v�Ńg�����W�X�^�ɋt�����̒����d�����������Ĕj��Ȃ��悤�Ƀ_�C�I�[�h�������ċt�N�d�͂��E���Ă��K�v������܂��B �@�_�C�I�[�h�����Ȃ��Ă��ꌩ����Ɛ���ɓ���͂��܂����A�u�g���Ă��邤���ɂ����Ă��������v�Ƃ�����H�ɂȂ�܂��B �@�O�[�q���M�����[�^��AC-MOS IC��Ƃ����ւ�P���ȉ�H�ł����A���̉�H�}�ɂ́u�N������Ă�����ɓ��삷��v�悤�ȗv�f�͔��ɏ��Ȃ��A�N���l�����̏�ō���ĂȂ�Ƃ����삵�Ă��������̂��̂��Ǝv���܂��B �@�������A�ȒP�Ɋ�{�`�����l���Ă��������悤�ȁu���퓮��̂��߂̌��܂育���v������A���ꂼ���a���ɂ���ƍ������H������ɓ��삹���ɔY�ނ��ƂɂȂ�܂��B �@�E�E�E����A�K���ɍ���Ă���肪�N�����ɓ��삵���Ⴄ���b�L�[�ȏꍇ������܂����ǂˁB �@�u����Ȃ̍��܂����I�v�ƌ��J����̂͌l�̎��R�ł��B �@����̓d�q��H���I����g�o��u���O�͑�R����܂����A�����ɍڂ��Ă��镨�����̂܂܍���ē�����������ɓ��삷�邩�ǂ����́E�E�E �@��͂�u��鑤�v�̘r�O��m�����K�v�ł��B ���Ԏ� 2009/4/8
[�lj�] �@���łɁAC-MOS���W�b�NIC��4000�ԃV���[�Y���g�����ꍇ�̉�H�}�ł��B �@�u�����v�b�V����ON/OFF�ł���X�C�b�`(�����[)�v�u�d�q�I���^�l�[�g�X�C�b�`(�����[)�v����肽���Ƃ����������̉�H�}���Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@4000�ԃV���[�Y�͓d���d�����ő�18V�ł�����A�Ԃ�12V�ł��̂܂g���O�[�q���M�����[�^��5V�d�������K�v������܂���B�@�܂�4000�ԃV���[�Y�̓��͂̓V���~�b�g��H�ł͂���܂��AC-MOS���W�b�N���L�̓��͓����̂��߃`���^�����O�h�~��H���q�����イ�Ԃ�Ƀ`���^�����O��}���Č�쓮���h���܂��B(74HC76�̂悤�Ȃ������ȓ���͂��܂���) �@74HC76�Ƃ̓s���z�u���S���Ⴂ�܂��̂ʼn�H�}�͈قȂ�܂����A������̂ق����O�[�q���M�����[�^��IC���Q�g��74HC�V���[�Y�g�p�̉�H���͈��オ��ł��B(5V�d���������̂Ń����[��DC12V�p���K�v�ł�) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��Ԏ����肪�Ƃ�������܂��B �@�܂��͑���HP�̃T�|�[�g�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��A��ώ���Ȃ��Ƃ����ł����܂��āA�{���ɐ\����܂���ł����B �@���݂����ȏ��S�҂ł��������Ղ��悤�ɁA���ݍӂ��Ă������������肪�Ƃ�������܂��B�e���i�ɍ��߂�ꂽ�Ӗ������������ł����݂����ł��B �@�ꂩ��܂��`�������W�����Ă��������܂��B �@�܂���������Ɋ�{����d�C������Ă݂����Ǝv���܂��B �@�{���ɂ��肪�Ƃ�������܂����B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��͍�����ꂽ���̂������Ɠ����悤�ɉ���(?)���Ă݂Ă��������B �@���̌�́A�d�q�H����܂������̋@��ɂ����悤�ł����炿����ƕ������ق����ǂ��Ǝv���܂����A�ő��ɂ��Ȃ��̂ł������قǕ������Ƃ��A���̎��X�ŕK�v�ȏ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�܂�������鎞�ɁA�����Ƃ�������L���E��H�}���ڂ��Ă���Ƃ�����Q�l�ɍ�����̂悤�ȑ傫�ȃn�Y���͂��܂�����Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E �@����̎��ŕ��i���H�ɂ��ċ����������Ȃ�ꂽ�̂ł�����A�������Ō��\�ł����牽����H��g�ݗ��ĂȂ���V��Œ�����ƍK���ł��B ���Ԏ� 2009/4/8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 4/16 |
�@�����y�����q�������Ă��������Ă��܂��B �@���̋L���Ŏv����������܂����̂œ��e���܂����B �@�����ɏo�Ă���u7805�̎g�����v�u���W�b�N�h�b�̎g�����v�u�p�X�R���v�͎������l�̎��s�i���Ⴂ�H�j�����Ĕ��ɕs����ȉ�H���������������܂��B �@�d�q�H����n�߂����ɂ��ꂩ�l�Ɠ��l�A����������̒m���ō��n�߂��L�b�`���^�C�}�[������ł����B �@���ł������b�ɏo���܂����A�����͉��x�����W�b�N�̔z�����m�F���āu�Ԉ���ĂȂ��̂ɓ����Ȃ��v�u�h�b�����Ă��Ȃ����H�v�Ȃ�Ďv��������������̂ł��B �@�Ǘ��l����̔��ɒ��J�Ȑ����������Ȃ��炯�コ��̑O�����Ȏp���ɂ�����Ɗ������Ȃ����L���ł����B �@�G�z�Ȃ���ŋ߂̎Ԃ͎������Ȃǂ��}�C�R�����琧�䂷�鎖�������̂ŁA��������ςȂƂ�����V���[�g������Ƃ��̃}�C�R�������ʎ�������܂��B�ԗ��z�����͏\���ɋC�����Ă��������܂��悤���肢���܂��B Mojo �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�V�S�g�b�P�S��lj������^�C�v�A�S�O�O�O�Ԃł̉�H�S�č�邱�Ƃ��o���܂����B�R���f���T�̓�����g�����W�X�^�̂��Ƃ������Ȃ�ƂȂ��ł��������ł����悤�Ɏv���܂��B �@�S�O�O�O�Ԃ̂h�b�̉�H����Ԉ��肵�Ă��܂��̂ŁA��������ԂɎ��t���悤�Ǝv���Ă���܂��B �@������C�ɂȂ邱�Ƃ�����̂ł��B �@�d���𗎂Ƃ��Ă��玟�ɓd������ꂽ���Ƀ����[���n�m�ɂȂ�����n�e�e�ɂȂ����肵�܂��B�o����Ύn�߂͂n�e�e�̕����������̂ł����A����Ȃ��Ƃ͉\�ł��傤���H�������@������̂ł�����A�����Ԃ̋����Ō��\�ł��̂ŁA���`���X�������肢�v���܂��@�B �@�����J�Ȃ������A�������{���ɂ��肪�Ƃ�������܂����B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@������H�����삵�ĂȂɂ��ł��B �@�u���ɓd������ꂽ���Ƀ����[���n�m�ɂȂ�����n�e�e�ɂȂ����肵�܂��v�Ƃ������Ƃł����A����͂�����܂��ł��B �@���W�b�NIC�̏o��(���ɍ���g�p����FF�̂悤�ɁA�����̏���ێ�����悤�ȉ�H)�́w�d���������ɂ͕s��ł�(�ǂ��Ȃ邩�킩��Ȃ�)�x�B��������W�b�NIC���g�p�����ł̊�b�ƌ�������̂ł��B �@���ʂ͂����̋L���ł��悭�����Ă���u�p���[�I�����Z�b�g��H�v�Ƃ�����H���g���āA�d�������������ɂ͕K����H�����Z�b�g����悤�ɂ��āA�o�͂��s��ł͂Ȃ������Ə�����ԂŋN�������H�ɂ��܂��B �@������������Ӑ}�I�Ƀp���[�I�����Z�b�g��H�����Ă��܂����B �@����̉�H�̖ړI���u�����Ԃ̎������̃X�C�b�`�v������ł��B �@�����Ńs���Ɨ��Ȃ��l�́A�������Ԃɉ�H�𓋍ڂ��鎞�ɂ��Ԉ�����z�������Ă��܂��ł��傤�B �@�����Ԃ̎������̔z���𗝉����Ă���l�Ȃ�A���̉�H�̓d�����u�������q���[�Y�v������ł��傤�B �@�����ĊԈ���Ă`�b�b�d��(�A�N�Z�T���[�d��)�Ȃǂ���͎��Ȃ��Ǝv���܂��B �@�u�������q���[�Y�v�̓o�b�e���[�����ɓd�C����������Ă��āA�������r�₦�邱�Ƃ͂���܂����B �@�d������Ȃ��̂ł����炲����́u�d���𗎂Ƃ��Ă��玟�ɓd������ꂽ���v�Ƃ������Ԃ͔������Ȃ��킯�ŁA����ȐS�z�͂ǂ��ɂ������̂ł��B �@���������A������o�b�e���[���グ�Ă��܂��������A�o�b�e���[���������鎞���炢�ł��傤���B �@�Ԃ̎������̓L�[��}���ĂȂ��Ă��_���ł��܂���ˁB �@�l���Ԃ̒��Ŏ�������K�v�Ƃ���V�[���͎Ԃ��~�߂Ă��āA�G���W���������Ă��Ȃ����ł��N���肤��킯�ŁA�L�[��}���Ă��Ȃ��Ă��������͂��ł�������悤�Ɏ������q���[�Y�̓L�[�X�C�b�`�ʒu�ɊW�Ȃ��o�b�e���[�Ɍq�����Ă��܂��B �@���̎��������u�O����ł���납��ł����삷��X�C�b�`�v�Ȃ̂ł�����A���R�L�[��}���Ă����Ԃɂ͊W�Ȃ�����ł��Ȃ���Ȃ�܂����B �@������A���̓_����H�̓d�����������̃����v��_��������ׂ̓d��(�q���[�Y)������̂����R�Ȃ킯�ŁA�����͐�邱�Ƃ̖����d���ł�����p���[�I�����Z�b�g��H�͕s�v�Ȃ킯�ł��B �@�܂����A���̉�H�̓d����ACC�d���Ȃǂ������āu�L�[���Ă��鎞��������ł��Ȃ��X�C�b�`�v�Ȃ�Ă����i���Z���X�ȕ�����낤�Ƃ���Ă���̂Ȃ�b�͕ʂł����E�E�E �@����Ƃ��A�u�`���C���h���b�N�v(�Ƃ͏����Ⴂ�܂���)�̂悤�ɑO�ʼn^�]�҂��L�[��ON�ɂ��Ă���Ԃ������������{�^������ł��Ȃ��悤�ɂ������Ƃ��A������������ȗp�r�Ŏg�p�����̂ł�����p���[�I�����Z�b�g��H���K�v�ł��ˁB 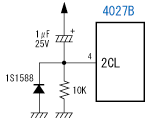 �� ��������ȗp�r�Ŏg�p��������
�� ��������ȗp�r�Ŏg�p���������� �����o�b�e���[���オ��ꍇ �� �K���[�W�ɓ���Ă���Ԃɉ����̃g���u���ł��̉�H�̓d�����ؒf����āA�ēx�d���������Ď������������ςȂ��ɂȂ��ăo�b�e���[�オ��ɂȂ�Ȃ����C�ɂȂ��Ė�����ꂸ��10�������ɃK���[�W�ɍs���Ă��܂��ꍇ �@�����ɊY�����鎞�ɂ͓d���͐��悤�ȏ�������A�p���[�I�����Z�b�g��H��t���Ă������ق����ǂ��ł��傤�B �@���̉�H�̏���d����C-MOS IC���g���Ă��邨�����őҋ@���͐��\�}�C�N���A���y�A���x�ŁA�قړd�C������Ȃ��̂Ŏ������q���[�Y����d��������Ă����̉�H�̏���Ńo�b�e���[���オ��悤�Ȏ��͂���܂���B ���Ԏ� 2009/4/23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�v���ʂ�̉�H���������܂����B �@�Ǘ��l�l�̂��������ʂ�A���������q��������ɑ��삷��̂ł��B�Q�x�o�b�e���[���オ��܂����B���̉�H��g�ݍ��݁A�d���͂`�b�b�����낤�Ǝv���Ă���܂��B�G���W���������ԂŎ�������_���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��̂ŁA���̕����ǂ��̂ł��B���ׂ̈̓d���������͂n�e�e���ǂ������̂ł��B �@�{���ɖڂ���A���ӂ��Ă���܂��B���肪�Ƃ�������܂����B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ԂŐF�X�ȕ����Ɂu�`���C���h���b�N�̂悤�ȕ��v��t�������Ƃ�������]�͂悭���܂��B �@��{�I�ɂ́u���[�J�[���Ή����Ă����������̂��E�E�E�v�Ƃ����悤�ȉ�������Ȃ̂ŎԂ�ԍڋ@��̐v�̂����������ɂ͕����Ă��܂��B �@�u�J�[�I�[�f�B�I��c��������ɐG��̂ŁA�X�C�b�`�ނ�S���֎~�ɂ���B���X�C�b�`���~�����v�Ƃ��B �@�u�W�ł��t���Ă����Ă��������B�v�Ƃ������Ԏ��ł��܂���ł����B ���Ԏ� 2009/4/24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԁE�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�������������̂ł����A�ǂ̂悤�ȉ�H���l�����܂����A���肢�v���܂��B �@���݂̔z����12V���E�C���J�[�����[����č��E�̃X�C�b�`���A�e�E�C���J�[�Ɍq�����Ă��܂��B�����Ƀ|�W�V�����̋@�\�������������Ǝv���Ă��܂��B �݂͂� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�E�C���J�[�����v���펞�_�������ă|�W�V�������ɂ���A�Ƃ������͎̂��͏��߂Ēm��܂����B �@���ׂČ���ƁA�����ƍ��Έ�@�ł͖����悤�ł��ˁB �E�g�p����Ă���E�C���J�[�����[�́u�Q�����v �E�|�W�V�������ɂ́u�����v�������� �E�E�C���J�[�_�ł��畜�A����ۂɁu�������_���v�������� �E�E�C���J�[���͂P�O�v �Ƃ������v�]�ł��̂ŁA�����ʼn�H�}�������Ă݂܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�E�E�E�E���\�������肵����H�}�ɂȂ�܂����B �@��{�́u�o�v�l����ɂ�钲����H�v�ł��B �@OP�A���vIC LM324���g�p�����O�p�g���U��H�ƁA���͓d���ɂ���ăX���b�V�����h(�������l)�d�������߂ĎO�p�g�Ɣ�r���邱�Ƃŏo�͂�0�`100���̊Ԃ��o�v�l�R���g���[������d�͐����H�ł��B �@��b�́u�Ԃ̃G�A�R�����ǂ��ADC12�t�@���̕��ʒ��߉�H�v�Ɠ����ł��B �� �E�C���J�[���_�ł��Ă��Ȃ��� (���펞) �@���E�Ɨ��̂o�v�l�R���g���[����H�ɂ���āA�E�C���J�[��������(����)��Ԃœ_�����܂��B �@�o�v�l����ł�����A�g�p�o���u�͏]���̃t�B�������g�d���ł��k�d�c���ł��ǂ���ł������ł��܂��B(�k�d�c�����g�p���ăn�C�t���ɂȂ�ꍇ�̓n�C�t����͂��Ă�������) �@���邳��VR1�EVR3�Œ��߂��܂��B �@���邳���߂����E�Ɨ��ŕʁX�ɒ��߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂�����Ɩʓ|�ł����A�P�̔��Œ��R�ō��E�����̉�H�ɒ��ߗp�̓d����^���āA��̓_�œ��쎞�̐���ɂ��ꂼ��̔��Α��̉�H���e�����Ȃ��悤�ɂ���ɂ͂����������i���������ĉ�H�����G�ɂȂ�̂ŁA����͍��E�̉�H���ʂɍ���Ē��ߗp�̔��Œ��R���ʁX�ɂȂ��Ă��܂��B �@�����ȒP�ɍ���Ԃ�A�ŏ��ɒ��߂��鎞�ɂ͂ق�̏���������Ԃ������܂��B �@���̒�����H�ɂ́u�������_���v�@�\���t���Ă��܂��̂ŁA�o�C�N�̃L�[���ēd������ꂽ���ɂ��������炶��`���Ƃ������_�����͂��߂܂��B �@�܂����̋@�\�̂��߂Ɂu���邳�v�߂��锼�Œ��R���Ă��A���ۂ̓d���̖��邳���ς�̂ɂق�̏����^�C�����O������܂��B �@���邳�߂��鎞�ɂ́u�x���v�̔��Œ��R�͍Œ�ɉĂ������ق������߂����₷���ł��B(�Œ�ł������x��܂�) �� �E�C���J�[�_�Ŏ� �@�E�C���J�[�X�C�b�`��ON�ɂȂ�A�E�C���J�[�����[��ʂ��Ă��̉�H�̓��͂ɓd���������ƁA��������m���ăg�����W�X�^(2SC1815)�������A�o�v�l������d���ɂȂ��Ă���d���R���f���T(10��F)����d�����܂��B �@����d����0V�ɂȂ�̂ło�v�l�o�͂�0%�ƂȂ�A������H����E�C���J�[����_��������@�\�͒�~���������܂��B(�Ԍ��Ή�) �@�E�C���J�[�_�Œ��͂��̕��d��H�̓����Ō�����Ԃł͓_�������A�E�C���J�[�����[�o�R�ŋ��������_�ŏ�Ԃ̃E�C���J�[�_���d�����V���b�g�L�[�o���A�_�C�I�[�h��ʂ��Ē��ڃE�C���J�[���ɋ������邱�ƂŃ����[�̓_�Ŏ����ŃE�C���J�[��_�ł����܂��B (������o�v�l�_����H���̏Ⴕ�Ă��A�E�C���J�[�͒ʏ�ʂ�_�ł��܂�) �� �E�C���J�[��������� �@�E�C���J�[�̓_�ł��I������ƁA���d��~��H�͓����Ȃ��Ȃ�܂��̂œd���R���f���T�́u�x���v���Œ��RVR2�EVR4��R8�ER14���o�R���āu�������Ɓv����d���܂ŏ[�d����܂��B �@���́u�������[�d�v��H�̓����ŃE�C���J�[OFF���班���o���Ă��炶��`���ƌ��̌�����Ԃɖ߂�܂��B �@�A���A�ݒ肪���܂�Â��Ɓu����`�v���Ƃ͌������Ɂu�X�b�v�Ɠ_�����Ă��܂��悤�Ɍ�����ł��傤�B �� ���� �@���ߌ��́u���邳�v�Ɓu�x���v�̔��Œ��R�����ł��̂Œ����I�ɒ��߂��Ă���������Ǝv���܂��B �@���D�݂̖��邳�ƁA����`���Ɠ_������x�����Ԃ߂��Ă��������B �@12V�̃o�C�N/�ԗp�́u�E�C���J�[�����[�v�͎����Ă��Ȃ��̂ŁA�܂��̓E�C���J�[�����[�������(��)���ꂩ��{��H�̓���e�X�g���s���܂������A���ɑ傫�Ȗ��͖����Ǝv���܂��B �@�E�C���J�[�����[�̓������߂��Ȃ�Ƃ����삷��M���M�����x�ɂ��Ă����ƁA�d���ڌq�������ɂ́u�J�`�J�`�v�Ɛ���ɓ��삵�܂������A�_�C�I�[�h�������œd���Ɍq���Ɠd���s���ɂȂ蓮�삵�Ȃ��Ȃ�܂����B �@���ʂ͎s�̂̃E�C���J�[�����[�͂���ȃ^�C�g�Ȑݒ�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A�_�C�I�[�h��ʂ����{��H���q�����ꍇ�ɃE�C���J�[�����[�����삵�Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ́A�悭����u�n�C�t����v�Ɠ����悤�ɓK���Ȓ�R���E�C���J�[�X�C�b�`�̌�ɂ��Ă��������B �@���A��H�I�ɂ͖@�I�ɖ�肪�����g�p���@���ł���悤�ɐv���Ă��܂����A�^�p�ɂ������Ă͈�@�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��イ�Ԃ�ɒ��ӂ��Ă��g�p���������B ���Ԏ� 2009/4/1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Z���������肪�Ƃ��������܂��B �@�ŏ��̓|�W�V�����̋@�\���������邾����������A�����[���g���č�낤�Ǝv���Ă����̂ł����A���܂��܂��̋@�\���������o�C�N���������Ă��܂����̂ł��A�����Ŏ�������낤�Ƃ��낢�뒲�l�����̂ł��A�����l���������Ă�����͂�������悤�ŁAHP��ʼn�H�������̂ł����F����Â��Ă��āA�����[�������Ă�����������Ȃ��Ȃ����삷��܂ł͍s���Ȃ������̂ł��B �@IC��Ő���o����̂ŁA�������삵�悤�Ǝv���܂��B �݂͂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[�̌����Ń����[�Łu�|�W�V�������v�u�E�C���J�[���v���ւ���ΊȒP�ɍ�鎖���ł��܂��ˁB�A�����̏ꍇ�ł��u�����v�̉�H�͉����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł��B �@�����d�q���i��PIC�}�C�R���Ȃ��g���ăX�C�b�`����Œ���/�_�ł�ؑւł���E�C���J�[�����[���̂�v���Ă��܂��Ƃ������@������܂��ˁB �@����̓o�C�N�̃E�C���J�[�����[��X�C�b�`�܂��ɂ͉����͂����A�P�ɃE�C���J�[���ɍs���Ă���z���̊Ԃɋ��ނ����ō쓮����Ƃ����A�������Ɋy�ȕ��@�ōl���Ă��܂��B �@�g�p���i��IC��ƃg�����W�X�^�EFET�ȂǁA���Ȃ菭�Ȃ����i�ŖړI��B���ł��܂����̂ŁA���А��삵�Ă݂Ă��������B �@���ƁA����̉�H�͍��E�Ɨ��ŁA�E�C���J�[���ɂ́u�_�ł��Ă��Ȃ����v�̓|�W�V�������̂܂܂ł��B(USA���ƌ����炵���ł�) �@�E�C���J�[���ɗ����̒����������Ă��܂������ꍇ�͂�����Ɖ�H��ς��ĘA�����ɂ��ł��܂����A�ǂ����Łu�E�C���J�[���ɔ��Α��ɉe����^����͎̂Ԍ��ɒʂ�Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����L�q�������̂ł������Ă��܂��B�s�̂̉����p���j�b�g�ł͘A����(�Ɨ����ɃX�C�b�`�Őؑւ���)�̂��̂�����悤�ł��ˁB ���Ԏ� 2009/4/2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�͂��߂܂��āB �l�b�g��p�j���Ă���܂�����A������̃T�C�g�����R��������ȗ��Q�l�ɂ����Ă��������Ă���܂��B �����₳���Ă����������e�Ȃ̂ł����A�ȑO�ق��̕��������₳��Ă������e�́u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v�ɂ��ĂȂ̂ł����A���̉�H�}�����ɐ��삳���Ă��������܂����B �����ŋ@�\�̒lj��ɂ��Ă̎���ɂȂ�̂ł����A �������_���@�\�̂���������������E�E�E�Ƃ������ɂȂ�܂��B �����̃E�C���J�[��LED�ɂȂ��Ă���܂��āA���邳�A�x���̑o����F�X�������Ă݂܂������ǂ����������ő�P�x�܂łł͂Ȃ��A���ς��ƍő�P�x�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �d���ɑւ��Ď����Ă݂�Ƃ��������i�l�I�Ȋ��z�Ő\����܂��j�ł����̂�LED�ł��������ɂȂ�Ȃ����Ǝv���܂��Ă����₳���Ă��������Ă���܂��B ���Z�����Ƃ���\�������܂��A�ȂɂƂ����낵�����肢�������܂��B kuro �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�I�[�g�o�C�̃E�C���J�[�Ƀ|�W�V�����̋@�\�v�̉�H�ł́A���邳�̐����PWM�ōs���Ă���̂�LED�ł��d���ł��قƂ�Ǔ����悤�ɂڂ�`���Ɩ��邭�Ȃ�܂��B�����ς݂ł��B �@�ł��̂�������LED�Ή��̉�H�ł��B �@LED�ł͂��ς��Ɠ_�����Ă��܂��̂́APWM�ł͂Ȃ��d����������̉�H�ł͂悭����b�ł����A���̉�H�ł͂��̂悤�Ȏ��͋N����Ȃ��͂��Ȃ̂ł����B �@������ŏ������悤�� >�A���A�ݒ肪���܂�Â��Ɓu����`�v���Ƃ͌������Ɂu�X�b�v�Ɠ_�����Ă��܂��悤�Ɍ�����ł��傤�B �Ƃ����悤�ȏǏ�ł͂���܂��H �@�d���ł͖��邳���߂�ڂ�`���Ƃ������_�����Ă���̂ł������H�̐���ɂ͊ԈႢ�͖����Ƃ͎v���܂����A�ȉ��̓_���m�F�E�ύX���Ă��������B (1) PWM��H�̐���s� �@�u�x���vVR���O�I�[���̈ʒu�ɂ��āA�u���邳�vVR�����邮�����A���̂��邮��ʒu�ɉ�����LED�̖��邳�͕ς�܂����H �@�ʒu�ɏu���ɉ������ĕς�APWM�ɂ�閾�邳���߉�H�͐��������삳��Ă���̂�(2)�ɐi�݂܂��B �@���߂Ȃ琻��~�X�ł��B (2) �x�����Ԃ̊m�F�ƕύX �@�u�x���vVR��K���Ȉʒu�ɉāA10��F�̓d���R���f���T�̗��[�d�����e�X�^�[�Ōv���āA�E�C���J�[�_�Œ����قڂO�u(���������_�łɂ��킹�ėh�炬�܂�)�A�_�ł��I������炶��`���Ɓu���邳�vVR�Őݒ肵���d���܂ł�����莞�Ԃ������ďオ���Ă��邩�ǂ����B �@���ꂪ�������ł͂Ȃ��Ĉ�u�ŏオ��悤�Ȃ�u�x���vVR�܂��̐���~�X�ł��B �@�������d�����オ��̂�LED�����ς��Ɠ_������Ȃ�A�u�x���vVR��200K������1M���̕i�ɕύX�����x�����Ԃ��������A����ł��ڂ�`���ƂȂ�Ȃ����m�F���Ă��������B �@�Ȃ�Ȃ��ꍇ�A�{��H�ȊO�ɃE�C���J�[�����[���ʏ�i�łȂ��Ƃ��A���Ɍ���������\��������܂��B �@����ňꉞ�͂ڂ�`���ƂȂ邪�A����ł��܂�������莞�Ԃ��Z���đ����_�����Ă��܂��Ȃ�A�X��1M���̒�R���u�x���vVR�ƒ���ɓ����Ȃǂ��Ă��������B�����܂ł���Ɠd���Ȃǂł͂ƂĂ��x���đ�ώg���Â炢��H�ɂȂ�܂��B ���Ԏ� 2010/5/10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�����̉A���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B ���u�x���vVR���O�I�[���̈ʒu�ɂ��āA�u���邳�vVR�����邮�����A���̂��邮��ʒu�ɉ�����LED�̖��邳�͕ς�܂����H �Ȃ̂ł����A���Ȃ����邳�͒��߂ł��܂����B �����͈͂�3/5�������LED�͖��邳MAX�A�d���Ȃ�4/5���炢�Ŗ��邳MAX�E�E�E�Ƃ����������ł��B ���x���vVR��K���Ȉʒu�ɉāA10��F�̓d���R���f���T�̗��[�d�����e�X�^�[�Ōv���� �������Ɠd���͂������Ă��܂��B��3.5V���炢����_�����n��3.8���炢�łƂ܂銴���ł��B ���u�x���vVR��200K������1M���̕i�ɕύX���Ēx�����Ԃ������� �茳��1M����VR������܂����̂Ō������Ă݂܂����B �x�����Ԃ͂��Ȃ蒷���Ȃ�܂������A�_�����n�߂����ȁH�Ǝv���Ƃ����ݒ�̖��邳�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�iLED�j �d���̏ꍇ�́u�ځ[�[�[��[�[�[���v�Ƃ��������ł���ɂ��������������̂ł����E�E�E �j���A���X�Ȃ̂ł��`�����ɂ����̂ł����A��]�͂��́u�ځ[�[�[��[�[�[���v�Ƃ����悤�Ȋ����Ȃ̂ł��B �܂��x��VR��1M���̒�R�͂܂����܂��Ă���܂���̂Ŏ����Ă݂܂��B kuro �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�P�������Ă���悤�Ȃ̂ŁB �@���̉�H�ł́u�x���v���Ԃ́A�u(�E�C���J�[OFF����)�����v���_�����͂��߂�܂ł̎����v�ł͂Ȃ��A�u(�E�C���J�[OFF����)���炭�������鎞�ԂƁA�����v���_�����͂�����(����`�Ɠ_������ߒ�)���܂ށA�����v���ݒ�̖��邳�ɂȂ�܂őS�Ă̎����v�ł��B �@�����āE�E�E����L�����ɂ������Ă��܂��悤�� >�A���A�ݒ肪���܂�Â��Ɓu����`�v���Ƃ͌������Ɂu�X�b�v�Ɠ_�����Ă��܂��悤�Ɍ�����ł��傤�B �Ƃ�������ɂȂ�̂ł����A3.8V�Ȃ�Ă����Ⴂ�d��(���Â�)�ꍇ�͂܂��ɂ���ɂ�����A�_���J�n�d��(��3.6V)����ݒ�d��(3.8V)�܂ł̊ԂȂ��������0.2V���������悤�Ȏg�����ł́A�قڈ�u�œ_������悤�Ɍ����Ă�����܂��ł��B �@PWM�̊�M���ł���O�p�g�͖�3.6�`10V(�d��12V��)�̊ԂŃX�C���O���Ă��܂��B �@����ɑ��Ă������_���p�̃R���f���T�̓d����0�`�ݒ�d���̊Ԃŏ[�d����܂�����A0�`3.6V�̊Ԃ͑S���_�����܂����B �@���̓d���͈ꌩ���_�Ɍ����܂����A�E�C���J�[�̎w�����E�C���J�[���ւ̋��d�ł����m�邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A���̋��d�̓E�C���J�[�̓_�Ŏ����Œf�����邽�߂ɒf�����̊��Ԃ����Ƃ��d�C����Ă�����̓X�C�b�`����ꂽ�̂��A�_�ł́g�Łh�̊��Ԃ��͓d�C�I�ɂ͂킩��܂���A�d�C�I�ɂ͂ǂ���̏ꍇ���R���f���T�ɂ͏[�d���͂��܂�܂�������ő������v�̓_�����J�n����ƃE�C���J�[�_�Œ��ɂ��ڂ���_�����Ă��܂��A����@�Œ�߂�ꂽ�_�Œ��ɂ͊��S�ɏ�������Ƃ����K��ɉ���Ȃ��Ȃ�܂��B �@�����Łu�O�p�g�̍Œ�d��3.6V�ɒB����܂ł͌���Ȃ��v�Ƃ��������𗘗p���āA�E�C���J�[�_�ł́g�_�h�ŕ��d�����R���f���T�d�����g�Łh�ŏ[�d����ď㏸���Ă��A���́g�Łh���Ԃł͑S�R3.6V�ɒB���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃœ_�Œ��Ɍ���ē_�����Ȃ��悤�ȕی�@�\�ɂȂ��Ă��܂��B �@�����Ă����ݒ�d����3.8V�Ȃ�Ă����Ⴂ�d���ɂ��Ă��܂����ꍇ�A�x�����Ԓ��̂͂��߂���قڍŌ�߂���0�`3.6V�̊��Ԃ͏����ŁA3.6�`3.8V�Ƃ��������킸���̊Ԃłڂ�`�Ɩ��邭�Ȃ�̂ŁA���Ԕ�ōl����Γ��R�����Ƃ����Ԃɖ��邭�Ȃ��Ă��܂��悤�Ɍ����邱�Ƃ͂��������������邩�Ǝv���܂��B �@������12V��LED�����Ȃ��Ŗ��邳�Ȃǂ�ڂŌ��Ċm���߂āA�܂�������Ȓ�d���ɐݒ肵�Ďg�����Ƃ͖����Ǝv���Ă����̂ł����E�E�E�B 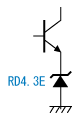 �@�R���f���T���[�d�Ȑ��Ȃǂ���l���āA�[�d���Ԃ̂�����L�̌�_���h�~���Ԃ͒Z���A�������_���J�n���犮���܂ł̎��Ԃ͉����Ƃ�����₱��������]��������ɂ́E�E�E�E�}�̂悤�Ƀg�����W�X�^�̃G�~�b�^��GND�̊Ԃ�4.3V�̃c�F�i�[�_�C�I�[�h�����ĕ��d���̍Œ�d����GND���x������グ�Ă��������B
�@�R���f���T���[�d�Ȑ��Ȃǂ���l���āA�[�d���Ԃ̂�����L�̌�_���h�~���Ԃ͒Z���A�������_���J�n���犮���܂ł̎��Ԃ͉����Ƃ�����₱��������]��������ɂ́E�E�E�E�}�̂悤�Ƀg�����W�X�^�̃G�~�b�^��GND�̊Ԃ�4.3V�̃c�F�i�[�_�C�I�[�h�����ĕ��d���̍Œ�d����GND���x������グ�Ă��������B�@RD4.3E���g�p�����ꍇ�ɂ���3.5V�O���ɂȂ�܂��B �@����ŕ��d���ɂ�3.5V�ɕ��d���A�[�d���ɂ�3.5��3.8V�܂ł̕ω��ɂȂ�̂ŁA�x�����Ԓ��̓_���ω����Ԃ̕����S�̂̎��Ԃ̒��Ő�߂銄�����傫���Ȃ��āA�������_�����Ă���悤�Ɍ����܂��B �@��{�̉�H�œ��ɖ�肪�����ꍇ(�ݒ�d����S�̂̒��ʂŎg���ꍇ)�͂��̂悤�ȉ����͂��Ȃ��ł��������B �@�E�C���J�[�_�Œ��ɓ_���J�n���Ă��܂��āA��@�ȃE�C���J�[�ɂȂ��Ė��ƂȂ�ꍇ������܂��B ���Ԏ� 2010/5/25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�������A�����肪�Ƃ��������܂��B �����A�茳�ɂ���3.2V�̃c�F�i�[�_�C�I�[�h�������ɓ���Ă݂��Ƃ���A�܂��������z�ʂ�̍쓮�����Ă���܂����I�I ���̋x�݂ɂł����{���ɍs���Ă�����4.3V�̃c�F�i�[���Ă��悤���Ǝv���Ă���܂��B ���N�Ԃ�ɔ��c���Ă�����A�����ȕ��̉�H�������Č��܂������A�Ȃ��Ȃ����z�ʂ�ɂ͍s�����������肵�Ă���܂��������z�����Ȃ��đ喞���ł��B �F�X���ׂĂ��邤����PIC�Ƃ����}�C�R���ł�PWM������o����ƒm�葁�����C�^�[���w�����A�������܉������Ў�Ƀv���O�����̕����ł��B�ł����A�Ƃ�������͂萻��ł��郌�x���ɂȂ�܂Ŏ��Ԃ������肻���ł��E�E�E �d�q�H��A�y�����ł��ˁB�f�l�Ȃ���ɏ����́u���������āA���������āE�E�E�v�Ɩϑz���Ă���܂��B �ƂĂ����ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B kuro �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���茳��3.2V�̃c�F�i�[�������āA�����e�X�g�ł��Ă悩�����ł��ˁB �@���{���ɕ��i�B�ɍs�������ɁA4.3V�ȊO��3.6V���������āA�ǂꂪ��Ԃ��D�݂ɍ�������������邩��r���Ă݂�̂������Ǝv���܂��B �@����ł́A�c�F�i�[���āA�ŏI�I�ɂ���]�̕��������������邱�Ƃ����F�肵�Ă��܂��B ���Ԏ� 2010/5/28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���d�ǃt���C���O������X�^�[�g�V�O�i���̐��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB �@����A�X�^�[�g�V�O�i���̐�����l���Ă���̂ł����A�Ȃ��Ȃ���肭�쓮�����鎖���o�����A������̂��͂�q�ł�����Ǝv�����e�����Ă��������܂����B �@�܂��A����͂S�̂k�d�c�p�l���i�k�d�c����p�l���R�O���x�j�����Ԃɓ_���A���������čs���V�X�e���ŁA�_���ɂ��킹�āA�s�B�E�s�B�E�s�B�E�|�[���ƃu�U�[��点�܂��B �@�X�^�[�g�{�^�������������ɂQ�b�قǃu�A�u�A�u�ƃX�^�[�g���}�̂悤�Ƀu�T�[������Ƃ����̂ł����B �@���̉�H���ƈꗗ�́A�~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐���AF-1���X�^�[�g�V�O�i���̐���ALED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��)�Ȃǂ��Q�l�ɂ��č�ꂻ���ł������ALapRecorder 2000���g�p���Č��d�ǃV�X�e���ɂ��v�����X�^�[�g�V�O�i����H�Ƌ��ɍ쓮���������̂ł��B �@��̂̓��쏇���� �@�X�^�[�g�{�^�����������X�^�[�g�V�O�i�����쓮���ԁA�ԁA���A�Ɠ_���A���_���Ɠ����Ɍv���X�^�[�g�B�܂��A�X�^�[�g���ɗΓ_���O�ɃX�^�[�g�̌��d�ǂ��ƁA�t���C���O�Ƃ��ău�A�u�A�u�A�ƃu�U�[�Ɨ̂k�d�c��_�łŒm�点�����̂ł��B �@���݂�LapRecorder 2000���g�p���Č��d�ǃV�X�e���Ōv�������Ă���̂ł����A�V�O�i�����g�p���č쓮������t���[�`���[�g�܂ł͏o�����̂ł����A�̐S�̉�H���o�����ɂ��܂��B �@����������ł��������Ă��������邩�s���ł����A�X�������肢�������܂��B �Ղꂳ�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�uLapRecorder 2000�v�Ƃ����\�t�g�͏��߂Ēm��܂������AHelp�t�@�C����ǂ�ł��O���̑��u�ƘA����������A�O������R���g���[������悤�ɂ͏o���Ă��܂���ˁB �@�Ƃ������́A�����ɂȂ�ꂽ���V�O�i�����u�ƃp�\�R���͘A���ł��܂���A�����ɂȂ�u�X�^�[�g�X�C�b�`�v�̓V�O�i���삳���邱�Ƃ͂ł��Ă��A�uLapRecorder 2000�v�̃X�^�[�g�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������ŋX�����̂ł��ˁB �@�u�X�^�[�g�X�C�b�`�v�������O�ɁuLapRecorder 2000�v�̊J�n�{�^�����}�E�X�ŃN���b�N���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B �@���̏�Łu�W���J�[�i���[�h�v�Ōv��������Ƃ����菇�ł�낵���̂ł��傤���H �@���������������B �@���Ɂu�X�^�[�g�{�^�������������ɂQ�b�قǃu�A�u�A�u�Ɓv�Ƃ������ł����A�X�^�[�g�{�^�����������畁�ʂ̓V�O�i�����_��������̂ł����A�V�O�i�����_�����ăs�E�s�E�s�A�{�[���ƃJ�E���g�_�E�����鉹�Ƃ��̃u�A�u�A�u�����d�Ȃ��Ĕ������Ă��܂��Ă���낵���̂ł��傤���H �@����Ƃ��u�A�u�A�u�Ɩ�ꏊ�ƃs�E�s�E�s�A�{�[���Ɩ�ꏊ�͗���Ă��ĉ��͕������Ȃ��̂ł��傤���H �@�t���C���O���o�ɂ��āB �@�t���C���O�����o�����ꍇ���Ƌ��Ɂu�̓_�Łv�Ƃ������Ƃł����A���_��(�_�łł���)����Ƃ������͐l�ԍH�w�I�Ɂu�X�^�[�g�V�O�i���̓_���v�ƌ�F���܂��H �@���ʂ́u�Ԃ܂��͉��F�����̑S�����v�̓_�Łv�Ȃǂňُ��m�点��̂ł����A��_�ł������@�Ƃ����̂́A���������Ď��̒m��Ȃ����������[�E���[�X�Ǝ��̃��[���ł����������@�����݂���̂ł��傤���H �@�����̌������[�X�ł��������Γ_�ł��g���Ă���̂Ȃ炻��ɂ��킹��̂��ǂ��̂ł��傤���A�c�O�Ȃ��玄�͂����������[�X���������Ƃ������̂ŁA�Q�l�܂łɂǂ����Ŏg���Ă���̂ł����炨�������������B �@���Ƃ���͉�H�}�̐v�Ȃǂɂ͊W����܂��A�C�ɂȂ�̂Ŏ��₳���Ă��������܂��B �@�uLapRecorder 2000�v�ɂ̓h���b�O���[�X���[�h�ŃV�O�i����_��������@�\���lj�����Ă��܂����A����p�̉�H�𗘗p����Ղꂳ��l�̂���]�̃V�O�i��(�S�_)�_���A�����ă\�t�g��ł̃t���C���O���o�E�V�O�i���\���Ȃǂ͑S�āuLapRecorder 2000�v�Ŏ����\�ł��BIC��H�ŕ��G�ȉ�H������肸���ƃV���v���ł��B �@�uLapRecorder 2000�v�̍�҂̕��ɑ��k����Ƃ������@�͂����ɂȂ�܂������H(�f��ꂽ����u�C�̖����v�ɗ����H) �@�Ղꂳ��l�̓��͂���܂������[���A�h���X�ł̓G���[�ɂȂ育�A���⎿�⎖�������͂��ł��܂���ł����̂ŁA����ł�������͌��J�ł����Ē����܂����B ���Ԏ� 2009/3/23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��A���ؐ��ɗL��������܂��B �@�܂��A���t���肸�Ő\�������܂���B �@�܂��A���[���A�h���X���L���~�X�̗l�ł����f�����|���������܂����B �@�܂��ALapRecorder 2000�̃\�t�g��ł̏������͍l���Ă��܂���ł����B �@�O�����u�ɂăX�^�[�g�V�O�i�����쓮�������������ׂł��B �@���̈׃h���b�N���[�h�̃V�O�i���̎g�p�Ȃǂ͌������Ă��܂���ł����B >�@�u�X�^�[�g�X�C�b�`�v�������O�ɁuLapRecorder 2000�v�̊J�n�{�^�����}�E�X�ŃN���b�N���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���̏�Łu�W���J�[�i���[�h�v�Ōv��������Ƃ����菇�ł�낵���̂ł��傤���H �@���̒ʂ�ł��B �@�܂��A�W���J�[�i�̌v���Ŏg�p���Ă��܂����A�Ԃł͖����A�I�[�g�o�C�̃W���J�[�i�Ŏg�p���܂��B �@�X�^�[�g�{�^����̃u�A�u�A�u�ƌ��������ɕt���Ă̓X�^�[�g�̍��}�̂���ł����B�Ȃ̂Ŗ����Ă��ǂ��̂ł����B >�@�t���C���O���o�ɂ��āB �@�t���C���O�����o�����ꍇ���Ƌ��Ɂu�̓_�Łv�Ƃ������Ƃł����A���_��(�_�łł���)����Ƃ������͐l�ԍH�w�I�Ɂu�X�^�[�g�V�O�i���̓_���v�ƌ�F���܂��H �@���ʂ́u�Ԃ܂��͉��F�����̑S�����v�̓_�Łv�Ȃǂňُ��m�点��̂ł� �@�S�������ċ�Ƃ���ł��ˁB���������ċC���t���܂����B �@���p������������ł��B �@�܂Ƃ߂܂��ƁA�V�O�i�����̂͌v����Ƃ͓Ɨ����Ă��āA�̐M���i�_���j�ŁALapRecorder 2000�̃X�^�[�g�̐M�����o����n�j�Ȃ̂ł��B �@�t���C���O��Ԃł��̐M����LapRecorder 2000�ɑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B �@���[�X�̌v�����͍̂s���ׂł��B �@�܂��A��肭�Z�߂��Ă��܂��A���������Ă��������܂��ł��傤���H �Ղꂳ�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
>�̐M���i�_���j�ŁALapRecorder 2000�̃X�^�[�g�̐M�����o����n�j�Ȃ̂ł��B �@�Ƃ�������͕s�v�ł���ˁB(����Ƃ���q����悤�ȓ���Ȍv�����s���̂ł����H) (1) �u�X�^�[�g�̐M���v�Ƃ������̂�LapRecorder 2000�̑���J�n(�\�t�g�̓�����J�n����)���Ӗ�����̂ł���A����͂ł��Ȃ�����蓮�œ���J�n����(�}�E�X�ŃN���b�N)�����Ă���V�O�i���͕ʓr���삷��Ƃ����`�ɂȂ�Ə����܂����B (2) �u�X�^�[�g�v�ʒu�̌��d�ǂ̐M����LapRecorder 2000�Ɂu�����v���_���܂œ`�B���Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��Łu�X�^�[�g�M�����o����v�����ƁA����ȍ~�́u�t���C���O�ł�����͂���v�Ƃ����������Ƒ������Ă��܂��܂��B �@�����v���_������O�ł��A���d�ǂ̔����M����LapRecorder 2000�ɓ`����K�v������(�t���C���O�ł��^�C������)�̂ł���A�V�O�i���̏�Ԃɂ͑S���W�Ȃ����d�ǂ�LapRecorder 2000�͂Ȃ�����ςȂ�(���ɐؒf�����͂��Ȃ�)�Ƃ������ł悢�킯�ł���ˁB �@����Ƃ��A��������ʂ̃W���J�[�i�ł̃^�C������Ƃ͈Ⴂ�A�܂�ŃT�[�L�b�g���[�h�̂悤���u�����v�Ŏ�(�o�C�N)���X�^�[�g�����Ƃ݂Ȃ��āA�����v���_���Ɠ�����LapRecorder 2000�ɂ̓X�^�[�g���d�ǂ̐M�����[���I�ɑ���B�����Ă���ȍ~�͎��ۂɎ�(�o�C�N)���X�^�[�g�ʒu��ʉ߂��Ă����d�ǂ̐M���̓J�b�g���Ă����Ė{���̎�(�o�C�N)�̃X�^�[�g�^�C���͖�������B�v�u�X�ɂ��̌�̓^�C�}�[�������ŋ[���[���^�C���X�^�[�g�M����H�͉������āA��(�o�C�N)���P�k�`�o���ăX�^�[�g�n�_��ʉ߂������ɂ͌��d�ǂ̐M���͂��̂܂�LapRecorder 2000�ɓ`���ă^�C���v�����s���v�E�E�E�Ƃ����悤�ȕs�v�c�Ȍv���V�X�e���삳�ꂽ���̂ł��傤���H �@�u�̐M���i�_���j�ŁALapRecorder 2000�̃X�^�[�g�̐M�����o����n�j�Ȃ̂ł��B�v�Ƃ�������]���ǂ̂悤�ȈӖ��Ȃ̂��A������Ƃ킩�肩�˂܂��B �@�u�[���T�[�L�b�g���[�h�v�݂����ȕ��G�ȏ��������������̂ł͂Ȃ��A���ʂɃW���J�[�i���[�h�Ń^�C���v�������āA�w�P���ɃV�O�i���c���[��_�����������B�t���C���O�͌��o���ăG���[�_�������������B�x�Ƃ�����H������]�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H �@���̂ւ킩��Ȃ��Ɛv�ł��܂���̂ŁA���������������B �@���[�������͂��ł��Ȃ����ł����A���N�ɓ����Ă��炠����A������ł����p�̃v���o�C�_ODN�̃��[���T�[�o�̐ݒ肪�ς����悤�ŁA������Ŏg�p���Ă���悤��Web���[���V�X�e���ŁA���M���T�[�o��ő����̖��O���̏���ݒ肵��(����������)�����肵�Ă����郁�[���́u�X�p�����[���ł��낤�v�Ɣ��f���Ă���̂��A��苑�ۂƂ�������������������ODN�Ɏ�M����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���悤�ł��B(Time Out�Ŏ���Ȃ�) �@�����ւ�\�������܂��A�v���o�C�_��ODN�������p�̕��ɂ̓��[���ł̂��A�����ł��Ȃ��Ȃ����悤�ł��̂ŁA������������܂�����ODN�̃T�|�[�g�����ɂ��A�����������B(�����Ώ��͂���Ȃ��ł��傤����) ���Ԏ� 2009/3/25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��A���ؐ��ɗL��������܂��B �@�܂��܂��A���t���肸�Ő\�������܂���B �@������LapRecorder 2000���g�p���Ă̑���ł́A���d�ǂ��Q�g�p���Ă��܂��B�X�^�[�g�����d�ǂ�ʉ߂������_�ƃS�[�������d�ǂ�ʉ߂������_��LapRecorder 2000�ɐM���𑗂��Ă܂��B �@����̂����k�̓X�^�[�g���̌��d�ǐM�����u�A�����v�Ŏ�(�o�C�N)���X�^�[�g�����Ƃ݂Ȃ��āA�����v���_���Ɠ�����LapRecorder 2000�ɂ̓X�^�[�g���d�ǂ̐M�����[���I�ɑ���B�����ŁA�ǂ��̂ł��B �@�X�^�[�g�V�O�i���ōs�������̂́A �@�X�^�[�g�{�^���ŃX�^�[�g�V�O�i�����쓮�������v�_�������������d�ǂ�ʉ߂����ۂ̓t���C���O�̏������s�������̂ł��B �@�܂��A�����v�_����LapRecorder 2000���ɂ͋[���I�ɃX�^�[�g�̐M���𑗂��悢�킯�ł��B �@�P���ɁA�̐M���i�_���j�ŁALapRecorder 2000�̃X�^�[�g�̐M�����o����n�j�Ȃ̂ł��B�Ɛ\�������ŐV���ȋ^��𓊂������Ă��܂��A�\����܂���B �@�܂��A���[���Ɋւ��Ă������f�����|���������܂����B �@����͕ʂ̃��[���A�h���X�����ē��������܂��B �Ղꂳ�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ҋ@���̓V�O�i������[����������]�B �@�u�X�^�[�g�{�^���v�n�m�� �@�@�@�@�R�b�O[��������]�d�d�v�b�� �@�@�@�@�Q�b�O[��������]�d�d�v�b�� �@�@�@�@�P�b�O[��������]�d�d�v�b�� �@�@�@�@�O�b�c[��������]�d�d�|�[�� �@�O�b�Ɠ�����LapRecorder 2000�ɋ[���u�X�^�[�g���d�ǁv�M���𑗂�B �@�O�b�����ɂ͎��ۂ̌��d�ǐM��(�Ԃ��ʂ����M��)�͖����B �@�܂��X�^�[�g�O�ɃX�^�[�g���d�ǂ���M���������ꍇ��LapRecorder 2000�ɂ��̂܂܁u�X�^�[�g���d�ǁv�M���𑗂�(�t���C���O�ł��v��)�Ƌ��ɃV�O�i���͒�~���āA�t���C���O��Ԃ�[��������]��[����������]�_�łƁu�v�b�v�b�v�b�v�b�c�v�u�U�[��炷�B �@�Ƃ�������ł�낵���̂ł��ˁH �@���ƁA����ɗV�O�i���ɂȂ�����ƁA�t���C���O���o��������ɂ͎蓮�Łu�V�O�i��OFF�v�{�^���������ă����v�������̂��A����Ƃ���莞��(���b)��Ɏ����I�ɏ�����(�A���蓮�X�C�b�`�����p�ŔC�ӂɂ�������)�̂��A�ǂ��炪��낵���ł����H �@�蓮�{�^���݂̂ɂ���ƁA�t���C���O�������ɂ͂��Ȃ�g���邳���h��Ԃ��X�C�b�`���܂ł����Ƒ����܂��B ���Ԏ� 2009/3/26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Z�������A���e�g�ɑΉ����Ē����A���ɗL��������܂��B �@�܂������A���Ԏ��̒ʂ�ł������܂��B �@�V�O�i���n�e�e�Ɋւ��Ă͎蓮�X�C�b�`���p�Ŏ����I�ɏ����铮�삪��]�ł��B �@������̐����s���ŁA�ƂĂ������f�����|���������Ă��鎖�Ǝv���܂��B �@���̏�����肵�Ă��l�т������܂��B �Ղꂳ�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����ł́A���̎d�l�Őv��i�߂����Ǝv���܂��B �@���݁A�F�l�̖ڂɌ����Ă����ȂƂ���Ń��[���ł��̂悤�Ȗ₢���킹���Ԏ����₢���킹���Ԏ����₢���킹���Ԏ��Ƙb��i�߂Ă��镨�Ȃǂ��܂߂܂��Đ����̓y���f�B���O�ł��̂ŁA���������Ԃ��܂��B ���Ԏ� 2009/3/26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����ł͉�H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� HC00,HC08���̃Q�[�g�̃s���ԍ��͕X��U���Ă��܂��B
��������ɂ͔z�����₷���悤�����R�ɑI��ł��������B �� ���쐧�� �@74HC00��NAND��H���g�����u�q�r�t���b�v�t���b�v�v�Łu���쒆�v���u��~���v���̃X�C�b�`���O���s���܂��B �@�u��~���v���ɂ͎蓮�́u���Z�b�g�X�C�b�`�v�ȊO�ɁA�d��ON���Ƀ��Z�b�g����(���Ȃ��ƊeIC�̏�Ԃ͕s��)�p���[�I�����Z�b�g��H�ƁA�V�O�i����H����u�J�n��W�b��Ɏ������Z�b�g����v�M�����g�p���邩�ǂ����́u�������Z�b�g(��/�s��)�X�C�b�`�v�����t���Ă��܂��B�������Z�b�g�@�\���g�p���Ȃ��ꍇ�̓X�C�b�`��OFF���ɑI�����Ă����Ă��������B �� �N���b�N���U�^�N���b�N���� �@�^�C�}�[IC 555��10Hz�̃N���b�N�M���U�����A�����10�i�J�E���^��74HC390��1/10��������1Hz�̃N���b�N�M�������A�V�O�i�����P�b�����ɓ_�������Ă䂫�܂��B �@�N���b�N�M���̔��U���g����VR1�Ŕ��������Ă��������B �@����̕�����H�ł�74HC390�ɓ����Ă���Q�g�ڂ�10�i�J�E���^�̈ꕔ�����p���āA�t���C���O���莞�ɃV�O�i���𑁂��_�ł�����ׂ�2.5Hz(10Hz/4����)�̐M�������܂��B �� �V�O�i���̐i�s��H �@�W�r�b�g�V�t�g���W�X�^��74HC164���g�p���ăV�O�i�������ɓ_�������܂��B �@�X�^���o�C(���Z�b�g)���͑S�Ă̏o�͂�L�ł��B �@�u���샂�[�h(RUN)�v�ɂȂ�ƁA�N���b�N���͂������邲�Ƃ�QA,QB,QC�Ə���H�ɂȂ��Ă䂫�܂��̂ŁA���ꂼ��Ɂu��1�v�u��2�v�u���v�u�v�̃����v��_���������H���q���ΐԂ��珇�ɓ_�����Ă䂭�V�O�i���͂ł��܂��B (�N���b�N������H�̓s���ŁA�X�C�b�`ON����ŏ��̐ԓ_���܂�1�b�̑҂����Ԃ�����܂�) �@������ �@�@�@�@�R�b�O[��������] �@�@�@�@�Q�b�O[��������] �@�@�@�@�P�b�O[��������] �@�@�@�@�O�b�c[��������] �ƁA�u�v���_������Ɓu��1�v�u��2�v�u���v�͏�������悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���̂ł��̂܂�LED�h���C�o��H�Ɍq���̂ł͂Ȃ��A74HC00��74HC08�ŗΓ_���Őԉ����������W�b�N��H���쐬���Ă����܂��B �@�܂��A���ꂾ���ł͍���́u�t���C���O���ɓ_�ł������v�Ƃ����@�\�͑S������܂���̂ŁA�������������ׂɁu�f�[�^�Z���N�^�v74HC157�Ő��펞�̃V�O�i���i�s�Ƃ͕ʂɁu�t���C���O���ɂ̓V�O�i���i�s�Ƃ͊W�����ԉ���_�ŁA�͏����v�Ƃ�����H�ɐ�ւ��܂��B �@�E�E�E�E�Ƃ��Ă��ʓ|�ł��ˁB �@�V�t�g���W�X�^�̂W�i�ڂ̏o��QH�́u�������Z�b�g�v�p�̐M���Ƃ��ė��p���Ă��܂��B �@�u�v���_�����Ă���R�b��Ɏ����I�ɃV�X�e�������Z�b�g����܂��B(�X�C�b�`�ł��̋@�\��OFF�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂�) �� �����v�h���C�o �@����͂S�n���̏o�͂ł�����A�g�����W�X�^�A���C�͎g�킸�ɕ��ʂ̃g�����W�X�^�ɂ��X�C�b�`���O��H�ł��B �@����ʂɂS�f�q�̃g�����W�X�^�A���C���g���Ă������̂ł����E�E�E7�`8�n���K�v�Ȃ�z�����ʓ|�Ȃ̂Ńg�����W�X�^�A���C�A���ꖢ���Ȃ�ʂɃg�����W�X�^�ō쐬�ƃ��[�������߂Ă��܂��B �� �t���C���O�����H�ƁA���d�ǐM���̏o�͉�H �@�t���C���O����́u�V�O�i�����ɂȂ�܂ł̊��v�ɍs���܂��B �@�X�^�[�g�X�C�b�`�������Ă��Ȃ���(�X�^���o�C��)�̓t���C���O������s���܂���̂ŁA�Z���T�[���Ղ��Ă��o�b�ɂ͐M���͓`�B����܂���B �@�V�O�i���i�s��H���Łu�v���_������܂ł̊�(�̔��]�M����H)�̊��ԂɌ��d�ǃZ���T�[����������u�t���C���O�v�Ɣ��肵�܂��B �@�t���C���O����͂q�r�t���b�v�t���b�v���Z�b�g���ĕێ�����܂��B��x�t���C���O���o���������H�����Z�b�g�����܂Ńt���C���O��Ԃ�ێ����܂��B �@�t���C���O����q�r�t���b�v�t���b�v�̏o�͂ŏo�͂̃����V���b�g�^�C�}�[74HC221���N�����āA�o�b�Ɂu�t���C���O���N�����v�Ƃ����X�^�[�g�M����`�B���܂��B �@�����A�t���C���O����������ɗV�O�i���܂ŃV�O�i�����i�s�����ꍇ�A�ΐM���ŏo�͂̃����V���b�g�^�C�}�[���N�����Ăo�b�Ɂu���_�������v�Ƃ����X�^�[�g�M����`�B���܂��B �@���_������ƃt���C���O����͍s���Ȃ��Ȃ�܂�����A���ۂɌ��d�ǂ̑O���Ԃ��ʂ������ɃZ���T�[�����������M���͖�������܂��B �@���́u�t���C���O����v�u�ɂȂ����v�Ƃ������̐M���͈�xL(L�A�N�e�B�u�ł�)�ɂȂ������H�����Z�b�g�����܂�L�̂܂܂ł�����A�ǂ��炩�Е�����ɏo����A������x�ʂ̗��R�ło�b�ɏo�͐M�����o�邱�Ƃ͂���܂���B �@�o�b�ւ̏o�̓p���X����VR2��0�`1�b���x�̊Ԃʼnςł��܂��B �@�o�b�Ɛ������q�����Ă��邩�ǂ����̃e�X�g�p�X�C�b�`������܂��̂ŁA�ڑ��̃e�X�g���ɂ��g�p���������B �� �T�E���h��H �@�Ԃ܂��͉��F�̃V�O�i���Ŗ�u�v�b�v�Ƃ����Z�����́A�eLED�_���p�M�������R�ƃR���f���T�ɂ�������H�ŒZ���p���X���쐬���āA�V���~�b�g�^��NAND�Q�[�gIC 74HC132�ō쐬��������g���U��H���쓮�����u�U�[�����o���܂��B �@�V�O�i���̂ق���74HC221�̂Q��H�����Ă���Б��̉�H�Ń����V���b�g�^�C�}�[��H�����A����ɂ��0�`2�b���x�̊ԂŔC�ӂ̎���74HC132�̃u�U�[����炷��H�삳���܂��B �@�V�O�i�����̃u�U�[�����鎞�Ԃ�VR3�Œ��߂��܂��B �@�u�v�b�v����u�|�[�v���̉����͂��ꂼ��VR4�EVR5�ł��D���ȉ����ɒ��߂��Ă��������B(��240Hz�`4.3KHz��) �@�t���C���O���ɂ͐ԉ�LED��2.5Hz�œ_�ł��܂��̂ŁA���̓_�łɂ��킹�āu�v�b�v�b�v�b�v�b�v�b�v�ƃt���C���O���艹����܂��B �@�����o�͂̓A���vIC�� LM386N�ŃX�s�[�J�[��点��悤�ɂ��܂��B �@����̉�H�ł�LM386�ɂ�12V�d����^���Ă��܂��̂ł��傫�ȃp���[�ŃX�s�[�J�[���쓮�ł��܂����A����ł��L���T�[�L�b�g�ł͉��ʕs���ł��傤����A�K�v�ɉ����ĕʂ̃A���v��X�s�[�J�[���Ɍq���ł��������B �� �k�d�c�p�l�� �@�ԁE���E��LED�ɂ��F�X����܂����A�ǂ�LED���g���邩�킩��܂���̂ňꉞ�Ή��\�̂悤�ȕ����ڂ��Ă����܂��B 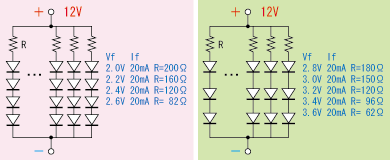 �@12V�d���Ŏg�p����ꍇ�AVf��2.0�`2.6V�̕i(��ɐԂ≩���)�ł����LED���S�{����AVf��2.8�`3.6V�̕i(��ɐ┒)�ł����LED���R�{����A�ɂ��ēd��������R����{�A������P���j�b�g�Ƃ��ĕK�v�ȃ��j�b�g�������Ɍq���łP�̃p�l�����쐬���Ă��������B(�p�l����LED���ǂ����ׂ邩(�~�`�H�l�p�H)�͂����R��) �@���̈ꗗ�\��LED��If=20mA�̕i�Ōv�Z���Ă��܂��B ���Ԏ� 2009/3/29
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�ƂĂ������Z�̒���H�}�̐v�����Ē����A���ɗL��������܂��B �@�ƂĂ�������₷���������Ɋ��ӁA���ӂł��B �@��͂�A���ꂾ�����G�ȉ�H�ɂȂ�Ǝ��̋Z�ʂł͂ƂĂ������ł����B �@�������i���B��A����ɂ����肽���Ǝv���܂��B �@���̓x�́A����Ȃ�����ɍŌ�܂ł��t���������Ă��������A���ɗL��������܂����B �Ղꂳ�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���W�b�N��H����IC���X�ƌ��\����������ւƎv���܂��B �@���������Ă��܂��悤�ɁA��H�̊e�@�\�̕��������œ���e�X�g���s���Ίm���Ɋ����Ɏ���܂��̂ŁA����Ă��ɂ�����萻�삵�Ă݂Ă��������B �@�u�X�^�[�g�{�^������������v�v�v�v�ƍ��}�����o��v�Ƃ�������]���A���̉�H�̃X�^�[�g�{�^���������Ă���Ԃ��_������܂ł̂P�b�̃u�����N�ʂ��āA�N���b�N����5Hz�M���Ƃ��킹�ăT�E���h��H��ON�ɂ���Ƃ������W�b�N��H��lj��������]�ʂ�Ɏ����ł��܂��B �@����̉�H�ł͂������������ƍX��IC���������Ă�₱�����Ȃ�̂Ő��荞�݂܂���ł������A������ɂ��������lj��������s����̂��ʔ����ł��傤�B ���Ԏ� 2009/4/1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB�A��AC�d�������[�AOFF�x���t�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�n�߂܂��āB�����y�����q�������Ē����Ă���܂��B �@���|�I�ȏ��ʂœǂ݉���������A�f�l�ł�������l�A�H�v���ꂽ����ɓ���������܂��B �@����A���m�b�����肵�������e�����Ē����܂����B �@PC�̃f�B�X�v���C�̑ҋ@�d�͂��J�b�g�������i���́A�����ȓd���X�C�b�`��J���ׂł����j�APC�̓d���ƃf�B�X�v���C�̓d����A�������镨����肽���ƍl���܂����B �@�P���ɁAUSB����d������胊���[���쓮������Ηǂ��Ǝv���̂ł����A���肪����܂��āA����PC���ւ��@���g�p���Ĉ��̃f�B�X�v���C�Ŏg���Ă���܂��B �@�P���ɁA����PC��USB�d�������c�Ȃ�Ď������Ă��܂��ƁAPC������\��������Ƒf�l�Ȃ���l���Ă���܂����A��肭���������@�͌�����܂��ł��傤���B�܂��A�����[��OFF��5�`10�b�قǒx�点�����ƍl���Ă���܂��B �i�f�B�X�v���C���X�^���o�C�ɂȂ�����ɓd����ؒf�������̂ł��B�j �@�����[���g���o�͂�ɂ���Ηǂ��̂��Ƃ͎v���̂ł����A�d�q��H���ł̃X�}�[�g�ȉ����@��������܂���ł��傤���B �i�d�q��H�y�у����[�̓d���́A��ɓd���𓊓�����PC�������Ē��������̂ł����A����ł��傤���B�j �@�ǂ����A�X�������肢�v���܂��B levitron �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����[���Q�g���ďo�͂��u����v�ɂ���ƁAPC���Q��Ƃ��d�������Ȃ��ƃ��j�^�̓d��������܂���ˁA�����́u����v�ł��ˁB �@�Ƃ܂��d�d�ׂ��Ȏ��͂����Ƃ��āA�uUSB��PC����d��������v�Ƃ�����PC�̓d�����ꂽ������d���͂����܂��ŁA����Ȍナ���[������ׂ̓d���͖����Ȃ�܂���ˁB �@���j�^�����ׂ�AC100V�͗��Ă���Ƃ͎v���܂����A��������͓d�������Ȃ��Ƃ����������ł͂�����Ƃ����ւ��B �@���ʂ̂T�u���^�����[(USB��5V������)���g�����Ƃ��Ă��A100�`200mA�̃R�C���d����10�b�قǕێ�����̂ɂ�2F���x�̋���ȓd���R���f���T���K�v�ł��B���ł͓d�C��d�w�R���f���T�������Ă��܂��̂ł���őΏ����Ă��܂�����܂łł����A����̓����[�̑����H�v���āA�d���̕ێ��ɂ͕��ʂ̓d���R���f���T���g�������l���܂��B �@���ʁu�����[�v�ƌ����Ɠd���R�C���������Ă��āA���̓S�ŏo���������i���K�`���K�`���Ǝ��͂ň��������ăX�C�b�`���ւ��镔�i�̎����w���܂����A���̒��ɂ͂��̋@�B���������ēd�q���i�ő�p�����u�\���b�h�X�e�[�g�����[(�����̃����[/SSR)�v�Ƃ�����������܂��B �@�\���b�h�X�e�[�g�����[�̐���p���͂̓t�H�g�J�v���̒���LED��_�������邾���Ȃ̂ŁA���̓��͂Ȃ�d������Ă��d���R���f���T���g���Ă��炭����𑱂�����悤�ɂ���̂͊ȒP�ł��B �@�e���[�J�[���犮���i�̃\���b�h�X�e�[�g�����[�������Ă��܂������\�����̂ŁA����͏H���d�q�́u�\���b�h�E�X�e�[�g�E�����[�i�r�r�q�j�L�b�g �Q�T�`�i�Q�O�`�j�^�C�v K-00203�v(250�~)���g�p���܂��B �@�E�E�E����A�����Ɏg����Ǝv���Ĕ����Ă����āA�g�킸�ɕ��i���ɂ��܂��Ă����̂Łi�O�O�G �@�����H����K-00203�Ȃ�u�[���N���X�����X�i�o��H�����g���C�A�b�N�g�p�v�Ȃ̂ŃX�C�b�`�ؑ֎��̃m�C�Y�����ɏo�ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�d�����̕��ʂ̃����[���Ɛړ_��ON/OFF�̎��Ƀm�C�Y(���ł͉ΉԂƂ�)���o�Ă��܂����������܂���B���̓_�����̂ō\������Ă��ăm�C�Y����d�q�I�ɂ����\���b�h�X�e�[�g�����[��AC�d����ON/OFF������ɂ͗��z�I�ȃ����[�ł��B(����������) �@AC���̗e�ʂɂ���Đ���ޔ����Ă��܂��̂ŁA�K�v�ȕ����w�����Ă��������B�������H���L�b�g�ł͂Ȃ��s�̂̃\���b�h�X�e�[�g�����[�ł��\���܂���B(���Ԃ̐ݒ�͑����ς�܂�) ���N���b�N����Ɗg��\��
�@��H�͔��ɊȒP�ŁA�Q��PC�����USB���狟�������DC 5V�́u�ǂ����PC�̓d���������Ă��v�����p�_�C�I�[�h��ʂ��ă\���b�h�X�e�[�g�����[�����܂��B�_�C�I�[�h�̓����łQ��USB(2���PC)�̓V���[�g�⊱�͂��܂���B�@�����ꂩ�Е��A�܂��͗�����PC�̓d���������Ă����Ԃł̓����[��ON�ł��B �@������PC�̓d�������Γd���d���͖����Ȃ�܂����A�d���R���f���T�ɒ~����ꂽ�d�C�Ń\���b�h�X�e�[�g�����[�͂��炭�͓��삵�Â��܂��B �@�H���L�b�gK-00203���g�p�����ꍇ�A4700��F��Ŗ�R�b���x�͕ێ����܂�������A10�b�قǒx�����������̂ł���R���Ă��������B(15000��F�̃R���f���T������ł�������ł������ł���) �@PC���Q��g��Ȃ��Ă��APC���ő��̎��Ӌ@��̓d�����܂Ƃ߂�ON/OFF����d���^�b�v���������A���̕��ɂ����p�ł��܂��B ���Ԏ� 2009/3/23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Z�����Œ��̂��A�L�������܂��B �@SSR��p���邱�ƂŊȒP�ɍς܂��鎖���ł���̂ł��ˁB�Ȃ�قǂł��B �@���ŁA�����Ȃ̂ł���USB1�̂�ON�ɂȂ����ꍇ�ɁAUSB1���_�C�I�[�h��SSR��USB2 �Ɠd���������l�Ȏ��͖����̂ł��傤���H �iLED��_����������x�̓d���ł�����A���͖��������ł����A�C�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�j �@�ǂ����A�X�������肢�v���܂��B levitron �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���[�ƁA�ǂ�������炻�̃��[�g�œd���������̂��A�n����̕����@���ɔ����Ȃ�����͂��肦�܂���B �@���d�r�Ɠ��d���ōl���Ă��������B �@�d���������͓̂d�r�̃v���X�ƃ}�C�i�X�ɓ��d���̂Q�̒[�q���q�����Ƃ��Ɂu�d�C������郋�[�v(��)����������v���炻�̗ւ����邮��Ɠd��������ē��d��������킯�ł���ˁB �@levitron�l�̂��l���́uUSB2�ɓd���������v�Ƃ������_�́A��̊��d�r�Ɠ��d�����q���Ō����Ă��鎞�ɐV���Ɂu���d�r�Q�v(USB2�̂����)��p�ӂ��āA���d�r�Q�̃}�C�i�X�ɂɈ�{�������[�h�����Ȃ��Ō��̊��d�r�P�̃}�C�i�X�ɂƌq������A����s�v�c�A�v���X�ɂɉ����q���ł��Ȃ��͂��̊��d�r�Q�ɂ��d��������Ċ��d�r�Q�͏��Ղ��Ă����Ă��܂��I(�܂��͏[�d����Ă��܂�!?)�Ƃ����ƂĂ��M�����Ȃ����ۂ��N���邱�ƂɂȂ�܂��B �@������������levitron�l���d�C�H��������ꍇ�A�q���ԈႢ�₻�̑��̕s�(�d�C�I�ɊԈ�����l���������m���ł̒v���I�ȃ~�X)�Ńp�\�R����j�^�[���Ă��܂��\���������Ɛ��@�ł��܂��̂ŁA����̐���͂�����߂�ꂽ�ق����ǂ���������܂���ˁB ���Ԏ� 2009/3/25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 3/27 |
�@�����Ӓv���܂��B �@�����Ⴂ�Ȏ�������Ă��܂��A�\�������܂���ł����B �i���삵�����́AUSB�o�͂̃A�^�v�^�œ���`�F�b�N���Ă���PC�Ɍq���l�ɒv���܂��B�j �@�L�������܂����B levitron �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���������L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�̕s�Ǔ��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB�g���u�������̂��m�b�����݂��������B �@�ڊo�܂��A���[���̗L��/�������g�O���^�C�v�̉����{�^���X�C�b�`(2��H)�Ő��䂷���H���쐻���Ă��܂��B �@���v��100�~�V���b�v(CanDo)�́u�f�W�^���A���[���N���b�N�v�ŁA���d�u�U�[(?)�ւ̐�(2�{)��1�{�����2��H�̈���ɓ���܂��B �@�A���[�������X�C�b�`���������Đؒf����Ƌ��ɁA�A���[����������Ԃł��邱�Ƃ�LED Flasher(LM3909)���g�p����LED��_�ł����܂�(�X�C�b�`������2��H�̂���������g�p����LM3909�ɓd�����������܂�)�B �@�d�r�̓A���J���P2�^�P�{�ł�(�R���f���T�͐ڑ����Ă܂���)�B �@LM3909�ɐڑ����Ă���e�ʂ�100uF�Ŗ�1�b������LED���キ�_�ł����܂�(�X�C�b�`�̃X�g���[�N���Z���̂ʼn�������ł��L��/������Ԃ�����悤��LED�����܂���)�B �@�g���u���͎��`�ǂ��A�X�C�b�`�������Ɏ��v��������ԂɃ��Z�b�g���ꂽ�苶������A�A���[�����ȍ~�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃł��B �@�A���[�������̃X�C�b�`�����ɂ�荂�d������������LSI���듮��(�j��)�����̂��ALM3909�ւ̓d�������ŏu�ԓI�ɓd�����������Č듮�삵���̂��A�u�U�[����̈��o����(�{���|��)�������̂��ȂǂƎv�������˂Ă��܂��B �@��낵�����肢�v���܂��B maru �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�L�����E�h�D�̃A���[���N���b�N�̂����̂ǂ�ł��傤�ˁH �@�����`�̕��A�����Ŕ������J�o�[���X���C�h���镨�A�ʐ^���ĂɂȂ��Ă��镨�A�Ȃnj�������͐���ނ���܂��B �@�ŁA�茳�ɂ���L�����E�h�D�̃f�W�^���A���[���N���b�N�ł͂Q�䒆���́u����Ƀ��[�h���ς�v�u����Ƀ��Z�b�g�����v�Ƃ�����������܂��B�Q��O�ɂ͕��ʂł��A�������烂�[�h�ݒ蒆�ɂȂ��ē_�ł��Ă�����A(�钆�Ƀ��Z�b�g���ꂽ�悤��)�S�R�Ⴄ���ԂɂȂ��Ă�����B�܂�ŗH�삪�o�Ď��v��G���Ă���悤�ł��B �@�X�C�b�`�̓����v���A�b�v���v���_�E�����シ����̂��A�����������삪�s����Ȃ̂��E�E�E�B �@���ɓd���̕����R���f���T�Ȃǂ͌����܂���̂ŁA�����q���ꍇ�͓d���R���f���T�ł����Ă������ق����ǂ��Ǝv���܂��B �@�܂��A�u�U�[�ɂ͉��ʂ�傫������ׂɕ���ɃR�C�����q�����Ă��܂�����A�O�ɏo�Ă���u�U�[�̔z��������Ə����R�C�������������Ă����Ԃł�����A���Ȕg�`�̃X�p�C�N�m�C�Y���o�܂���ł��ˁB��̃p�^�[���J�b�g�����ăX�C�b�`���q���ꏊ����邩�A�R�C���̑��������Ă����ƃR�C���ƃu�U�[�̗������ꏏ�ɐ��悤�ɔz�������ق��������ł��傤�ˁB �@���̎茳�ɂ����䂪���܂��ܕs�Ǖi�Ŗ钆�ɏ���ɓ����Ă��܂��̂��A�S���̐��i���キ�Č�쓮�����₷���̂��͕�����܂��A�d���܂��Ȃǂɕs�����c��v�ł͂���悤�ł�����A���̂ւ�U�߂Ă݂Ă͂������ł��傤���B �@�]�k�ł����A�u�g�O���^�C�v�v�Ƃ����̂̓X�C�b�`����_���o�Ă��ăp�`�p�`�Ɩ_�̌�����ς��Đ�ւ���X�C�b�`�̎����w���܂��B�u�����{�^���v���̃v�b�V���X�C�b�`�̎��ł͂���܂���B �@����IT�p���p�\�R���̋@�\�ł́u�g�O��(�ؑ�)�v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���̂ł��傤���A�d�q���i�̃X�C�b�`�ł́u�g�O���X�C�b�`�v�Ƃ����`�ł͖_���˂��o���X�C�b�`�̌`�E��ނ�\���܂��B �@�肽���Ӗ��́u�I���^�l�[�g���̃v�b�V���X�C�b�`�v�Ə����̂������ł��B �@�u�I���^�l�[�g�v�^�C�v�͈����ON�ɂȂ�ێ��A���������OFF�ɂȂ�ێ��B�Ƃ��������Ń����v�b�V������x��ON��OFF����ւ�铮���������̂�\���܂��B �@�t�ɂ悭���������Ă���Ԃ���ON(������OFF)�Ƃ����X�C�b�`�́u���[�����^���[���̃v�b�V���X�C�b�`�v�Ə����܂��B�p��̃��[�����g(moment)�̈Ӗ����킩����̂܂܂ł���ˁB ���Ԏ� 2009/3/13
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 3/14 |
�@�����̂����肪�Ƃ��������܂��B �@�N���b�N�́u�����Ŕ������J�o�[���X���C�h���镨�v�ł��B �@�����Ē������������낢�뎎���Ă܂������܂��B �@�u�]�k�v�͂��w�E�̒ʂ�̈Ӗ��Ŏg���Ă��܂��܂���(^_^; maru �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�d���܂��̕⋭�ƌ������ƂŁAIC�̓d�����߂ɂ��܂��Ȃ���0.1uF�A�d����68uF�����Ă݂܂����B �@30��(�P������)�̃A���[��ON�ƁA�A���[���r���ł�OFF/ON���v100��ȏ�J��Ԃ��Ă��ُ�͔������܂���ł����B�f�W�^����H�̃��W�b�N�C���Ƃ͂����܂��A�]���͂����ƕp�x�����������Ă��܂����̂ł���ʼn����ł����\������ł��B �@���������肪�Ƃ��������܂����B maru �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�Ǐo�Ȃ��Ȃ��Ă悩�����ł��ˁB �@�R���f���T�œd���܂��̕ϓ��ɑ���⏞������ďǏo�Ȃ��Ȃ����̂ł�����A��͂肱�̃N���b�N��IC�͓d���m�C�Y�ȂǂɎア�^�C�v�̐v�ɂȂ��Ă���悤�ŁE�E�E �@�����Ŗ钆�ɂ��������X�C�b�`�������N���b�N�́A���́u�����Ŕ������J�o�[���X���C�h���镨�v�ł��B ���Ԏ� 2009/3/16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �X���b�g�J�[�pLED���C�g���j�b�g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�X���b�g�J�[�p���w�b�h�����v���X�g�b�v�����v���쁚 �@http://www.gysra.com/special/setting3.html�̃y�[�W���Q�l�ɍ�����̂ł��������[���T���܂����E�E�E�����S�Ăk�d�c���g�������y�ʂłk�d�c���̃w�b�h���C�g*2�u���[�L�����v*2�ō�肽���̂ł��B����Ȓt�قȎ�����肵�Ă����܂���B�}�ɓd�C�̐��E�ɋ������o�Ă��Ă��낢��ςȎ��₵�Ă����܂���B �̂� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��H�̌������̂͂�����ŏЉ��Ă�����@���Ƃ�Ƃ��āA�����v�̕�����S��LED�ɑウ�āALED�͋ɐ��̂��镔�i�ł����疜����}�V������]���ďW�d�q���v���X�}�C�i�X�t�Ɍq�����Ă��܂��ċt�d�����������Ă����Ȃ��悤�ɕی�p�̃_�C�I�[�h�Ȃǂ�����Ƃ��̂悤�ȉ�H�ɂȂ�܂��B �@�ǂ����Ȃ�e�[�������v�͎��ԂɎ������u�����o���u(�_�u����)�v�`���Ɍ����āA���s���̓|�W�V���������v�Ƃ��ĈÂ��ԐFLED�������āA�u���[�L���ɐ��{�̖��邳�Ńp�b�ƌ���悤�ɂ��܂��傤�B �@�X���b�g�J�[�ł��������u���[�L�����v(�_�u������)���������Ă��郉�C�g���j�b�g���̔�����Ă��邩�͒m��܂��A���܂茩�����Ȃ��̂ł���R�[�X�Ŗڗ��ł��傤�B(�݂�Ȃ������Ă����炷�݂܂���) �@�|�W�V���������v���K�v�����ꍇ��6.1K�̒�R�͕t���Ȃ��Ă��\���܂���B 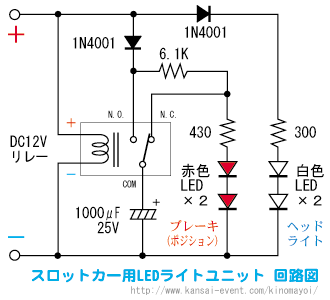  �@�X���b�g�J�[�ƌ����Ă��Ԃ̃T�C�Y(�X�P�[��)������ނ���܂�����A�������ȕ��ł̓����[�Ȃ�đg�ݍ��ނɂ͎ԑ̂����������Ă��߂��Ǝv���܂��B
�@�X���b�g�J�[�ƌ����Ă��Ԃ̃T�C�Y(�X�P�[��)������ނ���܂�����A�������ȕ��ł̓����[�Ȃ�đg�ݍ��ނɂ͎ԑ̂����������Ă��߂��Ǝv���܂��B�@���̎ʐ^�̂悤�ȏ��M���p�̃����[(OMRON G5V-1 12V)�Ȃ炩�Ȃ菬�����̂�1/32���ɂ͑g�ݍ��݂₷���Ǝv���܂��B(10�~�ʂƌ���ׂď��������킩��) �@G5V-1�̒[�q�z�u�̓����N��̃��[�J�[�y�[�W�ɏo�Ă��܂��B �@�u���[�L�����v��_��������ׂ̓d���R���f���T��1000��F���炢�̗e�ʂ̕����g��Ȃ��ƂقƂ�Ǔ_�����܂���B �@100��F���x�ł̓����[��OFF�ɂȂ����u�ԂɁu�p�b�v�Ɠ_�����āA���̂܂܈Â��Ȃ�0.5�b���炢�ŏI���E�E�E���x�ł��B �@���ۂ̑��s���ɂ̓`�����`�����Ǝw���ɂ߂Ĉ�u�����X���b�g�����J���͂��Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA100��F���x�łق�̈�u�u���[�L���_������̂ł������̂�������܂��A1000��F�ʂɂ��Ă�����2�`3�b�͓_�����܂�����A������I���ă}�V�����Ԃ����鎞�ȂǂɌ������Ă��犮�S�ɒ�~����܂ł̊ԃu���[�L�����v���_�����āu�����Ԃ炵���v�U�����܂��B �@�A��1000��F���炢�ɂȂ�ƁA�R���f���T�̑傫�����傫���Ȃ�܂�����}�V���ɍڂ�Ȃ����Ƃ��l�����܂��̂ŁA�����͂������̃}�V���̃{�f�B�T�C�Y�Ȃǂƍl�����킹�ēK�X�R���f���T�̗e�ʂ����߂Ă��������B �@���������đ傫�ȕ���ςނƏd�S�������Ȃ��đ��s���s����ɂȂ�����J�[�u�Ŕ��ōs���Ă��܂��܂�������قǂɁB ���Ԏ� 2009/3/11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�T�����̂̓����[�̑����U�{����̂ɉ�H�}���ƂT�{�����g��Ȃ��̂łǂ�����̂��ȁ[�Ǝv���Ă܂����B���܂������ǂ̂悤�ɂȂ����A�킩��܂���B��A�ł���A���i�̃��X�g�������Ă��������B1N4001�Ƃ͂Ȃ�ł����H �@��낵�����肢���܂��B �̂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@1�m4001����܂����B�����p�_�C�I�[�h�@�ł��ˁB �@�ł�1�m4001�͂Ȃ������ł��B�����1�m4007���L���ł�������ł����v�ł����H �̂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���т��т����܂���B �@��̕��i�̂��Ƃ͒u���Ă��镔�i���͌�����܂����B �@�Ō��6.1���Ƃ�6.1�����̒�R���悭��430��300��430���ƌ������Ƃ��ł���ˁH����Ƃ�4.3�����ł��ǂ��̂��H �@�����܂���A�X�������肢���܂��B �̂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
 �@�Ƃ肠�����A�����[�̌��B
�@�Ƃ肠�����A�����[�̌��B�@�̂�l���w�����ꂽ�����[�����̎ʐ^�̂悤�ɓ����z���}���v�����g����Ă���悤�ȕ���������悩�����ł��ˁB (�����܂܂ł�����c) �@�����[�̂悤�ȕ��i�̓��[�J�[�E�V���[�Y�E�^�Ԃɂ���Ē[�q�z��͑S�R�Ⴂ�܂��B �@�ł������ʓI�ȁu�~V�̃����[�v�Ƃ��Đv������̂ł͉�H�}�ł����Ɏ����̂ǂ̑��ɔz�����邩�̐��������܂���B �w���Ҏ��g�������Œ��ׂĎg���̂�������܂�
�ł��B�@�₽���Ǝv���邩������܂��A�d�q���i���Ă����������������̂ł��B 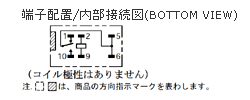 �@���Ƃ�������ɏo����OMRON G5V-1 12V�Ȃ�A���[�J�[�����J���Ă�����ɉE�̂悤�Ȑ}������܂�����A�u�����[�̉�H�}�͂T�{�����Ȃ��̂ɁA�����[�{�̂ɂ͂U�{���������v�Ƃ����ꍇ�ł��ǂ��ɂȂ��悢���͗e�Ղɒm�邱�Ƃ��ł��܂��B(BOTTOM VIEW�͗������猩���}�ł�)
�@���Ƃ�������ɏo����OMRON G5V-1 12V�Ȃ�A���[�J�[�����J���Ă�����ɉE�̂悤�Ȑ}������܂�����A�u�����[�̉�H�}�͂T�{�����Ȃ��̂ɁA�����[�{�̂ɂ͂U�{���������v�Ƃ����ꍇ�ł��ǂ��ɂȂ��悢���͗e�Ղɒm�邱�Ƃ��ł��܂��B(BOTTOM VIEW�͗������猩���}�ł�)�@���Ƃ���G5V-1�����̔z������������Ƃ����āA�����`�̑��Ђ̂U�{���̃����[�������z���Ƃ͌��炸�A����ĂȂ��ƃV���[�g�����蓮���Ȃ�������Ƃ����������X����܂�����A�����Ƃ��g�p�ɂȂ郊���[�̎d�l�ׂĎg���Ă��������B �@���̂悤�ȃ����[�̏ꍇ�͂����Ă��͕��i�X�Ŕ����Ă��鎞�ɕ��i��I�Ɍ^�ԁE�l�i�ƈꏏ�ɓ����z���}�����ɏ�����Ă���Ǝv���܂�����A�������Ƀ�������邱�Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B �@�����ɔz���}�������ꍇ�̓��W�Ŕ������ɓX������Ɍ����Ĕz���}�������Ă�����Ă��������B�X������������e���������邱�Ƃ�Y�ꂸ�ɁB �@���̓l�b�g�����B���Ă���̂ő�胁�[�J�[�̐��i�ł���l�b�g�����Ńf�[�^�V�[�g������ł��܂����A�d�q���i�X�Ŕ����Ă��镔�i�̏�S�ăl�b�g�Ŏ�ɓ���킯�ł͂���܂���A���͂Œ��ׂ��Ȃ����͍w�����ɕK�����X�Ŋm�F�����Ă��畔�i���悤�ɂ��܂��傤�B �@���Ɂu�����i�v�Ȃǂƈ��������Ă��镨�́A���ȊO�̉�А��Ńl�b�g�ɂ͏��������������������̂ň�������Ǝ���o���ƌ�Œɂ��ڂ��݂܂��B (���S�҂̕��̓l�b�g�ʔ͎̂g��Ȃ��ŁA�K�����i�X�ɍs���ēX������Ɋm�F���Ĕ����Ă�������) �@���̕��i�ɂ��Ă͐F�X�ƒ��ׂ��Ē��X�ƒm�����Ă���悤�ł��̂ł��̒��q�Ŋ撣���Ă��������I (�uK�v�́u�L���v�ł��B�~1000�ł�����K���t���Ă���̂ƕt���Ă��Ȃ��̂ł͑S�R�Ⴂ�܂����) �@�d�q��H�ɂ��ċ�����������č��o���_�ɗ����ꂽ��Ԃł�����A�ł����(������)�d�q�H��̓��发���P�`�Q�������ĉ�H�}�̓ǂݕ��╔�i�̎�ނȂǂ��w�K���Ă��������B(�w�K�Ƃ������̓�����̂ł͂���܂���) �@���������l�b�g�ɗ����Ă��Ă͗~���������ł��Ȃ�������A�f�ГI�ȏ��Ō�Ŏ��s���錳�ɂȂ�܂��B �@����҂̕���Ώۂɂ������e�ō���Ă���u���Ёv�ł���A�܂��͕K�v�ȏ���m���͂ЂƂ܂Ƃ߂ɂ��ē�����͂��ł��B �@�w�C�̖����x�ł͂��́u�������v�R�[�i�[�ł�[������]�ɏ����Ă��܂��悤�ɁA�u��H�}�̓ǂݕ��́H�v�Ȃǂ̏����I�Ȃ�����ɂ͌䓚�����Ȃ����ɂ��Ă��܂��B �@��H�}�Ȃǂ̒��s������́u���ȐӔC�v�őg�ݗ��ĂĂ��������A�Ƃ����X�^���X�ł��B�{���ɓ���n�_�ɗ����ꂽ���ɂ͌�������������܂��A�����܂őΉ����Ă���ƃL���������̂ŁE�E�E ���Ԏ� 2009/3/12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���肪�Ƃ��������܂��B �@���发�ƕ��i�𒍕����܂����B�{���͏H�t���ɍs�����������̂ł����A�d���̊W�ł܂Ƃ܂������Ԃ��Ƃꂸ�A�m�d�s�Ŕ����܂����B �@����ł��� �@�R���g���[���[���n�m�|�n�e�e����ƃw�b�h���C�g��������������̂����P����ɂ̓w�b�g���C�g���ɂ��d���R���f���T�[�̏����߂̂��̂�����Α��v�ł���ˁH �@�Ƃɂ����F�X�����Č��܂��B�ŏI�I�ȖڕW�͏��^�y�ʂȂ̂Ŋ撣��܂��B�㎄�̂���Ă���X���b�g�J�[��32/1�ł���������24/1�ɂ�����o���\��ł� �̂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂��n�߂�ꂽ����Łu�w�b�h���C�g���ɂ��d���R���f���T�[������v�Ƃ������z���ł���̂͂����������̂ł��B �@���̂Ƃ���ŁA���̉�H�ł̓w�b�h���C�g���ɂ͓d���̓d�������̂܂܂�����܂�����A�R���g���[���[���ɂ߂ēd����������ƃ��C�g�͈Â��Ȃ�܂��B �@�����p�_�C�I�[�h��ʂ�����ɓK���ȓd���R���f���T���������w�b�h���C�g�͓d���d�����������Ă������̊Ԃł���Ώ����Â��Ȃ���x�Ō���Â��܂��B �@�R���f���T�̗e�ʂ͐��S��F�ł����̂��A�����F�������ƑS�R�ێ����Ă���Ȃ��̂��A�Ȃǂ����Ў������Ċm���߂Ă݂Ă��������B �@���̌��ʂ����g�̖ړI��B���ł��镔�i���ǂꂩ������A�����g�̎�Őv���ꂽ�d�q��H�̊����ł�����B���������肱�ꂩ��̓d�q���i�̎�舵���ɂ���Ɏ��M�����܂���I ���Ԏ� 2009/3/16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �Ԃ̓d����15V�ɏ����������H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�ˑR�����܂���A�ȑO�̂c�b-�c�b�����R���o�[�^�[���݂Ă��������u�グ�����Ǝv���܂����o����Ήω\��15�u���炢�ɂ������̂ł����ǂ�����Ηǂ��ł����H�o����Ε��i�������Ă��������B �@��A������Ԃɂ���ꍇ���ʂɃo�b�e���[�ɂȂ������ŁA�Ԃ̓d����ς��鎖���o����̂ł����H���ɁA���̉�H������Ɨǂ��挩�����ȕ�����܂����A�R������K�\���������̂ŁA���Ȃ݂Ƀz�b�g�C�i���}�ł͌��ʂ������܂���ł����m���ɏu�ԓI�ɓd���͏オ��݂����ł�������܂łł����B�@�ʕ��ł����X�������肢���܂��B �̂� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�u�ȑO�̂c�b-�c�b�����R���o�[�^�[�v���Ăǂ�ł����H �@�Ԃ̓d�����グ��DC/DC�R���o�[�^�̋L���͏��������������̂łǂ�̂��Ƃ��w���Ă���̂��S���킩��܂���B�ǂ̋L�������m�ɂ��������������B �@���Ƃ��z�b���C�i�Y�}�̂悤���o�b�e���[�ɔz�����q���������Ƃ����lj��Łu�Ԃ̓d�����オ��v�Ƃ����悤�ȑ��u�͂��̐��E�ɂ͑��݂��܂���B(�������z�b�g�C�i���}���d�����グ��ׂ̑��u�ł͂���܂���) �@�Ԃ̃o�b�e���[����ʂ̃o�b�e���[(�T�u�o�b�e���[)���[�d����ׂ̃Z�p���[�^�ɏ����@�\���t���Ă��镨�Ȃǂ͒T������Ǝv���܂��B�L�����s���O�J�[���Ŏg���T�u�o�b�e���[�����肵�ď[�d����悤�ȖړI�̑��u�ł��ˁB�Ԃ̓d�����グ����R���ǂ�����悤�ȑ��u�ł͖����ł��B �@�Ԃ̃o�b�e���[��Ԏ��̂̓d����15V�ɏグ��悤�ȑ��u�͑��݂��܂���B �@�����_�Όn���܂߂ĎԂ̓d���n��S��15V�ɂ������̂ł���A���C�g�Ȃǂ̑�d��������鑕�u�ɂ܂ŏ[���ȓd�����������悤�Ƃ����炻�ꂱ����������|����ȑ��u���K�v�ɂȂ�A�ƂĂ������Ŏ�����o����邭�炢�̓d�C�E�d�q�Z�p�̕������삵�ĎԂ������ł���Ƃ͎v���܂���B�d�C�����Ԃ�����ł��邭�炢�̐l�łȂ��ƍ��܂����B �@�u�R��v�Ȃǂ̒P�ꂪ�o�ė���Ƃ������͂��������g���������ꂽ���̂ł��傤���E�E�E �@���Ȃ݂ɁA�z�b�g�C�i���}�͍�N�Q���Ɍ�������ψ���u�@�\�ɍ����I�ȍ����������v�Ƃ��Ĕr�����߂��o���Ă��܂���ˁi�O�O�G ���Ԏ� 2009/3/9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����܂���ł����B���̂g�o�ƍ������Ă����݂����ł��B �@��A�d�����ԑS�̂������������̂ł͂Ȃ��A�v���O�̃X�p�[�N�������o���Ȃ����ȁ`���Ǝv���܂��āA�m���A�v���O�̃X�p�[�N�̓o�b�e���[����̓d�����W���Ă��Ǝv�����̂Ńo�b�e���[�ɏ����c�b�|�c�b�R���o�[�^�[������X�p�[�N�������Ȃ�Ȃ����ȂƎv���܂����B�i�������̓C�O�i�C�^�[�̊ԂɁj��ȉ��Ƃ��͓d���R���f���T�[�ł�����ˁB�S�`�T��ނ̊m���E�E�E �@�Ƃɂ�������ȕ��͂Ő\�������܂���ł����B �̂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�R��オ��̂�������܂��A��e�ʃI���^�l�[�^�[�ɕύX�����Ɖ���������ʂ����邩���H �@���Ƃ��ł����A�Ԃ̔��d�@80Amp��130Amp�Ɏd�l�ύX���ꂽ���ł��B �@�d�C�ɂ͏ڂ����Ȃ��̂ʼn��̍�����������܂��A�A�A�A�B �@�����̂ŔR����ɂ������������ł��ˁE�E�E�B ���[ �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ǂ���HP�ƍ�������Ă����̂��E�E�E�͂܂������Ƃ��āA�u�C�̖����v�ł��Ԃ̑��s�Ɋւ��镔���̉����ȂǁA�̏Ⴕ���ꍇ�����Ɋւ���悤�ȕ��̉����ɂ͂����͂��Ă��܂���̂ł��������������B �@CDI�ɓd�����������Ă��郉�C����藣����DC/DC�R���o�[�^���œd���������āu�������v�X�p�[�N�������Ȃ�̂ł�����R�����ɖ𗧂�������܂��A���X���������Ă���u�����Ŏ��������邭�炢�̒m���̕�����H���H�삳�ꂽ�ꍇ�v�Ƃ��������ŁA�H��̒t�ق���C���n���_�Ȃǂő��s���̐U����Ŏg�p���ɓˑR���̑��u����ꂽ��H �@�Ԃ������ő��s���ɓˑR�G���W�����~�܂��Ă��܂��Đ���s�\�ɂȂ����ꍇ�Ƀv���̃��[�T�[�̂悤�Ƀn���h���ق��Ŏ��̂�������Ĉ��S�ɒ�~���邱�Ƃ��ł���ł��傤���H �@����҂̕����v���̃��C�Z���X���������̃��[�T�[�̕��ŁA�����ȊO�ł̃��[�X�⎎�����s�����Ŏg���Ƃ������肳�ꂽ�p�r�ł���Ή�������̉�������ꏏ�ɍl���邱�Ƃ����邩������܂��A��ʓ��𑖂镁�ʂ̎����Ԃ̓��͓d���n�̉���(���ɉ�ꂽ��G���W�����~�܂�^�C�v)�́u�C�̖����v�ł͐�ɂ����ߒv���܂���B �@���[�T�[�̕��Ȃ炲�����̃`�[���̃��J�j�b�N�̕��̂ق����A��育�g�p���̃}�V���ɂ��Ă悭�����m�ł��傤���ˁi�O�O�G �@�����ȓd�q��H���Ƃ������A�ł���{�I�ȁu�v���O�̃����e�i���X�v�u�I�C�������v�Ȃǂ����܂߂ɂ���Ƃ��A���[�l�̂������̂悤�ɎԂ̓d���n���̂��̂��f�B�[���[�Ɍ������Ă�����ċ��͂ȕ��ɂ���ȂǁA�����ԍH���f�B�[���[�ł���Ă��炦����ǂ�A�Ƃłł����{�����e�i���X�ɗ͂�����A�R��͂���Ȃ�̒l���ێ��ł���Ǝv���܂��B �@���ہA���N�������Ă���Ԃ��ƃv���O��S�������e�����ɑ����Ă���̂ƁA�����ƃ����e���Ă���̂ł̓G���W������p���[������Ă���l�Ԃ̔��Ŋ�������قǕς��Ă��܂����E�E�E�B �@�������������Ԃ̊�{�����e�i���X���s���Ă��āA�Ȃ����u�X�ɉ������ǂ������v�Ƃ�������]�ł�����\�������܂���B �@�����ł͑Ώ��ł��܂���̂łǂ����Ԃ̉������s���Ă�����̃T�C�g�E�u���O�Ȃǂł����k���������B ���Ԏ� 2009/3/10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�G���W���̔R�����Ƃ̂��Ƃł����A�����f�l�������Ƃ��ł͋t�Ɉ������Ă��܂��̂ł�߂����������ł��B �@�ꏊ���A�G���W���v�҂Ƃ��b������@����ɑ����̂Łi���d��������Ă܂����E�E�j�F�X�Ə�����Ă���̂ł����A�P���ɓd�����グ�����炢�ł͔R�Č����ɕω��͏o�܂���B �@�s�X�g���̏��������O������d���n�܂�A��莞�Ԍ�ɒ�~����B �@���ꂪ��{����ł����A���d�d�����Ⴂ�ƊJ�n�_���x��A�܂��I���������Ȃ�܂��B �@���ꂪ�����Ӗ����邩�ƌ����A�g���N�i�n�́E�E�E�����Ӗ����Ⴄ�̂ł����B�j�ɉe�����܂��B �@�܂�A�K��d�������|�����Ă���Β荏�ɁH���d���n�܂�E�E�ƌ������Ƃł��B �@�����������͕������Ă��炦���Ǝv���̂ł����A���̒��x�ł͉��ǂȂ�ʉ����ɂȂ��Ă��܂��ƌ������Ƃł��B �@�I���^�l�[�^�[�̌������b��ɏオ���Ă��錩�����ł����A�G���W�������炷��Η]�v�ȃ��X�������邾���Ȃ̂ł��B �@�R��]�X�ł���Ή^�]���@��ς��邾���Ő������P����܂��B �@�G���W���v���ɂ����ẮA�v����ɃX�p�[�N�m�C�Y������Ȃ��悤�ɒ�R����v���O�Ƃ��m�C�Y���X�P�[�u���H�Ƃ��őΏ����܂����A�����������ɒ�R������d��������������ɍs���͂��ł����A�v����g���N�ɂ͖w�lje���͏o�܂���B �@��������͐��Ƃ��Ώ�����̂ŁA�����Ɠ����̂����m��܂��B �@������ɂ���A�����̃G���W���i�d�q����^�C�v�j�́A����ɂ�����ǂ����ɕϒ��𗈂����܂���E�E�E�ƌ������Ƃł��B �@�G���W�����ƂɃf�[�^�[������ă������ɓ���܂�����B �������q �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����Łu�������v�Ɗ��ʂ��ŏ����Ă���Ӗ��𗝉�����Ă�����Ȃ疳�ʂȉ����͂���Ȃ��ł��傤�B �@�����Ă�����������ʂ�A�ʏ�ł������̃����e�i���X��^�]���@�̉��P�Ȃǂ́u�ł������̎��͂���Ă���A����ȏ�ɒNj��������v�Ƃ����悤���ɘ_�����߂Ă�����Ȃ�A�d���ύX�₻�ꂱ��CDI���������ē_�^�C�~���O��ύX����Ȃǂ̉������u���ȐӔC�v�ōs����̂͗ǂ��Ǝv���܂���B��x���x(��������Ƃ��ȁc)�G���W�����I�V���J�ɂ��Ă��܂������Ɋw�K���ĉ����ǂ����@�ɂ��ǂ蒅���邩������܂���B(����������܂łɕ����㏞�͂��Ȃ�̕��ɂȂ�ł��傤���ǁc) �@�������A�N���}(�����Ă����̓J�^�J�i)�̐��E�ł͂ƂĂ��Ȋw�Z�p�╨���E�H�w�ł͐M�����Ȃ��悤�ȃ`���[�j���O��ǂ��Ƃ�����A��������������E�߂���₻��Ȕ�n���Ȋw�I�ȍ����Ŕ����Ă���g���f�����i���܂���ʂ��Ă���̂������ł�����ˁB �@����ɂ��Ă��A�Ԃ̐��䃆�j�b�g��ROM��͂��ăp�����[�^��ς����肵���͉̂��������̂̎v���o(��) �@�܂����E�ł͂��߂ăR���s���[�^����̓_�^�C�~���O����Ȃ�ĕ����o�����͊�ɏ���Ă镔�i�����g���Ȃb�o�t�Ǝ��ӕ��i�ŕ�������͂��y�ł����ˁE�E�E ���Ԏ� 2009/3/11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 3/12 |
�@�F���肪�Ƃ��������܂��B �̂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���W�R���T�[�{�̃��o�[�X��H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���W�R���̃v���|�Ƀ��o�[�X�X�C�b�`������܂���B�����ŁA��M�@�ƃT�[�{�̊Ԃɐڑ����ăv���|�̃X�`�b�N�����Ƌt�����ɃT�[�{�삳�����H�������Ă������������Ǝv���܂��B�ł����2SC1815�Ƃ����肵�₷�����i���Ə�����܂��B kaze �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@2SC1815���g���ƂȂ�ƁA2SC1815(�⑼�̃g�����W�X�^)���R�Ƒ��̒�R��R���f���T����R�ł��Ȃ�Ƃ�ł��Ȃ��K�͂̉�H�����Ȃ��Ƃ����܂���ˁB �@����ȑ�|����ȉ�H�����W�R�����ɐςݍ��ނ̂���ςł��傤����A�����Ɗy�ɍ����H�ő�p�������Ǝv���܂��B �@�T�[�{�p���X���͒ʏ��1.5msec�𒆐S�ɍ��E�̉�]�͍ő�}0.5msec���ڂ����鎖�ő��삵�܂�����A�u1�`2msec�v�ƌ����Ă��܂��B �@��������o�[�X�������1.5msec�̎��͕ς炸1.5msec�A2msec�̎��ɂ�1msec�A1msec�̎���2msec�Ǝ��Ԏ���1.5msec�𒆐S�ɔ��]�����Ȃ���Ȃ�܂��玞�Ԃ����Z�����H���K�v�ƂȂ�A���̎��̌v�Z���� Trev �� 3msec �| Tnor
(Trev: ���o�[�X���ATnor: �m�[�}�����A�A�� 3msec �� Tnor �� 0msec)
�ŕ\�������ł��܂��B�@���̎��Ԃ̔��]��d�q��H���s���悢�̂ŁA�^�C�}�[�Ƙ_����H��p���Ď������܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@�^�C�}�[��H�͂���������݂�74HC221���g���������V���b�g��H�ł��B�@�����Ō��̃m�[�}���p���X�ɓ�������3msec�̊�p���X���쐬���܂��B �@������74HC00��NAND��H���g���Ċ�p���X���猳�̃m�[�}���p���X�̂Ԃ���������������Ԃ����o�̓p���X���o�����ƂŎ��Ԃ̔��]���s���܂��B �@��p���X����VR1�Ŕ��������܂��B �@�v���|���ňʒu�𒆗��ɂ��Ă����A�T�[�{�������ɂȂ�悤��VR1�߂��܂��B �@74HC221�����肵�ē��삷��Œ�Ԃ�1msec�ɋ߂��^�C�}�[���Ԃ̂��߁A��R�ƃR���f���T�ŋ��߂���^�C�}�[���Ԃ̌v�Z���Ǝ��ۂ̃^�C�}�[���ԂɃY���������܂�����A��R�l�Ȃǂ��Œ肵�Č��߂������Ȃ��Ŕ��Œ��R���Ē��߂��K�v�ł��B�莝����74HC221�ł͂��̐��l�Ŕ��Œ��R�����S������ł��傤��3msec�ɂȂ�܂������AIC�̃��[�J�[�̈Ⴂ�ȂǂŔ��Œ��R�̉�]�p�Ŏ��܂肫��Ȃ��ꍇ�͓K�X��R�l�E�R���f���T�̒l�߂��Ă��������B �@�e�e�X�g�\��LED�͎�M�@����̐���M�������Ȃ��Ɠ_�����܂���B �@�_�����Ă�����p���X��\�����Ă��邽�߂Ɂu��������Ɠ_���v���邾���ŖڂɌ����ē_�ł���킯�ł͂Ȃ��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B �@LED2�̓T�[�{�̉�]�p�ɉ����Ĕ����ɖ��邳���ς�܂����玞�Ԃ]���ē��삵�Ă��邩�ǂ����͊m�F�ł���Ǝv���܂��B �@�������ɁA����������H����M�@���ɑg�ݍ��ނ̂��ǂ��ł����A���M�@(�v���|)�ɂQ��H�Q�ړ_�̃g�O���X�C�b�`(�܂��̓X���C�h�X�C�b�`)���P���āA�X�e�B�b�N�̒��̃{�����[���̋ɐ��]������u���o�[�X�X�C�b�`�v�������ق��������ĊȒP�ł����Ǝv���̂ł����E�E�E ���Ԏ� 2009/3/8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���������T�[�{�p���X�̎d�g�݂����������������肪�Ƃ��������܂��B���w�E�̂Ƃ���܂��A�v���|���ł́u���o�[�X�X�C�b�`�v�����Ă݂����Ƃ��v���܂��B���W�������Ă݂���GND�Ǝv����4�̃{�����[���ɂȂ����Ă��鍕�����Ƒ�2�{��3�{���e�X�̃{�����[���ɐڑ�����Ă܂����ǂ̂悤�ɕύX�����炢���̂ł��傤���H kaze �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@����܂����A�����������₪�o��Ƃ́E�E�E(����Ƃ������V��̌����点�H) �@�u���o�[�X�v���Ăǂ������Ӗ��ł����H �@�{�����[�����E�ɉ��獶�ɉ��悤�ɁA���ɉ���E�ɉ��悤�ɂ��邾������Ȃ��ł����H �@���Ƃ�����A�{�����[���̍��E�̒[�q���t�Ɍq����悤�ɂ�����������ł���ˁB���Ɂu�{�����[���̋ɐ��]���������o�[�X�X�C�b�`�v�Ƌ�̓I�ɏ����Ă���̂ɁE�E�E 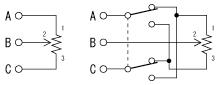 ���Ԏ� 2009/3/9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@����������Ă��܂��܂������A�����点�Ƃ��܂���������܂���B�{�����[���̋ɐ��]�Ƃ̂��Ƃō��E�̒[�q���t�ɂ��Ă݂܂������T�[�{������̕����ɉ�]���u�[���Ƃ��������Ď~�܂��Ă��܂��܂����B�����ŁA�t�^�o�̃v���|�͋ɐ������ЂƋt�i�ڍוs���ł���...�j�ƕ��������Ƃ��������̂ŊԈ�����������Ǝv�����₵�܂����B�����Ă݂����Ƃ��L�ڂ���悩�����̂ł��������܂���B�i���͂��܂茩�����Ȃ��`�l�@40�l�g���̃v���|�ł��̂ʼn�������Ȃ��Ƃ����Ă���̂�....�j kaze �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����点�E�E�E�Ƃ����̂͏�k�ł����A���ʂ̃v���|�̃W���C�X�e�B�b�N�ł���Q�{�̐������ւ��邾���ŋɐ����]�͂ł��āA���o�[�X����ɂȂ�͂��ł��B �@�s�̂́u�W���C�X�e�B�b�N���i�v�͂ǂ���ɃX�e�B�b�N��|���Ă������ɒ�R�l���ς�悤�ɍ���Ă��Ȃ��Ǝg�����ɂȂ�܂��A���܂Ō��Ă������W�R���v���|�̒��̃W���C�X�e�B�b�N������ɏ����Ē����ʒu�Œ�R�l�������A�Е��ɉO�I�[���A���Ε����ɉ��̃{�����[���̍ő�l�Ƃ����̂���ʓI�ł��B �@�W���C�X�e�B�b�N�̃X�e�B�b�N���̂�90�x�ȉ����������Ȃ��̂����ʂł����{�����[���͖�300�x�O��͉�]���܂��̂ŁA�X�e�B�b�N�̉��ɂ�����p�[�c���M���ɂȂ��Ă��āA�{�����[�����ɕt����ꂽ�M���Ɗ��݂����ăX�e�B�b�N�̏��Ȃ����p�Ń{�����[�����͑S�͈̂̔͂܂ʼn悤�ȃ��J�ɂȂ��Ă��镨�������ł��ˁB �@�����������J���Ȃ������ł̓{�����[���͑S�̂ɉ�炸�ɒ��_�����肾���g�p����悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�X�e�B�b�N��[�܂œ|���Ă���R�l�͂O�I�[���ɂ͂Ȃ�Ȃ���������܂����A�X�e�B�b�N�������Ń{�����[�������_�ɂȂ��Ă���ȏ�A�ɐ��]�����Ă��ςł����R�l�͈͓̔͂����Ȃ̂Ń��o�[�X���͉\�Ȃ킯�ł��B �@���g���̃t�^�o�̃v���|�Ń{�����[���̋ɐ��]��������T�[�{���[�ɉ�����܂܂ɂȂ�̂ł�����A����́u�蔲���X�e�B�b�N�v(�ʂɂ����������i������킯�ł͂���܂���)���g���Ă���\��������܂��B �@�M���ɂ��{�����[���S�̂̒�R���g�p����悤�ȃ��J��g�ݍ��ގ�Ԃ������P�`���āA�{�����[�����ɒ��ڃX�e�B�b�N����ڑ����Ă��āA�ǂ��炩�Е��̋ɂ���90�x���炢�����g���Ă��Ȃ��悤�Ȑ����蔲���ȃW���C�X�e�B�b�N�ł��B �@���������\�����Ɖ��肷��A�ɐ��]�����ƂƂĂ��傫�Ȓ�R�l�̃{�����[���ɂȂ��āA���̓���͈͂Ƃ͑S�R����Ă��܂��܂����烊�o�[�X����ł͂Ȃ��Ȃ�܂���ˁB �@�ʂɔėp���i���g���킯�ł��Ȃ��A���̃v���|�̒������œ���������A�Ƃ�����p�v�ł�����������W���C�X�e�B�b�N�����đg�ݍ���ł��Ă��s�v�c�ł͂���܂���B �@���̃X�e�B�b�N�̒�R�l���v������ɂ킩��ł��傤�B �@���������{�����[���̑S����g���Ă��Ȃ��悤�Ȑ�p�v�̕��ł�����z����ς��邾���̃��o�[�X���͖����ł��̂ŁA�����Ɠ���ȉ�H��v���ăv���|���������邩(����͂��̃v���|�̐�p�v�ɂȂ�̂Łu�C�̖����v�̎���R�[�i�[�ł͑Ώ����܂���)�A��L�̃��o�[�X���u����M�@���ɕt���邵���Ȃ��ł��ˁB �@���Ȃ��Ƃ��A�������܂Ō��Ă����v���|�ł͂���Ȏ蔲���X�e�B�b�N�͎g���Ă��܂���ł������E�E�E�B���E�͍L���̂ŃR�X�g�_�E���ׂ̈ɂ������������g���Ă��Ă��s�v�c�ł͂���܂���B ���Ԏ� 2009/3/10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 5/8 |
�@�����x��Ă����܂���B�悤�₭�A�������Ă�����������H�}�ɏ]�����삵�������܂����B�����������ł����B���炵����H���������Ă��������{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B kaze �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�J�[�Z�L�����e�B�̃����R���̓d�r���O�����[�d�ł����H�ɂ��ĉ��������������肢���܂��B�P�l�d�r�P�{�ō쓮���郊���R���ł����A�d�r���ꃖ�����������Ȃ����߁A�G�l���[�v���g�p�����[�d���ɉ����������ƍl���Ă���܂����A���S�҂̂��߉�H���킩��܂���B��̓I�ɂ̓����R�����������Ăc�b�W���b�N��������悤�ɂ��A�[�d�p�d���������Ƃ��ɏ[�d���s���A�[�d���������R���@�\�������Ȃ��悤�ɂ������ƍl���Ă���܂��B�[�d�d���̓G�l���[�v�[�d�킩������Ă��邱�Ƃ��l���Ă���܂��B �@����ď[�d�������G�l���[�v�[�d�킪����ɔ���ł���ł���ō��Ȃ�ł����E�E�E�B�����ł���A�[�d�������R���@�\�������Ă��d���������ƍl���Ă���܂��B�����R���̓N���t�H�[�h50.5�w�p�ł��B��낵�����肢���܂��B �y���M�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�s�̂̒P�O/�P�l�p�̏[�d�킩��z����L���ēd�r���[�d����ꍇ�̕s��ɂ��Ă��d�r�E�o�b�e���[�E�[�d��u2007�N�v�̉ߋ����O�y�[�W�́uBQ-390�ŒP��d�r(min2800mAh)���[�d�ł��܂����H�v�ɏڂ��������Ă��܂��̂ł����������B �@�܂��A�����R���ɒ��ڔz�������ă����R���̒��ɓ��ꂽ�[�d�r�ɏ[�d������ꍇ�́A�[�d�킩��{���̓d�r�̓d����荂���[�d�d���������邱�ƂɂȂ�A���d���Ń����R���̉�H�����Ă��܂��\�����l�����܂��B �@���̃����R���̓d�q��H���ǂ̒��x�̓d���܂őς�����̂����킩��Ȃ��ꍇ�́A���̂悤�ȉ����͍s��Ȃ��ق����悢�ł��傤�B �@�V�i�A���J�����d�r��1.6�`1.7V���x�ł͉��Ȃ��āA�[�d�킩�瑗��o�����d�����ő�1.7V���z���Ȃ������m�F�ł���Ƃ��A������[�d���Ă��鎞�ɓd�r���O��ď[�d���ׂ������Ȃ������ɂ��g�p���̏[�d�킩��1.7V�ȏオ��ɏo�͂���Ȃ��Ƃ��A��������������������ƌ������ꂽ��ň��S�����m�F�����Ώ[�d��Ƃ̒������s�\�ł͂Ȃ��Ǝv���܂���B �@�������A���̃����R���̓d�r�[�q��5V���炢�������Ă��S�R���Ȃ��̂ł���������ƈ��S�Ȃ̂ł����B(����ȃ����R���͖����ł��傤��) ���Ԏ� 2009/3/4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 3/5 |
�@���}�Ȃ��{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@�Ȃ��Ȃ�����悤�ł��ˁB �@�����������������悤�ɁA�����R���E�[�d��̐��\�����ꂼ�꒲�ׂ���ōČ����������ƍl���Ă���܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����B �y���M�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5V���͂�0.5�b����1�b�����[��ON�ɂ����H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB �@�����y�����q�������Ē����Ă��܂��B �@����A���m�b�����肵�������e�����Ē����܂����B �@���e�́A�TV���͎������[����莞�ԓ��삳����Ƃ������̂ł��B �@���͂͏�ɊĎ����Ă���A�����[�̏o�͂�0.5�b����1�b�ȓ��ɂ������̂ł��B �@PIC��p���Đ��䂵�悤�Ƃ����̂ł����A�v���O�����������̂���H�������̂��A�����[ON��Ԃ������Ă��܂��܂��B �@����PIC�i16F84A)�̐���͂�����߂�2SC1815�A2�Łi�P�͓��͊Ď��p�A�����P�̓����[�쓮�p�j��H��g�����Ƃ��܂������ǂ����v���ǂ���ɂ͓��삵�܂���B �@�����p�j�b�N��Ԃł��B �@�\�ł���Ή�H�������ĉ������B �@��낵�����肢���܂��B ��������� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̖ړI���ʂ����̂ł���g�����W�X�^�ł���H�͍��܂����A�����ł͒N������Ă����m�ɓ��삷�郏���V���b�g��H��IC�Őv���܂��B �@�g�p����IC�͍��܂ʼn��x���o�Ă��Ă���74HC221�ł��B �@�����V���b�g�^�C�}�[��H���Q��H�����Ă��܂��B(����͂P��H�����g���܂���) �@�u�^�C�}�[IC 555�ł�����Ȃ��́H�v�Ǝv���邩������܂��A555�̃g���K�[�q�́u����(�l�K�e�B�u)���́v�Ȃ̂ŁA����̂��v�]�́u�T�u�ɂȂ�����v�Ƃ����u����(�|�W�e�B�u)���́v�œ��삳����ɂ̓g�����W�X�^��IC�œ��̓��x���]�����Ă��Ȃ���Ȃ炸�A���i���]���ɕK�v�ɂȂ�܂��B �@���̓_74HC221�ɂ͐�������(B)�ƕ�������(^A)������܂�����A���͒[�q�͐�������(B)�ɐڑ����邾���Ń^�C�}�[�삳������̂ŗ]���ȕ��i�͕K�v����܂���B �@��H�}�ł��B 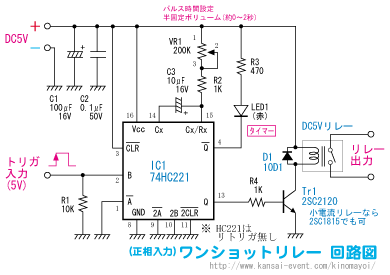 �@���쎞�Ԃ�VR1�Ŗ�O�`�Q�b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@�������Œ��R�̉�]���S���łO�`�P�b�̊ԂŒ��߂������̂ł����100K�̔��Œ��R�ɂ���Ή\�ł����A�ǂ����Ă���R��R���f���T�̌덷�ōő�P�b�ɂȂ�Ȃ������l�����܂��̂ŁA�]�T�������čő��Q�b�̒l�ɂ��Ă��܂��B���̂�����̒l�͂��D���Ȃ悤�ɂǂ����B �@74HC221�́u���g���K�v�@�\�͂���܂���A�^�C�}�[���쒆�ɓ��͂��r��čēx�T�u���͂������Ă��^�C�}�[�����͂���܂����B �@��x�^�C�}�[���Ԃ��߂��ă����[��OFF�ɂȂ�A���̌�ɂ܂����͂�0V��5V�ƕω��������Ɏ��̃^�C�}�[���X�^�[�g���܂��B �@�����g�����W�X�^�Q�ō��Ɓu���g���K�\�v�ɂȂ�܂��B(�\�ɂȂ�Ƃ������́A�^�C�}�[���ɍēx�g���K��������̂�h�~�����H�͂Q�ł͓��) �@�^�C�}�[���ɍēx�g���K�M�����������������^�C�}�[�������������̂ł���A���g���K�@�\������74HC123���g�p���Ă��������B��H�}�͑S�������ł��B ���Ԏ� 2009/2/27
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B �@74HC221�ł����c�ρi�B�B�j���������B �@�����l�b�g�Œ�������H��g��ł݂悤�Ǝv���܂��B �@�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B �@���̒m���ł͓���A�P�������炢�Y��ł܂����B�B�B ��������� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�ړI�ɂ��������i��T���̂��d�q��H�v�̋Ɉ�(?)�ł�����A���Ȃ�l�b�g�ŐF�X�ƌ����ł���ǂ�����ł��̂ŁA��������v���Ă�������J���Ă������T���̂���ł��ˁB �@�ŋ߂͂������d�q��H�E�H��̎G���Ȃǂ����s(�Ƃ������ꎞ���r�₦�Ă��������ċ����Ă���c)����Ă��܂��̂ŁA���������{�𑱂��ēǂ�ŕ������Ă݂�̂��ʔ����ł���B �@���łɁAIC�ōH�삪�ł�����PIC�Ő��䂷����@����x�l�������Ă݂Ă��������B (0) �o�̓|�[�g��L�ɂ��Ă���(������) (1) ���͂�H�ɂȂ�܂ő҂� �@�@�@�@�� H�Ȃ甲���Ď��� (2) �o�̓|�[�g��H�ɂ��� (3) ��莞��(��]�̎���)���[�v���� (4) �o�̓|�[�g��L�ɂ��� (5) ���͂�L�ɂȂ�܂ő҂� �@�@�@�@�� L�Ȃ甲����(1)�ɂ��ǂ� �@���C���̃v���O�����͂��������ꂾ���ł��B �@�u�C�̖����v�ł̓v���O�����̃R�[�h���̂ɂ��Ă͌䓚�����Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��̂��A�R�[�h�͂������ŏ����ꂽ���߂Ȃ���l���Ă��������B �@�e�X�e�b�v�������ƃR�[�f�B���O��������Ƀg���u�����N�������Ȍ������������炢�Z���v���O�����ł���ˁB �@�悭�Y�����̂�(5)�́u���͂�L�ɂȂ�܂ő҂v�ŁA���ꂪ�����ƃ^�C�}�[�I�����_�ł�����(1)�ɖ߂�Ƃ��̎��_�ł܂����͂�H�Ȃ炷�������Ă܂��o�͂�H�ɂ��Ă��܂��܂��B���͂�H�̊Ԃ����Ƃ���̌J��Ԃ��Ń����[��ON�ɂȂ���ςȂ��ƂȂ�܂���ˁB �@(5)��(0)��(1)�̊Ԃɓ���Ă��܂��Ɠd���������ɍŏ�������͂�H�ɂȂ��Ă������ɂ̓^�C�}�[�͓��삵�Ȃ��Ŏ���L����H�ւ̗����オ���҂��ƂɂȂ�܂����A���̏��Ԓʂ肾�Ɠd���������ɓ��͂�H���Ƃ����Ƀ^�C�}�[�����삵�܂��B���̂�����̐v�͓��͂ɉ����q�����Ă���̂��Ƃ��A�ǂ�������������҂���̂��ɂ���Ĉ���Ă��܂��B �@��������������ςݏd�˂ĖړI�ɂ����������������̂��u�v���O���~���O�v�ł�����A�����Ə���ǂ��čl���āA�e�i�K���Ƃɐ���ɓ��삷��R�[�h���������܂�����悤�ɂȂ�܂���B ���Ԏ� 2009/2/28
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԁE24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@24V�ԂŃo�b�e���[�̓d���ቺ�A���[�����쐬�������̂ł����A�����Ă��������B ������ �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
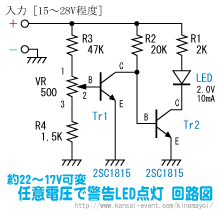 �@��{�I�ɂ́w�d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H�x�Ɠ����ŁA��R�l��ς��������ł��̂ŏڂ��������͂�������������������B
�@��{�I�ɂ́w�d�r�̓d�����WV�ʂ���UV�܂ʼn���������LED�����点���H�x�Ɠ����ŁA��R�l��ς��������ł��̂ŏڂ��������͂�������������������B�@���̉�H�ł̓o�b�e���[�x���d���͖�17�`22V�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@���o�b�e���[�ł����20�`21V�ȉ��Ōx�����炢�ɒ��߂��Ă����悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���Ԏ� 2009/2/23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM�g�����X�~�b�^�[��USB�ŁH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��āB �@����A����FM�g�����X�~�b�^�[���܂����B �@BELKIN����o�Ă���F8V3080ja�Ƃ������i�ł��B �@����� �P4�d�rx2 �� �V�K�[�\�P�b�g(12V) ��2�n���̓d���̓��͂������Ă��܂��B �@�����Ă�����AUSB�|�[�g����̓d���œ��삳����ׂ������������Ǝv���Ă��܂��B �@KA78L05AZ �Ƃ������g���Ă����̂ŁA������ 5V�Ȃ̂��ȁH�Ɨ��\�ɍl���A�ȒP�Ƀp�^�[����ǂ���������A�����ɂ��̏o�͒[�q�� 5V ��������Ă݂��Ƃ���A�N�����t����ʂ͏o�Ă��܂����������ɓd�r�����̃}�[�N���o�Ă��܂����B �@�����ō��x�́A�d�r�{�b�N�X�� 5V ����� (*1) ���Ă݂�ƁA�ꌩ����ɓ��삵�܂����B �@�d�C��H�͐��w�Z�ł����������x�̒m�������Ȃ��A�����������\�ȉ����������ɂ͂ł��܂���B �@�����ł��q�˂������̂ł����A 1. �d�r(3V)����5V�ւ̏�����H������ƍl���Ă��ǂ��̂ł��傤���H �@���Ȃ݂ɃR�C�����ЂƂd����H�t�߂ɂ���܂��B 2. ������H��������5V����������Ă����Ƃ���Ȃ�A �@�O�q�̍s��(*1)�͈��S�ł����H �@�܂�A������H�̓��͂ɏ�����̓d��(�������͂���ȏ�)��������ƁA��ʓI�ɉ����N����̂ł����H 3. �t�ɏ�L����Ȃ��̂ł���A�ǂ�������H�����Έ��S/�ȒP�ł����H �@���ɂ��̏ꍇ�A5V->3V �� 5V->12V �͂ǂ��炪���ȒP�Ō����������ł����H �@������낵����A���������������B �@��낵�����肢���܂��B ���Ђ� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���̃g�����X�~�b�^�[�̓d����H���ǂ̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���̂��́A���͕������Ă��Ȃ��̂ł킩��܂���B �@���̃��[�J�[�̐v�҂ł͂���܂���̂ŁA�������ނ̒�����ǂ̂悤�ȉ�H�ɂ��Ă���̂��́A�������������Ƃ������l�ɂ͒N�ɂ��킩��Ȃ��ł��傤�B �@78L05�������Ă����Ƃ������ł����A���̉�H���{����5V�n�Ȃ̂��A���d�r�Q�{�œ���3V�n��78L05��12V����5V�ɗ��Ƃ����Ƃ͂��Ă��A���̌��3V�n�ւ̍~�����i���t���Ă��Ȃ��Ƃ͌���܂���B �@�܂����z���̂悤�ɁA�d�r��3V��������H���g�p���Ă��āA����5V�n�œ����Ă���Ƃ����m������܂���B �@�c�O�Ȃ���A���ꂾ���̏��͊�����ɃA�N�Z�X���Ē��ڂǂ��ɉ��u��^����@�B�����ɓ��삳�����邩�̓A�h�o�C�X�̂��悤������܂���B �@���Ƃ��A������H�̓��͂ɏo�͓d����荂���d����^�����ꍇ�́A�X�C�b�`���O���삪���������Ȃ��ă`���b�p����������Ă���g�����W�X�^��ON�����ςȂ��ɂ��ċ���ɃV���[�g���A�g�����W�X�^��R�C�����Ă��Ă��܂�DC�R���o�[�^IC���������Ƃ�����܂����A�����łȂ��ĒP�ɃX�C�b�`���O���~�܂��ăR�C������o�͂ɓ��͓d�����_�_�R��ɂȂ�DC�R���o�[�^IC������܂��B �@78x05���̎O�[�q���M�����[�^IC�́A���͂ɓd�����������ɏo�͑�����d��������������܂��B �@���������g�����͕��ʂ͂��܂��A�d����H�ŏo�͑��̕����R���f���T���傫�ȏꍇ�ɂ́A�d��������Ƃ��Ȃǂɋt�����ĎO�[�q���M�����[�^���܂�����A�t������͑��ɉI����_�C�I�[�h�����鎖���w�肳��Ă��܂��B(�ڂ����̓f�[�^�V�[�g������������) �@�����������i���ǂ̂悤�Ɋ��Őڑ����Ă��āA�d�r�ƊO���d���̐ؑւ����������ǂ̂悤�ȉ�H�ɂ��Ă���̂�(�P�Ƀ_�C�I�[�h�����H)�Ȃǂ́A�{���ɂ��̊�����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂���A�ǂ��ɂȂɂ�ڑ����ėǂ����͂������œd���܂��̉�H�}��S�ď����N�����āA���̒�������S�ȏꏊ(?)��T���Ȃ���Ȃ�܂���B �@�z�������ʼn�H�̂ǂ����ɓd���������Ă���ƁA�����̊Ԃ͓�����������܂��A�O�[�q���M�����[�^�Ȃǂ��t���ɑς����˂����ɉ�ꂽ��A���̂ǂ����̕��i���ߓd���Ȃǂʼn��Ă��܂��Ă�����������܂���ˁB �@�[���ɉ�H����͂��āA���S�ȉ������ł��Ȃ��ꍇ�͌����ĉ�H�����������肨�����ȓd������������͂��Ȃ��ł��������B (�܂��A�ʂɂ��̋@�킪���Ă������Ƃ������ł�������R�ɁE�E�E�Ƃ��������ł���) �@USB��5V�œ����������̂ł���A12V�ɏ�������͕̂ϊ������̖ʂł͈����̂ŁA�f����3V�ɍ~�������ق����ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@��h���b�v�^�C�v�̎O�[�q���M�����[�^�ŊȒP��5V����3V(3.3V)�͍��܂�����A�H����ȒP�ŒN�ł��قڊԈႢ�̖����~���d���̂ق����������������ł��ˁB ���Ԏ� 2009/2/23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B �@�d�C��H���Ė{���ɑ@�ׂȂ̂ł��ˁB �@�v���̈ӌ��������Ė{���ɂ��ꂵ���v���܂��B �@���ꂩ����A�����Ƃ�����ĕ��������Ǝv���܂��B �@�g�����X�~�b�^�[�́A���ƂȂ���3.3V�ɍ~�����Ďg���܂��B �@���߂āA���肪�Ƃ��������܂����B ���Ђ� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�K�i�����܂��Ă��镨��݊��i�Ƃ��������ŋC�y�ɕ��i��I��ʼn�H����ꂽ�肷�锽�ʁA��H�}������������ł��g�����i�̌^�ԁE���[�J�[�ɂ���Đ��\����(�ő�)��i���Ⴄ�ꍇ������ȂǁA���Ȃ�C������E�ł���i�O�O�G ���Ԏ� 2009/2/25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԁE�J�[�i�r�̃o�b�N�M����x���������H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂܂��� �@2�N�قǑO���ԓ��̃��[�������v��LED�Ŏ�������Ă��܂������A���N�ɓ���܂��ă����^�b�`�n�U�[�h��555�^�C�}�[�ō���Ă���d�q�H��Ƀn�}���Ă��܂��B �@���x�i�r�ɓ���o�b�N�M����0.5�b���x�点���̌�7�b�ʐM���������Ȃ��Ă������ł����H����肽���̂ł����A�Ȃ��Ȃ����܂���ɂ͍s���܂���B �@���Ƃ��g�����W�X�^�ō�肽���̂ł����AIC���g��Ȃ��Əo���Ȃ����̂ł��傤���B �@��낵�����肢�v���܂��B �݂͂� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@IC���g�����ق����ǂ���H�����܂����A�u�g�����W�X�^�Łv�Ƃ������ő����̕s����Ȗʂ�����܂����g�����W�X�^�ō�����ꍇ�̉�H�}�������܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@��H�́uON�x����H�v�ƁuOFF�x����H�v�̂Q�̃^�C�}�[��H�ō\������Ă��܂��B�� ON�x����H �@�o�b�N�M��������ƁAC1���[�d����܂��BC1�̏[�d�d����VR1�ER1�Ő������Ă��܂�����������[�d����AC1�̓d����Tr1�삳������d���܂ŏオ���Tr1�ETr2�����삵�܂��B �@���Ԃ�VR1�Ŗ�0�`2�b���x�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �� OFF�x����H �@Tr2�����삷��ƁAC2����u�ŏ[�d����Tr3�ETr4�����삵�ATr4�̏o�͂����̉�H�́u�o�b�N�x���M���v�Ƃ��ĊO���ɏo�͂���܂��B �@�o�b�N���͂�����C1�����d���n�߂Ė�1�`2�b��Tr1�ETr2����~���AC2�����d���n�߂܂��B �@C2�̓d����Tr3�̓���d����������Tr3�ETr4����~���܂��̂Łu�o�b�N�x���M���v�͂���܂Œx�����܂��B �@OFF�ɂȂ�܂ł̎��Ԃ�VR2�Ŗ�5�`10�b�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@OFF�x����H�����삵�Ă���ԂɃo�b�N�M�����܂������ON���Ԃ͉�������܂��B �@�u�o�b�N�x���M���v�̏o�͂�Tr4�łȂ�ׂ�������ւ��悤�ɂ͂��Ă��܂����A����Tr3���ׂɐ��b�Ԃ��_���_���Ɖ����葱����R���f���T�̓d���ł�����AIC��ON/OFF����悤�Ȃ������肵���M���ł͂���܂���B��1�b���x������12V����0V�܂ʼn�����܂��B����̖ړI�́u�J�[�i�r�ɓ��͂���v�Ƃ����ڑ��ł���Ή��̖��������͂��ł����AIC�̏o�͂̂悤�ɏu�ԓI��0V�ɗ��Ƃ������ꍇ�͍X�Ƀg�����W�X�^�⑼���i�𐔌����ăq�X�e���V�X��H�Ȃǂ�g�ݍ��܂Ȃ���Ȃ�܂���B ���Ԏ� 2009/2/17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���肪�Ƃ��������܂� �@�����������H�ƈႤ�Ƃ����Tr2��������VR2��R8�̑O�ɓ��ꂽ��Tr4�ł͂Ȃ���Tr3�Ń����[��t�������ł��B �@���̂���ON�����̌�OFF�����͂���̂ł����AOFF�������Ƀo�b�N�M���������ON���������Ă��܂��M�����r��Ă��܂��܂����B �@IC���g�����ق����ǂ��̂͂킩��̂ł����A��������������͂ǂ����Ⴄ�̂����m�肽���āA�g�����W�X�^�ł��肢���Ă��܂��܂����B �@������肽���Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B �݂͂� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�M�����r��Ă��܂��Ǐ�́A�������{�I�ȂƂ��낪�Ԉ���Ă���Ǝv���܂��B �@�����[�����Ȃ�g�����W�X�^�Q��(�Q�i�ڂ�NPN��)�ł��쐬�͉\�ł����A��Ă���ēx�o�b�N�M��������^�C�~���O��������ON�x�����Z���ԂɂȂ��Ă��܂����̕��Q���o�܂��B �@�R���f���T�̐ϕ���H�E�g�����W�X�^��ON/OFF������@�Ȃǂ͒P���Ȃ����݂ł����A�ړI�ɂ��킹�Đ��������삷��悤�ɂ���ɂ͂ǂ̂悤�ɂ���Ηǂ��̂��ȂǁA�F�X�������Ă݂�Ɩʔ����Ǝv���܂���B ���Ԏ� 2009/2/19
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ԁE�E�C���J�[�A���R�[�i�[�����v�E�����[ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�����Ԃ̃E�C���J�[���_�ł��Ă���Ԃ��������[���n�m�������H�i�R�[�i�[�����v���������̂Łj����肽���̂ł����A�h�o�C�X���肢���܂��B �@�ߋ��̓��e����u555�����V���b�g�^�C�}�[���ĉ����\�v�𗘗p���ďo����̂��m�F���܂������A�����Ə��Ȃ����i�_���ō쐬�ł��܂��� �N�} �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���ꂾ���Ɍ��肵���p�r�ł���A���i�͂����Ə��Ȃ��čς݂܂��B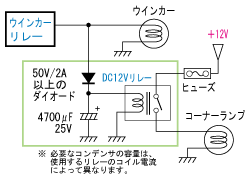 �@�P���ɁA�d���R���f���T�ɓd�C�𗭂߂āA���̓d�C�Ń����[�����邾���ł��B
�@�P���ɁA�d���R���f���T�ɓd�C�𗭂߂āA���̓d�C�Ń����[�����邾���ł��B�@�d���R���f���T�̓E�C���J�[�̓_�ŗp�d���ŏ[�d����܂��B �@�P���ɓd���R���f���T���E�C���J�[�z���Ɍq���������ł́A�d���R���f���T�ɗ��߂��d�C�̓E�C���J�[���_�ł̍ۂɏ��������Ƃ���ɃE�C���J�[�d���ɂ�����ď����Ă��܂��܂�����A�_�C�I�[�h�ŋt���͂��Ȃ��悤�ɂ��܂��B �@�d���R���f���T�ɒ~����ꂽ�d�C�Ń����[������A�d���R���f���T�����d���ă����[�����삵�Ȃ��Ȃ�܂ł̎��Ԃ̓����[�������Â��܂��̂ŁA�_�ł���E�C���J�[���狟�������d�C�ł������[�͓����Â��A�{���ɃE�C���J�[�̃X�C�b�`����ēd������������Ȃ��Ȃ���0.5�`1�b���x�̌�ɐ�܂��B(���Ԃ̓R���f���T�̗e�ʂƃ����[�R�C���̏���d���ɂ���ĕς��܂�) �@�����[�Ɏ����ԗp�i�X�Ŕ����Ă����G�[������20A�S�Ƀ����[���x�́A��r�I�傫�ȃR�C���d���������i���g���Ă��A4700��F�ʂŃE�C���J�[�̓_�Ŏ����ł̓����[���r��Ȃ��Ǝv���܂��B �@������ł̓G�[���������[�Ȃǂł̓e�X�g�͂��Ă��܂���̂ŁA�g�������[�ɂ��킹�ăR���f���T�̗e�ʂ͑��������Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/2/16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �u�O/��v�u��/�E�v�����̃��W�R���J�[�̉����͉\�H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���W�R���̎Ԃ̉����ɂ��Ă������˒v���܂��B �@���������̃��W�R���œ����Ԃ������Ă���̂ł����C�O�i�C��ށC�E�C���̑���͏o����̂ł����C�������R���g���[�����邱�Ƃ��o���܂���B�����ŁC����Ȃ̂ł����C�Ԃ�����X�s�[�h���R���g���[���o����悤�ɉ������邱�Ƃ��o���Ȃ��ł��傤���H �@�����C�\�ł���ǂ̂悤�ɉ�������悢�������Ē����Ȃ��ł��傤���B��낵�����肢�v���܂��B �ԍ� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�R���g���[���Ɂu�O/��v�u��/�E�v�̃{�^�����t���Ă��邾���̃��W�R���J�[�Ƃ������ł��ˁB �@�����������i�̓X�s�[�h�R���g���[������悤�ɂ͍���Ă��܂���̂ŁA��{�I�ɂ͊ȒP�ɕ��i��t���ւ�����lj���������x�ł̓X�s�[�h���߂��ł���悤�ɂ͂Ȃ�܂���B �@�X�s�[�h�R���g���[���p�̓d�q��H��lj�����Ƃ��āA��(���i)�ɂ���Ă͔�r�I�ȒP�ɂł��܂����A��(���i)�ɂ���Ă͂قډ����s�\�ȕ�������܂��B �@�����ł���̂́A��M�@�̎�M��H�ƃ��[�^�[�h���C�u��H���ʂ̉�H�EIC���ɂȂ��Ă���ꍇ�B �@���[�^�[�h���C�o�̐���M�������o���āA�X�s�[�h�R���g���[���p�̉�H��lj����Ă�邱�ƂŁA������x�̓X�s�[�h���ςł���悤�ɂȂ�܂��B �@�������A���M�@�����X�s�[�h�R���g���[�����ł���悤�ɉ�������K�v������܂��B �@�����āA�Ԃɓ��ڂ���X�s�[�h���ߋ@�\��PIC�}�C�R�����ō�邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA������������PIC�}�C�R���̃v���O�����Z�p���K�v�ɂȂ�܂��B (��������l����f�W�^��IC��A�i���O��H�̑g�ݍ��킹�ł�����ł��傤���A����ȕ��i���������傫�ȉ�H����郉�W�R���J�[�Ƃ͎v���܂���) �@�����ł��Ȃ��^�C�v�̕��́A��M��H�ƃ��[�^�[�̃R���g���[����H����̂ɂȂ������W���[�����l�܂�Ă���ԂŁA���̏ꍇ�͎�M��H���ƑS�������ʂ̂��̂ɐςݑւ��Ȃ��ƑS�������͂ł��܂���B �@���̎Ԃ������ł��Ȃ��ꍇ�A�}�C�N���V���[�Y���̃��W�R���p�����^�v���|�ꎮ���Ă��Đςݑւ���Ȃǂ̉������嗬�ł��ˁB�������A���������v���|�E�T�[�{�Ȃǂ��g�p�ł���傫���̎Ԃł���K�v�͂���܂����E�E�E �@�������W�R���ł̓R���g���[���ł��Ȃ��^�~���E�~�j�l��̃{�f�B�Ƀ}�C�N���n�̃T�[�{����ςݍ���Ń��W�R���J�[�ɉ�������Ă��������������Ⴂ�܂��̂ŁA���̒��x�̑傫���̎Ԃ���Ȃ�T�[�{�ꎮ�̍w���Ɛςݍ��݂ʼn������ł���Ƃ������Ƃł��B �@���莝���̎Ԏ�E���[�J�[���i���Ȃǂ����������������܂���ł����̂ŁA���̒��x�̈�ʓI�Ȃ��b�������A�h�o�C�X�ł��܂������������������B �@�����āA���̎�ނ̂�����̏ꍇ�A�Ԏ킪�������Ă������ł͎����Ă��܂���̂Łu�����ɁA���̕��i��t���āA����ȉ�H�}�Łv�Ƌ�̓I�ɂ͂������ł��܂���̂ł��������������B ���Ԏ� 2009/2/16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �d�����]�Ԃ̃��[�^�[�R���g���[���[�H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�d�����]�Ԃ̐�������Ă���܂��B �@�����̃T�C�g�̃��[�^�[�ƃR���g���[���[���g���� http://www.zdpshop.com/motor_01.htm �@�d�����]�Ԃ���낤�ƍl���Ă��܂��B �@���̍ہA�����R���g���[���̎w�ߕ������uDC 0�u�`5V�A�@���̓C���s�[�_���X�@25K���v�Ȃ̂ł����A������DC 0�u�`5V�����]�Ԃ̃_�C�i���Ȃǂő������Ƃ��\�ł��傤���H�H �@�_�C�i���͌𗬂������Ȃ̂ŁA�p���X�ɕϊ����悭�킩��܂���B �@����� �@���ɂ����Ɨǂ����@������܂��ł��傤���H�H �r�c �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�܂���ɐ�����@�ɂ��āB �@�uDC 0�`5V�v�Ƃ������ł��̂ŁA�p���X�Ȃǂł͖����A�������d�������ł��B �@����[�q��0V�����������ɂ̓��[�^�[����~�A2.5V�Ȃ�g���N50%�A5.0V�Ȃ�g���N100%�Ƃ����������ł��ˁB �@�}�ɂ���u�{�����[���ɂ�鐧��v�ł́A�������̑��u����5V��0V�Ƀ{�����[�����[���q���ŁA�X���C�_�[�̉ϓd���𐧌�[�q�ɖ߂��Ă��邾���ł��傤�B �@���āA���̃��[�^�[�R���g���[���[���u�_�C�i�����v�R���g���[������Ӑ}���悭�킩��܂���B �@�_�C�i���͎��]�Ԃ̎ԗւ̉�]���x�ɉ����Ĕ��d�ʂ��ς�锭�d�@�ł����A���̓d���@��ς��]�ԂŎ����̃_�C�i���̔��d�ʂŃ��[�^�[���R���g���[�����Ă����������܂��䂭�Ƃ͍l����̂ł��B �@�_�C�i���̔��d����𗬂��ɐ����E�������āA����Ȃ�̕��ׂ������Ă��X�s�[�h�ɉ����������d���������܂����A���]�Ԃ̃_�C�i���ł͂���̓X�s�[�h�ɒ����I�ɔ�Ⴗ��Ƃ͎v���܂���B(�����A������Ⴗ��_�C�i���������Ă���̂Ȃ炻����w�����Ă��g�������Ηǂ������ł����c) �@����X�s�[�h�̎��ɂ͂��̎��̃_�C�i���d����^��������d���ŏo�͂���郂�[�^�[�g���N�ł͌��݃X�s�[�h�Ƌύt����ꂸ�p���[���ߑ��̏ꍇ�́u�������Ȃ��Ă��ǂ�ǂ�X�s�[�h���オ���Ă��܂��댯�Ȏ��]���v�ɂȂ�\����A�t�Ƀp���[�s�����ɌX���āu���ł����Ȃ��Ƃǂ�ǂ����邾���́A�S�R���[�^�[�ł͑���Ȃ����]���v�ɂȂ��Ă��܂�����A����������Ԃ��X�s�[�h��ɂ���ĕς�����肷�鎖���e�Ղɑz�������܂��B �@���܂��_�C�i���̔��d�Ȑ����X�s�[�h�R���g���[�������Ǝ����~�~Km(�C�ӂɂ���)������Ō�������悤�ɐv�ł���A�����~�~Km�܂ł̓��[�^�[�ʼn������āA�Ȃ�ׂ��~�~Km/h��ۂ��A����ȏ�̃X�s�[�h�ɂ͐l�Ԃ����ł����Ƃ��A�ʔ������]�Ԃ͍��邩������܂���B �@���삳��鎩�]�Ԃ��`�F�[�����O���āA�y�_����������]�̓y�_�����ɐڑ������_�C�i���������Ƃ������قȍ\���ɉ������A�y�_����������]�X�s�[�h�Ń��[�^�[�̃g���N��ς��Ă�낤�I�Ƃ����g�����Ȃ�_�C�i���̔��d���\���ׂ����C�ɂ��Ȃ��Ă�����Ȃ�̕��͍��܂��ˁB �@���Ƃ����g�̏�Q�҂̕��p�́A�������̋r�͂ł͎��]�Ԃ͂����Ȃ����A�d�����]�ԂŃX�s�[�h�́u�j�Z�y�_���v�̉�]�ő��삵�����A�Ƃ���������]�ł���Ή\�ł��ˁB (�A��������l�̗͈ȊO�ő��鎩�]�Ԃ͓��H��ʖ@�ŋK������Ă��܂�)
�@�P�Ɏ��]�Ԃ̃X�s�[�h���_�C�i���Ō��o���āA���[�^�[�̃g���N��ς��悤(�ȒP�ɓd���A�V�X�g���]�Ԃ��o����I)�݂����Ȕ��z�ł͖����Ǝv���܂��̂ŁA�����X������_�C�i���͂ǂ��ɕt���ĉ��̉�]�����m����̂��Ȃǂ��������肦��Ǝv���܂��B �@���̃��[�^�[�ƃR���g���[���[�́A���炩�̓d�C���u����̓d������œ������Ƃ������́A�}�ɂ��o�Ă��܂��悤�ɐ���[�q�Ɂu�{�����[���v�����āA���̃{�����[�����n���h���ɌŒ肷��Ȃǂ��āu�c�}�~�v�����[�^�[�̃g���N��ω���������A�Ƃ������g���������镨�ł��ˁB �@�u�c�}�~�v�ł͐l�Ԃ̎w�Ő��䂵�ɂ����̂ŁA�������H�Ȃǂ����āu�A�N�Z�����o�[�v�݂����Ȍ`�ɂ�����̂Ȃ̂ł��傤�B �@�������A�K�ȁu���炩�̑��u�v���q���Ύ����^�]��g���N����ȂǓ�������\���Ǝv���܂����A����͂����ɂȂ鎩�]�Ԃɍ��킹�Ă̒��߂�J�����K�v�ɂȂ�܂��̂ŁA�����Ő���������ȒP�ɉ�H�}�������ł�����̂ł͂���܂���B �@�������x�Ȑ�������ꂽ���̂ł���A���̑��u�̃p���[������R���g���[�����@�ƁA���삳��鎩�]�Ԃ̋@�B�I�ȍ\���E�Z���T�[�Z�p�ȂǂƂ̑g�ݍ��킹����������āA�������Őv�E���삷�邵�����@�͂���܂���B ���Ԏ� 2009/2/13
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����X���炵�܂��B �@����������̂Ń����N��̃y�[�W���Ă݂܂����B �@���̎���́u�d������p��5V���_�C�i�����瓾�����v�Ƃ������Ȃ̂��Ƃ����܂������A�R���g���[���̎w�ߕ����Ƃ��āu�d������v�Ɓu�ϒ�R�퐧��v�����L����Ă��鎖����A�P�ɑ��x�̒��߂����Ȃ�ϒ�R��ڑ����邾���ŗǂ��A�ʓd���͖����Ă��ǂ��悤�Ɏv���܂����B (�����N��̃R���g���[�����́u�z���̐ڑ����@�v�Ƃ����C���X�g�������ł���ˁB) >������l�̗͈ȊO�ő��鎩�]�Ԃ͓��H��ʖ@�ŋK�� �@��C�ɍs�����ۂɁA���{�ł͂܂������Ȃ��u�d�����]�ԁv��������O�̂悤�ɊX�𑖂��Ă���̂����āA���X�����܂����v���܂����B(�ŋ߂͓��{�ł��s�̎Ԃ��o�Ă����悤�ł����B) �@�����N��̃y�[�W�̃p�[�c�͋��Z��⋳�ނƂ��Ă̈����̔��Ƃ̎��̂悤�ł͂���܂����A�u�����@�t���]�ԁv�Ƃ��āA�i���o�[�������Ƃ�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B(����Ȃ�̏��ނ��葱�����K�v�ł��傤���ǁj �@���ۂɎ���̓d�����]�ԂɃi���o�[������ď���Ă������������悤�ł��B �@�d�����]�ԁA���{�����ł����y���ė~�������̂ł��ˁB jr7cwk �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@������R�ŗǂ��Ǝv���܂�����(���������ɏ����܂���)�A�u�_�C�i���Ȃǂő����v�Ƃ������b�ł́A�X�g���[�g�Ɏ��_�C�i���̉�]�d���Ń��[�^�[��]�𑀂�Ƃ����Ӗ��Ɍ����܂��B �@�ł��̂ŐF�X�Ɛ����͂��܂������A�Ō�Ɂu�����X������_�C�i���͂ǂ��ɕt���ĉ��̉�]�����m����̂��Ȃǂ��������肦��Ǝv���܂��B�v�Ǝ���җl�ɋt�Ɏ���𓊂������Ă��܂��̂ŁA���̂���������������{���ɉ��������������̂��͎������ɂ͂킩��܂���B �@�u�����Ȃ��Ă�100%�d�C�̗͂ő���v�d�����]���́A�����ɍs���Ȃ��Ă����{�̑��̐S���������ɍs���Α�R����܂���(��) �@�������A��@�d�����]���ł��B �@�d���A�V�X�g���]�ԁE�d���Ԉ֎q�̂悤�ɖ@��̓��͐����ƃX�s�[�h�����@�\���ڂ������Ȃ�u���]�ԁv�Ŗ��Ƌ��ł��ǂ��̂ł����A���]�ԂɃ��[�^�[���ڂ��������̕��͓��R��@�ŁA���C�g��u���[�L�����v�Ȃǂ̕ۈ����u��t������ŎԌ����ăi���o�[���擾����Ό����@�����]�ԂƓ����̎��i�Ō����𑖂�܂��B �@�E�E�E�Ƃ������͓��R�m���Ă��܂��B �@�S���Ȃǂł͌l�c�Ƃ̎��]�ԓX��A�A�N�Z�T���[���𒆐S�Ƃ����u��Ҍ����A���G�ݓX�v�ŗA���d�����]�Ԃ��̔�����Ă��āA�����l�͂��ꂪ��@���ƒm�炸�ɔ����ē��X�ƊX�������Ă��܂��B �@�X�������R��@���͒m���Ă��܂�����A�u���鎞�ɐ����͂����A���q������ɓ��H�ŏ���Ă��邾���v�Ɩ@�̖ڂ������������Ă��܂��B �@����g����\��̃��[�^�[�E�R���g���[���[�̃y�[�W���������A����җl�͌����œ��X�Ə��悤�ȖړI�ł͂Ȃ��A���Z��ɎQ�����邩�A�R�̒��Ȃǂ́u���L�n�v�ŗV��镨�Ƃ͎v���Ă��܂��̂ŁA�{���̒��ł��u�d���A�V�X�g���]�Ԃ���肽���Ƃ����ړI�ł͖����ł��傤���v�Ǝ��̍l���������Ă��܂��B �@���̏�ŁA�ړI��ǂ̂悤�ȓd�����]�Ԃɂ������̂�������җl���������Ă�������A�����������炢�ׂ͍��ȃA�h�o�C�X���ł��܂����A���ꂪ�킩��Ȃ��ȏ�u�_�C�i���v���g���Ă��̓d�͂ŃX�s�[�h�R���g���[��������̂��A�P�ɓd������肽�������Ȃ̂��A�̂�����ɂ��Ă������猩�Ă��鎄�����ɂ͂���ȏ㉽���A�h�o�C�X�͂ł��܂���B ���Ԏ� 2009/2/14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���߂܂��� �@�w���ՂŃ~�j�l��̑����s���ɂ�����A���[�X�p�̃X�^�[�g�V�O�i���삵�Ă���T�C�e�B�N�X�Ɛ\���܂��B �@�F�X�����������Ă����Ƃ��낱����HP�ɍs�������܂����B �@�����Œ��ׂĉ�H�}��v�����̂ł������܂��s�����������݂����܂����B �@���삵�悤�Ƃ��Ă���̂� �@�^�~���̑��Ŏg�p����Ă���O��2���ẪV�O�i����d�q��H�ō�肽���Ȃƍl���Ă��܂��B �@�_���܂ł̗���� �@�O��SW(�g�O��)ON�Ő�LED���_�� �AOFF�Ő�LED����������LED�_��+�u�U�[���Ȃ�A3�b��OFF �����ł��� �E�d����AC100V��DC�X�C�b�`���O�A�_�v�^���g�p �E1���ɂ�LED16�g�p(�v4���Ő�LED�A��LED�e32��) �ELED�͂�����������悤�ɂ������̂œd���R���f���T�����݂����B(���M�������킶������銴����) �E��LED�͒����P�x�^�C�v��VF���ϒl2V��IF��20mA�ł��B �E��LED�͒����P�x�^�C�v��VF���ϒl3.4V��IF��20mA�ł��B �@�u�U�[�ɂ��Ăł����Ԃ̃z�[���̉��̂悤�Ȋ����ɂ������ł��B �@�����\����܂���B������낵�����肢�v���܂��B �T�C�e�B�N�X �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
 �@�����̃~�j�l��̃��[�X������Â��Ă������ɍ�����V�O�i��������܂��B
�@�����̃~�j�l��̃��[�X������Â��Ă������ɍ�����V�O�i��������܂��B�@���̎ʐ^�̂悤�Ȃ��̂ŁA�ԁE��AC100V�d���\���A�����[�g�X�C�b�`�A�͓d�q��H�^�C�}�[�ɂ���莞�ԓ_���A�d�q����炷�A���v�E�X�s�[�J�[���ځA�Ƃ��������ł��B �@�O���̓^�~���̃��[�V���O�V�O�i���Ɏ����Ă��܂����A�������[�X�Ŏg�p���Ă����u1/1000�b�^�C���v���E�����E���ʎ����v�Z�V�X�e���v�Ɛڑ����邽�߂ɏ����X�C�b�`�܂��̎d�l������Ă��܂��B (�ʐ^�͏c�u����Ԃł�) �@�ȑO�����^�~���̖{���́A�z�[���ɂ͕��ʂ̎����ԗp�z�[�����g�p���Ă��āA�̃����v�̔z������X�C�b�`���O�d�����q���A�Γd���ƘA������12V�z�[����炵�Ă��܂����B �@�ł��̂Ń^�~���X�^�[�g�V�O�i���̃X�^�[�g���́u�����Ԃ̃z�[�����ɕ�������v�Ƃ����킯�ł��B �@�������Ɏ����Ԃ̃z�[���͉����T�C�Y���傫���̂ŁA���̃V�O�i���ł͓d�q�u�U�[��H(�P��)�ɂ��Ă��܂��B �@����̉�H�ł͂����Ɩ{���ɋ߂Â��܂��傤�B �@�܂��A���[�r�[�ł́u�ԓ_���v�̍ۂɂ��Z���u�r�b�v�Ɩ��Ă��܂����A����̓^�~���̃V�O�i���ɂ͖����@�\�ŁA�����v���V�X�e������́u�J�E���g�_�E���E�X�^�[�g�v�����̍ۂ̃J�E���g�����o�����߂̕��ŁA�^�~���̃~�j�l�샌�[�X�Ȃǂł͎g�p����Ă��܂���̂ō���̉�H�}�ł͓��ڂ��Ă��܂���B �@�\���ɓd�����g�����[�r�[�̂悤�Ɏ��R�Ɂu�ڂ���v�Ə�����̂ł����ALED���Ɓu�p�b�v�Ƃ��āu�p�b�v�Ə����Ă��܂��܂��ˁB �@������LED�h���C�o��H�̂ق��ł������_���E��������������悤�ȉ�H�ɂ��܂��傤�B �@����̉�H�}�ł��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� ���암�@R1�Ńv���_�E�����ꂽ����X�C�b�`�Łu�Ԃ̏ꍇ��ON��HI���x���v�u�̏ꍇ��OFF��LOW���x���v��I�����܂��B �� �ԃ����v�h���C�o �@�X�C�b�`�̓d�C�M���Őԃ����v��_���E����������h���C�o��H�ł��B �@�u�����������������v�Ƃ�������]�̂��߁A���ڃg�����W�X�^��FET���q���̂ł͂Ȃ��A�ϕ���H�ŐM���̕ω���x�������Ă��܂��B �@����]�ɂ͂���܂��A�u�������_���v����ׂ̉�H���g�ݍ���ł��܂��B���d���ɋ߂���������������܂��B(�s�v�Ȃ�_�����̔��Œ��R�͒[�ɉĂ������A�ŏ����甼�Œ��R�������ɃW�����p�ł悢�ł�) �@�x����H��ON�̍ۂ�OFF�̍ۂŕʁX�̓d��������H��ʂ�܂��̂ŁAON�̎��ɂڂ�`���Ɠ_�����鎞�ԂƁAOFF�̎��ɂڂ�`���Ə����鎞�Ԃ�ʁX�ɐݒ�ł��܂��B �@OFF�̑��͂��܂�x������ƁA�X�C�b�`�����Ă�������炭�͓_���������Ă���x��ď�����悤�ɂȂ�܂����璍�ӂ��Ă��������B �� �^�C�}�[ �@�̃����v�̓X�C�b�`�̐�ւ��M���ł��̂܂ܓ_���E��������̂ł͂Ȃ��A�^�C�}�[IC 555�̃����V���b�g��H�ň�莞�Ԃ����_�������܂��B �@�_�����Ԃ͖�0.5�b�`���b�܂ł̊Ԃ�VR1�Œ��߂ł��܂��B �� �����v�h���C�o �@�ԃ����v�h���C�o�Ɠ��l�ɁA�����v���������_���E���������������H��t���Ă��܂��B �@�M�����̉�H���Ⴄ���߁A���Œ��R�̒��߈ʒu�Ǝ��Ԃ͐ԃ����v���Ƒ����͈Ⴂ�܂��B���ꂼ��Ɨ����Ē��߂��Ă��������B �� �z�[����������H �@C-MOS ���W�b�NIC�� 4011B���g�p��������g���U��H���Q�g�g�p���܂��B �@�Ȃ��Q�g�g�p���邩�Ƃ����ƁA�u�����Ԃ̃z�[���v�̂悤�ȉ�������]�Ƃ������Ƃł��̂ŁA�����Ԃ̃z�[���͕����{�̓d���z�[��(�g���b�N���̓G�A�z�[��)�𑩂˂Ĕ��������Ă��܂��̂ŁA����Ɏ�����ׂɂQ�̎��g���̉��������A������~�L�V���O���āu�a���v������Ď����Ԃ̃z�[�����Ɏ������������o���܂��B �@VR6��VR7�ł��ꂼ�ꉹ���߂ł��܂��̂ŁA�K�X���������u�����Ԃ̃z�[�������I�v�Ǝv���鉹���ɒ��߂��Ă��������B �@���A�z�[�����͗����v���_�����Ă������(0.5�`���b)������܂���A����ł͉����̒��߂��ł��܂���̂Łu�T�E���h�e�X�g�X�C�b�`�v��t���Ă��܂��B �@�u�e�X�g�v���ɐ�ւ���ƃz�[��������ςȂ��ɂȂ�܂�����A�S�s���܂ʼn����̒��߂����Ă��������܂��B �� �o�̓A���v �@�A���vIC�� LM386N ���g�p�����ȒP�Ȓ���g�A���v�ł��B �@4�`16�����x�̃C���s�[�_���X�̏��^�X�s�[�J�[���쓮�ł��܂��̂ŁA�����ȃR�[�X�ł�����̒��x�̃A���v�o�͂ł��イ�Ԃ�ȉ��ʂ������܂��B �@���������Ƒ傫�ȉ����~�����ꍇ�́ALM386N�A���v�̂����ɕʓr�����Ƒ�o�͂̃A���v�ƃX�s�[�J�[���q���ł��������B �� LED�p�l�� �@LED�p�l���͂��ꂼ��u�ԁ~16�v�u�~16�v�Ƃ������ƂŁA������DC 12V�œ_��������悤��R�l���v�Z���Ă��܂��B �� �d�� �@�d���͕ʓrAC�A�_�v�^�[�Ȃǂ�DC 12V���������Ă��������B �@�d���͕\������LED�̂��ߏ��Ȃ��A12V/1A���x��AC�A�_�v�^�[�ł��イ�Ԃ�ł��B �� ����ƃe�X�g �@���߂��锼�Œ��R�A���ʒ��ߗp�{�����[���ƒ������͂�������܂����A�����ɏ����������̏��ɉ�H�����삷�邩�e�X�g���Ă䂯�����g���u���������Ă��̏���͒��ׂ₷���ł��傤�B �@�d�������Ă��邩�͍ŏ��ɒ��ׂȂ���Ȃ�܂��i�O�O�G �@�~�j�l�샌�[�X�����ł͂Ȃ��A���W�R�����[�X�₻�̑��̐M���@�ɂ��g���܂�����A�g�ݍ��ރP�[�X��`���ړI�ɂ��킹�čH�v����Ƃ悢�ł��ˁB �@100V�̓d�����g�p�����A�\������LED���g�p���Ă���̂�12V�o�b�e���[�ł����삵�܂�����AAC�d���̖����T�[�L�b�g�ł��g�p�ł��܂��B ���Ԏ� 2009/2/11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@��������肪�Ƃ��������܂��B �@���\���G�ȉ�H���ȂƎv���Ă܂������ӊO�ƃp�[�c�������Ȃ������݂����ł��ˁB �@�����͈�C�ɉ�H��g�����Ƃ������炤�܂������Ȃ������悤�ł��B �@�����ӏ����e�����ÂœƗ����Ă���悤�Ȃ̂ŗL��ł��B �@�撣���Đ��삵�Ă݂܂��B �@�s���ȓ_���������玿�₳���Ă��������܂��B �@�{���ɗL��������܂����B �@���Ɛ���r���̏��u���O�Ō��J�������̂ł����H �@���e�ɂ��Ă͉�H�}�͌��J��������̊O���Ȃǂ��L���ɏ����A�ڍׂƂ��Ă�����Ƀ����N��\��`�ɂ������̂ł��������ł��傤���H �@�����҂����܂��B �T�C�e�B�N�X �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�K�v�Ƃ����@�\���P���Ȃ��߁A���̒��x�̉�H�E���i�ōς݂܂��B �@�u�������_���E�����v�̉�H�͊ȈՓI�Ȃ��̂ł��̂ő����N�Z������܂����E�E�E�B �@�u���O�Ő���ߒ��̌��J�͗ǂ��ł��ˁB �@����������Ă݂����Ǝv������ɂ͗ǂ������ɂȂ�܂��ˁB �@���J���ꂽ�為��URL�����������������B ���Ԏ� 2009/2/12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 2010 5/12 |
1�N�قǑO�Ɂu�~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐���v�̎��₵���҂ł��B ���Ԃ��o���Ă��܂��܂������ŋ߂ɂȂ��č��n�߁A�u���O�Ō��J�����̂ł��m�点���܂��B ���X�Ɍ��J���Ă����\��Ȃ̂ŋX�������肢���܂� �T�C�e�B�N�X �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 2012 12/11 |
�u�~�j�l��Ȃǃ��[�X�p�X�^�[�g�V�O�i���̐���v �ł͑�ς����b�ɂȂ�܂����B ���u���O������܂����̂ŐV�����y�[�W�����ē����܂��B �X�^�[�g�V�O�i������L���ꗗ http://ameblo.jp/saitx/theme-10056837453.html ���쓮�� http://www.youtube.com/watch?v=vUaRlWP52Tw �X�������肢���܂� �T�C�e�B�N�X �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �����g������̂����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�J�[�̋G�߂ł��������g������̒��q�����������Ă܂��B �@�����g�U���͊���Ă܂��A���U�������Ȃ�����キ�Ȃ����肵�܂��B�����Ȃ������ł��������͎キ�Ȃ��Ă�C�����܂��B �@�������j�b�g�̊������ƃp���[�g�����W�X�^1�ƃ_�C�I�[�h�A�R�C���A�R���f���T�A��R�A���Œ��R������A�h�b�͂��Ă܂���B�`�b�S�W�u�͐���ɋ�������Ă܂��B�������j�b�g�͂ǂ̂悤�ȉ�H��������Ă���̂ł��傤���H KAZE �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�����Ȃ�����A�キ�Ȃ����肷�錴���͂��̏��i���������蒲�ׂȂ��ƁA�����g�U���q�������Ȃ��Ă���̂��A�g�����W�X�^�Ȃlj�H�������Ȃ��Ă���̂��͂킩��܂���̂ŁA���[�J�[�ɏC���ɏo���ꂽ�ق��������Ǝv���܂��B �@�����g�U���q�Ƃ͈��̃X�s�[�J�[�̂悤�Ȃ��̂ŁA�g�����W�X�^��H���Ŕ��������������g���g���̓d����������ƁA���̎��g���ŐU�����܂��B �@���ʂ͒����g�U���q�Ƃ��̐U���𑼂ɓ`����U�����Z�b�g�ɂȂ��������g���Ă���Ǝv���܂��B �@�����g�U���q�̓s�G�]�f�q�Ȃǂ́u���d�f�q�v�ƌĂ��d����������ƐL�т���k�肷��f�q�������P�[�X�ɓ��ꂽ���ŁA������d���Ŕ����ȓ��������܂��B �@�U���q�ɂ͋��U���g��������A�������̎��g���ߕӂōł������悭�U�����܂��B�����g�U���q�͂��̖��̒ʂ蒴���g�т̎��g���ōł��悭�U�����܂��B �@���̒����g�U���q�̒��̐U���f�q�����Ă��܂��U���ł��Ȃ��Ȃ��Ă���\��������܂����A���U��H�̂ǂ������ɂ�ŕs����ɂȂ��Ă���Ƃ��������l�����܂��B �@�܂��A���U�E���U�q���Œ肵�Ă��镔��(�l�W�H)���ǂ����ɂ�ŐU�����z�����Ă��܂��Ă��āA�U�����キ�Ȃ��Ă���悤�Ȍ̏���l�����܂��B �@�l�W�ȂǂȂ���߂�Ηǂ��̂ł����A�ق��f�q���H�̌̏�Ȃ�f�l���e�X�^�[���Ō��Ă��킩�镨�ł͂���܂���̂ŁA�����E�C���̓��[�J�[�ɔC���܂��傤�B ���Ԏ� 2009/2/10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�p���[�g�����W�X�^�ƒ�R���������Đ���ɂȂ�܂����B���U���g����1600-1750KHZ���ő�̖��������̂悤�ŋ��U���̐U���f�q�̃C���s�[�_���X��49���O��Ƃ����Ƃ���܂ł͒��ׂ܂����B �@����ɂȂ�܂������ǂ�������H���삵�Ă��邩����������܂��B2�̂k�̊Ԃ���o�͂���Ă�̂Ńn�[�g���[�`�H �@�������j�b�g�̈�ʓI��H������Ή�H����ɂ��Ēm�肽���ł���... KAZE �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�g�����W�X�^���ɂ�ł��������ł����H �@�����ĂȂɂ��ł��B �@�u�������j�b�g�̈�ʓI��H�v�Ƃ����͈̂�x�����������Ƃ�����܂���̂ŁA�����������ׂ���Ɨǂ��Ǝv���܂��B �@�̎����������̂�IC�ł����B �@���U���g���Ȃǂ̃f�[�^�ɂ��ẮA���݂��g���ɂȂ��Ă��������̒����g�U���q�̌^�Ԃ��烁�[�J�[�����Ȃǂׂ�ꂽ�̂ł��ˁB �@�u�����̗ǂ����U���g���v�͑f�q���Ƃ�t�̂ƐڐG���鑕�u�����̍\���ɂ���ĈႢ�܂�����A���莝���̑f�q��1600-1750KHZ���ő�̖����������Ƃ��Ă��A���̑f�q�⑼���[�J�[�̉������j�b�g�ł͑S���Ⴄ���g���ɂȂ�܂��ˁB �@�����g�U���q�ɂ͈�ʓI�ȁu�����g�v�ƌĂ����g����38�`40KHz��ɍ������U���q������܂����A���g���̍������ł͐�MHz�ɓ������Ă��镨������܂��B���\KHz���z�����炻��͂����u�����g�v�ł͖������g���ł����E�E�E�B ���Ԏ� 2009/2/20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �g�����X���X�ŃN���X�g�[�N�̂ł���C���^�[�z����H�H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@��B�Ắu�r�f�I�J�����^�摀�샍�{�b�g�v�����ő�ς����b�ɂȂ�܂����B �@����A�V����PIC�Ɋւ��鎿��𓊍e�����̂ł������Ȃ������̂ʼn����̎�Ⴂ�œ͂��Ȃ��������Ⴕ���́A�ގ�����b��𓊍e�����̂ʼn��Ȃ������̂ł��傤���H �@�����ł���Α�ώ��炵�܂����B �@����A�V���Ɏ��₳���Ă������������̂ł����u�N���X�g�[�N�̏o����g�����X���X�̃C���^�[�z���v�͏o���Ȃ����̂ł��傤���H�o������C�����X�ɂ������̂ł������i���肪����ł�������A�d�g�@�Ȃǂ̖�肪������̂ł���ΗL���ł��ł��B �@�����A���m�b��q�؏o����K���ł��B 40�߂��̏��S�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���A���̃C���~�l�[�V�����Ɏg����u�����[�v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�ԍڗp�̉��A���̃C���~�l�[�V�����삵�����Ǝv���Ă��܂��B �@�����Z���T�[�ł͂Ȃ��A�f�b�L�̃X�s�[�J�[�܂��͂q�b�`���C�����璼�ڐM�������o���A�����[�i�������x�̑������́j����āA�`�b�b�d���ŃC���~�l�[�V������_�������悤�Ǝv���Ă��܂��B �@�Ȃɂ��A�g�������ȃ����[�i�\���b�h�A�d����킸�j�͂Ȃ����̂ł��傤���H �������� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@������ƕ��͂�����ӂ�ŁA����̘_�_���s���ł����A�u�X�s�[�J�[�܂��̓��C������M�������v�Ƃ����M�����ŁA�u�g�������ȃ����[�͂Ȃ��ł��傤���H�v�Ƃ���������E�E�E�Ƃ������́A�r���ɉ������ʉ�H��M���A���v���g�킸���A�X�s�[�J�[��C���M���œ����ǂ������[�͖������H�Ƃ������b���ł��ˁB �@�E�E�E�����ށB����B �@�܂����C���M���͖�10mVp-p�ł�����A����Ȕ���ȓd�C�M���œ��������[�͂܂�����܂���B��ɑ�����H���K�v�ł��B �@�܂��A�d�������[�̏ꍇ�͉����M���ɂ��킹�āu�����œ_���v�Ȃ�Ă������炠���Ƃ����܂ɐړ_���C�J��Ă��܂��܂�����A�����ɘA�����Č��������ł���悤�ȃC���~�l�[�V�����ɂ͎g���܂���B �@�X�s�[�J�[�o�͂���̓d�C�M���Ȃ�A���Ȃ�̉��ʂŃX�s�[�J�[��点��A���v�̏o�͂ł���ΐ��u���x�̐U��������܂�����A�@�B�������[�͖����Ƃ��Ă������̃����[�ł���Γ��삳���邱�Ƃ��ł��܂��ˁB 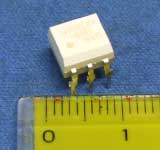 �@���Ƃ��ΉE�̎ʐ^�́AOMRON��MOS FET �����[�uG3VM-61B1�v(�����Œʔ� 470�~)�ł���A�t�H�g�J�v�����͂œ��͓d����1V�����œ����A�o�͂�AC 500mA(�����p���ڑ���DC 1000mA)�܂Ŏg�p�ł��܂��B
�@���Ƃ��ΉE�̎ʐ^�́AOMRON��MOS FET �����[�uG3VM-61B1�v(�����Œʔ� 470�~)�ł���A�t�H�g�J�v�����͂œ��͓d����1V�����œ����A�o�͂�AC 500mA(�����p���ڑ���DC 1000mA)�܂Ŏg�p�ł��܂��B�@�uSSR�v�u�\���b�h�X�e�[�g�E�����[�v(�����̃����[)�̈��ł����A����SSR�ƌĂԂƕ��ב��̐�����g���C�A�b�N���g�p���Ă��āu�𗬂̐���Ɏg���v�p�r�̕��̎����w���܂��̂ŁA�����p�r�ŃX�C�b�`���O��FET���g�p�������ł�SSR�ł͂Ȃ��uMOS FET �����[�v���ƌŗL�̖��O�ŌĂт܂��B(SSR�ɂ������g�p�̕�������܂����d�d) 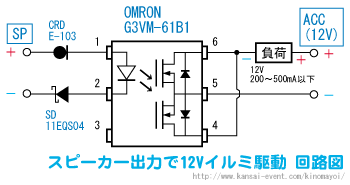 �@���ב���DC�g�p�Ƃ��Ē��̂Q��FET���p��(����)�Ŏg�p���āA�ő�1000mA�܂ł̓d����������悤�ɂ��Ă����܂��B �@�A���A�u�ő�1000mA�v�Ƃ̓X�C�b�`���O�p��FET�����S�ɓ��삳���A������R���Œ�ɂ����ꍇ�̐�ő��i�ł��̂ŁA����̂悤�ɉ����M���́u�A�i���O���́v�Ŏg�p�����ꍇ�ɂ�FET�����S��ON�ɂȂ肫��Ȃ����Ԃ����X����܂�����A�����ł�����x�̒�R�l�ɂȂ葹��(���M)���傫���Ȃ�܂��B �@�ł�����A�u�ő�1000mA�Ə����Ă��邩�炢��1000mA�����Ă����v�v�Ƃ������ł͂Ȃ��A�����ȉ��A��������Ə��Ȃ��d���̕��ׂ����q���ł͂����܂���B �@�傫�ȓd���𗬂����ׂ��q���ŃA�i���O�Ŏg�p���Ă���ƁAMOS FET �����[������\��������܂��B �@���ꂾ���̒P���ȉ�H�ŁA���ׂ�DC12V�œ_������LED�����v�Ȃǂ��q�����ꍇ�A�X�s�[�J�[�̉��ʂ��グ�čs���ƃ`���`���Ɠ_�����͂��߁A����ɉ��ʂ��グ��Ƃ��Ȃ�h��ɉ��ɂ��킹�ē_�ł��܂��B �@�������A�_�ł̗ʂ̓X�s�[�J�[���ʂɂ��킹�đ������邾���ŁA�X�s�[�J�[���ʂ͕����₷�����ʂɂ��Ă����āA�C���~�l�[�V�����́u�������x�v��ς��邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�����ꒃ�o�͂̑傫�ȃA���v��ς�ł��āA�Ԃ̊O�܂ŃK���K������炵�Ă���悤�ȃX�[�p�[�I�[�f�B�I��ς�ł���̂ł�����A���̉�H�̓��͂ɐ��\�`���S���̔��Œ��R��{�����[����ɂ��Ċ��x�������Ă��g����ł��傤���A���ʂ̃J�[�I�[�f�B�I���x�ł͒�R�ɂ��ςł͂��܂���p�I�Ȕ͈͂ł̒��߂͖����ł��傤�B �@�����Ɠ��͊��x�����߂ł��āA���R�ɃC���~�l�[�V�����̖��Ń��x����ς������̂ł���A��͂���͉�H�ɂ͓d�q��H�ő�����H���Ƃ���āA���R�ɃQ�C����X���b�V�����h���x����ς�����悤�ɂ���̂��x�X�g�ł��ˁB �@�u�g�������ȃ����[�v�Ƃ��������₪�A���ɉ���������x�������H�͎��삳��Ă��āA�o�͂Ƀg�����W�X�^��FET�ł͂Ȃ��u�����[���g�������A���Ǘǂ�����m��Ȃ��v�Ƃ������ł���A���Љ���悤�Ȍ��ڑ���MOS FET �����[�����ɂ��F�X����܂�����A�ړI�ɂ���������T���Ă݂Ă��������B ���Ԏ� 2009/2/6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED���U���Ԃɏ�������u�P���^�C�}�[�v(10�b�O�\���u�U�[��) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@LED�^�C���A�b�v�^�C�}���~�����̂ł����A�ǂ������炢���̂������炸�������Ă����Ƃ��낱����̃T�C�g�ɂ��ǂ蒅���܂����B �@LED6�ʂň�������v�������Ă���1���őS�ď�������悤�ȕ�����肽���̂ł��������Ē����܂��ł��傤�� �@��������v���_���Ă������ł������̂ł����B �@�o����^�C���A�b�v10�b�ʑO�Ƀs�s�b�Ɖ�����Ɨ��z�Ȃ̂ł����B�^�C���A�b�v�Ɠ����ł��\���܂���B �@���݂܂���A�X�������肢�������܂��B ���� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�uLED���T���Ԃɏ����āA���Ԃ�30�b�`60���Ŏ��R�ɉρA�I���Ń����[����ƃu�U�[�����v�Ƃ�������җl�̖ړI�ɂ҂�������L�b�g�������d�q�������_�[�L�b�g����̔�������Ă����̂ł����E�E�E�E���͂���܂���ˁB �@������AN6781�Ƃ����^�C�}�[IC�𗘗p�������̂ŁA�~�����@�\�̑唼���P�`�b�v��IC�ɓ�������Ă��܂����B(�g�ݗ��ĂĂ��Ȃ������P�Z�b�g�茳�ɂ���܂���) �@������AN6781���̂�����ł͓��肵��Â�IC�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��̂ŁA����͕��ʂɉ����ł�����ł��郍�W�b�NIC���őg�ݗ��Ă��H���l���܂��B �@����܂��A��������̗��s��PIC�ō���14�`18�s����PIC��ŏo���Ă��܂��悤�ȕ��Ȃ̂ł����B �� LED���U�A�X�^�[�g���ɑS�_���A10�b�����ɏ��Ԃɏ������Ă䂭�B �� �u10�b�O�v�Ɂu�s�s�b�I�v�ƃA���[���E�u�U�[����B �� 60�b�őSLED�������A����Ɂu�I���vLED���_���A�A���[���E�u�U�[���u�s�s�s�s�s�c�v�ƘA���Ŗ�B �� �X��10�b�Ŏ������Z�b�g����āu�I���vLED�������A�A���[���E�u�U�[����~�B (�������Z�b�g�͋֎~���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�֎~�����ꍇ�͎蓮�Ń��Z�b�g����܂Ŗ�Â���) �@���������^�C�}�[�����܂��傤�B �@��H�}�́u10�b�~�U�J�E���g��60�b�v�^�C�v�ł����A�N���b�N���U���g����ύX������D���Ȏ��Ԃ̃^�C�}�[�ɕύX���ł��܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�@IC���U�g���A���\�z������{���Ȃǂ��������������ׂɓd�q��H���S�҂̕��͍�鎞�Ɏ��s����\�������Ȃ荂���ł����A�u���b�N���ɂ����Ɠ��삳������ŏI�I�ɂ͑S�Ẳ�H���������܂��B�� ���쐧�� �@74HC00��NAND�Q�[�g���Q�g����RS-�t���b�v�t���b�v�Łu���쒆(RUN)�v���u��~��(STOP)�v�����ւ��܂��B �@�u�X�g�b�v�v�X�C�b�`���ɂ��p���[�I�����Z�b�g��H�����t���āA�d������ꂽ���ɂ͕K�����Z�b�g��Ԃɂ��܂��B�ł��ȂƊe���W�b�NIC�̏o�͂��s���Ȃ̂łƂ�ł��Ȃ��\���⓮�������\��������܂��B �@�܂��A�u�X�g�b�v�v�X�C�b�`���ɂ̓^�C�}�[��H����u�������Z�b�g�v��������ׂ̔z�����q���ł��܂��B(����͕s�v�Ȃ�z�����Ȃ��Ă��\���܂���) �@�u��~��(STOP)�v��Ԃ��N���b�N������H���U�i�K�\���J�E���^�����Z�b�g���Ă��܂��B �� �N���b�N���U (10Hz) �@�^�C�}�[IC 555���g�p�������U��H�ŁA���U���g����10Hz�ł��B �@VR1�Ŏ��g����������ł��܂��̂ŁA�^�C�}�[���삪�������u10�b������LED���P������v�悤�ɒ��߂��܂��B �@�U�i�K��LED�����������̂ɗ~�������g���́u10�b�ň��v�Ȃ̂�0.1Hz�ł��B �@�^�C�}�[IC 555���g�p���āu0.1HZ�̔��U��H�v���ȒP�ɂł��܂����A���̏ꍇ��555�̓�����H�̐����ɂ���Ă�����ƍ��������Ƃ��������܂��B �@���쐧���H�ŃX�^���o�C���͔��U������~�߂Ă����āA�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`����������555�̔��U���J�n����悤�ɂ���Ή�H�͊ȒP�ɂȂ�܂����A���萔�����߂Ă���R���f���T�͔��U��~����0V�ɕ��d����Ă��āA���U����1/3Vcc��2/3Vcc�̊ԂŃX�C���O���܂��B �@���U���J�n���čŏ��̉���0V����2/3Vcc�܂œd�����オ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA0��1/3Vcc�̊Ԃ�d�����オ�鎞�Ԃ����]���Ƀ^�C�}�[���쎞�Ԃ��L�т܂��B �@�ŏ���LED��������܂ŗ]���Ȏ��Ԃ��܂������ԂɂȂ�A�Q�ڂ�LED�ȍ~��������̂͐ݒ�(��])�������ԏ��Ƃ����傫�Ȍ덷���܂^�C�}�[�ɂȂ�A�P�i�K��10�b���炢���ƖڂɌ����Ď��ԍ����������C���������̂ł��B (�C�ɂ��Ȃ��E�E�E�Ȃ炢���̂ł���) �@����555�^�C�}�[��0.1Hz���U�Ŏ��R�ɔ��U�����Ă����āALED�̂U�i�J�E���^�������Z�b�g���Ă����E�E�E�X�^�[�g�������ɂ�555�^�C�}�[�͏���ɓ����Ă��܂�����A�ŏ��̈��ڂ̃J�E���g�܂ł��{����10�b�ł���m���͔��ɒႭ�A0�`10�b�̊ԂŁu�^�C���v�Ƃ��������Ƃ�ł��Ȃ��^�C�}�[�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@����Ȕ���p�I�ȃ^�C�}�[�͗v��܂���A�����Ƃ����^�C�}�[�ɂ��܂��傤�B �@�����ł͕K�v�Ȏ��g����100�{��10Hz�Ŕ��U�����Ă����܂��B �@�܂�555�̏o�͂Ƀe�X�g�p��LED10��ڑ����Ă��܂��̂ŁA555�蔭�U�̗l�q���m�F�ł��܂��B �� �N���b�N���� (1/100) �@10Hz�Ŕ��U������555�̏o�͂�������1/100�ɂ��܂��B �@���ۂɂ�74HC390�Ƃ����u�Q�i�@10�i�J�E���^(Decade Counter)�v�Ƃ���IC���g�p���܂��B �@74HC390�̒��ɂ́u�S�r�b�g�̂Q�i���J�E���^�v���Q�g�����Ă��āA���ꂼ��0����1,2,3�ƃJ�E���g�A�b�v���܂����A10�ɂȂ�ƃ��Z�b�g�����0�ɖ߂�10�i�����P���J�E���g����@�\(�S�r�b�g�̏o�͂�0�`9)������܂��B �@�Q��H�����Ă��܂��̂ŃJ�X�P�[�h�ڑ�(���ԂɌq��)�����10�i�~�Q����100�܂�(0�`99)�J�E���g����J�E���^�[�ɂȂ�܂��B �@�����ɕK�v�Ȏ��g����100�{�̎��g���Ŕ��U�����Ă���555�̐M������͂��Ă��ƁA�o�͂����1/100���ꂽ���g���̐M�������o���A�ړI��0.1Hz��LED�\�����P�����ׂ̐M�����o�Ă��܂��B �@���̃N���b�N������H�̓X�^���o�C���̓��Z�b�g����Ă��āA�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������ꂽ������J�E���g���J�n���܂��B �@�N���b�N���͂�555�����R���U���Ă��܂�����A�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������ꂽ���_��555�̔��U���̗l�q���P�T�C�N��(0.1�b)�̒��ʼn������x���͂킩��܂��A�s��Ȃ̂́u�ő�0.1�b�̌덷�v�Ƃ����͈͂Ɏ��܂�܂��̂ŁA���̉�H�̏ꍇ�̓^�C�}�[�X�^�[�g���̉�H������̌덷��0.1�b�ȓ��ƂȂ�A���Ȃ萳�m�Ȏ��Ԃ����ނ��Ƃ��ł��܂��B (555�̔��U���g�����̂��Y���Ă���͕̂ʖ��ł�) �@74HC390�̏o�͂ɂ͊e�J�E���^�̏o�͂Ƀe�X�g�p��LED8�ELED9��ڑ����Ă��܂��̂ŁA���������u1�b�v�u10�b�v�̃N���b�N�M�����m�F�ł��܂��B �@7490����10�i�J�E���^�̉�H���悭�����m�̕��͂��̉�H�}�����āu����H�v�Ǝv��ꂽ��������܂���B �@�e�i�����J�E���^�a(�T�i�J�E���^)�ɐ�ɐM�������A�J�E���^�`(�Q�i)�ɃJ�E���^�a�̏o�͂����Ă��܂��B �@���ʂ��J�E���^�`(�Q�i)�łQ�������������J�E���^�a(�T�i)�ɓ���A�o�͂̂S�r�b�g�f�[�^��������BCD�R�[�h�ɂȂ�悤�Ɏg���̂���ł����A�����BCD�f�[�^�����o���̂��ړI�ł͂Ȃ��A��������ׂ̉�H�Ȃ̂ł��̂悤�ɐڑ����Ă��܂��B �@�������A��Βʂ��`���a�ƌq���̂ƍ���̂悤���a���`�ƌq���̂ł́u1/10�ɂ���v�Ƃ����@�\�ł͓����ł�����u�Ȃ�ł���ȕςȂ��Ƃ��H�v�Ƌ^��Ɏv����Ǝv���܂��B �@�����a���`�Ƃ��Ă���̂́u�e�X�g�pLED�����₷���悤�ɁI�v�Ƃ����z���ł��B �@�`���a�Ƃ���ƁA�S�r�b�g����ǂ̏o��(����A����MSB�ł���)������u���͎����̔���(Duty=50%)�œ_�ł���M���v�͎��o���܂���BQD����M�������ƃo�C�i���J�E���^���T�i�Ń��Z�b�g���Ă���W�Łu��r�I�p�b�p�b�ƒZ���_�ł���\���v�ɂȂ�܂��B �@�a���`�Ƃ���ƁA�Ō�̒i��QA��1/2������H�̏o�͂ł�����A�u�Y���Duty=50%�́A���X�̎����œ_�ł��錩�₷��LED�\���v�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@�ʂɁu�ǂ��ł������v�Ǝv�������܂ōS��K�v�͖����̂ł����A�^�C�}�[�������������鎞��LED�\���͌��₷���ق����������ȁE�E�E�ƍl�������ʂł��B �� �U�i�K�\���J�E���^�[ �@�N���b�N������H�ō��ꂽ0.1Hz�̐M����LED�𑀍삷��o�͂����Ԃ�H�ɂ��Ă䂭��H�ł��B �@LED�����Ԃɑ��삷�邽�߂Ɂu�V�t�g���W�X�^�v��74HC164���g�p���܂��B �@�X�^���o�C���͂�͂肱�̉�H�̃��Z�b�g����Ă��܂��B �@���ׂĂ̏o�͂�L�ł��B �@�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������ƃ��Z�b�g�͉�������A�N���b�N������H���痈��u10�b�Ɉ��(0.1Hz)�̃p���X�̗����オ��v�ŃV�t�g���W�X�^�̏o�͂́u�P�ׁv�̃f�[�^���o�P�c�����[�̗v�̂ňړ����܂��B �@�f�[�^���͒[�q�`�E�a��Vcc�ɂȂ���Ă��܂�����A�o�͒[�q�͈��N���b�N������x��QA���珇�ɂP����H�ɂȂ�܂��B �@�U�ڂ̏o��Qf�͂U��ڂ̃p���X��H�ɂȂ�܂��B����́u10�b�~�U���60�b�o���v�Ƃ�����ԂŁA�ړI�́u60�b�o�߁v��\���܂��B �@QF�͔��]�����āu60�b�o�߂�L�v�Ƃ����M�������܂��B����͂U�S�Ă�LED�����������ɂ��ꂪ�u���Z�b�g����Ă����ԂȂ̂��A�^�C�}�[������������ԂȂ̂��v���U��LED����͂킩��Ȃ��̂ŁA�^�C�}�[���I��������������u�I���v�\���p��LED��_��������ׂł��B �@�������u�u�U�[���邵�A�����LED�v��Ȃ��I�v�̂ł�����A���]��H��LED���͌q���Ȃ��Ă����\�ł��B �@�^�C�}�[�I����X��10�b��QG��H�ɂȂ�܂��̂ŁA���������ł����炱�̐M���Łu���Z�b�g�v�X�C�b�`���������̂Ɠ����̓�����s�킹�āA���Ă���u�U�[��10�b�Ŏ�����~�����܂��傤�B �@������u��x��͂��߂���A�蓮�Œ�~����܂ł͖葱���Ă����ė~�����I�v�Ƃ�����]�ł�����z�����Ȃ��Ă����\�ł����A�܂�QH���X��10�b���H�ɂȂ�܂�����A����I�����20�b�Ń��Z�b�g����Ȃ�QH����M�������������ƂɂȂ�܂��B�ړI�ɂ��킹�ĐF�X�Ɠ���̗l�q��ύX���邱�Ƃ��\�ł��B �� LED�h���C�o �@74HC164�ɒ���LED���q���ł��܂��ƁA�U�_�������74HC164�̋��e�d�����z���ēd���������ׂ�IC���Ă��܂��܂��B �@�����ŊO���Ƀg�����W�X�^���q����LED�ɗ����d���̓g�����W�X�^��ON/OFF������̂���ʓI�ł����A�����ł̓g�����W�X�^�ƃo�C�A�X��R�����P�̃p�b�P�[�W�ɓ����Ă��Ďg���₷���u�g�����W�X�^�A���C�v���g�p���܂��B �@�ȑO�uF-1���X�^�[�g�V�O�i���̐����v�ł�TD62083AP���g�p���܂������A����͏����ႤTD62384AP���g�p���܂��B �@TD62384AP�́u���͂�L�v�̎��ɏo�̓g�����W�X�^��ON�ɂ���g�����W�X�^�A���C�ł��B �@�]���ăV�t�g���W�X�^74HC164�̏o�͂�L�̂Ƃ��A�܂胊�Z�b�g����Ă���Ԃ�A�J�E���g���ł��܂�H�ɂȂ��Ă��Ȃ��r�b�g�Ɍq���ꂽLED��ON�ɂȂ�܂��B �@���̔]�_���̃g�����W�X�^�A���C���g�p���邱�ƂŁu�܂�H�ɂȂ��Ă��Ȃ�LED�͓_���v�uH�ɂȂ���������v�Ƃ����^�C�}�[�\�����\�ɂȂ�܂��B �@�����A���ꂾ���ł́u���Z�b�g�����V�t�g���W�X�^�̏o�͂�L�v�ł�����LED�͓_�����Ă��܂����ƂɂȂ�A�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������O����LED��6�_�����Ă���̂͂��܂����������܂���B �@��͂�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`���������u�Ԃ�LED���U��ĂɃp�b�Ɠ_�����āA���Ԃɏ����Ă䂭�ق��������ł���ˁB �@���ׂ̈����쐧����H����_RUN�M�������炢�A�^�C�}�[���쒆�̂�LED��_��������悤��LED�̃R�������g�����W�X�^(2SA950)�ŃR���g���[�����Ă��܂��B �� �u�U�[�����H �@�u�U�[�́u60�b�œ���I���������Ƀs�s�s�s�s�ƘA���v�ƁA����]�́u�I��10�b�O�Ƀs�s�b�I�ƂQ���v��܂��B �@60�b�I������QF��H�ɂȂ�A74HC02��OR�Q�[�g�Ŕ��肵�ău�U�[��ON�ɂ��܂��B �@�u10�b�O�v�́A50�b�o�ߎ���H�ɂȂ�QE�M���𗘗p���A�����C10�ER16�̔�����H�ŒZ����(���傤�ǁu�s�s�I�v�ƂQ��鎞��)������H�M���ɂ��Ă����74HC02��OR�Q�[�g�̕Б��ɓ��͂��Ĕ��f�����Ă��܂��B �@�e�X�g��H�ł͂��̒萔�ł��傤�ǁu�s�s�I�v�Ɩ�܂������A���܂��Q���Ȃ��Ƃ���Q�`�T����x�ʼnς��������ɂ�R16�ɒ����1M���̔��Œ��R�����Ē��߂ł���悤�ɂ��Ă��̂��悢�ł��悤�B �� �u�U�[�Ԋu (5Hz) �@�u�s�s�s�s�s�c�v�ƒf�����Ė�A���[���E�u�U�[�̒f���Ԋu�����߂锭�U��H�ł��B �@�A���[�����ɕ�������悤��5Hz�ɐݒ肵�Ă��܂��B �� �u�U�[���� �@�u�U�[�́u�s�[���v�̎��g��(����)�����߂锭�U��H�ł��B �@VR2�ʼn����߂ł��܂��B �� �d����H �@���̉�H���d���T�u�p�ł��B �@�u5V�̈��艻�d���v�Ȃǂ���d���������邩�A��H�}����͏ȗ����Ă��܂����u7805���̎O�[�q���M�����[�^�����g�p����5V�d����H�v�Ȃǂ��q���ʼn������B �� �g�ݗ��Ăƒ��� �@�g�ݗ��Ă͉�H�}�ɉ����đg�ݗ��Ă邾���ł��B���ɓ�����Ƃ͖����Ƃ͎v���܂����A�Ȃɂ���IC����z�����������̂ŊԈ��Ȃ��悤�ɁA�܂��d��������O�ɂ͉��x���z���~�X�����������m�F���܂��傤�B �@�d��������ƁA����ł�����p���[�I�����Z�b�g��������̂�LED�͑S�ď������Ă��܂��B �@�m�F�p��LED��t���Ă��Ȃ��̂ŖڂŊm�F�ł��܂���e�X�^�[�Ă邱�ƂɂȂ�܂����A74HC00��3�ԃs��[Q]��0V�A6�ԃs��[_Q]��5V�Ȃ琳��ł��B �@�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`��������RS-�t���b�v�t���b�v�̏o�͔͂��]����3�ԃs��[Q]��5V�A6�ԃs��[_Q]��0V�ɕω����܂��B �@���쐧���H��RS-�t���b�v�t���b�v������ł���N���b�N���U�n�̃e�X�g�ł��B �@�d���������555�̘e��LED10�������œ_�ł��Ă���͂��ł��B �@�_�ł��Ă��Ȃ����555�̔��U��H�Ƀ~�X������܂��B �@�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`��������74HC390�̘e��LED8�E9���_�ł��͂��߂܂��B �@�_�ł��Ȃ����555����74HC390�܂��Ƀ~�X������܂��B �@LED8�͂P�b�ԂɈ��ALED9��10�b�ԂɈ��_�ł��܂��B �@���������Ȃ���VR1�߂��āuLED9��10�b�ԂɈ�����_�ł���v�悤�ɃN���b�N���g������������Ă��������B �@LED9��10�b�ԂɈ��_�ł�����ƁA���̓_�ł��Ƃ�74HC164�Ɍq�����Ă���LED1�`6�����������Ă䂭�͂��ł��B �@�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������ăN���b�N���U���͂��܂��Ă�LED1�`6���_�����Ȃ��A���Ԃɏ����Ă䂩�Ȃ��Ȃǂ̏ꍇ��74HC164��LED�h���C�o��H�t�߂Ƀ~�X������܂��B �@LED���������_�����A�������������LED5�����������Ƃ��Ɂu�s�s�b�I�v�ƃu�U�[���Q���܂��B �@��Ȃ��ꍇ��74HC164����u�U�[�W�̉�H������̂ǂ����Ƀ~�X������܂��B �@�܂�LED6������������u�U�[���u�s�s�s�s�s�c�v�ƘA���Ŗ�܂��B �@���ꂪ��Ȃ��ꍇ�����l��74HC164����u�U�[�W�̉�H�ׂĂ݂Ă��������B �@70�b�ڂŎ����I�Ƀ��Z�b�g��������A�S�Ă�LED�������A�u�U�[����~����͂��ł��B �@������~���Ȃ��ꍇ��74HC164��TD62384���o�R���Ẵ��Z�b�g�z���ׂĂ��������B �@�u�U�[�f���p�̔��U��H�����삵�Ă���悤�����m�F�ł���悤��LED11�����Ă��܂��B �@�u�U�[����Ƃ��ɂ�LED11���_�ł��܂��B �@����LED11���_�ł��Ă���̂Ƀu�U�[����Ȃ��ꍇ���u�U�[������H�̕����ׂĂ��������B �@�S�Ă����삷��Ί����ł��B �� ���쎞�Ԃ�ς��� �@�^�C�}�[IC 555�̔��U���g�������߂Ă����R�E�R���f���T�̒l��ς���u60�b�^�C�}�[�v�ȊO�̎��Ԃɂ��ݒ�ł��܂��B (�v�Z���@��555�̃f�[�^�V�[�g�ɏ����Ă���܂�) �@�A�����̏ꍇ�́u�s�s�b�I�v�ƂQ���̂́u10�b�O�v�ł͂Ȃ��u(�ύX����)�P�J�E���g�O�̎��ԁv�ł��邱�ƁA��H�E�z����ς��Ȃ���U�i�K�̃_�E���J�E���^�����ɂ͕ς�肪�������Ƃ��悭���ӂ��ĉ������Ă��������B ���Ԏ� 2009/1/30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����肪�Ƃ��������܂��B �@��]�ʂ�̓��e�ő�ς��ꂵ���v���܂��B �@�d�q��H���S�҂Ȃ��̂ŁA���Ԃ������ă`�������W���Č������Ǝv���܂��B �@�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B ���� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555���g�����u�ݒ莞�Ԃ̌��ON�v�ɂȂ�^�C�}�[ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�͂��߂ē��e���܂��B�����d�q��H����������x�̃��W�R���I���W�ł��B�u�C�̖����v�l�̃y�[�W�͔��ɂ��߂ɂȂ邵���S���邱�Ƃ���ł��B �@���̂��сA�v�b�V���X�C�b�`�������Ĉ�莞�ԁi0�`10�b���x�j�ŃA���[��������P���ȃA���[���^�C�}����낤�ƍl���ALM555���g���ΊȒP����ȂƎv�����̂ł����A�������ɂԂ��������Ă��܂��܂����B �@�����m�̂悤��LM555��OUT�[�q�̓^�C�}���쒆�̂�High�A�d���������ƃ^�C���A�E�g����Low�Ȃ̂ŁAPNPTr�{�u�U�[�Ŋm���Ƀ^�C���A�E�g���u�U�[�͂Ȃ�܂����A�d�����������u�U�[���Ȃ��Ă��܂��Ǝv���̂ł��B�g���K�[�q�Ƀv�b�V���X�C�b�`�ƕ���ɃR���f���T��t����Γd�������Ɠ����Ƀ^�C�}�����삷��悤�ɂł���Ǝv���܂����A�����܂Ńv�b�V���X�C�b�`�������Ă����莞�ԂŃA���[���A�Ƃ������ł��B555�^�C�}�ɂ�������Ă���킯�ł͂���܂���B�ǂ�ȉ�H���K���������������������肪�����ł��B��낵�����肢���܂��B kuwa �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�^�C�}�[IC 555�͂����ւ�g���₷���^�C�}�[��H�Ȃ̂ŐF�X�Ȏg���������܂����A�m���Ɂu�^�C�}�[�̎��Ԃ��I�������ON�v�Ƃ����g�����ɂ͂��̂܂܂ł͎g�p�ł��܂���B �@�ʏ��555�̃����V���b�g�^�C�}�[�ł́A�u�X�C�b�`���������������莞�Ԃ����o�͂�ON�ɂ���v��H�ł��ˁB �@���l���̂悤�ɁA�����o�͂]���āu�^�C�}�[�����삵�Ă��Ȃ�����ON�v�Ƃ�����H�����ƁA�d�������đҋ@���Ă���Ƃ��ɂ��u�U�[����Â��Ă��܂��܂��B �@�u�X�C�b�`�������ƈ�莞�Ԃ����u�U�[���~�߂�^�C�}�[�v�Ƃ����w���e�R�ȕ��ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB �@�����ł̓^�C�}�[��H�ɂ�555�ȊO�̕����g�p����̂ł͂Ȃ��A���̂܂�555�̃����V���b�g�^�C�}�[�ɁA�u���Ԃ��I��������ɏo�͂�ON�ɂ����H�v��lj����ĖړI���������܂��傤�B �@�lj�����̂̓��W�b�NIC��74HC00��������ł��B �@74HC00��NAND�Q�[�g���S������IC�ŁA�C�̖����ł͉��x���o�ꂵ�Ă��܂��ˁB �@����lj������H�́A (1) �d����ON���������ł͏o�͂�OFF (2) �u�X�^�[�g�X�C�b�`�v�������ă^�C�}�[���쒆���o��OFF (3) �^�C�}�[�����삵�I�������o��ON (4) �u���Z�b�g�X�C�b�`�v�������Əo��OFF �Ƃ�������������H�ł��B �@����̐v�̃L���́A�K�v�Ƃ��铮����u�X�^�[�g�X�C�b�`�������Ȃ��ƁA�o�͂�ON�ɂ����H�����Ȃ��v�Ƃ����u�X�^�[�g�X�C�b�`�������ꂽ�������H�v������Ă���āA����ƃ^�C�}�[�̏o�͂�g�ݍ��킹�鎖�ł�����Ƃ�₱�����^�C�}�[�@�\���������܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
�� �^�C�}�[��H (0�`��1��) �@�^�C�}�[��H��555���g�p������ʓI�ȃ����V���b�g�^�C�}�[�ł��B �@�^�C�}�[���Ԃ�VR1������P���܂łŒ��߂ł��܂��B �@�u�X�^�[�g�X�C�b�`�v�̂ق��Ɂu���Z�b�g�X�C�b�`�v���t���Ă��܂��B �@���Z�b�g�X�C�b�`�ɂ��p���[�I�����Z�b�g��H�����Ă��܂��B �@555���͓̂d��������ƃ��Z�b�g����Ă��܂����A��Ɍq���u�X�^�[�g�X�C�b�`�������ꂽ�������H�v�͍ŏ��ɋ������Z�b�g���Ă��K�v������̂Ń��Z�b�g�X�C�b�`���ɓd�������ň�Z�b�g��������d�|����lj����Ă����܂��B �@�u�X�^�[�g�X�C�b�`�v�u���Z�b�g�X�C�b�`�v��555�̃^�C�}�[���X�^�[�g�^���Z�b�g����ȊO�ɁA��́u�X�^�[�g�X�C�b�`�������ꂽ�������H�v���X�^�[�g�^���Z�b�g�����܂��B �� ��Ԕ��ʉ�H �@����̉�H�̐S�����ł��B �@74HC00��NAND�Q�[�g�`���a�Łu�q�r�t���b�v�t���b�v�v������Ă��܂��B �@�q�r�t���b�v�t���b�v���ߋ��ɉ��x���o�Ă��Ă��܂����A�u���Z�b�g�v�u�Z�b�g�v�̂Q�̏�Ԃ�ێ�����X�C�b�`(�������[)�̂悤�ȓ����������H�ł��B �@_SET���͂�_RESET���͂͒ʏ��H���x���ɂ��Ă����A�ǂ��炩��L�ɂ���Ɓu�Z�b�g���(Q=H/_Q=L)�v�u���Z�b�g���(Q=L/_Q=H)�v�̂����ꂩ�̏�Ԃɐݒ肵�A���͂�H�ɖ߂��Ă����̏�Ԃ�ێ����܂��B �@_SET���͂ɂ́u�X�^�[�g�v�X�C�b�`��ڑ����Ă��܂�����A�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������ƃt���b�v�t���b�v�̓Z�b�g����܂��B �@_RESET���͂ɂ́u���Z�b�g�v�X�C�b�`��ڑ����Ă��܂�����A�u���Z�b�g�v�X�C�b�`�������ƃt���b�v�t���b�v�̓��Z�b�g����܂��B �@_RESET���͂ɂ̓p���[�I�����Z�b�g��H���q�����Ă��܂�����A�d������ꂽ���ɂ̓t���b�v�t���b�v�̓��Z�b�g����܂��B �@�܂�A�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������Əo��Q��H�ɁA�u���Z�b�g�v�X�C�b�`�������Əo��Q��L�ɂȂ邱�ƂŁuQ�̓X�^�[�g�X�C�b�`����������o�͂�ON�ɂ��Ă��ǂ��̂��ǂ����̐���M���v�Ɏg����悤�ɂȂ�܂��B �@��́u����M����ON�̎��A�^�C�}�[���Ԑ�Ńu�U�[�o��ON�v�Ƃ�����H������Ă��悢�����ł��B �@���܂����74HC00�̎c���NAND�Q�[�g�Q�ō��Ă��܂��̂ŁA���傤��IC��ōς݂܂��B �@555�̏o�͂�NAND�Q�[�g�b�ŐM�����]���Ă����܂��B�^�C�}�[���쒆��L�A�ҋ@���E�^�C�}�[�I������H�ɂȂ�܂��B �@NAND�Q�[�g�c�́u�^�C�}�[�o�͂]��������H�A���A�X�^�[�g�X�C�b�`�������ꂽ�������H�̏o�͂�H�v�̏ꍇ�̂݁u�o�͂�H��(NOT������)���]��L�v�ɂ�������������Ƃ��ē����Ă��܂��B �@����������́u�������X�^�[�g�X�C�b�`��������Ă��Ȃ��ꍇ(Q=L)�A��ɏo�͂�ON(_Y=L)�ɂ����܂���I�v �@�]���ēd������ꂽ�����ł̓u�U�[�o�͂͐��ON�ɂ͂Ȃ�܂���B �@�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`��������Q=H�ɂȂ�܂�����u�o�͂�ON�ɂ��鎖������(ENABLE)���܂��v�B �@����ƃu�U�[�o�͂�ON�ɂȂ��Ă��܂������ł����A�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`���������u�Ԃ�555�^�C�}�[��������J�n����_OUT��L�ɂȂ�܂�����ANAND�Q�[�g�c��_OUT���̏������������Ȃ�(H�ł͖���)�̂ŏo�͂ɕς��͂���܂���B �@�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������Ɖ�H�}���ł̓t���b�v�t���b�v�̓���m�F�p�ɂ��Ă���LED2���_�����܂��B �@������LED1�̃^�C�}�[���쒆LED���_�����܂��B �@�ݒ莞�Ԃ��o�߂���555�̏o�͂�L�ɖ߂��LED1�͏������܂��B �@�����ɁA_OUT��H�ɂȂ�܂��̂ŁANAND�Q�[�g�c�͗����̓��͂�H�ɂȂ�A�͂��߂ďo��_Y��L�ɂȂ�܂��B���ꂪ�u�U�[��炷�M���ł��B �@�^�C�}�[���삪�I��������Ԃ���́A���̂܂܂ł͉�H�͉����ω����܂���̂Ńu�U�[�͖���ςȂ��ɂȂ�܂��B �@���̏�ԂŁu���Z�b�g�v�X�C�b�`�������ƁA�t���b�v�t���b�v�����Z�b�g����܂��̂�NAND�Q�[�g�c�͏����������Ȃ��Ȃ�A�o��_Y��H�ɂȂ�܂��̂Ńu�U�[�͒�~���܂��B �@�u���Z�b�g�v�X�C�b�`�́A555�̃��Z�b�g�[�q�ɂ��q���Ă��܂��̂ŁA�u�U�[����O�Ƀ^�C�}�[���~�߂邱�Ƃɂ��g�p�ł��܂��B�^�C�}�[���X�^�[�g�����Ď��Ԃ�����O�Ɂu���Z�b�g�v�X�C�b�`�������^�C�}�[�͉�������܂��B �@�܂��A�u�U�[�����Ă����ԂŁu�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������ƍēx�^�C�}�[��������͂��߁A�^�C�}�[���쒆���Ԃ̓u�U�[����~���܂��B���Ԃ��o�Ƃ܂��u�U�[����n�߂܂��B �@�^�C�}�[���Ԓ��Ɂu�X�^�[�g�v�X�C�b�`�����x�����Ă��A�ĉ����͂��܂���̂ōŏ��Ɉ�x�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`�������Ă���ݒ莞�Ԍo�ƃ^�C�}�[�͐�܂��B �@���̂�����͎���H��LED1�`3�̌���������Ȃ��炢�낢��ƃX�C�b�`�������Ċm���߂Ă݂Ă��������B���͂Ő��������肸���Ƃ킩��₷���ł��傤�B �� �u�U�[�h���C�o��H �@NAND�Q�[�g�c�̏o�͂�L�Ńu�U�[ON�Ƃ��Ă��܂��̂ŁAPNP�g�����W�X�^�Ńu�U�[�̓d������ꂽ������肷���H�ł��B �@����m�F�p��LED3�����Ă��܂��B �� �g�ݗ��ĂƓ���m�F �@���i���͏��Ȃ��̂őg�ݗ��Ă͂���قǓ���͖����Ǝv���܂��B �@�eIC�̃s���ԍ������Ԉ��Ȃ���E�E�E�E �@����`�F�b�N�͂܂���555�̃^�C�}�[��H����s���܂��B �@�d������ꂽ�����ł�LED1�͏��������܂܂ł��B �@�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`��������LED1���_�����A��莞�Ԍ�ɏ������܂��B �@���Ԃ�VR1�łO�b(��u)�����P�����x�̊ԂŒ��߂ł��܂��B �@LED1�̓_�����Ɂu���Z�b�g�v�X�C�b�`��������LED1�͏������܂��B �@�����܂ł�����łȂ��ꍇ��555�ƃX�C�b�`�܂��̔z�����m�F���Ă��������B �@���͏�Ԕ��f��H�̃`�F�b�N�ł��B �@�d������ꂽ�����ł�LED2�͏��������܂܂ł��B �@�u�X�^�[�g�v�X�C�b�`��������LED2���_�����A���̂܂܂ł͓_�������܂܂ł��B �@�u���Z�b�g�v�X�C�b�`��������LED2�͏������܂��B �@�����܂ł�����łȂ��ꍇ��NAND�Q�[�g�`�E�a�ƃX�C�b�`�܂��̔z�����m�F���Ă��������B �@LED2���������_���^��������A�^�C�}�[�̓��삪�I��(LED1������)�������_�Ńu�U�[�o�͂�ON�ɂȂ�ALED3���_���E�u�U�[����͂��ł��B �@�����܂ł�����łȂ��ꍇ��NAND�Q�[�g�b�E�c�ƃg�����W�X�^�܂��̔z�����m�F���Ă��������B �@�S�Ẵ`�F�b�N���I���Ί����ł��B �@����̉�H�}�̂��̂ł́A�^�C�}�[���Ԃ��߂���ƌ�̓u�U�[������ςȂ��ł����A�u�Ԃ̃h�A���b�N�E�A�����b�N�̐M�����1�b�قǒx�点�����v�Ŏ�����74HC221���g�p�����x���^�C�}�[��H���g�p����A�u�X�C�b�`�������Ďw�莞�Ԍ�Ƀu�U�[����͂��߁A��莞�Ԗ����玩���I�Ɏ~�܂�v�Ƃ�����H���ȒP�ɍ��܂��B �@���̎����I�Ɏ~�܂�ق��̉�H�ɊO���Ɂu�E�Ԃ̓d���v��ڑ�����J�[���[�X�̃X�^�[�g�V�O�i���̂悤�ȕ������A�u�X�C�b�`����������ԃV�O�i������莞�ԓ_���A���̌�ɐV�O�i���ɕς���Đ��b�ԃu�U�[����B�V�O�i���ƃu�U�[�͐��b��Ɏ�����~����B�v�Ƃ������ȁA���W�R���₻�̑��̃��[�X�̃X�^�[�g���y�����Ȃ�悤�ȑ��u�����܂��B (���܂��E�E�E�ƌ������ߋ��ɐ�����܂���) �@����̖ړI�́u�A���[����炵�����v�Ƃ������ł��̂ŁA�u�U�[�͖���ςȂ��ŗǂ�(�ꉞ���Z�b�g�X�C�b�`�͕t���܂������c)�Ƃ͎v���̂ł����A�p�r�ɂ���Ă̓u�U�[�͎����Ŏ~�܂����ق����ǂ��ꍇ���������ł���ˁB ���Ԏ� 2009/1/23
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�����̂����肪�Ƃ��������܂��B �@�Ȃ�قǂł��B���b�`�Ƃ����W�b�N��H���ȂƑz�����Ă��܂������A�������̓I�ȉ�H�ɂ��Ă�����ĂȂ�قǂł��ˁB �@�����쐬���Ă݂܂��B���肪�Ƃ��������܂����B kuwa �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�Ǘ��l���܁A��ς����b�ɂȂ��Ă���܂��B �@�܂��A�A�h�o�C�X���������������݂����Ē����܂��B �@��������ł��BPIC�Ɖt���\���iLCD�j���g���ĉ��x�v����肽���Ǝv���Ă܂��B �@�\����ʂɂ͂P�s�ڂɐ����A�Q�s�ڂɃo�[�O���t�\�������������ł��B �@�����̍쐬�Ɋւ�������o����{�A�Q�l���A���䑶�m�̕������ĉ������܂��B �@�X�������肢�v���܂��B ikikko �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@PIC�{�t���{���x�Z���T�[IC�Ő��삷��Ȃ�E�E�E �@�v���O�������b����ŏ����Ȃ�u���̂����ł���b���o�h�b���p��H�v�B �@�A�Z���u���ŏ����Ȃ�u�₳����PIC�}�C�R�� �v���O���~���O���d�q�H���v�Ƃ����{������悤�ł��B �@���Ƀ|�s�����[�Ȑ�����e�Ȃ̂ŁA���ɂ�����������Ђ͂���Ǝv���܂��B �@�S��������e�������āIgoo�ɁuPIC�Ɖt���iLCD�j�\���@���g���ĉ��x�v���� (����ҁFmihiro3)�v�Ƃ������Ⓤ�e������Ă���悤�ł��̂ŁA�����̂悤�Ȍl�T�C�g�ł͂Ȃ��A�吨�̕������Ă��邠����̃T�C�g�ł����ƗL�p�ȏ�W�܂�Ƃ����ł��ˁB ���Ԏ� 2009/1/22
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 1/22 |
�@�����̂��Ԏ��^�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �@�����Ă����������{�ŕ����悤�Ǝv���܂��B �@���肪�Ƃ��������܂����B ikikko �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �H���d�q��K-02190�L�b�g��������H�ɉ��������H�}�H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�H���d�q�́uK-02190 �S�`�Q�T�u�i�ő�T�`�j�σX�C�b�`���O��d���d���L�b�g�v���̓d���L�b�g���g���ā@����12V�o��24V�@DC-DC�A�b�v�R���o�[�^�ɉ����������̂ł����ǁ@�o����@��H�}�@��낵�����肢���܂� �吼 �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�c�O�ł����ł��܂����B �@���̃L�b�g�Ŏg�p����Ă���KIC-125�́u�X�C�b�`���O�E�_�E���R���o�[�^�E���W���[���v�ł��B �@�d����Ⴍ���邱�Ƃ͂ł��Ă��A�������č������邱�Ƃ͂ł��܂���B ���Ԏ� 2009/1/20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e 12/21 |
�@���肪�Ƃ��������܂�
�吼 �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �t���d��̂k�d�c�\�����ւ̃q���g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�O�ɓ��e������������܂��B �@�Γ���ŋ����㎋�̕��e�̂��߂ɁA�d��̕\�����t������V�Z�O�̑傫�Ȕ����_�C�I�[�h�\���ɕϊ��ł��Ȃ����̂��Ǝv���Ă��܂��B �@�L�[���͂̕����́AA�S�T�C�Y�̂�������̓d����������̂łȂ�Ƃ����܂��B�ʓd���̊O�t���̕��@�ł����܂��܂���B �@�Ȃɂ��q���g�ł��ǂ��̂ł��������������B �@�t������EL�V�[�g�����Ă݂܂������P�x�E�R���g���X�g������Ȃ��悤�ł��B �@��낵�����肢�������܂��B nakryou �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��̓I�ɂǂ̓d��ŁE�E�E�Ƃ����悤�Ȏw�������(�^�Ԃ��Ă����͎����Ă��Ȃ��ł��傤���ǁc)����܂���̂ŁA�u��ʓI�ȉt���d��v�łƂ������ł������q���g�������Ă݂܂��B �@�d��ȂǂŎg�p����Ă���t���\����̌�������B �@�t���\���p�l���ɂ͂������̍\���E����������܂����A�d��Ŏg�p����Ă���t���p�l���́uTN�^�C�v�v�ƌĂ��ł��\�����P���ȉt���f�B�X�v���C�ł��B 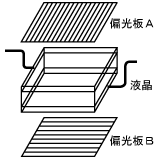 �@�t���p�l���͈ꌩ����Ɠ����ȃK���X�ł����A���ۂ͕����̑w���d�˂č���Ă��܂��B
�@�t���p�l���͈ꌩ����Ɠ����ȃK���X�ł����A���ۂ͕����̑w���d�˂č���Ă��܂��B�@�^���t������������A���̏㉺�������d�����v�����g���ꂽ�K���X�ŋ���ł��܂��B �@�����d���ɓd����������ƁA���̊Ԃɂ����t�������ɓd��������邵���݂ł��B(���ۂɂ͓d���l�͂قڂO�ł�) �@���̂Q���̃K���X�̕\�Ɨ��ɂ��Ό����Ƃ�������ȃt�B�������\���Ă��܂��B �@�Ό����́u������̕����̐U���̌������ʂ��v�Ƃ����s�v�c�ȃt�B���^�[�ł��B 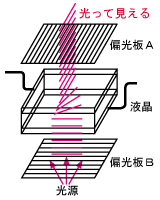 �@�t���ɓd���������Ȃ��Ƃ��A�t���̒���ʉ߂�����́u�Ό��������X�O�x��]���܂��v�B
�@�t���ɓd���������Ȃ��Ƃ��A�t���̒���ʉ߂�����́u�Ό��������X�O�x��]���܂��v�B�@�]���āA���ɒu�����������甭����ꂽ360�x�܂�ׂ�Ȃ��U�������镁�ʂ̌����A�Ό��`�ň��̕����̂�(���̐}�ł͐���)�̐U�����������������ʂ��Ă��A���̌����t����ʉ߂���ۂɂ́u90�x�悶����v�}�ł͐��������ɕΌ��������ɂȂ�܂��B�������Ό��`�͐��������̐U���̌��̂ݒʂ��悤�ɓ\���Ă��܂�����A�t����ʂ��Đ��������U���ɂȂ������͕Ό�����ʂ邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA�l�Ԃ̖ڂŌ���Ɓu�����Ă���(����)�v�悤�Ɍ����܂��B �@�o�b�N���C�g�̖����t���d��ł́A�\��������������\�����ƒʂ�Ƃ��A�����ăp�l���̗��ɓ\���Ă��锽�˔��璵�˕Ԃ��������\�ƒʂ�Ƃ��̓�����ۂ�ʂ��āA�p�l�������������܂��B 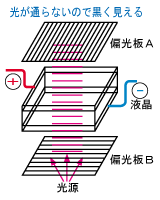 �@�t�������ɓd����������ƁA�u�Ό���������]���Ȃ��Ȃ�܂��v�B���͑f�ʂ肷��̂ł��B
�@�t�������ɓd����������ƁA�u�Ό���������]���Ȃ��Ȃ�܂��v�B���͑f�ʂ肷��̂ł��B�@90�x��]���Ȃ��Ȃ�ƁA�Ό��a�Ő��������ɕΌ����ꂽ����90�x���炵���p�x���Ό��`���ʂ�Ȃ��Ȃ�܂��B �@�����ʂ�܂���A�l�Ԃ������ꍇ�́u�����v�\���ƂȂ�܂��B �@�d��̉t���p�l���ł͂͂�����Ɓu�����̌`�v��\�����邾���Ȃ̂ŁA�t���R���g���[�����f�W�^���Łu���v�u���v�Ƃ͂������ւ��܂����A�m�[�g�p�\�R�����̉t���p�l��(STN�t��)�ł́u�F�̔Z���v��\���ׂɉt���ɂ�����d�����R���g���[�����铙�̃A�i���O�I�ȗv�f���܂܂��悤�ɂȂ�܂��B �@�t���p�l�����u���v�u���v��\�����錴���͂��̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA���Ƃ��Ήt���̕����̈ꕔ���Ɂu�d�����������Ă����ON�v�u�d�����������OFF�v�Ɣ���ł���ΊȒP�ɑ��̕\�����u�ɐڑ��ł������ł��ˁB �@�Ƃ��낪�ǂ������I�����͖≮�������܂���B �@��̐}�̂悤�ɉt�������Ƀv���X�ƃ}�C�i�X�̓d���������Ă����ƁA�t�����������Ă��܂��܂��I �@�t�������͔��ɕq���ȉ��w�����Ȃ̂ŁA�d�C�𗬂����ςȂ��ɂ���Ƃ����ɕ��Ă��܂��̂ł��B �@�ł͂Ȃ��t���p�l���͉t�����������ɂ����ƕ\���ł��Ă���̂ł��傤���H �@���̔閧�́u���v�Ńh���C�u���Ă��邩��Ȃ̂ł��B �@������\�����镔���ɂ́A�u�\�����v���X�A�������}�C�i�X�v�Ƃ�����ԂƁu�\�����}�C�i�X�A�������v���X�v�Ƃ�����Ԃ�Z���ԂɌ��݂ɐ�ւ��āA��ɕЕ����̓d�����肩����̂ł͖�����Ԃɂ��Ă��Ήt�������͉��邱�Ƃ��Ȃ��A�����Ɠ����Â���̂ł��B �@�u���v�Ƃ����Ă��𗬂̓d�����g�p���Č𗬓d����������̂ł͂Ȃ��A�ʏ�̒����P�d������u�[���I�Ɍ𗬂̂悤�ɂ݂��������@�v�ʼnt���Ɍ��݂ɓd���������܂��B �@�t���p�l���̕\�E���ɂ͂��ꂼ��f�W�^����H�̏o�͂��q�����Ă��āA�o�͂��g�̏ꍇ�̓v���X�̓d���A�o�͂��k�̎��ɂ͂O�u�ɂȂ�悤�ɂ��ꂼ�ꐧ�䂵�Ă��A�u���\���̎��ɂ͕\�Ɨ��͈Ⴄ(����)�M���v�u���\���̎��ɂ͕\�E�����ɓ����M���v�Ƃ��Ă��܂��B �@�����Ă��̕\����H�������Ŕ��U���Ă��锭�M���łg�^�k���ւ��Ă�邱�ƂŁA�\�����镔���͌𗬂œd����������A�\�����Ȃ������́u�\�E�����ɓ����d����������̂Ŏ����t���ɂ͓d���͗���Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���̂悤�Ȍ��݂ɕς���Ă���M������u���v���u���v���肷��ɂ͕��G�ȍl�������K�v�ł����A������r�I�ȒP�Ɏ����ł������W�b�NIC������܂��B �@�u�d�w�|�n�q�v�Ƃ������W�b�N��H��������74HC86�Ƃ���IC������ł��B 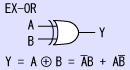 �@�����r���I�@�\�œ���EX-OR�Q�[�g������̉t���̓��쌟�o�Ɏg�p����ۂ́u�Q�̓��͂̓��e���Ⴄ�ꍇ��H�A�����ꍇ��L�v�Ɠǂݑւ��邱�ƂŁA�\�E�������݂ɈႤ�d�����x���́u���v�̎��͏o��H�A�������x���́u���v�̎��ɂ͏o��L�Ƃ����f�W�^���o�͂������܂��̂ŁA��͂��̏o�͂ɁuH�̎����V�Z�O�k�d�c��_���������H�v���q���悢�킯�ł��B �@�����͊ȒP�Ȃ̂ł����E�E�E�E �@���ۂɂ�74HC86�ډt���p�l���Ɍq���ʼnt���\����Ԃ����o���邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�t���܂�肪C-MOS IC�Łu�T�u�n�v�ł���A�t���h���C�u��5V�̓d�����g�p���Ă���̂ł���Β���74HC86���q���ł��\���܂��A�u�t���d��v�͂����Ă��͓d����1.5V�̃{�^���d�r���P�`�Q�{��1.5�`3V�ł���ˁB �@1.5V�Ȃǂł͓d�������肸��5V�n(2�`6V)��74HC�V���[�Y�̃��W�b�NIC�͐��������͂f�ł��܂���B3V�d���̓d��ł��A�t���ɂ������Ă���d����3V�߂��܂ł�������̂ł����A�����Ⴂ�ꍇ�͔���͓���Ȃ�܂��B ���N���b�N����Ɗg��\��
 �@���Ƃ��ΉE�̐}�͓d��p�ł͂���܂��A���^�t���f�B�X�v���C�R���g���[���[�ł͍ł��|�s�����[��HD44780�̉t���h���C�u�[�q�̐M���t���[���}�ł��B
�@���Ƃ��ΉE�̐}�͓d��p�ł͂���܂��A���^�t���f�B�X�v���C�R���g���[���[�ł͍ł��|�s�����[��HD44780�̉t���h���C�u�[�q�̐M���t���[���}�ł��B�@���̏ꍇ�͓d���d�����T���������t���h���C�u�d����p�ӂ��Ă��āA�����}�̂悤�Ɏ������Ŋe�M�����ɗ^���ĉt���𑀍삵�Ă��܂��B �@�A���}��Vcc�ƂȂ��Ă���d�����A���ۂɂ͓d���d���Œ��R�ŕ������ēd�������������̂��g���Ă���̂���ʓI�ł�����A���������ꍇ�͒P���ɓd���d����1/2���x�����ɏォ�����Ŕ��f����̂�����ł��傤�B �@���̂悤��5V�n�ł����W�b�N�n�̔���d���ł͔���ł��Ȃ����̂�A1.5V�n�̂��̂ł������Ɠ����悤�ɂ���ɂ́A�e�M�����̓d����Ⴂ�d�����烍�W�b�N�d���܂ŕϊ�����ׂɃg�����W�X�^��FET���g�p�������x���ϊ���H������Ă��K�v������A����͎g�p����d��̉�H�ɂ���Đv���������Ă��܂��B�ł����炱���ł��̂��̃Y�o���̉�H�}����邱�Ƃ͂ł��܂���B�c�O�ł����������Ō������Ă��������B �@�܂��A�t���p�l�����V�Z�O�\���ł����A�\���������̊e�Z�O�����g���q�������u�R�����v�[�q���Q�ȏ�ɕ�����Ă�����A�}�g���b�N�X�ڑ��Ń_�C�i�~�b�N�h���C�u����Ă����肷��ꍇ�ɂ͌𗬂��������Ă�����ԈȊO�Ɂu���d�����(�I������Ă��Ȃ�����)�v�����݂��܂��̂ŁA�����������o���ă_�C�i�~�b�N�h���C�u�ɑΉ��������H�Ȃǂ����ւG�ȉ�H��g�ݍ��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�ꍇ������܂��B �@��������g���ɂȂ���d��ɂ���Ă��ꂼ��Ⴂ�܂��̂ŁA���̓d��@�\LSI�Ɖt���p�l�����ǂ̂悤�Ɍq�����Ă��āA�t���p�l�����ł̊e�Z�O�����g�̔z�����ǂ̂悤�ȕi�Ȃ̂������ׂđ���l���Ă��������B �@�W���d��Ȃ�P���ɂ��V�Z�O�����g�{dp(�����_)�łW�Z�O�����g�Ԃ�̉�H�A�W���ō��v�U�S�Z�O�����g�Ԃ��EX-OR��d�������H�Q���K�v�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ȃ��|����ȍH��ɂȂ�܂��B ���@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@��
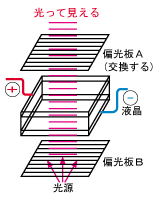 �@�S��������l�����̓d������p���l���܂����B
�@�S��������l�����̓d������p���l���܂����B�@�t���\���̌����͏�Ő��������ʂ�ł����A�Ό����̈ʑ����u�\�����������ɂ����v���ƂŁu���ƍ��ɓ���ւ����v���Ƃ��ł��܂��B �@�u��ʂ��܂����ŁA�V�Z�O�̕��������F�v�̓d�삪�ł��܂��B �@���̂܂܂ł̓o�b�N���C�g�̖������ˌ^�t���ł͕��������Â����Č��Â炢�ł����A�������ė�����LED�����Ȃǂ̖��邢������u���ƌ��\�܂Ԃ������炢�̂V�Z�O�\���d��ɂȂ�܂��B �@�`�S�T�C�Y���炢�̋���d��Ȃ�t���\���������Ȃ�傫�����i������A�������u���o�b�N�t���A���邢LED�o�b�N���C�g�t���v�ɉ������Ă��Ύ��F�������������オ��Ǝv���܂��B �@���X�d��ɂ��Ă���Ό��̕Б������āA90�x��]�����Ă݂Ă��������B�P���Ԃ炢�����d�˂��܂��A�Ό����Ɖt���K���X���d�Ȃ��Ă��镔�����܂����ɂȂ�͂��ł��B �@�������̕��@�Ńe�X�g�ł���Η�����LED��EL�o�b�N���C�g��u���Ă݂āA�ǂ̒��x���邭������̂��������Ă݂Ă��������B �@����ŏ[���Ȏ��F���ɂł���Ƃ킩��A�l�b�g�ʔ̂ȂǂŕΌ��t�B�������Ă��邨�X�ŕK�v�ȃT�C�Y�̕Ό��t�B�������w�����ēd��t���ɓ\��n�j�ł��B �@�ʔ̂̕Ό��t�B�����͐���~�`�����~(�Z�b�g�������ɂ��)�����܂�����A������䓯���d������Ό������������Ďg���ق������オ�肩������܂���B �@�����̓d��ɂ��ꂼ�ꂩ�甍�������Ό��ł��ڐA����ƁA���o�b�N�̏a���t���d�삪�Q��ł�������܂��i�O�O�G �@�����d�삩��Ό������ė��p�ł���̂́A�����܂Œ����^�C�v�̉t���p�l�����g�p���Ă��āA��Ő��������ʂ�\�Ɨ��̕Ό������ꂼ��90�x�Ⴄ�i�ł���ꍇ�ł��B�e�X�g���鎞�ɂ悭���m���߂��������B �@���́A�t���p�l���̒��ɂ͏�Ő��������悤�ȁu�����v�u�����v�̕Ό��ł͂Ȃ��u��45�x�v�̕Ό��p�̃V�[�g��\���������������g�p���Ă���^�C�v���������Ƃ�����܂��B �@�����V�[�g�ł����A�\�Ɨ��ŕБ��𗠕Ԃ��ē\��(���̐��i�̓P�[�X�ɋ���ł��邾���ł���)������90�x�����ɂȂ�܂��̂ŁA�킴�킴�������Ɂu�\�p�v�Ɓu���p�v�ɃJ�b�g�T�C�Y��ς���K�v�������A�����t�B�������ʐ��Y���邾���Ȃ̂Ő���������������Ƃ������@�ł��B �@�������̂悤�ȁu��45�x�v�̕Ό��t�B�������g�p�����t���p�l���ł���A�P���ɕЖʂ��u���Ԃ������v�Ŕ������]�ł��Ă��܂��܂��B �@30�N���O�̃f�W�^�����v�Ō��܂������A�����d��ł����̂悤�ȁu�����팸�̃A�C�f�A�v���g���Ă����炢���ł��ˁB �@���̕��@�ł͂�͂�t���p�l���̐��\���王�F�������イ�Ԃ�ł͖����Ɣ��f����܂�����A��͂肩�Ȃ��|����ȉ�H������ĂV�Z�OLED�����点�邵�������ł��ˁE�E�E�B ���Ԏ� 2009/1/14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@����ɂ��́A�͂��߂܂��āB �@�����y�����A��������Ȃ���q�������Ă��������Ă���܂��B �@���̂��т͂P�O�O�~���i�u�{�����[���A���v�E�{�����[�������ՁI�I�v�ɂ��Ă��������������e�������܂��B �@�������Ɨp�ԓ��ŒʋΎ��AFM�g�����X�~�b�^�o�R�ɂ�MP3�v���C���[�̉��y���Ă���܂����AMP3�v���C���[�̃{�����[�����ő�ɂ��Ă��A�ǂ����Ă����W�I����o�鉹���������̂ŁA�J�[���W�I�̃{�����[����傫�����܂����A�j���[�X�����ƕs�p�ӂɑI�ǂ�ς���ƁA�J�[���W�I�̃{�����[�������̂܂܂Ȃ̂ő傫�ȉ��łт����肷��H�ڂɂȂ��Ă��܂����B �@�����ʼnߋ��̋L�����v���o���A�uMP3�v���C���[�v���u�{�����[���A���v�v���uFM�g�����X�~�b�^�v���u�J�[���W�I�v�̔z��ɂ��A���u�{�����[���A�b�v�v�̓d���i�d�r�{�b�N�X�̂Ƃ���j�ɂP�QV�V�K�[���C�^�[����̓d�������o�����n���_�t�����e�X�g���Ă݂��Ƃ���A�X�C�b�`�I�����炵�炭�����u�{�����[���A���v�v���烂�N���N�����オ���Ă��܂��܂����O�O�G �@�f�[�^�V�[�g�ɂ͋����d��max.�P�TV�Ƃ���܂����A�P�O�O�~���i�Ȃ̂łǂ����V���[�g���������m�F���Ă��玎���܂������A�Q��ڂ��������ʂƂȂ�܂����B�@�d�r���v�炸�̂����A�C�f�A���Ǝv�����̂ł����B�B�B �@�s�i�C�̂������H�ŋA����������ł���̂ŁA�����f�l�d�C�H��܂����̂��ƂɃ`�������W���Ă݂܂������A�܂��͑厸�s�ɏI���܂����O�O �@�����Ԃ��������܂����炱���܂ł̘b�ʼn������C�Â��̓_�A�A�h�o�C�X������K���ł��B �@�P�O�O�~�V���b�v�Ŏv�Ă��Ȃ���f�ނF������A�C�̖��������HP�����Ȃ����H�}�����ǂ�����A�n���_�t����������A�ƂĂ��y�����̂ŁA�����ƋC�����Ȃ���Ō��́u�{�����[���A���v�v�͉������̎��̃`�������W���l���悤�Ǝv���Ă��܂��B�@�h��B ���낢�� �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@���E�E�E�E�ł����B����͂����ւ�ł��ˁB �@�l�����錴���͂Q����܂��B �@�P�́u�{�����[���A���v��12V�p�̐v�ł͖����v�Ƃ������ł��ˁB �@�m�����{�����[���A���v�̏Љ�y�[�W�ɍڂ��Ă��܂��悤�ɁA���Ŏg���Ă���A���vIC TDA2822M�̓d���d����1.8�`15V�ƍL�͈͂ł����A�c�O�Ȃ���{�����[���A�b�v��15V���g�p�ł���悤�ɂ͏o���Ă��܂���B �@���̊�������ɂȂ�A�d�������p��220��F�̓d���R���f���T��10V�i�ł�����A�d�C�̐��E�ł͂��̔����`80�����x�̓d���Ŏg���̂����ʂŁA��������ɎԂ̓d����������12�`15V����������ߓd���Ŕj�Ă��܂��܂��B �@�d���R���f���T���j��ƁA�����L���ɂ����̃K�X(��)���������܂��B �@�����P�́u������ڑ���TDA2822M���Ă��Ă��܂������v�B �@������{�����[���A���v�̉�H�}�����Ȃ���l���Ă��������B �@TDA2822M�̓A���v��H���Q������IC�ŁA�Q���E�E���`�����l���p�ɕʁX�Ɏg���ăX�e���I�A���v����ꂽ��A�{�����[���A�b�v�̂悤�ɂQ���t�ʑ��ɂȂ�悤�ɔz�����ĂQ�łP�̃A���v�Ƃ��ē��삳���A�o�͂��S�{�ɂł����u���b�W�ڑ��Ƃ����A���v��H�����܂��B�����Ŏg���Ă����H�̓I�[�f�B�I�̐��E�ł�BTL�ڑ�(Bridged Transformer Less �ڑ�)�Ƃ������@�ł��B �@BTL�ڑ��͏����̊��d�r�̂悤�ȒP�d���ł��ʏ�̃A���v�̂Q�{�̓d���E�d�����X�s�[�J�[�ɂ����āA�S�{�̉��ʂ���Ƃ��������ւ�������ǂ��A���v�Ȃ̂ł����P��������������A����́u�o�͂ɂ̓X�s�[�J�[�����q���ł͂����Ȃ��v�Ƃ������ł��B �@���X�X�s�[�J�[(�{�����[���A�b�v�̏ꍇ�̓C���z��)��炷�ׂ̃A���v�Ȃ̂ł��̒ʂ�̎g���������Ă���Ȃ�ǂ��̂ł����A�����o�͂��uGND�����ʂ̕ʂ̉�H�v�ƌq�����A���v��H���V���[�g���ďĂ��Ă��܂��܂��B �@�{�����[���A���v�̉�H�}������ƁA�C���z���[�q�ɂ͏㑤�̃A���v(������Ȍ��A���v�`�ƌĂт܂�)�Ɖ����̃A���v(�Ȍ��A���v�a)�̊e�o�͂��q�����Ă��܂��B �@���̐ڑ�������ƁA�C���z���[�q�ɂ͉�H��GND(�A�[�X)�͐ڑ�����Ă��܂����ˁH �@���ʂ͉����̓��͒[�q��o�͒[�q�̕Б��͉�H��GND(�A�[�X)�ɐڑ�����Ă��āAGND�d����0V�̊�Ƃ��Ă�������̓d���ŐM����\���̂ł����ABTL�̏ꍇ��GND�Ƃ̊Ԃɓd���𗬂��̂ł͂Ȃ��A�e�A���v�̏o�͂����݂����t�ʑ��ɂ��鎖�ŁA�Q�̃A���v�̏o�͂ʼn^������Ȉ����̂悤�ɃX�s�[�J�[���쓮���܂��B �@�܂�A�����M���ɂ��킹��
�u�A���v�`������(�d��������)�����A���v�a����������(�d�����Ⴂ)�v
�悤�ɏo�͓d�������āA�X�s�[�J�[��傫���h���Ԃ鎖�ő傫�ȉ����o����̂ł��B�u�A���v�`����������(�d�����Ⴂ)�����A���v�a������(�d��������)�v �@���̂悤��BTL�ڑ��̃A���v�͏���A���v�`�E�A���v�a�͉��炩�̓d�����o�͂��Ă��܂��B���Ƃ����ʂ��O�ł��X�s�[�J�[�[�q�̃v���X���E�}�C�i�X���ɂ͓d���d���̖��̓d�����o�͂���Ă��܂��B �@�������A����BTL�o�͂̃X�s�[�J�[�[�q���Ԉ���đ��̃A���v��I�[�f�B�I���u�Ɍq�������ɂ͂ǂ��Ȃ�ł��傤�H �@���Ԃ͂Q��ލl�����܂��B �@�������u�q����̃I�[�f�B�I���u�ƃ{�����[���A���v���d�����������Ă����ꍇ�B�v �@�{�����[���A���v����͂Ɍq�����Ă��鑕�u�̓d���ƁA�{�����[���A���v�̏o��(�C���z���[�q)�Ɍq�����u�̓d�����S���ʁX�Łu�ǂ����q�����Ă��Ȃ��v�ꍇ�ɂ͖��͂���܂���B �@�o�͐�̃I�[�f�B�I�@��̓��͒[�q�ɂ́ABTL�o�͂����A���v�`�E�A���v�a�̏o�͓d���������͓d���Ƃ��ē`�����邾���ŁA�̏���Ȃɂ����܂���B �@�������u�q����̃I�[�f�B�I���u�ƃ{�����[���A���v���d�����ڑ�����Ă����ꍇ�B�v �@���Ƃ��A�{�����[���A���v�̓d�������d�r�ł͖��������̑��u�̓d�����番���Ă��炢�A���̑��u�ɉ����o�͂����悤�Ƃ����ꍇ�B �@���낢�ʗl�̗p�r�ł���g�����X�~�b�^�[�����d�r�d���ł͂Ȃ��A�Ԃ̃V�K�[�\�P�b�g�Ɏh���ĎԂ���d����Ⴄ�^�C�v�ŁA���̃g�����X�~�b�^�[�Ɠ����悤�Ƀ{�����[���A�b�v���Ԃ̃V�K�[�\�P�b�g����̓d���Ɍq���ł��܂������ȂǁB �@���̏ꍇ�A�ڑ���̃I�[�f�B�I�@��̓��͒[�q�̕Б��͓d����GND(�A�[�X)�ɐڑ�����Ă��܂�����A�{�����[���A���v�̒��̃A���v��H�̂����Б�(�A���v�`)�̏o�͂́u��葤�̋@��̒���GND�ƃV���[�g����I�v���ƂɂȂ�A�A���vIC���Ă��܂��B �@��{�I�ɁwBTL�ڑ��̃A���v�̏o�͂́A�X�s�[�J�[�ȊO�ɂ͌q���ł͂����Ȃ��x�Ƃ����֎~���������Ȃ���Ȃ�܂���B �@�{�����[���A���v�̓C���t�H����炷�Ƃ����p�r�ȊO�ɂ͎g�p���鎖�͍l�����Ă��܂���A����̂悤�ȉ����M���̓`�B�o�H�̓r���ɋ��ށu�{�����[�����ߗp�̃v���A���v�v�Ƃ��Ďg�p����ɂ͕s�K�ł��B �@�����g�����X�~�b�^�[�̓d�����Ԃ���̏ꍇ�́AGND�����ʂɂȂ��Ă��܂���ԂŎg�p����̂ł���A �@�@�ump3�v���[���[�͓d�r�쓮�Ŏg���v(�{�����[���A���v��GND���q�����) �@�@�u�{�����[���A���v���d�r�쓮�Ŏg���v �Ƃ������ɁA�d�����o�͐�̃g�����X�~�b�^�[�ƕ���������Ԃł���Ζ��͖����ł��傤�B����ɒ�i�ʂ�̓d�r�쓮�ł���Ήߓd���œd���R���f���T���������Ă��܂��S�z������܂���B �@�g�����X�~�b�^�[�͓d�r�쓮�ŁA��肪�uBTL�ڑ��ɂ��IC�j���v�łȂ��ĒP�ɓd�����ߓd���œd���R���f���T���p���N���Ă���̂ł���A25V�i�ȂǂɌ�������Γ���͂���Ǝv���܂��B(�����Ă܂���) �@��肪�uBTL�ڑ��ɂ��IC�j���v�ł����Ă��A������Ɖ�H�����������BTL�V���[�g�͉���ł���̂ł����A��������̌������ǂ��ɂ���̂����ʂł��܂���̂ŁA����͂����ł͏����Ȃ����ɂ��܂��ˁB�������͂����Ȃ蒷���Ȃ��Ă��܂��܂������B �@�d���̃R���f���T�����̖��Ȃ�A�R���f���T���������ōς݂܂����ˁB ���Ԏ� 2009/1/11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�d�r�����̌o�ߕ�����Z�������A���J�ȃA�h�o�C�X���^�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�������l�t���ŌĂ�Œ������k�̋ɂ݂ł��B���炢�����܂����B �@���@���̂Ƃ���u�{�����[���A���v�v�ƁuFM�g�����X�~�b�^�v�͓����V�K�[���C�^��GND�ɂ��Ă��܂��Ă����̂ŁA�N����ׂ����ċN�����������������̂ł��ˁB�@�Q��́u�{�����[���A���v�v�ɂ͂��킢�����Ȃ��Ƃ����܂������A�Ȃ�قǂ������ɂȂ�܂����B �@BTL�V���[�g�͊ȒP�ȉ����ʼn���ł���ƌ������Ƃł��̂ŁA�c����́u�{�����[���A���v�v�̗L�����p�̂��ߕ����Ă݂܂��B �@���m�͋��낵���ł��ˁB�@���v����MP3�v���C���[��FM�g�����X�~�b�^������悤�ȉ�H�\���ɂȂ�Ȃ��ăz���g�悩�����ł��B�O�O�G �@�A�h�o�C�X���Ȃ���A�����̎��s�ʼn߂��Ă��܂��Ƃ���ł������A���s�̌������킩��ƁA�܂��D��S�������y�����Ȃ��Ă��܂����B��������낢��Ȏ����E�����ȋL�����y���܂��Ă��������܂��ˁB���Z�������A�ق�Ƃ��ɂ��肪�Ƃ��������܂����B ���낢�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@��͂�d�����ʂɂ�������ĂāABTL�V���[�g��IC���Ă��Ă��܂��Ă����悤�ł��ˁB �@������������ł���Ή����ɂ͋ߓ���ʂ�܂��B �@�{�����[���A�b�v�I�̊���������đ��������@����ԂȂ̂ł����A�p�^�[���J�b�g�Ȃǂ��ʓ|�Ȃ��߂Ɉȉ��́w�{�����[���A�b�v�I��FM�g�����X�~�b�^�[ ���p�P�[�u���x������Ĉ��S��BTL�V���[�g���������̂��H�삪�ȒP�ł��B �@�\�Z��200�`300�~���炢�i�O�O�G (�������Ŕ�����100�~�䂩���H) 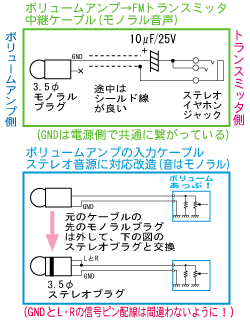 �@�w���p�P�[�u���x�̖����́ABTL�V���[�g���Ă��܂��A���v�̏o��(�C���z���[�q��GND��)�ƃg�����X�~�b�^�[�̓��͂�GND����藣���������̓����B
�@�w���p�P�[�u���x�̖����́ABTL�V���[�g���Ă��܂��A���v�̏o��(�C���z���[�q��GND��)�ƃg�����X�~�b�^�[�̓��͂�GND����藣���������̓����B�@���ɁA�A���v�̉����M���𐳂����g�����X�~�b�^�[�̓��͒[�q�Ɛڑ�����ׂɓd���R���f���T������ʼn����M���ł���𗬐M���݂̂�ʂ��悤�ɂ��Ă�鎖�B �@�E�̉�H�}�ł͂����Q�̖������ʂ����P�[�u�������悤�ɂ��Ă��܂��B �@�����M����BTL�o�͂̂ǂ���̒[�q(�A���v�`�E�a)����ł����o���܂����A�����o�͂��A���v�`��������o�Ă���̂ŁA �@�v���O�̃`�b�v(��[)�����A���v�a�̏o�͂Ȃ̂ō���͎g�p���܂���̂łǂ��ɂ��q���܂���B �@�g�p����Ă���W���b�N�̎d�l��������ƕς����i�ŁA�����ł̓`�b�v(��[)���������o�͂��o�Ă���Ƃ̏����܂����B�����������܂��B �@�A���vIC�̏o�͂͒�������������Ă��܂��̂ŁA���̒����特���M���������g�����X�~�b�^�ɒʂ��ׂ�10��F�̓d���R���f���T�Œ������J�b�g���܂��B �@���ۂɂ́A�g�����X�~�b�^�[�̓��͉�H�ɂ��R���f���T�������Ă��āA�����������܂܂ܐM����`���Ă����v�ȉ�H���l�����܂����A�����łȂ��ꍇ�⏔�X�̐S�z���炱���ł͓d���R���f���T���A���v��H�̈�Ƃ��Ă̏o�͒����J�b�g�p�Ƃ����ʒu�t���łƂ���܂��B(������͂킩��Ȃ��Ă����\�ł��B�����q���ł��������B) �@�d���R���f���T��ʂ��������M���̓��m�����ł����A���������g�����X�~�b�^�̓X�e���I(���Ǝv���c)�Ȃ̂ł����ƃX�e���I�ʼn���������悤�ɁA���p�P�[�u���̏o�͂́u�X�e���I�W���b�N�v�ɂ����k�E�q�̗����ɉ������悹�Ă����܂��傤�B �@�u���͎Ԃ̃��W�I�̓��m�����Ȃ�ł��E�E�E�v�Ȃ�ăI�`�����邩������܂��i�O�O�G �@���p�P�[�u���̓r���̃P�[�u�������͂Ȃ�ׂ��V�[���h�����g�p�����ق����A��������̊O���m�C�Y�̍�����h����̂ł����A���p�P�[�u���𐔃Z���`���x�̒����ō��Ȃ���ɐ_�o���ɂȂ�K�v�������Ǝv���܂��B���ʂ̔z���Ɏg���r�j�[���핢���ł����\�ł��B �@���āA�������Ē��p�P�[�u��������ă{�����[���A�b�v�I�ƃg�����X�~�b�^�[�̊Ԃɋ��߂�BTL�V���[�g�������A������Ɖ����M����`���邱�Ƃ��ł��܂��B �@�����ABTL�ł͖����Ȃ����̂ŃA���v�̃Q�C���͕Б��̃A���v��ł̑����x�Ԃ��ɂȂ�܂��B���������ڂɃ{�����[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂���B �@���łɉ�H�}�̉������A�w�{�����[���A�b�v�̓��͂��X�e���I�M���Ή��Ɂx��������B �@���X�{�����[���A�b�v�ɂ��Ă���v���O�̓��m�����v���O�Ȃ̂ŁAmp3�v���C���[�ɑ}���Ă����E�̕Б��̉��������������܂���B �@����ł͂��������̃X�e���I���y�������ƕ����܂���A�{�����[���A�b�v�ɂ����ƃX�e���I�̍��E�����̉�������͂ł���悤�Ƀv���O���������܂��B �@�������A���̉����̓v���O��ς��č��E�̐M�����~�b�N�X���邾���ł��B���̓��m�����ɂȂ�܂��B �@�X�e���I�̂܂ܑ������āA�X�e���I�Ńg�����X�~�b�^�[�ɑ���ɂ̓{�����[���A�b�v�I�̒��̊�����āu�����Ƃ����X�e���I�A���v�v�ɑ�������Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA�����ł͂����܂ł̉����Z�p�̖������ł��y���߂�{�����[���A�b�v�I�ł����ƃX�e���I������������������������E�E�E���x�ɗ��߂Ă����܂��B �@�������ă{�����[���A�b�v�I���牌���o�Ȃ��悤�ɂ��Ă��A�d�����ʂł��g�p�ł��܂��̂ŁA����220��F��25V�i�ȂǂɌ���������̂܂�DC12V�̓d���ł��g�p�ł���ł��傤�B �@�Ȃ�ƂȂ��ł����A���X��3V�p�̊�E��H���i�ő催�肬���12�`15V�œ������̂��Ȃ��C������������������܂��̂ŁA�����\�Z��������100�~�V���b�v�_�C�\�[�́u315�~�V�K�[�\�P�b�g�p�g�ѓd�b�[�d��v�𗘗p���āA12V��5V�̓d�����u�Ƃ��ă{�����[���A�b�v�I�ɂ�DC5V�̓d����^����ق����C���I�ɂ����S�Ȃ悤�ȋC�����܂��B(���̏ꍇ�ł�GND�͋��ʂɂȂ�܂���) �@����Ȃ�{�����[���A�b�v�I��̓d���R���f���T�͎��ւ��Ȃ��Ă��ǂ��ł����A�uDC/DC�R���o�[�^�d�����g���āv�Ȃ�Ęb�ɂȂ�ƂȂ�ƂȂ��u�d�q���N�S�v�����������܂��H(��) ���Ԏ� 2009/1/12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�u�����Ă݂܂��v�Ƃ͌����Ă݂����̂́A�V���[�g���ǎ��Ⴊ�Ȃ��Ȃ������炸�ϋl�܂��Ă��Ƃ���ł����B�������悭�悭�l�����玩���ԊW�̎���ł������B�@����Ȓ����Ԏ���m��A�{���ɋ������܂��B���i_ _�j�� �@�Ȃ�قƁA�R���f���T�Œ����������Ւf�����ł��ˁB �@�v���O��W���b�N�͂P�O�O�~�V���b�v�́u�����P�[�u���v�̍ɂ�����܂����A�u������Ɖ�����v��u���̓��e�ł����~�͈����v���Ə������L���ɂ���P�O�O�~�V���b�v�n�̕i�X�́A�J�~����ɏ��������Ȃ�����قƂ�Ǎw���E�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�����̍ɂ�����Ɩ��ɗ��Ƃ��������悤�ł��B�@DC/DC�R���o�[�^�̃L�����E�h�D�ECar Charger�����ɂł��̂ŁA�������Ԏ���ǂ�ł���Œ�����u�ɂ킩�d�q���N�S�v�������������ςȂ��ł��B�O�O �@���������A���p�P�[�u���A�X�e���I�M���Ή��A�Tv�d�����A�Ǝ�������Č��܂��B�@�ŏI�I�ɂ͂��ł���H�̌����锼�����̃^�b�p�[���P�[�X�ɂ��āA������ۂ����Ď��Ȗ����������߂�\��ł��O�O �@�A�h�o�C�X�݂̂Ȃ炸���N���N���܂ŗ^���Ă��������āA�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��I ���낢�� �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�L�����E�h�D�̓I�[�f�B�I�E�r�f�I�p�̒��p�P�[�u����ϊ��P�[�u���̕�ɂł�����ˁB �@�t���Ă���v���O��P�[�u���̒P�����l����ƁA�d�q�p�[�c�X�Ńv���O���Ă��ăn���_�Â�������A100�ς̒��p�P�[�u�����������Ďg�����ق����������A�ŏ�����P�[�u�����t���Ă��邵�Ƃ����ւ�֗��ł��B �@�V�K�[�A�_�v�^�����ɍw������Ă���̂ł�����A��͍H�삷�邾���ł��ˁB �@���ꂾ���ɂ�����Ă���̂Ȃ�A������ɃK�~�K�~�����Ȃ��悤���͉����ƒ���ŕ֗��ɂȂ�悤�ȕi������Ė��_�҉�ł���Ƃ����ł��ˁi�O�O�G ���Ԏ� 2009/1/14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@�w�{�����[���A���v�x�̃X�e���I�������Ƀ`�������W���Ă��܂����A���̉ߒ��ŐV���Ȏ����������B �@�Ȃ�ƁA�W���b�N���X�e���I�d�l�ł����B �@�����̊W�ŁA�W���b�N�������O���Ă悭�悭���߂Ă݂���A���������������B�v���O�̐�[���ڐG����d�ɂ����������̓d�ɂɐڑ�����Ă���̂ł��B �@���ۂɃw�b�h�z���ڑ����ăe�X�^�œ������Ă݂���E�E�E�Ȃ�ƃX�e���I�d�l�ł����B �@���ʂɌ�����X�e���I�W���b�N�Ƃ͈Ⴂ�A�v���O���������̃s��(IC��1p���ڑ�����Ă���ق�)���v���O��[(�܂�L��)�ɂȂ��Ă��܂��B �@IC��3p���ڑ�����Ă���̂�COM(GND)�C�����ڑ�����Ă��Ȃ��̂��v���O�̒��d��(R��)�ł����B (R�ɂ̓��m�����̃v���O���������߂A���������ON�̃X�C�b�`�ɁB) �@���ʓI�ɂ�IC��1p�����v���O�̐�[�ɂȂ��Ă���A���͂Ɓu�t�ʑ��v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ł��B �@������SW�t�̃��m�����W���b�N���Ǝv���Ă����̂ł����E�E�E�v�����݂Ƃ͋��낵���ł��ˁB �@�Ȃ��A���ݍs���Ă�������̏ڍׂ͉��L�A�h���X�ɂāB http://samidare.jp/jr7cwk/lavo.php?p=log&lid=65713 jr7cwk �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�������Ȏd�l�̃W���b�N���g�p����Ă���̂ł��ˁB �@���������ؐ��i�B �@���p�R�[�h�����ʂ̒��S������M�������܂��ˁB ���Ԏ� 2009/1/26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���������[�����낢��ȕ]���L�����Q�l�ɂ����Ă��������Ă��܂��B �@�ŋ�Panasonic�̎����ԗp�o�b�e���������葕�u�uLifeWINK�v�̎d�g�݂ɋ����������Ă��܂��B�Ǘ��l���܂ɂ�������������ł����琥���݂���͂���������K���ł��B ���q�̃p�p �l
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@�uLifeWINK�v(���C�t�E�C���N)�ł����A���߂Ēm��܂����i�O�O�G �@�p�i�\�j�b�N �X�g���[�W�o�b�e���[���������LIFE WINK�����y�[�W�ɂ��ƁA�o�b�e���[�̓d���ϓ��ȂǂׂĎ����肷�鑕�u�̂悤�ł��ˁB �@���ׂĂ݂��YouTube��LIFEWINK�̓���(LED�̓_�ł̗l�q)���オ���Ă��܂��ˁB �@�u�����݁v�́A�o�b�e���[�d���𒆂̃}�C�R����A/D�R���o�[�^�ŏ�ɓǂݍ��݁A�G���W���n�����̓d���̗��������A���u���̓d���ቺ�Ȃǂ̗l�q�𒆂̃v���O�����Ō������Ď�����Ԃ�ߕ��d�E�ߏ[�d�̌x�������v��_����������̂ł��ˁB �@�ق��ɖ{�̗��ʂɂ���u���x�Z���T�[�v�Ńo�b�e���[�̉��x���Ď����Ă���悤�ł����A����́u���ʐM�v�Ő�p�́uPanasonic��p�o�b�e���[�e�X�^�[�v�Ƀf�[�^�ʐM�����Ȃ��Ɩ{�݂̂̂ł̓��[�U�[�̓`�F�b�N�ł��Ȃ��悤�ł��B �@�����̃v���O�����ł͂��̉��x�f�[�^���A�G�߂̕ω��ɂ��o�b�e���[�d���̕ω��x�̕���Ƃ��Ďg�p���Ă���\���͍����ł��B �@�o�b�e���[�̎����ʂ���ɂ̓o�b�e���[���V�i��Ԃ̎���LIFEWINK���Ƃ���āu�w�K�v�����Ȃ���Ȃ炸�A���̏����f�[�^�ƁA���X�ƕω�����o�b�e���[�̓d����Ԃ̕ω����ׂČv�Z���ʂ�LED�ɕ\�����Ă���̂ŁA(�}�C�R�������̕��d��̂悤��)�P���Ɂu�d�������u�ɂȂ�����x�����v�Ȃ�Ă�������ł͖����Ǝv���܂���B �@�uPanasonic�o�b�e���[��p�v�Ƃ����̂��A���Ђ�Panasonic�o�b�e���[�ł���Ηx�ɉ����Ăǂ̒��x�̓d���ϓ��ɂȂ邩�̃f�[�^�������Ă���ׁA���̃p�����[�^���v���O�������ɑg�ݍ���Ōv�Z���Ă���ł��傤����A���Ѓo�b�e���[�ł͐���������ł��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B(��������������Ă��A�����܂��ɂ͔���ł���ł��傤����) �@�z�����猾���邱�Ƃ́u�G���W����~���̓d���ቺ�ȂǂŊ�b�̗͂͌v���Ă��邾�낤�v�u�G���W���n�����̓d���̗������ݓx�ŗx(������R�̑����x)�肵�ăf�[�^�����Ă��邾�낤�v�Ƃ������ł��B �@�����V�i���̃f�[�^�Ɣ�r�APanasonic�Г��̃o�b�e���[���\�f�[�^�ƏƂ炵���킹�ĂT�i�K�̎����\�����\�ɂ��Ă��鑕�u�ł��낤�Ƃ������ł��B �@���āA�u�����݁v��u������s�����@�v��Panasonic�̏ڂ����@�\�����ŗe�Ղɑz�������܂����A���́u�v���O�������e�v�ɂ��Ă͊O������ȒP�ɂ͒����┻�ʂ͂ł��Ȃ��ł��悤�B �@��ɏ����܂����悤�ɁA�}�C�R�����̕��d��̓���ׂ�Ȃ�P���ɓd����d���𑪒肵�ăO���t�����铙���Ē����ł��܂����A����LIFEWINK�͂��̂悤�ȒP������ł͂Ȃ��A�o�b�e���[�d���̕ω��x���ڂ������ׂĂ���@��ł�����O�����璲�ׂ�ׂɂ͓��l�ɗl�X�ȕ���Ԃ��Č�����LIFEWINK�ɓd�����Ƃ��ė^���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�Ԏ�ɂ���ĈႤ�X�^�[�^�[���[�^�[��]���̓d���ω��܂Ŋw�K���Ă���悤�ł�����A���ꂪ�Ⴆ�܂��o�N���̓d���ω��p�^�[���̕ω��̋�Ȃǂ��Ⴂ�A���Ԃł̎g�p���Č�����͔̂��ɓ���ł��ˁB �@���ꂾ���̎����ݔ��삵�Ă܂œ��e���������Ǝv���Ώۂł͂���܂���̂ŁA������ł͒����͒v���܂���B �@LIFEWINK�{�͈̂������ł����A���������悤�Ǝv����Panasonic�u���[�o�b�e���[������Ȃ��Ƃ����܂��A�Ȃɂ��G���W���n�����ɂǂ̒��x�̓d��������ăo�b�e���[�d�����Ƃꂭ�炢�ቺ����̂��A�����Ă��̎��̓d���ω��g�`�́H�E�E�E�ׂ�ׂ������Ԃ����͎����Ă��܂����B �@���m�Ȏ����f�[�^��ɂ́A�܂����Ԃ���䔃���K�v�������̂ł����i�O�O�G ���Ԏ� 2009/1/4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���e |
�@���Ԏ���ς��肪�Ƃ��������܂��B �@���낢�������Ƃ�����Ă���悤�ł��ˁB�������}�C�R���B �@�ʌ��Ńp�i�\�j�b�N�Ɏf�����Ƃ���A�����㐔�\����n�����̓d���~��(?)���w�K���ĎԂ̌̂̃f�[�^�����W����Ƃ̂��ƁB �@�ȒP�Ƀ��Z�b�g�Ȃ�Ăł�����������܂���ˁB �@��ς��肪�Ƃ��������܂����B ���q�̃p�p �l
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���Ԏ� |
�@Panasonic�̉������������ł�����A�{���ɂ��Ȃ蕡�G�Ƀf�[�^������Ă��̐ςݏd�˂Ńo�b�e���[�̏�Ԃf���Ă���̂ł��悤�ˁB �@�u�ǂ̈ʂ܂ŗ�����A���i�K�������v�Ȃǂ̓���̃`�F�b�N�͕���������Ǝv���܂��B �@����ƁALIFE WINK�̋@�\�ׂĂ��邤���Ɂu�V�i�o�b�e���[�ɕt������A���̃o�b�e���[�Ɖ^�������ɂ���̂��H�v�Ƃ����C�ɂ͂Ȃ�܂����B �@�ǂ��������Z�b�g�X�C�b�`���t���Ă���A�V�����o�b�e���[�������ɂ̓��Z�b�g����LIFE WINK�͂��̂܂g���܂킵���o����Έ����オ��̂ł����A�����������ɂ͍���Ă��Ȃ��悤�ŁE�E�E�B �@�����J���Ċ������A�ǂ����Ƀ��Z�b�g�[�q������̂�������܂���B �@���i�̐��i�㖳���\���̂ق��������ł��ˁB�����L��Ί��ɒN������͂��ă��Z�b�g���@���l�b�g�ŗ���Ă���ł��悤�B �@���������v����Ȃ�E�E�E���ʐM�@�\�𗘗p���āA�O���̒[������R�}���h����Œ��̃������[�����������郊�Z�b�g�@�\��g�ݍ��݂܂��ˁB �@Panasonic�̐�p���[���Ƃ͌��ʐM�ł���悤�ł�����A�P�ɋL�^�����o�b�e���[��Ԃ̋L�^�f�[�^��ǂݏo�������ł͂Ȃ��A�{�̂̃n�[�h�E�F�A�`�F�b�N�@�\���d���Ȃǂ̔������@�\�A�������[�f�[�^�̏������Ȃǂ̓����e�i���X�S���҂����ł��ł���悤�ɒʐM�R�}���h�Ƃ��ăv���O�������Ă����܂��B �@���������B���R�}���h�݂����ȕ������ۂɑg�ݍ��܂�Ă��Ă��A���R�{�̂��J���Ċ�����������ł̓T�b�p���킩��܂���A���ʐM���g���ă��Z�b�g�ł���@�\�������Ă��Ă��������G���h���[�U�[�ɂ͂���グ�ł��B �@�������K�\�����X�^���h�ɂ����p�̌��ʐM���o�b�e���[�`�F�b�J�[�ɂ����̂悤�ȃ����e�i���X�@�\�͓���ĂȂ��APanasonic�̊J���E�C������ɂ����p�̌��[���ł�������͂ł��Ȃ��ł��傤�B �@���[�J�[�����炷��A����ɉ�������ĉ��x�����Z�b�g����Ďg���܂킳���悤�Ȋ댯�����������S�Ȑv�ł��B �@�E�E�E�������A�{���ɂ��������@�\�������Ă�����A�ł����B ���Ԏ� 2009/1/15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����ȑO�̓����͂����灨 [2008�N�㔼�̉ߋ����O]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�T���₷���ړI�E��H�̃W�������ʈꗗ�͂����灨 [�W�������ʈꗗ]
�悭�g�����i�́u���̐}�v�͂����灨 [�悭�g�����i�́u���̐}�v]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(C) �u�C�̖����v�^Kansai-Event.com
�{�L���̖��f�]�ځE�]�p�Ȃǂ͂�����������
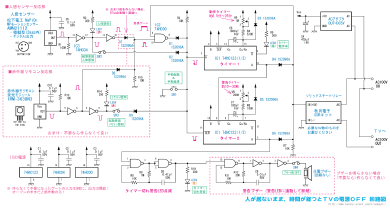
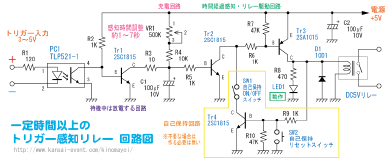
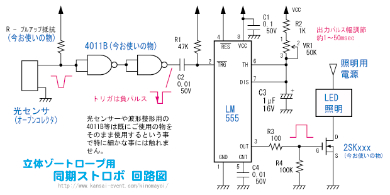

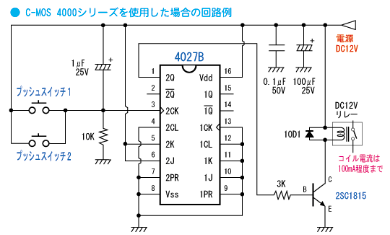
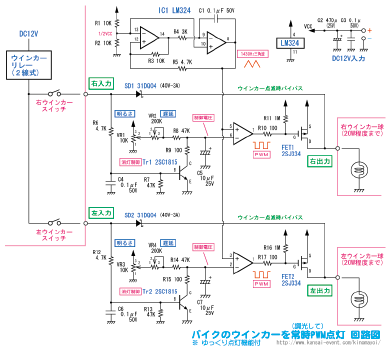
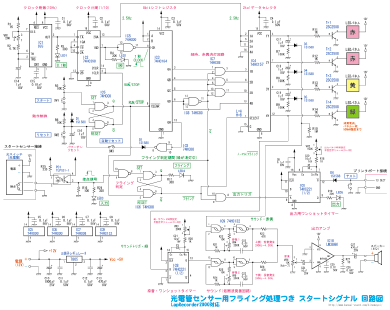
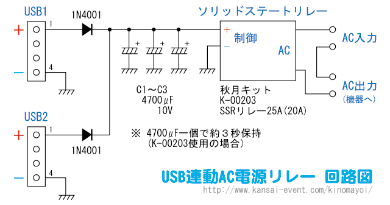
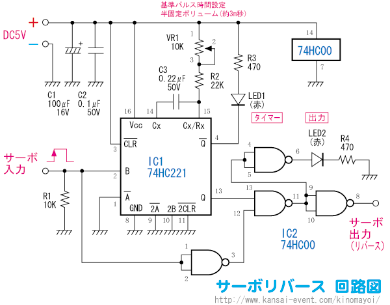
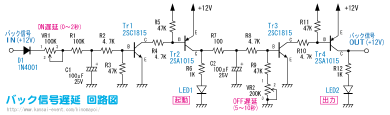
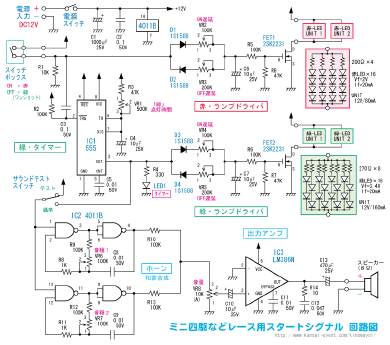
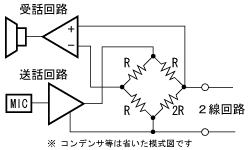 �@�E�̖͎��}�̂悤�ɁA��R�݂̂��u���b�W��H���\�����A���̑Ίp�ɂɁu���b��H�v�Ɓu��b��H�v��ڑ����܂��B
�@�E�̖͎��}�̂悤�ɁA��R�݂̂��u���b�W��H���\�����A���̑Ίp�ɂɁu���b��H�v�Ɓu��b��H�v��ڑ����܂��B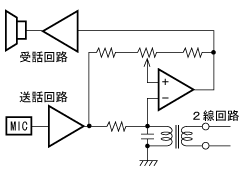 �@�d�b���̒ʐM��H�̋��ȏ��Ȃǂł́A�E�}�̂悤��OP�A���v�ƃg�����X���g�p�����n�C�u���b�h��H���f�ڂ���Ă���Ǝv���܂��B
�@�d�b���̒ʐM��H�̋��ȏ��Ȃǂł́A�E�}�̂悤��OP�A���v�ƃg�����X���g�p�����n�C�u���b�h��H���f�ڂ���Ă���Ǝv���܂��B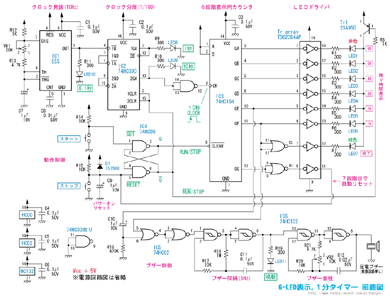
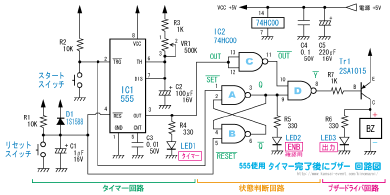
 �u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�
�u�C�̖����v�C�ɂȂ�����E�ꗗ�y�[�W�ɖ߂�